�Ջ��l�̃A�C�f�A
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�g�b�v�y�[�W�ɖ߂� �T�C�g�}�b�v
(�C���x�~�ɂ��DPF�̎��ȍĐ��𑣐i���A�|�X�g���˂�r�C�Ǔ����˂�DPF�����Đ��̕p�x���팸���ADPF�Đ����̔R���Q���h�~����B�j
�ŏI�X�V���F�@2014�N2��23��
 |
�P�D���s�̃p�e�B�L�����[�g��ጸ����DPF���u�̊T�v�Ɩ��_
�@�c�oF(Diesel Particulate Filter)�́A�f�B�[�[���G���W������r�o�����p�e�B�L�����[�g���R�[�W�F���C�g��Y���]�f
����ނƂ������E���Z���~�b�N�X���琬��E�H�[���t���[���m���X�̃t�B���^�i�}�P����ѐ}�Q�Q�Ɓj�ɂ��ߏW���ăp�e�B
�L�����[�g��ጸ���鑕�u���B
�L�����[�g��ጸ���鑕�u���B
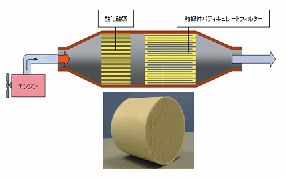 |
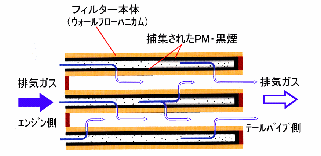 |
20���`30���Ԃɂ킽���ĘA������600���̍�����Ԃ��������邱�Ƃɂ��A�t�B���^�ɕߏW���ꂽ�p�e�B�L����
�[�g��R�Ă����ď�������B����ɂ���čĂѐV���Ƀt�B���^���p�e�B�L�����[�g��ߏW�ł���悤�ɂ��邱�Ƃ��J��Ԃ�
�s���A�t�B���^��A�����Ďg�p���Ă����悤�ɂ��Ă���B�����ŁA�t�B���^�ɕߏW���ꂽ�p�e�B�L�����[�g��R�Ă����ď�����
�čēx�A�t�B���^���p�e�B�L�����[�g��ߏW�ł���悤�ɂ��邱�Ƃ��w�t�B���^�̍Đ��x���́w�c�o�e�̍Đ��x�Ə̂��铮���
����B
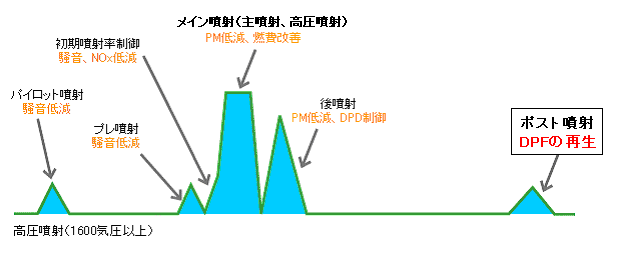
�@���āA�}�R�ɃR�������[���̔R�����˓������������B�V�����_���ŔR�Ă����邽�߂̔R�����˂̓p�C���b�g���˂����
���˂܂łł���A�Ō�ɕ��˂����|�X�g���˂̓V�����_�̒��ŔR����R�₷���Ƃ��ړI�ł͂Ȃ��A�r�C�ǂ֔R����
���邽�߂̕��˂ł���B�r�C�ǂ֗��ꂽ�R���́A�c�o�e�ɑ͐ς����p�e�B�L�����[�g��R�₷���߂Ɏg������
�̂��B
���˂܂łł���A�Ō�ɕ��˂����|�X�g���˂̓V�����_�̒��ŔR����R�₷���Ƃ��ړI�ł͂Ȃ��A�r�C�ǂ֔R����
���邽�߂̕��˂ł���B�r�C�ǂ֗��ꂽ�R���́A�c�o�e�ɑ͐ς����p�e�B�L�����[�g��R�₷���߂Ɏg������
�̂��B
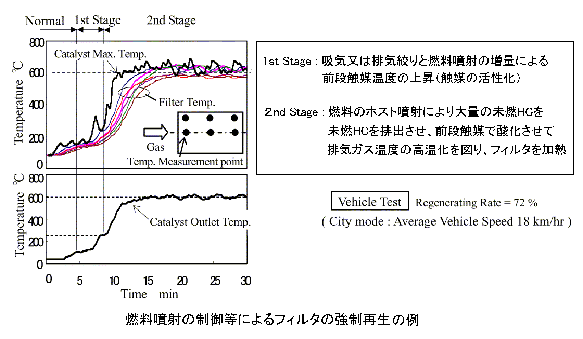
�@���āA�c�o�e�Ƀp�e�B�L�����[�g���͐ς�������ƃt�B���^�[���ڋl�܂���N�����ăt�B���^�ɂ͗n����T�����邽
�߁A���ʂ̃p�e�B�L�����[�g���t�B���^�ɑ͐ς���p�e�B�L�����[�g��R�Ă����ď�������K�v������B�����Ń|�X�g��
�˂��s���A���̃|�X�g���˂̔R�����t�B���^�̏㗬�ɔz�u���ꂽ�_���G�}�ŔR�Ă����Ĕr�C�K�X���x��600���܂ŏ㏸
������B�|�X�g���˂��p�����邱�Ƃɂ����20�`30���Ԃɂ킽���ăt�B���^��600���Ɉێ����i�}�S�Q�Ɓj�A�t�B���^�ɑ͐�
�����p�e�B�L�����[�g��R�₵�s������DPF�̃t�B���^���Đ�����悤�ɂ����̂��A�|�X�g���˕����ɂ��DPF�̍Đ��ł�
��B���������āADPF�̃t�B���^�Đ��Ɏg����|�X�g���˂̔R���́A�V�����_���ŔR�Ă��Ȃ����߂ɃG���W���o
�͂ɂ͉����^���Ȃ����߁ADPF�̍Đ��p�x�̑����ɂ���ă|�X�g���˂������A�R���̘Q����������Ƃɂ�
��B
�߁A���ʂ̃p�e�B�L�����[�g���t�B���^�ɑ͐ς���p�e�B�L�����[�g��R�Ă����ď�������K�v������B�����Ń|�X�g��
�˂��s���A���̃|�X�g���˂̔R�����t�B���^�̏㗬�ɔz�u���ꂽ�_���G�}�ŔR�Ă����Ĕr�C�K�X���x��600���܂ŏ㏸
������B�|�X�g���˂��p�����邱�Ƃɂ����20�`30���Ԃɂ킽���ăt�B���^��600���Ɉێ����i�}�S�Q�Ɓj�A�t�B���^�ɑ͐�
�����p�e�B�L�����[�g��R�₵�s������DPF�̃t�B���^���Đ�����悤�ɂ����̂��A�|�X�g���˕����ɂ��DPF�̍Đ��ł�
��B���������āADPF�̃t�B���^�Đ��Ɏg����|�X�g���˂̔R���́A�V�����_���ŔR�Ă��Ȃ����߂ɃG���W���o
�͂ɂ͉����^���Ȃ����߁ADPF�̍Đ��p�x�̑����ɂ���ă|�X�g���˂������A�R���̘Q����������Ƃɂ�
��B
�@�ŋ߂��R�����r�C�Ǔ����˂����|�X�g���˂Ɠ��l�Ƀt�B���^���x���㏸���ADPF���Đ�������@��p����g���b�N���s
�̂����悤�ɂȂ����B�������A�����r�C�Ǔ����˕�����DPF�Đ����|�X�g���˕����Ɠ��l��DPF�Đ����ɂ͔R����Q
��邱�Ƃ��Ƃɂ͑S���ς�肪�����V�X�e���ł���B
�̂����悤�ɂȂ����B�������A�����r�C�Ǔ����˕�����DPF�Đ����|�X�g���˕����Ɠ��l��DPF�Đ����ɂ͔R����Q
��邱�Ƃ��Ƃɂ͑S���ς�肪�����V�X�e���ł���B
�Q�D�|�X�g���ˍĐ���DPF���ڏ��^�g���b�N�ł́A�R�O���O����̎����s�R��̈����ƕs�
�@��ʂɃf�B�[�[���g���b�N�ł́A�G���W�������g���b�N�̑��s�����ɂ����ē����p�e�B�L�����[�g�����ʂɔr�o����
��̂́A�ȉ��Ɏ������g���b�N�̑��s����G���W���^�]�̑��쎞�ł���B
��̂́A�ȉ��Ɏ������g���b�N�̑��s����G���W���^�]�̑��쎞�ł���B
�@�@�f�B�[�[���g���b�N�̔��i�Ƃ���ɑ����}������
�A�@�G���W���̎n����
�@���āA���^�f�B�[�[���g���b�N�̑����́A�s�s���ő�z�ւ���E���X�̔z�����̉ݕ��̏W�z�Ɩ��ɑ����g���Ă�
��Ƃ̂��Ƃł���B���̏W�z�Ɩ��̏��^�f�B�[�[���g���b�N�́A�P���̂قƂ�ǑS�Ă̑��s�n�悪�l���̖��W�����Z��
�⏤�X�X�ł���A�M��������_�ł̒�~�E���i��a�ɂ�錸���E�����^�]�������A�܂��˕ʂ̔z�B���ɍs����G
���W���̒�~�ƍĎn���̕p�x���������Ƃł���B���̂悤�ɁA�l�����W�n��̏W�z�Ɩ��ł́A�Z�����ł̔��i�E��~
������E�����A����уG���W���̒�~�E�Ďn���̍ۂ��p�e�B�L�����[�g�����ʂɔr�o����A����炪DPF���u�̃t�B���^
�ɉߏ�ɕߏW�E�͐ς���邱�ƂɂȂ�B���������̂悤�ȃg���b�N���s�ƃG���W���^�]�̏�Ԃł́A�Z�����ł̕p�ɂȃg��
�b�N�̔��i�E��~������E�����ł��邽�ߔr�C�K�X���x���傫���ϓ����邽�߁ADPF�̃t�B���^�̓p�e�B�L�����[�g���_
���E�����ł���600���̍����Ɉێ��ł��Ȃ��B
��Ƃ̂��Ƃł���B���̏W�z�Ɩ��̏��^�f�B�[�[���g���b�N�́A�P���̂قƂ�ǑS�Ă̑��s�n�悪�l���̖��W�����Z��
�⏤�X�X�ł���A�M��������_�ł̒�~�E���i��a�ɂ�錸���E�����^�]�������A�܂��˕ʂ̔z�B���ɍs����G
���W���̒�~�ƍĎn���̕p�x���������Ƃł���B���̂悤�ɁA�l�����W�n��̏W�z�Ɩ��ł́A�Z�����ł̔��i�E��~
������E�����A����уG���W���̒�~�E�Ďn���̍ۂ��p�e�B�L�����[�g�����ʂɔr�o����A����炪DPF���u�̃t�B���^
�ɉߏ�ɕߏW�E�͐ς���邱�ƂɂȂ�B���������̂悤�ȃg���b�N���s�ƃG���W���^�]�̏�Ԃł́A�Z�����ł̕p�ɂȃg��
�b�N�̔��i�E��~������E�����ł��邽�ߔr�C�K�X���x���傫���ϓ����邽�߁ADPF�̃t�B���^�̓p�e�B�L�����[�g���_
���E�����ł���600���̍����Ɉێ��ł��Ȃ��B
�@���̂��߁ADPF�̃t�B���^�ɂ̓p�e�B�L�����[�g���͐ς������邱�ƂɂȂ�B�V�����K���iH17�N�j�K���̏��^�f�B�[�[
���g���b�N�ɂ͐V���Ƀ|�X�g���ˎ�DPF���u�����ڂ���Ă��邪�A�����|�X�g���ˎ�DPF���u�ł̓|�X�g���˂Ŕr�C
�ǂɔR�����������A���̃|�X�g���˔R�����_���G�}�ŔR�Ă����Ĕr�C�K�X���x��600���܂ō��������đ͐ς�
���p�e�B�L�����[�g��R�Ă����ăt�B���^���珜�����ăt�B���^���Đ����Ă���B����͔r�C�Ǔ����˕�����DPF��
���̏ꍇ���S�������ł���B�����āA���̃t�B���^���Đ����鏈�u���A�g���b�N�̑��s���ɍs����̂������Đ��ƌĂ�
��A��Ԓ��ɍs����̂��蓮�Đ��ƌĂ�Ă�����̂ł���B
���g���b�N�ɂ͐V���Ƀ|�X�g���ˎ�DPF���u�����ڂ���Ă��邪�A�����|�X�g���ˎ�DPF���u�ł̓|�X�g���˂Ŕr�C
�ǂɔR�����������A���̃|�X�g���˔R�����_���G�}�ŔR�Ă����Ĕr�C�K�X���x��600���܂ō��������đ͐ς�
���p�e�B�L�����[�g��R�Ă����ăt�B���^���珜�����ăt�B���^���Đ����Ă���B����͔r�C�Ǔ����˕�����DPF��
���̏ꍇ���S�������ł���B�����āA���̃t�B���^���Đ����鏈�u���A�g���b�N�̑��s���ɍs����̂������Đ��ƌĂ�
��A��Ԓ��ɍs����̂��蓮�Đ��ƌĂ�Ă�����̂ł���B
�@���ۂ̏W�z�Ɩ����Ől�����W�n����^�s���s�����V�����K���iH17�N�j�K���̃|�X�g���ˎ�DPF���u����
�����^�f�B�[�[���g���b�N�ł́A�P�ʑ��s����������̃G���W���{�̂���̃p�e�L�����[�g�r�o�ʂ��������邽
�߁A�|�X�g���˂ɂ��t�B���^�̍Đ����p�ɂɍs�����Ƃ��K�v���������B���̃|�X�g���˂ɂ��DPF�̎����Đ���
�p�x�ɔ�Ⴕ�ĔR�����Q���邽�߁A�|�X�g���ˍĐ���DPF���ڂ̐V�����K���iH17�N�j�K���̏��^�f�B�[�[
���g���b�N�ł͎����s�R������������������ƂɂȂ�B���̃|�X�g���ˎ�DPF���u���ڂ��V�����K���iH17�N�j�K��
�̏��^�f�B�[�[���g���b�N�ɂ������R����ɂ��āA�C���^�[�l�b�g�̌f���ɂ͎��̂悤�ȏ������݂�����ꂽ�B
�����^�f�B�[�[���g���b�N�ł́A�P�ʑ��s����������̃G���W���{�̂���̃p�e�L�����[�g�r�o�ʂ��������邽
�߁A�|�X�g���˂ɂ��t�B���^�̍Đ����p�ɂɍs�����Ƃ��K�v���������B���̃|�X�g���˂ɂ��DPF�̎����Đ���
�p�x�ɔ�Ⴕ�ĔR�����Q���邽�߁A�|�X�g���ˍĐ���DPF���ڂ̐V�����K���iH17�N�j�K���̏��^�f�B�[�[
���g���b�N�ł͎����s�R������������������ƂɂȂ�B���̃|�X�g���ˎ�DPF���u���ڂ��V�����K���iH17�N�j�K��
�̏��^�f�B�[�[���g���b�N�ɂ������R����ɂ��āA�C���^�[�l�b�g�̌f���ɂ͎��̂悤�ȏ������݂�����ꂽ�B
| |
|
| |
���r�o�K�X�K����4HK1��190�n�͂��ڂ����t�H���[�h�@�_���v�i���^�g���b�N�j���t���ύڃA�N�Z���S�J�Ń��b�^�[������Tkm�ȏ㑖��
�̂� �V�����K���̃G���t�i���^�g���b�N�j��4JJ-1�͂Q���ς݂łP���������������悹�ĂȂ��̂ɃA�N�Z�������`���Ɠ���ł����b�^�[���� ��T km�B�@�E�E�E�E������Ȃ�ł��J�^���O�̔����ȉ��͂Ȃ����낤�ɁB����Ȃ̂ŔR�����ǂ�������� �B���ł���̂��s�v�c�łȂ� �܂���B �i���G���t�ɂ��ẮA���ɂ��R�5km/���b�^�[���x�Ƃ��鐔���̏������݂�����ꂽ�B�j |
| |
�V�����K���K���̃L�����^�[�Ƃ��R��͍�����A1�g�����Ń��b�^�[������6km�Ƃ������B |
| |
�����g�������z�����邽�߂ɐV�����K���K���̃_���i�i�ύڗ�2�g���A���^�g���b�N�j����đ����Ă݂���A�����������Ⴄ�Ƃ͂����A
�R��͎d���ŏ���Ă�4�g���i���^�g���b�N�j�Ɠ������������炢�������B |
| |
�����FA
�G���t5.2����(�R��́j�T.�T�`�U�ikm�^���b�g���j���傢����B �n�ꂾ���ƊX���A�X�g�b�v���S�[�͏��Ȃ߂���B �@�@�@�@�� �����FB �������炢�ł��B ������ƍr�����ƂT���炢�ł��ˁB �����ł��A����100�L�����炢�ŁA���b�^�[�T���炢�ł��B�ςׂ͎݉Ԑώԁi�ԗ��^���g���b�N�j�Ȃ̂ŁA�Q�g���ς݂łP�D5�g���ڂ��Ă��� �����ق��ł��B �@�@�@�@�� �����FC �c�o�c�t���Ă�Ԃ͍Đ��Ă��ŗ]�v�ɔR���g������ �A�ǂ����Ă��R������Ȃ��ȁB �����U�i�G���t�j�̑��ɂl�i�O�H�ӂ����L�����^�[�H�j���g�i����f���g���H�j�������^���Ŏg�������ǁA�ǂ���ς���B �ύڂłT�����^�k �����Ηǂ�������B |
�@�ȏ�̂悤�ɁA�C���^�[�l�b�g�̌f���̏������݂�����ƁA�|�X�g���ˎ�DPF���u���ڂ��V�����K���iH17�N�j�K��
�̏��^�f�B�[�[���g���b�N���l�����W�n��ʼn^�s�����ꍇ�������s�R��͂T�`�U�@�q/���b�g�����x�Ƃ̂��Ƃł���B�V
�����K���iH17�N�j�ƈȑO�̋K���ł����V�Z���K���iH15�N)�̓K���������^�f�B�[�[���g���b�N���l�����W�n��ʼn^�s
�����ꍇ�̎����s�R���\�Q�Ɏ������B���̕\�Q���疾�炩�Ȃ悤���A�V�����K���iH17�N�j�K�����|�X�g���ˎ�
DPF���u�𓋍ڂ������^�f�B�[�[���g���b�N�́A�ȑO�̋K���ł����V�Z���K���iH15�N)�K�����|�X�g���ˎ�
DPF���u�𓋍ڂ��Ă��Ȃ����^�f�B�[�[���g���b�N�ɔ�ׁA�����s�R���R�O�����������Ă����̂ł���B����
�悤���r�C�Ǖ��ˍĐ�����DPF���u�ɂ�����DPF�Đ��ɂ��R����́A�|�X�g���ˍĐ���DPF���u�̏ꍇ�ł��S��
���l�ł���B
�̏��^�f�B�[�[���g���b�N���l�����W�n��ʼn^�s�����ꍇ�������s�R��͂T�`�U�@�q/���b�g�����x�Ƃ̂��Ƃł���B�V
�����K���iH17�N�j�ƈȑO�̋K���ł����V�Z���K���iH15�N)�̓K���������^�f�B�[�[���g���b�N���l�����W�n��ʼn^�s
�����ꍇ�̎����s�R���\�Q�Ɏ������B���̕\�Q���疾�炩�Ȃ悤���A�V�����K���iH17�N�j�K�����|�X�g���ˎ�
DPF���u�𓋍ڂ������^�f�B�[�[���g���b�N�́A�ȑO�̋K���ł����V�Z���K���iH15�N)�K�����|�X�g���ˎ�
DPF���u�𓋍ڂ��Ă��Ȃ����^�f�B�[�[���g���b�N�ɔ�ׁA�����s�R���R�O�����������Ă����̂ł���B����
�悤���r�C�Ǖ��ˍĐ�����DPF���u�ɂ�����DPF�Đ��ɂ��R����́A�|�X�g���ˍĐ���DPF���u�̏ꍇ�ł��S��
���l�ł���B
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
�@�V�����K���iH17�N�j�K���̏��^�f�B�[�[���g���b�N���V�Z���K���iH15�N)�K���̏��^�f�B�[�[���g���b�N�ɔ�ׁA�R
�O���O����̎����s�R��������Ă����������́A�l�����W�n��𑖍s����ꍇ�̕p�ɂȔ��i�E��~������E��
���ɂ���ăG���W���{�̂���̃p�e�L�����[�g�r�o�ʂ��������邽�߂��|�X�g���ˍĐ���DPF���u�̍Đ��p�x���K�R
�I�ɑ������A���ʓI�Ƀ|�X�g���˂���Q��R���̗ʂ��������Ă��܂����߂��l������B�V�����K���ɓK�������e��
�̃|�X�g���ˍĐ���DPF���u���ڂ̏��^�f�B�[�[���g���b�N�̔R���l�Ɉ������Ă��邱�Ƃɂ��āA�e���[�J�[��
���ɃR�X�g�D��Ń|�X�g���ˍĐ���DPF���u���̗p���ĔR����������w�ԐM���I�݂�Ȃœn��Ε|���Ȃ��x�Ƃ�
�l���őΉ������̂��A�Ⴕ���̓|�X�g���ˍĐ���DPF���u�ȊO�Ɂw�R����]���ɂ��Ȃ��Ŕr�o�K�X�ł���Z�p�x
�������Ă��Ȃ����߂ł���̂��A�����͑��̗��R������̂��͕s���ł���B
�O���O����̎����s�R��������Ă����������́A�l�����W�n��𑖍s����ꍇ�̕p�ɂȔ��i�E��~������E��
���ɂ���ăG���W���{�̂���̃p�e�L�����[�g�r�o�ʂ��������邽�߂��|�X�g���ˍĐ���DPF���u�̍Đ��p�x���K�R
�I�ɑ������A���ʓI�Ƀ|�X�g���˂���Q��R���̗ʂ��������Ă��܂����߂��l������B�V�����K���ɓK�������e��
�̃|�X�g���ˍĐ���DPF���u���ڂ̏��^�f�B�[�[���g���b�N�̔R���l�Ɉ������Ă��邱�Ƃɂ��āA�e���[�J�[��
���ɃR�X�g�D��Ń|�X�g���ˍĐ���DPF���u���̗p���ĔR����������w�ԐM���I�݂�Ȃœn��Ε|���Ȃ��x�Ƃ�
�l���őΉ������̂��A�Ⴕ���̓|�X�g���ˍĐ���DPF���u�ȊO�Ɂw�R����]���ɂ��Ȃ��Ŕr�o�K�X�ł���Z�p�x
�������Ă��Ȃ����߂ł���̂��A�����͑��̗��R������̂��͕s���ł���B
�@����A�V�����K���iH17�N�j�K���̃|�X�g���ˍĐ���DPF���u���ڂ����^�f�B�[�[���g���b�N�̔̔��ݐϑ䐔
�ɔ�Ⴕ�ăR�������[�����ˑ��u���ւ�|�X�g���˂ɂ��DPF�Đ��Ɏg����y���̘Q��������A�n����
�g���̌����̈�Ɖ]���Ă����_���Y�f�iCO�Q�j���傫�����₵�čs���́A�Љ�I�ɂ��d��Ȗ����
�͖������낤���B���̏�A�|�X�g���ˍĐ���DPF���u�ɂ������|�X�g���˂ɂ��DPF�̍Đ��Z�p�́A�|�X�g���˂�
�ꂽ�y���̕������V�����_���ǂɕt�����ăG���W���I�C���ɍ������A�y���ŃG���W���I�C������߂���錇��
�������Ă���悤���B�y���Ŋ�߂��ꂽ�G���W���I�C���͔S�y�̒ቺ�������N�������߁A�p�ɂȃG���W���I�C��������
�K�v�ƂȂ�A�G���W���I�C���̘Q��ƂȂ�̂ł�����Ȏ����̖ʂ���͖��ł���B���݂ɁA����͔r�C�Ǔ����˕���
��DPF�Đ��̏ꍇ�ɂ��A�y���ŃG���W���I�C������߂���錇�ׂ������̂������ł���B
�ɔ�Ⴕ�ăR�������[�����ˑ��u���ւ�|�X�g���˂ɂ��DPF�Đ��Ɏg����y���̘Q��������A�n����
�g���̌����̈�Ɖ]���Ă����_���Y�f�iCO�Q�j���傫�����₵�čs���́A�Љ�I�ɂ��d��Ȗ����
�͖������낤���B���̏�A�|�X�g���ˍĐ���DPF���u�ɂ������|�X�g���˂ɂ��DPF�̍Đ��Z�p�́A�|�X�g���˂�
�ꂽ�y���̕������V�����_���ǂɕt�����ăG���W���I�C���ɍ������A�y���ŃG���W���I�C������߂���錇��
�������Ă���悤���B�y���Ŋ�߂��ꂽ�G���W���I�C���͔S�y�̒ቺ�������N�������߁A�p�ɂȃG���W���I�C��������
�K�v�ƂȂ�A�G���W���I�C���̘Q��ƂȂ�̂ł�����Ȏ����̖ʂ���͖��ł���B���݂ɁA����͔r�C�Ǔ����˕���
��DPF�Đ��̏ꍇ�ɂ��A�y���ŃG���W���I�C������߂���錇�ׂ������̂������ł���B
�@�Ƃ���ŁADPF���������ꂽ�V�����K���K���g���b�N�E�o�X���s�s�����s�ɑ��p���ꂽ�ꍇ�ADPF����������Ă���
�����^�̃g���b�N�E�o�X�ɔ�ׂ�DPF�̋����Đ��ɂ��R��������ACO2�̔r�o���������Ă���悤�Ȍ���ł����
��������炸�A�g���b�N���[�J�[�̊e�Ђ̐V�����K���K���g���b�N�̃J�^���O�ɂ́A�ȉ��̂悤�Ȑ�`���傪�ւ炵����
�L�ڂ���Ă���B
�����^�̃g���b�N�E�o�X�ɔ�ׂ�DPF�̋����Đ��ɂ��R��������ACO2�̔r�o���������Ă���悤�Ȍ���ł����
��������炸�A�g���b�N���[�J�[�̊e�Ђ̐V�����K���K���g���b�N�̃J�^���O�ɂ́A�ȉ��̂悤�Ȑ�`���傪�ւ炵����
�L�ڂ���Ă���B
�@�@�@�@�@�@�u�G�R���W�[�Ɣ��������a���関���u���^�́E�E�E�E�v�@�i�O�H�ӂ����j
�@�@�@�@�@�@�u���ƈ��S�̃t�����g�����i�[����v�@�i���쎩���ԁj
�@�@�@�@�@�@�u����̐���s���v�@�i�����U�����ԁj
�@�@�@�@�@�@�u���E�ō������̊����\�����E�E�E�E�v�@�i���Y�f�B�[�[���j
�@�e�Ђ̃J�^���O�ɂ��ƁA�f���炵�������\�̃g���b�N���s�̂���Ă���Ƃ̂��ƁB�������A�C���^�[�l�b�g�̌f����
�́w�A�C�h�����O�X�g�b�v�̔z���摽����ŁA�����B �V�������ƌ������A(DPF�������Đ�����j�R�đ��u�t���ʼn�
�{���y�������Ă��ꏏ����Ȃ����B�x�Ƃ̉^�]�肩��̓{��̏������݂�����ꂽ�B�e�g���b�N���́[�J�[�ɑ��A��
���s�R��̈����ʼn^�s�o��̕��S�����������[�U�[�͐V�����K���K���̃g���b�N�̑��}�ȔR����P�������]��ł�
�邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��B
�́w�A�C�h�����O�X�g�b�v�̔z���摽����ŁA�����B �V�������ƌ������A(DPF�������Đ�����j�R�đ��u�t���ʼn�
�{���y�������Ă��ꏏ����Ȃ����B�x�Ƃ̉^�]�肩��̓{��̏������݂�����ꂽ�B�e�g���b�N���́[�J�[�ɑ��A��
���s�R��̈����ʼn^�s�o��̕��S�����������[�U�[�͐V�����K���K���̃g���b�N�̑��}�ȔR����P�������]��ł�
�邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��B
�@�Ȃ��A�V�����K���iH17�N�j�K���܂��̓|�X�g�V�����K���iH21�N�AH22�N�j���f�B�[�[���g���b�N�ɓ��ڂ���Ă����|�X
�g���ˎ��܂��͔r�C�Ǔ��R�����ˎ���DPF���u�́A�^�]�苃�����̑��u�ł����ɁA�M�����E�ϋv���ɂ������̖�
�肪����悤���B����ɂ��ăC���^�[�l�b�g�̌f���ɁA�^�]��Ǝv����l�B����DPF���u�ɑ��鐔�����s����
�������݂�����ꂽ�B����猻�s��DPF���u�ɑ���g���b�N�^�]���g���b�N�����W�҂�2011�N7�����݂̏�����
�݂�\�R�ɂ܂Ƃ߂��B
�g���ˎ��܂��͔r�C�Ǔ��R�����ˎ���DPF���u�́A�^�]�苃�����̑��u�ł����ɁA�M�����E�ϋv���ɂ������̖�
�肪����悤���B����ɂ��ăC���^�[�l�b�g�̌f���ɁA�^�]��Ǝv����l�B����DPF���u�ɑ��鐔�����s����
�������݂�����ꂽ�B����猻�s��DPF���u�ɑ���g���b�N�^�]���g���b�N�����W�҂�2011�N7�����݂̏�����
�݂�\�R�ɂ܂Ƃ߂��B
| |
| 106 �F�����������������ς��B�F2009/01/17(�y) 19:45:21 ID:zHrrou49
�@�@�@�@�g���u���A�����Ǝv���B �@�@�@�@���u�̎����͂ǂꂭ�炢�Ȃ̂������H 107 �F�����������������ς��B�F2009/01/25(��) 05:19:09 ID:McsB82oh �@�@�@�@�ȑO�A�r�`�ŏĂ��Ă��烉�W�G�[�^�[���j���I �@�@�@�@�������Q�x�� 108 �F�����������������ς��B�F2009/01/25(��) 21:36:15 ID:pW3s3ou/ �@�@�@�@���K�i�g���b�N�f�B�[���[�̃T�[�r�X�̈Ӗ��j�̵ڂɌ��킹���猇�וi����� �@�@�@�@�ڰё吙 113 �F110�F2009/03/04(��) 12:52:02 ID:CHNvQgMy �@�@�@�@���O�������{�ׂ̂���A�Z���T�[���r�M�ŗo�����Ă��ƃf������d�b�����܂�����E�E�E 115 �F�����������������ς��B�F2009/03/18(��) 18:47:26 ID:b/igabH+ �@�@�@�@�����Ă�l�����������ɂݕt����قǎ_���ς��L���Ɣ����������� �@�@�@�@���X�ƏĂ������Đ������オ���ăI�[�o�[�q�[�g������ �@�@�@�@�Q��C���������ǂȂ��Ȃ��E�E�E����ȎԂ͉��̂����H 116 �F�����������������ς��B�F2009/03/21(�y) 08:59:28 ID:F4cInw0a >>115 �@�@�@����Ȃ̌��\����͂�����B�������ԗ��Ђŕ����҂ł��o��A���[�J�[�������܂��ȑΉ�����Ǝv����B 118 �F�����������������ς��B�F2009/03/22(��) 01:03:30 ID:XWLOpd9l �@�@�@�@�R�O���ԁA�G���W�����鐡�O�܂Ńu���܂킹�I�I �@�@�@�@�c�o�e �R�P�邩�@�G���W�� �R�P�邩�@��Ɉ�� 120 �F�����������������ς��B�F2009/03/28(�y) 22:34:51 ID:vAA9xZvO �@�@�@�@�c�o�q�r�K�X�N���|�i�|�@�t���Ă邩����� �@�@�@�@�t���Ė����Ԃ� ���Ȃ��@�O���Ă��܂��� �h����� �h�I�I 121 �F�����������������ς��B�F2009/03/29(��) 07:28:03 ID:9CzfgYLW �@�@�@�@���˃}�t���[�ɂ��������ǂ��������ȁc�B�����������c (>_<) 122 �F�����������������ς��B�F2009/03/29(��) 09:20:36 ID:nO74eM9m �@�@�@�@�����͂ǂ��ł��������ǁA�r�C�K�X�̓��������B 137 �F�����������������ς��B�F2010/10/14(��) 21:04:03 ID:cvXU9E23 �@�@�@�@���N�̓~�A�c�o�c�蓮�ŏĂ�����A���đ����ɂ����܂��c�o�c�����v�����Ă��܂������������B �@�@�@�@�R��ڂ̔R�Ă��I�������G���W���`�F�b�N�����v�_��orz �@�@�@�@�ȗ��A�T�Ɉ�x�͉ɂȎ��ɋ����ŔR�Ă����Ă܂� �@�@�@�@�����U�͂c�o�c��������������łc�o�c�R�Ăł��܂��� �@�@�@�@���܂��ĂȂ��ƒ��������Ă����܂��� 141 �F�����������������ς��B�F2010/11/29(��) 01:26:31 ID:gBT515Sk �@�@�@�@���ʂȔR���g���čĐ������āA�Đ����͑����Ɣ����o���� �@�@�@�@�G���W���I�C�����߂ăG���W������A�C���W�F�N�^�[��DPR�l�܂点�Ă݂���� �@�@�@�@�{��DPR�}�t���[���S�I�ڋl�܂�ɂ��G���W�����\�ቺ�A�p���[���S�R�o�Ȃ��Ȃ�܂����B�C�����30���~�A���s �@�@�@�@124,000�q��������I�I 147 �F�����������������ς��B�F2011/04/19(��) 18:32:00.26 ID:xaI+c4EX >>144 �@�@�@�@����g���^�Ԃ�������ۏ؉����ŏC�������I �@�@�@�@http://toyota.jp/recall/kaisyu/110106.html 150 �F�����������������ς��B�F2011/04/20(��) 23:13:14.62 ID:kwpZHuqS �@�@�@�@DPD�蓮�Đ��{�^�������Ă݂���A�����Đ��̎��ƈ���đ��s�ł��Ȃ��Ă��炢�ڂɑ������B |
�@�ȏ�̂悤�ȁADPF���u�̕s����������Ă��錻���Ⴢ��炵���S���{�g���b�N����́A���L�̕\�S�Ɏ���
���悤�ɁA�s��ł�DPF���u�̕s����̎��W�ƁA���y��ʏȂɑ���DPF���u�̕s�������\�����ꂽ
�悤���B
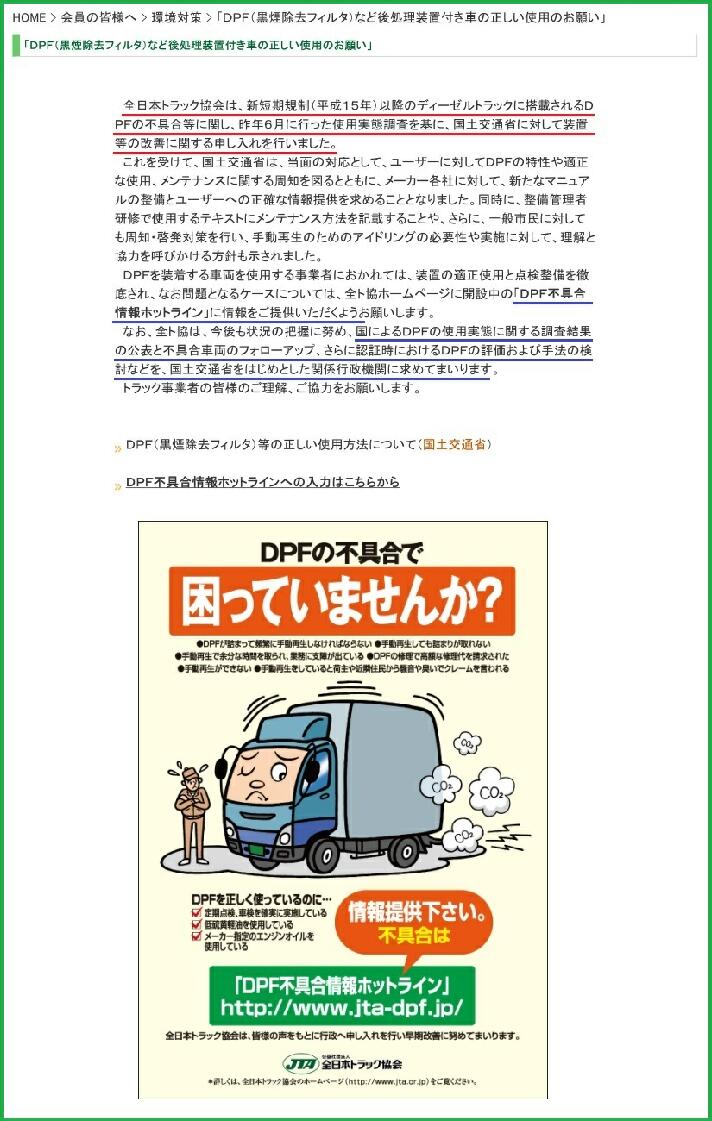
�@���݁i��2013�N5��30���j�̂Ƃ���A�R�������[���̃|�X�g���˕������r�C�Ǔ����˕������R���Q���CO2����̌�
�ׂ����鋭���Đ���p�ɂɕK�v�Ƃ���DPF���u�𓋍ڂ����g���b�N�����s�̂���Ă��Ȃ��B���̂��߁A�g���b�N�^�]��
�́ADPF�`�F�b�N�����v�̕p�ɂȓ_���ɂ��ʓ|��DPF�����Đ��̏��u�E��Ԃ�����������ɁA�{���̎��ȍĐ��@
�\�̗��DPF���u�̌̏�̑����ɂ���������Ă���悤���B���̂悤�ȏ���A��L�̕\�S�̂悤�ɁA�S���{�g���b�N
����́A���y��ʏȂɑ���DPF���u�̕s�������\�����ꂽ�悤�ł���B�ʂ����āA���̂悤�ȑS���{�g���b�N��
��̐\������������Ƃɂ��A���y��ʏȂ́A�펯�I�ɍl����g���b�N���[�J��DPF���u�̌��ׂ���������Z�p
�̑����J�����w�����邾���̂悤�Ɏv���邪�A���ۂ̂Ƃ���͔@���Ȃ��̂ł��낤���B
�ׂ����鋭���Đ���p�ɂɕK�v�Ƃ���DPF���u�𓋍ڂ����g���b�N�����s�̂���Ă��Ȃ��B���̂��߁A�g���b�N�^�]��
�́ADPF�`�F�b�N�����v�̕p�ɂȓ_���ɂ��ʓ|��DPF�����Đ��̏��u�E��Ԃ�����������ɁA�{���̎��ȍĐ��@
�\�̗��DPF���u�̌̏�̑����ɂ���������Ă���悤���B���̂悤�ȏ���A��L�̕\�S�̂悤�ɁA�S���{�g���b�N
����́A���y��ʏȂɑ���DPF���u�̕s�������\�����ꂽ�悤�ł���B�ʂ����āA���̂悤�ȑS���{�g���b�N��
��̐\������������Ƃɂ��A���y��ʏȂ́A�펯�I�ɍl����g���b�N���[�J��DPF���u�̌��ׂ���������Z�p
�̑����J�����w�����邾���̂悤�Ɏv���邪�A���ۂ̂Ƃ���͔@���Ȃ��̂ł��낤���B
�@�Ƃ���ŁA���Ԃł͐̂���u���Ή��̏o�O�v�Ɖ]����Ⴆ���ǂ��m���Ă���B���́u���Ή��̏o�O�v�Ƃ́A�o�O��
�q�����܂�̒x���ɓX�֓��̓d�b������ƁA�X�̎�l�����ۂɂ���䥂łĂ����Ȃ��ł���ɂ��������
���A��l���q�Ɂu���x�A�X���o���Ƃ���ł��v�Ɠ�����l�q�𑨂������̂ł���B����́A�u���������ʼn����d������
�Ă��炸�A�}���Ŏd��������������w�͂������s�킸�A����Ɏd���̐i���ɂ��ĕ��C�ʼnR�����v�悤�ȏꍇ��
�Ⴆ�Ƃ��Ďg���Ă���B
�q�����܂�̒x���ɓX�֓��̓d�b������ƁA�X�̎�l�����ۂɂ���䥂łĂ����Ȃ��ł���ɂ��������
���A��l���q�Ɂu���x�A�X���o���Ƃ���ł��v�Ɠ�����l�q�𑨂������̂ł���B����́A�u���������ʼn����d������
�Ă��炸�A�}���Ŏd��������������w�͂������s�킸�A����Ɏd���̐i���ɂ��ĕ��C�ʼnR�����v�悤�ȏꍇ��
�Ⴆ�Ƃ��Ďg���Ă���B
�@���A���ɁA���y��ʏȂւ́uDPF���u�̕s�������\������v�ɑ��A���y��ʏȂ��S���{�g���b�N����ɑ��A
DPF���u�̌������̋Z�p�I�Ȗڏ��������ɂ�������炸�A�u���Ή��̏o�O�v���Ȃ���́uDPF���u�̌������ɉs
�ӓw�͒��v�Ƃ̉��Ă���ꍇ�ł���A�߂������ɁuDPF���u�̑����̌������v�������ł��Ȃ��\�����ɂ�
�č������ƂɂȂ�B�������A���y��ʏȂ��{���ɁuDPF���u�̕s������v�ł���Z�p�𑁊��Ɏ��p���ł���ڏ����{
���ɂ���Ȃ�A���̉̒��ɂ́A�s������̋Z�p�I�ȓ��e�̊T�v��������Ă��锤�ł���B�ʂ����āA���y��
�ʏȂ̉��ɂ́A�uDPF���u�̑����̌������v�̉\�ȋ�̓I�ȋZ�p���L�ڂ���Ă����̂ł��낤���B���͂Ƃ�
����A�S���{�g���b�N����́uDPF���u�̕s�������\������v�ɑ��鍑�y��ʏȂ̉̓��e��S���{�g���b�N
����̃z�[���y�[�W��Ɍ��J���Ă��������������̂ł���B
DPF���u�̌������̋Z�p�I�Ȗڏ��������ɂ�������炸�A�u���Ή��̏o�O�v���Ȃ���́uDPF���u�̌������ɉs
�ӓw�͒��v�Ƃ̉��Ă���ꍇ�ł���A�߂������ɁuDPF���u�̑����̌������v�������ł��Ȃ��\�����ɂ�
�č������ƂɂȂ�B�������A���y��ʏȂ��{���ɁuDPF���u�̕s������v�ł���Z�p�𑁊��Ɏ��p���ł���ڏ����{
���ɂ���Ȃ�A���̉̒��ɂ́A�s������̋Z�p�I�ȓ��e�̊T�v��������Ă��锤�ł���B�ʂ����āA���y��
�ʏȂ̉��ɂ́A�uDPF���u�̑����̌������v�̉\�ȋ�̓I�ȋZ�p���L�ڂ���Ă����̂ł��낤���B���͂Ƃ�
����A�S���{�g���b�N����́uDPF���u�̕s�������\������v�ɑ��鍑�y��ʏȂ̉̓��e��S���{�g���b�N
����̃z�[���y�[�W��Ɍ��J���Ă��������������̂ł���B
�@�Ȃ��A�S���{�g���b�N����{���ɍ��y��ʏȂ́uDPF���u�̕s��������ł���Z�p�̊J�����g���b�N���[�J�ɑ�
�ċ��͂Ɏw�����v�Ƃ́u���Ή��̏o�O�v�ɗނ���݂藈�����S���{�g���b�N�����肽���Ȃ��̂ł���A
�S���{�g���b�N�����DPF���u�̕s����e�Ղɉ����ł����㏈������V�X�e���i�������J2005-69238�j�̋Z�p��
���Ɏ��p�����邱�Ƃ����y��ʏȂɗv�]�����ł���ƍl������B���̂Ȃ�A���݂̂Ƃ���A�uDPF���u�̕s���
�����ł���Z�p�v�́A�㏈������V�X�e���i�������J2005-69238�j�����ł���ƍl�����邽�߂��B���̂悤�ȋ�̓I��
�uDPF���u�̕s��������ł���Z�p�v�𑁋}�Ɏ��p�����邱�Ƃ����y��ʏȂɗv�]���Ȃ�����A�g���b�N���[�U�́A��
�ꂩ������X�Ǝ��ȍĐ��@�\�̗�錻�s��DPF���u�̌̏�̑����ɋ������ꑱ���邱�ƂɂȂ��Ă��܂����ꂪ������
����ƍl�����邪�A�@���Ȃ��̂ł��낤���B
�ċ��͂Ɏw�����v�Ƃ́u���Ή��̏o�O�v�ɗނ���݂藈�����S���{�g���b�N�����肽���Ȃ��̂ł���A
�S���{�g���b�N�����DPF���u�̕s����e�Ղɉ����ł����㏈������V�X�e���i�������J2005-69238�j�̋Z�p��
���Ɏ��p�����邱�Ƃ����y��ʏȂɗv�]�����ł���ƍl������B���̂Ȃ�A���݂̂Ƃ���A�uDPF���u�̕s���
�����ł���Z�p�v�́A�㏈������V�X�e���i�������J2005-69238�j�����ł���ƍl�����邽�߂��B���̂悤�ȋ�̓I��
�uDPF���u�̕s��������ł���Z�p�v�𑁋}�Ɏ��p�����邱�Ƃ����y��ʏȂɗv�]���Ȃ�����A�g���b�N���[�U�́A��
�ꂩ������X�Ǝ��ȍĐ��@�\�̗�錻�s��DPF���u�̌̏�̑����ɋ������ꑱ���邱�ƂɂȂ��Ă��܂����ꂪ������
����ƍl�����邪�A�@���Ȃ��̂ł��낤���B
�@����Ƃ��A���y��ʏȂɑ���S���{�g���b�N����́uDPF���u�̕s�������\������v�̐^�̖ړI�́A���ȍĐ�
�@�\�̗�錻�s��DPF���u�̌��ׂɊւ���g���b�N���[�U�́u�s�����K�X�����v��_�������̂ł��낤���B���̏ꍇ��
�́A���y��ʏȂƑS���{�g���b�N����u���s��DPF���u�̌����P�ɉs�ӓw�͒��v���A�s�[�����邽�߂̒��Ԍ���
�^�ʖڊ�Ŗނ��炵�������Ă���ƌ��邱�Ƃ��\�ł���B���̂悤�Ȃ��Ƃ������ł���A���y��ʏȂƑS���{�g���b�N
����́A���ɁA���ȍĐ��@�\�̗�錻�s��DPF���u�ɂ�����̏�̑����ɂ���đ���Ȕ�Q�E���f�����Ă���g��
�b�N���[�U�̑��݂�S���Y�ꋎ���Ă��邱�ƂɂȂ�Ǝv�����A�@���Ȃ��̂ł��낤���B
�@�\�̗�錻�s��DPF���u�̌��ׂɊւ���g���b�N���[�U�́u�s�����K�X�����v��_�������̂ł��낤���B���̏ꍇ��
�́A���y��ʏȂƑS���{�g���b�N����u���s��DPF���u�̌����P�ɉs�ӓw�͒��v���A�s�[�����邽�߂̒��Ԍ���
�^�ʖڊ�Ŗނ��炵�������Ă���ƌ��邱�Ƃ��\�ł���B���̂悤�Ȃ��Ƃ������ł���A���y��ʏȂƑS���{�g���b�N
����́A���ɁA���ȍĐ��@�\�̗�錻�s��DPF���u�ɂ�����̏�̑����ɂ���đ���Ȕ�Q�E���f�����Ă���g��
�b�N���[�U�̑��݂�S���Y�ꋎ���Ă��邱�ƂɂȂ�Ǝv�����A�@���Ȃ��̂ł��낤���B
�@���������A�V�����r�o�K�X�K���i��2005�N�K���j�K���̂��߂�DPF���u�𓋍ڂ����g���b�N�̎s�̂������ŊJ�n����
�Ĉȗ��A����7�N�ԋ߂����o�߂��Ă���̂ł���B����ɂ�������炸�ADPF���u�̕s��E���ׂ́A�����ɖw�lj��P��
��Ă��Ȃ��悤���B���̌��ʁA�g���b�N���[�U�͒����ɂ킽����DPF���u�̕s��E���ׂɋ������ꑱ���Ă���悤�ł�
��B����ɂ��āA�g���b�N���[�U�ɂ́A���D���l�Ƃ��������悤���Ȃ��B���̂悤�ɁA�����ɂ킽���ăg���b�N���[�U�ɑ�
��̋]���킹�����Ă���g���b�N���[�J��A���̂悤�ȃg���b�N���[�J�̍s�ׂ�e�F���Ă���l���̍��y��ʏȁE�S
���{�g���b�N����̊����̐l�B�́A�Ɩ��Ӗ��̋ɂ݂̂悤�Ɏv���邪�A�@���Ȃ��̂ł��낤���B
�Ĉȗ��A����7�N�ԋ߂����o�߂��Ă���̂ł���B����ɂ�������炸�ADPF���u�̕s��E���ׂ́A�����ɖw�lj��P��
��Ă��Ȃ��悤���B���̌��ʁA�g���b�N���[�U�͒����ɂ킽����DPF���u�̕s��E���ׂɋ������ꑱ���Ă���悤�ł�
��B����ɂ��āA�g���b�N���[�U�ɂ́A���D���l�Ƃ��������悤���Ȃ��B���̂悤�ɁA�����ɂ킽���ăg���b�N���[�U�ɑ�
��̋]���킹�����Ă���g���b�N���[�J��A���̂悤�ȃg���b�N���[�J�̍s�ׂ�e�F���Ă���l���̍��y��ʏȁE�S
���{�g���b�N����̊����̐l�B�́A�Ɩ��Ӗ��̋ɂ݂̂悤�Ɏv���邪�A�@���Ȃ��̂ł��낤���B
�@������A�f�B�[�[����DPF���u�́A2003�N��������{�̃f�B�[�[���g���b�N�ɍ̗p����n�߂āA���ɂP�O�N�ȏ�̍Ό�
���o�߂��Ă���B����ɂ�������炸�A����DPF���u�̃t�B���^�Đ��̕s��́A�w��lj�������Ă��Ȃ��悤�ł���B
���̂��Ƃ́A���L�̍ŋ߂̃C���^�[�l�b�g��̏����f���m�邱�Ƃ��ł���̂ł͂Ȃ����낤���B
���o�߂��Ă���B����ɂ�������炸�A����DPF���u�̃t�B���^�Đ��̕s��́A�w��lj�������Ă��Ȃ��悤�ł���B
���̂��Ƃ́A���L�̍ŋ߂̃C���^�[�l�b�g��̏����f���m�邱�Ƃ��ł���̂ł͂Ȃ����낤���B
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14104629869;_ylt=A3xTwst7iQlT5EsA8gFP__N7?fr=rcmd_chie
_detail
_detail
�@�ȏ�̃C���^�[�l�b�g��̃g���b�N���[�U����̏�������悤�ɁA���s��DPF���u�ɂ̓t�B���^�Đ��̃V�X�e��
�ɏd��Ȍ��ׂ����邱�Ƃ͖��炩�ł���B���̂��߁A�g���b�N���[�U�́A���X�̃f�B�[�[���g���b�N�̉^�s�Ɩ��ł͑���
�̋]�����������Ă���̂�����̂悤���B������A2003�N����DPF���u�����{�̃f�B�[�[���g���b�N�ɍ̗p����n��
�Ă���P�O�N�ȏ�̍Ό����o�߂��Ă���ɂ�������炸�A���͕̏ς���Ă��Ȃ��̂ł���B���̂��Ƃ���A�g���b�N��
�[�J�⍑�y��ʏȂ́A���s��DPF���u�ɂ̓t�B���^�Đ��̖��������ł����i�E���@���Z�p�I�Ɋ��S�Ɏ�l�܂��
�ł���Ɛ��������B
�ɏd��Ȍ��ׂ����邱�Ƃ͖��炩�ł���B���̂��߁A�g���b�N���[�U�́A���X�̃f�B�[�[���g���b�N�̉^�s�Ɩ��ł͑���
�̋]�����������Ă���̂�����̂悤���B������A2003�N����DPF���u�����{�̃f�B�[�[���g���b�N�ɍ̗p����n��
�Ă���P�O�N�ȏ�̍Ό����o�߂��Ă���ɂ�������炸�A���͕̏ς���Ă��Ȃ��̂ł���B���̂��Ƃ���A�g���b�N��
�[�J�⍑�y��ʏȂ́A���s��DPF���u�ɂ̓t�B���^�Đ��̖��������ł����i�E���@���Z�p�I�Ɋ��S�Ɏ�l�܂��
�ł���Ɛ��������B
�@����ɂ�������炸�ADPF���u�̖������ɗL���ȕM�Ғ�Ă��C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j���㏈��
����V�X�e���i�������J2005-69238�j�̂Q���̓����Z�p���A�g���b�N���[�J�⍑�y��ʏȂ́A��Ȃɖ����E�َE���Ă���
�悤�ł���B�ʂ����āA�g���b�N���[�J�⍑�y��ʏȂ́A������DPF���u�̖������ɗL���ȂQ���̓����Z�p���A��
��A���N��܂Ŗ����E�َE��������̂ł��낤���B�Ȃ��A���̂Q���̓����Z�p�́A2024�N���ɂ͓����������ł��邱��
�ɂȂ邽�߁A���ɁA���s��DPF���u�̖��������\�N��ɐ摗�肵���ꍇ�ɂ́A�g���b�N���[�J�́A���̂Q���̓���
�Z�p�����R����Ɏ��Ђ̃f�B�[�[���g���b�N�ɍ̗p���邱�Ƃ��\�ƂȂ�B���̏ꍇ�A���ꂩ��\�N��܂ŁADPF���u
�̌��ז�肪��������Ȃ����ƂɂȂ��Ă��܂��Ɛ��@�����B����́A�g���b�N���[�U�ɂ́u���D���l�v�Ƃ��������悤��
�Ȃ����Ԃł͖������낤���B
����V�X�e���i�������J2005-69238�j�̂Q���̓����Z�p���A�g���b�N���[�J�⍑�y��ʏȂ́A��Ȃɖ����E�َE���Ă���
�悤�ł���B�ʂ����āA�g���b�N���[�J�⍑�y��ʏȂ́A������DPF���u�̖������ɗL���ȂQ���̓����Z�p���A��
��A���N��܂Ŗ����E�َE��������̂ł��낤���B�Ȃ��A���̂Q���̓����Z�p�́A2024�N���ɂ͓����������ł��邱��
�ɂȂ邽�߁A���ɁA���s��DPF���u�̖��������\�N��ɐ摗�肵���ꍇ�ɂ́A�g���b�N���[�J�́A���̂Q���̓���
�Z�p�����R����Ɏ��Ђ̃f�B�[�[���g���b�N�ɍ̗p���邱�Ƃ��\�ƂȂ�B���̏ꍇ�A���ꂩ��\�N��܂ŁADPF���u
�̌��ז�肪��������Ȃ����ƂɂȂ��Ă��܂��Ɛ��@�����B����́A�g���b�N���[�U�ɂ́u���D���l�v�Ƃ��������悤��
�Ȃ����Ԃł͖������낤���B
�R�D�|�X�g���ˍĐ���DPF���ڏ��^�g���b�N��2015�N�d�ʎԔR���ɓK���ł��闝�R
�@���݁A�e�g���b�N���[�J�̓|�X�g���ˎ�DPF���u�𓋍ڂ��Ď����s�R��啝�Ɉ��������V�����K���iH17�N�j�K����
���^�f�B�[�[���g���b�N�i�ύڗʂQ�g���j��2015�N�d�ʎԔR��10.35�q/���b�g���ɓK���g���b�N�Ƃ��Ĕ̔����Ă���B��
���s�R��T�`�U�@�q/���b�g���̏��^�g���b�N��2015�N�d�ʎԔR��10.35�q/���b�g���ɓK�����Ă���̂ł���B���Ƃ�
�s�v�c�Ȃ��Ƃł��邪�A����ɂ͈ȉ��Ɏ����悤�ȗ��R���l������B
���^�f�B�[�[���g���b�N�i�ύڗʂQ�g���j��2015�N�d�ʎԔR��10.35�q/���b�g���ɓK���g���b�N�Ƃ��Ĕ̔����Ă���B��
���s�R��T�`�U�@�q/���b�g���̏��^�g���b�N��2015�N�d�ʎԔR��10.35�q/���b�g���ɓK�����Ă���̂ł���B���Ƃ�
�s�v�c�Ȃ��Ƃł��邪�A����ɂ͈ȉ��Ɏ����悤�ȗ��R���l������B
�@���������G�l���M�[������ȃG�l���M�[�����d�ʎԔ��f����ψ���E�d�ʎԔR��������̍ŏI���
�܂Ƃߎ����ɂ��Ə��^�f�B�[�[���g���b�N�i�ύڗʂQ�g���j���d�ʎԃ��[�h�R��l�͈ȉ��̎菇�ŎZ�o����Ă��邻��
���B
�܂Ƃߎ����ɂ��Ə��^�f�B�[�[���g���b�N�i�ύڗʂQ�g���j���d�ʎԃ��[�h�R��l�͈ȉ��̎菇�ŎZ�o����Ă��邻��
���B
�@�ύڗ��Q�g���̏��^�g���b�N�̏d�ʎԃ��[�h�R��l�̌v�Z�͈ȉ��̒ʂ�ł���B
�@�@�G���W�������ő��肵���R��}�b�v��p���A�s�s�����s���[�h�iJE�O�T���[�h�j�Ɠs�s�ԑ��s���[�h�i�c�f���z�t
80km/h�葬���[�h�j�̊e���[�h�̔R��l���v�Z�V���~���[�V�����ŎZ�o����B
80km/h�葬���[�h�j�̊e���[�h�̔R��l���v�Z�V���~���[�V�����ŎZ�o����B
�A�@�s�s�����s���[�h�R��l�Ɠs�s�ԑ��s���[�h�R��l�̊e�R��ɎԎ�ɉ����Đݒ肳�ꂽ�W����p���ĉ��d����
���ċ��߂�B
���ċ��߂�B
�@�y �v�Z���z
�@�ȏ�̏d�ʎԃ��[�h�R��l�̌v�Z�ߒ�������ƁA�|�X�g���ˍĐ���DPF���ڂ̐V�����K���iH17�N�j�K���̏��^�f�B
�[�[���g���b�N�̏d�ʎԃ��[�h�R��l�̎Z�o�ɂ́A�|�X�g���ˍĐ���DPF���u�ɂ�����t�B���^�̍Đ����̃|�X�g����
�̔R������ʂ��S���ɖ�������Ă���悤���B
�[�[���g���b�N�̏d�ʎԃ��[�h�R��l�̎Z�o�ɂ́A�|�X�g���ˍĐ���DPF���u�ɂ�����t�B���^�̍Đ����̃|�X�g����
�̔R������ʂ��S���ɖ�������Ă���悤���B
�@�Ƃ���ŁA�V�����K���iH17�N�j�K���̃|�X�g���ˍĐ���DPF���ڂ̏��^�f�B�[�[���g���b�N�́A�W�z�Ɩ����ɑ����g
���A�l�����W�n����^�s���邱�Ƃ������B�����āA�Z�����ł̔��i�E��~������E�����̕p�x�����������߂��G���W
���{�̂���̃p�e�L�����[�g�r�o�ʂ��������邱�Ƃ����c�o�e�Ƀp�e�L�����[�g���������͐ς��邱�ƂɂȂ�B���̂��߁A
�|�X�g���˂ɂ��t�B���^�̍Đ����p�ɂɍs�����Ƃ��K�v�ƂȂ�A�|�X�g���˂ɂ�鑽���̔R���������邱�ƂɂȂ�B
����DPF�Đ��̂��߂����Ɏg����|�X�g���˂̔R������ʂ́A���^�g���b�N�̏d�ʎԃ��[�h�R��l�̎Z�o�ɂ͗p��
���Ă��Ȃ��悤���B
���A�l�����W�n����^�s���邱�Ƃ������B�����āA�Z�����ł̔��i�E��~������E�����̕p�x�����������߂��G���W
���{�̂���̃p�e�L�����[�g�r�o�ʂ��������邱�Ƃ����c�o�e�Ƀp�e�L�����[�g���������͐ς��邱�ƂɂȂ�B���̂��߁A
�|�X�g���˂ɂ��t�B���^�̍Đ����p�ɂɍs�����Ƃ��K�v�ƂȂ�A�|�X�g���˂ɂ�鑽���̔R���������邱�ƂɂȂ�B
����DPF�Đ��̂��߂����Ɏg����|�X�g���˂̔R������ʂ́A���^�g���b�N�̏d�ʎԃ��[�h�R��l�̎Z�o�ɂ͗p��
���Ă��Ȃ��悤���B
�@���̂悤���d�ʎԃ��[�h�R��l�́A�G���W���o�͂̂��߂ɏ�����R������ʂ���Z�o���ꂽ�R�����
���\������邱�ƂɂȂ��Ă���B�����āA�d�ʎԃ��[�h�R��l�̌v�Z�ɂ́A���ۂ̃g���b�N�E�o�X�̑��s�ɔ����|�X
�g���ˍĐ���DPF�ɂ�����t�B���^�̍Đ����̃|�X�g���˂̔R������ʂ��S���Z�����ꂸ�A�t�B���^�Đ�����
�|�X�g���˂ɂ��R���̘Q��́A���S�ɖ�������Ă���悤���B���̂��Ƃ́A���y��ʏȂ�DPF�̍Đ��̂��߂̃|
�X�g���˂̔R�����g���b�N�̉^�s�ɕs�K�v�ȔR���Ƃ݂Ȃ��Ă��邱�Ƃ��Ӗ�����B��̑S�́A�d�ʎԃ��[�h�R��l�̎Z
�o�@�����߂����y��ʏȂł́A�c�o�e���u�̍Đ��̂��߂ɏ�����R���́A�J�[�N�[�����g�p����ꍇ�Ɠ��l�ɁA�g
���b�N�^�]�肪���g�̚n�D�̂��߂ɍD���D��ŏ���Ă���l���Ă���̂ł��낤���B�M�҂ɂ͗����ɋꂵ�ނƂ����
����B
���\������邱�ƂɂȂ��Ă���B�����āA�d�ʎԃ��[�h�R��l�̌v�Z�ɂ́A���ۂ̃g���b�N�E�o�X�̑��s�ɔ����|�X
�g���ˍĐ���DPF�ɂ�����t�B���^�̍Đ����̃|�X�g���˂̔R������ʂ��S���Z�����ꂸ�A�t�B���^�Đ�����
�|�X�g���˂ɂ��R���̘Q��́A���S�ɖ�������Ă���悤���B���̂��Ƃ́A���y��ʏȂ�DPF�̍Đ��̂��߂̃|
�X�g���˂̔R�����g���b�N�̉^�s�ɕs�K�v�ȔR���Ƃ݂Ȃ��Ă��邱�Ƃ��Ӗ�����B��̑S�́A�d�ʎԃ��[�h�R��l�̎Z
�o�@�����߂����y��ʏȂł́A�c�o�e���u�̍Đ��̂��߂ɏ�����R���́A�J�[�N�[�����g�p����ꍇ�Ɠ��l�ɁA�g
���b�N�^�]�肪���g�̚n�D�̂��߂ɍD���D��ŏ���Ă���l���Ă���̂ł��낤���B�M�҂ɂ͗����ɋꂵ�ނƂ����
����B
�@����ł́A���y��ʏȂ͂c�o�e���u�̍Đ��̂��߂ɏ���ꂽ�R�����g���b�N���[�U�̎�E�n�D�ɂ��R�������
���Ȃ��Ă���ƍl�����闝�R�́A�d�l���ɂ��d�ʎԃ��[�h�R��l�̋L�ڍ��ڂ��݂����Ă������A���s���ɉ^�]
��̈ӎv�ɖ��W�ɏ�����R���ł���ɂ�������炸DPF���u�ɂ�����Đ����̏���R���̗D���\�����鍀
�ڂ��������߂��B
���Ȃ��Ă���ƍl�����闝�R�́A�d�l���ɂ��d�ʎԃ��[�h�R��l�̋L�ڍ��ڂ��݂����Ă������A���s���ɉ^�]
��̈ӎv�ɖ��W�ɏ�����R���ł���ɂ�������炸DPF���u�ɂ�����Đ����̏���R���̗D���\�����鍀
�ڂ��������߂��B
�@���̂悤�ɁA���y��ʏȂ���߂Ă��錻�s�̏d�ʎԃ��[�h�R��l�̎Z�o�@�ł́A�Đ����̔R���̘Q����Ȃ�
DPF���u�̋Z�p���J�������Ƃ��Ă��A�g���b�N�̎d�l���ɔR���Q��̍팸���������I�ȔF�l��\���ł��Ȃ��̂���
��ł���B���̂��߁A���Ƀg���b�N���[�J�̈ӗ~�I��DPF�W�ɏ]������Z�p�҂������Ƃ��A���̔ނ���i�ɍĐ�����
�R���Q����Ȃ�DPF���u�̊J����\���o���Ƃ��Ă��A�����ł��R�X�g�A�b�v�̉\��������Η]���̗ǐS�I�ȏ�i��
�Ȃ�����A���Y�Z�p�̌����J����������Ȃ��̂ł͂Ȃ����낤���B�Ȃ��Ȃ�A�g���b�N���[�J���R���Q��̏��Ȃ�
DPF���u���J���ł��Ă�������i�������Ƃ��Ă����̔R����P�̒��x���d�l���ɖ��L���Đ�`���邱�Ƃ��ł��Ȃ��B
DPF���u�̋Z�p���J�������Ƃ��Ă��A�g���b�N�̎d�l���ɔR���Q��̍팸���������I�ȔF�l��\���ł��Ȃ��̂���
��ł���B���̂��߁A���Ƀg���b�N���[�J�̈ӗ~�I��DPF�W�ɏ]������Z�p�҂������Ƃ��A���̔ނ���i�ɍĐ�����
�R���Q����Ȃ�DPF���u�̊J����\���o���Ƃ��Ă��A�����ł��R�X�g�A�b�v�̉\��������Η]���̗ǐS�I�ȏ�i��
�Ȃ�����A���Y�Z�p�̌����J����������Ȃ��̂ł͂Ȃ����낤���B�Ȃ��Ȃ�A�g���b�N���[�J���R���Q��̏��Ȃ�
DPF���u���J���ł��Ă�������i�������Ƃ��Ă����̔R����P�̒��x���d�l���ɖ��L���Đ�`���邱�Ƃ��ł��Ȃ��B
�@�����āA����DPF���u�ɃR�X�g�A�b�v���������ꍇ�ɂ́A�g���b�N�̉��i�����͂̒ቺ�������悤�ȕs���v�����Ă���
���\�����������߂ł���B���������Č����_�ł͊e�g���b�N���[�J�́ADPF���u�̍Đ��ɂ��R���Q������A��
���i�݂̂��d������DPF�Đ��Z�p���̗p���Ă�����̂ƍl������B�ȏ�̂悤�ȏ���A�V�����K���iH17�N�j�K
���̊e�Ђ̏��^�f�B�[�[���g���b�N�̎����s�R��̈����́A�e�Ђ����^�g���b�N�ɍĐ����ɔR�����������Q���|�X
�g���ˍĐ����c�o�e���u���̗p���Ă��邱�Ƃ���Ȍ����ƍl�����A����Ƃ����̏������čs�����̂ƍl������B��
�̂悤�ȏ�����������ő�̌����́A���y��ʏȂ���߂Ă��錻�s�̏d�ʎԃ��[�h�R��l�̎Z�o�ɂ����āA�|
�X�g���ˍĐ���DPF���u�ɂ�����t�B���^�̍Đ����̃|�X�g���˂̔R����������S�ɖ�������Ă��邱�Ƃł��Ȃ�
���낤���B
���\�����������߂ł���B���������Č����_�ł͊e�g���b�N���[�J�́ADPF���u�̍Đ��ɂ��R���Q������A��
���i�݂̂��d������DPF�Đ��Z�p���̗p���Ă�����̂ƍl������B�ȏ�̂悤�ȏ���A�V�����K���iH17�N�j�K
���̊e�Ђ̏��^�f�B�[�[���g���b�N�̎����s�R��̈����́A�e�Ђ����^�g���b�N�ɍĐ����ɔR�����������Q���|�X
�g���ˍĐ����c�o�e���u���̗p���Ă��邱�Ƃ���Ȍ����ƍl�����A����Ƃ����̏������čs�����̂ƍl������B��
�̂悤�ȏ�����������ő�̌����́A���y��ʏȂ���߂Ă��錻�s�̏d�ʎԃ��[�h�R��l�̎Z�o�ɂ����āA�|
�X�g���ˍĐ���DPF���u�ɂ�����t�B���^�̍Đ����̃|�X�g���˂̔R����������S�ɖ�������Ă��邱�Ƃł��Ȃ�
���낤���B
�@���̂悤�ɁA�t�B���^�Đ��̕p�x�̍����d�l�Ƃ��ă|�X�g���˂ő��ʂ̔R���˂��A���t�B���^�Đ��p�x��
�����|�X�g���ˍĐ���DPF���u�𓋍ڂ����f�B�[�[���g���b�N�ł����Ă��A���̃f�B�[�[���g���b�N�̏d�ʎԃ��[
�h�R��l�̌v�Z�ɂ͂c�o�e�Đ��ł̏���R���ʂ��S���Z������Ȃ��̂ŁA���̏d�ʎԃ��[�h�R��l����������
���Ƃ͖����B�Ȍ��Ɍ����A�d�ʎԃ��[�h�R��l�̌v�Z�ł͂c�o�e�Đ��ł̔R������ʂ���Ɖ��肳��Ă����
���B���̂��Ƃ́A���y��ʏȂ��g���b�N���[�J�ɁwDPF���u�̍Đ����ɘQ����R�����o�������팸����Z�p�̊J
�����s�v�ł���Ƃ̂��n�t����^�������Ɓx�ɂ����������Ƃł���B
�����|�X�g���ˍĐ���DPF���u�𓋍ڂ����f�B�[�[���g���b�N�ł����Ă��A���̃f�B�[�[���g���b�N�̏d�ʎԃ��[
�h�R��l�̌v�Z�ɂ͂c�o�e�Đ��ł̏���R���ʂ��S���Z������Ȃ��̂ŁA���̏d�ʎԃ��[�h�R��l����������
���Ƃ͖����B�Ȍ��Ɍ����A�d�ʎԃ��[�h�R��l�̌v�Z�ł͂c�o�e�Đ��ł̔R������ʂ���Ɖ��肳��Ă����
���B���̂��Ƃ́A���y��ʏȂ��g���b�N���[�J�ɁwDPF���u�̍Đ����ɘQ����R�����o�������팸����Z�p�̊J
�����s�v�ł���Ƃ̂��n�t����^�������Ɓx�ɂ����������Ƃł���B
�@����ɂ��A�|�X�g���ˍĐ���DPF���u�̍Đ����ɘQ���R�����팸�ł���Z�p�̊J���̓g���b�N���[�J�Ԃɂ���
��Z�p�J�������̍��ڂ���O����Ă���\�����ے�ł��Ȃ��B���ɂƂ��떾�m�ȏ؋��͖������A����̃g���b�N���[
�J�ł��^���ɂ��̂c�o�e�Đ����̔R���Q����팸����Z�p�J���̗D�揇�ʂ����������Ă���\�����\���ɍl�����
��B���̏���R�����팸����DPF�̍Đ��Z�p�̎��p�����x��邱�Ƃɂ��A���^�g���b�N�^�A����ɂ����āA����͍X
�ɔR�������̏���ʂ��������ACO�Q�̔r�o���������Ă������̂Ɨ\�z�����B���̖��ɂ��āA���{��g���b�N���[
�J�̌�������������̂Ȃ琥��Ƃ������Ă݂������̂ł���B
��Z�p�J�������̍��ڂ���O����Ă���\�����ے�ł��Ȃ��B���ɂƂ��떾�m�ȏ؋��͖������A����̃g���b�N���[
�J�ł��^���ɂ��̂c�o�e�Đ����̔R���Q����팸����Z�p�J���̗D�揇�ʂ����������Ă���\�����\���ɍl�����
��B���̏���R�����팸����DPF�̍Đ��Z�p�̎��p�����x��邱�Ƃɂ��A���^�g���b�N�^�A����ɂ����āA����͍X
�ɔR�������̏���ʂ��������ACO�Q�̔r�o���������Ă������̂Ɨ\�z�����B���̖��ɂ��āA���{��g���b�N���[
�J�̌�������������̂Ȃ琥��Ƃ������Ă݂������̂ł���B
�@���āA�����V�����K���iH17�N�j�K���̃|�X�g���ˍĐ���DPF���u�𓋍ڂ̊e�g���b�N���[�J�̏��^�f�B�[�[��
�g���b�N�̏d�ʎԃ��[�h�R��l�́A�|�X�g���ˍĐ���DPF���u�̍Đ���S���s��Ȃ���ԁi�|�X�g���˂ɂ��R
�������̏�ԁj�̔R����Z�o�������̂ł��邽�߁A2015�N�d�ʎԔR���ɓK�����Ă����ƍl������B
�������A���ۂɐV�����K���iH17�N�j�K���̃|�X�g���ˍĐ���DPF���u�𓋍ڂ������^�f�B�[�[���g���b�N���W�z�Ɩ�
���Ől�����W�n��𑖍s�����ꍇ�ɂ́A�p�ɂ�DPF�Đ��ɑ��ʂ̔R��������邽�߁A�����s�R��͑啝�Ɉ�����
�邱�ƂɂȂ�͓̂��R�ł���B���������āA�|�X�g���ˍĐ���DPF���u�𓋍ڂ̏��^�f�B�[�[���g���b�N�̏d�ʎԃ��[�h
�R��l�́A�����s�R��Ƒ傫���������Ă��܂��͓̂��R�ł���B���{�́A�d�ʎԃ��[�h�R��l�ɂc�o�e�Đ��ɏ�����
�R�������Z�����d�ʎԃ��[�h�R��l�ɉ��肷�ׂ��ł͂Ȃ����낤���B
�g���b�N�̏d�ʎԃ��[�h�R��l�́A�|�X�g���ˍĐ���DPF���u�̍Đ���S���s��Ȃ���ԁi�|�X�g���˂ɂ��R
�������̏�ԁj�̔R����Z�o�������̂ł��邽�߁A2015�N�d�ʎԔR���ɓK�����Ă����ƍl������B
�������A���ۂɐV�����K���iH17�N�j�K���̃|�X�g���ˍĐ���DPF���u�𓋍ڂ������^�f�B�[�[���g���b�N���W�z�Ɩ�
���Ől�����W�n��𑖍s�����ꍇ�ɂ́A�p�ɂ�DPF�Đ��ɑ��ʂ̔R��������邽�߁A�����s�R��͑啝�Ɉ�����
�邱�ƂɂȂ�͓̂��R�ł���B���������āA�|�X�g���ˍĐ���DPF���u�𓋍ڂ̏��^�f�B�[�[���g���b�N�̏d�ʎԃ��[�h
�R��l�́A�����s�R��Ƒ傫���������Ă��܂��͓̂��R�ł���B���{�́A�d�ʎԃ��[�h�R��l�ɂc�o�e�Đ��ɏ�����
�R�������Z�����d�ʎԃ��[�h�R��l�ɉ��肷�ׂ��ł͂Ȃ����낤���B
�@�ȏ�̂悤�ɁA�|�X�g���ˍĐ���DPF���u�𓋍ڂ̏��^�f�B�[�[���g���b�N�̏d�ʎԃ��[�h�R��l�͎����s�R��Ƃ�
�֘A�����Ⴍ�A���p�I�ɂ͈Ӗ��̂Ȃ����l�ƍl������B�g���b�N���[�J�͏��^�g���b�N���s�s�����s���J��Ԃ����ꍇ
�ɂ́A�G���W���{�̂���̃p�e�L�����[�g�r�o���������ăt�B���^�ɑ͐ς���p�e�L�����[�g���������邽�߂�DPF��
�u�̍Đ��ɑ��ʂ̔R����Q��A�����s�R��啝�Ɉ������Ă��܂����Ƃɂ͐G�ꂸ�A�e���[�J��������2015�N�d��
�ԔR���ɓK��������R��̏��^�g���b�N�Ɛ�`���Ĕ̔����Ă���̂ł���B���̂��߁A�V�����K���iH17�N�j�K����
�|�X�g���ˍĐ���DPF���u�𓋍ڂ������^�f�B�[�[���g���b�N�̃��[�U����A����̉^�s�ł̎����s�R��ɂ����钘��
�������̕s�������܂��Ă���͓̂��R�̂��Ƃƌ�����B���̖�����������B��̕��@�́A�|�X�g���˂�r�C�Ǔ���
�˂��g�p���Ȃ��ŔR���Q��̏��Ȃ��V����DPF�Đ��Z�p�����p�����邱�Ƃł���B
�֘A�����Ⴍ�A���p�I�ɂ͈Ӗ��̂Ȃ����l�ƍl������B�g���b�N���[�J�͏��^�g���b�N���s�s�����s���J��Ԃ����ꍇ
�ɂ́A�G���W���{�̂���̃p�e�L�����[�g�r�o���������ăt�B���^�ɑ͐ς���p�e�L�����[�g���������邽�߂�DPF��
�u�̍Đ��ɑ��ʂ̔R����Q��A�����s�R��啝�Ɉ������Ă��܂����Ƃɂ͐G�ꂸ�A�e���[�J��������2015�N�d��
�ԔR���ɓK��������R��̏��^�g���b�N�Ɛ�`���Ĕ̔����Ă���̂ł���B���̂��߁A�V�����K���iH17�N�j�K����
�|�X�g���ˍĐ���DPF���u�𓋍ڂ������^�f�B�[�[���g���b�N�̃��[�U����A����̉^�s�ł̎����s�R��ɂ����钘��
�������̕s�������܂��Ă���͓̂��R�̂��Ƃƌ�����B���̖�����������B��̕��@�́A�|�X�g���˂�r�C�Ǔ���
�˂��g�p���Ȃ��ŔR���Q��̏��Ȃ��V����DPF�Đ��Z�p�����p�����邱�Ƃł���B
�S�D�d�ʎԔR���̐ݒ�ړI����傫�������������s�̏d�ʎԃ��[�h�R��l
�@�g���b�N���[�U����уg���b�N���[�J�̃g���b�N�ݕ��A������ɂ�����ȃG�l���M�[�i�ȔR��j��CO�Q�팸�̎��g�݂�
���i�����悤�ɂ��邽�߁A���y��ʏȂ͔R��̗D�ꂽ�g���b�N�̕��y��}��ϓ_����A�u�G�l���M�[�̎g�p�̍�����
�ɂ��@���v�i�ʏ́F�����ȃG�l�@�j���������A�d�ʎԁi�ԗ����d��2.5t���̎�����[1]�j�ɑ���R�����߁A2006
�N4��1������{�s�����B2015�N�x�i����27�N�x�j����B���̖ڕW�N�x�Ƃ��A�g���b�N�E�o�X���[�J�[�͎ԗ����d�ʂ���
�ɒ�߂�ꂽ�d�ʎԔR��l�̊�B���ƁA2006�N4���ȍ~�ɔ̔�����V�^�Ԃɂ��āA���i�J�^���O�֏d�ʎԃ��[�h
�R��l�̕\�����`���t����ꂽ�B���̂悤�ɁA�d�ʎԃ��[�h�R��l�͏ȃG�l���M�[�i�ȔR��j�̗D��f����l�Ƃ�
�č��y��ʏȂ����������Ƃ̂��Ƃł���B
���i�����悤�ɂ��邽�߁A���y��ʏȂ͔R��̗D�ꂽ�g���b�N�̕��y��}��ϓ_����A�u�G�l���M�[�̎g�p�̍�����
�ɂ��@���v�i�ʏ́F�����ȃG�l�@�j���������A�d�ʎԁi�ԗ����d��2.5t���̎�����[1]�j�ɑ���R�����߁A2006
�N4��1������{�s�����B2015�N�x�i����27�N�x�j����B���̖ڕW�N�x�Ƃ��A�g���b�N�E�o�X���[�J�[�͎ԗ����d�ʂ���
�ɒ�߂�ꂽ�d�ʎԔR��l�̊�B���ƁA2006�N4���ȍ~�ɔ̔�����V�^�Ԃɂ��āA���i�J�^���O�֏d�ʎԃ��[�h
�R��l�̕\�����`���t����ꂽ�B���̂悤�ɁA�d�ʎԃ��[�h�R��l�͏ȃG�l���M�[�i�ȔR��j�̗D��f����l�Ƃ�
�č��y��ʏȂ����������Ƃ̂��Ƃł���B
�@����A�V�����K���iH17�N�j�K���̃|�X�g���ˍĐ���DPF���ڂ̏��^�f�B�[�[���g���b�N�i�ύڗʂQ�g���AGVW4.7�g���j
�́A�W�z�Ɩ����ɑ����g���A�l�����W�n��𑖍s���邱�Ƃ���̂ł��邱�Ƃ���Z�����ł̔��i�E��~������E��
���̕p�x�����������߂ɂc�o�e�Ƀp�e�L�����[�g�̑͐ς��������A�|�X�g���˂ɂ��t�B���^�Đ����p�ɂɍs���A����
�ł̓|�X�g���˂ő����̔R���������Ă���B���̌��ʁA�O�q�̂Q���̕\�Q�Ɏ������悤�ɁA�|�X�g���ˎ�DPF���u��
�ڂ��V�����K���iH17�N�j�K���̏��^�f�B�[�[���g���b�N���l�����W�n����^�s�����ꍇ�������s�R��́A�|�X�g����
�ɂ��p�ɂȃt�B���^�̍Đ��ɑ��ʂ̔R��������Ă��܂����߁A�T�`�U�@�q/���b�g�����x�܂ň������Ă���Ƃ̂��Ƃ�
����B�i���݂��|�X�g���ˎ�DPF���u�𓋍ڂ��Ă��Ȃ��V�Z���K���iH15�N)�̓K���������^�f�B�[�[���g���b�N���l��
���W�n��ʼn^�s�����ꍇ�̎����s�R����V�`�W�@�q/���b�g���ł���B�j�Ƃ��낪�d�l����J�^���O�ɋL�ڂ��ꂽ�V����
�K���iH17�N�j�K�����V�Z���K���iH15�N)�̓K�����^�g���b�N���d�ʎԃ��[�h�R��l��10�ikm/���b�g���j�O��ŗ������
���邱�Ƃ��l������A�V�����K���iH17�N�j�K���̏��^�f�B�[�[���g���b�N�ł̎����s�R����̎�v���́A�p�ɂ�
DPF�Đ����ɏ�����|�X�g���˔R���ł���Ɛ��肳���B
�́A�W�z�Ɩ����ɑ����g���A�l�����W�n��𑖍s���邱�Ƃ���̂ł��邱�Ƃ���Z�����ł̔��i�E��~������E��
���̕p�x�����������߂ɂc�o�e�Ƀp�e�L�����[�g�̑͐ς��������A�|�X�g���˂ɂ��t�B���^�Đ����p�ɂɍs���A����
�ł̓|�X�g���˂ő����̔R���������Ă���B���̌��ʁA�O�q�̂Q���̕\�Q�Ɏ������悤�ɁA�|�X�g���ˎ�DPF���u��
�ڂ��V�����K���iH17�N�j�K���̏��^�f�B�[�[���g���b�N���l�����W�n����^�s�����ꍇ�������s�R��́A�|�X�g����
�ɂ��p�ɂȃt�B���^�̍Đ��ɑ��ʂ̔R��������Ă��܂����߁A�T�`�U�@�q/���b�g�����x�܂ň������Ă���Ƃ̂��Ƃ�
����B�i���݂��|�X�g���ˎ�DPF���u�𓋍ڂ��Ă��Ȃ��V�Z���K���iH15�N)�̓K���������^�f�B�[�[���g���b�N���l��
���W�n��ʼn^�s�����ꍇ�̎����s�R����V�`�W�@�q/���b�g���ł���B�j�Ƃ��낪�d�l����J�^���O�ɋL�ڂ��ꂽ�V����
�K���iH17�N�j�K�����V�Z���K���iH15�N)�̓K�����^�g���b�N���d�ʎԃ��[�h�R��l��10�ikm/���b�g���j�O��ŗ������
���邱�Ƃ��l������A�V�����K���iH17�N�j�K���̏��^�f�B�[�[���g���b�N�ł̎����s�R����̎�v���́A�p�ɂ�
DPF�Đ����ɏ�����|�X�g���˔R���ł���Ɛ��肳���B
�@���̂悤�ɁA�V�����K���iH17�N�j�K���̏��^�f�B�[�[���g���b�N�̎����s�R��́A���̃g���b�N�ɓ��ڂ���Ă���|�X
�g���ˍĐ���DPF�ł̕p�ɂ�DPF�Đ����̃|�X�g���˔R���̑����ɂ��A�|�X�g���ˍĐ���DPF�𓋍ڂ��Ă��Ȃ��V
�Z���K���iH15�N)�̓K���������^�f�B�[�[���g���b�N���ڂ̎����s�R����������R�O���O����������Ă��܂��Ă����
���肳���B���̂��Ƃ���A�|�X�g���ˍĐ���DPF���ڂ̏��^�f�B�[�[���g���b�N�ŏ�����|�X�g���˂̔R�������
���S�ɖ������錻�s�̏d�ʎԃ��[�h�R��l�́A�����s�R��Ƒ傫���������Ă��܂��Ă��邱�Ƃ͗e�Ղɗ����ł��邱��
�ł���B���̂��Ƃ���A�V�����K���iH17�N�j�K���̃|�X�g���ˍĐ���DPF���ڂ̏��^�f�B�[�[���g���b�N�ɂ�����
�́A���y��ʏȂ����i�J�^���O�ւ̕\�����`���t�����d�ʎԃ��[�h�R��l�͂��̏��^�g���b�N�̏ȃG�l���M�[
�i�ȔR��j�̗D���f�ł���l�ł͂Ȃ��悤�ɍl������B
�g���ˍĐ���DPF�ł̕p�ɂ�DPF�Đ����̃|�X�g���˔R���̑����ɂ��A�|�X�g���ˍĐ���DPF�𓋍ڂ��Ă��Ȃ��V
�Z���K���iH15�N)�̓K���������^�f�B�[�[���g���b�N���ڂ̎����s�R����������R�O���O����������Ă��܂��Ă����
���肳���B���̂��Ƃ���A�|�X�g���ˍĐ���DPF���ڂ̏��^�f�B�[�[���g���b�N�ŏ�����|�X�g���˂̔R�������
���S�ɖ������錻�s�̏d�ʎԃ��[�h�R��l�́A�����s�R��Ƒ傫���������Ă��܂��Ă��邱�Ƃ͗e�Ղɗ����ł��邱��
�ł���B���̂��Ƃ���A�V�����K���iH17�N�j�K���̃|�X�g���ˍĐ���DPF���ڂ̏��^�f�B�[�[���g���b�N�ɂ�����
�́A���y��ʏȂ����i�J�^���O�ւ̕\�����`���t�����d�ʎԃ��[�h�R��l�͂��̏��^�g���b�N�̏ȃG�l���M�[
�i�ȔR��j�̗D���f�ł���l�ł͂Ȃ��悤�ɍl������B
�@�������Ȃ���A���y��ʏȂ������̏��^�g���b�N�̏ȃG�l���M�[�i�ȔR��j��CO�Q�̍팸�̗D��f����l�Ƃ��ď�
�i�J�^���O�ɏd�ʎԃ��[�h�R��l�̋L�ڂ��`���t���Ă��邱�Ƃ���A���m���̖R������ʍ����͏��^�g���b�N�̏ȃG
�l���M�[�i�ȔR��j��CO�Q�̍팸�̗D��f�ޗ��ɂȂ�ƌ��z������Ă��Ă��s�v�c�ł͂Ȃ��B���i�J�^���O�Ɂw�d
�ʎԃ��[�h�R��l��2015�N�x�R����B���x�ƋL�ڂ��ꂽ�V�����K���iH17�N�j�K�����|�X�g���ˍĐ���
DPF���ڂ̏��^�f�B�[�[���g���b�N���R��ƐM���čw�����Ă��A�������^�f�B�[�[���g���b�N�����ۂɓs�s����
��̂ɉ^�s�������[�U���R��ɂ߂Ĉ��������ɑ������邱�ƂɂȂ�Ɨ\�z�����B
�i�J�^���O�ɏd�ʎԃ��[�h�R��l�̋L�ڂ��`���t���Ă��邱�Ƃ���A���m���̖R������ʍ����͏��^�g���b�N�̏ȃG
�l���M�[�i�ȔR��j��CO�Q�̍팸�̗D��f�ޗ��ɂȂ�ƌ��z������Ă��Ă��s�v�c�ł͂Ȃ��B���i�J�^���O�Ɂw�d
�ʎԃ��[�h�R��l��2015�N�x�R����B���x�ƋL�ڂ��ꂽ�V�����K���iH17�N�j�K�����|�X�g���ˍĐ���
DPF���ڂ̏��^�f�B�[�[���g���b�N���R��ƐM���čw�����Ă��A�������^�f�B�[�[���g���b�N�����ۂɓs�s����
��̂ɉ^�s�������[�U���R��ɂ߂Ĉ��������ɑ������邱�ƂɂȂ�Ɨ\�z�����B
�@���̂悤���V�����K���iH17�N�j�K���̃|�X�g���ˍĐ���DPF�𓋍ڂ������^�f�B�[�[���g���b�N���i�J�^���O�ɂ���
�āA�����s�R��Ƃ̘������傫���d�ʎԃ��[�h�R��l���w2015�N�x�R����B���x�ł��邱�Ƃ��L�ڂ��A�|�X�g����
�Đ���DPF�̔R���Q��ɂ��ĉ����L�ڂ���Ă��Ȃ����Ƃ́A���̏��^�f�B�[�[���g���b�N�̏��i�J�^���O�Ƃ��Ă͖��
�ł͂Ȃ����Ǝv���Ă���B�g���b�N���[�J�[�͌��s�̎����s�R��̈����V�����K���iH17�N�j�K���|�X�g���ˍĐ���DPF
���ڂ̏��^�f�B�[�[���g���b�N���R��E��CO�Q�Ɛ�`���Ă��邱�ƂɗǐS�̙�ӂ������Ȃ��̂ł��낤���B
�āA�����s�R��Ƃ̘������傫���d�ʎԃ��[�h�R��l���w2015�N�x�R����B���x�ł��邱�Ƃ��L�ڂ��A�|�X�g����
�Đ���DPF�̔R���Q��ɂ��ĉ����L�ڂ���Ă��Ȃ����Ƃ́A���̏��^�f�B�[�[���g���b�N�̏��i�J�^���O�Ƃ��Ă͖��
�ł͂Ȃ����Ǝv���Ă���B�g���b�N���[�J�[�͌��s�̎����s�R��̈����V�����K���iH17�N�j�K���|�X�g���ˍĐ���DPF
���ڂ̏��^�f�B�[�[���g���b�N���R��E��CO�Q�Ɛ�`���Ă��邱�ƂɗǐS�̙�ӂ������Ȃ��̂ł��낤���B
�@���������āA���y��ʏȂ�g���b�N���[�J������҂ɐ��m�ȏ��i�������ӎv������Ȃ�A���^�f�B�[�[��
�g���b�N�̏��i�J�^���O��2015�N�x�i����27�N�x�j�̊�B���Ƃ̋L�q�Ƌ��ɋL�ڂ��ꂽ�d�ʎԃ��[�h�R��l�̌��
�w�������A�l�����W�n����^�s�����ꍇ�ɂ��A�|�X�g���˂ɂ��p�ɂȃt�B���^�̍Đ��̂��߂ɑ��ʂ̔R���������
���̂ő��s�R��啝�Ɉ������܂��B�x�Ƃ̋L�ڂ��w�����邱�Ƃ��K�v�ł͂Ȃ����Ǝv���Ă���B����ɂ����ď��^�f
�B�[�[���g���b�N�̏��i�J�^���O���w���҂ɐ��m�ȏ�����Ă���̂ʼn�����肪�Ȃ��Ƃ���Ȃ�A��w��˂�
�M�҂ɂ��̗��R�������ł���悤�ɉ�����Ղ��������������������Ǝv���Ă���B
�g���b�N�̏��i�J�^���O��2015�N�x�i����27�N�x�j�̊�B���Ƃ̋L�q�Ƌ��ɋL�ڂ��ꂽ�d�ʎԃ��[�h�R��l�̌��
�w�������A�l�����W�n����^�s�����ꍇ�ɂ��A�|�X�g���˂ɂ��p�ɂȃt�B���^�̍Đ��̂��߂ɑ��ʂ̔R���������
���̂ő��s�R��啝�Ɉ������܂��B�x�Ƃ̋L�ڂ��w�����邱�Ƃ��K�v�ł͂Ȃ����Ǝv���Ă���B����ɂ����ď��^�f
�B�[�[���g���b�N�̏��i�J�^���O���w���҂ɐ��m�ȏ�����Ă���̂ʼn�����肪�Ȃ��Ƃ���Ȃ�A��w��˂�
�M�҂ɂ��̗��R�������ł���悤�ɉ�����Ղ��������������������Ǝv���Ă���B
�T�D�|�X�g���ˍĐ���DPF���ڏ��^�g���b�N�̐��Y�p���ɂ�鎑���Q���CO�Q����
�@�O�q�̒ʂ�A�V�����K���iH17�N�j�K���̃|�X�g���ˍĐ���DPF���ڂ����^�f�B�[�[���g���b�N�́A�W�z�Ɩ����ɑ���
�g���Ă���A�Z�����ł̔��i�E��~������E�����̕p�x�����������߂ɃG���W���{�̂���̃p�e�L�����[�g�r�o����
�����ăt�B���^�ɑ͐ς���p�e�L�����[�g���������邽�߁A�|�X�g���˂ɂ��t�B���^�̍Đ����p�ɂɍs���đ��ʂ�
�R�����Q���Ă��邱�Ƃ́A�Ȏ����̎Љ�j�[�Y�ɔ�����s�ׂƎv���Ă���B���������āA����A�V�����K���iH17
�N�j�K���̃|�X�g���ˎ�DPF���u���ڂ����^�f�B�[�[���g���b�N�̔̔��ݐϑ䐔�ɔ�Ⴕ�ăR�������[������
���u���ւ�|�X�g���˂ɂ��DPF�Đ��Ɏg����y���̘Q��������A�n�����g���̌����̈�Ɖ]����
�����_���Y�f�iCO�Q�j���傫�����₵�Ă������ƂɂȂ�B
�g���Ă���A�Z�����ł̔��i�E��~������E�����̕p�x�����������߂ɃG���W���{�̂���̃p�e�L�����[�g�r�o����
�����ăt�B���^�ɑ͐ς���p�e�L�����[�g���������邽�߁A�|�X�g���˂ɂ��t�B���^�̍Đ����p�ɂɍs���đ��ʂ�
�R�����Q���Ă��邱�Ƃ́A�Ȏ����̎Љ�j�[�Y�ɔ�����s�ׂƎv���Ă���B���������āA����A�V�����K���iH17
�N�j�K���̃|�X�g���ˎ�DPF���u���ڂ����^�f�B�[�[���g���b�N�̔̔��ݐϑ䐔�ɔ�Ⴕ�ăR�������[������
���u���ւ�|�X�g���˂ɂ��DPF�Đ��Ɏg����y���̘Q��������A�n�����g���̌����̈�Ɖ]����
�����_���Y�f�iCO�Q�j���傫�����₵�Ă������ƂɂȂ�B
�@�������Ȃ���A���y��ʏȂ͖����ɏd�ʎԃ��[�h�R��l���ȃG�l���M�[�i�ȔR��j�̗D��f����l�Ƃ��Đ�����
�ƐM���A�����I�ɖ��Ӗ��ȁw2015�N�x�i����27�N�x�j��R���B���x�����^�f�B�[�[���g���b�N�̗ݐϑ䐔�̑�����
���������ďȃG�l��CO�Q�팸���i�W���Ă����Ɩ{���ɍl���Ă���̂ł��납�B����ɔ����āA�M�҂̓|�X�g���ˎ�DPF
���u�𓋍ڂ������^�f�B�[�[���g���b�N�̗ݐϔ̔��䐔����������̂ɔ�Ⴕ�ĔR�������̘Q���CO�Q�������i�W�x
���Ă������ƂɂȂ�ƍl���Ă���B�M�҂̐������Ԉ���Ă���Ζ��͖������A���ɕM�҂̐������I�����Ă���Ƃ���
�A���y��ʏȂ̗\�z�Ƃ͋t�ɁA��R��Ɛ�`����Ă���w2015�N�x�i����27�N�x�j��R���B���x�̃|�X�g���ˎ�
DPF���u�𓋍ڂ������^�f�B�[�[���g���b�N�̔̔��ݐϑ䐔�̑����ɔ�Ⴕ���y���̏���ʂ��������A��C����CO�Q
���������Ă����Ƃ�����肪�������邱�ƂɂȂ�B
�ƐM���A�����I�ɖ��Ӗ��ȁw2015�N�x�i����27�N�x�j��R���B���x�����^�f�B�[�[���g���b�N�̗ݐϑ䐔�̑�����
���������ďȃG�l��CO�Q�팸���i�W���Ă����Ɩ{���ɍl���Ă���̂ł��납�B����ɔ����āA�M�҂̓|�X�g���ˎ�DPF
���u�𓋍ڂ������^�f�B�[�[���g���b�N�̗ݐϔ̔��䐔����������̂ɔ�Ⴕ�ĔR�������̘Q���CO�Q�������i�W�x
���Ă������ƂɂȂ�ƍl���Ă���B�M�҂̐������Ԉ���Ă���Ζ��͖������A���ɕM�҂̐������I�����Ă���Ƃ���
�A���y��ʏȂ̗\�z�Ƃ͋t�ɁA��R��Ɛ�`����Ă���w2015�N�x�i����27�N�x�j��R���B���x�̃|�X�g���ˎ�
DPF���u�𓋍ڂ������^�f�B�[�[���g���b�N�̔̔��ݐϑ䐔�̑����ɔ�Ⴕ���y���̏���ʂ��������A��C����CO�Q
���������Ă����Ƃ�����肪�������邱�ƂɂȂ�B
�@�܂��A���̑��ɂ��|�X�g���˂ɂ��DPF���Đ�����Z�p�ɂ��A�|�X�g���˂��ꂽ�y���������V�����_���ǂɕt����
�ăG���W���I�C���ɍ������A�y���ŃG���W���I�C������߂���錇��������悤���B�y���Ŋ�߂��ꂽ�G���W���I�C
���͔S�x�̒ቺ�������N�������߁A�p�ɂȃG���W���I�C���̌������K�v�ƂȂ�A�G���W���I�C���̘Q��ƂȂ�̂ŁA��
����Ȏ����̖ʂ�����ł���B
�ăG���W���I�C���ɍ������A�y���ŃG���W���I�C������߂���錇��������悤���B�y���Ŋ�߂��ꂽ�G���W���I�C
���͔S�x�̒ቺ�������N�������߁A�p�ɂȃG���W���I�C���̌������K�v�ƂȂ�A�G���W���I�C���̘Q��ƂȂ�̂ŁA��
����Ȏ����̖ʂ�����ł���B
�U�DDPF�Đ����̘Q��R���̍팸�Ƌ��ɁA�����s�R��̍팸���\�ȋC���x�~�G���W��
�@�O�q�̂悤�ɁA�s�s���ł̉ݕ��W�z�̃G���W���^�]�̈�ɂ�����R������̕p�x���z�͒��ᑬ��1/2���ׂ���
�S���ׂ̍�����ł̔R������ʂ������B���^�g���b�N�ɂQ�̋C���Q�𐧌䂷��C���x�~�G���W���y�C���x�~�G��
�W���i�������J2005-54771�j�z�𓋍ڂ����ꍇ�A�}�S�̐Ԑ��ň͂��ᑬ��1/2����ł͈���̋C���Q��S����
�^�]���đ��̋C���Q��ᕉ�^�]���A�ڕW�̃G���W���o�͂ʼn^�]����B����ɂ���āA�S���^�]�̋C���Q�̃T�C�N
���������������ĔR������P���A���^�g���b�N�ɋC���x�~�G���W���𓋍ڂ����ꍇ�ɂ͒�����̃T�C�N�������̌���
�ɂ�鑖�s�R����P����A���^�n�C�u���b�h�g���b�N�Ɠ����ȏ�̔R����P���\�ƂȂ�B���������āA���^�g���b�N��
�R����P�ɂ͍����ȃn�C�u���b�h�V�X�e�������C���x�~�G���W���̗̍p�𐄐i���ׂ��ƍl������B
�S���ׂ̍�����ł̔R������ʂ������B���^�g���b�N�ɂQ�̋C���Q�𐧌䂷��C���x�~�G���W���y�C���x�~�G��
�W���i�������J2005-54771�j�z�𓋍ڂ����ꍇ�A�}�S�̐Ԑ��ň͂��ᑬ��1/2����ł͈���̋C���Q��S����
�^�]���đ��̋C���Q��ᕉ�^�]���A�ڕW�̃G���W���o�͂ʼn^�]����B����ɂ���āA�S���^�]�̋C���Q�̃T�C�N
���������������ĔR������P���A���^�g���b�N�ɋC���x�~�G���W���𓋍ڂ����ꍇ�ɂ͒�����̃T�C�N�������̌���
�ɂ�鑖�s�R����P����A���^�n�C�u���b�h�g���b�N�Ɠ����ȏ�̔R����P���\�ƂȂ�B���������āA���^�g���b�N��
�R����P�ɂ͍����ȃn�C�u���b�h�V�X�e�������C���x�~�G���W���̗̍p�𐄐i���ׂ��ƍl������B
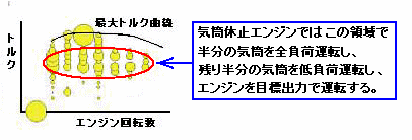
�@�����āA�C���x�~�G���W���ɂ����āA�}�S�̐Ԑ��ň͂��ᑬ��1/2����ł͈���̋C���Q��S���^�]����
���̋C���Q��ᕉ�^�]���A�ڕW�̃G���W���o�͂ʼn^�]�����ꍇ�A�S���^�]�̋C���Q�̔r�C���x�͍����Ȃ邽�߁A
���̋C���Q��DPF���u�ł̓|�X�g���˂�p���邱�ƂȂ����R�Đ����s���ADPF�Đ��ɂ��R��̈����͐���������
�����ʂ�����B�����āA�ő�g���N�Ȑ��t�߂ł͑S�C���ł��^�]���邽�߁A�����̋C���Q��DPF���u�̃t�B���^�͎�
�R�Đ��ł��邱�ƂɂȂ�B���̂悤�ɂ��āA�C���x�~�G���W���ł́A���^�g���b�N�̓s�s�����s�ɂ����ẮA������
��̃T�C�N�������̌���ɂ�鑖�s�R����P�����Ƌ��ɁA���s����DPF���u�̃t�B���^�����R�Đ��ł���
���ƂɂȂ邽�߁ADPF���u�̍Đ��̂��߂̔R���Q��͉���ł������B
���̋C���Q��ᕉ�^�]���A�ڕW�̃G���W���o�͂ʼn^�]�����ꍇ�A�S���^�]�̋C���Q�̔r�C���x�͍����Ȃ邽�߁A
���̋C���Q��DPF���u�ł̓|�X�g���˂�p���邱�ƂȂ����R�Đ����s���ADPF�Đ��ɂ��R��̈����͐���������
�����ʂ�����B�����āA�ő�g���N�Ȑ��t�߂ł͑S�C���ł��^�]���邽�߁A�����̋C���Q��DPF���u�̃t�B���^�͎�
�R�Đ��ł��邱�ƂɂȂ�B���̂悤�ɂ��āA�C���x�~�G���W���ł́A���^�g���b�N�̓s�s�����s�ɂ����ẮA������
��̃T�C�N�������̌���ɂ�鑖�s�R����P�����Ƌ��ɁA���s����DPF���u�̃t�B���^�����R�Đ��ł���
���ƂɂȂ邽�߁ADPF���u�̍Đ��̂��߂̔R���Q��͉���ł������B
�@���^�g���b�N���n�C�u���b�h�V�X�e����DPF���u�̃t�B���^�Đ��ɗD�ꂽ�@�\�����邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ����A���s��
�̔R����P�̋@�\���R�������Ƃ��l������A���^�n�C�u���b�h�g���b�N���R�X�g�p�[�t�H�[�}���X�̗��g���b�N�ƌ���
��̂ł͂Ȃ����낤���B�܂��A���s�̏��^�g���b�N�ɗp�����Ă����R�������[���̃|�X�g���˂ɂ��DPF���u�̃t�B��
�^�Đ��́A�����s�R���30�������������錇�וi�ł���B���̂��߁A�Ȏ����E�ȃG�l�����CO�Q�팸���ŗD�悳���
����ɂ́ADPF���u�ɂ�����|�X�g���˂ɂ��t�B���^�̍Đ����@�����}�Ɍ������ׂ��ł���B�܂��A���̂悤���t�B��
�^�Đ������R����̌��ׂ́A�r�C�Ǔ��R�����ˎ���DPF���u�̏ꍇ�ɂ����Ă����l�ł���B
�̔R����P�̋@�\���R�������Ƃ��l������A���^�n�C�u���b�h�g���b�N���R�X�g�p�[�t�H�[�}���X�̗��g���b�N�ƌ���
��̂ł͂Ȃ����낤���B�܂��A���s�̏��^�g���b�N�ɗp�����Ă����R�������[���̃|�X�g���˂ɂ��DPF���u�̃t�B��
�^�Đ��́A�����s�R���30�������������錇�וi�ł���B���̂��߁A�Ȏ����E�ȃG�l�����CO�Q�팸���ŗD�悳���
����ɂ́ADPF���u�ɂ�����|�X�g���˂ɂ��t�B���^�̍Đ����@�����}�Ɍ������ׂ��ł���B�܂��A���̂悤���t�B��
�^�Đ������R����̌��ׂ́A�r�C�Ǔ��R�����ˎ���DPF���u�̏ꍇ�ɂ����Ă����l�ł���B
�@���̂悤�ɁA�|�X�g���ˍĐ���DPF���u�𓋍ڂ����V�����K���iH17�N�j�K�������^�f�B�[�[���g���b�N�́A��
���J�n�ȗ��A�|�X�g���˂ɂ��DPF�Đ��ɋN�������R����ɂ��g���b�N���[�U�̌o�ϓI���S��������Ƌ�
�ɁACO�Q����ɂ������ׂ����������Ă����̂ł���B�m���ɁA�|�X�g���ˍĐ�����������DPF���u�̍�
���Z�p�ł��邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��B�������A����������ƌ����āA�g���b�N���[�J�͊e�Ђ̎Љ�I�ӔC��Y��ė��v�D���
����ɖڂ�D���A���ꂩ������X�ƁuCO�Q����̉ߑ�Ȋ����ׁv�A�u�Ζ��G�l���M�[�̘Q��v����сu���[�U�̔R��
���̕��S�v�������|�X�g���ˎ�DPF���u���̗p��������̂ł��낤���B
���J�n�ȗ��A�|�X�g���˂ɂ��DPF�Đ��ɋN�������R����ɂ��g���b�N���[�U�̌o�ϓI���S��������Ƌ�
�ɁACO�Q����ɂ������ׂ����������Ă����̂ł���B�m���ɁA�|�X�g���ˍĐ�����������DPF���u�̍�
���Z�p�ł��邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��B�������A����������ƌ����āA�g���b�N���[�J�͊e�Ђ̎Љ�I�ӔC��Y��ė��v�D���
����ɖڂ�D���A���ꂩ������X�ƁuCO�Q����̉ߑ�Ȋ����ׁv�A�u�Ζ��G�l���M�[�̘Q��v����сu���[�U�̔R��
���̕��S�v�������|�X�g���ˎ�DPF���u���̗p��������̂ł��낤���B
�@�����āA���^�f�B�[�[���g���b�N�ɂ������|�X�g���˂ɂ��DPF�Đ��ł�30���O��̔R�������������̂ł���
�A100���~���x�������ȏ��^�n�C�u���b�h�g���b�N���w������Ηǂ��Ɖ]���̂��g���b�N���[�J�̌������ł��낤���B��
�ʂ̃g���b�N���[�U�ɂƂ��Ă͍��Șb�ł���B���͂Ƃ�����A�R���Q��̌������R�������[���̃|�X�g���˂�p����DPF
���u�̍Đ����@��������������ǂ��ׂ����Ƃ́A���[�J�̍ő�̎Љ�I�Ӗ��ł���ƌ����Ă��ԈႢ�ł͂Ȃ����낤�B
�A100���~���x�������ȏ��^�n�C�u���b�h�g���b�N���w������Ηǂ��Ɖ]���̂��g���b�N���[�J�̌������ł��낤���B��
�ʂ̃g���b�N���[�U�ɂƂ��Ă͍��Șb�ł���B���͂Ƃ�����A�R���Q��̌������R�������[���̃|�X�g���˂�p����DPF
���u�̍Đ����@��������������ǂ��ׂ����Ƃ́A���[�J�̍ő�̎Љ�I�Ӗ��ł���ƌ����Ă��ԈႢ�ł͂Ȃ����낤�B
�@�ȏ�̂��Ƃ���A�����_�ł��n�C�u���b�h�V�X�e���ȊO�Ŏ����s�R������������Ȃ��悤��DPF���u�̃t�B���^
�Đ��̐V���ȋZ�p�̊J�����g���b�N���[�J�̋i�ق̉ۑ��Ǝv����B����ɂ��āA�M�҂��C���x�~�G���W���i��
�����J2005-54771�j�̋Z�p��A������㏈������V�X�e���i�������J2005-69238�j�̋Z�p��g�ݍ��킹��A����
�s�R������������邱�ƂȂ�DPF���u�̃t�B���^�Đ����\�ƍl���Ă���B���������āA�R�������[���̃|�X�g���˂ɂ�
��DPF���u�̃t�B���^�Đ����r�C�Ǔ����˕�����DPF�Đ��ɋN�������R���Q���CO2����̗����̖�����������
���߁A�����Z�p�̑������p�����]�܂��Ƃ��낾�B
�Đ��̐V���ȋZ�p�̊J�����g���b�N���[�J�̋i�ق̉ۑ��Ǝv����B����ɂ��āA�M�҂��C���x�~�G���W���i��
�����J2005-54771�j�̋Z�p��A������㏈������V�X�e���i�������J2005-69238�j�̋Z�p��g�ݍ��킹��A����
�s�R������������邱�ƂȂ�DPF���u�̃t�B���^�Đ����\�ƍl���Ă���B���������āA�R�������[���̃|�X�g���˂ɂ�
��DPF���u�̃t�B���^�Đ����r�C�Ǔ����˕�����DPF�Đ��ɋN�������R���Q���CO2����̗����̖�����������
���߁A�����Z�p�̑������p�����]�܂��Ƃ��낾�B
�@���̗��R�́A�����s�R������������Ȃ���DPF���u�̃t�B���^���Đ��ł���Z�p�ɂ����́A�n�C�u���b�h�V�X�e��
��A�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j������㏈������V�X�e���i�������J2005-69238�j�̋Z�p�̑��ɂ���
�̂Ƃ��둶�݂��Ȃ��ƍl���Ă���B�Ȃ��A�����Z�p�ȊO�Ɏ����s�R������������Ȃ�DPF���u�̃t�B���^�Đ����ł�
��Z�p�������m�̏ꍇ�ɂ́A����Ƃ�E���[�����ł���������������Ɗ���Ă���B���̏ꍇ�ɂ́A���̃z�[���y�[
�W�̓��e�𑁋}�ɒ����������ł���B
��A�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j������㏈������V�X�e���i�������J2005-69238�j�̋Z�p�̑��ɂ���
�̂Ƃ��둶�݂��Ȃ��ƍl���Ă���B�Ȃ��A�����Z�p�ȊO�Ɏ����s�R������������Ȃ�DPF���u�̃t�B���^�Đ����ł�
��Z�p�������m�̏ꍇ�ɂ́A����Ƃ�E���[�����ł���������������Ɗ���Ă���B���̏ꍇ�ɂ́A���̃z�[���y�[
�W�̓��e�𑁋}�ɒ����������ł���B
�@�܂��A�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p�ɂ��ẮA������^�g���b�N�̃G���W���ɍ̗p���邱�Ƃ�
�����10�����x�̔R����P�ł��邱�Ƃɂ��Ă��C���x�~�G���W���ɂ���^�g���b�N�̒�R��ɏڏq���A�m�n����
���ɗL���ł��邱�Ƃɂ��Ă��C���x�~�ɂ��A�R��팸�ƔA�fSCR�G�}�ł�NO���팸���\���I�ɋL�ڂ�����̂�
�����������������B
�����10�����x�̔R����P�ł��邱�Ƃɂ��Ă��C���x�~�G���W���ɂ���^�g���b�N�̒�R��ɏڏq���A�m�n����
���ɗL���ł��邱�Ƃɂ��Ă��C���x�~�ɂ��A�R��팸�ƔA�fSCR�G�}�ł�NO���팸���\���I�ɋL�ڂ�����̂�
�����������������B
�@���݂̊e�g���b�N���[�J�́A���ݐi�s�`�œ��X�A�R�����|�X�g���˂�r�C�Ǔ����˂���p����DPF���u�̍Đ��ɂ�
���R����Ńg���b�N���[�U�ɉߏ�Ȍo�ϓI���S�����������鋤�ɁA�^�A����̗]����CO�Q����ɉ��S�������Ă���
���ƂɂȂ�B����ɂ��Ċe���̌o�c�����́A���Q�҂Ƃ��Ă̐ӔC��Ɋ����Ă���Ȃ�A���}�����Ђ̏��^�f�B�[�[
���g���b�N�ɍ̗p����Ă���R�������[�����|�X�g���˂�p����DPF���u�̐��Y�𑁋}�ɒ��~�ł���悤�ɁA�|�X�g����
��K�v�Ƃ��Ȃ�DPF���u�̐V�����Đ��Z�p�̊J���Ɏ��}�A���肷�ׂ��ƍl����B
���R����Ńg���b�N���[�U�ɉߏ�Ȍo�ϓI���S�����������鋤�ɁA�^�A����̗]����CO�Q����ɉ��S�������Ă���
���ƂɂȂ�B����ɂ��Ċe���̌o�c�����́A���Q�҂Ƃ��Ă̐ӔC��Ɋ����Ă���Ȃ�A���}�����Ђ̏��^�f�B�[�[
���g���b�N�ɍ̗p����Ă���R�������[�����|�X�g���˂�p����DPF���u�̐��Y�𑁋}�ɒ��~�ł���悤�ɁA�|�X�g����
��K�v�Ƃ��Ȃ�DPF���u�̐V�����Đ��Z�p�̊J���Ɏ��}�A���肷�ׂ��ƍl����B
�@�ނ��A����������������A�o�c�������ӔC���ƊW�Ȃ��A�R���̘Q��h�~�ł���DPF���u�̍Đ��Z�p���J
���ł����g���b�N���[�J�������g���b�N�̔̔��䐔���ł��邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ����낤�B�����āA���̋Z�p����
�p�������g���b�N���[�J�́A���{�̎s�ꂩ��ޏꂷ�邱�ƂɂȂ�̂ł͂Ȃ����낤���B
���ł����g���b�N���[�J�������g���b�N�̔̔��䐔���ł��邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ����낤�B�����āA���̋Z�p����
�p�������g���b�N���[�J�́A���{�̎s�ꂩ��ޏꂷ�邱�ƂɂȂ�̂ł͂Ȃ����낤���B
�@��L�{�����Ō�蓙���������܂�����A���[�����ɂĂ��w�E�������܂��B�܂��A�^��_�A������A�䊴�z���A�ǂ̂悤
�Ȏ����ł����\�ł��B�Ջ��l���ĂɃ��[���������肢��������A�o����͈͂őΉ������Ă��������܂��B
�Ȏ����ł����\�ł��B�Ջ��l���ĂɃ��[���������肢��������A�o����͈͂őΉ������Ă��������܂��B

|
