�Ջ��l�̃A�C�f�A
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�T�C�g�}�b�v
�@�@�@ �@ �@�@�@�@�@�@ �Ё@�@ ��
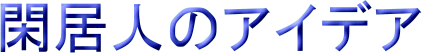

| |
�@���e�̈ꕔ�C��
|
| |
�@�u�e�Ђ̐V�����r�o�K�X�K���i2005�N�j�Ή��Z�p�v�̍��ɕ\��NjL |
| |
�@�u�|�X�g�V�����r�o�K�X�K���K���̃A�C�f�A�v�̍��ɕ\��NjL |
| |
�@�u�f�B�[�[���ɔ��15����CO2�팸���\��DDF�G���W���v�̍���lj�
|
| |
�@�uDDF�^�]�ƃf�B�[�[���^�]�̑I�����\�Ȃc�c�e��^�g���b�N�v�̍���lj� |
| |
�@�u�V�R�K�X���獇����DME��GTL�́A�f�B�[�[���g���b�N�̔R���ɕs�K�v�̍���lj� |
| |
�@�u���X�̎G���v |
| |
�@�u���^�n�C�u���b�h�g���b�N�͏�p�Ԃ̂悤�ȔR����P������v�̍���lj� |
| |
�@�u�C���x�~��DPF���Đ��𑣐i (�R����̖h�~�ɗL���j�v�̍���lj� |
| |
�@�u�C���x�~�G���W���ɂ���^�g���b�N�̒�R��v�̍���lj� |
| |
�@�u��^�g���b�N�́u�b�n�Q�팸�v�Ɓu�E�Ζ��v�̋Z�p�́A�����s�����H�v�̍���lj� |
| |
�@�u�C���x�~�́A�R��팸�ƔA�f�r�b�q�G�}�̂m�n���팸�̌���ɗL�����I�v�̍���lj� |
| |
�@�u�y�������G�l���M�[������30�������DME�𐄏�����@�B�w��̋^��v�̍���lj� |
| |
�@�u���{�͑�^�g���b�N�̐V���Ȓ�R��E��r�o�K�X��𑁊��ɐݒ肹��I�v�̍���lj� |
| |
�@�u�����߳��ނ́A��^�g���b�N�̑��s�R��̉��P������ȋZ�p�I�v�̍���lj� |
| |
�@�u�V�R�K�X��Ă�CNG��^�g���b�N�́A�d�ʎԔR���ɕs�K���̌��׃g���b�N�v�̍���lj� |
| |
�@�u���{�̒E�Ζ��E��Y�f���ɖ����ȋZ�p�����������ʈ��S���������v�̍���lj� |
| |
�@�u��Ƃ̕i�����^����^�g���b�N�̔R����P�̍��\�܂����Ȑ�`�v�̍���lj� |
| |
�@�u�o�C�I�}�X�R����DME�ɂ�鎩���Ԃ̒�Y�f�E�E�Ζ��́A�s�\���I�v�̍���lj� |
| |
�@�u�č������ɂ���^�g���b�N��NO���K�����{�s����������{���{�̑Ӗ��v�̍���lj� |
| |
�@�u�C���x�~�́A�f�B�[�[���r�C�K�X�̃G�l���M�[���u�̌���������v�̍���lj� |
| |
�@�u�G�l���M�[�����𑽗ʂɘQ���DME�g���b�N�𐄏�����ُ�Ȑl�B�v�̍���lj� |
| |
�@�u�w�ҁE���Ƃ����{�\�Z�̎���������̊l���ɗp���鍼�\�I�Ȏ�@�v�̍���lj� |
| |
�@�u�f�B�[�[���̋C���x�~�́A�R�[���h�X�^�[�g��NO���팸�ɂ��L�����I�v�̍���lj� |
| |
�@�u���쎩���Ԃ��_�����\�����R����P�@�\�̗��C���x�~�V�X�e���v�̍���lj� |
| |
�@�u��^�g���b�N��NO���팸�ƔR�����ɗL���ȋC���x�~��َE����w�ҏ����v�̍���lj� |
| |
�@�u�f�B�[�[���d�ʎ�2016�NNOx�K����0.4g/kWh�́A�s���Ȋɘa�̌��K���v�̍���lj� |
| |
�@�u�G���W���̋C���x�~�́A�����^�q���̍X�Ȃ�R�����������v�̍���lj� |
| |
�@�u2015�N��������E�v���h�E�ި���َԂ͕s���\�t�g�ŋK���ᔽ��NO����r�o�v�̍���lj� |
| |
�@�u�O�H�����Ԃ̃J�^���O�R��s������@�Ȍ����ŒNjy���鍑���Ȃ̏X���v�̍���lj� |
| |
�@�u�x���c�́A�f�B�[�[���Ԃ�NOx�ߑ�̃��R�[������{�ł����{�v�̍���lj� |
| |
�{�y�[�W�̍ŏI�X�V���F2014�N6��30��
�P�D��^�g���b�N�iGVW�P�Q�g���z���j�̔r�o�K�X�K���ƔR��K���ɂ���
�@�������ɂ��A�ߔN�A�����Ԕr�o�K�X�K������������Ă������ʁA��C���̂m�n���╂�V���q���́A�ɂ�
���Ȍ����X���������Ă���B�������A�s�s�̑�C���͖����\���ɉ��P���ꂢ��Ƃ͂����Ȃ��̂�����ł���B���̂�
�߁A���݁A�f�B�[�[�������Ԃ���r�o�����NOx����уp�e�B�L�����[�g�i�o�l�j�́A�s�s�̑�C�������������Ă����
��̌����Ƃ��]���Ă���B���̂��߁A�f�B�[�[���g���b�N�E�o�X�́A���݂̓��{�o�ς���юs�������̊�Ղ��x����
����ɂ�������炸�A���Ԃ���͌������ڂŌ����Ă���B���̂悤�ȏ���A�]��������������Ĕr�o�K�X�K����
�������s���Ă���A��^�g���b�N�E�o�X�iGVW�P�Q�g���z���j�ɑ��A�ŋ߂ł͕���17�N�i2005�N�j�̐V�����r�o�K�X�K
���ɑ����ĕ���21�N�i2009�N�j�Ƀ|�X�g�V�����r�o�K�X�K�������{���ꂽ�B
���Ȍ����X���������Ă���B�������A�s�s�̑�C���͖����\���ɉ��P���ꂢ��Ƃ͂����Ȃ��̂�����ł���B���̂�
�߁A���݁A�f�B�[�[�������Ԃ���r�o�����NOx����уp�e�B�L�����[�g�i�o�l�j�́A�s�s�̑�C�������������Ă����
��̌����Ƃ��]���Ă���B���̂��߁A�f�B�[�[���g���b�N�E�o�X�́A���݂̓��{�o�ς���юs�������̊�Ղ��x����
����ɂ�������炸�A���Ԃ���͌������ڂŌ����Ă���B���̂悤�ȏ���A�]��������������Ĕr�o�K�X�K����
�������s���Ă���A��^�g���b�N�E�o�X�iGVW�P�Q�g���z���j�ɑ��A�ŋ߂ł͕���17�N�i2005�N�j�̐V�����r�o�K�X�K
���ɑ����ĕ���21�N�i2009�N�j�Ƀ|�X�g�V�����r�o�K�X�K�������{���ꂽ�B
�@�������Ȃ���A�č������ɂ���^�g���b�N��NO���K�����{�s����������{���{�̑Ӗ��ɏڏq���Ă���悤�ɁA���{��
�����̑�^�g���b�N�̂m�n���K���́A2016�N�̎��{�\��ł�NO�� �� 0.4 g/kWh�j�ł���A2010�N���č��̂m�n��
�K���iNO�� �� 0.27 g/kWh�j���������Ɋɂ��m�n���K����������{�s���ꑱ�������悤�ł���B�܂��A�ߔN�̒n
�����g���h�~�̖ʂ���v�]����Ă���b�n�Q�팸�ɑΉ����邽�߁A���݂�GVW�R�D�T�g���ȏ�̃g���b�N�ɂ�����2015�N
�x�i����27�N�x�j�d�ʎԔR�����ݒ肳��Ă���B����ɂ���āA��^�g���b�N�E�o�X�iGVW�P�Q�g���z���j�ɂ����Ă��R
��K�������{����Ă��邪�A�ŋ߂ł͂�����������Ă��邽�߁A�߂������ɐ��{�i���y��ʏȁj��2015�N�x�i����27
�N�x�j�d�ʎԔR�������������V���Ȋ��ݒ肷�ׂ��ł͂Ȃ����낤���B
�����̑�^�g���b�N�̂m�n���K���́A2016�N�̎��{�\��ł�NO�� �� 0.4 g/kWh�j�ł���A2010�N���č��̂m�n��
�K���iNO�� �� 0.27 g/kWh�j���������Ɋɂ��m�n���K����������{�s���ꑱ�������悤�ł���B�܂��A�ߔN�̒n
�����g���h�~�̖ʂ���v�]����Ă���b�n�Q�팸�ɑΉ����邽�߁A���݂�GVW�R�D�T�g���ȏ�̃g���b�N�ɂ�����2015�N
�x�i����27�N�x�j�d�ʎԔR�����ݒ肳��Ă���B����ɂ���āA��^�g���b�N�E�o�X�iGVW�P�Q�g���z���j�ɂ����Ă��R
��K�������{����Ă��邪�A�ŋ߂ł͂�����������Ă��邽�߁A�߂������ɐ��{�i���y��ʏȁj��2015�N�x�i����27
�N�x�j�d�ʎԔR�������������V���Ȋ��ݒ肷�ׂ��ł͂Ȃ����낤���B
�Q�D���}�ȉ������K�v�ȑ�^�g���b�N�iGVW�P�Q�g���z���j�̋Z�p�I�ȉۑ�
�@���݂̃|�X�g�V�����r�o�K�X�K���i2009�N�K���j�ɓK�����Ă����^�g���b�N�iGVW�P�Q�g���z���j�ɂ����ẮA�ȉ���
�������悤�ȉۑ������Ă���B����ɂ��āA�g���b�N���[�J���ۑ�����̌����J���Ɍ����ɓw�͂���āA�����̃g���b
�N���[�U���ۑ�����̑���������]��ł�����̂Ǝv����B
�������悤�ȉۑ������Ă���B����ɂ��āA�g���b�N���[�J���ۑ�����̌����J���Ɍ����ɓw�͂���āA�����̃g���b
�N���[�U���ۑ�����̑���������]��ł�����̂Ǝv����B
���@���������܂߂��S�ẴG���W���^�]�̈�ł̑��EGR�̎������đ啝�Ȃm�n���팸��}��A�A�fSCR��
�m�n���팸���S���y�����ĔA�f������ʂ��팸�����邱�ƁB
�m�n���팸���S���y�����ĔA�f������ʂ��팸�����邱�ƁB
���@�f�B�[�[���G���W���̉i���̉ۑ�ł���X�Ȃ�R����P��}���Ă������ƁB
���@�c�o�e�����Đ��̉��팸���āA�����Đ��ɂ��R���̘Q����o���邾���}�����邱�ƁB
���@�r�C�K�X���x���ቷ�ƂȂ鑖�s���ɂ����āA�A�fSCR�V�X�e���̂m�n���ጸ�@�\�����コ���邱�ƁB
�@���݂̂Ƃ���AGVW�P�Q�g���z���̑�^�f�B�[�[���g���b�N�E�o�X�ɂ�����|�X�g�V�����K���K���ɂ́A�e�g���b�N���[�J
�͑����ĐV�����r�o�K�X�K���Ŏ��p�����ꂽ�m�n���팸�̔A�f�r�b�q�G�}�ƃp�e�B�L�����[�g�팸��DPF���u��g����
���Z�p��p���Ă���悤�ł���B���̂��߁A���݁A�s��Ő��������s���Ă���V�����r�o�K�X�K��(����17�N[��2005
�N]�K���j�K���̑�^�f�B�[�[���g���b�N�E�o�X��A�s�̒��̃|�X�g�V�����K����(����21�N[��2009�N]�K���j�K���̑�^
�f�B�[�[���g���b�N�E�o�X�̂قƂ�ǂ̎ԗ��ɂ́ADPF���u����������Ă���̂ł���B����DPF���u�ɂ��ẮA�e��
�̐V�����r�o�K�X�K���i2005�N�j�Ή��Z�p�ɏڏq�����悤�ɁA�|�X�g���˂܂��͂g�b�r�C�Ǖ��˂ɂ��p�ɂ�DPF�Đ�
�ɂ���ĔR������������錇�ׂ�����Ă���̂ł���B���̒��ł��|�X�g���˂ɂ��DPF���u���Đ����鑕�u�ł́A�y
���ɂ���ăG���W���I�C������߂������肪�����Ă���̂ł���B�����̌��s�̃|�X�g���ˍĐ�����g�b�r�C�Ǖ�
�ˍĐ�����DPF���u�̖��_�ɂ��ẮA�C���x�~��DPF�̎��ȍĐ��𑣐i����V�Z�p�̃y�[�W�ɏڏq�����̂ł�
���������������B�܂��A�A�f�r�b�q�G�}�ł͔r�C�K�X���x���Ⴂ�G���W���̒ᕉ�ׂł͂m�n�����\���ɍ팸�ł��Ȃ���
�_������A����̍X�Ȃ�m�n���K���̋����ւ̓K���ɍۂ��Ă͑��}�ɉ��P���ׂ��Z�p�I�ȉۑ�ƍl������B
�͑����ĐV�����r�o�K�X�K���Ŏ��p�����ꂽ�m�n���팸�̔A�f�r�b�q�G�}�ƃp�e�B�L�����[�g�팸��DPF���u��g����
���Z�p��p���Ă���悤�ł���B���̂��߁A���݁A�s��Ő��������s���Ă���V�����r�o�K�X�K��(����17�N[��2005
�N]�K���j�K���̑�^�f�B�[�[���g���b�N�E�o�X��A�s�̒��̃|�X�g�V�����K����(����21�N[��2009�N]�K���j�K���̑�^
�f�B�[�[���g���b�N�E�o�X�̂قƂ�ǂ̎ԗ��ɂ́ADPF���u����������Ă���̂ł���B����DPF���u�ɂ��ẮA�e��
�̐V�����r�o�K�X�K���i2005�N�j�Ή��Z�p�ɏڏq�����悤�ɁA�|�X�g���˂܂��͂g�b�r�C�Ǖ��˂ɂ��p�ɂ�DPF�Đ�
�ɂ���ĔR������������錇�ׂ�����Ă���̂ł���B���̒��ł��|�X�g���˂ɂ��DPF���u���Đ����鑕�u�ł́A�y
���ɂ���ăG���W���I�C������߂������肪�����Ă���̂ł���B�����̌��s�̃|�X�g���ˍĐ�����g�b�r�C�Ǖ�
�ˍĐ�����DPF���u�̖��_�ɂ��ẮA�C���x�~��DPF�̎��ȍĐ��𑣐i����V�Z�p�̃y�[�W�ɏڏq�����̂ł�
���������������B�܂��A�A�f�r�b�q�G�}�ł͔r�C�K�X���x���Ⴂ�G���W���̒ᕉ�ׂł͂m�n�����\���ɍ팸�ł��Ȃ���
�_������A����̍X�Ȃ�m�n���K���̋����ւ̓K���ɍۂ��Ă͑��}�ɉ��P���ׂ��Z�p�I�ȉۑ�ƍl������B
�@�Ƃ���ŁAGVW�Q�O�`�Q�T�g���̑�^�g���b�N���K�v�\���ȑ��s���\���ێ����邽�߂ɂ́A�P�R���b�g�����̕W���G���W��
�𓋍ڂ���K�v������B���̂��߁A���쎩���Ԃ́A���̃N���X�̑�^�g���b�N�ɂ͂P�R���b�g�����̂̕W���G���W������
���Ă���̂ł���B�Ƃ��낪�A�|�X�g�V�����r�o�K�X�K���i�Q�O�O�X�N�K���j�ɓK���������쎩���Ԃ̂P�R���b�g�����̕W��
�G���W���𓋍ڂ����V�i�}�j���A���g�����~�b�V������GVW�Q�T�g���N���X�̑�^�g���b�N�̈ꕔ�Ԏ�ł́A2015�N�x�i����
27�N�x�j�d�ʎԔR���ɖ��B���Ɖ]���ߎS�ȏɊׂ��Ă���悤���B�܂��A�O�H�ӂ����ɂ����Ă��A�P�R���b�g������
�W���G���W���𓋍ڂ���7�i�}�j���A���g�����X�~�b�V������GVW�Q�O�`�Q�T�g���̑�^�_���v�ł́A2015�N�x�i����27�N
�x�j�d�ʎԔR���ɖ��B���̏�Ԃł���B�@���������āA���쎩���ԁA�O�H�ӂ����ł́A���̂悤�ȂP�R���b�g�����̕W
���G���W���𓋍ڂ���7�i�}�j���A���g�����X�~�b�V�����̑�^�g���b�N�̑S�Ă̎Ԏ��2015�N�x�i����27�N�x�j�d�ʎԔR
���ɓK���ł���悤�ɂ��邽�߂ɁA�f�B�[�[���G���W���̔R��팸�̋Z�p���J�����邱�Ƃ��i�ق̉ۑ�ƌ����
��B
�𓋍ڂ���K�v������B���̂��߁A���쎩���Ԃ́A���̃N���X�̑�^�g���b�N�ɂ͂P�R���b�g�����̂̕W���G���W������
���Ă���̂ł���B�Ƃ��낪�A�|�X�g�V�����r�o�K�X�K���i�Q�O�O�X�N�K���j�ɓK���������쎩���Ԃ̂P�R���b�g�����̕W��
�G���W���𓋍ڂ����V�i�}�j���A���g�����~�b�V������GVW�Q�T�g���N���X�̑�^�g���b�N�̈ꕔ�Ԏ�ł́A2015�N�x�i����
27�N�x�j�d�ʎԔR���ɖ��B���Ɖ]���ߎS�ȏɊׂ��Ă���悤���B�܂��A�O�H�ӂ����ɂ����Ă��A�P�R���b�g������
�W���G���W���𓋍ڂ���7�i�}�j���A���g�����X�~�b�V������GVW�Q�O�`�Q�T�g���̑�^�_���v�ł́A2015�N�x�i����27�N
�x�j�d�ʎԔR���ɖ��B���̏�Ԃł���B�@���������āA���쎩���ԁA�O�H�ӂ����ł́A���̂悤�ȂP�R���b�g�����̕W
���G���W���𓋍ڂ���7�i�}�j���A���g�����X�~�b�V�����̑�^�g���b�N�̑S�Ă̎Ԏ��2015�N�x�i����27�N�x�j�d�ʎԔR
���ɓK���ł���悤�ɂ��邽�߂ɁA�f�B�[�[���G���W���̔R��팸�̋Z�p���J�����邱�Ƃ��i�ق̉ۑ�ƌ����
��B
�@�܂��A�����̐��Y�����ł��ƂȂ�Ζ��s�[�N�̎�����}�����ƌ����邱�Ƃ���A����̐��E�̑��Ζ����Y�ʂ͌�
���X���ɂ���ƍl������B�����_��100���̔R����Ζ��Ɉˑ����Ă����^�g���b�N�ɂ����ẮA����̐Ζ������s
���ɂ��y�������̕N���≿�i�����ɔ������E�Ζ��ւ̎{���}�ɋ��߂��Ă���Ƃ���ł���
���X���ɂ���ƍl������B�����_��100���̔R����Ζ��Ɉˑ����Ă����^�g���b�N�ɂ����ẮA����̐Ζ������s
���ɂ��y�������̕N���≿�i�����ɔ������E�Ζ��ւ̎{���}�ɋ��߂��Ă���Ƃ���ł���
�� ����̐Ζ������̌͊��ɂ��y���s���ɔ����A�g���b�N�ݕ��A������ɂ�����G�l���M�[��@�Ǘ��Ƃ���
�̒E�Ζ��̗A���̐����������邱�ƁB
�̒E�Ζ��̗A���̐����������邱�ƁB
�@���݂̑�^�g���b�N��100���̔R����Ζ��Ɉˑ����Ă��邱�Ƃ̃G�l���M�[��@�Ǘ���̖������������i�Ƃ�
�āA�����̊w�҂���ƂƊ֘A��Ƃ́A�����̑�^�g���b�N�̔R���ɂ͓V�R�K�X�R���̂c�l�d�Ƃf�s�k���œK�ł���Ǝ�
�����A��������邽�߂̋Z�p�J����ɍs���Ă���Ƃ���ł���B�������A�u�Ջ��l�v���u��^�g���b�N�̔R���ɂc
�l�d�܂��͂f�s�k��p����v���Ƃ́A�u�G�l���M�[�����̘Q��v�A�u�R�������̍����v����сu�b�n�Q�̍팸�s�\�v��
���������N�������Ƃ͂قڊԈႢ�Ȃ��ƍl���Ă���B�S�Ă̕���ŏȎ�����b�n�Q�팸���ŗD�悳��鍡���ł́A
�c�l�d��f�s�k�́A��^�g���b�N�̔R���Ƃ��Ă͒v���I�Ȍ��ׂ�����Ă���ƍl���ėǂ����낤�B���������āA�V�R�K�X����
������DME��GTL�́A�f�B�[�[���g���b�N�̔R���ɕs�K�ł���A��^�g���b�N�̔R���ɂc�l�d��f�s�k��p���邱�Ƃ͐��
�ɔ�����ׂ��ƍl���Ă���B�����āA�ꕔ�̊w�ҁE���Ƃ�����ɐ������Ă����^�g���b�N�̔R���ɂc�l�d��f�s�k��p
���邱�Ƃ͋��̍����Ǝv���Ďd�����Ȃ��B�u�Ջ��l�v�́u�����̑�^�g���b�N�ɂc�l�d��f�s�k��R���Ɏg�p����v�G�l���M
�[�����̘Q��ƐM���Ă��邪�A����Ɛ^�t�̈ӌ��ł����^�g���b�N�ɂc�l�d��f�s�k�̓����𐄐i����Ă���w�ҁE���
�Ƃ̗��_�E�������A����Ƃ��������������������Ɗ���Ă���B
�āA�����̊w�҂���ƂƊ֘A��Ƃ́A�����̑�^�g���b�N�̔R���ɂ͓V�R�K�X�R���̂c�l�d�Ƃf�s�k���œK�ł���Ǝ�
�����A��������邽�߂̋Z�p�J����ɍs���Ă���Ƃ���ł���B�������A�u�Ջ��l�v���u��^�g���b�N�̔R���ɂc
�l�d�܂��͂f�s�k��p����v���Ƃ́A�u�G�l���M�[�����̘Q��v�A�u�R�������̍����v����сu�b�n�Q�̍팸�s�\�v��
���������N�������Ƃ͂قڊԈႢ�Ȃ��ƍl���Ă���B�S�Ă̕���ŏȎ�����b�n�Q�팸���ŗD�悳��鍡���ł́A
�c�l�d��f�s�k�́A��^�g���b�N�̔R���Ƃ��Ă͒v���I�Ȍ��ׂ�����Ă���ƍl���ėǂ����낤�B���������āA�V�R�K�X����
������DME��GTL�́A�f�B�[�[���g���b�N�̔R���ɕs�K�ł���A��^�g���b�N�̔R���ɂc�l�d��f�s�k��p���邱�Ƃ͐��
�ɔ�����ׂ��ƍl���Ă���B�����āA�ꕔ�̊w�ҁE���Ƃ�����ɐ������Ă����^�g���b�N�̔R���ɂc�l�d��f�s�k��p
���邱�Ƃ͋��̍����Ǝv���Ďd�����Ȃ��B�u�Ջ��l�v�́u�����̑�^�g���b�N�ɂc�l�d��f�s�k��R���Ɏg�p����v�G�l���M
�[�����̘Q��ƐM���Ă��邪�A����Ɛ^�t�̈ӌ��ł����^�g���b�N�ɂc�l�d��f�s�k�̓����𐄐i����Ă���w�ҁE���
�Ƃ̗��_�E�������A����Ƃ��������������������Ɗ���Ă���B
�@���݁ADME�ɊW����l�B�́A�uDME�̓f�B�[�[���G���W���̍������������R���ł���A�����̗L�]�ȔR���v�Ƃ�
��`������ɍs�Ȃ��Ă���悤���B�Ⴆ�A�y�������G�l���M�[�������R�O�������c�l�d�𐄏�����@�B�w���
�^���̃y�[�W�ɏڏq���Ă���悤�ɁA���{�@�B�w�2010�N5�����iVol.113�AN0.1098�j�Ɍf�ڂ��ꂽ�uDME�g���b�N�̍�
�V�J���v�̘_���ɂ����āADME�ƌy���Ƃَ̈�̔R���̗D��̋c�_�ɕK�{��Well-to-Wheel�̃��C�t�T�C�N���A�Z
�X�����g�iLCA�j�ɂ��]����S���s�킸�A�uDME�������̗L�]�ȔR���v�Ɗw�p�I�ȍ������������ɔ�����_���咣��
��DME�̐�`���s���Ă���̂ł���B���̓��{�@�B�w��Ɍf�ڂ��ꂽDME�g���b�N�̘_���́A�֑��`��ʂ�z���A
���U��`�ɋ߂��悤�Ɏv����̂��B
��`������ɍs�Ȃ��Ă���悤���B�Ⴆ�A�y�������G�l���M�[�������R�O�������c�l�d�𐄏�����@�B�w���
�^���̃y�[�W�ɏڏq���Ă���悤�ɁA���{�@�B�w�2010�N5�����iVol.113�AN0.1098�j�Ɍf�ڂ��ꂽ�uDME�g���b�N�̍�
�V�J���v�̘_���ɂ����āADME�ƌy���Ƃَ̈�̔R���̗D��̋c�_�ɕK�{��Well-to-Wheel�̃��C�t�T�C�N���A�Z
�X�����g�iLCA�j�ɂ��]����S���s�킸�A�uDME�������̗L�]�ȔR���v�Ɗw�p�I�ȍ������������ɔ�����_���咣��
��DME�̐�`���s���Ă���̂ł���B���̓��{�@�B�w��Ɍf�ڂ��ꂽDME�g���b�N�̘_���́A�֑��`��ʂ�z���A
���U��`�ɋ߂��悤�Ɏv����̂��B
�@�Ƃ���ŁA�n�C�u���b�h��p�Ԃ̂P�O���[�h�R��l�́A�ʏ�̃K�\������p�Ԃ����Q�{���x�̔R����オ�����Ă�
��B���̂��߁A�n�C�u���b�h��p�Ԃ̓��[�U�̐l�C�������A�����I�ɕ��y���Ă���悤�ł��B�������A�g���b�N���[�J���s
�̂��Ă��鏬�^�n�C�u���b�h�g���b�N�i�ύڗʂQ�g���N���X�j�̏d�ʎԃ��[�h�R��l�́A�ʏ�̏��^�f�B�[�[���g���b�N����
�ő�łP�O�����x�̔R�����ɉ߂��Ȃ��悤���B�ڍׂ́A���^�n�C�u���b�h �g���b�N�̓n�C�u���b�h��p�Ԃ̂悤�ȔR��
���P�������̃y�[�W�������������������B���̂悤�ɁA���݂̏��^�n�C�u���b�h�g���b�N�́A�����ԗ����i�Ɍ��������R
��팸�������Ă��Ȃ��悤���B���������āA���݂̔R��\���啝�Ɍ��コ��Ȃ�����A���^�n�C�u���b�h�g���b�N��
�L�����y���邱�Ƃ͂Ȃ����̂Ɨ\�z�����B
��B���̂��߁A�n�C�u���b�h��p�Ԃ̓��[�U�̐l�C�������A�����I�ɕ��y���Ă���悤�ł��B�������A�g���b�N���[�J���s
�̂��Ă��鏬�^�n�C�u���b�h�g���b�N�i�ύڗʂQ�g���N���X�j�̏d�ʎԃ��[�h�R��l�́A�ʏ�̏��^�f�B�[�[���g���b�N����
�ő�łP�O�����x�̔R�����ɉ߂��Ȃ��悤���B�ڍׂ́A���^�n�C�u���b�h �g���b�N�̓n�C�u���b�h��p�Ԃ̂悤�ȔR��
���P�������̃y�[�W�������������������B���̂悤�ɁA���݂̏��^�n�C�u���b�h�g���b�N�́A�����ԗ����i�Ɍ��������R
��팸�������Ă��Ȃ��悤���B���������āA���݂̔R��\���啝�Ɍ��コ��Ȃ�����A���^�n�C�u���b�h�g���b�N��
�L�����y���邱�Ƃ͂Ȃ����̂Ɨ\�z�����B
�R�D�����̔R��\�Ɗ����\�ɗD�ꂽ��^�g���b�N���������邽�߂̗L���ȋZ�p
�@�u�Ջ��l�v�́A����܂Ő��\�N�ԁA�g���b�N���[�J�[�Ńf�B�[�[���r�o�K�X��ɊW�����Ɩ��Ɍg����Ă����B�E���
���Ă��璷���������o�߂��Ă��邪�A�s�v�c�Ȃ��Ƃɖ����ɑ�^�f�B�[�[���g���b�N�E�o�X�̔r�o�K�X�ጸ�Z�p�ւ̋�
��������邱�Ƃ͂Ȃ��B����͑��ɔM���ł����������Ă��Ȃ����߂ł͂Ȃ����Ǝv���Ă���B�ɂȐ����̓k�R�ɁA
����̔r�o�K�X�K�������ɖ𗧂������ȐV���ȋZ�p���l�Ă��A�|�X�g�V�����r�o�K�X�K���K���́u�A�C�f�A�v�ɂ܂Ƃ�
���B���̎�ȋZ�p�́A�f�B�[�[���G���W���̃����b�g��傫�����Ȃ����ƂȂ��r�o�K�X�̒ጸ���\�ƍl�������C���x�~
�G���W���i�������J2005-54771�j�A�㏈������V�X�e���i�������J2005-69238�j�A�p���X�d�f�q�V�X�e���i�������J2005-
54778�j�̂R���̏o������ł���B
���Ă��璷���������o�߂��Ă��邪�A�s�v�c�Ȃ��Ƃɖ����ɑ�^�f�B�[�[���g���b�N�E�o�X�̔r�o�K�X�ጸ�Z�p�ւ̋�
��������邱�Ƃ͂Ȃ��B����͑��ɔM���ł����������Ă��Ȃ����߂ł͂Ȃ����Ǝv���Ă���B�ɂȐ����̓k�R�ɁA
����̔r�o�K�X�K�������ɖ𗧂������ȐV���ȋZ�p���l�Ă��A�|�X�g�V�����r�o�K�X�K���K���́u�A�C�f�A�v�ɂ܂Ƃ�
���B���̎�ȋZ�p�́A�f�B�[�[���G���W���̃����b�g��傫�����Ȃ����ƂȂ��r�o�K�X�̒ጸ���\�ƍl�������C���x�~
�G���W���i�������J2005-54771�j�A�㏈������V�X�e���i�������J2005-69238�j�A�p���X�d�f�q�V�X�e���i�������J2005-
54778�j�̂R���̏o������ł���B
�@�O�q�̂悤�ɁA���쎩���Ԃ�O�H�ӂ����́A�|�X�g�V�����r�o�K�X�K���i2009�N�K���j�ɓK�������P�R���b�g���̕W��
�G���W�����ڂ�7�i�}�j���A���g�����X�~�b�V����������GVW25�g���̑�^�g���b�N�E�g���N�^�̈ꕔ�̎Ԏ킪2015�N�x�i��
��27�N�x�j�d�ʎԔR���ɕs�K���ƂȂ��Ă���悤�ł���B��^�g���b�N�ɂP�P���b�g�����G���W�����̗p���Ă���UD�g
���b�N�X�����l�ł���B���̂��߁A���쎩���ԁA�O�H�ӂ��������UD�g���b�N�X�́A��^�g���b�N�̑S�Ԏ��2015�N�x
�i����27�N�x�j�d�ʎԔR���ɓK��������Z�p�J���ɕK���Ɏ��g��ł�����̂ƍl������B
�G���W�����ڂ�7�i�}�j���A���g�����X�~�b�V����������GVW25�g���̑�^�g���b�N�E�g���N�^�̈ꕔ�̎Ԏ킪2015�N�x�i��
��27�N�x�j�d�ʎԔR���ɕs�K���ƂȂ��Ă���悤�ł���B��^�g���b�N�ɂP�P���b�g�����G���W�����̗p���Ă���UD�g
���b�N�X�����l�ł���B���̂��߁A���쎩���ԁA�O�H�ӂ��������UD�g���b�N�X�́A��^�g���b�N�̑S�Ԏ��2015�N�x
�i����27�N�x�j�d�ʎԔR���ɓK��������Z�p�J���ɕK���Ɏ��g��ł�����̂ƍl������B
�@����A10 ���b�g���̃_�E���T�C�W���O�G���W�����̗p���Ă��邽�߂ɑ��s���̗���^�g���b�N��^�g���b�N��̔�����
���邢���U�����Ԃł́A�����O�H�Ɠ��l�̑��s���\�̗D�ꂽ13 ���b�g�����̕W���T�C�Y�̃G���W���𓋍ڂ�����^
�g���b�N�����i�����Ăق����Ƃ̔̔����傩��̗v�]���������̂Ɨ\�z�����B���������āA���쎩���ԁAUD�g���b�N�X�A
�O�H�ӂ�������т����U�����Ԃ̑S�Ẵg���b�N���[�J�́A13 ���b�g�����̕W���T�C�Y�̃G���W���𓋍ڂ����S�Ă̑�^
�g���b�N�E�g���N�^�ł�2015 �N�x�i����27�N�x�j�d�ʎԔR���ɓK�������邽�߂̔R����P�̐V���ȋZ�p��K�v�Ƃ�
�Ă��邱�Ƃ͖��炩�ł���B����13 ���b�g�����̕W���T�C�Y�̃G���W���𓋍ڂ�����^�g���b�N��2015 �N�x�i����27�N
�x�j�d�ʎԔR���ɗe�ՂɓK�������邱�Ƃ��ł���Z�p���A�M�Ғ�Ă̂Q�^�[�{�ߋ��@�������C���x�~�G���W���i��
�����J2005-54771�j�ł���B
���邢���U�����Ԃł́A�����O�H�Ɠ��l�̑��s���\�̗D�ꂽ13 ���b�g�����̕W���T�C�Y�̃G���W���𓋍ڂ�����^
�g���b�N�����i�����Ăق����Ƃ̔̔����傩��̗v�]���������̂Ɨ\�z�����B���������āA���쎩���ԁAUD�g���b�N�X�A
�O�H�ӂ�������т����U�����Ԃ̑S�Ẵg���b�N���[�J�́A13 ���b�g�����̕W���T�C�Y�̃G���W���𓋍ڂ����S�Ă̑�^
�g���b�N�E�g���N�^�ł�2015 �N�x�i����27�N�x�j�d�ʎԔR���ɓK�������邽�߂̔R����P�̐V���ȋZ�p��K�v�Ƃ�
�Ă��邱�Ƃ͖��炩�ł���B����13 ���b�g�����̕W���T�C�Y�̃G���W���𓋍ڂ�����^�g���b�N��2015 �N�x�i����27�N
�x�j�d�ʎԔR���ɗe�ՂɓK�������邱�Ƃ��ł���Z�p���A�M�Ғ�Ă̂Q�^�[�{�ߋ��@�������C���x�~�G���W���i��
�����J2005-54771�j�ł���B
�@���ɁA���쎩���Ԃ́A�����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p���^�g���b�N�ɍ̗p�����ꍇ�ɂ́A��
�^�g���b�N���T�`10 �����x�̔R������P�ł��邽�߁A�P�R���b�g���̕W���G���W�����ڂ̂V�i�}�j���A���g�����~�b�V
�����������S�Ă̑�^�g���b�N�E�g���N�^�̏d�ʎԃ��[�h�R���2015�N�x�i����27�N�x�j�d�ʎԔR���ɗe
�ՂɓK�������邱�Ƃ��ł����ƍl������B�O�H�ӂ�����UD�g���b�N�X�̏ꍇ�����l�ł���B����ɂ��ẮA�C���x
�~�G���W���ɂ���^�g���b�N�̒�R��ɏڏq���Ă���̂ł����������������B
�^�g���b�N���T�`10 �����x�̔R������P�ł��邽�߁A�P�R���b�g���̕W���G���W�����ڂ̂V�i�}�j���A���g�����~�b�V
�����������S�Ă̑�^�g���b�N�E�g���N�^�̏d�ʎԃ��[�h�R���2015�N�x�i����27�N�x�j�d�ʎԔR���ɗe
�ՂɓK�������邱�Ƃ��ł����ƍl������B�O�H�ӂ�����UD�g���b�N�X�̏ꍇ�����l�ł���B����ɂ��ẮA�C���x
�~�G���W���ɂ���^�g���b�N�̒�R��ɏڏq���Ă���̂ł����������������B
�@�O�q�̒ʂ�A���쎩���ԁA�O�H�ӂ��������UD�g���b�N�X�́A�|�X�g�V�����r�o�K�X�K���i2009�N�K���j�ɓK���̑�^
�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W���̏d�ʎԃ��[�h�R��l�𐔃p�[�Z���g���x�̍팸���ł��Ȃ�����2015�N�x�i����27�N
�x�j�d�ʎԔR�������B���̉ۑ������Ă���B����A�����U�����Ԃ́A���쎩���ԁA�O�H�ӂ����̂Q�Ђ������r
�C�ʂ̃G���W�����^�g���b�N�ɍ̗p���A�G���W���_�E���T�C�W���O�ɂ���ĔR��팸��}���đ�^�g���b�N�̑啔����
2015�N�x�i����27�N�x�j�d�ʎԔR���ɓK�������Ă��邪�A���̏ꍇ�ɂ͑�^�g���b�N�̑��s���\�Ɏ�̋]����
�������Ă���Ԏ������悤���B���������āA�����U�����Ԃɂ����Ă��A��^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W���ɂ�����R
��팸�̕K�v���́A���̃g���b�N���[�J�ƕς��Ȃ����̂ƍl������B���������đS�Ẵg���b�N���[�J�ɂ����āA��^�g
���b�N���C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p���̗p����A�R�����̉ۑ�́A�e�Ղɉ����ł���̂�
����B�Ȃ��A�C���x�~�G���W���i�������J�Q�O�O�T�|�T�S�V�V�P�j���啝�Ɂu�R����P�v�Ɓu�m�n���팸�v�̗����������ł���D
�ꂽ����������B���̗��R�ɂ��ẮA�C���x�~�́A�R��팸�ƔA�fSCR��NO���팸���̌���ɗL�����I�̃y�[�W
���䗗�������������B
�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W���̏d�ʎԃ��[�h�R��l�𐔃p�[�Z���g���x�̍팸���ł��Ȃ�����2015�N�x�i����27�N
�x�j�d�ʎԔR�������B���̉ۑ������Ă���B����A�����U�����Ԃ́A���쎩���ԁA�O�H�ӂ����̂Q�Ђ������r
�C�ʂ̃G���W�����^�g���b�N�ɍ̗p���A�G���W���_�E���T�C�W���O�ɂ���ĔR��팸��}���đ�^�g���b�N�̑啔����
2015�N�x�i����27�N�x�j�d�ʎԔR���ɓK�������Ă��邪�A���̏ꍇ�ɂ͑�^�g���b�N�̑��s���\�Ɏ�̋]����
�������Ă���Ԏ������悤���B���������āA�����U�����Ԃɂ����Ă��A��^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W���ɂ�����R
��팸�̕K�v���́A���̃g���b�N���[�J�ƕς��Ȃ����̂ƍl������B���������đS�Ẵg���b�N���[�J�ɂ����āA��^�g
���b�N���C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p���̗p����A�R�����̉ۑ�́A�e�Ղɉ����ł���̂�
����B�Ȃ��A�C���x�~�G���W���i�������J�Q�O�O�T�|�T�S�V�V�P�j���啝�Ɂu�R����P�v�Ɓu�m�n���팸�v�̗����������ł���D
�ꂽ����������B���̗��R�ɂ��ẮA�C���x�~�́A�R��팸�ƔA�fSCR��NO���팸���̌���ɗL�����I�̃y�[�W
���䗗�������������B
�@�܂��A�o�l�팸�̂��߂ɑ�������Ă���c�o�e���u�ł́A�|�X�g���˂܂��͂g�b�r�C�Ǖ��˂ɂ��p�ɂ�DPF�Đ��ɂ�
���ĔR������������錇�ׂ�����Ă���B������|�X�g���˂܂��͂g�b�r�C�Ǖ��˂�p���邱�Ɩ���DPF�̍Đ�����
�\�ɂ���Z�p���㏈������V�X�e���i�������J2005-69238�j�ł���B���̓����Z�p�́A�R���Q����邱�ƂȂ�DPF
�̍Đ����\�ɂ��邽�߁A����̑��s�R���傫���팸���邱�Ƃ��\�ƂȂ�̂ł���B����ɂ��ẮA�R�����
�|�X�g���˂��~�߁A�C���x�~��DPF���Đ�����V�Z�p�ɏڏq���Ă���̂ŁA�䗗�������������B�܂��A�f�B�[�[���̋C
���x�~�́A�R�[���h�X�^�[�g��NO���팸�ɂ��L�����I�ɏڏq���Ă���悤�ɁA�Q�^�[�{�������C���x�~�G���W���i������
�J2005-54771�j�̓����Z�p�́AJE�O�T���[�h�̃R�[���h���[�h�������ɂ�����NO���̔r�o���팸���邱�Ƃ̉\�ł���B
���ĔR������������錇�ׂ�����Ă���B������|�X�g���˂܂��͂g�b�r�C�Ǖ��˂�p���邱�Ɩ���DPF�̍Đ�����
�\�ɂ���Z�p���㏈������V�X�e���i�������J2005-69238�j�ł���B���̓����Z�p�́A�R���Q����邱�ƂȂ�DPF
�̍Đ����\�ɂ��邽�߁A����̑��s�R���傫���팸���邱�Ƃ��\�ƂȂ�̂ł���B����ɂ��ẮA�R�����
�|�X�g���˂��~�߁A�C���x�~��DPF���Đ�����V�Z�p�ɏڏq���Ă���̂ŁA�䗗�������������B�܂��A�f�B�[�[���̋C
���x�~�́A�R�[���h�X�^�[�g��NO���팸�ɂ��L�����I�ɏڏq���Ă���悤�ɁA�Q�^�[�{�������C���x�~�G���W���i������
�J2005-54771�j�̓����Z�p�́AJE�O�T���[�h�̃R�[���h���[�h�������ɂ�����NO���̔r�o���팸���邱�Ƃ̉\�ł���B
�@�����āA����A��^�g���b�N�̒E�Ζ���CO�Q�팸���Ɏ����������߂ɂ͔@���Ȃ�{���{�����ׂ�����
�����A�u�Ջ��l�v�́A�V�R�K�X�ƌy���p����u�c�c�e��^�g���b�N�v���J�����A�L�����y�����邱�Ɓv�Ǝ��M
�������ē��������B�䂪���ł͗]��m���Ă��Ȃ����A���̒��ɂ��f�B�[�[���ɔ�ׂP�T���̂b�n�Q�팸���\�Ȃc�c�e
�G���W���Ɖ]���G���W���Z�p�����ɑ��݂��A����DDF�G���W���𓋍ڂ���DDF�^�]�ƃf�B�[�[���^�]�̑I�����\�Ȃc�c
�e��^�g���b�N �͓V�R�K�X�̕⋋���ł��Ȃ��n��ł͌y���݂̂ʼn^�s�����ĉݕ��A�����s�����Ƃ��ł��邱�Ƃ͊��ɒm
���Ă���B�����āA2011�N8������X�E�F�[�f���̃{���{�E�g���b�N�X�́A����DDF�G���W���𓋍ڂ�����^DDF�g���b�N�E
�g���N�^�̎s�̂��J�n�����Ƃ̂��Ƃł���B���ɁA���̂c�c�e�^�]�ƃf�B�[�[���^�]�̑I�����\�ȃf���A���^�]���[�h��
�@�\�������DDF��^�g���b�N����{�S���ɕ��y�����邱�Ƃɂ��A�C��ϓ��g�g���Ɋ�Â������s�c�菑�̂b�n�Q
�팸�Ɋւ����^�g���b�N����ł̖ڕW��e�ՂɒB�����邱�Ƃ��\����A�E�Ζ��ɂ��Ζ��G�l���M�[�ɑ����
�@�Ǘ����[���ł��A�܂��R���ɂ͈����ȓV�R�K�X�����p�ł���Ɖ]���A��^�g���b�N�B�g���N�^�̕���ɂ��������I��
�i���Ɖ��P�������炷���Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��ƍl���Ă���B
�����A�u�Ջ��l�v�́A�V�R�K�X�ƌy���p����u�c�c�e��^�g���b�N�v���J�����A�L�����y�����邱�Ɓv�Ǝ��M
�������ē��������B�䂪���ł͗]��m���Ă��Ȃ����A���̒��ɂ��f�B�[�[���ɔ�ׂP�T���̂b�n�Q�팸���\�Ȃc�c�e
�G���W���Ɖ]���G���W���Z�p�����ɑ��݂��A����DDF�G���W���𓋍ڂ���DDF�^�]�ƃf�B�[�[���^�]�̑I�����\�Ȃc�c
�e��^�g���b�N �͓V�R�K�X�̕⋋���ł��Ȃ��n��ł͌y���݂̂ʼn^�s�����ĉݕ��A�����s�����Ƃ��ł��邱�Ƃ͊��ɒm
���Ă���B�����āA2011�N8������X�E�F�[�f���̃{���{�E�g���b�N�X�́A����DDF�G���W���𓋍ڂ�����^DDF�g���b�N�E
�g���N�^�̎s�̂��J�n�����Ƃ̂��Ƃł���B���ɁA���̂c�c�e�^�]�ƃf�B�[�[���^�]�̑I�����\�ȃf���A���^�]���[�h��
�@�\�������DDF��^�g���b�N����{�S���ɕ��y�����邱�Ƃɂ��A�C��ϓ��g�g���Ɋ�Â������s�c�菑�̂b�n�Q
�팸�Ɋւ����^�g���b�N����ł̖ڕW��e�ՂɒB�����邱�Ƃ��\����A�E�Ζ��ɂ��Ζ��G�l���M�[�ɑ����
�@�Ǘ����[���ł��A�܂��R���ɂ͈����ȓV�R�K�X�����p�ł���Ɖ]���A��^�g���b�N�B�g���N�^�̕���ɂ��������I��
�i���Ɖ��P�������炷���Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��ƍl���Ă���B
�S�D���݂̑�^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W���ɂ�����d�v�ȉۑ�Ƃ��̉�����i�܂Ƃ߁j
�@����܂ł̐���������Ղ����邽�߁A���݂̑�^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W���������Ă���d�v�ȉۑ�����A��
�ꂼ��̉ۑ�̉����ɗL���ȕM�Ғ�Ă̂R���̓����Z�p[�i�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�A�㏈������
�V�X�e���i�������J2005-69238�j�A������DDF�G���W���i�������J2008-51121�j]�ނ��A�e�����Z�p�ɂ���Ă��ꂼ
��̉ۑ肪�����ł���Z�p�I�ȍ�p�E���ʂ���������y�[�W���ȉ��̕\�P�ɂ܂Ƃ߂��B�i�����������N���b�N�ɂ��A��
�̃y�[�W��\���j
�ꂼ��̉ۑ�̉����ɗL���ȕM�Ғ�Ă̂R���̓����Z�p[�i�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�A�㏈������
�V�X�e���i�������J2005-69238�j�A������DDF�G���W���i�������J2008-51121�j]�ނ��A�e�����Z�p�ɂ���Ă��ꂼ
��̉ۑ肪�����ł���Z�p�I�ȍ�p�E���ʂ���������y�[�W���ȉ��̕\�P�ɂ܂Ƃ߂��B�i�����������N���b�N�ɂ��A��
�̃y�[�W��\���j
| |
|
|
|
| |
�E�g���b�N�̎����s�ő��p����
��G���W���������^�]���� ������R��팸�ɂ��A �T�`�P�O���̏d�ʎԃ��[�h�R ��l������ �i�e�g���b�N���[�J�́A�|�X�g�V �����K���r�o�K�X�K���K�� �̑�^�g���b�N�E�g���b�N�̑S�� ���2015�N�x�d�ʎԔR��� ���ɒB��������ۑ�������j |
2005-54771�j |
�E�C���x�~�G���W���ɂ���^�g���b�N�̒�R
� �E�C���x�~�́A�R��팸�ƔA�fSCR��NO���� �����̌���ɗL�����I �E���^�n�C�u���b�h �g���b�N�̓n�C�u���b�h��p �Ԃ̂悤�ȔR����P������ �E�C���x�~��DPF�̎��ȍĐ��𑣐i����V�Z �p �E���{�͑�^�g���b�N�̐V���Ȓ�R��E��r�o �K�X��𑁊��ɐݒ肹��I �E�����߳��ނ��ި���ٔR���啝�ɉ��P �ł���Ƃ̎咣�́A��肾�I �E��Ƃ̕i�����^����^�g���b�N�̔R����P�� ���\�܂����Ȑ�` |
| |
�E�y����R���Ƃ���f�B�[�[��
�G���W���̔R��팸�ɂ��A �T�`�P�O����CO�Q���팸 �E�V�R�K�X�p����DDF�G�� �W���̗̍p�ɂ��A �P�T����CO�Q���팸 |
2005-54771�j 2008-51121�j |
�E�C���x�~�G���W���ɂ���^�g���b�N�̒�R
� �E�C���x�~�́A�R��팸�ƔA�fSCR��NO���� �����̌���ɗL�����I �E�C���x�~��DPF�̎��ȍĐ��𑣐i����V�Z �p �E�f�B�[�[���ɔ�ׂP�T���̂b�n�Q�팸���\ �Ȃc�c�e�G���W�� �EDDF�^�]�ƃf�B�[�[���^�]�̑I�����\�� �c�c�e��^�g���b�N �E�V�R�K�X���獇����DME��GTL�́A�f�B�[�[ ���g���b�N�̔R���ɕs�K ��^�g���b�N�̂b�n2�팸�ƒE�Ζ����������� �Z�p�́A�����ɕs�����H �E���{�͑�^�g���b�N�̐V���Ȓ�R��E��r�o �K�X��𑁊��ɐݒ肹��I �E���{�̒E�Ζ��E��Y�f���ɖ����Ȍ������� �{�����ʈ��S�������� �E��Ƃ̕i�����^����^�g���b�N�̔R����P�� ���\�܂����Ȑ�` �E�o�C�I�}�X�R����DME�ɂ�鎩���Ԃ̒�Y �f�E�E�Ζ��́A�s�\���I |
| �팸�j |
�E�|�X�g���˂ɂ��DPF�Đ���
����Đ�����DPF���u���R�� �Q��̖h�~�ƁA�y���ɂ�� �G���W���I�C���̊�ߖh�~ �E�g�b�r�C�Ǖ��˂ɂ��DPF�� ���ɂ���Đ�����DPF���u�� �R���Q��̖h�~ |
2005-54771�j �J2005-69238�j |
�E�C���x�~�́A�R��팸�ƔA�fSCR��NO����
�����̌���ɗL�����I �E�C���x�~��DPF�̎��ȍĐ��𑣐i����V�Z �p |
| |
�E�ᕉ���ɂm�n���W�G�}��
��������}���Ăm�n���팸�� �i���A0.23 g/kWh�iWHTC �r�o�K�X�����@�j��B�� |
2005-54771�j �J2005-69238�j |
|
| |
�E�f�B�[�[���g���b�N��DDF�G
���W�����̗p���邱�Ƃɂ� ��A50���̒E�Ζ������� (�Ζ��s�[�N��̌y���s���� ���O��) (������C���h�̌o�ϔ��W�ɂ� ��̏����̌y���̕s���ƍ��� �̐�s��) |
2008-51121�j |
�E�V�R�K�X���獇����DME��GTL�́A�f�B�[�[
���g���b�N�̔R���ɕs�K �E�f�B�[�[���ɔ�ׂP�T���̂b�n�Q�팸���\ �Ȃc�c�e�G���W�� �EDDF�^�]�ƃf�B�[�[���^�]�̑I�����\�� �c�c�e��^�g���b�N ��^�g���b�N�̂b�n2�팸�ƒE�Ζ����������� �Z�p�́A�����ɕs�����H �y�������G�l���M�[�������R�O�������c�l �d�𐄏�����@�B�w��̋^�� �E�o�C�I�}�X�R����DME�ɂ�鎩���Ԃ̒�Y �f�E�E�Ζ��́A�s�\���I |
�@���݂̑�^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W���ɂ����āA���}�ɉ�����}��ׂ��d�v�ȉۑ�́A�\�P�Ɏ������悤���u�R��
���P�v�A�uCO2�팸�v�A�u�ᕉ���ɂ�����A�fSCR�G�}�̍������ɂ��m�n���̍팸�v�A�u�|�X�g���˂܂��͂g�b
�r�C�Ǖ��˂��s�v��DPF���u�̎��ȍĐ��̑��i�v����сu�E�Ζ��v�ł���ƍl������B�����āA�M�҂���Ă���
����R���̓����Z�p�����p�����邱�Ƃɂ��A�\�P�Ɏ�������^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W���̏d�v�ۑ�̑S�Ă�e��
�ɉ������邱�Ƃ��\�ɂȂ�̂��B
���P�v�A�uCO2�팸�v�A�u�ᕉ���ɂ�����A�fSCR�G�}�̍������ɂ��m�n���̍팸�v�A�u�|�X�g���˂܂��͂g�b
�r�C�Ǖ��˂��s�v��DPF���u�̎��ȍĐ��̑��i�v����сu�E�Ζ��v�ł���ƍl������B�����āA�M�҂���Ă���
����R���̓����Z�p�����p�����邱�Ƃɂ��A�\�P�Ɏ�������^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W���̏d�v�ۑ�̑S�Ă�e��
�ɉ������邱�Ƃ��\�ɂȂ�̂��B
�@����A�ŋ߂̎����ԋZ�p�����{�@�B�w��̍u�����_���W���ɂ����ẮA�\�P�Ɏ�������^�g���b�N�p�f�B�[�[
���G���W���̉ۑ������ړI�Ƃ��������̘_�������\����Ă��邪�A�����̘_���ɂ͑�^�g���b�N�p�f�B�[�[���G��
�W���̕\�P�̏d�v�ۑ���\���ɉ��P�ł���Z�p���c�O�Ȃ��Ƃɖw��NjL�ڂ���Ă��Ȃ��悤�ł���B�܂��A�����ԋZ�p
��́u�Q�O�P�O�N�l�Ƃ���܂̃e�N�m���W�[�W�v(2010�N5��19�`21�j�Ő��E�I�Ȍ����@�ւł���AVL�i�I�[�X�g���A�j�̃w��
���[�g�E���X�g����u�����A�f�B�[�[���G���W���̔R�����ɂ́A�u�R���s���[�^�v�Z�p�����܂��g���v�Ƃ̐�����lj�
���āu�t���N�V�������X�i���C�����j�̒ጸ�v�Ɓu�V�����_�[���̔R�ĉ��P�v�̃G���W���H�w�̋��ȏ��ɋL�ڂ���Ă�����
�̋Z�p���ڂɂ����25���̌������オ�\�Ɣ��\���Ă��邪�A��̓I�ȋZ�p���e�͉��������Ă��Ȃ��悤���B����́A
���E�I�Ȍ����@�ւ�AVL����̓I�ȋZ�p���e�������������ɁA�f�B�[�[���G���W���̌�������̒P�Ȃ��]���q�ׂ�
����ɉ߂��Ȃ��̂��BAVL�͑S���₵�����e�̍u�����s�������̂��B
���G���W���̉ۑ������ړI�Ƃ��������̘_�������\����Ă��邪�A�����̘_���ɂ͑�^�g���b�N�p�f�B�[�[���G��
�W���̕\�P�̏d�v�ۑ���\���ɉ��P�ł���Z�p���c�O�Ȃ��Ƃɖw��NjL�ڂ���Ă��Ȃ��悤�ł���B�܂��A�����ԋZ�p
��́u�Q�O�P�O�N�l�Ƃ���܂̃e�N�m���W�[�W�v(2010�N5��19�`21�j�Ő��E�I�Ȍ����@�ւł���AVL�i�I�[�X�g���A�j�̃w��
���[�g�E���X�g����u�����A�f�B�[�[���G���W���̔R�����ɂ́A�u�R���s���[�^�v�Z�p�����܂��g���v�Ƃ̐�����lj�
���āu�t���N�V�������X�i���C�����j�̒ጸ�v�Ɓu�V�����_�[���̔R�ĉ��P�v�̃G���W���H�w�̋��ȏ��ɋL�ڂ���Ă�����
�̋Z�p���ڂɂ����25���̌������オ�\�Ɣ��\���Ă��邪�A��̓I�ȋZ�p���e�͉��������Ă��Ȃ��悤���B����́A
���E�I�Ȍ����@�ւ�AVL����̓I�ȋZ�p���e�������������ɁA�f�B�[�[���G���W���̌�������̒P�Ȃ��]���q�ׂ�
����ɉ߂��Ȃ��̂��BAVL�͑S���₵�����e�̍u�����s�������̂��B
�@�܂��AAVL�́A��̓I�ȃf�B�[�[���̌�������̕��@�Ƃ��āu�r�C�M��d�C�G�l���M�[�ɕς���R���o�[�^�[��t����
���ƂŁA6 - 7���قnj�������悹�ł���v�Ɣ��\���Ă��邪�A����̓f�B�[�[���G���W���̔r�C�K�X�̔M�G�l���M�[����
���L���T�C�N���A�r�C�K�X�^�[�r���܂��̓X�^�[�����O�G���W�����œ��͂ɕϊ����A���̓��͂Ŕ��d�@���쓮���ēd�C�G
�l���M�[��������鑕�u��t���������̂ƍl������B���́u�r�C�M��d�C�G�l���M�[�ɕς���R���o�[�^�[�v�́A�Η�
���d�����^�D���ł̓f�B�[�[���G���W������i�o�͂ʼn^�]����邽�߂ɏ�ɍ����̔r�C�K�X��r�o���邽�߂ɍ�
�������ʼnғ��ł��邽�߁A���ɉΗ͔��d�����^�D���ɂ����čL�����y���Ă��鑕�u�ł���B�������A��^�f�B�[�[��
�g���b�N�͏�ɃG���W���o�͂��ϓ������ɕ������ׂ̉^�]�ŒႢ�r�C�K�X���x�ƂȂ邱�Ƃ��������߁A��^�g���b�N
�Ɂu�r�C�M��d�C�G�l���M�[�ɕς���R���o�[�^�[�v�𓋍ڂ����ꍇ�ɂ͌���������������Ă��܂����ƂɂȂ�B���̂�
�߁A��^�g���b�N�ɂ��̃R���o�[�^�[�𓋍ڂ��Ă��\���ȔR��̌���͓���B���������āAAVL�����̃R���o�[�^�[��
���ڂɂ���đ�^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W���̌�����6 - 7���قlj��P�ł���Ƃ̍u���ł̔��\�́A�傫�Ȍ��ł�
�Ȃ����낤���B���݂ɁA�r�C�K�X�̔r�C�M��r�C�K�X�^�[�r���œ��͂Ƃ��Ď��o���^�[�{�R���p�E���h�́A�����߳
��ނ��ި���ٔR���啝�ɉ��P�ł���Ƃ̎咣�́A��肾�I�ɏڏq���Ă���悤�ɁA�C�����̍ō����͂����߂邱�Ƃ�
���G���W���̍��o�͉����\�ȋZ�p�ł���A�R�����̋@�\�����Ȃ��A�d�ʎԃ��[�h�R����P�������������P�ł��Ȃ�
�悤�ȔR����P�ɕs�K�ȋZ�p�ł���B�@
���ƂŁA6 - 7���قnj�������悹�ł���v�Ɣ��\���Ă��邪�A����̓f�B�[�[���G���W���̔r�C�K�X�̔M�G�l���M�[����
���L���T�C�N���A�r�C�K�X�^�[�r���܂��̓X�^�[�����O�G���W�����œ��͂ɕϊ����A���̓��͂Ŕ��d�@���쓮���ēd�C�G
�l���M�[��������鑕�u��t���������̂ƍl������B���́u�r�C�M��d�C�G�l���M�[�ɕς���R���o�[�^�[�v�́A�Η�
���d�����^�D���ł̓f�B�[�[���G���W������i�o�͂ʼn^�]����邽�߂ɏ�ɍ����̔r�C�K�X��r�o���邽�߂ɍ�
�������ʼnғ��ł��邽�߁A���ɉΗ͔��d�����^�D���ɂ����čL�����y���Ă��鑕�u�ł���B�������A��^�f�B�[�[��
�g���b�N�͏�ɃG���W���o�͂��ϓ������ɕ������ׂ̉^�]�ŒႢ�r�C�K�X���x�ƂȂ邱�Ƃ��������߁A��^�g���b�N
�Ɂu�r�C�M��d�C�G�l���M�[�ɕς���R���o�[�^�[�v�𓋍ڂ����ꍇ�ɂ͌���������������Ă��܂����ƂɂȂ�B���̂�
�߁A��^�g���b�N�ɂ��̃R���o�[�^�[�𓋍ڂ��Ă��\���ȔR��̌���͓���B���������āAAVL�����̃R���o�[�^�[��
���ڂɂ���đ�^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W���̌�����6 - 7���قlj��P�ł���Ƃ̍u���ł̔��\�́A�傫�Ȍ��ł�
�Ȃ����낤���B���݂ɁA�r�C�K�X�̔r�C�M��r�C�K�X�^�[�r���œ��͂Ƃ��Ď��o���^�[�{�R���p�E���h�́A�����߳
��ނ��ި���ٔR���啝�ɉ��P�ł���Ƃ̎咣�́A��肾�I�ɏڏq���Ă���悤�ɁA�C�����̍ō����͂����߂邱�Ƃ�
���G���W���̍��o�͉����\�ȋZ�p�ł���A�R�����̋@�\�����Ȃ��A�d�ʎԃ��[�h�R����P�������������P�ł��Ȃ�
�悤�ȔR����P�ɕs�K�ȋZ�p�ł���B�@
�@����AVL����������u�r�C�M��d�C�G�l���M�[�ɕς���R���o�[�^�[�v�́A��^���b�N�̑��s�ő��p�����f�B�[�[��
�f�B�[�[���G���W���̕������^�]���ɂ͔r�C�K�X���x���Ⴍ�A�r�C�K�X�̔M��d�C�G�l���M�[�ɕς���ۂ̌�����
��錇�_������B���̌��_�i�����ׁj�����P���邽�߂ɂ́A�f�B�[�[���G���W���̕������^�]���̔r�C�K�X���x����
��������V���ȋZ�p��lj����邱�Ƃ��K�v�ł���B���������āAAVL�̒�Ă̂悤�ɁA�u�r�C�M��d�C�G�l���M�[�ɕς�
��R���o�[�^�[�v��P�ɑ�^�g���b�N�ɓ��ڂ��������ł́A��^�g���b�N�̏\���ȔR�����͖]�߂Ȃ��̂ł���B����
AVL����^�g���b�N�̔R�����̂��߂Ɂu�r�C�M��d�C�G�l���M�[�ɕς���R���o�[�^�[�v���^�g���b�N�ɓ��ڂ��邱
�Ƃ��Ă������̂ł���A��^���b�N�̑��s�ő��p�����f�B�[�[���f�B�[�[���G���W���̕������^�]���ɔr�C�K
�X���x������������Z�p���ŏ��ɒ�Ă��ׂ��ł͂Ȃ����ƍl������B�f�B�[�[���G���W���̕������^�]���ɔr�C
�K�X���x���������ł���Z�p���������Ȃ��Łu�r�C�M��d�C�G�l���M�[�ɕς���R���o�[�^�[�v���^�g���b�N�ɓ�
�ڂ���Ƃ�AVL�̍u���ł̒�ẮA�u�Ջ��l�v�ɂ͋��̍����Ǝv����̂��BAVL�����̂悤�ȍu�����\�����Ă���Ƃ���
������ƁA�f�B�[�[���G���W���̔R�����ɂ��Ă�AVL���Z�p�A�C�f�A���͊����A�傫�ȕǂɓ˂��������Ă���悤��
�l������B�����āA���̂悤��AVL�ɑ����̃g���b�N���[�J����^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W���̔R�����̃R���T��
�e�B���O��O���������ɎĂ��錻����l����ƁA����̑�^�g���b�N�ɂ͔R�����ɑ傫�Ȋ��҂��ł��Ȃ��ƍl����
�̂��Ó��ł͂Ȃ����낤���B
�f�B�[�[���G���W���̕������^�]���ɂ͔r�C�K�X���x���Ⴍ�A�r�C�K�X�̔M��d�C�G�l���M�[�ɕς���ۂ̌�����
��錇�_������B���̌��_�i�����ׁj�����P���邽�߂ɂ́A�f�B�[�[���G���W���̕������^�]���̔r�C�K�X���x����
��������V���ȋZ�p��lj����邱�Ƃ��K�v�ł���B���������āAAVL�̒�Ă̂悤�ɁA�u�r�C�M��d�C�G�l���M�[�ɕς�
��R���o�[�^�[�v��P�ɑ�^�g���b�N�ɓ��ڂ��������ł́A��^�g���b�N�̏\���ȔR�����͖]�߂Ȃ��̂ł���B����
AVL����^�g���b�N�̔R�����̂��߂Ɂu�r�C�M��d�C�G�l���M�[�ɕς���R���o�[�^�[�v���^�g���b�N�ɓ��ڂ��邱
�Ƃ��Ă������̂ł���A��^���b�N�̑��s�ő��p�����f�B�[�[���f�B�[�[���G���W���̕������^�]���ɔr�C�K
�X���x������������Z�p���ŏ��ɒ�Ă��ׂ��ł͂Ȃ����ƍl������B�f�B�[�[���G���W���̕������^�]���ɔr�C
�K�X���x���������ł���Z�p���������Ȃ��Łu�r�C�M��d�C�G�l���M�[�ɕς���R���o�[�^�[�v���^�g���b�N�ɓ�
�ڂ���Ƃ�AVL�̍u���ł̒�ẮA�u�Ջ��l�v�ɂ͋��̍����Ǝv����̂��BAVL�����̂悤�ȍu�����\�����Ă���Ƃ���
������ƁA�f�B�[�[���G���W���̔R�����ɂ��Ă�AVL���Z�p�A�C�f�A���͊����A�傫�ȕǂɓ˂��������Ă���悤��
�l������B�����āA���̂悤��AVL�ɑ����̃g���b�N���[�J����^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W���̔R�����̃R���T��
�e�B���O��O���������ɎĂ��錻����l����ƁA����̑�^�g���b�N�ɂ͔R�����ɑ傫�Ȋ��҂��ł��Ȃ��ƍl����
�̂��Ó��ł͂Ȃ����낤���B
�@����AVL�����́u�r�C�M��d�C�G�l���M�[�ɕς���R���o�[�^�[�v����^�g���b�N�p�Ƃ��Ď��p�ɑς����鍂��������
�ғ��ł���悤�ɂ��邽�߂ɂ́A�C���x�~�́A�f�B�[�[���r�C�K�X�̃G�l���M�[���u�̌����������ɏڏq���Ă�
��悤�ɁA��^���b�N�̑��s�ő��p�����f�B�[�[���f�B�[�[���G���W���̕������^�]���ł̔r�C�K�X���x�̍�����
��}�邱�Ƃ��K�v�ł���B���̕��@�Ƃ��āA���̃R���o�[�^���̗p����ꍇ�ɂ́A�u�Ջ��l�v��Ă��C���x�~�G���W���i��
�����J2005-54771�j�̓����Z�p��p���邱���K�{�ƍl���Ă���B�t�Ȍ�����������AAVL�����̔r�C�M��d�C�G�l
���M�[�ɕς���R���o�[�^�[�̃V�X�e���Ɂu�Ջ��l�v��Ă��C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p��p
���Ȃ��ꍇ�ɂ́A�����̌��オ�]�߂Ȃ��̂ł���B���̂��߁AAVL����Ă���u�r�C�M��d�C�G�l���M�[�ɕς���R��
�o�[�^�[�v�̃V�X�e���ł́A�d�ʎԃ��[�h�R��̌��オ�\���łȂ��A���p���Ɍ������Z�p�ƍl������B�f�B�[�[���G��
�W���̔M�����̌����}��Z�p�Ƃ��āAAVL�����́u�R���o�[�^�[�̃V�X�e�����Ă������̂ł���A�f�B�[�[���G��
�W���̕������^�]���̔r�C�K�X���x������������Z�p�ł���u�Ջ��l�v��Ă��C���x�~�G���W���i�������J2005-
54771�j�̓����Z�p�̗̍p�������ɒ�Ă��ׂ��ł���B
�ғ��ł���悤�ɂ��邽�߂ɂ́A�C���x�~�́A�f�B�[�[���r�C�K�X�̃G�l���M�[���u�̌����������ɏڏq���Ă�
��悤�ɁA��^���b�N�̑��s�ő��p�����f�B�[�[���f�B�[�[���G���W���̕������^�]���ł̔r�C�K�X���x�̍�����
��}�邱�Ƃ��K�v�ł���B���̕��@�Ƃ��āA���̃R���o�[�^���̗p����ꍇ�ɂ́A�u�Ջ��l�v��Ă��C���x�~�G���W���i��
�����J2005-54771�j�̓����Z�p��p���邱���K�{�ƍl���Ă���B�t�Ȍ�����������AAVL�����̔r�C�M��d�C�G�l
���M�[�ɕς���R���o�[�^�[�̃V�X�e���Ɂu�Ջ��l�v��Ă��C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p��p
���Ȃ��ꍇ�ɂ́A�����̌��オ�]�߂Ȃ��̂ł���B���̂��߁AAVL����Ă���u�r�C�M��d�C�G�l���M�[�ɕς���R��
�o�[�^�[�v�̃V�X�e���ł́A�d�ʎԃ��[�h�R��̌��オ�\���łȂ��A���p���Ɍ������Z�p�ƍl������B�f�B�[�[���G��
�W���̔M�����̌����}��Z�p�Ƃ��āAAVL�����́u�R���o�[�^�[�̃V�X�e�����Ă������̂ł���A�f�B�[�[���G��
�W���̕������^�]���̔r�C�K�X���x������������Z�p�ł���u�Ջ��l�v��Ă��C���x�~�G���W���i�������J2005-
54771�j�̓����Z�p�̗̍p�������ɒ�Ă��ׂ��ł���B
�@���݂ɁAAVL�́u�r�C�M��d�C�G�l���M�[�ɕς���R���o�[�^�[�v�ł̓f�B�[�[���G���W���̔r�C�K�X����G�l���M�[
���������6 - 7���i�d�ʎԃ��[�h�R��H�j�̌�������悹����Ƃ̔��\���s���Ă��邪�A����AVL��ẴR���o�[�^�[
���ғ������ۂ̌����͋ɂ߂ĒႢ�Ɨ\�z����邽�߁A���̃R���o�[�^�[���^�g���b�N�ɓ��ڂ����ꍇ�ɂ́A���ۂɑ�
�^�g���b�N�̏d�ʎԃ��[�h�R���6 - 7���قǂ̔R�����悹���邱�Ƃ͋ɂ߂ē�����̂ƍl������B����ɂ���
�́AAVL�͖��ӔC�Ȍ�������̐��l�\�����Ă���̂ł͂Ȃ����Ɗ����Ă���B
���������6 - 7���i�d�ʎԃ��[�h�R��H�j�̌�������悹����Ƃ̔��\���s���Ă��邪�A����AVL��ẴR���o�[�^�[
���ғ������ۂ̌����͋ɂ߂ĒႢ�Ɨ\�z����邽�߁A���̃R���o�[�^�[���^�g���b�N�ɓ��ڂ����ꍇ�ɂ́A���ۂɑ�
�^�g���b�N�̏d�ʎԃ��[�h�R���6 - 7���قǂ̔R�����悹���邱�Ƃ͋ɂ߂ē�����̂ƍl������B����ɂ���
�́AAVL�͖��ӔC�Ȍ�������̐��l�\�����Ă���̂ł͂Ȃ����Ɗ����Ă���B
�@�܂��AAVL�����̍u���Œ�Ă��Ă��������̌�������̋Z�p���G���W���_�E���T�C�W���O�ł���B���̃G���W���_
�E���T�C�W���O�́A�Â�����ǂ��m��ꂽ�R�����̋Z�p�ł���A��^�f�B�[�[���g���b�N�̃��[�J������܂ŋ����ĊJ��
�����{���Ă����Z�p�ł��邽�߁A�Z�p�I�ɂ͉��̖ڐV�����������R�����̎�@�ł���B
�E���T�C�W���O�́A�Â�����ǂ��m��ꂽ�R�����̋Z�p�ł���A��^�f�B�[�[���g���b�N�̃��[�J������܂ŋ����ĊJ��
�����{���Ă����Z�p�ł��邽�߁A�Z�p�I�ɂ͉��̖ڐV�����������R�����̎�@�ł���B
�@�ȏ�̂悤�ɁA���E�I�Ȍ����@�ւł���AVL��2010�N�T���̍u���̒�ẮA�f�B�[�[���G���W���̌�������ɂ�
�Ă͌ÓT�I�Ȋ��m�̋Z�p�Ɍ����Ă���A�Z�p�I�ȖڐV�����͌���ꂸ�A��^�g���b�N�̔R�����ɑ��}�ɍ̗p�ł���
�悤�ȐV�����Z�p�������Ă��Ă��Ȃ��悤���B���̂��Ƃ́A���E�I�Ȍ����@�ւł���AVL�ł��A�f�B�[�[���G���W��
�̔R�����ɗL���ȋZ�p����Ăł��Ȃ����Ƃ������Ă���؋��Ƃ��l������B���̂悤�Ȃ��Ƃ���A���E�̑�w�E����
�@�ցE�g���b�N���[�J���̊w�ҁE���Ƃ̐l�B�ł��A�\�P�Ɏ�������^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W���Ɋւ���d�v�ۑ��
�����̕��@�́A�����ɉ������o���Ă��Ȃ��ƌ����Ă��ߌ��ł͂Ȃ��悤�ɍl������B����ɂ�������炸�A�w��ǂ�
�w�ҁE���Ƃ́A�M�Ғ�Ă̂R���̓����Z�p�����S�ɖ������Ă��邱�Ƃ́A�u�Ջ��l�v�ɂ͗����ɋꂵ�ނƂ���ł���B
�Ă͌ÓT�I�Ȋ��m�̋Z�p�Ɍ����Ă���A�Z�p�I�ȖڐV�����͌���ꂸ�A��^�g���b�N�̔R�����ɑ��}�ɍ̗p�ł���
�悤�ȐV�����Z�p�������Ă��Ă��Ȃ��悤���B���̂��Ƃ́A���E�I�Ȍ����@�ւł���AVL�ł��A�f�B�[�[���G���W��
�̔R�����ɗL���ȋZ�p����Ăł��Ȃ����Ƃ������Ă���؋��Ƃ��l������B���̂悤�Ȃ��Ƃ���A���E�̑�w�E����
�@�ցE�g���b�N���[�J���̊w�ҁE���Ƃ̐l�B�ł��A�\�P�Ɏ�������^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W���Ɋւ���d�v�ۑ��
�����̕��@�́A�����ɉ������o���Ă��Ȃ��ƌ����Ă��ߌ��ł͂Ȃ��悤�ɍl������B����ɂ�������炸�A�w��ǂ�
�w�ҁE���Ƃ́A�M�Ғ�Ă̂R���̓����Z�p�����S�ɖ������Ă��邱�Ƃ́A�u�Ջ��l�v�ɂ͗����ɋꂵ�ނƂ���ł���B
�@
�@���������āA�ŋ߂̊w�ҁE���Ƃ́A�u�Z�p�̐^����Njy���ĎЉ�̔��W�ɍv������v�Ɖ]�������ҁE�Z�p�҂Ƃ��Ă�
�{���̎g���E�ǐS�����S�ɖY��Ă��܂��Ă���悤�Ɏv����̂��B���G���W���Z�p���́u�Ջ��l�v�Ƃ��Ă͎₵�����肾�B
�����āA�ނ�͐V���Ȍ����J���Ɏ��g�ޔM�ӂ�r�����Ă���悤�ł���A����܂Ŏ��{���Ă��������J�����㐶�厖
�Ƀ_���_���ƑĐ��Ōp�����Ă��邾���ł͂Ȃ����낤���B���̂悤�Ȏp���Ō����J���Ɏ��g��ł��ẮA���݂̑�^�g
���b�N�p�f�B�[�[���G���W���̉ۑ�����ɉ���v���ł��Ȃ����Ƃ͖��炩�ł���A���e�̖R�����_���������\�ł���
���Ȃ����Ƃ́A���R�̐���s���ƍl������B
�{���̎g���E�ǐS�����S�ɖY��Ă��܂��Ă���悤�Ɏv����̂��B���G���W���Z�p���́u�Ջ��l�v�Ƃ��Ă͎₵�����肾�B
�����āA�ނ�͐V���Ȍ����J���Ɏ��g�ޔM�ӂ�r�����Ă���悤�ł���A����܂Ŏ��{���Ă��������J�����㐶�厖
�Ƀ_���_���ƑĐ��Ōp�����Ă��邾���ł͂Ȃ����낤���B���̂悤�Ȏp���Ō����J���Ɏ��g��ł��ẮA���݂̑�^�g
���b�N�p�f�B�[�[���G���W���̉ۑ�����ɉ���v���ł��Ȃ����Ƃ͖��炩�ł���A���e�̖R�����_���������\�ł���
���Ȃ����Ƃ́A���R�̐���s���ƍl������B
�@���̂悤�ɁA����̑�w�E�����@�ցE�g���b�N���[�J�́A��^�g���b�N�ɂ��ĔR�������܂ރf�B�[�[���G���W���̏d
�v�ȉۑ�����ɖڗ������v���ł���_�������\�ł��Ă��Ȃ��悤���B���̂��߁A����̑�w�E�����@�ցE�g���b�N���[�J
�ɂ����錤���J���̌��x���ł́A�߂������ɑ�^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W���̏d�v�ȉۑ��S�ĉ������邱��
���ɂ߂č���Ȃ悤�Ɏv����B�����āA���݂̏ł́A�g���b�N���[�J�́A���ɍ��y��ʏȂ��Q�O�P�T�N�x�d�ʎԔR
������T�����x�̋��������������ꍇ�A���̂Ƃ���e�g���b�N���[�J�ɂ͂��̔R���ɓK���ł���\�͂��Ȃ���
�߂Ƀg���b�N�̐��Y���ł��Ȃ��Ȃ邱�Ƃ���A���y��ʏȂɂQ�O�P�T�N�x�d�ʎԔR���̋����̒x���������v�]������
����Ȃ��Ɛ��������B
�v�ȉۑ�����ɖڗ������v���ł���_�������\�ł��Ă��Ȃ��悤���B���̂��߁A����̑�w�E�����@�ցE�g���b�N���[�J
�ɂ����錤���J���̌��x���ł́A�߂������ɑ�^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W���̏d�v�ȉۑ��S�ĉ������邱��
���ɂ߂č���Ȃ悤�Ɏv����B�����āA���݂̏ł́A�g���b�N���[�J�́A���ɍ��y��ʏȂ��Q�O�P�T�N�x�d�ʎԔR
������T�����x�̋��������������ꍇ�A���̂Ƃ���e�g���b�N���[�J�ɂ͂��̔R���ɓK���ł���\�͂��Ȃ���
�߂Ƀg���b�N�̐��Y���ł��Ȃ��Ȃ邱�Ƃ���A���y��ʏȂɂQ�O�P�T�N�x�d�ʎԔR���̋����̒x���������v�]������
����Ȃ��Ɛ��������B
�@�܂��A����ł́A���{�́u�f�B�[�[���d�ʎ� NO�� �� 0.23 g/kWh ��NO���K�������v�A�uCO2�팸�v����сu�E�Ζ��v����
�L���Ȑ���������ł��o���Ȃ���Ԃł���A��������̏́A�����������̂Ɨ\�z�����B�������Ȃ���A�����_�ʼn�
�ɑ�w�E�����@�ցE�g���b�N���[�J���ɂ����ĕM�Ғ�Ă̂R���̓����Z�p�ɏ���Z�p�̊J���ɖڏ��������Ă���Ȃ�
�A���̕M�҂̗\�������S�ɕ�����邱�ƂɂȂ�B�����ŁA�N�����u�Ջ��l�v�̂R���̓����Z�p�ɏ���Z�p����w�E��
���@�ցE�g���b�N���[�J���ɂ����Ċ��ɊJ������Ă��邱�Ƃ��䑶���̏ꍇ�ɂ́A���̋Z�p�ɂ��Ă̊T�v��Ƃ�
�u�Ջ��l�v�ɂ��������������Ɗ���Ă��鎟��ł���B���̋Z�p���u�Ջ��l�v��Ă̂R���̓����Z�p�𗽉킵�Ă������
�ł���A���̃z�[���y�[�W���ɒ����������ƍl���Ă���B
�L���Ȑ���������ł��o���Ȃ���Ԃł���A��������̏́A�����������̂Ɨ\�z�����B�������Ȃ���A�����_�ʼn�
�ɑ�w�E�����@�ցE�g���b�N���[�J���ɂ����ĕM�Ғ�Ă̂R���̓����Z�p�ɏ���Z�p�̊J���ɖڏ��������Ă���Ȃ�
�A���̕M�҂̗\�������S�ɕ�����邱�ƂɂȂ�B�����ŁA�N�����u�Ջ��l�v�̂R���̓����Z�p�ɏ���Z�p����w�E��
���@�ցE�g���b�N���[�J���ɂ����Ċ��ɊJ������Ă��邱�Ƃ��䑶���̏ꍇ�ɂ́A���̋Z�p�ɂ��Ă̊T�v��Ƃ�
�u�Ջ��l�v�ɂ��������������Ɗ���Ă��鎟��ł���B���̋Z�p���u�Ջ��l�v��Ă̂R���̓����Z�p�𗽉킵�Ă������
�ł���A���̃z�[���y�[�W���ɒ����������ƍl���Ă���B
�@���͂Ƃ�����A��w�E�����@�ցE�g���b�N���[�J�����M�҂̒�Ă��Ă�����p���̗e�Ղȁu�C���x�~�G���W���i�������J
2005-54771�j�A�㏈������V�X�e���i�������J2005-69238�j�A������DDF�G���W���i�������J2008-51121�j�v�̂R���̓�
���Z�p�̌����J���𑁋}�Ɏ��{����A��^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W���������Ă��鑽���̏d�v�ȉۑ肪������
�����ł��A��^�g���b�N�ɂ�������P�����₩�Ɏ����ł���̂ł���B�u�Ջ��l�v����Ă��Ă���R���̓����Z�p�ɂ��
�Ď������\�ȑ�^�g���b�N�̐��\����̓��e���ȉ��̕\�Q�Ɏ����B
2005-54771�j�A�㏈������V�X�e���i�������J2005-69238�j�A������DDF�G���W���i�������J2008-51121�j�v�̂R���̓�
���Z�p�̌����J���𑁋}�Ɏ��{����A��^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W���������Ă��鑽���̏d�v�ȉۑ肪������
�����ł��A��^�g���b�N�ɂ�������P�����₩�Ɏ����ł���̂ł���B�u�Ջ��l�v����Ă��Ă���R���̓����Z�p�ɂ��
�Ď������\�ȑ�^�g���b�N�̐��\����̓��e���ȉ��̕\�Q�Ɏ����B
| �� ��^�g���b�N�ł́A2015�N�x�d�ʎԔR�������T���ȏ�̔R����P������
�� �f�B�[�[���d�ʎ� NO�� �� 0.23 g/kWh �K���iWHTC�������[�h�j�𑁊��B��
�@�@�i�������R�c��̑攪�����\�ɂ́ANO�� �� 0.23 g/kWh �܂ł�NO���팸�̖ڕW���L�ڍς݁j
�@�i���݂ɁA2016�N�\��̃f�B�[�[���d�ʎԂ�NO���K���l�� NO�� �� 0.4 g/kWh [WHTC�����@�A��\�����\]�j
�� ��^�g���b�N���r�o����CO2�̂P�T�����x���팸
�� �|�X�g���˂܂��͂g�b�r�C�Ǖ��˂ɂ��DPF�Đ���������ADPF�̎��ȍĐ��̑��i�ɂ��
�@�@��^�g���b�N�̔R���Q���h�~
�� �u�y��50���{�V�R�K�X50���v�̔R���ł̑�^�g���b�N�̉^�s���\�Ƃ��A50���̒E�Ζ� ������
|
�@�M�Ғ�Ă̂R���̓����Z�p�����p�����邱�Ƃɂ���āA�ȏ�̕\�Q�Ɏ�����NO���팸���܂ޑ�^�g���b�N�̐��\����
�̑S�Ă������Ɏ����ł���̂ł���B�������A���݂́A�M�Ғ�Ă̂R���̓����Z�p�����̂������̑�w�E�����@�ցE�g
���b�N���[�J���̊w�ҁE���Ƃɂ͖�������Ă���̂��B����ɂ��A�߂������ANO���팸���܂ޑ�^�g���b�N�̑啝��
���\���オ������Ƃ͊m���Ɨ\�z�����B���̂��߁A�u�f�B�[�[���d�ʎԂ� NO�� �� 0.23 g/kWh�iWHTC�r�o�K�X����
�@�j�̋K���������x������Ă��邱�Ɓv�ɂ��A�����͑�C�����P�̒�����Ɏ���邱�Ƃ��������t����
��Ă��܂��̂ł���B�����āA�g���b�N���[�U�ɂƂ��Ắu�R��̉��P���ꂽ��^�g���b�N�̎s�̂��x��Ă��܂����Ƃ�A�|
�X�g���˂܂��͂g�b�r�C�Ǖ��˂ɂ��DPF���u�̍Đ��ł̔R���Q�������p������Ă��܂����Ɓv�ɂ���Čo�ϓI��
�s���v�����Ă��܂��̂��B
�̑S�Ă������Ɏ����ł���̂ł���B�������A���݂́A�M�Ғ�Ă̂R���̓����Z�p�����̂������̑�w�E�����@�ցE�g
���b�N���[�J���̊w�ҁE���Ƃɂ͖�������Ă���̂��B����ɂ��A�߂������ANO���팸���܂ޑ�^�g���b�N�̑啝��
���\���オ������Ƃ͊m���Ɨ\�z�����B���̂��߁A�u�f�B�[�[���d�ʎԂ� NO�� �� 0.23 g/kWh�iWHTC�r�o�K�X����
�@�j�̋K���������x������Ă��邱�Ɓv�ɂ��A�����͑�C�����P�̒�����Ɏ���邱�Ƃ��������t����
��Ă��܂��̂ł���B�����āA�g���b�N���[�U�ɂƂ��Ắu�R��̉��P���ꂽ��^�g���b�N�̎s�̂��x��Ă��܂����Ƃ�A�|
�X�g���˂܂��͂g�b�r�C�Ǖ��˂ɂ��DPF���u�̍Đ��ł̔R���Q�������p������Ă��܂����Ɓv�ɂ���Čo�ϓI��
�s���v�����Ă��܂��̂��B
�@�܂��A���{�i���y��ʏȁE���ȁE�o�ώY�Əȁj�́A�����ς�炸�A��^�g���b�N��CO�Q�팸��E�Ζ��Ɋւ��ăo�C�I
�}�X�R���̂悤�Ȏ����̕s�\�Ȑ���v��p�����������Ȃ��f�������čs��������A�����āu�������R�c��̑�
�������\�ɒ���ڕW�Ƃ��Ė��L����Ă���f�B�[�[���d�ʎ� NO�� �� 0.23 g/kWh���x���܂ł�NO���K��������x����
�������A�܂��Ⴆ��2015�N�x�d�ʎԔR������T�����x�������̂悤�ȁA�����̍X�Ȃ�d�ʎԔR���̋�����
�\���S���\���ł��Ȃ��������čs�����̂Ɛ��������B
�}�X�R���̂悤�Ȏ����̕s�\�Ȑ���v��p�����������Ȃ��f�������čs��������A�����āu�������R�c��̑�
�������\�ɒ���ڕW�Ƃ��Ė��L����Ă���f�B�[�[���d�ʎ� NO�� �� 0.23 g/kWh���x���܂ł�NO���K��������x����
�������A�܂��Ⴆ��2015�N�x�d�ʎԔR������T�����x�������̂悤�ȁA�����̍X�Ȃ�d�ʎԔR���̋�����
�\���S���\���ł��Ȃ��������čs�����̂Ɛ��������B
�@�Ƃ���ŁA���{�̎Љ�ł́A�ސE���ĉ���̊�ƁE�c�̂ɑ����Ȃ��Ȃ���������A���̐l�̓|���R�c�̌��Z�p���ƌ���
�����X�����������悤���B���̂悤�ȃ|���R�c�̌��Z�p���̕M�҂���Ă���R���̓����Z�p�́A�f�B�[�[���G���W��
�W�̊w�ҁE���Ƃ��Z�p�̓��e���ڍׂɌ������邱�Ɩ����A�u�c�t�ȋZ�p�v�ƌ��Ȃ���Ă��܂��Ă�����̂Ɛ�������
��B�������Ȃ���A�|���R�c�̌��Z�p���̕M�҂́A���̂悤�Ȃ��Ƃ���^�g���b�N�ɂ�������{��NO���팸���܂ސ��\��
�オ�啝�ɒx���̂ł͂Ȃ����Ə���Ɏv���Ă���B
�����X�����������悤���B���̂悤�ȃ|���R�c�̌��Z�p���̕M�҂���Ă���R���̓����Z�p�́A�f�B�[�[���G���W��
�W�̊w�ҁE���Ƃ��Z�p�̓��e���ڍׂɌ������邱�Ɩ����A�u�c�t�ȋZ�p�v�ƌ��Ȃ���Ă��܂��Ă�����̂Ɛ�������
��B�������Ȃ���A�|���R�c�̌��Z�p���̕M�҂́A���̂悤�Ȃ��Ƃ���^�g���b�N�ɂ�������{��NO���팸���܂ސ��\��
�オ�啝�ɒx���̂ł͂Ȃ����Ə���Ɏv���Ă���B
�@���āA�ŋ߂̑�^�g���b�N�̎����́A�r���ŃI�[�o�[�z�[�����s���K�v�͂��邪�A���s�����łP�T�O�������ȏオ�펯
�Ƃ���Ă���B���̂��߁A��^�g���b�N�̃V�X�e���E���u�ɂ͏�ɍ����ϋv���ƐM���������߂��Ă���B���������āA
��^�g���b�N�ɐV�����V�X�e���E���u���̗p����ꍇ�ɂ́A���ϋv���ƍ��M�������m�ۂ��邽�߁A�������Ԃ��₵��
�V�X�e���╔�i�̊J�����s���Ă���B���̂悤�ɁA��^�g���b�N�ɗp����V�X�e���E���u�̊J���ɂ͒������Ԃ��K�v
�Ȃ��߁A�V���ȋZ�p���̗p����ꍇ�ɂ́A���̃V�X�e���E���u�̊�{�I�ȃA�C�f�A�E�T�v���g���b�N�ƊE���ł͌Â�����
�b��ɂȂ��Ă��邱�Ƃ������B
�Ƃ���Ă���B���̂��߁A��^�g���b�N�̃V�X�e���E���u�ɂ͏�ɍ����ϋv���ƐM���������߂��Ă���B���������āA
��^�g���b�N�ɐV�����V�X�e���E���u���̗p����ꍇ�ɂ́A���ϋv���ƍ��M�������m�ۂ��邽�߁A�������Ԃ��₵��
�V�X�e���╔�i�̊J�����s���Ă���B���̂悤�ɁA��^�g���b�N�ɗp����V�X�e���E���u�̊J���ɂ͒������Ԃ��K�v
�Ȃ��߁A�V���ȋZ�p���̗p����ꍇ�ɂ́A���̃V�X�e���E���u�̊�{�I�ȃA�C�f�A�E�T�v���g���b�N�ƊE���ł͌Â�����
�b��ɂȂ��Ă��邱�Ƃ������B
�@�Ⴆ�A�V�����K���i2005�N�K���j�̑�^�g���b�N�ɐV���ɍ̗p���ꂽ�u�A�fSCR�G�}���u�v�́A���̋Z�p���g���b�N��
�E�ōŏ��ɘb��ƂȂ����̂͂P�X�V�V�N���Ƀ{�C���[�p�̑��u�Ƃ��Ď��p�����ꂽ���ł������B�e�g���b�N���[�J�Ƃ��A��
���菭����ɂ��̋Z�p�̊J���̌������J�n���A���ۂɂ��̋Z�p���^�g���b�N�ɍ̗p���ꂽ�̂͐V�����K���i2005�N
�K���j�ł���B�������V�����K���i2005�N�K���j�̑�^�g���b�N�ɐV���ɍ̗p���ꂽ�uDPF���u�v�́A�g���b�N���[�J�̌��Z
�p���̕M�҂����̑��u�̊J���̏����ɏ����W�������A���̎����͂P�X�X�O�N�O��ł������ƋL�����Ă���B��������
�āA�u�A�fSCR�G�}���u�v�ƁuDPF���u�v�́A���ɋZ�p�J���̂��߂Ɏ��ɂQ�O�N�O��̍Ό����₵�Ă���̂ł���B
�E�ōŏ��ɘb��ƂȂ����̂͂P�X�V�V�N���Ƀ{�C���[�p�̑��u�Ƃ��Ď��p�����ꂽ���ł������B�e�g���b�N���[�J�Ƃ��A��
���菭����ɂ��̋Z�p�̊J���̌������J�n���A���ۂɂ��̋Z�p���^�g���b�N�ɍ̗p���ꂽ�̂͐V�����K���i2005�N
�K���j�ł���B�������V�����K���i2005�N�K���j�̑�^�g���b�N�ɐV���ɍ̗p���ꂽ�uDPF���u�v�́A�g���b�N���[�J�̌��Z
�p���̕M�҂����̑��u�̊J���̏����ɏ����W�������A���̎����͂P�X�X�O�N�O��ł������ƋL�����Ă���B��������
�āA�u�A�fSCR�G�}���u�v�ƁuDPF���u�v�́A���ɋZ�p�J���̂��߂Ɏ��ɂQ�O�N�O��̍Ό����₵�Ă���̂ł���B
�@�܂��A�M�҂����������f�B�[�[���G���W���̃v���X�g���[�N���˃|���v�i���i���FTICS�j�́A�ŏ��̃A�C�f�A������Ƃ�
�ďo�肵�ĊJ�����J�n���Ă���P�O�N���x���o�߂�����ɁA�v���X�g���[�N���˃|���v���̗p������^�g���b�N���s�̂�
�����̂ł���B���̂悤�Ȃ��Ƃ���A��^�g���b�N�ɐV���ȃV�X�e���E���u���̗p����ꍇ�ɂ́A��^�g���b�N�ɕK�v�ȍ�
�ϋv���E���M�������m�ۂ����V�X�e���E���u�����������邽�߂ɁA�ʏ�A�P�O�N�ȏ�̏\���ȊJ�����Ԃ��K�v�ȏꍇ��
�����ƍl������B
�ďo�肵�ĊJ�����J�n���Ă���P�O�N���x���o�߂�����ɁA�v���X�g���[�N���˃|���v���̗p������^�g���b�N���s�̂�
�����̂ł���B���̂悤�Ȃ��Ƃ���A��^�g���b�N�ɐV���ȃV�X�e���E���u���̗p����ꍇ�ɂ́A��^�g���b�N�ɕK�v�ȍ�
�ϋv���E���M�������m�ۂ����V�X�e���E���u�����������邽�߂ɁA�ʏ�A�P�O�N�ȏ�̏\���ȊJ�����Ԃ��K�v�ȏꍇ��
�����ƍl������B
�@���̂悤�ɁA��^�g���b�N�̃f�B�[�[���G���W���ɐV���ȃV�X�e���E���u���̗p����ꍇ�ɂ́A�ʏ�P�O�N���x�̏\����
�J�����Ԃ��K�v�ƂȂ�ꍇ�������ƊE���B���̂悤�ȃg���b�N�ƊE�ɂ�������炸�A���̂Ƃ����w�E�����@�ցE�g��
�b�N���[�J�ł́A�\�P�Ɏ�������^�g���b�N�́u�R����P�v�A�uCO2�팸�v�A�uNOx�팸�v�A�uDPF�̎��ȍĐ��̑�
�i�v�A����сu�E�Ζ��v�̏d�v�ȉۑ�ɂ��āA����̉ۑ�ł������ł���Z�p������J���ł��Ă��Ȃ��悤
���B���̂悤�ɁA��w�E�����@�ցE�g���b�N���[�J�ɂ����Ė����ɑ�^�g���b�N�̏d�v�ۑ�������ł���Z�p���s
���̌���ł́A�u�Ջ��l�v��Ă̂R���̓����Z�p�����p�����Ȃ��ꍇ�ɂ́A���܂Ōo���Ă��\�Q�Ɏ�������^
�g���b�N�̐��\����̑S�Ă������ł��Ȃ��\��������B
�J�����Ԃ��K�v�ƂȂ�ꍇ�������ƊE���B���̂悤�ȃg���b�N�ƊE�ɂ�������炸�A���̂Ƃ����w�E�����@�ցE�g��
�b�N���[�J�ł́A�\�P�Ɏ�������^�g���b�N�́u�R����P�v�A�uCO2�팸�v�A�uNOx�팸�v�A�uDPF�̎��ȍĐ��̑�
�i�v�A����сu�E�Ζ��v�̏d�v�ȉۑ�ɂ��āA����̉ۑ�ł������ł���Z�p������J���ł��Ă��Ȃ��悤
���B���̂悤�ɁA��w�E�����@�ցE�g���b�N���[�J�ɂ����Ė����ɑ�^�g���b�N�̏d�v�ۑ�������ł���Z�p���s
���̌���ł́A�u�Ջ��l�v��Ă̂R���̓����Z�p�����p�����Ȃ��ꍇ�ɂ́A���܂Ōo���Ă��\�Q�Ɏ�������^
�g���b�N�̐��\����̑S�Ă������ł��Ȃ��\��������B
�@���͂Ƃ�����A�킪���̑�w�E�����@�ցE�g���b�N���[�J�́A�����ɕ\�Q�Ɏ�������^�g���b�N�̐��\������\�ɂ���
�Z�p������J���ł��Ă��Ȃ����Ƃ͎����̂悤���B���̂悤�ȏɂ�������炸�A��w�E�����@�ցE�g���b�N���[�J��
�w�ҁE���Ƃ́A�u�Ջ��l�v��Ă̂R���̓����Z�p�����Ă���̂ł���B����ɂ���āA���ۂɖ��f�����Ă��܂�
�̂́A�u��C�����P�̒�v�ɔ������������ʎs���ł���A�u�R���啝�ɉ��P������^�g���b�N�̔̔��J�n��
�x���A���s��DPF���u�̎����Đ��E�蓮�Đ��ł̔R���̐��ꗬ���v��������ꑱ����g���b�N���[�U�ł���A�u�\�Q��
������NO���K�������A�d�ʎԔR���̋����ACO�Q�팸�A�ȃG�l�A�E�Ζ��v�̐����i�ł��Ȃ����{�i���y��ʏȁE
���ȁE�o�ώY�Əȁj�ł���B���ɁA���{�i���y��ʏȁE���ȁE�o�ώY�Əȁj�̒S�������̐l�B�́A�ނ�̐E���ł���
�uNO����CO�Q�̍팸�ɂ���C���̉��P�v�A�u�ȃG�l���M�[�̎����v�A�u�E�Ζ��̎����v���S���s�\�Ȃ��߁A�R���Ղ�
�̏ɂ���ƍl������B
�Z�p������J���ł��Ă��Ȃ����Ƃ͎����̂悤���B���̂悤�ȏɂ�������炸�A��w�E�����@�ցE�g���b�N���[�J��
�w�ҁE���Ƃ́A�u�Ջ��l�v��Ă̂R���̓����Z�p�����Ă���̂ł���B����ɂ���āA���ۂɖ��f�����Ă��܂�
�̂́A�u��C�����P�̒�v�ɔ������������ʎs���ł���A�u�R���啝�ɉ��P������^�g���b�N�̔̔��J�n��
�x���A���s��DPF���u�̎����Đ��E�蓮�Đ��ł̔R���̐��ꗬ���v��������ꑱ����g���b�N���[�U�ł���A�u�\�Q��
������NO���K�������A�d�ʎԔR���̋����ACO�Q�팸�A�ȃG�l�A�E�Ζ��v�̐����i�ł��Ȃ����{�i���y��ʏȁE
���ȁE�o�ώY�Əȁj�ł���B���ɁA���{�i���y��ʏȁE���ȁE�o�ώY�Əȁj�̒S�������̐l�B�́A�ނ�̐E���ł���
�uNO����CO�Q�̍팸�ɂ���C���̉��P�v�A�u�ȃG�l���M�[�̎����v�A�u�E�Ζ��̎����v���S���s�\�Ȃ��߁A�R���Ղ�
�̏ɂ���ƍl������B
�@���̒��ł��A���ɎЉ�I�j�[�Y�̍�����^�g���b�N�̔R�������NO���팸�������ł���̐��𑁊��ɍ\�z����őP
�̕��@�́A�ł��邾�������ɔr�o�K�X�K���ƔR��K���̃I�v�V�����Ƃ��āA�\�R�Ɏ������悤��NO���팸�ƔR�������K
�肵���u��NO���E��R��g���b�N�E�o�X�̊�i�āj�v��V���ɐݒ肷�邱�Ƃł���B���́u��NO���E��R����Ԃ̊
�i�āj�v�ł́A�\�R�Ɏ������ʂ�A2005�N�̑攪�����\�ɂm�n���̒���ڕW�Ƃ��Ď�����Ă��� 0.7 g/kWh�� 1/3���x�� 0.
23 g/kWh�̂m�n�� �K���l�ƁA2015�N�x�d�ʎԔR������ 10�� ���x�̔R������サ����^�g���b�N�́u��NO���E��R
��g���b�N�E�o�X�̊�i�āj�v��ݒ肷�邱�Ƃ��K�ł͂Ȃ����ƍl���Ă���B�����āA��^�g���b�N���C���x�~�G���W
���i�������J2005-54771�j���̗p���邱�Ƃɂ��A���{�͑�^�g���b�N�̐V���Ȓ�R��E��r�o�K�X��𑁊�
�ɐݒ肹��I�ɏڏq���Ă���悤�ȁu�m�n����0.23 g/kWh �� 2015�N�x�d�ʎԔR������ 10�� ���x�̔R��
������v���K�肵����NO���E��R��g���b�N�E�o�X�̊�����ۂɎ{�s���ꂽ�ꍇ�ɂ́A���̊��B��������
�^�g���b�N����e�ՂɎ��p�����A�s�̂ł����̂ł���B
�̕��@�́A�ł��邾�������ɔr�o�K�X�K���ƔR��K���̃I�v�V�����Ƃ��āA�\�R�Ɏ������悤��NO���팸�ƔR�������K
�肵���u��NO���E��R��g���b�N�E�o�X�̊�i�āj�v��V���ɐݒ肷�邱�Ƃł���B���́u��NO���E��R����Ԃ̊
�i�āj�v�ł́A�\�R�Ɏ������ʂ�A2005�N�̑攪�����\�ɂm�n���̒���ڕW�Ƃ��Ď�����Ă��� 0.7 g/kWh�� 1/3���x�� 0.
23 g/kWh�̂m�n�� �K���l�ƁA2015�N�x�d�ʎԔR������ 10�� ���x�̔R������サ����^�g���b�N�́u��NO���E��R
��g���b�N�E�o�X�̊�i�āj�v��ݒ肷�邱�Ƃ��K�ł͂Ȃ����ƍl���Ă���B�����āA��^�g���b�N���C���x�~�G���W
���i�������J2005-54771�j���̗p���邱�Ƃɂ��A���{�͑�^�g���b�N�̐V���Ȓ�R��E��r�o�K�X��𑁊�
�ɐݒ肹��I�ɏڏq���Ă���悤�ȁu�m�n����0.23 g/kWh �� 2015�N�x�d�ʎԔR������ 10�� ���x�̔R��
������v���K�肵����NO���E��R��g���b�N�E�o�X�̊�����ۂɎ{�s���ꂽ�ꍇ�ɂ́A���̊��B��������
�^�g���b�N����e�ՂɎ��p�����A�s�̂ł����̂ł���B
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
�@���̂��߁A���{�i���y��ʏȁE���ȁE�o�ώY�Əȁj�̒S�������̐l�B�́A�g���b�N���[�J�ɑ��A�u�Ջ��l�v����Ă�
��R���̓����Z�p�̌����J���ɑ��}�ɒ��肷��悤�Ɏw�����ׂ��ƍl���邪�A�@���Ȃ��̂ł��낤���B�����Ɖ���Ղ���
���A���{�i���y��ʏȁE���ȁE�o�ώY�Əȁj���g���b�N���[�J�ɑ��āu�Ջ��l�v��Ă̂R���̓����Z�p�y�C��
�x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�A�㏈������V�X�e���i�������J2005-69238�j�A������DDF�G���W���i��
�����J2008-51121�j�z�̌����J���𑬂₩�ɊJ�n����悤�Ɏw�����Ȃ���A�ň��̏ꍇ�ɂ͕\�Q�Ɏ�����
NO���팸���܂ޑ�^�g���b�N�̐��\���オ�ی��Ȃ��摗�肳���\�����������Ƃ����N���Ă��������B
��R���̓����Z�p�̌����J���ɑ��}�ɒ��肷��悤�Ɏw�����ׂ��ƍl���邪�A�@���Ȃ��̂ł��낤���B�����Ɖ���Ղ���
���A���{�i���y��ʏȁE���ȁE�o�ώY�Əȁj���g���b�N���[�J�ɑ��āu�Ջ��l�v��Ă̂R���̓����Z�p�y�C��
�x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�A�㏈������V�X�e���i�������J2005-69238�j�A������DDF�G���W���i��
�����J2008-51121�j�z�̌����J���𑬂₩�ɊJ�n����悤�Ɏw�����Ȃ���A�ň��̏ꍇ�ɂ͕\�Q�Ɏ�����
NO���팸���܂ޑ�^�g���b�N�̐��\���オ�ی��Ȃ��摗�肳���\�����������Ƃ����N���Ă��������B
�@�@�Ƃ���ŁA���R�O�͂Q�O�O�X�N�X���Q�Q���ɍ��A�{���ŊJ���ꂽ���A�C��ϓ���]����łQ�O�Q�O�N�܂łɉ�
�����ʃK�X���P�X�X�O�N��łQ�T���팸������{�̒����ڕW��\�������B�ȃG�l�̔��B�������{�ł�CO�Q�̂Q�T���팸
�̎������ɂ߂č���ł��邱�Ƃ͊��ɐ��E�I�ɗǂ��m���Ă��邱�Ƃ������āA���R�̔��I��CO�Q�팸�錾
�ɑ��A���A�ł͂قƂ�ǒ��ڂ���Ȃ������悤���B�펯�I�ɍl����Δ��R�O�̘I���Ȕ����s�ׁE���Ȑ�`�ł�
�邱�Ƃ��e�Ղɔ��f�ł��邽�߁A�e���̃}�X�R�~�������Ė��������̂ł͂Ȃ����낤���B���ʂ��猾���ACO�Q�팸��
���Đ��E�e������O�Ȕ��f�̊�ɍs�����Ă��邱�Ƃ𗝉��ł��Ă��Ȃ����R�O�́ACO�Q�̂Q�T���팸��\����
�邱�Ƃɂ���Đ��E�̏̎^����̂Ə���Ɏv�����݁ACO�Q�r�o�Ɋւ��ē��{�̎Љ�S�̂ɏd����������Ƃ߂Ă�
�܂����̂��B���̂悤�ȓI�O��̔��R�O�̍s���́A�����ɂƂ��Ă͖��f�Șb�ł���B
�����ʃK�X���P�X�X�O�N��łQ�T���팸������{�̒����ڕW��\�������B�ȃG�l�̔��B�������{�ł�CO�Q�̂Q�T���팸
�̎������ɂ߂č���ł��邱�Ƃ͊��ɐ��E�I�ɗǂ��m���Ă��邱�Ƃ������āA���R�̔��I��CO�Q�팸�錾
�ɑ��A���A�ł͂قƂ�ǒ��ڂ���Ȃ������悤���B�펯�I�ɍl����Δ��R�O�̘I���Ȕ����s�ׁE���Ȑ�`�ł�
�邱�Ƃ��e�Ղɔ��f�ł��邽�߁A�e���̃}�X�R�~�������Ė��������̂ł͂Ȃ����낤���B���ʂ��猾���ACO�Q�팸��
���Đ��E�e������O�Ȕ��f�̊�ɍs�����Ă��邱�Ƃ𗝉��ł��Ă��Ȃ����R�O�́ACO�Q�̂Q�T���팸��\����
�邱�Ƃɂ���Đ��E�̏̎^����̂Ə���Ɏv�����݁ACO�Q�r�o�Ɋւ��ē��{�̎Љ�S�̂ɏd����������Ƃ߂Ă�
�܂����̂��B���̂悤�ȓI�O��̔��R�O�̍s���́A�����ɂƂ��Ă͖��f�Șb�ł���B
�@�����͉]���Ă��A���ɓ��{�͑啝�Ȃb�n�Q�팸�𐢊E�Ɍ������Đ錾�������Ƃ���A��^�g���b�N�ɂ�����b�n�Q�팸��
�K�v������������ттĂ����̂ł���B����A�o�ώY�ƏȂ�2006�N5���́u�V�E���ƃG�l���M�[�헪�v�ł́u�ق�100��
��Ζ��n�R���Ɉˑ�����^�A����̓G�l���M�[�����\���̒��ōł��Ǝ㐫���������߂ɐΖ��ˑ�����̒E�p��}
��ׂ��v�Ƃ��C�u����A2030�N�܂łɁA�^�A����̐Ζ��ˑ��x��80�����x�Ƃ��邱�Ƃ�ڎw���v�Ƃ�����\���Ă���
�̂��B���̂悤�Ɍ��݂̐��{�͑�^�g���b�N�ɂ����Ă͂b�n�Q�팸�ƒE�Ζ��Ɖ]�����h�ȕ��j�E�ڕW�X�ƌf���Ă���
�̂ł���B�������Ȃ��炱�����j�E�ڕW�������ł������Ȏ{��͉������\����Ă��Ȃ��悤�ł���B����ɂ��ẮA
�u��^�g���b�N�́u�b�n2�팸�v�Ɓu�E�Ζ��v�̋Z�p�́A�����ɕs�����H�v�A�u���{�̒E�Ζ��E��Y�f���Ɋ�^���Ȃ�������
�M�S�Ȍ�ʈ��S���������v����сu�o�C�I�}�X�R����DME�ɂ�鎩���Ԃ̒�Y�f�E�E�Ζ��́A�s�\���I�v�ɏڏq��
���悤�ɁA�u�Ջ��l�v�͐��{��W�Ȓ�����^�g���b�N�̂b�n�Q�팸�ƒE�Ζ��̐����ϋɓI�ɐ��i���Ă���悤�ɂ͂�
�Ă��l�����Ȃ��̂��B
�K�v������������ттĂ����̂ł���B����A�o�ώY�ƏȂ�2006�N5���́u�V�E���ƃG�l���M�[�헪�v�ł́u�ق�100��
��Ζ��n�R���Ɉˑ�����^�A����̓G�l���M�[�����\���̒��ōł��Ǝ㐫���������߂ɐΖ��ˑ�����̒E�p��}
��ׂ��v�Ƃ��C�u����A2030�N�܂łɁA�^�A����̐Ζ��ˑ��x��80�����x�Ƃ��邱�Ƃ�ڎw���v�Ƃ�����\���Ă���
�̂��B���̂悤�Ɍ��݂̐��{�͑�^�g���b�N�ɂ����Ă͂b�n�Q�팸�ƒE�Ζ��Ɖ]�����h�ȕ��j�E�ڕW�X�ƌf���Ă���
�̂ł���B�������Ȃ��炱�����j�E�ڕW�������ł������Ȏ{��͉������\����Ă��Ȃ��悤�ł���B����ɂ��ẮA
�u��^�g���b�N�́u�b�n2�팸�v�Ɓu�E�Ζ��v�̋Z�p�́A�����ɕs�����H�v�A�u���{�̒E�Ζ��E��Y�f���Ɋ�^���Ȃ�������
�M�S�Ȍ�ʈ��S���������v����сu�o�C�I�}�X�R����DME�ɂ�鎩���Ԃ̒�Y�f�E�E�Ζ��́A�s�\���I�v�ɏڏq��
���悤�ɁA�u�Ջ��l�v�͐��{��W�Ȓ�����^�g���b�N�̂b�n�Q�팸�ƒE�Ζ��̐����ϋɓI�ɐ��i���Ă���悤�ɂ͂�
�Ă��l�����Ȃ��̂��B
�@���̂悤�ȏ����Ă���ƁA�u�Ջ��l�v�̓|���R�c���Z�p���Ƃ��Ă̌������X�ƗN���Ă���̂���B�����ŁA���݂̑�
�^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W���̑����̉ۑ���������邽�߂ɁA�u�Ջ��l�v�i�M�ҁj���C���x�~�G���W���i�������J2005
-54771�j�A�㏈������V�X�e���i�������J2005-69238�j�����������DDF�G���W���i�������J2008-51121�j�̂R���̓�
�����l�Ă��A��Ă��Ă���̂ł���B���̒��Łu����ۑ�v�Ƌ���Ă����^�g���b�N�̃f�B�[�[���G���W���́u�R���
�P�v�A�uCO2�팸�v�A�u�ᕉ���ɂ�����G�}�i�r�o�K�X�㏈�����u�j�̍������ɂ��NOx�팸��DPF�̎��ȍĐ����i�v�A
�u�|�X�g���˂܂��͂g�b�r�C�Ǖ��˂��s�v��DPF���u�̍Đ��v�A����сu�E�Ζ��v�̉ۑ肪�A�u�Ջ��l�v��Ă̂R���̓�
���Z�p�ɂ���ĉ����ł���ƍl����̂́A�u�Ջ��l�v�̒P�Ȃ�Ƃ�P����ł��낤���B
�^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W���̑����̉ۑ���������邽�߂ɁA�u�Ջ��l�v�i�M�ҁj���C���x�~�G���W���i�������J2005
-54771�j�A�㏈������V�X�e���i�������J2005-69238�j�����������DDF�G���W���i�������J2008-51121�j�̂R���̓�
�����l�Ă��A��Ă��Ă���̂ł���B���̒��Łu����ۑ�v�Ƌ���Ă����^�g���b�N�̃f�B�[�[���G���W���́u�R���
�P�v�A�uCO2�팸�v�A�u�ᕉ���ɂ�����G�}�i�r�o�K�X�㏈�����u�j�̍������ɂ��NOx�팸��DPF�̎��ȍĐ����i�v�A
�u�|�X�g���˂܂��͂g�b�r�C�Ǖ��˂��s�v��DPF���u�̍Đ��v�A����сu�E�Ζ��v�̉ۑ肪�A�u�Ջ��l�v��Ă̂R���̓�
���Z�p�ɂ���ĉ����ł���ƍl����̂́A�u�Ջ��l�v�̒P�Ȃ�Ƃ�P����ł��낤���B
�@�Ō�ɁA���̃z�[���y�[�W�̑S�Ẵy�[�W�Ō���^��ƍl������L�ړ��e�ɂ��C�t���̏ꍇ�ɂ́A�S�O�������w
�E������������K���ł��B�܂��A�ǂ̂悤�Ȃ��Ƃł��\���܂���̂ŁA���_���܂߂ė����Ȍ�ӌ��E�䊴�z���������
����Ǝv���Ă���܂��B
�E������������K���ł��B�܂��A�ǂ̂悤�Ȃ��Ƃł��\���܂���̂ŁA���_���܂߂ė����Ȍ�ӌ��E�䊴�z���������
����Ǝv���Ă���܂��B


