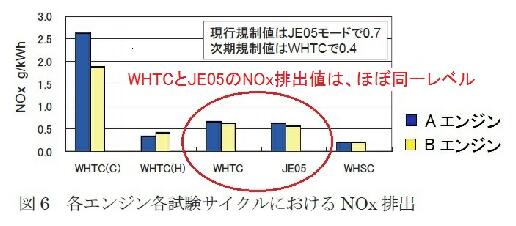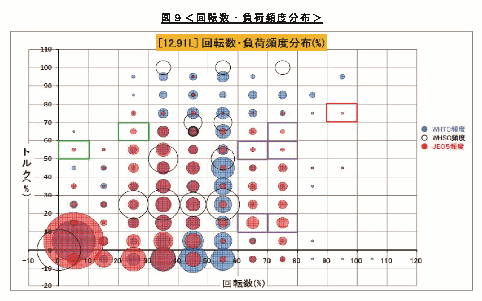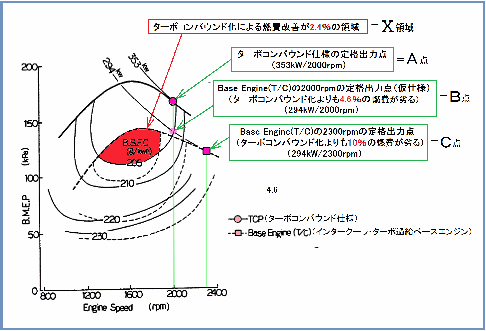|
�Ջ��l�̃A�C�f�A
�g�b�v�y�[�W�ɖ߂��@�@�@�@�T�C�g�}�b�v
|
�ŏI�X�V���F2016�N7��1��
 |
�P�D��^�g���b�N�̕���ł́A�̂��瑱���Ă��郁�[�J�Ԃ�����ȔR����P�̋���
�@��^�g���b�N�́A���{�̌o�ϊ����Ɛ����̕����ʂł̎����S���Ă��邱�Ƃ͒N�����F�߂�Ƃ���ł���B��k��
�ג����`������Ă�����{�ł̑S���I�ȉݕ��A�����s�����߁A��^�g���b�N�̏ꍇ�ɂ͈����1000km�ȏ�����s��
�邱�Ƃ��������͂Ȃ��B��ʓI�ɒ������A���Ɏg�p����邱�Ƃ̑�����^�g���b�N�͂P��������̔R������ʂ������B
���ɔR��̗���^�g���b�N���w�����Ă��܂����^����Ђ́A���̓�����^�s�o��̑���S���邱�ƂɂȂ�B��
�̂悤�ȏ�ԂɊׂ邱�Ƃ�����邽�߁A�^����Ђ͍w�������g���b�N�̔R���������ɊĎ����Ă���̂ł���B��
�̂悤�ɁA�g���b�N�̔R��̗ǔۂ��^����Ђ̎��v�ɉe�����邱�Ƃ���A�̂���^����Ђ̓g���b�N���[�J�ɑ��ď�
�ɔR��팸���������߂Ă���B���̂悤�ȉ^���ƊE�Ɋe���[�J�����Ђ̃g���b�N�鍞�ލۂ̑傫�ȕ���ƂȂ��
���R����ゾ�B�����������Ƃ���A�e�g���b�N���[�J�̏d�v�Ȍ����J���ۑ�̈�́A���̎���ł��K����������
����e�[�}���A�g���b�N�́w�R�����x�ł���B�t�Ɍ����A�R��̗��g���b�N��̔����Ă��܂������[�J�́A���̌��
�̔��ɂ����ăV�F�A��ቺ�����Ă��܂��s�K�Ɍ������Ă��܂����ƂɂȂ�B
�ג����`������Ă�����{�ł̑S���I�ȉݕ��A�����s�����߁A��^�g���b�N�̏ꍇ�ɂ͈����1000km�ȏ�����s��
�邱�Ƃ��������͂Ȃ��B��ʓI�ɒ������A���Ɏg�p����邱�Ƃ̑�����^�g���b�N�͂P��������̔R������ʂ������B
���ɔR��̗���^�g���b�N���w�����Ă��܂����^����Ђ́A���̓�����^�s�o��̑���S���邱�ƂɂȂ�B��
�̂悤�ȏ�ԂɊׂ邱�Ƃ�����邽�߁A�^����Ђ͍w�������g���b�N�̔R���������ɊĎ����Ă���̂ł���B��
�̂悤�ɁA�g���b�N�̔R��̗ǔۂ��^����Ђ̎��v�ɉe�����邱�Ƃ���A�̂���^����Ђ̓g���b�N���[�J�ɑ��ď�
�ɔR��팸���������߂Ă���B���̂悤�ȉ^���ƊE�Ɋe���[�J�����Ђ̃g���b�N�鍞�ލۂ̑傫�ȕ���ƂȂ��
���R����ゾ�B�����������Ƃ���A�e�g���b�N���[�J�̏d�v�Ȍ����J���ۑ�̈�́A���̎���ł��K����������
����e�[�}���A�g���b�N�́w�R�����x�ł���B�t�Ɍ����A�R��̗��g���b�N��̔����Ă��܂������[�J�́A���̌��
�̔��ɂ����ăV�F�A��ቺ�����Ă��܂��s�K�Ɍ������Ă��܂����ƂɂȂ�B
�@���́A�R����ɂ��}���Ȕ̔��V�F�A�̒ቺ�́A���ɑ�^�g���b�N�̕���ɂ����Ē������B���̔̔��V�F�A��ቺ
�������g���b�N���[�J�����N��Ƀ��f���`�F���W���s���ĔR������P������^�g���b�N��̔��o����悤�ɂȂ����Ƃ���
���A���̔̔��V�F�A�����̃��x���܂ʼn���܂ł�10�N���x�̍Ό���v���Ă��܂��Ɖ]���Ă���B���̂悤�ɑ�^
�g���b�N�ɂƂ��Ă̔R��̈����́A�g���b�N���[�J�Ƃ��Ă̒v�����ɂȂ肩�˂Ȃ����Ƃ���A�g���b�N���[�J�̔R����P��
�i���ɑ����u�J���ۑ�v�ƌ�����̂ł͂Ȃ����낤���B
�������g���b�N���[�J�����N��Ƀ��f���`�F���W���s���ĔR������P������^�g���b�N��̔��o����悤�ɂȂ����Ƃ���
���A���̔̔��V�F�A�����̃��x���܂ʼn���܂ł�10�N���x�̍Ό���v���Ă��܂��Ɖ]���Ă���B���̂悤�ɑ�^
�g���b�N�ɂƂ��Ă̔R��̈����́A�g���b�N���[�J�Ƃ��Ă̒v�����ɂȂ肩�˂Ȃ����Ƃ���A�g���b�N���[�J�̔R����P��
�i���ɑ����u�J���ۑ�v�ƌ�����̂ł͂Ȃ����낤���B
�Q�D�f�B�[�[���G���W���ɂ�����r�o�K�X�ጸ�ƔR����P
�@�f�B�[�[���G���W���ł́A�m�n���͔R�Ď����̔R�Ă̋Ǖ��I�ȍ����̗̈�Ő�������A�o�l�i�p�[�e�B�L�����C�g�j��
�j�ƂȂ�J�[�{���A�X���[�N����тb�n�͔R�Ď����̋Ǖ��I�Ȏ_�f�s���̗̈�Ő�������A�o�l�\�����̂g�b�i���R
�R���j�͔R�Ď����̉Ή��`�d�̓��B�ł��Ȃ��R���̉ߏ��ߗ̈�Ő��������Ɖ]���Ă���B���̂��߁A�f�B�[
�[���G���W���̂m�n���A�g�b�A�b�n�A�o�l����тo�l�̔r�o�K�X���팸���邽�߂ɂ́A�R�Ē��̔R�Ď����̍����̈�A
�_�f�s���̈您��єR���̉ߏ��ߗ̈���ł�����菭�Ȃ�����悤�ȔR�Ă������邽�߂ɁA�R�Ď����̋�C�ʂ�
���₵�A�R���̔�������ǍD�ȕ��z��}���č����C�̌`���𑣐i���A���S�ȔR�Ăɋ߂Â��邱�Ƃ��K�v�ƂȂ�B
�j�ƂȂ�J�[�{���A�X���[�N����тb�n�͔R�Ď����̋Ǖ��I�Ȏ_�f�s���̗̈�Ő�������A�o�l�\�����̂g�b�i���R
�R���j�͔R�Ď����̉Ή��`�d�̓��B�ł��Ȃ��R���̉ߏ��ߗ̈�Ő��������Ɖ]���Ă���B���̂��߁A�f�B�[
�[���G���W���̂m�n���A�g�b�A�b�n�A�o�l����тo�l�̔r�o�K�X���팸���邽�߂ɂ́A�R�Ē��̔R�Ď����̍����̈�A
�_�f�s���̈您��єR���̉ߏ��ߗ̈���ł�����菭�Ȃ�����悤�ȔR�Ă������邽�߂ɁA�R�Ď����̋�C�ʂ�
���₵�A�R���̔�������ǍD�ȕ��z��}���č����C�̌`���𑣐i���A���S�ȔR�Ăɋ߂Â��邱�Ƃ��K�v�ƂȂ�B
�@���a47�N�V���̃f�B�[�[���Ԃ̍����K���J�n�i�R���[�h�@�j�ȗ��A�f�B�[�[���G���W���̌����J���̖ړI�͂����
�ł̔R����P�ɐV���ɔr�o�K�X�팸�̌����ڕW����������B�r�o�K�X�팸�ɂ͔R�ĉ��P���K�{�ł��邽�߁A����
�����ɂ̓��[�J�E�����@�ւ̃f�B�[�[���G���W���̌����J���͔R�����Ɣr�o�K�X�팸�̂��߂̔R�ĉ��P�ɑS��
���X�����ꂽ�ė����悤�Ɏv����B�ŋ߂ł́A�f�B�[�[���G���W���̌����J���ɂ͔R�ĉ��P�ɔA�f�r�b�q�G�}��c
�o�e���u�Ȃǂ̔r�o�K�X�㏈���������A�\�P�Ɏ������Z�p�ɂ�茻�݂̔R��Ɣr�o�K�X���\������^�f�B�[�[��
�g���b�N�����p�����ꂽ�̂ł���B
�ł̔R����P�ɐV���ɔr�o�K�X�팸�̌����ڕW����������B�r�o�K�X�팸�ɂ͔R�ĉ��P���K�{�ł��邽�߁A����
�����ɂ̓��[�J�E�����@�ւ̃f�B�[�[���G���W���̌����J���͔R�����Ɣr�o�K�X�팸�̂��߂̔R�ĉ��P�ɑS��
���X�����ꂽ�ė����悤�Ɏv����B�ŋ߂ł́A�f�B�[�[���G���W���̌����J���ɂ͔R�ĉ��P�ɔA�f�r�b�q�G�}��c
�o�e���u�Ȃǂ̔r�o�K�X�㏈���������A�\�P�Ɏ������Z�p�ɂ�茻�݂̔R��Ɣr�o�K�X���\������^�f�B�[�[��
�g���b�N�����p�����ꂽ�̂ł���B
| |
|
|
| |
|
�s�X�g���L���r�e�B�`��̍œK�� |
| �R�����˕ق̃V�����_���S���{�S�ى� | ||
| |
|
�R�����˂̍������{���i���ˉ� |
| |
|
|
| |
|
�^�[�{�ߋ��@�̌�������{VG�^�[�{�������E�G�X�g�Q�[�g�� |
| �C���^�[�N�[���� | ||
| |
|
|
| |
�@����܂ł̃f�B�[�[���G���W���ɂ�����r�o�K�X�ጸ�ƔR����P�́A���N�ɂ킽���Č������ǂ��������Ă�����
�Ƃ������Č��݂ł͌��E�ɋ߂Â��Ă���A��L�̃G���W���{�̂̋Z�p���ǂł͔R����P��������Ȃ��Ă��Ă�
��B�܂��A�p�e�B�L�����[�g�K�����������Ȃ����V�����K���iH17�N�j�ȍ~�̔r�C�K�X�K���ł́A�p�e�L�����[�g�팸��
���߂ɍ̗p���ꂽ�|�X�g���ˍĐ���DPF���u��r�C�Ǖ��ˍĐ�����DPF���u�́A���炩�ɔR��̈������������u
�ł���ɂ�������炸�A������g�킴��Ȃ��ƂȂ��Ă��Ă���̂ł����B
�Ƃ������Č��݂ł͌��E�ɋ߂Â��Ă���A��L�̃G���W���{�̂̋Z�p���ǂł͔R����P��������Ȃ��Ă��Ă�
��B�܂��A�p�e�B�L�����[�g�K�����������Ȃ����V�����K���iH17�N�j�ȍ~�̔r�C�K�X�K���ł́A�p�e�L�����[�g�팸��
���߂ɍ̗p���ꂽ�|�X�g���ˍĐ���DPF���u��r�C�Ǖ��ˍĐ�����DPF���u�́A���炩�ɔR��̈������������u
�ł���ɂ�������炸�A������g�킴��Ȃ��ƂȂ��Ă��Ă���̂ł����B
�@�����|�X�g���ˍĐ���DPF���u���|�X�g���˂��A�C���x�~��DPF�̎��ȍĐ��𑣐i (�����Đ��̍팸�ŔR���
��h�~�j�ɏڍׂɐ������Ă���悤�ɁA�V�����_�̒��ŔR����R�₷���Ƃ��ړI�ł͂Ȃ��A�|�X�g���˂̔R���͐G�}��
�_�������邱�Ƃɂ���Ĕr�C���x��600���O��ɏ㏸�����A�c�o�e�ɑ͐ς����p�e�B�L�����[�g�R�Ă��A�������邽�߂�
���̂ł���B���̃|�X�g���ˎ�DPF���u�𓋍ڂ������^�f�B�[�[���g���b�N�������g�p�����l�����W�n��̏W�z��
�����ł͔��i�E��~���p�ɂɍs���邽�߂ɃG���W������̃p�e�L�����[�g�r�o�ʂ��������邱�Ƃ���A�|�X�g����
�ɂ��t�B���^�̍Đ����p�ɂɍs�����Ƃ��K�v�ƂȂ�B���̃|�X�g���˂ɂ��DPF�̎����Đ��̕p�x�ɔ�Ⴕ�ĔR��
���Q���邽�߁A�|�X�g���ˍĐ���DPF���ڂ̐V�����K���iH17�N�j�K���̏��^�f�B�[�[���g���b�N�ł́A�����s�R
��������������Ă��܂��̂��B�ܘ_�A�r�C�Ǖ��ˍĐ�����DPF���u�ł��ADPF�̎����Đ��̕p�x�ɔ�Ⴕ�ĔR��
���Q���邱�Ƃ́A�|�X�g���ˍĐ���DPF���u�����l�ł���B
��h�~�j�ɏڍׂɐ������Ă���悤�ɁA�V�����_�̒��ŔR����R�₷���Ƃ��ړI�ł͂Ȃ��A�|�X�g���˂̔R���͐G�}��
�_�������邱�Ƃɂ���Ĕr�C���x��600���O��ɏ㏸�����A�c�o�e�ɑ͐ς����p�e�B�L�����[�g�R�Ă��A�������邽�߂�
���̂ł���B���̃|�X�g���ˎ�DPF���u�𓋍ڂ������^�f�B�[�[���g���b�N�������g�p�����l�����W�n��̏W�z��
�����ł͔��i�E��~���p�ɂɍs���邽�߂ɃG���W������̃p�e�L�����[�g�r�o�ʂ��������邱�Ƃ���A�|�X�g����
�ɂ��t�B���^�̍Đ����p�ɂɍs�����Ƃ��K�v�ƂȂ�B���̃|�X�g���˂ɂ��DPF�̎����Đ��̕p�x�ɔ�Ⴕ�ĔR��
���Q���邽�߁A�|�X�g���ˍĐ���DPF���ڂ̐V�����K���iH17�N�j�K���̏��^�f�B�[�[���g���b�N�ł́A�����s�R
��������������Ă��܂��̂��B�ܘ_�A�r�C�Ǖ��ˍĐ�����DPF���u�ł��ADPF�̎����Đ��̕p�x�ɔ�Ⴕ�ĔR��
���Q���邱�Ƃ́A�|�X�g���ˍĐ���DPF���u�����l�ł���B
�@���̂��߁A�V�����K���iH17�N�j�K�����|�X�g���ˎ�DPF���u�𓋍ڂ������^�f�B�[�[���g���b�N�́A�ȑO�̋K����
�����V�Z���K���iH15�N)�K�����|�X�g���ˎ�DPF���u�𓋍ڂ��Ă��Ȃ����^�f�B�[�[���g���b�N�ɔ�ׁA�����s�R��
���R�O���O����������Ă���̂ł���B���̂��Ƃ́A�r�C�Ǖ��ˍĐ�����DPF���u�ł��S�����l�ł���B
�����V�Z���K���iH15�N)�K�����|�X�g���ˎ�DPF���u�𓋍ڂ��Ă��Ȃ����^�f�B�[�[���g���b�N�ɔ�ׁA�����s�R��
���R�O���O����������Ă���̂ł���B���̂��Ƃ́A�r�C�Ǖ��ˍĐ�����DPF���u�ł��S�����l�ł���B
�R�D�J�������܂߂���v�ȃf�B�[�[���G���W���̔R����P�̋Z�p
�@�\�Q�́A�Љ�{�����R�c�������E��ʐ����R�c���ʑ̌n�����������E��X����c�����i2008�N
2��14���i�o�T�Fhttp://www.mlit.go.jp/singikai/koutusin/koutu/kankyou/goudou9/080214/03.pdf�j���L�ڂ���Ă���
�f�B�[�[���G���W������уK�\�����G���W���₻���͌��Ƃ��鎩���Ԃ̎�v�ȔR��팸�Z�p��������Ă���B
2��14���i�o�T�Fhttp://www.mlit.go.jp/singikai/koutusin/koutu/kankyou/goudou9/080214/03.pdf�j���L�ڂ���Ă���
�f�B�[�[���G���W������уK�\�����G���W���₻���͌��Ƃ��鎩���Ԃ̎�v�ȔR��팸�Z�p��������Ă���B
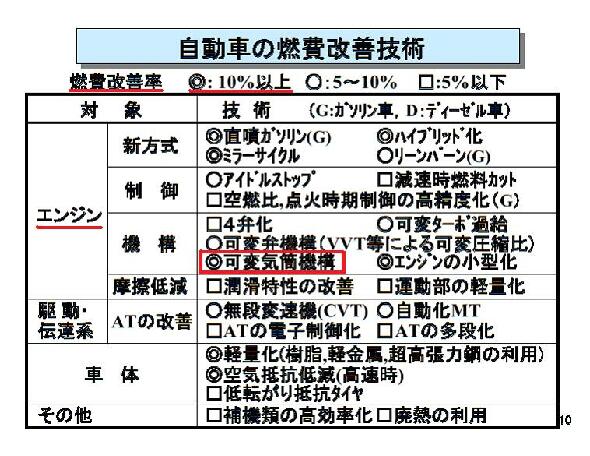
���F�Ԏ��͕M�҂̒NjL�����@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�@�\�Q�ɂ����ĂP�O���ȏ�̃G���W���R�����ł���ƋL�ڂ���Ă���Z�p�̒��ŁA�f�B�[�[���G���W���K�p�\��
�R����P�Z�p�Ƃ��Ă̓n�C�u���b�h���A�~���[�T�C�N���A�ϋC���@�\�i�C���x�~�G���W�����j����уG���W���̏��^
���ł���B�����̒��̉ϋC���@�\�i�C���x�~�G���W�����j�ȊO�̋Z�p�ł́A�^�[�{�ߋ��f�B�[�[���G���W����
�ڂ�����^�g���b�N�łP�O���ȏ�̔R����P��}�邱�Ƃ́A����Ǝv����B���̗��R���ȉ��̕\�R�Ɏ������B
�R����P�Z�p�Ƃ��Ă̓n�C�u���b�h���A�~���[�T�C�N���A�ϋC���@�\�i�C���x�~�G���W�����j����уG���W���̏��^
���ł���B�����̒��̉ϋC���@�\�i�C���x�~�G���W�����j�ȊO�̋Z�p�ł́A�^�[�{�ߋ��f�B�[�[���G���W����
�ڂ�����^�g���b�N�łP�O���ȏ�̔R����P��}�邱�Ƃ́A����Ǝv����B���̗��R���ȉ��̕\�R�Ɏ������B
| |
|
| |
�@�]���̓s�s�����s�̏�p�Ԃł́A�R��̗��K�\�����G���W���̒ᕉ�ׂł̉^�]�����p�����
���߁A�K�\�����G���W����p�Ԃ̔R������Ȃ����������B�n�C�u���b�h�V�X�e���̏�p�Ԃ́A
�ᕉ�ׂ̃G���W���̉^�]�̈�����[�^�[�쓮�ő�ւ��ĔR��̈����K�\�����G���W���̒ᕉ�^�]
���ł��邾�����Ȃ����邱�Ƃɂ���ĔR����P���\�ɂ������̂ł���B
�@����A���^�f�B�[�[���g���b�N�́A��p�Ԃ����p���[�E�G�C�g���V�I�i�G���W���o�͓������
GVW[�ԗ����d��]�j�����{���傫���B���̂��߁A������^�f�B�[�[���g���b�N�ł́A��p�Ԃ̏ꍇ
�����f�B�[�[�����W����������ʼn^�s����邱�ƂɂȂ�B���̂悤�ɁA�R������̗��ᕉ��
�^�]�̕p�x�����Ȃ����^�g���b�N�ł́A�ᕉ�ׂ̃G���W���̉^�]�̈�����[�^�[�쓮�ő�ւ���
�n�C�u���b�h�V�X�e�������Ă����[�^�[�쓮����g�ł���@����Ȃ����߁A�n�C�u���b�h
�V�X�e���ɂ��R����P�̌��ʂ��\���ɔ����ł��Ȃ����ƂɂȂ�B���̂悤�ɁA���^�f�B�[�[��
�g���b�N�ł��u���[�L�G�l���M�[������ꍇ�������āA�G���W���쓮�̑��s�ɂ�����R��팸��
�قƂ�ǂł��Ȃ����߁A���^�n�C�u���b�h�g���b�N�ł̓n�C�u���b�h��p�Ԃ̂悤�ȓs�s�����s
�ł̔R��̉��P�͍����ł���B
�@�܂��A��^�f�B�[�[���g���b�N�́A���^�f�B�[�[���g���b�N�����p���[�E�G�C�g���V�I�i�G���W��
�o�͓������GVW[�ԗ����d��]�j�����{���傫���A�������s�s�Ԃ̍������H��M���̏��Ȃ�
�n�������̘A�������������s����̂̂ł���B���̂����A��^�n�C�u���b�h�g���b�N�ł́A
���i�E��~�̑����s�s�����s�̏��^�n�C�u���b�h�g���b�N�����X�ɔR����P�ł��Ȃ�
���Ƃ͖��炩�ł���B���������āA��^�g���b�N��Ώۂɍl�����ꍇ�ɂ́A�n�C�u���b�h��
�ɂ��P�O���ȏ�̔R����P���\�Ƃ���}�R�̋L�ڂɂ͋^�₪����ƍl�������B
���������āA�����i���A��^�n�C�u���b�h�g���b�N���L�����y���čs�����Ƃ́A�L�蓾�Ȃ��ƍl����
�ԈႢ�Ȃ��̂ł͂Ȃ����낤���B
(�ڍׂ����^�n�C�u���b�h �g���b�N�͏�p�Ԃ̂悤�ȔR����P���������Q�Ɓj�@
|
| |
�@���݁A�K�\�����G���W���Ŏ��p������Ă���~���[�T�C�N���́A�z�C�ق̑������͒x���ɂ����
���k�s���ɔ�ׂĖc���s�������A�쓮�K�X�̖c������P�ȏ�ɑ傫�����ăG���W���̃T�C�N�� ���������サ�ĔR������P�ł���悤�ɂ������̂ł���B���̃~���[�T�C�N���̉^�]���ɂ͎����� �s���e�ς��������Ȃ邽�߁A���r�C�ʂɌ��������G���W���̍ő�o�́i�ő�g���N�j���o�͂���Ȃ� ���ƂɂȂ�B���̂悤�ɁA�~���[�T�C�N���^�]�͕������^�]���݂̂ɉ^�]�ł���^�]�`�Ԃƌ��� �����x���Ȃ��B�g���^�̃v���E�X�̂悤�ȃn�C�u���b�h�V�X�e���ł́A�G���W���̍ő�g���N���K�v�� �������ɂ̓��[�^�쓮�͂�t�����邱�Ƃɂ���āA�~���[�T�C�N���G���W���̃n�C�u���b�h��p�Ԃ� �ʏ�̃K�\�����G���W���̏�p�ԂƓ����ɑ��s���\���m�ۂ��Ă���̂�����ł���B �@�܂��A�n�C�u���b�h�V�X�e���̖����]���̎����ԂɃ~���[�T�C�N���G���W���𓋍ڂ���ꍇ�ɂ́A �z�C�ق̉σo���u�^�C�~���O�@�\���̗p���邱�Ƃɂ���ď]���̃G���W���Ɠ����̍ő�o�� �i�ő�g���N�j�邱�Ƃ��\�ƂȂ�B���̉σo���u�^�C�~���O�@�\��������~���[�T�C�N�� �V�X�e�����f�B�[�[���G���W���ɓK�p�����ꍇ�A�~���[�T�C�N���^�]���̈��k��̑啝�Ȓቺ�� �����邽�߁A���k���x�̒ቺ�������Čy���̎��Ȓ����s�\�ɂȂ�B���̂��߁A�f�[�[���G���W�� �ł̓K�\�����G���W���̃��x���܂ō����c����ʼn^�]���邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B�����̔��p�f�B�[�[�� �G���W���ɂ�����~���[�T�C�N���̔R����P�͂Q�����x�ɗ��܂��Ă���̂�����ł���B (�o�T�@http://niigata-power.com/whats_new/080924_AHX.html�j ���������āA�z�C�ق̉σo���u�^�C�~���O�@�\��p�����~���[�T�C�N���V�X�e�����f�B�[�[�� �G���W���ɓK�p�����ꍇ�ł��R����P�͐��p�[�Z���g���x�ɗ��܂邽�߁A�~���[�T�C�N�� �ł͂P�O���ȏ�̔R����P���\�Ƃ���\�R�̋L�ڂ́A��^�f�B�[�[���g���b�N��Ώ� �Ƃ����ꍇ�ɂ͌��ƌ��ĊԈႢ�Ȃ����낤�B |
| |
�@��ʓI��660cc�̔r�C�ʐ���������y�����Ԃ́A�ԗ����d�ʂ��������1000�����̏��^��p��
�������s�R����X��������B����͌y�����ԃG���W���̃g���N�����^��p�ԃG���W���̃g���N �����Ⴂ���߁A�y�����Ԃ����^��p�Ԃ������ϓI�ɃG���W���̍���]���ő��s������Ȃ� ���߂ł���B�������A�y�����Ԃ�660cc�̃G���W���ߋ����Ē��]�����܂߂đS�ẴG���W����] �̈�̃g���N�����^��p�Ԃ�1000�����̃G���W���Ɠ���ɂȂ�悤�ɂ���A��A�y�����Ԃ� �R��͏��^��p�Ԃ̔R������P���邱�Ƃ��\�ƂȂ�B�y�����Ԃ�660cc�̃G���W���ߋ����� ���]�����܂߂đS�ẴG���W����]�̈�̃g���N�����^��p�Ԃ�1000�����̃G���W���Ɠ���� ����ɂ́A�u�e�ʂ̈قȂ�Q��̃^�[�{�ߋ��@��ɔz���Q�i�ߋ��V�X�e���v���̗p���邩�A �Ⴕ���́u�@�B���ߋ��ƃ^�[�{�ߋ��̑g�ݍ��킹���ߋ��V�X�e���v���̗p����K�v������B �@���̂悤�Ɂu�Q�i�ߋ��V�X�e���v��u�@�B���ߋ��ƃ^�[�{�ߋ��̑g�ݍ��킹���ߋ��V�X�e���v�� �p�����G���W���_�E���T�C�W���O�ł̓G���W���̑啝�ȏ��^���ɂ��R��팸���\�ł��邪�A �R�X�g�ʂ�����p���̖ʂł͖�肪����̂ł͂Ȃ����낤���B���������āA��^�g���b�N�ɂ����� �G���W���̏��r�C�ʉ��́A���s���\�̒ቺ�����e�ł���͈͂Ɏ��܂�30�����x�̃_�E�� �T�C�W���O�����E�ł͖������ƍl������B�܂��A�A�G���W�����^���ɂ��r�C�u���[�L�̐��\ �ቺ�́A��^�g���b�N�ɂ����Ă͒v���I�ȕs����邱�ƂɂȂ�B���̕s���h�~���邽�߁A �G���W�����^���ɂ��r�C�u���[�L�̐��\�ቺ��h�~���邽�߂ɁA�d�C���A�i�v���Ύ��܂��� �������̃��^�[�_��V���ɒlj��܂��͑�^����}��K�v������B���̃��^�[�_�̒lj����^���́A �R�X�g�A�b�v��ԗ��d�ʂ̑����v���ƂȂ�A��^�g���b�N�ɂƂ��čD�܂������Ƃł͂Ȃ��B �@�G���W���̏��^���ɂ��\���ȔR����P�́A���^������O�̃G���W���Ɠ���̃g���N�����i�o�� �����j���m�ۂł��Ă��邱�Ƃ��O��ł���B�S�ẴG���W�����^�[�{�ߋ��d�l�̑�^�g���b�N�p �f�B�[�[���G���W���̐��E�ɂ����āA�G���W���̏��^���ɂ��R��팸��}�邽�߂ɂ́A ���r�C�ʂɂ��ăG���W���̓����ō����͂�啝�ɑ��������ďo�͂��ێ�����K�v������B �߂������A����ɂ킽��G���W���Z�p�i�ޗ��Z�p�A�V�[���Z�p�A�g���C�|���W�Z�p�j�� �S����ł̋Z�p�J�������ٓI�ɐi�W����Ƃ͍l������Ƃ���A����̃f�B�[�[���g���b�N �̃G���W���̍ő�g���N�Ȑ��i�o�͓����j��傫���ቺ�����Ȃ��ŃG���W�����i�i�ɏ��^�� ���邱�Ƃ́A�����_�ł͓�����Ƃł͂Ȃ����ƍl������B���������āA�G���W���̏��^�� �ɂ���ĂP�O���ȏ�̔R����P���\�Ƃ���\�R�̋L�ڂ͌��̂悤�Ɏv����̂ł����B |
�@�܂��A�]������^�f�B�[�[���g���b�N�ɂƂ��Ă͔R����P���ŏd�v�̉ۑ�ł��邽�߁A����̃g���b�N���[�J�ł���
�ɐV�����f�B�[�[���G���W���̔R�����Z�p�̊J���ɒ��킵�Ă���悤���B�f�B�[�[���G���W���̔R����P�Ɋ֘A
���A�^�[�{�R���p�E���h�A��i�ߋ�����тk�o�k�@�d�f�q�iLow Pressure Loop EGR�j���J�����s���Ă���A�ꕔ���[�J
�ł͂�������ɏ��i�����ĂƂ��������B�i�\�S�Q�ƕ��j
�ɐV�����f�B�[�[���G���W���̔R�����Z�p�̊J���ɒ��킵�Ă���悤���B�f�B�[�[���G���W���̔R����P�Ɋ֘A
���A�^�[�{�R���p�E���h�A��i�ߋ�����тk�o�k�@�d�f�q�iLow Pressure Loop EGR�j���J�����s���Ă���A�ꕔ���[�J
�ł͂�������ɏ��i�����ĂƂ��������B�i�\�S�Q�ƕ��j
| |
|
|
|
| |
�V���ɔr�C�K�X
�̃G�l���M�[�� ��������� �^�[�r����t�� ���A������� �G�l���M�[�� �G���W������ �Ƃ��Ď��o�� ���u |
�@����^�[�r���̓����̔r�C�K�X�͒ቷ�E�ሳ�ł��邽�߁A�r�C�K�X
�̃G�l���M�[�̃|�e���V�������Ⴂ�B���̂��ߔr�C�K�X�̑̐ϗ��� �������A����^�[�r���͑�^�����K�v�ƂȂ�B���̌��ʃR�X�g�������A ���ԗ����ڂ��e�ՂȂ��Ƃł͂Ȃ��B�܂��A�R����P�́A�������� ���肳����ɁA���̍����ח̈�ɂ�����R�0�`1.5�����x�� ���P��邾���Ƃ̂��Ƃł���B���������āA�^�[�{�R���p�E���h �ɂ��d�ʎԃ��[�h�R��l�̉��P�́A�����ח̈�ɂ�����R����P �̔����ȉ��A����0�`0.7���ȉ��ł͂Ȃ����Ɛ��������B �@���������āA���̃^�[�{�R���p�E���h�̋Z�p�́A�R�����ł͖����A �����ő刳�͂��㏸�����邱�Ɩ����o�͂������ł����i�ł��� ���Ƃ��ő�̓����ł���B���������āA�R����P�̖ʂ��猩��A �R�X�g�p�[�t�H�[�}���X�̒Ⴂ�Z�p�Ɖ]����B (�ڍׂ��^�[�{�R���p�E���h�́A��^�g���b�N�̑��s�R��̉��P������� �Z�p���I�A�C���x�~�́A�f�B�[�[���r�C�K�X�̃G�l���M�[���u�� �������������Q�Ɓj�@ |
�{���{�A�f�g���C�g
�f�B�[�[���̑�^ �g���b�N�p�G���W�� �ɍ̗p����Ă���B |
| |
�Q��̃^�[�{
�ߋ��@�� �ɔz�u���� ��i�K�ʼnߋ� ����V�X�e�� �܂��� �؊��ق𑽗p ���ăG���W�� ����̔r�C�K�X�̗� ��𐧌�\ �ɂ��ď��^�� ��^�̃^�[�{ �ߋ��@����� �Ⴕ���͒��� �ɍ쓮�ł��� �悤�ɔz�u���A �G���W���� �^�]������ �]���ĂQ��� �ߋ��̍쓮�� �œK�ɐ��� ����V�X�e���B �i�V�[�P���V���� �^�[�{�V�X�e�� �Ƃ��]���j |
�@���s�̉ߋ��@��p�����ꍇ�ł��L���G���W�����ח̈�ō���
�ߋ��@�����̉ߋ����\�ƂȂ鍂�ߋ��^�̓�i�ߋ������́A ���������ɐ��p�[�Z���g�̔R����P�������܂��B���������� ���ʂ邽�߂ɂ́A2��̉ߋ��@�������ɍ������ʼn^�]�ł��� �܂ŋ��C�̉ߋ������グ��K�v������A���̏ꍇ�̈��͔�� 3�`4�ɒB����Ǝv����B���̎��̃G���W���̐������ϗL�� �o������3.5MPa���x�܂ō����Ȃ�ƍl�����邽�߁A��������p�� ���邽�߂ɂ́A�G���W���͖��\�L�̒������̓������ɑς���悤�� �������m�ۂ���Z�p��A�܂��V���ȏ����̋Z�p���J������K�v ������B �܂��A�R�ĉ��x���������㏸���邽�߁A�G���W����p�ɂ��Ă��Z�p �J�����s���K�v������ƍl������B���ɁA���̍��ߋ��^�̓�i �ߋ������̋Z�p�������ł����Ƃ��Ă��A�G���W���͏��r�C�ʂ� �Ȃ邪�啝�ȃR�X�g�A�b�v�ƂȂ�A���]���̃^�[�{�G���W������ �X�ɃG���W���ߓn�^�]���̏o�͉����̒x�����\���� ����B���̂��߁A���ߋ����̓�i�ߋ������́A���ʁA�g���b�N�p �Ƃ��Ď��p������͓̂���Z�p�Ɛ��������B ����A�G���W���̒������̉�]���x�ł͉ߋ�����]�葝���� �����ɒႢ��]���x�ʼnߋ������グ�A�G���W���̓����ő刳�́A �ő�g���N����эō��o�͂��]���̃G���W����葽���̑���� ��������Ƌ��ɁA���]���̃g���N��啝�ɑ���������ᑬ�g���N �����^�̓�i�ߋ�����������B���̒ᑬ�g���N�����^�̓�i �ߋ������́A�č��̃C���^�[�i�V���i���̃G���W�� MaxxForce5�A11�A13�̂R�@��ɍ̗p����Ă���B���̕����ł́A �g���b�N�̉^�]����啝�Ɍ���ł��郁���b�g������A���s���� �ᑬ�M�A��̎g�p�p�x�̑����ɂ�鑽���̑��s�R��̉��P�� �\�ł��邪�A��i�ߋ��ɂ��G���W�����̂̒������R����P �̌��ʂ͓����Ȃ��B �Ȃ��A����ɔz�u�������^�Ƒ�^�̃^�[�{�ߋ��@�̋��C�ʘH�� �r�C�ʘH�̂��ꂼ��ɒʘH�̐؊��ق�݂��Ă��G���W���^�] �����ɂ���ċ��C�Ɣr�C�K�X�̗�����œK�ɐ��䂷�� �Q�i�V�[�P���V�����^�[�{�V�X�e���ɂ���ĉ��}�̂悤�ɃG���W�� �̒ᑬ�g���N�̌��オ�\�ł���B 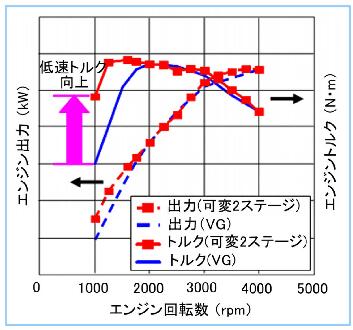 pdf�j 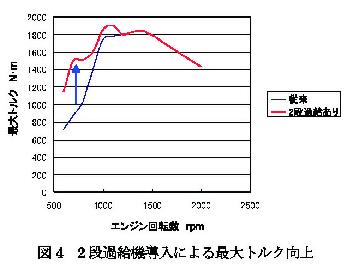 �Q�i�V�[�P���V�����^�[�{�V�X�e���ł́A�G���W���{�̂̔R��͏�����
���ł�����x�ł���A�R��팸�̃����b�g�͋ɂ߂ď��Ȃ����̂ł���B�� ���A�Q�i�V�[�P���V�����^�[�{�V�X�e���̃G���W���ᑬ�̃g���N�A�b�v�� ��^����Q�i�^�[�{�̏��^�^�[�{�̑���ɓd���A�V�X�g�^�[�{�ߋ��@ ��p����V�X�e������Ă���Ă���B���́u�d���A�V�X�g�^�[�{�ߋ��@�{ �^�[�{�ߋ��@�̃V�X�e���v�ł́A�G���W���̒��]�ɂ�����g���N�̌��� �ɂ���ăg���b�N�̉^�]�����啝�Ɍ���ł��郁���b�g������B�������A�� �́u�d���A�V�X�g�^�[�{�ߋ��@�{�^�[�{�ߋ��@�̃V�X�e���v���܂߁A���� �̉ߋ��@��p����Q�i�V�[�P���V�����^�[�{�V�X�e���ɂ����ĔR��팸 �Ɍ��ʂ��F�߂���̂́A���s���ɂ�����ᑬ�M�A��̎g�p�p�x�̑� ���ɂ��͂��ȑ��s�R��̉��P�����ł���B |
�@�����U�����Ԃ�
�|�X�g�V�����K�� �K���̒��^�g���b�N �łQ�i�V�[�P���V�� ���^�[�{�V�X�e���� ���ڂ��Ă��邽�߁A �����U�̒��^�g���b�N �ł́A���}�̂悤�� �G���W���ɒ��] �ł̃g���N������ �ł��Ă�����̂� �l������B���� ���߁A���̒��^ �g���b�N�͑��Ђ� ���^�g���b�N�ɔ�� �ēs�s���ި���� �̑��s�������� ����Ă���ƌ���� �邪�A�R��팸 ���ʂɂ��ẮA �^��ł���B �@�����Ƃ��A��i �ߋ��ɂ��R�� ����̌��ʂ͒Ⴂ ���A�G���W���� �ᑬ�g���N�̑��� �ɂ��g���b�N�� ���������̑��s�� ������ł��邽 �߁A�ᑬ�g���N �����^�̓�i �ߋ��G���W���� �č��ł����p�� ����Ă���B |
| |
�@�㏈���G�}��
�̃K�X���^�[�{ �̏㗬�i�ߋ��@ �̃R���v���b�T �̓����j�Ɋҗ� ����Low Pressure Loop (LPL) EGR HPL EGR��LPL EGR�p���� ���Ƃɂ���� ���p�����\ |
�@LPL�� EGR�́C�ߓn�^�]���ɉ����x������C�ቷ�����
��EGR���\�ł���D�܂��C�S�ẴK�X���^�[�r����ʉ߂��� ���߁C�r�C�G�l���M�[�̉���C�ߋ����̑������\�ƂȂ�D �������A�㏈���G�}��̔r�C�K�X�ł���EGR�K�X�ɂ͌y������ ���f�̔R�ĂŐ�������ʂ�H�QO�i�����j���܂܂�Ă���B �R���v���b�T�̓����Ɋҗ����������𑽂��܂�EGR�K�X�͉ߋ��@ �̃R���v���b�T�ō�������AAir to Air�C���^�[�N�[����50�����x �̉��x�ȉ��ɗ�p�����B���̏ꍇ�ɂ̓C���^�[�N�[���̓��ǖ� �ɐ������I�������肪������ƍl������B �@���ɁA�~�G�ł͋C�����ቺ���邽�߁AEGR�K�X�̍������� �������C��Air to Air�C���^�[�N�[����20�`30�����x�܂ŗ�p �����ꍇ������B���̂悤�Ȏ��ɃG���W���ɑ�ʂ�EGR�K�X�� �җ�����^�]���s��ꂽ�ꍇ�ɂ́A�M�҂̖ϑz��������Ȃ����A Air to Air�C���^�[�N�[�����ł͑�ʂ̐������I�����A���̘I�� ����������Air to Air�@�C���^�[�N�[�����l�܂点����A�V�����_�� �ɑ��ʂ̐������z������ăG���W���I�C���ɍ�������댯�� �l������B���̂��߁ALPL�� EGR�����p�ɋ�����ꍇ�ɂ́A LPL EGR�́A���肳�ꂽ�G���W���̉^�]�����łł̍쓮���� �\���ɂȂ���̂ƍl������B �@�Ȃ��A�]����HPL�i=High Pressure Loop�j�@EGR�݂̂𓋍ڂ��� �G���W���ł́A�u�[�X�g���̍����ߋ��@�����̗ǂ��G���W���^�] �̈�ł�EGR���\�ɂ��邽�߂ɂ́A�ߋ��@������ቺ������ �G���W���^�]�ƂȂ邽�߂ɁA��̔R������錇�_�� �������B�������AHPL EGR��LPL EGR�̗�����EGR�V�X�e���� �G���W���^�]�����ɂ���Đ�ւ���\���Ƃ��ėp���邱�� �ɂ���āA�u�[�X�g���̍����ߋ��@�����̗ǂ��G���W���^�]�̈� �ɂ�������G���W���̔R�����h�~���邱�Ƃ��\�ƂȂ� ���߁A�����Ƃ��R������P�ł�����ʂ�����B�������Ȃ���A LPL EGR�̕��p�ɂ��R����P�̌��ʂ͂���قǒ����� ���̂ł͂Ȃ��B |
�@HPL EGR��LPL
EGR�p���邱�� �ɂ���āA������ �R����P���\ �ł���B �������A���̔R�� ���P�̌��ʂ� ����قǒ����� ���̂ł͂Ȃ��B |
| |
�@�z�C�ًy��
�r�C�ق���� �܂��͓d���� �ō쓮������ �V�X�e�� |
�@�����쓮���ŋz�C�قƔr�C�ق����t�g�����z�C�قƔr�C�ق�
�J�����Ԗʐς������ł���J�����X�V�X�e���ł́A�G���W���� �|���s���O�����̍팸�ɂ��R��ጸ���\�Ȃ�B�܂��z�C�� �̑������͒x���ɂ�葊�ΓI�ɖc���s��������~���[ �T�C�N���ɂ�藝�_�I�ɔR��ጸ��}�邱�Ƃ��\�ł���B �����ŁA�ŋ߂̔��p�G���W���ł͖������ŋz�C�قƔr�C�ق��쓮 ����J�����X�V�X�e�����̗p���A�f�B�[�[���G���W���ŋz�C�ق� �������͒x���ɂ�葊�ΓI�ɖc���s�������ă~���[ �T�C�N���ʼn^�]����@�\���̗p����A���������̔R��ጸ�� �}���Ă���B �@���̃J�����X�V�X�e���́A�e�Ղɕ��������Ƀ~���[�T�C�N�� �Ƃ��ĉ^�]���A�R��ጸ���\�ɂ���ȊO�ɂ��A����̐؊��� �ȒP�ɃG���W���̋t��]���\�Ȃ��߁A�t��]�̕K�v�ȑD���p �f�B�[�[���Ŏ��p������Ă���B���̂悤�ɁA���p�f�B�[�[�� �G���W���ł́A�J�����X�V�X�e���́A�R����P�ƒ�R�X�g�̋t�] ���u�Ƃ��Ă̋@�\�������ł��邽�߂Ɏ��p������Ă���悤���B �Ȃ��A�����̔��p�f�B�[�[���G���W���ɂ��~���[�T�C�N���� �R����P�͂Q�����x(�o�T�@http://niigata-power.com/whats_new/ 080924_AHX.html�j�ɗ��܂��Ă���̂�����̂悤�ł���B ���āA�{�b�V�����͂��ߐ��Ђ̕��i���[�J�[�́A�g���b�N�p�G���W�� �̖����쓮�ŋz�C�قƔr�C�ق����t�g���A�R�Ď��z�E�r�C�� �s���J�����X�V�X�e�����J�����Ă���A�����I�Ƀg���b�N���[�J�[�� �ւ̕��i������_���Ă���悤���B�܂��A�����U�����ԁA���� �����ԂȂǂ̑�^�g���b�N���[�J�[���Ǝ��ɃJ�����X�G���W���� �������n�߂Ă���Ƃ̂��Ƃł���B���̃J�����X�G���W���̗ǂ� �Ƃ���́A�z�C�قƔr�C�ق̊J���ʐς傳���ă|���s���O �������팸���ĔR����P���邱�Ƃ�A�z�C�قٕ̕����𐧌� �����~���[�T�C�N���^�]���s�킹�邱�Ƃɂ���ĕ������ׂ̔R�� �����P���邱�Ƃ��ł��邱�Ƃł���B �@�������Ȃ���A�g���b�N�p�̍����f�B�[�[���G���W���ɂ��̃J�����X �V�X�e�����̗p�����ꍇ�ɂ́A�|���s���O�����̍팸�̂��͂��� �R����P�ƃ~���[�T�C�N���ɂ��Q�����x�̔R����P�����v���� �R��̉��P�ʂ��A�����ō쓮������J�����X�V�X�e���ł� �ً쓮�����ɂ��R��������Ă��]�肠��\���ȔR��̉��P ���l���ł��邩�ǂ����ɂ��āA���݁A��������Ă���Ƃ��� �ł���B�܂��A�J�����X�V�X�e����p�����~���[�T�C�N���ɂ���� �L�����k��̉ω��ł��邱�Ƃ𗘗p���ė\�����f�B�[�[���R�� �̈���g�傷�錤�����s���Ă���B�������A�x�[�X�ƂȂ�\���� �f�B�[�[���R�Ă͕s����ȔR�Ăł��邽�߂Ɏ��p�����̂��̂� ��Ԃ܂�Ă���Z�p�ł���B���ɃJ�����X�V�X�e�����\���� �f�B�[�[���R�Ă̗̈�g��ɉ��炩�̌��ʂ��������Ƃ��Ă��A �\�����f�B�[�[���R�Ă̋Z�p�����p���̖R�������Ƃ��l����A �J�����X�V�X�e�����\�����f�B�[�[���R�ĂɗL���Ȃ��Ƃ� �J�����X�V�X�e���̑������p���̍����ƍl����̂͑��v�ł���B �܂��A�J�����X�V�X�e���́A�d�q���䑕�u�iECU�j����̐M���� ���䂷������ŋz�C�قƔr�C�ق����t�g������\���ł���B���� �J�����X�V�X�e���̖��́A�M���̌�쓮���N�������ꍇ�ɂ� �قƃs�X�g�����Փ˂��Ă��܂��댯�����邱�Ƃ��B���ɃG���W���� �����^�]�ŃJ�����X�V�X�e������쓮���N�����A�قƃs�X�g���� �Փ˂��ĕَP���܂�ăV�����_���ɒE�������ꍇ�ɂ́A�u���� �G���W���{�̂ɉ�œI�ȑŌ������Ă��܂����ƂɂȂ�B ���������āA�J�����X�V�X�e���̓d�q���䑕�u�ɂ͓�d�A�O�d�� ���S��H��݂���K�v�����邪�A��^���p�G���W���ł͓�d�A �O�d�͌����ɋy���A�l�d�A�d�̈��S��H��݂����Ƃ��Ă��A �x�[�X�G���W�����ɂ߂č����Ȃ��߂ɃG���W���R�X�g�̑����� ���ɂȂ邱�Ƃ͖����ƍl������B��^���p�G���W���� �J�����X�V�X�e���ł́A�t�]�p�̃J���V���t�g���s�v�ƂȂ邽�߁A �R�X�g������������������Ȃ��B�������A�����ȃg���b�N�p �f�B�[�[���G���W���̏ꍇ�ɂ́A�J�����X�V�X�e���̓d�q���� ���u�ɓ�d�A�O�d�̈��S��H��݂��邱�Ƃ̓R�X�g�����̖ʂ� ���������̂�����ƍl������B �@����ɂ���A�e�Ђ̃J�����X�V�X�e�������J�����i�W����A ����A�J�����X�V�X�e���́A�u�R�X�g�A�b�v�̒��x�v��u�͂��ȔR�� ���P�̎��ԁv�����炩�ƂȂ�A�u�R�X�g�p�[�t�H�[�}���X�v�̖ʂ��� �g���b�N�p�Ƃ��Ď��p�����ɂ߂č���ȋZ�p�ł��邱�Ƃ����炩�� �Ȃ�̂ł͂Ȃ����낤���B |
�@�J�����X�V�X�e��
�͐���̐؊��� �ȒP�ɃG���W���� �t��]���\�� ���ƂƁA�������� �Ƀ~���[�T�C�N���^ �]�ɂ��R��ጸ ���\�Ȃ��Ƃ���A �D���p�f�B�[�[�� �Ŋ��Ɏ��p������ �Ă���B |
�@��^�g���b�N���[�J�ł́A��^�f�B�[�[���g���b�N�̔R����P�̂��߂ɁA�^�[�{�R���p�E���h���i�ߋ��ɉ����A�m�n��
�팸�̑啝�ȍ팸�Ƃ���ɔ����R����̖h�~��_���Ăk�o�k�@�d�f�q�iLow Pressure Loop EGR�j�̐V�Z�p���J����
�s���Ă���B�������Ȃ���A�����_�ł͂����V�Z�p�́A��^�g���b�N�̏\���ȔR����P�������ł���@�\�͖���
�ƍl������B���������āA�߂������A�k�o�k�@�d�f�q�iLow Pressure Loop EGR�j�ȊO�̋Z�p�́A�s�̂̑�^�f�B�[�[��
�g���b�N�ɍL���̗p����Ă����\���͂���قǍ����Ȃ��̂ł͂Ȃ����Ǝv���Ă���B
�팸�̑啝�ȍ팸�Ƃ���ɔ����R����̖h�~��_���Ăk�o�k�@�d�f�q�iLow Pressure Loop EGR�j�̐V�Z�p���J����
�s���Ă���B�������Ȃ���A�����_�ł͂����V�Z�p�́A��^�g���b�N�̏\���ȔR����P�������ł���@�\�͖���
�ƍl������B���������āA�߂������A�k�o�k�@�d�f�q�iLow Pressure Loop EGR�j�ȊO�̋Z�p�́A�s�̂̑�^�f�B�[�[��
�g���b�N�ɍL���̗p����Ă����\���͂���قǍ����Ȃ��̂ł͂Ȃ����Ǝv���Ă���B
�S�D��^�g���b�N����ɂ����鍡��̏d�v�ۑ�͔R��팸�̋Z�p�J��
�@��^�g���b�N�̕���ł́A����A�|�X�g�V�����r�o�K�X�K���i2009�N�K���j�₻�̌�̍X�Ȃ�m�n���팸�����K����
�̓K���ɂ͂m�n���Ƃo�l�̍팸���K�v�ł��邪�A�m�n���팸�͔A�f�r�b�q�G�}�A�o�l�팸�͂c�o�e���u�ɂ��ڕW���x��
�ɓ��B�����邱�Ƃ��\�ł���Ɖ]���Ă���B���̂悤�Ƀf�B�[�[���G���W���̔r�o�K�X�ጸ�ɂ��ẮA���̕�
�@�E��i�͌ł܂���邱�Ƃ͑����̐��Ƃ��F�߂�Ƃ���ł���B�f�B�[�[���G���W���ɂ�����r�o�K�X�㏈���Z
�p�����p�����ꂽ���Ƃɂ��A����܂ł̂悤�ȃf�B�[�[���G���W���̔R�ĉ��P�ɕ����r�o�K�X�팸�̕K�R���͑�
�������ނ������̂ƍl���ĊԈႢ���Ȃ��B���݂ł́A��^�f�B�[�[���g���b�N�ɂ����鏫���I�Ȕr�o�K�X�K���́A�r�o
�K�X�㏈���̋Z�p�ɂ���ēK�����\�ɂȂ����ƍl���ĊԈႢ�Ȃ����낤�B
�̓K���ɂ͂m�n���Ƃo�l�̍팸���K�v�ł��邪�A�m�n���팸�͔A�f�r�b�q�G�}�A�o�l�팸�͂c�o�e���u�ɂ��ڕW���x��
�ɓ��B�����邱�Ƃ��\�ł���Ɖ]���Ă���B���̂悤�Ƀf�B�[�[���G���W���̔r�o�K�X�ጸ�ɂ��ẮA���̕�
�@�E��i�͌ł܂���邱�Ƃ͑����̐��Ƃ��F�߂�Ƃ���ł���B�f�B�[�[���G���W���ɂ�����r�o�K�X�㏈���Z
�p�����p�����ꂽ���Ƃɂ��A����܂ł̂悤�ȃf�B�[�[���G���W���̔R�ĉ��P�ɕ����r�o�K�X�팸�̕K�R���͑�
�������ނ������̂ƍl���ĊԈႢ���Ȃ��B���݂ł́A��^�f�B�[�[���g���b�N�ɂ����鏫���I�Ȕr�o�K�X�K���́A�r�o
�K�X�㏈���̋Z�p�ɂ���ēK�����\�ɂȂ����ƍl���ĊԈႢ�Ȃ����낤�B
�@�Ƃ��낪�A�����r�o�K�X�㏈���̒���PM�팸�ɍ̗p����Ă���DPF���u�ł́A�K��ʈȏ��PM���t�B���^�ɑ͐�
�����ꍇ�ɂ́A�r�C�K�X���x��600�����x�̍����ɐ��䂷��蓮�Đ��܂��͎����Đ����s���K�v������B���݁A�c�o
�e���u�̃t�B���^���蓮�Đ��܂��͎����Đ�������@�Ƃ��ẮA�����̔R�ďI����̌y���˂���|�X�g���˕�
���i����A�����U�����̗p�j�Ɣr�C�Ǔ���HC�C���W�F�N�^�[����y���iHC�j�˂���g�b�r�C�Ǖ��˕���(�O�H�ӂ�
���A�t�c�A�{���{�����̗p�j�̂Q��ނ̍Đ����������p������Ă���B�����|�X�g���˕����Ƃg�b�r�C�Ǖ��˕�����
����̕����ɂ����Ă��A�c�o�e���u�̃t�B���^�Đ����ɂ͑��ʂ̔R����Q��錇�ׂ�����Ă��邱�Ƃ͕ς��͂�
���̂ł���B
�����ꍇ�ɂ́A�r�C�K�X���x��600�����x�̍����ɐ��䂷��蓮�Đ��܂��͎����Đ����s���K�v������B���݁A�c�o
�e���u�̃t�B���^���蓮�Đ��܂��͎����Đ�������@�Ƃ��ẮA�����̔R�ďI����̌y���˂���|�X�g���˕�
���i����A�����U�����̗p�j�Ɣr�C�Ǔ���HC�C���W�F�N�^�[����y���iHC�j�˂���g�b�r�C�Ǖ��˕���(�O�H�ӂ�
���A�t�c�A�{���{�����̗p�j�̂Q��ނ̍Đ����������p������Ă���B�����|�X�g���˕����Ƃg�b�r�C�Ǖ��˕�����
����̕����ɂ����Ă��A�c�o�e���u�̃t�B���^�Đ����ɂ͑��ʂ̔R����Q��錇�ׂ�����Ă��邱�Ƃ͕ς��͂�
���̂ł���B
�@�Ȃ��A�|�X�g���ˍĐ���DPF���u��g�b�r�C�Ǖ��ˍĐ���DPF���u�𓋍ڂ��Ă����s�s�ԑ��s�̑�^�f�B�[�[���g
���b�N�ł́A�p�ɂɔ��i�E��~���J��Ԃ��s�s�����s�̏��^�g���b�N�ɍs�����p�ɂȃt�B���^�Đ���K�v�Ƃ��Ȃ��B
���̂��߁A�s�s�ԑ��s�̑�^�f�B�[�[���g���b�N�ł��t�B���^�Đ������|�X�g���˂�g�b�r�C�Ǖ����ɂ���R���Q��
�͂���قǑ����͂Ȃ��ƍl�����邪�A�t�B���^�Đ������|�X�g���˂�g�b�r�C�Ǖ����ɂ��ɂ��R���Q��͊F��
�ł͂Ȃ��B���������āA���݂̂悤�ȔR�����P���ŏd�v�ۑ�ɂȂ��Ă��鎞��ł́A�g���b�N�̒ʏ푖�s�ɂ����ă|�X
�g���˂�g�b�r�C�Ǖ��˓��̔R���ʂɘQ����t�B���^�Đ����s�v�ɂł���c�o�e���u�̍Đ��V�X�e���̊J����
�f�B�[�[���g���b�N�̋i�ق̉ۑ�ƍl������B
���b�N�ł́A�p�ɂɔ��i�E��~���J��Ԃ��s�s�����s�̏��^�g���b�N�ɍs�����p�ɂȃt�B���^�Đ���K�v�Ƃ��Ȃ��B
���̂��߁A�s�s�ԑ��s�̑�^�f�B�[�[���g���b�N�ł��t�B���^�Đ������|�X�g���˂�g�b�r�C�Ǖ����ɂ���R���Q��
�͂���قǑ����͂Ȃ��ƍl�����邪�A�t�B���^�Đ������|�X�g���˂�g�b�r�C�Ǖ����ɂ��ɂ��R���Q��͊F��
�ł͂Ȃ��B���������āA���݂̂悤�ȔR�����P���ŏd�v�ۑ�ɂȂ��Ă��鎞��ł́A�g���b�N�̒ʏ푖�s�ɂ����ă|�X
�g���˂�g�b�r�C�Ǖ��˓��̔R���ʂɘQ����t�B���^�Đ����s�v�ɂł���c�o�e���u�̍Đ��V�X�e���̊J����
�f�B�[�[���g���b�N�̋i�ق̉ۑ�ƍl������B
�@���݂ɁA�|�X�g���˕����̂c�o�e�Đ����ɂ�����R���Q��ɂ��ẮA�R����̃|�X�g���˂��~�߁A�C���x�~��
DPF���Đ�����V�Z�p�̃y�[�W�ɏڏq���Ă���B���̃y�[�W�ł́A�|�X�g���ˍĐ���DPF���u�𓋍ڂ��Ă����V����
�K���iH17�N�j�K���̏��^�f�B�[�[���g���b�N������DPF�𓋍ڂ��Ă��Ȃ��V�Z���K���iH15�N)�K�������^�f�B�[�[��
�g���b�N�ɔ�ׁA�R�O���O����̎����s�R��������Ă��錻�ǎ҂ɂ͗ǂ��������Ă�����������̂Ǝv����B
���ɑ����̃f�B�[�[���g���b�N�ɑ�������Ă����|�X�g���ˍĐ���DPF���u�ł́A�l�����W�n��𑖍s����ꍇ�̕p
�ɂȔ��i�E��~������E�����ɂ����DPF���u�̃t�B���^�Ƀp�e�B�L�����[�g�̑͐ς��������Ȃ邽�߂��|�X�g���˂ɂ�
��t�B���^�Đ����p�x���������A�|�X�g���˂ɂ���R���Q������Ď����s�R��������Ă���̂�����ł���B��
���A�g�b�r�C�Ǖ��˕����̂c�o�e�Đ����̔R���Q����|�X�g���˕����ƑS�����l�ł���B
DPF���Đ�����V�Z�p�̃y�[�W�ɏڏq���Ă���B���̃y�[�W�ł́A�|�X�g���ˍĐ���DPF���u�𓋍ڂ��Ă����V����
�K���iH17�N�j�K���̏��^�f�B�[�[���g���b�N������DPF�𓋍ڂ��Ă��Ȃ��V�Z���K���iH15�N)�K�������^�f�B�[�[��
�g���b�N�ɔ�ׁA�R�O���O����̎����s�R��������Ă��錻�ǎ҂ɂ͗ǂ��������Ă�����������̂Ǝv����B
���ɑ����̃f�B�[�[���g���b�N�ɑ�������Ă����|�X�g���ˍĐ���DPF���u�ł́A�l�����W�n��𑖍s����ꍇ�̕p
�ɂȔ��i�E��~������E�����ɂ����DPF���u�̃t�B���^�Ƀp�e�B�L�����[�g�̑͐ς��������Ȃ邽�߂��|�X�g���˂ɂ�
��t�B���^�Đ����p�x���������A�|�X�g���˂ɂ���R���Q������Ď����s�R��������Ă���̂�����ł���B��
���A�g�b�r�C�Ǖ��˕����̂c�o�e�Đ����̔R���Q����|�X�g���˕����ƑS�����l�ł���B
�@�Ƃ���ŁACO�Q�팸��Ȏ����E�ȃG�l���M�[�����߂�ŋ߂̎Љ�j�[�Y�̍��܂���A�f�B�[�[���G���W������
�̂̃g���b�N�E�o�X��ΏۂƂ��āA�d�ʎԁi�ԗ����d��2.5t��)�̎����Ԃɑ���2015�N�x�i����27�N�x�j�d�ʎԔR��
���V���ɋK�肵���@�����{�s���ꂽ�B����ɂ��A����̑�^�g���b�N�Ɋ֘A�����Z�p�J���ɂ��ẮA�r�o�K
�X�팸�����f�B�[�[���G���W���̔R��팸�i��CO�Q�팸�j�̋Z�p�J���ɏd�_���ڂ���čs�����̂ƍl������B
�̂̃g���b�N�E�o�X��ΏۂƂ��āA�d�ʎԁi�ԗ����d��2.5t��)�̎����Ԃɑ���2015�N�x�i����27�N�x�j�d�ʎԔR��
���V���ɋK�肵���@�����{�s���ꂽ�B����ɂ��A����̑�^�g���b�N�Ɋ֘A�����Z�p�J���ɂ��ẮA�r�o�K
�X�팸�����f�B�[�[���G���W���̔R��팸�i��CO�Q�팸�j�̋Z�p�J���ɏd�_���ڂ���čs�����̂ƍl������B
�@���̂悤�ɁACO�Q�팸��Ȏ����E�ȃG�l���M�[�����߂��Ă��錻�݁A��^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W���֘A�̔R
����P���ł��d�v�ȉۑ�̈�ł���B���̉ۑ�̉����ɂ́A�G���W���{�̂̔R������P���邱�ƂƁA���s�̃|�X�g
���ˍĐ������Ƃg�b�r�C�Ǖ��ˍĐ������̂c�o�e���u�ɂ�����t�B���^�Đ����̔R���Q����팸���邱�Ƃ��K�v�ł�
��B�����f�B�[�[���G���W���{�̂̔R��팸�ƁA���s�̂c�o�e���u�̃t�B���^�Đ����ɂ�����R���Q��̖h�~
�̗������L���ȋZ�p�Ƃ����A�M�҂��Q�^�[�{�ߋ��@�������C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j���l��
�����B���̂Q�^�[�{�ߋ��@�����̋C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�́A��^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W����
�̗p���邱�Ƃɂ�����A��^�f�B�[�[���g���b�N�̔R��T�`�P�O�����x�����P�ł�����̂ƍl���Ă���B�Ȃ��A�|�X�g
���˂��g�b�r�C�Ǖ����ɂ��t�B���^�Đ��̕p�x�����������ĔR���Q��̌��ʂ�{�������邽�߂ɂ́A�㏈������
�V�X�e���i�������J2005-69238�j��g�ݍ��킹�邱�Ƃ��L���ł���B
����P���ł��d�v�ȉۑ�̈�ł���B���̉ۑ�̉����ɂ́A�G���W���{�̂̔R������P���邱�ƂƁA���s�̃|�X�g
���ˍĐ������Ƃg�b�r�C�Ǖ��ˍĐ������̂c�o�e���u�ɂ�����t�B���^�Đ����̔R���Q����팸���邱�Ƃ��K�v�ł�
��B�����f�B�[�[���G���W���{�̂̔R��팸�ƁA���s�̂c�o�e���u�̃t�B���^�Đ����ɂ�����R���Q��̖h�~
�̗������L���ȋZ�p�Ƃ����A�M�҂��Q�^�[�{�ߋ��@�������C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j���l��
�����B���̂Q�^�[�{�ߋ��@�����̋C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�́A��^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W����
�̗p���邱�Ƃɂ�����A��^�f�B�[�[���g���b�N�̔R��T�`�P�O�����x�����P�ł�����̂ƍl���Ă���B�Ȃ��A�|�X�g
���˂��g�b�r�C�Ǖ����ɂ��t�B���^�Đ��̕p�x�����������ĔR���Q��̌��ʂ�{�������邽�߂ɂ́A�㏈������
�V�X�e���i�������J2005-69238�j��g�ݍ��킹�邱�Ƃ��L���ł���B
�T�D�e�C���̕��א���̍œK�ȃ}�l�W�����g�ɂ��f�B�[�[���G���W���̔R����P
�@����܂Ő��̒��ɍL�����y���Ă���Ζ��R���̌y����R���Ƃ���f�B�[�[���G���W���ł͔R����P�̊����͂b�n�Q
�팸�̊����Ɠ������Ȃ邽�߁A���̃f�B�[�[���G���W���́u�R����P�v�́u�b�n�Q�팸�v�Ɠ����Ӗ��i���`��ɋ߂��Ӗ��j
�������ƂɂȂ�B���̃f�B�[�[���G���W���ɂ��āA�����ԋZ�p��s�́u�����ԋZ�p�v��Vol.64�ANo.�P�A2010
�i2010�N1���P�����s�j�Ɍf�ڂ̘_���u�f�B�[�[���G���W�����̂P�O�N�v�i���ҁF�ѓc�P�� �c�勳���Ƒ��R���j�́u�T ����
��Ɂv�ɂ́A�ȉ��̂悤�ɋL�q����Ă���B
�팸�̊����Ɠ������Ȃ邽�߁A���̃f�B�[�[���G���W���́u�R����P�v�́u�b�n�Q�팸�v�Ɠ����Ӗ��i���`��ɋ߂��Ӗ��j
�������ƂɂȂ�B���̃f�B�[�[���G���W���ɂ��āA�����ԋZ�p��s�́u�����ԋZ�p�v��Vol.64�ANo.�P�A2010
�i2010�N1���P�����s�j�Ɍf�ڂ̘_���u�f�B�[�[���G���W�����̂P�O�N�v�i���ҁF�ѓc�P�� �c�勳���Ƒ��R���j�́u�T ����
��Ɂv�ɂ́A�ȉ��̂悤�ɋL�q����Ă���B
�T�@������
�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E �r�o�K�X�̃N���[������B�������f�B�[�[���G���W���ɂƂ��āA�r�oCO�Q�̂����
��팸�͍�����傫�Ȓ���ۑ��ł���A����ۑ�̒B���ɂ́A�]���̃f�B�[�[���G���W���̗v�f�Z�p�J���ɉ�
���A�R���A�R�āA�G�}�̌����A�V�X�e������̓������Z�p�����߂��Ă���B�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E
|
�@���̂悤�ɁA���̔ѓc�P�� �c�勳���Ƒ��R���̘_���ł́A�f�B�[�[���G���W����CO�Q�팸�i���R����P�j���u�傫��
����ۑ�v�ƒf�肳��Ă���A���́u�ۑ�B���v�ɂ́u�]���̃f�B�[�[���G���W���̗v�f�V�X�e���ɉ����A�R���A�R�āA
�G�}�̌����A�V�X�e������̓������Z�p�����߂��Ă���v�ƋL�ڂ���Ă��邾�����B�����āA�f�B�[�[���G���W����
CO�Q�팸�i���R����P�j�ɗL���ȋZ�p����̓I�Ɉ���L�q����Ă��Ȃ��̂��B���̂悤�ɁA�ѓc �c�勳���Ƒ��R
���̒��҂́A��̓I�ȋZ�p�A�C�e��������������Ɩ����A�f�B�[�[���G���W����CO�Q�팸�i���R����P�j�́u�傫��
����ۑ�v�Ǝ咣���Ă���݂̂ł���B���̎咣��Ղ����t�Œu��������A�u�ǂ��f�B�[�[���G���W�����J����
��I�v�Əq�ׂĂ���ɉ߂��Ȃ��̂ł���B����́A���Ƃ����g�ɖ����咣�ł͂Ȃ����낤���B
����ۑ�v�ƒf�肳��Ă���A���́u�ۑ�B���v�ɂ́u�]���̃f�B�[�[���G���W���̗v�f�V�X�e���ɉ����A�R���A�R�āA
�G�}�̌����A�V�X�e������̓������Z�p�����߂��Ă���v�ƋL�ڂ���Ă��邾�����B�����āA�f�B�[�[���G���W����
CO�Q�팸�i���R����P�j�ɗL���ȋZ�p����̓I�Ɉ���L�q����Ă��Ȃ��̂��B���̂悤�ɁA�ѓc �c�勳���Ƒ��R
���̒��҂́A��̓I�ȋZ�p�A�C�e��������������Ɩ����A�f�B�[�[���G���W����CO�Q�팸�i���R����P�j�́u�傫��
����ۑ�v�Ǝ咣���Ă���݂̂ł���B���̎咣��Ղ����t�Œu��������A�u�ǂ��f�B�[�[���G���W�����J����
��I�v�Əq�ׂĂ���ɉ߂��Ȃ��̂ł���B����́A���Ƃ����g�ɖ����咣�ł͂Ȃ����낤���B
�@���݁A�e�g���b�N���[�J�̑����̃G���W���Z�p�҂́A�f�B�[�[���G���W���̔R����P��CO�Q�팸�ɗL���ȋZ�p���J
�����ׂ��A���X�A�������ƍl������B���̂悤�ȃg���b�N���[�J�̑����̃G���W���Z�p�҂́A�f�B�[�[���G���W���̔R
����P��CO�Q�팸�̋Z�p��̎��������߂Ď����ԋZ�p��s�́u�����ԋZ�p�v��Vol.64�ANo.�P�A2010�i2010�N1��
�P�����s�j�Ɍf�ڂ̘_���u�f�B�[�[���G���W�����̂P�O�N�v��ǂ�ł�����̂ƍl������B�������A���̘_����ǂݏI
���A���҂̔ѓc�P�� �c�勳���Ƒ��R�����A�u�f�B�[�[���G���W����CO�Q�팸�i���R����P�j���u�傫�Ȓ���ۑ�v�Ǝ�
������Ă��邱�Ƃɗ��_���ꂽ�l�����������̂��͂Ȃ����낤���B���̂悤�ɁA�ѓc�P�� �c�勳���Ƒ��R���̘_��
�́A�u�f�B�[�[���G���W���̔R����P��CO�Q�팸�v�Ɍ��ʂ̂���Z�p�𑁊��Ɏ���������悤�ɒP�Ɏ��B���サ�Ă�
�邾���ł���A���̒��ɂ͉ۑ�̉����ɖ𗧂Z�p�I�Ȓm���������L�ڂ���Ă��Ȃ��̂��B
�����ׂ��A���X�A�������ƍl������B���̂悤�ȃg���b�N���[�J�̑����̃G���W���Z�p�҂́A�f�B�[�[���G���W���̔R
����P��CO�Q�팸�̋Z�p��̎��������߂Ď����ԋZ�p��s�́u�����ԋZ�p�v��Vol.64�ANo.�P�A2010�i2010�N1��
�P�����s�j�Ɍf�ڂ̘_���u�f�B�[�[���G���W�����̂P�O�N�v��ǂ�ł�����̂ƍl������B�������A���̘_����ǂݏI
���A���҂̔ѓc�P�� �c�勳���Ƒ��R�����A�u�f�B�[�[���G���W����CO�Q�팸�i���R����P�j���u�傫�Ȓ���ۑ�v�Ǝ�
������Ă��邱�Ƃɗ��_���ꂽ�l�����������̂��͂Ȃ����낤���B���̂悤�ɁA�ѓc�P�� �c�勳���Ƒ��R���̘_��
�́A�u�f�B�[�[���G���W���̔R����P��CO�Q�팸�v�Ɍ��ʂ̂���Z�p�𑁊��Ɏ���������悤�ɒP�Ɏ��B���サ�Ă�
�邾���ł���A���̒��ɂ͉ۑ�̉����ɖ𗧂Z�p�I�Ȓm���������L�ڂ���Ă��Ȃ��̂��B
�@���������āA���̘_���̔ѓc�P���c�勳���Ƒ��̒��҂R���̎咣�ړI�Ȍ��t�ɒu��������A�f�B�[�[���G
���W����CO�Q�팸�i���R����P�j�́A�u�Z�p�I�ɔ����ǂ���v�̏ɂ���Ƃ̈Ӗ��ł���A�u�����_�ł͋Z�p�I�ȉ�
���s���v�Ɨ������Ă��傫�ȊԈႢ�͖����ƍl������B ���̋L�q�̓��e�ɂ��āA�����̂Ƀf�B�[�[���G���W
���̌����J���Ɍg������o���̂��錳�Z�p���̕M�҂ɂƂ��ẮA�҂������肾�B
���W����CO�Q�팸�i���R����P�j�́A�u�Z�p�I�ɔ����ǂ���v�̏ɂ���Ƃ̈Ӗ��ł���A�u�����_�ł͋Z�p�I�ȉ�
���s���v�Ɨ������Ă��傫�ȊԈႢ�͖����ƍl������B ���̋L�q�̓��e�ɂ��āA�����̂Ƀf�B�[�[���G���W
���̌����J���Ɍg������o���̂��錳�Z�p���̕M�҂ɂƂ��ẮA�҂������肾�B
�@���݂ɁA�u�����ԋZ�p�v���́A����[�߂Ă��鎩���ԋZ�p��̉���ɍŐV�̋Z�p����`���邱�Ƃ��{���̖�
�I�̔��ł���B���̂悤�ȁu�����ԋZ�p�v���ɁA�ѓc�P���c�勳���Ƒ��̒��҂R���́A�f�B�[�[���W�҂������ɋ�
�����Ă���ۑ�����̎����ƂȂ�悤�ȋZ�p�I�Ȏ����〈��������������A�������A�ォ��ڐ��Łu�f�B�[�[���G��
�W����CO�Q�팸�i���R����P�j�͑傫�Ȓ���ۑ�v�Ƃ��ēǎ҂̎����ԋZ�p��̉���ɉۑ���������B���シ��_
���\���Ă���̂��B���̂悤�Ȏ��B����Łu�����ԋZ�p�v���̎��ʂ������̂́A�u�y�[�W�̖��ʁv�A�u�����̘Q��v
�ł͂Ȃ����낤���B�Ȃ��Ȃ�A�����ԋZ�p��̑����̉���́A�Ζ���ŏ�i���疈���̂悤�ɁA�u�R����P�ɗL����
�Z�p�𑁊��ɊJ������I�v�Ƃ̎��B������Ă���Ɛ��@������邽�߂��B�����ԋZ�p��̉���̋Z�p�҂́A��
�Ђɏo����A������ӂ܂ŔR����P�̋Z�p�J���𑣂����B����Ŏ��Ƀ^�R���ł��Ă���̂ł���B�����̎���
�ԋZ�p��̉�������̂悤�ȏɒu����Ă��钆�ŁA�V���ȋZ�p������邱�Ƃ����҂��āu�����ԋZ�p�v��
�̃y�[�W���J���Ă݂�ƁA�_���̒��Ɏ��B����̌��t������Ă���̂ł���B�����ڂɂ��������ԋZ�p��̉��
�̒��ɂ́A�u���̖𗧂����I�v�Ɠ{����o����l������������̂ł͂Ȃ����낤���B���̂悤�ȐV���ȋZ�p�����L��
�����Ɏ��B���シ��_�����f�ڂ����u�����ԋZ�p�v���̕ҏW�Ɍg������l�B�́A��́A�����l���Ă���̂��Ɩ₢
���������Ƃ��낾�B
�I�̔��ł���B���̂悤�ȁu�����ԋZ�p�v���ɁA�ѓc�P���c�勳���Ƒ��̒��҂R���́A�f�B�[�[���W�҂������ɋ�
�����Ă���ۑ�����̎����ƂȂ�悤�ȋZ�p�I�Ȏ����〈��������������A�������A�ォ��ڐ��Łu�f�B�[�[���G��
�W����CO�Q�팸�i���R����P�j�͑傫�Ȓ���ۑ�v�Ƃ��ēǎ҂̎����ԋZ�p��̉���ɉۑ���������B���シ��_
���\���Ă���̂��B���̂悤�Ȏ��B����Łu�����ԋZ�p�v���̎��ʂ������̂́A�u�y�[�W�̖��ʁv�A�u�����̘Q��v
�ł͂Ȃ����낤���B�Ȃ��Ȃ�A�����ԋZ�p��̑����̉���́A�Ζ���ŏ�i���疈���̂悤�ɁA�u�R����P�ɗL����
�Z�p�𑁊��ɊJ������I�v�Ƃ̎��B������Ă���Ɛ��@������邽�߂��B�����ԋZ�p��̉���̋Z�p�҂́A��
�Ђɏo����A������ӂ܂ŔR����P�̋Z�p�J���𑣂����B����Ŏ��Ƀ^�R���ł��Ă���̂ł���B�����̎���
�ԋZ�p��̉�������̂悤�ȏɒu����Ă��钆�ŁA�V���ȋZ�p������邱�Ƃ����҂��āu�����ԋZ�p�v��
�̃y�[�W���J���Ă݂�ƁA�_���̒��Ɏ��B����̌��t������Ă���̂ł���B�����ڂɂ��������ԋZ�p��̉��
�̒��ɂ́A�u���̖𗧂����I�v�Ɠ{����o����l������������̂ł͂Ȃ����낤���B���̂悤�ȐV���ȋZ�p�����L��
�����Ɏ��B���シ��_�����f�ڂ����u�����ԋZ�p�v���̕ҏW�Ɍg������l�B�́A��́A�����l���Ă���̂��Ɩ₢
���������Ƃ��낾�B
�@���āA����܂ł̃f�B�[�[���G���W�������W���Ă������j�̒��ŁA�f�B�[�[���G���W���͔R�ĉ��P�ɂ���Ă�����x
�̔R����P�i��CO�Q�팸�j���}���Ă��������͐����ɔF�߂邪�A���݂ł̓f�B�[�[���G���W���̔R����P�i��CO
�Q�팸�j�̋Z�p�J�����傫�ȕǂɓ˂��������Ă��邱�Ƃ͊m���Ȃ悤���B����A�X�Ȃ�R����P�i��CO�Q�팸�j������
���čs�����߂ɂ́A�M�҂͑��C���G���W���̊e�C���̕��א�����œK�Ƀ}�l�W�����g���邱�Ƃ��K�v�Ǝv���Ă���B��
���āA���́u�C�����א���}�l�W�����g�v�̍œK���ȊO�ɁA�f�B�[�[���G���W���ɂ�����\���ȔR����P�i��CO�Q��
���j�͍���ł͂Ȃ����Ǝv���Ă���B�f�B�[�[���G���W���̔R����P�i��CO�Q�팸�j���e�ՂɎ����ł���u�C�����א�
��}�l�W�����g�v�Ƃ��āA�M�҂���Ă��Ă���̂��Q�^�[�{�ߋ��@�����́w�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�x
�̋Z�p�ł���B���̃g���b�N�p�f�B�[�[���G���W���̔R���e�Ղɉ��P�ł���C���x�~�f�B�[�[���G���W���ɂ��āA
�ȉ��ɂ��̊T�v���������B
�̔R����P�i��CO�Q�팸�j���}���Ă��������͐����ɔF�߂邪�A���݂ł̓f�B�[�[���G���W���̔R����P�i��CO
�Q�팸�j�̋Z�p�J�����傫�ȕǂɓ˂��������Ă��邱�Ƃ͊m���Ȃ悤���B����A�X�Ȃ�R����P�i��CO�Q�팸�j������
���čs�����߂ɂ́A�M�҂͑��C���G���W���̊e�C���̕��א�����œK�Ƀ}�l�W�����g���邱�Ƃ��K�v�Ǝv���Ă���B��
���āA���́u�C�����א���}�l�W�����g�v�̍œK���ȊO�ɁA�f�B�[�[���G���W���ɂ�����\���ȔR����P�i��CO�Q��
���j�͍���ł͂Ȃ����Ǝv���Ă���B�f�B�[�[���G���W���̔R����P�i��CO�Q�팸�j���e�ՂɎ����ł���u�C�����א�
��}�l�W�����g�v�Ƃ��āA�M�҂���Ă��Ă���̂��Q�^�[�{�ߋ��@�����́w�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�x
�̋Z�p�ł���B���̃g���b�N�p�f�B�[�[���G���W���̔R���e�Ղɉ��P�ł���C���x�~�f�B�[�[���G���W���ɂ��āA
�ȉ��ɂ��̊T�v���������B
�U�D�C���x�~�G���W���ɂ���^�f�B�[�[���g���b�N�̔R����P
�U�|�P�D�A�C�h���X�g�b�v�ƈقȂ�^�[�{�ߋ��f�B�[�[���G���W���̋C���x�~�V�X�e��
�A�C�h���X�g�b�v�͎����Ԃ̒�Ԏ��ɃG���W�����~���邾���̂��̂ł���B���������ăA�C�h���X�g�b�v�ɂ���ē���
���R������̉��P�̗ʂ́A�����ׂň��̉�]���Ɉێ�����Ă���A�C�h�������O���̔R�����ʂɃA�C�h������
�O�^�]���Ԃ��悶��ΎZ�o�������̂��B���̂��߃A�C�h���X�g�b�v�ɂ��R����P�́A�����ԑ��s�̑����Ԑ���
���̃A�C�h�����O�^�]�̐�߂鑍���Ԑ�����������A�P���Ɍv�Z�ł���̂ł���B
���R������̉��P�̗ʂ́A�����ׂň��̉�]���Ɉێ�����Ă���A�C�h�������O���̔R�����ʂɃA�C�h������
�O�^�]���Ԃ��悶��ΎZ�o�������̂��B���̂��߃A�C�h���X�g�b�v�ɂ��R����P�́A�����ԑ��s�̑����Ԑ���
���̃A�C�h�����O�^�]�̐�߂鑍���Ԑ�����������A�P���Ɍv�Z�ł���̂ł���B
�@����ɑ��A�^�[�{�ߋ��f�B�[�[���G���W���ɂ�����C���x�~�̋Z�p�́A�A�C�h���X�g�b�v�Ƒ傫���قȂ�Z�p�ł�
��B�悸�A�^�[�{�ߋ��f�B�[�[���G���W���̋C���x�~�̃V�X�e���ł́A�\�R�Ɏ������悤�ɁA�^�[�{�ߋ��@�̑䐔����
��B�悸�A�^�[�{�ߋ��f�B�[�[���G���W���̋C���x�~�̃V�X�e���ł́A�\�R�Ɏ������悤�ɁA�^�[�{�ߋ��@�̑䐔����
�߂ċ��C�������قȂ����Q��ނ̃V�X�e�������݂���B
| |
|
|
| |
|
���@�Q��̃^�[�{�ߋ��@�����ɑ�������Q�^�[�{�����̋C���x�~�f�B�[�[��
�G ���W���̋C���x�~�V�X�e���B
���@���̃V�X�e���̏� �ׂ��C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̃y�[�W �������������������B |
| |
���@�C���x�~�̍ő�ړI�ł������������̑啝�ȔR��팸��SCR�G�}
�̊������i�ɂ��\����NO���팸���\
�i�T�`�P�O�����x�̎����s�R���d�ʎԃ��[�h�R��l�̍팸���\�j ���@�x�~�^�]����C���Q�̋z�C�قƔr�C�ق̗����A���͕Ј���𖧕� ��z�E�r�C�ق̃��t�g���䂪�s�v |
|
| |
���@�^�[�{�ߋ��@�͂Q��i���������e�ʁj �̂��߃R�X�g�������傫������
���@���C�n�Ɣr�C�n�����G |
|
| |
|
���@�]���̃V���O���^�[�{��Q�i�ߋ��̃f�B�[�[���G���W����P���ɋC���x�~��
���ꍇ �̋C���x�~�̃V�X�e���ł���B
���@�{���{�̂b�n�Q�팸�i���R�����j�̋Z�p�������� �@�@�i�z�E�r�C�ق��x�~�����V���O���^�[�{�����̋C���x�~�𐄏�����L���j �i�o�T�Fhttp://www.its.ucdavis.edu/events/outreachevents/asilomar2007/ presentations/Day%202%20Session%201/Anthony%20Greszler.pdf�j 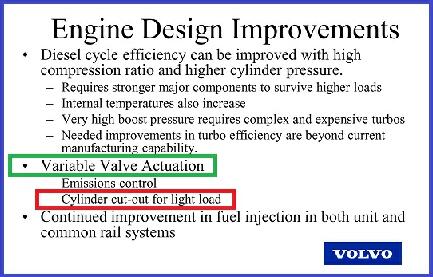 |
| |
���@�V���O���^�[�{�̃f�B�[�[���G���W���ł́A�^�[�{�ߋ��@�͂P��i��������e
�ʁj���߂ɃR�X�g���������Ȃ�����
���@���C�n�Ɣr�C�n���V���v�� |
|
| |
���@�C���x�~�̍ő�ړI�ł������������̔R��팸��SCR�G�}�̊���
���ɂ��NO���팸���啝�ɗ�邱��
���@�C���x�~�^�]���̔M�����̌����}�邽�߂ɂ́A�x�~�^�]����C���Q�� �z�C�قƔr�C�ق̗����A���͕Ј���𖧕���z�E�r�C�ق̃��t�g���䂪 �K�v (���݂ɁA�x�~�^�]����C���Q�̋z�C�قƔr�C�ق̗����A���͕Ј���𖧕� ��z�E�r�C�ق̃��t�g��������{���Ȃ��ꍇ�͔r�C�K�X���x�̒ቺ�ɂ��A�f SCR�G�}�ł�NO���팸�@�\����錇�_������B�j ���@�G���W���̑S�C���̉ғ���Ԃ���ꕔ�̋C�����x�~����^�]�Ɉڍs����
�ہA�x�~����C���Q�̋z�C�قƔr�C�ق̗����A���͕Ј���𖧕������u�Ԃ�
�͉ߋ��@�𗬂�鋋�C�ʂ��}�����邽�߁A�ߋ��@�̃u���A���T�[�W�����N����
�s�����������B����̕s���h�~���邽�߂ɂ́A�G���W���̑S�C���̉�
���^�]����ꕔ�C�����x�~�^�]�ɂ͊ɂ₩�Ɉڍs������K�v������B���̂�
�߁A���̋z�E�r�C�ًx�~�����̋C���x�~�V�X�e�����̗p�����ꍇ�A�S�C���̉�
���^�]����ꕔ�C�����x�~�^�]�ֈڍs�����鎞�̏o�͂́A�ɂ₩�ɒቺ����
�邱�Ƃ��K�v�ł���B���̌��ʁA�z�E�r�C�ًx�~�����̋C���x�~���̗p����
�f�B�[�[���G���W���́A�������̗��o�͐���̃G���W���ƂȂ錇�_����
�����ƁB
|
|
�@���̂悤�ɁA�ߋ��f�B�[�[���G���W���ł́A�u�Q�^�[�{�����v�Ɓu�z�E�r�C�ًx�~�����v�̂Q��ނ̋C���x�~�V�X�e����
����B����̕����̋C���x�~�G���W���ɂ����Ă��A�C���x�~�^�]���̉ғ��C���ł́u��p�����̌����v�A�u�T�C�N��
�����̌���v�ɂ��R����P�������邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��B�������A�����Q��ނ̋C���x�~�G���W���ł̋C���x�~
�^�]���s���������^�]���r����ƁA�Q�^�[�{�����C���x�~�V�X�e���̃^�[�{�ߋ��@�̉ߋ��@�����́A
�z�E�r�C�ًx�~�C���x�~�V�X�e���̃^�[�{�ߋ��@�̉ߋ��@����������ɍ��������ʼn^�]�ł���̂ł���B
�����āA�Q�^�[�{�����ł̋C���x�~�G���W���́A�z�E�r�C�ًx�~�̂ŋC���x�~�G���W���ɔ�r���āA�C���x�~
�̉^�]�̈悪�L�����Ƃ������̈�ł����B���̂��߁A�u�Q�^�[�{�����C���x�~�V�X�e���v�̕����u�z�E�r�C�ًx
�~�C���x�~�V�X�e���v�ɔ�ׂėD�ꂽ�R����P��������̂��B����ɂ��ẮA�C���x�~�G���W���ɂ���^�g��
�b�N�̒�R��̃y�[�W�ɂ��������L�ڂ��Ă���̂ŁA������䗗�������������B
����B����̕����̋C���x�~�G���W���ɂ����Ă��A�C���x�~�^�]���̉ғ��C���ł́u��p�����̌����v�A�u�T�C�N��
�����̌���v�ɂ��R����P�������邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��B�������A�����Q��ނ̋C���x�~�G���W���ł̋C���x�~
�^�]���s���������^�]���r����ƁA�Q�^�[�{�����C���x�~�V�X�e���̃^�[�{�ߋ��@�̉ߋ��@�����́A
�z�E�r�C�ًx�~�C���x�~�V�X�e���̃^�[�{�ߋ��@�̉ߋ��@����������ɍ��������ʼn^�]�ł���̂ł���B
�����āA�Q�^�[�{�����ł̋C���x�~�G���W���́A�z�E�r�C�ًx�~�̂ŋC���x�~�G���W���ɔ�r���āA�C���x�~
�̉^�]�̈悪�L�����Ƃ������̈�ł����B���̂��߁A�u�Q�^�[�{�����C���x�~�V�X�e���v�̕����u�z�E�r�C�ًx
�~�C���x�~�V�X�e���v�ɔ�ׂėD�ꂽ�R����P��������̂��B����ɂ��ẮA�C���x�~�G���W���ɂ���^�g��
�b�N�̒�R��̃y�[�W�ɂ��������L�ڂ��Ă���̂ŁA������䗗�������������B
�@�{���{�́A�C���x�~�̃K�\�����G���W���Ɠ��l�ȁA�z�E�r�C�ق��x�~���ăV�����_�𖧕���@�\�����z�E�r�C��
�x�~�����̃f�B�[�[���G���W���̋C���x�~�V�X�e�����Ă��Ă��邪�A���{�̃g���b�N���[�J���{���{�Ɠ��l�̋z�E�r
�C�ًx�~�����̃f�B�[�[���G���W���̋C���x�~�V�X�e�����l���Ă���悤�ł���B���Ƃ��������B���{�̃g���b�N���[
�J���o�肵�Ă���f�B�[�[���G���W���̋z�E�r�C�ًx�~�����̋C���x�~�V�X�e���Ɋւ�������E���p�V�Ă��A�ȉ���
�\�Q�Ɏ������B
�x�~�����̃f�B�[�[���G���W���̋C���x�~�V�X�e�����Ă��Ă��邪�A���{�̃g���b�N���[�J���{���{�Ɠ��l�̋z�E�r
�C�ًx�~�����̃f�B�[�[���G���W���̋C���x�~�V�X�e�����l���Ă���悤�ł���B���Ƃ��������B���{�̃g���b�N���[
�J���o�肵�Ă���f�B�[�[���G���W���̋z�E�r�C�ًx�~�����̋C���x�~�V�X�e���Ɋւ�������E���p�V�Ă��A�ȉ���
�\�Q�Ɏ������B
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
�@�ȏ�̕\�Q�Ɏ��������{�̃g���b�N���[�J������܂ŏo�肵�Ă���C���x�~�Ɋւ�������E���p�V�Ă�����
�ƁA�w�ǑS�Ă��z�E�r�C�ًx�~�����̋C���x�~�V�X�e���Ɍ����Ă����悤���B�����āA��������ȍ~�ɏڏq��
���悤�ȕM�Ғ�Ă��Q�^�[�{�����̋C���x�~�V�X�e��[�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j]�ɗގ����������o
��́A���̂Ƃ���P���������悤�ł���B
�ƁA�w�ǑS�Ă��z�E�r�C�ًx�~�����̋C���x�~�V�X�e���Ɍ����Ă����悤���B�����āA��������ȍ~�ɏڏq��
���悤�ȕM�Ғ�Ă��Q�^�[�{�����̋C���x�~�V�X�e��[�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j]�ɗގ����������o
��́A���̂Ƃ���P���������悤�ł���B
�@�����āA���_���猾���ƁA�z�E�r�C�ًx�~�����̋C���x�~�V�X�e���́A�M�҂���Ă��Ă����Q�^�[�{�����̋C���x
�~�V�X�e��[�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j]�����C���x�~�ʼn^�]�ł���G���W�����ׂ��Ⴂ���_����
��B���̌��ʁA�z�E�r�C�ًx�~�����̋C���x�~�V�X�e���́A�Q�^�[�{�����̋C���x�~�X�e��[�C���x�~�G���W���i��
�����J2005-54771�j]�ɔ�r���A��^�g���b�N�̍��������s���̔R����P��d�ʎԃ��[�h�R��̉��P���啝�ɗ��
���_�E���ׂ�����B����ɂ��ẮA���쎩���Ԃ��_�����\�����R����P�@�\�̗��C���x�~�V�X�e���̃y�[�W��
�ڍׂ��Ă���̂ŁA�����̂�����͂����������������B
�~�V�X�e��[�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j]�����C���x�~�ʼn^�]�ł���G���W�����ׂ��Ⴂ���_����
��B���̌��ʁA�z�E�r�C�ًx�~�����̋C���x�~�V�X�e���́A�Q�^�[�{�����̋C���x�~�X�e��[�C���x�~�G���W���i��
�����J2005-54771�j]�ɔ�r���A��^�g���b�N�̍��������s���̔R����P��d�ʎԃ��[�h�R��̉��P���啝�ɗ��
���_�E���ׂ�����B����ɂ��ẮA���쎩���Ԃ��_�����\�����R����P�@�\�̗��C���x�~�V�X�e���̃y�[�W��
�ڍׂ��Ă���̂ŁA�����̂�����͂����������������B
�@���̂悤�ɁA�z�E�r�C�ق̖����ɂ��z�E�r�C�ًx�~�����̋C���x�~�V�X�e���ł́A�V���O���^�[�{�����̑�^
�g���b�N�p�U�C���ߋ��f�B�[�[���G���W���̏ꍇ�ɂ́A�R�C�����x�~����G���W���^�]���w�Ǖs�\�Ɖ]���v���I��
���ׂ����邽�߂��B����A���̂悤�ȋz�E�r�C�ًx�~�����̋C���x�~�V�X�e���ƈقȂ�A�Q�^�[�{�����̋C���x�~�G
���W��[�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j]�́A0�`�P/2 ���ׂ̍L���^�]�̈�ŋC���x�~���\�ƂȂ�D�ꂽ
������������Z�p�ł���B���̂悤�ɁA�Q�^�[�{�����̋C���x�~�G���W��[�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j]
�́A�L���G���W���^�]�̈�ŋC���x�~���\�Ȃ��߁A�z�E�r�C�ًx�~�����̋C���x�~�V�X�e���̉ߋ��f�B�[�[���G
���W���ɔ�r���āA�C���x�~�ɂ��u�R�����v�ƁuSCR�G�}�ł�NO���팸�v�̖ʂŗD�ꂽ���ʂ������ł���̂ł�
��B
�g���b�N�p�U�C���ߋ��f�B�[�[���G���W���̏ꍇ�ɂ́A�R�C�����x�~����G���W���^�]���w�Ǖs�\�Ɖ]���v���I��
���ׂ����邽�߂��B����A���̂悤�ȋz�E�r�C�ًx�~�����̋C���x�~�V�X�e���ƈقȂ�A�Q�^�[�{�����̋C���x�~�G
���W��[�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j]�́A0�`�P/2 ���ׂ̍L���^�]�̈�ŋC���x�~���\�ƂȂ�D�ꂽ
������������Z�p�ł���B���̂悤�ɁA�Q�^�[�{�����̋C���x�~�G���W��[�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j]
�́A�L���G���W���^�]�̈�ŋC���x�~���\�Ȃ��߁A�z�E�r�C�ًx�~�����̋C���x�~�V�X�e���̉ߋ��f�B�[�[���G
���W���ɔ�r���āA�C���x�~�ɂ��u�R�����v�ƁuSCR�G�}�ł�NO���팸�v�̖ʂŗD�ꂽ���ʂ������ł���̂ł�
��B
�@���͂Ƃ�����A�\�P�Ɏ������悤�ɁA�{���{�E�g���b�N�X����{�̃g���b�N���[�J�̃G���W���Z�p�҂́A�C���x�~�̋Z
�p�Ƃ��ẮA�u�R�����v�ƁuSCR�G�}�ł�NO���팸�v�̌��ʂ̗��z�E�r�C�ًx�~�����̋C���x�~�V�X�e���̉ߋ�
�f�B�[�[���G���W���̋C���x�~���l���Ă���悤�ł���B���̋z�E�r�C�ًx�~�����̋C���x�~�V�X�e���́A�K�\�����G
���W���ƋC���x�~�V�X�e�������̂܂ܖ͕킵���Z�p���ߋ��f�B�[�[���G���W���ɓK�p�����̂Ɛ��@�����B���̂��Ƃ�
��A�g���b�N���[�J�̃G���W���̃G���W���Z�p�҂́A�ߋ��f�B�[�[���G���W���ł́u�R�����v�ƁuSCR�G�}�ł�NO����
���v�̋@�\�̗��z�E�r�C�ًx�~�����̋C���x�~�V�X�e���������Ɏv�������Ȃ������Ƃ���A�ނ�̔��z����
�O�ɖR�����ƌ����Ă��d���������̂ł͂Ȃ����낤���B
�p�Ƃ��ẮA�u�R�����v�ƁuSCR�G�}�ł�NO���팸�v�̌��ʂ̗��z�E�r�C�ًx�~�����̋C���x�~�V�X�e���̉ߋ�
�f�B�[�[���G���W���̋C���x�~���l���Ă���悤�ł���B���̋z�E�r�C�ًx�~�����̋C���x�~�V�X�e���́A�K�\�����G
���W���ƋC���x�~�V�X�e�������̂܂ܖ͕킵���Z�p���ߋ��f�B�[�[���G���W���ɓK�p�����̂Ɛ��@�����B���̂��Ƃ�
��A�g���b�N���[�J�̃G���W���̃G���W���Z�p�҂́A�ߋ��f�B�[�[���G���W���ł́u�R�����v�ƁuSCR�G�}�ł�NO����
���v�̋@�\�̗��z�E�r�C�ًx�~�����̋C���x�~�V�X�e���������Ɏv�������Ȃ������Ƃ���A�ނ�̔��z����
�O�ɖR�����ƌ����Ă��d���������̂ł͂Ȃ����낤���B
�@�������Ȃ���A��^�g���b�N�ɂ�����u�R�����v�ƁuNO���팸�v�̉ۑ��������g���b�N���[�J�̃G���W���̃G���W���Z
�p�҂́A�M�҂̒�Ă���Q�^�[�{�����̋C���x�~�G���W��[�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j]�̋Z�p��m��
���ƂɂȂ�A�\�����u�d�ʎԃ��[�h�R��̌���v�ƁuSCR�G�}�ł�NO���팸�v�������ł��邽�߂ɁA�������ƂȂ��Q�^�[
�{�����̋C���x�~�V�X�e�����̗p����\���������ƍl������B�������Ȃ���A�M�҂̒�Ă���Q�^�[�{�����̋C
���x�~�G���W��[�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j]�̋Z�p��m�邱�ƂɂȂ��Ă��A����܂Œʂ�̃K�\�����G
���W���Ɠ��l�̋z�E�r�C�ق𖧕���@�\�����z�E�r�C�ًx�~�����̋C���x�~�V�X�e���̋C���x�~�f�B�[�[���G
���W���̌����E�J�����s���G���W���Z�p�ҁE���Ƃ����݂����Ƃ���A���̐l�B�̓^�[�{�ߋ��f�B�[�[���G���W����
���ď\���Ȓm�����������킹�Ă��Ȃ��ƍl���ĊԈႢ�Ȃ����낤�B
�p�҂́A�M�҂̒�Ă���Q�^�[�{�����̋C���x�~�G���W��[�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j]�̋Z�p��m��
���ƂɂȂ�A�\�����u�d�ʎԃ��[�h�R��̌���v�ƁuSCR�G�}�ł�NO���팸�v�������ł��邽�߂ɁA�������ƂȂ��Q�^�[
�{�����̋C���x�~�V�X�e�����̗p����\���������ƍl������B�������Ȃ���A�M�҂̒�Ă���Q�^�[�{�����̋C
���x�~�G���W��[�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j]�̋Z�p��m�邱�ƂɂȂ��Ă��A����܂Œʂ�̃K�\�����G
���W���Ɠ��l�̋z�E�r�C�ق𖧕���@�\�����z�E�r�C�ًx�~�����̋C���x�~�V�X�e���̋C���x�~�f�B�[�[���G
���W���̌����E�J�����s���G���W���Z�p�ҁE���Ƃ����݂����Ƃ���A���̐l�B�̓^�[�{�ߋ��f�B�[�[���G���W����
���ď\���Ȓm�����������킹�Ă��Ȃ��ƍl���ĊԈႢ�Ȃ����낤�B
�U�|�Q�D�@�Q�^�[�{�ߋ��@�����̋C���x�~�G���W���̃��J�j�Y��
���̂Q�^�[�{�ߋ��@�������C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�ł́A�}�P�Ɏ������悤�ɁA���C���f�B�[�[���G
���W�����P�C���Q�Ƒ�Q�C���Q�ɕ����A�C���Q���ɓƗ������z�C�ʘH�A�r�C�ʘH�A�d�f�q�K�X�ʘH�̊e�ʘH���
���A�����ʘH���ɂd�f�q�فA�d�f�q�N�[���A�d�f�q�ʘH�A�ߋ����u�A���C�C���^�[�N�[���A�r�C�i��فA�c�o�e���u�A�_��
�G�}���u�A�m�n���z���Ҍ����u�A�A�f�r�b�q���u���̋z�r�C�֘A���䑕�u��z�u���A�C���Q���̋z����C�A�d�f�q�K
�X����єr�C�K�X�̗��ꂪ�݂��ɍ������Ȃ�����ʘH�̉�H�Ƃ���B
���W�����P�C���Q�Ƒ�Q�C���Q�ɕ����A�C���Q���ɓƗ������z�C�ʘH�A�r�C�ʘH�A�d�f�q�K�X�ʘH�̊e�ʘH���
���A�����ʘH���ɂd�f�q�فA�d�f�q�N�[���A�d�f�q�ʘH�A�ߋ����u�A���C�C���^�[�N�[���A�r�C�i��فA�c�o�e���u�A�_��
�G�}���u�A�m�n���z���Ҍ����u�A�A�f�r�b�q���u���̋z�r�C�֘A���䑕�u��z�u���A�C���Q���̋z����C�A�d�f�q�K
�X����єr�C�K�X�̗��ꂪ�݂��ɍ������Ȃ�����ʘH�̉�H�Ƃ���B
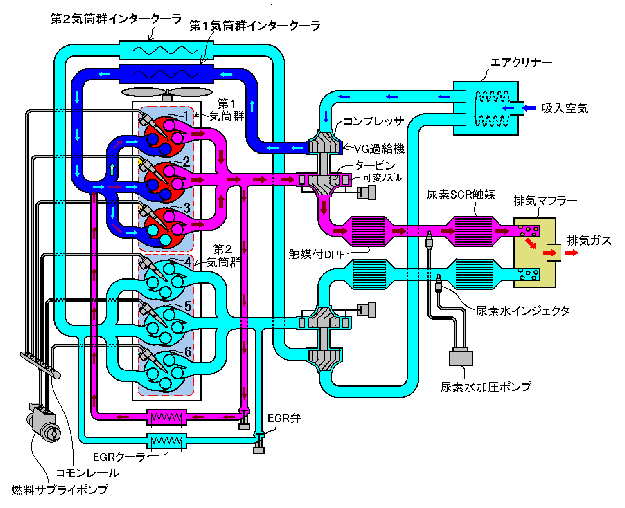
|
�@�@�@�@�@�@�@�@�}�P�@�C���Q�ʐ���G���W���̕������ׂɂ�����^�]���
|
|
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i��P�C���Q���ғ��A��Q�C���Q���x�~�j
|
�@�����Đ}�Q�Ɏ������悤�ɁA�G���W���d�b�t�̐M���ɂ��A�v��P�C���Q�Ƒ�Q�C���Q�ւ̔R�������A�ߋ����u�����
�r�C�㏈�����u�͋C���Q���ɓƗ����Đ��䂷����̂ł���B����ɂ���ăG���W���̕������^�]�ł́A���ꂩ��
���̋C���Q�ɔR�����������ăG���W���o�͂�������ғ��C���Q�Ƃ��ĉ^�]���A���̋C���Q�ɂ͔R�������𒆎~
����x�~�C���Q�Ƃ��ĉ^�]���A�ߋ����u����єr�C�㏈�����u�́A���ꂼ��̋C���Q�ɓK����������s���B�Ȃ��A
���������̉ғ��C���Q�͈�莞�Ԗ��ɑ�P�C���Q�Ƒ�Q�C���Q�Ƃ��ւ���悤�ɂ���B
�r�C�㏈�����u�͋C���Q���ɓƗ����Đ��䂷����̂ł���B����ɂ���ăG���W���̕������^�]�ł́A���ꂩ��
���̋C���Q�ɔR�����������ăG���W���o�͂�������ғ��C���Q�Ƃ��ĉ^�]���A���̋C���Q�ɂ͔R�������𒆎~
����x�~�C���Q�Ƃ��ĉ^�]���A�ߋ����u����єr�C�㏈�����u�́A���ꂼ��̋C���Q�ɓK����������s���B�Ȃ��A
���������̉ғ��C���Q�͈�莞�Ԗ��ɑ�P�C���Q�Ƒ�Q�C���Q�Ƃ��ւ���悤�ɂ���B
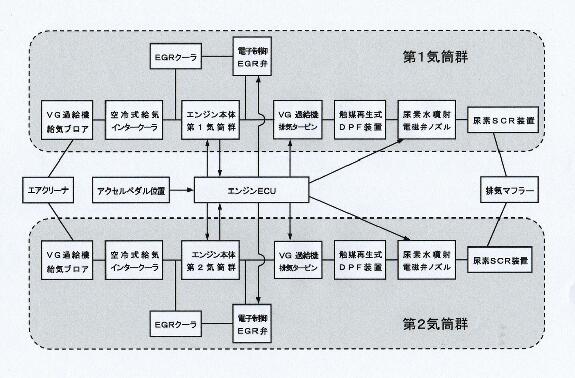
�U�|�R�@�Q�^�[�{�ߋ��@�����̋C���x�~�G���W���ŕ��������ɔR����P����闝�R
�@�C���x�~�G���W�����Q/�S���ׂʼn^�]����ꍇ�A�}�P�Ɏ������悤�ɑ�P�C���Q���ғ��C���Q�Ƃ��ĉ^�]�����ꍇ��
��Q�C���Q�͋x�~�C���Q�Ƃ��ĉ^�]����B���̎��A�ғ��C���Q�̑�P�C���Q�́A�S/�S���ׂ̉^�]�ƂȂ邽�߁A��P�C
���Q�̂d�f�q���u�A�ߋ����u����єr�C�K�X�㏈�����u�͑S����Ԃʼn^�]����邽�߁A�V�����_�����͂�������
�Ȃ��ăT�C�N�������������Ȃ��ĔR��ǍD�ƂȂ�A�r�C�K�X���x�������ƂȂ��đ�P�C���Q�̂c�o�e���u�ł͎��R��
�������i������ԂƂȂ�B
��Q�C���Q�͋x�~�C���Q�Ƃ��ĉ^�]����B���̎��A�ғ��C���Q�̑�P�C���Q�́A�S/�S���ׂ̉^�]�ƂȂ邽�߁A��P�C
���Q�̂d�f�q���u�A�ߋ����u����єr�C�K�X�㏈�����u�͑S����Ԃʼn^�]����邽�߁A�V�����_�����͂�������
�Ȃ��ăT�C�N�������������Ȃ��ĔR��ǍD�ƂȂ�A�r�C�K�X���x�������ƂȂ��đ�P�C���Q�̂c�o�e���u�ł͎��R��
�������i������ԂƂȂ�B
�@���̂��߁A�|�X�g���ˎ�DPF���u�ɂ����ă|�X�g���˂Ŕr�C�ǂɔR�����������A���̃|�X�g���˔R�����_���G�}��
�R�Ă����Ĕr�C�K�X���x��600���܂ō��������đ͐ς����p�e�B�L�����[�g��R�Ă����ăt�B���^���狭���I�ɏ�����
�鏈�u���s�v�ƂȂ�A�t�B���^�Đ��ł̃|�X�g���˂̔R���Q��������Ƃ��\��Ȃ�B���̌��ʁA��P�C���Q�ł�
�����T�C�N�������Œ�R��Ŋ��c�o�e���u�̎��R�Đ������i������Ԃ��^�]�p���������ł��邱�ƂȂ�B������
���̎��̑�Q�C���Q�͋x�~�C���Q�Ƃ��ĉ^�]���Ă��邽�ߑ�Q�C���Q�̗�p�����͗�ɋ߂����߁A�C���x�~�G���W
�����Q/�S���ׂʼn^�]����ꍇ�̗�p�����͓����o�͂�S�C�����ғ�����]���̃G���W���ɔ�ׂāA�قڔ����܂�
�����ł��邱�Ƃ��R�����P�̑傫�ȗ��R�̈�ł���B
�R�Ă����Ĕr�C�K�X���x��600���܂ō��������đ͐ς����p�e�B�L�����[�g��R�Ă����ăt�B���^���狭���I�ɏ�����
�鏈�u���s�v�ƂȂ�A�t�B���^�Đ��ł̃|�X�g���˂̔R���Q��������Ƃ��\��Ȃ�B���̌��ʁA��P�C���Q�ł�
�����T�C�N�������Œ�R��Ŋ��c�o�e���u�̎��R�Đ������i������Ԃ��^�]�p���������ł��邱�ƂȂ�B������
���̎��̑�Q�C���Q�͋x�~�C���Q�Ƃ��ĉ^�]���Ă��邽�ߑ�Q�C���Q�̗�p�����͗�ɋ߂����߁A�C���x�~�G���W
�����Q/�S���ׂʼn^�]����ꍇ�̗�p�����͓����o�͂�S�C�����ғ�����]���̃G���W���ɔ�ׂāA�قڔ����܂�
�����ł��邱�Ƃ��R�����P�̑傫�ȗ��R�̈�ł���B
�@�܂��B���̋C���x�~�G���W�����O�`�Q/�S���ׂ̊Ԃʼn^�]����ꍇ�A�}�P�Ɏ������悤�ɑ�P�C���Q���ғ��C���Q��
���ĉ^�]�����ꍇ�͑�Q�C���Q�͋x�~�C���Q�Ƃ��ĉ^�]����B���̏ꍇ���A�ғ��C���Q�̑�P�C���Q�́A�����o�͂�
�S�C�����ғ�����]���̃G���W���ɔ�ׂāA�Q�{�̐������ϗL�����͂ʼn^�]���邽�߁A��P�C���Q�̃T�C�N������
�������Ȃ��ĔR��ǍD�ƂȂ��A�����o�͂�S�C�����ғ�����]���̃G���W���ɔ�ׂāA��p�������قڔ����܂�
�������邱�Ƃ��R�����P�̗v���ƂȂ�B�܂�A���̉^�]�̈您���ď]���̃G���W���^�]�ł͂Q�C���ɋ������Ă���
�R�����ғ��C���Q�̂P�C���ɋ������邱�ƂɂȂ邽�߁A�ғ��C���Q�̋C���͓����̍ō����͂ƍō����x���㏸��
��Ƌ��ɗ�p�������������邱�Ƃɂ���č����G���W���T�C�N�������������邽�߂ł���B�Q�^�[�{�ߋ��@������
�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�ł͂��̂悤�ȃG���W���T�C�N���}�l�W�����g���s�����Ƃɂ���ăG���W����
���������̔R��e�ՂɌ���ł���̂ł���B
���ĉ^�]�����ꍇ�͑�Q�C���Q�͋x�~�C���Q�Ƃ��ĉ^�]����B���̏ꍇ���A�ғ��C���Q�̑�P�C���Q�́A�����o�͂�
�S�C�����ғ�����]���̃G���W���ɔ�ׂāA�Q�{�̐������ϗL�����͂ʼn^�]���邽�߁A��P�C���Q�̃T�C�N������
�������Ȃ��ĔR��ǍD�ƂȂ��A�����o�͂�S�C�����ғ�����]���̃G���W���ɔ�ׂāA��p�������قڔ����܂�
�������邱�Ƃ��R�����P�̗v���ƂȂ�B�܂�A���̉^�]�̈您���ď]���̃G���W���^�]�ł͂Q�C���ɋ������Ă���
�R�����ғ��C���Q�̂P�C���ɋ������邱�ƂɂȂ邽�߁A�ғ��C���Q�̋C���͓����̍ō����͂ƍō����x���㏸��
��Ƌ��ɗ�p�������������邱�Ƃɂ���č����G���W���T�C�N�������������邽�߂ł���B�Q�^�[�{�ߋ��@������
�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�ł͂��̂悤�ȃG���W���T�C�N���}�l�W�����g���s�����Ƃɂ���ăG���W����
���������̔R��e�ՂɌ���ł���̂ł���B
�@�����ē��l�ɁA���̋C���x�~�G���W�����Q/�S�`�S/�S���ׂ̊Ԃʼn^�]����ꍇ�A��P�C���Q�Ƒ�Q�C���Q�����ɉғ�
�C���Q�Ƃ��ĉ^�]���邪�A��P�C���Q���S/�S���ׂʼn^�]���đ�Q�C���Q��s������o�͂�₤�������^�]�Ƃ�����
���A��Q�C���Q�͏o�͂�₤�������^�]�ƂȂ邽�ߔR��̈����^�]�ƂȂ邪�A��P�C���Q�͂S/�S���^�]�̂���
�ɃT�C�N�������������Ȃ��ĔR��ǍD�ȉ^�]�ƂȂ�B���̂悤�ɃG���W���T�C�N���}�l�W�����g���s�����Ƃɂ���āA�Q
/�S�`�S/�S���ׂ̊Ԃʼn^�]����G���W���S�̂̔R��́A�S�C�����o�͂ʼnғ�����ꍇ�ɔ�r���āA��R���
���Ƃ��\�ƂȂ�B
�C���Q�Ƃ��ĉ^�]���邪�A��P�C���Q���S/�S���ׂʼn^�]���đ�Q�C���Q��s������o�͂�₤�������^�]�Ƃ�����
���A��Q�C���Q�͏o�͂�₤�������^�]�ƂȂ邽�ߔR��̈����^�]�ƂȂ邪�A��P�C���Q�͂S/�S���^�]�̂���
�ɃT�C�N�������������Ȃ��ĔR��ǍD�ȉ^�]�ƂȂ�B���̂悤�ɃG���W���T�C�N���}�l�W�����g���s�����Ƃɂ���āA�Q
/�S�`�S/�S���ׂ̊Ԃʼn^�]����G���W���S�̂̔R��́A�S�C�����o�͂ʼnғ�����ꍇ�ɔ�r���āA��R���
���Ƃ��\�ƂȂ�B
�@�ȏ�ɐ��������悤�ȋC���x�~�G���W���̑�P�C���Q��D��I�ɉғ����邹������s�����ꍇ�ɂ́A�C���x�~�G
���W���̊e�o�͔͈͂ɑΉ������P�C���Q�Ƒ�Q�C���Q�̊e�C���Q�̉^�]�́A�}�R�Ɏ������ʂ�ƂȂ�B
���W���̊e�o�͔͈͂ɑΉ������P�C���Q�Ƒ�Q�C���Q�̊e�C���Q�̉^�]�́A�}�R�Ɏ������ʂ�ƂȂ�B
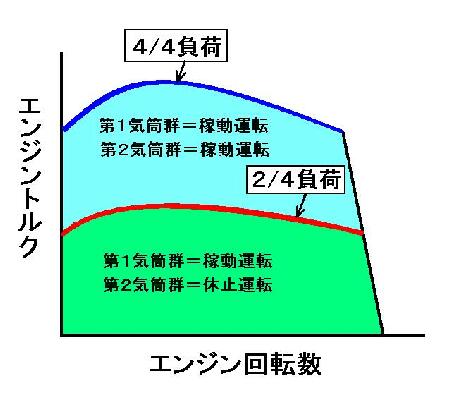
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
�@�ȏ�̂悤���Q�^�[�{�ߋ��@�����̋C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�ł́A�]���̑S�C���������ׂ�
�ғ�������G���W���ɔ�ׂāA���ɐ}�R�Ɏ������ΐF�ƐԐ�����ѐԐ��ɐڂ�����F�̗̈�̕��ׁi�Q/�S�`�R/�S��
�ׁj�̔R����P����邱�ƂɂȂ�B�Ȃ��A�����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j���啝�ɔR�������ł�
�闝�R�ɂ��ẮA�C���x�~�ɂ��A�R��팸�ƔA�fSCR�G�}�ł�NO���팸���\���I�̃y�[�W�ł��ڏq���Ă���
�̂ŁA�����������������B
�ғ�������G���W���ɔ�ׂāA���ɐ}�R�Ɏ������ΐF�ƐԐ�����ѐԐ��ɐڂ�����F�̗̈�̕��ׁi�Q/�S�`�R/�S��
�ׁj�̔R����P����邱�ƂɂȂ�B�Ȃ��A�����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j���啝�ɔR�������ł�
�闝�R�ɂ��ẮA�C���x�~�ɂ��A�R��팸�ƔA�fSCR�G�}�ł�NO���팸���\���I�̃y�[�W�ł��ڏq���Ă���
�̂ŁA�����������������B
�U�|�S�@�C���x�~�G���W���ő�^�f�B�[�[���g���b�N�̑��s�R����P����闝�R
�@�O�q�̒ʂ�A��^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W���̔R����P�̂��߂̂ɁA�^�[�{�R���p�E���h�A��i�ߋ����A�~���[
�T�C�N������уJ�����X�V�X�e�����悤�ȐV�����Z�p�̌����J�����s���Ă���悤�ł���B�������A�����Z�p�̒�
�ŁA�~���[�T�C�N���ł͂Q�����x�̔R�����P���\�ł��邪�A���̑��̋Z�p�ɂ�����R�����P�͂P���ɂ������Ȃ�
���X������̂ɉ߂��Ȃ��̂��B�����������A�����Z�p���߂������A�s�̂̑�^�f�B�[�[���g���b�N�ɍL���̗p�����
�\���͋ɂ߂ĒႢ�ƍl������B
�T�C�N������уJ�����X�V�X�e�����悤�ȐV�����Z�p�̌����J�����s���Ă���悤�ł���B�������A�����Z�p�̒�
�ŁA�~���[�T�C�N���ł͂Q�����x�̔R�����P���\�ł��邪�A���̑��̋Z�p�ɂ�����R�����P�͂P���ɂ������Ȃ�
���X������̂ɉ߂��Ȃ��̂��B�����������A�����Z�p���߂������A�s�̂̑�^�f�B�[�[���g���b�N�ɍL���̗p�����
�\���͋ɂ߂ĒႢ�ƍl������B
�@�����ŁA�M�҂���^�g���b�N�̑啝�ȔR����P�������߂���p�I�ȋZ�p�Ƃ��Ē�Ă��Ă���̂��Q�^�[�{�ߋ��@��
�����w�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�x�ł���B�O�q�̂悤�ɁA�M�҂���Ă̋C���x�~�G���W���ł��P�C��
�Q�Ƒ�Q�C���Q�̓�̋C���Q�ɕ����A�C���x�~�G���W�����O�`�Q/�S���ׂ̉^�]�ł͂P�C���Q�܂��͑�Q�C���Q��
����̋C���Q���ғ��^�]���Ďc��̋C���Q���x�~�^�]����B����ɂ���āA��ׂāA���̉ғ��C���Q�͑S�C������
���̏o�͂ʼnғ�����]���̃G���W���̂Q�{�̐������ϗL�����͂ʼn^�]�ł��邽�߁A�T�C�N�������������Ȃ��ĔR��
���ǍD�ƂȂ��A�����o�͂�S�C�����ғ�����]���̃G���W���ɔ�ׂāA��p�������قڔ������邱�Ƃ��R�����P
�̗v���ƂȂ�B�����āA���̋C���x�~�G���W�����Q/�S�`�S/�S���ׂ̉^�]�ł́A��P�C���Q�Ƒ�Q�C���Q�����ɉғ��C
���Q�Ƃ��ĉ^�]����B���������C���Q�̏o�͈͂قȂ�A��P�C���Q���S/�S���ׂʼn^�]���đ�Q�C���Q��s������o��
��₤�������^�]�Ƃ����ꍇ�ɂ́A��Q�C���Q���o�͂�₤�R��̈����������^�]�ƂȂ邽�߉^�]�ƂȂ邪�A
��P�C���Q�͂S/�S���^�]�̂��߂ɃT�C�N�������������Ȃ��ĔR��ǍD�ȉ^�]�ƂȂ�B���̏ꍇ�ł��A�Q/�S�`�S/�S
���ׂ̊Ԃʼn^�]����G���W���S�̂̔R��́A�S�C�����o�͂ʼnғ�����ꍇ�ɔ�r���āA��R��邱�Ƃ���
�\�ƂȂ�B
�����w�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�x�ł���B�O�q�̂悤�ɁA�M�҂���Ă̋C���x�~�G���W���ł��P�C��
�Q�Ƒ�Q�C���Q�̓�̋C���Q�ɕ����A�C���x�~�G���W�����O�`�Q/�S���ׂ̉^�]�ł͂P�C���Q�܂��͑�Q�C���Q��
����̋C���Q���ғ��^�]���Ďc��̋C���Q���x�~�^�]����B����ɂ���āA��ׂāA���̉ғ��C���Q�͑S�C������
���̏o�͂ʼnғ�����]���̃G���W���̂Q�{�̐������ϗL�����͂ʼn^�]�ł��邽�߁A�T�C�N�������������Ȃ��ĔR��
���ǍD�ƂȂ��A�����o�͂�S�C�����ғ�����]���̃G���W���ɔ�ׂāA��p�������قڔ������邱�Ƃ��R�����P
�̗v���ƂȂ�B�����āA���̋C���x�~�G���W�����Q/�S�`�S/�S���ׂ̉^�]�ł́A��P�C���Q�Ƒ�Q�C���Q�����ɉғ��C
���Q�Ƃ��ĉ^�]����B���������C���Q�̏o�͈͂قȂ�A��P�C���Q���S/�S���ׂʼn^�]���đ�Q�C���Q��s������o��
��₤�������^�]�Ƃ����ꍇ�ɂ́A��Q�C���Q���o�͂�₤�R��̈����������^�]�ƂȂ邽�߉^�]�ƂȂ邪�A
��P�C���Q�͂S/�S���^�]�̂��߂ɃT�C�N�������������Ȃ��ĔR��ǍD�ȉ^�]�ƂȂ�B���̏ꍇ�ł��A�Q/�S�`�S/�S
���ׂ̊Ԃʼn^�]����G���W���S�̂̔R��́A�S�C�����o�͂ʼnғ�����ꍇ�ɔ�r���āA��R��邱�Ƃ���
�\�ƂȂ�B
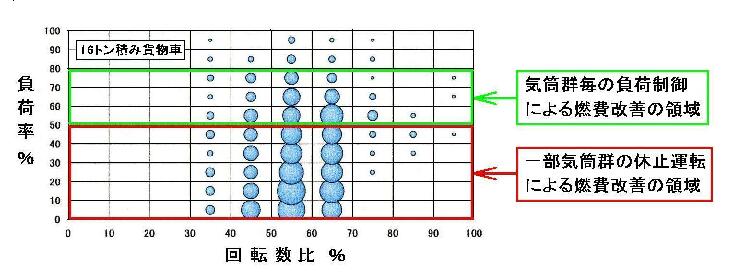
�@�ȏ���C���x�~�G���W���̋C���Q����ɂ��āA���ۂ̑�^�g���b�N�ł̐���ɂ��Ď��������̂��A�}�S�ł�
��B�����}�S�́A��^�g���b�N�iGVW�F�Q�T�g���A�ő�ύڗʂP�U�g���j�ɔ��ύځi�W�g���̐ύځj���������ŁA��T�����R
���\�Ŏ����ꂽ���Ȃ��s�������s���Ԓ�������ɐV�����r�o�K�X�K���p�������[�h�ł���d�c���[�h���^�]����
�ꍇ�̃G���W�����ׂƉ�]����̎g�p�i�p�x�̃f�[�^�i�o�T�F��ʈ��S���������Ahttp://www.ntsel.go.jp/ronbun
/happyoukai/14files/algorithm.pdf�j�ɁA�M�҂���Ă��Ă���Q�^�[�{�ߋ��@�����̋C���x�~�G���W���i�������J2005
-54771�j�ł�����P�C���Q�Ƒ�Q�C���Q�̓�̋C���Q�ɕ������A�P�C���Q�Ƒ�Q�C���Q�̕��ׂ�Ɨ����Đ��䂷��
�C���x�~�G���W���̋C���Q����ɂ��R����P�̉\�ȉ^�]�̈��NjL�������̂ł���B���̐}�S�̐Ԑ��g����
�^�]�̈�ł�����̋C���Q���ғ��^�]���Ďc��̋C���Q���x�~�^�]���邱�Ƃɂ���ĔR������P���A�ΐ��g���̉^
�]�̈�ł�����̋C���Q�ł͂S/�S���ׂʼn^�]���Ďc��̋C���Q�����^�]���邱�Ƃɂ���ĔR������P���邱
�Ƃ��\�ƂȂ�B
��B�����}�S�́A��^�g���b�N�iGVW�F�Q�T�g���A�ő�ύڗʂP�U�g���j�ɔ��ύځi�W�g���̐ύځj���������ŁA��T�����R
���\�Ŏ����ꂽ���Ȃ��s�������s���Ԓ�������ɐV�����r�o�K�X�K���p�������[�h�ł���d�c���[�h���^�]����
�ꍇ�̃G���W�����ׂƉ�]����̎g�p�i�p�x�̃f�[�^�i�o�T�F��ʈ��S���������Ahttp://www.ntsel.go.jp/ronbun
/happyoukai/14files/algorithm.pdf�j�ɁA�M�҂���Ă��Ă���Q�^�[�{�ߋ��@�����̋C���x�~�G���W���i�������J2005
-54771�j�ł�����P�C���Q�Ƒ�Q�C���Q�̓�̋C���Q�ɕ������A�P�C���Q�Ƒ�Q�C���Q�̕��ׂ�Ɨ����Đ��䂷��
�C���x�~�G���W���̋C���Q����ɂ��R����P�̉\�ȉ^�]�̈��NjL�������̂ł���B���̐}�S�̐Ԑ��g����
�^�]�̈�ł�����̋C���Q���ғ��^�]���Ďc��̋C���Q���x�~�^�]���邱�Ƃɂ���ĔR������P���A�ΐ��g���̉^
�]�̈�ł�����̋C���Q�ł͂S/�S���ׂʼn^�]���Ďc��̋C���Q�����^�]���邱�Ƃɂ���ĔR������P���邱
�Ƃ��\�ƂȂ�B
�@����ɂ���Ď����s�̑�^�g���b�N�ɂ�������p�I�ȃG���W���^�]�̈�̂قڑS��ɂ킽���āA�C���x�~�G���W��
�Œ�R��m�ۂł���C���Q�̐��䂪�\�ƂȂ�B���̂Q�^�[�{�ߋ��@�������C���x�~�G���W���i�������J2005
-54771�j�̋Z�p����^�g���b�N���̗p�����ꍇ�ɂ��A�]���̑S�C�����ϓ��o�͂ʼnғ�����G���W���ɔ�r��
�āA�T�`�P�O�����x���d�ʎԃ��[�h�R��l������s�R��l�����P�ł�����̂Ɨ\�z���Ă���B�Ȃ��A�S�C������
�ɉғ�������]���G���W���ɔ�r���āA�����Q�^�[�{�ߋ��@�����̋C���x�~�G���W���i�������J2005-54771)�́A�R
�����ɉ����A�m�n�����팸�ł��鍪���ɂ��ẮA�C���x�~�́A�R��팸�ƔA�fSCR��NO���팸���̌���ɗL
�����I�ɂ��ڏq���Ă���̂ł����������������B
�Œ�R��m�ۂł���C���Q�̐��䂪�\�ƂȂ�B���̂Q�^�[�{�ߋ��@�������C���x�~�G���W���i�������J2005
-54771�j�̋Z�p����^�g���b�N���̗p�����ꍇ�ɂ��A�]���̑S�C�����ϓ��o�͂ʼnғ�����G���W���ɔ�r��
�āA�T�`�P�O�����x���d�ʎԃ��[�h�R��l������s�R��l�����P�ł�����̂Ɨ\�z���Ă���B�Ȃ��A�S�C������
�ɉғ�������]���G���W���ɔ�r���āA�����Q�^�[�{�ߋ��@�����̋C���x�~�G���W���i�������J2005-54771)�́A�R
�����ɉ����A�m�n�����팸�ł��鍪���ɂ��ẮA�C���x�~�́A�R��팸�ƔA�fSCR��NO���팸���̌���ɗL
�����I�ɂ��ڏq���Ă���̂ł����������������B
�@�Ƃ���ŁA����̓K�\�����G���W���̏ꍇ�ł͂��邪�A�}�c�_�̐l�����v���̍u���i2015�N12��14���j�ł́A�l����
�v���̓}�c�_2.5�k �r�j�x�`�b�s�h�u�G���W���ɂ�����C���x�~�ɂ���ăG���W���̒ᕉ�ׂ̉^�]�̈�ł̑啝�ȔR���
�P�̉\����}������Ă���B ���̂��Ƃ���A�}�c�_�́A�߂������ɂ͋C���x�~�G���W���𓋍ڂ��������Ԃ��s��
�ɓ�������\��������̂ł͂Ȃ����ƍl������B���̏ꍇ�A�f�B�[�[���ɂ����Ă��C���x�~���̗p����������
���s�̂���\���������ɂ����ƍl������B�A
�v���̓}�c�_2.5�k �r�j�x�`�b�s�h�u�G���W���ɂ�����C���x�~�ɂ���ăG���W���̒ᕉ�ׂ̉^�]�̈�ł̑啝�ȔR���
�P�̉\����}������Ă���B ���̂��Ƃ���A�}�c�_�́A�߂������ɂ͋C���x�~�G���W���𓋍ڂ��������Ԃ��s��
�ɓ�������\��������̂ł͂Ȃ����ƍl������B���̏ꍇ�A�f�B�[�[���ɂ����Ă��C���x�~���̗p����������
���s�̂���\���������ɂ����ƍl������B�A
�i�o�T�Fhttp://car.watch.impress.co.jp/docs/news/20151214_735090.html�Ɍf�ڂ̐}http://car.watch.impress.co.jp/img/car/docs/735/
090/html/71.jpg.htm�jl
090/html/71.jpg.htm�jl
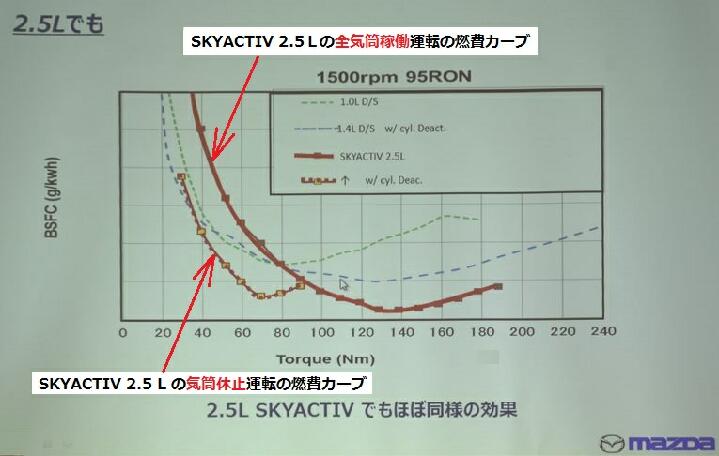 |
�@2016�N4�����݁A�}�c�_�ł́A�ȉ��̂Q�@��̃f�B�[�[���G���W���Y���Ă��邻���ł���B
���@SKYACTIV-D 1.5�@�F�@1.5���b�g���E����4�C��DOHC16�o���u�����G���W�� VG�^�[�{
���@SKYACTIV-D 2.2�@�F�@2.2���b�g���E����4�C��DOHC16�o���u�����G���W�� 2�X�e�[�W�^�[�{
���̂悤�ȏ̉��ŁA�}�c�_�̐l�����v���̍u���i2015�N12��14���j�ł́A�ȉ��̂悤�ɁA�f�B�[�[���G���W���̂�
�R�����ł��u�C���x�~�v�̗̍p���L���Ƃ����|�̔��\���s���Ă���悤���B
�R�����ł��u�C���x�~�v�̗̍p���L���Ƃ����|�̔��\���s���Ă���悤���B
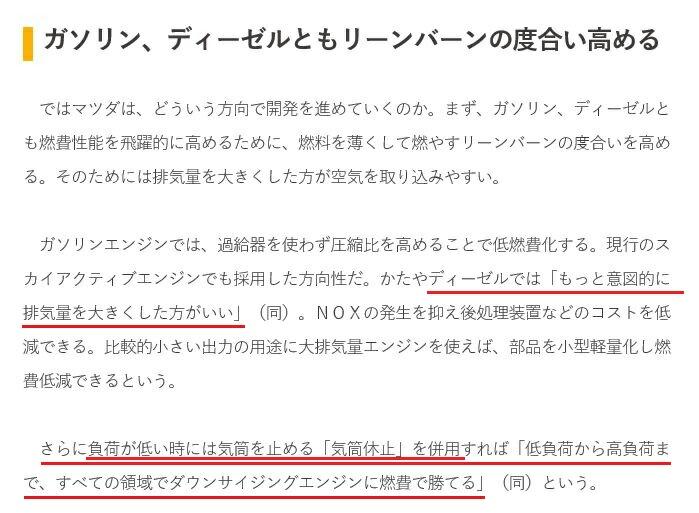 |
�@���Ă��āA�ȏ�̋L������ސ�����ƁA�߂������A�}�c�_�̃f�B�[�[���G���W���ɂ͋C���x�~���̗p������
�\�����ɂ߂č����ƍl������B���̏ꍇ�̋C���x�~�V�X�e���́A�C���x�~�G���W���i�������J2005-
54771�j�̓����Z�p���̗p���邱�Ƃ��ł��K�ł͂Ȃ����ƍl������B���̗��R�́A�C���x�~�G���W���i��
�����J2005-54771�j�̓����ɂ͈ȉ��Ɏ�������̗D�ꂽ�@�\�E���\��������Z�p�ł��邽�߂��B
�\�����ɂ߂č����ƍl������B���̏ꍇ�̋C���x�~�V�X�e���́A�C���x�~�G���W���i�������J2005-
54771�j�̓����Z�p���̗p���邱�Ƃ��ł��K�ł͂Ȃ����ƍl������B���̗��R�́A�C���x�~�G���W���i��
�����J2005-54771�j�̓����ɂ͈ȉ��Ɏ�������̗D�ꂽ�@�\�E���\��������Z�p�ł��邽�߂��B
�� �ʏ�A�����Ԃ́A�����ԗp�G���W���̋}���ȏo�͑����̓I�m�ȕ��א���ɂ���āA����ȑ��s���\��
����B���̂��߁A�C���x�~���̗p�����ߋ��f�B�[�[���G���W���𓋍ڂ��������Ԃ��}���ȕ��גቺ��K�v��
���鑖�s��Ԃɂ����ẮA�G���W���͑S�C���ғ�����C���x�~�ɓ˓����邱�ƂɂȂ�B���̍ہA�C���x�~�G
���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p���̗p�����ߋ��f�B�[�[���G���W���ł́A�^�[�{�ߋ��@�ɔ�����
��^�[�{�T�[�W�����O�̕s������S�ɉ�����邱�Ƃ��ł���B��̋Z�p�ł���
����B���̂��߁A�C���x�~���̗p�����ߋ��f�B�[�[���G���W���𓋍ڂ��������Ԃ��}���ȕ��גቺ��K�v��
���鑖�s��Ԃɂ����ẮA�G���W���͑S�C���ғ�����C���x�~�ɓ˓����邱�ƂɂȂ�B���̍ہA�C���x�~�G
���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p���̗p�����ߋ��f�B�[�[���G���W���ł́A�^�[�{�ߋ��@�ɔ�����
��^�[�{�T�[�W�����O�̕s������S�ɉ�����邱�Ƃ��ł���B��̋Z�p�ł���
�� �C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p���̗p���������ԗp�^�[�{�ߋ��f�B�[�[���G���W
���́A�C���x�~�^�]���ɂ����ẮA�x�~�C���̋z�E�r�C�ق̍쓮���~������@�\�i���C���𖧕�ԂɈ�
�����鑕�u�j��V���ɒlj�����K�v���������Ƃ��傫�ȓ����ł���B
���́A�C���x�~�^�]���ɂ����ẮA�x�~�C���̋z�E�r�C�ق̍쓮���~������@�\�i���C���𖧕�ԂɈ�
�����鑕�u�j��V���ɒlj�����K�v���������Ƃ��傫�ȓ����ł���B
�i���݂ɁA���s�̎s�̒��̋C���x�~�K�\�����G���W���̑S�@��ɂ́A�x�~�C���̋z�E�r�C�ق̍쓮���~������@
�\[���C���𖧕�ԂɈێ����鑕�u]����������Ă���B�j
�\[���C���𖧕�ԂɈێ����鑕�u]����������Ă���B�j
�@�Ƃ���ŁA�ŋ߂̊O���q�H�̑�^�ݕ��D�ł́A�G���W���̋C���x�~�́A�����^�q���̍X�Ȃ�R����オ�\�ɏ�
�q���Ă���悤�ɁA�D���̉^�q���̔R����̍팸��}�邽�߁A�D���̑啝�Ȍ����^�q�����{����Ă���B�܂�A��
��̑D���́A�����^�q�̂��߂ɃG���W�������ׂʼn^�]����p�x���������������Ă���Ƃ̂��Ƃł���B���̌���
�^�q�̎�i�̈�Ƃ��āA�]���̑�^�̍��؋q�D�ɍ̗p����Ă��镡����̃f�B�[�[�����d���u�i�����}���Q��
���j��p�����D���̓d�C���i���u���ݕ��D�i���R���e�i�D�A�^���J�[�A�o���ς݉ݕ��D���j�ɍ̗p���邱�Ƃ���Ă���
����B
�q���Ă���悤�ɁA�D���̉^�q���̔R����̍팸��}�邽�߁A�D���̑啝�Ȍ����^�q�����{����Ă���B�܂�A��
��̑D���́A�����^�q�̂��߂ɃG���W�������ׂʼn^�]����p�x���������������Ă���Ƃ̂��Ƃł���B���̌���
�^�q�̎�i�̈�Ƃ��āA�]���̑�^�̍��؋q�D�ɍ̗p����Ă��镡����̃f�B�[�[�����d���u�i�����}���Q��
���j��p�����D���̓d�C���i���u���ݕ��D�i���R���e�i�D�A�^���J�[�A�o���ς݉ݕ��D���j�ɍ̗p���邱�Ƃ���Ă���
����B
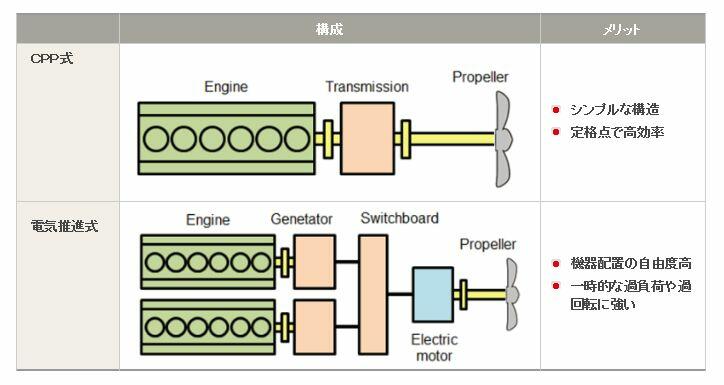 |
�@���̕�����̃f�B�[�[�����d���u�i�����}���Q�ƕ��j��p�����D���̓d�C���i�V�X�e���ɂ����Ĉꕔ�̃G���W��
���~���ĉ^�]�����ꍇ�́A�G���W���̕������^�]�ɂ����Ĉꕔ�̃G���W�����C���x�~�����ꍇ�Ɠ����̋@�\�E
���ʂ�����ƍl������B�Ⴆ�A���C���f�B�[�[���G���W�����P�C���Q�Ƒ�Q�C���Q�̓�̋C���Q�ɕ������C
���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋C���x�~�G���W���ɂ����ĂP�^�Q�ȉ��̃g���N�ł͋C���x�~�ɂ���đ��r
�C�ʂ̂P�^�Q�̔r�C�ʂʼn^�]���邱�Ƃ��\�ł���A�����āA��L���D���̓d�C���i�V�X�e�����P�^�Q�ȉ��̃g���N
�ł͂Q��̃G���W���̒��̕Е��̃G���W���ł����ʼn^�]���邱�Ƃ��ł���̂ł���B���̂悤�ȉ^�]��Ԃł́A�C��
�x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p���̗p�����G���W���Ə�L���D���̓d�C���i�V�X�e���̃G���W��
�́A�P�^�Q�ȉ��̃g���N�ł������̃G���W�����r�C�ʂ��ɂ����m�_�E���T�C�W���O�G���W���v�̏�Ԃł̃G���W��
�^�]�ƍl���邱�Ƃ��ł���̂ł���B
���~���ĉ^�]�����ꍇ�́A�G���W���̕������^�]�ɂ����Ĉꕔ�̃G���W�����C���x�~�����ꍇ�Ɠ����̋@�\�E
���ʂ�����ƍl������B�Ⴆ�A���C���f�B�[�[���G���W�����P�C���Q�Ƒ�Q�C���Q�̓�̋C���Q�ɕ������C
���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋C���x�~�G���W���ɂ����ĂP�^�Q�ȉ��̃g���N�ł͋C���x�~�ɂ���đ��r
�C�ʂ̂P�^�Q�̔r�C�ʂʼn^�]���邱�Ƃ��\�ł���A�����āA��L���D���̓d�C���i�V�X�e�����P�^�Q�ȉ��̃g���N
�ł͂Q��̃G���W���̒��̕Е��̃G���W���ł����ʼn^�]���邱�Ƃ��ł���̂ł���B���̂悤�ȉ^�]��Ԃł́A�C��
�x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p���̗p�����G���W���Ə�L���D���̓d�C���i�V�X�e���̃G���W��
�́A�P�^�Q�ȉ��̃g���N�ł������̃G���W�����r�C�ʂ��ɂ����m�_�E���T�C�W���O�G���W���v�̏�Ԃł̃G���W��
�^�]�ƍl���邱�Ƃ��ł���̂ł���B
�U�|�T�@�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�Ƌz�E�r�C�ْ�~���Ƃ̑���
�@�U�C���̉ߋ��f�B�[�[���̋C���x�~�G���W���ɂ����āA���쎩���Ԃ́u�S�C���A���̉ߋ��@��������z�E�r�C��
��~���̋C���x�~�V�X�e���v�ł́A�R�C�����x�~����G���W���^�]�̗̈�͖w�Ǒ��݂��Ȃ��B�������A�M�Ғ�Ă�2�^
�[�{�����̋C���x�~�V�X�e���i���C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�j�ł́A�G���W����1�^�Q���ȉ��ɂ���
�āA�R�C���̋C���Q�������ғ�����C���x�~�^�]���\�ł���B
��~���̋C���x�~�V�X�e���v�ł́A�R�C�����x�~����G���W���^�]�̗̈�͖w�Ǒ��݂��Ȃ��B�������A�M�Ғ�Ă�2�^
�[�{�����̋C���x�~�V�X�e���i���C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�j�ł́A�G���W����1�^�Q���ȉ��ɂ���
�āA�R�C���̋C���Q�������ғ�����C���x�~�^�]���\�ł���B
�@�����āA��^�g���b�N�̎��ۂ̑��s�ɂ����ẮA�G���W���^�]��1�^�Q���ȉ��̌y���ׂ����p����邽�߁A
�y���ׂɂ����ĂR�C�����x�~����G���W���^�]���\���M�Ғ�Ă�2�^�[�{�����̋C���x�~�V�X�e���i���C
���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�j�́A��^�g���b�N�̏\���ȑ��s�R��̌��オ�\�ł���B
�y���ׂɂ����ĂR�C�����x�~����G���W���^�]���\���M�Ғ�Ă�2�^�[�{�����̋C���x�~�V�X�e���i���C
���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�j�́A��^�g���b�N�̏\���ȑ��s�R��̌��オ�\�ł���B
�����ĂƕM�Ғ�Ă̋C���x�~�V�X�e�����ߋ��U�C���G���W���ɂ�����ғ��C�����̃}�b�v�ƔR��̔�r
| |
|
�i�P�j �M�Ғ�Ă��C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j
�̋C���x�~����̃}�b�v�@�i�U�C���ߋ��G���W���j
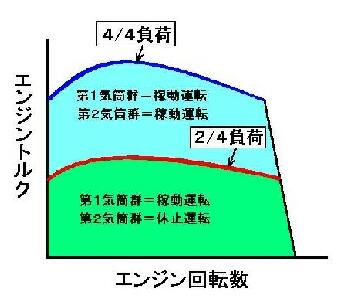 |
�i�P�j ����́u�z�E�r�C�ْ�~���̋C���x�~�V�X�e���v
�ɂ���C���x�~����̃}�b�v�@�i�U�C���ߋ��G���W���j
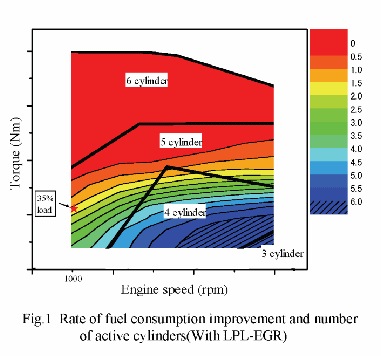 |
�i�Q�j��^�g���b�N�̍��������s���̔R����P
�@�E�������H�̑��s�R��́A�T�`�P�O���̒ጸ
�@�@�i���҂̐���j
|
�i�Q�j��^�g���b�N�̍��������s���̔R����P
�@�E�������H�̑��s�R��́A�S���̉��P
|
�i�Q�j��^�g���b�N��JE0�T���[�h�̔R����P
�@�E�d�ʎԃ��[�h�R��́A�T�`�P�O���̒ጸ
�@�@�i���҂̐���j
|
�i�R�j��^�g���b�N��JE0�T���[�h�̔R����P
�E�d�ʎԃ��[�h�R��́A�Q�`�R���̉��P
�@�i���҂̐���j
|
�@�ȏ�̂��Ƃ���A�����I�ɑ�^�g���b�N�̔R������}��Z�p�Ƃ��ẮA���҂���Ă��Ă����C���x�~�G���W
���i�������J2005-54771�j���䂪���ōL�����p�������\���́A�قڊԈႢ�Ȃ��ƍl�������B�Ȃ��A����
�����Ԓ�Ắu�S�C���A���̉ߋ��@��������z�E�r�C�ْ�~���̋C���x�~�V�X�e���v�̋Z�p�ɔ�r�����ꍇ�A�M��
��Ă��C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�́A��^�g���b�N�̔R����i�i�ɉ��P�ł���@�\�E���\��������
�Z�p�ł���B���̂��Ƃɂ��ẮA���쎩���Ԃ��_�����\�����R����P�@�\�̗��C���x�~�V�X�e���̃y�[�W�ɏ�
�q���Ă���̂ŁA�����̂�����͂����������������B
���i�������J2005-54771�j���䂪���ōL�����p�������\���́A�قڊԈႢ�Ȃ��ƍl�������B�Ȃ��A����
�����Ԓ�Ắu�S�C���A���̉ߋ��@��������z�E�r�C�ْ�~���̋C���x�~�V�X�e���v�̋Z�p�ɔ�r�����ꍇ�A�M��
��Ă��C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�́A��^�g���b�N�̔R����i�i�ɉ��P�ł���@�\�E���\��������
�Z�p�ł���B���̂��Ƃɂ��ẮA���쎩���Ԃ��_�����\�����R����P�@�\�̗��C���x�~�V�X�e���̃y�[�W�ɏ�
�q���Ă���̂ŁA�����̂�����͂����������������B
�V�D�C���x�~�^�]���̐U����h�~������@�ɂ���
�@�z���_�̓C���X�p�C�A�ƃG���V�I����V�^�U�C���G���W����i-VTEC�Ə̂���V�����_�[��芷����σV�����_�[�V
�X�e�����̗p���Ă���B����͎����Ԃ̑��s�ɉ����ĂU�C���^�]�A�S�C���^�]����тR�C���^�]�ɐ芷���邱
�ƂŔR��̌��エ��єr�o�K�X���x���̒ጸ���s���Ă���B�Ȃ��C���x�~���ɔ���������L�̃G���W���U���ɂ�
�ẮA�A�N�e�B�u�R���g���[���G���W���}�E���g�iACM�j�ɂ���Ēጸ���Ă���Ƃ̂��ƁB���́A�@�\�ƍ\���͈ȉ��̒ʂ�
�ł���B�i�o�T�@http://www.honda.co.jp/factbook/auto/INSPIRE/200712/11.html�Q�Ɓj
�X�e�����̗p���Ă���B����͎����Ԃ̑��s�ɉ����ĂU�C���^�]�A�S�C���^�]����тR�C���^�]�ɐ芷���邱
�ƂŔR��̌��エ��єr�o�K�X���x���̒ጸ���s���Ă���B�Ȃ��C���x�~���ɔ���������L�̃G���W���U���ɂ�
�ẮA�A�N�e�B�u�R���g���[���G���W���}�E���g�iACM�j�ɂ���Ēጸ���Ă���Ƃ̂��ƁB���́A�@�\�ƍ\���͈ȉ��̒ʂ�
�ł���B�i�o�T�@http://www.honda.co.jp/factbook/auto/INSPIRE/200712/11.html�Q�Ɓj
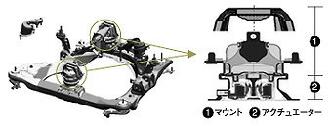 |
�@���̃A�N�e�B�u�R���g���[���G���W���}�E���g�iACM�j
�́A�}�T�̃G���W���}�E���g�\���}�Ɏ����Ă��� �悤�ɁA�T�C�h�}�E���g�ƃg�����X�~�b�V�����A�b�p�[ �}�E���g�������厲�t�߂ɔz�u����Ă���B |
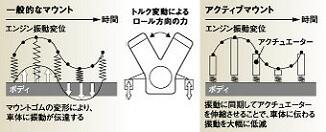 |
�@�}�U�̃G���W���}�E���g�V�X�e���\���}�Ɏ�����
����悤�ɁA�G���W���U���̕ψʂ��N�����N��]�ϓ� ���琄�肵�đł������悤�ɍ쓮���A�C���x�~ �^�]���̃G���W���U����}����悤�ɂ������̂ł���B |
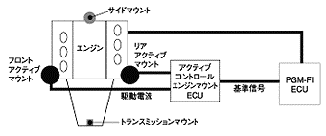 |
�@�}�V�̃G���W���}�E���g�T�O�}�Ɏ������悤�ɁA
�G���W���̑O����x�����邱�̃}�E���g�́A�t�� �}�E���g�̉����ɓ��������A�N�`���G�[�^�[���A �G���W���U���ɑ����ʑ��E�������ŐL�k������ ���ƂŐU�����z�����A�C���x�~��Ԃł��邱�Ƃ� ���������Ȃ������h�U���\���������Ă���B |
�@�ȏ�̂悤�ɁA�G���W���̑O����x������A�N�e�B�u�R���g���[���G���W���}�E���g�́A�t���}�E���g�̉����ɓ�����
���A�N�`���G�[�^�[���A�G���W���U���ɑ����ʑ��E�������ŐL�k�����邱�ƂŐU�����z�����AV�^�U�C���G���W���̋C
���x�~�^�]���ɔ�������U�����C���x�~�^�]��Ԃł��邱�Ƃ����������Ȃ������h�U���\���������Ă���̂ł�
��B�z���_�̓d�q����̃A�N�e�B�u�R���g���[���G���W���}�E���g�́A�ȒP�Ɍ����A�����ŐL�яk�݂���G���W���}
�E���g�Ȃ̂��B
���A�N�`���G�[�^�[���A�G���W���U���ɑ����ʑ��E�������ŐL�k�����邱�ƂŐU�����z�����AV�^�U�C���G���W���̋C
���x�~�^�]���ɔ�������U�����C���x�~�^�]��Ԃł��邱�Ƃ����������Ȃ������h�U���\���������Ă���̂ł�
��B�z���_�̓d�q����̃A�N�e�B�u�R���g���[���G���W���}�E���g�́A�ȒP�Ɍ����A�����ŐL�яk�݂���G���W���}
�E���g�Ȃ̂��B
�@�C���x�~�ɂ���ăA���o�����X�ɂȂ��đ��傷��U�����G���W���}�E���g����ǂ�(���ʑ�)�ŐL�яk�݂��邱�Ƃɂ�
���ċz�����Ă��܂��̂ł���B�z���_�̋C���x�~�G���W�����ڂ̃C���X�p�C�A�E�G���V�I���E�A�R�[�h�ɂ͓��C�S���H��
���̓d�C���A�N�e�B�u����G���W���}�E���g�i�}�W�Q�Ɓj���̗p����Ă���Ƃ̂��Ƃł���B ���̂悤�ɁA�z���_�ł̓G
���W���̑O��x���ɃG���W���U���ɑ����ʑ��E�������ŐL�k������t���̃A�N�e�B�u�R���g���[���G���W���}�E���g
���̗p���邱�Ƃɂ���ċC���x�~�^�]���̐U�����ԑ̂ɓ`�d���邱�Ƃ�h�~���A��p�Ԃ⏬�^�g���b�N�i�k�Č����j��
���Ă̏��i�����m�ۂł��Ă���̂ł���B
���ċz�����Ă��܂��̂ł���B�z���_�̋C���x�~�G���W�����ڂ̃C���X�p�C�A�E�G���V�I���E�A�R�[�h�ɂ͓��C�S���H��
���̓d�C���A�N�e�B�u����G���W���}�E���g�i�}�W�Q�Ɓj���̗p����Ă���Ƃ̂��Ƃł���B ���̂悤�ɁA�z���_�ł̓G
���W���̑O��x���ɃG���W���U���ɑ����ʑ��E�������ŐL�k������t���̃A�N�e�B�u�R���g���[���G���W���}�E���g
���̗p���邱�Ƃɂ���ċC���x�~�^�]���̐U�����ԑ̂ɓ`�d���邱�Ƃ�h�~���A��p�Ԃ⏬�^�g���b�N�i�k�Č����j��
���Ă̏��i�����m�ۂł��Ă���̂ł���B

�@�����AV�^�U�C���G���W���͒���U�C���G���W��������]�o�����X�̗��G���W���ł���B�������A�z���_�͓��C�S
���H�Ƃ̓d�q����̃A�N�e�B�u�R���g���[���G���W���}�E���g�̋Z�p�ɂ���ĐU���ʂŖ��̑���V�^�U�C���G���W��
�̋C���x�~�^�]�̐U�������������ނ��Ƃɐ������Ă���̂ł���B���̓��C�S���H�Ƃ̋Z�p���^�g���b�N�f�B�[�[
���G���W���ɉ��p����A��^�g���b�N�ɂQ�^�[�{�ߋ��@�����̋C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j���̗p��
���ꍇ�Ɋ뜜�����C���x�~�^�]���̐U���ɂ��ẮA��������S�ɉ��������ނ��Ƃ��e�Ղɂł���ƍl������B
���������āA��^�g���b�N�̒���U�C���G���W�����C���x�~�����邱�Ƃɂ��ẮA�U���Ɋւ����Q�͉��������ƍl
���ėǂ��̂ł͂Ȃ����낤���B
���H�Ƃ̓d�q����̃A�N�e�B�u�R���g���[���G���W���}�E���g�̋Z�p�ɂ���ĐU���ʂŖ��̑���V�^�U�C���G���W��
�̋C���x�~�^�]�̐U�������������ނ��Ƃɐ������Ă���̂ł���B���̓��C�S���H�Ƃ̋Z�p���^�g���b�N�f�B�[�[
���G���W���ɉ��p����A��^�g���b�N�ɂQ�^�[�{�ߋ��@�����̋C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j���̗p��
���ꍇ�Ɋ뜜�����C���x�~�^�]���̐U���ɂ��ẮA��������S�ɉ��������ނ��Ƃ��e�Ղɂł���ƍl������B
���������āA��^�g���b�N�̒���U�C���G���W�����C���x�~�����邱�Ƃɂ��ẮA�U���Ɋւ����Q�͉��������ƍl
���ėǂ��̂ł͂Ȃ����낤���B
�@���̂悤�ȋZ�p�����p����A�ߋ��f�B�[�[���G���W���̋C���x�~�^�]���ɐ�����Ɨ\�z����邷�G���W���U����
�h�~���邱�Ƃ��e�ՂȂ��Ƃ͖��炩���B���ɁA��^�g���b�N�̃L���u�ł́w���o�[(�S��)�X�v�����O�x�w�R�C���X�v�����O�x
�w�G�A�X�v�����O�x����p�����L���u�T�X�y���V�����Ŏx������Ă���B���̂��߁A��^�g���b�N�̏ꍇ�ɂ́A�C���x�~
�̃G���W���U�����^�]��ɓ`�d����\���ƂȂ��Ă���A�C���x�~�^�]�ɂ�����U�����ɂ��ẮA��p�Ԃ��
���e�Ղɉ����ł���Ɛ��������B
�h�~���邱�Ƃ��e�ՂȂ��Ƃ͖��炩���B���ɁA��^�g���b�N�̃L���u�ł́w���o�[(�S��)�X�v�����O�x�w�R�C���X�v�����O�x
�w�G�A�X�v�����O�x����p�����L���u�T�X�y���V�����Ŏx������Ă���B���̂��߁A��^�g���b�N�̏ꍇ�ɂ́A�C���x�~
�̃G���W���U�����^�]��ɓ`�d����\���ƂȂ��Ă���A�C���x�~�^�]�ɂ�����U�����ɂ��ẮA��p�Ԃ��
���e�Ղɉ����ł���Ɛ��������B
�W�D�Q�^�[�{�ߋ��@�����̋C���x�~�G���W���ɂ�����R�X�g�A�b�v�̌���
�@�Ƃ���ŁAMPI�i�}���`�|�C���g�C���W�F�N�V�����j�̃K�\�����G���W�����C���x�~����ꍇ�ɂ́A�σo���u�@�\�ɂ�
���ă��b�J�[�A�[�����x�~�����邩�A�܂��͒��������̖�����ւ��o���u���t�^�[�𗘗p���A�z�C�o���u��S��
������悤�ɂ��A���Ȃ��Ƃ��z�C���~�����ĔR���������~�����邱�Ƃ��K�v�ƂȂ�B���̂��߁A�z���_�̋C���x�~
�K�\�����G���W���ł́A�σo���u�^�C�~���O�@�\���̗p���ċx�~����C���̋z�C�o���u�Ɣr�C�o���u��S������
��悤�ɂ��Ă���A�]���̋C���x�~���Ȃ��G���W���ɔ�ׂăR�X�g���ł���ƍl������B
���ă��b�J�[�A�[�����x�~�����邩�A�܂��͒��������̖�����ւ��o���u���t�^�[�𗘗p���A�z�C�o���u��S��
������悤�ɂ��A���Ȃ��Ƃ��z�C���~�����ĔR���������~�����邱�Ƃ��K�v�ƂȂ�B���̂��߁A�z���_�̋C���x�~
�K�\�����G���W���ł́A�σo���u�^�C�~���O�@�\���̗p���ċx�~����C���̋z�C�o���u�Ɣr�C�o���u��S������
��悤�ɂ��Ă���A�]���̋C���x�~���Ȃ��G���W���ɔ�ׂăR�X�g���ł���ƍl������B
�@��^�g���b�N�p�^�[�{�ߋ��f�B�[�[���G���W���ɉσo���u�^�C�~���O�@�\�𓋍ڂ��ċC���x�~�G���W�������邱��
�́A�ꉞ�A�\�ł���B����́A�]���̑�^�g���b�N�p�^�[�{�ߋ��f�B�[�[���G���W���Ƀz���_�̃K�\�����G���W����
���l�̋z�r�C�n�̃��J�j�Y�����̗p���ċC���x�~�G���W��������Ηǂ��̂ł���B���̑�^�g���b�N�p�̉σo��
�u�^�C�~���O�����̋C���x�~�G���W���ł́A�ғ��C���̔r�C�K�X�G�l���M�[��L���ɗ��p���ă^�[�{�ߋ��@���쓮��
���邽�߁A��^�^�[�{�ߋ��f�B�[�[���G���W���ɉσo���u�^�C�~���O�V�X�e�����̗p���ċx�~����C���̋z�C�ق�
�S���������邱�Ƃ��K�{�ƂȂ�B
�́A�ꉞ�A�\�ł���B����́A�]���̑�^�g���b�N�p�^�[�{�ߋ��f�B�[�[���G���W���Ƀz���_�̃K�\�����G���W����
���l�̋z�r�C�n�̃��J�j�Y�����̗p���ċC���x�~�G���W��������Ηǂ��̂ł���B���̑�^�g���b�N�p�̉σo��
�u�^�C�~���O�����̋C���x�~�G���W���ł́A�ғ��C���̔r�C�K�X�G�l���M�[��L���ɗ��p���ă^�[�{�ߋ��@���쓮��
���邽�߁A��^�^�[�{�ߋ��f�B�[�[���G���W���ɉσo���u�^�C�~���O�V�X�e�����̗p���ċx�~����C���̋z�C�ق�
�S���������邱�Ƃ��K�{�ƂȂ�B
�@���̂��ߑ�^�g���b�N�p�^�[�{�ߋ��f�B�[�[���G���W���p�̉σo���u�^�C�~���O�V�X�e���Ƃ��āA�D���p�̑�^�f
�B�[�[���G���W���Ŏ��p������Ă���z�C�ًy�єr�C�ق�����܂��͓d���͂ō쓮������J�����X�V�X�e����K�\��
���G���W���Ŏ��p������Ă���σo���u�^�C�~���O�@�\��V���ɊJ�����邱�Ƃ��K�v�ƂȂ�B���ɑ�^�^�[�{�ߋ�
�f�B�[�[���G���W���p�̉σo���u�^�C�~���O�@�\���J�����đ�^�^�[�{�ߋ��f�B�[�[���G���W���̋C���x�~�^�]��
�����ł����Ƃ��Ă��A�����ȉσo���u�^�C�~���O�@�\���̗p���Ă��邽�߂ɑ�^�g���b�N�p�̋C���x�~�G���W���͑�
���ȃR�X�g�����������A���i�Ƃ��Ďs��Ɏ�����邩�ǂ����͑傢�ɋ^��ł���B����ɑ��A�M�҂���Ă�
��Q�^�[�{�ߋ��@�����̋C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p�ł́A�σo���u�^�C�~���O�@�\���s�v��
��R�X�g�̑�^�g���b�N�p�̋C���x�~�G���W�������p���ł���̂ł���B
�B�[�[���G���W���Ŏ��p������Ă���z�C�ًy�єr�C�ق�����܂��͓d���͂ō쓮������J�����X�V�X�e����K�\��
���G���W���Ŏ��p������Ă���σo���u�^�C�~���O�@�\��V���ɊJ�����邱�Ƃ��K�v�ƂȂ�B���ɑ�^�^�[�{�ߋ�
�f�B�[�[���G���W���p�̉σo���u�^�C�~���O�@�\���J�����đ�^�^�[�{�ߋ��f�B�[�[���G���W���̋C���x�~�^�]��
�����ł����Ƃ��Ă��A�����ȉσo���u�^�C�~���O�@�\���̗p���Ă��邽�߂ɑ�^�g���b�N�p�̋C���x�~�G���W���͑�
���ȃR�X�g�����������A���i�Ƃ��Ďs��Ɏ�����邩�ǂ����͑傢�ɋ^��ł���B����ɑ��A�M�҂���Ă�
��Q�^�[�{�ߋ��@�����̋C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p�ł́A�σo���u�^�C�~���O�@�\���s�v��
��R�X�g�̑�^�g���b�N�p�̋C���x�~�G���W�������p���ł���̂ł���B
�@���āA���s�̑�^�g���b�N�ɗp�����Ă���U�C���̃^�[�{�ߋ��f�B�[�[���G���W���ɂ͂P��̉ߋ��@�����������
����A���̃G���W����P���ɋC���x�~����悤�ɂ����G���W�����A�V���O���^�[�{�����̋C���x�~�G���W���ł���B��
�̃V���O���^�[�{�����̋C���x�~�G���W���ł́A�T�C�N���������l������A���R�A�σo���u�^�C�~���O��������
�p����K�v������B�������A���̉σo���u�^�C�~���O���̗p�����V���O���^�[�{�����̋C���x�~�G���W���̏ꍇ��
�́A�P��̃G���W���ɂP��̑�^�^�[�{�ߋ��@�����ڂ����\���ł��邽�߁A���̋C���x�~�G���W���̕���������
�����Ă͏�ɑ�^�̃^�[�{�ߋ��@���쓮�����邱�ƂɂȂ邽�߂Ƀ^�[�{�ߋ��@�̍쓮���̌������Ⴍ�Ȃ�A�{����
�C���x�~�G���W�̓����ł��镔�������̔R��\���ɉ��P�ł��Ȃ����_������B����ɑ��A�M�҂���Ă���Q
�^�[�{�ߋ��@�����̋C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�ł͋C���Q���ɏ��^�̃^�[�{�ߋ��@�𓋍ڂ��Ă���
���Ƃ���A�G���W���̕������^�]���ɂ͏��^�̃^�[�{�ߋ��@�����������ʼn^�]�ł���\���ƂȂ��Ă��邽�߂Ƀ|
���s���O�����̍팸�i���̃|���s���O�d���̊l���j���ł��A�啝�ȔR����P�������邱�Ƃ��傫�ȓ����ł���B
����A���̃G���W����P���ɋC���x�~����悤�ɂ����G���W�����A�V���O���^�[�{�����̋C���x�~�G���W���ł���B��
�̃V���O���^�[�{�����̋C���x�~�G���W���ł́A�T�C�N���������l������A���R�A�σo���u�^�C�~���O��������
�p����K�v������B�������A���̉σo���u�^�C�~���O���̗p�����V���O���^�[�{�����̋C���x�~�G���W���̏ꍇ��
�́A�P��̃G���W���ɂP��̑�^�^�[�{�ߋ��@�����ڂ����\���ł��邽�߁A���̋C���x�~�G���W���̕���������
�����Ă͏�ɑ�^�̃^�[�{�ߋ��@���쓮�����邱�ƂɂȂ邽�߂Ƀ^�[�{�ߋ��@�̍쓮���̌������Ⴍ�Ȃ�A�{����
�C���x�~�G���W�̓����ł��镔�������̔R��\���ɉ��P�ł��Ȃ����_������B����ɑ��A�M�҂���Ă���Q
�^�[�{�ߋ��@�����̋C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�ł͋C���Q���ɏ��^�̃^�[�{�ߋ��@�𓋍ڂ��Ă���
���Ƃ���A�G���W���̕������^�]���ɂ͏��^�̃^�[�{�ߋ��@�����������ʼn^�]�ł���\���ƂȂ��Ă��邽�߂Ƀ|
���s���O�����̍팸�i���̃|���s���O�d���̊l���j���ł��A�啝�ȔR����P�������邱�Ƃ��傫�ȓ����ł���B
�@���������āA�M�҂���Ă���Q�^�[�{�ߋ��@�����̋C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�Z�p�́A�z���_�̃K
�\������p�Ԃɍ̗p����Ă���悤�ȉσo���u�^�C�~���O�����̋C���x�~�G���W���Z�p�ɔ�ׂă^�[�{�ߋ��f�B�[
�[���G���W���ł̕��������̔R����P�̋@�\���i�i�ɗD��Ă��邽�߁A��^�g���b�N�p�̃^�[�{�ߋ��f�B�[�[��
�G���W���ɂ�����C���x�~�̃G���W���Z�p�ɂ́A�d�ʎԃ��[�h�R��l������s�R��l�̑啝�ȉ��P�ɗL���ȂQ�^�[
�{�ߋ��@�����̋C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j���̗p���ׂ��ł���ƍl���Ă���B
�\������p�Ԃɍ̗p����Ă���悤�ȉσo���u�^�C�~���O�����̋C���x�~�G���W���Z�p�ɔ�ׂă^�[�{�ߋ��f�B�[
�[���G���W���ł̕��������̔R����P�̋@�\���i�i�ɗD��Ă��邽�߁A��^�g���b�N�p�̃^�[�{�ߋ��f�B�[�[��
�G���W���ɂ�����C���x�~�̃G���W���Z�p�ɂ́A�d�ʎԃ��[�h�R��l������s�R��l�̑啝�ȉ��P�ɗL���ȂQ�^�[
�{�ߋ��@�����̋C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j���̗p���ׂ��ł���ƍl���Ă���B
�X�D�f�B�[�[���G���W���̔R�ĉ��P�ɂ��R��팸������Ȍ���ɂ���
�@�@�O�q�̒ʂ�A����܂Ő��̒��ɍL�����y���Ă���Ζ��R���̌y����R���Ƃ���f�B�[�[���G���W���ł͔R��팸
�̊����͂b�n�Q�팸�̊����Ɠ������Ȃ邽�߁A���̃f�B�[�[���G���W���́u�R�����P�v�́u�b�n�Q�팸�v�Ɠ����Ӗ��i���`
��ɋ߂��Ӗ��j�������ƂɂȂ�B���̃f�B�[�[���G���W���ɂ��ẮA�O�q�̂悤�ɁA�����ԋZ�p��s�́u������
�Z�p�v��Vol.64�ANo�P�A2010�i2010�N1���P�����s�j�̔ѓc�P�� �c���勳���@���R�����u�f�B�[�[���G���W�����̂P�O�N�v
�ɂ̓f�B�[�[���G���W����CO�Q�팸���u�傫�Ȓ���ۑ�v�ƒf�肵�A���́u�ۑ�B���v�ɂ��u�]���̃f�B�[�[���G���W��
�̗v�f�V�X�e���ɉ����A�R���A�R�āA�G�}�̌����A�V�X�e������̓������Z�p�����߂��Ă���v�ƋL�ڂ���Ă�
��A�f�B�[�[���G���W���̐��\�E�r�o�K�X�ɂ������قƂ�ǑS�Ă̗v�f�E���ڂ̉��ǂƂ����̘A�g�����œK����
���K�v�Ƃ���|���L�ڂ���Ă���̂��B������t�̌������Œ[�I�ɒ��킷�ƁA�����_�ł��f�B�[�[���G���W���̔R
��팸�i���b�n�Q�팸�j�́A�u�Z�p�I�ɔ����ǂ���̏v�ɂ����Ƃ̈Ӗ��ɗ����ł���̂ł���B�����ċ�������
�ɁA���̔ѓc�P�� �c���勳���@���R�����u�f�B�[�[���G���W�����̂P�O�N�v�ɂ͂b�n�Q�팸�i���R��팸�j�̕K�v����
�i���Ă��邪�A�b�n�Q�팸�i���R��팸�j�̋�̓I�ȋZ�p�I�헪�̎����������L�ڂ���Ă��Ȃ��̂ł���B
�̊����͂b�n�Q�팸�̊����Ɠ������Ȃ邽�߁A���̃f�B�[�[���G���W���́u�R�����P�v�́u�b�n�Q�팸�v�Ɠ����Ӗ��i���`
��ɋ߂��Ӗ��j�������ƂɂȂ�B���̃f�B�[�[���G���W���ɂ��ẮA�O�q�̂悤�ɁA�����ԋZ�p��s�́u������
�Z�p�v��Vol.64�ANo�P�A2010�i2010�N1���P�����s�j�̔ѓc�P�� �c���勳���@���R�����u�f�B�[�[���G���W�����̂P�O�N�v
�ɂ̓f�B�[�[���G���W����CO�Q�팸���u�傫�Ȓ���ۑ�v�ƒf�肵�A���́u�ۑ�B���v�ɂ��u�]���̃f�B�[�[���G���W��
�̗v�f�V�X�e���ɉ����A�R���A�R�āA�G�}�̌����A�V�X�e������̓������Z�p�����߂��Ă���v�ƋL�ڂ���Ă�
��A�f�B�[�[���G���W���̐��\�E�r�o�K�X�ɂ������قƂ�ǑS�Ă̗v�f�E���ڂ̉��ǂƂ����̘A�g�����œK����
���K�v�Ƃ���|���L�ڂ���Ă���̂��B������t�̌������Œ[�I�ɒ��킷�ƁA�����_�ł��f�B�[�[���G���W���̔R
��팸�i���b�n�Q�팸�j�́A�u�Z�p�I�ɔ����ǂ���̏v�ɂ����Ƃ̈Ӗ��ɗ����ł���̂ł���B�����ċ�������
�ɁA���̔ѓc�P�� �c���勳���@���R�����u�f�B�[�[���G���W�����̂P�O�N�v�ɂ͂b�n�Q�팸�i���R��팸�j�̕K�v����
�i���Ă��邪�A�b�n�Q�팸�i���R��팸�j�̋�̓I�ȋZ�p�I�헪�̎����������L�ڂ���Ă��Ȃ��̂ł���B
�@���������A���s�c�菑���P�X�X�V�N�P�Q���P�P���ɋc�������CO�Q�팸�̕K�v�����L���F������n�߂ĂP�O�N���x��
�̒����N�����o�߂��Ă���̂ł���B����ɂ�������炸�A�Q�O�P�O�N�P���P�����s�́u�����ԋZ�p�v���̔ѓc�P��
�c���勳���@���R�����u�f�B�[�[���G���W�����̂P�O�N�v�ł́A�����ɔR�����P�i���b�n�Q�팸�j���u�Z�p�I�ɔ����ǂ�
��̏v�ɂ���|���̋L���i�_���j���L�ڂ���Ă���̂��B�����āA���̎����ԋZ�p�����S���S��l�̉����
�z�z����Ă���̂��B���̂��߁A�����ԗp�f�B�[�[���G���W���W�̊w�ҁE���Ƃ̋��ʔF���́A�u�f�B�[�[���G��
�W���̔R����\���ɍ팸�ł���Z�p�͖����Ɍ����o����Ă��Ȃ��v�Ƃ̌����ň�v���Ă���l���ĊԈႢ�Ȃ��̂�
�͂Ȃ����낤���B
�̒����N�����o�߂��Ă���̂ł���B����ɂ�������炸�A�Q�O�P�O�N�P���P�����s�́u�����ԋZ�p�v���̔ѓc�P��
�c���勳���@���R�����u�f�B�[�[���G���W�����̂P�O�N�v�ł́A�����ɔR�����P�i���b�n�Q�팸�j���u�Z�p�I�ɔ����ǂ�
��̏v�ɂ���|���̋L���i�_���j���L�ڂ���Ă���̂��B�����āA���̎����ԋZ�p�����S���S��l�̉����
�z�z����Ă���̂��B���̂��߁A�����ԗp�f�B�[�[���G���W���W�̊w�ҁE���Ƃ̋��ʔF���́A�u�f�B�[�[���G��
�W���̔R����\���ɍ팸�ł���Z�p�͖����Ɍ����o����Ă��Ȃ��v�Ƃ̌����ň�v���Ă���l���ĊԈႢ�Ȃ��̂�
�͂Ȃ����낤���B
�@���̂��Ƃ́A��^�g���b�N��CO�Q�팸�i���R��팸�j�̋Z�p�J�����A���̂P�O�N�ԁA���̐��ʂ������Ȃ��������Ƃ�
�؋��ƍl������B���{�̃g���b�N���[�J�S�Ёi����A�����U�A�t�c�A�O�H�ӂ����j�⑽���̑�w�E�������ł͌��݂�����
���̋Z�p�ҁE���ƁE�w�҂��f�B�[�[���G���W���̔R��팸�̋Z�p�J���ɓ���A�K���̓w�͂�����Ă��邱�ƂƎv��
���A�T���O��̔R�����P���\��12�i�@�B�������g�����X�~�b�V�����ɕC�G����悤�ȔR��팸�������ł���f�B�[
�[���G���W���̔R�����P�Z�p�������ɊJ���ł��Ă��Ȃ��悤���B����̌������i�̏㏸���������Ȃ��Љ�
�̒��ōX�Ȃ�b�n�Q�팸�i���R��팸�j�̎Љ�j�[�Y�̍��܂���l����ƁA���ڂɒl����悤�ȃf�B�[�[���G���W����
�R�����P�Z�p������̃g���b�N���[�J�E��w�E��������������\����Ă��Ȃ����Ƃ́A�J���ׂ����Ƃł͂Ȃ����낤���B
�؋��ƍl������B���{�̃g���b�N���[�J�S�Ёi����A�����U�A�t�c�A�O�H�ӂ����j�⑽���̑�w�E�������ł͌��݂�����
���̋Z�p�ҁE���ƁE�w�҂��f�B�[�[���G���W���̔R��팸�̋Z�p�J���ɓ���A�K���̓w�͂�����Ă��邱�ƂƎv��
���A�T���O��̔R�����P���\��12�i�@�B�������g�����X�~�b�V�����ɕC�G����悤�ȔR��팸�������ł���f�B�[
�[���G���W���̔R�����P�Z�p�������ɊJ���ł��Ă��Ȃ��悤���B����̌������i�̏㏸���������Ȃ��Љ�
�̒��ōX�Ȃ�b�n�Q�팸�i���R��팸�j�̎Љ�j�[�Y�̍��܂���l����ƁA���ڂɒl����悤�ȃf�B�[�[���G���W����
�R�����P�Z�p������̃g���b�N���[�J�E��w�E��������������\����Ă��Ȃ����Ƃ́A�J���ׂ����Ƃł͂Ȃ����낤���B
�@�ȏ�̂悤�ȏɊӂ݁A�f�B�[�[���G���W���̔R����P�Z�p�Ƃ��ĕM�҂���Ă��Ă���Z�p���A�e�C���̕��ׂ�
�œK�Ƀ}�l�W�����g���ĉ^�]����Q�^�[�{�ߋ��@�������C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�ł���B����A��^
�̃g���b�N�E�g���N�^�̓|�X�g�V�����i2009�N�K���j�Ƃ���ɑ����m�n���K���������ɓK��������K�v�����邪�A���̂悤
�ȏꍇ�ɂ����Ă������C���x�~�f�B�[�[���G���W���Z�p���̗p���邱�Ƃɂ���āA�V�i�}�j���A���g�����~�b�V��
���𓋍ڂ����ԗ����܂߂��S�Ԏ�̃g���b�N�E�o�X�ɂ����āA�d�ʎԃ��[�h�R���2015�N�x�i����27�N�x�j�B
���ڕW�̏d�ʎԔR���ɗe�ՂɓK�������邱�Ƃ��ł����̂ł���B�ܘ_�A�P�Q�i�@�B�������g�����X�~�b�V����
�̃g���b�N�E�g���N�^�ł͍X�Ȃ�R�����P�������ł���̂��B
�œK�Ƀ}�l�W�����g���ĉ^�]����Q�^�[�{�ߋ��@�������C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�ł���B����A��^
�̃g���b�N�E�g���N�^�̓|�X�g�V�����i2009�N�K���j�Ƃ���ɑ����m�n���K���������ɓK��������K�v�����邪�A���̂悤
�ȏꍇ�ɂ����Ă������C���x�~�f�B�[�[���G���W���Z�p���̗p���邱�Ƃɂ���āA�V�i�}�j���A���g�����~�b�V��
���𓋍ڂ����ԗ����܂߂��S�Ԏ�̃g���b�N�E�o�X�ɂ����āA�d�ʎԃ��[�h�R���2015�N�x�i����27�N�x�j�B
���ڕW�̏d�ʎԔR���ɗe�ՂɓK�������邱�Ƃ��ł����̂ł���B�ܘ_�A�P�Q�i�@�B�������g�����X�~�b�V����
�̃g���b�N�E�g���N�^�ł͍X�Ȃ�R�����P�������ł���̂��B
�@���݁A����̃g���b�N���[�J�ł��R�ĉ��P�ɂ��R����オ�Z�p�I�ɔ����ǂ���ł��邱�Ƃ��l����A�e�g���b�N
���[�J�͋��ɂQ�^�[�{�ߋ��@�����̋C���x�~�f�B�[�[���G���W�����J�����S�O�Ȃ��J�n����̂����R�̐���s���ƍl
������B�������A����ł̓g���b�N���[�J�ł͂��̂悤�ȏ펯���ʗp���Ȃ��悤���B�e�g���b�N���[�J�̑�^�g���b�N�p�f
�B�[�[���G���W���̔R�����P�Z�p���S������Z�p�҂́A����܂Ńf�B�[�[���G���W���̔R�ĉ��P�̐��Ƃ���̂�
����B�ނ�͔R�ĉ��P�ɂ���ĔR������r�o�K�X�ጸ����Ɩ��ɒ��炭�]�����Ă������Ƃ�����A�A�R�ĉ��P�̖�
�͂Ɏ��߂���āu�R�ĉ��P�͖��\�v�Ƃ���ߋ��̎����ɂƂ���Ă���A�R�ĉ��P�ȊO�ɋ����������̂ł���B��
�̂��߁A�M�҂���Ă���u�Q�^�[�{�ߋ��@�����̋C���x�~�f�B�[�[���G���W���ɂ��R�����P�̋Z�p�v���e�g���b�N��
�[�J�̐��Ƃ������ĖَE���Ă���̂ł͂Ȃ����낤���B
���[�J�͋��ɂQ�^�[�{�ߋ��@�����̋C���x�~�f�B�[�[���G���W�����J�����S�O�Ȃ��J�n����̂����R�̐���s���ƍl
������B�������A����ł̓g���b�N���[�J�ł͂��̂悤�ȏ펯���ʗp���Ȃ��悤���B�e�g���b�N���[�J�̑�^�g���b�N�p�f
�B�[�[���G���W���̔R�����P�Z�p���S������Z�p�҂́A����܂Ńf�B�[�[���G���W���̔R�ĉ��P�̐��Ƃ���̂�
����B�ނ�͔R�ĉ��P�ɂ���ĔR������r�o�K�X�ጸ����Ɩ��ɒ��炭�]�����Ă������Ƃ�����A�A�R�ĉ��P�̖�
�͂Ɏ��߂���āu�R�ĉ��P�͖��\�v�Ƃ���ߋ��̎����ɂƂ���Ă���A�R�ĉ��P�ȊO�ɋ����������̂ł���B��
�̂��߁A�M�҂���Ă���u�Q�^�[�{�ߋ��@�����̋C���x�~�f�B�[�[���G���W���ɂ��R�����P�̋Z�p�v���e�g���b�N��
�[�J�̐��Ƃ������ĖَE���Ă���̂ł͂Ȃ����낤���B
�@�Ƃ���ŁA�����ʂ̘b��Ɉ��邱�ƂɂȂ邪�A�C���^�[�l�b�g�̃u���O�u�������L�ƌo�ϓW�]�v�i�o�T�Fhttp://blog.
goo.ne.jp/2005tora/�j�ł́A���L�̐}10�Ɏ������悤�ɋߔN�̃f�W�^���d�q�@�폤�i�̐��E�ɂ������Ƃ̋��S��
���āA����Ղ�������Ă���B
goo.ne.jp/2005tora/�j�ł́A���L�̐}10�Ɏ������悤�ɋߔN�̃f�W�^���d�q�@�폤�i�̐��E�ɂ������Ƃ̋��S��
���āA����Ղ�������Ă���B
| �@�A�����J�͂W�O�N�㔼���܂ł͐����Ƃł��Z�p�͂⎑�{�̑傫���ň��|�I�ȋ����������Ă����B�q�b�`�ɂ��Ă����g���[���ɂ��Ă�
�R�_�b�N�ɂ��Ă����E�I�ȃi���o�[������Ƃ������B�Ƃ��낪�����̎s�����{�̃\�j�[��p�i�\�j�b�N��t�W�t�B�����Ȃǂ��i�o ���Ă��Ďs�ꋣ���Ŕj��Ă��܂����B�A�����J��Ƃ͌����ċZ�p�͂ŗ���Ă����킯�ł͂Ȃ��A�t���Z�p��f�W�^���J������ �g�ѓd�b�̓A�����J��Ƃ������������̂��B �@�Ƃ��낪�����̎s��������܂��Ƃ��ĉ�Бg�D������̕ω��ɍ��킹�Ă������ƂɎ��s���Ă��܂����B�q�b�`�������̃u���E���ǃe���r ����t���e���r�ɐ�ւ��铊����ɂ���ł���ԂɃV���[�v���J���[�t���p�l�������p�����Ă��܂����B�\�j�[�� �g���j�g�����E�u���E���ǃe���r�ɍS�邠�܂�ɉt���e���r�ɂ͒x���������悤�Ȃ��̂��낤�B�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E �@�\�j�[�̓E�H�[�N�}����g���j�g�����E�J���[�e���r�ňꎞ������܂������AiPod��T���X���̉t���e���r�ɔj�ꂽ�B���̉�Ђ� ���������Ɍo�c���f�̌�肪�������̂ł����A�����������z�����s����܂����v���グ�Ă���̂ɐ�̂Ă鎖���o���鎖 �Ȃ̂��낤���H�@�В�����̂Ă�Ɣ��f���Ă���̂Ă��镔��̖����������邾�낤�B�E�E�E�E�E�E |
�@�ȏ�̂悤�ɁA�q�b�`��g���[����R�_�b�N�̃A�����J�̓d�q�@���Ƃ͉t���Z�p��f�W�^���J������g�ѓd�b��
���E�ōŏ��ɊJ�����Ă���̂ł���B���̂悤�ɃA�����J�̓d�q�@���Ƃ͐܊p�A�V�Z�p����g������i���i���J��
���Ă���ɂ�������炸�A�����̏��i����ʂɕ��y���鎞��̌��݂ł́A���{�Ȃǂ̃A�����J���O�̊�Ƃ����
�ƂȂ��Ă���̂ł���B���̌o�܂̏ڍׂ͖��m�ł͂Ȃ����A�q�b�`��g���[����R�_�b�N�̃A�����J�̓d�q�@����
�ł͋������i�̒S���҂̎��ȕېg�ɂ���i�Z�p���i�̊J����W�Q����H�쓙�ɂ���ď��i�J����Y�ݔ���
�\���ȓ������ł��Ȃ��������߂ɁA�����̐V�J�����i������҂̃j�[�Y�ɉ����邱�Ƃ��ł��Ȃ��������߂ł͂�
�����낤���B�A�����J��ƂƉ]���ǂ��e��Ƃł̋����̏��i�̒S���҂ɂ�鎩�ȕېg�̂��߂ɁA���̊�Ƃ̐�i�Z
�p���ڂ̉���I�ȐV���i�̊J�����i��W�Q����y������悤���B���̂悤�ɁA���i�������Ƃ������I�ɏd�v
�ȋZ�p�̊J���ɏ����ł��x���������ꍇ�ɂ́A���E�K�͂̊�Ƃł����Ă��ȒP�ɔp��Ă��܂��̂ł���B������A
�����J�̓d�q�@���Ƃ̋��S������ƁA���{�̊�Ƃ������͂킪�g�ƍl����ׂ��ł͂Ȃ����낤���B
���E�ōŏ��ɊJ�����Ă���̂ł���B���̂悤�ɃA�����J�̓d�q�@���Ƃ͐܊p�A�V�Z�p����g������i���i���J��
���Ă���ɂ�������炸�A�����̏��i����ʂɕ��y���鎞��̌��݂ł́A���{�Ȃǂ̃A�����J���O�̊�Ƃ����
�ƂȂ��Ă���̂ł���B���̌o�܂̏ڍׂ͖��m�ł͂Ȃ����A�q�b�`��g���[����R�_�b�N�̃A�����J�̓d�q�@����
�ł͋������i�̒S���҂̎��ȕېg�ɂ���i�Z�p���i�̊J����W�Q����H�쓙�ɂ���ď��i�J����Y�ݔ���
�\���ȓ������ł��Ȃ��������߂ɁA�����̐V�J�����i������҂̃j�[�Y�ɉ����邱�Ƃ��ł��Ȃ��������߂ł͂�
�����낤���B�A�����J��ƂƉ]���ǂ��e��Ƃł̋����̏��i�̒S���҂ɂ�鎩�ȕېg�̂��߂ɁA���̊�Ƃ̐�i�Z
�p���ڂ̉���I�ȐV���i�̊J�����i��W�Q����y������悤���B���̂悤�ɁA���i�������Ƃ������I�ɏd�v
�ȋZ�p�̊J���ɏ����ł��x���������ꍇ�ɂ́A���E�K�͂̊�Ƃł����Ă��ȒP�ɔp��Ă��܂��̂ł���B������A
�����J�̓d�q�@���Ƃ̋��S������ƁA���{�̊�Ƃ������͂킪�g�ƍl����ׂ��ł͂Ȃ����낤���B
�@���āA�����ő�^�g���b�N�̔R�����̘b�ɖ߂邪�A�u�����ԋZ�p�v��Vol.64�ANo.�P�A2010�Ɍf�ڂ̘_���u�f�B�[�[��
�G���W�����̂P�O�N�v�i���ҁF�ѓc�P�� �c�勳���Ƒ��R���j�ɋL�q����Ă���悤�ɁA���݂̂Ƃ����^�f�B�[�[���g���b
�N�ɂ�����R�ĉ��P�́A�u�Z�p�I�ɔ����ǂ���v�̂悤�ł���B���̏�ŊJ�������Ƃ��āA�M�҂͑�^�f�B�[�[
���g���b�N���R��팸���e�ՂɎ����ł���V�Z�p�Ƃ��āu�Q�^�[�{�ߋ��@�����̋C���x�~�f�B�[�[���G���W���i������
�J2005-54771�j�v�̋Z�p���Ă��Ă���̂ł����B�����C���x�~�f�B�[�[���G���W���i�������J2005-54771�j�̊J��
�ɒ��肵�Ȃ���^�g���b�N���[�J�́A�O�q���q�b�`��g���[����R�_�b�N�̃A�����J�̓d�q�@���Ƃ̂悤�ɁA����A
���ނ̓������ǂ鋰�ꂪ����̂ł͂Ȃ����낤���B���������āA���ꂩ��������Ɏ��Ђ̋Ɛт�L��������^�g��
�b�N���[�J�́A���}�Ɂu�Q�^�[�{�ߋ��@�����̋C���x�~�f�B�[�[���G���W���v�̊J���ɒ��肵�A���₩�ɑ�^�f�B�[�[
���g���b�N�̔R��팸���������A2015�N�x�d�ʎԔR���ɓK�������u�Q�^�[�{�ߋ��@�����̋C���x�~�f�B�[�[���G
���W���v�̂P�R���b�g���̕W���G���W�����ڂ̂V�i�}�j���A���g�����~�b�V�����̑�^�g���b�N�E�g���N�^�𑁊��Ɏs��ɓ�
�����邱�Ƃł���B����ɂ���āA���߂đ�^�g���b�N���[�J�̓��[�U�̃j�[�Y�ɓI�m�ɉ����邱�Ƃ��ł���̂ł���B
���x���������A�g���b�N���[�J�̒��Ŏ��Ђ̐��ނ�����������̂ł���A�O�q�̃A�����J�̓d�q�@��ƊE�ɂ�����
�����Ȋ�Ɛ��ނ̎��s�ʋ��t�Ƃ��ׂ����B
�G���W�����̂P�O�N�v�i���ҁF�ѓc�P�� �c�勳���Ƒ��R���j�ɋL�q����Ă���悤�ɁA���݂̂Ƃ����^�f�B�[�[���g���b
�N�ɂ�����R�ĉ��P�́A�u�Z�p�I�ɔ����ǂ���v�̂悤�ł���B���̏�ŊJ�������Ƃ��āA�M�҂͑�^�f�B�[�[
���g���b�N���R��팸���e�ՂɎ����ł���V�Z�p�Ƃ��āu�Q�^�[�{�ߋ��@�����̋C���x�~�f�B�[�[���G���W���i������
�J2005-54771�j�v�̋Z�p���Ă��Ă���̂ł����B�����C���x�~�f�B�[�[���G���W���i�������J2005-54771�j�̊J��
�ɒ��肵�Ȃ���^�g���b�N���[�J�́A�O�q���q�b�`��g���[����R�_�b�N�̃A�����J�̓d�q�@���Ƃ̂悤�ɁA����A
���ނ̓������ǂ鋰�ꂪ����̂ł͂Ȃ����낤���B���������āA���ꂩ��������Ɏ��Ђ̋Ɛт�L��������^�g��
�b�N���[�J�́A���}�Ɂu�Q�^�[�{�ߋ��@�����̋C���x�~�f�B�[�[���G���W���v�̊J���ɒ��肵�A���₩�ɑ�^�f�B�[�[
���g���b�N�̔R��팸���������A2015�N�x�d�ʎԔR���ɓK�������u�Q�^�[�{�ߋ��@�����̋C���x�~�f�B�[�[���G
���W���v�̂P�R���b�g���̕W���G���W�����ڂ̂V�i�}�j���A���g�����~�b�V�����̑�^�g���b�N�E�g���N�^�𑁊��Ɏs��ɓ�
�����邱�Ƃł���B����ɂ���āA���߂đ�^�g���b�N���[�J�̓��[�U�̃j�[�Y�ɓI�m�ɉ����邱�Ƃ��ł���̂ł���B
���x���������A�g���b�N���[�J�̒��Ŏ��Ђ̐��ނ�����������̂ł���A�O�q�̃A�����J�̓d�q�@��ƊE�ɂ�����
�����Ȋ�Ɛ��ނ̎��s�ʋ��t�Ƃ��ׂ����B
�@��^�g���b�N�́u�R��팸�v��uCO�Q�팸�v�����߂��Ă��鎞��ɁA��^�g���b�N�̔R��팸�ɐ��̌��͂�
������C���x�~�G���W���̋Z�p�̏d�v���𗝉��ł��Ȃ���^�g���b�N���[�J�́A�O�q�̃A�����J�̓d�q�@�탁
�[�J�ɂ������Ɛ��ނ̓Q�މ\�����ɂ߂č����ƍl������B�@
������C���x�~�G���W���̋Z�p�̏d�v���𗝉��ł��Ȃ���^�g���b�N���[�J�́A�O�q�̃A�����J�̓d�q�@�탁
�[�J�ɂ������Ɛ��ނ̓Q�މ\�����ɂ߂č����ƍl������B�@
�@�܂��A��^�f�B�[�[���g���b�N�ɂQ�^�[�{�ߋ��@�����̋C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p���̗p����
�ۂ̃R�X�g�A�b�v�́A�C���x�~�G���W�����ɂ�VG�^�[�{�ߋ��@�ADPF���u�AEGR���u�̊e���i�����ꂼ��Q��Â�
�K�v�ƂȂ邽�߁A�����̕��i���̑������R�X�g�㏸�̌����ł���B�������A���̕��i�����Q�{�ƂȂ邪�e���i�̔\
�́E�e�ʂ��P�^�Q�ƂȂ邽�߂ɂP�䓖����̃R�X�g�������ł���B���̂��߁A�C���x�~�G���W���i�������J2005-
54771�j�̋Z�p���̗p����ۂ̃R�X�g�����͍��X�A�Q�O�����x�Ɛ��������B�f�B�[�[���G���W���̈ꕔ�̕��i�̃R�X
�g�A�b�v���Q�O�����x�ƂȂ邾���ő�^�g���b�N�̏d�ʎԃ��[�h�R��T�`�P�O��������ł���Z�p�́A�C���x�~�G���W
���i�������J2005-54771�j�̋Z�p�����ł���B
�ۂ̃R�X�g�A�b�v�́A�C���x�~�G���W�����ɂ�VG�^�[�{�ߋ��@�ADPF���u�AEGR���u�̊e���i�����ꂼ��Q��Â�
�K�v�ƂȂ邽�߁A�����̕��i���̑������R�X�g�㏸�̌����ł���B�������A���̕��i�����Q�{�ƂȂ邪�e���i�̔\
�́E�e�ʂ��P�^�Q�ƂȂ邽�߂ɂP�䓖����̃R�X�g�������ł���B���̂��߁A�C���x�~�G���W���i�������J2005-
54771�j�̋Z�p���̗p����ۂ̃R�X�g�����͍��X�A�Q�O�����x�Ɛ��������B�f�B�[�[���G���W���̈ꕔ�̕��i�̃R�X
�g�A�b�v���Q�O�����x�ƂȂ邾���ő�^�g���b�N�̏d�ʎԃ��[�h�R��T�`�P�O��������ł���Z�p�́A�C���x�~�G���W
���i�������J2005-54771�j�̋Z�p�����ł���B
�@���̂悤�ɑ����̃R�X�g�A�b�v���������Ƃ��Ă��A�C���~�G���W���𓋍ڂ�����^�g���b�N�����p�������ꍇ�ɂ́A�]
���̑S�C�����ϓ��o�͂ʼnғ�����G���W���ɔ�r���āA�G���W���{�̂łT�`�P�O�����x�̔R����P�������A����
��A�|�X�g���ˎႵ���͔r�C�Ǔ����˂ɂ��t�B���^�Đ��̕p�x�����������ă|�X�g���˂ɂ��R���Q��̖h�~�ɂ�
��R����P���t���ł��郁���b�g�������邱�ƂɂȂ�B���̂��Ƃ���A�Q�^�[�{�ߋ��@�����̋C���x�~�G���W���i����
���J2005-54771�j�̗p�̋C���x�~�G���W���𓋍ڂ�����^�g���b�N�𑁋}�Ɏ��p�����邱�Ƃ́A�����_�Œx�X�Ƃ���
�i�܂Ȃ���^�g���b�N�̕���ł̂T�`�P�O�����x�̔R��팸����тb�n�Q�팸�������ł���̂ł���B����ɂ���āA�g
���b�N���[�J�ɂƂ��Ă͏d�v�ȏȃG�l���M�[��CO�Q�팸�̎Љ�I�Ӗ����ʂ����A�g���b�N���[�U�ɂƂ��Ă͉^�s�o���
�팸�����b�g������ł���悤�ɂȂ�B���������āA�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p���̗p������^�g
���b�N�̎��p�́A��^�g���b�N�̃��[�J�ƃ��[�U�̗����ɂƂ��ċɂ߂Ċ�������Ƃ��B
���̑S�C�����ϓ��o�͂ʼnғ�����G���W���ɔ�r���āA�G���W���{�̂łT�`�P�O�����x�̔R����P�������A����
��A�|�X�g���ˎႵ���͔r�C�Ǔ����˂ɂ��t�B���^�Đ��̕p�x�����������ă|�X�g���˂ɂ��R���Q��̖h�~�ɂ�
��R����P���t���ł��郁���b�g�������邱�ƂɂȂ�B���̂��Ƃ���A�Q�^�[�{�ߋ��@�����̋C���x�~�G���W���i����
���J2005-54771�j�̗p�̋C���x�~�G���W���𓋍ڂ�����^�g���b�N�𑁋}�Ɏ��p�����邱�Ƃ́A�����_�Œx�X�Ƃ���
�i�܂Ȃ���^�g���b�N�̕���ł̂T�`�P�O�����x�̔R��팸����тb�n�Q�팸�������ł���̂ł���B����ɂ���āA�g
���b�N���[�J�ɂƂ��Ă͏d�v�ȏȃG�l���M�[��CO�Q�팸�̎Љ�I�Ӗ����ʂ����A�g���b�N���[�U�ɂƂ��Ă͉^�s�o���
�팸�����b�g������ł���悤�ɂȂ�B���������āA�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p���̗p������^�g
���b�N�̎��p�́A��^�g���b�N�̃��[�J�ƃ��[�U�̗����ɂƂ��ċɂ߂Ċ�������Ƃ��B
�P�O�D�g���b�N�E�o�X�ɑ��� 2015�N�x�d�ʎԔR���ɂ��R��K��
�@2006�N4��1������{�s���ꂽ�u�G�l���M�[�̎g�p�̍������Ɋւ���@���v�i�ʏ́F�����ȃG�l�@�j�̉����ɂ��A��
���Ɏ����\�U�̏d�ʎԁi�ԗ����d��2.5t��)�̎����Ԃɑ���2015�N�x�i����27�N�x�j�d�ʎԔR�����K�肳��
���B
���Ɏ����\�U�̏d�ʎԁi�ԗ����d��2.5t��)�̎����Ԃɑ���2015�N�x�i����27�N�x�j�d�ʎԔR�����K�肳��
���B

�@���̏d�ʎԔR���́A2015�N�x�i����27�N�x�j����B���̖ڕW�N�x�Ƃ��Ă��邽�߁A�g���b�N���[�J��2015�N
�x�܂łɎԗ����d�ʂ��Ƃɒ�߂�ꂽ�d�ʎԔR��l�̊�l�ɓK��������K�v������B�܂��A2006�N4���ȍ~�ɔ�
������V�^�Ԃɂ��āA���i�J�^���O�֔R��l��\�����Ȃ���Ȃ�Ȃ����ƂɂȂ����B���̂��߁A�g���b�N���[�J�ł�
�}篁A�g���b�N�̑��s�R������P����K�v�ɔ����邱�ƂɂȂ����̂ł���B
�x�܂łɎԗ����d�ʂ��Ƃɒ�߂�ꂽ�d�ʎԔR��l�̊�l�ɓK��������K�v������B�܂��A2006�N4���ȍ~�ɔ�
������V�^�Ԃɂ��āA���i�J�^���O�֔R��l��\�����Ȃ���Ȃ�Ȃ����ƂɂȂ����B���̂��߁A�g���b�N���[�J�ł�
�}篁A�g���b�N�̑��s�R������P����K�v�ɔ����邱�ƂɂȂ����̂ł���B
�@���̏d�ʎԔR��K���ł́A�g���b�N���[�J�[��2015�N�x�ɏo�ׂ���g���b�N�ŋK���̐��l��B������K�v������B��
���āA�B���ł��Ȃ���Όo�Y�ȂȂǂ������̊��������邻�����B����ł����P����Ȃ��ƃ��[�J�[����Ԏ햼�����\
���A�������Ȃ��Ƃ̂��Ƃł���B�����āA2015�N�x�d�ʎԔR���ɕs�K���̎�Ԃ́A���Y�̑ł��肪�������
�ł���B
���āA�B���ł��Ȃ���Όo�Y�ȂȂǂ������̊��������邻�����B����ł����P����Ȃ��ƃ��[�J�[����Ԏ햼�����\
���A�������Ȃ��Ƃ̂��Ƃł���B�����āA2015�N�x�d�ʎԔR���ɕs�K���̎�Ԃ́A���Y�̑ł��肪�������
�ł���B
�@����A�č��ł��I�o�}�đ哝�̂͂Q�O�P�O�N�T���Q�P���ɒ��^�Ƒ�^�̃g���b�N��ΏۂƂ������̔R�������
���鏑�Ȃ��^�A�ȁA�G�l���M�[�ȂȂǂɑ������̂ł���B����ɂ��ƕč��ł͂Q�O�P�P�N�V�����܂łɒ��^�Ƒ�^��
�g���b�N��ΏۂƂ������̔R�����肵�A�P�S�N���f������K�p�ΏۂƂ���Ƃ̂��Ƃł���B���̂悤�ɕč��ł��g���b
�N�̔R���̐��肪�X�^�[�g���A�g���b�N�̔R�����P�̎��g�݂��X�^�[�g�����̂ł���B���̂��Ƃ��l����ƁA�g���b
�N�̔R��팸�͐��E�̂������ƌ��ėǂ��̂ł͂Ȃ����낤���B
���鏑�Ȃ��^�A�ȁA�G�l���M�[�ȂȂǂɑ������̂ł���B����ɂ��ƕč��ł͂Q�O�P�P�N�V�����܂łɒ��^�Ƒ�^��
�g���b�N��ΏۂƂ������̔R�����肵�A�P�S�N���f������K�p�ΏۂƂ���Ƃ̂��Ƃł���B���̂悤�ɕč��ł��g���b
�N�̔R���̐��肪�X�^�[�g���A�g���b�N�̔R�����P�̎��g�݂��X�^�[�g�����̂ł���B���̂��Ƃ��l����ƁA�g���b
�N�̔R��팸�͐��E�̂������ƌ��ėǂ��̂ł͂Ȃ����낤���B
�@��ʂɃg���b�N�̑��s�R������P���邽�߂ɂ́A�펯�I�ɂ̓G���W���̔R��팸���L���Ȏ�i�ł���B�������Ȃ�
��G���W���̔R�����P�́A����܂Œ��N�ɓn���Č�������ė�����������A����A�Z���Ԃɏ\���Ȑ��ʂ��グ�邱��
��������Ƃł���B����ɑ��g�����X�~�b�V�����̑��i���̓R�X�g�㏸�̋]���͂��邪�A�m���Ƀg���b�N�̑��s�R��
�����P�ł��邱�Ƃ���A�g���b�N���[�J�͑����ăg�����X�~�b�V�����̑��i���ɏ��o�����ƍl������B�č��̂悤�ȑ�
�����f���̂悤�Ƀg�����X�~�b�V�����̕p�ɂȃM�A�`�F���W���s�v�ȏꍇ�ɂ͑��i�g�����X�~�b�V�����ł����Ă��g���b�N
�^�]��̕��S�͑����Ȃ����A���{�̂悤�ȋ������ł͑��i�g�����X�~�b�V�����̗̍p�͕p�ɂȃM�A�`�F���W���K�v�Ƃ�
�邽�߂Ƀg���b�N�^�]�艻�ɉߓx�̕��S�������邱�ƂɂȂ�B�����Ńg���b�N���[�J�͓��{�ł��g�p�\�ȑ��i�g�����X
�~�b�V�����Ƃ��Ă��邽�߁A�P�Q�i�̋@�B�������g�����X�~�b�V�����̊J�����s�����B
��G���W���̔R�����P�́A����܂Œ��N�ɓn���Č�������ė�����������A����A�Z���Ԃɏ\���Ȑ��ʂ��グ�邱��
��������Ƃł���B����ɑ��g�����X�~�b�V�����̑��i���̓R�X�g�㏸�̋]���͂��邪�A�m���Ƀg���b�N�̑��s�R��
�����P�ł��邱�Ƃ���A�g���b�N���[�J�͑����ăg�����X�~�b�V�����̑��i���ɏ��o�����ƍl������B�č��̂悤�ȑ�
�����f���̂悤�Ƀg�����X�~�b�V�����̕p�ɂȃM�A�`�F���W���s�v�ȏꍇ�ɂ͑��i�g�����X�~�b�V�����ł����Ă��g���b�N
�^�]��̕��S�͑����Ȃ����A���{�̂悤�ȋ������ł͑��i�g�����X�~�b�V�����̗̍p�͕p�ɂȃM�A�`�F���W���K�v�Ƃ�
�邽�߂Ƀg���b�N�^�]�艻�ɉߓx�̕��S�������邱�ƂɂȂ�B�����Ńg���b�N���[�J�͓��{�ł��g�p�\�ȑ��i�g�����X
�~�b�V�����Ƃ��Ă��邽�߁A�P�Q�i�̋@�B�������g�����X�~�b�V�����̊J�����s�����B
�@�}�X�͑�^�g���b�N�ɂ�����P�Q�i�@�B�������g�����X�~�b�V�����́u�s�X�n�E���R�H�E���ύڎ��̃V�t�g�p�^�[���v��
�u�R�ԘH�E�ύڎ��̃V�t�g�p�^�[���v�����������̂ł���B���̂悤�ɂP�Q�i�@�B�������g�����X�~�b�V�����ɂ���āA���s
���̖��ʂȃG���W����]���̏㏸��}���ĔR�����P�ɔ��Q�̌��ʂ�����̂ł���B�Ȃ��A���̂P�Q�i�̋@�B��
�����g�����X�~�b�V�����̌��_�͍����ł��邱�Ƃ��B
�u�R�ԘH�E�ύڎ��̃V�t�g�p�^�[���v�����������̂ł���B���̂悤�ɂP�Q�i�@�B�������g�����X�~�b�V�����ɂ���āA���s
���̖��ʂȃG���W����]���̏㏸��}���ĔR�����P�ɔ��Q�̌��ʂ�����̂ł���B�Ȃ��A���̂P�Q�i�̋@�B��
�����g�����X�~�b�V�����̌��_�͍����ł��邱�Ƃ��B
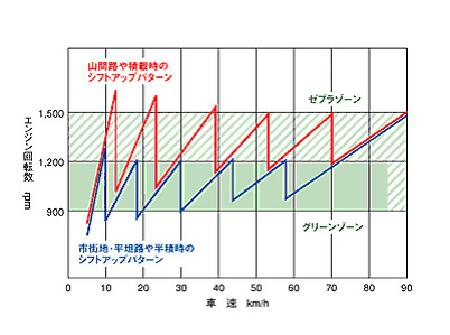
�@�S�g���b�N���[�J�̂P�R���b�g���̕W���G���W���𓋍ڂ����V�����r�o�K�X�K���i2005�N�K���j�̂V�i�}�j���A���g����
�X�~�b�V�����t�̑�^�g���b�N�́A�啔���̎Ԏ킪2015�N�x�i����27�N�x�j�d�ʎԔR���ɕs�K���ł���B�e�g���b
�N���[�J�́A�V�����J�������R��̗ǂ�12�i�@�B�������g�����X�~�b�V�������̗p���邱�Ƃɂ���āA�V�����r�o�K�X�K
���i2005�N�K���j�̑�^�g���b�N�E�g���N�^�̑��s�R��팸�ł���悤�ɂ��āA2015�N�x�i����27�N�x�j�d�ʎԔR���
���ւ̓K����}���Ă���B�\�V�ɂ͓��쎩���Ԃ̑�^�g���b�N�E�g���N�^�̏d�ʎԃ��[�h�R��l���������B20t����
��^�g���b�N�u�v���t�B�A�v�ł͂V�i�}�j���A���g�����X�~�b�V�����̏d�ʎԃ��[�h�R��l��3.80�`3.95km/L�ł���̂ɑ�
���A12�i�@�B�������g�����X�~�b�V�����̏d�ʎԃ��[�h�R��l��4.05�@km/L�ł���B����̑�^�g���b�N�u�v���t�B�A�v��
�͂V�i�}�j���A���g�����X�~�b�V�������̗p�����ꍇ�ɔ�ׂ�12�i�@�B�������g�����X�~�b�V�������̗p�����ꍇ�ɂ͏d
�ʎԃ��[�h�R��l��2.5�`6.5���̔R�����P���\�Ȃ悤���B
�X�~�b�V�����t�̑�^�g���b�N�́A�啔���̎Ԏ킪2015�N�x�i����27�N�x�j�d�ʎԔR���ɕs�K���ł���B�e�g���b
�N���[�J�́A�V�����J�������R��̗ǂ�12�i�@�B�������g�����X�~�b�V�������̗p���邱�Ƃɂ���āA�V�����r�o�K�X�K
���i2005�N�K���j�̑�^�g���b�N�E�g���N�^�̑��s�R��팸�ł���悤�ɂ��āA2015�N�x�i����27�N�x�j�d�ʎԔR���
���ւ̓K����}���Ă���B�\�V�ɂ͓��쎩���Ԃ̑�^�g���b�N�E�g���N�^�̏d�ʎԃ��[�h�R��l���������B20t����
��^�g���b�N�u�v���t�B�A�v�ł͂V�i�}�j���A���g�����X�~�b�V�����̏d�ʎԃ��[�h�R��l��3.80�`3.95km/L�ł���̂ɑ�
���A12�i�@�B�������g�����X�~�b�V�����̏d�ʎԃ��[�h�R��l��4.05�@km/L�ł���B����̑�^�g���b�N�u�v���t�B�A�v��
�͂V�i�}�j���A���g�����X�~�b�V�������̗p�����ꍇ�ɔ�ׂ�12�i�@�B�������g�����X�~�b�V�������̗p�����ꍇ�ɂ͏d
�ʎԃ��[�h�R��l��2.5�`6.5���̔R�����P���\�Ȃ悤���B
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
�@���̕\�V�Ɏ�����Ă���悤�ɁA�|�X�g�V�����r�o�K�X�K���i2009�N�K���j�ɍŏ��ɓK�������P�R���b�g���̕W���G��
�W�����ڂ̓����20t�����^�g���b�N�u�v���t�B�A�v��12�i�@�B�������g�����X�~�b�V�����̗̍p�ɂ���ďd�ʎ�
�R�����͂��ɒ����邱�Ƃɂ���ėʎԃ��[�h�R��l��B�����A�h������2015�N�x�d�ʎԔR���ɓK�����Ă�
��̂ł���B���������āA12�i�@�B�������g�����X�~�b�V���������R��̗��V�i�}�j���A���g�����X�~�b�V�������̗p
���Ă���20t�����^�g���b�N�u�v���t�B�A�v�̑����̎Ԏ��2015�N�x�d�ʎԔR���ɕs�K���ƂȂ��Ă���B����
�Ɠ��l�ɁA20t�ȉ��̑�^�g���N�^�u�v���t�B�A�v �̏ꍇ��2015�N�x�d�ʎԔR�����B���ł��Ă���́A12�i�@�B��
�����g�����X�~�b�V�������̗p�����Ԏ킪��̂ł���B�����āA�V�i�}�j���A���g�����X�~�b�V������2015�N�x�d�ʎԔR��
��ɓK�����Ă���20t�����^�g���b�N�u�v���t�B�A�v�͂P�O���b�g���ȉ��̏��^�y�ʃG���W���𓋍ڂ����ԗ��Ɍ�
���Ă���̂ł���B���̂悤��2015�N�x�d�ʎԔR���ɓK�����Ă���20t�����^�g���b�N�u�v���t�B�A�v��12
�i�@�B�������g�����X�~�b�V�������͂P�O���b�g���ȉ��̏��^�y�ʃG���W���̓��ڂɂ��R�����P�Ɉˑ����Ă���̂�
����B���������āA�|�X�g�V�����r�o�K�X�K���i2009�N�K���j�ɍŏ��ɓK��������^�g���b�N�ł́A�����œ��͐��\��
�D�ꂽ�P�R���b�g���̕W���G���W�����ڂ̂V�i�}�j���A���g�����X�~�b�V������20t�����^�g���b�N�u�v���t�B�A�v��
2015�N�x�d�ʎԔR���ɓK���ł��Ă��Ȃ������B�������A���̌�̉��ǂɂ��A�ŋ߂̂V�i�}�j���A���g�����X�~�b
�V������20t�����^�g���b�N�u�v���t�B�A�v�ł́A�V�i�}�j���A���g�����X�~�b�V�����̎ԗ��ł��A2015�N�x�d�ʎԔR
���ɓK�������Ԏ킪�̔������悤�ɂȂ����悤���B
�W�����ڂ̓����20t�����^�g���b�N�u�v���t�B�A�v��12�i�@�B�������g�����X�~�b�V�����̗̍p�ɂ���ďd�ʎ�
�R�����͂��ɒ����邱�Ƃɂ���ėʎԃ��[�h�R��l��B�����A�h������2015�N�x�d�ʎԔR���ɓK�����Ă�
��̂ł���B���������āA12�i�@�B�������g�����X�~�b�V���������R��̗��V�i�}�j���A���g�����X�~�b�V�������̗p
���Ă���20t�����^�g���b�N�u�v���t�B�A�v�̑����̎Ԏ��2015�N�x�d�ʎԔR���ɕs�K���ƂȂ��Ă���B����
�Ɠ��l�ɁA20t�ȉ��̑�^�g���N�^�u�v���t�B�A�v �̏ꍇ��2015�N�x�d�ʎԔR�����B���ł��Ă���́A12�i�@�B��
�����g�����X�~�b�V�������̗p�����Ԏ킪��̂ł���B�����āA�V�i�}�j���A���g�����X�~�b�V������2015�N�x�d�ʎԔR��
��ɓK�����Ă���20t�����^�g���b�N�u�v���t�B�A�v�͂P�O���b�g���ȉ��̏��^�y�ʃG���W���𓋍ڂ����ԗ��Ɍ�
���Ă���̂ł���B���̂悤��2015�N�x�d�ʎԔR���ɓK�����Ă���20t�����^�g���b�N�u�v���t�B�A�v��12
�i�@�B�������g�����X�~�b�V�������͂P�O���b�g���ȉ��̏��^�y�ʃG���W���̓��ڂɂ��R�����P�Ɉˑ����Ă���̂�
����B���������āA�|�X�g�V�����r�o�K�X�K���i2009�N�K���j�ɍŏ��ɓK��������^�g���b�N�ł́A�����œ��͐��\��
�D�ꂽ�P�R���b�g���̕W���G���W�����ڂ̂V�i�}�j���A���g�����X�~�b�V������20t�����^�g���b�N�u�v���t�B�A�v��
2015�N�x�d�ʎԔR���ɓK���ł��Ă��Ȃ������B�������A���̌�̉��ǂɂ��A�ŋ߂̂V�i�}�j���A���g�����X�~�b
�V������20t�����^�g���b�N�u�v���t�B�A�v�ł́A�V�i�}�j���A���g�����X�~�b�V�����̎ԗ��ł��A2015�N�x�d�ʎԔR
���ɓK�������Ԏ킪�̔������悤�ɂȂ����悤���B
�@�Ƃ���ŁA12�i�@�B�������g�����X�~�b�V�����̔R��팸�Ɋւ��钲�����������y��ʏȌn�̓Ɨ��s���@�l�A���
���S���������Ŏ��{���ꂽ�悤���B���̒����ł́A�G���W���r�C��9.8L�`13L�܂ł�7���}�j���A���g�����X�~�b�V��
��3��A�r�C��13L��12�i�@�B�������g�����X�~�b�V������2��̌v5���Ώۂɂ������������{���ꂽ�������B���ꂼ
��̎ԗ��́A�G���W��������ԗ��d�ʂȂǂ��قȂ��Ă���A�e�ԗ��̃G���W���������c13���[�h�ɂ�葪�肷��ƂƂ�
�ɁA�i�d05���[�h�A����80�L���葬���s�A���̑g�ݍ��킹�ɂ��R��𑪒�A�G���W�������ɑ��R�������������
�v���͂��ꂽ�Ƃ̂��Ƃł���B�����āA��������ƂɃV�~�����[�V�����ɂ��A�G���W���ƃ~�b�V�����̑g�ݍ��킹��
�œK�������݂��s��ꂽ�̂ł���B���̌��ʁA�s�̂���Ă����^�g���b�N�̃G���W���ƃ~�b�V�����Ƃ̑g�ݍ��킹��
�œK������Ȃǂŕ���2.21���̔R������}�邱�Ƃ��\�ɂȂ�Ƃ̌��ʂ���ʈ��S���������̃t�H�[�����ŕ�
�����ꂽ�Ƃ̂��Ƃ��B�i�o�T�FSPN�@�C���t�H���[�V����http://www.spn-partner.com/info/2009/112001.htm�j
���S���������Ŏ��{���ꂽ�悤���B���̒����ł́A�G���W���r�C��9.8L�`13L�܂ł�7���}�j���A���g�����X�~�b�V��
��3��A�r�C��13L��12�i�@�B�������g�����X�~�b�V������2��̌v5���Ώۂɂ������������{���ꂽ�������B���ꂼ
��̎ԗ��́A�G���W��������ԗ��d�ʂȂǂ��قȂ��Ă���A�e�ԗ��̃G���W���������c13���[�h�ɂ�葪�肷��ƂƂ�
�ɁA�i�d05���[�h�A����80�L���葬���s�A���̑g�ݍ��킹�ɂ��R��𑪒�A�G���W�������ɑ��R�������������
�v���͂��ꂽ�Ƃ̂��Ƃł���B�����āA��������ƂɃV�~�����[�V�����ɂ��A�G���W���ƃ~�b�V�����̑g�ݍ��킹��
�œK�������݂��s��ꂽ�̂ł���B���̌��ʁA�s�̂���Ă����^�g���b�N�̃G���W���ƃ~�b�V�����Ƃ̑g�ݍ��킹��
�œK������Ȃǂŕ���2.21���̔R������}�邱�Ƃ��\�ɂȂ�Ƃ̌��ʂ���ʈ��S���������̃t�H�[�����ŕ�
�����ꂽ�Ƃ̂��Ƃ��B�i�o�T�FSPN�@�C���t�H���[�V����http://www.spn-partner.com/info/2009/112001.htm�j
�@�ȏ�̂悤�ɁA12�i�@�B�������g�����X�~�b�V�����ɂ��R�����P�̊����́A�Ⴂ���l�Ƃ��Ă͌�ʈ��S������
���̒������ʂ̕���2.21��������Ă���A�������l�Ƃ��Ă͑O�q�̓���̑�^�g���b�N�u�v���t�B�A�v�̏d�ʎԃ�
�[�h�R��l����Z�o�������ςS�����x�̐��l������B����ɂ̓f�t�䓙���܂߂��Ԏ�̑��Ⴊ���邱�Ƃ��l������
�ƁA��^�̃g���b�N�E�g���N�^�ł́A12�i�@�B�������g�����X�~�b�V�����̗̍p�͂V�i�}�j���A���g�����X�~�b�V����
�ɔ�ׂĕ��ςT���O��̔R��팸���ł���l����̂��K���ł͂Ȃ����낤���B
���̒������ʂ̕���2.21��������Ă���A�������l�Ƃ��Ă͑O�q�̓���̑�^�g���b�N�u�v���t�B�A�v�̏d�ʎԃ�
�[�h�R��l����Z�o�������ςS�����x�̐��l������B����ɂ̓f�t�䓙���܂߂��Ԏ�̑��Ⴊ���邱�Ƃ��l������
�ƁA��^�̃g���b�N�E�g���N�^�ł́A12�i�@�B�������g�����X�~�b�V�����̗̍p�͂V�i�}�j���A���g�����X�~�b�V����
�ɔ�ׂĕ��ςT���O��̔R��팸���ł���l����̂��K���ł͂Ȃ����낤���B
�@�Ƃ���ŁA�����U�͂V�i�}�j���A���g�����X�~�b�V�����ɔ�ׂ�12�i�@�B�������g�����X�~�b�V�����ł͕���11���̔R��
���P���\�ƌ����ɔ��\���Ă���B�i�o�T�F�����U�v���X�����[�Xhttp://www.isuzu.co.jp/press/2003/6_2gig_1.html�j�@
����12�i�@�B�������g�����X�~�b�V�����ł͕���11���̔R��팸�ł���Ɩ��L���������U�̔��\�ł́A�u�Г�����
�l�v�ƒ��L����Ă��邱�Ƃ���A12�i�@�B�������g�����X�~�b�V�����̐�`�̂��߂ɒP�ɂ����U�Г��̓���Ȏ����f�[
�^�\���Ă���\���������ɂ���ƍl������B���̂��߁A12�i�@�B�������g�����X�~�b�V�����ł͕���11���̔R
�����P�Ƃ��邢���U�̔��\�́A12�i�@�B�������g�����X�~�b�V�����ɂ��R��팸�̒��x���ߑ�ɕ]�����Ă���悤��
�v����B���������āA�V�i�}�j���A���g�����X�~�b�V�����ɔ�ׂ��ꍇ��12�i�@�B�������g�����X�~�b�V�����̎����I
�ȔR��팸�́A�O�q�̂悤�ɂT�����x�ƍl����̂��Ó��ł͂Ȃ��Ǝv���Ă���B�Ȃ��A�ŋ߁i��2014�N6�����݁j��
�́A���쎩���Ԃ�16�i�@�B�������g�����X�~�b�V�����i��http://www.hino.co.jp/profia/economy/index.html�j�̑�^�g
���N�^���s�̂��Ă���Ƃ̂��Ƃł���B
���P���\�ƌ����ɔ��\���Ă���B�i�o�T�F�����U�v���X�����[�Xhttp://www.isuzu.co.jp/press/2003/6_2gig_1.html�j�@
����12�i�@�B�������g�����X�~�b�V�����ł͕���11���̔R��팸�ł���Ɩ��L���������U�̔��\�ł́A�u�Г�����
�l�v�ƒ��L����Ă��邱�Ƃ���A12�i�@�B�������g�����X�~�b�V�����̐�`�̂��߂ɒP�ɂ����U�Г��̓���Ȏ����f�[
�^�\���Ă���\���������ɂ���ƍl������B���̂��߁A12�i�@�B�������g�����X�~�b�V�����ł͕���11���̔R
�����P�Ƃ��邢���U�̔��\�́A12�i�@�B�������g�����X�~�b�V�����ɂ��R��팸�̒��x���ߑ�ɕ]�����Ă���悤��
�v����B���������āA�V�i�}�j���A���g�����X�~�b�V�����ɔ�ׂ��ꍇ��12�i�@�B�������g�����X�~�b�V�����̎����I
�ȔR��팸�́A�O�q�̂悤�ɂT�����x�ƍl����̂��Ó��ł͂Ȃ��Ǝv���Ă���B�Ȃ��A�ŋ߁i��2014�N6�����݁j��
�́A���쎩���Ԃ�16�i�@�B�������g�����X�~�b�V�����i��http://www.hino.co.jp/profia/economy/index.html�j�̑�^�g
���N�^���s�̂��Ă���Ƃ̂��Ƃł���B
�P�P�D�|�X�g�V�����K���ɓK���̑�^�g���b�N�ɂ����� 2015�N�x�d�ʎԔR���ւ̓K��
�P�P�|�P�@���쎩���Ԃ̃|�X�g�V�����r�o�K�X�K���̑�^�g���b�N�ɂ�����R��\
�@���쎩���Ԃ́A�Q�O�O�X�N�r�o�K�X�K���i�|�X�g�V�����j�ɓK���������uE�P�RC�v�G���W�����ڂ̑�^�g���b�N�u����v
���t�B�A�v�����ǂ��A�Q�O�P�O�N�V���P����蔭���i2010�N04��20���v���X�����[�X�A�o�T�Fhttp://www.hino.co.jp/j/
corporate/newsrelease/pressrelease/detail.php?id=279�j�����B���̓��쎩���Ԃ̃v���X�����[�X�ɂ́u�R��\�̌�
��ɂ�蕽��27�N�x�R���B���Ԃ̐ݒ��啝�Ɋg�債�܂����v�ƋL�ڂ���Ă���B�����āA����̃z�[���y�[�W
�́u�G�A���[�v�v�Ə̂����y�[�W�i�o�T�Fhttp://www.hino.co.jp/j/airloop/index.html�j�ł́A�}11�Ɏ������悤�Ɂu�����
��C�ɖ{�C�v�Ƒ肵�A�V�����|�X�g�V�����r�o�K�X�K���̃g���b�N�͏]���̐V�����K���̃g���b�N�ɔ�ׂĂT���̔R��
���P����������Ă���ƋL�ڂ���Ă���B
���t�B�A�v�����ǂ��A�Q�O�P�O�N�V���P����蔭���i2010�N04��20���v���X�����[�X�A�o�T�Fhttp://www.hino.co.jp/j/
corporate/newsrelease/pressrelease/detail.php?id=279�j�����B���̓��쎩���Ԃ̃v���X�����[�X�ɂ́u�R��\�̌�
��ɂ�蕽��27�N�x�R���B���Ԃ̐ݒ��啝�Ɋg�債�܂����v�ƋL�ڂ���Ă���B�����āA����̃z�[���y�[�W
�́u�G�A���[�v�v�Ə̂����y�[�W�i�o�T�Fhttp://www.hino.co.jp/j/airloop/index.html�j�ł́A�}11�Ɏ������悤�Ɂu�����
��C�ɖ{�C�v�Ƒ肵�A�V�����|�X�g�V�����r�o�K�X�K���̃g���b�N�͏]���̐V�����K���̃g���b�N�ɔ�ׂĂT���̔R��
���P����������Ă���ƋL�ڂ���Ă���B
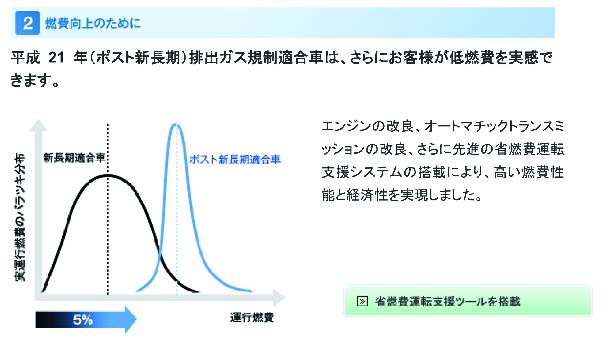
�@�����āA���쎩���Ԃ́uE�P�RC�v�G���W�����ڂ̑�^�g���b�N�u����v���t�B�A�v���Q�O�P�O�N�V���P���ɔ��������̂ɑ�
���A�r�C��8.9L�́uA�O�XC�v�^�G���W���𓋍ڂ�����^�g���b�N�u����v���t�B�A�v���Q�O�P�O�N�X���P���ɔ��������B����
���A�����̓��쎩���Ԃ̑�^�g���b�N�E�g���N�^�͂Q�O�O�T�N�r�o�K�X�K���i�V�����j�̎��Ɠ��l�ɁA�|�X�g�V�����K��
�K���́uE�P�RC�v����сuA�O�XC�v�̃G���W���𓋍ڂ���7�i�}�j���A���g�����X�~�b�V������GVW�Q�T�g���̑啔���̎Ԏ�
�ł͂Q�O�P�T�N�x�d�ʎԔR���ɕs�K���ł������B���̗�Ƃ��đ�^�g���b�N�u����v���t�B�A�v��FS�i�U�~�S)�J�[�S��
�S�Ԏ�ɂ�����Q�O�P�T�N�x�d�ʎԔR���ւ̓K�����ȉ��̕\�X�Ɏ����B
���A�r�C��8.9L�́uA�O�XC�v�^�G���W���𓋍ڂ�����^�g���b�N�u����v���t�B�A�v���Q�O�P�O�N�X���P���ɔ��������B����
���A�����̓��쎩���Ԃ̑�^�g���b�N�E�g���N�^�͂Q�O�O�T�N�r�o�K�X�K���i�V�����j�̎��Ɠ��l�ɁA�|�X�g�V�����K��
�K���́uE�P�RC�v����сuA�O�XC�v�̃G���W���𓋍ڂ���7�i�}�j���A���g�����X�~�b�V������GVW�Q�T�g���̑啔���̎Ԏ�
�ł͂Q�O�P�T�N�x�d�ʎԔR���ɕs�K���ł������B���̗�Ƃ��đ�^�g���b�N�u����v���t�B�A�v��FS�i�U�~�S)�J�[�S��
�S�Ԏ�ɂ�����Q�O�P�T�N�x�d�ʎԔR���ւ̓K�����ȉ��̕\�X�Ɏ����B
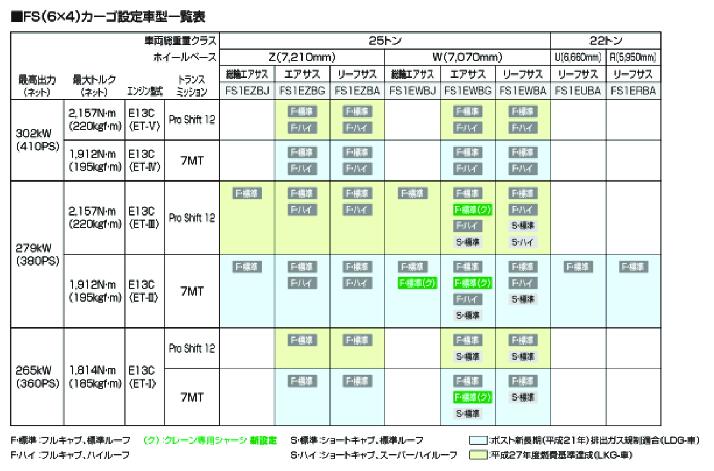
�@�O�q�̂悤�ɁA12�i�@�B�������g�����X�~�b�V�������̗p�����u����v���t�B�A�v�̑�^�J�[�S�g���b�N�̏ꍇ�ɂ͂V�i
�}�j���A���g�����X�~�b�V�������̗p�����ꍇ�ɔ�ׂďd�ʎԃ��[�h�R��l�͂T���O��i2.5�`6.5���j�̔R�����P����
�\�ł���B�������A�Q�O�P�O�N�V���P���ɔ������ꂽ�uE�P�RC�v�G���W���ƂQ�O�P�O�N�X���P���ɔ������ꂽ�uA�O�XC�v�G���W��
�̐V�����|�X�g�V�����r�o�K�X�K���̑�^�J�[�S�g���b�N�ł́A�{���ɏ]���̐V�����K���̑�^�g���b�N�p�G���W��
�ɔ�ׂĖ{���ɂT���̔R����P�ł����̂ł��낤���B���ɁA�|�X�g�V�����r�o�K�X�K���̑�^�J�[�S�g���b�N����
�ۂɂT���̔R����P�ł��Ă����̂ł���A�Q�O�P�O�N�V���P���ɔ������ꂽ�uE�P�RC�v�G���W���ƂQ�O�P�O�N�X���P��
�ɔ������ꂽ�uA�O�XC�v�G���W�������ڂ��ꂽ�V�����|�X�g�V�����r�o�K�X�K���̓��쎩���Ԃ�����������^�g���b
�N�E�g���N�^�̑S�Ă̎Ԏ킪�]�T�������ĂQ�O�P�T�N�x�d�ʎԔR���ɂ͓K���ł��Ă��锤�ł���B
�}�j���A���g�����X�~�b�V�������̗p�����ꍇ�ɔ�ׂďd�ʎԃ��[�h�R��l�͂T���O��i2.5�`6.5���j�̔R�����P����
�\�ł���B�������A�Q�O�P�O�N�V���P���ɔ������ꂽ�uE�P�RC�v�G���W���ƂQ�O�P�O�N�X���P���ɔ������ꂽ�uA�O�XC�v�G���W��
�̐V�����|�X�g�V�����r�o�K�X�K���̑�^�J�[�S�g���b�N�ł́A�{���ɏ]���̐V�����K���̑�^�g���b�N�p�G���W��
�ɔ�ׂĖ{���ɂT���̔R����P�ł����̂ł��낤���B���ɁA�|�X�g�V�����r�o�K�X�K���̑�^�J�[�S�g���b�N����
�ۂɂT���̔R����P�ł��Ă����̂ł���A�Q�O�P�O�N�V���P���ɔ������ꂽ�uE�P�RC�v�G���W���ƂQ�O�P�O�N�X���P��
�ɔ������ꂽ�uA�O�XC�v�G���W�������ڂ��ꂽ�V�����|�X�g�V�����r�o�K�X�K���̓��쎩���Ԃ�����������^�g���b
�N�E�g���N�^�̑S�Ă̎Ԏ킪�]�T�������ĂQ�O�P�T�N�x�d�ʎԔR���ɂ͓K���ł��Ă��锤�ł���B
�@�������A�\�X�Ɏ������悤�ɁA����̐V�����́@2009�N�r�o�K�X�K���i�|�X�g�V�����j�K���̂Q�O�P�O�N�V���P���ɔ�
�����ꂽ�uE�P�RC�v�G���W�����ڂ́u����v���t�B�A�v�̑�^�J�[�S�g���b�N�iGVW�Q�T�g���j�́A�ȑO�̐V�����K���i�Q�O�O
�T�N�K���j�̎���Ɠ��l�ɁA7�i�}�j���A���g�����X�~�b�V������GVW�Q�T�g���̑�^�g���b�N���Q�O�P�T�N�x�d�ʎԔR���
���ɓK���ł��Ă��Ȃ������̂ł���B
�����ꂽ�uE�P�RC�v�G���W�����ڂ́u����v���t�B�A�v�̑�^�J�[�S�g���b�N�iGVW�Q�T�g���j�́A�ȑO�̐V�����K���i�Q�O�O
�T�N�K���j�̎���Ɠ��l�ɁA7�i�}�j���A���g�����X�~�b�V������GVW�Q�T�g���̑�^�g���b�N���Q�O�P�T�N�x�d�ʎԔR���
���ɓK���ł��Ă��Ȃ������̂ł���B
�@���̂悤�ɁA���쎩���Ԃł́A�|�X�g�V�����r�o�K�X�K���K���̂P�R���b�g���̕W���G���W���uE�P�RC�v�𓋍ڂ�����
�^�g���b�N�������Q�O�P�O�N�N�V���P���ɂ́A7�i�}�j���A���g�����X�~�b�V������GVW�Q�T�g���̎�͎Ԏ�ł����^
�J�[�S�g���b�N�����Q�O�P�T�N�x�d�ʎԔR���ɖ��K���ł������B���̂��߁A���쎩���Ԃ́A�uE�P�RC�v�𓋍ڂ�����
�^�g���b�N�E�g���N�^�̂T�R���̎Ԏ킪�Q�O�P�T�N�x�d�ʎԔR���ɕs�K���ł������B���̏����P���邽�߁A����
�����Ԃł́AE�P�RC�^�G���W���i�r�C��12.9L�j���ڂ̂V�i�}�j���A���g�����X�~�b�V����������^�g���b�N�u����v��
�t�B�A�v�����ǂ��A���̎Ԏ�̏d�ʎԃ��[�h�R��l�����サ���B���̕��@�́A�G���W���̍ő�g���N��2.5�����x��
������Ƌ��ɃG���W�����]���̃g���N�����A�쓮�n�̃M�A����œK�����ďd�ʎԃ��[�h�R��莞�̃G���W��
�̒��]����}���ďd�ʎԃ��[�h�R������P��}�������̂Ɛ��肳���B����ɂ���āAE�P�RC�^�G���W���i�r�C��
12.9L�j���ڂ̂V�i�}�j���A���g�����X�~�b�V����������^�g���b�N�u����v���t�B�A�v�̑����̎Ԏ���Q�O�P�T�N�x�R��
��ɓK�������邱�Ƃɐ��������B���̌��ʁA�Q�O�P�P�N�Q���P���ɔ������ꂽE�P�RC�^�G���W���i�r�C��12.9L�j�𓋍�
������^�g���b�N�u����v���t�B�A�v�̂Q�O�P�T�N�x�d�ʎԔR���ɕs�K���̎Ԏ�́A�P�V���܂ŏ��Ȃ����邱�Ƃ��ł�
���̂ł���B
�^�g���b�N�������Q�O�P�O�N�N�V���P���ɂ́A7�i�}�j���A���g�����X�~�b�V������GVW�Q�T�g���̎�͎Ԏ�ł����^
�J�[�S�g���b�N�����Q�O�P�T�N�x�d�ʎԔR���ɖ��K���ł������B���̂��߁A���쎩���Ԃ́A�uE�P�RC�v�𓋍ڂ�����
�^�g���b�N�E�g���N�^�̂T�R���̎Ԏ킪�Q�O�P�T�N�x�d�ʎԔR���ɕs�K���ł������B���̏����P���邽�߁A����
�����Ԃł́AE�P�RC�^�G���W���i�r�C��12.9L�j���ڂ̂V�i�}�j���A���g�����X�~�b�V����������^�g���b�N�u����v��
�t�B�A�v�����ǂ��A���̎Ԏ�̏d�ʎԃ��[�h�R��l�����サ���B���̕��@�́A�G���W���̍ő�g���N��2.5�����x��
������Ƌ��ɃG���W�����]���̃g���N�����A�쓮�n�̃M�A����œK�����ďd�ʎԃ��[�h�R��莞�̃G���W��
�̒��]����}���ďd�ʎԃ��[�h�R������P��}�������̂Ɛ��肳���B����ɂ���āAE�P�RC�^�G���W���i�r�C��
12.9L�j���ڂ̂V�i�}�j���A���g�����X�~�b�V����������^�g���b�N�u����v���t�B�A�v�̑����̎Ԏ���Q�O�P�T�N�x�R��
��ɓK�������邱�Ƃɐ��������B���̌��ʁA�Q�O�P�P�N�Q���P���ɔ������ꂽE�P�RC�^�G���W���i�r�C��12.9L�j�𓋍�
������^�g���b�N�u����v���t�B�A�v�̂Q�O�P�T�N�x�d�ʎԔR���ɕs�K���̎Ԏ�́A�P�V���܂ŏ��Ȃ����邱�Ƃ��ł�
���̂ł���B
�@����A���쎩���Ԃ́A�Q�O�O�X�N�r�o�K�X�K���i�|�X�g�V�����j�ɓK�������r�C��8.9L�́uA�O�XC�v�^�G���W���𓋍ڂ�
����^�g���b�N�u����v���t�B�A�v�ł́A�V�i�}�j���A���g�����X�~�b�V�����𒆐S���S�W���̎Ԏ킪�Q�O�P�T�N�x�R��
�ɕs�K���̏�Ԃł���B�������A�uA�O�XC�v�^�G���W���𓋍ڂ�����^�g���b�N�u����v���t�B�A�v�̏d�ʎԃ��[�h�R��l
�����サ�A���̎Ԏ���Q�O�P�T�N�x�R���ɓK�������邱�Ƃ͋ɂ߂ē���̂ł͂Ȃ����ƍl������B���̗��R
�́A�uA�O�XC�v�^�G���W���̒ᑬ�g���N������ȏ�ɑ��傷�邱�Ƃ��e�Ղł͖����A���̂��߁A���́uA�O�XC�v�^�G���W��
�𓋍ڂ�����^�g���b�N�̋쓮�n�̃M�A����œK�����ďd�ʎԃ��[�h�R��莞�̃G���W���̒��]����}���ďd
�ʎԃ��[�h�R������P��}�邱�Ƃ��ɂ߂č���Ȃ悤�ɍl�����邩�炾�B���R�A���ꂩ����uA�O�XC�v�^�G���W����
�ڂ�����^�g���b�N�u����v���t�B�A�v�̑����̎Ԏ���Q�O�P�T�N�x�R���ɓK��������悤�ɁA���쎩���Ԃł͓w��
���s����Ƃ͎v�����A�ނ�̋��߂錋�ʂ��o���邩�ǂ����͑傢�ɋ^�₾�B
����^�g���b�N�u����v���t�B�A�v�ł́A�V�i�}�j���A���g�����X�~�b�V�����𒆐S���S�W���̎Ԏ킪�Q�O�P�T�N�x�R��
�ɕs�K���̏�Ԃł���B�������A�uA�O�XC�v�^�G���W���𓋍ڂ�����^�g���b�N�u����v���t�B�A�v�̏d�ʎԃ��[�h�R��l
�����サ�A���̎Ԏ���Q�O�P�T�N�x�R���ɓK�������邱�Ƃ͋ɂ߂ē���̂ł͂Ȃ����ƍl������B���̗��R
�́A�uA�O�XC�v�^�G���W���̒ᑬ�g���N������ȏ�ɑ��傷�邱�Ƃ��e�Ղł͖����A���̂��߁A���́uA�O�XC�v�^�G���W��
�𓋍ڂ�����^�g���b�N�̋쓮�n�̃M�A����œK�����ďd�ʎԃ��[�h�R��莞�̃G���W���̒��]����}���ďd
�ʎԃ��[�h�R������P��}�邱�Ƃ��ɂ߂č���Ȃ悤�ɍl�����邩�炾�B���R�A���ꂩ����uA�O�XC�v�^�G���W����
�ڂ�����^�g���b�N�u����v���t�B�A�v�̑����̎Ԏ���Q�O�P�T�N�x�R���ɓK��������悤�ɁA���쎩���Ԃł͓w��
���s����Ƃ͎v�����A�ނ�̋��߂錋�ʂ��o���邩�ǂ����͑傢�ɋ^�₾�B
�@�܂��A���쎩���Ԃ́A�����_�ł́uE�P�RC�v�G���W���i�r�C��12.9L�j���ڎԌ^�̂U�i�}�j���A���g�����X�~�b�V����
��������^�g���b�N�u����v���t�B�A�v���Q�O�P�T�N�x�R���ɂ����邱�Ƃ��ł��Ă��Ȃ��悤���B���̂��߁A���쎩��
�Ԃ́AE�P�RC�^�G���W���i�r�C��12.9L�j���ڎԌ^�̂U�i�}�j���A���g�����X�~�b�V����������^�g���b�N�u����v���t
�B�A�v�̎Ԏ퓙�́A�Q�O�P�P�N�Q���P���ɂQ�O�P�T�N�x�R���ɕs�K���̎d�l�Ŕ������Ă���̂ł���B���̂悤�ɁA�uE
�P�RC�v�܂��́uA�O�XC�v�̉��ꂩ�̃G���W���𓋍ڂ����|�X�g�V�����r�o�K�X�K���̑�^�g���b�N�E�g���N�^�u����v���t
�B�A�v�̑����̎Ԏ�́A�����ɂQ�O�P�T�N�x�R���ɕs�K���̏�Ԃł��邱�Ƃ������̂悤���B�ڍׂ�http://www.
mlit.go.jp/jidosha/nenpi/nenpikouhyou/track.htm���Q�Ƃ��Ă������������B
��������^�g���b�N�u����v���t�B�A�v���Q�O�P�T�N�x�R���ɂ����邱�Ƃ��ł��Ă��Ȃ��悤���B���̂��߁A���쎩��
�Ԃ́AE�P�RC�^�G���W���i�r�C��12.9L�j���ڎԌ^�̂U�i�}�j���A���g�����X�~�b�V����������^�g���b�N�u����v���t
�B�A�v�̎Ԏ퓙�́A�Q�O�P�P�N�Q���P���ɂQ�O�P�T�N�x�R���ɕs�K���̎d�l�Ŕ������Ă���̂ł���B���̂悤�ɁA�uE
�P�RC�v�܂��́uA�O�XC�v�̉��ꂩ�̃G���W���𓋍ڂ����|�X�g�V�����r�o�K�X�K���̑�^�g���b�N�E�g���N�^�u����v���t
�B�A�v�̑����̎Ԏ�́A�����ɂQ�O�P�T�N�x�R���ɕs�K���̏�Ԃł��邱�Ƃ������̂悤���B�ڍׂ�http://www.
mlit.go.jp/jidosha/nenpi/nenpikouhyou/track.htm���Q�Ƃ��Ă������������B
�@����A�O�H�ӂ����́A�P�R���b�g���̕W���G���W���𓋍ڂ���7�i�}�j���A���g�����X�~�b�V�����̑�^�_���v�g���b�N��
�����ɂQ�O�P�T�N�x�d�ʎԔR���ɂ͕s�K���ł���B���������āA���쎩���Ԃ�O�H�ӂ����ɂ����Ă��A��^�g���b
�N�p�f�B�[�[���G���W���̂P�R���b�g���̕W���G���W���̏d�ʎԃ��[�h�R��l���T�p�[�Z���g���x�����P��}�錤���J
�����i�ق̍ŏd�v�ۑ�ł��邱�Ƃɂ͕ς��͖������̂Ɛ��������B
�����ɂQ�O�P�T�N�x�d�ʎԔR���ɂ͕s�K���ł���B���������āA���쎩���Ԃ�O�H�ӂ����ɂ����Ă��A��^�g���b
�N�p�f�B�[�[���G���W���̂P�R���b�g���̕W���G���W���̏d�ʎԃ��[�h�R��l���T�p�[�Z���g���x�����P��}�錤���J
�����i�ق̍ŏd�v�ۑ�ł��邱�Ƃɂ͕ς��͖������̂Ɛ��������B
�P�P�|�Q�@�t�c�g���b�N�X�̃|�X�g�V�����r�o�K�X�K���̑�^�g���b�N�ɂ�����R��\
�@�t�c�g���b�N�X�́A�|�X�g�V�����r�o�K�X�K���̂��߂ɁA�{���{�O���[�v�Ƌ����ő�^�g���b�N�p��GH11�G���W���i��
�r�C��11���b�g���j�G���W�����J�������Ƃ̂��Ƃł���B����GH11�G���W���́A���̔r�C�ʂ��P�P���b�g���Ƃ��A�]���^��
��ׂQ���b�g���̏��r�C�ʉ����s���Ă���̂ł���B����GH11�G���W���̓G���W���_�E���T�C�W���O�ɂ���đ�^
�g���b�N�̔R������P��}����Ă���B�������A�|�X�g�V�����r�o�K�X�K���K���̑�^�g���b�N�Q�V�X�Ԍ^�̒��ŁA�Q
�O�P�T�N�x�d�ʎԔR���B���Ԃ͂P�Q�R�Ԍ^�ɉ߂��Ȃ��悤���B�܂�A�t�c�g���b�N�X�̃|�X�g�V�����r�o�K�X�K��
�ɓK��������^�g���b�N�ł́A���ڃG���W�����]���̂P�R���b�g������GH11�G���W���i�P�P���b�g���j�ɂQ���b�g���̃G���W
���_�E���T�C�W���O�i���r�C�ʉ��j���s���Ă���ɂ�������炸�A�T�U���̑�^�g���b�N���Q�O�P�T�N�x�d�ʎԔR���
���ɕs�K���ƂȂ��Ă��܂��Ă���̂ł���B���̂��Ƃ́A�s��ł̑�^�g���b�N�̔̔������ɂ����āA�t�c�g���b�N�X��
�����s���ȗ���ɗ�������Ă���\�����ے�ł��Ȃ��悤�ɍl������B
�r�C��11���b�g���j�G���W�����J�������Ƃ̂��Ƃł���B����GH11�G���W���́A���̔r�C�ʂ��P�P���b�g���Ƃ��A�]���^��
��ׂQ���b�g���̏��r�C�ʉ����s���Ă���̂ł���B����GH11�G���W���̓G���W���_�E���T�C�W���O�ɂ���đ�^
�g���b�N�̔R������P��}����Ă���B�������A�|�X�g�V�����r�o�K�X�K���K���̑�^�g���b�N�Q�V�X�Ԍ^�̒��ŁA�Q
�O�P�T�N�x�d�ʎԔR���B���Ԃ͂P�Q�R�Ԍ^�ɉ߂��Ȃ��悤���B�܂�A�t�c�g���b�N�X�̃|�X�g�V�����r�o�K�X�K��
�ɓK��������^�g���b�N�ł́A���ڃG���W�����]���̂P�R���b�g������GH11�G���W���i�P�P���b�g���j�ɂQ���b�g���̃G���W
���_�E���T�C�W���O�i���r�C�ʉ��j���s���Ă���ɂ�������炸�A�T�U���̑�^�g���b�N���Q�O�P�T�N�x�d�ʎԔR���
���ɕs�K���ƂȂ��Ă��܂��Ă���̂ł���B���̂��Ƃ́A�s��ł̑�^�g���b�N�̔̔������ɂ����āA�t�c�g���b�N�X��
�����s���ȗ���ɗ�������Ă���\�����ے�ł��Ȃ��悤�ɍl������B
�@����A���쎩���Ԃ�O�H�ӂ����́A�P�R���b�g���̕W���G���W���𓋍ڂ���7�i�}�j���A���g�����X�~�b�V������GVW�Q
�T�g���̎�͎Ԏ�ł����^�J�[�S�g���b�N�ł��Q�O�P�T�N�x�d�ʎԔR���Ɋ��ɓK���ł��Ă���̂ł���B��������
�āA�t�c�g���b�N�X�́A��͎Ԏ�ł���P�P���b�g���̕W���G���W���𓋍ڂ�����^�J�[�S�g���b�N�̔R�������������
�����āA���쎩���Ԃ�O�H�ӂ����ɑ傫����������Ă��܂��Ă���悤�Ɍ�����B���̔R��\�̗�҉�
���߂ɁA�t�c�g���b�N�X�͓��쎩���Ԃ�O�H�ӂ����Ɠ��l�ɁA�i�ق̍ŏd�v�̉ۑ�Ƃ��đ�^�g���b�N�p�f�B�[�[���G
���W���̏d�ʎԃ��[�h�R��l���T�p�[�Z���g���x�̍팸��}�錤���J���ɑ��͂������Ď��g�ޕK�v�������Ă���
���̂ƍl������B
�T�g���̎�͎Ԏ�ł����^�J�[�S�g���b�N�ł��Q�O�P�T�N�x�d�ʎԔR���Ɋ��ɓK���ł��Ă���̂ł���B��������
�āA�t�c�g���b�N�X�́A��͎Ԏ�ł���P�P���b�g���̕W���G���W���𓋍ڂ�����^�J�[�S�g���b�N�̔R�������������
�����āA���쎩���Ԃ�O�H�ӂ����ɑ傫����������Ă��܂��Ă���悤�Ɍ�����B���̔R��\�̗�҉�
���߂ɁA�t�c�g���b�N�X�͓��쎩���Ԃ�O�H�ӂ����Ɠ��l�ɁA�i�ق̍ŏd�v�̉ۑ�Ƃ��đ�^�g���b�N�p�f�B�[�[���G
���W���̏d�ʎԃ��[�h�R��l���T�p�[�Z���g���x�̍팸��}�錤���J���ɑ��͂������Ď��g�ޕK�v�������Ă���
���̂ƍl������B
�@���݂ɁA�t�c�g���b�N�X�́A���s���\�̈�����G���W���ϋv���̒ቺ�̃��X�N���đ�^�g���b�N�̃G���W�����]��
�ɂP�R���b�g������P�P���b�g���ɂQ���b�g�����x�̑��r�C�ʂ����炵�ăG���W���_�E���T�C�W���O�����ɂ�������炸�A
��^�g���b�N�̂T�U�����Q�O�P�T�N�x�d�ʎԔR���ɕs�K���ƂȂ��Ă��܂��Ă���̂ł���B���̂��߁A���݂̂t�c�g
���b�N�ł́A�G���W���R������P����Z�p�J�����ł��d�v�ȉۑ�ƂȂ��Ă���̂ł͂Ȃ����ƍl������B
�ɂP�R���b�g������P�P���b�g���ɂQ���b�g�����x�̑��r�C�ʂ����炵�ăG���W���_�E���T�C�W���O�����ɂ�������炸�A
��^�g���b�N�̂T�U�����Q�O�P�T�N�x�d�ʎԔR���ɕs�K���ƂȂ��Ă��܂��Ă���̂ł���B���̂��߁A���݂̂t�c�g
���b�N�ł́A�G���W���R������P����Z�p�J�����ł��d�v�ȉۑ�ƂȂ��Ă���̂ł͂Ȃ����ƍl������B
�P�P�|�R�@�O�H�ӂ����̃|�X�g�V�����K���̑�^�g���b�N�ɂ�����R��\
�@�O�H�ӂ����́A�V���������R�������[���V�X�e���̔R�����ˑ��u�uX-Pulse�v���J�����A������|�X�g�V�����r�o�K
�X�K���i�Q�O�O�X�N�K���j�ɓK��������^�g���b�N�u�X�[�p�[�O���[�g�v�̃G���W���ɍ̗p�����Ƃ̂��ƁB�O�H�ӂ����́uX-
Pulse�v�ɂ��āA�w�uX-Pulse�v�i�����R�������[���V�X�e���j���A�R�����˂̍������ƁA�R�����˗��̉σR���g���[��
�������B���X�ƕω�����G���W���^�]�����̒��ł��A��ɍœK�ȔR�Ă����Ȃ��A�r�o�K�X�̒ጸ�ƔR�����ɍv��
���܂��B�x�i�o�T�Fhttp://www.mitsubishi-fuso.com/jp/lineup/truck/super_great/10/point/fuel_01.html�j�Ƃ��������Ă�
��A�R�����P�ɗL���ȗD�ꂽ���\�̔R�����ˑ��u�Ƃ̂��Ƃ��B
�X�K���i�Q�O�O�X�N�K���j�ɓK��������^�g���b�N�u�X�[�p�[�O���[�g�v�̃G���W���ɍ̗p�����Ƃ̂��ƁB�O�H�ӂ����́uX-
Pulse�v�ɂ��āA�w�uX-Pulse�v�i�����R�������[���V�X�e���j���A�R�����˂̍������ƁA�R�����˗��̉σR���g���[��
�������B���X�ƕω�����G���W���^�]�����̒��ł��A��ɍœK�ȔR�Ă����Ȃ��A�r�o�K�X�̒ጸ�ƔR�����ɍv��
���܂��B�x�i�o�T�Fhttp://www.mitsubishi-fuso.com/jp/lineup/truck/super_great/10/point/fuel_01.html�j�Ƃ��������Ă�
��A�R�����P�ɗL���ȗD�ꂽ���\�̔R�����ˑ��u�Ƃ̂��Ƃ��B
�@�O�H�ӂ����́uX-Pulse�v�i�����R�������[���V�X�e���j�̗̍p�ɂ���ċ͂��ɔR����P�ɐ������A����܂ł̐V����
�r�o�K�X�K���i2005�N�K���j�K�����ɂ͂Q�O�P�T�N�x�d�ʎԔR���ɖ��B���ł������V�i�}�j���A���g�����X�~�b�V
�����Ԃ��|�X�g�V�����r�o�K�X�K���i2009�N�K���j�ł͂Q�O�P�T�N�x�d�ʎԔR���ɐh�����ĒB�������Ă���悤���B
�������A�|�X�g�V�����r�o�K�X�K���ɓK�������O�H�ӂ����̑�^�g���b�N�E�g���N�^�u�X�[�p�[�O���[�g�v��12�i�@�B��
�����g�����X�~�b�V�������̗p�����Ԏ�̏d�ʎԃ��[�h�R��l�́A�Q�O�P�T�N�x�d�ʎԔR�����͂��ɒ������M���M
���̔R��l�œK���ł��Ă����Ԃɉ߂��Ȃ��悤�ł���B
�r�o�K�X�K���i2005�N�K���j�K�����ɂ͂Q�O�P�T�N�x�d�ʎԔR���ɖ��B���ł������V�i�}�j���A���g�����X�~�b�V
�����Ԃ��|�X�g�V�����r�o�K�X�K���i2009�N�K���j�ł͂Q�O�P�T�N�x�d�ʎԔR���ɐh�����ĒB�������Ă���悤���B
�������A�|�X�g�V�����r�o�K�X�K���ɓK�������O�H�ӂ����̑�^�g���b�N�E�g���N�^�u�X�[�p�[�O���[�g�v��12�i�@�B��
�����g�����X�~�b�V�������̗p�����Ԏ�̏d�ʎԃ��[�h�R��l�́A�Q�O�P�T�N�x�d�ʎԔR�����͂��ɒ������M���M
���̔R��l�œK���ł��Ă����Ԃɉ߂��Ȃ��悤�ł���B
�@����E�O�H����^�g���b�N��13���b�g�����̃G���W�����̗p���Ă���̂ɑ��A�����U�����Ԃ͓�����^�g���b�N��10
���b�g���N���X�i9.839���b�g���j�̏��r�C�ʂ̃G���W�����̗p���Ă���B�����A��^�g���b�N�ɂ����ăG���W���_�E���T�C
�W���O���s���Ă���̂ł���B���̃G���W�����_�E���T�C�W���O����10���b�g���N���X�i9.839���b�g���j�̏��r�C�ʃG���W
���𓋍ڂ��̂���^�g���b�N�́A��̑��s���\����邪�A13���b�g�����̃G���W���𓋍ڂ�����^�g���b�N�ɔ�ׂ�
�d�ʎԃ��[�h�R���啝�����P�ł��郁���b�g������B���̌��ʁA�����U�����Ԃ́A�|�X�g�V�����r�o�K�X�K���i�Q�O�O
�X�N�K���j�ɓK��������^�g���b�N�u�M�K�v��99���̎Ԏ킪�Q�O�P�T�N�x�d�ʎԔR���ɓK�������Ă���悤���B
���b�g���N���X�i9.839���b�g���j�̏��r�C�ʂ̃G���W�����̗p���Ă���B�����A��^�g���b�N�ɂ����ăG���W���_�E���T�C
�W���O���s���Ă���̂ł���B���̃G���W�����_�E���T�C�W���O����10���b�g���N���X�i9.839���b�g���j�̏��r�C�ʃG���W
���𓋍ڂ��̂���^�g���b�N�́A��̑��s���\����邪�A13���b�g�����̃G���W���𓋍ڂ�����^�g���b�N�ɔ�ׂ�
�d�ʎԃ��[�h�R���啝�����P�ł��郁���b�g������B���̌��ʁA�����U�����Ԃ́A�|�X�g�V�����r�o�K�X�K���i�Q�O�O
�X�N�K���j�ɓK��������^�g���b�N�u�M�K�v��99���̎Ԏ킪�Q�O�P�T�N�x�d�ʎԔR���ɓK�������Ă���悤���B
�@���̂悤�ɁA�|�X�g�V�����r�o�K�X�K���ɓK����������E�O�H�EUD����^�g���b�N�̈ꕔ�Ԏ킪�Q�O�P�T�N�x�d�ʎ�
�R���ɖ��K���ł��錻��ƈقȂ�A�����U�����Ԃ̑�^�g���b�N�̖w�ǂ̎Ԏ�ł͂Q�O�P�T�N�x�d�ʎԔR��
�ɓK���ł��Ă���̂ł���B�������A���̔R��\���D�ꂽ�����U�����Ԃ̑�^�g���b�N�ɑ��A�����U�����Ԃ̑�^
�g���b�N�̃��[�U�́A�K�������������Ă��Ȃ��悤���B�G���W���_�E���T�C�W���O�ɂ���ĔR�����P��}���Ă��邢���U
�����Ԃ̑�^�g���b�N�ɑ��A�C���^�[�l�b�g�̌f���ł́A�^�]��Ǝv����l����A���r�C�ʂ̃_�E���T�C�W���O
�̃G���W���𓋍ڂ��������U�̑�^�g���b�N���A�\�P�O�Ɏ������悤�ȕs���̏������݂������B
�R���ɖ��K���ł��錻��ƈقȂ�A�����U�����Ԃ̑�^�g���b�N�̖w�ǂ̎Ԏ�ł͂Q�O�P�T�N�x�d�ʎԔR��
�ɓK���ł��Ă���̂ł���B�������A���̔R��\���D�ꂽ�����U�����Ԃ̑�^�g���b�N�ɑ��A�����U�����Ԃ̑�^
�g���b�N�̃��[�U�́A�K�������������Ă��Ȃ��悤���B�G���W���_�E���T�C�W���O�ɂ���ĔR�����P��}���Ă��邢���U
�����Ԃ̑�^�g���b�N�ɑ��A�C���^�[�l�b�g�̌f���ł́A�^�]��Ǝv����l����A���r�C�ʂ̃_�E���T�C�W���O
�̃G���W���𓋍ڂ��������U�̑�^�g���b�N���A�\�P�O�Ɏ������悤�ȕs���̏������݂������B
| |
�������������������ς��B�F2010/10/08(��) 04:58:45 ID:m5cY4xJR
�w�i�����U�́j6W(15.681���b�g���j����6U�i9.839���b�g���j�͔R����P���ړI���낤�B�����U�ȊO���R��d���Ȏԍ������Ă����
�v���A�M���M���̑��s���\�܂ŗ��Ƃ��ĔR���Nj����Ă����Ȃ����H�h���C�o�[���猩��Ό��Șb�ł͂��邪�B�x
|
| 45 �F�����������������ς��B�F2010/10/06(��) 12:43:37 ID:0z6N/mv0
�w�������A(�����U�̑�^�g���b�N�E�g���N�^�p�G���W���@��ł́A�j10���b�g���i6UZ1�F��Ƀg���b�N�p�j�� 16���b�g���i6WG1�F��ɏd�ʃg���N�^�p�j���c�Ȃ�āA���ɒ[����ȁB ���������_���v�Ƃ���6UZ1���ڎԂɂ�16�iMT���L��炵���ȁB �n�C�E���[����+-����3���Ƃ������ʔ����\�������������B �����܂ł��Ȃ�6WG1�ŗǂ���Ȃ����ȁc �x |
�@���̂悤�ɁA�|�X�g�V�����r�o�K�X�K���ɓK�����������U�����Ԃ̑�^�g���b�N�ɂ��āA�R�����P����������Ă�
�邱�Ƃ͊�������A�G���W���̏��r�C�ʉ��ɂ��_�E���T�C�W���O�ɂ���đ�^�g���b�N�̑��s���\���ቺ���Ă���
�����Ƃɂ��āA�^�]��͕s���������n�߂Ă���悤���B�܂��A��^�g���b�N�̃G���W�����_�E���T�C�W���O�����ꍇ
�́A�r�C�u���[�L�̐��\���ቺ���A��^�g���b�N�̍~��s���Ɋ댯�����ƂɂȂ�B�����G���W���_�E���T�C�W��
�O�ɂ���Ēቺ�����r�C�u���[�L�͂̕s����⊮���邽�߁A�V�����d�C����������̃��^�[�_��V���ɒlj��܂���
���^�[�_�̑�^�����K�v�ƂȂ�B���̃��^�[�_�̒lj����^���́A�R�X�g�A�b�v��ԗ��d�ʂ̑����v���ƂȂ�A��^�g
���b�N�ɂƂ��čD�܂������Ƃł͂Ȃ��B���̂��߁A��^�g���b�N�ɂ�����啝�ȃG���W���_�E���T�C�W���O�́A�f�����b�g
�����݂���̂ł���B
�邱�Ƃ͊�������A�G���W���̏��r�C�ʉ��ɂ��_�E���T�C�W���O�ɂ���đ�^�g���b�N�̑��s���\���ቺ���Ă���
�����Ƃɂ��āA�^�]��͕s���������n�߂Ă���悤���B�܂��A��^�g���b�N�̃G���W�����_�E���T�C�W���O�����ꍇ
�́A�r�C�u���[�L�̐��\���ቺ���A��^�g���b�N�̍~��s���Ɋ댯�����ƂɂȂ�B�����G���W���_�E���T�C�W��
�O�ɂ���Ēቺ�����r�C�u���[�L�͂̕s����⊮���邽�߁A�V�����d�C����������̃��^�[�_��V���ɒlj��܂���
���^�[�_�̑�^�����K�v�ƂȂ�B���̃��^�[�_�̒lj����^���́A�R�X�g�A�b�v��ԗ��d�ʂ̑����v���ƂȂ�A��^�g
���b�N�ɂƂ��čD�܂������Ƃł͂Ȃ��B���̂��߁A��^�g���b�N�ɂ�����啝�ȃG���W���_�E���T�C�W���O�́A�f�����b�g
�����݂���̂ł���B
�P�P�|�T�@�g���b�N���[�J�S�Ђ̑�^�g���b�N�̃G���W���r�C�ʂ̔�r
�@�\�P�P�Ƀ|�X�g�V�����r�o�K�X�K���ɓK�������g���b�N���[�J�S�Ђ̑�^�g���b�N���G���W���������B
| |
|
| |
�U�q�P�O �i12.808���b�g���j |
| |
�d�P�R�b �i12.913���b�g���j�A�`�O�X�b �i8.866���b�g���j |
| |
�f�g�P�P �i10.836���b�g���j |
| |
�U�t�y�P �i9.839���b�g���j |
�@�|�X�g�V�����r�o�K�X�K���ɓK��������^�g���b�N�i�܂ރ_���v�j�ɂ́A�O�H�ł͂P�R���b�g�����̃G���W�����̗p��
��A����ł͂P�R���b�g�����ƂX���b�g�����̂Q�@��̃G���W�������ڂ���Ă���B�����āA�t�c�g���b�N�X�ł͂P�P���b�g��
���̃G���W�����̗p����Ă���A�����U�����Ԃ͔r�C�ʂ��_�E���T�C�W���O�����P�O���b�g�����̃G���W���݂̂��p��
���Ă���B���̂悤�ɁA����A�����U����^�g���b�N�ɂX�`�P�O���b�g�����̃_�E���T�C�W���O�����G���W�����̗p����
����ő�̖ړI�́A��^�g���b�N���Q�O�P�T�N�x�d�ʎԔR���ɓK���A��^�g���b�N���[�J�Ԃ�����ȔR����ɑ�
�������Ƃł���B
��A����ł͂P�R���b�g�����ƂX���b�g�����̂Q�@��̃G���W�������ڂ���Ă���B�����āA�t�c�g���b�N�X�ł͂P�P���b�g��
���̃G���W�����̗p����Ă���A�����U�����Ԃ͔r�C�ʂ��_�E���T�C�W���O�����P�O���b�g�����̃G���W���݂̂��p��
���Ă���B���̂悤�ɁA����A�����U����^�g���b�N�ɂX�`�P�O���b�g�����̃_�E���T�C�W���O�����G���W�����̗p����
����ő�̖ړI�́A��^�g���b�N���Q�O�P�T�N�x�d�ʎԔR���ɓK���A��^�g���b�N���[�J�Ԃ�����ȔR����ɑ�
�������Ƃł���B
�@�������Ȃ���A����ł́A�}�P�Q�Ɏ������悤�ɁA����A�����U����^�g���b�N�ɂX�`�P�O���b�g�����̃_�E���T�C�W���O
�����G���W�����̗p���Ă�����^�J�[�S�g���b�N�iGVW25�g���j�̏d�ʎԃ��[�h�R��́A�P�R���b�g�����̃G���W�����̗p
����Ă�����^�J�[�S�g���b�N�iGVW25�g���j�̏d�ʎԃ��[�h�R��ɔ�r���āA�͏��̉��P�Ɏ~�܂��Ă���悤�ł���B
���̂��Ƃ́A��^�J�[�S�g���b�N�iGVW25�g���j�ɂ����ẮA���݂̃g���b�N���[�J�̋Z�p�ł̓G���W���_�E���T�C�W���O
�ɂ��d�ʎԃ��[�h�R��i�����s�R��j�̌��オ����Ȃ��Ƃ���Ă���d�v�ȏ؋��Ɖ]����̂ł͂Ȃ����낤���B
�����G���W�����̗p���Ă�����^�J�[�S�g���b�N�iGVW25�g���j�̏d�ʎԃ��[�h�R��́A�P�R���b�g�����̃G���W�����̗p
����Ă�����^�J�[�S�g���b�N�iGVW25�g���j�̏d�ʎԃ��[�h�R��ɔ�r���āA�͏��̉��P�Ɏ~�܂��Ă���悤�ł���B
���̂��Ƃ́A��^�J�[�S�g���b�N�iGVW25�g���j�ɂ����ẮA���݂̃g���b�N���[�J�̋Z�p�ł̓G���W���_�E���T�C�W���O
�ɂ��d�ʎԃ��[�h�R��i�����s�R��j�̌��オ����Ȃ��Ƃ���Ă���d�v�ȏ؋��Ɖ]����̂ł͂Ȃ����낤���B
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
�@�܂��A��^�g���b�N�i�܁A��^�_���v�j�Ƀ_�E���T�C�W���O�����G���W�����ڂ����ꍇ�A�Q�O�P�T�N�x�d�ʎԔR����
�K�����Ղ��ł��郁���b�g�����邱�Ƃ��ł��邪�A���̈���ł̓_�E���T�C�W���O�����G���W�����^�g���b�N�i�܁A
��^�_���v�j�ɓ��ڂ����ꍇ�ɂ́A�ȉ��̕\�P�R�Ɏ������f�����b�g�����邱�Ƃ��\���ɔF�����ׂ��ł���B
�K�����Ղ��ł��郁���b�g�����邱�Ƃ��ł��邪�A���̈���ł̓_�E���T�C�W���O�����G���W�����^�g���b�N�i�܁A
��^�_���v�j�ɓ��ڂ����ꍇ�ɂ́A�ȉ��̕\�P�R�Ɏ������f�����b�g�����邱�Ƃ��\���ɔF�����ׂ��ł���B
| |
|
| |
�@�_�E���T�C�W���O�����G���W���ɂ������r�C�u���[�L�̐����͂̒ቺ���⊮���邽�߂ɂ́A�d�C��,
�i�v���Ύ��܂��͖������̃��^�[�_�̑�^�����K�v�ƂȂ�B���̃��^�[�_�̑�^���́A�R�X�g�A�b�v��ԗ��d�ʂ��� ����v���ƂȂ�A��^�g���b�N�̃R�X�g�A�b�v��ԗ��d�ʂ̑������������ƂɂȂ�B |
| |
�@�_�E���T�C�W���O�����ߋ��G���W���ł́A�Ⴆ���ߋ�����}�����Ƃ��Ă��W�O�O�������ȉ��̃G���W����]���̗̈�ł̓^�[�{�ߋ�
�@�̌����̒������ቺ�ɂ��G���W���̑S���׃g���N���ቺ���錇�_������B�܂��A�G���W���_�E���T�C�W���O�̒��x�ɔ�Ⴕ��
�G���W����]�����̊������ʂ��ቺ���ăG���W����]�̊����G�l���M�[�����Ȃ��Ȃ�B���̂��߁A�_�E���T�C�W���O�����ߋ��G
���W���ł́A�W�O�O�������ȉ��̃G���W����]���ł̃N���b�`�~�[�e�B���O���ɂ�����G���W���̑S���׃g���N�ƃG���W����
��]�G�l���M�[�̍��v�i����^�g���b�N�i�����邽�߂̋쓮�́j���啝�ɒቺ����B���̌��ʁA�_�E���T�C�W���O��
���ߋ��G���W�����ڂ̑�^�g���b�N�̔��i���́A�r�C�ʂ̑傫���W���T�C�Y�̃G���W���𓋍ڂ����ꍇ�ɔ�r���āA��
�^�g���b�N�̔��i���\���傫���ቺ���邱�ƂɂȂ�B
�@���̃G���W���_�E���T�C�W���̔��i�쓮�͂̕s����⊮���ĕK�v�E�\���ȑ�^�g���b�N�ł̔��i���\���m�ۂł���ŗǂ̎�i�E �Z�p�Ƃ��ẮA�n�C�u���b�h�̂悤�ȓd�C���[�^�ɂ�锭�i���A�V�X�g������@���̗p���邱�Ƃł���B �@�܂��A�d�C���[�^��p���Ĕ��i���̓��͂��A�V�X�g����n�C�u���b�h������邪�A�Q�i�ߋ��V�X�e���ɂ��G���W���ᑬ���̍��g ���N�����A�G���W���_�E���T�C�W���̔��i���\�̉ɂ͌��ʂ�����B�������A���̂Q�i�ߋ��V�X�e���ł́A�W�O�O�������ȉ��̃G�� �W����]���ł̃N���b�`�~�[�e�B���O���ɂ�����G���W���̒��]�̑S���׃g���N�́A�u�f�ߋ��@�𓋍ڂ����r�C�ʂ̑傫���W���T �C�Y�̃G���W���̓��Y�G���W����]�̑S���׃g���N������邽�߁A�G���W���_�E���T�C�W���̑�^�g���b�N�̔��i���\���W���T�C �Y�̃G���W���𓋍ڂ�����^�g���b�N�ɗ�邱�Ƃ͊ԈႢ�������낤�B |
| |
�@�_�E���T�C�W���O�����G���W���ł́A�G���W���̔M���ׂ̑���ɂ��G���W���ϋv���̒ቺ�������N�����\�����ے�ł� �Ȃ��B |
�@�ȏ�̂悤�ɁA��^�g���b�N���_�E���T�C�W���O�����G���W�����̗p�����ꍇ�ɂ́A�d�ʎԃ��[�h�R��̉��P���͏�
�ł���ɂ�������炸�A��^�g���b�N�̔r�C�u���[�L�͂̒ቺ�┭�i���\�̒ቺ���܂ޑ�^�g���b�N�̓��͐��\��
��������������s����Ă��܂����ƂɂȂ�B���̏�A�G���W���̃_�E���T�C�W���O�́A�M���ׂ̑���ɂ��G���W
���ϋv���̒ቺ�������N�����f�����b�g�����݂��邱�Ƃ��\���ɔF�����ׂ��ł���B
�ł���ɂ�������炸�A��^�g���b�N�̔r�C�u���[�L�͂̒ቺ�┭�i���\�̒ቺ���܂ޑ�^�g���b�N�̓��͐��\��
��������������s����Ă��܂����ƂɂȂ�B���̏�A�G���W���̃_�E���T�C�W���O�́A�M���ׂ̑���ɂ��G���W
���ϋv���̒ቺ�������N�����f�����b�g�����݂��邱�Ƃ��\���ɔF�����ׂ��ł���B
�@���̂悤�ȏ���A�|�X�g�V�����r�o�K�X�K���̌��݂ł́A���s���\�̒ቺ���C�Ɏ~�߂Ȃ��ŋ͂��ȔR�����
���d�v������g���b�N���[�U�͂����U���������`�b�O�X �i�X���b�g���j�G���W�����ڂ���^�g���b�N���w�����A���s���\��
�d������g���b�N���[�U�͎O�H�ӂ����������d�P�R�b �i�P�R���b�g���j���ڂ���^�g���b�N���w�����Ă���̂ł͂Ȃ���
�낤���B�����āA���҂̒��Ԃ̃��[�U�́AUD�̑�^�g���b�N���w�����A�����̑��s���\�̋]�����o�債�ċ͂��ȔR��
���P�����߂Ă���̂ł͂Ȃ����낤���B���̂悤�ɁA�s�̂���Ă����^�g���b�N�̎s��ł́A�R��d����s���\
�d�����̑��ʂȏ��i�\���ƂȂ��Ă���悤���B���̂��Ƃ́A��^�g���b�N���w������e�^���Ǝ҂ɂƂ��ẮA�e���[�U
�̉^�s�ɓK�������[�J�̃g���b�N��I�����邱�Ƃ��ł��邽�߁A�g���b�N���[�U�ɂ͍D�܂������Ƃƍl������B
���d�v������g���b�N���[�U�͂����U���������`�b�O�X �i�X���b�g���j�G���W�����ڂ���^�g���b�N���w�����A���s���\��
�d������g���b�N���[�U�͎O�H�ӂ����������d�P�R�b �i�P�R���b�g���j���ڂ���^�g���b�N���w�����Ă���̂ł͂Ȃ���
�낤���B�����āA���҂̒��Ԃ̃��[�U�́AUD�̑�^�g���b�N���w�����A�����̑��s���\�̋]�����o�債�ċ͂��ȔR��
���P�����߂Ă���̂ł͂Ȃ����낤���B���̂悤�ɁA�s�̂���Ă����^�g���b�N�̎s��ł́A�R��d����s���\
�d�����̑��ʂȏ��i�\���ƂȂ��Ă���悤���B���̂��Ƃ́A��^�g���b�N���w������e�^���Ǝ҂ɂƂ��ẮA�e���[�U
�̉^�s�ɓK�������[�J�̃g���b�N��I�����邱�Ƃ��ł��邽�߁A�g���b�N���[�U�ɂ͍D�܂������Ƃƍl������B
�P�P�|�U�@��^�g���b�N�E�g���N�^�̔R��팸�́A�S�g���b�N���[�J�̍ł��d�v�ȊJ���ۑ�
�@�䂪���ő�^�g���b�N�E�g���N�^��̔����Ă�����쎩���ԁA�����U�����ԁA�O�H�ӂ����AUD�g���b�N�X����у{���{
�̊e���[�J�ɂ����āA�|�X�g�V�����r�o�K�X�K���i�Q�O�O�X�N�K���j�ɓK��������^�g���b�N�E�g���N�^�̒��ŁA�Q�O�P�T�N
�x�d�ʎԔR���ɕs�K���ƂȂ��Ă���Ԏ�̊�����\�P�S�Ɏ������B
�̊e���[�J�ɂ����āA�|�X�g�V�����r�o�K�X�K���i�Q�O�O�X�N�K���j�ɓK��������^�g���b�N�E�g���N�^�̒��ŁA�Q�O�P�T�N
�x�d�ʎԔR���ɕs�K���ƂȂ��Ă���Ԏ�̊�����\�P�S�Ɏ������B
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
8e0ef07935a1�j |
| |
|
|
| |
|
|
�@�\�P�R������ƁA�����U�����Ԃ̑�^�g���b�N�E�g���N�^�̖w�ǂ̎Ԏ킪�Q�O�P�T�N�x�d�ʎԔR���ɓK�����Ă���
���A����̓G���W���̏��r�C�ʉ��ɂ��_�E���T�C�W���O�̌��ʂƍl������B��^�g���b�N�E�g���N�^�̃G���W�����_
�E���T�C�W���O�����ꍇ�ɂ́A��^�g���b�N�E�g���N�^�̒�R����\�ɂȂ邪�A�ԗ��̑��s���\�����悤�ɂȂ�
���߁A�S�Ẵ��[�U�Ɋ��}������^�g���b�N�ł͖����ƍl������B�܂��A���쎩���ԁAUD�g���b�N�X����юO�H��
�����̑�^�g���b�N�E�g���N�^�ɂ����ẮA�|�X�V�����r�o�K�X�K���i�Q�O�O�X�N�K���j�ɓK�����������̎Ԏ�̑�^�g���b
�N�E�g���N�^���Q�O�P�T�N�x�d�ʎԔR���ɕs�K���ƂȂ��Ă���̂�����ł���B
���A����̓G���W���̏��r�C�ʉ��ɂ��_�E���T�C�W���O�̌��ʂƍl������B��^�g���b�N�E�g���N�^�̃G���W�����_
�E���T�C�W���O�����ꍇ�ɂ́A��^�g���b�N�E�g���N�^�̒�R����\�ɂȂ邪�A�ԗ��̑��s���\�����悤�ɂȂ�
���߁A�S�Ẵ��[�U�Ɋ��}������^�g���b�N�ł͖����ƍl������B�܂��A���쎩���ԁAUD�g���b�N�X����юO�H��
�����̑�^�g���b�N�E�g���N�^�ɂ����ẮA�|�X�V�����r�o�K�X�K���i�Q�O�O�X�N�K���j�ɓK�����������̎Ԏ�̑�^�g���b
�N�E�g���N�^���Q�O�P�T�N�x�d�ʎԔR���ɕs�K���ƂȂ��Ă���̂�����ł���B
�@���̂��Ƃ���A��^�g���b�N���[�J�ɂ����ẮA��^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W���̏d�ʎԃ��[�h�R��l���T�p�[�Z��
�g���x�̉��P���\�ɂ���Z�p�𑁋}�ɊJ�����A�e�Ђ̑�^�g���b�N�E�g���N�^�̑S�Ԏ���Q�O�P�T�N�x�d�ʎԔR���
���ɓK���ł���悤�ɂ��邱�Ƃ��i�ق̉ۑ�ł��邱�Ƃ͖��炩�ł���B�����āA�����U�����Ԃɂ����Ă��A���s���\
�̍���13���b�g�����̃G���W���𓋍ڂ����}�j���A���~�b�V�������ڂ̑�^�g���b�N�E�g���N�^���Q�O�P�T�N�x�d�ʎԔR��
��ɓK���ł���Z�p���J���ł���A�����U�����Ԃ����s���\�̍�����r�C�ʃG���W���𓋍ڂ�����^�g���b�N�E
�g���N�^�����i�ɉ����邱�Ƃ��\�ƂȂ�̂ł���B
�g���x�̉��P���\�ɂ���Z�p�𑁋}�ɊJ�����A�e�Ђ̑�^�g���b�N�E�g���N�^�̑S�Ԏ���Q�O�P�T�N�x�d�ʎԔR���
���ɓK���ł���悤�ɂ��邱�Ƃ��i�ق̉ۑ�ł��邱�Ƃ͖��炩�ł���B�����āA�����U�����Ԃɂ����Ă��A���s���\
�̍���13���b�g�����̃G���W���𓋍ڂ����}�j���A���~�b�V�������ڂ̑�^�g���b�N�E�g���N�^���Q�O�P�T�N�x�d�ʎԔR��
��ɓK���ł���Z�p���J���ł���A�����U�����Ԃ����s���\�̍�����r�C�ʃG���W���𓋍ڂ�����^�g���b�N�E
�g���N�^�����i�ɉ����邱�Ƃ��\�ƂȂ�̂ł���B
�@���݂̃|�X�g�V�����r�o�K�X�K���i2009�N�K���j�ɓK��������^�g���b�N�E�g���N�^�i��^�_���v���܂ށj�ɂ����āA�P
�O���b�g���G���W���𓋍ڂ��������U��X���b�g���G���W���𓋍ڂ�������̑�^�g���b�N�E�g���N�^�́A�R��\�ɗD��
�Ă��邪���i�����̓��͐��\�ɖ�肪����ƍl������B�����āA�P�R���b�g���G���W���𓋍ڂ�������ƎO�H�̑�^
�g���b�N�E�g���N�^�́A�Q�O�P�T�N�x�d�ʎԔR���ɑS�Ԏ��K���ł���悤�ɂ���Z�p�̊J�����}���ł��邱�Ƃ͖�
�炩���B���������āA����ł͓���A�����U�A�t�c����юO�H�̊e�g���b�N���[�J�̊J������ɂ����ẮA���}�ɑ�^�g
���b�N�E�g���N�^�̏d�ʎԃ��[�h�R��l���T�p�[�Z���g���x�̉��P���\�ɂ���Z�p�̑����������������v������Ă�
�邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��ƍl������B
�O���b�g���G���W���𓋍ڂ��������U��X���b�g���G���W���𓋍ڂ�������̑�^�g���b�N�E�g���N�^�́A�R��\�ɗD��
�Ă��邪���i�����̓��͐��\�ɖ�肪����ƍl������B�����āA�P�R���b�g���G���W���𓋍ڂ�������ƎO�H�̑�^
�g���b�N�E�g���N�^�́A�Q�O�P�T�N�x�d�ʎԔR���ɑS�Ԏ��K���ł���悤�ɂ���Z�p�̊J�����}���ł��邱�Ƃ͖�
�炩���B���������āA����ł͓���A�����U�A�t�c����юO�H�̊e�g���b�N���[�J�̊J������ɂ����ẮA���}�ɑ�^�g
���b�N�E�g���N�^�̏d�ʎԃ��[�h�R��l���T�p�[�Z���g���x�̉��P���\�ɂ���Z�p�̑����������������v������Ă�
�邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��ƍl������B
�P�P�|�V�D��@�s�ׂ̃V�X�e������ŔR������}���Ă����g���b�N���[�J�̔R����P�̍���
�@�����U�����Ԃ́A�|�X�g�V�����r�o�K�X�K���i2009�N��2010�N�K���j��NO���K���ɓK��������Z�p�Ƃ��āA��^�g��
�b�N�u�M�K�v�ɂ͔A�fSCR�G�}���̗p���A���^�g���b�N�u�t�H���[�h�v����я��^�g���b�N�u�G���t�v�ɂ͑��EGR�ƕ��ˎ�
���̒x�����̗p�����B���EGR�ƕ��ˎ����̒x�����̗p�����u�t�H���[�h�v�Ɓu�G���t�v�́A�A�fSCR�G�}���̗p�����O
�H�ӂ����̒��^�g���b�N�u�t�H�C�^�\�v�ɔ�ׁA�K�R�I�ɔR���邱�ƂɂȂ�B���ɁA�R���𑽗ʂɏ���鍂����
�H���s�̏ꍇ�ɂ́A�����U�����Ԃ̒��^�g���b�N�u�t�H���[�h�v����я��^�g���b�N�u�G���t�v�́A�R��̗ǂ��A�fSCR
�G�}���̗p���Ă���O�H�ӂ����̒��^�g���b�N�u�t�H�C�^�\�v����я��^�g���b�N�u�L�����^�[�v�ɔ�r���đ��ʂ̔R����
����邱�ƂɂȂ�B���̂��߁A�����U�����Ԃ́u�t�H���[�h�v����сu�G���t�v�̔R���邱�Ƃ��^�]��ɊȒP�ɋC
�t����Ă��܂����ƂɂȂ�B���̏ꍇ�ɂ́A�u�t�H���[�h�v����сu�G���t�v�̔R��s�ǂ̕]�����L�܂邱�Ƃ�h�~���邽
�߁A�����U�����Ԃ͔R���𑽗ʂɏ���鍂�����H�ł́u�t�H���[�h�v����сu�G���t�v�̘A�����s�ł̎O�H�ӂ�����
�u�t�H�C�^�\�v��u�L�����^�[�v�Ɠ����̔R����m�ۂ��Ă������Ƃ��K�v�ł���B������\�ɂ���ȒP�ȕ��@�́AJE05
�r�o�K�X�������[�h�͂��AJE05���[�h�ʼn^�]�����G���W�����ׂ�G���W����]���x�Ƃ����̌p���^�]������
�ԓ��m�ɂ��AJE05���[�h�ʼn^�]����Ȃ��G���W���^�]�̏������������ꂽ�ꍇ�ɂ�EGR�̍쓮�╬�ˎ����̒x
���𒆎~���A�^�[�{�ߋ������������̉^�]�ɐ�ւ��ăG���W���̔R������シ��G���W������ɐ�ւ��鐧��V
�X�e�����u�t�H���[�h�v����сu�G���t�v�ɓ��ڂ��邱�Ƃł���B
�b�N�u�M�K�v�ɂ͔A�fSCR�G�}���̗p���A���^�g���b�N�u�t�H���[�h�v����я��^�g���b�N�u�G���t�v�ɂ͑��EGR�ƕ��ˎ�
���̒x�����̗p�����B���EGR�ƕ��ˎ����̒x�����̗p�����u�t�H���[�h�v�Ɓu�G���t�v�́A�A�fSCR�G�}���̗p�����O
�H�ӂ����̒��^�g���b�N�u�t�H�C�^�\�v�ɔ�ׁA�K�R�I�ɔR���邱�ƂɂȂ�B���ɁA�R���𑽗ʂɏ���鍂����
�H���s�̏ꍇ�ɂ́A�����U�����Ԃ̒��^�g���b�N�u�t�H���[�h�v����я��^�g���b�N�u�G���t�v�́A�R��̗ǂ��A�fSCR
�G�}���̗p���Ă���O�H�ӂ����̒��^�g���b�N�u�t�H�C�^�\�v����я��^�g���b�N�u�L�����^�[�v�ɔ�r���đ��ʂ̔R����
����邱�ƂɂȂ�B���̂��߁A�����U�����Ԃ́u�t�H���[�h�v����сu�G���t�v�̔R���邱�Ƃ��^�]��ɊȒP�ɋC
�t����Ă��܂����ƂɂȂ�B���̏ꍇ�ɂ́A�u�t�H���[�h�v����сu�G���t�v�̔R��s�ǂ̕]�����L�܂邱�Ƃ�h�~���邽
�߁A�����U�����Ԃ͔R���𑽗ʂɏ���鍂�����H�ł́u�t�H���[�h�v����сu�G���t�v�̘A�����s�ł̎O�H�ӂ�����
�u�t�H�C�^�\�v��u�L�����^�[�v�Ɠ����̔R����m�ۂ��Ă������Ƃ��K�v�ł���B������\�ɂ���ȒP�ȕ��@�́AJE05
�r�o�K�X�������[�h�͂��AJE05���[�h�ʼn^�]�����G���W�����ׂ�G���W����]���x�Ƃ����̌p���^�]������
�ԓ��m�ɂ��AJE05���[�h�ʼn^�]����Ȃ��G���W���^�]�̏������������ꂽ�ꍇ�ɂ�EGR�̍쓮�╬�ˎ����̒x
���𒆎~���A�^�[�{�ߋ������������̉^�]�ɐ�ւ��ăG���W���̔R������シ��G���W������ɐ�ւ��鐧��V
�X�e�����u�t�H���[�h�v����сu�G���t�v�ɓ��ڂ��邱�Ƃł���B
�@���̂悤�ɁA�G���W���^�]��Ԃ�JE05���[�h���̔r�o�K�X�������[�h�̃G���W���^�]��������O�ꂽ�ۂɂ́A�G��
�W����r�o�K�X�ጸ�@�\��S�Ē�~���Ē�R���Ԃʼn^�]�ł���悤�ɐ��䂷��u�������@�\�v�́A20�N�ȏ������
�̂Ɉ���g���b�N���[�J����^�g���b�N�̓d�q�^�C�}�[�ł��̈�@�Ȑ�����s���A�����̉^�A�Ȃ����@����Ƃ��đ�
�ڋʐH��������Ƃ�����B���̍�����ANO�����������ĊȒP�Ƀg���b�N�̑��s�R������コ�����@�ȃG���W����
��́A�G���W���W�҂̒N������@�ƔF�����Ă��邱�Ƃ��B
�W����r�o�K�X�ጸ�@�\��S�Ē�~���Ē�R���Ԃʼn^�]�ł���悤�ɐ��䂷��u�������@�\�v�́A20�N�ȏ������
�̂Ɉ���g���b�N���[�J����^�g���b�N�̓d�q�^�C�}�[�ł��̈�@�Ȑ�����s���A�����̉^�A�Ȃ����@����Ƃ��đ�
�ڋʐH��������Ƃ�����B���̍�����ANO�����������ĊȒP�Ƀg���b�N�̑��s�R������コ�����@�ȃG���W����
��́A�G���W���W�҂̒N������@�ƔF�����Ă��邱�Ƃ��B
�@�������A�ŋ߂�MSN�@�Y�o�j���[�X�i2011�N6��3�� 20��56���j�ɂ��ƁA�����U�����Ԃ̃f�B�[�[���S�g���g���b�N�u�t
�H���[�h�v���A�����Q�Q�N�̔r�o�K�X�K���i�|�X�g�V�����K���j�̓K���ԂƔF�肳��Ă���ɂ�������炸�A�V���[�V�_
�C�i���ł̎����s��Ԃł͂m�n���i���f�_�����j����̂R�{�ȏ�r�o����Ă������Ƃ�2011�N6��3���A�����s��
�Ȋw�������̒����ŕ��������悤���B����Ɋւ��A�����U�����Ԃ͓����A���y��ʏȂɃt�H���[�h�v�W�W�U��̃��R�[
����͂��o���Ƃ̂��ƁB����̂����U�����̒��^�g���b�N�h�t�H���[�h�ɂ�����G���W������́A���̌ÓT�I�Ƃ�������
��@�ȃG���W������Ɏ��Ă���悤�Ɏv�����A�@���Ȃ��̂ł��낤���B
�H���[�h�v���A�����Q�Q�N�̔r�o�K�X�K���i�|�X�g�V�����K���j�̓K���ԂƔF�肳��Ă���ɂ�������炸�A�V���[�V�_
�C�i���ł̎����s��Ԃł͂m�n���i���f�_�����j����̂R�{�ȏ�r�o����Ă������Ƃ�2011�N6��3���A�����s��
�Ȋw�������̒����ŕ��������悤���B����Ɋւ��A�����U�����Ԃ͓����A���y��ʏȂɃt�H���[�h�v�W�W�U��̃��R�[
����͂��o���Ƃ̂��ƁB����̂����U�����̒��^�g���b�N�h�t�H���[�h�ɂ�����G���W������́A���̌ÓT�I�Ƃ�������
��@�ȃG���W������Ɏ��Ă���悤�Ɏv�����A�@���Ȃ��̂ł��낤���B
�@����ɂ��āA�����s�́u�r�o�K�X�ጸ���\����������@�\�𓋍ڂ��Ă����v�Ɣ��f�����悤���B�s���ǂɂ�
��ƁA�g���b�N�͎���60�q/hr�̎ԑ���200�b���x�𑖍s������ɂ́A�ԍڃR���s���[�^�[�������I�ɍ쓮���A���
��R�{����360ppm�̔Z�x�̂m�n����r�o����Ƃ����B������u�������@�\�v�Ǝw�E�����Ƃ̂��ƁB�}1�Q�́A�����s��
���Ȋw���������v�����������U�����Ԃ̒��^�g���b�N�h�t�H���[�h�̈ꕔ�O���[�h�̔r�o�K�X�������ʂł���B����
�ɂ��ƁA�����J�n���30�b���_����60km/h�̒葬���s���J�n�������ɂ͋K���l���Ɏ��܂��Ă������[�h�v����
NO���l�������J�n���230�b���_���o�߂���ƓˑR�A3�`4�{�ɑ��������Ƃ̂��Ƃ��B�����āANO���̑����Ɠ����ɁA
CO2��220ppm����140ppm�܂ő啝�ɒጸ���Ă��邱�Ƃ���A�R������͌��サ�Ă�����̂Ɛ��@�����B�M�҂̐�
���ł́A�����U�����Ԃ̒��^�g���b�N�h�t�H���[�h�ɂ�����K���r�o�K�X�ጸ���\�́u�������@�\�v�̃G���W������v
���O�����́AJE05���[�h�ʼn^�]����Ȃ��G���W���^�]��ԂƂȂ������Ƃ����m���ꂽ���_�Łu���EGR�𒆎~�v���A�u�R
�����ˎ�����i�p�v�����A�X�Ɂu�^�[�{�ߋ��@�����������̉^�]�v�ɐ�ւ��邱�Ƃɂ���ăG���W���R������コ��
��Ɖ]���A��@�ȃG���W���̃V�X�e��������s���Ă������̂ƍl������B
��ƁA�g���b�N�͎���60�q/hr�̎ԑ���200�b���x�𑖍s������ɂ́A�ԍڃR���s���[�^�[�������I�ɍ쓮���A���
��R�{����360ppm�̔Z�x�̂m�n����r�o����Ƃ����B������u�������@�\�v�Ǝw�E�����Ƃ̂��ƁB�}1�Q�́A�����s��
���Ȋw���������v�����������U�����Ԃ̒��^�g���b�N�h�t�H���[�h�̈ꕔ�O���[�h�̔r�o�K�X�������ʂł���B����
�ɂ��ƁA�����J�n���30�b���_����60km/h�̒葬���s���J�n�������ɂ͋K���l���Ɏ��܂��Ă������[�h�v����
NO���l�������J�n���230�b���_���o�߂���ƓˑR�A3�`4�{�ɑ��������Ƃ̂��Ƃ��B�����āANO���̑����Ɠ����ɁA
CO2��220ppm����140ppm�܂ő啝�ɒጸ���Ă��邱�Ƃ���A�R������͌��サ�Ă�����̂Ɛ��@�����B�M�҂̐�
���ł́A�����U�����Ԃ̒��^�g���b�N�h�t�H���[�h�ɂ�����K���r�o�K�X�ጸ���\�́u�������@�\�v�̃G���W������v
���O�����́AJE05���[�h�ʼn^�]����Ȃ��G���W���^�]��ԂƂȂ������Ƃ����m���ꂽ���_�Łu���EGR�𒆎~�v���A�u�R
�����ˎ�����i�p�v�����A�X�Ɂu�^�[�{�ߋ��@�����������̉^�]�v�ɐ�ւ��邱�Ƃɂ���ăG���W���R������コ��
��Ɖ]���A��@�ȃG���W���̃V�X�e��������s���Ă������̂ƍl������B
�@����̂����U�����̒��^�g���b�N�h�t�H���[�h�ɂ������@�ȃG���W������́A���̌ÓT�I�Ƃ��������@����Ɏ�
�Ă���悤�Ɏv�����A�@���Ȃ��̂ł��낤���B�������AMSN�@�Y�o�j���[�X�ɂ��ƁA�����U�����Ԃ́u�G���W������v��
�O�����̉e���ŁA�ᑬ��Ԃł̌p�����s��}���ȉ����̍ۂɁA�m�n���̔r�o�l���������鋰�ꂪ����v�Ƃ��A�u����
����ȂǁA�Ӑ}�I�Ȃ��̂ł͂Ȃ��B�v�Ɛ������Ă���悤�ł���B�������A�����s���Ȋw�����������\�����}�P�Q�ɂ�
��A�t�H���[�h������60�q/hr�̔�r�I�A�������x��200�b���x�𑖍s������ɁuNO���̌����v�ƁuCO�Q�̌����v����
����A�����U�����Ԃ́u�ᑬ��Ԃł̌p�����s�łm�n���̔r�o�l����������v�Ƃ̓����s�́u�������@�\�v�̐}����
�w�E�ɑ��āA�����U�����Ԃ͊��S�ɈӖ��s���ȕى��\���Ă���̂��B���̂��Ƃ�����A�����U�����Ԃ̓|�X�g�V
�����K���K���̃t�H���[�h�̔R����������ł����P���邽�߂ɁA��ނɂ�܂ꂸ�A��@�ȃG���W��������̗p����
�������̂Ɛ��������B�܂��A�����s���Ȋw�����������\������@�ȃG���W������̎Ԏ�́A�u�ԗ��^���FSKG-
FRR90S2�v(�SHK1-TCS�G���W�����ځj�ł���B�����s�ɂ�鍡��Ɉ�@�s�ׂ̓E���́A�u�ԗ��^���FSKG-FRR90S2�v
(�SHK1-TCS�G���W�����ځj�̎Ԏ킾���ł��邪�A�����U�����Ԃł͑��̎Ԏ�ɂ����Ă��A���̂悤�Ȉ�@�ȃG���W��
����𓋍ڂ��ĔR������}���Ă���\���́A�S�������̂ł��낤���B���O�҂Ȃ���A�����̂���Ƃ���ł���B
�Ă���悤�Ɏv�����A�@���Ȃ��̂ł��낤���B�������AMSN�@�Y�o�j���[�X�ɂ��ƁA�����U�����Ԃ́u�G���W������v��
�O�����̉e���ŁA�ᑬ��Ԃł̌p�����s��}���ȉ����̍ۂɁA�m�n���̔r�o�l���������鋰�ꂪ����v�Ƃ��A�u����
����ȂǁA�Ӑ}�I�Ȃ��̂ł͂Ȃ��B�v�Ɛ������Ă���悤�ł���B�������A�����s���Ȋw�����������\�����}�P�Q�ɂ�
��A�t�H���[�h������60�q/hr�̔�r�I�A�������x��200�b���x�𑖍s������ɁuNO���̌����v�ƁuCO�Q�̌����v����
����A�����U�����Ԃ́u�ᑬ��Ԃł̌p�����s�łm�n���̔r�o�l����������v�Ƃ̓����s�́u�������@�\�v�̐}����
�w�E�ɑ��āA�����U�����Ԃ͊��S�ɈӖ��s���ȕى��\���Ă���̂��B���̂��Ƃ�����A�����U�����Ԃ̓|�X�g�V
�����K���K���̃t�H���[�h�̔R����������ł����P���邽�߂ɁA��ނɂ�܂ꂸ�A��@�ȃG���W��������̗p����
�������̂Ɛ��������B�܂��A�����s���Ȋw�����������\������@�ȃG���W������̎Ԏ�́A�u�ԗ��^���FSKG-
FRR90S2�v(�SHK1-TCS�G���W�����ځj�ł���B�����s�ɂ�鍡��Ɉ�@�s�ׂ̓E���́A�u�ԗ��^���FSKG-FRR90S2�v
(�SHK1-TCS�G���W�����ځj�̎Ԏ킾���ł��邪�A�����U�����Ԃł͑��̎Ԏ�ɂ����Ă��A���̂悤�Ȉ�@�ȃG���W��
����𓋍ڂ��ĔR������}���Ă���\���́A�S�������̂ł��낤���B���O�҂Ȃ���A�����̂���Ƃ���ł���B
�}�P�Q�@���^�g���b�N�h�t�H���[�h��60km/h�葬���s�ɂ�����250�b�̌o�ߌ�́uNO�������v�ƁuCO�Q�����v�̃f�[�^
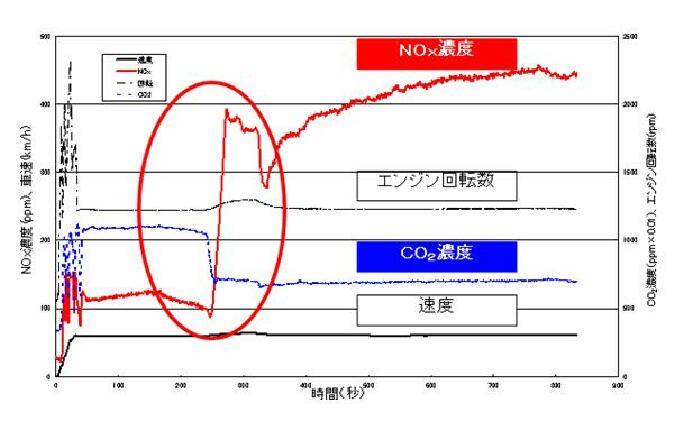
�@
�@�����s���Ȋw�������́A�M�҂̋L���ł�20�N�ȏ���ȑO�ɁA��^�g���b�N�̂ő��s���̔r�o�K�X�v�����\��
�V���[�V�_�C�i�r�o�K�X�����ݔ������Ă���̂��B���������āA���̃V���[�V�_�C�i�̔r�o�K�X�����ݔ���p��
��A���s���̈�莞�Ԃ̌o�ߌ��NO�����������ĔR������コ����悤�ɃG���W�������ύX�����@�ȃV
�X�e���𓋍ڂ����g���b�N�̔r�o�K�X���������{�����ꍇ�ɂ́A�G���W������̈�@�����ۉ������I�����Ă��܂��̂�
����B���̂��Ƃ́A�����U�����Ԃ����R�A�̂���n�m���Ă��锤�ł��邪�A���́A�ȒP�Ɉ�@�����I������悤�ȃG��
�W������̃g���b�N��̔������̂ł��낤���B
�V���[�V�_�C�i�r�o�K�X�����ݔ������Ă���̂��B���������āA���̃V���[�V�_�C�i�̔r�o�K�X�����ݔ���p��
��A���s���̈�莞�Ԃ̌o�ߌ��NO�����������ĔR������コ����悤�ɃG���W�������ύX�����@�ȃV
�X�e���𓋍ڂ����g���b�N�̔r�o�K�X���������{�����ꍇ�ɂ́A�G���W������̈�@�����ۉ������I�����Ă��܂��̂�
����B���̂��Ƃ́A�����U�����Ԃ����R�A�̂���n�m���Ă��锤�ł��邪�A���́A�ȒP�Ɉ�@�����I������悤�ȃG��
�W������̃g���b�N��̔������̂ł��낤���B
�@�����U�����Ԃł̓g���b�N�̔R����オ�������ׂ��i�ق̉ۑ�ł��邪�A���̉ۑ�������ł���Z�p�������Ɍ�
�o���Ă��Ȃ����߁A�t�H�[���[�h�Ɉ�@�ȃG���W��������̗p�������{�I�Ȍ����ł͂Ȃ����Ɛ��������B�����_��
�́A�����U�����Ԃɂ����Ă͔R�����ɗL���ȋZ�p�������J���ł��Ă��Ȃ����Ƃ���A�G���W���J���̒S���҂��ꂵ
����Ɉ�@�ȃG���W������Ɏ���o���A���ꂪ�I�����Ă��܂������̂Ɛ��������B�u�n����Γ݂��v�Ƃ͐��ɂ��̂�
���Ȃ��Ƃ��w���Ă���̂ł͂Ȃ����낤���B���̂悤�ɁA�����U�����Ԃ���@�ƌ�����s�ׂɑ��������Ƃ́A�����̎�
���ɂƂ��Ă͒p�����������Ƃ��낤�B���͂Ƃ�����A�����_�ł����U�����Ԃ́A�R�����̂��߂ɓ����s�����@��
���������w�E�����ւ���܂ł��g���Ă��܂����Ƃ��������ƁA�g���b�N�̔R�����̂��߂Ɂu�Ȃ�ӂ���\���Ă����
�Ȃ��v�悤�ȏɊׂ��Ă���̂ł͂Ȃ����낤���B�����āA�s�K�ɂ��A�����U�����Ԃ́A�t�H�[���[�h�ɂ�����R���
��̂��߂̈�@�ȃG���W��������s���Ă������Ƃ������s�ɔ�������Ă��܂����̂ł���B���R�̂��Ƃł͂��邪�A
�����s�͕���23�N5���ɁA���y��ʏȂɑ��āA���H�^���ԗ��@�ᔽ�Œʕ��Ƃ̂��Ƃ��B
�o���Ă��Ȃ����߁A�t�H�[���[�h�Ɉ�@�ȃG���W��������̗p�������{�I�Ȍ����ł͂Ȃ����Ɛ��������B�����_��
�́A�����U�����Ԃɂ����Ă͔R�����ɗL���ȋZ�p�������J���ł��Ă��Ȃ����Ƃ���A�G���W���J���̒S���҂��ꂵ
����Ɉ�@�ȃG���W������Ɏ���o���A���ꂪ�I�����Ă��܂������̂Ɛ��������B�u�n����Γ݂��v�Ƃ͐��ɂ��̂�
���Ȃ��Ƃ��w���Ă���̂ł͂Ȃ����낤���B���̂悤�ɁA�����U�����Ԃ���@�ƌ�����s�ׂɑ��������Ƃ́A�����̎�
���ɂƂ��Ă͒p�����������Ƃ��낤�B���͂Ƃ�����A�����_�ł����U�����Ԃ́A�R�����̂��߂ɓ����s�����@��
���������w�E�����ւ���܂ł��g���Ă��܂����Ƃ��������ƁA�g���b�N�̔R�����̂��߂Ɂu�Ȃ�ӂ���\���Ă����
�Ȃ��v�悤�ȏɊׂ��Ă���̂ł͂Ȃ����낤���B�����āA�s�K�ɂ��A�����U�����Ԃ́A�t�H�[���[�h�ɂ�����R���
��̂��߂̈�@�ȃG���W��������s���Ă������Ƃ������s�ɔ�������Ă��܂����̂ł���B���R�̂��Ƃł͂��邪�A
�����s�͕���23�N5���ɁA���y��ʏȂɑ��āA���H�^���ԗ��@�ᔽ�Œʕ��Ƃ̂��Ƃ��B
�@�Ȃ��A�����s���Ȋw�����������\������@�ȃG���W������𓋍ڂ����u�����U�����ԁv�̒��^�g���b�N�F�t�H�[��
�[�h�̎ԗ��^���́A�uSKG-FRR90S2�v�ł��邪�A���̎Ԏ�ɂ͂SHK1-TCS�G���W�������ڂ���Ă���B�������A���̂S
HK1-TCS�G���W���́A�������ƂɁu������^���^���p�ԗp�X�[�p�[�N���[���f�B�[�[���G���W���̊J���v�Ƃ��Ď�����
�Z�p��̑�61�� �����ԋZ�p��܂̋Z�p�J���܁i��ҁF���� �p�����A���� �P�V���A��� �a�M���A���� �O�K
���A�� �a�F���j����܂��Ă������Ƃ��B�܂�A�SHK1-TCS�G���W���̓X�[�p�[�N���[���f�B�[�[���G���W���Ƃ��Ď���
�ԋZ�p���\������Ă����̂ł���B�Ƃ��낪�A���̂SHK1-TCS�G���W���́A�m�n���̔r�o�l�̈����������邱�Ƃ�
����đ��s�R��̌����}��G���W������v���O�����Ő��䂵�Ă������Ƃ𓌋��s���Ȋw�����������y��ʏȂ�
���H�^���ԗ��@�ᔽ�Œʕ����^�g���b�N�F�t�H�[���[�h�ɓ��ڂ���Ă����̂ł����B
�[�h�̎ԗ��^���́A�uSKG-FRR90S2�v�ł��邪�A���̎Ԏ�ɂ͂SHK1-TCS�G���W�������ڂ���Ă���B�������A���̂S
HK1-TCS�G���W���́A�������ƂɁu������^���^���p�ԗp�X�[�p�[�N���[���f�B�[�[���G���W���̊J���v�Ƃ��Ď�����
�Z�p��̑�61�� �����ԋZ�p��܂̋Z�p�J���܁i��ҁF���� �p�����A���� �P�V���A��� �a�M���A���� �O�K
���A�� �a�F���j����܂��Ă������Ƃ��B�܂�A�SHK1-TCS�G���W���̓X�[�p�[�N���[���f�B�[�[���G���W���Ƃ��Ď���
�ԋZ�p���\������Ă����̂ł���B�Ƃ��낪�A���̂SHK1-TCS�G���W���́A�m�n���̔r�o�l�̈����������邱�Ƃ�
����đ��s�R��̌����}��G���W������v���O�����Ő��䂵�Ă������Ƃ𓌋��s���Ȋw�����������y��ʏȂ�
���H�^���ԗ��@�ᔽ�Œʕ����^�g���b�N�F�t�H�[���[�h�ɓ��ڂ���Ă����̂ł����B
�@���ɁA�����s���Ȋw��������2011�N6�����ɂSHK1-TCS�G���W���𓋍ڂ��������U�����̒��^�g���b�N�@�h�t�H��
�[�h�h�u�ԗ��^���FSKG-FRR90S2�v�̕s���ȃG���W����������Ă��Ȃ���A���̃t�H���[�h�u�ԗ��^���FSKG-
FRR90S2�v�́A���݂�������NO���𐂂ꗬ�������Ă����\�����ے�ł��Ȃ��B���̂悤�ȁu�X�[�p�[�_�[�e�B�[�G���W
���H�v�Ƃ��l������SHK1-TCS�G���W���́A2011�N5���J�Â̎����ԋZ�p��t�G���ɂ����āA�u������^���^��
�p�ԗp�X�[�p�[�N���[���f�B�[�[���G���W���̊J���v�̐��ʂƂ��āA��61�� �����ԋZ�p��܂̋Z�p�J���܂���܂�
�Ă����Ƃ́A���т��̂ł���B�ʂ����āA�����U�����Ԃ́A���̑�61�� �����ԋZ�p��܂̋Z�p�J���܂�ԏシ���
�ł��낤���B����Ƃ��A�����U�����Ԃ́A�����ɂ킽���āu������^���^���p�ԗp�X�[�p�[�N���[���f�B�[�[���G���W
���̊J���v�Ƃ��Ď����ԋZ�p��̑�61�� �����ԋZ�p��܂̋Z�p�J���܂̎�܂���Ƃ̉h�_�Ƃ��Čւ葱���Ă���
����ł��낤���B�����āA��҂̍��� �p�����A���� �P�V���A��� �a�M���A���� �O�K���A�� �a�F���́A�����
�o���E���������ɂ́u��61�� �����ԋZ�p��܂̋Z�p�J���܂̎�܁v�ƋL�ڂ����̂ł��낤���B�����āA���h�ȗ�
���K����߂Ă��鎩���ԋZ�p��́A�u������^���^���p�ԗp�X�[�p�[�N���[���f�B�[�[���G���W���̊J���v�Ƃ���
�����ԋZ�p��̑�61�� �����ԋZ�p��܂̋Z�p�J���܂ɑΏۂƂȂ����u�SHK1-TCS�G���W���v�𓋍ڂ������^�g���b
�N�F�t�H�[���[�h�i�ԗ��^��SKG-FRR90S2�j�����y��ʏȂɓ��H�^���ԗ��@�ᔽ�Œʕ�Ă��鎖��������
�����̂ł��낤���B
�[�h�h�u�ԗ��^���FSKG-FRR90S2�v�̕s���ȃG���W����������Ă��Ȃ���A���̃t�H���[�h�u�ԗ��^���FSKG-
FRR90S2�v�́A���݂�������NO���𐂂ꗬ�������Ă����\�����ے�ł��Ȃ��B���̂悤�ȁu�X�[�p�[�_�[�e�B�[�G���W
���H�v�Ƃ��l������SHK1-TCS�G���W���́A2011�N5���J�Â̎����ԋZ�p��t�G���ɂ����āA�u������^���^��
�p�ԗp�X�[�p�[�N���[���f�B�[�[���G���W���̊J���v�̐��ʂƂ��āA��61�� �����ԋZ�p��܂̋Z�p�J���܂���܂�
�Ă����Ƃ́A���т��̂ł���B�ʂ����āA�����U�����Ԃ́A���̑�61�� �����ԋZ�p��܂̋Z�p�J���܂�ԏシ���
�ł��낤���B����Ƃ��A�����U�����Ԃ́A�����ɂ킽���āu������^���^���p�ԗp�X�[�p�[�N���[���f�B�[�[���G���W
���̊J���v�Ƃ��Ď����ԋZ�p��̑�61�� �����ԋZ�p��܂̋Z�p�J���܂̎�܂���Ƃ̉h�_�Ƃ��Čւ葱���Ă���
����ł��낤���B�����āA��҂̍��� �p�����A���� �P�V���A��� �a�M���A���� �O�K���A�� �a�F���́A�����
�o���E���������ɂ́u��61�� �����ԋZ�p��܂̋Z�p�J���܂̎�܁v�ƋL�ڂ����̂ł��낤���B�����āA���h�ȗ�
���K����߂Ă��鎩���ԋZ�p��́A�u������^���^���p�ԗp�X�[�p�[�N���[���f�B�[�[���G���W���̊J���v�Ƃ���
�����ԋZ�p��̑�61�� �����ԋZ�p��܂̋Z�p�J���܂ɑΏۂƂȂ����u�SHK1-TCS�G���W���v�𓋍ڂ������^�g���b
�N�F�t�H�[���[�h�i�ԗ��^��SKG-FRR90S2�j�����y��ʏȂɓ��H�^���ԗ��@�ᔽ�Œʕ�Ă��鎖��������
�����̂ł��낤���B
�J���v�Ƒ肵�Ď����ԋZ�p��܂̋Z�p�J���܂���܂������A���̈ꃕ�����2011�N6���ɓ����s���Ȋw��������
�t�H�[���[�h�̂SHK1-TCS�G���W���ɂ�����R�����̂��߂̈�@�ȃG���W����������Ă���̂ł���B�����
��������炸�A�����ԋZ�p��́A�SHK1-TCS�G���W���ł̈�@�ȃG���W�����䂱�̂��Ƃɂ͉������y�����A2012�N1
��1���ɔ��s�́u�I�[�g�e�N�m���W�[2012�v�́u��61�� �����ԋZ�p��܂̋Z�p�J���� �J���҃C���^�r���[�W�v��
Chapter 6 �ł́A�u������^���^���p�ԗp�X�[�p�[�N���[���f�B�[�[���G���W���̊J���v�ɂ��āA��҂̍��� �p
�����A��� �a�M���A���� �O�K���A�� �a�F���@(�ʐ^�P�Q�Ɓj�̃C���^�r���[�L�����f�ڂ��Ă���̂ł���B
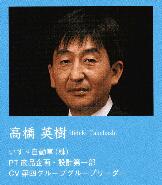 |
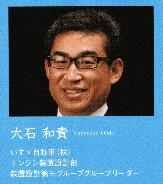 |
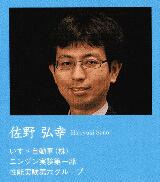 |
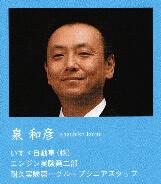 |
| |
|||
�@���̃C���^�r���[�L���̒��ł́A�SHK1-TCS�G���W�����J���������� �p�����A��� �a�M���A���� �O�K���A�� �a
�F���́A�uNO�������G�}�����Ń|�X�g�V�����K����B�������A����I�Ȓ��^�g���b�N�p�̃_�E���T�C�W���O�G���W����
���������v�ƌւ炵���ɏq�ׂĂ���B�����āA�A�SHK1-TCS�G���W���ł́A�ϑw����EGR�N�[���̗̍p��2�i�ߋ��̍�
�K�Ȑ���ɂ���āA�G���W���^�]�̈�̑S��ɂ킽����EGR�����]���ɔ�ׂĂT�`�P�O�����������邱�Ƃɂ���Ď�
���ł������Ƃ��Ί�Ō���Ă���B���̂悤�ɁA�J���҂̍��� �p�����A��� �a�M���A���� �O�K���A�� �a�F�����G��
�W�����\�̍��������M���X�ɍ��ꂵ���SHK1-TCS�G���W���́A���^�g���b�N�ɓ��ڂ���A�|�X�g�V�����r�o�K�X�K��
�ɓK�����������U�����Ԃ̒��^�g���b�N�Ƃ���2010�N5��17���ɔ������ꂽ�̂ł���B
�F���́A�uNO�������G�}�����Ń|�X�g�V�����K����B�������A����I�Ȓ��^�g���b�N�p�̃_�E���T�C�W���O�G���W����
���������v�ƌւ炵���ɏq�ׂĂ���B�����āA�A�SHK1-TCS�G���W���ł́A�ϑw����EGR�N�[���̗̍p��2�i�ߋ��̍�
�K�Ȑ���ɂ���āA�G���W���^�]�̈�̑S��ɂ킽����EGR�����]���ɔ�ׂĂT�`�P�O�����������邱�Ƃɂ���Ď�
���ł������Ƃ��Ί�Ō���Ă���B���̂悤�ɁA�J���҂̍��� �p�����A��� �a�M���A���� �O�K���A�� �a�F�����G��
�W�����\�̍��������M���X�ɍ��ꂵ���SHK1-TCS�G���W���́A���^�g���b�N�ɓ��ڂ���A�|�X�g�V�����r�o�K�X�K��
�ɓK�����������U�����Ԃ̒��^�g���b�N�Ƃ���2010�N5��17���ɔ������ꂽ�̂ł���B
�@�������A���̂SHK1-TCS�G���W���𓋍ڂ������^�g���b�N�́A���̎ԑ��̑��s��250�b���x���o�߂�����ɂ́A��
�@�ȃG���W��������s����NO���𐂂ꗬ���đ��s�R��̉��P��}���Ă����s���Ȑ���̃g���b�N�ł��邱�Ƃ������s
���\���A����23�N5���ɍ��y��ʏȂɓ��H�^���ԗ��@�ᔽ�Ƃ��Ēʕ��̂ł���B���̂悤�ɁA�����U�����Ԃ��|
�X�g�V�����r�o�K�X�K���ɓK�������SHK1-TCS�G���W���𓋍ڂ������^�g���b�N�́A2010�N5��17���̔��������1
�N���o�߂���2011�N6���ɂSHK1-TCS�G���W�������s�R��̉��P��}�邽�߂ɕs���ȃG���W��������s���Ă�����
�Ƃ��A�s�K�ɂ����ԂɘI�����Ă��܂����ƂɂȂ����B
�@�ȃG���W��������s����NO���𐂂ꗬ���đ��s�R��̉��P��}���Ă����s���Ȑ���̃g���b�N�ł��邱�Ƃ������s
���\���A����23�N5���ɍ��y��ʏȂɓ��H�^���ԗ��@�ᔽ�Ƃ��Ēʕ��̂ł���B���̂悤�ɁA�����U�����Ԃ��|
�X�g�V�����r�o�K�X�K���ɓK�������SHK1-TCS�G���W���𓋍ڂ������^�g���b�N�́A2010�N5��17���̔��������1
�N���o�߂���2011�N6���ɂSHK1-TCS�G���W�������s�R��̉��P��}�邽�߂ɕs���ȃG���W��������s���Ă�����
�Ƃ��A�s�K�ɂ����ԂɘI�����Ă��܂����ƂɂȂ����B
���̂悤�ɁA�SHK1-TCS�G���W���𓋍ڂ������^�g���b�N�́A2010�N5��17���̔��������1�N���x�����o�߂��Ă���
��2011�N6���̎��_�ŁA������������������SHK1-TCS�G���W�������s�R��̉��P��}�邽�߂ɕs���ȃG���W����
����s���Ă������Ƃ������s�ɂ���ēE������Ă���̂��B���̂��߁A�����U�����Ԃ́A2010�N5��17���̔�������
����A�s���ȃG���W������̂SHK1-TCS�G���W���𓋍ڂ������^�g���b�N��̔����Ă������̂Ɛ��������B����ɂ�
������炸�A2012�N1��1���ɔ��s�́u�I�[�g�e�N�m���W�[2012�v�́u��61�� �����ԋZ�p��܂̋Z�p�J���� �J���҃C
���^�r���[�W�v�̋L���ł́A2011�N6���ɘI�������SHK1-TCS�G���W���̕s�@�ȃG���W�������ɂ��āA�����U������
�̂SHK1-TCS�G���W�����J���҂̍��� �p�����A��� �a�M���A���� �O�K���A�� �a�F���́A���́u�C���^�r���[�v�ł�
�SHK1-TCS�G���W���ł̕s���ȃG���W������ɂ�鑖�s�R��̉��P��}���Ă��������ɂ��āA�������y���Ă��Ȃ�
�悤���B����ǂ��납�A�����C���^�r���[�W�̋L���ɂ��ƁA�uNO�������G�}�����Ń|�X�g�V�����K����B�������A���
�I�Ȓ��^�g���b�N�p�̃_�E���T�C�W���O�G���W�������������v�ƌւ炵���ɔ������Ă���̂ł���B���疳�p�Ƃ͂��̂�
���Ȃ��Ƃ��w���Ǝv�����A�@���Ȃ��̂ł��낤���B
��2011�N6���̎��_�ŁA������������������SHK1-TCS�G���W�������s�R��̉��P��}�邽�߂ɕs���ȃG���W����
����s���Ă������Ƃ������s�ɂ���ēE������Ă���̂��B���̂��߁A�����U�����Ԃ́A2010�N5��17���̔�������
����A�s���ȃG���W������̂SHK1-TCS�G���W���𓋍ڂ������^�g���b�N��̔����Ă������̂Ɛ��������B����ɂ�
������炸�A2012�N1��1���ɔ��s�́u�I�[�g�e�N�m���W�[2012�v�́u��61�� �����ԋZ�p��܂̋Z�p�J���� �J���҃C
���^�r���[�W�v�̋L���ł́A2011�N6���ɘI�������SHK1-TCS�G���W���̕s�@�ȃG���W�������ɂ��āA�����U������
�̂SHK1-TCS�G���W�����J���҂̍��� �p�����A��� �a�M���A���� �O�K���A�� �a�F���́A���́u�C���^�r���[�v�ł�
�SHK1-TCS�G���W���ł̕s���ȃG���W������ɂ�鑖�s�R��̉��P��}���Ă��������ɂ��āA�������y���Ă��Ȃ�
�悤���B����ǂ��납�A�����C���^�r���[�W�̋L���ɂ��ƁA�uNO�������G�}�����Ń|�X�g�V�����K����B�������A���
�I�Ȓ��^�g���b�N�p�̃_�E���T�C�W���O�G���W�������������v�ƌւ炵���ɔ������Ă���̂ł���B���疳�p�Ƃ͂��̂�
���Ȃ��Ƃ��w���Ǝv�����A�@���Ȃ��̂ł��낤���B
�@���ɁA�S���������SHK1-TCS�G���W�����uNO�������G�}�����Ń|�X�g�V�����K����B�������A����I�Ȓ��^�g���b�N
�p�̃_�E���T�C�W���O�G���W���v�ł���A�D�ꂽ�R��\������G���W���ł���A�����U�����Ԃ̃G���W���Z�p
�҂��r�o�K�X�ጸ���\�́u�������@�\�v������@�ȃG���W������v���O�������SHK1-TCS�G���W���ɍ̗p����K
�v�͑S���Ȃ��������Ǝv�����A�@���Ȃ��̂ł��낤���B���̂悤�ɁA��@�ȃG���W������v���O�������̗p�������
�Ȃ������SHK1-TCS�G���W�����u��61�� �����ԋZ�p��܂̋Z�p�J���܁v����܂������Ƃɂ��ẮA�M�҂ɂ͋^��
�Ɏv���Ďd���������̂ł���B
�p�̃_�E���T�C�W���O�G���W���v�ł���A�D�ꂽ�R��\������G���W���ł���A�����U�����Ԃ̃G���W���Z�p
�҂��r�o�K�X�ጸ���\�́u�������@�\�v������@�ȃG���W������v���O�������SHK1-TCS�G���W���ɍ̗p����K
�v�͑S���Ȃ��������Ǝv�����A�@���Ȃ��̂ł��낤���B���̂悤�ɁA��@�ȃG���W������v���O�������̗p�������
�Ȃ������SHK1-TCS�G���W�����u��61�� �����ԋZ�p��܂̋Z�p�J���܁v����܂������Ƃɂ��ẮA�M�҂ɂ͋^��
�Ɏv���Ďd���������̂ł���B
�@�ܘ_�A�����U�����Ԃ́A�SHK1-TCS�G���W�������ڂ��ꂽ���^�g���b�N�ł́A���̎ԑ��̑��s��250�b���x���o
�߂�����ɂ́A��@�ȃG���W��������s����NO���𐂂ꗬ���đ��s�R��̉��P��}���Ă����s���ȍs�ׂ̎��s�҂�
���̕s���Ȏd�l�̏��F�҂̎��������\�͂��Ă��Ȃ��B���������āA�SHK1-TCS�G���W���ɂ������@�ȃG���W������
�̗̍p�ɂ��NO���𐂂ꗬ�̐��m�ȓ����҂͕s���ł���B�������A�펯�I�ɍl����A���� �p�����A��� �a�M
���A���� �O�K���A�� �a�F�����J�������u������^���^���p�ԗp�X�[�p�[�N���[���f�B�[�[���G���W���v�̂SHK1-
TCS�G���W�����J�����Ĕ��������͂��P�N��Ɉ�@�ȃG���W������̕s�@�ȃG���W���Ƃ��ē����s�ɓE�����ꂽ����
�́A�u��61�� �����ԋZ�p��܂̋Z�p�J���� �v����܂������� �p�����A��� �a�M���A���� �O�K���A�� �a�F���̏�
������@�ȃG���W��������s����NO���𐂂ꗬ�������{�l�̋Z�p�҂ƍl���đ傫�ȊԈႢ���Ȃ��̂ł͂Ȃ����Ɛ�
�@�����B
�@�Ƃ���ŁA2�i�ߋ��Ɖ]���ǂ��A���C�|�[�g�̈��͂����r�C�|�[�g�̈��͂������ɂ��Ȃ���EGR���̑����͕s�\
�ł���B����A�ߋ��f�B�[�[���G���W���ł́A�����^�[�{�����̍쓮�ɂ���ă|���s���O�����̒ጸ���A�R������
�}�邽�߂ɂ́A�r�C�|�[�g�i�^�[�r�������j�̈��͂������C�|�[�g�i�^�[�{�R���v���b�T�o�����u�[�X�g�j�̈��͂���
���ƂȂ�^�]�̈�������邱�Ƃł���B���̂悤�ɁA�^�[�{�ߋ��ɂ����ẮANO���팸�ƔR����オ�������鐧
�䂪�K�v�ƂȂ�B���������āA�SHK1-TCS�G���W���ł́A�G���W���^�]�̈�ɂ킽����EGR�ʂ��T�`�P�O������
����NO�������G�}�����Ń|�X�g�V�����K����B���������Ƃ́A�Ⴂ�����Ń^�[�{�ߋ��@���쓮�����鐧���
�s�����ƂɂȂ邽�߂Ɂu�G���W���̃|���s���O�������������ăG���W���R��̈����v�������Ƌ��ɁA�u�T�`�P�O��
��EGR�ʂ̑����ɂ��p�e�B�L�����[�g�r�o�ʂ̑����ɔ���DPF���u�̋����Đ��p�x�̑���ɋN�������R
���Q��i���R����j�v�������Ă��܂������߁A�SHK1-TCS�G���W�����v���I�Ȍ��ׂ�������G���W����
�d�オ���Ă��܂����̂ł͂Ȃ����Ɛ���������B
�@���̂悤�ɁA�SHK1-TCS�G���W���ł́A�V����2�i�ߋ��̋Z�p���̗p����Ă���Ƃ͉]���A�^�[�{�̉ߋ����̐����
���EGR�ʂ��ɑ��������ă|�X�g�V�����K���i��2009�N�K���j��B���ł���悤�ɂ������ʁA�K�R�I�Ɂu�|���s��
�O�����̑����v�ƁuDPF���u�̋����Đ��p�x�̑���ɂ��R���Q��v�ɂ���ăG���W���̔R������������Ƃɂ��A
���^�g���b�N�F�t�H�[���[�h�ł͎����s�R�����Ă��܂������̂Ɛ��@�����B���݂ɁA�d�ʎԃ��[�h�R��̎����@
�ł́A�p�e�B�L�����[�g�r�o�ʂ̑����ɔ���DPF���u�̋����Đ��p�x�̑���ɂ��R���Q��i���R����j�́A�R��
�v���ł͖�������Ă��邽�߁A���^�g���b�N�F�t�H�[���[�h�̏d�ʎԃ��[�h�R��̌v���ɂ͉��̈��e�����y�ڂ��Ȃ�
�̂ł���B���̂��߁A�SHK1-TCS�G���W���𓋍ڂ����|�X�g�V�����K���K���̒��^�g���b�N�F�t�H�[���[�h�́A2015�N
�x�d�ʎԔR���ɓK�������d�ʎԃ��[�h�R��̃g���b�N�Ƃ��āA���y��ʏȂ̌^���F����邱�Ƃ��ł����悤
���B���̂��Ƃ��A�����U�����Ԃ́AEGR�ʂ��T�`�P�O����������NO�������G�}���������^�g���b�N�F�t�H�[���[�h���SHK1
-TCS�G���W�����|�X�g�V�����K���ɓK����������@���̂����v���Ɉ�ł͂Ȃ����ƍl������B
�@�����͌����Ă��A���^�g���b�N�F�t�H�[���[�h�́A�u�T�`�P�O����EGR�ʂ̑����ɂ��p�e�B�L�����[�g�r�o�ʂ̑�����
����DPF���u�̋����Đ��p�x�̑���ɋN�������R���Q��i���R����j�v�̂SHK1-TCS�G���W���𓋍ڂ��Ă��邽
�߁A�p�e�B�L�����[�g�r�o�ʂ̑����ɔ���DPF���u�̋����Đ��p�x�̑���ɂ��R���Q��i���R����j�̕s���v
�i���n���f�B�L���b�v�j���瓦��邱�Ƃ��s�\�ƍl������B�����ŁA�����U�����Ԃ��{�C�łSHK1-TCS�G���W����
�ڂ������^�g���b�N�F�t�H�[���[�h�̎����s�R������P�������̂ł���A�|�X�g�V������NO���K���ւ̓K���Z�p��
�A�fSCR�G�}���u�ɕύX���ׂ��ƍl����B�����āA�SHK1-TCS�G���W���𓋍ڂ������^�g���b�N�F�t�H�[���[�h�́A�T�`
�P�O����EGR�ʂ��������i�E�Z�p�ɂ�����|�X�g�V������NO���K���ւ̓K����}���Ă��錻������߂Ȃ���
��A�����s�R��̈����Ɖ]���n���f�B�L���b�v����J������Ȃ��̂ł͂��Ɗ����Ă���B
�@�Ƃ���ŁA�SHK1-TCS�G���W���ɍ̗p���ꂽ2�i�ߋ��́A�\�S�́u�R��팸�̂��߂̋Z�p�J���v�ɋL�ڂ����悤�ɁA��
���g���N�̌���ɂ͗L���ł��邪�A�R����P�̋@�\�����Ȃ��Z�p�ł���B���̂悤�ɁA�����A�R����P�̋@�\�̏�
�Ȃ��Q�i�ߋ����SHK1-TCS�G���W���ɍ̗p���Ă���ɂ�������炸�A�����U�����Ԃ́A����2�i�ߋ����{���̃^�[�{
���䂩���E���������ȑ��EGR�����{�����悤���B���̂��߁A�SHK1-TCS�G���W���ł́ANO�������G�}�����Ń|�X
�g�V�����K����B���ł��Ă͂��邪�A�������A�|�X�g�V�����K���ɓK���ł���G���W����������̂܂��{�����ꍇ
�ɂ́A���ۂ̎s��ł̓G���W�����R��̗���ԂŎg�p�����悤�ɂȂ邱�Ƃ͖��炩���B���̂��߁A�SHK1-TCS�G
���W���𓋍ڂ����|�X�g�V�����K���K���̒��^�g���b�N �h�t�H���[�h�h�u�ԗ��^���FSKG-FRR90S2�v���s�̂����ꍇ��
�́A�g���b�N���[�U����R����̃N���[�����E�����邱�Ƃ́A�N�ł��e�Ղɗ\�z�ł��邱�Ƃł���B
�@�����ŁA�����U�����Ԃ́A���^�g���b�N�h�t�H���[�h�u�ԗ��^���FSKG-FRR90S2�v�́A�����̓�������u�r�o�K�X�ጸ
�@�\�������đ��ʂ�NO����r�o����G���W������v���O�����v���̗p���AJE05���[�h�ʼn^�]����Ȃ��G���W���^
�]��ԂƂȂ������Ƃ����m���ꂽ���_�Łu�^�[�{�ߋ��@�����������̉^�]�v�ɐ�ւ��邱�Ƃɂ���ă^�[�r��������
�����u�[�X�g�����㏸�����ă|���s���O�����̒ጸ�i���^�[�{�ߋ��@�ɂ�鐳�̎d�������ĔR����P�j������G���W
������ɐ�ւ����悤���B�O�q�̃G���W�����䂪��ւ�����ۂ̔r�o�K�X�f�[�^�̐}12������ƁACO2�Z�x��
1100ppm����700ppm�ɑ啝�Ɍ������Ă���B����CO2�r�o�Z�x�̌����́A�����U�����Ԃ̋K���r�o�K�X�ጸ���\
�́u�������@�\�v�́u��@�ȃG���W������v�ɂ���ĔR����P�̂��߂Ƀ^�[�r���������ɑ��ău�[�X�g������������
�鐧����s���Ă��邱�Ƃ��ő�̌����Ɛ��������B���́u��@�̃G���W������v�ɂ��A�^�[�{�ߋ��@�̍쓮������
�����EGR���̑傫�Ȓቺ�i��EGR������H�j�ɂ���āA���C�ʂ��啝�ɑ��債�Ĕr�C�K�X�����߂��ACO2�r�o�Z
�x���傫�������������̂ƍl������B�|���s���O�����̒ጸ���ɂ��R����P�����A�ߋ��@�����̌���ɂ��
���C�ʂ̑���������CO2�r�o�Z�x�����������Ɖ��肵���ꍇ�ɂ́A�u��@�̃G���W������v�ɂ���ăG���W�����C��
�́A57���������������ƂɂȂ�B���̏ꍇ�A�u��@�ȃG���W������v�ɂ��57���̋��C�ʂ����債�Ă��邱�ƂɂȂ邪�A
����57���̋��C�ʂ����債�Ĕr�C�K�X����߂���Ă���ɂ�������炸�ANO���Z�x��120ppm����400ppm�ɑ�����
�����Ă���̂ł���B����57���̋��C�ʂ̑��債������̏����ɂ�����NO���Z�x��120ppm����400ppm�ɑ�������
�ꍇ��NO���r�o�d�ʂ�P���Ɍv�Z����ƁANO���r�o�ʁi�d�ʁj��5.2�{�ɑ������Ă��邱�ƂɂȂ�B
�@�����Ƃ��A�SHK1-TCS�G���W���́u��@�ȃG���W������v�ɂ���ĔR����P���}���Ă��邽�߁A���C�ʂ̑���ɂ�
��CO2�̊�߂���P���Ɍv�Z�����u��@�ȃG���W������v�ɂ��G���W�����C�ʂ̑����̊����́A57���������Ȃ�
�ƍl������B�����ŁA�SHK1-TCS�G���W���́u��@�ȃG���W������v�ɂ��R��̌���ɂ��CO�Q�팸������������
���ɂ����āANO���Z�x��120ppm����400ppm�ɑ��������ۂ�NO���r�o�̏d�ʑ�����P���Ɍv�Z�����B���̌��ʁA�M
�҂̌v�Z�ł́A�SHK1-TCS�G���W���ł́u��@�ȃG���W������v�ɂ���āA�T���̔R����P�̏ꍇ�ɂ͔r�o�K�X�K��
�ɓK�������G���W������̎������T�{��NO����r�o���A�P�O���̔R����P�̏ꍇ�ɂ�4.7�{�̑��ʂ�NO���𐂂ꗬ
���Ă������ƂɂȂ�̂ł���B�ȏ�̂��Ƃ���A�����U�����Ԃ̃G���W���Z�p�҂́A�SHK1-TCS�G���W���ɂ����āuNO��
�����G�}�����Ń|�X�g�V�����K����B�������A����I�Ȓ��^�g���b�N�p�̃_�E���T�C�W���O�G���W���͊��������v�ƍ�
�ꂵ�Ă��邪�A���ۂɂ͂��̃G���W���𓋍ڂ����s�̂̃t�H���[�h�ł́A�R����P��}�邽�߂Ɂu��@�ȃG���W����
��v�ɂ���Ĕr�o�K�X�K���K���̑��̃g���b�N����4�`5�{���x�̑��ʂ�NO����r�o���Ă������Ƃ͊m���Ȃ悤���B
�@�����āA�s�v�c�Ȃ��ƂɁA���̂悤�Ȓ��^�g���b�N�p�G���W���u�SHK1-TCS�G���W���̊J���v�ɑ��Ď����ԋZ�p�
2011�N5���Ɂu��61�� �����ԋZ�p��܂̋Z�p�܁v�����^���Ă���̂��B���̋Z�p�܂̎�܂̑ΏۂƂȂ����u�SHK1-
TCS�G���W���v�ɂ�����u��@�ȃG���W������v�̔��Љ�I�ȍs�ׂ�2011�N6���ɖ��炩�ɂȂ����ɂ�������炸�A
2012�N1��22�����݂ł́A�����ԋZ�p��́A���̎�܂̎��^�́u�������v���̏��u�����{���Ă��Ȃ��悤���B����
��A�����ԋZ�p��́A2012�N1��1���ɔ��s�́u�I�[�g�e�N�m���W�[2012�v�́u��61�� �����ԋZ�p��܂̋Z�p�J����
�J���҃C���^�r���[�W�v�ɂ����āA�u�i�SHK1-TCS�G���W�����J���������Ƃɂ��j�f�B�[�[���G���W���J���Z�p�Ƃ����_
�ʼn��Đ��̈������s�����Ǝv���܂��B�v�Ƃ̂����U�����Ԃ̃G���W���Z�p�҂̔������f�ڂ���Ă���̂ł���B��
���s���Ȋw���������E�������SHK1-TCS�G���W�����u��@�ȃG���W������v�ɂ���Ĕr�o�K�X�K���K���̃g���b�N
����4�`5�{���x�̑��ʂ�NO���𐂂ꗬ���Ă�����������A�����U�����Ԃ̓N���[���G���W���̊J���ł͖����A�_�[
�e�B�i=�����j�G���W���̋Z�p�J���ɉ��Đ��̈������s���Ă���悤�Ɍ�����̂ł���B�����āA�����U�����Ԃ̃G��
�W���Z�p�҂̐����Ƃ���́A�u��@�ȃG���W������v�������s�ɂ���Ė\�I����Ă���ɂ�������炸�A�ǐS�̙�ӂ�
������悤�ȑf�U��������A�u�f�B�[�[���G���W���J���Z�p�Ƃ����_�ʼn��Đ��̈������s�����Ǝv���܂��B�v�ƌ�����
����疳�p�̑ԓx�ɂ́A��k�Ƃ��v����悤�ȋ����ȊO�ɉ��҂ł��Ȃ��B�����āA���̔�����2012�N1��1���ɔ��s
�́u�I�[�g�e�N�m���W�[2012�v�́u��61�� �����ԋZ�p��܂̋Z�p�J���� �J���҃C���^�r���[�W�v�ɓ��X�ƌf�ڂ����
����̂ł���B����Ƃ��A�����U�����Ԃ̃G���W���Z�p�҂́A���̂悤�Ȕ������J��Ԃ��A�����āA�i���v�Вc�@�l�j��
���ԋZ�p��́A�u��@�ȃG���W������v�̔̔����т����SHK1-TCS�G���W�������Đ��̈������s�����G���W����
���ď^��������̂ł��낤���B
�@���ɁA2011�N6��3���ɓ����s�ɂ���āu��@�ȃG���W������v���\�I����Ă��܂������^�g���b�N�h�t�H���[�h�h�ɓ���
�́u�SHK1-TCS�G���W���v�ɂ��āA�i���v�Вc�@�l�j�����ԋZ�p��́u�I�[�g�e�N�m���W�[2012�v�i2012�N1��1�����s�j
�ł́A�uNO�������G�}�����Ń|�X�g�V�����K����B�������f�B�[�[���G���W���́A�����������Č}����ꂽ�̂ł���v��
�L�ڂ���Ă���A���������A�fSCR�G�}���̗p�������Ђ̋Z�p������Ă��邩�̂悤�Ȉ�ۂ�ǎ҂ɗ^����L�q��
�s���Ă���B���̂悤�Ȃ����U�����Ԃ̃f�B�[�[���G���W���̍����Z�p�͂��֎�����悤�Ȍ`�e������g���A�����U
�����Ԃ́u�L���v�܂��́u���ێ����L���v�Ƃ��v�����L���́u�I�[�g�e�N�m���W�[2012�v�s���鎩���ԋZ�p���
�́A���͂�펯�����@�����l�B���ҏW�Ɍg����Ă���悤�ɂ��������Ȃ��̂ł���B���̗l�q������ƁA�����ԋZ�p
��ł́A�u��ɒ����I�A�q�ϓI�ȗ��ꂩ�琽�ӂ������Č������e��ʂ��Љ�ɐ�������������悤�ɓw�߂܂��v��
�錾�����ϗ��K��̑��݂��Y�ꋎ���A�܂��A�ϗ��ψ���̂悤�ȑg�D�E�̐����S���@�\���Ă��Ȃ��悤�Ɏv����
���A�@���Ȃ��̂ł��낤���B���̂悤�Ȃ��Ƃł́A����܂Œz����Ă����i���v�Вc�@�l�j�����ԋZ�p��̌��ЁE�M��
�����Ȃ���̂ł͂Ȃ����낤���B�i���v�Вc�@�l�j�����ԋZ�p��̖��[�̉���̈�l�ɂ���M�҂ɂƂ��ẮA�₵
�����肾�B
�@�ȏ�̂��Ƃ́A�i���v�Вc�@�l�j�����ԋZ�p��́u�I�[�g�e�N�m���W�[2012�v�i2012�N1��1�����s�j�́u��61�� ����
�ԋZ�p��܂̋Z�p�J���� �J���҃C���^�r���[�W�v��Chapter 6 �u�u������^���^���p�ԗp�X�[�p�[�N���[���f�B�[�[
���G���W���̊J���v�ɂ����Ď�҂̍��� �p�����A��� �a�M���A���� �O�K���A�� �a�F���̃C���^�r���[�L����q
�����A��w�ɍ˂̃|���R�c���Z�p���̕M�҂��R�����m������g���Đ����������Ƃł���B���̕M�҂̐����ɂ��āA
��肪����A����Ƃ������̕M�҂�E���[���̈���ɁA���̓��e�������肢�����������B���̕M�҂̐����Ɍ�肪
����A�����ɒ����������ƍl���Ă���
�@�Ƃ���ŁA2011�N6���Ƀt�H�[���[�h�̂SHK1-TCS�G���W���ɂ�����R�����̂��߂̈�@�ȃG���W������𓌋�
�s���Ȋw���������������鎞�_�܂ł́A���̎Ԏ�̃t�H�[���[�h�̔�����ɂ́A�������H���ɘA�����s���ɂ�
�R��̈����������N�������ɍς�ł������߁A���[�U�̖������Ă������̂ƍl������B�������A�����Ԏ��
�t�H�[���[�h���G���W������́A����A��@�v���O���������R�[���Ə̂��Ė@�ߏ���̃v���O�����ɉ��C����邽�߁A
���Ă���̓t�H���[�h�̍������s���̔R��͂���܂ł�舫�����A�s��V�F�A�̒ቺ���������Ƃ͊ԈႢ�Ȃ����낤�B
�����҉邽�߂ɂ́A�����U�����Ԃ͑��}�Ƀt�H���[�h�̔R����P��}��K�v�����邱�Ƃ͖��炩���B���̔R��
���P���߁A����A�����U�����Ԃ́A���������ɎO�H�ӂ����̒��^�g���b�N�̂悤�Ƀt�H���[�h�ɁA�A�fSCR�G�}���̗p
���ĔR������P����K�v������ƍl������B�������A�����U�����ԂɂƂ��Ă̓t�H���[�h�̓��H�^���ԗ��@�ᔽ��
�̒ʕ�́A�\�z�����Ă��Ȃ������ˑR�̏o�����̂��߁A�t�H���[�h�ɔA�fSCR�G�}���̗p���鏀���͑S���ł��Ă���
�����̂Ɛ��@�����B�����s���u��@�ȃG���W������v�̓E���̌�A���ɂ����U�����Ԃ��A�fSCR�G�}���̗p�����t
�H���[�h�����}���ŊJ�������Ƃ��Ă��A�O�H�ӂ����̃t�@�C�^�[���̑��Ђ̒��^�g���b�N�Ɠ����̔R��̃t�H���[�h��
�̔����J�n�ł���̂́A�P�N���2011�N6���ȍ~�ł͂Ȃ����낤���B
�s���Ȋw���������������鎞�_�܂ł́A���̎Ԏ�̃t�H�[���[�h�̔�����ɂ́A�������H���ɘA�����s���ɂ�
�R��̈����������N�������ɍς�ł������߁A���[�U�̖������Ă������̂ƍl������B�������A�����Ԏ��
�t�H�[���[�h���G���W������́A����A��@�v���O���������R�[���Ə̂��Ė@�ߏ���̃v���O�����ɉ��C����邽�߁A
���Ă���̓t�H���[�h�̍������s���̔R��͂���܂ł�舫�����A�s��V�F�A�̒ቺ���������Ƃ͊ԈႢ�Ȃ����낤�B
�����҉邽�߂ɂ́A�����U�����Ԃ͑��}�Ƀt�H���[�h�̔R����P��}��K�v�����邱�Ƃ͖��炩���B���̔R��
���P���߁A����A�����U�����Ԃ́A���������ɎO�H�ӂ����̒��^�g���b�N�̂悤�Ƀt�H���[�h�ɁA�A�fSCR�G�}���̗p
���ĔR������P����K�v������ƍl������B�������A�����U�����ԂɂƂ��Ă̓t�H���[�h�̓��H�^���ԗ��@�ᔽ��
�̒ʕ�́A�\�z�����Ă��Ȃ������ˑR�̏o�����̂��߁A�t�H���[�h�ɔA�fSCR�G�}���̗p���鏀���͑S���ł��Ă���
�����̂Ɛ��@�����B�����s���u��@�ȃG���W������v�̓E���̌�A���ɂ����U�����Ԃ��A�fSCR�G�}���̗p�����t
�H���[�h�����}���ŊJ�������Ƃ��Ă��A�O�H�ӂ����̃t�@�C�^�[���̑��Ђ̒��^�g���b�N�Ɠ����̔R��̃t�H���[�h��
�̔����J�n�ł���̂́A�P�N���2011�N6���ȍ~�ł͂Ȃ����낤���B
�P�Q�D�u�C���x�~�v�̋Z�p�́A��^�g���b�N�̔R����팸����œK��i
�@
�P�Q�|�P�D���ߋ��K�\�����G���W���Ɖߋ��f�B�[�[���G���W���ňقȂ�C���x�~�̋@�\�E����
�@���C���G���W���̕��������ɋC���x�~����ꍇ�A�R�Ă��x�~����C���̋z�r�C�ق����z���_�����ߋ��K
�\�����G���W���ƁA�M�҂���Ă����Q��̏��^�ߋ��@�����ɔz�u�����ߋ��f�B�[�[���̋C���x�~�G���W���i������
�J2005-54771�j�ł́A�����u�C���x�~�v�Ƃ͌����Ă����҂̋C���x�~�ɂ����ʂ́A�����A�قȂ����ʂ������Ă���B
���̌����́A�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�ł��ߋ��@�G���W���ł��邱�Ƃɉ����A�R�����˗ʂ̑�����
�G���W���o�͂𐧌䂷��f�B�[�[���G���W���ł���̂ɑ��A�z���_�̋C���x�~�G���W���ł͖��ߋ��G���W���ł���
���Ƃɉ����A���_��R��ߖT�̔R�������C�їʂ̑����ɂ���ăG���W���o�͂𐧌䂷��K�\�����G���W���ł��邽��
���B�ȉ��Ƀz���_�̖��ߋ��̋C���x�~�K�\�����G���W���ƕM�Ғ�Ẳߋ��̋C���x�~�f�B�[�[���G���W���i������
�J2005-54771�j�ɂ��āA�C���x�~�̌��ʂ̗��R�Ƃ��̍������ȒP�ɂ܂Ƃ߂��B
�\�����G���W���ƁA�M�҂���Ă����Q��̏��^�ߋ��@�����ɔz�u�����ߋ��f�B�[�[���̋C���x�~�G���W���i������
�J2005-54771�j�ł́A�����u�C���x�~�v�Ƃ͌����Ă����҂̋C���x�~�ɂ����ʂ́A�����A�قȂ����ʂ������Ă���B
���̌����́A�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�ł��ߋ��@�G���W���ł��邱�Ƃɉ����A�R�����˗ʂ̑�����
�G���W���o�͂𐧌䂷��f�B�[�[���G���W���ł���̂ɑ��A�z���_�̋C���x�~�G���W���ł͖��ߋ��G���W���ł���
���Ƃɉ����A���_��R��ߖT�̔R�������C�їʂ̑����ɂ���ăG���W���o�͂𐧌䂷��K�\�����G���W���ł��邽��
���B�ȉ��Ƀz���_�̖��ߋ��̋C���x�~�K�\�����G���W���ƕM�Ғ�Ẳߋ��̋C���x�~�f�B�[�[���G���W���i������
�J2005-54771�j�ɂ��āA�C���x�~�̌��ʂ̗��R�Ƃ��̍������ȒP�ɂ܂Ƃ߂��B
�iA)�@�z���_�̖��ߋ��K�\�����G���W���ɂ����ċC���x�~�ɂ��R��팸�ł��闝�R
�@�C���x�~����U�C���̃z���_�̖��ߋ��K�\�����G���W���̕��������ɂ����āA�R�C�����z�r�C����ُ�Ԃ�
���ē��Y�̂R�C�����x�~������C���x�~�^�]���s�����ꍇ�ɂ́A�啝�ȃG���W���R������P���\�ƂȂ�B���̋C
���x�~�^�]�ɂ�����R�����P�̗��R��\�P�T�ɂ܂Ƃ߂��B�Ȃ��A�z���_�́A���N�O���炱�̋C���x�~�K�\�����G���W
�����s�̎Ԃɍ̗p����A��p�Ԃ⏬�^�g���b�N�̔R��팸��}���Ă���Ƃ̂��Ƃł���B
���ē��Y�̂R�C�����x�~������C���x�~�^�]���s�����ꍇ�ɂ́A�啝�ȃG���W���R������P���\�ƂȂ�B���̋C
���x�~�^�]�ɂ�����R�����P�̗��R��\�P�T�ɂ܂Ƃ߂��B�Ȃ��A�z���_�́A���N�O���炱�̋C���x�~�K�\�����G���W
�����s�̎Ԃɍ̗p����A��p�Ԃ⏬�^�g���b�N�̔R��팸��}���Ă���Ƃ̂��Ƃł���B
| |
|
|
| |
|
|
| |
�x�~�C���̃|���s���O�����̍팸 | �@�R�Ă��x�~����C���ŏ�ɋz�r�C�ق���邱�Ƃɂ��A����
�C���͋z�r�C�ق̍쓮���~���A�|���s���O�������Ƃ���B |
| �x�~�C���̋z�r�C�ق̋쓮������ጸ | �@�x�~�C���̋z�r�C�ق̊J���~���邽�߁A�z�r�C�ق��쓮
���铮�͂��قƂ�Ǐ���Ȃ����߁A�x�~�C���̋z�r�C�ق̋� ��������ጸ����B�B |
|
| �R�ċC���̃|���s���O�����̍팸 | �@�R�ċC���̃X���b�g�����J���C���ɂȂ�A�R�ċC���̋z�C��R
�����Ȃ��Ȃ�A�R�ċC���̋z�C�̃|���s���O�������ጸ����B |
|
| �R�ċC���̗�p�����̍팸 | �@�U�C���G���W���̕��������ɂ����āA�R�C��������R�Ă���
���ꍇ�́A�S�C����R�Ă������ꍇ�ɔ�ׁA�����R��������� �G���W���ł̗�p�ʐς������ƂȂ�B���̂��߁A�ꕔ���C���x�~ �^�]�������̔R�ċC���ł̗�p�����͔����ł��邽�߁A�]���G ���W�������啝�ɍ팸�ł��邱�ƂɂȂ�B |
|
| �R�ċC���̃T�C�N�������̌��� | �@�U�C���G���W���̕��������ɂ����āA�R�C��������R�Ă���
���C���x�~�G���W���̔R�ċC���̍ō����́E�ō����x�́A�S�C ����R�Ă������]���G���W���̍ō����́E�ō����x�����ɍ��� �Ȃ�B���̋C���x�~�G���W���̕��������ɂ�����R�ċC���� �����ō����́E�ō����x�́A�K�R�I�ɍ����T�C�N������������ ��邱�ƂɂȂ�B �@���̌��ʁA�C���x�~�G���W���̕��������ɂ����ẮA�]���G ���W�������啝�ɍ팸�ł��邱�ƂɂȂ�B |
|
�@�����K�\�����G���W���̋C���x�~�́A�\�P�T�Ɏ������悤�ɁA�G���W���̕������^�]�ɂ�����R����P��
�B��̌��ʁE�����b�g�ł��邪�A���̔R����P�̌��ʂ��R�O�����x�i��q�̐}�P�R�Q�Ɓj�ɂ��B����ꍇ������
�قǁA�����Ԃ̑��s�R��̌���ɋɂ߂ėL���ȋZ�p�ł��邱�Ƃ������ł���B
�B��̌��ʁE�����b�g�ł��邪�A���̔R����P�̌��ʂ��R�O�����x�i��q�̐}�P�R�Q�Ɓj�ɂ��B����ꍇ������
�قǁA�����Ԃ̑��s�R��̌���ɋɂ߂ėL���ȋZ�p�ł��邱�Ƃ������ł���B
�iB)�@�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�ɂ�����ߋ��f�B�[�[���̔R���NO�����팸�ł��闝�R
�@�M�҂���Ă��Ă����Q��̃^�[�{�ߋ��@�����ɑ�������Q�^�[�{�������ߋ��f�B�[�[�����C���x�~�G���W���i��
�����J2005-54771�j�ɂ����āA�Ⴆ���U�C�����f�B�[�[���G ���W���̕��������ɂ����āA�R�C�����x�~�C���Ƃ���
�c��̂R�C����R�ċC���Ƃ��ĉ^�]���s�����ꍇ�ɂ́A�啝�ȃG���W���R������P��NO���̍팸���\�ƂȂ�B����
�C���Q����ɂ��C���x�~�^�]�ł̔R�����P��NO���팸�̗��R���A�\�P�U�ɂ܂Ƃ߂��B
�����J2005-54771�j�ɂ����āA�Ⴆ���U�C�����f�B�[�[���G ���W���̕��������ɂ����āA�R�C�����x�~�C���Ƃ���
�c��̂R�C����R�ċC���Ƃ��ĉ^�]���s�����ꍇ�ɂ́A�啝�ȃG���W���R������P��NO���̍팸���\�ƂȂ�B����
�C���Q����ɂ��C���x�~�^�]�ł̔R�����P��NO���팸�̗��R���A�\�P�U�ɂ܂Ƃ߂��B
| |
|
|
| |
|
|
| |
�R�ċC���̃|���s���O�����̍팸 | �@�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j���U�C���f�B�[�[���G ���W��
�ł́A�R�C���ɂP������^�ߋ��@�����A����ɔz�u�����Q��̏��^�� ���@���ɂQ�̋C���Q�ɕ������A�Q�̋C���Q��Ɨ����ĕ��ׂ𐧌䂷�� �\���ł���B�����āA���������ɂ����āA����̋C���Q�i�R�C���j��R�� �C���Ƃ��ĉ^�]���A�����̋C���Q�i�R�C���j���x�~�C���Ƃ��ĉ^�]����B���� ���A�R�ċC���Ƃ��ĉ^�]����C���Q�i�R�C���j�ɂ͂R�C���̉ߋ��ɍœK�ȗe �ʂ̏��^�ߋ��@�����Ă���̂ŁA����̋C���Q�i�R�C���j���x�~�C���� ���ĉ^�]�����ۂ̔R�ċC���Ƃ��ĉ^�]����C���Q�i�R�C���j�̏��^�ߋ��@ �̉ߋ��@�����́A1��̑�^�ߋ��@�������]���̂U�C���G���W���̉� ���@�����������������ʼn^�]�ł��邽�߁A�|���s���O�������啝�ɍ팸 �ł��邱�Ƃł���B �i�֘A�y�[�W�F�C���x�~�́A�R��팸�ƔA�fSCR��NO���팸���̌���ɗL �����I�Q�Ɓj |
| �R�ċC���̗�p�����̍팸 | �@�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j���U�C���f�B�[�[���G ���W��
�ł́A���������ɂ����āA����̋C���Q�i�R�C���j��R�ċC���Ƃ��ĉ^�] ���A�����̋C���Q�i�R�C���j���x�~�C���Ƃ��ĉ^�]����B�R�ĉ^�]�������C ���Q�i�R�C���j�ɂ����鋟���R��������̃G���W���ł̗�p�ʐς́A�S�C ����R�Ă�����]���G���W���ɂ����鋟���R��������̃G���W���ł̗�p �ʐς̔����ɏk���ł��邱�ƂɂȂ�B���̂��߁A�Ј���̋C���Q���x�~�^ �]�������ɂ́A�R�ĉ^�]���������̋C���Q�ł̗�p�����������ł��邽 �߁A�]���G���W�������啝�ɍ팸�ł��邱�Ƃł���B �i�֘A�y�[�W�F�C���x�~�́A�R��팸�ƔA�fSCR��NO���팸���̌���ɗL �����I�Q�Ɓj |
|
| �R�ċC���̃T�C�N�������̌��� | �@�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j���U�C���f�B�[�[���G ���W��
�ł́A���������ɂ����āA����̋C���Q�i�R�C���j��R�ċC���Ƃ��ĉ^�] ���A�����̋C���Q�i�R�C���j���x�~�C���Ƃ��ĉ^�]����B�R�ĉ^�]�������C ���Q�i�R�C���j�̊e�C���̍ō����́E�ō����x�́A�S�C����R�Ă�����] ���G���W���ɂ�����e�C���̍ō����́E�ō����x�������ł��邱�ƂɂȂ�B ���̋C���x�~�G���W���̕��������ɂ�����R�ĉ^�]����C���Q�̍��� �ō����́E�ō����x�́A�K�R�I�ɍ����T�C�N�������������邱�ƂɂȂ�B �@���̋C���x�~�G���W���̕��������ɂ�����R�ĉ^�]�̋C���Q�ł̍� �����́E�ō����x�̏㏸�̓T�C�N�����������シ�邽�߁A�C���x�~�G���W ���i�������J2005-54771�j���]���G���W�������啝�ɔR����팸�ł��� ���Ƃł���B �i�֘A�y�[�W�F�C���x�~�́A�R��팸�ƔA�fSCR��NO���팸���̌���ɗL �����I�Q�Ɓj |
|
| �R�ċC���̔r�C�����̍팸 | �@�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j���U�C���f�B�[�[���G ���W��
�ł́A���������ɂ����āA����̋C���Q�i�R�C���j��R�ċC���Ƃ��ĉ^�]
���A�����̋C���Q�i�R�C���j���x�~�C���Ƃ��ĉ^�]����B�R�ĉ^�]�������C
���Q�i�R�C���j�̊e�C���̔R�Ăɏ���鋋�C�ʂ́A�S�C����R�Ă�����
�]���G���W���ɂ�����e�C���̔R�Ăɏ���鋋�C�ʂ̂P�^�Q�ƂȂ邽
�߁A�r�C���������邱�Ƃ��\�ƂȂ�B
�i�֘A�y�[�W�F�C���x�~�́A�R��팸�ƔA�fSCR��NO���팸���̌���ɗL �����I�Q�Ɓj |
|
| DPF�ł̃t�B���^�̎��ȍĐ��̑��i | �C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j���U�C���f�B�[�[���G ���W����
�́A���������ɂ����āA����̋C���Q�i�R�C���j��R�ċC���Ƃ��ĉ^�] ���A�����̋C���Q�i�R�C���j���x�~�C���Ƃ��ĉ^�]����B�R�ĉ^�]�������C ���Q�i�R�C���j�̊e�C���̔r�C�K�X���x�́A�S�C����R�Ă�����]���G�� �W���ɂ�����e�C���̔r�C�K�X���x���������ł��邱�ƂɂȂ�B���̋C�� �x�~�G���W���̕��������ɂ�����R�ĉ^�]�̋C���Q�ł̍����r�C�K�X ���x�́A�R�ĉ^�]����C���Q��DPF���u�̃t�B���^�ɑ͐ς����p�e�B�L���� �[�g�̔R�Ă��\�ɂ��邽�߁ADPF���u�̎��ȍĐ������i����邱�Ƃɂ� ��B�����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�ɂ�����DPF���u�̎� �ȍĐ��̑��i�́A�]���G���W���ɂ�����DPF���u�̎蓮�Đ��Ƌ����Đ� �̕p�x���팸���\�ƂȂ�B �@���̂悤�ɁA�C���x�~�G���W���́A�]���G���W������DPF���u�̎蓮�� ���Ƌ����Đ��̕p�x���啝�ɍ팸�ł��邽�߁A�R��팸�ł��邱�Ƃł� ��B �i�֘A�y�[�W�F�R����̃|�X�g���˂��~�߁A�C���x�~��DPF���Đ�����V �Z�p�Q�Ɓj |
|
| �f�B�[�[���G���W���̔r�C�K�X�G�l
���M�[�����鑕�u�E�Z�p�̌��� �̌��� �i�r�C�K�X�G�l���M�[�����鑕 �u�E�Z�p���u���J�j�J���^�[�{�R���p�E ���h�v�A�u�G���N�g���b�N�^�[�{�R���p�E ���h�v�A�u�����L���T�C�N���v�A�u�M�d�f �q�v����сu�X�^�[�����O�G���W���v ���j |
��^�g���b�N�̎��ۂ̑��s�R��i�������s�R��j�̏\���Ȍ����}�肽��
�̂ł���A�G���W���̍ő�g���N�̃G���W����]���x�̈�ł̕�������
�̉^�]�̈�ɂ�����R������シ�邱�Ƃ��̗v�ł���B�C���x�~�G���W��
�i�������J2005-54771�j�̋Z�p�́A�G���W���������ׂ̉^�]�̈�̔r�C
�K�X�̔M�G�l���M�[�E���̓G�l���M�[�����߂邱�Ƃ��ł��邽�߁A���̋C��
�x�~�̋Z�p���f�B�[�[���G���W���̔r�C�K�X�̔M�G�l���M�[�E���̓G�l��
�M�[����]���͂�d�C�G�l���M�[�ɉ��鑕�u�E�Z�p�i���u���J�j�J���^
�[�{�R���p�E���h�v�A�u�G���N�g���b�N�^�[�{�R���p�E���h�v�A�u�����L���T�C�N
���v�A�u�M�d�f�q�v����сu�X�^�[�����O�G���W���v���j�Ƒg���킹�邱�Ƃɂ��
�āA��^�g���b�N�����ۂ̑��s�R��i�������s�R��j�̏\���Ȍ��オ����
�Ď����ł���̂ł���B
�i�֘A�y�[�W�F�C���x�~�́A�f�B�[�[���r�C�K�X�̃G�l���M�[���u�� �����������Q�Ɓj |
|
| |
�A�fSCR�G�}�ł�NO���팸�̑��i | �@�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j���U�C���f�B�[�[���G ���W��
�ł́A���������ɂ����āA����̋C���Q�i�R�C���j��R�ċC���Ƃ��ĉ^�] ���A�����̋C���Q�i�R�C���j���x�~�C���Ƃ��ĉ^�]����B�R�ĉ^�]�������C ���Q�i�R�C���j�̊e�C���̔r�C�K�X���x�́A�S�C����R�Ă�����]���G�� �W���ɂ�����e�C���̔r�C�K�X���x���������ł��邱�ƂɂȂ�B �@���̋C���x�~�G���W���̕��������ɂ�����R�ĉ^�]�̋C���Q�ł̍� ���r�C�K�X���x�́A�R�ĉ^�]����C���Q�̔A�fSCR�G�}�ł̍���NO���� �������ێ����邱�Ƃ��\�ƂȂ�B�����C���x�~�G���W���i�������J2005- 54771�j�ɂ������A�fSCR�G�}�ł̍���NO���팸���̈ێ��́A�]���G���W �������啝��NO�����팸�ł��邱�Ƃł���B �i�֘A�y�[�W�F�C���x�~�́A�f�B�[�[���̂m�n���팸�ƔR�����̈ꋓ���� �̋Z�p���I���Q�ƕ��j |
�@��^�g���b�N�̎��ۂ̑��s�R��i�������s�R��j�̏\���Ȍ����}�肽���̂ł���A�G���W���̍ő�g���N�̃G��
�W����]���x�̈�ł̕������ׂ̉^�]�̈�ɂ�����R������シ�邱�Ƃ��̗v�ł���B���ɁA���̃G���W��������
�ׂ̉^�]�̈���r�C�K�X�̔M�G�l���M�[�E���̓G�l���M�[�����߂邱�Ƃ��Z�p�Ă��ɉ\�ɂȂ�A�f�B�[�[���G
���W���̔r�C�K�X�̔M�G�l���M�[�E���̓G�l���M�[����]���͂�d�C�G�l���M�[�ɉ��鑕�u�E�Z�p�i���u���J�j
�J���^�[�{�R���p�E���h�v�A�u�G���N�g���b�N�^�[�{�R���p�E���h�v�A�u�����L���T�C�N���v�A�u�M�d�f�q�v����сu�X�^�[�����O
�G���W���v���j���^�g���b�N�p�G���W���ɍ̗p���邱�Ƃɂ���āA��^�g���b�N�����ۂ̑��s�R��i�������s�R��j��
�\���Ȍ��オ���߂Ď����ł���̂ł���B
�W����]���x�̈�ł̕������ׂ̉^�]�̈�ɂ�����R������シ�邱�Ƃ��̗v�ł���B���ɁA���̃G���W��������
�ׂ̉^�]�̈���r�C�K�X�̔M�G�l���M�[�E���̓G�l���M�[�����߂邱�Ƃ��Z�p�Ă��ɉ\�ɂȂ�A�f�B�[�[���G
���W���̔r�C�K�X�̔M�G�l���M�[�E���̓G�l���M�[����]���͂�d�C�G�l���M�[�ɉ��鑕�u�E�Z�p�i���u���J�j
�J���^�[�{�R���p�E���h�v�A�u�G���N�g���b�N�^�[�{�R���p�E���h�v�A�u�����L���T�C�N���v�A�u�M�d�f�q�v����сu�X�^�[�����O
�G���W���v���j���^�g���b�N�p�G���W���ɍ̗p���邱�Ƃɂ���āA��^�g���b�N�����ۂ̑��s�R��i�������s�R��j��
�\���Ȍ��オ���߂Ď����ł���̂ł���B
�@�C���x�~�V�X�e���́A�|���v�����̑傫���K�\�����G���W���̕������ׂő傫�ȔR����P�����҂ł���Z�p�ł�
�邪�A�������ׂł̃|���v��������r�I���Ȃ��f�B�[�[���G���W���ɂ����Ă������̔R����P���\�ɂ���Z�p��
����B�����āA�C���x�~�V�X�e���́A�K�\�����G���W���ł͔R����P�̌��ʂ��������ł��Ȃ����A�f�B�[�[���G���W��
�ł́A�\�P�U�Ɏ������悤�ɁA�u�A�fSCR�G�}�̊������i�ɂ��NO���̑啝�ȍ팸�v��uDPF�ł̃t�B���^�̎��ȍĐ�
�̑��i�v���\�ɂ���Z�p�ł���B���ɁA�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p�́A�u�G���W����������
���̔R�����v�A�u�A�fSCR�G�}�̊������i�ɂ��NO���̑啝�ȍ팸�v�A�uDPF�ł̃t�B���^�̎��ȍĐ��̑��i�v����
���u�f�B�[�[���G���W���̔r�C�K�X�G�l���M�[�����鑕�u�E�Z�p�̌����̌����v���\�ɂ���@�\������B����
���߁A�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p�́A���݂̑�^�f�B�[�[���g���b�N�́uNO���̍팸�v�Ɓu���s
�R�����v����сuDPF�Đ��ɂ�����R���Q��̍팸�v�ɍv���ł���Z�p�ł��邱�Ƃ́A�ԈႢ�Ȃ����낤�B
�邪�A�������ׂł̃|���v��������r�I���Ȃ��f�B�[�[���G���W���ɂ����Ă������̔R����P���\�ɂ���Z�p��
����B�����āA�C���x�~�V�X�e���́A�K�\�����G���W���ł͔R����P�̌��ʂ��������ł��Ȃ����A�f�B�[�[���G���W��
�ł́A�\�P�U�Ɏ������悤�ɁA�u�A�fSCR�G�}�̊������i�ɂ��NO���̑啝�ȍ팸�v��uDPF�ł̃t�B���^�̎��ȍĐ�
�̑��i�v���\�ɂ���Z�p�ł���B���ɁA�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p�́A�u�G���W����������
���̔R�����v�A�u�A�fSCR�G�}�̊������i�ɂ��NO���̑啝�ȍ팸�v�A�uDPF�ł̃t�B���^�̎��ȍĐ��̑��i�v����
���u�f�B�[�[���G���W���̔r�C�K�X�G�l���M�[�����鑕�u�E�Z�p�̌����̌����v���\�ɂ���@�\������B����
���߁A�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p�́A���݂̑�^�f�B�[�[���g���b�N�́uNO���̍팸�v�Ɓu���s
�R�����v����сuDPF�Đ��ɂ�����R���Q��̍팸�v�ɍv���ł���Z�p�ł��邱�Ƃ́A�ԈႢ�Ȃ����낤�B
�@���̂悤�ɁA�K�\�����G���W���ɂ�����C���x�~�́A�P�ɑ啝�ȃG���W���R������P�ł��邾���̋Z�p�ɉ߂��Ȃ��B
�����āA���̃K�\�����G���W���ɍ̗p����Ă���u�x�~�C�����ɂ͋z�C�قƔr�C�ق̗����܂��͋z�C�ق�ٕ̏��
�Ɉێ���������̋C���x�~�̋Z�p�v�́A�ߋ��G���W���̑�^�g���b�N�ɂ��̂܂ܓK�p���Ă��A��^�g���b�N�ɂ�����\
���ȔR����P�������ł���@�\���傫����邱�Ƃɗ��ӂ��ׂ��ł���B���������āA�C���x�~�ɂ���ĉߋ��f�B�[�[
���G���W���̑�^�g���b�N�̔R����\���ɉ��P���邽�߂ɂ́A���ߋ��K�\�����G���W���ɍ̗p����Ă���x�~�C����
�̋z�C�قƔr�C�ق̗����܂��͋z�C�ق�����ٕ̏�ԂɈێ�����������^�g���b�N�̉ߋ��f�B�[�[���G���W��
�̋C���x�~�Z�p�Ƃ��ėp���邱�Ƃ͋��̍����ł��邱�Ƃ��̂ɖ�����ׂ��ł���B���̗��R���C���x�~�́A�f�B�[�[
���̂m�n���팸�ƔR�����̈ꋓ�����̋Z�p���I������C���x�~�́A�f�B�[�[���r�C�K�X�̃G�l���M�[���u��
�����������̃y�[�W�ɏڏq���Ă���̂ŁA�����ł͐������ȗ�����B
�����āA���̃K�\�����G���W���ɍ̗p����Ă���u�x�~�C�����ɂ͋z�C�قƔr�C�ق̗����܂��͋z�C�ق�ٕ̏��
�Ɉێ���������̋C���x�~�̋Z�p�v�́A�ߋ��G���W���̑�^�g���b�N�ɂ��̂܂ܓK�p���Ă��A��^�g���b�N�ɂ�����\
���ȔR����P�������ł���@�\���傫����邱�Ƃɗ��ӂ��ׂ��ł���B���������āA�C���x�~�ɂ���ĉߋ��f�B�[�[
���G���W���̑�^�g���b�N�̔R����\���ɉ��P���邽�߂ɂ́A���ߋ��K�\�����G���W���ɍ̗p����Ă���x�~�C����
�̋z�C�قƔr�C�ق̗����܂��͋z�C�ق�����ٕ̏�ԂɈێ�����������^�g���b�N�̉ߋ��f�B�[�[���G���W��
�̋C���x�~�Z�p�Ƃ��ėp���邱�Ƃ͋��̍����ł��邱�Ƃ��̂ɖ�����ׂ��ł���B���̗��R���C���x�~�́A�f�B�[�[
���̂m�n���팸�ƔR�����̈ꋓ�����̋Z�p���I������C���x�~�́A�f�B�[�[���r�C�K�X�̃G�l���M�[���u��
�����������̃y�[�W�ɏڏq���Ă���̂ŁA�����ł͐������ȗ�����B
�@���͂Ƃ�����A���ߋ��K�\�����G���W���ɍ̗p����Ă���x�~����C���̋z�C�ق܂��͔r�C�ق̕��@�A�Ⴕ
���͋z�C�قƔr�C�ق̗�����ٕɐ��䂷��C���x�~�V�X�e���Ƃ͈قȂ�A�V�����Q�^�[�{�������C���x�~
�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p�i�}�P������\�P�U�Q�Ɓj���^�g���b�N�̔R�����̎�i�Ƃ����M��
����Ă��Ă���̂ł���B���̂Q��̃^�[�{�ߋ��@�����ɑ�������Q�^�[�{�������ߋ��f�B�[�[�����C��
�x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�́A��^�g���b�N�̏\���ȁu�R����P�v����ł͂Ȃ��A�����ɁuNO����
���v�Ɓu�c�o�e�̍Đ����i�v�������ł����D�ꂽ�Z�p�ł��邱�Ƃ��������Ă��������B
���͋z�C�قƔr�C�ق̗�����ٕɐ��䂷��C���x�~�V�X�e���Ƃ͈قȂ�A�V�����Q�^�[�{�������C���x�~
�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p�i�}�P������\�P�U�Q�Ɓj���^�g���b�N�̔R�����̎�i�Ƃ����M��
����Ă��Ă���̂ł���B���̂Q��̃^�[�{�ߋ��@�����ɑ�������Q�^�[�{�������ߋ��f�B�[�[�����C��
�x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�́A��^�g���b�N�̏\���ȁu�R����P�v����ł͂Ȃ��A�����ɁuNO����
���v�Ɓu�c�o�e�̍Đ����i�v�������ł����D�ꂽ�Z�p�ł��邱�Ƃ��������Ă��������B
�@�M�҂́A���̃z�[���y�[�W��2006�N4���ɊJ�݂��A���̋C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j����^�f�B�[�[��
�g���b�N�ɍ̗p���邱���ɂ����NO���ƔR����ɍ팸�ł��邱�Ƃ�i���Ă���B����ɂ�������炸�A�����Ƀg���b
�N���[�J�̐��Ƃ́A��Ȃ��C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p�����Ă���̂��B�����āA�\�P�S��
�������悤�ɁA�����̃g���b�N���[�J�ł́A�|�X�g�V�����r�o�K�X�K���i�Q�O�O�X�N�K���j�ɓK��������^�g���b�N�E�g���N�^
�̒��łQ�O�P�T�N�x�d�ʎԔR���ɕs�K���̑����̎Ԏ������Ă���̂ł���B�������g���b�N���[�J�ł́A�f�B�[
�[���G���W���Ɋւ���R����P�̋Z�p�͕s����I�悵�Ă���s���_�ȏ�Ԃ��A�����܂ŕ��u��������̂ł��낤
���B
�g���b�N�ɍ̗p���邱���ɂ����NO���ƔR����ɍ팸�ł��邱�Ƃ�i���Ă���B����ɂ�������炸�A�����Ƀg���b
�N���[�J�̐��Ƃ́A��Ȃ��C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p�����Ă���̂��B�����āA�\�P�S��
�������悤�ɁA�����̃g���b�N���[�J�ł́A�|�X�g�V�����r�o�K�X�K���i�Q�O�O�X�N�K���j�ɓK��������^�g���b�N�E�g���N�^
�̒��łQ�O�P�T�N�x�d�ʎԔR���ɕs�K���̑����̎Ԏ������Ă���̂ł���B�������g���b�N���[�J�ł́A�f�B�[
�[���G���W���Ɋւ���R����P�̋Z�p�͕s����I�悵�Ă���s���_�ȏ�Ԃ��A�����܂ŕ��u��������̂ł��낤
���B
�@���݁A�K�\������p�Ԃ̐��E�ł́A�z���_�AGM����уN���C�X���[���C���x�~�G���W�����̗p�����ʏ�̃K�\����
��p�Ԃ̎Ԏ�������A�R��̌����}���Ă��鎞��ł���B����A�킪���̑����̑�^�g���b�N���[�J�ł́A�O
�q�̕\�P�S�Ɏ������悤�ɁA�|�X�g�V�����r�o�K�X�K���i�Q�O�O�X�N�K���j�ɓK���̑�^�g���b�N�E�g���N�^���Q�O�P�T�N�x
�d�ʎԔR���ɖ��B���̑����̎Ԏ������Ă���̂ł���B���̂��Ƃ́A��^�g���b�N���[�J�ɂ����āA�����ɗL
���ȔR��팸�̋Z�p���J���ł��Ă��Ȃ����Ƃ������؋��ł͂Ȃ����낤���B����ɂ�������炸�A�����̑�^�g��
�b�N���[�J�́A�R����P�ɗL�����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p��َE���Ă���̂ł���B���̂悤
�ɁA�Q�O�P�T�N�x�d�ʎԔR���ɖ��B���̎Ԏ�𐔑��������Ă���g���b�N���[�J���A�u�R�����P�Ɠ�����NO���팸
���\���C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p�v�����Ă���̂ł���B��^�g���b�N���[�J�̋Z�p�n��
�����́A��́A�����l���Ă���̂ł��낤���B�M�҂ɂ͑S�������ł��Ȃ����Ƃł���B
��p�Ԃ̎Ԏ�������A�R��̌����}���Ă��鎞��ł���B����A�킪���̑����̑�^�g���b�N���[�J�ł́A�O
�q�̕\�P�S�Ɏ������悤�ɁA�|�X�g�V�����r�o�K�X�K���i�Q�O�O�X�N�K���j�ɓK���̑�^�g���b�N�E�g���N�^���Q�O�P�T�N�x
�d�ʎԔR���ɖ��B���̑����̎Ԏ������Ă���̂ł���B���̂��Ƃ́A��^�g���b�N���[�J�ɂ����āA�����ɗL
���ȔR��팸�̋Z�p���J���ł��Ă��Ȃ����Ƃ������؋��ł͂Ȃ����낤���B����ɂ�������炸�A�����̑�^�g��
�b�N���[�J�́A�R����P�ɗL�����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p��َE���Ă���̂ł���B���̂悤
�ɁA�Q�O�P�T�N�x�d�ʎԔR���ɖ��B���̎Ԏ�𐔑��������Ă���g���b�N���[�J���A�u�R�����P�Ɠ�����NO���팸
���\���C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p�v�����Ă���̂ł���B��^�g���b�N���[�J�̋Z�p�n��
�����́A��́A�����l���Ă���̂ł��낤���B�M�҂ɂ͑S�������ł��Ȃ����Ƃł���B
�@���݂ɁA�f�B�[�[���G���W���̋C���x�~�ɂ��ẮA2007�N�Ɏ����ԋZ�p���o�ł��ꂽ�u�����ԎY�ƋZ�p��
���ƋZ�p���W�E�R���V�i���I�@2030�N�����Ԃ͂����Ȃ�@��3���@���{�ɂ����鎩���ԔR���̃V�i���I�i�艿�F6300
�~�j�v�́u3 �����̎����ԗp���̓V�X�e���̔R�����Z�p�v�̍��ɂ́A�w�E�E�E�E�E�σo���u�^�C�~���O�ɂ��A��������
���Ɉꕔ�̋C���̃o���u��ق��邱�Ƃɂ��C���x�~�����{�ł���B�C���x�~�V�X�e���̓f�B�[�[���G���W���ł�
�L���ł��邪�A�������ׂŃ|���v�����̑傫���K�\�����G���W���̕����傫�ȁi�R��́j���P���ʂ����҂ł�
��B�E�E�E�E�E�x�ƋL�ڂ���Ă���B���̋L�q���e�́A�C���x�~�̔R����P�̈�ʂ���������A���_�ł���A�Ԉ���Ă�
����̂ł͂Ȃ��B�������A���O�Ƀf�B�[�[���G���W���ł͋C���x�~�ɂ��R����P�͋͂��ł��邽�߁A�f�B�[�[���G
���W���ɋC���x�~�ɂ��R����P�́A�n���ȃG���W���Z�p�҂̂��邱�Ƃ̂悤�Ȉ�ۂ�ǎ҂ɗ^���鏑�����ł���B
�{���ɁA�C���x�~�ɂ���ăf�B�[�[���G���W���̔R����P�́A�n���ȋZ�p�J���̂悤�ɂ́A�M�҂ɂ͂ƂĂ��v���Ȃ�
�̂ł���B
���ƋZ�p���W�E�R���V�i���I�@2030�N�����Ԃ͂����Ȃ�@��3���@���{�ɂ����鎩���ԔR���̃V�i���I�i�艿�F6300
�~�j�v�́u3 �����̎����ԗp���̓V�X�e���̔R�����Z�p�v�̍��ɂ́A�w�E�E�E�E�E�σo���u�^�C�~���O�ɂ��A��������
���Ɉꕔ�̋C���̃o���u��ق��邱�Ƃɂ��C���x�~�����{�ł���B�C���x�~�V�X�e���̓f�B�[�[���G���W���ł�
�L���ł��邪�A�������ׂŃ|���v�����̑傫���K�\�����G���W���̕����傫�ȁi�R��́j���P���ʂ����҂ł�
��B�E�E�E�E�E�x�ƋL�ڂ���Ă���B���̋L�q���e�́A�C���x�~�̔R����P�̈�ʂ���������A���_�ł���A�Ԉ���Ă�
����̂ł͂Ȃ��B�������A���O�Ƀf�B�[�[���G���W���ł͋C���x�~�ɂ��R����P�͋͂��ł��邽�߁A�f�B�[�[���G
���W���ɋC���x�~�ɂ��R����P�́A�n���ȃG���W���Z�p�҂̂��邱�Ƃ̂悤�Ȉ�ۂ�ǎ҂ɗ^���鏑�����ł���B
�{���ɁA�C���x�~�ɂ���ăf�B�[�[���G���W���̔R����P�́A�n���ȋZ�p�J���̂悤�ɂ́A�M�҂ɂ͂ƂĂ��v���Ȃ�
�̂ł���B
�@���̃G���W�����������ɃG���W���̈ꕔ�̋C�����x�~����C���x�~�̌����E�����́A�A�C�h�����O�X�g�b�v�ɂ��
�R����P�ƑS�������ł���B���̂Ȃ�A�A�C�h�����O�X�g�b�v�́A�C���x�~�ł̔R����P�Ɠ��l�ɁA�z�C�X���b�g���o
���u�������Ȃ��f�B�[�[���G���W���ł��R����P���\�ł���B�������A�K�\�����G���W���̃A�C�h�����O�^�]�ł̋z
�C�X���b�g���o���u�̏����ȊJ�x�̍ۂɂ́A�傫�ȃ|���v�����ɂ��ߑ�ȔR����������N�����Ă���̂ł���B
���̂��߁A�K�\�����G���W���ł̃A�C�h�����O�X�g�b�v�ł͑傫�ȔR����P�̌��ʂ����҂ł��邱�ƂɂȂ�B�������Ȃ�
��A�K�\�����G���W���ł̃A�C�h�����O�X�g�b�v�ɂ��R����P�ɂ͉����y�Ȃ����A�f�B�[�[���G���W���ł̃A�C�h����
�O�X�g�b�v�̏ꍇ�ł��A���ꑊ���̔R����P���\�ł���B���̂��߁A�킪���ł́A�g���b�N�E�o�X�̔R����P��}��
���߁A�\�N�ȏ���̂���f�B�[�[���g���b�N��f�B�[�[���o�X�ɐ���ɃA�C�h�����O�X�g�b�v���̗p����Ă������Ƃ͎�
���ł���B���̂悤�ȃA�C�h�����O�X�g�b�v�̌�����l����ƁA�C���x�~�V�X�e���́A�������ׂŃ|���v�����̑傫��
�K�\�����G���W���̕����傫�ȔR����P�ɑ傫�Ȍ��ʂ����邪�A�K�\�����G���W���قǂł͂Ȃ����̂́A�f�B�[�[
���G���W���ł��\���ȔR����P��}�邱�Ƃ��\�ƍl������B
�R����P�ƑS�������ł���B���̂Ȃ�A�A�C�h�����O�X�g�b�v�́A�C���x�~�ł̔R����P�Ɠ��l�ɁA�z�C�X���b�g���o
���u�������Ȃ��f�B�[�[���G���W���ł��R����P���\�ł���B�������A�K�\�����G���W���̃A�C�h�����O�^�]�ł̋z
�C�X���b�g���o���u�̏����ȊJ�x�̍ۂɂ́A�傫�ȃ|���v�����ɂ��ߑ�ȔR����������N�����Ă���̂ł���B
���̂��߁A�K�\�����G���W���ł̃A�C�h�����O�X�g�b�v�ł͑傫�ȔR����P�̌��ʂ����҂ł��邱�ƂɂȂ�B�������Ȃ�
��A�K�\�����G���W���ł̃A�C�h�����O�X�g�b�v�ɂ��R����P�ɂ͉����y�Ȃ����A�f�B�[�[���G���W���ł̃A�C�h����
�O�X�g�b�v�̏ꍇ�ł��A���ꑊ���̔R����P���\�ł���B���̂��߁A�킪���ł́A�g���b�N�E�o�X�̔R����P��}��
���߁A�\�N�ȏ���̂���f�B�[�[���g���b�N��f�B�[�[���o�X�ɐ���ɃA�C�h�����O�X�g�b�v���̗p����Ă������Ƃ͎�
���ł���B���̂悤�ȃA�C�h�����O�X�g�b�v�̌�����l����ƁA�C���x�~�V�X�e���́A�������ׂŃ|���v�����̑傫��
�K�\�����G���W���̕����傫�ȔR����P�ɑ傫�Ȍ��ʂ����邪�A�K�\�����G���W���قǂł͂Ȃ����̂́A�f�B�[�[
���G���W���ł��\���ȔR����P��}�邱�Ƃ��\�ƍl������B
�@���̂Ȃ�A�������ׂɂ�����C���x�~�ɂ��G���W���̔R����P�́A�K�\�����G���W���ƃf�B�[�[���G���W���̗�
���ɂ������R�ċC�����u�|���v�����̍팸�v�{�u�T�C�N�������̌���v�{�u�r�C�����̍팸�v�{�u��p�����̍팸�v��
����Ď����ł�����̂ł���B���������āA�|���v�����̏��Ȃ��f�B�[�[���G���W���ł́A�������ׂɂ�����C���x�~
�̔R����P���K�\�����G���W����菭�Ȃ��Ȃ邱�Ƃ͓��R�ł���B�������Ȃ���A�A�������ׂɂ�����C���x�~�̔R��
���P�́A�u�|���v�����̍팸�v�ȊO�ɂ������̗v���ɂ���ĒB������Ă���B���̂����A�f�B�[�[���G���W���̋C���x
�~�́A�u�|���v�����̍팸�v�ȊO�́u�T�C�N�������̌���v�{�u�r�C�����̍팸�v�{�u��p�����̍팸�v�ɂ�����\��
�ȔR��̉��P���ł���̂ł���B���ɁA�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p�́A�u���J�j�J���^�[�{�R��
�p�E���h�v�A�u�G���N�g���b�N�^�[�{�R���p�E���h�v�A�u�����L���T�C�N���v�A�u�M�d�f�q�v����сu�X�^�[�����O�G���W���v����
�f�B�[�[���G���W���̔r�C�K�X�̃G�l���M�[�����鑕�u�E�Z�p���̗p�E���������f�B�[�[���G���W���̕�������
�̔R�����\���Ɍ���ł���@�\������Ă���B���̂��߁A�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p�́A��
�^�f�B�[�[���g���b�N�ɂ͍œK�ȋC���x�~�̋Z�p�ł��邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��ƍl������B
���ɂ������R�ċC�����u�|���v�����̍팸�v�{�u�T�C�N�������̌���v�{�u�r�C�����̍팸�v�{�u��p�����̍팸�v��
����Ď����ł�����̂ł���B���������āA�|���v�����̏��Ȃ��f�B�[�[���G���W���ł́A�������ׂɂ�����C���x�~
�̔R����P���K�\�����G���W����菭�Ȃ��Ȃ邱�Ƃ͓��R�ł���B�������Ȃ���A�A�������ׂɂ�����C���x�~�̔R��
���P�́A�u�|���v�����̍팸�v�ȊO�ɂ������̗v���ɂ���ĒB������Ă���B���̂����A�f�B�[�[���G���W���̋C���x
�~�́A�u�|���v�����̍팸�v�ȊO�́u�T�C�N�������̌���v�{�u�r�C�����̍팸�v�{�u��p�����̍팸�v�ɂ�����\��
�ȔR��̉��P���ł���̂ł���B���ɁA�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p�́A�u���J�j�J���^�[�{�R��
�p�E���h�v�A�u�G���N�g���b�N�^�[�{�R���p�E���h�v�A�u�����L���T�C�N���v�A�u�M�d�f�q�v����сu�X�^�[�����O�G���W���v����
�f�B�[�[���G���W���̔r�C�K�X�̃G�l���M�[�����鑕�u�E�Z�p���̗p�E���������f�B�[�[���G���W���̕�������
�̔R�����\���Ɍ���ł���@�\������Ă���B���̂��߁A�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p�́A��
�^�f�B�[�[���g���b�N�ɂ͍œK�ȋC���x�~�̋Z�p�ł��邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��ƍl������B
�@�Ƃ���ŁA���݁A�f�B�[�[���G���W���ɂ��ẮA�\���ȔR����P���\�ȋZ�p���J���ł��ĂȂ����߂ɁA�f�B�[�[
���R��̌���͋Z�p�I�ɔ����ǂ���̏ł���B���̏́A���݁A�g���b�N���[�J�ł́A2006�N4��1������{�s
���ꂽ2015�N�x�d�ʔR��K���ɕs�K���̑�^�g���b�N�𑽂������Ă��邱�Ƃ�������炩���B���̂悤�ɁA�f�B�[�[��
�G���W���̔R����オ�Z�p�I�ɔ����ǂ���̏�Ŕj���邽�߂ɂ��A�C���x�~�̃f�B�[�[���G���W���̋Z�p�J��
�ɐS���𒍂����Ƃ��K�v�ƍl���邪�A�@���Ȃ��̂ł��낤���B���ɁA�C���x�~�̋Z�p�́A�K�\�����G���W���ł͔R���
�P�̋@�\�����Ȃ����A�f�B�[�[���G���W���ł͔R����P�̋@�\�̊O�ɂ������̃f�B�[�[���G���W�����\�̌���Ɋ�
�^�ł���@�\�����킹�����Ă��邱�Ƃł���B
���R��̌���͋Z�p�I�ɔ����ǂ���̏ł���B���̏́A���݁A�g���b�N���[�J�ł́A2006�N4��1������{�s
���ꂽ2015�N�x�d�ʔR��K���ɕs�K���̑�^�g���b�N�𑽂������Ă��邱�Ƃ�������炩���B���̂悤�ɁA�f�B�[�[��
�G���W���̔R����オ�Z�p�I�ɔ����ǂ���̏�Ŕj���邽�߂ɂ��A�C���x�~�̃f�B�[�[���G���W���̋Z�p�J��
�ɐS���𒍂����Ƃ��K�v�ƍl���邪�A�@���Ȃ��̂ł��낤���B���ɁA�C���x�~�̋Z�p�́A�K�\�����G���W���ł͔R���
�P�̋@�\�����Ȃ����A�f�B�[�[���G���W���ł͔R����P�̋@�\�̊O�ɂ������̃f�B�[�[���G���W�����\�̌���Ɋ�
�^�ł���@�\�����킹�����Ă��邱�Ƃł���B
�@���ɒ��҂��������Ă����������Ƃ́A�K�\�����G���W���̏ꍇ�ƈقȂ�A�f�B�[�[���G���W���ɂ������C���x�~�G��
�W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p���A�R����P�����̂��߂����ɑ��݂��Ă���Z�p�ł͂Ȃ����Ƃ��B����́A�C��
�x�~�́A�f�B�[�[���̂m�n���팸�ƔR�����̈ꋓ�����̋Z�p���I���C���x�~��DPF�̎��ȍĐ��𑣐i (�����Đ�
�̍팸�ŔR�����h�~�j������č������ɂ���^�g���b�N��NO���K�����{�s����������{���{�̑Ӗ��̃y�[�W
�ɏڏq���Ă���悤�ɁA�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p�́A�f�B�[�[���G���W���ɂ����ẮA�u�G���W
�����������̔R�����v�A�u�A�fSCR�G�}�̊������i�ɂ��NO���̑啝�ȍ팸�v�A�uDPF�ł̃t�B���^�̎��ȍĐ�
�̑��i�v������u�f�B�[�[���G���W���̔r�C�K�X�G�l���M�[�����鑕�u�E�Z�p�̌����̌����v���\�ɂ���D��
���@�\������Ă��邱�Ƃł����B�@
�W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p���A�R����P�����̂��߂����ɑ��݂��Ă���Z�p�ł͂Ȃ����Ƃ��B����́A�C��
�x�~�́A�f�B�[�[���̂m�n���팸�ƔR�����̈ꋓ�����̋Z�p���I���C���x�~��DPF�̎��ȍĐ��𑣐i (�����Đ�
�̍팸�ŔR�����h�~�j������č������ɂ���^�g���b�N��NO���K�����{�s����������{���{�̑Ӗ��̃y�[�W
�ɏڏq���Ă���悤�ɁA�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p�́A�f�B�[�[���G���W���ɂ����ẮA�u�G���W
�����������̔R�����v�A�u�A�fSCR�G�}�̊������i�ɂ��NO���̑啝�ȍ팸�v�A�uDPF�ł̃t�B���^�̎��ȍĐ�
�̑��i�v������u�f�B�[�[���G���W���̔r�C�K�X�G�l���M�[�����鑕�u�E�Z�p�̌����̌����v���\�ɂ���D��
���@�\������Ă��邱�Ƃł����B�@
�@����2007�N6�������s�̎����ԋZ�p��̏o�ŕ��w�����ԎY�ƋZ�p�헪�ƋZ�p���W�E�R���V�i���I�@2030�N������
�͂����Ȃ�@��3���@���{�ɂ����鎩���ԔR���̃V�i���I�i�艿�F6300�~�j�x�ɂ�����L�q������ƁA2006�N4���ɊJ��
�����z�|���y�[�W�ŕM�҂���Ă��Ă���f�B�[�[���G���W���́u�R����P�v�A�u�A�fSCR�G�}�ɂ�����NO���팸����
����v����сuDPF���u�̎��ȍĐ��̑��i�ɂ��蓮�Đ��Ǝ����Đ��ɂ�����R���Q��̍팸�v�ɗL�����C���x�~
�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p�̑��݂́A�����̎����ԋZ�p��̐��Ƃ̖ڂɂ͐G��Ă��Ȃ������̂�
���낤���B����Ƃ��|���R�c���Z�p���̕M�҂���Ă���Z�p�́A���̒��g��S���������邱�Ƃ��Ȃ��A���p�����s��
�\�ȒP�Ȃ�ϑz�Z�p�Ƃ��Ė������ꂽ�̂ł��낤���B
�͂����Ȃ�@��3���@���{�ɂ����鎩���ԔR���̃V�i���I�i�艿�F6300�~�j�x�ɂ�����L�q������ƁA2006�N4���ɊJ��
�����z�|���y�[�W�ŕM�҂���Ă��Ă���f�B�[�[���G���W���́u�R����P�v�A�u�A�fSCR�G�}�ɂ�����NO���팸����
����v����сuDPF���u�̎��ȍĐ��̑��i�ɂ��蓮�Đ��Ǝ����Đ��ɂ�����R���Q��̍팸�v�ɗL�����C���x�~
�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p�̑��݂́A�����̎����ԋZ�p��̐��Ƃ̖ڂɂ͐G��Ă��Ȃ������̂�
���낤���B����Ƃ��|���R�c���Z�p���̕M�҂���Ă���Z�p�́A���̒��g��S���������邱�Ƃ��Ȃ��A���p�����s��
�\�ȒP�Ȃ�ϑz�Z�p�Ƃ��Ė������ꂽ�̂ł��낤���B
�@���ꂵ�Ă��A�����ԋZ�p����h�ȕ\����f���Ȃ�������g�����ȋZ�p�����W�߂��o�ŕ������s���ꂽ����
�ɂ���Ė��f����̂́A�����ԋZ�p���M���ďo�ŕ����w��������A���̏o�ŕ���}���ٓ��ł��̓��e�ɐG�ꂽ
�Z�p�҂ł��邱�Ƃ́A�ԈႢ�Ȃ����낤�B���̉e�����ǂ����͒肩�ł͂Ȃ����A�u�f�B�[�[���G���W���̕������ׂɂ�
����|���v�����̓K�\�����G���W���ɔ�ׂď��Ȃ����߁A�������ׂł̃|���v�����̍팸�ɂ���ĔR����P���\
�ɂ���C���x�~�́A�f�B�[�[���G���W���̔R����P�̋Z�p�Ƃ��Ă̓R�X�g�ʂ���l����Ǝ��i�̉\��������B����
�����āA�f�B�[�[���G���W���ɋC���x�~�̋Z�p���̗p���邱�Ƃ́A���̍������B�v�ƒP���ɐM������ł��܂��Ă��鈣
��ȃf�B�[�[���G���W���̊w�ҁE���Ƃ��������܂�Ă��܂����\�����l������̂ł͂Ȃ����낤���B�������Ȃ�
��A���̓������킫�܂����w�ҁE���ƂȂ�A�f�B�[�[���G���W���̔R�����Ɋ�^�ł������ȋZ�p�����������o
���Ă��Ȃ�����̗ǂ��F������A�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p�ɋ�������������Ă���l������
���炸����Ǝv�����A����͕M�҂̒P�Ȃ��l�P����ł��낤���B
�ɂ���Ė��f����̂́A�����ԋZ�p���M���ďo�ŕ����w��������A���̏o�ŕ���}���ٓ��ł��̓��e�ɐG�ꂽ
�Z�p�҂ł��邱�Ƃ́A�ԈႢ�Ȃ����낤�B���̉e�����ǂ����͒肩�ł͂Ȃ����A�u�f�B�[�[���G���W���̕������ׂɂ�
����|���v�����̓K�\�����G���W���ɔ�ׂď��Ȃ����߁A�������ׂł̃|���v�����̍팸�ɂ���ĔR����P���\
�ɂ���C���x�~�́A�f�B�[�[���G���W���̔R����P�̋Z�p�Ƃ��Ă̓R�X�g�ʂ���l����Ǝ��i�̉\��������B����
�����āA�f�B�[�[���G���W���ɋC���x�~�̋Z�p���̗p���邱�Ƃ́A���̍������B�v�ƒP���ɐM������ł��܂��Ă��鈣
��ȃf�B�[�[���G���W���̊w�ҁE���Ƃ��������܂�Ă��܂����\�����l������̂ł͂Ȃ����낤���B�������Ȃ�
��A���̓������킫�܂����w�ҁE���ƂȂ�A�f�B�[�[���G���W���̔R�����Ɋ�^�ł������ȋZ�p�����������o
���Ă��Ȃ�����̗ǂ��F������A�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p�ɋ�������������Ă���l������
���炸����Ǝv�����A����͕M�҂̒P�Ȃ��l�P����ł��낤���B
�P�Q�|�Q�D�C���x�~�̉ߋ��f�B�[�[���G���W���́A�����Z�p�̉��p�ɂėe�ՂɎ������\
�@�C���x�~�̖��ߋ��K�\�����G���W���𓋍ڂ�����p�ԂƏ��^�g���b�N�́A�\�P�V�Ɏ������悤�ɁA�����O�ɂ����Ċ�
�ɏ��i������Ă��鎩���ԃ��[�J������A�܂��A���ꂩ��s�����\�肵�Ă��鎩���ԃ��[�J������悤���B����
�����āA���݂ł̓K�\�����G���W���ɂ�����C���x�~�ɂ��R����P�̋Z�p�́A���Ɋm������Ă���Z�p�ƍl���đ�
���ȊԈႢ�͖����ƍl���ėǂ��̂ł͂Ȃ����낤���B
�ɏ��i������Ă��鎩���ԃ��[�J������A�܂��A���ꂩ��s�����\�肵�Ă��鎩���ԃ��[�J������悤���B����
�����āA���݂ł̓K�\�����G���W���ɂ�����C���x�~�ɂ��R����P�̋Z�p�́A���Ɋm������Ă���Z�p�ƍl���đ�
���ȊԈႢ�͖����ƍl���ėǂ��̂ł͂Ȃ����낤���B
���@2003�N�ɁA�z���_���C���X�p�C�A��V�^6�C���ɁAVCM�Ə̂��č̗p�����B����̓G���V�I����A�R�[�h�n�C�u���b�h�A�k�Ďd�l�I�f
�b�Z�C�ɂ��̗p���ꂽ�B |
���@2004�N�ɁA�N���C�X���[���w�~�G���W���ɁAMDS�Ə̂��č̗p�����B
|
���@2005�N�ɁAGM��Displacement on Demand�Ə̂��č̗p�����B�z���_���V�r�b�N�n�C�u���b�h�̐V���f����4�C�����ׂĂ̋x�~��
�̗p�����B |
���@2007�N�ɁA�z���_���k�Č����A�R�[�h�y�уC���X�p�C�A��V6�G���W���ɁA6-4-3��3�i�K�ɋC�������ւ���V�^��VCM����
�p�����B4�C���^�]���ɂ͊e�o���N��2�C�������^�]�����B |
| ���@2008�N4�����z���_���Đ��W�����{CR-V�A�p�C���b�g���t�����f���`�F���W���A�V�^�����\���ꂽ�B�p�C���b�g�́A�z���_��
�k�Ăƈꕔ�̒n��ł̂ݔ̔����Ă����^SUV�B���Y���A�����J�ōs���A���{�ɂ͓�������Ă��Ȃ��B�G���W���͂���܂Œʂ�3.5���b �^�[V6�𓋍ڂ��邪�A�ŐV�̋C���x�~�V�X�e��������邱�ƂŁA�R����サ���̂��|�C���g�B�p�C���b�g�ɓ��ڂ����V6�G���W���́A�� �s�ɂ��3�C���A4�C���A6�C���Ɖғ�����s�X�g�������ω�����̂��������B |
| ���@GM��2008�N9��2���A�V�{���[�w�J�}���x�̃t���b�O�V�b�v�O���[�h�A�uSS�v�̎ʐ^�������J�����BSS�Ƃ̓X�[�p�[�E�X�|�[�c�̗��B��
��J�}������ݒ肳��Ă����`���̍ŋ����f�����B6.2���b�g���EV8OHV���j�b�g��6MT��LS3�^�i�w�R���x�b�g�x�p�̃f�`���[���Łj�A6AT�� L99�^�ƃG���W���`�����قȂ�B�ő�o��/�ő�g���N��6MT��422ps/56.4kgm�A6AT��400ps/54.5kgm�B6AT�͋C���x�~�V�X�e������ �p���āA�R��ɔz�����Ă���B |
| ���@�ăN���C�X���[�́A2011�N���f���́u�_�b�W�E�f�������S�iDodge Durango�j�v�������J�����B�X�|�[�c�E���[�e�B���e�B(SUV)�Ƃ���
�o�ꂵ�����̐V�^�u�f�������S�v�ɂ́A�ϋC���V�X�e��(MDS)�𓋍ڂ���5.7���b�^�[�EHEMI�G���W�����p�ӂ���Ă���B����2011�N�^ �u�_�b�W�E�f�������S�v�́A2010�N��4�l�����ɕč��Ŕ̔������\��Ƃ̂��Ƃł���B |
| ���@�����Z�f�XAMG�́A5.5���b�^�[V8���R�z�C�G���W���ɁA�R�����ɍv������g�C���x�~�V�X�e���h�𓋍ڂ����V���j�b�g�gM152�h��
���\�����B���G���W���́A2011�N9���̃t�����N�t���g�V���[�Ńf�r���[�\���SLK55 AMG�ɓ��ڂ����B���̂��є��\���ꂽ�C�� �x�~�V�X�e���t���G���W���́A���q���⌸�����ȂǃG���W�����ׂ����Ȃ���Ԃ̂Ƃ��ɁA�ꕔ�̃V�����_�[���x�~���A�R������ʂ�� ��������Ƃ������́B����ɗގ�����Z�p�́A750hp���ւ�F1��V8�G���W���ɂ��̗p����Ă���BM152���j�b�g�́A�]����5.5���b�^�[V8 ���p���[��62hp�A�g���N��3.1kg-m�A�b�v���A�ō��o��422hp�A�ő�g���N55.1kg-m��啝�ȏo�̓A�b�v�������B����ɔR����]���̓� �r�C�ʃG���W�����30�����サ�Ă���Ƃ����B |
| �@���@�t�H���N�X���[�Q���̎�̓_�E���T�C�W���O�G���W���ł���1.4���b�g������4�C���K�\�����̃X�[�p�[�`���[�W���{�^�[�{��
�����ڂ�TSI�G���W���ɋC���x�~�V�X�e����2012�N����̗p����Ɣ��\�����B�i2111�N9��2���Ƀt�H���N�X���[�Q�������\�j���̃V �X�e���́A�N���[�W���O���s�Ȃǂ̒ᕉ���ɁA4�C���̂�����2�C�����x�~���邻�����B���̋C����~�V�X�e���́A�G���W���̉�]�� ��1400-4000rpm�A�g���N��25�`75Nm�͈̔͂ł���A���ł��쓮���邻�����B���B�̃h���C�r���O�T�C�N���̂��悻70%�̑��s ���������̂Ȃ��Ɏ��܂�Ƃ̂��ƁB���������āA�����Ă��鎞�Ԃ̑唼��2�C�����s���Ă��ƂɂȂ�悤���B�����āA�t�H���N�X���[�Q�� �ɂ��ƁA�Ⴆ��50km/h�ŃN���[�W���O���A�M�A��3���܂���4���ɂ���ꍇ�A100km���s������A��1.0���b�g���̃K�\������ߖ邱 �Ƃ��ł���Ƃ����B �@�@�@���̃t�H���N�X���[�Q���̃^�[�{�ߋ�����TSI�G���W���ł́A��p�Ԃ⏬�^�g���b�N�̖��ߋ��K�\�����ԂŊ��ɐ��������p������� �����C���̋z�E�r�C�ق��펞������C���x�~�̋Z�p���̗p����Ă���Ɛ��@�����B �@�@�@ �@�@�@�i���L�j ���Ԉ�ʂł́A�P��̃G���W���ɂP��Ƀ^�[�{�ߋ��@�������ʏ�̃^�[�{�ߋ��G���W���ɂ����Ă����ߋ��K�\�����Ɠ��l�̋x�~���� �C���̋z�E�r�C�ق��펞������C���x�~�V�X�e�����c�_����Ă���B���̂P��Ƀ^�[�{�ߋ��@�G���W���ɂ����ẮA�����̋C�����x �~����C���x�~�^�]���ł́A�ғ�����c�蔼���̋C���̍����^�]�ł͉ߋ��@�̌������Ⴍ�Ȃ邽�߂ɕK�v�Ƃ���u�[�X�g���ɍ��� �邱�Ƃ�����ł���B���̂��߁A�ғ�����c�蔼���̋C���̑S���^�]�ł́A�ғ�����c�蔼���̋C���ɂ̓u�[�X�g���̕s���̂��߂� �K�v�ȋ��C�ʂ������ł��Ȃ����߁A�ғ�����c�蔼���̋C���ɉ^�]�ł́A���̃^�[�{�ߋ��G���W���̍ő�g���N�̂P�^�Q�̃g���N�ł̉^ �]���s�\�ƂȂ錇�_������B�������ATSI�G���W���ł��X�[�p�[�`���[�W��(�@�B�쓮���ߋ��@�j�����Ă��邽�߁A���̃X�[�p�[�`�� �[�W������g����A�C���x�~�^�]�����ғ��C���Q�������ɉߋ����č����ׂʼn^�]���邱�Ƃ��\�ƂȂ�B���̂��߃t�H���N�X���[�Q ���̃X�[�p�[�`���[�W���𓋍ڂ����^�[�{�ߋ���TSI�G���W�������ߋ��K�\�����ɓK�����z�E�r�C�ق��펞������C���x�~�̋Z�p���� �p���Ă��A���ߋ��K�\�����̏ꍇ�Ɠ����̔R����P���\�Ɛ��@�����B���̌��ʁA�t�H���N�X���[�Q���́A�X�[�p�[�`���[�W���{�^�[�{ �ߋ����ڂ�TSI�G���W���ɁA���ߋ��K�\�����Ɠ��l�̋x�~����C���̋z�E�r�C�ق��펞������C���x�~�V�X�e�����̗p���ꂽ���̂� �l������B |
| ���@2012�N�Ƀ��f���`�F���W����鎟���^�u�A�E�f�B A3�v�́A�S��ނ̃{�f�B�`�Ԃœo�ꂵ�A���s�ɂ���ĂS�C���̂���������
�Q�C�����x�~������C���x�~�@�\�𓋍ڂ���G���W�����̗p�����Ƃ����B���̎����^�u�A�E�f�B A3�v�ɂ́A�t�H���N�X���[�Q���ɍ̗p�� ��Ă���̃X�[�p�[�`���[�W���������^�[�{�ߋ��̋C���x�~��TSI�G���W�������ڂ����Ƃ̂��Ƃł���B |
| ���@2012�N�P���J�Â̕č��ŊJ�������f�g���C�g���[�^�[�V���[2012�ɂ����āA�t�H���N�X���[�Q���̃O���[�v�͂����A���O��
�[�v�P�����x���g���[�ƃA�E�f�B�������J�������C���x�~�ɐV����V8�K�\�����G���W�����𓋍ڂ���w�R���`�l���^��GT V8�x�� �\�����B���̐V��������V�^8�C���K�\�����G���W���́A�r�C�ʂ�4.0���b�g���ŁA2�̃^�[�{�`���[�W���[�ʼnߋ����邱�Ƃɂ��A�ő�o ��507ps/6000rpm�A�ő�g���N67.3kgm/1700-5000rpm���B����́A��{�I�ɓ����G���W����ςރA�E�f�B�wS6�x�wS7�X�|�[�c�o�b �N�x�̍ő�o��420ps�A�ő�g���N56.1kgm�ɑ��āA87ps�A11kgm���͋����B���̃G���W���͊����\�ɂ��z���B�ᕉ����4�C����� �~����C���x�~�V�X�e�����̗p���A�u���[�L�G�l���M�[�V�X�e���Ȃǂ������B�x���g���[�́u6.0���b�g����W12�C���G���W�����ڎ� �Ɣ�r���āA�ő�40���R���CO2�r�o�ʂ����P�v�Ɛ������Ă���B |
| ���@�C�^���A�̃X�[�p�[�J�[���[�J�[�A�����{���M�[�j�̍ŐV��A�w�A���F���^�h�[��LP700�]4�x��2013�N���f���́A�C���x�~�V
�X�e�����̗p����Ƃ̂��ƁB6.5���b�g��V�^12�C���K�\�����G���W���́A�������H�ɂ�����N���[�W���O���ȂǁA�ᕉ��ԂŔ���
��6�C�����~����B����ɂ��A�ő��20���̔R��������������Ƃ����B
�i�o�T�F7��27���A�X�E�F�[�f���̎����ԃ��f�B�A�A�wauto motor & sport�x�������́j |
�@�ȏ�̕\�P�V������ƁA���Ăł͋ߔN�A�K�\�����G���W���𓋍ڂ�����p�Ԃ⏬�^�g���b�N�̕���ł́A�C���x�~�G
���W�����̗p���ĔR��팸��}�郁�[�J�����X�ƌ���Ă���悤���B���̗��R�́A��r�C�ʂ̃K�\���������Ԃ̓s�s
�����̍����ő��s���Ȃ���Ԃł̋C���x�~�ɂ��R����P�̌��ʂ����������߂ƍl������B�����͌����Ă��A�z��
�_�̃n�C�u���b�h��p�Ԃɓ��ڂ�1.3���b�g����1.5���b�g���̃G���W���ɋC���x�~�̋Z�p�����ɍ̗p����Ă����A�t�H
���N�X���[�Q���̎�̓_�E���T�C�W���O�G���W���ł���1.4���b�g������4�C���K�\�����̃X�[�p�[�`���[�W���{�^�[�{
�ߋ����ڂ�TSI�G���W���ɋC���x�~�V�X�e����2012�N����̗p����\��ł���B���̂��Ƃ���A�C���x�~�̋Z�p����
�r�C�ʂ̃K�\���������Ԃł��R�����ɂ��L���ł��邱�Ƃ́A���炩���B
���W�����̗p���ĔR��팸��}�郁�[�J�����X�ƌ���Ă���悤���B���̗��R�́A��r�C�ʂ̃K�\���������Ԃ̓s�s
�����̍����ő��s���Ȃ���Ԃł̋C���x�~�ɂ��R����P�̌��ʂ����������߂ƍl������B�����͌����Ă��A�z��
�_�̃n�C�u���b�h��p�Ԃɓ��ڂ�1.3���b�g����1.5���b�g���̃G���W���ɋC���x�~�̋Z�p�����ɍ̗p����Ă����A�t�H
���N�X���[�Q���̎�̓_�E���T�C�W���O�G���W���ł���1.4���b�g������4�C���K�\�����̃X�[�p�[�`���[�W���{�^�[�{
�ߋ����ڂ�TSI�G���W���ɋC���x�~�V�X�e����2012�N����̗p����\��ł���B���̂��Ƃ���A�C���x�~�̋Z�p����
�r�C�ʂ̃K�\���������Ԃł��R�����ɂ��L���ł��邱�Ƃ́A���炩���B
�@�Ƃ��낪�A�ȉ��̕\�P�W�Ɏ����������G�l���M�[���A�����A�������R�c��ɂ����{�����ԍH�Ɖ�̃q�A����
�O�ł́A�}�P�R�Ɏ������悤�ɁA���{�����ԍH�Ɖ�́u�K�\�����G���W���̕��������ɂ����ĂR�O���̔R����P����
�\�ł��邪�A�����C�����G���W���ւ̓K�p�ɂ͐U���}�����̍X�Ȃ�Z�p�J�����K�v�v�Ɛ������Ă���悤���B����A
���݁A�����̏��^��p�Ԃɂ͏��r�C�ʂŋC�����̏��Ȃ��S�C���K�\���������ڂ���Ă���ɂł���B���̂悤�Ȍ���
���n�m�������{�����ԍH�Ɖ�́A�����G�l���M�[���A�����A�������R�c��ɂ��q�A�����O�̐��������ɂ���
�āA���^��p�Ԃɓ��ڂ���Ă��鏬�r�C�ʂ̂S�C���i�������C�����H�j�̃K�\�����G���W���ł́A�U������������
��Z�p�����J���̂��߂ɋC���x�~�̋Z�p��p���ď��^��p�Ԃ̑��s�R������シ�邱�Ƃ�����ł��邩�̂悤��
��ۂ�^����L�q������ꂽ�B
�O�ł́A�}�P�R�Ɏ������悤�ɁA���{�����ԍH�Ɖ�́u�K�\�����G���W���̕��������ɂ����ĂR�O���̔R����P����
�\�ł��邪�A�����C�����G���W���ւ̓K�p�ɂ͐U���}�����̍X�Ȃ�Z�p�J�����K�v�v�Ɛ������Ă���悤���B����A
���݁A�����̏��^��p�Ԃɂ͏��r�C�ʂŋC�����̏��Ȃ��S�C���K�\���������ڂ���Ă���ɂł���B���̂悤�Ȍ���
���n�m�������{�����ԍH�Ɖ�́A�����G�l���M�[���A�����A�������R�c��ɂ��q�A�����O�̐��������ɂ���
�āA���^��p�Ԃɓ��ڂ���Ă��鏬�r�C�ʂ̂S�C���i�������C�����H�j�̃K�\�����G���W���ł́A�U������������
��Z�p�����J���̂��߂ɋC���x�~�̋Z�p��p���ď��^��p�Ԃ̑��s�R������シ�邱�Ƃ�����ł��邩�̂悤��
��ۂ�^����L�q������ꂽ�B
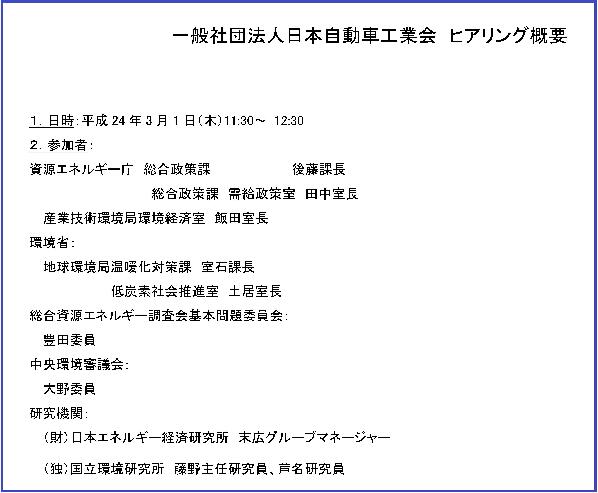
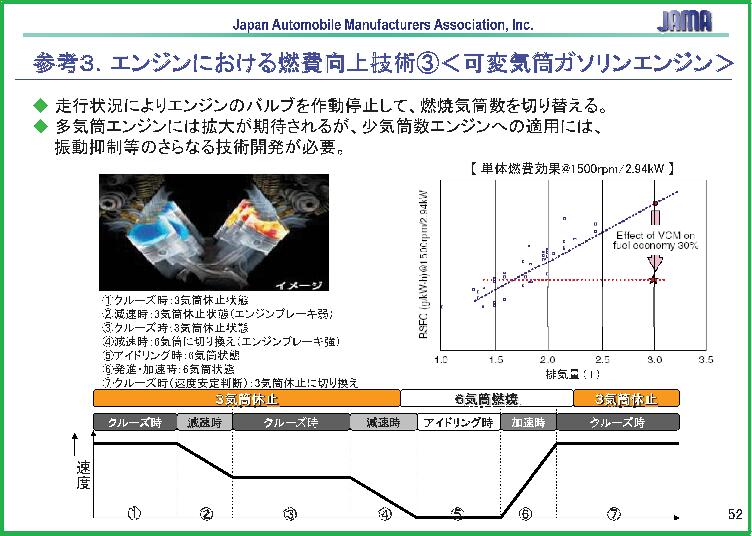
�@���āA���݂̓��{�̏��^��p�Ԃɂ́A�C�������ł����Ȃ��S�C���G���W�������ڂ���Ă���A�y�����Ԃ̃G���W��
�ł́A�S�C���ƂR�C���̃G���W�������ڂ���Ă���B���̂悤�ȏɂ����āA���̐}�P�R�̃q�A�����O�����̒��ł́A
���{�����ԍH�Ɖ�͎����G�l���M�[���A�����A�������R�c��ɑ��A�u�R���b�g���̃K�\�����G���W���ɂ���
�āA�C���x�~�^�]���̂P�T�O�O�������^�Q�D�X�S���v�̕������הR��͂P�D�V���b�g���̃K�\�����G���W���̑S�C��
�^�]�ł̔R��ɑ������A���̋C���x�~�̉^�]�ɂ���ĕ��������̔R����R�O�������P���邱�Ƃ��\�ł�
��B�������A���̋C���x�~�̋Z�p�������C�����G���W���ւ̓K�p�ł���悤�ɂ��邽�߂́A�U���}�����̍X
�Ȃ�Z�p�J�����K�v�ł���v�Ɛ��������Ă���̂��B���̂悤�ɁA���{�����ԍH�Ɖ�́A�����G�l���M�[���A��
���A�������R�c��ɑ��A�u�����C���̃K�\�����G���W���ɋC���x�~���̗p�����ꍇ�ɂ͐U����肪�������邽
�߁A���݂̋Z�p���x���ł͋C���x�~�̗̍p������v�Ɛ������Ă���B�܂�A���{�����ԍH�Ɖ�́A�����C���̃K
�\�����G���W���ɋC���x�~���̗p����ꍇ�ɂ͉��̖��������Ȃ����A�������A�����C���̃K�\�����G���W���ɋC��
�x�~���̗p�����ꍇ�ɂ͐U����肪��������Ƃ̈ӌ��E�咣�̂悤���B�������Ȃ���A���{�����ԍH�Ɖ�́A�C��
�x�~���̗p�����ꍇ�ł̐U����肪��������G���W���̋C�����m�Ɏ����Ă��Ȃ��̂��B�����āA�C���x�~����
��ȃK�\�����G���W���́A�u�����C�����̃K�\�����G���W���v�ƁA�����B���Ȍ��t��p���Đ������Ă��邱�Ƃ���A�q
�A�����O�����{���������G�l���M�[���A�����A�������R�c��̐l�B���C���x�~�̖��_�𐳊m�ɗ��������悤
�ɂ͂ƂĂ��v���Ȃ��̂ł���B
�ł́A�S�C���ƂR�C���̃G���W�������ڂ���Ă���B���̂悤�ȏɂ����āA���̐}�P�R�̃q�A�����O�����̒��ł́A
���{�����ԍH�Ɖ�͎����G�l���M�[���A�����A�������R�c��ɑ��A�u�R���b�g���̃K�\�����G���W���ɂ���
�āA�C���x�~�^�]���̂P�T�O�O�������^�Q�D�X�S���v�̕������הR��͂P�D�V���b�g���̃K�\�����G���W���̑S�C��
�^�]�ł̔R��ɑ������A���̋C���x�~�̉^�]�ɂ���ĕ��������̔R����R�O�������P���邱�Ƃ��\�ł�
��B�������A���̋C���x�~�̋Z�p�������C�����G���W���ւ̓K�p�ł���悤�ɂ��邽�߂́A�U���}�����̍X
�Ȃ�Z�p�J�����K�v�ł���v�Ɛ��������Ă���̂��B���̂悤�ɁA���{�����ԍH�Ɖ�́A�����G�l���M�[���A��
���A�������R�c��ɑ��A�u�����C���̃K�\�����G���W���ɋC���x�~���̗p�����ꍇ�ɂ͐U����肪�������邽
�߁A���݂̋Z�p���x���ł͋C���x�~�̗̍p������v�Ɛ������Ă���B�܂�A���{�����ԍH�Ɖ�́A�����C���̃K
�\�����G���W���ɋC���x�~���̗p����ꍇ�ɂ͉��̖��������Ȃ����A�������A�����C���̃K�\�����G���W���ɋC��
�x�~���̗p�����ꍇ�ɂ͐U����肪��������Ƃ̈ӌ��E�咣�̂悤���B�������Ȃ���A���{�����ԍH�Ɖ�́A�C��
�x�~���̗p�����ꍇ�ł̐U����肪��������G���W���̋C�����m�Ɏ����Ă��Ȃ��̂��B�����āA�C���x�~����
��ȃK�\�����G���W���́A�u�����C�����̃K�\�����G���W���v�ƁA�����B���Ȍ��t��p���Đ������Ă��邱�Ƃ���A�q
�A�����O�����{���������G�l���M�[���A�����A�������R�c��̐l�B���C���x�~�̖��_�𐳊m�ɗ��������悤
�ɂ͂ƂĂ��v���Ȃ��̂ł���B
�@���̂悤�ɁA���{�����ԍH�Ɖ�̃q�A�����O�����̒��̐}�P�R�ɂ́A�C���x�~�̋Z�p�����p������ۂ̏�Q�ƂȂ�
�U����肪��������̂́A�u�����C�����v�̃G���W���̏ꍇ�ƋL�ڂ���Ă��邾���ł���B���̃q�A�����O�����́A��
�{�����ԍH�Ɖ�̋Z�p�����ł���Ȃ���A�C���x�~�ł̐U����肪��������u�����C�����v�̋�̓I�ȁu�C�����v
����������Ă��Ȃ��̂��B���̃q�A�����O�����́A���{�����ԍH�Ɖ�쐬���������ȋZ�p�����ł���ɂ�������
�炸�A�u�����C�����̃G���W���ł͋C���x�~�̋Z�p�����p������ۂ̏�Q�ƂȂ�U����肪��������v�Ƃ̔����
���B���ȓ��e���L�ڂ���Ă���A�Z�p�����Ƃ��Ď��i�ł���悤�Ɏv����̂��B���������̂ł���B���������āA���{
�����ԍH�Ɖ�̃q�A�����O�����ł́A���݂̋Z�p���x���ŐU�����̂��߂ɋC���x�~�̗̍p������ȃK�\�����G
���W���́A�u�S�C���ȉ��v�Ɓu�R�C���ȉ��v�̉���̃G���W���ł��邩�́A���݂̂Ƃ���s���ł���B����A�q�A�����O��
���ꂽ�l�B������A�C���x�~�̗̍p������ȃG���W�����S�C���ȉ��ƂR�C���ȉ��̉���ł��邩�ɂ��Ă̎����
�s���Ă��Ȃ��悤���B��̑S�́A�����G�l���M�[���A�����A�������R�c��̐l�B�́A�C���x�~������ȃK�\
�����G���W���̋C�����́A�u�S�C���ȉ��v�Ɓu�R�C���ȉ��v�̉���̋C�����Ɨ�������Ă���̂ł��낤���B
�U����肪��������̂́A�u�����C�����v�̃G���W���̏ꍇ�ƋL�ڂ���Ă��邾���ł���B���̃q�A�����O�����́A��
�{�����ԍH�Ɖ�̋Z�p�����ł���Ȃ���A�C���x�~�ł̐U����肪��������u�����C�����v�̋�̓I�ȁu�C�����v
����������Ă��Ȃ��̂��B���̃q�A�����O�����́A���{�����ԍH�Ɖ�쐬���������ȋZ�p�����ł���ɂ�������
�炸�A�u�����C�����̃G���W���ł͋C���x�~�̋Z�p�����p������ۂ̏�Q�ƂȂ�U����肪��������v�Ƃ̔����
���B���ȓ��e���L�ڂ���Ă���A�Z�p�����Ƃ��Ď��i�ł���悤�Ɏv����̂��B���������̂ł���B���������āA���{
�����ԍH�Ɖ�̃q�A�����O�����ł́A���݂̋Z�p���x���ŐU�����̂��߂ɋC���x�~�̗̍p������ȃK�\�����G
���W���́A�u�S�C���ȉ��v�Ɓu�R�C���ȉ��v�̉���̃G���W���ł��邩�́A���݂̂Ƃ���s���ł���B����A�q�A�����O��
���ꂽ�l�B������A�C���x�~�̗̍p������ȃG���W�����S�C���ȉ��ƂR�C���ȉ��̉���ł��邩�ɂ��Ă̎����
�s���Ă��Ȃ��悤���B��̑S�́A�����G�l���M�[���A�����A�������R�c��̐l�B�́A�C���x�~������ȃK�\
�����G���W���̋C�����́A�u�S�C���ȉ��v�Ɓu�R�C���ȉ��v�̉���̋C�����Ɨ�������Ă���̂ł��낤���B
�@�����ŁA���{�����ԍH�Ɖ�咣����u�U�����̂��߂ɋC���x�~�̗̍p������ȃG���W���̋C�����v��\�z��
�邱�Ƃɂ����B�悸�A�C���x�~�G���W���ɂ��Ă̌����_�̎s�̎ԏ��Ƃ��ẮA���{�����ԍH�Ɖ�̉���ł���
�z���_�́A�C���x�~�̂P�D�R���b�g���S�C���K�\�����G���W���𓋍ڂ����t�B�b�g�n�C�u���b�h����������B����́A�z��
�_���C���x�~���̗p�����S�C���K�\�����G���W���̏�p�Ԃ��C���x�~�^�]���̕s���ȐU����d�q��������ɂ��
�ėL���ɗ}����Z�p�����p�����A����҂ɖ������ĖႦ��S�C���̋C���x�~�K�\�����G���W���̎����Ԃ��s�̂��Ă�
��̂ł���B
�邱�Ƃɂ����B�悸�A�C���x�~�G���W���ɂ��Ă̌����_�̎s�̎ԏ��Ƃ��ẮA���{�����ԍH�Ɖ�̉���ł���
�z���_�́A�C���x�~�̂P�D�R���b�g���S�C���K�\�����G���W���𓋍ڂ����t�B�b�g�n�C�u���b�h����������B����́A�z��
�_���C���x�~���̗p�����S�C���K�\�����G���W���̏�p�Ԃ��C���x�~�^�]���̕s���ȐU����d�q��������ɂ��
�ėL���ɗ}����Z�p�����p�����A����҂ɖ������ĖႦ��S�C���̋C���x�~�K�\�����G���W���̎����Ԃ��s�̂��Ă�
��̂ł���B
�@����A���{�̋C���������Ȃ����^��p�Ԃ̏ꍇ�A����܂ł͂S�C���G���W���������������A�ŋ߂ł͂S�C���G���W
�����������Ă���悤���B�����āA�y�����Ԃ̃G���W���ł͂S�C���ƂR�C�������݂��Ă���悤�ł���B���̂悤�Ȍ���
���l����ƁA�z���_���G���W���}�E���g�̓d�q��������ɂ��S�C���K�\�����G���W���̋C���x�~�̐��U�Z�p
��h���Z�p���������A���p�����Ă��邱�Ƃ���A���{�����ԍH�Ɖ2012�N3��1���̐��{�i�������G�l���M
�[���A�����A�������R�c��j�̃q�A�����O�Ŏ咣�����u�U�����̂��߂ɋC���x�~�̗̍p������ȏ���
�C�����̃G���W���v�́A�R�C���K�\�����G���W���ƍl���ĊԈႢ���Ȃ��Ɛ��@�����B���̂悤�ɁA�S�C���K�\����
�G���W���̋C���x�~�V�X�e���𓋍ڂ��������Ԃ��s�̂���Ă��錻����ӂ݂��A���{�����ԍH�Ɖ�����G
�l���M�[���A�����A�������R�c��ɑ��A�C���x�~�̗̍p������ȃG���W���̋C�����𐳒��ɐ�������̂�
����A�q�A�����O�����ɂ́u�R�C���̃K�\�����G���W���𓋍ڂ����y�����ԂɋC���x�~���̗p�����ꍇ�ɂ͐U����
�肪�������邽�߁A���݂̋Z�p���x���ł͎��p��������v�ƋL�ڂ��ׂ��ł������ƍl������B�������A���ۂ̃q�A
�����O�Ő������ꂽ�����ɂ́A���{�����ԍH�Ɖ�͓��e��ύX���A�u�����C���̃K�\�����G���W���ɋC���x�~���̗p
�����ꍇ�ɂ͐U����肪�������邽�߁A���݂̋Z�p���x���ł͎��p��������v�ƞB���Ȑ��������L�ڂ��Ă����
���B���̋L�ړ��e�Ɍ��͔F�߂��Ȃ��B�������A�C���x�~�̋Z�p���̗p���Ď����Ԃ̑��s�R���ϋɓI�Ɍ��コ
���邱�Ƃɑ��A���{�����ԍH�Ɖ�͋ɂ߂ď��ɓI�Ȉӌ��E�����E�l�������c�̂̂悤�Ɏv����̂ł���B
�����������Ă���悤���B�����āA�y�����Ԃ̃G���W���ł͂S�C���ƂR�C�������݂��Ă���悤�ł���B���̂悤�Ȍ���
���l����ƁA�z���_���G���W���}�E���g�̓d�q��������ɂ��S�C���K�\�����G���W���̋C���x�~�̐��U�Z�p
��h���Z�p���������A���p�����Ă��邱�Ƃ���A���{�����ԍH�Ɖ2012�N3��1���̐��{�i�������G�l���M
�[���A�����A�������R�c��j�̃q�A�����O�Ŏ咣�����u�U�����̂��߂ɋC���x�~�̗̍p������ȏ���
�C�����̃G���W���v�́A�R�C���K�\�����G���W���ƍl���ĊԈႢ���Ȃ��Ɛ��@�����B���̂悤�ɁA�S�C���K�\����
�G���W���̋C���x�~�V�X�e���𓋍ڂ��������Ԃ��s�̂���Ă��錻����ӂ݂��A���{�����ԍH�Ɖ�����G
�l���M�[���A�����A�������R�c��ɑ��A�C���x�~�̗̍p������ȃG���W���̋C�����𐳒��ɐ�������̂�
����A�q�A�����O�����ɂ́u�R�C���̃K�\�����G���W���𓋍ڂ����y�����ԂɋC���x�~���̗p�����ꍇ�ɂ͐U����
�肪�������邽�߁A���݂̋Z�p���x���ł͎��p��������v�ƋL�ڂ��ׂ��ł������ƍl������B�������A���ۂ̃q�A
�����O�Ő������ꂽ�����ɂ́A���{�����ԍH�Ɖ�͓��e��ύX���A�u�����C���̃K�\�����G���W���ɋC���x�~���̗p
�����ꍇ�ɂ͐U����肪�������邽�߁A���݂̋Z�p���x���ł͎��p��������v�ƞB���Ȑ��������L�ڂ��Ă����
���B���̋L�ړ��e�Ɍ��͔F�߂��Ȃ��B�������A�C���x�~�̋Z�p���̗p���Ď����Ԃ̑��s�R���ϋɓI�Ɍ��コ
���邱�Ƃɑ��A���{�����ԍH�Ɖ�͋ɂ߂ď��ɓI�Ȉӌ��E�����E�l�������c�̂̂悤�Ɏv����̂ł���B
�@���݂ɁA���{�̎����ԃ��[�J�̒��Ŏ��ۂɋC���x�~�̋Z�p��p���ĔR����P��}���Ă���̂̓z���_�����ł���
���A�����_�ŋC���x�~�G���W���̎����Ԃ����Ɏs�̍ς݁A�܂��͋߂������̎s�̗\��\���Ă��鉢�Ă̎���
�ԃ��[�J�́A�f�l�A�N���C�X���[�A�����Z�f�XAMG�A�t�H���N�X���[�Q���A�A�E�f�B����уx���g���[�ł���B���̂悤�ɁA
�ŋ߁A�R������ړI�Ƃ��ċC���x�~�G���W�����ڂ̎����Ԃ��s�̂��鎩���ԃ��[�J�̑������������B���̂悤�ɁA
���E�I�ɋC���x�~�ɂ��R�����̗L�������F�߂�����ł���ɂ�������炸�A�C���x�~�̋Z�p����
�̗p�̑��̓��{�����ԍH�Ɖ�̉���̉�ЂɂƂ��ẮA�����G�l���M�[���A�����A�������R�c��ɋC���x�~
�̔R�����̗L������F�����ĖႢ�����Ȃ��悤�ȈӐ}������悤�ɕM�҂ɂ͌�����̂ł���B
���A�����_�ŋC���x�~�G���W���̎����Ԃ����Ɏs�̍ς݁A�܂��͋߂������̎s�̗\��\���Ă��鉢�Ă̎���
�ԃ��[�J�́A�f�l�A�N���C�X���[�A�����Z�f�XAMG�A�t�H���N�X���[�Q���A�A�E�f�B����уx���g���[�ł���B���̂悤�ɁA
�ŋ߁A�R������ړI�Ƃ��ċC���x�~�G���W�����ڂ̎����Ԃ��s�̂��鎩���ԃ��[�J�̑������������B���̂悤�ɁA
���E�I�ɋC���x�~�ɂ��R�����̗L�������F�߂�����ł���ɂ�������炸�A�C���x�~�̋Z�p����
�̗p�̑��̓��{�����ԍH�Ɖ�̉���̉�ЂɂƂ��ẮA�����G�l���M�[���A�����A�������R�c��ɋC���x�~
�̔R�����̗L������F�����ĖႢ�����Ȃ��悤�ȈӐ}������悤�ɕM�҂ɂ͌�����̂ł���B
�@�ȏ�̂��Ƃ���A���{�����ԍH�Ɖ�̉���ł���e�����ԃ��[�J�́A�C���x�~�̋Z�p�ɂ��ẮA����ł́u�R�C
���ȉ��̏����C�����̃K�\�����G���W���ł́A���݂̋Z�p���x���ŐU�����̂��߂ɋC���x�~������v�ł���A��
�A�u�S�C���̃K�\�����G���W���ł́A���݂̋Z�p���x���ł��U���̖�肪�������߂ɋC���x�~�G���W�����̗p����
���Ƃɂ���đ����̏��^�K�\���������Ԃ̑��s�R��̌��オ�\�v�Ƃ̔F���������Ă�����̂Ɛ��������B��������
�āA�q�A�����O�����ɂ͖��L����Ă��Ȃ����A���{�����ԍH�Ɖ�̉���ł���e�����ԃ��[�J�́A���݂̓��{�̏�
�^��p�Ԃ̃G���W���ɂ͂S�C���ȏ�̋C�����̃G���W�����̗p����Ă��邽�߁A���{�̌y�����ԈȊO�̑S�ẴK
�\���������Ԃ́A�C���x�~�̋Z�p���̗p���邱�Ƃɂ���đ啝�Ȕ�����}�邱�Ƃ��\�ł��邱�Ƃ��\���ɔF���E
�������Ă�����̂Ɛ��@�����B
���ȉ��̏����C�����̃K�\�����G���W���ł́A���݂̋Z�p���x���ŐU�����̂��߂ɋC���x�~������v�ł���A��
�A�u�S�C���̃K�\�����G���W���ł́A���݂̋Z�p���x���ł��U���̖�肪�������߂ɋC���x�~�G���W�����̗p����
���Ƃɂ���đ����̏��^�K�\���������Ԃ̑��s�R��̌��オ�\�v�Ƃ̔F���������Ă�����̂Ɛ��������B��������
�āA�q�A�����O�����ɂ͖��L����Ă��Ȃ����A���{�����ԍH�Ɖ�̉���ł���e�����ԃ��[�J�́A���݂̓��{�̏�
�^��p�Ԃ̃G���W���ɂ͂S�C���ȏ�̋C�����̃G���W�����̗p����Ă��邽�߁A���{�̌y�����ԈȊO�̑S�ẴK
�\���������Ԃ́A�C���x�~�̋Z�p���̗p���邱�Ƃɂ���đ啝�Ȕ�����}�邱�Ƃ��\�ł��邱�Ƃ��\���ɔF���E
�������Ă�����̂Ɛ��@�����B
�@���͂Ƃ�����A�C���x�~��p����K�\���������Ԃ̑��s�R���e�Ղ����P���邱�����\�ł��邽�߁A�C���x
�~�̋Z�p���̗p���鎩���ԃ��[�J��Ԏ킪�A����A�܂��܂��������Ă������Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��ƍl������B�����āA
���A�āA���̎����ԃ��[�J�ł̓K�\�����G���W���ł̋C���x�~�ɂ��R�����̋Z�p���L����ʉ������邱�Ƃ�
�m���Ȃ悤���B�������A���݁A���A�āA���̉���̎s��ɂ����Ă��e���[�J�[����C���x�~�̋Z�p�ɂ���ĔR�����
��}������p�Ԃ⏬�^�g���b�N�����X�Ɣ�������A�N�X�A���̎Ԏ����������X���ɂ���B���̗�Ƃ��āA�č��ɂ�
����2005�N�`2007�N�ł̋C���x�~�G���W�����ڎ����Ԃ̔̔��䐔����\�P�X����ѐ}�P�S�Ɏ����B
�~�̋Z�p���̗p���鎩���ԃ��[�J��Ԏ킪�A����A�܂��܂��������Ă������Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��ƍl������B�����āA
���A�āA���̎����ԃ��[�J�ł̓K�\�����G���W���ł̋C���x�~�ɂ��R�����̋Z�p���L����ʉ������邱�Ƃ�
�m���Ȃ悤���B�������A���݁A���A�āA���̉���̎s��ɂ����Ă��e���[�J�[����C���x�~�̋Z�p�ɂ���ĔR�����
��}������p�Ԃ⏬�^�g���b�N�����X�Ɣ�������A�N�X�A���̎Ԏ����������X���ɂ���B���̗�Ƃ��āA�č��ɂ�
����2005�N�`2007�N�ł̋C���x�~�G���W�����ڎ����Ԃ̔̔��䐔����\�P�X����ѐ}�P�S�Ɏ����B
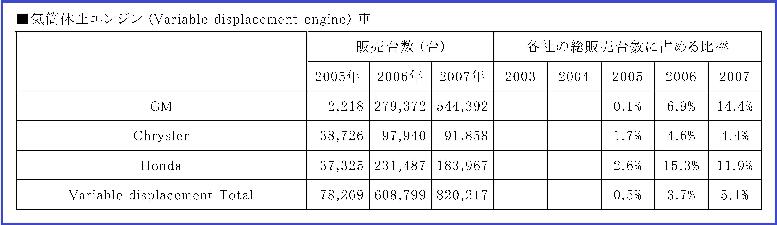
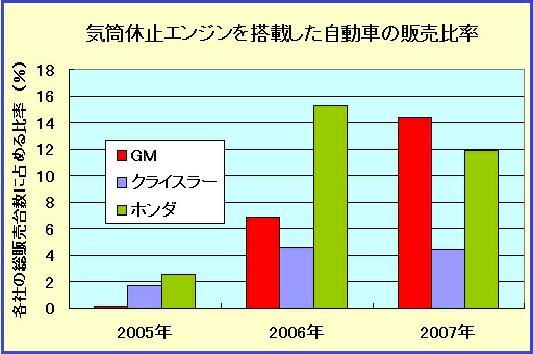
�߂��A�C���x�~�G���W���𓋍ڂ����K�\���������Ԃ̔̔��̔䗦���������Ă���X���̂悤���B
�@����ł́A��p�Ԃ⏬�^�g���b�N�ł͖��ߋ��K�\�����G���W���������̗p����Ă���A���ߋ��K�\�����G���W���ł�
�x�~�^�]���ɋC���̋z�E�r�C�ق��펞�����邱�Ƃɂ���ĊȒP�ɏ\���ȔR����オ�\�ȋC���x�~�G���W����
���p���ł��邽�߂ƍl������B�Ƃ��낪�A���ߋ��K�\�����ɓK�����z�E�r�C�ق��펞������C���x�~�̋Z�p�́A
�^�[�{�ߋ���TSI�G���W���ł́A�C���x�~�ʼn^�]�ł���G���W���̉^�]�͈͂������Ȃ�B�������ATSI�G���W���ł��X�[
�p�[�`���[�W��(�@�B�쓮���ߋ��@�j�����Ă��邽�߁A���̃X�[�p�[�`���[�W������g����A�C���x�~�^�]��
���ғ��C���Q�������ɉߋ����Ĕ�r�I�A�����ׂł��ŋC���x�~�̉^�]���邱�Ƃ��\�ƂȂ�B���̌��ʁA����TSI�G
���W���́A���B�̃h���C�r���O�T�C�N���̂��悻70%�̑��s�������C���x�~�̉^�]�ɂ���đ��s�ł���Ƃ̂��Ƃ��B
�x�~�^�]���ɋC���̋z�E�r�C�ق��펞�����邱�Ƃɂ���ĊȒP�ɏ\���ȔR����オ�\�ȋC���x�~�G���W����
���p���ł��邽�߂ƍl������B�Ƃ��낪�A���ߋ��K�\�����ɓK�����z�E�r�C�ق��펞������C���x�~�̋Z�p�́A
�^�[�{�ߋ���TSI�G���W���ł́A�C���x�~�ʼn^�]�ł���G���W���̉^�]�͈͂������Ȃ�B�������ATSI�G���W���ł��X�[
�p�[�`���[�W��(�@�B�쓮���ߋ��@�j�����Ă��邽�߁A���̃X�[�p�[�`���[�W������g����A�C���x�~�^�]��
���ғ��C���Q�������ɉߋ����Ĕ�r�I�A�����ׂł��ŋC���x�~�̉^�]���邱�Ƃ��\�ƂȂ�B���̌��ʁA����TSI�G
���W���́A���B�̃h���C�r���O�T�C�N���̂��悻70%�̑��s�������C���x�~�̉^�]�ɂ���đ��s�ł���Ƃ̂��Ƃ��B
�@�Ƃ���ŁA�X�[�p�[�`���[�W���𓋍ڂ����^�[�{�ߋ���TSI�G���W�����C���x�~�����ꍇ�ɂ́A���ߋ��K�\�����̏�
���Ɠ��l�ɁA�z�E�r�C�ُ펞���̑��u���K�{�ł���B�������A���݂̑�^�g���b�N�́A�X�[�p�[�`���[�W���𓋍ڂ�
���^�[�{�ߋ��̃f�B�[�[���G���W�������ڂ���Ă����Ȃ��B���̂��߁A�����z�E�r�C�ُ펞�������̋C���x�~�Z
�p�́A�ȉ��̗��R�ɂ��A�^�[�{�ߋ��f�B�[�[���G���W���̑�^�g���b�N�ɑ�������K�v�������B���̑���ɁA�^�[
�{�ߋ��f�B�[�[���G���W���̑�^�g���b�N�̃^�[�{�ߋ��@�́A�M�Ғ�Ă��C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j
�̂悤�ɁA��^�̃V���O���^�[�{�ߋ�����Q��̏��^�^�[�{�����z�u�����Q�^�[�{�ߋ������ɕύX����K�v����
��B
�@ �z�E�r�C�ُ펞���̑��u�́A�啝�ȃR�X�g����������
�A ���������̃|���s���O���������Ȃ��f�B�[�[���G���W���ł́A���������̃|���s���O���������Ȃ��K�\����
�G���W���ɔ�r���A�z�E�r�C�ُ펞���̑��u�����Ă��C���x�~�^�]���̔R����P�����Ȃ����ƁA
�B �X�[�p�[�`���[�W�������ڂ���Ă��Ȃ���^�f�B�[�[���g���b�N�ł��A�x�~�C���̋z�C�Ɣr�C�̓�������̂܂�
�쓮�����Ă��X�[�p�[�`���[�W���̋��C�ʂɔr�o����G�l���M�[�����͐����Ȃ��̂ŁA�u�z�E�r�C�ق��펞����
��������̋C���x�~�Z�p�v���̗p����K�v���������ƁB
�@���̂悤�ɁA�M�Ғ�Ẵf�B�[�[���G���W���p���C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p�́A�K�\�����G��
�W���̋C���x�~�ɕK�{�̋z�E�r�C�ُ펞���̑��u���s�v�ł���B�������A���̂Ƃ���A�̔��Ԏ�̈ꕔ�Ƃ͉]���A
��^�g���b�N�E�g���N�^�ɂ�����2015�N�x�d�ʎԔR���ɕs�K���̎Ԏ����������쎩���ԁA�����U�����ԁA�O�H
�ӂ��������UD�g���b�N�X�̃g���b�N���[�J�S�Ђ́A���̕M�Ғ�Ă̋C���x�~�Z�p��S���������Ă���悤���B���{�̃g
���b�N���[�J�́A�R�����ɗL�����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p��َE�������ŁA���ꂩ���
2015�N�x�d�ʎԔR���ɕs�K���̑�^�g���b�N�E�g���N�^�̎Ԏ�����ʂ��Ȃ����X�Ɣ̔�����������j�ł��낤���B
�@���݂ɁA�M�҂�2006�N4���ɊJ�݂����z�[���y�[�W�ɂ����đ�^�g���b�N�̉ߋ��f�B�[�[���G���W�����C���x�~��
�����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�\���Ĉȗ��A���ɂT�N�ȏ���o�߂��Ă���̂ł���B�������A����
�Ƃ���A���쎩���ԁA�����U�����ԁA�O�H�ӂ��������UD�g���b�N�X�̃g���b�N���[�J�S�Ђ́A���̋Z�p����Ȃɖ�����
�Ă���悤���B�@���̂悤�ɁA�g���b�N���[�J�S�Ђ́A�\���ȔR�������\�ɂ����C���x�~�G���W���i�������J2005-
54771�j�̋Z�p�������������ŁA���ꂩ����_�����\���̂�����@��𑨂��đ�^�g���b�N�ł̔R����P���Z�p
�I�ɍ���ł��邱�Ƃ𐭕{�␢�Ԃɐ���ɃA�s�[�����čs�����Ƃɂ��A���ꂩ����K���ŏd�ʎԔR���̋�����
�摗���i��������̂ł��낤���B���ꂪ�����ł���A���疳�p���r�������Ɛ����ɂ��ċ��т����Ƃ��낾�B
�����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�\���Ĉȗ��A���ɂT�N�ȏ���o�߂��Ă���̂ł���B�������A����
�Ƃ���A���쎩���ԁA�����U�����ԁA�O�H�ӂ��������UD�g���b�N�X�̃g���b�N���[�J�S�Ђ́A���̋Z�p����Ȃɖ�����
�Ă���悤���B�@���̂悤�ɁA�g���b�N���[�J�S�Ђ́A�\���ȔR�������\�ɂ����C���x�~�G���W���i�������J2005-
54771�j�̋Z�p�������������ŁA���ꂩ����_�����\���̂�����@��𑨂��đ�^�g���b�N�ł̔R����P���Z�p
�I�ɍ���ł��邱�Ƃ𐭕{�␢�Ԃɐ���ɃA�s�[�����čs�����Ƃɂ��A���ꂩ����K���ŏd�ʎԔR���̋�����
�摗���i��������̂ł��낤���B���ꂪ�����ł���A���疳�p���r�������Ɛ����ɂ��ċ��т����Ƃ��낾�B
�@�Ƃ���ŁA�ŋ߂ł́A�I�C���s�[�N�̎�����}���Ă��邱�Ƃ�A�����E�C���h�̂悤�ȑ����̐l������������ł�����
�Ԃ̕��y���i��ł������Ƃ��\�z����邱�Ƃ������āA�����I�ɂ͌������i���㏸���Ă������Ƃ͊ԈႢ�����B����
�āA�~�����i�s���Ă�����{�ȊO�̍��ł́A�����ԗp�̃K�\�����ƌy���̉��i�͌��݂ł����Ȃ�̃��x���܂ō�����
���Ă���悤���B���̂��߁A�R��̗ǂ������Ԃ�������Ȃ��Ȃ��Ă���A���E�̎����ԃ��[�J�ł͎����Ԃ̔R��팸
�̍팸�������܂��܂��������Ȃ��Ă������̂Ɨ\�z�����B
�Ԃ̕��y���i��ł������Ƃ��\�z����邱�Ƃ������āA�����I�ɂ͌������i���㏸���Ă������Ƃ͊ԈႢ�����B����
�āA�~�����i�s���Ă�����{�ȊO�̍��ł́A�����ԗp�̃K�\�����ƌy���̉��i�͌��݂ł����Ȃ�̃��x���܂ō�����
���Ă���悤���B���̂��߁A�R��̗ǂ������Ԃ�������Ȃ��Ȃ��Ă���A���E�̎����ԃ��[�J�ł͎����Ԃ̔R��팸
�̍팸�������܂��܂��������Ȃ��Ă������̂Ɨ\�z�����B
�@�܂��A�ŋ߂̎����Ԃɂ�����R��팸�i��CO�Q�팸�j�̎Љ�I�ȃj�[�Y����A2015�N�x�d�ʎԔR�������{��
�Ă�����{�Ɠ��l�ɁA�č��ł��g���b�N�Ȃǂ̏��p�Ԃɑ��A2014�`18�N��5�N�ԂɁA���p�ԃ��[�J�[�e�ЂɁA�ő�
20���̔R���������߂�Ƃ������������e�̔R��K���̎b��Ă�NHTSA�i�č��^�A�ȓ��H��ʈ��S�ǁj��EPA�i��
���ی�ǁj������\���ꂽ�B���̎b��Ăł́A�ł��n�[�h���������̂͑�^�g���[���[�Ȃǂɑ�����̂ŁA20����
�R����P�ڕW���ۂ��Ă���悤���B
�Ă�����{�Ɠ��l�ɁA�č��ł��g���b�N�Ȃǂ̏��p�Ԃɑ��A2014�`18�N��5�N�ԂɁA���p�ԃ��[�J�[�e�ЂɁA�ő�
20���̔R���������߂�Ƃ������������e�̔R��K���̎b��Ă�NHTSA�i�č��^�A�ȓ��H��ʈ��S�ǁj��EPA�i��
���ی�ǁj������\���ꂽ�B���̎b��Ăł́A�ł��n�[�h���������̂͑�^�g���[���[�Ȃǂɑ�����̂ŁA20����
�R����P�ڕW���ۂ��Ă���悤���B
�@�ȏ�̂��Ƃ���A�]���A�g���b�N���[�J�ł͒P�Ȃ鏤�i�͂̈�ɉ߂��Ȃ�������^�g���b�N�E�g���N�^�ł̔R�����P
�́A���ꂩ��͔R��K���ւ̓K���̉ۂɊւ��Ɖ]���A�d��ȉۑ��w���킳���悤�ɂȂ��Ă����̂ł���B��
�������āA����A�e�g���b�N���[�J�́A����܂ňȏ�ɑ�^�g���b�N�E�g���N�^�̔R�����P�̊J���𐄐i����K�v������
�Ă����ƌ����邾�낤�B
�́A���ꂩ��͔R��K���ւ̓K���̉ۂɊւ��Ɖ]���A�d��ȉۑ��w���킳���悤�ɂȂ��Ă����̂ł���B��
�������āA����A�e�g���b�N���[�J�́A����܂ňȏ�ɑ�^�g���b�N�E�g���N�^�̔R�����P�̊J���𐄐i����K�v������
�Ă����ƌ����邾�낤�B
�P�Q�|�R�D���V�G�B�V�[�C�[���C���x�~�̎������ʂ̔��\�𒆎~���Ă��闝�R�́A�����H
�@���V�G�B�V�[�C�[�́A�����ԃ��[�J�[�ƕ��i��Ђ��o�����A�g���b�N���[�J�S��(����A�����U�A�t�c�A�O�H�ӂ���)����
�����҂��h������Ă���f�B�[�[���G���W���̌������ł���B���L�̂悤�ɁA���̇��V�G�B�V�[�C�[����A�Q�O�O�X�N��
���A�u���V�G�B�V�[�C�[�͂Q�O�O�S�N�Ɏ��{�����f�B�[�[���G���W���̋C���x�~�̎����ɂ����āA�R�����P�̌��ʂ��m
�F���Ă����v �Ƃ̏������V�G�B�V�[�C�[�����M�����d���[���ɂ���ĕM�҂͓��肵�Ă���B�����A���̂d���[����
���e�����V�G�B�V�[�C�[�̓����Ō��F����Ă����Ƃ́A���̂d���[���̂b���������̇��V�G�B�V�[�C�[�̐��F�O��
���ɑ��t����Ă��邱�Ƃ�������炩�ł���B
�����҂��h������Ă���f�B�[�[���G���W���̌������ł���B���L�̂悤�ɁA���̇��V�G�B�V�[�C�[����A�Q�O�O�X�N��
���A�u���V�G�B�V�[�C�[�͂Q�O�O�S�N�Ɏ��{�����f�B�[�[���G���W���̋C���x�~�̎����ɂ����āA�R�����P�̌��ʂ��m
�F���Ă����v �Ƃ̏������V�G�B�V�[�C�[�����M�����d���[���ɂ���ĕM�҂͓��肵�Ă���B�����A���̂d���[����
���e�����V�G�B�V�[�C�[�̓����Ō��F����Ă����Ƃ́A���̂d���[���̂b���������̇��V�G�B�V�[�C�[�̐��F�O��
���ɑ��t����Ă��邱�Ƃ�������炩�ł���B
 |
�@�Ƃ��낪�A���̂d���[�������M���ꂽ009�N12��26���̎��_�ł́A���̋C���x�~�̎������I�����Ă�����ɂT�N��
����o�߂����Ă���ɂ�������炸�A�����ɇ��V�G�B�V�[�C�[�̓f�B�[�[���G���W���̋C���x�~�̎������ʂ\��
�Ă��Ȃ��悤���B�ʏ�A��ʂ̌������ł́A�������{�̗��N�ɂ͂��̎������ʂ��܂Ƃ߂��Ĕ��\�������̂��B��
�����A���V�G�B�V�[�C�[�ł́A���p�����e�ՂŔR�����P�Ɍ��ʂ�����C���x�~�̎������Q�O�O�S�N�Ɏ��{���ꂽ�ɂ�
������炸�A���̎������ʂ̔��\���T�N�ȏ���x�点�����Ă���̂ł���B���̏́A��ʓI�Ȍ����@�ւ̍s
���E�����Ƃ��Ă͉��Ƃ���Ȃ��Ƃł���B
����o�߂����Ă���ɂ�������炸�A�����ɇ��V�G�B�V�[�C�[�̓f�B�[�[���G���W���̋C���x�~�̎������ʂ\��
�Ă��Ȃ��悤���B�ʏ�A��ʂ̌������ł́A�������{�̗��N�ɂ͂��̎������ʂ��܂Ƃ߂��Ĕ��\�������̂��B��
�����A���V�G�B�V�[�C�[�ł́A���p�����e�ՂŔR�����P�Ɍ��ʂ�����C���x�~�̎������Q�O�O�S�N�Ɏ��{���ꂽ�ɂ�
������炸�A���̎������ʂ̔��\���T�N�ȏ���x�点�����Ă���̂ł���B���̏́A��ʓI�Ȍ����@�ւ̍s
���E�����Ƃ��Ă͉��Ƃ���Ȃ��Ƃł���B
�@���̈���ŁA���̌������ł́A�f�B�[�[���R��̌����}��ړI�̂��߂ɁA��G���W����]�����P�O�O�O�������ɂ���
�ĉߏ�ɍ������C�u�[�X�g���i���T�O�O���o���j�܂ʼnߋ����ē��������o���������Q�SMPa�Ƃ�����p�����ɂ߂č���Ȑ�
�i�Z�p�̎������������{�������A���̌����ł̓f�B�[�[���̔R�����Ɏ��s�����Ƃ̎������ʂ�ϋɓI�ɔ��\
�i���Fhttp://www.nace.jp/J-Research_Outline2.htm�j���Ă���̂��B���̂悤�ɁA���V�G�B�V�[�C�[�́A���p�����e�Ղ�
�R����P�Ɍ��ʂ����� �u�C���x�~�v �̂悤�Ȏ������ʂ\�����A���p���̋ɂ߂č���ȔR�����P�Z�p�̎�����
�ʂ�����I�����Ĕ��\���Ă���悤�ł���B���̂��Ƃ́A���V�G�B�V�[�C�[�́A�f�B�[�[���G���W���̔R�����P���ɂ�
�č���ł��邱�Ƃ𐢊Ԃ̐l�B�Ɉ�ەt���邽�߂̐��_�U���̊�������̂ɍs���Ă���悤�ɕM�҂ɂ͎v����̂�
����B
�ĉߏ�ɍ������C�u�[�X�g���i���T�O�O���o���j�܂ʼnߋ����ē��������o���������Q�SMPa�Ƃ�����p�����ɂ߂č���Ȑ�
�i�Z�p�̎������������{�������A���̌����ł̓f�B�[�[���̔R�����Ɏ��s�����Ƃ̎������ʂ�ϋɓI�ɔ��\
�i���Fhttp://www.nace.jp/J-Research_Outline2.htm�j���Ă���̂��B���̂悤�ɁA���V�G�B�V�[�C�[�́A���p�����e�Ղ�
�R����P�Ɍ��ʂ����� �u�C���x�~�v �̂悤�Ȏ������ʂ\�����A���p���̋ɂ߂č���ȔR�����P�Z�p�̎�����
�ʂ�����I�����Ĕ��\���Ă���悤�ł���B���̂��Ƃ́A���V�G�B�V�[�C�[�́A�f�B�[�[���G���W���̔R�����P���ɂ�
�č���ł��邱�Ƃ𐢊Ԃ̐l�B�Ɉ�ەt���邽�߂̐��_�U���̊�������̂ɍs���Ă���悤�ɕM�҂ɂ͎v����̂�
����B
�@���������A���V�G�B�V�[�C�[���T�N�ȏ���̂� �w�f�B�[�[���G���W���́u�C���x�~�ɂ���ĔR�����P���\�v�ł��邱
�Ƃ������I�Ɋm�F�x ���Ă����̂ł���A���̎������I����ɔ@���Ȃ闝�R�ł��̎������ʂ̔��\�N�ɂ킽��
�Ē��~�������Ă���̂ł��낤���B����ɂ��Đ���������������ƁA���y��ʏȂ��u�C���x�~�̋Z�p��p����A
�f�B�[�[���g���b�N�̑啝�ȔR�����P���\�ł���v�Ƃ̎�����m�邱�ƂɂȂ�A���y��ʏȂ͂Q�O�P�T�N�x�d�ʎ�
�R���ɑ����V���ȔR�����}���Őݒ肵�Ă��܂����ꂪ�����Ƃ͌����Ȃ��B���̂悤�Ȏ��ԂɂȂ邱�Ƃ����O
�ɉ�����邽�߁A�����ԃ��[�J�̊W�҂𒆐S�ɑg�D���ꂽ���V�G�B�V�[�C�[�́u�C���x�~�ɂ�����R�����P�̌�
�ʁv�̌������\�𒆎~���邱�Ƃ����߂��\�����ے�ł��Ȃ��B
�Ƃ������I�Ɋm�F�x ���Ă����̂ł���A���̎������I����ɔ@���Ȃ闝�R�ł��̎������ʂ̔��\�N�ɂ킽��
�Ē��~�������Ă���̂ł��낤���B����ɂ��Đ���������������ƁA���y��ʏȂ��u�C���x�~�̋Z�p��p����A
�f�B�[�[���g���b�N�̑啝�ȔR�����P���\�ł���v�Ƃ̎�����m�邱�ƂɂȂ�A���y��ʏȂ͂Q�O�P�T�N�x�d�ʎ�
�R���ɑ����V���ȔR�����}���Őݒ肵�Ă��܂����ꂪ�����Ƃ͌����Ȃ��B���̂悤�Ȏ��ԂɂȂ邱�Ƃ����O
�ɉ�����邽�߁A�����ԃ��[�J�̊W�҂𒆐S�ɑg�D���ꂽ���V�G�B�V�[�C�[�́u�C���x�~�ɂ�����R�����P�̌�
�ʁv�̌������\�𒆎~���邱�Ƃ����߂��\�����ے�ł��Ȃ��B
�@���̂悤�ɁA���V�G�B�V�[�C�[�������N���ɂ킽���ċC���x�~�̎������ʂ̔��\���Ӑ}�I�ɒ��~���Ă��邱�Ƃ���
���ł���A�V�G�B�V�[�C�[���f�B�[�[���G���W���́u�R�����P�v�A�u�ȃG�l���M�]�v����сuCO�Q�팸�v�̊ւ���Z�p��
���āA�u�f�B�[�[���G���W���̔R�����P���e�ՂɎ��p���ł���Z�p�͕s���ł���v�ƂɊԈ�������M���A��
�}�I�ȏ��̑���E�H����s���Ă��邱�ƂɂȂ�ƌ�����̂ł͂Ȃ����낤���B���̂悤�ȍs�ׂ��V�G�B�V�[�C�[�̖{
���Ɩ��ł���Ƃ���Ȃ�A���V�G�B�V�[�C�[�������I�Ȍ����@�ւł���ƍl����͍̂��{�I�Ɍ��ł���A���̌�
�����̔��\�ɂ͂����̋^�╄��t���Č���K�v������̂ł͂Ȃ����낤���B
���ł���A�V�G�B�V�[�C�[���f�B�[�[���G���W���́u�R�����P�v�A�u�ȃG�l���M�]�v����сuCO�Q�팸�v�̊ւ���Z�p��
���āA�u�f�B�[�[���G���W���̔R�����P���e�ՂɎ��p���ł���Z�p�͕s���ł���v�ƂɊԈ�������M���A��
�}�I�ȏ��̑���E�H����s���Ă��邱�ƂɂȂ�ƌ�����̂ł͂Ȃ����낤���B���̂悤�ȍs�ׂ��V�G�B�V�[�C�[�̖{
���Ɩ��ł���Ƃ���Ȃ�A���V�G�B�V�[�C�[�������I�Ȍ����@�ւł���ƍl����͍̂��{�I�Ɍ��ł���A���̌�
�����̔��\�ɂ͂����̋^�╄��t���Č���K�v������̂ł͂Ȃ����낤���B
�@���V�G�B�V�[�C�[�������N���ɂ킽���ċC���x�~�̎������ʂ̔��\���Ӑ}�I�ɒ��~���Ă��邱�Ƃ́A�V�G�B�V�[�C
�[�̏���ł���A�@���Ɉᔽ���Ă���킯�ł��Ȃ��̂ŁA���O�҂���ᔻ���闝�R�͉��������Ƃ̐V�G�B�V�[�C
�[�̊W�҂���̔��_���������Ă��������B�m���ɁA���̔��_�͖@���I�ɂ͐��������A���`�I�ɂ͐r���^��ł�
��B���̂悤�ȁu�@���Ɉᔽ�����Ȃ���Ή����s���Ă��ǂ��v�Ƃ̕s�����ȍl�����́A��ʂ̎Љ�ł͎��͂̐M����
�����Ă��܂��̂���ł���B���������āA�V�G�B�V�[�C�[�̋Z�p�ҁE���ƁE�����҂́A�ǐS�E�펯������������l�B��
����Ȃ�A���͂Ƃ�����A�킪���ɂ�����g���b�N����ɂ�����uCO�Q�팸�v��u�Ζ��G�l���M�[����̍팸�v��
�i���邱�Ƃ����R�̐Ӗ��ł���Ƃ̈ӎ������ׂ��ł���B���̂��߁A�@���Ȃ闝�R�����낤�Ƃ��A���V�G�B�V�[�C�[
�́A�Q�O�O�S�N�Ɏ擾�����u�C���x�~�ɂ����ĔR��팸�̌��ʂ��m�F�����������ʂ̃f�[�^�v�𑬂₩�Ɍ��\���ׂ�
�Ǝv���̂ł���B
�[�̏���ł���A�@���Ɉᔽ���Ă���킯�ł��Ȃ��̂ŁA���O�҂���ᔻ���闝�R�͉��������Ƃ̐V�G�B�V�[�C
�[�̊W�҂���̔��_���������Ă��������B�m���ɁA���̔��_�͖@���I�ɂ͐��������A���`�I�ɂ͐r���^��ł�
��B���̂悤�ȁu�@���Ɉᔽ�����Ȃ���Ή����s���Ă��ǂ��v�Ƃ̕s�����ȍl�����́A��ʂ̎Љ�ł͎��͂̐M����
�����Ă��܂��̂���ł���B���������āA�V�G�B�V�[�C�[�̋Z�p�ҁE���ƁE�����҂́A�ǐS�E�펯������������l�B��
����Ȃ�A���͂Ƃ�����A�킪���ɂ�����g���b�N����ɂ�����uCO�Q�팸�v��u�Ζ��G�l���M�[����̍팸�v��
�i���邱�Ƃ����R�̐Ӗ��ł���Ƃ̈ӎ������ׂ��ł���B���̂��߁A�@���Ȃ闝�R�����낤�Ƃ��A���V�G�B�V�[�C�[
�́A�Q�O�O�S�N�Ɏ擾�����u�C���x�~�ɂ����ĔR��팸�̌��ʂ��m�F�����������ʂ̃f�[�^�v�𑬂₩�Ɍ��\���ׂ�
�Ǝv���̂ł���B
�@�Ȃ��A���V�G�B�V�[�C�[�̃z�[���y�[�W������ƁA���̌������̉��v�ɂ́A�u���V�G�B�V�[�C�[�́A�O�g�̇��V�R��
�V�X�e���������i'87�N2���ݗ��j�̊�b�������ʂ��p���A����ɒ���Q�E�������f�B�[�[���R�ăV�X�e���̎��p
��������i�߂邽�߂ɐݗ����ꂽ�v�Ɩ��L����Ă���A�����ԃ��[�J�ƕ��i���[�J�����͂��Ď����ԗp�f�B�[�[���G��
�W���ɂ�������ւ̕��ׂ������ł��y�����Ă����Z�p���J�����A�䂪���̏ȃG�l���M�[���C���̉��P�ɍv��
���Ă������Ƃ�ړI�Ƃ��Ă���悤�ɋL�ڂ���Ă���B�Ƃ��낪�A���V�G�B�V�[�C�[�́A�Q�O�O�S�N�Ɏ擾�����u�C���x�~��
�����ĔR��팸�̌��ʂ��m�F�����������ʂ̃f�[�^�v�̌��\��摗��ɂ��Ă��������ƁA���̌������̖{��
�̖ړI�����{�ɂ��r�o�K�X�K����R��K���̋����������ł��x�点�邱�Ƃł͂Ȃ����Ƌ^�O������Ă��܂��̂�
����B
�V�X�e���������i'87�N2���ݗ��j�̊�b�������ʂ��p���A����ɒ���Q�E�������f�B�[�[���R�ăV�X�e���̎��p
��������i�߂邽�߂ɐݗ����ꂽ�v�Ɩ��L����Ă���A�����ԃ��[�J�ƕ��i���[�J�����͂��Ď����ԗp�f�B�[�[���G��
�W���ɂ�������ւ̕��ׂ������ł��y�����Ă����Z�p���J�����A�䂪���̏ȃG�l���M�[���C���̉��P�ɍv��
���Ă������Ƃ�ړI�Ƃ��Ă���悤�ɋL�ڂ���Ă���B�Ƃ��낪�A���V�G�B�V�[�C�[�́A�Q�O�O�S�N�Ɏ擾�����u�C���x�~��
�����ĔR��팸�̌��ʂ��m�F�����������ʂ̃f�[�^�v�̌��\��摗��ɂ��Ă��������ƁA���̌������̖{��
�̖ړI�����{�ɂ��r�o�K�X�K����R��K���̋����������ł��x�点�邱�Ƃł͂Ȃ����Ƌ^�O������Ă��܂��̂�
����B
�@�����Ƃ��A�M�҂͂���Ȃ�Ɋm���Ǝv����o�܂Łu���V�G�B�V�[�C�[���C���x�~�̔R�����P�̌��ʂ��Q�O�O�S�N�̎�
���Ŋm�F�ς݁v�Ƃ̏������Ƃ���A���̏��́A�u�����v�ł��邱�ƂɊԈႢ�Ȃ��Ǝv���Ă���B�������Ȃ���A��
�̍��̋L�ړ��e�ɂ͐����������܂܂�Ă��邽�߁A�ꕔ�ɂ͕M�҂̎�����F�����邩���m��Ȃ��B�����ŁA���V�G
�B�V�[�C�[�̊W�҂����̍����{�����ꂽ�ہA���炩�Ɍ��ƋC�t���ꂽ�L�ڂɂ��ẮA�����̕M�҂�E���[����
�ĂɎ����ɂ��Ă̘A��������������A������L�ړ��e�͑����ɒ������鏊���ł���B
���Ŋm�F�ς݁v�Ƃ̏������Ƃ���A���̏��́A�u�����v�ł��邱�ƂɊԈႢ�Ȃ��Ǝv���Ă���B�������Ȃ���A��
�̍��̋L�ړ��e�ɂ͐����������܂܂�Ă��邽�߁A�ꕔ�ɂ͕M�҂̎�����F�����邩���m��Ȃ��B�����ŁA���V�G
�B�V�[�C�[�̊W�҂����̍����{�����ꂽ�ہA���炩�Ɍ��ƋC�t���ꂽ�L�ڂɂ��ẮA�����̕M�҂�E���[����
�ĂɎ����ɂ��Ă̘A��������������A������L�ړ��e�͑����ɒ������鏊���ł���B
�P�Q�|�S�D�C���x�~�G���W���͑�^�g���b�N�ɂ�����R��팸�̉ۑ�����ɗL��
�@
�@�O�q�̒ʂ�A�M�҂���Ă���u�Q�^�[�{�ߋ��@�������C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�v�̋Z�p�͑�^
�g���b�N�E�g���N�^�̑S�Ԏ���Q�O�P�T�N�x�d�ʎԔR���ɗe�ՂɓK�������邱�Ƃ͖ܘ_�A��^�g���b�N�̔R����X��
���P�ł���ł��L���Ȏ�i�ł���B
�g���b�N�E�g���N�^�̑S�Ԏ���Q�O�P�T�N�x�d�ʎԔR���ɗe�ՂɓK�������邱�Ƃ͖ܘ_�A��^�g���b�N�̔R����X��
���P�ł���ł��L���Ȏ�i�ł���B
�@�Ƃ���ŁA���݂̂悤�ɐΖ��s�[�N���}���Č������i���������鎞��ɂȂ������Ƃ��C�t�����A�ߋ��̐����o����
�������������ފԍۂ̋Z�p�n�������N�Ղ���悤�ȃg���b�N���[�J�ł́A�]���̉�������́u��R�X�g�v�Ɓu�R�ĉ��P�v
����̂̃G���W���R��̉��P�������p���������̂ƍl������B�������A�����̋Z�p�J���ɑ���̎����ƍH��
�𓊓������Ƃ��Ă��A����܂ł̃f�B�[�[���G���W���̌����J���̒������j��U��Ԃ��Č���ƁA����A�Z���ԂɂT��
���x�̔R����P���������邱�Ƃ͋ɂ߂ē���̂ł͂Ȃ����낤���B���������āA���̂悤�ȃg���b�N���[�J�ł́A����
�̌����J���̕��j�]�����s���鎞�_�܂ŁA��^�g���b�N�E�g���N�^�̔R����X�Ɍ��サ�Ă������Ƃ́A�e�Ղł͂Ȃ�
�ƍl������B
�������������ފԍۂ̋Z�p�n�������N�Ղ���悤�ȃg���b�N���[�J�ł́A�]���̉�������́u��R�X�g�v�Ɓu�R�ĉ��P�v
����̂̃G���W���R��̉��P�������p���������̂ƍl������B�������A�����̋Z�p�J���ɑ���̎����ƍH��
�𓊓������Ƃ��Ă��A����܂ł̃f�B�[�[���G���W���̌����J���̒������j��U��Ԃ��Č���ƁA����A�Z���ԂɂT��
���x�̔R����P���������邱�Ƃ͋ɂ߂ē���̂ł͂Ȃ����낤���B���������āA���̂悤�ȃg���b�N���[�J�ł́A����
�̌����J���̕��j�]�����s���鎞�_�܂ŁA��^�g���b�N�E�g���N�^�̔R����X�Ɍ��サ�Ă������Ƃ́A�e�Ղł͂Ȃ�
�ƍl������B
�@�@�����āA�O�q�̂悤�ɁA�����ԋZ�p��s�́u�����ԋZ�p�v��Vol.64�ANo.�P�A2010�i2010�N1���P�����s�j�̔ѓc�P
�� �c���勳���@���R�����́u�f�B�[�[���G���W�����̂P�O�N�v�ɂ̓f�B�[�[���G���W����CO�Q�팸�i���R����P�j��
�u�傫�Ȓ���ۑ�v�ƒf�肵�A���́u�ۑ�B���v�ɂ́u�]���̃f�B�[�[���G���W���̗v�f�V�X�e���ɉ����A�R���A�R�āA
�G�}�̌����A�V�X�e������̓������Z�p�����߂��Ă���v�ƋZ�p�I�ȏœ_�̕s���ȓ��e���L�ڂ���Ă���B����
��[�I�ɒ��킷�ƁA�f�B�[�[���G���W���̔R�����P�i���b�n�Q�팸�j�́A�u�Z�p�I�ɔ����ǂ���̏v�Ɖ]���邾��
���B���̂��Ƃ́A���̂P�O�N�ԂɃf�B�[�[���G���W���̔R�ĉ��P�ɂ��R��팸�i���b�n�Q�팸�j�ɗL���ȋZ�p�J���ɑ�
���Ȑi�W�������Ȃ��������Ƃ��q�ׂĂ�����̂ƍl������B
�� �c���勳���@���R�����́u�f�B�[�[���G���W�����̂P�O�N�v�ɂ̓f�B�[�[���G���W����CO�Q�팸�i���R����P�j��
�u�傫�Ȓ���ۑ�v�ƒf�肵�A���́u�ۑ�B���v�ɂ́u�]���̃f�B�[�[���G���W���̗v�f�V�X�e���ɉ����A�R���A�R�āA
�G�}�̌����A�V�X�e������̓������Z�p�����߂��Ă���v�ƋZ�p�I�ȏœ_�̕s���ȓ��e���L�ڂ���Ă���B����
��[�I�ɒ��킷�ƁA�f�B�[�[���G���W���̔R�����P�i���b�n�Q�팸�j�́A�u�Z�p�I�ɔ����ǂ���̏v�Ɖ]���邾��
���B���̂��Ƃ́A���̂P�O�N�ԂɃf�B�[�[���G���W���̔R�ĉ��P�ɂ��R��팸�i���b�n�Q�팸�j�ɗL���ȋZ�p�J���ɑ�
���Ȑi�W�������Ȃ��������Ƃ��q�ׂĂ�����̂ƍl������B
�@�܂��A2011�N9�����s�́u�����ԋZ�p�v���iVol.65,No.9,2011)�́u�����ԗp�G���W���Z�p�J���̌���Ə����v�i�\�T�Q
�Ɓj�Ƒ肵���_���́u3.2.�@�d�ʎԂ̔R����P�v�̍��ɂ����āA���҂̑���c��w�̑吹�����́A��^�g�f�B�[�[���g
���b�N�E�o�X�i���d�ʎԁj�ɂ���������s��d�ʎԃ��[�h�R������シ���i�Ƃ��āA��^�g���b�N�̎����s�R���d
�ʎԃ��[�h�R����\���ɉ��P�ł���@�\��L����Z�p�Ƃ��āu�^�[�{�ߋ��̑��i���v�A�u�^�[�{�R���p�E���h�v�A�u�����L
���T�C�N���v����сu�M�d�f�q�v�̋Z�p�𐄋�����Ă��邱�Ƃɂ��āA�M�҂ɂ͋^��Ɏv���Ďd�����Ȃ��B���̗��R
�́A�C���x�~�́A�f�B�[�[���r�C�K�X�̃G�l���M�[���u�̌����������̃y�[�W�ɏڏq���Ă���悤�ɁA�u�^�[�{
�R���p�E���h�v�A�u�����L���T�C�N���v����сu�M�d�f�q�v���̔r�C�K�X�G�l���M�[������Z�p��p���đ�^�g���b�N
�̎����s�R���d�ʎԃ��[�h�R����\���Ɍ��シ�邽�߂ɂ́A��^�g���b�N�̎��ۂ̑��s���ɂ�����G���W���^�]
�̕��וp�x�������G���W���������ׂ̔r�C�K�X���x�������������C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z
�p��g���킹�邱�Ƃ��K�v�E�s���ł���ƍl���Ă��邽�߂ł���B
�Ɓj�Ƒ肵���_���́u3.2.�@�d�ʎԂ̔R����P�v�̍��ɂ����āA���҂̑���c��w�̑吹�����́A��^�g�f�B�[�[���g
���b�N�E�o�X�i���d�ʎԁj�ɂ���������s��d�ʎԃ��[�h�R������シ���i�Ƃ��āA��^�g���b�N�̎����s�R���d
�ʎԃ��[�h�R����\���ɉ��P�ł���@�\��L����Z�p�Ƃ��āu�^�[�{�ߋ��̑��i���v�A�u�^�[�{�R���p�E���h�v�A�u�����L
���T�C�N���v����сu�M�d�f�q�v�̋Z�p�𐄋�����Ă��邱�Ƃɂ��āA�M�҂ɂ͋^��Ɏv���Ďd�����Ȃ��B���̗��R
�́A�C���x�~�́A�f�B�[�[���r�C�K�X�̃G�l���M�[���u�̌����������̃y�[�W�ɏڏq���Ă���悤�ɁA�u�^�[�{
�R���p�E���h�v�A�u�����L���T�C�N���v����сu�M�d�f�q�v���̔r�C�K�X�G�l���M�[������Z�p��p���đ�^�g���b�N
�̎����s�R���d�ʎԃ��[�h�R����\���Ɍ��シ�邽�߂ɂ́A��^�g���b�N�̎��ۂ̑��s���ɂ�����G���W���^�]
�̕��וp�x�������G���W���������ׂ̔r�C�K�X���x�������������C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z
�p��g���킹�邱�Ƃ��K�v�E�s���ł���ƍl���Ă��邽�߂ł���B
�@�Ƃ���ŁA�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̂́A�f�B�[�[���G���W���������ׂ�SCR�G�}�������x����
�������ĔA�fSCR�G�}��NO���팸�����啝�Ɍ��シ�邽�߂ɁA�G���W���������ׂ̉^�]�p�x�̍���JE�O�T���[�h�r
�o�K�X�����ł��啝�Ȃm�n���팸�ƁA�T�`�P�O���̃��[�h�R��l���팸�ł���D�ꂽ�R����P�Ɣr�o�K�X�팸�̋@�\
��L���������Z�p�ł���B�����ŁA���̃y�[�W��ǂ܂ꂽ���X�ɂ��������������������Ƃ́A�ŋ߂̎����ԋZ�p���
���{�@��w��̍u����ɂ����āA�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�ɏ���悤�ȁA�d�ʎԃ��[�h�R���
���P��JE�O�T���[�h��NO���팸���\�ɂ���Z�p�����\���ꂽ�Ƃ̏����A����Ƃ��A��������������������
�v������B
�������ĔA�fSCR�G�}��NO���팸�����啝�Ɍ��シ�邽�߂ɁA�G���W���������ׂ̉^�]�p�x�̍���JE�O�T���[�h�r
�o�K�X�����ł��啝�Ȃm�n���팸�ƁA�T�`�P�O���̃��[�h�R��l���팸�ł���D�ꂽ�R����P�Ɣr�o�K�X�팸�̋@�\
��L���������Z�p�ł���B�����ŁA���̃y�[�W��ǂ܂ꂽ���X�ɂ��������������������Ƃ́A�ŋ߂̎����ԋZ�p���
���{�@��w��̍u����ɂ����āA�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�ɏ���悤�ȁA�d�ʎԃ��[�h�R���
���P��JE�O�T���[�h��NO���팸���\�ɂ���Z�p�����\���ꂽ�Ƃ̏����A����Ƃ��A��������������������
�v������B
�@�Ƃ���ŁA�R�ĉ��P�ɂ��G���W���R��̌���̋Z�p�J�����傫�ȕǂɓ˂��������Ă��錻��Ɋ���҂�A�g���b�N
���[�J�̋Z�p�n�����̐l�B�́A�����ɑ�^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W���ł͔R�ĉ��P�ɂ���ĂT�����x�̔R���
�P�ł���ƐM������ł���̂ł͂Ȃ����낤���B�����āA�����ɏ]���Ɠ����悤�Ɂu��R�X�g�v�Ɓu�R�ĉ��P�v�ɌŎ�����
�����J�����Ɏw�����Ă���̂ł��낤���B����̌Â��o����m���̊k�ɕ��Ă��Ă��ẮA�Z�p�̐i���E���W
�ɂ́A�Z�p�I�ɑΉ����Ă����Ȃ����̂Ǝv����B���̂悤�Ȃ��Ƃł́A��^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W���̔R���
�P�̐��ʂ͏グ��ꂸ�A���ꂩ������̔R�����P�̖����X�ɐ摗�肷�邱�ƂɂȂ��Ă��܂��̂ł͂Ȃ����낤���B
���[�J�̋Z�p�n�����̐l�B�́A�����ɑ�^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W���ł͔R�ĉ��P�ɂ���ĂT�����x�̔R���
�P�ł���ƐM������ł���̂ł͂Ȃ����낤���B�����āA�����ɏ]���Ɠ����悤�Ɂu��R�X�g�v�Ɓu�R�ĉ��P�v�ɌŎ�����
�����J�����Ɏw�����Ă���̂ł��낤���B����̌Â��o����m���̊k�ɕ��Ă��Ă��ẮA�Z�p�̐i���E���W
�ɂ́A�Z�p�I�ɑΉ����Ă����Ȃ����̂Ǝv����B���̂悤�Ȃ��Ƃł́A��^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W���̔R���
�P�̐��ʂ͏グ��ꂸ�A���ꂩ������̔R�����P�̖����X�ɐ摗�肷�邱�ƂɂȂ��Ă��܂��̂ł͂Ȃ����낤���B
�@���Ă��āA���݂̑�^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W���ł́u�R�ĉ��P�v�ɂ��R����オ�u�Z�p�I�ɔ����ǂ���v�ł�
��ɂ�������炸�A�g���b�N���[�J�̃G���W���Z�p�ҒB����ȂɁu�Q�^�[�{�ߋ��@�����̋C���x�~�G���W���Z�p�v���
�E���Ă��邱�Ƃɂ��āA�M�҂������������R���ȉ��̕\�Q�O�ɂ܂Ƃ߂��B
��ɂ�������炸�A�g���b�N���[�J�̃G���W���Z�p�ҒB����ȂɁu�Q�^�[�{�ߋ��@�����̋C���x�~�G���W���Z�p�v���
�E���Ă��邱�Ƃɂ��āA�M�҂������������R���ȉ��̕\�Q�O�ɂ܂Ƃ߂��B
���@�C���x�~�G���W���ɂ����镔�������̔R��팸�ɂ��ė������ł��Ȃ����߁A���̋Z�p��َE
�@
�@���̃z�[���y�[�W�ł́A�C���x�~�G���W���́u���������̉ғ��C���̃G���W���T�C�N���̍��������v�Ɓu��p�����팸�i��p�ʐς̔�
���j�v�ɂ��T�`�P�O���̔R����팸�ł���Ɛ������Ă���B�������A�M�҂ɂ͕����̍쐬�\�͂�Z�p���e�̐����\�͂������������Ă��邱
�Ƃ������āA�g���b�N���[�J�̃G���W���Z�p�҂́A�{�z�[���y�[�W�̓��e���\���ɗ����ł��Ȃ����Ƃ���A�C���x�~�G���W���̋Z�p��َE��
�Ă���̂ł��낤���B
|
���@��ʎs���̒�Ă�f�l�A�C�f�A�ƒf�肵�A�v���̟����ɂ������Ƃ��āA�ⓚ���p�ł��̋Z�p������
�@
�@�v���ӎ��̋����g���b�N���[�J�̃G���W���Z�p�҂ɂ́A�̂����ʎs������̒�ċZ�p�ɂẮA�f�l���l�������p���̖����Ԕ����Ȃ�
�̂ł���Ƃ̌Œ�ϔO�������悤���B���������āA���̃z�[���y�[�W�̋C���x�~�G���W���Z�p�̐����́A�g���b�N���[�J�̃G���W���Z�p�҂�
�Ƃ��Ắu�֏��̗������v�ɂ���鉿�l�Ƃ����Ȃ��ƍl���Ă���̂ł͂Ȃ����낤���B�܂��A��ʎs������Ă���C���x�~�G���W���̋Z�p��
�����J�������邱�Ƃ́A�v�������C���Ă���g���b�N���[�J�̃G���W���Z�p�҂ɂƂ��Ă͒p�J�ł���A����ł����{�������Ȃ����ƍl���Ă����
�\�����\���A�l������B���̂��߁A�g���b�N���[�J�̃G���W���Z�p�҂́A�M�҂���Ă��Ă���C���x�~�G���W���̋Z�p��َE���Ă���̂�
���낤���B
|
���@�Г��I�Ȕᔻ�̕��o������Ĉ�ʎs������Ă���Z�p�́A��Ȃɋ���
�@
�@�g���b�N���[�J�ł́A���z�̎���������̓������Ă���ɂ�������炸�A��^�g���b�N�̑����̎Ԏ킪2015�N�x�d�ʎԔR���ɓK����
���Ȃ���������Ă���̂ł���B���̖������̂��߂ɁA���J���h��AVL�̂悤�Ȍ����@�ւł͖����A��ʎs�����P�ɔ]���ōl�����C��
�x�~�G���W���̋Z�p���̗p�����ꍇ�A���̃g���b�N���[�J�ł̓G���W���W�̋Z�p�҂͎ԑ̊W����̋Z�p�ғ�����u���ʔѐH���v�Ȃǂ�
���\�Ȕn���ҌĂ�肳���\�����ɂ߂č����B�����ŁA�G���W���Z�p�҂�����ᔻ�̓I�ɂȂ��Ă��܂������O�ɉ�����邽�߁A
�M�҂���Ă��Ă���C���x�~�G���W���̋Z�p��َE���Ă���\��������B
�@�����ŁA���ɁA�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p�����J���h��AVL�̂悤�ȊC�O�̌����@�ւ̒�Ăł������Ȃ�A����
�̃G���W���Z�p�҂��C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p�ł́u���������̔R����P�ɂ���ďd�ʎԃ��[�h�R������
���邱�Ɓv�ƁA�u���������̃G���W�����������̔r�C�K�X���x�̍������ɂ��A�fSCR�G�}�̊������ɂ���Ăm�n���̍팸�������ł�
�邱�Ɓv�ӂɂȂ��ĎГ��Ő���������̂ƍl������B���݂ɁA�ނ�̍s���̖ړI�́A�G���W���Z�p�̗D�����������Ⴊ����L�\��
�Z�p�҂ł��邱�Ƃ�K���ŎГ��ŃA�s�[�����A�����n�ɏ�邽�߂ł���B�����āA���̕��@��p����A���̋Z�p�J���Ɏ��s�����Ƃ��Ă��A
�ӔC�����J���h��AVL�ɓ]�łł��A���炪�ӂ߂����Ƃ��瓦��邱�Ƃ��ł��邩�炾�B�ނ�̍s���́A���̕��@���T�����[�}���Љ�ŏo
���𐬌�������錍�ł��邩�炾�낤�B���̂悤�Ȃ��Ƃ́A�G���W���Z�p�҂ɂƂ��Ď₵���l���Ǝv�����A�@���Ȃ��̂ł��낤���B
|
���@���[�J�̋Z�p�҂͏o�������ɍő�̊S������A�o���̏�Q�ɂȂ肩�˂Ȃ��V�Z�p�ɂ͖��S
�@
�@�̂�����{�͎��s�Ɍ������Љ�ł��邱�Ƃ͗ǂ��m���Ă���C���X�N�̍����V�Z�p�̊J���Ɋւ���ăT�����[�}���l���ł̗��ގ҂ɂ�
�肽���Ȃ��l���Ă���l�������Ɖ]���Ă���B�����āA���l����Ă����G���W���̔R��팸���̐V�Z�p�ɑ��A�u�\�������G�v�A�u�R�X�g
���Ŏ��p���Ɍ�����v�A�u�d�ʑ��������v�A�u���ڐ��ɓ��v�A�u�J����c��v�A�u���ʂ��^��v �ƔN����N���A�\���Ԃ̉̂��̂��悤
�ɑ吺�ł��������ᔻ���J��Ԃ����Ƃɂ���āA��i�� �u�o����l�ԁv �Ƃ��Ĕ��荞�ނ��Ƃ��o���̑����ƍl���Ă���l�������悤�ł�
��B���Ắu�t�F�A�v���[���_�v���O�ꂵ���Љ�ł́A���̐l����Ă����V�Z�p��ᔻ����ꍇ�ɂ́A�ᔻ����l����Ă̐V�Z�p���Ă�
��`�����ׂ����Ƃ����ɁA���R�̂��Ƃƍl�����Ă���B���̗��R�͎���̊e�l�����҂̋c�_�̓��e�𐳓��ɕ]�����邽�߂ł��낤�B
�������A�����̓��{�̉�Ђł́A�V��Ă�ᔻ����l����Ă����`����Ȃ����Ă���������ɁA���{�l�ɋ����i�ݍ�������
�`���A����l����Ă����V�Z�p�ɑ��Ď���̖w�ǂ̐l����Ăɔᔻ���n�߂�ƂȂ��Ă��܂��̂ł���B���̂��߁A������A�^�ʖڂ�
�V�Z�p���l���Ē�Ă����҂��퍐�̗���ɂȂ�A����A�S���V�Z�p���l���Ă��Ȃ�����̑����̐l�������̗���ōD������ɔᔻ�ł���
����ɂȂ�̂ł���B�o��Y���ł���Ղ����{�̉�Ђ̓����ł͂Ȃ����낤���B
�@
�@���̂悤�ɁA�V�Z�p���Ă����ꍇ�ɂ͔퍐�̗���ɗ�������A�������猟���̔@���������Njy����Ă��܂����Ƃ��ɂ߂đ����̂ł���B
���̂��߁A�g���b�N���[�J�̑����̃G���W���Z�p�҂́A���炪���X�N�̔����V�Z�p���Ă��Ȃ��悤�ɂ��邱�Ƃ��o���̓�����O��Ȃ��ŃT��
���[�}���������Ȃ�����Œ�ɏ����ł���ƐS���Ă���悤���B�����āA��i����J�����w�����ꂽ�Z�p�ɂ��ẮA�Ⴆ�������g���^
��Ɋ����Ă���Z�p�ł����Ă��A���_�̎w�E���o�����������邱�Ƃɂ������i�̐S��ǂ����邱�Ƃ��A����̐l���������ł�����
�ɏo���E���i�ł���d�v�ȏ����p�ƍl���Ă���l�������悤���B���ꂪ�g���b�N���[�J�ɒ��V��I�ȋZ�p�҂𖠉������Ă���傫�Ȍ�����
�͂Ȃ����낤���B
�@���̂悤���g���b�N���[�J�̃G���W���Z�p�҂��A�����C���x�~�G���W���Ɖ]���V�Z�p���R����P�ɗL���ł��邱�Ƃ𗝉������Ƃ��Ă��A����
�Z�p���Ă����ꍇ�ɑ��������i�����̐l������ܒ@��������A�C���x�~�G���W���̋Z�p��َE����\���͏\���ɍl������B��
�̂悤�ȉ�Ђł́A�u�ᔻ���邱�Ƃ��d�v�Ȏd���̈�v�ƔF������A�u�ᔻ�̔\�͂̌��オ�o���̍ő�̕���v�Ƃ̊Ԉ�����l��������
�Ă���l�B�����Ă�����̂Ɨ\�z�����B���̂悤�ȉ�Ђł́A�u�V�Z�p�̒�Ăɑ���ᔻ���V�����Z�p�J���̏d��ȏ�ǁv�ɂȂ���
���邱�ƂɋC�t���Ă��Ȃ����Ƃ͖��炩���B�܂��A�f�B�[�[���G���W���̂悤�ȂP�O�O�N�ȏ�̒������j���o�Ĕ��W���Ă����Z�p�̋ƊE��
�́A���Ђ̋Z�p��^���邱�Ƃ��ŏd�v�̎d���ƍl���Ă���l�������悤���B���̂悤�Ȑl�B�́A�������g�ł͍ŏ�����V�����Z�p���J����
����Ƃ͐S�ꂩ��v���Ă��Ȃ����Ƃ����̉�Ђ̍ő�̕a���i�����j�ł͂Ȃ����낤���B
|
�@���Ă��āA����A�����U�A�t�c�A�O�H�ӂ����̊e�g���b�N���[�J�̃G���W���Z�p�҂́A�R�X�g�����̏��Ȃ��R�ĉ��P��
�T�����x�̔R����オ�����ł���ƁA�����ɐM���Ă���悤���B���̂��߁A�g���b�N���[�J�̃G���W���Z�p�҂́A�R�X�g
������u�Q�^�[�{�ߋ��@�����̑�^�g���b�N�p�C���x�~�f�B�[�[���G���W���̋Z�p�v����Ȃɖ����������Ă����
���������B�R�X�g�����̔@���ɂ�����炸�A�X�Ȃ�R����P�̌��ʂ�����ȔR�ĉ��P������̃f�B�[�[���G���W
���ɂƂ��Ă̋Z�p�I�ȉ��l�̖w��ǖ������ƂɋC�t���Ă��Ȃ��悤���B���ɁA�g���b�N���[�J�̋Z�p�n�����ɂ́A�V��
�@���̐M�҂̔@���u�R�ĉ��P�ɂ��R����オ�\�v�ƍ����ł��M���ċ^��Ȃ��ÓT�I�ȃf�B�[�[���G���W���Z�p��
�������Ɏ嗬���߂Ă���̂ł͂Ȃ����ƍl������B����́A�M�҂̕��������ł��낤���B
�T�����x�̔R����オ�����ł���ƁA�����ɐM���Ă���悤���B���̂��߁A�g���b�N���[�J�̃G���W���Z�p�҂́A�R�X�g
������u�Q�^�[�{�ߋ��@�����̑�^�g���b�N�p�C���x�~�f�B�[�[���G���W���̋Z�p�v����Ȃɖ����������Ă����
���������B�R�X�g�����̔@���ɂ�����炸�A�X�Ȃ�R����P�̌��ʂ�����ȔR�ĉ��P������̃f�B�[�[���G���W
���ɂƂ��Ă̋Z�p�I�ȉ��l�̖w��ǖ������ƂɋC�t���Ă��Ȃ��悤���B���ɁA�g���b�N���[�J�̋Z�p�n�����ɂ́A�V��
�@���̐M�҂̔@���u�R�ĉ��P�ɂ��R����オ�\�v�ƍ����ł��M���ċ^��Ȃ��ÓT�I�ȃf�B�[�[���G���W���Z�p��
�������Ɏ嗬���߂Ă���̂ł͂Ȃ����ƍl������B����́A�M�҂̕��������ł��낤���B
�@���������āA����A�g���b�N�ƊE�ł́u�R�ĉ��P�ɂ��R����オ�\�v�ƍl����V���@���̂悤�ȁu�R�ĉ��P���v��
�M�҂̃}�C���h�R���g���[�����o�߂�܂ŁA�T���O��̔R�����P�͎����ł��Ȃ��Ɨ\�z�����B����܂ł̔R�ĉ��P
����̂Ƃ����Z�p�i���̒������j���l����ƁA�f�B�[�[���R�Ẳ��P�ɂ���čX�Ȃ�R����オ�ɂ߂ėe�Ղł͂�
���ƍl����̂��Ó��ł͂Ȃ����낤���B���̂��߁A�R�ĉ��P�����ɍS���Ă���A���E�����A�b�ƌ��킹��悤�ȐV
�Z�p�̊J���ɐ������Ȃ�����A�T���O��̔R�����P�͎����ł��Ȃ��ƍl������B���̂悤�Ȋv�V�I�ȃf�B�[�[���R
�Ẳ��P�Z�p�́A�]���̓V�˂Ŗ�������s�\�ł͂Ȃ����낤���B���������āA�g���b�N���[�J�́u�R�ĉ��P�ɂ��R
�����v��M�Ă��鑽���̃G���W���Z�p�ҁE���ƂɁA�߂����ɑ�^�g���b�N�̔R�������������邱�Ƃ����҂�
�邱�Ƃ́A���ʂƉ]�����̂��낤�B
�M�҂̃}�C���h�R���g���[�����o�߂�܂ŁA�T���O��̔R�����P�͎����ł��Ȃ��Ɨ\�z�����B����܂ł̔R�ĉ��P
����̂Ƃ����Z�p�i���̒������j���l����ƁA�f�B�[�[���R�Ẳ��P�ɂ���čX�Ȃ�R����オ�ɂ߂ėe�Ղł͂�
���ƍl����̂��Ó��ł͂Ȃ����낤���B���̂��߁A�R�ĉ��P�����ɍS���Ă���A���E�����A�b�ƌ��킹��悤�ȐV
�Z�p�̊J���ɐ������Ȃ�����A�T���O��̔R�����P�͎����ł��Ȃ��ƍl������B���̂悤�Ȋv�V�I�ȃf�B�[�[���R
�Ẳ��P�Z�p�́A�]���̓V�˂Ŗ�������s�\�ł͂Ȃ����낤���B���������āA�g���b�N���[�J�́u�R�ĉ��P�ɂ��R
�����v��M�Ă��鑽���̃G���W���Z�p�ҁE���ƂɁA�߂����ɑ�^�g���b�N�̔R�������������邱�Ƃ����҂�
�邱�Ƃ́A���ʂƉ]�����̂��낤�B
�@�Ƃ���ŁA�e�g���b�N���[�J�̃G���W���Z�p�҂���i���������ݒ肳��āu��^�g���b�N�ɂ����ĂT�����x�̔R����
�P�v�̎��㖽�߂����ꍇ�ɂ́A�ނ�́u�M���҂͘m�����͂ށv�v���ŁA�M�Ғ�Ắu�Q�^�[�{�ߋ��@�����̋C
���x�~�f�B�[�[���G���W���i�������J2005-54771�j�v�̋Z�p�̌��ʂ��m�F���邽�߂̍�Ƃɒ��肷����̂Ɨ\�z����
����B�����āA���́u�Q�^�[�{�ߋ��@�����̋C���x�~�f�B�[�[���G���W���i�������J2005-54771�j�v�̊J�������s�����g
���b�N���[�J�ł́A���̃V�X�e�����̂�����قǕ��G�ł͂Ȃ����߂ɂT�`�P�O�����x�̔R������P������^�g���b�N�p
�G���W���𑼎Ђɐ�삯�Ď����ł���K�^�Ɍb�܂�邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��Ȃ����낤�B
�P�v�̎��㖽�߂����ꍇ�ɂ́A�ނ�́u�M���҂͘m�����͂ށv�v���ŁA�M�Ғ�Ắu�Q�^�[�{�ߋ��@�����̋C
���x�~�f�B�[�[���G���W���i�������J2005-54771�j�v�̋Z�p�̌��ʂ��m�F���邽�߂̍�Ƃɒ��肷����̂Ɨ\�z����
����B�����āA���́u�Q�^�[�{�ߋ��@�����̋C���x�~�f�B�[�[���G���W���i�������J2005-54771�j�v�̊J�������s�����g
���b�N���[�J�ł́A���̃V�X�e�����̂�����قǕ��G�ł͂Ȃ����߂ɂT�`�P�O�����x�̔R������P������^�g���b�N�p
�G���W���𑼎Ђɐ�삯�Ď����ł���K�^�Ɍb�܂�邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��Ȃ����낤�B
�@�ȏ�̂��Ƃ���A�u�Q�^�[�{�ߋ��@�����̋C���x�~�f�B�[�[���G���W�������p�ɐ��������g���b�N���[�J�́A�T
�`�P�O�����x�̏d�ʎԃ��[�h�R��l�����P���ł��邽�߁A���Ђ̑�^�g���b�N�̏��i�͂��ꋓ�ɍ��߂邱��
���ł���v ���Ƃ��A���̃y�[�W�̏d�v�ȕM�҂̎咣�̈�ł���B�G�z�Ȃ���A����A�����Q�^�[�{�ߋ��@������
�C���x�~�f�B�[�[���G���W���i�������J2005-54771�j�����i�������g���b�N���[�J�́A���Ђ����R��̗D��
����^�g���b�N�E�g���N�^��o�����Ƃ��ł��邽�߁A���̌�̔̔��V�F�A��{�����ď����g�ɂȂ邱�Ƃ͊Ԉ�
���Ȃ��ƐM���Ă���B
�`�P�O�����x�̏d�ʎԃ��[�h�R��l�����P���ł��邽�߁A���Ђ̑�^�g���b�N�̏��i�͂��ꋓ�ɍ��߂邱��
���ł���v ���Ƃ��A���̃y�[�W�̏d�v�ȕM�҂̎咣�̈�ł���B�G�z�Ȃ���A����A�����Q�^�[�{�ߋ��@������
�C���x�~�f�B�[�[���G���W���i�������J2005-54771�j�����i�������g���b�N���[�J�́A���Ђ����R��̗D��
����^�g���b�N�E�g���N�^��o�����Ƃ��ł��邽�߁A���̌�̔̔��V�F�A��{�����ď����g�ɂȂ邱�Ƃ͊Ԉ�
���Ȃ��ƐM���Ă���B
�P�Q�|�T�D�C���x�~�G���W���̌����J�������{���Ȃ���^�g���b�N���[�J�̕s�v�c
�@�Q�O�P�O�N�X�����݁A�����̃g���b�N���[�J�ł́A�|�X�g�V�����r�o�K�X�K���i2009�N�K���j�ɓK�������ꕔ�̑�^�g��
�b�N�ł͂Q�O�P�T�N�x�d�ʎԔR���ɓK���ł��Ă��Ȃ��̂ł���B���̂悤�ɁA�Q�O�P�O�N�X�����݁A�|�X�g�V�����r
�o�K�X�K���i�Q�O�O�X�N�K���j�ɓK��������^�g���b�N�ɂ����āA�Ԏ�̑����̑��Ⴊ������̂́A�����̑�^�g���b�N��
�[�J�ɂ����ĂQ�O�P�T�N�x�d�ʎԔR���ɓK���ł��Ă��Ȃ��Ԏ������Ă���̂ł���B���̂��߁A�����̑�^�g��
�b�N���[�J�ɂ����āA�e�Ђ��̔�����S�Ă̑�^�g���b�N���Q�O�P�T�N�x�d�ʎԔR���ɓK�������邽�߂ɂ́A��^
�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W���̏d�ʎԃ��[�h�R��l���T�p�[�Z���g���x�����P���ł���V���ȋZ�p���J������K�v
�ƂȂ��Ă���̂����B
�b�N�ł͂Q�O�P�T�N�x�d�ʎԔR���ɓK���ł��Ă��Ȃ��̂ł���B���̂悤�ɁA�Q�O�P�O�N�X�����݁A�|�X�g�V�����r
�o�K�X�K���i�Q�O�O�X�N�K���j�ɓK��������^�g���b�N�ɂ����āA�Ԏ�̑����̑��Ⴊ������̂́A�����̑�^�g���b�N��
�[�J�ɂ����ĂQ�O�P�T�N�x�d�ʎԔR���ɓK���ł��Ă��Ȃ��Ԏ������Ă���̂ł���B���̂��߁A�����̑�^�g��
�b�N���[�J�ɂ����āA�e�Ђ��̔�����S�Ă̑�^�g���b�N���Q�O�P�T�N�x�d�ʎԔR���ɓK�������邽�߂ɂ́A��^
�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W���̏d�ʎԃ��[�h�R��l���T�p�[�Z���g���x�����P���ł���V���ȋZ�p���J������K�v
�ƂȂ��Ă���̂����B
�@�Ƃ���ŁA��^�g���b�N�̔R��K���ł���2015�N�x�d�ʎԔR����2006�N4��1���Ɏ{�s���ꂽ�B���̂��߁A��^
�g���b�N���[�J���S�N�ȏ���O����2015�N�x�d�ʎԔR���ɑ�^�g���b�N��K�������邽�߂ɁA,�K���ŔR��팸�Z
�p�̊J���Ɏ��g��ł������ł���B�������Ȃ���A�����̑�^�g���b�N���[�J�́A����܂łɊe�Ђ��̔������^�g��
�b�N�̑S�Ă̎Ԏ���Q�O�P�T�N�x�d�ʎԔR���ɓK���������^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W���̋Z�p���J���ł���
�������悤���B���̑傫�Ȍ����́A�e�g���b�N���[�J�̊������R�X�g�A�b�v�������Ȃ���^�g���b�N�̔R�����P�̋Z�p��
���肵���J�����w�����Ă������߂ł͂Ȃ����Ǝv���Ă���B���̂��Ƃ́A�e�g���b�N���[�J�̊������R�����P�̓��
�\���ɗ������Ă��Ȃ����߂Ɛ��������B���R�̂��ƂȂ���A��^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W���̔R�����P�́A����
�ȂɊÂ��͂Ȃ��̂ł���B
�g���b�N���[�J���S�N�ȏ���O����2015�N�x�d�ʎԔR���ɑ�^�g���b�N��K�������邽�߂ɁA,�K���ŔR��팸�Z
�p�̊J���Ɏ��g��ł������ł���B�������Ȃ���A�����̑�^�g���b�N���[�J�́A����܂łɊe�Ђ��̔������^�g��
�b�N�̑S�Ă̎Ԏ���Q�O�P�T�N�x�d�ʎԔR���ɓK���������^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W���̋Z�p���J���ł���
�������悤���B���̑傫�Ȍ����́A�e�g���b�N���[�J�̊������R�X�g�A�b�v�������Ȃ���^�g���b�N�̔R�����P�̋Z�p��
���肵���J�����w�����Ă������߂ł͂Ȃ����Ǝv���Ă���B���̂��Ƃ́A�e�g���b�N���[�J�̊������R�����P�̓��
�\���ɗ������Ă��Ȃ����߂Ɛ��������B���R�̂��ƂȂ���A��^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W���̔R�����P�́A����
�ȂɊÂ��͂Ȃ��̂ł���B
���b�N�������̎Ԏ���������܂܂ł���B����ɂ��āA��������^�g���b�N���[�J�́A���Ђ̑�^�g���b�N�E�g���N�^��
�������Ԏ킪�Q�O�P�T�N�x�d�ʎԔR���ɕs�K���ƂȂ��Ă��邱�Ƃ����l���̂悤�ɖ������A���Ђ̑�^�g���b�N�E
�g���N�^���u��R��v��u�G�R���W�[�v�ł���Ɛ����ɐ�`���Ă���̂ł���B����ɂ��āA�g���b�N���[�J�̐��Ƃ́A
�ӔC�̂���Љ�l�Ƃ��Ēp���������Ȃ��̂ł��낤�����B���̂悤�ȃg���b�N���[�J�̍s�ׂ́A�����ɂ���Ă͍��\�I��
�����Ă��d�����Ȃ��̂ł͂Ȃ����낤���B
�@����A��^�g���b�N��2015�N�x�d�ʎԔR�����{�s���ꂽ��������2006�N4��7���ɁA�M�҂��z�[���y�[�W���J
�݂��A��^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W���̂T�`10���p�[�Z���g���x�̏d�ʎԃ��[�h�R��l�̉��P���\�ȋZ�p�ł�
���C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j���Ă����̂ł���B�������A�M�҂���Ă���C���x�~�G���W���i����
���J2005-54771�j�̋Z�p�́A��^�G���W���p�ߋ��@�̔����̗e�ʂ̉ߋ��@���Q��ɑ��₷�K�v�����邽�߂ɑ���
�̃R�X�g�A�b�v�����Ƃ���A�R�X�g�A�b�v�������g���b�N���[�J�����������ꂽ�̂ł͂Ȃ����낤���B���̌��ʁA������
��^�g���b�N���[�J�́A�\�P�S�Ɏ������悤�ȑ�^�g���b�N�̑����̎Ԏ�ɂ����āA2015�N�x�d�ʎԔR���ɓK���ł�
�Ă��Ȃ��Ԏ��̔�������Ȃ��Ɖ]���A��^�g���b�N���[�J�Ƃ��Ă͕s�l�ȏ��i�\���̗l����悵�Ă��܂����̂�
����B
�݂��A��^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W���̂T�`10���p�[�Z���g���x�̏d�ʎԃ��[�h�R��l�̉��P���\�ȋZ�p�ł�
���C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j���Ă����̂ł���B�������A�M�҂���Ă���C���x�~�G���W���i����
���J2005-54771�j�̋Z�p�́A��^�G���W���p�ߋ��@�̔����̗e�ʂ̉ߋ��@���Q��ɑ��₷�K�v�����邽�߂ɑ���
�̃R�X�g�A�b�v�����Ƃ���A�R�X�g�A�b�v�������g���b�N���[�J�����������ꂽ�̂ł͂Ȃ����낤���B���̌��ʁA������
��^�g���b�N���[�J�́A�\�P�S�Ɏ������悤�ȑ�^�g���b�N�̑����̎Ԏ�ɂ����āA2015�N�x�d�ʎԔR���ɓK���ł�
�Ă��Ȃ��Ԏ��̔�������Ȃ��Ɖ]���A��^�g���b�N���[�J�Ƃ��Ă͕s�l�ȏ��i�\���̗l����悵�Ă��܂����̂�
����B
�@���x���̌J��Ԃ��Ƃ͂Ȃ邪�A�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�́A��^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W����
�R����T�����x�����P�ł���Z�p�ł���B����A�ŋ߂̎����ԋZ�p�����{�@�B�w��Ŕ��\����Z�p������ƁA�M
�҂̌����Ƃ������邩���m��Ȃ����A�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�Ɠ������x���̔R����P���\��
����Z�p�̔��\�E���Ă������悤�Ɍ�����̂ł���B�����_�ł́A��^�g���b�N�֘A�̔R��팸�̋Z�p�J��
���x�X�Ƃ��Đi��ł��Ȃ��̂ł͂Ȃ����낤���B�M�҂̂悤�ȋƊE�̏��ɑa���҂��猩�����A��^�g���b�N���[�J
�́A2015�N�x�܂łɑS�Ă̑�^�g���b�N�E�g���N�^�̑S�Ԏ��2015�N�x�d�ʎԔR���ɓK��������Z�p�������ł�
�Ă���悤�ɂ͎v���Ȃ��̂ł���B���̂悤�ȏɂ���ɂ�������炸�A�g���b�N���[�J�̐��Ƃ́A�T�`10�����x
�̏d�ʎԃ��[�h�R��l�̉��P���\���C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p���A��Ȃɖ����������Ă�
��̂��B�M�҂ɂ́A���ɕs�v�c�Ȃ��ƂɎv���Ďd�����Ȃ��B
�R����T�����x�����P�ł���Z�p�ł���B����A�ŋ߂̎����ԋZ�p�����{�@�B�w��Ŕ��\����Z�p������ƁA�M
�҂̌����Ƃ������邩���m��Ȃ����A�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�Ɠ������x���̔R����P���\��
����Z�p�̔��\�E���Ă������悤�Ɍ�����̂ł���B�����_�ł́A��^�g���b�N�֘A�̔R��팸�̋Z�p�J��
���x�X�Ƃ��Đi��ł��Ȃ��̂ł͂Ȃ����낤���B�M�҂̂悤�ȋƊE�̏��ɑa���҂��猩�����A��^�g���b�N���[�J
�́A2015�N�x�܂łɑS�Ă̑�^�g���b�N�E�g���N�^�̑S�Ԏ��2015�N�x�d�ʎԔR���ɓK��������Z�p�������ł�
�Ă���悤�ɂ͎v���Ȃ��̂ł���B���̂悤�ȏɂ���ɂ�������炸�A�g���b�N���[�J�̐��Ƃ́A�T�`10�����x
�̏d�ʎԃ��[�h�R��l�̉��P���\���C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p���A��Ȃɖ����������Ă�
��̂��B�M�҂ɂ́A���ɕs�v�c�Ȃ��ƂɎv���Ďd�����Ȃ��B
�P�R�D����̂m�n���K���̋������e
�P�R�|�P�@�������R�c��̑�\�����\�Ɏ����ꂽ��^�g���b�N�E�o�X�̂m�n���K���̋���
�@
�@����̔r�o�K�X�K���̋����ɂ��āA2010�N��7��28���ɒ������R�c�����Ȃɑ�\�����\���s���
���B���̑�\�����\�ɂ��ƁAGVW7.5�g�������̑�^�g���b�N�E�o�X�̂m�n���K���̋����́A�\�Q�P�Ɏ������ʂ�A����
�̂m�n���K���l�@���@0.4 g/kWh�@�ł���A2016�N�Ɏ��{���\�肳��Ă���Ƃ̂��Ƃł����B
���B���̑�\�����\�ɂ��ƁAGVW7.5�g�������̑�^�g���b�N�E�o�X�̂m�n���K���̋����́A�\�Q�P�Ɏ������ʂ�A����
�̂m�n���K���l�@���@0.4 g/kWh�@�ł���A2016�N�Ɏ��{���\�肳��Ă���Ƃ̂��Ƃł����B
| |
|
|
| |
|
|
�@���������̂m�n���K���l�i�|�X�g�E�|�X�g�V�����j�̔r�o�K�X�����ł́A�ȉ��Ɏ����������@�̕ύX���s����Ƃ�
���Ƃł���B
���Ƃł���B
�@ �Z�p�J���R�X�g�̌y�����Ɏ����邽�߁A���s�̔r�o�K�X�����T�C�N���iJE05 ���[�h�j���A�䂪�����Q��̂��ƍ�
�A���B�o�ψψ�����Ԋ���a���E�t�H�[�����i�ȉ��uUN-ECE/WP29�v�Ƃ����B�j�ɂ����č��肳�ꂽ���E���ꎎ
���T�C�N���ł���WHTC�iWorld Harmonized Transient Cycle�j�ɕύX����B
�A���B�o�ψψ�����Ԋ���a���E�t�H�[�����i�ȉ��uUN-ECE/WP29�v�Ƃ����B�j�ɂ����č��肳�ꂽ���E���ꎎ
���T�C�N���ł���WHTC�iWorld Harmonized Transient Cycle�j�ɕύX����B
�A �r�o�K�X�㏈�����u�̏����Ⴂ�G���W����Ԏ��̔r�o�K�X�̒ጸ��}�邽�߁A�]���̃G���W���g�@���i�z
�b�g�X�^�[�g�j�r�o�K�X�����ɉ����A�G���W����Ԏ��i�R�[���h�X�^�[�g�j�r�o�K�X���������A�R�[���h�X�^�[�g�r�o�K
�X�����ɂ�鑪��l��14���̔䗦�ŁA�܂��A�z�b�g�X�^�[�g�r�o�K�X�����ɂ�鑪��l��86���̔䗦�ŁA���ꂼ��d
�ݕt�����č��v�����l��r�o�K�X����l�Ƃ���B
�b�g�X�^�[�g�j�r�o�K�X�����ɉ����A�G���W����Ԏ��i�R�[���h�X�^�[�g�j�r�o�K�X���������A�R�[���h�X�^�[�g�r�o�K
�X�����ɂ�鑪��l��14���̔䗦�ŁA�܂��A�z�b�g�X�^�[�g�r�o�K�X�����ɂ�鑪��l��86���̔䗦�ŁA���ꂼ��d
�ݕt�����č��v�����l��r�o�K�X����l�Ƃ���B
�@���ɁA�R�[���h�X�^�[�g�r�o�K�X�����ɂ��ẮA����܂ł̔r�o�K�X�K���̋����ɂ��A�z�b�g�X�^�[�g���̔r�o�K
�X�ʂ́A���ɒႢ���x���ƂȂ����A����A�R�[���h�X�^�[�g���̔r�o�K�X�ʂ����ΓI�ɑ傫���Ȃ�ƍl�����
�Ƃ̂��ƁB���������āA�z�b�g�X�^�[�g���̔r�o�K�X����l�݂̂ɂ��K���ł́A�r�o�K�X��L���ɒጸ�ł��Ȃ��ƍl
�����邽�߁A�����r�o�K�X�K���ɂ����ẮA�R�[���h�X�^�[�g���̔r�o�K�X���������邱�Ƃ��K���Ƃ̗��R��
����B
�X�ʂ́A���ɒႢ���x���ƂȂ����A����A�R�[���h�X�^�[�g���̔r�o�K�X�ʂ����ΓI�ɑ傫���Ȃ�ƍl�����
�Ƃ̂��ƁB���������āA�z�b�g�X�^�[�g���̔r�o�K�X����l�݂̂ɂ��K���ł́A�r�o�K�X��L���ɒጸ�ł��Ȃ��ƍl
�����邽�߁A�����r�o�K�X�K���ɂ����ẮA�R�[���h�X�^�[�g���̔r�o�K�X���������邱�Ƃ��K���Ƃ̗��R��
����B
�@���āA��L�̕\�Q�P�̎����̂m�n���K���l�́A�Q005�N�̑攪�����\�ɂm�n���̒���ڕW�Ƃ��Ď�����Ă����@0.7 g/
kWh�� 1/3���x�i���@0.23�@g/kWh�j����0.4 g/kWh�܂łɕs���Ɋɘa���ꂽ�o�܂ɂ��āA����܂ł̒������R�c
��̓��\��i�Ɓj��ʈ��S���������̘_���̊T�v���A�ȉ��̕\A�ɉ���Ղ��܂Ƃ߂��B
kWh�� 1/3���x�i���@0.23�@g/kWh�j����0.4 g/kWh�܂łɕs���Ɋɘa���ꂽ�o�܂ɂ��āA����܂ł̒������R�c
��̓��\��i�Ɓj��ʈ��S���������̘_���̊T�v���A�ȉ��̕\A�ɉ���Ղ��܂Ƃ߂��B
| |
|||
| |
�� �f�B�[�[���d�ʎԁi12�g�������̐V�^�ԁj�ɂ����āA�u�攪�����\�̋��e��
�x�ڕW�l�i���ϒl�j�� 0.7 ��/��W���v�i���z�b�g�X�^�[�g��JE05���[�h�����j��
2009�N�Ɏ��{
�i���F�č��̃f�B�[�[���d�ʎԂ́A�u2010�N��NO���K���l��0.27��/kW���i���z�b�g�X�^�[�g�{�R�[�� �h�X�^�[�g��1199���[�h�j�����{�j �� �u���\�̈Ӌ`�v�Ƃ��āA�u�����2009�N�ڕW��0.7��/kW�������{���邱�Ƃ� ���A2009�`2010�N���_�ł͑�^�f�B�[�[���g���b�N�̕���Ő��E�ō��� �x���@��NO���K�������{�Ŏ��{�����v�ƋL�ڂ���Ă��邪�A����͌��ł� ��B�i2009�`2010�N���̃f�B�[�[���d�ʎԂɂ����ẮA���{�͕č��̔�r���� �đ啝�Ɋɂ��K�������{�j �� ���́u�攪�����\�v�ɂ́A�����̃f�B�[�[���d�ʎԂ�NO���K�������Ƃ��āA ����ڕW�i��0.7��/kW����1/3 ��0.23��/kW���j��� |
||
| |
�� �f�B�[�[���d�ʎԁi7.5�g�������̐V�^�ԁj���u��\�����\�̋��e���x�ڕW
�l�i���ϒl�j�� 0.4 ��/��W���v�i���z�b�g�X�^�[�g�{�R�[���h�X�^�[��WHTC��
�[�h�����j��2016�N�Ɏ��{
�i���F�č��̃f�B�[�[���d�ʎԂ́A�u2010�N��NO���K���l��0.27��/kW���i���z�b�g�X�^�[�g�{�R�[�� �h�X�^�[�g��1199���[�h�j�����{�j �� �u��\�����\�̋��e���x�ڕW�l�i���ϒl�j�� 0.4 ��/��W���iWHTC���[ �h�j�v�́A�攪�����\�̒���ڕW��0.23��/kW���i��0.7��/kW����1/3�FJE05 ���[�h�j�Ɂu�B���Ă���ƍl������v�ƋL������Ă���B���̂��Ƃ���A�䂪�� �̏����I�ȃf�B�[�[���d�ʎԂ�NO���K�������́A�攪�����\�̒���ڕW��0. 23��/kW���iJE05���[�h)�̃��x���ɂ���K�v�̂��邱�Ƃ𒆉����R�c��\ ���ɏ��m�E�������Ă��邱�Ƃ������������̂ƍl������B �����āA�f�B�[�[���d�ʎԂ�NO���K���������m���ɑ攪�����\�̒���ڕW��0. 23��/kW���iJE05���[�h)�̃��x���Ƃ��邽�߁A��\�����\�ɓY�t�̑�\���� �ɂ́A�iJE�O�T���[�h��NO���F0.4 ��/��W���j���iWHTC���[�h��NO���F0.26 ��/kW���j�� �����āA�u�\���ȃf�[�^���łȂ����߁A�����܂ł��ڈ��Ƃ��ĂƂ炦��ׂ��� �́v�Ƃ̒������L����Ă���B �܂�A�u��\�����\�̋��e���x�ڕW�l�i���ϒl�j�� 0.4 ��/��W���Ƒ攪�����\ �̒���ڕW��0.23��/kW���Ɠ����ł��邱�Ƃ��\���Ȏ����f�[�^�ɂ���Ċm�F�� ��Ă��Ȃ����߁A����̎������ʂɂ���Ċm�肷�ׂ����Ǝ�������A�������� �L�ڂ���Ă��邱�ƂɂȂ�B |
||
| �u�����d�ʎԗp�����T�C�N ���̔r�o�K�X���\�]���v 2014�v�Ŕ��\ |
�� JE�O�T���[�h���G���W���́A���E�ᕉ�ׂ̗̈�Ɍ��肵���^�]�i���}�́Z��
�̈�j�ł��邪�A WHTC���[�h���G���W���́A���E�ᕉ�ׁ{�����ׂ̑S�̈�ʼn^
�]�i���}�́Z�{�Z�̗̈�j�ł���B
�� �R��̋����G���W���̒���C�G���W���́A�G���W���̍����ׂ̗̈�i��JE�O �T�AWHTC�A�vHSC�̃G���W���^�]�́Z�̕��ח̈�j�ł́A�A�f���̋������~ �܂��͍팸���A�A�fSCR�G�}��NO���̊Ҍ��ɂ��r�C�K�X�@�\���Ӑ}�I �ɒ��~�܂��͒ቺ������u�r�o�K�X����̖������v�̐�����̗p���Ă���E�@�E ��@�ȃG���W���Ɛ��������B �� ���}�́A�u�r�o�K�X����̖������v��C�G���W���Ɏ����f�[�^���폜����JE�O �T���[�h�AWHTC���[�h�AWHSC���[�h��NO���r�o�l�ł���B
�� �d�ʎԗp�����T�C�N����WHTC���[�h�i���R�[���h�X�^�[�g�{�z�b�g�X�^�[�g�j��
JE�O�T���[�h�i���z�b�g�X�^�[�g�j��NO���r�o�l�́A�قړ���ł��邱�Ƃ����炩��
����B���������āA���{�̃f�B�[�[���d�ʎԂ�NO���K���́A�߂������ɂ́A��
�������\��NO������ڕW�Ɠ�����NO����0.23 ��/kW���i��WHTC���[�h�j�̃��x
���ɋ������ׂ����Ƃ͖��炩�ł���B
�������R�c��E��\�����\�Ɏ����ꂽ�u�f�B�[�[���d�ʎԂɂ�����NO�����e ���x�ڕW�l�F0.4 ��/��W���i��WHTC���[�h�j�́A�攪�����\��NO������ڕW�F0.23 ��/kW���i��JE�O�T���[�h�j�Ɠ����̃��x���ł���v�Ƃ̓��\�̓��e�́A���S�Ɍ�� �ł���Ɛ��@�����B �� �Ȃ��A�������R�c��E��\�����\�Ɏ����ꂽ�u�f�B�[�[���d�ʎԂɂ����� NO�����e���x�ڕW�l�F0.4 ��/��W���i��WHTC���[�h�j�́A�攪�����\��NO������ �ڕW�F0.23 ��/kW���i��JE�O�T���[�h�j�Ɠ����̃��x���ł���v�Ƃ̓��\�ɂ��āA �u�T�ˑÓ��Ȑ����Ƃ�����v�Ƃ���i�Ɓj��ʈ��S���������̗�؉��ꎁ�̎� ���́A�G���W���̍����ׂ̗̈�ł̔A�fSCR�G�}��NO���팸���\���ɋ@�\�� �Ȃ��悤�ɐ��䂵���u�r�o�K�X����̖������v���̗p������@�E�E�@�����C�G ���W���ɂ�����WHTC���[�h�ł̍���NO���r�o�l�������̂ƂȂ��Ă���͖̂��� ���ł���B�u�r�o�K�X����̖������v���̗p������@�E�E�@�����C�G���W���� NO���r�o�l�����NO�����e���x�ڕW�l�F0.4 ��/��W���i��WHTC���[�h�j�́A�� �������\��NO������ڕW�F0.23 ��/kW���i��JE�O�T���[�h�j�Ɠ����̃��x���ł���v ���Ƃ��������Ƃ́i�Ɓj��ʈ��S���������̗�؉��ꎁ�̘_�����\�́A�f �B�[�[���d�ʎԂ�2016�NNO����0.4 ��/��W�����s����NO���K���̊ɘa�ł��邱�� ���B�����邽�߂̌Ƒ��ȍs�ׂƍl������B |
�O�q�̒ʂ�A�m�n���K���ɂ��ẮA���Ȃ̒������R�c��́A2005�N4���̑攪�����\�ɂ́A�f�B�[�[���d�ʎ�
�ɂ��āA0.7 g/kWh�� 1/3���x�i���@0.23�@g/kWh�j�̂m�n���̒���ڕW��������Ă���B���������āA�|�X�g�r�o�K�X
�K���ɑ���2009�N�ɂm�n���K�������́A���R�A���̂m�n��������ڕW�ł���@0.23�@g/kWh�ɂȂ�Ƒ����̐l���\�z����
�����B�������A�������R�c��̑�\�����\�i2010�N7��28���Ɋ��Ȃɓ��\�j�ł́A2016�N�Ƀf�B�[�[���d�ʎ�
�i7.5�g�������̐V�^�ԁj�́u��\�����\�̋��e���x�ڕW�l�i���ϒl�j�� 0.4 ��/��W���v�i���z�b�g�X�^�[�g�{�R�[���h�X�^
�[��WHTC���[�h�����j�̎��{�����\���ꂽ�B�������Ȃ���A�f�B�[�[���d�ʎ�2016�NNOx�K����0.4g/kWh�́A�s��
�Ȋɘa�̌��K���ɏڏq���Ă���悤�ɁA���{�̃f�B�[�[���d�ʎԂ�NO���K���́A�߂������ɂ́A�攪�����\��
NO������ڕW�Ɠ�����NO����0.23 ��/kW���i��WHTC���[�h�j�̃��x���ɋ������ׂ����Ƃ͖��炩�ł���B
�ɂ��āA0.7 g/kWh�� 1/3���x�i���@0.23�@g/kWh�j�̂m�n���̒���ڕW��������Ă���B���������āA�|�X�g�r�o�K�X
�K���ɑ���2009�N�ɂm�n���K�������́A���R�A���̂m�n��������ڕW�ł���@0.23�@g/kWh�ɂȂ�Ƒ����̐l���\�z����
�����B�������A�������R�c��̑�\�����\�i2010�N7��28���Ɋ��Ȃɓ��\�j�ł́A2016�N�Ƀf�B�[�[���d�ʎ�
�i7.5�g�������̐V�^�ԁj�́u��\�����\�̋��e���x�ڕW�l�i���ϒl�j�� 0.4 ��/��W���v�i���z�b�g�X�^�[�g�{�R�[���h�X�^
�[��WHTC���[�h�����j�̎��{�����\���ꂽ�B�������Ȃ���A�f�B�[�[���d�ʎ�2016�NNOx�K����0.4g/kWh�́A�s��
�Ȋɘa�̌��K���ɏڏq���Ă���悤�ɁA���{�̃f�B�[�[���d�ʎԂ�NO���K���́A�߂������ɂ́A�攪�����\��
NO������ڕW�Ɠ�����NO����0.23 ��/kW���i��WHTC���[�h�j�̃��x���ɋ������ׂ����Ƃ͖��炩�ł���B
�P�R�|�Q�@�����̂m�n���K���̋������ɂ�����r�o�K�X�����@��NO���팸�̓�Ղɂ���
�@���L�̐}�P�T�̓��{�̔r�o�K�X�����@�iJE�O�T�j�A���B�̎����@�iETC�j����ѕč��̎����@�iFTP�j�̂��ꂼ��̎�
�����̃G���W�����ׂƉ�]���x�̕��z������ƁA�����B�̎����@�iETC�j��č��̎����@�iFTP�j�ɔ�ׁA���{�̎�
���@�iJE�O�T�j�ł̃G���W�����ׂ͂��Ȃ�Ⴂ���Ƃ������ł���ł���B���̂��Ƃ́A���Ẵg���b�N�́A�����̃g���b�N
�ɔ�ׂăG���W���̍����ׂ����p����鑖�s�ł���ƍl���ĊԈႢ�Ȃ��Ɛ��������B
�����̃G���W�����ׂƉ�]���x�̕��z������ƁA�����B�̎����@�iETC�j��č��̎����@�iFTP�j�ɔ�ׁA���{�̎�
���@�iJE�O�T�j�ł̃G���W�����ׂ͂��Ȃ�Ⴂ���Ƃ������ł���ł���B���̂��Ƃ́A���Ẵg���b�N�́A�����̃g���b�N
�ɔ�ׂăG���W���̍����ׂ����p����鑖�s�ł���ƍl���ĊԈႢ�Ȃ��Ɛ��������B
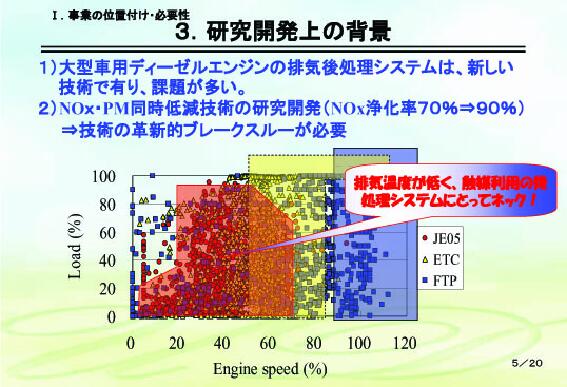
�@���̂��߁A���{�̔r�o�K�X�����@�iJE�O�T�j���A�fSCR�G�}�����̔r�C�K�X���x�́A���B�̎����@�iETC�j�����
�č��̎����@�iFTP�j�̂��ꂼ��̎��������A�fSCR�G�}�����̔r�C�K�X���x�����Ⴂ�X���ɂ��邱�Ƃ��e�Ղ�
�\�z�ł��邱�Ƃł����B���ہA���s���r�o�K�X�����@�ł���JE05 ���[�h�����ł́A�ȉ��̐}�P�U�Ɏ������悤�ɁA�A
�fSCR�G�}���̔r�o�K�X�㏈�����u�̓�����ɂ�����r�o�K�X�̕��ω��x�́A�P�X�V���ł���AJE�O�T���[�h�r�o�K
�X�����̖��̎��Ԃ��Q�O�O���ȉ��̉��x���x�ł���B �������A�A�fSCR�G�}�����̔r�C�K�X���x���Q�O�O����
���̏ꍇ�ɂ́A�A�fSCR�G�}�ɂ�����NO���팸�����}���ɒቺ��������������Ă���̂ł���B���̂����A���B��
�����@�iETC�j����ѕč��̎����@�iFTP�j�ɔ�r���A���{�̔r�o�K�X�����@�iJE�O�T�j�ł�SCR�G�}�����t�߂̔r�C
�K�X���x���Ⴍ�Ȃ�A�A�fSCR�G�}�ɂ��NO���팸�����ቺ���Ă��܂���������Ă��邽�̂ł���B
�č��̎����@�iFTP�j�̂��ꂼ��̎��������A�fSCR�G�}�����̔r�C�K�X���x�����Ⴂ�X���ɂ��邱�Ƃ��e�Ղ�
�\�z�ł��邱�Ƃł����B���ہA���s���r�o�K�X�����@�ł���JE05 ���[�h�����ł́A�ȉ��̐}�P�U�Ɏ������悤�ɁA�A
�fSCR�G�}���̔r�o�K�X�㏈�����u�̓�����ɂ�����r�o�K�X�̕��ω��x�́A�P�X�V���ł���AJE�O�T���[�h�r�o�K
�X�����̖��̎��Ԃ��Q�O�O���ȉ��̉��x���x�ł���B �������A�A�fSCR�G�}�����̔r�C�K�X���x���Q�O�O����
���̏ꍇ�ɂ́A�A�fSCR�G�}�ɂ�����NO���팸�����}���ɒቺ��������������Ă���̂ł���B���̂����A���B��
�����@�iETC�j����ѕč��̎����@�iFTP�j�ɔ�r���A���{�̔r�o�K�X�����@�iJE�O�T�j�ł�SCR�G�}�����t�߂̔r�C
�K�X���x���Ⴍ�Ȃ�A�A�fSCR�G�}�ɂ��NO���팸�����ቺ���Ă��܂���������Ă��邽�̂ł���B
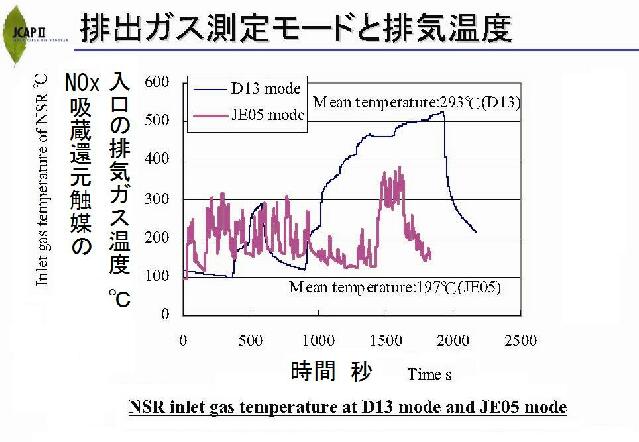
�@���̂悤�ɁA���s�̃f�B�[�[���G���W����JE�O�T���[�h�r�o�K�X�����ɂ����ẮA�A�fSCR�G�}�̓�����ɂ�����r
�C�K�X�̉��x���r�o�K�X�����̖��̎��Ԃ��Q�O�O���ȉ��̉��x�ɒቺ���Ă��܂����߂ɔA�fSCR�G�}�ł�NO��
�팸�����������ቺ���A�A�fSCR�G�}�ɂ��\����NO���̍팸������ȏɊׂ��Ă����̂��A����܂ł̉䂪��
�̌���ł������B
�C�K�X�̉��x���r�o�K�X�����̖��̎��Ԃ��Q�O�O���ȉ��̉��x�ɒቺ���Ă��܂����߂ɔA�fSCR�G�}�ł�NO��
�팸�����������ቺ���A�A�fSCR�G�}�ɂ��\����NO���̍팸������ȏɊׂ��Ă����̂��A����܂ł̉䂪��
�̌���ł������B
�@�Ƃ��낪�A����̎����Ԕr�o�K�X�ጸ��̂�����ɂ��āi��\�����\�j�ł́A������NO���K���̔r�o�K�X����
�@�i2016�N���܂łɎ��{�\��j�́A�u���s�̔r�o�K�X�����T�C�N���iJE05 ���[�h�j���A�䂪�����Q��̂��ƍ��A���B�o
�ψψ�����Ԋ���a���E�t�H�[�����i�ȉ��uUN-ECE/WP29�v�Ƃ����B�j�ɂ����č��肳�ꂽ���E���ꎎ���T�C�N
���ł���WHTC�iWorld Harmonized Transient Cycle�j�ɕύX����v�Ƃ̂��Ƃł���B
�@�i2016�N���܂łɎ��{�\��j�́A�u���s�̔r�o�K�X�����T�C�N���iJE05 ���[�h�j���A�䂪�����Q��̂��ƍ��A���B�o
�ψψ�����Ԋ���a���E�t�H�[�����i�ȉ��uUN-ECE/WP29�v�Ƃ����B�j�ɂ����č��肳�ꂽ���E���ꎎ���T�C�N
���ł���WHTC�iWorld Harmonized Transient Cycle�j�ɕύX����v�Ƃ̂��Ƃł���B
�@
�@���́u����̎����Ԕr�o�K�X�ጸ��̂�����ɂ��āi��\���j�v�̒���WHTC�����@�ɂ��ẮA�w�^�]��
��ɂ��āAWHTC�́AJE05���[�h�Ɣ�r���č���]�����ׂ܂ōL�����Ă��邪�AJE05���[�h�̍���]���ᕉ�ח̈�
�̂����ꕔ�J�o�[�ł��Ă��Ȃ�����������B����́A�����T�C�N���㔼�̍������s�����̕��ׂ̈Ⴂ�ɂ����̂�
���邪�A���ꂼ��̉^�]�̈�́A�傫�����Ⴗ����̂ł͂Ȃ��B�x�ƋL�ڂ���Ă���B
��ɂ��āAWHTC�́AJE05���[�h�Ɣ�r���č���]�����ׂ܂ōL�����Ă��邪�AJE05���[�h�̍���]���ᕉ�ח̈�
�̂����ꕔ�J�o�[�ł��Ă��Ȃ�����������B����́A�����T�C�N���㔼�̍������s�����̕��ׂ̈Ⴂ�ɂ����̂�
���邪�A���ꂼ��̉^�]�̈�́A�傫�����Ⴗ����̂ł͂Ȃ��B�x�ƋL�ڂ���Ă���B
�@�������A�}�P�V��WHTC�����@�ɂ�����Q��ނ̃G���W���i12.91���b�g���A4.01���b�g���j�̉�]���E���וp�x���z�}��
�������悤�ɁAWHTC�����@�͏]���̔r�o�K�X�����T�C�N���iJE05 ���[�h�j���������ׂ̉^�]�̈悪�L���Ȃ��Ă���
���Ƃ͖��炩�ł���B���̂��߁AWHTC�����@�̔r�o�K�X�������̔A�fSCR�G�}�̓����̔r�C�K�X���x��JE05 ��
�[�h���������ɂȂ�p�x���������邱�Ƃ��m���ł���B
�������悤�ɁAWHTC�����@�͏]���̔r�o�K�X�����T�C�N���iJE05 ���[�h�j���������ׂ̉^�]�̈悪�L���Ȃ��Ă���
���Ƃ͖��炩�ł���B���̂��߁AWHTC�����@�̔r�o�K�X�������̔A�fSCR�G�}�̓����̔r�C�K�X���x��JE05 ��
�[�h���������ɂȂ�p�x���������邱�Ƃ��m���ł���B
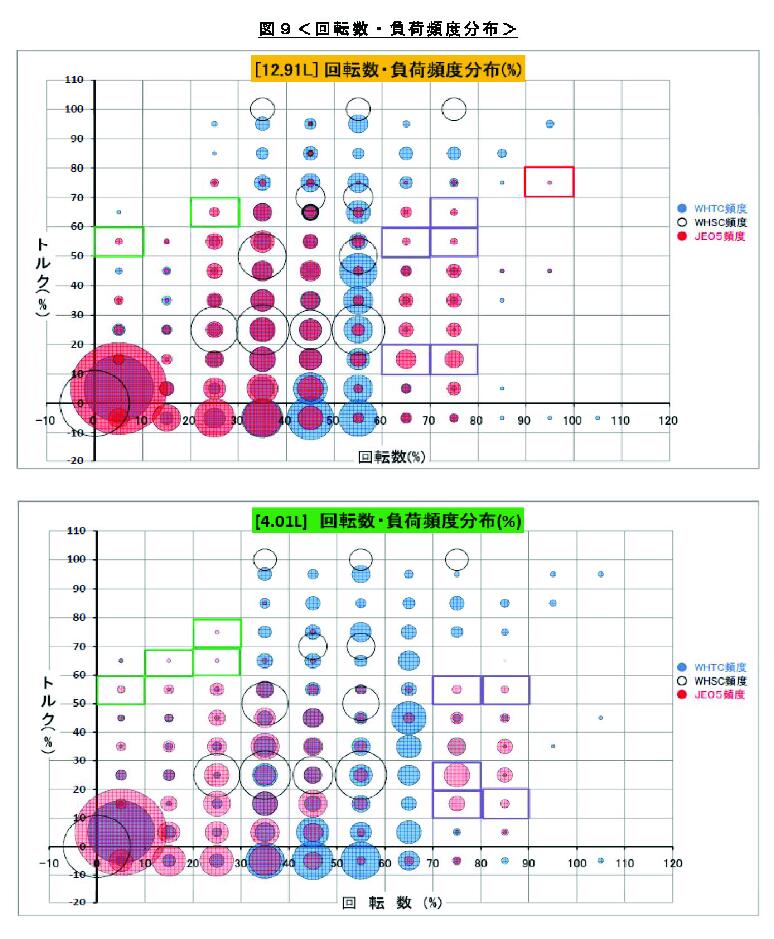
�@���̂悤�ɁAWHTC�����@�ł̔r�C�K�X���x�͏]����JE05 ���[�h�����̔r�C�K�X���x��荂���ƂȂ�^�]�̈悪
�L�����߁AWHTC�����@�ł̔r�o�K�X�����ł́A���s�̔r�o�K�X�����T�C�N���iJE05 ���[�h�j�̔r�o�K�X�����̏�
�������A�fSCR�G�}������NO���팸���Ɉێ��ł���̂ł���B�܂�A���s�̔r�o�K�X�����T�C�N���iJE05 ���[
�h�j�̔r�o�K�X�����ɔ�ׂāAWHTC�����@�ł̔r�o�K�X�����́A�A�fSCR�G�}�ɂ���đ�����NO�����팸�ł����
�l������̂ł���B���̌��ʁAWHTC�ő��肳�ꂽNO���r�o�l�́A�]����JE05 ���[�h�Ŕr�o�K�X�����œ���ꂽ
NO���r�o�l�����啝�ɒႢ�l�܂łɊȒP�ɍ팸�ł���悤�ɂȂ���̂Ɨ\�z�����B
�L�����߁AWHTC�����@�ł̔r�o�K�X�����ł́A���s�̔r�o�K�X�����T�C�N���iJE05 ���[�h�j�̔r�o�K�X�����̏�
�������A�fSCR�G�}������NO���팸���Ɉێ��ł���̂ł���B�܂�A���s�̔r�o�K�X�����T�C�N���iJE05 ���[
�h�j�̔r�o�K�X�����ɔ�ׂāAWHTC�����@�ł̔r�o�K�X�����́A�A�fSCR�G�}�ɂ���đ�����NO�����팸�ł����
�l������̂ł���B���̌��ʁAWHTC�ő��肳�ꂽNO���r�o�l�́A�]����JE05 ���[�h�Ŕr�o�K�X�����œ���ꂽ
NO���r�o�l�����啝�ɒႢ�l�܂łɊȒP�ɍ팸�ł���悤�ɂȂ���̂Ɨ\�z�����B
�@�Ƃ��낪�A����̎����Ԕr�o�K�X�ጸ��̂�����ɂ��āi��\�����\�j�ł́A2016�N�̔r�o�K�X�����@�ł�
NO�������������R�[���h�X�^�[�g�r�o�K�X�������lj�����邽�߂ɑ攪�����\�ɒ���Ă����f�B�[�[���d�ʎ�
��NOx�r�o�ʂ�09�N�K���i0.7g/kWh�j��1/3���x�Ƃ��钧��ڕW�l���A�����̂m�n���K���l�@���@0.4 g/kWh�@�ɘa����
�Ƃ̂��Ƃł���B�������A2016�N�̔r�o�K�X�����@�ɍ̗p�����\���WHTC�����@�ł̔r�o�K�X�����ł́A���s��
�r�o�K�X�����T�C�N���iJE05 ���[�h�j�̔r�o�K�X�����̏ꍇ�����A�fSCR�G�}�ɂ���ėe�Ղɑ�����NO���̍팸
���ł���\�����ے�ł��Ȃ��B���������āA2016�N�̔r�o�K�X�����@�ł́ANO�������������R�[���h�X�^�[�g�r�o
�K�X�������lj��������̂́A���̈���ł͔A�fSCR�G�}�ɂ���đ�����NO���̍팸���ł���WHTC�����@���̗p
����邽�߁A2016�N�̔r�o�K�X�����@�ɍ̗p�����WHTC�����@�ɂ����ẮANO�����P���ɑ�������Ƃ͕M�҂ɂ�
�l�����Ȃ��̂ł���B
NO�������������R�[���h�X�^�[�g�r�o�K�X�������lj�����邽�߂ɑ攪�����\�ɒ���Ă����f�B�[�[���d�ʎ�
��NOx�r�o�ʂ�09�N�K���i0.7g/kWh�j��1/3���x�Ƃ��钧��ڕW�l���A�����̂m�n���K���l�@���@0.4 g/kWh�@�ɘa����
�Ƃ̂��Ƃł���B�������A2016�N�̔r�o�K�X�����@�ɍ̗p�����\���WHTC�����@�ł̔r�o�K�X�����ł́A���s��
�r�o�K�X�����T�C�N���iJE05 ���[�h�j�̔r�o�K�X�����̏ꍇ�����A�fSCR�G�}�ɂ���ėe�Ղɑ�����NO���̍팸
���ł���\�����ے�ł��Ȃ��B���������āA2016�N�̔r�o�K�X�����@�ł́ANO�������������R�[���h�X�^�[�g�r�o
�K�X�������lj��������̂́A���̈���ł͔A�fSCR�G�}�ɂ���đ�����NO���̍팸���ł���WHTC�����@���̗p
����邽�߁A2016�N�̔r�o�K�X�����@�ɍ̗p�����WHTC�����@�ɂ����ẮANO�����P���ɑ�������Ƃ͕M�҂ɂ�
�l�����Ȃ��̂ł���B
�@�ȏ�̂悤�ɁA����̎����Ԕr�o�K�X�ጸ��̂�����ɂ��āi��\�����j�ɋL�ڂ���Ă���u�V���ȃR�[
���h�X�^�[�g�r�o�K�X�����ɂ��NO���̑����́A�V����WHTC�r�o�K�X�����ɂ������A�fSCR�G�}�ɂ��NO���̍팸
�ɂ���Ē������ɂł���\�����ے�ł��Ȃ��ƍl���Ă���B���������āA�����̂m�n���K���l�́A005�N�̑攪����
�\�ɂm�n���̒���ڕW�Ƃ��Ď�����Ă����@0.7 g/kWh�� 1/3���x�i���@0.23�@g/kWh�j��������I�ɑ啝�Ȋɘa���s��
�ꂽ�̂ł͖������Ǝv���Ă���B���̂��Ƃɂ��ẮA���̎����f�[�^���L���Ă��Ȃ��M�҂̒P�Ȃ�z���ł����Ȃ�
���A����ɂ��Đ��Ƃ̈ӌ����f���Ă݂������̂��B
���h�X�^�[�g�r�o�K�X�����ɂ��NO���̑����́A�V����WHTC�r�o�K�X�����ɂ������A�fSCR�G�}�ɂ��NO���̍팸
�ɂ���Ē������ɂł���\�����ے�ł��Ȃ��ƍl���Ă���B���������āA�����̂m�n���K���l�́A005�N�̑攪����
�\�ɂm�n���̒���ڕW�Ƃ��Ď�����Ă����@0.7 g/kWh�� 1/3���x�i���@0.23�@g/kWh�j��������I�ɑ啝�Ȋɘa���s��
�ꂽ�̂ł͖������Ǝv���Ă���B���̂��Ƃɂ��ẮA���̎����f�[�^���L���Ă��Ȃ��M�҂̒P�Ȃ�z���ł����Ȃ�
���A����ɂ��Đ��Ƃ̈ӌ����f���Ă݂������̂��B
�P�S�D�f�B�[�[���R�Ẳ��P�ł́A�啝�ȔR����オ����ȏ�
�P�S�|�P�@NEDO�́u�����x�R�Đ���G���W�V�X�e���̌����J���v�ł́A�R����̑厸�s
�@�f�B�[�[���G���W���̔R���NO���̍팸�ɂ��ẮA�����ʂŌ��������{����Ă��邪�A�ŋ߂̗L���Ȍ����v���W
�F�N�g�́A�}�P�W�Ɏ������V�G�l���M�[�E�Y�ƋZ�p�����J���@�\�iNEDO)�̊v�V�I���������Q�ԑ����Z�p�J���i�N
���[���f�B�[�[���v���W�F�N�g�A2004�`2009�N�j���B���̔R����P��NO���팸�̌����́A8��6��5�S���~�̗\�Z�Ŏ��{
���ꂽ�u�����x�R�Đ���G���W�V�X�e���̌����J���v�̑�^�v���W�F�N�g�ł���B���̌����J���ł́A�R�i�ߋ��V�X�e
����300MP���̒������R�����˂ɂ�鍂���ϗL�������A����уJ�����X�V�X�e����g�ݍ���ŁuPCI�iPremixed.
Compression Ignition combustion�j�R�āv�yHCCI�iHomogeneous-Charge Compression Ignitionnen�j�R�ĂƂ��]���z�̗�
����g�債�A����ɂ���āANO�����|�X�g�V������1/3�ጸ���A�R�������10�����P����ڕW���������悤��
������̂ł������B�ܘ_�A���̂悤�ȃG���W���d�l�́A�G���W���̃R�X�g������d�ʑ�����S���l�����Ȃ��ŏ����̎�
�p����������ł̏����ɋZ�p�̉\����Njy���錤���J���ł��������߂ƍl������B�����āA���̌����J��
�ɂ͓������W���~�ȏ�̖c��ȗ\�Z����������Ă��Ă������Ƃ���A���̌����J�����J�n���ꂽ2004�N�����A
�uPCI�R�āv�̑����ɐM�҂́A�f�B�[�[����NO���팸�ƔR�����P�̉ۑ肪�ꋓ�ɉ����ł���Ɗ��҂��Ă������̂ƍl��
����B
�F�N�g�́A�}�P�W�Ɏ������V�G�l���M�[�E�Y�ƋZ�p�����J���@�\�iNEDO)�̊v�V�I���������Q�ԑ����Z�p�J���i�N
���[���f�B�[�[���v���W�F�N�g�A2004�`2009�N�j���B���̔R����P��NO���팸�̌����́A8��6��5�S���~�̗\�Z�Ŏ��{
���ꂽ�u�����x�R�Đ���G���W�V�X�e���̌����J���v�̑�^�v���W�F�N�g�ł���B���̌����J���ł́A�R�i�ߋ��V�X�e
����300MP���̒������R�����˂ɂ�鍂���ϗL�������A����уJ�����X�V�X�e����g�ݍ���ŁuPCI�iPremixed.
Compression Ignition combustion�j�R�āv�yHCCI�iHomogeneous-Charge Compression Ignitionnen�j�R�ĂƂ��]���z�̗�
����g�債�A����ɂ���āANO�����|�X�g�V������1/3�ጸ���A�R�������10�����P����ڕW���������悤��
������̂ł������B�ܘ_�A���̂悤�ȃG���W���d�l�́A�G���W���̃R�X�g������d�ʑ�����S���l�����Ȃ��ŏ����̎�
�p����������ł̏����ɋZ�p�̉\����Njy���錤���J���ł��������߂ƍl������B�����āA���̌����J��
�ɂ͓������W���~�ȏ�̖c��ȗ\�Z����������Ă��Ă������Ƃ���A���̌����J�����J�n���ꂽ2004�N�����A
�uPCI�R�āv�̑����ɐM�҂́A�f�B�[�[����NO���팸�ƔR�����P�̉ۑ肪�ꋓ�ɉ����ł���Ɗ��҂��Ă������̂ƍl��
����B
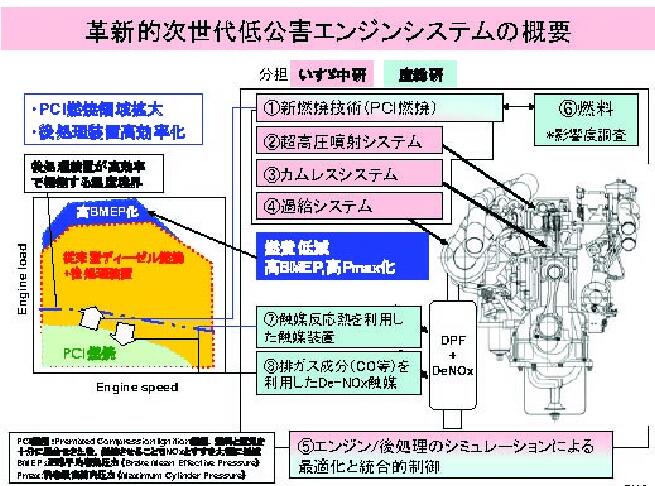
�@�@�����W���~�ȏ�̖c��ȗ\�Z�𒍂�����Ŗ蕨����Ŏ��{���ꂽ�u�����x�R�Đ���G���W�V�X�e���̌����J
���v�̌����J���ɍ̗p���ꂽ�R��Ɣr�o�K�X�����P�Z�p�́A�ȉ��̒ʂ�ł���B
���v�̌����J���ɍ̗p���ꂽ�R��Ɣr�o�K�X�����P�Z�p�́A�ȉ��̒ʂ�ł���B
�@ �V�R�ċZ�p�iPCI�R�āj�F���肵��PCI�R�āAPCI�R�ė̈�g��
�A ���������˃V�X�e���F�R�O�OMPa (�������˂قǕ������̓��ʔ䕪�z���ψꉻ�j
�B �J�����X�V�X�e���F�z�E�r�C�ق̊J���ʐς̍œK���i�σo���u�@�\�j
�C �ߋ��V�X�e���F�R�i�ߋ�
�D �G���W��/�㏈���̃V���~���[�V�����ɂ��œK���Ɠ����I����
�E �R���F�Z�^�����E������
�F �G�}�����M�𗘗p�����G�}���u�FDPF�{DeNO��
�G �r�o�K�X�����iCO���j�𗘗p����DeNO���G�}�F
�@�Ƃ��낪�A���́u�����x�R�Đ���G���W�V�X�e���̌����J���v�́A�̐S�̔R�����P�ɂ��Ă͎S�邽�錋�ʂŏI��
���Ă��܂����悤���B���̏؋��Ƃ��ẮA����܂ł̑�����NEDO�̌����J���̗�ƈقȂ�A���̌����J���ł͓�����
�ڕW�ƍŏI���ʂƂ̔R�����P���]��ɂ��������߂��Ă��邩��ł���B���̃v���W�F�N�g�ł�2015�N�x�d�ʎԔR���
�������P�O���̑啝�ȔR�����P��ڕW�Ɍf���Ȃ���A�ŏI���ʂł́A2015�N�x�d�ʎԔR�������Q�����R��
���������Ă��܂����̂ł���B
���Ă��܂����悤���B���̏؋��Ƃ��ẮA����܂ł̑�����NEDO�̌����J���̗�ƈقȂ�A���̌����J���ł͓�����
�ڕW�ƍŏI���ʂƂ̔R�����P���]��ɂ��������߂��Ă��邩��ł���B���̃v���W�F�N�g�ł�2015�N�x�d�ʎԔR���
�������P�O���̑啝�ȔR�����P��ڕW�Ɍf���Ȃ���A�ŏI���ʂł́A2015�N�x�d�ʎԔR�������Q�����R��
���������Ă��܂����̂ł���B
�@���̂悤�ɁA���̌����J���̎��ۂ̍ŏI���ʂ́A�}�P�X�Ɏ������悤�ɁANOx�͖ڕW��B���������A���݂̏ȃG�l��
�M�[�E�Ȏ����E��CO2�̎���ɋ��߂��Ă���̐S�v�̔R�����P�͖ڕW��10���팸�ɂ͑S���y���A2015�N�x�d
�ʎԔR���ɑ��ĂQ���̈����ƂȂ��Ă��܂����̂ł���B���s�̑�^�g���b�N��2015�N�x�d�ʎԔR���ɓK��
���Ă��邱�Ƃ���A�u�����x�R�Đ���G���W�V�X�e���̌����J���v�ɂ�����2015�N�x�d�ʎԔR���ɑ��ĂQ����
�R����́A���̌����J���������Ȃ܂ł̑厸�s�ɏI������Ɖ]����̂ł͂Ȃ����낤���B
�M�[�E�Ȏ����E��CO2�̎���ɋ��߂��Ă���̐S�v�̔R�����P�͖ڕW��10���팸�ɂ͑S���y���A2015�N�x�d
�ʎԔR���ɑ��ĂQ���̈����ƂȂ��Ă��܂����̂ł���B���s�̑�^�g���b�N��2015�N�x�d�ʎԔR���ɓK��
���Ă��邱�Ƃ���A�u�����x�R�Đ���G���W�V�X�e���̌����J���v�ɂ�����2015�N�x�d�ʎԔR���ɑ��ĂQ����
�R����́A���̌����J���������Ȃ܂ł̑厸�s�ɏI������Ɖ]����̂ł͂Ȃ����낤���B
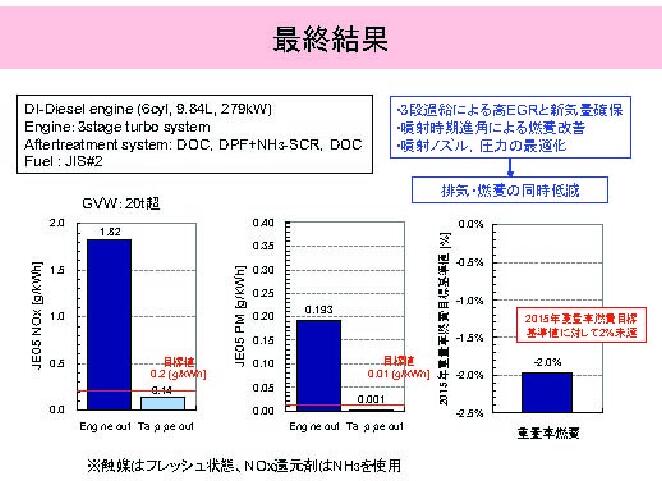
�@���́u�����x�R�Đ���G���W�V�X�e���̌����J���v�̌����J���ł́A�P�O���b�g���̃G���W���ŏ]���̂P�R���b�g����
�G���W���̕W�����x���̏o�͂邽�߂ɕK�v�ƂȂ�z����C�ʂ��m�ۂ��邱�Ƃ͖ܘ_�ł��邪�A�X�ɍ�����C��
�藦�ł̉^�]���\�ɂ���PM�̍팸��NO���팸�̐�D�ł���PCI�R�āv�̉^�]�̈���g�傷�邽�߂ɂR�i�ߋ��V
�X�e�����̗p���ꂽ�悤���B���̂R�i�ߋ��V�X�e���ł́A���C�ʂ͑����ł��邪�A���������̎��͂�50�`60�����x
�ƌ�����^�[�{�ߋ��@���R����A�����ĉߋ�����ꍇ�ɂ́A�|���s���O������������͖��炩�ł���B���̂R�i
�ߋ��V�X�e���ł́A�]���̒P�i�̉ߋ��f�B�[�[���G���W�������R��������Ă��܂������ɂȂ邱�Ƃ́A�e�Ղɗ\
�z�ł��邱�Ƃł���B
�G���W���̕W�����x���̏o�͂邽�߂ɕK�v�ƂȂ�z����C�ʂ��m�ۂ��邱�Ƃ͖ܘ_�ł��邪�A�X�ɍ�����C��
�藦�ł̉^�]���\�ɂ���PM�̍팸��NO���팸�̐�D�ł���PCI�R�āv�̉^�]�̈���g�傷�邽�߂ɂR�i�ߋ��V
�X�e�����̗p���ꂽ�悤���B���̂R�i�ߋ��V�X�e���ł́A���C�ʂ͑����ł��邪�A���������̎��͂�50�`60�����x
�ƌ�����^�[�{�ߋ��@���R����A�����ĉߋ�����ꍇ�ɂ́A�|���s���O������������͖��炩�ł���B���̂R�i
�ߋ��V�X�e���ł́A�]���̒P�i�̉ߋ��f�B�[�[���G���W�������R��������Ă��܂������ɂȂ邱�Ƃ́A�e�Ղɗ\
�z�ł��邱�Ƃł���B
�@�܂��A���̌����J���ł́A�����ł�PM�팸��}�邽�߂ƔR�ĉ��P�����҂��āA300MP���̒������R�����˂��̗p��
�ꂽ�ƍl������B�������A�R���̍������˂ł́A���ˌn�̋쓮�����ɂ��R��������R�ĉ��P�ɂ��R���
�オ���Ȃ��ꍇ�́A�G���W���R��̈����̗v���ƂȂ邱�Ƃ́A�f�B�[�[���G���W���̊J���o���҂ł���ΒN�ł��n�m
���Ă��邱�Ƃł���B���̂悤�ɁA�u�����x�R�Đ���G���W�V�X�e���̌����J���v�̌����J���́A�v��i�K�ɂ�����
NO���̍팸��PM�̍팸���������邱�ƂɊ��҂��邱�Ƃɂ͉��̈٘_����������Ȃ��B�������A���̌����J���̔R��
�ɂ��ẮA�R�����P���s�m��v���̔R�ĉ��P�Ɋ��҂��邾���ł���A���̑��̑��������̎��͂�70���ȉ��ƌ�
����^�[�{�ߋ��@���R����A�������ꍇ�̃|���s���O�����̑�����A300MP���̒������R�����˂̋쓮�����̑�
���ɂ���ĔR��������̈�������\���́A���̌����J���̌v��̏������班���͗\�z����l�������̂ł͂Ȃ�
���낤���B
�ꂽ�ƍl������B�������A�R���̍������˂ł́A���ˌn�̋쓮�����ɂ��R��������R�ĉ��P�ɂ��R���
�オ���Ȃ��ꍇ�́A�G���W���R��̈����̗v���ƂȂ邱�Ƃ́A�f�B�[�[���G���W���̊J���o���҂ł���ΒN�ł��n�m
���Ă��邱�Ƃł���B���̂悤�ɁA�u�����x�R�Đ���G���W�V�X�e���̌����J���v�̌����J���́A�v��i�K�ɂ�����
NO���̍팸��PM�̍팸���������邱�ƂɊ��҂��邱�Ƃɂ͉��̈٘_����������Ȃ��B�������A���̌����J���̔R��
�ɂ��ẮA�R�����P���s�m��v���̔R�ĉ��P�Ɋ��҂��邾���ł���A���̑��̑��������̎��͂�70���ȉ��ƌ�
����^�[�{�ߋ��@���R����A�������ꍇ�̃|���s���O�����̑�����A300MP���̒������R�����˂̋쓮�����̑�
���ɂ���ĔR��������̈�������\���́A���̌����J���̌v��̏������班���͗\�z����l�������̂ł͂Ȃ�
���낤���B
�@���������āA�u�����x�R�Đ���G���W�V�X�e���̌����J���v�̌����J���̓����ڕW�̈������R���10��
�̉��P��ڕW�ɂ������Ƃ́A�P�Ȃ�\�Z���l�����邽�߂̕��ւ��g�����悤�Ɏv����̂��B�����āA���̌����J����
���ۂ̌��ʂ́A�}�P�X�Ɏ������悤�ɁANOx��PM�͍팸�ł������A�R���2015�N�x�d�ʎԔR���Q���̈����ƂȂ�
�Ă��܂����Ƃ̂��Ƃł���B���̂悤�ȁA�u�����x�R�Đ���G���W�V�X�e���̌����J���v�ɂ�����PCI�R�Ă��܂߂��R��
���P�ł̔R����オ�s�����ɏI������������ƁA���̃f�B�[�[���R�Ẳ��P�ɂ���ĔR�������������邱��
�́A�ɂ߂č���ł���ƁA�N�ł��ȒP�ɗ\�z�ł���̂ł͂Ȃ����낤���B���x�����p���邪�A�����ԋZ�p��s��
�u�����ԋZ�p�v��Vol.64�ANo.�P�A2010�i2010�N1���P�����s�j�̔ѓc�P�� �c���̑勳���@���R�����́u�f�B�[�[���G��
�W�����̂P�O�N�v�ɂ̓f�B�[�[���G���W����CO�Q�팸�i���R��팸�j���u�傫�Ȓ���ۑ�v�ƒf�肵�A�R�ĉ��P�ɂ��f
�B�[�[���G���W���̔R��팸���u�Z�p�I�ɔ����ǂ���̏v�Ƃ̎�|���L�ڂ���Ă���̂́A����NEDO�́u����
�x�R�Đ���G���W�V�X�e���̌����J���v�i2004�`2009�N�j�ł̔R����̌������ʂ܂��Ă̋L�q�Ƃ��l�����
��B
�̉��P��ڕW�ɂ������Ƃ́A�P�Ȃ�\�Z���l�����邽�߂̕��ւ��g�����悤�Ɏv����̂��B�����āA���̌����J����
���ۂ̌��ʂ́A�}�P�X�Ɏ������悤�ɁANOx��PM�͍팸�ł������A�R���2015�N�x�d�ʎԔR���Q���̈����ƂȂ�
�Ă��܂����Ƃ̂��Ƃł���B���̂悤�ȁA�u�����x�R�Đ���G���W�V�X�e���̌����J���v�ɂ�����PCI�R�Ă��܂߂��R��
���P�ł̔R����オ�s�����ɏI������������ƁA���̃f�B�[�[���R�Ẳ��P�ɂ���ĔR�������������邱��
�́A�ɂ߂č���ł���ƁA�N�ł��ȒP�ɗ\�z�ł���̂ł͂Ȃ����낤���B���x�����p���邪�A�����ԋZ�p��s��
�u�����ԋZ�p�v��Vol.64�ANo.�P�A2010�i2010�N1���P�����s�j�̔ѓc�P�� �c���̑勳���@���R�����́u�f�B�[�[���G��
�W�����̂P�O�N�v�ɂ̓f�B�[�[���G���W����CO�Q�팸�i���R��팸�j���u�傫�Ȓ���ۑ�v�ƒf�肵�A�R�ĉ��P�ɂ��f
�B�[�[���G���W���̔R��팸���u�Z�p�I�ɔ����ǂ���̏v�Ƃ̎�|���L�ڂ���Ă���̂́A����NEDO�́u����
�x�R�Đ���G���W�V�X�e���̌����J���v�i2004�`2009�N�j�ł̔R����̌������ʂ܂��Ă̋L�q�Ƃ��l�����
��B
�@���̂悤�ɁA�R�ĉ��P�ɂ��R��팸���傫�ȕǂɓ˂��������Ă��錻��Ɋӂ݁A�R�ĉ��P�ȊO�̕��@�ɂ��f�B
�[�[���G���W���̔R�������\�ɂ��邽�߂ɁA�M�҂��C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p���^�g
���b�N�ɍ̗p���邱�Ƃ��Ă��Ă���B���̋C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p�͔R����P�Ƌ���NO��
�팸���\�ł��邽�߁ANO���̓|�X�g�V������1/3�ጸ�i���@0.23�@g/kWh�j��B�����A�R���2015�N�x�d�ʎԔR
������T�����P�������ł���u�������A��������v�̋Z�p�ł���B�����āA�M�҂�2006�N4��7���ɖ{�z�[���y�[
�W���J�݂��Ĉȗ��A�p�������C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p���e�̎��m�ɓw�߁A���̋Z�p�ɂ��
�R����P��NO���팸�ɗL���ł��邱�Ƃ��ׁX�Ƒi���Ă���̂ł���B���R�̂��ƂȂ���A��ʌl�̕M�҂���Ă���
�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p�͖�����������A���̒��ł́A�O�q�̂悤�ɁA�W���~�ȏ���̗\
�Z�𒍂�����Ŏ��{���ꂽNEDO�́u�����x�R�Đ���G���W�V�X�e���̌����J���v�i2004�`2009�N�j�ł́A�R����P
�ɉ��̐��ʂ��グ��ꂸ�Ɏ��s���Ă���B�������A�����_�ő����̃g���b�N���[�J�ł́A�f�B�[�[���G���W���̔R����
�P�Z�p���J���ł��Ă��Ȃ����Ƃ���A7�i�}�j���A���g�����X�~�b�̂P�R���b�g���W���G���W�����ڑ�^�g���b�N�E�g���N�^
�̑����̎Ԏ킪�Q�O�P�T�N�x�d�ʎԔR���ɕs�K���Ɖ]���悤�ȁA�s�l�ȏɊׂ��Ă���̂ł͂Ȃ����낤���B
�[�[���G���W���̔R�������\�ɂ��邽�߂ɁA�M�҂��C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p���^�g
���b�N�ɍ̗p���邱�Ƃ��Ă��Ă���B���̋C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p�͔R����P�Ƌ���NO��
�팸���\�ł��邽�߁ANO���̓|�X�g�V������1/3�ጸ�i���@0.23�@g/kWh�j��B�����A�R���2015�N�x�d�ʎԔR
������T�����P�������ł���u�������A��������v�̋Z�p�ł���B�����āA�M�҂�2006�N4��7���ɖ{�z�[���y�[
�W���J�݂��Ĉȗ��A�p�������C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p���e�̎��m�ɓw�߁A���̋Z�p�ɂ��
�R����P��NO���팸�ɗL���ł��邱�Ƃ��ׁX�Ƒi���Ă���̂ł���B���R�̂��ƂȂ���A��ʌl�̕M�҂���Ă���
�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p�͖�����������A���̒��ł́A�O�q�̂悤�ɁA�W���~�ȏ���̗\
�Z�𒍂�����Ŏ��{���ꂽNEDO�́u�����x�R�Đ���G���W�V�X�e���̌����J���v�i2004�`2009�N�j�ł́A�R����P
�ɉ��̐��ʂ��グ��ꂸ�Ɏ��s���Ă���B�������A�����_�ő����̃g���b�N���[�J�ł́A�f�B�[�[���G���W���̔R����
�P�Z�p���J���ł��Ă��Ȃ����Ƃ���A7�i�}�j���A���g�����X�~�b�̂P�R���b�g���W���G���W�����ڑ�^�g���b�N�E�g���N�^
�̑����̎Ԏ킪�Q�O�P�T�N�x�d�ʎԔR���ɕs�K���Ɖ]���悤�ȁA�s�l�ȏɊׂ��Ă���̂ł͂Ȃ����낤���B
�P�S�|�Q�@PCI�i=HCCI)�R�Ă̗B��̓����E���ʂ́AJE05���[�h�ł̂P�����x�̔R����P
�@�ߔN�A�f�B�[�[���G���W���̕���ŐV�����o�ꂵ���uPCI �R��(Premixed. Compression Ignition combustion�R�āF�\
�������k���ΔR�āj�́A�uHCCI �R��(Homogeneous-Charge Compression Ignitionnen�R�āF�\�������k���ΔR�āj�v
�Ƃ��̂����A�v�V�I�ȔR�ĂƂ��Ă���܂Œ��ڂ��W�߂Ă����Z�p�ł���BPCI �i=HCCI) �R�ẮA20�N�ȏ���O����
�����ԃ��[�J�E�����@�ցE��w���Ő���Ɍ����J�������{����Ă����Z�p���B���N�O�Ɏ�ȂŌ����̃f�B�[�[���G
���W���Z�p�҂���u���݂̃f�B�[�[���R�Č�����PCI �i=HCCI) �R�Ă��嗬�ł���A��̂Ƀf�B�[�[���G���W���̌�
���J����ނ����M�҂ɂ�PCI �i=HCCI) �R�Ă̊J���o�����������߂ɃG���W���Z�p���̍����i�i���ߋ��̐l�j�v�ƌ�
���A����̗�������������̂��B����PCI �i=HCCI) �R�ĂɊւ��鋻���[�������_�����A�i�Ёj�����ԋZ�p��́u��
���ԋZ�p Vol. 65�ANo. 3�A2011�v�Ɍf�ڂ́u�f�B�[�[���G���W���ɂ�����PCI�R�ēK�p���̃G���W������Z�p�v�i2011
�N3���P�����s�A���ҁF���R�^���A�c粌\�� [�O�H�ӂ����g���b�N�E�o�X��]�j���B
�������k���ΔR�āj�́A�uHCCI �R��(Homogeneous-Charge Compression Ignitionnen�R�āF�\�������k���ΔR�āj�v
�Ƃ��̂����A�v�V�I�ȔR�ĂƂ��Ă���܂Œ��ڂ��W�߂Ă����Z�p�ł���BPCI �i=HCCI) �R�ẮA20�N�ȏ���O����
�����ԃ��[�J�E�����@�ցE��w���Ő���Ɍ����J�������{����Ă����Z�p���B���N�O�Ɏ�ȂŌ����̃f�B�[�[���G
���W���Z�p�҂���u���݂̃f�B�[�[���R�Č�����PCI �i=HCCI) �R�Ă��嗬�ł���A��̂Ƀf�B�[�[���G���W���̌�
���J����ނ����M�҂ɂ�PCI �i=HCCI) �R�Ă̊J���o�����������߂ɃG���W���Z�p���̍����i�i���ߋ��̐l�j�v�ƌ�
���A����̗�������������̂��B����PCI �i=HCCI) �R�ĂɊւ��鋻���[�������_�����A�i�Ёj�����ԋZ�p��́u��
���ԋZ�p Vol. 65�ANo. 3�A2011�v�Ɍf�ڂ́u�f�B�[�[���G���W���ɂ�����PCI�R�ēK�p���̃G���W������Z�p�v�i2011
�N3���P�����s�A���ҁF���R�^���A�c粌\�� [�O�H�ӂ����g���b�N�E�o�X��]�j���B
�@���́u�����ԋZ�p�v���̎O�H�ӂ����̘_���ɂ́A�}�Q�O�Ɏ������u�R�����ˎ�����EGR���̒�������ʏ�R�Ă�JE
�O�T���[�h�̔R��v�Ɓu�ʏ�R�Ă�PCI �R�Ă�g������JE�O�T���[�h�̔R��v�̔�r�}������Ă����B���̐}�P�V�ɂ��
�ƁANO���l�iJE�O�T���[�h�j�� 2.0 g/kWh �ł́A�ʏ�R�Ă�PCI �R�Ă̔R��͓����ł��邪�ANO���l�iJE�O�T���[�h�j��
1.0 g/kWh �ł́APCI �R�Ă̔R��͒ʏ�R�Ă����P���̍팸���ł���Ƃ̂��Ƃ��B����ɂ��āA�{�_���ł́uPCI
�R�Ă�K�p�������ʁANO�����x���� 1.5 g/kWh �ȉ��̒�NO�����ł́A�P����R�����ꂽ�v�Ƃ��A�uPCI �R�Ă̓K
�p�́ANO�����x�����Ⴂ�ꍇ�ɂ͔R����P�̉\��������v�ƌւ炵���ɋL�ڂ���Ă���B
�O�T���[�h�̔R��v�Ɓu�ʏ�R�Ă�PCI �R�Ă�g������JE�O�T���[�h�̔R��v�̔�r�}������Ă����B���̐}�P�V�ɂ��
�ƁANO���l�iJE�O�T���[�h�j�� 2.0 g/kWh �ł́A�ʏ�R�Ă�PCI �R�Ă̔R��͓����ł��邪�ANO���l�iJE�O�T���[�h�j��
1.0 g/kWh �ł́APCI �R�Ă̔R��͒ʏ�R�Ă����P���̍팸���ł���Ƃ̂��Ƃ��B����ɂ��āA�{�_���ł́uPCI
�R�Ă�K�p�������ʁANO�����x���� 1.5 g/kWh �ȉ��̒�NO�����ł́A�P����R�����ꂽ�v�Ƃ��A�uPCI �R�Ă̓K
�p�́ANO�����x�����Ⴂ�ꍇ�ɂ͔R����P�̉\��������v�ƌւ炵���ɋL�ڂ���Ă���B
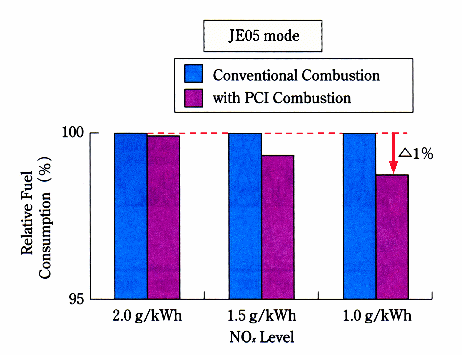
�@���̂悤�ɁA�{�_���ł́A�u1.0 g/kWh ��NO���l�iJE�O�T���[�h�j�ɂ����āA�ʏ�R�Ăɔ�r����PCI �R�āi=HCCI �R
�āj�̔R��P���̍팸�v�Ƃ̎����f�[�^�������ɁA�uPCI �R�ẮANO�����x�����Ⴂ�ꍇ�ɂ͔R����P�̉\����
����v�ƌ��_�Â����Ă���B���̌��_�ɂ��ĕM�҂́A���X�A�^��Ɋ�������̂ł���B���G���W���Z�p���̕M��
�́A�̂̌o������A�������̔R�������C�ۏ������̕ϓ��ɂ���ăG���W���R��̑���l���P�����x�̑���덷
������̂ƔF�����Ă���B���������āA�P�����x�̃G���W���̔R����P�́A����덷�͈͓̔��̂悤�Ɏv�����
���B���̂��߁A���̘_���ł́A�uNO�����x����1.0 g/kWh �iJE�O�T���[�h�j�̒Ⴂ�ꍇ�ł�PCI �R�Ăɂ��JE�O�T���[�h
�̔R����P�͗]����҂ł��Ȃ��v�ƋL�ڂ���̂��K�Ȃ悤�ɍl���Ă���B�Ȃ��A����PCI �i=HCCI) �R�ẮA�O�q��
��R��ƒ�NO���̃f�B�[�[���G���W���̖ړI�Ƃ���NEDO�̃N���[���f�B�[�[���v���W�F�N�g[2004�`2009�N]�ɂ��g��
���܂ꂽ�����J�������{����A���̌��ʕł͐}�P�X�Ɏ������悤��2015�N�x�d�ʎԃ��[�h�R���ɔ�ׂ�
�Q���̔R����������ƋL�ځi�o�T�Fhttp://app3.infoc.nedo.go.jp/gyouji/events/FK/rd/2008/nedoevent.2009-02-
16.5786478868/shiryo.pdf�j����Ă���B���������āA���̕�����APCI �i=HCCI) �R�ẮA�f�B�[�[���G���W���̔R
�����Ɋ�^�ł��Ȃ��Z�p�ł��邱�Ƃ��e�Ղɐ��������B
�āj�̔R��P���̍팸�v�Ƃ̎����f�[�^�������ɁA�uPCI �R�ẮANO�����x�����Ⴂ�ꍇ�ɂ͔R����P�̉\����
����v�ƌ��_�Â����Ă���B���̌��_�ɂ��ĕM�҂́A���X�A�^��Ɋ�������̂ł���B���G���W���Z�p���̕M��
�́A�̂̌o������A�������̔R�������C�ۏ������̕ϓ��ɂ���ăG���W���R��̑���l���P�����x�̑���덷
������̂ƔF�����Ă���B���������āA�P�����x�̃G���W���̔R����P�́A����덷�͈͓̔��̂悤�Ɏv�����
���B���̂��߁A���̘_���ł́A�uNO�����x����1.0 g/kWh �iJE�O�T���[�h�j�̒Ⴂ�ꍇ�ł�PCI �R�Ăɂ��JE�O�T���[�h
�̔R����P�͗]����҂ł��Ȃ��v�ƋL�ڂ���̂��K�Ȃ悤�ɍl���Ă���B�Ȃ��A����PCI �i=HCCI) �R�ẮA�O�q��
��R��ƒ�NO���̃f�B�[�[���G���W���̖ړI�Ƃ���NEDO�̃N���[���f�B�[�[���v���W�F�N�g[2004�`2009�N]�ɂ��g��
���܂ꂽ�����J�������{����A���̌��ʕł͐}�P�X�Ɏ������悤��2015�N�x�d�ʎԃ��[�h�R���ɔ�ׂ�
�Q���̔R����������ƋL�ځi�o�T�Fhttp://app3.infoc.nedo.go.jp/gyouji/events/FK/rd/2008/nedoevent.2009-02-
16.5786478868/shiryo.pdf�j����Ă���B���������āA���̕�����APCI �i=HCCI) �R�ẮA�f�B�[�[���G���W���̔R
�����Ɋ�^�ł��Ȃ��Z�p�ł��邱�Ƃ��e�Ղɐ��������B
�@�����Ƃ��A�ŋ߂̎O�H�ӂ����ł́A�C�ۏ�����R�����ϓ������ꍇ�ł��P���̔R���̗L�Ӎ��𐳊m�Ɍv
���ł��鍂���x�̃G���W���R���̋Z�p�⎎���ݔ�����������Ă���̂��낤�B�����āA�G���W���R��������x��
����ł���Z�p�I�ȃo�b�N�O�����h�����邱�Ƃ��炱���A�O�H�ӂ����́ANO���l�� 1.0 g/kWh �ɂ�����PCI �R�Ă̔R
��ʏ�R�Ă����P���̍팸���ł��鎎���f�[�^�\���Ă�����̂ƍl������B�������A���̎����f�[�^�̌���
��ς��ċq�ϓI�ɕ]������ƁAPCI �R�āi=HCCI �R�āj�̋Z�p�ł́ANO���l�� 1.0 g/kWh �ɂ�����PCI �R�āi=HCCI
�R�āj�̔R��iJE�O�T���[�h�j�͒ʏ�R�Ăɔ�ׂċ͂��ɂP�����x��������ł��Ă��Ȃ��ƌ�����̂ł���B���̂���
����APCI �R�āi=HCCI �R�āj�ł́A����덷�Ǝv�����R�����̓����E���ʂ����Ȃ��ƒf�肷�邱�Ƃ��ł���̂��B
���ł��鍂���x�̃G���W���R���̋Z�p�⎎���ݔ�����������Ă���̂��낤�B�����āA�G���W���R��������x��
����ł���Z�p�I�ȃo�b�N�O�����h�����邱�Ƃ��炱���A�O�H�ӂ����́ANO���l�� 1.0 g/kWh �ɂ�����PCI �R�Ă̔R
��ʏ�R�Ă����P���̍팸���ł��鎎���f�[�^�\���Ă�����̂ƍl������B�������A���̎����f�[�^�̌���
��ς��ċq�ϓI�ɕ]������ƁAPCI �R�āi=HCCI �R�āj�̋Z�p�ł́ANO���l�� 1.0 g/kWh �ɂ�����PCI �R�āi=HCCI
�R�āj�̔R��iJE�O�T���[�h�j�͒ʏ�R�Ăɔ�ׂċ͂��ɂP�����x��������ł��Ă��Ȃ��ƌ�����̂ł���B���̂���
����APCI �R�āi=HCCI �R�āj�ł́A����덷�Ǝv�����R�����̓����E���ʂ����Ȃ��ƒf�肷�邱�Ƃ��ł���̂��B
�@���̂悤�ɁA�u�����ԋZ�p Vol. 65�ANo. 3�A2011�v�Ɍf�ڂ���Ă���O�H�ӂ����g���b�N�E�o�X����PCI �R�āi=HCCI �R
�āj�Ɋւ���_��������ƁAPCI �R�Ăł́A�͂��P�����x�̃G���W���R����P�iJE�O�T���[�h�j�ɉ߂����A���̂P�����x
�̃G���W���R����P�iJE�O�T���[�h�j��PCI �R�āi=HCCI �R�āj�̗B��̌��ʁE�����̂悤���B���̘_������ǂ��ꂽ
�G���W���Z�p�ҁE�w�҂ł���A�f�B�[�[���G���W���̔R�����Z�p�̈��PCI �R�āi=HCCI �R�āj�������邱��
�ɂ��ẮA�p�����������S�O�����̂ł͂Ȃ����낤���B�����āA����܂ŁuPCI �R�āi=HCCI �R�āj�������f�B�[�[
���̋��ɂ̔R�āv�Ɛ�^����Ă��������̃f�B�[�[���W�̊w�҂�Z�p�҂̌�ӌ����f���Ă݂������̂��B
�āj�Ɋւ���_��������ƁAPCI �R�Ăł́A�͂��P�����x�̃G���W���R����P�iJE�O�T���[�h�j�ɉ߂����A���̂P�����x
�̃G���W���R����P�iJE�O�T���[�h�j��PCI �R�āi=HCCI �R�āj�̗B��̌��ʁE�����̂悤���B���̘_������ǂ��ꂽ
�G���W���Z�p�ҁE�w�҂ł���A�f�B�[�[���G���W���̔R�����Z�p�̈��PCI �R�āi=HCCI �R�āj�������邱��
�ɂ��ẮA�p�����������S�O�����̂ł͂Ȃ����낤���B�����āA����܂ŁuPCI �R�āi=HCCI �R�āj�������f�B�[�[
���̋��ɂ̔R�āv�Ɛ�^����Ă��������̃f�B�[�[���W�̊w�҂�Z�p�҂̌�ӌ����f���Ă݂������̂��B
�@�����ȑO�̂��Ƃł͂��邪�A��Ȃ̏�Ō����f�B�[�[���Z�p�҂���u�����̂ɑސE�����M�҂̂悤�ȃf�B�[�[����
�́APCI �i=HCCI) �R�Ă̊J���o�����������߂ɁA���ɍ����i�i���ߋ��̐l�j���v�Ƃ̎w�E�������Ƃ�����B����
�āA��ɕs����Ȓ��Ζ�肪����PCI �i=HCCI) �R�Ă��f�B�[�[���̔���I�Ȕ��W�Ɋ�^����Ő�[�Z�p�ƐS����
�Ă��錻���f�B�[�[���Z�p�҂ɂ��āA�M�҂́u���̃f�B�[�[���G���W���Z�p�҂̗c�t���v�����������̂��B
�́APCI �i=HCCI) �R�Ă̊J���o�����������߂ɁA���ɍ����i�i���ߋ��̐l�j���v�Ƃ̎w�E�������Ƃ�����B����
�āA��ɕs����Ȓ��Ζ�肪����PCI �i=HCCI) �R�Ă��f�B�[�[���̔���I�Ȕ��W�Ɋ�^����Ő�[�Z�p�ƐS����
�Ă��錻���f�B�[�[���Z�p�҂ɂ��āA�M�҂́u���̃f�B�[�[���G���W���Z�p�҂̗c�t���v�����������̂��B
�@���āA�{�_���ł́ANO���l�� 1.0 g/kWh �ɂ�����PCI �R�āi=HCCI �R�āj�̋͂��P�����x�̔R��팸�������ɂ��A
�u�T�D�܂Ƃ߁v�ł́A�u�g�p����d���n�̔R������̕ω��ɉ�������悤�ɃG���W�����䂪�œK���ł���APCI
�R�āi=HCCI �R�āj�̎��p�����ԋ߂ł���v�ƋL�ڂ���Ă���B�����̂��Ƃ���A�O�H�ӂ����́APCI �R�āi=HCCI
�R�āj�����p���ł���Ɩ{�C�ōl���APCI �R�āi=HCCI �R�āj�������̃f�B�[�[���G���W���̔R��팸�̏d�v�ȋZ�p
�ƈʒu�Â��Ă���悤�Ɋ�����̂́A�M�҂����ł��낤���B
�u�T�D�܂Ƃ߁v�ł́A�u�g�p����d���n�̔R������̕ω��ɉ�������悤�ɃG���W�����䂪�œK���ł���APCI
�R�āi=HCCI �R�āj�̎��p�����ԋ߂ł���v�ƋL�ڂ���Ă���B�����̂��Ƃ���A�O�H�ӂ����́APCI �R�āi=HCCI
�R�āj�����p���ł���Ɩ{�C�ōl���APCI �R�āi=HCCI �R�āj�������̃f�B�[�[���G���W���̔R��팸�̏d�v�ȋZ�p
�ƈʒu�Â��Ă���悤�Ɋ�����̂́A�M�҂����ł��낤���B
�@�Ƃ���ŁA�ڍׂ͏Ȃ����APCI �R�ẮA���䂳�ꂽ�m�b�L���O�ƌ�����R�Ăł��邽�߁A�y���̃Z�^�����̂悤
�ȔR��������C�̉��x�����ɑ傫���e����������������B���̂��߁A���̋Z�p���^�g���b�N�E�g���N�^�ɍ�
�p�����ꍇ�ɂ́A�����Ɍ����Ύs��ł̎��p���s�ɂ����Ă͖�肪��������̂ł͂Ȃ����Ɖ]���Ă���B���ɁA
�O�H�ӂ������͂��P�����x�̔R��팸�ɂ��߂ɑ�^�g���b�N�E�g���N�^�ɔR�Ă̕s�����PCI �i=HCCI) �R�Ă̋Z�p��
�̗p�����ꍇ�ɂ́A�����̑�^�g���b�N�E�g���N�^�͌̏���N�������X�N��`�����ƂɂȂ�Ɨ\�z�����B�O�H�ӂ�������
��X�N��`���Ăł�PCI �i=HCCI) �R�Ă̋Z�p���^�g���b�N�E�g���N�^�ɍ̗p���闝�R��������AJE�O�T���[�h�̔R
����͂��P�����x��������ł��Ȃ�PCI �i=HCCI) �R�ĈȊO�ɁA�O�H�ӂ������f�B�[�[���G���W���̔R��팸�ɗL��
�ȋZ�p���������o���Ă��Ȃ����߂Ƃ��l������B
�ȔR��������C�̉��x�����ɑ傫���e����������������B���̂��߁A���̋Z�p���^�g���b�N�E�g���N�^�ɍ�
�p�����ꍇ�ɂ́A�����Ɍ����Ύs��ł̎��p���s�ɂ����Ă͖�肪��������̂ł͂Ȃ����Ɖ]���Ă���B���ɁA
�O�H�ӂ������͂��P�����x�̔R��팸�ɂ��߂ɑ�^�g���b�N�E�g���N�^�ɔR�Ă̕s�����PCI �i=HCCI) �R�Ă̋Z�p��
�̗p�����ꍇ�ɂ́A�����̑�^�g���b�N�E�g���N�^�͌̏���N�������X�N��`�����ƂɂȂ�Ɨ\�z�����B�O�H�ӂ�������
��X�N��`���Ăł�PCI �i=HCCI) �R�Ă̋Z�p���^�g���b�N�E�g���N�^�ɍ̗p���闝�R��������AJE�O�T���[�h�̔R
����͂��P�����x��������ł��Ȃ�PCI �i=HCCI) �R�ĈȊO�ɁA�O�H�ӂ������f�B�[�[���G���W���̔R��팸�ɗL��
�ȋZ�p���������o���Ă��Ȃ����߂Ƃ��l������B
�@���݂�PCI �i=HCCI) �R�Ă͎�Ɂu�R�����ˎ�����ʏ�R�Ă̏ꍇ�����啝�ɐi�p������v�����ʼn\�ł��邽
�߁APCI �i=HCCI) �R�Ăɕs�K�ȔR��������C�����̍ۂɂ́A�ً}���Ə̂��APCI �i=HCCI) �R�ẴG���W���^
�]�̈�ł����Ă��A�����ɒʏ�R�Ă̔R�����ˎ�����x�p������PCI �i=HCCI) �R�Ă̕s����������邱�Ƃ���
�\�ł���B���̂悤�ɁA�{����PCI �i=HCCI) �R�ẴG���W���^�]�̈��ʏ�R�Ă̐���ɐ�ւ����ꍇ�ɂ́A�u��
����NO�������v�Ɓu�P�����x�̏d�ʎԃ��[�h�R��̑����v���������APCI �i=HCCI) �R�Ăɕs�K�ȔR��������C����
�̏ł���^�g���b�N�E�g���N�^��ʏ�R�Ăʼn~���ɑ��s�����邱�Ƃ��ł���̂��B
�߁APCI �i=HCCI) �R�Ăɕs�K�ȔR��������C�����̍ۂɂ́A�ً}���Ə̂��APCI �i=HCCI) �R�ẴG���W���^
�]�̈�ł����Ă��A�����ɒʏ�R�Ă̔R�����ˎ�����x�p������PCI �i=HCCI) �R�Ă̕s����������邱�Ƃ���
�\�ł���B���̂悤�ɁA�{����PCI �i=HCCI) �R�ẴG���W���^�]�̈��ʏ�R�Ă̐���ɐ�ւ����ꍇ�ɂ́A�u��
����NO�������v�Ɓu�P�����x�̏d�ʎԃ��[�h�R��̑����v���������APCI �i=HCCI) �R�Ăɕs�K�ȔR��������C����
�̏ł���^�g���b�N�E�g���N�^��ʏ�R�Ăʼn~���ɑ��s�����邱�Ƃ��ł���̂��B
�@���̂悤�ɁAPCI �R�āi=HCCI �R�āj�̃f�B�[�[���G���W���ł́APCI �R�āi=HCCI �R�āj�ɕs�K�ȔR��������C
�����ł�PCI �i=HCCI) �R�ẴG���W���^�]�̈��ʏ�R�Ă̐���ʼn^�]����ً}���̐�����v���O�����ɑg��
���݁A�K�v�ɉ����Ď��R���݂ɒʏ�R�Ă̐���ŃG���W�����^�]���邱�Ƃ��\���B���������āAPCI �i=HCCI) �R��
�G���W���Ƃ��č��y��ʏȂ̃G���W���R�����āA�u�|�X�g�V�����r�o�K�X�K���i2009�N�K���j�̓K���v�Ɓu�P�����x
�̏d�ʎԃ��[�h�R��̌���v�̎d�l���̑�^�g���b�N�E�g���N�^�Ƃ��č��y��ʏȂ̔F����A��^�g���b�N�E�g���N
�^�̎s��ł̑����̎����s���ɂ͒ʏ�R�Ăʼn~���ɑ��s������悤�ɂ���悤�ɃG���W���𐧌䂷�邱�Ƃ��\�ƍl
������B���ɁA�g���b�N���[�J��PCI �i=HCCI) �R�Ă̋Z�p���^�g���b�N�E�g���b�N�ɍ̗p����ۂɁA���̂悤�ȌƑ���
�G���W��������̗p�����ꍇ�ɂ́A��ʂ̎s�����猵�����w�e����邱�Ƃ͖��炩���B���������āA�g���b�N���[�J����
�^�g���b�N�E�g���N�^��PCI �i=HCCI) �R�Ă̋Z�p���̗p����ꍇ�ɂ́A�ً}���̖��ڂŖ{����PCI �i=HCCI) �R�Ă�
�G���W���^�]�̈��ʏ�R�Ă̐���ɕp�ɂɐ�ւ��鐧�䂪�ғ����Ă��܂��\��������B���̂悤�Ȃ��ƂɂȂ�
�A���ڏ�ł�PCI �i=HCCI) �R�Ă̋Z�p�����p�����ꂽ�Ƃ��Ă��A���p�ʂł͖����ɓ������Z�p�Ɖ]����̂ł͂�
�����낤���B
�����ł�PCI �i=HCCI) �R�ẴG���W���^�]�̈��ʏ�R�Ă̐���ʼn^�]����ً}���̐�����v���O�����ɑg��
���݁A�K�v�ɉ����Ď��R���݂ɒʏ�R�Ă̐���ŃG���W�����^�]���邱�Ƃ��\���B���������āAPCI �i=HCCI) �R��
�G���W���Ƃ��č��y��ʏȂ̃G���W���R�����āA�u�|�X�g�V�����r�o�K�X�K���i2009�N�K���j�̓K���v�Ɓu�P�����x
�̏d�ʎԃ��[�h�R��̌���v�̎d�l���̑�^�g���b�N�E�g���N�^�Ƃ��č��y��ʏȂ̔F����A��^�g���b�N�E�g���N
�^�̎s��ł̑����̎����s���ɂ͒ʏ�R�Ăʼn~���ɑ��s������悤�ɂ���悤�ɃG���W���𐧌䂷�邱�Ƃ��\�ƍl
������B���ɁA�g���b�N���[�J��PCI �i=HCCI) �R�Ă̋Z�p���^�g���b�N�E�g���b�N�ɍ̗p����ۂɁA���̂悤�ȌƑ���
�G���W��������̗p�����ꍇ�ɂ́A��ʂ̎s�����猵�����w�e����邱�Ƃ͖��炩���B���������āA�g���b�N���[�J����
�^�g���b�N�E�g���N�^��PCI �i=HCCI) �R�Ă̋Z�p���̗p����ꍇ�ɂ́A�ً}���̖��ڂŖ{����PCI �i=HCCI) �R�Ă�
�G���W���^�]�̈��ʏ�R�Ă̐���ɕp�ɂɐ�ւ��鐧�䂪�ғ����Ă��܂��\��������B���̂悤�Ȃ��ƂɂȂ�
�A���ڏ�ł�PCI �i=HCCI) �R�Ă̋Z�p�����p�����ꂽ�Ƃ��Ă��A���p�ʂł͖����ɓ������Z�p�Ɖ]����̂ł͂�
�����낤���B
�@�Ȃ��A����PCI �R�āi=HCCI �R�āj�̋Z�p�́A�R�����ˎ������ߑ��ɐ��䂷�邱�Ƃ���̂ł��邽�߁A�R�X�g�A�b�v
�����Ȃ����Ƃ����_�ł��邪�A�R����P������덷�͈͓��̋ɂ߂ď��Ȃ����̂ł���B�����A�u�����낤�E�����낤�v
�̓T�^�I�ȔR�����Z�p���B����ɑ��A�M�҂���Ă���C���x�~�f�B�[�[���G���W���i�������J2005-54771�j�́A
�d�ʎԃ��[�h�R��l������s�R��T�`�P�O�������P�ł���@�\�̑��ɁA�i�d�O�T���[�h�r�o�K�X�����ł̃G���W���^
�]�p�x�̍��������������r�b�q�G�}��������x���������ł��邽�߂ɔA�f�r�b�q�G�}�ł̂m�n���팸����啝��
����ł���D�ꂽ�@�\���������Ă��邪�A��̃R�X�g�����̂��u�ʂɏ��v�ł���B
�����Ȃ����Ƃ����_�ł��邪�A�R����P������덷�͈͓��̋ɂ߂ď��Ȃ����̂ł���B�����A�u�����낤�E�����낤�v
�̓T�^�I�ȔR�����Z�p���B����ɑ��A�M�҂���Ă���C���x�~�f�B�[�[���G���W���i�������J2005-54771�j�́A
�d�ʎԃ��[�h�R��l������s�R��T�`�P�O�������P�ł���@�\�̑��ɁA�i�d�O�T���[�h�r�o�K�X�����ł̃G���W���^
�]�p�x�̍��������������r�b�q�G�}��������x���������ł��邽�߂ɔA�f�r�b�q�G�}�ł̂m�n���팸����啝��
����ł���D�ꂽ�@�\���������Ă��邪�A��̃R�X�g�����̂��u�ʂɏ��v�ł���B
�@���݁A�Q�O�P�T�N�x�d�ʎԔR���̋����ɓK��������Z�p���J������K�v���ɔ����Ă���e�g���b�N���[�J��
�Z�p�҂́A�����̃R�X�g�������߂ɁA�T�`�P�O���̔R������サ��NO�����\���ɉ��P�ł���C���x�~�f�B�[�[���G
���W���i�������J2005-54771�j����Ȃɖ������Ă���B���̈���ŁA�P�����x�̔R������P�ł��Ȃ�PCI �R�āi=
HCCI �R�āj�̋Z�p�����p�����邱�ƂɎ������Ă���悤���B���̂悤��PCI �R�āi=HCCI �R�āj�̋Z�p�𐒔q����e
�g���b�N���[�J�̋Z�p�҂̗l�q�����Ă���ƁA�u�푈���̐��_�_�œG��|���v�z�v�ł���|���i��PCI �R�ā�HCCI �R
�āj���g���ēG�̐�ԁi���Q�O�P�T�N�x�d�ʎԔR���̋����j�����ށi���R���̋����ɓK���j����l�����Ɏ���
����B���̂悤�Ȑ��_�_�ł͓G�̐�ԁi���Q�O�P�T�N�x�d�ʎԔR���̋����j�����ށi���R���̋����ɓK���j��
�邱�Ƃ�����Ȃ��Ƃ͖��炩���B�����ŁA�ΐ�ԃ��P�b�g�i�C���x�~�f�B�[�[���G���W��[�������J2005-54771]�̋Z
�p�j��(����^�g���b�N�E�g���N�^�ɍ̗p�j���ēG�̐�ԁi���Q�O�P�T�N�x�d�ʎԔR���̋����j�����ށi���R���
���̋����ɓK���j�������ł���̂ł���B���̂悤�Ȃ��Ƃ͐푈�i����^�g���b�N�̔R�����)�ł͏펯�ł͂Ȃ����낤
���B��R�X�g�̒|���i��PCI �R�ā�HCCI �R�āj�œG�̐�ԁi���Q�O�P�T�N�x�d�ʎԔR���̋����j�����ށi���R��
��̋����ɓK���j���邱�Ƃ��ł���ƍl����̂́A�S���n���Ƃ��������悤���Ȃ��B
�Z�p�҂́A�����̃R�X�g�������߂ɁA�T�`�P�O���̔R������サ��NO�����\���ɉ��P�ł���C���x�~�f�B�[�[���G
���W���i�������J2005-54771�j����Ȃɖ������Ă���B���̈���ŁA�P�����x�̔R������P�ł��Ȃ�PCI �R�āi=
HCCI �R�āj�̋Z�p�����p�����邱�ƂɎ������Ă���悤���B���̂悤��PCI �R�āi=HCCI �R�āj�̋Z�p�𐒔q����e
�g���b�N���[�J�̋Z�p�҂̗l�q�����Ă���ƁA�u�푈���̐��_�_�œG��|���v�z�v�ł���|���i��PCI �R�ā�HCCI �R
�āj���g���ēG�̐�ԁi���Q�O�P�T�N�x�d�ʎԔR���̋����j�����ށi���R���̋����ɓK���j����l�����Ɏ���
����B���̂悤�Ȑ��_�_�ł͓G�̐�ԁi���Q�O�P�T�N�x�d�ʎԔR���̋����j�����ށi���R���̋����ɓK���j��
�邱�Ƃ�����Ȃ��Ƃ͖��炩���B�����ŁA�ΐ�ԃ��P�b�g�i�C���x�~�f�B�[�[���G���W��[�������J2005-54771]�̋Z
�p�j��(����^�g���b�N�E�g���N�^�ɍ̗p�j���ēG�̐�ԁi���Q�O�P�T�N�x�d�ʎԔR���̋����j�����ށi���R���
���̋����ɓK���j�������ł���̂ł���B���̂悤�Ȃ��Ƃ͐푈�i����^�g���b�N�̔R�����)�ł͏펯�ł͂Ȃ����낤
���B��R�X�g�̒|���i��PCI �R�ā�HCCI �R�āj�œG�̐�ԁi���Q�O�P�T�N�x�d�ʎԔR���̋����j�����ށi���R��
��̋����ɓK���j���邱�Ƃ��ł���ƍl����̂́A�S���n���Ƃ��������悤���Ȃ��B
�@���������āA�Q�O�P�T�N�x�d�ʎԔR���̋����ɓK�������邽�߂ɂ́A��̃R�X�g�A�b�v�����A�d�ʎԃ��[�h
�R��l���T�`�P�O�������P�ł���C���x�~�f�B�[�[���G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p���̗p���邱�Ƃ��œK
�ł��邱�Ƃ́A�펯�I�ɍl����Ζ��炩�Ȃ��Ƃ��B�������A�e�g���b�N���[�J�̋Z�p�҂́A��R�X�g�ł��邪�̂�PCI �R
�āi=HCCI �R�āj�̋Z�p�ő�^�g���b�N�E�g���N�^�̂Q�O�P�T�N�x�d�ʎԔR���̋����ɕs�K���̎Ԏ����������
���ł��邪�A���F�A�����ł͂Ȃ����낤���B���Ɋ��m�Șb�ł͂��邪�A�e�g���b�N���[�J�̋Z�p�҂́A�V���@���̐M��
�̂悤�ɁuPCI �R�āi=HCCI �R�āj�v�̌o�T�E������ӐM���Ă���̂ł��낤�B���͂Ƃ�����A�e�g���b�N���[�J�̑�����
�Z�p�҂��s����Ȓ���PCI �R�āi=HCCI �R�āj���u�v�V�I�Ȗ����̔R�ċZ�p�v�ƐM���ċ^��Ȃ��Ƃ���́A
�uPCI �R�āi=HCCI �R�āj�v�̐V���@���Ƀ}�C���h�R���g���[������Ă��܂��Ă���悤�ł���A�~������Ƃł���ƍl
������B
�R��l���T�`�P�O�������P�ł���C���x�~�f�B�[�[���G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p���̗p���邱�Ƃ��œK
�ł��邱�Ƃ́A�펯�I�ɍl����Ζ��炩�Ȃ��Ƃ��B�������A�e�g���b�N���[�J�̋Z�p�҂́A��R�X�g�ł��邪�̂�PCI �R
�āi=HCCI �R�āj�̋Z�p�ő�^�g���b�N�E�g���N�^�̂Q�O�P�T�N�x�d�ʎԔR���̋����ɕs�K���̎Ԏ����������
���ł��邪�A���F�A�����ł͂Ȃ����낤���B���Ɋ��m�Șb�ł͂��邪�A�e�g���b�N���[�J�̋Z�p�҂́A�V���@���̐M��
�̂悤�ɁuPCI �R�āi=HCCI �R�āj�v�̌o�T�E������ӐM���Ă���̂ł��낤�B���͂Ƃ�����A�e�g���b�N���[�J�̑�����
�Z�p�҂��s����Ȓ���PCI �R�āi=HCCI �R�āj���u�v�V�I�Ȗ����̔R�ċZ�p�v�ƐM���ċ^��Ȃ��Ƃ���́A
�uPCI �R�āi=HCCI �R�āj�v�̐V���@���Ƀ}�C���h�R���g���[������Ă��܂��Ă���悤�ł���A�~������Ƃł���ƍl
������B
�@���݂ɁA�uPCI �R�āi=HCCI �R�āj�v�̐V���@���ł́A�uPCI �R�āi=HCCI �R�āj�v���R�����ˎ����̑�����
�����ŃR�X�g�������w��NJF���ł���Ȃ���A�R������NO���팸�̐��ʂ������閲�̂悤�ȔR�Ăł����
�o�T�E������搂��Ă���ƌ��Ȃ��A���낪�����������B�����āA���́uPCI �R�āi=HCCI �R�āj�v�̐V���@���́A
���{�̃G���W���W�̊w�ҁE���ƁE�Z�p�҂̐l�B�̒��ŁA1995�N������}���ɑ����n�߂��悤���B
�����āA���́uPCI �R�āi=HCCI�R�āj�v�̑f���炵���ɂ��āA����܂Ŗ�20�N�Ԃɂ킽���ĐM�ғ��m�����X�ƖO��
�����Ȃ��Ŋy�����c�_�E���_���s���Ă����悤�ł���B�������A�����_�ł́A�R������NO���팸�Ɋւ��A�ڗ�����
���ʂ͓����Ă��Ȃ��悤�ł���B�������A�uPCI �R�āi=HCCI �R�āj�v���̐M�҂ɂƂ��ẮA�uPCI �R�āi=HCCI
�R�āj�v�ɂ�������p��̗L�����������m�F�ł��Ă��Ȃ��Ă��A�V���@���̐M�҂ł��邱�Ƃɓ��ʂ̖�������
������Ă���悤�Ɏv����̂ł���B
�@���ɁA�uPCI �R�āi=HCCI �R�āj�v�̋Z�p���f�B�[�[���~�̔R����P��m�n���팸�ɗL���ȋZ�p�ł���A�ŋ�
��PCI �R�āi=HCCI �R�āj�v�̓����o���_�����\���v�X�A�������Ă��锤�ł���B�Ƃ��낪�A��������
�u����26�N�x�����o��Z�p�����������i�T�v�j�����ԃG���W���Z�p�v����27�N3���ihttps://www.jpo.go.jp/
shiryou/pdf/gidou-houkoku/26_9.pdf�j������ƁA���}�̂悤�ɁA2012�N�ł�PCI �R�āi=HCCI �R�āj�v�̓����o���
shiryou/pdf/gidou-houkoku/26_9.pdf�j������ƁA���}�̂悤�ɁA2012�N�ł�PCI �R�āi=HCCI �R�āj�v�̓����o���
�_�����\�����炩�Ɍ������Ă���̂ł���B
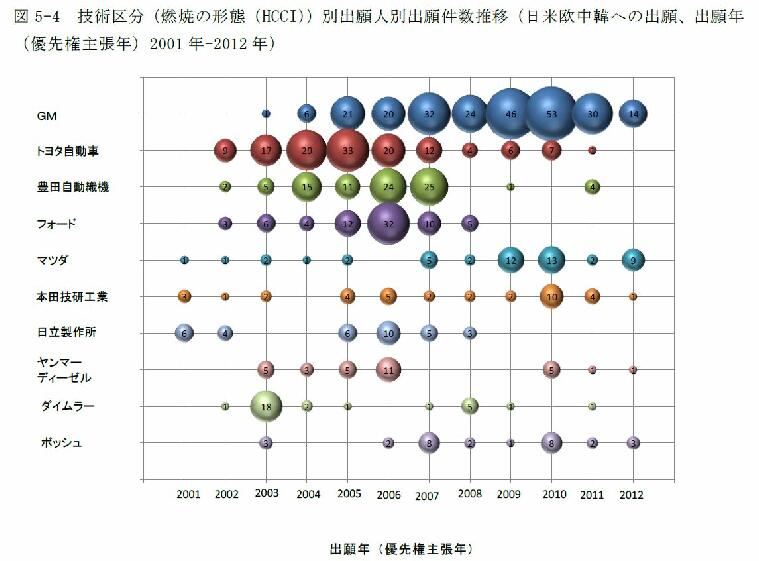 |
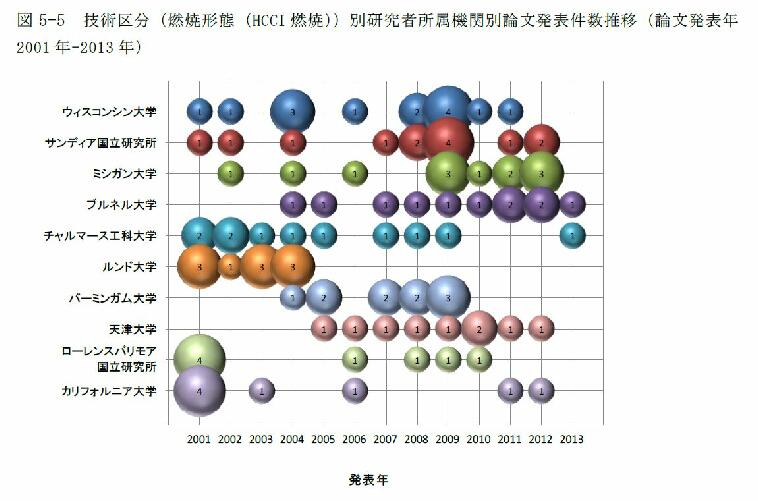 |
�@���̕���27�N3���̓������́u����26�N�x�����o��Z�p�����������i�T�v�j�����ԃG���W���Z�p�v��
�����ꂽ���ʂ���A�����_�i��2016�N2�����݁j�ɂ����ẮA�uPCI �R�āi=HCCI �R�āj�v���f�B�[�[���G���W����
�R����P��m�n���팸�ɖ����ȋZ�p�ł��邱�Ƃ������؋��̈�ł͂Ȃ����ƁB
�@���̃f�B�[�[���G���W���́uPCI �R�āi=HCCI �R�āj�v�̋Z�p�́A��20�N���ȑO�Ƀf�B�[�[���R�Ă̐�i�Z�p
�Ƃ��āuPCI �R�āi=HCCI �R�āj�v����Ă��ꂽ���Ƃ��āA���̐�i�Z�p�̊J���ɑ����̊w�҂��ӋC�g�X�Ɖ��
�ɒ��肵���悤�ł���B���E���Ŗc��Ȍ�����Ɛl�����������ꂽ�����J�������{���ꂽ�B�������A�����̊w�ҁE
���Ƃ̑���ȓw�͂ɂ��A�ŋ߂ł̓f�B�[�[���G���W���́uPCI �R�āi=HCCI �R�āj�v�́A�����ԗp�f�B�[�[��
�G���W���Ŏ��p�����s�\�ł��邱�Ƃ����炩�ɂȂ��Ă����悤�ł���B�܂��ɁA�u��R�����đl��C�x�v�̌���
�ʂ�̓^���ƌ�����̂ł͂Ȃ����낤���B���̌����́A���s�̎����ԗp�f�B�[�[���G���W���ł͑�C���x���傫��
�ω�����ɂ����Ă���Ɉ��肵�����Ȓ����\�Ƃ���R�ăV�X�e���ł��邱�Ƃ��K�{�ł��邪�A���E��
�e�n���G�ߕϓ��ɂ���Đ������C���x���傫���ϓ����錻��ł́uPCI �R�āi=HCCI �R�āj�v�̒������C
�͈��肵����������i�����Ό��ۂ̕p���j�Ȃ��߂ɉ~���ɃG���W�����^�]�ł��Ȃ����{�I�ȋZ�p��̌��ׂ�
���߂Ɛ��������B
�@���̂��߁A����܂ł́uPCI �R�āi=HCCI �R�āj�v���i�ɔR�ċZ�p�Ƃ��Đ����ɐ������Ă��������̊w�҂́A
�u��A�̂���PCI �R�āi=HCCI �R�āj���֒m�����v�Ƃ̑ԓx�����n�߂��悤�ł���B���������ƁA���{�̑�����
�f�B�[�[���G���W���ɊW����w�ҁE���Ƃ���ĂɁu��̂Ђ�Ԃ��v������s���́A����ɐ₦�Ȃ����ӔC��
�ɂ݂̂悤�Ɏv�����A�@���Ȃ��̂ł��낤���B�{���Ȃ�A�uPCI �R�āi=HCCI �R�āj�v�̋Z�p�ɂ��āA�����ԗp
�f�B�[�[���G���W���ł̎��p�s�\�Ȍ��ׂ̏ڍׂȐ����E��͂̔��\���s���đR��ׂ��ƍl�����邪�E�E�E�E�E�E�E�B
�@�����ԋZ�p��́u�Q�O�P�O�N�l�Ƃ���܂̃e�N�m���W�[�W�v(2010�N5��19�`21�j�Ő��E�I�Ȍ����@�ւł���AVL�i�I�[
�X�g���A�j�̃w�����[�g�E���X�g����u�����A�f�B�[�[���G���W���̔R�����ɂ́A�u�R���s���[�^�v�Z�p�����܂��g
���v�Ƃ̐�����lj����āu�t���N�V�������X�i���C�����j�̒ጸ�v�Ɓu�V�����_�[���̔R�ĉ��P�v�̃G���W���H�w�̋��ȏ�
�ɋL�ڂ���Ă����̋Z�p���ڂɂ����25���̌������オ�\�Ɣ��\���Ă��邪�A��̓I�ȋZ�p���e�͉�������
�Ă��Ȃ��悤���B����́A���E�I�Ȍ����@�ւ�AVL����̓I�ȋZ�p���e�������������ɁA�f�B�[�[���G���W���̌���
����̒P�Ȃ��]���q�ׂĂ���ɉ߂��Ȃ��̂��BAVL�͑S���₵�����e�̍u�����s�������̂��B
�X�g���A�j�̃w�����[�g�E���X�g����u�����A�f�B�[�[���G���W���̔R�����ɂ́A�u�R���s���[�^�v�Z�p�����܂��g
���v�Ƃ̐�����lj����āu�t���N�V�������X�i���C�����j�̒ጸ�v�Ɓu�V�����_�[���̔R�ĉ��P�v�̃G���W���H�w�̋��ȏ�
�ɋL�ڂ���Ă����̋Z�p���ڂɂ����25���̌������オ�\�Ɣ��\���Ă��邪�A��̓I�ȋZ�p���e�͉�������
�Ă��Ȃ��悤���B����́A���E�I�Ȍ����@�ւ�AVL����̓I�ȋZ�p���e�������������ɁA�f�B�[�[���G���W���̌���
����̒P�Ȃ��]���q�ׂĂ���ɉ߂��Ȃ��̂��BAVL�͑S���₵�����e�̍u�����s�������̂��B
�@�܂��AAVL�́A��̓I�ȃf�B�[�[���̌�������̕��@�Ƃ��āu�r�C�M��d�C�G�l���M�[�ɕς���R���o�[�^�[��t
���邱�ƂŁA6 - 7���قnj�������悹�ł���v�Ɣ��\���Ă��邪�A����̓f�B�[�[���G���W���̔r�C�K�X�̔M�G�l���M
�[�������L���T�C�N���A�r�C�K�X�^�[�r���܂��̓X�^�[�����O�G���W�����œ��͂ɕϊ����A���̓��͂Ŕ��d�@���쓮��
�ēd�C�G�l���M�[��������鑕�u��t���������̂ƍl������B���́u�r�C�M��d�C�G�l���M�[�ɕς���R���o�[�^
�[�v�́A�Η͔��d�����^�D���ł̓f�B�[�[���G���W������i�o�͂ʼn^�]����邽�߂ɏ�ɍ����̔r�C�K�X��r�o
���邽�߂ɍ��������ʼnғ��ł��邽�߁A���ɉΗ͔��d�����^�D���ɂ����čL�����y���Ă��鑕�u�ł���B�������A
��^�f�B�[�[���g���b�N�͏�ɃG���W���o�͂��ϓ������ɕ������ׂ̉^�]�ŒႢ�r�C�K�X���x�ƂȂ邱�Ƃ�������
�߁A��^�g���b�N�Ɂu�r�C�M��d�C�G�l���M�[�ɕς���R���o�[�^�[�v�𓋍ڂ����ꍇ�ɂ͌���������������Ă��܂���
�ƂɂȂ�B���̂��߁A��^�g���b�N�ɂ��̃R���o�[�^�[�𓋍ڂ��Ă��\���ȔR��̌���͓���B���������āAAVL����
�̃R���o�[�^�[�̓��ڂɂ���đ�^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W���̌�����6 - 7���قlj��P�ł���Ƃ̍u���ł̔��\
�́A�傫�Ȍ��ł͂Ȃ����낤���B�@
���邱�ƂŁA6 - 7���قnj�������悹�ł���v�Ɣ��\���Ă��邪�A����̓f�B�[�[���G���W���̔r�C�K�X�̔M�G�l���M
�[�������L���T�C�N���A�r�C�K�X�^�[�r���܂��̓X�^�[�����O�G���W�����œ��͂ɕϊ����A���̓��͂Ŕ��d�@���쓮��
�ēd�C�G�l���M�[��������鑕�u��t���������̂ƍl������B���́u�r�C�M��d�C�G�l���M�[�ɕς���R���o�[�^
�[�v�́A�Η͔��d�����^�D���ł̓f�B�[�[���G���W������i�o�͂ʼn^�]����邽�߂ɏ�ɍ����̔r�C�K�X��r�o
���邽�߂ɍ��������ʼnғ��ł��邽�߁A���ɉΗ͔��d�����^�D���ɂ����čL�����y���Ă��鑕�u�ł���B�������A
��^�f�B�[�[���g���b�N�͏�ɃG���W���o�͂��ϓ������ɕ������ׂ̉^�]�ŒႢ�r�C�K�X���x�ƂȂ邱�Ƃ�������
�߁A��^�g���b�N�Ɂu�r�C�M��d�C�G�l���M�[�ɕς���R���o�[�^�[�v�𓋍ڂ����ꍇ�ɂ͌���������������Ă��܂���
�ƂɂȂ�B���̂��߁A��^�g���b�N�ɂ��̃R���o�[�^�[�𓋍ڂ��Ă��\���ȔR��̌���͓���B���������āAAVL����
�̃R���o�[�^�[�̓��ڂɂ���đ�^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W���̌�����6 - 7���قlj��P�ł���Ƃ̍u���ł̔��\
�́A�傫�Ȍ��ł͂Ȃ����낤���B�@
�@����AVL����������u�r�C�M��d�C�G�l���M�[�ɕς���R���o�[�^�[�v�́A��^���b�N�̑��s�ő��p�����f�B�[�[
���f�B�[�[���G���W���̕������^�]���ɂ͔r�C�K�X���x���Ⴍ�A�r�C�K�X�̔M��d�C�G�l���M�[�ɕς���ۂ̌�
������錇�_������B���̌��_�i�����ׁj�����P���邽�߂ɂ́A�f�B�[�[���G���W���̕������^�]���̔r�C�K�X��
�x������������V���ȋZ�p��lj����邱�Ƃ��K�v�ł���B���������āAAVL�̒�Ă̂悤�ɁA�u�r�C�M��d�C�G�l��
�M�[�ɕς���R���o�[�^�[�v��P�ɑ�^�g���b�N�ɓ��ڂ��������ł́A��^�g���b�N�̏\���ȔR�����͖]�߂Ȃ��̂�
����B����AVL����^�g���b�N�̔R�����̂��߂Ɂu�r�C�M��d�C�G�l���M�[�ɕς���R���o�[�^�[�v���^�g���b�N
�ɓ��ڂ��邱�Ƃ��Ă������̂ł���A��^���b�N�̑��s�ő��p�����f�B�[�[���f�B�[�[���G���W���̕�������
�^�]���ɔr�C�K�X���x������������Z�p���ŏ��ɒ�Ă��ׂ��ł͂Ȃ����ƍl������B�f�B�[�[���G���W���̕���
���^�]���ɔr�C�K�X���x���������ł���Z�p���������Ȃ��Łu�r�C�M��d�C�G�l���M�[�ɕς���R���o�[�^
�[�v���^�g���b�N�ɓ��ڂ���Ƃ�AVL�̍u���ł̒�ẮA�M�҂ɂ͋��̍����Ǝv����̂��BAVL�����̂悤�ȍu��
���\�����Ă���Ƃ��������ƁA�f�B�[�[���G���W���̔R�����ɂ��Ă�AVL���Z�p�A�C�f�A���͊����A�傫�ȕǂ�
�˂��������Ă���悤�ɍl������B�����āA���̂悤��AVL�ɑ����̃g���b�N���[�J����^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W
���̔R�����̃R���T���e�B���O��O���������ɎĂ��錻����l����ƁA����̑�^�g���b�N�ɂ͔R�����ɑ�
���Ȋ��҂��ł��Ȃ��ƍl����̂��Ó��ł͂Ȃ����낤���B
���f�B�[�[���G���W���̕������^�]���ɂ͔r�C�K�X���x���Ⴍ�A�r�C�K�X�̔M��d�C�G�l���M�[�ɕς���ۂ̌�
������錇�_������B���̌��_�i�����ׁj�����P���邽�߂ɂ́A�f�B�[�[���G���W���̕������^�]���̔r�C�K�X��
�x������������V���ȋZ�p��lj����邱�Ƃ��K�v�ł���B���������āAAVL�̒�Ă̂悤�ɁA�u�r�C�M��d�C�G�l��
�M�[�ɕς���R���o�[�^�[�v��P�ɑ�^�g���b�N�ɓ��ڂ��������ł́A��^�g���b�N�̏\���ȔR�����͖]�߂Ȃ��̂�
����B����AVL����^�g���b�N�̔R�����̂��߂Ɂu�r�C�M��d�C�G�l���M�[�ɕς���R���o�[�^�[�v���^�g���b�N
�ɓ��ڂ��邱�Ƃ��Ă������̂ł���A��^���b�N�̑��s�ő��p�����f�B�[�[���f�B�[�[���G���W���̕�������
�^�]���ɔr�C�K�X���x������������Z�p���ŏ��ɒ�Ă��ׂ��ł͂Ȃ����ƍl������B�f�B�[�[���G���W���̕���
���^�]���ɔr�C�K�X���x���������ł���Z�p���������Ȃ��Łu�r�C�M��d�C�G�l���M�[�ɕς���R���o�[�^
�[�v���^�g���b�N�ɓ��ڂ���Ƃ�AVL�̍u���ł̒�ẮA�M�҂ɂ͋��̍����Ǝv����̂��BAVL�����̂悤�ȍu��
���\�����Ă���Ƃ��������ƁA�f�B�[�[���G���W���̔R�����ɂ��Ă�AVL���Z�p�A�C�f�A���͊����A�傫�ȕǂ�
�˂��������Ă���悤�ɍl������B�����āA���̂悤��AVL�ɑ����̃g���b�N���[�J����^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W
���̔R�����̃R���T���e�B���O��O���������ɎĂ��錻����l����ƁA����̑�^�g���b�N�ɂ͔R�����ɑ�
���Ȋ��҂��ł��Ȃ��ƍl����̂��Ó��ł͂Ȃ����낤���B
�@����AVL�����́u�r�C�M��d�C�G�l���M�[�ɕς���R���o�[�^�[�v����^�g���b�N�p�Ƃ��Ď��p�ɑς����鍂������
�ʼnғ��ł���悤�ɂ��邽�߂ɂ́A��^���b�N�̑��s�ő��p�����f�B�[�[���f�B�[�[���G���W���̕������^�]��
�ł̔r�C�K�X���x�̍�������}�邱�Ƃ��K�v�ł���B���̕��@�Ƃ��āA���̃R���o�[�^���̗p����ꍇ�ɂ́A�M�Ғ�
�Ă��C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p��p���邱���K�{�ƍl���Ă���B�t�Ȍ�����������A
AVL�����̔r�C�M��d�C�G�l���M�[�ɕς���R���o�[�^�[�̃V�X�e���ɕM�Ғ�Ă��C���x�~�G���W���i�������J
2005-54771�j�̓����Z�p��p���Ȃ��ꍇ�ɂ́A�����̌��オ�]�߂Ȃ��̂ł���B���̂��߁AAVL����Ă���u�r�C
�M��d�C�G�l���M�[�ɕς���R���o�[�^�[�v�̃V�X�e���ł́A�d�ʎԃ��[�h�R��̌��オ�\���łȂ��A���p���Ɍ���
���Z�p�ƍl������B�f�B�[�[���G���W���̔M�����̌����}��Z�p�Ƃ��āAAVL�����́u�R���o�[�^�[�̃V�X�e����
��Ă������̂ł���A�f�B�[�[���G���W���̕������^�]���̔r�C�K�X���x������������Z�p�ł���M�Ғ��
���C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p�̗̍p�������ɒ�Ă��ׂ��ł���B
�ʼnғ��ł���悤�ɂ��邽�߂ɂ́A��^���b�N�̑��s�ő��p�����f�B�[�[���f�B�[�[���G���W���̕������^�]��
�ł̔r�C�K�X���x�̍�������}�邱�Ƃ��K�v�ł���B���̕��@�Ƃ��āA���̃R���o�[�^���̗p����ꍇ�ɂ́A�M�Ғ�
�Ă��C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p��p���邱���K�{�ƍl���Ă���B�t�Ȍ�����������A
AVL�����̔r�C�M��d�C�G�l���M�[�ɕς���R���o�[�^�[�̃V�X�e���ɕM�Ғ�Ă��C���x�~�G���W���i�������J
2005-54771�j�̓����Z�p��p���Ȃ��ꍇ�ɂ́A�����̌��オ�]�߂Ȃ��̂ł���B���̂��߁AAVL����Ă���u�r�C
�M��d�C�G�l���M�[�ɕς���R���o�[�^�[�v�̃V�X�e���ł́A�d�ʎԃ��[�h�R��̌��オ�\���łȂ��A���p���Ɍ���
���Z�p�ƍl������B�f�B�[�[���G���W���̔M�����̌����}��Z�p�Ƃ��āAAVL�����́u�R���o�[�^�[�̃V�X�e����
��Ă������̂ł���A�f�B�[�[���G���W���̕������^�]���̔r�C�K�X���x������������Z�p�ł���M�Ғ��
���C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p�̗̍p�������ɒ�Ă��ׂ��ł���B
�@���݂ɁAAVL�́u�r�C�M��d�C�G�l���M�[�ɕς���R���o�[�^�[�v�ł̓f�B�[�[���G���W���̔r�C�K�X����G�l���M
�[���������6 - 7���i�d�ʎԃ��[�h�R��H�j�̌�������悹����Ƃ̔��\���s���Ă��邪�A����AVL��ẴR���o�[
�^�[���ғ������ۂ̌����͋ɂ߂ĒႢ�Ɨ\�z����邽�߁A���̃R���o�[�^�[���^�g���b�N�ɓ��ڂ����ꍇ�ɂ́A��
�ۂɑ�^�g���b�N�̏d�ʎԃ��[�h�R���6 - 7���قǂ̔R�����悹���邱�Ƃ͋ɂ߂ē�����̂ƍl������B����
�ɂ��ẮAAVL�͖��ӔC�Ȍ�������̐��l�\�����Ă���̂ł͂Ȃ����Ɗ����Ă���B
�[���������6 - 7���i�d�ʎԃ��[�h�R��H�j�̌�������悹����Ƃ̔��\���s���Ă��邪�A����AVL��ẴR���o�[
�^�[���ғ������ۂ̌����͋ɂ߂ĒႢ�Ɨ\�z����邽�߁A���̃R���o�[�^�[���^�g���b�N�ɓ��ڂ����ꍇ�ɂ́A��
�ۂɑ�^�g���b�N�̏d�ʎԃ��[�h�R���6 - 7���قǂ̔R�����悹���邱�Ƃ͋ɂ߂ē�����̂ƍl������B����
�ɂ��ẮAAVL�͖��ӔC�Ȍ�������̐��l�\�����Ă���̂ł͂Ȃ����Ɗ����Ă���B
�@�܂��AAVL�����̍u���Œ�Ă��Ă��������̌�������̋Z�p���G���W���_�E���T�C�W���O�ł���B���̃G���W��
�_�E���T�C�W���O�́A�Â�����ǂ��m��ꂽ�R�����̋Z�p�ł���A��^�f�B�[�[���g���b�N�̃��[�J������܂ŋ�����
�J�������{���Ă����Z�p�ł��邽�߁A�Z�p�I�ɂ͉��̖ڐV�����������R�����̎�@�ł���B
�_�E���T�C�W���O�́A�Â�����ǂ��m��ꂽ�R�����̋Z�p�ł���A��^�f�B�[�[���g���b�N�̃��[�J������܂ŋ�����
�J�������{���Ă����Z�p�ł��邽�߁A�Z�p�I�ɂ͉��̖ڐV�����������R�����̎�@�ł���B
�@�ȏ�̂悤�ɁA���E�I�Ȍ����@�ւł���AVL��2010�N�T���̍u���ł̒�ẮA�f�B�[�[���G���W���̌��������
���Ă͌ÓT�I�Ȋ��m�̋Z�p�Ɍ����Ă���A�Z�p�I�ȖڐV�����͖����B�����āA��^�g���b�N�̔R�����Ɏ��ۂ�
�𗧂������ȐV�����Z�p�������������Ȃ��̂ł���B����ɂ�������炸�A���݁A���{�̑����̃g���b�N���[�J��
�L����AVL����f�B�[�[���G���W�����̋Z�p�R���T���e�B���O���Ă���悤�ł��邪�AAVL�̃R���T���e�B���O��
�R�X�g�p�[�t�H�[�}���X�͔@���Ȃ��̂ł��낤���B
���Ă͌ÓT�I�Ȋ��m�̋Z�p�Ɍ����Ă���A�Z�p�I�ȖڐV�����͖����B�����āA��^�g���b�N�̔R�����Ɏ��ۂ�
�𗧂������ȐV�����Z�p�������������Ȃ��̂ł���B����ɂ�������炸�A���݁A���{�̑����̃g���b�N���[�J��
�L����AVL����f�B�[�[���G���W�����̋Z�p�R���T���e�B���O���Ă���悤�ł��邪�AAVL�̃R���T���e�B���O��
�R�X�g�p�[�t�H�[�}���X�͔@���Ȃ��̂ł��낤���B
�P�S�|�S�D��ʌ��̽��߰�ذ��ި���ٴݼ�����̔R�����́A���s�̗\��
�@�Ɨ��s���@�l ��ʈ��S���������ł́A�\�Q�Q�ɂ����悤�ɁA2010�N11��24�i���j�E25���i�j�Ɂu��ʈ��S����
�����t�H�[�����Q�O�P�O�v�Ə̂���Z�p���\�̍u����J�Â��ꂽ�悤���B���̍u����ɂ́A�䂪�����\���鑽����
��ʊW�̊w�ҁE���Ƃ��o�Ȃ���A����̕��y�����҂���鎟���㎩���Ԃɂ��Ă̋Z�p���\�Ƃ����Ɋւ�
��c�_���s��ꂽ�Ƃ̂��Ƃł���B
| |
|
| |
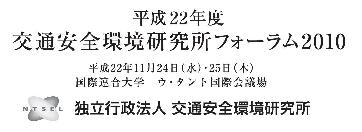 |
�@�����i�Ɓj�ʈ��S���������̍u�����\��ł́A�u�X�[�p�[�N���[���f�B�[�[���iSCD�j�G���W���ɂ�����V�W�J�v��
�肵����^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W���̔R������_���������J���̘_��������Ă���B���̘_����q�ǂ�
���Ă����������Ƃ���A�L�q�̓��e�ɑ����̋^��_���ڂɕt�����̂ŁA�\�Q�R�ɂ܂Ƃ߂��B
�肵����^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W���̔R������_���������J���̘_��������Ă���B���̘_����q�ǂ�
���Ă����������Ƃ���A�L�q�̓��e�ɑ����̋^��_���ڂɕt�����̂ŁA�\�Q�R�ɂ܂Ƃ߂��B
| |
|
���
����
�@�@�@�V�G�B�V�[�C�[ �F �� �F�O�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ |
�i�Ɓj�ʈ��S���������ƐV�G�B�V�[�C�[�Ƃ̋��� |
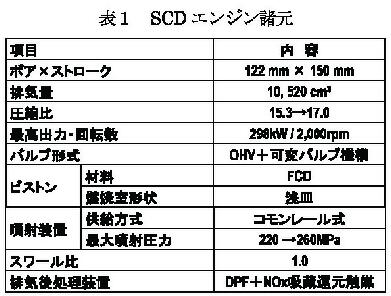 �i�\�P�̃x�[�X�G���W���͓��쎩���Ԃ�PC�P�P�^�Ɛ���j
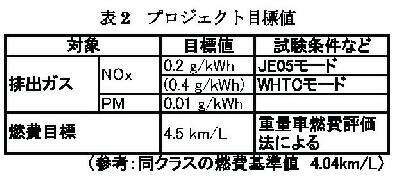 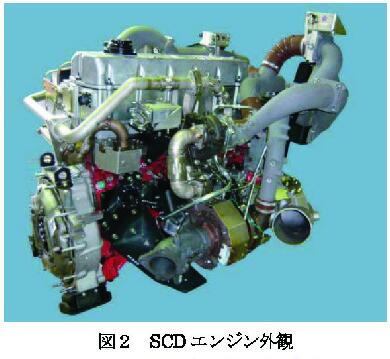 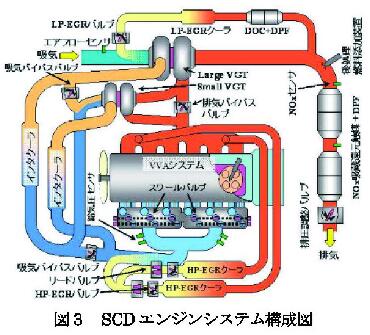 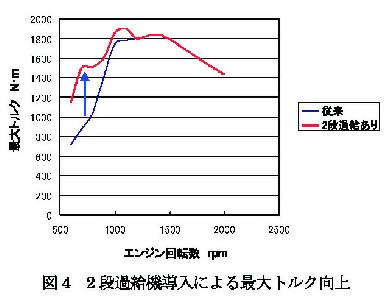 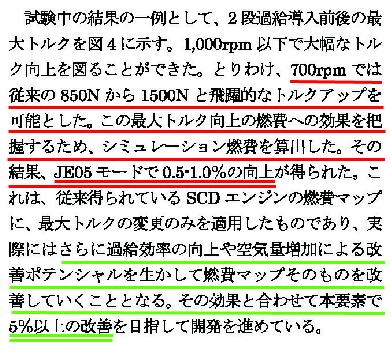 |
�@���L�̌�ʈ��S���������́u�X�[�p�[�N���[���f�B�[�[��
�iSCD�j�G���W���ɂ�����V�W�J�v�̘_���i�Ȍ�A�u��ʈ��S��
��������SCD�G���W���_���v�Ə̂��j�ł́A���L�́u�}�R�@SCD�G
���W���V�X�e���\���}�v�Ɏ�����Ă���悤�ɁA�ȉ��̋Z�p���g
�ݍ��܂�Ă���B
�� �Q�i�V�[�P���V�����ߋ��@
�� �����R�������[���i��260MPa�j
�� LP-EGR�̗̍p�ɂ��EGR����̍��x��
���X
�@�����āA���L�̌�ʈ��S����������SCD�G���W���_���̐}
�R�̃V�X�e���ł́A1000rpm�ȉ��̒ᑬ�ł̃G���W���g���N�A�b
�v�ɂ��AJE�O�T���[�h�R�0.5�`1.0�����x�̉��P�ł�������
�̂��ƁB���̒��x�̔R����P�͔R���̍ۂɐ����鑪��덷
�͈̔͂ɉ߂��Ȃ��B���������āA���̒��x�̔R����P��_����
�ւ炵���ɋL�ڂ��邱�Ƃ́A�@���Ȃ��̂ł��낤���B
�@����A�{�y�[�W�� �y�P�S�|�P�@NEDO�́u�����x�R�Đ���G���W
�V�X�e���̌����J���v�ł́A�R����̑厸�s�z �̍��Ŏ�����
����悤�ɁA8���~�ȏ�̗\�Z�Ŏ��{���ꂽNEDO�Ƃ����U������
�����̊v�V�I���������Q�ԑ����Z�p�J���i�N���[���f�B�[�[
���v���W�F�N�g�A2004�`2009�N�j�́u�����x�R�Đ���G���W�V�X
�e���̌����J���v�̑�^�v���W�F�N�g�ł́A��^�g���b�N�p�f�B�[
�[���G���W���Ɉȉ��̋Z�p��g�ݍ��V�X�e���ɂ��NO����
���ƔR����P�̌����J�������Ɏ��{����Ă���B
�� �R�i�ߋ��V�X�e���i�����ϗL�������j
�� 300MP���̒������R�����ˁi�����ϗL�������j�A�� �J�����X
�V�X�e����g�ݍ��uPCI�R�āv(PCI�R�ā�HCCI�R�āj
����NEDO�̌����J���ł́A�P�S�|�P���̐}�P�U�Ɏ������悤�ɁA
�R��팸�͖ڕW��10���팸�ɂ͑S���y���A2015�N�x�d
�ʎԔR���ɑ��ĂQ���̈������m�F���ꂽ�B���̂悤
�ɁANEDO�̃N���[���f�B�[�[���v���W�F�N�g�́A�f�B�[�[���̔R��
���P�ɂ��Ċ��S�Ɏ��s�ł��������Ƃ�����Ă���̂ł�
��B
�@���āA��ʈ��S����������SCD�G���W���_���ɋL�ڂ����
���鍶�L�́u�}�R�@SCD�G���W���V�X�e���\���}�v�ɐ��荞�܂�
����v�ȋZ�p�́A�O�q�̂W-1���Ŏ������f�B�[�[���̔R����P
�ɂ��Ċ��S�Ɏ��s����NEDO�̊v�V�I���������Q�ԑ����Z
�p�J���i�N���[���f�B�[�[���v���W�F�N�g�A2004�`2009�N�j�́u��
���x�R�Đ���G���W�V�X�e���̌����J���v�Ɨގ��̋Z�p���w��
�ǂł���B���̂��߁A��ʈ��S���������́u�}�R�@SCD�G���W
���V�X�e���\���}�v�ɐ��荞�܂ꂽ�Z�p�ɂ���ăf�B�[�[���G��
�W���̏\���ȔR����P�́A�S�����҂ł��Ȃ����Ƃ͖����łł�
��B�����āA���L�̌�ʈ��S����������SCD�G���W���_����
�́AJE�O�T���[�h�R�0.5�`1.0�����x�̉��P���������Ȃ���
���ƋL�ڂ���Ă��邱�Ƃ́A���R�̌��ʂł͂Ȃ����ƍl�����
��B
�@�Ƃ���ŁA��ʈ��S���������̗�؉��ꎁ�A�Έ�f���A��
���㎁����ѐV�G�B�V�[�C�[�̐� �F�O���́A���L�̌�ʈ�
�S����������SCD�G���W���_���ł́A�u�}�R�@SCD�G���W���V
�X�e���\���}�v�̋Z�p�ɂ���āA����A�u�ߋ��@�����̌�����
�C�ʑ����ŔR��}�b�v�����P���A���L�̐}�R�̃V�X�e���łT����
��iJE�O�T���[�h�j�̔R����P��ڎw���v�ƋL�ڂ���Ă���B����
���A�M�҂ɂ͂��̂悤�Ȃ��Ƃ������ł���Ƃ͂ƂĂ��l�����Ȃ�
�̂��B�Ȃ��Ȃ�A�ߋ��@�̌���������́A�M�c���̖����^�[�r
����u���A�̍ޗ����J���ł����ꍇ�ɏ��߂ċ��C��r�C�K�X��
�R��������ɖh�~�ł���ꍇ��A�^�[�r���H�����ɔ��ł���ޗ�
��������̋Z�p���J���ł����ꍇ�ɂ����āA���߂Ď����ł�
�邱�Ƃł���B�����̉ߋ��@�W�̋Z�p���A����A����I�ɔ�
�W���Ȃ�����A�߂������ɉߋ��@�̌������傫������ł����
�\���͑S�������ƍl����̂��Ó��ł���B�܂��AJE�O�T���[�h��
�̓G���W���������ח̈�ł̉^�]�䗦���������߁AJE�O�T���[
�h�̏\���ȔR�����ɂ́A�������ח̈�ł̔R����P���K�v
�ł���B�����A�f�B�[�[���G���W���͕������ׂł͒�������C��
��̏�Ԃʼn^�]�����̂ł���B����ɂ�������炸�A���L��
��ʈ��S����������SCD�G���W���_���ł́A��C�ʂ̑���
�ŔR��}�b�v�����P�ł���Ǝ咣����Ă��鍪�����M�҂ɂ͗ǂ�
�����ł��Ȃ��Ƃ���ł���B���������āA���L�̘_���ɂ����āA��
�ʈ��S���������̗�A�Έ�A���̏�������ѐV�G�B�V�[
�C�[�̐����́A�u�ߋ��@�����̌�����C�ʑ����ŔR��}�b
�v�����P���A���L�̐}�R�̃V�X�e���łT���ȏ�iJE�O�T���[�h�j��
�R����P��ڎw���v�ƋL�q����Ă��邪�A�����I�ȔR����P��
�Z�p����̓I�ɉ���������Ă��Ȃ��̂ł���B���������āA���L
�̘_���ɂ�����u�T���ȏ�iJE�O�T���[�h�j�̔R����P�v�̏q�́A
���҂̒P�Ȃ��]���q�ׂĂ��邾���ł���A�f�B�[�[���G���W��
�̏\���ȔR����P�����ۂɎ����ł���\���͑S�������Ǝv��
����B
�@�������A�M�҂̗\�z�ɔ����A��ʈ��S���������̗�؉���
���A�Έ�f���A����㎁����ѐV�G�B�V�[�C�[�̐� �F�O��
���A���L�̘_���ɋL�ڂ���Ă���悤�ɁA�u�}�R�@SCD�G���W���V
�X�e���\���}�v�̋Z�p��p���āu�ߋ��@�����̌�����C�ʑ�
���ŔR��}�b�v�����P���A���L�̐}�R�̃V�X�e���łT���ȏ�iJE
�O�T���[�h�j�̔R����P��ڎw���ĊJ����i�߂�v���Ƃɂ���āA��
�^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W���̔R����T���ȏ���̉��P����
�Ɏ����ł����Ƃ���A����͖��@������̈̋Ƃł����
�]����̂ł͂Ȃ����낤���B
�@�ʂ����āA��ʈ��S���������̗�؉��ꎁ�A�Έ�f���A��
���㎁����ѐV�G�B�V�[�C�[�̐� �F�O���́A�{���Ƀf�B�[
�[���R������P���錻�݂̖��p�t�̐l�B�ł���̂��A�����
���A����܂Ō��O��������g���Č����\�Z���l�����Ă����P�Ȃ�
�y�e���t�E���\�t�ɗނ���l�B�ł���̂��́A���̂Ƃ���s����
����B���͂Ƃ�����A��ʈ��S���������̗�؉��ꎁ�A�Έ�
�f���A����㎁����ѐV�G�B�V�[�C�[�̐� �F�O�����R���
�P�̖��p�t���A�Ⴕ���̓y�e���t�E���\�t���̉���ł��邩�́A
�߂������ɂ͖��炩�ɂȂ邱�Ƃł���A�M�҂ɂ͋����[�X�ł�
��B���̌��ʂ��y���݂��B
�Ƃ���ŁA���L�̘_���́A�����̑�^�g���b�N��2015�N�x�d�ʎ�
�R���ɓK�����Ă���2010�N11��24�i���j�E25���i�j�ɊJ��
����Ă���u��ʈ��S���������t�H�[�����Q�O�P�O�v�ł����\��
��Ă���B���̂��Ƃ���A���L�̘_���̓ǎ҂́A���̘_���̃x�[
�X�G���W��(���쎩���Ԃ�PC11�^�Ɛ����j�̏d�ʎԃ��[�h�R��
�l�́A2015�N�x�d�ʎԔR���ɓK�����Ă���R��x���ƍl
���Ă�����̂Ɛ��������B�������A���L�̌�ʈ��S��������
�́u�X�[�p�[�N���[���f�B�[�[���iSCD�j�G���W���ɂ�����V�W�J�v
�̘_���ł́A��^�g���b�N�p�̃x�[�X�G���W��(���쎩���Ԃ�
PC11�^�Ɛ����j�̏d�ʎԃ��[�h�R��l��2015�N�x�d�ʎԔR��
��ɓK�����Ă���|�������L�ڂ���Ă��Ȃ��悤���B���̂���
����A���L�̘_���̃x�[�X�G���W��(���쎩���Ԃ�PC11�^�Ɛ�
���j�̔R��l(�Ⴆ��JE�O�T���[�h�R��j�Ƃ��ė�����l���v����
�ꂽ�ƋL�ڂ��Ă����A���L�́u�}�R�@SCD�G���W���V�X�e���\
���}�v�Ŕ@���Ȃ�R��l���v������悤�Ƃ��A���̍��L�́u�}�R�@
SCD�G���W���V�X�e���\���}�v�̋Z�p��p���āu�ߋ��@������
������C�ʑ����ŔR��}�b�v�����P���A���L�̐}�R�̃V�X�e
���łT���ȏ�iJE�O�T���[�h�j�̔R����P�������ł����v�Ƙ_����
�L�ڂ��Ă����̌��������Ȃ����ƂɂȂ�̂ł���B�v�́A�x�[�X
�G���W��(���쎩���Ԃ�PC11�^�Ɛ����j���P�O�N�ȏ���Â��^��
�G���W���̂��߁A�R��̈����x�[�X�G���W���ł��邱�Ƃ��L�ڂ�
�Ă����A�u�}�R�@SCD�G���W���V�X�e���\���}�v�̋Z�p��p����
���Ƃɂ����JE�O�T���[�h�ł̂T����P�O���̔R����P�̎�����
�ʂ��������Ƃ́A�ɂ߂ĊȒP�Ȃ��Ƃł���B�ܘ_�A���̂悤�Ȏ�@
�ł܂Ƃ߂�ꂽ�_���́A�f�B�[�[���G���W���̔R�����̋Z�p�I
�Ȑi���Ɋ�^���Ȃ����Ƃ͓��R�ł���B�����āA���̂悤�ȕ��@
�́A���\�t��y�e���t�����풃�ю��ɗp�����@���B�������A
���{���\����w�ҁE���Ƃł����ʈ��S���������̗��
���ꎁ�A�Έ�f���A����㎁����ѐV�G�B�V�[�C�[�̐� �F
�O�������\�����_���ɂ����ẮA���̂悤�ȍ��\��y�e���ɗ�
�����@����g���Ę_�����쐬����邱�Ƃ́A�펯�I�ɂ͈��
�����̂ƍl�����邪�E�E�E�E�E�E�B
|
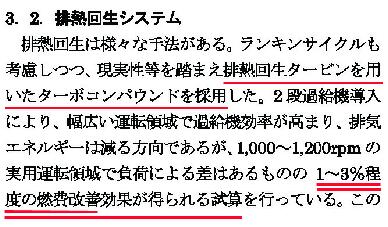 |
�@�O�q�́u�Q�D�f�B�[�[���G���W���ɂ�����r�o�K�X�ጸ�ƔR���
�P�v�ɋL�ڂ��Ă���ʂ�A �^�[�{�R���p�E���h�̔r�M����^�[�r��
�̓����̔r�C�K�X�́A�^�[�{�ߋ��@�̃^�[�r�������̔r�C�K�X
�̉��x�E���͂����ቷ�E�ሳ�ł��邽�߁A�r�C�K�X�̃G�l���M
�[�̃|�e���V�������Ⴂ�B���̂��ߔr�C�K�X�̑̐ϗ��ʂ������A
����^�[�r���͑�^�����K�v�ƂȂ�B���̌��ʃR�X�g�������A��
�ԗ����ڂ��e�ՂȂ��Ƃł͂Ȃ��B�܂��A�^�[�{�R���p�E���h�́A
��^�g���b�N�̑��s�R��̉��P������ȋZ�p���I�̃y�[�W�ɏ�
�q���Ă���悤�ɁA�^�[�{�R���p�E���h�ɂ��R��́A�G���W����
�ő�g���N�̉^�]��ԂłQ���O�オ���P�ł��邾���ł���B����
�āA��^�g���b�N�̎��ۂ̑��s��d�ʎԃ��[�h�R��v���Ɏg�p��
���G���W���^�]�́A�ő�g���N�̃G���W���̉�]���x�t�߂�
�����ł̂Q/�R���ȉ��̒����ȉ��̒�����]�̎��Ɍ��肳
����ɁA���̍����ח̈�̗̈悪�啔���ł���B���������āA
�]���̃G���W���Ƀ^�[�{�R���p�E���h�����������ł́A��^�g
���b�N�̎����s��d�ʎԃ��[�h�R��l�̉��P�́A�^�[�{�R���p�E
���h�ɂ��G���W���̍ő�g���N�̉^�]��Ԃł̂Q���O��̔R��
���P�̔����ȉ��A�����P.0 ���ȉ��ł͂Ȃ����Ɛ��������B
�@���������āA���Ă̑�^�g���b�N�E�g���N�^�Ƀ^�[�{�R���p�E���h�� �̗p����ő�̖ړI�́A�R�����ł͖����A�����ő刳�͂��� �������邱�Ɩ����o�͂������ł����i�ł���悤���B���̏؋� �ɁA�{���{�A�X�J�j�A���́A��^�g���N�^�p�̃G���W���Ƀ^�[�{�R ���p�E���h���̗p���Ă���̂����B �@���āA���L����ʈ��S����������SCD�G���W���_���ɂ��� �āA��ʈ��S���������̗�؉��ꎁ�A�Έ�f���A����� ������ѐV�G�B�V�[�C�[�̐� �F�O�����^�[�{�R���p�E���h�̍� �p�ɂ���ĂP�`�R�����x�̔R����P�i��JE�O�T���[�h�Ɛ����j�ƋL �q����Ă���B���L����ʈ��S����������SCD�G���W���_�� �ɂ������P�`�R�����x�̔R����P�̎��Z���ʂ́A���E�̈�ʏ� ��ɔ�ׂĐ��{�̔R����P�ł���A���̎��Z�ɗp����ꂽ�r�M ����^�[�r���̃^�[�r�������Ƃ��Ĕ��I�ȍ���������p���� �v�Z���ꂽ���̂Ɛ��������B���R�̂��ƂȂ���A���\�v�Z�ɖ� ����荂���^�[�r��������p�����ꍇ�ɂ́A�傫�ȔR����P�� �Z�o�ł���̂ł���B���̐́A�^�[�{�G���W���̐��\�V���~���[ �V�����v�Z�����I�ɍs���Ă������Z�p���̕M�҂��猩��A ���I�ȍ����^�[�r��������p�����G���W���R��̌v�Z�́A �ԈႢ�Ȃ����\�s�ׂł���A�Z�p�҂Ƃ��Ă̗ǐS�̌�����@�� �Ɏ����s�ׂƍl���Ă���B���x�����ǂ��J��Ԃ����A�^�[�{�R���p �E���h�́A��^�g���b�N�̑��s�R��̉��P������ȋZ�p���I�̃y �[�W�ɏڏq���Ă���悤�ɁA�^�[�{�R���p�E���h�ɂ��R��́A�G ���W���̍ő�g���N�̉^�]��ԂłQ���O�オ���P�ł��邾���� ����B�]���̂P�i�ߋ���Q�i�ߋ��̃f�B�[�[���G���W���Ƀ^�[�{ �R���p�E���h��P�ɑ������������̃V�X�e���ɂ����āA�ʈ��S�� ���������̗�؉��ꎁ�A�Έ�f���A����㎁����ѐV�G�B�V �[�C�[�̐� �F�O�������Z�������ʁA���L�̂悤���u1000rpm �`1200rpm�̎��p�^�]�̈�łP�`�R���̔R����P���ʂ������ ��v�Ƃ̋L�q�́A���ł���Ɛ��������B �@���������A����̃f�B�[�[���g���b�N�Ƀ^�[�{�R���p�E���h�𓋍� ����ꍇ�́A��^�g���b�N�̎����s��JE05���[�h�ł̓G���W���� �����ׂ̉^�]�p�x���������߁A�ߋ��@�̔r�C�^�[�r�������r �I�A�Ⴂ���x�̔r�C�K�X�̂��r�o����邽�߁A�^�[�{�R���p�E�� �h�̉^�[�r���ɂ���ĉ���ł���G�l���M�[�́A�K�R�I�ɏ� �Ȃ��Ȃ�B���������āA�^�[�r���ł̃G�l���M�[����́A�Ⴂ �^�[�r�������ʼn^�]������Ȃ������������Ȃ�̂ł���B�� �������āA���̂悤�ȏh�������^�[�{�R���p�E���h��p���ăf �B�[�[���G���W���̔R������P���悤�Ƃ��邱�Ƃ́A����ł��邱 �Ƃ����炩���B���̂��߁A���L����ʈ��S����������SCD�G ���W���_���ɂ����āA��ʈ��S���������̗�؉��ꎁ�A�Έ� �f���A����㎁����ѐV�G�B�V�[�C�[�̐� �F�O�����^�[�{ �R���p�E���h���f�B�[�[���G���W���̔R����P�̎�i�ƔF������ �Ă��邱�Ƃ͌��ƍl������B�����āA�{���{��X�J�j�A�̉��� �̃g���b�N���[�J�́A�^�[�{�R���p�E���h�͓����ő刳�͂��㏸�� ���邱�Ɩ����o�͂������ł����i�Ɨ������Ă���悤�ł���B�� ���āA�]���̂P�i�ߋ���Q�i�ߋ��̃f�B�[�[���G���W���Ƀ^�[�{ �R���p�E���h��P�ɑ������������̃^�[�{�R���p�E���h�V�X�e���� ���ẮA���Ẵg���b�N���[�J�i���{���{��X�J�j�A���j�̔F���E �������������悤�ɍl������B �@�Ƃ���ŁA�^�[�{�R���p�E���h��p���ăf�B�[�[���G���W���̔R ��������ł����P������@�́A�M�҂́A�C���x�~�́A�f�B�[�[�� �r�C�K�X�̃G�l���M�[���u�̌����������ɏڏq���Ă����� ��悤�ɁA��^���b�N�̑��s�ő��p�����f�B�[�[���f�B�[�[���G ���W���̕������^�]���̔r�C�K�X���x�̍�������}�邱�Ƃ� �K�v�ł���A���̕��@�Ƃ��āA�M�Ғ�Ă��C���x�~�G���W���i�� �����J2005-54771�j�̓����Z�p��p���邱�Ƃ��L���ł���B�� �������āA���̌�ʈ��S����������SCD�G���W�����^�[�{�R�� �p�E���h�g���킹�Ď����s�R��܂��͏d�ʎԃ��[�h�R���{�C �ʼn��P�������̂ł���A�S�O�Ȃ����L����ʈ��S�������� ��SCD�G���W�����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�� �Z�p���̗p���ׂ��ƍl������B�������Ȃ���A�|���R�c���Z�p�� �̕M�҂���Ă��Ă����C���x�~�G���W���i�������J2005- 54771�j�̋Z�p��SCD�G���W���ɍ̗p���邱�Ƃ́A��ʈ��S�� �������̗�؉��ꎁ�A�Έ�f���A����㎁����ѐV�G�B�V�[ �C�[�̐� �F�O���ɂƂ��ẮA���{���\����f�B�[�[���G���W ���̊w�ҁE���ƂƂ��Ă̎����S�E�ʎq�E�v���C�h�������Ȃ��Ǝv �����A�@���Ȃ��̂ł��낤���B �@�������A���̌�ʈ��S���������̃^�[�{�R���p�E���h�𓋍� �����]����SCD�G���W������Q�i�^�[�{��p�~���A�V���ɕ���Q�^ �[�{�i�Q�^�[�{�j���������C���x�~�G���W���i�������J2005- 54771�j�̋Z�p��lj������^�[�{�R���p�E���h�̗p�́u�V���ȉ��� �^��SCD�G���W���v�ɉ��ǂ����ꍇ�ɂ́A���́u�V���ȉ��nj^�� SCD�G���W���v�́A�^�[�{�R���p�E���h�ɂ�镔�����^�]���� �R����P���{�����A���̏�ɐV�����C���x�~�G���W���i������ �J2005-54771�j�ɂ��G���W�����������̔R����P�̌��ʂ� �lj�����A2015�N�x�d�ʎԔR�����P�O�����R����サ�� 4. 5 �����^���b�g���̏d�ʎԃ��[�h�R��̑�^�g���b�N�p�f�B�[�[�� �G���W�����e�ՂɎ����ł���Ɨ\�z�����B���̌�ʈ��S�� �������̒���R��́u�V���ȉ��nj^��SCD�G���W���v�́A��� ���S���������̗�؉��ꎁ�A�Έ�f���A����㎁����� �V�G�B�V�[�G�[�̐� �F�O���̏��������Ӗ��Ȏ��g�̎��� �S�E�ʎq�E�v���C�h�̚ʑ��ɂ��Ă̊S�������Y��A�E�C������ �ď]����ʈ��S����������SCD�G���W�����C���x�~�G���W�� �i�������J2005-54771�j�̋Z�p���̗p���邱�Ƃɂ���āA�e�Ղ� �����ł��邱�Ƃł���B �@���̂悤�ɁA��ʈ��S���������̗�؉��ꎁ�A�Έ�f���A ����㎁����ѐV�G�B�V�[�C�[�̐� �F�O���̏��������g �̗��s�s�Ȏ����S�E�ʎq�E�v���C�h�ɖ��S�ɂȂ邾���ŁA�C�� �x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p��lj������V���� SCD�G���W���̎������\�ƂȂ�A2015�N�x�d�ʎԔR���� �P�O�����R����サ�� 4.5 �����^���b�g���̏d�ʎԃ��[�h�R��� ��^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W���������ł���̂ł���B���� �āA����ɂ���āA���{�ɂ������^�g���b�N�̔���I�Ȕ���� ���ɔ��W�E���i�ł���̂ł���B�������邱�Ƃɂ���āA�ʈ��S�� ���������̗�؉��ꎁ�A�Έ�f���A����㎁����ѐV�G�B�V �[�C�[�̐� �F�O���̏����́A���{�̑�^�g���b�N�̔R����� �ɑ傫���v�����A�㐢�ɖ����c�����Ƃ��ł���Ɛ��@�����B���� �Ƃ�����A��ʈ��S���������̗�؉��ꎁ�A�Έ�f���A��� ��㎁����ѐV�G�B�V�[�C�[�̐� �F�O�����E�C���錈�f���� ���ׂ��ƍl���邪�A�@���Ȃ��̂ł��낤���B�M�҂͑傢�Ɋ��҂� �Ă���Ƃ���ł���B �@ |
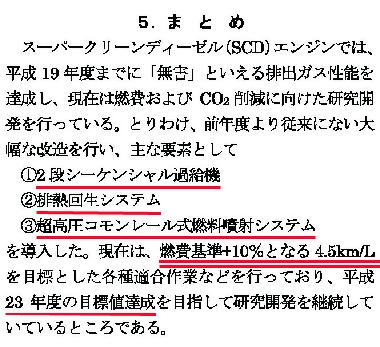 |
�@���L����ʈ��S����������SCD�G���W���_���ɂ����ẮA
SCD�G���W���ɑg�ݍ��܂ꂽ�e��̔R��팸�̋Z�p�ƁA���ꂼ
��̋Z�p�ɂ�����R����P�̖ڕW�����L����Ă���A������
�Z�߂�ƈȉ��̒ʂ�ł���B�i�Ȃ��A�e�Z�p�̂����̔R����P
�̖ڕW�́A�������琄�@����ƁA�����JE�O�T���[�h�̔R��Ɨ\
�������B�j
�� �Q�i�V�[�P���V�����ߋ��@
�R����P���T��
�� �������R�������[���i��260MPa�j
�@�@�R����P���R�`�T��
�� �r�M����V�X�e���i���^�[�{�R���p�E���h�j �@�@�R����P���P�`�R�� �ȏ�̂悤�ɁA���L����ʈ��S����������SCD�G���W���_�� �ł́A�ŋ߁A�b��ƂȂ��Ă���ڐV�����Z�p�́A�啝�ȔR����P ���\�ƍl�����悤�ȋL�q�Ŗ�������Ă���B���������ƁA �u�o�i�i�̂���������v��A�z������悤�ȔR����P�Z�p�́u��� ����v�̗l����悵�Ă���B���̋ɂߕt���́A���L����ʈ��S�� ����������SCD�G���W���_���́u�T�@�� �� �߁v�ł́A�u�Q�i�V�[�P ���V�����ߋ��@�v�{�u�r�M����V�X�e���v�{�u�������R�������[ ���v�ɂ���đ�^�g���b�N�iGVW�Q�T�g���j��2015�N�x�d�ʎԔR�� ����P�O�����R����サ��4.5 �����^���b�g���̏d�ʎԃ��[�h�R ������Q�R�N�x�Ɏ����ł���Ɛ錾����Ă��邱�Ƃł͂Ȃ��� �낤���B���҂̌�ʈ��S���������̗�؉��ꎁ�A�Έ�f���A ����㎁����ѐV�G�B�V�[�C�[�̐� �F�O���̏����́A���� �Q�R�N�x�����L����ʈ��S����������SCD�G���W���_���� �u�T�@�� �� �߁v�ɋL�ڂ��ꂽ��^�g���b�N�̔R�����̖ڕW�i���d �ʎԗʎԃ��[�h�R��F 4.5 �����^���b�g���j��{���Ɏ����ł���l �����Ă���̂ł��낤���B���݂ɁA�M�҂͂��̖ڕW�B������ �܁E���s����\�����ɂ߂č����Ǝv���Ă���B �@�Ȃ��Ȃ�ANEDO�̊v�V�I���������Q�ԑ����Z�p�J���i�N ���[���f�B�[�[���v���W�F�N�g�A2004�`2009�N�j�́u�����x�R�Đ� ��G���W�V�X�e���̌����J���v�ł́A�u���i�ߋ��V�X�e���v�{ �u�������R�������[���v�𓋍ڂ����f�B�[�[���ł͊��ɔR����P �̍���Ȃ��Ƃ��m�F����Ă���̂ł���B�܂��A�u�^�[�{�R���p�E ���h�V�X�e���v�ɂ��ẮA���̃V�X�e���𓋍ڂ�����^�g���b�N ���s�̂��Ă���{���{�A�f�g���C�g�f�B�[�[��������́u�^�[�{�R�� �p�E���h�ł͔R����P������v�Ƃ̏���M����Ă���̂� ����B�����̂��Ƃ���A�u�Q�i�V�[�P���V�����ߋ��@�v���u�r�M�� ���V�X�e���v���u�������R�������[���v�̊e�Z�p�́A����܂ł� �����J���ɂ���ĔR����P���w��NJ��҂ł��Ȃ����Ƃ����ɔ� �����Ă���̂ł���B �@���������āA��ʈ��S���������̗�؉��ꎁ�A�Έ�f���A ����㎁����ѐV�G�B�V�[�C�[�̐� �F�O���̏����́A�u�Q �i�V�[�P���V�����ߋ��@�v�{�u�r�M����V�X�e���v�{�u�������R �������[���v���̗p������ʈ��S����������SCD�G���W���ɂ� ���āA��^�g���b�N�iGVW�Q�T�g���j�ɂ�����2015�N�x�d�ʎԔR�� ����P�O�����R����サ�� 4.5 �����^���b�g���̏d�ʎԃ��[�h�R ��̖ڕW���Q�R�N�x�ɒB������Ɛ錾���Ă��邪�A����SCD �G���W���ɑg�ݍ��܂ꂽ�Z�p�����ł͂��̖ڕW�̔R��������� �邱�Ƃ͕s�\�ƍl������B �@���̑�^�g���b�N�iGVW�Q�T�g���j�ɂ�����2015�N�x�d�ʎԔR�� ����P�O�����R����サ�� 4.5 �����^���b�g���̏d�ʎԃ��[�h�R ��̖ڕW��B������B��̕��@�́A��ʈ��S���������̃^ �[�{�R���p�E���h�𓋍ڂ����]����SCD�G���W������Q�i�^�[�{�� �p�~���A�V���ɕ���Q�^�[�{�i�Q�^�[�{�j���C���x�~�G���W���i�� �����J2005-54771�j�̋Z�p��lj������^�[�{�R���p�E���h�̗p �̐V���ȉ��nj^��SCD�G���W���ɉ��ǂ��邱�Ƃł���B���̐V�� �ȉ��nj^��SCD�G���W���́A�^�[�{�R���p�E���h�ɂ�镔������ �^�]���̔{�������R����P���C���x�~�G���W���i�������J2005 -54771�j�ɂ��G���W�����������̔R����P�̌��ʂ��lj��� ��A2015�N�x�d�ʎԔR�����P�O�����R����サ�� 4.5 ���� �^���b�g���̏d�ʎԃ��[�h�R��̑�^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W �����e�ՂɎ����ł��邱�ƂɂȂ�B�������A�|���R�c���Z�p���� �M�҂���Ă��Ă����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j �̋Z�p��SCD�G���W���ɍ̗p���邱�Ƃ́A��ʈ��S�������� �̗�؉��ꎁ�A�Έ�f���A����㎁����ѐV�G�B�V�[�C�[�� �� �F�O���̊w�ҁE���ƂƂ��Ă̎����S�E�ʎq�E�v���C�h���� ���Ȃ����̂Ɛ��@�����B �@���̌��ʁA2012�N7��23�����݂ł́A��ʈ��S���������� ��؉��ꎁ�A�Έ�f���A����㎁����ѐV�G�B�V�[�C�[�̐� �� �F�O���́A��ʈ��S����������SCD�G���W����p������ �^�g���b�N�iGVW�Q�T�g���j�ɂ�����2015�N�x�d�ʎԔR�����P �O�����R����サ�� 4.5 �����^���b�g���̏d�ʎԃ��[�h�R��� ���Q�R�N�x�ɒB������Ƃ̍��L�̖ڕW�́A�����ɒB���ł����Ƃ� ���\���s���Ă��Ȃ��悤���B�����Ƃ��A��ʈ��S���������� SCD�G���W���̌����J�������s�ɏI������Ƃ̔��\���s���Ă� �Ȃ��悤�Ɍ�����B���̂悤�ȏ���A��ʈ��S���� �����̗�؉��ꎁ�A�Έ�f���A����㎁����ѐV�G�B�V�[�C �[�̐� �F�O���́A��ʈ��S����������SCD�G���W����p ���������v���W�F�N�g�̌��ʂɂ��ẮA���ꂩ����u�_���}���E�� ��v�𑱂���Ӑ}�E�ӌ��̂悤�Ɏv���邪�A�@���Ȃ��̂ł��낤 ���B �@���ɁA��ʈ��S����������SCD�G���W���v���W�F�N�g�̋��J �������s�ɏI����Ă����ꍇ�ł��A���̎������ʂ����\����� �A��ʈ��S����������SCD�G���W���v���W�F�N�g�́A������ �f�B�[�[���G���W���W�̊w�ҁE���Ƃɂ́u�R�����ɖ����� �Z�p�v�Ƃ��Ă̋M�d�ȋZ�p�����邱�ƂɂȂ�A�����I �ɂ��M�d�ȋZ�p���Ƃ��čL�����p�����ł��锤�ł���B���� �āA���̂悤�Ȕ��\�ɂ���āA��ʈ��S����������SCD�G���W ���v���W�F�N�g�ɒ������܂ꂽ����������̐ŋ��́A�����͍��� �̐����ɐ�������邱�ƂɂȂ�ƍl������B�������A��ʈ��S ���������̗�؉��ꎁ�A�Έ�f���A����㎁����ѐV�G�B �V�[�C�[�̐� �F�O������ʈ��S����������SCD�G���W�� �̌����v���W�F�N�g�̎������ʂ��āA���ꂩ����u�_���}���E�� ��v�𑱂����ꍇ�A���{�̑����̃f�B�[�[���G���W���W�̊w �ҁE���Ƃɂ́A�u�R�����ɖ����ȋZ�p�v�̋Z�p��� ��Ȃ����ƂɂȂ�A��ʈ��S����������SCD�G���W���v���W�F �N�g�ɒ������܂ꂽ����������́A���������u�ǂԐ�v�Ɏ̂Ă� �ꂽ�@���A�ŋ��̖��ʎg���ɏI����Ă��܂��ƍl������B �@����A�O�q��14-1���Ɏ�����NEDO�́u�����x�R�Đ���G���W �V�X�e���̌����J���v�ł́A�R����̑厸�s�𐳒��ɕ� �Ă���̂ł���B���̂悤��NEDO�̌����J���̏ꍇ�ɂ͕s���� �ŏI�����������J���̏ꍇ�ɂ́A���s���������J���̎����f�[ �^�������̐l�ɋZ�p���Ƃ��Đ����Ɏ������ʂ�����Ă� ��̂ł���B�Ƃ��낪�A����NEDO�̃v���W�F�N�g�Ɠ��l�ɐŋ����g ���Ă���ɂ�������炸�A��ʈ��S����������SCD�G���W���v ���W�F�N�g�̌��ʂ́A�R�����Ɏ��s�������Ƃɂ���Ď����f�[�^ �𖢌��\�Ƃ��A��ʈ��S����������SCD�G���W���v���W�F�N�g ��S�������ʈ��S���������̗�؉��ꎁ�A�Έ�f���A�� ���㎁����ѐV�G�B�V�[�C�[�̐� �F�O���ɂ���Ă��̃v�� �W�F�N�g�̋M�d�Ȏ����f�[�^������ׂ���Ă���悤�Ɍ������ �ł���B���̂��Ƃ������ł���A��ʈ��S����������SCD �G���W���v���W�F�N�g��S�������ʈ��S���������̗�؉��� ���A�Έ�f���A����㎁����ѐV�G�B�V�[�C�[�̐� �F�O�� �́A�ꗬ�̊w�ҁE���ƁE�Z�p�҂Ƃ��Ĕ������ׂ��������E�� �S�̌��������l�B�̂悤�Ɏv���邪�A�{���̂Ƃ���͔@���Ȃ��� �ł��낤���B �@���ɁA��ʈ��S���������̗�؉��ꎁ�A�Έ�f���A���� �㎁����ѐV�G�B�V�[�C�[�̐� �F�O���́A�w�ҁE���ƁE�Z�p �҂Ƃ��Ă̗ǐS�E���ӂ��������l�B�ł���A��ʈ��S���� ������SCD�G���W���v���W�F�N�g�ɂ����ē����̖ڕW�ł����� �u��^�g���b�N�iGVW�Q�T�g���j�ɂ�����2015�N�x�d�ʎԔR�� ���P�O���̔R����コ���� 4.5 �����^���b�g���̏d�ʎԃ��[�h�R ��v���B���\��̊����ł��镽��23�N�x�ɖ��B�ɏI������Ƃ� �Ă��A����̓��{�̑�^�g���b�N�ɂ�����R�����̋Z�p�J���� ���p�ł���悤�ɂ��邽�߁A���̎��_�Ō�ʈ��S���������� SCD�G���W���v���W�F�N�g�̌����J���̎����f�[�^�𐳒��Ɍ��\ ���Ă��锤�ł͂Ȃ����낤���B�Ȃ��Ȃ�A�����J���̎��s�f�[ �^���A���̌�̌����J���̐��i�ɂ͋M�d�Ȋ����̃f�[�^�Ƃ��� ���������Ƃ��ł��邽�߂ł���B���̂��Ƃ���A���{�̗\�Z�i���� ���j���g���Č����v���W�F�N�g�����{����w�ҁE���Ƃ́A�ǐS�E ���ӂ̂���l�B�łȂ���A�ŋ��̖��ʎg���ɂȂ�悤�Ɏv�� �邪�A�@�����Ȃ��̂ł��낤���B�ܘ_�A��ʈ��S���������� SCD�G���W���v���W�F�N�g�����s�ɏI������ꍇ�Ɍ�ʈ��S�� �������̗�؉��ꎁ�A�Έ�f���A����㎁����ѐV�G�B�V�[ �C�[�̐� �F�O�������̃v���W�F�N�g�̌�����̑S�z�𐭕{�� �ԊҁE�Ԕ[����A�������ʂ��u����J�v�A�u�����\�A�u����ׂ��v �Ƃ����Ă�������邱�Ƃł���B�t�Ɍ����A��ʈ��S������ ���̗�؉��ꎁ�A�Έ�f���A����㎁����ѐV�G�B�V�[�C�[ �̐� �F�O�������̃v���W�F�N�g�̌�����̑S�z�𐭕{�ɕ� �ҁE�Ԕ[���Ȃ��̂ł���A���̃v���W�F�N�g�̋M�d�Ȏ������� �́A��ɔ��\�E���\���s���ׂ��ł���B���Ɍ�ʈ��S������ ���̗�؉��ꎁ�A�Έ�f���A����㎁����ѐV�G�B�V�[�C�[ �̐� �F�O�������̃v���W�F�N�g�̋M�d�Ȏ������ʂ��u��� �J�v�A�u�����\�A�u����ׂ��v�Ƃ����ꍇ�́A���{�̗\�Z�i���ŋ��j �̎��I���p�Ǝw�e����Ă��d���̖������Ƃł͂Ȃ����낤���B �@ �@�܂��A���ɁA����23�N�x�ɏI���\��̌�ʈ��S���������� SCD�G���W���v���W�F�N�g���^�[�{�R���p�E���h���̗p���Ă���ɂ� ������炸�A�u��^�g���b�N�iGVW�Q�T�g���j�ɂ�����2015�N�x�d�� �ԔR�����P�O���̔R����コ���� 4.5 �����^���b�g���̏d�� �ԃ��[�h�R��v�̔R�����̖ڕW�����B���ł��������Ƃ����� �ɂ���Ċm�F����A���̌��ʂ����\���ꂽ�̂ł���A�f�B�[�[ ���G���W���̕��������̔r�C�K�X���x������������Z�p��g �ݍ��킹�Ȃ��ꍇ�ɂ́A�^�[�{�R���p�E���h���̗p���Ă���^�g�� �b�N�̎����s�R���d�ʎԃ��[�h�R������P���邱�Ƃ������ ���邱�Ƃ������ꂽ���ƂɂȂ�B�����āA���̂��Ƃ́A�^�[�{�R�� �p�E���h�̗̍p�ɂ��d�ʎԃ��[�h�R��̉��P��}�邽�߂ɂ́A �C���x�~�́A�f�B�[�[���r�C�K�X�̃G�l���M�[���u�̌��� �������ɏڏq�M���Ă���悤�ɁA�^�[�{�R���p�E���h���̗p����G ���W���̕��������̔r�C�K�X���x������������Z�p�Ƃ��āA �Ⴆ���C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p��g�� �킹�邱�Ƃ��K�v�E�s���ł���Ƃ̐����̍����𑽂��̊w�ҁE ���Ƃɒ��邱�ƂɂȂ�B �@���Ă��āA���݂̂Ƃ���A���̌�ʈ��S����������SCD�G�� �W���v���W�F�N�g�̎������ʂ́A����24�N7��23�����݂ł��A�� ���\�E�B���̏�Ԃɕێ�����Ă���悤�ł���B�ʂ����āA���� ����ʈ��S����������SCD�G���W���v���W�F�N�g�̎������� �����\����邱�Ƃ͖����̂ł��낤���B���̂悤�Ȃ��Ƃɂ���āA ��������W�߂��M�d�Ȑŋ��ɂ���Ď��{���ꂽ��ʈ��S���� ������SCD�G���W���v���W�F�N�g�̎������ʂ�����̓��{�̑� �^�g���b�N�ɂ�����R�����̋Z�p�J���ɉi���ɐ�������Ȃ� �̂ł���A��ʈ��S���������̗�؉��ꎁ�A�Έ�f���A ����㎁����ѐV�G�B�V�[�C�[�̐� �F�O���́A�u�ŋ��D�_�v �̔���Ƃ�Ȃ��悤�Ɏv���邪�A�@���Ȃ��̂ł��낤���B |
��V�W�J�v�ł́A�u�Q�i�V�[�P���V�����ߋ��@�v���u�r�M����V�X�e���i�^�[�{�R���p�E���h�j�v���u�������R�������[���v
�̋Z�p��p����2015�N�x�d�ʎԔR�����P�O�����R����サ�� 4.5 �����^���b�g���̏d�ʎԃ��[�h�R��̑�^�g��
�b�N�iGVW�Q�T�g���j�������Q�R�N�x����������\��Ɛ錾����Ă���B�������A�u�Q�i�V�[�P���V�����ߋ��@�v���u�r�M��
���V�X�e���i�^�[�{�R���p�E���h�j�v���u�������R�������[���v�̊e�Z�p�́A������f�B�[�[���̔R����P�̌��ʂ��w��
�NJ��҂ł��Ȃ��V�X�e���ł���B���������āA�����Q�R�N�x���d�ʎԃ��[�h�R� 4.5 �����^���b�g���̑�^�g���b�N
�iGVW�Q�T�g���j����������ڕW�B���͎��s�ɏI�����̂Ɨ\�z�����B
�@���̌�ʈ��S����������SCD�G���W���_���̒��҂̈�l�́A�V�G�B�V�[�C�[�̐� �F�O���ł���B���݂ɁA�V
�G�B�V�[�C�[�́A�����ԃ��[�J�[�ƕ��i��Ђ��o�����A�g���b�N���[�J�S��(����A�����U�A�t�c�A�O�H�ӂ���)���猤����
���h������Ă��錤�����ł���B�����āA�V�G�B�V�[�C�[�̏햱������ł���� �F�O���́A�V�G�B�V�[�C�[�̏��
�����̃g�b�v�ł���A����̐V�G�B�V�[�C�[�̌����������w������Ă�����̂Ɛ��@�����B���̐V�G�B�V�[�G�[�ł́A
�{�y�[�W�� �y�P�Q�|�R�D���V�G�B�V�[�C�[���C���x�~�̎������ʂ̔��\�𒆎~���Ă��闝�R�́A�����H�z�̍��ɏڏq
���Ă���悤�ɁA���V�G�B�V�[�C�[�́A�Q�O�O�S�N�Ƀf�B�[�[���G���W���̋C���x�~�̎��������{���A���̋C���x�~�ɂ�
����R����P�̌��ʂ��m�F���������f�[�^���擾���Ă���悤�ł���B�������A���V�G�B�V�[�C�[�́A�C���x�~�̎���
���I�����Ă�����ɂW�N�ȏ���o�߂��Ă���ɂ�������炸�A�C���x�~�̔R����P���m�F�ł����������ʂ𖢂���
���\���Ă��Ȃ��̂��B���̂悤�ɁA���V�G�B�V�[�C�[�̓���̌��������̃g�b�v�Ƃ��Ďw������Ă���� �F�O���́A
�f�B�[�[���G���W���ł̋C���x�~���R����P�ɑ傫�Ȍ��ʂ��ł��邱�Ƃ������ɂ���Ď��g�Ŋm�F����Ă����
��������炸�A���̎����f�[�^���㐶�厖�Ɋ��̈����o���ɕۊǂ���Ă�����̂Ɛ��@�����B���̏�����ƁA
���V�G�B�V�[�C�[�̐� �F�O���́A���{�̑�^�g���b�N�̔R��������ł����コ���悤�Ƃ���w�ҁE���ƂƂ��Ă̖{
���̎g���E�ӎ��Ɍ����Ă��邢��悤�Ɏv���邪�A�@���Ȃ��̂ł��낤���B�ܘ_�A����ɂ��ẮA�� �F�O���̏�
��Ƃ����A����܂łł��邪�E�E�E�E�E�E�E�B
�G�B�V�[�C�[�́A�����ԃ��[�J�[�ƕ��i��Ђ��o�����A�g���b�N���[�J�S��(����A�����U�A�t�c�A�O�H�ӂ���)���猤����
���h������Ă��錤�����ł���B�����āA�V�G�B�V�[�C�[�̏햱������ł���� �F�O���́A�V�G�B�V�[�C�[�̏��
�����̃g�b�v�ł���A����̐V�G�B�V�[�C�[�̌����������w������Ă�����̂Ɛ��@�����B���̐V�G�B�V�[�G�[�ł́A
�{�y�[�W�� �y�P�Q�|�R�D���V�G�B�V�[�C�[���C���x�~�̎������ʂ̔��\�𒆎~���Ă��闝�R�́A�����H�z�̍��ɏڏq
���Ă���悤�ɁA���V�G�B�V�[�C�[�́A�Q�O�O�S�N�Ƀf�B�[�[���G���W���̋C���x�~�̎��������{���A���̋C���x�~�ɂ�
����R����P�̌��ʂ��m�F���������f�[�^���擾���Ă���悤�ł���B�������A���V�G�B�V�[�C�[�́A�C���x�~�̎���
���I�����Ă�����ɂW�N�ȏ���o�߂��Ă���ɂ�������炸�A�C���x�~�̔R����P���m�F�ł����������ʂ𖢂���
���\���Ă��Ȃ��̂��B���̂悤�ɁA���V�G�B�V�[�C�[�̓���̌��������̃g�b�v�Ƃ��Ďw������Ă���� �F�O���́A
�f�B�[�[���G���W���ł̋C���x�~���R����P�ɑ傫�Ȍ��ʂ��ł��邱�Ƃ������ɂ���Ď��g�Ŋm�F����Ă����
��������炸�A���̎����f�[�^���㐶�厖�Ɋ��̈����o���ɕۊǂ���Ă�����̂Ɛ��@�����B���̏�����ƁA
���V�G�B�V�[�C�[�̐� �F�O���́A���{�̑�^�g���b�N�̔R��������ł����コ���悤�Ƃ���w�ҁE���ƂƂ��Ă̖{
���̎g���E�ӎ��Ɍ����Ă��邢��悤�Ɏv���邪�A�@���Ȃ��̂ł��낤���B�ܘ_�A����ɂ��ẮA�� �F�O���̏�
��Ƃ����A����܂łł��邪�E�E�E�E�E�E�E�B
�@���̈���ɂ����āA�V�G�B�V�[�C�[�̐� �F�O���́A�f�B�[�[���R��̑傫�ȉ��P�����҂ł��Ȃ��u�Q�i�V�[�P��
�V�����ߋ��@�v���u�r�M����V�X�e���i�^�[�{�R���p�E���h�j�v���u�������R�������[���v�̋Z�p��g�����邱�Ƃɂ��A
2015�N�x�d�ʎԔR�����P�O�����R����サ�� 4.5 �����^���b�g���̏d�ʎԃ��[�h�R��̑�^�g���b�N�iGVW�Q�T�g
���j�������Q�R�N�x����������Ɛ錾������ʈ��S���������́uSCD�G���W���̌����J���v�̃v���W�F�N�g�ɎQ�悳
��A�_���̒��҂Ɉ�l�Ƃ��Ė���A�˂��Ă���̂ł���B�������A��ʈ��S����������SCD�G���W���̌����J
���v���W�F�N�g�ł́A�R����P�̌��ʂ��w��NJ��҂ł��Ȃ��u�Q�i�V�[�P���V�����ߋ��@�v���u�r�M����V�X�e���i�^�[
�{�R���p�E���h�j�v���u�������R�������[���v�̋Z�p���g�ݍ��܂�A�R����P�ɑ傫�Ȍ��ʂ�����u�C���x�~�v��
�Z�p���g�ݍ��܂�Ă��Ȃ��̂ł���B���̏�����ƁA�V�G�B�V�[�C�[�̐� �F�O���́A���̘_���̋����҂ł�
����ʈ��S���������̗�؉��ꎁ�A�Έ�f���A����㎁�ɑ��A�u�C���x�~�ɂ���ăf�B�[�[���G���W���̔R
����P�̌��ʂ��m�F���������f�[�^�v�������J������Ă��Ȃ��\��������ƍl������B
�V�����ߋ��@�v���u�r�M����V�X�e���i�^�[�{�R���p�E���h�j�v���u�������R�������[���v�̋Z�p��g�����邱�Ƃɂ��A
2015�N�x�d�ʎԔR�����P�O�����R����サ�� 4.5 �����^���b�g���̏d�ʎԃ��[�h�R��̑�^�g���b�N�iGVW�Q�T�g
���j�������Q�R�N�x����������Ɛ錾������ʈ��S���������́uSCD�G���W���̌����J���v�̃v���W�F�N�g�ɎQ�悳
��A�_���̒��҂Ɉ�l�Ƃ��Ė���A�˂��Ă���̂ł���B�������A��ʈ��S����������SCD�G���W���̌����J
���v���W�F�N�g�ł́A�R����P�̌��ʂ��w��NJ��҂ł��Ȃ��u�Q�i�V�[�P���V�����ߋ��@�v���u�r�M����V�X�e���i�^�[
�{�R���p�E���h�j�v���u�������R�������[���v�̋Z�p���g�ݍ��܂�A�R����P�ɑ傫�Ȍ��ʂ�����u�C���x�~�v��
�Z�p���g�ݍ��܂�Ă��Ȃ��̂ł���B���̏�����ƁA�V�G�B�V�[�C�[�̐� �F�O���́A���̘_���̋����҂ł�
����ʈ��S���������̗�؉��ꎁ�A�Έ�f���A����㎁�ɑ��A�u�C���x�~�ɂ���ăf�B�[�[���G���W���̔R
����P�̌��ʂ��m�F���������f�[�^�v�������J������Ă��Ȃ��\��������ƍl������B
�@���ɁA�Q�O�O�S�N�ɐV�G�B�V�[�C�[���擾�����C���x�~�̋Z�p�ɂ���ăf�B�[�[���G���W���̔R������P�ł�������
�f�[�^��V�G�B�V�[�C�[�̐� �F�O������ʈ��S���������̗�؉��ꎁ�A�Έ�f���A����㎁�ɊJ�����Ă�
�Ȃ��������Ƃ������ł���A�V�G�B�V�[�C�[�̐� �F�O���͌�ʈ��S������������̂́u�X�[�p�[�N���[���f�B
�[�[���iSCD�j�G���W���ɂ���^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W�����R�����v���W�F�N�g�v�̍��܁E���s���ŏ�����
���Ă����\��������ƍl������B�܂�A�V�G�B�V�[�C�[�̐� �F�O���́A��ʈ��S���������̐��
�Ƃɑ��A��^�g���b�N�̎����s�R���d�ʎԃ��[�h�R��̉��P�ɑ傫�Ȍ��ʂ����҂ł��Ȃ��u�Q�i�V�[�P���V����
�ߋ��@�v���u�������R�������[���v��A�C���x�~�́A�f�B�[�[���r�C�K�X�̃G�l���M�[���u�̌����������̃y�[
�W�ɏڏq���Ă���悤�ɁA�C���x�~�̋Z�p��g�ݍ��킹�Ȃ��ꍇ�ɂ͑�^�g���b�N�̎����s�R���d�ʎԃ��[�h�R
��̉��P�ɑ傫�Ȍ��ʂ����҂ł��Ȃ��u�^�[�{�R���p�E���h�v�̋Z�p����R��Z�p�Ƃ��Č�ʈ��S���������̐�
��Ƃɐ������Ă����\�����l������B���̈���ŁA�V�G�B�V�[�C�[�̐� �F�O���́A���V�G�B�V�[�C�[���Q�O�O�S
�N�Ƀf�B�[�[���G���W���̋C���x�~�̎��������{���ďd�ʎԃ��[�h�R��̉��P���ʂ��m�F���������f�[�^����ʈ�
�S���������̗�؉��ꎁ�A�Έ�f���A����㎁�ɊJ�����Ă��Ȃ��\�����l������B
�f�[�^��V�G�B�V�[�C�[�̐� �F�O������ʈ��S���������̗�؉��ꎁ�A�Έ�f���A����㎁�ɊJ�����Ă�
�Ȃ��������Ƃ������ł���A�V�G�B�V�[�C�[�̐� �F�O���͌�ʈ��S������������̂́u�X�[�p�[�N���[���f�B
�[�[���iSCD�j�G���W���ɂ���^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W�����R�����v���W�F�N�g�v�̍��܁E���s���ŏ�����
���Ă����\��������ƍl������B�܂�A�V�G�B�V�[�C�[�̐� �F�O���́A��ʈ��S���������̐��
�Ƃɑ��A��^�g���b�N�̎����s�R���d�ʎԃ��[�h�R��̉��P�ɑ傫�Ȍ��ʂ����҂ł��Ȃ��u�Q�i�V�[�P���V����
�ߋ��@�v���u�������R�������[���v��A�C���x�~�́A�f�B�[�[���r�C�K�X�̃G�l���M�[���u�̌����������̃y�[
�W�ɏڏq���Ă���悤�ɁA�C���x�~�̋Z�p��g�ݍ��킹�Ȃ��ꍇ�ɂ͑�^�g���b�N�̎����s�R���d�ʎԃ��[�h�R
��̉��P�ɑ傫�Ȍ��ʂ����҂ł��Ȃ��u�^�[�{�R���p�E���h�v�̋Z�p����R��Z�p�Ƃ��Č�ʈ��S���������̐�
��Ƃɐ������Ă����\�����l������B���̈���ŁA�V�G�B�V�[�C�[�̐� �F�O���́A���V�G�B�V�[�C�[���Q�O�O�S
�N�Ƀf�B�[�[���G���W���̋C���x�~�̎��������{���ďd�ʎԃ��[�h�R��̉��P���ʂ��m�F���������f�[�^����ʈ�
�S���������̗�؉��ꎁ�A�Έ�f���A����㎁�ɊJ�����Ă��Ȃ��\�����l������B
�@�ȏ�̂悤�Ȃ��Ƃ����Ɏ����ł���A��ʈ��S���������̗�؉��ꎁ�A�Έ�f���A����㎁�́A��ʈ��S
����������SCD�G���W���̌����J���v���W�F�N�g�Ɏ��s�ɓ������߂́i���j�V�G�B�V�[�C�[�̐� �F�O���̖d����
�������������n���ȃs�G���������Ă��邱�ƂɂȂ�ƍl������B���̏ꍇ�ɂ́A��ʈ��S���������̐��Ƃɑ�
���ẮA����Ɖ]�����t�������Ă͂܂�Ȃ��̂ł͂Ȃ����낤���B�����͌����Ă��A���̂悤�ȍ��\�I�Ȃ��Ƃ��{���ł�
�����ꍇ�A�x�������̐V�G�B�V�[�C�[�̐� �F�O�����ᔻ����邱�Ƃ͖ܘ_�ł��邪�A�x���ꂽ���̌�ʈ��S��
�������̗�؉��ꎁ�A�Έ�f���A����㎁�̕��X���f�B�[�[���G���W���̔R����P�Z�p�ɂ��Ă̒m���E���
���W�̕s����p������ׂ��ł���A���Ȃ��ׂ����Ƃł͂Ȃ����낤���B
����������SCD�G���W���̌����J���v���W�F�N�g�Ɏ��s�ɓ������߂́i���j�V�G�B�V�[�C�[�̐� �F�O���̖d����
�������������n���ȃs�G���������Ă��邱�ƂɂȂ�ƍl������B���̏ꍇ�ɂ́A��ʈ��S���������̐��Ƃɑ�
���ẮA����Ɖ]�����t�������Ă͂܂�Ȃ��̂ł͂Ȃ����낤���B�����͌����Ă��A���̂悤�ȍ��\�I�Ȃ��Ƃ��{���ł�
�����ꍇ�A�x�������̐V�G�B�V�[�C�[�̐� �F�O�����ᔻ����邱�Ƃ͖ܘ_�ł��邪�A�x���ꂽ���̌�ʈ��S��
�������̗�؉��ꎁ�A�Έ�f���A����㎁�̕��X���f�B�[�[���G���W���̔R����P�Z�p�ɂ��Ă̒m���E���
���W�̕s����p������ׂ��ł���A���Ȃ��ׂ����Ƃł͂Ȃ����낤���B
�@���āA���ۂ̂Ƃ���́A�V�G�B�V�[�C�[�̐� �F�O���́A��ʈ��S���������́u�X�[�p�[�N���[���f�B�[�[��
�iSCD�j�G���W���ɂ���^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W���̒�R��v���W�F�N�g�v�̏����̒i�K�ŁA��ʈ��S������
���̗�؉��ꎁ�A�Έ�f���A����㎁�ɑ��A�u�Q�O�O�S�N�ɐV�G�B�V�[�C�[���擾�����C���x�~�̋Z�p���f�B�[�[
���G���W���̔R����P���m�F���������f�[�^�v���J�����Ă����̂ł��낤���B���̋C���x�~�̎����f�[�^�J���̗L��
�ɂ��āA�M�҂͌�ʈ��S���������̗�؉��ꎁ�A�Έ�f���A����㎁�ɐ���Ƃ��m�F���Ă݂������̂��B
�iSCD�j�G���W���ɂ���^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W���̒�R��v���W�F�N�g�v�̏����̒i�K�ŁA��ʈ��S������
���̗�؉��ꎁ�A�Έ�f���A����㎁�ɑ��A�u�Q�O�O�S�N�ɐV�G�B�V�[�C�[���擾�����C���x�~�̋Z�p���f�B�[�[
���G���W���̔R����P���m�F���������f�[�^�v���J�����Ă����̂ł��낤���B���̋C���x�~�̎����f�[�^�J���̗L��
�ɂ��āA�M�҂͌�ʈ��S���������̗�؉��ꎁ�A�Έ�f���A����㎁�ɐ���Ƃ��m�F���Ă݂������̂��B
�@�Ƃ���ŁA��ʈ��S���������̖����i���Ɩ��j�́A�}�Q�P�́u��ʈ��S���������̖����v�Ɏ����Ă���悤�ɁA
�u�����Ԃ̊��Z�p��i��������K���l�j�Ă̍���i�����[�����[�J����̍쐬�ҁj�v��u���̐���ɑ���
�s���ւ̋Z�p�x���v�Ƃ̂��Ƃł���B
�u�����Ԃ̊��Z�p��i��������K���l�j�Ă̍���i�����[�����[�J����̍쐬�ҁj�v��u���̐���ɑ���
�s���ւ̋Z�p�x���v�Ƃ̂��Ƃł���B
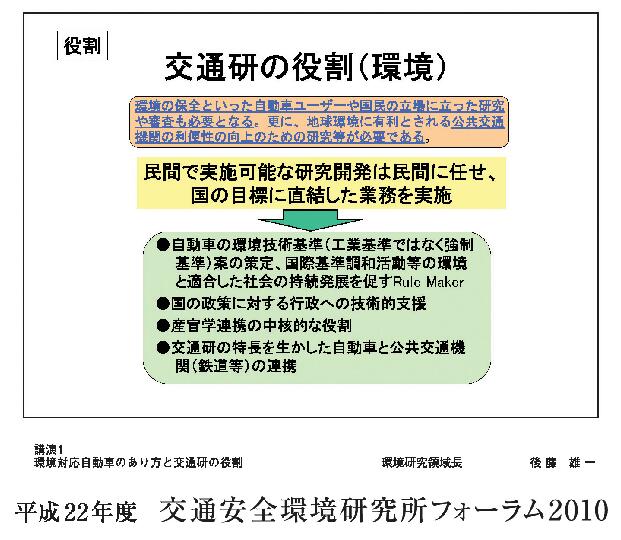
�@�ȏ�̐}�Q�P�̋L�ڂɂ��ƁA��ʈ��S���������͎����Ԃ̊��Z�p��Ă̍���ɏd�v�ȐE�ӂ��Ă�
��Ƃ̂��Ƃł���B���������āA��ʈ��S���������̐��Ƃ���^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W���̒�R�����
��ł��邱�Ƃ�{�S���������ꍇ�ɂ́A���y��ʏȂ�2015�N�x�d�ʎԔR���̋�����啝�ɒx������\��
����ƍl������B
��Ƃ̂��Ƃł���B���������āA��ʈ��S���������̐��Ƃ���^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W���̒�R�����
��ł��邱�Ƃ�{�S���������ꍇ�ɂ́A���y��ʏȂ�2015�N�x�d�ʎԔR���̋�����啝�ɒx������\��
����ƍl������B
�@���ݎ��{���̌�ʈ��S���������́u�X�[�p�[�N���[���f�B�[�[���iSCD�j�G���W���ɂ���^�g���b�N�p�f�B�[�[
���G���W�����R�����v���W�F�N�g�v�ɂ����āA�����J���̖ڕW�ł���2015�N�x�d�ʎԔR�����10��������
�����d�ʎԃ��[�h�R�� 4.5 �����^���b�g���� ��^�g���b�N�iGVW�Q�T�g���j�������ł����Ƀv���W�F�N�g�����s�ɏI�����
�ꍇ�ɂ́A��ʈ��S���������̐��Ɓi��؉��ꎁ�A�Έ�f���A����㎁�j�́A��^�g���b�N�̔R����P���Z
�p�I�ɍ���ł��邱�Ƃ�g�������Ĕ[�����邱�͊ԈႢ�Ȃ��B���̏ꍇ�ɂ́A���y��ʏȂ�2015�N�x�d�ʎԔR���
���̋����́A��ʈ��S���������̐��Ƃ̈ӌ��������Ԃ̊��Z�p��̍���ɔ��f�����Ƃ̐}�P�W�̓�
�e���琄������ƁA�啝�ɒx�������\��������B
���G���W�����R�����v���W�F�N�g�v�ɂ����āA�����J���̖ڕW�ł���2015�N�x�d�ʎԔR�����10��������
�����d�ʎԃ��[�h�R�� 4.5 �����^���b�g���� ��^�g���b�N�iGVW�Q�T�g���j�������ł����Ƀv���W�F�N�g�����s�ɏI�����
�ꍇ�ɂ́A��ʈ��S���������̐��Ɓi��؉��ꎁ�A�Έ�f���A����㎁�j�́A��^�g���b�N�̔R����P���Z
�p�I�ɍ���ł��邱�Ƃ�g�������Ĕ[�����邱�͊ԈႢ�Ȃ��B���̏ꍇ�ɂ́A���y��ʏȂ�2015�N�x�d�ʎԔR���
���̋����́A��ʈ��S���������̐��Ƃ̈ӌ��������Ԃ̊��Z�p��̍���ɔ��f�����Ƃ̐}�P�W�̓�
�e���琄������ƁA�啝�ɒx�������\��������B
�@�ȏ�̂悤�Ȍ�ʈ��S���������̖������n�m������ŁA�V�G�B�V�[�C�[�̐� �F�O���́A��ʈ��S������
���̐��Ɓi��؉��ꎁ�A�Έ�f���A����㎁�j�ɑ�^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W���̒�R�������ł��邱
�Ƃ���点�āu���y��ʏȂ�2015�N�x�d�ʎԔR���̋�����啝�ɒx���v�����邱�Ƃ�ړI���A�u��ʈ��S��
��������SCD�G���W���ɂ���^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W���̒�R��v���W�F�N�g�v�ɎQ�����ꂽ�Ɛ������邱�Ƃ�
�\�ł���B���ɁA���̂��Ƃ������ł���A�V�G�B�V�[�C�[�̐� �F�O���̓w�͂ɂ���āA��ʈ��S��������
�́u�X�[�p�[�N���[���f�B�[�[���iSCD�j�G���W���ɂ���^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W�����R�����v���W�F�N�g�v
�����s�ɓ�����\���������ɂ������B���̂悤�ɁA�u���y��ʏȂ�2015�N�x�d�ʎԔR���̋����v��啝
�ɒx�������邽�߂ɁA�V�G�B�V�[�C�[�̐� �F�O���́A���g�̒p�����炷���Ƃ��o�債����ŁA��ʈ��S��������
�́u�X�[�p�[�N���[���f�B�[�[���iSCD�j�G���W���ɂ���^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W�����R�����v���W�F�N�g�v
�����s�ɏI��点��ړI�̂��߂ɂ��̃v���W�F�N�g�ɎQ�����Ă���悤�Ɍ�����̂ł���B���̗l�q�ɂ��ĕM�҂�
����Ȍ������J�������ĖႤ�ƁA�����e���Ǝv�����s�ׂɎ��Ă���悤�Ɏv����̂��B�ʂ����āA�V�G�B�V�[�C�[�̐�
�� �F�O������ʈ��S���������́u�X�[�p�[�N���[���f�B�[�[���iSCD�j�G���W���̃v���W�F�N�g�v�ɎQ������Ă���
�{���̖ړI�́A���Ȃ̂ł��낤���B�C�ɂȂ�Ƃ���ł���B
���̐��Ɓi��؉��ꎁ�A�Έ�f���A����㎁�j�ɑ�^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W���̒�R�������ł��邱
�Ƃ���点�āu���y��ʏȂ�2015�N�x�d�ʎԔR���̋�����啝�ɒx���v�����邱�Ƃ�ړI���A�u��ʈ��S��
��������SCD�G���W���ɂ���^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W���̒�R��v���W�F�N�g�v�ɎQ�����ꂽ�Ɛ������邱�Ƃ�
�\�ł���B���ɁA���̂��Ƃ������ł���A�V�G�B�V�[�C�[�̐� �F�O���̓w�͂ɂ���āA��ʈ��S��������
�́u�X�[�p�[�N���[���f�B�[�[���iSCD�j�G���W���ɂ���^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W�����R�����v���W�F�N�g�v
�����s�ɓ�����\���������ɂ������B���̂悤�ɁA�u���y��ʏȂ�2015�N�x�d�ʎԔR���̋����v��啝
�ɒx�������邽�߂ɁA�V�G�B�V�[�C�[�̐� �F�O���́A���g�̒p�����炷���Ƃ��o�債����ŁA��ʈ��S��������
�́u�X�[�p�[�N���[���f�B�[�[���iSCD�j�G���W���ɂ���^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W�����R�����v���W�F�N�g�v
�����s�ɏI��点��ړI�̂��߂ɂ��̃v���W�F�N�g�ɎQ�����Ă���悤�Ɍ�����̂ł���B���̗l�q�ɂ��ĕM�҂�
����Ȍ������J�������ĖႤ�ƁA�����e���Ǝv�����s�ׂɎ��Ă���悤�Ɏv����̂��B�ʂ����āA�V�G�B�V�[�C�[�̐�
�� �F�O������ʈ��S���������́u�X�[�p�[�N���[���f�B�[�[���iSCD�j�G���W���̃v���W�F�N�g�v�ɎQ������Ă���
�{���̖ړI�́A���Ȃ̂ł��낤���B�C�ɂȂ�Ƃ���ł���B
�@���āA��^�g���b�N��2015�N�x�d�ʎԔR���̋���������ۂ̊�Ă̍���i�����[�����[�J�j�̐E�ӂ���
�ʈ��S�������������{����u�X�[�p�[�N���[���f�B�[�[���iSCD�j�G���W���ɂ���^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W��
���R�����v���W�F�N�g�v�ɂ��A�u���y��ʏȂ̏d�ʎԔR���̋����̑啝�Ȓx���v�����]�E�M�]���Ă���ƍl
������g���b�N���[�J�o���̐V�G�B�V�[�C�[�����͂��Ă���̂ł���B���̂悤�ɁA��ʈ��S���������́u�X�[�p�[
�N���[���f�B�[�[���iSCD�j�G���W���̃v���W�F�N�g�v�́A��^�g���b�N�ɂ����Ă̔R����K�����鑤�̌�ʈ��S����
�����i�����y��ʏȁj�ƁA�R����K������鑤�̐V�G�B�V�[�C�[�i���g���b�N���[�J�̏o����Ёj�Ƃ̋��������ł���B
���ɁA���y��ʏȂ������̗��v�����g���b�N���[�J�̗��v��ӌ���D�悷��ӌ��������Ă���ꍇ�ɂ́A��ʈ��S
���������́u�X�[�p�[�N���[���f�B�[�[���iSCD�j�G���W���ɂ���^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W�����R�����
�v���W�F�N�g�v�́A�����J���̖ڕW�ł���2015�N�x�d�ʎԔR�����10�������コ�����d�ʎԃ��[�h�R�� 4.5 ����
�^���b�g���� ��^�g���b�N�iGVW�Q�T�g���j�������ł����Ƀv���W�F�N�g�����s�ɏI��点�邱�Ƃ��{���̖ړI�̂悤��
�l������B���́u�X�[�p�[�N���[���f�B�[�[���iSCD�j�G���W���̃v���W�F�N�g�v�����s�����邱�Ƃɂ���āA��ʈ��S��
���������ƐV�G�B�V�[�C�[�́A2015�N�x�d�ʎԔR���̋�����摗�肷�邽�߂ɖނ��炵�������ł��闝�R�E����
�̃f�[�^�������ɑ����邱�Ƃ��ł���̂ł���B�����āA���̃v���W�F�N�g�̎��s�̂���ē���ꂽ�����f�[�^����g
����A���y��ʏȂ�2015�N�x�d�ʎԔR���̋����ɑΉ��ł���Z�p�������ɊJ���ł��Ă��Ȃ��Ɖ]�����Ƃ�
�ނ��炵�������ł���̂��B����ɂ���āA���{�i�����y��ʏȁj�́A�߂������A�N������ᔻ���邱�Ɩ����A��^�g
���b�N��2015�N�x�d�ʎԔR���̋����X�ƒx�������邱�Ƃ��\�ƂȂ�B
�ʈ��S�������������{����u�X�[�p�[�N���[���f�B�[�[���iSCD�j�G���W���ɂ���^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W��
���R�����v���W�F�N�g�v�ɂ��A�u���y��ʏȂ̏d�ʎԔR���̋����̑啝�Ȓx���v�����]�E�M�]���Ă���ƍl
������g���b�N���[�J�o���̐V�G�B�V�[�C�[�����͂��Ă���̂ł���B���̂悤�ɁA��ʈ��S���������́u�X�[�p�[
�N���[���f�B�[�[���iSCD�j�G���W���̃v���W�F�N�g�v�́A��^�g���b�N�ɂ����Ă̔R����K�����鑤�̌�ʈ��S����
�����i�����y��ʏȁj�ƁA�R����K������鑤�̐V�G�B�V�[�C�[�i���g���b�N���[�J�̏o����Ёj�Ƃ̋��������ł���B
���ɁA���y��ʏȂ������̗��v�����g���b�N���[�J�̗��v��ӌ���D�悷��ӌ��������Ă���ꍇ�ɂ́A��ʈ��S
���������́u�X�[�p�[�N���[���f�B�[�[���iSCD�j�G���W���ɂ���^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W�����R�����
�v���W�F�N�g�v�́A�����J���̖ڕW�ł���2015�N�x�d�ʎԔR�����10�������コ�����d�ʎԃ��[�h�R�� 4.5 ����
�^���b�g���� ��^�g���b�N�iGVW�Q�T�g���j�������ł����Ƀv���W�F�N�g�����s�ɏI��点�邱�Ƃ��{���̖ړI�̂悤��
�l������B���́u�X�[�p�[�N���[���f�B�[�[���iSCD�j�G���W���̃v���W�F�N�g�v�����s�����邱�Ƃɂ���āA��ʈ��S��
���������ƐV�G�B�V�[�C�[�́A2015�N�x�d�ʎԔR���̋�����摗�肷�邽�߂ɖނ��炵�������ł��闝�R�E����
�̃f�[�^�������ɑ����邱�Ƃ��ł���̂ł���B�����āA���̃v���W�F�N�g�̎��s�̂���ē���ꂽ�����f�[�^����g
����A���y��ʏȂ�2015�N�x�d�ʎԔR���̋����ɑΉ��ł���Z�p�������ɊJ���ł��Ă��Ȃ��Ɖ]�����Ƃ�
�ނ��炵�������ł���̂��B����ɂ���āA���{�i�����y��ʏȁj�́A�߂������A�N������ᔻ���邱�Ɩ����A��^�g
���b�N��2015�N�x�d�ʎԔR���̋����X�ƒx�������邱�Ƃ��\�ƂȂ�B
�@���������A�V�G�B�V�[�C�[�̋��͂Ŏ��{����Ă����ʈ��S���������́u�X�[�p�[�N���[���f�B�[�[���iSCD�j�G��
�W���̃v���W�F�N�g�v�́A��X�̐g�߂Ȏs�������ł̖h�Ƃ̏ꍇ�ɗႦ��A�h�Ɗ֘A�̖@���i�Y�@�j���쐬����x
�@���i���ƌ����ψ���j���Y�@�Ŕ�������D�_�Ƌ������Ďs���̈��S�𐄐i���邽�߂ɌY�@�̔���������V��
�ȌY�@���쐬���邽�߂̒����E���������{���Ă���悤�ȍ\�}�ɂ�������̂ł���B���̂悤�ȌY�@�̔���������Y
�@�쐬�̉ߒ��ɂ����āA�x�@���ƓD�_�Ƃ̋����������������ꍇ�ɁA�x�@���́u�D�_�̎�̓���m��v���߂ɓD�_
�̋��͂��s���Ƃٖ̕����s�����Ƃ��Ă��A�M�҂ɂ͕s�K�E�s�ސT�Ȃ悤�Ɏv����̂ł���B�X�ɁA���̌x�@����
�D�_�Ƃ̒����E�����v���W�F�N�g���D�_�̋����v��������Čx�@�����Y�@�̔���������V���ȌY�@�쐬�̒x
����ړI�Ƃ������̂ł���A�S��������Ȃ��s�ׂł��邱�Ƃ͖��炩���B���̔�g�͔�߂���������Ȃ��B����
���A��ʈ��S���������ƐV�G�B�V�[�C�[�����͂��Ď��{����Ă���u�X�[�p�[�N���[���f�B�[�[���iSCD�j�G���W����
�v���W�F�N�g�v�́A�x�@���ƓD�_�Ƃ̒����E�����v���W�F�N�g�������悤�ȁA�u�K�����鑤�ƋK������鑤�Ƃ̋��������v
�̍\�}�ł���A�M�҂ɂ́u�������킵���v�Ƃ̎v�����@������Ȃ��̂ł���B���������āA���݁A���y��ʏȓ��Ō���
���Ɛ���������^�g���b�N�Ɋւ���2015�N�x�d�ʎԔR���̋����ɂ��ẮA�u�D�_�ɓ���Ȃ킹��v�悤�Ȍ�
�U�L���C�z�������Ă��܂����A����͕M�҂����ł͖����Ǝv���Ă���B
�W���̃v���W�F�N�g�v�́A��X�̐g�߂Ȏs�������ł̖h�Ƃ̏ꍇ�ɗႦ��A�h�Ɗ֘A�̖@���i�Y�@�j���쐬����x
�@���i���ƌ����ψ���j���Y�@�Ŕ�������D�_�Ƌ������Ďs���̈��S�𐄐i���邽�߂ɌY�@�̔���������V��
�ȌY�@���쐬���邽�߂̒����E���������{���Ă���悤�ȍ\�}�ɂ�������̂ł���B���̂悤�ȌY�@�̔���������Y
�@�쐬�̉ߒ��ɂ����āA�x�@���ƓD�_�Ƃ̋����������������ꍇ�ɁA�x�@���́u�D�_�̎�̓���m��v���߂ɓD�_
�̋��͂��s���Ƃٖ̕����s�����Ƃ��Ă��A�M�҂ɂ͕s�K�E�s�ސT�Ȃ悤�Ɏv����̂ł���B�X�ɁA���̌x�@����
�D�_�Ƃ̒����E�����v���W�F�N�g���D�_�̋����v��������Čx�@�����Y�@�̔���������V���ȌY�@�쐬�̒x
����ړI�Ƃ������̂ł���A�S��������Ȃ��s�ׂł��邱�Ƃ͖��炩���B���̔�g�͔�߂���������Ȃ��B����
���A��ʈ��S���������ƐV�G�B�V�[�C�[�����͂��Ď��{����Ă���u�X�[�p�[�N���[���f�B�[�[���iSCD�j�G���W����
�v���W�F�N�g�v�́A�x�@���ƓD�_�Ƃ̒����E�����v���W�F�N�g�������悤�ȁA�u�K�����鑤�ƋK������鑤�Ƃ̋��������v
�̍\�}�ł���A�M�҂ɂ́u�������킵���v�Ƃ̎v�����@������Ȃ��̂ł���B���������āA���݁A���y��ʏȓ��Ō���
���Ɛ���������^�g���b�N�Ɋւ���2015�N�x�d�ʎԔR���̋����ɂ��ẮA�u�D�_�ɓ���Ȃ킹��v�悤�Ȍ�
�U�L���C�z�������Ă��܂����A����͕M�҂����ł͖����Ǝv���Ă���B
�@�Ƃ���ŁA�O�q���y�P�S�|�P NEDO�̒����x�R�Đ���G���W�V�X�e���̌����J���z�ł́A�R����̑厸�s�z�ɋL��
�����ʂ�ANEDO�̊v�V�I���������Q�ԑ����Z�p�J���i�N���[���f�B�[�[���v���W�F�N�g�A2004�`2009�N�j�́u����
�x�R�Đ���G���W�V�X�e���̌����J���i�\�Z�F�W���~�ȏ�j�v�̑�^�v���W�F�N�g�ł���B����NEDO�́u�����x�R�Đ�
��G���W�v�ł́A�u�R�i�ߋ��V�X�e���v�A�u300MP���̒������R�����ˁv�A�u�J�����X�V�X�e���v�A�uPCI�iPremixed.
Compression Ignition combustion�j�R�āv�̋Z�p���g�ݍ��݁A2015�N�x�d�ʎԔR�������P�O���̑啝�ȔR���
���̖ڕW���f���Č����J�������{���ꂽ�B�������A���̌��ʂ́A2015�N�x�d�ʎԔR�������Q���̔R�����
�Ȃ��Ă��܂����̂ł���B���̂悤�ɁANEDO�́u�R�i�ߋ��V�X�e���v�A�u300MP���̒������R�����ˁv�A�u�J�����X�V�X�e
���v�A�uPCI�R�āv���Z�p���̗p������^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W���̌����ł́ANO���͖ڕW��B���������̂́A�R
����P�͊F���̔ߎS�Ȍ��ʂƂȂ��Ă��܂��Ă���̂��B
�����ʂ�ANEDO�̊v�V�I���������Q�ԑ����Z�p�J���i�N���[���f�B�[�[���v���W�F�N�g�A2004�`2009�N�j�́u����
�x�R�Đ���G���W�V�X�e���̌����J���i�\�Z�F�W���~�ȏ�j�v�̑�^�v���W�F�N�g�ł���B����NEDO�́u�����x�R�Đ�
��G���W�v�ł́A�u�R�i�ߋ��V�X�e���v�A�u300MP���̒������R�����ˁv�A�u�J�����X�V�X�e���v�A�uPCI�iPremixed.
Compression Ignition combustion�j�R�āv�̋Z�p���g�ݍ��݁A2015�N�x�d�ʎԔR�������P�O���̑啝�ȔR���
���̖ڕW���f���Č����J�������{���ꂽ�B�������A���̌��ʂ́A2015�N�x�d�ʎԔR�������Q���̔R�����
�Ȃ��Ă��܂����̂ł���B���̂悤�ɁANEDO�́u�R�i�ߋ��V�X�e���v�A�u300MP���̒������R�����ˁv�A�u�J�����X�V�X�e
���v�A�uPCI�R�āv���Z�p���̗p������^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W���̌����ł́ANO���͖ڕW��B���������̂́A�R
����P�͊F���̔ߎS�Ȍ��ʂƂȂ��Ă��܂��Ă���̂��B
�@����A��ʈ��S���������́u�X�[�p�[�N���[���f�B�[�[���iSCD�j�G���W���v�ɂ́A�u�Q�i�V�[�P���V�����ߋ��@�v��
�u�r�M����V�X�e���i�^�[�{�R���p�E���h�j�v���u�������R�������[���v�̋Z�p�������g�ݍ��ނ܂�Ă��邪�A��ʈ��S
���������́u�X�[�p�[�N���[���f�B�[�[���iSCD�j�G���W���v��NEDO�́u�����x�R�Đ���G���W�v�ɐV�����u�r�M��
���V�X�e���i�^�[�{�R���p�E���h�j�v���g�ݍ��܂�Ă��邾���ł���B���݂ɁA�^�[�{�R���p�E���h�́A�^�[�{�R���p�E��
�h�́A��^�g���b�N�̑��s�R��̉��P������ȋZ�p���I�ɏڏq���Ă���悤�ɁA�C�����̍ō����͂����߂邱�ƂȂ��A
�G���W���̍��o�͉����\�ȋZ�p�ł���A�R�����̋@�\�͏��Ȃ��A�d�ʎԃ��[�h�R����P�������������P�ł��Ȃ�
�悤�ȔR����P�ɕs�K�ȋZ�p�ł���B���������āA��ʈ��S���������́u�X�[�p�[�N���[���f�B�[�[���iSCD�j
�G���W���v�́A2015�N�x�d�ʎԔR�������Q���̔R����������ꂽNEDO�́u�����x�R�Đ���G��
�W�v�ɏ\���ȔR����P�̋@�\�������Ȃ��u�r�M����V�X�e���i�^�[�{�R���p�E���h�j�v��V���ɒlj������V�X�e
���ƌ��邱�Ƃ��\���B���̂��߁A2015�N�x�d�ʎԔR�������Q���̔R����������ꂽNEDO�́u�����x�R
�Đ���G���W�v�̌����J���ɑg�ݍ��܂ꂽ�Z�p�ɁA�d�ʎԃ��[�h�R����P�������������P�ł��Ȃ��^�[�{�R���p�E��
�h��g�ݍ��킹�Ă��R����P������Ȃ��Ƃ́A�������ʂ�����܂ł��������炩�Ȃ��Ƃ��B���������āA��ʈ��S��
�������́u�X�[�p�[�N���[���f�B�[�[���iSCD�j�G���W���v�̌����J���́A2015�N�x�d�ʎԔR�������P�O������
�啝�ȔR����팸����ڕW�̒B���́A���S�ɕs�\�ł��邱�Ƃ��N�ł��e�Ղɗ\�z�ł��邱�Ƃł���B
�u�r�M����V�X�e���i�^�[�{�R���p�E���h�j�v���u�������R�������[���v�̋Z�p�������g�ݍ��ނ܂�Ă��邪�A��ʈ��S
���������́u�X�[�p�[�N���[���f�B�[�[���iSCD�j�G���W���v��NEDO�́u�����x�R�Đ���G���W�v�ɐV�����u�r�M��
���V�X�e���i�^�[�{�R���p�E���h�j�v���g�ݍ��܂�Ă��邾���ł���B���݂ɁA�^�[�{�R���p�E���h�́A�^�[�{�R���p�E��
�h�́A��^�g���b�N�̑��s�R��̉��P������ȋZ�p���I�ɏڏq���Ă���悤�ɁA�C�����̍ō����͂����߂邱�ƂȂ��A
�G���W���̍��o�͉����\�ȋZ�p�ł���A�R�����̋@�\�͏��Ȃ��A�d�ʎԃ��[�h�R����P�������������P�ł��Ȃ�
�悤�ȔR����P�ɕs�K�ȋZ�p�ł���B���������āA��ʈ��S���������́u�X�[�p�[�N���[���f�B�[�[���iSCD�j
�G���W���v�́A2015�N�x�d�ʎԔR�������Q���̔R����������ꂽNEDO�́u�����x�R�Đ���G��
�W�v�ɏ\���ȔR����P�̋@�\�������Ȃ��u�r�M����V�X�e���i�^�[�{�R���p�E���h�j�v��V���ɒlj������V�X�e
���ƌ��邱�Ƃ��\���B���̂��߁A2015�N�x�d�ʎԔR�������Q���̔R����������ꂽNEDO�́u�����x�R
�Đ���G���W�v�̌����J���ɑg�ݍ��܂ꂽ�Z�p�ɁA�d�ʎԃ��[�h�R����P�������������P�ł��Ȃ��^�[�{�R���p�E��
�h��g�ݍ��킹�Ă��R����P������Ȃ��Ƃ́A�������ʂ�����܂ł��������炩�Ȃ��Ƃ��B���������āA��ʈ��S��
�������́u�X�[�p�[�N���[���f�B�[�[���iSCD�j�G���W���v�̌����J���́A2015�N�x�d�ʎԔR�������P�O������
�啝�ȔR����팸����ڕW�̒B���́A���S�ɕs�\�ł��邱�Ƃ��N�ł��e�Ղɗ\�z�ł��邱�Ƃł���B
�@���̂悤�ȏɂ����āA���̌�ʈ��S���������́u�X�[�p�[�N���[���f�B�[�[���iSCD�j�G���W���v�̌����J����
�����āA2015�N�x�d�ʎԔR���ɔ䂵�ĂP�O���̔R����P�̖ڕW���B���ł���B��̕��@�́A���݂��u�X�[�p�[
�N���[���f�B�[�[���iSCD�j�G���W���v�ɁA�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p��V���ɍ̗p���邱�Ƃł�
��ƕM�҂͍l���Ă���B�������邽�߂ɂ́A�ʈ��S���������̗�؉��ꎁ�A�Έ�f���A�����A����ю��V�G�B
�V�[�C�[�̐� �F�O���̏������K�ȕ��j�ύX�̗E�f�������K�v������B����ɂ���āA��ʈ��S����������
�u�X�[�p�[�N���[���f�B�[�[���iSCD�j�G���W���v�́A�ȉ��̕\�Q�S�Ɏ������C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j��
�����b�g�ɂ��A2015�N�x�d�ʎԔR���ɔ䂵�ĂP�O���̔R����P��}��ڕW���e�ՂɎ����ł��A����Ɠ�����NO
���팸���\�ƂȂ�̂ł���B
�����āA2015�N�x�d�ʎԔR���ɔ䂵�ĂP�O���̔R����P�̖ڕW���B���ł���B��̕��@�́A���݂��u�X�[�p�[
�N���[���f�B�[�[���iSCD�j�G���W���v�ɁA�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p��V���ɍ̗p���邱�Ƃł�
��ƕM�҂͍l���Ă���B�������邽�߂ɂ́A�ʈ��S���������̗�؉��ꎁ�A�Έ�f���A�����A����ю��V�G�B
�V�[�C�[�̐� �F�O���̏������K�ȕ��j�ύX�̗E�f�������K�v������B����ɂ���āA��ʈ��S����������
�u�X�[�p�[�N���[���f�B�[�[���iSCD�j�G���W���v�́A�ȉ��̕\�Q�S�Ɏ������C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j��
�����b�g�ɂ��A2015�N�x�d�ʎԔR���ɔ䂵�ĂP�O���̔R����P��}��ڕW���e�ՂɎ����ł��A����Ɠ�����NO
���팸���\�ƂȂ�̂ł���B
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
�@�ȏ�̂悤�ɁA��ʈ��S���������́u�X�[�p�[�N���[���f�B�[�[���iSCD�j�G���W���v���C���x�~�G���W���i������
�J2005-54771�j�̋Z�p��lj�����A��L�̕\�Q�Q�Ɏ������悤�ȁA�啝�ȔR����P��NO���팸���\���B���ɁA��
�̒��̔R����P�̌��ʂɂ���āA��ʈ��S���������́u�X�[�p�[�N���[���ɂ��f�B�[�[���iSCD�j�G���W���v�́A
�ڕW�Ɍf�����Ă���2015�N�x�d�ʎԔR����10���̌��サ��4.5 �����^���b�g���̏d�ʎԃ��[�h�R��� ��^�g
���b�N�iGVW�Q�T�g���j���m���Ɏ����ł���̂ł���B
�J2005-54771�j�̋Z�p��lj�����A��L�̕\�Q�Q�Ɏ������悤�ȁA�啝�ȔR����P��NO���팸���\���B���ɁA��
�̒��̔R����P�̌��ʂɂ���āA��ʈ��S���������́u�X�[�p�[�N���[���ɂ��f�B�[�[���iSCD�j�G���W���v�́A
�ڕW�Ɍf�����Ă���2015�N�x�d�ʎԔR����10���̌��サ��4.5 �����^���b�g���̏d�ʎԃ��[�h�R��� ��^�g
���b�N�iGVW�Q�T�g���j���m���Ɏ����ł���̂ł���B
�@����ɂ��ẮA��ʈ��S���������̗�؉��ꎁ�A�Έ�f���A����㎁�A����ѐV�G�B�V�[�C�[�̐� �F�O
�����A���̃y�[�W���C���x�~�́A�R��팸�ƔA�fSCR��NO���팸���̌���ɗL�����I���n�ǂ��Ă���������A�C
���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p���u�X�[�p�[�N���[���f�B�[�[���iSCD�j�G���W���v�̔R�����ɑ傫��
��^�ł��邱�Ƃ��\���ɗ����ł��锤���B�����āA��ʈ��S����������SCD�G���W���̃v���W�F�N�g���C���x�~�G
���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p��V���ɉ������ꍇ�A���̃v���W�F�N�g�̖ڕW���e�ՂɒB���ł���\������
�߂č����Ȃ�̂ł���B�����ŁA���̌�ʈ��S����������SCD�G���W���̃v���W�F�N�g�ɂ��āA�{�z�[���y�[�W��
�{���҂ɍ���̃v���W�F�N�g�̐��i���@��\�z���ĖႤ������A�e���r�̃N�C�Y�ԑg���ɂ܂Ƃ߁A�\�Q�T�Ɏ������B
�����A���̃y�[�W���C���x�~�́A�R��팸�ƔA�fSCR��NO���팸���̌���ɗL�����I���n�ǂ��Ă���������A�C
���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p���u�X�[�p�[�N���[���f�B�[�[���iSCD�j�G���W���v�̔R�����ɑ傫��
��^�ł��邱�Ƃ��\���ɗ����ł��锤���B�����āA��ʈ��S����������SCD�G���W���̃v���W�F�N�g���C���x�~�G
���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p��V���ɉ������ꍇ�A���̃v���W�F�N�g�̖ڕW���e�ՂɒB���ł���\������
�߂č����Ȃ�̂ł���B�����ŁA���̌�ʈ��S����������SCD�G���W���̃v���W�F�N�g�ɂ��āA�{�z�[���y�[�W��
�{���҂ɍ���̃v���W�F�N�g�̐��i���@��\�z���ĖႤ������A�e���r�̃N�C�Y�ԑg���ɂ܂Ƃ߁A�\�Q�T�Ɏ������B
| �i��ҁ@�F�@�����ŁA�F����Ɏ���ł��B
�i��҂̎�����e ��ʈ��S���������́u�Q�i�V�[�P���V�����ߋ��@�v���u�r�M����V�X�e���i�^�[�{�R���p�E���h�j�v���u�������R�������[���v�̋Z�p�� ���X�[�p�[�N���[���f�B�[�[���iSCD�j�G���W���̌����ł́A��^�g���b�N��2015�N�x�d�ʎԔR���l�����P�O���̔R��̉��P�� ���s�ɏI���Ɨ\�z����܂��B�������A����SCD�G���W�����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p���̗p�����2015�N�x�d�� �ԔR����10���̌��サ��4.5 �����^���b�g���̏d�ʎԃ��[�h�R��� ��^�g���b�N�iGVW�Q�T�g���j���m���Ɏ����ł���Ɨ\�z����Ă��� ���B ���āA�A����́u��ʈ��S���������̃X�[�p�[�N���[���f�B�[�[���iSCD�j�G���W���̃v���W�F�N�g�v�ł́A��ʈ��S���������̗�؉� �ꎁ�A�Έ�f���A����㎁�A����ѐV�G�B�V�[�C�[�̐� �F�O���̏������A�v���W�F�N�g�̍���̐��i�ɂ��āA�@�܂��͇A�̉���� ���j���I������邩�ɂ��Ă̗\�z�������ĉ����� �@�@���̃v���W�F�N�g��SCD�G���W���ł́A�\���ȔR����P�͍���ƍl�����܂��B���������āA����SCD�G���W���̌����J���ɂ����āA�d �ʎԔR���̋��������肷��E�ӂ�����ʈ��S���������̐��Ɓi��؉��ꎁ�A�Έ�f���A����㎁�j�́A��^�g���b�N�̔R ����P���Z�p�I�ɐ�]�I�ł��邱�Ƃ�Ɋ���������ł��傤�B�����āA����SCD�G���W���̌����Ŗ��炩�ƂȂ����u�R����P���s�̎����f �[�^�v�́A2015�N�x�d�ʎԔR���̋�����摗�肷��ۂɖނ��炵�������ł��闝�R�E�����Ƃ��ė��p�ł��܂��B�����āA�����̎����f �[�^����g���邱�Ƃɂ����2015�N�x�d�ʎԔR���̋�����x�������邱�ƂɒN�������ł��Ȃ������o�����Ƃ��\�ƂȂ�� ���B����ɂ���č��y��ʏȂ����ۂ�2015�N�x�d�ʎԔR�����������鎟���̔R�������������ꍇ�ɂ́A�g���b�N���[�J�́A�R�� ���P�̌����J���̓������팸�ł��邽�߁A���̊�Ɠw�͂������ɗ��v����̉��b���邱�Ƃ��ł���̂ł��B���̏ꍇ�A�g���b�N���[�J �́A����ΔG���Ɉ��̗��v����ɂ��邱�ƂɂȂ�܂��̂ŁA���y��ʏȂɁu���ӁI���ӁI�v�Ɖ]�����ƂɂȂ�܂��B����ɑ��A�g���b�N�� �[�U�́A���ꂩ������X�ƔR����P�̐i�W���Ȃ���^�g���b�N���w���������Ȃ���Ȃ炸�A�^�s�R��팸�ł��Ȃ��]���������邱 �ƂɂȂ�A�g���b�N���[�U�ɂƂ��Ă͗J�T�Ȏ��オ�������ƂɂȂ�܂��B �A�@���̃v���W�F�N�g��SCD�G���W���ł́A�\���ȔR����P�͍���ƍl�����܂��B�������A����SCD�G���W�����C���x�~�G���W���i������ �J2005-54771�j�̋Z�p��V���ɒlj����邱�Ƃɂ��A2015�N�x�d�ʎԔR�����ő�łP�O�����̔R������サ�� 4.5 �����^���b�g���̏d �ʎԃ��[�h�R��̑�^�g���b�N�iGVW�Q�T�g���j���Q�R�N�x�Ɏ��������邱�Ƃ��ł���\��������܂��B����ɂ���āA2015�N�x�d�ʎ� �R���̋����𑁊��Ɏ��{�ł���悤�ɂȂ�܂��B���̏ꍇ�ɂ́A�ȃG�l���M�[��CO2�팸�����߂鍑���̊肢���������邱�Ƃ��ł��� �Ƌ��ɁA�g���b�N���[�U�͔R����P���ꂽ��^�g���b�N���w���ł���悤�ɂȂ�܂��B���̂��Ƃ́A�g���b�N���[�U���҂��]�^�s�R��� ���P�������ł��邱�ƂɂȂ�̂ł��B����ɂ���āA�g���b�N���[�U�����ӊ������邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��ł��傤�B �i��ҁ@�F�@����ł́A�����SCD�G���W���̃v���W�F�N�g�̐��i�ɂ����āA����A�F����́A��ʈ��S�����������@�܂��͇A�̉����
���j��I������悤�ɂȂ�Ɨ\�z����܂����B��ґ���ł������������B
|
���� ���āA��ʈ��S���������̗�؉��ꎁ�A�Έ�f���A����㎁�A����ѐV�G�B�V�[�C�[�̐� �F�O���̏�
���́A��ʈ��S���������̃X�[�p�[�N���[���f�B�[�[���iSCD�j�G���W���̃v���W�F�N�g�̐��i�ɂ����āA�C���x�~
�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p��V���ɒlj�����2015�N�x�d�ʎԔR�����ő�̏ꍇ�ɂ́A10���̔R
����サ��4.5 �����^���b�g���̏d�ʎԃ��[�h�R��� ��^�g���b�N�iGVW�Q�T�g���j�������ł���\��������B�������A
�ނ�ɂ́A4.5 �����^���b�g���̏d�ʎԃ��[�h�R��̑�^�g���b�N�iGVW�Q�T�g���j���������ł��������A�����̏ȃG�l��
�M�[��CO2�팸�̗v�]�ɉ�����ӎv���{���ɂ���̂ł��낤���B����Ƃ��A�X�[�p�[�N���[���f�B�[�[���iSCD�j�G��
�W���̃v���W�F�N�g�ɋC���x�~�̋Z�p��lj����Ȃ��ŏ]���ʂ�̔R����P�̍���ȋZ�p�������̗p���������J����
�p�����A�����ڕW�Ƃ���2015�N�x�d�ʎԔR��10���̔R�����̖ڕW�B���ɂɎ��s���������f�[�^����g���A
2015�N�x�d�ʎԔR���̋�����x�������ĔR����P�̌����J����̍팸��}��A�g���b�N���[�J�̗��v�����ɋ�
�́E�v������Ӑ}�������Ă���̂ł��낤���B
���́A��ʈ��S���������̃X�[�p�[�N���[���f�B�[�[���iSCD�j�G���W���̃v���W�F�N�g�̐��i�ɂ����āA�C���x�~
�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p��V���ɒlj�����2015�N�x�d�ʎԔR�����ő�̏ꍇ�ɂ́A10���̔R
����サ��4.5 �����^���b�g���̏d�ʎԃ��[�h�R��� ��^�g���b�N�iGVW�Q�T�g���j�������ł���\��������B�������A
�ނ�ɂ́A4.5 �����^���b�g���̏d�ʎԃ��[�h�R��̑�^�g���b�N�iGVW�Q�T�g���j���������ł��������A�����̏ȃG�l��
�M�[��CO2�팸�̗v�]�ɉ�����ӎv���{���ɂ���̂ł��낤���B����Ƃ��A�X�[�p�[�N���[���f�B�[�[���iSCD�j�G��
�W���̃v���W�F�N�g�ɋC���x�~�̋Z�p��lj����Ȃ��ŏ]���ʂ�̔R����P�̍���ȋZ�p�������̗p���������J����
�p�����A�����ڕW�Ƃ���2015�N�x�d�ʎԔR��10���̔R�����̖ڕW�B���ɂɎ��s���������f�[�^����g���A
2015�N�x�d�ʎԔR���̋�����x�������ĔR����P�̌����J����̍팸��}��A�g���b�N���[�J�̗��v�����ɋ�
�́E�v������Ӑ}�������Ă���̂ł��낤���B
�@�����Q�R�N�x�̎������ʂ̔��\�����邱�Ƃɂ���āA��ʈ��S���������̃X�[�p�[�N���[���f�B�[�[���iSCD�j�G
���W���̃v���W�F�N�g�́A��ʈ��S���������i�����y��ʏȁj�������ƃg���b�N���[�J�̉���̗��v���l���Ď��{��
��Ă��邩�����m�ɂȂ邾�낤�B���͂Ƃ�����A���̃v���W�F�N�g�̌��ʔ��\���y���݂��B
���W���̃v���W�F�N�g�́A��ʈ��S���������i�����y��ʏȁj�������ƃg���b�N���[�J�̉���̗��v���l���Ď��{��
��Ă��邩�����m�ɂȂ邾�낤�B���͂Ƃ�����A���̃v���W�F�N�g�̌��ʔ��\���y���݂��B
�@�Ȃ��A���̍��̋L�ړ��e�ɂ͐����������܂܂�Ă��邽�߁A�ꕔ�ɂ͕M�҂̎�����F�����邩���m��Ȃ��B����
�ŁA�i�Ɓj��ʈ��S������������ч��V�G�B�V�[�C�[�̊W�҂����̍����{�����ꂽ�ہA���炩�Ɍ��ƋC�t����
���L�ڂɂ��ẮA�����̕M�҂�E���[�����ĂɎ����ɂ��Ă̌�A��������������A������L�ړ��e�͑�����
�����������ƍl���Ă���B
�ŁA�i�Ɓj��ʈ��S������������ч��V�G�B�V�[�C�[�̊W�҂����̍����{�����ꂽ�ہA���炩�Ɍ��ƋC�t����
���L�ڂɂ��ẮA�����̕M�҂�E���[�����ĂɎ����ɂ��Ă̌�A��������������A������L�ړ��e�͑�����
�����������ƍl���Ă���B
�y 2014�N�P���ɒNjL�̃R�����g �z
�@ �ȏ�̌�ʈ��S���������̃X�[�p�[�N���[���f�B�[�[���iSCD�j�G���W���̃v���W�F�N�g�Ɋւ��镽��23�N�x��
�������ʂ́A����26�N�P�����݂ł������\�̂悤�ł���B����SCD�G���W���̃v���W�F�N�g�̌��ʂ������\�Ƃ��ꂽ
�����E���@�́A��ʈ��S���������̃X�[�p�[�N���[���f�B�[�[���iSCD�j�G���W���̃v���W�F�N�g�́A10���̔R���
�サ��4.5 �����^���b�g���̏d�ʎԃ��[�h�R��� ��^�g���b�N�iGVW�Q�T�g���j����������ڕW�B���Ɏ��s�������߂Ɛ�
������A���̏؋��B�ł̂��߂Ɏ������ʂ��łɑ��苎��ꂽ���̂ƍl������B���̂悤�ɁA���{�\�Z�ɂ���Ď��{
���ꂽSCD�G���W���̎��������v���W�F�N�g�����s���A���̎������ʂ�����\�Ƃ��ꂽ�ꍇ�ɂ́A�������������{��
����ʈ��S���������̗�؉��ꎁ�A�Έ�f���A����㎁�A����ѐV�G�B�V�[�C�[�̐� �F�O���̏��������I
���Y�ł��鎎�����ʂ��������������Ƃɑ�������ƍl������B�����āA���̂悤�Ȏ������ʂ̎������́A���h�Ȍ�
�I�ȍ��Y�����̂����s�ׂɑ�������̂ł͂Ȃ����낤���B���̂Ȃ�A���{�\�Z���������ꂽ���������v���W�F�N�g
�ł���Ȃ���A�����������ʂ���ʍ������S�����p�E���p�ł��Ȃ����߂ł���B���������A���s�������������v���W�F
�N�g�Ƃ͉]���A���̎������ʂ́A���̑����̌����J���ҁi�����j�ɂƂ��ẮA�u�����A���{���Ă͂����Ȃ�����������
�d�v�ȏ؋��v�Ƃ��āA�����̎��������e�[�}�̑I��E����ɍۂ��Ă̎Q�l�e�[�^�Ƃ��ė��p�ł���̂ł���B��������
�āA���s�����v���W�F�N�g�̌��ʂ��A�����������瓾��ꂽ�d�v�Ȑ��ʁE�����ł��邱�Ƃ�����ł���B���������āA��
��A����SCD�G���W���̃v���W�F�N�g�ɓ������ꂽ���{�\�Z���u���ʌ����v�E�u�Q��v�Ƃ��Ȃ����߂ɂ́A��ʈ��S��
�������̃X�[�p�[�N���[���f�B�[�[���iSCD�j�G���W���̃v���W�F�N�g�Ɋւ��镽��23�N�x�̎������ʂ́A���₩�Ɍ�
�\���ׂ��ƍl���邪�A�@���Ȃ��̂ł��낤���B�Ȃ��A���̂悤�Ȍ��ɂ��ẮA��v�����@�̊č��́A�s���Ȃ��̂�
���낤���B
�������ʂ́A����26�N�P�����݂ł������\�̂悤�ł���B����SCD�G���W���̃v���W�F�N�g�̌��ʂ������\�Ƃ��ꂽ
�����E���@�́A��ʈ��S���������̃X�[�p�[�N���[���f�B�[�[���iSCD�j�G���W���̃v���W�F�N�g�́A10���̔R���
�サ��4.5 �����^���b�g���̏d�ʎԃ��[�h�R��� ��^�g���b�N�iGVW�Q�T�g���j����������ڕW�B���Ɏ��s�������߂Ɛ�
������A���̏؋��B�ł̂��߂Ɏ������ʂ��łɑ��苎��ꂽ���̂ƍl������B���̂悤�ɁA���{�\�Z�ɂ���Ď��{
���ꂽSCD�G���W���̎��������v���W�F�N�g�����s���A���̎������ʂ�����\�Ƃ��ꂽ�ꍇ�ɂ́A�������������{��
����ʈ��S���������̗�؉��ꎁ�A�Έ�f���A����㎁�A����ѐV�G�B�V�[�C�[�̐� �F�O���̏��������I
���Y�ł��鎎�����ʂ��������������Ƃɑ�������ƍl������B�����āA���̂悤�Ȏ������ʂ̎������́A���h�Ȍ�
�I�ȍ��Y�����̂����s�ׂɑ�������̂ł͂Ȃ����낤���B���̂Ȃ�A���{�\�Z���������ꂽ���������v���W�F�N�g
�ł���Ȃ���A�����������ʂ���ʍ������S�����p�E���p�ł��Ȃ����߂ł���B���������A���s�������������v���W�F
�N�g�Ƃ͉]���A���̎������ʂ́A���̑����̌����J���ҁi�����j�ɂƂ��ẮA�u�����A���{���Ă͂����Ȃ�����������
�d�v�ȏ؋��v�Ƃ��āA�����̎��������e�[�}�̑I��E����ɍۂ��Ă̎Q�l�e�[�^�Ƃ��ė��p�ł���̂ł���B��������
�āA���s�����v���W�F�N�g�̌��ʂ��A�����������瓾��ꂽ�d�v�Ȑ��ʁE�����ł��邱�Ƃ�����ł���B���������āA��
��A����SCD�G���W���̃v���W�F�N�g�ɓ������ꂽ���{�\�Z���u���ʌ����v�E�u�Q��v�Ƃ��Ȃ����߂ɂ́A��ʈ��S��
�������̃X�[�p�[�N���[���f�B�[�[���iSCD�j�G���W���̃v���W�F�N�g�Ɋւ��镽��23�N�x�̎������ʂ́A���₩�Ɍ�
�\���ׂ��ƍl���邪�A�@���Ȃ��̂ł��낤���B�Ȃ��A���̂悤�Ȍ��ɂ��ẮA��v�����@�̊č��́A�s���Ȃ��̂�
���낤���B
�P�T�D�C���x�~�f�B�[�[���i�������J2005-54771�j�ɂ��X�Ȃ�NO���팸�ƔR�����
�@�O�q�̒ʂ�A�C���x�~�f�B�[�[���G���W���i�������J2005-54771�j�́A�d�ʎԃ��[�h�R��l������s�R�
�T�`�P�O�������P�ł���@�\�̑��ɁA�i�d�O�T���[�h�r�o�K�X�����@��WHTC�r�o�K�X�����@�ł̃G���W���^�]
�p�x�̍��������������r�b�q�G�}��������x���������ł��邽�߂ɔA�f�r�b�q�G�}�ł̂m�n���팸�����
���Ɍ���ł���@�\������B�X�ɁA�C���x�~��DPF�̎��ȍĐ��𑣐i����V�Z�p�ɏڏq���Ă���悤�ɁA�C���x
�~�f�B�[�[���G���W���i�������J2005-54771�j�ł́A���s����DPF���u�̃t�B���^�����R�Đ��ł��邱�ƂɂȂ邽�߁A
�|�X�g���˂�r�C�Ǖ��˂ɂ��t�B���^�Đ����̔R���̘Q���h�~�ł�����ʂ�����B
�T�`�P�O�������P�ł���@�\�̑��ɁA�i�d�O�T���[�h�r�o�K�X�����@��WHTC�r�o�K�X�����@�ł̃G���W���^�]
�p�x�̍��������������r�b�q�G�}��������x���������ł��邽�߂ɔA�f�r�b�q�G�}�ł̂m�n���팸�����
���Ɍ���ł���@�\������B�X�ɁA�C���x�~��DPF�̎��ȍĐ��𑣐i����V�Z�p�ɏڏq���Ă���悤�ɁA�C���x
�~�f�B�[�[���G���W���i�������J2005-54771�j�ł́A���s����DPF���u�̃t�B���^�����R�Đ��ł��邱�ƂɂȂ邽�߁A
�|�X�g���˂�r�C�Ǖ��˂ɂ��t�B���^�Đ����̔R���̘Q���h�~�ł�����ʂ�����B
�@���̂悤���C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j���A�T�`�P�O���̃��[�h�R��l�̉��P�Ƒ啝�Ȃm�n����
���̗������\�ɂ���ꋓ�����̗D�ꂽ�Z�p�ł���B�����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�ɂ����đ�
�����R����P�Ƃm�n���팸���\����\���I�E�@�\�I�ȍ����ɂ��Ă��A�C���x�~�́A�R��팸�ƔA�fSCR��NO��
�팸���̌���ɗL�����I�ɏڏq���Ă���̂ŁA�����̂�����͐���Ƃ������������������B
���̗������\�ɂ���ꋓ�����̗D�ꂽ�Z�p�ł���B�����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�ɂ����đ�
�����R����P�Ƃm�n���팸���\����\���I�E�@�\�I�ȍ����ɂ��Ă��A�C���x�~�́A�R��팸�ƔA�fSCR��NO��
�팸���̌���ɗL�����I�ɏڏq���Ă���̂ŁA�����̂�����͐���Ƃ������������������B
�Ƃ���ŁA2010�N�V��28�����\�̒������R�c��E��C������́u����̎����Ԕr�o�K�X�ጸ��̂������
���āi��\�����\�j�v�ł́A�\�Q�U�Ɏ������悤�ɁA�u����A�ȉ��̂悤�ȋZ�p�̐i�W�������ނ��Ƃɂ��A�R��̐L
�т�����m�����A�G���W���o���́iNO���́j�r�o�ʂ�1.5g/kWh���x�܂Œጸ���邱�Ƃ͉\�ł���ƍl�����
��B�v�ƋL�ڂ���Ă���B
���āi��\�����\�j�v�ł́A�\�Q�U�Ɏ������悤�ɁA�u����A�ȉ��̂悤�ȋZ�p�̐i�W�������ނ��Ƃɂ��A�R��̐L
�т�����m�����A�G���W���o���́iNO���́j�r�o�ʂ�1.5g/kWh���x�܂Œጸ���邱�Ƃ͉\�ł���ƍl�����
��B�v�ƋL�ڂ���Ă���B
�@�����āA���̒������R�c��E��C���������\�����\�ł́A�uNO���팸�v�Ɓu�R��̐L�т�����m�ہv�ł��邽
�߂��u�����Z�p�v�Ƃ��āA�ȉ��̋Z�p������Ă���B(�\�Q�S�Q�Ɓj
�߂��u�����Z�p�v�Ƃ��āA�ȉ��̋Z�p������Ă���B(�\�Q�S�Q�Ɓj
�@
�@�@�E�@2�i�ߋ��A2�i�ߋ������ɂ��G���W���_�E���T�C�W���O
�@�@�E�@EGR���̌���AEGR����̍��x���A�ꕔ�Ԏ�ւ�LP-EGR�̗̍p
�@�@�E�@�R�����ˈ��͂̌���APCI�R�Ăł͈̔͊g�哙�̔R�����ː���̍��x��
�@�@�E�@�ꕔ�Ԏ�ւ̃^�[�{�R���p�E���h�V�X�e���̗̍p
�@�������Ȃ���A�����̋Z�p�ɂ����NO���̍팸�͉\�Ǝv�����A�R����\���Ɍ��シ��Z�p�Ƃ��Ă͋^��Ɏv��
��Z�p�̂悤���B
��Z�p�̂悤���B
| |
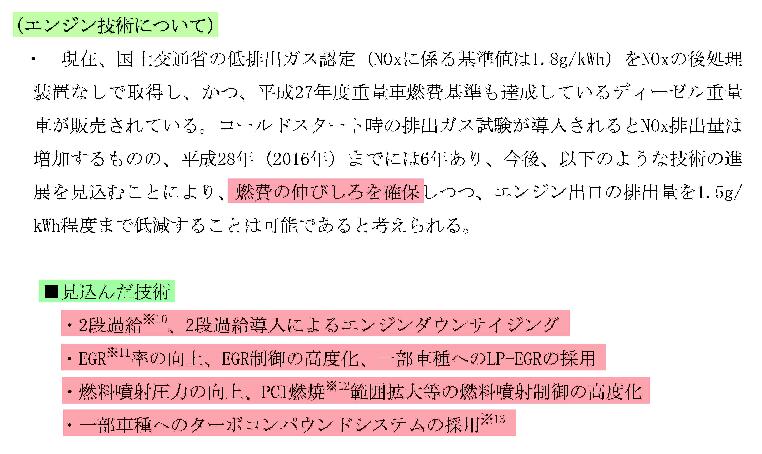 |
�@�������A�������R�c��E��C���������\�����\�ɂ́A�������L���Z�p��p���āu�R��̐L�т�����m�ہv
�Ɩ��L����Ă���B���̓��e���펯�I�ɔ��f����ƁA�������R�c��E��C������̎����Ԕr�o�K�X����
����̊w�ҁE���Ƃ́A������L�̋Z�p�ɂ���āu���Ȃ��Ƃ��T�p�[�Z���g���x�̏\���ȔR�����v�����҂�
�����Ǝ咣����Ă�����̂Ɛ��������B�������A�ȉ��Ɏ������悤�ɁA�M�҂͏�L�̉���̋Z�p���f�B�[�[���G���W
���̔R����\���Ɍ���ł���@�\��L���Ă��炸�A�����̔R����P�ɗL���ł���Ƃ��Ă��A���̔R����P�̊�����
�͋ɂ߂ď��Ȃ��Ǝv����̂ł���B���̗��R�ɂ��āA�ȉ��̕\�Q�V�ɂ܂Ƃ߂��̂Ō䗗�������������B
�Ɩ��L����Ă���B���̓��e���펯�I�ɔ��f����ƁA�������R�c��E��C������̎����Ԕr�o�K�X����
����̊w�ҁE���Ƃ́A������L�̋Z�p�ɂ���āu���Ȃ��Ƃ��T�p�[�Z���g���x�̏\���ȔR�����v�����҂�
�����Ǝ咣����Ă�����̂Ɛ��������B�������A�ȉ��Ɏ������悤�ɁA�M�҂͏�L�̉���̋Z�p���f�B�[�[���G���W
���̔R����\���Ɍ���ł���@�\��L���Ă��炸�A�����̔R����P�ɗL���ł���Ƃ��Ă��A���̔R����P�̊�����
�͋ɂ߂ď��Ȃ��Ǝv����̂ł���B���̗��R�ɂ��āA�ȉ��̕\�Q�V�ɂ܂Ƃ߂��̂Ō䗗�������������B
�� �u2�i�ߋ��̗̍p�ɂ��G���W���_�E���T�C�W���O�v�ɂ���
�@�Ȃ��A����ɔz�u�������^�Ƒ�^�̃^�[�{�ߋ��@���G���W���^�]�����ɂ���č쓮����ߋ��@���ւ����Q�i�ߋ��̈��ł����V�[�P ���V�����E�c�C���^�[�{�V�X�e���ɂ���ăG���W���̒ᑬ�g���N�̌��オ�\�ł��邪�A�G���W���{�̂̔R��͏����팸�ł�����x�ł���A �R��팸�̃����b�g�͋ɂ߂ď��Ȃ����̂ł���B�܂��A�V�[�P���V�����E�c�C���^�[�{�V�X�e���̃G���W���ᑬ�̃g���N�A�b�v�Ɋ�^����c�C ���^�[�{�̏��^�^�[�{�̑���ɓd���A�V�X�g�^�[�{�ߋ��@��p����V�X�e������Ă���Ă���B���́u�d���A�V�X�g�^�[�{�ߋ��@�{�^�[�{ �ߋ��@�̃V�X�e���v�ł́A�G���W���̒��]�ɂ�����g���N�̌���ɂ���ăg���b�N�̉^�]�����啝�Ɍ���ł��郁���b�g������B�������A�� �́u�d���A�V�X�g�^�[�{�ߋ��@�{�^�[�{�ߋ��@�̃V�X�e���v���܂߁A�����̉ߋ��@��p����V�[�P���V�����E�c�C���^�[�{�V�X�e���ɂ����� �R��팸�Ɍ��ʂ��F�߂���̂́A���s���ɂ�����ᑬ�M�A��̎g�p�p�x�̑����ɂ��͂��ȑ��s�R��̉��P�����ł���B�������� �āA�Q�i�ߋ��͏d�ʎԃ��[�h�R������P���đ�^�g���b�N��2015�N�x�d�ʎԔR����啝�ɏ���R����P�������ł���Z�p�Ŗ����� �Ƃ͖��炩�ł��� �@���݂ɁA�O�q�́u�P�P�|�V�D��@�s�ׂ̃V�X�e������ŔR������}���Ă����g���b�N���[�J�̔R����P�̍����v�̍��ɏڏq���Ă���悤 �ɁA�����U�����Ԃ́A���^�g���b�N�h�t�H���[�h���Q�i�V�[�P���V�����E�c�C���^�[�{�V�X�e���̂SHK1-TCS�G���W�����̗p���Ă��邪�A2011�N 6���ɂSHK1-TCS�G���W�����u��@�ȃG���W������v�ɂ���Ĕr�o�K�X�K���K���̃g���b�N����4�`5�{���x�̑��ʂ�NO���𐂂ꗬ���đ� �s�R��̌����}���Ă������Ƃ𓌋��s���Ȋw���������E�����A���y��ʏȂɈ�@�s�ׂ�ʕ��Ƃ̂��ƁB���̂��Ƃ���A�����Q�i�V �[�P���V�����E�c�C���^�[�{�V�X�e���̋Z�p���R�����ɗL���ł���Ȃ�A�����U�����Ԃ͂��̋Z�p���̗p�����SHK1-TCS�G���W���� �u��@�ȃG���W������v�ɂ���đ��s�R��̌����}��K�v�͑S���Ȃ��̂ł���B���̂悤�ɁA�����U�����Ԃ́A�����Q�i�V�[�P���V�����E�c �C���^�[�{�V�X�e�����̗p�����SHK1-TCS�G���W���ɂ����āA�u��@�ȃG���W������v�ɂ���đ��s�R��̌����}���Ă������Ƃ���A�Q�i�V �[�P���V�����E�c�C���^�[�{�V�X�e�����R�����̋@�\�����Z�p�ł��邱�Ƃ̏؋��𐢊ԂɍL�����m�����߂��悤�Ɏv����̂ł���B |
| �� �uEGR���̌���AEGR����̍��x���A�ꕔ�Ԏ�ւ�LP-EGR�̗̍p�v�ɂ���
�@�������R�c��E��C������̑�\�����\�ɋL�ڂ��ꂽ�uEGR���̌���AEGR����̍��x���A�ꕔ�Ԏ�ւ�LP-EGR�̋Z�p�̗p�� ���邪�A���̋Z�p���^�g���b�N�ɍ̗p���邱�Ƃɂ���āANO���̍팸���\�ł��邱�Ƃ́A�M�҂����ӂ���Ƃ��낾�B�������A���̋Z�p�ɂ�� ����^�g���b�N�̏d�ʎԃ��[�h�R������P����2015�N�x�d�ʎԔR����啝�ɏ���R����P������Ȃ��Ƃ͐�������܂ł��Ȃ��A�� �炩�Ȃ��Ƃł���B���������āA���̋Z�p�ɂ���đ�^�g���b�N�̏\���ȔR����P������Ȃ��Ƃɂ��Ă̐����͏ȗ����邱�Ƃɂ���B |
| �� �u�R�����ˈ��͂̌���APCI�R�Ăł͈̔͊g�哙�̔R�����ː���̍��x���v�ɂ���
�@�O�q�́u�P�S�|�P�@NEDO�̒����x�R�Đ���G���W�V�X�e���̌����J���ł́A�R����̑厸�s�v�ɂĐ��������ʂ�A�R�i�ߋ���300MP��
�̒������R�����˂́uPCI�R�Ắv��g�������Z�p��p�����R����P��NEDO�̌����J���ł́A2015�N�x�d�ʎԔR���ɑ��ĂQ��
�̔R����̌��ʂ�����Ă���B����ɂ�������炸�A�������R�c��E��C������̑�\�����\�ł́A�u�R�����ˈ��͂̌�
��APCI�R�Ăł͈̔͊g�哙�̔R�����ː���̍��x���v�ɂ���đ�^�g���b�N�̔R����オ�\�Ƃ̎�|�̋L�q���F�߂���B
�@�O�q���P�S�|�P����NEDO�̌����J���ł́A�����u�R�i�ߋ���300MP���̒������R�����˂�PCI�R�Ă�g�������Z�p�v�ł͑�^�g���b�N��
�R����オ����ƕ���Ă���ɂ�������炸�A���́u�Q�i�ߋ��ƒ������R�����˂�PCI�R�āv�̋Z�p���̗p���邱�Ƃɂ���đ�^�g���b
�N���u�R��̐L�т�����m�ہv���\�ƒ������R�c��E��C������̑�\�����\�ɂ͖��L����Ă���B�������R�c��E��C����
��̎����Ԕr�o�K�X���ψ���̊w�ҁE���Ƃ́A�����u�Q�i�ߋ��ƒ������R�����˂�PCI�R�āv�̋Z�p�̗̍p�ɂ���ăf�B�[�[���G��
�W���̏\���ȔR����P���\�Ǝ咣����Ă���悤�ł��邪�A�A�M�҂ɂ͂����̋Z�p�ɂ���ĔR����P�������ł��鍪���E���R���S����
���ł��Ȃ��̂ł���B�������R�c��E��C������̎����Ԕr�o�K�X���ψ���̊w�ҁE���Ƃ́ANEDO�́u�����x�R�Đ���G��
�W�V�X�e���̌����J���v�̌������ʂ̕���܂�Ƃ̌�ӌ����������Ȃ̂ł��낤���B���͂Ƃ�����A�����Ԕr�o�K�X���ψ���̊w
�ҁE���Ƃ�NEDO���u�R�i�ߋ���300MP���̒������R�����˂�PCI�R�Ă�g�������Z�p�v�ł̓f�B�[�[���G���W���̔R����P�Ɏ��s����
�������ʂ̕�����Ă���悤�ł���A���̗��R��m�肽�����̂ł���B
|
�� �u�ꕔ�Ԏ�ւ̃^�[�{�R���p�E���h�V�X�e���̗̍p�v�ɂ���
�@���������āA���̃^�[�{�R���p�E���h�̋Z�p�́A�R�����ł͖����A�����ő刳�͂��㏸�����邱�Ɩ����o�͂������ł����i�ł��邱�� ���ő�̓����ł���B�ȏ�̓��e���^�[�{�R���p�E���h�Z�p�ɂ��Ă̐��E�̑�^�g���b�N�ƊE�ɂ����錻��F���ł���B�����Č��݁A�{ ���{�A�f�g���C�g�f�B�[�[���̑�^�g���b�N�p�G���W���ɍ̗p����Ă���B �@���̂悤�ɁA�^�[�{�R���p�E���h���̗p������^�g���b�N���s�̂��Ă����C�O�̃g���b�N���[�J���u�^�[�{�R���p�E���h�̋Z�p�́A�R�����ł�
�����A�����ő刳�͂��㏸�����邱�Ɩ����o�͂������ł����i�ł���v�Ɛ������Ă���ɂ�������炸�A�������R�c��E��C������
�̑�\�����\�ł́A�^�[�{�R���p�E���h�̋Z�p���f�B�[�[���G���W���̔R����P�̋Z�p�̈�Ƃ��ċL�ڂ���Ă���̂ł���B�������R
�c��E��C������̎����Ԕr�o�K�X���ψ���̊w�ҁE���Ƃ́A�^�[�{�R���p�E���h�ł̏\���ȔR����P�������ł���V�����H�v
�┭�z�܂��̓A�C�f�A��������Ă���̂��낤���B���ɂ��̂悤�ȐV�����H�v�E���z�E�A�C�f�A���̓I�ȃG���W���Z�p���������ł���Ȃ�
�A����Ƃ���I���Ă��������������̂ł���B
�@�Ȃ��A�^�[�{�R���p�E���h����^�g���b�N�̏\���ȔR����P�̍���ȗ��R�ɂ��ẮA�^�[�{�R���p�E���h�ɂ���^�g���b�N�̏\���ȔR��
���P�͍���I������C���x�~�́A�f�B�[�[���r�C�K�X�̃G�l���M�[���u�̌����������̃y�[�W�ɏڏq���Ă���̂ŁA�䗗������
�������B
|
�@�ȏ�̂悤�ɁA2010�N�V��28�����\�̒������R�c��E��C���������\�����\�i�\�Q�T�Q�Ɓj�ɂ́A������
�R�c��̎����Ԕr�o�K�X���ψ���̊w�ҁE���Ƃ���^�g���b�N���[�J �S�Ђ��܂ގ����ԃ��[�J�ɑ��čs�����q
�A�����O��ʂ��ē���ꂽ�R����P�̋Z�p���u2�i�ߋ��v�A�uEGR���̌���i�ꕔ�ɂ�LP-EGR�̗p�j�v�A�u�R�����ˈ�
�͂̌����PCI�R�āv�A�u�^�[�{�R���p�E���h�v�̋Z�p�ł���B�������A�����̋Z�p�́A�������^�g���b�N�̏d�ʎԃ�
�[�h�R��܂��͎����s�R����P�������̋͂��ȔR����P�������҂ł��Ȃ��悤�ȁA�R����P�̖ʂł́u�K���N�^�Z
�p�v�܂��́u�|���R�c�Z�p�v�ƌ����Ă��ߌ��ł͖����悤�ȋZ�p�ł���B
�R�c��̎����Ԕr�o�K�X���ψ���̊w�ҁE���Ƃ���^�g���b�N���[�J �S�Ђ��܂ގ����ԃ��[�J�ɑ��čs�����q
�A�����O��ʂ��ē���ꂽ�R����P�̋Z�p���u2�i�ߋ��v�A�uEGR���̌���i�ꕔ�ɂ�LP-EGR�̗p�j�v�A�u�R�����ˈ�
�͂̌����PCI�R�āv�A�u�^�[�{�R���p�E���h�v�̋Z�p�ł���B�������A�����̋Z�p�́A�������^�g���b�N�̏d�ʎԃ�
�[�h�R��܂��͎����s�R����P�������̋͂��ȔR����P�������҂ł��Ȃ��悤�ȁA�R����P�̖ʂł́u�K���N�^�Z
�p�v�܂��́u�|���R�c�Z�p�v�ƌ����Ă��ߌ��ł͖����悤�ȋZ�p�ł���B
�@���̂悤�ɁA��\�����\�ɗ��ꂽ�Z�p�́A����̋Z�p���f�B�[�[���G���W���ł̖ڗ������R����オ�ł���@
�\��L���Ă��Ȃ����߁A�����̋Z�p���^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W���ɍ̗p���Ă��A�����̑�^�g���b�N������\
���ȔR�����͖w��NJ��҂ł��Ȃ����Ƃ����炩���B���{���\����G���W���W�̊w�ҁE���Ƃō\�����ꂽ��
���Ԕr�o�K�X����ψ����^�g���b�N���[�J �S�Ђ��܂ގ����ԃ��[�J�ɑ��čs�����q�A�����O��ʂ��ē���ꂽ
�R����P�̋Z�p������ɍ쐬�����������R�c��E��C���������\�����\�ł���Ȃ���A�c�O�Ȃ��ƂɁA��
�\�����\�ɗ��ꂽ�Z�p�ɂ���đ�^�g���b�N�́u�R��̐L�т���m�ہi���R�����j�v��搂��Ă��邱�Ƃ���f����
���f����ƁA���̗��ꂽ�Z�p�����p�������Ƃ��Ă��A��^�g���b�N�ł̔��X����R����P���������Ȃ����Ƃɂ�
��Ɨ����ł�����e�ł���B
�\��L���Ă��Ȃ����߁A�����̋Z�p���^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W���ɍ̗p���Ă��A�����̑�^�g���b�N������\
���ȔR�����͖w��NJ��҂ł��Ȃ����Ƃ����炩���B���{���\����G���W���W�̊w�ҁE���Ƃō\�����ꂽ��
���Ԕr�o�K�X����ψ����^�g���b�N���[�J �S�Ђ��܂ގ����ԃ��[�J�ɑ��čs�����q�A�����O��ʂ��ē���ꂽ
�R����P�̋Z�p������ɍ쐬�����������R�c��E��C���������\�����\�ł���Ȃ���A�c�O�Ȃ��ƂɁA��
�\�����\�ɗ��ꂽ�Z�p�ɂ���đ�^�g���b�N�́u�R��̐L�т���m�ہi���R�����j�v��搂��Ă��邱�Ƃ���f����
���f����ƁA���̗��ꂽ�Z�p�����p�������Ƃ��Ă��A��^�g���b�N�ł̔��X����R����P���������Ȃ����Ƃɂ�
��Ɨ����ł�����e�ł���B
�@���̂��Ƃ́A���̑�\�����\�����\���ꂽ2010�N�V��28���̎��_�ł́A�킪������^�g���b�N���[�J �S�Ђ��܂ގ�
���ԃ��[�J����{���\����G���W���W�̊w�ҁE���Ƃ��A��^�g���b�N�̏d�ʃ��[�h�R�������s�R��𐔃p�[
�Z���g���x�̌��オ���҂ł���Z�p���������o���Ă��Ȃ������؋��ł͂Ȃ����낤���B���̌�̎����ԃ��[�J�̕�
���\�⎩���ԋZ�p���ѓ��{�@�B�w��w�̍u�����e�����Ă��A���݂̂Ƃ���A��^�g���b�N�̏d�ʃ��[�h�R���
�����s�R��𐔃p�[�Z���g���x�̌��オ�����ł����Ƃ���Z�p�ɂ��Ă̔��\���F���ł���B���̂悤�ȏ���
���f����ƁA�M�����Ȃ����ł͂��邪�A�g���b�N���[�J�́A��^�g���b�N�̔R����P��ړI�Ƃ���Z�p�J���Ƃ��āA��
���_�ł́A�d�ʃ��[�h�R�������s�R��̉��P���P�������ɉ߂��Ȃ��Z�p�̊J���������Ɏ��{���Ă���̂ł��낤
���B���ɁA���ꂪ�����ł���A���Ƃ�����Ȃ��Ƃł���B
���ԃ��[�J����{���\����G���W���W�̊w�ҁE���Ƃ��A��^�g���b�N�̏d�ʃ��[�h�R�������s�R��𐔃p�[
�Z���g���x�̌��オ���҂ł���Z�p���������o���Ă��Ȃ������؋��ł͂Ȃ����낤���B���̌�̎����ԃ��[�J�̕�
���\�⎩���ԋZ�p���ѓ��{�@�B�w��w�̍u�����e�����Ă��A���݂̂Ƃ���A��^�g���b�N�̏d�ʃ��[�h�R���
�����s�R��𐔃p�[�Z���g���x�̌��オ�����ł����Ƃ���Z�p�ɂ��Ă̔��\���F���ł���B���̂悤�ȏ���
���f����ƁA�M�����Ȃ����ł͂��邪�A�g���b�N���[�J�́A��^�g���b�N�̔R����P��ړI�Ƃ���Z�p�J���Ƃ��āA��
���_�ł́A�d�ʃ��[�h�R�������s�R��̉��P���P�������ɉ߂��Ȃ��Z�p�̊J���������Ɏ��{���Ă���̂ł��낤
���B���ɁA���ꂪ�����ł���A���Ƃ�����Ȃ��Ƃł���B
�@�����Ƃ��A���̓��\�̍쐬�Ɍg�����������R�c��̎����Ԕr�o�K�X���ψ���̃����o�[�́A���{���\����
�悤���G���W���W����Ƃ���w�ҁE���Ƃł��邱�Ƃ���A���̓��\�ɗ��ꂽ������Z�p��p���Ă���^�g��
�b�N�̏d�ʎ҃��[�h�R�������s�̔R��\���Ɍ���ł��Ȃ����Ƃ𗝉��E�F������Ă���l�q���f����B���̏�
���Ƃ��ẮA���̓��\�ɗ��ꂽ�Z�p�ɂ��ẮA���X�Ɓu�R�����̋Z�p�v�Ƃ͋L�ڂ������u�R��̐L�т�����m
�ہv�ł���Z�p�Ƃ̋����قǂ̍T���߂ȕ\�����g���Ă���̂ł���B���̂��Ƃ́A���̓��\�ɗ��ꂽ�Z�p����
�p�������Ƃ��Ă��A�ɂ߂��͏��ȔR�����ɗ��܂邱�Ƃ��ÂɔF�߂Ă����Ɏv����̂ł���B
�悤���G���W���W����Ƃ���w�ҁE���Ƃł��邱�Ƃ���A���̓��\�ɗ��ꂽ������Z�p��p���Ă���^�g��
�b�N�̏d�ʎ҃��[�h�R�������s�̔R��\���Ɍ���ł��Ȃ����Ƃ𗝉��E�F������Ă���l�q���f����B���̏�
���Ƃ��ẮA���̓��\�ɗ��ꂽ�Z�p�ɂ��ẮA���X�Ɓu�R�����̋Z�p�v�Ƃ͋L�ڂ������u�R��̐L�т�����m
�ہv�ł���Z�p�Ƃ̋����قǂ̍T���߂ȕ\�����g���Ă���̂ł���B���̂��Ƃ́A���̓��\�ɗ��ꂽ�Z�p����
�p�������Ƃ��Ă��A�ɂ߂��͏��ȔR�����ɗ��܂邱�Ƃ��ÂɔF�߂Ă����Ɏv����̂ł���B
�@�ȏ�̂��Ƃ���A�������R�c��E��C���������\�����\���R����P�ɂ��Ă̍T���߂ȕ\���́A���̓��\
�쐬��S�����ꂽ�����Ԕr�o�K�X���ψ���̊w�ҁE���Ƃ��\�����\�ɗ��ꂽ�Z�p����^�g���b�N�̔��X
�����R����P�ł��邱�ƍl���ĊԈႢ�������悤���B�܂�A�\�����\���u�R��̐L�т�����m�ہv�̋L�q�́A�\����
�\�́u2�i�ߋ��v�A�uEGR���̌���i�ꕔ�ɂ�LP-EGR�̗p�j�v�A�u�R�����ˈ��͂̌����PCI�R�āv�A�u�^�[�{�R���p�E��
�h�v�̂��ꂼ��̋Z�p�̔R����P���ʂ͂P�������ł��邽�߁A�����̒��̉��ꂩ�̋Z�p�̎����������ʂ��߂�
�����ɔ��\����A��^�g���b�N�̏\���ȔR����オ����ł��邱�Ƃ����E�ؖ����ꂽ�ꍇ�ɂ��A�����Ԕr�o�K�X��
��ψ���̊w�ҁE���Ƃ��쐬�����\�����\�̓��e���傫�Ȍ�肪���������Ƃ̌���������咣���邽�߂̎��O
�̒P�Ȃ�A���o�C�H��i���ӔC����j�̋L�q�̂悤�ɂ��v����̂ł���B
�쐬��S�����ꂽ�����Ԕr�o�K�X���ψ���̊w�ҁE���Ƃ��\�����\�ɗ��ꂽ�Z�p����^�g���b�N�̔��X
�����R����P�ł��邱�ƍl���ĊԈႢ�������悤���B�܂�A�\�����\���u�R��̐L�т�����m�ہv�̋L�q�́A�\����
�\�́u2�i�ߋ��v�A�uEGR���̌���i�ꕔ�ɂ�LP-EGR�̗p�j�v�A�u�R�����ˈ��͂̌����PCI�R�āv�A�u�^�[�{�R���p�E��
�h�v�̂��ꂼ��̋Z�p�̔R����P���ʂ͂P�������ł��邽�߁A�����̒��̉��ꂩ�̋Z�p�̎����������ʂ��߂�
�����ɔ��\����A��^�g���b�N�̏\���ȔR����オ����ł��邱�Ƃ����E�ؖ����ꂽ�ꍇ�ɂ��A�����Ԕr�o�K�X��
��ψ���̊w�ҁE���Ƃ��쐬�����\�����\�̓��e���傫�Ȍ�肪���������Ƃ̌���������咣���邽�߂̎��O
�̒P�Ȃ�A���o�C�H��i���ӔC����j�̋L�q�̂悤�ɂ��v����̂ł���B
�@���̂悤�ɁA�������R�c��E��C����������\�����\�ɂ�NO���팸�ƔR��팸�̋Z�p�Ƃ��Đ������̐V�Z�p
������Ă��邪�A�����̐V�Z�p�́A����̋Z�p���R����P�̖ʂɊւ��Ă���^�g���b�N�̏d�ʎԃ��[�h�R��
�܂��͎����s�R��P�������̋͂��ȔR����P�������҂ł��Ȃ��̂ł���B���̂��߁A�������\�����\�ɋ������
��Ă���V�Z�p��p���Ă���^�g���b�N�̏\���ȏd�ʎԃ��[�h�R��܂��͎����s�R��̌��オ����Ȃ��Ƃ͖��炩
���B���̂��߁A�����A�������\�����\�ɋL�ڂ��ꂽ�V�Z�p��p���Ă���^�g���b�N�̏\���ȏd�ʎԃ��[�h�R��܂���
�����s�R��̌��オ����Ȃ��Ƃ��I�������ۂ̌�����̂悤�ɁA�������\�����\�ɂ́u��^�g���b�N�̏\���ȏd��
�ԃ��[�h�R��܂��͎����s�R��̌���v�Ƃ͋L�q�����A�R��ɂ��Ă͋ɂ߂čT���߂��u�R��̐L�т���m�ہv�ƋL
�q���Ă���̂ł͂Ȃ����낤���B
������Ă��邪�A�����̐V�Z�p�́A����̋Z�p���R����P�̖ʂɊւ��Ă���^�g���b�N�̏d�ʎԃ��[�h�R��
�܂��͎����s�R��P�������̋͂��ȔR����P�������҂ł��Ȃ��̂ł���B���̂��߁A�������\�����\�ɋ������
��Ă���V�Z�p��p���Ă���^�g���b�N�̏\���ȏd�ʎԃ��[�h�R��܂��͎����s�R��̌��オ����Ȃ��Ƃ͖��炩
���B���̂��߁A�����A�������\�����\�ɋL�ڂ��ꂽ�V�Z�p��p���Ă���^�g���b�N�̏\���ȏd�ʎԃ��[�h�R��܂���
�����s�R��̌��オ����Ȃ��Ƃ��I�������ۂ̌�����̂悤�ɁA�������\�����\�ɂ́u��^�g���b�N�̏\���ȏd��
�ԃ��[�h�R��܂��͎����s�R��̌���v�Ƃ͋L�q�����A�R��ɂ��Ă͋ɂ߂čT���߂��u�R��̐L�т���m�ہv�ƋL
�q���Ă���̂ł͂Ȃ����낤���B
���̂��Ƃ́A�����Ԕr�o�K�X���ψ���̊w�ҁE���Ƃ����\�����\�ɗ��ꂽ�������̐V�Z�p��p���Ă���^
�g���b�N�̔R����オ�ł��Ȃ����Ƃ�\�ߗ\���E�z�肵�Ă���悤�ɂ��v����̂ł���B���������āA��^�g���b�N�̏\
���ȏd�ʎԃ��[�h�R��܂��͎����s�R��̌���ɂ��ẮA�������R�c��E��C������̎����Ԕr�o�K�X
�Ɋւ�����\�����\�ɂ́A���݂̔R��Ɋւ���Z�p���𐳊m�ɋL�ڂ���Ƃ���A�u�����_�ł͑�^�g��
�b�N�̏d�ʎԃ��[�h�R�������s�R����\���Ɍ���ł���傽��Z�p���s���v�ƋL�q���ׂ��ƍl���邪�A�@��
�Ȃ��̂ł��낤���B����ɂ��Ă��A���̑��\�����\�ł́A�R����P�Ɋւ��Ă̋Z�p���̓��e���ӎ��I�ɔc�����h
���L�q�E���͂ƂȂ��Ă���悤�Ɏv�����A���̂悤�ȕ��ʂɂ����Ӑ}�E�ړI�́A��́A���Ȃ̂ł��낤���B
�g���b�N�̔R����オ�ł��Ȃ����Ƃ�\�ߗ\���E�z�肵�Ă���悤�ɂ��v����̂ł���B���������āA��^�g���b�N�̏\
���ȏd�ʎԃ��[�h�R��܂��͎����s�R��̌���ɂ��ẮA�������R�c��E��C������̎����Ԕr�o�K�X
�Ɋւ�����\�����\�ɂ́A���݂̔R��Ɋւ���Z�p���𐳊m�ɋL�ڂ���Ƃ���A�u�����_�ł͑�^�g��
�b�N�̏d�ʎԃ��[�h�R�������s�R����\���Ɍ���ł���傽��Z�p���s���v�ƋL�q���ׂ��ƍl���邪�A�@��
�Ȃ��̂ł��낤���B����ɂ��Ă��A���̑��\�����\�ł́A�R����P�Ɋւ��Ă̋Z�p���̓��e���ӎ��I�ɔc�����h
���L�q�E���͂ƂȂ��Ă���悤�Ɏv�����A���̂悤�ȕ��ʂɂ����Ӑ}�E�ړI�́A��́A���Ȃ̂ł��낤���B
�@
�@�ȏ�̂悤���������R�c��E��C����������\�����\�̔R��֘A�̋L�q�Ɋւ���M�҂̔ᔻ�ɑ��A����
���\�̍쐬���������Ԕr�o�K�X���ψ���̊w�ҁE���Ƃ���́A������\�����\�͕\��Ɏ�����Ă���ʂ�A
�u����̎����Ԕr�o�K�X�ጸ��̂�����ɂ��āi��\�����\�j�v�̔r�o�K�X�W�̓��\�ł���A�R��W�̓��\
�ł͂Ȃ��Ƃ̔��_���ꂻ���ł���B�����ł���Ȃ�A���̑�\�����\�͕\��ɖ��W�ȔR����P�Ɋւ�����e�̋L
�ڂ��s�v�ł��邱�ƂɂȂ�B�Ƃ��낪�A����܂ł̒����ɂ킽��f�B�[�[���G���W����NO���팸�̋Z�p�J���̗��j��
�����āA���C�C���^�[�N�����̋��C���䑕�u��A�fSCR�G�}���̔r�C�K�X�㏈�����u�ȊO�̔R�����ˎ������䓙
�̃G���W���{�̂�NO�����팸����Z�p�̏ꍇ�ɂ́A�w�Ǘ�O�Ȃ�NO���̒ጸ�ʂɔ�Ⴕ�ĔR��̈����������uNO����
�R��̃g���[�h�I�t�i���w���j�̊W�v�����邱�Ƃ��m�F����Ă���B
���\�̍쐬���������Ԕr�o�K�X���ψ���̊w�ҁE���Ƃ���́A������\�����\�͕\��Ɏ�����Ă���ʂ�A
�u����̎����Ԕr�o�K�X�ጸ��̂�����ɂ��āi��\�����\�j�v�̔r�o�K�X�W�̓��\�ł���A�R��W�̓��\
�ł͂Ȃ��Ƃ̔��_���ꂻ���ł���B�����ł���Ȃ�A���̑�\�����\�͕\��ɖ��W�ȔR����P�Ɋւ�����e�̋L
�ڂ��s�v�ł��邱�ƂɂȂ�B�Ƃ��낪�A����܂ł̒����ɂ킽��f�B�[�[���G���W����NO���팸�̋Z�p�J���̗��j��
�����āA���C�C���^�[�N�����̋��C���䑕�u��A�fSCR�G�}���̔r�C�K�X�㏈�����u�ȊO�̔R�����ˎ������䓙
�̃G���W���{�̂�NO�����팸����Z�p�̏ꍇ�ɂ́A�w�Ǘ�O�Ȃ�NO���̒ጸ�ʂɔ�Ⴕ�ĔR��̈����������uNO����
�R��̃g���[�h�I�t�i���w���j�̊W�v�����邱�Ƃ��m�F����Ă���B
�@���̂悤�ɁA�R���NO���r�o�Ƃ��g���[�h�I�t�i���w���j�̊W�����邽�߁A�d�ʎԁi���g���b�N���j��������
�R�c��E��C������́u����̎����Ԕr�o�K�X�ጸ��̂�����ɂ��āi��\�����\�j�v�̍ŏd�v�̓��e��
NOx�팸�̖ڕW���x�������Ȃɓ��\���邱�Ƃł��邪�A��\�����\�ł͔R����P�Ɋւ���Z�p����ʂɂ��Ă�
���y����Ă�����̂ƍl������B�������Ȃ���A���̑�\�����\�ł́A�u�R��̐L�т�����m�ہv������x�̔R���
�P�������҂ł��Ȃ��悤�Ȉ���Ȍ����̂���Z�p��������Ă��Ȃ����Ƃ́A�c�O�Ȃ��Ƃł���B�������A������
���R�c��E��C���������\�����\�i2010�N�V���j�ł��A���̂��ł��d�v�����ׂ��ߋ��̑攪�����\�i��2005�N
�S���j��NO������ڕW��0.23 g/kWh (���|�X�g�V�����K���l 0.7 g/kWh [�d�ʎ�2009�E2010�N�K��] �̂R���̂P�j��
�����ANO����0.4 g/kWh�̑啝�Ɋɘa����NO���r�o�l�����Ȃɓ��\���Ă���̂ł���B
�R�c��E��C������́u����̎����Ԕr�o�K�X�ጸ��̂�����ɂ��āi��\�����\�j�v�̍ŏd�v�̓��e��
NOx�팸�̖ڕW���x�������Ȃɓ��\���邱�Ƃł��邪�A��\�����\�ł͔R����P�Ɋւ���Z�p����ʂɂ��Ă�
���y����Ă�����̂ƍl������B�������Ȃ���A���̑�\�����\�ł́A�u�R��̐L�т�����m�ہv������x�̔R���
�P�������҂ł��Ȃ��悤�Ȉ���Ȍ����̂���Z�p��������Ă��Ȃ����Ƃ́A�c�O�Ȃ��Ƃł���B�������A������
���R�c��E��C���������\�����\�i2010�N�V���j�ł��A���̂��ł��d�v�����ׂ��ߋ��̑攪�����\�i��2005�N
�S���j��NO������ڕW��0.23 g/kWh (���|�X�g�V�����K���l 0.7 g/kWh [�d�ʎ�2009�E2010�N�K��] �̂R���̂P�j��
�����ANO����0.4 g/kWh�̑啝�Ɋɘa����NO���r�o�l�����Ȃɓ��\���Ă���̂ł���B
�@�������A������\�����\�ɂ����āA�攪�����\��NO������ڕW��َE���Ă��閾�m�ȍ�����������Ă��Ȃ�����
���A�M�҂ɂ͈ٗl�Ȃ��Ƃ̂悤�Ɏv���邪�A�@���Ȃ��̂ł��낤���B���̂悤�ɁA��\�����\�ł��A�d�ʎԁi���g���b�N
���j�̊ɂ�NO���r�o�l�\���A�Ȃ����ANO���r�o�ƃg���[�h�I�t�i���w���j�̊W������R��ɂ��āA�R��
���P�̌��ʂ����Ȃ��Z�p��K���ɐ��������Ă��邾���̂悤�ł���B���������āA���̑�\�����\�́A���Ƃ���
�e�����������R�c��E��C������������Ԕr�o�K�X�ጸ�Ɋւ��铚�\�ƌ����Ă��d���������̂ł͂Ȃ���
�낤���B���̂��߁A���̓��\�̍쐬�����������R�c��E��C������̎����Ԕr�o�K�X���ψ���̊w�ҁE���
�Ƃ̐l�B�ɂ͐^�ʖڂɔC�����ʂ������Ƃ���ӎv�E�ӗ~���Ȃ悤�Ɏv���邪�A���ۂ̂Ƃ���͔@���̂��̂ł���
�����B���R�̂��Ƃł͂��邪�A���̂悤�Ȗ��ӔC�Ƃ��v�����\�����\���쐬���������Ԕr�o�K�X���ψ���̊w
�ҁE���Ƃɂ́A�����Ԕr�o�K�X���ψ���̈ψ��C�p�̋Ɩ��ɌW��鑊���̕�V�������̔[�߂��ŋ�����x
�����Ă��锤���B����ɂ��Ă��A�[�Ŏ҂̈�l�Ƃ��ẮA���^���̔[���̂ł��Ȃ��v���������N����̂́A�M��
�����ł��낤���B
���A�M�҂ɂ͈ٗl�Ȃ��Ƃ̂悤�Ɏv���邪�A�@���Ȃ��̂ł��낤���B���̂悤�ɁA��\�����\�ł��A�d�ʎԁi���g���b�N
���j�̊ɂ�NO���r�o�l�\���A�Ȃ����ANO���r�o�ƃg���[�h�I�t�i���w���j�̊W������R��ɂ��āA�R��
���P�̌��ʂ����Ȃ��Z�p��K���ɐ��������Ă��邾���̂悤�ł���B���������āA���̑�\�����\�́A���Ƃ���
�e�����������R�c��E��C������������Ԕr�o�K�X�ጸ�Ɋւ��铚�\�ƌ����Ă��d���������̂ł͂Ȃ���
�낤���B���̂��߁A���̓��\�̍쐬�����������R�c��E��C������̎����Ԕr�o�K�X���ψ���̊w�ҁE���
�Ƃ̐l�B�ɂ͐^�ʖڂɔC�����ʂ������Ƃ���ӎv�E�ӗ~���Ȃ悤�Ɏv���邪�A���ۂ̂Ƃ���͔@���̂��̂ł���
�����B���R�̂��Ƃł͂��邪�A���̂悤�Ȗ��ӔC�Ƃ��v�����\�����\���쐬���������Ԕr�o�K�X���ψ���̊w
�ҁE���Ƃɂ́A�����Ԕr�o�K�X���ψ���̈ψ��C�p�̋Ɩ��ɌW��鑊���̕�V�������̔[�߂��ŋ�����x
�����Ă��锤���B����ɂ��Ă��A�[�Ŏ҂̈�l�Ƃ��ẮA���^���̔[���̂ł��Ȃ��v���������N����̂́A�M��
�����ł��낤���B
�@�Ƃ���ŁA���݂̍��y��ʏȂł́A�߂�������2015�N�x�d�ʎԔR�����X�ɋ��������Ă���������Ă���
�悤���B����ɂ�������炸�A���̑�\�����\�ɗ��ꂽNO���팸�Z�p�́A�u�R��̐L�т���m�ہv�ƋL�ڂ��ꂽ
�������^�g���b�N�̏d�ʎԃ��[�h�R��܂��͎����s�R����P�������̋͂��ȔR����P�������҂ł��Ȃ��悤�ȁA�R
����P�̖ʂł́u�K���N�^�Z�p�H�v�܂��́u�|���R�c�Z�p�H�v�����������Ă��Ȃ��悤���B���̂��Ƃ́A���̑�\����
�\�ɗ��ꂽNO���팸�Z�p�̊J���ɐ��������Ƃ��Ă��A������NO���K���ƔR��K���̗����ɓK���ł����^�g���b
�N�����p���ł��Ȃ��\���������ɂ���Ɛ��@�����B���̂悤�ɍl����ƁA�ߋ��̑攪�����\��NO������ڕW��
�َE����NO���팸��啝�Ɋɂ߂���\�����\�ł���ɂ�������炸�A���̑�\�����\�ɗ��ꂽNO���팸�̋Z
�p�́A�u�������v�̂悤���u�K���N�^�Z�p�H�v�܂��́u�|���R�c�Z�p�H�v�����������Ă��Ȃ��̂́A�₵������ł���B
�悤���B����ɂ�������炸�A���̑�\�����\�ɗ��ꂽNO���팸�Z�p�́A�u�R��̐L�т���m�ہv�ƋL�ڂ��ꂽ
�������^�g���b�N�̏d�ʎԃ��[�h�R��܂��͎����s�R����P�������̋͂��ȔR����P�������҂ł��Ȃ��悤�ȁA�R
����P�̖ʂł́u�K���N�^�Z�p�H�v�܂��́u�|���R�c�Z�p�H�v�����������Ă��Ȃ��悤���B���̂��Ƃ́A���̑�\����
�\�ɗ��ꂽNO���팸�Z�p�̊J���ɐ��������Ƃ��Ă��A������NO���K���ƔR��K���̗����ɓK���ł����^�g���b
�N�����p���ł��Ȃ��\���������ɂ���Ɛ��@�����B���̂悤�ɍl����ƁA�ߋ��̑攪�����\��NO������ڕW��
�َE����NO���팸��啝�Ɋɂ߂���\�����\�ł���ɂ�������炸�A���̑�\�����\�ɗ��ꂽNO���팸�̋Z
�p�́A�u�������v�̂悤���u�K���N�^�Z�p�H�v�܂��́u�|���R�c�Z�p�H�v�����������Ă��Ȃ��̂́A�₵������ł���B
�@���āA�������R�c��E��C���������\�����\���u�R��̐L�т�����m�ہv�Ɩ��L����Ă���Z�p�ƁA�O�q��
�u�P�S�|�P�v���Ɏ������uNEDO�̒����x�R�Đ���G���W�V�X�e���̌����J���v�ɐ��荞�܂ꂽ�Z�p�̔�r���ȉ��̕\
�Q�W�Ɏ������B
�u�P�S�|�P�v���Ɏ������uNEDO�̒����x�R�Đ���G���W�V�X�e���̌����J���v�ɐ��荞�܂ꂽ�Z�p�̔�r���ȉ��̕\
�Q�W�Ɏ������B
�\�Q�W�@�uNEDO�̒����x�R�Đ���G���W�V�X�e���̌����J���v�Ɓu�����R�c�����\�����\�v�Ƃ��Z�p�̔�r
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
�@���̕\�Q�W���疾�炩�Ȃ悤�ɁA�����R�c�����\�����\�ɗ��ꂽ�Z�p�́A�O�q�́u�P�S�|�P�v���Ɏ�����
2015�N�x�d�ʎԔR�������d�ʎԃ��[�h�R��Q�������������uNEDO�̒����x�R�Đ���G���W�V�X�e���̌�
���J���v�̋Z�p�ɁA�d�ʎԃ��[�h�R��̉��P���ʂ̏��Ȃ��uLow Pressure Loop (LPL)�����⎮EGR�N�[���v�Ɓu�^�[
�{�R���p�E���h�v���lj�����Ă��邾�����B���������āA�����R�c�����\�����\�ɗ��ꂽ�Z�p�ł́A�|�X�g�V
�����r�o�K�X�K���K���̑����̑�^�g���b�N���B�����Ă���2015�N�x�d�ʎԔR�����\���ɔR�������ł���
�����̂Ɨ\�z�����B����ɂ�������炸�A�������R�c��̎����Ԕr�o�K�X���ψ���̊w�ҁE���Ƃ́A����
���R�c�����\�����\�ɗ��ꂽ�Z�p�ɂ���āA���Ȃ��Ƃ��T�p�[�Z���g���x�̔R����P�������Ɋ��҂�����悤
�ȁu�R��̐L�т�����m�ہv�Ɩ��L����Ă���ɂł���B���̂悤�ɁA�����R�c�����\�����\�ɂ́A2015�N�x�d
�ʎԔR�����\���ɔR�������ł��Ȃ��Z�p����Ă���̂ł���B����ɂ�������炸�A������\�����\
�ɂ́A�����̗���Ă���Z�p�ɂ�����u�R��̐L�ё�m���v�ł���ƋL�ڂ���Ă��邱�Ƃ́A�M�҂ɂ͓���A��
���̂ł��Ȃ����Ƃ��B
2015�N�x�d�ʎԔR�������d�ʎԃ��[�h�R��Q�������������uNEDO�̒����x�R�Đ���G���W�V�X�e���̌�
���J���v�̋Z�p�ɁA�d�ʎԃ��[�h�R��̉��P���ʂ̏��Ȃ��uLow Pressure Loop (LPL)�����⎮EGR�N�[���v�Ɓu�^�[
�{�R���p�E���h�v���lj�����Ă��邾�����B���������āA�����R�c�����\�����\�ɗ��ꂽ�Z�p�ł́A�|�X�g�V
�����r�o�K�X�K���K���̑����̑�^�g���b�N���B�����Ă���2015�N�x�d�ʎԔR�����\���ɔR�������ł���
�����̂Ɨ\�z�����B����ɂ�������炸�A�������R�c��̎����Ԕr�o�K�X���ψ���̊w�ҁE���Ƃ́A����
���R�c�����\�����\�ɗ��ꂽ�Z�p�ɂ���āA���Ȃ��Ƃ��T�p�[�Z���g���x�̔R����P�������Ɋ��҂�����悤
�ȁu�R��̐L�т�����m�ہv�Ɩ��L����Ă���ɂł���B���̂悤�ɁA�����R�c�����\�����\�ɂ́A2015�N�x�d
�ʎԔR�����\���ɔR�������ł��Ȃ��Z�p����Ă���̂ł���B����ɂ�������炸�A������\�����\
�ɂ́A�����̗���Ă���Z�p�ɂ�����u�R��̐L�ё�m���v�ł���ƋL�ڂ���Ă��邱�Ƃ́A�M�҂ɂ͓���A��
���̂ł��Ȃ����Ƃ��B
�@�܂��A���̒������R�c��E��C���������\�����\�ɋL�ڂ��ꂽ�Z�p�Ƃقړ����Z�p��g�ݍ������G��
�W�����A�u��ʈ��S���������t�H�[�����Q�O�P�O�v�Ŕ��\�̘_���u�X�[�p�[�N���[���f�B�[�[���iSCD�j�G���W���ɂ���
��V�W�J�v�̘_���Ŕ��\����Ă���SCD�G���W���ł���B���̌�ʈ��S����������SCD�G���W���ɂ́A�u�Q�i�V�[
�P���V�����ߋ��@�v�{�u�r�M����V�X�e���v�{�u�������R�������[���v�̋Z�p���̗p����Ă����A����SCD�G���W���ɂ�
����2015�N�x�d�ʎԔR�����P�O�����R����サ�� 4.5 �����^���b�g���̏d�ʎԃ��[�h�R��̑�^�g���b�N�iGVW�Q
�T�g���j������23�N�x�������ł������ʈ��S�����������錾���Ă���B�����ȑO�̃e���r�R�}�[�V�����ŗL����
�Ȃ����u���Ȃ����Ȃ牎�ł��ł���v�Ƃ̗��s��́u���ȉ��v�Ɠ��l�ɁA�u2015�N�x�d�ʎԔR������̂P�O���̔R
�����̖ڕW���f����͉̂��ł��ł���v���Ƃł���A�u�ڕW�咣�����̖��ӔC�ȉ��v�Ƃ��`�e�������Ȃ�s�ׂł���B
���ɁA�l���ڕW���f�����ꍇ�́A���̖ڕW��B�����邱�Ƃ����h�Ȑl�Ԃ̏��B�P�Ȃ�ڕW�������f���āu������
����̊l���v��u���Ԃ̒��ځv�������W�߁A���̌�Ɂu�ق�i�_���}���j�����ߍ��ށv�̂́A���\�t�Ɖ���ς��Ȃ���
�����l�Ԃ̂��邱�Ƃł͂Ȃ����낤���B
�W�����A�u��ʈ��S���������t�H�[�����Q�O�P�O�v�Ŕ��\�̘_���u�X�[�p�[�N���[���f�B�[�[���iSCD�j�G���W���ɂ���
��V�W�J�v�̘_���Ŕ��\����Ă���SCD�G���W���ł���B���̌�ʈ��S����������SCD�G���W���ɂ́A�u�Q�i�V�[
�P���V�����ߋ��@�v�{�u�r�M����V�X�e���v�{�u�������R�������[���v�̋Z�p���̗p����Ă����A����SCD�G���W���ɂ�
����2015�N�x�d�ʎԔR�����P�O�����R����サ�� 4.5 �����^���b�g���̏d�ʎԃ��[�h�R��̑�^�g���b�N�iGVW�Q
�T�g���j������23�N�x�������ł������ʈ��S�����������錾���Ă���B�����ȑO�̃e���r�R�}�[�V�����ŗL����
�Ȃ����u���Ȃ����Ȃ牎�ł��ł���v�Ƃ̗��s��́u���ȉ��v�Ɠ��l�ɁA�u2015�N�x�d�ʎԔR������̂P�O���̔R
�����̖ڕW���f����͉̂��ł��ł���v���Ƃł���A�u�ڕW�咣�����̖��ӔC�ȉ��v�Ƃ��`�e�������Ȃ�s�ׂł���B
���ɁA�l���ڕW���f�����ꍇ�́A���̖ڕW��B�����邱�Ƃ����h�Ȑl�Ԃ̏��B�P�Ȃ�ڕW�������f���āu������
����̊l���v��u���Ԃ̒��ځv�������W�߁A���̌�Ɂu�ق�i�_���}���j�����ߍ��ށv�̂́A���\�t�Ɖ���ς��Ȃ���
�����l�Ԃ̂��邱�Ƃł͂Ȃ����낤���B
�@���̂悤�ɁA��ʈ��S���������ɂ����镽��23�N�x�́u�X�[�p�[�N���[���f�B�[�[���iSCD�j�G���W���v�̌����v��
�W�F�N�g�ł́A�uSCD�G���W���ɂ����2015�N�x�d�ʎԔR�����P�O�����R����サ�� 4.5 �����^���b�g���̏d�ʎԃ�
�[�h�R��̑�^�g���b�N�iGVW�Q�T�g���j�������v����Ƃ̗E�܂����ڕW���f���Ă��邪�A���̖ڕW��B�����邱�Ƃ͐�
�ɖ����ł���ƕM�҂ɂ͎v����̂ł���B����ɂ��Ă̏ڍׂ́A�O�q�́u�P�S�|�S�D��ʌ��̽��߰�ذ��ި���
ٴݼ�����̔R�����́A���s�̗\���v�̍��ɏڏq���Ă���̂ŁA�䗗�������������B
�W�F�N�g�ł́A�uSCD�G���W���ɂ����2015�N�x�d�ʎԔR�����P�O�����R����サ�� 4.5 �����^���b�g���̏d�ʎԃ�
�[�h�R��̑�^�g���b�N�iGVW�Q�T�g���j�������v����Ƃ̗E�܂����ڕW���f���Ă��邪�A���̖ڕW��B�����邱�Ƃ͐�
�ɖ����ł���ƕM�҂ɂ͎v����̂ł���B����ɂ��Ă̏ڍׂ́A�O�q�́u�P�S�|�S�D��ʌ��̽��߰�ذ��ި���
ٴݼ�����̔R�����́A���s�̗\���v�̍��ɏڏq���Ă���̂ŁA�䗗�������������B
�@�����͌����Ă��A�������R�c��E��C���������\�����\�ɗ��ꂽ�Z�p�̒��ɂ͔R����P�̉\����
����Z�p���S�������킯�ł͂Ȃ��B�h�����ĔR�����̉\��������ƕM�҂��v���Z�p�́A�G���W���_�E���T�C�W��
�O�ƃ^�[�{�R���p�E���h�V�X�e���ł͂Ȃ����낤���B�������A�����̋Z�p�ɂ��Ă��A�\���ȔR����P���\�ƌ���
��Z�p�ł͂Ȃ��ƍl������B�悸�A�G���W���_�E���T�C�W���O�́A�P�P�|�S���Ő��������悤�ɁA�r�C�u���[�L�̐���
�͂̕s����s���\�̒ቺ���������߁A��^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W���ł͑啝�Ȕr�C�ʂ�����������ł���B
���������āA��^�g���b�N�Ƃ��Ă̏\���ȑ��s���\������Ȃ���G���W���_�E���T�C�W���O�ɂ���ď\���ɔR�������
�ƃg���b�N�̍������s���\���m�ۂ��邱�Ƃ́A�ɂ߂ē���B�����āA���ɁA�^�[�{�R���p�E���h�V�X�e�����́A�O�q��
�\�S�Ɏ������悤�ɃG���W������������ 0�`1.5%���x�̔R����P����邾���ł���B���̂��߁A�^�[�{�R���p�E
���h�V�X�e���ł��d�ʎԃ��[�h�R��l�̉��P�́A�����ח̈�ɂ�����R����P�̔����ȉ��A����0�`0.7���ȉ���
���x���Ó��ƍl������B���̂��߁A�^�[�{�R���p�E���h�ɂ��d�ʎԃ��[�h�R��̉��P�́A�^�[�{�R���p�E���h�ɂ�
���^�g���b�N�̏\���ȔR����P�͍���I�ɏڏq���Ă���悤�ɁA�傫�����ς����ĂP�������̋͂��ȉ��P�ɗ���
����̂Ɛ��������B
����Z�p���S�������킯�ł͂Ȃ��B�h�����ĔR�����̉\��������ƕM�҂��v���Z�p�́A�G���W���_�E���T�C�W��
�O�ƃ^�[�{�R���p�E���h�V�X�e���ł͂Ȃ����낤���B�������A�����̋Z�p�ɂ��Ă��A�\���ȔR����P���\�ƌ���
��Z�p�ł͂Ȃ��ƍl������B�悸�A�G���W���_�E���T�C�W���O�́A�P�P�|�S���Ő��������悤�ɁA�r�C�u���[�L�̐���
�͂̕s����s���\�̒ቺ���������߁A��^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W���ł͑啝�Ȕr�C�ʂ�����������ł���B
���������āA��^�g���b�N�Ƃ��Ă̏\���ȑ��s���\������Ȃ���G���W���_�E���T�C�W���O�ɂ���ď\���ɔR�������
�ƃg���b�N�̍������s���\���m�ۂ��邱�Ƃ́A�ɂ߂ē���B�����āA���ɁA�^�[�{�R���p�E���h�V�X�e�����́A�O�q��
�\�S�Ɏ������悤�ɃG���W������������ 0�`1.5%���x�̔R����P����邾���ł���B���̂��߁A�^�[�{�R���p�E
���h�V�X�e���ł��d�ʎԃ��[�h�R��l�̉��P�́A�����ח̈�ɂ�����R����P�̔����ȉ��A����0�`0.7���ȉ���
���x���Ó��ƍl������B���̂��߁A�^�[�{�R���p�E���h�ɂ��d�ʎԃ��[�h�R��̉��P�́A�^�[�{�R���p�E���h�ɂ�
���^�g���b�N�̏\���ȔR����P�͍���I�ɏڏq���Ă���悤�ɁA�傫�����ς����ĂP�������̋͂��ȉ��P�ɗ���
����̂Ɛ��������B
�@�������Ȃ���A���̃^�[�{�R���p�E���h���^�g���b�N�p�G���W���ɍ̗p�����ꍇ�ɁA�^�[�{�R���p�E���h�ł̔r�C�K
�X�G�l���M�[�̉�����������サ�A�^�[�{�R���p�E���h�ɂ���đ�^�g���b�N�̔R����\���ɉ��P�ł��钍�ڂ��ׂ�
���@�����݂���B���̕��@�́A�C���x�~�́A�f�B�[�[���r�C�K�X�̃G�l���M�[���u�̌����������ɏڏq���Ă�
��悤�ɁA��^���b�N�̑��s�ő��p�����f�B�[�[���f�B�[�[���G���W���̕������^�]���̔r�C�K�X���x�̍�����
��}�邱�Ƃ��K�v�ł���B���̃G���W�����������̔r�C�K�X���x�̍�������}����@�Ƃ��āA�M�Ғ�Ă�2�^�[�{
�ߋ��@�������C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p��p���邱�Ƃ��L���ł���B������C���x�~�G
���W���i�������J2005-54771�j�̂Q��̃^�[�{�ߋ��@�̂��ꂼ��̔r�C�^�[�r���̔r�C�K�X�o���̊e�X�ɉ���^�[
�r��������V�X�e���A�����A[�Q�^�[�{�ߋ��@�������C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j]��[�Q�^�[�{�R���p
�E���h]��g�ݍ��킹�����ʂȃ^�[�{�R���p�E���h�V�X�e���ł���B���̓��ʂ��^�[�{�R���p�E���h�V�X�e����p���邱
�Ƃɂ���ď��߂ă^�[�{�R���p�E���h�ɂ���^�g���b�N�̏\���ȑ��s�R��i��JE05���[�h�R��A�d�ʎԃ��[�h�R��
���j�����P�ł���ƍl������B
�X�G�l���M�[�̉�����������サ�A�^�[�{�R���p�E���h�ɂ���đ�^�g���b�N�̔R����\���ɉ��P�ł��钍�ڂ��ׂ�
���@�����݂���B���̕��@�́A�C���x�~�́A�f�B�[�[���r�C�K�X�̃G�l���M�[���u�̌����������ɏڏq���Ă�
��悤�ɁA��^���b�N�̑��s�ő��p�����f�B�[�[���f�B�[�[���G���W���̕������^�]���̔r�C�K�X���x�̍�����
��}�邱�Ƃ��K�v�ł���B���̃G���W�����������̔r�C�K�X���x�̍�������}����@�Ƃ��āA�M�Ғ�Ă�2�^�[�{
�ߋ��@�������C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p��p���邱�Ƃ��L���ł���B������C���x�~�G
���W���i�������J2005-54771�j�̂Q��̃^�[�{�ߋ��@�̂��ꂼ��̔r�C�^�[�r���̔r�C�K�X�o���̊e�X�ɉ���^�[
�r��������V�X�e���A�����A[�Q�^�[�{�ߋ��@�������C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j]��[�Q�^�[�{�R���p
�E���h]��g�ݍ��킹�����ʂȃ^�[�{�R���p�E���h�V�X�e���ł���B���̓��ʂ��^�[�{�R���p�E���h�V�X�e����p���邱
�Ƃɂ���ď��߂ă^�[�{�R���p�E���h�ɂ���^�g���b�N�̏\���ȑ��s�R��i��JE05���[�h�R��A�d�ʎԃ��[�h�R��
���j�����P�ł���ƍl������B
�@�Ƃ���ŁA�������R�c��E��C���������\�����\�Ɏ�����Ă����Z�p�̒��ɂ͔R�����˂̍������ɔ�����
�������̑����ɂ���ĔR�������������Z�p���܂܂�Ă���B���������āA�������R�c��E��C���������\
�����\�Ɏ�����Ă����Z�p�ɂ���ĉ��ɋ͂��ȔR����P�������ł����Ƃ��Ă��A�G���W���R��̑���̌덷�͈͂�
����P���ɂ������Ȃ����X����R����P�ł͂Ȃ����ƍl���Ă���B���������āA�����̋Z�p�ɂ���āu�R��̐L�т�
����m�ہv���邱�Ƃ��ł���Ƃ���\�����\���L�ڂ́A�M�҂ɂ͖��炩�Ɂu�����߂��I�v�̂悤�Ɏv����̂ł���B��
���āA�������R�c��E��C���������\�����\���u�R��̐L�т�����m�ہv����ƋL�q�������̂ł���A����
�Z�p�����̒P�Ƃ̗̍p�����ꍇ�ł��T�`�P�O���̏d�ʎԃ��[�h�R��̉��P�������߂��C���x�~�G���W���i�������J
2005-54771�j�������邱�Ƃ��s���ł͂Ȃ����낤���B�������A�����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p
�ƕ���ɔz�u���������̃^�[�{�R���p�E���h�V�X�e���̋Z�p��g�������ꍇ�ɂ́A�X�ɃG���W���̕������^�]��
���r�C�K�X�̃G�l���M�[���^�[�{�R���p�E���h�ʼn������ۂ̉���^�[�r���̔M����������ł��邽�߁A�^�[�{�R��
�p�E���h�ɂ���^�g���b�N�̔R����\���ɉ��P�ł�����ʂ�����̂��B�u�����s������v�Ƃ́A���ɂ��̂悤�Ȃ��Ƃ�
�w���̂ł͂Ȃ����낤���B
�������̑����ɂ���ĔR�������������Z�p���܂܂�Ă���B���������āA�������R�c��E��C���������\
�����\�Ɏ�����Ă����Z�p�ɂ���ĉ��ɋ͂��ȔR����P�������ł����Ƃ��Ă��A�G���W���R��̑���̌덷�͈͂�
����P���ɂ������Ȃ����X����R����P�ł͂Ȃ����ƍl���Ă���B���������āA�����̋Z�p�ɂ���āu�R��̐L�т�
����m�ہv���邱�Ƃ��ł���Ƃ���\�����\���L�ڂ́A�M�҂ɂ͖��炩�Ɂu�����߂��I�v�̂悤�Ɏv����̂ł���B��
���āA�������R�c��E��C���������\�����\���u�R��̐L�т�����m�ہv����ƋL�q�������̂ł���A����
�Z�p�����̒P�Ƃ̗̍p�����ꍇ�ł��T�`�P�O���̏d�ʎԃ��[�h�R��̉��P�������߂��C���x�~�G���W���i�������J
2005-54771�j�������邱�Ƃ��s���ł͂Ȃ����낤���B�������A�����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p
�ƕ���ɔz�u���������̃^�[�{�R���p�E���h�V�X�e���̋Z�p��g�������ꍇ�ɂ́A�X�ɃG���W���̕������^�]��
���r�C�K�X�̃G�l���M�[���^�[�{�R���p�E���h�ʼn������ۂ̉���^�[�r���̔M����������ł��邽�߁A�^�[�{�R��
�p�E���h�ɂ���^�g���b�N�̔R����\���ɉ��P�ł�����ʂ�����̂��B�u�����s������v�Ƃ́A���ɂ��̂悤�Ȃ��Ƃ�
�w���̂ł͂Ȃ����낤���B
�@�Ƃ��낪�A2010�N�V��28���ɔ��\���ꂽ�������R�c��E��C���������\�����\�ł́A�f�B�[�[���G���W����
�R����\���Ɍ���ł���@�\���Ȃ��Z�p��������Ă��邽�߁A�����̃f�B�[�[���G���W���̔R����P�͖w���
���҂ł��Ȃ��B����ɂ�������炸�A�u�R��̐L�т�����m�ہv�Ɠ��X�ƋL�q����Ă��邱�Ƃ́A�P�ɓǎ҂�f�킷��
���ł͂Ȃ����Ǝv����̂ł���B�������R�c��̎����Ԕr�o�K�X���ψ���̊w�ҁE���Ƃ́A������
�R�c��E��C���������\�����\�ɋL�ڂ���Ă���u2�i�ߋ��v�A�uEGR���̌���i�ꕔ�ɂ�LP-EGR��
�p�j�v�A�u�R�����ˈ��͂̌����PCI�R�āv�A�u�^�[�{�R���p�E���h�v�̋Z�p�����p�����邾���ŁA�����̑�^�f
�B�[�[���g���b�N�ł͍Œ�ł�2015�N�x�d�ʎԔR���ɑ��ā{�T�����x�̔R����オ�����ł���Ɩ{�S
����M�����Ă���̂ł��낤���B���̂悤�ɂ͎v���Ȃ��̂́A�߂������ȁA�M�҂���w��˂̏��Ȃł��낤���B
�R����\���Ɍ���ł���@�\���Ȃ��Z�p��������Ă��邽�߁A�����̃f�B�[�[���G���W���̔R����P�͖w���
���҂ł��Ȃ��B����ɂ�������炸�A�u�R��̐L�т�����m�ہv�Ɠ��X�ƋL�q����Ă��邱�Ƃ́A�P�ɓǎ҂�f�킷��
���ł͂Ȃ����Ǝv����̂ł���B�������R�c��̎����Ԕr�o�K�X���ψ���̊w�ҁE���Ƃ́A������
�R�c��E��C���������\�����\�ɋL�ڂ���Ă���u2�i�ߋ��v�A�uEGR���̌���i�ꕔ�ɂ�LP-EGR��
�p�j�v�A�u�R�����ˈ��͂̌����PCI�R�āv�A�u�^�[�{�R���p�E���h�v�̋Z�p�����p�����邾���ŁA�����̑�^�f
�B�[�[���g���b�N�ł͍Œ�ł�2015�N�x�d�ʎԔR���ɑ��ā{�T�����x�̔R����オ�����ł���Ɩ{�S
����M�����Ă���̂ł��낤���B���̂悤�ɂ͎v���Ȃ��̂́A�߂������ȁA�M�҂���w��˂̏��Ȃł��낤���B
�@�܂��A�������R�c��E��C���������\�����\�ł��A�G���W���o����NO���r�o�ʁiWHTC�r�o�K�X�����@�j��
1.5g/kWh���x�܂Œጸ������ŔA�fSCR�G�}����NO���㏈���Z�p�ɂ���āA�u�㏈�����u�ւ̉ߓx�Ȉˑ�������A
���̏����z�b�g�X�^�[�g���A�R�[���h�X�^�[�g���̕��ρi�R�[���h�X�^�[�g�䗦14���j��75%���x�Ƃ��邱�Ƃ͉\��
����ƍl������B�v�ƋL�ڂ���Ă���B�܂�A2016�N�Ɏ��{���\�肳��Ă��鎟����NO���ጸ�ڕW�l�͎��́i�P�j
���ŎZ�o���ꂽ�Ƃ̂��Ƃł���B
1.5g/kWh���x�܂Œጸ������ŔA�fSCR�G�}����NO���㏈���Z�p�ɂ���āA�u�㏈�����u�ւ̉ߓx�Ȉˑ�������A
���̏����z�b�g�X�^�[�g���A�R�[���h�X�^�[�g���̕��ρi�R�[���h�X�^�[�g�䗦14���j��75%���x�Ƃ��邱�Ƃ͉\��
����ƍl������B�v�ƋL�ڂ���Ă���B�܂�A2016�N�Ɏ��{���\�肳��Ă��鎟����NO���ጸ�ڕW�l�͎��́i�P�j
���ŎZ�o���ꂽ�Ƃ̂��Ƃł���B
�@�@�i�G���W���o���̔r�o�ʂ�1.5g/kWh���x�j�~�i�A�fSCR�G�}����75���̍팸�j��0.375g/kWh�@�E�E�E�E�E�i�P�j
�@���̌��ʂ���ɁA2010�N�V��28�����\�̒������R�c��E��C������́u����̎����Ԕr�o�K�X�ጸ��
��̂�����ɂ��āi��\�����\�j�v�ł́A��L���i�P�j���ŎZ�o���ꂽ0.375g/kWh�̐��l����ɁA2016�N��
���{���\�肳��Ă��鎟����NO���ጸ�ڕW�l�́u0.4g/kWh�v�iWHTC�r�o�K�X�����@�j�Ɍ������ꂽ�Ƃ̂���
�ł���B
��̂�����ɂ��āi��\�����\�j�v�ł́A��L���i�P�j���ŎZ�o���ꂽ0.375g/kWh�̐��l����ɁA2016�N��
���{���\�肳��Ă��鎟����NO���ጸ�ڕW�l�́u0.4g/kWh�v�iWHTC�r�o�K�X�����@�j�Ɍ������ꂽ�Ƃ̂���
�ł���B
�@���̂悤�ɁA2010�N�V���̒������R�c�����\�����\�ɂ����āA�������̑�^�g���b�N�ɑ���2016�N��NO��
�� 0.4 g/kWh�̋K����������邱�Ƃ����\����Ă���B�������A�}�Q�Q�|�P����ѐ}�Q�Q�|�Q�O�Ɏ��������{�A�č��A��
�B�̏��p��(�ԗ����d��3.5����)��NO����PM�̋K�������̕ϑJ������Ɩ��炩�Ȃ悤�ɁA�č��ł́A����2010�N��NO
�� �� 0.27 g/kWh�ɋK�����������{����Ă���̂��B�������A���{�ł́A2016�N�ɂ����NO���� 0.4 g/kWh��NO���K��
�����������ɉ߂��Ȃ����Ƃ��A�������R�c�����\�����\�Ŕ��\���ꂽ�̂ł���B���������āA2016�N��NO��
�� 0.4 g/kWh�̋K�����������{���ꂽ���_�ł��A���{�ł͌��݂��č���NO�� �� 0.27 g/kWh�̋K�����������Ɋ�
��NO���K�������{���ꑱ������悤���B
�� 0.4 g/kWh�̋K����������邱�Ƃ����\����Ă���B�������A�}�Q�Q�|�P����ѐ}�Q�Q�|�Q�O�Ɏ��������{�A�č��A��
�B�̏��p��(�ԗ����d��3.5����)��NO����PM�̋K�������̕ϑJ������Ɩ��炩�Ȃ悤�ɁA�č��ł́A����2010�N��NO
�� �� 0.27 g/kWh�ɋK�����������{����Ă���̂��B�������A���{�ł́A2016�N�ɂ����NO���� 0.4 g/kWh��NO���K��
�����������ɉ߂��Ȃ����Ƃ��A�������R�c�����\�����\�Ŕ��\���ꂽ�̂ł���B���������āA2016�N��NO��
�� 0.4 g/kWh�̋K�����������{���ꂽ���_�ł��A���{�ł͌��݂��č���NO�� �� 0.27 g/kWh�̋K�����������Ɋ�
��NO���K�������{���ꑱ������悤���B
�@
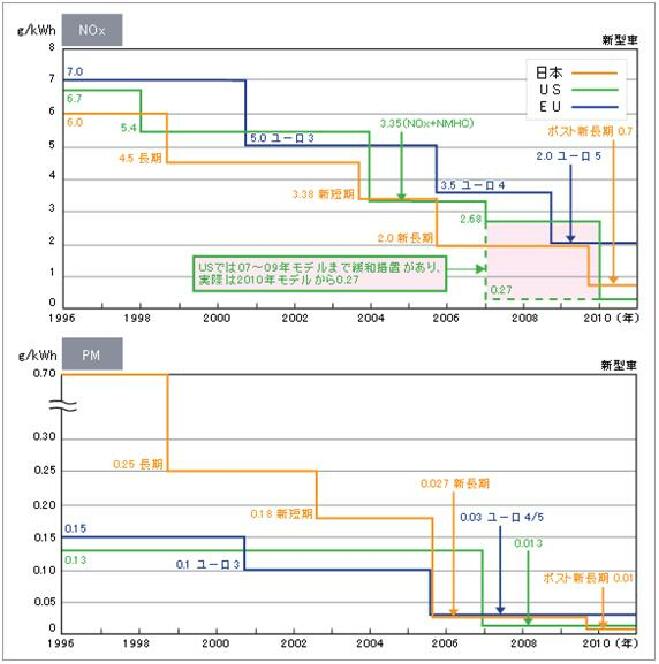
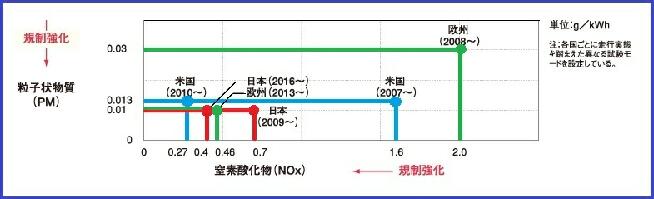
�@���݂ɁA���̒������R�c�2010�N�V������\�����\�����\����2016�N�Ɏ��{�\���NO�� �� 0.4 g/kWh�̋K
�������́A2005�N�ɔ��\���ꂽ�攪�����\�ɋL�ڂ���Ă��鏫����NO���팸�̖ڈ��Ƃ��Ă�NO���팸������ڕW
�ł���0.7 g/kWh�� 1/3���x�i���@0.23�@g/kWh���x���j�����S�ɖ������Ă���ł���B�����āA��\�����\�ɂ́A�攪
�����\�ɖ��L���ꂽ������NO���팸�̖ڈ��Ƃ���NO���팸������ڕW�iNO����0.23g/kWh�j�̂ɂ����������Ƃ�
�v���闝�R�����X�Ɨ���Ă���̂ł���B���̂悤�ɁA�攪�����\�ɖ��L���ꂽ������NO���팸������ڕW
�iNO����0.23g/kWh�j����啝�Ɋɘa����Ă���̂ł���B���̑傫���ɘa���ꂽ������NO���K���l���@���Ȃ鍪����
�������R�c�����\�����\�œ��\���ꂽ�̂��ɂ��āA�{���̗��R��m�肽���Ƃ���ł���B
�������́A2005�N�ɔ��\���ꂽ�攪�����\�ɋL�ڂ���Ă��鏫����NO���팸�̖ڈ��Ƃ��Ă�NO���팸������ڕW
�ł���0.7 g/kWh�� 1/3���x�i���@0.23�@g/kWh���x���j�����S�ɖ������Ă���ł���B�����āA��\�����\�ɂ́A�攪
�����\�ɖ��L���ꂽ������NO���팸�̖ڈ��Ƃ���NO���팸������ڕW�iNO����0.23g/kWh�j�̂ɂ����������Ƃ�
�v���闝�R�����X�Ɨ���Ă���̂ł���B���̂悤�ɁA�攪�����\�ɖ��L���ꂽ������NO���팸������ڕW
�iNO����0.23g/kWh�j����啝�Ɋɘa����Ă���̂ł���B���̑傫���ɘa���ꂽ������NO���K���l���@���Ȃ鍪����
�������R�c�����\�����\�œ��\���ꂽ�̂��ɂ��āA�{���̗��R��m�肽���Ƃ���ł���B
�@�č������啝�Ɋɂ�NO���K�������{�Ōp�����Ď��{����邱�Ƃɂ��A���{�̃g���b�N���[�J�͕č��̃g���b�N���[
�J����NO���팸�̋Z�p�J�����ߖ�ł��邱�Ƃ͖��炩���B����NO���팸�̌��������̍팸�ɂ���ĔP�o���ꂽ
�����͑S�ė��v�Ƃ��Čv��ł��邽�߁A���{�̃g���b�N���[�J�͕č��̃g���b�N���[�J�������v����e�ՂɌ��コ��
�邱�Ƃ��\�Ȍo�c������ɓ��ꂽ���ƂɂȂ�B���̂��߁A2010�N�V���ɒ������R�c����\������\�����\
��NO�� �� 0.4 g/kWh�̋K�������i2016�N���{�\��j���m�������{�̃g���b�N���[�J�̌o�c�����́A���{�⒆����
�R�c���NO���팸�̋Z�p�J����̐ߖ�ɂ�闘�v����̑��蕨�������Ƃ��āA���에�����Ċ�̂ł͂Ȃ�
���낤���B�������A��ʂ̍����́A�č�����NO���K�����ɂ����߂�NO���Z�x�̍�����C���ɔ����ꑱ������f��
��邱�ƂɂȂ�̂��B
�J����NO���팸�̋Z�p�J�����ߖ�ł��邱�Ƃ͖��炩���B����NO���팸�̌��������̍팸�ɂ���ĔP�o���ꂽ
�����͑S�ė��v�Ƃ��Čv��ł��邽�߁A���{�̃g���b�N���[�J�͕č��̃g���b�N���[�J�������v����e�ՂɌ��コ��
�邱�Ƃ��\�Ȍo�c������ɓ��ꂽ���ƂɂȂ�B���̂��߁A2010�N�V���ɒ������R�c����\������\�����\
��NO�� �� 0.4 g/kWh�̋K�������i2016�N���{�\��j���m�������{�̃g���b�N���[�J�̌o�c�����́A���{�⒆����
�R�c���NO���팸�̋Z�p�J����̐ߖ�ɂ�闘�v����̑��蕨�������Ƃ��āA���에�����Ċ�̂ł͂Ȃ�
���낤���B�������A��ʂ̍����́A�č�����NO���K�����ɂ����߂�NO���Z�x�̍�����C���ɔ����ꑱ������f��
��邱�ƂɂȂ�̂��B
�@���̂悤�ɁA2016�N�̓��{�̎����K���ɂ����Ă���^�g���b�N��NO���K�����č������啝�Ɋɘa����Ă���Ƃ���
������ƁA���{�i�����ȁE���y��ʏȁj�̊����⒆�����R�c��̎����Ԕr�o�K�X���ψ���̊w�ҁE���Ƃ�
�l�B�́A�g���b�N���[�J�ɑ��Ă͗D�����A�����ɑ��Ă͌������{����s���Ă���悤�Ɏv���邪�A����͕M�҂̒P��
��Ό��ł��낤���B
������ƁA���{�i�����ȁE���y��ʏȁj�̊����⒆�����R�c��̎����Ԕr�o�K�X���ψ���̊w�ҁE���Ƃ�
�l�B�́A�g���b�N���[�J�ɑ��Ă͗D�����A�����ɑ��Ă͌������{����s���Ă���悤�Ɏv���邪�A����͕M�҂̒P��
��Ό��ł��낤���B
�@�Ƃ���ŁA�M�҂́A�T�N�ȏ���ȑO�ƂȂ�2006�N4��7���ɁA���߂ăz�[���y�[�W���J�݂����B�����ł��ANO���팸��
�����ɏd�ʎԃ��[�h�R������オ�\���C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p�����J���Ă���B�����āA
�����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p����^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W�����̗p�����ꍇ�ɂ́A�A�N
�Z�y�_���̓����ݗ�50���ȉ��̒ᕉ���ɂ������A�fSCR�G�}�̓����̔r�C�K�X���x��2�{�߂��ɍ������ł���
���߁A�u�A�fSCR�G�}�̏����z�b�g�X�^�[�g���A�R�[���h�X�^�[�g���̕��ρi�R�[���h�X�^�[�g�䗦14���j�łW�T����
�x�Ƃ���v���Ƃ��\�ł���Z�p�����\�����B���̋C���x�~�̋Z�p��p����A������NO���ጸ�̖ڕW�l�́A����
�i�Q�j���ŎZ�o�����l�܂Œጸ���邱�Ƃ��\�ƂȂ�B
�����ɏd�ʎԃ��[�h�R������オ�\���C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p�����J���Ă���B�����āA
�����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p����^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W�����̗p�����ꍇ�ɂ́A�A�N
�Z�y�_���̓����ݗ�50���ȉ��̒ᕉ���ɂ������A�fSCR�G�}�̓����̔r�C�K�X���x��2�{�߂��ɍ������ł���
���߁A�u�A�fSCR�G�}�̏����z�b�g�X�^�[�g���A�R�[���h�X�^�[�g���̕��ρi�R�[���h�X�^�[�g�䗦14���j�łW�T����
�x�Ƃ���v���Ƃ��\�ł���Z�p�����\�����B���̋C���x�~�̋Z�p��p����A������NO���ጸ�̖ڕW�l�́A����
�i�Q�j���ŎZ�o�����l�܂Œጸ���邱�Ƃ��\�ƂȂ�B
�@�@�i�G���W���o���̔r�o�ʂ�1.5g/kWh���x�j�~�i�A�fSCR�G�}����85���̍팸�j��0.225g/kWh�@�E�E�E�E�E�i�Q�j
�@���̂悤�ɁA����A��^�g���b�N�ɋC���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j���̗p�����ꍇ�ɂ́A��L���i�Q�j����
�Z�o���ꂽ0.225g/kWh����A�����̑�^�g���b�N��NO���r�o�l�́u0.23g/kWh�v�iWHTC�r�o�K�X�����@�j�܂ŗe�Ղɍ�
�����邱�Ƃ��\�ł���A�d�ʎԃ��[�h�R����T�`�P�O��������ł���̂��B���̂悤�ɁA2010�N�V��28�����\�̒�
�����R�c��E��C������́u����̎����Ԕr�o�K�X�ጸ��̂�����ɂ��āi��\�����\�j�v�ɋL��
����Ă���e��Z�p�ɁA�V�����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p��lj����邱�Ƃɂ���āA��
���̑�^�g���b�N�ɂ����ẮuNO���r�o�l��0.23g/kWh�܂ł̍팸�v�Ɓu�d�ʎԃ��[�h�R��̂T�`�P�O���̌�
��v���\�ƂȂ�B
�Z�o���ꂽ0.225g/kWh����A�����̑�^�g���b�N��NO���r�o�l�́u0.23g/kWh�v�iWHTC�r�o�K�X�����@�j�܂ŗe�Ղɍ�
�����邱�Ƃ��\�ł���A�d�ʎԃ��[�h�R����T�`�P�O��������ł���̂��B���̂悤�ɁA2010�N�V��28�����\�̒�
�����R�c��E��C������́u����̎����Ԕr�o�K�X�ጸ��̂�����ɂ��āi��\�����\�j�v�ɋL��
����Ă���e��Z�p�ɁA�V�����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p��lj����邱�Ƃɂ���āA��
���̑�^�g���b�N�ɂ����ẮuNO���r�o�l��0.23g/kWh�܂ł̍팸�v�Ɓu�d�ʎԃ��[�h�R��̂T�`�P�O���̌�
��v���\�ƂȂ�B
�@���������āA�����A�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p�����p���ł���ڏ������������_�ŁA������
���R�c��́A��\�����\�ł�2016�N�̎���NO���K���iNO����0.4g/kWh�j�iWHTC�r�o�K�X�����@�j�ɑ����āA������
���ɑ�^�g���b�NNO���K���̋����iNO�� �� 0.23 g/kWh )�iWHTC�r�o�K�X�����@�j�̓��\���o�����Ƃ��\�ƂȂ�B��
��ɂ���āA��^�g���b�N����ɂ�����u��NO���v�Ɓu��R��i����CO2�j�v��i�W�����A�䂪���ɂ������C���̉�
�P�����I�ɑ��i�����邱�Ƃ��ł���ƍl������B�������������B��̕��@�́A�C���x�~�G���W���i�������J
2005-54771�j�̋Z�p�𓋍ڂ�����^�g���b�N���g���b�N���[�J���������Ɏs�̉�����邱�Ƃ��K�v���B���̂��߂ɂ́A
���Ȃ⍑�y��ʏȂ���̂Ƃ������{�����͂ȃ��[�_�[�V�b�v�������C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j
�̌����J���𑣐i���A�����Z�p�������Ɏ��p�����邱�Ƃł���B���̂悤�ɁA�C���x�~�G���W���i�������J2005-
54771�j�̋Z�p���^�g���b�N�ɍ̗p���邱�Ƃɂ�����č��������������{��NO���K����NO���K���ɋ����iNO�� �� 0.
23 g/kWh )�iWHTC�r�o�K�X�����@�j��e�ՂɎ������邱�Ƃ��\�ł��邪�A���̂��Ƃɂ��ẮA�č������ɂ���
�^�g���b�N��NO���K�����{�s����������{���{�̑Ӗ��̃y�[�W�ɂ��ڏq���Ă���̂ŁA�䗗�������������B
���R�c��́A��\�����\�ł�2016�N�̎���NO���K���iNO����0.4g/kWh�j�iWHTC�r�o�K�X�����@�j�ɑ����āA������
���ɑ�^�g���b�NNO���K���̋����iNO�� �� 0.23 g/kWh )�iWHTC�r�o�K�X�����@�j�̓��\���o�����Ƃ��\�ƂȂ�B��
��ɂ���āA��^�g���b�N����ɂ�����u��NO���v�Ɓu��R��i����CO2�j�v��i�W�����A�䂪���ɂ������C���̉�
�P�����I�ɑ��i�����邱�Ƃ��ł���ƍl������B�������������B��̕��@�́A�C���x�~�G���W���i�������J
2005-54771�j�̋Z�p�𓋍ڂ�����^�g���b�N���g���b�N���[�J���������Ɏs�̉�����邱�Ƃ��K�v���B���̂��߂ɂ́A
���Ȃ⍑�y��ʏȂ���̂Ƃ������{�����͂ȃ��[�_�[�V�b�v�������C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j
�̌����J���𑣐i���A�����Z�p�������Ɏ��p�����邱�Ƃł���B���̂悤�ɁA�C���x�~�G���W���i�������J2005-
54771�j�̋Z�p���^�g���b�N�ɍ̗p���邱�Ƃɂ�����č��������������{��NO���K����NO���K���ɋ����iNO�� �� 0.
23 g/kWh )�iWHTC�r�o�K�X�����@�j��e�ՂɎ������邱�Ƃ��\�ł��邪�A���̂��Ƃɂ��ẮA�č������ɂ���
�^�g���b�N��NO���K�����{�s����������{���{�̑Ӗ��̃y�[�W�ɂ��ڏq���Ă���̂ŁA�䗗�������������B
�P�U�D�V���ȁu��NO���E��R��Ԋ�v�̓����ɂ��g���b�N�̒���Q���E�ȔR��𑣐i
�@��^�g���b�N�ɂ����ẮA2010�N7��28���ɒ������R�c�����Ȃɑ�\�����\����o����AGVW7.5�g����
���̑�^�g���b�N�E�o�X��NO���ƔR��̍X�Ȃ�K���̋������A2016�N�Ɏ{�s����m�n����0.4 g/kWh�̋K����
�{�����\���ꂽ�B�������A�������R�c��E��C��������攪�����\�i2005�N�j�ł́A������NO���팸��
�ڈ��Ƃ���NO���팸������ڕW�Ə̂���0.7 g/kWh�� 1/3���x�i���@0.23�@g/kWh���x���j��NO���K���̋���
���x������������Ă����̂ł���B�������A�������R�c��E��C������ł͂����攪�����\�i2005�N�j��
���j�i�L�q�j�̂ɂ��āA2010�N7��28���̑�\�����\��2016�N�Ɏ{�s����鎟����NO���K���l�͂m�n��
��0.4 g/kWh�ɑ啝�Ɋɘa���Ă��܂����̂ł���B
���̑�^�g���b�N�E�o�X��NO���ƔR��̍X�Ȃ�K���̋������A2016�N�Ɏ{�s����m�n����0.4 g/kWh�̋K����
�{�����\���ꂽ�B�������A�������R�c��E��C��������攪�����\�i2005�N�j�ł́A������NO���팸��
�ڈ��Ƃ���NO���팸������ڕW�Ə̂���0.7 g/kWh�� 1/3���x�i���@0.23�@g/kWh���x���j��NO���K���̋���
���x������������Ă����̂ł���B�������A�������R�c��E��C������ł͂����攪�����\�i2005�N�j��
���j�i�L�q�j�̂ɂ��āA2010�N7��28���̑�\�����\��2016�N�Ɏ{�s����鎟����NO���K���l�͂m�n��
��0.4 g/kWh�ɑ啝�Ɋɘa���Ă��܂����̂ł���B
�@�������R�c�2016�N�Ɏ{�s�̎���NO���K���l���m�n����0.4 g/kWh�ɑ啝�Ɋɘa�������R�Ƃ��āA��
�����R�c���E��C�������̑�\�����\�ł́A�V���ɃR�[���h�X�^�[�g���܂V�������E���ꎎ���T�C
�N���ł���WHTC���r�o�K�X�����@�ւ̕ύX���s���邱�Ƃ���ȗ��R�Ƃ��ċ������Ă���B�������A���
�����̗��ꂩ�猾�킹�ĖႦ�A�r�o�K�X�����@�ɑ����̕ύX���������Ƃ��Ă��A���{�ɂ������C����
�X�ɉ��P���Ă������߂ɂ́A2010�N7��28���̑�\�����\�ɂ�����2016�N�Ɏ{�s����m�n���K���l�Ƃ��ẮA
�攪�����\�i2005�N�j�ɋL�ڂ���Ă���NO���팸������ڕW�Ƃ��Ă�0.7 g/kWh�� 1/3���x�i�� 0.23 g/kWh
���x���j��NO���K���l�����\����đR��ׂ��ł͂Ȃ����낤���B
�����R�c���E��C�������̑�\�����\�ł́A�V���ɃR�[���h�X�^�[�g���܂V�������E���ꎎ���T�C
�N���ł���WHTC���r�o�K�X�����@�ւ̕ύX���s���邱�Ƃ���ȗ��R�Ƃ��ċ������Ă���B�������A���
�����̗��ꂩ�猾�킹�ĖႦ�A�r�o�K�X�����@�ɑ����̕ύX���������Ƃ��Ă��A���{�ɂ������C����
�X�ɉ��P���Ă������߂ɂ́A2010�N7��28���̑�\�����\�ɂ�����2016�N�Ɏ{�s����m�n���K���l�Ƃ��ẮA
�攪�����\�i2005�N�j�ɋL�ڂ���Ă���NO���팸������ڕW�Ƃ��Ă�0.7 g/kWh�� 1/3���x�i�� 0.23 g/kWh
���x���j��NO���K���l�����\����đR��ׂ��ł͂Ȃ����낤���B
�@�܂��A�R��K���̋����ɂ��ẮA�M�҂̌l�I�ȗ\�z�ł��邪�A2015�N�x�d�ʎԔR���ɑ����Ď�
���̔R���ł́{�P�O�����x�H�����{�����Ɛ������Ă���B������^�g���b�N�ɂ����鏫���̂m�n���ƔR
��̋K�������ɗe�ՂɓK���ł���悤�ɂ���Z�p�Ƃ��ẮA�m�n���팸�ƔR����P�̗����������ł���Q�^�[
�{�ߋ��@�������C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j���ł��L�͂ȋZ�p�ł���ƕM�҂͐M���Ă���B����
���A�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�́A�A�N�Z�������ݗʂ�50���ȉ��ł̋C���x�~�̉^�]�̈�ł́A��
�[�^�����O�����i�t���N�V���������j�͕ς��Ȃ����̂́A�r�C�����Ɨ�p�����̍팸�ɉ����ăT�C�N�������̌��オ
�ł���Ɖ]���A�ŋ߂̗��s�̌��t�Ō����u�A�N�Z�������ݗʂ�50���ȉ��ł̃G���W���_�E���T�C�W���O�̉^�]�v��
����đ啝�ȔR��팸���ł���̂ł���B
���̔R���ł́{�P�O�����x�H�����{�����Ɛ������Ă���B������^�g���b�N�ɂ����鏫���̂m�n���ƔR
��̋K�������ɗe�ՂɓK���ł���悤�ɂ���Z�p�Ƃ��ẮA�m�n���팸�ƔR����P�̗����������ł���Q�^�[
�{�ߋ��@�������C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j���ł��L�͂ȋZ�p�ł���ƕM�҂͐M���Ă���B����
���A�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�́A�A�N�Z�������ݗʂ�50���ȉ��ł̋C���x�~�̉^�]�̈�ł́A��
�[�^�����O�����i�t���N�V���������j�͕ς��Ȃ����̂́A�r�C�����Ɨ�p�����̍팸�ɉ����ăT�C�N�������̌��オ
�ł���Ɖ]���A�ŋ߂̗��s�̌��t�Ō����u�A�N�Z�������ݗʂ�50���ȉ��ł̃G���W���_�E���T�C�W���O�̉^�]�v��
����đ啝�ȔR��팸���ł���̂ł���B
�@�������A���������ƂɁA�M�҂���Ă����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p�́A�g���b�N���[�J��M����
���{�̊w�ҁE�����ҁE���Ƃ��n�߂Ƃ��āA�����́u�R��팸�v�A�uCO2�팸�v����сuNOx�팸�v�̑������߂ł��鍑
�y��ʏȂ���Ȃ�����َE����Ă���l�q���f���邱�Ƃł���B�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j��
�Z�p�����p�����đ�^�g���b�N�̑啝���R����P�Ƃm�n���팸���\�ɂ���A���y��ʏȂ���Ȃ͎���
���m�n���K�������ƔR��K���������e�ՂɎ��{�ł���悤�ɂȂ�A��^�g���b�N�ɂ�����NO����CO�Q�̍팸��
���i�ł��邱�Ƃɉ����A�ȃG�l���M�[�̐���������Ɏ����ł����̂ł���B����ɂ�������炸�A���y��ʏȂ�
���Ȃ��������C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p���������邱�Ƃ́A�w�s�������Ȃ��Ă͂����Ȃ�
���Ƃ����Ȃ��s����x�ɑ���������̂ƍl������B���̍��y��ʏȂ���Ȃ̕s��ׂ́A��^�g���b�N���R����P
�Ƃm�n���팸��啝�ɒx�点�Ă��܂����ƂɂȂ�����B���̂悤�Ȏ��ԂɊׂ邱�Ƃ�����邽�߁A���y��ʏȂƊ��Ȃ�
�͖{���̎d���𗧔h�ɉʂ����s�����N�����Ē����������̂������B
���{�̊w�ҁE�����ҁE���Ƃ��n�߂Ƃ��āA�����́u�R��팸�v�A�uCO2�팸�v����сuNOx�팸�v�̑������߂ł��鍑
�y��ʏȂ���Ȃ�����َE����Ă���l�q���f���邱�Ƃł���B�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j��
�Z�p�����p�����đ�^�g���b�N�̑啝���R����P�Ƃm�n���팸���\�ɂ���A���y��ʏȂ���Ȃ͎���
���m�n���K�������ƔR��K���������e�ՂɎ��{�ł���悤�ɂȂ�A��^�g���b�N�ɂ�����NO����CO�Q�̍팸��
���i�ł��邱�Ƃɉ����A�ȃG�l���M�[�̐���������Ɏ����ł����̂ł���B����ɂ�������炸�A���y��ʏȂ�
���Ȃ��������C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p���������邱�Ƃ́A�w�s�������Ȃ��Ă͂����Ȃ�
���Ƃ����Ȃ��s����x�ɑ���������̂ƍl������B���̍��y��ʏȂ���Ȃ̕s��ׂ́A��^�g���b�N���R����P
�Ƃm�n���팸��啝�ɒx�点�Ă��܂����ƂɂȂ�����B���̂悤�Ȏ��ԂɊׂ邱�Ƃ�����邽�߁A���y��ʏȂƊ��Ȃ�
�͖{���̎d���𗧔h�ɉʂ����s�����N�����Ē����������̂������B
�@�Ƃ���ŁA���݁A�e�g���b�N���[�J�́A�f�B�[�[���G���W���̔R�����P�ɂ���ď\���ȔR����P�������ł���Z�p��
�J�����o���Ă��Ȃ��悤���B�������A�g���b�N���[�J�S��(����A�����U�A�t�c�A�O�H�ӂ���)���猤���҂��h������Ă���
�@���V�G�B�V�[�C�[�́A�u���V�G�B�V�[�C�[�͂Q�O�O�S�N�Ɏ��{�����f�B�[�[���G���W���̋C���x�~�̎����ɂ����āA�R
��팸�̌��ʂ��m�F�v ���Ă����悤�ł���B�������A���̇��V�G�B�V�[�C�[�́A�f�B�[�[���G���W���̋C���x�~�̎���
�ɂ����āA�R�����P�̌��ʂ��m�F���Ă����������I�����Ă�����ɂT�N�ȏ���o�߂��Ă���ɂ�������炸�A������
�C���x�~�̎������ʂ\���Ă��Ȃ����Ƃ̂��ƁB����Ɋւ��A�g���b�N���[�J�S�Ђ����V�G�B�V�[�C�[�ɂ�����C���x
�~�ɂ��R�����P�̌��ʂ̔��\��j�~���Ă���\�����ے�ł��Ȃ����낤�B
�J�����o���Ă��Ȃ��悤���B�������A�g���b�N���[�J�S��(����A�����U�A�t�c�A�O�H�ӂ���)���猤���҂��h������Ă���
�@���V�G�B�V�[�C�[�́A�u���V�G�B�V�[�C�[�͂Q�O�O�S�N�Ɏ��{�����f�B�[�[���G���W���̋C���x�~�̎����ɂ����āA�R
��팸�̌��ʂ��m�F�v ���Ă����悤�ł���B�������A���̇��V�G�B�V�[�C�[�́A�f�B�[�[���G���W���̋C���x�~�̎���
�ɂ����āA�R�����P�̌��ʂ��m�F���Ă����������I�����Ă�����ɂT�N�ȏ���o�߂��Ă���ɂ�������炸�A������
�C���x�~�̎������ʂ\���Ă��Ȃ����Ƃ̂��ƁB����Ɋւ��A�g���b�N���[�J�S�Ђ����V�G�B�V�[�C�[�ɂ�����C���x
�~�ɂ��R�����P�̌��ʂ̔��\��j�~���Ă���\�����ے�ł��Ȃ����낤�B
�@���ɁA�g���b�N���[�J���u���V�G�B�V�[�C�[�͂Q�O�O�S�N�Ɏ��{�����f�B�[�[���G���W���̋C���x�~�̎����ɂ����āA�R
�����P�̌��ʂ��m�F���Ă����v ���Ƃ�m���Ă��Ȃ���A�e�g���b�N���[�J�̑��ӂƂ��ăg���b�N���[�J�i�����ԍH�Ɖ�j��
���Ȃ⍑�y��ʏȂɁA�Q�O�P�T�N�x�d�ʎԔR���̎��̏d�ʎԔR���̋�����x�点�ė~�����|���A�ɗz
�ɑi���Ă���Ƃ���A�M�҂ɂ̓g���b�N���[�J�i�����ԍH�Ɖ�j�����y��ʏȂɑ��Ĕw�M�I�ȍs�ׂ��s���Ă����
���Ɍ�����̂ł���B
�����P�̌��ʂ��m�F���Ă����v ���Ƃ�m���Ă��Ȃ���A�e�g���b�N���[�J�̑��ӂƂ��ăg���b�N���[�J�i�����ԍH�Ɖ�j��
���Ȃ⍑�y��ʏȂɁA�Q�O�P�T�N�x�d�ʎԔR���̎��̏d�ʎԔR���̋�����x�点�ė~�����|���A�ɗz
�ɑi���Ă���Ƃ���A�M�҂ɂ̓g���b�N���[�J�i�����ԍH�Ɖ�j�����y��ʏȂɑ��Ĕw�M�I�ȍs�ׂ��s���Ă����
���Ɍ�����̂ł���B
�@���̂悤���A�T�`10���̏d�ʎԃ��[�h�R��팸�ł��A�G���W�����������̔A�fSCR�G�}�̊������i�ɂ���
����NO�����팸�ł����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p���e���b�N���[�J�������������ŁA�e�g���b
�N���[�J�̏����������{�����ԍH�Ɖ���y��ʏȂ��Q�O�P�T�N�x�d�ʎԔR�����������鎟�̏d�ʎԔR���
���̐ݒ�̒x�������ɗv�]���Ă���Ƃ���A���{�����ԍH�Ɖ�́A�i�ʂɌ�����s�ׂ��s���Ă���ƌ��킴���
���Ȃ����낤�B
����NO�����팸�ł����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p���e���b�N���[�J�������������ŁA�e�g���b
�N���[�J�̏����������{�����ԍH�Ɖ���y��ʏȂ��Q�O�P�T�N�x�d�ʎԔR�����������鎟�̏d�ʎԔR���
���̐ݒ�̒x�������ɗv�]���Ă���Ƃ���A���{�����ԍH�Ɖ�́A�i�ʂɌ�����s�ׂ��s���Ă���ƌ��킴���
���Ȃ����낤�B
�@�܂��A���Ƀg���b�N���[�J�i���{�����ԍH�Ɖ�j�̏d�ʎԔR�������̒x���v�]�����y��ʏȂ�����A�Q�O�P
�T�N�x�d�ʎԔR���̎����̊�ݒ�̎�����x�点�邱�Ƃ���������Ă���Ƃ���A�e�g���b�N���[�J���u��
��K���v�Ɗ����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̂悤�Ȏ�̃R�X�g�A�b�v���R����P�̋Z�p�J����
�摗��ɂ��邱�ƂɂȂ邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ����낤�B���̂��Ƃ́A���y��ʏȂ���R��E��NO���̑�^�g���b�N�̎��p��
��j�~����s�ׂ̕Ж_��S���ł���ƌ����Ă��d�����Ȃ��̂ł͂Ȃ����낤���B
�T�N�x�d�ʎԔR���̎����̊�ݒ�̎�����x�点�邱�Ƃ���������Ă���Ƃ���A�e�g���b�N���[�J���u��
��K���v�Ɗ����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̂悤�Ȏ�̃R�X�g�A�b�v���R����P�̋Z�p�J����
�摗��ɂ��邱�ƂɂȂ邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ����낤�B���̂��Ƃ́A���y��ʏȂ���R��E��NO���̑�^�g���b�N�̎��p��
��j�~����s�ׂ̕Ж_��S���ł���ƌ����Ă��d�����Ȃ��̂ł͂Ȃ����낤���B
�P�U�|�P�@�V���ȑ�^�g���b�N�̒�NO���E��R����Ԃ̊�i�āj
�@��^�g���b�N�̔R��팸��NO���팸�������ł���̐��𑁊��ɍ\�z����őP�̕��@�́A�ł��邾��������
�I�v�V�����Ƃ������Ȃƍ��y��ʏȂ�NO���팸�ƔR�������K�肵���u��NO���E��R��g���b�N�E�o�X�̊
�i�āj�v���V�����ݒ肷�邱���ł���B���́u��NO���E��R����Ԃ̊�i�āj�v�ł́A�\�Q�X�Ɏ������悤�ɁA2005�N
�̑攪�����\���m�n���̒���ڕW�Ƃ��Ď�����Ă��� 0.7 g/kWh�� 1/3���x�� 0.23 g/kWh���m�n�� �K���l���A2015�N
�x�d�ʎԔR������ �{�P�O�� ���x�̔R�������������l��ݒ肷�邱�Ƃ��K�ł͂Ȃ����ƍl���Ă���B
�I�v�V�����Ƃ������Ȃƍ��y��ʏȂ�NO���팸�ƔR�������K�肵���u��NO���E��R��g���b�N�E�o�X�̊
�i�āj�v���V�����ݒ肷�邱���ł���B���́u��NO���E��R����Ԃ̊�i�āj�v�ł́A�\�Q�X�Ɏ������悤�ɁA2005�N
�̑攪�����\���m�n���̒���ڕW�Ƃ��Ď�����Ă��� 0.7 g/kWh�� 1/3���x�� 0.23 g/kWh���m�n�� �K���l���A2015�N
�x�d�ʎԔR������ �{�P�O�� ���x�̔R�������������l��ݒ肷�邱�Ƃ��K�ł͂Ȃ����ƍl���Ă���B
�@�����āA�����V���ɐݒ肵���\�Q�V�́u��NO���E��R����Ԃ̊�i�āj�v�ɓK��������^�g���b�N�ɂ́A�ŋ��̗D��
��^�����D���Ő���K�p�Ƃ��邱�Ƃł���B���Ɂu��NO���E��R����Ԃ̊�i�āj�v�ɓK��������^�g���b�N�ɑ�
�Đŋ��̗D����^���鐧�x��������A��^�g���b�N�̐Ő��D�������������߂ɁA�e�g���b�N���[�J�͕K��
���C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p�����p�����邱�ƂɂȂ�̂ł���B�����āA�e�g���b�N���[�J������
�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p�������đ�^�g���b�N�ɍ̗p����A�Z�p�I�ɂ͉��̖�������
�u��NO���E��R����Ԃ̊�i�āj�v�ɓK����������Q�E�ȃG�l�̑����̑�^�g���b�N���e�g���b�N���[�J���狣���Ĕ�
���������̂Ɨ\�z�����B�Ȃ��A�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p�ɂ��R����P��NO���팸�̏�
�ׂɂ��ẮA�C���x�~�G���W���ɂ���^�g���b�N�̒�R��A�܂����C���x�~�́A�R��팸�ƔA�fSCR��NO����
�����̌���ɗL�����I���Q�Ƃ��Ē��������B
��^�����D���Ő���K�p�Ƃ��邱�Ƃł���B���Ɂu��NO���E��R����Ԃ̊�i�āj�v�ɓK��������^�g���b�N�ɑ�
�Đŋ��̗D����^���鐧�x��������A��^�g���b�N�̐Ő��D�������������߂ɁA�e�g���b�N���[�J�͕K��
���C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p�����p�����邱�ƂɂȂ�̂ł���B�����āA�e�g���b�N���[�J������
�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p�������đ�^�g���b�N�ɍ̗p����A�Z�p�I�ɂ͉��̖�������
�u��NO���E��R����Ԃ̊�i�āj�v�ɓK����������Q�E�ȃG�l�̑����̑�^�g���b�N���e�g���b�N���[�J���狣���Ĕ�
���������̂Ɨ\�z�����B�Ȃ��A�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p�ɂ��R����P��NO���팸�̏�
�ׂɂ��ẮA�C���x�~�G���W���ɂ���^�g���b�N�̒�R��A�܂����C���x�~�́A�R��팸�ƔA�fSCR��NO����
�����̌���ɗL�����I���Q�Ƃ��Ē��������B
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
�@����A���������ɁA���Ȃ����y��ʏȂ��m�n���K����0.23�@g/kWh��2015�N�x�d�ʎԔR���́{�P�O�����x��
������K�肵���\�Q�X�́u��NO���E��R����Ԃ̊�i�āj�v���{�s�����Ƃ��Ă��A�e�g���b�N���[�J�͑�^�g���b�N���C
���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p���̗p����������A�ȒP�ɑ�^�g���b�N���u��NO���E��R����Ԃ�
��i�āj�v�ɓK�������邱�Ƃ��\�ł����B
������K�肵���\�Q�X�́u��NO���E��R����Ԃ̊�i�āj�v���{�s�����Ƃ��Ă��A�e�g���b�N���[�J�͑�^�g���b�N���C
���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p���̗p����������A�ȒP�ɑ�^�g���b�N���u��NO���E��R����Ԃ�
��i�āj�v�ɓK�������邱�Ƃ��\�ł����B
�@�����āA�V���ȁu��NO���E��R����Ԃ̊�i�āj�v�ɓK��������^�g���b�N�ɑ��A�]�����G�R�J�[���łƓ��l�ɁA
�ŋ���D������A�e�g���b�N���[�J�͋������C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p�J���ɒ��肷�����
�Ɨ\�z�����B���̌��ʁA���Ȃ葁�������ɂm�n�� ��0.23 g/kWh�܂ō팸���A2015�N�x�d�ʎԔR�������{�P�O��
���x�̔R������������V���Ȓ�NO���E��R��g���b�N�̎s�ꂪ�o�����邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��Ǝv���Ă���B����ɂ��
�āA�킪���ɂ������^�g���b�N�̕���ɂ�����uNO���̍팸�v�A�u�ȃG�l���M�[�v����сu��CO2�v������I�ɐ��i��
���邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��ƍl������B
�ŋ���D������A�e�g���b�N���[�J�͋������C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p�J���ɒ��肷�����
�Ɨ\�z�����B���̌��ʁA���Ȃ葁�������ɂm�n�� ��0.23 g/kWh�܂ō팸���A2015�N�x�d�ʎԔR�������{�P�O��
���x�̔R������������V���Ȓ�NO���E��R��g���b�N�̎s�ꂪ�o�����邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��Ǝv���Ă���B����ɂ��
�āA�킪���ɂ������^�g���b�N�̕���ɂ�����uNO���̍팸�v�A�u�ȃG�l���M�[�v����сu��CO2�v������I�ɐ��i��
���邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��ƍl������B
�P�U�|�Q�@���{�̏d�ʎ�NO���K���l�ɂ��Ă̎��H��E�w�҂ɂ��Ӗ��s���Ȑ������e
�@����c��w�̑��������������ꂽ���{�����ԍH�Ɖ�̃z�[���y�[�W�Ɍf�ڂ́u�N���[���E�f�B�[�[���G���W���Z
�p�Ə����v�Ƒ肷��y�[�W�ɂ́A�ȉ��̕\�R�O�Ɏ������悤�ɁA�u��i���̏d�ʎԂ�NO���K����r�}�v��������Ă�
��B���̐}�ɂ��ƁA���{�̏d�ʎԂ̃|�X�g�V����NO���K����NO�� �� 0.7 g/��W���ł���ɂ�������炸�A�d�ʎԂ�
�|�X�g�V����NO���K���l�Ƃ���NO�� �� 0.23 g/��W���̋K���l���NjL����Ă���̂ł���B���̏d�ʎԂ̃|�X�g�V����
NO���K���l�ł́ANO�� �� 0.23 g/��W���̖��Ӗ��ȋK���l�����L����Ă��邱�Ƃ́A���{�����ԍH�Ɖ�̃z�[���y�[
�W�̓ǎ҂Ɍ�����Z�p�W�̏�����Ă��邱�ƂɂȂ�ƍl������B
�p�Ə����v�Ƒ肷��y�[�W�ɂ́A�ȉ��̕\�R�O�Ɏ������悤�ɁA�u��i���̏d�ʎԂ�NO���K����r�}�v��������Ă�
��B���̐}�ɂ��ƁA���{�̏d�ʎԂ̃|�X�g�V����NO���K����NO�� �� 0.7 g/��W���ł���ɂ�������炸�A�d�ʎԂ�
�|�X�g�V����NO���K���l�Ƃ���NO�� �� 0.23 g/��W���̋K���l���NjL����Ă���̂ł���B���̏d�ʎԂ̃|�X�g�V����
NO���K���l�ł́ANO�� �� 0.23 g/��W���̖��Ӗ��ȋK���l�����L����Ă��邱�Ƃ́A���{�����ԍH�Ɖ�̃z�[���y�[
�W�̓ǎ҂Ɍ�����Z�p�W�̏�����Ă��邱�ƂɂȂ�ƍl������B
�@���̏�A���{�̏d�ʎԂ̃|�X�g�V����NO���K����NO�� �� 0.7 g/��W���̃|�C���g����NO�� �� 0.23 g/��W���̃|�C���g
�܂Ŗ��Ӗ��ȑ������L�ڂ���Ă��邪�A����NO�� �� 0.7 �`0.23 g/��W���̑����ɂ́A��́A���̈Ӗ�������̂ł���
�����B���̑������A���{�̏d�ʎԂ̃|�X�g�V����NO���K���l�ɂ͖��W�ȋL�ڂł���B���̂Ȃ�A���̑攪����
�\�i2005�N���\�j�́u����ڕWNO�� �� 0.23 g/��W���v�́A�������R�c��̑�\�����\�i2010�N���\�j�ł́A���S��
�폜����Ă��邽�߂��B�Ƃ��낪�A���������́A���{�̏d�ʎԂɂ��Ă̒������R�c��̑攪�����\�i2005�N��
�\�j�̒��ɋL�q����Ă����u����ڕWNO�� �� 0.23 g/��W���v�������_�i2013�N7��26�����݁j�ł��������R�c���
���{�̏d�ʎԂɂ�����NO���̍팸�ڕW�Ƃ��ė��h�ɐ����Ă��邩�̔@�����X�ƋL�ڂ���Ă���̂ł���B
�܂Ŗ��Ӗ��ȑ������L�ڂ���Ă��邪�A����NO�� �� 0.7 �`0.23 g/��W���̑����ɂ́A��́A���̈Ӗ�������̂ł���
�����B���̑������A���{�̏d�ʎԂ̃|�X�g�V����NO���K���l�ɂ͖��W�ȋL�ڂł���B���̂Ȃ�A���̑攪����
�\�i2005�N���\�j�́u����ڕWNO�� �� 0.23 g/��W���v�́A�������R�c��̑�\�����\�i2010�N���\�j�ł́A���S��
�폜����Ă��邽�߂��B�Ƃ��낪�A���������́A���{�̏d�ʎԂɂ��Ă̒������R�c��̑攪�����\�i2005�N��
�\�j�̒��ɋL�q����Ă����u����ڕWNO�� �� 0.23 g/��W���v�������_�i2013�N7��26�����݁j�ł��������R�c���
���{�̏d�ʎԂɂ�����NO���̍팸�ڕW�Ƃ��ė��h�ɐ����Ă��邩�̔@�����X�ƋL�ڂ���Ă���̂ł���B
�@�������A�������R�c��̑�\�����\�i2010�N���\�j��f���ɓǂ���ł́A���݂ł����{�̏d�ʎԂɂ�����
�u����ڕWNO�� �� 0.23 g/��W���v���ݒ肳��Ă���Ƃ́A�M�҂ɂ͂ǂ����Ă������ł��Ȃ����Ƃł���B�ʂ����āA����
���R�c��́A���{�̏d�ʎԂɑ��A�{���Ɂu����ڕWNO�� �� 0.23 g/��W���v��ݒ肵�Ă��邱�ƂɂȂ��Ă���̂�
���낤���B���ɁA���{�̏d�ʎԂɑ��A�����I�ȁu����ڕWNO�� �� 0.23 g/��W���v��ݒ肵�Ă��邱�ƂȂ��Ă���̂�
����A�@���Ȃ闝�R�Œ������R�c��̑�\�����\�i2010�N���\�j�ɂ́A�d�ʎԁi���g���b�N�j�́u����ڕWNO��
�� 0.23 g/��W���v�����L����Ă��Ȃ��̂ł��낤���B���̏���A�펯�I�ɍl����A�����_�ł͓��{�̏d�ʎԂ�
���A�����I�ȁu����ڕWNO�� �� 0.23 g/��W���v���ݒ肳��Ă��Ȃ��ƍl����̂��Ó��̂悤�Ɏv����B����ɂ�
������炸�A����c��w�̑��������������ꂽ���{�����ԍH�Ɖ�̃z�[���y�[�W�Ɍf�ڂ́u�N���[���E�f�B�[�[��
�G���W���Z�p�Ə����v�Ƒ肷��y�[�W�ɂ́A���{�̏d�ʎԂɑ��ď����I�ȁu����ڕWNO�� �� 0.23 g/��W���v���ݒ肳
��Ă���悤�ɋL�ڂ���Ă��邱�Ƃ́A���d�s�v�c�Ȃ��Ƃł���B
�u����ڕWNO�� �� 0.23 g/��W���v���ݒ肳��Ă���Ƃ́A�M�҂ɂ͂ǂ����Ă������ł��Ȃ����Ƃł���B�ʂ����āA����
���R�c��́A���{�̏d�ʎԂɑ��A�{���Ɂu����ڕWNO�� �� 0.23 g/��W���v��ݒ肵�Ă��邱�ƂɂȂ��Ă���̂�
���낤���B���ɁA���{�̏d�ʎԂɑ��A�����I�ȁu����ڕWNO�� �� 0.23 g/��W���v��ݒ肵�Ă��邱�ƂȂ��Ă���̂�
����A�@���Ȃ闝�R�Œ������R�c��̑�\�����\�i2010�N���\�j�ɂ́A�d�ʎԁi���g���b�N�j�́u����ڕWNO��
�� 0.23 g/��W���v�����L����Ă��Ȃ��̂ł��낤���B���̏���A�펯�I�ɍl����A�����_�ł͓��{�̏d�ʎԂ�
���A�����I�ȁu����ڕWNO�� �� 0.23 g/��W���v���ݒ肳��Ă��Ȃ��ƍl����̂��Ó��̂悤�Ɏv����B����ɂ�
������炸�A����c��w�̑��������������ꂽ���{�����ԍH�Ɖ�̃z�[���y�[�W�Ɍf�ڂ́u�N���[���E�f�B�[�[��
�G���W���Z�p�Ə����v�Ƒ肷��y�[�W�ɂ́A���{�̏d�ʎԂɑ��ď����I�ȁu����ڕWNO�� �� 0.23 g/��W���v���ݒ肳
��Ă���悤�ɋL�ڂ���Ă��邱�Ƃ́A���d�s�v�c�Ȃ��Ƃł���B
�� �o�T�̃z�[���y�[�W�@���{�����ԍH�Ɖ� JAMAGAZINE�@2012�N3����
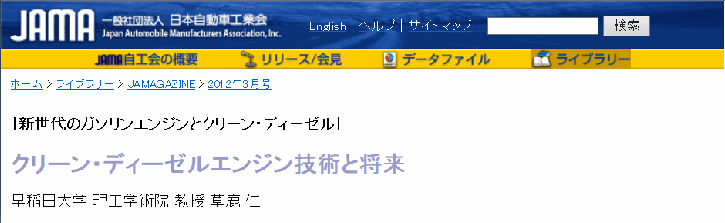 |
�� ��i���̏d�ʎԂ�NO���K����r�}
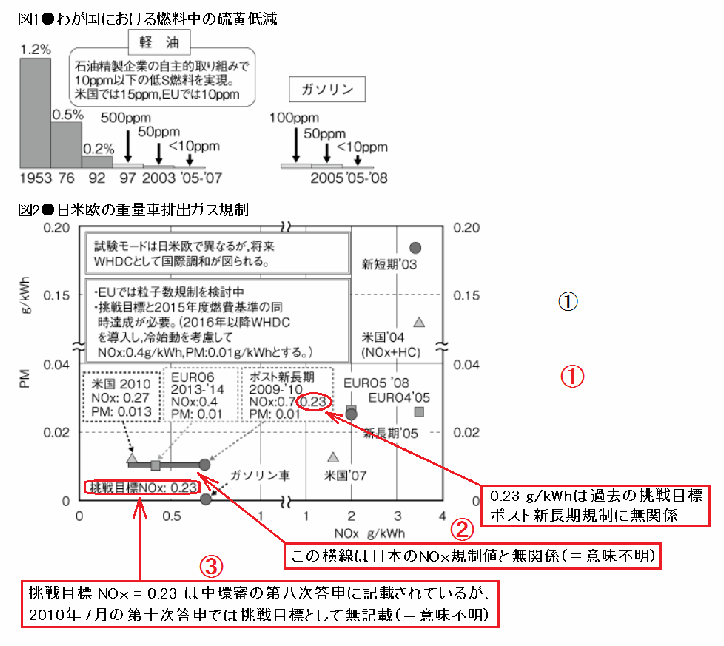 ���ړ_ �F �ȉ��Ɏ������O�q�̐}�Q�Q-�Q�Ɣ�r����ƁA����c��w�̑����������܂Ƃ߂���}�ɂ́A
�@�@�@�@�@�@�@�����_�̓��{�̏d�ʎԂ�NO���K���Ɩ��W�ȁu����ڕWNO�� �� 0.23 g/��W���v�����Ӗ���
�@�@�@�@�@�@�@�L�ڂ���Ă��邱�Ƃ�����B
�@�@�@�@�@�@�@����Ƃ��A�Ⴕ�����āA�������R�c��̎����Ԕr�o�K�X�Ɋւ����\�����\�ɂ́A����Ȃ��
�@�@�@�@�@�@�@�u����ڕWNO�� �� 0.23 g/��W���v���L�ڂ��ꂽ�u������v�Ȃ�ʁu���̑�\�����\���v�����݂���
�@�@�@�@�@�@�@�̂ł��낤���B
|
�@���������A�u����ڕWNO�� �� 0.23 g/��W���v�́A�������R�c��̑攪�����\�i2005�N�j�̕��ɂ͖��L�����
���邪�A���̌�̒������R�c��̑�\�����\�i2010�N�j�̕��ɂ͋L�ڂ���Ă��Ȃ��̂ł���B�����āA�攪
�����\�i2005�N�j�ɋL�ڂ��ꂽ���{�ł̏d�ʎԂ̏����̔r�o�K�X�K�����e��S�ʓI�Ɍ������A�C�����ꂽ�̂���\
�����\�i2010�N�j�̕��ł��邽�߁A�펯�I�ɂ́A�����_�̓��{�ł̏d�ʎԂ̏����̔r�o�K�X�K�������̓��e
�́A���̌�̑�\�����\�i2010�N�j�̕��Ɏ�����Ă��锤�ł���B���������āA�����_�̓��{�ł̏d�ʎԂ̏�
���̔r�o�K�X�K�������̐��{���j�̒��ɂ́A�u����ڕWNO�� �� 0.23 g/��W���v�����݂��Ȃ��ƌ���̂��Ó��Ȃ悤
�Ɏv����̂ł���B
���邪�A���̌�̒������R�c��̑�\�����\�i2010�N�j�̕��ɂ͋L�ڂ���Ă��Ȃ��̂ł���B�����āA�攪
�����\�i2005�N�j�ɋL�ڂ��ꂽ���{�ł̏d�ʎԂ̏����̔r�o�K�X�K�����e��S�ʓI�Ɍ������A�C�����ꂽ�̂���\
�����\�i2010�N�j�̕��ł��邽�߁A�펯�I�ɂ́A�����_�̓��{�ł̏d�ʎԂ̏����̔r�o�K�X�K�������̓��e
�́A���̌�̑�\�����\�i2010�N�j�̕��Ɏ�����Ă��锤�ł���B���������āA�����_�̓��{�ł̏d�ʎԂ̏�
���̔r�o�K�X�K�������̐��{���j�̒��ɂ́A�u����ڕWNO�� �� 0.23 g/��W���v�����݂��Ȃ��ƌ���̂��Ó��Ȃ悤
�Ɏv����̂ł���B
�@�Ƃ���ŁA�ߔN�A���E�āE���ɂ����ċK������������Ă���r�o�K�X�̐����́APM��NO���ł���B���̒���PM�K��
�ɂ��ẮA���{�̃|�X�g�V�����i2009�N�j�K���A�č���2010�ɔN�K�������2013�N����̉��B��EURO�O�U�K����
PM�K���l�� 0.1�`0.13 g/��W���ł��邽�߁A���E�āE����PM�K���l���u�قړ����v�ƌ`�e���邱�Ƃ́A�K�ƍl�����
��B�������ANO���K���l�ɂ��ẮA�č������ɂ���^�g���b�N��NO���K�����{�s����������{���{�̑Ӗ��ɏڏq��
�Ă���悤�ɁA���݂̓��{�̃|�X�g�V�����i2009�N�jNO���K���l�́A�č���2010�N��NO���K�������2013�N����̉�
�B��EURO�O�U��NO���K���l�ɔ�r���āA�啝�Ɋɂ��K���ƂȂ��Ă���B���̂��߁A���E�āE����NO���K�����u�قړ�
���v�Ƒ������Đ������邱�Ƃ́A���S�Ȍ��ƍl������B���̂悤�ɁA���E�āE���ɂ����āAPM�K����NO���K���ɏ�
���S���قȂ��Ă���B����ɂ�������炸�A�ȉ��Ɏ������悤�ɓ��{�����ԍH�Ɖ�̃z�[���y�[�W�Ɍf�ڂ́u�N���[
���E�f�B�[�[���G���W���Z�p�Ə����v�Ƒ肷��y�[�W�ɂ́A����c��w�̑��������́A�ȉ��ɂɎ������悤�ɁA���E�āE
���̑�^�g���b�N�̔r�o�K�X�K���Ɋւ��A���{�̃|�X�g�V�����i2009�N�j�r�o�K�X�K���l�́A�č���2010�ɔN�r�o�K
�X�K���l�ƁA2013�N����̉��B��EURO�O�U�r�o�K�X�K���l�Ƃ��u�قړ����v�Ƃ̌�������e���L�ڂ���Ă���B
�ɂ��ẮA���{�̃|�X�g�V�����i2009�N�j�K���A�č���2010�ɔN�K�������2013�N����̉��B��EURO�O�U�K����
PM�K���l�� 0.1�`0.13 g/��W���ł��邽�߁A���E�āE����PM�K���l���u�قړ����v�ƌ`�e���邱�Ƃ́A�K�ƍl�����
��B�������ANO���K���l�ɂ��ẮA�č������ɂ���^�g���b�N��NO���K�����{�s����������{���{�̑Ӗ��ɏڏq��
�Ă���悤�ɁA���݂̓��{�̃|�X�g�V�����i2009�N�jNO���K���l�́A�č���2010�N��NO���K�������2013�N����̉�
�B��EURO�O�U��NO���K���l�ɔ�r���āA�啝�Ɋɂ��K���ƂȂ��Ă���B���̂��߁A���E�āE����NO���K�����u�قړ�
���v�Ƒ������Đ������邱�Ƃ́A���S�Ȍ��ƍl������B���̂悤�ɁA���E�āE���ɂ����āAPM�K����NO���K���ɏ�
���S���قȂ��Ă���B����ɂ�������炸�A�ȉ��Ɏ������悤�ɓ��{�����ԍH�Ɖ�̃z�[���y�[�W�Ɍf�ڂ́u�N���[
���E�f�B�[�[���G���W���Z�p�Ə����v�Ƒ肷��y�[�W�ɂ́A����c��w�̑��������́A�ȉ��ɂɎ������悤�ɁA���E�āE
���̑�^�g���b�N�̔r�o�K�X�K���Ɋւ��A���{�̃|�X�g�V�����i2009�N�j�r�o�K�X�K���l�́A�č���2010�ɔN�r�o�K
�X�K���l�ƁA2013�N����̉��B��EURO�O�U�r�o�K�X�K���l�Ƃ��u�قړ����v�Ƃ̌�������e���L�ڂ���Ă���B
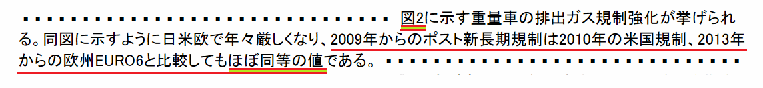 |
�@���݂ɁA���݂̓��E�āE���̑�^�g���b�N��NOx�K���ɂ��Đ�������ƁA�č���2010�N�K���l �� 0.27 g/��W���A��
�B��EURO�O�U�i2006�N�j�K���l �� 0.4 g/��W���A���{�̃|�X�g�V�����i2009�N�j�K���l �� 0.7 g/��W���ł���B���̂悤
�ɁA���{�̃|�X�g�V�����i2009�N�j�r�o�K�X�K���l�́A�āE���̑�^�g���b�N��NOx�K���l�Ƒ傫���قȂ��Ă���̂ł�
��B
�B��EURO�O�U�i2006�N�j�K���l �� 0.4 g/��W���A���{�̃|�X�g�V�����i2009�N�j�K���l �� 0.7 g/��W���ł���B���̂悤
�ɁA���{�̃|�X�g�V�����i2009�N�j�r�o�K�X�K���l�́A�āE���̑�^�g���b�N��NOx�K���l�Ƒ傫���قȂ��Ă���̂ł�
��B
�@���������āA����c��w�̑��������́A���{�����ԍH�Ɖ�̃z�[���y�[�W�ɂ́A���E�āE���̑�^�g���b�N�̔r�o
�K�X�K���Ɋւ��A���E�āE����PM�K���l���r����Ɓu�قړ����v�ł��邪�A���E�āE����NO���K���l���r����Ɓu��
�{���啝�Ɋɂ�NO���K�������{���v�ƋL�ڂ��ׂ��ł������ƍl������B�������A���������́A���E�āE���̑�^�g���b
�N�̔r�o�K�X�K���l���u�قړ����v�ƁA�M�҂ɂ͌��Ǝv����̓��e���L�ڂ���Ă���̂ł���B�܂�A��������
�́A�č��≢�B�ɔ�ׂē��{���ɂ߂Ċɂ�NO���K�������{���Ă��邱�Ƃ��Ӑ}�I�ɉB������Ă���悤�ɂ�������
�̂ł���B
�K�X�K���Ɋւ��A���E�āE����PM�K���l���r����Ɓu�قړ����v�ł��邪�A���E�āE����NO���K���l���r����Ɓu��
�{���啝�Ɋɂ�NO���K�������{���v�ƋL�ڂ��ׂ��ł������ƍl������B�������A���������́A���E�āE���̑�^�g���b
�N�̔r�o�K�X�K���l���u�قړ����v�ƁA�M�҂ɂ͌��Ǝv����̓��e���L�ڂ���Ă���̂ł���B�܂�A��������
�́A�č��≢�B�ɔ�ׂē��{���ɂ߂Ċɂ�NO���K�������{���Ă��邱�Ƃ��Ӑ}�I�ɉB������Ă���悤�ɂ�������
�̂ł���B
�@����Ƃ��A���������́A�����_�ȉ���NO���K���̋��������Ӗ��ł��邽�߁ANO���K���l0.27�`0.�V g/��W����NOx
�K�����u�قړ����v�Ƃ̈�ʐl�ƈقȂ���قȔ��f��������ꂽ�l���ł��낤���B�������������قȔ��f���
�l���ł���A�A�č��≢�B�ɔ�ׂē��{���ɂ߂Ċɂ�NO���K�������{���Ă��邱�Ƃ��Ӑ}�I�ɉB������ӎv����
���A�����āA���E�āE���̑�^�g���b�N�̔r�o�K�X�K���l���u�قړ����v�ƋL�ڂ��ꂽ�̂ł��낤���B�������Ȃ���A
���E�āE����NO���K���l��0.27�`0.�V g/��W���̑��Ⴊ����ɂ�������炸�A���E�āE���̔r�o�K�X�K���l�i��
NO���K�����܂ށj���u�قړ����v�Ƃ��鑐�������̋L�q�́A�펯�I�Ɍ���Ζ��炩�Ȍ��ƍl������B����
�āA�r�o�K�X�K���ɂ��Ă̐��Ƃ𐔑������������{�����ԍH�Ɖ���E�āE���̔r�o�K�X�K���l�i��NO
���K�����܂ށj�̌�����L���X�ƃz�[���y�[�W�Ɍf�ڂ��Ă��邱�Ƃ��A�M�҂ɂ͕s�v�c�Ɏv���Ďd���̖�
�������ł���B
�K�����u�قړ����v�Ƃ̈�ʐl�ƈقȂ���قȔ��f��������ꂽ�l���ł��낤���B�������������قȔ��f���
�l���ł���A�A�č��≢�B�ɔ�ׂē��{���ɂ߂Ċɂ�NO���K�������{���Ă��邱�Ƃ��Ӑ}�I�ɉB������ӎv����
���A�����āA���E�āE���̑�^�g���b�N�̔r�o�K�X�K���l���u�قړ����v�ƋL�ڂ��ꂽ�̂ł��낤���B�������Ȃ���A
���E�āE����NO���K���l��0.27�`0.�V g/��W���̑��Ⴊ����ɂ�������炸�A���E�āE���̔r�o�K�X�K���l�i��
NO���K�����܂ށj���u�قړ����v�Ƃ��鑐�������̋L�q�́A�펯�I�Ɍ���Ζ��炩�Ȍ��ƍl������B����
�āA�r�o�K�X�K���ɂ��Ă̐��Ƃ𐔑������������{�����ԍH�Ɖ���E�āE���̔r�o�K�X�K���l�i��NO
���K�����܂ށj�̌�����L���X�ƃz�[���y�[�W�Ɍf�ڂ��Ă��邱�Ƃ��A�M�҂ɂ͕s�v�c�Ɏv���Ďd���̖�
�������ł���B
�@��ʓI�ɂ́A�����_�ȉ���0.27�`0.�V g/��W����NOx�K���l���u�قړ����v�Ɣ��f���邱�Ƃɘ_���I�Ȗ����������
�l������B���̏؋��Ƃ��ċ������邱�Ƃ́A�|�X�g�V�����i2009�N�j��NO���K���l �� 0.7 g/��W������40������
NOx�K������������NOx�K���l�� �� 0.4 g/��W�� (2016�N���{�\��j�Ƃ��钆�����R�c����\�����\�i2010
�N�j�����Ȃɒ�o���ꂽ���Ƃł���B����́A�|�X�g�V�����i2009�N�j��NO���K���l �� 0.7 g/��W������40������
NOx�K�����������邱�Ƃɂ���āA���{�̑�C�������P�����Ƃ̍l���Ɋ�Â��čs��ꂽ�s�ׂł���ƍl�����
�邽�߂ł���B
�l������B���̏؋��Ƃ��ċ������邱�Ƃ́A�|�X�g�V�����i2009�N�j��NO���K���l �� 0.7 g/��W������40������
NOx�K������������NOx�K���l�� �� 0.4 g/��W�� (2016�N���{�\��j�Ƃ��钆�����R�c����\�����\�i2010
�N�j�����Ȃɒ�o���ꂽ���Ƃł���B����́A�|�X�g�V�����i2009�N�j��NO���K���l �� 0.7 g/��W������40������
NOx�K�����������邱�Ƃɂ���āA���{�̑�C�������P�����Ƃ̍l���Ɋ�Â��čs��ꂽ�s�ׂł���ƍl�����
�邽�߂ł���B
�@���̂悤�ɁA�������R�c��̑�\�����\�i2010�N�j�ł́A�|�X�g�V�����i2009�N�j��NOx�K�����������邱�Ƃ���
�\����Ă��鎖�������画�f����ƁA���{�����ԍH�Ɖ�̃z�[���y�[�W�ɂ����鑐���������č���2010�N�K���l
�� 0.27 g/��W���A���B��EURO�O�U�i2006�N�j�K���l �� 0.4 g/��W���A���{�̃|�X�g�V�����i2009�N�j�K���l �� 0.7 g/��
W�����K���l �� 0.7 g/��W���̎O��NOx�K�����x�����u�قړ����v�Ƃ�����e�̋L�ڂ́A�_���I�Ȗ���������ƌ�
�ĊԈႢ�Ȃ��ƍl������B���Ȃ킿�A���{�����ԍH�Ɖ�̃z�[���y�[�W�̒��ɑ�^�g���b�N��NO�K���l�ɂ��āA
�č���NOx�K���l��0.27 g/��W���A���B��NOx�K���l��0.4 g/��W���A���{��NOx�K���l��0.7 g/��W���̎O��NOx�K
�����x�����u�قړ����v�Ǝ咣������{�����ԍH�Ɖ�̃z�[���y�[�W JAMAGAZINE�@2012�N3�����ihttp://www.
jama.or.jp/lib/jamagazine/201203/03.html�j�Ɍf�ڂ��ꂽ����c��w�̑��������̋L�q�́A�u�o�L�ڂȌ�������e�v
�ƌ���̂��Ó��Ȃ悤�Ɏv����̂ł���B
�\����Ă��鎖�������画�f����ƁA���{�����ԍH�Ɖ�̃z�[���y�[�W�ɂ����鑐���������č���2010�N�K���l
�� 0.27 g/��W���A���B��EURO�O�U�i2006�N�j�K���l �� 0.4 g/��W���A���{�̃|�X�g�V�����i2009�N�j�K���l �� 0.7 g/��
W�����K���l �� 0.7 g/��W���̎O��NOx�K�����x�����u�قړ����v�Ƃ�����e�̋L�ڂ́A�_���I�Ȗ���������ƌ�
�ĊԈႢ�Ȃ��ƍl������B���Ȃ킿�A���{�����ԍH�Ɖ�̃z�[���y�[�W�̒��ɑ�^�g���b�N��NO�K���l�ɂ��āA
�č���NOx�K���l��0.27 g/��W���A���B��NOx�K���l��0.4 g/��W���A���{��NOx�K���l��0.7 g/��W���̎O��NOx�K
�����x�����u�قړ����v�Ǝ咣������{�����ԍH�Ɖ�̃z�[���y�[�W JAMAGAZINE�@2012�N3�����ihttp://www.
jama.or.jp/lib/jamagazine/201203/03.html�j�Ɍf�ڂ��ꂽ����c��w�̑��������̋L�q�́A�u�o�L�ڂȌ�������e�v
�ƌ���̂��Ó��Ȃ悤�Ɏv����̂ł���B
�@���̂悤�ɁA���{�����ԍH�Ɖ�̃z�[���y�[�W�ɂ́A�d�v�Ȏ����Ԕr�o�K�X�̋K�������̈�ł���NO���ɂ�
�Ă��A�u�č���2010�NNO���K���l �� 0.27 g/��W���v�Ɓu���{�̃|�X�g�V�����i2009�N�jNO���K���l �� 0.7 g/��
W���v�Ƃ��u�قړ����v�Ƃ���j���p�Ƃ��v����咣���s���Ă����̂ł���B��������c��w�̑��������̎�
���ɂ͋����ł��邪�A����ɂ������đ��������̌�����Z�p������{�����ԍH�Ɖ�z�[���y�[�W��
���X�ƌf�ڂ������Ă��邱�Ƃ́A�������ɂł����B���̂��Ƃ́A���ʓI�Ɂu���{�̒����Ȋw�ҁv�Ɓu���{�̎�v�Y��
�ł��鎩���ԃ��[�J�̒c�́v���������A���{�ɂ������^�g���b�N��NO���K���ɂ��Ắu�o�L�ڂȌ�����Z�p���v
���g�U���Ă���悤�Ɍ����邪�A����͕M�҂̒P�Ȃ�Ό��ł��낤���B���̂悤�ȍs�ׂ́A�u�R���v���C�A���X�i���@��
����j�v�̈ӎv���������Ă���悤�Ɍ����邪�A�@���Ȃ��̂ł��낤��
�Ă��A�u�č���2010�NNO���K���l �� 0.27 g/��W���v�Ɓu���{�̃|�X�g�V�����i2009�N�jNO���K���l �� 0.7 g/��
W���v�Ƃ��u�قړ����v�Ƃ���j���p�Ƃ��v����咣���s���Ă����̂ł���B��������c��w�̑��������̎�
���ɂ͋����ł��邪�A����ɂ������đ��������̌�����Z�p������{�����ԍH�Ɖ�z�[���y�[�W��
���X�ƌf�ڂ������Ă��邱�Ƃ́A�������ɂł����B���̂��Ƃ́A���ʓI�Ɂu���{�̒����Ȋw�ҁv�Ɓu���{�̎�v�Y��
�ł��鎩���ԃ��[�J�̒c�́v���������A���{�ɂ������^�g���b�N��NO���K���ɂ��Ắu�o�L�ڂȌ�����Z�p���v
���g�U���Ă���悤�Ɍ����邪�A����͕M�҂̒P�Ȃ�Ό��ł��낤���B���̂悤�ȍs�ׂ́A�u�R���v���C�A���X�i���@��
����j�v�̈ӎv���������Ă���悤�Ɍ����邪�A�@���Ȃ��̂ł��낤��
�@�Ȃ��A��L�̕\�R�O�́u��i���̏d�ʎԂ�NO���K����r�}�v�ł́A���������͈ȉ��̂R�ӏ��ɈӖ��s���ȁuNO��
�� 0.23 g/��W���v�Ƃ̋L�ڂ����Ă���̂ł���B
�� 0.23 g/��W���v�Ƃ̋L�ڂ����Ă���̂ł���B
�@ ���{�̃|�X�g�V�����K���l�̉ӏ��ɋK���l�Ɩ��W�ȁuNO�� �� 0.23 g/��W���v���L�ځi�\�R�O�Q�Ɓj
�A ���{�̃|�X�g�V����NOx�K���l�̃|�C���g����NO�� �� 0.23 g/��W���̃|�C���g�̊Ԃɓ��{��NO���K���Ɩ��W��
�������L�ځi�\�R�O�Q�Ɓj
�������L�ځi�\�R�O�Q�Ɓj
�B �������R�c��̑�\�����\�i2010�N���\�j�ɖ��L����Ă��Ȃ��u����ڕWNO�� �� 0.23 g/��W���v�Ӗ��ɋL
�ځi�\�R�O�Q�Ɓj
�ځi�\�R�O�Q�Ɓj
�@�m���ɁA�������R�c��̑攪�����\�i2005�N���\�j�ɂ́A�ȉ��̕\�R�P�Ɏ������悤�ɁA�u����ڕWNO��
�� 0.23 g/��W���i���|�X�g�V����NO�� �� 0.7 g/��W����1/3NO�����x�j�v�ƋL�ڂ���Ă����B�Ƃ��낪�A���̌�
�̒������R�c��̑�\�����\�i2010�N�j�ł́A�|�X�g�V�����K���i2009�N�K���j��������������NO���K��
�i2016�N���{�\��j�ł́ANO�� �� 0.4 g/��W���Ɩ��L���ꂽ�B���̌��ʁA�攪�����\�i2005�N���\�j�́u����
�ڕWNO�� �� 0.23 g/��W���v�́A�������R�c��ɂ����2010�N�̎��_�Ŋ��S�ɔ��̂ɂ��ꂽ�̂ł���B
�� 0.23 g/��W���i���|�X�g�V����NO�� �� 0.7 g/��W����1/3NO�����x�j�v�ƋL�ڂ���Ă����B�Ƃ��낪�A���̌�
�̒������R�c��̑�\�����\�i2010�N�j�ł́A�|�X�g�V�����K���i2009�N�K���j��������������NO���K��
�i2016�N���{�\��j�ł́ANO�� �� 0.4 g/��W���Ɩ��L���ꂽ�B���̌��ʁA�攪�����\�i2005�N���\�j�́u����
�ڕWNO�� �� 0.23 g/��W���v�́A�������R�c��ɂ����2010�N�̎��_�Ŋ��S�ɔ��̂ɂ��ꂽ�̂ł���B
 |
�@�ȏ�̕\�R�P�ɋL�ڂ���Ă���悤�ɁA�������R�c��̎����Ԕr�o�K�X�̑攪�����\�i2005�N���\�j�ɋL�ڂ���
�Ă���u����ڕWNO�� �� 0.23 g/��W���v�́A�����Ԕr�o�K�X�̑�\�����\�i2010�N���\�j�ɂ�������{�̏d�ʎԂ̎�
���r�o�K�X�K���ł���2016�N��NO���K���̋����ڕW�Ƃ��Ė��m�ɋL�ڂ���Ă����̂ł���B�������Ȃ���A������
���R�c��́A2016�N���{�\��ł́uNO�� �� 0.23 g/��W���v�́u����ڕW�v�������r�o�K�X�K���Ƃ����ꍇ�A���{�̏d
�ʎԂ͂��̎����r�o�K�X�K���i2016�N���{�\��j�ɓK�������邱�Ƃ�����Ɣ��f�����悤���B�������R�c��́A��
���Ԕr�o�K�X�̑攪�����\�i2005�N���\�j�ɋL�ڂ́u����ڕWNO�� �� 0.23 g/��W���v��p�~���A�����Ԕr�o�K�X�̑�
�\�����\�i2010�N���\�j�ɂ͎����r�o�K�X�K���l�i2016�N���{�\��j�Ƃ��ẮA�uNO�� �� 0.4 g/��W���v��NO���K���l
�\�����̂ł���B���̌��ʁA�������R�c��̎����Ԕr�o�K�X�̑�\�����\�i2010�N���\�j�ɂ́A�����r�o�K
�X�K���l�i2016�N���{�\��j�ł���uNO�� �� 0.4 g/��W���v���L�ڂ���Ă��邾���ł���B�����āA��\�����\�i2010
�N���\�j�ɂ́A�����r�o�K�X�K���l�i2016�N���{�\��j�ł���uNO�� �� 0.4 g/��W���v�̑��ɂ́A2016�N���{
�\��̎����r�o�K�X�K���̎���NO���K�������́u����ڕW�v�͉����L�ڂ���Ă��Ȃ��̂������ł���B����
�����āA�����_�i��2013�N8�����_�j�ɂ����āA�펯�I�ɓ��{�̏d�ʎԂ�NO���팸�́u����ڕWNO�� �� 0.23
g/��W���v�����݂��Ȃ��ƍl����̂��Ó��Ȃ悤�ł���B
�Ă���u����ڕWNO�� �� 0.23 g/��W���v�́A�����Ԕr�o�K�X�̑�\�����\�i2010�N���\�j�ɂ�������{�̏d�ʎԂ̎�
���r�o�K�X�K���ł���2016�N��NO���K���̋����ڕW�Ƃ��Ė��m�ɋL�ڂ���Ă����̂ł���B�������Ȃ���A������
���R�c��́A2016�N���{�\��ł́uNO�� �� 0.23 g/��W���v�́u����ڕW�v�������r�o�K�X�K���Ƃ����ꍇ�A���{�̏d
�ʎԂ͂��̎����r�o�K�X�K���i2016�N���{�\��j�ɓK�������邱�Ƃ�����Ɣ��f�����悤���B�������R�c��́A��
���Ԕr�o�K�X�̑攪�����\�i2005�N���\�j�ɋL�ڂ́u����ڕWNO�� �� 0.23 g/��W���v��p�~���A�����Ԕr�o�K�X�̑�
�\�����\�i2010�N���\�j�ɂ͎����r�o�K�X�K���l�i2016�N���{�\��j�Ƃ��ẮA�uNO�� �� 0.4 g/��W���v��NO���K���l
�\�����̂ł���B���̌��ʁA�������R�c��̎����Ԕr�o�K�X�̑�\�����\�i2010�N���\�j�ɂ́A�����r�o�K
�X�K���l�i2016�N���{�\��j�ł���uNO�� �� 0.4 g/��W���v���L�ڂ���Ă��邾���ł���B�����āA��\�����\�i2010
�N���\�j�ɂ́A�����r�o�K�X�K���l�i2016�N���{�\��j�ł���uNO�� �� 0.4 g/��W���v�̑��ɂ́A2016�N���{
�\��̎����r�o�K�X�K���̎���NO���K�������́u����ڕW�v�͉����L�ڂ���Ă��Ȃ��̂������ł���B����
�����āA�����_�i��2013�N8�����_�j�ɂ����āA�펯�I�ɓ��{�̏d�ʎԂ�NO���팸�́u����ڕWNO�� �� 0.23
g/��W���v�����݂��Ȃ��ƍl����̂��Ó��Ȃ悤�ł���B
�@���̂悤�ɁA��\�����\�i2010�N���\�j�ɓ��{�̏d�ʎԂɂ����鎟���r�o�K�X�K���ł���2016�N��NO���K���Ƃ���
�́A�������R�c��̑�\�����\�i2010�N�j�ł�NO�� �� 0.4 g/��W�����������L����Ă��邪�ANO���팸�́u�����
�W�v�͉����L�ڂ���Ă��Ȃ��̂ł���B�����āA���̒������R�c��̎����Ԕr�o�K�X�̑�\�����\�i2010�N���\�j
���疾�炩�Ȃ��Ƃ́A���{�̏d�ʎԂ�NO�� �� 0.4 g/��W���̎���NO���K���l�́A���s�̕č��K��(2010�N) NO�� �� 0.
27 g/��W���i�d�ʎԁj��� �� 33 �����x���ɂ�NO���K���l�ƂȂ��Ă��܂��Ă���A���ꂪ��R���鎖���ł���B���̂悤
�ɁA���{��NO���K���l�����s�̕č��K��(2010�N) NO�� �� 0.27 g/��W���i�d�ʎԁj��� �� 33 �����x���ɂ�NO���K��
���߂������������������{����悤�Ƃ��Ă��邱�Ƃ������ł���B
�́A�������R�c��̑�\�����\�i2010�N�j�ł�NO�� �� 0.4 g/��W�����������L����Ă��邪�ANO���팸�́u�����
�W�v�͉����L�ڂ���Ă��Ȃ��̂ł���B�����āA���̒������R�c��̎����Ԕr�o�K�X�̑�\�����\�i2010�N���\�j
���疾�炩�Ȃ��Ƃ́A���{�̏d�ʎԂ�NO�� �� 0.4 g/��W���̎���NO���K���l�́A���s�̕č��K��(2010�N) NO�� �� 0.
27 g/��W���i�d�ʎԁj��� �� 33 �����x���ɂ�NO���K���l�ƂȂ��Ă��܂��Ă���A���ꂪ��R���鎖���ł���B���̂悤
�ɁA���{��NO���K���l�����s�̕č��K��(2010�N) NO�� �� 0.27 g/��W���i�d�ʎԁj��� �� 33 �����x���ɂ�NO���K��
���߂������������������{����悤�Ƃ��Ă��邱�Ƃ������ł���B
�@�����āA���{�̏d�ʎԂɊւ��ẮA�啝�Ɋɋ߂������ɂ����Ă�NO���K���l���č��ɔ�r���Ă��������L�����
�����̒m��n�邱�Ƃ�}����Ӑ}�E�ړI�̂��߂ɁA���{�̏d�ʎԂɂ����鎟���r�o�K�X�K���̐ݒ�Ɋ֗^���鐭
�{�W�ҁE�w���o���҂ɋ߂�����c��w�̑��������́A�\�R�O�Ɏ������u��i���̏d�ʎԂ�NO���K����r�}�v�̒�
�ɁA�����_�ɂ�����d�ʎԂ̏����I�Ȕr�o�K�X�K�������Ɋւ�����{���{���j�Ɩ��W�ȁu����ڕWNO�� �� 0.
23 g/��W���v�̌����_�ʼn��̍����������Ӗ��s���̇@�`�B�̐��l���A�����ɋL�ڂ��Ă���ƍl������B�X�Ɍ��킹
�ĖႦ�A���������uNO�� �� 0.23 g/��W���v�̒ႢNO���l�́A�ŏ�����uNO���̒���ڕW�l�v�ł�����NO���K���l�ł�
�������߁A��L�̕\�R�O�́u��i���̏d�ʎԂ�NO���K����r�}�v�̒��̓��{��NO���K���̊֘A�������l�Ƃ��āuNO��
�� 0.23 g/��W���v���L�ڂ��邱�Ǝ��̂��傫�Ȍ���������v���ɂȂ�ƍl�����邪�A�@���Ȃ��̂ł��낤���B
�����̒m��n�邱�Ƃ�}����Ӑ}�E�ړI�̂��߂ɁA���{�̏d�ʎԂɂ����鎟���r�o�K�X�K���̐ݒ�Ɋ֗^���鐭
�{�W�ҁE�w���o���҂ɋ߂�����c��w�̑��������́A�\�R�O�Ɏ������u��i���̏d�ʎԂ�NO���K����r�}�v�̒�
�ɁA�����_�ɂ�����d�ʎԂ̏����I�Ȕr�o�K�X�K�������Ɋւ�����{���{���j�Ɩ��W�ȁu����ڕWNO�� �� 0.
23 g/��W���v�̌����_�ʼn��̍����������Ӗ��s���̇@�`�B�̐��l���A�����ɋL�ڂ��Ă���ƍl������B�X�Ɍ��킹
�ĖႦ�A���������uNO�� �� 0.23 g/��W���v�̒ႢNO���l�́A�ŏ�����uNO���̒���ڕW�l�v�ł�����NO���K���l�ł�
�������߁A��L�̕\�R�O�́u��i���̏d�ʎԂ�NO���K����r�}�v�̒��̓��{��NO���K���̊֘A�������l�Ƃ��āuNO��
�� 0.23 g/��W���v���L�ڂ��邱�Ǝ��̂��傫�Ȍ���������v���ɂȂ�ƍl�����邪�A�@���Ȃ��̂ł��낤���B
�@�����ԍH�Ɖ�̃z�[���y�[�W�Ɍf�ڂ́u�N���[���E�f�B�[�[���G���W���Z�p�Ə����v�Ƒ肷��y�[�W�́u��i���̏d
�ʎԂ�NO���K����r�}�v�̒��ɁA���̌����_�ł͏d�ʎԂ�NO���K�������Ɋւ��钆�����R�c��̎����Ԕr�o�K
�X�K���Ɩ��W�Ȑ��l�ł���uNO�� �� 0.23 g/��W���v�̒ႢNO���l���L�ڂ��邱�Ƃɂ���āA�����ԍH�Ɖ�̃z�[��
�y�[�W���{�������ǎ҂̒��ɂ́A���{�̏d�ʎԂ�NO���K���l�����s�̕č��K��(2010�N) NO�� �� 0.27 g/��W���Ɠ�
���ł���Ƃ̊��Ⴂ���ɋN�����Ă��܂��Ă���l�B�����������݂���\��������B���ɁA����c��w�̑���������
�Ӑ}�I�ɓ��{�����ԍH�Ɖ�̃z�[���y�[�W�Ɍf�ڂ́u�N���[���E�f�B�[�[���G���W���Z�p�Ə����v�Ƒ肷��y�[�W��
�ǎ҂ɓ��{�̏d�ʎԂ�NO���K���l�����s�̕č��K��(2010�N) NO�� �� 0.27 g/��W���Ɠ����ł���悤�Ȉ�ۑ����
�ϋɓI�ɍs���Ă����Ƃ���A�R�X�������Ƃł͂Ȃ����낤���B����ɂ��Ă��A�O�q�̕\�R�O�̓��{�����ԍH�Ɖ��
�z�[���y�[�W�Ɍf�ڂ́u�N���[���E�f�B�[�[���G���W���Z�p�Ə����v�Ƒ肷��y�[�W�́u��i���̏d�ʎԂ�NO���K����
�r�}�v�̒��̇@�`�B�̂R�ӏ��ɁuNO�� �� 0.23 g/��W���v�Ɋւ���L�ڂ����������ɂ������̂ł��邩�ɂ��āA����
�c��w�̑��������̌�ӌ����f���Č��������̂ł���B�Ȃ��A���̎����ԍH�Ɖ�́u���v�E�u�ԈႢ�v�̃z�[���y�[
�W�i��http://www.jama.or.jp/lib/jamagazine/201203/03.html�j�́A2014�N1��12�����݂ł����J����Ă���A�u���v��
��������Ă��Ȃ��悤���B�����ԍH�Ɖ�Ƒ���c��w�̑��������́A���̃z�[���y�[�W�̊Ԉ�������e�ɂ��Ă�
�u�����v�Ɓu���l�сv������ӎv������̂ł��낤���B
�ʎԂ�NO���K����r�}�v�̒��ɁA���̌����_�ł͏d�ʎԂ�NO���K�������Ɋւ��钆�����R�c��̎����Ԕr�o�K
�X�K���Ɩ��W�Ȑ��l�ł���uNO�� �� 0.23 g/��W���v�̒ႢNO���l���L�ڂ��邱�Ƃɂ���āA�����ԍH�Ɖ�̃z�[��
�y�[�W���{�������ǎ҂̒��ɂ́A���{�̏d�ʎԂ�NO���K���l�����s�̕č��K��(2010�N) NO�� �� 0.27 g/��W���Ɠ�
���ł���Ƃ̊��Ⴂ���ɋN�����Ă��܂��Ă���l�B�����������݂���\��������B���ɁA����c��w�̑���������
�Ӑ}�I�ɓ��{�����ԍH�Ɖ�̃z�[���y�[�W�Ɍf�ڂ́u�N���[���E�f�B�[�[���G���W���Z�p�Ə����v�Ƒ肷��y�[�W��
�ǎ҂ɓ��{�̏d�ʎԂ�NO���K���l�����s�̕č��K��(2010�N) NO�� �� 0.27 g/��W���Ɠ����ł���悤�Ȉ�ۑ����
�ϋɓI�ɍs���Ă����Ƃ���A�R�X�������Ƃł͂Ȃ����낤���B����ɂ��Ă��A�O�q�̕\�R�O�̓��{�����ԍH�Ɖ��
�z�[���y�[�W�Ɍf�ڂ́u�N���[���E�f�B�[�[���G���W���Z�p�Ə����v�Ƒ肷��y�[�W�́u��i���̏d�ʎԂ�NO���K����
�r�}�v�̒��̇@�`�B�̂R�ӏ��ɁuNO�� �� 0.23 g/��W���v�Ɋւ���L�ڂ����������ɂ������̂ł��邩�ɂ��āA����
�c��w�̑��������̌�ӌ����f���Č��������̂ł���B�Ȃ��A���̎����ԍH�Ɖ�́u���v�E�u�ԈႢ�v�̃z�[���y�[
�W�i��http://www.jama.or.jp/lib/jamagazine/201203/03.html�j�́A2014�N1��12�����݂ł����J����Ă���A�u���v��
��������Ă��Ȃ��悤���B�����ԍH�Ɖ�Ƒ���c��w�̑��������́A���̃z�[���y�[�W�̊Ԉ�������e�ɂ��Ă�
�u�����v�Ɓu���l�сv������ӎv������̂ł��낤���B
�@�܂��A�ȉ��̕\�R�Q�́u�����Q�T�N�x��ʈ��S���������u����ő���c��w�̑吹���������\�����ŋ߂̏d��
�Ԃ�NO���K���̔�r�}�v�Ɏ������悤�ɁA�吹�������܂��A���{�̏d�ʎԂ�NO���K���Ƃ��āuNO�� �� 0.23 g/��W���v��
�K���l���L�ڂ���Ă���B
�Ԃ�NO���K���̔�r�}�v�Ɏ������悤�ɁA�吹�������܂��A���{�̏d�ʎԂ�NO���K���Ƃ��āuNO�� �� 0.23 g/��W���v��
�K���l���L�ڂ���Ă���B
�@ ���{�̃|�X�g�V�����K���l�̉ӏ��ɋK���l�Ɩ��W�ȁuNO�� �� 0.23 g/��W���v���L�ځi�\�R�Q�Q�Ɓj
�A ���{�̃|�X�g�V����NOx�K���l�̃|�C���g����NO�� �� 0.23 g/��W���̃|�C���g�̊Ԃɓ��{��NO���K���Ɩ��W��
�������L�ځi�\�R�Q�Q�Ɓj
�������L�ځi�\�R�Q�Q�Ɓj
�@���̂悤�ɁA�O�q�̑���c��w�̑��������Ɠ��l�ɁA����c��w�̑吹�������A�����Q�T�N�x��ʈ��S������
���u����œ��{�̏d�ʎԂɂ����āA�uNO�� �� 0.23 g/��W���v��NO���K���l���������邩�̔@���u���̘_���E������
���ɋL�ڂ���Ă���̂ł���B����c��w�̑吹���������{�̏d�ʎԂ̃|�X�g�V����NO���K���ɂ����Ă͌�����
�Ȃ��uNO�� �� 0.23 g/��W���v��NO���K���l�X�ƋL�ڂ���Ă���ɂ��Ă��Ƃɂ��ẮA�M�҂ɂ͌��̂悤�Ɏv
����̂ł���B����Ƃ��A���{�̏d�ʎԂ̃|�X�g�V����NO���K���ɂ����āA�uNO�� �� 0.23 g/��W���v�̋K���l���{����
���݂��Ă���̂ł��낤���B
���u����œ��{�̏d�ʎԂɂ����āA�uNO�� �� 0.23 g/��W���v��NO���K���l���������邩�̔@���u���̘_���E������
���ɋL�ڂ���Ă���̂ł���B����c��w�̑吹���������{�̏d�ʎԂ̃|�X�g�V����NO���K���ɂ����Ă͌�����
�Ȃ��uNO�� �� 0.23 g/��W���v��NO���K���l�X�ƋL�ڂ���Ă���ɂ��Ă��Ƃɂ��ẮA�M�҂ɂ͌��̂悤�Ɏv
����̂ł���B����Ƃ��A���{�̏d�ʎԂ̃|�X�g�V����NO���K���ɂ����āA�uNO�� �� 0.23 g/��W���v�̋K���l���{����
���݂��Ă���̂ł��낤���B
�� �吹���������\�����u���� �F �����Q�T�N�x��ʈ��S���������u����
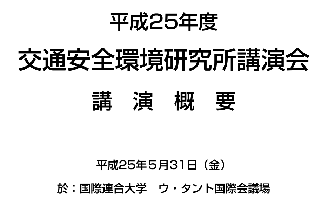 |
�� �吹�����̍u���̑�� �F �f�B�[�[�������Ԃ̔r�o�K�X��Z�p�̍ŐV����
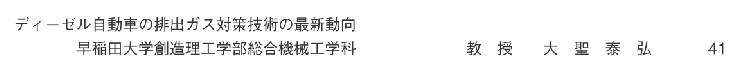 |
�� �吹�������u���Ŕ��\�����č�����щ��B�i��EURO)�̏d�ʎԂ�NO���K����r�}
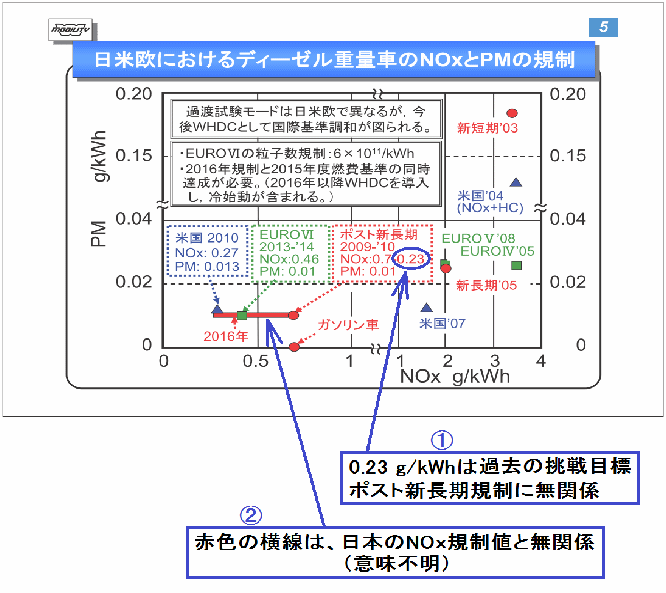 ���ړ_ �F �ȉ��Ɏ������O�q�̐}�Q�Q-�Q�Ɣ�r����ƁA����c��w�̑吹�������܂Ƃ߂���}�ɂ́A
�@�@�@�@�@�@�@�����_�̓��{�̏d�ʎԂ̃|�X�g�V�����K����NO���K���Ɩ��W�ȁuNO�� �� 0.23 g/��W���v��
�@�@�@�@�@�@�@���Ӗ��ɋL�ڂ���Ă��邱�Ƃ�����B
�@�@�@�@�@�@�@����Ƃ��A�Ⴕ�����āA�������R�c��̎����Ԕr�o�K�X�Ɋւ����\�����\�ɂ́A����̂悤��
�@�@�@�@�@�@�@�uNO�� �� 0.23 g/��W���v��NO���K���l���L�ڂ��ꂽ�u������v�Ȃ�ʁu���̑�\�����\�v��u�u����
�@�@�@�@�@�@�@�@NOx�K���l�v�����݂���̂ł��낤���B
|
�@��L�̕\�R�Q�Ɏ������悤�ɁA�����Q�T�N�x��ʈ��S���������u����ő吹���������\�����u���{�̏d�ʎԂ�
�|�X�g�V�����K���i2009�N-2010�N�K���j��NO���K���l��NO�� �F 0.7 - 0.23 g/��W���v�ƋL�ڂ̎�������ʈ��S����
�����̃z�[���y�[�W�ɓ��X�ƌf�ڂ���Ă���B���������ƁA�u�d�ʎԂ̃|�X�g�V�����K���ɂ�NO�� �� 0.23 g/��W��
�̋K�������ۂɑ��݂��邩�̔@���L�ڂ��ꂽ�����̓��e����ʈ��S���������E�������̈撷�̌㓡�Y�ꎁ
�����ӂ���Ă���悤�ł���B���݂ɁA�O�q���}�Q�P�Ɏ������悤�ɁA��ʈ��S���������̖����i���Ɩ��j�́A�u��
���Ԃ̊��Z�p��i�H�Ɗ�ł͂Ȃ�������j�Ă̍��肷�郋�[�����[�J�i���@�߂̍쐬�ҁj�v�ł��鎩������
�Ă���������̈撷�̌㓡�Y�ꎁ���f�����Ă���悤���B���̂��߁A�㓡�Y�ꎁ�͌�ʈ��S���������ɏ���
����Ă���E�Ӗʂ�����A���{�̏d�ʎԂ̃|�X�g�V�����K���i2009�N-2010�N�K���j��NO���K���l��NO�� �� 0.7 g/��
W���̌���ɐ[���֗^���ꂽ���̂ƍl������B���̏�A��ʈ��S���������̌㓡�Y�ꎁ������c��w�̑吹��
���́A�����������R�c��E��C������E�����Ԕr�o�K�X���ψ���̈ψ��ł��邱�Ƃ���A�|�X�g�V�����r�o
�K�X�K���̋K���l�ݒ�̃x�[�X�ƂȂ钆�����R�c��̓��\���쐬���ꂽ�����҂ł���悤���B���̂��߁A�㓡�Y
�ꎁ���吹�����̗����́A���{�̏d�ʎԂ̃|�X�g�V�����K���i2009�N-2010�N�K���j��NO���K���l��NO�� �� 0.7 g/
��W���ł��邱�Ƃ��n�m����Ă������ł���B
�|�X�g�V�����K���i2009�N-2010�N�K���j��NO���K���l��NO�� �F 0.7 - 0.23 g/��W���v�ƋL�ڂ̎�������ʈ��S����
�����̃z�[���y�[�W�ɓ��X�ƌf�ڂ���Ă���B���������ƁA�u�d�ʎԂ̃|�X�g�V�����K���ɂ�NO�� �� 0.23 g/��W��
�̋K�������ۂɑ��݂��邩�̔@���L�ڂ��ꂽ�����̓��e����ʈ��S���������E�������̈撷�̌㓡�Y�ꎁ
�����ӂ���Ă���悤�ł���B���݂ɁA�O�q���}�Q�P�Ɏ������悤�ɁA��ʈ��S���������̖����i���Ɩ��j�́A�u��
���Ԃ̊��Z�p��i�H�Ɗ�ł͂Ȃ�������j�Ă̍��肷�郋�[�����[�J�i���@�߂̍쐬�ҁj�v�ł��鎩������
�Ă���������̈撷�̌㓡�Y�ꎁ���f�����Ă���悤���B���̂��߁A�㓡�Y�ꎁ�͌�ʈ��S���������ɏ���
����Ă���E�Ӗʂ�����A���{�̏d�ʎԂ̃|�X�g�V�����K���i2009�N-2010�N�K���j��NO���K���l��NO�� �� 0.7 g/��
W���̌���ɐ[���֗^���ꂽ���̂ƍl������B���̏�A��ʈ��S���������̌㓡�Y�ꎁ������c��w�̑吹��
���́A�����������R�c��E��C������E�����Ԕr�o�K�X���ψ���̈ψ��ł��邱�Ƃ���A�|�X�g�V�����r�o
�K�X�K���̋K���l�ݒ�̃x�[�X�ƂȂ钆�����R�c��̓��\���쐬���ꂽ�����҂ł���悤���B���̂��߁A�㓡�Y
�ꎁ���吹�����̗����́A���{�̏d�ʎԂ̃|�X�g�V�����K���i2009�N-2010�N�K���j��NO���K���l��NO�� �� 0.7 g/
��W���ł��邱�Ƃ��n�m����Ă������ł���B
�@���������āA�吹�������㓡�Y�ꎁ�́A���{�̏d�ʎԂ̃|�X�g�V�����K���i2009�N-2010�N�K���j�ɂ�����NO���K
���ɂ́ANO�� �� 0.23 g/��W���̋K���l�����݂��Ă��Ȃ����Ƃ��\���ɏ��m����Ă��锤�ł���B����ɂ��������
���A�����Q�T�N�x��ʈ��S���������u����ő吹���������\������L�̕\�R�Q�̍u�������ɂ́A���{�̏d�ʎ�
�̃|�X�g�V�����K���i2009�N-2010�N�K���j��NO���K���l��NO�� �F 0.7 - 0.23 g/��W���v�ƋL�ڂ��ꂽ������
��ʈ��S���������̃z�[���y�[�W�ɓ��X�ƌf�ڂ���Ă����̂ł���B���������ƁA����c��w �吹������
��ʈ��S���������̃G���W���W�̐ӔC�҂ł���㓡�Y�ꎁ�́A���{�̏d�ʎԂ̃|�X�g�V�����K���i2009�N-
2010�N�K���j�ɂ�NO�� �� 0.23 g/��W�����K���l�����ۂɑ��݂��邩�̂悤�ȍ���̐}�\��p���A���{�̎����ԁi�d
�ʎԁj�r�o�K�X�K���ɂ��Ă̌�����Z�p�����Ӑ}�I�Ɍ��`����s�ׂ��s���Ă���悤�ɂ�������̂ł���B
���ɂ́ANO�� �� 0.23 g/��W���̋K���l�����݂��Ă��Ȃ����Ƃ��\���ɏ��m����Ă��锤�ł���B����ɂ��������
���A�����Q�T�N�x��ʈ��S���������u����ő吹���������\������L�̕\�R�Q�̍u�������ɂ́A���{�̏d�ʎ�
�̃|�X�g�V�����K���i2009�N-2010�N�K���j��NO���K���l��NO�� �F 0.7 - 0.23 g/��W���v�ƋL�ڂ��ꂽ������
��ʈ��S���������̃z�[���y�[�W�ɓ��X�ƌf�ڂ���Ă����̂ł���B���������ƁA����c��w �吹������
��ʈ��S���������̃G���W���W�̐ӔC�҂ł���㓡�Y�ꎁ�́A���{�̏d�ʎԂ̃|�X�g�V�����K���i2009�N-
2010�N�K���j�ɂ�NO�� �� 0.23 g/��W�����K���l�����ۂɑ��݂��邩�̂悤�ȍ���̐}�\��p���A���{�̎����ԁi�d
�ʎԁj�r�o�K�X�K���ɂ��Ă̌�����Z�p�����Ӑ}�I�Ɍ��`����s�ׂ��s���Ă���悤�ɂ�������̂ł���B
�@�����āA���₵�����A���Ȃ��������R�c��E��C������E�����Ԕr�o�K�X���ψ���̈ψ��ł�������c��
�w�̑吹��������ʈ��S���������̌㓡�Y�ꎁ�̗����ɂ��u������d�ʎԂ̃|�X�g�V�����K����NO���K���l
���g�U���銈���v���A���Ȃ����y��ʏȂɂ���ċ����I�ɒ��~�����邪����Ă��Ȃ��̂́A�@���Ȃ闝�R������
�̂ł��낤���B���ɁA��ʈ��S���������̎����ԐR�����́A�r�o�K�X���������{���A���{�̏d�ʎԂ��|�X�g�V��
���r�o�K�X�K���i2009�N-2010�N�K���j�̓K�ۂ�R������@�ւł���B���̍��y��ʏȂ̌�G���ł�����ʈ��S��
���������̃z�[���y�[�W�̌f�ڋL���̒��ɁA���{�̏d�ʎԂ̃|�X�g�V�����K���i2009�N-2010�N�K���j�Ƃ��Ă�NO
�� �� 0.23 g/��W���̋K���l�����݂��邩�@���A�����NO���K���l���������ɂ��킽���ē��X�ƋL�ڂ���Ă��邱�Ƃ�
��a�����o����̂́A�M�҂����ł��낤���B
�w�̑吹��������ʈ��S���������̌㓡�Y�ꎁ�̗����ɂ��u������d�ʎԂ̃|�X�g�V�����K����NO���K���l
���g�U���銈���v���A���Ȃ����y��ʏȂɂ���ċ����I�ɒ��~�����邪����Ă��Ȃ��̂́A�@���Ȃ闝�R������
�̂ł��낤���B���ɁA��ʈ��S���������̎����ԐR�����́A�r�o�K�X���������{���A���{�̏d�ʎԂ��|�X�g�V��
���r�o�K�X�K���i2009�N-2010�N�K���j�̓K�ۂ�R������@�ւł���B���̍��y��ʏȂ̌�G���ł�����ʈ��S��
���������̃z�[���y�[�W�̌f�ڋL���̒��ɁA���{�̏d�ʎԂ̃|�X�g�V�����K���i2009�N-2010�N�K���j�Ƃ��Ă�NO
�� �� 0.23 g/��W���̋K���l�����݂��邩�@���A�����NO���K���l���������ɂ��킽���ē��X�ƋL�ڂ���Ă��邱�Ƃ�
��a�����o����̂́A�M�҂����ł��낤���B
�@����Ƃ��A�ȏ���\�R�Q�Ɏ������u�����Q�T�N�x��ʈ��S���������u����ő吹���������\�����ŋ߂̏d�ʎ�
��NO���K���̔�r�}�v�̒��Ɏ�����Ă���悤�ɁA���{�̏d�ʎԂ̃|�X�g�V�����K���i2009�N-2010�N�K���j�ɂ���
�Ă�NO�� �� 0.23 g/��W�����K���l�����ۂɑ��݂��邽�߁A���Ȃ����y��ʏȂ́A�d�ʎԂ�NO�� �� 0.23 g/��W��
���K���l�̕\�L�����Ƃ���M�҂̎咣���Ԉ���Ă���Ƃ̌����ł��낤���B���ɁA�������Ȃ����y��ʏȂ̌�
���̒ʂ�ł���A�M�҂̓��{�̏d�ʎԂ̃|�X�g�V�����K���i2009�N-2010�N�K���j�ɂ����āA�uNO�� �� 0.23 g/��W
�����K���l�����݂��Ȃ��v�Ƃ���M�҂̎w�E�́A���S�Ɍ��ƂȂ�B���̏ꍇ�́A�M�҂̎w�E�����ł���Ƃ��闝
�R�E�����������Ă���������K���ł���B�����āA�M�҂��[���ł���A���̃z�[���y�[�W�ɋL�ڂ��Ă���u���{��
�|�X�g�V�����K���i2009�N-2010�N�K���j�ɂ͏d�ʎԂɂ�����NO�� �� 0.23 g/��W�����K���l�����݂��Ȃ��v�Ƃ̋L�q
�́A�����ɏC���E�����������ƍl���Ă���B�������A�����_�ł́A��L���\�R�Q�Ɏ������u���{�̏d�ʎԂ̃|�X�g�V��
���K���i2009�N-2010�N�K���j�ɂ����āA�d�ʎԂ�NO�� �� 0.23 g/��W�����K���l�̕\�L�v�����ł���ƁA�M�҂͌ł�
�M������B
��NO���K���̔�r�}�v�̒��Ɏ�����Ă���悤�ɁA���{�̏d�ʎԂ̃|�X�g�V�����K���i2009�N-2010�N�K���j�ɂ���
�Ă�NO�� �� 0.23 g/��W�����K���l�����ۂɑ��݂��邽�߁A���Ȃ����y��ʏȂ́A�d�ʎԂ�NO�� �� 0.23 g/��W��
���K���l�̕\�L�����Ƃ���M�҂̎咣���Ԉ���Ă���Ƃ̌����ł��낤���B���ɁA�������Ȃ����y��ʏȂ̌�
���̒ʂ�ł���A�M�҂̓��{�̏d�ʎԂ̃|�X�g�V�����K���i2009�N-2010�N�K���j�ɂ����āA�uNO�� �� 0.23 g/��W
�����K���l�����݂��Ȃ��v�Ƃ���M�҂̎w�E�́A���S�Ɍ��ƂȂ�B���̏ꍇ�́A�M�҂̎w�E�����ł���Ƃ��闝
�R�E�����������Ă���������K���ł���B�����āA�M�҂��[���ł���A���̃z�[���y�[�W�ɋL�ڂ��Ă���u���{��
�|�X�g�V�����K���i2009�N-2010�N�K���j�ɂ͏d�ʎԂɂ�����NO�� �� 0.23 g/��W�����K���l�����݂��Ȃ��v�Ƃ̋L�q
�́A�����ɏC���E�����������ƍl���Ă���B�������A�����_�ł́A��L���\�R�Q�Ɏ������u���{�̏d�ʎԂ̃|�X�g�V��
���K���i2009�N-2010�N�K���j�ɂ����āA�d�ʎԂ�NO�� �� 0.23 g/��W�����K���l�̕\�L�v�����ł���ƁA�M�҂͌ł�
�M������B
�@���͂Ƃ�����A�吹�������㓡�Y�ꎁ�́A���{�̏d�ʎԂ̃|�X�g�V�����K���i2009�N-2010�N�K���j��NO�� �� 0.
23 g/��W���̌������K���l�����ۂɑ��݂���Ƃ̌����^����悤�ȏ����g�U���Ă�����̂ƕM�҂͍l���Ă���B
�܂��A���{�̏d�ʎԂ̃|�X�g�V�����K���i2009�N-2010�N�K���j�ɂ��Ă̌��������ϋɓI�Ɍ��`����u����c
��w�̑吹�����v�Ɓu��ʈ��S���������̌㓡�Y�ꎁ�v�̖ړI�́A�M�҂̎א�����Ƃ���ł́A���{�̏d�ʎԂ�
�|�X�g�V�����K���i2009�N-2010�N�K���j�ɂ�����NO���K���l���č���2010�N��NO�� �� 0.27 g/��W���Ɠ����ł����
�̌�����F������{�����ɗ^����Ӑ}������悤�ɂ��v����̂ł���B���ɁA���ꂪ�����ł���A����c��w��
�吹��������ʈ��S���������̌㓡�Y�ꎁ�̍s�ׂ́A���{�̎����Ԕr�o�K�X�K���̐ݒ�Ɋ֗^����Ă���w
�ҁE���ƂƂ��Ắu�s�͂��疜�v�Ǝv�����A����͕M�҂̒P�Ȃ�u����v��u���Ⴂ�v�ł��낤���B
23 g/��W���̌������K���l�����ۂɑ��݂���Ƃ̌����^����悤�ȏ����g�U���Ă�����̂ƕM�҂͍l���Ă���B
�܂��A���{�̏d�ʎԂ̃|�X�g�V�����K���i2009�N-2010�N�K���j�ɂ��Ă̌��������ϋɓI�Ɍ��`����u����c
��w�̑吹�����v�Ɓu��ʈ��S���������̌㓡�Y�ꎁ�v�̖ړI�́A�M�҂̎א�����Ƃ���ł́A���{�̏d�ʎԂ�
�|�X�g�V�����K���i2009�N-2010�N�K���j�ɂ�����NO���K���l���č���2010�N��NO�� �� 0.27 g/��W���Ɠ����ł����
�̌�����F������{�����ɗ^����Ӑ}������悤�ɂ��v����̂ł���B���ɁA���ꂪ�����ł���A����c��w��
�吹��������ʈ��S���������̌㓡�Y�ꎁ�̍s�ׂ́A���{�̎����Ԕr�o�K�X�K���̐ݒ�Ɋ֗^����Ă���w
�ҁE���ƂƂ��Ắu�s�͂��疜�v�Ǝv�����A����͕M�҂̒P�Ȃ�u����v��u���Ⴂ�v�ł��낤���B
�@�Ƃ���ŁA���Ԃł́u���v�E�u�ԈႢ�v�ɂ��āu��ƂȂ����I�v�ƎӍ߂��ċ������̂͏��w���܂ł̎q���̏ꍇ��
�l���Ă���l�B������������悤���B�����āA���̂悤�Ȑl�B�́A��l�̐��E�ł́A�u���v�E�u�ԈႢ�v��F�߂ĎӍ߂�
�邱�Ƃ́A����܂ł̐M�p�E�M����r������Ƃ̍l���Ɋ�Â��ď�ɍs������Ƃ̂��Ƃł���B�܂�A���ȕېg�̂�
�߂Ɂu�R�͍Ō�܂Ŋт��ʂ��I�v�Ƃ̐M�O���������E�܂����l�B�ł���B���̂悤�Ȑl�B���C���^�[�l�b�g�̃z�[���y
�[�W�ɂ����āA�u���v�E�u�ԈႢ�v�̋Z�p�����L�ڂ����ꍇ�A�v���I�ȐM�p�E�M���̑r���������Ƃ̍l��������A�z
�[���y�[�W�́u���v�E�u�Ԉ�v�̋L�ړ��e���u�폜�v��u�����v�����ɕ��u�������邩�A����Ƃ������Ɂu�폜�v��u��
���v���s�������Ɏ~�߂ċ��U���̊g�U�ɂ��Ắu���l�сv��u�Ӎ߁v���ȗ��������u�ɂ��邩�̉��ꂩ�ł���Ɛ�
�������B���ɁA�����ԍH�Ɖ�ɊW����l�B�A����c��w�̑���������吹�����A����сi�Ɓj��ʈ��S����
�����̌㓡�Y�ꎁ�����ȕېg�̂��߂Ɂu�R�͍Ō�܂Ŋт��ʂ��I�v�Ƃ̐M�O���������l�B�ł��Ȃ�A�O�q�̎���
�ԍH�Ɖ����ʈ��S�����������u���v�E�u�ԈႢ�v���F�߂���C���^�[�l�b�g�̃z�[���y�[�W���u�����v���s���
�Ȃ����ꂪ�����ɂ���ƍl������B�Ȃ��A���̂悤�ɁA���U���́u�����v���s���Ȃ��ꍇ�ɂ́A�C���^�[�l�b�g��
�����U�̋Z�p����M���ꂽ����������������ď����Ȃ����Ƃ́A�����҂��̂ɖ����Ă����ׂ��ł͂Ȃ����낤
���B
�l���Ă���l�B������������悤���B�����āA���̂悤�Ȑl�B�́A��l�̐��E�ł́A�u���v�E�u�ԈႢ�v��F�߂ĎӍ߂�
�邱�Ƃ́A����܂ł̐M�p�E�M����r������Ƃ̍l���Ɋ�Â��ď�ɍs������Ƃ̂��Ƃł���B�܂�A���ȕېg�̂�
�߂Ɂu�R�͍Ō�܂Ŋт��ʂ��I�v�Ƃ̐M�O���������E�܂����l�B�ł���B���̂悤�Ȑl�B���C���^�[�l�b�g�̃z�[���y
�[�W�ɂ����āA�u���v�E�u�ԈႢ�v�̋Z�p�����L�ڂ����ꍇ�A�v���I�ȐM�p�E�M���̑r���������Ƃ̍l��������A�z
�[���y�[�W�́u���v�E�u�Ԉ�v�̋L�ړ��e���u�폜�v��u�����v�����ɕ��u�������邩�A����Ƃ������Ɂu�폜�v��u��
���v���s�������Ɏ~�߂ċ��U���̊g�U�ɂ��Ắu���l�сv��u�Ӎ߁v���ȗ��������u�ɂ��邩�̉��ꂩ�ł���Ɛ�
�������B���ɁA�����ԍH�Ɖ�ɊW����l�B�A����c��w�̑���������吹�����A����сi�Ɓj��ʈ��S����
�����̌㓡�Y�ꎁ�����ȕېg�̂��߂Ɂu�R�͍Ō�܂Ŋт��ʂ��I�v�Ƃ̐M�O���������l�B�ł��Ȃ�A�O�q�̎���
�ԍH�Ɖ����ʈ��S�����������u���v�E�u�ԈႢ�v���F�߂���C���^�[�l�b�g�̃z�[���y�[�W���u�����v���s���
�Ȃ����ꂪ�����ɂ���ƍl������B�Ȃ��A���̂悤�ɁA���U���́u�����v���s���Ȃ��ꍇ�ɂ́A�C���^�[�l�b�g��
�����U�̋Z�p����M���ꂽ����������������ď����Ȃ����Ƃ́A�����҂��̂ɖ����Ă����ׂ��ł͂Ȃ����낤
���B
�@�U�e�ɂ��p�ɂ��A�ȏ�̎����ԍH�Ɖ����ʈ��S���������́u���v�E�u�ԈႢ�v�̋Z�p�����f�ڂ����z�[���y
�[�W�ɂ��āA�����ԍH�Ɖ�̊W�ҁA�吹�����E���������i����c��w�j�A������㓡�Y�ꎁ�i��ʈ��S����
�����j�́A����A�z�[���y�[�W�́u���v�E�u�Ԉ�v�̋L�ړ��e�𖧂��ɍ폜�v��u�����v�Ɓu���l�сv��u�Ӎ߁v���s���̂�
���낤���B����Ƃ��A�u���v�E�u�ԈႢ�v�̔����E���\�ɖj��肵�Č��������������ߍ���ł��܂��S�Z�ł��낤���B����
�Ƃ��A�펯�I�ɍl����A���U���M�������邱�Ƃ́A���ʂ̐l�Ԃɂ͗ǐS�̙�ӂɑς����Ȃ����Ƃ��Ǝv��
���A�@���Ȃ��̂ł��낤���B����̐���s�������ڂ����Ƃ���ł���B�Ȃ��A����������ԍH�Ɖ����ʈ��S��
�������́u���v�E�u�ԈႢ�v�̋Z�p�����f�ڂ����z�[���[�W�̏��u�E�Ώ��̕��@�ɂ���āA�W���鏔���̐l�Ԑ�
���_�Ԍ��邱�Ƃ��ł��邩���m��Ȃ��B�M�҂ɂƂ��ẮA�����ÁX�Ȃ��Ƃł���B
�[�W�ɂ��āA�����ԍH�Ɖ�̊W�ҁA�吹�����E���������i����c��w�j�A������㓡�Y�ꎁ�i��ʈ��S����
�����j�́A����A�z�[���y�[�W�́u���v�E�u�Ԉ�v�̋L�ړ��e�𖧂��ɍ폜�v��u�����v�Ɓu���l�сv��u�Ӎ߁v���s���̂�
���낤���B����Ƃ��A�u���v�E�u�ԈႢ�v�̔����E���\�ɖj��肵�Č��������������ߍ���ł��܂��S�Z�ł��낤���B����
�Ƃ��A�펯�I�ɍl����A���U���M�������邱�Ƃ́A���ʂ̐l�Ԃɂ͗ǐS�̙�ӂɑς����Ȃ����Ƃ��Ǝv��
���A�@���Ȃ��̂ł��낤���B����̐���s�������ڂ����Ƃ���ł���B�Ȃ��A����������ԍH�Ɖ����ʈ��S��
�������́u���v�E�u�ԈႢ�v�̋Z�p�����f�ڂ����z�[���[�W�̏��u�E�Ώ��̕��@�ɂ���āA�W���鏔���̐l�Ԑ�
���_�Ԍ��邱�Ƃ��ł��邩���m��Ȃ��B�M�҂ɂƂ��ẮA�����ÁX�Ȃ��Ƃł���B
�@���Ă��āA���{�Ɖ��Ă̐�i���̏d�ʎԂ̐��m��NO���K���̔�r�}�́A���L�Ɏ������}�i�O�q�̐}�Q�Q-�Q�Ɠ����j
�̒ʂ�ł���B���̉��}�i���O�q�̐}�Q�Q-�Q�Ɠ����j������ƁA���s�̕č��K��(2010�N) NO�� �� 0.27 g/��W���ɔ�r
���A2016�N�̎��_�ł����{�̏d�ʎ�NO���K���l�� �� 33 �����x������Ă��邱�Ƃ���ڗđR�ł���B���̂悤�ɁA��
�{�̏d�ʎԂ�NO���K���́A�č���NO���K���ɔ�ׂĖ��炩�ɊÂ��Ċɂ������邽�߂ɂ́A�������R�c
��̑攪�����\�i2005�N���\�j�́u����ڕWNO�� �� 0.23 g/��W���v��NO���r�o�l���x������{�̏d�ʎԂ�NO���K��
�l�Ƃ��đ��}�ɐݒ肷�邱�Ƃł���B���̂��Ƃɂ��ẮA2009�N10��8���ɕM�҂����̃y�[�W���J�݂��Ĉȗ��A�M��
����т��Ď咣���Ă������Ƃł���B�����āA�C���x�~�́A�f�B�[�[���̂m�n���팸�ƔR�����̈ꋓ�����̋Z�p���I
�ɂ��ڏq���Ă���悤�ɁA��^�g���b�N���C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p���̗p�����ꍇ�ɂ́A����
NO�� �� 0.23 g/��W����NO���̔r�o���x�����e�ՂɒB���ł��邽�߁A�߂������ɓ��{�̏d�ʎԂ�NO���K���l�𐢊E
�ōł����������x����NO�� �� 0.23 g/��W���ɓK�������邱�Ƃɂ��ẮA�Z�p�I�ȏ�Q���肪���������ƍl���Ă�
��B
�̒ʂ�ł���B���̉��}�i���O�q�̐}�Q�Q-�Q�Ɠ����j������ƁA���s�̕č��K��(2010�N) NO�� �� 0.27 g/��W���ɔ�r
���A2016�N�̎��_�ł����{�̏d�ʎ�NO���K���l�� �� 33 �����x������Ă��邱�Ƃ���ڗđR�ł���B���̂悤�ɁA��
�{�̏d�ʎԂ�NO���K���́A�č���NO���K���ɔ�ׂĖ��炩�ɊÂ��Ċɂ������邽�߂ɂ́A�������R�c
��̑攪�����\�i2005�N���\�j�́u����ڕWNO�� �� 0.23 g/��W���v��NO���r�o�l���x������{�̏d�ʎԂ�NO���K��
�l�Ƃ��đ��}�ɐݒ肷�邱�Ƃł���B���̂��Ƃɂ��ẮA2009�N10��8���ɕM�҂����̃y�[�W���J�݂��Ĉȗ��A�M��
����т��Ď咣���Ă������Ƃł���B�����āA�C���x�~�́A�f�B�[�[���̂m�n���팸�ƔR�����̈ꋓ�����̋Z�p���I
�ɂ��ڏq���Ă���悤�ɁA��^�g���b�N���C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p���̗p�����ꍇ�ɂ́A����
NO�� �� 0.23 g/��W����NO���̔r�o���x�����e�ՂɒB���ł��邽�߁A�߂������ɓ��{�̏d�ʎԂ�NO���K���l�𐢊E
�ōł����������x����NO�� �� 0.23 g/��W���ɓK�������邱�Ƃɂ��ẮA�Z�p�I�ȏ�Q���肪���������ƍl���Ă�
��B
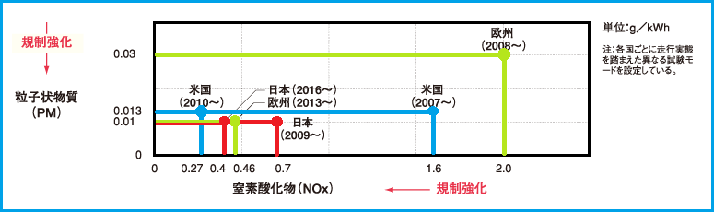
�P�U�|�R�@�V���ȁu��NO���E��R����Ԃ̊�v�����ɂ���NO���E��R��̑��i
�@�����A�ԗ��d��3.5��������^�g���b�N�ɑ����u�\�Q�X����NO���E��R����Ԃ̊(�āj�v�̂悤�����݂�
�u�����\�ɗD�ꂽ�o�X�E�g���b�N�v�̔F��ԂƂ��邱�Ƃɂ���āA��^�g���b�N�̒�NO�����ƒ�R��𑣐i���邱��
���\�ł���B���̍ہA������NO���E��R����Ԃ̊�ɓK�������ԗ��d��3.5��������^�g���b�N�ɑ��ẮA
���݂̒���Q��p�ԂɎg�p����Ă���ȉ��̂悤�ȃX�e�b�J�ɗގ������V���ȃX�e�b�J��ݒ肵�A�������\�t����
���Ƃ��ǂ��̂ł͂Ȃ����낤���B
�u�����\�ɗD�ꂽ�o�X�E�g���b�N�v�̔F��ԂƂ��邱�Ƃɂ���āA��^�g���b�N�̒�NO�����ƒ�R��𑣐i���邱��
���\�ł���B���̍ہA������NO���E��R����Ԃ̊�ɓK�������ԗ��d��3.5��������^�g���b�N�ɑ��ẮA
���݂̒���Q��p�ԂɎg�p����Ă���ȉ��̂悤�ȃX�e�b�J�ɗގ������V���ȃX�e�b�J��ݒ肵�A�������\�t����
���Ƃ��ǂ��̂ł͂Ȃ����낤���B
 |
 |
�@�����̎{���V���Ɏ��{���邱�Ƃɂ���āA���{�̑�^�g���b�N����ɂ����āA��C���̉��P�ƏȃG�l���M�[
���啝�ɐi�W�����邱�Ƃ��ł���ƍl������B���̂��߂ɂ́A���Ȃƍ��y��ʏ��R��́A���}��2016�N�Ɏ�
�{���\�肳��Ă��鎟���m�n���K���l�@���@0.4 g/kWh �Ƃ͈قȂ����V����3.5���������o�X�E�g���b�N�ɑ���
�u��NO���E��R����Ԋ�i�āj�v���u�����\�ɗD�ꂽ�o�X�E�g���b�N�v�̔F����̓K�����x�������邱
�Ƃ��K�ƍl���Ă���B���́u��NO���E��R����Ԃ̊�i�āj�v�̓K���Ԃɂ́A�V���ȗD���Ő��̓K�p��
�J�n���邱�Ƃł���B
���啝�ɐi�W�����邱�Ƃ��ł���ƍl������B���̂��߂ɂ́A���Ȃƍ��y��ʏ��R��́A���}��2016�N�Ɏ�
�{���\�肳��Ă��鎟���m�n���K���l�@���@0.4 g/kWh �Ƃ͈قȂ����V����3.5���������o�X�E�g���b�N�ɑ���
�u��NO���E��R����Ԋ�i�āj�v���u�����\�ɗD�ꂽ�o�X�E�g���b�N�v�̔F����̓K�����x�������邱
�Ƃ��K�ƍl���Ă���B���́u��NO���E��R����Ԃ̊�i�āj�v�̓K���Ԃɂ́A�V���ȗD���Ő��̓K�p��
�J�n���邱�Ƃł���B
�@���̂悤���A���ȁA���y��ʏȂɂ́A�f�B�[�[���d�ʎԂɂ��Ă��\�Q�Q�̊�ɓK��������NO���E��R���
�Ԃɑ��Ă̗D���Ő��̂𑁊��ɓ������Ē����������̂ł���B����ɂ���đ�^�g���b�N���[�J���]���ȏ�ɒ�R
��Z�p�̊J���ɐ^���Ɏ��g�ނ��Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��ƍl������B
�Ԃɑ��Ă̗D���Ő��̂𑁊��ɓ������Ē����������̂ł���B����ɂ���đ�^�g���b�N���[�J���]���ȏ�ɒ�R
��Z�p�̊J���ɐ^���Ɏ��g�ނ��Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��ƍl������B
�@�܂��A���Ȃƍ��y��ʏȂ��V���ȁu��NO���E��R����Ԋ�v�ɓK��������^�g���b�N�ɑ��A�]�����G�R�J�[
���łƓ��l�̐ł̗D�����s���A���ʓI�ɂ����Ȃ�2005�N�̑攪�����\���m�n���̒���ڕW�Ƃ��Ď�����Ă���
�@0.7 g/kWh�� 1/3���x�i���@0.23�@g/kWh�j��NO���팸�����̂܂��{�ł��邱�ƂɂȂ�̂ł���B���̂��Ƃ́A�攪��
���\�ɋL�ڂ���Ă����m�n���̒���ڕW��V���Ȋ�i���K���j�ɔ��f�ł������ƂɂȂ�̂��B���̂悤�ȑ�^�g���b�N
�̔R��팸��CO�Q�팸�̎{����ȃG�l���M�[�Ƒ�C�����P�ɐϋɓI�ȍs���̏Ƃ��č����Ɏ������Ƃɂ��A��
�y��ʏ��͍����]���������̂ƍl������B
���łƓ��l�̐ł̗D�����s���A���ʓI�ɂ����Ȃ�2005�N�̑攪�����\���m�n���̒���ڕW�Ƃ��Ď�����Ă���
�@0.7 g/kWh�� 1/3���x�i���@0.23�@g/kWh�j��NO���팸�����̂܂��{�ł��邱�ƂɂȂ�̂ł���B���̂��Ƃ́A�攪��
���\�ɋL�ڂ���Ă����m�n���̒���ڕW��V���Ȋ�i���K���j�ɔ��f�ł������ƂɂȂ�̂��B���̂悤�ȑ�^�g���b�N
�̔R��팸��CO�Q�팸�̎{����ȃG�l���M�[�Ƒ�C�����P�ɐϋɓI�ȍs���̏Ƃ��č����Ɏ������Ƃɂ��A��
�y��ʏ��͍����]���������̂ƍl������B
�@�ȏ�̂悤�ȐV���Ȑ��x�̓����ɂ���Ē�R��g���b�N�̏��i�������i����邱�Ƃɂ��A��^�g���b�N�̃��[�U
�́A������2015�N�x�d�ʎԔR�������{�P�O �� ���x�����P������R��̑�^�g���b�N���w���ł���悤�ɂȂ邽
�߁A�ݕ��A���Ɩ��ɂ�����R����̍팸�̉��b������ł���̂ł���B�������A�g���b�N���[�J�ɂƂ��ẮA�C���x�~
�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p�𑁊��Ɏ��p�����邽�߂̌����J���Ɩ����ɖZ�ƂȂ邪�A�߂������A����
���{���Ȃ���Ȃ�Ȃ������J���ł���B���̂��߁A�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p�̊J���̎�
�{�����������A���܂邾���̂��Ƃł���A�傫�ȋ]���⑹�������̂ł͖����ƍl������B
�́A������2015�N�x�d�ʎԔR�������{�P�O �� ���x�����P������R��̑�^�g���b�N���w���ł���悤�ɂȂ邽
�߁A�ݕ��A���Ɩ��ɂ�����R����̍팸�̉��b������ł���̂ł���B�������A�g���b�N���[�J�ɂƂ��ẮA�C���x�~
�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p�𑁊��Ɏ��p�����邽�߂̌����J���Ɩ����ɖZ�ƂȂ邪�A�߂������A����
���{���Ȃ���Ȃ�Ȃ������J���ł���B���̂��߁A�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p�̊J���̎�
�{�����������A���܂邾���̂��Ƃł���A�傫�ȋ]���⑹�������̂ł͖����ƍl������B
�@���̂悤�ɁA���Ȃ����y��ʏȂ��V�����u��NO���E��R����Ԃ̊�v�̐��x�������ꍇ�A�e�g���b�N���[
�J���C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p���̗p����NO�����E��R�������^�g���b�N�������Ĕ�������
���Ƃ͖����ł���B���݂ɁA���Ȃ����y��ʏȂ��u��NO���E��R����Ԋ�v�̐��x�����邱�Ƃɂ���āA
���{��g���b�N���[�U����э����ɂ͑���̗��v�������炳��A�܂��A�g���b�N���[�J�ɂƂ��Ă��傫���]���⑹����
�������̂ł͖����B���������āA���Ȃ����y��ʏȂ��g���b�N�E�o�X�E�g���b�N��ΏۂƂ����u��NO���E��R���
��v�i�\�Q�V���Q�Ɓj�̐��x���V���ɓ����������Ƃ́A�킪���ɂ������^�g���b�N�̍X�Ȃ��NO�����ƒ�R
��𑣐i���邽�߂ɂ͍őP�̍�ł͂Ȃ����낤���B�Ȃ��A��^�g���b�N�̐V�����u��NO���E��R��g���b�N�E�o�X
�̊�v�ɂ��ẮA���{�͑�^�g���b�N�̐V���Ȓ�R��E��r�o�K�X��𑁊��ɐݒ肹��I�ɂ��ڏq���Ă����
�ŁA�䗗�������������B
�J���C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p���̗p����NO�����E��R�������^�g���b�N�������Ĕ�������
���Ƃ͖����ł���B���݂ɁA���Ȃ����y��ʏȂ��u��NO���E��R����Ԋ�v�̐��x�����邱�Ƃɂ���āA
���{��g���b�N���[�U����э����ɂ͑���̗��v�������炳��A�܂��A�g���b�N���[�J�ɂƂ��Ă��傫���]���⑹����
�������̂ł͖����B���������āA���Ȃ����y��ʏȂ��g���b�N�E�o�X�E�g���b�N��ΏۂƂ����u��NO���E��R���
��v�i�\�Q�V���Q�Ɓj�̐��x���V���ɓ����������Ƃ́A�킪���ɂ������^�g���b�N�̍X�Ȃ��NO�����ƒ�R
��𑣐i���邽�߂ɂ͍őP�̍�ł͂Ȃ����낤���B�Ȃ��A��^�g���b�N�̐V�����u��NO���E��R��g���b�N�E�o�X
�̊�v�ɂ��ẮA���{�͑�^�g���b�N�̐V���Ȓ�R��E��r�o�K�X��𑁊��ɐݒ肹��I�ɂ��ڏq���Ă����
�ŁA�䗗�������������B
�P�V�@�C���x�~�̑�^�g���b�N���ŏ��Ɏ��p�����ĔR����ɏ������郁�[�J�́H
�@�킪���ł́A1974�N�Ƀf�B�[�[�������Ԃ�NO���i���f�_�����j�̔r�o�K�X�K�����J�n���肳��Ĉȗ��A�f�B�[�[��
�G���W���ł́uNO���ƔR��g���[�h�I�t�W�ɂ���v���Ƃ���A�f�B�[�[���G���W���ł̔R�����͓���Ƃ̈ӌ��E
�咣��ڂɂ��邱�Ƃ����������B����́A����܂ő����̒����Ȋw�ҁE���Ƃ́uNO���ƔR��̃g���[�h�I�t�W�v�̓�
���������ăf�B�[�[���G���W���ł̔R����P�̓����͐�����Ă������߂��B�������A���́uNO���ƔR��̃g���[�h�I
�t�W�v�́A�f�B�[�[���R�ĂɌ��肵����̎��ۂł���A�f�B�[�[���G���W���S�̂̔R����c�_����ꍇ�ɂ͓��i
�Ɏ��グ�邱�Ƃł͂Ȃ��B�������A����́A�����̒����Ȋw�ҁE���Ƃ̓f�B�[�[���G���W���̔R����P�̎�i���f
�B�[�[���R�Ă̌������サ���O���ɂȂ��A�ނ�̔��z���R�����������Ƃ��ő�̌����ł��������߂ł͂Ȃ����낤
���B���̂悤�Ȃ��Ƃ���A����܂Ő��\�N�Ԃɂ킽��A�f�B�[�[���G���W���ł́uNO���ƔR��̃g���[�h�I�t�W�v�̓���
�ɂ���ăf�B�[�[���G���W���ł�NO���팸�ƔR�����Ƃ��Ɏ������邱�Ƃ́A�ɂ߂č���Ƃ̏펯���蒅���Ă�
���B���̂��߁A�Z�p���i���������݂ł��A�����Ɂu�f�B�[�[���ɂ�����NO���ƔR��̃g���[�h�I�t�̎����v���甲����
��Ă��Ȃ��w�ҁE���Ƃ������悤�Ɋ�����̂ł���B
�G���W���ł́uNO���ƔR��g���[�h�I�t�W�ɂ���v���Ƃ���A�f�B�[�[���G���W���ł̔R�����͓���Ƃ̈ӌ��E
�咣��ڂɂ��邱�Ƃ����������B����́A����܂ő����̒����Ȋw�ҁE���Ƃ́uNO���ƔR��̃g���[�h�I�t�W�v�̓�
���������ăf�B�[�[���G���W���ł̔R����P�̓����͐�����Ă������߂��B�������A���́uNO���ƔR��̃g���[�h�I
�t�W�v�́A�f�B�[�[���R�ĂɌ��肵����̎��ۂł���A�f�B�[�[���G���W���S�̂̔R����c�_����ꍇ�ɂ͓��i
�Ɏ��グ�邱�Ƃł͂Ȃ��B�������A����́A�����̒����Ȋw�ҁE���Ƃ̓f�B�[�[���G���W���̔R����P�̎�i���f
�B�[�[���R�Ă̌������サ���O���ɂȂ��A�ނ�̔��z���R�����������Ƃ��ő�̌����ł��������߂ł͂Ȃ����낤
���B���̂悤�Ȃ��Ƃ���A����܂Ő��\�N�Ԃɂ킽��A�f�B�[�[���G���W���ł́uNO���ƔR��̃g���[�h�I�t�W�v�̓���
�ɂ���ăf�B�[�[���G���W���ł�NO���팸�ƔR�����Ƃ��Ɏ������邱�Ƃ́A�ɂ߂č���Ƃ̏펯���蒅���Ă�
���B���̂��߁A�Z�p���i���������݂ł��A�����Ɂu�f�B�[�[���ɂ�����NO���ƔR��̃g���[�h�I�t�̎����v���甲����
��Ă��Ȃ��w�ҁE���Ƃ������悤�Ɋ�����̂ł���B
�@���̂悤�ȏ���ςł���Z�p���A�M�҂̒�Ă���C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p�ł���B��
�̋Z�p�́A�uNO���팸�ƔR�����̗������\�ɂ������I�ȋZ�p�v�ł��邱�Ƃ𑽂��̊w�ҁE���Ƃɂ͉���������
�Ă������������ƍl���Ă����B�����āA���N�̃f�B�[�[���G���W���́u���]��Q�H�v�Ƃ����������ȁuNO���ƔR��̃g���[
�h�I�t�W�v�̓����ɂ���āu�f�B�[�[���G���W���̔R����オ����v�Ƃ���펯���L�b�p���Ǝ̂ċ����Ē��������Ǝv
���Ă���B�Ȃ��A�����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j���Z�p�̓������܂Ƃ߂�ƁA�ȉ��̒ʂ�ł���B
�̋Z�p�́A�uNO���팸�ƔR�����̗������\�ɂ������I�ȋZ�p�v�ł��邱�Ƃ𑽂��̊w�ҁE���Ƃɂ͉���������
�Ă������������ƍl���Ă����B�����āA���N�̃f�B�[�[���G���W���́u���]��Q�H�v�Ƃ����������ȁuNO���ƔR��̃g���[
�h�I�t�W�v�̓����ɂ���āu�f�B�[�[���G���W���̔R����オ����v�Ƃ���펯���L�b�p���Ǝ̂ċ����Ē��������Ǝv
���Ă���B�Ȃ��A�����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j���Z�p�̓������܂Ƃ߂�ƁA�ȉ��̒ʂ�ł���B
�@�@�E�@�T�`�P�O���̏d�ʎԃ��[�h�R��̍팸
�@�@�@�@�@�i�ڍׂ́A�C���x�~�́A�R��팸�ƔA�fSCR��NO���팸���̌���ɗL�����I�A���쎩���Ԃ��_�����\��
���R����P�@�\�̗��C���x�~�V�X�e�����Q�Ɓj
���R����P�@�\�̗��C���x�~�V�X�e�����Q�Ɓj
�@�@�E�@�r�C�K�X���x�̍������ɂ��A�fSCR�G�}�ł̏\����NO���̍팸
�@�@�@�@�@�i�ڍׂ́A�C���x�~�́A�R��팸�ƔA�fSCR��NO���팸���̌���ɗL�����I�A�f�B�[�[���̋C���x�~�́A
�R�[���h�X�^�[�g��NO���팸�ɂ��L�����I���Q�Ɓj
�R�[���h�X�^�[�g��NO���팸�ɂ��L�����I���Q�Ɓj
�@�@�E�@�r�C�K�X���x�̍������ɂ��DPF�̎��ȍĐ��̑��i�ɂ��R���Q���h�~
�@(�R����̌����ł���DPF���u���蓮�܂��͎����̍Đ��p�x���팸�j
�@�@�@�@�@�@�i�ڍׂ́A�C���x�~��DPF�̎��ȍĐ��𑣐i (�R����̖h�~�ɗL���j���Q�Ɓj
�@����܂ł������ԋZ�p�����{�@�B�w��̍u����̔��\�_����_���W�̌f�ژ_�����������A�C���x�~�G���W
���i�������J2005-54771�j�ɕC�G����u�R���NO���̗������팸�ł���Z�p�v�ɑ����������Ƃ��Ȃ��B�f�B�[�[���G��
�W���̔R������NO���팸�Ɋւ��A�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�Ɠ������A�Ⴕ���͂��̋Z�p�𗽉킷
��Z�p���䑶���̏ꍇ�ɂ́A����Ƃ����������������Ǝv���Ă���B���ɁA�ŋ߂ł́A����̑�w�E�����@�ցE�g���b
�N���[�J������\���ȔR��������������Z�p���J�������Ƃ̔��\��ڂɂ������Ƃ������B
���i�������J2005-54771�j�ɕC�G����u�R���NO���̗������팸�ł���Z�p�v�ɑ����������Ƃ��Ȃ��B�f�B�[�[���G��
�W���̔R������NO���팸�Ɋւ��A�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�Ɠ������A�Ⴕ���͂��̋Z�p�𗽉킷
��Z�p���䑶���̏ꍇ�ɂ́A����Ƃ����������������Ǝv���Ă���B���ɁA�ŋ߂ł́A����̑�w�E�����@�ցE�g���b
�N���[�J������\���ȔR��������������Z�p���J�������Ƃ̔��\��ڂɂ������Ƃ������B
�@�Ƃ���ŁA�M�҂͂P�X�V�Q�N�Ɏ����ԃ��[�J�ɏA�E���A���N�A�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W���̌����J���Ɍg������o
��������B�����ŕM�҂��S�����A�����ȔR����P�ɐ��������Z�p���u�������v��u�C���^�[�N�[���ߋ����v�ł������B��
���͖��ߋ��̕������R�Ď��̃g���b�N�p�f�B�[�[���G���W������ʓI�ł���������ɁA�u�ߗ�������\�R�Ď�����
IDI�R�Ă��璼�����ւ�DI�R�ĕ����̕ϊ��v��u�f�B�[�[���G���W���̃C���^�[�N�[���ߋ����v�̋Z�p��V���ɍ̗p��
�邱�Ƃɂ���āA�T�`�P�T�����x�̃f�B�[�[���G���W���̔R�����ł����̂ł���B
��������B�����ŕM�҂��S�����A�����ȔR����P�ɐ��������Z�p���u�������v��u�C���^�[�N�[���ߋ����v�ł������B��
���͖��ߋ��̕������R�Ď��̃g���b�N�p�f�B�[�[���G���W������ʓI�ł���������ɁA�u�ߗ�������\�R�Ď�����
IDI�R�Ă��璼�����ւ�DI�R�ĕ����̕ϊ��v��u�f�B�[�[���G���W���̃C���^�[�N�[���ߋ����v�̋Z�p��V���ɍ̗p��
�邱�Ƃɂ���āA�T�`�P�T�����x�̃f�B�[�[���G���W���̔R�����ł����̂ł���B
�@�����u�������v��u�C���^�[�N�[���ߋ����v�́A�G���W���T�C�N�����_��ɂ����āA���Ƀf�B�[�[���G���W���̔M��
����ł��邱�Ƃ��ǂ��m���Ă��Z�p�ł���B�������A����܂ł̓^�[�{�ߋ��@��R�����ˑ��u���̐��\�����
�Ă������߂ɂ����Z�p�̎��p�����x��Ă������̂ł���B�������A�M�҂��f�B�[�[���G���W���J����S����������
�́A���x�A�^�[�{�ߋ��@��R�����ˑ��u���̐��\������I�Ɍ��サ������ł��������߁A�u�������v��u�C���^�[�N
�[���ߋ����v�̋Z�p��K�p�����g���b�N�p�f�B�[�[���G���W���́A�G���W���T�C�N���̗��_�ʂ�ɑ啝�ȔR������
�����̂ł���B�t�Ȍ�����������A�f�B�[�[���G���W���̐��p�[�Z���g�̔M�����̌�����������邽�߂ɂ́A����
�G���W���̍l�Êw�̕���ɂȂ��Ă��邩������Ȃ����A�G���W���T�C�N�����_����e�Ղɏؖ��ł���Z�p�ɂ���ď�
�߂Ď����ł�����̂Ǝv���Ă���B
����ł��邱�Ƃ��ǂ��m���Ă��Z�p�ł���B�������A����܂ł̓^�[�{�ߋ��@��R�����ˑ��u���̐��\�����
�Ă������߂ɂ����Z�p�̎��p�����x��Ă������̂ł���B�������A�M�҂��f�B�[�[���G���W���J����S����������
�́A���x�A�^�[�{�ߋ��@��R�����ˑ��u���̐��\������I�Ɍ��サ������ł��������߁A�u�������v��u�C���^�[�N
�[���ߋ����v�̋Z�p��K�p�����g���b�N�p�f�B�[�[���G���W���́A�G���W���T�C�N���̗��_�ʂ�ɑ啝�ȔR������
�����̂ł���B�t�Ȍ�����������A�f�B�[�[���G���W���̐��p�[�Z���g�̔M�����̌�����������邽�߂ɂ́A����
�G���W���̍l�Êw�̕���ɂȂ��Ă��邩������Ȃ����A�G���W���T�C�N�����_����e�Ղɏؖ��ł���Z�p�ɂ���ď�
�߂Ď����ł�����̂Ǝv���Ă���B
�@�������A�ŋ߂̊w�҂�Z�p�҂́A�u�R�������[���ɂ�鍂�������i���˂₻�̑��i���˂̕��˗ʂƕ��ˎ����̐�
��v�A�uVG�^�[�{�ɂ��ߋ��ʂ̐���v����сuEGR�̗ʂƉ��x�̐���v�������̃G���W���^�]�ɍœK�ȏ�ԂɂȂ��
�������ɐ��䂷�邱�Ƃɂ���ăf�B�[�[���G���W���́uNO���팸�v�Ƌ��Ɂu�R�����v�������ł���Ǝ咣����Ă���l
�������悤���B�������A���́u�f�B�[�[���G���W���^�]�̐�������v�́A�uNO���팸�v�ɂ͗L���ł��邪�A�u�R�����v��
�͗]��傫�Ȍ��ʂ��ł��Ȃ����̂ƍl������B���݂Ɂu�R�����v�́A�u�f�B�[�[���T�C�N���̔M�����̌���v�A
�u��p�����̍팸�v�A�u���C�����̍팸�v����сu�|���s���O�����̍팸�v���̌ÓT�I�ȃG���W���T�C�N�����_�ɂ���
�āA�̂����w�̃G���W���H�w�̎��Ƃŋ������Ă���悤�ȋZ�p�ɂ���ď��߂Ď����ł���悤�Ɏv����̂ł���B
���������āA�u�G���W���^�]�̐�������v�ɂ���ĔR����シ��Ƃ̍ŋ߂̃G���W���W�̊w�҂�Z�p�ҏ����̈�
���E�咣�́A�f�B�[�[���G���W���ɂ�����R�����̊�]���q�ׂĂ��邾���ɂ悤�Ɏv����̂��B�M�҂��猩��A
���̂悤�Ȃ��Ƃ́A�P�Ɂu�f�B�[�[���G���W���̔R�����v�̊�Ղ̓������A�_�╧�Ɋ肤�����������Ă��邾���̂�
���Ɍ�����̂ł���B
��v�A�uVG�^�[�{�ɂ��ߋ��ʂ̐���v����сuEGR�̗ʂƉ��x�̐���v�������̃G���W���^�]�ɍœK�ȏ�ԂɂȂ��
�������ɐ��䂷�邱�Ƃɂ���ăf�B�[�[���G���W���́uNO���팸�v�Ƌ��Ɂu�R�����v�������ł���Ǝ咣����Ă���l
�������悤���B�������A���́u�f�B�[�[���G���W���^�]�̐�������v�́A�uNO���팸�v�ɂ͗L���ł��邪�A�u�R�����v��
�͗]��傫�Ȍ��ʂ��ł��Ȃ����̂ƍl������B���݂Ɂu�R�����v�́A�u�f�B�[�[���T�C�N���̔M�����̌���v�A
�u��p�����̍팸�v�A�u���C�����̍팸�v����сu�|���s���O�����̍팸�v���̌ÓT�I�ȃG���W���T�C�N�����_�ɂ���
�āA�̂����w�̃G���W���H�w�̎��Ƃŋ������Ă���悤�ȋZ�p�ɂ���ď��߂Ď����ł���悤�Ɏv����̂ł���B
���������āA�u�G���W���^�]�̐�������v�ɂ���ĔR����シ��Ƃ̍ŋ߂̃G���W���W�̊w�҂�Z�p�ҏ����̈�
���E�咣�́A�f�B�[�[���G���W���ɂ�����R�����̊�]���q�ׂĂ��邾���ɂ悤�Ɏv����̂��B�M�҂��猩��A
���̂悤�Ȃ��Ƃ́A�P�Ɂu�f�B�[�[���G���W���̔R�����v�̊�Ղ̓������A�_�╧�Ɋ肤�����������Ă��邾���̂�
���Ɍ�����̂ł���B
�@��ʓI�ɁA�f�B�[�[���G���W���̔R�����ł������Ƃ�ΊO�I�ɐ�������ꍇ�́A���̐��ʂƂ��Ă͏��Ȃ��Ƃ���
�p�[�Z���g���x�̉��P���������Ƃ��펯�ł͂Ȃ����낤���B���̐��p�[�Z���g�̃��x���̔R����P�́A�G���W���T�C
�N�����_�ł̔R�����i�M�����̑���j�������ł���Z�p�ɂ���ď��߂Ď����ł�����̂ƍl������B����ɑ�
���A�f�B�[�[���G���W����NO���Z�x�͌��X���������̃��x���ł���B���̂��߁A����NO���̍팸�ɂ��ẮA�R�Ď���
�̈ꕔ�̋Ǐ��I�ȍ����̉Ή��̈�Ŕ�������NO�����������̃��x���ō팸���邱�Ƃɂ���āANO���팸���Ƃ��Ă͐�
�\�p�[�Z���g�̃��x���̉��P���ł������ƂɂȂ�B���̂悤�ɁANO���̍팸�͔R�Ă̔����Ȑ���ɂ���ĔR�Ď�����
�ꕔ�̋Ǐ��I�ȍ����̉Ή��̈�̏k����}�邱�Ƃɂ���ĉ\�ɂł�����̂ł���A�G���W���T�C�N���̗��_�ł�
�M�����̌���ɂ���Ď����ł���R��팸�Ƃ͑S���قȂ���̂ł���B���̂��߁A�u�R�����v�ƁuNO���팸�v�́A�S��
�َ��̊J���ƍl����ׂ��ł͂Ȃ����낤���B
�p�[�Z���g���x�̉��P���������Ƃ��펯�ł͂Ȃ����낤���B���̐��p�[�Z���g�̃��x���̔R����P�́A�G���W���T�C
�N�����_�ł̔R�����i�M�����̑���j�������ł���Z�p�ɂ���ď��߂Ď����ł�����̂ƍl������B����ɑ�
���A�f�B�[�[���G���W����NO���Z�x�͌��X���������̃��x���ł���B���̂��߁A����NO���̍팸�ɂ��ẮA�R�Ď���
�̈ꕔ�̋Ǐ��I�ȍ����̉Ή��̈�Ŕ�������NO�����������̃��x���ō팸���邱�Ƃɂ���āANO���팸���Ƃ��Ă͐�
�\�p�[�Z���g�̃��x���̉��P���ł������ƂɂȂ�B���̂悤�ɁANO���̍팸�͔R�Ă̔����Ȑ���ɂ���ĔR�Ď�����
�ꕔ�̋Ǐ��I�ȍ����̉Ή��̈�̏k����}�邱�Ƃɂ���ĉ\�ɂł�����̂ł���A�G���W���T�C�N���̗��_�ł�
�M�����̌���ɂ���Ď����ł���R��팸�Ƃ͑S���قȂ���̂ł���B���̂��߁A�u�R�����v�ƁuNO���팸�v�́A�S��
�َ��̊J���ƍl����ׂ��ł͂Ȃ����낤���B
�@���������āA���݁A�g���b�N���[�J�̋Z�p�҂��w�E�����@�ւ̊w�ҁE���Ƃ��f�B�[�[���G���W����NO���팸�ƔR
�����̗����Ɋ�^�ł���Ɗ��҂���Ă���PCI�R�āi��HCCI�R�āj�ɗނ���Z�p�́A�G���W���T�C�N���̗��_�ł�
�M�����̌��オ�����ł��Ȃ��Z�p���B���̂悤�ȋZ�p��p���ăf�B�[�[���G���W���̏\���ȔR������}�邱�Ƃ́A
�����Ď�������邱�Ƃ��Ȃ��ƍl������B����A�G���W���T�C�N���̗��_���猩���ꍇ�̔M�����̌��オ�����ł�
�Ȃ��Z�p�̌����J�������p�����悤�Ƃ��A��^�g���b�N�E�g���N�^�̏\���ȔR��͌��シ�邱�Ƃ͓�����낤�B����
���Ƃ𗝉��ł��Ȃ��g���b�N���[�J�́A��^�g���b�N�E�g���N�^�̑����̎Ԏ���Q�O�P�T�N�x�d�ʎԔR���ɕs�K���̏�
�Ԃŕ��u���Ă��܂����ƂɂȂ���̂ƍl������B
�����̗����Ɋ�^�ł���Ɗ��҂���Ă���PCI�R�āi��HCCI�R�āj�ɗނ���Z�p�́A�G���W���T�C�N���̗��_�ł�
�M�����̌��オ�����ł��Ȃ��Z�p���B���̂悤�ȋZ�p��p���ăf�B�[�[���G���W���̏\���ȔR������}�邱�Ƃ́A
�����Ď�������邱�Ƃ��Ȃ��ƍl������B����A�G���W���T�C�N���̗��_���猩���ꍇ�̔M�����̌��オ�����ł�
�Ȃ��Z�p�̌����J�������p�����悤�Ƃ��A��^�g���b�N�E�g���N�^�̏\���ȔR��͌��シ�邱�Ƃ͓�����낤�B����
���Ƃ𗝉��ł��Ȃ��g���b�N���[�J�́A��^�g���b�N�E�g���N�^�̑����̎Ԏ���Q�O�P�T�N�x�d�ʎԔR���ɕs�K���̏�
�Ԃŕ��u���Ă��܂����ƂɂȂ���̂ƍl������B
�@���āA�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j���G���W���T�C�N�����_�I�ɂ��M����������ł��邱�Ƃɂ���
���A�C���x�~�́A�R��팸�ƔA�fSCR��NO���팸���̌���ɗL�����I�ɏڏq���Ă���̂Ō䗗�������������B����
�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�́A�R���NO���̗������팸�ł���ɂ߂ėD�ꂽ�Z�p�ł���B��������
�āA�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�́A��^�g���b�N�E�g���N�^�̑S�Ԏ���u2016�N�Ɏ��{���\�肳��Ă���
����NO���K���̋����v��A2013�N6�����݂ɂ����č��y��ʏȂ����������u2015�N�x�R���ɑ��������R��K��
�̋����v�ɓK�������邽�߁A����A�g���b�N���[�J�����}�ɊJ�����Ă����ׂ��Z�p�ł��邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ����낤�B
���A�C���x�~�́A�R��팸�ƔA�fSCR��NO���팸���̌���ɗL�����I�ɏڏq���Ă���̂Ō䗗�������������B����
�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�́A�R���NO���̗������팸�ł���ɂ߂ėD�ꂽ�Z�p�ł���B��������
�āA�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�́A��^�g���b�N�E�g���N�^�̑S�Ԏ���u2016�N�Ɏ��{���\�肳��Ă���
����NO���K���̋����v��A2013�N6�����݂ɂ����č��y��ʏȂ����������u2015�N�x�R���ɑ��������R��K��
�̋����v�ɓK�������邽�߁A����A�g���b�N���[�J�����}�ɊJ�����Ă����ׂ��Z�p�ł��邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ����낤�B
�@�����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̍ő�̓����́A�W���T�C�Y�i��r�C�ʁj�̃G���W���𓋍ڂ�����
�^�g���b�N��A�_�E���T�C�W���O�i���r�C�ʁj�̃G���W���𓋍ڂ�����^�g���b�N�ȂǁA����̑�^�g���b�N�ɂ����Ă��T
�`�P�O���̊����ŏd�ʎԃ��[�h�R�������ł��邱�Ƃ��B���̂悤�ɁA�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z
�p�́A�G���W���T�C�Y�̑召�i���r�C�ʂ̑召�j�̔@���ɂ�����炸�A���̋Z�p���̗p��������̑�^�g���b�N�ł��A
�d�ʎԃ��[�h�R�������ł���̂ł���B
�^�g���b�N��A�_�E���T�C�W���O�i���r�C�ʁj�̃G���W���𓋍ڂ�����^�g���b�N�ȂǁA����̑�^�g���b�N�ɂ����Ă��T
�`�P�O���̊����ŏd�ʎԃ��[�h�R�������ł��邱�Ƃ��B���̂悤�ɁA�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z
�p�́A�G���W���T�C�Y�̑召�i���r�C�ʂ̑召�j�̔@���ɂ�����炸�A���̋Z�p���̗p��������̑�^�g���b�N�ł��A
�d�ʎԃ��[�h�R�������ł���̂ł���B
�@�Ƃ���ŁA�ŋ߂ł́A���\�N���̂���FF��p�Ԃɑ����� �u�d����p�t�@���v�Ɛ��N�O����n�C�u���b�h��p�Ԃɑ�
�����u�d���E�H�[�^�[�|���v�v�̋Z�p��V���ɍ̗p���邱�Ƃɂ��A��^�g���b�N�E�g���N�^�̏d�ʎԃ��[�h�R����{
�T���������i��http://car.watch.impress.co.jp/docs/news/20140624_654839.html�j�ł����Ƃ̂��Ƃł���B���̏�p��
�W�ɂ���������Z�p�ł���u�d����p�t�@���v�Ɓu�d���E�H�[�^�[�|���v�v�̐V���ȑ����ɂ��A��^�g���b�N�E�g���N�^
�̑S�Ԏ��2015�N�x�d�ʎԔR���ɂ����邱�Ƃ��\�ɂȂ����Ƃ̂��Ƃł���B�������A�߂������ɁA2015�N�x�d
�ʎԔR���́{�P�O�����x�̊���������{���ꂽ�ꍇ�́A���̐V���ɋ������ꂽ�R���ɑ�^�g���b�N�E�g��
�N�^��K�������邱�Ƃ́A�ɂ߂č���ƍl������B���́{�P�O�����x�̊�������ꂽ�����̔R���ɑ�^�g���b
�N�E�g���N�^��K�������邱�Ƃ��\�ȋZ�p�́A�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p�ł���B������
���āA�s��ł��R����ŗD�ʂɗ��������g���b�N���[�J�́A�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p�J��
�ɑ��}�ɒ��肷�邱�Ƃł͂Ȃ����낤���B
�����u�d���E�H�[�^�[�|���v�v�̋Z�p��V���ɍ̗p���邱�Ƃɂ��A��^�g���b�N�E�g���N�^�̏d�ʎԃ��[�h�R����{
�T���������i��http://car.watch.impress.co.jp/docs/news/20140624_654839.html�j�ł����Ƃ̂��Ƃł���B���̏�p��
�W�ɂ���������Z�p�ł���u�d����p�t�@���v�Ɓu�d���E�H�[�^�[�|���v�v�̐V���ȑ����ɂ��A��^�g���b�N�E�g���N�^
�̑S�Ԏ��2015�N�x�d�ʎԔR���ɂ����邱�Ƃ��\�ɂȂ����Ƃ̂��Ƃł���B�������A�߂������ɁA2015�N�x�d
�ʎԔR���́{�P�O�����x�̊���������{���ꂽ�ꍇ�́A���̐V���ɋ������ꂽ�R���ɑ�^�g���b�N�E�g��
�N�^��K�������邱�Ƃ́A�ɂ߂č���ƍl������B���́{�P�O�����x�̊�������ꂽ�����̔R���ɑ�^�g���b
�N�E�g���N�^��K�������邱�Ƃ��\�ȋZ�p�́A�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p�ł���B������
���āA�s��ł��R����ŗD�ʂɗ��������g���b�N���[�J�́A�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p�J��
�ɑ��}�ɒ��肷�邱�Ƃł͂Ȃ����낤���B
�@�Ƃ���ŁA���J���h��AVL�̂悤�Ȑ��E�I�ɗL���Ȍ����@�ւ�����Z�p�ł͖����A�M�҂̂悤�Ȉ�ʐl�����
����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p�̌����J�������{�����ۂɂ́A�����̃g���b�N���[�J�̎Г���
�́A�G���W���n�Z�p�҂ɑ��āu���\�v�ƍ��]�����\�����ɂ߂č����B���������āA���ȕېg�ɋ��X�Ƃ����G���W
���Z�p�n�����������e���͂����g���b�N���[�J�ł́A���̂悤�ȎГ�����̔ᔻ������A�C���x�~�G���W���i����
���J2005-54771�j�̋Z�p���������邱�ƂɂȂ�̂ł͂Ȃ����낤���B���̏ꍇ�A���̃g���b�N���[�J�́A����̑�
�^�g���b�N�E�g���N�^�̔R��팸�̋����Ɍ�������Ă��܂����̂Ɨ\�z�����B
����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p�̌����J�������{�����ۂɂ́A�����̃g���b�N���[�J�̎Г���
�́A�G���W���n�Z�p�҂ɑ��āu���\�v�ƍ��]�����\�����ɂ߂č����B���������āA���ȕېg�ɋ��X�Ƃ����G���W
���Z�p�n�����������e���͂����g���b�N���[�J�ł́A���̂悤�ȎГ�����̔ᔻ������A�C���x�~�G���W���i����
���J2005-54771�j�̋Z�p���������邱�ƂɂȂ�̂ł͂Ȃ����낤���B���̏ꍇ�A���̃g���b�N���[�J�́A����̑�
�^�g���b�N�E�g���N�^�̔R��팸�̋����Ɍ�������Ă��܂����̂Ɨ\�z�����B
�@���͂Ƃ�����A����A�e�g���b�N���[�J���C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p�J���ɒ��肷�邩�ۂ���
���A�e�g���b�N���[�J�ɂ����鍡��̑�^�g���b�N�E�g���N�^�̔R��̗D���肳��Ă��܂����̂Ǝv���Ă���B�ʂ�
���āA�R����̌�������^�g���b�N�E�g���N�^�̔̔��s��ɂ����āA����̊e�g���b�N���[�J�ɂ����鏤�i�̗͂D��
�́A�@���Ȃ��̂ɂȂ�̂ł��낤���B���ʂ��y���݂��B
���A�e�g���b�N���[�J�ɂ����鍡��̑�^�g���b�N�E�g���N�^�̔R��̗D���肳��Ă��܂����̂Ǝv���Ă���B�ʂ�
���āA�R����̌�������^�g���b�N�E�g���N�^�̔̔��s��ɂ����āA����̊e�g���b�N���[�J�ɂ����鏤�i�̗͂D��
�́A�@���Ȃ��̂ɂȂ�̂ł��낤���B���ʂ��y���݂��B
�@�܂��A2006�N4���P����2015�N�x�d�ʎԔR�����{�s����Ċ���5�N���x�̍Ό����o�߂��Ă��邱�Ƃ���A����
�R��K�����������ׂ��������������Ă��邽�߂��A�T�����x�̔R������v������d�ʎԔR���̋������s��
���\��������B�܂��A�ŋ߂ł͉��L�̗��R�ɂ���Đ��E�̐Ζ����v���N������X�������Ă���A�߂������A�y
�����i�̍������\�z����Ă���B
�R��K�����������ׂ��������������Ă��邽�߂��A�T�����x�̔R������v������d�ʎԔR���̋������s��
���\��������B�܂��A�ŋ߂ł͉��L�̗��R�ɂ���Đ��E�̐Ζ����v���N������X�������Ă���A�߂������A�y
�����i�̍������\�z����Ă���B
�@�E�@���݂̓I�C���s�[�N�̎�����}���Ă���A���E�̌������Y�ʂ́A����A�Q���̌X��
�E�@�G�W�v�g�̖��剻�����ɒ[���������e���̐����s���ɂ��A�����ł̌������Y�ʂ͌����̋���
�@�E�@�����A�C���h���̐V�����́A�o�ϔ��W�⎩���Ԕ̔��̌����ɂ��Ζ�����ʂ̑���ŁA�����̕N��
�@�E�@�����{��k�Ђł̔ߎS�ȕ����������̂ɂ���Ĕ������̐��_�̍��܂肩��Η͔��d���������A���E�e���ł�
�Ζ����v�̑���
�Ζ����v�̑���
�@�ȏ�̂悤�Ȍ������Y�̌����ƐΖ�����̑���ɉ����A�ߔN�ł̕č�FRB�̃h���̑�ʔ��s�ɔ����h�����l�̉�
���ɂ��A�߂������A�������i�͂Q�O�O�h���^�o�����܂ŏ㏸����Ɖ]���Ă���B���̂悤�ȏꍇ�ɂ́A����A�䂪
���������̉~���ɂȂ����Ƃ��Ă��y���̎s�̉��i�͌��s�̂Q�{�߂��̂Q�O�O�~�^���b�g������܂ō������Ă��܂�
�\�����ے�ł��Ȃ��B���̂悤�Ȏ���ɂ́A�g���b�N���[�U�̔R�����̗v���E�j�[�Y�����܂邱�Ƃ͕K�����B�Ƃ�
�낪�A�ŋ߂̓��{�@�B�w��⎩���ԋZ�p��̍u����ł́A�f�B�[�[���G���W���ł̏\���ȔR����P�����҂ł����
���đ����̊w�ҁE���Ƃ����ڂ���悤�ȐV�Z�p����������Ȃ��̂�����̂悤���B
���ɂ��A�߂������A�������i�͂Q�O�O�h���^�o�����܂ŏ㏸����Ɖ]���Ă���B���̂悤�ȏꍇ�ɂ́A����A�䂪
���������̉~���ɂȂ����Ƃ��Ă��y���̎s�̉��i�͌��s�̂Q�{�߂��̂Q�O�O�~�^���b�g������܂ō������Ă��܂�
�\�����ے�ł��Ȃ��B���̂悤�Ȏ���ɂ́A�g���b�N���[�U�̔R�����̗v���E�j�[�Y�����܂邱�Ƃ͕K�����B�Ƃ�
�낪�A�ŋ߂̓��{�@�B�w��⎩���ԋZ�p��̍u����ł́A�f�B�[�[���G���W���ł̏\���ȔR����P�����҂ł����
���đ����̊w�ҁE���Ƃ����ڂ���悤�ȐV�Z�p����������Ȃ��̂�����̂悤���B
�@�Ƃ��낪�A���ŋ߂܂ł́A�G���W���W�̊w�ҁE���Ƃ́AHCCI�R�āi��PCI�R�āj���f�B�[�[���G���W���́uNO��
�ƔR��̃g���[�h�I�t�̌o�������V�Z�p�v�ł���A���̋Z�p���f�B�[�[���G���W���́uNO���팸�v�Ɓu�R�����v��
�������鋆�ɂ̃f�B�[�[���R�ċZ�p�Ƃ��ē��{�@�B�w��⎩���ԋZ�p��̍u����ł͑傢�Ɏ��Ě�����A����
�Z�p�Ɋւ��鑽���̘_�������\����Ă����B�����āA��y�̌����̃f�B�[�[���G���W���Z�p�҂���́AHCCI�R��
�i��PCI�R�āj�̏o���ɂ��f�B�[�[���R�Ă̐��E������I�ɐi�����A�����̂ɑސE�����M�҂̎����Ă���悤�Ȍ�
�����ȃf�B�[�[���R�Ă̋Z�p���S���ʗp���Ȃ�����ɂȂ����Ɛ錾����Ă��܂����̂ł���B
�ƔR��̃g���[�h�I�t�̌o�������V�Z�p�v�ł���A���̋Z�p���f�B�[�[���G���W���́uNO���팸�v�Ɓu�R�����v��
�������鋆�ɂ̃f�B�[�[���R�ċZ�p�Ƃ��ē��{�@�B�w��⎩���ԋZ�p��̍u����ł͑傢�Ɏ��Ě�����A����
�Z�p�Ɋւ��鑽���̘_�������\����Ă����B�����āA��y�̌����̃f�B�[�[���G���W���Z�p�҂���́AHCCI�R��
�i��PCI�R�āj�̏o���ɂ��f�B�[�[���R�Ă̐��E������I�ɐi�����A�����̂ɑސE�����M�҂̎����Ă���悤�Ȍ�
�����ȃf�B�[�[���R�Ă̋Z�p���S���ʗp���Ȃ�����ɂȂ����Ɛ錾����Ă��܂����̂ł���B
�@�������A���̌�̌������i�ނɂ�āA�f�B�[�[����HCCI�R�āi��PCI�R�āj�̋Z�p�́A�R�Ă̕s�����肪����
�ł��Ȃ���ɁA�f�B�[�[���G���W���́uNO���팸�v�Ɓu�R�����v�̌��ʂ��ɂ߂ċ͂��ł��邱�Ƃ����炩�ƂȂ�����
�߁A���݂ł͂��̋Z�p�𒍖ڂ���w�ҁE���Ƃ̐����}���ɏ��Ȃ��Ȃ����悤�ł���B���̗l�q�����Ă���ƁA�����
�ł̃f�B�[�[����HCCI�R�āi��PCI�R�āj�̋Z�p�̃h���`���������́A��́A���������̂ł��낤���B�����āA�f�B�[�[
����HCCI�R�āi��PCI�R�āj�ɗL���V�ɂȂ��Ă����w�ҁE���Ƃ́A���݁A����̔n���������������͒p���Ă����
�ł��낤���B
�ł��Ȃ���ɁA�f�B�[�[���G���W���́uNO���팸�v�Ɓu�R�����v�̌��ʂ��ɂ߂ċ͂��ł��邱�Ƃ����炩�ƂȂ�����
�߁A���݂ł͂��̋Z�p�𒍖ڂ���w�ҁE���Ƃ̐����}���ɏ��Ȃ��Ȃ����悤�ł���B���̗l�q�����Ă���ƁA�����
�ł̃f�B�[�[����HCCI�R�āi��PCI�R�āj�̋Z�p�̃h���`���������́A��́A���������̂ł��낤���B�����āA�f�B�[�[
����HCCI�R�āi��PCI�R�āj�ɗL���V�ɂȂ��Ă����w�ҁE���Ƃ́A���݁A����̔n���������������͒p���Ă����
�ł��낤���B
�@���������A�f�B�[�[���G���W�������܂�Ă��̕��A�u�f�B�[�[�����v�́A����܂ő����̐l�B������A�S�N�ȏ�ɋy
�ԉ��nj����𑱂��Ă����ۑ�ł���B�����āA�R�Ď����ɂ����đ��_�̒����m���ɋN�������Ƃ��K�{�ƂȂ�HCCI
�R�āi��PCI�R�āj�̎���������Ȃ��Ƃ́A�f�B�[�[���G���W���̗��j������Ηe�Ղɔ��f�ł��邱�Ƃ��B���̂悤��
���Ƃɓ��������Ȃ��̂́A�ŋ߂̑����̊w�ҁE���Ƃ́A�葁���u���v�𐬂����Ƃ����ɐS�������Ă��邽�߂ł͂Ȃ�
���낤���B�n���������Ƃł���B
�ԉ��nj����𑱂��Ă����ۑ�ł���B�����āA�R�Ď����ɂ����đ��_�̒����m���ɋN�������Ƃ��K�{�ƂȂ�HCCI
�R�āi��PCI�R�āj�̎���������Ȃ��Ƃ́A�f�B�[�[���G���W���̗��j������Ηe�Ղɔ��f�ł��邱�Ƃ��B���̂悤��
���Ƃɓ��������Ȃ��̂́A�ŋ߂̑����̊w�ҁE���Ƃ́A�葁���u���v�𐬂����Ƃ����ɐS�������Ă��邽�߂ł͂Ȃ�
���낤���B�n���������Ƃł���B
�@����HCCI�R�āi��PCI�R�āj�ɂ��f�B�[�[���G���W���́uNO���팸�v�Ɓu�R�����v�������ł��邱�Ƃ����炩�ƂȂ�
�����݂ł́A��^�g���b�N�́uNO���팸�v�Ɓu�R�����v��}�邱�Ƃɍs���l�܂�̏Ɋׂ��Ă�����̂ƍl������B
���̌��ʁA�č������ɂ���^�g���b�N��NO���K�����{�s����������{���{�̑Ӗ��ɏڏq���Ă���悤�ɁA���{�ł�
�u�č������ɂ����{�̑�^�g���b�N��NO���K���l�v�̔r�o�K�X�K�����{�s��������j�ڂɊׂ��Ă���ƍl������B
�����āA���{���{�i�����y��ʏȁj��2015�N�x�d�ʎԔR��������������^�g���b�N�̐V������R��̊���
��ł��Ȃ��ɂȂ��Ă���ƍl������B�����āA���{�́A������u���Ή��̏o�O�I�v�̌��̂悤�ɁA�u�č�������
�����{�̑�^�g���b�N��NO���K���l�̋����v�Ɓu2015�N�x�d�ʎԔR���������v���u�K���ŏ������I�v�Ƃ̍�����n
���ɂ������\���J��Ԃ��Ă���悤�ł���B���̗l�q�ł́A�������^�g���b�N��NO���ƔR��̋K���������ی��Ȃ���
���肷�鍰�_�ł��낤���B���ɁA���ꂪ�����ł���A���{�i�����ȁE���y��ʏȁj�́A������̂�ɂ��閳�\�Ȑl
�Ԃ̏W�܂�ƌ����Ă��d�����Ȃ��̂ł͂Ȃ����낤���B
�����݂ł́A��^�g���b�N�́uNO���팸�v�Ɓu�R�����v��}�邱�Ƃɍs���l�܂�̏Ɋׂ��Ă�����̂ƍl������B
���̌��ʁA�č������ɂ���^�g���b�N��NO���K�����{�s����������{���{�̑Ӗ��ɏڏq���Ă���悤�ɁA���{�ł�
�u�č������ɂ����{�̑�^�g���b�N��NO���K���l�v�̔r�o�K�X�K�����{�s��������j�ڂɊׂ��Ă���ƍl������B
�����āA���{���{�i�����y��ʏȁj��2015�N�x�d�ʎԔR��������������^�g���b�N�̐V������R��̊���
��ł��Ȃ��ɂȂ��Ă���ƍl������B�����āA���{�́A������u���Ή��̏o�O�I�v�̌��̂悤�ɁA�u�č�������
�����{�̑�^�g���b�N��NO���K���l�̋����v�Ɓu2015�N�x�d�ʎԔR���������v���u�K���ŏ������I�v�Ƃ̍�����n
���ɂ������\���J��Ԃ��Ă���悤�ł���B���̗l�q�ł́A�������^�g���b�N��NO���ƔR��̋K���������ی��Ȃ���
���肷�鍰�_�ł��낤���B���ɁA���ꂪ�����ł���A���{�i�����ȁE���y��ʏȁj�́A������̂�ɂ��閳�\�Ȑl
�Ԃ̏W�܂�ƌ����Ă��d�����Ȃ��̂ł͂Ȃ����낤���B
�@���̂悤�ɁA���{�̃g���b�N���[�J�E��w�E�����@�ւ̃f�B�[�[���G���W���ɊW����w�ҁE���Ƃɂ́A�u�R���NO��
�Ƃ̃g���[�h�I�t�������ł���Z�p�v�̋Z�p�Ă�A�C�f�A���s���E���R�̏Ɋׂ��Ă��邽�߁A�u�R���NO���Ƃ̃g��
�[�h�I�t�������v���A�f�B�[�[���G���W���́u�R����P�v�ƁuNO���팸�v�𐄐i�ł���V�����Z�p�������J���ł��Ă��Ȃ�
�̂������̂悤�ł���B�����_�ł́A��^�g���b�N�́u�R����P�v�ƁuNO���팸�v�𐄐i�ł���Z�p�J���̌��ʂ����S��
�������ł��邽�߁A�߂������A���{�̑�^�g���b�N���u�R����P�v�ƁuNO���팸�v�������ł���\���͊F���ƍl
������B���̂��߁A���{���{�́A��^�g���b�N�́u2015�N�x�d�ʎԔR�������������V���Ȓ�R��̊�v����
��ł��Ȃ���ɁA�č��̂m�n���K�������ɂ���^�g���b�N��NO���K�������{���{�s����������Ȃ��̂�����̂�
���ł����B���̌��ʁA���{�ɂ�����u��C���̉��P�v�A�u��^�g���b�N��CO2��A�����_�ł́A�킪���ɂ����錻�s
�̑�^�g���b�N�ł̕s�\���ȁuNO���K���v�Ɓu�R��K���v���߂������ɉ������ċ����ł���ڏ����S�������悤�Ɍ�����
���A�@���Ȃ��̂ł��낤���B
�Ƃ̃g���[�h�I�t�������ł���Z�p�v�̋Z�p�Ă�A�C�f�A���s���E���R�̏Ɋׂ��Ă��邽�߁A�u�R���NO���Ƃ̃g��
�[�h�I�t�������v���A�f�B�[�[���G���W���́u�R����P�v�ƁuNO���팸�v�𐄐i�ł���V�����Z�p�������J���ł��Ă��Ȃ�
�̂������̂悤�ł���B�����_�ł́A��^�g���b�N�́u�R����P�v�ƁuNO���팸�v�𐄐i�ł���Z�p�J���̌��ʂ����S��
�������ł��邽�߁A�߂������A���{�̑�^�g���b�N���u�R����P�v�ƁuNO���팸�v�������ł���\���͊F���ƍl
������B���̂��߁A���{���{�́A��^�g���b�N�́u2015�N�x�d�ʎԔR�������������V���Ȓ�R��̊�v����
��ł��Ȃ���ɁA�č��̂m�n���K�������ɂ���^�g���b�N��NO���K�������{���{�s����������Ȃ��̂�����̂�
���ł����B���̌��ʁA���{�ɂ�����u��C���̉��P�v�A�u��^�g���b�N��CO2��A�����_�ł́A�킪���ɂ����錻�s
�̑�^�g���b�N�ł̕s�\���ȁuNO���K���v�Ɓu�R��K���v���߂������ɉ������ċ����ł���ڏ����S�������悤�Ɍ�����
���A�@���Ȃ��̂ł��낤���B
�@���̂悤�ȏɊӂ݁A���݂����{�ł̑�^�g���b�N��NO���ƔR��̋K�������̕s�\���ȏ�Ŕj���A�������]
�ނ悤�ȑ�^�g���b�N�́uNO���K���v�Ɓu�R��K���v�ɋ����ł���Z�p�Ƃ��āA�M�҂́A�C���x�~�G���W���i�������J
2005-54771�j���Ă��Ă���B�����āA�C���x�~�́A�f�B�[�[���̂m�n���팸�ƔR�����̈ꋓ�����̋Z�p���I�ɏ�
�q���Ă���悤�ɁA�����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�́A�f�B�[�[���G���W���̒��N�̉ۑ�ł�����NO��
�팸���ɂ͔R������������A�R��̉��P���ɂ�NO��������������u�R���NO���Ƃ̃g���[�h�I�t�v�������ł��邱�Ƃ�
�����ł���B
�ނ悤�ȑ�^�g���b�N�́uNO���K���v�Ɓu�R��K���v�ɋ����ł���Z�p�Ƃ��āA�M�҂́A�C���x�~�G���W���i�������J
2005-54771�j���Ă��Ă���B�����āA�C���x�~�́A�f�B�[�[���̂m�n���팸�ƔR�����̈ꋓ�����̋Z�p���I�ɏ�
�q���Ă���悤�ɁA�����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�́A�f�B�[�[���G���W���̒��N�̉ۑ�ł�����NO��
�팸���ɂ͔R������������A�R��̉��P���ɂ�NO��������������u�R���NO���Ƃ̃g���[�h�I�t�v�������ł��邱�Ƃ�
�����ł���B
�@���������āA�����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�́A���N�A�f�B�[�[���G���W���̊w�ҁE���Ƃ������
�ŕK���ɒT�����߂Ă����u�f�B�[�[���G���W���̔R���NO���Ƃ̓����̍팸�������ł���v�V�I�ȋZ�p�v�Ɖ]�����
�ł͂Ȃ����낤���B�Ƃ��낪�A�c�O�����ƂɁA�����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p�́A���݂̂Ƃ���A
���{�̐��{�i�����ȁE���y��ʏȁj��f�B�[�[���G���W���̊w�ҁE���Ɠ�����́A���̂����S�ɖ����E�َE����
�Ă���̂ł���B���̈���ŁA���{�̐��{���^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W���̌����J���ɊW���Ă���l�B�́A
���{�@�B�w��E���{�����ԋZ�p��̍u����E�Z�p���Ȃǂɂ����ăf�B�[�[���G���W����NO���팸��R����P�Ɋ�
���鑽���̘_��������ɔ��\�E���\����Ă���B�������Ȃ���A�����̘_���̒��g���������A��������{�̑�^
�g���b�N�́uNOx�팸�v�Ɓu�R����P�v�𑁊��ɁA�������m���Ɏ����ł������ȋZ�p�́A�c�O�Ȃ���F���̂悤���B�����
��������炸�A���{�̐��{���^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W���̌����J���ɊW���Ă���l�B�́A���݂̑�^�g��
�b�N�̍ł��d�v�Ȃł���uNOx�팸�v�Ɓu�R����P�v�̉ۑ��e�Ղɉ����ł����C���x�~�G���W���i�������J2005-
54771�j�����S�ɖ����E�َE���Ă���̂́A�@���Ȃ闝�R������̂ł��낤���B
�ŕK���ɒT�����߂Ă����u�f�B�[�[���G���W���̔R���NO���Ƃ̓����̍팸�������ł���v�V�I�ȋZ�p�v�Ɖ]�����
�ł͂Ȃ����낤���B�Ƃ��낪�A�c�O�����ƂɁA�����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p�́A���݂̂Ƃ���A
���{�̐��{�i�����ȁE���y��ʏȁj��f�B�[�[���G���W���̊w�ҁE���Ɠ�����́A���̂����S�ɖ����E�َE����
�Ă���̂ł���B���̈���ŁA���{�̐��{���^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W���̌����J���ɊW���Ă���l�B�́A
���{�@�B�w��E���{�����ԋZ�p��̍u����E�Z�p���Ȃǂɂ����ăf�B�[�[���G���W����NO���팸��R����P�Ɋ�
���鑽���̘_��������ɔ��\�E���\����Ă���B�������Ȃ���A�����̘_���̒��g���������A��������{�̑�^
�g���b�N�́uNOx�팸�v�Ɓu�R����P�v�𑁊��ɁA�������m���Ɏ����ł������ȋZ�p�́A�c�O�Ȃ���F���̂悤���B�����
��������炸�A���{�̐��{���^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W���̌����J���ɊW���Ă���l�B�́A���݂̑�^�g��
�b�N�̍ł��d�v�Ȃł���uNOx�팸�v�Ɓu�R����P�v�̉ۑ��e�Ղɉ����ł����C���x�~�G���W���i�������J2005-
54771�j�����S�ɖ����E�َE���Ă���̂́A�@���Ȃ闝�R������̂ł��낤���B
�@
�@���̂悤�ɁA�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p���E�َE���Ă�����{�@�B�w��E���{�����ԋZ
�p��̍u����\�̘_��������[�J����̃q�A�����O���s���ĕs�\���ȋZ�p������W�߁A���̏������
���{�̐��{�i�����ȁE���y��ʏȁj���A���{�́uNOx�ƔR��̋K�������v�̉ہE�v�ۂf���Ă��錻��ł́A�X
�Ȃ���{�́uNOx�ƔR��̋K������������v�Ƃ̌��_�ƂȂ��Ă��܂��̂́A���R�̂��Ƃł͂Ȃ����낤���B���̌��ʁA
���{�ł́A��^�g���b�N��2015�N�x�d�ʎԔR���̋�����摗��Ƃ��A����ł��č������ɂ����{�̑�^�g���b
�N��NO���K�����{�s�������Ă���̂ł͂Ȃ����ƍl������B
�p��̍u����\�̘_��������[�J����̃q�A�����O���s���ĕs�\���ȋZ�p������W�߁A���̏������
���{�̐��{�i�����ȁE���y��ʏȁj���A���{�́uNOx�ƔR��̋K�������v�̉ہE�v�ۂf���Ă��錻��ł́A�X
�Ȃ���{�́uNOx�ƔR��̋K������������v�Ƃ̌��_�ƂȂ��Ă��܂��̂́A���R�̂��Ƃł͂Ȃ����낤���B���̌��ʁA
���{�ł́A��^�g���b�N��2015�N�x�d�ʎԔR���̋�����摗��Ƃ��A����ł��č������ɂ����{�̑�^�g���b
�N��NO���K�����{�s�������Ă���̂ł͂Ȃ����ƍl������B
�@���̂��߁A���{�̐��{�i�����ȁE���y��ʏȁj�́A����̑�^�g���b�N�ɂ�����NOx�ƔR��̊ɂ��K�����A���ꂩ
����u���炾��v�Ǝ{�s�������čs���S�Z�ł��낤���B���݂ɁA���{�̐��{������̊ɂ���^�g���b�N�̋K����������
�{�s�������邱�Ƃ́A�g���b�N���[�J�ɂ͑傫�ȗ��v�ݑ�����v���̈�ł��邽�߂ɁA�����傢�Ɋ��}���Ă�
�邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ����낤�B�������A���{�̐��{�ɂ���^�g���b�N�̊ɂ�NOx�K���ɂ���Ė��f����̂͑����̓�
�{�����ł���A�����āA��^�g���b�N�̊ɂ��R��K���ɂ���Ė��f����̂͑����̓��{�̃g���b�N���[�U�ł��邱��
�͊ԈႢ�Ȃ����낤�B���̏�����ƁA���݂̓��{�̐��{�́A��Ɓi���g���b�N���[�J)�ɂ͗D�����A�����ɂ͌�����
�{������s���Ă��邱�Ƃ��A�N�ł������ł���̂ł͂Ȃ����낤���B
����u���炾��v�Ǝ{�s�������čs���S�Z�ł��낤���B���݂ɁA���{�̐��{������̊ɂ���^�g���b�N�̋K����������
�{�s�������邱�Ƃ́A�g���b�N���[�J�ɂ͑傫�ȗ��v�ݑ�����v���̈�ł��邽�߂ɁA�����傢�Ɋ��}���Ă�
�邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ����낤�B�������A���{�̐��{�ɂ���^�g���b�N�̊ɂ�NOx�K���ɂ���Ė��f����̂͑����̓�
�{�����ł���A�����āA��^�g���b�N�̊ɂ��R��K���ɂ���Ė��f����̂͑����̓��{�̃g���b�N���[�U�ł��邱��
�͊ԈႢ�Ȃ����낤�B���̏�����ƁA���݂̓��{�̐��{�́A��Ɓi���g���b�N���[�J)�ɂ͗D�����A�����ɂ͌�����
�{������s���Ă��邱�Ƃ��A�N�ł������ł���̂ł͂Ȃ����낤���B
�@�Ƃ���ŁA����܂œ��{�̑����̃f�B�[�[���G���W�w�ҁE�Z�p�ҁE���Ƃ́A�u���������ˁv�A�u�R�i�ߋ��i���Q�i��
���j�v�A�uHCCI�R�āi��PCI�R�āj�v�̐�i�Z�p���J�����邱�Ƃɂ���đ啝�ȁuNO���̍팸�v�Ɓu�R��̌���v����������
��^�g���b�N�p�́u�N���[���f�B�[�[���G���W���v�����p���ł���Ɛ����ɑ升�����A�ǂ���������N������
NEDO����ʂ��Đ��\���̐��{�̓��ʉ�v�̗\�Z���䂪����Ŏg���܂����Ă����悤���B���̈���m�d�c�n �v�V�I
���������Q�ԑ����Z�p�J���́u�����x�R�Đ���G���W�V�X�e���̌����J���i�������ԁF2004�N8���`2009�N3
���A�\�Z�F�W���~�ȏ�j�vhttp://app3.infoc.nedo.go.jp/gyouji/events/FK/rd/2008/nedoevent.2009-02-16.5786478868
/shiryo.pdf�ł���B
���j�v�A�uHCCI�R�āi��PCI�R�āj�v�̐�i�Z�p���J�����邱�Ƃɂ���đ啝�ȁuNO���̍팸�v�Ɓu�R��̌���v����������
��^�g���b�N�p�́u�N���[���f�B�[�[���G���W���v�����p���ł���Ɛ����ɑ升�����A�ǂ���������N������
NEDO����ʂ��Đ��\���̐��{�̓��ʉ�v�̗\�Z���䂪����Ŏg���܂����Ă����悤���B���̈���m�d�c�n �v�V�I
���������Q�ԑ����Z�p�J���́u�����x�R�Đ���G���W�V�X�e���̌����J���i�������ԁF2004�N8���`2009�N3
���A�\�Z�F�W���~�ȏ�j�vhttp://app3.infoc.nedo.go.jp/gyouji/events/FK/rd/2008/nedoevent.2009-02-16.5786478868
/shiryo.pdf�ł���B
�@���̂m�d�c�n �v�V�I���������Q�ԑ����Z�p�J���́u�����x�R�Đ���G���W�V�X�e���̌����J���i�������ԁF
2004�N8���`2009�N3���A�\�Z�F�W���~�ȏ�j�v�́A��^�g���b�N�̂Q�O�P�T�N�x�d�ʎԔR�������Q���̔R���
�����Ă��܂��A�ߎS�Ȏ������ʂŏI�~�����̂ł���B�����āA���̂m�d�c�n�̌����J���̕�ǂ��{�̑����̃f
�B�[�[���G���W�w�ҁE�Z�p�ҁE���Ƃ́A����܂ł̑�^�g���b�N�̔R������シ��B��̎�@�Ƃ��Ă̊��҂𗠐�
�ꂽ���ƂɂȂ�A䩑R�Ƃ��Đ����p�������Ɋׂ��Ă��܂����悤���B���̂��Ƃ���A����܂œ��{�̑����̃f�B�[
�[���G���W�w�ҁE�Z�p�ҁE���Ƃ������E���`���Ă����u���������ˁv�A�u�R�i�ߋ��i���Q�i�ߋ��j�v�A�uHCCI�R�āi��PCI
�R�āj�v�̐�i�Z�p���J�����邱�Ƃɂ���đ啝�ȁuNO���̍팸�v�Ɓu�R��̌���v������������^�g���b�N�p�́u�N���[
���f�B�[�[���G���W���v�̎��p�����\�Ƃ��鎩�M���X�ȑ����́A��́A���������̂ł��낤���B
2004�N8���`2009�N3���A�\�Z�F�W���~�ȏ�j�v�́A��^�g���b�N�̂Q�O�P�T�N�x�d�ʎԔR�������Q���̔R���
�����Ă��܂��A�ߎS�Ȏ������ʂŏI�~�����̂ł���B�����āA���̂m�d�c�n�̌����J���̕�ǂ��{�̑����̃f
�B�[�[���G���W�w�ҁE�Z�p�ҁE���Ƃ́A����܂ł̑�^�g���b�N�̔R������シ��B��̎�@�Ƃ��Ă̊��҂𗠐�
�ꂽ���ƂɂȂ�A䩑R�Ƃ��Đ����p�������Ɋׂ��Ă��܂����悤���B���̂��Ƃ���A����܂œ��{�̑����̃f�B�[
�[���G���W�w�ҁE�Z�p�ҁE���Ƃ������E���`���Ă����u���������ˁv�A�u�R�i�ߋ��i���Q�i�ߋ��j�v�A�uHCCI�R�āi��PCI
�R�āj�v�̐�i�Z�p���J�����邱�Ƃɂ���đ啝�ȁuNO���̍팸�v�Ɓu�R��̌���v������������^�g���b�N�p�́u�N���[
���f�B�[�[���G���W���v�̎��p�����\�Ƃ��鎩�M���X�ȑ����́A��́A���������̂ł��낤���B
�@���̂悤�ɁA�m�d�c�n �v�V�I���������Q�ԑ����Z�p�J���́u�����x�R�Đ���G���W�V�X�e���̌����J���v���S��
�Ȍ��ʂŏI������̂ł��邪�A�����͉]���Ă��A����NEDO�̌����J���̎��s�́A���{�̑����̃f�B�[�[���G���W�w
�ҁE�Z�p�ҁE���ƂɁA�f�B�[�[���G���W���́uNO���̍팸�v�Ɓu�R��̌���v���ɂ߂ē�����Ƃ��v���m�炵�߂��悤
���B����ɂ���āA���{�̑����̃f�B�[�[���G���W�w�ҁE�Z�p�ҁE���Ƃ́A�f�B�[�[���G���W���́uNO���̍팸�v�Ɓu�R
��̌���v�𑬂₩�Ɏ������邽�߂ɂ́A�V�����Z�p�ɑ��ė\�f�E�G�O���������ɐ^���Ɍ����J���Ɏ��g�ނ�
�����Ƃ�N�����Ɋ������悤�Ɏv�����̂ł���B���̗��R�́A���̂m�d�c�n �v�V�I���������Q�ԑ����Z�p�J����
�u�����x�R�Đ���G���W�V�X�e���̌����J���v�̔ߎS�Ȍ��ʂ̕I�����ɁA���̒��O����ĂɓV������グ
�ė��_���Ă����l�q�����Ă��܂�������ł���B
�Ȍ��ʂŏI������̂ł��邪�A�����͉]���Ă��A����NEDO�̌����J���̎��s�́A���{�̑����̃f�B�[�[���G���W�w
�ҁE�Z�p�ҁE���ƂɁA�f�B�[�[���G���W���́uNO���̍팸�v�Ɓu�R��̌���v���ɂ߂ē�����Ƃ��v���m�炵�߂��悤
���B����ɂ���āA���{�̑����̃f�B�[�[���G���W�w�ҁE�Z�p�ҁE���Ƃ́A�f�B�[�[���G���W���́uNO���̍팸�v�Ɓu�R
��̌���v�𑬂₩�Ɏ������邽�߂ɂ́A�V�����Z�p�ɑ��ė\�f�E�G�O���������ɐ^���Ɍ����J���Ɏ��g�ނ�
�����Ƃ�N�����Ɋ������悤�Ɏv�����̂ł���B���̗��R�́A���̂m�d�c�n �v�V�I���������Q�ԑ����Z�p�J����
�u�����x�R�Đ���G���W�V�X�e���̌����J���v�̔ߎS�Ȍ��ʂ̕I�����ɁA���̒��O����ĂɓV������グ
�ė��_���Ă����l�q�����Ă��܂�������ł���B
�@�Ƃ��낪�A�����̃g���b�N���[�J�́A�m�d�c�n �v�V�I���������Q�ԑ����Z�p�J���́u�����x�R�Đ���G���W�V�X�e
���̌����J���v���S�߂Ȍ��ʂŏI��������Ƃ�m��Ȃ���A�R����P���w��NJ��҂ł��Ȃ��u���������ˁv�A�u�Q�i��
���͂R�i�̉ߋ��v�A�uHCCI�R�āi��PCI�R�āj�v���̋Z�p�J�����A���ς�炸�����Ɏ��{�������Ă���悤���B�����āA
�M�҂���Ă��Ă����^�g���b�N�̔R����P�ɗL�����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p���A�����ɖ�
���E�َE���Ă���悤�ł���B���̂悤�ɓ��{�̃g���b�N���[�J�́A��^�g���b�N�̔R����P�ɖ����ȋZ�p�J����M�S��
�����J���𑱂������A�R����P�ɗL�����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p���E�َE���Ă���
�悤�ł���B����ɂ��ẮA���{�̃g���b�N���[�J�̋Z�p�ҁE���Ƃ́A��Ђɏo���ėV��ł����ɂ������Ȃ�
������A�f�B�[�[���G���W���̔R����P�������ł���Z�p�A�C�f�A���͊����Ă��邽�߂Ɏd���Ȃ��A�����A��^�g���b
�N�p�f�B�[�[���G���W���́u�R����P�v�ƁuNO���팸�v���w��NJ��҂ł��Ȃ��u���������ˁv�A�u�Q�i�܂��͂R�i�̉�
���v�A�uHCCI�R�āi��PCI�R�āj�v���̋Z�p�J�������炾��ƌ����������Ă���悤�Ɏv����̂ł���B
���̌����J���v���S�߂Ȍ��ʂŏI��������Ƃ�m��Ȃ���A�R����P���w��NJ��҂ł��Ȃ��u���������ˁv�A�u�Q�i��
���͂R�i�̉ߋ��v�A�uHCCI�R�āi��PCI�R�āj�v���̋Z�p�J�����A���ς�炸�����Ɏ��{�������Ă���悤���B�����āA
�M�҂���Ă��Ă����^�g���b�N�̔R����P�ɗL�����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p���A�����ɖ�
���E�َE���Ă���悤�ł���B���̂悤�ɓ��{�̃g���b�N���[�J�́A��^�g���b�N�̔R����P�ɖ����ȋZ�p�J����M�S��
�����J���𑱂������A�R����P�ɗL�����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p���E�َE���Ă���
�悤�ł���B����ɂ��ẮA���{�̃g���b�N���[�J�̋Z�p�ҁE���Ƃ́A��Ђɏo���ėV��ł����ɂ������Ȃ�
������A�f�B�[�[���G���W���̔R����P�������ł���Z�p�A�C�f�A���͊����Ă��邽�߂Ɏd���Ȃ��A�����A��^�g���b
�N�p�f�B�[�[���G���W���́u�R����P�v�ƁuNO���팸�v���w��NJ��҂ł��Ȃ��u���������ˁv�A�u�Q�i�܂��͂R�i�̉�
���v�A�uHCCI�R�āi��PCI�R�āj�v���̋Z�p�J�������炾��ƌ����������Ă���悤�Ɏv����̂ł���B
�@�Ƃ���ŁA�ȉ��̕\�R�R�ɂ́A����25�N5��31���ɊJ�Â��ꂽ�u�����Q�T�N�x��ʈ��S���������u����v�ɂ���
�āA����c��w�@�吹�����́u�f�B�[�[�������Ԃ̔r�o�K�X��Z�p�̍ŐV�����v�̍u�������̈ꕔ���Ɏ������B
���̑吹�����́u�u�������v�̂Q�X�y�[�W�ɂ́u�����Ԃ̔R����P�Z�p�v���܂Ƃ߂��Ă���B���̒��ł́A�f�B�[�[
������уK�\���������Ԃ̔R����P�����P�O���ȏ�̋Z�p�Ƃ��āA���ϋC���@�\�i���C���x�~�j�����X�Ƌ������
�Ă���B�Ƃ��낪�A���̑吹�����́u�u�������v�̂R�O�y�[�W�́u�f�B�[�[�����p�Ԃ̍��������v�̗Z�p�̒���
�́A�u�ϋC���@�\�i���C���x�~�j�v�̋Z�p���L�ڂ���Ă��Ȃ��̂ł���B
�āA����c��w�@�吹�����́u�f�B�[�[�������Ԃ̔r�o�K�X��Z�p�̍ŐV�����v�̍u�������̈ꕔ���Ɏ������B
���̑吹�����́u�u�������v�̂Q�X�y�[�W�ɂ́u�����Ԃ̔R����P�Z�p�v���܂Ƃ߂��Ă���B���̒��ł́A�f�B�[�[
������уK�\���������Ԃ̔R����P�����P�O���ȏ�̋Z�p�Ƃ��āA���ϋC���@�\�i���C���x�~�j�����X�Ƌ������
�Ă���B�Ƃ��낪�A���̑吹�����́u�u�������v�̂R�O�y�[�W�́u�f�B�[�[�����p�Ԃ̍��������v�̗Z�p�̒���
�́A�u�ϋC���@�\�i���C���x�~�j�v�̋Z�p���L�ڂ���Ă��Ȃ��̂ł���B
| |
 |
| |
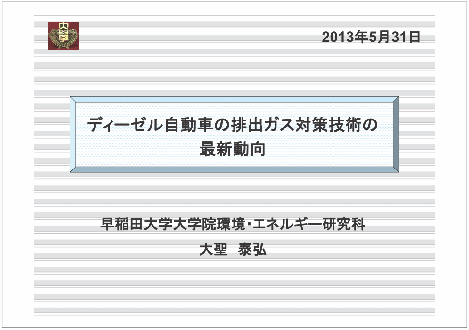 |
| |
�@�@���@����c��w�@�吹�����̍u�������̂Q�X�y�[�W
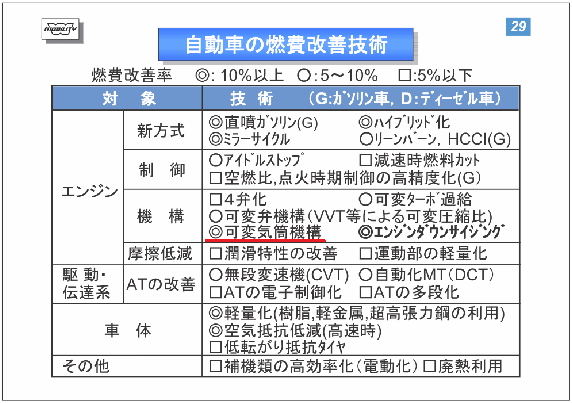 �@�@���@����c��w�@�吹�����̍u�������̂R�O�y�[�W
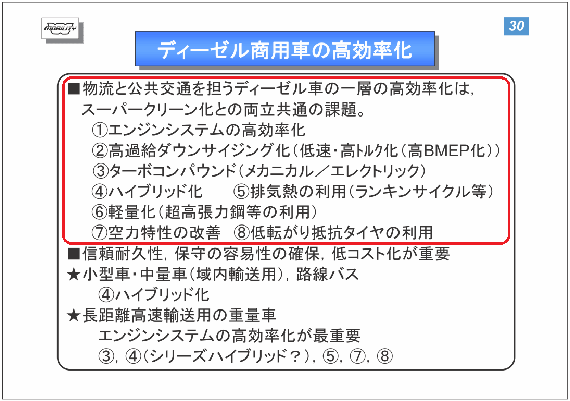 �@�y ���L �z
�@��L�̂R�O�y�[�W�̕\�i�Ԙg���Q�Ɓj�Ɏ����ꂽ�u�������ƌ�����ʂ�S���f�B�[�[���Ԃ̈�w�̍���
�����́A�X�[�p�[�N���[�����Ƃ̗������ʂ̉ۑ�v�̍��Ɏ����ꂽ�@�`�G�̋Z�p�ɂ́A29�y�[�W�ɗ� �����ꂽ�f�B�[�[���G���W���̔R�����̋Z�p�ł���u�ϋC���@�\�v���L�ڂ���Ă��炸�A�����E�r�� ����Ă���B |
�@���̑吹�����̍u�������̂R�O�y�[�W�u�f�B�[�[�����p�Ԃ̍��������v�̃y�[�W�ɗ��ꂽ�Z�p�́A���̑啔��
�̋Z�p����^�g���b�N�̑��s�R���d�ʎԃ��[�h�R����\���ɉ��P�ł��Ȃ��㕨�ł���悤�ɁA�M�҂ɂ͎v�����
�ł���B�����ŁA�吹�������u�������̂R�O�y�[�W�u�f�B�[�[�����p�Ԃ̍��������v�̃y�[�W�ɗ��ꂽ�Z�p����
�^�g���b�N�iGVW25�g���j�ɍ̗p�����ꍇ�A������^�g���b�N�iGVW25�g���j�������s�R����d�ʎԃ��[�h�R��̉��P��
�͏��ł���ƕM�҂������������R���A�\�R�S�ɂ܂Ƃ߂��B
�̋Z�p����^�g���b�N�̑��s�R���d�ʎԃ��[�h�R����\���ɉ��P�ł��Ȃ��㕨�ł���悤�ɁA�M�҂ɂ͎v�����
�ł���B�����ŁA�吹�������u�������̂R�O�y�[�W�u�f�B�[�[�����p�Ԃ̍��������v�̃y�[�W�ɗ��ꂽ�Z�p����
�^�g���b�N�iGVW25�g���j�ɍ̗p�����ꍇ�A������^�g���b�N�iGVW25�g���j�������s�R����d�ʎԃ��[�h�R��̉��P��
�͏��ł���ƕM�҂������������R���A�\�R�S�ɂ܂Ƃ߂��B
�i�u�����Q�T�N�x��ʈ��S���������u����v�ɂ�����吹�����̍u�������́u�f�B�[�[�����p�Ԃ̍��������v�y�[�W�Q�Ɓj
| |
|
|||||||||||||||||
�@ �G���W���V�X�e���̍�������
|
�� ��̓I�ȋZ�p���e���s�L�ڂ̂��߁A�ǎ҂ɂ͈Ӗ��s��
�@�@�i�M�҂ɂ́A���Ӗ��ȋL�q�Ǝv�������B�j |
|||||||||||||||||
�A ���ߋ��_�E���T�C�W���O��
�@�@�i�ᑬ�E���g���N���i��BMEP���j
|
�� �i���R�F���̂P�j�����_�ł̓g���b�N�p�f�B�[�[���G���W���́A�S�ĂɃC���^�[�N�[���ߋ����̗p��
�ł��邽�߂ɏ��r�C�ʉ�����ʉ����Ă���A���ߋ��G���W�����嗬�̃K�\�����G���W���̂悤�ȁA��
���ȃ_�E���T�C�W���O������ł���B
�� �i���R�F���̂Q�j�K�\���������Ԃ̏ꍇ�ɂ́A�_�E���T�C�W���O�ɂ���ăG���W�����������ł�
�z�C�i��ق̊J�x��傫�����邱�Ƃ��ł��邽�߁A�|���s���O�����̒ጸ�ɂ������s�R��̌���
���\�ł���B
�������A�f�B�[�[���G���W���́A�z�C�i��ق��������߂ɃK�\�����G���W���ɔ�ׂăG���W���̒ᕉ
�^�]���̃|���s���O���������Ȃ����Ƃ���A�_�E���T�C�W���O�ɂ���Ď����s�R�����ł���
�\���͋͏��ł���B
�� �i���R�F���̂R�j��^�g���b�N�̎����s���̃G���W���̕��ϕ��ׂ��K�\����j��p�Ԃɔ�r���đ�
���ɍ����ׂł��邱�Ƃ���A�����A��^�g���b�N�ł̓_�E���T�C�W���O���ɂ��R�����̃}�[�W��
�̓K�\����j��p�Ԃɔ�ׂď��Ȃ��B
�� �i�؋��F���̂P�j��^�J�[�S�g���b�N�iGVW25�g���j�̓��ڃG���W���ƃ��[�h�R�
�@���݁A��^�J�[�S�g���b�N�iGVW25�g���j�ɂ͂X�`1�R���b�g���̃G���W�������ڂ���Ă��邪�A�d��
�ԃ��[�h�R��͂قړ����ł���B���������āA��^�J�[�S�g���b�N�iGVW25�g���j�ɂ����ẮA�_�E��
�T�C�W���O�ɂ��R�����́A�͏��ł���B
�@�Ȃ��A���ߋ��_�E���T�C�W���O���ɂ���^�g���b�N���R����オ �͏��ɉ߂��Ȃ����R�ɂ���
�́A�C���x�~�́A�f�B�[�[���̂m�n���팸�ƔR�����̈ꋓ�����̋Z�p���I�̕\�P�S�ɂ��ڏq���Ă�
��̂ŁA�����������������B
|
|||||||||||||||||
�B �^�[�{�R���p�E���h��
�@�@�i���J�j�J���^�G���N�g���b�N�j
|
�� �ȉ��̐}�́A��^�g���b�N�p��12.91���b�g���G���W���ł�JE05 ���[�h�̉�]���E���וp�x���z
�����������̂ł���A���̐}���疾�炩�Ȃ悤���d�ʎԃ��[�h�R�������s�R������P���邽�߂�
�́A�ő�g���N�̃G���W����]���x�̈�ł̕��������̔R����P��}�邱�Ƃ��K�v�ł��邱�Ƃ�
���炩���B
�� �ȉ��̐}�́A�O�H�d�H�� �y���z�O�� ���S�������������{�@��w��_���W�iB�ҁj51��467��
�i��60-7�j�́u�r�C�^�[�{�R���p�E���h�G���W���̃G�l���M��������v�Ɍf�ڂ�12.88���b�g���̃C���^
�[�N���E�^�[�{�ߋ��G���W���̃x�[�X�G���W�������J�j�J���E�^�[�{�R���p�E���h�������ꍇ�̔R������
���̔�r�}�ł���B��L�̐}A���疾�炩�Ȃ悤�ɁA��^�g���b�N���d�ʎԃ��[�h�R�������s�R��
�����P���邽�߂ɂ́A�ő�g���N�̃G���W����]���x�̈�ł̕��������̔R����P��}�邱�Ƃ�
�K�v�ł���B
�@����A���L�̐}B���疾�炩�Ȃ��Ƃ́A�^�[�{�R���p�E���h���ɂ���čő�g���N�ߖT�̔R��́A2.
4�����x�̌��オ�F�߂���B�������A��^�g���b�N���d�ʎԃ��[�h�R�������s�R������P���邽
�߂ɏd�v�ȁA�ő�g���N�̃G���W����]���x�̈�ł̕��������̔R��́A���̃^�[�{�R���p�E��
�h���ɂ���Ėw��lj��P�ł��Ă��Ȃ����Ƃł���B����������,�^�[�{�R���p�E���h���ɂ���^�g���b�N
���d�ʎԃ��[�h�R�������s�R��̉��P�́A����Ȃ���p�[�Z���g�ɋ߂��Ɛ��������B���̂��Ƃ�
��A���ۂ̑�^�g���b�N�̑��s�ł́A�^�[�{�R���p�E���h���ɂ��R����オ�ɂ߂ď��Ȃ����̂ƍl
�����B���������āA�^�[�{�R���p�E���h���ɂ��d�ʎԃ��[�h�R��̉��P�́A�P���ɂ�������
���l����̂��Ó��ł����B
|
|||||||||||||||||
�C �n�C�u���b�h��
|
�� �����ł͌��������R�ɑ��s�ł���P�Ԃ̑�^�g���b�N�́AGVW�i�ԗ����d��)��25�g���ȉ��Ƃ�
�K�肪����B���̂��߁A��^�g���b�N�iGVW25�g���j�ł́A�n�C�u���b�h���ɂ��ԗ��{�̂̏d
�ʑ����́A���̑����d�ʂɑ��������ύډݕ��̌������������ƂɂȂ�A�ύډݕ�����������
��Ȃ��Ɋׂ錇�_�������B�����āA���̐ύډݕ��̌��������́A���̊����ŗA���ݕ�
�̃R�X�g�����������N�����Ă��܂���肪������B
�� ���������āA�ύڃo�b�e���[�̑啝�ȑ����������n�C�u���b�h���́A�s�s�Ԃ̉ݕ��A���̎�͂� �����^�g���b�N�i�ԗ����d25�g���j�̃n�C�u���b�h���́A����ȗp�r�̌��肳��A��ʂɍL�����y�� ��\�����F���ƍl������B���������āA���̂��߁A�g���b�N�^���Ǝ҂́A�����\���ɂ�鑽���� �R����オ������ꍇ�ł��A�]�������ԗ��{�̂̏d�ʑ���������^�g���b�N�iGVW25�g���j������ ���������Ă���̂����B���������āA���݂̃g���b�N�ł̉ݕ��A���̎�͂�S���g���b�N��^ �g���b�N�i�ԗ����d25�g���j�ɂ́A�n�C�u���b�h���͖��Ӗ��ȋZ�p�ƌ����Ă��ߌ��ł͖����ƍl ������B �Ȃ��A�s�s�Ԃ̉ݕ��A���̎�͂ł����^�g���b�N�i�ԗ����d25�g���j�̃n�C�u���b�h������ʂɍL�� ���y����\�����F���ƍl���������R�ɂ��ẮA���^�n�C�u���b�h �g���b�N�̓n�C�u���b�h��p �Ԃ̂悤�ȔR����P�������̃y�[�W�ɂ��ڏq���Ă���̂ŁA�����������������B |
|||||||||||||||||
�D �r�C�M�̗��p
�@�@�i�����L���T�C�N�����j
|
�� �u�����L���T�C�N���v�A�u�M�d�f�q�v����сu�X�^�[�����O�G���W���v���̃f�B�[�[���G���W���̔r�C
�K�X�̃G�l���M�[���������������u�E�Z�p����Ă���Ă���B�������A�����́A������f�B�[�[
���G���W���̔r�C�K�X�̔M�G�l���M�[����o�͂������Z�p�ł���B
����A�O�q�́u�B �^�[�{�R���p�E���h���v�̍��̐}A�Ɏ������悤�ɁA��^�g���b�N�iGVW25�g���j����
���s���d�ʎԃ��[�h�R����i��JE�O�T���[�h�����j�ɂ�����G���W���̉^�]�̈�̓G���W������
���ׂ���̂ł���B�Ƃ��낪�A���̃f�B�[�[���G���W���̕������ׂł͔r�C�K�X���x���ቺ���邽
�߁A��^�g���b�N�iGVW25�g���j�̃G���W���Ɂu�r�C�K�X�̃G�l���M�[�����鑕�u�E�Z�p�v����
�ꍇ�ɂ́A�r�C�K�X���x���Ⴂ���߁A�@ �r�C�K�X�ۗ̕L����G�l���M�[���Ⴂ���ƁA�A �r�C�K�X
���x�̒ቷ���ɂ����Ắu�r�C�K�X�̃G�l���M�[�����鑕�u�E�Z�p�v�̉^�]�����i����
���j���ቺ���邱�Ƃ̖�肪��������B���������āA��^�g���b�N�iGVW25�g���j�������s���d�ʎԃ�
�[�h�R����i��JE�O�T���[�h�����j�ɂ�����G���W���̉^�]�̈�ł̃G���W���������ׂ̔r�C�K�X
���x������������Z�p�E���u�p���Ȃ��ꍇ�ɂ́A�u�r�C�K�X�̃G�l���M�[�����鑕�u�E�Z
�p�v�ɂ���^�g���b�N�iGVW25�g���j�������s�R����d�ʎԃ��[�h�R��̉��P�́A�͏��ł���A�P��
�ɂ������Ȃ��l����̂��Ó��ł����B
�@�Ȃ��A�r�C�M���p�i�����L���T�C�N���j�ɂ���^�g���b�N���R����オ �͏��ɉ߂��Ȃ����R�ɂ�
���ẮA�C���x�~�́A�f�B�[�[���r�C�K�X�̃G�l���M�[���u�̌����������̃y�[�W�ɂ��ڏq��
�Ă���̂ŁA�����������������B
|
|||||||||||||||||
�E �y�ʉ�
�@�@�i�������͍|�̗��p�j
|
�� �����ł͌��������R�ɑ��s�ł���P�Ԃ̑�^�g���b�N�́AGVW�i�ԗ����d��)��25�g���ȉ��Ƃ�
�K�肪����B���̂��߁A��^�g���b�N�iGVW25�g���j�ł́A�ԗ��{�̂��������͍|�̑��p�ɂ��
���ԗ��{�̂̌y�ʉ���}�ꂽ�ꍇ�́A�ԗ��{�̂̌y�ʉ����������ύډݕ��̑������\
�ƂȂ��ăg���b�N���[�U�̗��v�i���ݕ��A���R�X�g�̌����j�ƂȂ�B�������A��^�g���b�N
�iGVW25�g���j�̎����s�R���d�ʎԃ��[�h�R��̉��P�ɂ͖����ł���B
�i��GVW25�g���̑�^�g���b�N�̏��i�͂̌���݂̂ł���B�j �i���������A�y�ʉ��̋Z�p�J���̓f�B�[�[���G���W���̔R�ċZ�p�̊J���Ƃ͖��W�ȍ��ڂł���B ���̂��߁A�y�ʉ��̋Z�p�J���ɂ��g���b�N�̔R����P�́A�f�B�[�[���G���W���̔R�ċZ�p�̊W �҂ɂƂ��ẮA�������������_�╧�ɋF��Z�p�ł���B�j |
|||||||||||||||||
�F ��͓����̉��P
|
�� ���݁A�V�^�̑�^�g���b�N�̊J�����ɂ́A�����������ɂ���ĊO�ό`��̍œK�����}���Ă�
�邽�߁A��͓����̉��P�ɂ��P���ȏ�̏d�ʎԃ��[�h�R��̌���͍���Ɨ\�z
�i���������A��͕���̋Z�p�J���̓f�B�[�[���G���W���̋Z�p�J���͂Ƃ͖��W�ȍ��ڂł���B�� �̂��߁A��͓����̋Z�p�J���ɂ��g���b�N�̔R����P�́A�f�B�[�[���G���W���W�҂ɂƂ��ẮA �������������_�╧�ɋF��Z�p�ł���B�j |
|||||||||||||||||
�G ��]����^�C���̗��p
|
�� ����̃^�C�����[�J�̋Z�p�J���Ɋ���
�i���������A��]����^�C���̋Z�p�J�����A�f�B�[�[���G���W���W�҂ɂ͖��W�ȍ��ڂł���B�� �̂��߁A��]����^�C���̋Z�p�J���ɂ��g���b�N�̔R����P�́A�f�B�[�[���G���W���W�҂ɂƂ� �ẮA�������������_�╧�ɋF��Z�p�ł���B�j |
�@�ȏ�̂悤�ɁA����25�N5��31���́u�����Q�T�N�x��ʈ��S���������u����v�ɂ�����吹�����́u�f�B�[�[��
�����Ԃ̔r�o�K�X��Z�p�̍ŐV�����v�ɂ��Ă̍u���̒��łR�O�y�[�W�́u�f�B�[�[�����p�Ԃ̍��������v����
�킿�u��^�g���b�N�̔R�����v�ɗL���Ƒ吹�������������ꂽ�@�`�G�̔R�����Z�p�́A�������^�g���b�N
�iGVW25�g���j�������s�R����d�ʎԃ��[�h�R��̂P�������̉��P�ɉ߂��Ȃ����߁A������u�g���Ȃ��Z�p�v�Ⴕ����
�u�K���N�^�Z�p�v�ƌ`�e�����������悤���B�����ŁA������@�`�G���Z�p�̖��_��c�����Ղ����邽�߂ɁA�ȉ��̂悤
���ނ��Ă݂��̂ŁA�����������������B
�����Ԃ̔r�o�K�X��Z�p�̍ŐV�����v�ɂ��Ă̍u���̒��łR�O�y�[�W�́u�f�B�[�[�����p�Ԃ̍��������v����
�킿�u��^�g���b�N�̔R�����v�ɗL���Ƒ吹�������������ꂽ�@�`�G�̔R�����Z�p�́A�������^�g���b�N
�iGVW25�g���j�������s�R����d�ʎԃ��[�h�R��̂P�������̉��P�ɉ߂��Ȃ����߁A������u�g���Ȃ��Z�p�v�Ⴕ����
�u�K���N�^�Z�p�v�ƌ`�e�����������悤���B�����ŁA������@�`�G���Z�p�̖��_��c�����Ղ����邽�߂ɁA�ȉ��̂悤
���ނ��Ă݂��̂ŁA�����������������B
�� �Ӗ��s���ȋZ�p (����̓I�ȋZ�p���e�������������A�P�Ȃ��]�E�ړI���u�R����P�Z�p�v�ƋL�ځj
�@�@�@ �G���W���V�X�e���̍��������F�@�\�E��p�E�\���ɂ��Ă̋L�ڂ��S���������߁A�P�Ɂu���h�ȋZ�p�v�Ƃ̐����ɉ߂��Ȃ��B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����Ɍ����A�������̃G���W���V�������������Ƃ̊�]�������L�ڂ���Ă��邱�ƂɂȂ�B
�� ���Ⴂ�̋Z�p (�����s��GVW25�g���̑�^�g���b�N�ł́A�u���ɍ̗p�ς݁v�A�u�R����P�̋@�\���A�Ⴕ���͍̗p�s���v�̋Z�p�j
�@�@�A���ߋ��_�E���T�C�W���O���F�����_�Ŗ��ߋ��G���W�����嗬�ł���A���������������Ƀ|���s���O�����̑傫���K�\�����G���W��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ł́A���ߋ��_�E���T�C�W���O���ɂ�镔�������̃|���s���O�����̍팸�ɂ��R����P���L��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ł���B����A��^�g���b�N�̃f�B�[�[���G���W���ł́A(a) ���ɍ��ߋ��G���W�������y���Ă��邱�ƁA
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@(b) �K�\�����G���W���ɔ�r���ăf�B�[�[���G���W���̕��������̃|���s���O�������啝�ɏ��Ȃ�����
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@(c) ��^�g���b�N�̎����s���̃G���W�����ׂ��K�\������p�Ԃɔ�r���đ啝�ɍ����ׂł��邱�ƁA
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ȏ�̗v���ɂ��A��^�g���b�N�ł͍��ߋ��_�E���T�C�W���O���ɂ��X�Ȃ�\���ȔR�����͍���
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ł���B���������āA��^�g���b�N�̔R�����̋Z�p�Ƃ��āu���ߋ��_�E���T�C�W���O���v�������邱�Ƃ́A
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ŋ߂̃K�\������p�Ԃ̔R�����Z�p�̘b����A�����l�����ɂ��̂܂ܑ�^�g���b�N�̔R������
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Z�p�Ƃ��Ĉ��p���銨�Ⴂ�Ɛ����B
�@�@�B �^�[�{�R���p�E���h���F�{���A�^�[�{�R���p�E���h���g���N�Əo�͂̑���ɗL���ȋZ�p�ł��邱�Ƃ�Y��A�R��ጸ�̋Z�p�Ɗ��Ⴂ
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�������́B
�@�@�E �y�ʉ��F��^�g���b�N�iGVW25�g���j�ł́A�ݕ��̐ύڗʂ̑������\�Ȃ��߁A�g���b�N�̏��i�͂����シ��Z�p�ł���A�d�ʎԃ��[�h
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�R��̉��P�Z�p�ł͖����B
�� ���p�����F���̋Z�p (�����s��GVW25�g���̑�^�g���b�N�ł́A���[�U�����₷��Z�p�j
�@�@�C �n�C�u���b�h���F�o�b�e���[�����[�^�[���ڂɂ��ԗ��{�̂̏d�ʑ����ɂ���Đύڗʂ��������߁A�s�s�Ԃ̉ݕ��A������Ŏ�͂�
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��^�g���b�N�iGVW25�g���j���[�U���S�ʓI�ɋ��₷��Z�p
�� �A�C�f�A�s���̋Z�p (�����ۂ̃g���b�N�p�G���W���̉^�]�𗝉����Ă��Ȃ����ƂɋN�������u�P�Ȃ�b��v�I�ȋZ�p�j
�@�@�D �r�C�M�̗��p�F��^�g���b�N�iGVW25�g���j�������s���ɂ��G���W���������ׂ���̂̂��߂��r�C�K�X���x���Ⴂ���A���̒Ⴂ
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�r�C�K�X���x�̏�Ԃɂ����Ē�����ł̍쓮�����ł��Ȃ���Ԃɂ������r�C�K�X�̃G�l���M�[�����ĔR���
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����}�낤�Ƃ���u�n���ۏo���v�̋Z�p�B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�������ł̍쓮�����Ԃ��r�C�K�X�̃G�l���M�[�����ĔR��̌����}�낤�Ƃ���ꍇ�ɂ́A�Ⴆ�A
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̂悤�ȋZ�p�p���ăG���W�������������r�C�K�X���x��������
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���邱�Ƃ��K�{�B
�� ���͖{��̋Z�p (���f�B�[�[���G���W���̐��Ƃɖ��W�ȋZ�p�j
�@�@�F ��͓����̉��P�F�f�B�[�[���G���W���W�ȊO�̊w�ҁF���Ƃ̓w�͂Ɋ���
�@�@�G ��]����^�C���̗��p�f�B�[�[���G���W���W�ȊO�̊w�ҁF���Ƃ̓w�͂Ɋ���
�@���������A����25�N5��31���́u�����Q�T�N�x��ʈ��S���������u����v�ɂ����āA�吹�����́A�Q�X�y�[�W��
�u�����Ԃ̔R����P�Z�p�v�̒��ɂ́u�ϋC���@�\�i���C���x�~�j�v���f�B�[�[�������Ԃ���уK�\���������Ԃ̔R
����P�����P�O���ȏ�̋Z�p�Ƃ��ċ������Ă���̂ł���B����ɂ�������炸�A���̎��̂R�O�y�[�W�ł́u�f�B�[
�[�����p�Ԃ̍��������v�̒��ł́A���̂�����Ȃ����A��^�g���b�N�̔R�����Z�p�Ƃ��āA���s�R���d�ʎԃ��[
�h�R��P�������̋͂��ȉ��P���������Ȃ��Z�p��A�ԗ����y�ʉ����̑�^�g���b�N�iGVW25�g���j�̏��i�͂���
�シ��Z�p�����A���O�̃y�[�W�Łu�P�O���ȏ�̔R����P�v�ƋL�ڂ���Ă���u�ϋC���@�\�i���C���x�~�j�v
�������E�َE����Ă����B
�u�����Ԃ̔R����P�Z�p�v�̒��ɂ́u�ϋC���@�\�i���C���x�~�j�v���f�B�[�[�������Ԃ���уK�\���������Ԃ̔R
����P�����P�O���ȏ�̋Z�p�Ƃ��ċ������Ă���̂ł���B����ɂ�������炸�A���̎��̂R�O�y�[�W�ł́u�f�B�[
�[�����p�Ԃ̍��������v�̒��ł́A���̂�����Ȃ����A��^�g���b�N�̔R�����Z�p�Ƃ��āA���s�R���d�ʎԃ��[
�h�R��P�������̋͂��ȉ��P���������Ȃ��Z�p��A�ԗ����y�ʉ����̑�^�g���b�N�iGVW25�g���j�̏��i�͂���
�シ��Z�p�����A���O�̃y�[�W�Łu�P�O���ȏ�̔R����P�v�ƋL�ڂ���Ă���u�ϋC���@�\�i���C���x�~�j�v
�������E�َE����Ă����B
�@���̂悤�ɁA�u�����Q�T�N�x��ʈ��S���������u����v�ł̑吹�����̍u������������ƁA�Q�X�y�[�W�ɂ̓f�B�[
�[�������Ԃ̔R����P�����P�O���ȏ�̋Z�p�Ƃ��āu�ϋC���@�\�i���C���x�~�j�v���L�ڂ���Ă��邪�A�R�O�y�[�W
�́u�f�B�[�[�����p�Ԃ̍��������v�̋Z�p�̒��ɂ́u�ϋC���@�\�i���C���x�~�j�v�̋Z�p���L�ڂ���Ă��炸�A��
�Ȗ����Ɋׂ������e�ƂȂ��Ă���B���̂悤�ɁA�吹�������_���I�����̍u���X�ƍs��ꂽ���Ƃ́A�����̋ɂ�
�ł���B������A�吹�����́A�_���I���������̂Ƃ������ɁA�����I�ȃf�B�[�[���g���b�N�̔R�����Z�p�Ƃ��Ă�
�u�ϋC���@�\�i���C���x�~�j�v��ے�i�������E�َE�j������e�̍u�����s��ꂽ�悤�ł���B
�[�������Ԃ̔R����P�����P�O���ȏ�̋Z�p�Ƃ��āu�ϋC���@�\�i���C���x�~�j�v���L�ڂ���Ă��邪�A�R�O�y�[�W
�́u�f�B�[�[�����p�Ԃ̍��������v�̋Z�p�̒��ɂ́u�ϋC���@�\�i���C���x�~�j�v�̋Z�p���L�ڂ���Ă��炸�A��
�Ȗ����Ɋׂ������e�ƂȂ��Ă���B���̂悤�ɁA�吹�������_���I�����̍u���X�ƍs��ꂽ���Ƃ́A�����̋ɂ�
�ł���B������A�吹�����́A�_���I���������̂Ƃ������ɁA�����I�ȃf�B�[�[���g���b�N�̔R�����Z�p�Ƃ��Ă�
�u�ϋC���@�\�i���C���x�~�j�v��ے�i�������E�َE�j������e�̍u�����s��ꂽ�悤�ł���B
�@���̂悤�ɁA�����I�ȃf�B�[�[���g���b�N�̔R�����Z�p�Ƃ��Ắu�ϋC���@�\�i���C���x�~�j�v��ے肵�����e��
�u����吹�������s��ꂽ���R�𐄑�����ƁA���̓�̗��R���l������B
�u����吹�������s��ꂽ���R�𐄑�����ƁA���̓�̗��R���l������B
�� ��P�̗��R
�u�ϋC���@�\�i���C���x�~�j�v���������^�g���b�N�iGVW25�g���j�̔R����P�̋Z�p�Ƃ��Ă��u���i�v�A�Ⴕ
���́u���Z�p�v�ł���A���p�s�\�ȋZ�p�Ƃ̈ӌ��E������吹������������Ă���\��������B���̂���
�́A�M�҂ɂ́A�ƂĂ��M�����Ȃ����Ƃ��B���̃f�B�[�[�����p�ԁi��GVW25�g���̑�^�g���b�N�j�Ɂu�ϋC���@�\�i��
�C���x�~�j�v�i���Ⴆ�A�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�j�������Ƃ����p���ł��Ȃ��Ƒ吹�������m�M��
���Ă��闝�R�E������m�肽�����̂ł���B
���́u���Z�p�v�ł���A���p�s�\�ȋZ�p�Ƃ̈ӌ��E������吹������������Ă���\��������B���̂���
�́A�M�҂ɂ́A�ƂĂ��M�����Ȃ����Ƃ��B���̃f�B�[�[�����p�ԁi��GVW25�g���̑�^�g���b�N�j�Ɂu�ϋC���@�\�i��
�C���x�~�j�v�i���Ⴆ�A�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�j�������Ƃ����p���ł��Ȃ��Ƒ吹�������m�M��
���Ă��闝�R�E������m�肽�����̂ł���B
�� ��Q�̗��R
�@�u�ϋC���@�\�i���C���x�~�j�v���������^�g���b�N�iGVW25�g���j�̔R����P�̋Z�p�Ƃ��ėL�]�Ƃ��Đ�������ƁA
��^�g���b�N�iGVW25�g���j�̔R����P�̋Z�p�Ƃ��ĕM�Ғ�Ă��C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j���ԐړI��
�������邱�ƂɂȂ��Ă��܂����ƂɂȂ�B���̂悤�ɁA��^�g���b�N�iGVW25�g���j�̔R����P�̋Z�p�Ƃ��āA�ސE�����|��
�R�c���Z�p���̓����Z�p�𐄏�����u�s���_�H�v�Ⴕ���́u�����S�̑����v���吹�������l�����Ă���\������
��B�����|���R�c���Z�p���̓����Z�p�𐄏�����u�s���_�H�v�������ړI�̂��߂ɁA�吹�����́A�����I�ȃf�B�[
�[���g���b�N�̔R�����Z�p�Ƃ��Ắu�ϋC���@�\�i���C���x�~�j�v��ے肷����e�̍u�����s��ꂽ�\�����l
������B�����Ƃ��A�M�Ғ�Ă��C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p���ԐړI�ɐ������邱�Ƃ���
������ړI�̂��߂ɁA�u�����e�̘_���I���������̂Ƃ������ɁA�����I�ȃf�B�[�[���g���b�N�̔R�����Z�p�Ƃ���
�́u�ϋC���@�\�i���C���x�~�j�v��ے肷����e�̍u����吹�������s��ꂽ�Ƃ͎v���Ȃ����E�E�E�E�E�E�E�E�B
��^�g���b�N�iGVW25�g���j�̔R����P�̋Z�p�Ƃ��ĕM�Ғ�Ă��C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j���ԐړI��
�������邱�ƂɂȂ��Ă��܂����ƂɂȂ�B���̂悤�ɁA��^�g���b�N�iGVW25�g���j�̔R����P�̋Z�p�Ƃ��āA�ސE�����|��
�R�c���Z�p���̓����Z�p�𐄏�����u�s���_�H�v�Ⴕ���́u�����S�̑����v���吹�������l�����Ă���\������
��B�����|���R�c���Z�p���̓����Z�p�𐄏�����u�s���_�H�v�������ړI�̂��߂ɁA�吹�����́A�����I�ȃf�B�[
�[���g���b�N�̔R�����Z�p�Ƃ��Ắu�ϋC���@�\�i���C���x�~�j�v��ے肷����e�̍u�����s��ꂽ�\�����l
������B�����Ƃ��A�M�Ғ�Ă��C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p���ԐړI�ɐ������邱�Ƃ���
������ړI�̂��߂ɁA�u�����e�̘_���I���������̂Ƃ������ɁA�����I�ȃf�B�[�[���g���b�N�̔R�����Z�p�Ƃ���
�́u�ϋC���@�\�i���C���x�~�j�v��ے肷����e�̍u����吹�������s��ꂽ�Ƃ͎v���Ȃ����E�E�E�E�E�E�E�E�B
�@�̂��琢�Ԃł́u��ʓI�ɉR�͗ǂ��Ȃ��v�Ƃ����邪�A��ԋꂵ���̂͑��l�ɉR�����Ă��邱�Ƃł͂Ȃ��A����
�ɉR�����Ă���Ƃ��ł���B�������A���̒��ɂ͑��l�ɉR�����Ă����C�ł�����l�����邶��Ȃ��H�Ǝv����
��������Ȃ����A���l�ɑ��Ăǂ�Ȃɖ����o�Ŗ��ӎ��Ȃ悤�ɐU�����Ă��A�{�l�̐��݈ӎ��ɂ͍��ݍ��܂�Ă�
��B���̂��߁A�u�R�����v���Ƃ́A�{�l���u�ǐS�̙�Ӂv�ɑς���Ɖ]���S�̏d�ׂ������������J�T�Ȑl���𑗂�Ȃ�
��Ȃ�Ȃ����ƂɂȂ�B�����܂ł��āA�吹�������u�����e�̘_���I���������̂Ƃ������ɁA�����I�ȃf�B�[�[���g
���b�N�̔R�����Z�p�Ƃ��Ắu�ϋC���@�\�i���C���x�~�j�v���E�َE������e�̍u�������čs��ꂽ�Ƃ͎v��
�Ȃ��̂ł���B���̂��߁A�ȏ�̑�Q�̗��R�́A�펯�I�ɍl����A�����I�ɂ͗L�蓾�Ȃ��ƍl������B
�ɉR�����Ă���Ƃ��ł���B�������A���̒��ɂ͑��l�ɉR�����Ă����C�ł�����l�����邶��Ȃ��H�Ǝv����
��������Ȃ����A���l�ɑ��Ăǂ�Ȃɖ����o�Ŗ��ӎ��Ȃ悤�ɐU�����Ă��A�{�l�̐��݈ӎ��ɂ͍��ݍ��܂�Ă�
��B���̂��߁A�u�R�����v���Ƃ́A�{�l���u�ǐS�̙�Ӂv�ɑς���Ɖ]���S�̏d�ׂ������������J�T�Ȑl���𑗂�Ȃ�
��Ȃ�Ȃ����ƂɂȂ�B�����܂ł��āA�吹�������u�����e�̘_���I���������̂Ƃ������ɁA�����I�ȃf�B�[�[���g
���b�N�̔R�����Z�p�Ƃ��Ắu�ϋC���@�\�i���C���x�~�j�v���E�َE������e�̍u�������čs��ꂽ�Ƃ͎v��
�Ȃ��̂ł���B���̂��߁A�ȏ�̑�Q�̗��R�́A�펯�I�ɍl����A�����I�ɂ͗L�蓾�Ȃ��ƍl������B
�@���������āA���̍u���ő吹�������u�ϋC���@�\�i���C���x�~�j�v��ے肷����e�\���ꂽ�̂́A�O�q�̑�P
�̗��R�Ƃ��Ă��ċ������悤�ȁA�ϋC���@�\�i���C���x�~�j�v�͍������^�g���b�N�iGVW25�g���j�̔R����P�̋Z�p
�Ƃ��Ă��u���i�v�A�Ⴕ���́u���Z�p�v�ł���A���p�s�\�ȋZ�p�ł���ƁA�吹�������m�M����Ă���̂ł͂Ȃ�����
���������B���ɁA���̐������I�����Ă���ꍇ�ɂ́A�吹�����́A�u�ϋC���@�\�i���C���x�~�j�v���f�B�[�[���g
���b�N�̔R�����Z�p�Ƃ��Ắu���i�v�A�Ⴕ���́u���Z�p�v�ł���Ƃ̊m�M����Ă��邱�ƂɂȂ�B���̂��߁A�吹��
���́A����̃f�B�[�[���g���b�N�̔R�����Z�p�ɂ��Ă̔��\��u���̍ۂɂ��A����܂łƓ��l�ɁA�u�ϋC���@
�\�i���C���x�~�j�v�̋Z�p���u�ے�v�܂��́u�����E�َE�v���ꑱ���������̂ƍl������B
�̗��R�Ƃ��Ă��ċ������悤�ȁA�ϋC���@�\�i���C���x�~�j�v�͍������^�g���b�N�iGVW25�g���j�̔R����P�̋Z�p
�Ƃ��Ă��u���i�v�A�Ⴕ���́u���Z�p�v�ł���A���p�s�\�ȋZ�p�ł���ƁA�吹�������m�M����Ă���̂ł͂Ȃ�����
���������B���ɁA���̐������I�����Ă���ꍇ�ɂ́A�吹�����́A�u�ϋC���@�\�i���C���x�~�j�v���f�B�[�[���g
���b�N�̔R�����Z�p�Ƃ��Ắu���i�v�A�Ⴕ���́u���Z�p�v�ł���Ƃ̊m�M����Ă��邱�ƂɂȂ�B���̂��߁A�吹��
���́A����̃f�B�[�[���g���b�N�̔R�����Z�p�ɂ��Ă̔��\��u���̍ۂɂ��A����܂łƓ��l�ɁA�u�ϋC���@
�\�i���C���x�~�j�v�̋Z�p���u�ے�v�܂��́u�����E�َE�v���ꑱ���������̂ƍl������B
�@�����͉]���Ă��A�M�҂̌l�I�ȋ�������A��^�g���b�N�iGVW25�g���j�̏d�ʎԃ��[�h�R����T�����x���ȒP�ɉ��P
�ł���C���x�~�i���C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�j�̗D�ꂽ�Z�p���u�ے�v�܂��́u�����E�َE�v������
�������̐^�ӂ́A�M�҂ɂ͑S�������ł��Ȃ����Ƃ��B�J��Ԃ��ɂȂ邪�A������A�吹�����́A���O�̃y�[�W���u��
�C���@�\�i���C���x�~�j�v���u�f�B�[�[�������Ԃɂ������P�O���ȏ�̔R����P�̉\�ȋZ�p�v�ƋL�ڂ���Ă��邽��
�ł���B���̂Ȃ�A�����Ƃ��C���x�~�̋Z�p�����p��������ȁu���v�̋Z�p�ł���Ƃ̑吹�����̔F���ł���Ȃ�
�A�O�y�[�W�̂Q�X�y�[�W�́u�����Ԃ̔R����P�Z�p�v�̒��ɂ́A�吹�����́A�u�ϋC���@�\�i���C���x�~�j�v���L
�ڂ��Ă��Ȃ��ƍl�����邽�߂ł���B���̂��߁A�M�҂ɂ́A�Q�X�y�[�W�́u�����Ԃ̔R����P�Z�p�v�ƂR�O�y�[�W��
�u�f�B�[�[�����p�Ԃ̍��������v�̋L�ړ��e�ɂ́A���炩�ɘ_���I�Ȗ���������Ǝv����̂ł���B
�ł���C���x�~�i���C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�j�̗D�ꂽ�Z�p���u�ے�v�܂��́u�����E�َE�v������
�������̐^�ӂ́A�M�҂ɂ͑S�������ł��Ȃ����Ƃ��B�J��Ԃ��ɂȂ邪�A������A�吹�����́A���O�̃y�[�W���u��
�C���@�\�i���C���x�~�j�v���u�f�B�[�[�������Ԃɂ������P�O���ȏ�̔R����P�̉\�ȋZ�p�v�ƋL�ڂ���Ă��邽��
�ł���B���̂Ȃ�A�����Ƃ��C���x�~�̋Z�p�����p��������ȁu���v�̋Z�p�ł���Ƃ̑吹�����̔F���ł���Ȃ�
�A�O�y�[�W�̂Q�X�y�[�W�́u�����Ԃ̔R����P�Z�p�v�̒��ɂ́A�吹�����́A�u�ϋC���@�\�i���C���x�~�j�v���L
�ڂ��Ă��Ȃ��ƍl�����邽�߂ł���B���̂��߁A�M�҂ɂ́A�Q�X�y�[�W�́u�����Ԃ̔R����P�Z�p�v�ƂR�O�y�[�W��
�u�f�B�[�[�����p�Ԃ̍��������v�̋L�ړ��e�ɂ́A���炩�ɘ_���I�Ȗ���������Ǝv����̂ł���B
�@����A���݁A�z���_�A�t�H���N�X���[�Q���A�A�E�f�B�AGM�A�N���C�X���[�����u�ϋC���@�\�i���C���x�~�j�v������
�s�̂̃K�\���������Ԃ̈ꕔ�Ԏ�ɓ��ڂ��Ă��錻����l����ƁA�u�ϋC���@�\�i���C���x�~�j�v����^�f�B�[�[
���g���b�N���R����P�̋Z�p�Ƃ����u���i�v�A�Ⴕ���́u���Z�p�v�ł���Ƃ́A�ƂĂ��M�҂ɂ͎v���Ȃ��B���̂悤�ɁA�K
�\���������Ԃɂ����āu�ϋC���@�\�i���C���x�~�j�v�����p������Ă�����l����ƁA����25�N5��31���́u��
���Q�T�N�x��ʈ��S���������u����v�ł̑吹�����̍u�����e�i��OHP�j�ɂ����āA�Q�X�y�[�W�ł́u�ϋC���@
�\�i���C���x�~�j�v���f�B�[�[�������Ԃ̔R����P�����P�O���ȏ�̋Z�p�Ƃ��ċ����炨���Ȃ���A�R�O�y�[�W�ł́u�f
�B�[�[�����p�Ԃ̍��������v��}��Z�p�̒��Ɂu�ϋC���@�\�i���C���x�~�j�v���L�ڂ���Ă��Ȃ��͖̂��炩��
�u�_���I�����v������ƍl�����A�܂��A�u���v�Ƃ��l������B���̂悤�Ȓ����������������e�̑吹�����̍u���ɂ�
���āA���̍u����ɎQ�����ꂽ�w�ҁE���ƁE�Z�p�҂̒��ɂ́A���炩�̋^����o�����l�������Ǝv�����A�@���Ȃ�
�̂ł��낤���B
�s�̂̃K�\���������Ԃ̈ꕔ�Ԏ�ɓ��ڂ��Ă��錻����l����ƁA�u�ϋC���@�\�i���C���x�~�j�v����^�f�B�[�[
���g���b�N���R����P�̋Z�p�Ƃ����u���i�v�A�Ⴕ���́u���Z�p�v�ł���Ƃ́A�ƂĂ��M�҂ɂ͎v���Ȃ��B���̂悤�ɁA�K
�\���������Ԃɂ����āu�ϋC���@�\�i���C���x�~�j�v�����p������Ă�����l����ƁA����25�N5��31���́u��
���Q�T�N�x��ʈ��S���������u����v�ł̑吹�����̍u�����e�i��OHP�j�ɂ����āA�Q�X�y�[�W�ł́u�ϋC���@
�\�i���C���x�~�j�v���f�B�[�[�������Ԃ̔R����P�����P�O���ȏ�̋Z�p�Ƃ��ċ����炨���Ȃ���A�R�O�y�[�W�ł́u�f
�B�[�[�����p�Ԃ̍��������v��}��Z�p�̒��Ɂu�ϋC���@�\�i���C���x�~�j�v���L�ڂ���Ă��Ȃ��͖̂��炩��
�u�_���I�����v������ƍl�����A�܂��A�u���v�Ƃ��l������B���̂悤�Ȓ����������������e�̑吹�����̍u���ɂ�
���āA���̍u����ɎQ�����ꂽ�w�ҁE���ƁE�Z�p�҂̒��ɂ́A���炩�̋^����o�����l�������Ǝv�����A�@���Ȃ�
�̂ł��낤���B
�@���Ă��āA���ɁA�吹�������u���Ŏ咣���ꂽ�悤�ɂȑ��s�R���d�ʎԃ��[�h�R��P�������̋͂��ȉ��P����
�����Ȃ��R�����̋Z�p�i�\�R�R�̇@�`�G�Q�Ɓj�����p�����ĂT�����x�̑�^�g���b�N�̏d�ʎԃ��[�h�R������P
��}�낤�Ƃ����ꍇ�A�P�������̔R����P�Z�p���T��ވȏ���W�߂ƂȂ�B���̂��߁A�吹�������u���ŗ�
�ꂽ�ʂ�̋Z�p���J�����ĂT�����x�̑�^�g���b�N�̏d�ʎԃ��[�h�R������P���������悤�Ƃ���ƁA���̋Z�p�J��
�̂��߂ɖc��ȁu�v�Ǝ����̐l���v�A�u�����ݔ��v���K�v�ƂȂ邽�߁A�K�R�I�ɊJ�����Ԃ������Ȃ邱�Ɛ�������
��B���̂Ȃ�A���Ɂu����������v������ł����Ă��A���̌����J�����I���������_�ŊJ���v���Ǝ����ݔ����s�v
�ɂƗ\�z����邽�߁A�T�����x�̑�^�g���b�N�̏d�ʎԃ��[�h�R������P�̌����J���ɕK�v�Ƃ̗��R�������ɂ��āA
�e�g���b�N���[�J�����̌����J���ɓ������đ啝�ȁu�J���v���̑����v�Ɓu�����ݔ��̑��݁v���邱�Ƃ�����Ȃ��߂�
����B
�����Ȃ��R�����̋Z�p�i�\�R�R�̇@�`�G�Q�Ɓj�����p�����ĂT�����x�̑�^�g���b�N�̏d�ʎԃ��[�h�R������P
��}�낤�Ƃ����ꍇ�A�P�������̔R����P�Z�p���T��ވȏ���W�߂ƂȂ�B���̂��߁A�吹�������u���ŗ�
�ꂽ�ʂ�̋Z�p���J�����ĂT�����x�̑�^�g���b�N�̏d�ʎԃ��[�h�R������P���������悤�Ƃ���ƁA���̋Z�p�J��
�̂��߂ɖc��ȁu�v�Ǝ����̐l���v�A�u�����ݔ��v���K�v�ƂȂ邽�߁A�K�R�I�ɊJ�����Ԃ������Ȃ邱�Ɛ�������
��B���̂Ȃ�A���Ɂu����������v������ł����Ă��A���̌����J�����I���������_�ŊJ���v���Ǝ����ݔ����s�v
�ɂƗ\�z����邽�߁A�T�����x�̑�^�g���b�N�̏d�ʎԃ��[�h�R������P�̌����J���ɕK�v�Ƃ̗��R�������ɂ��āA
�e�g���b�N���[�J�����̌����J���ɓ������đ啝�ȁu�J���v���̑����v�Ɓu�����ݔ��̑��݁v���邱�Ƃ�����Ȃ��߂�
����B
�@�����āA�吹�������u���ŗ��ꂽ�P�������̔R����P�������҂ł��Ȃ��Z�p���T��ވȏ���W�߂邱�Ƃ�
���A�ŏI�I�ɂT�����x�̑�^�g���b�N�̏d�ʎԃ��[�h�R��̉��P���B���ł����Ƃ��Ă��A���̑�^�g���b�N�́A�ɂ�
�ăR�X�g���̎��p���̗���^�g���b�N�ƂȂ邱�Ƃ����炩�ł���B����́A��^�g���b�N�́A�o�ϊ����̐��Y�ݔ���
����������̂ł���A����ґ�i�ł͖������߂ł���B�����āA���̂悤�ȂT�����x�̔R������P����������Ă�
�Ă��A�ɂ߂č����ȑ�^�g���b�N�́A�o�ϐ��̖ʂ���g���b�N���[�U���狑�₳���Ɨ\�z����邽�߁A�L�����y����
�\�����F���Ɛ��������B���������āA�吹�������u���ŗ��ꂽ�������̔R����P�̋Z�p���̗p���ĂT����
�x�̏d�ʎԃ��[�h�R��̌����B��������^�g���b�N�����p�����邱�Ƃ́A�펯�I�ɍl����Εs�\�ƍl����̂�
�Ó��ł͂Ȃ����낤���B
���A�ŏI�I�ɂT�����x�̑�^�g���b�N�̏d�ʎԃ��[�h�R��̉��P���B���ł����Ƃ��Ă��A���̑�^�g���b�N�́A�ɂ�
�ăR�X�g���̎��p���̗���^�g���b�N�ƂȂ邱�Ƃ����炩�ł���B����́A��^�g���b�N�́A�o�ϊ����̐��Y�ݔ���
����������̂ł���A����ґ�i�ł͖������߂ł���B�����āA���̂悤�ȂT�����x�̔R������P����������Ă�
�Ă��A�ɂ߂č����ȑ�^�g���b�N�́A�o�ϐ��̖ʂ���g���b�N���[�U���狑�₳���Ɨ\�z����邽�߁A�L�����y����
�\�����F���Ɛ��������B���������āA�吹�������u���ŗ��ꂽ�������̔R����P�̋Z�p���̗p���ĂT����
�x�̏d�ʎԃ��[�h�R��̌����B��������^�g���b�N�����p�����邱�Ƃ́A�펯�I�ɍl����Εs�\�ƍl����̂�
�Ó��ł͂Ȃ����낤���B
�@����ɑ��A�吹�������u�����Q�T�N�x��ʈ��S���������u����v�̍u���Ŗ����E�َE���ꂽ�u�ϋC���@�\
�i���C���x�~�j�v�̋Z�p�����p�����đ�^�g���b�N�̔R������P����ꍇ�A�u�ϋC���@�\�i���C���x�~�j�v�̂P��ނ�
�Z�p���̗p���邾���ŊȒP�ɑ�^�g���b�N�̏d�ʎԃ��[�h�R����T�����x�̌��オ�e�ՂɎ����ł���ƍl������B
���̂��߁A�߂������ɑ�^�g���b�N�̏d�ʎԃ��[�h�R����T�����x�̌�����������悤�Ƃ����ꍇ�A�u�����Q�T
�N�x��ʈ��S���������u����v�ł̑吹�����̍u���ŒE���ꂽ��^�g���b�N�̔R����P�̋Z�p
�������E�J������̂ł͖����A�吹�������u���Ŗ����E�َE���ꂽ�u�ϋC���@�\�i���C���x�~�j�v�̋Z�p��
���p�����錤���E�J���𑁋}�ɍs�����Ƃ��̗v�ƍl�������B�����āA���̏ꍇ�ɗp�����^�g���b�N�p�́u��
�C���@�\�i���C���x�~�j�v�̋Z�p�́A�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j��I���E�̗p���ׂ��ƍl����B���̂�
��A�����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�́A�z�C�فE�r�C�ق̒�~�@�\���s�v�Ȃ��߂ɒ�R�X�g�ł�
��A�������A�C���^�[�N�[���ߋ��f�B�[�[���G���W���ł����Ă��A�[�����ׁ`�P�^�Q���ׂ̉^�]�͈͓��Ŋ��S�ɋC���x
�~�̉^�]���\�ȗD�ꂽ���\�������ł��������L���Ă��邽�߂��B
�i���C���x�~�j�v�̋Z�p�����p�����đ�^�g���b�N�̔R������P����ꍇ�A�u�ϋC���@�\�i���C���x�~�j�v�̂P��ނ�
�Z�p���̗p���邾���ŊȒP�ɑ�^�g���b�N�̏d�ʎԃ��[�h�R����T�����x�̌��オ�e�ՂɎ����ł���ƍl������B
���̂��߁A�߂������ɑ�^�g���b�N�̏d�ʎԃ��[�h�R����T�����x�̌�����������悤�Ƃ����ꍇ�A�u�����Q�T
�N�x��ʈ��S���������u����v�ł̑吹�����̍u���ŒE���ꂽ��^�g���b�N�̔R����P�̋Z�p
�������E�J������̂ł͖����A�吹�������u���Ŗ����E�َE���ꂽ�u�ϋC���@�\�i���C���x�~�j�v�̋Z�p��
���p�����錤���E�J���𑁋}�ɍs�����Ƃ��̗v�ƍl�������B�����āA���̏ꍇ�ɗp�����^�g���b�N�p�́u��
�C���@�\�i���C���x�~�j�v�̋Z�p�́A�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j��I���E�̗p���ׂ��ƍl����B���̂�
��A�����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�́A�z�C�فE�r�C�ق̒�~�@�\���s�v�Ȃ��߂ɒ�R�X�g�ł�
��A�������A�C���^�[�N�[���ߋ��f�B�[�[���G���W���ł����Ă��A�[�����ׁ`�P�^�Q���ׂ̉^�]�͈͓��Ŋ��S�ɋC���x
�~�̉^�]���\�ȗD�ꂽ���\�������ł��������L���Ă��邽�߂��B
�@�����Ƃ��A���̍u�������Â��ꂽ��ʈ��S���������E�������̈�̌㓡 �Y�� �̈撷�́A�吹�����̍u��
���e�ɉ��̖������������̂Ɣ��f����Ɣ��f����Ă���悤���B�܂�A�㓡 �Y�� ���́A�u�ϋC���@�\�i���C���x
�~�j����^�f�B�[�[���g���b�N���R����P�̋Z�p�Ƃ��ẮA���i�E���ׂ̋Z�p�ł���v�Ƃ̑吹�����̈ӌ��E�����Ɏ^
������Ă���ƍl������B���̂��Ƃ́A���̍u����̏I����A���̑吹�����̍u�����e����ʈ��S���������z
�[���y�[�W��Ɍ��J���A���̑吹�����̍u�����e�𐢂̒��ɍL���g�U�����邱�ƂɌ㓡 �Y�� �������͂���Ă��邱
�Ƃ�������炩�ł���B
���e�ɉ��̖������������̂Ɣ��f����Ɣ��f����Ă���悤���B�܂�A�㓡 �Y�� ���́A�u�ϋC���@�\�i���C���x
�~�j����^�f�B�[�[���g���b�N���R����P�̋Z�p�Ƃ��ẮA���i�E���ׂ̋Z�p�ł���v�Ƃ̑吹�����̈ӌ��E�����Ɏ^
������Ă���ƍl������B���̂��Ƃ́A���̍u����̏I����A���̑吹�����̍u�����e����ʈ��S���������z
�[���y�[�W��Ɍ��J���A���̑吹�����̍u�����e�𐢂̒��ɍL���g�U�����邱�ƂɌ㓡 �Y�� �������͂���Ă��邱
�Ƃ�������炩�ł���B
�@����ɂ��Ă��A���̑�^�g���b�N�̔R�����ɗL���ȁu�ϋC���@�\�i���C���x�~�j�v���E�َE����u�������{��
�ꂽ�吹������A�u�ϋC���@�\�i���C���x�~�j�v�̋Z�p���E�َE����吹�����̍u�����e�̊g�U�ɐϋɓI��
�s���Ă���㓡 �Y�� ���̍s���́A����������������A���{�̑�^�g���b�N�̔R�����̑��₩�Ȑi�W��j
�~�E�x�������邽�߂̊����̂悤�Ɍ�����̂ł���B�v����ɁA�吹�����ƌ㓡 �Y�� ���̗����́A�u�ϋC���@�\
�i���C���x�~�j�v�̋Z�p��O��I�ɖ����E�َE��������u���E���\��������J��Ԃ����Ƃɂ��A�e�Ղɑ�^�g���b�N��
������T�����x�̏d�ʎԃ��[�h�R���R���e�ՂɌ���ł����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̎��p��
��j�ފ�����ϋɓI�ɍs���Ă���悤�Ɏv����̂ł���B���̂��Ƃ́A���{�̑�^�g���b�N�ɂ�����R����P�̐i�W
�ɂƂ��āA�D�܂����Ƃł͂Ȃ��ƍl������B
�ꂽ�吹������A�u�ϋC���@�\�i���C���x�~�j�v�̋Z�p���E�َE����吹�����̍u�����e�̊g�U�ɐϋɓI��
�s���Ă���㓡 �Y�� ���̍s���́A����������������A���{�̑�^�g���b�N�̔R�����̑��₩�Ȑi�W��j
�~�E�x�������邽�߂̊����̂悤�Ɍ�����̂ł���B�v����ɁA�吹�����ƌ㓡 �Y�� ���̗����́A�u�ϋC���@�\
�i���C���x�~�j�v�̋Z�p��O��I�ɖ����E�َE��������u���E���\��������J��Ԃ����Ƃɂ��A�e�Ղɑ�^�g���b�N��
������T�����x�̏d�ʎԃ��[�h�R���R���e�ՂɌ���ł����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̎��p��
��j�ފ�����ϋɓI�ɍs���Ă���悤�Ɏv����̂ł���B���̂��Ƃ́A���{�̑�^�g���b�N�ɂ�����R����P�̐i�W
�ɂƂ��āA�D�܂����Ƃł͂Ȃ��ƍl������B
�@�Ȃ��A�O�q�́u�U�|�P�D�A�C�h���X�g�b�v�ƈقȂ�^�[�{�ߋ��f�B�[�[���G���W���̋C���x�~�V�X�e���v�̍��́u�\�R�@
�e��̋C���x�~�G���W���̃V�X�e���v�̒��Ɏ������悤�ɁA�X�F�[�f���̃g���b�N���[�J�ł���VOLVO�́A�f�B�[�[
���G���W���̔R�����Z�p�Ƃ��āA�u�C���x�~�v�������Ă���i���L�̕\�R�T�Q�Ɓj�B����ɂ�������炸�A�O
�q�̂悤�ɁA�吹��������^�f�B�[�[���g���b�N�̔R�����̋Z�p�Ƃ��āA���āu�C���x�~�v����Ȃɖ����E��
�E����Ă����̂ł���B���������ƁA�u�f�B�[�[�����p�Ԃ̍��������v��}��Z�p�v�Ƃ��Ắu�ϋC���@�\�i���C
���x�~�j�v�̔R�����̋@�\�E���ʂɂ��āA�吹�����������́A�g���b�N���[�J�ł���VOLVO�Ƃ����S�ɈقȂ��Ă�
�邱�Ƃ������ł���̂ł͂Ȃ����낤���B
�e��̋C���x�~�G���W���̃V�X�e���v�̒��Ɏ������悤�ɁA�X�F�[�f���̃g���b�N���[�J�ł���VOLVO�́A�f�B�[�[
���G���W���̔R�����Z�p�Ƃ��āA�u�C���x�~�v�������Ă���i���L�̕\�R�T�Q�Ɓj�B����ɂ�������炸�A�O
�q�̂悤�ɁA�吹��������^�f�B�[�[���g���b�N�̔R�����̋Z�p�Ƃ��āA���āu�C���x�~�v����Ȃɖ����E��
�E����Ă����̂ł���B���������ƁA�u�f�B�[�[�����p�Ԃ̍��������v��}��Z�p�v�Ƃ��Ắu�ϋC���@�\�i���C
���x�~�j�v�̔R�����̋@�\�E���ʂɂ��āA�吹�����������́A�g���b�N���[�J�ł���VOLVO�Ƃ����S�ɈقȂ��Ă�
�邱�Ƃ������ł���̂ł͂Ȃ����낤���B
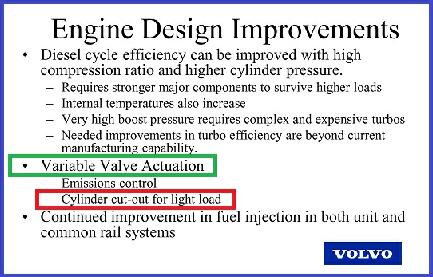
pdf�j
�@�ȏ�̂悤�ɁA����c��w�̑吹�����́A�u�f�B�[�[�������Ԃ̔r�o�K�X��Z�p�̍ŐV�����v�̍u����
���̂Q�X�y�[�W�u�����Ԃ̔R����P�Z�p�v�̒��ł����f�B�[�[�������Ԃ���уK�\���������Ԃ̔R����P��
���P�O���ȏ�̋Z�p�Ƃ��āu�ϋC���@�\�i���C���x�~�j�v�����Ă��邢��ɂ�������炸�A���R���s��
�ł͂��邪�A�R�O�y�[�W�́u�f�B�[�[�����p�Ԃ̍��������v�̋Z�p�Ƃ��Ắu�ϋC���@�\�i���C���x�~�j�v��
�ȗ����A����ȊO����^�g���b�N�iGVW25�g���j�������s�R����d�ʎԃ��[�h�R��̉��P���P�������́u�Ⴆ
�Ȃ������̋Z�p�v�𐄏�����Ă���̂ł���B���͂Ƃ�����A����c��w�̑吹�������u�ϋC���@�\�i���C��
�x�~�j�v�i���Ⴆ�A�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�j�̋Z�p����ȂɌ�������Ă��闝�R���A����Ƃ��m��
�������̂��B
���̂Q�X�y�[�W�u�����Ԃ̔R����P�Z�p�v�̒��ł����f�B�[�[�������Ԃ���уK�\���������Ԃ̔R����P��
���P�O���ȏ�̋Z�p�Ƃ��āu�ϋC���@�\�i���C���x�~�j�v�����Ă��邢��ɂ�������炸�A���R���s��
�ł͂��邪�A�R�O�y�[�W�́u�f�B�[�[�����p�Ԃ̍��������v�̋Z�p�Ƃ��Ắu�ϋC���@�\�i���C���x�~�j�v��
�ȗ����A����ȊO����^�g���b�N�iGVW25�g���j�������s�R����d�ʎԃ��[�h�R��̉��P���P�������́u�Ⴆ
�Ȃ������̋Z�p�v�𐄏�����Ă���̂ł���B���͂Ƃ�����A����c��w�̑吹�������u�ϋC���@�\�i���C��
�x�~�j�v�i���Ⴆ�A�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�j�̋Z�p����ȂɌ�������Ă��闝�R���A����Ƃ��m��
�������̂��B
�@����ɂ��Ă��A���{�̃f�B�[�[���G���W���W�̑����̐��ƁE�Z�p�҂́A�吹�������u�����Q�T�N�x��ʈ��S��
���������u����v�ɂ����Đ�������Ă�����^�g���b�N�iGVW25�g���j�������s�R�����d�ʎԃ��[�h�R��̉��P
�Z�p�̓��e�ɂ��Ĕ[�����A�N���^��Ɏv���Ă��Ȃ��̂ł��낤���B���݂ɁA�K�\������p�Ԃ�K�\�������^�g���b�N
�ɂ����ẮA���Ƀz���_��t�H���N�X���[�Q�����̓��E�āE���̑����̎����ԃ��[�J���u�ϋC���@�\�i���C���x�~�j�v
���s�̎Ԃɍ̗p���Ă��������ƁA�����ԗp�K�\�����G���W���̐��E�ł́A�u�ϋC���@�\�i���C���x�~�j�v�́A
���ɕ��y���n�߂���ʓI�ȋZ�p�ƍl������B����A2006�N4���ɊJ�݂����M�҂��z�[���y�[�W�ɂ����āA������
�p�f�B�[�[���G���W���̐��E�ł́A�u�ϋC���@�\�i���C���x�~�j�v�́A�������p�����ꂽ�Ⴊ�������Ƃ��l����ƁA
��R��E��NO���̐V�����Z�p�Ƃ��đ��}�Ɍ����J���ɒ��肷�ׂ��ƍl������B�����āA���̃f�B�[�[���G���W���p��
���čł��D�ꂽ�u�ϋC���@�\�i���C���x�~�j�v�̋Z�p���M�Ғ�Ă��C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�ł�
��B
���������u����v�ɂ����Đ�������Ă�����^�g���b�N�iGVW25�g���j�������s�R�����d�ʎԃ��[�h�R��̉��P
�Z�p�̓��e�ɂ��Ĕ[�����A�N���^��Ɏv���Ă��Ȃ��̂ł��낤���B���݂ɁA�K�\������p�Ԃ�K�\�������^�g���b�N
�ɂ����ẮA���Ƀz���_��t�H���N�X���[�Q�����̓��E�āE���̑����̎����ԃ��[�J���u�ϋC���@�\�i���C���x�~�j�v
���s�̎Ԃɍ̗p���Ă��������ƁA�����ԗp�K�\�����G���W���̐��E�ł́A�u�ϋC���@�\�i���C���x�~�j�v�́A
���ɕ��y���n�߂���ʓI�ȋZ�p�ƍl������B����A2006�N4���ɊJ�݂����M�҂��z�[���y�[�W�ɂ����āA������
�p�f�B�[�[���G���W���̐��E�ł́A�u�ϋC���@�\�i���C���x�~�j�v�́A�������p�����ꂽ�Ⴊ�������Ƃ��l����ƁA
��R��E��NO���̐V�����Z�p�Ƃ��đ��}�Ɍ����J���ɒ��肷�ׂ��ƍl������B�����āA���̃f�B�[�[���G���W���p��
���čł��D�ꂽ�u�ϋC���@�\�i���C���x�~�j�v�̋Z�p���M�Ғ�Ă��C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�ł�
��B
�P�W�@���쎩���Ԃ́A2020�N�ɃG���W���P�̔R���10���̉��P��ڎw�����j�\
�@�Ƃ���ŁA�\�R�U�Ɏ������悤�ɁA���쎩���ԇ��̉����^�ꖱ�������9��25���ɓs���ŊJ�����Z�p������ŁA
2020�N���߂ǂɃf�B�[�[���G���W���P�̔R���10���̉��P��ڎw�����j�𖾂炩�ɂ����Ƃ̂��Ƃł���B
2020�N���߂ǂɃf�B�[�[���G���W���P�̔R���10���̉��P��ڎw�����j�𖾂炩�ɂ����Ƃ̂��Ƃł���B
�i�o�T�Fhttp://response.jp/article/2013/09/26/207149.html�Ahttp://e-nenpi.com/article/detail/207149�j
| |
|
| �� �����̎�|
�@�@���쎩���ԇ��̍���̔R����P�̊J���ڕW�ƋZ�p�J���̊T�v����� �� ������ 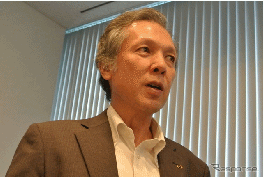 �@�@���ĉ��̔r�o�K�X�ƔR��̋K������ �@�@�@�E ���쎩���Ԃ́A�u2015�N�x�d�ʎԔR������������鎞����2022�`2025�N�v�Ɨ\�z 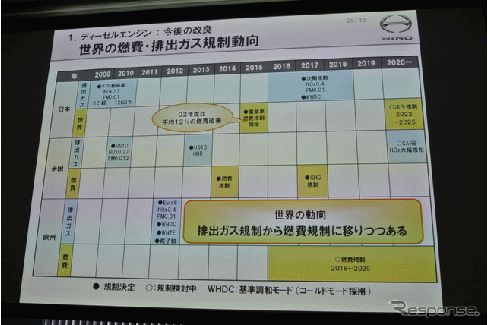 �@�@�@�E �u2020�N���߂ǂɃf�B�[�[���G���W���P�̔R���10���̉��P��ڎw���v�Ƃ̂��� 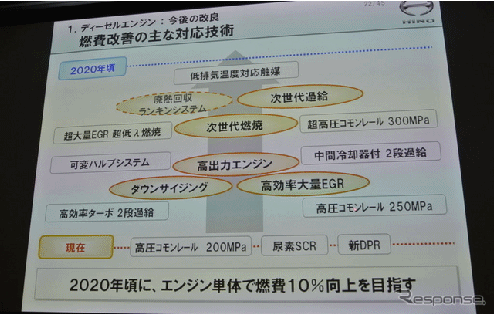 �@�B ���쎩���Ԃɂ����鍡��̔R����P�̌����J���̓��e
�@�@�@�E ��ȔR����P�̂��߂̊J���Z�p�́A�u������R�āv�A�u�p�M����v�A�u�_�E���T�C�W���O�v�A�u�V�G�}�v��
�@�@�@�@����Ƃ̂��Ɓi���C���x�~�̋Z�p�J���́A�܂܂�Ă��Ȃ��͗l�j
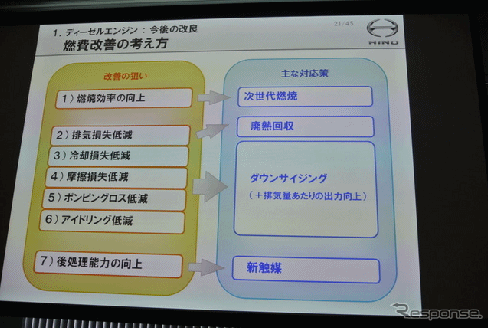
�@�@�@�E �R����P�̊J���Z�p�̒��ŁA���Ɂu�p�M����v�̌��ʂɓ��쎩���Ԃ����҂��Ă���͗l 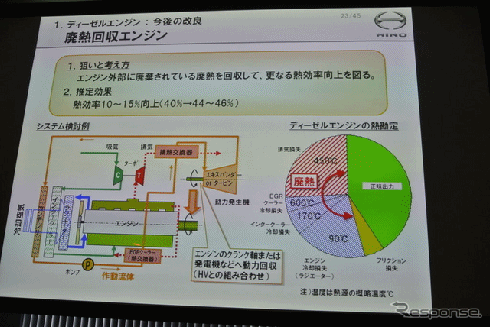 |
�@�ȏ�̕\�R�U�Ɏ������悤�ɁA���쎩���ԇ��́A2013�N9��25���ɓs���ŋZ�p��������J�Â��A�u2020�N���߂ǂ�
�f�B�[�[���G���W���P�̔R���10���̉��P��ڎw�����j�v�𖾂炩�ɂ����Ƃ̂��ƁB���̃f�B�[�[���G���W����10��
�̔R����P�́A�u2015�N�x�d�ʎԔR������������鎞����2022�`2025�N�v�Ɨ\�z���A���́u2015�N�x�d�ʎԔR
���������v�ɑΉ����邽�߂Ɛ��������B���̂��߁A�펯�I�ɂ́A�������쎩���ԇ������\�����u�f�B�[�[���G
���W���̔R���10�����P�v�́A���m�ɋL�ڂ���Ƃ���u���쎩���ԇ��́A2020�N���߂ǂɃf�B�[�[���G���W���P��
�ŏd�ʎԃ��[�h�R��܂��̓g���b�N�E�o�X�̎����s�R���10���̉��P��ڎw�����j�v�ƂȂ���̂Ɛ��������B����
�āA�u�f�B�[�[���G���W���̔R���10�����P�v�́A�g���b�N�E�o�X�̎����s�ɂ����ċɂ߂ĉ^�]�p�x�̒Ⴂ�G���W����
�ő�g���N�_��ō��o�͓_�̔R��ł͖������ł���B���̂Ȃ�A�G���W���̍ő�g���N�_��ō��o�͓_�̔R���
�P�́A�g���b�N�E�o�X�̎����s�̔R����P�ɉ�����^���Ȃ����炾�B���������āA���쎩���ԇ��́u2020�N���Ƀf�B�[
�[���G���W���P�̔R���10���̉��P�v�́A�u�d�ʎԃ��[�h�R��܂��̓g���b�N�E�o�X�̎����s�R���10���̉��P�v�Ɨ�
�����ׂ��ƍl������B
�f�B�[�[���G���W���P�̔R���10���̉��P��ڎw�����j�v�𖾂炩�ɂ����Ƃ̂��ƁB���̃f�B�[�[���G���W����10��
�̔R����P�́A�u2015�N�x�d�ʎԔR������������鎞����2022�`2025�N�v�Ɨ\�z���A���́u2015�N�x�d�ʎԔR
���������v�ɑΉ����邽�߂Ɛ��������B���̂��߁A�펯�I�ɂ́A�������쎩���ԇ������\�����u�f�B�[�[���G
���W���̔R���10�����P�v�́A���m�ɋL�ڂ���Ƃ���u���쎩���ԇ��́A2020�N���߂ǂɃf�B�[�[���G���W���P��
�ŏd�ʎԃ��[�h�R��܂��̓g���b�N�E�o�X�̎����s�R���10���̉��P��ڎw�����j�v�ƂȂ���̂Ɛ��������B����
�āA�u�f�B�[�[���G���W���̔R���10�����P�v�́A�g���b�N�E�o�X�̎����s�ɂ����ċɂ߂ĉ^�]�p�x�̒Ⴂ�G���W����
�ő�g���N�_��ō��o�͓_�̔R��ł͖������ł���B���̂Ȃ�A�G���W���̍ő�g���N�_��ō��o�͓_�̔R���
�P�́A�g���b�N�E�o�X�̎����s�̔R����P�ɉ�����^���Ȃ����炾�B���������āA���쎩���ԇ��́u2020�N���Ƀf�B�[
�[���G���W���P�̔R���10���̉��P�v�́A�u�d�ʎԃ��[�h�R��܂��̓g���b�N�E�o�X�̎����s�R���10���̉��P�v�Ɨ�
�����ׂ��ƍl������B
�@�������쎩���ԇ��́u2020�N���߂ǂɃf�B�[�[���G���W���P�̔R���10���̉��P�i���d�ʎԃ��[�h�R��܂��̓g��
�b�N�E�o�X�̎����s�R���10���̉��P�j��}���i�E���@�ɂ��āA���� �^ �ꖱ������́A�u������R�āv�A�u�p�M
����v�A�u�_�E���T�C�W���O�v�A�u�V�G�}�v�̋Z�p�J���𐄐i���邱�Ƃɂ�����u�f�B�[�[���G���W���̔R���10���̉�
�P�v����������Ɛ������ꂽ�悤���B�������A���̓��쎩���ԇ������� �^ �ꖱ����������ꂽ�u������R�āv�A
�u�p�M����v�A�u�_�E���T�C�W���O�v�A�u�V�G�}�v�̂S��ނ̋Z�p�ł́A�u2020�N���߂ǂɃf�B�[�[���G���W���P�̔R���
10���̉��P�v���������邱�Ƃ́A�|���R�c���Z�p���̕M�҂̏���C�܂܂ȗ\���ł́A�ɂ߂č���Ȃ悤�Ɋ�����̂�
����B���̗��R�͈ȉ��̕\�R�V�̒ʂ�ł���B
�b�N�E�o�X�̎����s�R���10���̉��P�j��}���i�E���@�ɂ��āA���� �^ �ꖱ������́A�u������R�āv�A�u�p�M
����v�A�u�_�E���T�C�W���O�v�A�u�V�G�}�v�̋Z�p�J���𐄐i���邱�Ƃɂ�����u�f�B�[�[���G���W���̔R���10���̉�
�P�v����������Ɛ������ꂽ�悤���B�������A���̓��쎩���ԇ������� �^ �ꖱ����������ꂽ�u������R�āv�A
�u�p�M����v�A�u�_�E���T�C�W���O�v�A�u�V�G�}�v�̂S��ނ̋Z�p�ł́A�u2020�N���߂ǂɃf�B�[�[���G���W���P�̔R���
10���̉��P�v���������邱�Ƃ́A�|���R�c���Z�p���̕M�҂̏���C�܂܂ȗ\���ł́A�ɂ߂č���Ȃ悤�Ɋ�����̂�
����B���̗��R�͈ȉ��̕\�R�V�̒ʂ�ł���B
| �R����P�̋Z�p | |
| |
�E ���́u������R�āv�ɂ��Ă̋�̓I�ȔR����P�ɗL���ȋZ�p�������L�ڂ���Ă��Ȃ��B�������A�O�q�́u14-
1�v���Ɏ�����NEDO�ɂ��f�B�[�[���G���W���̔r�o�K�X�ƔR������P����u�����x�R�Đ���G���W�V�X�e���̌�
���J���v�̃v���W�F�N�g�́A�@ �V�R�ċZ�p�iPCI�R�āj�A�A �R�O�OMPa�̒��������˃V�X�e���A�B �J�����X�V�X�e��
�i�σo���u�@�\�j�A�C �R�i�ߋ��V�X�e���A�D �G���W��/�㏈���̃V���~���[�V�����ɂ��œK���Ɠ����I����A
�E �e��̃Z�^�����E��������ύX�����R���A�F �G�}�����M�𗘗p�����G�}���u�A�G �r�o�K�X�����iCO���j��
�p����DeNO���G�}�̐V�Z�p���g�ݍ��܂ꂽ�B�������A����NEDO�́u�����x�R�Đ���G���W�V�X�e���̌����J
���v�̃v���W�F�N�g�́A2015�N�x�d�ʎԔR�������P�O���̑啝�ȔR����P��ڕW�Ɍf���Ȃ���A�ŏI���ʂ�
�́A2015�N�x�d�ʎԔR�������Q�����R���������S�邽�錋�_�ƂȂ��Ă��܂����Ƃ̂��Ƃł���B
�@���������āA�����_�ł́A��ʓI�ɂ͔R�ĉ��P�ɗL���ȋZ�p�́u�s���v�ƍl�����Ă���B�������A���쎩����
���̉��� �^ �ꖱ������́A�u�R�O�OMPa�̒��������˃V�X�e���v�A�u�σo���u�@�\�v�A�u�R�i�ߋ��V�X�e���v����
�u������R�āv�Ə̂����R�ĉ��P�ɂ���ăf�B�[�[���G���W���̔R������P����Ƃ��Ă���B�������A���́u������R
�āv�ɑg�ݍ��܂ꂽ�Z�p�̖w��ǂ́A2015�N�x�d�ʎԔR�������Q�����R��̈����������N�������Z�p�ł�
�邱�Ƃ���A���́u������R�āv�̋Z�p�ɂ���ăf�B�[�[���G���W���̏d�ʎԃ��[�h�R��̉��P��}�邱�Ƃ͍����
�\�������B�������A���� �^ �ꖱ������́A�O�q��NEDO�̃v���W�F�N�g�Ɨގ������u������R�āv�Ə̂��閼��
�������E�܂����Z�p��p���ăf�B�[�[���G���W���̔R������P����Ɛ錾���Ă���̂ł���B�ʂ����āA���쎩��
�ԇ��́A���Ԃ̏펯���悤�Ȏ�����̐V���ȔR�ĉ��P�̋Z�p�̈āE�A�C�f�A��ۗL���Ă���̂ł�
�낤���B���ꂪ�{���ł���A�f���炵�����Ƃł��邪�A���ʂɍl����u�����v�ƌ���̂��Ó��Ȃ悤�Ɏv�����
�ł���B���̂��߁A�R�ĉ��P�ɗL���ȋ�̓I�ȐV�Z�p������������ɁA�u������R�āv�̐V�Z�p�ɂ���ăf�B�[
�[���G���W���̔R����P��}��Ƃ̓��쎩���ԇ��̉��� �^ �ꖱ������̐����́A�M�҂ɂ́u���M�����̔R��
�������������v�Ƃ̒P�Ȃ�u��]�v�E�u�v�]�v�E�u����v���q�ׂĂ���ɉ߂��Ȃ��悤�Ɏv����̂ł���B���̂��߁A����
���쎩���ԇ��́u������R�āv�Ə̂���Z�p�ɂ���ăf�B�[�[���G���W���̔R����P������ƌ���̂�
�Ó��ƍl������B
|
| |
�E �C���x�~�́A�f�B�[�[���r�C�K�X�̃G�l���M�[���u�̌����������̃y�[�W�ɏڏq���Ă���悤�ɁA�^�[�{ �R���p�E���h���̔r�C�K�X�̃G�l���M�[���u��p�����ꍇ�́u�d�ʎԃ��[�h�R��܂��̓g���b�N�E�o �X�̎����s�R��v�́A�P���ȉ��̔��X������P�ł���B���ɁA���Ĕr�C�K�X�̃G�l���M�[���u��p���� �u�d�ʎԃ��[�h�R��܂��̓g���b�N�E�o�X�̎����s�R��v�̉��P��}�肽���Ȃ�A�G���W���̕��������ɔr�C �K�X���x���������ł���Q�^�[�{�����̋C���x�~�V�X�e���i���C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�j�Ƃ� �g�ݍ��킹���K�{�ł���B���������āA�Q�^�[�{�����̋C���x�~�V�X�e���Ƃ̑g�ݍ��킹���ɔr�C�K�X�̃G�l�� �M�[���u�̒P�Ǝg�p�ɂ���āu�d�ʎԃ��[�h�R��܂��̓g���b�N�E�o�X�̎����s�R��v�̉��P��}�낤�Ƃ��� �s�ׂ́A�u���̍����v�ƍl������B���̂��߁A���́u������R�āv�Ə̂���Z�p�ɂ���ăf�B�[�[���G���W���̔R ����P������ƌ���̂��Ó��ƍl������B���̂��߁A���́u�p�M����v�Ə̂���Z�p�ɂ���ăf�B�[�[���G ���W���̔R����P�́A�P���ȉ��̔��X������P�ƌ���̂��Ó��ƍl������B |
| |
�E �O�q�̕\�P�Q�Ɏ������悤�ɁA���݂̊e�g���b�N���[�J�̑�^�J�[�S�g���b�N�iGVW25�g���j�ɓ��ڂ̃G���W���́A�X
�`�P�Q���b�g���ł��邪�A�X���b�g���̃G���W���͂P�Q���b�g���̃G���W�����Q�T�����_�E���T�C�W���O�����G���W���Ƃ�
���Ă���B���쎩���ԇ��̂X���b�g���ƂP�Q���b�g���̃G���W���𓋍ڂ��e��^�J�[�S�g���b�N�iGVW25�g���j�̔R���
��r����ƁA�ȉ��̒ʂ�A���҂̏d�ʎԃ��[�h�R��̍��͋͏��ł���B
�@�@�� �X���b�g���G���W���𓋍ڂ�����^�J�[�S�g���b�N�iGVW25�g���j�̏d�ʎԃ��[�h�R��F4.15�`4.05 (km/���j
�@�@�� �P�Q���b�g���G���W���𓋍ڂ�����^�J�[�S�g���b�N�iGVW25�g���j�̏d�ʎԃ��[�h�R��F4.10�`4.05 (km/���j
�E �ȏ�̂悤�ɁA�ߋ��G���W���̔��e�Ō���A�G���W���r�C�ʂ̂Q�T���̃_�E���T�C�W���O�̏ꍇ�ɂ́A�d�ʎ�
���[�h�R��̉��P������ł���̂�����̂悤���B���������āA���݂̉ߋ��f�B�[�[���G���W���ł́A�r�C�ʂ̃_
�E���T�C�E�W���O�ɂ���ē����锤�́u�r�C�����̒ጸ�v�A�u��p�����̒ጸ�v�A�u���C�����̒ጸ�v�A�u�|���s��
�O�����̒ጸ�v�ɂ��R����P�̃����b�g�́A�V�����_���̍ō����͂̑���ɂ��f�����b�g�Ƒ��E����Ă���̂�
����Ɛ��@�����B���������āA�r�C�ʂ̃_�E���T�C�E�W���O�ɂ���Ĉ����N�������V�����_���̍ō����͂̑�
��ɂ��R����̃f�����b�g���팸�ł����i�E���@�̈āE�A�C�f�A��������A�_�E���T�C�E�W���O�ɂ��d��
�ԃ��[�h�R��̉��P�́A�u����̋�_�v�E�u�P�Ȃ�ϑz�v�ɂ����߂��Ȃ����ƂɂȂ�ƍl������B���� �^ �ꖱ��
�����̓V�����_���̍ō����͂̑���ɂ��f�����b�g�����������i�E���@��������Ă���̂ł��낤���B�펯�I
�ɍl����A�V�����_���̍ō����͂̑���ɂ��f�����b�g���������邱�Ƃ͋ɂ߂č���ƍl������B���̂��߁A
�����u�_�E���T�C�W���O�v�Ə̂���Z�p�ɂ���ăf�B�[�[���G���W���̔R����P�́A�P�������̔��X�����
�x�̉��P�ƌ���̂��Ó��ƍl������B
|
| |
�E ��w�ɍ˂̃|���R�c���Z�p���̕M�҂́A����܂Łu�G�}�ɂ��ߋ��f�B�[�[���G���W���̔R����P���\�v�Ƃ�
�b�����ɂ������Ƃ������B���� �^ �ꖱ������������̉ߋ��f�B�[�[���G���W���ɂ�����R����P�̂S�{���̈�
�Ƃ��āu�V�G�}�v���������Ă���́A�������ɂł���B�펯�I�ɍl����A�G�}�ɂ���ăf�B�[�[���G���W����
�R����P�͍���ƌ���̂��Ó��ƍl������B���������āA���́u�V�G�}�v�Ə̂���Z�p�ɂ���ăf�B�[�[���G
���W���̔R����P���������邱�Ƃ́A����ƌ���̂��Ó��ƍl������B�������A���ɁA���쎩���ԇ����f�B
�[�[���G���W���̔R������P�ł���u�V�G�}�v���J�������Ȃ�A����͐��I�́u�唭���v�ƂȂ�̂ł͂Ȃ����낤
���B���̂悤�Ȕ����́A�M�҂ɂ͕s�\�Ɏv���邪�A���� �^ �ꖱ����������X�Ɣ��\����Ă���̂ŁA�u�����
�ݔq���v�Ɖ]�����ƂŁA���҂��Ȃ��ő҂��Ƃɂ���B�A
|
�@�ȏ�̕\�R�V�Ɏ������悤�ɁA���쎩���ԇ������� �^ �ꖱ����������ꂽ�u������R�āv�A�u�p�M����v�A�u�_
�E���T�C�W���O�v�A�u�V�G�}�v�̂S��ނ̋Z�p�ɂ��āA�d�ʎԃ��[�h�R��܂��̓g���b�N�E�o�X�̎����s�R������P��
���ēZ�߂�ƁA�u�p�M����v���P�����x�̉��P�ł���A�u�_�E���T�C�W���O�v�����X������P�ɉ߂����A���̑��́u��
����R�āv�Ɓu�V�G�}�v�́A�R��̉��P������Ȃ��F���ɋ߂��Ɛ��������B���̂悤���d�ʎԃ��[�h�R��܂��̓g��
�b�N�E�o�X�̎����s�R������P����@�\�E���\������������u������R�āv�A�u�p�M����v�A�u�_�E���T�C�W��
�O�v�A�u�V�G�}�v�̂S��ނ̋Z�p�������J���𐄐i���邱�Ƃɂ���āA���쎩���ԇ������� �^ �ꖱ�����
�́A�u2020�N���Ƀf�B�[�[���G���W���P�̔R���10���̉��P�i���d�ʎԃ��[�h�R��܂��̓g���b�N�E�o�X�̎�
���s�R���10���̉��P�j����������Ƌ������ɂ̑�_�Ȑ錾�����Ă����̂ł���B�����Ƃ��A�|���R�c���Z�p��
�̕M�҂��猩��A���� �^ �ꖱ����������ꂽ�u������R�āv�A�u�p�M����v�A�u�_�E���T�C�W���O�v�A�u�V�G�}�v
�̂S��ނ̋Z�p�ł́A�d�ʎԃ��[�h�R��܂��̓g���b�N�E�o�X�̎����s�R��ɂ��ẮA�P�`�Q���̔R�����P������
�҂ł��Ȃ��悤�Ɏv���Ďd���������̂ł���B
�E���T�C�W���O�v�A�u�V�G�}�v�̂S��ނ̋Z�p�ɂ��āA�d�ʎԃ��[�h�R��܂��̓g���b�N�E�o�X�̎����s�R������P��
���ēZ�߂�ƁA�u�p�M����v���P�����x�̉��P�ł���A�u�_�E���T�C�W���O�v�����X������P�ɉ߂����A���̑��́u��
����R�āv�Ɓu�V�G�}�v�́A�R��̉��P������Ȃ��F���ɋ߂��Ɛ��������B���̂悤���d�ʎԃ��[�h�R��܂��̓g��
�b�N�E�o�X�̎����s�R������P����@�\�E���\������������u������R�āv�A�u�p�M����v�A�u�_�E���T�C�W��
�O�v�A�u�V�G�}�v�̂S��ނ̋Z�p�������J���𐄐i���邱�Ƃɂ���āA���쎩���ԇ������� �^ �ꖱ�����
�́A�u2020�N���Ƀf�B�[�[���G���W���P�̔R���10���̉��P�i���d�ʎԃ��[�h�R��܂��̓g���b�N�E�o�X�̎�
���s�R���10���̉��P�j����������Ƌ������ɂ̑�_�Ȑ錾�����Ă����̂ł���B�����Ƃ��A�|���R�c���Z�p��
�̕M�҂��猩��A���� �^ �ꖱ����������ꂽ�u������R�āv�A�u�p�M����v�A�u�_�E���T�C�W���O�v�A�u�V�G�}�v
�̂S��ނ̋Z�p�ł́A�d�ʎԃ��[�h�R��܂��̓g���b�N�E�o�X�̎����s�R��ɂ��ẮA�P�`�Q���̔R�����P������
�҂ł��Ȃ��悤�Ɏv���Ďd���������̂ł���B
�@����A���쎩���ԇ��̉i�g �w���A�� �K�����A���� �����Y���́A�����ԋZ�p���2013�N�H�G���ɂ����āA��
���f�B�[�[���G���W���̋C���x�~�ɂ��ču����\�肵�Ă����悤���B���̏؋��ɁA���̏H�G���̃v���O������
�́A�u�ߋ��f�B�[�[���G���W���̋C���x�~�ɂ��Ă̈�l�@�v�i�o�T�Fhttp://tech.jsae.or.jp/2013aki/pc/speech.aspx?
id=69�j�Ƒ肷��_���̏��^���f�ڂ���Ă���B����ɂ��ƁA�z�E�r�C�ًx�~�����Ɛ��肳���C���x�~�V�X�e����
�Z�p��p�����R����P�̎��������{���A���ɑ�^�g���b�N���������H���s�ł̂S�����x�̔R����オ���҂ł����
�q�ׂ��Ă���B���̂��Ƃ���A���쎩���ԇ��́A2013�N�̏t���ɂ́A�z�E�r�C�ًx�~�����Ɛ��肳���C���x�~�V
�X�e���̋Z�p��p�����ꍇ�ɑ�^�g���b�N���������H���s�ł̂S�����x�̔R����オ�\�Ȃ��Ƃ������I�Ɋm�F��
�Ă������̍l������B���̋Z�p���́A���쎩���ԇ��̌o�c�����ł��鉓�� �^ �ꖱ������͏n�m���Ă��锤��
����B����ɂ�������炸�A���� �^ �ꖱ������́A���̔R����P�ɗL�����C���x�~�V�X�e���̋Z�p���̈ӂɏ��O
���A�u������R�āv�A�u�p�M����v�A�u�_�E���T�C�W���O�v�A�u�V�G�}�v�̂S��ނ̔R����P�@�\�̗��Z�p��g�ݍ��킹
�邽�߂��d�ʎԃ��[�h�R�������s�R��ŏI�I���P�`�Q���̔R�����P�������҂ł��Ȃ��Z�p�̊J���𐄐i����
�Ƃ̐�������A�@���Ȃ铮�@�E���R�ɂ����2013�N9��25�����J�Â����̂ł��납�B
���f�B�[�[���G���W���̋C���x�~�ɂ��ču����\�肵�Ă����悤���B���̏؋��ɁA���̏H�G���̃v���O������
�́A�u�ߋ��f�B�[�[���G���W���̋C���x�~�ɂ��Ă̈�l�@�v�i�o�T�Fhttp://tech.jsae.or.jp/2013aki/pc/speech.aspx?
id=69�j�Ƒ肷��_���̏��^���f�ڂ���Ă���B����ɂ��ƁA�z�E�r�C�ًx�~�����Ɛ��肳���C���x�~�V�X�e����
�Z�p��p�����R����P�̎��������{���A���ɑ�^�g���b�N���������H���s�ł̂S�����x�̔R����オ���҂ł����
�q�ׂ��Ă���B���̂��Ƃ���A���쎩���ԇ��́A2013�N�̏t���ɂ́A�z�E�r�C�ًx�~�����Ɛ��肳���C���x�~�V
�X�e���̋Z�p��p�����ꍇ�ɑ�^�g���b�N���������H���s�ł̂S�����x�̔R����オ�\�Ȃ��Ƃ������I�Ɋm�F��
�Ă������̍l������B���̋Z�p���́A���쎩���ԇ��̌o�c�����ł��鉓�� �^ �ꖱ������͏n�m���Ă��锤��
����B����ɂ�������炸�A���� �^ �ꖱ������́A���̔R����P�ɗL�����C���x�~�V�X�e���̋Z�p���̈ӂɏ��O
���A�u������R�āv�A�u�p�M����v�A�u�_�E���T�C�W���O�v�A�u�V�G�}�v�̂S��ނ̔R����P�@�\�̗��Z�p��g�ݍ��킹
�邽�߂��d�ʎԃ��[�h�R�������s�R��ŏI�I���P�`�Q���̔R�����P�������҂ł��Ȃ��Z�p�̊J���𐄐i����
�Ƃ̐�������A�@���Ȃ铮�@�E���R�ɂ����2013�N9��25�����J�Â����̂ł��납�B
�@�����ŁA�C���x�~�V�X�e���Ɋ֘A�������쎩���ԇ��̓��������n��I�ɋC���x�~�Ɋւ��铮��������ƁA��
���̂ƒʂ�ł���B
���̂ƒʂ�ł���B
�@ ���쎩���ԇ��́A2013�N6�����{���܂łɎ����ԋZ�p���2013�N�H�G���ɂ�����C���x�~�V�X�e���Ɋւ�
��_�����\��\������Ă���ƍl�����邽�߁A�z�E�r�C�ًx�~�����Ɛ��肳����C���x�~�V�X�e���̋Z�p��p
�����ꍇ�ɑ�^�g���b�N���������H���s�ł̂S�����x�̔R����オ�\�Ȃ��Ƃ������I�Ɋm�F���Ă����Ɛ�
�������B
��_�����\��\������Ă���ƍl�����邽�߁A�z�E�r�C�ًx�~�����Ɛ��肳����C���x�~�V�X�e���̋Z�p��p
�����ꍇ�ɑ�^�g���b�N���������H���s�ł̂S�����x�̔R����オ�\�Ȃ��Ƃ������I�Ɋm�F���Ă����Ɛ�
�������B
�A �Ƃ��낪�A2013�N8�����{�ɂ��A�����ԋZ�p���2013�N�H�G���ɂ�����u�ߋ��f�B�[�[���G���W���̋C���x�~
�ɂ��Ă̈�l�@�v�Ƒ肷��C���x�~�V�X�e���̘_�����\����艺���鏈�u���s�����悤�ł���B�������A�����ԋZ
�p��́A�K��ɂ��A���쎩���ԇ������\����\��ł������u�C���x�~�V�X�e���̋Z�p��p�����ꍇ�ɂ͑�^�g
���b�N���������H���s�łS�����x�̔R����オ���҂ł���v�ƋL�ڂ��ꂽ���e�̘_�����^��2013�N8�����{��
�����ԋZ�p��̃C���^�[�l�b�g�Ō��J�����̂ł���B
�ɂ��Ă̈�l�@�v�Ƒ肷��C���x�~�V�X�e���̘_�����\����艺���鏈�u���s�����悤�ł���B�������A�����ԋZ
�p��́A�K��ɂ��A���쎩���ԇ������\����\��ł������u�C���x�~�V�X�e���̋Z�p��p�����ꍇ�ɂ͑�^�g
���b�N���������H���s�łS�����x�̔R����オ���҂ł���v�ƋL�ڂ��ꂽ���e�̘_�����^��2013�N8�����{��
�����ԋZ�p��̃C���^�[�l�b�g�Ō��J�����̂ł���B
�B �ȏ�̂��Ƃ���A���쎩���ԇ��́A�C���x�~�V�X�e���ɂ���^�g���b�N���������H���s�ł̂S�����x�̔R���
��̋@�\�E���ʂ������I�Ɋ��Ɋm�F�ς݂Ɛ��������B����ɂ�������炸�A���̌��2013�N9��25���ɊJ�Â���
�����쎩���ԇ����f�B�[�[���G���W���̔R����P�Ɋւ���Z�p�J����������ɂ����āA���� �^ �ꖱ������́A
���s�R����P�̋@�\�����u������R�āv�A�u�p�M����v�A�u�_�E���T�C�W���O�v�A�u�V�G�}�v�̂S��ނ̋Z�p��
�g�ݍ��킹���u2020�N���߂ǂɃf�B�[�[���G���W���P�̔R���10���̉��P�i���d�ʎԃ��[�h�R��܂��̓g���b
�N�E�o�X�̎����s�R���10���̉��P�j����������Ƃ̖��d�s�v�c�Ȕ��\�X�ƍs�����̂ł���B���̂Ȃ�
�A���������s�̔R����P�̋@�\�����S��ނ̋Z�p��g�ݍ��킹�����ł́A�g���b�N�E�o�X�̏d�ʎԃ��[�h�R��
�܂��͎����s�R��������I�ɂP�`�Q���̔R�����P���������Ȃ��Ɛ�������邽�߂��B�����āA2013�N9��25���ȑO
�����쎩���ԇ��������J���ɂ���Ċm�F�ς݂́u��^�g���b�N���������H���s�ł̂S�����x�̔R����オ�\�v��
���Ƃ������I�Ɋm�F���Ă��������C���x�~�V�X�e���̋Z�p�́A���� �^ �ꖱ����������S�ɖ����E�َE�����悤��
����B���̂悤�ɁA�������H���s�łS�����x�̔R����オ���҂ł���u�C���x�~�V�X�e���v�̋Z�p�����쎩���ԇ���
�����E�َE������Ȃ��������R�͕s���ł���B����ɂ��āA�M�҂�����C�܂܂��v�������̂́A�ȉ��̓�
�̗��R�ł���B
��̋@�\�E���ʂ������I�Ɋ��Ɋm�F�ς݂Ɛ��������B����ɂ�������炸�A���̌��2013�N9��25���ɊJ�Â���
�����쎩���ԇ����f�B�[�[���G���W���̔R����P�Ɋւ���Z�p�J����������ɂ����āA���� �^ �ꖱ������́A
���s�R����P�̋@�\�����u������R�āv�A�u�p�M����v�A�u�_�E���T�C�W���O�v�A�u�V�G�}�v�̂S��ނ̋Z�p��
�g�ݍ��킹���u2020�N���߂ǂɃf�B�[�[���G���W���P�̔R���10���̉��P�i���d�ʎԃ��[�h�R��܂��̓g���b
�N�E�o�X�̎����s�R���10���̉��P�j����������Ƃ̖��d�s�v�c�Ȕ��\�X�ƍs�����̂ł���B���̂Ȃ�
�A���������s�̔R����P�̋@�\�����S��ނ̋Z�p��g�ݍ��킹�����ł́A�g���b�N�E�o�X�̏d�ʎԃ��[�h�R��
�܂��͎����s�R��������I�ɂP�`�Q���̔R�����P���������Ȃ��Ɛ�������邽�߂��B�����āA2013�N9��25���ȑO
�����쎩���ԇ��������J���ɂ���Ċm�F�ς݂́u��^�g���b�N���������H���s�ł̂S�����x�̔R����オ�\�v��
���Ƃ������I�Ɋm�F���Ă��������C���x�~�V�X�e���̋Z�p�́A���� �^ �ꖱ����������S�ɖ����E�َE�����悤��
����B���̂悤�ɁA�������H���s�łS�����x�̔R����オ���҂ł���u�C���x�~�V�X�e���v�̋Z�p�����쎩���ԇ���
�����E�َE������Ȃ��������R�͕s���ł���B����ɂ��āA�M�҂�����C�܂܂��v�������̂́A�ȉ��̓�
�̗��R�ł���B
�� ���̐������R
�@���쎩���ԇ��������ԋZ�p���2013�N�H�G���Ɂu�ߋ��f�B�[�[���G���W���̋C���x�~�ɂ��Ă̈�l�@�v�Ƒ�
����_���̔��\���A���炩�̎�Ⴂ�Ō���Đ\������ł��܂����u���́v�̉\��������ƍl������B���̌��ʁA��
��܂ł̓��쎩���ԇ��̎Г��̋Z�p�J���̐��ʂł���u�C���x�~�V�X�e���̋Z�p��p�����ꍇ�ɂ́A��^�g���b�N
���������H���s�ł̂S�����x�̔R����オ�\�v�Ƃ̋ɔ�̋Z�p������ԋZ�p���2013�N�H�G���v���O
�����̘_�����^�i��2013�N8�����{���Ɍ��\�j�ɋL�ڂ���A���쎩���ԇ��ɂƂ��Ă͕s�{�ӂȂ�����L�����Ԉ�ʂ�
���\����Ă��܂����\��������B�Ƃ��낪�A���́u�f�B�[�[���G���W�����C���x�~�V�X�e���ɂ��R����P�v�ɂ�
�āA���ɁA�g���b�N���[�J�Ԃ̔铽����H�ɗނ����茈�߂����݂���A���̋���Ɉᔽ���邱�ƂɂȂ�B���ɁA��
�̂悤�Ȕ铽����H����������Ă����Ƃ���A�����ԋZ�p���2013�N�H�G���v���O�����̘_�����^��������
�̃g���b�N���[�J�̊W�҂���A�铽����H�Ɉᔽ���Ă���Ƃ̎w�E���A���쎩���ԇ����Q�Ăāu���\�_���̎�
�����v�ƁA�u�C���x�~�V�X�e���ɂ���S�����x�̔R�����v�̋Z�p����ے肷�邽�߂��� �^ �ꖱ�������2013�N
9��25�������쎩���ԇ����u�C���x�~�V�X�e���v���E�َE�����u10�����R�����P�̌����J���̕��j�v�̕��\
�̋L�҉���}篁A�J�Â����\��������Ɛ��������B
����_���̔��\���A���炩�̎�Ⴂ�Ō���Đ\������ł��܂����u���́v�̉\��������ƍl������B���̌��ʁA��
��܂ł̓��쎩���ԇ��̎Г��̋Z�p�J���̐��ʂł���u�C���x�~�V�X�e���̋Z�p��p�����ꍇ�ɂ́A��^�g���b�N
���������H���s�ł̂S�����x�̔R����オ�\�v�Ƃ̋ɔ�̋Z�p������ԋZ�p���2013�N�H�G���v���O
�����̘_�����^�i��2013�N8�����{���Ɍ��\�j�ɋL�ڂ���A���쎩���ԇ��ɂƂ��Ă͕s�{�ӂȂ�����L�����Ԉ�ʂ�
���\����Ă��܂����\��������B�Ƃ��낪�A���́u�f�B�[�[���G���W�����C���x�~�V�X�e���ɂ��R����P�v�ɂ�
�āA���ɁA�g���b�N���[�J�Ԃ̔铽����H�ɗނ����茈�߂����݂���A���̋���Ɉᔽ���邱�ƂɂȂ�B���ɁA��
�̂悤�Ȕ铽����H����������Ă����Ƃ���A�����ԋZ�p���2013�N�H�G���v���O�����̘_�����^��������
�̃g���b�N���[�J�̊W�҂���A�铽����H�Ɉᔽ���Ă���Ƃ̎w�E���A���쎩���ԇ����Q�Ăāu���\�_���̎�
�����v�ƁA�u�C���x�~�V�X�e���ɂ���S�����x�̔R�����v�̋Z�p����ے肷�邽�߂��� �^ �ꖱ�������2013�N
9��25�������쎩���ԇ����u�C���x�~�V�X�e���v���E�َE�����u10�����R�����P�̌����J���̕��j�v�̕��\
�̋L�҉���}篁A�J�Â����\��������Ɛ��������B
�� ���̐������R
�@�]��������쎩���ԇ����Г��Ŏ��{���Ă����z�E�r�C�ًx�~�����̋C���x�~�V�X�e���̌����J���̌��ʂ��u��
���f�B�[�[���G���W���̋C���x�~�ɂ��Ă̈�l�@�v�Ƒ肷�锭�\�_���ɂ܂Ƃ߁A2013�N���{�Ɏ����ԋZ�p��ɓ�
�e�����悤���B�Ƃ낪�A���̌�A���쎩���ԇ����Г��Ŏ��{���Ă����u�Q�^�[�{�����̋C���x�~�V�X�e���i���C���x�~
�G���W���i�������J2005-54771�j�j�v�̌����J���̎������ʂ��A�u�z�E�r�C�ًx�~�����̋C���x�~�V�X�e���v�����u��
�R��v�ƁuNO���팸�v�̗��ʂŊi�i�ɗD��Ă��邱�Ƃ����������\��������B���̏ꍇ�A���쎩���ԇ��́A�z�E�r
�C�ًx�~�����̋C���x�~�V�X�e���̌����J�����Z�p�I�ȉ��l�̖������Ɨ��������Ɛ��������B���̂悤�ȁA�Z�p
�I�ɖ����l�ȁu�z�E�r�C�ًx�~�����̋C���x�~�V�X�e���v�̘_�����\�́A���쎩���ԇ��̒p�ƂȂ邽�߁A�}篁A�u��
���f�B�[�[���G���W���̋C���x�~�ɂ��Ă̈�l�@�v�Ƒ肷��u�z�E�r�C�ًx�~�����̋C���x�~�V�X�e���v�̘_����
�\���u�扺���v�ɂ����\��������Ɛ��������B
���f�B�[�[���G���W���̋C���x�~�ɂ��Ă̈�l�@�v�Ƒ肷�锭�\�_���ɂ܂Ƃ߁A2013�N���{�Ɏ����ԋZ�p��ɓ�
�e�����悤���B�Ƃ낪�A���̌�A���쎩���ԇ����Г��Ŏ��{���Ă����u�Q�^�[�{�����̋C���x�~�V�X�e���i���C���x�~
�G���W���i�������J2005-54771�j�j�v�̌����J���̎������ʂ��A�u�z�E�r�C�ًx�~�����̋C���x�~�V�X�e���v�����u��
�R��v�ƁuNO���팸�v�̗��ʂŊi�i�ɗD��Ă��邱�Ƃ����������\��������B���̏ꍇ�A���쎩���ԇ��́A�z�E�r
�C�ًx�~�����̋C���x�~�V�X�e���̌����J�����Z�p�I�ȉ��l�̖������Ɨ��������Ɛ��������B���̂悤�ȁA�Z�p
�I�ɖ����l�ȁu�z�E�r�C�ًx�~�����̋C���x�~�V�X�e���v�̘_�����\�́A���쎩���ԇ��̒p�ƂȂ邽�߁A�}篁A�u��
���f�B�[�[���G���W���̋C���x�~�ɂ��Ă̈�l�@�v�Ƒ肷��u�z�E�r�C�ًx�~�����̋C���x�~�V�X�e���v�̘_����
�\���u�扺���v�ɂ����\��������Ɛ��������B
�@�����āA����܂ł̌����ɂ���ē��쎩���ԇ����J�������S�����x���R����P�̌��ʁE���\��������u�C���x�~
�V�X�e���v�̋Z�p�����̂��ˑR�ɕ����E�j�����A�u�C���x�~�V�X�e���v���E�َE�E���������u������R�āv�A�u�p�M��
���v�A�u�_�E���T�C�W���O�v�A�u�V�G�}�v�̂S��ނ����̋Z�p��g�ݍ��킹���u2020�N���߂ǂɃf�B�[�[���G���W���P��
�R���10���̉��P�i���d�ʎԃ��[�h�R��܂��̓g���b�N�E�o�X�̎����s�R���10���̉��P�j��}��v�Ɖ]���A�f�B�[�[
���G���W���W�̊w�ҁE���ƁE�Z�p�������Ƌ��������u�C���x�~���E�َE�����R����P�̊J�����j�v���A���쎩
���ԇ������� �^ �ꖱ����������������Ƃ������ł���B
�V�X�e���v�̋Z�p�����̂��ˑR�ɕ����E�j�����A�u�C���x�~�V�X�e���v���E�َE�E���������u������R�āv�A�u�p�M��
���v�A�u�_�E���T�C�W���O�v�A�u�V�G�}�v�̂S��ނ����̋Z�p��g�ݍ��킹���u2020�N���߂ǂɃf�B�[�[���G���W���P��
�R���10���̉��P�i���d�ʎԃ��[�h�R��܂��̓g���b�N�E�o�X�̎����s�R���10���̉��P�j��}��v�Ɖ]���A�f�B�[�[
���G���W���W�̊w�ҁE���ƁE�Z�p�������Ƌ��������u�C���x�~���E�َE�����R����P�̊J�����j�v���A���쎩
���ԇ������� �^ �ꖱ����������������Ƃ������ł���B
�@���͂Ƃ�����A���� �^ �ꖱ���������������J�Â����u�C���x�~�V�X�e���v���E�َE�����u��^�g���b�N��10��
���R�����P��}�����쎩���ԇ��������J���̕��j�v�\���A�C���x�~�V�X�e���̋Z�p��ˑR�ɕ��悤�Ƃ���
�s�ׂɂ��ẮA�P�Ȃ����쎩���ԇ��̎��쎩���ɂ�钃�Ԍ��ƌ��邱�Ƃ��\�ł���B����ɂ��ẮA�ŏ��́A
�|���R�c���G���W���Z�p���̕M�҂ł��A�v�킸���쎩���ԇ����C�ł��������̂��ƕs�v�c�Ɏv���Ă��܂����B����
���A���ꂪ���쎩���ԇ��ɂ�鎩�쎩���̒��Ԍ��ƌ���ƁA���ɔ[���ł��邱�Ƃł����B
���R�����P��}�����쎩���ԇ��������J���̕��j�v�\���A�C���x�~�V�X�e���̋Z�p��ˑR�ɕ��悤�Ƃ���
�s�ׂɂ��ẮA�P�Ȃ����쎩���ԇ��̎��쎩���ɂ�钃�Ԍ��ƌ��邱�Ƃ��\�ł���B����ɂ��ẮA�ŏ��́A
�|���R�c���G���W���Z�p���̕M�҂ł��A�v�킸���쎩���ԇ����C�ł��������̂��ƕs�v�c�Ɏv���Ă��܂����B����
���A���ꂪ���쎩���ԇ��ɂ�鎩�쎩���̒��Ԍ��ƌ���ƁA���ɔ[���ł��邱�Ƃł����B
�@�Ƃ���ŁA���� �^ �ꖱ������́A�f�B�[�[���G���W���̔R����P�̌����J���Ɋ֘A�����Ɩ��̌o�������Ȃ��l
���̂悤�ɐ��������B���̗��R�́A��L�̉��� �^ �ꖱ������̔��\�����ɂ����ẮA�_�E���T�C�W���O�̔R��
���P�̗v�f�Ƃ��ċ@�B�H�w�̕��ʂ��猩���u�r�C�����ጸ�v�A�u��p�����ጸ�v�A�u���C�����ጸ�v�A�u�|���s���O����
�ጸ�v�A�u�A�C�h�����O�ጸ�v���L�ڂ���Ă��邪�A�G���W���H�w�̕��ʂ��猩���̐S�v�́u�T�C�N�������̌���v����
���������L�ڂƂȂ��Ă��邽�߂ł���B
���̂悤�ɐ��������B���̗��R�́A��L�̉��� �^ �ꖱ������̔��\�����ɂ����ẮA�_�E���T�C�W���O�̔R��
���P�̗v�f�Ƃ��ċ@�B�H�w�̕��ʂ��猩���u�r�C�����ጸ�v�A�u��p�����ጸ�v�A�u���C�����ጸ�v�A�u�|���s���O����
�ጸ�v�A�u�A�C�h�����O�ጸ�v���L�ڂ���Ă��邪�A�G���W���H�w�̕��ʂ��猩���̐S�v�́u�T�C�N�������̌���v����
���������L�ڂƂȂ��Ă��邽�߂ł���B
�@���̂Ȃ�A�_�E���T�C�W���O�ɂ��f�B�[�[���G���W���̔R����P�̏d�v�ȗv���̈�́A�V�����_�̂o���� (=��
�����ϗL�����́j�����߂邱�Ƃɂ���ăG���W���̍����T�C�N�������������邽�߂ł���B���̂悤�ɁA�O�q�̕\�R
�W�Ɏ��������� �^ �ꖱ������̔��\�����ɂ����ẮA�_�E���T�C�W���O�̔R����P�̗v�f�Ƃ��ċ@�B�H�w�̕���
���猩���u�r�C�����ጸ�v�A�u��p�����ጸ�v�A�u���C�����ጸ�v�A�u�|���s���O�����ጸ�v�A�u�A�C�h�����O�ጸ�v���L��
����Ă��邪�A�G���W���H�w�̕��ʂ��猩���̐S�v�́u�T�C�N�������̌���v�������������L�ڂƂȂ��Ă���B���̂�
���ɁA�_�E���T�C�W���O�̔R����P�̗v�f�E�v���Ƃ��āA�u�T�C�N�������̌���v���L�ڂ���Ă��Ȃ����Ƃ��琄����
��ƁA���� �^ �ꖱ��������_�E���T�C�W���O�ɂ��R����P�̃G���W���T�C�N���̃��J�j�Y����S���������Ă��Ȃ�
�ƍl������B�����āA���̂悤�Ȏ�����ΊO�I�ɔ��\�������Ƃ́A���쎩���ԇ��Ƃ��ẮA�p�����������Ƃł͂Ȃ���
�Ǝv�����A�@���Ȃ��̂ł��낤���B���̂��Ƃ���A���� �^ �ꖱ������́A�ߋ��Ƀf�B�[�[���G���W���̔R����P�̌�
���J���Ɋ֘A�����Ɩ���S�����ꂽ�o�����������߁A�u���R�@�ցv��u�G���W���H�w�v�̋��ȏ��ɕK���L�ڂ���Ă�
��u�G���W���T�C�N���v�̍���^�ʖڂɓǂ܂ꂽ���Ƃ������l���̂悤�ɐ�������邪�A�@���Ȃ��̂ł��낤���B����
�āA�G�z�Ȃ���A�ЂƂ��ƌ��킹�ĖႦ�A���̂悤�ȍs�ׂ́A�����ȋZ�p�ҁE���ƂƂ��Ēp���������͖����̂ł���
�����B
�����ϗL�����́j�����߂邱�Ƃɂ���ăG���W���̍����T�C�N�������������邽�߂ł���B���̂悤�ɁA�O�q�̕\�R
�W�Ɏ��������� �^ �ꖱ������̔��\�����ɂ����ẮA�_�E���T�C�W���O�̔R����P�̗v�f�Ƃ��ċ@�B�H�w�̕���
���猩���u�r�C�����ጸ�v�A�u��p�����ጸ�v�A�u���C�����ጸ�v�A�u�|���s���O�����ጸ�v�A�u�A�C�h�����O�ጸ�v���L��
����Ă��邪�A�G���W���H�w�̕��ʂ��猩���̐S�v�́u�T�C�N�������̌���v�������������L�ڂƂȂ��Ă���B���̂�
���ɁA�_�E���T�C�W���O�̔R����P�̗v�f�E�v���Ƃ��āA�u�T�C�N�������̌���v���L�ڂ���Ă��Ȃ����Ƃ��琄����
��ƁA���� �^ �ꖱ��������_�E���T�C�W���O�ɂ��R����P�̃G���W���T�C�N���̃��J�j�Y����S���������Ă��Ȃ�
�ƍl������B�����āA���̂悤�Ȏ�����ΊO�I�ɔ��\�������Ƃ́A���쎩���ԇ��Ƃ��ẮA�p�����������Ƃł͂Ȃ���
�Ǝv�����A�@���Ȃ��̂ł��낤���B���̂��Ƃ���A���� �^ �ꖱ������́A�ߋ��Ƀf�B�[�[���G���W���̔R����P�̌�
���J���Ɋ֘A�����Ɩ���S�����ꂽ�o�����������߁A�u���R�@�ցv��u�G���W���H�w�v�̋��ȏ��ɕK���L�ڂ���Ă�
��u�G���W���T�C�N���v�̍���^�ʖڂɓǂ܂ꂽ���Ƃ������l���̂悤�ɐ�������邪�A�@���Ȃ��̂ł��낤���B����
�āA�G�z�Ȃ���A�ЂƂ��ƌ��킹�ĖႦ�A���̂悤�ȍs�ׂ́A�����ȋZ�p�ҁE���ƂƂ��Ēp���������͖����̂ł���
�����B
�@���������āA�u�C���x�~�V�X�e���v���u�_�E���T�C�W���O�v�̊e�X�̋Z�p�ɂ��āA�f�B�[�[���G���W���̔R����P��
�v���ɂ��Đ���������A�u���C�����ጸ�v�������āA�ȉ��̂悤�ɗ��҂��قړ��ނ̗v���ɂ���ăG���W���R���
���P���Ă��邱�Ƃ�����B
�v���ɂ��Đ���������A�u���C�����ጸ�v�������āA�ȉ��̂悤�ɗ��҂��قړ��ނ̗v���ɂ���ăG���W���R���
���P���Ă��邱�Ƃ�����B
�� �u�_�E���T�C�W���O�v�ɂ�����G���W���R����P�̗v��
�@�@�r�C�����ጸ�A��p�����ጸ�A���C�����ጸ�A�|���s���O�����ጸ�A�A�C�h�����O�R��ጸ�A�T�C�N��������
��
��
�� �u�C���x�~�V�X�e���v�ɂ�����G���W���R����P�̗v��
�@�@�r�C�����ጸ�A��p�����ጸ�A�|���s���O�����ጸ�A�A�C�h�����O�R��ጸ�A�T�C�N����������
�@�܂��A�u�C���x�~�V�X�e���v���u�_�E���T�C�W���O�v�́A�f�B�[�[���G���W���̔R����P�ɗL���ȓ��ނ̋Z�p�ł����
���ɁA�u�_�E���T�C�W���O�v�̃f�B�[�[���G���W���Ɂu�C���x�~�V�X�e���v�̋Z�p��g�ݍ��ꍇ�ɂ́A�u�_�E���T�C
�W���O�v�̔R����P�̌��ʂɁu�C���x�~�V�X�e���v�̔R����P�̌��ʂ���悹�ł��邱�ƂɂȂ�A�u�C���x�~�V�X�e
���v���u�_�E���T�C�W���O�v�͐��ɑ����ɂ̗ǂ��Z�p�ł���B�����āA�f�B�[�[���G���W���̔R����P���u�C���x�~
�V�X�e���v�̋Z�p���̗p����Ȃ�A�u�C���x�~�V�X�e���v�Ƃ��āA���쎩���ԇ������Ɍ����J�������{������
���肳���u�z�E�r�C�ًx�~�����Ɛ��肳���C���x�~�V�X�e���v�����i�i�ɑ�^�g���b�N�̔R����P�i���d
�ʎԃ��[�h�R��܂��͎����s�R��j�ɋɂ߂ėL�����Q�^�[�{�����̋C���x�~�V�X�e���i���C���x�~�G���W��
�i�������J2005-54771�j�j�̌����J�������{���ׂ��ƍl������B
���ɁA�u�_�E���T�C�W���O�v�̃f�B�[�[���G���W���Ɂu�C���x�~�V�X�e���v�̋Z�p��g�ݍ��ꍇ�ɂ́A�u�_�E���T�C
�W���O�v�̔R����P�̌��ʂɁu�C���x�~�V�X�e���v�̔R����P�̌��ʂ���悹�ł��邱�ƂɂȂ�A�u�C���x�~�V�X�e
���v���u�_�E���T�C�W���O�v�͐��ɑ����ɂ̗ǂ��Z�p�ł���B�����āA�f�B�[�[���G���W���̔R����P���u�C���x�~
�V�X�e���v�̋Z�p���̗p����Ȃ�A�u�C���x�~�V�X�e���v�Ƃ��āA���쎩���ԇ������Ɍ����J�������{������
���肳���u�z�E�r�C�ًx�~�����Ɛ��肳���C���x�~�V�X�e���v�����i�i�ɑ�^�g���b�N�̔R����P�i���d
�ʎԃ��[�h�R��܂��͎����s�R��j�ɋɂ߂ėL�����Q�^�[�{�����̋C���x�~�V�X�e���i���C���x�~�G���W��
�i�������J2005-54771�j�j�̌����J�������{���ׂ��ƍl������B
�@���̂Ȃ�A�u�_�E���T�C�W���O�v�̃G���W���ɂQ�^�[�{�����̋C���x�~�V�X�e���i���C���x�~�G���W���i�������J
2005-54771�j�j��g�ݍ��킹���ꍇ�ɂ́A�u�_�E���T�C�W���O�v�̃G���W���̃G���W���̂P�^�Q���ȉ��̋C���x�~�^
�]�ł́A�u�_�E���T�C�W���O�v�̃G���W�����X�ɂP�^�Q�̑��r�C�ʂɌ����������G���W�����^�]�ł��邽�߁A�u�_�E���T
�C�W���O�v�̃G���W���̂P�^�Q���ȉ��̉^�]�ł͍X�Ȃ�R����P���\�ƂȂ�̂ł���B���̂悤�ɁA�Q�^�[�{����
�̋C���x�~�V�X�e���i���C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�j�́A�x�[�X�ƂȂ�G���W�����u�_�E���T�C�W���O�v
�ł��邩�ۂ��ɂ�����炸�A�S�ẴG���W���̂P�^�Q���ȉ��̉^�]�̈�ɂ����āA�啝�ȔR����P���\�ƂȂ�
�V�Z�p�ł���B�������A���� �^ �ꖱ������́A2013�N9��25���̐�����ɂ����āA�f�B�[�[���G���W���̔R����P
�̋Z�p�Ƃ��ėL�����u�C���x�~�V�X�e���v���E�َE���Ă��邱�Ƃ���A�u�_�E���T�C�W���O�v�̔R����P�̌��ʂ�
�u�C���x�~�V�X�e���v�̔R����P�̌��ʂ���悹�ł��邱�Ƃ𗝉����Ă��Ȃ��悤�ɂ��v����̂ł���B���̂��Ƃ���
���A���� �^ �ꖱ������́A�ߋ��Ƀf�B�[�[���G���W���̔R����P�̌����J���Ɋ֘A�����Ɩ��̌o�������Ȃ��l��
�̂悤�ɐ�������邪�A�@���Ȃ��̂ł��낤���B���̂��Ƃ��l������A���쎩���Ԃ��_�����\�����R����P�@�\��
���C���x�~�V�X�e���ɏڏq���Ă���悤���^�[�{�ߋ��@�̃T�[�W���O�����̍\���I�Ȍ��ׂ̂��߂ɑ�^�g���b�N
�̑��s�R����\���ɉ��P���邱�Ƃ�����ȁu�z�E�r�C�ْ�~���̋C���x�~�V�X�e���v�̌����J�����A���쎩���Ԃ�
���{���A�����Ę_�����\���s�������Ƃ����ƂȂ������邱�Ƃł���B
2005-54771�j�j��g�ݍ��킹���ꍇ�ɂ́A�u�_�E���T�C�W���O�v�̃G���W���̃G���W���̂P�^�Q���ȉ��̋C���x�~�^
�]�ł́A�u�_�E���T�C�W���O�v�̃G���W�����X�ɂP�^�Q�̑��r�C�ʂɌ����������G���W�����^�]�ł��邽�߁A�u�_�E���T
�C�W���O�v�̃G���W���̂P�^�Q���ȉ��̉^�]�ł͍X�Ȃ�R����P���\�ƂȂ�̂ł���B���̂悤�ɁA�Q�^�[�{����
�̋C���x�~�V�X�e���i���C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�j�́A�x�[�X�ƂȂ�G���W�����u�_�E���T�C�W���O�v
�ł��邩�ۂ��ɂ�����炸�A�S�ẴG���W���̂P�^�Q���ȉ��̉^�]�̈�ɂ����āA�啝�ȔR����P���\�ƂȂ�
�V�Z�p�ł���B�������A���� �^ �ꖱ������́A2013�N9��25���̐�����ɂ����āA�f�B�[�[���G���W���̔R����P
�̋Z�p�Ƃ��ėL�����u�C���x�~�V�X�e���v���E�َE���Ă��邱�Ƃ���A�u�_�E���T�C�W���O�v�̔R����P�̌��ʂ�
�u�C���x�~�V�X�e���v�̔R����P�̌��ʂ���悹�ł��邱�Ƃ𗝉����Ă��Ȃ��悤�ɂ��v����̂ł���B���̂��Ƃ���
���A���� �^ �ꖱ������́A�ߋ��Ƀf�B�[�[���G���W���̔R����P�̌����J���Ɋ֘A�����Ɩ��̌o�������Ȃ��l��
�̂悤�ɐ�������邪�A�@���Ȃ��̂ł��낤���B���̂��Ƃ��l������A���쎩���Ԃ��_�����\�����R����P�@�\��
���C���x�~�V�X�e���ɏڏq���Ă���悤���^�[�{�ߋ��@�̃T�[�W���O�����̍\���I�Ȍ��ׂ̂��߂ɑ�^�g���b�N
�̑��s�R����\���ɉ��P���邱�Ƃ�����ȁu�z�E�r�C�ْ�~���̋C���x�~�V�X�e���v�̌����J�����A���쎩���Ԃ�
���{���A�����Ę_�����\���s�������Ƃ����ƂȂ������邱�Ƃł���B
�@�Ƃ���ŁA�]���Ɠ��l�����쎩���ԇ����z�E�r�C�ًx�~�����̋C���x�~�V�X�e�������ɏW�����Č����J�������{
���Ă���ꍇ�ɂ́A������R����P���s�\���ȃg���b�N�E�o�X�����J���ł��Ȃ��Ɛ��������B�����āA�C���x�~�G��
�W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p�J����^���Ɏ��{����g���b�N���[�J�́A�z�E�r�C�ًx�~�����̋C���x�~�V�X�e
���ɔ�r���ăf�B�[�[���G���W���̒�R��ƒ�NO�����̋@�\�E���ʂ��������߁A�߂������A���쎩���ԇ��̃g���b
�N�E�o�X�̏��i�͂��ȒP�ɗ��킷��g���b�N�E�o�X���s�̂��邱�Ƃ��\�ɂȂ�ƍl������B�������A�]���Ɠ��l�ɁA
��������������A�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋C���x�~�̋Z�p�ɖ��S�ȃg���b�N���[�J�����݂���
�Ƃ���A���̃g���b�N���[�J�̃G���W���W�̐��ƁE�Z�p�҂͑����������āu�n���v����ƍl���đ傫�ȊԈႢ��
�������낤�B�ܘ_�A�C���x�~�ɂ���đ�^�g���b�N�̔R����P��}�邽�߂̌����J���ɂ������A�Q�^�[�{�����̋C��
�x�~�V�X�e���ł����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p���E�َE���A�������z�E�r�C�ًx�~�@�\��
�K�v�ȏ���R����P�̋@�\������z�E�r�C�ًx�~�����̋C���x�~�V�X�e���ɑ��͂��W�����ċZ�p�J�����s���g���b
�N���[�J���u�n���v�ȃG���W���W�̐��ƁE�Z�p�҂����𗘂�����Ђƍl���ĊԈႢ�Ȃ��ƍl������B
���Ă���ꍇ�ɂ́A������R����P���s�\���ȃg���b�N�E�o�X�����J���ł��Ȃ��Ɛ��������B�����āA�C���x�~�G��
�W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p�J����^���Ɏ��{����g���b�N���[�J�́A�z�E�r�C�ًx�~�����̋C���x�~�V�X�e
���ɔ�r���ăf�B�[�[���G���W���̒�R��ƒ�NO�����̋@�\�E���ʂ��������߁A�߂������A���쎩���ԇ��̃g���b
�N�E�o�X�̏��i�͂��ȒP�ɗ��킷��g���b�N�E�o�X���s�̂��邱�Ƃ��\�ɂȂ�ƍl������B�������A�]���Ɠ��l�ɁA
��������������A�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋C���x�~�̋Z�p�ɖ��S�ȃg���b�N���[�J�����݂���
�Ƃ���A���̃g���b�N���[�J�̃G���W���W�̐��ƁE�Z�p�҂͑����������āu�n���v����ƍl���đ傫�ȊԈႢ��
�������낤�B�ܘ_�A�C���x�~�ɂ���đ�^�g���b�N�̔R����P��}�邽�߂̌����J���ɂ������A�Q�^�[�{�����̋C��
�x�~�V�X�e���ł����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p���E�َE���A�������z�E�r�C�ًx�~�@�\��
�K�v�ȏ���R����P�̋@�\������z�E�r�C�ًx�~�����̋C���x�~�V�X�e���ɑ��͂��W�����ċZ�p�J�����s���g���b
�N���[�J���u�n���v�ȃG���W���W�̐��ƁE�Z�p�҂����𗘂�����Ђƍl���ĊԈႢ�Ȃ��ƍl������B
�@
�@���Ă��āA�O�q�̒ʂ�A���̕M�Ғ�Ă��C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p�́A�Q��̃^�[�{��
���@�����ɑ�������Q�^�[�{�����̋C���x�~�V�X�e���ł���B�����āA���̂Q�^�[�{�����̋C���x�~�V�X�e����
�́A�Q�������C���Q�̊e�C���Q�̉^�]���ׂ�Ɨ����Đ��䂷�邱�Ƃɂ��A��^�g���b�N�̎����s�R���啝�ɉ��P
���邱�Ƃ��\�ł���B�����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p�ɂ���������s�R���啝�ɉ�
�P���鐧��Ƃ́A�ȉ����\�R�W�Ɏ������u�R��ጸ�^�̋C���Q����@�v�ł���B
���@�����ɑ�������Q�^�[�{�����̋C���x�~�V�X�e���ł���B�����āA���̂Q�^�[�{�����̋C���x�~�V�X�e����
�́A�Q�������C���Q�̊e�C���Q�̉^�]���ׂ�Ɨ����Đ��䂷�邱�Ƃɂ��A��^�g���b�N�̎����s�R���啝�ɉ��P
���邱�Ƃ��\�ł���B�����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p�ɂ���������s�R���啝�ɉ�
�P���鐧��Ƃ́A�ȉ����\�R�W�Ɏ������u�R��ጸ�^�̋C���Q����@�v�ł���B
| |
�� �ߋ��f�B�[�[���G���W���� �O�`�Q�^�S���ׂ̒ᕉ�ח̈�̉^�]����
�Е��̋C���Q�̊e�C���ł͂O�`�S�^�S���ׂ̉ғ��C���Ƃ��ĉ^�]���A�����̋C���Q�̊e�C���ł͋x�~�C���Ƃ�
�ĉ^�]����B
�� �ߋ��f�B�[�[���G���W���̂Q�^�S�`�S�^�S���ׂ̍����ח̈�̉^�]����
�Е��̋C���Q�̊e�C���ł͑S���ׁi���S�^�S���ׁj�̈�蕉�ׂ̉ғ��C���Ƃ��ĉ^�]���A�����̋C���Q�̊e�C
���ł͂O�`�S�^�S�̕K�v�ȕ��ׂɒ��߂���ғ��C���Ƃ��ĉ^�]����B
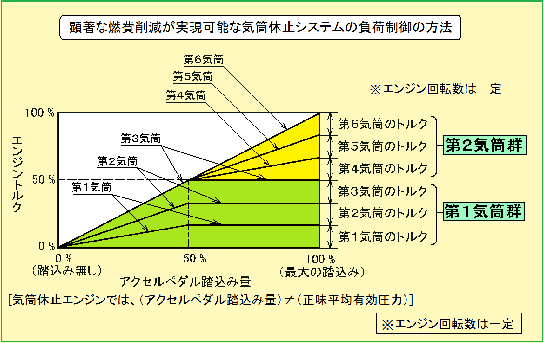 |
�@�Ȃ��A�ȏ�́u�R��ጸ�^�̋C���Q����@�v�̐���̏ڍׂ́A�C���x�~�́A�f�B�[�[���̂m�n���팸�ƔR������
�ꋓ�����̋Z�p���I�̃y�[�W�̐}�V�ɏڂ����L�ڂ��Ă���̂ŁA�����̂�����͂����������������B
�ꋓ�����̋Z�p���I�̃y�[�W�̐}�V�ɏڂ����L�ڂ��Ă���̂ŁA�����̂�����͂����������������B
�@���́u�R��ጸ�^�̋C���Q����@�v�́A�Q�^�[�{�����̋C���x�~�V�X�e���i���C���x�~�G���W���i�������J2005-
54771�j�j�������\�ȋC���Q�̏o�͐�����@�ł���A�z�E�r�C�ًx�~�����̋C���x�~�V�X�e���i�����쎩���ԇ���
�����ԋZ�p���2013�N�H�G���Ř_�����\���u�扺���v�����C���x�~�V�X�e���j�ł͐��䂪�s�\�ȋC���Q�̏o
�͐�����@�ł���B���������āA�Q�^�[�{�����̋C���x�~�V�X�e���i���C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�j
�́A�z�E�r�C�ًx�~�����̋C���x�~�V�X�e���ɔ�r���đ�^�g���b�N�̏d�ʎԃ��[�h�R�������s�R��̑啝�ȉ�
�P���\�ƂȂ�B���̂��߁A�Q�^�[�{�����̋C���x�~�V�X�e���ł����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓�
���Z�p���̗p�����ߋ��f�B�[�[���G���W������^�g���b�N�ɍ̗p�����ꍇ�ɂ́A�s�s�Ԃ̉ݕ��A���ɂ����ċC���x
�~�ɂ��R����P�̌��ʂ��\���ɔ����ł��邱�ƂɂȂ�B
54771�j�j�������\�ȋC���Q�̏o�͐�����@�ł���A�z�E�r�C�ًx�~�����̋C���x�~�V�X�e���i�����쎩���ԇ���
�����ԋZ�p���2013�N�H�G���Ř_�����\���u�扺���v�����C���x�~�V�X�e���j�ł͐��䂪�s�\�ȋC���Q�̏o
�͐�����@�ł���B���������āA�Q�^�[�{�����̋C���x�~�V�X�e���i���C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�j
�́A�z�E�r�C�ًx�~�����̋C���x�~�V�X�e���ɔ�r���đ�^�g���b�N�̏d�ʎԃ��[�h�R�������s�R��̑啝�ȉ�
�P���\�ƂȂ�B���̂��߁A�Q�^�[�{�����̋C���x�~�V�X�e���ł����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓�
���Z�p���̗p�����ߋ��f�B�[�[���G���W������^�g���b�N�ɍ̗p�����ꍇ�ɂ́A�s�s�Ԃ̉ݕ��A���ɂ����ċC���x
�~�ɂ��R����P�̌��ʂ��\���ɔ����ł��邱�ƂɂȂ�B
�P�X�@��^�g���b�N�̔R����P�ɗL���ȋC���x�~�̋Z�p��َE����s�ׁE�ΊO���\�̂܂Ƃ�
�@���{�̃f�B�[�[���G���W���W�̊w�ҁE���ƁE�Z�p�҂̑����̐l�B�́A��^�g���b�N���d�ʎԃ��[�h�R������
�s�R���啝�ɉ��P�ł���C���x�~�V�X�e�����ɓx�̊������A���̋Z�p�̎��p�������Ƃ��Ă����������Ɗ����
����悤�Ɍ�����̂ł���B�����āA���̏�����ƁA���{�̃f�B�[�[���G���W���W�̊w�ҁE���ƁE�Z�p�҂̖w
��ǂ̐l�B�́A�������R�c��E��C����������\���e�Ɏ^�����邱�Ƃ��u�ꗬ�̏v�Ƃ̊�ȐM�O�E�Œ��
�O�E����ςɑ����Ă��邽�߂ɁA�ӐM�I�ɋC���x�~�V�X�e���̋Z�p���E�َE����s�ׂ��s���Ă���悤�ł�
��B���ꂪ�����ł���A���Ɉ���Ȃ��Ƃł͂Ȃ����낤���B���̏��ȒP�ɔc���ł���悤�ɁA�ȏ�̊e���ɂ�
���ďڏq������^�g���b�N�����s�R���d�ʎԃ��[�h�R��̉��P�ɋɂ߂ėL�����C���x�~�̋Z�p���E�َE����
�s�ׁE�ΊO���\�ɂ��āA�ȉ��ɂ܂Ƃ߂��B
�s�R���啝�ɉ��P�ł���C���x�~�V�X�e�����ɓx�̊������A���̋Z�p�̎��p�������Ƃ��Ă����������Ɗ����
����悤�Ɍ�����̂ł���B�����āA���̏�����ƁA���{�̃f�B�[�[���G���W���W�̊w�ҁE���ƁE�Z�p�҂̖w
��ǂ̐l�B�́A�������R�c��E��C����������\���e�Ɏ^�����邱�Ƃ��u�ꗬ�̏v�Ƃ̊�ȐM�O�E�Œ��
�O�E����ςɑ����Ă��邽�߂ɁA�ӐM�I�ɋC���x�~�V�X�e���̋Z�p���E�َE����s�ׂ��s���Ă���悤�ł�
��B���ꂪ�����ł���A���Ɉ���Ȃ��Ƃł͂Ȃ����낤���B���̏��ȒP�ɔc���ł���悤�ɁA�ȏ�̊e���ɂ�
���ďڏq������^�g���b�N�����s�R���d�ʎԃ��[�h�R��̉��P�ɋɂ߂ėL�����C���x�~�̋Z�p���E�َE����
�s�ׁE�ΊO���\�ɂ��āA�ȉ��ɂ܂Ƃ߂��B
�P�X�|�P�@�f�B�[�[���ł̋C���x�~�̔R����P�̎������ʂ��V�G�B�V�[�C�[�̐� �F�O��
�@�O�q���P�Q�|�R���ɏڏq�����悤�ɁA���V�G�B�V�[�C�[�́A�����ԃ��[�J�[�ƕ��i��Ђ��o�����A�g���b�N���[�J�S��
(����A�����U�A�t�c�A�O�H�ӂ���)���猤���҂��h������Ă���f�B�[�[���G���W���̌������ł���B�M�҂����V�G�B
�V�[�C�[�����M�����d���[���ł́A���V�G�B�V�[�C�[���u�Q�O�O�S�N�Ɏ��{�����f�B�[�[���G���W���̋C���x�~�̎���
�ɂ����āA�R�����P�̌��ʂ��m�F���Ă����v �Ƃ̂��Ƃ��L�ڂ���Ă����B�M�҂̐����ł́A���V�G�B�V�[�C�[������
�����{�����C���x�~�V�X�e���́A�Q�^�[�{�����̋C���x�~�V�X�e���i���C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�j��
����R����P�̋@�\�E���ʂ̗��z�E�r�C�ًx�~�����Ɛ��肳���B�������A�O������В��@���@�F�O���́A����
�C���x�~�V�X�e���ɂ���ăf�B�[�[���G���W���̔R����P���Q�O�O�S�N�Ɋm�F���ꂽ�ɂ�������炸�A2013�N6���ɑ�
�C����܂ł̍ݔC���ɂ́A�C���x�~�ɂ��R����P�̎������ʂ\���Ă��Ȃ��悤���B
(����A�����U�A�t�c�A�O�H�ӂ���)���猤���҂��h������Ă���f�B�[�[���G���W���̌������ł���B�M�҂����V�G�B
�V�[�C�[�����M�����d���[���ł́A���V�G�B�V�[�C�[���u�Q�O�O�S�N�Ɏ��{�����f�B�[�[���G���W���̋C���x�~�̎���
�ɂ����āA�R�����P�̌��ʂ��m�F���Ă����v �Ƃ̂��Ƃ��L�ڂ���Ă����B�M�҂̐����ł́A���V�G�B�V�[�C�[������
�����{�����C���x�~�V�X�e���́A�Q�^�[�{�����̋C���x�~�V�X�e���i���C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�j��
����R����P�̋@�\�E���ʂ̗��z�E�r�C�ًx�~�����Ɛ��肳���B�������A�O������В��@���@�F�O���́A����
�C���x�~�V�X�e���ɂ���ăf�B�[�[���G���W���̔R����P���Q�O�O�S�N�Ɋm�F���ꂽ�ɂ�������炸�A2013�N6���ɑ�
�C����܂ł̍ݔC���ɂ́A�C���x�~�ɂ��R����P�̎������ʂ\���Ă��Ȃ��悤���B
�P�X�|�Q�@�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p�������E�َE���钆�����R�c��
�@�O�q�̂P�T���ɏڏq�����悤�ɁA2010�N�V��28�����\�̒������R�c��E��C������́u����̎����Ԕr�o�K
�X�ጸ��̂�����ɂ��āi��\�����\�j�v�ł́A�\�Q�U�Ɏ������悤�ɁA�u����A�ȉ��̂悤�ȋZ�p�̐i�W��������
���Ƃɂ��A�R��̐L�т�����m�����A�G���W���o���́iNO���́j�r�o�ʂ�1.5g/kWh���x�܂Œጸ���邱�Ƃ͉�
�\�ł���ƍl������B�v�ƋL�ڂ���Ă���B�����āA������\�����\�ł́A�u�R��̐L�т�����m�ہv���邽�߂��u��
���Z�p�v�Ƃ��āA�������R�c���C��������Ԕr�o�K�X���ψ���́A�ȉ��̋Z�p�������B�@
�X�ጸ��̂�����ɂ��āi��\�����\�j�v�ł́A�\�Q�U�Ɏ������悤�ɁA�u����A�ȉ��̂悤�ȋZ�p�̐i�W��������
���Ƃɂ��A�R��̐L�т�����m�����A�G���W���o���́iNO���́j�r�o�ʂ�1.5g/kWh���x�܂Œጸ���邱�Ƃ͉�
�\�ł���ƍl������B�v�ƋL�ڂ���Ă���B�����āA������\�����\�ł́A�u�R��̐L�т�����m�ہv���邽�߂��u��
���Z�p�v�Ƃ��āA�������R�c���C��������Ԕr�o�K�X���ψ���́A�ȉ��̋Z�p�������B�@
�@�@�E�@2�i�ߋ��A2�i�ߋ������ɂ��G���W���_�E���T�C�W���O
�@�@�E�@EGR���̌���AEGR����̍��x���A�ꕔ�Ԏ�ւ�LP-EGR�̗̍p
�@�@�E�@�R�����ˈ��͂̌���APCI�R�Ăł͈̔͊g�哙�̔R�����ː���̍��x��
�@�@�E�@�ꕔ�Ԏ�ւ̃^�[�{�R���p�E���h�V�X�e���̗̍p
�@���Ƃ����Ă��A��\�����\�Ɂu�R��̐L�т�����m�ہv���L�ڂ��ꂽ�Z�p�́A�������^�g���b�N�̏d�ʎԃ��[�h�R
�������s�R����P�������������P�ł��Ȃ��R����P�̋@�\�����Z�p�ł���A�R����P�̖ʂ��猩��u�K���N
�^�Z�p�v��u�|���R�c�Z�p�v�ɕ��ނ����Z�p�ł��邱�Ƃ́A�ԈႢ�����ƍl������B�����āA2006�N4���ɊJ�݂���
�M�҂̃z�[���y�[�W�ɋL�ڂ�����^�g���b�N�̏d�ʎԃ��[�h�R�������s�R����T�����x�̉��P���\���C���x�~
�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p�́A2010�N�V��28�����\�̉����R�c��E��C���������\����
�\�ł͊��S�ɖ����E�َE����Ă���̂ł���B�v����ɁA��\�����\�̌��Ă��쐬�����������R�c���C����
����Ԕr�o�K�X���ψ���̃����o�[�́A��^�g���b�N�����s�R���d�ʎԃ��[�h�R��̉��P�ɋɂ߂ėL�����C
���x�~�̋Z�p���E�َE�����̂ł���B
�������s�R����P�������������P�ł��Ȃ��R����P�̋@�\�����Z�p�ł���A�R����P�̖ʂ��猩��u�K���N
�^�Z�p�v��u�|���R�c�Z�p�v�ɕ��ނ����Z�p�ł��邱�Ƃ́A�ԈႢ�����ƍl������B�����āA2006�N4���ɊJ�݂���
�M�҂̃z�[���y�[�W�ɋL�ڂ�����^�g���b�N�̏d�ʎԃ��[�h�R�������s�R����T�����x�̉��P���\���C���x�~
�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p�́A2010�N�V��28�����\�̉����R�c��E��C���������\����
�\�ł͊��S�ɖ����E�َE����Ă���̂ł���B�v����ɁA��\�����\�̌��Ă��쐬�����������R�c���C����
����Ԕr�o�K�X���ψ���̃����o�[�́A��^�g���b�N�����s�R���d�ʎԃ��[�h�R��̉��P�ɋɂ߂ėL�����C
���x�~�̋Z�p���E�َE�����̂ł���B
�P�X�|�R�@�_���I�Ȗ���������ɂ��������ɋC���x�~�̋Z�p���E�َE����吹 ���勳���̍u�����\
�@�O�q�̂P�V���ɏڏq�����悤�ɁA����25�N5��31���ɊJ�Â��ꂽ�u�����Q�T�N�x��ʈ��S���������u����v�ɂ�
���āA����c��w�@�吹�����́u�f�B�[�[�������Ԃ̔r�o�K�X��Z�p�̍ŐV�����v�̍u�������̂̂Q�X�y�[�W��
�́u�����Ԃ̔R����P�Z�p�v���܂Ƃ߂��Ă���B���̒��ł́A�f�B�[�[������уK�\���������Ԃ̔R����P�����P
�O���ȏ�̋Z�p�Ƃ��āA���ϋC���@�\�i���C���x�~�j�����X�Ƌ������Ă���B�Ƃ��낪�A���̑吹�����́u�u����
���v�̂R�O�y�[�W�́u�f�B�[�[�����p�Ԃ̍��������v�̋Z�p�̒��ɂ́u�ϋC���@�\�i���C���x�~�j�v�̋Z�p���L�ڂ�
��Ă��炸�A���Ȗ����Ɋׂ������e�ƂȂ��Ă���B���̂悤�ɁA�吹�����́A�_���I���������̂Ƃ������ɁA�����I��
�f�B�[�[���g���b�N�̔R�����Z�p�Ƃ��Ắu�ϋC���@�\�i���C���x�~�j�v���E�َE�i���ے�j������e�̍u����
�s��ꂽ�悤�ł���B
���āA����c��w�@�吹�����́u�f�B�[�[�������Ԃ̔r�o�K�X��Z�p�̍ŐV�����v�̍u�������̂̂Q�X�y�[�W��
�́u�����Ԃ̔R����P�Z�p�v���܂Ƃ߂��Ă���B���̒��ł́A�f�B�[�[������уK�\���������Ԃ̔R����P�����P
�O���ȏ�̋Z�p�Ƃ��āA���ϋC���@�\�i���C���x�~�j�����X�Ƌ������Ă���B�Ƃ��낪�A���̑吹�����́u�u����
���v�̂R�O�y�[�W�́u�f�B�[�[�����p�Ԃ̍��������v�̋Z�p�̒��ɂ́u�ϋC���@�\�i���C���x�~�j�v�̋Z�p���L�ڂ�
��Ă��炸�A���Ȗ����Ɋׂ������e�ƂȂ��Ă���B���̂悤�ɁA�吹�����́A�_���I���������̂Ƃ������ɁA�����I��
�f�B�[�[���g���b�N�̔R�����Z�p�Ƃ��Ắu�ϋC���@�\�i���C���x�~�j�v���E�َE�i���ے�j������e�̍u����
�s��ꂽ�悤�ł���B
�P�X�|�S�@�C���x�~�̋Z�p���E�َE������쎩���ԇ��̉��� �^ �ꖱ������̋Z�p������
�@�O�q���P�W�|�Q���ɏڏq�����悤�ɁA�����ԋZ�p���2013�N�H�G���ɂ����锭�\�\������쎩���ԇ��̘_����
�^�Ɂu�C���x�~�̋Z�p���̗p������^�g���b�N���������H���s�ł͂S�����x�̔R����P�����҂ł���v�ƋL�ڂ����
���邱�Ƃ���A2013�N�t���ɂ́A���쎩���ԇ��͋C���x�~�̋Z�p�ɂ���^�g���b�N�̔R����P�̋@�\�E���ʂ��m
�F�ς݂Ɛ��������B�������A���쎩���ԇ��̉��� �^ �ꖱ������́A2013�N9��25���ɊJ�Â̋Z�p������ɂ���
�āA���Ђ̌����J���ɂ���đ�^�g���b�N�̑��s�R����S�������P�ł��邱�Ƃ��m�F�����z�E�r�C�ًx�~�����Ɛ�����
���C���x�~�̋Z�p���̂ċ���A���ĔR����P�̋@�\�̗���u������R�āv�A�u�p�M����v�A�u�_�E���T�C�W���O�v�A
�u�V�G�}�v�̂S��ނ̋Z�p��g�ݍ��킹�āu2020�N�����g���b�N�E�o�X�ł�10�����R����P�������v����Ƃ̔��\���s
�����B������A�����S��ނ̊e�X�̋Z�p�́A���s�R���d�ʎԃ��[�h�R��O�`�P�����x�̉��P���������߂Ȃ���
���ȔR����P�̋@�\�E���ʂ����������Z�p�ł���B���̂悤���A�S���̑��s�R��̉��P���m�F�ς݂̋C���x�~��
�Z�p�������̂ċ���A���s�R���d�ʎԃ��[�h�R��O�`�P�����x�̉��P���������߂Ȃ��́u������R�āv�A�u�p�M
����v�A�u�_�E���T�C�W���O�v�A�u�V�G�}�v�̂S��ނ��R����P�@�\�����Z�p���������đI�������J�������{���A
�u2020�N�����g���b�N�E�o�X�ł�10�����R����P�������v�Ƃ̃g���b�N�E�o�X�̒���R���}��Ƒ�_�Ȕ��\��������
�����ԇ��̉��� �^ �ꖱ������̈Ӑ}�́A��́A���Ȃ̂ł��낤���B���������āA���쎩���ԇ��̉��� �^ �ꖱ��
�����́A��^�g���b�N�̑��s�R����S�������P�ł����z�E�r�C�ًx�~�����̋C���x�~�̋Z�p���u��������v�ɂ�������
���Ɍ��������邽�߂ɁA�킴�킴���ŋ���������ꂽ�̂ł��낤���B
�^�Ɂu�C���x�~�̋Z�p���̗p������^�g���b�N���������H���s�ł͂S�����x�̔R����P�����҂ł���v�ƋL�ڂ����
���邱�Ƃ���A2013�N�t���ɂ́A���쎩���ԇ��͋C���x�~�̋Z�p�ɂ���^�g���b�N�̔R����P�̋@�\�E���ʂ��m
�F�ς݂Ɛ��������B�������A���쎩���ԇ��̉��� �^ �ꖱ������́A2013�N9��25���ɊJ�Â̋Z�p������ɂ���
�āA���Ђ̌����J���ɂ���đ�^�g���b�N�̑��s�R����S�������P�ł��邱�Ƃ��m�F�����z�E�r�C�ًx�~�����Ɛ�����
���C���x�~�̋Z�p���̂ċ���A���ĔR����P�̋@�\�̗���u������R�āv�A�u�p�M����v�A�u�_�E���T�C�W���O�v�A
�u�V�G�}�v�̂S��ނ̋Z�p��g�ݍ��킹�āu2020�N�����g���b�N�E�o�X�ł�10�����R����P�������v����Ƃ̔��\���s
�����B������A�����S��ނ̊e�X�̋Z�p�́A���s�R���d�ʎԃ��[�h�R��O�`�P�����x�̉��P���������߂Ȃ���
���ȔR����P�̋@�\�E���ʂ����������Z�p�ł���B���̂悤���A�S���̑��s�R��̉��P���m�F�ς݂̋C���x�~��
�Z�p�������̂ċ���A���s�R���d�ʎԃ��[�h�R��O�`�P�����x�̉��P���������߂Ȃ��́u������R�āv�A�u�p�M
����v�A�u�_�E���T�C�W���O�v�A�u�V�G�}�v�̂S��ނ��R����P�@�\�����Z�p���������đI�������J�������{���A
�u2020�N�����g���b�N�E�o�X�ł�10�����R����P�������v�Ƃ̃g���b�N�E�o�X�̒���R���}��Ƒ�_�Ȕ��\��������
�����ԇ��̉��� �^ �ꖱ������̈Ӑ}�́A��́A���Ȃ̂ł��낤���B���������āA���쎩���ԇ��̉��� �^ �ꖱ��
�����́A��^�g���b�N�̑��s�R����S�������P�ł����z�E�r�C�ًx�~�����̋C���x�~�̋Z�p���u��������v�ɂ�������
���Ɍ��������邽�߂ɁA�킴�킴���ŋ���������ꂽ�̂ł��낤���B
�@�ȏ��19-1���ɋL�ڂ����悤�ɁA�u���V�G�B�V�[�C�[�̑O������В��@���@�F�O���v�́A�Q�O�O�S�N�Ɏ��{����
�f�B�[�[���G���W���̔R�����P�̌��ʂ��m�F�����C���x�~�̎������ʂ�2013�N�ɑޔC���鎞�_�܂ŁA����
�\�̏��u���s�����悤�ł���B�����āA�ȏ��19-2�`3���ɋL�ڂ����悤�ɁA�u�������R�c��E��C������E
�����Ԕr�o�K�X���ψ���v�A�u����c��w�@�吹�����v�A����сu���쎩���ԇ��̉��� �^ �ꖱ������v
�́A����̃f�B�[�[���G���W���̔R����P�̂��߂Ɍ����J�����ׂ��Ƃ��Đ��������Z�p���ڂ���A�g���b�N�E
�o�X�����s�R���d�ʎԃ��[�h�R��̉��P�ɋɂ߂ėL�����C���x�~�V�X�e���̋Z�p�����S�ɖ����E�َE�E
���O��������悤�ł���B���̂��Ƃ�����A�f�B�[�[���G���W���́u�C���x�~�V�X�e���v�́A���{�̃f�B�[�[���G���W��
�W�̊w�ҁE���ƁE�Z�p�҂�������̂��������Ă��邱�Ƃ����́A��R���������̂悤���B
�f�B�[�[���G���W���̔R�����P�̌��ʂ��m�F�����C���x�~�̎������ʂ�2013�N�ɑޔC���鎞�_�܂ŁA����
�\�̏��u���s�����悤�ł���B�����āA�ȏ��19-2�`3���ɋL�ڂ����悤�ɁA�u�������R�c��E��C������E
�����Ԕr�o�K�X���ψ���v�A�u����c��w�@�吹�����v�A����сu���쎩���ԇ��̉��� �^ �ꖱ������v
�́A����̃f�B�[�[���G���W���̔R����P�̂��߂Ɍ����J�����ׂ��Ƃ��Đ��������Z�p���ڂ���A�g���b�N�E
�o�X�����s�R���d�ʎԃ��[�h�R��̉��P�ɋɂ߂ėL�����C���x�~�V�X�e���̋Z�p�����S�ɖ����E�َE�E
���O��������悤�ł���B���̂��Ƃ�����A�f�B�[�[���G���W���́u�C���x�~�V�X�e���v�́A���{�̃f�B�[�[���G���W��
�W�̊w�ҁE���ƁE�Z�p�҂�������̂��������Ă��邱�Ƃ����́A��R���������̂悤���B
�P�X�|�T�@�g���b�N�E�o�X�����s�R���d�ʎԃ��[�h�R��̉��P��摗�肵�A�x�������锽�Љ�I�ȍs��
�@���̂悤�ɁA�u���V�G�B�V�[�C�[�̑O������В��@���@�F�O���v�͋C���x�~�ɂ��R����P�̎������ʂ𖢔��\
�Ƃ��ĎЊO��Ƃ��A�u�������R�c��E��C������E�����Ԕr�o�K�X���ψ���v�A�u����c��w�@�吹�����v�A��
��сu���쎩���ԇ��̉��� �^ �ꖱ������v�̓��{���\����w�ҁE���ƁE�Z�p�҂ł��鏔���́A�ȉ��̕\�R�X��
�������g���b�N�E�o�X�����s�R���d�ʎԃ��[�h�R����O�`�P���������P�ł��Ȃ����̕������癗�ނ����Z�p���
���A����̃f�B�[�[���G���W���̔R����P�̂��߂Ɍ����J�����ׂ��Ƃ��Đ������Ă���B�����āA�ނ�́A�P��̋Z
�p�ɂ���ăg���b�N�E�o�X�����s�R���d�ʎԃ��[�h�R����T�����x�����P�����҂ł��錤���J�����A����E
�ł��Ă��Ȃ��̂ł���B���������āA���{���\����w�ҁE���Ƃ̏������E����Z�p�̌����J����
�i���Ă��A�߂������A���ۂɃf�B�[�[���g���b�N�E�o�X�����s�R���d�ʎԃ��[�h�R����T�����x�����P�������ł���
�\���́A�F���Ɨ\�������B�v����ɁA���̕�������́u���ށv��u�R�s�[�E�y�[�X�g�v�����̓��ӂȓ��{�̊w�ҁE��
��Ƃ���������Z�p�̌����J���́A�u���܂葹�̂����т�ׂ��v�Ɖ]����̂ł͂Ȃ����낤���B
�Ƃ��ĎЊO��Ƃ��A�u�������R�c��E��C������E�����Ԕr�o�K�X���ψ���v�A�u����c��w�@�吹�����v�A��
��сu���쎩���ԇ��̉��� �^ �ꖱ������v�̓��{���\����w�ҁE���ƁE�Z�p�҂ł��鏔���́A�ȉ��̕\�R�X��
�������g���b�N�E�o�X�����s�R���d�ʎԃ��[�h�R����O�`�P���������P�ł��Ȃ����̕������癗�ނ����Z�p���
���A����̃f�B�[�[���G���W���̔R����P�̂��߂Ɍ����J�����ׂ��Ƃ��Đ������Ă���B�����āA�ނ�́A�P��̋Z
�p�ɂ���ăg���b�N�E�o�X�����s�R���d�ʎԃ��[�h�R����T�����x�����P�����҂ł��錤���J�����A����E
�ł��Ă��Ȃ��̂ł���B���������āA���{���\����w�ҁE���Ƃ̏������E����Z�p�̌����J����
�i���Ă��A�߂������A���ۂɃf�B�[�[���g���b�N�E�o�X�����s�R���d�ʎԃ��[�h�R����T�����x�����P�������ł���
�\���́A�F���Ɨ\�������B�v����ɁA���̕�������́u���ށv��u�R�s�[�E�y�[�X�g�v�����̓��ӂȓ��{�̊w�ҁE��
��Ƃ���������Z�p�̌����J���́A�u���܂葹�̂����т�ׂ��v�Ɖ]����̂ł͂Ȃ����낤���B
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
�@�Ƃ��낪�A���{�̃f�B�[�[���G���W������Ƃ���w�ҁE���ƁE�Z�p�҂́A��L�̕\�R�X�Ɏ�������^�g���b�N�p�f
�B�[�[���G���W�������s�R���d�ʎԃ��[�h�R��O�`�P���������P�ł��Ȃ��u�|���R�c�Z�p�v��u�K���N�^�Z�p�v����
�i�Z�p�Ɛ������A�߂�������2015�N�x�d�ʎԔR���̋����ɔ����邽�߂ɁA������u�|���R�c�Z�p�v��u�K���N�^
�Z�p�v�̌����J�����s�ӁA���i���Ƃ̖��ӔC�ȍu���E�L�����A�Â����̂̂悤�ɖO�����������X�Ɣ��\�������Ă���
�悤���B�����āA���̔��\��ڂɂ����f�B�[�[���G���W���̋Z�p���e�ɕs�ē��Ȉ�ʂ̐l�́A�߂������ɂ́A��^�g��
�b�N�����s�R���d�ʎԃ��[�h�R��傫�����P�������̂Ɗ��҂��Ă��܂��ƍl������B
�B�[�[���G���W�������s�R���d�ʎԃ��[�h�R��O�`�P���������P�ł��Ȃ��u�|���R�c�Z�p�v��u�K���N�^�Z�p�v����
�i�Z�p�Ɛ������A�߂�������2015�N�x�d�ʎԔR���̋����ɔ����邽�߂ɁA������u�|���R�c�Z�p�v��u�K���N�^
�Z�p�v�̌����J�����s�ӁA���i���Ƃ̖��ӔC�ȍu���E�L�����A�Â����̂̂悤�ɖO�����������X�Ɣ��\�������Ă���
�悤���B�����āA���̔��\��ڂɂ����f�B�[�[���G���W���̋Z�p���e�ɕs�ē��Ȉ�ʂ̐l�́A�߂������ɂ́A��^�g��
�b�N�����s�R���d�ʎԃ��[�h�R��傫�����P�������̂Ɗ��҂��Ă��܂��ƍl������B
�@�����āA�u�������R�c��E��C������E�����Ԕr�o�K�X���ψ���v�A�u����c��w�@�吹�����v�A����сu����
�����ԇ��̉��� �^ �ꖱ������v�̓��{���\����w�ҁE���ƁE�Z�p�҂ł��鏔���́A��^�g���b�N�i���f�u�v�Q�T�g
���j�̏d�ʎԃ��[�h�R�������s�R����P�������������P�ł��Ȃ��R����P�̖ʂ��猩��u�K���N�^�Z�p�v��u�|��
�R�c�Z�p�v�ł��邱�Ƃ�m��Ȃ���A�������Z�p�Ƃ��Č����J���𐄏����A����������^�g���b�N�����s�R���d��
�ԃ��[�h�R��傫�����P�����Ƃ̊��҂���������悤�ȍ��\�I�H�Ȑ����͓I�ɍs���Ă����悤�ł���B����
�āA���̏́A���݂������Ă���悤���B
�����ԇ��̉��� �^ �ꖱ������v�̓��{���\����w�ҁE���ƁE�Z�p�҂ł��鏔���́A��^�g���b�N�i���f�u�v�Q�T�g
���j�̏d�ʎԃ��[�h�R�������s�R����P�������������P�ł��Ȃ��R����P�̖ʂ��猩��u�K���N�^�Z�p�v��u�|��
�R�c�Z�p�v�ł��邱�Ƃ�m��Ȃ���A�������Z�p�Ƃ��Č����J���𐄏����A����������^�g���b�N�����s�R���d��
�ԃ��[�h�R��傫�����P�����Ƃ̊��҂���������悤�ȍ��\�I�H�Ȑ����͓I�ɍs���Ă����悤�ł���B����
�āA���̏́A���݂������Ă���悤���B
�@���̈���ŁA�ނ�́A��^�g���b�N�i���f�u�v�Q�T�g���j�̏d�ʎԃ��[�h�R�������s�R���啝�ɉ��P���邱�Ƃ���
�\�ȋC���x�~�V�X�e���̋Z�p�ɂ��ẮA�����E�َE�������Ă���̂ł���B�Ⴆ�A�O�q���P�Q�|�R���̏ڏq����
����悤�ɁA���V�G�B�V�[�C�[�̑O�В� �� �F�O���́A�Q�O�O�S�N�Ƀf�B�[�[���G���W���̋C���x�~�̎��������{
���A���̋C���x�~�ɂ�����R����P�̌��ʂ��m�F���������f�[�^���擾���Ă���̂ł���B�������A�� �F�O���́A
�C���x�~�ɂ��R����P�̎������ʂ𖢔��\�Ƃ��ĎЊO��Ƃ��A�C���x�~�̎������I�����Ă�����ɂW�N�ȏ���o
�߂��Ă���ɂ�������炸�A�f�B�[�[���G���W���̗L���ȔR����P�̋Z�p���u�ЊO���\���Ȃ����R�H�v���s�g���āA�C
���x�~�̔R����P���m�F�ł����������ʂ̏��g�U��}���Ă����悤�ł���B
�\�ȋC���x�~�V�X�e���̋Z�p�ɂ��ẮA�����E�َE�������Ă���̂ł���B�Ⴆ�A�O�q���P�Q�|�R���̏ڏq����
����悤�ɁA���V�G�B�V�[�C�[�̑O�В� �� �F�O���́A�Q�O�O�S�N�Ƀf�B�[�[���G���W���̋C���x�~�̎��������{
���A���̋C���x�~�ɂ�����R����P�̌��ʂ��m�F���������f�[�^���擾���Ă���̂ł���B�������A�� �F�O���́A
�C���x�~�ɂ��R����P�̎������ʂ𖢔��\�Ƃ��ĎЊO��Ƃ��A�C���x�~�̎������I�����Ă�����ɂW�N�ȏ���o
�߂��Ă���ɂ�������炸�A�f�B�[�[���G���W���̗L���ȔR����P�̋Z�p���u�ЊO���\���Ȃ����R�H�v���s�g���āA�C
���x�~�̔R����P���m�F�ł����������ʂ̏��g�U��}���Ă����悤�ł���B
�@�܂��A���쎩���ԇ����A�����ԋZ�p���2013�N�H�G���̃v���O�����ɂ́A�z�E�r�C�ًx�~�����Ɛ��肳���C
���x�~�V�X�e���̋Z�p��p�����R����P�̎��������{���A���ɑ�^�g���b�N���������H���s�ł̂S�����x�̔R���
�オ���҂ł���L�ڂ������^���f�ڂ���Ă��邪�A���쎩���ԇ��̉��� �^ �ꖱ������́A2013�N9��25���ɔ��\
�����u2020�N���߂ǂɃf�B�[�[���G���W���P�̔R���10���̉��P��ڎw�����j�v�Ŏ������u�f�B�[�[���G���W���̔R��
���P�̋Z�p�J���v�̒��ɂ́A�C���x�~�V�X�e���̌����J���������E�َE���Ă���̂ł���B�܂��A�M�҂́A2006�N4
���ɊJ�݂����M�҂̃z�[���y�[�W�ɂ����āA��^�g���b�N�̏d�ʎԃ��[�h�R�������s�R����T�����x�̉��P����
�\���Q�^�[�{�����̋C���x�~�V�X�e���i���C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�j�̓����Z�p�ɂ��ďڍׂɐ�
�����Ă��邽�߁A�����̓��{�̃f�B�[�[���G���W���W�̊w�ҁE���ƁE�Z�p�҂́A�Q�^�[�{�����̋C���x�~�V�X�e��
�̑��݂�F�����Ă���Ɛ��������B
���x�~�V�X�e���̋Z�p��p�����R����P�̎��������{���A���ɑ�^�g���b�N���������H���s�ł̂S�����x�̔R���
�オ���҂ł���L�ڂ������^���f�ڂ���Ă��邪�A���쎩���ԇ��̉��� �^ �ꖱ������́A2013�N9��25���ɔ��\
�����u2020�N���߂ǂɃf�B�[�[���G���W���P�̔R���10���̉��P��ڎw�����j�v�Ŏ������u�f�B�[�[���G���W���̔R��
���P�̋Z�p�J���v�̒��ɂ́A�C���x�~�V�X�e���̌����J���������E�َE���Ă���̂ł���B�܂��A�M�҂́A2006�N4
���ɊJ�݂����M�҂̃z�[���y�[�W�ɂ����āA��^�g���b�N�̏d�ʎԃ��[�h�R�������s�R����T�����x�̉��P����
�\���Q�^�[�{�����̋C���x�~�V�X�e���i���C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�j�̓����Z�p�ɂ��ďڍׂɐ�
�����Ă��邽�߁A�����̓��{�̃f�B�[�[���G���W���W�̊w�ҁE���ƁE�Z�p�҂́A�Q�^�[�{�����̋C���x�~�V�X�e��
�̑��݂�F�����Ă���Ɛ��������B
�@�������A�O�q�̕\�S�P�Ɏ��������{���\����w�ҁE���ƁE�Z�p�҂̏�������^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W����
�R����P�̂��߂��E����Z�p�́A��������s�R���d�ʎԃ��[�h�R��O�`�P���������P�ł��Ȃ��Z�p��
�����J���𐄐i���Ă��A���O�`�P���������P�ł��Ȃ��u�K���N�^�Z�p�v��u�|���R�c�Z�p�v�����𗅗�Ă���A��^�g
���b�N�����s�R���d�ʎԃ��[�h�R��T�����x�̉��P�������߂�u�C���x�~�V�X�e���v�������E�َE�E���O�����
����̂ł���B���̂悤�ɁA���@�F�O���A�������R�c��̎����Ԕr�o�K�X���ψ���̃����o�[�A�吹�����A
���� �^ �ꖱ����̂悤�ȃf�B�[�[���G���W���W�̓��{���\����悤�Ȋw�ҁE���ƁE�Z�p�҂́A�����𑵂݂�
�ăg���b�N�E�o�X�����s�R���d�ʎԃ��[�h�R��̉��P�ɋɂ߂ėL�����C���x�~�V�X�e���̋Z�p���̊g�U��j�~
���銈�����s���Ă���ƌ��邱�Ƃ��\�ł���B�����āA���̂悤�ȋC���x�~�V�X�e���̋Z�p���̊g�U��j�~����
�����̌��ʁA���{�̃g���b�N�E�o�X�ɂ����鍡������s�R���d�ʎԃ��[�h�R��̉��P�̐i�W�́A�ԈႢ�Ȃ��x����
������Ɛ��������B
�R����P�̂��߂��E����Z�p�́A��������s�R���d�ʎԃ��[�h�R��O�`�P���������P�ł��Ȃ��Z�p��
�����J���𐄐i���Ă��A���O�`�P���������P�ł��Ȃ��u�K���N�^�Z�p�v��u�|���R�c�Z�p�v�����𗅗�Ă���A��^�g
���b�N�����s�R���d�ʎԃ��[�h�R��T�����x�̉��P�������߂�u�C���x�~�V�X�e���v�������E�َE�E���O�����
����̂ł���B���̂悤�ɁA���@�F�O���A�������R�c��̎����Ԕr�o�K�X���ψ���̃����o�[�A�吹�����A
���� �^ �ꖱ����̂悤�ȃf�B�[�[���G���W���W�̓��{���\����悤�Ȋw�ҁE���ƁE�Z�p�҂́A�����𑵂݂�
�ăg���b�N�E�o�X�����s�R���d�ʎԃ��[�h�R��̉��P�ɋɂ߂ėL�����C���x�~�V�X�e���̋Z�p���̊g�U��j�~
���銈�����s���Ă���ƌ��邱�Ƃ��\�ł���B�����āA���̂悤�ȋC���x�~�V�X�e���̋Z�p���̊g�U��j�~����
�����̌��ʁA���{�̃g���b�N�E�o�X�ɂ����鍡������s�R���d�ʎԃ��[�h�R��̉��P�̐i�W�́A�ԈႢ�Ȃ��x����
������Ɛ��������B
�@���̂悤�ɁA�u���V�G�B�V�[�C�[�̑O������В��@���@�F�O���v�A�u�������R�c��E��C������E�����Ԕr�o�K
�X���ψ���v�A�u����c��w�@�吹�����v�A����сu���쎩���ԇ��̉��� �^ �ꖱ������v�̏����́A���{�̃g���b
�N�E�o�X�ɂ��������s�R���d�ʎԃ��[�h�R��̉��P�̐i�W��j�~���銈����ϋɓI�ɍs���Ă��邱�Ƃ́A�w�ҁE��
��ƁE�Z�p�҂Ƃ��Ă̖{���̐Ӗ��E�E���ɔ������s�ׂł��邽�߁A���ʂ̐l�Ԃł���A�u���ӂ̔O�v��u�ǐS�̙�
�Ӂv��������Ǝv�����A�@���Ȃ��̂ł��낤���B����Ƃ��A�C���x�~�̋Z�p���u�����E�َE�v���邩�A����Ƃ��������邩
�͊w�ҁE���ƁE�Z�p�҂̌l�̎��R�ł���A���l����u�Ƃ₩��������؍����ł͂Ȃ��v�Ƃ̎v�l�̎�����ł���
���߁A���s�R���d�ʎԃ��[�h�R��̉��P�ɋɂ߂ėL�����C���x�~�V�X�e���̋Z�p���̊g�U��j�~����s�ׁE
�����ɂ��ẮA�u���ӂ̔O�v��u�ǐS�̙�Ӂv�������Ȃ��K���Ȑl�B�ł��낤���B
�X���ψ���v�A�u����c��w�@�吹�����v�A����сu���쎩���ԇ��̉��� �^ �ꖱ������v�̏����́A���{�̃g���b
�N�E�o�X�ɂ��������s�R���d�ʎԃ��[�h�R��̉��P�̐i�W��j�~���銈����ϋɓI�ɍs���Ă��邱�Ƃ́A�w�ҁE��
��ƁE�Z�p�҂Ƃ��Ă̖{���̐Ӗ��E�E���ɔ������s�ׂł��邽�߁A���ʂ̐l�Ԃł���A�u���ӂ̔O�v��u�ǐS�̙�
�Ӂv��������Ǝv�����A�@���Ȃ��̂ł��낤���B����Ƃ��A�C���x�~�̋Z�p���u�����E�َE�v���邩�A����Ƃ��������邩
�͊w�ҁE���ƁE�Z�p�҂̌l�̎��R�ł���A���l����u�Ƃ₩��������؍����ł͂Ȃ��v�Ƃ̎v�l�̎�����ł���
���߁A���s�R���d�ʎԃ��[�h�R��̉��P�ɋɂ߂ėL�����C���x�~�V�X�e���̋Z�p���̊g�U��j�~����s�ׁE
�����ɂ��ẮA�u���ӂ̔O�v��u�ǐS�̙�Ӂv�������Ȃ��K���Ȑl�B�ł��낤���B
�@���͂Ƃ�����A�u���V�G�B�V�[�C�[�̑O������В��@���@�F�O���v�A�u�������R�c��E��C������E�����Ԕr
�o�K�X���ψ���v�A�u����c��w�@�吹�����v�A����сu���쎩���ԇ��̉��� �^ �ꖱ������v�̏����́A�f�B�[�[
���G���W���̕���ɂ����ē��{���\����w�ҁE���ƁE�Z�p�҂ł���B���̂��߁A�ނ�̐�������f�B�[�[���G��
�W���W�̏����Z�p�́A���ɂ���炪�R����P�̋@�\�E���ʂ̗��Z�p�ł����Ă��A�g���b�N���[�J�⌤���@�֓���
�����Ċ����Ɍ����J�������{�����X��������B���̂��߁A���{���\����w�ҁE���ƁE�Z�p�҂̏����������E
�َE���Ă���C���x�~�̋Z�p�́A�g���b�N�E�o�X�����s�R���d�ʎԃ��[�h�R��̉��P�ɋɂ߂ėL���ȋZ�p�ł�����
���A�����J���ɒ��肳���\�����ɂ߂ĒႢ�ƍl������B
�o�K�X���ψ���v�A�u����c��w�@�吹�����v�A����сu���쎩���ԇ��̉��� �^ �ꖱ������v�̏����́A�f�B�[�[
���G���W���̕���ɂ����ē��{���\����w�ҁE���ƁE�Z�p�҂ł���B���̂��߁A�ނ�̐�������f�B�[�[���G��
�W���W�̏����Z�p�́A���ɂ���炪�R����P�̋@�\�E���ʂ̗��Z�p�ł����Ă��A�g���b�N���[�J�⌤���@�֓���
�����Ċ����Ɍ����J�������{�����X��������B���̂��߁A���{���\����w�ҁE���ƁE�Z�p�҂̏����������E
�َE���Ă���C���x�~�̋Z�p�́A�g���b�N�E�o�X�����s�R���d�ʎԃ��[�h�R��̉��P�ɋɂ߂ėL���ȋZ�p�ł�����
���A�����J���ɒ��肳���\�����ɂ߂ĒႢ�ƍl������B
�@���������āA���{���\����w�ҁE���ƁE�Z�p�҂ł����u���V�G�B�V�[�C�[�̑O������В��@���@�F�O���v�A�u��
�����R�c��E��C������E�����Ԕr�o�K�X���ψ���v�A�u����c��w�@�吹�����v�A����сu���쎩���ԇ���
���� �^ �ꖱ������v�������ɂ��u�C���x�~�ɂ��R����P�̎������ʂ̖����\�Ƃ��ĉB������s�ׁv��u�C���x
�~�̋Z�p���E�َE����s�ׁv�́A���ʓI�ɋC���x�~�̌����J���̊J�n��x�点�邱�ƂɂȂ�A��������{�̃g��
�b�N�E�o�X�ɂ��������s�R���d�ʎԃ��[�h�R��̉��P�̐i�W���ԈႢ�Ȃ��x��������v���ɂȂ���̂���������
��B���̂��Ƃ́A�g���b�N�E�o�X�̃��[�U�ɂƂ��Ắu���f���̏�Ȃ����́v�ƍl���邪�A�@���Ȃ��̂ł��낤���B�܂��A��
�{�̃g���b�N�E�o�X�ɂ��������s�R���d�ʎԃ��[�h�R��̉��P�̒x���́A�g���b�N�E�o�X������b�n�Q�팸��摗��
�ɂ��邽�߁A�b�n�Q�팸������Ă��錻�݂ł́A���Љ�I�ȍs�ׂł��邱�Ƃ́A�����ł���B
�����R�c��E��C������E�����Ԕr�o�K�X���ψ���v�A�u����c��w�@�吹�����v�A����сu���쎩���ԇ���
���� �^ �ꖱ������v�������ɂ��u�C���x�~�ɂ��R����P�̎������ʂ̖����\�Ƃ��ĉB������s�ׁv��u�C���x
�~�̋Z�p���E�َE����s�ׁv�́A���ʓI�ɋC���x�~�̌����J���̊J�n��x�点�邱�ƂɂȂ�A��������{�̃g��
�b�N�E�o�X�ɂ��������s�R���d�ʎԃ��[�h�R��̉��P�̐i�W���ԈႢ�Ȃ��x��������v���ɂȂ���̂���������
��B���̂��Ƃ́A�g���b�N�E�o�X�̃��[�U�ɂƂ��Ắu���f���̏�Ȃ����́v�ƍl���邪�A�@���Ȃ��̂ł��낤���B�܂��A��
�{�̃g���b�N�E�o�X�ɂ��������s�R���d�ʎԃ��[�h�R��̉��P�̒x���́A�g���b�N�E�o�X������b�n�Q�팸��摗��
�ɂ��邽�߁A�b�n�Q�팸������Ă��錻�݂ł́A���Љ�I�ȍs�ׂł��邱�Ƃ́A�����ł���B
�@����ɂ��Ă��s���Ȃ��Ƃ́A���{���\����w�ҁE���ƁE�Z�p�҂̏������g���b�N�E�o�X�����s�R���d�ʎԃ�
�[�h�R��̂P�����x�������P�ł��Ȃ��R����P�́u�|���R�c�Z�p�v��u�K���N�^�Z�p�v�����E��Ăł��Ȃ�����ɂ�
���āA�R����P�̋@�\�E���ʂ̗��z�E�r�C�ًx�~�����ł���^�g���b�N���������H���s�łS���̔R��ጸ���\
���C���x�~�V�X�e�����E�َE���Ă���̂ł���B���̂悤�ɁA�g���b�N�E�o�X�����s�R���d�ʎԃ��[�h�R�����
�P����ɂ߂ėL���ȋC���x�~�V�X�e���̋Z�p�������E�َE���邱�Ƃ́A�z�E�r�C�ًx�~�����ƂQ�^�[�{�����̗�����
�C���x�~�V�X�e�����łɑ��邱�ƂɂȂ�B���̂悤�����{���\����w�ҁE���ƁE�Z�p�҂̏����́A�����̃g���b
�N�E�o�X�ɂ������R����P�Ə̂��āA�u�|���R�c�Z�p�v��u�K���N�^�Z�p�v�̋Z�p�J����ϋɓI�ɐ����������A���s�R
���d�ʎԃ��[�h�R������P����ɂ߂ėL���ȋC���x�~�V�X�e���i�������_�ł̓����o��́u�z�E�r�C�ًx�~��
���v�Ɓu�Q�^�[�{�����v�̂Q�����̖͗l�j�̋Z�p�������E�َE���Ă���悤�ł����B���̂悤�Ȕނ�̍s���́A�M�҂ɂ͑S
�������ł��Ȃ����Ƃł���B
�[�h�R��̂P�����x�������P�ł��Ȃ��R����P�́u�|���R�c�Z�p�v��u�K���N�^�Z�p�v�����E��Ăł��Ȃ�����ɂ�
���āA�R����P�̋@�\�E���ʂ̗��z�E�r�C�ًx�~�����ł���^�g���b�N���������H���s�łS���̔R��ጸ���\
���C���x�~�V�X�e�����E�َE���Ă���̂ł���B���̂悤�ɁA�g���b�N�E�o�X�����s�R���d�ʎԃ��[�h�R�����
�P����ɂ߂ėL���ȋC���x�~�V�X�e���̋Z�p�������E�َE���邱�Ƃ́A�z�E�r�C�ًx�~�����ƂQ�^�[�{�����̗�����
�C���x�~�V�X�e�����łɑ��邱�ƂɂȂ�B���̂悤�����{���\����w�ҁE���ƁE�Z�p�҂̏����́A�����̃g���b
�N�E�o�X�ɂ������R����P�Ə̂��āA�u�|���R�c�Z�p�v��u�K���N�^�Z�p�v�̋Z�p�J����ϋɓI�ɐ����������A���s�R
���d�ʎԃ��[�h�R������P����ɂ߂ėL���ȋC���x�~�V�X�e���i�������_�ł̓����o��́u�z�E�r�C�ًx�~��
���v�Ɓu�Q�^�[�{�����v�̂Q�����̖͗l�j�̋Z�p�������E�َE���Ă���悤�ł����B���̂悤�Ȕނ�̍s���́A�M�҂ɂ͑S
�������ł��Ȃ����Ƃł���B
�@���݂ɁA�Q�^�[�{�����̋C���x�~�V�X�e���i���C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�j�́A�O�q�̂悤�ɋz�E�r
�C�ًx�~�����̋C���x�~�V�X�e�������i�i�ɗD�ꂽ�R����P�̋@�\�E���ʂ�����Z�p�ł���B���̂Q�^�[�{
�����̋C���x�~�V�X�e���i���C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�j���E�َE���邱�Ƃ́A��^�g���b�N����
�����H���s�łU�`�V���̔R��ጸ�i���g���b�N�E�o�X�����s�R���d�ʎԃ��[�h�R����T���̔R��ጸ�j����������
�Z�p�����̗��R�������A�łɑ��邱�ƂɂȂ�̂ł���B���̂��Ƃ��l����ƁA���{���\����w�ҁE���ƁE�Z�p�҂�
�����u���V�G�B�V�[�C�[�̑O������В��@���@�F�O���v�A�u�������R�c��E��C������E�����Ԕr�o�K�X����
����v�A�u����c��w�@�吹�����v�A����сu���쎩���ԇ��̉��� �^ �ꖱ������v�������́A�g���b�N�E�o�X�̔R���
�P��摗�肷�邽�߂̊������ӗ~�I�ɍs���Ă���悤�Ɏv���邪�A����́A�M�҂̕Ό��ł��낤���B
�C�ًx�~�����̋C���x�~�V�X�e�������i�i�ɗD�ꂽ�R����P�̋@�\�E���ʂ�����Z�p�ł���B���̂Q�^�[�{
�����̋C���x�~�V�X�e���i���C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�j���E�َE���邱�Ƃ́A��^�g���b�N����
�����H���s�łU�`�V���̔R��ጸ�i���g���b�N�E�o�X�����s�R���d�ʎԃ��[�h�R����T���̔R��ጸ�j����������
�Z�p�����̗��R�������A�łɑ��邱�ƂɂȂ�̂ł���B���̂��Ƃ��l����ƁA���{���\����w�ҁE���ƁE�Z�p�҂�
�����u���V�G�B�V�[�C�[�̑O������В��@���@�F�O���v�A�u�������R�c��E��C������E�����Ԕr�o�K�X����
����v�A�u����c��w�@�吹�����v�A����сu���쎩���ԇ��̉��� �^ �ꖱ������v�������́A�g���b�N�E�o�X�̔R���
�P��摗�肷�邽�߂̊������ӗ~�I�ɍs���Ă���悤�Ɏv���邪�A����́A�M�҂̕Ό��ł��낤���B
�@���̂悤�ɁA���{���\����w�ҁE���ƁE�Z�p�҂̏�������v���͂��ċC���x�~�̋Z�p���E�َE���铮�@
�́A�M�҂ɂ͑S������Ȃ��B�����āA���{���\����w�ҁE���ƁE�Z�p�҂̏������f�B�[�[���G���W���R����P��
�L�����C���x�~�̌����J���̊J�n��x�点���g���b�N�E�o�X���R����P�̐i�W��j�~����s�ׂ̕�V�Ƃ��āA�ނ�
�ɂ͉��炩���u���Ԃ�v������̂ł��낤���B����Ƃ��A�ނ�ɂ͉��́u���Ԃ�v���������A�|���R�c���Z�p���̒�Ă�
��C���x�~�̋Z�p�i���C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�j���C�ɐH��Ȃ����߂ɁA���̋C���x�~�̋Z�p��
���p�����ɑj�~�������Ƃ̗~�]�������߂̍s���ł��낤���B�����āA���̗l�q������ƁA�C���x�~�̋Z�p��
�����E�َE�̓��@���u�̌��Ԃ�v�ł���A�u����I�Ȍ����点�̗~�]�������߂̍s���v�ł���A����̏ꍇ
���u���V�G�B�V�[�C�[�̑O������В��@���@�F�O���v�A�u�������R�c��E��C������E�����Ԕr�o�K�X���ψ�
��v�A�u����c��w�@�吹�����v�A����сu���쎩���ԇ��̉��� �^ �ꖱ������v����������~�������ƂɎ�����
�Ă���悤�Ɏv���邪�A�@���Ȃ��̂ł��낤���B
�́A�M�҂ɂ͑S������Ȃ��B�����āA���{���\����w�ҁE���ƁE�Z�p�҂̏������f�B�[�[���G���W���R����P��
�L�����C���x�~�̌����J���̊J�n��x�点���g���b�N�E�o�X���R����P�̐i�W��j�~����s�ׂ̕�V�Ƃ��āA�ނ�
�ɂ͉��炩���u���Ԃ�v������̂ł��낤���B����Ƃ��A�ނ�ɂ͉��́u���Ԃ�v���������A�|���R�c���Z�p���̒�Ă�
��C���x�~�̋Z�p�i���C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�j���C�ɐH��Ȃ����߂ɁA���̋C���x�~�̋Z�p��
���p�����ɑj�~�������Ƃ̗~�]�������߂̍s���ł��낤���B�����āA���̗l�q������ƁA�C���x�~�̋Z�p��
�����E�َE�̓��@���u�̌��Ԃ�v�ł���A�u����I�Ȍ����点�̗~�]�������߂̍s���v�ł���A����̏ꍇ
���u���V�G�B�V�[�C�[�̑O������В��@���@�F�O���v�A�u�������R�c��E��C������E�����Ԕr�o�K�X���ψ�
��v�A�u����c��w�@�吹�����v�A����сu���쎩���ԇ��̉��� �^ �ꖱ������v����������~�������ƂɎ�����
�Ă���悤�Ɏv���邪�A�@���Ȃ��̂ł��낤���B
�@����܂ł����{���\����f�B�[�[���G���W���W�̊w�ҁE���ƁE�Z�p�҂́A�_�����\��u�����܂߂��S�Ă̋@
��𑨂��āA�f�B�[�[���g���b�N�E�o�X�̒�R��̐V�Z�p��K���Ɍ����J�����ł��邱�Ƃ��咣���Ă������Ƃ́A��
�R���鎖���ł���B�������A�ނ�̎��ۂ̍s��������ƁA�g���b�N�E�o�X�����s�R���d�ʎԃ��[�h�R������P�����
�߂ėL���ȋC���x�~�V�X�e���̋Z�p����Ȃ������E�َE�������A�����C���x�~�V�X�e���̔R����P�̗D�ꂽ�@�\�E
���ʂ��I�����Ȃ��悤�ɂ��邽�߂̓w�͂��Ă����悤�Ɏv����̂ł���B���̂悤�ɁA���{���\����f�B�[�[��
�G���W���W�̊w�ҁE���ƁE�Z�p�҂́A�C���x�~�V�X�e�����E�َE���邱�Ƃɂ��A�f�B�[�[���g���b�N�E�o�X��
�������R��̐v���Ȑ��i��ؖ]�����������g���b�N�E�o�X�̃��[�U�̊��҂��m���ɗ��葱���Ă���ƍl�����
��B���̂��Ƃɂ��āA���{���\����f�B�[�[���G���W���W�̊w�ҁE���ƁE�Z�p�҂ɂ́A���́u�߈����v��u���
�߂����v�̊���ɔY�܂���邱�Ƃ������̂ł��낤���B�����āA�ނ玩�g�́A�l�ԂƂ��Ēp���������s�ׂ��s���Ă��邱
�ƂɑS���C�t���Ă��Ȃ��̂ł��낤���B
��𑨂��āA�f�B�[�[���g���b�N�E�o�X�̒�R��̐V�Z�p��K���Ɍ����J�����ł��邱�Ƃ��咣���Ă������Ƃ́A��
�R���鎖���ł���B�������A�ނ�̎��ۂ̍s��������ƁA�g���b�N�E�o�X�����s�R���d�ʎԃ��[�h�R������P�����
�߂ėL���ȋC���x�~�V�X�e���̋Z�p����Ȃ������E�َE�������A�����C���x�~�V�X�e���̔R����P�̗D�ꂽ�@�\�E
���ʂ��I�����Ȃ��悤�ɂ��邽�߂̓w�͂��Ă����悤�Ɏv����̂ł���B���̂悤�ɁA���{���\����f�B�[�[��
�G���W���W�̊w�ҁE���ƁE�Z�p�҂́A�C���x�~�V�X�e�����E�َE���邱�Ƃɂ��A�f�B�[�[���g���b�N�E�o�X��
�������R��̐v���Ȑ��i��ؖ]�����������g���b�N�E�o�X�̃��[�U�̊��҂��m���ɗ��葱���Ă���ƍl�����
��B���̂��Ƃɂ��āA���{���\����f�B�[�[���G���W���W�̊w�ҁE���ƁE�Z�p�҂ɂ́A���́u�߈����v��u���
�߂����v�̊���ɔY�܂���邱�Ƃ������̂ł��낤���B�����āA�ނ玩�g�́A�l�ԂƂ��Ēp���������s�ׂ��s���Ă��邱
�ƂɑS���C�t���Ă��Ȃ��̂ł��낤���B
�@���݂ɁA�M�҂�2006�N4���ɊJ�݂����z�[���y�[�W�ɂ����ẮA�Q�^�[�{�����̋C���x�~�V�X�e���i���C���x�~�G
���W���i�������J2005-54771�j�j���g���b�N�E�o�X�����s�R���d�ʎԃ��[�h�R����T���̔R��ጸ�̎������\��
�����Z�p�ł��邱�Ƃ�K���ői���Ă����B�������Ȃ���A����܂œ��{�̊w�ҁE���ƁE�Z�p�҂́A�����Q�^�[�{����
�̋C���x�~�V�X�e���i���C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�j�������Z�p�����S�ɖ����E�َE�������Ă�����
���N�����l����ƁA�ނ�ɂ��C���x�~�V�X�e���̔R����P�̋Z�p���E�B�����Ă������Ƃ����́u�߈����v��u��
��߂����v�̊���ɔY�܂���邱�Ƃ������l�B�̂悤�Ɏv����̂ł���B�����āA���̂悤�Ȍ��i�́A�����I�Ȗ{�\��
�ۏo���ɂ����~�]�̂܂܂́u��肽������v�̔ڂ����l�B���w�ҁE���ƁE�Z�p�҂Ƃ��đ���U����舕����Ă����
���ɕM�҂ɂ͌�����̂ł���B�������A����́A�M�҂̒P�Ȃ�Ό������m��Ȃ��B�Ƃ��낪�A���ꂪ�����ł���A��
�{�̃f�B�[�[���g���b�N�E�o�X�̒�R����肤�������g���b�N�E�o�X�̃��[�U�́A���ꂩ������҂𗠐��邱�Ƃ�
�Ȃ�B
���W���i�������J2005-54771�j�j���g���b�N�E�o�X�����s�R���d�ʎԃ��[�h�R����T���̔R��ጸ�̎������\��
�����Z�p�ł��邱�Ƃ�K���ői���Ă����B�������Ȃ���A����܂œ��{�̊w�ҁE���ƁE�Z�p�҂́A�����Q�^�[�{����
�̋C���x�~�V�X�e���i���C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�j�������Z�p�����S�ɖ����E�َE�������Ă�����
���N�����l����ƁA�ނ�ɂ��C���x�~�V�X�e���̔R����P�̋Z�p���E�B�����Ă������Ƃ����́u�߈����v��u��
��߂����v�̊���ɔY�܂���邱�Ƃ������l�B�̂悤�Ɏv����̂ł���B�����āA���̂悤�Ȍ��i�́A�����I�Ȗ{�\��
�ۏo���ɂ����~�]�̂܂܂́u��肽������v�̔ڂ����l�B���w�ҁE���ƁE�Z�p�҂Ƃ��đ���U����舕����Ă����
���ɕM�҂ɂ͌�����̂ł���B�������A����́A�M�҂̒P�Ȃ�Ό������m��Ȃ��B�Ƃ��낪�A���ꂪ�����ł���A��
�{�̃f�B�[�[���g���b�N�E�o�X�̒�R����肤�������g���b�N�E�o�X�̃��[�U�́A���ꂩ������҂𗠐��邱�Ƃ�
�Ȃ�B
�@�������Ȃ���A���{���������g���b�N�E�o�X�̃��[�U�́A�f�B�[�[���g���b�N�E�o�X�̒�R��̊�]���̂Ă�K�v
�́A�S�������ƍl������B���̗��R�́A�킪���ɂ�����ŋ߂̎����Ԃ̔R�����ݒ肳��Ă���ȉ��̌o�܁E
������Δ���̂ł͂Ȃ����낤���B
�́A�S�������ƍl������B���̗��R�́A�킪���ɂ�����ŋ߂̎����Ԃ̔R�����ݒ肳��Ă���ȉ��̌o�܁E
������Δ���̂ł͂Ȃ����낤���B
�� �ŋ߂̎����Ԃɂ�����R���̐ݒ�
�@�@�@�@2006�N 3���F �d�ʎԁi�g���b�N�A�o�X���j�̃g�b�v�����i�[��̍���@�i2015�N�x�ڕW�j
�@�@�@�@2007�N 7���F ��p�ԁA���^�o�X�A���^�ݕ��Ԃ̃g�b�v�����i�[��̍���@�i2015�N�x�ڕW�j
�@�@�@�@2013�N 3���F ��p�ԁA���^�o�X�̃g�b�v�����i�[��̍���i2020�N�x�ڕW�j
�ȏ�̂悤�ɁA�u��p�ԁA���^�o�X�A���^�ݕ��ԁv�Ɓu�d�ʎԁi�g���b�N�A�o�X���j�v�̔R��K���ɂ��ẮA����܂ŁA
���Ɂu2015�N�x�R���v���ݒ肳��Ă����B�������A�u��p�ԁA���^�o�X�v�ɂ��ẮA�u2015�N�x�R���v������
�����V���ȁu2020�N�x�R���v��2013�N 3���ɐݒ肳�ꂽ�̂ł���B���̂��߁A�u���^�ݕ��ԁv�Ɓu�d�ʎԁi�g���b
�N�A�o�X���j�v�ɂ��Ă��A�u2015�N�x�R���v�����������V���ȁu�R���v���߂������ɐݒ肳���ƍl�����
��B���̏ꍇ�́u�߂������v�Ƃ́A�u2014�N�`2015�N�v���ł͂Ȃ����Ɛ��������B���̗��R�́A�u��p�ԁA���^�o�X�v
�ɂ��ẮA�u2015�N�x�R���v�����������V���ȁu2020�N�x�R���v��2013�N 3���Ɋ��ɐݒ肳��Ă��邽��
�ł���B
���Ɂu2015�N�x�R���v���ݒ肳��Ă����B�������A�u��p�ԁA���^�o�X�v�ɂ��ẮA�u2015�N�x�R���v������
�����V���ȁu2020�N�x�R���v��2013�N 3���ɐݒ肳�ꂽ�̂ł���B���̂��߁A�u���^�ݕ��ԁv�Ɓu�d�ʎԁi�g���b
�N�A�o�X���j�v�ɂ��Ă��A�u2015�N�x�R���v�����������V���ȁu�R���v���߂������ɐݒ肳���ƍl�����
��B���̏ꍇ�́u�߂������v�Ƃ́A�u2014�N�`2015�N�v���ł͂Ȃ����Ɛ��������B���̗��R�́A�u��p�ԁA���^�o�X�v
�ɂ��ẮA�u2015�N�x�R���v�����������V���ȁu2020�N�x�R���v��2013�N 3���Ɋ��ɐݒ肳��Ă��邽��
�ł���B
�Q�O�@���y��ʏȂ̕���26�N�x�̗\�Z�T�v�ł́A��^�g���b�N�̔R����P�̌�����͊F��
�@���y��ʏȁE�����ԋǂ́A��^�ԁi���d�ʎԁj����ɂ�����u��Y�f���i����R��j�v�Ɓu�r�o�K�X�ጸ�v��}����
�ɁA����23�N�x�`����26�N�x�ɂ����āA�u�������^�ԊJ���E���Ɖ����i���Ɓv�Ə̂��錤���J���v���W�F�N�g����
�{���Ă���悤���B�����āA���̃v���W�F�N�g�ł́A���L�̕\�S�O�Ɏ���������23�N�x�̗\�Z�T�v�ɂ��ƁA�ȉ��̋Z�p
�̌����J�������{����Ă���悤�ł���B
�ɁA����23�N�x�`����26�N�x�ɂ����āA�u�������^�ԊJ���E���Ɖ����i���Ɓv�Ə̂��錤���J���v���W�F�N�g����
�{���Ă���悤���B�����āA���̃v���W�F�N�g�ł́A���L�̕\�S�O�Ɏ���������23�N�x�̗\�Z�T�v�ɂ��ƁA�ȉ��̋Z�p
�̌����J�������{����Ă���悤�ł���B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@ ���E���^�g���b�N�̓d�C�E�v���O�C���n�C�u���b�h�g���b�N
�@�@�@�@�@�@ �@�A �������n�C�u���b�h�g���b�N
�@�@�@�@�@ �@�@�B �����\�d���H���o�X
�@�@�@�@�@�@�@�C ������o�C�I�f�B�[�[���G���W��
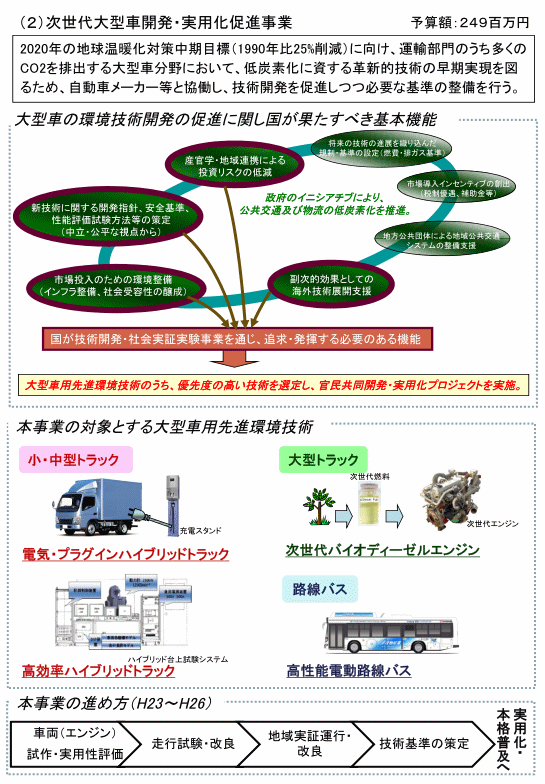 |
�@���̍��y��ʏȁE�����ԋǂ́u�������^�ԊJ���E���Ɖ����i���Ɓv�̃v���W�F�N�g�ł́A��^�ԁi���d�ʎԁj�̕�
��ɂ�����u��Y�f���i����R��j�v�Ɓu�r�o�K�X�ጸ�v��}�邱�Ƃ��ړI�Ƃ��Čf�����Ă���B�������A���̃v���W
�F�N�g�ɂ����Ď��{����Ă��鏬�E���^�g���b�N�́u�d�C�E�v���O�C���n�C�u���b�h�g���b�N�v�A�u�������n�C�u���b�h�g���b
�N�v�A�u�����\�d���H���o�X�v�A����сu������o�C�I�f�B�[�[���G���W���v�̊e�Z�p�́A�����A���p���ɐ��������Ƃ�
�Ă��A�킪���̉^�A�����CO2�팸���\���Ӎ팸�ł�����x�̑䐔�̃g���b�N�ɍ̗p����čL�����y�����邱�Ƃ���
��Ɛ��������B���������āA���̃v���W�F�N�g�́A�����I�ɁA�킪���̉^�A�����CO2�r�o�̍팸�ɖw�Ǎv���ł�
�Ȃ��Z�p�̌����J���Ɛ��������B���̗��R�́A�ȉ��̒ʂ�ł���B
��ɂ�����u��Y�f���i����R��j�v�Ɓu�r�o�K�X�ጸ�v��}�邱�Ƃ��ړI�Ƃ��Čf�����Ă���B�������A���̃v���W
�F�N�g�ɂ����Ď��{����Ă��鏬�E���^�g���b�N�́u�d�C�E�v���O�C���n�C�u���b�h�g���b�N�v�A�u�������n�C�u���b�h�g���b
�N�v�A�u�����\�d���H���o�X�v�A����сu������o�C�I�f�B�[�[���G���W���v�̊e�Z�p�́A�����A���p���ɐ��������Ƃ�
�Ă��A�킪���̉^�A�����CO2�팸���\���Ӎ팸�ł�����x�̑䐔�̃g���b�N�ɍ̗p����čL�����y�����邱�Ƃ���
��Ɛ��������B���������āA���̃v���W�F�N�g�́A�����I�ɁA�킪���̉^�A�����CO2�r�o�̍팸�ɖw�Ǎv���ł�
�Ȃ��Z�p�̌����J���Ɛ��������B���̗��R�́A�ȉ��̒ʂ�ł���B
�i�P�j �d���H���o�X�ɂ��CO2�r�o�̍팸������ȗ��R
�@�킪����2010�N���̕��ʃg���b�N�ۗ̕L�䐔��228����ł���̂ɑ��A���^�o�X���܂߂��H���o�X�̑S�䐔
�́A��U����i�o�T�Fhttp://www.mlit.go.jp/common/000017063.pdf�j�ł���B���̂悤�ɁA���ʃg���b�N�ۗ̕L�䐔��2.
6���̎ԗ��䐔�����g�p����Ă��Ȃ��B�������A�H���o�X�̂P���̑��s�����́A�g���b�N�̂P���̑��s�����̂R����1
���x�ł���B���̂悤�ɁA�H���o�X�́A���ʃg���b�N��2.6���ۗ̕L�䐔�ɂ����߂��Ȃ����Ƃɉ����A�g���b�N�̂P���̑�
�s���������ʃg���b�N�̂R����1���x�ł��邱����A�H���o�X�ŏ����Ă���R���ʁi���y���ʁj�́A�킪���̕���
�g���b�N�̕���ŏ����Ă���Ζ��i���y���j�̑�����ʂ�1�����x�ȉ��̋ɂ��͂��ł���B���̂��Ƃ���A�킪��
�ł́A�H���o�X�����CO2�r�o�K�X�ʂ́A���ʃg���b�N����r�o����Ă���CO2�̑�����ʂ�1�����x�ȉ��Ɛ��@��
���B���������āA�����A���ɘH���o�X�̑S����d���H���o�X�ɓ]���ł����Ƃ��Ă��A���ʃg���b�N�̕��삩��r�o��
���CO2�̂P�����x�ȉ������팸�ł��Ȃ��̂ł���B�v����ɁA�d���H���o�X�́A���ʃg���b�N�̕��삩���CO2�r
�o�ʂ̑���덷�̒��x����CO2�̍팸���ł��Ȃ��̂��B���̂悤��CO2�ɖ����ł���Ɨ\�������ɂ�������炸�A
�H���o�X�̓d�����ɂ����CO2�r�o�̍팸��}�낤�Ƃ���Ӗ��s���Ȍ����J����26�N�x�ɍ��y��ʏȂ����{
����\��Ƃ̂��Ƃł���B�߂������A���ɁA���̌����J�����������A�S�Ă̘H���o�X���d���H���o�X�ɓ]���ł�����
���Ă��A���ʃg���b�N�S�̂���̑�CO2�r�o�ʂ�1�����x�ȉ��̍팸�ɉ߂��Ȃ��B���������āA�H���o�X�̓d�����́A
�킪���̒�Y�f�Љ�i����CO2�Љ�j�̎����ɂ͖w�Ǎv���ł��Ȃ����Ɛ��������B
�́A��U����i�o�T�Fhttp://www.mlit.go.jp/common/000017063.pdf�j�ł���B���̂悤�ɁA���ʃg���b�N�ۗ̕L�䐔��2.
6���̎ԗ��䐔�����g�p����Ă��Ȃ��B�������A�H���o�X�̂P���̑��s�����́A�g���b�N�̂P���̑��s�����̂R����1
���x�ł���B���̂悤�ɁA�H���o�X�́A���ʃg���b�N��2.6���ۗ̕L�䐔�ɂ����߂��Ȃ����Ƃɉ����A�g���b�N�̂P���̑�
�s���������ʃg���b�N�̂R����1���x�ł��邱����A�H���o�X�ŏ����Ă���R���ʁi���y���ʁj�́A�킪���̕���
�g���b�N�̕���ŏ����Ă���Ζ��i���y���j�̑�����ʂ�1�����x�ȉ��̋ɂ��͂��ł���B���̂��Ƃ���A�킪��
�ł́A�H���o�X�����CO2�r�o�K�X�ʂ́A���ʃg���b�N����r�o����Ă���CO2�̑�����ʂ�1�����x�ȉ��Ɛ��@��
���B���������āA�����A���ɘH���o�X�̑S����d���H���o�X�ɓ]���ł����Ƃ��Ă��A���ʃg���b�N�̕��삩��r�o��
���CO2�̂P�����x�ȉ������팸�ł��Ȃ��̂ł���B�v����ɁA�d���H���o�X�́A���ʃg���b�N�̕��삩���CO2�r
�o�ʂ̑���덷�̒��x����CO2�̍팸���ł��Ȃ��̂��B���̂悤��CO2�ɖ����ł���Ɨ\�������ɂ�������炸�A
�H���o�X�̓d�����ɂ����CO2�r�o�̍팸��}�낤�Ƃ���Ӗ��s���Ȍ����J����26�N�x�ɍ��y��ʏȂ����{
����\��Ƃ̂��Ƃł���B�߂������A���ɁA���̌����J�����������A�S�Ă̘H���o�X���d���H���o�X�ɓ]���ł�����
���Ă��A���ʃg���b�N�S�̂���̑�CO2�r�o�ʂ�1�����x�ȉ��̍팸�ɉ߂��Ȃ��B���������āA�H���o�X�̓d�����́A
�킪���̒�Y�f�Љ�i����CO2�Љ�j�̎����ɂ͖w�Ǎv���ł��Ȃ����Ɛ��������B
�i�Q�j �u�d�C�E�v���O�C���v�܂��́u�������v�̒����^�n�C�u���b�h�g���b�N�ɂ��CO2�r�o�̍팸������ȗ��R
�@���^�n�C�u���b�h �g���b�N�̓n�C�u���b�h��p�Ԃ̂悤�ȔR����P�������ɂ��ڏq���Ă���悤�ɁA���E���^�n�C�u���b
�h�g���b�N�́A�]���̒��E���^�f�B�[�[���g���b�N�ɔ�r����10�`20���́uCO2�팸�v�Ɓu�R����P�v���������Ȃ��̂�
����B�������A���̒��E���^�n�C�u���b�h�g���b�N�́A�A��������R�@�ւ̑��ɓd���@�ƍ����ȃo�b�e���[�𓋍ڂ���K
�v�����邽�߁A�]���̃f�B�[�[�����E���^�g���b�N�ɔ�r���ĂP�䓖����ŕS���~�`���S���~�������ȏ��E���^�g���b
�N�ɂȂ�B���������āA���E���^�n�C�u���b�h�g���b�N�ł́A�n�C�u���b�h���ɂ��R����P��10�`20�����x�����ɁA��
�������̊Ԃ̑����s�������Z�����Ƃ���A���E���^�n�C�u���b�h�g���b�N�̎ԗ����i�̑�������R����P�ɂ��ԗ�
�����̊Ԃ̔R����팸�ɂ���ĕ⊮���邱�Ƃ�����ƂȂ�B���̂��߁A���E���^�n�C�u���b�h�g���b�N�������g���b
�N���[�U�́A�]���̒��E���^�f�B�[�[���g���b�N���g�p�����ꍇ�ɔ�ׁA�^�s�R�X�g�̑����S����K�v�������邱
�ƂɂȂ�B���������āA�^�A�����CO2�팸�ɐϋɓI�ȍs���������ȃg���b�N���[�U�ȊO�ɂ́A�]���̒��E���^�f�B
�[�[���g���b�N�𒆁E���^�n�C�u���b�h�g���b�N�ɕύX����g���b�N���[�U�́A�����Ƃ��ɂ߂ď��Ȃ��Ɛ��������B����
���Ƃ́A�킪���ɂ����ĐύڗʂQ�g���N���X�̏��^�n�C�u���b�h�g���b�N�́A��P�O�N�O����s�̂���Ă��邪�A���^�g��
�b�N�̔N�ԑ��̔��䐔�ɐ�߂鏬�^�n�C�u���b�h�g���b�N�̊����́A�������x�ɗ��܂��Ă��錻��������ł���
���Ƃł���B���l�ȗ��R����A�߂������A���ɁA���E���^�́u�d�C�E�v���O�C���n�C�u���b�h�g���b�N�v���s�̂��ꂽ�Ƃ���
���A�]���̒��E���^�f�B�[�[���g���b�N�𒆁E���^�́u�d�C�E�v���O�C���n�C�u���b�h�g���b�N�v�ɕύX����g���b�N���[�U
���A�ɂ߂ď��Ȃ��Ɛ��������B���̂��߁A�����Ƃ��r�o�K�X��Ɣr�o�K�X�K���ɓK���������E���^�f�B�[�[���g��
�b�N�ɂ���ĉݕ��A�����\�ȏɂ����ẮA���z�̓�����K�v�Ƃ���u�d�C�E�v���O�C���n�C�u���b�h�g���b�N�v��
�u�������n�C�u���b�h�g���b�N�v�Ɋ��ĕύX����g���b�N���[�U�́A�ɂ߂ď��Ȃ��ƍl����̂��Ó��ł͂Ȃ����낤���B��
�̗��R�́A�����A���E���^�f�B�[�[���g���b�N���璆�E���^�́u�d�C�E�v���O�C���n�C�u���b�h�g���b�N�v�Ɓu�������n�C�u��
�b�h�g���b�N�v�ɕύX����ꍇ�ɂ́A�ԗ������̊��Ԃ̔R����̍팸�����ԗ��w����̑�����⊮�ł��Ȃ����߂�
�u���[�U�̃f�����b�g�E�s���v�v�������鋰����\���ɗ\�z����邽�߂ł���B���������āA�����I�ɏ��E���^�g���b
�N�́u�d�C�E�v���O�C���n�C�u���b�h�g���b�N�v�Ɓu�������n�C�u���b�h�g���b�N�v�������ōL�����y���čs�����Ƃ́A
�ɂ߂č���Ɛ��������B���������āA���E���^�g���b�N�́u�d�C�E�v���O�C���n�C�u���b�h�g���b�N�v�Ɓu�������n
�C�u���b�h�g���b�N�v���J�����ꂽ�Ƃ��Ă��A�킪���̒�Y�f�Љ�i����CO2�Љ�j�̎����ɂ͖w�Ǎv���ł���
���Ɨ\��������B
�h�g���b�N�́A�]���̒��E���^�f�B�[�[���g���b�N�ɔ�r����10�`20���́uCO2�팸�v�Ɓu�R����P�v���������Ȃ��̂�
����B�������A���̒��E���^�n�C�u���b�h�g���b�N�́A�A��������R�@�ւ̑��ɓd���@�ƍ����ȃo�b�e���[�𓋍ڂ���K
�v�����邽�߁A�]���̃f�B�[�[�����E���^�g���b�N�ɔ�r���ĂP�䓖����ŕS���~�`���S���~�������ȏ��E���^�g���b
�N�ɂȂ�B���������āA���E���^�n�C�u���b�h�g���b�N�ł́A�n�C�u���b�h���ɂ��R����P��10�`20�����x�����ɁA��
�������̊Ԃ̑����s�������Z�����Ƃ���A���E���^�n�C�u���b�h�g���b�N�̎ԗ����i�̑�������R����P�ɂ��ԗ�
�����̊Ԃ̔R����팸�ɂ���ĕ⊮���邱�Ƃ�����ƂȂ�B���̂��߁A���E���^�n�C�u���b�h�g���b�N�������g���b
�N���[�U�́A�]���̒��E���^�f�B�[�[���g���b�N���g�p�����ꍇ�ɔ�ׁA�^�s�R�X�g�̑����S����K�v�������邱
�ƂɂȂ�B���������āA�^�A�����CO2�팸�ɐϋɓI�ȍs���������ȃg���b�N���[�U�ȊO�ɂ́A�]���̒��E���^�f�B
�[�[���g���b�N�𒆁E���^�n�C�u���b�h�g���b�N�ɕύX����g���b�N���[�U�́A�����Ƃ��ɂ߂ď��Ȃ��Ɛ��������B����
���Ƃ́A�킪���ɂ����ĐύڗʂQ�g���N���X�̏��^�n�C�u���b�h�g���b�N�́A��P�O�N�O����s�̂���Ă��邪�A���^�g��
�b�N�̔N�ԑ��̔��䐔�ɐ�߂鏬�^�n�C�u���b�h�g���b�N�̊����́A�������x�ɗ��܂��Ă��錻��������ł���
���Ƃł���B���l�ȗ��R����A�߂������A���ɁA���E���^�́u�d�C�E�v���O�C���n�C�u���b�h�g���b�N�v���s�̂��ꂽ�Ƃ���
���A�]���̒��E���^�f�B�[�[���g���b�N�𒆁E���^�́u�d�C�E�v���O�C���n�C�u���b�h�g���b�N�v�ɕύX����g���b�N���[�U
���A�ɂ߂ď��Ȃ��Ɛ��������B���̂��߁A�����Ƃ��r�o�K�X��Ɣr�o�K�X�K���ɓK���������E���^�f�B�[�[���g��
�b�N�ɂ���ĉݕ��A�����\�ȏɂ����ẮA���z�̓�����K�v�Ƃ���u�d�C�E�v���O�C���n�C�u���b�h�g���b�N�v��
�u�������n�C�u���b�h�g���b�N�v�Ɋ��ĕύX����g���b�N���[�U�́A�ɂ߂ď��Ȃ��ƍl����̂��Ó��ł͂Ȃ����낤���B��
�̗��R�́A�����A���E���^�f�B�[�[���g���b�N���璆�E���^�́u�d�C�E�v���O�C���n�C�u���b�h�g���b�N�v�Ɓu�������n�C�u��
�b�h�g���b�N�v�ɕύX����ꍇ�ɂ́A�ԗ������̊��Ԃ̔R����̍팸�����ԗ��w����̑�����⊮�ł��Ȃ����߂�
�u���[�U�̃f�����b�g�E�s���v�v�������鋰����\���ɗ\�z����邽�߂ł���B���������āA�����I�ɏ��E���^�g���b
�N�́u�d�C�E�v���O�C���n�C�u���b�h�g���b�N�v�Ɓu�������n�C�u���b�h�g���b�N�v�������ōL�����y���čs�����Ƃ́A
�ɂ߂č���Ɛ��������B���������āA���E���^�g���b�N�́u�d�C�E�v���O�C���n�C�u���b�h�g���b�N�v�Ɓu�������n
�C�u���b�h�g���b�N�v���J�����ꂽ�Ƃ��Ă��A�킪���̒�Y�f�Љ�i����CO2�Љ�j�̎����ɂ͖w�Ǎv���ł���
���Ɨ\��������B
�@�܂��A�����ł́A���������R�ɑ��s�ł���P�Ԃ̑�^�g���b�N�Ƃ��ẮAGVW�i�ԗ����d��)��25�g���ȉ��Ƃ�
��K�肪�݂����Ă���B���̂��߁AGVW��25�g���̑�^�g���b�N�ł́A�n�C�u���b�h���ɂ��ԗ��{�̂̏d
�ʑ��������ꍇ�ɂ́A�ԗ��{�̂̏d�ʑ����d�ʂƓ������ύډݕ��̏d�ʂ�����������Ȃ��̂ł���B��
���낪�A���̓s�s�ԉݕ��A���̎�͂ł����^�g���b�N�i��VW25�g���j�ɂ����ẮA�ԗ��{�̂̏d�ʑ����ɂ�
��ύډݕ��ʂ̌����́A���̌��������ɔ�Ⴕ�ĉݕ��A���̃R�X�g�����������N�����Ă��܂����ƂɂȂ�B��
�̂��߁A�����\���ɂ�鑽���̔R����オ������ꍇ�ł��A�]�������ԗ��{�̂̏d�ʂ��������Ă��܂�����^
�g���b�N�iGVW25�g���j�́A���̑�^�g���b�N�̔[���E�w�����g���b�N�^���Ǝ҂����₵�Ă���̂�����ł���B��������
�āA�n�C�u���b�h�g���b�N���ɂ��ԗ��{�̂̏d�ʑ����̕s��ɋN�����Đύڗʂ������������ׂ�����^
�g���b�N�iGVW25�g���j���g���b�N�^���Ǝ҂����čw�����A�ݕ��A���̋Ɩ��Ɏg�p�����\���ɂ��ẮA��
���Ƃ��w�ǖ������̂ƍl�������B
��K�肪�݂����Ă���B���̂��߁AGVW��25�g���̑�^�g���b�N�ł́A�n�C�u���b�h���ɂ��ԗ��{�̂̏d
�ʑ��������ꍇ�ɂ́A�ԗ��{�̂̏d�ʑ����d�ʂƓ������ύډݕ��̏d�ʂ�����������Ȃ��̂ł���B��
���낪�A���̓s�s�ԉݕ��A���̎�͂ł����^�g���b�N�i��VW25�g���j�ɂ����ẮA�ԗ��{�̂̏d�ʑ����ɂ�
��ύډݕ��ʂ̌����́A���̌��������ɔ�Ⴕ�ĉݕ��A���̃R�X�g�����������N�����Ă��܂����ƂɂȂ�B��
�̂��߁A�����\���ɂ�鑽���̔R����オ������ꍇ�ł��A�]�������ԗ��{�̂̏d�ʂ��������Ă��܂�����^
�g���b�N�iGVW25�g���j�́A���̑�^�g���b�N�̔[���E�w�����g���b�N�^���Ǝ҂����₵�Ă���̂�����ł���B��������
�āA�n�C�u���b�h�g���b�N���ɂ��ԗ��{�̂̏d�ʑ����̕s��ɋN�����Đύڗʂ������������ׂ�����^
�g���b�N�iGVW25�g���j���g���b�N�^���Ǝ҂����čw�����A�ݕ��A���̋Ɩ��Ɏg�p�����\���ɂ��ẮA��
���Ƃ��w�ǖ������̂ƍl�������B
�i�R�j ������o�C�I�f�B�[�[���G���W���ɂ��CO2�r�o�̍팸������ȗ��R
�@�o�C�I�f�B�[�[���R���́A�A�������������Ƃ��ăA���J���G�}����p���ăA���R�[���Ɣ��������A���`���G�X�e����
���邱�Ƃɂ���Đ��������R���ł���B���̂��߁A���������H�����������S�O���i�J�����[�x�[�X�j�̓��{�ɂ�����
�́A�g���b�N�ݕ��A������ɕK�v�ȗʂ̃o�C�I�}�X�R���̌����ƂȂ�A���������������邱�Ƃ��s�\�Ȃ��Ƃ͖���
�����B�����Đ��E�ɖڂ������Ă��A�n����̐��E�S�̂ł̐l�������␅�����̕s���ȂǂŐH����@�̓������c�_
����Ă��錻�݂ł́A�킪���̉^�A����ł̒E�Ζ��ƒ�Y�f�Љ�i����CO2�Љ�j�̎����ɍv���ł�����x�̗ʂ�
�o�C�I�}�X�R����A�����邱�Ƃ�����Ȃ��Ƃ͖����ł���B�܂��A���E�ɖڂ������Ă��A���E�l����70���l��˔j��
���ɂ�������炸�A�e���̓��ꎖ���@����̗��R����l��������}���邱�Ƃ�����Ȕ��W�r�㍑������������
����B���̂��߁A���ۘA����2050�N�ɂ�90���l�i�����ʏo�����̏ꍇ�j�ɒB����Ƃ������v���o���Ă���B���̂悤
�ȍ���̐��E�l���̑����┭�W�r�㍑�̐������x���̌���ɂ��H�����v�̑����������A�߂������ɊԈႢ
�Ȃ��H���s���̖�肪��������Ɗ뜜����Ă���B���̂悤�ȏɂ����āA���{�̑�^�ԁi���d�ʎԁj����ɂ�
����u��Y�f���i����R��j�v��}�邽�߂Ƃ͉]���A�A�������������Ƃ����o�C�I�f�B�[�[���R���̕K�v��
����{���m�ۂ���͍̂���ł��邱�Ƃ���A�o�C�I�f�B�[�[���R�����g�p����o�C�I�f�B�[�[���G���W���̑�
�^�ԁi���d�ʎԁj����{�ŕ��y�����邱�Ƃ́A�s�\�ł���Ɛ��������B���������āA�o�C�I�f�B�[�[���G��
�W�����J�����ꂽ�Ƃ��Ă��A�킪���̒�Y�f�Љ�i����CO2�Љ�j�̎����ɂ͖w�Ǎv���ł��Ȃ��Ɛ�������
��B�Ȃ��A�o�C�I�}�X�R����DME���A�f�B�[�[���G���W���̔R���Ƃ��Ď��i�ł���B���̗��R�ɂ��ẮA�o�C�I�}�X
�R����DME�ɂ�鎩���Ԃ̒�Y�f�E�E�Ζ��́A�s�\���I�̃y�[�W�ɏڏq���Ă���̂ŁA�����̂�����͌䗗����
���������B
���邱�Ƃɂ���Đ��������R���ł���B���̂��߁A���������H�����������S�O���i�J�����[�x�[�X�j�̓��{�ɂ�����
�́A�g���b�N�ݕ��A������ɕK�v�ȗʂ̃o�C�I�}�X�R���̌����ƂȂ�A���������������邱�Ƃ��s�\�Ȃ��Ƃ͖���
�����B�����Đ��E�ɖڂ������Ă��A�n����̐��E�S�̂ł̐l�������␅�����̕s���ȂǂŐH����@�̓������c�_
����Ă��錻�݂ł́A�킪���̉^�A����ł̒E�Ζ��ƒ�Y�f�Љ�i����CO2�Љ�j�̎����ɍv���ł�����x�̗ʂ�
�o�C�I�}�X�R����A�����邱�Ƃ�����Ȃ��Ƃ͖����ł���B�܂��A���E�ɖڂ������Ă��A���E�l����70���l��˔j��
���ɂ�������炸�A�e���̓��ꎖ���@����̗��R����l��������}���邱�Ƃ�����Ȕ��W�r�㍑������������
����B���̂��߁A���ۘA����2050�N�ɂ�90���l�i�����ʏo�����̏ꍇ�j�ɒB����Ƃ������v���o���Ă���B���̂悤
�ȍ���̐��E�l���̑����┭�W�r�㍑�̐������x���̌���ɂ��H�����v�̑����������A�߂������ɊԈႢ
�Ȃ��H���s���̖�肪��������Ɗ뜜����Ă���B���̂悤�ȏɂ����āA���{�̑�^�ԁi���d�ʎԁj����ɂ�
����u��Y�f���i����R��j�v��}�邽�߂Ƃ͉]���A�A�������������Ƃ����o�C�I�f�B�[�[���R���̕K�v��
����{���m�ۂ���͍̂���ł��邱�Ƃ���A�o�C�I�f�B�[�[���R�����g�p����o�C�I�f�B�[�[���G���W���̑�
�^�ԁi���d�ʎԁj����{�ŕ��y�����邱�Ƃ́A�s�\�ł���Ɛ��������B���������āA�o�C�I�f�B�[�[���G��
�W�����J�����ꂽ�Ƃ��Ă��A�킪���̒�Y�f�Љ�i����CO2�Љ�j�̎����ɂ͖w�Ǎv���ł��Ȃ��Ɛ�������
��B�Ȃ��A�o�C�I�}�X�R����DME���A�f�B�[�[���G���W���̔R���Ƃ��Ď��i�ł���B���̗��R�ɂ��ẮA�o�C�I�}�X
�R����DME�ɂ�鎩���Ԃ̒�Y�f�E�E�Ζ��́A�s�\���I�̃y�[�W�ɏڏq���Ă���̂ŁA�����̂�����͌䗗����
���������B
�@�ȏ�̂悤�ɁA���y��ʏȁE�����ԋǁi����ʈ��S���������j�́u�������^�ԊJ���E���Ɖ����i���Ɓi����23
�N�x�`����26�N�x�j�v�ł́A��^�ԁi���d�ʎԁj����ɂ�����u��Y�f���i����R��j�v�Ɓu�r�o�K�X�ጸ�v��}�邱��
��ړI�Ƃ��āA���E���^�g���b�N�́u�d�C�E�v���O�C���n�C�u���b�h�g���b�N�v�A�u�������n�C�u���b�h�g���b�N�v�A�����\�d��
�H���o�X�A����ю�����o�C�I�f�B�[�[���G���W���̌����J�������{����Ă���B�������A���̌����J���ɐ�������
�Ƃ��Ă��A����A�킪���ɂ������^�ԁi���d�ʎԁj����ɂ�����u��Y�f���i����R��j�v�Ɓu�r�o�K�X�ጸ�v�Ɋ�
�^����\���͊F���Ɛ��������B���̂悤�ɁA���{�̑�^�ԁi���d�ʎԁj����ɂ�����u��Y�f���i����R��j�v
�Ɓu�r�o�K�X�ጸ�v�ɍv�����Ȃ��u�������^�ԊJ���E���Ɖ����i���Ɓv�Ə̂��錤���J���ɑ��A���y��ʏȁE����
�ԋǁi����ʈ��S���������j�́A����24�N�x�`����26�N�x�ɂ����āA�ȉ��Ɏ������悤�ɁA���z�Ŗ�P�O���~�̐�
�{�\�Z����������Ă���̂ł���B
�N�x�`����26�N�x�j�v�ł́A��^�ԁi���d�ʎԁj����ɂ�����u��Y�f���i����R��j�v�Ɓu�r�o�K�X�ጸ�v��}�邱��
��ړI�Ƃ��āA���E���^�g���b�N�́u�d�C�E�v���O�C���n�C�u���b�h�g���b�N�v�A�u�������n�C�u���b�h�g���b�N�v�A�����\�d��
�H���o�X�A����ю�����o�C�I�f�B�[�[���G���W���̌����J�������{����Ă���B�������A���̌����J���ɐ�������
�Ƃ��Ă��A����A�킪���ɂ������^�ԁi���d�ʎԁj����ɂ�����u��Y�f���i����R��j�v�Ɓu�r�o�K�X�ጸ�v�Ɋ�
�^����\���͊F���Ɛ��������B���̂悤�ɁA���{�̑�^�ԁi���d�ʎԁj����ɂ�����u��Y�f���i����R��j�v
�Ɓu�r�o�K�X�ጸ�v�ɍv�����Ȃ��u�������^�ԊJ���E���Ɖ����i���Ɓv�Ə̂��錤���J���ɑ��A���y��ʏȁE����
�ԋǁi����ʈ��S���������j�́A����24�N�x�`����26�N�x�ɂ����āA�ȉ��Ɏ������悤�ɁA���z�Ŗ�P�O���~�̐�
�{�\�Z����������Ă���̂ł���B
�� ����23�N�x�̗\�Z�z�ƌ������e�i��http://www.mlit.go.jp/common/000147904.pdf�j
�@�@�i�P�j�@�\�Z�z
�@�@�@�@�@�@�@2��4��9�S���~
�@�@�i�Q�j�@�������e
�@�@�@�@�@�@�@�@ ���E���^�g���b�N�̓d�C�E�v���O�C���n�C�u���b�h�g���b�N
�@�@�@�@�@�@�@�A �������n�C�u���b�h�g���b�N
�@�@�@�@�@�@�@�B �����\�d���H���o�X
�@�@�@�@�@�@�@�C ������o�C�I�f�B�[�[���G���W��
�� ����24�N�x�̗\�Z�z�ƌ������e�i��http://www.mlit.go.jp/common/000188770.pdf�j
�@�@�i�P�j�@�\�Z�z
�@�@�@�@�@�@�@2��4��9�S���~
�@�@�i�Q�j�@�������e
�@�@�@�@�@�@�@�@ ���E���^�g���b�N�̓d�C�E�v���O�C���n�C�u���b�h�g���b�N
�@�@�@�@�@�@�@�A ������o�C�I�f�B�[�[���G���W��
�� ����25�N�x�̗\�Z�z�ƌ������e�i��http://www.mlit.go.jp/common/000989100.pdf�j
�@�@�i�P�j�@�\�Z�z
�@�@�@�@�@�@�@2��4��9�S���~
�@�@�i�Q�j�@�������e
�@�@�@�@�@�@�@�@ ���E���^�g���b�N�̓d�C�E�v���O�C���n�C�u���b�h�g���b�N
�@�@�@�@�@�@�@�A ���E���^�g���b�N�̍������n�C�u���b�h�g���b�N
�@�@�@�@�@�@�@�B �����\�d���H���o�X
�� ����26�N�x�̗\�Z�z�ƌ������e�i��http://www.mlit.go.jp/common/000989100.pdf�j
�@�@�i�P�j�@�\�Z�z
�@�@�@�@�@�@�@2��4��8�S���~
�@�@�i�Q�j�@�������e
�@�@�@�@�@�@�@�@ ���E���^�g���b�N�̓d�C�E�v���O�C���n�C�u���b�h�g���b�N
�@�@�@�@�@�@�@�A ���E���^�g���b�N�̍������n�C�u���b�h�g���b�N
�@�@�@�@�@�@�@�B �����\�d���H���o�X
�Ȃ��A�M�҂�����24�N1��24���Ɍ��J�����z�[���y�[�W�F���{�̒�Y�f�ƒE�Ζ��ɖ����ȋZ�p�����������ʈ��S
���������ɂ����āA�u�������^�ԊJ���E���Ɖ����i���Ɓv�́u���E���^�g���b�N�̓d�C�E�v���O�C���n�C�u���b�h�g��
�b�N�v�ƁA�u���E���^�g���b�N�̍������n�C�u���b�h�g���b�N�v�A�u�����\�d���H���o�X�v�A����сu�o�C�I�f�B�[�[���G���W
���v�̋Z�p�J�������������Ƃ��Ă��A���{�̉^�A����́uCO2�r�o�̍팸�v�E�u��Y�f���i����R��j�v�ɖ����ł���
�Ƒi�����B�������A���y��ʏȁE�����ԋǁi����ʈ��S���������j�́A�M�҂̈ӌ������A�킪���ɂ������^
�ԁi���d�ʎԁj����ɂ�����u��Y�f���i����R��j�v�Ɓu�r�o�K�X�ጸ�v�Ɋ�^����\�����F���Ɛ��������u��
�����^�ԊJ���E���Ɖ����i���Ɓv�̖��ʂƎv���錤���J���ɂ́A���z�X���X��T�S���~���̑��z�̐��{�\�Z��
�����Ď��{����Ă���悤�ł���B
���������ɂ����āA�u�������^�ԊJ���E���Ɖ����i���Ɓv�́u���E���^�g���b�N�̓d�C�E�v���O�C���n�C�u���b�h�g��
�b�N�v�ƁA�u���E���^�g���b�N�̍������n�C�u���b�h�g���b�N�v�A�u�����\�d���H���o�X�v�A����сu�o�C�I�f�B�[�[���G���W
���v�̋Z�p�J�������������Ƃ��Ă��A���{�̉^�A����́uCO2�r�o�̍팸�v�E�u��Y�f���i����R��j�v�ɖ����ł���
�Ƒi�����B�������A���y��ʏȁE�����ԋǁi����ʈ��S���������j�́A�M�҂̈ӌ������A�킪���ɂ������^
�ԁi���d�ʎԁj����ɂ�����u��Y�f���i����R��j�v�Ɓu�r�o�K�X�ጸ�v�Ɋ�^����\�����F���Ɛ��������u��
�����^�ԊJ���E���Ɖ����i���Ɓv�̖��ʂƎv���錤���J���ɂ́A���z�X���X��T�S���~���̑��z�̐��{�\�Z��
�����Ď��{����Ă���悤�ł���B
�@�Ƃ���ŁA���́u�������^�ԊJ���E���Ɖ����i���Ɓv�̋Z�p�̒��ŁA��^�f�B�[�[���g���b�N�E�g���N�^��CO2�팸
�̂��߂ɍ̗p�\�ȋZ�p�́A�u�o�C�I�f�B�[�[���G���W���v�����ł���B�������A�����A���ɁA�⏕�����̎�i�ɂ��
�ăo�C�I�f�B�[�[���G���W�����ڂ̑�^�f�B�[�[���g���b�N�E�g���N�^�̎s��ł̑䐔�������\�ł������Ƃ��Ă��A�^
�A�����CO2�팸���\���ɕ]���ł���\���ȑ䐔�������ɕ��y�����ĉғ��ł���ʂ̃o�C�I�f�B�[�[���R�����
�{���m�ۂł��Ȃ����Ƃ́A�펯�I�ɍl����Ζ��炩�ł���B����ɂ�������炸�A���y��ʏȁE�����ԋǁi����ʈ�
�S���������j�̐l�B���A�u�o�C�I�f�B�[�[���G���W���v���̗p������^�f�B�[�[���g���b�N�E�g���N�^���L�����y������
��^�f�B�[�[���g���b�N�E�g���N�^��CO2�팸����Ƃ̖ژ_����{�S����M�Ă���Ƃ���A�u���̍����v�Ƃ̌���
���ᔻ���Ă����R�ƍl������B
�̂��߂ɍ̗p�\�ȋZ�p�́A�u�o�C�I�f�B�[�[���G���W���v�����ł���B�������A�����A���ɁA�⏕�����̎�i�ɂ��
�ăo�C�I�f�B�[�[���G���W�����ڂ̑�^�f�B�[�[���g���b�N�E�g���N�^�̎s��ł̑䐔�������\�ł������Ƃ��Ă��A�^
�A�����CO2�팸���\���ɕ]���ł���\���ȑ䐔�������ɕ��y�����ĉғ��ł���ʂ̃o�C�I�f�B�[�[���R�����
�{���m�ۂł��Ȃ����Ƃ́A�펯�I�ɍl����Ζ��炩�ł���B����ɂ�������炸�A���y��ʏȁE�����ԋǁi����ʈ�
�S���������j�̐l�B���A�u�o�C�I�f�B�[�[���G���W���v���̗p������^�f�B�[�[���g���b�N�E�g���N�^���L�����y������
��^�f�B�[�[���g���b�N�E�g���N�^��CO2�팸����Ƃ̖ژ_����{�S����M�Ă���Ƃ���A�u���̍����v�Ƃ̌���
���ᔻ���Ă����R�ƍl������B
�@�����Ƃ��A���y��ʏȁE�����ԋǁi����ʈ��S���������j�̐l�B�́A��^�f�B�[�[���g���b�N�i��GVW�Q�O�`�Q�T�g
���j���^�f�B�[�[���g���N�^�́uCO2�r�o�̍팸�v�E�u��Y�f���i����R��j�v�ɂ��ẮA�u�ׂ��p�v�������̂ɁA��
�^�f�B�[�[���g���b�N�E�g���N�^���g���b�N�ݕ��A�������CO2�r�o�̑傫�ȕ������߂Ă��邱�Ƃɖڂ��Ԃ�A��^
�f�B�[�[���g���b�N�E�g���N�^��CO2�r�o������̂܂܂ɕ��u���Ă��A�킪���̉^�A����ɂ�����CO2�r�o�̍팸����
�\�Ƃ��钿��ȗ����������ʂ����Ƃ��Ă��邩���m��Ȃ��B�@���̂悤�ɁA��^�f�B�[�[���g���b�N�E�g���N�^��CO2�r
�o�팸�̂��߂Ɍ����J�����ׂ��Z�p���s���ł���Ƃ��āA�̐��Ƃ������A�o���ĉ��������ɗV��ŕ��
����ɂ������Ȃ��B�����Ŏd���Ȃ��A�E��ł̎��Ԓׂ����ł���悤�ɁA���y��ʏȁE�����ԋǂ́A�g���b�N�E�o
�X����́uCO2�r�o�̍팸�v�E�u��Y�f���i����R��j�v�ɖw��ǖ����Ȍ����J���ł��邱�Ƃ����m�̏�ŁA
�u���E���^�g���b�N�̓d�C�E�v���O�C���n�C�u���b�h�g���b�N�ƍ������n�C�u���b�h�g���b�N�v�A�u�����\�d���H���o
�X�v�A����сu�o�C�I�f�B�[�[���G���W���v�̋Z�p�̌����J�������y��ʏȁE�����ԋǂ���ʈ��S��������
�ɑ��Ďd���Ȃ����{�����Ă���\�����l������B���̏ꍇ�A���̏́A�e�i�� ���y��ʏȁE�����ԋǁj��
�q���i����ʈ��S���������j���@���悭�V���邽�߂ɁA�����i����10���~�j�Ȋߋ�i���u�������^�ԊJ���E����
�����i���Ɓi����23�N�x�`����26�N�x�j�v���W�F�N�g�v��^���Ă���悤�ȍ\�}�Ɍ����Ă��܂����A����͕M�҂�����
�Ό��ł��낤���B���ɂ��A���̂悤�Ȃ��Ƃ������ł���A������n���ɂ����s�ׂ̂悤�Ɏv�����A�@���Ȃ��̂ł��낤
���B
���j���^�f�B�[�[���g���N�^�́uCO2�r�o�̍팸�v�E�u��Y�f���i����R��j�v�ɂ��ẮA�u�ׂ��p�v�������̂ɁA��
�^�f�B�[�[���g���b�N�E�g���N�^���g���b�N�ݕ��A�������CO2�r�o�̑傫�ȕ������߂Ă��邱�Ƃɖڂ��Ԃ�A��^
�f�B�[�[���g���b�N�E�g���N�^��CO2�r�o������̂܂܂ɕ��u���Ă��A�킪���̉^�A����ɂ�����CO2�r�o�̍팸����
�\�Ƃ��钿��ȗ����������ʂ����Ƃ��Ă��邩���m��Ȃ��B�@���̂悤�ɁA��^�f�B�[�[���g���b�N�E�g���N�^��CO2�r
�o�팸�̂��߂Ɍ����J�����ׂ��Z�p���s���ł���Ƃ��āA�̐��Ƃ������A�o���ĉ��������ɗV��ŕ��
����ɂ������Ȃ��B�����Ŏd���Ȃ��A�E��ł̎��Ԓׂ����ł���悤�ɁA���y��ʏȁE�����ԋǂ́A�g���b�N�E�o
�X����́uCO2�r�o�̍팸�v�E�u��Y�f���i����R��j�v�ɖw��ǖ����Ȍ����J���ł��邱�Ƃ����m�̏�ŁA
�u���E���^�g���b�N�̓d�C�E�v���O�C���n�C�u���b�h�g���b�N�ƍ������n�C�u���b�h�g���b�N�v�A�u�����\�d���H���o
�X�v�A����сu�o�C�I�f�B�[�[���G���W���v�̋Z�p�̌����J�������y��ʏȁE�����ԋǂ���ʈ��S��������
�ɑ��Ďd���Ȃ����{�����Ă���\�����l������B���̏ꍇ�A���̏́A�e�i�� ���y��ʏȁE�����ԋǁj��
�q���i����ʈ��S���������j���@���悭�V���邽�߂ɁA�����i����10���~�j�Ȋߋ�i���u�������^�ԊJ���E����
�����i���Ɓi����23�N�x�`����26�N�x�j�v���W�F�N�g�v��^���Ă���悤�ȍ\�}�Ɍ����Ă��܂����A����͕M�҂�����
�Ό��ł��낤���B���ɂ��A���̂悤�Ȃ��Ƃ������ł���A������n���ɂ����s�ׂ̂悤�Ɏv�����A�@���Ȃ��̂ł��낤
���B
�@����Ƃ��A�ŋ߂̍��y��ʏȁE�����ԋǁi����ʈ��S���������j�̐l�B�́A��^�f�B�[�[���g���b�N�E�g���N�^�E�o
�X�i���d�ʎԁj��CO2�r�o�팸�ɂ��āA�ŏ����班���̊S�E�g�����������Ă��Ȃ��̂ł��낤���B���̏ꍇ�ɂ́A
���y��ʏȁE�����ԋǁi����ʈ��S���������j�l�B�́A��^�f�B�[�[���g���b�N�E�g���N�^��CO2�r�o�팸��
�w��ǖ����ł��邱�Ƃ�m��Ȃ���A�Ɩ��֘A�ł��邱�Ƃ𗝗R�ɍŋ߂̏�p�ԂŘb��́u�n�C�u���b�h����
�ԁv�A�u�d�C�E�v���O�C���n�C�u���b�h�����ԁv�A�u�d�C�����ԁv�A�u�o�C�I�R���v�̋Z�p���g���b�N�E�o�X�ɉ��p��
��u�������^�ԊJ���E���Ɖ����i���Ɓv�̃v���W�F�N�g�̌����J�����A�쎟�n�I�ȋ�������A���X�Ƃ��Ď�
�{���Ă���\��������B�����āA���̂悤�ȃv���W�F�N�g�ɑ��z�Ŗ�P�O���~���̑��z�̌����i���ŋ��j�𓊓�����
����̂ł���B���ɂ��A���̂悤�Ȃ��Ƃ������ł���A�E�����p�̋ɂ݂̂悤�Ɏv�����A�@���Ȃ��̂ł��낤���B
�X�i���d�ʎԁj��CO2�r�o�팸�ɂ��āA�ŏ����班���̊S�E�g�����������Ă��Ȃ��̂ł��낤���B���̏ꍇ�ɂ́A
���y��ʏȁE�����ԋǁi����ʈ��S���������j�l�B�́A��^�f�B�[�[���g���b�N�E�g���N�^��CO2�r�o�팸��
�w��ǖ����ł��邱�Ƃ�m��Ȃ���A�Ɩ��֘A�ł��邱�Ƃ𗝗R�ɍŋ߂̏�p�ԂŘb��́u�n�C�u���b�h����
�ԁv�A�u�d�C�E�v���O�C���n�C�u���b�h�����ԁv�A�u�d�C�����ԁv�A�u�o�C�I�R���v�̋Z�p���g���b�N�E�o�X�ɉ��p��
��u�������^�ԊJ���E���Ɖ����i���Ɓv�̃v���W�F�N�g�̌����J�����A�쎟�n�I�ȋ�������A���X�Ƃ��Ď�
�{���Ă���\��������B�����āA���̂悤�ȃv���W�F�N�g�ɑ��z�Ŗ�P�O���~���̑��z�̌����i���ŋ��j�𓊓�����
����̂ł���B���ɂ��A���̂悤�Ȃ��Ƃ������ł���A�E�����p�̋ɂ݂̂悤�Ɏv�����A�@���Ȃ��̂ł��낤���B
�@�Ƃ���ŁA�O�q�̂P�S�|�S���u��ʌ��̽��߰�ذ��ި���ٴݼ�����̔R�����v�ɏڏq���Ă���悤�ɁA����22
�N11��24�i���j�E25���i�j�ɊJ�Ấu��ʈ��S���������t�H�[�����Q�O�P�O�v�́u�X�[�p�[�N���[���f�B�[�[���iSCD�j
�G���W���ɂ�����V�W�J�v�Ƒ肵���u���ł́A�u�Q�i�V�[�P���V�����ߋ��@�v�A�u�����R�������[���i��260MPa�j�v�A�uLP-
EGR�̗̍p�ɂ��EGR����̍��x���v���̋Z�p��p���Ă��A��^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W����JE�O�T���[�h�R���
�R��́A0.5�`1.0�����x�̋͂��̉��P�������҂ł��Ȃ��Ƃ̔��\�ł������B���́u�X�[�p�[�N���[���f�B�[�[���iSCD�j
�G���W���v�̌����J���́A��ʈ��S���������̊֘A����w�ҁE���Ƃ̑S�����m�b���o�������A��^�g���b�N�p�f
�B�[�[���G���W���̃��[�h�R��̉��P�������ł���Ƃ̖ژ_���E�\�z�������Ď��{���ꂽ���̂Ɛ�������邪�A����
�����J���������Ɏ��s���Ă��܂������Ƃ�����22�N11���̍u���i��http://www.ntsel.go.jp/forum/2010files/10-06p.
pdf�j�Ŕ��\����Ă���B���̂悤�ɁA�u�X�[�p�[�N���[���f�B�[�[���iSCD�j�G���W���v�̌����J�������s�ɏI���������
�ɂ��A��ʈ��S���������̊w�ҁE���Ƃ̐l�B�́A�ނ�̋Z�p�͂ł͑�^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W���̏d��
�ԃ��[�h�R����P������ł��邱�Ƃ��A�g�������Ď��������̂ł͂Ȃ����낤���B
�N11��24�i���j�E25���i�j�ɊJ�Ấu��ʈ��S���������t�H�[�����Q�O�P�O�v�́u�X�[�p�[�N���[���f�B�[�[���iSCD�j
�G���W���ɂ�����V�W�J�v�Ƒ肵���u���ł́A�u�Q�i�V�[�P���V�����ߋ��@�v�A�u�����R�������[���i��260MPa�j�v�A�uLP-
EGR�̗̍p�ɂ��EGR����̍��x���v���̋Z�p��p���Ă��A��^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W����JE�O�T���[�h�R���
�R��́A0.5�`1.0�����x�̋͂��̉��P�������҂ł��Ȃ��Ƃ̔��\�ł������B���́u�X�[�p�[�N���[���f�B�[�[���iSCD�j
�G���W���v�̌����J���́A��ʈ��S���������̊֘A����w�ҁE���Ƃ̑S�����m�b���o�������A��^�g���b�N�p�f
�B�[�[���G���W���̃��[�h�R��̉��P�������ł���Ƃ̖ژ_���E�\�z�������Ď��{���ꂽ���̂Ɛ�������邪�A����
�����J���������Ɏ��s���Ă��܂������Ƃ�����22�N11���̍u���i��http://www.ntsel.go.jp/forum/2010files/10-06p.
pdf�j�Ŕ��\����Ă���B���̂悤�ɁA�u�X�[�p�[�N���[���f�B�[�[���iSCD�j�G���W���v�̌����J�������s�ɏI���������
�ɂ��A��ʈ��S���������̊w�ҁE���Ƃ̐l�B�́A�ނ�̋Z�p�͂ł͑�^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W���̏d��
�ԃ��[�h�R����P������ł��邱�Ƃ��A�g�������Ď��������̂ł͂Ȃ����낤���B
�@����ł��A��ʈ��S���������̊w�ҁE���Ƃ́A�ȒP�ɂ͒��߂��A���́u�X�[�p�[�N���[���f�B�[�[���iSCD�j�G
���W���v�ɍX�Ɂu�r�M�V�X�e���i���^�[�{�R���p�E���h�H�j�v����lj����邱�Ƃɂ���āA��^�g���b�N�p�f�B�[�[���G
���W���ɂ�����2015�N�x�d�ʎԔR���́{10���̔R������ڕW�Ƃ��錤���J����23�N�x�Ɏ��{����Ƃ�
���C�̐錾������22�N11���̍u���œ��X�ƍs���Ă����̂ł���B�������A�^�[�{�R���p�E���h�́A��^�g���b�N��
���s�R��̉��P������ȋZ�p���I�ɏڏq���Ă���悤�ɁA�^�[�{�R���p�E���h�́A�����A��^�g���b�N�p�f�B�[�[���G
���W���̍ő�g���N�̑���ɂ͗D�ꂽ���ʂ����邪�A�d�ʎԃ��[�h�R��̂P�����x�������P�ł��Ȃ��R����P
�@�\�̗��Z�p�ł���B�Ƃ��낪�A�����̌�ʈ��S���������̊w�ҁE���Ƃ́A�߂������ƂɁA�^�[�{�R���p�E���h
���d�ʎԃ��[�h�R������P����@�\�̗�邱�Ƃ𗝉����Ă��Ȃ������悤���B���̂��߁A��ʈ��S���������̊w
�ҁE���Ƃ�����22�N11���̍u���ł́A�u�X�[�p�[�N���[���f�B�[�[���iSCD�j�G���W���v�ɍX�Ɂu�r�M�V�X�e��
�i���^�[�{�R���p�E���h�H�j�v��lj����āu2015�N�x�d�ʎԔR���́{10���̔R������}��\��v�Ɛ錾���Ă���
�����悤�ł���B
���W���v�ɍX�Ɂu�r�M�V�X�e���i���^�[�{�R���p�E���h�H�j�v����lj����邱�Ƃɂ���āA��^�g���b�N�p�f�B�[�[���G
���W���ɂ�����2015�N�x�d�ʎԔR���́{10���̔R������ڕW�Ƃ��錤���J����23�N�x�Ɏ��{����Ƃ�
���C�̐錾������22�N11���̍u���œ��X�ƍs���Ă����̂ł���B�������A�^�[�{�R���p�E���h�́A��^�g���b�N��
���s�R��̉��P������ȋZ�p���I�ɏڏq���Ă���悤�ɁA�^�[�{�R���p�E���h�́A�����A��^�g���b�N�p�f�B�[�[���G
���W���̍ő�g���N�̑���ɂ͗D�ꂽ���ʂ����邪�A�d�ʎԃ��[�h�R��̂P�����x�������P�ł��Ȃ��R����P
�@�\�̗��Z�p�ł���B�Ƃ��낪�A�����̌�ʈ��S���������̊w�ҁE���Ƃ́A�߂������ƂɁA�^�[�{�R���p�E���h
���d�ʎԃ��[�h�R������P����@�\�̗�邱�Ƃ𗝉����Ă��Ȃ������悤���B���̂��߁A��ʈ��S���������̊w
�ҁE���Ƃ�����22�N11���̍u���ł́A�u�X�[�p�[�N���[���f�B�[�[���iSCD�j�G���W���v�ɍX�Ɂu�r�M�V�X�e��
�i���^�[�{�R���p�E���h�H�j�v��lj����āu2015�N�x�d�ʎԔR���́{10���̔R������}��\��v�Ɛ錾���Ă���
�����悤�ł���B
�@�����A�u�r�M�V�X�e���i���^�[�{�R���p�E���h�H�j�v�ɂ�����d�ʎԃ��[�h�R��̉��P�̋@�\����邱�Ƃ𗝉���
�Ă��Ȃ�������ʈ��S���������̊w�ҁE���Ƃ́A�m���s���̂��߂Ƃ͉]���A���Ƃ��p�����������Ƃ��������Ă�
�܂��Ă������̂��B���̌�A��ʈ��S���������ł́A���ۂɁu�r�M�V�X�e���i���^�[�{�R���p�E���h�H�j�v���
�����Ă��u�X�[�p�[�N���[���f�B�[�[���iSCD�j�G���W���v�̌����J���́A�����Ŏ��ۂɏ\���ȔR����P���ł��Ȃ�����
�̂��A�Ⴕ���́A�����r���ł̕s�����C�t�����̂��͕s���ł��邪�A�d�ʎԃ��[�h�R��̉��P�Ɏ��s�������̂Ɛ�
�@�����B����́A����26�N3�����݂ł��A�u�r�M�V�X�e���i���^�[�{�R���p�E���h�H�j�v��lj������u�X�[�p�[�N��
�[���f�B�[�[���iSCD�j�G���W���v�ɂ���āA2015�N�x�d�ʎԔR���́{10���̔R������B�������Ƃ̔��\���s
���Ă��Ȃ����Ƃ�������炩�ł͂Ȃ����낤���B�܂�A��ʈ��S���������́A�u�r�M�V�X�e���i���^�[�{�R
���p�E���h�H�j�v�ɂ���^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W���̔R����\���ɉ��P���邱�Ƃ�����ł��邱�Ƃ�F��������
�̂Ɛ��������B���̂��Ƃ́A�M�҂ɂƂ��Ă͓��R�̌��ʂƍl�����邪�A��ʈ��S���������̊w�ҁE���Ƃɂ�
���Ă͑����ȏՌ��ł������̂ł͖������낤���B����ɂ���āA��ʈ��S���������̊w�ҁE���Ƃ́A�ނ�̒m��
�������̒m����Z�p�͂������Ă��A��^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W���̏d�ʎԃ��[�h�R��̏\���ȉ��P����
��ł��邱�Ƃ�ɐɎv���m�����\�����l������B���ɁA���ꂪ�����ł���A���Ƃ�����Ȃ��Ƃł͂Ȃ����낤
���B
�Ă��Ȃ�������ʈ��S���������̊w�ҁE���Ƃ́A�m���s���̂��߂Ƃ͉]���A���Ƃ��p�����������Ƃ��������Ă�
�܂��Ă������̂��B���̌�A��ʈ��S���������ł́A���ۂɁu�r�M�V�X�e���i���^�[�{�R���p�E���h�H�j�v���
�����Ă��u�X�[�p�[�N���[���f�B�[�[���iSCD�j�G���W���v�̌����J���́A�����Ŏ��ۂɏ\���ȔR����P���ł��Ȃ�����
�̂��A�Ⴕ���́A�����r���ł̕s�����C�t�����̂��͕s���ł��邪�A�d�ʎԃ��[�h�R��̉��P�Ɏ��s�������̂Ɛ�
�@�����B����́A����26�N3�����݂ł��A�u�r�M�V�X�e���i���^�[�{�R���p�E���h�H�j�v��lj������u�X�[�p�[�N��
�[���f�B�[�[���iSCD�j�G���W���v�ɂ���āA2015�N�x�d�ʎԔR���́{10���̔R������B�������Ƃ̔��\���s
���Ă��Ȃ����Ƃ�������炩�ł͂Ȃ����낤���B�܂�A��ʈ��S���������́A�u�r�M�V�X�e���i���^�[�{�R
���p�E���h�H�j�v�ɂ���^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W���̔R����\���ɉ��P���邱�Ƃ�����ł��邱�Ƃ�F��������
�̂Ɛ��������B���̂��Ƃ́A�M�҂ɂƂ��Ă͓��R�̌��ʂƍl�����邪�A��ʈ��S���������̊w�ҁE���Ƃɂ�
���Ă͑����ȏՌ��ł������̂ł͖������낤���B����ɂ���āA��ʈ��S���������̊w�ҁE���Ƃ́A�ނ�̒m��
�������̒m����Z�p�͂������Ă��A��^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W���̏d�ʎԃ��[�h�R��̏\���ȉ��P����
��ł��邱�Ƃ�ɐɎv���m�����\�����l������B���ɁA���ꂪ�����ł���A���Ƃ�����Ȃ��Ƃł͂Ȃ����낤
���B
�@���͂Ƃ�����A���y��ʏȁE�����ԋǁi����ʈ��S���������j�̊w�ҁE���Ƃ̐l�B�́A����22�N11���̏���
��ɂ́A�ނ玩�g����^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W���̏d�ʎԃ��[�h�R��̉��P���Z�p�I�Ɋ��S�Ɂu��l�܂�v��
�Ɋׂ��Ă����悤�ł���B���̂��߁A���y��ʏȁE�����ԋǁi����ʈ��S���������j�́A�u�X�[�p�[�N���[
���f�B�[�[���iSCD�j�G���W���v�ł̏d�ʎԃ��[�h�R��̉��P�̕s�������u���Ŕ��\��������22�N11���̏���
��ɂ́A�J����^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W�����̂̉��P�ɂ���d�ʎԃ��[�h�R��̌���Ɏ��g�ނ��Ƃ�
�L�b�p���ƒ��߂����Ƃɂ����̂ł͂Ȃ����Ɛ��������B�����āA���y��ʏȁE�����ԋǁi����ʈ��S������
���j�́A����23�N�x�\�Z�T�v�i��http://www.mlit.go.jp/common/000147904.pdf�j���疾�炩�Ȃ悤�ɁA��
�^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W���̉��ǂɂ��d�ʎԃ��[�h�R��̉��P�̌����J�������S�ɕ������A�A����23
�N�x�`����26�N�x�̂S�N�Ԃ̌v��Łu���E���^�g���b�N�̓d�C�E�v���O�C���n�C�u���b�h�g���b�N�v�A�u���E���^�g��
�b�N�̍������n�C�u���b�h�g���b�N�v�A�u�����\�d���H���o�X�v�A����сu�o�C�I�f�B�[�[���G���W���v���̎ԗ���
�W�����Z�p��A�o�C�I�f�B�[�[���R���i���E�y���j�ɊW�����Z�p�ɂ��A���{�̉^�A����́uCO2�r�o��
�팸�v�E�u��Y�f���i����R��j�v��}�邱�Ƃɕ��j�̕ύX���s�����\�����l������B
��ɂ́A�ނ玩�g����^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W���̏d�ʎԃ��[�h�R��̉��P���Z�p�I�Ɋ��S�Ɂu��l�܂�v��
�Ɋׂ��Ă����悤�ł���B���̂��߁A���y��ʏȁE�����ԋǁi����ʈ��S���������j�́A�u�X�[�p�[�N���[
���f�B�[�[���iSCD�j�G���W���v�ł̏d�ʎԃ��[�h�R��̉��P�̕s�������u���Ŕ��\��������22�N11���̏���
��ɂ́A�J����^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W�����̂̉��P�ɂ���d�ʎԃ��[�h�R��̌���Ɏ��g�ނ��Ƃ�
�L�b�p���ƒ��߂����Ƃɂ����̂ł͂Ȃ����Ɛ��������B�����āA���y��ʏȁE�����ԋǁi����ʈ��S������
���j�́A����23�N�x�\�Z�T�v�i��http://www.mlit.go.jp/common/000147904.pdf�j���疾�炩�Ȃ悤�ɁA��
�^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W���̉��ǂɂ��d�ʎԃ��[�h�R��̉��P�̌����J�������S�ɕ������A�A����23
�N�x�`����26�N�x�̂S�N�Ԃ̌v��Łu���E���^�g���b�N�̓d�C�E�v���O�C���n�C�u���b�h�g���b�N�v�A�u���E���^�g��
�b�N�̍������n�C�u���b�h�g���b�N�v�A�u�����\�d���H���o�X�v�A����сu�o�C�I�f�B�[�[���G���W���v���̎ԗ���
�W�����Z�p��A�o�C�I�f�B�[�[���R���i���E�y���j�ɊW�����Z�p�ɂ��A���{�̉^�A����́uCO2�r�o��
�팸�v�E�u��Y�f���i����R��j�v��}�邱�Ƃɕ��j�̕ύX���s�����\�����l������B
�@���̂悤�ɁA���y��ʏȁE�����ԋǁi����ʈ��S���������j�̊w�ҁE���Ƃ̐l�B�́A����23�N�x�ȍ~���猻��
�Ɏ���܂ŁA���s�̃g���b�N�ݕ��A���̎�͓��͌��ł���f�B�[�[���G���W���̏d�ʎԃ��[�h�R������P����̐S�v
�̌����J�������S�ɕ������Ă��܂����悤�ł���B���̂悤�ɁA���y��ʏȁE�����ԋǁi����ʈ��S���������j�́A
����23�N�x�����ɂ̓f�B�[�[���G���W���̏d�ʎԃ��[�h�R������P���錤���J����������Ă��܂������Ƃɂ��A�g
���b�N�E�o�X�p(���d�ʎԗp�j�̃f�B�[�[���G���W���ɂ�����d�ʎԃ��[�h�R��̉��P�Ɋւ��鍑�y��ʏȁE�����ԋ�
�̍ŋ߂̎��O�̎����f�[�^�����F���ɂȂ��Ă��܂��Ă��邱�Ƃł���B���̂��߁A���y��ʏȁE�����ԋǂ́A�߂�
������2015�N�x�d�ʎԔR���̋�������������ۂɂ́A�g���b�N���[�J�̎����f�[�^��ӌ����\�b�N����
�̂܂܉L�ۂ݂ɂ��A�g���b�N���[�J�̎咣�ɉ�����2015�N�x�d�ʎԔR������������V�����d�ʎԔR���
����ݒ肹����Ȃ��Ɋׂ��Ă��܂����ꂪ�����ɂ���ƍl������B�܂�A���y��ʏȁE�����ԋ�
�́A�߂�������2015�N�x�d�ʎԔR����K�ȃ��x���ɋ�������藧�Ă������Ă��܂��Ă���̂ł͂Ȃ�
���Ɗ뜜�����̂ł���B���ɁA���ꂪ�����ł���A���y��ʏȁE�����ԋǂ��{���̐E����^�����ɐ��s����
�@�\���r�����Ă���悤�Ɏv���邪�A�A�@���Ȃ��̂ł��낤���B
�Ɏ���܂ŁA���s�̃g���b�N�ݕ��A���̎�͓��͌��ł���f�B�[�[���G���W���̏d�ʎԃ��[�h�R������P����̐S�v
�̌����J�������S�ɕ������Ă��܂����悤�ł���B���̂悤�ɁA���y��ʏȁE�����ԋǁi����ʈ��S���������j�́A
����23�N�x�����ɂ̓f�B�[�[���G���W���̏d�ʎԃ��[�h�R������P���錤���J����������Ă��܂������Ƃɂ��A�g
���b�N�E�o�X�p(���d�ʎԗp�j�̃f�B�[�[���G���W���ɂ�����d�ʎԃ��[�h�R��̉��P�Ɋւ��鍑�y��ʏȁE�����ԋ�
�̍ŋ߂̎��O�̎����f�[�^�����F���ɂȂ��Ă��܂��Ă��邱�Ƃł���B���̂��߁A���y��ʏȁE�����ԋǂ́A�߂�
������2015�N�x�d�ʎԔR���̋�������������ۂɂ́A�g���b�N���[�J�̎����f�[�^��ӌ����\�b�N����
�̂܂܉L�ۂ݂ɂ��A�g���b�N���[�J�̎咣�ɉ�����2015�N�x�d�ʎԔR������������V�����d�ʎԔR���
����ݒ肹����Ȃ��Ɋׂ��Ă��܂����ꂪ�����ɂ���ƍl������B�܂�A���y��ʏȁE�����ԋ�
�́A�߂�������2015�N�x�d�ʎԔR����K�ȃ��x���ɋ�������藧�Ă������Ă��܂��Ă���̂ł͂Ȃ�
���Ɗ뜜�����̂ł���B���ɁA���ꂪ�����ł���A���y��ʏȁE�����ԋǂ��{���̐E����^�����ɐ��s����
�@�\���r�����Ă���悤�Ɏv���邪�A�A�@���Ȃ��̂ł��낤���B
�@�Ȃ��A�ȏ�̂悤�Ȍ����́A�M�҂����̕Ό������m��Ȃ��B�������Ȃ���A�����_�ō��y��ʏȁE�����ԋǁi��
��ʈ��S���������j�́A�s�s�ԉݕ��A���̎�͂ł����^�f�B�[�[���g���b�N�i��GVW�Q�O�`�Q�T�g���j���
�^�f�B�[�[���g���N�^�́uCO2�r�o�̍팸�i���R����P�j�v�̎��p�I�ȋZ�p�J����w��lj������{�����A����
23�N�x�`����26�N�x�̊ԂɁA�u���E���^�g���b�N�̓d�C�E�v���O�C���n�C�u���b�h�g���b�N�ƍ������n�C�u���b�h�g
���b�N�v�A�u�����\�d���H���o�X�v�A����сu�o�C�I�f�B�[�[���G���W���v�̂悤�ȁA���{�̋߂������ɂ�����g��
�b�N�E�o�X�i���d�ʎԁj�́uCO2�r�o�̍팸�i���R����P�j�v��E�Ζ��ɖw��Ǎv���ł��Ȃ��Z�p�J���ł����
��������炸�A���̌����J���ɍ��y��ʏȁE�����ԋǂ��C�O�ǂ���P�O���~���̑��z�̐ŋ��ʂɓ�����
�Ă����悤�Ɏv���Ďd���������̂ł���B�����āA���̂悤�ȏ�悵�Ă���̂́A���݂̍��y��ʏȁE������
�ǁi����ʈ��S���������j�̌����J�����A���{�̉^�A����́uCO2�r�o�̍팸�v�E�u��Y�f���i����R��j�v����
�сu�E�Ζ��v�������ł��i�W�����悤�Ƃ���ӎv�E�ӗ~�������Ȃ��l�B�ɂ���Đ��i����Ă��邱�Ƃ������̂悤�Ɏv��
�邪�A����͕M�҂����̕��������ł��낤���B
��ʈ��S���������j�́A�s�s�ԉݕ��A���̎�͂ł����^�f�B�[�[���g���b�N�i��GVW�Q�O�`�Q�T�g���j���
�^�f�B�[�[���g���N�^�́uCO2�r�o�̍팸�i���R����P�j�v�̎��p�I�ȋZ�p�J����w��lj������{�����A����
23�N�x�`����26�N�x�̊ԂɁA�u���E���^�g���b�N�̓d�C�E�v���O�C���n�C�u���b�h�g���b�N�ƍ������n�C�u���b�h�g
���b�N�v�A�u�����\�d���H���o�X�v�A����сu�o�C�I�f�B�[�[���G���W���v�̂悤�ȁA���{�̋߂������ɂ�����g��
�b�N�E�o�X�i���d�ʎԁj�́uCO2�r�o�̍팸�i���R����P�j�v��E�Ζ��ɖw��Ǎv���ł��Ȃ��Z�p�J���ł����
��������炸�A���̌����J���ɍ��y��ʏȁE�����ԋǂ��C�O�ǂ���P�O���~���̑��z�̐ŋ��ʂɓ�����
�Ă����悤�Ɏv���Ďd���������̂ł���B�����āA���̂悤�ȏ�悵�Ă���̂́A���݂̍��y��ʏȁE������
�ǁi����ʈ��S���������j�̌����J�����A���{�̉^�A����́uCO2�r�o�̍팸�v�E�u��Y�f���i����R��j�v����
�сu�E�Ζ��v�������ł��i�W�����悤�Ƃ���ӎv�E�ӗ~�������Ȃ��l�B�ɂ���Đ��i����Ă��邱�Ƃ������̂悤�Ɏv��
�邪�A����͕M�҂����̕��������ł��낤���B
�@�����Ƃ��A���̂悤�ȍ��y��ʏȁE�����ԋǁi����ʈ��S���������j�́u�������^�ԊJ���E���Ɖ����i���Ɓv��
�̂���v���W�F�N�g�̐��s�ɂ��A�\�Z�i���ŋ��j�̖��ʌ����Ǝv�����s�ׂ�����27�N3�����܂ő����̂ł���B�����
���č����̗��ꂩ�猾�킹�ĖႦ�A���y��ʏȁE�����ԋǁi����ʈ��S���������j�� �o���邾����������
�Ɂu�������^�ԊJ���E���Ɖ����i���Ɓv�Ə̂���v���W�F�N�g�𒆎~���A�ŋ��̖��ʌ����v�����s�ׂ𑁋}�Ɏ~��
�ė~�������̂ł���B������A�����̍����́A��J���Đŋ���[�߂Ă���̂ł���B���̂��߁A���y��ʏȁE�����ԋ�
�i����ʈ��S���������j�̐l�B�́A��ɐŋ��ɗL�����p�ɗ��ӂ��ׂ��Ǝv�����A�@���Ȃ��̂ł��낤���B
�̂���v���W�F�N�g�̐��s�ɂ��A�\�Z�i���ŋ��j�̖��ʌ����Ǝv�����s�ׂ�����27�N3�����܂ő����̂ł���B�����
���č����̗��ꂩ�猾�킹�ĖႦ�A���y��ʏȁE�����ԋǁi����ʈ��S���������j�� �o���邾����������
�Ɂu�������^�ԊJ���E���Ɖ����i���Ɓv�Ə̂���v���W�F�N�g�𒆎~���A�ŋ��̖��ʌ����v�����s�ׂ𑁋}�Ɏ~��
�ė~�������̂ł���B������A�����̍����́A��J���Đŋ���[�߂Ă���̂ł���B���̂��߁A���y��ʏȁE�����ԋ�
�i����ʈ��S���������j�̐l�B�́A��ɐŋ��ɗL�����p�ɗ��ӂ��ׂ��Ǝv�����A�@���Ȃ��̂ł��낤���B
�@�Ƃ���ŁA�M�҂̃z�[���y�[�W���f�B�[�[���ɔ�ׂP�T���̂b�n�Q�팸���\�Ȃc�c�e�G���W���ADDF�^�]�ƃf�B�[�[
���^�]�̑I�����\�Ȃc�c�e��^�g���b�N �A��^�g���b�N�́u�b�n2�팸�v�Ɓu�E�Ζ��v�̋Z�p�́A�����ɕs�����H�A�C��
�x�~�́A�f�B�[�[���̂m�n���팸�ƔR�����̈ꋓ�����̋Z�p���I���̃y�[�W�ł́A�߂������ɓ��{�̉^�A�����
�uCO2�r�o�̍팸�v�E�u��Y�f���i����R��j�v��e�ՂɎ����ł����i�E�Z�p�Ƃ��āA�C���x�~�G���W���i�������J
2005-54771�j�̃f�B�[�[���C���x�~�̋Z�p��A������DDF�G���W���i�������J2008-51121�j��DDF�G���W���̋Z�p��
��Ă��Ă���B�����̋Z�p�����p�����邱�Ƃɂ���āA��^�f�B�[�[���g���b�N�ɂ�����CO2�̑啝�ȍ팸���e�Ղ�
�����ł���̂ł���B�Ƃ��낪�A���y��ʏȁi����ʈ��S���������j�̐l�B�́A�f�B�[�[���g���b�N�E�g���N�^�E�o�X��
�����āACO2�̑啝�ȍ팸���e�ՂɎ����ł����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j��ACO2�̍팸�ƒE�Ζ�
���ɉ\�ɂ���������DDF�G���W���i�������J2008-51121�j��DDF�G���W���̋Z�p���Ă��Ă���B�����̋Z
�p�����p�����邱�Ƃɂ���āA��^�f�B�[�[���g���b�N�ɂ�����CO2�̑啝�ȍ팸���e�ՂɎ����ł���̂ł���B�Ƃ�
�낪�A���y��ʏȁi����ʈ��S���������j�̐l�B�́A�f�B�[�[���g���b�N�E�g���N�^�E�o�X�ɂ����āACO2�̑�
���ȍ팸���e�ՂɎ����ł����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j��ACO2�̍팸�ƒE�Ζ�����
�\�ɂ���������DDF�G���W���i�������J2008-51121�j�̓����Z�p����Ȃɖ����E�َE���Ă���悤���B ��
��́A�M�҂̂悤�Ȉ�ʐl�̒�Ă���Z�p�������J�����邱�Ƃ́A���ƂƂ��Ắu�ւ�v��u�����S�v�ɏ�������
��A�u�p�v�������Ƃ̎v�����琶�����s���̂悤�Ɏv���邪�A�@���Ȃ��̂ł��낤���B
���^�]�̑I�����\�Ȃc�c�e��^�g���b�N �A��^�g���b�N�́u�b�n2�팸�v�Ɓu�E�Ζ��v�̋Z�p�́A�����ɕs�����H�A�C��
�x�~�́A�f�B�[�[���̂m�n���팸�ƔR�����̈ꋓ�����̋Z�p���I���̃y�[�W�ł́A�߂������ɓ��{�̉^�A�����
�uCO2�r�o�̍팸�v�E�u��Y�f���i����R��j�v��e�ՂɎ����ł����i�E�Z�p�Ƃ��āA�C���x�~�G���W���i�������J
2005-54771�j�̃f�B�[�[���C���x�~�̋Z�p��A������DDF�G���W���i�������J2008-51121�j��DDF�G���W���̋Z�p��
��Ă��Ă���B�����̋Z�p�����p�����邱�Ƃɂ���āA��^�f�B�[�[���g���b�N�ɂ�����CO2�̑啝�ȍ팸���e�Ղ�
�����ł���̂ł���B�Ƃ��낪�A���y��ʏȁi����ʈ��S���������j�̐l�B�́A�f�B�[�[���g���b�N�E�g���N�^�E�o�X��
�����āACO2�̑啝�ȍ팸���e�ՂɎ����ł����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j��ACO2�̍팸�ƒE�Ζ�
���ɉ\�ɂ���������DDF�G���W���i�������J2008-51121�j��DDF�G���W���̋Z�p���Ă��Ă���B�����̋Z
�p�����p�����邱�Ƃɂ���āA��^�f�B�[�[���g���b�N�ɂ�����CO2�̑啝�ȍ팸���e�ՂɎ����ł���̂ł���B�Ƃ�
�낪�A���y��ʏȁi����ʈ��S���������j�̐l�B�́A�f�B�[�[���g���b�N�E�g���N�^�E�o�X�ɂ����āACO2�̑�
���ȍ팸���e�ՂɎ����ł����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j��ACO2�̍팸�ƒE�Ζ�����
�\�ɂ���������DDF�G���W���i�������J2008-51121�j�̓����Z�p����Ȃɖ����E�َE���Ă���悤���B ��
��́A�M�҂̂悤�Ȉ�ʐl�̒�Ă���Z�p�������J�����邱�Ƃ́A���ƂƂ��Ắu�ւ�v��u�����S�v�ɏ�������
��A�u�p�v�������Ƃ̎v�����琶�����s���̂悤�Ɏv���邪�A�@���Ȃ��̂ł��낤���B
�X�ɁA�M�҂́u�Ό��H�v�E�u�ϑz�H�v�𗦒��Ɍ��킹�ĖႦ�A��^�f�B�[�[���g���b�N�E�g���N�^�E�o�X�ɂ�����uCO2��
���i����R��j�v�ƁoNO���팸�v�ɗL�����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j��ACO2�팸�ƒE�Ζ�����
�\�ɂ���������DDF�G���W���i�������J2008-51121�j�̓����Z�p����Ȃɖ����E�َE���Ȃ���A�킪���̉^�A��
��́u��Y�f���i����R��j�v�Ɓu�r�o�K�X�ጸ�v�ɖw��NJ�^�ł��Ȃ��u�������^�ԊJ���E���Ɖ����i���Ɓi��
��23�N�x�`����26�N�x�j�v�̃v���W�F�N�g�ɖ�P�O���~���̑��z�̐ŋ��𓊓����鍑�y��ʏȁE�����ԋǁi����ʈ�
�S���������j�̍s���́A�킪���̉^�A����ɂ�����u��Y�f���i����R��j�v�Ɓu�r�o�K�X�ጸ�v���߂������Ɏ�
���ł���Ƃ̊��҂������Ɏ������邽�߂̒P�Ȃ鍼�\�I�ȍs�ׂ̂悤�Ɏv����̂ł���B���̊m���ȏ؋����
�邱�Ƃ́A�����_�ł͍���ł���B�������A���{�����ɂ����āA�u���E���^�g���b�N�̓d�C�E�v���O�C���n�C�u���b�h
�g���b�N�v�A�u���E���^�g���b�N�̍������n�C�u���b�h�g���b�N�v�A�u�����\�d���H���o�X�v�A����сu�o�C�I�f�B�[�[
���G���W���̃g���b�N�E�o�X�v�̑��䐔�́A�g���b�N�E�o�X�S�̂̋͂��Ȋ����̑䐔������߂Ă��Ȃ���������
���I�Ɍ��������鎞������������Ɨ\�������B���̎����������������_�ŁA���y��ʏȁE�����ԋǁi����
�ʈ��S���������j�́u�������^�ԊJ���E���Ɖ����i���Ɓi����23�N�x�`����26�N�x�j�v�̖ژ_�����A��
���ɔj�]�������Ƃ�N�����m�F�ł���ƍl������B�������A����ł́A�킪���̉^�A����ɂ�����u��Y�f���i��
��R��j�v�A�u�r�o�K�X�ጸ�v�A�u�E�Ζ��v�́A�u�����łɒx���I�v�ƂȂ�A�u����旧�����I�v�̎c�O�ȏɊׂ邱��
�ɂȂ�ƍl������B
���i����R��j�v�ƁoNO���팸�v�ɗL�����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j��ACO2�팸�ƒE�Ζ�����
�\�ɂ���������DDF�G���W���i�������J2008-51121�j�̓����Z�p����Ȃɖ����E�َE���Ȃ���A�킪���̉^�A��
��́u��Y�f���i����R��j�v�Ɓu�r�o�K�X�ጸ�v�ɖw��NJ�^�ł��Ȃ��u�������^�ԊJ���E���Ɖ����i���Ɓi��
��23�N�x�`����26�N�x�j�v�̃v���W�F�N�g�ɖ�P�O���~���̑��z�̐ŋ��𓊓����鍑�y��ʏȁE�����ԋǁi����ʈ�
�S���������j�̍s���́A�킪���̉^�A����ɂ�����u��Y�f���i����R��j�v�Ɓu�r�o�K�X�ጸ�v���߂������Ɏ�
���ł���Ƃ̊��҂������Ɏ������邽�߂̒P�Ȃ鍼�\�I�ȍs�ׂ̂悤�Ɏv����̂ł���B���̊m���ȏ؋����
�邱�Ƃ́A�����_�ł͍���ł���B�������A���{�����ɂ����āA�u���E���^�g���b�N�̓d�C�E�v���O�C���n�C�u���b�h
�g���b�N�v�A�u���E���^�g���b�N�̍������n�C�u���b�h�g���b�N�v�A�u�����\�d���H���o�X�v�A����сu�o�C�I�f�B�[�[
���G���W���̃g���b�N�E�o�X�v�̑��䐔�́A�g���b�N�E�o�X�S�̂̋͂��Ȋ����̑䐔������߂Ă��Ȃ���������
���I�Ɍ��������鎞������������Ɨ\�������B���̎����������������_�ŁA���y��ʏȁE�����ԋǁi����
�ʈ��S���������j�́u�������^�ԊJ���E���Ɖ����i���Ɓi����23�N�x�`����26�N�x�j�v�̖ژ_�����A��
���ɔj�]�������Ƃ�N�����m�F�ł���ƍl������B�������A����ł́A�킪���̉^�A����ɂ�����u��Y�f���i��
��R��j�v�A�u�r�o�K�X�ጸ�v�A�u�E�Ζ��v�́A�u�����łɒx���I�v�ƂȂ�A�u����旧�����I�v�̎c�O�ȏɊׂ邱��
�ɂȂ�ƍl������B
�@���̂悤�ȏɊׂ邱�Ƃ��o���邾�������ɉ������őP�̕��@�E����́A�o���邾���������u�C���x�~�G���W
���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p���̗p������^�f�B�[�[���g���b�N�v��A�u������DDF�G���W���i������
�J2008-51121�j�̓����Z�p���̗p����DDF��^�g���b�N�v�𑁊��Ɏ��p�����邱�Ƃł���B�����̐V�Z�p��
���A���{�̑�^�g���b�N�E�g���N�^�E�o�X�̕���ɂ�����uCO2�팸�i����Y�f���E��R��j�v��u�E�Ζ��i��
��^�g���b�N�p�R���ɓV�R�K�X�̎g�p�j�v���e�ՂɎ����ł���̂ł���B���̂��߁A���y��ʏȁE�����ԋ�
�i����ʈ��S���������j�́A�u�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p�̗p������^�f�B�[�[
���g���b�N�v��A�u������DDF�G���W���i�������J2008-51121�j�̓����Z�p���̗p����DDF��^�g���b�N�v�̌�
���J���𑁊��ɊJ�n���A���{�ɂ������^�g���b�N�ɂ�����uCO2�팸�i����Y�f���E��R��j�v��u�E�Ζ��v
�𑣐i���ė~�������̂ł���B
���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p���̗p������^�f�B�[�[���g���b�N�v��A�u������DDF�G���W���i������
�J2008-51121�j�̓����Z�p���̗p����DDF��^�g���b�N�v�𑁊��Ɏ��p�����邱�Ƃł���B�����̐V�Z�p��
���A���{�̑�^�g���b�N�E�g���N�^�E�o�X�̕���ɂ�����uCO2�팸�i����Y�f���E��R��j�v��u�E�Ζ��i��
��^�g���b�N�p�R���ɓV�R�K�X�̎g�p�j�v���e�ՂɎ����ł���̂ł���B���̂��߁A���y��ʏȁE�����ԋ�
�i����ʈ��S���������j�́A�u�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p�̗p������^�f�B�[�[
���g���b�N�v��A�u������DDF�G���W���i�������J2008-51121�j�̓����Z�p���̗p����DDF��^�g���b�N�v�̌�
���J���𑁊��ɊJ�n���A���{�ɂ������^�g���b�N�ɂ�����uCO2�팸�i����Y�f���E��R��j�v��u�E�Ζ��v
�𑣐i���ė~�������̂ł���B
�Q�P�@��^�g���b�N�i���d�ʎԁj��2015�N�x�R���̋����̃��x��
�@���݁A���y��ʏȂŌ�������Ă���u�d�ʎԁi����^�̃g���b�N�E�o�X���j�v�́u2015�N�x�R���v�����������V��
�ȔR���̃��x���́A�M�҂̌l�I�ȗ\�z�ł́A�T�����x�̔R����P���v���������̂Ɛ��������B��������
�ꍇ�A�\�Q�U�Ɏ������������R�c��̑�\�����\�ɋL�ڂ̑�^�g���b�N�i���d�ʎԁj�̔R����P�Z�p��A�\�S�P��
���������P�Z�p���A���s�R���d�ʎԃ��[�h�R������P�ł���@�\�E���\�̗��u�K���N�^�Z�p�v��u�|���R�c�Z�p�v
�𐔑����g�ݍ��킹�邱�Ƃɂ�����Đh�����ĂT�����x�̔R����P�������ł����Ƃ��Ă��A���̑�^�g���b�N�i���d��
�ԁj�́A�c��ȃR�X�g�A�b�v�̂��߂Ɏ��p���̑S���������̂ɂȂ邱�Ƃ����炩���B
�ȔR���̃��x���́A�M�҂̌l�I�ȗ\�z�ł́A�T�����x�̔R����P���v���������̂Ɛ��������B��������
�ꍇ�A�\�Q�U�Ɏ������������R�c��̑�\�����\�ɋL�ڂ̑�^�g���b�N�i���d�ʎԁj�̔R����P�Z�p��A�\�S�P��
���������P�Z�p���A���s�R���d�ʎԃ��[�h�R������P�ł���@�\�E���\�̗��u�K���N�^�Z�p�v��u�|���R�c�Z�p�v
�𐔑����g�ݍ��킹�邱�Ƃɂ�����Đh�����ĂT�����x�̔R����P�������ł����Ƃ��Ă��A���̑�^�g���b�N�i���d��
�ԁj�́A�c��ȃR�X�g�A�b�v�̂��߂Ɏ��p���̑S���������̂ɂȂ邱�Ƃ����炩���B
�@����ɑ��A�u2015�N�x�R���v���T�`�P�O�� ���x�̔R����P�����߂������V���ȁu�d�ʎԁi�g���b�N�A�o�X���j��
�R���v�ɓK��������ꍇ�A�c��ȃR�X�g�A�b�v���������ƂȂ��e�ՂɓK�������邱�Ƃ̂ł���Z�p�́A�����_�ł��Q
�^�[�{�����̋C���x�~�V�X�e���i���C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�j�̓����Z�p�ȊO�ɖ����Ɛ�������
��B���������āA���y��ʏȂ��߂������i��2014�N�`2015�N���j�Ɂu�d�ʎԁi�g���b�N�A�o�X���j�v�ɂ��Ắu2015�N�d
�ʎԓx�R���v�����������V���ȁu�d�ʎԔR���v��ݒ�E���\�����ꍇ�ɂ́A�u���V�G�B�V�[�C�[�̑O�������
���@���@�F�O���v�A�u�������R�c��E��C������E�����Ԕr�o�K�X���ψ���v�A�u����c��w�@�吹�����v�A
����сu���쎩���ԇ��̉��� �^ �ꖱ������v���܂ޓ��{���\����f�B�[�[���G���W���W�̊w�ҁE���ƁE�Z�p
�҂́A����܂ł́u�C���x�~�V�X�e���v���E�َE����s�ׁE��������ĂɎ��~�߁A�u���Ɂu�N�q�^�ρv���A�Q�^�[
�{�����̋C���x�~�V�X�e���i���C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�j���J�����邱�Ƃ��ȑO����ϋɓI�ɐ���
���Ă������̂悤�Ȕ����E���\�ɑ�]��������̂Ɛ��������B
�R���v�ɓK��������ꍇ�A�c��ȃR�X�g�A�b�v���������ƂȂ��e�ՂɓK�������邱�Ƃ̂ł���Z�p�́A�����_�ł��Q
�^�[�{�����̋C���x�~�V�X�e���i���C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�j�̓����Z�p�ȊO�ɖ����Ɛ�������
��B���������āA���y��ʏȂ��߂������i��2014�N�`2015�N���j�Ɂu�d�ʎԁi�g���b�N�A�o�X���j�v�ɂ��Ắu2015�N�d
�ʎԓx�R���v�����������V���ȁu�d�ʎԔR���v��ݒ�E���\�����ꍇ�ɂ́A�u���V�G�B�V�[�C�[�̑O�������
���@���@�F�O���v�A�u�������R�c��E��C������E�����Ԕr�o�K�X���ψ���v�A�u����c��w�@�吹�����v�A
����сu���쎩���ԇ��̉��� �^ �ꖱ������v���܂ޓ��{���\����f�B�[�[���G���W���W�̊w�ҁE���ƁE�Z�p
�҂́A����܂ł́u�C���x�~�V�X�e���v���E�َE����s�ׁE��������ĂɎ��~�߁A�u���Ɂu�N�q�^�ρv���A�Q�^�[
�{�����̋C���x�~�V�X�e���i���C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�j���J�����邱�Ƃ��ȑO����ϋɓI�ɐ���
���Ă������̂悤�Ȕ����E���\�ɑ�]��������̂Ɛ��������B
�@�����āA���{���\����f�B�[�[���G���W���W�̊w�ҁE���ƁE�Z�p�҂̐l�B���A�Q�^�[�{�����̋C���x�~�V�X�e
���i���C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�j����^�g���b�N�̑��s�R���d�ʎԃ��[�h�R��̉��P�ɗD�ꂽ�@
�\�E���\����������Z�p�ł��邱�Ƃ����̐̂�������Ă����ƕى����A���̋C���x�~�V�X�e���̋Z�p�J������
���ł͎��������ł������ƕٖ�����̂ł͂Ȃ����Ɛ��������B���̂悤�ɁA���y��ʏȂ��߂������i��2014�N�`
2015�N���j�Ɂu2015�N�x�R���v����P�O�� ���x�̔R����P��K�v�Ƃ���V���ȁu�d�ʎԁi�g���b�N�A�o�X���j�̔R��
��v��ݒ�E���\�����ꍇ�ɂ́A���{���\����f�B�[�[���G���W���W�̊w�ҁE���ƁE�Z�p�҂���́A���ȕ�
�g�̂��߂̋ȕى��E�ٖ������������ł���B����قlj����Ȃ������ɁA���̂悤�ȃh���}�`�b�N�ȓW�J��ڂɂ���
���Ƃ́A�ދ��ȓ��퐶���𑗂��Ă���|���R�c���Z�p���̕M�҂ɂƂ��Ă͊y���݂Ȃ��Ƃ��B
���i���C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�j����^�g���b�N�̑��s�R���d�ʎԃ��[�h�R��̉��P�ɗD�ꂽ�@
�\�E���\����������Z�p�ł��邱�Ƃ����̐̂�������Ă����ƕى����A���̋C���x�~�V�X�e���̋Z�p�J������
���ł͎��������ł������ƕٖ�����̂ł͂Ȃ����Ɛ��������B���̂悤�ɁA���y��ʏȂ��߂������i��2014�N�`
2015�N���j�Ɂu2015�N�x�R���v����P�O�� ���x�̔R����P��K�v�Ƃ���V���ȁu�d�ʎԁi�g���b�N�A�o�X���j�̔R��
��v��ݒ�E���\�����ꍇ�ɂ́A���{���\����f�B�[�[���G���W���W�̊w�ҁE���ƁE�Z�p�҂���́A���ȕ�
�g�̂��߂̋ȕى��E�ٖ������������ł���B����قlj����Ȃ������ɁA���̂悤�ȃh���}�`�b�N�ȓW�J��ڂɂ���
���Ƃ́A�ދ��ȓ��퐶���𑗂��Ă���|���R�c���Z�p���̕M�҂ɂƂ��Ă͊y���݂Ȃ��Ƃ��B
�@�ȏ�̂悤�ɁA���y��ʏȂ��߂������i��2014�N�`2015�N���j�Ɂu2015�N�x�R���v���T�����x�̔R����P����
�߂������V���ȁu�d�ʎԁi�g���b�N�A�o�X���j�̔R���v��ݒ�E���\�����ꍇ�ɂ́A���y��ʏȂ��u2015�N�d�ʎԓx
�R���v�����������V���ȁu�d�ʎԔR���v��ݒ�E���\�����ꍇ�ɂ́A���{���\����f�B�[�[���G���W���W
�̊w�ҁE���ƁE�Z�p�҂��A�Q�^�[�{�����̋C���x�~�V�X�e���i���C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�j�̔R��
���P�̗D�ꂽ�@�\�E���ʂ��E�َE���ł��Ȃ��Ȃ邱�Ƃ��m���Ɨ\�������̂ł���B���������āA���{���\����
�f�B�[�[���G���W���W�̊w�ҁE���ƁE�Z�p�҂��R����P�̗D�ꂽ�@�\�E���ʂ��Q�^�[�{�����̋C���x�~�V�X�e��
�i���C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�j���E�َE������Ԃ́A�c��P�`�Q�N���x�̎c��͂��Ɛ�������
��B�����͉]���Ă��A�ނ���A�u2015�N�d�ʎԓx�R���v�����������V���ȁu�d�ʎԔR���v���ݒ�E���\�����
�M���M���̓����܂ŁA�Q�^�[�{�����̋C���x�~�V�X�e���i���C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�j���E�َE
���銈���𑱂��邱�Ƃ́A�ԈႢ�Ȃ��Ɛ�������邪�A�@���Ȃ��̂ł��낤���B
�߂������V���ȁu�d�ʎԁi�g���b�N�A�o�X���j�̔R���v��ݒ�E���\�����ꍇ�ɂ́A���y��ʏȂ��u2015�N�d�ʎԓx
�R���v�����������V���ȁu�d�ʎԔR���v��ݒ�E���\�����ꍇ�ɂ́A���{���\����f�B�[�[���G���W���W
�̊w�ҁE���ƁE�Z�p�҂��A�Q�^�[�{�����̋C���x�~�V�X�e���i���C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�j�̔R��
���P�̗D�ꂽ�@�\�E���ʂ��E�َE���ł��Ȃ��Ȃ邱�Ƃ��m���Ɨ\�������̂ł���B���������āA���{���\����
�f�B�[�[���G���W���W�̊w�ҁE���ƁE�Z�p�҂��R����P�̗D�ꂽ�@�\�E���ʂ��Q�^�[�{�����̋C���x�~�V�X�e��
�i���C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�j���E�َE������Ԃ́A�c��P�`�Q�N���x�̎c��͂��Ɛ�������
��B�����͉]���Ă��A�ނ���A�u2015�N�d�ʎԓx�R���v�����������V���ȁu�d�ʎԔR���v���ݒ�E���\�����
�M���M���̓����܂ŁA�Q�^�[�{�����̋C���x�~�V�X�e���i���C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�j���E�َE
���銈���𑱂��邱�Ƃ́A�ԈႢ�Ȃ��Ɛ�������邪�A�@���Ȃ��̂ł��낤���B
�Q�Q�@��^�g���b�N�̔R�����̉ߋ��E���݁E����
�@�Ƃ낱��ŁA�����̃g���b�N���[�J�ł́A�ꕔ�̎Ԏ�ł͂��邪�A2015�N�x�d�ʎԔR���ɕs�K���̑�^�g���b�N
������Ă���̂�����ł���B�����āA�ŋ߂ł͍��y��ʏȂ�o�ώY�ƏȂɂ�����2015�N�x�d�ʎԔR���̋�
������������n�߂Ă���Ƃ̉\������B���̂��߁A�g���b�N���[�J�ɂƂ��ẮA�f�B�[�[���G���W�����R������}��
�Z�p�̎������i�ق̉ۑ�ƍl������B���̂悤�ȏɂ����āA���쎩���ԇ��́A�����ԋZ�p���2013�N�H�G
�����_�����^�Ɂu�C���x�~�̋Z�p���̗p������^�g���b�N���������H���s�ł͂S�����x�̔R����P�����҂ł�
��v�ƋL�ڂ����̂ł���B���̂悤�ɁA���쎩���ԇ�����^�g���b�N�̔R����P�̋Z�p�Ƃ��̎������ʂ̊J�����s��
�����@�E���R�́A��́A���Ȃ̂ł��낤���B����ɂ��āA�M�҂���O����ȗ��R��������A����́A�M�҂̃z�[
���y�[�W�ɂ����āu�A���{�̃g���b�N���[�J�̐��ƁE�Z�p�҂́A�f�B�[�[���G���W���̔R����\���̉��P�ł���Z�p
������J���ł��Ă��Ȃ��S�߂ȏɍ݂�v�Ǝ��X�ɋL�ڂ������Ƃ��e�����Ă��邱�Ƃ��\�����ے�ł��Ȃ���
�l������B�܂�A�M�҂��g���b�N���[�J�ɑ���Z�p�J���̔\�͕s����Ɏw�E�������Ƃɑ��A�g���b�N���[�J
�̐��ƁE�Z�p�҂��A�����S�E�v���C�h�����������Ƃ��猃�{���ĉ��Y��A�u���쎩���ԇ��ɂ��C���x�~�̍�
�p�ɂ���^�g���b�N�̂S�����x�̔R����P�v�̘_���������ԋZ�p��̓��e���悤�Ƃ����\�����l������B
������Ă���̂�����ł���B�����āA�ŋ߂ł͍��y��ʏȂ�o�ώY�ƏȂɂ�����2015�N�x�d�ʎԔR���̋�
������������n�߂Ă���Ƃ̉\������B���̂��߁A�g���b�N���[�J�ɂƂ��ẮA�f�B�[�[���G���W�����R������}��
�Z�p�̎������i�ق̉ۑ�ƍl������B���̂悤�ȏɂ����āA���쎩���ԇ��́A�����ԋZ�p���2013�N�H�G
�����_�����^�Ɂu�C���x�~�̋Z�p���̗p������^�g���b�N���������H���s�ł͂S�����x�̔R����P�����҂ł�
��v�ƋL�ڂ����̂ł���B���̂悤�ɁA���쎩���ԇ�����^�g���b�N�̔R����P�̋Z�p�Ƃ��̎������ʂ̊J�����s��
�����@�E���R�́A��́A���Ȃ̂ł��낤���B����ɂ��āA�M�҂���O����ȗ��R��������A����́A�M�҂̃z�[
���y�[�W�ɂ����āu�A���{�̃g���b�N���[�J�̐��ƁE�Z�p�҂́A�f�B�[�[���G���W���̔R����\���̉��P�ł���Z�p
������J���ł��Ă��Ȃ��S�߂ȏɍ݂�v�Ǝ��X�ɋL�ڂ������Ƃ��e�����Ă��邱�Ƃ��\�����ے�ł��Ȃ���
�l������B�܂�A�M�҂��g���b�N���[�J�ɑ���Z�p�J���̔\�͕s����Ɏw�E�������Ƃɑ��A�g���b�N���[�J
�̐��ƁE�Z�p�҂��A�����S�E�v���C�h�����������Ƃ��猃�{���ĉ��Y��A�u���쎩���ԇ��ɂ��C���x�~�̍�
�p�ɂ���^�g���b�N�̂S�����x�̔R����P�v�̘_���������ԋZ�p��̓��e���悤�Ƃ����\�����l������B
�@���̂悤�ɁA�R����P�̌��ʂ��\���ɔ����ł��Ȃ��R����P�̋@�\�̗��z�E�r�C�ًx�~�����̋C���x�~�V�X�e
�����̗p������^�g���b�N�̏ꍇ�ł����Ă��A�C���x�~�̌��ʂɂ��A���쎩���ԇ��̍u���_���̏��^�ɂ́A��^�g
���b�N�̍������H���s�ł͂S�����x�̔R����P�����҂ł���Ƃ̂��Ƃł���B����A�M�҂�2006�N4���ɊJ�݂����z
�[���y�[�W�̓������ɋL�ڂ��Ă���Q�^�[�{�����̋C���x�~�V�X�e���i���C���x�~�G���W���i�������J2005-
54771�j�j�́A�u���쎩���ԇ����z�E�r�C�ًx�~�����̋C���x�~�V�X�e���v�����i�i�ɗD�ꂽ�R����P�̋@�\�E���\
�̂�������Z�p�ł���B���̂��Ƃ���A�M�҂�2006�N4������z�[���y�[�W�ɂ����āA��^�g���b�N�ɂQ�^�[�{������
�C���x�~�V�X�e���i���C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�j�̓����Z�p���̗p�����ꍇ�ɂ́A�T�`�P�O�� ���x
�̏d�ʎԃ��[�h�R�������s�R��\�Ƃ���L�ڂɑ傫�Ȍ��̖������Ƃ������ł�����̂ƍl������B����
�āA�Q�^�[�{�����̋C���x�~�V�X�e���̏ꍇ�ɂ́A��^�g���b�N���������H���s�ł��T�`�P�O�� ���R����P���\��
��������邱�Ƃ��Ó��ł��邱�Ƃ������Ē�����̂ł͂Ȃ����낤���B
�����̗p������^�g���b�N�̏ꍇ�ł����Ă��A�C���x�~�̌��ʂɂ��A���쎩���ԇ��̍u���_���̏��^�ɂ́A��^�g
���b�N�̍������H���s�ł͂S�����x�̔R����P�����҂ł���Ƃ̂��Ƃł���B����A�M�҂�2006�N4���ɊJ�݂����z
�[���y�[�W�̓������ɋL�ڂ��Ă���Q�^�[�{�����̋C���x�~�V�X�e���i���C���x�~�G���W���i�������J2005-
54771�j�j�́A�u���쎩���ԇ����z�E�r�C�ًx�~�����̋C���x�~�V�X�e���v�����i�i�ɗD�ꂽ�R����P�̋@�\�E���\
�̂�������Z�p�ł���B���̂��Ƃ���A�M�҂�2006�N4������z�[���y�[�W�ɂ����āA��^�g���b�N�ɂQ�^�[�{������
�C���x�~�V�X�e���i���C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�j�̓����Z�p���̗p�����ꍇ�ɂ́A�T�`�P�O�� ���x
�̏d�ʎԃ��[�h�R�������s�R��\�Ƃ���L�ڂɑ傫�Ȍ��̖������Ƃ������ł�����̂ƍl������B����
�āA�Q�^�[�{�����̋C���x�~�V�X�e���̏ꍇ�ɂ́A��^�g���b�N���������H���s�ł��T�`�P�O�� ���R����P���\��
��������邱�Ƃ��Ó��ł��邱�Ƃ������Ē�����̂ł͂Ȃ����낤���B
�@���̂悤�ɁA���쎩���ԇ��������ԋZ�p���2013�N�H�G�����_�����^�Ɂu�C���x�~�̋Z�p���̗p������^�g��
�b�N���������H���s�ł͂S�����x�̔R����P�����҂ł���v�ƋL�ڂ������Ƃɂ��A���{�̃f�B�[�[���G���W���W
�̊w�ҁE���ƁE�Z�p�҂̒��ɂ́A�C���x�~�����s�R��̉��P�ɋɂ߂ėL���ȋZ�p�ł��邱���A����A�x�܂��Ȃ�
����F������l�������ė�����̂ƍl������B���̏�����ƁA���{�̃f�B�[�[���G���W���W�̊w�ҁE���ƁE
�Z�p�҂́A�ڂɐG���V�����Z�p���̖{���𗝉����A���̋Z�p�̋@�\����ʂ̗\���E��������\�̗͂��l��
�������悤�Ɏv����̂ł���B�v����ɁA����́A���{�̃f�B�[�[���G���W���W�̊w�ҁE���ƁE�Z�p�҂ɂ́A�V�Z
�p�̊J���ɕs�����Ȑl�Ԃ������Ɖ]�����Ƃł͂Ȃ����낤���B
�b�N���������H���s�ł͂S�����x�̔R����P�����҂ł���v�ƋL�ڂ������Ƃɂ��A���{�̃f�B�[�[���G���W���W
�̊w�ҁE���ƁE�Z�p�҂̒��ɂ́A�C���x�~�����s�R��̉��P�ɋɂ߂ėL���ȋZ�p�ł��邱���A����A�x�܂��Ȃ�
����F������l�������ė�����̂ƍl������B���̏�����ƁA���{�̃f�B�[�[���G���W���W�̊w�ҁE���ƁE
�Z�p�҂́A�ڂɐG���V�����Z�p���̖{���𗝉����A���̋Z�p�̋@�\����ʂ̗\���E��������\�̗͂��l��
�������悤�Ɏv����̂ł���B�v����ɁA����́A���{�̃f�B�[�[���G���W���W�̊w�ҁE���ƁE�Z�p�҂ɂ́A�V�Z
�p�̊J���ɕs�����Ȑl�Ԃ������Ɖ]�����Ƃł͂Ȃ����낤���B
�@�Ȃ��A���쎩���ԇ��́u�C���x�~�̋Z�p���̗p������^�g���b�N���������H���s�ł͂S�����x�̔R����P������
�ł���v�Ƙ_�����^�����炩�ɂȂ������Ƃɂ��A��^�g���b�N�ɂQ�^�[�{�����̋C���x�~�V�X�e���i���C���x�~�G���W
���i�������J2005-54771�j�j�̓����Z�p���̗p�����ꍇ�ɂ́A�T�`�P�O�� ���x�̏d�ʎԃ��[�h�R�������s�R�
�\�Ƃ����M�҂�2006�N4������̃z�[���y�[�W�̋L�����e���M���ł��邱�Ƃ��A���{�̊w�ҁE���ƁE�Z�p�҂��[
�������������̂ƍl������B�����Ƃ��A���������S�E�v���C�h�̋Â�ł܂����ꕔ�̊w�ҁE���ƁE�Z�p�҂́A���g
�ɂ͑�^�g���b�N�̏\���ȔR����P�̎����Ɋ�^�ł���Z�p���̎������킹���F���ł��邱�Ƃ�I�ɏグ�A�M��
���z�[���y�[�W�ɋL�ڂ����Q�^�[�{�����̋C���x�~�V�X�e���i���C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�j�ɂ�
�ẮA����܂Œʂ�A�ے�I�Ȍ�����������A�܂��A�����E�َE�̕��j���т��ʂ��ƍl�����邪�E�E�E�E�E�B�����āA����
�́A�����S�E�v���C�h�̌����Ɖ������ꕔ���Ύ��I�Ȑ��i���������w�ҁE���ƁE�Z�p�҂ł��邪�̂̓��قȍs����
���邩���m��Ȃ����E�E�E�E�E�B�B
�ł���v�Ƙ_�����^�����炩�ɂȂ������Ƃɂ��A��^�g���b�N�ɂQ�^�[�{�����̋C���x�~�V�X�e���i���C���x�~�G���W
���i�������J2005-54771�j�j�̓����Z�p���̗p�����ꍇ�ɂ́A�T�`�P�O�� ���x�̏d�ʎԃ��[�h�R�������s�R�
�\�Ƃ����M�҂�2006�N4������̃z�[���y�[�W�̋L�����e���M���ł��邱�Ƃ��A���{�̊w�ҁE���ƁE�Z�p�҂��[
�������������̂ƍl������B�����Ƃ��A���������S�E�v���C�h�̋Â�ł܂����ꕔ�̊w�ҁE���ƁE�Z�p�҂́A���g
�ɂ͑�^�g���b�N�̏\���ȔR����P�̎����Ɋ�^�ł���Z�p���̎������킹���F���ł��邱�Ƃ�I�ɏグ�A�M��
���z�[���y�[�W�ɋL�ڂ����Q�^�[�{�����̋C���x�~�V�X�e���i���C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�j�ɂ�
�ẮA����܂Œʂ�A�ے�I�Ȍ�����������A�܂��A�����E�َE�̕��j���т��ʂ��ƍl�����邪�E�E�E�E�E�B�����āA����
�́A�����S�E�v���C�h�̌����Ɖ������ꕔ���Ύ��I�Ȑ��i���������w�ҁE���ƁE�Z�p�҂ł��邪�̂̓��قȍs����
���邩���m��Ȃ����E�E�E�E�E�B�B
�@�����Ƃ��A���݂͈ˑR�Ƃ��āA��^�g���b�N�̔R����P�ł���Z�p�����������o���Ă��Ȃ��g���b�N���[�J�̍�����
���ł����ɂ�������炸�A�g���b�N���[�J���R����P��NO���팸�ɗL�����C���x�~�G���W���i�������J2005-
54771�j�̋Z�p�̊J�������ۂɂ͊�Ȃɋ��₵�Ă���ł���B�������A�g���b�N���[�J�̃f�B�[�[���G���W���W��
�Z�p�ҁE���Ƃ́A���肩��͑�^�g���b�N�̔R�������\�ɂ���V�Z�p�̊J�������߂��Ă��邽�߁A���ɂ���
���ďa�ʂ����A�uNO���r�o�ƔR��\�̃g���[�h�I�t�W�̍���������Ȃ��߁A�f�B�[�[���G���W���̔R���
�P������I�v�ƋZ�p�J���ɐ[���ɔY��ł��邩�̂悤�ȉ��Z���s���Ă���̂ł͂Ȃ����ƁA�M�҂ɂ͎v����̂ł�
��B���̗��R�́A�C���x�~�́A�f�B�[�[���̂m�n���팸�ƔR�����̈ꋓ�����̋Z�p���I�̃y�[�W�ɏڏq���Ă����
���ɁA�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p��p����A���Ƃ��ȒP���uNO���r�o�ƔR��\�̃g���[�h�I
�t�W�̍������\�v�ƂȂ�A�f�B�[�[���G���W���̏d�ʎԃ��[�h�R����P�ł��邱�Ƃ��g���b�N���[�J�̃f�B�[�[��
�G���W���W�̋Z�p�ҁE���Ƃ́A�]���̔n���łȂ�����A�{�S�ł͏\���ɗ������Ă���Ɛ��@����邽�߂ł���B
���ɁA���쎩���ԇ��������ԋZ�p���2013�N�H�G�����_�����^�Ɂu�C���x�~�̋Z�p���̗p������^�g���b�N��
�������H���s�ł͂S�����x�̔R����P�����҂ł���v�ƋL�ڂ������Ƃɂ��A�C���x�~�̗L�����ɋC�t�����w�ҁE��
��ƁE�Z�p�҂������̂ł͂Ȃ����낤���B
���ł����ɂ�������炸�A�g���b�N���[�J���R����P��NO���팸�ɗL�����C���x�~�G���W���i�������J2005-
54771�j�̋Z�p�̊J�������ۂɂ͊�Ȃɋ��₵�Ă���ł���B�������A�g���b�N���[�J�̃f�B�[�[���G���W���W��
�Z�p�ҁE���Ƃ́A���肩��͑�^�g���b�N�̔R�������\�ɂ���V�Z�p�̊J�������߂��Ă��邽�߁A���ɂ���
���ďa�ʂ����A�uNO���r�o�ƔR��\�̃g���[�h�I�t�W�̍���������Ȃ��߁A�f�B�[�[���G���W���̔R���
�P������I�v�ƋZ�p�J���ɐ[���ɔY��ł��邩�̂悤�ȉ��Z���s���Ă���̂ł͂Ȃ����ƁA�M�҂ɂ͎v����̂ł�
��B���̗��R�́A�C���x�~�́A�f�B�[�[���̂m�n���팸�ƔR�����̈ꋓ�����̋Z�p���I�̃y�[�W�ɏڏq���Ă����
���ɁA�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p��p����A���Ƃ��ȒP���uNO���r�o�ƔR��\�̃g���[�h�I
�t�W�̍������\�v�ƂȂ�A�f�B�[�[���G���W���̏d�ʎԃ��[�h�R����P�ł��邱�Ƃ��g���b�N���[�J�̃f�B�[�[��
�G���W���W�̋Z�p�ҁE���Ƃ́A�]���̔n���łȂ�����A�{�S�ł͏\���ɗ������Ă���Ɛ��@����邽�߂ł���B
���ɁA���쎩���ԇ��������ԋZ�p���2013�N�H�G�����_�����^�Ɂu�C���x�~�̋Z�p���̗p������^�g���b�N��
�������H���s�ł͂S�����x�̔R����P�����҂ł���v�ƋL�ڂ������Ƃɂ��A�C���x�~�̗L�����ɋC�t�����w�ҁE��
��ƁE�Z�p�҂������̂ł͂Ȃ����낤���B
�@�����āA���݂́A�g���b�N���[�J�̃f�B�[�[���G���W���W�̋Z�p�ҁE���Ƃ́A�uNO���r�o�ƔR��\�̃g���[�h�I�t
�W�̍���������Ȃ��߁A�f�B�[�[���G���W���̔R����P������I�v�Ƃ̌����ʂ��Ȃ��Ȃ�����������������
�ƍl�����邽�߁A�e�g���b�N���[�J�́A����������̔@���A��𑈂����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j��
�Z�p�J���ɒ��肷����̂Ɨ\�z�����B���̎��́A�g���b�N���[�J�̃f�B�[�[���G���W���W�̋Z�p�ҁE���Ƃ́A��
��܂ł̋C���x�~���E�َE���Ă����ߋ��𑼐l���̂悤�ɔᔻ���A���H��ʊ炵�ăT�����[�}���Ƃ��Ă̐��v��
�ێ����čs�����߂ɁA�K���ɂȂ����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p�J���𐄐i������̂Ɛ��@����
��B
�W�̍���������Ȃ��߁A�f�B�[�[���G���W���̔R����P������I�v�Ƃ̌����ʂ��Ȃ��Ȃ�����������������
�ƍl�����邽�߁A�e�g���b�N���[�J�́A����������̔@���A��𑈂����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j��
�Z�p�J���ɒ��肷����̂Ɨ\�z�����B���̎��́A�g���b�N���[�J�̃f�B�[�[���G���W���W�̋Z�p�ҁE���Ƃ́A��
��܂ł̋C���x�~���E�َE���Ă����ߋ��𑼐l���̂悤�ɔᔻ���A���H��ʊ炵�ăT�����[�}���Ƃ��Ă̐��v��
�ێ����čs�����߂ɁA�K���ɂȂ����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p�J���𐄐i������̂Ɛ��@����
��B
�@�����āA�M�҂��l���邻�̎����́A�č������ɂ���^�g���b�N��NO���K�����{�s����������{���{�̑Ӗ��ɏڏq
�����悤�ɁA���{���{���č�������������^�g���b�N��NO���K���̎{�s�\��������A���{�͑�^�g���b�N�̐V��
�Ȓ�R��E��r�o�K�X��𑁊��ɐݒ肹��I�ɏڏq�����悤�ɁA���{���{����^�g���b�N�̐V���Ȓ�R��E��r�o
�K�X��̎{�s�\�������A�Ⴕ���́A2015�N�x�d�ʎԔR���ɑ��ĂT�����x�̔R���̋����\����
���ł͂Ȃ������l������B�t�Ɍ����A���{�̃g���b�N���[�J�́A���{��2015�N�x�d�ʎԔR���̂T�����x�̊�
�������\���Ȃ�����A�����J�����ɂ�����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̊J���ɒ��肵�Ȃ���
�\�����ɂ߂č����Ɛ��@�����B���������āA���̎�������������܂ŁA���{�̑�^�g���b�N����ɂ�����ڗ�����
�R�����E�Ζ��G�l���M�[�팸�������ł��Ȃ����̂ƍl������B��킭�A���{��2015�N�x�d�ʎԔR����
�T�����x�̊�����𑁊��Ɍ��f���A���\���ė~�������̂ł���B�ܘ_�A���̂��Ƃɂ��āA�g���b�N���[�U�������
�����Ď^���̈ӂ�\�����邾�낤���A���{�̌y������ʂ�������x�̍팸�������ł��邱�ƂɂȂ�A�ǂ����Ɛs����
�ł���B�����͐��{�i�����y��ʏȁE�o�ώY�Əȁj�����ƍ����̗��v�̂��߂ɁA�ꔧ�E����2015�N�x�d�ʎԔR���
���̂T�����x�̊�����𑁋}�ɔ��\�E���{���ė~�������̂ł���B
�����悤�ɁA���{���{���č�������������^�g���b�N��NO���K���̎{�s�\��������A���{�͑�^�g���b�N�̐V��
�Ȓ�R��E��r�o�K�X��𑁊��ɐݒ肹��I�ɏڏq�����悤�ɁA���{���{����^�g���b�N�̐V���Ȓ�R��E��r�o
�K�X��̎{�s�\�������A�Ⴕ���́A2015�N�x�d�ʎԔR���ɑ��ĂT�����x�̔R���̋����\����
���ł͂Ȃ������l������B�t�Ɍ����A���{�̃g���b�N���[�J�́A���{��2015�N�x�d�ʎԔR���̂T�����x�̊�
�������\���Ȃ�����A�����J�����ɂ�����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̊J���ɒ��肵�Ȃ���
�\�����ɂ߂č����Ɛ��@�����B���������āA���̎�������������܂ŁA���{�̑�^�g���b�N����ɂ�����ڗ�����
�R�����E�Ζ��G�l���M�[�팸�������ł��Ȃ����̂ƍl������B��킭�A���{��2015�N�x�d�ʎԔR����
�T�����x�̊�����𑁊��Ɍ��f���A���\���ė~�������̂ł���B�ܘ_�A���̂��Ƃɂ��āA�g���b�N���[�U�������
�����Ď^���̈ӂ�\�����邾�낤���A���{�̌y������ʂ�������x�̍팸�������ł��邱�ƂɂȂ�A�ǂ����Ɛs����
�ł���B�����͐��{�i�����y��ʏȁE�o�ώY�Əȁj�����ƍ����̗��v�̂��߂ɁA�ꔧ�E����2015�N�x�d�ʎԔR���
���̂T�����x�̊�����𑁋}�ɔ��\�E���{���ė~�������̂ł���B
�@�Ƃ���ŁA�f�B�[�[���G���W���ɂ����āA�Â�����NO���팸���ɂ͔R��������A�R����㎞�ɂ�NO������������
�uNO���ƔR��̃g���[�h�I�t(���w���j�̊W���ǂ��m���Ă���B�����āA��^�g���b�N�̓��͌��ł���f�B�[�[��
�G���W���ɑ��Ă̍ŏ��̔r�o�K�X�K���iNO���K���j�����a49�N�r�o�K�X�K���i�� 1974�N�{�s�j�����{����Ĉȗ��A
NO���K���̋����ɂ��NO���팸�ɔ����R����̖h�~��A�����̒����푈�ɋN��������P���I�C���V���b�N�̑���
���������A�y�������̎�����}�������߂ɁA�g���b�N���[�J�Ԃł́A�������R�����̋������n�܂����B���̌��ʁA
1970�N��O���ɂ́A�g���b�N���[�J�͈�Ăɑ�^�g���b�N�̃G���W�����]�����u�\�R�Ď��f�B�[�[���v����R��̗D��
���u�������f�B�[�[���v�ɐi�������A10�`15�� ���x�̑��s�R������コ�����̂ł���B
�uNO���ƔR��̃g���[�h�I�t(���w���j�̊W���ǂ��m���Ă���B�����āA��^�g���b�N�̓��͌��ł���f�B�[�[��
�G���W���ɑ��Ă̍ŏ��̔r�o�K�X�K���iNO���K���j�����a49�N�r�o�K�X�K���i�� 1974�N�{�s�j�����{����Ĉȗ��A
NO���K���̋����ɂ��NO���팸�ɔ����R����̖h�~��A�����̒����푈�ɋN��������P���I�C���V���b�N�̑���
���������A�y�������̎�����}�������߂ɁA�g���b�N���[�J�Ԃł́A�������R�����̋������n�܂����B���̌��ʁA
1970�N��O���ɂ́A�g���b�N���[�J�͈�Ăɑ�^�g���b�N�̃G���W�����]�����u�\�R�Ď��f�B�[�[���v����R��̗D��
���u�������f�B�[�[���v�ɐi�������A10�`15�� ���x�̑��s�R������コ�����̂ł���B
�@���̌���A�g���b�N��ɂ��ẮA�P��I�ȔR����Ɠx�d�Ȃ�r�o�K�X�K���̋����ɂ��A�g���b�N���[�J�ł͑�^
�g���b�N�̔R����P�̌����J��������Ɏ��{����Ă����B�������A��^�g���b�N�̔R����P�́A�G���W���̏ꍇ�ɂ�
�M�����̌��オ�K�v�ł���A�ԑ̂̑��s��R�i����C��R�E�]�����R���j�̍팸��g���b�X�~�b�V�����̑��i����
�ɂ��g���b�N�E��̃p���[�g���C���̍������ɂ��G���W���̉^�]��Ԃ̍œK���̐��䂪�K�v�ƂȂ�A�Z�p�I�ɂ�
�R�X�g�I�ɂ������̍�������A�e�ՂȂ��Ƃł͂Ȃ��B����ANO���̔r�o�ɂ��ẮA�R�Ď����̔R�ĉ��x��_�f�Z
�x�Ɉˑ�����ppm �I�[�_�[��NO�����������邽�߂�NO���ł̍����팸���̎����́A�R��̌���ɔ�ׂ�A�e��
�Ɖ]����̂ł͂Ȃ����낤���B���̏؋��Ƃ��āA��^�g���b�N�̃|�X�g�V�����K����NOx�K���l��0.7��/��Wh�́A�ŏ�
�����a49�N�r�o�K�X�K����NOx�K���l�̂T���܂ō팸����Ă��邱�Ƃ���������B
�g���b�N�̔R����P�̌����J��������Ɏ��{����Ă����B�������A��^�g���b�N�̔R����P�́A�G���W���̏ꍇ�ɂ�
�M�����̌��オ�K�v�ł���A�ԑ̂̑��s��R�i����C��R�E�]�����R���j�̍팸��g���b�X�~�b�V�����̑��i����
�ɂ��g���b�N�E��̃p���[�g���C���̍������ɂ��G���W���̉^�]��Ԃ̍œK���̐��䂪�K�v�ƂȂ�A�Z�p�I�ɂ�
�R�X�g�I�ɂ������̍�������A�e�ՂȂ��Ƃł͂Ȃ��B����ANO���̔r�o�ɂ��ẮA�R�Ď����̔R�ĉ��x��_�f�Z
�x�Ɉˑ�����ppm �I�[�_�[��NO�����������邽�߂�NO���ł̍����팸���̎����́A�R��̌���ɔ�ׂ�A�e��
�Ɖ]����̂ł͂Ȃ����낤���B���̏؋��Ƃ��āA��^�g���b�N�̃|�X�g�V�����K����NOx�K���l��0.7��/��Wh�́A�ŏ�
�����a49�N�r�o�K�X�K����NOx�K���l�̂T���܂ō팸����Ă��邱�Ƃ���������B
�@���݂ɁA�|�X�g�V�����K���̎���NOx�K���l��0.4 ��/��Wh�i��2016�N���{�\��j�̏ꍇ�ɂ́A�ŏ������a49�N�r
�o�K�X�K����NOx�K���l�̖� �R ���܂ō팸����邱�ƂɂȂ�B�܂�A��^�g���b�N�̔r�o�K�X�K���ł́ANO�����P�O
�O���߂��팸����������Ă���̂ł���B���݂ɁA��ʓI�ɔR����P�Ə̂���ۂɂ́A�P�O�O���̔R�����ƌ`�e��
���ꍇ�ɂ́A�R���̃��b�^�[������̑��s������2�{�ɂȂ邱�Ƃɂ��Ӗ����A�G���W���̏ꍇ�ɂ�2�{�̔M�����ƂȂ�
���Ƃɑ������A���̂悤�ȔR����P����^�g���b�N�ɂ����Ď������邱�Ƃ��펯�I�Ɂu�s�\�v�ł��邱�Ƃ͊ԈႢ��
�����ƍl������B
�o�K�X�K����NOx�K���l�̖� �R ���܂ō팸����邱�ƂɂȂ�B�܂�A��^�g���b�N�̔r�o�K�X�K���ł́ANO�����P�O
�O���߂��팸����������Ă���̂ł���B���݂ɁA��ʓI�ɔR����P�Ə̂���ۂɂ́A�P�O�O���̔R�����ƌ`�e��
���ꍇ�ɂ́A�R���̃��b�^�[������̑��s������2�{�ɂȂ邱�Ƃɂ��Ӗ����A�G���W���̏ꍇ�ɂ�2�{�̔M�����ƂȂ�
���Ƃɑ������A���̂悤�ȔR����P����^�g���b�N�ɂ����Ď������邱�Ƃ��펯�I�Ɂu�s�\�v�ł��邱�Ƃ͊ԈႢ��
�����ƍl������B
�@���̂悤�ɁA��^�g���b�N�ɂ����ẮANO���팸�ɔ�r���A���s�R���d�ʎԃ��[�h�R��̉��P�͋ɂ߂č���ł�
��B�������A����ł��g���b�N���[�J�́A1970�N��O������P���I�C���V���b�N�ȗ��A�������R����ɑł������߂�
�����ɑ�^�g���b�N�̑��s�R���d�ʎԃ��[�h�R��̉��P�ɓw�߂Ă����̂ł���B���̕s�f�̓w�͂̌��ʁA���݂�
��^�f�B�[�[���g���b�N�ł̑��s�R��B������Ă���B�����ŁA�ȉ����\�S�P�ɂ́A��P���I�C���V���b�N���_�@�Ƃ�
�ĔR�����P�̎s��j�[�Y�����܂���1970�N���ȍ~�ɂ��āA��^�g���b�N�ɂ�����T�� ���x�ȏ�̑��s�R���d
�ʎԃ��[�h�R��̉��P�����ۂɎ�������Ă����Z�p���A�N�㏇�ɐ��������B�܂��A���̕\�S�P�ɂ́A���ɋ߂�������
���y��ʏȂ�2015�N�x�d�ʎԔR������{�P�O�� ���x�̔R���̂����������{���ꂽ�ꍇ�ɂ����āA�e�g��
�b�N���[�J���s�{�ӂɂ��̗p������Ȃ���^�g���b�N�̏d�ʎԃ��[�h�R��̉��P�Z�p�ɂ��Ă��t�L�����̂ŁA
�����������������B
��B�������A����ł��g���b�N���[�J�́A1970�N��O������P���I�C���V���b�N�ȗ��A�������R����ɑł������߂�
�����ɑ�^�g���b�N�̑��s�R���d�ʎԃ��[�h�R��̉��P�ɓw�߂Ă����̂ł���B���̕s�f�̓w�͂̌��ʁA���݂�
��^�f�B�[�[���g���b�N�ł̑��s�R��B������Ă���B�����ŁA�ȉ����\�S�P�ɂ́A��P���I�C���V���b�N���_�@�Ƃ�
�ĔR�����P�̎s��j�[�Y�����܂���1970�N���ȍ~�ɂ��āA��^�g���b�N�ɂ�����T�� ���x�ȏ�̑��s�R���d
�ʎԃ��[�h�R��̉��P�����ۂɎ�������Ă����Z�p���A�N�㏇�ɐ��������B�܂��A���̕\�S�P�ɂ́A���ɋ߂�������
���y��ʏȂ�2015�N�x�d�ʎԔR������{�P�O�� ���x�̔R���̂����������{���ꂽ�ꍇ�ɂ����āA�e�g��
�b�N���[�J���s�{�ӂɂ��̗p������Ȃ���^�g���b�N�̏d�ʎԃ��[�h�R��̉��P�Z�p�ɂ��Ă��t�L�����̂ŁA
�����������������B
| |
|
|
| |
�E�u�\�R�Ď��f�B�[�[���v�����u�������f�B�[�[���v�ɕύX | |
| |
�E�u���ߋ��f�B�[�[���v�����u�C���^�[�N���ߋ��f�B�[�[���v�ɕύX | |
| |
�E�g���b�N���u�A�C�h�������O�X�g�b�v�v�̎��p��
�i�����U�����Ԃ��ȃG�l��܂���܂��A���̌�A���̋Z�p���g���b�N�E�o �X�ɍL�����y�j |
|
| |
�E2015�N�x�d�ʎԔR�����{�s
�i���̊�ɓK��������^�g���b�N�ɗD���Ő��̓K�p���J�n�j |
|
| |
�E�u�V�i�}�j���A���g�����X�~�b�V�����v����
�u12�i�@�B�������g�����X�~�b�V�����v�ɕύX �i��^�g���b�N�ɍ����ȁu12�i�@�B�������g�����X�~�b�V�����v�𓋍� ���邱�Ƃɂ��A���{�̃g���b�N���[�J�́A�啔���̑�^�g���b�N�� 2015�N�x�d�ʎԔR���ɐh�����ēK���j |
|
| |
�E�u���َ�̧ݶ����ݸށv�����u�d�q����I�[�g�N�[���t�@���J�b�v
�����O�v�ɕύX �E�u�]���^���������߁v�����u�d�q����ϗ��ʃE�H�[�^�[�|���v�v �ɕύX �i�o�T�Fhttp://www.mitsubishi-fuso.com/jp/news/news_content/ 140529/140529.html�j |
|
| |
�E�u�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�v�̓����Z�p
���̗p�H �i�߂�������2015�N�x�d�ʎԔR����10�����x�̋�����}���� �V���ȔR���̋��������y��ʏȂ����{�����ꍇ�ɂ́A �́A�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p���^ �g���b�N�Ɉ�Ăɍ̗p�������̂Ɨ\�z�����B���̂Ȃ�A�d�ʎ� ���[�h�R��� 5�`10�� ���x���̉��P���\�ɂ���Z�p�́A ���̂Ƃ���A�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̑��ɂ� ��������Ȃ����߂ł���B�j �i���쎩���Ԃ́u�z�E�r�C�ْ�~���̋C���x�~�V�X�e���v�́A ���쎩���Ԃ��_�����\�����R����P�@�\�̗��C���x�~�V�X�e�� �Ɏ������悤�ɁA�G���W�����������ɋx�~�ł���C������ �����Ɏ~�܂�\���I�Ȍ��ׂ̂��߁A�g���b�N�̑��s�R������P ����Z�p�Ƃ��Ă͎��i�ł���B�j |
|
�@�ȏ�̂悤�ɁA1970�N��O������P���I�C���V���b�N�����^�g���b�N�ɂ����āA ���s�R���d�ʎԃ��[�h�R���
�T�� ���x�̉��P���������邽�߂ɍ̗p����Ă����Z�p�́A�ȉ��̂T���ڂł���B
�T�� ���x�̉��P���������邽�߂ɍ̗p����Ă����Z�p�́A�ȉ��̂T���ڂł���B
�@ �u�������f�B�[�[���v
�A �u�C���^�[�N���ߋ��f�B�[�[���v
�B �u�A�C�h�������O�X�g�b�v�v
�C �u12�i�@�B�������g�����X�~�b�V�����v
�D �u�d�q����I�[�g�N�[���t�@���J�b�v�����O�v�Ɓu�d�q����ϗ��ʃE�H�[�^�[�|���v�v�̑g����
�@�ȏ�̏��Z�p�̒����D�� �u�d�q����I�[�g�N�[���t�@���J�b�v�����O�v�Ɓu�d�q����ϗ��ʃE�H�[�^�[�|���v�v��
�g�����́A�ŋ߁i��2014�N6���j�A�O�H�ӂ����̑�^�g���b�N�ɏ��߂č̗p���ꂽ�Z�p�ł���B�����Ƃ��A�u�d�q����I
�[�g�N�[���t�@���J�b�v�����O�v�͐��\�N���̂��畁�y����FF�쓮��p�ԁi���t�����g�G���W���E�t�����g�h���C�u�̏�p
�ԁj�ɍ̗p����Ă����u�d����p�t�@���v�Ƌ@�\�E���\�������Z�p�ł���A�u�d�q����ϗ��ʃE�H�[�^�[�|���v�v�͍�
�߂̃n�C�u���b�h��p�Ԃɍ̗p����Ă���u�d���E�H�[�^�[�|���v�v�Ƌ@�\�E���\�������Z�p�ł���B���������āA �u�d
�q����I�[�g�N�[���t�@���J�b�v�����O�v�Ɓu�d�q����ϗ��ʃE�H�[�^�[�|���v�v�́A���ɏ�p�Ԃɍ̗p�ς�
�̑��s�R����P�̋@�\�E���\��L�����ގ��Z�p���^�f�B�[�[���g���b�N�ɗ��p�����ƌ��邱�Ƃ��ł����B
�g�����́A�ŋ߁i��2014�N6���j�A�O�H�ӂ����̑�^�g���b�N�ɏ��߂č̗p���ꂽ�Z�p�ł���B�����Ƃ��A�u�d�q����I
�[�g�N�[���t�@���J�b�v�����O�v�͐��\�N���̂��畁�y����FF�쓮��p�ԁi���t�����g�G���W���E�t�����g�h���C�u�̏�p
�ԁj�ɍ̗p����Ă����u�d����p�t�@���v�Ƌ@�\�E���\�������Z�p�ł���A�u�d�q����ϗ��ʃE�H�[�^�[�|���v�v�͍�
�߂̃n�C�u���b�h��p�Ԃɍ̗p����Ă���u�d���E�H�[�^�[�|���v�v�Ƌ@�\�E���\�������Z�p�ł���B���������āA �u�d
�q����I�[�g�N�[���t�@���J�b�v�����O�v�Ɓu�d�q����ϗ��ʃE�H�[�^�[�|���v�v�́A���ɏ�p�Ԃɍ̗p�ς�
�̑��s�R����P�̋@�\�E���\��L�����ގ��Z�p���^�f�B�[�[���g���b�N�ɗ��p�����ƌ��邱�Ƃ��ł����B
�@���̂悤�ɁA �u�d�q����I�[�g�N�[���t�@���J�b�v�����O�v�Ɓu�d�q����ϗ��ʃE�H�[�^�[�|���v�v�́A��p�Ԃł̔R
����P�̋@�\�E���\�����p�����Z�p�ł��邽�߁A��^�g���b�N�̕���ŐV���ɓƎ��ɊJ�����ꂽ�V�K�̔R����P�Z
�p�ƌĂԂ��Ƃɂ͏����S�O�����ƍl������B�������Ȃ���u�d�q����I�[�g�N�[���t�@���J�b�v�����O�v�������ɉ���
�ĉϐ��䂵�Č����I�ȃG���W����p���������邽�߂ɕK�v�ɉ�������p�t�@�������Ƃŋ쓮������ጸ���A
�u�d�q����ϗ��ʃE�H�[�^�[�|���v�v�́A�d����p�t�@���Ɠ��l�ɂŕK�v�ɉ����ė�p���ʂ��z�����ăG���W����
�����I�ɗ�p���ăE�H�[�^�[�|���v�̗]���ȋ쓮������ጸ���邱�Ƃɂ��A�u��^�g���b�N�ɂ������{�T�� ���x
�̏d�ʎԃ��[�h�R��̉��P���\�v�ƂȂ��B����ɂ���āA2014�N�̎��_�ɂ����āA��^�g���b�N�́A2015�N�x�d��
�ԔR���́{�T���̒�R��������ł����悤�ł���B
����P�̋@�\�E���\�����p�����Z�p�ł��邽�߁A��^�g���b�N�̕���ŐV���ɓƎ��ɊJ�����ꂽ�V�K�̔R����P�Z
�p�ƌĂԂ��Ƃɂ͏����S�O�����ƍl������B�������Ȃ���u�d�q����I�[�g�N�[���t�@���J�b�v�����O�v�������ɉ���
�ĉϐ��䂵�Č����I�ȃG���W����p���������邽�߂ɕK�v�ɉ�������p�t�@�������Ƃŋ쓮������ጸ���A
�u�d�q����ϗ��ʃE�H�[�^�[�|���v�v�́A�d����p�t�@���Ɠ��l�ɂŕK�v�ɉ����ė�p���ʂ��z�����ăG���W����
�����I�ɗ�p���ăE�H�[�^�[�|���v�̗]���ȋ쓮������ጸ���邱�Ƃɂ��A�u��^�g���b�N�ɂ������{�T�� ���x
�̏d�ʎԃ��[�h�R��̉��P���\�v�ƂȂ��B����ɂ���āA2014�N�̎��_�ɂ����āA��^�g���b�N�́A2015�N�x�d��
�ԔR���́{�T���̒�R��������ł����悤�ł���B
�@�ȏ�̂悤�ɁA�����N���ɂ킽��Z�p�ҁE���Ƃ̒n���ȓw�͂ɂ���āA��^�g���b�N�ɂ�����{�T�����x�̑��s
�R��̌�����\�ɂ���e��̃f�B�[�[���G���W���Z�p�����p������Ă����̂ł���B���̂悤�ȃf�B�[�[���G���W
���ɂ�����R����P�̋Z�p�J���̌o�܁E���т�����ƁA��^�g���b�N�̑��s�R���d�ʎԃ��[�h�R��́{�T�� ���x
�����P���邱�Ƃ��@���ɓ�����Ƃ����锤�ł���B���������āA�߂������ɑ�^�g���b�N�̎����s�R���d�ʎԃ�
�[�h�R��{�T�����x�ȏ� �̉��P�������ł���V�����R�����̋Z�p���������邱�Ƃ́A�ɂ߂ē�����Ƃł���B
����ɂ��āA�M�҂��l����Ƃ���ł́A�����_�ɂ����đ�^�g���b�N�̎����s�R���d�ʎԃ��[�h�R��{�T����
�x�ȏ� �̉��P���\�ɂ���V�����Z�p�́A���̂Ƃ���A�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̑��ɂ͑��݂�
�Ȃ��ƍl���Ă���B�܂�A�|�X�g�V�����r�o�K�X�K���i��2009�N�K���j�K���̎d�l�Ɂu�d�q����I�[�g�N�[��
�t�@���J�b�v�����O�v�Ɓu�d�q����ϗ��ʃE�H�[�^�[�|���v�v���̗p������^�g���b�N�i��2015�N�x�d�ʎԔR��
��{�T���̒B���̑�^�g���b�N�j�ɁA�V�����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p��g��
���邱�Ƃɂ��A2015�N�x�d�ʎԔR������{�P�O���ȏ�̔R������B��������^�g���b�N���m���Ɏ�
���ł����Ɨ\�z�����B
�R��̌�����\�ɂ���e��̃f�B�[�[���G���W���Z�p�����p������Ă����̂ł���B���̂悤�ȃf�B�[�[���G���W
���ɂ�����R����P�̋Z�p�J���̌o�܁E���т�����ƁA��^�g���b�N�̑��s�R���d�ʎԃ��[�h�R��́{�T�� ���x
�����P���邱�Ƃ��@���ɓ�����Ƃ����锤�ł���B���������āA�߂������ɑ�^�g���b�N�̎����s�R���d�ʎԃ�
�[�h�R��{�T�����x�ȏ� �̉��P�������ł���V�����R�����̋Z�p���������邱�Ƃ́A�ɂ߂ē�����Ƃł���B
����ɂ��āA�M�҂��l����Ƃ���ł́A�����_�ɂ����đ�^�g���b�N�̎����s�R���d�ʎԃ��[�h�R��{�T����
�x�ȏ� �̉��P���\�ɂ���V�����Z�p�́A���̂Ƃ���A�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̑��ɂ͑��݂�
�Ȃ��ƍl���Ă���B�܂�A�|�X�g�V�����r�o�K�X�K���i��2009�N�K���j�K���̎d�l�Ɂu�d�q����I�[�g�N�[��
�t�@���J�b�v�����O�v�Ɓu�d�q����ϗ��ʃE�H�[�^�[�|���v�v���̗p������^�g���b�N�i��2015�N�x�d�ʎԔR��
��{�T���̒B���̑�^�g���b�N�j�ɁA�V�����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p��g��
���邱�Ƃɂ��A2015�N�x�d�ʎԔR������{�P�O���ȏ�̔R������B��������^�g���b�N���m���Ɏ�
���ł����Ɨ\�z�����B
�Q�R�@���y��ʏȂ���^�g���b�N�̔R���̋��������{���鎞���i�ڕW�N�x�̍���j
�@�킪���̎����ԔR�������肷�鍑�y��ʏȂ̎����ԔR�����ψ���́A�ȉ��̕\�S�Q�Ɏ������悤�ɁA
�u�����Ԃ̔R���̖ڕW�N�x�́A�����I�ȋZ�p�i�W�����Ă�����Őݒ肷����j�v���������������Ƃ̂��Ƃ�
����B���̂��Ƃ́A�d�ʎԁi����^�g���b�N�j�̔R�����̏����I�ȋZ�p�i�W�̌��ʂ���������܂ŁA���y��ʏ�
�̎����ԔR�����ψ���́A���s��2015�N�x�d�ʎԔR�����������鎟���̏d�ʎԔR���̖ڕW�N�x
�̐ݒ�i=���\�j���s��Ȃ��Ɛ錾���Ă���悤�ɂ�������̂ł���B
�u�����Ԃ̔R���̖ڕW�N�x�́A�����I�ȋZ�p�i�W�����Ă�����Őݒ肷����j�v���������������Ƃ̂��Ƃ�
����B���̂��Ƃ́A�d�ʎԁi����^�g���b�N�j�̔R�����̏����I�ȋZ�p�i�W�̌��ʂ���������܂ŁA���y��ʏ�
�̎����ԔR�����ψ���́A���s��2015�N�x�d�ʎԔR�����������鎟���̏d�ʎԔR���̖ڕW�N�x
�̐ݒ�i=���\�j���s��Ȃ��Ɛ錾���Ă���悤�ɂ�������̂ł���B
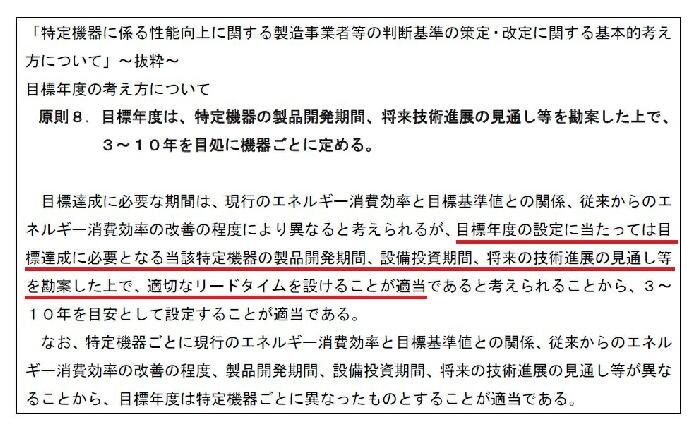 |
�@���݁A�킪���ł́A�ȏ�̂悤�Ȏ����ԔR���̌���v���Z�X���̗p����Ă��邽�߁A����A�g���b�N���[�J��
�u��^�g���b�N�̑��s�R��̑啝�ȉ��P���Z�p�I�ɍ���v�Ƃ̋��U�̋Z�p���e�̘_�����\����ϋɓI�ɍs���A����
���U�̋Z�p�������y��ʏȂ̎����ԔR�����ψ���x���ꂽ�ꍇ�ɂ́A�����ԔR�����ψ����2015
�N�x�d�ʎԔR�����������鎟���̏d�ʎԔR���̖ڕW�N�x��摗�肵�������邱�ƂɂȂ�Ɛ��������B
�u��^�g���b�N�̑��s�R��̑啝�ȉ��P���Z�p�I�ɍ���v�Ƃ̋��U�̋Z�p���e�̘_�����\����ϋɓI�ɍs���A����
���U�̋Z�p�������y��ʏȂ̎����ԔR�����ψ���x���ꂽ�ꍇ�ɂ́A�����ԔR�����ψ����2015
�N�x�d�ʎԔR�����������鎟���̏d�ʎԔR���̖ڕW�N�x��摗�肵�������邱�ƂɂȂ�Ɛ��������B
�@���̂悤�Ȏ����ԔR���̌���v���Z�X���̗p����Ă�����{�ɂ����āA���쎩���Ԃ��_�����\�����R����P
�@�\�̗��C���x�~�V�X�e���ɏڏq���Ă���悤�ɁA�����ԋZ�p��2014�N�H�G���ɂ����āA���쎩���Ԃ́A�\��
�I�Ȍ��ׂ����u�z�E�r�C�ْ�~���̋C���x�~�V�X�e���v�̘_���i�����ԋZ�p����ԍ�20145364�j�\�����̂�
����B�����āA���̓��쎩���Ԃ̘_���ł́A�u�z�E�r�C�ْ�~���̋C���x�~�V�X�e���v�́A�\���I�Ȍ��ׂ������߁A
����I�ȋZ�p�J���ɂ���Č��_�E��_�������ł��Ȃ�����A��^�g���b�N�̑��s�R��̏\���ȉ��P������Ƃ�����e
���L�ڂ���Ă���B���́u�z�E�r�C�ْ�~���̋C���x�~�V�X�e���v���\���I�Ȍ��ׂ̂��߂ɑ�^�g���b�N�̔R�����
�ɖ����Ƃ�����쎩���Ԃ̘_���́A�ꌩ�����Ƃ���A�ɂ߂ē��R�̌��_���q�ׂĂ���ɉ߂��Ȃ��悤�Ɍ�������e��
����B�������Ȃ���A�����ŕM�҂���قɎv���邱�Ƃ́A�ꗬ��Ƃ̓��쎩���Ԃ��ŏ�����\���I�Ȍ��ׂ̖��炩��
�u�z�E�r�C�ْ�~���̋C���x�~�V�X�e���v�������đI���E��Ă��A���̋Z�p�ł͑�^�g���b�N�̑��s�R��̏\���ȉ��P
������Ƃ���u���肫�������_�v�E�u���킸�����Ȃ̌��_�v���܂Ƃ߂��_���������ԋZ�p���2014�N�H�G���œ��X��
���\���Ă��邱�Ƃł���B
�@�\�̗��C���x�~�V�X�e���ɏڏq���Ă���悤�ɁA�����ԋZ�p��2014�N�H�G���ɂ����āA���쎩���Ԃ́A�\��
�I�Ȍ��ׂ����u�z�E�r�C�ْ�~���̋C���x�~�V�X�e���v�̘_���i�����ԋZ�p����ԍ�20145364�j�\�����̂�
����B�����āA���̓��쎩���Ԃ̘_���ł́A�u�z�E�r�C�ْ�~���̋C���x�~�V�X�e���v�́A�\���I�Ȍ��ׂ������߁A
����I�ȋZ�p�J���ɂ���Č��_�E��_�������ł��Ȃ�����A��^�g���b�N�̑��s�R��̏\���ȉ��P������Ƃ�����e
���L�ڂ���Ă���B���́u�z�E�r�C�ْ�~���̋C���x�~�V�X�e���v���\���I�Ȍ��ׂ̂��߂ɑ�^�g���b�N�̔R�����
�ɖ����Ƃ�����쎩���Ԃ̘_���́A�ꌩ�����Ƃ���A�ɂ߂ē��R�̌��_���q�ׂĂ���ɉ߂��Ȃ��悤�Ɍ�������e��
����B�������Ȃ���A�����ŕM�҂���قɎv���邱�Ƃ́A�ꗬ��Ƃ̓��쎩���Ԃ��ŏ�����\���I�Ȍ��ׂ̖��炩��
�u�z�E�r�C�ْ�~���̋C���x�~�V�X�e���v�������đI���E��Ă��A���̋Z�p�ł͑�^�g���b�N�̑��s�R��̏\���ȉ��P
������Ƃ���u���肫�������_�v�E�u���킸�����Ȃ̌��_�v���܂Ƃ߂��_���������ԋZ�p���2014�N�H�G���œ��X��
���\���Ă��邱�Ƃł���B
�@�܂�A���쎩���Ԃ́A���ʂ̃G���W���Z�p�ҁE���Ƃł���Ηe�Ղɗ����ł������ȍ\���I�Ȍ��ׂ����u�z�E
�r�C�ْ�~���̋C���x�~�V�X�e���v�������Ē�Ă��A���̎g�����ɂȂ�Ȃ��u�C���x�~�V�X�e���v�̌��_�E��_����
�����đ�^�g���b�N�̑��s�R��̏\���ȉ��P�������ł���Ƌȓ��e�̘_���i�����ԍ�20145364�j�������ԋZ�p
��2014�N�H�G���ŋ��������\�����ƌ��邱�Ƃ��\�ł���B���̏ꍇ�A���̍\���I�Ȍ��ׂ́u�C���x�~�V�X�e���v
�̘_���\������쎩���Ԃ̖ړI�́A��^�g���b�N�̑��s�R��̏\���ȉ��P������Ƃ��鋕�U�I�Ȃ̋Z�p���
�̐Z���E�g�U��}���Ă���ƌ��邱�Ƃ��\�ł���B�����āA���̓��쎩���Ԃ́u�z�E�r�C�ْ�~���̋C���x�~�V�X�e
���v�̌��Z�p�̘_�����\�́A�C���x�~�G���W���ɂ���^�g���b�N�̒�R����C���x�~�́A�f�B�[�[���̂m�n��
�팸�ƔR�����̈ꋓ�����̋Z�p���I�ɏڏq���Ă����^�g���b�N�̔R������NO���팸�̗������Ɏ����ł�
���C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p�𑒂苎�邱�Ƃ��ő�̖ړI�ł͂Ȃ����ƁA�|���R�c���Z�p
���̕M�҂ɂ͎v����̂ł���B
�r�C�ْ�~���̋C���x�~�V�X�e���v�������Ē�Ă��A���̎g�����ɂȂ�Ȃ��u�C���x�~�V�X�e���v�̌��_�E��_����
�����đ�^�g���b�N�̑��s�R��̏\���ȉ��P�������ł���Ƌȓ��e�̘_���i�����ԍ�20145364�j�������ԋZ�p
��2014�N�H�G���ŋ��������\�����ƌ��邱�Ƃ��\�ł���B���̏ꍇ�A���̍\���I�Ȍ��ׂ́u�C���x�~�V�X�e���v
�̘_���\������쎩���Ԃ̖ړI�́A��^�g���b�N�̑��s�R��̏\���ȉ��P������Ƃ��鋕�U�I�Ȃ̋Z�p���
�̐Z���E�g�U��}���Ă���ƌ��邱�Ƃ��\�ł���B�����āA���̓��쎩���Ԃ́u�z�E�r�C�ْ�~���̋C���x�~�V�X�e
���v�̌��Z�p�̘_�����\�́A�C���x�~�G���W���ɂ���^�g���b�N�̒�R����C���x�~�́A�f�B�[�[���̂m�n��
�팸�ƔR�����̈ꋓ�����̋Z�p���I�ɏڏq���Ă����^�g���b�N�̔R������NO���팸�̗������Ɏ����ł�
���C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p�𑒂苎�邱�Ƃ��ő�̖ړI�ł͂Ȃ����ƁA�|���R�c���Z�p
���̕M�҂ɂ͎v����̂ł���B
�@���̂悤�ȁA�u�z�E�r�C�ْ�~���̋C���x�~�V�X�e���v�̌��Z�p�������Ę_�����\������쎩���Ԃ̍s�ׂ́A
�w�R�H�ł��吺�œ��X�Ǝ咣��������A���̒��́u�n���H�v�͐M���Ă��܂����́x�Ƃ���Â�����J�Ś�����Ă��鍼
�\�t�I�Ȏv�l�Ɋ�Â������̂̂悤�Ɏv����̂ł���B�܂�A�������ł��A�u�R�͍Ō�܂œf���ʂ��I�v�Ƃ̎�@��
����B���̂悤�ȁA���\�I�ȋZ�p�_���̔��\����쎩���Ԃ̊��������F�����w�i�ɂ́A�����̉��ꂩ�̎����ɘ_
���̌��ׂ��I�������Ƃ��Ă��A�u�z�E�r�C�ْ�~���̋C���x�~�V�X�e���v�̌��ט_���ɂ���āu��^�g���b�N�̑��s�R
��̑啝�ȉ��P���Z�p�I�ɍ���v�Ƃ̋��U�̋Z�p��Z���E�g�U�ł������Ƃɂ��A2015�N�x�d�ʎԔR����
�������鎟���̏d�ʎԔR���̖ڕW�N�x�̐摗��Ɖ]���ړI���B���ł��Ă��邢��Ƃ̍l���Ɋ�Â��̂ł͂Ȃ�
���Ɛ��������B���͂Ƃ�����A���쎩���Ԃ́u�z�E�r�C�ْ�~���̋C���x�~�V�X�e���v�̘_���̌��ׂ��I��������
�ɂ́A���ɓ��쎩���ԂƑ��̃g���b�N���[�J�́A2015�N�x�d�ʎԔR�����������鎟���̏d�ʎԔR���̖ڕW
�N�x�̐摗��Ɖ]�������Ă��邱�ƂɂȂ肻�����B
�w�R�H�ł��吺�œ��X�Ǝ咣��������A���̒��́u�n���H�v�͐M���Ă��܂����́x�Ƃ���Â�����J�Ś�����Ă��鍼
�\�t�I�Ȏv�l�Ɋ�Â������̂̂悤�Ɏv����̂ł���B�܂�A�������ł��A�u�R�͍Ō�܂œf���ʂ��I�v�Ƃ̎�@��
����B���̂悤�ȁA���\�I�ȋZ�p�_���̔��\����쎩���Ԃ̊��������F�����w�i�ɂ́A�����̉��ꂩ�̎����ɘ_
���̌��ׂ��I�������Ƃ��Ă��A�u�z�E�r�C�ْ�~���̋C���x�~�V�X�e���v�̌��ט_���ɂ���āu��^�g���b�N�̑��s�R
��̑啝�ȉ��P���Z�p�I�ɍ���v�Ƃ̋��U�̋Z�p��Z���E�g�U�ł������Ƃɂ��A2015�N�x�d�ʎԔR����
�������鎟���̏d�ʎԔR���̖ڕW�N�x�̐摗��Ɖ]���ړI���B���ł��Ă��邢��Ƃ̍l���Ɋ�Â��̂ł͂Ȃ�
���Ɛ��������B���͂Ƃ�����A���쎩���Ԃ́u�z�E�r�C�ْ�~���̋C���x�~�V�X�e���v�̘_���̌��ׂ��I��������
�ɂ́A���ɓ��쎩���ԂƑ��̃g���b�N���[�J�́A2015�N�x�d�ʎԔR�����������鎟���̏d�ʎԔR���̖ڕW
�N�x�̐摗��Ɖ]�������Ă��邱�ƂɂȂ肻�����B
�@�����āA2015�N�x�d�ʎԔR���̋����̖ڕW�N�x��2024�N�x�܂ł̐摗�肪�����ł����ꍇ�A��^�g���b�N��
�R������NO���팸�̗������Ɏ����ł����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p����������
�̎������}���邽�߁A���쎩���ԂƑ��̃g���b�N���[�J�́A���̓����Z�p�����R�C�܂܂Ɏ��Ђ̑�^�g���b�N�ɍ̗p
���闘�v�邱�Ƃ��ł���̂ł���B����ɑ��A���ɁA����A���y��ʏȂ̎����ԔR�����ψ���u�z�E�r
�C�ْ�~���̋C���x�~�V�X�e���v�̌��ט_���i�����ԋZ�p����ԍ�20145364�j�ɘf�킳����u��^�g���b�N�̑��s
�R��̑啝�ȉ��P���Z�p�I�ɍ���v�Ƃ̔F����A�������邱�Ƃɂ��A��^�g���b�N����2015�N�x�d�ʎԔR���
�����������鎟���̏d�ʎԔR���̖ڕW�N�x��2024�N�x�܂ł̐摗�肷�邱�ƂɂȂ�A��^�g���b�N�̔R���
���NO���팸�̒x��ɂ����f����̂́A�����̈�ʍ����ł��邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ����낤�B���̂Ȃ�A���{�͑�
�^�g���b�N�̐V���Ȓ�R��E��r�o�K�X��𑁊��ɐݒ肹��I�ɏڏq���Ă���悤�ɁA�C���x�~�G���W��
�i�������J2005-54771�j�̓����Z�p���^�g���b�N�ɍ̗p�����ꍇ�A�u�m�n���r�o�l�� 0.23 g/kWh�iJE05���[
�h or WHTC���[�h)�܂ł̍팸�v�Ɓu2015�N�x�d�ʎԃ��[�h�R�������{�P�O�����x�̔R�����v��B����
����^�g���b�N���e�ՂɎ����ł���̂ł���B
�R������NO���팸�̗������Ɏ����ł����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p����������
�̎������}���邽�߁A���쎩���ԂƑ��̃g���b�N���[�J�́A���̓����Z�p�����R�C�܂܂Ɏ��Ђ̑�^�g���b�N�ɍ̗p
���闘�v�邱�Ƃ��ł���̂ł���B����ɑ��A���ɁA����A���y��ʏȂ̎����ԔR�����ψ���u�z�E�r
�C�ْ�~���̋C���x�~�V�X�e���v�̌��ט_���i�����ԋZ�p����ԍ�20145364�j�ɘf�킳����u��^�g���b�N�̑��s
�R��̑啝�ȉ��P���Z�p�I�ɍ���v�Ƃ̔F����A�������邱�Ƃɂ��A��^�g���b�N����2015�N�x�d�ʎԔR���
�����������鎟���̏d�ʎԔR���̖ڕW�N�x��2024�N�x�܂ł̐摗�肷�邱�ƂɂȂ�A��^�g���b�N�̔R���
���NO���팸�̒x��ɂ����f����̂́A�����̈�ʍ����ł��邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ����낤�B���̂Ȃ�A���{�͑�
�^�g���b�N�̐V���Ȓ�R��E��r�o�K�X��𑁊��ɐݒ肹��I�ɏڏq���Ă���悤�ɁA�C���x�~�G���W��
�i�������J2005-54771�j�̓����Z�p���^�g���b�N�ɍ̗p�����ꍇ�A�u�m�n���r�o�l�� 0.23 g/kWh�iJE05���[
�h or WHTC���[�h)�܂ł̍팸�v�Ɓu2015�N�x�d�ʎԃ��[�h�R�������{�P�O�����x�̔R�����v��B����
����^�g���b�N���e�ՂɎ����ł���̂ł���B
�@�ȏ�̂悤�ɁA�u�C���x�~�V�X�e���v�Ə̂���Z�p�ɂ́A�����ԋZ�p��2014�N�H�G�������쎩���Ԃ��_���i����
�ԍ�20145364�j�ɂ܂Ƃ߂����\�������s�R����P�̋@�\�E���\�ɍ\���I�Ȍ��ׂ����u�z�E�r�C�ْ�~���̋C���x
�~�V�X�e���v�̑��ɂ��A��^�g���b�N��NO���팸�Ƒ��s�R����P�̋@�\�ɗD�ꂽ�C���x�~�G���W���i�������J2005-
54771�j�̋Z�p��2005�N3���ɓ������J����Ă���̂ł���B���̂悤�ɁA��^�g���b�N��NO���팸�Ƒ��s�R����P��
�ɂ߂ėL���ł���A���A�e�ՂɎ��p�����\�Ȃ��C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋C���x�~�̋Z�p��
���ɑ��݂��Ă���ɂ�������炸�A���쎩���Ԃ͎������Z�p��2014�N�H�G�����\���I�Ȍ��ׂ������߂Ɏ��p
���̍���ȓ��قȁu�z�E�r�C�ْ�~���̋C���x�~�V�X�e���v���_���i�����ԍ�20145364�j�\�����̂ł���B
�ԍ�20145364�j�ɂ܂Ƃ߂����\�������s�R����P�̋@�\�E���\�ɍ\���I�Ȍ��ׂ����u�z�E�r�C�ْ�~���̋C���x
�~�V�X�e���v�̑��ɂ��A��^�g���b�N��NO���팸�Ƒ��s�R����P�̋@�\�ɗD�ꂽ�C���x�~�G���W���i�������J2005-
54771�j�̋Z�p��2005�N3���ɓ������J����Ă���̂ł���B���̂悤�ɁA��^�g���b�N��NO���팸�Ƒ��s�R����P��
�ɂ߂ėL���ł���A���A�e�ՂɎ��p�����\�Ȃ��C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋C���x�~�̋Z�p��
���ɑ��݂��Ă���ɂ�������炸�A���쎩���Ԃ͎������Z�p��2014�N�H�G�����\���I�Ȍ��ׂ������߂Ɏ��p
���̍���ȓ��قȁu�z�E�r�C�ْ�~���̋C���x�~�V�X�e���v���_���i�����ԍ�20145364�j�\�����̂ł���B
�@�������쎩���Ԃ��u���_���i�����ԍ�20145364�j�����\�����u�z�E�r�C�ْ�~���̋C���x�~�V�X�e���v�́A�\���I
�Ȍ��ׂ������߂Ɏ��p���̋ɂ߂č���ȓ��قȋZ�p�ł���B�������쎩���Ԃ��u���_���ł́A��{�I�ȍ\���I
�Ɍ��ׂ̂���C���x�~��I�����A���̋C���x�~�̋Z�p�̕s����ڍׂɉ�͂��Ď��p�����ɂ߂č���Ȃ��Ƃ���
��������e�̓Z�߂���ŁA��^�g���b�N�̔R����オ�Z�p�I�ɗe�ՂłȂ��ƌ��_�t���Ă���悤���B�܂�A������
�Z�p��2014�N�H�G�������쎩���Ԃ����\�����u���_���i�����ԍ�20145364�j�́A��^�g���b�N�̔R����P�Z�p��
�����ŏ����猇�ׂ����炩�ȁu�z�E�r�C�ْ�~���̋C���x�~�V�X�e���v�������đI�����A���́u�C���x�~�v�̋Z�p�̖�
��_���ڍׂɉ�͂��āA���p���̖����Z�p�ł��邱�Əڍׂɐ������Ă���̂ł���B�ʏ�A�ꗬ�̊�Ƃ̘_����
�́A�ŏ����猇�ׂ����炩�ȋZ�p�ɂ��āA���̋Z�p�̖��_���ڍׂɉ�͂��āA���p���̖����Z�p�ł��邱�ƌ�
�_�t����u���쎩���v�̂悤�Ȗ��ʂȘ_���͔��\���Ȃ����̂ł���B����́A���̊�Ƃ��u�n���ۏo���v�ƌ����錤
���J���𐢊ԂɎN�����ƂɂȂ邽�߂ł���B
�Ȍ��ׂ������߂Ɏ��p���̋ɂ߂č���ȓ��قȋZ�p�ł���B�������쎩���Ԃ��u���_���ł́A��{�I�ȍ\���I
�Ɍ��ׂ̂���C���x�~��I�����A���̋C���x�~�̋Z�p�̕s����ڍׂɉ�͂��Ď��p�����ɂ߂č���Ȃ��Ƃ���
��������e�̓Z�߂���ŁA��^�g���b�N�̔R����オ�Z�p�I�ɗe�ՂłȂ��ƌ��_�t���Ă���悤���B�܂�A������
�Z�p��2014�N�H�G�������쎩���Ԃ����\�����u���_���i�����ԍ�20145364�j�́A��^�g���b�N�̔R����P�Z�p��
�����ŏ����猇�ׂ����炩�ȁu�z�E�r�C�ْ�~���̋C���x�~�V�X�e���v�������đI�����A���́u�C���x�~�v�̋Z�p�̖�
��_���ڍׂɉ�͂��āA���p���̖����Z�p�ł��邱�Əڍׂɐ������Ă���̂ł���B�ʏ�A�ꗬ�̊�Ƃ̘_����
�́A�ŏ����猇�ׂ����炩�ȋZ�p�ɂ��āA���̋Z�p�̖��_���ڍׂɉ�͂��āA���p���̖����Z�p�ł��邱�ƌ�
�_�t����u���쎩���v�̂悤�Ȗ��ʂȘ_���͔��\���Ȃ����̂ł���B����́A���̊�Ƃ��u�n���ۏo���v�ƌ����錤
���J���𐢊ԂɎN�����ƂɂȂ邽�߂ł���B
�@�Ƃ��낪�A���쎩���Ԃ́A���̂悤�ȁu��Ђ̒p�v�����̂Ƃ������A���s�R����P�̋@�\�E���\�ɍ\���I�Ȍ��ׂ���
�u�z�E�r�C�ْ�~���̋C���x�~�V�X�e���v�̘_���������ԋZ�p��2014�N�H�G�������\�����̂ł���B���̂悤��
���疳�p�Ƃ��v�������Ș_������쎩���Ԃ������ԋZ�p��2014�N�H�G���ɂ����Ċ����Ĕ��\�����̂́A�u�C���x
�~�v�Ə̂���Z�p�́A�f�B�[�[���G���W�����ڂ̑�^�g���b�N�ɂ��������s�R��i���d�ʎԃ��[�h�R��j�̉��P������
�ł���Ƃ̕��]���L�߂邱�Ƃ��_���̉\�����l������B�����āA���̐^�̖ړI�́A��^�g���b�N��NO���팸�Ƒ�
�s�R����P�̋@�\�ɗD�ꂽ�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p�𑒂苎�邽�߂̑�ŋ��̂悤
�ɂ�������̂ł���B���̂��Ƃɂ��ẮA��^�g���b�N�̑��s�R��̉��P�Z�p�̊J�����i���w�����闧��ɂ��鍑
�y��ʏȂ́A���̓��쎩���Ԃ̍s�ׂ�e�F���Ă���悤�ł���A���y��ʏȂ��܂����s�R����P�̋@�\�ɗD��
���@�\�E���\�������C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p���E�َE������쎩���Ԃ̕��j
�Ɏ^�����Ă��邱�ƂɂȂ�B�������A���̂悤�Ȃ��Ƃ́A���y��ʏȂ̎{��Ƃ��ẮA�����I�ɗL�蓾�Ȃ��ƍl����̂�
�Ó��Ǝv����B���̂Ȃ�A���{�̃g���b�N���[�J�̋Z�p�ҁE���Ƃ⍑�y��ʏȂ̊����̑S�Ă̐l�B�́A��^�g��
�b�N�ɂ����鑁���̑啝�ȑ��s�R��̌����ؖ]���Ă��锤�ƁA�펯�I�ɂ͐�������邽�߂ł���B
�u�z�E�r�C�ْ�~���̋C���x�~�V�X�e���v�̘_���������ԋZ�p��2014�N�H�G�������\�����̂ł���B���̂悤��
���疳�p�Ƃ��v�������Ș_������쎩���Ԃ������ԋZ�p��2014�N�H�G���ɂ����Ċ����Ĕ��\�����̂́A�u�C���x
�~�v�Ə̂���Z�p�́A�f�B�[�[���G���W�����ڂ̑�^�g���b�N�ɂ��������s�R��i���d�ʎԃ��[�h�R��j�̉��P������
�ł���Ƃ̕��]���L�߂邱�Ƃ��_���̉\�����l������B�����āA���̐^�̖ړI�́A��^�g���b�N��NO���팸�Ƒ�
�s�R����P�̋@�\�ɗD�ꂽ�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p�𑒂苎�邽�߂̑�ŋ��̂悤
�ɂ�������̂ł���B���̂��Ƃɂ��ẮA��^�g���b�N�̑��s�R��̉��P�Z�p�̊J�����i���w�����闧��ɂ��鍑
�y��ʏȂ́A���̓��쎩���Ԃ̍s�ׂ�e�F���Ă���悤�ł���A���y��ʏȂ��܂����s�R����P�̋@�\�ɗD��
���@�\�E���\�������C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p���E�َE������쎩���Ԃ̕��j
�Ɏ^�����Ă��邱�ƂɂȂ�B�������A���̂悤�Ȃ��Ƃ́A���y��ʏȂ̎{��Ƃ��ẮA�����I�ɗL�蓾�Ȃ��ƍl����̂�
�Ó��Ǝv����B���̂Ȃ�A���{�̃g���b�N���[�J�̋Z�p�ҁE���Ƃ⍑�y��ʏȂ̊����̑S�Ă̐l�B�́A��^�g��
�b�N�ɂ����鑁���̑啝�ȑ��s�R��̌����ؖ]���Ă��锤�ƁA�펯�I�ɂ͐�������邽�߂ł���B
�@�Ƃ���ŁA�킪���̔R�����蓙�ɂ��Č������s�����y��ʏȂ̎����ԔR�����ψ���́A���L���\�S�R
�Ɏ������悤�ɁA���{���\����G���W���W�̊w�ҁE���Ƃɂ���č\������Ă���B
�Ɏ������悤�ɁA���{���\����G���W���W�̊w�ҁE���Ƃɂ���č\������Ă���B
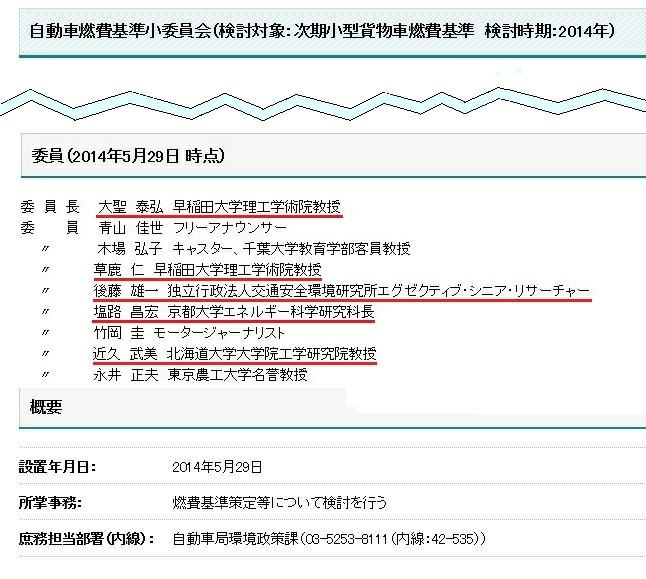 |
�@���̂悤�ɁA���y��ʏȂ̎����ԔR�����ψ���́A�ψ�������є����̈ψ������{���\����G���W����
�W�̊w�ҁE���Ƃō\������Ă���B���̂��߁A�G���W���W�̊w�ҁE���Ƃ��ߔ������߂鍑�y��ʏȂ̎���
�ԔR�����ψ���́A�C���x�~�G���W���ɂ���^�g���b�N�̒�R����C���x�~�́A�f�B�[�[���̂m�n���팸��
�R�����̈ꋓ�����̋Z�p���I�ɏڏq���Ă���悤�ɁA2014�N9�����_�ł͓��R�̂��ƂȂ���A�u�m�n���r�o�l�� 0.
23 g/kWh�iJE05���[�h or WHTC���[�h)�܂ł̍팸�v�Ɓu2015�N�x�d�ʎԃ��[�h�R�������{�P�O�����x�̔R���
��v��B��������^�g���b�N�������ł���B��̕��@�E��i���C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p
�ł��邱�Ƃ��\���ɗ����E�F�����Ă�����̂Ɛ��������B���̂Ȃ�A�����C���x�~�G���W���i�������J2005-
54771�j�̓����Z�p�́A2005�N3���ɓ������J����A2006�N4��7�����J�̕M�҂̃C���^�[�l�b�g�̃z�[���y�[�W�Ō�
�J������B
�W�̊w�ҁE���Ƃō\������Ă���B���̂��߁A�G���W���W�̊w�ҁE���Ƃ��ߔ������߂鍑�y��ʏȂ̎���
�ԔR�����ψ���́A�C���x�~�G���W���ɂ���^�g���b�N�̒�R����C���x�~�́A�f�B�[�[���̂m�n���팸��
�R�����̈ꋓ�����̋Z�p���I�ɏڏq���Ă���悤�ɁA2014�N9�����_�ł͓��R�̂��ƂȂ���A�u�m�n���r�o�l�� 0.
23 g/kWh�iJE05���[�h or WHTC���[�h)�܂ł̍팸�v�Ɓu2015�N�x�d�ʎԃ��[�h�R�������{�P�O�����x�̔R���
��v��B��������^�g���b�N�������ł���B��̕��@�E��i���C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p
�ł��邱�Ƃ��\���ɗ����E�F�����Ă�����̂Ɛ��������B���̂Ȃ�A�����C���x�~�G���W���i�������J2005-
54771�j�̓����Z�p�́A2005�N3���ɓ������J����A2006�N4��7�����J�̕M�҂̃C���^�[�l�b�g�̃z�[���y�[�W�Ō�
�J������B
�@�܂��A���y��ʏȂ̎����ԔR�����ψ���́A�\���l���̉ߔ��������{���\����G���W���W�̊w�ҁE��
��Ƃł��邽�߁A�����ԋZ�p��2014�N�H�G���ɂ��������쎩���Ԃ����\�����i�����ԋZ�p����ԍ�
20145364�j���u�z�E�r�C�ْ�~���̋C���x�~�V�X�e���v�̎��p���̍���Ȍ��Z�p�ł��邱�Ƃ𐫊i�ɗ������Ă���
���̂Ɛ��������B���������āA���쎩���Ԃ����Z�p�́u�z�E�r�C�ْ�~���̋C���x�~�V�X�e���v�̘_�����\�ɂ�
���āu��^�g���b�N�̑��s�R��̑啝�ȉ��P���Z�p�I�ɍ���v�Ƃ̋��U�I�ȋZ�p�����g�U���đ�^�g���b�N����
2015�N�x�d�ʎԔR�����������������̏d�ʎԔR���̖ڕW�N�x��啝�ɐ摗��i���Ⴆ�A�C���x�~�G��
�W���i�������J2005-54771�j�̓����������ł���2024�N�x���܂ł̐摗��j���悤�Ƃ��Ă��A�펯�I�ɍl����A���S
�ɖ��ʂȓk�J�ɏI�����̂Ɛ��@�����B���̂��߁A�Ⴆ���쎩���Ԃ����Z�p�̘_�����\���s���đ�^�g���b�N
����2015�N�x�d�ʎԔR�����������鎟���̏d�ʎԔR���̖ڕW�N�x��啝�ɐ摗������悤�Ƃ��Ă��A��
�݂��C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p���̗p���邱�Ƃɂ���āu�m�n���r�o�l�� 0.23 g/
kWh�iJE05���[�h or WHTC���[�h)�܂ł̍팸�v�Ɓu2015�N�x�d�ʎԃ��[�h�R�������{�P�O�����x�̔R��
����v��B��������^�g���b�N�����p�����邱�Ƃ��\�Ȃ��߁A���y��ʏȂ̎����ԔR�����ψ��
2015�N�x�d�ʎԔR�����������������̏d�ʎԔR���̖ڕW�N�x��2020�N�x���Ɛݒ�i�����\�j����
���A��^�g���b�N�̐��Y��̔����p�����{���邱�ƂɊւ��ẮA�킪���̑�^�g���b�N�̔R�����̋Z�p�ʂ�
�猩��Ă��A���̕s�s���⍬���������Ȃ��ł���B
��Ƃł��邽�߁A�����ԋZ�p��2014�N�H�G���ɂ��������쎩���Ԃ����\�����i�����ԋZ�p����ԍ�
20145364�j���u�z�E�r�C�ْ�~���̋C���x�~�V�X�e���v�̎��p���̍���Ȍ��Z�p�ł��邱�Ƃ𐫊i�ɗ������Ă���
���̂Ɛ��������B���������āA���쎩���Ԃ����Z�p�́u�z�E�r�C�ْ�~���̋C���x�~�V�X�e���v�̘_�����\�ɂ�
���āu��^�g���b�N�̑��s�R��̑啝�ȉ��P���Z�p�I�ɍ���v�Ƃ̋��U�I�ȋZ�p�����g�U���đ�^�g���b�N����
2015�N�x�d�ʎԔR�����������������̏d�ʎԔR���̖ڕW�N�x��啝�ɐ摗��i���Ⴆ�A�C���x�~�G��
�W���i�������J2005-54771�j�̓����������ł���2024�N�x���܂ł̐摗��j���悤�Ƃ��Ă��A�펯�I�ɍl����A���S
�ɖ��ʂȓk�J�ɏI�����̂Ɛ��@�����B���̂��߁A�Ⴆ���쎩���Ԃ����Z�p�̘_�����\���s���đ�^�g���b�N
����2015�N�x�d�ʎԔR�����������鎟���̏d�ʎԔR���̖ڕW�N�x��啝�ɐ摗������悤�Ƃ��Ă��A��
�݂��C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p���̗p���邱�Ƃɂ���āu�m�n���r�o�l�� 0.23 g/
kWh�iJE05���[�h or WHTC���[�h)�܂ł̍팸�v�Ɓu2015�N�x�d�ʎԃ��[�h�R�������{�P�O�����x�̔R��
����v��B��������^�g���b�N�����p�����邱�Ƃ��\�Ȃ��߁A���y��ʏȂ̎����ԔR�����ψ��
2015�N�x�d�ʎԔR�����������������̏d�ʎԔR���̖ڕW�N�x��2020�N�x���Ɛݒ�i�����\�j����
���A��^�g���b�N�̐��Y��̔����p�����{���邱�ƂɊւ��ẮA�킪���̑�^�g���b�N�̔R�����̋Z�p�ʂ�
�猩��Ă��A���̕s�s���⍬���������Ȃ��ł���B
�@�Ƃ��낪�A�\�����Ȃ����炩�̐����I�ȉe���͂ɂ���āA���ɁA���y��ʏȂ̎����ԔR�����ψ����
���{���\����G���W���W�̂T�l�̊w�ҁE���Ƃ́A������^�g���b�N��NO���팸�Ƒ��s�R����P�̋@�\
�ɗD�ꂽ�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p��ے�A�Ⴕ���͖����E�َE�������A����
�ł͍\���I�Ȍ��ׂ����u�z�E�r�C�ْ�~���̋C���x�~�V�X�e���v�̓��쎩���Ԃ̘_���i�����ԋZ�p���
�ԍ�20145364�j�ɂ����鋕�U�̋Z�p���������Ƃ���x���ŗ�Ȕ��f�������đ�^�g���b�N�p�f�B�[�[���G
���W���̔R����P�̋Z�p�������Ɂu���J���v�̏ɂ���ƔF�肷��\�����l������B���̍ۂɂ́A
�u2015�N�x�d�ʎԃ��[�h�R�������{�P�O�����x�̔R�����v�̃��x���̔R���̋������C���x�~�G
���W���i�������J2005-54771�j�̓������̏��ł���2024�N�x���ɐݒ�i�����\�j���邱�Ƃ����y��ʏȂ̎�
���ԔR�����ψ�����肷����̂Ɛ��������B���̏ꍇ�ɂ́A�����ԔR�����ψ���g���b�N���[�J
�i�����{�����ԍH�Ɖ�j�́u���͂ȉe���́H�Ɏx�z����Ă���v���Ƃ�A�Ⴕ���́u���ʂȎ�����z���H���Ă���v
�悤�ȏɒu����Ă���\�����ɂ߂č����Ɛ��@�����B
���{���\����G���W���W�̂T�l�̊w�ҁE���Ƃ́A������^�g���b�N��NO���팸�Ƒ��s�R����P�̋@�\
�ɗD�ꂽ�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p��ے�A�Ⴕ���͖����E�َE�������A����
�ł͍\���I�Ȍ��ׂ����u�z�E�r�C�ْ�~���̋C���x�~�V�X�e���v�̓��쎩���Ԃ̘_���i�����ԋZ�p���
�ԍ�20145364�j�ɂ����鋕�U�̋Z�p���������Ƃ���x���ŗ�Ȕ��f�������đ�^�g���b�N�p�f�B�[�[���G
���W���̔R����P�̋Z�p�������Ɂu���J���v�̏ɂ���ƔF�肷��\�����l������B���̍ۂɂ́A
�u2015�N�x�d�ʎԃ��[�h�R�������{�P�O�����x�̔R�����v�̃��x���̔R���̋������C���x�~�G
���W���i�������J2005-54771�j�̓������̏��ł���2024�N�x���ɐݒ�i�����\�j���邱�Ƃ����y��ʏȂ̎�
���ԔR�����ψ�����肷����̂Ɛ��������B���̏ꍇ�ɂ́A�����ԔR�����ψ���g���b�N���[�J
�i�����{�����ԍH�Ɖ�j�́u���͂ȉe���́H�Ɏx�z����Ă���v���Ƃ�A�Ⴕ���́u���ʂȎ�����z���H���Ă���v
�悤�ȏɒu����Ă���\�����ɂ߂č����Ɛ��@�����B
�@�Ȃ��A���ɁA�g���b�N���[�J�i�����{�����ԍH�Ɖ�j�������ԔR�����ψ���ɋ����e���͂��y�ڂ����Ƃɂ����
���{���u2015�N�x�d�ʎԃ��[�h�R�������{�P�O�����x�̔R�����v�̃��x���̎����̔R���̋������P
�O�N���2024�N�x���̎��{�Ƃ��邱�Ƃɐ��������ꍇ�ɂ́A�g���b�N���[�J�́A2024�N�x�ɏ��ł����C���x�~�G���W
���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p���g���b�N���[�J������Ď��R����ɑ�^�g���b�N�ɍ̗p�ł��邱�ƂɂȂ�B����
�āA���̂��Ƃ́A�����ԔR�����ψ���玟���̔R���ɑ�^�g���b�N��e�ՂɓK�������鉶�b�������ŗ^
�����邱�ƂɂȂ�A���A�M�҂̓��������ł̓����Z�p�i�����M���ĉ���肵�������Z�p�H�j�����Ђ̍l�Ă���
�Z�p�̂悤�ɋU�����Đ�`������T���^�����邱�ƂɂȂ�B����́A�g���b�N���[�J�ɂƂ��Ắu�������I������
��I�v�ł���A���̎~�܂�Ȃ����ƂɂȂ�ƍl������B���̂��߁A����A���y��ʏȁE�����ԔR�����ψ���
���u2015�N�x�d�ʎԃ��[�h�R���v�̋����̖ڕW�N�x��2024�N�x���ɐݒ�i=���\�j�����ꍇ�ɂ́A�g���b
�N���[�J�i�����{�����ԍH�Ɖ�j�Ǝ����ԔR�����ψ���Ƃ̕s�ސT�Ȗ����H�����݂���\���́A�ے�
�ł��Ȃ����Ƃł���B
���{���u2015�N�x�d�ʎԃ��[�h�R�������{�P�O�����x�̔R�����v�̃��x���̎����̔R���̋������P
�O�N���2024�N�x���̎��{�Ƃ��邱�Ƃɐ��������ꍇ�ɂ́A�g���b�N���[�J�́A2024�N�x�ɏ��ł����C���x�~�G���W
���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p���g���b�N���[�J������Ď��R����ɑ�^�g���b�N�ɍ̗p�ł��邱�ƂɂȂ�B����
�āA���̂��Ƃ́A�����ԔR�����ψ���玟���̔R���ɑ�^�g���b�N��e�ՂɓK�������鉶�b�������ŗ^
�����邱�ƂɂȂ�A���A�M�҂̓��������ł̓����Z�p�i�����M���ĉ���肵�������Z�p�H�j�����Ђ̍l�Ă���
�Z�p�̂悤�ɋU�����Đ�`������T���^�����邱�ƂɂȂ�B����́A�g���b�N���[�J�ɂƂ��Ắu�������I������
��I�v�ł���A���̎~�܂�Ȃ����ƂɂȂ�ƍl������B���̂��߁A����A���y��ʏȁE�����ԔR�����ψ���
���u2015�N�x�d�ʎԃ��[�h�R���v�̋����̖ڕW�N�x��2024�N�x���ɐݒ�i=���\�j�����ꍇ�ɂ́A�g���b
�N���[�J�i�����{�����ԍH�Ɖ�j�Ǝ����ԔR�����ψ���Ƃ̕s�ސT�Ȗ����H�����݂���\���́A�ے�
�ł��Ȃ����Ƃł���B
�@���̂悤�ɁA�g���b�N���[�J�i�����{�����ԍH�Ɖ�j�Ǝ����ԔR�����ψ���Ƃ̕s�ސT�Ȗ����H�ɂ���č��y��
�ʏȁE�����ԔR�����ψ���u2015�N�x�d�ʎԃ��[�h�R���v�̋����̖ڕW�N�x��2024�N�x���ɐݒ�i=��
�\�j���鐬�ʂ��m���ɓ�����̂ł���A�g���b�N���[�J�i�����{�����ԍH�Ɖ�j�́A�ɂ߂ē������ʂ̑傫������
�ɂȂ邪�A���̂悤�ȃe���r�h���}�̂悤�Ȋ��������ۂɎ��{���悤�Ƃ��Ă��邩�ۂ��́A�M�҂ɂ͕s���ł���B������
�Ȃ���A���쎩���Ԃ����Z�p���u�z�E�r�C�ْ�~���̋C���x�~�V�X�e���v���u���_���i�����ԍ�20145364�j����
���ԋZ�p��2014�N�H�G�������\���A��^�g���b�N�̔R����オ�Z�p�I�ɍ���Ƃ��鋕�U�I�ȋZ�p�����g�U����
�d�ʎԂ̎����R���̎��{��摗��i���Ⴆ�A�Q�O�Q�S�N�x���Ɏ��{�j���邱�Ƃ�_�������邱�Ƃ͎����ƍl����
���A�@���Ȃ��̂ł��낤���B
�ʏȁE�����ԔR�����ψ���u2015�N�x�d�ʎԃ��[�h�R���v�̋����̖ڕW�N�x��2024�N�x���ɐݒ�i=��
�\�j���鐬�ʂ��m���ɓ�����̂ł���A�g���b�N���[�J�i�����{�����ԍH�Ɖ�j�́A�ɂ߂ē������ʂ̑傫������
�ɂȂ邪�A���̂悤�ȃe���r�h���}�̂悤�Ȋ��������ۂɎ��{���悤�Ƃ��Ă��邩�ۂ��́A�M�҂ɂ͕s���ł���B������
�Ȃ���A���쎩���Ԃ����Z�p���u�z�E�r�C�ْ�~���̋C���x�~�V�X�e���v���u���_���i�����ԍ�20145364�j����
���ԋZ�p��2014�N�H�G�������\���A��^�g���b�N�̔R����オ�Z�p�I�ɍ���Ƃ��鋕�U�I�ȋZ�p�����g�U����
�d�ʎԂ̎����R���̎��{��摗��i���Ⴆ�A�Q�O�Q�S�N�x���Ɏ��{�j���邱�Ƃ�_�������邱�Ƃ͎����ƍl����
���A�@���Ȃ��̂ł��낤���B
�@�ȏ�̂��Ƃ����Ă���ƁA������u2015�N�x�d�ʎԃ��[�h�R���v�̋����̐ݒ�ɍۂ��ẮA�A���y��ʏȁE��
���ԔR�����ψ�����肷���u2015�N�x�d�ʎԃ��[�h�R���v�̋��������{����ڕW�N�x�̐ݒ�ɍۂ���
�́A���y��ʏȁE�����ԔR�����ψ�����肷��ڕW�N�x�̎����i��2020�N���A�Ⴕ����2024�N���j�̉��ꂩ
�ɂ���āA�����ԔR�����ψ���̃G���W���W�̂T�l�̊w�ҁE���Ƃɂ�������{�̏d�v�ȋK���W�̐E��
���s�̎p����A�����ԔR�����ψ���̏����̐l�Ԑ������_�Ԍ��邱�Ƃ��ł���ƍl������B
���ԔR�����ψ�����肷���u2015�N�x�d�ʎԃ��[�h�R���v�̋��������{����ڕW�N�x�̐ݒ�ɍۂ���
�́A���y��ʏȁE�����ԔR�����ψ�����肷��ڕW�N�x�̎����i��2020�N���A�Ⴕ����2024�N���j�̉��ꂩ
�ɂ���āA�����ԔR�����ψ���̃G���W���W�̂T�l�̊w�ҁE���Ƃɂ�������{�̏d�v�ȋK���W�̐E��
���s�̎p����A�����ԔR�����ψ���̏����̐l�Ԑ������_�Ԍ��邱�Ƃ��ł���ƍl������B
| |
|
| |
�� �C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p�̗̍p�ɂ��A
�����_�ő�^�g���b�N�̏\���ȔR����オ�\�Ƃ̔��f����A�d�ʎԂ� �����R�����Q�O�Q�O�N�x���Ɏ��{���邱�Ƃ����� �� �����ԔR�����ψ���́A��^�g���b�N�̔R����P�̋Z�p�I�Ȑi�W�𐳊m�� �c��������ŁA�w�ҁE���Ƃ̗ǐS�ɒ����ɐE���𐋍s |
| |
�� �R����P�ɗL�����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p��
�����E�َE�������ŁA�f�B�[�[���G���W���̔R����P�̗L���ȋZ�p�����J�� �Ƃ̔��f���A�d�ʎԂ̎����R�����Q�O�Q�S�N�x���Ɏ��{���邱�Ƃ����� �i�����ԔR�����ψ���́A�g���b�N���[�J�i�����{�����ԍH�Ɖ�j���̋���
���͓��ɂ��A�R����P�ɗL�����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j��
�����������ł���Q�O�Q�S�N�x���ɏd�ʎԂ̎����R���̎��{������j
�� �����ԔR�����ψ���́A��^�g���b�N�̔R����P�ɗL����
�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p�̑��݂��E�َE��
�f�B�[�[���G���W���̔R����P�̗L���ȋZ�p�����J���Ƃ̍��\�I�ȋZ�p�J����
����c���̝s�����ɂ��A�w�ҁE���ƂƂ��Ă̈�Ђ̗ǐS�����̂Ă��E���̐��s |
| �� �C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p����^�g���b�N��
�R����P�ɖ����Ɣ��f�������ʂł���̂��A�Ⴕ���́A�C���^�[�l�b�g���ɂ�� �����W�̔\�͕s���ɂ���C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�� �����Z�p�̑��݂̔F�����@�ł��邩�̉��ꂩ�̌����ɂ��A�f�B�[�[���� �R����P�̗L���ȋZ�p�����J���ƕ]���E���肵�����ʁA�d�ʎԂ̎����R���� �Q�O�Q�S�N�x���Ɏ��{���邱�Ƃ����� �� �����ԔR�����ψ���̃G���W���W�̂T�l�̊w�ҁE���Ƃ́A
�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p�ɂ������^�g���b�N��
�R����P�̋@�\�E���\������s�\�ł���ꍇ��A���̓����Z�p�Ɋւ���
�Z�p���̎��W�s�\�ł������ꍇ�ɂ́A�G���W���W�̊w�ҁE���ƂƂ��Ă�
�E�����s�̔\�͂ɋ^��
|
�@�����Ƃ��A���y��ʏȂ̎����ԔR�����ψ���́A�ψ�������є����̈ψ������{���\����G���W���W��
�����Ȋw�ҁE���Ƃł���A�Ȃ����A�{���͑S������簂Ȏu�̈ψ��ō\������Ă��邱�Ƃ��l������ƁA�펯�I��
�l����A���ۂɃg���b�N���[�J�i�����{�����ԍH�Ɖ�j�Ǝ����ԔR�����ψ���Ƃ̖����H�̉\���͊F���ƍl
������B�����͉]���Ă��A����A�킪�����d�ʎԂ̎����R���̎��{�N�x�����ۂɁu�Q�O�Q�O�N�x���v���A�Ⴕ��
�́u�Q�O�Q�S�N�x���v�̉���̎����ɐݒ肳���̂��́A�傢�ɒ��ڂ����Ƃ���ł���B
�����Ȋw�ҁE���Ƃł���A�Ȃ����A�{���͑S������簂Ȏu�̈ψ��ō\������Ă��邱�Ƃ��l������ƁA�펯�I��
�l����A���ۂɃg���b�N���[�J�i�����{�����ԍH�Ɖ�j�Ǝ����ԔR�����ψ���Ƃ̖����H�̉\���͊F���ƍl
������B�����͉]���Ă��A����A�킪�����d�ʎԂ̎����R���̎��{�N�x�����ۂɁu�Q�O�Q�O�N�x���v���A�Ⴕ��
�́u�Q�O�Q�S�N�x���v�̉���̎����ɐݒ肳���̂��́A�傢�ɒ��ڂ����Ƃ���ł���B
�@���͂Ƃ�����A�䂪���ɂ������^�g���b�N�̔���I�Ȏ����s�R��i���d�ʎԃ��[�h�R��j�̉��P�𑁊��Ɏ�����
�邽�߂ɂ́A�悸�A���쎩���Ԃ��܂ޓ��{�̃g���b�N���[�J�́A�^�[�{�ߋ��@�̃T�[�W���O�����̍\���I�Ȍ��ׂ̂�
�߂ɑ�^�g���b�N�̑��s�R����\���ɉ��P���邱�Ƃ�����ȁu�z�E�r�C�ْ�~���̋C���x�~�V�X�e���v�̌����J����
���}�ɒ��~���ׂ��ƍl������B�����āA��^�g���b�N�́u�����s�R��v��u�d�ʎԃ��[�h�R��v���\���Ɍ���ł�
�钘�Ғ�Ă��C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p�̌����J���ɁA�����A���g�ނ��Ƃ�
�K�v�E�s���ƍl����B
�邽�߂ɂ́A�悸�A���쎩���Ԃ��܂ޓ��{�̃g���b�N���[�J�́A�^�[�{�ߋ��@�̃T�[�W���O�����̍\���I�Ȍ��ׂ̂�
�߂ɑ�^�g���b�N�̑��s�R����\���ɉ��P���邱�Ƃ�����ȁu�z�E�r�C�ْ�~���̋C���x�~�V�X�e���v�̌����J����
���}�ɒ��~���ׂ��ƍl������B�����āA��^�g���b�N�́u�����s�R��v��u�d�ʎԃ��[�h�R��v���\���Ɍ���ł�
�钘�Ғ�Ă��C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p�̌����J���ɁA�����A���g�ނ��Ƃ�
�K�v�E�s���ƍl����B
�@���݂ɁA�ŋ߂̑�^�̊O�q�D�ł́A�R����̍팸��}��ړI�̂��߂ɁA�D����Ⴍ�}���������^�q������I��
�L�����{����Ă���Ƃ̂��Ƃł���B���ɁA�R���e�i�D�́A�R����̍팸��}��ړI�̂��߂ɁA��i�o�͂̂S�O���`�P
�O���̃G���W���o�͂ōq�s����啝�Ȍ����^�q�����{����Ă���悤�ł���B���̏ꍇ�A�G���W���̋C���x�~�́A��
���^�q���̍X�Ȃ�R����オ�\�ɏڏq���Ă���悤�ɁA�M�Ғ�Ă��C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j��
�����Z�p�́A�D���̑啝�Ȍ����^�q�̍X�Ȃ�R��̌����}�邱�Ƃ��\�ƂȂ�B���̂��߁A�߂������A�C���x�~
�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p�́A��^�g���b�N�����Ŗ����A��^�̑D���ɂ����Ă��L���̗p��������
�Ɛ��������B
�L�����{����Ă���Ƃ̂��Ƃł���B���ɁA�R���e�i�D�́A�R����̍팸��}��ړI�̂��߂ɁA��i�o�͂̂S�O���`�P
�O���̃G���W���o�͂ōq�s����啝�Ȍ����^�q�����{����Ă���悤�ł���B���̏ꍇ�A�G���W���̋C���x�~�́A��
���^�q���̍X�Ȃ�R����オ�\�ɏڏq���Ă���悤�ɁA�M�Ғ�Ă��C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j��
�����Z�p�́A�D���̑啝�Ȍ����^�q�̍X�Ȃ�R��̌����}�邱�Ƃ��\�ƂȂ�B���̂��߁A�߂������A�C���x�~
�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p�́A��^�g���b�N�����Ŗ����A��^�̑D���ɂ����Ă��L���̗p��������
�Ɛ��������B
�Q�S�@�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�́A��^�g���b�N�̒�NO���ƒ�R�������
�@�������R�c��E��C������̎����Ԕr�o�K�X���ψ�����܂ޓ��{�̊w�ҁE���ƁE�Z�p�҂̑����̐l�B
�́A��^�g���b�N��NO���팸�ƔR�����ɗL���ȋC���x�~��َE����w�ҏ����ɏڏq���Ă���悤�ɁA�]���Ɠ��l��
��^�g���b�N���d�ʎԃ��[�h�R�������s�R����T�`�P�O�����x�����P�ł����C���x�~�G���W���i�������J2005-
54771�j�̋Z�p�������_�i��2014�N10�����_�j�ł͊��S�ɖ����E�َE���Ă���悤�ł���B���̈���ŁA�������R�c
��E��C������̎����Ԕr�o�K�X���ψ�����܂ޓ��{�̊w�ҁE���ƁE�Z�p�҂̑����̐l�B�́A�P�������̔R
������P�ł��Ȃ��Z�p�̊W�߂ɂ���ď����I�ɑ�^�g���b�N�̏\���ȔR����P�������ł���ƍ�����咣��
������Ƃ���A�ނ�͓��{�̑�^�g���b�N�ɂ�����R�����̐i�W��j�Q����s�ׁE�������s���Ă���悤�ɂ���
����̂ł���B����́A���h�Ȕ��Љ�I�s�ׂ̂悤�Ɏv���邪�A�@���Ȃ��̂ł��낤���B
�́A��^�g���b�N��NO���팸�ƔR�����ɗL���ȋC���x�~��َE����w�ҏ����ɏڏq���Ă���悤�ɁA�]���Ɠ��l��
��^�g���b�N���d�ʎԃ��[�h�R�������s�R����T�`�P�O�����x�����P�ł����C���x�~�G���W���i�������J2005-
54771�j�̋Z�p�������_�i��2014�N10�����_�j�ł͊��S�ɖ����E�َE���Ă���悤�ł���B���̈���ŁA�������R�c
��E��C������̎����Ԕr�o�K�X���ψ�����܂ޓ��{�̊w�ҁE���ƁE�Z�p�҂̑����̐l�B�́A�P�������̔R
������P�ł��Ȃ��Z�p�̊W�߂ɂ���ď����I�ɑ�^�g���b�N�̏\���ȔR����P�������ł���ƍ�����咣��
������Ƃ���A�ނ�͓��{�̑�^�g���b�N�ɂ�����R�����̐i�W��j�Q����s�ׁE�������s���Ă���悤�ɂ���
����̂ł���B����́A���h�Ȕ��Љ�I�s�ׂ̂悤�Ɏv���邪�A�@���Ȃ��̂ł��낤���B
�@���Ă��āA���ɁA�������R�c��E��C������̎����Ԕr�o�K�X���ψ�����܂ޓ��{�̊w�ҁE���ƁE�Z�p
�҂��]�����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j���܂ދC���x�~�̋Z�p�������E�َE���Ă����s�ׁE�����̌�
��Ȃ��A�Ȍ�A��^�g���b�N�̏����I�ȔR����P�̂��߂ɋC���x�~�̋Z�p�𐄏�������j�ɑ�ύX����悤��
�ǂ��悤�ł���A���{�̉ݕ��A��������ȃG�l���M�[�̐��i��}�邱�ƂɂȂ�B�����āA���{�̑�^�g���b�N��
���[�U�́A�R����P�̉��b�ɗ����邱�ƂɂȂ�B�����āA���ꂪ�������R�c��E��C������̎����Ԕr�o�K�X
���ψ�����܂ޓ��{�̊w�ҁE���ƁE�Z�p�҂̖{���̐E�Ə�̎g���ƍl���邪�A�@���Ȃ��̂ł��낤���B��킭
�A�������R�c��E��C������̎����Ԕr�o�K�X���ψ�����܂ޓ��{�̊w�ҁE���ƁE�Z�p�҂́A����܂�
�̋C���x�~�̋Z�p�������E�َE���Ă����ߋ��̍s�ׁE�����̌��Ȃ��A�S�Ă̍����̊��҂ɉ����悤�ɁA�����
��^�g���b�N�̏����I�ȔR����P�̂��߂ɁA�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p�̎��p���Ɍ���
���ϋɓI�Ȋ����ɋC�́E���͂��X�����Ă��������������̂ł���B
�҂��]�����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j���܂ދC���x�~�̋Z�p�������E�َE���Ă����s�ׁE�����̌�
��Ȃ��A�Ȍ�A��^�g���b�N�̏����I�ȔR����P�̂��߂ɋC���x�~�̋Z�p�𐄏�������j�ɑ�ύX����悤��
�ǂ��悤�ł���A���{�̉ݕ��A��������ȃG�l���M�[�̐��i��}�邱�ƂɂȂ�B�����āA���{�̑�^�g���b�N��
���[�U�́A�R����P�̉��b�ɗ����邱�ƂɂȂ�B�����āA���ꂪ�������R�c��E��C������̎����Ԕr�o�K�X
���ψ�����܂ޓ��{�̊w�ҁE���ƁE�Z�p�҂̖{���̐E�Ə�̎g���ƍl���邪�A�@���Ȃ��̂ł��낤���B��킭
�A�������R�c��E��C������̎����Ԕr�o�K�X���ψ�����܂ޓ��{�̊w�ҁE���ƁE�Z�p�҂́A����܂�
�̋C���x�~�̋Z�p�������E�َE���Ă����ߋ��̍s�ׁE�����̌��Ȃ��A�S�Ă̍����̊��҂ɉ����悤�ɁA�����
��^�g���b�N�̏����I�ȔR����P�̂��߂ɁA�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p�̎��p���Ɍ���
���ϋɓI�Ȋ����ɋC�́E���͂��X�����Ă��������������̂ł���B
�@���͂Ƃ�����A�C���x�~�́A�f�B�[�[���̂m�n���팸�ƔR�����̈ꋓ�����̋Z�p���I�ɂ��ڏq���Ă���悤�ɁA�M
�Ғ�Ắu�f�B�[�[���G���W���̔R���NO���Ƃ̓����̍팸�������ł���v�V�I�ȋZ�p�v�ł����C���x�~�G���W��
�i�������J2005-54771�j�̓����Z�p�����p������A���{�i�����ȁE���y��ʏȁj�́A���{�́uNOx�ƔR��̋K��
�����v���e�ՂɎ����ł���ƕM�҂͌ł��M���Ă���B�܂�A�č������ɂ���^�g���b�N��NO���K�����{�s��������
���{���{�̑Ӗ��ɂ��ڏq���Ă���悤�ɁA��^�g���b�N���C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p����
�p���邱�Ƃɂ���āA�����_�ł́A�u���{�̑�^�g���b�N�ɂ����Ă��č������ɂ�NO���K���v�����{������Ȃ�
�ߎS�ȏ��A�����ɉ����E�����ł���̂ł���B���̑��ɂ��A�ȉ����\�S�T�Ɏ������悤�ɁA�C���x�~�G���W���i��
�����J2005-54771�j�̓����Z�p�́A�uDPF���u�ł̎��ȍĐ��̉^�]�̈�̊g��ɂ��R�����v�A�u�^�[�{�R���p�E
���h���̔r�M�G�l���M�[�̉������������v�A�u�G���W���������ׂɂ������A�fSCR�G�}�̐G�}�������ɂ��NO��
�팸�v�A�u�g�p�ߒ��Ԃɂ�����A�fSCR�G�}��HC��ł̉v�A������uJE�O�T���[�h�ł̃R�[���h�X�^�[�g�����ɂ�
����NOx�r�o�̍팸�v�̗D�ꂽ�@�\�E���\�������ł��邽���A���݂���^�g���b�N�������Ă���ۑ�̖w��ǂ�����
�ł���V�Z�p�ł���B�܂��A�f�B�[�[���̋C���x�~�́A�R�[���h�X�^�[�g��NO���팸�ɂ��L�����I�ɏڏq���Ă���悤
�ɁA�Q�^�[�{�������C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p�́AJE�O�T���[�h�̃R�[���h�X�^�[�g������
�ɂ�����NO���̔r�o���팸���邱�Ƃ̉\�ł���B
�Ғ�Ắu�f�B�[�[���G���W���̔R���NO���Ƃ̓����̍팸�������ł���v�V�I�ȋZ�p�v�ł����C���x�~�G���W��
�i�������J2005-54771�j�̓����Z�p�����p������A���{�i�����ȁE���y��ʏȁj�́A���{�́uNOx�ƔR��̋K��
�����v���e�ՂɎ����ł���ƕM�҂͌ł��M���Ă���B�܂�A�č������ɂ���^�g���b�N��NO���K�����{�s��������
���{���{�̑Ӗ��ɂ��ڏq���Ă���悤�ɁA��^�g���b�N���C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p����
�p���邱�Ƃɂ���āA�����_�ł́A�u���{�̑�^�g���b�N�ɂ����Ă��č������ɂ�NO���K���v�����{������Ȃ�
�ߎS�ȏ��A�����ɉ����E�����ł���̂ł���B���̑��ɂ��A�ȉ����\�S�T�Ɏ������悤�ɁA�C���x�~�G���W���i��
�����J2005-54771�j�̓����Z�p�́A�uDPF���u�ł̎��ȍĐ��̉^�]�̈�̊g��ɂ��R�����v�A�u�^�[�{�R���p�E
���h���̔r�M�G�l���M�[�̉������������v�A�u�G���W���������ׂɂ������A�fSCR�G�}�̐G�}�������ɂ��NO��
�팸�v�A�u�g�p�ߒ��Ԃɂ�����A�fSCR�G�}��HC��ł̉v�A������uJE�O�T���[�h�ł̃R�[���h�X�^�[�g�����ɂ�
����NOx�r�o�̍팸�v�̗D�ꂽ�@�\�E���\�������ł��邽���A���݂���^�g���b�N�������Ă���ۑ�̖w��ǂ�����
�ł���V�Z�p�ł���B�܂��A�f�B�[�[���̋C���x�~�́A�R�[���h�X�^�[�g��NO���팸�ɂ��L�����I�ɏڏq���Ă���悤
�ɁA�Q�^�[�{�������C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p�́AJE�O�T���[�h�̃R�[���h�X�^�[�g������
�ɂ�����NO���̔r�o���팸���邱�Ƃ̉\�ł���B
| |
|
|
| |
�����������C���x�~�̌��ʂɂ��A�d�ʎԃ��[�h�R��͂T�`�P�O���̌��オ�\
�i���������ɂ�����u�T�C�N�������̌���v����сu��p�����̍팸�v�ɂ��R����P���ʁj �m�Ⴆ�A�C���x�~�́A�f�B�[�[���̂m�n���팸�ƔR�����̈ꋓ�����̋Z�p���I���Q�Ɓn |
|
| |
���������̔r�C�K�X�̍������ɂ��ADPF���u�ł̎��ȍĐ��̉^�]�̈�̊g��ɂ��R�����
�i�㏈������V�X�e���i�������J2005-69238�j���̗p�����ꍇ�ɂ́A�X�Ȃ�R���Q��̖h�~�𑣐i�j �i�|�X�g���˂܂���HC�r�C�Ǖ��˂�DPF�����Đ��̉������A�����Đ��ɂ��R���Q���h�~�j �m�Ⴆ�A�C���x�~��DPF�̎��ȍĐ��𑣐i (�����Đ��̍팸�ŔR�����h�~�j���Q�Ɓn |
|
| |
���������̔r�C�K�X�̍������ɂ��A�^�[�{�R���p�E���h�ł̔r�M�G�l���M�[�̉������������
�m�Ⴆ�A�^�[�{�R���p�E���h�́A��^�g���b�N�̑��s�R��̉��P������ȋZ�p���I���Q�Ɓn �m�Ⴆ�A�C���x�~�́A�f�B�[�[���̂m�n���팸�ƔR�����̈ꋓ�����̋Z�p���I���Q�Ɓn [�Ⴆ�A�C���x�~�́A�f�B�[�[���r�C�K�X�̃G�l���M�[���u�̌������������Q�Ɓn |
|
| |
���������̔r�K�X���x�̍������ɂ��A�A�fSCR�G�}�ł�NO���팸���̌��オ�\
�m�Ⴆ�A�C���x�~�́A�f�B�[�[���̂m�n���팸�ƔR�����̈ꋓ�����̋Z�p���I���Q�Ɓn |
|
| �D | �����s�����r�K�X���x�̍����ێ��@�\�ɂ��A�g�p�ߒ��Ԃɂ�����A�fSCR�G�}��HC��ł̉�
�i�㏈������V�X�e���i�������J2005-69238�j���ꍇ�ɂ́A�X�Ȃ�A�fSCR�G�}��HC��ł̉j
�m�Ⴆ�A�C���x�~��DPF�̎��ȍĐ��𑣐i (�����Đ��̍팸�ŔR�����h�~�j���Q�Ɓn
|
|
| |
JE�O�T���[�h�ł̃R�[���h�X�^�[�g�����ɂ�����NOx�r�o�̍팸
�iJE�O�T���̃R�[���h�X�^�[�g������NO���r�o��啝�ɍ팸�ł���B��̎��p�I�ȋZ�p�j [�Ⴆ�A�f�B�[�[���̋C���x�~�́A�R�[���h�X�^�[�g��NO���팸�ɂ��L�����I���Q��] |
|
�@�ȏ�̂悤�ɁA�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p�����p�����A���̋Z�p���^�g���b�N�ɐV���ɍ̗p
���邱�Ƃɂ���āA���݂̑�^�g���b�N�̉ۑ肪�w��lj����ł���̂ł���B���̂��߁A����̑�^�g���b�N�ɂ�����
�R�����̑��i��}�邽�߂ɂ́A�������R�c��̎����Ԕr�o�K�X���ψ�����܂ސ��{�E�����i�����ȁE��
�y��ʏȓ��j�̐l�B�́A�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p�𑁊��Ɏ��p�����邽�߂̍s�����N����
�ׂ��ƍl���邪�A�@���Ȃ��̂ł��낤���B
���邱�Ƃɂ���āA���݂̑�^�g���b�N�̉ۑ肪�w��lj����ł���̂ł���B���̂��߁A����̑�^�g���b�N�ɂ�����
�R�����̑��i��}�邽�߂ɂ́A�������R�c��̎����Ԕr�o�K�X���ψ�����܂ސ��{�E�����i�����ȁE��
�y��ʏȓ��j�̐l�B�́A�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p�𑁊��Ɏ��p�����邽�߂̍s�����N����
�ׂ��ƍl���邪�A�@���Ȃ��̂ł��낤���B
�@
�@�Ƃ���ŁA�]�k�ł��邪�A�p��̌��Ɂu�n�𐅕ӂɓ������Ƃ͂ł��邪�A�i�n�ɂ��̋C���Ȃ���j�������܂��邱��
�͂ł��Ȃ��v�yA man may lead a horse to the water�C but he cannot make him drink�iunless he will�j�z�Ɖ]�����̂���
�邻�����B����́A2015�N�x�d�ʎԔR���ɕs�K���̎Ԏ������Ă����g���b�N���[�J��A�č������ɂ����{��
��^�g���b�N��NO���K�����{�s�������Ă�����{���{�i�����ȁE���y��ʏȁj���A�C���x�~�G���W���i�������J2005
-54771�j�̋Z�p����Ȃɖ����E�َE���Ă���l�q�ɓ��ěƂ܂肻�����B
�͂ł��Ȃ��v�yA man may lead a horse to the water�C but he cannot make him drink�iunless he will�j�z�Ɖ]�����̂���
�邻�����B����́A2015�N�x�d�ʎԔR���ɕs�K���̎Ԏ������Ă����g���b�N���[�J��A�č������ɂ����{��
��^�g���b�N��NO���K�����{�s�������Ă�����{���{�i�����ȁE���y��ʏȁj���A�C���x�~�G���W���i�������J2005
-54771�j�̋Z�p����Ȃɖ����E�َE���Ă���l�q�ɓ��ěƂ܂肻�����B
�@�܂��A�u�������ދC�̖����n�ɐ������܂��邽�߂ɂ́A�A�������܂Ŕn�ʂɑ��点��I�i���A�������܂Ŕn���
���Ēu���I�j�v�Ƃ̗��o�[�W�����̌�������悤���B���̗��o�[�W�����̌��̈Ӗ��̉����ăg���b�N���[�J�̍s����\��
����ƁA�e�g���b�N���[�J���]���ʂ���R����P�ɖ����ȋZ�p�̊J�����������J���̌����i���J���̐l�H�A�ݔ��A��
���j��Q��Ă��܂�������A���y��ʏȁE�����ԋǂ̕���26�N�x�\�Z�T�v�Ɏ�����Ă���u2015�N�x�d�ʎԔR��
��v�̋������e�����\�i��2014�N�̂Ȃ���A���{���{�i�����ȁE���y��ʏȁj���č������ɂ����{�̑�^�g��
�b�N��NO���K�����{�s���������Ԃ����̂܂ܕ��u���������ꍇ��A�u2015�N�x�d�ʎԔR���v�̋������e����
���\�̏ꍇ�ɂ́A���{�̃g���b�N���[�J�͐^���ɑ�^�g���b�N�́u�R����P�v��uNO���팸�v�̌����J���Ɏ��g�܂Ȃ�
�ƍl�����邩��ł���B�������A����A��^�g���b�N�E�o�X�̕���ɂ����āA���{���{�i�����ȁE���y��ʏȁj����
���Ɠ����ȏ�̌������u��NO���K���v�⎟���́u�R���̋����v�\�����ꍇ�ɂ́A���{�̃g���b�N���[�J�����X
�Ȃ�����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p�����p���ɒ��肷��ƍl������B����ɂ���āA���{��
��^�g���b�N�E�o�X�̕���ł́A�č��Ɠ����ȏ�Ɍ�������^�g���b�N��NO���K�����{�s�ł���悤�ɂȂ�Ƌ��ɁA�X��
��2015�N�x�d�ʎԔR�����T�����x�������������̏d�ʎԔR���𑬂₩�ɐݒ�ł��邱�ƂɂȂ�ƍl����
���B
���Ēu���I�j�v�Ƃ̗��o�[�W�����̌�������悤���B���̗��o�[�W�����̌��̈Ӗ��̉����ăg���b�N���[�J�̍s����\��
����ƁA�e�g���b�N���[�J���]���ʂ���R����P�ɖ����ȋZ�p�̊J�����������J���̌����i���J���̐l�H�A�ݔ��A��
���j��Q��Ă��܂�������A���y��ʏȁE�����ԋǂ̕���26�N�x�\�Z�T�v�Ɏ�����Ă���u2015�N�x�d�ʎԔR��
��v�̋������e�����\�i��2014�N�̂Ȃ���A���{���{�i�����ȁE���y��ʏȁj���č������ɂ����{�̑�^�g��
�b�N��NO���K�����{�s���������Ԃ����̂܂ܕ��u���������ꍇ��A�u2015�N�x�d�ʎԔR���v�̋������e����
���\�̏ꍇ�ɂ́A���{�̃g���b�N���[�J�͐^���ɑ�^�g���b�N�́u�R����P�v��uNO���팸�v�̌����J���Ɏ��g�܂Ȃ�
�ƍl�����邩��ł���B�������A����A��^�g���b�N�E�o�X�̕���ɂ����āA���{���{�i�����ȁE���y��ʏȁj����
���Ɠ����ȏ�̌������u��NO���K���v�⎟���́u�R���̋����v�\�����ꍇ�ɂ́A���{�̃g���b�N���[�J�����X
�Ȃ�����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p�����p���ɒ��肷��ƍl������B����ɂ���āA���{��
��^�g���b�N�E�o�X�̕���ł́A�č��Ɠ����ȏ�Ɍ�������^�g���b�N��NO���K�����{�s�ł���悤�ɂȂ�Ƌ��ɁA�X��
��2015�N�x�d�ʎԔR�����T�����x�������������̏d�ʎԔR���𑬂₩�ɐݒ�ł��邱�ƂɂȂ�ƍl����
���B
�@
�@���̗��R�́A���x���q�ׂ�悤�ɁA�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p�́A�u�R�����v�ƁuNO��
�팸�v�̗����������ł��邽�߂ł���B���̂悤�ɁA�����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p����
�p�������łɂ́A����ē��{�̑�^�f�B�[�[���g���b�N�E�o�X�́A�č��Ɠ����ȏ�̌�����NO���r�o�l��������
��ɁA�X��2015�N�x�d�ʎԔR�������{�P�O�����x�ȏ�̏d�ʎԃ��[�h�R��̌��オ�����ł���̂ł���B��
�Ƃ��f���炵�������Z�p�ł͂Ȃ����낤���B
�팸�v�̗����������ł��邽�߂ł���B���̂悤�ɁA�����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p����
�p�������łɂ́A����ē��{�̑�^�f�B�[�[���g���b�N�E�o�X�́A�č��Ɠ����ȏ�̌�����NO���r�o�l��������
��ɁA�X��2015�N�x�d�ʎԔR�������{�P�O�����x�ȏ�̏d�ʎԃ��[�h�R��̌��オ�����ł���̂ł���B��
�Ƃ��f���炵�������Z�p�ł͂Ȃ����낤���B
�@���łɐ\���グ��ƁA�Q�O�P�U�N�R���R���ɍ��y��ʏȂ́A�N���[���f�B�[�[���G���W�������ڂƐ�`���Ďs�̂���
�Ă��錻�s�̃����h�N���[�U�[�E�v���h�i�g���^�j�̃f�B�[�[���Ԃ́A�����ߍx�̓~��̂P�O���ߖT�ȉ��ł̘H�㑖�s��
�͕ی쐧��\�t�g�ɂ���Ăm�n���팸���u���~�����邽�߂ɂm�n���K���l�̂Q�D�X�{�`�P�Q�D�V�{�̍��Z�x�̂m�n����
�ꗬ�����ׁH�̂��邱�Ƃ\�����B�������A�������ƂɁA���y��ʏȂ́A���̓~��̘H�㑖�s�łm�n���𐂂ꗬ����
���h�N���[�U�[�E�v���h�i�g���^�j�̃f�B�[�[���Ԃ��G�R�J�[���ł̐��{�̗D������č�����s�̂��邱�Ƃ����F��
�Ă���悤�ł���B
�Ă��錻�s�̃����h�N���[�U�[�E�v���h�i�g���^�j�̃f�B�[�[���Ԃ́A�����ߍx�̓~��̂P�O���ߖT�ȉ��ł̘H�㑖�s��
�͕ی쐧��\�t�g�ɂ���Ăm�n���팸���u���~�����邽�߂ɂm�n���K���l�̂Q�D�X�{�`�P�Q�D�V�{�̍��Z�x�̂m�n����
�ꗬ�����ׁH�̂��邱�Ƃ\�����B�������A�������ƂɁA���y��ʏȂ́A���̓~��̘H�㑖�s�łm�n���𐂂ꗬ����
���h�N���[�U�[�E�v���h�i�g���^�j�̃f�B�[�[���Ԃ��G�R�J�[���ł̐��{�̗D������č�����s�̂��邱�Ƃ����F��
�Ă���悤�ł���B
�@���݂ɁA���B�̃f�B�[�[�������Ԃł́A�Q�O�P�V�N�X���ɂ́u�H�㑖�s��NOx�r�o�l����㎎����NOx��l�̂Q�D
�P�{�ȓ��v�̘H�㑖�s��NOx�r�o�l�ɋK������\������ɔ��\���Ă���B�������A�����V���f�W�^���̂Q�O�P�U�N�R��
�T���̕��L���ɂ��ƁA���{�̍��y��ʏȂ́A���ꂩ��T�N��i���Q�O�Q�P�N�Q�����H�j�ɉ��B�Ɠ��l�̃f�B�[�[��
�����Ԃł̘H�㑖�s��NOx�r�o�l�̋K�����{���������n�߂��悤�ł���B���ꂪ�����ł���A�����ߍx�̓~��
�̂P�O���ߖT�ȉ��ł̘H�㑖�s�łm�n���K���l�̂Q�D�X�{�`�P�Q�D�V�{�̍��Z�x�̂m�n���̐��ꗬ���̌��ׂ����P������
���h�N���[�U�[�E�v���h�i�g���^�j�̃f�B�[�[���Ԃ́A�Q�O�Q�P�N�Q�����ɂȂ�܂ŁA���{�ł͎s�̂���Ȃ��\���������
�l������B����́A�g���^�����Ԃ������h�N���[�U�[�E�v���h�i�g���^�j�̃f�B�[�[���Ԃ̘H�㑖�s�ł̍��Z�x�̂m�n��
�̐��ꗬ���̌��ׂ����P�ł���Z�p�����J���ƁA���y��ʏȂ��F�����Ă��邽�߂ł��낤���B
�P�{�ȓ��v�̘H�㑖�s��NOx�r�o�l�ɋK������\������ɔ��\���Ă���B�������A�����V���f�W�^���̂Q�O�P�U�N�R��
�T���̕��L���ɂ��ƁA���{�̍��y��ʏȂ́A���ꂩ��T�N��i���Q�O�Q�P�N�Q�����H�j�ɉ��B�Ɠ��l�̃f�B�[�[��
�����Ԃł̘H�㑖�s��NOx�r�o�l�̋K�����{���������n�߂��悤�ł���B���ꂪ�����ł���A�����ߍx�̓~��
�̂P�O���ߖT�ȉ��ł̘H�㑖�s�łm�n���K���l�̂Q�D�X�{�`�P�Q�D�V�{�̍��Z�x�̂m�n���̐��ꗬ���̌��ׂ����P������
���h�N���[�U�[�E�v���h�i�g���^�j�̃f�B�[�[���Ԃ́A�Q�O�Q�P�N�Q�����ɂȂ�܂ŁA���{�ł͎s�̂���Ȃ��\���������
�l������B����́A�g���^�����Ԃ������h�N���[�U�[�E�v���h�i�g���^�j�̃f�B�[�[���Ԃ̘H�㑖�s�ł̍��Z�x�̂m�n��
�̐��ꗬ���̌��ׂ����P�ł���Z�p�����J���ƁA���y��ʏȂ��F�����Ă��邽�߂ł��낤���B
�@�Ƃ��낪�A���̌��s�̃����h�N���[�U�[�E�v���h�i�g���^�j�̃f�B�[�[���Ԃ��C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j
�̓����Z�p���̗p�����ꍇ�ɂ́A�~��̘H�㑖�s�ō��Z�x�̂m�n���̐��ꗬ�����ׂ�e�Ղɉ��P���邱�Ƃ��\��
����B�܂�A�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p���̗p���������h�N���[�U�[�E�v���h�i�g���^�j�̃f
�B�[�[���Ԃ́A�~��̘H�㑖�s�ɂ����Ă��A�m�n���K���l�̃N���[���Ȃm�n���r�o��Ԃł̂̉^�q���\�ɂȂ�B����
�ɂ��ẮA�C���x�~�́A�v���h�i����j�ި���َԂ̓~��̂m�n�����ꗬ���̌��ׂ����P�ɏڏq���Ă���̂ŁA������
������́A�䗗�������������B
�̓����Z�p���̗p�����ꍇ�ɂ́A�~��̘H�㑖�s�ō��Z�x�̂m�n���̐��ꗬ�����ׂ�e�Ղɉ��P���邱�Ƃ��\��
����B�܂�A�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p���̗p���������h�N���[�U�[�E�v���h�i�g���^�j�̃f
�B�[�[���Ԃ́A�~��̘H�㑖�s�ɂ����Ă��A�m�n���K���l�̃N���[���Ȃm�n���r�o��Ԃł̂̉^�q���\�ɂȂ�B����
�ɂ��ẮA�C���x�~�́A�v���h�i����j�ި���َԂ̓~��̂m�n�����ꗬ���̌��ׂ����P�ɏڏq���Ă���̂ŁA������
������́A�䗗�������������B
�@�Ƃ���ŁA�ŋ߁A�u�����A�e���r�̃j���[�X�����Ȃ���A��Ɂy�n���͎��ȂȂ��Ꭱ��Ȃ��`��z�Ƒ��l��n���ɂ���
���t��p�ɂəꂢ�Ă���s���ǂ̘V�l������v�Ƃ̘b�����ɂ����B���̂悤�ȘV�l���̒s���ǂł́A����̑S�Ă̐l
�Ԃ��n���҂Ɍ������܂��Ǐ�̏o��ꍇ������悤���B���̘b���A���߂čŋ߂̉䂪�g��U��Ԃ����Ƃ���A�g��
�b�N���[�J�̃G���W���Z�p�҂��n���Ɍ����Ă��܂��M�҂́A���Ɏ������g���s���ǂ̘V�l�̒��ԓ�������Ă���̂�
�͂Ȃ����ƁA�����s���Ɋ����n�߂Ă���Ƃ���ł���B�ߍ��ł͈�Â̐i���ɂ��A�V�l�̒s���ǂ́A���������ɂ�
���ďǏ�̐i�s�������x�点�邱�Ƃ��ł���Ƃ̂��Ƃ��B���āA�M�҂͖����ɂł��a�@�Őf�Ă�����������ǂ��̂ł�
�낤���B
���t��p�ɂəꂢ�Ă���s���ǂ̘V�l������v�Ƃ̘b�����ɂ����B���̂悤�ȘV�l���̒s���ǂł́A����̑S�Ă̐l
�Ԃ��n���҂Ɍ������܂��Ǐ�̏o��ꍇ������悤���B���̘b���A���߂čŋ߂̉䂪�g��U��Ԃ����Ƃ���A�g��
�b�N���[�J�̃G���W���Z�p�҂��n���Ɍ����Ă��܂��M�҂́A���Ɏ������g���s���ǂ̘V�l�̒��ԓ�������Ă���̂�
�͂Ȃ����ƁA�����s���Ɋ����n�߂Ă���Ƃ���ł���B�ߍ��ł͈�Â̐i���ɂ��A�V�l�̒s���ǂ́A���������ɂ�
���ďǏ�̐i�s�������x�点�邱�Ƃ��ł���Ƃ̂��Ƃ��B���āA�M�҂͖����ɂł��a�@�Őf�Ă�����������ǂ��̂ł�
�낤���B
�@��L�̖{�����Ō�蓙���������܂�����A���[�����ɂĂ��w�E�������B�܂��A�^��_�A������A�䊴�z���A�ǂ̂悤
�Ȏ����ł����\�ł��B�Ջ��l���ĂɃ��[���������肢��������A�o����͈͂őΉ������Ă��������܂��B
�Ȏ����ł����\�ł��B�Ջ��l���ĂɃ��[���������肢��������A�o����͈͂őΉ������Ă��������܂��B

|