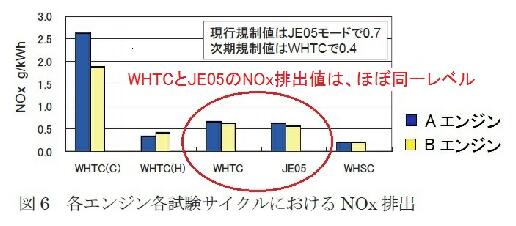�Ջ��l�̃A�C�f�A �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�g�b�v�y�[�W�ɖ߂��@�@�@�@�@�T�C�g�}�b�v
�ŏI�X�V���F2016�N11��12��
 |
�P�D��^�g���b�N�p�ߋ��f�B�[�[���G���W���̔R��팸���A�i�ق̉ۑ�ł��闝�R
�@�f�B�[�[���G���W���̃p�e�B�L�����[�g�i�o�l�j��啝�ɍ팸�ł���R�ĉ��P�ȊO�̕��@�Ƃ��ẮA�C���^�[�N�[���ߋ�
�ɂ�鋋�C�ʂ̑���Ƃc�o�e���u(�f�B�[�[�����q���ߏW���u�j�ł��邱�Ƃ́A�P�O�N�ȏ���O����L���m���Ă���
���Ƃł���B�V�Z���r�o�K�X�K���i2003�N��2004�N�K���j�̎���ł͂c�o�e���u���M�����̗��̋Z�p�ł��������߁A
�o�l�K���̌������V�Z���r�o�K�X�K���ɓK���������i�Ƃ��āA�قƂ�ǑS�Ẵg���b�N�ɂ́A�C���^�[�N�[���ߋ��f�B
�[�[���G���W�����̗p���ꂽ�̂ł���B���̌�̐V�����r�o�K�X�K���i2005�N�K���j���o�ă|�X�g�V�����r�o�K�X�K
���i2009�N�K���j�Ɏ���o�l�Ƃm�n���̋K�������ɓK���ł���悤�ɂ��邽�߁A���݂ł͑S�Ă̑�^�g���b�N�ɂ́A�c�o�e
���u�ƔA�f�r�b�q�G�}���u�𓋍ڂ����C���^�[�N�[���ߋ��f�B�[�[���G���W�����̗p����Ă���̂����B
�ɂ�鋋�C�ʂ̑���Ƃc�o�e���u(�f�B�[�[�����q���ߏW���u�j�ł��邱�Ƃ́A�P�O�N�ȏ���O����L���m���Ă���
���Ƃł���B�V�Z���r�o�K�X�K���i2003�N��2004�N�K���j�̎���ł͂c�o�e���u���M�����̗��̋Z�p�ł��������߁A
�o�l�K���̌������V�Z���r�o�K�X�K���ɓK���������i�Ƃ��āA�قƂ�ǑS�Ẵg���b�N�ɂ́A�C���^�[�N�[���ߋ��f�B
�[�[���G���W�����̗p���ꂽ�̂ł���B���̌�̐V�����r�o�K�X�K���i2005�N�K���j���o�ă|�X�g�V�����r�o�K�X�K
���i2009�N�K���j�Ɏ���o�l�Ƃm�n���̋K�������ɓK���ł���悤�ɂ��邽�߁A���݂ł͑S�Ă̑�^�g���b�N�ɂ́A�c�o�e
���u�ƔA�f�r�b�q�G�}���u�𓋍ڂ����C���^�[�N�[���ߋ��f�B�[�[���G���W�����̗p����Ă���̂����B
�@����A2006�N4��1������{�s���ꂽ�u�G�l���M�[�̎g�p�̍������Ɋւ���@���v�i�ʏ́F�����ȃG�l�@�j�̉����ɂ�
��A�ȉ��Ɏ����\�U�̏d�ʎԁi�ԗ����d��2.5t��)�̎����Ԃɑ���2015�N�x�i����27�N�x�j�d�ʎԔR�����K�肳
�ꂽ�B ���̏d�ʎԔR���́A2015�N�x�i����27�N�x�j����B���̖ڕW�N�x�Ƃ��Ă��邽�߁A�g���b�N���[�J��2015
�N�x�܂łɎԗ����d�ʂ��Ƃɒ�߂�ꂽ�d�ʎԔR��l�̊�l�ɓK��������K�v������B�܂��A2006�N4���ȍ~�ɔ�
������V�^�Ԃɂ��āA���i�J�^���O�֏d�ʎԃ��[�h�R��l��\�����Ȃ���Ȃ�Ȃ����ƂɂȂ����B����ȍ~�A�g���b
�N���[�J�ł͋}篁A�g���b�N�̏d�ʎԃ��[�h�R����팸����K�v�ɔ����邱�ƂɂȂ����̂ł���B
��A�ȉ��Ɏ����\�U�̏d�ʎԁi�ԗ����d��2.5t��)�̎����Ԃɑ���2015�N�x�i����27�N�x�j�d�ʎԔR�����K�肳
�ꂽ�B ���̏d�ʎԔR���́A2015�N�x�i����27�N�x�j����B���̖ڕW�N�x�Ƃ��Ă��邽�߁A�g���b�N���[�J��2015
�N�x�܂łɎԗ����d�ʂ��Ƃɒ�߂�ꂽ�d�ʎԔR��l�̊�l�ɓK��������K�v������B�܂��A2006�N4���ȍ~�ɔ�
������V�^�Ԃɂ��āA���i�J�^���O�֏d�ʎԃ��[�h�R��l��\�����Ȃ���Ȃ�Ȃ����ƂɂȂ����B����ȍ~�A�g���b
�N���[�J�ł͋}篁A�g���b�N�̏d�ʎԃ��[�h�R����팸����K�v�ɔ����邱�ƂɂȂ����̂ł���B
�@���̂��߁A�ߔN�ł́A�g���b�N�̏d�ʎԃ��[�h�R����팸���邱�Ƃ��g���b�N�p�f�B�[�[���G���W���ɂ�����ŏd�v��
�������ڂł��邱�Ƃ́A�N�����F�߂�Ƃ���ł���B�������Ȃ���f�B�[�[���G���W���̏d�ʎԃ��[�h�R��̉��P�́A��
��܂Œ��N�ɓn���Č�������ė�����������A����A�Z���Ԃɏ\���Ȑ��ʂ��m���Ɏ������邱�Ƃ�����ۑ�ł���B
����ɑ��g�����X�~�b�V�����̑��i���͑啝�ȃR�X�g�㏸�̋]���͂��邪�A�m���Ƀg���b�N�̏d�ʎԃ��[�h�R������P
�ł��邱�Ƃ���A�g���b�N���[�J�͐�𑈂��ăg�����X�~�b�V�����̑��i���ɏ��o�����ƍl������B�Ƃ��낪�A�č��̂悤
�ȑ嗤���f���̂悤�Ƀg�����X�~�b�V�����̕p�ɂȃM�A�`�F���W���s�v�ȏꍇ�ɂ͑��i�g�����X�~�b�V�����ł����Ă��g���b
�N�^�]��̕��S�͑����Ȃ����A���{�̂悤�ȋ������ł͑��i�g�����X�~�b�V�����̗̍p�͕p�ɂȃM�A�`�F���W���K�v�Ƃ�
�邽�߂Ƀg���b�N�^�]�艻�ɉߓx�̕��S�������邱�ƂɂȂ�B�����Ńg���b�N���[�J�͓��{�ł��g�p�\�ȑ��i�g�����X�~
�b�V�����Ƃ��Ă��邽�߁A�P�Q�i�̋@�B�������g�����X�~�b�V�����̊J�����s�����̂ł���B�����āA�����U�A����A�O�H��
�����A�t�c�g���b�N�X�̂S�Ђ́A���̂P�Q�i�̋@�B�������g�����X�~�b�V�������̗p���邱�Ƃɂ���āA��^�g���b�N�E�g���N�^
��2015�N�x�i����27�N�x�j�d�ʎԔR���ɐh�����ēK�������邱�Ƃ��ł��Ă���̂��B
�������ڂł��邱�Ƃ́A�N�����F�߂�Ƃ���ł���B�������Ȃ���f�B�[�[���G���W���̏d�ʎԃ��[�h�R��̉��P�́A��
��܂Œ��N�ɓn���Č�������ė�����������A����A�Z���Ԃɏ\���Ȑ��ʂ��m���Ɏ������邱�Ƃ�����ۑ�ł���B
����ɑ��g�����X�~�b�V�����̑��i���͑啝�ȃR�X�g�㏸�̋]���͂��邪�A�m���Ƀg���b�N�̏d�ʎԃ��[�h�R������P
�ł��邱�Ƃ���A�g���b�N���[�J�͐�𑈂��ăg�����X�~�b�V�����̑��i���ɏ��o�����ƍl������B�Ƃ��낪�A�č��̂悤
�ȑ嗤���f���̂悤�Ƀg�����X�~�b�V�����̕p�ɂȃM�A�`�F���W���s�v�ȏꍇ�ɂ͑��i�g�����X�~�b�V�����ł����Ă��g���b
�N�^�]��̕��S�͑����Ȃ����A���{�̂悤�ȋ������ł͑��i�g�����X�~�b�V�����̗̍p�͕p�ɂȃM�A�`�F���W���K�v�Ƃ�
�邽�߂Ƀg���b�N�^�]�艻�ɉߓx�̕��S�������邱�ƂɂȂ�B�����Ńg���b�N���[�J�͓��{�ł��g�p�\�ȑ��i�g�����X�~
�b�V�����Ƃ��Ă��邽�߁A�P�Q�i�̋@�B�������g�����X�~�b�V�����̊J�����s�����̂ł���B�����āA�����U�A����A�O�H��
�����A�t�c�g���b�N�X�̂S�Ђ́A���̂P�Q�i�̋@�B�������g�����X�~�b�V�������̗p���邱�Ƃɂ���āA��^�g���b�N�E�g���N�^
��2015�N�x�i����27�N�x�j�d�ʎԔR���ɐh�����ēK�������邱�Ƃ��ł��Ă���̂��B
�@���������āA�P�Q�i�̋@�B�������g�����X�~�b�V�������ڂ̏ꍇ�����T���O��̔R����V�i�}�j���A�g�����X�~�b�V
�������ڂ�����^�g���b�N�E�g���N�^�́A�����_�ł�2015�N�x�d�ʎԔR���ɓK���ł��Ă��Ȃ��̂ł���B���������āA
����̋Z�p�J�����i�W���A��������T�����x�̔R����팸�ł���Z�p�����p���ł�������A�V�i�}�j���A�g�����X
�~�b�V�������ڂ̑�^�g���b�N�E�g���N�^��2015�N�x����͔̔��𒆎~������Ȃ����Ԃ������Ă��܂����ƂɂȂ��Ă�
�܂��̂��B���̂悤�Ȏ��ԂɊׂ邱�Ƃ�����邽�߁A�M�҂͑�^�g���b�N�E�g���N�^�ɂT�`�P�O�����x�̔R��팸���\��
�Q�^�[�{�ߋ��@�����̋C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p���̗p���邱�Ƃ��ł��]�܂����Ǝv���A��Ă�
�Ă���̂ł���B���̋C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p����^�g���b�N���̗p�����ꍇ�A�T�`�P�O�����x
�����d�ʎԃ��[�h�R��l���啝�ȍ팸�������߂邽�߁A�V�i�}�j���A���g�����X�~�b�V�����̎Ԏ킪�Q�O�P�T�N�x�R���
���ɗe�ՂɓK���ł���̂��B����ɂ��ẮA�C���x�~�G���W���ɂ���^�g���b�N�̒�R��̃y�[�W�ɂ��L�ڂ���
����̂ł����������������B�{�y�[�W�ł́A�C���x�~�G���W���̒��ł��Q�^�[�{�ߋ��@�����̋C���x�~�G���W���i����
���J2005-54771�j�̋Z�p�̓����ƁA���Y�G���W���ɂ�����R����P��NO���팸�̊e�X�̖ړI�ɓK�����C���Q�̉^�]
����@�ɂ��ďڍׂɏq�ׂ邱�ɂ���B
�������ڂ�����^�g���b�N�E�g���N�^�́A�����_�ł�2015�N�x�d�ʎԔR���ɓK���ł��Ă��Ȃ��̂ł���B���������āA
����̋Z�p�J�����i�W���A��������T�����x�̔R����팸�ł���Z�p�����p���ł�������A�V�i�}�j���A�g�����X
�~�b�V�������ڂ̑�^�g���b�N�E�g���N�^��2015�N�x����͔̔��𒆎~������Ȃ����Ԃ������Ă��܂����ƂɂȂ��Ă�
�܂��̂��B���̂悤�Ȏ��ԂɊׂ邱�Ƃ�����邽�߁A�M�҂͑�^�g���b�N�E�g���N�^�ɂT�`�P�O�����x�̔R��팸���\��
�Q�^�[�{�ߋ��@�����̋C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p���̗p���邱�Ƃ��ł��]�܂����Ǝv���A��Ă�
�Ă���̂ł���B���̋C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p����^�g���b�N���̗p�����ꍇ�A�T�`�P�O�����x
�����d�ʎԃ��[�h�R��l���啝�ȍ팸�������߂邽�߁A�V�i�}�j���A���g�����X�~�b�V�����̎Ԏ킪�Q�O�P�T�N�x�R���
���ɗe�ՂɓK���ł���̂��B����ɂ��ẮA�C���x�~�G���W���ɂ���^�g���b�N�̒�R��̃y�[�W�ɂ��L�ڂ���
����̂ł����������������B�{�y�[�W�ł́A�C���x�~�G���W���̒��ł��Q�^�[�{�ߋ��@�����̋C���x�~�G���W���i����
���J2005-54771�j�̋Z�p�̓����ƁA���Y�G���W���ɂ�����R����P��NO���팸�̊e�X�̖ړI�ɓK�����C���Q�̉^�]
����@�ɂ��ďڍׂɏq�ׂ邱�ɂ���B
�Q�D�啝�ȔR����オ�\�ȋC���x�~�̃V�X�e���Ƃ́H
�Q�|�P�@����܂Ŋ��ɒ�Ă���Ă����C���x�~�V�X�e��
�@�Ƃ���ŁA��^�g���b�N�E�g���N�^�̃^�[�{�ߋ��f�B�[�[���G���W�����u�C���x�~�G���W���v��������@�Ƃ��ẮA�\�P�Ɏ�
�����悤�ɁA�^�[�{�ߋ��@�̑䐔���܂߂ċ��C�Ɣr�C�̉�H���S���قȂ����Q��ނ̃V�X�e�����l������B
�����悤�ɁA�^�[�{�ߋ��@�̑䐔���܂߂ċ��C�Ɣr�C�̉�H���S���قȂ����Q��ނ̃V�X�e�����l������B
| |
|
|
| |
|
���@�Q��̃^�[�{�ߋ��@�����ɑ�������Q�^�[�{�����̋C���x�~�f�B�[�[��
�G ���W���̋C���x�~�V�X�e���B
���@���̃V�X�e���̏� �ׂ��C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̃y�[�W �������������������B |
| |
���@�C���x�~�̍ő�ړI�ł���G���W�����������̃^�[�r���o���̔r�C
�K�X���x���������ł��邽�߁A�啝�ȑ��s�R��̉��P�i���d�ʎԃ��[�h�R
��̉��P�j��SCR�G�}�̊������i�ɂ��\����NO���팸���\
�i�T�`�P�O�����x�̏d�ʎԃ��[�h�R��l�̍팸���\�j ���@�x�~�^�]����C���Q�̋z�C�قƔr�C�ق̗����A���͕Ј���𖧕� ��z�E�r�C�ق̃��t�g���䂪�s�v |
|
| |
���@�^�[�{�ߋ��@�͂Q��i���������e�ʁj �̂��߃R�X�g�������傫������
���@���C�n�Ɣr�C�n�����G |
|
| |
|
���@�]���̃V���O���^�[�{��Q�i�ߋ��̃f�B�[�[���G���W����P���ɋC���x�~��
���ꍇ �̋C���x�~�̃V�X�e���ł���B (������́A�G���W���̑S���̋C����
�z�C�|�[�g�E�r�C�|�[�g�ɏ��Ȃ��Ƃ��P��̃^�[�{�ߋ��@���A�������\����
�ߋ��̃f�B�[�[���G���W���ł���B�j
���@�{���{�̂b�n�Q�팸�i���R�����j�̋Z�p�������� �@�@�i�z�E�r�C�ق��x�~�����V���O���^�[�{�����̋C���x�~�𐄏�����L���j �i�o�T�Fhttp://www.its.ucdavis.edu/events/outreachevents/asilomar2007/ presentations/Day%202%20Session%201/Anthony%20Greszler.pdf�j 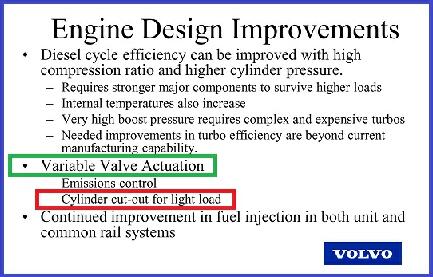 |
| |
���@�V���O���^�[�{�̃f�B�[�[���G���W���ł́A�^�[�{�ߋ��@�͂P��i��������e
�ʁj���߂ɃR�X�g���������Ȃ�����
���@���C�n�Ɣr�C�n���V���v�� |
|
| |
���@�C���x�~�̍ő�ړI�ł������������̃^�[�r���o���̔r�C�K�X���x
�����������ł��Ȃ����߁A�R��팸��SCR�G�}�̊������ɂ��NO���팸
���啝�ɗ�邱��
���@�C���x�~�^�]���̔M�����̌����}�邽�߂ɂ́A�x�~�^�]����C���Q�� �z�C�قƔr�C�ق̗����A���͕Ј���𖧕���z�E�r�C�ق̃��t�g���䂪 �K�v�ɂȂ邱��(�����݂ɁA�x�~�^�]����C���Q�̋z�C�قƔr�C�ق̗����A�� �͕Ј���𖧕���z�E�r�C�ق̃��t�g��������{���Ȃ��ꍇ�͔r�C�K�X���x �̒ቺ�ɂ��A�fSCR�G�}�ł�NO���팸�@�\����錇�_������B�j ���@�U�C���̉ߋ��f�B�[�[���G���W���ɂ����āA�P�^�Q���ׂɂ����ĂR�C�� �̋x�~�^�]�i���R�C�������̉ғ��^�]�j���ł��Ȃ����� (������́A�G���W�� �̑S���̋C���̋z�C�|�[�g�E�r�C�|�[�g�ɏ��Ȃ��Ƃ��P��̃^�[�{�ߋ��@���A�� �����\���̋C���x�~�G���W���ł́A���̂P��̃^�[�{�ߋ��@���P�^�Q���ׂł̂R �C���̋x�~�^�]���ɂ͉ߋ��@�������������ቺ���Ă��܂����Ƃ������ł���B�j ���@�z�E�r�C�ًx�~�����̋C���x�~���̗p�����f�B�[�[���G���W���́A��
�����̗��o�͐���̃G���W���ƂȂ錇�_�����邱���i������́A�G���W��
�̑S�C���̉ғ���Ԃ���ꕔ�̋C�����x�~����^�]�Ɉڍs����ہA�x�~����
�C���Q�̋z�C�قƔr�C�ق̗����A���͕Ј���𖧕������u�Ԃɂ͉ߋ��@��
����鋋�C�ʂ��}�����邽�߁A�ߋ��@�̃u���A���T�[�W�����N�����s�����
������B����̕s���h�~���邽�߂ɂ́A�G���W���̑S�C���̉ғ��^�]����
�ꕔ�C�����x�~�^�]�ɂ͊ɂ₩�Ɉڍs������K�v������B���̂��߁A���̋z�E
�r�C�ًx�~�����̋C���x�~�V�X�e�����̗p�����ꍇ�A�S�C���̉ғ��^�]����
�ꕔ�C�����x�~�^�]�ֈڍs�����鎞�̏o�͂́A�ɂ₩�ɒቺ������K�v�̂�
�邱�Ƃ������ł���B�j
|
|
�@���̂悤�ɁA�ߋ��f�B�[�[���G���W���ł́A�u�Q�^�[�{�����v�Ɓu�z�E�r�C�ًx�~�����v�̂Q��ނ̋C���x�~�V�X�e����
����B����̕����̋C���x�~�G���W���ɂ����Ă��A�C���x�~�^�]���̉ғ��C���ł́u��p�����̌����v�A�u�T�C�N����
���̌���v�ɂ��R����P�������邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��B�������A�����Q��ނ̋C���x�~�G���W���ł̋C���x�~�^�]
���s���������^�]���r����ƁA�Q�^�[�{�����C���x�~�V�X�e���̃^�[�{�ߋ��@�̉ߋ��@�����́A�z�E�r
�C�ًx�~�����C���x�~�V�X�e���̃^�[�{�ߋ��@�̉ߋ��@����������ɍ��������ʼn^�]�ł���̂ł���B��
���āA�Q�^�[�{�����ł̋C���x�~�G���W���́A�z�E�r�C�ًx�~�̂ŋC���x�~�G���W���ɔ�r���āA�C���x�~�̉^
�]�̈悪�L�����Ƃ������̈�ł����B���̂��߁A�u�Q�^�[�{�����C���x�~�V�X�e���v�̕����u�z�E�r�C�ًx�~�C��
�x�~�V�X�e���v�ɔ�ׂėD�ꂽ�R����P��������̂��B����ɂ��ẮA�C���x�~�G���W���ɂ���^�g���b�N�̒�
�R��̃y�[�W�ɂ��������L�ڂ��Ă���̂ŁA������䗗�������������B
����B����̕����̋C���x�~�G���W���ɂ����Ă��A�C���x�~�^�]���̉ғ��C���ł́u��p�����̌����v�A�u�T�C�N����
���̌���v�ɂ��R����P�������邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��B�������A�����Q��ނ̋C���x�~�G���W���ł̋C���x�~�^�]
���s���������^�]���r����ƁA�Q�^�[�{�����C���x�~�V�X�e���̃^�[�{�ߋ��@�̉ߋ��@�����́A�z�E�r
�C�ًx�~�����C���x�~�V�X�e���̃^�[�{�ߋ��@�̉ߋ��@����������ɍ��������ʼn^�]�ł���̂ł���B��
���āA�Q�^�[�{�����ł̋C���x�~�G���W���́A�z�E�r�C�ًx�~�̂ŋC���x�~�G���W���ɔ�r���āA�C���x�~�̉^
�]�̈悪�L�����Ƃ������̈�ł����B���̂��߁A�u�Q�^�[�{�����C���x�~�V�X�e���v�̕����u�z�E�r�C�ًx�~�C��
�x�~�V�X�e���v�ɔ�ׂėD�ꂽ�R����P��������̂��B����ɂ��ẮA�C���x�~�G���W���ɂ���^�g���b�N�̒�
�R��̃y�[�W�ɂ��������L�ڂ��Ă���̂ŁA������䗗�������������B
�@�{���{�́A�K�\�����G���W���Ɠ��l�̋z�E�r�C�ق��x�~���ăV�����_�𖧕���@�\�����z�E�r�C�ًx�~�����̋C
���x�~�V�X�e�����Ă��Ă��邪�A���{�̃g���b�N���[�J���{���{�Ɠ��l�̋z�E�r�C�ًx�~�����̋C���x�~�V�X�e����
�l���Ă���悤�ł���B���Ƃ��������B���{�̃g���b�N���[�J���o�肵�Ă���z�E�r�C�ًx�~�����̋C���x�~�V�X�e����
�ւ�������E���p�V�Ă��A�ȉ��̕\�Q�Ɏ������B
���x�~�V�X�e�����Ă��Ă��邪�A���{�̃g���b�N���[�J���{���{�Ɠ��l�̋z�E�r�C�ًx�~�����̋C���x�~�V�X�e����
�l���Ă���悤�ł���B���Ƃ��������B���{�̃g���b�N���[�J���o�肵�Ă���z�E�r�C�ًx�~�����̋C���x�~�V�X�e����
�ւ�������E���p�V�Ă��A�ȉ��̕\�Q�Ɏ������B
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
�@�ȏ�̕\�Q�̓��{�̃g���b�N���[�J������܂ŏo�肵�Ă���C���x�~�Ɋւ�������E���p�V�ẮA�z�E�r�C�ًx�~��
���̋C���x�~�V�X�e���Ɍ����Ă���悤���B�����āA�M�҂���Ă��Ă����Q�^�[�{�����̋C���x�~�V�X�e��[�C���x
�~�G���W���i�������J2005-54771�j]�ɗގ����������o��́A���̂Ƃ���P���������悤���B
���̋C���x�~�V�X�e���Ɍ����Ă���悤���B�����āA�M�҂���Ă��Ă����Q�^�[�{�����̋C���x�~�V�X�e��[�C���x
�~�G���W���i�������J2005-54771�j]�ɗގ����������o��́A���̂Ƃ���P���������悤���B
�@���������A�z�E�r�C�ًx�~�����̋C���x�~�V�X�e���́A�M�҂���Ă��Ă����Q�^�[�{�����̋C���x�~�V�X�e��[�C��
�x�~�G���W���i�������J2005-54771�j]�����C���x�~�ʼn^�]�ł���G���W�����ׂ��Ⴂ���_������B�����āA�M�҂̗\
�z�ł́A�z�E�r�C�ق̖����ɂ��z�E�r�C�ًx�~�����̋C���x�~�V�X�e���̃V���O���^�[�{�����̉ߋ��f�B�[�[��
�G���W���̋C���x�~�́A0�`1/3 ���ׂ̋����^�]�̈�ł����C���x�~�̉^�]���ł����A�z�E�r�C�ًx�~�����̋C���x
�~�V�X�e���̂Q�i�ߋ��f�B�[�[���G���W���̋C���x�~�ł�0�`2/5 ���ׂ̋����^�]�̈�ł����C���x�~�̉^�]���ł�
�Ȃ��Ɖ]�����_������B���̂悤�ȋz�E�r�C�ًx�~�����̋C���x�~�V�X�e���ƈقȂ�A�Q�^�[�{�����̋C���x�~�G���W��
[�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j]�́A0�`�P/2 ���ׂ̍L���^�]�̈�ŋC���x�~���\�ƂȂ�D�ꂽ������
�������Z�p�ł���B���̂悤�ɁA�Q�^�[�{�����̋C���x�~�G���W��[�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j]�́A�L��
�G���W���^�]�̈�ŋC���x�~���\�Ȃ��߁A�z�E�r�C�ًx�~�����̋C���x�~�V�X�e���̉ߋ��f�B�[�[���G���W���ɔ�
�r���āA�C���x�~�ɂ��u�R�����v�ƁuSCR�G�}�ł�NO���팸�v�̖ʂŗD�ꂽ���ʂ������ł���̂ł���B
�x�~�G���W���i�������J2005-54771�j]�����C���x�~�ʼn^�]�ł���G���W�����ׂ��Ⴂ���_������B�����āA�M�҂̗\
�z�ł́A�z�E�r�C�ق̖����ɂ��z�E�r�C�ًx�~�����̋C���x�~�V�X�e���̃V���O���^�[�{�����̉ߋ��f�B�[�[��
�G���W���̋C���x�~�́A0�`1/3 ���ׂ̋����^�]�̈�ł����C���x�~�̉^�]���ł����A�z�E�r�C�ًx�~�����̋C���x
�~�V�X�e���̂Q�i�ߋ��f�B�[�[���G���W���̋C���x�~�ł�0�`2/5 ���ׂ̋����^�]�̈�ł����C���x�~�̉^�]���ł�
�Ȃ��Ɖ]�����_������B���̂悤�ȋz�E�r�C�ًx�~�����̋C���x�~�V�X�e���ƈقȂ�A�Q�^�[�{�����̋C���x�~�G���W��
[�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j]�́A0�`�P/2 ���ׂ̍L���^�]�̈�ŋC���x�~���\�ƂȂ�D�ꂽ������
�������Z�p�ł���B���̂悤�ɁA�Q�^�[�{�����̋C���x�~�G���W��[�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j]�́A�L��
�G���W���^�]�̈�ŋC���x�~���\�Ȃ��߁A�z�E�r�C�ًx�~�����̋C���x�~�V�X�e���̉ߋ��f�B�[�[���G���W���ɔ�
�r���āA�C���x�~�ɂ��u�R�����v�ƁuSCR�G�}�ł�NO���팸�v�̖ʂŗD�ꂽ���ʂ������ł���̂ł���B
�@���͂Ƃ�����A�\�P�Ɏ������悤�ɁA�{���{�E�g���b�N�X����{�̃g���b�N���[�J�̃G���W���Z�p�҂́A�C���x�~�̋Z�p
�Ƃ��ẮA�u�R�����v�ƁuSCR�G�}�ł�NO���팸�v�̌��ʂ̗��z�E�r�C�ًx�~�����̋C���x�~�V�X�e���̉ߋ��f�B�[
�[���G���W���̋C���x�~���l���Ă���悤�ł���B���̋z�E�r�C�ًx�~�����̋C���x�~�V�X�e���́A�K�\�����G���W��
�ƋC���x�~�V�X�e�������̂܂ܖ͕킵���Z�p���ߋ��f�B�[�[���G���W���ɓK�p�������̂Ɛ��@�����B���̂��Ƃ���A��
���̃g���b�N���[�J�̃G���W���̃G���W���Z�p�҂́A�ߋ��f�B�[�[���G���W���ł́u�R�����v�ƁuSCR�G�}�ł�NO���팸�v
�̋@�\�̗��z�E�r�C�ًx�~�����̋C���x�~�V�X�e���������Ɏv�������Ȃ������Ƃ���A�ނ�̔��z���ӊO��
�R�����ƌ����Ă��d���������̂ł͂Ȃ����낤���B
�Ƃ��ẮA�u�R�����v�ƁuSCR�G�}�ł�NO���팸�v�̌��ʂ̗��z�E�r�C�ًx�~�����̋C���x�~�V�X�e���̉ߋ��f�B�[
�[���G���W���̋C���x�~���l���Ă���悤�ł���B���̋z�E�r�C�ًx�~�����̋C���x�~�V�X�e���́A�K�\�����G���W��
�ƋC���x�~�V�X�e�������̂܂ܖ͕킵���Z�p���ߋ��f�B�[�[���G���W���ɓK�p�������̂Ɛ��@�����B���̂��Ƃ���A��
���̃g���b�N���[�J�̃G���W���̃G���W���Z�p�҂́A�ߋ��f�B�[�[���G���W���ł́u�R�����v�ƁuSCR�G�}�ł�NO���팸�v
�̋@�\�̗��z�E�r�C�ًx�~�����̋C���x�~�V�X�e���������Ɏv�������Ȃ������Ƃ���A�ނ�̔��z���ӊO��
�R�����ƌ����Ă��d���������̂ł͂Ȃ����낤���B
�@�������Ȃ���A��^�g���b�N�ɂ�����u�R�����v�ƁuNO���팸�v�̉ۑ��������g���b�N���[�J�̃G���W���̃G���W���Z�p
�҂́A�M�҂̒�Ă���Q�^�[�{�����̋C���x�~�G���W��[�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j]�̋Z�p��m�邱��
�ɂȂ�A�\�����u�d�ʎԃ��[�h�R��̌���v�ƁuSCR�G�}�ł�NO���팸�v�������ł��邽�߂ɁA�������ƂȂ��Q�^�[�{��
���̋C���x�~�V�X�e�����̗p����\���������ƍl������B�������Ȃ���A�M�҂̒�Ă���Q�^�[�{�����̋C���x
�~�G���W��[�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j]�̋Z�p��m�邱�ƂɂȂ��Ă��A����܂Œʂ�̃K�\�����G���W����
���l�̋z�E�r�C�ق𖧕���@�\�����z�E�r�C�ًx�~�����̋C���x�~�V�X�e���̋C���x�~�f�B�[�[���G���W����
�����E�J���ɌŎ�����G���W���Z�p�ҁE���Ƃ����݂����Ƃ���A���̐l�B�́A�ꕔ�̋C���Q���x�~����^�]���
�ɂ����ẮA�Ⴂ�����ł����^�[�{�ߋ��킪�쓮���Ȃ����Ƃ𗝉��ł��Ȃ����\�ȃf�B�[�[���G���W���Z�p�ҁE����
�ƍl������B
�҂́A�M�҂̒�Ă���Q�^�[�{�����̋C���x�~�G���W��[�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j]�̋Z�p��m�邱��
�ɂȂ�A�\�����u�d�ʎԃ��[�h�R��̌���v�ƁuSCR�G�}�ł�NO���팸�v�������ł��邽�߂ɁA�������ƂȂ��Q�^�[�{��
���̋C���x�~�V�X�e�����̗p����\���������ƍl������B�������Ȃ���A�M�҂̒�Ă���Q�^�[�{�����̋C���x
�~�G���W��[�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j]�̋Z�p��m�邱�ƂɂȂ��Ă��A����܂Œʂ�̃K�\�����G���W����
���l�̋z�E�r�C�ق𖧕���@�\�����z�E�r�C�ًx�~�����̋C���x�~�V�X�e���̋C���x�~�f�B�[�[���G���W����
�����E�J���ɌŎ�����G���W���Z�p�ҁE���Ƃ����݂����Ƃ���A���̐l�B�́A�ꕔ�̋C���Q���x�~����^�]���
�ɂ����ẮA�Ⴂ�����ł����^�[�{�ߋ��킪�쓮���Ȃ����Ƃ𗝉��ł��Ȃ����\�ȃf�B�[�[���G���W���Z�p�ҁE����
�ƍl������B
�Q�|�Q�@�M�Ғ�Ă��C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�Ƌz�E�r�C�ْ�~���Ƃ̑���
�@�ߋ��U�C���f�B�[�[���̋C���x�~�G���W���ɂ����āA���쎩���Ԃ́u�S�C���A���̉ߋ��@��������z�E�r�C�ْ�~
���̋C���x�~�V�X�e���v�ł́A�R�C�����x�~����G���W���^�]�̗̈�͖w�Ǒ��݂��Ȃ��B�������A�M�Ғ�Ă�2�^�[�{��
���̋C���x�~�V�X�e���i���C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�j�ł́A�G���W����1�^�Q���ȉ��ɂ����āA�R�C
���̋C���Q�������ғ�����C���x�~�^�]���\�ł���B
���̋C���x�~�V�X�e���v�ł́A�R�C�����x�~����G���W���^�]�̗̈�͖w�Ǒ��݂��Ȃ��B�������A�M�Ғ�Ă�2�^�[�{��
���̋C���x�~�V�X�e���i���C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�j�ł́A�G���W����1�^�Q���ȉ��ɂ����āA�R�C
���̋C���Q�������ғ�����C���x�~�^�]���\�ł���B
�@�����āA��^�g���b�N�̎��ۂ̑��s�ɂ����ẮA�G���W���^�]��1�^�Q���ȉ��̌y���ׂ����p����邽�߁A
�y���ׂɂ����ĂR�C�����x�~����G���W���^�]���\���M�Ғ�Ă�2�^�[�{�����̋C���x�~�V�X�e���i���C��
�x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�j�́A��^�g���b�N�̏\���ȑ��s�R��̌��オ�\�ł���B
�y���ׂɂ����ĂR�C�����x�~����G���W���^�]���\���M�Ғ�Ă�2�^�[�{�����̋C���x�~�V�X�e���i���C��
�x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�j�́A��^�g���b�N�̏\���ȑ��s�R��̌��オ�\�ł���B
�����ĂƕM�Ғ�Ă̋C���x�~�V�X�e�����ߋ��U�C���G���W���ɂ�����ғ��C�����̃}�b�v�ƔR��̔�r
| |
|
�i�P�j �M�Ғ�Ă��C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j
�̋C���x�~����̃}�b�v�@�i�U�C���ߋ��G���W���j
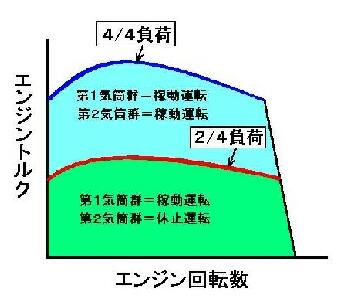 |
�i�P�j ����́u�z�E�r�C�ْ�~���̋C���x�~�V�X�e���v
�ɂ���C���x�~����̃}�b�v�@�i�U�C���ߋ��G���W���j
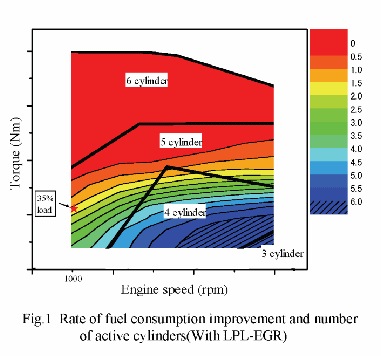 |
�i�Q�j��^�g���b�N�̍��������s���̔R����P
�@�E�������H�̑��s�R��́A�T�`�P�O���̒ጸ
�@�@�i���҂̐���j
|
�i�Q�j��^�g���b�N�̍��������s���̔R����P
�@�E�������H�̑��s�R��́A�S���̉��P
|
�i�Q�j��^�g���b�N��JE0�T���[�h�̔R����P
�@�E�d�ʎԃ��[�h�R��́A�T�`�P�O���̒ጸ
�@�@�i���҂̐���j
|
�i�R�j��^�g���b�N��JE0�T���[�h�̔R����P
�E�d�ʎԃ��[�h�R��́A�Q�`�R���̉��P
�@�i���҂̐���j
|
�@�ȏ�̂��Ƃ���A�����I�ɑ�^�g���b�N�̔R������}��Z�p�Ƃ��ẮA���҂���Ă��Ă����C���x�~�G���W
���i�������J2005-54771�j���䂪���ōL�����p�������\���́A�قڊԈႢ�Ȃ��ƍl�������B�Ȃ��A���쎩
���Ԓ�Ắu�S�C���A���̉ߋ��@��������z�E�r�C�ْ�~���̋C���x�~�V�X�e���v�̋Z�p�ɔ�r�����ꍇ�A�M�Ғ�
�Ă��C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�́A��^�g���b�N�̔R����i�i�ɉ��P�ł���@�\�E���\���������Z�p
�ł���B���̂��Ƃɂ��ẮA���쎩���Ԃ��_�����\�����R����P�@�\�̗��C���x�~�V�X�e���̃y�[�W�ɏڏq����
����̂ŁA�����̂�����͂����������������B
���i�������J2005-54771�j���䂪���ōL�����p�������\���́A�قڊԈႢ�Ȃ��ƍl�������B�Ȃ��A���쎩
���Ԓ�Ắu�S�C���A���̉ߋ��@��������z�E�r�C�ْ�~���̋C���x�~�V�X�e���v�̋Z�p�ɔ�r�����ꍇ�A�M�Ғ�
�Ă��C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�́A��^�g���b�N�̔R����i�i�ɉ��P�ł���@�\�E���\���������Z�p
�ł���B���̂��Ƃɂ��ẮA���쎩���Ԃ��_�����\�����R����P�@�\�̗��C���x�~�V�X�e���̃y�[�W�ɏڏq����
����̂ŁA�����̂�����͂����������������B
�R�D�@�Q�^�[�{�ߋ��@�����̋C���x�~�G���W���̃��J�j�Y��
�@���̂Q�^�[�{�ߋ��@�������C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�ł́A�}�P�Ɏ������悤�ɁA���C���f�B�[�[
���G���W�����P�C���Q�Ƒ�Q�C���Q�ɕ����A�C���Q���ɓƗ������z�C�ʘH�A�r�C�ʘH�A�d�f�q�K�X�ʘH�̊e�ʘH���
���A�����ʘH���ɂd�f�q�فA�d�f�q�N�[���A�d�f�q�ʘH�A�ߋ����u�A���C�C���^�[�N�[���A�r�C�i��فA�c�o�e���u�A�_���G
�}���u�A�m�n���z���Ҍ����u�A�A�f�r�b�q���u���̋z�r�C�֘A���䑕�u��z�u���A�C���Q���̋z����C�A�d�f�q�K�X��
��єr�C�K�X�̗��ꂪ�݂��ɍ������Ȃ�����ʘH�̉�H�Ƃ���B
���G���W�����P�C���Q�Ƒ�Q�C���Q�ɕ����A�C���Q���ɓƗ������z�C�ʘH�A�r�C�ʘH�A�d�f�q�K�X�ʘH�̊e�ʘH���
���A�����ʘH���ɂd�f�q�فA�d�f�q�N�[���A�d�f�q�ʘH�A�ߋ����u�A���C�C���^�[�N�[���A�r�C�i��فA�c�o�e���u�A�_���G
�}���u�A�m�n���z���Ҍ����u�A�A�f�r�b�q���u���̋z�r�C�֘A���䑕�u��z�u���A�C���Q���̋z����C�A�d�f�q�K�X��
��єr�C�K�X�̗��ꂪ�݂��ɍ������Ȃ�����ʘH�̉�H�Ƃ���B
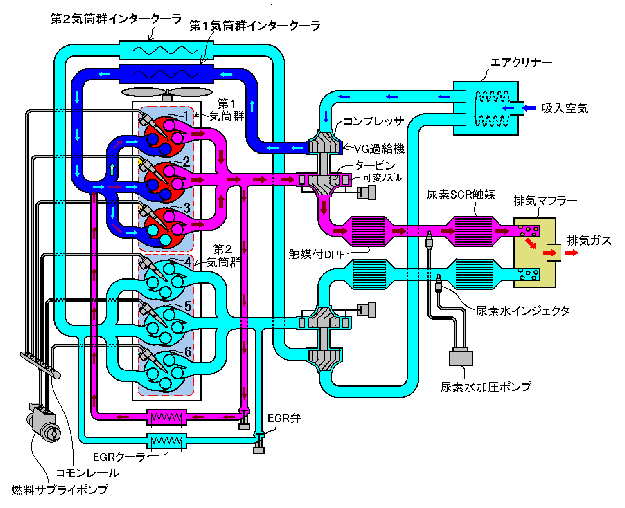
|
�@�@�@�@�@�@�@�@�}�P�@�C���Q�ʐ���G���W���̕������ׂɂ�����^�]���
|
|
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i��P�C���Q���ғ��A��Q�C���Q���x�~�j
|
�@�����Đ}�Q�Ɏ������悤�ɁA�G���W���d�b�t�̐M���ɂ��A�v��P�C���Q�Ƒ�Q�C���Q�ւ̔R�������A�ߋ����u����єr
�C�㏈�����u�͋C���Q���ɓƗ����Đ��䂷����̂ł���B����ɂ���ăG���W���̕������^�]�ł́A���ꂩ�����
�C���Q�ɔR�����������ăG���W���o�͂�������ғ��C���Q�Ƃ��ĉ^�]���A���̋C���Q�ɂ͔R�������𒆎~����x
�~�C���Q�Ƃ��ĉ^�]���A�ߋ����u����єr�C�㏈�����u�́A���ꂼ��̋C���Q�ɓK����������s���B�Ȃ��A��������
���̉ғ��C���Q�͈�莞�Ԗ��ɑ�P�C���Q�Ƒ�Q�C���Q�Ƃ��ւ���悤�ɂ���B
�C�㏈�����u�͋C���Q���ɓƗ����Đ��䂷����̂ł���B����ɂ���ăG���W���̕������^�]�ł́A���ꂩ�����
�C���Q�ɔR�����������ăG���W���o�͂�������ғ��C���Q�Ƃ��ĉ^�]���A���̋C���Q�ɂ͔R�������𒆎~����x
�~�C���Q�Ƃ��ĉ^�]���A�ߋ����u����єr�C�㏈�����u�́A���ꂼ��̋C���Q�ɓK����������s���B�Ȃ��A��������
���̉ғ��C���Q�͈�莞�Ԗ��ɑ�P�C���Q�Ƒ�Q�C���Q�Ƃ��ւ���悤�ɂ���B
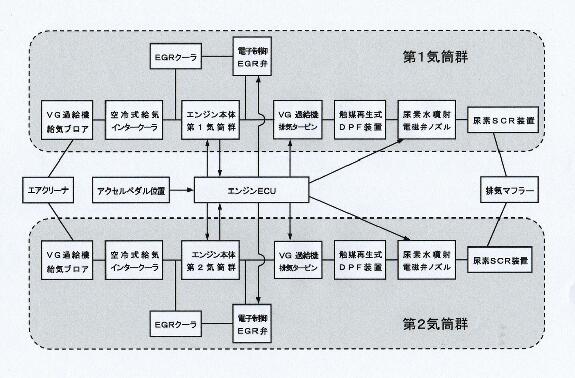
�S�D�@�Q�^�[�{�ߋ��@�����̋C���x�~�ŕ���������NOx�ƔR����P����闝�R
�S�|�P�D�@�r�C�K�X���x�̍�����R��̃G���W���^�]�̏����i�ߋ��f�B�[�[���G���W���j
�@���݂̃|�X�g�V�����r�o�K�X�K���i�Q�O�O�X�N�K���j�K������^�g���b�N�p�C���^�[�N�[���ߋ��f�B�[�[���G���W���́A
�A�fSCR�G�}���u�Ƃc�o�e���u���̗p���邱�Ƃɂ����NO����PM���팸���A�K���ɓK�������Ă���B���̃C���^�[�N�[��
�ߋ��f�B�[�[���G���W���́A�}�R�̖͎��}�Ɏ������悤�ɁA�������ϗL�����͂̑����ɔ���Ⴕ�ĔR��������lj�
���A�������ϗL�����́iPme�j�̑����ɔ�Ⴕ�ă^�[�r�������A�^�[�r���o������єA�f�r�b�q�G�}�����̔r�C�K�X��
�x�������ƂȂ���������邱�Ƃ͍L���m���Ă��邱�Ƃł���B
�A�fSCR�G�}���u�Ƃc�o�e���u���̗p���邱�Ƃɂ����NO����PM���팸���A�K���ɓK�������Ă���B���̃C���^�[�N�[��
�ߋ��f�B�[�[���G���W���́A�}�R�̖͎��}�Ɏ������悤�ɁA�������ϗL�����͂̑����ɔ���Ⴕ�ĔR��������lj�
���A�������ϗL�����́iPme�j�̑����ɔ�Ⴕ�ă^�[�r�������A�^�[�r���o������єA�f�r�b�q�G�}�����̔r�C�K�X��
�x�������ƂȂ���������邱�Ƃ͍L���m���Ă��邱�Ƃł���B
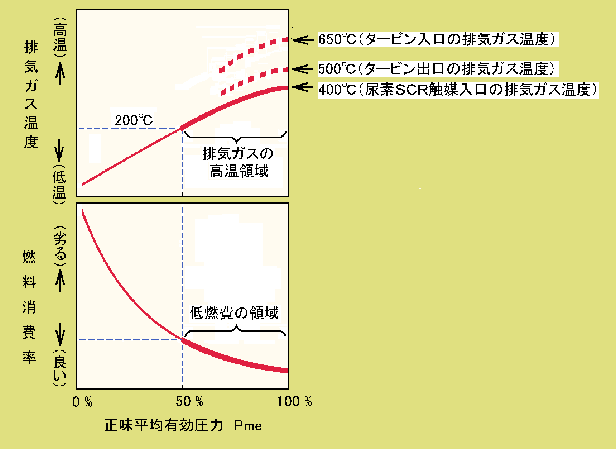
�@��ʂ̑�^�g���b�N�p�C���^�[�N�[���ߋ��f�B�[�[���G���W���ł́A�}�R�̖͎��}�̒��ɋL�ڂ����悤�ɁA�T�O���ߖT
�ȏ�̐������ϗL�����͂ł́A�Ⴂ�R��ŃG���W�����^�]�ł���̂��B�����āA�T�O���ߖT�ȏ�̐������ϗL������
�ł́A�r�C�K�X���x���A�fSCR�G�}�̓�����t�߂ɂ����ĂQ�O�O�����x�ȏ�̏�ɍ������x�ŃG���W�����^�]�����
����B
�ȏ�̐������ϗL�����͂ł́A�Ⴂ�R��ŃG���W�����^�]�ł���̂��B�����āA�T�O���ߖT�ȏ�̐������ϗL������
�ł́A�r�C�K�X���x���A�fSCR�G�}�̓�����t�߂ɂ����ĂQ�O�O�����x�ȏ�̏�ɍ������x�ŃG���W�����^�]�����
����B
�S�|�Q�D�@�C���x�~�i�������J2005-54771�j�ɂ��A�fSCR�G�}�ł̑啝��NO���팸
�A�fSCR�G�}�ɔA�f�����������Ĕr�C�K�X����NO����NO�����Ҍ�����ꍇ�A�}�S�Ɏ������悤��SCR�G�}�������x��
�P�W�O���ȉ��ɒቺ�����NO���팸�̋@�\�������ɒቺ�������������B
�P�W�O���ȉ��ɒቺ�����NO���팸�̋@�\�������ɒቺ�������������B
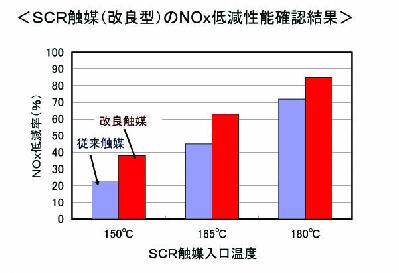
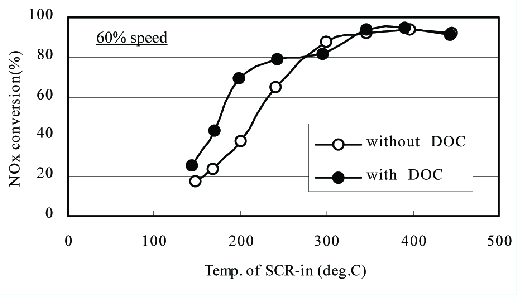
�@���݂ɁA��^�f�B�[�[���g���b�N��JE�O�T���[�h�r�o�K�X�����ɂ����ẮA�A�fSCR�G�}���̔r�o�K�X�㏈�����u��
������ɂ�����r�o�K�X�̕��ω��x�́A�}�T�Ɏ������悤�ɂP�X�V���ł���AJE�O�T���[�h�r�o�K�X�����̖��̎���
���Q�O�O���ȉ��̉��x���x�ł���B
������ɂ�����r�o�K�X�̕��ω��x�́A�}�T�Ɏ������悤�ɂP�X�V���ł���AJE�O�T���[�h�r�o�K�X�����̖��̎���
���Q�O�O���ȉ��̉��x���x�ł���B
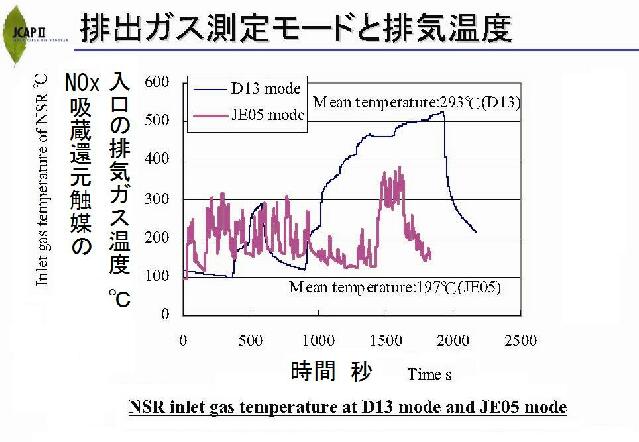
�@�}�T���疾�炩�Ȃ悤�ɁA���s�̃f�B�[�[���G���W����JE�O�T���[�h�r�o�K�X�����ɂ����ẮA�A�fSCR�G�}�̓����
�ɂ�����r�C�K�X�̉��x�́A�r�o�K�X�����̖��̎��Ԃ��Q�O�O���ȉ��̉��x�ł��邱�Ƃ�����B���̂�ȂQ�O�O��
�ȉ��̒Ⴂ�r�C�K�X�ɔA�fSCR�G�}���\�I����Ă���ꍇ�ɂ́A�A�fSCR�G�}�ł�NO���팸�����������ቺ����B
���̌��ʁA���s�̃f�B�[�[���G���W���ł́A�A�fSCR�G�}�ɂ��\����NO���̍팸������ƂƂȂ��Ă���̂ł���B��
��AJE�O�T���[�h�r�o�K�X�����ł̃f�B�[�[���G���W����NO���r�o���\���ɍ팸�ł���悤�ɂ��邽�߂ɂ́AJE�O�T���[
�h�r�o�K�X�����ł̔r�C�K�X���x�ቺ����G���W���̌y���ׂɂ����ASCR�G�}�����t�߂̔r�C�K�X���x���Q�O�O����
��ɍ��������邱�Ƃ��]�܂����B����������A�A�N�Z���y�_�������ݗʂ����Ȃ��A�N�Z���y�_���ʒu�ł�SCR�G�}
�����̕t�߂̔r�C�K�X���x���Q�O�O���ȏ�ɍ������ł���悤�ɃG���W���𐧌䂷�邱�Ƃɂ���āA�A�fSCR�G�}��
NO���팸�̋@�\�����߂邱�Ƃ��\�ƂȂ�̂ł���B������^�f�B�[�[���g���b�N�p�̋C���x�~�G���W���i�������J
2005-54771�j�ɂ�����NO�����P���ł��闝�R���A�\�R�ɂ܂Ƃ߂��B
�ɂ�����r�C�K�X�̉��x�́A�r�o�K�X�����̖��̎��Ԃ��Q�O�O���ȉ��̉��x�ł��邱�Ƃ�����B���̂�ȂQ�O�O��
�ȉ��̒Ⴂ�r�C�K�X�ɔA�fSCR�G�}���\�I����Ă���ꍇ�ɂ́A�A�fSCR�G�}�ł�NO���팸�����������ቺ����B
���̌��ʁA���s�̃f�B�[�[���G���W���ł́A�A�fSCR�G�}�ɂ��\����NO���̍팸������ƂƂȂ��Ă���̂ł���B��
��AJE�O�T���[�h�r�o�K�X�����ł̃f�B�[�[���G���W����NO���r�o���\���ɍ팸�ł���悤�ɂ��邽�߂ɂ́AJE�O�T���[
�h�r�o�K�X�����ł̔r�C�K�X���x�ቺ����G���W���̌y���ׂɂ����ASCR�G�}�����t�߂̔r�C�K�X���x���Q�O�O����
��ɍ��������邱�Ƃ��]�܂����B����������A�A�N�Z���y�_�������ݗʂ����Ȃ��A�N�Z���y�_���ʒu�ł�SCR�G�}
�����̕t�߂̔r�C�K�X���x���Q�O�O���ȏ�ɍ������ł���悤�ɃG���W���𐧌䂷�邱�Ƃɂ���āA�A�fSCR�G�}��
NO���팸�̋@�\�����߂邱�Ƃ��\�ƂȂ�̂ł���B������^�f�B�[�[���g���b�N�p�̋C���x�~�G���W���i�������J
2005-54771�j�ɂ�����NO�����P���ł��闝�R���A�\�R�ɂ܂Ƃ߂��B
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
�@���̋C���x�~�G���W���̕��������ɂ�����R�ĉ^�]�̋C���Q�ł�
�����r�C�K�X���x�́A�R�ĉ^�]����C���Q�̔A�fSCR�G�}�ł̍��� NO���팸�����ێ����邱�Ƃ��\�ƂȂ�B���̋C���x�~�G���W���i���� ���J2005-54771�j�ɂ�����A�fSCR�G�}�ł̍���NO���팸���̈ێ��́A �]���G���W�������啝��NO�����팸�ł��邱�Ƃł���B �@�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̂U�C���f�B�[�[���G ���W�� �ł́A���������ɂ����āA����̋C���Q�i�R�C���j��R�ċC���Ƃ��ĉ^�] ���A�����̋C���Q�i�R�C���j���x�~�C���Ƃ��ĉ^�]����B�R�ĉ^�]������ �C���Q�i�R�C���j�̊e�C���̔r�C�K�X���x�́A�S�C����R�Ă�����]�� �G���W���ɂ�����e�C���̔r�C�K�X���x���������ł��邱�ƂɂȂ�B |
�@�܂��A�ŋ߂ł́A�u�A�f�r�b�q�G�}�̒ቷ�������̌����v�Ƒ肷��_�������������\����Ă���悤�ł���B�����͉]��
�Ă��A�A�f�r�b�q�G�}�̒ቷ�������̑��i�́A������������邱�Ƃ��ɂ߂č���ȋZ�p�J���ł���B���̂��߁A���ɁA
���̋Z�p�J�����听�������߂��Ƙ_�����Ŕ��\���ꂽ�Ƃ��Ă��A�A�f�r�b�q�G�}��NOx�팸�����}���ɒቺ���鉷�x
�����݂�200������ő�ł����\�����x�̒ቷ�����}��邾���Ɨ\�z�����B���̂Ƃ���A�ቷ�ł�NO���팸���̍�
���G�}�Ƃ��Ă͓��[�I���C�g���L�]�̂悤�ł��邪�A���̓��[�I���C�g�̎��p��̖��͉��������̂ł��낤���B�܂��A
���̓��[�I���C�g��p���邱�Ƃɂ���āu�ቷ�̔r�C�K�X�ɂ�����NO���팸���̌���v���\�Ƃ��Ă��ANOx�팸�����}
���ɒቺ���鉷�x�����݂̔A�f�r�b�q�G�}�ɂ�����200������ő�ł����\�����x�̒ቷ�����}��邾���ł���B
�Ă��A�A�f�r�b�q�G�}�̒ቷ�������̑��i�́A������������邱�Ƃ��ɂ߂č���ȋZ�p�J���ł���B���̂��߁A���ɁA
���̋Z�p�J�����听�������߂��Ƙ_�����Ŕ��\���ꂽ�Ƃ��Ă��A�A�f�r�b�q�G�}��NOx�팸�����}���ɒቺ���鉷�x
�����݂�200������ő�ł����\�����x�̒ቷ�����}��邾���Ɨ\�z�����B���̂Ƃ���A�ቷ�ł�NO���팸���̍�
���G�}�Ƃ��Ă͓��[�I���C�g���L�]�̂悤�ł��邪�A���̓��[�I���C�g�̎��p��̖��͉��������̂ł��낤���B�܂��A
���̓��[�I���C�g��p���邱�Ƃɂ���āu�ቷ�̔r�C�K�X�ɂ�����NO���팸���̌���v���\�Ƃ��Ă��ANOx�팸�����}
���ɒቺ���鉷�x�����݂̔A�f�r�b�q�G�}�ɂ�����200������ő�ł����\�����x�̒ቷ�����}��邾���ł���B
�@����ɑ��A�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p�����p������A�f�B�[�[���g���b�N�E�o�X�̎���
�s����JE05���[�h�̏d�ʎԔr�o�K�X�������ɂ�����G���W���^�]�p�x�̍����P�^�Q���ȉ��̃G���W���^�]��Ԃ�
�����ẮA�C���x�~�ɂ��R�ĂɎg����z����C�ʂ������ƂȂ邽�߂ɔr�C�K�X���x���Q�{�߂��ɍ������ł����
�ł���B���̂悤�ɁA�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j���̗p�����ꍇ�ɂ́A�f�B�[�[���g���b�N�E�o�X�̎����s
����JE05���[�h�̏d�ʎԔr�o�K�X�������̔r�C�K�X���x���Q�{�߂��ɍ������ł��邽�߁A�]���̃f�B�[�[���G���W��
�ł͔r�C�K�X���x�̒Ⴂ�G���W���������^�]���ɂ����Ă��A���s�̔A�f�r�b�q�G�}�ɂ�����NOx�팸���̑啝�Ȍ�
�オ�e�ՂɎ����ł���̂ł���B
�s����JE05���[�h�̏d�ʎԔr�o�K�X�������ɂ�����G���W���^�]�p�x�̍����P�^�Q���ȉ��̃G���W���^�]��Ԃ�
�����ẮA�C���x�~�ɂ��R�ĂɎg����z����C�ʂ������ƂȂ邽�߂ɔr�C�K�X���x���Q�{�߂��ɍ������ł����
�ł���B���̂悤�ɁA�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j���̗p�����ꍇ�ɂ́A�f�B�[�[���g���b�N�E�o�X�̎����s
����JE05���[�h�̏d�ʎԔr�o�K�X�������̔r�C�K�X���x���Q�{�߂��ɍ������ł��邽�߁A�]���̃f�B�[�[���G���W��
�ł͔r�C�K�X���x�̒Ⴂ�G���W���������^�]���ɂ����Ă��A���s�̔A�f�r�b�q�G�}�ɂ�����NOx�팸���̑啝�Ȍ�
�オ�e�ՂɎ����ł���̂ł���B
�S�|�R�@�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�ɂ��啝�ȔR��̌���
�@�M�҂���Ă��Ă����Q��̃^�[�{�ߋ��@�����ɑ�������Q�^�[�{�������ߋ��f�B�[�[�����C���x�~�G���W���i����
���J2005-54771�j�ɂ����āA�Ⴆ���U�C�����f�B�[�[���G ���W���̕��������ɂ����āA�R�C�����x�~�C���Ƃ��Ďc��
�̂R�C����R�ċC���Ƃ��ĉ^�]���s�����ꍇ�ɂ́A�啝�ȃG���W���R��̍팸��NO���̍팸���\�ƂȂ�B���̋C��
�Q����ɂ��C���x�~�^�]�ł̔R��팸��NO���팸�̗��R���A�\�S�ɂ܂Ƃ߂��B
���J2005-54771�j�ɂ����āA�Ⴆ���U�C�����f�B�[�[���G ���W���̕��������ɂ����āA�R�C�����x�~�C���Ƃ��Ďc��
�̂R�C����R�ċC���Ƃ��ĉ^�]���s�����ꍇ�ɂ́A�啝�ȃG���W���R��̍팸��NO���̍팸���\�ƂȂ�B���̋C��
�Q����ɂ��C���x�~�^�]�ł̔R��팸��NO���팸�̗��R���A�\�S�ɂ܂Ƃ߂��B
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
�@�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j���U�C���f�B�[�[��
�G ���W���ł́A�R�C���ɂP������^�ߋ��@�����A����ɔz�u �����Q��̏��^�ߋ��@���ɂQ�̋C���Q�ɕ������A�Q�̋C���Q ��Ɨ����ĕ��ׂ𐧌䂷��\���ł���B�����āA���������� �����āA����̋C���Q�i�R�C���j��R�ċC���Ƃ��ĉ^�]���A������ �C���Q�i�R�C���j���x�~�C���Ƃ��ĉ^�]����B���̎��A�R�ċC�� �Ƃ��ĉ^�]����C���Q�i�R�C���j�ɂ͂R�C���̉ߋ��ɍœK�ȗe�� �̏��^�ߋ��@�����Ă���̂ŁA����̋C���Q�i�R�C���j�� �x�~�C���Ƃ��ĉ^�]�����ۂ̔R�ċC���Ƃ��ĉ^�]����C���Q �i�R�C���j�̏��^�ߋ��@�̉ߋ��@�����́A1��̑�^�ߋ��@�� ���������]���̂U�C���G���W���̉ߋ��@������������������ �^�]�ł��邽�߁A�|���s���O�������啝�ɍ팸�ł��邱�Ƃł���B |
| |
�@�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j���U�C���f�B�[�[��
�G ���W���ł́A���������ɂ����āA����̋C���Q�i�R�C���j�� �R�ċC���Ƃ��ĉ^�]���A�����̋C���Q�i�R�C���j���x�~�C���Ƃ��� �^�]����B�R�ĉ^�]�������C���Q�i�R�C���j�ɂ����鋟���R�� ������̃G���W���ł̗�p�ʐς́A�S�C����R�Ă�����]�� �G���W���ɂ����鋟���R��������̃G���W���ł̗�p�ʐς̔��� �ɏk���ł��邱�ƂɂȂ�B���̂��߁A�Ј���̋C���Q���x�~�^�] �������ɂ́A�R�ĉ^�]���������̋C���Q�ł̗�p���������� �ł��邽�߁A�]���G���W�������啝�ɍ팸�ł��邱�Ƃł���B �@�ŋ߁A���L�Ɏ������悤�ɁA���{�@�B�w�2013�N8�����i2018.
8 Vol. 116 No. 1137)�̔N�ӂ̔M�H�w�̃y�[�W�ł́A�u�W�E2�E2 �R�� �Z�p�E�R���v�̍��ɂ����āA�R�Ď����̒ᗬ�����ɂ��f�B�[�[���G ���W���̗�p�����̒ጸ�ɂ��A���[���b�p�̏�p�Ԃ̔R��莎 �����[�hNECD�łT���̔R����オ�m�F���ꂽ�ƋL�ڂ���Ă���B 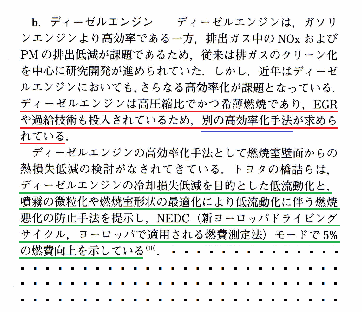 �̔N�ӂ̔M�H�w�́u�W�E2�E2 �R�ċZ�p�E�R���v�̍��j �@��ʓI�ɁA��p�Ԃł̔R����莎�����[�h�ł́A�G���W���̋�
�߂Ēᕉ�^�]�̕p�x���������A���̂悤�ȃG���W���^�]��Ԃɂ� ���Ă��V�����_���̒ᗬ�����ɂ��f�B�[�[���G���W���̗�p���� �̒ጸ�ɂ��A�T���̔R����オ�\�Ƃ̂��Ƃł���B����A��^�g ���b�N�̏ꍇ�́A�����s��d�ʎԃ��[�h�R��̑���^�]���[�h�i�� JE�O�T���[�h�j�ł��G���W�����ׂ��T�O���ȉ��ł̉^�]�p�x�������� �Ƃ���A�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p��� �^�g���b�N�̗̍p���邱�Ƃɂ���āA�V�����_�̗�p�ʐς��w�I �ɔ����ɂȂ邽�߂ɁA�����s��d�ʎԃ��[�h�R��̑���^�]���[�h �i��JE�O�T���[�h�j�ł̃G���W����p�����́A�啝�̍팸�ł��邱�Ƃ� �Ȃ�B���̂��߁A��^�g���b�N���C���x�~�G���W���i�������J2005- 54771�j�̋Z�p���̗p�����ꍇ�ɂ́A��^�g���b�N�̎����s��d�ʎ� ���[�h�R��傫�����P�ł��邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��ƍl������B |
|
| |
�@���������A���z�T�C�N���ł����J���m�[�T�C�N���ł́A�ȉ��̎���
�������ʂ�A���M���̉��x�s�g�������ɂȂ�قǁA�����M������
�Ȃ�̂ł���B���������āA�r�C�K�X�G�l���M�[���u�̓����
�̔r�C�K�X���x���ቷ�ƂȂ��^�g���b�N�̎��ۂ̑��s�ł́A
�r�C�K�X�G�l���M�[���u�̗̍p�ɂ���^�g���b�N�̑��s
�R����\���Ɍ��シ�邱�Ƃ͓���B
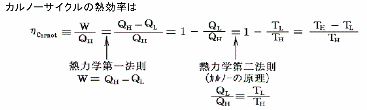 �@�@�@�@�@�@�@�������A�Y���@�g�F���M���̉��x�A�k�F��M���̉��x engine(gas_cycle)1.htm�j �@���̂悤�ɁA�t�@�ւł���J���m�[�T�C�N���́A��Ή��x�sH
�̍����M���ƁA��Ή��x�sL�̒ቷ�M���̊Ԃō쓮����M�@��
�̒��Łu�ł������̗ǂ����͔M�@�ցv�ł���B���̃J���m�[
�T�C�N���̌����͔M���̐�Ή��x�݂̂Ō��܂�A���M���̉��x
�������ɂ��������A�J���m�[�T�C�N���̔M�������ǂ��Ȃ��
�ł���B���̂��Ƃ́A�G���W���Z�p�҂łȂ��Ă��A�N�����m����
����ɂ߂ď펯�I�Ȃ��Ƃ��B
�@���̃J���m�[�T�C�N���Ɠ��l�ɁA�f�B�[�[���T�C�N���ɂ����Ă��A �ғ�����G���W���̋C���̍ō����x�����������邱�Ƃɂ��A �f�B�[�[���G���W���̔M����������ł��邱�Ƃ́A�G���W���� �Z�p�ҁE���Ƃł���A�e�Ղɗ����ł��邱�Ƃ��B �@�Ⴆ�A���݂̑�^�g���b�N�ɓ��ڂ���Ă���U�C���^�[�{ �G���W���̕������^�]�ɂ����āA�R�C�����x�~���Ďc��� �R�C�����ғ�����C���x�~�̉^�]������s�����ꍇ�̉ғ� �C���̔R�����˂́A�U�C�����ɉғ�����]���̃G���W�� �̂Q�{�߂��̔R�����˗ʂƂȂ�B���̂��߁A���̋C���x�~�^�] �̏�Ԃł́A�ғ��C���̋C�����̔R�ĉ��x�́A�]���̑S�C�� ���ɉғ�����]���G���W���̋C�����̔R�ĉ��x��{�� ���鍂�������e�ՂɎ����ł��邱�ƂɂȂ�B���̋C���x�~ �G���W���̕������^�]�̉ғ��C���ɂ�����C�����̔R�� ���x�̍������́A�ғ��C���̃T�C�N�������̌��オ�\�� �ƂȂ�B �@����A���݂̑�^�g���b�N�̎����s���ɂ́A�f�B�[�[���G���W�� �̕������^�]����̂ł��錻��l����ƁA��^�g���b�N�� �����s���̔R������}�邽�߂ɂ́A�f�B�[�[���G���W���̕��� �����̔R����P���s���K�v������B���̕��������̔R�� �C���̃T�C�N�����������シ�邽�߂ɂ́A�J���m�[�T�C�N���� ��������Ɠ������A�f�B�[�[���G���W���̕��������̔R�ċC�� �̔R�ĉ��x�������ɂ��邱�Ƃ��B���̕��������̔R�ċC���� �������ɂ���āA�f�B�[�[���G���W���̕��������̔R��A �e�ՂɌ���ł���̂ł���B������������ł���Z�p���A�M�� �̒�Ă��Ă����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�� ����B �@���̋C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j���̗p���� �U�C���f�B�[�[���G ���W���ł́A���������ɂ����ẮA ����̋C���Q�i�R�C���j��R�ċC���Ƃ��ĉ^�]���A������ �C���Q�i�R�C���j���x�~�C���Ƃ��ĉ^�]����B�R�����˂��� �C���Q�i�R�C���j�̊e�C���̍ō����́E�ō����x�́A��� �S�C���ɔR�����˂���]���G���W���̊e�C���̍ō����́E �ō����x�����Q�{�߂��̍���������������̂��B���̋C�� �x�~�G���W���̕��������ɂ�����R�ĉ^�]����C���Q�� �����ō����́E�ō����x�́A�K�R�I�ɍ����T�C�N�������� �����邱�ƂɂȂ�B���������āA��^�g���b�N�̃G���W���� �C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p���̗p���� �ꍇ�ɂ́A��^�g���b�N�̏d�ʎԃ��[�h�R�������s�R��� �啝�Ȍ��オ�\�ƂȂ�B |
|
| |
�@�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j���U�C���f�B�[�[��
�G ���W���ł́A���������ɂ����āA����̋C���Q�i�R�C���j�� �R�ċC���Ƃ��ĉ^�]���A�����̋C���Q�i�R�C���j���x�~�C���Ƃ��� �^�]����B�R�ĉ^�]�������C���Q�i�R�C���j�̊e�C���̔R�Ă� ����鋋�C�ʂ́A�S�C����R�Ă�����]���G���W���ɂ����� �e�C���̔R�Ăɏ���鋋�C�ʂ̂P�^�Q�ƂȂ邽�߁A�r�C������ �������邱�Ƃ��\�ƂȂ�B |
|
| |
�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j���U�C���f�B�[�[���G
���W���ł́A���������ɂ����āA����̋C���Q�i�R�C���j�� �R�ċC���Ƃ��ĉ^�]���A�����̋C���Q�i�R�C���j���x�~�C���Ƃ��� �^�]����B�R�ĉ^�]�������C���Q�i�R�C���j�̊e�C���̔r�C�K�X ���x�́A�S�C����R�Ă�����]���G���W���ɂ�����e�C���̔r�C �K�X���x���������ł��邱�ƂɂȂ�B���̋C���x�~�G���W���� ���������ɂ�����R�ĉ^�]�̋C���Q�ł̍����r�C�K�X���x �́A�R�ĉ^�]����C���Q��DPF���u�̃t�B���^�ɑ͐ς����p�e�B �L�����[�g�̔R�Ă��\�ɂ��邽�߁ADPF���u�̎��ȍĐ������i ����邱�ƂɂȂ�B�����C���x�~�G���W���i�������J2005- 54771�j�ɂ�����DPF���u�̎��ȍĐ��̑��i�́A�]���G���W�� �ƂȂ�B �@���̂悤�ɁA�C���x�~�G���W���́A�]���G���W������DPF���u �̎蓮�Đ��Ƌ����Đ��̕p�x���啝�ɍ팸�ł��邽�߁A�R� �팸�ł��邱�Ƃł���B |
|
�S�|�S�D�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�ɂ��G���W���o�͂̉ߓn�������̌���
�@���݂̖w��ǂ̑�^�g���b�N�ɂ́A�P��̑�^�̉ߋ��@�������u�V���O���^�[�{�����v�̂U�C���ߋ��f�B�[�[���G
���W�������ڂ���Ă���B����ɑ��A�M�҂���Ă��Ă��C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�́A�Q��̏��^��
�ߋ��@�������u�Q�^�[�{�����v�̂U�C���ߋ��f�B�[�[���G���W���ł���B���̂悤�ɁA�M�҂���Ă��Ă��C���x�~�G
���W���i�������J2005-54771�j�̉ߋ��@�͏��^�ł��邽�߁A�]���̑�^�ߋ��@�ɔ�ׂĉߋ��@�̉�]�������ʂ���
�������Ƃ������ł���B
���W�������ڂ���Ă���B����ɑ��A�M�҂���Ă��Ă��C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�́A�Q��̏��^��
�ߋ��@�������u�Q�^�[�{�����v�̂U�C���ߋ��f�B�[�[���G���W���ł���B���̂悤�ɁA�M�҂���Ă��Ă��C���x�~�G
���W���i�������J2005-54771�j�̉ߋ��@�͏��^�ł��邽�߁A�]���̑�^�ߋ��@�ɔ�ׂĉߋ��@�̉�]�������ʂ���
�������Ƃ������ł���B
�@�����āA�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p���̗p������^�f�B�[�[���g���b�N������������Ƃ��ɃA�N
�Z���y�_�����}���ɓ��ݍ��ꍇ�ɂ́A�ߋ��@�̉�]�������ʂ����������Ƃ���Z���Ԃʼnߋ��@�̉�]���㏸��
���邱�Ƃ��ł���̂��B���̂悤�ȃA�N�Z���y�_�����}���ȓ��ݍ��ۂɂ́A�Z���Ԃł̉ߋ��@�̉�]���㏸����
���Ƃ��ł��A����ɂ���đ��₩�ɏ\���ȋ��C�u�[�X�g���͂傳���ĖڕW�Ƃ���G���W���o�͂邱�Ƃ��ł����
�ł���B���������āA�Q��̏��^�̉ߋ��@������u�Q�^�[�{�����v���C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�́A
���݂̖w��ǂ̑�^�g���b�N�ɍ̗p����Ă���P��̑�^�̉ߋ��@�������u�V���O���^�[�{�����v�̉ߋ��f�B�[�[
���G���W���ɔ�r���A�����������ŃG���W���o�͂𐧌�ł��邱�Ƃ������̈���B����ɂ���āA�C���x�~�G���W��
�i�������J2005-54771�j�̋Z�p���̗p������^�g���b�N�́A���s��������ł���̂ł���B
�Z���y�_�����}���ɓ��ݍ��ꍇ�ɂ́A�ߋ��@�̉�]�������ʂ����������Ƃ���Z���Ԃʼnߋ��@�̉�]���㏸��
���邱�Ƃ��ł���̂��B���̂悤�ȃA�N�Z���y�_�����}���ȓ��ݍ��ۂɂ́A�Z���Ԃł̉ߋ��@�̉�]���㏸����
���Ƃ��ł��A����ɂ���đ��₩�ɏ\���ȋ��C�u�[�X�g���͂傳���ĖڕW�Ƃ���G���W���o�͂邱�Ƃ��ł����
�ł���B���������āA�Q��̏��^�̉ߋ��@������u�Q�^�[�{�����v���C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�́A
���݂̖w��ǂ̑�^�g���b�N�ɍ̗p����Ă���P��̑�^�̉ߋ��@�������u�V���O���^�[�{�����v�̉ߋ��f�B�[�[
���G���W���ɔ�r���A�����������ŃG���W���o�͂𐧌�ł��邱�Ƃ������̈���B����ɂ���āA�C���x�~�G���W��
�i�������J2005-54771�j�̋Z�p���̗p������^�g���b�N�́A���s��������ł���̂ł���B
�S�|�T�D�]���̃G���W���ɂ����āA��R��ƔA�fSCR�ɂ��NO���팸���s�\���ȉ^�]�̈�
�@�@�@�@
�@�O�q�̒ʂ�A�S�C�����펞�ғ�����]���̉ߋ��f�B�[�[���G���W���ɂ����ẮA�������ϗL������Pme���T�O����
�^�]�̈�ɂ����Ă͔R��Ⴍ���Ȃ�Ƌ��ɁA�A�fSCR�G�}��SCR�G�}�����t�߂̔r�C�K�X���x���Q�O�O���ȏ�̍�
���ƂȂ邽�ߔA�fSCR�G�}��NO���팸�̋@�\�����܂���NO�������팸���Œጸ�ł���̂ł���B
�^�]�̈�ɂ����Ă͔R��Ⴍ���Ȃ�Ƌ��ɁA�A�fSCR�G�}��SCR�G�}�����t�߂̔r�C�K�X���x���Q�O�O���ȏ�̍�
���ƂȂ邽�ߔA�fSCR�G�}��NO���팸�̋@�\�����܂���NO�������팸���Œጸ�ł���̂ł���B
�@�]�����S�C�����펞�ғ�����]���G���W���ɂ����ẮA�}�U�|�Q�Ɏ������悤���A�N�Z���y�_�������ݗʂ̔�Ⴕ��
�S�C�����������G���W����͂ʼnғ����鐧��ƂȂ��Ă���B���������āAPme���T�O���ȏ�ƂȂ�^�]�̈�́A�}�U�|�P
�Ɏ������A�N�Z���y�_�������ݗʂ��T�O���ȏ�̐ԐF�̉^�]�̈�ł���B���̂��߁A���ۂ̑�^�g���b�N�̑��s����
�ő��p�����A�N�Z���y�_�������ݗʂ��T�O���ȉ��̃G���W���^�]���ɂ́A�R�������ɁA�A�fSCR�G�}��SCR�G
�}�����t�߂̔r�C�K�X���x���Q�O�O���ȉ��̒ቷ�ƂȂ��ĔA�fSCR�G�}��NO���팸�̋@�\���ቺ���Ă��Ă��܂�����
��NO���̍팸���s�\���ȏ�ԂƂȂ�̂��B
�S�C�����������G���W����͂ʼnғ����鐧��ƂȂ��Ă���B���������āAPme���T�O���ȏ�ƂȂ�^�]�̈�́A�}�U�|�P
�Ɏ������A�N�Z���y�_�������ݗʂ��T�O���ȏ�̐ԐF�̉^�]�̈�ł���B���̂��߁A���ۂ̑�^�g���b�N�̑��s����
�ő��p�����A�N�Z���y�_�������ݗʂ��T�O���ȉ��̃G���W���^�]���ɂ́A�R�������ɁA�A�fSCR�G�}��SCR�G
�}�����t�߂̔r�C�K�X���x���Q�O�O���ȉ��̒ቷ�ƂȂ��ĔA�fSCR�G�}��NO���팸�̋@�\���ቺ���Ă��Ă��܂�����
��NO���̍팸���s�\���ȏ�ԂƂȂ�̂��B
�@�@
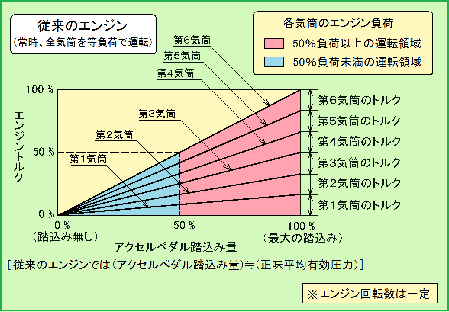
�T�D�C���x�~�V�X�e���ɂ��R��팸�ƔA�fSCR�G�}�ł�NO���팸�̌���
�@���C���f�B�[�[���G���W�����P�C���Q�Ƒ�Q�C���Q�ɕ������Q�^�[�{�ߋ��@�����̋C���x�~�f�B�[�[���G���W��
�i�������J2005-54771�j�ł́A�S�ẴG���W���^�]�����ɂ����Ċe�C���Q�̕��ׂ�C�ӂɐ��䂷�邱�Ƃ��\�ł�
��B���̑�\�I�ȑ�P�C���Q�Ƒ�Q�C���Q�̋C���Q�𐧌䂷����@�Ƃ��āA�\�T�Ɏ������悤�ɁA��ʂ���Ɓu�R��ጸ
�^�v�ƁuNO���ጸ�^�v�̂Q��ނ̃^�C�v�̐���@�ɕ��������B
�i�������J2005-54771�j�ł́A�S�ẴG���W���^�]�����ɂ����Ċe�C���Q�̕��ׂ�C�ӂɐ��䂷�邱�Ƃ��\�ł�
��B���̑�\�I�ȑ�P�C���Q�Ƒ�Q�C���Q�̋C���Q�𐧌䂷����@�Ƃ��āA�\�T�Ɏ������悤�ɁA��ʂ���Ɓu�R��ጸ
�^�v�ƁuNO���ጸ�^�v�̂Q��ނ̃^�C�v�̐���@�ɕ��������B
| |
|
| |
��P�C���Q�Ƒ�Q�C���Q�̉��ꂩ����̋C���Q����ɗD��I�ɉғ�������C���Q�̉^�]�𐧌�i�}�V�|�R�Q
�Ɓj |
| |
�A�N�Z���y�_�������ݗ�Accel���T�O������G���W�����ׂɂ����Ă��P�C���Q�Ƒ�Q�C���Q���̏o��
�œ����ɉғ�������C���Q�̉^�]�𐧌�i�}�W�|�R�Q�Ɓj |
�T�|�P�D�R��ጸ�^�̋C���Q����@�̏ꍇ�i�}�V���Q�ƕ��j
�@�Q�^�[�{�ߋ��@�����̋C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�ɂ������R��ጸ�^�ł́A���C���f�B�[�[���G���W
�����P�C���Q�Ƒ�Q�C���Q�ɕ������Q�^�[�{�ߋ��@�����̋C���x�~�f�B�[�[���G���W���ɂ�������P�C���Q�Ƒ�Q�C
���Q�̉��ꂩ����̋C���Q����ɗD��I�ɉғ��������C���Q�̉^�]����@�ł���B�}�V�|�Q�́A��ɑ�P�C���Q��
�D�悵�ĉғ��������ꍇ�̔R��ጸ�^�̋C���Q�̉^�]����@�ł���B���̏ꍇ�A��Q�C���Q�͑�P�C���Q�̉ғ���
���ł͕s������G���W���o�͂�⊮����o�͂ʼnғ�������悤�ɂ��āA�S�ẴG���W���^�]�����ŕK�v�ȃG���W���o��
�ʼn^�]�ł���悤�ɂ����C���Q�̉^�]����@���B�ܘ_�A��Q�C���Q��D�悵�ĉғ���������P�C���Q��⊮����o��
�ŃG���W�����^�]���邱�Ƃ��\�ł���B���̋C���x�~�G���W�������p�ŗp������ۂɂ́A�G���W���S�̂̑ϋv����
�r�o�K�X�㏈�����u�̋@�\�Ƒϋv���̂��߁A��P�C���Q��D�悵�ĉғ��������ꍇ�Ƒ�Q�C���Q��D�悵�ĉғ�����
���ꍇ���̎��ۂ̏ꍇ�����̃G���W���^�]���Ԗ��ɐ�ւ���悤�ɂ���B
�����P�C���Q�Ƒ�Q�C���Q�ɕ������Q�^�[�{�ߋ��@�����̋C���x�~�f�B�[�[���G���W���ɂ�������P�C���Q�Ƒ�Q�C
���Q�̉��ꂩ����̋C���Q����ɗD��I�ɉғ��������C���Q�̉^�]����@�ł���B�}�V�|�Q�́A��ɑ�P�C���Q��
�D�悵�ĉғ��������ꍇ�̔R��ጸ�^�̋C���Q�̉^�]����@�ł���B���̏ꍇ�A��Q�C���Q�͑�P�C���Q�̉ғ���
���ł͕s������G���W���o�͂�⊮����o�͂ʼnғ�������悤�ɂ��āA�S�ẴG���W���^�]�����ŕK�v�ȃG���W���o��
�ʼn^�]�ł���悤�ɂ����C���Q�̉^�]����@���B�ܘ_�A��Q�C���Q��D�悵�ĉғ���������P�C���Q��⊮����o��
�ŃG���W�����^�]���邱�Ƃ��\�ł���B���̋C���x�~�G���W�������p�ŗp������ۂɂ́A�G���W���S�̂̑ϋv����
�r�o�K�X�㏈�����u�̋@�\�Ƒϋv���̂��߁A��P�C���Q��D�悵�ĉғ��������ꍇ�Ƒ�Q�C���Q��D�悵�ĉғ�����
���ꍇ���̎��ۂ̏ꍇ�����̃G���W���^�]���Ԗ��ɐ�ւ���悤�ɂ���B
�@�}�V�|�Q�Ɏ�������ɑ�P�C���Q���D��ғ��̔R��ጸ�^�̋C���Q����@�ɂ����ẮA�S�C�����펞�ғ�����]
���̃G���W���ɔ�r���A�S�ẴG���W�����ח̈�i�A�N�Z���y�_�������ݗʂ��i�O���j�`�i���P�O�O���j�ŏ�ɍ����ׂʼn�
���ł��邽�߂ɍ����M�����Ɣr�C�K�X�̍��������ێ��ł���̂ł���B���̔R��ጸ�^�̋C���Q����@�ʼn^�]����
�x�~�C���G���W���i�������J2005-54771�j�ɂ�����R��팸��NO���팸���������e�C���̐������ϗL����Pme���T
�O���ȏ�ƂȂ�^�]�̈�́A�}�V�|�P�̐ԐF�Ŏ������^�]�̈�̍L�͈͂ɋy�Ԃ��Ƃ�����B���̂悤�ɁA�Q�^�[�{�ߋ�
�@�����̋C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̐}�V�|�P�̐ԐF��Pme���T�O���ȏ�ƂȂ�^�]�̈��́A��ɑS
�C�����ғ�����]���G���W�����}�U�|�P�̐ԐF��Pme���T�O���ȏ�ƂȂ�^�]�̈��ɔ�r���A�L���G���W���^�]�̈�
�ł��R��팸�Ɣr�C�K�X�̍������ɔ����A�fSCR�G�}�ɂ��̊������ɂ����NO�����팸�ł��Ă��邱�Ƃ����炩��
����B
���̃G���W���ɔ�r���A�S�ẴG���W�����ח̈�i�A�N�Z���y�_�������ݗʂ��i�O���j�`�i���P�O�O���j�ŏ�ɍ����ׂʼn�
���ł��邽�߂ɍ����M�����Ɣr�C�K�X�̍��������ێ��ł���̂ł���B���̔R��ጸ�^�̋C���Q����@�ʼn^�]����
�x�~�C���G���W���i�������J2005-54771�j�ɂ�����R��팸��NO���팸���������e�C���̐������ϗL����Pme���T
�O���ȏ�ƂȂ�^�]�̈�́A�}�V�|�P�̐ԐF�Ŏ������^�]�̈�̍L�͈͂ɋy�Ԃ��Ƃ�����B���̂悤�ɁA�Q�^�[�{�ߋ�
�@�����̋C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̐}�V�|�P�̐ԐF��Pme���T�O���ȏ�ƂȂ�^�]�̈��́A��ɑS
�C�����ғ�����]���G���W�����}�U�|�P�̐ԐF��Pme���T�O���ȏ�ƂȂ�^�]�̈��ɔ�r���A�L���G���W���^�]�̈�
�ł��R��팸�Ɣr�C�K�X�̍������ɔ����A�fSCR�G�}�ɂ��̊������ɂ����NO�����팸�ł��Ă��邱�Ƃ����炩��
����B
�@
| |
||||||||||||||||||||||||||||||
| |
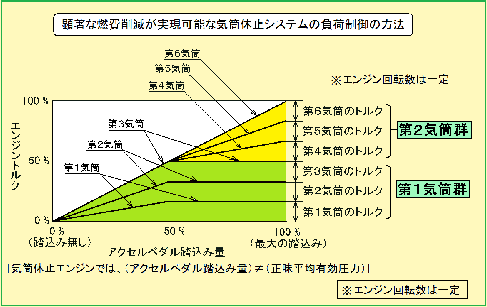 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| |
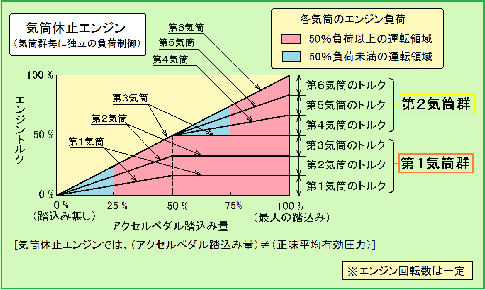 |
�Ȃ��A�}�V�|�P�Ɏ������悤�ɏ�ɑ�P�C���Q��D��肵�ĉғ�����C���Q����̏ꍇ�ɂ́A�R���NO���̍팸�̗��
�^�]�̈�͐F�̃A�N�Z���y�_�������ݗ�Accel���O���� Accel���Q�T���̑S�^�]�̈�ƂT�O���� Accel���V�T������
���̋ɂ����Ȃ��^�]�̈�ł��邱�͈�ڗđR�ł���B
�^�]�̈�͐F�̃A�N�Z���y�_�������ݗ�Accel���O���� Accel���Q�T���̑S�^�]�̈�ƂT�O���� Accel���V�T������
���̋ɂ����Ȃ��^�]�̈�ł��邱�͈�ڗđR�ł���B
�@�Ƃ���ŁA�d�ʎԂ̔r�o�K�X������d�ʎԔR���̎Z�o�ɓK�p�����JE�O�T���[�h�ł́A�}�W�Ɏ������悤�ɁA�T
�O���ȉ��̃G���W�����ׂ̎g�p�p�x���ӊO�Ƒ����̂ł���B�}�W�̂Ɏ��������וp�x�́A�p���[�E�G�C�g���V�I(���P
�ɃG���W���n�͓�����̎ԗ����d�ʁj����r�I�A�������ύڗʂQ�g�����x�̃g���b�N�̂��߁A�G���W���y���ׂ̎g�p�p
�x�������ƍl������B������p���[�E�G�C�g���V�I���傫���f�u�v�Q�T�g���̑�^�g���b�N�ł́A�}�W�̃G���W������
�p�x���������A�G���W�������ׂ̎g�p�p�x�͑�������ƍl������A�������Ȃ���AJE�O�T���[�h�ɂ��f�u�v�Q�T�g��
�̑�^�g���b�N�ɂ�����d�ʎԂ̔r�o�K�X������d�ʎԔR���̎Z�o�ł��A�T�O�����ߕӂ̃G���W���g���N�̎g
�p�p�x�������Ɛ��肳���B
�O���ȉ��̃G���W�����ׂ̎g�p�p�x���ӊO�Ƒ����̂ł���B�}�W�̂Ɏ��������וp�x�́A�p���[�E�G�C�g���V�I(���P
�ɃG���W���n�͓�����̎ԗ����d�ʁj����r�I�A�������ύڗʂQ�g�����x�̃g���b�N�̂��߁A�G���W���y���ׂ̎g�p�p
�x�������ƍl������B������p���[�E�G�C�g���V�I���傫���f�u�v�Q�T�g���̑�^�g���b�N�ł́A�}�W�̃G���W������
�p�x���������A�G���W�������ׂ̎g�p�p�x�͑�������ƍl������A�������Ȃ���AJE�O�T���[�h�ɂ��f�u�v�Q�T�g��
�̑�^�g���b�N�ɂ�����d�ʎԂ̔r�o�K�X������d�ʎԔR���̎Z�o�ł��A�T�O�����ߕӂ̃G���W���g���N�̎g
�p�p�x�������Ɛ��肳���B
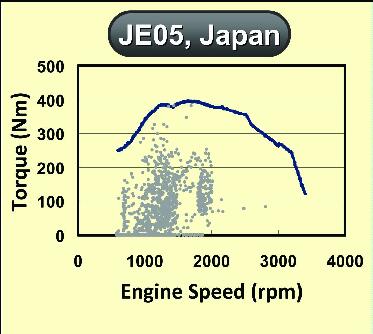
�@���̂悤�ɁAJE�O�T���[�h�ɂ��f�u�v�Q�T�g���̑�^�g���b�N�ɂ�����d�ʎԂ̔r�o�K�X������d�ʎԔR���̎Z
�o�ɂ����ĂT�O���ȉ��i���A�N�Z���y�_�������ݗ��T�O���ȉ��j�̃G���W���g���N�̎g�p�p�x���������̂ł���B����
���A��ɑS�C�����ғ�����]���G���W�����N�Z���y�_�������ݗ��T�O�����ߕ��ł́A�}�U�̐F�Ŏ����Ă���悤
�ɁA�R�������ɁA�A�fSCR�G�}��SCR�G�}�����t�߂̔r�C�K�X���x���Q�O�O���ȉ��̒ቷ�ƂȂ��ĔA�fSCR�G
�}��NO���팸�̋@�\���ቺ���Ă��Ă��܂��̂ł���B���̂��߁A�]���̃G���W���ɂ�����JE�O�T���[�h�ɂ���^�g���b
�N�̏d�ʎԂ̔r�o�K�X�����ł��A�fSCR�G�}��SCR�G�}�����t�߂̔r�C�K�X���x���Q�O�O���ȉ��̒ቷ��Ԃł�
�^�]���������߁A�A�fSCR�G�}�̂��\���Ȃm�n���ጸ������ƂȂ��Ă���B���l�ɁAJE�O�T���[�h�ɂ���^�g���b�N
�̏d�ʎԏd�ʎԔR��l���Z�o����ꍇ�ɂ����Ă��A�}�U�̐F�Ŏ����Ă����N�Z���y�_�������ݗ��T�O�����ߕӂ�
�R��̗��̈�̎g�p�p�x���������߁A�R��������Ă��܂��̂ł���B
�o�ɂ����ĂT�O���ȉ��i���A�N�Z���y�_�������ݗ��T�O���ȉ��j�̃G���W���g���N�̎g�p�p�x���������̂ł���B����
���A��ɑS�C�����ғ�����]���G���W�����N�Z���y�_�������ݗ��T�O�����ߕ��ł́A�}�U�̐F�Ŏ����Ă���悤
�ɁA�R�������ɁA�A�fSCR�G�}��SCR�G�}�����t�߂̔r�C�K�X���x���Q�O�O���ȉ��̒ቷ�ƂȂ��ĔA�fSCR�G
�}��NO���팸�̋@�\���ቺ���Ă��Ă��܂��̂ł���B���̂��߁A�]���̃G���W���ɂ�����JE�O�T���[�h�ɂ���^�g���b
�N�̏d�ʎԂ̔r�o�K�X�����ł��A�fSCR�G�}��SCR�G�}�����t�߂̔r�C�K�X���x���Q�O�O���ȉ��̒ቷ��Ԃł�
�^�]���������߁A�A�fSCR�G�}�̂��\���Ȃm�n���ጸ������ƂȂ��Ă���B���l�ɁAJE�O�T���[�h�ɂ���^�g���b�N
�̏d�ʎԏd�ʎԔR��l���Z�o����ꍇ�ɂ����Ă��A�}�U�̐F�Ŏ����Ă����N�Z���y�_�������ݗ��T�O�����ߕӂ�
�R��̗��̈�̎g�p�p�x���������߁A�R��������Ă��܂��̂ł���B
�@����ɑ��A�Q�^�[�{�ߋ��@�����̋C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j���R��ጸ�^�̋C���Q����@�ɂ���
�ẮA�N�Z���y�_�������ݗʂT�O���ȉ��ł��}�V�|�P�̐ԐF�Ŏ�����Pme���T�O���ȏ�ƂȂ��L���G���W���^�]�̈悪
���݂��A����Pme���T�O���ȏ���ԐF�̉^�]�̈�ł͒�R��ŃG���W���^�]���\�ł���A����SCR�G�}�����t�߂�
�r�C�K�X���x���Q�O�O���ȏ�������������G���W���^�]���ł��邱�Ƃɂ���đfSCR�G�}�����������ANO����啝�ɍ�
���ł���̂ł���B�����āA�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j���R��ጸ�^�̋C���Q����@�ɂ����ẮA�}�V
�|�P�̐F�Ŏ�����Pme���T�O���ȉ��̔A�fSCR�G�}��SCR�G�}�����t�߂̔r�C�K�X���x���Q�O�O���ȉ��̒ቷ��
�Ԃ̋�C���ߏ�ȉ^�]�̈�ł́A��ʂd�f�q�Ƃg�b�b�h��o�b�h�Ə̂����Ǎ������k���ΔR�Ă̋Z�p�ɂ���đ����Ȃ��
���m�n���팸��}��A�i�d�O�T�r�o�K�X�����ɂ�����m�n���팸����悹���邱�Ƃ��\�ł���B
�ẮA�N�Z���y�_�������ݗʂT�O���ȉ��ł��}�V�|�P�̐ԐF�Ŏ�����Pme���T�O���ȏ�ƂȂ��L���G���W���^�]�̈悪
���݂��A����Pme���T�O���ȏ���ԐF�̉^�]�̈�ł͒�R��ŃG���W���^�]���\�ł���A����SCR�G�}�����t�߂�
�r�C�K�X���x���Q�O�O���ȏ�������������G���W���^�]���ł��邱�Ƃɂ���đfSCR�G�}�����������ANO����啝�ɍ�
���ł���̂ł���B�����āA�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j���R��ጸ�^�̋C���Q����@�ɂ����ẮA�}�V
�|�P�̐F�Ŏ�����Pme���T�O���ȉ��̔A�fSCR�G�}��SCR�G�}�����t�߂̔r�C�K�X���x���Q�O�O���ȉ��̒ቷ��
�Ԃ̋�C���ߏ�ȉ^�]�̈�ł́A��ʂd�f�q�Ƃg�b�b�h��o�b�h�Ə̂����Ǎ������k���ΔR�Ă̋Z�p�ɂ���đ����Ȃ��
���m�n���팸��}��A�i�d�O�T�r�o�K�X�����ɂ�����m�n���팸����悹���邱�Ƃ��\�ł���B
�@�����āA�����œ��ɒ��ڂ��ׂ����Ƃ́A�u�R��ጸ�^�̋C���Q����@�v�́A�Q�^�[�{�����̋C���x�~�V�X�e���i���C��
�x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�j�������\�ȋC���Q�̏o�͐�����@�ł���A�z�E�r�C�ًx�~�����̋C���x�~
�V�X�e���i�����쎩���ԇ��������ԋZ�p���2013�N�H�G���Ř_�����\���u�扺���v�����C���x�~�V�X�e��http://
tech.jsae.or.jp/2013aki/pc/speech.aspx?id=69�j�ł͐��䂪�s�\�ȋC���Q�̏o�͐�����@�ł���B���������āA�Q�^
�[�{�����̋C���x�~�V�X�e���i���C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�j�́A�z�E�r�C�ًx�~�����̋C���x�~�V�X
�e���ɔ�r���đ�^�g���b�N�̏d�ʎԃ��[�h�R�������s�R��̑啝�ȉ��P���\�ƂȂ�B���̂��߁A�Q�^�[�{������
�C���x�~�V�X�e���ł����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p���̗p�����ߋ��f�B�[�[���G���W����
��^�g���b�N�ɍ̗p�����ꍇ�ɂ́A�s�s�Ԃ̉ݕ��A���ɂ����ċC���x�~�ɂ��R����P�̌��ʂ��\���ɔ����ł��邱
�ƂɂȂ�B
�x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�j�������\�ȋC���Q�̏o�͐�����@�ł���A�z�E�r�C�ًx�~�����̋C���x�~
�V�X�e���i�����쎩���ԇ��������ԋZ�p���2013�N�H�G���Ř_�����\���u�扺���v�����C���x�~�V�X�e��http://
tech.jsae.or.jp/2013aki/pc/speech.aspx?id=69�j�ł͐��䂪�s�\�ȋC���Q�̏o�͐�����@�ł���B���������āA�Q�^
�[�{�����̋C���x�~�V�X�e���i���C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�j�́A�z�E�r�C�ًx�~�����̋C���x�~�V�X
�e���ɔ�r���đ�^�g���b�N�̏d�ʎԃ��[�h�R�������s�R��̑啝�ȉ��P���\�ƂȂ�B���̂��߁A�Q�^�[�{������
�C���x�~�V�X�e���ł����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p���̗p�����ߋ��f�B�[�[���G���W����
��^�g���b�N�ɍ̗p�����ꍇ�ɂ́A�s�s�Ԃ̉ݕ��A���ɂ����ċC���x�~�ɂ��R����P�̌��ʂ��\���ɔ����ł��邱
�ƂɂȂ�B
�@���̂悤�ɁA�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j���Q�^�[�{�����C���x�~�V�X�e���������A���̐}�V��
�R��ጸ�^�̐���������ł������Ƃł���B�����āA�Q�^�[�{�ߋ��@�������C���x�~�G���W���i�������J2005-
54771�j�́A�}�V���R��ጸ�^�̋C���Q����@���̗p���邱�Ƃɂ���Č����ȔR��팸���\�ɂ���Ɠ����ɁA�r�C�K
�X�̍������ɔ����A�fSCR�G�}������SCR�G�}�̊������ɂ����NO���팸��}�邱�Ƃ��\�ł���B���������āA��^
�g���b�N�̔R������シ�邱�Ƃ��ő�̖ړI�Ƃ��ăf�B�[�[���G���W���ɋC���x�~�̋Z�p���̗p����ꍇ�ɂ́A�C���x
�~�G���W���i�������J2005-54771�j��p����ׂ��ł��邱�Ƃ͖��炩�Ȃ��Ƃ��B���̂��߁A����A��^�g���b�N�̔R���
���ڕW�Ɍf���Ȃ���z�E�r�C�ًx�~�������C���x�~�V�X�e�����̗p����g���b�N���[�J�����ꂽ�ꍇ�ɂ́A���̃g��
�b�N���[�J�̋Z�p�ҁE���Ƃ́A�u�����v�E�u�n���v�E�u�u�Ԕ����v�Ȑl�B�ƍl���ĊԈႢ�Ȃ����낤�B
�R��ጸ�^�̐���������ł������Ƃł���B�����āA�Q�^�[�{�ߋ��@�������C���x�~�G���W���i�������J2005-
54771�j�́A�}�V���R��ጸ�^�̋C���Q����@���̗p���邱�Ƃɂ���Č����ȔR��팸���\�ɂ���Ɠ����ɁA�r�C�K
�X�̍������ɔ����A�fSCR�G�}������SCR�G�}�̊������ɂ����NO���팸��}�邱�Ƃ��\�ł���B���������āA��^
�g���b�N�̔R������シ�邱�Ƃ��ő�̖ړI�Ƃ��ăf�B�[�[���G���W���ɋC���x�~�̋Z�p���̗p����ꍇ�ɂ́A�C���x
�~�G���W���i�������J2005-54771�j��p����ׂ��ł��邱�Ƃ͖��炩�Ȃ��Ƃ��B���̂��߁A����A��^�g���b�N�̔R���
���ڕW�Ɍf���Ȃ���z�E�r�C�ًx�~�������C���x�~�V�X�e�����̗p����g���b�N���[�J�����ꂽ�ꍇ�ɂ́A���̃g��
�b�N���[�J�̋Z�p�ҁE���Ƃ́A�u�����v�E�u�n���v�E�u�u�Ԕ����v�Ȑl�B�ƍl���ĊԈႢ�Ȃ����낤�B
�T�|�Q�DNO���ጸ�^�̋C���Q����@�̏ꍇ�i�}�X���Q�ƕ��j
�@�Q�^�[�{�ߋ��@�����̋C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�ɂ�����NO���ጸ�^�ł́A���C���f�B�[�[���G���W
�����P�C���Q�Ƒ�Q�C���Q�ɕ������Q�^�[�{�ߋ��@�����̋C���x�~�f�B�[�[���G���W���ɂ����āA�A�N�Z���y�_����
���ݗ�Accel���T�O���ȉ��̃G���W�����ׂɂ�������P�C���Q�Ƒ�Q�C���Q�̉��ꂩ����̋C���Q����ɗD��I�ɉ�
�������A�A�N�Z���y�_�������ݗ�Accel���T�O������G���W�����ׂɂ��������P�C���Q�Ƒ�Q�C���Q���̏o
�͂œ����ɉғ��������C���Q�̉^�]����@�ł���B�}�X�|�Q�́A�A�N�Z���y�_�������ݗ�Accel���T�O���ȉ��ɂ�����
��ɑ�P�C���Q��D�悵�ĉғ��������ꍇ��NO���ጸ�^�̋C���Q�̉^�]����@�ł���B�ܘ_�A�A�N�Z���y�_������
�ݗ�Accel���T�O���ȏ�ɂ����āA��P�C���Q�Ƒ�Q�C���Q����o�͂ŃG���W�����^�]����̂ł���B���̋C���x
�~�G���W�������p�ŗp������ۂɂ́A�G���W���S�̂̑ϋv����r�o�K�X�㏈�����u�̋@�\�Ƒϋv���̂��߁A��P�C
���Q��D�悵�ĉғ��������ꍇ�Ƒ�Q�C���Q��D�悵�ĉғ��������ꍇ���̎��ۂ̏ꍇ�����̃G���W���^�]���Ԗ�
�ɐ�ւ���悤�ɂ���B
�����P�C���Q�Ƒ�Q�C���Q�ɕ������Q�^�[�{�ߋ��@�����̋C���x�~�f�B�[�[���G���W���ɂ����āA�A�N�Z���y�_����
���ݗ�Accel���T�O���ȉ��̃G���W�����ׂɂ�������P�C���Q�Ƒ�Q�C���Q�̉��ꂩ����̋C���Q����ɗD��I�ɉ�
�������A�A�N�Z���y�_�������ݗ�Accel���T�O������G���W�����ׂɂ��������P�C���Q�Ƒ�Q�C���Q���̏o
�͂œ����ɉғ��������C���Q�̉^�]����@�ł���B�}�X�|�Q�́A�A�N�Z���y�_�������ݗ�Accel���T�O���ȉ��ɂ�����
��ɑ�P�C���Q��D�悵�ĉғ��������ꍇ��NO���ጸ�^�̋C���Q�̉^�]����@�ł���B�ܘ_�A�A�N�Z���y�_������
�ݗ�Accel���T�O���ȏ�ɂ����āA��P�C���Q�Ƒ�Q�C���Q����o�͂ŃG���W�����^�]����̂ł���B���̋C���x
�~�G���W�������p�ŗp������ۂɂ́A�G���W���S�̂̑ϋv����r�o�K�X�㏈�����u�̋@�\�Ƒϋv���̂��߁A��P�C
���Q��D�悵�ĉғ��������ꍇ�Ƒ�Q�C���Q��D�悵�ĉғ��������ꍇ���̎��ۂ̏ꍇ�����̃G���W���^�]���Ԗ�
�ɐ�ւ���悤�ɂ���B
�@����NO���ጸ�^���C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�ł́A�A�N�Z���y�_�������ݗ�Accel���Q�T����Accel��
�T�O���̃G���W���^�]�̈�ł͑�P�C���Q���D��ғ��ƂȂ�A�T�O���� Le �� �P�O�O�����̃G���W���^�]�̈�ł���P�C
���Q�Ƒ�Q�C���Q�̗����̋C���Q�͋��ɐ������ϗL����Pme���T�O���ȏ�̉^�]�̈�ƂȂ�B���̂��߁A�}�X�[�P��
�������悤�ɃA�N�Z���y�_�������ݗ�Accel���Q�T���ȏ�̐ԐF��Pme���T�O���ȏ�ł̃G���W���^�]�̈�ƂȂ�A����
�ԐF�̉^�]�̈�ł͔A�fSCR�G�}�̐G�}�����t�߂̔r�C�K�X���x���Q�O�O���ȏ�ɂȂ����A�fSCR�G�}�ɂ��NO��
�̍팸�����i�ł���̂ł���B�}�V�[�P�̒�R��^�̋C���Q�^�]����@��Pme���T�O���ȏ�ł̃G���W���^�]�̈�
�i�ԐF�̉^�]�̈�j�ɔ�r���A�}�X�[�P��NO���ጸ�^�̋C���Q�^�]����@��Pme���T�O���ȏ�ł̃G���W���^�]�̈�
�i�ԐF�̉^�]�̈�j�̕������炩�ɍL�����߁ANO���ጸ�^�̋C���Q�^�]����@�͒�R��^�̋C���Q�^�]����@���
���m�n���������팸�ł���̂ł���BNO���ጸ�^�̋C���Q�^�]����@�ł́A�A�N�Z���y�_�������ݗ�Accel���T�O����
����G���W���^�]�̈�ł���P�C���Q�Ƒ�Q�C���Q�Ƃ������̏o�͂œ����ɉғ������邽�߁A�]���̃G���W���Ɠ���
�̔R��\�ƂȂ�A���̃G���W���^�]�̈�ł̔R��͏]���̃G���W���Ɠ����ƂȂ�B���������āA�]���̑S�C���ғ��G
���W����r�����C���Q�^�]����@�̋C���x�~�G���W�����R��팸�ł���̂́A�A�N�Z���y�_�������ݗ�Accel���T
�O���ȉ��̉^�]�̈�Ɍ�����̂ł���B
�T�O���̃G���W���^�]�̈�ł͑�P�C���Q���D��ғ��ƂȂ�A�T�O���� Le �� �P�O�O�����̃G���W���^�]�̈�ł���P�C
���Q�Ƒ�Q�C���Q�̗����̋C���Q�͋��ɐ������ϗL����Pme���T�O���ȏ�̉^�]�̈�ƂȂ�B���̂��߁A�}�X�[�P��
�������悤�ɃA�N�Z���y�_�������ݗ�Accel���Q�T���ȏ�̐ԐF��Pme���T�O���ȏ�ł̃G���W���^�]�̈�ƂȂ�A����
�ԐF�̉^�]�̈�ł͔A�fSCR�G�}�̐G�}�����t�߂̔r�C�K�X���x���Q�O�O���ȏ�ɂȂ����A�fSCR�G�}�ɂ��NO��
�̍팸�����i�ł���̂ł���B�}�V�[�P�̒�R��^�̋C���Q�^�]����@��Pme���T�O���ȏ�ł̃G���W���^�]�̈�
�i�ԐF�̉^�]�̈�j�ɔ�r���A�}�X�[�P��NO���ጸ�^�̋C���Q�^�]����@��Pme���T�O���ȏ�ł̃G���W���^�]�̈�
�i�ԐF�̉^�]�̈�j�̕������炩�ɍL�����߁ANO���ጸ�^�̋C���Q�^�]����@�͒�R��^�̋C���Q�^�]����@���
���m�n���������팸�ł���̂ł���BNO���ጸ�^�̋C���Q�^�]����@�ł́A�A�N�Z���y�_�������ݗ�Accel���T�O����
����G���W���^�]�̈�ł���P�C���Q�Ƒ�Q�C���Q�Ƃ������̏o�͂œ����ɉғ������邽�߁A�]���̃G���W���Ɠ���
�̔R��\�ƂȂ�A���̃G���W���^�]�̈�ł̔R��͏]���̃G���W���Ɠ����ƂȂ�B���������āA�]���̑S�C���ғ��G
���W����r�����C���Q�^�]����@�̋C���x�~�G���W�����R��팸�ł���̂́A�A�N�Z���y�_�������ݗ�Accel���T
�O���ȉ��̉^�]�̈�Ɍ�����̂ł���B
�@
| |
||||||||||||||||||||||
| |
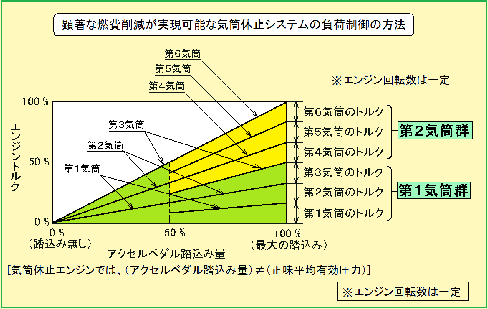 |
|||||||||||||||||||||
| |
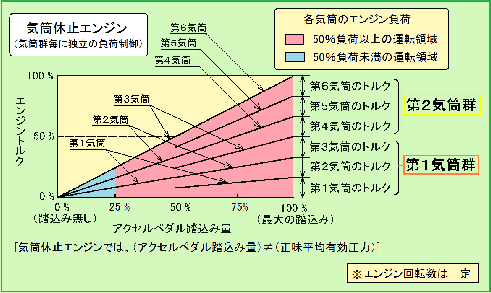 |
�@���������A�Q�^�[�{�ߋ��@�����̋C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j���A�N�Z���y�_�������ݗ�Accel���T�O��
�ȉ��ɂ����ẮA��R��^��NO���ጸ�^�̗��҂̋C���Q����́A�S������ł���B���������āA�u�T�|�P�D�R��ጸ�^
�̋C���Q����@�̏ꍇ�v�̍��ŏڏq���Ă��� �Q�^�[�{�ߋ��@�����̋C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�ɂ���
�ẮA�R��ጸ�^�̋C���Q����@�ɂ�����N�Z���y�_�������ݗʂT�O���ȉ��ł��}�V�|�P�̐ԐF�Ŏ�����Pme�i����
���ϗL�����j���T�O���ȏ�ƂȂ�R��̗ǍD���L���G���W���^�]�̈悪���݂��ANO���ጸ�^�̋C���Q����@�ɂ�����
�}�X�|�P�̐ԐF�Ŏ�����Pme�i�������ϗL�����j���T�O���ȏ�ƂȂ��L���G���W���^�]�̈悪���݂���B�C���x�~�G��
�W���i�������J2005-54771�j�ł͂�����Pme�i�������ϗL�����j���T�O���ȏ���ԐF���R��̗ǍD�ȍL���^�]�̈�
�����o���邽�߁A�i�d�O�T���[�h�^�]�ł̒�R���������ł���ł���B�����ē����ɁASCR�G�}�����t�߂̔r�C�K�X
���x���Q�O�O���ȏ�������������G���W���^�]���ł��邱�Ƃɂ���đfSCR�G�}�����������ANO����啝�ɍ팸�ł���
�̂ł���B�����āA�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j���R��ጸ�^�̋C���Q����@�ɂ����ẮA�}�X�|�P�̐�
�F�Ŏ�����Pme���T�O���ȉ��̔A�fSCR�G�}��SCR�G�}�����t�߂̔r�C�K�X���x���Q�O�O���ȉ��̒ቷ��Ԃ̋�C
���ߏ�ȉ^�]�̈�ł́A��ʂd�f�q�Ƃg�b�b�h��o�b�h�Ə̂����Ǎ������k���ΔR�Ă̋Z�p�ɂ���đ����Ȃ�Ƃ��m�n����
����}��A�i�d�O�T�r�o�K�X�����ɂ�����m�n���팸����悹���邱�Ƃ��\�ł���B
�ȉ��ɂ����ẮA��R��^��NO���ጸ�^�̗��҂̋C���Q����́A�S������ł���B���������āA�u�T�|�P�D�R��ጸ�^
�̋C���Q����@�̏ꍇ�v�̍��ŏڏq���Ă��� �Q�^�[�{�ߋ��@�����̋C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�ɂ���
�ẮA�R��ጸ�^�̋C���Q����@�ɂ�����N�Z���y�_�������ݗʂT�O���ȉ��ł��}�V�|�P�̐ԐF�Ŏ�����Pme�i����
���ϗL�����j���T�O���ȏ�ƂȂ�R��̗ǍD���L���G���W���^�]�̈悪���݂��ANO���ጸ�^�̋C���Q����@�ɂ�����
�}�X�|�P�̐ԐF�Ŏ�����Pme�i�������ϗL�����j���T�O���ȏ�ƂȂ��L���G���W���^�]�̈悪���݂���B�C���x�~�G��
�W���i�������J2005-54771�j�ł͂�����Pme�i�������ϗL�����j���T�O���ȏ���ԐF���R��̗ǍD�ȍL���^�]�̈�
�����o���邽�߁A�i�d�O�T���[�h�^�]�ł̒�R���������ł���ł���B�����ē����ɁASCR�G�}�����t�߂̔r�C�K�X
���x���Q�O�O���ȏ�������������G���W���^�]���ł��邱�Ƃɂ���đfSCR�G�}�����������ANO����啝�ɍ팸�ł���
�̂ł���B�����āA�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j���R��ጸ�^�̋C���Q����@�ɂ����ẮA�}�X�|�P�̐�
�F�Ŏ�����Pme���T�O���ȉ��̔A�fSCR�G�}��SCR�G�}�����t�߂̔r�C�K�X���x���Q�O�O���ȉ��̒ቷ��Ԃ̋�C
���ߏ�ȉ^�]�̈�ł́A��ʂd�f�q�Ƃg�b�b�h��o�b�h�Ə̂����Ǎ������k���ΔR�Ă̋Z�p�ɂ���đ����Ȃ�Ƃ��m�n����
����}��A�i�d�O�T�r�o�K�X�����ɂ�����m�n���팸����悹���邱�Ƃ��\�ł���B
�@���̂悤�ɁA�]���G���W���ɑ�����R��^��NO���ጸ�^�̗����̋C���Q����ɂ����ẮA�R��ጸ�Ƃm�n���ጸ��
���ʂɂ͑����̗D��͂�����̂́A����̋C���Q����̏ꍇ�ɂ����ĔR��ጸ�Ƃm�n���ጸ�ɑ傫�Ȍ��ʂ������
��̂ł���B�����ڍׂɌ����A�Q�^�[�{�ߋ��@�����̋C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�ł��A�N�Z���y�_��
�����ݗ�Accel���T�O������G���W���^�]�̈�ɂ����āA��R��^���C���Q����ł�NO���ጸ�^���������R��
�̍팸�ɗD��ANO���ጸ�^���C���Q����ł���R��^���������m�n���̍팸�ɗD��Ă���Ɖ]�����Ƃł���B
���ʂɂ͑����̗D��͂�����̂́A����̋C���Q����̏ꍇ�ɂ����ĔR��ጸ�Ƃm�n���ጸ�ɑ傫�Ȍ��ʂ������
��̂ł���B�����ڍׂɌ����A�Q�^�[�{�ߋ��@�����̋C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�ł��A�N�Z���y�_��
�����ݗ�Accel���T�O������G���W���^�]�̈�ɂ����āA��R��^���C���Q����ł�NO���ጸ�^���������R��
�̍팸�ɗD��ANO���ጸ�^���C���Q����ł���R��^���������m�n���̍팸�ɗD��Ă���Ɖ]�����Ƃł���B
�@�Ȃ��A�R��ጸ�^�̋C���Q����@���Q�^�[�{�ߋ��@�������C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�́A�]���G��
�W���ɔ�r���A�r�C�K�X�̍������ɔ����A�fSCR�G�}������SCR�G�}�̊������ɂ����NO�����팸�Ɠ����ɁA�ܘ_�A
�R��팸���\�ł���B���݂ɁA�z�E�r�C�ًx�~�������C���x�~�V�X�e���ł́A���̔R��ጸ�^�̋C���Q����
�����ł���ANO���ጸ�^�̋C���Q���䂪�s�\�ł����B���������āA��R��^��NO���ጸ�^�̗������\�ȋC
���Q����̕��@�́A�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j���Q�^�[�{�����C���x�~�̃V�X�e�������ł�
�����Ƃ����ӂ��Ă����K�v������B
�W���ɔ�r���A�r�C�K�X�̍������ɔ����A�fSCR�G�}������SCR�G�}�̊������ɂ����NO�����팸�Ɠ����ɁA�ܘ_�A
�R��팸���\�ł���B���݂ɁA�z�E�r�C�ًx�~�������C���x�~�V�X�e���ł́A���̔R��ጸ�^�̋C���Q����
�����ł���ANO���ጸ�^�̋C���Q���䂪�s�\�ł����B���������āA��R��^��NO���ጸ�^�̗������\�ȋC
���Q����̕��@�́A�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j���Q�^�[�{�����C���x�~�̃V�X�e�������ł�
�����Ƃ����ӂ��Ă����K�v������B
�T�|�R�D�C���x�~�ɂ�����R��ጸ�^��NO���ጸ�^�̊e�C���Q����@�̓����i�܂Ƃ߁j
�@�����s�ő��p������������^�]��Ԃɂ����āA�]���̑S�C���ғ��G���W���ɔ�r���A�Q�^�[�{�ߋ��@�����̋C��
�x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̗D�ꂽ���������L�̕\�U�ɂ܂Ƃ߂��B
�x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̗D�ꂽ���������L�̕\�U�ɂ܂Ƃ߂��B
| |
|
| |
���������ɉғ��C�������o�����ʼn^�]�ł��邱�Ƃɂ���ăT�C�N�����������サ�A�T�`�P�O���̒��x�d�ʎԃ��[�h�R���̍팸
���\�ƂȂ�B �i�}7�|1����ѐ}�X�|�P�̐ԐF�̃G���W���^�]�̈�j �i��R��^�̋C���Q����́A��Ȃ���R��̍팸�ɗL���j |
| |
���������̔r�C�K�X���x���������ł��邱�Ƃɂ�����A�fSCR�G�}�̐G�}�@�\�����サ�A�啝��NO���팸���\�ƂȂ�B
�i�}7�|1����ѐ}�X�|�P�̐ԐF�̃G���W���^�]�̈�j
�iNO���ጸ�^�̋C���Q����́A��Ȃ���m�n���̍팸�ɗL���j
|
| |
���������̔r�C�K�X���x������������邱�Ƃɂ��ADPF���u�ɂ�����t�B���^�̎��ȍĐ��̑��i���\�@
(DPF���u�ł̎蓮�Đ��⎩���Đ��̕p�x�����ɂ��|�X�g���˂�r�C�Ǔ����˂̔R���Q����팸�j
|
�U�D��^�g���b�N�ɂ����鍡��̂m�n���ƔR��̋K�������ɍv���ł���C���x�~�̋Z�p
�U�|�P�D��^�g���b�N�ɂ����鎟���̃|�X�g�|�X�g�r�o�K�X�K���ɂ�����m�n���̋K������
�@
�@��^�g���b�N�^�̃|�X�g�r�o�K�X�K��(2009�N�K���j�̎��̂m�n���̋K�������ɂ��ẮA2010�N��7��28���ɒ�����
���R�c�����Ȃɑ�\�����\���s��ꂽ�B���̑�\�����\�ɂ��ƁAGVW7.5�g�������̑�^�g���b�N�E�o�X�̂m�n
���K���̋����́A�\�P�R�Ɏ������ʂ�A�����̂m�n���K���l�@���@0.4 g/kWh�@�ł���A2016�N�Ɏ��{���\�肳��Ă����
�̂��Ƃł����B
���R�c�����Ȃɑ�\�����\���s��ꂽ�B���̑�\�����\�ɂ��ƁAGVW7.5�g�������̑�^�g���b�N�E�o�X�̂m�n
���K���̋����́A�\�P�R�Ɏ������ʂ�A�����̂m�n���K���l�@���@0.4 g/kWh�@�ł���A2016�N�Ɏ��{���\�肳��Ă����
�̂��Ƃł����B
| |
|
|
| |
|
|
�@���ȁE�������R�c��̑攪�����\�ł́A����ڕW�Ə̂��āu0.7 g/kWh�̂R���̂P�v�̍팸��������Ă����B����
���߁A�|�X�g�V�����̎��̋K�������ɂ�����m�n���K���l��0.23 g/kWh�O��̒l�܂ō팸�������̂ƕM�҂͍l����
�����B�e�g���b�N���[�J���|�X�g�V������̂ɂ�����m�n���K�������̋K���l��0.23 g/kWh�O��ł��邱�Ƃ�z�肵�A�m�n
���팸�Z�p�̌����J�����i�߂��Ă������̂ƍl������B�������A�|�X�g�V�����i2009�N�K���j��̂m�n���K��������
�K���l���\�S�Ɏ������悤��0.4 g/kWh�ł���Ƃ��������R�c�����Ȃɑ�\�����\�ɂ��A�����A�������ꂽ�B
�������R�c��r�o�K�X����̑�\�����\�ɂ́A�攪�����\�̒���ڕW�ł́u0.7 g/kWh�̂R���̂P�v�i��0.23 g/
kWh�j�̍팸��������Ă����B���̂��߁A�|�X�g�V�����̎��̋K�������ɂ�����m�n���K���l��0.23 g/kWh�j�܂ō팸��
�����̂Ƒ����̐l�͍l���Ă����B���̗��R�́A����܂ł̗�ł́A�R�c��̓��\�ɋL�ڂ��ꂽ�ڕW�ƋL�ڂ��ꂽ�K
���l�Ă���傫���ɘa�����K���l���{�s���ꂽ��͂قƂ�ǖ��������悤�ɋL�����Ă��邩��ł���B
���߁A�|�X�g�V�����̎��̋K�������ɂ�����m�n���K���l��0.23 g/kWh�O��̒l�܂ō팸�������̂ƕM�҂͍l����
�����B�e�g���b�N���[�J���|�X�g�V������̂ɂ�����m�n���K�������̋K���l��0.23 g/kWh�O��ł��邱�Ƃ�z�肵�A�m�n
���팸�Z�p�̌����J�����i�߂��Ă������̂ƍl������B�������A�|�X�g�V�����i2009�N�K���j��̂m�n���K��������
�K���l���\�S�Ɏ������悤��0.4 g/kWh�ł���Ƃ��������R�c�����Ȃɑ�\�����\�ɂ��A�����A�������ꂽ�B
�������R�c��r�o�K�X����̑�\�����\�ɂ́A�攪�����\�̒���ڕW�ł́u0.7 g/kWh�̂R���̂P�v�i��0.23 g/
kWh�j�̍팸��������Ă����B���̂��߁A�|�X�g�V�����̎��̋K�������ɂ�����m�n���K���l��0.23 g/kWh�j�܂ō팸��
�����̂Ƒ����̐l�͍l���Ă����B���̗��R�́A����܂ł̗�ł́A�R�c��̓��\�ɋL�ڂ��ꂽ�ڕW�ƋL�ڂ��ꂽ�K
���l�Ă���傫���ɘa�����K���l���{�s���ꂽ��͂قƂ�ǖ��������悤�ɋL�����Ă��邩��ł���B
�@���̂��߁A2005�N1���̑攪�����\�ł͒���ڕW�Ə̂���u0.7 g/kWh�̂R���̂P�v�i��0.23 g/kWh�j�̂m�n���팸�̖�
�W�l�ɓK���ł���悤�ɂ��邽�߂ɁA�e�g���b�N���[�J�⑽���̌����@�ւł́A����܂ŕK���ɂm�n���팸�̋Z�p�J����
���g��ł������̂ƍl������B����ɂ�������炸�ANO���팸�̋Z�p�J�����v�f�ʂ�ɐi�W�����A�m�n���팸�̋Z
�p�J���ɑ傫�Ȑ��ʂ������Ȃ������̂ł͂Ȃ����Ɛ��������̂ł���B���̒���ڕW��������NO���K���l�ɐݒ�
���ꂽ�ꍇ�ɂ́A���̂m�n���K���ɓK���ł���Z�p���s���ł��邱�Ƃ���A�g���b�N���[�J�S�Ђ��܂ގ����ԍH�Ɖ�̋�
�͂Ȕ������Ȃɐ\�����ꂽ�̂ł͂Ȃ����낤���B���̌��ʁA���Ȃ̔r�o�K�X�K����S������W�����K�^�ɂ�
�����ԍH�Ɖ�ւ̎v�����̂���D�����l�ł��������߁A�攪�����\�̒���ڕW���L�b�p���ƖY�ꋎ���āA�����̋K
���l�i�āj�@���@0.4 g/kWh�����肳�ꂽ�̂ł��낤���B����Ƃ��A�A�fSCR�G�}�ł��A�G���W���ᕉ�ׂ̔r�C���x����
���̎��̔A�f�r�b�q�̐G�}�������x���Q�O�O���ȉ��ł͔A�f�r�b�q�G�}�̂m�n���팸�����}���ɒቺ�����������
�ԍH�Ɖ���Ȃ̔r�o�K�X�K���S���̌W���ɕK���ɐ������Ĕ[�����������ʁA�m�n���̎����̋K���l�i�āj�@���@0.
4 g/kWh�����肳�ꂽ�̂ł��낤���B����Ƃ��A�����ԍH�Ɖ�m�n���̎����̋K���l�i�āj�@���@0.4 g/kWh����������
�ɂ��K���l��v�����Ă������A���Ȃ̔r�o�K�X�K���S���̌W���������ԍH�Ɖ�̗v�������ۂ��Ăm�n���̎�����
�K���l�i�āj�@���@0.4 g/kWh�Ɍ��肵���̂ł��낤���B���O�҂ɂ��f�B�[�[�������Ԃ̂f�u�v3.5�g�����̏d�ʎԂɂ���
���m�n���̎����K���l�i�āj���@0.4 g/kWh�Ɍ��܂����o�܂̐^���́A�s���ł���B
�W�l�ɓK���ł���悤�ɂ��邽�߂ɁA�e�g���b�N���[�J�⑽���̌����@�ւł́A����܂ŕK���ɂm�n���팸�̋Z�p�J����
���g��ł������̂ƍl������B����ɂ�������炸�ANO���팸�̋Z�p�J�����v�f�ʂ�ɐi�W�����A�m�n���팸�̋Z
�p�J���ɑ傫�Ȑ��ʂ������Ȃ������̂ł͂Ȃ����Ɛ��������̂ł���B���̒���ڕW��������NO���K���l�ɐݒ�
���ꂽ�ꍇ�ɂ́A���̂m�n���K���ɓK���ł���Z�p���s���ł��邱�Ƃ���A�g���b�N���[�J�S�Ђ��܂ގ����ԍH�Ɖ�̋�
�͂Ȕ������Ȃɐ\�����ꂽ�̂ł͂Ȃ����낤���B���̌��ʁA���Ȃ̔r�o�K�X�K����S������W�����K�^�ɂ�
�����ԍH�Ɖ�ւ̎v�����̂���D�����l�ł��������߁A�攪�����\�̒���ڕW���L�b�p���ƖY�ꋎ���āA�����̋K
���l�i�āj�@���@0.4 g/kWh�����肳�ꂽ�̂ł��낤���B����Ƃ��A�A�fSCR�G�}�ł��A�G���W���ᕉ�ׂ̔r�C���x����
���̎��̔A�f�r�b�q�̐G�}�������x���Q�O�O���ȉ��ł͔A�f�r�b�q�G�}�̂m�n���팸�����}���ɒቺ�����������
�ԍH�Ɖ���Ȃ̔r�o�K�X�K���S���̌W���ɕK���ɐ������Ĕ[�����������ʁA�m�n���̎����̋K���l�i�āj�@���@0.
4 g/kWh�����肳�ꂽ�̂ł��낤���B����Ƃ��A�����ԍH�Ɖ�m�n���̎����̋K���l�i�āj�@���@0.4 g/kWh����������
�ɂ��K���l��v�����Ă������A���Ȃ̔r�o�K�X�K���S���̌W���������ԍH�Ɖ�̗v�������ۂ��Ăm�n���̎�����
�K���l�i�āj�@���@0.4 g/kWh�Ɍ��肵���̂ł��낤���B���O�҂ɂ��f�B�[�[�������Ԃ̂f�u�v3.5�g�����̏d�ʎԂɂ���
���m�n���̎����K���l�i�āj���@0.4 g/kWh�Ɍ��܂����o�܂̐^���́A�s���ł���B
�@����ɂ��Ă��A2010�N��7��28���ɒ������R�c���C�������Ȃɑ�\�����\���s���A���E���ꎎ���T
�C�N���ł���WHTC�iWorld Harmonized Transient Cycle�j�ɕύX���A�]���̃G���W���g�@���i�z�b�g�X�^�[�g�j�r�o�K�X��
���ɉ����ăG���W����Ԏ��i�R�[���h�X�^�[�g�j�r�o�K�X������lj�����r�o�K�X�����@��ύX���A2016�N�Ɏ����̂m�n
���K���l�@���@0.4 g/kWh�@����^�g���b�N�^�̃|�X�g�r�o�K�X�K��(2009�N�K���j�̎��̂m�n���̋K�����������{�����
���Ƃ����炩�ɂȂ����̂������B���̂��Ƃɂ��āA�������R�c���C�������Ȃɑ�\�����\�ł́ANO���K
���l��ڕW��0.23 g/kWh����0.4 g/kWh�̑傫���ɘa�������R�Ƃ��āA�R�[���h�X�^�[�g�����̒lj���JE�O�T���[�h
����WHTC�ւ̎������[�h�̕ύX�Ȃǂ̂��グ�Ă���悤���B�������A�P�Ȃ鐄���ɉ߂��Ȃ����A������NO���K���l��
����ڕW��0.23 g/kWh����0.4 g/kWh�ɑ傫���ɘa�������R�Ƃ��āA�����_�ł́A�g���b�N���[�J�S�Ђ��܂ގ����ԃ��[�J
�����ȁE�������R�c���2005�N1���̑攪�����\�̒���ڕW�Ə̂���u0.7 g/kWh�̂R���̂P�v�i��0.23 g/kWh�j��
�łm�n�����팸�ł���Z�p���J���ł��Ȃ������\�����傢�ɂ��蓾��ƍl������B
�C�N���ł���WHTC�iWorld Harmonized Transient Cycle�j�ɕύX���A�]���̃G���W���g�@���i�z�b�g�X�^�[�g�j�r�o�K�X��
���ɉ����ăG���W����Ԏ��i�R�[���h�X�^�[�g�j�r�o�K�X������lj�����r�o�K�X�����@��ύX���A2016�N�Ɏ����̂m�n
���K���l�@���@0.4 g/kWh�@����^�g���b�N�^�̃|�X�g�r�o�K�X�K��(2009�N�K���j�̎��̂m�n���̋K�����������{�����
���Ƃ����炩�ɂȂ����̂������B���̂��Ƃɂ��āA�������R�c���C�������Ȃɑ�\�����\�ł́ANO���K
���l��ڕW��0.23 g/kWh����0.4 g/kWh�̑傫���ɘa�������R�Ƃ��āA�R�[���h�X�^�[�g�����̒lj���JE�O�T���[�h
����WHTC�ւ̎������[�h�̕ύX�Ȃǂ̂��グ�Ă���悤���B�������A�P�Ȃ鐄���ɉ߂��Ȃ����A������NO���K���l��
����ڕW��0.23 g/kWh����0.4 g/kWh�ɑ傫���ɘa�������R�Ƃ��āA�����_�ł́A�g���b�N���[�J�S�Ђ��܂ގ����ԃ��[�J
�����ȁE�������R�c���2005�N1���̑攪�����\�̒���ڕW�Ə̂���u0.7 g/kWh�̂R���̂P�v�i��0.23 g/kWh�j��
�łm�n�����팸�ł���Z�p���J���ł��Ȃ������\�����傢�ɂ��蓾��ƍl������B
�U�|�Q�D�����̑�^�g���b�N�ɂ�����m�n���K���̋����ɍv���ł���C���x�~
�@���āA�]���̃g���b�N�p�ߋ��f�B�[�[���G���W���́A�S�C�����ϓ��̕��ׂŏ�ɉғ�����\���ł���A�i�G���W���g��
�N�j���i�A�N�Z���y�_�������ݗʁj�ƂȂ�\���ł���B���̂��߁A�T�O�����G���W���g���N���T�O���̃A�N�Z���y�_������
�ݗʂƂȂ��Ă���B�����āA�}�R�Ɏ������悤�ɂT�O���ȉ��̒ᕉ�ׂ��G���W���g���N�ł͔A�fSCR�G�}�̓�����t�߂�
���x�͂Q�O�O�����x�ȉ��ƂȂ邱�Ƃ���A�}�U�Ɏ������悤�ɂT�O���ȉ��̃A�N�Z���y�_�������ݗʂ̃G���W���^�]��
�́ASCR�G�}������t�߂̉��x�͂Q�O�O�����x�ȉ��ƂȂ�̂ł���B����SCR�G�}������t�߂̉��x���Q�O�O�����x��
���ł́A�A�fSCR�G�}�̂m�n���팸�����������ቺ����̂ł���B���̂��߁A�]���̃G���W���ł��A�N�Z���y�_������
�ݗʂ��T�O���ȉ��̍L���G���W���^�]�̈�ɂ����ẮA�A�fSCR�G�}�̂m�n���팸�����������ቺ���Ă��܂��s���
�����Ă��܂��̂ł���B
�N�j���i�A�N�Z���y�_�������ݗʁj�ƂȂ�\���ł���B���̂��߁A�T�O�����G���W���g���N���T�O���̃A�N�Z���y�_������
�ݗʂƂȂ��Ă���B�����āA�}�R�Ɏ������悤�ɂT�O���ȉ��̒ᕉ�ׂ��G���W���g���N�ł͔A�fSCR�G�}�̓�����t�߂�
���x�͂Q�O�O�����x�ȉ��ƂȂ邱�Ƃ���A�}�U�Ɏ������悤�ɂT�O���ȉ��̃A�N�Z���y�_�������ݗʂ̃G���W���^�]��
�́ASCR�G�}������t�߂̉��x�͂Q�O�O�����x�ȉ��ƂȂ�̂ł���B����SCR�G�}������t�߂̉��x���Q�O�O�����x��
���ł́A�A�fSCR�G�}�̂m�n���팸�����������ቺ����̂ł���B���̂��߁A�]���̃G���W���ł��A�N�Z���y�_������
�ݗʂ��T�O���ȉ��̍L���G���W���^�]�̈�ɂ����ẮA�A�fSCR�G�}�̂m�n���팸�����������ቺ���Ă��܂��s���
�����Ă��܂��̂ł���B
�@����A�}�W�Ɏ������悤�ɁA�i�d�O�T���[�h�����ł̓G���W���g���Nl���T�O���ȉ����G���W���^�]�p�x�̍����B�}�W�͐�
�ڗʂQ�g�����x�̏��^�g���b�N�̗�Ɛ��肳��邪�A���̐ύڗʂQ�g�����x�̏��^�g���b�N�ł́A�T�O���ȉ����g���N�ŃG
���W�����^�]�����p�x���ɂ߂č����̂ł���B�O�q�̒ʂ�]���̃G���W���ł́i�G���W���g���N�j���i�A�N�Z���y�_��
�����ݗʁj�ƂȂ邽�߁A���̐ύڗʂQ�g�����x�̏��^�g���b�N�̂i�d�O�T���[�h�r�o�K�X�����́A�A�N�Z���y�_�������ݗ�
���T�O���ȉ��̗̈�ŃG���W���^�]�p�x�������̂ł���B���̂悤�ɁA���^�g���b�N�̂i�d�O�T���[�h�r�o�K�X�����ł́A
�T�O���ȉ��̃A�N�Z���y�_�������ݗʂł��G���W���^�]����̂ƂȂ邽�߁ASCR�G�}������t�߂̉��x���Q�O�O����
�x�ȉ��ƂȂ��ĔA�fSCR�G�}�̂m�n���팸�����������ቺ���Ă��܂��̂ł���B���������āA���̐ύڗʂQ�g�����x�̏��^
�g���b�N�̂i�d�O�T���[�h�r�o�K�X�����ł́A�A�fSCR�G�}�ɂ���Ăm�n����啝�ɍ팸���邱�Ƃ͓���̂�����ł�
��B
�ڗʂQ�g�����x�̏��^�g���b�N�̗�Ɛ��肳��邪�A���̐ύڗʂQ�g�����x�̏��^�g���b�N�ł́A�T�O���ȉ����g���N�ŃG
���W�����^�]�����p�x���ɂ߂č����̂ł���B�O�q�̒ʂ�]���̃G���W���ł́i�G���W���g���N�j���i�A�N�Z���y�_��
�����ݗʁj�ƂȂ邽�߁A���̐ύڗʂQ�g�����x�̏��^�g���b�N�̂i�d�O�T���[�h�r�o�K�X�����́A�A�N�Z���y�_�������ݗ�
���T�O���ȉ��̗̈�ŃG���W���^�]�p�x�������̂ł���B���̂悤�ɁA���^�g���b�N�̂i�d�O�T���[�h�r�o�K�X�����ł́A
�T�O���ȉ��̃A�N�Z���y�_�������ݗʂł��G���W���^�]����̂ƂȂ邽�߁ASCR�G�}������t�߂̉��x���Q�O�O����
�x�ȉ��ƂȂ��ĔA�fSCR�G�}�̂m�n���팸�����������ቺ���Ă��܂��̂ł���B���������āA���̐ύڗʂQ�g�����x�̏��^
�g���b�N�̂i�d�O�T���[�h�r�o�K�X�����ł́A�A�fSCR�G�}�ɂ���Ăm�n����啝�ɍ팸���邱�Ƃ͓���̂�����ł�
��B
�@�ύڗʂP�O�g���ȏ�̑�^�g���b�N�̃p���[�E�G�C�g���V�I�i�G���W���P�ʏo�͓�����̎ԗ����d�ʁj�́A���^�g���b�N
�̃p���[�E�G�C�g���V�I�����������߂ɁA��^�g���b�N�̂i�d�O�T���[�h�r�o�K�X�����ł͏��^�g���b�N�����A�N�Z���y
�_�������ݗʂ������A�傫���Ȃ邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��B��������^�g���b�N�̏ꍇ�ł��A�i�d�O�T���[�h�r�o�K�X�����ł��A
�N�Z���y�_�������ݗʂ��T�O���ߖT�ȉ��̃G���W���^�]�p�x�͋ɂ߂đ����̂ł���B���̂��߁A��^�g���b�N�̂m�n��
��啝�ɍ팸���邽�߂ɂ́A���^�g���b�N�̏ꍇ�Ɠ��l�ɁA�A�N�Z���y�_�������ݗʂ��T�O���ߖT�ȉ��̃G���W���^�]
�̈�����ꍇ�ł��ASCR�G�}������t�߂̉��x���Q�O�O�����x�ȏ�Ɉێ����ĔA�fSCR�G�}�̂m�n���팸���������ێ�
�ł��邱�Ƃ��K�v�ƂȂ�B
�̃p���[�E�G�C�g���V�I�����������߂ɁA��^�g���b�N�̂i�d�O�T���[�h�r�o�K�X�����ł͏��^�g���b�N�����A�N�Z���y
�_�������ݗʂ������A�傫���Ȃ邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��B��������^�g���b�N�̏ꍇ�ł��A�i�d�O�T���[�h�r�o�K�X�����ł��A
�N�Z���y�_�������ݗʂ��T�O���ߖT�ȉ��̃G���W���^�]�p�x�͋ɂ߂đ����̂ł���B���̂��߁A��^�g���b�N�̂m�n��
��啝�ɍ팸���邽�߂ɂ́A���^�g���b�N�̏ꍇ�Ɠ��l�ɁA�A�N�Z���y�_�������ݗʂ��T�O���ߖT�ȉ��̃G���W���^�]
�̈�����ꍇ�ł��ASCR�G�}������t�߂̉��x���Q�O�O�����x�ȏ�Ɉێ����ĔA�fSCR�G�}�̂m�n���팸���������ێ�
�ł��邱�Ƃ��K�v�ƂȂ�B
�@����܂ł̂Ƃ���A����I�ȑ�Z�p�����\����Ă��Ȃ����Ƃ���A�R��d��������^�g���b�N�ł̍���̂m�n��
�̍팸�ɂ́A�R����̌��_�̂���m�n���z���G�}���g���Ȃ��B���̂��߁A��^�g���b�N�ł̂m�n���̍팸�ɂ́A�]����
�Z�p�ł���N�[���h�d�f�q�̂d�f�q���̑����ƁA�A�f�r�b�q�G�}�̋Z�p�ɗ���ȊO�ɗL���ȕ��@�͂Ȃ����̂ƍl�����
��B���̏ꍇ�A�A�f�r�b�q�G�}�ɂ���ď\���Ȃm�n���팸��}��ɂ́A�}�T�Ɏ������悤�ɂr�b�q�G�}�������x��200����
�x�ɍ��߂�K�v������B�������A�S�C�����ϓ��̕��ׂŏ�ɉғ������]���̃G���W���ł́A�}�U�Ɏ������悤�ɁA�A�N
�Z���y�_�������ݗʂ��T�O���ȉ��ł��r�b�q�G�}�������x��200���ȉ��ƂȂ邽�߁A�A�f�r�b�q�G�}�ɂ���ď\���Ȃm
�n���팸��}��ɂ��Ƃ͍���ł���B����A�Q�^�[�{�ߋ��@�����̋C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�ł́A�}�X
�|�P�Ɏ������悤�ɁA�r�b�q�G�}�������x��200���ȉ��ƂȂ�̂��A�N�Z���y�_�������ݗʂ��Q�T���ȉ��̉^�]�̈��
�Ō����ł���̂ł���B���̌��ʁA�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�͏]���̒ʏ�̃G���W���i�S�C����
�ɉғ�����G���W���j�����A�f�r�b�q�G�}�ɂ���đ啝�Ȃm�n���팸��}�邱�Ƃ��\�ȋZ�p�ł���B
�̍팸�ɂ́A�R����̌��_�̂���m�n���z���G�}���g���Ȃ��B���̂��߁A��^�g���b�N�ł̂m�n���̍팸�ɂ́A�]����
�Z�p�ł���N�[���h�d�f�q�̂d�f�q���̑����ƁA�A�f�r�b�q�G�}�̋Z�p�ɗ���ȊO�ɗL���ȕ��@�͂Ȃ����̂ƍl�����
��B���̏ꍇ�A�A�f�r�b�q�G�}�ɂ���ď\���Ȃm�n���팸��}��ɂ́A�}�T�Ɏ������悤�ɂr�b�q�G�}�������x��200����
�x�ɍ��߂�K�v������B�������A�S�C�����ϓ��̕��ׂŏ�ɉғ������]���̃G���W���ł́A�}�U�Ɏ������悤�ɁA�A�N
�Z���y�_�������ݗʂ��T�O���ȉ��ł��r�b�q�G�}�������x��200���ȉ��ƂȂ邽�߁A�A�f�r�b�q�G�}�ɂ���ď\���Ȃm
�n���팸��}��ɂ��Ƃ͍���ł���B����A�Q�^�[�{�ߋ��@�����̋C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�ł́A�}�X
�|�P�Ɏ������悤�ɁA�r�b�q�G�}�������x��200���ȉ��ƂȂ�̂��A�N�Z���y�_�������ݗʂ��Q�T���ȉ��̉^�]�̈��
�Ō����ł���̂ł���B���̌��ʁA�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�͏]���̒ʏ�̃G���W���i�S�C����
�ɉғ�����G���W���j�����A�f�r�b�q�G�}�ɂ���đ啝�Ȃm�n���팸��}�邱�Ƃ��\�ȋZ�p�ł���B
�@���͂Ƃ�����A�M�҂��w�Q�^�[�{�ߋ��@�����̋C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�x�͒P�Ȃ��A�C�f�A�̒i�K��
�߂��Ȃ��̂��c�O�Ȃ��Ƃł���B���ɁA���̓����Z�p�����p���ł����Ƃ���A��^�g���b�N�ɂ������攪�����\�̒�
��ڕW�Ə̂���u0.7 g/kWh�̂R���̂P�v�̂m�n���팸���B���ł�����̂Ǝv���Ă���B����͒P�Ȃ�M�҂̗\�z�ł��邽
�߂ɉ��̐����͂������̂��c�O���B�M�҂̐g����Ȋ�]��I��Ɍ��킹�Ă��炦�A�S���錤���@�ւ����̓����Z
�p�̎���������^�ʖڂɎ��{���A�攪�����\�̒���ڕW���B���ł��邱�Ƃ𑁋}�Ɏ����ė~�����Ɗ���Ă���̂�
����B�����āA�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p�����p���̖ڏ��������łɂ́A���Ȃ��u�攪��
���\�̒���ڕW�Ə̂���0.7 g/kWh�̂R���̂P�̂m�n���팸�v�̂m�n���K�����{�s����A���{�̑�C���̉��P��傫��
�i�W�����Ă����������Ƃ�����Ă���̂ł���B
�߂��Ȃ��̂��c�O�Ȃ��Ƃł���B���ɁA���̓����Z�p�����p���ł����Ƃ���A��^�g���b�N�ɂ������攪�����\�̒�
��ڕW�Ə̂���u0.7 g/kWh�̂R���̂P�v�̂m�n���팸���B���ł�����̂Ǝv���Ă���B����͒P�Ȃ�M�҂̗\�z�ł��邽
�߂ɉ��̐����͂������̂��c�O���B�M�҂̐g����Ȋ�]��I��Ɍ��킹�Ă��炦�A�S���錤���@�ւ����̓����Z
�p�̎���������^�ʖڂɎ��{���A�攪�����\�̒���ڕW���B���ł��邱�Ƃ𑁋}�Ɏ����ė~�����Ɗ���Ă���̂�
����B�����āA�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p�����p���̖ڏ��������łɂ́A���Ȃ��u�攪��
���\�̒���ڕW�Ə̂���0.7 g/kWh�̂R���̂P�̂m�n���팸�v�̂m�n���K�����{�s����A���{�̑�C���̉��P��傫��
�i�W�����Ă����������Ƃ�����Ă���̂ł���B
�U�|�R�D����̑�^�g���b�N�ɂ�����R��팸�ɍv���ł���C���x�~�̋Z�p
�V���~���[�V�����v�Z�ŎZ�o�����l��p���邱�ƂɂȂ��Ă���B���̏d�ʎԃ��[�h�́A�s�s�����s���[�h�i�i�d�O�T���[�h�j��
�s�s�ԑ��s���[�h�i�c�f���z�t�W�O�����^���葬���[�h�j�̂Q��̃��[�h���̗p����Ă���B�i�Q��̃��[�h�����킹�āu�d
�ʎԃ��[�h�v�Ƃ����B�j�@�\�V�ɂ�20t ���̑�^�g���b�N�̏d�ʎԃ��[�h�R��l�̎Z�o���@���������B
| |
|
| |
�@�G�l���M�[��������i�R��j�̑�����@�́A�V�~�����[�V�����@�ɂ����̂Ƃ��A���̑��s���[�h�́A
�s�s�����s���[�h�i�i�d�O�T���[�h�j�Ɠs�s�ԑ��s���[�h�i�c�f���z�t�W�O�����^���葬���[�h�j�̂Q��� ���[�h���̗p����i�Q��̃��[�h�����킹�āu�d�ʎԃ��[�h�v�Ƃ����B�j�B �@�G�l���M�[��������i�R��j�́A�e���s���[�h�ɂ��^�s����ꍇ�ɂ�����R���P���b�g��������� ���s�������L�����[�g���ŕ\�����l�i���ꂼ��u�s�s�����s���[�h�R��l�v�u�s�s�ԑ��s���[�h�R��l�v �Ƃ����B�j�ɂ��āA�Ԏ�ɉ����ݒ肳�ꂽ�W����p���āA���d���a���ς����l�ł����āA�^���w�� �����ԂɌW��^���w�薔�͈�_���Y�f�����U�h�~���u�w�莩���ԂɌW�鑕�u�w��ɓ����� ���y��ʑ�b�����肵���l�i�R���l�j�i�ȉ��u�d�ʎԃ��[�h�R��l�v�Ƃ����B�j�Ƃ���B |
| |
�@�@�@�d���P�^�o�i��u�^�du�{��h�^�dh�p
�@�@�@�����ŁA�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�@�@�@�@�@�@�@�d �F�d�ʎԃ��[�h�R��l�ikm/���j
�@�@�@�@�@�@�@�du�F�s�s�����s���[�h�R��l�ikm/���j
�@�@�@�@�@�@�@�dh�F�s�s�ԑ��s���[�h�R��l�ikm/���j
�@�@�@�@�@�@�@��u�F�s�s�����s�����@�i��0.7�j
�@�@�@�@�@�@�@��h�F�s�s�ԑ��s�����@�i��0.3�j
|
���������āA20t ���̑�^�g���b�N�̏d�ʎԃ��[�h�R��l���팸����ɂ́A�i�d�O�T���[�h�i�s�s�����s���[�h�j�Ɠs�s�ԑ�
�s���[�h�i�c�f���z�t�W�O�����^���葬���[�h�j�̗����̑��s���[�h�ɂ���ĔR����팸����K�v������B�������A�i�d�O�T
���[�h�i�s�s�����s���[�h�j�͓s�s�ԑ��s���[�h�������s�������i�i�ɑ������B���̂��߁A�d�ʎԃ��[�h�R��l�̍�
���ɂ́A���ɂi�d�O�T���[�h�i�s�s�����s���[�h�j�̔R��팸���d�v�ł���B
�s���[�h�i�c�f���z�t�W�O�����^���葬���[�h�j�̗����̑��s���[�h�ɂ���ĔR����팸����K�v������B�������A�i�d�O�T
���[�h�i�s�s�����s���[�h�j�͓s�s�ԑ��s���[�h�������s�������i�i�ɑ������B���̂��߁A�d�ʎԃ��[�h�R��l�̍�
���ɂ́A���ɂi�d�O�T���[�h�i�s�s�����s���[�h�j�̔R��팸���d�v�ł���B
�U�|�R�[�ia�j�@�i�d�O�T���[�h�i�s�s�����s���[�h�j�̔R��팸�ɂ���
�@�]���̃g���b�N�p�ߋ��f�B�[�[���G���W���́A�S�C�����ϓ��̕��ׂŏ�ɉғ�����\���ł���A�i�G���W���g���N�j��
�i�A�N�Z���y�_�������ݗʁj�ƂȂ�\���ł���B���̂��߁A�T�O�����G���W���g���N���T�O���̃A�N�Z���y�_�������ݗʂ�
�Ȃ��Ă���B�����āA�}�R�Ɏ������悤�ɂT�O���ȉ��̒ᕉ�ׂ��G���W���g���N�ł͔R��������������Ƃ���A�}�U�Ɏ�
�����悤�ɂT�O���ȉ��̃A�N�Z���y�_�������ݗʂ̃G���W���^�]�ł́A�����������R������ƂȂ�̂ł���B���̂�
�߁A�]���̃G���W���ł��A�N�Z���y�_�������ݗʂ��T�O���ȉ��̍L���G���W���^�]�̈�ɂ����ẮA�R������Ȃ���
���܂��̂ł���B
�i�A�N�Z���y�_�������ݗʁj�ƂȂ�\���ł���B���̂��߁A�T�O�����G���W���g���N���T�O���̃A�N�Z���y�_�������ݗʂ�
�Ȃ��Ă���B�����āA�}�R�Ɏ������悤�ɂT�O���ȉ��̒ᕉ�ׂ��G���W���g���N�ł͔R��������������Ƃ���A�}�U�Ɏ�
�����悤�ɂT�O���ȉ��̃A�N�Z���y�_�������ݗʂ̃G���W���^�]�ł́A�����������R������ƂȂ�̂ł���B���̂�
�߁A�]���̃G���W���ł��A�N�Z���y�_�������ݗʂ��T�O���ȉ��̍L���G���W���^�]�̈�ɂ����ẮA�R������Ȃ���
���܂��̂ł���B
�@����A�}�W�Ɏ������悤�ɁA�i�d�O�T���[�h�����ł̓G���W���g���Nl���T�O���ȉ����G���W���^�]�p�x�̍����B�}�W�͐�
�ڗʂQ�g�����x�̏��^�g���b�N�̗�Ɛ��肳��邪�A���̐ύڗʂQ�g�����x�̏��^�g���b�N�ł́A�T�O���ȉ����g���N�ŃG
���W�����^�]�����p�x���ɂ߂č����̂ł���B�O�q�̒ʂ�]���̃G���W���ł́i�G���W���g���N�j���i�A�N�Z���y�_��
�����ݗʁj�ƂȂ邽�߁A���̐ύڗʂQ�g�����x�̏��^�g���b�N�̂i�d�O�T���[�h�r�o�K�X�����́A�A�N�Z���y�_�������ݗ�
���T�O���ȉ��̗̈�ŃG���W���^�]�p�x�������̂ł���B���̂悤�ɁA�]���̃G���W���𓋍ڂ������^�g���b�N�̂i�d�O�T
���[�h�r�o�K�X�����ł́A�R��̈����T�O���ȉ��̃A�N�Z���y�_�������ݗʂł��G���W���^�]����̂ƂȂ邽�߁A�i�d
�O�T���[�h�̔R��͈������Ă��܂��̂ł���B���������āA���^�g���b�N�̂i�d�O�T���[�h�i�s�s�����s���[�h�j���R���啝
�ɍ팸���邽�߂ɂ́A�A�N�Z���y�_�������ݗʂ��T�O���ߖT�ȉ��̃G���W���^�]�̈�ł��R���啝�ɉ��P���邱��
���K�v�ł���B
�ڗʂQ�g�����x�̏��^�g���b�N�̗�Ɛ��肳��邪�A���̐ύڗʂQ�g�����x�̏��^�g���b�N�ł́A�T�O���ȉ����g���N�ŃG
���W�����^�]�����p�x���ɂ߂č����̂ł���B�O�q�̒ʂ�]���̃G���W���ł́i�G���W���g���N�j���i�A�N�Z���y�_��
�����ݗʁj�ƂȂ邽�߁A���̐ύڗʂQ�g�����x�̏��^�g���b�N�̂i�d�O�T���[�h�r�o�K�X�����́A�A�N�Z���y�_�������ݗ�
���T�O���ȉ��̗̈�ŃG���W���^�]�p�x�������̂ł���B���̂悤�ɁA�]���̃G���W���𓋍ڂ������^�g���b�N�̂i�d�O�T
���[�h�r�o�K�X�����ł́A�R��̈����T�O���ȉ��̃A�N�Z���y�_�������ݗʂł��G���W���^�]����̂ƂȂ邽�߁A�i�d
�O�T���[�h�̔R��͈������Ă��܂��̂ł���B���������āA���^�g���b�N�̂i�d�O�T���[�h�i�s�s�����s���[�h�j���R���啝
�ɍ팸���邽�߂ɂ́A�A�N�Z���y�_�������ݗʂ��T�O���ߖT�ȉ��̃G���W���^�]�̈�ł��R���啝�ɉ��P���邱��
���K�v�ł���B
�@�Ƃ���ŁA�ύڗʂP�O�g���ȏ�̑�^�g���b�N�̃p���[�E�G�C�g���V�I�i�G���W���P�ʏo�͓�����̎ԗ����d�ʁj�́A��
�^�g���b�N�̃p���[�E�G�C�g���V�I�����������߂ɁA��^�g���b�N�̂i�d�O�T���[�h�����ł͏��^�g���b�N�����A�N�Z���y
�_�������ݗʂ������A�傫���Ȃ邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��B��������^�g���b�N�̏ꍇ�ł��A�i�d�O�T���[�h�����ł��A�N�Z���y
�_�������ݗʂ��T�O���ߖT�ȉ��̃G���W���^�]�p�x�͋ɂ߂đ����̂ł���B���̂��߁A��^�g���b�N�̂i�d�O�T���[�h
�i�s�s�����s���[�h�j���R���啝�ɍ팸���邽�߂ɂ́A���^�g���b�N�̏ꍇ�Ɠ��l�ɁA�A�N�Z���y�_�������ݗʂ��T
�O���ߖT�ȉ��̃G���W���^�]�̈�ł��R���啝�ɉ��P���邱�Ƃ��K�v�ł���B
�^�g���b�N�̃p���[�E�G�C�g���V�I�����������߂ɁA��^�g���b�N�̂i�d�O�T���[�h�����ł͏��^�g���b�N�����A�N�Z���y
�_�������ݗʂ������A�傫���Ȃ邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��B��������^�g���b�N�̏ꍇ�ł��A�i�d�O�T���[�h�����ł��A�N�Z���y
�_�������ݗʂ��T�O���ߖT�ȉ��̃G���W���^�]�p�x�͋ɂ߂đ����̂ł���B���̂��߁A��^�g���b�N�̂i�d�O�T���[�h
�i�s�s�����s���[�h�j���R���啝�ɍ팸���邽�߂ɂ́A���^�g���b�N�̏ꍇ�Ɠ��l�ɁA�A�N�Z���y�_�������ݗʂ��T
�O���ߖT�ȉ��̃G���W���^�]�̈�ł��R���啝�ɉ��P���邱�Ƃ��K�v�ł���B
�@���̑�^�g���b�N�ł̂d�O�T���[�h�i�s�s�����s���[�h�j�̏\���ȔR��팸��}�邽�߂ɂ́A��^�g���b�N���A�N�Z���y
�_�������ݗʂ��T�O���ߖT�ȉ��̃G���W���^�]�̈�ɂ����āA�}�R�Ɏ������������ϗL�����͂��T�O���ߖT�ȏ�̔R
��̗ǍD�ȃG���W���^�]�ł���悤�ɂ��邱�Ƃł���B���̂悤�ȃG���W���^�]���\�ɂ���Z�p���A�Q�^�[�{�ߋ��@��
���̋C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p���B���̋C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�ł́A�R���
���^�̋C���Q����@�ɂ����Ă̓N�Z���y�_�������ݗʂT�O���ȉ��ł��}�V�|�P�̐ԐF�Ŏ�����Pme�i�������ϗL��
���j���T�O���ȏ�ƂȂ�R��̗ǍD���L���G���W���^�]�̈悪���݂��ANO���ጸ�^�̋C���Q����@�ɂ����Ă��}�X�|�P
�̐ԐF�Ŏ�����Pme�i�������ϗL�����j���T�O���ȏ�ƂȂ�R��̗ǍD���L���G���W���^�]�̈悪���݂���B������
Pme�i�������ϗL�����j���T�O���ȏ���ԐF�̉^�]�̈�ł́A�i�d�O�T���[�h�^�]�ɂ�����R��̒ጸ�������ł����
����B
�_�������ݗʂ��T�O���ߖT�ȉ��̃G���W���^�]�̈�ɂ����āA�}�R�Ɏ������������ϗL�����͂��T�O���ߖT�ȏ�̔R
��̗ǍD�ȃG���W���^�]�ł���悤�ɂ��邱�Ƃł���B���̂悤�ȃG���W���^�]���\�ɂ���Z�p���A�Q�^�[�{�ߋ��@��
���̋C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p���B���̋C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�ł́A�R���
���^�̋C���Q����@�ɂ����Ă̓N�Z���y�_�������ݗʂT�O���ȉ��ł��}�V�|�P�̐ԐF�Ŏ�����Pme�i�������ϗL��
���j���T�O���ȏ�ƂȂ�R��̗ǍD���L���G���W���^�]�̈悪���݂��ANO���ጸ�^�̋C���Q����@�ɂ����Ă��}�X�|�P
�̐ԐF�Ŏ�����Pme�i�������ϗL�����j���T�O���ȏ�ƂȂ�R��̗ǍD���L���G���W���^�]�̈悪���݂���B������
Pme�i�������ϗL�����j���T�O���ȏ���ԐF�̉^�]�̈�ł́A�i�d�O�T���[�h�^�]�ɂ�����R��̒ጸ�������ł����
����B
�U�|�R�[�ib�j�@�s�s�ԑ��s���[�h�i�c�f���z�t�W�O�����^���葬���[�h�j�̔R��팸�ɂ���
�@���s�̈�ʓI�ȑ�^�g���b�N���s�s�ԑ��s���[�h�i�c�f���z�t�W�O�����^���葬���[�h�j�𑖍s�����ꍇ�A�G���W���̉^
�]�̈���T�O���̃G���W���g���N�ߖT�̎g�p�p�x���ł��������̎v����B�܂�A���̓s�s�ԑ��s���[�h�̑�^�g��
�b�N�̑��s�ł́A�A�N�Z���y�_�������ݗʂ��T�O���ߖT�ł̃G���W���^�]�p�x�������̂ł���B���̂��߁A�Q�^�[�{��
���@�����̋C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�����ẮA�R��ጸ�^�̋C���Q����@�ɂ����ẮA�A�N�Z���y
�_�������ݗʂT�O���ߖT�ł̃G���W���o�͂̑啔���́A�}�V�|�P�Ɏ������悤�ɁA��P�C���Q���P�O�O���ߖT��Pme�i��
�����ϗL�����j�ŃG���W�����^�]�����̈�ƂȂ�B���̌��ʁA�����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j���R��
�ጸ�^�̋C���Q����@���̗p������^�g���b�N���s�s�ԑ��s���[�h�i�c�f���z�t�W�O�����^���葬���[�h�j�𑖍s������
���A�]���̃G���W���𓋍ڂ�����^�g���b�N�ɔ�ׂċɂ߂ėǍD�ȔR������邱�ƂɂȂ�B
�]�̈���T�O���̃G���W���g���N�ߖT�̎g�p�p�x���ł��������̎v����B�܂�A���̓s�s�ԑ��s���[�h�̑�^�g��
�b�N�̑��s�ł́A�A�N�Z���y�_�������ݗʂ��T�O���ߖT�ł̃G���W���^�]�p�x�������̂ł���B���̂��߁A�Q�^�[�{��
���@�����̋C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�����ẮA�R��ጸ�^�̋C���Q����@�ɂ����ẮA�A�N�Z���y
�_�������ݗʂT�O���ߖT�ł̃G���W���o�͂̑啔���́A�}�V�|�P�Ɏ������悤�ɁA��P�C���Q���P�O�O���ߖT��Pme�i��
�����ϗL�����j�ŃG���W�����^�]�����̈�ƂȂ�B���̌��ʁA�����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j���R��
�ጸ�^�̋C���Q����@���̗p������^�g���b�N���s�s�ԑ��s���[�h�i�c�f���z�t�W�O�����^���葬���[�h�j�𑖍s������
���A�]���̃G���W���𓋍ڂ�����^�g���b�N�ɔ�ׂċɂ߂ėǍD�ȔR������邱�ƂɂȂ�B
�@�܂��A�����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j��NO���ጸ�^�̋C���Q����@�ɂ����Ă��A�A�N�Z���y�_������
�ݗʂT�O���ߖT�ł̃G���W���o�͂̑啔���́A�}�X�|�P�Ɏ������悤�ɁA��P�C���Q���T�O�`�P�O�O���ߖT��Pme�i����
���ϗL�����j�ŃG���W�����^�]�����̈�ƂȂ�B���̌��ʁA�����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j��NO����
���^�̋C���Q����@���̗p������^�g���b�N���s�s�ԑ��s���[�h�i�c�f���z�t�W�O�����^���葬���[�h�j�𑖍s�����ꍇ
�ɂ��A�]���̃G���W���𓋍ڂ�����^�g���b�N�ɔ�ׂėǍD�ȔR������邱�ƂɂȂ�B����NO���ጸ�^�̋C���Q��
��@���ꍇ�̔R��́A�R��ጸ�^�̋C���Q����@���C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̏ꍇ�̔R��ɔ�
�ׁA�����A��邱�Ƃ͒v�����̂Ȃ����Ƃł���B�������A�Q�^�[�{�ߋ��@�����̋C���x�~�G���W���i�������J2005-
54771�j�𓋍ڂ�����^�g���b�N���s�s�ԑ��s���[�h�i�c�f���z�t�W�O�����^���葬���[�h�j�̑��s���s�����ꍇ�ɂ́A�R
��ጸ�^��NO���ጸ�^�̉���̋C���Q����@���ꍇ�ɂ����Ă��A�A�]���̃G���W���𓋍ڂ�����^�g���b�N�ɔ�ׂ�
�啝�ɔR��팸�ł��邱�Ƃ͊ԈႢ�̂Ȃ����Ƃł���B
�ݗʂT�O���ߖT�ł̃G���W���o�͂̑啔���́A�}�X�|�P�Ɏ������悤�ɁA��P�C���Q���T�O�`�P�O�O���ߖT��Pme�i����
���ϗL�����j�ŃG���W�����^�]�����̈�ƂȂ�B���̌��ʁA�����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j��NO����
���^�̋C���Q����@���̗p������^�g���b�N���s�s�ԑ��s���[�h�i�c�f���z�t�W�O�����^���葬���[�h�j�𑖍s�����ꍇ
�ɂ��A�]���̃G���W���𓋍ڂ�����^�g���b�N�ɔ�ׂėǍD�ȔR������邱�ƂɂȂ�B����NO���ጸ�^�̋C���Q��
��@���ꍇ�̔R��́A�R��ጸ�^�̋C���Q����@���C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̏ꍇ�̔R��ɔ�
�ׁA�����A��邱�Ƃ͒v�����̂Ȃ����Ƃł���B�������A�Q�^�[�{�ߋ��@�����̋C���x�~�G���W���i�������J2005-
54771�j�𓋍ڂ�����^�g���b�N���s�s�ԑ��s���[�h�i�c�f���z�t�W�O�����^���葬���[�h�j�̑��s���s�����ꍇ�ɂ́A�R
��ጸ�^��NO���ጸ�^�̉���̋C���Q����@���ꍇ�ɂ����Ă��A�A�]���̃G���W���𓋍ڂ�����^�g���b�N�ɔ�ׂ�
�啝�ɔR��팸�ł��邱�Ƃ͊ԈႢ�̂Ȃ����Ƃł���B
�@
�V�D�C���x�~�͑�^�g���b�N�̔R����P�Ƃm�n���팸���\�ɂ���ꋓ�����ȋZ�p
�@�O�q�̂U�|�Q���ɂĐ��������悤�ɁA�Q�^�[�{�ߋ��@�����̋C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�𓋍ڂ�����
�^�g���b�N�ł́A�S�C�����ϓ��̕��ׂŏ�ɉғ������]���̃G���W���ł́A�A�N�Z���y�_�������ݗʂ��T�O���ȉ��ł�
�r�b�q�G�}�������x��200���ȉ��ƂȂ邽�߁A�A�f�r�b�q�G�}�ɂ���ď\���Ȃm�n���팸��}��ɂ��Ƃ͍���ł���B����
���A�Q�^�[�{�ߋ��@�����̋C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�ł́A�r�b�q�G�}�������x��200���ȉ��ƂȂ��
���A�N�Z���y�_�������ݗʂ��Q�T���ȉ��̉^�]�̈�ł���B���������āA�i�d�O�T���[�h�r�o�K�X�����ŃG���W���^�]�p
�x���ɂ߂č����A�N�Z���y�_�������ݗʂ��Q�T�`�T�O���̃G���W���^�]�̈�ł́A�]���̃G���W���̏ꍇ�ɂ��r�b�q�G
�}�������x��200���ȉ��ƂȂ邽�߂ɔA�f�r�b�q�G�}�ł͒Ⴂ�m�n�w��������Ȃ邽�߂ɏ\���Ȃm�n���팸��}�邱�Ƃ�
�ł��Ȃ����_������B�������A�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̏ꍇ�ɂ��r�b�q�G�}�������x��200���ȏ�
�ƂȂ邽�߂ɔA�f�r�b�q�G�}�ł͍����m�n�w���������ێ��ł��邽�߂ɏ\���Ȃm�n���팸��}�邱�Ƃ��ł���̂ł���B
���̂悤�ɁA�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�ł́A�]���̃G���W���ɔ�ׂ��i�d�O�T���[�h�r�o�K�X�����ɂ�
����m�n���r�o��啝�ɍ팸�ł��邱�Ƃ��A�傫�ȓ����̈�ł���B
�^�g���b�N�ł́A�S�C�����ϓ��̕��ׂŏ�ɉғ������]���̃G���W���ł́A�A�N�Z���y�_�������ݗʂ��T�O���ȉ��ł�
�r�b�q�G�}�������x��200���ȉ��ƂȂ邽�߁A�A�f�r�b�q�G�}�ɂ���ď\���Ȃm�n���팸��}��ɂ��Ƃ͍���ł���B����
���A�Q�^�[�{�ߋ��@�����̋C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�ł́A�r�b�q�G�}�������x��200���ȉ��ƂȂ��
���A�N�Z���y�_�������ݗʂ��Q�T���ȉ��̉^�]�̈�ł���B���������āA�i�d�O�T���[�h�r�o�K�X�����ŃG���W���^�]�p
�x���ɂ߂č����A�N�Z���y�_�������ݗʂ��Q�T�`�T�O���̃G���W���^�]�̈�ł́A�]���̃G���W���̏ꍇ�ɂ��r�b�q�G
�}�������x��200���ȉ��ƂȂ邽�߂ɔA�f�r�b�q�G�}�ł͒Ⴂ�m�n�w��������Ȃ邽�߂ɏ\���Ȃm�n���팸��}�邱�Ƃ�
�ł��Ȃ����_������B�������A�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̏ꍇ�ɂ��r�b�q�G�}�������x��200���ȏ�
�ƂȂ邽�߂ɔA�f�r�b�q�G�}�ł͍����m�n�w���������ێ��ł��邽�߂ɏ\���Ȃm�n���팸��}�邱�Ƃ��ł���̂ł���B
���̂悤�ɁA�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�ł́A�]���̃G���W���ɔ�ׂ��i�d�O�T���[�h�r�o�K�X�����ɂ�
����m�n���r�o��啝�ɍ팸�ł��邱�Ƃ��A�傫�ȓ����̈�ł���B
�@�܂��A�O�q�̂U�|�R���i�P�j���ɂĐ��������悤�A�s�s�����s���[�h�i�i�d�O�T���[�h�j�̔R��]���̃G���W���ɔ�ׂđ�
���ɉ��P�ł��A�O�q�̂U�|�R���i�Q�j���ɂĐ��������悤���s�s�ԑ��s���[�h�i�c�f���z�t�W�O�����^���葬���[�h�j�̔R��
���]���̃G���W���ɔ�ׂđ啝�ɉ��P�ł���̂ł���B���̂��ߓs�s�����s���[�h�i�i�d�O�T���[�h�j�Ɠs�s�ԑ��s���[
�h�i�c�f���z�t�W�O�����^���葬���[�h�j����Z�o������C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�𓋍ڂ�����^�g���b
�N�̏d�ʎԃ��[�h�R��́A�]���̃G���W���𓋍ڂ�����^�g���b�N�ɔ�ׂđ啝�ɔR��팸�ł��邱�Ƃ��A�������
�̑傫�ȓ����ł���B
���ɉ��P�ł��A�O�q�̂U�|�R���i�Q�j���ɂĐ��������悤���s�s�ԑ��s���[�h�i�c�f���z�t�W�O�����^���葬���[�h�j�̔R��
���]���̃G���W���ɔ�ׂđ啝�ɉ��P�ł���̂ł���B���̂��ߓs�s�����s���[�h�i�i�d�O�T���[�h�j�Ɠs�s�ԑ��s���[
�h�i�c�f���z�t�W�O�����^���葬���[�h�j����Z�o������C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�𓋍ڂ�����^�g���b
�N�̏d�ʎԃ��[�h�R��́A�]���̃G���W���𓋍ڂ�����^�g���b�N�ɔ�ׂđ啝�ɔR��팸�ł��邱�Ƃ��A�������
�̑傫�ȓ����ł���B
�@���̂悤�ɁA�M�҂���Ă��Ă����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�́A�i�d�O�T���[�h�r�o�K�X�����ɂ�
���ăG���W���ł̉^�]�p�x�̍����A�N�Z���y�_�������ݗ�Accel���T�O���ߖT�₻��ȉ��̃G���W���^�]�̈�
�ł́A�A�f�r�b�q�G�}�̊������ɂ��啝�Ȃm�n���팸���\�ɂ���@�\������A�܂��A�s�s�����s���[�h�i�i�d
�O�T���[�h�j�Ɠs�s�ԑ��s���[�h�i�c�f���z�t�W�O�����^���葬���[�h�j�̗����[�h�̔R��]���̃G���W���ɔ��
�đ啝�ɉ��P�ł��邽�߁A�d�ʎԃ��[�h�R��]���̃G���W���̏ꍇ�ɔ�ׂĂT�`�P�O�����팸�ł����@�\��
����B���������āA�����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�́A�T�`�P�O���̏d�ʎԃ��[�h�R��̉��P�Ƒ�
���Ȃm�n���팸�𗼕����\�ɂ����ꋓ�����̗D�ꂽ�Z�p�ƌ����Ă��ߌ��ł͂Ȃ��B
���ăG���W���ł̉^�]�p�x�̍����A�N�Z���y�_�������ݗ�Accel���T�O���ߖT�₻��ȉ��̃G���W���^�]�̈�
�ł́A�A�f�r�b�q�G�}�̊������ɂ��啝�Ȃm�n���팸���\�ɂ���@�\������A�܂��A�s�s�����s���[�h�i�i�d
�O�T���[�h�j�Ɠs�s�ԑ��s���[�h�i�c�f���z�t�W�O�����^���葬���[�h�j�̗����[�h�̔R��]���̃G���W���ɔ��
�đ啝�ɉ��P�ł��邽�߁A�d�ʎԃ��[�h�R��]���̃G���W���̏ꍇ�ɔ�ׂĂT�`�P�O�����팸�ł����@�\��
����B���������āA�����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�́A�T�`�P�O���̏d�ʎԃ��[�h�R��̉��P�Ƒ�
���Ȃm�n���팸�𗼕����\�ɂ����ꋓ�����̗D�ꂽ�Z�p�ƌ����Ă��ߌ��ł͂Ȃ��B
�@�������A�����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j���A�u�m�n���ƔR��̃g���[�h�I�t���������Ăm�n���̍팸�ƔR��
�̉��P���Ɏ����ł���ꋓ�����v�̋Z�p�ł��邱�Ƃ𗝉�����Ă���w�ҁE���Ƃ͏��Ȃ��悤���B�Ⴆ�A2011
�N9�����s�́u�����ԋZ�p�v���iVol.65,No.9,2011)�ɂ����āA����c��w�̑吹�����́u�����ԗp�G���W���Z�p�̌���
�Ə����v�Ƒ肵���_���\����Ă��邪�A���̒��́u3.2.�@�d�ʎԂ̔R����P�v�̍��ɂ����đ吹�����́A�ȉ��̕\�X
�̐Ԑ��Ɏ������悤�ɁA�d�ʎԁi���g���b�N�E�o�X�j�ɂ�����2016�N�̔r�o�K�X�K���ւ̓K���i��NO���K�������ւ̑�
���j��2015�N�x�d�ʎԔR���ւ̓K���i���R����P�j�̂��߂ɁA�u�f�B�[�[���G���W����NO���ƔR��̃g���[�h�I�t��
��������K�v������v�Əq�ׂ��Ă���B
�̉��P���Ɏ����ł���ꋓ�����v�̋Z�p�ł��邱�Ƃ𗝉�����Ă���w�ҁE���Ƃ͏��Ȃ��悤���B�Ⴆ�A2011
�N9�����s�́u�����ԋZ�p�v���iVol.65,No.9,2011)�ɂ����āA����c��w�̑吹�����́u�����ԗp�G���W���Z�p�̌���
�Ə����v�Ƒ肵���_���\����Ă��邪�A���̒��́u3.2.�@�d�ʎԂ̔R����P�v�̍��ɂ����đ吹�����́A�ȉ��̕\�X
�̐Ԑ��Ɏ������悤�ɁA�d�ʎԁi���g���b�N�E�o�X�j�ɂ�����2016�N�̔r�o�K�X�K���ւ̓K���i��NO���K�������ւ̑�
���j��2015�N�x�d�ʎԔR���ւ̓K���i���R����P�j�̂��߂ɁA�u�f�B�[�[���G���W����NO���ƔR��̃g���[�h�I�t��
��������K�v������v�Əq�ׂ��Ă���B
| |
|
| |
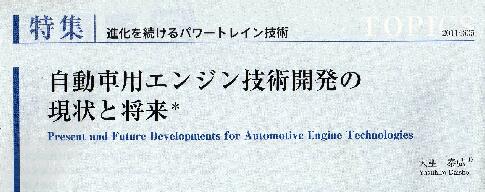 |
| |
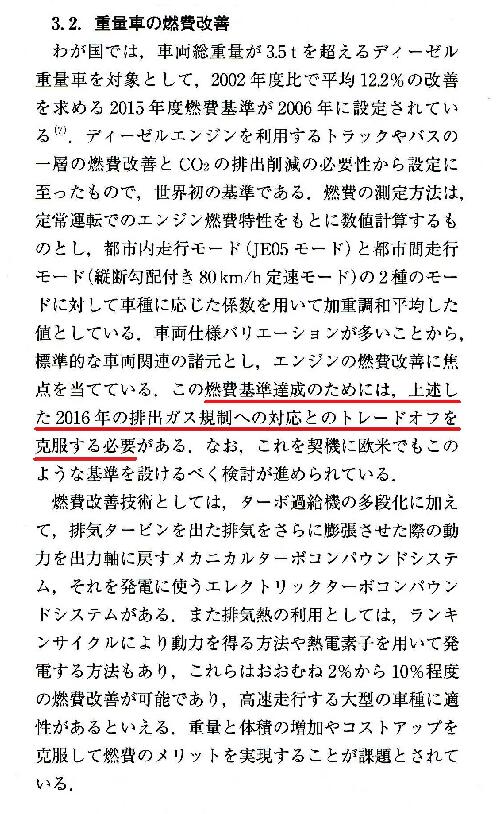 |
�@���̕\�W�Ɏ������u�����ԋZ�p�v���̓��e������ƁA����c��w�̑吹�������A�f�B�[�[����^�g���b�N�ɂ����Ă�
�uNO���̍팸�v�Ɓu�R��̉��P�v�ɂ̓g���[�h�I�t�̊W�����邽�߁A�uNO���̍팸�v�Ɓu�R��̉��P�v���Ɏ�������Z
�p�������_�ł͕s���ƔF������Ă�����̂Ɛ��@�����B���̂��߁A����c��w�̑吹�������A��^�g���b�N�ɂ���
�āA���{�̃g���b�N���[�J�ł́u2015�N�x�d�ʎԔR���̒B���v�ƁA�u2016�N��NO���K���l�� 0.4 g/kWh�iWHTC���[
�h�j�̔r�o�K�X�K���ւ̓K���v�̃g���[�h�I�t�̍������Z�p�I�Ɍ��E�ł���A���{�ł͂���ȏ�̃��x���́uNO���K��
�̋����v�Ɓu�R���̋����v������Ƃ̈ӌ���������Ă���悤�ɐ��������B�t�Ȍ�����������A�������R�c
����吹�������܂������Ԕr�o�K�X���ψ�����w�ҁE���Ƃ́A�u2015�N�x�d�ʎԔR�����\���ɒ�����R��
����v�ƁA�uNO���K���l�� 0.4 g/kWh�iWHTC���[�h�j�ȏ�̃��x���܂ł�NO���팸�v�̗������Ɏ����ł���Z�p��
�m������������ۗL����Ă��Ȃ����̂Ɛ��������B���̂��߁A2010�N7�����������R�c��̑�10�����\�ł́A
2016�N�Ɏ��{������{�̎�����NO���K���l�́A2010�N���č��̂m�n���K���iNO�� �� 0.27 g/kWh�j���������Ɋɂ�����
�uNO���� 0.4 g/kWh�iWHTC���[�h�j�v�\������Ȃ��������̂Ɛ��������B
�uNO���̍팸�v�Ɓu�R��̉��P�v�ɂ̓g���[�h�I�t�̊W�����邽�߁A�uNO���̍팸�v�Ɓu�R��̉��P�v���Ɏ�������Z
�p�������_�ł͕s���ƔF������Ă�����̂Ɛ��@�����B���̂��߁A����c��w�̑吹�������A��^�g���b�N�ɂ���
�āA���{�̃g���b�N���[�J�ł́u2015�N�x�d�ʎԔR���̒B���v�ƁA�u2016�N��NO���K���l�� 0.4 g/kWh�iWHTC���[
�h�j�̔r�o�K�X�K���ւ̓K���v�̃g���[�h�I�t�̍������Z�p�I�Ɍ��E�ł���A���{�ł͂���ȏ�̃��x���́uNO���K��
�̋����v�Ɓu�R���̋����v������Ƃ̈ӌ���������Ă���悤�ɐ��������B�t�Ȍ�����������A�������R�c
����吹�������܂������Ԕr�o�K�X���ψ�����w�ҁE���Ƃ́A�u2015�N�x�d�ʎԔR�����\���ɒ�����R��
����v�ƁA�uNO���K���l�� 0.4 g/kWh�iWHTC���[�h�j�ȏ�̃��x���܂ł�NO���팸�v�̗������Ɏ����ł���Z�p��
�m������������ۗL����Ă��Ȃ����̂Ɛ��������B���̂��߁A2010�N7�����������R�c��̑�10�����\�ł́A
2016�N�Ɏ��{������{�̎�����NO���K���l�́A2010�N���č��̂m�n���K���iNO�� �� 0.27 g/kWh�j���������Ɋɂ�����
�uNO���� 0.4 g/kWh�iWHTC���[�h�j�v�\������Ȃ��������̂Ɛ��������B
�@���ɁA���̘_���ɒ��ł́A�吹�����́A��^�g���b�N�̔R����P�Z�p�Ƃ��āA�u�^�[�{�ߋ��̑��i���v�A�u�^�[�{�R���p
�E���h�v�A�u�����L���T�C�N���v����сu�M�d�f�q�v�̋Z�p���������Ă���B�������A�u�^�[�{�ߋ��̑��i���v�Ɓu�^�[�{�R��
�p�E���h�v�̉���̋Z�p���f�B�[�[���G���W���̕������ׂ̔R����\���ɉ��P���邱�Ƃ�����ł���A�u�^�[�{�ߋ���
���i���v�Ɓu�^�[�{�R���p�E���h�v�̋Z�p���̗p���Ă���^�g���b�N�̏d�ʎԃ��[�h�R����\���Ɍ��シ�邱�Ƃ͍���ł�
��B���ɁA�u�^�[�{�R���p�E���h�v�A�u�����L���T�C�N���v����сu�M�d�f�q�v�̂悤�Ȕr�C�K�X�̃G�l���M�[������E��
�đ�^�g���b�N�̑��s�R������P���邽�߂ɂ́A�^�[�{�R���p�E���h�ɂ��f�B�[�[���g���b�N�̏\���ȔR����P�͍���
���I������C���x�~�́A�f�B�[�[���r�C�K�X�̃G�l���M�[���u�̌����������ɏڏq�����ʂ�A��^�g���b�N�̎�
�ۂ̑��s���ɂ�����G���W���^�]�p�x�̍����������ׂ̔r�C�K�X���x���������ł����C���x�~�G���W���i�������J
2005-54771�j�̂悤�ȋC���x�~�V�X�e���Ƃ̑g�ݍ��킹���K�{�ł���B�������A���̘_���ɂ́A�u�^�[�{�R���p�E���h�v
��u�����L���T�C�N���v���̃f�B�[�[���G���W���̔r�C�K�X�G�l���M�[���u�ɂ���^�g���b�N�̔R�����ɂ͋C
���x�~�V�X�e���Ƃ̑g�ݍ��킹�K�v�ł���Ƃ̋L�ڂ������������Ƃ��画�f����ƁA�r�C�K�X�̃G�l���M�[���u
�ɂ���^�g���b�N�̏\���ȔR�����ɂ́A�C���x�~�V�X�e���Ƃ̑g�ݍ��킹���K�v�ł���Ƃ̔F�����吹�����ɂ�
�����悤�ł���B
�E���h�v�A�u�����L���T�C�N���v����сu�M�d�f�q�v�̋Z�p���������Ă���B�������A�u�^�[�{�ߋ��̑��i���v�Ɓu�^�[�{�R��
�p�E���h�v�̉���̋Z�p���f�B�[�[���G���W���̕������ׂ̔R����\���ɉ��P���邱�Ƃ�����ł���A�u�^�[�{�ߋ���
���i���v�Ɓu�^�[�{�R���p�E���h�v�̋Z�p���̗p���Ă���^�g���b�N�̏d�ʎԃ��[�h�R����\���Ɍ��シ�邱�Ƃ͍���ł�
��B���ɁA�u�^�[�{�R���p�E���h�v�A�u�����L���T�C�N���v����сu�M�d�f�q�v�̂悤�Ȕr�C�K�X�̃G�l���M�[������E��
�đ�^�g���b�N�̑��s�R������P���邽�߂ɂ́A�^�[�{�R���p�E���h�ɂ��f�B�[�[���g���b�N�̏\���ȔR����P�͍���
���I������C���x�~�́A�f�B�[�[���r�C�K�X�̃G�l���M�[���u�̌����������ɏڏq�����ʂ�A��^�g���b�N�̎�
�ۂ̑��s���ɂ�����G���W���^�]�p�x�̍����������ׂ̔r�C�K�X���x���������ł����C���x�~�G���W���i�������J
2005-54771�j�̂悤�ȋC���x�~�V�X�e���Ƃ̑g�ݍ��킹���K�{�ł���B�������A���̘_���ɂ́A�u�^�[�{�R���p�E���h�v
��u�����L���T�C�N���v���̃f�B�[�[���G���W���̔r�C�K�X�G�l���M�[���u�ɂ���^�g���b�N�̔R�����ɂ͋C
���x�~�V�X�e���Ƃ̑g�ݍ��킹�K�v�ł���Ƃ̋L�ڂ������������Ƃ��画�f����ƁA�r�C�K�X�̃G�l���M�[���u
�ɂ���^�g���b�N�̏\���ȔR�����ɂ́A�C���x�~�V�X�e���Ƃ̑g�ݍ��킹���K�v�ł���Ƃ̔F�����吹�����ɂ�
�����悤�ł���B
�@���������A�u�^�[�{�R���p�E���h��A�u�����L���T�C�N���v����сu�M�d�f�q�v�̋Z�p�́A�G���W���̉��x�E���͓��̃G�l��
�M�[���G���W���o�͎��ɉ���V�X�e���ł���B���̂��߁A��^�g���b�N�̃G���W���Ɂu�����L���T�C�N���v�A�u�^�[�{�R
���p�E���h�����сu�M�d�f�q�v�̋Z�p�𓋍ڂ����ꍇ�ɂ́A�r�C�K�X���x�������ƂȂ�G���W���̑S���o�͉^�]��
�ɁA������x�̍��������Ŕr�C�K�X�̉��x�G�l���M�[���G���W���o�͎��ɉ��邱�Ƃ��ł��邽�߁A�G���W���R��
�̉��P��}�邱�Ƃ��\���B�������A��^�g���b�N�̎����s����d�ʎԃ��[�h�R��v���̃G���W���^�]���[�h�ł���JE
�O�T���[�h���ł́A�r�C�K�X���x�̒Ⴂ�G���W���������^�]����̂ƂȂ邽�߁A��^�g���b�N�̎����s�ɂ�����u�^�[
�{�R���p�E���h��A�u�����L���T�C�N���v����сu�M�d�f�q�v�ɂ��r�C�K�X�̉��x�G�l���M�[���G���W���o�͎��ɉ�
�鎞�̌����́A�啝�ɒቺ���邱�ƂɂȂ�B���̂悤�ɁA��^�g���b�N�̎����s��d�ʎԃ��[�h�R��̌v���i���V���~��
�[�V�����v�Z�j�ł́A�C���x�~�G���W���ɂ���^�g���b�N�̒�R��̃y�[�W�ɏڏq���Ă���悤�ɁA�r�C�K�X���x��
�Ⴂ�G���W���������ׂ̉^�]���啔�����߂邽�߁A��^�g���b�N�̃f�B�[�[���G���W���Ɂu�^�[�{�R���p�E���h�v�A�u��
���L���T�C�N���v����сu�M�d�f�q�v�̋Z�p���̗p�����Ƃ��Ă��A��^�g���b�N�̎����s�R���d�ʎԃ��[�h�R��́A�ɁA
�͂��ȉ��P�ɗ��܂���̂ƍl������B
�M�[���G���W���o�͎��ɉ���V�X�e���ł���B���̂��߁A��^�g���b�N�̃G���W���Ɂu�����L���T�C�N���v�A�u�^�[�{�R
���p�E���h�����сu�M�d�f�q�v�̋Z�p�𓋍ڂ����ꍇ�ɂ́A�r�C�K�X���x�������ƂȂ�G���W���̑S���o�͉^�]��
�ɁA������x�̍��������Ŕr�C�K�X�̉��x�G�l���M�[���G���W���o�͎��ɉ��邱�Ƃ��ł��邽�߁A�G���W���R��
�̉��P��}�邱�Ƃ��\���B�������A��^�g���b�N�̎����s����d�ʎԃ��[�h�R��v���̃G���W���^�]���[�h�ł���JE
�O�T���[�h���ł́A�r�C�K�X���x�̒Ⴂ�G���W���������^�]����̂ƂȂ邽�߁A��^�g���b�N�̎����s�ɂ�����u�^�[
�{�R���p�E���h��A�u�����L���T�C�N���v����сu�M�d�f�q�v�ɂ��r�C�K�X�̉��x�G�l���M�[���G���W���o�͎��ɉ�
�鎞�̌����́A�啝�ɒቺ���邱�ƂɂȂ�B���̂悤�ɁA��^�g���b�N�̎����s��d�ʎԃ��[�h�R��̌v���i���V���~��
�[�V�����v�Z�j�ł́A�C���x�~�G���W���ɂ���^�g���b�N�̒�R��̃y�[�W�ɏڏq���Ă���悤�ɁA�r�C�K�X���x��
�Ⴂ�G���W���������ׂ̉^�]���啔�����߂邽�߁A��^�g���b�N�̃f�B�[�[���G���W���Ɂu�^�[�{�R���p�E���h�v�A�u��
���L���T�C�N���v����сu�M�d�f�q�v�̋Z�p���̗p�����Ƃ��Ă��A��^�g���b�N�̎����s�R���d�ʎԃ��[�h�R��́A�ɁA
�͂��ȉ��P�ɗ��܂���̂ƍl������B
�@���̂悤�ɁA�u�^�[�{�R���p�E���h�v�A�u�����L���T�C�N���v����сu�M�d�f�q�v�̋Z�p�́A�G���W�����������̔R���
�P�̋@�\�����Z�p�ł���B���̂��߁A�����̋Z�p���^�g���b�N�ɍ̗p�����Ƃ��Ă��A��^�g���b�N�̎����s�R���
�d�ʎԃ��[�h�R����\���Ɍ��シ�邱�Ƃ́A����ł���B����ɂ�������炸�A2011�N9�����s�́u�����ԋZ�p�v��
�iVol.65,No.9,2011)�́u�����ԗp�G���W���Z�p�J���̌���Ə����v�i�\�T�Q�Ɓj�Ƒ肵���_���́u3.2.�@�d�ʎԂ̔R����P�v
�̍��ɂ����āA���҂̑���c��w�̑吹�����́A��^�g�f�B�[�[���g���b�N�E�o�X�i���d�ʎԁj�ɂ���������s��d��
�ԃ��[�h�R������シ���i�Ƃ��āA��^�g���b�N�̎����s�R���d�ʎԃ��[�h�R����\���ɉ��P�ł���@�\��L����
�Z�p�Ƃ��āu�^�[�{�ߋ��̑��i���v�A�u�^�[�{�R���p�E���h�v�A�u�����L���T�C�N���v����сu�M�d�f�q�v�̋Z�p�𐄋������
���邱�Ƃɂ��āA�M�҂ɂ͋^��Ɏv���Ďd�����Ȃ��̂ł���B���ɁA�C���x�~�́A�f�B�[�[���r�C�K�X�̃G�l���M�[
���u�̌���������������C���x�~�́A�f�B�[�[���r�C�K�X�̃G�l���M�[���u�̌����������̃y�[�W�ɏڏq
���Ă���悤�ɁA�u�^�[�{�R���p�E���h�v�A�u�����L���T�C�N���v����сu�M�d�f�q�v���̔r�C�K�X�G�l���M�[������Z
�p��p���đ�^�g���b�N�̎����s�R���d�ʎԃ��[�h�R����\���Ɍ��シ�邽�߂ɂ́A��^�g���b�N�̎��ۂ̑��s��
�ɂ�����G���W���^�]�̕��וp�x�������G���W���������ׂ̔r�C�K�X���x�������������C���x�~�G���W���i������
�J2005-54771�j�̋Z�p��g���킹�邱�Ƃ��K�v�E�s���ł���B
�P�̋@�\�����Z�p�ł���B���̂��߁A�����̋Z�p���^�g���b�N�ɍ̗p�����Ƃ��Ă��A��^�g���b�N�̎����s�R���
�d�ʎԃ��[�h�R����\���Ɍ��シ�邱�Ƃ́A����ł���B����ɂ�������炸�A2011�N9�����s�́u�����ԋZ�p�v��
�iVol.65,No.9,2011)�́u�����ԗp�G���W���Z�p�J���̌���Ə����v�i�\�T�Q�Ɓj�Ƒ肵���_���́u3.2.�@�d�ʎԂ̔R����P�v
�̍��ɂ����āA���҂̑���c��w�̑吹�����́A��^�g�f�B�[�[���g���b�N�E�o�X�i���d�ʎԁj�ɂ���������s��d��
�ԃ��[�h�R������シ���i�Ƃ��āA��^�g���b�N�̎����s�R���d�ʎԃ��[�h�R����\���ɉ��P�ł���@�\��L����
�Z�p�Ƃ��āu�^�[�{�ߋ��̑��i���v�A�u�^�[�{�R���p�E���h�v�A�u�����L���T�C�N���v����сu�M�d�f�q�v�̋Z�p�𐄋������
���邱�Ƃɂ��āA�M�҂ɂ͋^��Ɏv���Ďd�����Ȃ��̂ł���B���ɁA�C���x�~�́A�f�B�[�[���r�C�K�X�̃G�l���M�[
���u�̌���������������C���x�~�́A�f�B�[�[���r�C�K�X�̃G�l���M�[���u�̌����������̃y�[�W�ɏڏq
���Ă���悤�ɁA�u�^�[�{�R���p�E���h�v�A�u�����L���T�C�N���v����сu�M�d�f�q�v���̔r�C�K�X�G�l���M�[������Z
�p��p���đ�^�g���b�N�̎����s�R���d�ʎԃ��[�h�R����\���Ɍ��シ�邽�߂ɂ́A��^�g���b�N�̎��ۂ̑��s��
�ɂ�����G���W���^�]�̕��וp�x�������G���W���������ׂ̔r�C�K�X���x�������������C���x�~�G���W���i������
�J2005-54771�j�̋Z�p��g���킹�邱�Ƃ��K�v�E�s���ł���B
�@�Ƃ���ŁA�����U�����Ԃ́A�f�B�[�[���S�g���g���b�N�u�t�H���[�h�v�ɂ����āA�����Q�Q�N�̔r�o�K�X�K���i�|�X�g�V����
�K���j�̓K���Ԃł́A�Q�i�V�[�P���V�����^�[�{�V�X�e�����̗p���Ă���B�������A�C���x�~�G���W���ɂ���^�g���b�N
�̒�R��ɏڏq���Ă���悤�ɁA�����u�t�H���[�h�v�ł͑��s�R��s�ǂȂ��Ƃ������Ɛ�������邪�A�L�낤�����A
�����U�����Ԃ́A�s�̂����u�t�H���[�h�v���Q�i�V�[�P���V�����^�[�{�V�X�e���𓋍ڂ����SHK1-TCS�G���W���Ɉ�@�ȃG
���W��������s����NO���𐂂ꗬ���đ��s�R��̉��P��}�����s���ȃG���W��������̗p���Ă����̂ł���B�Ƃ���
���A���̕s���ȍs�ׂ����I�悵�A�����U�����Ԃ�����23�N5���ɓ����s�ɂ���č��y��ʏȂɓ��H�^���ԗ��@�ᔽ��
�ʕꂽ�̂��B���̂��Ƃ���A�Q�i�V�[�P���V�����^�[�{�V�X�e���̃G���W���ᑬ�̃g���N�A�b�v�Ɋ�^���邪�A�R��
�팸�̃����b�g�͋ɂ߂ď��Ȃ����̂ł��邱�Ƃ������̈�ł͂Ȃ����Ɛ��@�����B
�K���j�̓K���Ԃł́A�Q�i�V�[�P���V�����^�[�{�V�X�e�����̗p���Ă���B�������A�C���x�~�G���W���ɂ���^�g���b�N
�̒�R��ɏڏq���Ă���悤�ɁA�����u�t�H���[�h�v�ł͑��s�R��s�ǂȂ��Ƃ������Ɛ�������邪�A�L�낤�����A
�����U�����Ԃ́A�s�̂����u�t�H���[�h�v���Q�i�V�[�P���V�����^�[�{�V�X�e���𓋍ڂ����SHK1-TCS�G���W���Ɉ�@�ȃG
���W��������s����NO���𐂂ꗬ���đ��s�R��̉��P��}�����s���ȃG���W��������̗p���Ă����̂ł���B�Ƃ���
���A���̕s���ȍs�ׂ����I�悵�A�����U�����Ԃ�����23�N5���ɓ����s�ɂ���č��y��ʏȂɓ��H�^���ԗ��@�ᔽ��
�ʕꂽ�̂��B���̂��Ƃ���A�Q�i�V�[�P���V�����^�[�{�V�X�e���̃G���W���ᑬ�̃g���N�A�b�v�Ɋ�^���邪�A�R��
�팸�̃����b�g�͋ɂ߂ď��Ȃ����̂ł��邱�Ƃ������̈�ł͂Ȃ����Ɛ��@�����B
�@���̂悤�ɁA2011�N9�����s�́u�����ԋZ�p�v���iVol.65,No.9,2011)�́u�����ԗp�G���W���Z�p�J���̌���Ə����v�Ƒ�
�����_���ł́A2.2 (2)�́u�i�K�\�����G���W���́j�����\���ƔR����P�Z�p�v�̍��ł́A�吹�����́A�u�E�E�E�e��ϋ@�\
�̗��p�A���ڕ��˂��܂ޔR�������n����ɐ��k���A�E�E�E�E�E�E�A�ߋ��V�X�e���ɂ��G���W���̃_�E���T�C�W���O�A�e�^
�����̖��C���L�ޑ����̒ጸ�ȂǁE�E�E�E�E�v�ƋL�ڂ���A�K�\�����G���W���̔R����P�Ɋւ��鑽���̋Z�p������
�Ă��邪�A�������A�u3.2.�@�d�ʎԂ̔R����P�v�̍��ł́A�吹�����́A��^�g���b�N�̎����s�R���d�ʎԃ��[�h�R��
���\���ɉ��P�ł���@�\�E���ʂ����Ɨ\�z�����u�^�[�{�ߋ��̑��i���v�A�u�^�[�{�R���p�E���h�v�A�u�����L���T�C�N
���v����сu�M�d�f�q�v�̂悤�ȋZ�p�ł���ɂ�������炸�A���������m�Ő�������Ă���̂ł͂Ȃ����Ɛ��������B
���������āA���̘_����q������ƁA�吹�����́A����̍X�Ȃ��^�g���b�N�̏d�ʎԃ��[�h�R��̌��オ�ɂ߂Ď���
�̍���Ȃ��Ƃ���S�ł͐[���F������Ă���̂ł͂Ȃ����Ɛ��@�����B
�����_���ł́A2.2 (2)�́u�i�K�\�����G���W���́j�����\���ƔR����P�Z�p�v�̍��ł́A�吹�����́A�u�E�E�E�e��ϋ@�\
�̗��p�A���ڕ��˂��܂ޔR�������n����ɐ��k���A�E�E�E�E�E�E�A�ߋ��V�X�e���ɂ��G���W���̃_�E���T�C�W���O�A�e�^
�����̖��C���L�ޑ����̒ጸ�ȂǁE�E�E�E�E�v�ƋL�ڂ���A�K�\�����G���W���̔R����P�Ɋւ��鑽���̋Z�p������
�Ă��邪�A�������A�u3.2.�@�d�ʎԂ̔R����P�v�̍��ł́A�吹�����́A��^�g���b�N�̎����s�R���d�ʎԃ��[�h�R��
���\���ɉ��P�ł���@�\�E���ʂ����Ɨ\�z�����u�^�[�{�ߋ��̑��i���v�A�u�^�[�{�R���p�E���h�v�A�u�����L���T�C�N
���v����сu�M�d�f�q�v�̂悤�ȋZ�p�ł���ɂ�������炸�A���������m�Ő�������Ă���̂ł͂Ȃ����Ɛ��������B
���������āA���̘_����q������ƁA�吹�����́A����̍X�Ȃ��^�g���b�N�̏d�ʎԃ��[�h�R��̌��オ�ɂ߂Ď���
�̍���Ȃ��Ƃ���S�ł͐[���F������Ă���̂ł͂Ȃ����Ɛ��@�����B
�@�܂��A�����A��S���l�ɔz�z����Ă���u�����ԋZ�p�v���ɂ����āA��L�̕\�W�Ɏ������悤�ɑ吹�����́A�u���̔R
���i��2015�N�x�d�ʎԔR���j�B���̂��߂ɂ́A��q����2016�N�̔r�o�K�X�K���i��NO���K���l�F 0.4 g/kWh�j
�ւ̑Ή��Ƃ��g���[�h�I�t����������K�v������B�v�Əq�ׂ�Ă���B�����ǂނƁA�吹�����́A�g���b�N���[�J����^
�g���b�N�ɂ�����u2015�N�x�d�ʎԔR���̒B���v�ƁA�u2016�N��NO���K���l�� 0.4 g/kWh�iWHTC���[�h�j�̔r�o�K�X
�K���ւ̓K���v�̃g���[�h�I�t���������鍢��Ȍ����J���̉ۑ���ۂ���ꂽ�ƔF������Ă���悤���B���̂��Ƃ���
���@����ƁA�吹�����́A���݂ł��A�f�B�[�[���G���W���ɂ�����u�m�n���팸�ƔR����P�̃g���[�h�I�t�v�́A�����ɉ�
���̍���ȉۑ�ƔF������Ă���悤�ɐ��������̂ł���B
���i��2015�N�x�d�ʎԔR���j�B���̂��߂ɂ́A��q����2016�N�̔r�o�K�X�K���i��NO���K���l�F 0.4 g/kWh�j
�ւ̑Ή��Ƃ��g���[�h�I�t����������K�v������B�v�Əq�ׂ�Ă���B�����ǂނƁA�吹�����́A�g���b�N���[�J����^
�g���b�N�ɂ�����u2015�N�x�d�ʎԔR���̒B���v�ƁA�u2016�N��NO���K���l�� 0.4 g/kWh�iWHTC���[�h�j�̔r�o�K�X
�K���ւ̓K���v�̃g���[�h�I�t���������鍢��Ȍ����J���̉ۑ���ۂ���ꂽ�ƔF������Ă���悤���B���̂��Ƃ���
���@����ƁA�吹�����́A���݂ł��A�f�B�[�[���G���W���ɂ�����u�m�n���팸�ƔR����P�̃g���[�h�I�t�v�́A�����ɉ�
���̍���ȉۑ�ƔF������Ă���悤�ɐ��������̂ł���B
�@�m���ɁA�u�f�B�[�[���G���W���ɂ�����m�n���팸�ƔR����P�̃g���[�h�I�t�̉ۑ�̉���������v�ł��邱�Ƃ́A�M��
��1972�N�Ɏ����ԃ��[�J�ɏA�E������40�N���̂��牄�X�ƁA���Ƀ^�R���ł���قǕ������ꑱ���Ă������Ƃł���B��
�����A�M�҂���N�ސE���Ē������Ԃ��o�߂��Ă���ɂ�������炸�A���݂ł����ς�炸�A�u�f�B�[�[���G���W���ɂ�
����m�n���팸�ƔR����P�̃g���[�h�I�t�́A�����̓���ۑ�v�Ƃ���|�Ɠ��ނ̓��e���A�吹�������u�����ԋZ�p�v
����2011�N9�����̒��Ŏ咣����Ă��邱�Ƃɂ͋����ł���B���̂Ȃ�A���̑吹�����̎咣�ɂ��āA�M�҂͏���
�^��Ɏv���Ă��邩�炾�B���̗��R�́A�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p���d�ʎԁi���g���b�N�E�o�X�j
�ɍ̗p�����ꍇ�ɂ́A��^�g���b�N�ɂ�����u2015�N�x�d�ʎԔR���̒B���v�ƁA�u2016�N��NO���K���l�� 0.4 g/
kWh�iWHTC���[�h�j�̔r�o�K�X�K���ւ̓K���v�̃g���[�h�I�t�������ł���ƍl���Ă��邽�߂ł���B�����C���x�~�G��
�W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p���A��^�g���b�N�ɂ�����u2015�N�x�d�ʎԔR���̒B���v�ƁA�u2016�N��NO���K
���l�� 0.4 g/kWh�iWHTC���[�h�j�̔r�o�K�X�K���ւ̓K���v��e�ՂɎ����ł��邱�Ƃɂ��ẮA�{�y�[�W�̑��̍�
��A�C���x�~�G���W���ɂ���^�g���b�N�̒�R��̃y�[�W�ɂ��ڏq���Ă���̂ŁA�����̂�����͌䗗����������
���B
��1972�N�Ɏ����ԃ��[�J�ɏA�E������40�N���̂��牄�X�ƁA���Ƀ^�R���ł���قǕ������ꑱ���Ă������Ƃł���B��
�����A�M�҂���N�ސE���Ē������Ԃ��o�߂��Ă���ɂ�������炸�A���݂ł����ς�炸�A�u�f�B�[�[���G���W���ɂ�
����m�n���팸�ƔR����P�̃g���[�h�I�t�́A�����̓���ۑ�v�Ƃ���|�Ɠ��ނ̓��e���A�吹�������u�����ԋZ�p�v
����2011�N9�����̒��Ŏ咣����Ă��邱�Ƃɂ͋����ł���B���̂Ȃ�A���̑吹�����̎咣�ɂ��āA�M�҂͏���
�^��Ɏv���Ă��邩�炾�B���̗��R�́A�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p���d�ʎԁi���g���b�N�E�o�X�j
�ɍ̗p�����ꍇ�ɂ́A��^�g���b�N�ɂ�����u2015�N�x�d�ʎԔR���̒B���v�ƁA�u2016�N��NO���K���l�� 0.4 g/
kWh�iWHTC���[�h�j�̔r�o�K�X�K���ւ̓K���v�̃g���[�h�I�t�������ł���ƍl���Ă��邽�߂ł���B�����C���x�~�G��
�W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p���A��^�g���b�N�ɂ�����u2015�N�x�d�ʎԔR���̒B���v�ƁA�u2016�N��NO���K
���l�� 0.4 g/kWh�iWHTC���[�h�j�̔r�o�K�X�K���ւ̓K���v��e�ՂɎ����ł��邱�Ƃɂ��ẮA�{�y�[�W�̑��̍�
��A�C���x�~�G���W���ɂ���^�g���b�N�̒�R��̃y�[�W�ɂ��ڏq���Ă���̂ŁA�����̂�����͌䗗����������
���B
�@�������A�����ԋZ�p�v����2011�N9�����̓��e��q�������Ƃ���A�吹�����́A��^�g���b�N�̕������ׂɂ�����m�n��
�팸�ƔR����P���Ɏ����ł����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p�̑��݂������m�łȂ��悤�ł�
��B���̂��߁A�吹�����̋����q���܂߂��m�l�E�W�҂̕������̃z�[���y�[�W���䗗�ɂȂ�ꂽ�ꍇ�ɂ́A�C���x
�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p�̑��݂�吹�����Ɍ䏳�m�E��F������������悤�Ɍ�A�������������
�Ǝv���Ă���B�e�ɂ��p�ɂ��A�߂������A���{�̑����̃f�B�[�[���G���W���W�̊w�ҁE���Ƃ��A�����C���x�~�G���W
���i�������J2005-54771�j�̋Z�p�����p�����邽�߂̎��������������ɍs���悤�ɂȂ�A�킪���̑�^�g���b�N�́u�R
��팸�v�ƁuNO���팸�v�̃g���[�h�I�t��x�Ȃ��������邱�Ƃ�����Ă���Ƃ���ł���B
�팸�ƔR����P���Ɏ����ł����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p�̑��݂������m�łȂ��悤�ł�
��B���̂��߁A�吹�����̋����q���܂߂��m�l�E�W�҂̕������̃z�[���y�[�W���䗗�ɂȂ�ꂽ�ꍇ�ɂ́A�C���x
�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p�̑��݂�吹�����Ɍ䏳�m�E��F������������悤�Ɍ�A�������������
�Ǝv���Ă���B�e�ɂ��p�ɂ��A�߂������A���{�̑����̃f�B�[�[���G���W���W�̊w�ҁE���Ƃ��A�����C���x�~�G���W
���i�������J2005-54771�j�̋Z�p�����p�����邽�߂̎��������������ɍs���悤�ɂȂ�A�킪���̑�^�g���b�N�́u�R
��팸�v�ƁuNO���팸�v�̃g���[�h�I�t��x�Ȃ��������邱�Ƃ�����Ă���Ƃ���ł���B
���A�������A���̋Z�p�ł́u�f�B�[�[���G���W����NO���팸�ƔR����P�̃g���[�h�I�t�̍����v���s�\�Ƃ̌���������
��Ă���̂ł��낤���B���̏ꍇ�ɂ́A�吹�����̌䌩�������������������A�M�҂̍l�����Ɍ�肪����A������
�����ƁA�吹�����́u�f�B�[�[���G���W���ɂ�����m�n���팸�ƔR����P�̃g���[�h�I�t�́A�����̓���ۑ�v�Ƃ̎咣
�ɑ���ᔻ�ɂ��āA���l�т�\���グ�����ƍl���Ă���B���̂��߁A�吹�������C���x�~�G���W���i�������J
2005-54771�j�̋Z�p�̓��e�����Ɍ䏳�m�Ȃ�A���̋Z�p�ɂ��Ă̌䌩����Ƃ��������������������Ǝv����
����B
�@���āA2015�N�x�d�ʎԔR���̎����̔R���̃��[�h�R��̊������ł��邽�߂ɉ��Ƃ������Ȃ����A�C
���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p�́A2015�N�x�d�ʎԔR���ɑ������̔R���ɑ�^�g��
�b�N��K��������L�͂ȋZ�p�ł��邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��Ǝv���Ă���B�܂��A2016�N�Ɏ��{����鎟���̂m�n���K��
�����ɑ�^�g���b�N��K��������Z�p�Ƃ��ċC���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j���Z�p���̗p�����ꍇ
�ɂ́A����ɕt�����ĂT�`�P�O�����x�̎����s�R�������ł�����ʂ����������ƂɂȂ�B���̂��߁A���Y��^
�g���b�N�̏��i���̌���Ƃb�n�Q�팸�ɍv���ł��邱�ƂɂȂ�A��^�g���b�N���s�̂��郁�[�J�ɂ͑傫�ȗ��v�������炷
���̂ƐM���Ă���B
���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p�́A2015�N�x�d�ʎԔR���ɑ������̔R���ɑ�^�g��
�b�N��K��������L�͂ȋZ�p�ł��邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��Ǝv���Ă���B�܂��A2016�N�Ɏ��{����鎟���̂m�n���K��
�����ɑ�^�g���b�N��K��������Z�p�Ƃ��ċC���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j���Z�p���̗p�����ꍇ
�ɂ́A����ɕt�����ĂT�`�P�O�����x�̎����s�R�������ł�����ʂ����������ƂɂȂ�B���̂��߁A���Y��^
�g���b�N�̏��i���̌���Ƃb�n�Q�팸�ɍv���ł��邱�ƂɂȂ�A��^�g���b�N���s�̂��郁�[�J�ɂ͑傫�ȗ��v�������炷
���̂ƐM���Ă���B
�@�܂��A�m�n���K���ɂ��ẮA���Ȃ̒������R�c��́A2005�N4���̑攪�����\���@0.7 g/kWh�� 1/3���x�i���@
0.23�@g/kWh�j�̂m�n���̒���ڕW��������Ă���̂ł���B�������A2010�N�ɗ\�肳��Ă����\�����\�ł́A������
��ڕW��啝�Ɋɘa���ꂽ�m�n���̎����K���l��0.4 g/kWh(2016�N�̎��{�\��j�������悤���B���̗��R�́A��
�݂̎����ԋƊE�ɂ͒���ڕW��B���ł���Z�p���J���ł��Ă��Ȃ����������R�c����f���ꂽ���߂ł��낤�B��
�����A���Ȃ͉��ꂩ�̑��������ɒ���ڕW�̂m�n���K�����{�s���ׂ��Ƃ̕��j�ɂ͕ς��Ȃ��ƍl������B����
���Ȃ̒������R�c���2005�N4���̑攪�����\�Ɏ����ꂽ 0.7 g/kWh�� 1/3���x�i�� 0.23 g/kWh�j�̂m
�n������ڕW�𑁊��ɂm�n���K���l�Ƃ��Ď{�s�ł���悤�ɂ��邽�߂ɂ��A���Ȃ͑��}�Ɋe�g���b�N���[�J�⌤
���@�ւ��w�����A�i�d�O�T���[�h�r�o�K�X�����ɂ���Q�^�[�{�ߋ��@�����̋C���x�~�G���W���i�������J2005-
54771�j�ɂ������A�f�r�b�q�G�}�ł̏\���Ȃm�n���팸�������ł��邱�Ƃ��m�F���ׂ��ł͂Ȃ����낤���B
0.23�@g/kWh�j�̂m�n���̒���ڕW��������Ă���̂ł���B�������A2010�N�ɗ\�肳��Ă����\�����\�ł́A������
��ڕW��啝�Ɋɘa���ꂽ�m�n���̎����K���l��0.4 g/kWh(2016�N�̎��{�\��j�������悤���B���̗��R�́A��
�݂̎����ԋƊE�ɂ͒���ڕW��B���ł���Z�p���J���ł��Ă��Ȃ����������R�c����f���ꂽ���߂ł��낤�B��
�����A���Ȃ͉��ꂩ�̑��������ɒ���ڕW�̂m�n���K�����{�s���ׂ��Ƃ̕��j�ɂ͕ς��Ȃ��ƍl������B����
���Ȃ̒������R�c���2005�N4���̑攪�����\�Ɏ����ꂽ 0.7 g/kWh�� 1/3���x�i�� 0.23 g/kWh�j�̂m
�n������ڕW�𑁊��ɂm�n���K���l�Ƃ��Ď{�s�ł���悤�ɂ��邽�߂ɂ��A���Ȃ͑��}�Ɋe�g���b�N���[�J�⌤
���@�ւ��w�����A�i�d�O�T���[�h�r�o�K�X�����ɂ���Q�^�[�{�ߋ��@�����̋C���x�~�G���W���i�������J2005-
54771�j�ɂ������A�f�r�b�q�G�}�ł̏\���Ȃm�n���팸�������ł��邱�Ƃ��m�F���ׂ��ł͂Ȃ����낤���B
�V�D�C���x�~�ɂ���đ�^�g���b�N���K���\�ƂȂ鏫���̔R��K���Ƃm�n���K���̃��x��
�@�������R�c��̓��\���ɂ��āA�f�B�[�[���d�ʎԂɂ��Ă�NO���K�������Ɋւ���ŋ߂̓������ȉ��̕\A
�ɂ܂Ƃ߂��B
�ɂ܂Ƃ߂��B
| |
|||
| |
�� �f�B�[�[���d�ʎԁi12�g�������̐V�^�ԁj�ɂ����āA�u�攪�����\�̋��e���x
�ڕW�l�i���ϒl�j�� 0.7 ��/��W���v�i���z�b�g�X�^�[�g��JE05���[�h�����j��
2009�N�Ɏ��{
�i���F�č��̃f�B�[�[���d�ʎԂ́A�u2010�N��NO���K���l��0.27��/kW���i���z�b�g�X�^�[�g�{�R�[���h �X�^�[�g��1199���[�h�j�����{�j �� �u���\�̈Ӌ`�v�Ƃ��āA�u�����2009�N�ڕW��0.7��/kW�������{���邱�Ƃɂ� ��A2009�`2010�N���_�ł͑�^�f�B�[�[���g���b�N�̕���Ő��E�ō����x ���@��NO���K�������{�Ŏ��{�����v�ƋL�ڂ���Ă��邪�A����͌��ł���B �i2009�`2010�N���̃f�B�[�[���d�ʎԂɂ����ẮA���{�͕č��̔�r�����đ啝 �Ɋɂ��K�������{�j �� ���́u�攪�����\�v�ɂ́A�����̃f�B�[�[���d�ʎԂ�NO���K�������Ƃ��āA�� ��ڕW�i��0.7��/kW����1/3 ��0.23��/kW���j��� |
||
| |
�� �f�B�[�[���d�ʎԁi7.5�g�������̐V�^�ԁj���u��\�����\�̋��e���x�ڕW�l
�i���ϒl�j�� 0.4 ��/��W���v�i���z�b�g�X�^�[�g�{�R�[���h�X�^�[��WHTC���[�h
�����j��2016�N�Ɏ��{
�i���F�č��̃f�B�[�[���d�ʎԂ́A�u2010�N��NO���K���l��0.27��/kW���i���z�b�g�X�^�[�g�{�R�[���h �X�^�[�g��1199���[�h�j�����{�j �� �u��\�����\�̋��e���x�ڕW�l�i���ϒl�j�� 0.4 ��/��W���iWHTC���[�h�j�v �́A�攪�����\�̒���ڕW��0.23��/kW���i��0.7��/kW����1/3�FJE05���[�h�j �Ɂu�B���Ă���ƍl������v�ƋL������Ă���B���̂��Ƃ���A�䂪���̏����I �ȃf�B�[�[���d�ʎԂ�NO���K�������́A�攪�����\�̒���ڕW��0.23��/kW�� �iJE05���[�h)�̃��x���ɂ���K�v�̂��邱�Ƃ𒆉����R�c��\���ɏ��m�E�� �����Ă��邱�Ƃ������������̂ƍl������B �����āA�f�B�[�[���d�ʎԂ�NO���K���������m���ɑ攪�����\�̒���ڕW��0. 23��/kW���iJE05���[�h)�̃��x���Ƃ��邽�߁A��\�����\�ɓY�t�̑�\���� �́A�iJE�O�T���[�h��NO���F0.4 ��/��W���j���iWHTC���[�h��NO���F0.26 ��/kW���j������ �āA�u�\���ȃf�[�^���łȂ����߁A�����܂ł��ڈ��Ƃ��ĂƂ炦��ׂ����́v�Ƃ� �������L����Ă���B �܂�A�u��\�����\�̋��e���x�ڕW�l�i���ϒl�j�� 0.4 ��/��W���Ƒ攪�����\�� ����ڕW��0.23��/kW���Ɠ����ł��邱�Ƃ��\���Ȏ����f�[�^�ɂ���Ċm�F����� ���Ȃ����߁A����̎������ʂɂ���Ċm�肷�ׂ����Ǝ�������A���������L�ڂ� ��Ă��邱�ƂɂȂ�B |
||
| �u�����d�ʎԗp�����T�C�N ���̔r�o�K�X���\�]���v 2014�v�Ŕ��\ |
�� JE�O�T���[�h���G���W���́A���E�ᕉ�ׂ̗̈�Ɍ��肵���^�]�i���}�́Z�̗�
��j�ł��邪�A WHTC���[�h���G���W���́A���E�ᕉ�ׁ{�����ׂ̑S�̈�ʼn^�]
�i���}�́Z�{�Z�̗̈�j�ł���B
�� �R��̋����G���W���̒���C�G���W���́A�G���W���̍����ׂ̗̈�i��JE�O�T�A WHTC�A�vHSC�̃G���W���^�]�́Z�̕��ח̈�j�ł́A�A�f���̋������~�܂� �͍팸���A�A�fSCR�G�}��NO���̊Ҍ��ɂ��r�C�K�X�@�\���Ӑ}�I�ɒ��~ �܂��͒ቺ������u�r�o�K�X����̖������v�̐�����̗p���Ă���E�@�E��@�ȃG ���W���Ɛ��������B �� ���}�́A�u�r�o�K�X����̖������v��C�G���W���Ɏ����f�[�^���폜����JE�O�T ���[�h�AWHTC���[�h�AWHSC���[�h��NO���r�o�l�ł���B
�� �d�ʎԗp�����T�C�N����WHTC���[�h�i���R�[���h�X�^�[�g�{�z�b�g�X�^�[�g�j��
JE�O�T���[�h�i���z�b�g�X�^�[�g�j��NO���r�o�l�́A�قړ���ł��邱�Ƃ����炩��
����B���������āA���{�̃f�B�[�[���d�ʎԂ�NO���K���́A�߂������ɂ́A�攪
�����\��NO������ڕW�Ɠ�����NO����0.23 ��/kW���i��WHTC���[�h�j�̃��x����
�������ׂ����Ƃ͖��炩�ł���B
�������R�c��E��\�����\�Ɏ����ꂽ�u�f�B�[�[���d�ʎԂɂ�����NO�����e�� �x�ڕW�l�F0.4 ��/��W���i��WHTC���[�h�j�́A�攪�����\��NO������ڕW�F0.23��/ kW���i��JE�O�T���[�h�j�Ɠ����̃��x���ł���v�Ƃ̓��\�̓��e�́A���S�Ɍ��ł� ��Ɛ��@�����B �� �Ȃ��A�������R�c��E��\�����\�Ɏ����ꂽ�u�f�B�[�[���d�ʎԂɂ����� NO�����e���x�ڕW�l�F0.4 ��/��W���i��WHTC���[�h�j�́A�攪�����\��NO������� �W�F0.23 ��/kW���i��JE�O�T���[�h�j�Ɠ����̃��x���ł���v�Ƃ̓��\�ɂ��āA�u�T�� �Ó��Ȑ����Ƃ�����v�Ƃ���i�Ɓj��ʈ��S���������̗�؉��ꎁ�̎咣�́A �G���W���̍����ׂ̗̈�ł̔A�fSCR�G�}��NO���팸���\���ɋ@�\���Ȃ��悤 �ɐ��䂵���u�r�o�K�X����̖������v���̗p������@�E�E�@�����C�G���W���ɂ� ����WHTC���[�h�ł̍���NO���r�o�l�������̂ƂȂ��Ă���͖̂��炩�ł���B �u�r�o�K�X����̖������v���̗p������@�E�E�@�����C�G���W����NO���r�o�l�� ����NO�����e���x�ڕW�l�F0.4 ��/��W���i��WHTC���[�h�j�́A�攪�����\��NO ������ڕW�F0.23 ��/kW���i��JE�O�T���[�h�j�Ɠ����̃��x���ł���v���Ǝ������Ƃ� �i�Ɓj��ʈ��S���������̗�؉��ꎁ�̘_�����\�́A�f�B�[�[���d�ʎԂ� 2016�NNO����0.4 ��/��W�����s����NO���K���̊ɘa�ł��邱�Ƃ��B�����邽�߂� �Ƒ��ȍs�ׂƍl������B |
�O�q�̒ʂ�A�m�n���K���ɂ��ẮA���Ȃ̒������R�c��́A2005�N4���̑攪�����\�ɂ́A�f�B�[�[���d�ʎ�
�ɂ��āA0.7 g/kWh�� 1/3���x�i���@0.23�@g/kWh�j�̂m�n���̒���ڕW��������Ă���B���������āA�|�X�g�r�o�K�X�K
���ɑ���2009�N�ɂm�n���K�������́A���R�A���̂m�n��������ڕW�ł���@0.23�@g/kWh�ɂȂ�Ƒ����̐l���\�z���Ă�
���B�������A�������R�c��̑�\�����\�i2010�N7��28���Ɋ��Ȃɓ��\�j�ł́A2016�N�Ƀf�B�[�[���d�ʎԁi7.5�g
�������̐V�^�ԁj�́u��\�����\�̋��e���x�ڕW�l�i���ϒl�j�� 0.4 ��/��W���v�i���z�b�g�X�^�[�g�{�R�[���h�X�^�[��
WHTC���[�h�����j�̎��{�����\���ꂽ�B�������Ȃ���A�f�B�[�[���d�ʎ�2016�NNOx�K����0.4g/kWh�́A�s���Ȋɘa
�̌��K���ɏڏq���Ă���悤�ɁA���{�̃f�B�[�[���d�ʎԂ�NO���K���́A�߂������ɂ́A�攪�����\��NO�������
�W�Ɠ�����NO����0.23 ��/kW���i��WHTC���[�h�j�̃��x���ɋ������ׂ����Ƃ͖��炩�ł���B
�ɂ��āA0.7 g/kWh�� 1/3���x�i���@0.23�@g/kWh�j�̂m�n���̒���ڕW��������Ă���B���������āA�|�X�g�r�o�K�X�K
���ɑ���2009�N�ɂm�n���K�������́A���R�A���̂m�n��������ڕW�ł���@0.23�@g/kWh�ɂȂ�Ƒ����̐l���\�z���Ă�
���B�������A�������R�c��̑�\�����\�i2010�N7��28���Ɋ��Ȃɓ��\�j�ł́A2016�N�Ƀf�B�[�[���d�ʎԁi7.5�g
�������̐V�^�ԁj�́u��\�����\�̋��e���x�ڕW�l�i���ϒl�j�� 0.4 ��/��W���v�i���z�b�g�X�^�[�g�{�R�[���h�X�^�[��
WHTC���[�h�����j�̎��{�����\���ꂽ�B�������Ȃ���A�f�B�[�[���d�ʎ�2016�NNOx�K����0.4g/kWh�́A�s���Ȋɘa
�̌��K���ɏڏq���Ă���悤�ɁA���{�̃f�B�[�[���d�ʎԂ�NO���K���́A�߂������ɂ́A�攪�����\��NO�������
�W�Ɠ�����NO����0.23 ��/kW���i��WHTC���[�h�j�̃��x���ɋ������ׂ����Ƃ͖��炩�ł���B
�@����A��^�g���b�N�̂m�n�����팸����Z�p�Ƃ��āA�M�҂̃z�[���y�[�W�ł́A�S�N�O�����C���x�~�G���W���i�������J
2005-54771�j��M�S�ɒ�Ă��Ă����̂ł���B���̋C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p���̗p����A�i
�d�O�T���[�h�r�o�K�X�����ɂ����ăG���W���ł̉^�]�p�x�̍����A�N�Z���y�_�������ݗ�Accel���T�O���ߖT�₻���
���̃G���W���^�]�̈�ł́A�A�f�r�b�q�G�}�̊������ɂ��啝�Ȃm�n���팸���\�ɂ���@�\�����邽�߁A�i�d�O�T��
�[�h�r�o�K�X�����ł� 0.23�@g/kWh�̂m�n�����x���́A�]�T�œK���ł��锤�ł������B�ܘ_�A2016�N�Ɏ��{�\��̎���
�m�n���K���ɍ̗p�����V�������E���ꎎ���T�C�N���ł���WHTC�iWorld Harmonized Transient Cycle�j�ɕύX�����
���A�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p���̗p����A2005�N4���̑攪�����\�� 0.7 g/kWh�� 1/3��
�x�i���@0.23�@g/kWh�j�̂m�n���̍팸�ڕW���B���ł��邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��ƍl���Ă���B
2005-54771�j��M�S�ɒ�Ă��Ă����̂ł���B���̋C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p���̗p����A�i
�d�O�T���[�h�r�o�K�X�����ɂ����ăG���W���ł̉^�]�p�x�̍����A�N�Z���y�_�������ݗ�Accel���T�O���ߖT�₻���
���̃G���W���^�]�̈�ł́A�A�f�r�b�q�G�}�̊������ɂ��啝�Ȃm�n���팸���\�ɂ���@�\�����邽�߁A�i�d�O�T��
�[�h�r�o�K�X�����ł� 0.23�@g/kWh�̂m�n�����x���́A�]�T�œK���ł��锤�ł������B�ܘ_�A2016�N�Ɏ��{�\��̎���
�m�n���K���ɍ̗p�����V�������E���ꎎ���T�C�N���ł���WHTC�iWorld Harmonized Transient Cycle�j�ɕύX�����
���A�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p���̗p����A2005�N4���̑攪�����\�� 0.7 g/kWh�� 1/3��
�x�i���@0.23�@g/kWh�j�̂m�n���̍팸�ڕW���B���ł��邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��ƍl���Ă���B
��B
�@�܂��A��^�g���b�N���C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p���̗p����A�s�s�����s���[�h�i�i�d�O�T���[
�h�j�Ɠs�s�ԑ��s���[�h�i�c�f���z�t�W�O�����^���葬���[�h�j�̗����[�h�̔R��]���̃G���W���ɔ�ׂđ啝�ɉ��P
�ł��邽�߁A�d�ʎԃ��[�h�R��]���̃G���W���̏ꍇ�ɔ�ׂĂT�`�P�O�����팸�ł����@�\������B���������āA��
�^�g���b�N�ɋC���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j���̗p���邱�Ƃɂ���ẮA�d�ʎԃ��[�h�R����T�������P�͂�
��قǂ̒����J�����Ԃ�݂��Ȃ��Ă��e�ՂɎ����ł���̂ł���B
�h�j�Ɠs�s�ԑ��s���[�h�i�c�f���z�t�W�O�����^���葬���[�h�j�̗����[�h�̔R��]���̃G���W���ɔ�ׂđ啝�ɉ��P
�ł��邽�߁A�d�ʎԃ��[�h�R��]���̃G���W���̏ꍇ�ɔ�ׂĂT�`�P�O�����팸�ł����@�\������B���������āA��
�^�g���b�N�ɋC���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j���̗p���邱�Ƃɂ���ẮA�d�ʎԃ��[�h�R����T�������P�͂�
��قǂ̒����J�����Ԃ�݂��Ȃ��Ă��e�ՂɎ����ł���̂ł���B
�@���������āA2016�N�Ɏ��{���\�肳��Ă���uNO���K���l�� 0.4 g/kWh�iWHTC���[�h�j��NO���K�������v�Ƃ͕ʂɁA��
�������ɂ������A������^�g���b�N�Ɂu�m�n��� �� 0.23�@g/kWh�iWHTC���[�h�j�v�Ɓu2015�N�x�d�ʎԔR���́{�P
�O �����x������v�����߂��\�P�O�̐V���ȁu��NO���E��R��g���b�N�E�o�X�̊�i�āj�v�̎{��𐭕{�i���Ȃ����y��
�ʏȁj�����{�����ꍇ�ɂ́A���̒�NO���E��R��̊�ɑ�^�g���b�N��K�������邽�߂ɂ́A�e�g���b�N���[�J����^
�g���b�N�̔R����P��NO���팸�ɗL�����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̌����J�������{���A���̋Z�p����
�p������^�g���b�N�𑁋}�Ɏ��p�����邱�Ƃ��K�v�ł���B����ɂ���āA�킪���̑�^�g���b�N����ɂ�����uNO����
�팸�v�A�uCO�Q�̍팸�v����сu�ȃG�l���M�[���v������I�ɐi�W����ƍl������B���̂��Ƃ́A�ȃG�l���M�[��CO2
�팸�����߂鍑���̊肢���������邱�Ƃ��ł���Ƌ��ɁA�g���b�N���[�U�ɂƂ��ẮA����͔R����P���ꂽ��^�g��
�b�N���w�����邱�Ƃɂ���āA�^�s�R��̉��P�������ł��邱�ƂɂȂ�B���������āA����A���{�i���Ȃ����y���
�ȁj���������\�S�̐V���ȁu��NO���E��R��g���b�N�E�o�X�̊�i�āj�v�𐭕{���{�s�����ꍇ�ɂ́A���{�������̂���
�̎d���𗧔h�ɉʂ����Ă���Ƃ��āA�����S�̂���A�傢�Ɋ��ӂ���A�̎^����邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��B���̕\�P�O�Ɏ���
���V���ȁu��NO���E��R��g���b�N�E�o�X�̊�i�āj�v�ɂ��ẮA���{�͑�^�g���b�N�̐V���Ȓ�R��E��r�o�K�X�
�𑁊��ɐݒ肹��I�ɏڏq���Ă���̂ŁA�����̂�����́A����Ƃ��䗗�������������B
�������ɂ������A������^�g���b�N�Ɂu�m�n��� �� 0.23�@g/kWh�iWHTC���[�h�j�v�Ɓu2015�N�x�d�ʎԔR���́{�P
�O �����x������v�����߂��\�P�O�̐V���ȁu��NO���E��R��g���b�N�E�o�X�̊�i�āj�v�̎{��𐭕{�i���Ȃ����y��
�ʏȁj�����{�����ꍇ�ɂ́A���̒�NO���E��R��̊�ɑ�^�g���b�N��K�������邽�߂ɂ́A�e�g���b�N���[�J����^
�g���b�N�̔R����P��NO���팸�ɗL�����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̌����J�������{���A���̋Z�p����
�p������^�g���b�N�𑁋}�Ɏ��p�����邱�Ƃ��K�v�ł���B����ɂ���āA�킪���̑�^�g���b�N����ɂ�����uNO����
�팸�v�A�uCO�Q�̍팸�v����сu�ȃG�l���M�[���v������I�ɐi�W����ƍl������B���̂��Ƃ́A�ȃG�l���M�[��CO2
�팸�����߂鍑���̊肢���������邱�Ƃ��ł���Ƌ��ɁA�g���b�N���[�U�ɂƂ��ẮA����͔R����P���ꂽ��^�g��
�b�N���w�����邱�Ƃɂ���āA�^�s�R��̉��P�������ł��邱�ƂɂȂ�B���������āA����A���{�i���Ȃ����y���
�ȁj���������\�S�̐V���ȁu��NO���E��R��g���b�N�E�o�X�̊�i�āj�v�𐭕{���{�s�����ꍇ�ɂ́A���{�������̂���
�̎d���𗧔h�ɉʂ����Ă���Ƃ��āA�����S�̂���A�傢�Ɋ��ӂ���A�̎^����邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��B���̕\�P�O�Ɏ���
���V���ȁu��NO���E��R��g���b�N�E�o�X�̊�i�āj�v�ɂ��ẮA���{�͑�^�g���b�N�̐V���Ȓ�R��E��r�o�K�X�
�𑁊��ɐݒ肹��I�ɏڏq���Ă���̂ŁA�����̂�����́A����Ƃ��䗗�������������B
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
�@�]�k�ł͂��邪�A���Ȃ́A�������R�c���2005�N4���̑攪�����\�Ɏ����ꂽ 0.7 g/kWh�� 1/3���x�i�� 0.23
g/kWh�j�̂m�n������ڕW�𑁊��ɂm�n���K���l�Ƃ��Ď{�s���邱�Ƃɂ��āA����ƍN�́u���ʂȂ���܂ő҂Ƃ��z�g
�g�M�X�v�̂悤�ɁA�e�g���b�N���[�J���C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�ɂ������A�f�r�b�q�G�}�ł̕K�v�E�\��
�Ȃm�n���̍팸���ł��邱�Ƃ�����I�Ɋm�F�ł��鎞���܂ŋC���ɑ҂��j�ł���A�m�n������ڕW���m�n���K���l��
�ł��鎞���͗y�������ɒx��邱�ƂɂȂ�Ǝv����B����ɑ��A�L�b�G�g�́u�����ʂȂ�����Ă݂��悤�z�g�g�M
�X�v�̂悤�ɁA���Ȃ��e�g���b�N���[�J�ɑ��A�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�ɂ������A�f�r�b�q�G�}�ł�
�K�v�E�\���Ȃm�n���̍팸���ł��邱�Ƃ����I�Ɋm�F�����邱�Ƃ��s���A0.7 g/kWh�� 1/3���x�i�� 0.23 g/kWh�j
�̂m�n������ڕW���m�n���K���l�ɂ��邱�Ƃɂ��ẮA�g���b�N���[�J���܂ގ����ԋƊE�͕\�����������ł��Ȃ�����
�ɂȂ�B���̌��ʁA���������ɂm�n������ڕW���m�n���K���l�Ƃ��Ď{�s�ł��邾�낤�B����ɂ���āA�킪���̍X�Ȃ��
�C���̉��P��傫�����i���ł�����̎v���Ă���B
g/kWh�j�̂m�n������ڕW�𑁊��ɂm�n���K���l�Ƃ��Ď{�s���邱�Ƃɂ��āA����ƍN�́u���ʂȂ���܂ő҂Ƃ��z�g
�g�M�X�v�̂悤�ɁA�e�g���b�N���[�J���C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�ɂ������A�f�r�b�q�G�}�ł̕K�v�E�\��
�Ȃm�n���̍팸���ł��邱�Ƃ�����I�Ɋm�F�ł��鎞���܂ŋC���ɑ҂��j�ł���A�m�n������ڕW���m�n���K���l��
�ł��鎞���͗y�������ɒx��邱�ƂɂȂ�Ǝv����B����ɑ��A�L�b�G�g�́u�����ʂȂ�����Ă݂��悤�z�g�g�M
�X�v�̂悤�ɁA���Ȃ��e�g���b�N���[�J�ɑ��A�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�ɂ������A�f�r�b�q�G�}�ł�
�K�v�E�\���Ȃm�n���̍팸���ł��邱�Ƃ����I�Ɋm�F�����邱�Ƃ��s���A0.7 g/kWh�� 1/3���x�i�� 0.23 g/kWh�j
�̂m�n������ڕW���m�n���K���l�ɂ��邱�Ƃɂ��ẮA�g���b�N���[�J���܂ގ����ԋƊE�͕\�����������ł��Ȃ�����
�ɂȂ�B���̌��ʁA���������ɂm�n������ڕW���m�n���K���l�Ƃ��Ď{�s�ł��邾�낤�B����ɂ���āA�킪���̍X�Ȃ��
�C���̉��P��傫�����i���ł�����̎v���Ă���B
�@�Ƃ��낪�A���݂̓��{�̏́A�����_�ŏ\���Ȃm�n���팸�ƔR��팸�̋Z�p���J���ł��Ă��Ȃ��g���b�N���[�J�̋Z
�p�͂̕s���ɑ��A���Ȃ⍑�y��ʏȂ�����I�ȏ��u���u���Ă���悤�ł���B�������A���̂悤�Ȋ��Ȃ⍑�y��
�ʏȂ̃g���b�N���[�J�ɗD�����m�n�� �� 0.4 g/kWh��2016�N�̊ɂ��K���́A�g���b�N���[�J�̂m�n���ƔR����팸����Z�p
�J���̎��g�݂ɑӖ��������錴���Ɍq���茓�˂Ȃ��̂ł͂Ȃ����낤���B����ɂ���āA�g���b�N�ƊE�ɂ�����m
�n���팸����тb�n�Q�ƔR��팸�̋Z�p�J����x�点�A�����I�ɂ͓��{�̃g���b�N�Y�Ƃ̋Z�p�J���̐��ނ̌����ƂȂ�
�\�����ے�ł��Ȃ��B���������āA�g���b�N���[�J�ɑ�����Ȃ⍑�y��ʏȂ̍���̂悤�ȉ���̏��u�́A�K��
�������{�̎Y�Ɣ��W�ɍv�������ƂɂȂ�Ȃ����Ƃ��̂ɖ�����ׂ��ł͂Ȃ����낤���B���������āA�����̓��{�̔��W
���l����Ȃ�A���Ȃ⍑�y��ʏȂ͍����I�Ȕ͈͂ł̂m�n���ƔR��̌������K����ݒ肷�ׂ��ł͂Ȃ����ƍl��
����B
�p�͂̕s���ɑ��A���Ȃ⍑�y��ʏȂ�����I�ȏ��u���u���Ă���悤�ł���B�������A���̂悤�Ȋ��Ȃ⍑�y��
�ʏȂ̃g���b�N���[�J�ɗD�����m�n�� �� 0.4 g/kWh��2016�N�̊ɂ��K���́A�g���b�N���[�J�̂m�n���ƔR����팸����Z�p
�J���̎��g�݂ɑӖ��������錴���Ɍq���茓�˂Ȃ��̂ł͂Ȃ����낤���B����ɂ���āA�g���b�N�ƊE�ɂ�����m
�n���팸����тb�n�Q�ƔR��팸�̋Z�p�J����x�点�A�����I�ɂ͓��{�̃g���b�N�Y�Ƃ̋Z�p�J���̐��ނ̌����ƂȂ�
�\�����ے�ł��Ȃ��B���������āA�g���b�N���[�J�ɑ�����Ȃ⍑�y��ʏȂ̍���̂悤�ȉ���̏��u�́A�K��
�������{�̎Y�Ɣ��W�ɍv�������ƂɂȂ�Ȃ����Ƃ��̂ɖ�����ׂ��ł͂Ȃ����낤���B���������āA�����̓��{�̔��W
���l����Ȃ�A���Ȃ⍑�y��ʏȂ͍����I�Ȕ͈͂ł̂m�n���ƔR��̌������K����ݒ肷�ׂ��ł͂Ȃ����ƍl��
����B
�@���̂悤�ȁA���Ȃ⍑�y��ʏȂ��m�n���ƔR��̊ɂ��K����ݒ肷�邱�Ƃ́A����Ƃ��e�g���b�N���[�J���{�P�O����
�x�̏d�ʎԃ��[�h�R��̉��P��0.23 g/kWh�܂ł��啝�Ȃm�n���팸�𗼕��������ł���ꋓ�������C���x�~�G���W��
�i�������J2005-54771�j�̋Z�p����Ȃɖ�����������\�����\���ɍl������B���̂悤�ȁA�C���x�~�G���W���i��
�����J2005-54771�j�̋Z�p�J���̊J�n��摗��g���b�N���[�J�̍s�ׂ́A�䂪���ɂ������^�g���b�N����̂m�n���Ƃb
�n�Q�팸�ɂ���C���̉��P��Ȏ����E�ȃG�l���M�[�̐��i�Ɋւ��A�傫�Ȓx�����������̂ƍl������B
�x�̏d�ʎԃ��[�h�R��̉��P��0.23 g/kWh�܂ł��啝�Ȃm�n���팸�𗼕��������ł���ꋓ�������C���x�~�G���W��
�i�������J2005-54771�j�̋Z�p����Ȃɖ�����������\�����\���ɍl������B���̂悤�ȁA�C���x�~�G���W���i��
�����J2005-54771�j�̋Z�p�J���̊J�n��摗��g���b�N���[�J�̍s�ׂ́A�䂪���ɂ������^�g���b�N����̂m�n���Ƃb
�n�Q�팸�ɂ���C���̉��P��Ȏ����E�ȃG�l���M�[�̐��i�Ɋւ��A�傫�Ȓx�����������̂ƍl������B
�@����Ƃ��A�����̐��Ƃ�������g���b�N���[�J�ł́A���̋C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p�ɂ�����
�v���I�Ȍ��ׂ������o���Ď��p�s�̋Z�p�ƌ��Ă���̂ł��낤���B�����āA���̋Z�p��f�l�A�C�f�A�Ƃ��Ď�
�ċ����Ă���̂ł��낤���B���������A�M�҂��R�����G���W���m������������Ă��Ȃ��P�Ȃ�u���[�s�[�i�n���E�Ԕ����j�v
�ł��邽�߁A�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̒v���I�Ȍ��ׂ����o���Ă��Ȃ����߁A�Z�p�I�ɓڒ����Ȓ�
�Ă��s���Ă��邾���ł��낤���B
�v���I�Ȍ��ׂ������o���Ď��p�s�̋Z�p�ƌ��Ă���̂ł��낤���B�����āA���̋Z�p��f�l�A�C�f�A�Ƃ��Ď�
�ċ����Ă���̂ł��낤���B���������A�M�҂��R�����G���W���m������������Ă��Ȃ��P�Ȃ�u���[�s�[�i�n���E�Ԕ����j�v
�ł��邽�߁A�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̒v���I�Ȍ��ׂ����o���Ă��Ȃ����߁A�Z�p�I�ɓڒ����Ȓ�
�Ă��s���Ă��邾���ł��낤���B
�@����A����ɂ��ẮA�ŋ߁A�G���W���̃_�E���T�C�W���O���ɂ��R��팸�𐺍��ɐ�`����G���W�����Ƃ���
���B�������A�M�҂���Ă��Ă���Q�^�[�{�����̋C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�́A�A�N�Z�������ݗʂ�
50���ȉ��ł̋C���x�~�̉^�]�̈�ł́A���[�^�����O�����i�t���N�V���������j�͕ς��Ȃ����̂́A�r�C�����Ɨ�p
�����̍팸�ɉ����ăT�C�N�������̌��オ�ł��邽�߁A�啝�ȔR��팸���ł���G���W���_�E���T�C�W���O�ʼn^�]��
����Z�p�ł���B���̂悤�ȋZ�p�ł���ɂ�������炸�A�����̃g���b�N�p�G���W���̐��Ƃ���C���x�~�G���W���i��
�����J2005-54771�j���َE�����̂́A���Ƃ��s�v�c�Șb�ł���B
���B�������A�M�҂���Ă��Ă���Q�^�[�{�����̋C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�́A�A�N�Z�������ݗʂ�
50���ȉ��ł̋C���x�~�̉^�]�̈�ł́A���[�^�����O�����i�t���N�V���������j�͕ς��Ȃ����̂́A�r�C�����Ɨ�p
�����̍팸�ɉ����ăT�C�N�������̌��オ�ł��邽�߁A�啝�ȔR��팸���ł���G���W���_�E���T�C�W���O�ʼn^�]��
����Z�p�ł���B���̂悤�ȋZ�p�ł���ɂ�������炸�A�����̃g���b�N�p�G���W���̐��Ƃ���C���x�~�G���W���i��
�����J2005-54771�j���َE�����̂́A���Ƃ��s�v�c�Șb�ł���B
�@���݁A�C���x�~�V�X�e���́A�z���_���̐��Ђ̏�p�Ԃł͊��Ɏ��p������A�R��팸�ɑ傫�Ȍ��ʂ������Ă����
�̂��Ƃł���B�����āA�C���x�~�G���W���ɂ���^�g���b�N�̒�R���12-2���ɏڍׂɋL�ڂ����悤�ɁA�����ԃ��[
�J�[�ƕ��i��Ђ��o�����A�g���b�N���[�J�S��(����A�����U�A�t�c�A�O�H�ӂ���)���猤���҂��h������Ă��錤������
�g�D�ł��释�V�G�B�V�[�C�[�́A2004�N���C���x�~�G���W���ɂ�����R��ጸ�̌��ʂ̊m�F���ς܂��Ă���Ƃ̓`��
��������B�������A���V�G�B�V�[�C�[���C���x�~�̎����I����A�T�N�ȏ���o�߂��Ă���ɂ�������炸�A��������
�\����Ă��Ȃ��̂��B���̂��߁A�������ꂽ�C���x�~�̃V�X�e�����u�V���O���^�[�{�����v���A�Ⴕ���́u�Q�^�[�{�ߋ��@
�����i�������J2005-54771�j�v�̉��ꂩ�͕s�����B�������ʂ̔��\�̗L���ɂ�����炸�A���V�G�B�V�[�C�[�ɂ��C��
�x�~�G���W���ł̔R��ጸ�̌��ʂ����Ɋm�F����Ă���Ƃ̏����l����ƁA�M�҂���Ă��Ă���C���x�~�G���W��
�i�������J2005-54771�j�ɂ́A�v���I�Ȍ��ׂ͉��������ƍl���ėǂ��̂ł͂Ȃ����낤���B
�̂��Ƃł���B�����āA�C���x�~�G���W���ɂ���^�g���b�N�̒�R���12-2���ɏڍׂɋL�ڂ����悤�ɁA�����ԃ��[
�J�[�ƕ��i��Ђ��o�����A�g���b�N���[�J�S��(����A�����U�A�t�c�A�O�H�ӂ���)���猤���҂��h������Ă��錤������
�g�D�ł��释�V�G�B�V�[�C�[�́A2004�N���C���x�~�G���W���ɂ�����R��ጸ�̌��ʂ̊m�F���ς܂��Ă���Ƃ̓`��
��������B�������A���V�G�B�V�[�C�[���C���x�~�̎����I����A�T�N�ȏ���o�߂��Ă���ɂ�������炸�A��������
�\����Ă��Ȃ��̂��B���̂��߁A�������ꂽ�C���x�~�̃V�X�e�����u�V���O���^�[�{�����v���A�Ⴕ���́u�Q�^�[�{�ߋ��@
�����i�������J2005-54771�j�v�̉��ꂩ�͕s�����B�������ʂ̔��\�̗L���ɂ�����炸�A���V�G�B�V�[�C�[�ɂ��C��
�x�~�G���W���ł̔R��ጸ�̌��ʂ����Ɋm�F����Ă���Ƃ̏����l����ƁA�M�҂���Ă��Ă���C���x�~�G���W��
�i�������J2005-54771�j�ɂ́A�v���I�Ȍ��ׂ͉��������ƍl���ėǂ��̂ł͂Ȃ����낤���B
�W�D�R���NO���̍X�Ȃ�팸���ۑ�̑�^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W��
�W�|�P�DNEDO�́u�����x�R�Đ���G���W�V�X�e���̌����J���v�ł́A�R����̑厸�s
�@�f�B�[�[���G���W���̔R��팸�ɂ��ẮA�����ʂŌ��������{����Ă��邪�A�����A�ڂɌ��������ʂ�������
���Ȃ����Ƃ͎����ł���B�ŋ߁A���{���ꂽ�R���NO���팸�̌����Ƃ��ėL���ȃv���W�F�N�g�́A�}�P�O�Ɏ������V�G�l
���M�[�E�Y�ƋZ�p�����J���@�\�iNEDO)�̊v�V�I���������Q�ԑ����Z�p�J���i�N���[���f�B�[�[���v���W�F�N�g�A
2004�`2009�N�j�ł���A8��6��5�S���~�̗\�Z�Ŏ��{���ꂽ�u�����x�R�Đ���G���W�V�X�e���̌����J���v�̑�^�v��
�W�F�N�g�ł���B���̌����J���ł́A�R�i�ߋ��V�X�e����300MP���̒������R�����˂ɂ�鍂���ϗL�������A��
��уJ�����X�V�X�e����g�ݍ���ŁuPCI�R�āv(HCCI�R�ĂƂ��]���j�̗̈���g�債�A����ɂ���āANO����V
�����r�o�K�X�K���i�Q�O�O�T�N�K���j��1/3�ጸ���A�R�������10�����P����ڕW���f����ꂽ�B��
�_�A���̂悤�ȃG���W���d�l�́A�G���W���̃R�X�g������d�ʑ�����S���l�����Ȃ��ŏ����̎��p����������ł�
���Z�p�I�ȉ\����Njy���錤���J���ł��������߂ƍl������B�����āA���̌����J���ɂ͓������W���~�ȏ��
�c��ȗ\�Z����������Ă��Ă������Ƃ���A���̌����J�����J�n���ꂽ2004�N�����A�uPCI�R�āv�̐M�҂́A�f�B�[�[
����NO���팸�ƔR��팸�̉ۑ肪�ꋓ�ɉ����ł���Ɗ��҂���Ă������̂ƍl������B
���Ȃ����Ƃ͎����ł���B�ŋ߁A���{���ꂽ�R���NO���팸�̌����Ƃ��ėL���ȃv���W�F�N�g�́A�}�P�O�Ɏ������V�G�l
���M�[�E�Y�ƋZ�p�����J���@�\�iNEDO)�̊v�V�I���������Q�ԑ����Z�p�J���i�N���[���f�B�[�[���v���W�F�N�g�A
2004�`2009�N�j�ł���A8��6��5�S���~�̗\�Z�Ŏ��{���ꂽ�u�����x�R�Đ���G���W�V�X�e���̌����J���v�̑�^�v��
�W�F�N�g�ł���B���̌����J���ł́A�R�i�ߋ��V�X�e����300MP���̒������R�����˂ɂ�鍂���ϗL�������A��
��уJ�����X�V�X�e����g�ݍ���ŁuPCI�R�āv(HCCI�R�ĂƂ��]���j�̗̈���g�債�A����ɂ���āANO����V
�����r�o�K�X�K���i�Q�O�O�T�N�K���j��1/3�ጸ���A�R�������10�����P����ڕW���f����ꂽ�B��
�_�A���̂悤�ȃG���W���d�l�́A�G���W���̃R�X�g������d�ʑ�����S���l�����Ȃ��ŏ����̎��p����������ł�
���Z�p�I�ȉ\����Njy���錤���J���ł��������߂ƍl������B�����āA���̌����J���ɂ͓������W���~�ȏ��
�c��ȗ\�Z����������Ă��Ă������Ƃ���A���̌����J�����J�n���ꂽ2004�N�����A�uPCI�R�āv�̐M�҂́A�f�B�[�[
����NO���팸�ƔR��팸�̉ۑ肪�ꋓ�ɉ����ł���Ɗ��҂���Ă������̂ƍl������B
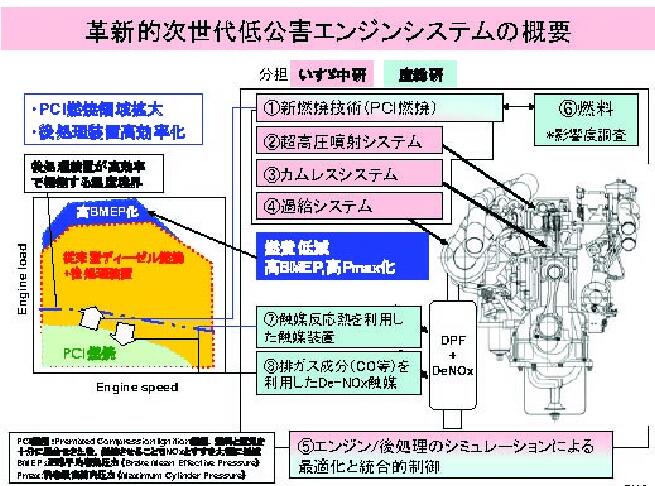
�@�@�Ƃ��낪�A�W���~�ȏ�̖c��ȗ\�Z�𒍂�����Ŗ蕨����Ŏ��{���ꂽ�u�����x�R�Đ���G���W�V�X�e���̌���
�J���v�̌����J���́A�̐S�̔R��팸�ɂ��Ă͎S�邽�錋�ʂŏI����Ă��܂����悤���B���̏؋��Ƃ��ẮA�����
�ł̑�����NEDO�̌����J���̗�ƈقȂ�A���̌����J���ł͓����̖ڕW�ƍŏI���ʂƂ̔R��팸���]��ɂ�������
�߂��Ă��邩��ł���B���̌����J���ł́A�P�O���̑啝�ȔR��팸�̖ڕW���f���Ȃ���A�ŏI���ʂł́A�������
�R��Q�����������Ă��܂����̂ł���B
�J���v�̌����J���́A�̐S�̔R��팸�ɂ��Ă͎S�邽�錋�ʂŏI����Ă��܂����悤���B���̏؋��Ƃ��ẮA�����
�ł̑�����NEDO�̌����J���̗�ƈقȂ�A���̌����J���ł͓����̖ڕW�ƍŏI���ʂƂ̔R��팸���]��ɂ�������
�߂��Ă��邩��ł���B���̌����J���ł́A�P�O���̑啝�ȔR��팸�̖ڕW���f���Ȃ���A�ŏI���ʂł́A�������
�R��Q�����������Ă��܂����̂ł���B
�@���̂悤�ɁA���̌����J���̎��ۂ̍ŏI���ʂ́A�ȉ��̐}�P�P�Ɏ������悤�ɁANOx�͖ڕW��B���������A��
�݂̏ȃG�l���M�[�E�Ȏ����E��CO2�̎���ɋ��߂��Ă���̐S�v�̔R��팸�͖ڕW��10���팸�ɂ͑S���y
���A2015�N�x�d�ʎԔR���ɑ��ĂQ���̈����ƂȂ��Ă��܂����̂ł���B���s�̑�^�g���b�N��2015�N�x
�d�ʎԔR���ɓK�����Ă��邱�Ƃ���A�u�����x�R�Đ���G���W�V�X�e���̌����J���v�ɂ�����2015�N�x�d�ʎԔR
���ɑ��ĂQ���̔R����́A���̌����J���������Ȃ܂ł̑厸�s�ɏI������Ɖ]����̂ł͂Ȃ����낤���B
�݂̏ȃG�l���M�[�E�Ȏ����E��CO2�̎���ɋ��߂��Ă���̐S�v�̔R��팸�͖ڕW��10���팸�ɂ͑S���y
���A2015�N�x�d�ʎԔR���ɑ��ĂQ���̈����ƂȂ��Ă��܂����̂ł���B���s�̑�^�g���b�N��2015�N�x
�d�ʎԔR���ɓK�����Ă��邱�Ƃ���A�u�����x�R�Đ���G���W�V�X�e���̌����J���v�ɂ�����2015�N�x�d�ʎԔR
���ɑ��ĂQ���̔R����́A���̌����J���������Ȃ܂ł̑厸�s�ɏI������Ɖ]����̂ł͂Ȃ����낤���B
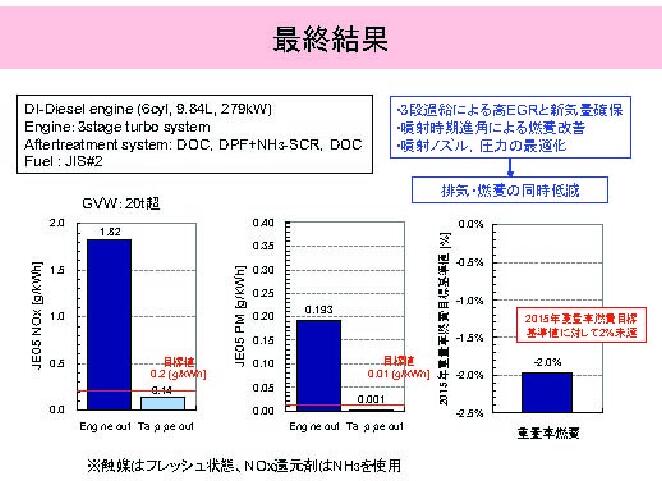
�@���́u�����x�R�Đ���G���W�V�X�e���̌����J���v�̌����J���ł́A�P�O���b�g���̃G���W���ŏ]���̂P�R���b�g���̃G
���W���̕W�����x���̏o�͂邽�߂ɕK�v�ƂȂ�z����C�ʂ��m�ۂ��邱�Ƃ͖ܘ_�ł��邪�A�X�ɍ�����C�ߏ�
���ł̉^�]���\�ɂ���PM�̍팸��NO���팸�̐�D�ł���PCI�R�āv�̉^�]�̈���g�傷�邽�߂ɂR�i�ߋ��V�X�e
�����̗p���ꂽ�悤���B���̂R�i�ߋ��V�X�e���ł́A���C�ʂ͑����ł��邪�A���������̎��͂�70���ȉ��ƌ�����
�^�[�{�ߋ��@���R����A�����ĉߋ�����ꍇ�ɂ́A�|���s���O������������͖��炩�ł���B���̂R�i�ߋ��V�X�e
���ł́A�]���̒P�i�̉ߋ��f�B�[�[���G���W�������R��������Ă��܂������ɂȂ邱�Ƃ́A�e�Ղɗ\�z�ł��邱�Ƃ�
����B�܂��A���̌����J���ł́A�����ł�PM�팸��}�邽�߂ƔR�ĉ��P�����҂��A300MP���̒������R�����˂��̗p
���ꂽ�ƍl������B
���W���̕W�����x���̏o�͂邽�߂ɕK�v�ƂȂ�z����C�ʂ��m�ۂ��邱�Ƃ͖ܘ_�ł��邪�A�X�ɍ�����C�ߏ�
���ł̉^�]���\�ɂ���PM�̍팸��NO���팸�̐�D�ł���PCI�R�āv�̉^�]�̈���g�傷�邽�߂ɂR�i�ߋ��V�X�e
�����̗p���ꂽ�悤���B���̂R�i�ߋ��V�X�e���ł́A���C�ʂ͑����ł��邪�A���������̎��͂�70���ȉ��ƌ�����
�^�[�{�ߋ��@���R����A�����ĉߋ�����ꍇ�ɂ́A�|���s���O������������͖��炩�ł���B���̂R�i�ߋ��V�X�e
���ł́A�]���̒P�i�̉ߋ��f�B�[�[���G���W�������R��������Ă��܂������ɂȂ邱�Ƃ́A�e�Ղɗ\�z�ł��邱�Ƃ�
����B�܂��A���̌����J���ł́A�����ł�PM�팸��}�邽�߂ƔR�ĉ��P�����҂��A300MP���̒������R�����˂��̗p
���ꂽ�ƍl������B
�@�������A�R���̍������˂ł́A���ˌn�̋쓮�����ɂ��R��������R�ĉ��P�ɂ��R��팸�����Ȃ��ꍇ�́A
�G���W���R��̈����̗v���ƂȂ邱�Ƃ́A�f�B�[�[���G���W���̊J���o���҂ł���ΒN�ł��n�m���Ă��邱�Ƃł���B��
�̂悤�ɁA�u�����x�R�Đ���G���W�V�X�e���̌����J���v�̌����J���́A�v��i�K�ɂ�����NO���̍팸��PM�̍팸��
�������邱�ƂɊ��҂��邱�Ƃɂ͉��̈٘_����������Ȃ��B�������A���̌����J���̔R��ɂ��ẮA�R��팸���s
�m��v���̔R�ĉ��P�Ɋ��҂��邾���ł���B����ɑ��A���������̎��͂�70���ȉ��H�ƌ�����^�[�{�ߋ��@���R
����A�������ꍇ�̃|���s���O�����̑�����A300MP���̒������R�����˂̋쓮�����̑����ɂ���ĔR���������
��������\���́A���̌����J���̌v��̏�������\�z����Ă����悤�Ɏv����̂ł���B���������āA�u�����x�R
�Đ���G���W�V�X�e���̌����J���v�̌����J���̓����ڕW�Ƃ��ĔR���10�����P����Ƃ������Ƃ́A�P�Ȃ�\�Z���l
�����邽�߂̌��O�����ł������悤�ɁA�M�҂ɂ͎v����̂��B
�G���W���R��̈����̗v���ƂȂ邱�Ƃ́A�f�B�[�[���G���W���̊J���o���҂ł���ΒN�ł��n�m���Ă��邱�Ƃł���B��
�̂悤�ɁA�u�����x�R�Đ���G���W�V�X�e���̌����J���v�̌����J���́A�v��i�K�ɂ�����NO���̍팸��PM�̍팸��
�������邱�ƂɊ��҂��邱�Ƃɂ͉��̈٘_����������Ȃ��B�������A���̌����J���̔R��ɂ��ẮA�R��팸���s
�m��v���̔R�ĉ��P�Ɋ��҂��邾���ł���B����ɑ��A���������̎��͂�70���ȉ��H�ƌ�����^�[�{�ߋ��@���R
����A�������ꍇ�̃|���s���O�����̑�����A300MP���̒������R�����˂̋쓮�����̑����ɂ���ĔR���������
��������\���́A���̌����J���̌v��̏�������\�z����Ă����悤�Ɏv����̂ł���B���������āA�u�����x�R
�Đ���G���W�V�X�e���̌����J���v�̌����J���̓����ڕW�Ƃ��ĔR���10�����P����Ƃ������Ƃ́A�P�Ȃ�\�Z���l
�����邽�߂̌��O�����ł������悤�ɁA�M�҂ɂ͎v����̂��B
�@
�@�����āA���̌����J���̎��ۂ̌��ʂ́A�}�P�T�Ɏ������悤�ɁANOx��PM�͍팸�ł������A�R���2015�N�x�d�ʎԔR
���Q���̈����ƂȂ��Ă��܂����Ƃ̂��Ƃł���B���̂悤�ȁA�u�����x�R�Đ���G���W�V�X�e���̌����J���v�ɂ�����
PCI�R�Ă��܂߂��R�ĉ��P�ł̔R��팸���s�����ɏI������������ƁA���̃f�B�[�[���R�Ẳ��P�ɂ���ĔR��
�팸���������邱�Ƃ́A�ɂ߂č���ł���ƁA�N�ł��ȒP�ɗ\�z�ł���̂ł͂Ȃ����낤���B�O�q�̂悤�ɁA�����ԋZ
�p��s�́u�����ԋZ�p�v��Vol.64�ANo.�P�A2010�i2010�N1���P�����s�j�̔ѓc�P�� �c���̑勳���@���R�����́u�f�B�[
�[���G���W�����̂P�O�N�v�ɂ̓f�B�[�[���G���W����CO�Q�팸�i���R��팸�j���u�傫�Ȓ���ۑ�v�ƒf�肵�A�R�ĉ��P
�ɂ��f�B�[�[���G���W���̔R��팸���u�Z�p�I�ɔ����ǂ���̏v�Ƃ̎�|���L�ڂ���Ă���̂́A����NEDO��
�u�����x�R�Đ���G���W�V�X�e���̌����J���v�i2004�`2009�N�j�ł̔R����̌������ʂ܂��Ă̋L�q�Ƃ��l����
���B
���Q���̈����ƂȂ��Ă��܂����Ƃ̂��Ƃł���B���̂悤�ȁA�u�����x�R�Đ���G���W�V�X�e���̌����J���v�ɂ�����
PCI�R�Ă��܂߂��R�ĉ��P�ł̔R��팸���s�����ɏI������������ƁA���̃f�B�[�[���R�Ẳ��P�ɂ���ĔR��
�팸���������邱�Ƃ́A�ɂ߂č���ł���ƁA�N�ł��ȒP�ɗ\�z�ł���̂ł͂Ȃ����낤���B�O�q�̂悤�ɁA�����ԋZ
�p��s�́u�����ԋZ�p�v��Vol.64�ANo.�P�A2010�i2010�N1���P�����s�j�̔ѓc�P�� �c���̑勳���@���R�����́u�f�B�[
�[���G���W�����̂P�O�N�v�ɂ̓f�B�[�[���G���W����CO�Q�팸�i���R��팸�j���u�傫�Ȓ���ۑ�v�ƒf�肵�A�R�ĉ��P
�ɂ��f�B�[�[���G���W���̔R��팸���u�Z�p�I�ɔ����ǂ���̏v�Ƃ̎�|���L�ڂ���Ă���̂́A����NEDO��
�u�����x�R�Đ���G���W�V�X�e���̌����J���v�i2004�`2009�N�j�ł̔R����̌������ʂ܂��Ă̋L�q�Ƃ��l����
���B
�W�|�Q�DPCI�i=HCCI)�R�Ă̗B��̓����E���ʂ́AJE05���[�h�ł̂P�����x�̔R����P
�@�ߔN�A�f�B�[�[���G���W���̕���ŐV�����o�ꂵ���uPCI �R��(Premixed. Compression Ignition combustion�R�āF�\��
�����k���ΔR�āj�́A�uHCCI �R��(Homogeneous-Charge Compression Ignitionnen�R�āF�\�������k���ΔR�āj�v�Ƃ�
�̂����A�v�V�I�ȔR�ĂƂ��Ă���܂Œ��ڂ��W�߂Ă����Z�p�ł���BPCI �i=HCCI) �R�ẮA10�N�ȏ���O���玩��
�ԃ��[�J�E�����@�ցE��w���Ő���Ɍ����J�������{����Ă����Z�p���B���N�O�Ɏ�ȂŌ����̃f�B�[�[���G���W��
�Z�p�҂���u���݂̃f�B�[�[���R�Č�����PCI �i=HCCI) �R�Ă��嗬�ł���A��̂Ƀf�B�[�[���G���W���̌����J����
�ނ����M�҂ɂ�PCI �i=HCCI) �R�Ă̊J���o�����������߂ɃG���W���Z�p���̍����i�i���ߋ��̐l�j�v�ƌ����A����
�̗�������������̂��B����PCI �i=HCCI) �R�ĂɊւ��鋻���[�������_�����A�i�Ёj�����ԋZ�p��́u�����ԋZ�p
Vol. 65�ANo. 3�A2011�v�Ɍf�ڂ́u�f�B�[�[���G���W���ɂ�����PCI�R�ēK�p���̃G���W������Z�p�v�i2011�N3���P����
�s�A���ҁF���R�^���A�c粌\�� [�O�H�ӂ����g���b�N�E�o�X��]�j���B
�����k���ΔR�āj�́A�uHCCI �R��(Homogeneous-Charge Compression Ignitionnen�R�āF�\�������k���ΔR�āj�v�Ƃ�
�̂����A�v�V�I�ȔR�ĂƂ��Ă���܂Œ��ڂ��W�߂Ă����Z�p�ł���BPCI �i=HCCI) �R�ẮA10�N�ȏ���O���玩��
�ԃ��[�J�E�����@�ցE��w���Ő���Ɍ����J�������{����Ă����Z�p���B���N�O�Ɏ�ȂŌ����̃f�B�[�[���G���W��
�Z�p�҂���u���݂̃f�B�[�[���R�Č�����PCI �i=HCCI) �R�Ă��嗬�ł���A��̂Ƀf�B�[�[���G���W���̌����J����
�ނ����M�҂ɂ�PCI �i=HCCI) �R�Ă̊J���o�����������߂ɃG���W���Z�p���̍����i�i���ߋ��̐l�j�v�ƌ����A����
�̗�������������̂��B����PCI �i=HCCI) �R�ĂɊւ��鋻���[�������_�����A�i�Ёj�����ԋZ�p��́u�����ԋZ�p
Vol. 65�ANo. 3�A2011�v�Ɍf�ڂ́u�f�B�[�[���G���W���ɂ�����PCI�R�ēK�p���̃G���W������Z�p�v�i2011�N3���P����
�s�A���ҁF���R�^���A�c粌\�� [�O�H�ӂ����g���b�N�E�o�X��]�j���B
�@���́u�����ԋZ�p�v���̎O�H�ӂ����̘_���ɂ́A�}�P�Q�Ɏ������u�R�����ˎ�����EGR���̒�������ʏ�R�Ă�JE�O
�T���[�h�̔R��v�Ɓu�ʏ�R�Ă�PCI �R�Ă�g������JE�O�T���[�h�̔R��v�̔�r�}������Ă����B���̐}�P�Q�ɂ��ƁA
NO���l�iJE�O�T���[�h�j�� 2.0 g/kWh �ł́A�ʏ�R�Ă�PCI �R�Ă̔R��͓����ł��邪�ANO���l�iJE�O�T���[�h�j�� 1.0 g/
kWh �ł́APCI �R�Ă̔R��͒ʏ�R�Ă����P���̍팸���ł���Ƃ̂��Ƃ��B����ɂ��āA�{�_���ł́uPCI �R�Ă�
�K�p�������ʁANO�����x���� 1.5 g/kWh �ȉ��̒�NO�����ł́A�P����R�����ꂽ�v�Ƃ��A�uPCI �R�Ă̓K�p�́ANO
�����x�����Ⴂ�ꍇ�ɂ͔R����P�̉\��������v�ƌւ炵���ɋL�ڂ���Ă���B
�T���[�h�̔R��v�Ɓu�ʏ�R�Ă�PCI �R�Ă�g������JE�O�T���[�h�̔R��v�̔�r�}������Ă����B���̐}�P�Q�ɂ��ƁA
NO���l�iJE�O�T���[�h�j�� 2.0 g/kWh �ł́A�ʏ�R�Ă�PCI �R�Ă̔R��͓����ł��邪�ANO���l�iJE�O�T���[�h�j�� 1.0 g/
kWh �ł́APCI �R�Ă̔R��͒ʏ�R�Ă����P���̍팸���ł���Ƃ̂��Ƃ��B����ɂ��āA�{�_���ł́uPCI �R�Ă�
�K�p�������ʁANO�����x���� 1.5 g/kWh �ȉ��̒�NO�����ł́A�P����R�����ꂽ�v�Ƃ��A�uPCI �R�Ă̓K�p�́ANO
�����x�����Ⴂ�ꍇ�ɂ͔R����P�̉\��������v�ƌւ炵���ɋL�ڂ���Ă���B
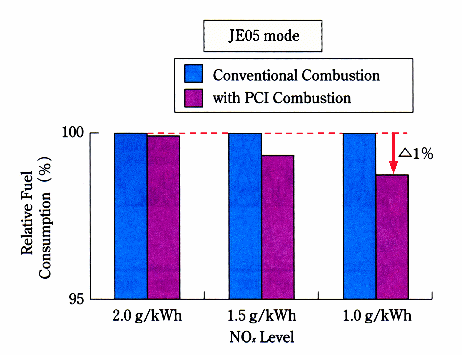
�@�{�_���ł́A�u1.0 g/kWh ��NO���l�iJE�O�T���[�h�j�ɂ����āA�ʏ�R�Ăɔ�r����PCI �R�āi=HCCI �R�āj�̔R�
�P���̍팸�v�Ƃ̎����f�[�^�������ɁA�uPCI �R�ẮANO�����x�����Ⴂ�ꍇ�ɂ͔R����P�̉\��������v�ƌ��_��
�����Ă���B���̌��_�ɂ��ĕM�҂́A���X�A�^��Ɋ�������̂ł���B���G���W���Z�p���̕M�҂́A�̂̌o����
��A�������̔R�������C�ۏ������̕ϓ��ɂ���ăG���W���R��̑���l���P�����x�̑���덷������̂ƔF
�����Ă���B���������āA�P�����x�̃G���W���̔R����P�́A����덷�͈͓̔��̂悤�Ɏv����̂��B���̂��߁A����
�_���ł́A�uNO�����x����1.0 g/kWh �iJE�O�T���[�h�j�̒Ⴂ�ꍇ�ł�PCI �R�Ăɂ��JE�O�T���[�h�̔R����P�͗]���
�҂ł��Ȃ��v�ƋL�ڂ���̂��K�Ȃ悤�ɍl���Ă���B�Ȃ��A����PCI �i=HCCI) �R�ẮA�O�q�̒�R��ƒ�NO���̃f�B
�[�[���G���W���̖ړI�Ƃ���NEDO�̃N���[���f�B�[�[���v���W�F�N�g[2004�`2009�N]�ɂ��g�ݍ��܂ꂽ�����J������
�{����A���̌��ʕł͐}�P�P�Ɏ������悤��2015�N�x�d�ʎԃ��[�h�R���ɔ�ׂ��Q���̔R����������ƋL
�ځi�o�T�Fhttp://app3.infoc.nedo.go.jp/gyouji/events/FK/rd/2008/nedoevent.2009-02-16.5786478868/shiryo.pdf�j��
��Ă���B���������āA���̕�����APCI �i=HCCI) �R�ẮA�f�B�[�[���G���W���̔R�����Ɋ�^�ł��Ȃ��Z�p��
���邱�Ƃ��e�Ղɐ��������B
�P���̍팸�v�Ƃ̎����f�[�^�������ɁA�uPCI �R�ẮANO�����x�����Ⴂ�ꍇ�ɂ͔R����P�̉\��������v�ƌ��_��
�����Ă���B���̌��_�ɂ��ĕM�҂́A���X�A�^��Ɋ�������̂ł���B���G���W���Z�p���̕M�҂́A�̂̌o����
��A�������̔R�������C�ۏ������̕ϓ��ɂ���ăG���W���R��̑���l���P�����x�̑���덷������̂ƔF
�����Ă���B���������āA�P�����x�̃G���W���̔R����P�́A����덷�͈͓̔��̂悤�Ɏv����̂��B���̂��߁A����
�_���ł́A�uNO�����x����1.0 g/kWh �iJE�O�T���[�h�j�̒Ⴂ�ꍇ�ł�PCI �R�Ăɂ��JE�O�T���[�h�̔R����P�͗]���
�҂ł��Ȃ��v�ƋL�ڂ���̂��K�Ȃ悤�ɍl���Ă���B�Ȃ��A����PCI �i=HCCI) �R�ẮA�O�q�̒�R��ƒ�NO���̃f�B
�[�[���G���W���̖ړI�Ƃ���NEDO�̃N���[���f�B�[�[���v���W�F�N�g[2004�`2009�N]�ɂ��g�ݍ��܂ꂽ�����J������
�{����A���̌��ʕł͐}�P�P�Ɏ������悤��2015�N�x�d�ʎԃ��[�h�R���ɔ�ׂ��Q���̔R����������ƋL
�ځi�o�T�Fhttp://app3.infoc.nedo.go.jp/gyouji/events/FK/rd/2008/nedoevent.2009-02-16.5786478868/shiryo.pdf�j��
��Ă���B���������āA���̕�����APCI �i=HCCI) �R�ẮA�f�B�[�[���G���W���̔R�����Ɋ�^�ł��Ȃ��Z�p��
���邱�Ƃ��e�Ղɐ��������B
�@�����Ƃ��A�ŋ߂̎O�H�ӂ����ł́A�C�ۏ�����R�����ϓ������ꍇ�ł��P���̔R���̗L�Ӎ��𐳊m�Ɍv��
�ł��鍂���x�̃G���W���R���̋Z�p�⎎���ݔ�����������Ă���̂��낤�B�����āA�G���W���R��������x�ɑ�
��ł���Z�p�I�ȃo�b�N�O�����h�����邱�Ƃ��炱���A�O�H�ӂ����́ANO���l�� 1.0 g/kWh �ɂ�����PCI �R�Ă̔R�
�ʏ�R�Ă����P���̍팸���ł��鎎���f�[�^�\���Ă�����̂ƍl������B�������A���̎����f�[�^�̌�����ς�
�ċq�ϓI�ɕ]������ƁAPCI �R�āi=HCCI �R�āj�̋Z�p�ł́ANO���l�� 1.0 g/kWh �ɂ�����PCI �R�āi=HCCI �R�āj��
�R��iJE�O�T���[�h�j�͒ʏ�R�Ăɔ�ׂċ͂��ɂP�����x��������ł��Ă��Ȃ��ƌ�����̂ł���B���̂��Ƃ���APCI
�R�āi=HCCI �R�āj�ł́A����덷�Ǝv�����R�����̓����E���ʂ����Ȃ��ƒf�肷�邱�Ƃ��ł���̂��B
�ł��鍂���x�̃G���W���R���̋Z�p�⎎���ݔ�����������Ă���̂��낤�B�����āA�G���W���R��������x�ɑ�
��ł���Z�p�I�ȃo�b�N�O�����h�����邱�Ƃ��炱���A�O�H�ӂ����́ANO���l�� 1.0 g/kWh �ɂ�����PCI �R�Ă̔R�
�ʏ�R�Ă����P���̍팸���ł��鎎���f�[�^�\���Ă�����̂ƍl������B�������A���̎����f�[�^�̌�����ς�
�ċq�ϓI�ɕ]������ƁAPCI �R�āi=HCCI �R�āj�̋Z�p�ł́ANO���l�� 1.0 g/kWh �ɂ�����PCI �R�āi=HCCI �R�āj��
�R��iJE�O�T���[�h�j�͒ʏ�R�Ăɔ�ׂċ͂��ɂP�����x��������ł��Ă��Ȃ��ƌ�����̂ł���B���̂��Ƃ���APCI
�R�āi=HCCI �R�āj�ł́A����덷�Ǝv�����R�����̓����E���ʂ����Ȃ��ƒf�肷�邱�Ƃ��ł���̂��B
�@���̂悤�ɁA�u�����ԋZ�p Vol. 65�ANo. 3�A2011�v�Ɍf�ڂ���Ă���O�H�ӂ����g���b�N�E�o�X����PCI �R�āi=HCCI �R
�āj�Ɋւ���_��������ƁAPCI �R�Ăł́A�͂��P�����x�̃G���W���R����P�iJE�O�T���[�h�j�ɉ߂����A���̂P�����x
�̃G���W���R����P�iJE�O�T���[�h�j��PCI �R�āi=HCCI �R�āj�̗B��̌��ʁE�����̂悤���B���̘_������ǂ��ꂽ�G
���W���Z�p�ҁE�w�҂ł���A�f�B�[�[���G���W���̔R�����Z�p�̈��PCI �R�āi=HCCI �R�āj�������邱�Ƃɂ�
���ẮA�p�����������S�O�����̂ł͂Ȃ����낤���B�����āA����܂ŁuPCI �R�āi=HCCI �R�āj�������f�B�[�[���̋�
�ɂ̔R�āv�Ɛ�^����Ă��������̃f�B�[�[���W�̊w�҂�Z�p�҂̌�ӌ����f���Ă݂������̂��B
�āj�Ɋւ���_��������ƁAPCI �R�Ăł́A�͂��P�����x�̃G���W���R����P�iJE�O�T���[�h�j�ɉ߂����A���̂P�����x
�̃G���W���R����P�iJE�O�T���[�h�j��PCI �R�āi=HCCI �R�āj�̗B��̌��ʁE�����̂悤���B���̘_������ǂ��ꂽ�G
���W���Z�p�ҁE�w�҂ł���A�f�B�[�[���G���W���̔R�����Z�p�̈��PCI �R�āi=HCCI �R�āj�������邱�Ƃɂ�
���ẮA�p�����������S�O�����̂ł͂Ȃ����낤���B�����āA����܂ŁuPCI �R�āi=HCCI �R�āj�������f�B�[�[���̋�
�ɂ̔R�āv�Ɛ�^����Ă��������̃f�B�[�[���W�̊w�҂�Z�p�҂̌�ӌ����f���Ă݂������̂��B
�@�����ȑO�̂��Ƃł͂��邪�A��Ȃ̏�Ō����f�B�[�[���Z�p�҂���u�����̂ɑސE�����M�҂̂悤�ȃf�B�[�[����
�́APCI �i=HCCI) �R�Ă̊J���o�����������߂ɁA���ɍ����i�i���ߋ��̐l�j���v�Ƃ̎w�E�������Ƃ�����B����
�āA��ɕs����Ȓ��Ζ�肪����PCI �i=HCCI) �R�Ă��f�B�[�[���̔���I�Ȕ��W�Ɋ�^����Ő�[�Z�p�ƐS������
���錻���f�B�[�[���Z�p�҂ɂ��āA�M�҂́u���̃f�B�[�[���G���W���Z�p�҂̗c�t���v�����������̂��B
�́APCI �i=HCCI) �R�Ă̊J���o�����������߂ɁA���ɍ����i�i���ߋ��̐l�j���v�Ƃ̎w�E�������Ƃ�����B����
�āA��ɕs����Ȓ��Ζ�肪����PCI �i=HCCI) �R�Ă��f�B�[�[���̔���I�Ȕ��W�Ɋ�^����Ő�[�Z�p�ƐS������
���錻���f�B�[�[���Z�p�҂ɂ��āA�M�҂́u���̃f�B�[�[���G���W���Z�p�҂̗c�t���v�����������̂��B
�@���āA�{�_���ł́ANO���l�� 1.0 g/kWh �ɂ�����PCI �R�āi=HCCI �R�āj�̋͂��P�����x�̔R��팸�������ɂ��A
�u�T�D�܂Ƃ߁v�ł́A�u�g�p����d���n�̔R������̕ω��ɉ�������悤�ɃG���W�����䂪�œK���ł���APCI �R
�āi=HCCI �R�āj�̎��p�����ԋ߂ł���v�ƋL�ڂ���Ă���B�����̂��Ƃ���A�O�H�ӂ����́APCI �R�āi=HCCI �R�āj
�����p���ł���Ɩ{�C�ōl���APCI �R�āi=HCCI �R�āj�������̃f�B�[�[���G���W���̔R��팸�̏d�v�ȋZ�p�ƈʒu
�Â��Ă���悤�Ɋ�����̂́A�M�҂����ł��낤���B
�u�T�D�܂Ƃ߁v�ł́A�u�g�p����d���n�̔R������̕ω��ɉ�������悤�ɃG���W�����䂪�œK���ł���APCI �R
�āi=HCCI �R�āj�̎��p�����ԋ߂ł���v�ƋL�ڂ���Ă���B�����̂��Ƃ���A�O�H�ӂ����́APCI �R�āi=HCCI �R�āj
�����p���ł���Ɩ{�C�ōl���APCI �R�āi=HCCI �R�āj�������̃f�B�[�[���G���W���̔R��팸�̏d�v�ȋZ�p�ƈʒu
�Â��Ă���悤�Ɋ�����̂́A�M�҂����ł��낤���B
�@�Ƃ���ŁA�ڍׂ͏Ȃ����APCI �R�Ă͌y���̃Z�^�����̂悤�ȔR��������C�����ɑ傫���e����������������B
���̂��߁A���̋Z�p���^�g���b�N�E�g���N�^�ɍ̗p�����ꍇ�ɂ́A�����Ɍ����Ύs��ł̎��p���s�ɂ����Ă͖�肪
��������̂ł͂Ȃ����Ɖ]���Ă���B���ɁA�O�H�ӂ������͂��P�����x�̔R��팸�ɂ��߂ɑ�^�g���b�N�E�g���N�^��
�R�Ă̕s�����PCI �i=HCCI) �R�Ă̋Z�p���̗p�����ꍇ�ɂ́A�����̑�^�g���b�N�E�g���N�^�͌̏���N�������X�N��`
�����ƂɂȂ�Ɨ\�z�����B�O�H�ӂ������̏�X�N��`���Ăł�PCI �i=HCCI) �R�Ă̋Z�p���^�g���b�N�E�g���N�^�ɍ�
�p���闝�R��������AJE�O�T���[�h�̔R����͂��P�����x��������ł��Ȃ�PCI �i=HCCI) �R�ĈȊO�ɁA�O�H�ӂ���
���f�B�[�[���G���W���̔R��팸�ɗL���ȋZ�p���������o���Ă��Ȃ����߂Ƃ��l������B
���̂��߁A���̋Z�p���^�g���b�N�E�g���N�^�ɍ̗p�����ꍇ�ɂ́A�����Ɍ����Ύs��ł̎��p���s�ɂ����Ă͖�肪
��������̂ł͂Ȃ����Ɖ]���Ă���B���ɁA�O�H�ӂ������͂��P�����x�̔R��팸�ɂ��߂ɑ�^�g���b�N�E�g���N�^��
�R�Ă̕s�����PCI �i=HCCI) �R�Ă̋Z�p���̗p�����ꍇ�ɂ́A�����̑�^�g���b�N�E�g���N�^�͌̏���N�������X�N��`
�����ƂɂȂ�Ɨ\�z�����B�O�H�ӂ������̏�X�N��`���Ăł�PCI �i=HCCI) �R�Ă̋Z�p���^�g���b�N�E�g���N�^�ɍ�
�p���闝�R��������AJE�O�T���[�h�̔R����͂��P�����x��������ł��Ȃ�PCI �i=HCCI) �R�ĈȊO�ɁA�O�H�ӂ���
���f�B�[�[���G���W���̔R��팸�ɗL���ȋZ�p���������o���Ă��Ȃ����߂Ƃ��l������B
�@���݂�PCI �i=HCCI) �R�Ă͎�Ɂu�R�����ˎ�����ʏ�R�Ă̏ꍇ�����啝�ɐi�p������v�����ʼn\�ł��邽
�߁APCI �i=HCCI) �R�Ăɕs�K�ȔR��������C�����̍ۂɂ́A�ً}���Ə̂��APCI �i=HCCI) �R�ẴG���W���^�]
�̈�ł����Ă��A�����ɒʏ�R�Ă̔R�����ˎ�����x�p������PCI �i=HCCI) �R�Ă̕s����������邱�Ƃ��\��
����B���̂悤�ɁA�{����PCI �i=HCCI) �R�ẴG���W���^�]�̈��ʏ�R�Ă̐���ɐ�ւ����ꍇ�ɂ́A�u���
NO�������v�Ɓu�P�����x�̏d�ʎԃ��[�h�R��̑����v���������APCI �i=HCCI) �R�Ăɕs�K�ȔR��������C�����̏�
�ł���^�g���b�N�E�g���N�^��ʏ�R�Ăʼn~���ɑ��s�����邱�Ƃ��ł���̂��B
�߁APCI �i=HCCI) �R�Ăɕs�K�ȔR��������C�����̍ۂɂ́A�ً}���Ə̂��APCI �i=HCCI) �R�ẴG���W���^�]
�̈�ł����Ă��A�����ɒʏ�R�Ă̔R�����ˎ�����x�p������PCI �i=HCCI) �R�Ă̕s����������邱�Ƃ��\��
����B���̂悤�ɁA�{����PCI �i=HCCI) �R�ẴG���W���^�]�̈��ʏ�R�Ă̐���ɐ�ւ����ꍇ�ɂ́A�u���
NO�������v�Ɓu�P�����x�̏d�ʎԃ��[�h�R��̑����v���������APCI �i=HCCI) �R�Ăɕs�K�ȔR��������C�����̏�
�ł���^�g���b�N�E�g���N�^��ʏ�R�Ăʼn~���ɑ��s�����邱�Ƃ��ł���̂��B
�@���̂悤�ɁAPCI �R�āi=HCCI �R�āj�̃f�B�[�[���G���W���ł́APCI �R�āi=HCCI �R�āj�ɕs�K�ȔR��������C��
���ł�PCI �i=HCCI) �R�ẴG���W���^�]�̈��ʏ�R�Ă̐���ʼn^�]����ً}���̐�����v���O�����ɑg�ݍ�
�݁A�K�v�ɉ����Ď��R���݂ɒʏ�R�Ă̐���ŃG���W�����^�]���邱�Ƃ��\���B���������āAPCI �i=HCCI) �R�ăG��
�W���Ƃ��č��y��ʏȂ̃G���W���R�����āA�u�|�X�g�V�����r�o�K�X�K���i2009�N�K���j�̓K���v�Ɓu�P�����x�̏d
�ʎԃ��[�h�R��̌���v�̎d�l���̑�^�g���b�N�E�g���N�^�Ƃ��č��y��ʏȂ̔F����A��^�g���b�N�E�g���N�^�̎s
��ł̑����̎����s���ɂ͒ʏ�R�Ăʼn~���ɑ��s������悤�ɂ���悤�ɃG���W���𐧌䂷�邱�Ƃ��\�ƍl�����
��B���ɁA�g���b�N���[�J��PCI �i=HCCI) �R�Ă̋Z�p���^�g���b�N�E�g���b�N�ɍ̗p����ۂɁA���̂悤�ȌƑ��ȃG���W��
������̗p�����ꍇ�ɂ́A��ʂ̎s�����猵�����w�e����邱�Ƃ͖��炩���B���������āA�g���b�N���[�J����^�g���b�N�E
�g���N�^��PCI �i=HCCI) �R�Ă̋Z�p���̗p����ꍇ�ɂ́A�ً}���̖��ڂŖ{����PCI �i=HCCI) �R�ẴG���W���^
�]�̈��ʏ�R�Ă̐���ɕp�ɂɐ�ւ��鐧����������Ȃ����߁APCI �i=HCCI) �R�Ă̋Z�p�����p������
���Ƃ͓���̂ł͂Ȃ����ƍl������B
���ł�PCI �i=HCCI) �R�ẴG���W���^�]�̈��ʏ�R�Ă̐���ʼn^�]����ً}���̐�����v���O�����ɑg�ݍ�
�݁A�K�v�ɉ����Ď��R���݂ɒʏ�R�Ă̐���ŃG���W�����^�]���邱�Ƃ��\���B���������āAPCI �i=HCCI) �R�ăG��
�W���Ƃ��č��y��ʏȂ̃G���W���R�����āA�u�|�X�g�V�����r�o�K�X�K���i2009�N�K���j�̓K���v�Ɓu�P�����x�̏d
�ʎԃ��[�h�R��̌���v�̎d�l���̑�^�g���b�N�E�g���N�^�Ƃ��č��y��ʏȂ̔F����A��^�g���b�N�E�g���N�^�̎s
��ł̑����̎����s���ɂ͒ʏ�R�Ăʼn~���ɑ��s������悤�ɂ���悤�ɃG���W���𐧌䂷�邱�Ƃ��\�ƍl�����
��B���ɁA�g���b�N���[�J��PCI �i=HCCI) �R�Ă̋Z�p���^�g���b�N�E�g���b�N�ɍ̗p����ۂɁA���̂悤�ȌƑ��ȃG���W��
������̗p�����ꍇ�ɂ́A��ʂ̎s�����猵�����w�e����邱�Ƃ͖��炩���B���������āA�g���b�N���[�J����^�g���b�N�E
�g���N�^��PCI �i=HCCI) �R�Ă̋Z�p���̗p����ꍇ�ɂ́A�ً}���̖��ڂŖ{����PCI �i=HCCI) �R�ẴG���W���^
�]�̈��ʏ�R�Ă̐���ɕp�ɂɐ�ւ��鐧����������Ȃ����߁APCI �i=HCCI) �R�Ă̋Z�p�����p������
���Ƃ͓���̂ł͂Ȃ����ƍl������B
�@�Ȃ��A�O�q�̕\�X�Ɏ������悤�ɁA�O�H�ӂ����ł̓|�X�g�V�����K���i2009�N�K���j�ɓK��������^�g���b�N�E�g���N�^��
�P�R���̎Ԏ킪�Q�O�P�T�N�x�d�ʎԔR���ɕs�K���Ɋׂ��Ă���̂����B���̎O�H�ӂ������u�����ԋZ�p�v����
�_���ł́A�uNO���l�� 1.0 g/kWh �ɂ�����PCI �R�āi=HCCI �R�āj�̔R��iJE�O�T���[�h�j�͒ʏ�R�Ăɔ�ׂċ͂���
�P�����x��������ł��Ă��Ȃ��v�Ɣ��\����Ɠ����ɁA�uPCI �R�āi=HCCI �R�āj�̎��p�����ԋ߂ł���v�ƋL�ڂ���Ă�
��̂��B���̂��߁A�O�H�ӂ����́A��^�g���b�N�E�g���N�^�̔R����P�̂��߂ɁAE�O�T���[�h�̔R����͂��P�����x�̑�
��덷���x�̔R�������ł��Ȃ�PCI �R�āi=HCCI �R�āj�̋Z�p���̗p���悤�Ƃ��Ă���l�q���f����B���̂��Ƃ�
�画�f����ƁA�O�H�ӂ����́A��^�g���b�N�E�g���N�^�̔R����\���Ɍ���ł���Z�p���S���J���ł��Ă��Ȃ��̂ł͂Ȃ�
���낤���B
�P�R���̎Ԏ킪�Q�O�P�T�N�x�d�ʎԔR���ɕs�K���Ɋׂ��Ă���̂����B���̎O�H�ӂ������u�����ԋZ�p�v����
�_���ł́A�uNO���l�� 1.0 g/kWh �ɂ�����PCI �R�āi=HCCI �R�āj�̔R��iJE�O�T���[�h�j�͒ʏ�R�Ăɔ�ׂċ͂���
�P�����x��������ł��Ă��Ȃ��v�Ɣ��\����Ɠ����ɁA�uPCI �R�āi=HCCI �R�āj�̎��p�����ԋ߂ł���v�ƋL�ڂ���Ă�
��̂��B���̂��߁A�O�H�ӂ����́A��^�g���b�N�E�g���N�^�̔R����P�̂��߂ɁAE�O�T���[�h�̔R����͂��P�����x�̑�
��덷���x�̔R�������ł��Ȃ�PCI �R�āi=HCCI �R�āj�̋Z�p���̗p���悤�Ƃ��Ă���l�q���f����B���̂��Ƃ�
�画�f����ƁA�O�H�ӂ����́A��^�g���b�N�E�g���N�^�̔R����\���Ɍ���ł���Z�p���S���J���ł��Ă��Ȃ��̂ł͂Ȃ�
���낤���B
�@���̂悤�ɁA��^�g���b�N�E�g���N�^�̔R�����̋Z�p�ɋ����Ă���O�H�ӂ����́A����PCI �R�āi=HCCI �R�āj�̋Z�p
���^�g���b�N�E�g���N�^�ɍ̗p������Ȃ�����ɒǂ����܂�Ă���\�����\���ɍl������B�ܘ_�A���̃g���b�N
���[�J������A�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�Ɠ������x�����R���NO�����팸�ł���悤�ȋZ�p�͉�����
�\����Ă��Ȃ��B�����̂��Ƃ���A�O�H�ӂ����Ɠ��l�A���̃g���b�N���[�J�ł��f�B�[�[���̃G���W���̏\���ȔR�����
�������ł���Z�p�̊J���ɐ������Ă��Ȃ����Ƃ́A���炩���B���̂��߁A�\�P�S�Ɏ����Ă���悤�ɑ��̃g���b�N���[�J��
��^�g���b�N�E�g���N�^�̑����̎Ԏ킪�Q�O�P�T�N�x�d�ʎԔR���ɕs�K���̏ł���B
���^�g���b�N�E�g���N�^�ɍ̗p������Ȃ�����ɒǂ����܂�Ă���\�����\���ɍl������B�ܘ_�A���̃g���b�N
���[�J������A�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�Ɠ������x�����R���NO�����팸�ł���悤�ȋZ�p�͉�����
�\����Ă��Ȃ��B�����̂��Ƃ���A�O�H�ӂ����Ɠ��l�A���̃g���b�N���[�J�ł��f�B�[�[���̃G���W���̏\���ȔR�����
�������ł���Z�p�̊J���ɐ������Ă��Ȃ����Ƃ́A���炩���B���̂��߁A�\�P�S�Ɏ����Ă���悤�ɑ��̃g���b�N���[�J��
��^�g���b�N�E�g���N�^�̑����̎Ԏ킪�Q�O�P�T�N�x�d�ʎԔR���ɕs�K���̏ł���B
�@�����āA�ŋ߂̎����ԋZ�p�����{�@�B�w��̍u�����_���W�ł̔��\���e�����Ă��A�R���NO���̗������\��
�ɍ팸�ł����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�ɕC�G����Z�p�ɁA�M�҂͑����������Ƃ��Ȃ��B�R���NO����
���ɍ팸�Ɋւ��A�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�Ɠ������A�Ⴕ���͂��̋Z�p�𗽉킷��Z�p���䑶���̏�
���ɂ́A����Ƃ����������������Ǝv���Ă���B�����_�ł��A��w�E�����@�ցE�g���b�N���[�J�̉���ɂ����Ă��A�\����
�R��������������Z�p���J���ł��Ă��Ȃ����߁A�S�Ă̎Ԏ�̑�^�g���b�N�E�g���N�^���Q�O�P�T�N�x�d�ʎԔR��
�ɓK�������邱�Ƃ��ł��Ȃ��悤���B�[�I�Ɍ����A��^�g���b�N�E�g���N�^�̔R��팸���Z�p�I�Ɏ�l�܂�̏Ɋ�
���Ă���̂ł͂Ȃ����낤���B
�ɍ팸�ł����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�ɕC�G����Z�p�ɁA�M�҂͑����������Ƃ��Ȃ��B�R���NO����
���ɍ팸�Ɋւ��A�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�Ɠ������A�Ⴕ���͂��̋Z�p�𗽉킷��Z�p���䑶���̏�
���ɂ́A����Ƃ����������������Ǝv���Ă���B�����_�ł��A��w�E�����@�ցE�g���b�N���[�J�̉���ɂ����Ă��A�\����
�R��������������Z�p���J���ł��Ă��Ȃ����߁A�S�Ă̎Ԏ�̑�^�g���b�N�E�g���N�^���Q�O�P�T�N�x�d�ʎԔR��
�ɓK�������邱�Ƃ��ł��Ȃ��悤���B�[�I�Ɍ����A��^�g���b�N�E�g���N�^�̔R��팸���Z�p�I�Ɏ�l�܂�̏Ɋ�
���Ă���̂ł͂Ȃ����낤���B
�@�����āA�ŋ߂̎����ԋZ�p�����{�@�B�w��̍u�����_���W�����Ă��A�R���NO���̗������\���ɍ팸�ł���
�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�ɕC�G����Z�p�ɕM�҂͑����������Ƃ��Ȃ��B�R���NO���̕��ɍ팸�Ɋ�
���A�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�Ɠ������A�Ⴕ���͂��̋Z�p�𗽉킷��Z�p���䑶���̏ꍇ�ɂ́A����
�Ƃ����������������Ǝv���Ă���B���̂悤�ɁA��w�E�����@�ցE�g���b�N���[�J�̉���ɂ����Ă��A�\���ȔR��������
������Z�p���J���ł��Ă��Ȃ����߁A�S�Ă̎Ԏ�̑�^�g���b�N�E�g���N�^���Q�O�P�T�N�x�d�ʎԔR���ɓK��������
���Ƃ��ł��Ȃ��̂�����̂悤���B�[�I�Ɍ����A��^�g���b�N�E�g���N�^�̔R��팸���Z�p�I�Ɏ�l�܂�̏Ɋׂ�
�Ă���̂ł͂Ȃ����낤���B
�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�ɕC�G����Z�p�ɕM�҂͑����������Ƃ��Ȃ��B�R���NO���̕��ɍ팸�Ɋ�
���A�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�Ɠ������A�Ⴕ���͂��̋Z�p�𗽉킷��Z�p���䑶���̏ꍇ�ɂ́A����
�Ƃ����������������Ǝv���Ă���B���̂悤�ɁA��w�E�����@�ցE�g���b�N���[�J�̉���ɂ����Ă��A�\���ȔR��������
������Z�p���J���ł��Ă��Ȃ����߁A�S�Ă̎Ԏ�̑�^�g���b�N�E�g���N�^���Q�O�P�T�N�x�d�ʎԔR���ɓK��������
���Ƃ��ł��Ȃ��̂�����̂悤���B�[�I�Ɍ����A��^�g���b�N�E�g���N�^�̔R��팸���Z�p�I�Ɏ�l�܂�̏Ɋׂ�
�Ă���̂ł͂Ȃ����낤���B
�@���݁A�Q�O�P�T�N�x�d�ʎԔR���ɕs�K���̎Ԏ�𐔑��������Ă���e�g���b�N���[�J�̋Z�p�҂́A�����̃R�X�g��
�����߂ɁA�T�`�P�O���̔R������サ��NO�����\���ɉ��P�ł���C���x�~�f�B�[�[���G���W���i�������J2005-
54771�j����Ȃɖ������Ă���B���̈���ŁA�P�����x�̔R������P�ł��Ȃ�PCI �R�āi=HCCI �R�āj��p���ĂQ�O�P�T
�N�x�d�ʎԔR�������d�ʎԃ��[�h�R��l���ő�łT�����x������^�g���b�N�E�g���N�^�̎Ԏ���Q�O�P�T�N�x�d
�ʎԔR���ɓK�������悤�Ƃ��Ă���̂��B���̂悤��PCI �R�āi=HCCI �R�āj�̋Z�p�𐒔q����e�g���b�N���[�J��
�Z�p�҂̗l�q�����Ă���ƁA�u�푈���̐��_�_�œG��|���v�z�v�ł���|���i��PCI �R�ā�HCCI �R�āj���g���ēG��
��ԁi���Q�O�P�T�N�x�d�ʎԔR���j�����ށi���R���̒B���j����l�����Ɏ��Ă���B���̂悤�Ȑ��_�_�ł͓G��
��ԁi���Q�O�P�T�N�x�d�ʎԔR���j�����ށi���R���̒B���j���邱�Ƃ�����Ȃ��Ƃ͖��炩���B�����ŁA�ΐ��
���P�b�g�i�C���x�~�f�B�[�[���G���W��[�������J2005-54771]�̋Z�p�j��(����^�g���b�N�E�g���N�^�ɍ̗p�j���ēG��
��ԁi���Q�O�P�T�N�x�d�ʎԔR���j�����ށi���R���̒B���j�������ł���̂ł���B���̂悤�Ȃ��Ƃ͐푈�i����
�^�g���b�N�̔R�����)�ł͏펯�ł͂Ȃ����낤���B��R�X�g�̒|���i��PCI �R�ā�HCCI �R�āj�œG�̐�ԁi���Q�O�P�T�N
�x�d�ʎԔR���j�����ށi���R���̒B���j���邱�Ƃ��ł���ƍl����̂́A�S���n���Ƃ��������悤���Ȃ��B
�����߂ɁA�T�`�P�O���̔R������サ��NO�����\���ɉ��P�ł���C���x�~�f�B�[�[���G���W���i�������J2005-
54771�j����Ȃɖ������Ă���B���̈���ŁA�P�����x�̔R������P�ł��Ȃ�PCI �R�āi=HCCI �R�āj��p���ĂQ�O�P�T
�N�x�d�ʎԔR�������d�ʎԃ��[�h�R��l���ő�łT�����x������^�g���b�N�E�g���N�^�̎Ԏ���Q�O�P�T�N�x�d
�ʎԔR���ɓK�������悤�Ƃ��Ă���̂��B���̂悤��PCI �R�āi=HCCI �R�āj�̋Z�p�𐒔q����e�g���b�N���[�J��
�Z�p�҂̗l�q�����Ă���ƁA�u�푈���̐��_�_�œG��|���v�z�v�ł���|���i��PCI �R�ā�HCCI �R�āj���g���ēG��
��ԁi���Q�O�P�T�N�x�d�ʎԔR���j�����ށi���R���̒B���j����l�����Ɏ��Ă���B���̂悤�Ȑ��_�_�ł͓G��
��ԁi���Q�O�P�T�N�x�d�ʎԔR���j�����ށi���R���̒B���j���邱�Ƃ�����Ȃ��Ƃ͖��炩���B�����ŁA�ΐ��
���P�b�g�i�C���x�~�f�B�[�[���G���W��[�������J2005-54771]�̋Z�p�j��(����^�g���b�N�E�g���N�^�ɍ̗p�j���ēG��
��ԁi���Q�O�P�T�N�x�d�ʎԔR���j�����ށi���R���̒B���j�������ł���̂ł���B���̂悤�Ȃ��Ƃ͐푈�i����
�^�g���b�N�̔R�����)�ł͏펯�ł͂Ȃ����낤���B��R�X�g�̒|���i��PCI �R�ā�HCCI �R�āj�œG�̐�ԁi���Q�O�P�T�N
�x�d�ʎԔR���j�����ށi���R���̒B���j���邱�Ƃ��ł���ƍl����̂́A�S���n���Ƃ��������悤���Ȃ��B
�@���������āA�Q�O�P�T�N�x�d�ʎԔR���ɕs�K���̑�^�g���b�N�E�g���N�^�̎Ԏ���Q�O�P�T�N�x�d�ʎԔR���ɓK
�������邽�߂ɂ́A��̃R�X�g�A�b�v�����A�d�ʎԃ��[�h�R��l���T�`�P�O�������P�ł���C���x�~�f�B�[�[���G
���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p���̗p���邱�Ƃ��œK�ł��邱�Ƃ́A�펯�I�ɍl����Ζ��炩�Ȃ��Ƃ��B�������A
�e�g���b�N���[�J�̋Z�p�҂́A��R�X�g�ł��邪�̂�PCI �R�āi=HCCI �R�āj�̋Z�p�ő�^�g���b�N�E�g���N�^�̂Q�O�P�T�N
�x�d�ʎԔR���ɕs�K���̎Ԏ�����̊�ɓK�����������悤�ł��邪�A���F�A�����ł͂Ȃ����낤���B���Ɋ��m
�Șb�ł͂��邪�A�e�g���b�N���[�J�̋Z�p�҂́A�V���@���̐M�҂̂悤�ɁuPCI �R�āi=HCCI �R�āj���v��ӐM���Ă���
�̂ł��낤�B���͂Ƃ�����A�e�g���b�N���[�J�̑����̋Z�p�҂��s����Ȓ���PCI �R�āi=HCCI �R�āj���u�v�V�I��
�����̔R�ċZ�p�v�ƐM���ċ^��Ȃ��Ƃ���́A���̍����ł���A�~������Ƃ��B
�������邽�߂ɂ́A��̃R�X�g�A�b�v�����A�d�ʎԃ��[�h�R��l���T�`�P�O�������P�ł���C���x�~�f�B�[�[���G
���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p���̗p���邱�Ƃ��œK�ł��邱�Ƃ́A�펯�I�ɍl����Ζ��炩�Ȃ��Ƃ��B�������A
�e�g���b�N���[�J�̋Z�p�҂́A��R�X�g�ł��邪�̂�PCI �R�āi=HCCI �R�āj�̋Z�p�ő�^�g���b�N�E�g���N�^�̂Q�O�P�T�N
�x�d�ʎԔR���ɕs�K���̎Ԏ�����̊�ɓK�����������悤�ł��邪�A���F�A�����ł͂Ȃ����낤���B���Ɋ��m
�Șb�ł͂��邪�A�e�g���b�N���[�J�̋Z�p�҂́A�V���@���̐M�҂̂悤�ɁuPCI �R�āi=HCCI �R�āj���v��ӐM���Ă���
�̂ł��낤�B���͂Ƃ�����A�e�g���b�N���[�J�̑����̋Z�p�҂��s����Ȓ���PCI �R�āi=HCCI �R�āj���u�v�V�I��
�����̔R�ċZ�p�v�ƐM���ċ^��Ȃ��Ƃ���́A���̍����ł���A�~������Ƃ��B
�W�|�R�@AVL�̍u���ł��R����P�̋�̓I�Ȓ�Ă͖����i�����ԋZ�p��2010�N�t�G���j
�@�����ԋZ�p��́u�Q�O�P�O�N�l�Ƃ���܂̃e�N�m���W�[�W�v(2010�N5��19�`21�j�Ő��E�I�Ȍ����@�ւł���AVL�i�I�[�X�g
���A�j�̃w�����[�g�E���X�g����u�����A�f�B�[�[���G���W���̔R�����ɂ́A�u�R���s���[�^�v�Z�p�����܂��g���v�Ƃ�
������lj����āu�t���N�V�������X�i���C�����j�̒ጸ�v�Ɓu�V�����_�[���̔R�ĉ��P�v�̃G���W���H�w�̋��ȏ��ɋL�ڂ�
��Ă����̋Z�p���ڂɂ����25���̌������オ�\�Ɣ��\���Ă��邪�A��̓I�ȋZ�p���e�͉��������Ă��Ȃ���
�����B����́A���E�I�Ȍ����@�ւ�AVL����̓I�ȋZ�p���e�������������ɁA�f�B�[�[���G���W���̌�������̒P��
���]���q�ׂĂ���ɉ߂��Ȃ��̂��BAVL�͑S���₵�����e�̍u�����s�������̂��B
���A�j�̃w�����[�g�E���X�g����u�����A�f�B�[�[���G���W���̔R�����ɂ́A�u�R���s���[�^�v�Z�p�����܂��g���v�Ƃ�
������lj����āu�t���N�V�������X�i���C�����j�̒ጸ�v�Ɓu�V�����_�[���̔R�ĉ��P�v�̃G���W���H�w�̋��ȏ��ɋL�ڂ�
��Ă����̋Z�p���ڂɂ����25���̌������オ�\�Ɣ��\���Ă��邪�A��̓I�ȋZ�p���e�͉��������Ă��Ȃ���
�����B����́A���E�I�Ȍ����@�ւ�AVL����̓I�ȋZ�p���e�������������ɁA�f�B�[�[���G���W���̌�������̒P��
���]���q�ׂĂ���ɉ߂��Ȃ��̂��BAVL�͑S���₵�����e�̍u�����s�������̂��B
�@�܂��AAVL�́A��̓I�ȃf�B�[�[���̌�������̕��@�Ƃ��āu�r�C�M��d�C�G�l���M�[�ɕς���R���o�[�^�[��t��
�邱�ƂŁA6 - 7���قnj�������悹�ł���v�Ɣ��\���Ă��邪�A����̓f�B�[�[���G���W���̔r�C�K�X�̔M�G�l���M�[
�������L���T�C�N���A�r�C�K�X�^�[�r���܂��̓X�^�[�����O�G���W�����œ��͂ɕϊ����A���̓��͂Ŕ��d�@���쓮���ēd
�C�G�l���M�[��������鑕�u��t���������̂ƍl������B���́u�r�C�M��d�C�G�l���M�[�ɕς���R���o�[�^�[�v�́A
�Η͔��d�����^�D���ł̓f�B�[�[���G���W������i�o�͂ʼn^�]����邽�߂ɏ�ɍ����̔r�C�K�X��r�o���邽��
�ɍ��������ʼnғ��ł��邽�߁A���ɉΗ͔��d�����^�D���ɂ����čL�����y���Ă��鑕�u�ł���B�������A��^�f�B�[
�[���g���b�N�͏�ɃG���W���o�͂��ϓ������ɕ������ׂ̉^�]�ŒႢ�r�C�K�X���x�ƂȂ邱�Ƃ��������߁A��^�g��
�b�N�Ɂu�r�C�M��d�C�G�l���M�[�ɕς���R���o�[�^�[�v�𓋍ڂ����ꍇ�ɂ͌���������������Ă��܂����ƂɂȂ�B����
���߁A��^�g���b�N�ɂ��̃R���o�[�^�[�𓋍ڂ��Ă��\���ȔR��̌���͓���B���������āAAVL�����̃R���o�[�^�[
�̓��ڂɂ���đ�^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W���̌�����6 - 7���قlj��P�ł���Ƃ̍u���ł̔��\�́A�傫�Ȍ���
�͂Ȃ����낤���B�@
�邱�ƂŁA6 - 7���قnj�������悹�ł���v�Ɣ��\���Ă��邪�A����̓f�B�[�[���G���W���̔r�C�K�X�̔M�G�l���M�[
�������L���T�C�N���A�r�C�K�X�^�[�r���܂��̓X�^�[�����O�G���W�����œ��͂ɕϊ����A���̓��͂Ŕ��d�@���쓮���ēd
�C�G�l���M�[��������鑕�u��t���������̂ƍl������B���́u�r�C�M��d�C�G�l���M�[�ɕς���R���o�[�^�[�v�́A
�Η͔��d�����^�D���ł̓f�B�[�[���G���W������i�o�͂ʼn^�]����邽�߂ɏ�ɍ����̔r�C�K�X��r�o���邽��
�ɍ��������ʼnғ��ł��邽�߁A���ɉΗ͔��d�����^�D���ɂ����čL�����y���Ă��鑕�u�ł���B�������A��^�f�B�[
�[���g���b�N�͏�ɃG���W���o�͂��ϓ������ɕ������ׂ̉^�]�ŒႢ�r�C�K�X���x�ƂȂ邱�Ƃ��������߁A��^�g��
�b�N�Ɂu�r�C�M��d�C�G�l���M�[�ɕς���R���o�[�^�[�v�𓋍ڂ����ꍇ�ɂ͌���������������Ă��܂����ƂɂȂ�B����
���߁A��^�g���b�N�ɂ��̃R���o�[�^�[�𓋍ڂ��Ă��\���ȔR��̌���͓���B���������āAAVL�����̃R���o�[�^�[
�̓��ڂɂ���đ�^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W���̌�����6 - 7���قlj��P�ł���Ƃ̍u���ł̔��\�́A�傫�Ȍ���
�͂Ȃ����낤���B�@
�@����AVL����������u�r�C�M��d�C�G�l���M�[�ɕς���R���o�[�^�[�v�́A��^���b�N�̑��s�ő��p�����f�B�[�[��
�f�B�[�[���G���W���̕������^�]���ɂ͔r�C�K�X���x���Ⴍ�A�r�C�K�X�̔M��d�C�G�l���M�[�ɕς���ۂ̌���
����錇�_������B���̌��_�i�����ׁj�����P���邽�߂ɂ́A�f�B�[�[���G���W���̕������^�]���̔r�C�K�X���x
������������V���ȋZ�p��lj����邱�Ƃ��K�v�ł���B���������āAAVL�̒�Ă̂悤�ɁA�u�r�C�M��d�C�G�l���M�[
�ɕς���R���o�[�^�[�v��P�ɑ�^�g���b�N�ɓ��ڂ��������ł́A��^�g���b�N�̏\���ȔR�����͖]�߂Ȃ��̂ł���B
����AVL����^�g���b�N�̔R�����̂��߂Ɂu�r�C�M��d�C�G�l���M�[�ɕς���R���o�[�^�[�v���^�g���b�N�ɓ��ڂ�
�邱�Ƃ��Ă������̂ł���A��^���b�N�̑��s�ő��p�����f�B�[�[���f�B�[�[���G���W���̕������^�]���ɔr
�C�K�X���x������������Z�p���ŏ��ɒ�Ă��ׂ��ł͂Ȃ����ƍl������B�f�B�[�[���G���W���̕������^�]����
�r�C�K�X���x���������ł���Z�p���������Ȃ��Łu�r�C�M��d�C�G�l���M�[�ɕς���R���o�[�^�[�v���^�g���b�N
�ɓ��ڂ���Ƃ�AVL�̍u���ł̒�ẮA�M�҂ɂ͋��̍����Ǝv����̂��BAVL�����̂悤�ȍu�����\�����Ă���Ƃ���
������ƁA�f�B�[�[���G���W���̔R�����ɂ��Ă�AVL���Z�p�A�C�f�A���͊����A�傫�ȕǂɓ˂��������Ă���悤��
�l������B�����āA���̂悤��AVL�ɑ����̃g���b�N���[�J����^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W���̔R�����̃R���T��
�e�B���O��O���������ɎĂ��錻����l����ƁA����̑�^�g���b�N�ɂ͔R�����ɑ傫�Ȋ��҂��ł��Ȃ��ƍl��
��̂��Ó��ł͂Ȃ����낤���B
�f�B�[�[���G���W���̕������^�]���ɂ͔r�C�K�X���x���Ⴍ�A�r�C�K�X�̔M��d�C�G�l���M�[�ɕς���ۂ̌���
����錇�_������B���̌��_�i�����ׁj�����P���邽�߂ɂ́A�f�B�[�[���G���W���̕������^�]���̔r�C�K�X���x
������������V���ȋZ�p��lj����邱�Ƃ��K�v�ł���B���������āAAVL�̒�Ă̂悤�ɁA�u�r�C�M��d�C�G�l���M�[
�ɕς���R���o�[�^�[�v��P�ɑ�^�g���b�N�ɓ��ڂ��������ł́A��^�g���b�N�̏\���ȔR�����͖]�߂Ȃ��̂ł���B
����AVL����^�g���b�N�̔R�����̂��߂Ɂu�r�C�M��d�C�G�l���M�[�ɕς���R���o�[�^�[�v���^�g���b�N�ɓ��ڂ�
�邱�Ƃ��Ă������̂ł���A��^���b�N�̑��s�ő��p�����f�B�[�[���f�B�[�[���G���W���̕������^�]���ɔr
�C�K�X���x������������Z�p���ŏ��ɒ�Ă��ׂ��ł͂Ȃ����ƍl������B�f�B�[�[���G���W���̕������^�]����
�r�C�K�X���x���������ł���Z�p���������Ȃ��Łu�r�C�M��d�C�G�l���M�[�ɕς���R���o�[�^�[�v���^�g���b�N
�ɓ��ڂ���Ƃ�AVL�̍u���ł̒�ẮA�M�҂ɂ͋��̍����Ǝv����̂��BAVL�����̂悤�ȍu�����\�����Ă���Ƃ���
������ƁA�f�B�[�[���G���W���̔R�����ɂ��Ă�AVL���Z�p�A�C�f�A���͊����A�傫�ȕǂɓ˂��������Ă���悤��
�l������B�����āA���̂悤��AVL�ɑ����̃g���b�N���[�J����^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W���̔R�����̃R���T��
�e�B���O��O���������ɎĂ��錻����l����ƁA����̑�^�g���b�N�ɂ͔R�����ɑ傫�Ȋ��҂��ł��Ȃ��ƍl��
��̂��Ó��ł͂Ȃ����낤���B
�@����AVL�����́u�r�C�M��d�C�G�l���M�[�ɕς���R���o�[�^�[�v����^�g���b�N�p�Ƃ��Ď��p�ɑς����鍂��������
�ғ��ł���悤�ɂ��邽�߂ɂ́A�C���x�~�́A�f�B�[�[���r�C�K�X�̃G�l���M�[���u�̌����������ɏڏq���Ă�
��悤�ɁA��^���b�N�̑��s�ő��p�����f�B�[�[���f�B�[�[���G���W���̕������^�]���ł̔r�C�K�X���x�̍���
����}�邱�Ƃ��K�v�ł���B���̕��@�Ƃ��āA���̃R���o�[�^���̗p����ꍇ�ɂ́A�M�Ғ�Ă��C���x�~�G���W���i��
�����J2005-54771�j�̓����Z�p��p���邱���K�{�ƍl���Ă���B�t�Ȍ�����������AAVL�����̔r�C�M��d�C�G�l
���M�[�ɕς���R���o�[�^�[�̃V�X�e���ɕM�Ғ�Ă��C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p��p����
���ꍇ�ɂ́A�����̌��オ�]�߂Ȃ��̂ł���B���̂��߁AAVL����Ă���u�r�C�M��d�C�G�l���M�[�ɕς���R���o
�[�^�[�v�̃V�X�e���ł́A�d�ʎԃ��[�h�R��̌��オ�\���łȂ��A���p���Ɍ������Z�p�ƍl������B�f�B�[�[���G���W
���̔M�����̌����}��Z�p�Ƃ��āAAVL�����́u�R���o�[�^�[�̃V�X�e�����Ă������̂ł���A�f�B�[�[���G���W
���̕������^�]���̔r�C�K�X���x������������Z�p�ł���M�Ғ�Ă��C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j
�̓����Z�p�̗̍p�������ɒ�Ă��ׂ��ł���B
�ғ��ł���悤�ɂ��邽�߂ɂ́A�C���x�~�́A�f�B�[�[���r�C�K�X�̃G�l���M�[���u�̌����������ɏڏq���Ă�
��悤�ɁA��^���b�N�̑��s�ő��p�����f�B�[�[���f�B�[�[���G���W���̕������^�]���ł̔r�C�K�X���x�̍���
����}�邱�Ƃ��K�v�ł���B���̕��@�Ƃ��āA���̃R���o�[�^���̗p����ꍇ�ɂ́A�M�Ғ�Ă��C���x�~�G���W���i��
�����J2005-54771�j�̓����Z�p��p���邱���K�{�ƍl���Ă���B�t�Ȍ�����������AAVL�����̔r�C�M��d�C�G�l
���M�[�ɕς���R���o�[�^�[�̃V�X�e���ɕM�Ғ�Ă��C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p��p����
���ꍇ�ɂ́A�����̌��オ�]�߂Ȃ��̂ł���B���̂��߁AAVL����Ă���u�r�C�M��d�C�G�l���M�[�ɕς���R���o
�[�^�[�v�̃V�X�e���ł́A�d�ʎԃ��[�h�R��̌��オ�\���łȂ��A���p���Ɍ������Z�p�ƍl������B�f�B�[�[���G���W
���̔M�����̌����}��Z�p�Ƃ��āAAVL�����́u�R���o�[�^�[�̃V�X�e�����Ă������̂ł���A�f�B�[�[���G���W
���̕������^�]���̔r�C�K�X���x������������Z�p�ł���M�Ғ�Ă��C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j
�̓����Z�p�̗̍p�������ɒ�Ă��ׂ��ł���B
�@���݂ɁAAVL�́u�r�C�M��d�C�G�l���M�[�ɕς���R���o�[�^�[�v�ł̓f�B�[�[���G���W���̔r�C�K�X����G�l���M�[
���������6 - 7���i�d�ʎԃ��[�h�R��H�j�̌�������悹����Ƃ̔��\���s���Ă��邪�A����AVL��ẴR���o�[�^�[
���ғ������ۂ̌����͋ɂ߂ĒႢ�Ɨ\�z����邽�߁A���̃R���o�[�^�[���^�g���b�N�ɓ��ڂ����ꍇ�ɂ́A���ۂɑ�
�^�g���b�N�̏d�ʎԃ��[�h�R���6 - 7���قǂ̔R�����悹���邱�Ƃ͋ɂ߂ē�����̂ƍl������B����ɂ���
�́AAVL�͖��ӔC�Ȍ�������̐��l�\�����Ă���̂ł͂Ȃ����Ɗ����Ă���B
���������6 - 7���i�d�ʎԃ��[�h�R��H�j�̌�������悹����Ƃ̔��\���s���Ă��邪�A����AVL��ẴR���o�[�^�[
���ғ������ۂ̌����͋ɂ߂ĒႢ�Ɨ\�z����邽�߁A���̃R���o�[�^�[���^�g���b�N�ɓ��ڂ����ꍇ�ɂ́A���ۂɑ�
�^�g���b�N�̏d�ʎԃ��[�h�R���6 - 7���قǂ̔R�����悹���邱�Ƃ͋ɂ߂ē�����̂ƍl������B����ɂ���
�́AAVL�͖��ӔC�Ȍ�������̐��l�\�����Ă���̂ł͂Ȃ����Ɗ����Ă���B
�@�܂��AAVL�����̍u���Œ�Ă��Ă��������̌�������̋Z�p���G���W���_�E���T�C�W���O�ł���B���̃G���W���_
�E���T�C�W���O�́A�Â�����ǂ��m��ꂽ�R�����̋Z�p�ł���A��^�f�B�[�[���g���b�N�̃��[�J������܂ŋ����ĊJ
�������{���Ă����Z�p�ł��邽�߁A�Z�p�I�ɂ͉��̖ڐV�����������R�����̎�@�ł���B
�E���T�C�W���O�́A�Â�����ǂ��m��ꂽ�R�����̋Z�p�ł���A��^�f�B�[�[���g���b�N�̃��[�J������܂ŋ����ĊJ
�������{���Ă����Z�p�ł��邽�߁A�Z�p�I�ɂ͉��̖ڐV�����������R�����̎�@�ł���B
�@�ȏ�̂悤�ɁA���E�I�Ȍ����@�ւł���AVL��2010�N�T���̍u���ł̒�ẮA�f�B�[�[���G���W���̌�������ɂ�
���Ă͌ÓT�I�Ȋ��m�̋Z�p�Ɍ����Ă���A�Z�p�I�ȖڐV�����͖����B�����āA��^�g���b�N�̔R�����Ɏ��ۂɖ�
�������ȐV�����Z�p�������������Ȃ��̂ł���B����ɂ�������炸�A���݁A���{�̑����̃g���b�N���[�J���L����
AVL����f�B�[�[���G���W�����̋Z�p�R���T���e�B���O���Ă���悤�ł��邪�AAVL�̃R���T���e�B���O�ɂ���đ�
�^�g���b�N�̔R��\���Ɍ���ł���\���́A�w��ǖ������̂ƍl���ėǂ��̂ł͂Ȃ����낤���B
���Ă͌ÓT�I�Ȋ��m�̋Z�p�Ɍ����Ă���A�Z�p�I�ȖڐV�����͖����B�����āA��^�g���b�N�̔R�����Ɏ��ۂɖ�
�������ȐV�����Z�p�������������Ȃ��̂ł���B����ɂ�������炸�A���݁A���{�̑����̃g���b�N���[�J���L����
AVL����f�B�[�[���G���W�����̋Z�p�R���T���e�B���O���Ă���悤�ł��邪�AAVL�̃R���T���e�B���O�ɂ���đ�
�^�g���b�N�̔R��\���Ɍ���ł���\���́A�w��ǖ������̂ƍl���ėǂ��̂ł͂Ȃ����낤���B
�W�|�S�D�����ԋZ�p���ő��������ŋ߂̃f�B�[�[�������̋^��_
�W�|�S�[(a)�@�����ԋZ�p��2010�N�P�����iVol.64�AN0.�P�A2010�j�̋L�ژ_���̋^��_
�@�����ԋZ�p��s�́u�����ԋZ�p�v��Vol.64�ANo.�P�A2010�i2010�N1���P�����s�j�̔ѓc�P�� �c���勳���@���R����
�́u�f�B�[�[���G���W�����̂P�O�N�v�ɂ̓f�B�[�[���G���W����CO�Q�팸�i���R��팸�j���u�傫�Ȓ���ۑ�v�ƒf�肵�A��
�́u�ۑ�B���v�ɂ́u�]���̃f�B�[�[���G���W���̗v�f�V�X�e���ɉ����A�R���A�R�āA�G�}�̌����A�V�X�e������̓�
�����Z�p�����߂��Ă���v�ƋL�ڂ���Ă���B�����[�I�ɒ��킷�ƁA�f�B�[�[���G���W���̔R��팸�i���b�n�Q��
���j�́A�u�Z�p�I�ɔ����ǂ���̏v�ɂ��邱�Əq�ׂ����̂ƍl������B���̂��Ƃ���A�ѓc�P�� �c���勳���@
���R�������A���̂P�O�N�ԂɃf�B�[�[���G���W���̔R�ĉ��P�ɂ��R��팸�i���b�n�Q�팸�j�ɗL���ȋZ�p�J���ɑ傫��
�i�W�������Ȃ������ƔF������Ă��邱�Ƃ��f����B
�@���̂悤�ɁA�u�����ԋZ�p�v���ɂ����āA2010�N�P�����́u�f�B�[�[���G���W�����̂P�O�N�v�i���ҁF�ѓc�P�� �c���勳
���@���R���j��2010�N8�����̓��W�F�N�Ӂ@�u�f�B�[�[���G���W���v�i���ҁFUD�g���b�N�X���@���ѐM�T���j�ɋL�ڂ���Ă�
����e������ƁA2010�N�̎��_�ł͑�^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W���ł��R�ĉ��P�ɂ��R��팸�i���b�n�Q�팸�j��
�L���ȋZ�p�����o����Ă��Ȃ����̂ƍl������B���̂��Ƃ���A�w��^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W���ɂ�����R��
�팸�́A�����_�ł��Z�p�I�ɔ����ǂ���̏��x�ƌ����Ă��ߌ��ł͂Ȃ����낤�B�������A�f�B�[�[���f�B�[�[���G
���W���̔R��팸�́A���̃G���W�����a�����Ĉȗ��A100�N�ȏ���c�X�Ɖ��nj������s�Ȃ��Ă����J���A�C�e���ł�
��B���̂��Ƃ��l����ƁA�R�ĉ��P�ɂ��f�B�[�[���G���W���̂T�����x�̔R��팸�́A������߂������Ɏ������邱
�Ƃ��ɂ߂č���Ȃ��Ƃł��邪�N�ł��e�Ղɑz���ł��邱�Ƃ��B
�W�|�S�[(b)�@�����ԋZ�p��2010�N8�����iVol.64�AN0.8�A2010�j�̓��W�F�N�ӂ̋^��_
�@�����ԋZ�p��2010�N8�����iVol.64�AN0.8�A2010�j�̓��W�F�N�Ӂ@�u�f�B�[�[���G���W���v�i���ҁFUD�g���b�N�X���@���ѐM
�T�@���j�́u�S�@�����J���̓����v�ɂ́A�f�B�[�[���G���W���̔r�o�K�X�ƔR����팸���邽�߂̍ŋ߂̋Z�p�������܂�
�߂��Ă���B���́u�S�@�����J���̓����v�ɂ́A�g���b�N���[�J���w�E�����@�ւ̑����̐��Ƃ��f�B�[�[���G���W��
�̔r�o�K�X�ƔR����팸���邽�߂ɗL���ƍl���Ă���Z�p�ɂ��āA�܂Ƃ߂��Ă��锤�ł���B�����N�Ӂ@�u�f�B�[�[
���G���W���v�́u�S�@�����J���̓����v�ɑ��A�M�҂��^��Ɋ�������e�ɂ��āA���L�̕\�P�P-�P�ɂ܂Ƃ߂��B
�T�@���j�́u�S�@�����J���̓����v�ɂ́A�f�B�[�[���G���W���̔r�o�K�X�ƔR����팸���邽�߂̍ŋ߂̋Z�p�������܂�
�߂��Ă���B���́u�S�@�����J���̓����v�ɂ́A�g���b�N���[�J���w�E�����@�ւ̑����̐��Ƃ��f�B�[�[���G���W��
�̔r�o�K�X�ƔR����팸���邽�߂ɗL���ƍl���Ă���Z�p�ɂ��āA�܂Ƃ߂��Ă��锤�ł���B�����N�Ӂ@�u�f�B�[�[
���G���W���v�́u�S�@�����J���̓����v�ɑ��A�M�҂��^��Ɋ�������e�ɂ��āA���L�̕\�P�P-�P�ɂ܂Ƃ߂��B
| |
|
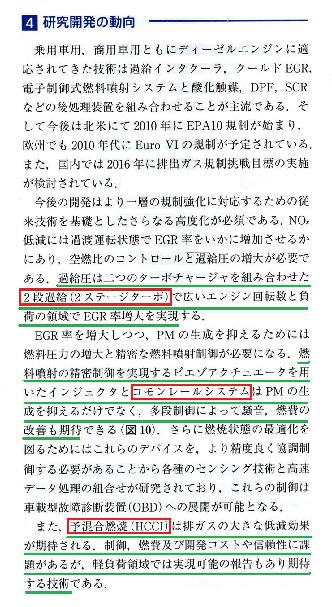 |
�@�����ԋZ�p��2010�N8�����̓��W�F�N�Ӂ@�u�f�B�[�[���G���W���v��
�u�S�@�����J���̓����v�ł́A����A�f�B�[�[���G���W����NO���팸��
�G���W���R��̍팸��}�邽�߂̗L���ȋZ�p�Ƃ��āA�g���b�N���[�J��
��w�E�����@�ւ̑����̐��Ƃ́A�ȉ��̋Z�p�Ɋ��҂���Ă���Ƃ�
���ƁB
���Q�i�ߋ�
���R�������[���i�������˂ƃs�G�]�C���W�F�N�^�ɂ�镬�˂̐�������j
���\�����R�āiHCCI�܂���PCI�j
�������A�O�q�̂W-1���Ŏ������悤�ɁA8���~�ȏ�̗\�Z�Ŏ��{���ꂽ
NEDO�̊v�V�I���������Q�ԑ����Z�p�J���i�N���[���f�B�[�[��
�v���W�F�N�g�A2004�`2009�N�j�́u�����x�R�Đ���G���W�V�X�e����
�����J���v�̑�^�v���W�F�N�g�ł͈ȉ��̋Z�p��g�ݍ��r�o�K�X
�팸�ƔR��팸�̌����J�������{���ꂽ�B
���@�R�i�ߋ��V�X�e���i�����ϗL�������j
���@300MP���̒������R�����ˁi�����ϗL�������j
���@�J�����X�V�X�e����g�ݍ��uPCI�R�āv
�@�@(PCI�R�ā�HCCI�R�āj
�@����NEDO�̑�^�v���W�F�N�g�ł́A�}�P�T�Ɏ������悤�ɁANOx�͖ڕW
��B���������A���݂̏ȃG�l���M�[�E�Ȏ����E��CO2�̎���ɋ��߂��
�Ă���̐S�v���R��팸�͖ڕW��10���팸�ɂ͑S���y���A
2015�N�x�d�ʎԔR���ɑ��ĂQ���̈����ƂȂ��Ă��܂���
�̂ł���B
�@�ȏ��NEDO�̑�^�v���W�F�N�g�̎������ʂ����\����Ă���ɂ�
������炸�A���L�������ԋZ�p��2010�N8�����̓��W�F�N�Ӂ@
�u�f�B�[�[���G���W���v�́u�S�@�����J���̓����v�ł́A���҂�UD
�g���b�N�X�����ѐM�T�����u�Q�i�ߋ��v�A�u�R�������[���ɂ�钴����
�R�����ˁv����сu�\�����R�āiHCCI�j�v�ɂ���ăf�B�[�[��
�G���W���̔R��팸�𖢂��Ɋ��҂���Ă���悤�ɋL�q����Ă���
���ƂɈ�a���������Ă���B
�@���������ԋZ�p��2010�N8�����̓��W�F�N�ӂ����҂ł���UD
�g���b�N�X�����ѐM�T���́ANEDO�̑�^�v���W�F�N�g�̎������ʂ�����
����Ɓu�Q�i�ߋ��v�{�u�R�������[���i�������˂ƃs�G�]�C���W�F�N�^�ɂ��
���˂̐�������j�v�{�u�\�����R�āiHCCI�܂���PCI�j�v�̋Z�p�ł͔R��
�팸������Ȃ��Ƃ͏��m����Ă���̂ł͂Ȃ����낤���B
�������Ȃ���A�����̋Z�p�ȊO�ɑ�^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W����
�R��팸�Z�p���c�_����Ă��Ȃ��̂ł͂Ȃ����낤���B�܂�A�����_
�ŔR��팸�ɗL���ȋZ�p�Ă������o���Ă��Ȃ����̂Ɛ��������B
���������āA���̏𐳒��ɋL�ڂ���A2010�N8�������N�ӂ�
�u�����J���̓����v�ł͑�^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W���̔R�
�팸�ł���Z�p���u���݂̂Ƃ���s���v�ƕs�l�ȓ��e�̋L�ڂƂȂ���
���܂��̂ł���B
�������A��牽�ł��u�f�B�[�[���G���W���̔R��팸�Z�p���s���v�Ƃ�
�L�q�ł��Ȃ����߁A���҂̏��ѐM�T���́A�s�{�ӂȂ����^�g���b�N�p
�f�B�[�[���G���W���̔R��팸�����҂ł���Z�p�Ƃ��Ďd�������u�Q�i
�ߋ��v�{�u�R�������[���i�������˂ƃs�G�]�C���W�F�N�^�ɂ�镬�˂̐���
����j�v�{�u�\�����R�āiHCCI�܂���PCI�j�v���L�ڂ����ꂽ�̂ł͂Ȃ�
���낤���B
�P�O�N�v�i���ҁF�ѓc�P�� �c���勳���@���R���j�ł͑�^�g���b�N�p �f�B�[�[���G���W���ł͔R�ĉ��P�ɂ��R��팸�i���b�n�Q�팸�j�� �u����ۑ�v�L�q����A�w��^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W���ɂ�����R�� �팸�́A�����_�ł͋Z�p�I�ɔ����ǂ���̏x�̎|���f���Ɏ咣 ����Ă���̂ł���B������ѓc�P�� �c���勳������^�g���b�N�p �f�B�[�[���G���W���ɂ�����R��팸���ɂ߂č���ł���Ƃ̌����� �����ɓf�I����Ă���̂ł͂Ȃ����Ǝv���Ă���B �@���݁A�|�X�g�V�����r�o�K�X�K���i2009�N�K���j�ɓK���̑�^�g���b�N�E �g���N�^�ł́A��q�̕\�X�Ɏ����Ă���悤�ɁA�����̎Ԏ킪2015�N�x �d�ʎԔR���ɕs�K���ƂȂ��Ă���̂ł���B���̂��Ƃ��琄�@ ����ƁA�g���b�N���[�J�ł͑�^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W���ɂ����� ���p���̍����R��팸�̋Z�p���J���ł��Ă��Ȃ����̂ƍl������B �@�������Ȃ���A�g���b�N���[�J�̋Z�p�҂ł��钘�҂̏��ѐM�T���́A �ѓc�P�� �c���勳���̂悤�ɋC�y�ɁA�w��^�g���b�N�p�f�B�[�[�� �G���W���ɂ�����R��팸�́A�����_�ł͋Z�p�I�ɔ����ǂ��� �̏��x�̎�|�̔��������邱�Ƃ��ł��Ȃ�����ł��邱�Ƃ͊m���� ���Ƃ��B���̗��R�́A���ɁAUD�g���b�N�X���̏��ѐM�T�����w��^ �g���b�N�p�f�B�[�[���G���W���̔R��팸�̋Z�p���s���x�Ƃ̔����� �s�����Ƃ���AUD�g���b�N�X���́A�g���b�N���[�J�̋Z�p�͂ɑ��� �g���b�N���[�U����M������r�����Ă��܂��ƍl�����邽�߂��B �@���̂悤�ɁA��^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W���̔R��팸�̋Z�p�J�� ����l�܂�̏Ɋׂ��Ă��鎞���ɁA�����ԋZ�p��2010�N8������ ���W�F�N�Ӂ@�u�f�B�[�[���G���W���v�̒��q��S�������ꂽUD�g���b�N�X ���̏��ѐM�T���̕s�K�ɂ́A�����̐l������̔O�������Ă��� �̂ł͂Ȃ����낤���B |
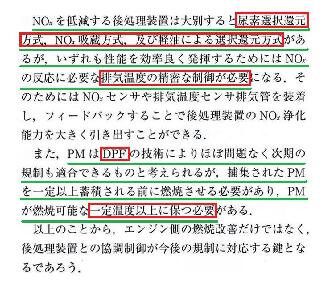 |
�@��ʓI�ɑ�����NOx�ጸ�̌㏈�����u�ɂ����č���NO���팸����
�������邽�߂ɂ́A�r�C�K�X���x����背�x���ȏ�̍����Ɉێ�����
���Ƃł���B���̂��߂ɂ́A�r�C�K�X���x�̒Ⴂ�G���W���ᕉ�ׂ�
�����Ĕr�C���x�����������鑕�u�E��i�i�A�C�f�A�j���K�v������B
�����āA���̔r�C���x�����������鑕�u�E��i���G���W���ɓ��ڂ��A
���̑��u�E��i��r�C�K�X���x�̃t�B�[�h�o�b�N���䂵�A��背�x��
�ȏ�̍����̔r�C�K�X���x�Ɉێ��ł���悤�ɂ���̂ł���B
����ɂ���āA���߂�NOx�ጸ�̌㏈�����u�ł�NO���팸��������
�ł���̂��B�������A���炩�̔r�C���x�����������鑕�u�E��i��p����
���Ɩ����A�u�r�C���x�̐����Ȑ���v�����ł�NOx�ጸ�̌㏈�����u
�ł�NO���팸���̌���͋ɂ߂č���ł���B
�@�Ƃ��낪�A�u�S�@�����J���̓����v�̍��L�̋L�q�ɂł́ANOx�ጸ��
�㏈�����u�ł̍���NO���팸�����������邽�߂ɁA���𐧌䂵��
��背�x���ȏ�̍����r�C���x�ɐ��䂷�邩�ɂ��āA��̓I��
�Z�p���e�������L�ڂ���Ă��Ȃ��̂ł���B����́ANO���팸�̉ۑ�
��������������Ă���̉߂��Ȃ��̂ł���B���̂悤��NO���팸�̉ۑ�
�����̋L�q�ł́A�����J���̓����ƌ����Ȃ����낤�B
��ʓI�ɉ]���āA���L�̂悤�Ɂu�����J���̓����v�̍��Ɂu�r�C�K�X ���x�̍����Ɉێ����邱�Ƃ��K�v�v�Ƃ́u�ۑ��v�������L�ڂ��A���� �u�ۑ�v������������Z�p�������L�ڂ���Ă��Ȃ��ꍇ�́A�u�ۑ�v�� ��������Z�p(�A�C�f�A�j���u�s���v�̂��߂ƍl���ĊԈႢ�Ȃ��� �l������B ���������č��L�̂悤�Ɂu�����J���̓����v�̍��ɂ́u�A�fSCR�G�} ���ɂ��NO���팸�̌����DPF���u�ł̋����Đ��̕p�x�팸 �̂��߂ɕK�v�ȃG���W���ᕉ���ɔr�C�K�X���x������������ �Z�p�́A�����_�ł͕s���ł���v�ƋL�q���ׂ��ł͂Ȃ����낤���B �@���āA�����ԋZ�p���́A���ǐ��x�ɂ���ċL���͐�������Ă���� �����Ă���B���̔N�ӂɂ����āA�u�����J���̓����v�Ƒ肵�����ڂ̒� �ł́A�G���W���ᕉ���ɔr�C�K�X���x�����������邽�߂̋�̓I�� �Z�p�������L�ڂ���Ă��Ȃ��̂��B���̂��Ƃ́A���҂̏��ѐM�T���� �r�C�K�X���x�����������邽�߂̋�̓I�ȋZ�p�ɂ��Ă̌��\�ł��� �m���E�����������łȂ������Ɖ]�����A�g���b�N���[�J���w�E���� �@�ւ̑����̐����������ԋZ�p���̔N�ӂɖ��L�ł���悤�� �u�r�C�K�X���x������������Z�p�̈āi�A�C�f�A�j�������A�Z�p�I�� �����ǂ���̏Ɋׂ��Ă���v�ƍl����̂��Ó��̂悤�Ɏv���� �̂ł���B �@����A�M�҂́A�u�f�B�[�[���G���W���ᕉ���ɔr�C�K�X���x�� ���������邽�߂̋Z�p�v�Ƃ��āA�Q�^�[�{�����̋C���x�~�G���W�� �i�������J2005-54771�j�v�̋Z�p���Ă��Ă���B�����C���x�~ �G���W���i�������J2005-54771�j�́A�A�N�Z���y�_�������ݗ� ��50���ȉ��̃G���W���^�]�̗̈�ɂ����Ĕ����̋C�����x�~ ���A����ɂ���āA�����I�ȃG���W���̃_�E���T�C�W���O�ɂ���� �R��팸�ł���Z�p���B���̔R��팸�Ɠ����ɁA�ғ��C���Q �̔r�C�K�X���x���\���ɍ������ł��邽�߁A�A�fSCR�G�}���� NO���팸�̌㏈�����u�ł�NO���팸��������ł��ADPF���u�� ���R�Đ��̑��i���\�ɂȂ��̂ł���B �@���̋C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p���A2006�N4�� �ɊJ�݂����M�҂̃z�[���y�[�W�ɋL�ڂ��A����4�N�ȏ���ȑO������J ���Ă���B�������A���L�������ԋZ�p���̔N�ӂ̋L�q���������A�M�� �̒�Ă����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�́A���S�ɖ��� ����Ă��邱�Ƃ������B �@�����_�Ŕr�C�K�X���x�������Ɉێ��ł���Z�p�Ă������ۗL ���Ă��Ȃ��g���b�N���[�J���w�E�����@�ւ̑����̐��Ƃ��A�r�C �K�X���x�̍������ɗL�����C���x�~�G���W���i�������J2005- 54771�j����ȂɖَE���A�ь������闝�R�́A��̑S�́A���Ȃ̂� ���낤���B |
�@�ȏ�̂��Ƃ���A���̎����ԋZ�p��2010�N8�����iVol.64�AN0.8�A2010�j�̓��W�F�N�Ӂ@�u�f�B�[�[���G���W���v�́u�S�@��
���J���̓����v�ɋL�ڂ��ꂽ�Z�p���e������ƁA�����̋Z�p�ɂ���č���̃f�B�[�[���G���W���̒�R��ƒ�m�n��
�𐄐i���Ă������Ƃ͓���̂ł͂Ȃ����Ǝv����B���́u�S�@�����J���̓����v�̋L�ړ��e�ɂ��Ă̋^��_���A�\
�P�P�|�Q�ɂ܂Ƃ߂��B
���J���̓����v�ɋL�ڂ��ꂽ�Z�p���e������ƁA�����̋Z�p�ɂ���č���̃f�B�[�[���G���W���̒�R��ƒ�m�n��
�𐄐i���Ă������Ƃ͓���̂ł͂Ȃ����Ǝv����B���́u�S�@�����J���̓����v�̋L�ړ��e�ɂ��Ă̋^��_���A�\
�P�P�|�Q�ɂ܂Ƃ߂��B
| |
�@�f�B�[�[���G���W���̔r�o�K�X�K���ɂ��ẮA����A�k�Ăł�2010��EPA10�K���A���B�ł�2010�N���Euro �Y�K���A�����ł�
2016�K�����\�肳��Ă���B�����̔r�o�K�X�K���ւ̓K���ɂ́A�����̎����ԃ��[�J����Ƃ́A�ߓn�^�]��Ԃł�EGR���̑�����
�K�v�ƍl���Ă���悤���B�����āA����EGR���̑����ɂ���Đ�����PM�����̕s����������邽�߁A�Q�i�ߋ��A����уs�G�]
�A�N�`���G�[�^��p�����R�������[���V�X�e���ɂ�鍂���������L���ƍl���Ă���l�������悤���B�������\�����R�āiHCCI or PCI)
�ɂ��NO����PM�̍팸�����҂���l�����ƌ�����B
�@�������A2004�`2009�N�Ɏ��{���ꂽNEDO�̊v�V�I���������Q�ԑ����Z�p�J���i�N���[���f�B�[�[���v���W�F�N�g�A�j�́u�����x�R��
����G���W�V�X�e���̌����J���v�ł́A�R�i�ߋ��V�X�e���A300MP���̒������R������������J���X�V�X�e����g�ݍ��uPCI
�R�āv�iPCI�R�ā�HCCI�R�āj�ł́A�R��팸�͖ڕW��10���팸�ɂ͑S���y���A2015�N�x�d�ʎԔR���ɑ��ĂQ���̈�����
���Ɋm�F����Ă���̂ł���B
�@���̂��Ƃ���A�����̎����ԃ��[�J����Ƃ������Z�p�Ƃ��Ċ��҂��Ă����Q�i�ߋ��A�R�������[���V�X�e���ɂ�鍂�����ˁA�����
�\�����R�āiHCCI or PCI)�́ANO���̍팸��PM�̑����h�~�ɂ͗L���ł͂��邪�A�R��팸�ɂ͌��ʂ������A�����_�ł͔R��팸��
�L���ȋZ�p�͌����o���Ă��Ȃ��悤���B
�@�����āA�A�fSCR�G�}���ɂ��NO���팸�̌����DPF���u�ł̋����Đ��̕p�x�팸�̂��߂ɕK�v�ȃG���W���ᕉ���ɔr�C
�K�X���x������������Z�p�́A�����_�ł��s���ƍl������B
|
�̓����v�ɋL�ڂ���Ă�����e������ƁA���̎��_�ł̎����ԋƊE��f�B�[�[���G���W���w��ł́A�f�B�[�[��
�G���W���̔R��팸�̋Z�p���s���ł���A�܂��A�fSCR�G�}����NO���팸�̌㏈�����u��ADPF���u�ł̋�
���Đ��̕p�x�팸�̂��߂̃G���W���ᕉ���ɔr�C�K�X���x������������Z�p���s���Ƃ̂��Ƃł���B
�W�|�S�[(c)�@�����ԋZ�p��2011�N8�����iVol.65�AN0.8�A2011�j�̓��W�F�N�ӂ̋^��_
�����ԋZ�p��2010�N8�����iVol.65�AN0.8�A2011�j�̓��W�F�N�Ӂ@�u�f�B�[�[���G���W���v�i���ҁF�����U�����ԇ��@�`���q
���@���j�́u�S�@�����J���̓����v�ɂ́A�f�B�[�[���G���W���̔r�o�K�X�ƔR����팸���邽�߂̍ŋ߂̋Z�p�������܂�
�߂��Ă���B���́u�S�@�����J���̓����v�ɂ́A�g���b�N���[�J���w�E�����@�ւ̑����̐��Ƃ��f�B�[�[���G���W��
�̔r�o�K�X�ƔR����팸���邽�߂ɗL���ƍl���Ă���Z�p�ɂ��āA�܂Ƃ߂��Ă��锤�ł���B�����N�Ӂ@�u�f�B�[�[
���G���W���v�́u�S�@�����J���̓����v�ɑ��A�M�҂��^��Ɋ�������e�ɂ��āA���L�̕\�P�P�|�R�ɂ܂Ƃ߂��B
���@���j�́u�S�@�����J���̓����v�ɂ́A�f�B�[�[���G���W���̔r�o�K�X�ƔR����팸���邽�߂̍ŋ߂̋Z�p�������܂�
�߂��Ă���B���́u�S�@�����J���̓����v�ɂ́A�g���b�N���[�J���w�E�����@�ւ̑����̐��Ƃ��f�B�[�[���G���W��
�̔r�o�K�X�ƔR����팸���邽�߂ɗL���ƍl���Ă���Z�p�ɂ��āA�܂Ƃ߂��Ă��锤�ł���B�����N�Ӂ@�u�f�B�[�[
���G���W���v�́u�S�@�����J���̓����v�ɑ��A�M�҂��^��Ɋ�������e�ɂ��āA���L�̕\�P�P�|�R�ɂ܂Ƃ߂��B
| |
|
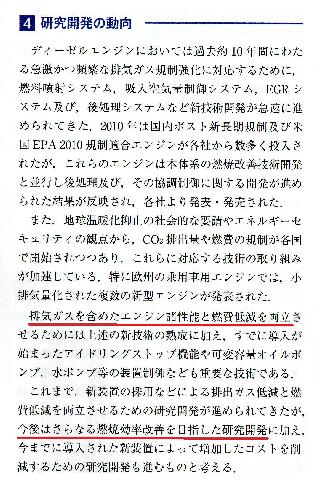 |
�@�����ԋZ�p��201�P�N8�����̓��W�F�N�Ӂ@�u�f�B�[�[���G���W���v��
�u�S�@�����J���̓����v�ł́A�����U�����Ԃ̊`���q�����́A����A
�u�r�o�K�X���܂߂��G���W�������\�ƔR��ጸ�̗����v��}�邽�߂�
�L���ȐV���ȋZ�p�Ƃ��āA�u����Ȃ�R�Č������P��ڎw��������
�J���v�ƋL�ڂ���Ă��邾���ł���B�����āA���̔R�Č������P�̊O��
�r�o�K�X�ጸ�ƔR����P�̕��@�Ƃ��ẮA���Ɏ��p������Ă���
�A�C�h���X�g�b�v�A�ϗe�ʃI�C���|���v�A���|���v���̑��u�����
�����A�����āA�s�̎Ԃɓ��ڂ̊����Z�p���u�n���v����Əq�ׂ���
����B
�@�������A�����Z�p�̉��ǂ́A�G���W���S�̂ŏ�Ɏ��{�����ׂ����e
�ł���A�r�o�K�X�팸�ƔR����P�Ɋ֘A�����Z�p�����Ɍ��肳���
���̂ł͂Ȃ��B���������āA�����ԋZ�p���̔N���́u�S�@�����J����
�����v�ɓ��ɋL�q����K�v�̖������e�ƍl������B
�@�܂��A���������f�B�[�[���G���W���͓��R�@�ւł��邽�߁A�R�ĉ��P
���K�v�Ȃ��Ƃ́A���̃G���W���̒a���ȗ��̏h���ł���A�����ĉۑ�
�ł�����B���������āA�����ԋZ�p���̓ǎ҂��m�肽�����Ƃ́A�R��
���P���\�ɂ����̓I�ȐV�����Z�p�ł��邪�A�`���q������
�u�S�@�����J���̓����v�ł́A�R�ĉ��P�̋�̓I�ȋZ�p�������L�ڂ���
�Ă��Ȃ��̂��B
�@���������āA�����U�����Ԃ̊`���q�����́A���L���u�S�@�����J����
�����v�ł́A�f�B�[�[���G���W���ɂ�����u�r�o�K�X�팸�v�A�u�R����P�v
����сu�R�ĉ��P�̕K�v���v�̉ۑ���q�ׂ��Ă��邾���ł���A����
�J���̓����ł���ۑ����������Z�p�̓��e�������L�ڂ����
���Ȃ��̂��B���������āA���L�́u�S�@�����J���̓����v�̍��́A����
�̖��ʎg���ƍl������B
�@�ȏ�̂悤�ɁA�g���b�N���[�J�̋Z�p�҂ł���`���q�����́A
�u�S�@�����J���̓����v�ł́A�f�B�[�[���G���W���ɂ�����u�r�o�K�X
�팸�v�A�u�R����P�v�̉ۑ�������ł���V�����Z�p����̓I�ɉ���
�L�ڂł��Ȃ������悤���B���̂��Ƃ���A�g���b�N���[�J�́A�����_
�ł̓f�B�[�[���G���W���ɂ�����uNO���팸�v�Ɓu�R����P�v��
�Z�p�I�Ɏ�l�܂�̏ł����ƍl���āA�傫�ȊԈႢ�͖���
���̂Ɛ��@�����B����͕M�҂̕��������ł��낤���B
�@�����Ƃ��A�����U�����Ԃ��ŋߗ��s�̃^�[�{�R���p�E���h�̌����J��
���s���Ă���Ƃ��Ă��A�����U�����Ԃ̎Ј��Ƃ��Ă̋@���ێ��̗���
����A�`���q�����͂��̔N�ӂ́u�S�@�����J���̓����v�̍��Ƀf�B�[
�[���́u�R����P�v�̐V�����Z�p�Ƃ��āA�^�[�{�R���p�E���h���L�ڂł�
�Ȃ������\�����ے�ł��Ȃ��B�������A
�ڏq���Ă���悤�ɁA�^�[�{�R���p�E���h�́A�f�B�[�[���R��̏\����
�R����P�ɂ͖����ȋZ�p�ł��邽�߁A�����U�����Ԃ̊`���q�����́A
�����U�����Ԃ̎Ј��Ƃ��Ă̋@���ێ��`���̗L���̔@����
������炸�A���̔N�ӂŃf�B�[�[���G���W���ɂ�����u�R����P�v��
�ۑ����������Z�p�������I�ɉ����L�ڂł��Ȃ����Ƃɕς��͖���
�ƍl������B
|
�@�ȏ�̂悤�ɁA�����ԋZ�p��2011�N8�����iVol.65�AN0.8�A2011�j���W�F�N�Ӂ@�u�f�B�[�[���G���W���v���u�S�@�����J��
�̓����v�ɋL�ڂ���Ă�����e������ƁA2010�N�Ɠ��l�ɁA���݂̎����ԋƊE��f�B�[�[���G���W���w���
�́A�f�B�[�[���G���W���̔R��팸�̋Z�p���s���ł���A�܂��A�fSCR�G�}����NO���팸�̌㏈�����u��A
DPF���u�ł̋����Đ��̕p�x�팸�̂��߂̃G���W���ᕉ���ɔr�C�K�X���x������������Z�p���s���̏�
���ł���Ɛ��@�����̂ł����B
�@�Ƃ���ŁA�f�B�[�[���G���W���̉ۑ�ł���u�R��팸�v�A�u�A�fSCR�G�}����NO���팸��DPF���u�ł̋����Đ��̕p
�x�팸�̂��߂̃G���W���ᕉ���ɔr�C�K�X���x���������v�́A�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p��
�̗p�ɂ���ėe�ՂɎ����ł���ƍl���Ă���B�ʂ����āA���N�̎����ԋZ�p��2012�N8�����̓��W�F�N�Ӂ@�u�f�B�[�[��
�G���W���v�ł́A����܂łƓ��l�ɁA�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p���E�َE���Ȃ���A����܂ł�
���ς�炸�A�f�B�[�[���G���W���̉ۑ�ł���u�R��팸�v�A�u�A�fSCR�G�}����NO���팸��DPF���u�ł̋����Đ���
�p�x�팸�̂��߂̃G���W���ᕉ���ɔr�C�K�X���x���������v�̋Z�p�͕s���Ƃ�����e���L�ڂ����̂ł��낤���B
���N�̎����ԋZ�p��2012�N8�����Ɍf�ڂ����Ɨ\�z�������W�F�N�Ӂ@�u�f�B�[�[���G���W���v�̋L�ړ��e���y����
�ł���B
�W�|�S�[(��)�@�����ԋZ�p��2012�N8�����iVol.66�AN0.8�A2012�j�̓��W�F�N�ӂ̋^��_
�����ԋZ�p��2012�N8�����iVol.66�AN0.8�A2012�j�̓��W�F�N�Ӂ@�u�f�B�[�[���G���W���v�i���ҁF���쎩���ԇ��@�����@��
�@���j�́u�S�@�����J���̓����v�ɂ́A�f�B�[�[���G���W���̔r�o�K�X�ƔR����팸���邽�߂̍ŋ߂̋Z�p�������܂Ƃ�
���Ă���B���́u�S�@�����J���̓����v�ɂ́A�g���b�N���[�J���w�E�����@�ւ̑����̐��Ƃ��f�B�[�[���G���W����
�r�o�K�X�ƔR����팸���邽�߂ɗL���ƍl���Ă���Z�p�ɂ��āA�܂Ƃ߂��Ă��锤�ł���B�����N�Ӂ@�u�f�B�[�[��
�G���W���v�́u�S�@�����J���̓����v�ɑ��A�M�҂��^��Ɋ�������e�ɂ��āA���L�̕\�P�P�|�S�ɂ܂Ƃ߂��B
�@���j�́u�S�@�����J���̓����v�ɂ́A�f�B�[�[���G���W���̔r�o�K�X�ƔR����팸���邽�߂̍ŋ߂̋Z�p�������܂Ƃ�
���Ă���B���́u�S�@�����J���̓����v�ɂ́A�g���b�N���[�J���w�E�����@�ւ̑����̐��Ƃ��f�B�[�[���G���W����
�r�o�K�X�ƔR����팸���邽�߂ɗL���ƍl���Ă���Z�p�ɂ��āA�܂Ƃ߂��Ă��锤�ł���B�����N�Ӂ@�u�f�B�[�[��
�G���W���v�́u�S�@�����J���̓����v�ɑ��A�M�҂��^��Ɋ�������e�ɂ��āA���L�̕\�P�P�|�S�ɂ܂Ƃ߂��B
| |
|
|||||||||||||||||||||||||||
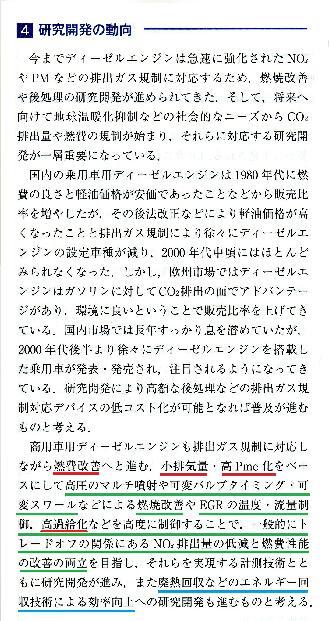 |
�P�D����������������NO���팸�ƔR��ጸ�̋Z�p�i���L�Q�Ɓj
�����ԋZ�p��201�P�N8�����̓��W�F�N�Ӂ@�u�f�B�[�[���G���W���v��
�u�S�@�����J���̓����v�ł́A���쎩���ԇ��@�����@���@���́A����A
�uNO���팸�ƔR��ጸ�̗����v��}�邽�߂̗L���ȐV���ȋZ�p�Ƃ��āA
�ȉ��̋Z�p���L�ڂ���Ă���B
���@�G���W���̃_�E���T�C�W���O
�@�@�E���r�C��
�@�@�E��Pme
�@�@�E���ߋ���
���@NO���r�o�ƔR��\�̃g���[�h�I�t�W�̉���
�@�@�iNO���r�o�ʂ̍팸�ƔR��\���P�̗����j
�@�@�E�����̃}���`����
�@�@�E�σo���u�^�C�~���O
�@�@�E�σX���[��
�@�@�EEGR�̉��x�E���ʐ���̍��x���䉻
���@�p�M����Ȃǂ̃G�l���M�[����Z�p
�@���쎩���ԇ��̐��� ���������L�́u�S�@�����J���̓����v�̒���
�����u�r�o�K�X�ƔR��ጸ�v�̋Z�p�́A�قƂ�ǂ�����10�N�ȏ��
�ȑO���瑽���̊w�ҁE���Ƃ��b��Ɏ��グ���Ă���u��C�܂݂�
�̋Z�p�v�ł���A���Ɍ��s�̑�^�g���b�N�ɍ̗p����Ď��p������Ă���
�Z�p�������B���̂��߁A���L�̘_����ǂf�B�[�[���G���W���Z�p��
�́A���� ���������L�ɋ������Z�p��p���āA����̑�^�g���b�N��
�u�r�o�K�X�ƔR��ጸ�v�ɑ傫���v���ł���Ƃ͍l����ƍl����l�B��
�����̂ł͂Ȃ����Ɛ��������B���̂悤�ɕM�҂��l���闝�R���A�ȉ�
�Ɏ����B
�P�|�P�@�G���W���̃_�E���T�C�W���O�̋^��_
�@�@�@�@�@�E���r�C��
�@�@�@�@�@�E��Pme
�@�@�@�@�@�E���ߋ���
�@��ʂɁA�G���W�����u���r�C�ʁv�ɂ��āu���ߋ����v���A�����āu��Pme�v
�Ƃ��āA��r�C�ʂ̃G���W���Ɠ����̏o�͂��m�ۂ���Z�p�I�Ȏ�@��
�u�G���W���̃_�E���T�C�W���O�v�ƌĂ�ł���B�����āA�]���̑�r�C��
�̃G���W���𓋍ڂ��������ԂƓ�����GVW�̎����ԂɁA���̑�r�C��
�G���W���Ɠ����̏o�͂��m�ۂ����_�E���T�C�W���O�G���W���𓋍ڂ���
�����Ԃ��s�̂���Ă���B�ŋ߂̏�p�Ԃ̃K�\�����G���W���ɂ�����
�_�E���T�C�W���O�G���W���Ƃ��ẮA�i�Ɓj�t�H���N�X���[�Q���i�u�v�j
�u�S���t�v�Ɓu�|���v�ɓ��ڂ���Ă���s�r�h�G���W�����L���ł���B
�@�Ƃ���ŁA�킪���ɂ������^�g���b�N�ɂ��ݕ��A���ɂ͒P�ԁi���ʏ�
�̑�^�J�[�S�g���b�N�̃^�C�v�j��p�����邱�Ƃ������B���̑�^�J�[�S
�g���b�N��GVW�i���ԗ����d�ʁj�́A���H��ʖ@�̕ۈ���ɂ���čő�
GWW��25�g���ȉ��ɐ�������Ă���B���̂��߁A�������̉ݕ���A��
����^���Ǝ҂́A�����̐ύڗʂ��\�ɂ��邽�߁AGVW25�g���̑�^
�J�[�S�g���b�N���g�p���邱�Ƃ������B���̂��߁A��^�g���b�N�̒��ł́A
�̔��䐔�̍ł������Ԏ킪GVW25�g���̑�^�J�[�S�g���b�N�ł���B
�@���݁A�����̃g���b�N���[�J�S�Ђɂ�����GVW25�g���̑�^�J�[�S�g���b�N
�ɓ��ڂ���Ă���G���W���́A���r�C�ʁA�ő�o�͂���яd�ʎԃ��[�h
�R���Z�߂�ƁA�ȉ��̒ʂ�ł���B
�������A�ȉ��̕\�ɋL�ڂ����d�ʎԃ��[�h�R��́A2015�N�x�d�ʎ�
�R���ɓK��������^�J�[�S�g���b�N�iGVW25�g���j�̔R���Z�߂�
���̂ł���B
�@��L�̕\�̂悤�ɁA���݁A�����̃g���b�N���[�J�S�Ђ��̔����Ă���
��^�J�[�S�g���b�N�iGVW25�g���j�ɂ́A�e�Ђ̑�^�J�[�S�g���b�N�ɂ́A
�l�X�Ȕr�C�ʂ̃G���W�������ڂ���Ă���B�����ŁA��^�J�[�S�g���b�N
�iGVW25�g���j�ɓ��ڂ���Ă���O�H�ӂ������U�q�P�O�G���W���i�P�R���b�g��
���j�Ƃ����U���U�t�y�P�G���W���i�P�O���b�g�����j���r����ƁA�����U��
�U�t�y�P���O�H�ӂ������U�q�P�O�����r�C�ʂ��Q�R�������r�C�ʂł���B
�������A�U�q�P�O�̏o�͂�257�`309 �i��W�j�A�U�t�y�P�̏o�͂�243�`294
�i��W�j�ł���A�O�H�ӂ������U�q�P�O�G���W���Ƃ����U���U�t�y�P�G���W����
�o�͂́A�قړ������x���ł���B���̗��R�́A���G���W���̏o�͂���^
�J�[�S�g���b�N�iGVW25�g���j�̕K�v�ȑ��s���\���������邽�߂̗v������
�Ă��铮�͂ł��邽�߂��B���������āA�����U���U�t�y�P�G���W�����r�C�ʂ�
�O�H�ӂ������U�q�P�O�G���W�����r�C�ʂ����Q�R�������r�C�ʂł����
������炸�A�����U���U�t�y�P�G���W���̏o�͂��O�H�ӂ������U�q�P�O
�G���W���Ƃقړ������x���ɂ��Ă���̂ł���B���̂��Ƃ���A�����U��
�U�t�y�P�G���W���́A��^�J�[�S�g���b�N�iGVW25�g���j�̕���ł́u�_�E��
�T�C�W���O�v�̃G���W���ƕ��ނ��邱�Ƃ��\���B
�@����A2015�N�x�d�ʎԔR���ɓK�������O�H�ӂ����̑�r�C��
�G���W���𓋍ڂ�����^�J�[�S�g���b�N�iGVW25�g���j�̏d�ʎԃ��[�h�R��
��4.05(km/���j�ł���A�����U�������̃_�E���T�C�W���O�G���W���𓋍ڂ���
��^�J�[�S�g���b�N�iGVW25�g���j�̏d�ʎԃ��[�h�R���4.15�`4.05 (km/���j
�ł���B���̂悤�ɁA�O�H�ӂ����̑�r�C�ʃG���W���̑�^�J�[�S
�g���b�N�iGVW25�g���j�Ƃ����U�����Ԃ̃_�E���T�C�W���O�G���W��
�̑�^�J�[�S�g���b�N�iGVW25�g���j�̏d�ʎԃ��[�h�R��́A����
2015�N�x�d�ʎԔR���ɃL���M���̐����Őh�����ēK���ł���
����4.15�`4.05 (km/���j���x�œ����ł���B���̂��Ƃ���A�����U
�����Ԃ́u�_�E���T�C�W���O�G���W���v�𓋍ڂ��Ă���2015�N�x
�d�ʎԔR���ɓK��������^�J�[�S�g���b�N�iGVW25�g���j�ł́A
�u�_�E���T�C�W���O�G���W���v���^�J�[�S�g���b�N�iGVW25�g���j��
�̗p���Ă���ɂ�������炸�A�d�ʎԃ��[�h�R��w�lj��P�ł���
���Ȃ����Ƃ����炩���B
�@�܂��A���쎩���Ԃ���^�J�[�S�g���b�N�iGVW25�g���j�ɂ����āA�P�R
���b�g�������d�P�R�b�����ڂ����Ԏ�ƂX���b�g�������`�O�X�b���ڂ���
�Ԏ�Ƃ�2015�N�x�d�ʎԔR���ɓK�������̏d�ʎԃ��[�h�R���
��r�����ꍇ���A���g���b�N�Ƃ��d�ʎԃ��[�h�R�4.15�`4.05 (km/���j��
���x���ł���A���G���W���𓋍ڂ�����^�g���b�N�̔R������ł���B
���̂��Ƃ���A�����U�����Ԃ̏ꍇ�Ɠ��l�ɁA���쎩���Ԃ��u�_�E��
�T�C�W���O�G���W���v�𓋍ڂ��Ă���2015�N�x�d�ʎԔR����
�K��������^�J�[�S�g���b�N�iGVW25�g���j�ł́A�u�_�E���T�C�W���O�v
�G���W���ɂ��d�ʎԃ��[�h�R��̉��P���ق�̋͂���������
�ł��Ă��Ȃ��悤�ł���B���̂悤�ɁA���쎩���Ԃɂ������^�J�[�S
�g���b�N�iGVW25�g���j�́u�_�E���T�C�W���O�G���W���v�ł��R����P��
�͏��ł��邱�Ƃ���A�쎩���ԇ��̐��� �����́A��^�g���b�N�ɂ�����
�u�_�E���T�C�W���O�v�G���W���ɂ��R����P������Ȃ��Ƃ��A���R�̂���
�Ȃ���\���ɏn�m���Ă��锤�ł���B
�@���̑�^�f�B�[�[���g���b�N�ɂ�����u�_�E���T�C�W���O�v�G���W���ɂ��R��
���P������ȗ��R������ƁA�ȉ��̒ʂ�ƍl������B �@ �f�B�[�[���G���W���́A�ŋ߂̌�����NO�������PM�̋K���ɓK������
���߁A�g���b�N�p�G���W���̑S�ĂɃC���^�[�N�[���ߋ����̗p�ς݂ł���B
�f�B�[�[���g���b�N�̃C���^�[�N�[���ߋ��f�B�[�[���G���W���ł͖��ߋ�
�G���W���ɔ�ׂĊ��ɃG���W�������r�C�ʂƂ����_�E���T�C�W���O��
�Ȃ��Ă���B���̂��߁A�g���b�N�p�̃C���^�[�N�[���ߋ��f�B�[�[��
�G���W���́A���ߋ��G���W�����嗬�̃K�\�����G���W���Ɠ��l�̐�����
�啝�ȃ_�E���T�C�W���O������ł���B
�i�������_�ł̓g���b�N�p�f�B�[�[���G���W���́A�S�ĂɃC���^�[
�N�[���ߋ����̗p�ςł��邽�߂ɏ��r�C�ʉ�����ʉ����Ă���A
���ߋ��G���W�����嗬�̃K�\�����G���W���̂悤�ȁA�啝�ȃ_�E��
�T�C�W���O������ł���B�j
�A �f�B�[�[���G���W���ɔ�r�����ꍇ�A�K�\�����G���W���͕�������
�̃|���s���O�������ɂ߂đ傫�����_��L���Ă���B���̃K�\����
�G���W���ł́A�ᕉ�ׂɂȂ�Ȃ���A�|���s���O���������傷�����
������B����A�z�C�̍i��ق��f�B�[�[���G���W���́A��������
�ł��|���s���O�������K�\�����G���W���̂悤�Ɍ����ɑ������錇�_��
�����̂������ł���B�܂��A�K�\���������ԁi����p�ԁE���^�g���b�N�j
�́A��^�g���b�N�ɔ�r���A�p���[�E�G�C�g���V�I�i�ԗ����d�ʓ������
�G���W���o�́j�̑傫���̂������ł���B���̂��߁A�f�B�[�[���G���W��
�ɔ�ׂĒᕉ�ׂɃ|���s���O���������傷��K�\�����G���W������^
�g���b�N�����ᕉ�ׂʼn^�]����錋�ʁA�ʏ�̃K�\���������Ԃ̑��s��
�f�B�[�[����^�g���b�N�ɔ�r���đ傫���|���s���O�����ɂ�鑖�s�R��
�̈����������Ă���̂�����ł���B���ꂪ�A�K�\���������Ԃ��f�B�[
�[�������Ԃɔ�r���āA�����s�R��啝�ɗ�錴���̈�ł���B
���������āA�K�\���������Ԃ̏ꍇ�ɂ́A�_�E���T�C�W���O�ɂ����
�����s�Ŏg�p�p�x�̍����G���W�����������̃K�\�����G���W����
�z�C�i��ق̊J�x��傫�����邱�Ƃ��\�ɂȂ邽�߁A�|���s���O����
�̒ጸ�ɂ������s�R��̌��オ�\�ƂȂ�B�������A�f�B�[�[��
�G���W���ł́A�����A�z�C�i��ق��������߁A�G���W���̒ᕉ�^�]��
�̃|���s���O���������Ȃ����߁A�_�E���T�C�W���O�ɂ���Ď����s�R��
������ł���\���͋͂��ł��邱�Ƃ������ł���B
�i���K�\���������Ԃ̏ꍇ�ɂ́A�_�E���T�C�W���O�ɂ���ăG���W��
���������ł̋z�C�i��ق̊J�x��傫�����邱�Ƃ��ł��邽�߁A
�|���s���O�����̒ጸ�ɂ������s�R��̌��オ�\�ł���B
�������A�f�B�[�[���G���W���́A�z�C�i��ق��������߂ɃK�\����
�G���W���ɔ�ׂăG���W���̒ᕉ�^�]���̃|���s���O������
���Ȃ����Ƃ���A�_�E���T�C�W���O�ɂ���Ď����s�R�����
�ł���\���͋͏��ł���B�j
�@�ȏ�̂��Ƃ���A�����_�ł́A��^�g���b�N�̕���ł̃G���W���̃_�E��
�T�C�W���O���ɂ���đ��s�R���d�ʎԃ��[�h�R������P�ł���ʂ�
�͂����邱�Ƃ����炩���B�����A���쎩���Ԃ́A��^�J�[�S�g���b�N
�iGVW25�g���j�Ƀ_�E���T�C�W���O�G���W���̂X���b�g�����E�`�O�X�b�𓋍�
�����g���b�N���s�̂��A���̃g���b�N���d�ʎԃ��[�h�R�4.15�`4.05
(km/���j�̃��x���ł��邽�߂ɁA��^�g���b�N�̕���ł̃G���W����
�_�E���T�C�W���O���ɂ���đ��s�R���d�ʎԃ��[�h�R��̏\���ȉ��P
������Ȃ��Ƃ́A�O�q�̕\�̒ʂ�A���쎩���Ԃ��s�̂��Ă����^
�g���b�N���d�P�R�b�i�P�R���b�g�����j�G���W���Ƃ`�O�X�b�i�X���b�g�����j�G���W��
�𓋍ڂ����Ԏ�̏d�ʎԃ��[�h�R��ʂ�قړ����ł��邱�Ƃ�����A
���炩�ł���B
�@
�@����ɂ�������炸�A���쎩���Ԃ����� �����́A���L�̂悤�ɁA
���r�C�ʁ{��Pme�{���ߋ����i���_�E���T�C�W���O�G���W���j��
����ĔR����P���\�Ǝ咣���Ă���̂��B����́A���� ������
�P�Ȃ�l�I�Ȋ�]�E��]�E�ϑz��A�܂��͐��̒��̉\�E�����E
�����L�ڂ������̂ɉ߂��Ȃ��悤�Ɏv�������A�@���Ȃ��̂�
���낤���B
�P�|�Q�@NO���ƔR��̃g���[�h�I�t����������Z�p�̋^��_
�@�@�@�iNO���r�o�ʂ̍팸�ƔR��\���P�̗����j
�@�@�E�����̃}���`����
�@�@�E�σo���u�^�C�~���O
�@�@�E�σX���[��
�@�@�EEGR�̉��x�E���ʐ���̍��x���䉻
�@�@���L�̋L�q������ƁA���� �����́A�u�����̃}���`���ˁv�{�u��
�o���u�^�C�~���O�v�{�u�σX���[���v�{�uEGR�̉��x�E���ʐ���̍��x
���䉻�v�̑g���킹�ɂ���āANO���r�o�ʂ̍팸�ƔR��\���P��
�\�ł���ANO���r�o�ƔR��\�̃g���[�h�I�t�W�������ł���Ƃ�
�ӌ��E�����̂悤���B�������A�����ŗ���Ă���u�����̃}���`
���ˁv�{�u�σo���u�^�C�~���O�v�{�u�σX���[���v�{�uEGR�̉��x�E
���ʐ���̍��x���䉻�v�̂قƂ�ǂ̋Z�p�́A10�N�O�Ɂu�����ԋZ�p�v
�����Ő���Ɏ��ʂ���킵���ߋ��̋Z�p�̂悤�ɕM�҂ɂ͎v�����
�ł���B
�@���̂悤�ɁA���L�̂悤�ɁA���� �������uNO���r�o�ƔR��\��
�g���[�h�I�t�W�̉����v�ɕK�v�Ƃ��ė������Z�p�́A10�N�ȏ��
�ȑO�́u�����ԋZ�p�v�����Ő���ɋL�ڂ��A�c�_����Ă����ÐF���R
����Z�p�ł���B���̂悤�ȌÓT�I�Ƃ����������ȌÂ��Z�p�ɂ���āA
�{���ɁuNO���r�o�ƔR��\�̃g���[�h�I�t�W�̉����v���ANO���r�o��
�̍팸�ƔR��\���P�̗����ł���ƁA���� �����́A�l���Ă���̂�
���낤���B
�@�M�҂̌������ł́A�u�R���������������NO���r�o������Ȃ����
�߂Â��鋆�ɂ̔R�ĉ��P�Z�p�v�Ƃ��đ傢�Ɏ��Ě�����Ă���HCCI�R��
�i��PCI�R�āj�́A�uNO���r�o�ƔR��\�̃g���[�h�I�t�W�̉����v��
���\�����Ȃ��A���p���̖������|���|���̋Z�p�ł��邱�Ƃ��ŋ߂�
�Ȃ��ĘI�悵���B���̂��߁A�u�f�B�[�[���G���W���v�́u�S�@�����J����
�����v�̍���NO���팸�ƔR�����ɗL���ȋZ�p�������L�ڂł��Ȃ��Ȃ�A
���̍��ɋL�ڂ���uNO���팸�ƔR����P�v�̋Z�p�����̌������邱�Ƃ�
����Đ�����f�B�[�[���G���W���W�̊w�ҁE���Ƃ̖��\�Ԃ肪�I��
���Ă��܂����ƂɁA���� �������ӔC���������̂ł͂Ȃ����ƍl������B
�@�����ŁA���� �����́A�ނ��炵�����ʂ߂���@�Ƃ��āA10�N�ȏ��
�ȑO�́u�����ԋZ�p�v����I�����������o���A�����ʂ��߂�����
�u�����̃}���`���ˁv�{�u�σo���u�^�C�~���O�v�{�u�σX���[���v�{
�uEGR�̉��x�E���ʐ���̍��x���䉻�v����10�N�ȏ���O�ɘb���
�Ȃ����Z�p��Ђ��[�������A�����̋Z�p�ɂ���āuNO���r�o��
�R��\�̃g���[�h�I�t�W�̉����v�ł���Ƌ����ɂ܂Ƃ߂��\����
����悤�ɐ��@�����B�������A�����̋Z�p�́A�����̌����@�ցA��w�E
���[�J���ɂ����āA����܂Œ��N�ɂ킽���Ď��{���Ă����J��������
���ځE���e�ł��邽�߁A����̍X�Ȃ�uNO���팸�ƔR����P�v���ɂ߂�
����Ȃ��Ƃ����炩���B���̌��ʁA���{�̃f�B�[�[���G���W���ɊW
����w�ҁE���Ƃ́A��^�g���b�N�ł̌���ȏ�́uNO���팸�ƔR��
���P�v���\�ɂ���Z�p���u�s���v�Ƃ̔F���ň�v���Ă���悤�ɁA
�M�҂ɂ͌�����̂ł���B
�@���̏؋��Ƃ��čl������̂́A2015�N�x�d�ʎԔR�����ݒ�
����Ă�����{�́A2016�N�ɂ����Ă��č������ɂ�NO���K�������{
����\��̒������R�c��̓��\���o����Ă��邱�Ƃ��B�i�ڍׂ�
�̃y�[�W���Q�ƕ��j
�@����A���{�̑�^�g���b�N��NO���K���̗��j�E�ϑJ������A�ߋ���
�w�ǂ̎���ɂ����āA���{�͕č�������������^�g���b�N��NO���K����
���{���Ă����̂ł���B�Ƃ��낪�A���̂悤�ȓ��{���A�����ōŋ߂ł́A
�ˑR�A2016�N�ɂ����Ă��č������ɂ�NO���K�����p�����Ď��{����
���Ƃ\�����̂ł���B���̂悤�ȁA���{�ɂ����ĕč������ɂ���^
�g���b�N��NO���K�����p�����Ď��{������Ȃ��Ɋׂ��Ă��܂���
�̂́A�������R�c��̊W�҂��܂߂����{�̃f�B�[�[���G���W����
�W����w�ҁE���Ƃ̑S�����A�u��^�g���b�N�ł̌���ȏ��
NO���팸�ƔR����P���\�ɂ���Z�p���s���ł���v�Ƃ̔F���ň�v
���Ă��邽�߂ƍl������B
�@�ȏ�̂��Ƃ���A���� ���������L�ɗ���10�N�ȏ���ȑO��
�ÐF���R����Z�p�ł́A���� �����̒P�Ȃ�l�I�Ȋ�]�E��]��
�L�ڂ������̂ɉ߂����A�߂������ɑ�^�g���b�N�́uNO���r�o��
�R��\�̃g���[�h�I�t�W�������v���邱�Ƃ́A�ɂ߂č���ł���
���Ɛ��@�����B���̂悤�ɁA���R����Z�p���ł���u�����ԋZ�p�v����
�����̖����u���҂̌l�I�Ȋ�]�E��]�v�̂悤�ȓ��e���L�ڂ���
���Ƃ́A���� ���������{�����ԋZ�p��̉���ł���ǎ҂����S��
�n���ɂ��Ă���悤�Ɏv���邪�A�@���Ȃ��̂ł��낤���B
�����āA�Z�p���ł���A���R�A�u��^�g���b�N�ɂ�����NO���r�o��
�R��\�̃g���[�h�I�t�W�������ł���Z�p�́A���̂Ƃ���
�s���v�ƌ���̋Z�p�J���̐i�W�ɂ��Đ����ɋL�q���ׂ��Ǝv�����A
�@���Ȃ��̂ł��낤���B
�P�|�R�@�p�M����Ȃǂ̃G�l���M�[����Z�p�̋^��_
�@�f�B�[�[���G���W���̔r�C�K�X�Ƃ��đ�C���ɔp������Ă���r�C�K�X
�̃G�l���M�[���瓮�͂�d�C�G�l���M�[�����o���u�f�B�[�[���r�C�K�X
�̃G�l���M�[���u�v�ɂ́A�ȉ��̂悤�ȋZ�p���l�����Ă���B
�@�E���J�j�J���^�[�{�R���p�E���h
�@�E�G���N�g���b�N�^�[�{�R���p�E���h
�@�E�����L���T�C�N��
�@�E�M�d�f�q
�@�E�X�^�[�����O�G���W��
�@�����̒��ŁA���݁A���p������Ă���Z�p�́A�{���{�A�X�J�j�A�A
�x���c���s�̂̑�^�g���b�N�E�g���N�^�ɍ̗p���Ă���u���J�j�J���^�[�{
�R���p�E���h�v�ł���B�������Ȃ���A�����u���J�j�J���^�[�{�R���p�E���h�v��
�̃y�[�W�ɏڏq���Ă���悤�ɁA�G���W���̍ō��g���N��ő�o�͂̑���
�ɂ͗L���ł��邪�A��^�g���b�N�̎����s�R���d�ʎԃ��[�h�R���
����ł���@�\�͋͏��ł���B�܂��A
�̃y�[�W�ɏڏq���Ă���悤�ɁA�f�B�[�[���G���W���ɒP�ɔr�C�K�X��
���݂̉^�]�\�ȃG�l���M�[���u�����������ł́A�G���W��
�̔R�����͍���ł���B���������āA�u�f�B�[�[���r�C�K�X��
�G�l���M�[����Z�p�ɂ��M�����̌���v�Ƃ̓ǎ҂Ɍ���������L�q��
�s���Ă���悤���B����u�v�𓋍ڂ��������ł́A��^�g���b�N��
�����s�R���d�ʎԃ��[�h�R�������ł���@�\�͋͏��ł���B
�@���������āA����ɂ�������炸�A���L�̂悤�ɁA�u�p�M����Ȃǂ�
�G�l���M�[�Z�p�ɂ��i�G���W���́j��������v�Ƃ̋��U�Ƃ�����
�����Ȏ咣���s���Ă���̂ł���B���̂悤�ȒP�Ȃ錾�t�̌�����
����āA���� �����́A���L��2012�N�́u�����ԋZ�p�v���̔N�ӂ�
�u�f�B�[�[���G���W���v�́u�S�@�����J���̓����v�ł́A�g���b�N���[�J��
��^�g���b�N�̔R�����̂��߂Ɂu�f�B�[�[���r�C�K�X�̃G�l���M�[
���u�v���̐V�����Z�p�ɉʊ��Ɏ��g��ł���悤�Ɏ��U���Ă���
�悤�Ɍ�����̂ł���B���̂Ȃ�A����܂œ��쎩���Ԃ́A�X�J�j�A��
�^�[�{�R���p�E���h���ڂ̃g���N�^��̔����Ă���A�^�[�{�R���p�E���h
���ڂɂ���ĕK�����������s�R���d�ʎԃ��[�h�R�����ł��Ȃ�
���Ƃ��n�m���Ă���\�������邽�߂��B���̂��Ƃ��l����ƁA���L��
���� �����́u�p�M����Ȃǂ̃G�l���M�[�Z�p�ɂ��i�G��
�W���́j��������v�̎咣�́A���̎����������ł���A�u���X����
���U�L�ځv�̂悤�ɁA�M�҂ɂ͎v����̂ł���B
|
|||||||||||||||||||||||||||
�Q�D���L�̋L�ړ��e�ɑ���M�҂̍l����������e�Ƃ��̍���
�@�@�@�i���p�ԗp�f�B�[�[���ɂ��āj
���@�����������咣����悤�ȑ�^�g���b�N�̃G���W���u���r�C�ʁv�ɂ���
�u���ߋ����v���A�����āu��Pme�v�Ƃ��āA�u��r�C�ʂ̃G���W���Ɠ�����
�o�͂��m�ہv����Z�p�I�Ȏ�@�́A��ʓI�ɂ́u�G���W���̃_�E��
�T�C�W���O�v�ƌĂ�Ă���B���̃G���W���_�E���T�C�W���O�ɂ����
��^�g���b�N�̏d�ʎԃ��[�h�R������シ�邱�Ƃ́A�ɂ߂������
���@�����B
�M�Ғ�ẴG���W���_�E���T�C�W���O�ł̔R��� �� ��^
�g���b�N�̎��ۂ̑��s����d�ʎԃ��[�h�R��v�����ɂ́A�G���W�����ׂ�
1/2�ȉ��̗̈�ł̉^�]�p�x�������Ȃ�������m���Ă���B�M�Ғ��
���C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p�́A�G���W�����ׂ�
1/2�ȉ��̗̈�ł́A�����̋C�����x�~���A�c��̔����̋C�����ғ�
����V�X�e���ł��邽�߁A��^�g���b�N�̎��ۂ̑��s����d�ʎԃ��[�h
�R���啝�Ɍ���ł���@�\�E���ʂ����邱�Ƃ��B���̑�^�g���b�N��
���ۂ̑��s����d�ʎԃ��[�h�R��v�����ɁA�p�ɂɔ����̋C����
�G���W�����^�]���邱�Ƃɂ���ĔR����P���\�ɂ���G���W���^�]���
�́A�G���W���̃_�E���T�C�W���O�ɗގ������^�]�ƌ��邱�Ƃ��\�ł���B
�i�����F�C���x�~�G���W���ɂ���^�g���b�N�̒�R����Q�Ɓj
���@�����������咣����悤�ɁA�u�����̃}���`���ˁv�{�u�σo���u
�^�C�~���O�v�{�u�σX���[���v�{�uEGR�̉��x�E���ʐ���̍��x���䉻�v
�̑g���킹�ɂ���āANO���r�o�ƔR��\�̃g���[�h�I�t�W���������A
�uNO���팸�v�Ɓu�R����P�v�𗼗����邱�Ƃ́A�ɂ߂�����Ɛ��@�����B
�M�Ғ�Ă�NO���ƔR��̃g���[�h�I�t�����̑� �� NO���r�o��
�R��\�̃g���[�h�I�t�W�̉����ɂ́A
�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p���L���ł���B
�i���̍����́A�{�y�[�W�̑��̋L�ڍ��ڂɏڏq���Ă���̂ŁA�ڍׂ�
������B�j
���@�����������咣����悤�ɁA�f�B�[�[���G���W���Ƀ^�[�{�R���p�E���h
�����p�M����Ȃǂ̃G�l���M�[����Z�p�����������̋Z�p�ł́A
�f�B�[�[���G���W���̔R�����́A�ɂ߂�����Ɛ��@�����B�i������
���Q�Ɓj
�M�Ғ�ẴG�l���M�[����ɂ��R������ �� �f�B�[�[��
�G���W���Ƀ^�[�{�R���p�E���h���̔p�M����Ȃǂ̃G�l���M�[����Z�p
�ɂ���đ�^�g���b�N�̏d�ʎԃ��[�h�R��̌�����������邽�߂ɂ́A
�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p�Ƃ̑g�ݍ��킹��
�K�{�ł���B�����āA�p�M����Ȃǂ̃G�l���M�[����Z�p�́A����
�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�Ƃ̑g�ݍ��킹�Ȃ�����A
��^�g���b�N�̏d�ʎԃ��[�h�R��̏\���Ȍ��オ�s�\�ł��邱�Ƃ�
�̂ɖ�����ׂ��ł���B�i�����́A
�Q�Ɓj
|
||||||||||||||||||||||||||||
�R�D���L�̏��p�ԗp�f�B�[�[���̕����ɑ���C�����
�@�@�@
�@���������āA���쎩���ԇ��̐��� �������S���������L��2012�N
8�����u�����ԋZ�p�v���ł̔N�Ӂu�f�B�[�[���G���W���v�́u�S�@����
�J���̓����v�̒��̏��p�ԗp�f�B�[�[���G���W���ɂ��ẮuNO��
�팸�v�Ɓu�R�����v�Ɋւ���L�q�́A�M�҂̌���Ƃ���ł́A
�S�Ă��u�o�L�ځH�v�̂悤�Ɏv����̂ł���B
�@���������āA�M�҂̌l�I�Ȉӌ������킹�ĖႦ�A���L�́u�S�@����
�J���̓����v�̏��p�ԗp�f�B�[�[���G���W���̉ӏ��ɂ��ẮA�ȉ���
�悤�ȋL�ڂɒ������ׂ��ł͂Ȃ����ƍl����B
�@���͂Ƃ�����A�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̑��ɑ�^
�g���b�N�p�f�B�[�[���̒�NO���ƒ�R����Ɏ����ł���Z�p������
������B�����邽�߂ɁA���쎩���ԇ��̌����̋Z�p�҂ł��鐴�� ����
�́A���L�̂悤�ȌÐF���R����u�����̃}���`���ˁv�{�u�σo���u
�^�C�~���O�v�{�u�σX���[���v�{�uEGR�̉��x�E���ʐ���̍��x���䉻�v
�̑g���킹�Z�p�ɂ���āANO���r�o�ƔR��\�̃g���[�h�I�t�W��
��������NO���팸�ƔR��������������Ƃ̊��S�ȋ��U�Ƃ��v����Z�p
�����A�p���������������A�����ԋZ�p�v���ɓ��X�ƋL�ڂ��Ă���悤�ɁA
�M�҂ɂ͌�����̂ł���B�����āA���̂悤�Ȃ��Ƃ��u�����ԋZ�p�v����
�ҏW�ψ���́A�e�F���Ă���Ǝv���邱�Ƃ��B
�@�Ȃ��A���쎩���ԇ��̐��� ������u�����ԋZ�p�v���̕ҏW�ψ��́A
�C���^�[�l�b�g�ł̋Z�p���̎��W���s��Ȃ����߁ANO���r�o�ƔR��\
�̃g���[�h�I�t�W����������NO���팸�ƔR����オ�\�ȕM�҂̃z�[��
�y�[�W�Œ�Ă��Ă����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p
���ɂ��āA�S���̖��m�E���m�ł���\�����l������B���̏ꍇ
�ɂ́A���݁A�M�҂̃z�[���y�[�W�́A�u��^�g���b�N�v�{�u�R��v��2���
�����ōŏ��̌����y�[�W�i10�ʈȓ��j�Ō��������ł��邪�A
���� �������C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p���������
�M�҂̃z�[���y�[�W���{�����Ă��Ȃ��\��������A���̋C���x�~��
�Z�p�𐴐� �����̖ڂɐG��Ă��Ȃ��\�����ے�ł��Ȃ��B�Ƃ��낪�A
�����ԋZ�p��201�P�N8�����̓��W�F�N�Ӂ@�u�f�B�[�[���G���W���v�̎Q�l
�����̏o�T��95�����z�[���y�[�W�ł���B���̂��Ƃ���A���� ������
�f�B�[�[���G���W���̏������W�����v�Ȏ�i���C���^�[�l�b�g�̌���
�ł��邱�Ƃ͖��炩���B���̂��Ƃ���A���� �����́A�M�҂̃z�[���y�[�W��
�{�����A�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p�����ɏ��m����
������̂ƍl������B
�@�������A���� �������C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p
���E�َE���Ă���̂́A���̋C���x�~�̋Z�p����^�g���b�N�p
�f�B�[�[���G���W����NO���팸�ƔR����オ����Ƃ̌����E�����ł����
���@�����B���ɁA���̐��@�������ł����Ă��A���� �����������ԋZ�p�v
���ɑ�^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W���̐��m�ȋZ�p���𐽈ӂ�������
�L�ڂ���ӎv�E�Ӑ}��L���Ă���Ȃ�A�ނ́A�����ԋZ�p�v�����u��^
�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W����NO���ƔR��̃g���[�h�I�t����������
NO���팸�ƔR�������Ɏ����ł���Z�p�́A�����_�ł͕s����
����v�Ƃ̓��e�ɂ��������ׂ��ł���ƍl����B
�@�܂��A���� �����́A�����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j��
�Z�p����^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W����NO���팸�ƔR����オ����
�Ƃ̌����E�����ł��邱�Ƃ������ł���Ȃ�ƁA�ނ͂��̓������o�肵��
�M�҂�n���Ȑl�ԁv�Ƃ̔F�����Ă�����̂ƍl������B����ɂ��ĂɁA
��^�g���b�N��NO���팸�ƔR����オ�\��
�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p�̗D�ꂽ���_�E���\��
�����ł��Ȃ����� �����́A�f�B�[�[���G���W���̋Z�p�҂Ƃ��Ă͊��S��
���i�ł���ƕM�҂͍l���Ă���B���̐��� �����ƕM�҂̈ӌ��E������
����ɂ��āA�ǎ҂̈ӌ����Ă݂����Ƃ���ł���B
�@�������Ȃ���A�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p����^
�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W����NO���팸�ƔR����オ����Ƃ̌����
�����E�����ł���Ƃ͉]���A�ÐF���R����u�����̃}���`���ˁv�{�u��
�o���u�^�C�~���O�v�{�u�σX���[���v�{�uEGR�̉��x�E���ʐ���̍��x
���䉻�v�̑g���킹�Z�p�ɂ���āANO���r�o�ƔR��\�̃g���[�h�I�t
�W����������NO���팸�ƔR�������Ɏ�������Ƃ̋��U�̋Z�p
�����u�����ԋZ�p�v���ɐ��� �������L�ڂ��邱�Ƃ́A����������
�ł͖������낤�B���������āA���L�̌�����L�ړ��e�́A���������ׂ�
�ƍl���邪�A�@���Ȃ��̂ł��낤���B���Ȃ��Ƃ��A���L�́u�����̃}���`
���ˁv�{�u�σo���u�^�C�~���O�v�{�u�σX���[���v�{�uEGR�̉��x�E
���ʐ���̍��x���䉻�v�̑g���킹�Z�p�ɂ���đ�^�g���b�N�p
�f�B�[�[���G���W���̒�NO���ƒ�R����Ɏ����ł���Ƃ̋L�ړ��e
�́A�펯����Z�p�҂̏o�L�ڂȋZ�p���ł��邱�Ƃ��f�B�[�[��
�G���W���W�̊w�ҁE���Ƃł���A�N�ł����j���Ă�����̂Ɛ���
�����B
�@���͂Ƃ�����A�����ԋZ�p�v���ɐ��m�ȋZ�p��������ɒ��邱��
�������ԋZ�p��̐Ӗ��ł���A���U�����L�ڂ��邱�Ƃ͋�����Ȃ�
���Ƃ��B���̂悤�Ȏ����ԋZ�p�v���ɁA���L�̂悤�ȋ��U�Ƃ��v����Z�p
�����f�ڂ��邱�Ƃ́A�����̎����ԋZ�p��̉���̐M���𗠐邱�Ƃ�
����A���̍߂͏d���ƌ��킴��Ȃ����낤�B����́A���Ɏc�O��
���Ƃ��B
|
||||||||||||||||||||||||||||
| �@�S�D���L�̋L�ړ��e�ɑ���M�҂̌l�I�Ȉӌ��E���z
�@���L�̋L�q�ł́A�uNO���r�o�ƔR��\�̃g���[�h�I�t�W�������ł��� �Z�p�v�Ƃ̗��h�ȏC��������Ă͂��邪�A���p�ԗp�f�B�[�[���G���W�� �̉ۑ�����̂��߂Ɋ̐S�ȁuNOx�팸�v�Ɓu�R�����v�Z�p�Ƃ��ẮA �P�O�N�O�̌Â��Z�p����Ă��邾���̕n���ȁu�N�Ӂv�ƂȂ��Ă���̂� ����B���̂悤�ȋZ�p���Ƃ��ĉ��l�̖R�������e�����N�ӂɋL�q�ł� �Ȃ��̂ł���A���쎩���ԇ��̐��� �����́A�ŏ����炱�̂S���� ����ɔz�z�����u�����ԋZ�p�v���̔N�ӂ̒S�������ނ���ׂ��ł����� �Ǝv�����A�@���Ȃ��̂ł��낤���B�܂��A�u�����ԋZ�p�v���̔N�ӂ�ǂ� ���{�����ԋZ�p��̖��[�̉�����傢�ɗ��_�����Ă��܂��L����ڂ� ����s�K���A�u�����ԋZ�p�v���̕ҏW�ψ����܂߂������ԋZ�p��� �W�҂͏����͍l���ė~�������̂ł���B����܂Ő��m�ȋZ�p���� ����ɔ��M���邱�Ƃ����炩�ɐ錾���Ă���ϗ��K��̎����ԋZ�p� ���L�̂悤�ȋ��U�Ƃ��v����Z�p���X�Ɣ��M���Ă��邱�Ƃɂ��āA �����ԋZ�p��̊W�҂́A�����͗ǐS�̙�ӂɔY�܂����悤�Ȃ��Ƃ� �����̂ł��낤���E�E�E�E�E�B |
�@�ȏ�̕\14�Ɏ����������ԋZ�p��2012�N8�����iVol.66�AN0.8�A2012�j���W�F�N�Ӂ@�u�f�B�[�[���G���W���v�́u�S�@����
�J���̓����v�œ��쎩���Ԃ̐��� �����������u�r�o�K�X�ƔR��ጸ�v�̋Z�p�́A�قƂ�ǂ�����10�N�ȏ���ȑO
���瑽���̊w�ҁE���Ƃ��b��Ɏ��グ���Ă���u��C�܂݂�̋Z�p�v�ł���A���Ɍ��s�̑�^�g���b�N�ɍ̗p����
�Ď��p������Ă���Z�p�������悤���B���̂��߁A���L�̘_����ǂf�B�[�[���G���W���Z�p�҂́A���� �����̋�
�����Z�p��p���āA����̑�^�g���b�N�́uNO���팸�v�Ɓu�R�����v�ɑ傫���v���ł���Ƃ͍l����ƍl����l�B����
���̂ł͂Ȃ����Ɛ��������B
�J���̓����v�œ��쎩���Ԃ̐��� �����������u�r�o�K�X�ƔR��ጸ�v�̋Z�p�́A�قƂ�ǂ�����10�N�ȏ���ȑO
���瑽���̊w�ҁE���Ƃ��b��Ɏ��グ���Ă���u��C�܂݂�̋Z�p�v�ł���A���Ɍ��s�̑�^�g���b�N�ɍ̗p����
�Ď��p������Ă���Z�p�������悤���B���̂��߁A���L�̘_����ǂf�B�[�[���G���W���Z�p�҂́A���� �����̋�
�����Z�p��p���āA����̑�^�g���b�N�́uNO���팸�v�Ɓu�R�����v�ɑ傫���v���ł���Ƃ͍l����ƍl����l�B����
���̂ł͂Ȃ����Ɛ��������B
�@�O�q���W�|�P���ɏڏq���Ă���悤�ɁA�V�G�l���M�[�E�Y�ƋZ�p�����J���@�\�iNEDO)�̊v�V�I���������Q�ԑ�
���Z�p�J���i�N���[���f�B�[�[���v���W�F�N�g�A2004�`2009�N�j�Ə̂���8��6��5�S���~�̗\�Z�Ŏ��{���ꂽ��^�v���W
�F�N�gNEDO�́u�����x�R�Đ���G���W�V�X�e���̌����J���v�ł́A�R�i�ߋ�����10���b�g���̃_�E���T�C�W���O�G���W��
�Ɂu�����̃}���`���ˁv�A�u�σo���u�^�C�~���O�v����сuEGR�̉��x�E���ʐ���̍��x���䉻�v����Z�p�荞�݁A
NO����V�����r�o�K�X�K���i�Q�O�O�T�N�K���j��1/3�ጸ�i��0.2 g/kWh)�ɒጸ���A�R�������10�����P�����
�W���f����ꂽ�B�������A����NEDO�v���W�F�N�g�́ANO���̖ڕW���B�����ꂽ�����ł���A�d�ʎԃ��[�h�R�2015�N
�x�d�ʎԔR�����Q������������S�邽�錋�ʂł������B�f�B�[�[���G���W���̐��Ƃł�����쎩���Ԃ̐���
�����́A����NO���ƔR��̃g���[�h�I�t�̍����Ɏ��s����2004�`2009�N�Ɏ��{��NEDO�v���W�F�N�g�̌������ʂ��A��
�R�A�n�m���Ă��锤�ł���B
���Z�p�J���i�N���[���f�B�[�[���v���W�F�N�g�A2004�`2009�N�j�Ə̂���8��6��5�S���~�̗\�Z�Ŏ��{���ꂽ��^�v���W
�F�N�gNEDO�́u�����x�R�Đ���G���W�V�X�e���̌����J���v�ł́A�R�i�ߋ�����10���b�g���̃_�E���T�C�W���O�G���W��
�Ɂu�����̃}���`���ˁv�A�u�σo���u�^�C�~���O�v����сuEGR�̉��x�E���ʐ���̍��x���䉻�v����Z�p�荞�݁A
NO����V�����r�o�K�X�K���i�Q�O�O�T�N�K���j��1/3�ጸ�i��0.2 g/kWh)�ɒጸ���A�R�������10�����P�����
�W���f����ꂽ�B�������A����NEDO�v���W�F�N�g�́ANO���̖ڕW���B�����ꂽ�����ł���A�d�ʎԃ��[�h�R�2015�N
�x�d�ʎԔR�����Q������������S�邽�錋�ʂł������B�f�B�[�[���G���W���̐��Ƃł�����쎩���Ԃ̐���
�����́A����NO���ƔR��̃g���[�h�I�t�̍����Ɏ��s����2004�`2009�N�Ɏ��{��NEDO�v���W�F�N�g�̌������ʂ��A��
�R�A�n�m���Ă��锤�ł���B
�@����ɂ�������炸�A�ȏ�̕\13�Ɏ������悤�ɁA���� �����́A2004�`2009�N�Ɏ��{��NEDO�v���W�F�N�g�ɐ��荞
�܂ꂽ�Z�p�Ɂu�σX���[���v�����������̋Z�p�ɂ���āA�f�B�[�[���G���W���́uNO���ƔR��̃g���[�h�I�t�̍�����
�\�v�ƁA�u�����ԋZ�p�v��2012�N8�����iVol.66�AN0.8�A2012�j���W�F�N�Ӂ@�u�f�B�[�[���G���W���v�́u�S�@�����J���̓�
���v�ɋL�ڂ��Ă���̂ł���B���́u�����ԋZ�p�v��2012�N8�����̔N�ӂ̋L�q������ƍl�����邽�߁A���̎|��
2012�N8���Ɏ����ԋZ�p��Ɏ������̂ł���B�Ƃ��낪�A�M�҂̗\�z�ɔ����A�u�����N�ӂ̋L�q�ɂ͌�肪�����v�Ƃ�
����������e�̉������ԋZ�p����������ł������B���̎��ɂ́A��u�A�䂪�ڂ��^�����̂ł���B����
�͉]���Ă��A�����ԋZ�p���̉��e�ɕs���Ăȕ��������X���������߁A�����A�����ԋZ�p��ɍĎ��������
�Ƃ���A�����ԋZ�p���͉����ۂ���|�̕Ԏ����������B���̂��Ƃ���A���݁A�����ԋZ�p��́A2004�`2009
�N�Ɏ��{��NEDO�v���W�F�N�g�ɐ��荞�܂ꂽ�Z�p�Ɂu�σX���[���v��lj����������̋Z�p�ɂ���āA�f�B�[�[���G��
�W���̒��N�̉ۑ�ł���uNO���ƔR��̃g���[�h�I�t�̍������\�ł���v�Ƃ̌����̂悤���B���̂Ƃ���A���̌�����
�������ӌ��E�咣������́u�����ԋZ�p�v���Ɍp�����Čf�ڂ���čs�����̂Ɛ��@�����B�M�҂ɂ́A�M�����Ȃ�����
�ł���B
�܂ꂽ�Z�p�Ɂu�σX���[���v�����������̋Z�p�ɂ���āA�f�B�[�[���G���W���́uNO���ƔR��̃g���[�h�I�t�̍�����
�\�v�ƁA�u�����ԋZ�p�v��2012�N8�����iVol.66�AN0.8�A2012�j���W�F�N�Ӂ@�u�f�B�[�[���G���W���v�́u�S�@�����J���̓�
���v�ɋL�ڂ��Ă���̂ł���B���́u�����ԋZ�p�v��2012�N8�����̔N�ӂ̋L�q������ƍl�����邽�߁A���̎|��
2012�N8���Ɏ����ԋZ�p��Ɏ������̂ł���B�Ƃ��낪�A�M�҂̗\�z�ɔ����A�u�����N�ӂ̋L�q�ɂ͌�肪�����v�Ƃ�
����������e�̉������ԋZ�p����������ł������B���̎��ɂ́A��u�A�䂪�ڂ��^�����̂ł���B����
�͉]���Ă��A�����ԋZ�p���̉��e�ɕs���Ăȕ��������X���������߁A�����A�����ԋZ�p��ɍĎ��������
�Ƃ���A�����ԋZ�p���͉����ۂ���|�̕Ԏ����������B���̂��Ƃ���A���݁A�����ԋZ�p��́A2004�`2009
�N�Ɏ��{��NEDO�v���W�F�N�g�ɐ��荞�܂ꂽ�Z�p�Ɂu�σX���[���v��lj����������̋Z�p�ɂ���āA�f�B�[�[���G��
�W���̒��N�̉ۑ�ł���uNO���ƔR��̃g���[�h�I�t�̍������\�ł���v�Ƃ̌����̂悤���B���̂Ƃ���A���̌�����
�������ӌ��E�咣������́u�����ԋZ�p�v���Ɍp�����Čf�ڂ���čs�����̂Ɛ��@�����B�M�҂ɂ́A�M�����Ȃ�����
�ł���B
�@�����Ƃ��A�\14�Ɏ����������@���@���̒������N�ӂ́u�S�@�����J���̓����v�ɋL�ڂ��Ă����Z�p�ɂ���đ�^�g���b�N
�́uNO���팸�v�Ɓu�R�����v���ɂ߂č���ƍl����̂́A�P�ɕM�҂��u�Ԕ����v�Łu�ڒ����v�ȃ|���R�c�̌��Z�p������
���Ƃ������ł��邩���m��Ȃ��B�����āA�u�����ԋZ�p�v��2012�N8�����iVol.66�AN0.8�A2012�j���W�F�N�Ӂ@�u�f�B�[�[��
�G���W���v�ɂ��āA�M�҂��o�L�ڂȌ�����ᔻ���s���Ă���\�����l������B�����āA���� �����A�Ⴕ���͎�����
�Z�p��̊W�҂��M�҂̐����Ɋ�Â����{�z�[���y�[�W�̋L�q�����ł���Ƃ̈ӌ��E�����ł���Ȃ�A�{�y�[�W
�̖����ɋL�ڂ��Ă���M�҂̃��[�����ɁA���}�ɂ��̎|�̂��A�����������������Ǝv���Ă���B������A�M�҂���N
�ސE�����|���R�c�̌��Z�p���ł���Ƃ͉]���A��������e�����̃z�[���y�[�W�ɋL�ڂ��邱�Ƃ́A�s�{�ӂł���B����
���߁A�ł��邱�ƂȂ�A���̃z�[���y�[�W�̋L�ړ��e�̌��ɂ��ẮA�����ɒ����������Ǝv���Ă���B
�́uNO���팸�v�Ɓu�R�����v���ɂ߂č���ƍl����̂́A�P�ɕM�҂��u�Ԕ����v�Łu�ڒ����v�ȃ|���R�c�̌��Z�p������
���Ƃ������ł��邩���m��Ȃ��B�����āA�u�����ԋZ�p�v��2012�N8�����iVol.66�AN0.8�A2012�j���W�F�N�Ӂ@�u�f�B�[�[��
�G���W���v�ɂ��āA�M�҂��o�L�ڂȌ�����ᔻ���s���Ă���\�����l������B�����āA���� �����A�Ⴕ���͎�����
�Z�p��̊W�҂��M�҂̐����Ɋ�Â����{�z�[���y�[�W�̋L�q�����ł���Ƃ̈ӌ��E�����ł���Ȃ�A�{�y�[�W
�̖����ɋL�ڂ��Ă���M�҂̃��[�����ɁA���}�ɂ��̎|�̂��A�����������������Ǝv���Ă���B������A�M�҂���N
�ސE�����|���R�c�̌��Z�p���ł���Ƃ͉]���A��������e�����̃z�[���y�[�W�ɋL�ڂ��邱�Ƃ́A�s�{�ӂł���B����
���߁A�ł��邱�ƂȂ�A���̃z�[���y�[�W�̋L�ړ��e�̌��ɂ��ẮA�����ɒ����������Ǝv���Ă���B
�@�Ȃ��A���� �����A�Ⴕ���͎����ԋZ�p�����炱���y�[�W�̋L�q�Ɍ�肪����Ƃ̔��_�̃��[���𑗂��Ă��������Ȃ�
����A���� �����A�Ⴕ���͎����ԋZ�p��́A�����ԋZ�p��2012�N8�����iVol.66�AN0.8�A2012�j���W�F�N�Ӂ@�u�f�B�[�[��
�G���W���v�́u�S�@�����J���̓����v�i���ҁF���쎩���ԇ��@���� �����j�̋L�q�����U�̋Z�p���ł��邱�Ƃ����m����
�Ă�����̂Ɨ��������Ă����������Ƃɂ���B
����A���� �����A�Ⴕ���͎����ԋZ�p��́A�����ԋZ�p��2012�N8�����iVol.66�AN0.8�A2012�j���W�F�N�Ӂ@�u�f�B�[�[��
�G���W���v�́u�S�@�����J���̓����v�i���ҁF���쎩���ԇ��@���� �����j�̋L�q�����U�̋Z�p���ł��邱�Ƃ����m����
�Ă�����̂Ɨ��������Ă����������Ƃɂ���B
�����ԋZ�p��2013�N8�����iVol.67�AN0.8�A2013�j�̓��W�F�N�Ӂ@�u�f�B�[�[���G���W���v�i���ҁF�O�H�ӂ����g���b�N�E�o�X
���@�����@�p���@���j�́u�S�@�����J���̓����v�ɂ́A�f�B�[�[���G���W���̔r�o�K�X�ƔR����팸���邽�߂̍ŋ߂̋Z
�p�������܂Ƃ߂��Ă���B���́u�S�@�����J���̓����v�ɂ́A�g���b�N���[�J���w�E�����@�ւ̑����̐��Ƃ��f�B�[
�[���G���W���̔r�o�K�X�ƔR����팸���邽�߂ɗL���ƍl���Ă���Z�p�ɂ��āA�܂Ƃ߂��Ă��锤�ł���B�����N
�Ӂ@�u�f�B�[�[���G���W���v�́u�S�@�����J���̓����v�ɑ��A�M�҂��^��Ɋ�������e�ɂ��āA���L�̕\�P�P�|�T�ɂ܂�
�߂��B
���@�����@�p���@���j�́u�S�@�����J���̓����v�ɂ́A�f�B�[�[���G���W���̔r�o�K�X�ƔR����팸���邽�߂̍ŋ߂̋Z
�p�������܂Ƃ߂��Ă���B���́u�S�@�����J���̓����v�ɂ́A�g���b�N���[�J���w�E�����@�ւ̑����̐��Ƃ��f�B�[
�[���G���W���̔r�o�K�X�ƔR����팸���邽�߂ɗL���ƍl���Ă���Z�p�ɂ��āA�܂Ƃ߂��Ă��锤�ł���B�����N
�Ӂ@�u�f�B�[�[���G���W���v�́u�S�@�����J���̓����v�ɑ��A�M�҂��^��Ɋ�������e�ɂ��āA���L�̕\�P�P�|�T�ɂ܂�
�߂��B
| |
|
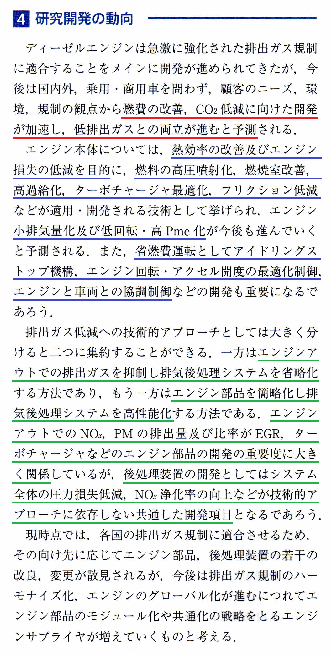 |
�P�D�����p������������NO���팸�ƔR��ጸ�̋Z�p�i���L�Q�Ɓj
�@�����ԋZ�p��2013�P�N8�����̓��W�F�N�Ӂ@�u�f�B�[�[���G���W���v��
�u�S�@�����J���̓����v�ł́A�O�H�ӂ����g���b�N�E�o�X���@�����p����
�́A����A�uNO���ECO2���̔r�o�K�X�팸�ƔR��ጸ�̗����v��}��
���߂̗L���ȐV���ȋZ�p�Ƃ��āA�ȉ��̋Z�p���L�ڂ���Ă���B
�����ō����p�����������Z�p�ɂ��āA��^�g���b�N�̔R����
�r�o�K�X�̐��\�����シ�錤���J���ƍl�����ꍇ�̕]���́A�ȉ���
�ʂ�ƍl������B
���@�M�����̉��P����уG���W�������i�����C�E�r�C�E��p�̑����H�j
�@�@�E�R���̍������ˉ��@���@�i���\�N�ȑO����̊J�����ځj
�@�@�E�R�Ď����P�@���@�i���\�N�ȑO����̊J�����ځj
�@�@�E���ߋ������@�i���\�N�ȑO����̊J�����ځj
�@�@�E�^�[�{�`���[�W���œK���@���@�i���\�N�ȑO����̊J�����ځj
�@�@�E�t���N�V�����ጸ�@���@�i���\�N�ȑO����̊J�����ځj
�@�@�E�G���W�����r�C�ʉ��@���@�i��^�g���b�N�ł��R����P���͏��j
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@[�O�q�̕\14�Ɂu�R����P���͏��v�̗��R���ڏq]
�@
���@�ȔR��^�]
�@�@�E�A�C�h�����O�X�g�b�v�@�\�@���@�i12�N�O�̏ȃG�l��܂̌ÓT�I�ȋZ�p�j
�@�@�E�G���W����]�E�A�N�Z���J�x�̍œK������@���@�i12�i�����~�b�V�����j
�@�@�E�G���W���Ǝԗ��̋�������@���@�i�����~�b�V�����ł̕��ʂ̐���j
���@�r�o�K�X�ጸ
�@�@�E�G���W���A�E�g�̔r�o�K�X�}���@���@�i�P�Ȃ��]�j
�@�@�E�r�C�㏈���V�X�e���̏ȗ����@���@�i�P�Ȃ��]�j
�@�@�E�G���W�����i�̊ȗ����@���@�i�P�Ȃ��]�j
�@�@�E�㏈�����u�̃V�X�e���S�̂̈��͑����ጸ�@���@�i�P�Ȃ��]�j
�@�@�E�㏈�����u��NO�����̌���@���@�i�P�Ȃ��]�j
�@���������ԋZ�p��2013�P�N8�����̔N�Ӂu�f�B�[�[���G���W���v��
�u�S �����J���̓����v�ł́A�O�H�ӂ����g���b�N�E�o�X���@�����p�����́A
NO���ECO2���̔r�o�K�X�팸�ƔR��ጸ�̗�����}��Z�p�Ƃ��āA10�N�`
���\�N���ȑO�̂��瑽���̊w�ҁE���Ƃ��b��Ɏ��グ���Ă���
�u��C�܂݂�̋Z�p�v��u�G���W�����r�C�ʉ��̂悤�ȑ�^�g���b�N�ł�
�R����P���͏��ȋZ�p�v�X�Ɨ��A�܂��A�����p�����̌l�I��
�u�P�Ȃ��]�v���L���Ă���悤�ł���B���̂悤�ɁA�u�����ԋZ�p�v����
�N�ӂ��u�P�Ȃ��]�v���L�ڂ���Ă���̂�����ƁA�����p�����́A
�u�����ԋZ�p�v���̔N�ӂ��u���J�̓��L���v�ł���Ɗ��Ⴂ���Ă���̂�
���낤���B�����ł���A���������̂ł���B
�@�����u�f�B�[�[���G���W���v�̔N�ӂ̌��e�́A�����p�����̏�i�����e
���`�F�b�N�E�_���E���ǂ��s���Ă���Ǝv�����A���̂悤�ȖR�������e�̌��e
�ł��O�H�ӂ����̃G���W���W�̊��������F���Ă���̂ł��낤���A�M��
�ɂ͋����ł���B���̏�A�ŐV�̎����ԊW�̋Z�p������{������
�Z�p��̉���ɒ��邱�Ƃ�W�Ԃ��Ă���u�����ԋZ�p�v�����A����
�悤��10�N�ȏ���ȑO�̋Z�p���]��������e�̔N�ӂ��o�ł����
���邱�Ǝ��́A�u�����ԋZ�p�v���̕ҏW�ψ����߂�l�B�̒m���E�\�͂�
�^��������邪�A�@���Ȃ��̂ł��낤���B
|
�@�ȏ�̕\�P�T�Ɏ����������ԋZ�p��2012�N8�����iVol.67�AN0.8�A2013�j���W�F�N�Ӂ@�u�f�B�[�[���G���W���v�́u�S�@����
�J���̓����v���O�H�ӂ����g���b�N�E�o�X���@�����@�p���@���������u�r�o�K�X�ƔR��̉��P�Z�p�v�́A�قƂ�ǂ���
��10�N�`���\�N���ȑO���瑽���̊w�ҁE���Ƃ��b��Ɏ��グ���Ă���u��C�܂݂�̋Z�p�v�ł���A���Ɍ��s��
��^�g���b�N�ɍ̗p����Ď��p������Ă���Z�p���w��ǂł���B�����ԋZ�p��2012�N8�����̔N�ӂ�f���ɓǂނƁA
�����p�� ���́A���{�̃g���b�N���[�J���ÐF���R����f�B�[�[���G���W���́u�r�o�K�X�ƔR��̉��P�Z�p�v�̉��nj���
�������{���Ă��Ȃ��悤�ɓǂݎ���̂ł���B�������A���́u�N�Ӂv�́u�����J���̓����v�̍��ł���ɂ�������炸�A
�r�o�K�X�ጸ�ɂ��āA��̓I�Ȍ����J���̓��e����������A�����p�� ���́u�P�Ȃ��]�v����X�ƋL�ڂ���Ă���
�̂ł���B���̂悤�ȁA�R�������e�̎����ԋZ�p������S���l�̓��{�����ԋZ�p��̉���ɔz�z����Ă���̂��B��
�̂��߁A�f�B�[�[���G���W���Ɋւ���V�����Z�p���邱�Ƃ����҂��āA���̎����ԋZ�p����ǂ����̓��{��
���ԋZ�p��̉���̖w��ǂ̐l�B�́A���]���A���_�����̂ł͂Ȃ����낤���B
�J���̓����v���O�H�ӂ����g���b�N�E�o�X���@�����@�p���@���������u�r�o�K�X�ƔR��̉��P�Z�p�v�́A�قƂ�ǂ���
��10�N�`���\�N���ȑO���瑽���̊w�ҁE���Ƃ��b��Ɏ��グ���Ă���u��C�܂݂�̋Z�p�v�ł���A���Ɍ��s��
��^�g���b�N�ɍ̗p����Ď��p������Ă���Z�p���w��ǂł���B�����ԋZ�p��2012�N8�����̔N�ӂ�f���ɓǂނƁA
�����p�� ���́A���{�̃g���b�N���[�J���ÐF���R����f�B�[�[���G���W���́u�r�o�K�X�ƔR��̉��P�Z�p�v�̉��nj���
�������{���Ă��Ȃ��悤�ɓǂݎ���̂ł���B�������A���́u�N�Ӂv�́u�����J���̓����v�̍��ł���ɂ�������炸�A
�r�o�K�X�ጸ�ɂ��āA��̓I�Ȍ����J���̓��e����������A�����p�� ���́u�P�Ȃ��]�v����X�ƋL�ڂ���Ă���
�̂ł���B���̂悤�ȁA�R�������e�̎����ԋZ�p������S���l�̓��{�����ԋZ�p��̉���ɔz�z����Ă���̂��B��
�̂��߁A�f�B�[�[���G���W���Ɋւ���V�����Z�p���邱�Ƃ����҂��āA���̎����ԋZ�p����ǂ����̓��{��
���ԋZ�p��̉���̖w��ǂ̐l�B�́A���]���A���_�����̂ł͂Ȃ����낤���B
�����ԋZ�p��2014�N8�����iVol.68�AN0.8�A2014�j�̓��W�F�N�Ӂ@�u�f�B�[�[���G���W���v�i���ҁF�t�c�g���b�N�X���@�O��@
���G�@���j�́u�S�@�����J���̓����v�ɂ́A�f�B�[�[���G���W���̔r�o�K�X�ƔR����팸���邽�߂̍ŋ߂̋Z�p������
�܂Ƃ߂��Ă���B���́u�S�@�����J���̓����v�ɂ́A�g���b�N���[�J���w�E�����@�ւ̑����̐��Ƃ��f�B�[�[���G��
�W���̔r�o�K�X�ƔR����팸���邽�߂ɗL���ƍl���Ă���Z�p�ɂ��āA�܂Ƃ߂��Ă��锤�ł���B�����N�Ӂ@�u�f�B
�[�[���G���W���v�́u�S�@�����J���̓����v�ɑ��A�M�҂��^��Ɋ�������e�ɂ��āA���L�̕\�P�P�|�U�ɂ܂Ƃ߂��B
���G�@���j�́u�S�@�����J���̓����v�ɂ́A�f�B�[�[���G���W���̔r�o�K�X�ƔR����팸���邽�߂̍ŋ߂̋Z�p������
�܂Ƃ߂��Ă���B���́u�S�@�����J���̓����v�ɂ́A�g���b�N���[�J���w�E�����@�ւ̑����̐��Ƃ��f�B�[�[���G��
�W���̔r�o�K�X�ƔR����팸���邽�߂ɗL���ƍl���Ă���Z�p�ɂ��āA�܂Ƃ߂��Ă��锤�ł���B�����N�Ӂ@�u�f�B
�[�[���G���W���v�́u�S�@�����J���̓����v�ɑ��A�M�҂��^��Ɋ�������e�ɂ��āA���L�̕\�P�P�|�U�ɂ܂Ƃ߂��B
| |
|
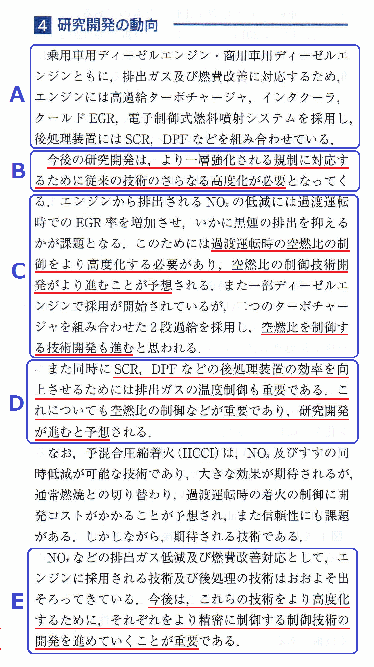 |
�� �f�B�[�[���G���W����NO���팸�ƔR��ጸ�̋Z�p���e
�@���L�̂`�i���ɂ́A���s���f�B�[�[���G���W���ł́A�r�o�K�X�팸
�ƔR����P�̂��߂Ɉȉ��̋Z�p���̗p����Ă���Əq�ׂ��Ă���B �E���ߋ��^�[�{�`���[�W���i���Q�i�ߋ����j
�E�C���^�[�N�[��
�E�N�[���h�d�f�q
�E�d�q���䎮�R�����˃V�X�e��
�E�㏈�����u�i���r�b�q�G�}�A�c�o�e���u�j
�@�����āA���L�̂a�i������тd�i���ɂ́A�ȏ�̌��s�f�B�[�[���G��
�W���ɍ̗p�̏��Z�p�̍X�Ȃ�u���x���v�ɂ���āA����̂m�n���y�єR ��̋K�������ɓK���\�Ƃ́u���ʂ��v���q�ׂ��Ă���B�����O�� ���G ���̌����ɂ́A�|���R�c���Z�p���̕M�҂ɂ͋^��Ɏv����Ƃ� ��ł���B �@���݂ɁA�߂������̑�^�g���b�N���m�n���K���y�єR��K���̋���
�̃��x����\�z����ƁA���{�͑�^�g���b�N�̐V���Ȓ�R��E��r�o�K �X��𑁊��ɐݒ肹��I�ɋL�ڂ����悤�ɁA�ȉ��̋K���l�̐��� �ɂȂ���̂Ɨ\�������B �E �m�n���K���̋����@���@0.23�@g/kWh
�i 2016�N�̎����m�n���K���l���� 43 �� ���j
�i2005�N�̑攪�����\��NO������ڕW���x���j
�E �R���̋����@
�@�@��2015�N�x�d�ʎ�Ӱ�ޔR������{10�����x�̌���
�@���̂悤�ɁA��^�f�B�[�[���g���b�N�ɂ����āA�u�m�n����0.23 (g/kWh)�v
�Ɓ@�u2015�N�x�d�ʎ�Ӱ�ޔR������{10�����x�̔R�����v�� ���{�����\�����ɂ߂č������A���̏ꍇ�A���L�̂`�i���ɋL�� �́u���s�f�B�[�[���G���W���ɍ̗p�̏��Z�p�̍X�Ȃ鍂�x���v������ �́A�m�n���ƔR��̋K���ɓK���ł��Ȃ��Ɛ��������B �@���������āA���{�̃g���b�N���[�J�������L�̂`�i������тa�i������
�тd�i���ɏq�ׂ��Ă���悤�ȋZ�p���u�����J���v�����{���Ă��邾 ���ł���A�����I���m�n���ƔR��̋K�������ɓK���ł����^�g���b �N�����p�����邱�Ƃ́A�|���R�c���Z�p���̕M�҂ɂ�����Ǝv���Ďd �����Ȃ��B�o���邱�ƂȂ�A�O�G ���̖{�S���f���Ă݂������̂� ����B �� ���L�́u�����J���̓����v�ɋL�ڂ̌����J���̉ۑ�
�@���L�̂a�i���ɂ́A����̍X�Ȃ�r�o�K�X�ƔR��̋K�������ɑ�
�����邽�߂ɂ́A�]���̋Z�p�̍X�Ȃ鍂�x�����K�v���q�ׂ��Ă� ��B���̂��߂ɉ������ׂ��Z�p�I�ȉۑ�Ƃ��āA���L�̂b�i������� �c�i���ɂ́A�ȉ��̂��Ƃ���������Ă���B �@ �G���W������r�o�����m�n���̍팸�̂��߂ɂ́A�ߓn�^�]��
�ł̂d�f�q�����w�����邱�Ɓi=�b�i���j �E�M�҂̌����F�ߓn�^�]���ɂd�f�q���������ăG���W������r�o��
���m�n���̍팸��}��Ƃ̋L�q�́A�٘_�����ޗ]�n�̂Ȃ����R�̂��� �ł���A�M�҂����ӂ���Ƃ���ł���B �A �ߓn�^�]���̋�R��̐������荂�x�����邱�Ɓi=�b�i���j
�E�M�҂̌����F�ߓn�^�]���ɋ�R���K�ɐ��䂷�邱�Ƃ́A�m�n���A
�o�l�A�����̑�����h�~���邽�߂ɕK�v�Ȃ��Ƃł��邽�߁A���̋L�q�� �٘_�����ޗ]�n�̂Ȃ����R�̂��Ƃł���A�M�҂����ӂ���Ƃ���ł� ��B �B 2�i�^�[�{�ߋ����̗p������R�䐧��̋Z�p�J���𑣐i����
�E�M�҂������F2�i�^�[�{�ߋ��i���Q�i�V�[�P���V�����^�[�{�V�X�e���j
���Ɓi=�b�i���j �́A�C���x�~�G���W���ɂ���^�g���b�N�̒�R��́u�R�D�J������ �܂߂���v�ȃf�B�[�[���G���W���̔R����P�̋Z�p�v�̍��̐}�S�ɏ� �q���Ă���悤�ɁA���i�g�����X�~�b�V�����Ƒg�ݍ��킹�đ��s���̃G�� �W����Ⴂ��]���Ɉێ��ł���悤�ɂ��邱�Ƃɂ��A�g���b�N�̑��s�R ������P�ł���悤�ɂ���Z�p�ł���B���������āA�u�b�i���v�ɂ����� �u2�i�^�[�{�ߋ��ɂ����R�䐧��v�Əq�ׂ��Ă��邱�Ƃɂ��ẮA �O�G �����u2�i�^�[�{�ߋ��V�X�e���v�̖{���̋@�\�E���\�ɂ� �āA����ė�������Ă���悤�Ɏv�����A�@���Ȃ��̂ł��낤���B �C SCR�����DPF���̌㏈�����u�̌�������̂��߂̔r�o�K
�X�̉��x����i���G���W�����������ɂ�����r�C�K�X���x�� �������j�̎����i=�c�i���j �E�M�҂̌����F�c�i���ɂ����āA�G���W�����������ɂ�����r�C�K
�X���x�̍���������������SCR�����DPF���̌㏈�����u�̌����� ���}��Əq�ׂ��Ă���B�������A�G���W�����������ɔr�C�K�X�� �x�����������邽�߂̋Z�p�ɂ��ẮA�t�c�g���b�N�X���̎O�G ��������L�ڂ���Ă��Ȃ��̂ł���B�܂�A���݂̃f�B�[�[���G ���W���ɂ�����uSCR�ɂ��m�n���팸�v��uDPF�̎��ȍĐ��̑��i�v�� �@�\����̉ۑ肪�q�ׂ��Ă��邾���ł���B����́A�O�q���\11 �Ɏ������u�����ԋZ�p��2010�N8�����iVol.64�AN0.8�A2010�j���W�F�N �Ӂ@�f�B�[�[���G���W���̂S�����J���̓����i���ҁFUD�g���b�N�X���@ ���ѐM�T�@���j�v�Ƃقړ������e�ł���B �@���̂��Ƃ́A2010�N8������4�N�o�߂������݁i2014�N8���j��
���AUD�g���b�N�X���̃G���W���Z�p�ҁE���Ƃ��G���W�������� ���ɂ�����r�C�K�X���x���������ɂ��SCR�����DPF���� �㏈�����u�̌��������}��ۑ�̉���������o���Ă��Ȃ��� ���ƍl������B���̂悤�ɁA�S�N�̍Ό����₵�Ă�SCR�����DPF ���̌㏈�����u�̌�������ɗL���ȃG���W�����������ɂ�����r �C�K�X���x���������̋Z�p���J���ł��Ȃ��ł���ɂ�������� ���A�ނ�̓f�B�[�[���G���W���̕��������ɂ�����r�C�K�X���x�� �������ɗL���ȕM�Ғ�Ă��C���x�~�G���W���i�������J2005- 54771�j�̓����Z�p�i��2006�N4���ɊJ�݂̃z�[���y�[�W��Ō��J�� �݁j����Ȃɖ����E�َE�������Ă���̂ł���B �@���̂��Ƃ́AUD�g���b�N�X����UD�g���b�N�X���ȊO�̃g���b�N���[�J�̃G
���W���Z�p�ҁE���Ƃ����l�ȏɊׂ��Ă�����̂Ɛ��������B�� �̂��Ƃ���A���{�̃g���b�N���[�J�̃G���W���Z�p�ҁE���Ƃ́A�N��l �Ƃ����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�ɂ�����G���W���� �������̔r�C�K�X���x�������̗D�ꂽ�@�\�E���\�𗝉��ł��Ȃ� ���Ƃ����������m��Ȃ��B���ɁA���ꂪ�����ł���A���Ƃ��Q���킵 �����ł͂Ȃ����낤���B����Ƃ��A�|���R�c���Z�p���̒�Ă������ �Z�p�k�i���C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�l���̗p���邱�� �ɁA���{�̃g���b�N���[�J�̃G���W���Z�p�ҁE���Ƃ̃v���C�h�E�����S �������Ȃ������ł��낤���B���ɁA�����ł���A���̑����䖝�͂��� �܂ő����邱�Ƃ��ł���̂ł��낤���B�|���R�c���Z�p���ɂƂ��ẮA �����[�X�Ȃ��Ƃł���B �i�Ȃ��A�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̃G���W��������
���ɂ�����r�C�K�X���x�̍������Ɋւ���@�\�E���\���ɂ��� �́A�C���x�~�G���W���ɂ���^�g���b�N�̒�R��A�C���x�~�� DPF�̎��ȍĐ��𑣐i (�����Đ��̍팸�ŔR�����h�~�j�A�C���x �~�́A�f�B�[�[���r�C�K�X�̃G�l���M�[���u�̌����������A�f�B �[�[���̋C���x�~�́A�R�[���h�X�^�[�g��NO���팸�ɂ��L�����I�A�� �쎩���Ԃ��_�����\�����R����P�@�\�̗��C���x�~�V�X�e���� �ڏq���Ă���̂ŁA�����̂�����͌䗗�������������B�j |
�W�|�S�[(g)�@�����ԋZ�p��2015�N8�����iVol.69�AN0.8�A2015�j�̓��W�F�N�ӂ̋^��_
�@�����ԋZ�p��2015�N8�����iVol.69�AN0.8�A2015�j�̓��W�F�N�Ӂ@�u�f�B�[�[���G���W���v�i���ҁF�����U�����ԇ��@�`��
�m���@���j�́u�S�@�����J���̓����v�ɂ́A�f�B�[�[���G���W���̔r�o�K�X�ƔR����팸���邽�߂̍ŋ߂̋Z�p������
�܂Ƃ߂��Ă���B���́u�S�@�����J���̓����v�ɂ́A�g���b�N���[�J���w�E�����@�ւ̑����̐��Ƃ��f�B�[�[���G��
�W���̔r�o�K�X�ƔR����팸���邽�߂ɗL���ƍl���Ă���Z�p�ɂ��āA�܂Ƃ߂��Ă��锤�ł���B�����N�Ӂ@�u�f�B
�[�[���G���W���v�́u�S�@�����J���̓����v�ɑ��A�M�҂��^��Ɋ�������e�ɂ��āA���L�̕\�P�P�|�V�ɂ܂Ƃ߂��B
�m���@���j�́u�S�@�����J���̓����v�ɂ́A�f�B�[�[���G���W���̔r�o�K�X�ƔR����팸���邽�߂̍ŋ߂̋Z�p������
�܂Ƃ߂��Ă���B���́u�S�@�����J���̓����v�ɂ́A�g���b�N���[�J���w�E�����@�ւ̑����̐��Ƃ��f�B�[�[���G��
�W���̔r�o�K�X�ƔR����팸���邽�߂ɗL���ƍl���Ă���Z�p�ɂ��āA�܂Ƃ߂��Ă��锤�ł���B�����N�Ӂ@�u�f�B
�[�[���G���W���v�́u�S�@�����J���̓����v�ɑ��A�M�҂��^��Ɋ�������e�ɂ��āA���L�̕\�P�P�|�V�ɂ܂Ƃ߂��B
| |
|
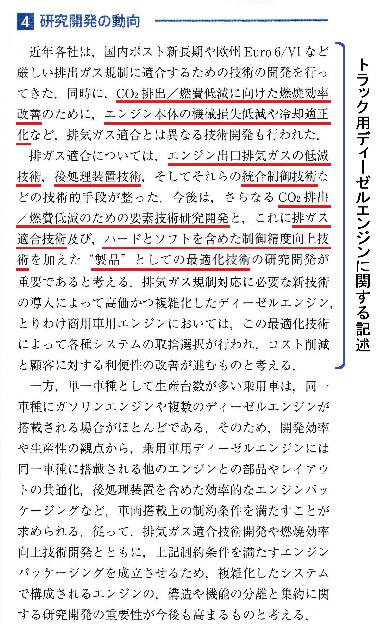 |
�� ��^�g���b�N�̓��{�A�č��A���B��NO���K���̌���
�č������ɂ���^�g���b�N��NO���K�����{�s����������{���{�̑�
���ɂ��ڏq���Ă���悤�ɁA��^�f�B�[�[���g���b�N�Ɋւ�����{�� NO���K���́A�����̋K���i2016�N�K���j�ł��A���A�Ă�NO���K����� ���ɂ��K���l���{�s����Ă���̂�����̂悤�ł���B ���B
2013�N��EURO�Y�i�ߓn���[�h�j�m�n�� �� 0.46 g/kWh
EEV(5)�i�ߓn���[�h�j�́ANO�� �� 0.2 g/kWh
���@EEV�FEnhanced Environmentally Friendly Vehicles�̗��BEEV�K
���l�́A��C���������ɐi�s���Ă���s�s���̒n��������̂� �߁A�����o�[�e���������I�Ɏg�p���邽�߂̒l�i��F�s�s�ւ̏�� ���ꐧ����݂���ۂ̊�Ƃ��Ďg�p�j�ŁA�b��l�B �č�
2010�N�̂m�n���K���́ANO�� �� 0.27 g/kWh
���{
2016�N�̂m�n���K���́A�m�n���� 0.4 g/kWh
�� ���{�̑�^�g���b�N�ɕK�v��NO���K���ƔR���̋����@
�Z��^�g���b�N��NO���K���̋���
�߂������̑�^�g���b�N���m�n���K���y�єR��K���̋����̃��x����
�\�z����ƁA���{�͑�^�g���b�N�̐V���Ȓ�R��E��r�o�K�X��� �����ɐݒ肹��I������č������ɂ���^�g���b�N��NO���K�����{ �s����������{���{�̑Ӗ��ɋL�ڂ����悤�ɁA�ȉ��̋K���l�̐��� �ɂȂ���̂Ɨ\�������B �@�@ �m�n���K���̋����@���@0.23�@g/kWh
�i 2016�N�̎����m�n���K���l���� 43 �� ���j
�i2005�N�̑攪�����\��NO������ڕW�j
�Z��^�g���b�N���R���̋����@
�E �R���̋����̌o��
2006�N 3���Ɂu2015�N�x�d�ʎԔR���v�̍���
2007�N 7���Ɂu2015�N�x���^�ݕ��ԔR���v�̍���
2015�N 7���Ɂu2022�N�x���^�ݕ��ԔR���v�̍���
�E ���^�ݕ��Ԃ̔R���̋����Ƃ��āA2015�N 7���Ɂu2022�N�x
���^�ݕ��ԔR���v�����ɍ��肳��Ă��邱�Ƃ��画�f���A��^�g ���b�N�i���d�ʎԁj�ɂ����Ă����}�ɔR���̋������K�v�ł��邱 �Ƃ͖��炩�ł���B���̏ꍇ�̑�^�g���b�N�̔R���̋����́A �ȉ��̃��x�����K�ƍl������B �@�@�@2015�N�x�d�ʎ�Ӱ�ޔR������{10�����x�̌���
�E����A���{�ɂ����đ��}�Ɏ��{���ׂ���^�g���b�N�ɕK�v��NO���K
���ƔR���̋����̃��x���́A�ȉ��̒ʂ�ƍl������B ��^�f�B�[�[���g���b�N��NO���̋K���̋���
�@�@�@�@�@�u�m�n����0.23 (g/kWh)�v
��^�f�B�[�[���g���b�N�̔R���̋���
�u2015�N�x�d�ʎ�Ӱ�ޔR������{10���̔R�����v
�E���݂̓��{�̑�^�g���b�N�ɂ����ẮA�ȏ��NO���ƔR��̋K��
�����̑��}�Ȏ��{�����߂��Ă���B �� ��^�g���b�N��NO���팸�ƔR����P�̂��߂̋Z�p�I�ۑ�
�E�����_�i2015�N8�����_�j�ɂ����āA��^�g���b�N�́u��NO�����v����
�сu��R��v���������邽�߂̉������ׂ��ۑ�͈ȉ��̒ʂ�ł� ��B �@ DPF���u�̋����Đ��̕p�x����
�A SCR�G�}�̒ቷ����
�BSCR�G�}��HC��ł̉����v
�C �d�ʎԃ��[�h�R��̉��P
�� ��^�g���b�N�̇@�`�C�̉ۑ�������ł���Z�p
�E��^�g���b�N�̇@�`�C�̉ۑ�������ł���Z�p�́A�{�y�[�W�̑���
�����C���x�~�G���W���ɂ���^�g���b�N�̒�R��̃y�[�W�ɏ� �q���Ă���悤�ɁA��^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W�����C���x�~�G�� �W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p���̗p���邱�Ƃł���B�� �݂̂Ƃ���A���̓����Z�p�ȊO�ɓ��{�̑�^�g���b�N�̎g�p�ߒ��� ���u�m�n����0.23�@g/kWh ��NO���K���v�Ɓu2015�N�x�d�ʎԔR�� ����{10�����x�̔R�����v�̋K�������ɓK�������邱�Ƃ́A���� �Ɛ��@�����B�Ƃ��낪�A��^�g���b�N��NO���팸�ƔR�����ɗL�� �ȋC���x�~��َE����w�ҏ����ɏڏq�̂悤�ɁA���{�̑�w�E���� �@�ւ̊w�ҁE���Ƃ⎩���ԃ��[�J�̋Z�p�҂́A�C���x�~�G���W�� �i�������J2005-54771�j�̓����Z�p�����S�ɖ����E�َE���Ă���� ������̂悤�ł���B �� ���L�́u�S�@�����J���̓����v�ɋL�ڂ̓��e
�E���L�́u�S�@�����J���̓����v�ł́A�u�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W��
�Ɋւ���L�q�v�̕����ł́A�����U�����ԇ��̊`���m�� ���́A��^ �g���b�N�́u��NO�����v����сu��R��v���������邽�߂̉������� ���ۑ��A���̉ۑ�����������̓I�ȋZ�p������L�ڂ��Ă��� ���悤�ł���B�����āA�����U�����ԇ��̊`���m�� �����L�ڂ��Ă� �邱�Ƃ́A�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W���̋Z�p�I�ȓ��e�̐�发�E�L ���ɋL�ڂ��ꂽ�u���ڂ̕\��v�������W�߂ė��Ă���悤�� ����B �uCO2�r�o�^�R��ጸ�Ɍ������R�Č����̉��P�v
�u�G���W���o���r�o�K�X�ጸ�̋Z�p�v
�u�㏈���Z�p�v
�u��������Z�p�v
�u�S�̂̋@�B�������p�K�����v
�uCO2�r�o�^�R��ጸ�̂��߂̗v�f�Z�p�����J���v
�u�r�o�K�X�K���Z�p�v
�u�n�[�h�ƃ\�t�g���܂߂����䐸�x����Z�p�v
�u�h���i�h�Ƃ��Ă̍œK���Z�p�̌����J���v
�u�R�X�g�팸�ƌڋq�ɑ��闘���̉��P�v
�E���L�́u�S�@�����J���̓����v�́u�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W���Ɋ�
����L�q�v�̕����ł́A��发�E�L���ɋL�ڂ��ꂽ�u���ڂ̕\��v�� �����W�߂ė��A��^�g���b�N�́u��NO�����v����сu��R�� ���v���������邽�߂̉������ׂ��ۑ��A���̉ۑ������������ �I�ȋZ�p������L�ڂ��Ă��Ȃ��B�܂�A���L�́u�S�@�����J�� �̓����v�́u�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W���Ɋւ���L�q�v�̕� ���́A�u��^�g���b�N�̒�NO��������ђ�R��̋Z�p������ ���Ă̋L�ڂ͏ȗ�����v�̂P�s�ōςޓ��e�ł���B���̂��߁A �ꌩ�����Ƃ���A�����ԋZ�p��2015�N8�����̔z�z��̓ǎ҂ł��� �����ԋZ�p��̖�S���l�̉�������S�Ɂu�n���v�ɂ������e�ƍl�� ����B�������A���̂悤�Ȍ����́A�M�҂ɂ͊��S�Ȍ��ƍl���Ă� ��B �E�����U�����ԇ��̊`���m�� ���́A�g���b�N���[�J�̐��ƁE�Z�p��
�ł��邽�߁A���R�̂��ƂȂ����^�g���b�N�́u��NO�����v����сu�� �R��v���������邽�߂ɇ@�`�C�̉ۑ�𑁋}�ɉ������ׂ����Ƃ� �\�ɏ��m���Ă��锤�ł���B���̂��߁A���L�́u�S�@�����J���� �����v�̍ŏ��ɇ@�`�C�̑�^�f�B�[�[���g���b�N�̉ۑ�L���� �A����ɑ����āA���R�A�@�`�C�̉ۑ���������錤���J���̍ŋ� �̓������L�ڂ���K�v�������邱�ƂɂȂ�B�Ƃ��낪�A�c�O�Ȃ��ƂɁA �����U�����ԇ��̊`���m�� ���́A��^�f�B�[�[���g���b�N�@�`�C�� �ۑ����������Z�p�̏��������ێ����Ă��Ȃ��Ɛ��������B�� �ɁA�����U�����ԇ��̊`���m�� �������^�ʖڂŐ����Ȑl���ł��� �A��^�f�B�[�[���g���b�N�@�`�C�̉ۑ����������Z�p�Ƃ��āA 2010�N�V��28�����\�̒������R�c��E��C������̑�\�� ���\�ɋL�ڂ��ꂽ�u2�i�ߋ��v�A�uEGR���̌���i�ꕔ�ɂ�LP-EGR�� �p�j�v�A�u�R�����ˈ��͂̌����PCI�R�āv�A�u�^�[�{�R���p�E���h�v�� �u�K���N�^�Z�p�v�܂��́u�|���R�c�Z�p�v�ƌ����Ă��ߌ��ł͂Ȃ��Z�p�� ���L�́u�S�@�����J���̓����v�����Ă������̂Ɛ��������B�Ƃ� �낪�A�����U�����ԇ��̊`���m�� ���́A2010�N�̒������R�c�� �̑�\�����\�Ɏ����ꂽ���ԈˑR�̎�C�̕t�����Z�p����� ���Ƃ����������̂ƍl������B�����ŁA�����U�����ԇ��̊`���m�� ���́A��^�f�B�[�[���g���b�N�@�`�C�̉ۑ����������Z�p�̏��� �����ێ����Ă��Ȃ�������B���E�B�����邽�߁A���L�́u�S�@�����J ���̓����v�́u�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W���Ɋւ���L�q�v�̕����� �́A��发�E�L���ɋL�ڂ��ꂽ�u���ڂ̕\��v�������W�߂ė��� ���A��^�g���b�N�́u��NO�����v����сu��R��v���������邽�߂� �������ׂ��ۑ��A���̉ۑ�����������̓I�ȋZ�p������L �ڂ��Ȃ����Ƃɂ����悤�ł���B�܂�A�����U�����ԇ��̊`���m�� ���́A��_�ɂ��A���L�́u�S�@�����J���̓����v�́u�g���b�N�p�f�B�[�[ ���G���W���Ɋւ���L�q�v�̕����́A�u��^�g���b�N�̒�NO�������� �ђ�R��̋Z�p�����ɂ��Ă̋L�ڂ͏ȗ�����v�̂P�s�ōς� ���e���A�Ӗ��������_���_���ƋL�q�����ƍl������B����́A���Ƃ� ���ꂽ���Ƃł͂Ȃ����낤���B �E���̂悤�ɁA�����ԋZ�p��2015�N8�����iVol.69�AN0.8�A2015�j�̓�
�W�F�N�ӂ̃f�B�[�[���G���W���́u�����J���̓����v�Ɂu��发�E�L ���ɋL�ڂ��ꂽ�\��v�������W�߂ė����j���p�Ƃ��v���� �L�������X�ƌf�ڂ���Ă��邱�Ƃ́A�M�҂ɂ͋������ɂł���B�� �̑S�́A�����ԋZ�p�v���̕ҏW�ψ����ϔC����Ă���l�B�̒m���E �\�́E�펯�ɋ^��������邪�A�@���Ȃ��̂ł��낤���B�@ �E���݂ɁA�����U�����ԇ��̊`���m�� ���́A�����ԋZ�p��2015�N8
�����̔N�ӂł́A�f�B�[�[���G���W�����uNO���팸�v�Ɓu�R����P�v�� �L�����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p�� ���E�َE���Ă��邱�Ƃ������ł���B���̌��ʁA��^�f�B�[�[���g���b �N�̑�^�g���b�N�̌p�����Y�Ԃ́u2015�N�x�d�ʎԔR������{ 10�����x�̔R�����v�Ɓu�m�n����0.23�@g/kWh ��NO���K���v�̎��{ ��x��������Ȃ������o����邱�ƂɂȂ�B���̂��Ƃ���A �����U�����ԇ��̊`���m�� ���́A�����ԋZ�p��2015�N8�����̔N �ӂ����p�������Љ�I�Ȋ������s���Ă���ƌ��邱�Ƃ��\�Ǝv�� ���A����͕M�҂̓�Ȃł��낤���B �E�Ȃ��A���ɁA���L�́u�S�@�����J���̓����v���M�҂��L�q����Ƃ���
�A�u��^�g���b�N�̒�NO�����A����ђ�R����������邽�߂ɂ́A ���}�ɇ@�`�C�̉ۑ���������邱�Ƃ��K�v�s���ł���B���̂��� �̗B��̕��@�́A�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓� ���Z�p���^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W���ɍ̗p���邱�Ƃł���B�v �Ƃ̓��e�ƂȂ邪�E�E�E�E�E�E�B |
�@�ŋ߂̂T�N���i2010�`2015�N�j�ɂ�����u�����ԋZ�p�v���̔N�ӂ́u�f�B�[�[���G���W���v�ł́u�����J���̓����v�Ɍf
�ڂ���Ă���u�f�B�[�[���G���W���̔r�o�K�X����ƔR����P�v�Ɋւ���L�ړ��e���A�ȉ��̕\�P�Q�ɂ܂Ƃ߂��B
| |
|
|
| |
�� �A�fSCR�G�}��NO���팸��DPF�̍Đ��̂�
�߂��G���W���ᕉ�ׂ̔r�C�K�X���x�� ���� ������Z�p�̊J�����K�v �i�������J���̓����ł͖����A�P���ۑ�̒� ���j |
�� ���L�́u�����J���̓����v�ɂ́A�f�B�[�[���̔r�o�K�X�ƔR���
���P���邽�߂̉ۑ�Ƃ��āA�G���W���ᕉ���ɔr�C�K�X���x�� ����������Z�p���K�v�Ƃ̂������L�ڂ���Ă���̉߂��Ȃ��B ���������āA���L�̓��e�𐳊m�ɏ��������ƁA�u�f�B�[�[���̔r�o �K�X�ƔR��̉��P�ɕK�v�ȃG���W���ᕉ���ɔr�C�K�X���x�� ����������Z�p�́A�����_�ł͕s���ł���v�Ƃ���ׂ��ł���B �� ����A2006�N4���ɊJ�݂����M�҂̃z�[���y�[�W�ł́A �u�f�B�[�[���G���W���ᕉ���ɔr�C�K�X���x���������ł��� ���߂ɁA���L�̃f�B�[�[���̔r�o�K�X�ƔR������P���邽�߂� �ۑ肪�ڏo�x�������ł���Q�^�[�{�����̋C���x�~�G���W�� �i�������J2005-54771�j�̋Z�p���Ă��Ă��邪�A���L�� ���҂́A���̋C���x�~�̋Z�p�����S�ɖ����E�َE���Ă���悤�� ����B |
| |
�� �R���єr�o�K�X�����P���邽�߂��t���N
�V�����̍팸�ƔR�ĉ��P�@ �i���V�K�̋�̓I�ȔR����P�Z�p�̋L�ڂ͖� ���j |
�� �t���N�V�����̍팸�ƔR�ĉ��P�́A���h���t�E�f�B�[�[����
1892�N�Ƀf�B�[�[���G���W�������Ĉȗ��A120�N�ȏ���̂��� ��т��ċZ�p�J�����s���Ă����ÐF���R����R�����̋Z�p �ł���B�i������Ƃ������i���̊J���p���悪�\�z�����N���� �F�߂�R����P�̋Z�p�j �� ���L�̓��e�́A���E���w���ł��L�ڂł���̋Z�p�ł���A �f�B�[�[���̔r�o�K�X�ƔR��̉��P�Z�p�������L�ڂ���Ă��Ȃ� �̂Ɠ����ł���B �� ����A�M�҂̒�Ă���Q�^�[�{�����̋C���x�~�G���W���i���� ���J2005-54771�j�̋Z�p�́A�u�A�fSCR�G�}���ɂ��NO���팸 �̌���v�A�u�����s���ɑ��p����G���W�����������̔R�� ����v�A�uDPF���u�ł̋����Đ��̕p�x�팸�ɂ��R����P�v�� �\�ł���B�A2006�N4���ɊJ�݂����M�҂̃z�[���y�[�W�ł́A ���̋C���x�~�̋Z�p�����J���Ă��邪�A���L�̒��҂́A����� ���S�ɖ����E�َE���Ă���悤�ł���B |
| |
�� �R����P����єr�o�K�X�ጸ�̋Z�p�Ƃ���
�������R�c��E��C������̑�\���� �\�ɋL�ڂ��ꂽ���̂Ɨ��A���ނ̋Z�p��� �� �@�@�E��Pme �@�@�E���ߋ��� �@�@�E�����̃}���`���� �@�@�E�σo���u�^�C�~���O �@�@�E�σX���[�� �@�@�EEGR�̉��x�E���ʐ���̍��x���� �@�@�E�p�M����Ȃǂ̃G�l���M�[����Z�p |
�� �O�q�̐}10�Ɏ������uNEDO�̊v�V�I���������Q�ԑ���
�Z�p�J���v���W�F�N�g�ł��钴���x�R�Đ���G���W�V�X�e���� �����J���v����сA�}10�Ɏ������uPCI �R�Ăɂ��R����P�� ���ʁv���т� �^�[�{�R���p�E���h�́A��^�g���b�N�̑��s�R��̉��P������ȋZ�p ���I�@���̏�疾�炩�Ȃ悤�ɁA���L�̂悤�Ȓ������R�c ��E��C������̑�\�����\�ɗ��ꂽ�Z�p�ł́A�f�B�[ �[���̔r�o�K�X���P�ƔR�����́A����Ȃ��Ƃ͖��炩�ł���B �� ����A�M�҂̒�Ă���Q�^�[�{�����̋C���x�~�G���W���i���� ���J2005-54771�j�̋Z�p�́A�O�q�̗��R�ɂ��A�u�A�fSCR�G�} ���ɂ��NO���팸�̌���v�A�u�����s���ɑ��p����G���W������ �����̔R�����v�A�uDPF���u�ł̋����Đ��̕p�x�팸�� ����ăf�B�[�[���G���W���̔R����P�v���\�ł���B�A2006�N4�� �ɊJ�݂����M�҂̃z�[���y�[�W�ł́A���̋C���x�~�̋Z�p�� ���J���Ă��邪�A���L�̒��҂́A����������S�ɖ����E�َE���� ����悤�ł���B |
| |
���@�R��E�r�o�K�X�̉��P�ƏȔR��^�]�@
�@�E�R���̍������ˉ� �@�E�R�Ď����P
�@�E���ߋ���
�@�E�t���N�V�����ጸ
�@�E�G���W�����r�C�ʉ�
�@�E�A�C�h�����O�X�g�b�v�@�\
�@�E�G���W����]�E�A�N�Z���J�x�̍œK������@
�@�E�G���W���Ǝԗ��̋�������@ �@�E�G���W���A�E�g�̔r�o�K�X�}��
�@�E�r�C�㏈���V�X�e���̏ȗ���
�@�E�G���W�����i�̊ȗ����@
�@�E�㏈�����u�̈��͑����ጸ
�@�E�㏈�����u��NO�����̌���
|
�� ���L�̎O�H�ӂ����ׯ��E����@�����p�����������Z�p
�́A�ȉ��̗��R�ő�^�g���b�N�̔r�o�K�X�팸�ƔR��ጸ�� ����ƍl������B �@ �ߋ�10�N�`���\�N���ȑO�Ɏ��p������Ĉȗ��A���N�� �킽���ĉ��ǂ���Ă����Z�p�ł��邽�߂ɍ���̐��\���オ �ɂ߂č���ȁu��C�܂݂�̋Z�p�v�̋Z�p�A �A ���ɑ�^�g���b�N�ɃC���^�[�N���ߋ��G���W�������ڂ���� ���錻��ɂ����āA�Y�����Y��h���E�L�z�[�e�̂悤�Ȏ������ �̐l�������҂���悤�ȔR����P��ړI�Ƃ����u�G���W�� ���r�C�ʉ��v�̋Z�p �B �O�H�ӂ����̍����p�����́u�P�Ȃ��]�v�����ł���A���� ��]����������̓I�ȍ\���E��@��������������Ă��Ȃ� �Z�p �@���L�ɗ��ꂽ�Z�p�́A�ȏ�̉��ꂩ�ɕ��ނł���
�r�o�K�X�팸��ƔR��ጸ�̋Z�p�ł���B���������āA2013�N
8�����s�̎����ԋZ�p���̔N�ӂɋL�ڂ���Ă���悤�ɁA���ɁA
�g���b�N���[�J�����L�̋Z�p�̌����J���������Ɏ��{���Ă���
�Ƃ��Ă��A�߂������ɑ�^�g���b�N�̖ڗ������\���Ȕr�o�K�X
�팸��ƔR��ጸ���������邱�Ƃ�����ƍl������B���Ԃ�
�ǂ������Ă���u����̍l���A�x�ނɎ������v�Ƃ́A����
�悤�ȋ����E�s�����w���̂ł͂Ȃ����낤���B
�� ����A�C���x�~�G���W���ɂ���^�g���b�N�̒�R��ɂ� �ڏq���Ă���悤�ɁA��^�g���b�N�ɂ����Ė{���ɔr�o�K�X�팸�� �R��ጸ�̗�����������}�邽�߂ɂ́A�M�҂���Ă��Ă��� �Q�^�[�{�������C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�� �Z�p�̎��p����}�邱�Ƃ��A�M�҂́A��Ă��Ă���B���̋C�� �x�~�̋Z�p���^�g���b�N�ɍ̗p����A�u�A�fSCR�G�}���� ���NO���팸�̌���v�A�u�����s���ɑ��p����G���W������ �����̔R�����v�A�uDPF���u�ł̋����Đ��̕p�x�팸�� ���f�B�[�[���G���W���̔R����P�v���\�ł���B2006�N4�� �ɊJ�݂����M�҂̃z�[���y�[�W�ł́A���̋C���x�~�̋Z�p�� ���J���Ă���B�������A����܂łƓ��l�ɁA���҂̎O�H�ӂ����� �̍����p�����̍��L�̔N�ӂł́A�r�o�K�X�팸�ƔR��ጸ�ɗL�� �ȋZ�p������L�ڂ��邱�Ƃ��ł��Ă��Ȃ��ɂ�������炸�A �C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p�����́A ��Ȃɖ����E�َE���Ă���悤�ł���B ���̖����E�َE�́A�O�H �ӂ����g���b�N�E�o�X���̃G���W���W�̊����̋����w���Ɉ˂� ���̂ł��낤���B |
| |
�� �X�Ȃ��r�o�K�X�팸�ƔR����P�̂��߂�
�́A���s���f�B�[�[���G���W���̋Z�p�̍�
�x�����K�v
�E���ߋ��^�[�{�`���[�W���i���Q�i�ߋ����j
�E�C���^�[�N�[��
�E�N�[���h�d�f�q
�E�d�q���䎮�R�����˃V�X�e��
�E�㏈�����u�i���r�b�q�G�}�A�c�o�e���u�j
�i�������J���̓����ł͖����A�P���ۑ�̒� ���j |
�� 2010�N8������4�N�o�߂������݁i2014�N8���j�ł��AUD�g��
�b�N�X���̃G���W���Z�p�ҁE���Ƃ��G���W�����������ɂ�
����r�C�K�X���x������������SCR�����DPF���̌㏈�����u
�̌��������}��ۑ�̉���������o���Ă��Ȃ����Ƃ����炩
���B
�@���̂悤�ɁA�G���W�����������ɂ�����r�C�K�X���x���������� �ۑ�����̋Z�p�J���ɂ��ẮA�g���b�N���[�J�ł͍ŋ߂̂S�N�Ԃ� �킽���Ė��ʂȍΌ����₳��Ă����悤�ł���B���̌��ʁASCR�� ���DPF���̌㏈�����u�̌�������ɗL���ȃG���W���������� �ɂ�����r�C�K�X���x���������̋Z�p���J���ł��Ă��Ȃ��ł� ��B����ɂ�������炸�A�g���b�N���[�J�̋Z�p�ҁE���Ƃ̓f�B�[�[�� �G���W���̕��������ɂ�����r�C�K�X���x���������ɗL���ȕM�� ��Ă��C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p�i�� 2006�N4���ɊJ�݂̃z�[���y�[�W��Ō��J�ς݁j����Ȃɖ����E�� �E�������Ă���悤�ł���B |
| |
�� ��发�E�L���ɋL�ڂ��ꂽ�u���ڂ̕\��v��
�����W�߂ė��A��^�g���b�N�́u��NO��
���v����сu��R��v���������邽�߂̉�����
�ׂ��ۑ��A���̉ۑ�����������̓I�ȋZ�p
������L�ڂ��Ă��Ȃ�
�y ���ҁF�����U�����ԇ��@�`���m���@�� �z |
�� �����U�����ԇ��̊`���m�� ���́A��^�g���b�N�́u��NO�����v����
�сu��R��v���������邽�߂̉������ׂ��ۑ��A���̉ۑ������
�����̓I�ȋZ�p������L�ڂ��Ă��Ȃ��悤�ł���B�����āA�����U
�����ԇ��̊`���m�� �����L�ڂ��Ă��邱�Ƃ́A�g���b�N�p�f�B�[�[��
�G���W���̋Z�p�I�ȓ��e�̐�发�E�L���ɋL�ڂ��ꂽ�u���ڂ̕\��v
�������W�߂ė��Ă���悤�ł���B
�@���̂��Ƃ���A��^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W���̃G���W��������
���ɂ�����r�C�K�X���x���������̉ۑ�����̋Z�p�J���ɂ�
�ẮA�g���b�N���[�J�ł͍ŋ߂̂U�N�Ԃɂ킽���Ė��ʂȍΌ����₳
��Ă����悤�ł���B���̌��ʁASCR�����DPF���̌㏈�����u�̌�
������ɗL���ȃG���W�����������ɂ�����r�C�K�X���x��������
�̋Z�p���J���ł��Ă��Ȃ��ł���B����ɂ�������炸�A�g���b�N
���[�J�̋Z�p�ҁE���Ƃ̓f�B�[�[���G���W���̕��������ɂ�����
�r�C�K�X���x���������ɗL���ȕM�Ғ�Ă��C���x�~�G���W���i����
���J2005-54771�j�̓����Z�p�i��2006�N4���ɊJ�݂̃z�[���y�[�W
��Ō��J�ς݁j����Ȃɖ����E�َE�������Ă���悤�ł���B
|
�@�Ƃ���ŁA�����ԋZ�p��̋g�쒨�G ���̕ҏW��L�i��2014�N8�����s�̔N�Ӂj�ɂ��A�u�����ԋZ�p��̔N��
���͎����ԋƊE�̋Z�p�i�W�̒�_�ϑ��f�[�^�ƈʒu�Â�����v�Ƃ̂��Ƃł���B���̂悤�Ȋϓ_���猩��ƁA�ȏ��
�\�P�V�Ɏ������ŋ߂̂S�N���i2010�`2014�N�j�ɂ�����u�����ԋZ�p�v���̔N�ӂ́u�f�B�[�[���G���W���v�ł́u�����J��
�̓����v�ł́A�ȉ��̂悤�ɁA�f�B�[�[���G���W���̕���ł́A�̐S�̔R�����Ɣr�o�K�X���P�ɂ��Ă̗L���ȋZ�p
����̓I�ɂقƂ�NjL�ڂ���Ă��Ȃ��悤�ł���B�i�ڍׂ͑O�q��8-4-(a)�`(��)�̍����Q�ƕ��j
���͎����ԋƊE�̋Z�p�i�W�̒�_�ϑ��f�[�^�ƈʒu�Â�����v�Ƃ̂��Ƃł���B���̂悤�Ȋϓ_���猩��ƁA�ȏ��
�\�P�V�Ɏ������ŋ߂̂S�N���i2010�`2014�N�j�ɂ�����u�����ԋZ�p�v���̔N�ӂ́u�f�B�[�[���G���W���v�ł́u�����J��
�̓����v�ł́A�ȉ��̂悤�ɁA�f�B�[�[���G���W���̕���ł́A�̐S�̔R�����Ɣr�o�K�X���P�ɂ��Ă̗L���ȋZ�p
����̓I�ɂقƂ�NjL�ڂ���Ă��Ȃ��悤�ł���B�i�ڍׂ͑O�q��8-4-(a)�`(��)�̍����Q�ƕ��j
�� 2010�N�F�G���W���ᕉ���̔r�C�K�X���x�̍��������K�v�Ƃ��ۑ肾���ł���A�Z�p�����̋L�ڂ́A�F��
�� 2011�N�F�R���єr�o�K�X�̉��P�̂��߁A�t���N�V�����팸�ƔR�ĉ��P������ÐF���R�����ʘ_�̋L��
�� 2012�N�F�R���єr�o�K�X�̉��P�Ɍ��ʂ��͏��̒��R�E��C����̑�\�����\�Ɠ��ނ̋Z�p�̗ɏI�n
�� 2013�N�F�R���єr�o�K�X�̉��P�Ɍ��ʂ��͏���10�N�ȏ���ȑO�̋Z�p�⒘�҂̊�]�E��]�̗ɏI�n
�� 2014�N�F�G���W���ᕉ���̔r�C�K�X���x�̍��������ۑ�́A�S�N�O�Ɠ��l�ɁA�������̏�ԂŎ�l�܂���
�� 2015�N�F��发�̍��ڂ̕\�肾���̗��Ă��邱�Ƃ���A5�N�O�Ɠ��l�ɁA�������̏�ԂŎ�l�܂���
�����v�ł́A���q��S������UD�g���b�N�X���A�����U�����ԇ��A���쎩���ԇ��O�H�ӂ����g���b�N�E�o�X���̋Z�p�ҁE��
��Ƃ́A�߂������Ɏ����ł������ȑ�^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W���̔R����P����єr�o�K�X�ጸ�̋Z�p���ق�
��NjL�ڂ���Ă��炸�A�]������́u��C�̕t�����V�Z�p�H�v��u����̍��x���H�v�̂悤�ȓǎ҂����Ɋ����Z�p���
�����Ă���̂ł���B����́A��^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W���̔R����P����єr�o�K�X�ጸ�ɗL���ȋZ�p���A��
�N�A����J���ł��ĂĂ��Ȃ����Ƃ��Ӗ�����ƍl������B���ɁA2010�N��2014�N�́u�f�B�[�[���G���W���v�̔N�ӂ�
����ɂ��u�G���W�����������ɂ�����r�C�K�X���x������������SCR�����DPF���̌㏈�����u�̌��������}��
�Ƃ̍ŏd�v�ۑ�v�������L�ڂ���Ă���A���̉ۑ���������邽�߂̃G���W�����������̔r�C�K�X���x����������
���̓I�ȊJ���Z�p�������q�ׂ��Ă��Ȃ����Ƃ́A�ŋ߂̃f�B�[�[���G���W���̌����J���ɂ�������@���Ɏ�
���Ă���ƍl������B���̂��Ƃ́A���N�A�u�����ԋZ�p��̔N�Ӎ��v��n���ɔ��s���邱�Ƃɂ���ē���ꂽ������
�ƊE�̋Z�p�i�W�̒�_�ϑ��f�[�^�ɂ���Ė��炩�ɂȂ������Ƃł���B���������ƁA�����ԋZ�p����C�Ɂu�ǂ��d
�������Ă���v���ƂɂȂ�A�����ԋZ�p��̑��݈Ӌ`���ĔF����������ł���B
�@���͂Ƃ�����A2010�N�`2015�N�̊e�N���N�Ӂi8�����j�ɂ����āA�G���W�����������ɂ�����r�C�K�X���x������
������SCR�����DPF���̌㏈�����u�̌��������}��Z�p�J���̕K�v����i���Ă���̂́A���ѐM�T ���ƎO��
���G ����UD�g���b�N�X���̋Z�p�ҁE���Ƃ����ł���B����UD�g���b�N�X���̏��ѐM�T ���ƎO�G ���Ɍ�����
���m�ȋZ�p���M�����^�ʖڂ��u�N�Ӂv�̎��M�҂Ƃ��Ă̎p���́A�^�ɒl������̂ƍl������B����ɑ��A
���쎩���ԇ� ���� �� ���A�����U�����ԇ� �`���q�� ���A�O�H�ӂ����g���b�N�E�o�X�� �����p�� ���́A�ނ�̒S����
���u�N�Ӂv�ɂ́A�f�B�[�[���G���W���ɂ����镔�������ɂ͔r�C�K�X���x�̍��������K�v�Ƃ̖������ȍŏd�v�ۑ�
�ɂ��ĉ����G��Ă��炸�A���̉ۑ���������邽�߂̋Z�p�J���̓����ɑS�����y���Ă��Ȃ��̂ł���B���̂��Ƃ�
��A���쎩���ԁA�����U�����ԁA�O�H�ӂ����̋Z�p�ҁE���Ƃ́A�����ԋZ�p����u�N�Ӂv���������Z�p�����L��
����C�\�����������Ă��邱�Ƃ����炩���B���̂悤���Ƃ́A�u�N�Ӂv�̓ǎ҂ł��������ԋZ�p��̖�S���l�̉����n
���ɂ����ԓx�ƌ�����̂ł͂Ȃ����낤���B����Ƃ��A���܂��ܕs�K�Ȃ��ƂɁA���쎩���ԇ� ���� �� ���A�����U����
�ԇ� �`���q�� ���A�O�H�ӂ����g���b�N�E�o�X�� �����p�� ���́A����̐l�������������̔r�C�K�X���x�̍�����
���f�B�[�[���G���W���̍ŏd�v�ۑ�Ƃ̔F�����F���̖��\�ȋZ�p�ҁE���Ƃł������Ƃ̂��Ƃł��낤���B����ɂ���
���A�ނ�̋L�q���e�́A�����ԋZ�p��u�N�Ӂv�̎��Z�p�I�Ȑi�W���̒�_�ϑ��̐��m�ȃf�[�^�̌����Ƃ�
��A���̍߂͌y�����̂ł͖����ƍl������B���̂��Ƃ��l����ƁA2011�N�`2013�N�̊e�N���N�Ӂi8�����j�̎��M��S
���������쎩���ԇ� ���� �� ���A�����U�����ԇ� �`���q�� ���A�O�H�ӂ����g���b�N�E�o�X�� �����p�� ���ɂ��A�[����
�Ȃ��ė~�����Ƃ���ł���B
������SCR�����DPF���̌㏈�����u�̌��������}��Z�p�J���̕K�v����i���Ă���̂́A���ѐM�T ���ƎO��
���G ����UD�g���b�N�X���̋Z�p�ҁE���Ƃ����ł���B����UD�g���b�N�X���̏��ѐM�T ���ƎO�G ���Ɍ�����
���m�ȋZ�p���M�����^�ʖڂ��u�N�Ӂv�̎��M�҂Ƃ��Ă̎p���́A�^�ɒl������̂ƍl������B����ɑ��A
���쎩���ԇ� ���� �� ���A�����U�����ԇ� �`���q�� ���A�O�H�ӂ����g���b�N�E�o�X�� �����p�� ���́A�ނ�̒S����
���u�N�Ӂv�ɂ́A�f�B�[�[���G���W���ɂ����镔�������ɂ͔r�C�K�X���x�̍��������K�v�Ƃ̖������ȍŏd�v�ۑ�
�ɂ��ĉ����G��Ă��炸�A���̉ۑ���������邽�߂̋Z�p�J���̓����ɑS�����y���Ă��Ȃ��̂ł���B���̂��Ƃ�
��A���쎩���ԁA�����U�����ԁA�O�H�ӂ����̋Z�p�ҁE���Ƃ́A�����ԋZ�p����u�N�Ӂv���������Z�p�����L��
����C�\�����������Ă��邱�Ƃ����炩���B���̂悤���Ƃ́A�u�N�Ӂv�̓ǎ҂ł��������ԋZ�p��̖�S���l�̉����n
���ɂ����ԓx�ƌ�����̂ł͂Ȃ����낤���B����Ƃ��A���܂��ܕs�K�Ȃ��ƂɁA���쎩���ԇ� ���� �� ���A�����U����
�ԇ� �`���q�� ���A�O�H�ӂ����g���b�N�E�o�X�� �����p�� ���́A����̐l�������������̔r�C�K�X���x�̍�����
���f�B�[�[���G���W���̍ŏd�v�ۑ�Ƃ̔F�����F���̖��\�ȋZ�p�ҁE���Ƃł������Ƃ̂��Ƃł��낤���B����ɂ���
���A�ނ�̋L�q���e�́A�����ԋZ�p��u�N�Ӂv�̎��Z�p�I�Ȑi�W���̒�_�ϑ��̐��m�ȃf�[�^�̌����Ƃ�
��A���̍߂͌y�����̂ł͖����ƍl������B���̂��Ƃ��l����ƁA2011�N�`2013�N�̊e�N���N�Ӂi8�����j�̎��M��S
���������쎩���ԇ� ���� �� ���A�����U�����ԇ� �`���q�� ���A�O�H�ӂ����g���b�N�E�o�X�� �����p�� ���ɂ��A�[����
�Ȃ��ė~�����Ƃ���ł���B
�@�Ȃ��A�f�B�[�[���G���W���̕��������̔r�C�K�X���x�������������̓I�ȊJ���Z�p���i�W���Ă��Ȃ����Ƃ́A
�ߔN�̎����ԋZ�p�����{�@��w��̍u����ł͑�^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W���̕��������ɂ�����r�C�K
�X���x������������L���ȋZ�p���J�����ꂽ�Ƃ̕┭�\�̍s��ꂽ�`�Ղ��������Ƃ���A�e�Ղɐ����ł��邱��
�ł���B����́A���{�̃g���b�N���[�J�ł̓f�B�[�[���G���W���̋Z�p�J���Ɏ��g�ސ^���Ȏp����\�͂Ɍ������Z�p
�ҁE���Ƃ��������߂Ă��邱�Ƃ����������m��Ȃ��B���̕ЗƂ��ẮA���쎩���Ԃ��_�����\�����R����P�@
�\�̗��C���x�~�V�X�e���ɏڏq�����悤�ɁA���ɃK�\�����G���W���Ŏ��p������Ă���u�z�E�r�C�ًx�~���̋C���x
�~�V�X�e���v���^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W���ɓK�p�����_������쎩���Ԃ�2014�N5���̎����ԋZ�p��t�G�u��
��Ŕ��\���Ă��邪�A���̋Z�p�ł͍\���I�Ȍ��ׂ̂��ߑ�^�g���b�N�̑��s�R����\�������P�ł��Ȃ��㕨�ł��Ƃ�
����M���m�邱�Ƃ��ł��邱�Ƃ��B���̂悤�ɁA���{�̃g���b�N���[�J����^�g���b�N�́u���s�R��̉��P�v��u��������
�̔r�C�K�X���x���������v�ɗL���ł�����̂́A�v���I�Ȍ��ׂ̂����u�z�E�r�C�ْ�~���̋C���x�~�V�X�e���v�̌�
����p�����������������X�Ɣ��\���Ă��邱�Ƃ́A��w�ɍ˂̃|���R�c���Z�p���̕M�҂ɂƂ��Ă��������ɂł���B��
�̂悤�ȏd������ׂ̂����u�z�E�r�C�ْ�~���̋C���x�~�V�X�e���v�̌����_���������\�ł��Ȃ����{�̃g���b�N���[
�J�ł���ɂ�������炸�A����̃g���b�N���[�J�̋Z�p�ҁE���Ƃ́A�S�����\�����킹�����̔@���A2006�N4���ɊJ��
�����M�҂̃z�[���y�[�W�Œ�Ă����f�B�[�[���G���W���̔R�����Ɣr�o�K�X���P�ɋɂ߂ėL�����C���x�~�G���W��
�i�������J2005-54771�j�̋Z�p����v�c�����ĖَE�E�������Ă���悤�ł���B
�@���͂Ƃ�����A���{�̌����@�ւ�g���b�N���[�J�̊w�ҁE���Ƃ��A�f�B�[�[���G���W���̔r�o�K�X�ƔR����P�ɗL
���ȂQ�^�[�{�������C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p���A����܂Œ��N�ɘj���ė��s�s�ɖ����E�َE��
�����Ă������Ƃ͎����ł���B���̌��ʁA�č������ɂ���^�g���b�N��NO���K�����{�s����������{���{�̑Ӗ��ɏ�
�q���Ă���悤�ɁA���{�ł͕č���NO���K���i��2010�N�K����NO�� �� 0.27 g/kWh�j�ɔ�ׂāA2016�N�̎��_�ł�NO��
�� 0.4 g/kWh�̊ɂ��m�n���K�������K���ł��Ȃ���NO���ɖʂő啝�ɗ���^�g���b�N���s�̂��ꑱ���Ă���ł�
��B�܂�A���݂̓��{�̃g���b�N���[�J��NO���ጸ�̋Z�p���x���́A�č��ɔ�ׂđ啝�ɗ���Ă�����̂Ɛ�������
��B���̂��Ƃ́A�ŋ߂̂S�N���i2010�`2014�N�j�ɂ�����u�����ԋZ�p�v���̔N�ӂ́u�f�B�[�[���G���W���v�q��S��
����UD�g���b�N�X���A�����U�����ԇ��A���쎩���ԇ��A�O�H�ӂ����g���b�N�E�o�X���̋Z�p�ҁE���Ƃ��g���b�N�p�f�B�[
�[���G���W���̔R�����Ɣr�o�K�X���P�ɂ��Ă̗L���ȋZ�p���L�ڂł��Ă��Ȃ����Ƃ�����A�e�Ղɗ����ł��邱��
�ł͂Ȃ����낤���B���̂��Ƃ���A�ŋ߂̃g���b�N���[�J�́A�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W���̔R�����Ɣr�o�K�X���P��
�Z�p�J�������S�Ɏ�l�܂�ł���ƍl������B�������A���̂悤�ȏł��A�s�v�c�Ȃ��ƂɁA���{�̌����@�ւ�g��
�b�N���[�J�̊w�ҁE���Ƃ́A���̂��m��Ȃ����A�f�B�[�[���G���W���̔r�o�K�X�ƔR����P�ɗL���ȂQ�^�[�{������
�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p����łɋ��ۂ��Ă���悤���B����܂ŁA���{�̑����̊w�ҁE����
�́uNO���ƔR��̊Ԃɂ̓g���[�h�I�t�i���w���j�̊W�����邽�߁A�f�B�[�[���G���W����NO���ƔR��Ƃ��ɉ�
�P���邱�Ƃ͓���v�ƁA�������Ő������Ă���B�������A�M�Ғ�Ă��C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z
�p�����p������Ηe�Ղɑ�^�g���b�N��NO���ƔR��Ƃ̓������P�������ł���̂ł���B
���ȂQ�^�[�{�������C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p���A����܂Œ��N�ɘj���ė��s�s�ɖ����E�َE��
�����Ă������Ƃ͎����ł���B���̌��ʁA�č������ɂ���^�g���b�N��NO���K�����{�s����������{���{�̑Ӗ��ɏ�
�q���Ă���悤�ɁA���{�ł͕č���NO���K���i��2010�N�K����NO�� �� 0.27 g/kWh�j�ɔ�ׂāA2016�N�̎��_�ł�NO��
�� 0.4 g/kWh�̊ɂ��m�n���K�������K���ł��Ȃ���NO���ɖʂő啝�ɗ���^�g���b�N���s�̂��ꑱ���Ă���ł�
��B�܂�A���݂̓��{�̃g���b�N���[�J��NO���ጸ�̋Z�p���x���́A�č��ɔ�ׂđ啝�ɗ���Ă�����̂Ɛ�������
��B���̂��Ƃ́A�ŋ߂̂S�N���i2010�`2014�N�j�ɂ�����u�����ԋZ�p�v���̔N�ӂ́u�f�B�[�[���G���W���v�q��S��
����UD�g���b�N�X���A�����U�����ԇ��A���쎩���ԇ��A�O�H�ӂ����g���b�N�E�o�X���̋Z�p�ҁE���Ƃ��g���b�N�p�f�B�[
�[���G���W���̔R�����Ɣr�o�K�X���P�ɂ��Ă̗L���ȋZ�p���L�ڂł��Ă��Ȃ����Ƃ�����A�e�Ղɗ����ł��邱��
�ł͂Ȃ����낤���B���̂��Ƃ���A�ŋ߂̃g���b�N���[�J�́A�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W���̔R�����Ɣr�o�K�X���P��
�Z�p�J�������S�Ɏ�l�܂�ł���ƍl������B�������A���̂悤�ȏł��A�s�v�c�Ȃ��ƂɁA���{�̌����@�ւ�g��
�b�N���[�J�̊w�ҁE���Ƃ́A���̂��m��Ȃ����A�f�B�[�[���G���W���̔r�o�K�X�ƔR����P�ɗL���ȂQ�^�[�{������
�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p����łɋ��ۂ��Ă���悤���B����܂ŁA���{�̑����̊w�ҁE����
�́uNO���ƔR��̊Ԃɂ̓g���[�h�I�t�i���w���j�̊W�����邽�߁A�f�B�[�[���G���W����NO���ƔR��Ƃ��ɉ�
�P���邱�Ƃ͓���v�ƁA�������Ő������Ă���B�������A�M�Ғ�Ă��C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z
�p�����p������Ηe�Ղɑ�^�g���b�N��NO���ƔR��Ƃ̓������P�������ł���̂ł���B
�@�������Ȃ���A���{�̌����@�ւ�g���b�N���[�J�̊w�ҁE���Ƃ��f�B�[�[���G���W���̔r�o�K�X�ƔR����P�ɗL����
�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p���ӌŒn�ɖ����E�َE���������Ă���ƁA���ꂩ�牽�N���o��
����A���{�̑�^�g���b�N�ɂ����Ă��A�č��̑�^�g���b�N�Ɠ����̌�����NO���K��������Ď��{����鎞�オ����
���邩�ǂ����ɂ��āA�N�����s���Ɏv���Ƃ���ł���B�����āA�啔���̍����́A�o���邾�������ɁA�č��̑�^�g��
�b�N�Ɠ����̌�����NO���K�������{�ł����{����鎞�オ�������ė~�������Ɗ���Ă��锤�ł���B�������A�C���x�~�G
���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p���E�َE������{���w�ҁE���ƁE�Z�p�҂̌���̍s�������Ă���ƁA
�č��̑�^�g���b�N�Ɠ����̌�����NO���K�������{�̑�^�g���b�N�Ɏ��{����鎞���̓�����\�����邱�Ƃ́A���
���Ƃ��B�����Ƃ��A���{�ɂ����錻���_�ł̑�^�g���b�N��NO���K���������č��ɔ�ׂđ啝�ɒx�����Ă��܂��Ă��邱
�Ƃɂ���Č��N��̔�Q����̂́A�命���̓��{�����ł��邱�Ƃ́A�ԈႢ�Ȃ����낤�B���̍������Ă����C
�����ɂ�錒�N��̔�Q�E���f�𑁊��ɑŔj����ӔC�̈�[��S���Ă����g���b�N���[�J�̊w�ҁE�����l�B�ɂ́A��
�̂��Ƃɂ��Ă̏\���Ȏ��o������̂ł��낤���B���̖{�S���A����Ƃ������Ă݂����Ƃ���ł���B
�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p���ӌŒn�ɖ����E�َE���������Ă���ƁA���ꂩ�牽�N���o��
����A���{�̑�^�g���b�N�ɂ����Ă��A�č��̑�^�g���b�N�Ɠ����̌�����NO���K��������Ď��{����鎞�オ����
���邩�ǂ����ɂ��āA�N�����s���Ɏv���Ƃ���ł���B�����āA�啔���̍����́A�o���邾�������ɁA�č��̑�^�g��
�b�N�Ɠ����̌�����NO���K�������{�ł����{����鎞�オ�������ė~�������Ɗ���Ă��锤�ł���B�������A�C���x�~�G
���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p���E�َE������{���w�ҁE���ƁE�Z�p�҂̌���̍s�������Ă���ƁA
�č��̑�^�g���b�N�Ɠ����̌�����NO���K�������{�̑�^�g���b�N�Ɏ��{����鎞���̓�����\�����邱�Ƃ́A���
���Ƃ��B�����Ƃ��A���{�ɂ����錻���_�ł̑�^�g���b�N��NO���K���������č��ɔ�ׂđ啝�ɒx�����Ă��܂��Ă��邱
�Ƃɂ���Č��N��̔�Q����̂́A�命���̓��{�����ł��邱�Ƃ́A�ԈႢ�Ȃ����낤�B���̍������Ă����C
�����ɂ�錒�N��̔�Q�E���f�𑁊��ɑŔj����ӔC�̈�[��S���Ă����g���b�N���[�J�̊w�ҁE�����l�B�ɂ́A��
�̂��Ƃɂ��Ă̏\���Ȏ��o������̂ł��낤���B���̖{�S���A����Ƃ������Ă݂����Ƃ���ł���B
�@�Ƃ���ŁA�����ԋZ�p��́u�ϗ��K��v�ł́A��M�ɂ��āu�������ʂ�ʂ��Љ�ɐ������������܂��B�v��
���X�Ɛ錾���Ă���̂ł���B����ɂ�������炸�A�O�q�̂悤�ɁA�ŋ߂̂S�N���i2010�`2014�N�j�ł́A�����ԋZ�p
��́A�u�����ԋZ�p�v���̔N�ӂɂ̓f�B�[�[���G���W���̔R����P����єr�o�K�X�ጸ�ł���Z�p���s���܂��͖��J
���̏�Ԃł��邱�Ƃ��u�Ӑ}�I�ɉB���H�v�A�Ⴕ���͉B�����u�L�ڂ�����E�폜�v���������ԋZ�p����S���l�̉����
�z�z���đ����Ă����悤�Ɍ�����̂ł���B���̂悤�ȏ�����ƁA��̑S�́A�u�����ԋZ�p�v���̕ҏW�ψ���̐l�B
�ɂ́A�E���ӔC���ӎ����čs�����Ă���Ƃ͂ƂĂ��v���Ȃ��̂ł���B�����āA�����ԋZ�p��ɂ́u�ϗ��K��v�Ȃ����
�����݂��Ă��邪�A����́A�P�Ȃ���蕨�ł���A���̈Ӗ��������悤�Ɏv����̂��B�����āA�����ԋZ�p��́A�����
�łƓ��l�ɁA�f�B�[�[���G���W���̔R����P����єr�o�K�X�ጸ�ɗL���ȋZ�p�������L�ڂ��Ă��Ȃ������ԋZ�p�v��
���A���ꂩ������H��ʊ�łS���l�̉���ɔz�z����S�Z�̉\�����ɂ߂č����悤�Ɏv����̂ł���B���ɂ��̂�
���Ȃ��Ƃ����ۂɍs����悤�ł���A�����ԋZ�p��́A���N�A�^�ʖڂɉ������߂Ă����������S�ɋ�M����
���邱�ƂɂȂ�ƍl�����邪�A�@���Ȃ��̂ł��낤���B
���X�Ɛ錾���Ă���̂ł���B����ɂ�������炸�A�O�q�̂悤�ɁA�ŋ߂̂S�N���i2010�`2014�N�j�ł́A�����ԋZ�p
��́A�u�����ԋZ�p�v���̔N�ӂɂ̓f�B�[�[���G���W���̔R����P����єr�o�K�X�ጸ�ł���Z�p���s���܂��͖��J
���̏�Ԃł��邱�Ƃ��u�Ӑ}�I�ɉB���H�v�A�Ⴕ���͉B�����u�L�ڂ�����E�폜�v���������ԋZ�p����S���l�̉����
�z�z���đ����Ă����悤�Ɍ�����̂ł���B���̂悤�ȏ�����ƁA��̑S�́A�u�����ԋZ�p�v���̕ҏW�ψ���̐l�B
�ɂ́A�E���ӔC���ӎ����čs�����Ă���Ƃ͂ƂĂ��v���Ȃ��̂ł���B�����āA�����ԋZ�p��ɂ́u�ϗ��K��v�Ȃ����
�����݂��Ă��邪�A����́A�P�Ȃ���蕨�ł���A���̈Ӗ��������悤�Ɏv����̂��B�����āA�����ԋZ�p��́A�����
�łƓ��l�ɁA�f�B�[�[���G���W���̔R����P����єr�o�K�X�ጸ�ɗL���ȋZ�p�������L�ڂ��Ă��Ȃ������ԋZ�p�v��
���A���ꂩ������H��ʊ�łS���l�̉���ɔz�z����S�Z�̉\�����ɂ߂č����悤�Ɏv����̂ł���B���ɂ��̂�
���Ȃ��Ƃ����ۂɍs����悤�ł���A�����ԋZ�p��́A���N�A�^�ʖڂɉ������߂Ă����������S�ɋ�M����
���邱�ƂɂȂ�ƍl�����邪�A�@���Ȃ��̂ł��낤���B
�W�|�T�D����c��w�E����������������^�g���b�N�ɂ�����i�قɉ������ׂ��ۑ�
�@���{�����ԍH�Ɖ�̃z�[���y�[�W��JAMAGAZINE�@�i2012�N3�����j�Ɍf�ڂ́u�N���[���E�f�B�[�[���G���W���Z�p��
�����v�Ƒ肷��y�[�W�ɂ����āA�ȉ��̕\�P�R�Ɏ������悤�ɁA����c��w�̑��������́A�u���p�ԃN���[�����Z�p�̍�
�Ɂu���p�ԁi����^�g���b�N���j�ɂ������i�قɉ������ׂ��ۑ肪����Ă���B
�����v�Ƒ肷��y�[�W�ɂ����āA�ȉ��̕\�P�R�Ɏ������悤�ɁA����c��w�̑��������́A�u���p�ԃN���[�����Z�p�̍�
�Ɂu���p�ԁi����^�g���b�N���j�ɂ������i�قɉ������ׂ��ۑ肪����Ă���B
�� �o�T�̃z�[���y�[�W �F ���{�����ԍH�Ɖ� JAMAGAZINE�@2012�N3����
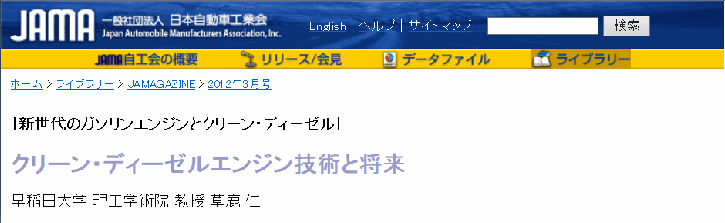 |
�� ���{�����ԍH�Ɖ� JAMAGAZINE�@2012�N3�����ɋL�ڂ���Ă���N���[���E�f�B�[�[���G���W���Z�p
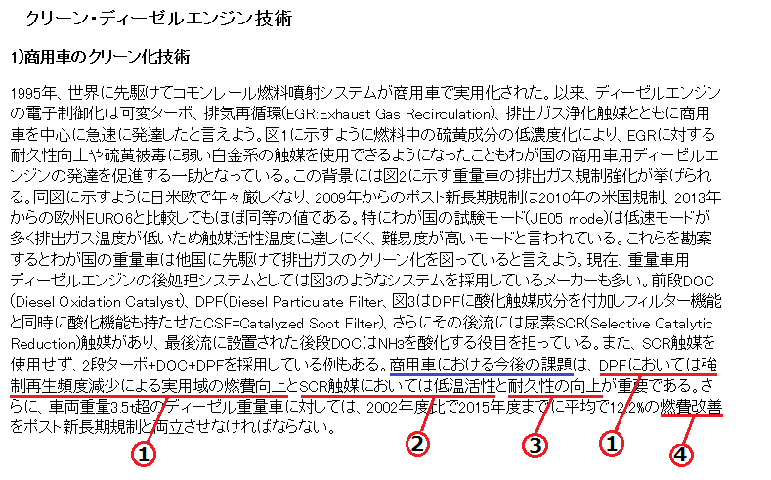 |
�@���̓��{�����ԍH�Ɖ�̃z�[���y�[�W��JAMAGAZINE�@�i2012�N3�����j�Ɍf�ڂ́u�N���[���E�f�B�[�[���G���W���Z
�p�Ə����v�Ƒ肷��y�[�W�ł́A����c��w�̑��������́A2012�N�̎��_�ł̑�^�g���b�N������i�قɉ��P���ׂ�
�d�v�ۑ�Ƃ��āA�ȉ��̂S���ڂƔF������Ă����悤���B
�p�Ə����v�Ƒ肷��y�[�W�ł́A����c��w�̑��������́A2012�N�̎��_�ł̑�^�g���b�N������i�قɉ��P���ׂ�
�d�v�ۑ�Ƃ��āA�ȉ��̂S���ڂƔF������Ă����悤���B
�@ �|�X�g���ˎ���r�C�Ǔ��R�����ˎ��̃t�B���^�Đ��V�X�e�����̗p����DPF���u�ɂ����鋭���Đ���
�p�x�����ɂ��R����̖h�~
�A SCR�G�}�ɂ�����ቷ�����̌���
�B SCR�G�}�̑ϋv���̌���iSCR�G�}��HC��ł̍Đ����u�H�j
�C �d�ʎԃ��[�h�R��̉��P
�@���̂悤�ɁA����c��w�̑��������́AJAMAGAZINE�@�i2012�N3�����j�Ɍf�ڂ́u�N���[���E�f�B�[�[���G���W���Z�p
�Ə����v�Ƒ肷��y�[�W�ł́A��^�g���b�N�̉��P���ׂ��d�v�ۑ�Ƃ��āA�ȏ�̇@�`�C�̂S���ڂ̑��}�ɉ������ׂ�
���E���肪����Ă���B���̑���c��w�̑���������������ꂽ�@�`�C�̂S���ڂ̑��}�ɉ������ׂ���^�g
���b�N�̉ۑ�́A�|���R�c���Z�p�̕M�҂����������ӂ���Ƃ���ł���B�����āA���̓��{�����ԍH�Ɖ�̃z�[���y�[�W
��JAMAGAZINE�i2012�N3�����j�Ɍf�ڂ́u�N���[���E�f�B�[�[���G���W���Z�p�Ə����v�ɂ����āA������������^�g���b
�N�̋i�قɉ��P���ׂ��S���ڂ̏d�v�ۑ�ƂƂ��ɋ��ɁA�����̉ۑ�̉����Ɏ�����Z�p�I�Ȏ������L�ڂ���Ă���
�A���̃z�[���y�[�W���{�������g���b�N���[�J�̃G���W���Z�p�҂ɂƂ��ẮA�ނ�̓���̌����J���̎菕���ɂȂ�
���̂ł���B�����āA���̏ꍇ�A���R�ɂ��A���̃z�[���y�[�W���{�������g���b�N���[�J�̃G���W���Z�p�҂́A�傢�Ɋ�
�ӂ��锤�ł���B
�Ə����v�Ƒ肷��y�[�W�ł́A��^�g���b�N�̉��P���ׂ��d�v�ۑ�Ƃ��āA�ȏ�̇@�`�C�̂S���ڂ̑��}�ɉ������ׂ�
���E���肪����Ă���B���̑���c��w�̑���������������ꂽ�@�`�C�̂S���ڂ̑��}�ɉ������ׂ���^�g
���b�N�̉ۑ�́A�|���R�c���Z�p�̕M�҂����������ӂ���Ƃ���ł���B�����āA���̓��{�����ԍH�Ɖ�̃z�[���y�[�W
��JAMAGAZINE�i2012�N3�����j�Ɍf�ڂ́u�N���[���E�f�B�[�[���G���W���Z�p�Ə����v�ɂ����āA������������^�g���b
�N�̋i�قɉ��P���ׂ��S���ڂ̏d�v�ۑ�ƂƂ��ɋ��ɁA�����̉ۑ�̉����Ɏ�����Z�p�I�Ȏ������L�ڂ���Ă���
�A���̃z�[���y�[�W���{�������g���b�N���[�J�̃G���W���Z�p�҂ɂƂ��ẮA�ނ�̓���̌����J���̎菕���ɂȂ�
���̂ł���B�����āA���̏ꍇ�A���R�ɂ��A���̃z�[���y�[�W���{�������g���b�N���[�J�̃G���W���Z�p�҂́A�傢�Ɋ�
�ӂ��锤�ł���B
�@�������Ȃ���A���̓��{�����ԍH�Ɖ�z�[���y�[�W�́u�N���[���E�f�B�[�[���G���W���Z�p�Ə����v�Ƃ̓��X����薼
���f�����y�[�W�ɂ́A���{���\����G���W����������Ƃ����w�҂̑��������́A��^�g���b�N�̋i�قɉ��P��
�ׂ��S���ڂ̏d�v�ۑ肪����Ă��邾���ł���A�����ۑ����������Z�p�I�Ȏ���������q�ׂ��Ă��Ȃ�
�̂ł���B���̂��߁A�u�N���[���E�f�B�[�[���G���W���Z�p�Ə����v�̃y�[�W���J���A���������҂��ĉ{�������g���b�N���[
�J�̑����̃G���W���Z�p�҂́A�K���⎸�]�������̂Ɛ��������B���̂悤�ɁA�u�N���[���E�f�B�[�[���G���W���Z�p�Ə�
���v�Ƃ̗��h�ȑ薼�̃y�[�W�ɑ������������}�ɑP���ׂ���^�g���b�N�̂S���ڂ̏d�v�ۑ����������Z�p�������q
�ׂ��Ă��Ȃ��B���̂��Ƃ��画�f����ƁA���������́A2012�N3���̎��_�ɂ����ẮA��^�g���b�N�̂S���ڂ̏d�v��
�����������Z�p�I�Ȃ̒�Ă⌤���J���̕��j�̈Ă�����������Ă��Ȃ������Ɣ��f���Ă��傫�ȊԈႢ��������
�̂Ɛ��������B����ł́A���̌�A�Q�N���x���o�߂���2014�N9�����݂ł́A���������́A��^�g���b�N�̇@�`�C�̂S
���ڂ̏d�v�ۑ����������Z�p�����o���ꂽ�̂ł��낤���B�|���R�c���Z�p���̕M�҂́A��w�ɍ˂̏�ɋZ�p���
�̎��W�\�͂���邱�Ƃ�����A���������́A��^�g���b�N�̇@�`�C�̂S���ڂ̏d�v�ۑ������������p�I�ȋZ�p����
�o���ꂽ�Ƃ̏��Ă��Ȃ��B��킭�A�{�z�[���y�[�W���{�����ꂽ���̒��ŁA������������^�g���b�N�̇@�`�C
�̂S���ڂ̏d�v�ۑ����������Z�p���Ă���Ă���Ƃ̏���������Ă���ꍇ�́A���̏���{�y�[�W�̖���
�̃��[���A�h���X�ɂ��A������������K���ł���B
���f�����y�[�W�ɂ́A���{���\����G���W����������Ƃ����w�҂̑��������́A��^�g���b�N�̋i�قɉ��P��
�ׂ��S���ڂ̏d�v�ۑ肪����Ă��邾���ł���A�����ۑ����������Z�p�I�Ȏ���������q�ׂ��Ă��Ȃ�
�̂ł���B���̂��߁A�u�N���[���E�f�B�[�[���G���W���Z�p�Ə����v�̃y�[�W���J���A���������҂��ĉ{�������g���b�N���[
�J�̑����̃G���W���Z�p�҂́A�K���⎸�]�������̂Ɛ��������B���̂悤�ɁA�u�N���[���E�f�B�[�[���G���W���Z�p�Ə�
���v�Ƃ̗��h�ȑ薼�̃y�[�W�ɑ������������}�ɑP���ׂ���^�g���b�N�̂S���ڂ̏d�v�ۑ����������Z�p�������q
�ׂ��Ă��Ȃ��B���̂��Ƃ��画�f����ƁA���������́A2012�N3���̎��_�ɂ����ẮA��^�g���b�N�̂S���ڂ̏d�v��
�����������Z�p�I�Ȃ̒�Ă⌤���J���̕��j�̈Ă�����������Ă��Ȃ������Ɣ��f���Ă��傫�ȊԈႢ��������
�̂Ɛ��������B����ł́A���̌�A�Q�N���x���o�߂���2014�N9�����݂ł́A���������́A��^�g���b�N�̇@�`�C�̂S
���ڂ̏d�v�ۑ����������Z�p�����o���ꂽ�̂ł��낤���B�|���R�c���Z�p���̕M�҂́A��w�ɍ˂̏�ɋZ�p���
�̎��W�\�͂���邱�Ƃ�����A���������́A��^�g���b�N�̇@�`�C�̂S���ڂ̏d�v�ۑ������������p�I�ȋZ�p����
�o���ꂽ�Ƃ̏��Ă��Ȃ��B��킭�A�{�z�[���y�[�W���{�����ꂽ���̒��ŁA������������^�g���b�N�̇@�`�C
�̂S���ڂ̏d�v�ۑ����������Z�p���Ă���Ă���Ƃ̏���������Ă���ꍇ�́A���̏���{�y�[�W�̖���
�̃��[���A�h���X�ɂ��A������������K���ł���B
��
�@���̂悤�ɁA2012�N3���ɔ��s�̓��{�����ԍH�Ɖ�z�[���y�[�W�́u�N���[���E�f�B�[�[���G���W���Z�p�Ə�
���v�̋L���ł́A���{���\����G���W����������Ƃ���鑁��c��w�E���������́u�@ DPF���u�̋�����
���̕p�x�����v�A�u�A SCR�G�}�̒ቷ�����v�A�u�BSCR�G�}��HC��ł̉����v�A�u�C �d�ʎԃ��[�h�R��̉�
�P�v�v�̂S���ڂ̑�^�g���b�N�̌����J�����ׂ��ۑ肾������A�����̉ۑ������������̓I�ȋZ�p�I��
�����E�J�����Ă��Ȃ��̂ł���B���������āA�������{�����ԍH�Ɖ�z�[���y�[�W�́u�N���[���E�f�B�[�[��
�G���W���Z�p�Ə����v�̋L���̓��e�ł́A��^�g���b�N�́u��NO�����v����сu��R��v�̎����ɂ́A���ړI��
�𗧂Z�p��w�lj������y����Ă��Ȃ��Ƃ����Ă��ߌ��ł͂Ȃ��悤���B
���v�̋L���ł́A���{���\����G���W����������Ƃ���鑁��c��w�E���������́u�@ DPF���u�̋�����
���̕p�x�����v�A�u�A SCR�G�}�̒ቷ�����v�A�u�BSCR�G�}��HC��ł̉����v�A�u�C �d�ʎԃ��[�h�R��̉�
�P�v�v�̂S���ڂ̑�^�g���b�N�̌����J�����ׂ��ۑ肾������A�����̉ۑ������������̓I�ȋZ�p�I��
�����E�J�����Ă��Ȃ��̂ł���B���������āA�������{�����ԍH�Ɖ�z�[���y�[�W�́u�N���[���E�f�B�[�[��
�G���W���Z�p�Ə����v�̋L���̓��e�ł́A��^�g���b�N�́u��NO�����v����сu��R��v�̎����ɂ́A���ړI��
�𗧂Z�p��w�lj������y����Ă��Ȃ��Ƃ����Ă��ߌ��ł͂Ȃ��悤���B
�@�܂��A��^�g���b�N��SCR�����DPF���̌㏈�����u�̌���������\�ɂ��邽�߂ɃG���W�����������ɂ�����
�r�C�K�X���x�̍��������\�ɂ���Z�p�J���̕K�v���ɂ��ẮA�ȉ��̂悤�ɁA�g���b�N���[�J�̋Z�p�ҁE���ƍ�
�߂̎����ԋZ�p���ŋL�ڂ���Ă�����e�Ɠ����ł���B
�r�C�K�X���x�̍��������\�ɂ���Z�p�J���̕K�v���ɂ��ẮA�ȉ��̂悤�ɁA�g���b�N���[�J�̋Z�p�ҁE���ƍ�
�߂̎����ԋZ�p���ŋL�ڂ���Ă�����e�Ɠ����ł���B
�i�P�j�@UD�g���b�N�X�� ���ѐM�T ��
�@�@�����ԋZ�p��2010�N8�����iVol.64�AN0.8�A�j�̓��W�F�N�ӂ��u�f�B�[�[���G���W���v�̍��ɂ́A�u�r�C�K�X���x�̍���
���v��}��Z�p�J���̕K�v�����L�ڂ���Ă���B�i�O�q�̂W�|�S�[(b)�̍����Q�ƕ��j
���v��}��Z�p�J���̕K�v�����L�ڂ���Ă���B�i�O�q�̂W�|�S�[(b)�̍����Q�ƕ��j
�i�Q�j�@UD�g���b�N�X�� �O�G ��
�@�@�����ԋZ�p��2014�N8�����iVol.68�AN0.8�A2014�j�̓��W�F�N�ӂ��u�f�B�[�[���G���W���v�̍��ɂ́A�u�r�C�K�X���x��
�������v��}��Z�p�J���̕K�v�����L�ڂ���Ă���B�i�O�q�̂W�|�S�[(��)�̍����Q�ƕ��j
�������v��}��Z�p�J���̕K�v�����L�ڂ���Ă���B�i�O�q�̂W�|�S�[(��)�̍����Q�ƕ��j
�@�ȏ�̂悤�ɁA2010�N�`2014�N�ɂ����āAUD�g���b�N�X�� ���ѐM�T ���� �O�G ���́A��^�g���b�N�ɂ������u�@
DPF���u�̋����Đ��̕p�x�����v�A�u�A SCR�G�}�̒ቷ�����v�A�u�BSCR�G�}��HC��ł̉����v�̉ۑ���������邽
�߂��r�C�K�X���x�̍�������}��Z�p�J���̕K�v���ƁA�X�Ȃ�u�C �d�ʎԃ��[�h�R��̉��P�v�̕K�v�������������
����悤���BUD�g���b�N�X�� ���ѐM�T ���� �O�G ���̗����́A����c��w�E���������Ɠ��l�ɁA�u�@ DPF���u��
�����Đ��̕p�x�����v�A�u�A SCR�G�}�̒ቷ�����v�A�u�BSCR�G�}��HC��ł̉����v�A�u�C �d�ʎԃ��[�h�R��̉�
�P�v�v�̂S���ڂ̑�^�g���b�N�̌����J�����ׂ��ۑ肾������A�����̉ۑ������������̓I�ȋZ�p�I��������
���E�J������Ă��Ȃ��̂ł���B�܂�A�O�G ���̗����́A����c��w�E���������Ɠ��l�ɁA��^�g���b�N�́u��
NO�����v����сu��R��v�̎���������Ƃ̂ɂ́A���ړI�ɖ𗧂Z�p���������E��������Ă��Ȃ��̂ł�
��B���̂悤�ɁA�ŋ߁i��2010�N�`2014�N�j�ɂ����ẮA���{���\����G���W���W�̒����ȑ���c��w�E������
���A����уg���b�N���[�J�ł���UD�g���b�N�X���̏��ѐM�T ���� �O�G ���̐��Ƃ́A���{�����ԍH�Ɖ�̃z�[��
�y�[�W�������ԋZ�p���̔N�ӂł́A��^�g���b�N�́u��NO�����v����сu��R��v���������邽�߂́u�@ DPF���u��
�����Đ��̕p�x�����v�A�u�A SCR�G�}�̒ቷ�����v�A�u�BSCR�G�}��HC��ł̉����v�A����сu�C �d�ʎԃ��[�h�R��
�̉��P�v���ۑ肾����������A�ۑ�������ł����̓I�ȋZ�p�������L�ڂ���Ă��Ȃ��̂ł���B
DPF���u�̋����Đ��̕p�x�����v�A�u�A SCR�G�}�̒ቷ�����v�A�u�BSCR�G�}��HC��ł̉����v�̉ۑ���������邽
�߂��r�C�K�X���x�̍�������}��Z�p�J���̕K�v���ƁA�X�Ȃ�u�C �d�ʎԃ��[�h�R��̉��P�v�̕K�v�������������
����悤���BUD�g���b�N�X�� ���ѐM�T ���� �O�G ���̗����́A����c��w�E���������Ɠ��l�ɁA�u�@ DPF���u��
�����Đ��̕p�x�����v�A�u�A SCR�G�}�̒ቷ�����v�A�u�BSCR�G�}��HC��ł̉����v�A�u�C �d�ʎԃ��[�h�R��̉�
�P�v�v�̂S���ڂ̑�^�g���b�N�̌����J�����ׂ��ۑ肾������A�����̉ۑ������������̓I�ȋZ�p�I��������
���E�J������Ă��Ȃ��̂ł���B�܂�A�O�G ���̗����́A����c��w�E���������Ɠ��l�ɁA��^�g���b�N�́u��
NO�����v����сu��R��v�̎���������Ƃ̂ɂ́A���ړI�ɖ𗧂Z�p���������E��������Ă��Ȃ��̂ł�
��B���̂悤�ɁA�ŋ߁i��2010�N�`2014�N�j�ɂ����ẮA���{���\����G���W���W�̒����ȑ���c��w�E������
���A����уg���b�N���[�J�ł���UD�g���b�N�X���̏��ѐM�T ���� �O�G ���̐��Ƃ́A���{�����ԍH�Ɖ�̃z�[��
�y�[�W�������ԋZ�p���̔N�ӂł́A��^�g���b�N�́u��NO�����v����сu��R��v���������邽�߂́u�@ DPF���u��
�����Đ��̕p�x�����v�A�u�A SCR�G�}�̒ቷ�����v�A�u�BSCR�G�}��HC��ł̉����v�A����сu�C �d�ʎԃ��[�h�R��
�̉��P�v���ۑ肾����������A�ۑ�������ł����̓I�ȋZ�p�������L�ڂ���Ă��Ȃ��̂ł���B
�@����ɑ��A�|���R�c���Z�p���̕M�҂�2004�N5��25���ɏo�肵���C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�i�o�T�F
http://www6.ipdl.inpit.go.jp/Tokujitu/tjsogodbk.ipdl�j�������̖����ɂ́A��^�g���b�N�ɂ����đ��}�ɉ������ׂ���
��Ƃ����u�@ DPF���u�̋����Đ��̕p�x�����v�A�u�A SCR�G�}�̒ቷ�����v�A����сu�C �d�ʎԃ��[�h�R��̉��P�v��
�����A�����̉ۑ���������邽�߂̋Z�p�Ƃ��āu�Q�^�[�{�����̋C���x�~�V�X�e���v�̏ڍׂƁuNO���팸�v�Ɓu�R���
�P�v�̋@�\�E���ʂ��L�ڂ��Ă���̂ł���B�����āA�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p�́A2005�N3
���ɓ������J����Ă����ɁA2006�N4��7�����J�̕M�҂̃C���^�[�l�b�g�̃z�[���y�[�W�ɂ����ċZ�p���e���ڍׂ�
�������Ă�����ł���B���������āA�ŋ߁i��2010�N�`2014�N�j�ɂ����ẮA���{���\����G���W���W�̒����ȑ�
��c��w�E���������A����уg���b�N���[�J�ł���UD�g���b�N�X���̏��ѐM�T ���� �O�G ���̐��Ƃ����{������
�H�Ɖ�̃z�[���y�[�W��AMAGAZINE�i2012�N3�����j�������ԋZ�p���̔N�Ӂi��2010�N�y��2014�N�̂W�����j�̒���
�q�ׂ��Ă�����^�g���b�N�́u��NO�����v����сu��R��v���������邽�߂́u�@ DPF���u�̋����Đ��̕p�x��
���v�A�u�A SCR�G�}�̒ቷ�����v�A�u�BSCR�G�}��HC��ł̉����v�A����сu�C �d�ʎԃ��[�h�R��̉��P�v���ۑ�́A
�|���R�c���Z�p���̕M�҂�2004�N5��25���ɏo�肵���C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p�̖���
���ɏڂ����L�ڂ��Ă���̂ł���B
http://www6.ipdl.inpit.go.jp/Tokujitu/tjsogodbk.ipdl�j�������̖����ɂ́A��^�g���b�N�ɂ����đ��}�ɉ������ׂ���
��Ƃ����u�@ DPF���u�̋����Đ��̕p�x�����v�A�u�A SCR�G�}�̒ቷ�����v�A����сu�C �d�ʎԃ��[�h�R��̉��P�v��
�����A�����̉ۑ���������邽�߂̋Z�p�Ƃ��āu�Q�^�[�{�����̋C���x�~�V�X�e���v�̏ڍׂƁuNO���팸�v�Ɓu�R���
�P�v�̋@�\�E���ʂ��L�ڂ��Ă���̂ł���B�����āA�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p�́A2005�N3
���ɓ������J����Ă����ɁA2006�N4��7�����J�̕M�҂̃C���^�[�l�b�g�̃z�[���y�[�W�ɂ����ċZ�p���e���ڍׂ�
�������Ă�����ł���B���������āA�ŋ߁i��2010�N�`2014�N�j�ɂ����ẮA���{���\����G���W���W�̒����ȑ�
��c��w�E���������A����уg���b�N���[�J�ł���UD�g���b�N�X���̏��ѐM�T ���� �O�G ���̐��Ƃ����{������
�H�Ɖ�̃z�[���y�[�W��AMAGAZINE�i2012�N3�����j�������ԋZ�p���̔N�Ӂi��2010�N�y��2014�N�̂W�����j�̒���
�q�ׂ��Ă�����^�g���b�N�́u��NO�����v����сu��R��v���������邽�߂́u�@ DPF���u�̋����Đ��̕p�x��
���v�A�u�A SCR�G�}�̒ቷ�����v�A�u�BSCR�G�}��HC��ł̉����v�A����сu�C �d�ʎԃ��[�h�R��̉��P�v���ۑ�́A
�|���R�c���Z�p���̕M�҂�2004�N5��25���ɏo�肵���C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p�̖���
���ɏڂ����L�ڂ��Ă���̂ł���B
�@�܂�A���{�����ԍH�Ɖ�̃z�[���y�[�W��AMAGAZINE�i2012�N3�����j�������ԋZ�p���̔N�Ӂi��2010
�N�y��2014�N�̂W�����j�̂悤�Ȑ��Ԃɉe���͂�M�����̍����Ƃ�����M�}�̂ɂ����āA����c��w�E
���������AUD�g���b�N�X���̏��ѐM�T ���� �O�G �����������A���ѐM�T ���A������O�G ���̂R��
����^�g���b�N�J���̍ŐV�̋Z�p���ƋL�ڂ��ꂽ�@�`�C�̉ۑ�́A�|���R�c���Z�p���̕M�҂�10�N���ȑO
��2004�N5��25���ɓ������ɏo�肵���C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����i�o�T�Fhttp://www6.
ipdl.inpit.go.jp/Tokujitu/tjsogodbk.ipdl�j�̖����ɖ��L���Ă����̂ł���B�܂��A���{�����ԍH�Ɖ��
AMAGAZINE�i2012�N3�����j�������ԋZ�p���i��2010�N�y��2014�N�̂W�����j�̔N�ӂɂ����āA���������́A��^�g��
�b�N���@�`�C���Z�p�J���̉ۑ���q�ׂ��Ă��邾���ł���A�����̉ۑ�������ł����̓I�ȋZ�p�ɂ��ẮA
���̏����E�J������Ă��Ȃ��B�������A�|���R�c���Z�p���̕M�҂�10�N�ȏ���̂ɏo�肵���C���x�~�G���W��
�i�������J2005-54771�j�̓����Z�p���^�g���b�N�ɍ̗p�����ꍇ�ɂ́A�@�`�C���Z�p�I�ۑ肪�S�ĉ����ł��邽
�߁A�e�Ղɑ�^�g���b�N�́u��NO�����v����сu��R��v�������ł���̂ł���B���̏ɂ��āA�ȉ��̕\�P�S�ɉ�
���Ղ��܂Ƃ߂��̂ŁA�䗗�������������B
�N�y��2014�N�̂W�����j�̂悤�Ȑ��Ԃɉe���͂�M�����̍����Ƃ�����M�}�̂ɂ����āA����c��w�E
���������AUD�g���b�N�X���̏��ѐM�T ���� �O�G �����������A���ѐM�T ���A������O�G ���̂R��
����^�g���b�N�J���̍ŐV�̋Z�p���ƋL�ڂ��ꂽ�@�`�C�̉ۑ�́A�|���R�c���Z�p���̕M�҂�10�N���ȑO
��2004�N5��25���ɓ������ɏo�肵���C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����i�o�T�Fhttp://www6.
ipdl.inpit.go.jp/Tokujitu/tjsogodbk.ipdl�j�̖����ɖ��L���Ă����̂ł���B�܂��A���{�����ԍH�Ɖ��
AMAGAZINE�i2012�N3�����j�������ԋZ�p���i��2010�N�y��2014�N�̂W�����j�̔N�ӂɂ����āA���������́A��^�g��
�b�N���@�`�C���Z�p�J���̉ۑ���q�ׂ��Ă��邾���ł���A�����̉ۑ�������ł����̓I�ȋZ�p�ɂ��ẮA
���̏����E�J������Ă��Ȃ��B�������A�|���R�c���Z�p���̕M�҂�10�N�ȏ���̂ɏo�肵���C���x�~�G���W��
�i�������J2005-54771�j�̓����Z�p���^�g���b�N�ɍ̗p�����ꍇ�ɂ́A�@�`�C���Z�p�I�ۑ肪�S�ĉ����ł��邽
�߁A�e�Ղɑ�^�g���b�N�́u��NO�����v����сu��R��v�������ł���̂ł���B���̏ɂ��āA�ȉ��̕\�P�S�ɉ�
���Ղ��܂Ƃ߂��̂ŁA�䗗�������������B
| ��2010�`2014�N�ɗ��ꂽ |
|
|
|
| �@ | |
��^�g���b�N�̎����s���ɑ��p�����
�G���W�����������ɂ�����
�r�C�K�X���x��������
|
�E�ۑ�����̓����Z�p
�E�W�����i�Q�l�j
�{�y�[�W�̑��̍��i�Ⴆ�A4�����Q�Ɓj
|
| �A | |
||
| �B | |
||
| �C | |
��^�g���b�N�̎����s���ɑ��p�����
�G���W�����������ɂ�����
�R��̌���
|
�E�ۑ�����̓����Z�p
�E�W�����i�Q�l�j
|
�@���Ă��āA�A�C���x�~�G���W���ɂ���^�g���b�N�̒�R������{�͑�^�g���b�N�̐V���Ȓ�R��E��r�o�K�X�
�𑁊��ɐݒ肹��I������č������ɂ���^�g���b�N��NO���K�����{�s����������{���{�̑Ӗ��ɏڏq���Ă���悤
�ɁA����͕M�҂̗\���ɉ߂��Ȃ����Ƃł��邪�A�����̉��ꂩ�̎����ɂ����āA�킪���̑�^�g���b�N�́A�u2015�N�x
�d�ʎԔR������{10�����x�̔R�����v�Ɓu�m�n����0.23�@g/kWh��NO���K���v�̋K�������́A�����I�Ɏ��{����
��Ȃ��ƍl������B�����āA�|���R�c���Z�p���̕M�҂�10�N�O��2004�N5��25���ɏo�肵���Q�^�[�{�����̋C��
�x�~�V�X�e�����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p�́A���{�����ԍH�Ɖ�̃z�[���y�[�W��
JAMAGAZINE�@�i2012�N3�����j�ɂ����đ���c��w�E�����������w�E�́u�@ DPF���u�̋����Đ��̕p�x�����v�A�u�A
SCR�G�}�̒ቷ�����v�A�u�BSCR�G�}��HC��ł̉����v�A����сu�C �d�ʎԃ��[�h�R��̉��P�v�̂S���ڂ̋Z�p�I��
�ۑ�̑S�Ă��������邱�Ƃ��\�ƂȂ�A�u2015�N�x�d�ʎԔR������{10�����x�̔R�����v�Ɓu�m�n����0.23�@g/
kWh��NO���K���v�̋K�������ɓK���\����^�g���b�N���e�ՂɎ����ł�����ł���B
�𑁊��ɐݒ肹��I������č������ɂ���^�g���b�N��NO���K�����{�s����������{���{�̑Ӗ��ɏڏq���Ă���悤
�ɁA����͕M�҂̗\���ɉ߂��Ȃ����Ƃł��邪�A�����̉��ꂩ�̎����ɂ����āA�킪���̑�^�g���b�N�́A�u2015�N�x
�d�ʎԔR������{10�����x�̔R�����v�Ɓu�m�n����0.23�@g/kWh��NO���K���v�̋K�������́A�����I�Ɏ��{����
��Ȃ��ƍl������B�����āA�|���R�c���Z�p���̕M�҂�10�N�O��2004�N5��25���ɏo�肵���Q�^�[�{�����̋C��
�x�~�V�X�e�����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p�́A���{�����ԍH�Ɖ�̃z�[���y�[�W��
JAMAGAZINE�@�i2012�N3�����j�ɂ����đ���c��w�E�����������w�E�́u�@ DPF���u�̋����Đ��̕p�x�����v�A�u�A
SCR�G�}�̒ቷ�����v�A�u�BSCR�G�}��HC��ł̉����v�A����сu�C �d�ʎԃ��[�h�R��̉��P�v�̂S���ڂ̋Z�p�I��
�ۑ�̑S�Ă��������邱�Ƃ��\�ƂȂ�A�u2015�N�x�d�ʎԔR������{10�����x�̔R�����v�Ɓu�m�n����0.23�@g/
kWh��NO���K���v�̋K�������ɓK���\����^�g���b�N���e�ՂɎ����ł�����ł���B
�@�Ƃ���ŁA�ߔN�̐V�Z�p�̊J���Ɖ]���A�R�O�N���x���̂ɔ��Ă��ꂽ�u���z�̃f�B�[�[���R�ċZ�p�I�v�A�u�����̔R
�ċZ�p�I�v�Ƃ��đ����ꂽ�f�B�[�[���G���W����HCCI �R�āi��PCI �R�āF�\�������k���ΔR�āj�̋Z�p���v���o����
��B�������A���̃f�B�[�[����HCCI �R�āi��PCI �R�āj�́ANO���팸�ɂ͗L���Ȃ��̂̔R�Ă��s����ȏ�ɁA�R���
�P�̌��ʂ��w�ǖ������Ƃ����炩�ƂȂ������߁A�ŋ߂ł͎��p���̖����u�V�Z�p�H�v�ƍl����w�ҁE���ƁE�Z�p�҂�
�����悤���B�����āA�f�B�[�[��HCCI �R�āi��PCI �R�āj�̐V�Z�p�́A�R�O�N���x�̍Ό��Ƒ����̊w�ҁE���ƁE�Z�p
�҂���𑈂��Č����J���ɋ��에�����A�c��ȗʂ̘_�������\���ꂽ�̂ł���B�������A�ŋ߂ł́A���̃f�B�[�[��
HCCI �R�āi��PCI �R�āj�̌����J���́A���ǂ̂Ƃ���A�厸�s�ł������ƍl�Ă���w�ҁE���ƁE�Z�p�҂������悤��
����B�ܘ_�A���߂̈����w�ҁE���ƁE�Z�p�҂͖������炵�������J���s���Ă���悤�ł��邪�A���s�ׂ̂悤
�Ɍ�����͕̂M�҂����ł��낤���B
�ċZ�p�I�v�Ƃ��đ����ꂽ�f�B�[�[���G���W����HCCI �R�āi��PCI �R�āF�\�������k���ΔR�āj�̋Z�p���v���o����
��B�������A���̃f�B�[�[����HCCI �R�āi��PCI �R�āj�́ANO���팸�ɂ͗L���Ȃ��̂̔R�Ă��s����ȏ�ɁA�R���
�P�̌��ʂ��w�ǖ������Ƃ����炩�ƂȂ������߁A�ŋ߂ł͎��p���̖����u�V�Z�p�H�v�ƍl����w�ҁE���ƁE�Z�p�҂�
�����悤���B�����āA�f�B�[�[��HCCI �R�āi��PCI �R�āj�̐V�Z�p�́A�R�O�N���x�̍Ό��Ƒ����̊w�ҁE���ƁE�Z�p
�҂���𑈂��Č����J���ɋ��에�����A�c��ȗʂ̘_�������\���ꂽ�̂ł���B�������A�ŋ߂ł́A���̃f�B�[�[��
HCCI �R�āi��PCI �R�āj�̌����J���́A���ǂ̂Ƃ���A�厸�s�ł������ƍl�Ă���w�ҁE���ƁE�Z�p�҂������悤��
����B�ܘ_�A���߂̈����w�ҁE���ƁE�Z�p�҂͖������炵�������J���s���Ă���悤�ł��邪�A���s�ׂ̂悤
�Ɍ�����͕̂M�҂����ł��낤���B
�@���̂悤�ɁA�f�B�[�[����HCCI �R�āi��PCI �R�āj�̌����J���̎��s������ƁA�@���قǍ��l�ɁA�f�B�[�[���G���W
���́uNO���팸�v�Ɓu�R����P�v���Ɏ����ł���V�Z�p���J�����邱�Ƃ�����ł��邩�������ł��锤�ł���B����
�āA���̃f�B�[�[����HCCI �R�āi��PCI �R�āj�ˌ����J���̎��s�̂悤�ɁA�f�B�[�[���G���W���́uNO���팸�v�Ɓu�R��
���P�v�̓��������́A�Z�p�I�ɋɂ߂ē�����Ƃł���B�������A���̍�������������̂��C���x�~�G���W���i������
�J2005-54771�j�̓����Z�p�ł���A�����āA���̓����Z�p�͑�^�f�B�[�[���g���b�N�́uNO���팸�v�Ɓu�R����P�v�̗���
���Ɏ����ł������I�ȐV�Z�p�ł���B���̂��߁A���݁i��2014�N9���j�̂Ƃ���A�u2015�N�x�d�ʎԔR����
��{10�����x�̔R�����v�Ɓu�m�n����0.23�@g/kWh��NO���K���v�̋K�������ɓK���ł����Z�p�́A�����C���x�~�G��
�W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p�̑��ɂ͑��݂����A���炭�A���ꂩ��P�O�N�`�Q�O�N���x���o�߂��āA�����̓�
���Z�p�𗽉킷���^�g���b�N�́uNO���팸�v�Ɓu�d�ʎԃ��[�h�R��̉��P�v�̗������Ɏ����ł���Z�p�͐��܂��
�����̂Ɛ��������B�����āA���̕M�Ғ�Ă��C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p�́A�uNO��
�팸�v�Ɓu�R����P�v�̋@�\�E���\��������ɍ\���I�ɊȒP�Ȃ��߂Ɏ��p�����e�Ղł��邱�Ƃ���A���̓����Z
�p���^�g���b�N�ɍ̗p�����ꍇ�A�u2015�N�x�d�ʎԔR������{10�����x�̔R�����v�Ɓu�m�n����0.23�@g
/kWh��NO���K���v�̃��x���̋K���ɓK��������^�g���b�N��2020�N�x���ɂ͎s�̂��\�ɂȂ�ƍl������B
���́uNO���팸�v�Ɓu�R����P�v���Ɏ����ł���V�Z�p���J�����邱�Ƃ�����ł��邩�������ł��锤�ł���B����
�āA���̃f�B�[�[����HCCI �R�āi��PCI �R�āj�ˌ����J���̎��s�̂悤�ɁA�f�B�[�[���G���W���́uNO���팸�v�Ɓu�R��
���P�v�̓��������́A�Z�p�I�ɋɂ߂ē�����Ƃł���B�������A���̍�������������̂��C���x�~�G���W���i������
�J2005-54771�j�̓����Z�p�ł���A�����āA���̓����Z�p�͑�^�f�B�[�[���g���b�N�́uNO���팸�v�Ɓu�R����P�v�̗���
���Ɏ����ł������I�ȐV�Z�p�ł���B���̂��߁A���݁i��2014�N9���j�̂Ƃ���A�u2015�N�x�d�ʎԔR����
��{10�����x�̔R�����v�Ɓu�m�n����0.23�@g/kWh��NO���K���v�̋K�������ɓK���ł����Z�p�́A�����C���x�~�G��
�W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p�̑��ɂ͑��݂����A���炭�A���ꂩ��P�O�N�`�Q�O�N���x���o�߂��āA�����̓�
���Z�p�𗽉킷���^�g���b�N�́uNO���팸�v�Ɓu�d�ʎԃ��[�h�R��̉��P�v�̗������Ɏ����ł���Z�p�͐��܂��
�����̂Ɛ��������B�����āA���̕M�Ғ�Ă��C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p�́A�uNO��
�팸�v�Ɓu�R����P�v�̋@�\�E���\��������ɍ\���I�ɊȒP�Ȃ��߂Ɏ��p�����e�Ղł��邱�Ƃ���A���̓����Z
�p���^�g���b�N�ɍ̗p�����ꍇ�A�u2015�N�x�d�ʎԔR������{10�����x�̔R�����v�Ɓu�m�n����0.23�@g
/kWh��NO���K���v�̃��x���̋K���ɓK��������^�g���b�N��2020�N�x���ɂ͎s�̂��\�ɂȂ�ƍl������B
�@�Ƃ��낪�A�������ƂɁA���{���\����G���W���W�̊w�҂̈�l�ł��鑁��c��w�E����������A�g���b�N���[�J�ł�
��UD�g���b�N�X���̐��ƁE�Z�p�҂̏��ѐM�T ���� �O�G ������^�g���b�N�ɂ������L �@�`�C �̋ɂ߂ĉ���
�̍���ȉۑ�̑��݂����������_���E�L���������{�����ԍH�Ɖ�̃z�[���y�[�W��AMAGAZINE�i2012�N3�����j��
�����ԋZ�p���̔N�Ӂi��2010�N�y��2014�N�̂W�����j�ɔ��\�E���J����Ă���B�܂�A����c��w�E����������UD�g
���b�N�X���̐��ƁE�Z�p�҂̏��ѐM�T ���̂R���́A2010�N�`2014�N�ɂ����āA��^�g���b�N�́uNO���팸�v�Ɓu�R���
�P�v�ɗL�����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p�̑��݂������S�ɖ����E�َE�����_���E�L������
���\����Ă���̂ł���B�܂�A��^�f�B�[�[���g���b�N�́uNO���팸�v�Ɓu�R����P�v�̎����ɕK�v�ȉۑ肾�����
���āA�ۑ�����������̓I�ȋZ�p�̏��J����E��Ă��s���Ă��炸�A�uNO���팸�v�Ɓu�d�ʎԃ��[�h�R���̉�
�P�v�ɗL�����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p�������E�َE���Ă����̂ł���B
��UD�g���b�N�X���̐��ƁE�Z�p�҂̏��ѐM�T ���� �O�G ������^�g���b�N�ɂ������L �@�`�C �̋ɂ߂ĉ���
�̍���ȉۑ�̑��݂����������_���E�L���������{�����ԍH�Ɖ�̃z�[���y�[�W��AMAGAZINE�i2012�N3�����j��
�����ԋZ�p���̔N�Ӂi��2010�N�y��2014�N�̂W�����j�ɔ��\�E���J����Ă���B�܂�A����c��w�E����������UD�g
���b�N�X���̐��ƁE�Z�p�҂̏��ѐM�T ���̂R���́A2010�N�`2014�N�ɂ����āA��^�g���b�N�́uNO���팸�v�Ɓu�R���
�P�v�ɗL�����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p�̑��݂������S�ɖ����E�َE�����_���E�L������
���\����Ă���̂ł���B�܂�A��^�f�B�[�[���g���b�N�́uNO���팸�v�Ɓu�R����P�v�̎����ɕK�v�ȉۑ肾�����
���āA�ۑ�����������̓I�ȋZ�p�̏��J����E��Ă��s���Ă��炸�A�uNO���팸�v�Ɓu�d�ʎԃ��[�h�R���̉�
�P�v�ɗL�����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p�������E�َE���Ă����̂ł���B
�@�@���̂悤�ȏɂ����āA���쎩���Ԃ́A�����ԋZ�p��2014�N�t�G���i��2014�N5��21���i���j�`23���i���j�J
�Áj�ɂ����āA�ȉ��̑��v���O�����̃R�s�[�Ɏ������u�ߋ��f�B�[�[���G���W���̋C���x�~�ɂ��Ă̈�l�@�v�i����
�ԍ�20145364�j�Ƒ肷���^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W���̋C���x�~�V�X�e���Ɋւ���_���̔��\�X�Ɗ��s����
�̂ł���B���{�̃g���b�N���[�J�̃g�b�v��Ƃł�����쎩���Ԃ������ԋZ�p��2014�N�H�G���Ŕ��\�����_���́A
���쎩���Ԃ��_�����\�����R����P�@�\�̗��C���x�~�V�X�e���ɏڏq���Ă���悤�ɁA�f�B�[�[���G���W���̋C��
�x�~�^�]���ɂ��^�[�{�ߋ��@���T�[�W���O������\���I�Ȍ��ׂ����u�z�E�r�C�ْ�~���̋C���x�~�V�X�e���v
�̔j���p�ȓ��e�ł������B����͕M�҂����̎א������m��Ȃ����A���̂悤�Ȍ��Z�p�̌��_�𖾂炩�ɂ��Ď��p��
���ɂ߂č���ƌ��_�t�����_���\�������쎩���Ԃ̔��\�̖ړI�́A�u�C���x�~�V�X�e���v�Ə̂���f�B�[�[���G
���W���̐V�Z�p���̂��̂���^�g���b�N�̑��s�R����\���ɉ��P���邱�Ƃ�����ł��邩�̂悤�ȁu�\�v��u����ρv��
�L�߂銈���ł���Ɛ��������B�����āA���̓��쎩���Ԃ̍\���I�Ȍ��ׂ́u�z�E�r�C�ْ�~���̋C���x�~�V�X�e���v
�̔j���p�_���̔��\�́A��^�g���b�N�́u��NO�����v����сu��R��v�ɗL���ȁu�Q�^�[�{�����̋C���x�~�V�X�e���i��
�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�j���Ӑ}�I���Ȃ߂邱�Ƃ��A�ő�̑_���̂悤�Ɏv����̂ł���B
�Áj�ɂ����āA�ȉ��̑��v���O�����̃R�s�[�Ɏ������u�ߋ��f�B�[�[���G���W���̋C���x�~�ɂ��Ă̈�l�@�v�i����
�ԍ�20145364�j�Ƒ肷���^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W���̋C���x�~�V�X�e���Ɋւ���_���̔��\�X�Ɗ��s����
�̂ł���B���{�̃g���b�N���[�J�̃g�b�v��Ƃł�����쎩���Ԃ������ԋZ�p��2014�N�H�G���Ŕ��\�����_���́A
���쎩���Ԃ��_�����\�����R����P�@�\�̗��C���x�~�V�X�e���ɏڏq���Ă���悤�ɁA�f�B�[�[���G���W���̋C��
�x�~�^�]���ɂ��^�[�{�ߋ��@���T�[�W���O������\���I�Ȍ��ׂ����u�z�E�r�C�ْ�~���̋C���x�~�V�X�e���v
�̔j���p�ȓ��e�ł������B����͕M�҂����̎א������m��Ȃ����A���̂悤�Ȍ��Z�p�̌��_�𖾂炩�ɂ��Ď��p��
���ɂ߂č���ƌ��_�t�����_���\�������쎩���Ԃ̔��\�̖ړI�́A�u�C���x�~�V�X�e���v�Ə̂���f�B�[�[���G
���W���̐V�Z�p���̂��̂���^�g���b�N�̑��s�R����\���ɉ��P���邱�Ƃ�����ł��邩�̂悤�ȁu�\�v��u����ρv��
�L�߂銈���ł���Ɛ��������B�����āA���̓��쎩���Ԃ̍\���I�Ȍ��ׂ́u�z�E�r�C�ْ�~���̋C���x�~�V�X�e���v
�̔j���p�_���̔��\�́A��^�g���b�N�́u��NO�����v����сu��R��v�ɗL���ȁu�Q�^�[�{�����̋C���x�~�V�X�e���i��
�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�j���Ӑ}�I���Ȃ߂邱�Ƃ��A�ő�̑_���̂悤�Ɏv����̂ł���B
�@���̂Ȃ�A���̓��쎩���Ԃ��z�E�r�C�ْ�~�����C���x�~�V�X�e���̘_���ł́A���쎩���Ԃ��v���I�Ȍ��ׂ�
���u����ȐV�Z�p�v�i���u�z�E�r�C�ْ�~�����C���x�~�V�X�e���v�j�������đI�����A���́u����ȐV�Z�p�v�̍\���I��
�s��E���_�i���ߋ��@�̃T�[�W���������j�̉������Z�p�I�ɋɂ߂č���ł��邱�Ƃ�_���I�i���V���~���[�V��
���v�Z���j�ɏؖ����Ă���̂ł���B����ɂ���āA�M�Ғ�Ă̂Q�^�[�{�����̋C���x�~�V�X�e���i���C���x�~�G���W
���i�������J2005-54771�j�j�Ɠ��쎩���Ԓ�Ă��z�E�r�C�ْ�~�����C���x�~�V�X�e���Ƃ̋@�\�E�\���̂̑����
�����Ă��Ȃ��f�B�[�[���G���W���W�̊w�ҁE���ƁE�Z�p�҂ɂ́A�S�Ă̋C���x�~�ɗނ���V�Z�p�́A�u��^�g���b�N
�̒�NO��������ђ�R��ɖ����v�ƌ����^���邱�Ƃ��\�ƂȂ�B�܂�A���̓��쎩���Ԃ́u�z�E�r�C�ْ�~��
�̋C���x�~�V�X�e���v�̔j���p�Ș_���́A�M�Ғ�Ă��C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p���u��^
�g���b�N�̒�NO��������ђ�R��ɖ����v�Ƃ̌����^���邽�߂����\���ꂽ�ƌ��邱�Ƃ��\�ł���B����́A�M��
�̎א������m��Ȃ����A�g���b�N���[�J�̃g�b�v��Ƃ̓��쎩���Ԃ����Ђ��鎩���ԋZ�p��̍u����ɂ����āA���ɁA
�V�Z�p�ł���f�B�[�[���G���W���̋C���x�~�Ɋւ���e�[�}�ɂ��āA�^�ʖڂȌ����J�����čŏ�����v���I��
���ׂ̖����ȁu�z�E�r�C�ْ�~���̋C���x�~�V�X�e���v�������Č����e�[�}�ɑI�肵�A���̋Z�p�̌��_���������
�]�������J���̍��\�I�Ȏ��쎩���̍s�ׂ��s���Ă������Ƃ������ł���A���쎩���Ԃ́A�������ᔻ�����ׂ���
�l���邪�A�@���Ȃ��̂ł��낤���B
���u����ȐV�Z�p�v�i���u�z�E�r�C�ْ�~�����C���x�~�V�X�e���v�j�������đI�����A���́u����ȐV�Z�p�v�̍\���I��
�s��E���_�i���ߋ��@�̃T�[�W���������j�̉������Z�p�I�ɋɂ߂č���ł��邱�Ƃ�_���I�i���V���~���[�V��
���v�Z���j�ɏؖ����Ă���̂ł���B����ɂ���āA�M�Ғ�Ă̂Q�^�[�{�����̋C���x�~�V�X�e���i���C���x�~�G���W
���i�������J2005-54771�j�j�Ɠ��쎩���Ԓ�Ă��z�E�r�C�ْ�~�����C���x�~�V�X�e���Ƃ̋@�\�E�\���̂̑����
�����Ă��Ȃ��f�B�[�[���G���W���W�̊w�ҁE���ƁE�Z�p�҂ɂ́A�S�Ă̋C���x�~�ɗނ���V�Z�p�́A�u��^�g���b�N
�̒�NO��������ђ�R��ɖ����v�ƌ����^���邱�Ƃ��\�ƂȂ�B�܂�A���̓��쎩���Ԃ́u�z�E�r�C�ْ�~��
�̋C���x�~�V�X�e���v�̔j���p�Ș_���́A�M�Ғ�Ă��C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p���u��^
�g���b�N�̒�NO��������ђ�R��ɖ����v�Ƃ̌����^���邽�߂����\���ꂽ�ƌ��邱�Ƃ��\�ł���B����́A�M��
�̎א������m��Ȃ����A�g���b�N���[�J�̃g�b�v��Ƃ̓��쎩���Ԃ����Ђ��鎩���ԋZ�p��̍u����ɂ����āA���ɁA
�V�Z�p�ł���f�B�[�[���G���W���̋C���x�~�Ɋւ���e�[�}�ɂ��āA�^�ʖڂȌ����J�����čŏ�����v���I��
���ׂ̖����ȁu�z�E�r�C�ْ�~���̋C���x�~�V�X�e���v�������Č����e�[�}�ɑI�肵�A���̋Z�p�̌��_���������
�]�������J���̍��\�I�Ȏ��쎩���̍s�ׂ��s���Ă������Ƃ������ł���A���쎩���Ԃ́A�������ᔻ�����ׂ���
�l���邪�A�@���Ȃ��̂ł��낤���B
�@���̂悤�ɁA���쎩���Ԃ́A�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p����^�g���b�N�̍X�Ȃ�uNO����
���v�Ɓu�R����P�v�𐄐i�ɕK�v�ȏ�L �@�`�C �̉ۑ����������Z�p�Ƃ��Ď��i�E����ł��邱�Ƃ����`���邽�߂ɁA
�u�z�E�r�C�ْ�~���̋C���x�~�v�Ɖ]�����قȋC���x�~�V�X�e���ڌ��Z�p�̔j���p�Ș_���������ԋZ�p��2014�N
�t�G���Ŕ��\�����Ɛ��������B���̂��Ƃ���A���쎩���Ԃ́A�p���O���������A��^�g���b�N�́uNO���팸�v�Ɓu�R��
���P�v�ɗL�����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p��ے肷�邽�߂̊�����K���ōs���Ă���悤
�ɁA�M�҂ɂ͎v����̂ł���B����́A�����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p�̓�������2024�N
�x�ɏ��ł��邱�Ƃ������E�W������̂ł͂Ȃ����Ɛ��������B
���v�Ɓu�R����P�v�𐄐i�ɕK�v�ȏ�L �@�`�C �̉ۑ����������Z�p�Ƃ��Ď��i�E����ł��邱�Ƃ����`���邽�߂ɁA
�u�z�E�r�C�ْ�~���̋C���x�~�v�Ɖ]�����قȋC���x�~�V�X�e���ڌ��Z�p�̔j���p�Ș_���������ԋZ�p��2014�N
�t�G���Ŕ��\�����Ɛ��������B���̂��Ƃ���A���쎩���Ԃ́A�p���O���������A��^�g���b�N�́uNO���팸�v�Ɓu�R��
���P�v�ɗL�����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p��ے肷�邽�߂̊�����K���ōs���Ă���悤
�ɁA�M�҂ɂ͎v����̂ł���B����́A�����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p�̓�������2024�N
�x�ɏ��ł��邱�Ƃ������E�W������̂ł͂Ȃ����Ɛ��������B
�@���̂Ȃ�A�����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p�̓����������ł���2024�N�x�ȑO�Ɂu2015
�N�x�d�ʎԔR������{10�����x�̔R�����v�Ɓu�m�n����0.23�@g/kWh��NO���K���v����^�g���b�N���K����������
�{����邱�ƂɂȂ����ꍇ�A�g���b�N���[�J�́A�����̋K���ɓK�����邽�߂ɂ͑�^�g���b�N���C���x�~�G���W���i����
���J2005-54771�j�̓����Z�p�����X�Ȃ�����d���Ȃ��ɍ̗p���邱�ƂɂȂ�B���̏ꍇ�A�g���b�N���[�J�́A���̓����Z
�p�������������������Ȃ����ƂɂȂ�B���̎��ɂ́A�e�g���b�N���[�J�́A�|���R�c���Z�p���̕M�҂��C��
�x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p���̗p���Ă��邽�߁A��i�̋Z�p�����ЂœƎ��ɊJ�����āu2015�N
�x�d�ʎԔR������{10�����x�̔R�����v�Ɓu�m�n����0.23�@g/kWh��NO���K���ւ̓K���v�����������ƌւ炵����
�`���邱�Ƃ��s�\�ɂȂ�B���̏�A�g���b�N���[�J�̋Z�p�ҁE���Ƃ́A�|���R�c���Z�p���̕M�҂̓����Z�p���g�p
�������Ƃɂ���ăv���C�h�E�����S���������A�S�߂Ȕs�k���ɕ����邱�ƂɂȂ�B���̂悤�ȏ������N�������
���ʂƂȂ����̂́A�����_���C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p�𗽉킷���^�g���b�N�́uNO����
���v�Ɓu�R�����v�̋Z�p���g���b�N���[�J�i�����{�����ԍH�Ɖ�j�ɂ��������J���ł��邱�Ƃ��ő�̌����ł����A�v��
���̂Ȃ����Ƃł���B
�N�x�d�ʎԔR������{10�����x�̔R�����v�Ɓu�m�n����0.23�@g/kWh��NO���K���v����^�g���b�N���K����������
�{����邱�ƂɂȂ����ꍇ�A�g���b�N���[�J�́A�����̋K���ɓK�����邽�߂ɂ͑�^�g���b�N���C���x�~�G���W���i����
���J2005-54771�j�̓����Z�p�����X�Ȃ�����d���Ȃ��ɍ̗p���邱�ƂɂȂ�B���̏ꍇ�A�g���b�N���[�J�́A���̓����Z
�p�������������������Ȃ����ƂɂȂ�B���̎��ɂ́A�e�g���b�N���[�J�́A�|���R�c���Z�p���̕M�҂��C��
�x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p���̗p���Ă��邽�߁A��i�̋Z�p�����ЂœƎ��ɊJ�����āu2015�N
�x�d�ʎԔR������{10�����x�̔R�����v�Ɓu�m�n����0.23�@g/kWh��NO���K���ւ̓K���v�����������ƌւ炵����
�`���邱�Ƃ��s�\�ɂȂ�B���̏�A�g���b�N���[�J�̋Z�p�ҁE���Ƃ́A�|���R�c���Z�p���̕M�҂̓����Z�p���g�p
�������Ƃɂ���ăv���C�h�E�����S���������A�S�߂Ȕs�k���ɕ����邱�ƂɂȂ�B���̂悤�ȏ������N�������
���ʂƂȂ����̂́A�����_���C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p�𗽉킷���^�g���b�N�́uNO����
���v�Ɓu�R�����v�̋Z�p���g���b�N���[�J�i�����{�����ԍH�Ɖ�j�ɂ��������J���ł��邱�Ƃ��ő�̌����ł����A�v��
���̂Ȃ����Ƃł���B
�@���̂悤�ɁA�g���b�N���[�J�́uNO���팸�v�Ɓu�R�����v�̋Z�p�J���̔\�͕s���������Ƃ͉]���A�|���R�c���Z�p����
�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p���̗p����ߎS�ȏɊׂ邱�Ƃ���������邽�߁A�g���b�N��
�[�J�i�����{�����ԍH�Ɖ�j�̒N�����@���Ȃ�Ƒ��Ȏ�i��M���Ă�������悤�Ƃ��邱�Ƃ́A���R�̐���s���Ɛ��@��
���B���̏ꍇ�̍ł��L���Ȏ�i�E���@�́A���y��ʏȂɁu2024�N�ȍ~��2015�N�d�ʎԔR���́{�P�O���x�̌�
��v�̔R��K�������̋����v�]���A���ȂɁu2024�N�ȍ~�ɂm�nX��0.23�@g/kWh��NO���K���v�̋��������Ɏ{�s���Ă�
�炱�Ƃł���B���̂Ȃ�A�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓�������2024�N5�������ł��邱�ƂɂȂ��Ă�
�邽�߁A�����u2024�N�ȍ~��2015�N�d�ʎԔR���́{�P�O���x�̌���v����сu2024�N�ȍ~�ɂm�nX��0.23�@g/kWh
��NO���K���v��2024�N5���ȍ~�Ɏ��{���Ă��炦�A���������Z�p�̎��{�̋������Ɏ��R�ɑ�^�g���b�N�ɍ̗p
���A������g���b�N���[�J�����R�C�܂܂ɔ̔��ł�������o����̂ł���B���̏�A�g���b�N���[�J�̐��ƁE�Z�p
�҂̎����S�E�v���C�h�ɏ��������Ƃ�����ł��郁���b�g��������̂ł���B
�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p���̗p����ߎS�ȏɊׂ邱�Ƃ���������邽�߁A�g���b�N��
�[�J�i�����{�����ԍH�Ɖ�j�̒N�����@���Ȃ�Ƒ��Ȏ�i��M���Ă�������悤�Ƃ��邱�Ƃ́A���R�̐���s���Ɛ��@��
���B���̏ꍇ�̍ł��L���Ȏ�i�E���@�́A���y��ʏȂɁu2024�N�ȍ~��2015�N�d�ʎԔR���́{�P�O���x�̌�
��v�̔R��K�������̋����v�]���A���ȂɁu2024�N�ȍ~�ɂm�nX��0.23�@g/kWh��NO���K���v�̋��������Ɏ{�s���Ă�
�炱�Ƃł���B���̂Ȃ�A�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓�������2024�N5�������ł��邱�ƂɂȂ��Ă�
�邽�߁A�����u2024�N�ȍ~��2015�N�d�ʎԔR���́{�P�O���x�̌���v����сu2024�N�ȍ~�ɂm�nX��0.23�@g/kWh
��NO���K���v��2024�N5���ȍ~�Ɏ��{���Ă��炦�A���������Z�p�̎��{�̋������Ɏ��R�ɑ�^�g���b�N�ɍ̗p
���A������g���b�N���[�J�����R�C�܂܂ɔ̔��ł�������o����̂ł���B���̏�A�g���b�N���[�J�̐��ƁE�Z�p
�҂̎����S�E�v���C�h�ɏ��������Ƃ�����ł��郁���b�g��������̂ł���B
�@���̂��߁A���݁i��2014�N���j�ł́A�g���b�N���[�J�i�����{�����ԍH�Ɖ�j�́A�C���x�~�G���W���i�������J2005-
54771�j�̓����Z�p�̓������̏��ł���2024�N�x�ȍ~�ɁA��^�g���b�N���u2015�N�d�ʎԔR���́{�P�O���x�̌�
��v����сu�m�nX��0.23�@g/kWh��NO���K���v�̋K�����������{�ƂȂ�����o�����߂̊�����ϋɓI�ɍs���Ă�
����̂Ɛ��������B���̈�Ƃ��āA���쎩���Ԃ��\���I�Ȍ��ׂ̂����j���p�ȓ��e���_���������ԋZ�p��2014
�N�t�G���Ŕ��\���A��^�g���b�N�́uNO���팸�v�Ɓu�R����P�v�ɗL�����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j��
�����Z�p�E���銈�����s���Ă��Ƃ́A�M�҂ɂ͕�������������̂悤�Ɏv����̂ł���B�����āA�O�q�̂悤�ɁA
�ŋ߁i��2010�N�`2014�N�j�ɔ��\�E���J���ꂽ�_���E�L���ł́A����c��w�E����������UD�g���b�N�X���̐��ƁE�Z
�p�҂̏��ѐM�T ������^�g���b�N�́uNO���팸�v�Ɓu�R����P�v�ɗL�����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j��
�����Z�p�̑��݂����S�ɖ����E�َE����Ă��邪�A����́A�g���b�N���[�J����^�g���b�N�ɂ������u2015�N�d�ʎԔR��
��́{�P�O���x�̌���v����сu�m�nX��0.23�@g/kWh��NO���K���v�̋K��������2024�N�x�ȍ~�Ƃ��銈���̐��ʂƌ�
�邱�Ƃ��\�ł���B
54771�j�̓����Z�p�̓������̏��ł���2024�N�x�ȍ~�ɁA��^�g���b�N���u2015�N�d�ʎԔR���́{�P�O���x�̌�
��v����сu�m�nX��0.23�@g/kWh��NO���K���v�̋K�����������{�ƂȂ�����o�����߂̊�����ϋɓI�ɍs���Ă�
����̂Ɛ��������B���̈�Ƃ��āA���쎩���Ԃ��\���I�Ȍ��ׂ̂����j���p�ȓ��e���_���������ԋZ�p��2014
�N�t�G���Ŕ��\���A��^�g���b�N�́uNO���팸�v�Ɓu�R����P�v�ɗL�����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j��
�����Z�p�E���銈�����s���Ă��Ƃ́A�M�҂ɂ͕�������������̂悤�Ɏv����̂ł���B�����āA�O�q�̂悤�ɁA
�ŋ߁i��2010�N�`2014�N�j�ɔ��\�E���J���ꂽ�_���E�L���ł́A����c��w�E����������UD�g���b�N�X���̐��ƁE�Z
�p�҂̏��ѐM�T ������^�g���b�N�́uNO���팸�v�Ɓu�R����P�v�ɗL�����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j��
�����Z�p�̑��݂����S�ɖ����E�َE����Ă��邪�A����́A�g���b�N���[�J����^�g���b�N�ɂ������u2015�N�d�ʎԔR��
��́{�P�O���x�̌���v����сu�m�nX��0.23�@g/kWh��NO���K���v�̋K��������2024�N�x�ȍ~�Ƃ��銈���̐��ʂƌ�
�邱�Ƃ��\�ł���B
�@���Ă��āA��^�g���b�N�ɂ��āA���y��ʏȂɁu2024�N�ȍ~��2015�N�d�ʎԔR���́{�P�O���x�̌���v�̔R��
�K�����������{���ĖႢ�A���ȂɁu2024�N�ȍ~�ɂm�n����0.23�@g/kWh�̋K�������v��NO���K���̋��������{���Ă���
���ł��L���ȕ��@�́A���y��ʏȂƊ��Ȃ̂��ꂼ��̈ψ���u�R��K���̋����v�ƁuNO���K���̋����v�̂��ꂼ
��̋K����2024�N�ȍ~�Ɍ��肵�ĖႤ���Ƃł���B���̏ꍇ�̕M�҂̐���������ʓI�ȕ��@�́A�ȉ��̕\�Q�O�Ɏ���
�����Ȃ�NO���K�������Ɍg����������R�c���C�E�����U��������Ԕr�o�K�X���ψ��ψ���̈ψ��ƁA
���y��ʏȂ̔R��K�������Ɍg��������ԔR�����ψ����̈ψ��߂�G���W���W�̊w�ҁE���Ƃ��g���b
�N���[�J�����d�ɐ������邱�Ƃł���B
�K�����������{���ĖႢ�A���ȂɁu2024�N�ȍ~�ɂm�n����0.23�@g/kWh�̋K�������v��NO���K���̋��������{���Ă���
���ł��L���ȕ��@�́A���y��ʏȂƊ��Ȃ̂��ꂼ��̈ψ���u�R��K���̋����v�ƁuNO���K���̋����v�̂��ꂼ
��̋K����2024�N�ȍ~�Ɍ��肵�ĖႤ���Ƃł���B���̏ꍇ�̕M�҂̐���������ʓI�ȕ��@�́A�ȉ��̕\�Q�O�Ɏ���
�����Ȃ�NO���K�������Ɍg����������R�c���C�E�����U��������Ԕr�o�K�X���ψ��ψ���̈ψ��ƁA
���y��ʏȂ̔R��K�������Ɍg��������ԔR�����ψ����̈ψ��߂�G���W���W�̊w�ҁE���Ƃ��g���b
�N���[�J�����d�ɐ������邱�Ƃł���B
�@������NO���K�������ƔR��K�������̋K�����x���Ǝ��{���������肷�錠�����Ϗ�����Ă�����Ȃ�������
���R�c���C�E�����U��������Ԕr�o�K�X���ψ��ψ���ƁA���y��ʏȂ̔R��K�������Ɍg��������ԔR��
����ψ���̖���́A�ȉ��̕\�P�T�Ɏ������ʂ�ł���B
���R�c���C�E�����U��������Ԕr�o�K�X���ψ��ψ���ƁA���y��ʏȂ̔R��K�������Ɍg��������ԔR��
����ψ���̖���́A�ȉ��̕\�P�T�Ɏ������ʂ�ł���B
�@�� �����ԔR�����ψ���̈ψ�����A 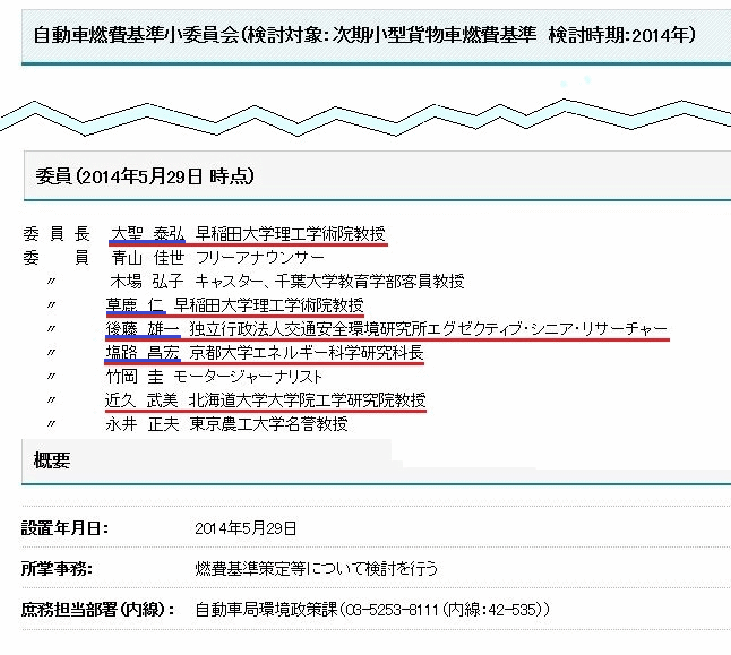 |
�@�� �������R�c���C�E�����U��������Ԕr�o�K�X���ψ����]
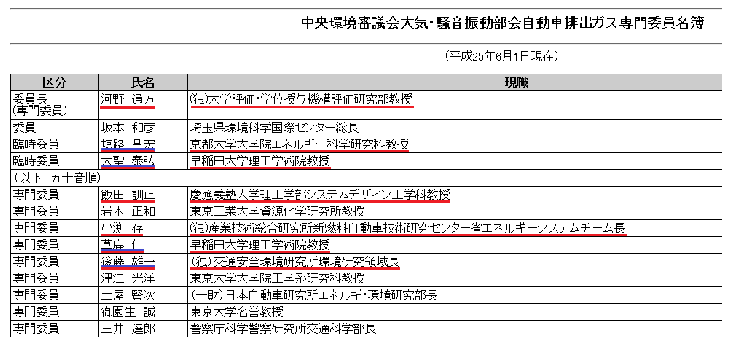 |
�@�@�@�@�@�@�ԐF�ƐF�̉����́A�����Ԕr�o�K�X���ψ��ψ���Ǝ����ԔR�����ψ���Ƃ����C����Ă���ψ�
�@�ȏ�̕\�Q�O�Ɏ������悤�ɁA���Ȃ�NO���K�������Ɍg����������R�c���C�E�����U��������Ԕr�o�K�X
���ψ��ψ���̃G���W���W�̊w�ҁE���Ƃ͈ψ������܂߂ĂV���ł���A���y��ʏȂ̔R��K�������Ɍg���
�����ԔR�����ψ����̃G���W���W�̊w�ҁE���Ƃ͈ψ������܂߂ĂT���ł���B�������A���ψ���ɂ͏d����
�ꂽ�G���W���W�̊w�ҁE���Ƃ͂S���ł���B���̂��ߗ��ψ���̃G���W���W�̊w�ҁE���Ƃ́A�ȉ��Ɏ�����
���� �W ���ł���B
���ψ��ψ���̃G���W���W�̊w�ҁE���Ƃ͈ψ������܂߂ĂV���ł���A���y��ʏȂ̔R��K�������Ɍg���
�����ԔR�����ψ����̃G���W���W�̊w�ҁE���Ƃ͈ψ������܂߂ĂT���ł���B�������A���ψ���ɂ͏d����
�ꂽ�G���W���W�̊w�ҁE���Ƃ͂S���ł���B���̂��ߗ��ψ���̃G���W���W�̊w�ҁE���Ƃ́A�ȉ��Ɏ�����
���� �W ���ł���B
| �吹�@�G | ����c��w���� |
| �����@�m | ����c��w���� |
| �㓡�@�Y�� | �i�Ɓj��ʈ��S���������G�O�[�N�e�B�u�E�V�j�A�E���T�[�`���[ |
| ���H�@���G | ���s��w���� |
| �ߋv�@���� | �k�C����w���� |
| �͖�@���� | �i�Ɓj��w�]���E�w�ʎ��^�@�\�]������������ |
| �ѓc�@�P�� | �c���`�m��w���� |
| �����@�� | �i�Ɓj�Y�����E�G�l���M�[�V�X�e���`�[���� |
�@���݁i��2014�N9���j�̂Ƃ���A���Ȃ�NO���K�������Ɍg��������Ԕr�o�K�X���ψ��ψ���A����э��y���
�Ȃ̔R��K�������Ɍg��������ԔR�����ψ���ɂ́A�����Ⴕ���͕Е��̈ψ���̈ψ��ɔC������Ă���G��
�W���W�̊w�ҁE���Ƃ́A�����W���ł���B�����āA�����i��2014�N9���j�A���̂W���̓��{���\����G���W���W
�̊w�ҁE���Ƃ́A���{�̎����Ԃɂ����鏫���́uNO���̋K���v�Ɓu�R��K���i���R���j�v�̋K�����������鐅��
�i���������郌�x���j�Ƌ��������{���鎞�����������A�����ݒ肷�鋭�����������{�i�����ȁE���y��ʏȁj����
�^�����Ă���̂ł���B
�Ȃ̔R��K�������Ɍg��������ԔR�����ψ���ɂ́A�����Ⴕ���͕Е��̈ψ���̈ψ��ɔC������Ă���G��
�W���W�̊w�ҁE���Ƃ́A�����W���ł���B�����āA�����i��2014�N9���j�A���̂W���̓��{���\����G���W���W
�̊w�ҁE���Ƃ́A���{�̎����Ԃɂ����鏫���́uNO���̋K���v�Ɓu�R��K���i���R���j�v�̋K�����������鐅��
�i���������郌�x���j�Ƌ��������{���鎞�����������A�����ݒ肷�鋭�����������{�i�����ȁE���y��ʏȁj����
�^�����Ă���̂ł���B
�@�����āA���������W���̓��{���\����G���W���W�̊w�ҁE���Ƃ́A���݁i��2014�N9���j�܂ł̂Ƃ���A
��^�g���b�N�ɂ������u�@ DPF���u�̋����Đ��̕p�x�����v�A�u�A SCR�G�}�̒ቷ�����v�A�u�BSCR�G�}��HC
��ł̉����v�A����сu�C �d�ʎԃ��[�h�R��̉��P�v�̂S���ڂ̍ŏd�v�ۑ�̑S�Ă����ނ̋Z�p�ʼn����ł�
��Z�p���A������āE�E���J����Ă��Ȃ��悤�ł���B���̂����A���̑����W���̓��{���\����G���W���W
�̊w�ҁE���Ƃ̑S���́A�����_�i��2014�N9���j�ł́A��^�g���b�N�ɂ����� �@�`�C�̂S���ڂ��ۑ�̑S�Ă�������
����Z�p���s���Ɣ��f����Ă���悤�Ɍ�����̂ł���B���̂��Ƃ���ސ�����ƁA���Ȃ�NO���K�������Ɍg�����
���Ԕr�o�K�X���ψ��ψ���ł́A�d�ʎԂ́u�m�n����0.4 g/kWh���X�ɋ��������m�n����0.23�@g/kWh�̋K�������v��
���{����������ł���A���y��ʏȂ̔R��K�������Ɍg��������ԔR�����ψ���ł��u2015�N�d�ʎԔR���
�����������������̔R��K���i���R���j�v�̋K�����������鐅���i���������郌�x���j�Ǝ��{����������̏�
�l������B
��^�g���b�N�ɂ������u�@ DPF���u�̋����Đ��̕p�x�����v�A�u�A SCR�G�}�̒ቷ�����v�A�u�BSCR�G�}��HC
��ł̉����v�A����сu�C �d�ʎԃ��[�h�R��̉��P�v�̂S���ڂ̍ŏd�v�ۑ�̑S�Ă����ނ̋Z�p�ʼn����ł�
��Z�p���A������āE�E���J����Ă��Ȃ��悤�ł���B���̂����A���̑����W���̓��{���\����G���W���W
�̊w�ҁE���Ƃ̑S���́A�����_�i��2014�N9���j�ł́A��^�g���b�N�ɂ����� �@�`�C�̂S���ڂ��ۑ�̑S�Ă�������
����Z�p���s���Ɣ��f����Ă���悤�Ɍ�����̂ł���B���̂��Ƃ���ސ�����ƁA���Ȃ�NO���K�������Ɍg�����
���Ԕr�o�K�X���ψ��ψ���ł́A�d�ʎԂ́u�m�n����0.4 g/kWh���X�ɋ��������m�n����0.23�@g/kWh�̋K�������v��
���{����������ł���A���y��ʏȂ̔R��K�������Ɍg��������ԔR�����ψ���ł��u2015�N�d�ʎԔR���
�����������������̔R��K���i���R���j�v�̋K�����������鐅���i���������郌�x���j�Ǝ��{����������̏�
�l������B
�@�Ƃ���ŁA�|���R�c���Z�p���̕M�҂�10�N�O��2004�N5��25���ɏo�肵���Q�^�[�{�����̋C���x�~�V�X�e�����C��
�x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p�́A2005�N3���ɓ������J����Ă����ɁA2006�N4��7�����J�̕M
�҂̃C���^�[�l�b�g�̃z�[���y�[�W�ɂ����ċZ�p���e���ڍׂɐ������Ă���B�����āA���̕M�҂̃z�[���y�[�W�́A�C
���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p�Ɋւ���Z�p���́A�C���^�[�l�b�g�̌����G���W���ł́A�ߋ���
�����āA�ȉ��Ɏ��������o�̎��т�����B
�x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p�́A2005�N3���ɓ������J����Ă����ɁA2006�N4��7�����J�̕M
�҂̃C���^�[�l�b�g�̃z�[���y�[�W�ɂ����ċZ�p���e���ڍׂɐ������Ă���B�����āA���̕M�҂̃z�[���y�[�W�́A�C
���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p�Ɋւ���Z�p���́A�C���^�[�l�b�g�̌����G���W���ł́A�ߋ���
�����āA�ȉ��Ɏ��������o�̎��т�����B
�� 2009�N6��11���@Yahoo�����Łu�|�X�g�V�����v�v�̂P�ꌟ���ɂ����āA6��8�猏���̂Q�ʂƂV�ʁi����P�y�[�W�ځj��
���o���ꂽ���т���B�i��2009�N6��11���ł́u�|�X�g�V�����v�̂P���Yahoo�������� ���Q�ƕ��j
���o���ꂽ���т���B�i��2009�N6��11���ł́u�|�X�g�V�����v�̂P���Yahoo�������� ���Q�ƕ��j
�� 2010�N2��24���@Yahoo�����Łu�g���b�N�v�{�u��R��v�̂Q�ꌟ���ɂ����āA102�������̂P�ʁi����P�y�[�W�ځj��
���o���ꂽ���т���B�i��2010�N2��24���ł́u�g���b�N�v�{�u��R��v�̂Q���Yahoo�������� ���Q�ƕ��j
���o���ꂽ���т���B�i��2010�N2��24���ł́u�g���b�N�v�{�u��R��v�̂Q���Yahoo�������� ���Q�ƕ��j
�@�ȏ�̂悤�ɁA2009�N6���`2010�N2���̍��ɂ͊��ɁA��^�g���b�N�́u�r�o�K�X�v��u�R��v�ɊW����p���p����
Yahoo�����ő�P�y�[�W�ڂ��C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p���������Ă���̂ł���B����
�āA�ߔN�̎����ԋZ�p���̔N�ӂ̎Q�l����������ƁA���̑������C���^�[�l�b�g���ł��邱�Ƃ��������ʂ�A�ŐV
�̐��ƁE�Z�p�҂͍ŐV�̋Z�p�����C���^�[�l�b�g�̃z�[���y�[�W������W���Ă���l�q���f����B���̂悤�ɁA�C
���^�[�l�b�g�͎�y�ȏ����W�̎�i�ł���B���̂��߁A�Љ�l�Ɗw���̋�ʖ����A�C���^�[�l�b�g�͑S�Ă̐l�̏d�v
�ȋZ�p���̎��W�̎�i�ɗp�����Ă���B
Yahoo�����ő�P�y�[�W�ڂ��C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p���������Ă���̂ł���B����
�āA�ߔN�̎����ԋZ�p���̔N�ӂ̎Q�l����������ƁA���̑������C���^�[�l�b�g���ł��邱�Ƃ��������ʂ�A�ŐV
�̐��ƁE�Z�p�҂͍ŐV�̋Z�p�����C���^�[�l�b�g�̃z�[���y�[�W������W���Ă���l�q���f����B���̂悤�ɁA�C
���^�[�l�b�g�͎�y�ȏ����W�̎�i�ł���B���̂��߁A�Љ�l�Ɗw���̋�ʖ����A�C���^�[�l�b�g�͑S�Ă̐l�̏d�v
�ȋZ�p���̎��W�̎�i�ɗp�����Ă���B
���������āA�M�҂̃z�[���y�[�W���{�����������̃G���W���ɋ����̂��鑽���̊w���́A2009�N6���`2010�N2���̎�
�_�ɂ����āA�����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p�ɂ��āuNO���팸�v�Ɓu�R����P�v�̗L����
��A���̐^�U�ɂ��āA���̊w�����ʊw�����w�̃G���W�����̋����Ɏ�����������̂Ɛ��@�����B�����āA�w��
�́A���N�A���w�Ƒ��Ƃ��J��Ԃ����߁A�M�҂̃z�[���y�[�W���{�������w���ɂ���C���x�~�G���W���i�������J2005-
54771�j�̓����Z�p�ɂ��ẮuNO���팸�v�Ɓu�R����P�v�̗L������A�Z�p�I�Ȑ^�U�ɂ��ẮA�G���W�����̋���
��2010�N2��������J��Ԃ��čs���Ă������̂Ɛ��������B�����āA���Ȃ̎����Ԕr�o�K�X���ψ��ψ���ƍ�
�y��ʏȂ̎����ԔR�����ψ���̃G���W�����̑����U���̑�w�����́A���R�A����܂ő����̊w���E�@���E��
�蓙����A�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p�ɂ��ẮuNO���팸�v�Ɓu�R����P�v�̗L������A�Z
�p�I�Ȑ^�U�ɂ��Ă̑����̎�������Ă����Ɛ��������B���Ȃ̂ƍ��y��ʏȂ̈ψ���ɑ�����Ă���G
���W�����̂U���̑�w�����́A2009�N6�����ȍ~�ł́A�ǂɂ悤�ȉ�����Ă����̂ł��낤���B
�_�ɂ����āA�����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p�ɂ��āuNO���팸�v�Ɓu�R����P�v�̗L����
��A���̐^�U�ɂ��āA���̊w�����ʊw�����w�̃G���W�����̋����Ɏ�����������̂Ɛ��@�����B�����āA�w��
�́A���N�A���w�Ƒ��Ƃ��J��Ԃ����߁A�M�҂̃z�[���y�[�W���{�������w���ɂ���C���x�~�G���W���i�������J2005-
54771�j�̓����Z�p�ɂ��ẮuNO���팸�v�Ɓu�R����P�v�̗L������A�Z�p�I�Ȑ^�U�ɂ��ẮA�G���W�����̋���
��2010�N2��������J��Ԃ��čs���Ă������̂Ɛ��������B�����āA���Ȃ̎����Ԕr�o�K�X���ψ��ψ���ƍ�
�y��ʏȂ̎����ԔR�����ψ���̃G���W�����̑����U���̑�w�����́A���R�A����܂ő����̊w���E�@���E��
�蓙����A�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p�ɂ��ẮuNO���팸�v�Ɓu�R����P�v�̗L������A�Z
�p�I�Ȑ^�U�ɂ��Ă̑����̎�������Ă����Ɛ��������B���Ȃ̂ƍ��y��ʏȂ̈ψ���ɑ�����Ă���G
���W�����̂U���̑�w�����́A2009�N6�����ȍ~�ł́A�ǂɂ悤�ȉ�����Ă����̂ł��낤���B
�@�����āA����܂ł̂Ƃ���A���̂U���̑�w�����i���͖쓹�������A���H���G�����A�吹�G�����A�ѓc�P�������A
���������ް���ђ��A���������A�ߋv���������j�́A�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p����
�^�g���b�N�ł��u�@ DPF���u�̋����Đ��̕p�x�����v�A�u�A SCR�G�}�̒ቷ�����v�A�u�BSCR�G�}��HC��ł̉����v�A
����сu�C �d�ʎԃ��[�h�R��̉��P�v�̂S���ڂ��ۑ�̉����ɗL���Ƃ̎����E���\������Ă��Ȃ��B���̂��Ƃ��琄��
����ƁA���̓����Z�p�ɂ��āuNO���팸�v�Ɓu�R����P�v�̗L������A�Z�p�I�Ȑ^�U�ɂ��Ċw���̎���ɂ��āA�U
���̑�w�����́A�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p����^�g���b�N���S���ڂ��ۑ�̉����̋@
�\�E���\�������A�|���R�c���Z�p���́u�o�L�ڂȓ����v�Ⴕ���́u�n���ȃ}�j�A�̈����ȓ����v�Ɛ�������Ă���̂����m
��Ȃ��B�܂��ŋ߂ł́A���쎩���Ԃ��_�����\�����R����P�@�\�̗��C���x�~�V�X�e���ɏڏq�����悤�ɁA���쎩
���Ԃ������ԋZ�p��2014�N�t�G���Ŕ��\�����v���I�ȋZ�p�I���ׂ������߂Ɏ��p�s�\�ȁu�z�E�r�C�ْ�~����
�C���x�~�V�X�e���v�̘_���̃R�s�[���w���Ɏ�n���āA�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j���Q�^�[�{�����̋C
���x�~�V�X�e�������Z�p�Ɛ������Ă��邩���m��Ȃ��B�����āA��^�g���b�N�̇@�`�C���S���ڂ��ۑ�������ł���
�Z�p�ɂ��ĉ��̎����������A�Z�p�I�ɕs���Ƃ̋����̉ɑ��A���₵���w�ǂ̊w���͔[�����Ȃ��ƍl������B
���������ް���ђ��A���������A�ߋv���������j�́A�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p����
�^�g���b�N�ł��u�@ DPF���u�̋����Đ��̕p�x�����v�A�u�A SCR�G�}�̒ቷ�����v�A�u�BSCR�G�}��HC��ł̉����v�A
����сu�C �d�ʎԃ��[�h�R��̉��P�v�̂S���ڂ��ۑ�̉����ɗL���Ƃ̎����E���\������Ă��Ȃ��B���̂��Ƃ��琄��
����ƁA���̓����Z�p�ɂ��āuNO���팸�v�Ɓu�R����P�v�̗L������A�Z�p�I�Ȑ^�U�ɂ��Ċw���̎���ɂ��āA�U
���̑�w�����́A�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p����^�g���b�N���S���ڂ��ۑ�̉����̋@
�\�E���\�������A�|���R�c���Z�p���́u�o�L�ڂȓ����v�Ⴕ���́u�n���ȃ}�j�A�̈����ȓ����v�Ɛ�������Ă���̂����m
��Ȃ��B�܂��ŋ߂ł́A���쎩���Ԃ��_�����\�����R����P�@�\�̗��C���x�~�V�X�e���ɏڏq�����悤�ɁA���쎩
���Ԃ������ԋZ�p��2014�N�t�G���Ŕ��\�����v���I�ȋZ�p�I���ׂ������߂Ɏ��p�s�\�ȁu�z�E�r�C�ْ�~����
�C���x�~�V�X�e���v�̘_���̃R�s�[���w���Ɏ�n���āA�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j���Q�^�[�{�����̋C
���x�~�V�X�e�������Z�p�Ɛ������Ă��邩���m��Ȃ��B�����āA��^�g���b�N�̇@�`�C���S���ڂ��ۑ�������ł���
�Z�p�ɂ��ĉ��̎����������A�Z�p�I�ɕs���Ƃ̋����̉ɑ��A���₵���w�ǂ̊w���͔[�����Ȃ��ƍl������B
�@���̂悤�ɁA���Ȃ������Ԕr�o�K�X���ψ��ψ���A����э��y��ʏȂ������ԔR�����ψ����̗����Ⴕ
���͕Е��̈ψ���ɓo�^����Ă��鑍���W���̃G���W���W�̊w�ҁE���Ƃ̑����́A���Ȃ��Ƃ�2009�N6�����ȍ~��
�����ẮA�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p�Ɋւ��鐔�����̎�����w������Ă���ƌ���
���B���̂��߁A���Ȃ������Ԕr�o�K�X���ψ��ψ���A����э��y��ʏȂ������ԔR�����ψ����̗���
�Ⴕ���͕Е��̈ψ���ɓo�^����Ă��鑍���W���̃G���W���W�̊w�ҁE���Ƃ̑啔���́A2009�N6�����̎��_��
�����āA��^�g���b�N�ɂ������u�@ DPF���u�̋����Đ��̕p�x�����v�A�u�A SCR�G�}�̒ቷ�����v�A�u�BSCR�G�}��HC
��ł̉����v�A����сu�C �d�ʎԃ��[�h�R��̉��P�v�̂S���ڂ̍ŏd�v�ۑ�̑S�Ă��C���x�~�G���W���i�������J
2005-54771�j�̓����Z�p�����������ł��邱�������m�E�F������Ă��锤�Ɛ��������B�������A���̑����W���̃G���W
���W�̊w�ҁE���Ƃ̑S���́A�����_�i��2014�N9���j�ł́A��^�g���b�N�ɂ�����@�`�C���S���ڂ̍ŏd�v�ۑ��
�S�Ă������ł����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p�����S�ɖ����E�َE����Ă���悤�ł���B
���͕Е��̈ψ���ɓo�^����Ă��鑍���W���̃G���W���W�̊w�ҁE���Ƃ̑����́A���Ȃ��Ƃ�2009�N6�����ȍ~��
�����ẮA�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p�Ɋւ��鐔�����̎�����w������Ă���ƌ���
���B���̂��߁A���Ȃ������Ԕr�o�K�X���ψ��ψ���A����э��y��ʏȂ������ԔR�����ψ����̗���
�Ⴕ���͕Е��̈ψ���ɓo�^����Ă��鑍���W���̃G���W���W�̊w�ҁE���Ƃ̑啔���́A2009�N6�����̎��_��
�����āA��^�g���b�N�ɂ������u�@ DPF���u�̋����Đ��̕p�x�����v�A�u�A SCR�G�}�̒ቷ�����v�A�u�BSCR�G�}��HC
��ł̉����v�A����сu�C �d�ʎԃ��[�h�R��̉��P�v�̂S���ڂ̍ŏd�v�ۑ�̑S�Ă��C���x�~�G���W���i�������J
2005-54771�j�̓����Z�p�����������ł��邱�������m�E�F������Ă��锤�Ɛ��������B�������A���̑����W���̃G���W
���W�̊w�ҁE���Ƃ̑S���́A�����_�i��2014�N9���j�ł́A��^�g���b�N�ɂ�����@�`�C���S���ڂ̍ŏd�v�ۑ��
�S�Ă������ł����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p�����S�ɖ����E�َE����Ă���悤�ł���B
�@�R��A���Ȃ������Ԕr�o�K�X���ψ��ψ���A����э��y��ʏȂ̔R�����ԔR�����ψ���������Ⴕ��
�͕Е��̈ψ���̈ψ��̑����W���̃G���W���W�̊w�ҁE���Ƃ́A��^�g���b�N�ɂ�����@�`�C���S���ڂ̍ŏd�v
�ۑ�̑S�Ă������ł����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p��@���Ȃ铮�@�E���R�ɂ���������E��
�E����Ă���̂ł��낤���B�|���R�c���Z�p���̕M�҂��א������C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z
�p�������E�َE�E�B������铮�@�E���R�́A�ȉ��̒ʂ�ł���B
�͕Е��̈ψ���̈ψ��̑����W���̃G���W���W�̊w�ҁE���Ƃ́A��^�g���b�N�ɂ�����@�`�C���S���ڂ̍ŏd�v
�ۑ�̑S�Ă������ł����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p��@���Ȃ铮�@�E���R�ɂ���������E��
�E����Ă���̂ł��낤���B�|���R�c���Z�p���̕M�҂��א������C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z
�p�������E�َE�E�B������铮�@�E���R�́A�ȉ��̒ʂ�ł���B
�� �������R A
�@���Ȃ⍑�y��ʏȂ̈ψ���̗����Ⴕ���͕Е��̈ψ��ł��鑍���W���̃G���W���W�̊w�ҁE���Ƃ́A��{
�I�Ƀf�B�[�[���G���W�����uNO���팸�v�Ɓu�R����P�v�̋Z�p�J���i���V�Z�p�̊J���j����E�ӂ�S���Ă����ɁA�����
�ő�^�g���b�N���uNO���팸�v�Ɓu�R����P�v���ɂ߂č���ȋZ�p�J���ł��邱�Ƃ��@��̂��邲�Ƃɑ����ʂŋ�������
�Ă����o�܂�����B����ɂ�������炸�A�����_�i��2014�N9���j�ɂ������C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j
�̓����Z�p����^�g���b�N�łɂ������u�@ DPF���u�̋����Đ��̕p�x�����v�A�u�A SCR�G�}�̒ቷ�����v�A�u�BSCR�G
�}��HC��ł̉����v�A����сu�C �d�ʎԃ��[�h�R��̉��P�v���S���ڂ̍ŏd�v�ۑ�������ł��邱�ƗB��̋Z�p�ł�
�邱�Ƃ𑽂��ɐl���m��Ƃ���ƂȂ�A���Ȃ⍑�y��ʏȂ̈ψ��ł��鑍���W���̃G���W���W�̊w�ҁE����
�́A�����J���̔\�͂��|���R�c���Z�p���̕M�҂ɔ�ׂė���Ă������Ƃ����炩�ƂȂ�A�����l���玸�]������A����
�Ă͊��Ȃ������Ԕr�o�K�X���ψ��ψ���⍑�y��ʏȂ̔R�����ԔR�����ψ���ɑ�����������̐M
�������Ă��Ă��܂����ꂪ����B���̂悤�ȏɂȂ邱�Ƃ����Ƃ��Ă���������������߁A���Ȃ⍑�y��ʏȂ̈�
���ł��鑍���W���̃G���W���W�̊w�ҁE���Ƃ́A���Ȍ�g�̂��߂ɁA�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j
�̓����Z�p����^�g���b�N�ɂ�����@�`�C���S���ڂ̍ŏd�v�ۑ�������ł���B��̋Z�p�ł��邱�Ƃ����Ƃ��Ă��B
������K�v������B�Ȃ��A�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p����^�g���b�N�ɂ�����@�`�C���S��
�ڂ̍ŏd�v�ۑ�������ł���B��̋Z�p�ł���Ƃ̋Z�p���̘I���́A�u�g���b�N���[�J�̐��ƁE�Z�p�ҁv�Ɓu����
�⍑�y��ʏȂ̈ψ��ł��鑍���W���̃G���W���W�̊w�ҁE���Ɓv�Ƃ̗��҂��Z�p�J���̔\�͕s����I�悷�邱��
�ɂȂ��B�p�𐢊ԂɎN�����ƂɂȂ�B�����������C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p�̉B���́A�u�g
���b�N���[�J�̐��ƁE�Z�p�ҁv�Ɓu���Ȃ⍑�y��ʏȂ̈ψ��ł��鑍���W���̃G���W���W�̊w�ҁE���Ɓv�Ƃ̗�
�҂̋��ʂ̗��v�ł��邽�߁A���҂���v�c�����āA���̓����Z�p�̔铽�ɍő���̓w�͂��X��������̂Ɛ�������
��B
�I�Ƀf�B�[�[���G���W�����uNO���팸�v�Ɓu�R����P�v�̋Z�p�J���i���V�Z�p�̊J���j����E�ӂ�S���Ă����ɁA�����
�ő�^�g���b�N���uNO���팸�v�Ɓu�R����P�v���ɂ߂č���ȋZ�p�J���ł��邱�Ƃ��@��̂��邲�Ƃɑ����ʂŋ�������
�Ă����o�܂�����B����ɂ�������炸�A�����_�i��2014�N9���j�ɂ������C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j
�̓����Z�p����^�g���b�N�łɂ������u�@ DPF���u�̋����Đ��̕p�x�����v�A�u�A SCR�G�}�̒ቷ�����v�A�u�BSCR�G
�}��HC��ł̉����v�A����сu�C �d�ʎԃ��[�h�R��̉��P�v���S���ڂ̍ŏd�v�ۑ�������ł��邱�ƗB��̋Z�p�ł�
�邱�Ƃ𑽂��ɐl���m��Ƃ���ƂȂ�A���Ȃ⍑�y��ʏȂ̈ψ��ł��鑍���W���̃G���W���W�̊w�ҁE����
�́A�����J���̔\�͂��|���R�c���Z�p���̕M�҂ɔ�ׂė���Ă������Ƃ����炩�ƂȂ�A�����l���玸�]������A����
�Ă͊��Ȃ������Ԕr�o�K�X���ψ��ψ���⍑�y��ʏȂ̔R�����ԔR�����ψ���ɑ�����������̐M
�������Ă��Ă��܂����ꂪ����B���̂悤�ȏɂȂ邱�Ƃ����Ƃ��Ă���������������߁A���Ȃ⍑�y��ʏȂ̈�
���ł��鑍���W���̃G���W���W�̊w�ҁE���Ƃ́A���Ȍ�g�̂��߂ɁA�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j
�̓����Z�p����^�g���b�N�ɂ�����@�`�C���S���ڂ̍ŏd�v�ۑ�������ł���B��̋Z�p�ł��邱�Ƃ����Ƃ��Ă��B
������K�v������B�Ȃ��A�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p����^�g���b�N�ɂ�����@�`�C���S��
�ڂ̍ŏd�v�ۑ�������ł���B��̋Z�p�ł���Ƃ̋Z�p���̘I���́A�u�g���b�N���[�J�̐��ƁE�Z�p�ҁv�Ɓu����
�⍑�y��ʏȂ̈ψ��ł��鑍���W���̃G���W���W�̊w�ҁE���Ɓv�Ƃ̗��҂��Z�p�J���̔\�͕s����I�悷�邱��
�ɂȂ��B�p�𐢊ԂɎN�����ƂɂȂ�B�����������C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p�̉B���́A�u�g
���b�N���[�J�̐��ƁE�Z�p�ҁv�Ɓu���Ȃ⍑�y��ʏȂ̈ψ��ł��鑍���W���̃G���W���W�̊w�ҁE���Ɓv�Ƃ̗�
�҂̋��ʂ̗��v�ł��邽�߁A���҂���v�c�����āA���̓����Z�p�̔铽�ɍő���̓w�͂��X��������̂Ɛ�������
��B
�� �������R B
�@��^�g���b�N�ɂ����āA���Ȃ��u�m�n����0.23�@g/kWh�̋K�������v�����{���A���y��ʏȂ��u2015�N�d�ʎԔR��
�́{�P�O���x�̌���v�̔R��K�������{�����ꍇ�A��^�g���b�N�ł��u�@ DPF���u�̋����Đ��̕p�x�����v�A�u�A SCR
�G�}�̒ቷ�����v�A�u�BSCR�G�}��HC��ł̉����v�A����сu�C �d�ʎԃ��[�h�R��̉��P�v�̂S���ڂ̍ŏd�v�ۑ��
������}�邽�߂ɂ́A�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p���̗p����K�v������B���̏ꍇ�A����
�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p�̓����������ł���2024�N�x�ȑO�Ɂu2015�N�x�d�ʎԔR���
������{10�����x�̔R�����v�Ɓu�m�n����0.23�@g/kWh��NO���K���v����^�g���b�N���K�����������{���ꂽ�ꍇ�A�g��
�b�N���[�J�́A�����̋K���ɑ�^�g���b�N��K�������邽�߂ɂ́A�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z
�p���̗p������Ȃ��B���ꂪ2024�N�x�ȑO�̏ꍇ�ɂ́A���̓����Z�p�ɂ͓����������݂��邽�߁A���̓����Z
�p�͗L���ő�^�g���b�N�ɍ̗p���邱�ƂɂȂ�B���̏�A���̓����Z�p�����ЂœƎ��ɊJ�����āu2015�N�x�d�ʎԔR��
�����{10�����x�̔R�����v�Ɓu�m�n����0.23�@g/kWh��NO���K���ւ̓K���v�����������ƌւ炵����`���邱�Ƃ��s
�\�ɂȂ�B���̂悤�ȏ́A�����̃g���b�N���[�J�̐��ƁE�Z�p�҂ɂƂ��ẮA�Z�p�J���̔\�͕s���������̎���
�����Ƃ͉]���A�p�J�̋ɂ݂ł���B��������O�ɉ�����邽�߂̍ŗǂ̎�i�E���@�́A�C���x�~�G���W���i�������J
2005-54771�j�̓�������2024�N5�������ł��邱�Ƃ܂��āA��^�g���b�N�̎g�p�ߒ����ɂ�����u2024�N�ȍ~��
2015�N�d�ʎԔR���́{�P�O���x�̌���v����сu2024�N�ȍ~�ɂm�nX��0.23�@g/kWh�܂ł̍팸�v�̂��ꂼ��̋K
�������y��ʏȂƊ��Ȃ�2024�N5���ȍ~�̎��{�ɒx�����ĖႤ�悤�ɁA�������i���u���ăg���b�N���[�J�����y
��ʏȂƊ����������Ƃł���B���ꂪ��������A���������Z�p�́A2024�N�ȍ~�̂��߂������������ł��A��
�{�̋������s�v�ɂȂ��Ď��R�ɑ�^�g���b�N�ɍ̗p���A������g���b�N���[�J�����R�C�܂܂ɔ̔��ł�������o
����̂ł���B���̂��߂ɂ́A���y��ʏȂƊ��Ȃ����ꂼ���NO���K���ƔR��K���̋������������肷��܂ŁA
�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p����^�g���b�N�ɂ�����@�`�C���S���ڂ̍ŏd�v�ۑ��������
����Ƃ̋Z�p�����B���������A��^�g���b�N�ɂ�����u2015�N�d�ʎԔR���́{�P�O���x�̌���v����сu�m�nX��0.
23�@g/kWh�܂ł̍팸�v���������邱�Ƃ�����ł�����̊ԁA�ێ����Ă������ƕK�v������B���̃g���b�N���[�J
�̗v�]�E��]�i���헪�E�d���j�𐬌������邽�߂ɂ́A���Ȃ������Ԕr�o�K�X���ψ��ψ���A����э��y��ʏ�
�������ԔR�����ψ����̗����Ⴕ���͕Е��̈ψ���̈ψ��ł��鑍���W���̃G���W���W�̊w�ҁE���Ƃ��A
�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p���E�َE��������Ƌ��ɁA��^�g���b�N�ɂ�����@�`�C���S
���ڂ̍ŏd�v�ۑ�������ł���Z�p���s���Ƃ̋Z�p����ϋɓI�Ɋg�U��������悤�ɁA�g���b�N���[�J���������
�i���u������̂Ɛ��������B
�́{�P�O���x�̌���v�̔R��K�������{�����ꍇ�A��^�g���b�N�ł��u�@ DPF���u�̋����Đ��̕p�x�����v�A�u�A SCR
�G�}�̒ቷ�����v�A�u�BSCR�G�}��HC��ł̉����v�A����сu�C �d�ʎԃ��[�h�R��̉��P�v�̂S���ڂ̍ŏd�v�ۑ��
������}�邽�߂ɂ́A�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p���̗p����K�v������B���̏ꍇ�A����
�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p�̓����������ł���2024�N�x�ȑO�Ɂu2015�N�x�d�ʎԔR���
������{10�����x�̔R�����v�Ɓu�m�n����0.23�@g/kWh��NO���K���v����^�g���b�N���K�����������{���ꂽ�ꍇ�A�g��
�b�N���[�J�́A�����̋K���ɑ�^�g���b�N��K�������邽�߂ɂ́A�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z
�p���̗p������Ȃ��B���ꂪ2024�N�x�ȑO�̏ꍇ�ɂ́A���̓����Z�p�ɂ͓����������݂��邽�߁A���̓����Z
�p�͗L���ő�^�g���b�N�ɍ̗p���邱�ƂɂȂ�B���̏�A���̓����Z�p�����ЂœƎ��ɊJ�����āu2015�N�x�d�ʎԔR��
�����{10�����x�̔R�����v�Ɓu�m�n����0.23�@g/kWh��NO���K���ւ̓K���v�����������ƌւ炵����`���邱�Ƃ��s
�\�ɂȂ�B���̂悤�ȏ́A�����̃g���b�N���[�J�̐��ƁE�Z�p�҂ɂƂ��ẮA�Z�p�J���̔\�͕s���������̎���
�����Ƃ͉]���A�p�J�̋ɂ݂ł���B��������O�ɉ�����邽�߂̍ŗǂ̎�i�E���@�́A�C���x�~�G���W���i�������J
2005-54771�j�̓�������2024�N5�������ł��邱�Ƃ܂��āA��^�g���b�N�̎g�p�ߒ����ɂ�����u2024�N�ȍ~��
2015�N�d�ʎԔR���́{�P�O���x�̌���v����сu2024�N�ȍ~�ɂm�nX��0.23�@g/kWh�܂ł̍팸�v�̂��ꂼ��̋K
�������y��ʏȂƊ��Ȃ�2024�N5���ȍ~�̎��{�ɒx�����ĖႤ�悤�ɁA�������i���u���ăg���b�N���[�J�����y
��ʏȂƊ����������Ƃł���B���ꂪ��������A���������Z�p�́A2024�N�ȍ~�̂��߂������������ł��A��
�{�̋������s�v�ɂȂ��Ď��R�ɑ�^�g���b�N�ɍ̗p���A������g���b�N���[�J�����R�C�܂܂ɔ̔��ł�������o
����̂ł���B���̂��߂ɂ́A���y��ʏȂƊ��Ȃ����ꂼ���NO���K���ƔR��K���̋������������肷��܂ŁA
�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p����^�g���b�N�ɂ�����@�`�C���S���ڂ̍ŏd�v�ۑ��������
����Ƃ̋Z�p�����B���������A��^�g���b�N�ɂ�����u2015�N�d�ʎԔR���́{�P�O���x�̌���v����сu�m�nX��0.
23�@g/kWh�܂ł̍팸�v���������邱�Ƃ�����ł�����̊ԁA�ێ����Ă������ƕK�v������B���̃g���b�N���[�J
�̗v�]�E��]�i���헪�E�d���j�𐬌������邽�߂ɂ́A���Ȃ������Ԕr�o�K�X���ψ��ψ���A����э��y��ʏ�
�������ԔR�����ψ����̗����Ⴕ���͕Е��̈ψ���̈ψ��ł��鑍���W���̃G���W���W�̊w�ҁE���Ƃ��A
�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p���E�َE��������Ƌ��ɁA��^�g���b�N�ɂ�����@�`�C���S
���ڂ̍ŏd�v�ۑ�������ł���Z�p���s���Ƃ̋Z�p����ϋɓI�Ɋg�U��������悤�ɁA�g���b�N���[�J���������
�i���u������̂Ɛ��������B
�@������A�u�g���b�N���[�J�̐��ƁE�Z�p�ҁv�Ɓu���Ȃ⍑�y��ʏȂ̈ψ��ł��鑍���W���̃G���W���W�̊w�ҁE��
��Ɓv�́A���ɁA�|���R�c���Z�p���̕M�҂��o�肵���C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p����^�g��
�b�N�ɂ�����@�`�C���S���ڂ̍ŏd�v�ۑ�������ł���B��̋Z�p�ł��邱�Ƃ�I�����Ă��܂��ƁA���҂̋Z�p�J����
�\�͕s����I�悷�邱�ƂɂȂ��A���Ԃɒp���N�����ƂɂȂ�B���̂悤�ȏɂȂ邱�Ƃ����O�ɉ�����邽�߂ɂ́A
�����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p����^�g���b�N�̇@�`�C���S���ڂ̍ŏd�v�ۑ�������ł�
��B��̋Z�p�ł��邱�Ƃ��������̏�������2024�N�x�܂��B�����邱�Ƃł���B
��Ɓv�́A���ɁA�|���R�c���Z�p���̕M�҂��o�肵���C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p����^�g��
�b�N�ɂ�����@�`�C���S���ڂ̍ŏd�v�ۑ�������ł���B��̋Z�p�ł��邱�Ƃ�I�����Ă��܂��ƁA���҂̋Z�p�J����
�\�͕s����I�悷�邱�ƂɂȂ��A���Ԃɒp���N�����ƂɂȂ�B���̂悤�ȏɂȂ邱�Ƃ����O�ɉ�����邽�߂ɂ́A
�����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p����^�g���b�N�̇@�`�C���S���ڂ̍ŏd�v�ۑ�������ł�
��B��̋Z�p�ł��邱�Ƃ��������̏�������2024�N�x�܂��B�����邱�Ƃł���B
�@�@���̂Ȃ�A���ɓ�������2024�N�x�������Ă��邽�߂ɁA���̓����Z�p������������������2024�N�x�ȍ~�ɐ�
�Y������e�g���b�N���[�J����^�g���b�N�ɂ́A���̓����Z�p�����Ђ̑�^�g���b�N�Ɏ��R�ɍ̗p���邱�Ƃ��\�ƂȂ�B
�����āA���������Z�p�̓�������2024�N�x�������Ă��邽�߂ɁA���������Z�p���e�g���b�N���[�J����^�g���b�N����
���Ŏ��R�ɍ̗p�ł��邽�߁A���̓������̏������������Z�p�ɂ��ẮA�l�Ď҂̑��݂����Ӗ��ƂȂ�B��������
�āA���̓������̏��������C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p�́A�N�����u�������������Z�p�v�܂�
�́u�������o�����Z�p�v�̂悤�ȈӖ��s���ȓ��e��吺�ŋ��ׂA�N�ł��C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j��
�����Z�p�́u���l�ҁv�ɂȂ邱�Ƃ��ł���ɂȂ�B���̂��߁A�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓���
�Z�p�̍l�Ăɑ��āu�g���b�N���[�J�̐��ƁE�Z�p�ҁv�Ɓu���Ȃ⍑�y��ʏȂ̈ψ��ł��鑍���W���̃G���W���W
�̊w�ҁE���Ɓv�̒N�����֗^���Ă��Ȃ����Ƃɂ��ẮA�N�������E�S�������Ƃ������Ȃ锤�ƍl������B
�Y������e�g���b�N���[�J����^�g���b�N�ɂ́A���̓����Z�p�����Ђ̑�^�g���b�N�Ɏ��R�ɍ̗p���邱�Ƃ��\�ƂȂ�B
�����āA���������Z�p�̓�������2024�N�x�������Ă��邽�߂ɁA���������Z�p���e�g���b�N���[�J����^�g���b�N����
���Ŏ��R�ɍ̗p�ł��邽�߁A���̓������̏������������Z�p�ɂ��ẮA�l�Ď҂̑��݂����Ӗ��ƂȂ�B��������
�āA���̓������̏��������C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p�́A�N�����u�������������Z�p�v�܂�
�́u�������o�����Z�p�v�̂悤�ȈӖ��s���ȓ��e��吺�ŋ��ׂA�N�ł��C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j��
�����Z�p�́u���l�ҁv�ɂȂ邱�Ƃ��ł���ɂȂ�B���̂��߁A�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓���
�Z�p�̍l�Ăɑ��āu�g���b�N���[�J�̐��ƁE�Z�p�ҁv�Ɓu���Ȃ⍑�y��ʏȂ̈ψ��ł��鑍���W���̃G���W���W
�̊w�ҁE���Ɓv�̒N�����֗^���Ă��Ȃ����Ƃɂ��ẮA�N�������E�S�������Ƃ������Ȃ锤�ƍl������B
�@���̂悤�ȏ������ɍ��o�����߂ɂ́A�g���b�N���[�J�̐��ƁE�Z�p�ҁv�Ɓu���Ȃ⍑�y��ʏȂ̈ψ��ł���
�����W���̃G���W���W�̊w�ҁE���Ɓv�́A�����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p����^�g���b
�N�ɂ�����@�`�C���S���ڂ̍ŏd�v�ۑ�������ł���B��̋Z�p�ł���Ƃ̋Z�p���2024�N�x���܂��B������K
�v������Ɛ��@�����B���̍����E���R�́A�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓�������2024�N�x�����ł�
�邽�߁A���̓����Z�p���e�g���b�N���[�J�����Ђ̑�^�g���b�N�ɖ����Ŏ��R����ɍ̗p���邱�Ƃ��\�ɂȂ�̂�
2024�N�x�ł��邽�߂��B���̂��߁A�g���b�N���[�J�̂Ƃ��đ҂��]�ޏ���������̂́A��^�g���b�N�̎g�p�ߒ���
�ɂ�����u2015�N�d�ʎԔR���́{�P�O���x�̌���v����сu�m�nX��0.23�@g/kWh�܂ł̍팸�v�̃��x���̋K�����A
2024�N5���ȍ~�̓��ʂɒx���������������y��ʏȂƊ��ɂ������m��E���肵�����_�ł���B���̏ꍇ�ɂ́A�g���b
�N���[�J�i�����{�����ԍH�Ɖ�j�́A���Ȃ⍑�y��ʏȂ̈ψ���̑����W���̃G���W���W�̊w�ҁE���Ƃ��瑽
��ȉ��b�H�E���蕨�H�������ƂɂȂ�A�ނ�ɂ͐��Ȋ��ӂ̈ӂ��\����锤�Ɛ��������B
�����W���̃G���W���W�̊w�ҁE���Ɓv�́A�����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p����^�g���b
�N�ɂ�����@�`�C���S���ڂ̍ŏd�v�ۑ�������ł���B��̋Z�p�ł���Ƃ̋Z�p���2024�N�x���܂��B������K
�v������Ɛ��@�����B���̍����E���R�́A�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓�������2024�N�x�����ł�
�邽�߁A���̓����Z�p���e�g���b�N���[�J�����Ђ̑�^�g���b�N�ɖ����Ŏ��R����ɍ̗p���邱�Ƃ��\�ɂȂ�̂�
2024�N�x�ł��邽�߂��B���̂��߁A�g���b�N���[�J�̂Ƃ��đ҂��]�ޏ���������̂́A��^�g���b�N�̎g�p�ߒ���
�ɂ�����u2015�N�d�ʎԔR���́{�P�O���x�̌���v����сu�m�nX��0.23�@g/kWh�܂ł̍팸�v�̃��x���̋K�����A
2024�N5���ȍ~�̓��ʂɒx���������������y��ʏȂƊ��ɂ������m��E���肵�����_�ł���B���̏ꍇ�ɂ́A�g���b
�N���[�J�i�����{�����ԍH�Ɖ�j�́A���Ȃ⍑�y��ʏȂ̈ψ���̑����W���̃G���W���W�̊w�ҁE���Ƃ��瑽
��ȉ��b�H�E���蕨�H�������ƂɂȂ�A�ނ�ɂ͐��Ȋ��ӂ̈ӂ��\����锤�Ɛ��������B
�@�������A���̂悤�Ȃ��Ƃ́A�����ɂ͂Ƃ��Ă͕s���v�E���f���r���������Ƃł���B���̂Ȃ�A�����C���x�~�G���W��
�i�������J2005-54771�j�́A��^�g���b�N���@�`�C���S���ڂ̍ŏd�v�ۑ�������_�ő����ɉ����ł���@�\�E
���\�����邽�߁A�u2015�N�x�d�ʎԔR������{10�����x�̔R�����v�Ɓu�m�n����0.23�@g/kWh��NO���K
���v�̃��x���̋K���ɓK��������^�g���b�N��2020�N�x���Ɏs�̂��邱�Ƃ��\�ɂ��������Z�p�ł���B����
�ɂ�������炸�A���Ȃ⍑�y��ʏȂ̈ψ��ł��鑍���W���̃G���W���W�̊w�ҁE���Ƃ��C���x�~�G���W���i��
�����J2005-54771�j���Z�p��������������E�َE�E�B�����������ꍇ�A��^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W���́uNO����
�팸�v�Ɓu�d�ʎԃ��[�h�R��̉��P�v�̋Z�p�������_�ŕs���Ƃ̌��_�������ɓ����o����A���̌��ʁA��^�g���b�N��
�g�p�ߒ��Ԃ��u2015�N�d�ʎԔR���́{�P�O���x�̌���v�̔R��K�������Ɓu�m�nX��0.23�@g/kWh�v��NO���K����
���́A2024�N�ȍ~�̎��{���~�ޓ��Ȃ��Ƃ̌��_�������o����邱�ƂɂȂ�B
�i�������J2005-54771�j�́A��^�g���b�N���@�`�C���S���ڂ̍ŏd�v�ۑ�������_�ő����ɉ����ł���@�\�E
���\�����邽�߁A�u2015�N�x�d�ʎԔR������{10�����x�̔R�����v�Ɓu�m�n����0.23�@g/kWh��NO���K
���v�̃��x���̋K���ɓK��������^�g���b�N��2020�N�x���Ɏs�̂��邱�Ƃ��\�ɂ��������Z�p�ł���B����
�ɂ�������炸�A���Ȃ⍑�y��ʏȂ̈ψ��ł��鑍���W���̃G���W���W�̊w�ҁE���Ƃ��C���x�~�G���W���i��
�����J2005-54771�j���Z�p��������������E�َE�E�B�����������ꍇ�A��^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W���́uNO����
�팸�v�Ɓu�d�ʎԃ��[�h�R��̉��P�v�̋Z�p�������_�ŕs���Ƃ̌��_�������ɓ����o����A���̌��ʁA��^�g���b�N��
�g�p�ߒ��Ԃ��u2015�N�d�ʎԔR���́{�P�O���x�̌���v�̔R��K�������Ɓu�m�nX��0.23�@g/kWh�v��NO���K����
���́A2024�N�ȍ~�̎��{���~�ޓ��Ȃ��Ƃ̌��_�������o����邱�ƂɂȂ�B
�@���������A���Ȃ⍑�y��ʏȂ̈ψ��ł��鑍���W���̃G���W���W�̊w�ҁE���Ƃ́A���������ł��邽�߁A��
�^�g���b�N�́uNO���̍팸�v�Ɓu�d�ʎԃ��[�h�R��̉��P�v�ɗL�����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z
�p�̋Z�p�����Ӑ}�I�ɖ����E�َE�E�B�����ē��{�̎����Ԃɂ����鏫���́uNO���̋K���v�Ɓu�R��K���i���R���
���j�v�̋K�������́u�����i���������郌�x���j�̐ݒ�v�Ɓu���{�����̐ݒ�v�����邱�Ƃ��֎~����Ă��锤�ł���B��
�������āA���Ȃ⍑�y��ʏȂ̈ψ���̑����W���̃G���W���W�̊w�ҁE���Ƃ��A�C���x�~�G���W���i�������J
2005-54771�j�̖����E�َE�E�B�����ē��{�̎����Ԃɂ����鏫���́uNO���̋K���v�Ɓu�R��K���i���R���j�v�̋K��
�����̓��e��ݒ肵���ꍇ�́A���炩�E���K��Ɉᔽ���邱�ƂɂȂ�ƍl������B���̂Ȃ�A��^�g���b�N���uNO��
�팸�v�Ɓu�R����P�v�ɗL�����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p�����E�َE�E�B�����Ĝ��ӓI�ɓ�
�{�̎����Ԃɂ����鏫���́uNO���̋K���v�Ɓu�R��K���i���R���j�v�̋K�������̓��e��ݒ肵���ꍇ�́A������
�����ɕs�����ȋ]���������邽�߂ł���B
�^�g���b�N�́uNO���̍팸�v�Ɓu�d�ʎԃ��[�h�R��̉��P�v�ɗL�����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z
�p�̋Z�p�����Ӑ}�I�ɖ����E�َE�E�B�����ē��{�̎����Ԃɂ����鏫���́uNO���̋K���v�Ɓu�R��K���i���R���
���j�v�̋K�������́u�����i���������郌�x���j�̐ݒ�v�Ɓu���{�����̐ݒ�v�����邱�Ƃ��֎~����Ă��锤�ł���B��
�������āA���Ȃ⍑�y��ʏȂ̈ψ���̑����W���̃G���W���W�̊w�ҁE���Ƃ��A�C���x�~�G���W���i�������J
2005-54771�j�̖����E�َE�E�B�����ē��{�̎����Ԃɂ����鏫���́uNO���̋K���v�Ɓu�R��K���i���R���j�v�̋K��
�����̓��e��ݒ肵���ꍇ�́A���炩�E���K��Ɉᔽ���邱�ƂɂȂ�ƍl������B���̂Ȃ�A��^�g���b�N���uNO��
�팸�v�Ɓu�R����P�v�ɗL�����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p�����E�َE�E�B�����Ĝ��ӓI�ɓ�
�{�̎����Ԃɂ����鏫���́uNO���̋K���v�Ɓu�R��K���i���R���j�v�̋K�������̓��e��ݒ肵���ꍇ�́A������
�����ɕs�����ȋ]���������邽�߂ł���B
�@����A���{�̎����Ԃɂ����鏫���́uNO���̋K���v�Ɓu�R��K���i���R���j�v�̋K��������ݒ肷��ۂɁA����
�⍑�y��ʏȂ̈ψ���̑����W���̃G���W���W�̊w�ҁE���Ƃ��A�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓�
���Z�p���E�َE�E�B�������̂��ۂ��f�����Ƃ��āA�|���R�c���Z�p���̕M�҂̌����������ȉ��Ɏ����B
�⍑�y��ʏȂ̈ψ���̑����W���̃G���W���W�̊w�ҁE���Ƃ��A�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓�
���Z�p���E�َE�E�B�������̂��ۂ��f�����Ƃ��āA�|���R�c���Z�p���̕M�҂̌����������ȉ��Ɏ����B
�� �C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̑��݂��l������������NO���ƔR��̋K��������ݒ�
�@�@��^�g���b�N�̎g�p�ߒ��Ԃ́A�u2015�N�x�d�ʎԔR������{10�����x�̔R�����v�Ɓu�m�n����0.23�@g/kWh
�@�@��NO���K���v�ւ̋K�������� 2020�N�x���̎��{�Ɨ\�������B
�� �C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̑��݂������E�َE���Ď�����NO���ƔR��̋K��������ݒ�
�@�@��^�g���b�N�̎g�p�ߒ��Ԃ́A�u2015�N�x�d�ʎԔR������{10�����x�̔R�����v�Ɓu�m�n����0.23�@g/kWh
�@�@��NO���K���v�ւ̋K�������� 202�S�N�x���̎��{�Ɨ\�������B
�@�ȏ�̂悤�ɁA�u2015�N�x�d�ʎԔR������{10�����x�̔R�����v�Ɓu�m�n����0.23�@g/kWh��NO���K���v�ւ̋K
�������̎������u2020�N�x���v�ł���̂��A����Ƃ��u2024�N�x���v�ł���̂��̑���ɂ���āA���Ȃ�NO���K��
�����Ɍg��������Ԕr�o�K�X���ψ��ψ���A����э��y��ʏȂ̔R��K�������Ɍg��������ԔR�����ψ�
����G���W���W�̊w�ҁE���Ƃ̂W���i�����̈ψ���A�Ⴕ���͕Е��̈ψ���̈ψ��ɔC������Ă���l���j���A�C
���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p���E�َE�E�B�������̂��ۂ��f���邱�Ƃ��\�ƍl�����
��B
�������̎������u2020�N�x���v�ł���̂��A����Ƃ��u2024�N�x���v�ł���̂��̑���ɂ���āA���Ȃ�NO���K��
�����Ɍg��������Ԕr�o�K�X���ψ��ψ���A����э��y��ʏȂ̔R��K�������Ɍg��������ԔR�����ψ�
����G���W���W�̊w�ҁE���Ƃ̂W���i�����̈ψ���A�Ⴕ���͕Е��̈ψ���̈ψ��ɔC������Ă���l���j���A�C
���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p���E�َE�E�B�������̂��ۂ��f���邱�Ƃ��\�ƍl�����
��B
�@���̂Ƃ���A���Ȃ������Ԕr�o�K�X���ψ��ψ���ƁA���y��ʏȂ������ԔR�����ψ���̗����̈ψ���
���鑁��c��w�E���������́A��^�g���b�N�ɂ������u�@ DPF���u�̋����Đ��̕p�x�����v�A�u�A SCR�G�}�̒ቷ��
���v�A�u�BSCR�G�}��HC��ł̉����v�A����сu�C �d�ʎԃ��[�h�R��̉��P�v�̂S���ڂ̍ŏd�v�ۑ�̑S�Ă������ł�
��B��̋Z�p�ł����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p���E�َE����Ă���B�������A�����C��
�x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p�́A������^�g���b�N�ɍ̗p�����ꍇ�ɂ��u2015�N�x�d�ʎԔR���
������{10�����x�̔R�����v�Ɓu�m�n����0.23�@g/kWh��NO���K���v�̋K���ɓK���\�ȑ�^�g���b�N�������ł���B
����Z�p�̂ł���B���̂��߁A����2004�N5��25���ɏo�肵���C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓�
���Z�p���^�g���b�N�ɍ̗p�����ꍇ�A�m�n���K���l �� 0.23 g/kWh�i���攪�����\��NO������ڕW�l�j�̋K��
���{���\���ɉ\�ƍl������B
���鑁��c��w�E���������́A��^�g���b�N�ɂ������u�@ DPF���u�̋����Đ��̕p�x�����v�A�u�A SCR�G�}�̒ቷ��
���v�A�u�BSCR�G�}��HC��ł̉����v�A����сu�C �d�ʎԃ��[�h�R��̉��P�v�̂S���ڂ̍ŏd�v�ۑ�̑S�Ă������ł�
��B��̋Z�p�ł����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p���E�َE����Ă���B�������A�����C��
�x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p�́A������^�g���b�N�ɍ̗p�����ꍇ�ɂ��u2015�N�x�d�ʎԔR���
������{10�����x�̔R�����v�Ɓu�m�n����0.23�@g/kWh��NO���K���v�̋K���ɓK���\�ȑ�^�g���b�N�������ł���B
����Z�p�̂ł���B���̂��߁A����2004�N5��25���ɏo�肵���C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓�
���Z�p���^�g���b�N�ɍ̗p�����ꍇ�A�m�n���K���l �� 0.23 g/kWh�i���攪�����\��NO������ڕW�l�j�̋K��
���{���\���ɉ\�ƍl������B
�@�Ƃ��낪�A���Ȃ������Ԕr�o�K�X���ψ��ψ���́A2010�N7��28�����\�̒������R�c��E��C�������
�u����̎����Ԕr�o�K�X�ጸ��̂�����ɂ��āi��\�����\�j�v�ɂ����āA��^�g���b�N�i���d�ʎԁj�ɑ��鎟��
��NO���K���ł́A�m�n���K���l �� 0.4 g/kWh(��2016�N�Ɏ��{�j�̕č������啝�Ɋɂ�NO���K���l�����肵�A���\�i��
�O�q���U�|�P�����Q�ƕ��j�����̂ł���B����́A�������R�c��E��C������́u��\�����\�v�ł́A2010�N6����
�������Ȃ������Ԕr�o�K�X���ψ��ψ���̃G���W�����̈ψ��i���͖쓹�������A�ѓc�P�������A�㓡�V��
�k�Ɓl�Y�����E�Z���^�[���A���H���G�����A���R�������劲�A�吹�G�����j����^�g���b�N�́uNO���팸�v�Ɓu�R���
�P�v�̗����̖ʂŗD�ꂽ�@�\�E���\�������C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p�̑��݂��E
�َE�������ʁA��^�g���b�N�i���d�ʎԁj�ɂ����Ăm�n���K���l �� 0.4 g/kWh(��2016�N�Ɏ��{�j�̊ɂ�������NO���K��
���ݒ肳�ꂽ�̂ł͂Ȃ����ƁA�|���R�c���Z�p���̕M�҂ɂ͎v���Ďd���������B���̂Ȃ�A��^�g���b�N�́uNO����
���v�Ɓu�R����P�v�̗����̖ʂŗD�ꂽ�@�\�E������B��̓����Z�p�ł����C���x�~�G���W���i�������J2005-
54771�j���E�َE���Ȃ���A�m�n���K���l �� 0.23 g/kWh�i���攪�����\��NO������ڕW�l�j�̋K�����{���\����
�\�ł������ƍl�����邽�߂ł���B
�u����̎����Ԕr�o�K�X�ጸ��̂�����ɂ��āi��\�����\�j�v�ɂ����āA��^�g���b�N�i���d�ʎԁj�ɑ��鎟��
��NO���K���ł́A�m�n���K���l �� 0.4 g/kWh(��2016�N�Ɏ��{�j�̕č������啝�Ɋɂ�NO���K���l�����肵�A���\�i��
�O�q���U�|�P�����Q�ƕ��j�����̂ł���B����́A�������R�c��E��C������́u��\�����\�v�ł́A2010�N6����
�������Ȃ������Ԕr�o�K�X���ψ��ψ���̃G���W�����̈ψ��i���͖쓹�������A�ѓc�P�������A�㓡�V��
�k�Ɓl�Y�����E�Z���^�[���A���H���G�����A���R�������劲�A�吹�G�����j����^�g���b�N�́uNO���팸�v�Ɓu�R���
�P�v�̗����̖ʂŗD�ꂽ�@�\�E���\�������C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p�̑��݂��E
�َE�������ʁA��^�g���b�N�i���d�ʎԁj�ɂ����Ăm�n���K���l �� 0.4 g/kWh(��2016�N�Ɏ��{�j�̊ɂ�������NO���K��
���ݒ肳�ꂽ�̂ł͂Ȃ����ƁA�|���R�c���Z�p���̕M�҂ɂ͎v���Ďd���������B���̂Ȃ�A��^�g���b�N�́uNO����
���v�Ɓu�R����P�v�̗����̖ʂŗD�ꂽ�@�\�E������B��̓����Z�p�ł����C���x�~�G���W���i�������J2005-
54771�j���E�َE���Ȃ���A�m�n���K���l �� 0.23 g/kWh�i���攪�����\��NO������ڕW�l�j�̋K�����{���\����
�\�ł������ƍl�����邽�߂ł���B
�@���̂悤�ɁA�����_�i��2014�N9���j�ł��A���Ȃ������Ԕr�o�K�X���ψ��ψ���ƍ��y��ʏȂ������ԔR���
�����ψ���̃G���W�����̊w�ҁE���Ƃ́A2004�N5��25���Ƀ|���R�c���Z�p���̕M�ҏo����C���x�~�G���W��
�i�������J2005-54771�j�̓����Z�p�N�ɂ킽���Ė����E�َE����Ă��邱�Ƃ͎����̂悤�ł���B�����āA���ꂩ��
���A�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p���E�َE����s�ׂ́A�p���������̂Ɛ��������B��
�̂Ȃ�A�߂������ɂ����āA���Ȃ������Ԕr�o�K�X���ψ��ψ���ƍ��y��ʏȂ������ԔR�����ψ���
�̃G���W�����̊w�ҁE���Ƃ́A���N�ɂ킽���Ė����E�َE����Ă����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j��
�����Z�p�̑��݂�ˑR�ɔF�߂āA�}篁A���̂��uNO���팸�v�Ɓu�R����P�v�̋@�\�E���\�ɗD�ꂽ�����Z�p�Ƃ��ď��F�E
�����E�^���A���̓����Z�p���^�g���b�N�ɍ̗p���邱�Ƃɂ�����u2015�N�x�d�ʎԔR������{10�����x�̔R��
����v�Ɓu�m�n����0.23�@g/kWh ��NO���K���v�̋K��������2020�N���Ɏ��{����Ɛ錾�E���\����邱�Ƃ��L�蓾�Ȃ��Ɛ�
�@����邽�߂ł���B
�����ψ���̃G���W�����̊w�ҁE���Ƃ́A2004�N5��25���Ƀ|���R�c���Z�p���̕M�ҏo����C���x�~�G���W��
�i�������J2005-54771�j�̓����Z�p�N�ɂ킽���Ė����E�َE����Ă��邱�Ƃ͎����̂悤�ł���B�����āA���ꂩ��
���A�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p���E�َE����s�ׂ́A�p���������̂Ɛ��������B��
�̂Ȃ�A�߂������ɂ����āA���Ȃ������Ԕr�o�K�X���ψ��ψ���ƍ��y��ʏȂ������ԔR�����ψ���
�̃G���W�����̊w�ҁE���Ƃ́A���N�ɂ킽���Ė����E�َE����Ă����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j��
�����Z�p�̑��݂�ˑR�ɔF�߂āA�}篁A���̂��uNO���팸�v�Ɓu�R����P�v�̋@�\�E���\�ɗD�ꂽ�����Z�p�Ƃ��ď��F�E
�����E�^���A���̓����Z�p���^�g���b�N�ɍ̗p���邱�Ƃɂ�����u2015�N�x�d�ʎԔR������{10�����x�̔R��
����v�Ɓu�m�n����0.23�@g/kWh ��NO���K���v�̋K��������2020�N���Ɏ��{����Ɛ錾�E���\����邱�Ƃ��L�蓾�Ȃ��Ɛ�
�@����邽�߂ł���B
�@�����āA���Ȃ������Ԕr�o�K�X���ψ��ψ���ƍ��y��ʏȂ������ԔR�����ψ���̃G���W�����
�������W���w�ҁE���Ƃ́A����A�����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p�̗̍p��K�v��
���鏫���̑�^�g���b�N�̎g�p�ߒ��Ԃ́uNO���K���v�Ɓu�R���i���R��K���j�v�̋����ɂ��ẮA���̓���
�Z�p�̓������̏��ł���2024�N5���ȍ~�̎��{�Ƃ��邱�ƂɌ��肷����̂Ɛ��������B���̂悤�ɁA���ɁA��
�{�ɂ����鍡��̑�^�g���b�N�́uNO���K���v�Ɓu�R���i���K���j�v�̋������A���̐����̒ʂ��2024�N5��
�ȍ~�ƂȂ�A���Ȃ������Ԕr�o�K�X���ψ��ψ���ƍ��y��ʏȂ������ԔR�����ψ���̃G���W
�����̊w�ҁE���Ƃ́A�g���b�N���[�J�i�����{�����ԍH�Ɖ�j�̗v�]�ɉ������K�����e�Ƃ��邽�߂ɐE����
���s���Ă���悤�Ɍ��������A����̓|���R�c���Z�p���̕M�҂̒P�Ȃ�Ό��ł��낤���B
�������W���w�ҁE���Ƃ́A����A�����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p�̗̍p��K�v��
���鏫���̑�^�g���b�N�̎g�p�ߒ��Ԃ́uNO���K���v�Ɓu�R���i���R��K���j�v�̋����ɂ��ẮA���̓���
�Z�p�̓������̏��ł���2024�N5���ȍ~�̎��{�Ƃ��邱�ƂɌ��肷����̂Ɛ��������B���̂悤�ɁA���ɁA��
�{�ɂ����鍡��̑�^�g���b�N�́uNO���K���v�Ɓu�R���i���K���j�v�̋������A���̐����̒ʂ��2024�N5��
�ȍ~�ƂȂ�A���Ȃ������Ԕr�o�K�X���ψ��ψ���ƍ��y��ʏȂ������ԔR�����ψ���̃G���W
�����̊w�ҁE���Ƃ́A�g���b�N���[�J�i�����{�����ԍH�Ɖ�j�̗v�]�ɉ������K�����e�Ƃ��邽�߂ɐE����
���s���Ă���悤�Ɍ��������A����̓|���R�c���Z�p���̕M�҂̒P�Ȃ�Ό��ł��낤���B
�@�����Ƃ��A���Ȃ������Ԕr�o�K�X���ψ��ψ���ƍ��y��ʏȂ������ԔR�����ψ���̃G���W����
��������W���̏����i���͖쓹�������A���H���G�����A�吹�G�����A�ѓc�P�������A���������ް���
ђ��A���������A�㓡�Y�괸è�ށE�Ʊ�Eػ�����A�ߋv���������j�́A��������{���\���閼������w
�ҁE���Ƃł��邽�߁A�|���R�c���Z�p���ł���M�ҏo����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓���
�Z�p�ɂ͐�w�ɍ˂̕M�҂ɂ͋C�t���Ȃ����Z�p�ł��邱�Ƃ��s����������Ă���ꍇ��A�Ⴕ���͂��̓���
�Z�p�𗽉킷��V�Z�p�̋Z�p����ۗL����Ă���ꍇ���l������B
��������W���̏����i���͖쓹�������A���H���G�����A�吹�G�����A�ѓc�P�������A���������ް���
ђ��A���������A�㓡�Y�괸è�ށE�Ʊ�Eػ�����A�ߋv���������j�́A��������{���\���閼������w
�ҁE���Ƃł��邽�߁A�|���R�c���Z�p���ł���M�ҏo����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓���
�Z�p�ɂ͐�w�ɍ˂̕M�҂ɂ͋C�t���Ȃ����Z�p�ł��邱�Ƃ��s����������Ă���ꍇ��A�Ⴕ���͂��̓���
�Z�p�𗽉킷��V�Z�p�̋Z�p����ۗL����Ă���ꍇ���l������B
�� �C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p�����Z�p�ł��邱�Ƃ��s����������Ă���ꍇ
�@
�@���̏ꍇ�ɂ́A���Ȃ������Ԕr�o�K�X���ψ��ψ���ƍ��y��ʏȂ������ԔR�����ψ���A���̓���
�Z�p���E�َE���A�������^�g���b�N�̎g�p�ߒ��Ԃ��u2015�N�x�d�ʎԔR������{10�����x�̔R���
��v�Ɓu�m�n����0.23�@g/kWh ��NO���K���v���K��������2024�N5���ȍ~�ɐݒ�����邱�Ƃ́A�S�������Ȃ��Ƃł�
��A���ɁA���R�̂��Ƃł���B
�Z�p���E�َE���A�������^�g���b�N�̎g�p�ߒ��Ԃ��u2015�N�x�d�ʎԔR������{10�����x�̔R���
��v�Ɓu�m�n����0.23�@g/kWh ��NO���K���v���K��������2024�N5���ȍ~�ɐݒ�����邱�Ƃ́A�S�������Ȃ��Ƃł�
��A���ɁA���R�̂��Ƃł���B
�� �C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p�𗽉킷��V�Z�p�̋Z�p����ۗL�̏ꍇ
�@
�@���̏ꍇ�ɂ́A���Ȃ������Ԕr�o�K�X���ψ��ψ���ƍ��y��ʏȂ������ԔR�����ψ���A���̓���
�Z�p���E�َE���A�������^�g���b�N�̎g�p�ߒ��Ԃ��u2015�N�x�d�ʎԔR������{10�����x�̔R���
��v�Ɓu�m�n����0.23�@g/kWh ��NO���K���v���K��������2020�N���ɐݒ�����đR��ׂ��ł��B
�Z�p���E�َE���A�������^�g���b�N�̎g�p�ߒ��Ԃ��u2015�N�x�d�ʎԔR������{10�����x�̔R���
��v�Ɓu�m�n����0.23�@g/kWh ��NO���K���v���K��������2020�N���ɐݒ�����đR��ׂ��ł��B
�i���̂Ȃ�A�č������ɂ���^�g���b�N��NO���K�����{�s����������{���{�̑Ӗ��ɏڏq���Ă���悤�ɁA���ɁA��
���̑�^�g���b�N�ł́A2010�N���m�n����0.27 g/kWh�̌��������s���Ă���B����ɑ��A2016�N�Ɏ��{���\�肳���
������{�̑�^�g���b�N�ł̎����m�n���K���ł́ANO�� �� 0.4 g/kWh�̊ɂ��K�����\�肳��Ă���B�j
���̑�^�g���b�N�ł́A2010�N���m�n����0.27 g/kWh�̌��������s���Ă���B����ɑ��A2016�N�Ɏ��{���\�肳���
������{�̑�^�g���b�N�ł̎����m�n���K���ł́ANO�� �� 0.4 g/kWh�̊ɂ��K�����\�肳��Ă���B�j
�@�����ŁA�����_�i��2014�N10�����݁j�ɂ����āA���Ȃ̎����Ԕr�o�K�X���ψ��ψ���ƍ��y��ʏȂ̎����ԔR
�����ψ���̃G���W�����̑����W���̏����i���͖쓹�������A���H���G�����A�吹�G�����A�ѓc�P����
���A���������ް���ђ��A���������A�㓡�Y�괸è�ށE�Ʊ�Eػ�����A�ߋv���������j�́A�C���x�~�G���W��
�i�������J2005-54771�j�̓����Z�p����^�g���b�N�́uNO���팸�v�Ɓu�R����P�v�ɖ����Ȍ��Z�p�ł���Ɣ��f�E����
����Ă���ꍇ��A�Ⴕ���͂��̓����Z�p�𗽉킷��V�Z�p�̋Z�p����ێ�����Ă���ꍇ�ɂ́A���̎|�����\�E
���\���Ă��������������̂ł���B�����āA���Ȃ̎����Ԕr�o�K�X���ψ��ψ���ƍ��y��ʏȂ̎����ԔR���
�����ψ���̃G���W�����̑����W���̏������C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p����^�g���b�N
�́uNO���팸�v�Ɓu�R����P�v�ɖ����Ȍ��Z�p�ł���Ɣ��f�E���肳�ꂽ���R��A�Ⴕ���͂��̓����Z�p�𗽉킷��V
�Z�p�̋Z�p������e��ΊO�I�Ɍ��\�E���\���Ē����������̂ł���B����ɂ���āA�|���R�c���Z�p���ł����w
�ɍ˂̕M�҂ɂ́A���Ȃƍ��y��ʏȂ̏��ψ���̃G���W�����̑����W���̏��������̓����Z�p�̈Ӑ}�I�Ȗ�
���E�َE�E�B�����s���Ă���Ƃ̕M�҂̌����ɑ傫�Ȍ��ł��������Ƃ����߂ė����ł��邱�ƂɂȂ�B
�����ψ���̃G���W�����̑����W���̏����i���͖쓹�������A���H���G�����A�吹�G�����A�ѓc�P����
���A���������ް���ђ��A���������A�㓡�Y�괸è�ށE�Ʊ�Eػ�����A�ߋv���������j�́A�C���x�~�G���W��
�i�������J2005-54771�j�̓����Z�p����^�g���b�N�́uNO���팸�v�Ɓu�R����P�v�ɖ����Ȍ��Z�p�ł���Ɣ��f�E����
����Ă���ꍇ��A�Ⴕ���͂��̓����Z�p�𗽉킷��V�Z�p�̋Z�p����ێ�����Ă���ꍇ�ɂ́A���̎|�����\�E
���\���Ă��������������̂ł���B�����āA���Ȃ̎����Ԕr�o�K�X���ψ��ψ���ƍ��y��ʏȂ̎����ԔR���
�����ψ���̃G���W�����̑����W���̏������C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p����^�g���b�N
�́uNO���팸�v�Ɓu�R����P�v�ɖ����Ȍ��Z�p�ł���Ɣ��f�E���肳�ꂽ���R��A�Ⴕ���͂��̓����Z�p�𗽉킷��V
�Z�p�̋Z�p������e��ΊO�I�Ɍ��\�E���\���Ē����������̂ł���B����ɂ���āA�|���R�c���Z�p���ł����w
�ɍ˂̕M�҂ɂ́A���Ȃƍ��y��ʏȂ̏��ψ���̃G���W�����̑����W���̏��������̓����Z�p�̈Ӑ}�I�Ȗ�
���E�َE�E�B�����s���Ă���Ƃ̕M�҂̌����ɑ傫�Ȍ��ł��������Ƃ����߂ė����ł��邱�ƂɂȂ�B
�@�X�ɁA�M�҂̌l�I�Ȋ�]�����킹�ĖႦ�A���Ȃ̎����Ԕr�o�K�X���ψ��ψ���ƍ��y��ʏȂ̎�����
�R�����ψ���̃G���W�����̑����W���̏�����A�Ⴕ���͑㗝�̕��ł��ǂ����A�����C���x�~�G���W���i����
���J2005-54771�j�̓����Z�p�̌��ד��e��A���̓����Z�p�𗽉킷��V�Z�p�̋Z�p���i���C���^�[�l�b�g��URL��
���j��M�҈��Ƀ��[�����M���Ă������������Ƃ���ł���B��������A�����C���x�~�G���W���i�������J2005-
54771�j�̓����Z�p��������^�g���b�N�ɂ�����@�`�C���S���ڂ̍ŏd�v�ۑ�������ł���B��̋Z�p�ł��邷��M
�҂̎咣�́A���S�Ȍ��ł��邱�Ƃ𗝉��E�[���ł��锤�ł���B�������A�����C���x�~�G���W���i�������J2005-
54771�j�̓����Z�p�̌��ד��e��A�Ⴕ���͂��̓����Z�p�𗽉킷��V�Z�p�̋Z�p����M�҂Ɍ�A������
�����Ȃ��ꍇ�́A���Ȃ̎����Ԕr�o�K�X���ψ��ψ���ƍ��y��ʏȂ̎����ԔR�����ψ���̃G��
�W�����̑����W���̏������A���̓����Z�p�̈Ӑ}�I�Ȗ����E�َE�E�B�����s���Ă���Ɖi���ɔ��f�E����
�����Ă������������ł���B
�R�����ψ���̃G���W�����̑����W���̏�����A�Ⴕ���͑㗝�̕��ł��ǂ����A�����C���x�~�G���W���i����
���J2005-54771�j�̓����Z�p�̌��ד��e��A���̓����Z�p�𗽉킷��V�Z�p�̋Z�p���i���C���^�[�l�b�g��URL��
���j��M�҈��Ƀ��[�����M���Ă������������Ƃ���ł���B��������A�����C���x�~�G���W���i�������J2005-
54771�j�̓����Z�p��������^�g���b�N�ɂ�����@�`�C���S���ڂ̍ŏd�v�ۑ�������ł���B��̋Z�p�ł��邷��M
�҂̎咣�́A���S�Ȍ��ł��邱�Ƃ𗝉��E�[���ł��锤�ł���B�������A�����C���x�~�G���W���i�������J2005-
54771�j�̓����Z�p�̌��ד��e��A�Ⴕ���͂��̓����Z�p�𗽉킷��V�Z�p�̋Z�p����M�҂Ɍ�A������
�����Ȃ��ꍇ�́A���Ȃ̎����Ԕr�o�K�X���ψ��ψ���ƍ��y��ʏȂ̎����ԔR�����ψ���̃G��
�W�����̑����W���̏������A���̓����Z�p�̈Ӑ}�I�Ȗ����E�َE�E�B�����s���Ă���Ɖi���ɔ��f�E����
�����Ă������������ł���B
�@�Ƃ���ŁA���{�ōŏ��Ƀf�B�[�[���Ԃ�NO���K�����{�s���ꂽ1974�N�̓������猻�݂Ɏ���܂�40�N�Ԃɂ킽��
�āA���{�̃G���W���W�̊w�ҁE���Ƃ́A�u�f�B�[�[���G���W����NO���팸�ƔR����P�̃g���[�h�I�t�̊W�v�̂���
��NO���ƔR����ɉ��P���邱�Ƃ��Z�p�I�ɍ���v�ł���ƈ�т��Ď咣����Ă��邪�A���̏͌��݁i��2014�N
9���j�ł��傫�ȕω��E�ύX�������Ȃ��悤�ł���B�Ƃ��낪���ۂɂ́A�O�q�̒ʂ�A���́u�f�B�[�[���G���W����NO��
�팸�ƔR����P�̃g���[�h�I�t�̊W�v�́A�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p�̗̍p�ɂ���đ�^
�g���b�N�́uNO���팸�v�Ɓu�R����P�v�̗������Ɏ����ł��邱�Ƃ����炩�ɂȂ����Ă���B�������A�����u�f�B�[�[��
�G���W����NO���팸�ƔR����P�̃g���[�h�I�t�v�̉ۑ肪�����ł��邱�Ƃ́A�O�q�̂悤�ɁA���Ȃ̎����Ԕr�o�K�X
���ψ��ψ���̃G���W�����̊w�ҁE���Ƃ�2009�N6���`2010�N2�����ɂ͊��ɏ��m�E�l������Ă���̂ł�
��B
�āA���{�̃G���W���W�̊w�ҁE���Ƃ́A�u�f�B�[�[���G���W����NO���팸�ƔR����P�̃g���[�h�I�t�̊W�v�̂���
��NO���ƔR����ɉ��P���邱�Ƃ��Z�p�I�ɍ���v�ł���ƈ�т��Ď咣����Ă��邪�A���̏͌��݁i��2014�N
9���j�ł��傫�ȕω��E�ύX�������Ȃ��悤�ł���B�Ƃ��낪���ۂɂ́A�O�q�̒ʂ�A���́u�f�B�[�[���G���W����NO��
�팸�ƔR����P�̃g���[�h�I�t�̊W�v�́A�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p�̗̍p�ɂ���đ�^
�g���b�N�́uNO���팸�v�Ɓu�R����P�v�̗������Ɏ����ł��邱�Ƃ����炩�ɂȂ����Ă���B�������A�����u�f�B�[�[��
�G���W����NO���팸�ƔR����P�̃g���[�h�I�t�v�̉ۑ肪�����ł��邱�Ƃ́A�O�q�̂悤�ɁA���Ȃ̎����Ԕr�o�K�X
���ψ��ψ���̃G���W�����̊w�ҁE���Ƃ�2009�N6���`2010�N2�����ɂ͊��ɏ��m�E�l������Ă���̂ł�
��B
�@���̂悤�ɁA����2009�N6���`2010�N2�����ɂ́A�f�B�[�[���G���W���ɂ�����NO���ƔR��̃g���[�h�I�t�̉ۑ肪��
���ł����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j���̗p������^�g���b�N�́uNO���팸�v�Ɓu�R����P�v�������Ɏ���
�ł��邱�Ƃ��L���m���Ă��锤�ł���B����ɂ�������炸�A2011�N9�����s�́u�����ԋZ�p�v���iVol.65,No.9,2011)��
�u�����ԗp�G���W���Z�p�J���̌���Ə����v�Ƒ肵���_���́u3.2.�@�d�ʎԂ̔R����P�v�̍��ɂ����āA���̘_���̒���
�ł���A�����Ȃ̎����Ԕr�o�K�X���ψ��ψ���ƍ��y��ʏȂ̎����ԔR�����ψ���̈ψ��ł��鑁��
�c��w�̑吹�����́A�d�ʎԁi���f�B�[�[���g���b�N�E�o�X�j�ɂ�����w2016�N�̔r�o�K�X�K���ւ̓K���x�Ɓw2015�N�x
�d�ʎԔR���ւ̓K���x�̃g���[�h�I�t�̍������K�v�ł���Əq�ׂ��Ă���B�܂�A����c��w�̑吹�����́A
2011�N9�����s�́u�����ԋZ�p�v���ɂ����āA�u�f�B�[�[���G���W����NO���팸�ƔR����P�̃g���[�h�I�t�̉ۑ肪����
�ł���Z�p�͖��J���v�Ƃ����|�̎咣���q�ׂ��Ă���B���̂��Ƃ́A2011�N9���̎��_�ł́A����c��w�̑吹��
�����f�B�[�[���G���W����NO���팸�ƔR����P�̃g���[�h�I�t�̉ۑ肪�����ł����C���x�~�G���W���i�������J2005-
54771�j�̓����Z�p�̑��݂����S�ɖ����E�َE����Ă������Ƃm�Ɏ������؋��ƍl������B
���ł����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j���̗p������^�g���b�N�́uNO���팸�v�Ɓu�R����P�v�������Ɏ���
�ł��邱�Ƃ��L���m���Ă��锤�ł���B����ɂ�������炸�A2011�N9�����s�́u�����ԋZ�p�v���iVol.65,No.9,2011)��
�u�����ԗp�G���W���Z�p�J���̌���Ə����v�Ƒ肵���_���́u3.2.�@�d�ʎԂ̔R����P�v�̍��ɂ����āA���̘_���̒���
�ł���A�����Ȃ̎����Ԕr�o�K�X���ψ��ψ���ƍ��y��ʏȂ̎����ԔR�����ψ���̈ψ��ł��鑁��
�c��w�̑吹�����́A�d�ʎԁi���f�B�[�[���g���b�N�E�o�X�j�ɂ�����w2016�N�̔r�o�K�X�K���ւ̓K���x�Ɓw2015�N�x
�d�ʎԔR���ւ̓K���x�̃g���[�h�I�t�̍������K�v�ł���Əq�ׂ��Ă���B�܂�A����c��w�̑吹�����́A
2011�N9�����s�́u�����ԋZ�p�v���ɂ����āA�u�f�B�[�[���G���W����NO���팸�ƔR����P�̃g���[�h�I�t�̉ۑ肪����
�ł���Z�p�͖��J���v�Ƃ����|�̎咣���q�ׂ��Ă���B���̂��Ƃ́A2011�N9���̎��_�ł́A����c��w�̑吹��
�����f�B�[�[���G���W����NO���팸�ƔR����P�̃g���[�h�I�t�̉ۑ肪�����ł����C���x�~�G���W���i�������J2005-
54771�j�̓����Z�p�̑��݂����S�ɖ����E�َE����Ă������Ƃm�Ɏ������؋��ƍl������B
�@�܂��A2010�N7���̒������R�c��E��C����́u��\�����\�v�ł́A2016�N���{�̑�^�g���b�N��NO���K��������
�����ẮA�u2015�N�d�ʎԔR���̋K���̑��݁v�Ɓu�f�B�[�[���G���W����NO���팸�ƔR����P�̃g���[�h�I�t�̖�
�����ȉۑ�v�𗝗R�ɋ����āA���Ȃ̎����Ԕr�o�K�X���ψ��ψ���̃G���W�����̊w�ҁE���Ƃ́A�m�n�� ��
0.23 g/kWh�i���攪�����\��NO������ڕW�l�j�܂ł̌�����NO���K���̋���������ƌ��߂��A�m�n���K���l �� 0.4 g
/kWh�i��2016�N���{�j�̑�^�g���b�N�ɂ�����ɂ�NO���K���̋��������肵���̂ł���B����́A�S�����������Ȃ�
�����Ԕr�o�K�X���ψ��ψ���̃G���W�����̊w�ҁE���Ƃ̏������C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j
�̓����Z�p���Ӑ}�I�ɖ����E�َE�E�B���������ʂƐ�������邪�A�@���Ȃ��̂ł��낤���B
�����ẮA�u2015�N�d�ʎԔR���̋K���̑��݁v�Ɓu�f�B�[�[���G���W����NO���팸�ƔR����P�̃g���[�h�I�t�̖�
�����ȉۑ�v�𗝗R�ɋ����āA���Ȃ̎����Ԕr�o�K�X���ψ��ψ���̃G���W�����̊w�ҁE���Ƃ́A�m�n�� ��
0.23 g/kWh�i���攪�����\��NO������ڕW�l�j�܂ł̌�����NO���K���̋���������ƌ��߂��A�m�n���K���l �� 0.4 g
/kWh�i��2016�N���{�j�̑�^�g���b�N�ɂ�����ɂ�NO���K���̋��������肵���̂ł���B����́A�S�����������Ȃ�
�����Ԕr�o�K�X���ψ��ψ���̃G���W�����̊w�ҁE���Ƃ̏������C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j
�̓����Z�p���Ӑ}�I�ɖ����E�َE�E�B���������ʂƐ�������邪�A�@���Ȃ��̂ł��낤���B
�@���͂Ƃ�����A�ŋ߂̃C���^�[�l�b�g�ɂ��Z�p���̎擾����ʉ����������Ă���A���Ȃ̎����Ԕr�o
�K�X���ψ��ψ���ƍ��y��ʏȂ̎����ԔR�����ψ���̃G���W�����̑����W���̏������A2009�N6������
����ɑ�^�g���b�N�́uNO���팸�v�Ɓu�R����P�v�ɗL�����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�ȓ����Z�p�̑���
��F������Ă��邱�Ƃ́A�����Ɛ��������B����ɂ�������炸�A�����_�i��2014�N9���j�ł����Ȃ̎����Ԕr�o�K
�X���ψ��ψ���ƍ��y��ʏȂ̎����ԔR�����ψ���̃G���W�����̑����W���̏����́A��^�g���b�N���S
���ڂ��ۑ�̉������Z�p�I�ɍ���Ƃ̎咣������Ă��邱�Ƃ���A�����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j��
�����Z�p���Ӑ}�I�ɖ����E�َE�E�B������Ă���ƌ��邱�Ƃ��Ó��Ȃ悤�Ɏv�����A�@���Ȃ��̂ł��낤���B�����āA��
�̏ꍇ�A��^�g���b�N�i�����Ɏg�p�ߒ��ԁj�ɂ�����u2015�N�x�d�ʎԔR������{10�����x�̔R�����v�Ɓu�m�n��
��0.23�@g/kWh ��NO���K���v�̃��x���̋K���́A���Ȃ̎����Ԕr�o�K�X���ψ��ψ���ƍ��y��ʏȂ̎����ԔR
�����ψ���A�ɂ߂č����m�����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓������̏��ł���2024�N�x��
�~�Ɏ��{�����\��E�v��̂悤�Ɏv���Ďd���������̂ł���B
�K�X���ψ��ψ���ƍ��y��ʏȂ̎����ԔR�����ψ���̃G���W�����̑����W���̏������A2009�N6������
����ɑ�^�g���b�N�́uNO���팸�v�Ɓu�R����P�v�ɗL�����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�ȓ����Z�p�̑���
��F������Ă��邱�Ƃ́A�����Ɛ��������B����ɂ�������炸�A�����_�i��2014�N9���j�ł����Ȃ̎����Ԕr�o�K
�X���ψ��ψ���ƍ��y��ʏȂ̎����ԔR�����ψ���̃G���W�����̑����W���̏����́A��^�g���b�N���S
���ڂ��ۑ�̉������Z�p�I�ɍ���Ƃ̎咣������Ă��邱�Ƃ���A�����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j��
�����Z�p���Ӑ}�I�ɖ����E�َE�E�B������Ă���ƌ��邱�Ƃ��Ó��Ȃ悤�Ɏv�����A�@���Ȃ��̂ł��낤���B�����āA��
�̏ꍇ�A��^�g���b�N�i�����Ɏg�p�ߒ��ԁj�ɂ�����u2015�N�x�d�ʎԔR������{10�����x�̔R�����v�Ɓu�m�n��
��0.23�@g/kWh ��NO���K���v�̃��x���̋K���́A���Ȃ̎����Ԕr�o�K�X���ψ��ψ���ƍ��y��ʏȂ̎����ԔR
�����ψ���A�ɂ߂č����m�����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓������̏��ł���2024�N�x��
�~�Ɏ��{�����\��E�v��̂悤�Ɏv���Ďd���������̂ł���B
�@�����āA���Ȃ̎����Ԕr�o�K�X���ψ��ψ���ƍ��y��ʏȂ̎����ԔR�����ψ���̃G���W�����̑���
�W���̏����i���͖쓹�������A���H���G�����A�吹�G�����A�ѓc�P�������A���������ް���ђ��A���������A
�㓡�Y�괸è�ށE�Ʊ�Eػ�����A�ߋv���������j�́A�R��ׂ������i���`2020�N���H�Ɛ����j�܂ł́A��^�g���b�N
�́uNO���팸�v�Ɓu�R����P�v�̗����̖ʂŗD�ꂽ�@�\�E���\�������C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j��
�����Z�p���E�َE�����������A������@��𑨂��āA�ȉ��̂悤�Ȏ���x��̎咣�������ɌJ��Ԃ�������
�Ɛ��������B
�W���̏����i���͖쓹�������A���H���G�����A�吹�G�����A�ѓc�P�������A���������ް���ђ��A���������A
�㓡�Y�괸è�ށE�Ʊ�Eػ�����A�ߋv���������j�́A�R��ׂ������i���`2020�N���H�Ɛ����j�܂ł́A��^�g���b�N
�́uNO���팸�v�Ɓu�R����P�v�̗����̖ʂŗD�ꂽ�@�\�E���\�������C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j��
�����Z�p���E�َE�����������A������@��𑨂��āA�ȉ��̂悤�Ȏ���x��̎咣�������ɌJ��Ԃ�������
�Ɛ��������B
�i���j ��^�g���b�N�ł��u�@ DPF���u�̋����Đ��̕p�x�����v�A�u�A SCR�G�}�̒ቷ�����v�A�u�BSCR�G�}��HC
��ł̉����v�A����сu�C �d�ʎԃ��[�h�R��̉��P�v�̂S���ڂ́A�����̍���ȃf�B�[�[���G���W���̋Z�p�I
�I�ȉۑ��i�����̑�^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W���̉ۑ�������ł���Z�p�́A�����_�ŕs���ł���Ƃ̈Ӗ��j
��ł̉����v�A����сu�C �d�ʎԃ��[�h�R��̉��P�v�̂S���ڂ́A�����̍���ȃf�B�[�[���G���W���̋Z�p�I
�I�ȉۑ��i�����̑�^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W���̉ۑ�������ł���Z�p�́A�����_�ŕs���ł���Ƃ̈Ӗ��j
�i���j NO���팸�ƔR����P�̃g���[�h�I�t�́A�����̍���ȃf�B�[�[���G���W���̋Z�p�I�I�ȉۑ��i�����̑�^�g
���b�N�p�f�B�[�[���G���W���ۑ�������ł���Z�p�́A�����_�ŕs���ł���Ƃ̈Ӗ��j
���b�N�p�f�B�[�[���G���W���ۑ�������ł���Z�p�́A�����_�ŕs���ł���Ƃ̈Ӗ��j
�@�O�q�̂悤�ɁA�i���j�Ɓi���j�̉ۑ���������đ�^�g���b�N���uNO���팸�v�Ɓu�R����P�v�̗������Ɏ����ł����C��
�x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p���2005�N3���ɓ������J����Ă����ɁA2006�N4��7�����J�̕M��
�̃C���^�[�l�b�g�̃z�[���y�[�W�i���u�Ջ��l�̃A�C�f�A�v�j�Ɍf�ڂ��Ă�����ł���B�����āA2009�N6���`2010�N2����
���ɂ͊��ɁA���̓����Z�p���u�r�o�K�X�v��u�R��v�ɊW����p���p����Yahoo�����ő�P�y�[�W�ڂɌ��o�E������
���Ă���̂ł���B���̂��߁A2009�N6���`2010�N2���̍��ɂ́A���Ȃ̎����Ԕr�o�K�X���ψ��ψ���ƍ��y��
�ʏȂ̎����ԔR�����ψ���̃G���W�����̑����W���̏����́A���̓����Z�p�̎��p���ɂ���^�g���b�N��
�uNO���팸�v�Ɓu�R����P�v�̗������ۑ�������ł��邱�Ƃ�F������Ă��锤�Ɛ��������B�������Ȃ���A���ꂩ��S
�`�T�N�o�߂��������_�i��2014�N10�����݁j�ł��A���Ȃ̎����Ԕr�o�K�X���ψ��ψ���ƍ��y��ʏȂ̎�����
�R�����ψ���̃G���W�����̑����W���̏����́A�ȏ�́i���j�̑�^�g���b�N�̇@�`�C�̉ۑ�������ł���Z�p
�����J���A����сA�i���j�� �f�B�[�[���G���W���́uNO���v�Ɓu�R��v�̃g���[�h�I�t�������ł���Z�p�����J���Ƃ���u��
���_�ł͋��U���v�Ɖ]����ÐF���R���錩���E�咣����v�c�����Č����Ɋg�U����Ă���悤�ł���B�B
�x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p���2005�N3���ɓ������J����Ă����ɁA2006�N4��7�����J�̕M��
�̃C���^�[�l�b�g�̃z�[���y�[�W�i���u�Ջ��l�̃A�C�f�A�v�j�Ɍf�ڂ��Ă�����ł���B�����āA2009�N6���`2010�N2����
���ɂ͊��ɁA���̓����Z�p���u�r�o�K�X�v��u�R��v�ɊW����p���p����Yahoo�����ő�P�y�[�W�ڂɌ��o�E������
���Ă���̂ł���B���̂��߁A2009�N6���`2010�N2���̍��ɂ́A���Ȃ̎����Ԕr�o�K�X���ψ��ψ���ƍ��y��
�ʏȂ̎����ԔR�����ψ���̃G���W�����̑����W���̏����́A���̓����Z�p�̎��p���ɂ���^�g���b�N��
�uNO���팸�v�Ɓu�R����P�v�̗������ۑ�������ł��邱�Ƃ�F������Ă��锤�Ɛ��������B�������Ȃ���A���ꂩ��S
�`�T�N�o�߂��������_�i��2014�N10�����݁j�ł��A���Ȃ̎����Ԕr�o�K�X���ψ��ψ���ƍ��y��ʏȂ̎�����
�R�����ψ���̃G���W�����̑����W���̏����́A�ȏ�́i���j�̑�^�g���b�N�̇@�`�C�̉ۑ�������ł���Z�p
�����J���A����сA�i���j�� �f�B�[�[���G���W���́uNO���v�Ɓu�R��v�̃g���[�h�I�t�������ł���Z�p�����J���Ƃ���u��
���_�ł͋��U���v�Ɖ]����ÐF���R���錩���E�咣����v�c�����Č����Ɋg�U����Ă���悤�ł���B�B
�@���̂悤�ɁA���Ȃ̎����Ԕr�o�K�X���ψ��ψ���ƍ��y��ʏȂ̎����ԔR�����ψ���̃G���W��
���̑����W���̏����́A2009�N6���`2010�N2���̍�������ɂS�`�T�N�̒����ɂ킽���āA�C���x�~�G���W
���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p���E�َE�E�Ⴕ���͉B������Ă���悤�ł���B���̑�^�g���b�N��
�uNO���팸�v�Ɓu�R����P�v�̗������Ɏ����ł�������Z�p�������E�َE�E�Ⴕ���͉B���́A���{���\����
�G���W�����̊w�ҁE���Ƃ͖̉쓹�������A���H���G�����A�吹�G�����A�ѓc�P�������A����������
����ђ��A���������A�㓡�Y�괸è�ށE�Ʊ�Eػ�����A�ߋv���������E�Z�p�҂��A���^�g���b�N�́uNO��
�팸�v�Ɓu�R����P�v�̐i���E���W��j�Q���锽�Љ�I��������ϋɓI�ɍs���Ă��邱�ƂɂȂ���v�����A�@
���Ȃ��̂ł��낤���B
���̑����W���̏����́A2009�N6���`2010�N2���̍�������ɂS�`�T�N�̒����ɂ킽���āA�C���x�~�G���W
���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p���E�َE�E�Ⴕ���͉B������Ă���悤�ł���B���̑�^�g���b�N��
�uNO���팸�v�Ɓu�R����P�v�̗������Ɏ����ł�������Z�p�������E�َE�E�Ⴕ���͉B���́A���{���\����
�G���W�����̊w�ҁE���Ƃ͖̉쓹�������A���H���G�����A�吹�G�����A�ѓc�P�������A����������
����ђ��A���������A�㓡�Y�괸è�ށE�Ʊ�Eػ�����A�ߋv���������E�Z�p�҂��A���^�g���b�N�́uNO��
�팸�v�Ɓu�R����P�v�̐i���E���W��j�Q���锽�Љ�I��������ϋɓI�ɍs���Ă��邱�ƂɂȂ���v�����A�@
���Ȃ��̂ł��낤���B
�@�����āA���Ȃ̎����Ԕr�o�K�X���ψ��ψ���ƍ��y��ʏȂ̎����ԔR�����ψ���̃G���W�����
�̑����W���̏������A�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p���E�َE�E�َE����Ă��铮
�@�E�ړI�́A�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p�̗̍p���K�v�ƂȂ�u2015�N�x�d�ʎԔR
������{10�����x�̔R�����v�Ɓu�m�n����0.23�@g/kWh ��NO���K���v�̃��x���i���K���l�j����^�g���b�N
�̎g�p�ߒ��ԂɎ��{�����{������2024�N5��25���ȍ~�ɐݒ肷�邽�߂ł͂Ȃ����Ɨ\�������B
�̑����W���̏������A�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p���E�َE�E�َE����Ă��铮
�@�E�ړI�́A�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p�̗̍p���K�v�ƂȂ�u2015�N�x�d�ʎԔR
������{10�����x�̔R�����v�Ɓu�m�n����0.23�@g/kWh ��NO���K���v�̃��x���i���K���l�j����^�g���b�N
�̎g�p�ߒ��ԂɎ��{�����{������2024�N5��25���ȍ~�ɐݒ肷�邽�߂ł͂Ȃ����Ɨ\�������B
�@���̂Ȃ�A��^�g���b�N�̎g�p�ߒ��Ԃɑ���u2015�N�x�d�ʎԔR������{10�����x�̔R�����v��
�u�m�n����0.23�@g/kWh ��NO���K���v�̃��x���i���K���l�j�̋K����2024�N5��25���ȍ~�Ɏ��{���邱�Ƃ��ݒ�
���ꂽ�ꍇ�A�����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓�������2024�N5��25���ɏ��ł��邽�߁A����
�����Z�p���g���b�N���[�J�������Ŏ��R����Ɏ��Ђ̃g���b�N�ɍ̗p�ł��邱�ƂɂȂ�B�����āA���̎��ɁA����
�����Z�p�ɔ��ׂȋ@�\��lj������ꍇ�ɂ́A���̓����Z�p�����ЊJ���̐V�Z�p�Ƒ�X�I�ɐ�`���Ă��@����
�G��Ȃ��Ɖ]������ȗ��v�E�����b�g���l�����邱�Ƃ��\�ɂȂ�B���̂��Ƃ́A�����������A�g���b�N���[�J���M��
�̍l�Ă��������Z�p�����@�I�ɉ����ł��邱�ƂɂȂ邽�߁A�g���b�N���[�J�̖��\�ȃG���W���W�̐��ƁE�Z�p��
�ɂƂ��ẮA�E����̍ō��̐��ʂ��グ���Ƃ��āA�Г�����̏^�E��^����邱�ƂɂȂ�Ɛ��������B
�u�m�n����0.23�@g/kWh ��NO���K���v�̃��x���i���K���l�j�̋K����2024�N5��25���ȍ~�Ɏ��{���邱�Ƃ��ݒ�
���ꂽ�ꍇ�A�����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓�������2024�N5��25���ɏ��ł��邽�߁A����
�����Z�p���g���b�N���[�J�������Ŏ��R����Ɏ��Ђ̃g���b�N�ɍ̗p�ł��邱�ƂɂȂ�B�����āA���̎��ɁA����
�����Z�p�ɔ��ׂȋ@�\��lj������ꍇ�ɂ́A���̓����Z�p�����ЊJ���̐V�Z�p�Ƒ�X�I�ɐ�`���Ă��@����
�G��Ȃ��Ɖ]������ȗ��v�E�����b�g���l�����邱�Ƃ��\�ɂȂ�B���̂��Ƃ́A�����������A�g���b�N���[�J���M��
�̍l�Ă��������Z�p�����@�I�ɉ����ł��邱�ƂɂȂ邽�߁A�g���b�N���[�J�̖��\�ȃG���W���W�̐��ƁE�Z�p��
�ɂƂ��ẮA�E����̍ō��̐��ʂ��グ���Ƃ��āA�Г�����̏^�E��^����邱�ƂɂȂ�Ɛ��������B
�@���̂悤�ɁA�g���b�N���[�J�i�����{�����ԍH�Ɖ�j���C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p�����@�I
�ɉ���肷��B��̕��@�E��i�́A��^�g���b�N�̎g�p�ߒ��Ԃɑ���u2015�N�x�d�ʎԔR������{10�����x��
�R�����v�Ɓu�m�n����0.23�@g/kWh ��NO���K���v�̃��x���i���K���l�j�̋K����2024�N5��25���ȍ~�Ɏ��{���邱�Ƃ��
�肵�ĖႤ���Ƃł���ƍl������B������������邽�߂ɂ́A���Ȃ̎����Ԕr�o�K�X���ψ��ψ���ƍ��y���
�Ȃ̎����ԔR�����ψ���̃G���W�����̑����W���̏����i���͖쓹�������A���H���G�����A�吹�G�����A
�ѓc�P�������A���������ް���ђ��A���������A�㓡�Y�괸è�ށE�Ʊ�Eػ�����A�ߋv���������j�������
�ł̂悤��������C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p������������E�َE�E�B���������A�i���j�̑�^
�g���b�N�́u�@ DPF���u�̋����Đ��̕p�x�����v�A�u�A SCR�G�}�̒ቷ�����v�A�u�BSCR�G�}��HC��ł̉����v�A����
�сu�C �d�ʎԃ��[�h�R��̉��P�v�̂S���ڂ��@�`�C�̉ۑ�������ł���Z�p�����J���A������i���j�̃f�B�[�[���G��
�W���́uNO���v�Ɓu�R��v�̃g���[�h�I�t�������ł���Z�p�����J���Ƃ��������Z�p����������L���g�U�������ĖႤ
���Ƃł���B
�ɉ���肷��B��̕��@�E��i�́A��^�g���b�N�̎g�p�ߒ��Ԃɑ���u2015�N�x�d�ʎԔR������{10�����x��
�R�����v�Ɓu�m�n����0.23�@g/kWh ��NO���K���v�̃��x���i���K���l�j�̋K����2024�N5��25���ȍ~�Ɏ��{���邱�Ƃ��
�肵�ĖႤ���Ƃł���ƍl������B������������邽�߂ɂ́A���Ȃ̎����Ԕr�o�K�X���ψ��ψ���ƍ��y���
�Ȃ̎����ԔR�����ψ���̃G���W�����̑����W���̏����i���͖쓹�������A���H���G�����A�吹�G�����A
�ѓc�P�������A���������ް���ђ��A���������A�㓡�Y�괸è�ށE�Ʊ�Eػ�����A�ߋv���������j�������
�ł̂悤��������C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p������������E�َE�E�B���������A�i���j�̑�^
�g���b�N�́u�@ DPF���u�̋����Đ��̕p�x�����v�A�u�A SCR�G�}�̒ቷ�����v�A�u�BSCR�G�}��HC��ł̉����v�A����
�сu�C �d�ʎԃ��[�h�R��̉��P�v�̂S���ڂ��@�`�C�̉ۑ�������ł���Z�p�����J���A������i���j�̃f�B�[�[���G��
�W���́uNO���v�Ɓu�R��v�̃g���[�h�I�t�������ł���Z�p�����J���Ƃ��������Z�p����������L���g�U�������ĖႤ
���Ƃł���B
�@�M�҂̌����Ƃ���ł́A�����_�i��2014�N10�����݁j�ł́A���Ȃ̎����Ԕr�o�K�X���ψ��ψ���ƍ��y
��ʏȂ̎����ԔR�����ψ���̃G���W�����̑����W���̏����i���͖쓹�������A���H���G�����A��
���G�����A�ѓc�P�������A���������ް���ђ��A���������A�㓡�Y�괸è�ށE�Ʊ�Eػ�����A��
�v���������j�́A����܂Ŋ��ɂS�`�T�N�ɂ킽�����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p��
���E�َE�E�B�����A�g���b�N���[�J�i�����{�����ԍH�Ɖ�j�̗v�]�ʂ�̑�^�g���b�N���uNO���팸�v�Ɓu�R����P�v
���Ɏ�������Z�p���s���Ƃ̍��\�I�Ȏ咣���A�ǐS�̙�ӂ������邱�Ɩ����ɕ��C�ŌJ��Ԃ���Ă�����
���ł���B���̏�����ƁA�g���b�N���[�J�i�����{�����ԍH�Ɖ�j���瑽���̎w���E�v���E�v�]�ɉ����邽�߂ɁA����
�����鎞���i��2020�N���H�j�ɓ��B����܂ŁA���l�̎咣�𑱂�������̂Ɨ\�������B���������ƁA�|���R�c���Z
�p���̕M�҂̂悤�ȉ��O�Ȑl�Ԃ��v�������Ƃ́A���̑����W���̓��{���\����G���W���W�̊w�ҁE���Ƃɂ́A
�]���̌��Ԃ肪������̂Ǝא����Ă��܂����A���ۂ̂Ƃ���͒m��R���������Ƃł���B�����Ƃ��A���ꂪ�����ł���A
���{���\����G���W�����̑����W���̊w�ҁE���Ƃ́A�g���b�N���[�J�i�����{�����ԍH�Ɖ�j�̒P�Ȃ�u���V��v
�ɉ߂��Ȃ��ƂɂȂ�Ǝv�����A���ۂ̂Ƃ���͔@���Ȃ��̂ł��낤���B
��ʏȂ̎����ԔR�����ψ���̃G���W�����̑����W���̏����i���͖쓹�������A���H���G�����A��
���G�����A�ѓc�P�������A���������ް���ђ��A���������A�㓡�Y�괸è�ށE�Ʊ�Eػ�����A��
�v���������j�́A����܂Ŋ��ɂS�`�T�N�ɂ킽�����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p��
���E�َE�E�B�����A�g���b�N���[�J�i�����{�����ԍH�Ɖ�j�̗v�]�ʂ�̑�^�g���b�N���uNO���팸�v�Ɓu�R����P�v
���Ɏ�������Z�p���s���Ƃ̍��\�I�Ȏ咣���A�ǐS�̙�ӂ������邱�Ɩ����ɕ��C�ŌJ��Ԃ���Ă�����
���ł���B���̏�����ƁA�g���b�N���[�J�i�����{�����ԍH�Ɖ�j���瑽���̎w���E�v���E�v�]�ɉ����邽�߂ɁA����
�����鎞���i��2020�N���H�j�ɓ��B����܂ŁA���l�̎咣�𑱂�������̂Ɨ\�������B���������ƁA�|���R�c���Z
�p���̕M�҂̂悤�ȉ��O�Ȑl�Ԃ��v�������Ƃ́A���̑����W���̓��{���\����G���W���W�̊w�ҁE���Ƃɂ́A
�]���̌��Ԃ肪������̂Ǝא����Ă��܂����A���ۂ̂Ƃ���͒m��R���������Ƃł���B�����Ƃ��A���ꂪ�����ł���A
���{���\����G���W�����̑����W���̊w�ҁE���Ƃ́A�g���b�N���[�J�i�����{�����ԍH�Ɖ�j�̒P�Ȃ�u���V��v
�ɉ߂��Ȃ��ƂɂȂ�Ǝv�����A���ۂ̂Ƃ���͔@���Ȃ��̂ł��낤���B
�@�����͉]���Ă��A���Ȃ̍��y��ʏȂ̈ψ����^�g���b�N�́uNO���팸�v�Ɓu�R����P�v�ɗL�����C���x�~
�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p����דI�ɖ����E�َE�E�B�����ăg���b�N���[�J�̗v�]�E��]�ɉ�
�����R���єr�o�K�X�i���m�n���j�Ɋւ��鏫���I�ȑ�^�g���b�N�̋K���������ɐݒ肷�邱�Ƃ́A�����ċ���
��邱�Ƃł͖������Ƃ��N�̖ڂɂ����炩���B�����āA���ɋ߂������ɂ����āA��^�g���b�N�̎g�p�ߒ��Ԃ��u2015
�N�x�d�ʎԔR������{10�����x�̔R�����v�Ɓu�m�n����0.23�@g/kWh ��NO���K���v���K�������̎��{��2024�N5
���ȍ~�ɐݒ肳�ꂽ�ꍇ�ɂ́A���Ȃ̎����Ԕr�o�K�X���ψ��ψ���ƍ��y��ʏȂ̎����ԔR�����ψ���
�G���W�����̑����W���̏��������{���\����G���W���W�̂̊w�ҁE���ƂƂ̕]���E����𗘗p���A��^�g���b
�N�̋K�����g���b�N���[�J�̗v�]�ɉ��������ӓI�ȓ��e���邱�Ƃ́A�����̐M����傫�����邱�ƂɂȂ�A�w�ҁE���
�ƂƂ��Ă͖ܘ_�̂��ƁA�l�ԂƂ��Ă��������E�ǐS�̌��������s�ׂƔ���Ă��d�����Ȃ��Ǝv�����A�@���Ȃ��̂ł�
�낤���B���̂��Ƃ��������邽�߂ɂ��A�e�ɂ��p�ɂ��A���Ȃ̎����Ԕr�o�K�X���ψ��ψ���ƍ��y��ʏȂ̎���
�ԔR�����ψ���ɂ����鍡��̐V���ȑ�^�g���b�N�̋K���ݒ�̓����𒍈Ӑ[�����Ă����K�v������ƍl�����
�́A�|���R�c���Z�p���̕M�҂����̕��������ł��낤���B
�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p����דI�ɖ����E�َE�E�B�����ăg���b�N���[�J�̗v�]�E��]�ɉ�
�����R���єr�o�K�X�i���m�n���j�Ɋւ��鏫���I�ȑ�^�g���b�N�̋K���������ɐݒ肷�邱�Ƃ́A�����ċ���
��邱�Ƃł͖������Ƃ��N�̖ڂɂ����炩���B�����āA���ɋ߂������ɂ����āA��^�g���b�N�̎g�p�ߒ��Ԃ��u2015
�N�x�d�ʎԔR������{10�����x�̔R�����v�Ɓu�m�n����0.23�@g/kWh ��NO���K���v���K�������̎��{��2024�N5
���ȍ~�ɐݒ肳�ꂽ�ꍇ�ɂ́A���Ȃ̎����Ԕr�o�K�X���ψ��ψ���ƍ��y��ʏȂ̎����ԔR�����ψ���
�G���W�����̑����W���̏��������{���\����G���W���W�̂̊w�ҁE���ƂƂ̕]���E����𗘗p���A��^�g���b
�N�̋K�����g���b�N���[�J�̗v�]�ɉ��������ӓI�ȓ��e���邱�Ƃ́A�����̐M����傫�����邱�ƂɂȂ�A�w�ҁE���
�ƂƂ��Ă͖ܘ_�̂��ƁA�l�ԂƂ��Ă��������E�ǐS�̌��������s�ׂƔ���Ă��d�����Ȃ��Ǝv�����A�@���Ȃ��̂ł�
�낤���B���̂��Ƃ��������邽�߂ɂ��A�e�ɂ��p�ɂ��A���Ȃ̎����Ԕr�o�K�X���ψ��ψ���ƍ��y��ʏȂ̎���
�ԔR�����ψ���ɂ����鍡��̐V���ȑ�^�g���b�N�̋K���ݒ�̓����𒍈Ӑ[�����Ă����K�v������ƍl�����
�́A�|���R�c���Z�p���̕M�҂����̕��������ł��낤���B
�@�b�͕ς�邪�A2014�N�t���ɁA�p���E�l�C�`���[���Ɍf�ڂ��ꂽ���ە����m��STAP�זE�̘_���́A�C���^�[�l�b�g
�̃u���O�Ŏw�E���ꂽ���Ƃ����[�ƂȂ�A���̘_�����摜�̐蒣�����H�����摜���g���ċ�����STAP�זE�̑���
���咣���Ă��錇�ט_���ł��邱�Ƃ������������Ƃł���B�B���̌��ʁASTAP�זE�̘_���͎�艺�����ASTAP�זE
���̂��̂̑��݂��ے肳�ꂽ�������������B�����������ە����m��STAP�זE�̘_���́A���E�I�Ȃd�r�זE�̌��Ђ�
������䔎�m�������ł��邽�߂Ƀl�C�`���[�Ɍf�ڂ��ꂽ�ƌ����邪�A�C���^�[�l�b�g�̌l�̃u���O�ɂ��_����
�f�[�^�̝s����s���̎w�E�ɂ���āA���U���e�̘_���Ƌ��e����A�_���̎�艺�����u�ƂȂ����̂ł���B���̏�
������ƁA�C���^�[�l�b�g�̔��B�������݂ł́A����܂ł̂悤�Ɋw�ҁE���Ƃ̌����������l���̏ꍇ�ɂ́A
������P���Ȃ����咣�┭�\���s���Ă��N���٘_�������Ȃ�����ł͖����Ȃ����悤�Ɏv�����A�@���Ȃ��̂ł���
�����B
�̃u���O�Ŏw�E���ꂽ���Ƃ����[�ƂȂ�A���̘_�����摜�̐蒣�����H�����摜���g���ċ�����STAP�זE�̑���
���咣���Ă��錇�ט_���ł��邱�Ƃ������������Ƃł���B�B���̌��ʁASTAP�זE�̘_���͎�艺�����ASTAP�זE
���̂��̂̑��݂��ے肳�ꂽ�������������B�����������ە����m��STAP�זE�̘_���́A���E�I�Ȃd�r�זE�̌��Ђ�
������䔎�m�������ł��邽�߂Ƀl�C�`���[�Ɍf�ڂ��ꂽ�ƌ����邪�A�C���^�[�l�b�g�̌l�̃u���O�ɂ��_����
�f�[�^�̝s����s���̎w�E�ɂ���āA���U���e�̘_���Ƌ��e����A�_���̎�艺�����u�ƂȂ����̂ł���B���̏�
������ƁA�C���^�[�l�b�g�̔��B�������݂ł́A����܂ł̂悤�Ɋw�ҁE���Ƃ̌����������l���̏ꍇ�ɂ́A
������P���Ȃ����咣�┭�\���s���Ă��N���٘_�������Ȃ�����ł͖����Ȃ����悤�Ɏv�����A�@���Ȃ��̂ł���
�����B
�@�����āA����STAP�זE�Ɋւ���_�������{���������呛���ɔ��W�����̂́A���l�N�q�̔��ƈ�ʏ������v��
����ł��������Ȋw�ҁE���Ƃ��A�f�[�^��s���E��₂��ċU�̎������ʂ��ł����グ�����\�I�ȓ��e�̘_���\
�������ƂɁA�����̐l���������A�x�̂��ꂽ����ł͖������낤���B����́A�d�r�זE�̌����Ő��E�I�ɗL���ȍ�
�䔎�m��i PS�זE�̌����Ńm�[�x���܂���܂����R�����������Ԃ����߁ASTAP�זE�̍��\�I�Ș_���\�����Ƃ�
�\������B���̂悤�ȉ\��������邱�Ƃ��������悤�ɁA�w�ҁE���Ƃɂ͌��������̔s�k�ɂ��v���C�h�E�����S��
�������Ƃɂ͑ς����Ȃ��Ɗ�������قȎv�l��H�̐l�����Ȃ��Ȃ��悤���B�v����ɁA���{�̒����Ȋw�ҁE���Ƃ�
���ɂ̓v���C�h�E�����S���������Ɖ�����邽�߂ɂ́A���\�I�ȍs�ׂ������C�ōs���l�������X�ɂ��đ��݂��邱��
�̏؋��ł͂Ȃ����낤���B
����ł��������Ȋw�ҁE���Ƃ��A�f�[�^��s���E��₂��ċU�̎������ʂ��ł����グ�����\�I�ȓ��e�̘_���\
�������ƂɁA�����̐l���������A�x�̂��ꂽ����ł͖������낤���B����́A�d�r�זE�̌����Ő��E�I�ɗL���ȍ�
�䔎�m��i PS�זE�̌����Ńm�[�x���܂���܂����R�����������Ԃ����߁ASTAP�זE�̍��\�I�Ș_���\�����Ƃ�
�\������B���̂悤�ȉ\��������邱�Ƃ��������悤�ɁA�w�ҁE���Ƃɂ͌��������̔s�k�ɂ��v���C�h�E�����S��
�������Ƃɂ͑ς����Ȃ��Ɗ�������قȎv�l��H�̐l�����Ȃ��Ȃ��悤���B�v����ɁA���{�̒����Ȋw�ҁE���Ƃ�
���ɂ̓v���C�h�E�����S���������Ɖ�����邽�߂ɂ́A���\�I�ȍs�ׂ������C�ōs���l�������X�ɂ��đ��݂��邱��
�̏؋��ł͂Ȃ����낤���B
�@���Ă��āA���Ȃ̎����Ԕr�o�K�X���ψ��ψ���ƍ��y��ʏȂ̎����ԔR�����ψ���̓��{���\����G
���W�����̑����W���̒����Ȋw�ҁE���Ƃ́A����܂ł�4�`5�N�ɂ킽��A��^�g���b�N�́uNO���팸�v�Ɓu�R����P�v
�ɗL�����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p���E�َE�E�B�����霓�ӓI�ȋZ�p���̎��W���s
���Ă����Ɛ���������B���̂��߁A��^�g���b�N�ɑ���2016�N���{��NO���K�������ł́A�s�\���ȋZ�p����
��ɐݒ肳�ꂽ�\�������S�ɂ͔ے�ł��Ȃ��ƍl������B���̂悤�ɁA��i���̓��{�ɂ����āA�����Ԃ̋K
����V���ɐݒ肷��ߒ��̒��ɁA�^�O�������������݂��邱�Ƃ́A�����čD�܂������ƂłȖ����ƍl������B
�����ɂ����čēx�A���̂悤�ȏ����o���Ȃ��悤�ɂ���߂ɂ��A���Ȃ̎����Ԕr�o�K�X���ψ��ψ���ƍ�
�y��ʏȂ̎����ԔR�����ψ���̑����W���̊w�ҁE���Ƃ́A��^�g���b�N�́uNO���팸�v�Ɓu�R����P�v�ɗL��
���C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p���E�َE�E�B������s�ׂ�x�܂��Ȃ���������_�i��2014
�N10�����݁j�ő����ɒ��~���A���l�N�q�̕i�ʁE�i���������ē��{�̐V���ȑ�^�g���b�N�̔R���NO���̋K��������
�����E�����ɐݒ肷�邱�Ƃ��̗v�ƍl������B
���W�����̑����W���̒����Ȋw�ҁE���Ƃ́A����܂ł�4�`5�N�ɂ킽��A��^�g���b�N�́uNO���팸�v�Ɓu�R����P�v
�ɗL�����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p���E�َE�E�B�����霓�ӓI�ȋZ�p���̎��W���s
���Ă����Ɛ���������B���̂��߁A��^�g���b�N�ɑ���2016�N���{��NO���K�������ł́A�s�\���ȋZ�p����
��ɐݒ肳�ꂽ�\�������S�ɂ͔ے�ł��Ȃ��ƍl������B���̂悤�ɁA��i���̓��{�ɂ����āA�����Ԃ̋K
����V���ɐݒ肷��ߒ��̒��ɁA�^�O�������������݂��邱�Ƃ́A�����čD�܂������ƂłȖ����ƍl������B
�����ɂ����čēx�A���̂悤�ȏ����o���Ȃ��悤�ɂ���߂ɂ��A���Ȃ̎����Ԕr�o�K�X���ψ��ψ���ƍ�
�y��ʏȂ̎����ԔR�����ψ���̑����W���̊w�ҁE���Ƃ́A��^�g���b�N�́uNO���팸�v�Ɓu�R����P�v�ɗL��
���C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p���E�َE�E�B������s�ׂ�x�܂��Ȃ���������_�i��2014
�N10�����݁j�ő����ɒ��~���A���l�N�q�̕i�ʁE�i���������ē��{�̐V���ȑ�^�g���b�N�̔R���NO���̋K��������
�����E�����ɐݒ肷�邱�Ƃ��̗v�ƍl������B
�@�������Ȃ���A�����_�i��2014�N10�����݁j�ɂ����ẮA���Ȃ̎����Ԕr�o�K�X���ψ��ψ���ƍ��y��ʏȂ�
�����ԔR�����ψ���̃G���W�����̑����W���̒����Ȋw�ҁE���Ƃł���͖쓹�������A���H���G�����A��
���G�����A�ѓc�P�������A���������ް���ђ��A���������A�㓡�Y�괸è�ށE�Ʊ�Eػ�����A�ߋv������
���́A������]���Ɠ��l�ɁA�i���j����^�g���b�N�ł��u�@ DPF���u�̋����Đ��̕p�x�����v�A�u�A SCR�G�}�̒ቷ��
���v�A�u�BSCR�G�}��HC��ł̉����v�A����сu�C �d�ʎԃ��[�h�R��̉��P�v�̂S���ڂ������̍���ȃf�B�[�[���G��
�W���̋Z�p�I�I�ȉۑ�Ƃ���咣���s���A�������i���j�� NO���팸�ƔR����P�̃g���[�h�I�t�������̍���ȃf�B�[�[
���G���W���̋Z�p�I�I�ȉۑ�Ƃ���咣���ꑱ�����Ă���悤�ł���B
�����ԔR�����ψ���̃G���W�����̑����W���̒����Ȋw�ҁE���Ƃł���͖쓹�������A���H���G�����A��
���G�����A�ѓc�P�������A���������ް���ђ��A���������A�㓡�Y�괸è�ށE�Ʊ�Eػ�����A�ߋv������
���́A������]���Ɠ��l�ɁA�i���j����^�g���b�N�ł��u�@ DPF���u�̋����Đ��̕p�x�����v�A�u�A SCR�G�}�̒ቷ��
���v�A�u�BSCR�G�}��HC��ł̉����v�A����сu�C �d�ʎԃ��[�h�R��̉��P�v�̂S���ڂ������̍���ȃf�B�[�[���G��
�W���̋Z�p�I�I�ȉۑ�Ƃ���咣���s���A�������i���j�� NO���팸�ƔR����P�̃g���[�h�I�t�������̍���ȃf�B�[�[
���G���W���̋Z�p�I�I�ȉۑ�Ƃ���咣���ꑱ�����Ă���悤�ł���B
�@���݂ɁA4�`5�N���ȑO�i��2009�N6�����j�Ɂu�|�X�g�V�����v�̂P��ɂ��Yahoo�����ɂāA�uNO���팸�v�Ɓu�R����P�v��
�L�����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p��6��8�猏���̂Q�ʂƂV�ʁi����P�y�[�W�ځj�Ō��o����
��悤�ɂȂ������_�ł́A���̓����Z�p���i���j�̇@�`�C�̉ۑ���i���j�� NO���ƔR��̃g���[�h�I�t�̉ۑ�������ł���
�Z�p�ł���Ƃ̋Z�p���́A�����W���̒����Ȋw�ҁE���Ƃ��m��y��ł������̂Ɛ��������B����́A�����W����
�w�ǂ���w�����ł��邱�Ƃ�A�C���^�[�l�b�g�̏��g�U�̋@�\�E���\���炷��A���ɁA���R�̂��Ƃł͂���Ɛ�����
���B���̂悤�ɁA�����W���̒����Ȋw�ҁE���Ƃ́A4�`5�N���ȑO�i��2009�N6�����j�ɂ͊��ɑ�^�g���b�N���i���j��
�@�`�C�̉ۑ���i���j�� NO���ƔR��̃g���[�h�I�t�̉ۑ�������ł����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓�
���Z�p�̏����@�m�E�F������Ă����ɂ�������炸�A��^�g���b�N���i���j�̇@�`�C�̉ۑ���i���j�� NO���ƔR��̃g��
�[�h�I�t�̉ۑ肪�Z�p�I�ɖ������Ƃ̎咣�𑱂����Ă����̂ł���B�܂�A�i���j���i���j�̉ۑ�̉����ɗL�����C
���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p�̑��݂��A���Ɍ����_�i��2014�N10�����_�j�܂ł�4�`5�N�Ԃ���
�}�I�ɉB���E�B������Ă����Ɛ��������B���̂悤�Ȍo�܁E�o�߂𗝉�����ƁA���Ȃ̎����Ԕr�o�K�X���ψ�
�ψ���ƍ��y��ʏȂ̎����ԔR�����ψ���̃G���W�����̑����W���̒����Ȋw�ҁE���Ƃ́A�����_
�i��2014�N10�����݁j�ȍ~���A����܂łƓ��l�Ɉ�v�c�����āA�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j��
�����Z�p���E�َE�E�B�����ꑱ����\�����ɂ߂č����Ɛ���������B
�L�����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p��6��8�猏���̂Q�ʂƂV�ʁi����P�y�[�W�ځj�Ō��o����
��悤�ɂȂ������_�ł́A���̓����Z�p���i���j�̇@�`�C�̉ۑ���i���j�� NO���ƔR��̃g���[�h�I�t�̉ۑ�������ł���
�Z�p�ł���Ƃ̋Z�p���́A�����W���̒����Ȋw�ҁE���Ƃ��m��y��ł������̂Ɛ��������B����́A�����W����
�w�ǂ���w�����ł��邱�Ƃ�A�C���^�[�l�b�g�̏��g�U�̋@�\�E���\���炷��A���ɁA���R�̂��Ƃł͂���Ɛ�����
���B���̂悤�ɁA�����W���̒����Ȋw�ҁE���Ƃ́A4�`5�N���ȑO�i��2009�N6�����j�ɂ͊��ɑ�^�g���b�N���i���j��
�@�`�C�̉ۑ���i���j�� NO���ƔR��̃g���[�h�I�t�̉ۑ�������ł����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓�
���Z�p�̏����@�m�E�F������Ă����ɂ�������炸�A��^�g���b�N���i���j�̇@�`�C�̉ۑ���i���j�� NO���ƔR��̃g��
�[�h�I�t�̉ۑ肪�Z�p�I�ɖ������Ƃ̎咣�𑱂����Ă����̂ł���B�܂�A�i���j���i���j�̉ۑ�̉����ɗL�����C
���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p�̑��݂��A���Ɍ����_�i��2014�N10�����_�j�܂ł�4�`5�N�Ԃ���
�}�I�ɉB���E�B������Ă����Ɛ��������B���̂悤�Ȍo�܁E�o�߂𗝉�����ƁA���Ȃ̎����Ԕr�o�K�X���ψ�
�ψ���ƍ��y��ʏȂ̎����ԔR�����ψ���̃G���W�����̑����W���̒����Ȋw�ҁE���Ƃ́A�����_
�i��2014�N10�����݁j�ȍ~���A����܂łƓ��l�Ɉ�v�c�����āA�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j��
�����Z�p���E�َE�E�B�����ꑱ����\�����ɂ߂č����Ɛ���������B
�@���̂悤�ɁA���Ȃ̎����Ԕr�o�K�X���ψ��ψ���ƍ��y��ʏȂ̎����ԔR�����ψ���̈ψ����Ϗ�����
�ď��������̎��i�E������^����ꂽ�w�ҁE���Ƃ��A�ނ�̐�啪��̋Z�p�����E�َE���ĉB���E�B�����邱
�Ƃ́A�ȑO�ɎЉ���ƂȂ����،��}�����������X�N�̏d�v�����̐������B���E�B�����ċq�Ɋ��Ⓤ���M����̔���
��s�ׂƗގ����Ă�����̂ł���B�ŋ߂̏،��}���́A�������X�N�̏d�v�����̐������B���E�B���̏ꍇ�ɂ́A�u���Z
���i�̔��@�v�̈ᔽ�Ƃ��Č������������邱�ƂɂȂ������A���Ȃ̎����Ԕr�o�K�X���ψ��ψ���ƍ��y��ʏ�
�̎����ԔR�����ψ���̈ψ��̊w�ҁE���Ƃ��d�v�ȋZ�p�����E�َE���Ă��A���ꂪ����݂ɂȂ��Ă��A
����������Ƃ������Ĕ����邱�Ƃ������Ɛ��@�����B���̂��߁A���Ȃ̎����Ԕr�o�K�X���ψ��ψ���
�ƍ��y��ʏȂ̎����ԔR�����ψ���̃G���W�����̑����W���̒����Ȋw�ҁE���Ƃ́A�����_�i��2014�N10
�����݁j�ȍ~���A����܂łƓ��l�Ƀ|���R�c���Z�p���̏o������̖��E�ƃg���b�N���[�J�̗v�]�������߂ɁA�C��
�x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p���E�َE�E�B�����������Ƃ��Ă��A���̙�߂��邱�Ƃ�������
�l������B�v����ɁA���̓����Z�p�̖����E�َE�E�B���𒆎~����̂��ۂ��́A���Ȃ̎����Ԕr�o�K�X���ψ�
�ψ���ƍ��y��ʏȂ̎����ԔR�����ψ���̃G���W�����̑����W���̒����Ȋw�ҁE���Ƃ̗ǐS�E�ϗ��ρE
�l�Ԑ������ɔC����Ă���ƍl������B
�ď��������̎��i�E������^����ꂽ�w�ҁE���Ƃ��A�ނ�̐�啪��̋Z�p�����E�َE���ĉB���E�B�����邱
�Ƃ́A�ȑO�ɎЉ���ƂȂ����،��}�����������X�N�̏d�v�����̐������B���E�B�����ċq�Ɋ��Ⓤ���M����̔���
��s�ׂƗގ����Ă�����̂ł���B�ŋ߂̏،��}���́A�������X�N�̏d�v�����̐������B���E�B���̏ꍇ�ɂ́A�u���Z
���i�̔��@�v�̈ᔽ�Ƃ��Č������������邱�ƂɂȂ������A���Ȃ̎����Ԕr�o�K�X���ψ��ψ���ƍ��y��ʏ�
�̎����ԔR�����ψ���̈ψ��̊w�ҁE���Ƃ��d�v�ȋZ�p�����E�َE���Ă��A���ꂪ����݂ɂȂ��Ă��A
����������Ƃ������Ĕ����邱�Ƃ������Ɛ��@�����B���̂��߁A���Ȃ̎����Ԕr�o�K�X���ψ��ψ���
�ƍ��y��ʏȂ̎����ԔR�����ψ���̃G���W�����̑����W���̒����Ȋw�ҁE���Ƃ́A�����_�i��2014�N10
�����݁j�ȍ~���A����܂łƓ��l�Ƀ|���R�c���Z�p���̏o������̖��E�ƃg���b�N���[�J�̗v�]�������߂ɁA�C��
�x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p���E�َE�E�B�����������Ƃ��Ă��A���̙�߂��邱�Ƃ�������
�l������B�v����ɁA���̓����Z�p�̖����E�َE�E�B���𒆎~����̂��ۂ��́A���Ȃ̎����Ԕr�o�K�X���ψ�
�ψ���ƍ��y��ʏȂ̎����ԔR�����ψ���̃G���W�����̑����W���̒����Ȋw�ҁE���Ƃ̗ǐS�E�ϗ��ρE
�l�Ԑ������ɔC����Ă���ƍl������B
�@ ���̂悤�ɁA���Ȃ̎����Ԕr�o�K�X���ψ��ψ���ƍ��y��ʏȂ̎����ԔR�����ψ���̃G���W�����
�̑����W���̒����Ȋw�ҁE���Ƃ���^�g���b�N�́uNO���팸�v�Ɓu�R����P�v�ɗL�����C���x�~�G���W���i�������J
2005-54771�j�̓����Z�p���E�َE�E�B���������邱�Ƃɍ�������������ꍇ�ɂ́A����̓|���R�c���Z�p���̕M��
�̌l�I�Ȑ����ł��邪�A����i��2014�N10���ȍ~�j�̓��{�̐V���ȑ�^�g���b�N�̔R���NO���̋K�������́A�]��
�Ɠ������A�g���b�N���[�J�̗v�]�E��]�ɉ������K���l�ƋK�������ɐݒ肳���\�����ɂ߂č����Ɨ\�������B����
�āA���̏ꍇ�ɂ́A���Ȃ̎����Ԕr�o�K�X���ψ��ψ���ƍ��y��ʏȂ̎����ԔR�����ψ���́A�C���x
�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p�̗̍p���K�v�ƂȂ�u2015�N�x�d�ʎԔR������{10�����x�̔R
�����v�Ɓu�m�n����0.23�@g/kWh ��NO���K���v�̃��x���i���K���l�j���^�g���b�N�̎g�p�ߒ��ԂɓK�p���鎞���Ƃ���
�́A�g���b�N���[�J�̈ӌ��E�v�]�����ׂ��A���̓����Z�p�̓����������ł���2024�N5��25���ȍ~�̐ݒ�ƂȂ��
�\�����ɂ߂č����Ɨ\�������B���̂悤�Ȃ��Ƃ́A������̂�ɂ������Ȃƍ��y��ʏȂ̈ψ���̐E�����s�Ǝv��
���A�@���Ȃ��̂ł��낤���B�Ȃ��A����ɂ��ẮA��^�g���b�N��NO���팸�ƔR�����ɗL���ȋC���x�~��َE����
�w�ҏ����̃y�[�W�ɂ����l�̓��e���ڏq���Ă���̂ŁA�����̂�����͌䗗�������������B
�̑����W���̒����Ȋw�ҁE���Ƃ���^�g���b�N�́uNO���팸�v�Ɓu�R����P�v�ɗL�����C���x�~�G���W���i�������J
2005-54771�j�̓����Z�p���E�َE�E�B���������邱�Ƃɍ�������������ꍇ�ɂ́A����̓|���R�c���Z�p���̕M��
�̌l�I�Ȑ����ł��邪�A����i��2014�N10���ȍ~�j�̓��{�̐V���ȑ�^�g���b�N�̔R���NO���̋K�������́A�]��
�Ɠ������A�g���b�N���[�J�̗v�]�E��]�ɉ������K���l�ƋK�������ɐݒ肳���\�����ɂ߂č����Ɨ\�������B����
�āA���̏ꍇ�ɂ́A���Ȃ̎����Ԕr�o�K�X���ψ��ψ���ƍ��y��ʏȂ̎����ԔR�����ψ���́A�C���x
�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p�̗̍p���K�v�ƂȂ�u2015�N�x�d�ʎԔR������{10�����x�̔R
�����v�Ɓu�m�n����0.23�@g/kWh ��NO���K���v�̃��x���i���K���l�j���^�g���b�N�̎g�p�ߒ��ԂɓK�p���鎞���Ƃ���
�́A�g���b�N���[�J�̈ӌ��E�v�]�����ׂ��A���̓����Z�p�̓����������ł���2024�N5��25���ȍ~�̐ݒ�ƂȂ��
�\�����ɂ߂č����Ɨ\�������B���̂悤�Ȃ��Ƃ́A������̂�ɂ������Ȃƍ��y��ʏȂ̈ψ���̐E�����s�Ǝv��
���A�@���Ȃ��̂ł��낤���B�Ȃ��A����ɂ��ẮA��^�g���b�N��NO���팸�ƔR�����ɗL���ȋC���x�~��َE����
�w�ҏ����̃y�[�W�ɂ����l�̓��e���ڏq���Ă���̂ŁA�����̂�����͌䗗�������������B
�W�|�U�@��^�g���b�N�E�g���N�^�ɂ�����Q�O�P�T�N�x�d�ʎԔR���ɕs�K���̊���
�@���݁A2015�N�x�d�ʎԔR���́A2006�N3���ɐ��肳��Ĉȗ��A�����_�i��2014�N9���j�ł����ɂW�N�ȏ���o��
���Ă���̂ł���B���������āA�킪���̃g���b�N���[�J���D�ꂽ�R��팸�̋Z�p���J���ς݂ł������Ȃ�A�킪����
�s�̂���Ă����^�g���b�N�̑S�Ԏ�́A2015�N�x�d�ʎԔR���ɓK���ł��Ă��锤�ł���B�������A����ł͕\�P
�U�Ɏ������悤�ɁA��^�g���b�N�̋͂��Ȉꕔ�̎Ԏ�ł́A������2015�N�x�d�ʎԔR���ɓK���ł��Ă��Ȃ��悤��
����B
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
8e0ef07935a1�j |
| |
|
|
| |
|
|
�����@���R���j��2010�N8�����̓��W�F�N�Ӂ@�u�f�B�[�[���G���W���v�i���ҁFUD�g���b�N�X���@���ѐM�T���j���w��^�g���b
�N�p�f�B�[�[���G���W���ɂ�����R��팸�́A�����_�ł��Z�p�I�ɔ����ǂ���̏��x�Ƃ̎�|���L�ړ��e�́A����
�̂悤�Ɏv����̂��B���̂悤�ɁA�f�B�[�[���G���W���ɂ�����R��팸�̋Z�p�J�����s���l���Ă��錻����l����ƁA
����AUD����юO�H���e�g���b�N���[�J���A���̐��N��ɂ̓f�B�[�[�����R�ĉ��P�ɂ��T�����x�̏d�ʎԃ��[�h�R��
�̍팸���\�ɂ���Z�p�����p���ł���悤�ɂȂ�Ƃ́A�M�҂ɂ͂ƂĂ��M�����Ȃ��̂ł���B
�@����A�����U�����Ԃ́A���s���\�ɑ����̋]�������A10���b�g�����̃_�E���T�C�W���O�����G���W�����^�g���b
�N�ɍ̗p���邱�Ƃɂ���āA��^�g���b�N��99���̎Ԏ��2015�N�x�d�ʎԔR���ɓK�������Ă���悤���B���̂悤
�ɂ����U�����Ԃł͑�^�g���b�N��10���b�g�����̃_�E���T�C�W���O�����G���W���𓋍ڂ��Ă���̂́A���s���\�̗D��
��13���b�g�����̕W���G���W�����^�g���b�N�ɓ��ڂ����ꍇ�ɂ́A�V�i�}�j���A���~�b�V�����𓋍ڂ����Ԏ�ł́A2015
�N�x�d�ʎԔR���ɂ͓K���ł��Ȃ��������߂ł͂Ȃ����Ɛ���������B�܂��A��^�g���b�N�̃G���W�����_�E���T
�C�W���O�����ꍇ�́A�r�C�u���[�L�̐��\���������ቺ���A��^�g���b�N�̍~��s���Ɋ댯�����ƂɂȂ�B�����G
���W���_�E���T�C�W���O�ɂ���Ēቺ�����r�C�u���[�L�͂̕s����⊮���邽�߁A�V�����d�C����������̃��^�[�_
��V���ɒlj��܂��̓��^�[�_�̑�^�����K�v�ƂȂ�B���̃��^�[�_�̒lj����^���́A�R�X�g�A�b�v��ԗ��d�ʂ̑���
�v���ƂȂ�A��^�g���b�N�ɂƂ��čD�܂������Ƃł͂Ȃ��B���̂悤�ɁA��^�g���b�N�ɂ�����啝�ȃG���W���_�E���T�C�W
���O�́A�f�����b�g�����݂���̂ł���B
�@�Ƃ���ŁA�ŋ��i��2014�N6���j�ł́A �u�d����p�t�@���v�Ɓu�d���E�H�[�^�[�|���v�v���̗p���邱�Ƃɂ��A2015�N�d��
�ԔR���{�T���̏d�ʎԃ��[�h�R���B��������^�g���b�N�̎s���i��http://car.watch.impress.co.jp/docs/news/
20140624_654839.html�j���J�n���ꂽ�悤���B�����Ƃ��A�u�d����p�t�@���v�v�͐��\�N���̂��畁�y����FF�쓮��p��
�Ɂi�t�����g�G���W���E�t�����g�h���C�u�̏�p�ԁj�ɍ̗p���ꂽ�Z�p�ł���A�u�d���E�H�[�^�[�|���v�͍ŋ߂̃n�C�u���b�h
��p�Ԃɍ̗p���ꂽ�Z�p�ł���B���������āA����� �u�d����p�t�@���v�Ɓu�d���E�H�[�^�[�|���v�v�́A���ɏ�p�Ԃɍ�
�p�ς݂̋Z�p���^�f�B�[�[���g���b�N�ɓ]�p���������ł���B���������āA�u�d����p�t�@���v�Ɓu�d���E�H�[�^�[�|��
�v�v�́A�V�K�̔R����P�Z�p�ƌĂԂ��Ƃɂ��S�O�����Z�p�ƍl������B�Ȃ��A�u�d����p�t�@���v�������ɉ����ĉ�
�ϐ��䂵�Č����I�ȃG���W����p���������邽�߂ɕK�v�Ȃ�����p�t�@�������Ƃŋ쓮�������ጸ���A�u�d���E�H
�[�^�[�|���v�v�́A�d����p�t�@���Ɠ��l�ɂŕK�v�Ȃ�����p���ʂ��z�����ăG���W���������I�ɗ�p���ăE�H�[�^
�[�|���v�̗]���ȋ쓮��ጸ���邱�Ƃɂ��A�G���W���R������P����悤�ɂ������̂ł���B�����u�d����p�t�@���v��
�u�d���E�H�[�^�[�|���v�v�́A�߂������A�S���[�J�̑�^�g���b�N�ɍ̗p����A�e�Ђ���2015�N�d�ʎԔR���{�T����
�d�ʎԃ��[�h�R���B��������^�g���b�N���s�̂������̂ƍl������B
�ԔR���{�T���̏d�ʎԃ��[�h�R���B��������^�g���b�N�̎s���i��http://car.watch.impress.co.jp/docs/news/
20140624_654839.html�j���J�n���ꂽ�悤���B�����Ƃ��A�u�d����p�t�@���v�v�͐��\�N���̂��畁�y����FF�쓮��p��
�Ɂi�t�����g�G���W���E�t�����g�h���C�u�̏�p�ԁj�ɍ̗p���ꂽ�Z�p�ł���A�u�d���E�H�[�^�[�|���v�͍ŋ߂̃n�C�u���b�h
��p�Ԃɍ̗p���ꂽ�Z�p�ł���B���������āA����� �u�d����p�t�@���v�Ɓu�d���E�H�[�^�[�|���v�v�́A���ɏ�p�Ԃɍ�
�p�ς݂̋Z�p���^�f�B�[�[���g���b�N�ɓ]�p���������ł���B���������āA�u�d����p�t�@���v�Ɓu�d���E�H�[�^�[�|��
�v�v�́A�V�K�̔R����P�Z�p�ƌĂԂ��Ƃɂ��S�O�����Z�p�ƍl������B�Ȃ��A�u�d����p�t�@���v�������ɉ����ĉ�
�ϐ��䂵�Č����I�ȃG���W����p���������邽�߂ɕK�v�Ȃ�����p�t�@�������Ƃŋ쓮�������ጸ���A�u�d���E�H
�[�^�[�|���v�v�́A�d����p�t�@���Ɠ��l�ɂŕK�v�Ȃ�����p���ʂ��z�����ăG���W���������I�ɗ�p���ăE�H�[�^
�[�|���v�̗]���ȋ쓮��ጸ���邱�Ƃɂ��A�G���W���R������P����悤�ɂ������̂ł���B�����u�d����p�t�@���v��
�u�d���E�H�[�^�[�|���v�v�́A�߂������A�S���[�J�̑�^�g���b�N�ɍ̗p����A�e�Ђ���2015�N�d�ʎԔR���{�T����
�d�ʎԃ��[�h�R���B��������^�g���b�N���s�̂������̂ƍl������B
�W�|�V�D��ʈ��S���������̽��߰�ި���ٴݼ�����̔R�����́A���s�̗\��
�@�Ɨ��s���@�l ��ʈ��S���������ł́A�\�P�V�ɂ����悤�ɁA2010�N11��24�i���j�E25���i�j�Ɂu��ʈ��S������
�t�H�[�����Q�O�P�O�v�Ə̂���Z�p���\�̍u����J�Â��ꂽ�悤���B���̍u����ɂ́A�䂪�����\���鑽���̌��
�W�̊w�ҁE���Ƃ��o�Ȃ���A����̕��y�����҂���鎟���㎩���Ԃɂ��Ă̋Z�p���\�Ƃ����Ɋւ���c�_
���s��ꂽ�Ƃ̂��Ƃł���B
| |
|
| |
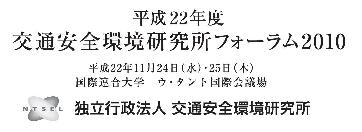 |
�@�����i�Ɓj�ʈ��S���������̍u�����\��ł́A�u�X�[�p�[�N���[���f�B�[�[���iSCD�j�G���W���ɂ�����V�W�J�v�Ƒ�
������^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W���̔R������_���������J���̘_��������Ă���B���̘_����q�ǂ�����
�����������Ƃ���A�L�q�̓��e�ɑ����̋^��_���ڂɕt�����̂ŁA�\�P�W�ɂ܂Ƃ߂��B
������^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W���̔R������_���������J���̘_��������Ă���B���̘_����q�ǂ�����
�����������Ƃ���A�L�q�̓��e�ɑ����̋^��_���ڂɕt�����̂ŁA�\�P�W�ɂ܂Ƃ߂��B
| |
|
���
����
�@�@�@ �@�V�G�B�V�[�C�[ �F �� �F�O�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ |
|
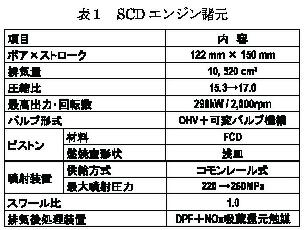 �i�\�P�̃x�[�X�G���W���͓��쎩���Ԃ�PC�P�P�^��
����j 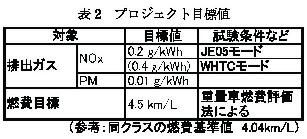  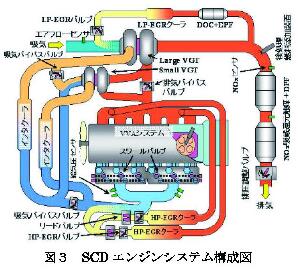 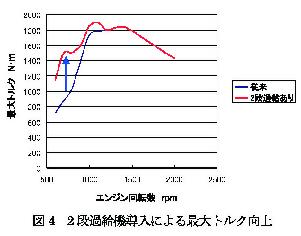 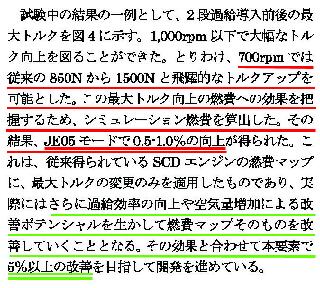 |
�@���L�̌�ʈ��S���������́u�X�[�p�[�N���[���f�B�[�[���iSCD�j
�G���W���ɂ�����V�W�J�v�̘_���i�Ȍ�A�u��ʈ��S����������SCD
�G���W���_���v�Ə̂��j�ł́A���L�́u�}�R�@SCD�G���W���V�X�e��
�\���}�v�Ɏ�����Ă���悤�ɁA�ȉ��̋Z�p���g�ݍ��܂�Ă���B
�� �Q�i�V�[�P���V�����ߋ��@
�� �����R�������[���i��260MPa�j
�� LP-EGR�̗̍p�ɂ��EGR����̍��x��
���X
�@�����āA���L�̌�ʈ��S����������SCD�G���W���_���̐}�R��
�V�X�e���ł́A1000rpm�ȉ��̒ᑬ�ł̃G���W���g���N�A�b�v�ɂ��A
JE�O�T���[�h�R�0.5�`1.0�����x�̉��P�ł������Ƃ̂��ƁB���̒��x
�̔R����P�͔R���̍ۂɐ����鑪��덷�͈̔͂ɉ߂��Ȃ��B
���������āA���̒��x�̔R����P��_���Ɍւ炵���ɋL�ڂ��邱�Ƃ́A
�@���Ȃ��̂ł��낤���B
�@����A�{�y�[�W�� �y�P�S�|�P�@NEDO�́u�����x�R�Đ���G���W
�V�X�e���̌����J���v�ł́A�R����̑厸�s�z �̍��Ŏ����Ă���
�悤�ɁA8���~�ȏ�̗\�Z�Ŏ��{���ꂽNEDO�Ƃ����U������������
�v�V�I���������Q�ԑ����Z�p�J���i�N���[���f�B�[�[��
�v���W�F�N�g�A2004�`2009�N�j�́u�����x�R�Đ���G���W�V�X�e����
�����J���v�̑�^�v���W�F�N�g�ł́A��^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W��
�Ɉȉ��̋Z�p��g�ݍ��V�X�e���ɂ��NO���팸�ƔR����P��
�����J�������Ɏ��{����Ă���B
�� �R�i�ߋ��V�X�e���i�����ϗL�������j
�� 300MP���̒������R�����ˁi�����ϗL�������j
�� �J�����X�V�X�e��
��g�ݍ��uPCI�R�āv(PCI�R�ā�HCCI�R�āj
����NEDO�̌����J���ł́A�P�S�|�P���̐}�P�U�Ɏ������悤�ɁA�R��
�팸�͖ڕW��10���팸�ɂ͑S���y���A2015�N�x�d�ʎԔR��
��ɑ��ĂQ���̈������m�F���ꂽ�B���̂悤�ɁANEDO�̃N���[��
�f�B�[�[���v���W�F�N�g�́A�f�B�[�[���̔R����P�ɂ��Ċ��S��
���s�ł��������Ƃ�����Ă���̂ł���B
�@���āA��ʈ��S����������SCD�G���W���_���ɋL�ڂ���Ă���
���L�́u�}�R�@SCD�G���W���V�X�e���\���}�v�ɐ��荞�܂ꂽ��v��
�Z�p�́A�O�q�̂W-1���Ŏ������f�B�[�[���̔R����P�ɂ��Ċ��S��
���s����NEDO�̊v�V�I���������Q�ԑ����Z�p�J���i�N���[��
�f�B�[�[���v���W�F�N�g�A2004�`2009�N�j�́u�����x�R�Đ���G���W
�V�X�e���̌����J���v�Ɨގ��̋Z�p���w��ǂł���B���̂��߁A
��ʈ��S���������́u�}�R�@SCD�G���W���V�X�e���\���}�v��
���荞�܂ꂽ�Z�p�ɂ���ăf�B�[�[���G���W���̏\���ȔR����P�́A
�S�����҂ł��Ȃ����Ƃ͖����łł���B�����āA���L�̌�ʈ��S��
��������SCD�G���W���_���ł́AJE�O�T���[�h�R�0.5�`1.0�����x
�̉��P���������Ȃ������ƋL�ڂ���Ă��邱�Ƃ́A���R�̌��ʂł�
�Ȃ����ƍl������B
�@�Ƃ���ŁA��ʈ��S���������̗�؉��ꎁ�A�Έ�f���A
����㎁����ѐV�G�B�V�[�C�[�̐� �F�O���́A���L�̌�ʈ��S
����������SCD�G���W���_���ł́A�u�}�R�@SCD�G���W���V�X�e��
�\���}�v�̋Z�p�ɂ���āA����A�u�ߋ��@�����̌�����C�ʑ�����
�R��}�b�v�����P���A���L�̐}�R�̃V�X�e���łT���ȏ�iJE�O�T���[�h�j
�̔R����P��ڎw���v�ƋL�ڂ���Ă���B�������A�M�҂ɂ͂��̂悤��
���Ƃ������ł���Ƃ͂ƂĂ��l�����Ȃ��̂��B�Ȃ��Ȃ�A�ߋ��@��
����������́A�M�c���̖����^�[�r����u���A�̍ޗ����J���ł���
�ꍇ�ɏ��߂ċ��C��r�C�K�X�̘R��������ɖh�~�ł���ꍇ��A
�^�[�r���H�����ɔ��ɂł���ޗ���������̋Z�p���J���ł���
�ꍇ�ɂ����āA���߂Ď����ł��邱�Ƃł���B�����̉ߋ��@�W��
�Z�p���A����A����I�ɔ��W���Ȃ�����A�߂������ɉߋ��@�̌�����
�傫������ł���\���͑S�������ƍl����̂��Ó��ł���B
�܂��AJE�O�T���[�h�ł̓G���W���������ח̈�ł̉^�]�䗦������
���߁AJE�O�T���[�h�̏\���ȔR�����ɂ́A�������ח̈�ł̔R��
���P���K�v�ł���B�����A�f�B�[�[���G���W���͕������ׂł͒�����
��C�ߏ�̏�Ԃʼn^�]�����̂ł���B����ɂ�������炸�A���L��
��ʈ��S����������SCD�G���W���_���ł́A��C�ʂ̑�����
�R��}�b�v�����P�ł���Ǝ咣����Ă��鍪�����M�҂ɂ͗ǂ�����
�ł��Ȃ��Ƃ���ł���B���������āA���L�̘_���ɂ����āA��ʈ��S
���������̗�A�Έ�A���̏�������ѐV�G�B�V�[�C�[��
�����́A�u�ߋ��@�����̌�����C�ʑ����ŔR��}�b�v�����P���A
���L�̐}�R�̃V�X�e���łT���ȏ�iJE�O�T���[�h�j�̔R����P��ڎw���v
�ƋL�q����Ă��邪�A�����I�ȔR����P�̋Z�p����̓I�ɉ���
������Ă��Ȃ��̂ł���B���������āA���L�̘_���ɂ�����
�u�T���ȏ�iJE�O�T���[�h�j�̔R����P�v�̏q�́A���҂̒P�Ȃ��]��
�q�ׂĂ��邾���ł���A�f�B�[�[���G���W���̏\���ȔR����P��
���ۂɎ����ł���\���͑S�������Ǝv���Ă���B
�@�������A�M�҂̗\�z�ɔ����A��ʈ��S���������̗�؉��ꎁ�A
�Έ�f���A����㎁����ѐV�G�B�V�[�C�[�̐� �F�O�����A
���L�̘_���ɋL�ڂ���Ă���悤�ɁA�u�}�R�@SCD�G���W���V�X�e��
�\���}�v�̋Z�p��p���āu�ߋ��@�����̌�����C�ʑ�����
�R��}�b�v�����P���A���L�̐}�R�̃V�X�e���łT���ȏ�iJE�O�T���[�h�j
�̔R����P��ڎw���ĊJ����i�߂�v���Ƃɂ���āA��^�g���b�N�p
�f�B�[�[���G���W���̔R����T���ȏ���̉��P�����Ɏ����ł���
�Ƃ���A����͖��@������̈̋Ƃł���Ɖ]����̂ł�
�Ȃ����낤���B
�@�ʂ����āA��ʈ��S���������̗�؉��ꎁ�A�Έ�f���A
����㎁����ѐV�G�B�V�[�C�[�̐� �F�O���́A�{����
�f�B�[�[���R������P���錻�݂̖��p�t�̐l�B�ł���̂��A
����Ƃ��A����܂Ō��O��������g���Č����\�Z���l�����Ă���
�P�Ȃ�y�e���t�E���\�t�ɗނ���l�B�ł���̂��́A���̂Ƃ���
�s���ł���B
�@���͂Ƃ�����A��ʈ��S���������̗�؉��ꎁ�A�Έ�f���A
����㎁����ѐV�G�B�V�[�C�[�̐� �F�O�����R����P��
���p�t���A�Ⴕ���̓y�e���t�E���\�t���̉���ł��邩�́A�߂�����
�ɂ͖��炩�ɂȂ邱�Ƃł���A�M�҂ɂ͋����[�X�ł���B���̌��ʂ�
�y���݂��B
�@�Ƃ���ŁA���L�̘_���́A�����̑�^�g���b�N��2015�N�x�d�ʎԔR��
��ɓK�����Ă���2010�N11��24�i���j�E25���i�j�ɊJ�Â���Ă���
�u��ʈ��S���������t�H�[�����Q�O�P�O�v�ł����\����Ă���B
���̂��Ƃ���A���L�̘_���̓ǎ҂́A���̘_���̃x�[�X�G���W��(����
�����Ԃ�PC11�^�Ɛ����j�̏d�ʎԃ��[�h�R��l�́A2015�N�x�d�ʎ�
�R���ɓK�����Ă���R��x���ƍl���Ă�����̂Ɛ��������B
�������A���L�̌�ʈ��S���������́u�X�[�p�[�N���[���f�B�[�[��
�iSCD�j�G���W���ɂ�����V�W�J�v�̘_���ł́A��^�g���b�N�p�̃x�[�X
�G���W��(���쎩���Ԃ�PC11�^�Ɛ����j�̏d�ʎԃ��[�h�R��l��
2015�N�x�d�ʎԔR���ɓK�����Ă���|�������L�ڂ���Ă��Ȃ�
�悤���B
�@
���̂��Ƃ���A���L�̘_���̃x�[�X�G���W��(���쎩���Ԃ�
PC11�^�Ɛ����j�̔R��l(�Ⴆ��JE�O�T���[�h�R��j�Ƃ��ė�����l��
�v�����ꂽ�ƋL�ڂ��Ă����A���L�́u�}�R�@SCD�G���W���V�X�e��
�\���}�v�Ŕ@���Ȃ�R��l���v������悤�Ƃ��A���̍��L��
�u�}�R�@SCD�G���W���V�X�e���\���}�v�̋Z�p��p���āu�ߋ��@������
������C�ʑ����ŔR��}�b�v�����P���A���L�̐}�R�̃V�X�e����
�T���ȏ�iJE�O�T���[�h�j�̔R����P�������ł����v�Ƙ_���ɋL�ڂ��Ă�
���̌��������Ȃ����ƂɂȂ�̂ł���B�v�́A�x�[�X�G���W��(����
�����Ԃ�PC11�^�Ɛ����j���P�O�N�ȏ���Â��^�̃G���W���̂��߁A
�R��̈����x�[�X�G���W���ł��邱�Ƃ��L�ڂ��Ă����A�u�}�R�@SCD
�G���W���V�X�e���\���}�v�̋Z�p��p���邱�Ƃɂ����JE�O�T���[�h
�ł̂T����P�O���̔R����P�̎������ʂ��������Ƃ́A�ɂ߂ĊȒP��
���Ƃł���B
�@�ܘ_�A���̂悤�Ȏ�@�ł܂Ƃ߂�ꂽ�_���́A�f�B�[�[��
�G���W���̔R�����̋Z�p�I�Ȑi���Ɋ�^���Ȃ����Ƃ͓��R�ł���B
�����āA���̂悤�ȕ��@�́A���\�t��y�e���t�����풃�ю��ɗp����
��@���B�������A���{���\����w�ҁE���Ƃł����ʈ��S��
�������̗�؉��ꎁ�A�Έ�f���A����㎁����ѐV�G�B�V�[�C�[
�̐� �F�O�������\�����_���ɂ����ẮA���̂悤�ȍ��\��y�e��
�ɗނ����@����g���Ę_�����쐬����邱�Ƃ́A�펯�I�ɂ�
��Ȃ����̂ƍl�����邪�E�E�E�E�E�E�B
|
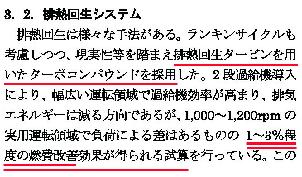 |
�@�O�q�́u�Q�D�f�B�[�[���G���W���ɂ�����r�o�K�X�ጸ�ƔR����P�v��
�L�ڂ��Ă���ʂ�A �^�[�{�R���p�E���h�̔r�M����^�[�r���̓����� �r�C�K�X�́A�^�[�{�ߋ��@�̃^�[�r�������̔r�C�K�X�̉��x�E���� �����ቷ�E�ሳ�ł��邽�߁A�r�C�K�X�̃G�l���M�[�̃|�e���V������ �Ⴂ�B���̂��ߔr�C�K�X�̑̐ϗ��ʂ������A����^�[�r���͑�^���� �K�v�ƂȂ�B���̌��ʃR�X�g�������A���ԗ����ڂ��e�ՂȂ��Ƃł͂Ȃ��B �^�[�{�R���p�E���h�́A��^�g���b�N�̑��s�R��̉��P������ȋZ�p���I �̃y�[�W�ɏڏq���Ă���悤�ɁA�^�[�{�R���p�E���h�ɂ��R��́A �G���W���̍ő�g���N�̉^�]��ԂłQ���O�オ���P�ł��邾���� ����B�����āA��^�g���b�N�̎��ۂ̑��s��d�ʎԃ��[�h�R��v���� �g�p�����G���W���^�]�́A�ő�g���N�̃G���W���̉�]���x�t�� �̒����ł̂Q/�R���ȉ��̒����ȉ��̒�����]�̎��Ɍ��� ������ɁA���̍����ח̈�̗̈悪�啔���ł���B���������āA �]���̃G���W���Ƀ^�[�{�R���p�E���h�����������ł́A��^ �g���b�N�̑��s��d�ʎԃ��[�h�R��l�̉��P�́A�^�[�{�R���p�E���h �ɂ��G���W���̍ő�g���N�̉^�]��Ԃł̂Q���O��̔R����P�� �����ȉ��A�����P.0 ���ȉ��ł͂Ȃ����Ɛ��������B �@���������āA���Ă̑�^�g���b�N�E�g���N�^�Ƀ^�[�{�R���p�E���h���̗p ����ő�̖ړI�́A�R�����ł͖����A�����ő刳�͂��㏸������ ���Ɩ����o�͂������ł����i�ł���悤���B���̏؋��ɁA�{���{�A �X�J�j�A���́A��^�g���N�^�p�̃G���W���Ƀ^�[�{�R���p�E���h���̗p ���Ă���̂����B �@���āA���L����ʈ��S����������SCD�G���W���_���ɂ����āA ��ʈ��S���������̗�؉��ꎁ�A�Έ�f���A����㎁����� �V�G�B�V�[�C�[�̐� �F�O�����^�[�{�R���p�E���h�̗̍p�ɂ���� �P�`�R�����x�̔R����P�i��JE�O�T���[�h�Ɛ����j�ƋL�q����Ă���B ���L����ʈ��S����������SCD�G���W���_���ɂ����� �P�`�R�����x�̔R����P�̎��Z���ʂ́A���E�̈�ʏ��ɔ�ׂ� ���{�̔R����P�ł���A���̎��Z�ɗp����ꂽ�r�M����^�[�r���� �^�[�r�������Ƃ��Ĕ��I�ȍ���������p���Čv�Z���ꂽ���̂� ���������B���R�̂��ƂȂ���A���\�v�Z�ɖ�����荂���^�[�r�� ������p�����ꍇ�ɂ́A�傫�ȔR����P���Z�o�ł���̂ł���B ���̐́A�^�[�{�G���W���̐��\�V���~���[�V�����v�Z�����I�� �s���Ă������Z�p���̕M�҂��猩��A���I�ȍ����^�[�r�� ������p�����G���W���R��̌v�Z�́A�ԈႢ�Ȃ����\�s�ׂł���A �Z�p�҂Ƃ��Ă̗ǐS�̌�����@���Ɏ����s�ׂƍl���Ă���B ���x�����ǂ��J��Ԃ����A �^�[�{�R���p�E���h�́A��^�g���b�N�̑��s�R��̉��P������ȋZ�p���I �̃y�[�W�ɏڏq���Ă���悤�ɁA�^�[�{�R���p�E���h�ɂ��R��́A �G���W���̍ő�g���N�̉^�]��ԂłQ���O�オ���P�ł��邾�� �ł���B�]���̂P�i�ߋ���Q�i�ߋ��̃f�B�[�[���G���W���� �^�[�{�R���p�E���h��P�ɑ������������̃V�X�e���ɂ����āA ������S���������̗�؉��ꎁ�A�Έ�f���A����㎁ ����ѐV�G�B�V�[�C�[�̐� �F�O�������Z�������ʁA���L�̂悤�� �u1000rpm�`1200rpm�̎��p�^�]�̈�łP�`�R���̔R����P���ʂ� ������v�Ƃ̋L�q�́A���ł���Ɛ��������B �@���������A����̃f�B�[�[���g���b�N�Ƀ^�[�{�R���p�E���h�𓋍ڂ��� �ꍇ�́A��^�g���b�N�̎����s��JE05���[�h�ł̓G���W���������ׂ� �^�]�p�x���������߁A�ߋ��@�̔r�C�^�[�r�������r�I�A�Ⴂ���x �̔r�C�K�X�̂��r�o����邽�߁A�^�[�{�R���p�E���h�̉^�[�r�� �ɂ���ĉ���ł���G�l���M�[�́A�K�R�I�ɏ��Ȃ��Ȃ�B���������āA �^�[�r���ł̃G�l���M�[����́A�Ⴂ�^�[�r�������ʼn^�] ������Ȃ������������Ȃ�̂ł���B���������āA���̂悤�� �h�������^�[�{�R���p�E���h��p���ăf�B�[�[���G���W���̔R�� �����P���悤�Ƃ��邱�Ƃ́A����ł��邱�Ƃ����炩���B���̂��߁A ���L����ʈ��S����������SCD�G���W���_���ɂ����āA ��ʈ��S���������̗�؉��ꎁ�A�Έ�f���A����㎁ ����ѐV�G�B�V�[�C�[�̐� �F�O�����^�[�{�R���p�E���h�� �f�B�[�[���G���W���̔R����P�̎�i�ƔF������Ă��邱�Ƃ� ���ƍl������B�����āA�{���{��X�J�j�A�̉��Ẵg���b�N ���[�J�́A�^�[�{�R���p�E���h�͓����ő刳�͂��㏸�����邱�Ɩ��� �o�͂������ł����i�Ɨ������Ă���悤�ł���B�����āA�]���� �P�i�ߋ���Q�i�ߋ��̃f�B�[�[���G���W���Ƀ^�[�{�R���p�E���h�� �P�ɑ������������̃^�[�{�R���p�E���h�V�X�e���ɂ��ẮA���� �̃g���b�N���[�J�i���{���{��X�J�j�A���j�̔F���E������������ �悤�ɍl������B �@�Ƃ���ŁA�^�[�{�R���p�E���h��p���ăf�B�[�[���G���W���̔R��� �����ł����P������@�́A�M�҂́A �C���x�~�́A�f�B�[�[���r�C�K�X�̃G�l���M�[���u�̌��������� �ɏڏq���Ă�������悤�ɁA��^���b�N�̑��s�ő��p�����f�B�[�[�� �f�B�[�[���G���W���̕������^�]���̔r�C�K�X���x�̍������� �}�邱�Ƃ��K�v�ł���A���̕��@�Ƃ��āA�M�Ғ�Ă� �C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p��p���邱�Ƃ� �L���ł���B���������āA���̌�ʈ��S����������SCD�G���W���� �^�[�{�R���p�E���h�g���킹�Ď����s�R��܂��͏d�ʎԃ��[�h�R��� �{�C�ʼn��P�������̂ł���A�S�O�Ȃ����L����ʈ��S�������� ��SCD�G���W�����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p�� �̗p���ׂ��ƍl������B�������Ȃ���A�|���R�c���Z�p���̕M�҂� ��Ă��Ă����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p��SCD �G���W���ɍ̗p���邱�Ƃ́A��ʈ��S���������̗�؉��ꎁ�A �Έ�f���A����㎁����ѐV�G�B�V�[�C�[�̐� �F�O���� �Ƃ��ẮA���{���\����f�B�[�[���G���W���̊w�ҁE���ƂƂ��� �̎����S�E�ʎq�E�v���C�h�������Ȃ��Ǝv�����A�@���Ȃ��̂ł��낤���B �@�������A���̌�ʈ��S���������̃^�[�{�R���p�E���h�𓋍ڂ��� �]����SCD�G���W������Q�i�^�[�{��p�~���A�V���ɕ���Q�^�[�{ �������C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p��lj� �����^�[�{�R���p�E���h�̗p�́u�V���ȉ��nj^��SCD�G���W���v�� ���ǂ����ꍇ�ɂ́A���́u�V���ȉ��nj^��SCD�G���W���v�́A �^�[�{�R���p�E���h�ɂ�镔�����^�]���̔R����P���{�����A ���̏�ɐV�����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�ɂ�� �G���W�����������̔R����P�̌��ʂ��lj�����A2015�N �x�d�ʎԔR�����P�O�����R����サ�� 4.5 �����^���b�g���� �d�ʎԃ��[�h�R��̑�^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W�����e�Ղ� �����ł���Ɨ\�z�����B���̌�ʈ��S���������̒���R��� �u�V���ȉ��nj^��SCD�G���W���v�́A��ʈ��S���������� ��؉��ꎁ�A�Έ�f���A����㎁����ѐV�G�B�V�[�G�[�� �� �F�O���̏��������Ӗ��Ȏ��g�̎����S�E�ʎq�E�v���C�h�� �ʑ��ɂ��Ă̊S�������Y��A�E�C�������ď]����ʈ��S ����������SCD�G���W���� �C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p���̗p���� ���Ƃɂ���āA�e�ՂɎ����ł��邱�Ƃł���B �@���̂悤�ɁA��ʈ��S���������̗�؉��ꎁ�A�Έ�f���A ����㎁����ѐV�G�B�V�[�C�[�̐� �F�O���̏��������g�� ���s�s�Ȏ����S�E�ʎq�E�v���C�h�ɖ��S�ɂȂ邾���ŁA �C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p��lj������V���� SCD�G���W���̎������\�ƂȂ�A2015�N�x�d�ʎԔR���� �P�O�����R����サ�� 4.5 �����^���b�g���̏d�ʎԃ��[�h�R��̑�^ �g���b�N�p�f�B�[�[���G���W���������ł���̂ł���B�����āA ����ɂ���āA���{�ɂ������^�g���b�N�̔���I�Ȕ���オ�� ���W�E���i�ł���̂ł���B�������邱�Ƃɂ���āA�ʈ��S�� �������̗�؉��ꎁ�A�Έ�f���A����㎁����� �V�G�B�V�[�C�[�̐� �F�O���̏����́A���{�̑�^�g���b�N�� �R�����ɑ傫���v�����A�㐢�ɖ����c�����Ƃ��ł���Ɛ��@ �����B���͂Ƃ�����A��ʈ��S���������̗�؉��ꎁ�A �Έ�f���A����㎁����ѐV�G�B�V�[�C�[�̐� �F�O���� �E�C���錈�f�������ׂ��ƍl���邪�A�@���Ȃ��̂ł��낤���B �M�҂͑傢�Ɋ��҂��Ă���Ƃ���ł���B�@ |
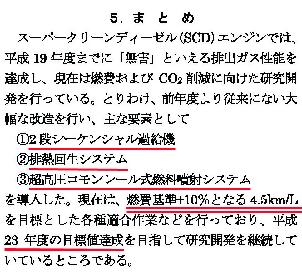 |
�@���L����ʈ��S����������SCD�G���W���_���ɂ����ẮASCD
�G���W���ɑg�ݍ��܂ꂽ�e��̔R��팸�̋Z�p�ƁA���ꂼ��̋Z�p �ɂ�����R����P�̖ڕW�����L����Ă���A������Z�߂�ƈȉ��� �ʂ�ł���B�i�Ȃ��A�e�Z�p�̂����̔R����P�̖ڕW�́A�������� ���@����ƁA�����JE�O�T���[�h�̔R��Ɨ\�������B�j �� �Q�i�V�[�P���V�����ߋ��@
�R����P���T��
�� �������R�������[���i��260MPa�j
�@�@�R����P���R�`�T��
�� �r�M����V�X�e���i���^�[�{�R���p�E���h�j �@�@�R����P���P�`�R�� �ȏ�̂悤�ɁA���L����ʈ��S����������SCD�G���W���_���ł́A �ŋ߁A�b��ƂȂ��Ă���ڐV�����Z�p�́A�啝�ȔR����P���\�� �l�����悤�ȋL�q�Ŗ�������Ă���B���������ƁA�u�o�i�i�̂����� ����v��A�z������悤�ȔR����P�Z�p�́u�������v�̗l����悵�� ����B���̋ɂߕt���́A���L����ʈ��S����������SCD�G���W�� �_���́u�T�@�� �� �߁v�ł́A�u�Q�i�V�[�P���V�����ߋ��@�v�{�u�r�M��� �V�X�e���v�{�u�������R�������[���v�ɂ���đ�^�g���b�N�iGVW�Q�T�g���j ��2015�N�x�d�ʎԔR�����P�O�����R����サ��4.5 �����^���b�g�� �̏d�ʎԃ��[�h�R������Q�R�N�x�Ɏ����ł���Ɛ錾����Ă��邱�� �ł͂Ȃ����낤���B���҂̌�ʈ��S���������̗�؉��ꎁ�A �Έ�f���A����㎁����ѐV�G�B�V�[�C�[�̐� �F�O���̏����́A �����Q�R�N�x �����L����ʈ��S����������SCD�G���W���_���́u�T�@�� �� �߁v�� �L�ڂ��ꂽ��^�g���b�N�̔R�����̖ڕW�i���d�ʎԗʎԃ��[�h�R�� �F 4.5 �����^���b�g���j��{���Ɏ����ł���l�����Ă���̂� ���낤���B���݂ɁA�M�҂͂��̖ڕW�B�������܁E���s����\���� �ɂ߂č����Ǝv���Ă���B �@�Ȃ��Ȃ�ANEDO�̊v�V�I���������Q�ԑ����Z�p�J�� �i�N���[���f�B�[�[���v���W�F�N�g�A2004�`2009�N�j�́u�����x�R�� ����G���W�V�X�e���̌����J���v�ł́A�u���i�ߋ��V�X�e���v�{ �u�������R�������[���v�𓋍ڂ����f�B�[�[���ł͊��ɔR����P�� ����Ȃ��Ƃ��m�F����Ă���̂ł���B�܂��A�u�^�[�{�R���p�E���h �V�X�e���v�ɂ��ẮA���̃V�X�e���𓋍ڂ�����^�g���b�N���s�� ���Ă���{���{�A�f�g���C�g�f�B�[�[��������́u�^�[�{�R���p�E���h �ł͔R����P������v�Ƃ̏���M����Ă���̂ł���B �����̂��Ƃ���A�u�Q�i�V�[�P���V�����ߋ��@�v���u�r�M��� �V�X�e���v���u�������R�������[���v�̊e�Z�p�́A����܂ł̌��� �J���ɂ���ĔR����P���w��NJ��҂ł��Ȃ����Ƃ����ɔ��� ���Ă���̂ł���B �@���������āA��ʈ��S���������̗�؉��ꎁ�A�Έ�f���A ����㎁����ѐV�G�B�V�[�C�[�̐� �F�O���̏����́A �u�Q�i�V�[�P���V�����ߋ��@�v�{�u�r�M����V�X�e���v�{�u������ �R�������[���v���̗p������ʈ��S����������SCD�G���W���� ����āA��^�g���b�N�iGVW�Q�T�g���j�ɂ�����2015�N�x�d�ʎԔR�� ����P�O�����R����サ�� 4.5 �����^���b�g���̏d�ʎԃ��[�h�R�� �̖ڕW���Q�R�N�x�ɒB������Ɛ錾���Ă��邪�A����SCD �G���W���ɑg�ݍ��܂ꂽ�Z�p�����ł͂��̖ڕW�̔R����������� ���Ƃ͕s�\�ƍl������B �@���̑�^�g���b�N�iGVW�Q�T�g���j�ɂ�����2015�N�x�d�ʎԔR�� ����P�O�����R����サ�� 4.5 �����^���b�g���̏d�ʎԃ��[�h�R�� �̖ڕW��B������B��̕��@�́A��ʈ��S���������̃^�[�{ �R���p�E���h�𓋍ڂ����]����SCD�G���W������Q�i�^�[�{�� �p�~���A�V���ɕ���Q�^�[�{�i�Q�^�[�{�j�� �C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p��lj����� �^�[�{�R���p�E���h�̗p�̐V���ȉ��nj^��SCD�G���W���ɉ��ǂ��� ���Ƃł���B ���̐V���ȉ��nj^��SCD�G���W���́A�^�[�{�R���p�E���h�ɂ�� �������^�]���̔{�������R����P�� �C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�ɂ��G���W������ �����̔R����P�̌��ʂ��lj�����A2015�N�x�d�ʎԔR�� ����P�O�����R����サ�� 4.5 �����^���b�g���̏d�ʎԃ��[�h �R��̑�^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W�����e�ՂɎ����ł��邱�� �ɂȂ�B �������A�|���R�c�̌��Z�p���̕M�҂���Ă��Ă��� �C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p��SCD�G���W���� �̗p���邱�Ƃ́A��ʈ��S���������̗�؉��ꎁ�A�Έ�f���A ����㎁����ѐV�G�B�V�[�C�[�̐� �F�O���̊w�ҁE���� �Ƃ��Ă̎����S�E�ʎq�E�v���C�h�������Ȃ����̂Ɛ��@�����B �@���̌��ʁA2012�N7��23�����݂ł́A��ʈ��S���������� ��؉��ꎁ�A�Έ�f���A����㎁����ѐV�G�B�V�[�C�[�� �� �F�O���́A��ʈ��S����������SCD�G���W����p������^ �g���b�N�iGVW�Q�T�g���j�ɂ�����2015�N�x�d�ʎԔR�����P�O���� �R����サ�� 4.5 �����^���b�g���̏d�ʎԃ��[�h�R����Q�R�N�x�� �B������Ƃ̍��L�̖ڕW�́A�����ɒB���ł����Ƃ̔��\���s���� ���Ȃ��悤���B�����Ƃ��A��ʈ��S����������SCD�G���W���̌��� �J�������s�ɏI������Ƃ̔��\���s���Ă��Ȃ��悤�Ɍ�����B ���̂悤�ȏ���A��ʈ��S���������̗�؉��ꎁ�A �Έ�f���A����㎁����ѐV�G�B�V�[�C�[�̐� �F�O���́A ��ʈ��S����������SCD�G���W����p���������v���W�F�N�g�� ���ʂɂ��ẮA���ꂩ����u�_���}���E�ٔ�v�𑱂���Ӑ}�E�ӌ��� �悤�Ɏv���邪�A�@���Ȃ��̂ł��낤���B �@���ɁA��ʈ��S����������SCD�G���W���v���W�F�N�g�̋��J���� ���s�ɏI����Ă����ꍇ�ł��A���̎������ʂ����\�����A ��ʈ��S����������SCD�G���W���v���W�F�N�g�́A������ �f�B�[�[���G���W���W�̊w�ҁE���Ƃɂ́u�R�����ɖ����� �Z�p�v�Ƃ��Ă̋M�d�ȋZ�p�����邱�ƂɂȂ�A�����I �ɂ��M�d�ȋZ�p���Ƃ��čL�����p�����ł��锤�ł���B �����āA���̂悤�Ȕ��\�ɂ���āA��ʈ��S����������SCD �G���W���v���W�F�N�g�ɒ������܂ꂽ����������̐ŋ��́A �����͍����̐����ɐ�������邱�ƂɂȂ�ƍl������B �������A��ʈ��S���������̗�؉��ꎁ�A�Έ�f���A����㎁ ����ѐV�G�B�V�[�C�[�̐� �F�O������ʈ��S���������� SCD�G���W���̌����v���W�F�N�g�̎������ʂ��āA���ꂩ��� �u�_���}���E�ٔ�v�𑱂����ꍇ�A���{�̑����̃f�B�[�[���G���W�� �W�̊w�ҁE���Ƃɂ́A�u�R�����ɖ����ȋZ�p�v�̋Z�p��� ������Ȃ����ƂɂȂ�A��ʈ��S����������SCD�G���W�� �v���W�F�N�g�ɒ������܂ꂽ����������́A���������u�ǂԐ�v�� �̂Ă�ꂽ�@���A���̖��ʎg���ɏI����Ă��܂��ƍl������B �@����A�O�q��14-1���Ɏ�����NEDO�́u�����x�R�Đ���G���W�V �X�e���̌����J���v�ł́A�R����̑厸�s�𐳒��ɕ��� ����̂ł���B���̂悤��NEDO�̌����J���̏ꍇ�ɂ͕s������ �I�����������J���̏ꍇ�ɂ́A���s���������J���̎����f�[�^ �������̐l�ɋZ�p���Ƃ��Đ����Ɏ������ʂ�����Ă��� �̂ł���B�Ƃ��낪�A����NEDO�̃v���W�F�N�g�Ɠ��l�ɐŋ��� �g���Ă���ɂ�������炸�A��ʈ��S����������SCD�G ���W���v���W�F�N�g�̌��ʂ́A�R�����Ɏ��s�������Ƃɂ���� �����f�[�^�𖢌��\�Ƃ��A��ʈ��S����������SCD�G���W�� �v���W�F�N�g��S�������ʈ��S���������̗�؉��ꎁ�A �Έ�f���A����㎁����ѐV�G�B�V�[�C�[�̐� �F�O���� ����Ă��̃v���W�F�N�g�̋M�d�Ȏ����f�[�^������ׂ���� ����悤�Ɍ�����̂ł���B���̂��Ƃ������ł���A ��ʈ��S����������SCD�G���W���v���W�F�N�g��S������ ��ʈ��S���������̗�؉��ꎁ�A�Έ�f���A����㎁ ����ѐV�G�B�V�[�C�[�̐� �F�O���́A�ꗬ�̊w�ҁE���ƁE �Z�p�҂Ƃ��Ĕ������ׂ��������E�ǐS�̌��������l�B�̂悤�� �v���邪�A�{���̂Ƃ���͔@���Ȃ��̂ł��낤���B �@���ɁA��ʈ��S���������̗�؉��ꎁ�A�Έ�f���A ����㎁����ѐV�G�B�V�[�C�[�̐� �F�O���́A�w�ҁE ���ƁE�Z�p�҂Ƃ��Ă̗ǐS�E���ӂ��������l�B�ł���A ��ʈ��S����������SCD�G���W���v���W�F�N�g�ɂ����� �����̖ڕW�ł������u��^�g���b�N�iGVW�Q�T�g���j �ɂ�����2015�N�x�d�ʎԔR�����P�O���̔R����コ���� 4.5 �����^���b�g���̏d�ʎԃ��[�h�R��v���B���\��̊����ł��� ����23�N�x�ɖ��B�ɏI������Ƃ��Ă��A����̓��{�̑�^ �g���b�N�ɂ�����R�����̋Z�p�J���Ɋ��p�ł���悤�� ���邽�߁A���̎��_�Ō�ʈ��S����������SCD�G���W�� �v���W�F�N�g�̌����J���̎����f�[�^�𐳒��Ɍ��\���Ă��锤�ł� �Ȃ����낤���B�Ȃ��Ȃ�A�����J���̎��s�f�[�^���A���̌�� �����J���̐��i�ɂ͋M�d�Ȋ����̃f�[�^�Ƃ��Đ��������Ƃ� �ł��邽�߂ł���B���̂��Ƃ���A���{�̗\�Z�i���ŋ��j���g���� �����v���W�F�N�g�����{����w�ҁE���Ƃ́A�ǐS�E���ӂ̂��� �l�B�łȂ���A�ŋ��̖��ʎg���ɂȂ�悤�Ɏv���邪�A �@�����Ȃ��̂ł��낤���B�ܘ_�A��ʈ��S����������SCD �G���W���v���W�F�N�g�����s�ɏI������ꍇ�Ɍ�ʈ��S�� �������̗�؉��ꎁ�A�Έ�f���A����㎁����� �V�G�B�V�[�C�[�̐� �F�O�������̃v���W�F�N�g�̌������ �S�z�𐭕{�ɕԊҁE�Ԕ[����A�������ʂ��u����J�v�A �u�����\�A�u����ׂ��v�Ƃ����Ă�������邱�Ƃł���B �t�Ɍ����A��ʈ��S���������̗�؉��ꎁ�A�Έ�f���A ����㎁����ѐV�G�B�V�[�C�[�̐� �F�O�������̃v���W�F�N�g ������̑S�z�𐭕{�ɕԊҁE�Ԕ[���Ȃ��̂ł���A ���̃v���W�F�N�g�̋M�d�Ȏ������ʂ́A��ɔ��\�E���\�� �s���ׂ��ł���B���Ɍ�ʈ��S���������̗�؉��ꎁ�A �Έ�f���A����㎁����ѐV�G�B�V�[�C�[�̐� �F�O���� ���̃v���W�F�N�g�̋M�d�Ȏ������ʂ��u����J�v�A�u�����\�v�A�u���E�v ���Ĉ���ׂ����ꍇ�́A���{�̗\�Z�i���ŋ��j�̎��I���p�� ����Ă��d���̖������Ƃł͂Ȃ����낤���B �@ �@�܂��A���ɁA����23�N�x�ɏI���\��̌�ʈ��S���������� SCD�G���W���v���W�F�N�g���^�[�{�R���p�E���h���̗p���Ă���ɂ� ������炸�A�u��^�g���b�N�iGVW�Q�T�g���j�ɂ�����2015�N�x�d�ʎ� �R�����P�O���̔R����コ���� 4.5 �����^���b�g���̏d�ʎ� ���[�h�R��v�̔R�����̖ڕW�����B���ł��������Ƃ������� ����Ċm�F����A���̌��ʂ����\���ꂽ�̂ł���A�f�B�[�[�� �G���W���̕��������̔r�C�K�X���x������������Z�p�� �g�ݍ��킹�Ȃ��ꍇ�ɂ́A�^�[�{�R���p�E���h���̗p���Ă���^ �g���b�N�̎����s�R���d�ʎԃ��[�h�R������P���邱�Ƃ����� �ł��邱�Ƃ������ꂽ���ƂɂȂ�B�����āA���̂��Ƃ́A�^�[�{ �R���p�E���h�̗̍p�ɂ��d�ʎԃ��[�h�R��̉��P��}�邽�߂ɂ́A �C���x�~�́A�f�B�[�[���r�C�K�X�̃G�l���M�[���u�̌��������� �ɏڏq�M���Ă���悤�ɁA�^�[�{�R���p�E���h���̗p����G���W�� �̕��������̔r�C�K�X���x������������Z�p�Ƃ��āA�Ⴆ�� �C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p��g���킹�� ���Ƃ��K�v�E�s���ł���Ƃ̐����̍����𑽂��̊w�ҁE���Ƃ� ���邱�ƂɂȂ�B �@���Ă��āA���݂̂Ƃ���A���̌�ʈ��S����������SCD �G���W���v���W�F�N�g�̎������ʂ́A����24�N7��23�����݂ł��A �����\�E�B���̏�Ԃɕێ�����Ă���悤�ł���B�ʂ����āA �������ʈ��S����������SCD�G���W���v���W�F�N�g�� �������ʂ����\����邱�Ƃ͖����̂ł��낤���B���̂悤�ɁA ��������W�߂��M�d�Ȑŋ��ɂ���Ď��{���ꂽ��ʈ��S�� ��������SCD�G���W���v���W�F�N�g�̎������ʂ�����̓��{�� ��^�g���b�N�ɂ�����R�����̋Z�p�J���ɉi���ɐ�������Ȃ� �̂ł���A��ʈ��S���������̗�؉��ꎁ�A�Έ�f���A ����㎁����ѐV�G�B�V�[�C�[�̐� �F�O���́A�u�ŋ��D�_�v �̔���Ƃ�Ȃ��悤�Ɏv���邪�A�@���Ȃ��̂ł��낤���B |
�V�W�J�v�ł́A�u�Q�i�V�[�P���V�����ߋ��@�v���u�r�M����V�X�e���i�^�[�{�R���p�E���h�j�v���u�������R�������[���v�̋Z
�p��p����2015�N�x�d�ʎԔR�����P�O�����R����サ�� 4.5 �����^���b�g���̏d�ʎԃ��[�h�R��̑�^�g���b�N
�iGVW�Q�T�g���j�������Q�R�N�x����������\��Ɛ錾����Ă���B�������A�u�Q�i�V�[�P���V�����ߋ��@�v���u�r�M����V
�X�e���i�^�[�{�R���p�E���h�j�v���u�������R�������[���v�̊e�Z�p�́A������f�B�[�[���̔R����P�̌��ʂ��w��NJ�
�҂ł��Ȃ��V�X�e���ł���B���������āA��ʈ��S����������SCD�i�X�[�p�[�N���[���f�B�[�[���j�G���W���̌����J
���v���W�F�N�g�������Q�R�N�x���d�ʎԃ��[�h�R��� 4.5 �����^���b�g���̑�^�g���b�N�iGVW�Q�T�g���j����������ڕW��
�B���́A���S�Ɏ��s�̌����ɂȂ���̂Ɨ\�z�����B
�@���̌�ʈ��S����������SCD�G���W���_���̒��҂̈�l�́A�V�G�B�V�[�C�[�̐� �F�O���ł���B���݂ɁA�V�G
�B�V�[�C�[�́A�����ԃ��[�J�[�ƕ��i��Ђ��o�����A�g���b�N���[�J�S��(����A�����U�A�t�c�A�O�H�ӂ���)���猤���҂��h
������Ă��錤�����ł���B�����āA�V�G�B�V�[�C�[�̏햱������ł���� �F�O���́A�V�G�B�V�[�C�[�̏�Ί�����
�g�b�v�ł���A����̐V�G�B�V�[�C�[�̌����������w������Ă�����̂Ɛ��@�����B���̐V�G�B�V�[�C�[�ł́A�C���x
�~�G���W���ɂ���^�g���b�N�̒�R��̃y�[�W�� �y�P�Q�|�R�D���V�G�B�V�[�C�[���C���x�~�̎������ʂ̔��\��
�~���Ă��闝�R�́A�����H�z�̍��ɏڏq���Ă���悤�ɁA���V�G�B�V�[�C�[�́A�Q�O�O�S�N�Ƀf�B�[�[���G���W���̋C���x
�~�̎��������{���A���̋C���x�~�ɂ�����R����P�̌��ʂ��m�F���������f�[�^���擾���Ă���悤�ł���B
�B�V�[�C�[�́A�����ԃ��[�J�[�ƕ��i��Ђ��o�����A�g���b�N���[�J�S��(����A�����U�A�t�c�A�O�H�ӂ���)���猤���҂��h
������Ă��錤�����ł���B�����āA�V�G�B�V�[�C�[�̏햱������ł���� �F�O���́A�V�G�B�V�[�C�[�̏�Ί�����
�g�b�v�ł���A����̐V�G�B�V�[�C�[�̌����������w������Ă�����̂Ɛ��@�����B���̐V�G�B�V�[�C�[�ł́A�C���x
�~�G���W���ɂ���^�g���b�N�̒�R��̃y�[�W�� �y�P�Q�|�R�D���V�G�B�V�[�C�[���C���x�~�̎������ʂ̔��\��
�~���Ă��闝�R�́A�����H�z�̍��ɏڏq���Ă���悤�ɁA���V�G�B�V�[�C�[�́A�Q�O�O�S�N�Ƀf�B�[�[���G���W���̋C���x
�~�̎��������{���A���̋C���x�~�ɂ�����R����P�̌��ʂ��m�F���������f�[�^���擾���Ă���悤�ł���B
����ɂ��ẮA���L�̂悤�ɁA���̇��V�G�B�V�[�C�[����A�Q�O�O�X�N�����A�u���V�G�B�V�[�C�[�͂Q�O�O�S�N�Ɏ��{����
�f�B�[�[���G���W���̋C���x�~�̎����ɂ����āA�R�����P�̌��ʂ��m�F���Ă����v �Ƃ̏������V�G�B�V�[�C�[����
��M�����d���[���ɂ���ĕM�҂͓��肵�Ă���B���̂d���[���̓��e�������̇��V�G�B�V�[�C�[�̐��F�O�В��ɑ��t
����Ă��邱�Ƃ���A�u���V�G�B�V�[�C�[�͂Q�O�O�S�N�Ɏ��{�����f�B�[�[���G���W���̋C���x�~�̎����ɂ����āA�R����
�P�̌��ʂ��m�F���Ă����v �Ƃ̏��́A���V�G�B�V�[�C�[�̓����Ō��F����Ă����Ɛ��������B�܂�A���V�G�B�V�[
�C�[���͂Q�O�O�S�N���Ƀf�B�[�[���G���W���̋C���x�~�ɂ��R�����P�̎����f�[�^���擾���Ă������Ƃ������ƍl��
����B
�f�B�[�[���G���W���̋C���x�~�̎����ɂ����āA�R�����P�̌��ʂ��m�F���Ă����v �Ƃ̏������V�G�B�V�[�C�[����
��M�����d���[���ɂ���ĕM�҂͓��肵�Ă���B���̂d���[���̓��e�������̇��V�G�B�V�[�C�[�̐��F�O�В��ɑ��t
����Ă��邱�Ƃ���A�u���V�G�B�V�[�C�[�͂Q�O�O�S�N�Ɏ��{�����f�B�[�[���G���W���̋C���x�~�̎����ɂ����āA�R����
�P�̌��ʂ��m�F���Ă����v �Ƃ̏��́A���V�G�B�V�[�C�[�̓����Ō��F����Ă����Ɛ��������B�܂�A���V�G�B�V�[
�C�[���͂Q�O�O�S�N���Ƀf�B�[�[���G���W���̋C���x�~�ɂ��R�����P�̎����f�[�^���擾���Ă������Ƃ������ƍl��
����B
 |
�@�Ƃ��낪�A���̂d���[�������M���ꂽ009�N12��26���̎��_�ł́A���̋C���x�~�̎������I�����Ă�����ɂT�N�ȏ�
���o�߂����Ă���ɂ�������炸�A�����ɇ��V�G�B�V�[�C�[�̓f�B�[�[���G���W���̋C���x�~�̎������ʂ\���Ă�
�Ȃ��悤���B�ʏ�A��ʂ̌������ł́A�������{�̗��N�ɂ͂��̎������ʂ��܂Ƃ߂��Ĕ��\�������̂��B�������A
���V�G�B�V�[�C�[�ł́A���p�����e�ՂŔR�����P�Ɍ��ʂ�����C���x�~�̎������Q�O�O�S�N�Ɏ��{���ꂽ�ɂ�������
�炸�A���̎������ʂ̔��\���T�N�ȏ���x�点�����Ă���̂ł���B���̏́A��ʓI�Ȍ����@�ւ̍s���E�����Ƃ�
�Ă͉��Ƃ���Ȃ��Ƃł���B
���o�߂����Ă���ɂ�������炸�A�����ɇ��V�G�B�V�[�C�[�̓f�B�[�[���G���W���̋C���x�~�̎������ʂ\���Ă�
�Ȃ��悤���B�ʏ�A��ʂ̌������ł́A�������{�̗��N�ɂ͂��̎������ʂ��܂Ƃ߂��Ĕ��\�������̂��B�������A
���V�G�B�V�[�C�[�ł́A���p�����e�ՂŔR�����P�Ɍ��ʂ�����C���x�~�̎������Q�O�O�S�N�Ɏ��{���ꂽ�ɂ�������
�炸�A���̎������ʂ̔��\���T�N�ȏ���x�点�����Ă���̂ł���B���̏́A��ʓI�Ȍ����@�ւ̍s���E�����Ƃ�
�Ă͉��Ƃ���Ȃ��Ƃł���B
�@���̈���ɂ����āA�V�G�B�V�[�C�[�̐� �F�O���́A�f�B�[�[���R��̑傫�ȉ��P�����҂ł��Ȃ��u�Q�i�V�[�P���V
�����ߋ��@�v���u�r�M����V�X�e���i�^�[�{�R���p�E���h�j�v���u�������R�������[���v�̋Z�p��g�����邱�Ƃɂ��A2015
�N�x�d�ʎԔR�����P�O�����R����サ�� 4.5 �����^���b�g���̏d�ʎԃ��[�h�R��̑�^�g���b�N�iGVW�Q�T�g���j����
���Q�R�N�x����������Ɛ錾������ʈ��S���������́uSCD�G���W���̌����J���v�̃v���W�F�N�g�ɎQ�悵�A�_����
���҂̈�l�Ƃ��Ė���A�˂Ă���̂��B�������A��ʈ��S����������SCD�G���W���̌����J���v���W�F�N�g�ł́A�R
����P�̌��ʂ��w��NJ��҂ł��Ȃ��u�Q�i�V�[�P���V�����ߋ��@�v���u�r�M����V�X�e���i�^�[�{�R���p�E���h�j�v���u��
�����R�������[���v�̋Z�p���g�ݍ��܂�Ă��邪�A�̐S�v���R����P�ɑ傫�Ȍ��ʂ�����u�C���x�~�v�̋Z�p��
�g�ݍ��܂�Ă��Ȃ��̂ł���B���̏�����ƁA�V�G�B�V�[�C�[�̐� �F�O���́A���̘_���̋����҂ł�����ʈ�
�S���������̗�؉��ꎁ�A�Έ�f���A����㎁�ɑ��A�u2004�N�ɐV�G�B�V�[�C�[���C���x�~�ɂ���ăf�B�[�[
���G���W���̔R����P�̌��ʂ��m�F���������f�[�^�v�������J�����Ă��Ȃ��\��������ƍl������B
�����ߋ��@�v���u�r�M����V�X�e���i�^�[�{�R���p�E���h�j�v���u�������R�������[���v�̋Z�p��g�����邱�Ƃɂ��A2015
�N�x�d�ʎԔR�����P�O�����R����サ�� 4.5 �����^���b�g���̏d�ʎԃ��[�h�R��̑�^�g���b�N�iGVW�Q�T�g���j����
���Q�R�N�x����������Ɛ錾������ʈ��S���������́uSCD�G���W���̌����J���v�̃v���W�F�N�g�ɎQ�悵�A�_����
���҂̈�l�Ƃ��Ė���A�˂Ă���̂��B�������A��ʈ��S����������SCD�G���W���̌����J���v���W�F�N�g�ł́A�R
����P�̌��ʂ��w��NJ��҂ł��Ȃ��u�Q�i�V�[�P���V�����ߋ��@�v���u�r�M����V�X�e���i�^�[�{�R���p�E���h�j�v���u��
�����R�������[���v�̋Z�p���g�ݍ��܂�Ă��邪�A�̐S�v���R����P�ɑ傫�Ȍ��ʂ�����u�C���x�~�v�̋Z�p��
�g�ݍ��܂�Ă��Ȃ��̂ł���B���̏�����ƁA�V�G�B�V�[�C�[�̐� �F�O���́A���̘_���̋����҂ł�����ʈ�
�S���������̗�؉��ꎁ�A�Έ�f���A����㎁�ɑ��A�u2004�N�ɐV�G�B�V�[�C�[���C���x�~�ɂ���ăf�B�[�[
���G���W���̔R����P�̌��ʂ��m�F���������f�[�^�v�������J�����Ă��Ȃ��\��������ƍl������B
�@���ɁA�V�G�B�V�[�C�[�̐� �F�O�����Q�O�O�S�N�ɐV�G�B�V�[�C�[���C���x�~�̋Z�p�ɂ���ăf�B�[�[���G���W���̔R
������P�ł��������f�[�^����ʈ��S���������̗�؉��ꎁ�A�Έ�f���A����㎁�ɊJ�����Ă��Ȃ���������
�������ł���A�V�G�B�V�[�C�[�̐� �F�O���͌�ʈ��S������������̂́u�X�[�p�[�N���[���f�B�[�[���iSCD�j
�G���W���ɂ���^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W�����R�����v���W�F�N�g�v�̍��܁E���s���ŏ�������Ă���
�\��������ƍl������B�܂�A�V�G�B�V�[�C�[�̐� �F�O���́A��ʈ��S���������̐��Ƃɑ��A��^�g��
�b�N�̎����s�R���d�ʎԃ��[�h�R��̉��P�ɑ傫�Ȍ��ʂ����҂ł��Ȃ��u�Q�i�V�[�P���V�����ߋ��@�v���u�������R
�������[���v��A�C���x�~�́A�f�B�[�[���r�C�K�X�̃G�l���M�[���u�̌����������̃y�[�W�ɏڏq���Ă���悤
�ɁA�C���x�~�̋Z�p��g�ݍ��킹�Ȃ��ꍇ�ɂ͑�^�g���b�N�̎����s�R���d�ʎԃ��[�h�R��̉��P�ɑ傫�Ȍ���
�����҂ł��Ȃ��u�^�[�{�R���p�E���h�v�̋Z�p���u��R��Z�p�v�Ƃ��Č�ʈ��S���������̐��Ƃɐ������Ă�����
�\��������ƍl������B
������P�ł��������f�[�^����ʈ��S���������̗�؉��ꎁ�A�Έ�f���A����㎁�ɊJ�����Ă��Ȃ���������
�������ł���A�V�G�B�V�[�C�[�̐� �F�O���͌�ʈ��S������������̂́u�X�[�p�[�N���[���f�B�[�[���iSCD�j
�G���W���ɂ���^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W�����R�����v���W�F�N�g�v�̍��܁E���s���ŏ�������Ă���
�\��������ƍl������B�܂�A�V�G�B�V�[�C�[�̐� �F�O���́A��ʈ��S���������̐��Ƃɑ��A��^�g��
�b�N�̎����s�R���d�ʎԃ��[�h�R��̉��P�ɑ傫�Ȍ��ʂ����҂ł��Ȃ��u�Q�i�V�[�P���V�����ߋ��@�v���u�������R
�������[���v��A�C���x�~�́A�f�B�[�[���r�C�K�X�̃G�l���M�[���u�̌����������̃y�[�W�ɏڏq���Ă���悤
�ɁA�C���x�~�̋Z�p��g�ݍ��킹�Ȃ��ꍇ�ɂ͑�^�g���b�N�̎����s�R���d�ʎԃ��[�h�R��̉��P�ɑ傫�Ȍ���
�����҂ł��Ȃ��u�^�[�{�R���p�E���h�v�̋Z�p���u��R��Z�p�v�Ƃ��Č�ʈ��S���������̐��Ƃɐ������Ă�����
�\��������ƍl������B
�@�ȏ�̂悤�Ȃ��Ƃ����Ɏ����ł���A��ʈ��S���������̗�؉��ꎁ�A�Έ�f���A����㎁�́A��ʈ��S
����������SCD�G���W���̌����J���v���W�F�N�g�Ɏ��s�ɓ������߂́i���j�V�G�B�V�[�C�[�̐� �F�O���̖d���Ɉ�
�����������n���ȃs�G���ƌ��邱�Ƃ��\���B���̏ꍇ�ɂ́A��ʈ��S���������̐��Ƃɑ��ẮA����Ɖ]����
�t�������Ă͂܂�Ȃ��̂ł͂Ȃ����낤���B�����͌����Ă��A���̂悤�ȍ��\�I�Ȃ��Ƃ��{���ł������ꍇ�A�x��������
�V�G�B�V�[�C�[�̐� �F�O�����ᔻ����邱�Ƃ͖ܘ_�ł��邪�A�x���ꂽ���̌�ʈ��S���������̗�؉��ꎁ�A
�Έ�f���A����㎁�̕��X���f�B�[�[���G���W���̔R����P�Z�p�ɂ��Ă̒m���E�����W�̕s����p�������
���ł���A���Ȃ��ׂ����Ƃł͂Ȃ����ƍl������B
����������SCD�G���W���̌����J���v���W�F�N�g�Ɏ��s�ɓ������߂́i���j�V�G�B�V�[�C�[�̐� �F�O���̖d���Ɉ�
�����������n���ȃs�G���ƌ��邱�Ƃ��\���B���̏ꍇ�ɂ́A��ʈ��S���������̐��Ƃɑ��ẮA����Ɖ]����
�t�������Ă͂܂�Ȃ��̂ł͂Ȃ����낤���B�����͌����Ă��A���̂悤�ȍ��\�I�Ȃ��Ƃ��{���ł������ꍇ�A�x��������
�V�G�B�V�[�C�[�̐� �F�O�����ᔻ����邱�Ƃ͖ܘ_�ł��邪�A�x���ꂽ���̌�ʈ��S���������̗�؉��ꎁ�A
�Έ�f���A����㎁�̕��X���f�B�[�[���G���W���̔R����P�Z�p�ɂ��Ă̒m���E�����W�̕s����p�������
���ł���A���Ȃ��ׂ����Ƃł͂Ȃ����ƍl������B
�@���āA���ۂ̂Ƃ���́A�V�G�B�V�[�C�[�̐� �F�O���́A��ʈ��S���������́u�X�[�p�[�N���[���f�B�[�[��
�iSCD�j�G���W���ɂ���^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W���̒�R��v���W�F�N�g�v�̏����̒i�K�ŁA��ʈ��S��������
�̗�؉��ꎁ�A�Έ�f���A����㎁�ɑ��A�u�Q�O�O�S�N�ɐV�G�B�V�[�C�[���C���x�~�̋Z�p�ɂ���ăf�B�[�[���G��
�W���̔R����P���m�F���A���̎����f�[�^���擾���Ă��鎖���v���J�����Ă����̂ł��낤���B���̋C���x�~�ɂ��R
����P�̎����f�[�^����ʈ��S���������̊W�҂ɊJ���������ۂ��ɂ��āA�M�҂͌�ʈ��S���������̗�
�؉��ꎁ�A�Έ�f���A����㎁�ɐ���Ƃ��m�F���Ă݂������̂��B
�iSCD�j�G���W���ɂ���^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W���̒�R��v���W�F�N�g�v�̏����̒i�K�ŁA��ʈ��S��������
�̗�؉��ꎁ�A�Έ�f���A����㎁�ɑ��A�u�Q�O�O�S�N�ɐV�G�B�V�[�C�[���C���x�~�̋Z�p�ɂ���ăf�B�[�[���G��
�W���̔R����P���m�F���A���̎����f�[�^���擾���Ă��鎖���v���J�����Ă����̂ł��낤���B���̋C���x�~�ɂ��R
����P�̎����f�[�^����ʈ��S���������̊W�҂ɊJ���������ۂ��ɂ��āA�M�҂͌�ʈ��S���������̗�
�؉��ꎁ�A�Έ�f���A����㎁�ɐ���Ƃ��m�F���Ă݂������̂��B
�@�Ƃ���ŁA��ʈ��S���������̖����i���Ɩ��j�́A�}�P�R�́u��ʈ��S���������̖����v�Ɏ����Ă���悤�ɁA�u��
���Ԃ̊��Z�p��i��������K���l�j�Ă̍���i�����[�����[�J����̍쐬�ҁj�v��u���̐���ɑ���s��
�ւ̋Z�p�x���v�Ƃ̂��Ƃł���B
���Ԃ̊��Z�p��i��������K���l�j�Ă̍���i�����[�����[�J����̍쐬�ҁj�v��u���̐���ɑ���s��
�ւ̋Z�p�x���v�Ƃ̂��Ƃł���B
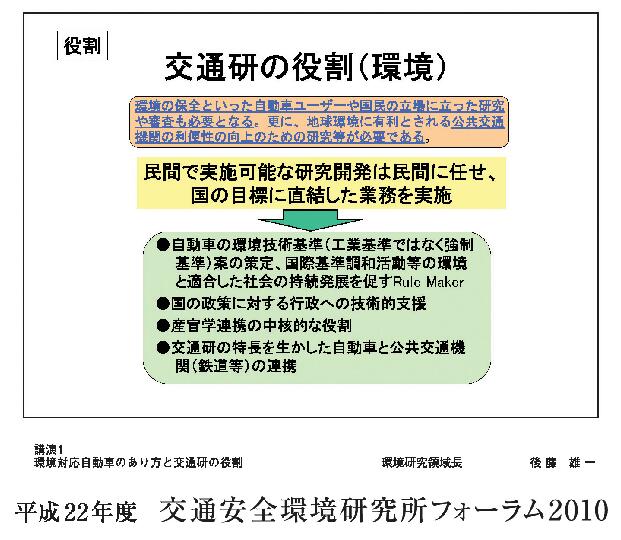
�@�ȏ�̂悤�ɁA��ʈ��S���������͎����Ԃ̊��Z�p��Ă̍���ɐE�ӂ��Ă���悤���B���̂��߁A���
���S���������̐��Ƃɑ�^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W���̒�R�������ł��邱�Ƃ�{�S���������ꍇ��
�́A���y��ʏȂ̏d�ʎԔR���̋������啝�ɒx���ł��邱�Ƃ͗e�Ղɗ\�z�ł��邱�Ƃł���B���A���ɁA��ʈ�
�S���������́u�X�[�p�[�N���[���f�B�[�[���iSCD�j�G���W���ɂ���^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W�����R�����
�v���W�F�N�g�v�ɂ����āA2015�N�x�d�ʎԔR�����10�������サ��4.5 �����^���b�g���̏d�ʎԃ��[�h�R��� ��^�g
���b�N�iGVW�Q�T�g���j���Q�R�N�x�������ł����A���̌����J���̖ڕW�����B���ƂȂ鎸�s�ɏI������ꍇ�ɂ́A��
�ʈ��S���������̐��Ɓi��؉��ꎁ�A�Έ�f���A����㎁�j�́A��^�g���b�N�̔R����P���Z�p�I�ɍ���ł�
�邱�Ƃ�Ɋ����邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��B���̏ꍇ�ɂ́A���y��ʏȂ̏d�ʎԔR���̋����́A��ʈ��S��������
�̐��Ƃ̈ӌ������f����邽�߂ɑ啝�ɒx���������̂ƍl������B
���S���������̐��Ƃɑ�^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W���̒�R�������ł��邱�Ƃ�{�S���������ꍇ��
�́A���y��ʏȂ̏d�ʎԔR���̋������啝�ɒx���ł��邱�Ƃ͗e�Ղɗ\�z�ł��邱�Ƃł���B���A���ɁA��ʈ�
�S���������́u�X�[�p�[�N���[���f�B�[�[���iSCD�j�G���W���ɂ���^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W�����R�����
�v���W�F�N�g�v�ɂ����āA2015�N�x�d�ʎԔR�����10�������サ��4.5 �����^���b�g���̏d�ʎԃ��[�h�R��� ��^�g
���b�N�iGVW�Q�T�g���j���Q�R�N�x�������ł����A���̌����J���̖ڕW�����B���ƂȂ鎸�s�ɏI������ꍇ�ɂ́A��
�ʈ��S���������̐��Ɓi��؉��ꎁ�A�Έ�f���A����㎁�j�́A��^�g���b�N�̔R����P���Z�p�I�ɍ���ł�
�邱�Ƃ�Ɋ����邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��B���̏ꍇ�ɂ́A���y��ʏȂ̏d�ʎԔR���̋����́A��ʈ��S��������
�̐��Ƃ̈ӌ������f����邽�߂ɑ啝�ɒx���������̂ƍl������B
�@�ȏ�̂悤�Ȍ�ʈ��S���������̖������n�m������ŁA���ɁA�V�G�B�V�[�C�[�̐� �F�O���́A��ʈ��S����
�����̐��Ɓi��؉��ꎁ�A�Έ�f���A����㎁�j�ɑ�^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W���̒�R�������ł��邱
�Ƃ�{�S�����点��āu���y��ʏȂ̏d�ʎԔR���̋�����啝�ɒx���v������ړI��B�����邽���A�u��ʈ�
�S����������SCD�G���W���ɂ���^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W���̒�R��v���W�F�N�g�v�ɎQ�����ꂽ�̂�������
����A��ʈ��S���������́u�X�[�p�[�N���[���f�B�[�[���iSCD�j�G���W���ɂ���^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W��
���R�����v���W�F�N�g�v�����s���A�߂��������� �F�O�����g���p�����炷���Ƃ��o��̏���s�����u�����e���v
�Ǝv�����s�ׂ̂悤�ɂ����邱�Ƃ��ł��������B
�����̐��Ɓi��؉��ꎁ�A�Έ�f���A����㎁�j�ɑ�^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W���̒�R�������ł��邱
�Ƃ�{�S�����点��āu���y��ʏȂ̏d�ʎԔR���̋�����啝�ɒx���v������ړI��B�����邽���A�u��ʈ�
�S����������SCD�G���W���ɂ���^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W���̒�R��v���W�F�N�g�v�ɎQ�����ꂽ�̂�������
����A��ʈ��S���������́u�X�[�p�[�N���[���f�B�[�[���iSCD�j�G���W���ɂ���^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W��
���R�����v���W�F�N�g�v�����s���A�߂��������� �F�O�����g���p�����炷���Ƃ��o��̏���s�����u�����e���v
�Ǝv�����s�ׂ̂悤�ɂ����邱�Ƃ��ł��������B
�@���āA��^�g���b�N��2015�N�x�d�ʎԔR���̋���������ۂ̊�Ă̍���i�����[�����[�J�j�̐E�ӂ����
���S���������́u�X�[�p�[�N���[���f�B�[�[���iSCD�j�G���W���ɂ���^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W�����R�
����v���W�F�N�g�v�ɂ��A�u���y��ʏȂ̏d�ʎԔR���̋����̑啝�Ȓx���v�����]���Ă���ƍl������g���b�N���[
�J���o������V�G�B�V�[�C�[�����͂��Ă���̂ł���B���̂悤�ɁA��ʈ��S���������́u�X�[�p�[�N���[���f�B�[�[
���iSCD�j�G���W���̃v���W�F�N�g�v�́A��^�g���b�N�ɂ����Ă̔R����K�����鑤�̍��y��ʏȁi��ʈ��S���������j
�ƁA�R����K������鑤�̐V�G�B�V�[�C�[�i�g���b�N���[�J�̏o����Ёj�Ƃ̋��������ł���B���ɁA���y��ʏȂ�����
�̗��v�����g���b�N���[�J�̗��v��ӌ���D�悷��ӌ��������Ă���ꍇ�ɂ́A���̋��������́A2015�N�x�d�ʎ�
�R���̋�����摗�肷�邽�߂ɖނ��炵�������ł��闝�R�E�����̃f�[�^�����W���邽�߂Ƃ̌��������藧������
���B���̏ꍇ�ɂ́A��ʈ��S���������ƐV�G�B�V�[�C�[�̗��̖ړI�i�����X�ƌ����ł��Ȃ��ړI���B�ꂽ�ړI�j�́A
��2015�N�x�d�ʎԔR�����10�������サ��4.5 �����^���b�g���̏d�ʎԃ��[�h�R��� ��^�g���b�N�iGVW�Q�T�g���j
�̋Z�p�����Q�R�N�x���������錤���ڕW�̒B�������s�ɏI��点�邱�Ƃł͂Ȃ����Ɛ��@�������Ƃ��\���B�Ȃ���
��A��ʈ��S���������ƐV�G�B�V�[�C�[�́A�u�X�[�p�[�N���[���f�B�[�[���iSCD�j�G���W���̃v���W�F�N�g�v�̔R�����
�Ɏ��s���������f�[�^�����A2015�N�x�d�ʎԔR���̋����ɑΉ��ł���Z�p�������ɊJ���ł��Ă��Ȃ����Ƃ�
�u�����v���̂悤�ɂ����Ƃ��炵�����{�i�����y��ʏȁA���ȓ��j�ɐ����ł��邽�߂ł���B���̂悤�Ȃ��Ƃ����Ɏ�����
����A�����̗��ꂩ��͋����Ȃ����Ƃ��B
���S���������́u�X�[�p�[�N���[���f�B�[�[���iSCD�j�G���W���ɂ���^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W�����R�
����v���W�F�N�g�v�ɂ��A�u���y��ʏȂ̏d�ʎԔR���̋����̑啝�Ȓx���v�����]���Ă���ƍl������g���b�N���[
�J���o������V�G�B�V�[�C�[�����͂��Ă���̂ł���B���̂悤�ɁA��ʈ��S���������́u�X�[�p�[�N���[���f�B�[�[
���iSCD�j�G���W���̃v���W�F�N�g�v�́A��^�g���b�N�ɂ����Ă̔R����K�����鑤�̍��y��ʏȁi��ʈ��S���������j
�ƁA�R����K������鑤�̐V�G�B�V�[�C�[�i�g���b�N���[�J�̏o����Ёj�Ƃ̋��������ł���B���ɁA���y��ʏȂ�����
�̗��v�����g���b�N���[�J�̗��v��ӌ���D�悷��ӌ��������Ă���ꍇ�ɂ́A���̋��������́A2015�N�x�d�ʎ�
�R���̋�����摗�肷�邽�߂ɖނ��炵�������ł��闝�R�E�����̃f�[�^�����W���邽�߂Ƃ̌��������藧������
���B���̏ꍇ�ɂ́A��ʈ��S���������ƐV�G�B�V�[�C�[�̗��̖ړI�i�����X�ƌ����ł��Ȃ��ړI���B�ꂽ�ړI�j�́A
��2015�N�x�d�ʎԔR�����10�������サ��4.5 �����^���b�g���̏d�ʎԃ��[�h�R��� ��^�g���b�N�iGVW�Q�T�g���j
�̋Z�p�����Q�R�N�x���������錤���ڕW�̒B�������s�ɏI��点�邱�Ƃł͂Ȃ����Ɛ��@�������Ƃ��\���B�Ȃ���
��A��ʈ��S���������ƐV�G�B�V�[�C�[�́A�u�X�[�p�[�N���[���f�B�[�[���iSCD�j�G���W���̃v���W�F�N�g�v�̔R�����
�Ɏ��s���������f�[�^�����A2015�N�x�d�ʎԔR���̋����ɑΉ��ł���Z�p�������ɊJ���ł��Ă��Ȃ����Ƃ�
�u�����v���̂悤�ɂ����Ƃ��炵�����{�i�����y��ʏȁA���ȓ��j�ɐ����ł��邽�߂ł���B���̂悤�Ȃ��Ƃ����Ɏ�����
����A�����̗��ꂩ��͋����Ȃ����Ƃ��B
�@�܂��A�V�G�B�V�[�C�[�̋��͂Ŏ��{����Ă����ʈ��S���������́u�X�[�p�[�N���[���f�B�[�[���iSCD�j�G���W��
�̃v���W�F�N�g�v�̒����E�����́A��X�̐g�߂Ȏs�������ł̖h�Ƃ̏ꍇ�ɗႦ��A�h�Ɗ֘A�̖@���i�Y�@�j���쐬
����x�@���i���ƌ����ψ���j���Y�@�Ŕ�������D�_�Ƌ������Ďs���̈��S�𐄐i���邽�߂ɌY�@�̔���������
�V���ȌY�@���쐬���邽�߂̒����E���������{���Ă���悤�ȍ\�}�ɂ�������̂ł���B���̂悤�ȌY�@�̔���������
�Y�@�쐬�̉ߒ��ɂ����āA�x�@���ƓD�_�Ƃ̋����������������ꍇ�ɁA�x�@���͓D�_�́u��̓���m��v���߂ɓD�_
�̋��͂��s���Ƃٖ̕����s�����Ƃ��Ă��A�M�҂ɂ͕s�K�E�s�ސT�Ȃ悤�Ɏv����̂ł���B�X�ɁA���̌x�@���ƓD
�_�Ƃ̒����E�����v���W�F�N�g���x�@���ɂ�����Y�@�̔���������V���ȌY�@�쐬�̒x����ړI�Ƃ��āA�D�_�����
���������E�����v���W�F�N�g�̏ꍇ�ł�����A�x�@���ɂ����邱�̂悤�Ȓ����E�����v���W�F�N�g�̎��{�́A�S���������
���s�ׂł��邱�Ƃ͖��炩���B�����Ƃ��A���̔�g�͔�߂���������Ȃ��B�������A��ʈ��S���������ƐV�G�B�V
�[�C�[�����͂��Ď��{����Ă���u�X�[�p�[�N���[���f�B�[�[���iSCD�j�G���W���̃v���W�F�N�g�v�́A�x�@���ƓD�_�Ƃ̒�
���E�����v���W�F�N�g�������悤�ȁA�u�K�����鑤�ƋK������鑤�Ƃ̋��������v�̍\�}�ł���A�M�҂ɂ͂������킵�v
�����@������Ȃ��̂ł���B���������āA���݁A���y��ʏȓ��Ō������Ɛ���������^�g���b�N�Ɋւ���2015�N�x�d
�ʎԔR���̋����ɂ��ẮA���̉ߒ��ɂ����āA�u�D�_�ɓ���Ȃ킹��v�悤�ȌӎU�L���l�q�������Ă��܂��̂�
����B
�̃v���W�F�N�g�v�̒����E�����́A��X�̐g�߂Ȏs�������ł̖h�Ƃ̏ꍇ�ɗႦ��A�h�Ɗ֘A�̖@���i�Y�@�j���쐬
����x�@���i���ƌ����ψ���j���Y�@�Ŕ�������D�_�Ƌ������Ďs���̈��S�𐄐i���邽�߂ɌY�@�̔���������
�V���ȌY�@���쐬���邽�߂̒����E���������{���Ă���悤�ȍ\�}�ɂ�������̂ł���B���̂悤�ȌY�@�̔���������
�Y�@�쐬�̉ߒ��ɂ����āA�x�@���ƓD�_�Ƃ̋����������������ꍇ�ɁA�x�@���͓D�_�́u��̓���m��v���߂ɓD�_
�̋��͂��s���Ƃٖ̕����s�����Ƃ��Ă��A�M�҂ɂ͕s�K�E�s�ސT�Ȃ悤�Ɏv����̂ł���B�X�ɁA���̌x�@���ƓD
�_�Ƃ̒����E�����v���W�F�N�g���x�@���ɂ�����Y�@�̔���������V���ȌY�@�쐬�̒x����ړI�Ƃ��āA�D�_�����
���������E�����v���W�F�N�g�̏ꍇ�ł�����A�x�@���ɂ����邱�̂悤�Ȓ����E�����v���W�F�N�g�̎��{�́A�S���������
���s�ׂł��邱�Ƃ͖��炩���B�����Ƃ��A���̔�g�͔�߂���������Ȃ��B�������A��ʈ��S���������ƐV�G�B�V
�[�C�[�����͂��Ď��{����Ă���u�X�[�p�[�N���[���f�B�[�[���iSCD�j�G���W���̃v���W�F�N�g�v�́A�x�@���ƓD�_�Ƃ̒�
���E�����v���W�F�N�g�������悤�ȁA�u�K�����鑤�ƋK������鑤�Ƃ̋��������v�̍\�}�ł���A�M�҂ɂ͂������킵�v
�����@������Ȃ��̂ł���B���������āA���݁A���y��ʏȓ��Ō������Ɛ���������^�g���b�N�Ɋւ���2015�N�x�d
�ʎԔR���̋����ɂ��ẮA���̉ߒ��ɂ����āA�u�D�_�ɓ���Ȃ킹��v�悤�ȌӎU�L���l�q�������Ă��܂��̂�
����B
�@�O�q���y�W�|�P NEDO�̒����x�R�Đ���G���W�V�X�e���̌����J���z�ł́A�R����̑厸�s�z�ɋL�ڂ����ʂ�A
NEDO�̊v�V�I���������Q�ԑ����Z�p�J���i�N���[���f�B�[�[���v���W�F�N�g�A2004�`2009�N�j�́u�����x�R�Đ���
�G���W�V�X�e���̌����J���i�\�Z�F�W���~�ȏ�j�v�̑�^�v���W�F�N�g�ł���B����NEDO�́u�����x�R�Đ���G���W�v��
�́A�u�R�i�ߋ��V�X�e���v�A�u300MP���̒������R�����ˁv�A�u�J�����X�V�X�e���v�A�uPCI�iPremixed. Compression Ignition
combustion�j�R�āv�̋Z�p���g�ݍ��݁A2015�N�x�d�ʎԔR�������P�O���̑啝�ȔR��팸�̖ڕW���f���Č���
�J�������{���ꂽ�B�������A���̌��ʂ́A2015�N�x�d�ʎԔR�������Q���̔R����ƂȂ��Ă��܂����̂ł���B
���̂悤�ɁANEDO�́u�R�i�ߋ��V�X�e���v�A�u300MP���̒������R�����ˁv�A�u�J�����X�V�X�e���v�A�uPCI�R�āv���Z�p����
�p������^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W���̌����ł́ANO���͖ڕW��B���������̂́A�R����P���������Ă��܂��Ɖ]��
�ߎS�Ȍ��ʂƂȂ��Ă��܂����̂ł���B
NEDO�̊v�V�I���������Q�ԑ����Z�p�J���i�N���[���f�B�[�[���v���W�F�N�g�A2004�`2009�N�j�́u�����x�R�Đ���
�G���W�V�X�e���̌����J���i�\�Z�F�W���~�ȏ�j�v�̑�^�v���W�F�N�g�ł���B����NEDO�́u�����x�R�Đ���G���W�v��
�́A�u�R�i�ߋ��V�X�e���v�A�u300MP���̒������R�����ˁv�A�u�J�����X�V�X�e���v�A�uPCI�iPremixed. Compression Ignition
combustion�j�R�āv�̋Z�p���g�ݍ��݁A2015�N�x�d�ʎԔR�������P�O���̑啝�ȔR��팸�̖ڕW���f���Č���
�J�������{���ꂽ�B�������A���̌��ʂ́A2015�N�x�d�ʎԔR�������Q���̔R����ƂȂ��Ă��܂����̂ł���B
���̂悤�ɁANEDO�́u�R�i�ߋ��V�X�e���v�A�u300MP���̒������R�����ˁv�A�u�J�����X�V�X�e���v�A�uPCI�R�āv���Z�p����
�p������^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W���̌����ł́ANO���͖ڕW��B���������̂́A�R����P���������Ă��܂��Ɖ]��
�ߎS�Ȍ��ʂƂȂ��Ă��܂����̂ł���B
�@����A��ʈ��S���������́u�X�[�p�[�N���[���f�B�[�[���iSCD�j�G���W���v�ɂ́A�u�Q�i�V�[�P���V�����ߋ��@�v��
�u�r�M����V�X�e���i�^�[�{�R���p�E���h�j�v���u�������R�������[���v�̋Z�p�������g�ݍ��ނ܂�Ă��邪�A��ʈ��S��
���������́u�X�[�p�[�N���[���f�B�[�[���iSCD�j�G���W���v��NEDO�́u�����x�R�Đ���G���W�v�ɐV�����u�r�M����V
�X�e���i�^�[�{�R���p�E���h�j�v���g�ݍ��܂�Ă��邾���ł���B�܂�A��ʈ��S���������́u�X�[�p�[�N���[���f
�B�[�[���iSCD�j�G���W���v�́A2015�N�x�d�ʎԔR�������Q���̔R����������ꂽNEDO�́u�����x
�R�Đ���G���W�v�ɏ\���ȔR����P�̋@�\�������Ȃ��u�r�M����V�X�e���i�^�[�{�R���p�E���h�j�v��V���ɒlj�
�����V�X�e���ƌ��邱�Ƃ��\���B���̂��߁A���������āA2015�N�x�d�ʎԔR�������Q���̔R�����������
��NEDO�́u�����x�R�Đ���G���W�v�̌����J���̌��ʂ��画�f����ƁA��ʈ��S���������́u�X�[�p�[�N���[���f
�B�[�[���iSCD�j�G���W���v�̌����J���́A2015�N�x�d�ʎԔR�������P�O�����̑啝�ȔR����팸����ڕW�̒B
���́A���S�ɕs�\�ł��邱�Ƃ��N�ł��e�Ղɗ����ł��邱�Ƃł���B
�u�r�M����V�X�e���i�^�[�{�R���p�E���h�j�v���u�������R�������[���v�̋Z�p�������g�ݍ��ނ܂�Ă��邪�A��ʈ��S��
���������́u�X�[�p�[�N���[���f�B�[�[���iSCD�j�G���W���v��NEDO�́u�����x�R�Đ���G���W�v�ɐV�����u�r�M����V
�X�e���i�^�[�{�R���p�E���h�j�v���g�ݍ��܂�Ă��邾���ł���B�܂�A��ʈ��S���������́u�X�[�p�[�N���[���f
�B�[�[���iSCD�j�G���W���v�́A2015�N�x�d�ʎԔR�������Q���̔R����������ꂽNEDO�́u�����x
�R�Đ���G���W�v�ɏ\���ȔR����P�̋@�\�������Ȃ��u�r�M����V�X�e���i�^�[�{�R���p�E���h�j�v��V���ɒlj�
�����V�X�e���ƌ��邱�Ƃ��\���B���̂��߁A���������āA2015�N�x�d�ʎԔR�������Q���̔R�����������
��NEDO�́u�����x�R�Đ���G���W�v�̌����J���̌��ʂ��画�f����ƁA��ʈ��S���������́u�X�[�p�[�N���[���f
�B�[�[���iSCD�j�G���W���v�̌����J���́A2015�N�x�d�ʎԔR�������P�O�����̑啝�ȔR����팸����ڕW�̒B
���́A���S�ɕs�\�ł��邱�Ƃ��N�ł��e�Ղɗ����ł��邱�Ƃł���B
�@���̂悤�ȏɂ����āA���̌�ʈ��S���������́u�X�[�p�[�N���[���f�B�[�[���iSCD�j�G���W���v�̌����J����
�����āA2015�N�x�d�ʎԔR���ɔ䂵�ĂP�O���̔R����P�̖ڕW���B���ł���B��̕��@�́A���݂��u�X�[�p�[�N
���[���f�B�[�[���iSCD�j�G���W���v�ɁA�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p��V���ɍ̗p���邱�Ƃł����
�M�҂͍l���Ă���B�������邽�߂ɂ́A�ʈ��S���������̗�؉��ꎁ�A�Έ�f���A�����A����ю��V�G�B�V�[
�C�[�̐� �F�O���̏������K�ȕ��j�ύX�̗E�f�������K�v������B����ɂ���āA��ʈ��S���������́u�X�[
�p�[�N���[���f�B�[�[���iSCD�j�G���W���v�́A�ȉ��̕\�P�X�Ɏ������C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̃����b�g
�ɂ��A2015�N�x�d�ʎԔR���ɔ䂵�ĂP�O���̔R����P��}��ڕW���e�ՂɎ����ł��A����Ɠ�����NO���팸��
�\�ƂȂ�̂ł���B
�����āA2015�N�x�d�ʎԔR���ɔ䂵�ĂP�O���̔R����P�̖ڕW���B���ł���B��̕��@�́A���݂��u�X�[�p�[�N
���[���f�B�[�[���iSCD�j�G���W���v�ɁA�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p��V���ɍ̗p���邱�Ƃł����
�M�҂͍l���Ă���B�������邽�߂ɂ́A�ʈ��S���������̗�؉��ꎁ�A�Έ�f���A�����A����ю��V�G�B�V�[
�C�[�̐� �F�O���̏������K�ȕ��j�ύX�̗E�f�������K�v������B����ɂ���āA��ʈ��S���������́u�X�[
�p�[�N���[���f�B�[�[���iSCD�j�G���W���v�́A�ȉ��̕\�P�X�Ɏ������C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̃����b�g
�ɂ��A2015�N�x�d�ʎԔR���ɔ䂵�ĂP�O���̔R����P��}��ڕW���e�ՂɎ����ł��A����Ɠ�����NO���팸��
�\�ƂȂ�̂ł���B
| |
|
|
| |
�����������C���x�~�̌��ʂɂ��A�d�ʎԃ��[�h�R��͂T�`�P�O���̌��オ�\
�i���������ɂ�����u�T�C�N�������̌���v����сu��p�����̍팸�v�ɂ��R����P���ʁj |
|
| |
���������̔r�C�K�X�̍������ɂ��ADPF���u�ł̎��ȍĐ��̉^�]�̈�̊g��ɂ��R�����
�i�|�X�g���˂܂���HC�r�C�Ǖ��˂�DPF�����Đ��̉������A�����Đ��ɂ��R���Q���h�~�j |
|
| |
���������̔r�C�K�X�̍������ɂ��A�^�[�{�R���p�E���h�ł̔r�M�G�l���M�[�̉������������ | |
| |
���������̔r�K�X���x�̍������ɂ��A�A�fSCR�G�}�ł�NO���팸���̌��オ�\ | |
�ȏ�̂悤�ɁA��ʈ��S���������́u�X�[�p�[�N���[���f�B�[�[���iSCD�j�G���W���v���C���x�~�G���W���i�������J
2005-54771�j�̋Z�p��lj�����A��L�̕\�P�S�Ɏ������悤�ȁA�啝�ȔR����P��NO���팸���\���B���ɁA���̒�
�̔R����P�̌��ʂɂ���āA��ʈ��S���������́u�X�[�p�[�N���[���ɂ��f�B�[�[���iSCD�j�G���W���v�́A�ڕW��
�f�����Ă���2015�N�x�d�ʎԔR����10���̌��サ��4.5 �����^���b�g���̏d�ʎԃ��[�h�R��� ��^�g���b�N
�iGVW�Q�T�g���j���m���Ɏ����ł���̂ł���B
2005-54771�j�̋Z�p��lj�����A��L�̕\�P�S�Ɏ������悤�ȁA�啝�ȔR����P��NO���팸���\���B���ɁA���̒�
�̔R����P�̌��ʂɂ���āA��ʈ��S���������́u�X�[�p�[�N���[���ɂ��f�B�[�[���iSCD�j�G���W���v�́A�ڕW��
�f�����Ă���2015�N�x�d�ʎԔR����10���̌��サ��4.5 �����^���b�g���̏d�ʎԃ��[�h�R��� ��^�g���b�N
�iGVW�Q�T�g���j���m���Ɏ����ł���̂ł���B
�@����ɂ��ẮA��ʈ��S���������̗�؉��ꎁ�A�Έ�f���A����㎁�A����ѐV�G�B�V�[�C�[�̐� �F�O
�����A���̃y�[�W���C���x�~�G���W���ɂ���^�g���b�N�̒�R����n�ǂ��Ă���������A�C���x�~�G���W���i��
�����J2005-54771�j�̋Z�p���u�X�[�p�[�N���[���f�B�[�[���iSCD�j�G���W���v�̔R�����ɑ傫����^�ł��邱�Ƃ��\��
�ɗ����ł��锤���B�����āA��ʈ��S����������SCD�G���W���̃v���W�F�N�g���C���x�~�G���W���i�������J2005-
54771�j�̋Z�p��V���ɉ������ꍇ�A���̃v���W�F�N�g�̖ڕW���e�ՂɒB���ł���\�����ɂ߂č����Ȃ�̂ł���B��
���ŁA���̌�ʈ��S����������SCD�G���W���̃v���W�F�N�g�ɂ��āA�{�z�[���y�[�W�̉{���҂ɍ���̃v���W�F�N
�g�̐��i���@��\�z���ĖႤ������A�e���r�̃N�C�Y�ԑg���ɂ܂Ƃ߁A�\�Q�O�Ɏ������B
�����A���̃y�[�W���C���x�~�G���W���ɂ���^�g���b�N�̒�R����n�ǂ��Ă���������A�C���x�~�G���W���i��
�����J2005-54771�j�̋Z�p���u�X�[�p�[�N���[���f�B�[�[���iSCD�j�G���W���v�̔R�����ɑ傫����^�ł��邱�Ƃ��\��
�ɗ����ł��锤���B�����āA��ʈ��S����������SCD�G���W���̃v���W�F�N�g���C���x�~�G���W���i�������J2005-
54771�j�̋Z�p��V���ɉ������ꍇ�A���̃v���W�F�N�g�̖ڕW���e�ՂɒB���ł���\�����ɂ߂č����Ȃ�̂ł���B��
���ŁA���̌�ʈ��S����������SCD�G���W���̃v���W�F�N�g�ɂ��āA�{�z�[���y�[�W�̉{���҂ɍ���̃v���W�F�N
�g�̐��i���@��\�z���ĖႤ������A�e���r�̃N�C�Y�ԑg���ɂ܂Ƃ߁A�\�Q�O�Ɏ������B
| �i��ҁ@�F�@�����ŁA�F����Ɏ���ł��B
�i��҂̎�����e ��ʈ��S���������́u�Q�i�V�[�P���V�����ߋ��@�v���u�r�M����V�X�e���i�^�[�{�R���p�E���h�j�v���u�������R�������[���v�̋Z�p�� ���荞�X�[�p�[�N���[���f�B�[�[���iSCD�j�G���W���́A��^�g���b�N��2015�N�x�d�ʎԔR���l�����R��̉��P���ł��܂���B �������A����SCD�G���W�����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p���̗p�����2015�N�x�d�ʎԔR����10���̌��サ�� 4.5 �����^���b�g���̏d�ʎԃ��[�h�R��� ��^�g���b�N�iGVW�Q�T�g���j���m���Ɏ����ł���Ɨ\�z����Ă��܂��B ���āA�A����́u��ʈ��S���������̃X�[�p�[�N���[���f�B�[�[���iSCD�j�G���W���̃v���W�F�N�g�v�ł́A��ʈ��S���������� ��؉��ꎁ�A�Έ�f���A����㎁�A����ѐV�G�B�V�[�C�[�̐� �F�O���̏������A�v���W�F�N�g�̍���̐��i�ɂ��āA�@�܂��͇A�� ����̕��j���I������邩�ɂ��Ă̗\�z���A�������������� �@�@���̃v���W�F�N�g��SCD�G���W���ł́A�\���ȔR����P�͍���ƍl�����܂��B���������āA����SCD�G���W���̌����J���ɂ����āA �d�ʎԔR���̋����̍���ɐE�ӂ��Ă����ʈ��S���������̐��Ɓi��؉��ꎁ�A�Έ�f���A����㎁�j�́A��^ �g���b�N�̔R����P���Z�p�I�ɐ�]�I�ł��邱�Ƃ�Ɋ���������ł��傤�B�����āA����SCD�G���W���̌����œ���ꂽ�R����P�� ���s���������f�[�^�́A2015�N�x�d�ʎԔR���̋�����摗�肷��ۂɖނ��炵�������ł��闝�R�E�����Ƃ��ė��p�ł��܂��B �����āA�����̎����f�[�^����g���邱�Ƃɂ����2015�N�x�d�ʎԔR���̋�����x�������邱�ƂɒN�������ł��Ȃ��� ���o�����Ƃ��\�ƂȂ�܂��B����ɂ���č��y��ʏȂ����ۂ�2015�N�x�d�ʎԔR���̋��������������ꍇ�ɂ́A�g���b�N ���[�J�́A�R����P�̌����J���̓������팸�ł��邽�߁A���̊�Ɠw�͂������ɗ��v����̉��b���邱�Ƃ��ł���̂ł��B ���̏ꍇ�A�g���b�N���[�J�́A����ΔG���Ɉ��̗��v����ɂ��邱�ƂɂȂ�܂��̂ŁA���y��ʏȂɁu���ӁI���ӁI�v�Ɖ]�����Ƃ� �Ȃ�܂��B����ɑ��A�g���b�N���[�U�́A���ꂩ������X�ƔR����P����Ă��Ȃ���^�g���b�N���w���������Ȃ���Ȃ炸�A �^�s�R��팸�ł��Ȃ��]���������邱�ƂɂȂ�܂��B �A�@���̃v���W�F�N�g��SCD�G���W���ł́A�\���ȔR����P�͍���ƍl�����܂��B�������A����SCD�G���W���� �C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p��V���ɒlj����邱�Ƃɂ��A2015�N�x�d�ʎԔR�����P�O�����R����サ�� 4.5 �����^���b�g���̏d�ʎԃ��[�h�R��̑�^�g���b�N�iGVW�Q�T�g���j���Q�R�N�x�Ɏ��������邱�Ƃ��ł��܂��B����ɂ���āA 2015�N�x�d�ʎԔR���̋����𑁊��Ɏ��{�ł���悤�ɂȂ�܂��B���̏ꍇ�ɂ́A�ȃG�l���M�[��CO2�팸�����߂鍑���̊肢�� �������邱�Ƃ��ł���Ƌ��ɁA�g���b�N���[�U�ɂƂ��ẮA����͔R����P���ꂽ��^�g���b�N���w�����邱�Ƃɂ���āA�^�s�R��� ���P�������ł��邱�ƂɂȂ�܂��B �i��ҁ@�F�@����ł́A��ʈ��S���������ɂ�����SCD�G���W���̃v���W�F�N�g�ɂ����āA����A�F����́A�@�܂��͇A�̉����
���i���j���I�������Ɛ�������܂����B��ґ���ł������������B
|
�@���� ���āA��ʈ��S���������̗�؉��ꎁ�A�Έ�f���A����㎁�A����ѐV�G�B�V�[�C�[�̐� �F�O���̏�
���́A��ʈ��S���������̃X�[�p�[�N���[���f�B�[�[���iSCD�j�G���W���̃v���W�F�N�g�̐��i�ɂ����āA�C���x�~�G
���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p��V���ɒlj�����2015�N�x�d�ʎԔR����10���̔R����サ��4.5 �����^��
�b�g���̏d�ʎԃ��[�h�R��� ��^�g���b�N�iGVW�Q�T�g���j���������A�����̏ȃG�l���M�[��CO2�팸�̗v�]�ɉ������
�v��������Ă���̂ł��낤���B����Ƃ��A�X�[�p�[�N���[���f�B�[�[���iSCD�j�G���W���̃v���W�F�N�g�ɋC���x�~�̋Z
�p��lj����Ȃ��ŏ]���ʂ�̔R����P�̍���ȋZ�p�������̗p���������J�����p�����A�����ڕW�Ƃ���2015�N�x�d
�ʎԔR����10���̔R�����Ɏ��s���������f�[�^�����p����2015�N�x�d�ʎԔR���̋�����x�������ĔR
����P�̌����J����̍팸��}��A�g���b�N���[�J�̗��v�����ɋ��́E�v������Ӑ}��������Ă���̂ł��낤���B
���́A��ʈ��S���������̃X�[�p�[�N���[���f�B�[�[���iSCD�j�G���W���̃v���W�F�N�g�̐��i�ɂ����āA�C���x�~�G
���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p��V���ɒlj�����2015�N�x�d�ʎԔR����10���̔R����サ��4.5 �����^��
�b�g���̏d�ʎԃ��[�h�R��� ��^�g���b�N�iGVW�Q�T�g���j���������A�����̏ȃG�l���M�[��CO2�팸�̗v�]�ɉ������
�v��������Ă���̂ł��낤���B����Ƃ��A�X�[�p�[�N���[���f�B�[�[���iSCD�j�G���W���̃v���W�F�N�g�ɋC���x�~�̋Z
�p��lj����Ȃ��ŏ]���ʂ�̔R����P�̍���ȋZ�p�������̗p���������J�����p�����A�����ڕW�Ƃ���2015�N�x�d
�ʎԔR����10���̔R�����Ɏ��s���������f�[�^�����p����2015�N�x�d�ʎԔR���̋�����x�������ĔR
����P�̌����J����̍팸��}��A�g���b�N���[�J�̗��v�����ɋ��́E�v������Ӑ}��������Ă���̂ł��낤���B
�@�����Q�R�N�x�ɔ��\����錋�_�����邱�Ƃɂ���āA��ʈ��S���������̃X�[�p�[�N���[���f�B�[�[���iSCD�j�G��
�W���̃v���W�F�N�g�́A��ʈ��S���������i�����y��ʏȁj�������ƃg���b�N���[�J�̉���̗��v���l���Ď��{�����
���邩����������̂ł͂Ȃ����낤���B���̃v���W�F�N�g�̌��ʔ��\���y���݂��B
�W���̃v���W�F�N�g�́A��ʈ��S���������i�����y��ʏȁj�������ƃg���b�N���[�J�̉���̗��v���l���Ď��{�����
���邩����������̂ł͂Ȃ����낤���B���̃v���W�F�N�g�̌��ʔ��\���y���݂��B
�@�Ȃ��A���̍��̋L�ړ��e�ɂ͐����������܂܂�Ă��邽�߁A�ꕔ�ɂ͕M�҂̎�����F�����邩���m��Ȃ��B����
�ŁA��ʈ��S������������ч��V�G�B�V�[�C�[�̊W�҂����̃z�[���y�[�W���{�����ꂽ�ہA���炩�Ɍ��ƋC�t
���ꂽ�L�ڂɂ��ẮA�����̕M�҂�E���[�����ĂɎ����ɂ��Ă̌�A��������������A������L�ړ��e�͑�
���ɒ����������ƍl���Ă���B
�ŁA��ʈ��S������������ч��V�G�B�V�[�C�[�̊W�҂����̃z�[���y�[�W���{�����ꂽ�ہA���炩�Ɍ��ƋC�t
���ꂽ�L�ڂɂ��ẮA�����̕M�҂�E���[�����ĂɎ����ɂ��Ă̌�A��������������A������L�ړ��e�͑�
���ɒ����������ƍl���Ă���B
�W�|�W�D�����ԋZ�p��2015�N9�����iVol.69�AN0.9�A2015�j�Ɍf�ڂ��ꂽ�_���̋^��_
�@����c��w�E�吹�O�����́A�����ԋZ�p��2015�N9�����iVol.69�AN0.9�A2015�j�Ɂu�����ԗp�p���[�g���C���̍���
�����Z�p�Ɋւ��铮���Ə����W�]�v�̘_�������\����Ă���B���̘_���́u�R�@�f�B�[�[���Ԃ̑�Z�p�v�̍��ɏq��
���Ă���u�f�B�[�[���G���W���̔r�o�K�X�팸�v�Ɓu�f�B�[�[���d�ʎԂ̔R����P�v�Ɋւ�����e�ɂ��āA���s����
�ɂ��A�|���R�c���Z�p���̕M�҂��^��Ɏv���Ƃ�����ȉ����\�Q�P�ɓZ�߂����Ē������B
�����Z�p�Ɋւ��铮���Ə����W�]�v�̘_�������\����Ă���B���̘_���́u�R�@�f�B�[�[���Ԃ̑�Z�p�v�̍��ɏq��
���Ă���u�f�B�[�[���G���W���̔r�o�K�X�팸�v�Ɓu�f�B�[�[���d�ʎԂ̔R����P�v�Ɋւ�����e�ɂ��āA���s����
�ɂ��A�|���R�c���Z�p���̕M�҂��^��Ɏv���Ƃ�����ȉ����\�Q�P�ɓZ�߂����Ē������B
| �]�v |
|
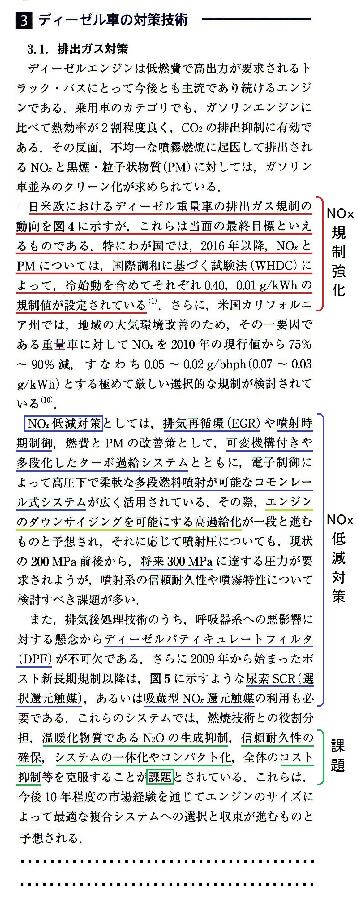 |
�� �č����������{�̑�^�g���b�N�̂mO���K���̌���
�ւ�����{��NO���K���́A�����̋K���i2016�N�K���j
�ł��A���A�Ă�NO���K�������ɂ��K���l���{�s�����
����̂�����̂悤�ł���B
���B
2013�N��EURO�Y�i�ߓn���[�h�j�m�n�� �� 0.46 g/kWh
EEV(5)�i�ߓn���[�h�j�́ANO�� �� 0.2 g/kWh
���@EEV�FEnhanced Environmentally Friendly Vehicles�̗��B
EEV�K���l�́A��C���������ɐi�s���Ă���s�s����
�n��������̂��߁A�����o�[�e���������I�Ɏg�p����
���߂̒l�i��F�s�s�ւ̏����ꐧ����݂���ۂ̊
�Ƃ��Ďg�p�j�ŁA�b��l�B
�č�
2010�N�̂m�n���K���́ANO�� �� 0.27 g/kWh
���{
2016�N�̂m�n���K���́A�m�n���� 0.4 g/kWh
�@���̂悤�ɁA��^�g���b�N�i���d�ʎԁj�Ɋւ��āA
���{�̂m�n���K���l�� 0.4 g/kWh�i2016�N�K���j�́A
�č��̂m�n���K���l�� 0.27 g/kWh�i2010�N�K���j����
�啝�Ɋɂ��̂�����ł���B
�܂�A2016�N�̎��_�ł����{�̑�^�g���b�N��
�m�n���K���́A�č�����50���߂��������̂m�n����r�o
����K�������{�����\��ł���A����͓��{��������
�r�o�K�X�K���̖ʂŁu��i���I�v�ƌ����Ă��d����
�����ƍl������B
�@���̏؋��Ƃ��ẮA���L�̂m�n���K�������i���Ԑ������j��
����ƁA���Ȃ̎����Ԕr�o�K�X���ψ��ψ���̈ψ���
�߂钘�҂��吹�O�����́A�č������啝�ɗ��
���{�̑�^�g���b�N�̂m�n���K���l�� 0.4 g/kWh
�i2016�N�K���j���u���ʂ̍ŏI�ڕW�v�Ƃ̋L�q���Ă���
���Ƃ�����M���m��邱�Ƃł���B
�@���̂��Ƃ���A���{�̎����Ԕr�o�K�X�̋K���l�����肷��
�C���w�ҁi���吹�O�����j���A���{�̑�^�g���b�N��
�m�n���K���́A�č��Ɠ������x���̌������m�n���K�������{
����\�肪�����ƍl������B���̏�����ƁA�č�����
����C���̒��Ő�������]������{�̍�����������
�{������p������邱�Ƃɂ��āA�吹�O������
�����̋^��������Ă��Ȃ����m�ȏ؋��ł͂Ȃ����ƍl��
����B
�@���̂悤�ɁA�č���������C���ł̐�����]�V�Ȃ�
����Ă�����{�����̕s�K�E�s���v�̌����̈�́A
���Ȃ̓��{�̎����Ԕr�o�K�X�̋K���l�����肷�鎩����
�r�o�K�X���ψ��ψ���̈ψ����ɑ吹�O�������C��
����Ă��邽�߂Ƃ��l�����邪�A����̓|���R�c���Z�p����
�M�҂̕Ό��ł��낤�����B
�� ���{�̑�^�g���b�N��NO���ጸ��ɂ���
�@ �č��̑�^�g���b�N�̂m�n���K���i2010�N�j �� 0.27 g/kWh
�ł��邱�Ƃ��l������ƁA�߂������̓��{�̑�^�g���b�N��
�@
�@�����āA2015�N�x�d�ʎԔR���̑��݂�����{��
�����āA���̂m�n���K���l �� 0.23�@g/kWh (WHTC���[�h)��
�@�Ƃ��낪�A���L�́u�m�n���ጸ�Z�p�v�̋L�q������ƁA���҂�
�i���������j�Ƃ��āA�ȉ����X����̊����̋Z�p����
����Ă��邾���ł���B
�E�r�C�ďz�i�d�f�q�j
�E���ˎ�������
�E�ϋ@�\�t�����i�������^�[�{�ߋ��V�X�e��
�E���i�R�����˂��\�ȃR�������[�����V�X�e��
�E���ߋ����ɂ��G���W���_�E���T�C�W���O�����i
�E�����I��300�l�o���̍����R�����ˁi�����200�l�o���j
�E�f�B�[�[���y�e�B�L�����[�g�t�B���^�i�c�o�e�j
�E�A�f�r�b�q�i�I���Ҍ��G�}�j
�E�z���^�m�n���Ҍ��G�}
�@���҂��吹�O������������^�g���b�N���m�n���ጸ
�Z�p�i���������j�́A300�l�o���̍����R������
�i����200�l�o���j�������āA���Ɏs�̂̃f�B�[�[���g���b�N��
�̗p����Ă���Z�p�����ł���B�Ƃ��낪�A����300�l�o����
�����R�����˂̋Z�p�́A�O�q���u�W�|�P�DNEDO��
�u�����x�R�Đ���G���W�V�X�e���̌����J���v�ł́A
�R����̑厸�s�v�̍��Ő��������悤�ɁA�r�o�K�X�팸
�̌��ʂ����Ȃ��A300MP���̒������R�����˂̋쓮������
�����ɂ���ĔR��̈������邱�Ƃ��V�G�l���M�[�E�Y�ƋZ�p
�����J���@�\�iNEDO)�̊v�V�I���������Q�ԑ����Z�p
�J���i�N���[���f�B�[�[���v���W�F�N�g�A2004�`2009�N�j�Ŏ���
�������
�@���̂��߁A���҂��吹�O���������ꂽ��^�g���b�N��
�m�n���ጸ�Z�p�i��300�l�o���̍����R�����˂̋Z�p���܂ށj
�ł́A2015�N�x�d�ʎԔR���̑��݂�����{�ɂ����āA
�m�n���K���l �� 0.23�@g/kWh (WHTC���[�h)�̑�^�g���b�N��
�������邱�Ƃ�����Ȃ��Ƃ́A���炩�ł���B�܂�A���L��
�_���ł́A���҂��吹�O�����́A�����I�ɑ�^�f�B�[�[��
�g���b�N�̂m�n�����\���ɍ팸�ł���Z�p�������ł���
���炸�A����グ�̏�Ԃ�I�悳��Ă���悤�ł���B
�@�ȏ�̂悤�ɁA���L���X�������^�g���b�N���m�n���ጸ
�Z�p�i���������j�ł́A�m�n���K���l �� 0.23�@g/kWh
(WHTC���[�h)�̑�^�g���b�N���������邱�Ƃ�����Ȃ��Ƃ́A
�����ł���B���̂��߁A���L�̂m�n���ጸ�Z�p�i���������j
�̋L�q�ł́A���҂��吹�O�����́A�m�n���K���l ��
0.23�@g/kWh (WHTC���[�h)�̑�^�g���b�N���������邱�Ƃ�
����ł��邱�Ƃ𐳒��ɔ���Ă���ƌ��邱�Ƃ��\��
����B
�@���̌��ʁA���L�̂m�n���K�������i���Ԑ������j�ł́A
���Ȃ̎����Ԕr�o�K�X���ψ��ψ���̈ψ����߂�
���҂̑吹�O�����́A�č������啝�ɗ����{�̑�^
�g���b�N�̂m�n���K���l�� 0.4 g/kWh�i2016�N�K���j���u���ʂ�
�ŏI�ڕW�v�Ƃ̋L�q���A����A���̃��x���ȏ�̂m�n���K��
��������{�ł͍s���\��̖������Ƃm�ɐ錾�����L�ڂ�
�s��ꂽ���̂ƍl������B
�@���������āA���L�̂m�n���K�������i���Ԑ������j�ɂ����āA
�č������啝�ɗ����{�̑�^�g���b�N�̂m�n���K���l
�� 0.4 g/kWh�i2016�N�K���j���u���ʂ̍ŏI�ڕW�v�Ƃ��閳�l
�Ȑ錾���s�킴��Ȃ������ƍl������B���̌����́A
���҂̑吹�O��������^�f�B�[�[���g���b�N���u�m�n����
0.23 (g/kWh)�v�Ɓu2015�N�x�d�ʎ�Ӱ�ޔR������
�킽���Ė����E�َE�𑱂��Ă��錋�ʂƐ��������B
���̂��Ƃ́A�C���x�~�G���W���ɂ���^�g���b�N�̒�R��A���{�͑�
�^�g���b�N�̐V���Ȓ�R��E��r�o�K�X��𑁊��ɐݒ肹��I�A�č��� ����ɂ���^�g���b�N��NO���K�����{�s����������{���{�̑Ӗ��A�f�B�[ �[���d�ʎ�2016�NNOx�K����0.4g/kWh�́A�s���Ȋɘa�̌��K���A�� �^�g���b�N��NO���팸�ƔR�����ɗL���ȋC���x�~��َE����w�ҏ��� �ɂ��ڏq���� ����̂ŁA�����̂�����͂������������B
�@���̂悤�ɁA��^�f�B�[�[���g���b�N�́u�m�n���팸�v�Ɓo�R��
�吹�O�����ɂƂ��ẮA�䎩�g�̎����S��v���C�h��
�����Ȃ����߂̍s�ׂ̂悤�Ɏv����B�������A����́A
���Ƃ������Ȏ��ł͂Ȃ����낤���B���̂��Ƃɂ��āA
�o���邱�ƂȂ�A���̃y�[�W�̓ǎ҂̈ӌ������Ē�������
���̂ł���B
�� ���{�̑�^�g���b�N�̔r�o�K�X��̉ۑ�ɂ���
�@���L�́u�ۑ�i���ΐ������j�v������ƁA���Ȃ̎�����
�r�o�K�X���ψ��ψ���̈ψ����߂钘�҂�
�吹�O�����́A��^�g���b�N�i���d�ʎԁj�̔r�o�K�X���
�ۑ�Ƃ��āA�S�������������Ă���B
�E���g�������̂m�Q�n�̐����}��
�E�M���ϋv���̊m��
�E�V�X�e���̈�̉���R���p�N�g��
�E�R�X�g�팸
�@���҂̑吹�O���������ꂽ��^�g���b�N�i���d�ʎԁj
�̔r�o�K�X����S���ڂ��ۑ�̒��́u���g��������
�m�Q�n�̐����}���v�̑��̂R���ڂ́A�g���b�N���[�J�̋Z�p�҂�
����̋Ɩ��œ��镱������u�M���ϋv���v�A�u�R���p�N�g���v�A
�u�R�X�g�팸�v�̏��i���Ɋւ���ۑ�ł���B���̋L�ړ��e��
����ƁA���҂̑吹�O�������u��^�g���b�N�i���d�ʎԁj��
�r�o�K�X��̉ۑ�v�ɂ��Ă̊S�́A�m�Q�n�ȊO��
�啔�����g���b�N���[�J�̋Z�p�҂Ɠ��l�ȏ��i���̌���ł���
�Ƃ̂��Ƃł���B�����āA���̏�����ƁA���҂̑吹
�O�����́A�w��I�Ȑ^����Nj�����w�҂ł͖����A���Y
����g���b�N�̏��i���ɐӔC�킳��Ă���g���b�N���[�J��
�Z�p�҂Ɠ��l�̎v�l��H��������Ă���悤�Ɍ����
��B����́A�w�҂Ƃ��Ă͔@���Ȃ��̂ł��낤���B
�@�܂��A2015�N���݂ɂ����āA��^�g���b�N�i���d�ʎԁj
�Ɋւ���
���{�̂m�n���K���l�� 0.4 g/kWh�i2016�N�K���j�́A
�č��̂m�n���K���l�� 0.27 g/kWh�i2010�N�K���j����
�啝�Ɋɂ�����ɂ��ẮA���҂̑吹�O�����́A
��^�g���b�N�i���d�ʎԁj�̔r�o�K�X��̉ۑ�Ƃ��Ă�
�F�����S�������悤�ł���B
�@���̌��ʁA���L�������ԋZ�p��2015�N9�����iVol.69�A
N0.9�A2015�j�̘_���̂悤�ɁA���Ȃ̎����Ԕr�o�K�X���
�ψ��ψ���̈ψ����߂钘�҂̑吹�O�����́A�č�
�����啝�ɗ����{�̑�^�g���b�N�̂m�n���K���l��
0.4 g/kWh�i2016�N�K���j���u���ʂ̍ŏI�ڕW�v�ɂ����
�q�ׂ��Ă���B
�@���̂悤�ɁA���L�̘_���̒��҂ł���吹�O���������{
�̑�^�g���b�N�̂m�n���K���l�� 0.4 g/kWh�i2016�N�K���j��
�u���ʂ̍ŏI�ڕW�v�Ǝ咣����Ă��邱�Ƃɂ��āA
�|���R�c���Z�p���̕M�҂������������R�́A�ȉ��̇@���A
�̒ʂ�ł���B
�@ ���Ȃ̎����Ԕr�o�K�X���ψ��ψ���̈ψ�����
�߂钘�҂̑吹�O�����́A2010�N7���̒������R�c��
�̑�\�����\�ɂ����āA��^�g���b�N�i���d�ʎԁj�̂m�n�����e
���x�ڕW�l�i���ϒl�j�� 0.4 ��/��W���iWHTC���[�h�j�v��
�攪�����\�̂m�n������ڕW��0.23��/kW���i��0.7��/kW��
��1/3�FJE05���[�h�j�̃��x���Ɂu�B���Ă���ƍl������v��
�i�d�O�T���[�h��WHTC���[�h�́A�قړ����̂m�n���r�o�l�ɂȂ�
�Ƃ̎������ʂ��i�Ɓj��ʈ��S���������̗�؉��ꎁ��
�_���Ɍf�ڂ���Ă���B���������āA��^�g���b�N�i���d�ʎԁj
��WHTC���[�h�̂m�n���r�o�l�� 0.4 ��/��W���́A�i�d�O�T���[�h
�ł��m�n���r�o�l�� 0.4 ��/��W���Ɠ����ł���Ɛ��������B
���̂��Ƃ���A���Ȃ̎����Ԕr�o�K�X���ψ��ψ���
�̈ψ����߂钘�҂̑吹�O�����́A2010�N7��
�̒������R�c��̑�\�����\�ɂ����āA
��^�g���b�N�i���d�ʎԁj�̂m�n�����e���x�ڕW�l
�i���ϒl�j�� 0.4 ��/��W���iWHTC���[�h�j���攪�����\
�̂m�n������ڕW��0.23��/kW���i�i�d�O�T���[�h�j�Ɠ�����
�����������e�́u���\�v���쐬�������ƂɂȂ���
�l������B
�吹�O�����́A���̑�\�����\�́u���v�E�u���U�v�̓��e
���B�����A���́u���v�E�u���U�v�����Ȃ����߂̎�i�Ƃ���
�u��^�g���b�N�i���d�ʎԁj�̂m�n�����e���x�ڕW�l�i���ϒl�j
�� 0.4 ��/��W���iWHTC���[�h�j���攪�����\�̂m�n������ڕW
��0.23��/kW���i��0.7��/kW����1/3�FJE05���[�h�j�̃��x����
�B���Ă���ƍl������v�Ƃ̌���������E�咣��������O��
���Čp�����Ă������Ƃ����S�����\��������ƍl������B
���̂��߁A���L�̘_���ł́A�吹�O�������R�����m��
��ŁA���{�̑�^�g���b�N�̂m�n���K���l�� 0.4 g/kWh
�i2016�N�K���j���u���ʂ̍ŏI�ڕW�v�Ƌ����Ɏ咣���Ă���
�\��������ƍl������B
�����ԃ��[�J�������ԗp���R�@�Z�p�����g���iAICE�j
���Ȃ����l������B���̓����Z�p���E�َE����
���ʁA�攪�����\�̑�^�g���b�N�̂m�n������ڕW
��0.23��/kW���i�v�g�s�b�j�����������i�E���@�����S�ɏ���
�������ƂɂȂ�B���̂��߁A���҂ł���吹�O�����́A
���{�̑�^�g���b�N�̂m�n���K���l�� 0.4 g/kWh
�i2016�N�K���j���u���ʂ̍ŏI�ڕW�v�Ǝ咣������Ȃ�
�Ȃ��Ă��܂����\��������B
�@���͂Ƃ�����A�吹�O�����́A��^�f�B�[�[���g���b�N��
�u�m�n���팸�v�Ɓu�R�����v�ɗL�����C���x�~�G���W���i�������J2005-
54771�j�̓����Z�p���E�َE���A��^�g���b�N �i���d�ʎԁj�̂m�n�����e���x�ڕW�l�i���ϒl�j
�� 0.4 ��/��W���iWHTC���[�h�j���攪�����\�̂m�n������ڕW
�Ɠ����Ƃ���o�L�ځi���f�^�����j�Ȕ��f����ɁA���{�̑�^
�g���b�N�̂m�n���K���l�� 0.4 g/kWh�i2016�N�K���j���u���ʂ�
�ŏI�ڕW�v�Ƃ̌�����咣���s���Ă���Ǝv�����A����́A
�|���R�c���Z�p���̕Ό��ł��낤���B�����āA�吹�O����
�����Ȃ̎����Ԕr�o�K�X���ψ��ψ���̈ψ����Ƃ���
���肵���攪�����\�̒���ڕW��0.23��/kW���̃��x����
���{�̏����I�ȃf�B�[�[���d�ʎԂ�NO���K�������̖ڕW��
������j�~���邽�߂ɁA��^�f�B�[�[���g���b�N�́u�m�n���팸�v
���P��ؖ]���鍑���ɑ��閾���Ȕw�M�I�ȍs���Ǝv�����A
�@���Ȃ��̂��낤���B�����āA�������R�c��̎����Ԕr�o
�K�X���ψ��ψ���̈ψ����̔C�ɂ���吹�O������
�s���́A���{�̑�^�g���b�N�i���d�ʎԁj�̂m�n���K���������
�č������啝�ɗ���Ԃɗ��܂点�Ă��܂����ƂɂȂ��
�l������B���̏�����ƁA���݂̓��{�ł͓K�ȑ�^
�g���b�N�i���d�ʎԁj�̑�C�����P�̎{���{�����
���Ȃ��ƒf�肵�Ă��ǂ��Ǝv�����A�@���Ȃ��̂ł��낤���B
|
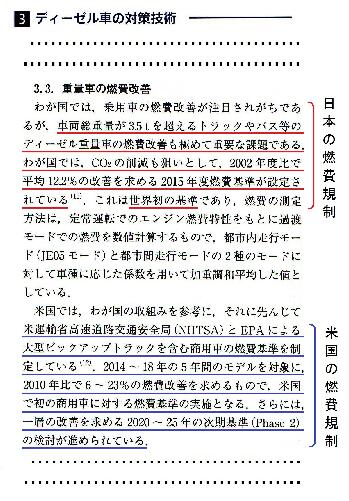 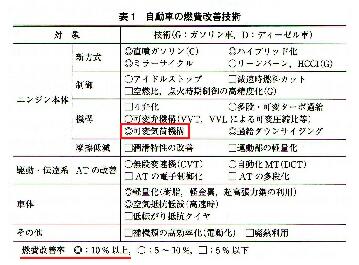 |
�� ���{�̑�^�g���b�N�i���d�ʎԁj�̔R��
�@���y��ʏȂ́A2006�N3����2015�N�x�f�B�[�[���d�ʎ� �R�����ݒ肳�ꂽ�B�Ⴆ�A��^�g���b�N�̎ԗ����d�� 20�g�������ł� 4.04 km/���b�g���̊�ł���B���̑�^ �g���b�N�i���d�ʎԁj�̔R���ɂ��āA���҂̑吹�O �����́A���L�̒ʂ�A�u���E���̊�v�ƌւ炵���ɏq�ׂ�� �Ă���B�Ƃ��낪�A���́u2015�N�x�f�B�[�[���d�ʎԔR�� ��v��2006�N3���ɐݒ肳��Ĉȗ��A�����_�i��2015�N 9�����݁j�ł͊���10�N�߂��o�߂��Ă���B����ɂ� ������炸�A���̑�^�g���b�N�i���d�ʎԁj�̔R���� �����́A���̂Ƃ���A�������\����Ă��Ȃ��B �܂��A���̋����̌������s��ꂢ��Ƃ̓����������Ȃ��B �@�������A�f�B�[�[�����^�ݕ��Ԃ́A�ȉ��̒ʂ�A�R���� ��������Ȃ����{����Ă��� �@�E1999�N3����2005�N�x�ڕW�̊�̍��� �@�E2007�N7����2015�N�x�ڕW�̊�̍��� �@�E2015�N7����2022�N�x�ڕW�̊�̍��� �i�o�T�Fhttp://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr10_000005.html�Q�Ɓj �@���̂悤�ɁA�f�B�[�[�����^�ݕ��Ԃ́A�R���̋����� ��Ȃ��ݒ肳��Ă���̂ɑ��A��^�f�B�[�[���g���b�N �i���d�ʎԁj�́A2006�N3����2015�N�x�f�B�[�[���d�ʎ� �R�����ݒ肳��Ĉȗ��A���̊�̋��������u����� ����悤�ł���B���̂悤�ɁA��^�f�B�[�[���g���b�N �i���d�ʎԁj�̔R���̋������ł��Ȃ��ő�̗��R�́A ���҂̑吹�O�������܂����{�̃G���W���W�̊w�ҁE ���Ƃ���^�f�B�[�[���g���b�N�́u�m�n���팸�v�Ɓu�R�����v �ɗL�����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓��� �Z�p���E�َE���Ă��錋�ʁA��^�f�B�[�[���g���b�N �i���d�ʎԁj�̔R����P�Z�p���u�s���v�̏Ɋׂ��� ���܂��Ă��邽�߂Ɛ��������B �@���݂ɁA�O���́u3.1. �r�o�K�X��v�ł͂X��ނ���^
�g���b�N���m�n���ጸ�Z�p������Ă��邪�A���L��
�u3.3. �d�ʎԂ̔R����P�v�̍��ł͔R����P�̋Z�p�̋L��
���F���ł���B���̂��Ƃ�������炩�Ȃ悤�ɁA���҂�
�吹�O�����́A��^�f�B�[�[���g���b�N�́u�m�n���팸�v��
�u�R�����v�ɗL�����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j
�̓����Z�p�̖����E�َE�ɂ͔M�S�Ȃ悤�Ɍ�����B
�@���̂Ȃ�A���̑吹�O�����̘_���ł́A���L��
�������u�\1 �����Ԃ̔R����P�Z�p�v�ł́A�u�ϋC���@�\
�i���C���x�~�j�v��10���ȏ�̃f�B�[�[���G���W���̔R����P
���\�ɂ���Z�p�ł��邱�Ƃ����L����Ă��邪�A���҂�
�吹�O�����́A���L�́u3.3. �d�ʎԂ̔R����P�v�̍��ł�
�R����P�̋Z�p�Ƃ��Ắu�C���x�~�v���L�ڂ���Ă��Ȃ�
�̂ł���B���̂��Ƃ�����A���҂̑吹�O�����́A��^
�f�B�[�[���g���b�N�́u�m�n���팸�v�Ɓu�R�����v�ɗL����
�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�����Z�p�̖����E�َE
�ɋ�����������Ă��邱�Ƃ��M���m�邱�Ƃ��ł���B
�W�̊w�ҁE���Ƃ���^�f�B�[�[���g���b�N�́u�m�n���팸�v �Ɓu�R�����v�ɗL�����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j �̓����Z�p���E�َE���Ă��錋�ʁA��^ �f�B�[�[���g���b�N�i���d�ʎԁj�̔R����P�Z�p���u�s���v�� �Ɋׂ��Ă��܂��Ă���Ɛ��������B���̂��Ƃ��A �u2015�N�x�f�B�[�[���d�ʎԔR���v��2006�N3���ɐݒ� ����Ĉȗ��A�����_�i��2015�N9�����݁j�ł͊���10�N�� ���o�߂��Ă��A���̑�^�g���b�N�i���d�ʎԁj���u2015�N�x �f�B�[�[���d�ʎԔR���{�P�O���v�̔R���̋����� �摗�肳��Ă��錴���ƂȂ��Ă���\�����l������B ����A���L�́u�č��̔R��K���v�̕���������ƁA�č��ł� ��^�s�b�N�A�b�v�g���b�N�E��^�g���b�N���܂ޏ��p�Ԃ� 2014�`2018�N�̃��f����ΏۂɔR��K�����J�n���A����� �����o�������� 2 �Ƃ���2020�`2025�N�̋K�������̌����� �i�߂��Ă���Ƃ̂��Ƃł���B���̂悤�ɁA���{�̃f�B�[�[�� ���^�ݕ��Ԃ�č��̑�^�g���b�N�ł́A�N��̌o�߂ɏ]���� �R��K���̋����������Ɏ��{�A�Ⴕ���͎��{�̌v�悪���s ����Ă���̂ł���B�Ƃ��낪�A��^�g���b�N�i���d�ʎԁj�́A �u2015�N�x�f�B�[�[���d�ʎԔR���v��2006�N3���ɐݒ� ����Ĉȗ��A�����_�i��2015�N9�����݁j�ł͊���10�N�߂� �o�߂��Ă��A������̌��������{����Ă��炸�A����� �́u�摗��v�E�u�x���v�����X�ƍs���Ă���̂�����̂悤�� ����B �@���̂悤�Ȃ��Ƃ́A�����ԃ��[�J�������ԗp���R�@�Z�p �����g���iAICE�j����̘d�G�Ǝv��������������^����� ���O�����������ԃ��[�J�ɑ��Ắu���Ԃ�v�E�u�ԗ�v�� ��Ƃ��l������B�����āA���ꂪ���Ɏ����ł���A���� ��n���ɂ����b�ł��邱�Ƃɂ͊ԈႢ���Ȃ��Ǝv���̂́A �M�҂����ł��낤���B |
�@���̎����ԋZ�p��2015�N9�����iVol.69�AN0.9�A2015�j�Ɍf�ڂ́u�����ԗp�p���[�g���C���̍��������Z�p�Ɋւ��铮
���Ə����W�]�v�i���ҁF����c��w�E�吹�O�����j�_���ł́A�u�������R�c��̎����Ԕr�o�K�X���ψ��ψ���
�̈ψ����v����сu���y��ʏȂ̎����ԔR�����ψ���̈ψ��v�߂��吹�O�����́A�č������啝�ɗ��
���{�̑�^�g���b�N�̂m�n���K���l�� 0.4 g/kWh�i2016�N�K���j���u���ʂ̍ŏI�ڕW�v�ɂ���Əq�ׁA2006�N3���ɐݒ肵
����^�g���b�N�i���d�ʎԁj�́u2015�N�x�f�B�[�[���d�ʎԔR���v�̋K�������ɂ́u���فv�u�ق�i���_���}���j�v����
�ߍ���ł���悤�ł���B
���Ə����W�]�v�i���ҁF����c��w�E�吹�O�����j�_���ł́A�u�������R�c��̎����Ԕr�o�K�X���ψ��ψ���
�̈ψ����v����сu���y��ʏȂ̎����ԔR�����ψ���̈ψ��v�߂��吹�O�����́A�č������啝�ɗ��
���{�̑�^�g���b�N�̂m�n���K���l�� 0.4 g/kWh�i2016�N�K���j���u���ʂ̍ŏI�ڕW�v�ɂ���Əq�ׁA2006�N3���ɐݒ肵
����^�g���b�N�i���d�ʎԁj�́u2015�N�x�f�B�[�[���d�ʎԔR���v�̋K�������ɂ́u���فv�u�ق�i���_���}���j�v����
�ߍ���ł���悤�ł���B
���j�̌���ɏd�v�Ȗ������ʂ����l���̈�l�ł����吹�O�����́A���������ԋZ�p��2015�N9�����̘_���ł́A
�攪�����\�̑�^�g���b�N�̂m�n������ڕW��0.23��/kW���i�v�g�s�b�j�̎��{��ے肵�A�u2015�N�x�f�B�[�[���d�ʎԔR��
��v�̊�����́u���فv�u�ق�i���_���}���j�v�����ߍ��ނ��Ƃɂ���ĔR�������́u�摗��v�E�u�x���v�X�Ɣ�
�\�E���\�������̂Ɛ��������B���̂悤�ɁA����c��w�E�吹�O��������^�g���b�N�́u�m�n������ڕW��0.23��/kW��
�i�v�g�s�b�j�v�ɏ����I�Ȏ��{��ے肵�A�u2015�N�x�d�ʎԔR������{�P�O���ȏ�̔R�����v�̑������{�Ɍ��y��
�Ȃ����Ƃ́A�|���R�c���Z�p���̕M�҂����������Ƃ���A�ȉ��Ɏ������@���A�̓�̌������l������B
�@ �吹�O�����́A�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p���E�َE����s�ׂ̌��ʁA��
�^�f�B�[�[���g���b�N�́u�m�n���팸�v�Ɓu�R�����v�ɗL���ȗB��̎�i�E���@������������ԁi�����Ǝ�����
�ԁj�������N���������Ƃɂ��A�u�m�n������ڕW��0.23��/kW���i�v�g�s�b�j�v�Ɓu2015�N�x�d�ʎԔR������{�P
�O���ȏ�̔R�����v�̋K��������ے肹����Ȃ��Ɋׂ��Ă��܂��Ă���\�������邱�ƁB
�^�f�B�[�[���g���b�N�́u�m�n���팸�v�Ɓu�R�����v�ɗL���ȗB��̎�i�E���@������������ԁi�����Ǝ�����
�ԁj�������N���������Ƃɂ��A�u�m�n������ڕW��0.23��/kW���i�v�g�s�b�j�v�Ɓu2015�N�x�d�ʎԔR������{�P
�O���ȏ�̔R�����v�̋K��������ے肹����Ȃ��Ɋׂ��Ă��܂��Ă���\�������邱�ƁB
�A �����ԃ��[�J�������ԗp���R�@�Z�p�����g���iAICE�j����2014�`2019�N�̊Ԃɘd�G�Ǝv�������z�̌�
����i���r�h�o�F�헪�I�C�m�x�[�V�����n���v���O�����j�����Ă���吹�O�����́A���̘d�G�i��������j
�́u���Ԃ�v�E�u�ԗ�v�Ƃ��āA��^�g���b�N�́u�m�n������ڕW��0.23��/kW���i�v�g�s�b�j�v�Ɓu2015�N�x�d�ʎԔR��
�����{�P�O���ȏ�̔R�����v���E�َE������Ȃ�����ɂ���\�������邱�ƁB�i����ɂ���
�́A��^�g���b�N��NO���팸�ƔR�����ɗL���ȋC���x�~��َE����w�ҏ����ɂ��ڏq�j
����i���r�h�o�F�헪�I�C�m�x�[�V�����n���v���O�����j�����Ă���吹�O�����́A���̘d�G�i��������j
�́u���Ԃ�v�E�u�ԗ�v�Ƃ��āA��^�g���b�N�́u�m�n������ڕW��0.23��/kW���i�v�g�s�b�j�v�Ɓu2015�N�x�d�ʎԔR��
�����{�P�O���ȏ�̔R�����v���E�َE������Ȃ�����ɂ���\�������邱�ƁB�i����ɂ���
�́A��^�g���b�N��NO���팸�ƔR�����ɗL���ȋC���x�~��َE����w�ҏ����ɂ��ڏq�j
�@���͂Ƃ�����A�u�������R�c��̎����Ԕr�o�K�X���ψ��ψ���̈ψ����v����сu���y��ʏȂ̎����ԔR���
�����ψ���̈ψ��v�߂��吹�O�����́A��C�����P��ȃG�l���M�[�̐��i�ɍv�������^�f�B�[�[���g��
�b�N�́u�m�n������ڕW��0.23��/kW���i�v�g�s�b�j�v�Ɓu2015�N�x�d�ʎԔR������{�P�O���ȏ�̔R�����v�̋K����
�����u�ے�v�Ⴕ���́u�摗��v�������C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p�ӓI�ȗ��R�i���d�G�H
�Ⴕ���͌l�I�ȃv���C�h�H�j�ɂ���Ė����E�َE���Ă���������ł���A���Љ�I�ȍs�ׂƂ��Č������f�߂����
�ׂ��ƍl���邪�A�@���Ȃ��̂ł��낤���B
�����ψ���̈ψ��v�߂��吹�O�����́A��C�����P��ȃG�l���M�[�̐��i�ɍv�������^�f�B�[�[���g��
�b�N�́u�m�n������ڕW��0.23��/kW���i�v�g�s�b�j�v�Ɓu2015�N�x�d�ʎԔR������{�P�O���ȏ�̔R�����v�̋K����
�����u�ے�v�Ⴕ���́u�摗��v�������C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p�ӓI�ȗ��R�i���d�G�H
�Ⴕ���͌l�I�ȃv���C�h�H�j�ɂ���Ė����E�َE���Ă���������ł���A���Љ�I�ȍs�ׂƂ��Č������f�߂����
�ׂ��ƍl���邪�A�@���Ȃ��̂ł��낤���B
�W�|�X�D��ʌ����ŋ߂̍u�����Ŕ��\�����f�B�[�[���G���W���̔r�o�K�X��̓��e
�W�|�X�|�P�D�u�A�fSCR�G�}�v�ɂ��NOx�팸�̑��i��}��Z�p�̒��
�@�ȉ����\�Q�Q�Ɏ������悤�ɁA2013�N12��5���A6���ɊJ�Â��ꂽ�Ɨ��s���@�l�E��ʈ��S���������̃t�H�[����
2013�ihttps://www.ntsel.go.jp/forum/forum2013.html�j�ɂ����āA��ʈ��S���������̗�؉��ꎁ�A�����������A
�R���������́A�����Ԃ̌������̐����G�l���M�[���o�b�e���[�ɒ~�d���A�r�C�K�X���x�̒Ⴂ�f�B�[�[���G���W����
�������^�]���ɒ~�d�G�l���M�[�Łu�A�fSCR�G�}�v�����M����NO���̍팸��}��Z�p���Ă����悤���B�@
2013�ihttps://www.ntsel.go.jp/forum/forum2013.html�j�ɂ����āA��ʈ��S���������̗�؉��ꎁ�A�����������A
�R���������́A�����Ԃ̌������̐����G�l���M�[���o�b�e���[�ɒ~�d���A�r�C�K�X���x�̒Ⴂ�f�B�[�[���G���W����
�������^�]���ɒ~�d�G�l���M�[�Łu�A�fSCR�G�}�v�����M����NO���̍팸��}��Z�p���Ă����悤���B�@
| |
|
| |
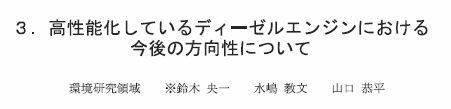 |
| |
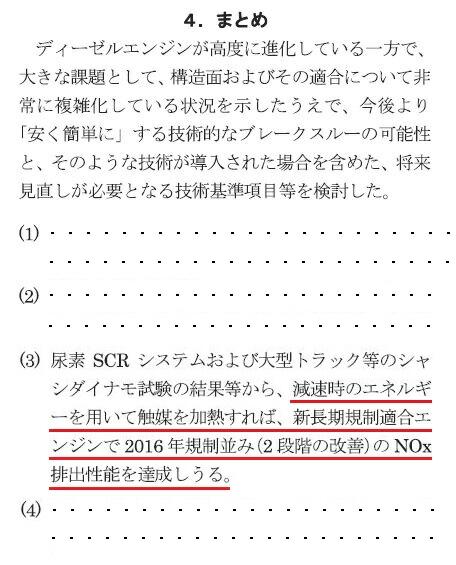 |
�@�n�C�u���b�h�����Ԃ��n�߂Ƃ��āA�ŋ߂̒ʏ�̏�p�Ԃł́A�o�b�e���[��L���p�V�^�ɒ~�d���������Ԃ̌�������
�����G�l���M�[�́A�����Ԃ̑��s�G�l���M�[�Ɏg����̂���ʓI�ł���B����́A�~�d���������Ԃ̌������̐�
���G�l���M�[�́A���[�^���쓮����ꍇ�ɂ͂X�O���O��̍��������Ŏ����Ԃ̑��s�G�l���M�[�ɕϊ��ł��邽�߂Ɏ�
���Ԃ̑��s�R��̍팸�ɋɂ߂ėL���ł��邽�߂��B���������āA�����Ԃ̌������̐����G�l���M�[�������Ԃ̑��s
�G�l���M�[�Ɋ��p����Z�p�́A���ꂩ����v�X�A�d�v������Ă������̂Ɛ��������B���̂��Ƃ́A���݂̎����Ԃ̐�
�E�E�ƊE�ł͏펯�ƍl������B
�����G�l���M�[�́A�����Ԃ̑��s�G�l���M�[�Ɏg����̂���ʓI�ł���B����́A�~�d���������Ԃ̌������̐�
���G�l���M�[�́A���[�^���쓮����ꍇ�ɂ͂X�O���O��̍��������Ŏ����Ԃ̑��s�G�l���M�[�ɕϊ��ł��邽�߂Ɏ�
���Ԃ̑��s�R��̍팸�ɋɂ߂ėL���ł��邽�߂��B���������āA�����Ԃ̌������̐����G�l���M�[�������Ԃ̑��s
�G�l���M�[�Ɋ��p����Z�p�́A���ꂩ����v�X�A�d�v������Ă������̂Ɛ��������B���̂��Ƃ́A���݂̎����Ԃ̐�
�E�E�ƊE�ł͏펯�ƍl������B
�@�Ƃ��낪�A��ʌ�����؉��ꎁ�A�����������A�R���������́A�����Ԃ̑��s�R��̌���ɗL���Ȓ~�d���������G
�l���M�[��NO���̍팸�̂��߂Ɂu�A�fSCR�G�}�v�̉��M�Ɏg���Ɖ]�����R�Ƃ�������Ȓ�Ă��s���Ă���B�����A�Z�p
�_���ɂ͏�k���L�ڂ��Ȃ����Ƃ��펯�ł���B���̂��Ƃ��l������ƁA�M�����Ȃ����Ƃł͂��邪�A��ʌ�����؉�
�ꎁ�A�����������A�R���������́A�~�d���������G�l���M�[�Łu�A�fSCR�G�}�v�����M����NO���팸�𑣐i����Z�p
�������I�ɗL���ȁu�V�Z�p�v�ł���Ɩ{�S����M�����Ă���ƍl����̂��Ó��ł͂Ȃ����낤���B����́A�|���R�c��
�Z�p���̕M�҂��猩��A�u���̍����v���B
�l���M�[��NO���̍팸�̂��߂Ɂu�A�fSCR�G�}�v�̉��M�Ɏg���Ɖ]�����R�Ƃ�������Ȓ�Ă��s���Ă���B�����A�Z�p
�_���ɂ͏�k���L�ڂ��Ȃ����Ƃ��펯�ł���B���̂��Ƃ��l������ƁA�M�����Ȃ����Ƃł͂��邪�A��ʌ�����؉�
�ꎁ�A�����������A�R���������́A�~�d���������G�l���M�[�Łu�A�fSCR�G�}�v�����M����NO���팸�𑣐i����Z�p
�������I�ɗL���ȁu�V�Z�p�v�ł���Ɩ{�S����M�����Ă���ƍl����̂��Ó��ł͂Ȃ����낤���B����́A�|���R�c��
�Z�p���̕M�҂��猩��A�u���̍����v���B
�@���݂ɁA�O�q�̂T���u�C���x�~�V�X�e���ɂ��R��팸�ƔA�fSCR�G�}�ł�NO���팸�̌���v�Ɏ������Ƃ���A�Q�^�[
�{�ߋ��@�������C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p���f�B�[�[���G���W���̕����������r�C�K
�X�����������邱�Ƃɂ���ĔA�fSCR�G�}�̍�������}��A�A�fSCR�G�}�ɂ��啝��NO���팸���������邱�Ƃ���
�\�ł���B���������āA�����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p���f�B�[�[���g���b�N�ɍ̗p����A
��^�f�B�[�[���g���b�N�i���f�B�[�[���d�ʎԁj��2016�NNO���K����0.4 g/kWh�ɂ͗]�T�œK�����\�ł���A���ȁE
�������R�c��̑攪�����\�i2005�N4���j�ɒ���Ă���NOx���@0.23�@g/kWh�j�̂m�n������ڕW��B�����邱�Ƃ�
�\�ł����ƍl������B������^�f�B�[�[���g���b�N�i���f�B�[�[���d�ʎԁj��NOx�팸�ɋɂ߂ėL�����C���x�~�G��
�W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p�́A�M�҂�2004�N5���ɓ����o�肵�A10�N���x���ȑO��2006�N4���ɂ͕M��
���z�[���y�[�W�Ō��J���Ă���B���̂��߁A2013�N12���̎��_�ł́A��ʌ�����؉��ꎁ�A�����������A�R������
���́A���̓����Z�p�̋Z�p���Ă������̂Ɛ��������B
�{�ߋ��@�������C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p���f�B�[�[���G���W���̕����������r�C�K
�X�����������邱�Ƃɂ���ĔA�fSCR�G�}�̍�������}��A�A�fSCR�G�}�ɂ��啝��NO���팸���������邱�Ƃ���
�\�ł���B���������āA�����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p���f�B�[�[���g���b�N�ɍ̗p����A
��^�f�B�[�[���g���b�N�i���f�B�[�[���d�ʎԁj��2016�NNO���K����0.4 g/kWh�ɂ͗]�T�œK�����\�ł���A���ȁE
�������R�c��̑攪�����\�i2005�N4���j�ɒ���Ă���NOx���@0.23�@g/kWh�j�̂m�n������ڕW��B�����邱�Ƃ�
�\�ł����ƍl������B������^�f�B�[�[���g���b�N�i���f�B�[�[���d�ʎԁj��NOx�팸�ɋɂ߂ėL�����C���x�~�G��
�W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p�́A�M�҂�2004�N5���ɓ����o�肵�A10�N���x���ȑO��2006�N4���ɂ͕M��
���z�[���y�[�W�Ō��J���Ă���B���̂��߁A2013�N12���̎��_�ł́A��ʌ�����؉��ꎁ�A�����������A�R������
���́A���̓����Z�p�̋Z�p���Ă������̂Ɛ��������B
�@�������Ȃ���A��ʌ�����؉��ꎁ�A�����������A�R���������́A2013�N12���̍u���_���ł́ANO���팸�̂���
�ɁA�����Ԃ̑��s�R��̌���ɗL���Ȓ~�d���������G�l���M�[���u�A�fSCR�G�}�v�̉��M�Ɏg���Ƃ̔n��������Ă�
�s���Ă���B���̒~�d���������G�l���M�[���u�A�fSCR�G�}�v�̉��M�Ɏg���ƂƂ̎咣�́A��ʌ�����؉��ꎁ�A����
�������A�R�����������C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p�̓�����S�������ł��Ă��Ȃ������ƌ�
�邱�Ƃ��\�ł���B�����A�u�L�ɏ����v�E�u�ɐ^��v�̔�g�ɗނ���ꍇ�ł���B
�ɁA�����Ԃ̑��s�R��̌���ɗL���Ȓ~�d���������G�l���M�[���u�A�fSCR�G�}�v�̉��M�Ɏg���Ƃ̔n��������Ă�
�s���Ă���B���̒~�d���������G�l���M�[���u�A�fSCR�G�}�v�̉��M�Ɏg���ƂƂ̎咣�́A��ʌ�����؉��ꎁ�A����
�������A�R�����������C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p�̓�����S�������ł��Ă��Ȃ������ƌ�
�邱�Ƃ��\�ł���B�����A�u�L�ɏ����v�E�u�ɐ^��v�̔�g�ɗނ���ꍇ�ł���B
�@����Ƃ��A�A��ʌ�����؉��ꎁ�A�����������A�R���������́A�f�B�[�[���G���W���̐��ƁE�Z�p�҂Ƃ��Ắu���i
�S�v���̔ڂ�����������M�Ғ�Ă��C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p���E�َE���邱�Ƃ��
�I�Ƃ��āA�f�B�[�[���d�ʎԂ�NOx�팸�̐V�Z�p�Ƃ��ċꂵ����������Ԃ̐����G�l���M�[���u�A�fSCR�G�}�v�̉��M
�Ɏg���Ƃ̔j���p�Ƃ��������u���_���\�����\�����l������B
�S�v���̔ڂ�����������M�Ғ�Ă��C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p���E�َE���邱�Ƃ��
�I�Ƃ��āA�f�B�[�[���d�ʎԂ�NOx�팸�̐V�Z�p�Ƃ��ċꂵ����������Ԃ̐����G�l���M�[���u�A�fSCR�G�}�v�̉��M
�Ɏg���Ƃ̔j���p�Ƃ��������u���_���\�����\�����l������B
�@�Ȃ��A�f�B�[�[���G���W�����ڂ̑�^�g���b�N�i���d�ʎԁj�ɂ�����2016�K���ւ̓K����X�Ȃ�NO���팸�ɂ́A�C��
�x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p�̑����̎��p�����K�v�ł��邱�Ƃ͖����ł���B����ɂ��������
���A�Ɨ��s���@�l�E��ʈ��S���������̃t�H�[����2013�ɂ�������ʌ�����؉��ꎁ�A�����������A�R��������
���C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p���E�َE�����u���_���\�������Ƃ́B���{�̃f�B�[�[
���d�ʎԂ�NOx�팸�Z�p�̐i�W��j�Q���銈�����s���Ă������ƂɂȂ�ƍl������B���݂ɁA��ʌ�����؉���
���A�����������A�R���������́A�����_�i��2016�N4�����݁j�ɂ����Ă��A�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j
�̓����Z�p���E�َE��f�s���Ă���̂ł��낤���B�����āA��^�g���b�N�i���d�ʎԁj�ɂ�����2016�K���ւ̓K����
�X�Ȃ�NO���팸�ɂ́A�����Ԃ̑��s�R��̌���ɗL���Ȓ~�d���������G�l���M�[��NO���̍팸�̂��߂Ɂu�A�fSCR
�G�}�v�����M����Ƃ́u�n���v�E�u�Ԕ����v�Ȏ咣���J��Ԃ��Ă���̂ł��낤���B���ɁA�����ł���A���Ƃ�����Ȃ��Ƃ�
����B
�x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p�̑����̎��p�����K�v�ł��邱�Ƃ͖����ł���B����ɂ��������
���A�Ɨ��s���@�l�E��ʈ��S���������̃t�H�[����2013�ɂ�������ʌ�����؉��ꎁ�A�����������A�R��������
���C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p���E�َE�����u���_���\�������Ƃ́B���{�̃f�B�[�[
���d�ʎԂ�NOx�팸�Z�p�̐i�W��j�Q���銈�����s���Ă������ƂɂȂ�ƍl������B���݂ɁA��ʌ�����؉���
���A�����������A�R���������́A�����_�i��2016�N4�����݁j�ɂ����Ă��A�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j
�̓����Z�p���E�َE��f�s���Ă���̂ł��낤���B�����āA��^�g���b�N�i���d�ʎԁj�ɂ�����2016�K���ւ̓K����
�X�Ȃ�NO���팸�ɂ́A�����Ԃ̑��s�R��̌���ɗL���Ȓ~�d���������G�l���M�[��NO���̍팸�̂��߂Ɂu�A�fSCR
�G�}�v�����M����Ƃ́u�n���v�E�u�Ԕ����v�Ȏ咣���J��Ԃ��Ă���̂ł��낤���B���ɁA�����ł���A���Ƃ�����Ȃ��Ƃ�
����B
���͂Ƃ�����A���R�̔@���ɂ�����炸�A�~�d���������G�l���M�[�Łu�A�fSCR�G�}�v�����M����NO���팸�𑣐i��
�����p�I�ȋZ�p�ɂ���ďd�ʎԂ�2016�NNO���K���ւ̓K�����\�Ƃ���o�L�ڂȍu���_���\�������Ƃ́A��
�ʌ�����؉��ꎁ�A�����������A�R�����������f�B�[�[���G���W�������ƁE�Z�p�҂Ƃ��Ă͎��i�ł��邱�Ƃ̏ؖ�
�ł͂Ȃ����ƍl������B���݂ɁA��ʌ�����؉��ꎁ�A�����������A�R���������́A�����_�i��2016�N4�����݁j��
���A�~�d���������G�l���M�[�Łu�A�fSCR�G�}�v�����M����NO���팸�𑣐i����n���ۏo���̋Z�p��p���ďd�ʎԂ�
2016�NNO���K���ɓK��������Ɖ]���j���p�Ȕ����E���\���J��Ԃ��Ă���̂ł��낤���B����Ƃ��A���p�I�ȃf�B�[�[��
�G���W����NOx�팸�Z�p��V���ɒ��Ă���̂ł��낤���B����ɂ��Ă̏����䎝���̕��́A�����̂d���[����
�Č䋳������������K���ł���B
�����p�I�ȋZ�p�ɂ���ďd�ʎԂ�2016�NNO���K���ւ̓K�����\�Ƃ���o�L�ڂȍu���_���\�������Ƃ́A��
�ʌ�����؉��ꎁ�A�����������A�R�����������f�B�[�[���G���W�������ƁE�Z�p�҂Ƃ��Ă͎��i�ł��邱�Ƃ̏ؖ�
�ł͂Ȃ����ƍl������B���݂ɁA��ʌ�����؉��ꎁ�A�����������A�R���������́A�����_�i��2016�N4�����݁j��
���A�~�d���������G�l���M�[�Łu�A�fSCR�G�}�v�����M����NO���팸�𑣐i����n���ۏo���̋Z�p��p���ďd�ʎԂ�
2016�NNO���K���ɓK��������Ɖ]���j���p�Ȕ����E���\���J��Ԃ��Ă���̂ł��낤���B����Ƃ��A���p�I�ȃf�B�[�[��
�G���W����NOx�팸�Z�p��V���ɒ��Ă���̂ł��낤���B����ɂ��Ă̏����䎝���̕��́A�����̂d���[����
�Č䋳������������K���ł���B
�@�Ȃ��A���̍��ł́u�~�d���������G�l���M�[�ŔA�fSCR�G�}�����M����NO�����팸����v�Ƃ̌�ʌ�����؉��ꎁ�A
�����������A�R������������Ă��u���̍����v�Ƃ���L�ڂ́A�M�҂̏���Ȍ����ł���B���̕M�҂̌����ɂ��āA
��ʌ��̏����ɔ��_������ꍇ�ɂ́A���̓��e��{�y�[�W�����̕M�҂̂d���[���A�h���X�ɂ͂����肢�����������B
���̌��ʁA�M�҂̏����Ɍ�肪������A�����ɒ�������\��ł���B�������A��ʌ��̏������甽�_�̂d���[��
������̂��Ȃ��ꍇ�ɂ́A��ʌ�����؉��ꎁ�A�����������A�R���������́A���̍����M�҂��L�ړ��e����S�ʓI
�ɔF�߂��Ă���Ɨ��������Ă����������Ƃɂ���B
�����������A�R������������Ă��u���̍����v�Ƃ���L�ڂ́A�M�҂̏���Ȍ����ł���B���̕M�҂̌����ɂ��āA
��ʌ��̏����ɔ��_������ꍇ�ɂ́A���̓��e��{�y�[�W�����̕M�҂̂d���[���A�h���X�ɂ͂����肢�����������B
���̌��ʁA�M�҂̏����Ɍ�肪������A�����ɒ�������\��ł���B�������A��ʌ��̏������甽�_�̂d���[��
������̂��Ȃ��ꍇ�ɂ́A��ʌ�����؉��ꎁ�A�����������A�R���������́A���̍����M�҂��L�ړ��e����S�ʓI
�ɔF�߂��Ă���Ɨ��������Ă����������Ƃɂ���B
�W�|�X�|�P�D��ʌ��E�㓡�Y�ꎁ�ɂ���f�B�[�[�������Ԃ�DPF�Đ��Z�p�̌�������i2013�N5���j
�@�ȉ����\�Q�R�Ɏ������悤�ɁA2013�N5��31���ɊJ�Â��ꂽ�Ɨ��s���@�l�E��ʈ��S���������u����2013�ihttps:/
/www.ntsel.go.jp/kouenkai/kouenkai25.html�j�ɂ����āA��ʈ��S���������̌㓡�Y�ꎁ�́ADPF�̍Đ�������I��
�u�R���̃|�X�g���ˁv��u�r�C�Ǔ��ւ̔R�����ˁv�ɂ���Ĕr�C�K�X���������鋭���Đ��̑��ɕ��@�������ƒf�肵��
�u�����s�����悤���B�@
/www.ntsel.go.jp/kouenkai/kouenkai25.html�j�ɂ����āA��ʈ��S���������̌㓡�Y�ꎁ�́ADPF�̍Đ�������I��
�u�R���̃|�X�g���ˁv��u�r�C�Ǔ��ւ̔R�����ˁv�ɂ���Ĕr�C�K�X���������鋭���Đ��̑��ɕ��@�������ƒf�肵��
�u�����s�����悤���B�@
| |
|
| |
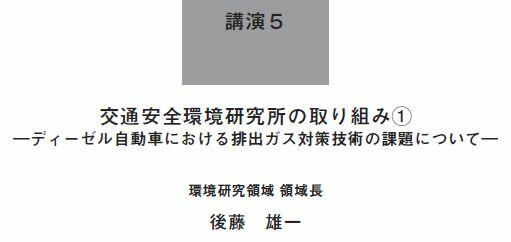 |
| |
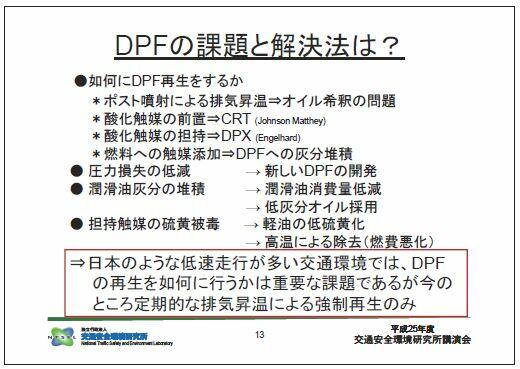 |
�@�C���x�~��DPF�̎��ȍĐ��𑣐i (�����Đ��̍팸�ŔR�����h�~�j�ɏڏq���Ă���悤�ɁA�c�o�e�Ƀp�e�B�L����
�[�g���͐ς�������ƃt�B���^�[���ڋl�܂���N�����ăt�B���^�ɂ͗n����T�����邽�߁A���ʂ̃p�e�B�L�����[�g
���t�B���^�ɑ͐ς���p�e�B�L�����[�g��R�Ă����ď�������K�v������B�����Łu�|�X�g���ˁv��u�r�C�Ǔ��ւ̔R����
�ˁv���s���A���́u�|�X�g���ˁv��u�r�C�Ǔ��ւ̔R�����ˁv�̔R�����t�B���^�̏㗬�ɔz�u���ꂽ�_���G�}�ŔR�Ă���
�Ĕr�C�K�X���x��600���܂ŏ㏸������B���̔R�����˂ɂ����20�`30���Ԃɂ킽���ăt�B���^��600���Ɉێ����ăB��
�^�ɑ͐ς����p�e�B�L�����[�g��R�₵�s������DPF�̃t�B���^���Đ�����悤�ɂ����̂��A�u�|�X�g���˕����v��u�r�C��
���ւ̔R�����˕����v�ɂ��DPF�̍Đ��ł���B���̂悤�ɁA��ʌ��̌㓡�Y�ꎁ���f�肷���u�|�X�g���˕����v��
�u�r�C�Ǔ��ւ̔R�����˕����v�ł��R�����˂ɂ�����I�Ȕr�C������DPF�̃t�B���^�Đ����s����i�E���@
�ł́A�r�C�����ŏ�����R���i���y���j�́A�V�����_���ŔR�Ă��Ȃ����߂Ƀf�B�[�[���G���W���̏o�͂ɂ�
�����^���Ȃ��B���̂��߁ADPF�̍Đ��p�x�̑����ɂ���Ď����ԑ��s���̃G���W���쓮�͂Ɩ��W�ȁu�|�X
�g���ˁv��u�r�C�Ǔ��ւ̔R�����ˁv�̏���R�����������A���ʓI�Ɏ����ԑ��s���̌y���̖��ʂȏ���ʂ�
���������ƂɂȂ�B
�[�g���͐ς�������ƃt�B���^�[���ڋl�܂���N�����ăt�B���^�ɂ͗n����T�����邽�߁A���ʂ̃p�e�B�L�����[�g
���t�B���^�ɑ͐ς���p�e�B�L�����[�g��R�Ă����ď�������K�v������B�����Łu�|�X�g���ˁv��u�r�C�Ǔ��ւ̔R����
�ˁv���s���A���́u�|�X�g���ˁv��u�r�C�Ǔ��ւ̔R�����ˁv�̔R�����t�B���^�̏㗬�ɔz�u���ꂽ�_���G�}�ŔR�Ă���
�Ĕr�C�K�X���x��600���܂ŏ㏸������B���̔R�����˂ɂ����20�`30���Ԃɂ킽���ăt�B���^��600���Ɉێ����ăB��
�^�ɑ͐ς����p�e�B�L�����[�g��R�₵�s������DPF�̃t�B���^���Đ�����悤�ɂ����̂��A�u�|�X�g���˕����v��u�r�C��
���ւ̔R�����˕����v�ɂ��DPF�̍Đ��ł���B���̂悤�ɁA��ʌ��̌㓡�Y�ꎁ���f�肷���u�|�X�g���˕����v��
�u�r�C�Ǔ��ւ̔R�����˕����v�ł��R�����˂ɂ�����I�Ȕr�C������DPF�̃t�B���^�Đ����s����i�E���@
�ł́A�r�C�����ŏ�����R���i���y���j�́A�V�����_���ŔR�Ă��Ȃ����߂Ƀf�B�[�[���G���W���̏o�͂ɂ�
�����^���Ȃ��B���̂��߁ADPF�̍Đ��p�x�̑����ɂ���Ď����ԑ��s���̃G���W���쓮�͂Ɩ��W�ȁu�|�X
�g���ˁv��u�r�C�Ǔ��ւ̔R�����ˁv�̏���R�����������A���ʓI�Ɏ����ԑ��s���̌y���̖��ʂȏ���ʂ�
���������ƂɂȂ�B
�@���̂��߁A�u�|�X�g���˕����v��u�r�C�Ǔ��ւ̔R�����˕����v��p����DPF�̃t�B���^�Đ����@�́A�R���Q��̒v
���I�Ȍ��ׂ̂��邱�Ƃ����m�̎����ł���B���̂��߁A�C���x�~��DPF�̎��ȍĐ��𑣐i (�����Đ��̍팸�ŔR��
������h�~�j�ɏڏq���Ă���悤�ɁA�S���{�g���b�N������y��ʏȂɑ��āu�|�X�g���˕����v��u�r�C�Ǔ��ւ̔R
�����˕����v�̉��P��\������Ă�����i��http://www.jta.or.jp/kankyo/chosa/DPF_taiou201212.html�j�ł���B�Ƃ�
�낪�A2013�N5��31���ɊJ�Â��ꂽ�Ɨ��s���@�l�E��ʈ��S���������u����2013�ł́A��ʌ��̌㓡�Y�ꎁ�́A
�R���Q��̒v���I�Ȍ��ׂ̂���u�|�X�g���˕����v��u�r�C�Ǔ��ւ̔R�����˕����v�̑��ɂ�DPF�̃t�B���^�Đ���
�s�\���f�肵�Ă���̂ł���B�܂�A��ʌ��̌㓡�Y�ꎁ�́A���s�̃f�B�[�[�������Ԃł��t�B���^�i��DPF�j��
���ȍĐ��̉��P�E���オ�Z�p�I�ɕs�\�ƒf�����Ă���̂ł���B
���I�Ȍ��ׂ̂��邱�Ƃ����m�̎����ł���B���̂��߁A�C���x�~��DPF�̎��ȍĐ��𑣐i (�����Đ��̍팸�ŔR��
������h�~�j�ɏڏq���Ă���悤�ɁA�S���{�g���b�N������y��ʏȂɑ��āu�|�X�g���˕����v��u�r�C�Ǔ��ւ̔R
�����˕����v�̉��P��\������Ă�����i��http://www.jta.or.jp/kankyo/chosa/DPF_taiou201212.html�j�ł���B�Ƃ�
�낪�A2013�N5��31���ɊJ�Â��ꂽ�Ɨ��s���@�l�E��ʈ��S���������u����2013�ł́A��ʌ��̌㓡�Y�ꎁ�́A
�R���Q��̒v���I�Ȍ��ׂ̂���u�|�X�g���˕����v��u�r�C�Ǔ��ւ̔R�����˕����v�̑��ɂ�DPF�̃t�B���^�Đ���
�s�\���f�肵�Ă���̂ł���B�܂�A��ʌ��̌㓡�Y�ꎁ�́A���s�̃f�B�[�[�������Ԃł��t�B���^�i��DPF�j��
���ȍĐ��̉��P�E���オ�Z�p�I�ɕs�\�ƒf�����Ă���̂ł���B
�@�Ƃ��낪�A�����ɂ́A���́u�|�X�g���˕����v��u�r�C�Ǔ��ւ̔R�����˕����v�ɂ�����R���Q��̕s�����������
DPF�̃t�B���^�Đ��̐V�Z�p�̓��������݂��Ă���̂ł���B���ꂪ�M�Ғ�Ă��C���x�~�G���W���i�������J2005-
54771�j�̓����Z�p�ł���B���̓����Z�p�́A�Ⴆ���U�C���f�B�[�[���G ���W���ł́A���������ɂ����āA����̋C
���Q�i�R�C���j��R�ċC���Ƃ��ĉ^�]���A�����̋C���Q�i�R�C���j���x�~�C���Ƃ��ĉ^�]���邱�Ƃɂ��A�L�͈͂̕���
���^�]���ɂ����ĔR�ĉ^�]�̋C���Q�i�R�C���j�ł͏�ɍ����̔r�C�K�X�i���r�C�}�t���[�����C���ɕ��o
����r�C�K�X�j�ɂ��t�B���^�i��DPF�j�̎��ȍĐ��̉��P�E�������\�ȋZ�p�ł���B�����āA���̓����Z�p����
�p�����f�B�[�[���G���W����DPF�̎��ȍĐ��ł́A�c�o�e�Đ��̂��߂̔R�����˂��s�K�v�Ȃ��߁A�u�|�X�g���˕�
���v��u�r�C�Ǔ��ւ̔R�����˕����v�̕s��ł���c�o�e�Đ����ɔ�������R���̘Q�������ł���D�ꂽ������
����B�����āA�����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p�����X��DPF�̎��ȍĐ��@�\�����コ����
�Z�p���㏈������V�X�e���i�������J2005-69238�j�̓����Z�p�ł���B
DPF�̃t�B���^�Đ��̐V�Z�p�̓��������݂��Ă���̂ł���B���ꂪ�M�Ғ�Ă��C���x�~�G���W���i�������J2005-
54771�j�̓����Z�p�ł���B���̓����Z�p�́A�Ⴆ���U�C���f�B�[�[���G ���W���ł́A���������ɂ����āA����̋C
���Q�i�R�C���j��R�ċC���Ƃ��ĉ^�]���A�����̋C���Q�i�R�C���j���x�~�C���Ƃ��ĉ^�]���邱�Ƃɂ��A�L�͈͂̕���
���^�]���ɂ����ĔR�ĉ^�]�̋C���Q�i�R�C���j�ł͏�ɍ����̔r�C�K�X�i���r�C�}�t���[�����C���ɕ��o
����r�C�K�X�j�ɂ��t�B���^�i��DPF�j�̎��ȍĐ��̉��P�E�������\�ȋZ�p�ł���B�����āA���̓����Z�p����
�p�����f�B�[�[���G���W����DPF�̎��ȍĐ��ł́A�c�o�e�Đ��̂��߂̔R�����˂��s�K�v�Ȃ��߁A�u�|�X�g���˕�
���v��u�r�C�Ǔ��ւ̔R�����˕����v�̕s��ł���c�o�e�Đ����ɔ�������R���̘Q�������ł���D�ꂽ������
����B�����āA�����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p�����X��DPF�̎��ȍĐ��@�\�����コ����
�Z�p���㏈������V�X�e���i�������J2005-69238�j�̓����Z�p�ł���B
�@���݂̎s�̂̃f�B�[�[���g���b�N���ł��R���Q��̒v���I�Ȍ��ׂ̂���u�|�X�g���˕����v��u�r�C�Ǔ��ւ̔R����
�˕����v��DPF�̃t�B���^���Đ����鑕�u����������Ă���B�������A�M�҂́A�R���Q��̌��ׂ�r�������C���x�~�G
���W���i�������J2005-54771�j���㏈������V�X�e���i�������J2005-69238�j�̎��ȍĐ������̂c�o�e�Đ��[�u�̓�
���Z�p��2004�N�ɓ����o�肵�Ă���̂ł���A�����āA�����P�O�N���ȑO��2006�N4���ɕM���̃z�[���y�[�W�Ō��J��
�Ă���B���̂��߁A�����̃f�B�[�[���G���W���̐��ƁE�Z�p�҂́A�����̓����Z�p�̑��݂�F�m���Ă�����̂Ɛ�
�@�����B����ɂ�������炸�A��ʌ����㓡�Y�ꎁ�́A2013�N5��31���ɊJ�Â��ꂽ�Ɨ��s���@�l�E��ʈ��S��
�������u����2013�ɂ����āA�u�|�X�g���˕����v��u�r�C�Ǔ��ւ̔R�����˕����v�̔R���Q��i�����ʂȔR������j��
����DPF�̃t�B���^�Đ����@���B�ꖳ��ł���ƒf�肵���n�������u�����s���Ă���̂ł���B���̂��Ƃ́A��ʌ���
�㓡�Y�ꎁ���C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�A�㏈������V�X�e���i�������J2005-69238�j�̓����̋Z�p
���e��S�������ł��Ă��Ȃ����Ƃ������ƍl������B
�˕����v��DPF�̃t�B���^���Đ����鑕�u����������Ă���B�������A�M�҂́A�R���Q��̌��ׂ�r�������C���x�~�G
���W���i�������J2005-54771�j���㏈������V�X�e���i�������J2005-69238�j�̎��ȍĐ������̂c�o�e�Đ��[�u�̓�
���Z�p��2004�N�ɓ����o�肵�Ă���̂ł���A�����āA�����P�O�N���ȑO��2006�N4���ɕM���̃z�[���y�[�W�Ō��J��
�Ă���B���̂��߁A�����̃f�B�[�[���G���W���̐��ƁE�Z�p�҂́A�����̓����Z�p�̑��݂�F�m���Ă�����̂Ɛ�
�@�����B����ɂ�������炸�A��ʌ����㓡�Y�ꎁ�́A2013�N5��31���ɊJ�Â��ꂽ�Ɨ��s���@�l�E��ʈ��S��
�������u����2013�ɂ����āA�u�|�X�g���˕����v��u�r�C�Ǔ��ւ̔R�����˕����v�̔R���Q��i�����ʂȔR������j��
����DPF�̃t�B���^�Đ����@���B�ꖳ��ł���ƒf�肵���n�������u�����s���Ă���̂ł���B���̂��Ƃ́A��ʌ���
�㓡�Y�ꎁ���C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�A�㏈������V�X�e���i�������J2005-69238�j�̓����̋Z�p
���e��S�������ł��Ă��Ȃ����Ƃ������ƍl������B
�@����Ƃ��A��ʌ����㓡�Y�ꎁ�́A�f�B�[�[���G���W���̐��ƁE�Z�p�҂Ƃ��Ắu���i�S�v���̔ڂ�����������M��
��Ă��C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�A�㏈������V�X�e���i�������J2005-69238�j�̓����Z�p���E
�َE���邱�Ƃ�ړI�Ƃ��āA�f�B�[�[���d�ʎԂ��u�|�X�g���˕����v��u�r�C�Ǔ��ւ̔R�����˕����v�̔R���Q��i����
�ʂȔR������j��DPF�̃t�B���^�Đ����@���B�ꖳ��ł���Ƃ̏o�L�ڂȍu�����s�����\�����l������B����
�������ł���A��ʌ����㓡�Y�ꎁ�̔��\���e���疾�炩�Ȃ��Ƃ́A�f�B�[�[���G���W���̕��������ɔr�C�K�X
���x�̍������ɂ����DPF�̎��ȍĐ��@�\�i�������C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�A�㏈������V�X
�e���i�������J2005-69238�j�̓����Z�p�̑����̎��p�����K�v�ł��邱�Ƃ̏؋��̈�ł͖������낤���B�����āA
�Ɨ��s���@�l�E��ʈ��S���������u����2013�ł̌㓡�Y�ꎁ�̍u�����e�́A���{�̃f�B�[�[���d�ʎԂ�NOx��
���Z�p�̐i�W��j�Q���銈�����s���Ă������ƂɂȂ�ƍl������B���݂ɁA��ʌ����㓡�Y�ꎁ�́A�����_�i��
2016�N4�����݁j�ɂ����Ă��A�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�A�㏈������V�X�e���i�������J2005-69238�j
�̓����Z�p���E�َE��f�s���Ă���̂ł��낤���B�����āA�f�B�[�[���d�ʎԂ��u�|�X�g���˕����v��u�r�C�Ǔ���
�̔R�����˕����v�̔R���Q��i�����ʂȔR������j��DPF�̃t�B���^�Đ����@���B�ꖳ��ł���Ƃ́u�n���v�E�u��
�����v�Ȏ咣���J��Ԃ��Ă���̂ł��낤���B���ɁA�����ł���A���Ƃ�����Ȃ��Ƃł���B
��Ă��C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�A�㏈������V�X�e���i�������J2005-69238�j�̓����Z�p���E
�َE���邱�Ƃ�ړI�Ƃ��āA�f�B�[�[���d�ʎԂ��u�|�X�g���˕����v��u�r�C�Ǔ��ւ̔R�����˕����v�̔R���Q��i����
�ʂȔR������j��DPF�̃t�B���^�Đ����@���B�ꖳ��ł���Ƃ̏o�L�ڂȍu�����s�����\�����l������B����
�������ł���A��ʌ����㓡�Y�ꎁ�̔��\���e���疾�炩�Ȃ��Ƃ́A�f�B�[�[���G���W���̕��������ɔr�C�K�X
���x�̍������ɂ����DPF�̎��ȍĐ��@�\�i�������C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�A�㏈������V�X
�e���i�������J2005-69238�j�̓����Z�p�̑����̎��p�����K�v�ł��邱�Ƃ̏؋��̈�ł͖������낤���B�����āA
�Ɨ��s���@�l�E��ʈ��S���������u����2013�ł̌㓡�Y�ꎁ�̍u�����e�́A���{�̃f�B�[�[���d�ʎԂ�NOx��
���Z�p�̐i�W��j�Q���銈�����s���Ă������ƂɂȂ�ƍl������B���݂ɁA��ʌ����㓡�Y�ꎁ�́A�����_�i��
2016�N4�����݁j�ɂ����Ă��A�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�A�㏈������V�X�e���i�������J2005-69238�j
�̓����Z�p���E�َE��f�s���Ă���̂ł��낤���B�����āA�f�B�[�[���d�ʎԂ��u�|�X�g���˕����v��u�r�C�Ǔ���
�̔R�����˕����v�̔R���Q��i�����ʂȔR������j��DPF�̃t�B���^�Đ����@���B�ꖳ��ł���Ƃ́u�n���v�E�u��
�����v�Ȏ咣���J��Ԃ��Ă���̂ł��낤���B���ɁA�����ł���A���Ƃ�����Ȃ��Ƃł���B
�@���͂Ƃ�����A���R�̔@���ɂ�����炸�A�f�B�[�[���d�ʎԂ��u�|�X�g���˕����v��u�r�C�Ǔ��ւ̔R�����˕����v
�̔R���Q��i�����ʂȔR������j��DPF�̃t�B���^�Đ����@���B�ꖳ��ł���Ƃ̏o�L�ڂȍu�����s������ʌ�
���㓡�Y�ꎁ�́A�f�B�[�[���G���W�������ƁE�Z�p�҂Ƃ��Ă͖��炩�Ɏ��i�ł��邱�Ƃ̏ؖ��ł͂Ȃ����ƍl�����
��B���݂ɁA��ʌ����㓡�Y�ꎁ�́A�����_�i��2016�N4�����݁j�ł��A�f�B�[�[���d�ʎԂ��u�|�X�g���˕����v��u�r
�C�Ǔ��ւ̔R�����˕����v�̔R���Q��i�����ʂȔR������j��DPF�̃t�B���^�Đ����@���B�ꖳ��ł���Ƃ̔j
���p�Ȕ����E���\���J��Ԃ��Ă���̂ł��낤���B����Ƃ��A�R���Q��i�����ʂȔR������j�̐����Ȃ�DPF�̃t�B���^
�Đ��Z�p��V���ɒ��Ă���̂ł��낤���B����ɂ��Ă̏����䎝���̕��́A�����̂d���[���ɂČ䋳������
������K���ł���B
�̔R���Q��i�����ʂȔR������j��DPF�̃t�B���^�Đ����@���B�ꖳ��ł���Ƃ̏o�L�ڂȍu�����s������ʌ�
���㓡�Y�ꎁ�́A�f�B�[�[���G���W�������ƁE�Z�p�҂Ƃ��Ă͖��炩�Ɏ��i�ł��邱�Ƃ̏ؖ��ł͂Ȃ����ƍl�����
��B���݂ɁA��ʌ����㓡�Y�ꎁ�́A�����_�i��2016�N4�����݁j�ł��A�f�B�[�[���d�ʎԂ��u�|�X�g���˕����v��u�r
�C�Ǔ��ւ̔R�����˕����v�̔R���Q��i�����ʂȔR������j��DPF�̃t�B���^�Đ����@���B�ꖳ��ł���Ƃ̔j
���p�Ȕ����E���\���J��Ԃ��Ă���̂ł��낤���B����Ƃ��A�R���Q��i�����ʂȔR������j�̐����Ȃ�DPF�̃t�B���^
�Đ��Z�p��V���ɒ��Ă���̂ł��낤���B����ɂ��Ă̏����䎝���̕��́A�����̂d���[���ɂČ䋳������
������K���ł���B
�@�Ȃ��A�S���{�g���b�N������y��ʏȂɑ��āu�|�X�g���˕����v��u�r�C�Ǔ��ւ̔R�����˕����v�̉��P�𑁊���
�������邽�߂ɂ́A�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p�̎��p���ȊO�Ɏ�i�E���@�������ƍl����
���B���̂��߁A2013�N5��31���ɊJ�Â��ꂽ�Ɨ��s���@�l�E��ʈ��S���������u����2013�ɂ����ẮA��ʌ�
���㓡�Y�ꎁ�́A���s�̃f�B�[�[���G���W���ł�DPF�̎��ȍĐ��@�\�̑��i�E�W�i�������C���x�~�G���W���i������
�J2005-54771�j�A�㏈������V�X�e���i�������J2005-69238�j�̓����Z�p�̑��}�̎��p�����咣���ׂ��ł������ƍl
������B
�������邽�߂ɂ́A�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p�̎��p���ȊO�Ɏ�i�E���@�������ƍl����
���B���̂��߁A2013�N5��31���ɊJ�Â��ꂽ�Ɨ��s���@�l�E��ʈ��S���������u����2013�ɂ����ẮA��ʌ�
���㓡�Y�ꎁ�́A���s�̃f�B�[�[���G���W���ł�DPF�̎��ȍĐ��@�\�̑��i�E�W�i�������C���x�~�G���W���i������
�J2005-54771�j�A�㏈������V�X�e���i�������J2005-69238�j�̓����Z�p�̑��}�̎��p�����咣���ׂ��ł������ƍl
������B
�@�Ȃ��A���̍��ł́u�f�B�[�[���d�ʎԂ��|�X�g���˕�����r�C�Ǔ��ւ̔R�����˕�����DPF�̃t�B���^�Đ����@��
�B�ꖳ��ł���v�Ƃ̌�ʌ����㓡�Y�ꎁ���������u���̍����v�Ƃ���L�ڂ́A�M�҂̏���Ȉӌ��ł���B���̕M��
�̈ӌ��ɂ��āA��ʌ����㓡�Y�ꎁ�ɔ��_������ꍇ�ɂ́A���̓��e��{�y�[�W�����̕M�҂̂d���[���A�h���X��
�͂����肢�����������B���̌��ʁA�M�҂̈ӌ��Ɍ�肪������A�����ɒ�������\��ł���B�������A��ʌ���
�㓡�Y�ꎁ�������_�̂d���[������̂��Ȃ��ꍇ�ɂ́A��ʌ����㓡�Y�ꎁ�́A���̍����M�҂��L�ړ��e����S��
�I�ɔF�߂��Ă���Ɨ��������Ă����������Ƃɂ���B
�B�ꖳ��ł���v�Ƃ̌�ʌ����㓡�Y�ꎁ���������u���̍����v�Ƃ���L�ڂ́A�M�҂̏���Ȉӌ��ł���B���̕M��
�̈ӌ��ɂ��āA��ʌ����㓡�Y�ꎁ�ɔ��_������ꍇ�ɂ́A���̓��e��{�y�[�W�����̕M�҂̂d���[���A�h���X��
�͂����肢�����������B���̌��ʁA�M�҂̈ӌ��Ɍ�肪������A�����ɒ�������\��ł���B�������A��ʌ���
�㓡�Y�ꎁ�������_�̂d���[������̂��Ȃ��ꍇ�ɂ́A��ʌ����㓡�Y�ꎁ�́A���̍����M�҂��L�ړ��e����S��
�I�ɔF�߂��Ă���Ɨ��������Ă����������Ƃɂ���B
�X�D�f�B�[�[���̒�R��ƒ�NO���ɗL���ȋC���x�~��َE������Ƃ̕s�v�c
�@���ȁE�������R�c��́A�g���b�N���[�J�̂m�n���팸�̋Z�p�J���̐i�W���s�\���ł��������߂�2005�N�̑攪��
���\���m�n������ڕW��NO���팸�������ł������ɂȂ��Ɣ��f���A��\�����\�i2010�N�V��28���j�ł��|�X�g�r�o�K�X�K
���i2009�N�K���j�̎��̂m�n���K�������i2016�N�Ɏ��{�j�ł� 0.4 g/kWh�� �ɂ��K���l��ݒ肵���̂ł͂Ȃ����ƍl��
����B����́A2016�N�̂m�n���K�������Ɋ֘A���A�g���b�N���[�J�ƊE���g���b�N���[�J�����ȁE�������R�c��ɑ�
������^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W���̔R��팸���\�ɂ���Z�p�̊J�����\��ʂ�ɐi�W���Ă��Ȃ����Ƃ����
���A�g���b�N���[�J�ƊE���ɂ��m�n���K���l�̐ݒ�������ʂł͂Ȃ����Ɛ��@�ł��������B
�@�M�҂̕������������m��Ȃ����A�ȏ���悤���o�܂ɂ��A���ɁA���ȁE�������R�c��́A��\�����\�i2010
�N�V��28���j�ɂ������m�n���K���l�Ƃ��āA���s�i2010�N�j�̕č��̂m�n���K���i�� 0.27 g/kWh�j���������Ɋɂ��m�n����
0.4 g/kWh�̋K���l�i2016�N���{�j�����\���Ă����Ƃ���A�������g���b�N���[�J���w�E�����@�ւ̑����̐��Ƃ���
�G�l���M�[�������C�����P�̎Љ�I�j�[�Y���ŗD��Ŏ������ׂ��Ƃ̋Z�p�҂Ƃ��čŒ���̃������i�E�����s
��̓����S��ǐS�j�������Ă��܂��Ă���Ɖ]����̂ł͂Ȃ����낤���B���̂悤�Ȃ��Ƃ����݂̐��E�ōs���Ă����
����A�����̂ɒ�N�ސE�����Z�p���̕M�҂ɂ͂ƂĂ��M�����Ȃ��̂ł���B����Ƃ��A���̂悤�ɕM�҂������Ă�
�܂��̂́A���X�̕M�҂̍l��������ʓI�ȏ펯����傫���������Ă��邽�߂ł��낤���B
�@�܂��A��^�g���b�N�̔R��ɂ��ẮA2006�N4���P����2015�N�x�d�ʎԔR�����{�s����Ċ���5�N���x�̍Ό�
���o�߂��Ă��邱�Ƃ���A���̔R��K�����������ׂ��������������Ă��邽�߂��A�T�����x�̔R������v������d
�ʎԔR���̋������s����\��������B����ɂ��ẮA�ŋ߁A���L�̗��R�ɂ���Đ��E�̐Ζ����v���N��
����X�������Ă���A�߂������A�y�����i�̍������\�z����Ă��邱�Ƃ��傫�ȗv���ƍl������B
�@�E�@���݂̓I�C���s�[�N�̎�����}���Ă���A���E�̌������Y�ʂ́A����A�Q���̌X��
�E�@�G�W�v�g�̖��剻�����ɒ[���������e���̐����s���ɂ��A�����ł̌������Y�ʂ͌����̋���
�@�E�@�����A�C���h���̐V�����́A�o�ϔ��W�⎩���Ԕ̔��̌����ɂ��Ζ�����ʂ̑���ŁA�����̕N��
�@�E�@�����{��k�Ђł̔ߎS�ȕ����������̂ɂ���Ĕ������̐��_�̍��܂肩��Η͔��d���������A���E�e���ł̐�
�����v�̑���
�����v�̑���
�@�ȏ�̂悤�Ȍ������Y�̌����ƐΖ�����̑���ɉ����A�ߔN�ł̕č�FRB�̃h���̑�ʔ��s�ɔ����h�����l�̉�
���ɂ��A�߂������A�������i�͂Q�O�O�h���^�o�����܂ŏ㏸����Ɖ]���Ă���B���̂悤�ȏꍇ�ɂ́A����A�䂪��
�������̉~���ɂȂ����Ƃ��Ă��y���̎s�̉��i�͌��s�̂Q�{�߂��̂Q�O�O�~�^���b�g������܂ō������Ă��܂��\
�����ے�ł��Ȃ��B���̂悤�Ȏ���ɂ́A�g���b�N���[�U�̔R�����̗v���E�j�[�Y�����܂邱�Ƃ͕K�����B�Ƃ��낪�A
�ŋ߂̓��{�@�B�w��⎩���ԋZ�p��̍u����ł́A�f�B�[�[���G���W���ł̏\���ȔR����P�����҂ł���Ƃ��đ���
�̊w�ҁE���Ƃ����ڂ���悤�ȐV�Z�p����������Ȃ��̂�����̂悤���B
���ɂ��A�߂������A�������i�͂Q�O�O�h���^�o�����܂ŏ㏸����Ɖ]���Ă���B���̂悤�ȏꍇ�ɂ́A����A�䂪��
�������̉~���ɂȂ����Ƃ��Ă��y���̎s�̉��i�͌��s�̂Q�{�߂��̂Q�O�O�~�^���b�g������܂ō������Ă��܂��\
�����ے�ł��Ȃ��B���̂悤�Ȏ���ɂ́A�g���b�N���[�U�̔R�����̗v���E�j�[�Y�����܂邱�Ƃ͕K�����B�Ƃ��낪�A
�ŋ߂̓��{�@�B�w��⎩���ԋZ�p��̍u����ł́A�f�B�[�[���G���W���ł̏\���ȔR����P�����҂ł���Ƃ��đ���
�̊w�ҁE���Ƃ����ڂ���悤�ȐV�Z�p����������Ȃ��̂�����̂悤���B
�@�����āA���ŋ߂܂ł́A�G���W���W�̊w�ҁE���Ƃ́AHCCI�R�āi��PCI�R�āj���f�B�[�[���G���W���́uNO���ƔR
��̃g���[�h�I�t�̌o�������V�Z�p�v�ł���A���̋Z�p���f�B�[�[���G���W���́uNO���팸�v�Ɓu�R�����v��������
�鋆�ɂ̃f�B�[�[���R�ċZ�p�Ƃ��ē��{�@�B�w��⎩���ԋZ�p��̍u����ł͑傢�Ɏ��Ě�����A���̋Z�p�Ɋ�
���鑽���̘_�������\����Ă����B�����āA��y�̌����̃f�B�[�[���G���W���Z�p�҂���́AHCCI�R�āi��PCI�R�āj
�̏o���ɂ��f�B�[�[���R�Ă̐��E������I�ɐi�����A�����̂ɑސE�����M�҂̎����Ă���悤�ȌÂ����ȃf�B�[
�[���R�Ă̋Z�p���S���ʗp���Ȃ�����ɂȂ����Ɛ錾����Ă��܂����̂ł���B
��̃g���[�h�I�t�̌o�������V�Z�p�v�ł���A���̋Z�p���f�B�[�[���G���W���́uNO���팸�v�Ɓu�R�����v��������
�鋆�ɂ̃f�B�[�[���R�ċZ�p�Ƃ��ē��{�@�B�w��⎩���ԋZ�p��̍u����ł͑傢�Ɏ��Ě�����A���̋Z�p�Ɋ�
���鑽���̘_�������\����Ă����B�����āA��y�̌����̃f�B�[�[���G���W���Z�p�҂���́AHCCI�R�āi��PCI�R�āj
�̏o���ɂ��f�B�[�[���R�Ă̐��E������I�ɐi�����A�����̂ɑސE�����M�҂̎����Ă���悤�ȌÂ����ȃf�B�[
�[���R�Ă̋Z�p���S���ʗp���Ȃ�����ɂȂ����Ɛ錾����Ă��܂����̂ł���B
�@�������A���̌�̌������i�ނɂ�āA�f�B�[�[����HCCI�R�āi��PCI�R�āj�̋Z�p�́A�R�Ă̕s�����肪����
�ł��Ȃ���ɁA�f�B�[�[���G���W���́uNO���팸�v�Ɓu�R�����v�̌��ʂ��ɂ߂ċ͂��ł��邱�Ƃ����炩�ƂȂ������߁A
���݂ł͂��̋Z�p�𒍖ڂ���w�ҁE���Ƃ̐����}���ɏ��Ȃ��Ȃ����悤�ł���B���̗l�q�����Ă���ƁA����܂ł�
�f�B�[�[����HCCI�R�āi��PCI�R�āj�̋Z�p�̃h���`���������́A��́A���������̂ł��낤���B�����āA�f�B�[�[����
HCCI�R�āi��PCI�R�āj�ɗL���V�ɂȂ��Ă����w�ҁE���Ƃ́A���݁A����̔n���������������͒p���Ă���̂ł��낤
���B
�ł��Ȃ���ɁA�f�B�[�[���G���W���́uNO���팸�v�Ɓu�R�����v�̌��ʂ��ɂ߂ċ͂��ł��邱�Ƃ����炩�ƂȂ������߁A
���݂ł͂��̋Z�p�𒍖ڂ���w�ҁE���Ƃ̐����}���ɏ��Ȃ��Ȃ����悤�ł���B���̗l�q�����Ă���ƁA����܂ł�
�f�B�[�[����HCCI�R�āi��PCI�R�āj�̋Z�p�̃h���`���������́A��́A���������̂ł��낤���B�����āA�f�B�[�[����
HCCI�R�āi��PCI�R�āj�ɗL���V�ɂȂ��Ă����w�ҁE���Ƃ́A���݁A����̔n���������������͒p���Ă���̂ł��낤
���B
�@���������A�f�B�[�[���G���W�������܂�Ă��̕��A�u�f�B�[�[�����v�́A�����̐l�B������A�S�N�ȏ�ɋy�ԉ��nj�
���𑱂��Ă����ۑ�ł���B�����āA�R�Ď����ɂ����đ��_�̒����m���ɋN�������Ƃ��K�{�ƂȂ�HCCI�R�āi��PCI
�R�āj�̎���������Ȃ��Ƃ́A�f�B�[�[���G���W���̗��j������Ηe�Ղɔ��f�ł��邱�Ƃ��B���̂悤�Ȃ��Ƃɒm�\��
�����Ȃ��̂́A�ŋ߂̑����̊w�ҁE���Ƃ́A�葁���u���v�𐬂����Ƃ����̏ł肪�����A�����̐^���E�{���𗝉����悤
�Ƃ���ړI�ӎ��Ɍ����Ă��邽�߂ł͂Ȃ����낤���B�S���n���������Ƃł���B
���𑱂��Ă����ۑ�ł���B�����āA�R�Ď����ɂ����đ��_�̒����m���ɋN�������Ƃ��K�{�ƂȂ�HCCI�R�āi��PCI
�R�āj�̎���������Ȃ��Ƃ́A�f�B�[�[���G���W���̗��j������Ηe�Ղɔ��f�ł��邱�Ƃ��B���̂悤�Ȃ��Ƃɒm�\��
�����Ȃ��̂́A�ŋ߂̑����̊w�ҁE���Ƃ́A�葁���u���v�𐬂����Ƃ����̏ł肪�����A�����̐^���E�{���𗝉����悤
�Ƃ���ړI�ӎ��Ɍ����Ă��邽�߂ł͂Ȃ����낤���B�S���n���������Ƃł���B
�@����HCCI�R�āi��PCI�R�āj�ɂ��f�B�[�[���G���W���́uNO���팸�v�Ɓu�R�����v�������ł��邱�Ƃ����炩�ƂȂ���
���݂ł́A��^�g���b�N�́uNO���팸�v�Ɓu�R�����v��}�邱�Ƃɍs���l�܂�̏Ɋׂ��Ă�����̂ƍl������B��
�̌��ʁA�č������ɂ���^�g���b�N��NO���K�����{�s����������{���{�̑Ӗ��ɏڏq���Ă���悤�ɁA���{�ł́u��
�������ɂ����{�̑�^�g���b�N��NO���K���l�v�̔r�o�K�X�K�����{�s��������j�ڂɊׂ��Ă���ƍl������B����
�āA���{��2015�N�x�d�ʎԔR��������������^�g���b�N�̐V������R��̊��ݒ�ł��Ȃ��ɂȂ��Ă���
�ƍl������B�����āA���{�́A������u���Ή��̏o�O�I�v�̌��̂悤�ɁA�u�č������ɂ����{�̑�^�g���b�N��NO���K
���l�̋����v�Ɓu2015�N�x�d�ʎԔR���������v���u�K���ŏ������I�v�Ƃ̍�����n���ɂ������\���J��Ԃ�����
�ŁA�������^�g���b�N��NO���ƔR��̋K���������ی��Ȃ��摗�肷�鍰�_�ł��낤���B���ɁA���ꂪ�����ł���A��
�{�i�����ȁE���y��ʏȁj�́A������̂�ɂ��閳�\�Ȑl�Ԃ̏W�܂�ƌ����Ă��d�����Ȃ��̂ł͂Ȃ����낤���B
���݂ł́A��^�g���b�N�́uNO���팸�v�Ɓu�R�����v��}�邱�Ƃɍs���l�܂�̏Ɋׂ��Ă�����̂ƍl������B��
�̌��ʁA�č������ɂ���^�g���b�N��NO���K�����{�s����������{���{�̑Ӗ��ɏڏq���Ă���悤�ɁA���{�ł́u��
�������ɂ����{�̑�^�g���b�N��NO���K���l�v�̔r�o�K�X�K�����{�s��������j�ڂɊׂ��Ă���ƍl������B����
�āA���{��2015�N�x�d�ʎԔR��������������^�g���b�N�̐V������R��̊��ݒ�ł��Ȃ��ɂȂ��Ă���
�ƍl������B�����āA���{�́A������u���Ή��̏o�O�I�v�̌��̂悤�ɁA�u�č������ɂ����{�̑�^�g���b�N��NO���K
���l�̋����v�Ɓu2015�N�x�d�ʎԔR���������v���u�K���ŏ������I�v�Ƃ̍�����n���ɂ������\���J��Ԃ�����
�ŁA�������^�g���b�N��NO���ƔR��̋K���������ی��Ȃ��摗�肷�鍰�_�ł��낤���B���ɁA���ꂪ�����ł���A��
�{�i�����ȁE���y��ʏȁj�́A������̂�ɂ��閳�\�Ȑl�Ԃ̏W�܂�ƌ����Ă��d�����Ȃ��̂ł͂Ȃ����낤���B
�@���̂悤�ɁA���{�̃g���b�N���[�J�E��w�E�����@�ւ̃f�B�[�[���G���W���ɊW����w�ҁE���Ƃ́A�f�B�[�[���G��
�W���́u�R����P�v�ƁuNO���팸�v�𐄐i�ł���V�����Z�p�����������o���Ă��Ȃ��̂������ȂƂ���ł͂Ȃ����낤���B
���̂��߂��A���{���{�́A��^�g���b�N�́u2015�N�x�d�ʎԔR�������������V���Ȓ�R��̊�v���ݒ�ł���
����ɁA�č��̂m�n���K�������ɂ���^�g���b�N��NO���K�������{���{�s������Ȃ��̂�����̂悤�ł����B����
�悤�Ȃ��Ƃ́A���{�ɂ�����u��C���̉��P�v�A�u��^�g���b�N��CO2�팸�ƏȃG�l���M�[�E�Ȏ����v�̐��i�ɑ��đ�
���ȏ�Q�ƂȂ邽�߁A�킪���ɂƂ��Ă͗R�X�������ł���B���̏�A�����_�ł́A�킪���ɂ����錻�s�̑�^�g���b
�N�ł̕s�\���ȁuNO���K���v�Ɓu�R��K���v���߂������ɉ������ċ����ł���ڏ����S�������悤�Ɍ����邪�A�@���Ȃ�
�̂ł��낤���B
�W���́u�R����P�v�ƁuNO���팸�v�𐄐i�ł���V�����Z�p�����������o���Ă��Ȃ��̂������ȂƂ���ł͂Ȃ����낤���B
���̂��߂��A���{���{�́A��^�g���b�N�́u2015�N�x�d�ʎԔR�������������V���Ȓ�R��̊�v���ݒ�ł���
����ɁA�č��̂m�n���K�������ɂ���^�g���b�N��NO���K�������{���{�s������Ȃ��̂�����̂悤�ł����B����
�悤�Ȃ��Ƃ́A���{�ɂ�����u��C���̉��P�v�A�u��^�g���b�N��CO2�팸�ƏȃG�l���M�[�E�Ȏ����v�̐��i�ɑ��đ�
���ȏ�Q�ƂȂ邽�߁A�킪���ɂƂ��Ă͗R�X�������ł���B���̏�A�����_�ł́A�킪���ɂ����錻�s�̑�^�g���b
�N�ł̕s�\���ȁuNO���K���v�Ɓu�R��K���v���߂������ɉ������ċ����ł���ڏ����S�������悤�Ɍ����邪�A�@���Ȃ�
�̂ł��낤���B
�@���̂悤�ȏɊӂ݁A���݂����{�ł̑�^�g���b�N��NO���ƔR��̋K�������̕s�\���ȏ�Ŕj���A�������]
�ނ悤�ȑ�^�g���b�N�́uNO���K���v�Ɓu�R��K���v�ɋ����ł���Z�p�Ƃ��āA�M�҂́A�C���x�~�G���W���i�������J2005-
54771�j���Ă��Ă���B�����āA�C���x�~�G���W���ɂ���^�g���b�N�̒�R��ɏڏq���Ă���悤�ɁA�����C���x�~
�G���W���i�������J2005-54771�j�́A�f�B�[�[���G���W���̒��N�̉ۑ�ł�����NO���팸���ɂ͔R������������A�R��
�̉��P���ɂ�NO��������������u�R���NO���Ƃ̃g���[�h�I�t�v�������ł��邱�Ƃ������ł���B
�ނ悤�ȑ�^�g���b�N�́uNO���K���v�Ɓu�R��K���v�ɋ����ł���Z�p�Ƃ��āA�M�҂́A�C���x�~�G���W���i�������J2005-
54771�j���Ă��Ă���B�����āA�C���x�~�G���W���ɂ���^�g���b�N�̒�R��ɏڏq���Ă���悤�ɁA�����C���x�~
�G���W���i�������J2005-54771�j�́A�f�B�[�[���G���W���̒��N�̉ۑ�ł�����NO���팸���ɂ͔R������������A�R��
�̉��P���ɂ�NO��������������u�R���NO���Ƃ̃g���[�h�I�t�v�������ł��邱�Ƃ������ł���B
�@���������āA�����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�́A���N�A�f�B�[�[���G���W���̊w�ҁE���Ƃ�����܂�
�K���ɒT�����߂Ă����u�f�B�[�[���G���W���̔R���NO���Ƃ̓����̍팸�������ł���v�V�I�ȋZ�p�v�Ɖ]����̂ł�
�Ȃ����낤���B�Ƃ��낪�A�c�O�����ƂɁA�����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p�́A���݂̂Ƃ���A���{
�̐��{�i�����ȁE���y��ʏȁj��f�B�[�[���G���W���̊w�ҁE���Ɠ�����́A���̂����S�ɖ����E�َE����Ă���
�̂ł���B���̈���ŁA���{�̐��{���^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W���̌����J���ɊW���Ă���l�B�́A���{�@�B
�w��E���{�����ԋZ�p��̍u����E�Z�p���Ȃǂɂ����đ����̘_���E�R�����g��ɔ��\�E���\�����Ă���B������
�Ȃ���A�����̘_���E�R�����g�̒��g���������A��������{�̑�^�g���b�N�́uNOx�팸�v�Ɓu�R����P�v�������ł���
���ȋZ�p�̔��\�E���\�́A�c�O�Ȃ���F���̂悤���B����ɂ�������炸�A���{�̐��{���^�g���b�N�p�f�B�[�[���G
���W���̌����J���ɊW���Ă���l�B�́A���݂̑�^�g���b�N�̍ł��d�v�Ȃł���uNOx�팸�v�Ɓu�R����P�v�̉ۑ��
�e�Ղɉ����ł����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�����S�ɖ����E�َE���Ă���̂́A�@���Ȃ闝�R������
�̂ł��낤���B
�K���ɒT�����߂Ă����u�f�B�[�[���G���W���̔R���NO���Ƃ̓����̍팸�������ł���v�V�I�ȋZ�p�v�Ɖ]����̂ł�
�Ȃ����낤���B�Ƃ��낪�A�c�O�����ƂɁA�����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p�́A���݂̂Ƃ���A���{
�̐��{�i�����ȁE���y��ʏȁj��f�B�[�[���G���W���̊w�ҁE���Ɠ�����́A���̂����S�ɖ����E�َE����Ă���
�̂ł���B���̈���ŁA���{�̐��{���^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W���̌����J���ɊW���Ă���l�B�́A���{�@�B
�w��E���{�����ԋZ�p��̍u����E�Z�p���Ȃǂɂ����đ����̘_���E�R�����g��ɔ��\�E���\�����Ă���B������
�Ȃ���A�����̘_���E�R�����g�̒��g���������A��������{�̑�^�g���b�N�́uNOx�팸�v�Ɓu�R����P�v�������ł���
���ȋZ�p�̔��\�E���\�́A�c�O�Ȃ���F���̂悤���B����ɂ�������炸�A���{�̐��{���^�g���b�N�p�f�B�[�[���G
���W���̌����J���ɊW���Ă���l�B�́A���݂̑�^�g���b�N�̍ł��d�v�Ȃł���uNOx�팸�v�Ɓu�R����P�v�̉ۑ��
�e�Ղɉ����ł����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�����S�ɖ����E�َE���Ă���̂́A�@���Ȃ闝�R������
�̂ł��낤���B
�@
���̂悤�ɁA�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p���E�َE���Ă�����{�@�B�w��E���{�����ԋZ�p��
���̍u����\�̘_��������[�J����̃q�A�����O���s���ĕs�\���ȋZ�p������W�߁A���̏�����ɓ��{
�̐��{�i�����ȁE���y��ʏȁj���A���{�́uNOx�ƔR��̋K�������v�̉ہE�v�ۂf���Ă��錻��ł́A�X�Ȃ��
�{�́uNOx�ƔR��̋K������������v�ƌ��_�ƂȂ��Ă��܂��̂́A���R�̂��Ƃł͂Ȃ����낤���B���̂��߁A���{�ł́A
��^�g���b�N��2015�N�x�d�ʎԔR���̋�����摗��Ƃ��A����ł��č������ɂ����{�̑�^�g���b�N��NO���K��
���{�s����������Ȃ���Ɋׂ��Ă����Ȍ����̈�ƍl������B
���̍u����\�̘_��������[�J����̃q�A�����O���s���ĕs�\���ȋZ�p������W�߁A���̏�����ɓ��{
�̐��{�i�����ȁE���y��ʏȁj���A���{�́uNOx�ƔR��̋K�������v�̉ہE�v�ۂf���Ă��錻��ł́A�X�Ȃ��
�{�́uNOx�ƔR��̋K������������v�ƌ��_�ƂȂ��Ă��܂��̂́A���R�̂��Ƃł͂Ȃ����낤���B���̂��߁A���{�ł́A
��^�g���b�N��2015�N�x�d�ʎԔR���̋�����摗��Ƃ��A����ł��č������ɂ����{�̑�^�g���b�N��NO���K��
���{�s����������Ȃ���Ɋׂ��Ă����Ȍ����̈�ƍl������B
�@���̌��ʁA���{�̐��{�i�����ȁE���y��ʏȁj�́A����̑�^�g���b�N�ɂ�����NOx�ƔR��̊ɂ��K�����A���ꂩ��
���u���炾��v�Ǝ{�s�������čs���S�Z�ł��낤���B���݂ɁA���{�̐��{������̊ɂ���^�g���b�N�̋K�����������{�s
�������邱�Ƃ́A�g���b�N���[�J���傫�ȗ��v�ݑ�����v���̈�ł��邽�߂ɑ傢�Ɋ��}���Ă��邱�Ƃ͊ԈႢ��
�����낤�B�������A���{�̐��{�ɂ���^�g���b�N�̊ɂ�NOx�K���ɂ���Ė��f����̂͑����̓��{�����ł���A����
�āA���{�̐��{�ɂ���^�g���b�N�̊ɂ��R��K���ɂ���Ė��f����̂͑����̓��{�̃g���b�N���[�U�ł��邱�Ƃ�
�ԈႢ�Ȃ����낤�B���̂悤�ȁA��Ɓi���g���b�N���[�J)�ɂ͗D�����A�����ɂ͌������{������s���Ă��錻�݂̓��{��
���{�̍s�����Ԃ𑽂��̍������m�邱�ƂɂȂ�A�����̐��{�ᔻ�����܂邱�Ƃ͕K�R�ƍl������B���̂悤�Ȕᔻ
�𐭕{�����O�ɉ������őP�̍�́A���{�͑�^�g���b�N�̐V���Ȓ�R��E��r�o�K�X��𑁊��ɐݒ肹��I��
�ڏq���Ă���悤�ɁA��^�g���b�N��ΏۂƂ����V���ȁu��NO���E��R��̊�v�𑁊��ɓ������邱�Ƃł͂Ȃ����낤
���B
���u���炾��v�Ǝ{�s�������čs���S�Z�ł��낤���B���݂ɁA���{�̐��{������̊ɂ���^�g���b�N�̋K�����������{�s
�������邱�Ƃ́A�g���b�N���[�J���傫�ȗ��v�ݑ�����v���̈�ł��邽�߂ɑ傢�Ɋ��}���Ă��邱�Ƃ͊ԈႢ��
�����낤�B�������A���{�̐��{�ɂ���^�g���b�N�̊ɂ�NOx�K���ɂ���Ė��f����̂͑����̓��{�����ł���A����
�āA���{�̐��{�ɂ���^�g���b�N�̊ɂ��R��K���ɂ���Ė��f����̂͑����̓��{�̃g���b�N���[�U�ł��邱�Ƃ�
�ԈႢ�Ȃ����낤�B���̂悤�ȁA��Ɓi���g���b�N���[�J)�ɂ͗D�����A�����ɂ͌������{������s���Ă��錻�݂̓��{��
���{�̍s�����Ԃ𑽂��̍������m�邱�ƂɂȂ�A�����̐��{�ᔻ�����܂邱�Ƃ͕K�R�ƍl������B���̂悤�Ȕᔻ
�𐭕{�����O�ɉ������őP�̍�́A���{�͑�^�g���b�N�̐V���Ȓ�R��E��r�o�K�X��𑁊��ɐݒ肹��I��
�ڏq���Ă���悤�ɁA��^�g���b�N��ΏۂƂ����V���ȁu��NO���E��R��̊�v�𑁊��ɓ������邱�Ƃł͂Ȃ����낤
���B
�P�O�D��ʌ��ɂ����ăf�B�[�[���������^�]���̔r�C�K�X���x�̍������Ɏ��s�����Z�p
�P�O�|�P�D�������^�]�̔r�C�K�X���x������������Ə̂���C���`�L�ȁu�M����R���o�[�^�v�̋Z�p
�̕������^�]�̕p�x���ɂ߂č����̂�����ł���B���̂��߁A�A�fSCR�G�}����NOx�ጸ�̌㏈�����u�ɂ���
�āA�����NO���K���̋����ɓK�����邽�߂̍���NO���팸�����������Ă������߂ɂ́A�r�C�K�X���x����背�x����
��̍����Ɉێ�����K�v������B�܂��A���݂�DPF���u�́A�G���W���������^�]�ł͎��ȍĐ�������ƂȂ邽�߁A
�|�X�g���˂�r�C�Ǔ��R�����˂ɂ��DPF���u�̋����Đ�����V�X�e�����̗p����Ă���B�����āA������g���b�N��
�����s�ł́A�G���W�����������^�]���ɂ߂đ������߁A����ł�DPF���u�̋����Đ����p�ɂɍ쓮����ꍇ����
���悤���B���̂��߁ADPF�̋����Đ��ɂ��R�����ADPF���u�̌̏ᑽ�����̃g���b�N���[�U�̕s�����T�ς���
����悤���B����DPF���u�̖��ɂ��ẮA�C���x�~��DPF�̎��ȍĐ��𑣐i (�����Đ��̍팸�ŔR�����h
�~�j�ɂ��ڏq���Ă���悤�ɁA���{�g���b�N������y��ʏȂ�DPF���u�̕s����̑��}�ȉ����E������\������
�Ă���悤�ł���B
�@�ȏ�̂悤�ȁADPF���u�̖������������NO���K�������ւ̓K����i�Ƃ��ẮA�g���b�N���[�J�̋Z�p�ҁE����
�́A�O�q�̕\�P�P�Ɏ������悤���A�G���W���̕������^�]���ɂ����Ĕr�C�K�X���x�̍�������}��Z�p���J���E����
���邱�Ƃ��K�v�Ƃ̔F���ň�v���Ă���悤���B���́u�G���W���������^�]���ɂ�����r�C�K�X���x�̍������v����
�^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W���̍ŏd�v�ۑ�ł���Ƃ��g���b�N���[�J�̋Z�p�ҁE���Ƃ̈ӌ��ɂ́A�M�҂����S�ɓ�
�ӂ���Ƃ��낾�B
�@�Ƃ��낪�A�����u�G���W���������^�]���̔r�C�K�X���x�̍������v����^�g���b�N�̍ŏd�v�ۑ�Ƃ���ӌ��E�咣��
�f�ڂ��ꂽ�\�P�P���L���́A�����ԋZ�p����2010�N8�����ł���B���̂��Ƃ���A�g���b�N���[�J�̋Z�p�ҁE���Ƃ���
�ޓ��{�̃f�B�[�[���G���W���W�̊w�ҁE���Ƃ́A�������u�G���W���������^�]���̔r�C�K�X���x�̍������v��
�Z�p�J���Ɏ��g��ł���ƍl������B�������A�����ԋZ�p����2010�N8���̋L���f�ڂ���R�N���x���o�߂���2013
�N6�����݂ł��A��^�g���b�N��NO���팸��DPF���u�̕s��̑��}�ȉ����̂��߂ɍł��d�v�ۑ�ł���u�G���W����
�����^�]���̔r�C�K�X���x�̍������v�ɗL���ȋZ�p���J�����ꂽ�Ƃ̘b�́A�s�v�c�Ȃ��ƂɁA���܂蕷�����ė���
�������B
�@���������̒��ŁA�u�G���W���������^�]���̔r�C�K�X���x�̍������v��ړI�Ƃ����Z�p�J���Ɩ��L�����Z�p��
���āA�ŋ߁A�M�҂��h�����Ėڂɂ����̂́A2013�N6�����݂̎Y�����̃z�[���y�[�W�̒��Łi�Ɓj�Y�ƋZ�p��������
���E�V�R�������ԋZ�p�����Z���^�[�i�Z���^�[���@�㓡 �V��@���j���S���ڂ̏d�_�����ۑ�̈�Ƃ��ċ����Ă���
�u�M����R���o�[�^�Z�p�v�Ə̂��錤���e�[�}�ł���B���̐V�R�������ԋZ�p�����Z���^�[���̌㓡 �V��@�����d�_
�����ۑ�Ƃ��Ď��g��ł���u�M����R���o�[�^�Z�p�v�́u�����̖ړI�A�v��̊T�v�v���A�ȉ����\�Q�S�Ɏ���
| �u�f�B�[�[���G���W���̕������^�]���ł̔r�C�K�X���x�̍�������_�����v�u�M����R���o�[�^�Z�p�v�̊T�v |
| �@�i�Ɓj�Y�ƋZ�p�����������E�V�R�������ԋZ�p�����Z���^�[�̏ȃG�l���M�[�V�X�e���`�[���ɂ����ẮA�R���
��ɔ����r�o�K�X���x�ቺ�ɂ��r�o�K�X�p�G�}�R���o�[�^�̐��\�ቺ�̖��ɑ��āA�M����^�R���o�[ �^�Ƃ���v�V�I�ȋZ�p�̊J���ɂ�鍎����ڎw���Ă��܂��i���}�Q�� �j�B���̋Z�p�́A�G�}�R���o�[�^�ɔM�� ���̋@�\���t�����邱�Ƃɂ��A�ቷ�r�o�K�X�����ł��G�}�w���x���㏸�����č��������������������悤�Ƃ��� ���̂ł��B���̐V�����R���o�[�^���J���ł���A 150 ���ȉ��̒ቷ�r�o�K�X�ł��Y�����f�ނ� NOx �������ł� ��悤�ɂȂ�Ɗ��҂���A����ɏ��������グ�邱�Ƃ��ł���A�t�B���^�[�����ŕߏW�������q���i PM �j���� ���ȉ��M�G�l���M�[�ŏċp���邱�Ƃ��\�ɂȂ�ƍl���Ă��܂��B 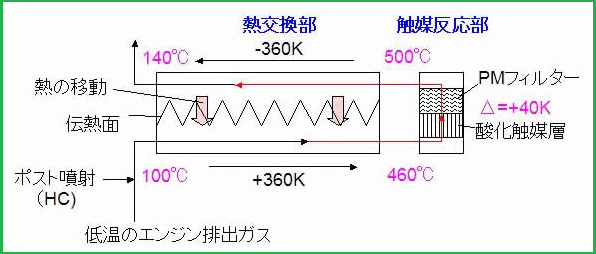 |
�ƁA�V�R�������ԋZ�p�����Z���^�[�̒��̌㓡 �V�� ���́A�d�_�����ۑ�̂S���ڒ��̂P���ڂ���L�̕\�Q�P�Ɏ���
���f�B�[�[���G���W���̕������^�]���̒ቷ�r�o�K�X�̏����ł��r�C�K�X���x�̍�������}�邽�߂́u�M����R
���o�[�^�Z�p�v�̌����Ɏ��g�܂�Ă���Ƃ̂��Ƃł���B���́u�M����R���o�[�^�v�̍쓮�v���Z�X�͈ȉ��̂悤�ł�
��B
�� �u�M����R���o�[�^�v�ɂ������r�o�K�X�̒ቷ��Ԃł́u�m�n���팸�v�Ɓu�c�o�e���u�̎��ȍĐ��̑��i�v�̃v���Z�X
�@�@ �G���W������r�o�����100���̔r�C�K�X���u�M����R���o�[�^�v��460���܂ʼn��M�����B
�@�A 460���܂ʼn��M���ꂽ�r�C�K�X�͎_���G�}�w�ɗ����������_�Łu�_���G�}�w�ł̃|�X�g���˔R���̔R�ĉ��M�v
�@�@�@�܂��́u�o�l�t�B���^�[�i���c�o�e���u�j�ł̂o�l�̔R���M�v�ɂ��A�r�C�K�X��500���܂ʼn��M�����B
�@�B ���́u�_���G�}�w�v�܂��́u�o�l�t�B���^�[�i���c�o�e���u�j�v��500���܂ʼn��M���ꂽ�r�C�K�X�́A�ēx�A�u�M���
�@�@�@�R���o�[�^�v�ɗ������A����500���܂ʼn��M���ꂽ�r�C�K�X���u�M����R���o�[�^�v�ɂ���āA�G���W������r�o
�@�@�@���ꂽ100���̔r�C�K�X��460���܂ʼn��M����B
�@�ȏ�̕M�҂̗������ԈႢ�łȂ���A�V�R�������ԋZ�p�����Z���^�[�̒��̌㓡 �V�� ���̏d�_�����e�[�}��
����u�M����R���o�[�^�v�́A�f�B�[�[���G���W���̕������ׂł̉ߋ��@�̃^�[�r���o������100���r�C�K�X���u�M���
�R���o�[�^�v�ɗ��������A�����āA�|�X�g���˔R�����_���G�}�Ŏ_�������Ĕr�C�K�X���x��40����������140���r�C
�K�X���u�M����R���o�[�^�v�ɗ��o������Ƃ̂��Ƃł���A���̊Ԃɔz�u����500�����ێ��ł���Ƃ̂��Ƃł���B�����āA
�o�l�t�B���^�[�i���c�o�e���u�j��A�f�r�b�q�G�}���̂m�n���팸�G�}��500���Ɉێ��������Ƃɂ��A�ߋ��@�̃^�[�r���o
������r�C�K�X��100���̃G���W���������ׂ̉^�]��Ԃɂ����Ă��A�o�l�t�B���^�[�i���c�o�e���u�j�̎��ȍĐ��̑��i
��A�f�r�b�q�G�}���̂m�n���팸�G�}�̊������ɂ��啝�Ȃm�n���팸�������ł���Ƃ̂��Ƃł���B���ɁA���ꂪ����
�ł���A�V�R�������ԋZ�p�����Z���^�[�̒��̌㓡 �V�� ���̏d�_�����e�[�}�ł���u�M����R���o�[�^�v�́A����
���̂悤�ȋZ�p�ł���B�����āA���́u�M����R���o�[�^�v�́A�M�҂ɂ́u�i�v�@�ցv���畉���́u�Z�p�H�v�̂悤�Ɏv����
�̂ł���B
�@������A�㓡 �V�� ���̏d�_�����e�[�}�́u�M����R���o�[�^�v�́A�u�M�������ƐG�}�������v�Ɂu100���̔r
�C�K�X�Ɣr�C�K�X���x��40�����㏸������M�ʕ��̃|�X�g���˔R���v���������A�u�M�������ƐG�}�������v����
�u140���̔r�C�K�X�v�����o����v���Z�X�ɂ����āA�u�M�������ƐG�}�������v�̌n�̒��ł͎����I�ɔr�C�K�X
���x��500���܂ŏ㏸���A�o�l�t�B���^�[�i���c�o�e���u�j�̎��ȍĐ��̑��i��A�f�r�b�q�G�}���̂m�n���팸�G
�}�̊������ɂ��啝�Ȃm�n���팸�������ł���Ƃ̂��Ƃł���B�܂�A�u�M�������ƐG�}�������v�Ɂu��������G
�l���M�[�v�Ɓu���o����G�l���M�[�v������ł���A�������u��������G�l���M�[��100���̔r�C�K�X�Ɣr�C�K�X���x��
40�����㏸������M�ʕ��̃|�X�g���˔R���v�ł���ɂ�������炸�A�s�v�c�Ȃ��ƂɁu�M�������ƐG�}�������v�̓���
�̐G�}�������ł́u�r�C�K�X���x��500���܂ŏ㏸�v����悤���B�r�C�K�X���x��140�������̃G�l���M�[�̔r�C�K�X
���u�M�������ƐG�}�������v�ɗ����Ɨ��o���Ă����ԂŁA�u�M�������ƐG�}�������v�̒��̔r�C�K�X��500���܂ŏ�
�����郁�J�j�Y�����M�҂ɂ͑S���s���ł���B�����āA�u�M�������ƐG�}�������v�̒��̔r�C�K�X��400����600���ł�
�����A500���ł��邱�Ƃ̗��R���A�M�҂ɂ͐������ł��Ȃ����Ƃ��B���������āA�㓡 �V�� ���́u�M����R���o�[�^�v��
�́A�u�M�������ƐG�}�������v�̒��Ɋj�������u�Ŕ��M�����ė�p�����鑕�u���d���܂�Ă���悤�Ȉ�ۂ���
�̂ł���B
�@�����āA���̌㓡 �V�� ���́u�M����R���o�[�^�v�́A�u�M�������ƐG�}�������v�Ɂu100���̔r�C�K�X�Ɣr�C�K�X���x
��40�������㏸�ł���M�ʕ��̃|�X�g���˔R���v���������A�u�M�������ƐG�}�������v����u140���̔r�C�K�X�v�����o
����v���Z�X�ɂ����āA�u�M�������ƐG�}�������v�̌n�̒��ł͎����I�ɔr�C�K�X���x���A�o�l�t�B���^�[�i���c�o�e��
�u�j�̎��ȍĐ��̑��i��A�f�r�b�q�G�}���̂m�n���팸�G�}�̊������ɂ��啝�Ȃm�n���팸�������ł���Ƃ̂��Ƃ�
����B���������āA���ꂪ�����Ȃ�A�㓡 �V�� ���̏d�_�����e�[�}�́u�M����R���o�[�^�v�́A�u�m�n���팸�v�Ɓu�c�o�e
�̎��ȍĐ����i�v���\�ȋ��فE�����́u���@�̋Z�p�v�ƌ����Ă��ߌ��ł͂Ȃ����낤���B�������A����́A�㓡 �V��
���̏d�_�����e�[�}�́u�M����R���o�[�^�v�������ł����ꍇ�ł���A���ꂪ�����ł��Ȃ������ꍇ�́A���{�\�Z���l
�����邽�߂̒P�Ȃ�u�y�e���E�n�b�^���E�C�J�T�}�E�C���`�L�v�Ƃ��Č������w�e�����ׂ������ƍl������B
�@����ɂ��ė����Ȋ��z�����킹�ĖႦ�A�A�|���R�c���Z�p���̕M�҂ɂ́A���̌㓡 �V�� ���́u�M����R���o�[
�^�v�͂̍쓮�𐳊m�ɗ������邱�Ƃ�����V�X�e���ł���B���������Ă��A�M�҂ɂ��ɂ�����قǂ����邽�߁A�M�҂�
�R�����o���E�m���������Đ������āA�㓡 �V�� �����������́u�M����R���o�[�^�v�̏����ɂ�������p���̉�
�ɂ��Đ����������ʁA�㓡 �V�� ���́u�M����R���o�[�^�Z�p�v�ɂ��ẮA�ȉ��Ɏ������悤�ȋ^�₪�����痣��
�Ȃ��̂ł���B���̂��߁A�M�҂ɂ��㓡 �V�� ���́u�M����R���o�[�^�Z�p�v���u�y�e���E�n�b�^���E�C�J�T�}�E�C���`�L��
�Z�p�i���H�w�I�ȍ������̖����Z�p�j�v�̂悤�ɂ����v���Ȃ��̂ł���B
�@�@ �r�C�K�X��M������̉��M���ɗ��������ăG���W������r�o�����100���̔r�C�K�X��460���܂ʼn��M�ł���
�@�@�@�\�͂����ԍډ\�ȃT�C�Y�Ǝ��p�\�ȉ��i���u�M����R���o�[�^�v���{���Ɏ����ł���̂ł��낤���B
�@�A �o�l�t�B���^�[�i���c�o�e���u�j�Ɂv�o�l���͐ς��Ă��Ȃ��ꍇ�A�u�o�l�t�B���^�[�i���c�o�e���u�j�ł̂o�l�̔R��
�@�@�@���M�v���s�\�Ȃ��߁A�u�_���G�}�w�ł̃|�X�g���˔R���̔R�ĉ��M�v���p�����邱�ƂɂȂ�ƍl�����邪�A
�@�@�@���̉^�]��Ԃł͏�Ƀ|�X�g���˂ɂ��R���̘Q���邱�ƂɂȂ�A��^�g���b�N�ɂ������R��E��b�n�Q��
�@�@�@�Љ�I�v���ɔ����邱�ƂɂȂ�̂ł͂Ȃ����낤���B
�@�����Ƃ��A�M�҂ɂ͔M������ɂ��Ă̒m���E�o�����F���ł��邽�߁A�㓡 �V�� ���́u�M����R���o�[�^�v�ɑ���
��L�̔ᔻ�͒P�Ȃ�M�҂̒��������̊��z�ɂȂ�B�������A�@���Ȃ�v�V�I�ȋZ�p�̔M����^�R���o�[�^�Ƃ͉]���A
���������ɂ�����^�[�{�ߋ��@�̃^�[�r������ቷ�̔r�o�K�X���r�o����Ă���f�B�[�[���G���W���̉^�]��Ԃ�
�����āA�G�}�w���x���㏸�����č��������������������A�t�B���^�[�����ŕߏW�������q���i PM �j�������ȉ��M
�G�l���M�[�ŏċp�ł�����x�̉��x�܂łɁA�u�G�}�w���x�v��u���q���i PM �j��͐ς�ߏW�����t�B���^�[�w�v����
�����ł��閂�@�̂悤�ȔM�����킪���ۂɎ��p���ł���Ƃ́A�ƂĂ��v���Ȃ��̂ł���B���̂Ȃ�A�M������ł́A
�M���̏��Ȃ��炸�̒�R���������Ȃ�����������A�M�������Ƃ��납��Ⴂ�Ƃ���ɂ�������Ȃ��s�t�ω��i��
�M�͊w���@��)�ɏ]�����������邽�߁A�M��������g�p���邾���Ńf�B�[�[���G���W���̕������^�]���̒ቷ�r
�o�K�X����������u�G�}�w���x�v���i�i�ɏ����ł���Ƃ��Ă��邱�Ƃ�A�uDPF�̃t�B���^�[�ɑ͐ς������q���i
PM �j��R�āv��������x�܂ō������ł���悤�ɂ́A�ǂ����Ă��M�����Ȃ����߂ł���B����́A��w�ɍ˂̃|���R�c
���Z�p���̔߂����ł��낤���B
�@�����ŁA�M������̐��Ƃɂ́A��L�̕\�P�R�Ɏ������V�R�������ԋZ�p�����Z���^�[���̌㓡 �V�� ���́u�M��
���R���o�[�^�v�ɕK�v�Ȍ��s�Z�p�Ő��삪�\���M������ɂ��Ă̎��Z���s���Ă���������K���ł���B���̎�
�Z�̑O������͈ȉ��̒ʂ�ł���B
�@�� �v�Ώہ@�F�@�f�u�v�Q�T�g���̑�^�g���b�N�i�P�R���b�g���̉ߋ��G���W�����ځj
�@�� �u�M����R���o�[�^�v���쓮����G���W���^�]�����@�F�@��]������ �P�S�O�O (������)�A�g���N�� �P�O (��)�@����
�@�� �u�M����R���o�[�^�v���쓮����G���W���̔r�C�K�X�����@�F�@���ʁ��P�R�U �i���b�g���^�b�j
�@�� �M������̔���M���̔r�C�K�X�̗����Ɨ��o���x�@�F�@�������x��100���A���o���x��460�����x
�@�� �M������̉��M���̔r�C�K�X�̗����Ɨ��o���x�@�F�@�������x��500���A���o���x��140�����x
�@
�@�M�����Z�p�ɂ��Ă̒m���E�o���̑S�������f�l�̕M�҂̗\�z�ł́A���̌㓡 �V�� �����������́u�M����R���o
�[�^�v���M������́A�Ⴆ�����ł����Ƃ��Ă��A�u��^�g���b�N�ɓ��ځE����������ȋ���ȃT�C�Y�v�Ɓu�c��Ȑ����R�X
�g�v�̑��u�ƂȂ邽�߁A�g���b�N�p�Ƃ��Ď��p�����ɂ߂č���Ȃȑ��u�ɂȂ�̂ł͂Ȃ����Ǝv���Ă���B
�@�Ƃ���ŁA�V�R�������ԋZ�p�����Z���^�[�̌����e�[�}�Љ�p���t���b�g�̃R�s�[�Ɏ������悤�ɁA��U�N���O�ɍ쐬
���ꂽ�i�Ɓj �Y�ƋZ�p�����������̐V�R�������ԋZ�p�����Z���^�[�ɂ����錤���e�[�}�Љ�̃p���t���b�g�ihttp://
unit.aist.go.jp/nfv/ci/pamphlets/aist_nfv_pamphlet0712_2.pdf,�A2007�N7���쐬�j�ɂ́A�V�R�������ԋZ�p�����Z���^
�[���̌㓡 �V�� ���́u�M����R���o�[�^�v�̌����e�[�}�����ɏЉ��Ă���悤���B�����āA�V�R�������ԋZ�p��
���Z���^�[���̌㓡 �V�� ���́A�A�f�B�[�[���G���W���̕������^�]���̒ቷ�r�o�K�X������������u�M����R��
�o�[�^�v�̌������s���Ă���A�����āA2013�N6�����݂̎Y�����̃z�[���y�[�W�̒��ł��A���ς�炸�A���́u�M����R
���o�[�^�v�̌����e�[�}���S���́u�d�_�����e�[�}�v�̒��̂P���Ƃ��ė���Ă���̂ł���B
���ꂽ�i�Ɓj �Y�ƋZ�p�����������̐V�R�������ԋZ�p�����Z���^�[�ɂ����錤���e�[�}�Љ�̃p���t���b�g�ihttp://
unit.aist.go.jp/nfv/ci/pamphlets/aist_nfv_pamphlet0712_2.pdf,�A2007�N7���쐬�j�ɂ́A�V�R�������ԋZ�p�����Z���^
�[���̌㓡 �V�� ���́u�M����R���o�[�^�v�̌����e�[�}�����ɏЉ��Ă���悤���B�����āA�V�R�������ԋZ�p��
���Z���^�[���̌㓡 �V�� ���́A�A�f�B�[�[���G���W���̕������^�]���̒ቷ�r�o�K�X������������u�M����R��
�o�[�^�v�̌������s���Ă���A�����āA2013�N6�����݂̎Y�����̃z�[���y�[�W�̒��ł��A���ς�炸�A���́u�M����R
���o�[�^�v�̌����e�[�}���S���́u�d�_�����e�[�}�v�̒��̂P���Ƃ��ė���Ă���̂ł���B
�@���̂��Ƃ���A�V�R�������ԋZ�p�����Z���^�[���̌㓡 �V�� ���́A�ߋ��U�N�Ԃ��u�M����R���o�[�^�v�̌�����
���X�Ǝ��g��ł���悤�ł���B���̗��R�𐄎@����ƁA�ȉ��̂悤�ȓ��@�E�v�����l������B
���X�Ǝ��g��ł���悤�ł���B���̗��R�𐄎@����ƁA�ȉ��̂悤�ȓ��@�E�v�����l������B
�@ �㓡 �V�� ���́A�u�M����R���o�[�^�v���f�B�[�[���G���W���̕������^�]���̒ቷ�r�o�K�X�̏����ł��A����
�ɔr�C�K�X���x���������ł���Ƃ̋����M�O�̎�����ł��邱�ƁB
�ɔr�C�K�X���x���������ł���Ƃ̋����M�O�̎�����ł��邱�ƁB
�A �㓡 �V�� ���́A�u�M����R���o�[�^�v�̑��ɂ́A�f�B�[�[���G���W���̕������^�]���̒ቷ�r�o�K�X�̏�����
���A���ۂɔr�C�K�X���x���������ł���Z�p�E�A�C�f�A�����z�ł��Ȃ��߂ɁA����܂Ŏd���Ȃ��Ƀ_���_���Ɓu�M����R
���o�[�^�v�̌������p�����Ă����ɉ߂��Ȃ����ƁB
���A���ۂɔr�C�K�X���x���������ł���Z�p�E�A�C�f�A�����z�ł��Ȃ��߂ɁA����܂Ŏd���Ȃ��Ƀ_���_���Ɓu�M����R
���o�[�^�v�̌������p�����Ă����ɉ߂��Ȃ����ƁB
�B ���{�\�Z�̎�����������l�����邽�߂ɂ́A���l�����u�R�E�y�e���E�n�b�^���E�C�J�T�}�E�C���`�L�v�Ǝv���悤�Ƃ��A
���I�ȍ����ڕW���`�U��\�킸�s���i���ł����グ�j���A�Ő�[�̊v�V�I�ȋZ�p�̌����Ƃ��ė\�Z�̐\�����ɋL
�ڂ��邱�Ƃɂ���Ď���������e�ՂɊl���ł����ɁA���N��̎����̏I�����ɂ́A�ڕW�̖��B���̗��R���ؖ�
���鎎���f�[�^��Y�t����A���̐ӔC�̒Nj����s���Ȃ����߁A���{�\�Z�̎���������́u�g�������̏����v��
�u�H�������v�̎|�݂�����ł���\�������邱�ƁB
���I�ȍ����ڕW���`�U��\�킸�s���i���ł����グ�j���A�Ő�[�̊v�V�I�ȋZ�p�̌����Ƃ��ė\�Z�̐\�����ɋL
�ڂ��邱�Ƃɂ���Ď���������e�ՂɊl���ł����ɁA���N��̎����̏I�����ɂ́A�ڕW�̖��B���̗��R���ؖ�
���鎎���f�[�^��Y�t����A���̐ӔC�̒Nj����s���Ȃ����߁A���{�\�Z�̎���������́u�g�������̏����v��
�u�H�������v�̎|�݂�����ł���\�������邱�ƁB
�@���݁A�V�R�������ԋZ�p�����Z���^�[���̌㓡 �V�� �����A�ߋ��U�N�Ԃ��u�M����R���o�[�^�v�̌����ɉ��X�Ǝ��
�g�ݑ����Ă��鐳�m�ȗ��R�́A�M�҂ɂ͕s���ł���B����ɂ��Ă��A�f�B�[�[���G���W���̕������^�]���̒ቷ�r
�o�K�X�̏����Ŕr�C�K�X���x�����������āu�m�n���팸�v�Ɓu�c�o�e���u�̎��ȍĐ��̑��i�v���\�ɂ���Z�p�Ƃ��āA��
���_�ł́A�V�R�������ԋZ�p�����Z���^�[���̌㓡 �V�� �����u�M����R���o�[�^�v�̌��������{���Ă��邱�Ƃ́A��
�R���鎖���̂悤���B
�g�ݑ����Ă��鐳�m�ȗ��R�́A�M�҂ɂ͕s���ł���B����ɂ��Ă��A�f�B�[�[���G���W���̕������^�]���̒ቷ�r
�o�K�X�̏����Ŕr�C�K�X���x�����������āu�m�n���팸�v�Ɓu�c�o�e���u�̎��ȍĐ��̑��i�v���\�ɂ���Z�p�Ƃ��āA��
���_�ł́A�V�R�������ԋZ�p�����Z���^�[���̌㓡 �V�� �����u�M����R���o�[�^�v�̌��������{���Ă��邱�Ƃ́A��
�R���鎖���̂悤���B
�@�������A�V�R�������ԋZ�p�����Z���^�[���̌㓡 �V�� ���́A�U�N���x�̍Ό����o�߂������݂ł��A�u�m�n���팸�v��
�u�c�o�e���u�̎��ȍĐ��̑��i�v�������ł���悤�ȁu�M����R���o�[�^�v�̌����́A�����ɐ������Ă��Ȃ��悤���B����
�܂Ŋ����U�N�Ԓ��x��������������ꂽ�ɂ�������炸�A���̌����ڕW�̒B���̌����݂������Ă��Ȃ��u�M����R
���o�[�^�v�̌������A�V�R�������ԋZ�p�����Z���^�[���̌㓡 �V�� ���́A���ꂩ����p�����Ď��{����\��ł��낤
���B�����āA���̌����́A���ꂩ������������A10�N��H�܂���20�N��H�܂ő�����̂ł��낤���B�����Ƃ��A�����A��
�� �V�� ���́u�M����R���o�[�^�v�̊J�����������A�����p���đ�^�g���b�N���u�m�n���팸�v�Ɓu�c�o�e���u�̎��ȍĐ�
�̑��i�v���{���Ɏ�������\���́A�M�҂ɂ́u�F���v�Ǝv�����A�@���Ȃ��̂ł��낤���B�����āA�V�R�������ԋZ�p��
���Z���^�[���̌㓡 �V�� ���́u�M����R���o�[�^�v�����́A�w�ҁE���Ƃ����{�\�Z�̎���������̊l���ɗp����
���\�I�Ȏ�@�ɋL�ڂ����u�R�E�y�e���E�n�b�^���E�C�J�T�}�E�C���`�L�v�ɗނ��錤���e�[�}�ɑ�������悤�Ɏv���邪�A
����͕M�҂���w�ɍ˂̃|���R�c���Z�p���ł��邱�ƂɋN�������傫�ȁu���Ⴂ�v�E�u�v���Ⴂ�v�ł��낤���B
�u�c�o�e���u�̎��ȍĐ��̑��i�v�������ł���悤�ȁu�M����R���o�[�^�v�̌����́A�����ɐ������Ă��Ȃ��悤���B����
�܂Ŋ����U�N�Ԓ��x��������������ꂽ�ɂ�������炸�A���̌����ڕW�̒B���̌����݂������Ă��Ȃ��u�M����R
���o�[�^�v�̌������A�V�R�������ԋZ�p�����Z���^�[���̌㓡 �V�� ���́A���ꂩ����p�����Ď��{����\��ł��낤
���B�����āA���̌����́A���ꂩ������������A10�N��H�܂���20�N��H�܂ő�����̂ł��낤���B�����Ƃ��A�����A��
�� �V�� ���́u�M����R���o�[�^�v�̊J�����������A�����p���đ�^�g���b�N���u�m�n���팸�v�Ɓu�c�o�e���u�̎��ȍĐ�
�̑��i�v���{���Ɏ�������\���́A�M�҂ɂ́u�F���v�Ǝv�����A�@���Ȃ��̂ł��낤���B�����āA�V�R�������ԋZ�p��
���Z���^�[���̌㓡 �V�� ���́u�M����R���o�[�^�v�����́A�w�ҁE���Ƃ����{�\�Z�̎���������̊l���ɗp����
���\�I�Ȏ�@�ɋL�ڂ����u�R�E�y�e���E�n�b�^���E�C�J�T�}�E�C���`�L�v�ɗނ��錤���e�[�}�ɑ�������悤�Ɏv���邪�A
����͕M�҂���w�ɍ˂̃|���R�c���Z�p���ł��邱�ƂɋN�������傫�ȁu���Ⴂ�v�E�u�v���Ⴂ�v�ł��낤���B
�Z�p�����Z���^�[�̌㓡 �V�� ���́A�u�M����R���o�[�^�v�ɂ��Ă��u��A�̌����J���ɋ�肪�����̂ŁA��
�O�ɂ����錤�����\��_�����\�ɂ�鐬�ʂ̎��m�ɓw�߂��B�v�ƋL�ڂ���Ă���B���̓��e�𗦒��ɓǂނƁA
�i�Ɓj�Y�ƋZ�p�����������̕����Q�S�N�x�E�Y�ƋZ�p�����������N��ɂ́A�u�M����R���o�[�^�v�̃V�X�e���̊J����
�������A�ȉ��̐��\�����������ƒN�������߂ł������ȋL�ڂƂȂ��Ă���B�܂�A�i�Ɓj�Y�ƋZ�p�����������E�V�R��
�����ԋZ�p�����Z���^�[�̌㓡 �V�� ���́A100���̔r�C�K�X���r�o�����f�B�[�[���G���W���̉^�]��Ԃɂ���
�āA�u�_���G�}�w�v�܂��́u�o�l�t�B���^�[�i���c�o�e���u�j�v��500���ō쓮�ł�����ٓI���u�M����R���o�[�^�v�̊J����
�����������Ƃ��ق̂߂������e���Q�S�N�x�E�Y�ƋZ�p�����������N��ɓ��X�Ƌ��U�Ǝv���錤�����ʂ̔��\���s
���Ă���̂ł���B�ܘ_�A���̂��ẮA���́i�Ɓj�Y�ƋZ�p�����������E�V�R�������ԋZ�p�����Z���^�[�̌㓡 �V
�� �����J���������\���Ă��鋕�U�Ǝv���錤�����ʂ��u�M����R���o�[�^�v�ɂ��ẮA�N���S�������Ă��Ȃ�����
�͓��R�̂��Ƃƍl������B
���F�u�M����R���o�[�^�v�̍쓮�\���̐����ƊJ���̖ڕW
�@�@ �G���W������r�o�����100���̔r�C�K�X���u�M����R���o�[�^�v��460���܂ʼn��M�����B
�@�A 460���܂ʼn��M���ꂽ�r�C�K�X�͎_���G�}�w�ɗ����������_�Łu�_���G�}�w�ł̃|�X�g���˔R���̔R�ĉ��M�v�܂���
�@�@�@�u�o�l�t�B���^�[�i���c�o�e���u�j�ł̂o�l�̔R���M�v�ɂ��A�r�C�K�X��500���܂ʼn��M�����B
�@�B ���́u�_���G�}�w�v�܂��́u�o�l�t�B���^�[�i���c�o�e���u�j�v��500���܂ʼn��M���ꂽ�r�C�K�X�́A�ēx�A�u�M����R���o�[�^�v�ɗ������A
�@�@�@����500���܂ʼn��M���ꂽ�r�C�K�X���u�M����R���o�[�^�v�ɂ���āA�G���W������r�o���ꂽ100���̔r�C�K�X��460���܂ʼn��M����B
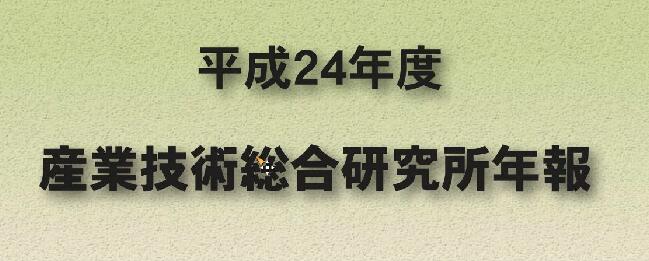 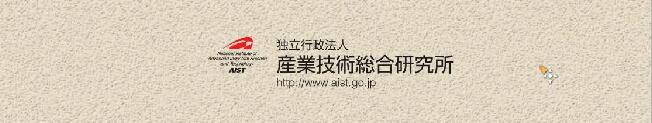 |
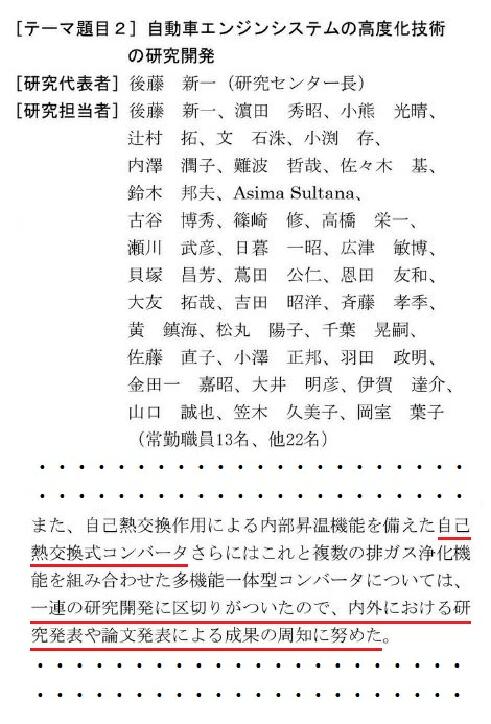 |
�@���͂Ƃ�����A�i�Ɓj�Y�ƋZ�p�����������̕����Q�S�N�x�E�Y�ƋZ�p�����������N��ł́A�V�R�������ԋZ�p����
�Z���^�[���̌㓡 �V�� ���Ƃ��̃O���[�v�̊w�ҁE���Ɓi�����F�������A���� �����A���X�� ��A���� �h�ꎁ
���j�́A���I�ȁu�M����R���o�[�^�v�̃V�X�e���̊J���ɐ����������̂悤�ȋ��U�̋L�ڂ��s���Ă���悤�ł���B
����́A�����Q�S�N�x�E�Y�ƋZ�p�����������N��̋L�ړ��e�́A����܂ł��i�Ɓj�Y�ƋZ�p�����������́u�M����R��
�o�[�^�v�ɓ������ꂽ���{�̌�����\�Z���K�ł������Ƃ��Ƃ����߂̋U���H��̂悤�Ɏv���Ďd�����Ȃ��B����
���A���ۂ́A�����u�M����R���o�[�^�v�̌����J�������S�Ȏ��s�ł���A�u������̖��ʌ����v�E�u���{�\�Z�̘Q��v�ƍl
������B���̂悤�ȁi�Ɓj�Y�ƋZ�p�����������ɂ������u�M����R���o�[�^�v�̌����J�������������Ƃ̋U���H��́A
ES�זE��iPS�זE�����D�ꂽ���\�זE��STAP�זE���J�������Ƃ̝s���_���\���邱�Ƃɂ���āA����܂œ���
���������̗L�����i����������̑Ó����j�����\�I�Ɏ��U��������STAP�זE�s���̑����Ɠ����̂悤�Ɏv����
�d���������B���̂Ȃ�A�u�i�Ɓj�Y�ƋZ�p�����������̔M����R���o�[�^�̊J�������v�Ɓu������STAP�זE�̊J��
�����v�́A���҂Ƃ����{�x���̌�����ɗ��u�������ʂ̝s���v�ƌ��邱�Ƃ��\�Ȃ��߂ł���B
�Z���^�[���̌㓡 �V�� ���Ƃ��̃O���[�v�̊w�ҁE���Ɓi�����F�������A���� �����A���X�� ��A���� �h�ꎁ
���j�́A���I�ȁu�M����R���o�[�^�v�̃V�X�e���̊J���ɐ����������̂悤�ȋ��U�̋L�ڂ��s���Ă���悤�ł���B
����́A�����Q�S�N�x�E�Y�ƋZ�p�����������N��̋L�ړ��e�́A����܂ł��i�Ɓj�Y�ƋZ�p�����������́u�M����R��
�o�[�^�v�ɓ������ꂽ���{�̌�����\�Z���K�ł������Ƃ��Ƃ����߂̋U���H��̂悤�Ɏv���Ďd�����Ȃ��B����
���A���ۂ́A�����u�M����R���o�[�^�v�̌����J�������S�Ȏ��s�ł���A�u������̖��ʌ����v�E�u���{�\�Z�̘Q��v�ƍl
������B���̂悤�ȁi�Ɓj�Y�ƋZ�p�����������ɂ������u�M����R���o�[�^�v�̌����J�������������Ƃ̋U���H��́A
ES�זE��iPS�זE�����D�ꂽ���\�זE��STAP�זE���J�������Ƃ̝s���_���\���邱�Ƃɂ���āA����܂œ���
���������̗L�����i����������̑Ó����j�����\�I�Ɏ��U��������STAP�זE�s���̑����Ɠ����̂悤�Ɏv����
�d���������B���̂Ȃ�A�u�i�Ɓj�Y�ƋZ�p�����������̔M����R���o�[�^�̊J�������v�Ɓu������STAP�זE�̊J��
�����v�́A���҂Ƃ����{�x���̌�����ɗ��u�������ʂ̝s���v�ƌ��邱�Ƃ��\�Ȃ��߂ł���B
�@�Ȃ��A�i�Ɓj�Y�ƋZ�p�������������㓡 �V�� ���A���F�������A���� �����A���X�� ��A���� �h�ꎁ���̊w�ҁE��
��Ƃ́A��^�g���b�N��NO���팸�ƔR�����ɗL���ȋC���x�~��َE����w�ҏ����́u�S�|�R�D�i�Ɓj�Y�ƋZ�p������
�����́u�����㎩���ԃG���W���A�g�����́v�̊w�ҁE���Ǝ҂̏ꍇ�v�̍��ɋL�ڂ��Ă���悤�ɁA2015�N�P���ɂ���
�ẮA�u�w���Z�@�ɂ��R�������ڍ�́v�Ɓu������X�[�p�[�G�}�v�̂Q��ނ����̑e���ȋZ�p�̌������i�ɂ����
�u�M����50���̃G���W���̎����v�Ɖ]���ŏ�����ڕW�B���̕s�\�ȁu�r�����m�Ȍ����J���v�𐭕{�̌����\�Z�Ŏ�
�{���Ă���悤�ł���B���́u�w���Z�@�ɂ��R�������ڍ�́v�Ɓu������X�[�p�[�G�}�v�̂Q��ނ����̃`���P�ȋZ
�p�Łu�M����50���̃G���W���̎����v�Ɖ]���֑�ϑz�Ƃ��v����ڕW���f���Ă����������ƁA�i�Ɓj�Y�ƋZ�p����
���������㓡 �V�� ���A���F�������A���� �����A���X�� ��A���� �h�ꎁ���̃O���[�v�̊w�ҁE���Ƃ́A�ߋ�
�́u�M����R���o�[�^�v�̌����J�������S�Ɏ��s�������Ƃɂ��ĉ��̔��Ȃ��Ă��Ȃ��悤�ł���B���̂��߁A���́i�Ɓj
�Y�ƋZ�p�����������ɂ�����G���W���W�̃O���[�v�̊w�ҁE���Ƃ́A������STAP�זE�����̏��ە����q����
���l�ɁA���{�\�Z�̌����J���̎��s�ɂ��ŋ��̖��ʌ��������邱�Ƃɂ��āA�߈�������������A���ӂ̔O���o��
�邱�Ƃ̖����}�����_�o�E���_�\���̐l�B�̂悤�Ɏv���邪�A�@���Ȃ��̂ł��낤���B�܂�A�i�Ɓj�Y�ƋZ�p��������
�����㓡 �V�� ���A���F�������A���� �����A���X�� ��A���� �h�ꎁ���̃O���[�v�̊w�ҁE���Ƃ́A�ŋ��̖�
�ʌ����s�����̂�������炸�A����ł͉��̔��Ȃ��s���Ă��Ȃ����Ƃ����Ԃ̂悤�ł���B
��Ƃ́A��^�g���b�N��NO���팸�ƔR�����ɗL���ȋC���x�~��َE����w�ҏ����́u�S�|�R�D�i�Ɓj�Y�ƋZ�p������
�����́u�����㎩���ԃG���W���A�g�����́v�̊w�ҁE���Ǝ҂̏ꍇ�v�̍��ɋL�ڂ��Ă���悤�ɁA2015�N�P���ɂ���
�ẮA�u�w���Z�@�ɂ��R�������ڍ�́v�Ɓu������X�[�p�[�G�}�v�̂Q��ނ����̑e���ȋZ�p�̌������i�ɂ����
�u�M����50���̃G���W���̎����v�Ɖ]���ŏ�����ڕW�B���̕s�\�ȁu�r�����m�Ȍ����J���v�𐭕{�̌����\�Z�Ŏ�
�{���Ă���悤�ł���B���́u�w���Z�@�ɂ��R�������ڍ�́v�Ɓu������X�[�p�[�G�}�v�̂Q��ނ����̃`���P�ȋZ
�p�Łu�M����50���̃G���W���̎����v�Ɖ]���֑�ϑz�Ƃ��v����ڕW���f���Ă����������ƁA�i�Ɓj�Y�ƋZ�p����
���������㓡 �V�� ���A���F�������A���� �����A���X�� ��A���� �h�ꎁ���̃O���[�v�̊w�ҁE���Ƃ́A�ߋ�
�́u�M����R���o�[�^�v�̌����J�������S�Ɏ��s�������Ƃɂ��ĉ��̔��Ȃ��Ă��Ȃ��悤�ł���B���̂��߁A���́i�Ɓj
�Y�ƋZ�p�����������ɂ�����G���W���W�̃O���[�v�̊w�ҁE���Ƃ́A������STAP�זE�����̏��ە����q����
���l�ɁA���{�\�Z�̌����J���̎��s�ɂ��ŋ��̖��ʌ��������邱�Ƃɂ��āA�߈�������������A���ӂ̔O���o��
�邱�Ƃ̖����}�����_�o�E���_�\���̐l�B�̂悤�Ɏv���邪�A�@���Ȃ��̂ł��낤���B�܂�A�i�Ɓj�Y�ƋZ�p��������
�����㓡 �V�� ���A���F�������A���� �����A���X�� ��A���� �h�ꎁ���̃O���[�v�̊w�ҁE���Ƃ́A�ŋ��̖�
�ʌ����s�����̂�������炸�A����ł͉��̔��Ȃ��s���Ă��Ȃ����Ƃ����Ԃ̂悤�ł���B
�@���̂悤�ɁA���{�̌����\�Z�����ӔC�Ȍ����J���ɓ��������ꍇ�����݂���w�i�ɂ́A���{�\�Z���g��������
�J���������ڕW�̖��B���Ŏ��s�̌��ʂɏI������Ƃ��Ă��A�w�\���Ɍ����v���W�F�N�g�̖��̂��L�ڂł�������P����
�ȏ�̌������ʕ��������̏I����ɒ�o����A���̌����J���̕s�����ɂ��Ă̒����E����������������
�߂ƍl������B�܂�A�w�ҁE���ƂɂƂ��ẮA���{�̌����\�Z�́u�g�����ҏ����I�v�E�u�l�������ҏ����I�v�̏�
�ɂ���ƍl�����邽�߂��B����ɂ��ẮA�w�ҁE���Ƃ����{�\�Z�̎���������̊l���ɗp���鍼�\�I�Ȏ�@��
�ڏq���Ă���̂ŁA�����̂�����͌䗗�������������B
�J���������ڕW�̖��B���Ŏ��s�̌��ʂɏI������Ƃ��Ă��A�w�\���Ɍ����v���W�F�N�g�̖��̂��L�ڂł�������P����
�ȏ�̌������ʕ��������̏I����ɒ�o����A���̌����J���̕s�����ɂ��Ă̒����E����������������
�߂ƍl������B�܂�A�w�ҁE���ƂɂƂ��ẮA���{�̌����\�Z�́u�g�����ҏ����I�v�E�u�l�������ҏ����I�v�̏�
�ɂ���ƍl�����邽�߂��B����ɂ��ẮA�w�ҁE���Ƃ����{�\�Z�̎���������̊l���ɗp���鍼�\�I�Ȏ�@��
�ڏq���Ă���̂ŁA�����̂�����͌䗗�������������B
�@�������Č���ƁA�i�Ɓj�Y�ƋZ�p�������������u�M����R���o�[�^�v���u�M����50���̃G���W���̎����v�̂悤�ȖڕW�B
���̕s�\�ȁu�r�����m�Ȍ����J���v�������e�[�}�Ɍf���Đ��{�̌����\�Z���l�����Ă��錻��́A�����̌�����
�����҂ł���㓡 �V�� ���A���F�������A���� �����A���X�� ��A���� �h�ꎁ���̊w�ҁE���ƂɂƂ��ẮA�]��
����̓���Ɩ���W�X�Ƃ��Ȃ��Ă���ɉ߂��Ȃ��̂����m��Ȃ��B�������A���̏́A�|���R�c���Z�p���̕M�҂���
����A�ُ�Ȃ��Ƃ��ƍl������B�Ƃ��낪�A�i�Ɓj�Y�ƋZ�p�����������̊w�ҁE���Ƃɂ͗����ł��Ȃ����Ƃ����m
��Ȃ��B���̂Ȃ�A�u�r�����m�Ȍ����J���v�������e�[�}�Ɍf���Đ��{�̌����\�Z�������ł������l������s�ׂ́A
���{�\�Z����������Ă��錤���@�ցE�����g�D�ł͌Â�����s���Ă��铖����O�̎��ۂƂ��l�����邽�߂ł���
���̕s�\�ȁu�r�����m�Ȍ����J���v�������e�[�}�Ɍf���Đ��{�̌����\�Z���l�����Ă��錻��́A�����̌�����
�����҂ł���㓡 �V�� ���A���F�������A���� �����A���X�� ��A���� �h�ꎁ���̊w�ҁE���ƂɂƂ��ẮA�]��
����̓���Ɩ���W�X�Ƃ��Ȃ��Ă���ɉ߂��Ȃ��̂����m��Ȃ��B�������A���̏́A�|���R�c���Z�p���̕M�҂���
����A�ُ�Ȃ��Ƃ��ƍl������B�Ƃ��낪�A�i�Ɓj�Y�ƋZ�p�����������̊w�ҁE���Ƃɂ͗����ł��Ȃ����Ƃ����m
��Ȃ��B���̂Ȃ�A�u�r�����m�Ȍ����J���v�������e�[�}�Ɍf���Đ��{�̌����\�Z�������ł������l������s�ׂ́A
���{�\�Z����������Ă��錤���@�ցE�����g�D�ł͌Â�����s���Ă��铖����O�̎��ۂƂ��l�����邽�߂ł���
�@�Ȃ��A���̍��̋L�ړ��e�́A�|���R�c���Z�p���̕M�҂̋����Ȍ���E�Ό������m��Ȃ��B�����ŁA�i�Ɓj�Y�ƋZ�p��
���������̌㓡 �V�� ���A���F�������A���� �����A���X�� ��A���� �h�ꎁ�����W�҂����̍����{�����ꂽ��
�ɁA���炩�Ɍ��ƋC�t���ꂽ���e�ɂ��ẮA�����̕M�҂�E���[�����ĂɎ����ɂ��Ă̌�A��������������
���B�����ŁA������L�ڂ�������A�����ɒ����������ƍl���Ă���B
���������̌㓡 �V�� ���A���F�������A���� �����A���X�� ��A���� �h�ꎁ�����W�҂����̍����{�����ꂽ��
�ɁA���炩�Ɍ��ƋC�t���ꂽ���e�ɂ��ẮA�����̕M�҂�E���[�����ĂɎ����ɂ��Ă̌�A��������������
���B�����ŁA������L�ڂ�������A�����ɒ����������ƍl���Ă���B
�P�O�|�Q�D�������^�]���̔r�C�K�X���x�̍������ɂ���ĉ����\�Ȃ��Ƃ����������V���ȉۑ�E�s�
�@����24�N8���̊��ȁE�������R�c��u����̎����Ԕr�o�K�X�ጸ��̂�����ɂ��āi��\�ꎟ���\)�����
�����\�ʓY�̐��ψ���ł́A����̌����ۑ�Ƃ��āA�u�G�}��HC��ł��������邽�߁A�g�p�ߒ��Ԃɂ�����
�A�fSCR�V�X�e�������I�ɏ�������Ȃǂɂ��HC����������邱�Ɓv�����߂��Ă���B������āA���y��
�ʏȂ���ъ��Ȃ́A����24�N10���Ɋw���o���҂���Ȃ颔r�o�K�X�㏈��������i�����F���H���G ���勳���j�v��
�����Őݒu���A�������J�n�����Ƃ̂��Ƃł���B�����āA���̌�����́A�A�fSCR�V�X�e���̐G�}��HC��ł���������
���߂ɂ́A400�`500���̏�Ԃ�40���Ԓ��x�ɂ킽���Ĉێ�����ɏ������䂪�K�v�ł���Ƃ̓��e�́u�r�o�K�X�㏈
��������ԕv��25�N3��14�ɔ��\�����B�ȉ����\�Q�U�ɁA���̊T�v�������B
�����\�ʓY�̐��ψ���ł́A����̌����ۑ�Ƃ��āA�u�G�}��HC��ł��������邽�߁A�g�p�ߒ��Ԃɂ�����
�A�fSCR�V�X�e�������I�ɏ�������Ȃǂɂ��HC����������邱�Ɓv�����߂��Ă���B������āA���y��
�ʏȂ���ъ��Ȃ́A����24�N10���Ɋw���o���҂���Ȃ颔r�o�K�X�㏈��������i�����F���H���G ���勳���j�v��
�����Őݒu���A�������J�n�����Ƃ̂��Ƃł���B�����āA���̌�����́A�A�fSCR�V�X�e���̐G�}��HC��ł���������
���߂ɂ́A400�`500���̏�Ԃ�40���Ԓ��x�ɂ킽���Ĉێ�����ɏ������䂪�K�v�ł���Ƃ̓��e�́u�r�o�K�X�㏈
��������ԕv��25�N3��14�ɔ��\�����B�ȉ����\�Q�U�ɁA���̊T�v�������B
| |
|
| |
|
| |
|
| |
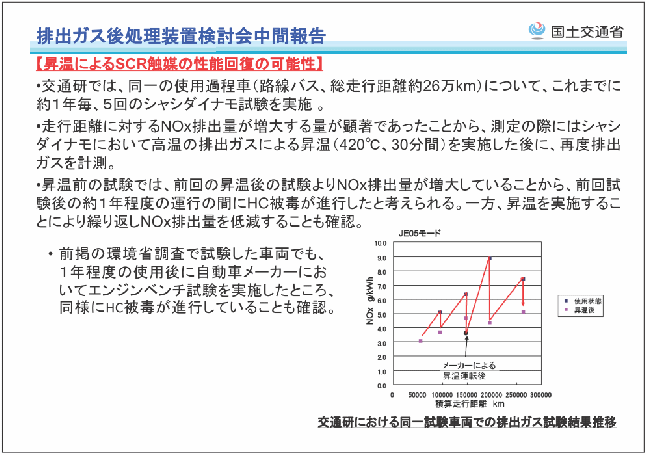 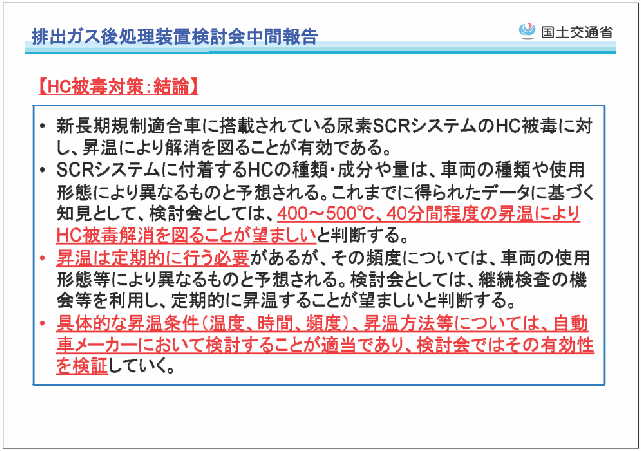 |
�@�ŋ߂̃|�X�g�V�����r�o�K�X�K��(��2009�N�r�o�K�X�K���j�ł́A�قƂ�ǂ̑�^�g���b�N�ɂ́uPM�팸�̂��߂�
DPF���u�v��uNO���팸�̂��߂̔A�fSCR���u�v�����ڂ���Ă���B�������A�����̑��u�ɂ����鍡��̉������ׂ�
�ۑ�Ƃ��āA�ȉ��̏��������悤�Ȕr�C�K�X���������ł���Z�p�𑁋}�Ɏ��p�����ׂ����Ƃ́A�f�B�[�[���G���W
������Ƃ���w�ҁE���Ƃ̊Ԃł́A���Ȃ�ȑO����F������A���m����Ă����ۑ�ł���B
DPF���u�v��uNO���팸�̂��߂̔A�fSCR���u�v�����ڂ���Ă���B�������A�����̑��u�ɂ����鍡��̉������ׂ�
�ۑ�Ƃ��āA�ȉ��̏��������悤�Ȕr�C�K�X���������ł���Z�p�𑁋}�Ɏ��p�����ׂ����Ƃ́A�f�B�[�[���G���W
������Ƃ���w�ҁE���Ƃ̊Ԃł́A���Ȃ�ȑO����F������A���m����Ă����ۑ�ł���B
�� DPF���u�̃t�B���^�Đ��̂��߂�30�����x�̘A�������r�C�K�X���x�̍������̈ێ����䂪�K�v�ł����B
�� ��^�g���b�N���܂ޖw�ǂ̃g���b�N�̎����s�ł̓G���W���̕������^�]�̕p�x�������B���̃G���W���̕�������
�^�]�ł͔r�C�K�X���x���ቺ���邽�߂ɔA�fSCR�G�}�ł�NO���팸�����ቺ���錇�_�E���ׂ�����B����̍X�Ȃ�
NO���K���̋����ɑ��ĔA�fSCR�G�}��p���ēK���ł���悤�ɂ��邽�߂ɂ́A�G���W���̕������^�]��
�̔r�C�K�X���x�̍�������}��Z�p���������A���̃G���W���̕������^�]�ł̔A�fSCR�G�}��NO���팸��
�����シ�邱�Ƃ��K�v�ł����B
�^�]�ł͔r�C�K�X���x���ቺ���邽�߂ɔA�fSCR�G�}�ł�NO���팸�����ቺ���錇�_�E���ׂ�����B����̍X�Ȃ�
NO���K���̋����ɑ��ĔA�fSCR�G�}��p���ēK���ł���悤�ɂ��邽�߂ɂ́A�G���W���̕������^�]��
�̔r�C�K�X���x�̍�������}��Z�p���������A���̃G���W���̕������^�]�ł̔A�fSCR�G�}��NO���팸��
�����シ�邱�Ƃ��K�v�ł����B
�@�Ƃ��낪�A�ŋ߁A�V���Ɏg�p�ߒ��g���b�N�ɂ�����NO���팸�@�\�̒ቺ�̖�肪���炩�ɂȂ������߁A���y��ʏȂ�
���Ȃ������Ţ�r�o�K�X�㏈��������v��ݒu���A���̖��̌��������Ƒ����@�̒������s��ꂽ�Ƃ̂��ƁB��
�̢�r�o�K�X�㏈��������v�����\�������ԕ̊T�v���A�O�q�̕\�Q�Q�ł���B���̒��ԕɂ��ƁA�A�fSCR��
�u�𓋍ڂ����g�p�ߒ��Ԃɂ����āA�����ɂ킽��A�fSCR���u�̌p���g�p���ɔA�fSCR���u��NO���팸�@�\�̒�
������s����s��Ŕ������Ă���Ƃ̂��Ƃł���B�����āA���̕s��̌����́A�A�fSCR�G�}��HC��ł�������
�̂��Ƃ��B�����āA�A�fSCR�G�}��HC��ł������ǂ��ł�����@�Ƃ��āA�A�fSCR�G�}��400�`500���ɂ������
��40���Ԓ��x�ɂ킽���Ĉێ�����ɏ������䂪�K�v�ł���Ƃ̂��Ƃł���B�ȏ�̌��ʁA���s�̎s�̒��̑�^�g���b
�N���܂ޖw�ǂ̃g���b�N�ɂ����ẮA�ȉ��̉ۑ肪�i�قɉ������ׂ��Ɖ]����B
���Ȃ������Ţ�r�o�K�X�㏈��������v��ݒu���A���̖��̌��������Ƒ����@�̒������s��ꂽ�Ƃ̂��ƁB��
�̢�r�o�K�X�㏈��������v�����\�������ԕ̊T�v���A�O�q�̕\�Q�Q�ł���B���̒��ԕɂ��ƁA�A�fSCR��
�u�𓋍ڂ����g�p�ߒ��Ԃɂ����āA�����ɂ킽��A�fSCR���u�̌p���g�p���ɔA�fSCR���u��NO���팸�@�\�̒�
������s����s��Ŕ������Ă���Ƃ̂��Ƃł���B�����āA���̕s��̌����́A�A�fSCR�G�}��HC��ł�������
�̂��Ƃ��B�����āA�A�fSCR�G�}��HC��ł������ǂ��ł�����@�Ƃ��āA�A�fSCR�G�}��400�`500���ɂ������
��40���Ԓ��x�ɂ킽���Ĉێ�����ɏ������䂪�K�v�ł���Ƃ̂��Ƃł���B�ȏ�̌��ʁA���s�̎s�̒��̑�^�g���b
�N���܂ޖw�ǂ̃g���b�N�ɂ����ẮA�ȉ��̉ۑ肪�i�قɉ������ׂ��Ɖ]����B
�@ DPF���u�̃t�B���^�Đ��A
�A �G���W���������^�]�����r�C�K�X���x�̒ቷ���ɂ������A�fSCR�G�}��NO���팸�@�\�̌����A
�B ��^�g���b�N�̎g�p�ߒ��ɂ�����NO���팸�@�\�̒ቺ�h�~�i���A�fSCR�G�}��HC��ł̉j�̂��߂ɁA
�G���W���������^�]�ɂ�����r�C�K�X���x�̍�������}��Z�p�̎��p��
�G���W���������^�]�ɂ�����r�C�K�X���x�̍�������}��Z�p�̎��p��
�@�t�Ɍ����A�G���W���������^�]�ɂ�����r�C�K�X���x�̍�������}��Z�p�����p���ł���A�����@ DPF
���u�̃t�B���^�Đ��A�A �G���W���������^�]���̔A�fSCR�G�}��NO���팸�@�\����A�B �g�p�ߒ��ɂ�����NO����
���@�\�̒ቺ�h�~�̎O�̉ۑ肪�����ɉ����ł��邱�ƂɂȂ�B
���u�̃t�B���^�Đ��A�A �G���W���������^�]���̔A�fSCR�G�}��NO���팸�@�\����A�B �g�p�ߒ��ɂ�����NO����
���@�\�̒ቺ�h�~�̎O�̉ۑ肪�����ɉ����ł��邱�ƂɂȂ�B
�@�������Ȃ���A�s�v�c�Ȃ��ƂɁA���y��ʏȂ���ъ��Ȃ������Őݒu������r�o�K�X�㏈��������v�́A���́u����
�v�ł́A�����ԃ��[�J�Ɂu�G���W���������^�]�ɂ�����r�C�K�X���x�̍�������}��Z�p�v�̊J�������߂Ă���
�����ł���B�����āA���́u�r�C�K�X���x�̍������̋Z�p�v�ɂ��ẮA���́u���ԕv�̒��ɂ͋Z�p�I�Ȏ���������
�L�ڂ���Ă��Ȃ��悤���B�ʂ����āA���́u������v�̍ŏI�ł́A�u�G���W���������^�]�ɂ�����r�C�K�X���x��
��������}��Z�p�v�ɂ��āA�����̎����E���y���s����̂ł��낤���B
�v�ł́A�����ԃ��[�J�Ɂu�G���W���������^�]�ɂ�����r�C�K�X���x�̍�������}��Z�p�v�̊J�������߂Ă���
�����ł���B�����āA���́u�r�C�K�X���x�̍������̋Z�p�v�ɂ��ẮA���́u���ԕv�̒��ɂ͋Z�p�I�Ȏ���������
�L�ڂ���Ă��Ȃ��悤���B�ʂ����āA���́u������v�̍ŏI�ł́A�u�G���W���������^�]�ɂ�����r�C�K�X���x��
��������}��Z�p�v�ɂ��āA�����̎����E���y���s����̂ł��낤���B
�@����Ƃ��A�ŋ߂̃|�X�g�V�����r�o�K�X�K���i��2009�N�r�o�K�X�K���j�ɓK��������^�g���b�N�ł́A�R���̃|�X�g��
�˂�r�C�Ǔ����˂��s����DPF���u�������Đ�����30���Ԓ��x�̔r�C�K�X�̍���������ɂ���āu�A�fSCR�G�}��
HC��ł̉v���\�ƍl�����邽�߁A���s��DPF���u�̋����Đ������I�Ɏ��{���鐧��������ԃ��[�J�ɋ`
���t���邱�Ƃ��A�u�r�o�K�X�㏈��������v�̊w���o���҂ɐl�B�͍l���Ă���̂ł��낤���B���ɂ����ł���Ȃ�A
�u�r�o�K�X�㏈��������v�̊w�ҁE���Ƃ́A�|�X�g���˂�r�C�Ǔ����˂�DPF���u�̋����Đ����R���Q��̌���
�ł��邱�Ƃ����Ă��邱�ƂɂȂ�A�u�A�fSCR�G�}��HC��ł̉v�̂��߂ɍX�Ȃ�R���Q��𐄏����Ă��邱��
�ɂȂ��Ă��܂��ƍl������B���̂悤�ȔR���Q��������s�ׂ́A���ɔ�����ׂ��ł���ƍl���邪�A�@���Ȃ��̂ł��낤
���B�Ȃ��A���́u������v�̒��ԕł́A�ቷ�ł̊����Ɏ�̗D�ꂽ���\�����Ɠ��[�I���C�g��A�fSCR�G�}��
�̗p���邱�Ƃ��������Ă��邪�A���[�I���C�g���g�p����Ƃ��Ă����s�̔A�fSCR�G�}�ɔ�ׂ�NO���팸���̌�������
���x�𐔏\���̒ቷ�����}���邾���ł���ANO���r�o�K�X�l���\���ɒጸ�ł���Z�p�ł͖����ƍl������B
�˂�r�C�Ǔ����˂��s����DPF���u�������Đ�����30���Ԓ��x�̔r�C�K�X�̍���������ɂ���āu�A�fSCR�G�}��
HC��ł̉v���\�ƍl�����邽�߁A���s��DPF���u�̋����Đ������I�Ɏ��{���鐧��������ԃ��[�J�ɋ`
���t���邱�Ƃ��A�u�r�o�K�X�㏈��������v�̊w���o���҂ɐl�B�͍l���Ă���̂ł��낤���B���ɂ����ł���Ȃ�A
�u�r�o�K�X�㏈��������v�̊w�ҁE���Ƃ́A�|�X�g���˂�r�C�Ǔ����˂�DPF���u�̋����Đ����R���Q��̌���
�ł��邱�Ƃ����Ă��邱�ƂɂȂ�A�u�A�fSCR�G�}��HC��ł̉v�̂��߂ɍX�Ȃ�R���Q��𐄏����Ă��邱��
�ɂȂ��Ă��܂��ƍl������B���̂悤�ȔR���Q��������s�ׂ́A���ɔ�����ׂ��ł���ƍl���邪�A�@���Ȃ��̂ł��낤
���B�Ȃ��A���́u������v�̒��ԕł́A�ቷ�ł̊����Ɏ�̗D�ꂽ���\�����Ɠ��[�I���C�g��A�fSCR�G�}��
�̗p���邱�Ƃ��������Ă��邪�A���[�I���C�g���g�p����Ƃ��Ă����s�̔A�fSCR�G�}�ɔ�ׂ�NO���팸���̌�������
���x�𐔏\���̒ቷ�����}���邾���ł���ANO���r�o�K�X�l���\���ɒጸ�ł���Z�p�ł͖����ƍl������B
�@����A�M�҂̃z�[���y�[�W�ł́A�u�G���W���������^�]�ɂ�����r�C�K�X���x�̍�������}��Z�p�v�ł����C���x
�~�G���W���i�������J2005-54771�j���㏈������V�X�e���i�������J2005-69238�j�̂Q���̓����Z�p���A�V�N�ȏ����
�O��2006�N4��������Љ�Ă���̂��B���̌�A�A�C���x�~��DPF�̎��ȍĐ��𑣐i (�����Đ��̍팸�ŔR���
��h�~�j�₱�̃y�[�W��lj����A�����̋Z�p���G���W���������^�]�ɂ�����r�C�K�X���x�̍������ɗL���ł���
���J�j�Y���ɂ��Ă��ڏq���Ă���̂ł���B�Ƃ��낪�A�����M�Ғ�Ắu�f�B�[�[���G���W���������^�]�ɂ�����
�r�C�K�X���x�̍�������}��Z�p�v�ɂ��ẮA�킪���̃g���b�N���[�J�⌤���@�ւ͊��S�ɖ������Ă���悤�ł�
��B����A�u��^�g���b�N�̎g�p�ߒ��ɂ�����NO���팸�@�\�̒ቺ�h�~�i���A�fSCR�G�}��HC��ł̉j�̂���
�ɁA�G���W���������^�]�ɂ�����r�C�K�X���x�̍�������}��Z�p�̎��p�����i�ق̉ۑ�v�Ɣ��\������r�o�K�X
�㏈��������v�́A�G���W���������^�]�ɂ�����r�C�K�X���x�̍�������}��Z�p�ł����C���x�~�G���W���i����
���J2005-54771�j������㏈������V�X�e���i�������J2005-69238�j���Q���̓����Z�p��₽���َE����̂ł��낤
���B
�~�G���W���i�������J2005-54771�j���㏈������V�X�e���i�������J2005-69238�j�̂Q���̓����Z�p���A�V�N�ȏ����
�O��2006�N4��������Љ�Ă���̂��B���̌�A�A�C���x�~��DPF�̎��ȍĐ��𑣐i (�����Đ��̍팸�ŔR���
��h�~�j�₱�̃y�[�W��lj����A�����̋Z�p���G���W���������^�]�ɂ�����r�C�K�X���x�̍������ɗL���ł���
���J�j�Y���ɂ��Ă��ڏq���Ă���̂ł���B�Ƃ��낪�A�����M�Ғ�Ắu�f�B�[�[���G���W���������^�]�ɂ�����
�r�C�K�X���x�̍�������}��Z�p�v�ɂ��ẮA�킪���̃g���b�N���[�J�⌤���@�ւ͊��S�ɖ������Ă���悤�ł�
��B����A�u��^�g���b�N�̎g�p�ߒ��ɂ�����NO���팸�@�\�̒ቺ�h�~�i���A�fSCR�G�}��HC��ł̉j�̂���
�ɁA�G���W���������^�]�ɂ�����r�C�K�X���x�̍�������}��Z�p�̎��p�����i�ق̉ۑ�v�Ɣ��\������r�o�K�X
�㏈��������v�́A�G���W���������^�]�ɂ�����r�C�K�X���x�̍�������}��Z�p�ł����C���x�~�G���W���i����
���J2005-54771�j������㏈������V�X�e���i�������J2005-69238�j���Q���̓����Z�p��₽���َE����̂ł��낤
���B
�@�������A������C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j���㏈������V�X�e���i�������J2005-69238�j�̂Q���̓�
���Z�p�́A�������^�g���b�N�̏d�ʎԃ��[�h�R����T�`�P�O��������ł���u���܂��i���]�\�E���Y���E�T�[�r�X�j���A
�u�����i�������E�����j�Ŏ����ł���̂ł���B���̂��߁A�M�҂ɂ́A�����Q���̓����Z�p�́A��^�g���b�N�̋i�ق̉�
������̂��߂́u�����s������v�̐V�����Z�p�Ǝv���Ă��邪�A�킪���̃f�B�[�[���G���W���W�̊w�ҁE���ƁE�Z
�p�҂ɂ́u���ɑ���Ȃ��ϑz�̃|���R�c�����Z�p�v�̂悤�ɂ��������ł��Ȃ��悤�ł���B����́A���Ɏc�O�Ȃ���
���B
���Z�p�́A�������^�g���b�N�̏d�ʎԃ��[�h�R����T�`�P�O��������ł���u���܂��i���]�\�E���Y���E�T�[�r�X�j���A
�u�����i�������E�����j�Ŏ����ł���̂ł���B���̂��߁A�M�҂ɂ́A�����Q���̓����Z�p�́A��^�g���b�N�̋i�ق̉�
������̂��߂́u�����s������v�̐V�����Z�p�Ǝv���Ă��邪�A�킪���̃f�B�[�[���G���W���W�̊w�ҁE���ƁE�Z
�p�҂ɂ́u���ɑ���Ȃ��ϑz�̃|���R�c�����Z�p�v�̂悤�ɂ��������ł��Ȃ��悤�ł���B����́A���Ɏc�O�Ȃ���
���B
�@�U��Ԃ��Č���A����܂ł̊��ȁE�������R�c��́u����̎����Ԕr�o�K�X�ጸ��̂�����ɂ��āv����
�����ẮA��ړI�́u�r�o�K�X�ጸ�̖ڕW�v�����Ŗ����A�K���r�o�K�X�ጸ�Z�p��r�o�K�X�ƃg���[�h�I�t�̊W�ɂ�
��Ɖ]���Ă���R��ጸ�Z�p�ɂ��Ă��A�K�����y����Ă���̂ł���B����ɂ�������炸�A���̢�r�o�K�X�㏈
��������v�̕ł́A�u�G���W���������^�]�ɂ�����r�C�K�X���x�̍�������}��Z�p�v�ɂ��Ă̋�̓I�ȋZ
�p�������L�ڂ���Ă��Ȃ��悤���B���̌����́A�P�ɢ�r�o�K�X�㏈��������v�̈ψ��̊w���o���҂ɂ͔R����Q��
���Ȃ��u�r�C�K�X���x�̍�������}��Z�p�v�̒m���������_�ŊF���ł��邽�߁A�d�������A�r�C�K�X���x�̍�������
�Z�p�������L�ڂ��Ă��Ȃ��̂ł��낤���B�����āA���́u���ԕv��ǂނƁA�r�C�K�X���x�̍������̋Z�p�́u������
���[�J�ŏ���ɍl�Ă��邱�Ƃ��K���v�ł���Ƃ��Ď����ԃ��[�J�����ɐӔC�������t���A���̋Z�p�̗L�����������w��
�o���҂́u������v���u���v�������s���ƋL�ڂ���Ă���悤�Ɍ�����̂ł���B
�����ẮA��ړI�́u�r�o�K�X�ጸ�̖ڕW�v�����Ŗ����A�K���r�o�K�X�ጸ�Z�p��r�o�K�X�ƃg���[�h�I�t�̊W�ɂ�
��Ɖ]���Ă���R��ጸ�Z�p�ɂ��Ă��A�K�����y����Ă���̂ł���B����ɂ�������炸�A���̢�r�o�K�X�㏈
��������v�̕ł́A�u�G���W���������^�]�ɂ�����r�C�K�X���x�̍�������}��Z�p�v�ɂ��Ă̋�̓I�ȋZ
�p�������L�ڂ���Ă��Ȃ��悤���B���̌����́A�P�ɢ�r�o�K�X�㏈��������v�̈ψ��̊w���o���҂ɂ͔R����Q��
���Ȃ��u�r�C�K�X���x�̍�������}��Z�p�v�̒m���������_�ŊF���ł��邽�߁A�d�������A�r�C�K�X���x�̍�������
�Z�p�������L�ڂ��Ă��Ȃ��̂ł��낤���B�����āA���́u���ԕv��ǂނƁA�r�C�K�X���x�̍������̋Z�p�́u������
���[�J�ŏ���ɍl�Ă��邱�Ƃ��K���v�ł���Ƃ��Ď����ԃ��[�J�����ɐӔC�������t���A���̋Z�p�̗L�����������w��
�o���҂́u������v���u���v�������s���ƋL�ڂ���Ă���悤�Ɍ�����̂ł���B
�@���������āA���́u���ԕv�̒ʂ�ł���A����A�����ԃ��[�J�����ɔr�C�K�X���x�̍������̋Z�p�J����^��
�ڂɎ��{�����A�e�����ԃ��[�J���c�����Č��������킹�āu�R����Q��Ȃ��r�C�K�X���x�̍������̋Z�p���l��
�ł��Ȃ��������߁A�]����DPF���u�̋����Đ��ɍ̗p���Ă���R���Q��̌����ȃ|�X�g���ˎ���r�C�ǔR�����ˎ�
�̔r�C�K�X���x�̍������Z�p�p�E���p����v�Ɓu������v�ɕE�����ꍇ�ɂ́A��r�o�K�X�㏈��������v
�́A�e�����ԃ��[�J�ɐG�}��HC��ł���������Z�p�̌����J���̑Ӗ����ӂł���̂ł��낤���B�܂�A���̒���
�̋L�ړ��e�ł́A��^�g���b�N�i���܁A��ʂ̃f�B�[�[���g���b�N�j�̎g�p�ߒ��Ԃł�NO���팸�@�\�̒ቺ�h�~�i��
�A�fSCR�G�}��HC��ł̉����E�j�̌����J�����������{���Ȃ��ꍇ�ł��A�u������v�͎����ԃ��[�J�̐ӔC���
�y�ł��Ȃ��悤�Ɏv����̂ł���B
�ڂɎ��{�����A�e�����ԃ��[�J���c�����Č��������킹�āu�R����Q��Ȃ��r�C�K�X���x�̍������̋Z�p���l��
�ł��Ȃ��������߁A�]����DPF���u�̋����Đ��ɍ̗p���Ă���R���Q��̌����ȃ|�X�g���ˎ���r�C�ǔR�����ˎ�
�̔r�C�K�X���x�̍������Z�p�p�E���p����v�Ɓu������v�ɕE�����ꍇ�ɂ́A��r�o�K�X�㏈��������v
�́A�e�����ԃ��[�J�ɐG�}��HC��ł���������Z�p�̌����J���̑Ӗ����ӂł���̂ł��낤���B�܂�A���̒���
�̋L�ړ��e�ł́A��^�g���b�N�i���܁A��ʂ̃f�B�[�[���g���b�N�j�̎g�p�ߒ��Ԃł�NO���팸�@�\�̒ቺ�h�~�i��
�A�fSCR�G�}��HC��ł̉����E�j�̌����J�����������{���Ȃ��ꍇ�ł��A�u������v�͎����ԃ��[�J�̐ӔC���
�y�ł��Ȃ��悤�Ɏv����̂ł���B
�@�������A��r�o�K�X�㏈��������v�́A�����ԃ��[�J�Ɂu�r�C�K�X���x�̍�������}��Z�p�v�̌����J�������B����
���邾���ł͖����A�r�C�K�X���x�̍������ɏ����ł��L���ƍl������Z�p���ɂ��Ă̑S�Ă̏��������ԃ��[
�J���ɍL������A�R����Q��Ȃ��g�p�ߒ��Ԃł�NO���팸�@�\�̒ቺ�h�~�i���A�fSCR�G�}��HC��ł̉�
���E�j�̌����J�����������{���Ȃ��ꍇ�ɂ́A�u������v�͎����ԃ��[�J�̐ӔC��Njy�ł���̂ł���B
���邾���ł͖����A�r�C�K�X���x�̍������ɏ����ł��L���ƍl������Z�p���ɂ��Ă̑S�Ă̏��������ԃ��[
�J���ɍL������A�R����Q��Ȃ��g�p�ߒ��Ԃł�NO���팸�@�\�̒ቺ�h�~�i���A�fSCR�G�}��HC��ł̉�
���E�j�̌����J�����������{���Ȃ��ꍇ�ɂ́A�u������v�͎����ԃ��[�J�̐ӔC��Njy�ł���̂ł���B
�@�Ⴆ�A�u�r�C�K�X���x�̍������Z�p�v�������ł���\���̂���Z�p�Ƃ��āA��r�o�K�X�㏈��������v�̕�
���C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j���㏈������V�X�e���i�������J2005-69238�j�̂Q���̓����Z�p���L��
���Ă����A�����ԃ��[�J�͔ۂ����ł��r�C�K�X���x�̍������̋Z�p�J����^�ʖڂɎ��{������Ȃ����Ƃ̂Ȃ�
�ƍl������B���������āA��r�o�K�X�㏈��������v�́A�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j���㏈������V�X
�e���i�������J2005-69238�j�̂Q���̓����Z�p���́u�r�C�K�X���x�̍������Z�p�v�������ł���\���̂���Z�p��
���āA��r�o�K�X�㏈��������v�̍ŏI���Ɂu�r�C�K�X���x�̍������̎Q�l�Z�p�v�Ƃ��Ė����r���ăL�b�`����
�L�ڂ��ׂ��ƍl���邪�A�@���Ȃ��̂ł��낤���B
���C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j���㏈������V�X�e���i�������J2005-69238�j�̂Q���̓����Z�p���L��
���Ă����A�����ԃ��[�J�͔ۂ����ł��r�C�K�X���x�̍������̋Z�p�J����^�ʖڂɎ��{������Ȃ����Ƃ̂Ȃ�
�ƍl������B���������āA��r�o�K�X�㏈��������v�́A�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j���㏈������V�X
�e���i�������J2005-69238�j�̂Q���̓����Z�p���́u�r�C�K�X���x�̍������Z�p�v�������ł���\���̂���Z�p��
���āA��r�o�K�X�㏈��������v�̍ŏI���Ɂu�r�C�K�X���x�̍������̎Q�l�Z�p�v�Ƃ��Ė����r���ăL�b�`����
�L�ڂ��ׂ��ƍl���邪�A�@���Ȃ��̂ł��낤���B
�P�O�|�R�D�M�҂���Ă��镔�����^�]�̔r�C�K�X���x�̍�������e�ՂɎ����ł���V�Z�p
�@��ʓI�ɂ́A��^�g���b�N�p�C���^�[�N�[���ߋ��f�B�[�[���G���W���́A�}�P�S�̖͎��}�Ɏ������悤�ɁA�������ϗL
�����͂̑����ɔ���Ⴕ�ĔR��������lj����A�������ϗL�����́iPme�j�̑����ɔ�Ⴕ�ă^�[�r�������A�^�[�r��
�o���̔r�C�K�X���x�������ƂȂ����������B�����āA�S���ׁi���P�O�O�����ׁj�̃^�[�r���o���̔r�C�K�X���x�͂T�O
�O�����x�ł���A�T�O�����ׂ̃^�[�r���o���̔r�C�K�X���x�͂Q�T�O�����x�ł���B
�����͂̑����ɔ���Ⴕ�ĔR��������lj����A�������ϗL�����́iPme�j�̑����ɔ�Ⴕ�ă^�[�r�������A�^�[�r��
�o���̔r�C�K�X���x�������ƂȂ����������B�����āA�S���ׁi���P�O�O�����ׁj�̃^�[�r���o���̔r�C�K�X���x�͂T�O
�O�����x�ł���A�T�O�����ׂ̃^�[�r���o���̔r�C�K�X���x�͂Q�T�O�����x�ł���B
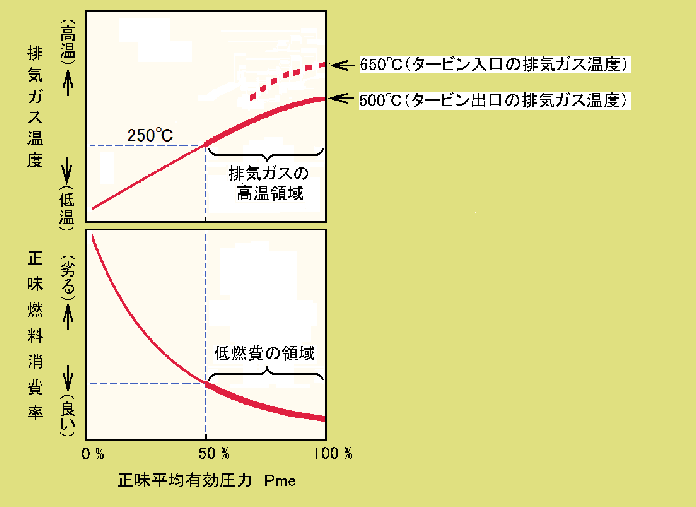
�@�����āA�ȉ��̐}�Q�W��JE�O�T�����WHTC�̎����@�ɂ�����Q��ނ̃G���W���i12.91���b�g���A4.01���b�g���j�̉�]
���E���וp�x���z�}�Ɏ������悤�ɁA�r�o�K�X�����T�C�N���iJE05 ���[�h�j��WHTC�����@�́A�g���b�N�̎����s�ɂ���
��G���W���^�]�p�x����쐬���ꂽ���̂ł��B���̂��߁A�g���b�N�̎����s�ł́A���̐}�P�T�Ɏ�����JE�O�T�����WHTC
�̎����@�ɂ�����Q��ނ̃G���W���i12.91���b�g���A4.01���b�g���j�̉�]���E���וp�x���z�}�Ɏ������悤�ɁA���ۂ̃G
���W���^�]�̑啔�����������ׂł���B���̂悤�ɁA�C���^�[�N�[���ߋ��f�B�[�[���G���W���𓋍ڂ�����ʂ̑�^�g��
�b�N�̑��s�ł́A�G���W���͒�����]�̂T�O�����ߖT�₻��ȉ��̗̈�ʼn^�]�����p�x�������̂ł���B
���E���וp�x���z�}�Ɏ������悤�ɁA�r�o�K�X�����T�C�N���iJE05 ���[�h�j��WHTC�����@�́A�g���b�N�̎����s�ɂ���
��G���W���^�]�p�x����쐬���ꂽ���̂ł��B���̂��߁A�g���b�N�̎����s�ł́A���̐}�P�T�Ɏ�����JE�O�T�����WHTC
�̎����@�ɂ�����Q��ނ̃G���W���i12.91���b�g���A4.01���b�g���j�̉�]���E���וp�x���z�}�Ɏ������悤�ɁA���ۂ̃G
���W���^�]�̑啔�����������ׂł���B���̂悤�ɁA�C���^�[�N�[���ߋ��f�B�[�[���G���W���𓋍ڂ�����ʂ̑�^�g��
�b�N�̑��s�ł́A�G���W���͒�����]�̂T�O�����ߖT�₻��ȉ��̗̈�ʼn^�]�����p�x�������̂ł���B
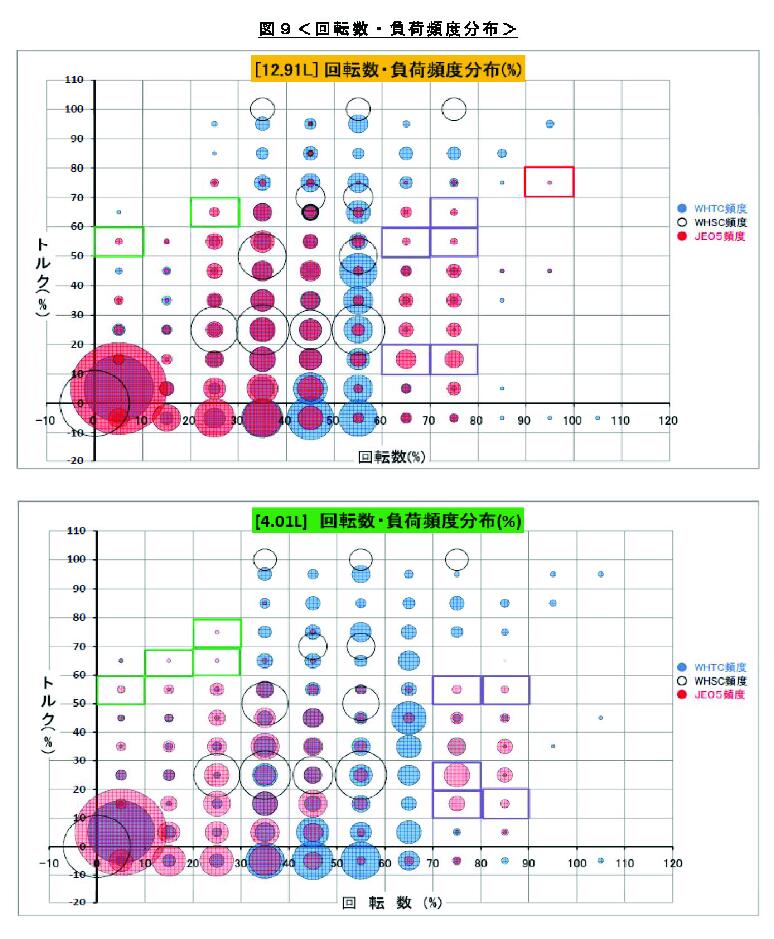
�@���̂悤�ɁA��^�g���b�N���܂ޖw�ǂ̃g���b�N�ɂ����āA�����s���r�o�K�X�����T�C�N���iJE05 ���[�h�j��WHTC����
�@�ɂ����Ďg�p�����G���W���^�]�́A������]�ȉ��̉�]�͈͂ŁA�Ȃ����A�r�C�K�X���x�i���ߋ��@�̃^�[�r��
�o���̔r�C�K�X���x�j���Q�T�O�����x�̂T�O�����ߖT���A����ȉ��̗̈�ʼn^�]�����p�x�������̂ł���B���̂�
�Ƃ���A��^�g���b�N���̎����s�ɂ������u�c�o�e���u�̎��ȍĐ��̑��i�v��}�邽�߂ɂ́A�G���W�����T�O�����ߖT
�₻��ȉ��̉^�]�̈�ł̔r�C�K�X���x����������}��K�v������B�����āA��^�g���b�N���̔r�o�K�X�����T�C�N
���iJE05 ���[�h�j��WHTC�����@�ł́A�G���W���^�]��������]�ȉ��̉�]�͈͂ŁA�Ȃ����A�r�C�K�X���x�i���ߋ�
�@�̃^�[�r���o���̔r�C�K�X���x�j���Q�T�O�����x�̂T�O�����ߖT���A����ȉ��̗̈�ʼn^�]�����p�x��������
�߁A��^�g���b�N�̂m�n�����팸���邽�߂ɂ́A�G���W�����T�O�����ߖT�₻��ȉ��̉^�]�̈�ł̔r�C�K�X���x��
��������}��K�v������B
�@�ɂ����Ďg�p�����G���W���^�]�́A������]�ȉ��̉�]�͈͂ŁA�Ȃ����A�r�C�K�X���x�i���ߋ��@�̃^�[�r��
�o���̔r�C�K�X���x�j���Q�T�O�����x�̂T�O�����ߖT���A����ȉ��̗̈�ʼn^�]�����p�x�������̂ł���B���̂�
�Ƃ���A��^�g���b�N���̎����s�ɂ������u�c�o�e���u�̎��ȍĐ��̑��i�v��}�邽�߂ɂ́A�G���W�����T�O�����ߖT
�₻��ȉ��̉^�]�̈�ł̔r�C�K�X���x����������}��K�v������B�����āA��^�g���b�N���̔r�o�K�X�����T�C�N
���iJE05 ���[�h�j��WHTC�����@�ł́A�G���W���^�]��������]�ȉ��̉�]�͈͂ŁA�Ȃ����A�r�C�K�X���x�i���ߋ�
�@�̃^�[�r���o���̔r�C�K�X���x�j���Q�T�O�����x�̂T�O�����ߖT���A����ȉ��̗̈�ʼn^�]�����p�x��������
�߁A��^�g���b�N�̂m�n�����팸���邽�߂ɂ́A�G���W�����T�O�����ߖT�₻��ȉ��̉^�]�̈�ł̔r�C�K�X���x��
��������}��K�v������B
�@���������āA��^�g���b�N���܂ޖw�ǂ̃g���b�N�ɂ����āA�����s�ɂ������u�c�o�e���u�̎��ȍĐ��̑��i�v�ƁA�u�A�f�r
�b�q�G�}���̂m�n���팸�G�}�̊������ɂ��m�n���̍팸�v���������邽�߂ɂ́A�r�C�K�X���x�i���ߋ��@�̃^�[�r���o
���̔r�C�K�X���x�j���Q�T�O�����x�̂T�O�����ߖT���A����ȉ��̗̈�Ŕr�C�K�X�̍��������邱�Ƃ��K�v�ł���B
���̃G���W���T�O�����ߖT���A����ȉ��̗̈�Ŕr�C�K�X�̍�������e�ՂɎ����ł���Z�p�Ƃ��āA�O�q�̂Q�`�X��
�ŏڏq���Ă���M�Ғ�Ă��C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�ł���B���̋C���x�~�́A�ȒP�ȃV�X�e���ɂ���
����炸�A�G���W���T�O�����ߖT�ł̏]���̃G���W���r�C�K�X���x�i���ߋ��@�̃^�[�r���o���̔r�C�K�X���x�j���Q
�T�O�����x�ł���̂ɑ��A�����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̃G���W���r�C�K�X���x�i���ߋ��@�̃^�[
�r���o���̔r�C�K�X���x�j�́A�قڂQ�{�̂T�O�O�����x�܂ŗe�Ղɍ������ł���̂ł���B�܂��A���̃G���W���r�C�K�X
���x�i���ߋ��@�̃^�[�r���o���̔r�C�K�X���x�j�̍������̋@�\�ɂ���A�f�B�[�[���̋C���x�~�́A�R�[���h�X�^�[�g
��NO���팸�ɂ��L�����I�ɏڏq���Ă���悤�ɁA�Q�^�[�{�������C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p
�́AJE�O�T���[�h�̃R�[���h�X�^�[�g�����ɂ�����NO���̔r�o���팸���邱�Ƃ��\�ł���B
�b�q�G�}���̂m�n���팸�G�}�̊������ɂ��m�n���̍팸�v���������邽�߂ɂ́A�r�C�K�X���x�i���ߋ��@�̃^�[�r���o
���̔r�C�K�X���x�j���Q�T�O�����x�̂T�O�����ߖT���A����ȉ��̗̈�Ŕr�C�K�X�̍��������邱�Ƃ��K�v�ł���B
���̃G���W���T�O�����ߖT���A����ȉ��̗̈�Ŕr�C�K�X�̍�������e�ՂɎ����ł���Z�p�Ƃ��āA�O�q�̂Q�`�X��
�ŏڏq���Ă���M�Ғ�Ă��C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�ł���B���̋C���x�~�́A�ȒP�ȃV�X�e���ɂ���
����炸�A�G���W���T�O�����ߖT�ł̏]���̃G���W���r�C�K�X���x�i���ߋ��@�̃^�[�r���o���̔r�C�K�X���x�j���Q
�T�O�����x�ł���̂ɑ��A�����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̃G���W���r�C�K�X���x�i���ߋ��@�̃^�[
�r���o���̔r�C�K�X���x�j�́A�قڂQ�{�̂T�O�O�����x�܂ŗe�Ղɍ������ł���̂ł���B�܂��A���̃G���W���r�C�K�X
���x�i���ߋ��@�̃^�[�r���o���̔r�C�K�X���x�j�̍������̋@�\�ɂ���A�f�B�[�[���̋C���x�~�́A�R�[���h�X�^�[�g
��NO���팸�ɂ��L�����I�ɏڏq���Ă���悤�ɁA�Q�^�[�{�������C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p
�́AJE�O�T���[�h�̃R�[���h�X�^�[�g�����ɂ�����NO���̔r�o���팸���邱�Ƃ��\�ł���B
�@�܂��A���݂�DPF���u�́A�G���W���������^�]�ł͎��ȍĐ�������ƂȂ邽�߁A�|�X�g���˂�r�C�Ǔ��R������
�ɂ��DPF���u�̋����Đ�����V�X�e�����̗p����Ă���B�����āA������g���b�N�̎����s�ł́A�G���W����������
�^�]���ɂ߂đ������߁A����ł�DPF���u�̋����Đ����p�ɂɍ쓮����ꍇ�������悤���B���̂��߁ADPF�̋�
���Đ��ɂ��R�����ADPF���u�̌̏Ⴊ�������Ă�����B�����ŁA���̖�������������@�Ƃ��āA�M�҂�
��Ă��Ă���Z�p���㏈������V�X�e���i�������J2005-69238�j�ł���B�����㏈������V�X�e���i�������J2005-
69238�j�́A�C���x�~��DPF�̎��ȍĐ��𑣐i (�����Đ��̍팸�ŔR�����h�~�j�ɏڏq���Ă���悤�ɁA��^�g���b
�N�̎����s���̃G���W���������^�]���ɂ�����r�C�K�X���x���ቷ�̏�Ԃɂ����Ă��A�c�o�e���u�̍������ێ���
�邱�Ƃɂ��A�u�c�o�e���u�̎��ȍĐ��v�����i�ł���Z�p�ł���B���������āA��^�g���b�N���㏈������V�X�e���i����
���J2005-69238�j�̋Z�p���̗p����A���݂̂c�o�e���u�̕s���肪���S�ɉ����E�������ł���̂ł���B
�ɂ��DPF���u�̋����Đ�����V�X�e�����̗p����Ă���B�����āA������g���b�N�̎����s�ł́A�G���W����������
�^�]���ɂ߂đ������߁A����ł�DPF���u�̋����Đ����p�ɂɍ쓮����ꍇ�������悤���B���̂��߁ADPF�̋�
���Đ��ɂ��R�����ADPF���u�̌̏Ⴊ�������Ă�����B�����ŁA���̖�������������@�Ƃ��āA�M�҂�
��Ă��Ă���Z�p���㏈������V�X�e���i�������J2005-69238�j�ł���B�����㏈������V�X�e���i�������J2005-
69238�j�́A�C���x�~��DPF�̎��ȍĐ��𑣐i (�����Đ��̍팸�ŔR�����h�~�j�ɏڏq���Ă���悤�ɁA��^�g���b
�N�̎����s���̃G���W���������^�]���ɂ�����r�C�K�X���x���ቷ�̏�Ԃɂ����Ă��A�c�o�e���u�̍������ێ���
�邱�Ƃɂ��A�u�c�o�e���u�̎��ȍĐ��v�����i�ł���Z�p�ł���B���������āA��^�g���b�N���㏈������V�X�e���i����
���J2005-69238�j�̋Z�p���̗p����A���݂̂c�o�e���u�̕s���肪���S�ɉ����E�������ł���̂ł���B
�@�Ȃ��A���̍��̋L�ړ��e�ɂ͐����������܂܂�Ă��邽�߁A�ꕔ�ɂ͕M�҂̎�����F�����邩���m��Ȃ��B����
�ŁA���̍��̋L�ړ��e�ɂ��āA���炩�Ɍ��ƍl������L�q�ɂ��ẮA�����̕M�҂�E���[�����ĂɎ����ɂ�
�Ă̌�A��������������A������L�ړ��e�͑����ɒ����������ƍl���Ă���B
�ŁA���̍��̋L�ړ��e�ɂ��āA���炩�Ɍ��ƍl������L�q�ɂ��ẮA�����̕M�҂�E���[�����ĂɎ����ɂ�
�Ă̌�A��������������A������L�ړ��e�͑����ɒ����������ƍl���Ă���B
�P�P�D��^�g���b�N�̒�R��E��NOx���EDPF�̎��ȍĐ����i���ɗL���ȋC���x�~�Z�p
�@�M�Ғ�Ắu�f�B�[�[���G���W���̔R���NO���Ƃ̓����̍팸�������ł���v�V�I�ȋZ�p�v�ł����C���x�~�G���W��
�i�������J2005-54771�j�̋Z�p�����p������A���{�i�����ȁE���y��ʏȁj�́A���{�́uNOx�ƔR��̋K�������v
���e�ՂɎ����ł���̂��B���ɁA�č������ɂ���^�g���b�N��NO���K�����{�s����������{���{�̑Ӗ��̃y�[�W��
�ڏq���Ă���u�č������ɂ����{�̑�^�g���b�N��NO���K�������{����������{���{�̔ߎS�ȏv�̖�肪������
����ɉ����E�����ł���̂ł���B����ɂ�������炸�A�������R�c��̎����Ԕr�o�K�X���ψ�����܂ސ��{�E
�����i�����ȁE���y��ʏȓ��j�́A�u�f�B�[�[���G���W���̔R���NO���Ƃ��ɍ팸�ł���v�V�I�ȐV�Z�p�v�ł���
�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p����Ȃɖ����E�َE���Ă���̂ł���B�Ȃ��A�����C���x�~�G���W��
�i�������J2005-54771�j�̓����Z�p�́A�f�B�[�[���̋C���x�~�́A�R�[���h�X�^�[�g��NO���팸�ɂ��L�����I�ɏڏq��
�Ă���悤�ɁAJE�O�T���[�h�ior WHTC���[�h�j�ł̃R�[���h�X�^�[�g�����ɂ�����NOx�r�o�̍팸�ɂ��L���ł���B
�i�������J2005-54771�j�̋Z�p�����p������A���{�i�����ȁE���y��ʏȁj�́A���{�́uNOx�ƔR��̋K�������v
���e�ՂɎ����ł���̂��B���ɁA�č������ɂ���^�g���b�N��NO���K�����{�s����������{���{�̑Ӗ��̃y�[�W��
�ڏq���Ă���u�č������ɂ����{�̑�^�g���b�N��NO���K�������{����������{���{�̔ߎS�ȏv�̖�肪������
����ɉ����E�����ł���̂ł���B����ɂ�������炸�A�������R�c��̎����Ԕr�o�K�X���ψ�����܂ސ��{�E
�����i�����ȁE���y��ʏȓ��j�́A�u�f�B�[�[���G���W���̔R���NO���Ƃ��ɍ팸�ł���v�V�I�ȐV�Z�p�v�ł���
�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p����Ȃɖ����E�َE���Ă���̂ł���B�Ȃ��A�����C���x�~�G���W��
�i�������J2005-54771�j�̓����Z�p�́A�f�B�[�[���̋C���x�~�́A�R�[���h�X�^�[�g��NO���팸�ɂ��L�����I�ɏڏq��
�Ă���悤�ɁAJE�O�T���[�h�ior WHTC���[�h�j�ł̃R�[���h�X�^�[�g�����ɂ�����NOx�r�o�̍팸�ɂ��L���ł���B
���͂Ƃ�����A���݂���^�g���b�N�������Ă���u�R��̌���v�ƁuNO���̍팸�v�Ɋ֘A�����w��ljۑ�������ł���V
�Z�p���C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p�ł���B�����̋@�\�ƌ��ʂ��\�Q�V�ɓZ�߂��̂ł���
���������B
�Z�p���C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p�ł���B�����̋@�\�ƌ��ʂ��\�Q�V�ɓZ�߂��̂ł���
���������B
| |
|
|
| |
�����������C���x�~�̌��ʂɂ��A�d�ʎԃ��[�h�R��͂T�`�P�O���̌��オ�\
�i���������ɂ�����u�T�C�N�������̌���v����сu��p�����̍팸�v�ɂ��R����P���ʁj �m�Ⴆ�A�C���x�~�́A�f�B�[�[���̂m�n���팸�ƔR�����̈ꋓ�����̋Z�p���I���Q�Ɓn |
|
| |
���������̔r�C�K�X�̍������ɂ��ADPF���u�ł̎��ȍĐ��̉^�]�̈�̊g��ɂ��R�����
�i�㏈������V�X�e���i�������J2005-69238�j���̗p�����ꍇ�ɂ́A�X�Ȃ�R���Q��̖h�~�𑣐i�j �i�|�X�g���˂܂���HC�r�C�Ǖ��˂�DPF�����Đ��̉������A�����Đ��ɂ��R���Q���h�~�j �m�Ⴆ�A�C���x�~��DPF�̎��ȍĐ��𑣐i (�����Đ��̍팸�ŔR�����h�~�j���Q�Ɓn |
|
| |
���������̔r�C�K�X�̍������ɂ��A�^�[�{�R���p�E���h�ł̔r�M�G�l���M�[�̉������������
�m�Ⴆ�A�^�[�{�R���p�E���h�́A��^�g���b�N�̑��s�R��̉��P������ȋZ�p���I���Q�Ɓn �m�Ⴆ�A�C���x�~�́A�f�B�[�[���̂m�n���팸�ƔR�����̈ꋓ�����̋Z�p���I���Q�Ɓn [�Ⴆ�A�C���x�~�́A�f�B�[�[���r�C�K�X�̃G�l���M�[���u�̌������������Q�Ɓn |
|
| |
���������̔r�K�X���x�̍������ɂ��A�A�fSCR�G�}�ł�NO���팸���̌��オ�\
�m�Ⴆ�A�C���x�~�́A�f�B�[�[���̂m�n���팸�ƔR�����̈ꋓ�����̋Z�p���I���Q�Ɓn |
|
| �D | �����s�����r�K�X���x�̍����ێ��@�\�ɂ��A�g�p�ߒ��Ԃɂ�����A�fSCR�G�}��HC��ł̉�
�i�㏈������V�X�e���i�������J2005-69238�j���ꍇ�ɂ́A�X�Ȃ�A�fSCR�G�}��HC��ł̉j
�m�Ⴆ�A�C���x�~��DPF�̎��ȍĐ��𑣐i (�����Đ��̍팸�ŔR�����h�~�j���Q�Ɓn
|
|
| |
JE�O�T���[�h���ł̃R�[���h�X�^�[�g�����ɂ�����NOx�r�o�̍팸
�iJE�O�T���̃R�[���h�X�^�[�g������NO���r�o��啝�ɍ팸�ł���B��̎��p�I�ȋZ�p�j [�Ⴆ�A�f�B�[�[���̋C���x�~�́A�R�[���h�X�^�[�g��NO���팸�ɂ��L�����I���Q��] |
|
�@�ȏ���\�R�U�ɓZ�߂��悤�ɁA���݂̑�^�g���b�N���C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p���̗p��
��G���W�����������̔r�C�K�X���x���������ł��邽�߁A�g���b�N�E�o�X�̎����s����JE05���[�h�ior WHTC���[
�h�j�̏d�ʎԔr�o�K�X�������ɂ�����u�c�o�e�̋����Đ��p�x�̌����v�A�u�G���W���̒ᕉ���i���r�C�K�X���x�̒ቷ
���j�ɂ������A�f�r�b�q�G�}��NOx�팸���̌���v�A�uJE�O�T���[�h�ior WHTC���[�h�j�ł̃R�[���h�X�^�[�g�����ɂ�����
NOx�r�o�̍팸�v���e�ՂɎ����ł���̂ł���B�����čX�ɁA�G���W���̕������הR��̉��P�ɂ��ɂ߂ėL���ȋZ�p
�ł��邽�߁A�g���b�N�̎����s�R���d�ʎԃ��[�h�R��T�����x�̉��P��������̂ł���B�Ƃ��낪�A���{�̊w
�ҁE���ƁE�Z�p�҂́A���݂���Ȃ��C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p���E�َE���Ă���̂�
����B
��G���W�����������̔r�C�K�X���x���������ł��邽�߁A�g���b�N�E�o�X�̎����s����JE05���[�h�ior WHTC���[
�h�j�̏d�ʎԔr�o�K�X�������ɂ�����u�c�o�e�̋����Đ��p�x�̌����v�A�u�G���W���̒ᕉ���i���r�C�K�X���x�̒ቷ
���j�ɂ������A�f�r�b�q�G�}��NOx�팸���̌���v�A�uJE�O�T���[�h�ior WHTC���[�h�j�ł̃R�[���h�X�^�[�g�����ɂ�����
NOx�r�o�̍팸�v���e�ՂɎ����ł���̂ł���B�����čX�ɁA�G���W���̕������הR��̉��P�ɂ��ɂ߂ėL���ȋZ�p
�ł��邽�߁A�g���b�N�̎����s�R���d�ʎԃ��[�h�R��T�����x�̉��P��������̂ł���B�Ƃ��낪�A���{�̊w
�ҁE���ƁE�Z�p�҂́A���݂���Ȃ��C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p���E�َE���Ă���̂�
����B
�P�P�D�f�B�[�[���ł̋C���x�~�̎��p���ɂ͋Z�p�I�ȉۑ肪���݂���Ƃ̌�����ӌ��E�咣
�@�ȉ����}�Q�W�Ɏ������悤�ɁA�p���o�[�Y��w�̃N���X�E�u���[�X�y�����́A����̃f�B�[�[���G���W����NO���팸��
�R����P�̐��\�����}��Z�p�Ƃ��āA�u�r�C�K�X�㏈���v�A�u�ψ��k��v�A�u�C���x�~�v�A�u�d�C�^�[�{�`���[ �W���[�v
��4�̋Z�p����Ă���B
�R����P�̐��\�����}��Z�p�Ƃ��āA�u�r�C�K�X�㏈���v�A�u�ψ��k��v�A�u�C���x�~�v�A�u�d�C�^�[�{�`���[ �W���[�v
��4�̋Z�p����Ă���B
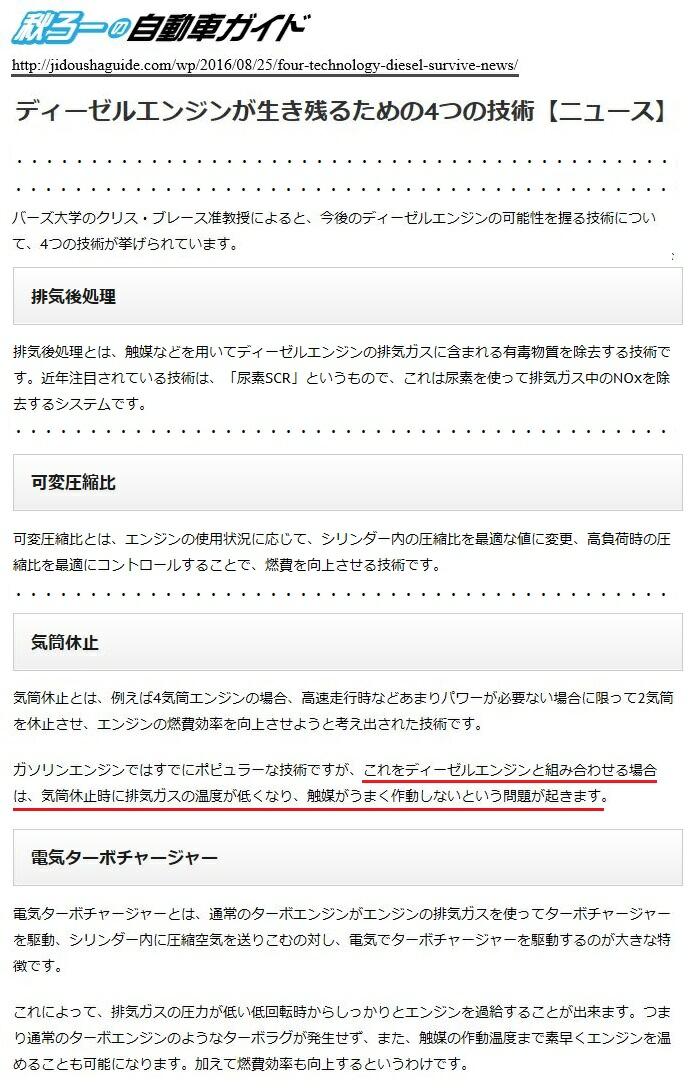 |
�@���̉p���o�[�Y��w�̃N���X�E�u���[�X�y���������Ă���f�B�[�[����4�̂��^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W
���̐��\����Z�p�̊ϓ_����]������ƁA�ȉ��̒ʂ�ƍl������B���Z�p�Ƃ��āA
���̐��\����Z�p�̊ϓ_����]������ƁA�ȉ��̒ʂ�ƍl������B���Z�p�Ƃ��āA
�@ �u�r�C�K�X�㏈���i�A�f�r�b�q�j�v �F �A�f�r�b�q�́A���{�E�k�āE���B�̑�^�g���b�N�Ɋ��ɍ̗p�ς݂̋Z�p
�A �u�ψ��k��v �F �����_�ő�^�g���b�N�ɖ��̗p�̃f�B�[�[���G���W���̐��\����̐V�Z�p
�B �u�C���x�~�v �F �����_�ő�^�g���b�N�ɖ��̗p�̃f�B�[�[���G���W���̐��\����̐V�Z�p
�C �u�d���^�[�{�`���[ �W���[�v �F ��^�g���b�N�̃G���W�����]���̃g���N����̋Z�p�i�Z�p�I�ȐV�K���͖����j
�@���̂悤�ɁA�p���o�[�Y��w�̃N���X�E�u���[�X�y�����́A�ȏ��4�̃f�B�[�[���G���W���̐��\����Z�p���^�f
�B�[�[���g���b�N�ɓK�p����Ƃ����ꍇ�ɂ́A�u�ψ��k��v�Ɓu�C���x�~�v ���V�Z�p�Ɖ]�������ł���B�����āA���̂Q��
�̐V�Z�p�̒��́u�ψ��k��v�́A�K�\�����G���W���ł͎����ԑ��s�R��̌���̍������ʂ�������B�������A����
�u�ψ��k��v�́A��^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W���ł͍��g���N�^�]���̓����ō����͂̒ጸ�ɂ��G���W���o��
�̌���̌��ʂ����炾���ł���A�R����P��NO���팸�̃G���W�����\����̋@�\�E���ʂ����Ȃ��Ɛ��������B����
�����āA��^�f�B�[�[���g���b�N�̕���Ɍ��肵���ꍇ�A�N���X�E�u���[�X�y�����́A�����I�ɂ̓f�B�[�[���G���W����
���\����i���R����P��NO���팸�j�̋Z�p�Ƃ��Ắu�C���x�~�v �̋Z�p������Ă��Ă��Ȃ��Ɣ��f�����B
�B�[�[���g���b�N�ɓK�p����Ƃ����ꍇ�ɂ́A�u�ψ��k��v�Ɓu�C���x�~�v ���V�Z�p�Ɖ]�������ł���B�����āA���̂Q��
�̐V�Z�p�̒��́u�ψ��k��v�́A�K�\�����G���W���ł͎����ԑ��s�R��̌���̍������ʂ�������B�������A����
�u�ψ��k��v�́A��^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W���ł͍��g���N�^�]���̓����ō����͂̒ጸ�ɂ��G���W���o��
�̌���̌��ʂ����炾���ł���A�R����P��NO���팸�̃G���W�����\����̋@�\�E���ʂ����Ȃ��Ɛ��������B����
�����āA��^�f�B�[�[���g���b�N�̕���Ɍ��肵���ꍇ�A�N���X�E�u���[�X�y�����́A�����I�ɂ̓f�B�[�[���G���W����
���\����i���R����P��NO���팸�j�̋Z�p�Ƃ��Ắu�C���x�~�v �̋Z�p������Ă��Ă��Ȃ��Ɣ��f�����B
�}�i���r�b�q�G�}�j�̍쓮�s�ǂ̖������ȉۑ肪���݂���Ƃ̐�����t�������Ă���B���̂��߁A�N���X�E�u���[�X�y��
���́A�����_�ł̓f�B�[�[���Ɂu�C���x�~�v�̋Z�p���̗p���邱�Ƃ͍���Ƃ̌����̂悤�ł���B���������āA�p���o�[
�Y��w�̃N���X�E�u���[�X�y�����́A��^�f�B�[�[���g���b�N�̕���Ɍ��肵���ꍇ�ɂ́A��^�f�B�[�[���g���b�N�̐�
�\����i���R����P��NO���팸�j���Ɏ����ł���f�B�[�[���G���W���̐��\����i���R����P��NO���팸�j�̋Z�p
�������I�ɒE��Ă��Ă��Ȃ��ƌ���̂��Ó��ƍl������B
�@����A�|���R�c���Z�p���̕M�҂́A�C���x�~�^�]�ƂȂ�G���W�����������ɂ͔r�C�K�X�̉��x���]���̃f�B�[�[
���̂Q�{�߂��܂ł̍������ł����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p���Ă��Ă��邷��B��������
�āA�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓������f�B�[�[���G���W���̋C���x�~�ɍ̗p�����ꍇ�ɂ́A�N���X�E�u
���[�X�y�����̎咣����u�C���x�~�v�̋Z�p���̗p�f�B�[�[���G���W���̎��p�����\�ƍl������B�����āA�����
����啝�ɔR����P��NO���팸������������^�f�B�[�[���g���b�N�̎s����������Ɏ����ł��邱�ƂɂȂ�B
���̂Q�{�߂��܂ł̍������ł����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p���Ă��Ă��邷��B��������
�āA�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓������f�B�[�[���G���W���̋C���x�~�ɍ̗p�����ꍇ�ɂ́A�N���X�E�u
���[�X�y�����̎咣����u�C���x�~�v�̋Z�p���̗p�f�B�[�[���G���W���̎��p�����\�ƍl������B�����āA�����
����啝�ɔR����P��NO���팸������������^�f�B�[�[���g���b�N�̎s����������Ɏ����ł��邱�ƂɂȂ�B
�@���̂悤�ɁA�p���o�[�Y��w�̃N���X�E�u���[�X�y�����̂悤�ɁA�p���̃G���W�����̊w�҂̓f�B�[�[���G���W����
���\����i���R����P��NO���팸�j�̋Z�p��E��Ă��Ă��邪�A�s�v�c�Ȃ��Ƃɓ��{�̃G���W�����̊w�҂̑S��
�́u�C���x�~�v�̋Z�p����v�c�����Ċ�Ȃɖ����E�َE���Ă���悤�ł���B���̂悤�ɓ��{�̃G���W�����̊w�҂̑S
���́A�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋C���x�~�Z�p���E�َE�����s�ׂ́A�����_�ł̓f�B�[�[���G
���W���̐��\����i���R����P��NO���팸�j�̎��p�\�ȋZ�p�����J���A�Ⴕ���͕s���ƌ��킴��Ȃ�����
�}�I�ɍ��o���Ă���؋��ƍl������B
���\����i���R����P��NO���팸�j�̋Z�p��E��Ă��Ă��邪�A�s�v�c�Ȃ��Ƃɓ��{�̃G���W�����̊w�҂̑S��
�́u�C���x�~�v�̋Z�p����v�c�����Ċ�Ȃɖ����E�َE���Ă���悤�ł���B���̂悤�ɓ��{�̃G���W�����̊w�҂̑S
���́A�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋C���x�~�Z�p���E�َE�����s�ׂ́A�����_�ł̓f�B�[�[���G
���W���̐��\����i���R����P��NO���팸�j�̎��p�\�ȋZ�p�����J���A�Ⴕ���͕s���ƌ��킴��Ȃ�����
�}�I�ɍ��o���Ă���؋��ƍl������B
�@�Ƃ���ŁA�č������ɂ���^�g���b�N��NO���K�����{�s����������{���{�̑Ӗ��A�f�B�[�[���d�ʎ�2016�NNOx�K
����0.4g/kWh�́A�s���Ȋɘa�̌��K���̃y�[�W�ɏڏq���Ă���悤�ɁA�č��ł�2010�N���m�n���K����NO�� ��
0.27 g/kWh�ł���ɂ�������炸�A���{�ł͑�^�g���b�N��2016�N���m�n���K����NO�� �� 0.4 g/kWh�̑�����
�ɂ��K�������{����Ă��邱�Ƃ́A��������������ł���B����́A���{�̃G���W�����̊w�҂̑S�����C���x
�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋C���x�~�Z�p����v�c�����Ė����E�َE���邱�Ƃɂ��A���{�̑�^�g���b�N��
�r�o�K�X�������[�h�����Ă̓f�B�[�[���G���W���̐��\����i���R����P��NO���팸�j�̎��p�\�ȋZ�p���F���A��
�����͕s���Ƃ��鋕�U�I�ȏ������ɑn�o�����\�����ɂ߂č����ƍl������B
����0.4g/kWh�́A�s���Ȋɘa�̌��K���̃y�[�W�ɏڏq���Ă���悤�ɁA�č��ł�2010�N���m�n���K����NO�� ��
0.27 g/kWh�ł���ɂ�������炸�A���{�ł͑�^�g���b�N��2016�N���m�n���K����NO�� �� 0.4 g/kWh�̑�����
�ɂ��K�������{����Ă��邱�Ƃ́A��������������ł���B����́A���{�̃G���W�����̊w�҂̑S�����C���x
�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋C���x�~�Z�p����v�c�����Ė����E�َE���邱�Ƃɂ��A���{�̑�^�g���b�N��
�r�o�K�X�������[�h�����Ă̓f�B�[�[���G���W���̐��\����i���R����P��NO���팸�j�̎��p�\�ȋZ�p���F���A��
�����͕s���Ƃ��鋕�U�I�ȏ������ɑn�o�����\�����ɂ߂č����ƍl������B
�@����ł́A�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋C���x�~�̓����Z�p�̖����E�َE�ɂ��̗p�ɂ��f�B�[
�[���G���W���̐��\����i���R����P��NO���팸�j�̋Z�p�����J���Ƃ̓��{�̃G���W�����̊w�҂̎咣�́A����
�����Z�p�̗̍p�ɂ���̐����R�X�g�̑���������^�f�B�[�[���g���b�N�̔̔����g���b�N���[�J�����X�Ɛ摗�����
�\�ɂ���K�{�����ƍl������B���̂Ȃ�A���ɂ����{�̃G���W�����̊w�҂��C���x�~�G���W���i�������J2005-
54771�j�̓����Z�p�̗̍p�ɂ���ē��{�̔r�o�K�X�������[�h�ł����{�̑�^�g���b�N���č���NO�� �� 0.27 g/kWh
�i��2010�N�K���j�ɓK�����\�ł���Ƃ̎咣���s�����Ȃ�A�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p
���̗p������̐����R�X�g�̑���������^�f�B�[�[���g���b�N�𑁋}�Ɏs�̂��J�n������Ȃ��Ɋׂ��Ă���
�����Ƃ��m���ƍl�����邽�߂ł���B���̂悤�ȉH�ڂɊׂ�����O�ɉ�����邽�߂ɂ́A���݁A�g���b�N���[�J�́A
�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p�ɂ��f�B�[�[���G���W���̐��\����i���R����P��NO���팸�j
�̏d�v�ȋZ�p������{�̃G���W�����̊w�҂ɉB�����ĖႤ�H����s���Ă�����̂Ɛ��������B
�[���G���W���̐��\����i���R����P��NO���팸�j�̋Z�p�����J���Ƃ̓��{�̃G���W�����̊w�҂̎咣�́A����
�����Z�p�̗̍p�ɂ���̐����R�X�g�̑���������^�f�B�[�[���g���b�N�̔̔����g���b�N���[�J�����X�Ɛ摗�����
�\�ɂ���K�{�����ƍl������B���̂Ȃ�A���ɂ����{�̃G���W�����̊w�҂��C���x�~�G���W���i�������J2005-
54771�j�̓����Z�p�̗̍p�ɂ���ē��{�̔r�o�K�X�������[�h�ł����{�̑�^�g���b�N���č���NO�� �� 0.27 g/kWh
�i��2010�N�K���j�ɓK�����\�ł���Ƃ̎咣���s�����Ȃ�A�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p
���̗p������̐����R�X�g�̑���������^�f�B�[�[���g���b�N�𑁋}�Ɏs�̂��J�n������Ȃ��Ɋׂ��Ă���
�����Ƃ��m���ƍl�����邽�߂ł���B���̂悤�ȉH�ڂɊׂ�����O�ɉ�����邽�߂ɂ́A���݁A�g���b�N���[�J�́A
�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p�ɂ��f�B�[�[���G���W���̐��\����i���R����P��NO���팸�j
�̏d�v�ȋZ�p������{�̃G���W�����̊w�҂ɉB�����ĖႤ�H����s���Ă�����̂Ɛ��������B
�@�R��A���{�̃G���W�����̊w�҂̑S���́A�@���Ȃ铮�@�E���R���C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋C
���x�~�Z�p���E�َE���Ă���̂ł��낤���B�|���R�c���Z�p���̕M�҂̐����ł́A�v���O�����f�B���N�^�[�̐��R
�둥���i���g���^�����ԁE�G���W���Z�p�̈�@�̈撷�j���哱���Ď��{����Ă��鎩���ԃ��[�J����������r�h�o�v�V
�R�ăv���W�F�N�g�ɂ����āA2014�N�x�`2018�N�x��5�N�ԂŖ�V�U���̑�w������(�P�疜�~�`�R�疜�~���x)�^(�N�ԁE
��l)�̌�����i�����z38���~�`50���~�j�����^�̉��`�ɕ邽�߁A���̖�V�U���̃G���W���W�̑�w�����́A�v
���O�����f�B���N�^�[�̐��R�둥���i���g���^�����ԁE�G���W���Z�p�̈�@�̈撷�j�̗v���ɂ��A�C���x�~�G���W���i��
�����J2005-54771�j���C���x�~�̓����Z�p���E�َE����s�ׂ��s���Ă���\��������B
���x�~�Z�p���E�َE���Ă���̂ł��낤���B�|���R�c���Z�p���̕M�҂̐����ł́A�v���O�����f�B���N�^�[�̐��R
�둥���i���g���^�����ԁE�G���W���Z�p�̈�@�̈撷�j���哱���Ď��{����Ă��鎩���ԃ��[�J����������r�h�o�v�V
�R�ăv���W�F�N�g�ɂ����āA2014�N�x�`2018�N�x��5�N�ԂŖ�V�U���̑�w������(�P�疜�~�`�R�疜�~���x)�^(�N�ԁE
��l)�̌�����i�����z38���~�`50���~�j�����^�̉��`�ɕ邽�߁A���̖�V�U���̃G���W���W�̑�w�����́A�v
���O�����f�B���N�^�[�̐��R�둥���i���g���^�����ԁE�G���W���Z�p�̈�@�̈撷�j�̗v���ɂ��A�C���x�~�G���W���i��
�����J2005-54771�j���C���x�~�̓����Z�p���E�َE����s�ׂ��s���Ă���\��������B
�@���ɁA���Ȃ̒������R�c���C�E�����U��������Ԕr�o�K�X���ψ���⍑�y��ʏȂ́u�r�o�K�X�s����
�Ă����f�B�[�[����p�ԓ��������@������������v����сu�R��K�������Ɍg��鎩���ԔR�����ψ���v
���̃����o�[�ł��邽�߂Ɂu���������v�Ⴕ���́u���������v�ɑ�������ƍl������吹�O�����A�ѓc�P����
���A���� �m�����̂R���Ƀv���O�����f�B���N�^�[�̐��R�둥���i���g���^�����ԁE�G���W���Z�p�̈�@�̈撷�j���r�h�o�v
�V�R�ăv���W�F�N�g�̌���������^���A�f�B�[�[���G���W���̐��\�����i���R����P��NO���팸�j�̋Z�p�ł����C���x
�~�G���W���i�������J2005-54771�j���̋C���x�~�̋Z�p���E�َE���邱�Ƃɂ���ē��{�̃f�B�[�[���G���W���Ɋ�
����Z�p���𑀍삷��H����s�����Ƃ��A�d�G�ɑ�������s�ׂƍl������B
�Ă����f�B�[�[����p�ԓ��������@������������v����сu�R��K�������Ɍg��鎩���ԔR�����ψ���v
���̃����o�[�ł��邽�߂Ɂu���������v�Ⴕ���́u���������v�ɑ�������ƍl������吹�O�����A�ѓc�P����
���A���� �m�����̂R���Ƀv���O�����f�B���N�^�[�̐��R�둥���i���g���^�����ԁE�G���W���Z�p�̈�@�̈撷�j���r�h�o�v
�V�R�ăv���W�F�N�g�̌���������^���A�f�B�[�[���G���W���̐��\�����i���R����P��NO���팸�j�̋Z�p�ł����C���x
�~�G���W���i�������J2005-54771�j���̋C���x�~�̋Z�p���E�َE���邱�Ƃɂ���ē��{�̃f�B�[�[���G���W���Ɋ�
����Z�p���𑀍삷��H����s�����Ƃ��A�d�G�ɑ�������s�ׂƍl������B
�@�����āA���̐��R�둥���i���g���^�����ԁj�̘d�G�H��̈З͂̂��߂Ɛ�������邪�A�吹�O�����A�ѓc�P����
���A���� �m�����̂R�����܂ނ̓��{�̖�V�U���̑�w�����̑S���́A�����_�ł��C���x�~�G���W���i�������J2005-
54771�j���̋C���x�~�̋Z�p�����S�ɖ����E�َE���Ă���̂�����̂悤�ł���B�ܘ_�A���{�̃G���W�����̊w��
�́A�����_�ł͋C���x�~�𗽉킷���f�B�[�[���G���W���̐��\�����i���R����P��NO���팸�j�̋Z�p��������\�E
��Ă��ł��Ă��Ȃ��̂�����ł���B����ɂ��ẮA�v���O�����f�B���N�^�[�̐��R�둥���i���g���^�����ԁE�G���W��
�Z�p�̈�@�̈撷�j����r�h�o�v�V�R�ăv���W�F�N�g�̌���������^���Ă��������i����V�U���j�̓��{�̃G���W������
�w�҂́A�����r�h�o�v���W�F�N�g�̌�����^�̉��`�ɕ邽�߂Ɍ����_�Ńf�B�[�[���G���W���̐��\�����i���R���
�P��NO���팸�j�ɍł��L���ȋC���x�~�������Ė����E�َE���Ă��錋�ʁA�f�B�[�[�������Ԃ̐��\����i���R����P
��NO���팸�j���摗�肳��Ă���\��������B
���A���� �m�����̂R�����܂ނ̓��{�̖�V�U���̑�w�����̑S���́A�����_�ł��C���x�~�G���W���i�������J2005-
54771�j���̋C���x�~�̋Z�p�����S�ɖ����E�َE���Ă���̂�����̂悤�ł���B�ܘ_�A���{�̃G���W�����̊w��
�́A�����_�ł͋C���x�~�𗽉킷���f�B�[�[���G���W���̐��\�����i���R����P��NO���팸�j�̋Z�p��������\�E
��Ă��ł��Ă��Ȃ��̂�����ł���B����ɂ��ẮA�v���O�����f�B���N�^�[�̐��R�둥���i���g���^�����ԁE�G���W��
�Z�p�̈�@�̈撷�j����r�h�o�v�V�R�ăv���W�F�N�g�̌���������^���Ă��������i����V�U���j�̓��{�̃G���W������
�w�҂́A�����r�h�o�v���W�F�N�g�̌�����^�̉��`�ɕ邽�߂Ɍ����_�Ńf�B�[�[���G���W���̐��\�����i���R���
�P��NO���팸�j�ɍł��L���ȋC���x�~�������Ė����E�َE���Ă��錋�ʁA�f�B�[�[�������Ԃ̐��\����i���R����P
��NO���팸�j���摗�肳��Ă���\��������B
�@�܂�A�����_�ɂ����ẮA�����i����V�U���j�̓��{�̃G���W�����̊w�҂́A�����ԃ��[�J����̌��������̂�
�Ă���ԗ�E�̍s�ׂƂ��āA�č������ɂ���^�g���b�N��NO���K�����{�s����������{���{�̑Ӗ��A�f�B�[�[��
�d�ʎ�2016�NNOx�K����0.4g/kWh�́A�s���Ȋɘa�̌��K���ɏڏq���Ă���悤�ɁA�f�B�[�[���G���W���̐��\����
�i���R����P��NO���팸�j�̋Z�p�ł����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p���E�َE���A������
���{�̑�^�g���b�N��NO���K�����č����啝�ɒx��Ă��邱�Ƃɂ��Ă͉��ً̈c�E�٘_�������Ă��Ȃ����̂Ɛ���
�����B���̂悤�ɁA���R�둥���i���g���^�����ԁj����r�h�o�v���W�F�N�g�̌���������^���Ă��������i����V�U���j�̓�
�{�̃G���W�����̊w�҂́A���{�̑�^�g���b�N��NO���K���̒x���ɑS�ʓI�ɋ��͂��Ă���\�����ɂ߂č����ƍl
������B
�Ă���ԗ�E�̍s�ׂƂ��āA�č������ɂ���^�g���b�N��NO���K�����{�s����������{���{�̑Ӗ��A�f�B�[�[��
�d�ʎ�2016�NNOx�K����0.4g/kWh�́A�s���Ȋɘa�̌��K���ɏڏq���Ă���悤�ɁA�f�B�[�[���G���W���̐��\����
�i���R����P��NO���팸�j�̋Z�p�ł����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p���E�َE���A������
���{�̑�^�g���b�N��NO���K�����č����啝�ɒx��Ă��邱�Ƃɂ��Ă͉��ً̈c�E�٘_�������Ă��Ȃ����̂Ɛ���
�����B���̂悤�ɁA���R�둥���i���g���^�����ԁj����r�h�o�v���W�F�N�g�̌���������^���Ă��������i����V�U���j�̓�
�{�̃G���W�����̊w�҂́A���{�̑�^�g���b�N��NO���K���̒x���ɑS�ʓI�ɋ��͂��Ă���\�����ɂ߂č����ƍl
������B
�@�����āA�f�B�[�[���G���W���̐��\�����i���R����P��NO���팸�j�̋Z�p�Ƃ��āA�吹�O�����A�ѓc�P�������A��
�� �m�����̂R�����܂����{�̖�V�U���̃G���W�����̊w�҂́A�p���o�[�Y��w�̃N���X�E�u���[�X�y�����̎咣��
�Ă��錻���_�ōł��L�]���f�B�[�[���G���W���̐��\����Z�p�ł����C���x�~����v�c�����Ė����E�َE���Ă��邱��
���A���R�둥���i���g���^�����ԁj����r�h�o�v���W�F�N�g�̌���������^�ɑ���E�ԗ�̈���؋��ł͂Ȃ�����
�l������B���̂��Ƃ́A�吹�O�����A�ѓc�P�������A���� �m�����̂R�����܂����{�̖�V�U���̃G���W������
�w�҂́A���R�둥���i���g���^�����ԁj����r�h�o�v���W�F�N�g�̌�����̎�̂Ƃ̈��������ɁA�u���{�̑�^�g���b�N��
NO���K�����č����啝�ɒx�点�邱�Ɓv��A�u��^�g���b�N��2015�N�x�d�ʎԔR���̋�����摗�肷�邱�Ɓv�ɏd
�v�Ȗ������ʂ����Ă��邱�ƂɂȂ�B���̂��Ƃ́A��V�U���̃G���W�����̊w�҂��߂������ɓ��{�̍���������ׂ�
��C�����P�Ƒ�^�g���b�N�̔R�����̗��v�����j�Q���Ă��邱�ƂɂȂ�ƍl������B�܂�A���{�̖�V�U����
�̃G���W�����̊w�҂́A���{�����̋]���ƈ��������Ɍ�����̎�̂��鎩�Ȃ̗��v�Ă��邱�ƂɂȂ�A�w�҂�
���Ă̗ǐS���L�b�p���Ǝ̂Ă����ɔڂ����l�B�ł͂Ȃ����ƍl������B
�� �m�����̂R�����܂����{�̖�V�U���̃G���W�����̊w�҂́A�p���o�[�Y��w�̃N���X�E�u���[�X�y�����̎咣��
�Ă��錻���_�ōł��L�]���f�B�[�[���G���W���̐��\����Z�p�ł����C���x�~����v�c�����Ė����E�َE���Ă��邱��
���A���R�둥���i���g���^�����ԁj����r�h�o�v���W�F�N�g�̌���������^�ɑ���E�ԗ�̈���؋��ł͂Ȃ�����
�l������B���̂��Ƃ́A�吹�O�����A�ѓc�P�������A���� �m�����̂R�����܂����{�̖�V�U���̃G���W������
�w�҂́A���R�둥���i���g���^�����ԁj����r�h�o�v���W�F�N�g�̌�����̎�̂Ƃ̈��������ɁA�u���{�̑�^�g���b�N��
NO���K�����č����啝�ɒx�点�邱�Ɓv��A�u��^�g���b�N��2015�N�x�d�ʎԔR���̋�����摗�肷�邱�Ɓv�ɏd
�v�Ȗ������ʂ����Ă��邱�ƂɂȂ�B���̂��Ƃ́A��V�U���̃G���W�����̊w�҂��߂������ɓ��{�̍���������ׂ�
��C�����P�Ƒ�^�g���b�N�̔R�����̗��v�����j�Q���Ă��邱�ƂɂȂ�ƍl������B�܂�A���{�̖�V�U����
�̃G���W�����̊w�҂́A���{�����̋]���ƈ��������Ɍ�����̎�̂��鎩�Ȃ̗��v�Ă��邱�ƂɂȂ�A�w�҂�
���Ă̗ǐS���L�b�p���Ǝ̂Ă����ɔڂ����l�B�ł͂Ȃ����ƍl������B
�@�܂��A�吹�O�����A�ѓc�P�������A���� �m�����̂R�����܂����{�̖�V�U���̃G���W�����̊w�҂��f�B�[�[��
�G���W���̐��\�����i���R����P��NO���팸�j�̋Z�p�ł����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j���̋C���x�~
�̑��݂���{�����Ŏ咣�E���\�E���\���鎞���́A2020�N���Ɨ\�z�����B���̂Ȃ�A����2020�N�Ɏ������C���x
�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p�ɂ���f�B�[�[���G���W���̐��\�����i���R����P��NO���팸�j���\
�ł��邱�Ƃ����炩�ɂȂ����ꍇ�ɂ́A���̂S�`5�N���2025�N�ߖT�ɓ��{�̑�^�f�B�[�[���g���b�N�ɂ��Ắu�č�
�Ɠ������x����NO���K���̋����v�Ɓu�u��^�g���b�N��2015�N�x�d�ʎԔR���̋����v�����{���邱�Ƃɂ��Ă͓�
�{�̎����ԊW�̋K�������̃X�P�W���[���Ƃ��Ă͒N�ً̈c��������w�ҁE���Ƃ�����Ȃ��ƍl������B����
�́A����܂ł̎����ԊW�̋K�������̏ꍇ�Ɠ��l�̓����ł��邽�߂��B
�G���W���̐��\�����i���R����P��NO���팸�j�̋Z�p�ł����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j���̋C���x�~
�̑��݂���{�����Ŏ咣�E���\�E���\���鎞���́A2020�N���Ɨ\�z�����B���̂Ȃ�A����2020�N�Ɏ������C���x
�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p�ɂ���f�B�[�[���G���W���̐��\�����i���R����P��NO���팸�j���\
�ł��邱�Ƃ����炩�ɂȂ����ꍇ�ɂ́A���̂S�`5�N���2025�N�ߖT�ɓ��{�̑�^�f�B�[�[���g���b�N�ɂ��Ắu�č�
�Ɠ������x����NO���K���̋����v�Ɓu�u��^�g���b�N��2015�N�x�d�ʎԔR���̋����v�����{���邱�Ƃɂ��Ă͓�
�{�̎����ԊW�̋K�������̃X�P�W���[���Ƃ��Ă͒N�ً̈c��������w�ҁE���Ƃ�����Ȃ��ƍl������B����
�́A����܂ł̎����ԊW�̋K�������̏ꍇ�Ɠ��l�̓����ł��邽�߂��B
�@���̂悤�ɁA�����̑�^�f�B�[�[���g���b�N��NO���K���ƔR���̐V���ȋ�����2025�N�ߖT�Ɏ��{���邱�Ƃ�����
�ł���A�C���x�~�G���W���ɂ���^�g���b�N�̒�R��ɂ��ڏq���Ă���悤�ɁA�C���x�~�G���W���i�������J2005
-54771�j�̓����Z�p�̓�������2024�N5���ɏI�����邽�߁A���̓����Z�p�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j
�̓����Z�p�̎��{���S���Ȃ��Ńg���b�N���[�J�����R���݂Ɏ��Ђ̑�^�g���b�N�ɍ̗p���邱�Ƃ��\�ƂȂ�B��
�̂��Ƃ́A�v���O�����f�B���N�^�[�̐��R�둥���i���g���^�����ԁE�G���W���Z�p�̈�@�̈撷�j���吹�O�����A�ѓc
�P�������A���� �m�����̂R�����܂����{�̖�V�U���̃G���W�����̊w�҂��r�h�o�v�V�R�ăv���W�F�N�g�̌��������
�^�����H��ɂ��A�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j���̋C���x�~�̑��݂�2020�N���܂œ��{�̖�V�U����
�G���W�����̊w�҂ɖ����E�َE���ĖႤ�d���������������ƂɂȂ�ƍl������B���̏ꍇ�ɂ́A�g���b�N���[�J�ɂƂ�
�Ă͏��̎~�܂�ʘb�ƍl������B
�ł���A�C���x�~�G���W���ɂ���^�g���b�N�̒�R��ɂ��ڏq���Ă���悤�ɁA�C���x�~�G���W���i�������J2005
-54771�j�̓����Z�p�̓�������2024�N5���ɏI�����邽�߁A���̓����Z�p�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j
�̓����Z�p�̎��{���S���Ȃ��Ńg���b�N���[�J�����R���݂Ɏ��Ђ̑�^�g���b�N�ɍ̗p���邱�Ƃ��\�ƂȂ�B��
�̂��Ƃ́A�v���O�����f�B���N�^�[�̐��R�둥���i���g���^�����ԁE�G���W���Z�p�̈�@�̈撷�j���吹�O�����A�ѓc
�P�������A���� �m�����̂R�����܂����{�̖�V�U���̃G���W�����̊w�҂��r�h�o�v�V�R�ăv���W�F�N�g�̌��������
�^�����H��ɂ��A�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j���̋C���x�~�̑��݂�2020�N���܂œ��{�̖�V�U����
�G���W�����̊w�҂ɖ����E�َE���ĖႤ�d���������������ƂɂȂ�ƍl������B���̏ꍇ�ɂ́A�g���b�N���[�J�ɂƂ�
�Ă͏��̎~�܂�ʘb�ƍl������B
�@�Ȃ��A�|���R�c���Z�p���̕M�҂̗\�z�ł́A�v���O�����f�B���N�^�[�̐��R�둥���i���g���^�����ԁE�G���W���Z�p��
��@�̈撷�j�́A�����̌�����2024�N5���ɏI�������C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓������{�����x��
�����Ɩ����Ɏ��R���݂Ɏ��Б�^�g���b�N�ɍ̗p���邱�Ƃ��\�ƂȂ闘�v��d���E�H��̂��߂��A�����ԃ��[�J��
��������r�h�o�v�V�R�ăv���W�F�N�g��������u���������v�Ⴕ���́u���������v�ł���吹�O�����A�ѓc�P��
�����A���� �m�����̂R���ɋ��^����Ƃ����A���{���f�B�[�[���G���W���Ɋւ���Z�p���𑀍삷���d�G���^�H�̊�
�����s���Ă���Ɛ��������B����́A�����ׂ����ۂł���B���̂悤�ȑ吹�O�����A�ѓc�P�������A���� �m������
�R���ɑ���d�G���^�̔ƍߍs�ׁH�ɂ���ē��{�̑�^�f�B�[�[���g���b�N��NO���K����R��K���̋�����摗�肷
�邽�߂̐��R�둥���i���g���^�����ԁj�̈�@�H�ȍH��́A�傢�ɖ��̂��邱�Ƃł͂Ȃ����Ǝv�����A�@���Ȃ��̂�
���낤���B
��@�̈撷�j�́A�����̌�����2024�N5���ɏI�������C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓������{�����x��
�����Ɩ����Ɏ��R���݂Ɏ��Б�^�g���b�N�ɍ̗p���邱�Ƃ��\�ƂȂ闘�v��d���E�H��̂��߂��A�����ԃ��[�J��
��������r�h�o�v�V�R�ăv���W�F�N�g��������u���������v�Ⴕ���́u���������v�ł���吹�O�����A�ѓc�P��
�����A���� �m�����̂R���ɋ��^����Ƃ����A���{���f�B�[�[���G���W���Ɋւ���Z�p���𑀍삷���d�G���^�H�̊�
�����s���Ă���Ɛ��������B����́A�����ׂ����ۂł���B���̂悤�ȑ吹�O�����A�ѓc�P�������A���� �m������
�R���ɑ���d�G���^�̔ƍߍs�ׁH�ɂ���ē��{�̑�^�f�B�[�[���g���b�N��NO���K����R��K���̋�����摗�肷
�邽�߂̐��R�둥���i���g���^�����ԁj�̈�@�H�ȍH��́A�傢�ɖ��̂��邱�Ƃł͂Ȃ����Ǝv�����A�@���Ȃ��̂�
���낤���B
�@���Ȃ��Ƃ������_�ł́A�r�h�o�v�V�R�ăv���W�F�N�g�̃v���O�����f�B���N�^�[�̐��R�둥���i���g���^�����ԁE�G���W���Z
�p�̈�@�̈撷�j�́A�d�G�̑��^�ɂ�����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋C���x�~�̓����Z�p����{��
�G���W���W�̊w�҂ɖ����E�َE�������邱�Ƃɐ������Ă���ƍl�����̂ł͂Ȃ����낤���B�����āA���̂悤�Șd�G
�̑��^�Ǝ��d����u����Ă�����{�́A��������s�@�s�ׂ����s����O�����Ƃł���ƌ����Ă��d���̖������Ƃ�
�Ȃ�̂ł͂Ȃ����낤���B�܂��A���R�둥���i���g���^�����Ԋ����j�̈�@�H�ȍs�ׂ́A����܂ł̃g���^�����Ԃ̐���
�Ȗ@�ߏ���i��ƃR���v���C�A���X�j���Ƃ̎Љ�I�ӔC�̊����̗��h�Ȑ錾�Ƃ͐������������悤�Ɏv�����A�@����
���̂ł��낤���B
�p�̈�@�̈撷�j�́A�d�G�̑��^�ɂ�����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋C���x�~�̓����Z�p����{��
�G���W���W�̊w�҂ɖ����E�َE�������邱�Ƃɐ������Ă���ƍl�����̂ł͂Ȃ����낤���B�����āA���̂悤�Șd�G
�̑��^�Ǝ��d����u����Ă�����{�́A��������s�@�s�ׂ����s����O�����Ƃł���ƌ����Ă��d���̖������Ƃ�
�Ȃ�̂ł͂Ȃ����낤���B�܂��A���R�둥���i���g���^�����Ԋ����j�̈�@�H�ȍs�ׂ́A����܂ł̃g���^�����Ԃ̐���
�Ȗ@�ߏ���i��ƃR���v���C�A���X�j���Ƃ̎Љ�I�ӔC�̊����̗��h�Ȑ錾�Ƃ͐������������悤�Ɏv�����A�@����
���̂ł��낤���B
�P�Q�D��^�g���b�N�ɂ����鑖�s�R���d�E�ʎԃ��[�h�R��̉��P�̉ߋ��E���݁E����
�@���������A��^�g���b�N�ɂ����ẮANO���팸�ɔ�r���A���s�R���d�ʎԃ��[�h�R��̉��P�͋ɂ߂č���ł���B��
�����A����ł��g���b�N���[�J�́A1970�N��O������P���I�C���V���b�N�ȗ��A�������R����ɑł������߂Ɍ�����
��^�g���b�N�̑��s�R���d�ʎԃ��[�h�R��̉��P�ɓw�߂Ă����̂ł���B���̕s�f�̓w�͂̌��ʁA���݂̑�^�f�B
�[�[���g���b�N�ł̑��s�R��B������Ă���B�����ŁA�ȉ����\�Q�X�ɂ́A��P���I�C���V���b�N���_�@�Ƃ��ĔR�����P
�̎s��j�[�Y�����܂���1970�N���ȍ~�ɂ��āA��^�g���b�N�ɂ�����T�� ���x�ȏ�̑��s�R���d�ʎԃ��[�h�R��
�̉��P�����ۂɎ�������Ă����Z�p���A�N�㏇�ɐ��������B�܂��A���̕\�S�P�ɂ́A���ɋ߂������ɍ��y��ʏȂ�
2015�N�x�d�ʎԔR������P�O�� ���x�̔R���̂����������{���ꂽ�ꍇ�ɂ����āA�e�g���b�N���[�J���s�{��
�ɂ��̗p������Ȃ���^�g���b�N�̏d�ʎԃ��[�h�R��̉��P�Z�p�ɂ��Ă��t�L�����̂ŁA�����������������B
�����A����ł��g���b�N���[�J�́A1970�N��O������P���I�C���V���b�N�ȗ��A�������R����ɑł������߂Ɍ�����
��^�g���b�N�̑��s�R���d�ʎԃ��[�h�R��̉��P�ɓw�߂Ă����̂ł���B���̕s�f�̓w�͂̌��ʁA���݂̑�^�f�B
�[�[���g���b�N�ł̑��s�R��B������Ă���B�����ŁA�ȉ����\�Q�X�ɂ́A��P���I�C���V���b�N���_�@�Ƃ��ĔR�����P
�̎s��j�[�Y�����܂���1970�N���ȍ~�ɂ��āA��^�g���b�N�ɂ�����T�� ���x�ȏ�̑��s�R���d�ʎԃ��[�h�R��
�̉��P�����ۂɎ�������Ă����Z�p���A�N�㏇�ɐ��������B�܂��A���̕\�S�P�ɂ́A���ɋ߂������ɍ��y��ʏȂ�
2015�N�x�d�ʎԔR������P�O�� ���x�̔R���̂����������{���ꂽ�ꍇ�ɂ����āA�e�g���b�N���[�J���s�{��
�ɂ��̗p������Ȃ���^�g���b�N�̏d�ʎԃ��[�h�R��̉��P�Z�p�ɂ��Ă��t�L�����̂ŁA�����������������B
| |
|
|
| |
�E�u�\�R�Ď��f�B�[�[���v�����u�������f�B�[�[���v�ɕύX | |
| |
�E�u���ߋ��f�B�[�[���v�����u�C���^�[�N���ߋ��f�B�[�[���v�ɕύX | |
| |
�E�g���b�N���u�A�C�h�������O�X�g�b�v�v�̎��p��
�i�����U�����Ԃ��ȃG�l��܂���܂��A���̌�A���̋Z�p���g���b�N�E�o �X�ɍL�����y�j |
|
| |
�E2015�N�x�d�ʎԔR�����{�s
�i���̊�ɓK��������^�g���b�N�ɗD���Ő��̓K�p���J�n�j |
|
| |
�E�u�V�i�}�j���A���g�����X�~�b�V�����v����
�u12�i�@�B�������g�����X�~�b�V�����v�ɕύX �i��^�g���b�N�ɍ����ȁu12�i�@�B�������g�����X�~�b�V�����v�𓋍� ���邱�Ƃɂ��A���{�̃g���b�N���[�J�́A�啔���̑�^�g���b�N�� 2015�N�x�d�ʎԔR���ɐh�����ēK���j |
|
| |
�E�u���َ�̧ݶ����ݸށv�����u�d�q����I�[�g�N�[���t�@���J�b�v
�����O�v�ɕύX �E�u�]���^���������߁v�����u�d�q����ϗ��ʃE�H�[�^�[�|���v�v �ɕύX �i�o�T�Fhttp://www.mitsubishi-fuso.com/jp/news/news_content/ 140529/140529.html�j |
|
| |
�E�u�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�v�̓����Z�p
���̗p�H �i�߂�������2015�N�x�d�ʎԔR����10�����x�̋�����}���� �V���ȔR���̋��������y��ʏȂ����{�����ꍇ�ɂ́A �́A�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p���^ �g���b�N�Ɉ�Ăɍ̗p�������̂Ɨ\�z�����B���̂Ȃ�A�d�ʎ� ���[�h�R��� 5�`10�� ���x���̉��P���\�ɂ���Z�p�́A ���̂Ƃ���A�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̑��ɂ� ��������Ȃ����߂ł���B�j �i���쎩���Ԃ́u�z�E�r�C�ْ�~���̋C���x�~�V�X�e���v�́A ���쎩���Ԃ��_�����\�����R����P�@�\�̗��C���x�~�V�X�e�� �Ɏ������悤�ɁA�G���W�����������ɋx�~�ł���C������ �����Ɏ~�܂�\���I�Ȍ��ׂ̂��߁A�g���b�N�̑��s�R������P ����Z�p�Ƃ��Ă͎��i�ł���B�j |
|
�@�ȏ�̂悤�ɁA1970�N��O������P���I�C���V���b�N�����^�g���b�N�ɂ����āA ���s�R���d�ʎԃ��[�h�R���
�T�� ���x�̉��P���������邽�߂ɍ̗p����Ă����Z�p�́A�ȉ��̂T���ڂł���B
�T�� ���x�̉��P���������邽�߂ɍ̗p����Ă����Z�p�́A�ȉ��̂T���ڂł���B
�@ �u�������f�B�[�[���v
�A �u�C���^�[�N���ߋ��f�B�[�[���v
�B �u�A�C�h�������O�X�g�b�v�v
�C �u12�i�@�B�������g�����X�~�b�V�����v
�D �u�d�q����I�[�g�N�[���t�@���J�b�v�����O�v�Ɓu�d�q����ϗ��ʃE�H�[�^�[�|���v�v�̑g����
�@�ȏ�̏��Z�p�̒����D�� �u�d�q����I�[�g�N�[���t�@���J�b�v�����O�v�Ɓu�d�q����ϗ��ʃE�H�[�^�[�|���v�v�̑g
�����́A�ŋ߁i��2014�N6���j�A�O�H�ӂ����̑�^�g���b�N�ɏ��߂č̗p���ꂽ�Z�p�ł���B�����Ƃ��A�u�d�q����I�[�g
�N�[���t�@���J�b�v�����O�v�͐��\�N���̂��畁�y����FF�쓮��p�ԁi���t�����g�G���W���E�t�����g�h���C�u�̏�p�ԁj��
�̗p����Ă����u�d����p�t�@���v�Ƌ@�\�E���\�������Z�p�ł���A�u�d�q����ϗ��ʃE�H�[�^�[�|���v�v�͍ŋ߂̃n
�C�u���b�h��p�Ԃɍ̗p����Ă���u�d���E�H�[�^�[�|���v�v�Ƌ@�\�E���\�������Z�p�ł���B���������āA �u�d�q����
�I�[�g�N�[���t�@���J�b�v�����O�v�Ɓu�d�q����ϗ��ʃE�H�[�^�[�|���v�v�́A���ɏ�p�Ԃɍ̗p�ς݂̔R���
�P�̋@�\�E���\��L�����ގ��Z�p���^�f�B�[�[���g���b�N�ɗ��p�����ƌ��邱�Ƃ��ł����B
�����́A�ŋ߁i��2014�N6���j�A�O�H�ӂ����̑�^�g���b�N�ɏ��߂č̗p���ꂽ�Z�p�ł���B�����Ƃ��A�u�d�q����I�[�g
�N�[���t�@���J�b�v�����O�v�͐��\�N���̂��畁�y����FF�쓮��p�ԁi���t�����g�G���W���E�t�����g�h���C�u�̏�p�ԁj��
�̗p����Ă����u�d����p�t�@���v�Ƌ@�\�E���\�������Z�p�ł���A�u�d�q����ϗ��ʃE�H�[�^�[�|���v�v�͍ŋ߂̃n
�C�u���b�h��p�Ԃɍ̗p����Ă���u�d���E�H�[�^�[�|���v�v�Ƌ@�\�E���\�������Z�p�ł���B���������āA �u�d�q����
�I�[�g�N�[���t�@���J�b�v�����O�v�Ɓu�d�q����ϗ��ʃE�H�[�^�[�|���v�v�́A���ɏ�p�Ԃɍ̗p�ς݂̔R���
�P�̋@�\�E���\��L�����ގ��Z�p���^�f�B�[�[���g���b�N�ɗ��p�����ƌ��邱�Ƃ��ł����B
�@���̂悤�ɁA �u�d�q����I�[�g�N�[���t�@���J�b�v�����O�v�Ɓu�d�q����ϗ��ʃE�H�[�^�[�|���v�v�́A��p�Ԃł̔R
����P�̋@�\�E���\�����p�����Z�p�ł��邽�߁A��^�g���b�N�̕���ŐV���ɓƎ��ɊJ�����ꂽ�V�K�̔R����P�Z�p
�ƌĂԂ��Ƃɂ͏����S�O�����ƍl������B�������Ȃ���u�d�q����I�[�g�N�[���t�@���J�b�v�����O�v�������ɉ�����
�ϐ��䂵�Č����I�ȃG���W����p���������邽�߂ɕK�v�ɉ�������p�t�@�������Ƃŋ쓮������ጸ���A�u�d�q
����ϗ��ʃE�H�[�^�[�|���v�v�́A�d����p�t�@���Ɠ��l�ɂŕK�v�ɉ����ė�p���ʂ��z�����ăG���W���������I
�ɗ�p���ăE�H�[�^�[�|���v�̗]���ȋ쓮������ጸ���邱�Ƃɂ��A�u��^�g���b�N�ɂ������{�T�� ���x�̏d�ʎ�
���[�h�R��́A���P���\�v�ƂȂ��B����ɂ���āA2014�N�̎��_�ɂ����āA��^�g���b�N�́A2015�N�x�d�ʎԔR���
���́{�T���̒�R��������ł����悤�ł���B
����P�̋@�\�E���\�����p�����Z�p�ł��邽�߁A��^�g���b�N�̕���ŐV���ɓƎ��ɊJ�����ꂽ�V�K�̔R����P�Z�p
�ƌĂԂ��Ƃɂ͏����S�O�����ƍl������B�������Ȃ���u�d�q����I�[�g�N�[���t�@���J�b�v�����O�v�������ɉ�����
�ϐ��䂵�Č����I�ȃG���W����p���������邽�߂ɕK�v�ɉ�������p�t�@�������Ƃŋ쓮������ጸ���A�u�d�q
����ϗ��ʃE�H�[�^�[�|���v�v�́A�d����p�t�@���Ɠ��l�ɂŕK�v�ɉ����ė�p���ʂ��z�����ăG���W���������I
�ɗ�p���ăE�H�[�^�[�|���v�̗]���ȋ쓮������ጸ���邱�Ƃɂ��A�u��^�g���b�N�ɂ������{�T�� ���x�̏d�ʎ�
���[�h�R��́A���P���\�v�ƂȂ��B����ɂ���āA2014�N�̎��_�ɂ����āA��^�g���b�N�́A2015�N�x�d�ʎԔR���
���́{�T���̒�R��������ł����悤�ł���B
�@�ȏ�̂悤�ɁA�����N���ɂ킽��Z�p�ҁE���Ƃ̒n���ȓw�͂ɂ���āA��^�g���b�N�ɂ�����{�T�����x�̑��s�R
��̌�����\�ɂ���Z�p�����p������Ă����̂ł���B���̂悤�ȔR����P�̋Z�p�J���̌o�܁E���т�����ƁA��
�^�g���b�N�̑��s�R���d�ʎԃ��[�h�R��́{�T�� ���x�����P���邱�Ƃ��@���ɓ�����Ƃ����锤�ł���B��������
�āA�߂������ɑ�^�g���b�N�̎����s�R���d�ʎԃ��[�h�R��{�T�����x�ȏ� �̉��P�������ł���V�����R���
��̋Z�p����肷�邱�Ƃ́A�ɂ߂ē�����Ƃł���B����ɂ��āA�M�҂��l����Ƃ���ł́A�����_�ɂ����đ�^�g
���b�N�̎����s�R���d�ʎԃ��[�h�R��{�T�����x�ȏ� �̉��P���\�ɂ���Z�p�́A���̂Ƃ���A�C���x�~�G���W
���i�������J2005-54771�j�̑��ɂ͑��݂��Ȃ��ƍl���Ă���B�܂�A�|�X�g�V�����r�o�K�X�K���i��2009�N�K���j
�K���̎d�l�Ɂu�d�q����I�[�g�N�[���t�@���J�b�v�����O�v�Ɓu�d�q����ϗ��ʃE�H�[�^�[�|���v�v���̗p����
��^�g���b�N�i��2015�N�x�d�ʎԔR���{�T���̒B���̑�^�g���b�N�j�ɁA�V�����C���x�~�G���W���i������
�J2005-54771�j�̓����Z�p��g�����邱�Ƃɂ��A2015�N�x�d�ʎԔR������{�P�O���ȏ�̔R������
�B��������^�g���b�N�������ł����Ɖ]�����Ƃł���B
��̌�����\�ɂ���Z�p�����p������Ă����̂ł���B���̂悤�ȔR����P�̋Z�p�J���̌o�܁E���т�����ƁA��
�^�g���b�N�̑��s�R���d�ʎԃ��[�h�R��́{�T�� ���x�����P���邱�Ƃ��@���ɓ�����Ƃ����锤�ł���B��������
�āA�߂������ɑ�^�g���b�N�̎����s�R���d�ʎԃ��[�h�R��{�T�����x�ȏ� �̉��P�������ł���V�����R���
��̋Z�p����肷�邱�Ƃ́A�ɂ߂ē�����Ƃł���B����ɂ��āA�M�҂��l����Ƃ���ł́A�����_�ɂ����đ�^�g
���b�N�̎����s�R���d�ʎԃ��[�h�R��{�T�����x�ȏ� �̉��P���\�ɂ���Z�p�́A���̂Ƃ���A�C���x�~�G���W
���i�������J2005-54771�j�̑��ɂ͑��݂��Ȃ��ƍl���Ă���B�܂�A�|�X�g�V�����r�o�K�X�K���i��2009�N�K���j
�K���̎d�l�Ɂu�d�q����I�[�g�N�[���t�@���J�b�v�����O�v�Ɓu�d�q����ϗ��ʃE�H�[�^�[�|���v�v���̗p����
��^�g���b�N�i��2015�N�x�d�ʎԔR���{�T���̒B���̑�^�g���b�N�j�ɁA�V�����C���x�~�G���W���i������
�J2005-54771�j�̓����Z�p��g�����邱�Ƃɂ��A2015�N�x�d�ʎԔR������{�P�O���ȏ�̔R������
�B��������^�g���b�N�������ł����Ɖ]�����Ƃł���B
�@���݂ɁA�ŋ߂̑�^�̊O�q�D�ł́A�R����̍팸��}��ړI�̂��߂ɁA�D����Ⴍ�}���������^�q������I�ɍL��
���{����Ă���Ƃ̂��Ƃł���B���ɁA�R���e�i�D�́A�R����̍팸��}��ړI�̂��߂ɁA��i�o�͂̂S�O���`�P�O����
�G���W���o�͂ōq�s����啝�Ȍ����^�q�����{����Ă���悤�ł���B���̏ꍇ�A�G���W���̋C���x�~�́A�����^�q
���̍X�Ȃ�R����オ�\�ɏڏq���Ă���悤�ɁA�M�Ғ�Ă��C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p
�́A�D���̑啝�Ȍ����^�q�̍X�Ȃ�R��̌����}�邱�Ƃ��\�ƂȂ�B���̂��߁A�߂������A�C���x�~�G���W���i��
�����J2005-54771�j�̓����Z�p�́A��^�g���b�N�����Ŗ����A��^�̑D���ɂ����Ă��L���̗p�������̂Ɛ��������B
���{����Ă���Ƃ̂��Ƃł���B���ɁA�R���e�i�D�́A�R����̍팸��}��ړI�̂��߂ɁA��i�o�͂̂S�O���`�P�O����
�G���W���o�͂ōq�s����啝�Ȍ����^�q�����{����Ă���悤�ł���B���̏ꍇ�A�G���W���̋C���x�~�́A�����^�q
���̍X�Ȃ�R����オ�\�ɏڏq���Ă���悤�ɁA�M�Ғ�Ă��C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p
�́A�D���̑啝�Ȍ����^�q�̍X�Ȃ�R��̌����}�邱�Ƃ��\�ƂȂ�B���̂��߁A�߂������A�C���x�~�G���W���i��
�����J2005-54771�j�̓����Z�p�́A��^�g���b�N�����Ŗ����A��^�̑D���ɂ����Ă��L���̗p�������̂Ɛ��������B
�P�R�D��^�g���b�N��NO���팸�ƔR����P�ɗL���ȓ����Z�p�ɑ��霓�ӓI�Ȍ����E����
�@���ɁA�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j���|���R�c���Z�p���̕M�҂̒�Ă�������Z�p�ł��邪�̂ɁA�f�B
�[�[���G���W���W�̓��{�̊w�ҁE���ƁE�Z�p�҂��A���̓����Z�p���E�َE�����Ă���̂ł���A����́A��
��̎����S�E�v���C�h�������Ȃ����߂̍s�ׁE�s���ł͂Ȃ����Ɛ��@�����B����́A���{�̊w�ҁE���ƁE�Z�p�҂́A
��ʂ̑命���̓��{�l�Ɠ������A�������i�S�i���Ƃ݁m�Ђ��݁n�A�i�݁m�˂��݁n�A���݁m���˂݁n�A������݁A���L���`
�̐S�j�̐��Ȃ����������m��Ȃ��B���̂悤�ȓ��{�̊w�ҁE���ƁE�Z�p�҂̐E��ł̍s���ɂ��ẴC���^�[�l�b�g
�̌f���̓��e���ȉ����\�R�O�Ɏ����B
�[�[���G���W���W�̓��{�̊w�ҁE���ƁE�Z�p�҂��A���̓����Z�p���E�َE�����Ă���̂ł���A����́A��
��̎����S�E�v���C�h�������Ȃ����߂̍s�ׁE�s���ł͂Ȃ����Ɛ��@�����B����́A���{�̊w�ҁE���ƁE�Z�p�҂́A
��ʂ̑命���̓��{�l�Ɠ������A�������i�S�i���Ƃ݁m�Ђ��݁n�A�i�݁m�˂��݁n�A���݁m���˂݁n�A������݁A���L���`
�̐S�j�̐��Ȃ����������m��Ȃ��B���̂悤�ȓ��{�̊w�ҁE���ƁE�Z�p�҂̐E��ł̍s���ɂ��ẴC���^�[�l�b�g
�̌f���̓��e���ȉ����\�R�O�Ɏ����B
| 41 �F���������R���N�F2011/06/30(��) 19:34:23.34 ID:jIUpqnBQ
�����E�̐E��ŁA20�N��s�J��������Ă������� ���X �V���������� ���̐V������� ��i�͑����R���Ƃ��čs�� �R�����ꂽ�l�� ��i�����ނ����A�����������l������ �u�����A�C�c���E�E�v�� �V���������邽�тɎ����ւ̎������čs�� |
�@�����\�Q�V�̌f���̓��e������ƁA�R�����ꂽ�l�́A�u�R���Ƃ�����i�v�����ނ̂ł͖����A�R���Ƃ���l�^�E�ޗ���
�q�E�Ăѐ���������u�����������l�v�����ނƂ̂��Ƃł���B����ɂ��Ă��A��Ђ̂��߂ɐ^�ʖڂɎd���������u��������
���l�v�ɂƂ��Ă͖��f�Ȃ��Ƃł���B����́A���i�S�̋������_�\���̐l�Ԃ́A�V�����Z�p���u�����������l�v��O
��I�ɍ��ނƉ]�����Ƃł��낤���B�܂�A���{�l�̒��ɂ́A�����҂̔\�͂ɑ��ĐS�ꂩ�玹�i����l����
���̂ł͂Ȃ����ƍl������B�����C���^�[�l�b�g�̌f���̓��e�Ɍ�����悤�����{�l�̐��_�\����s���p�^�[
�����琄�@����ƁA���{�̊w�ҁE���ƁE�Z�p�҂��C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p�������ɖ�
���E�َE���錴���Ƃ��āA���{�l�ɂ͎��i�S�̋����l�������̂ł͂Ȃ����Ƃ̐����́A���Ȃ����Ԉ���Ă��Ȃ��ƍl
�����邪�A�@���Ȃ��̂ł��낤���B���̂��߁A���̋C���x�~�V�X�e���������|���R�c���Z�p�̕M�҂́A���{�̃f
�B�[�[���G���W���W�̊w�ҁE���ƁE�Z�p�҂��獦�܂�Ă���\��������B�����A�����E�E�E�E�E�B
�q�E�Ăѐ���������u�����������l�v�����ނƂ̂��Ƃł���B����ɂ��Ă��A��Ђ̂��߂ɐ^�ʖڂɎd���������u��������
���l�v�ɂƂ��Ă͖��f�Ȃ��Ƃł���B����́A���i�S�̋������_�\���̐l�Ԃ́A�V�����Z�p���u�����������l�v��O
��I�ɍ��ނƉ]�����Ƃł��낤���B�܂�A���{�l�̒��ɂ́A�����҂̔\�͂ɑ��ĐS�ꂩ�玹�i����l����
���̂ł͂Ȃ����ƍl������B�����C���^�[�l�b�g�̌f���̓��e�Ɍ�����悤�����{�l�̐��_�\����s���p�^�[
�����琄�@����ƁA���{�̊w�ҁE���ƁE�Z�p�҂��C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p�������ɖ�
���E�َE���錴���Ƃ��āA���{�l�ɂ͎��i�S�̋����l�������̂ł͂Ȃ����Ƃ̐����́A���Ȃ����Ԉ���Ă��Ȃ��ƍl
�����邪�A�@���Ȃ��̂ł��낤���B���̂��߁A���̋C���x�~�V�X�e���������|���R�c���Z�p�̕M�҂́A���{�̃f
�B�[�[���G���W���W�̊w�ҁE���ƁE�Z�p�҂��獦�܂�Ă���\��������B�����A�����E�E�E�E�E�B
�@
�@���͂Ƃ�����A���{�̊w�ҁE���Ƃ�������O�����������@��̂��閈�ɐ�����f�u�B�[�[���G���W���̉������ׂ�
�ۑ�v�����𐺍��Ɏ咣�������邾���ł́A�f�B�[�[���G���W���̉ۑ�������ł���Z�p�Ă���\�͂�������A
�f�B�[�[���G���W�����u�c�o�e�̋����Đ��p�x�̌����v�A�u�G���W���̒ᕉ���i���r�C�K�X���x�̒ቷ���j�ɂ�����A
�f�r�b�q�G�}��NOx�팸���̌���v�A�u�R����P�v�A����сuJE�O�T���[�h�ior WHTC���[�h�j�ł̃R�[���h�X�^�[�g�����ɂ�
����NOx�r�o�̍팸�v�̉ۑ�����������N���[���E�f�B�[�[���G���W���́A�����i���A�����ł��Ȃ��̂ł���B�ʂ���
�āA���{�̊w�ҁE���Ƃ́A�ނ�̒������N���[���E�f�B�[�[���G���W���������ł���f�B�[�[���G���W���̑S�Ẳۑ�
�������ł���Z�p�Ă���l��������邱�Ɗ���Đ_�╧�ɋF��A�K�^�̓������C���ɑ҂̂ł��낤���B���ꂪ
�����ł���A���ɂ̑��͖{��ł���B�����āA����ł́A���{�̃f�B�[�[���G���W���W�̊w�ҁE���Ƃ́A�f�B�[
�[���G���W���ɉۂ���Ă���ۑ肾�����咣����u���ׁH�v�A�u�o�����Ȃ��H�v�ȋL���E�_���E�u���\��������Ɛ���
�����B�������Ȃ���A���̃y�[�W��ǂ܂ꂽ�Z�p�҂́A���̒��ɂ͔@���ɖ��ʂȓ��e�̋Z�p����������M����
�Ă��邱�Ƃ����������̂ł͂Ȃ����낤���B���̂悤�ɁA���{�̊w�ҁE���ƁE�́A�g���b�N�E�o�X�̏d�v�ȉۑ肾����
���X�ɏ����Ȃ���A�ۑ�����������i�E�Z�p�����߂Ĉł̒����u������������v�悤�ȎS�߂��𖡂���Ă���̂���
��ł͂Ȃ����낤���B����́A���Ǝ����ƍl������B
�ۑ�v�����𐺍��Ɏ咣�������邾���ł́A�f�B�[�[���G���W���̉ۑ�������ł���Z�p�Ă���\�͂�������A
�f�B�[�[���G���W�����u�c�o�e�̋����Đ��p�x�̌����v�A�u�G���W���̒ᕉ���i���r�C�K�X���x�̒ቷ���j�ɂ�����A
�f�r�b�q�G�}��NOx�팸���̌���v�A�u�R����P�v�A����сuJE�O�T���[�h�ior WHTC���[�h�j�ł̃R�[���h�X�^�[�g�����ɂ�
����NOx�r�o�̍팸�v�̉ۑ�����������N���[���E�f�B�[�[���G���W���́A�����i���A�����ł��Ȃ��̂ł���B�ʂ���
�āA���{�̊w�ҁE���Ƃ́A�ނ�̒������N���[���E�f�B�[�[���G���W���������ł���f�B�[�[���G���W���̑S�Ẳۑ�
�������ł���Z�p�Ă���l��������邱�Ɗ���Đ_�╧�ɋF��A�K�^�̓������C���ɑ҂̂ł��낤���B���ꂪ
�����ł���A���ɂ̑��͖{��ł���B�����āA����ł́A���{�̃f�B�[�[���G���W���W�̊w�ҁE���Ƃ́A�f�B�[
�[���G���W���ɉۂ���Ă���ۑ肾�����咣����u���ׁH�v�A�u�o�����Ȃ��H�v�ȋL���E�_���E�u���\��������Ɛ���
�����B�������Ȃ���A���̃y�[�W��ǂ܂ꂽ�Z�p�҂́A���̒��ɂ͔@���ɖ��ʂȓ��e�̋Z�p����������M����
�Ă��邱�Ƃ����������̂ł͂Ȃ����낤���B���̂悤�ɁA���{�̊w�ҁE���ƁE�́A�g���b�N�E�o�X�̏d�v�ȉۑ肾����
���X�ɏ����Ȃ���A�ۑ�����������i�E�Z�p�����߂Ĉł̒����u������������v�悤�ȎS�߂��𖡂���Ă���̂���
��ł͂Ȃ����낤���B����́A���Ǝ����ƍl������B
�@�������{�̊w�ҁE���Ƃ̔n�������u�����䖝�v�̏�����ƁA���Ƃ��u����J�Ȃ��Ɓv�ł���A�u����v�Ƃ��������l
�̂Ȃ��Ɏv����̂ł���B���̈�����g���b�N�E�o�X�̃��[�U�́A���ꂩ������������ďd�v�ȉۑ肪�������̌�
�ׁH��������g���b�N�E�o�X���w�����A�g�p������Ȃ���J��������ꑱ���邱�ƂɂȂ�B���̂悤�����{�̊w�ҁE��
��Ƃ��u�����䖝�v�ɂ���āA�ł����f�����Ă�����g���b�N�E�o�X�̃��[�U�ł���B���̏�����ƁA���{�̊w�ҁE
���Ƃɂ́A�g���b�N�E�o�X�̃��[�U�̕s���v�Ɏv�����y�Ȃ��g����Ȑl�B�������Ă���悤�Ɏv�����A�@���Ȃ���
�ł��낤���B
�̂Ȃ��Ɏv����̂ł���B���̈�����g���b�N�E�o�X�̃��[�U�́A���ꂩ������������ďd�v�ȉۑ肪�������̌�
�ׁH��������g���b�N�E�o�X���w�����A�g�p������Ȃ���J��������ꑱ���邱�ƂɂȂ�B���̂悤�����{�̊w�ҁE��
��Ƃ��u�����䖝�v�ɂ���āA�ł����f�����Ă�����g���b�N�E�o�X�̃��[�U�ł���B���̏�����ƁA���{�̊w�ҁE
���Ƃɂ́A�g���b�N�E�o�X�̃��[�U�̕s���v�Ɏv�����y�Ȃ��g����Ȑl�B�������Ă���悤�Ɏv�����A�@���Ȃ���
�ł��낤���B
�@�����Ƃ��A�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p���̗p���Ȃ��ꍇ�ɂ́A�g���b�N�E�o�X�̎����s����JE05
���[�h�ior WHTC���[�h�j�̏d�ʎԔr�o�K�X�������ɂ�����u�c�o�e�̋����Đ��p�x�̌����v�A�u�G���W���̒ᕉ���ɂ�
�����A�f�r�b�q�G�}��NOx�팸���̌���v�A�u�R����P�v�A����сuJE�O�T���[�h�ior WHTC���[�h�j�ł̃R�[���h�X�^�[�g��
���ɂ�����NOx�r�o�̍팸�v�̉ۑ�̉������o���Ȃ����߁A����قlj����Ȃ��������C���x�~�G���W���i�������J
2005-54771�j�̓����Z�p���E�َE���邱�Ƃ�����ɂȂ�Ǝv�����A�ʂ����Ĕ@���Ȃ��̂ł��낤���B�������A�߂���
���ɂ́A�f�B�[�[���G���W���̉ۑ������������Ȃ����オ�ԈႢ������������ƍl�����邽�߁A���̎��ɂ́A
�f�B�[�[���g���b�N�E�o�X���C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p���S�ʓI�ɍ̗p�������̂Ɨ\�z��
����B�@
���[�h�ior WHTC���[�h�j�̏d�ʎԔr�o�K�X�������ɂ�����u�c�o�e�̋����Đ��p�x�̌����v�A�u�G���W���̒ᕉ���ɂ�
�����A�f�r�b�q�G�}��NOx�팸���̌���v�A�u�R����P�v�A����сuJE�O�T���[�h�ior WHTC���[�h�j�ł̃R�[���h�X�^�[�g��
���ɂ�����NOx�r�o�̍팸�v�̉ۑ�̉������o���Ȃ����߁A����قlj����Ȃ��������C���x�~�G���W���i�������J
2005-54771�j�̓����Z�p���E�َE���邱�Ƃ�����ɂȂ�Ǝv�����A�ʂ����Ĕ@���Ȃ��̂ł��낤���B�������A�߂���
���ɂ́A�f�B�[�[���G���W���̉ۑ������������Ȃ����オ�ԈႢ������������ƍl�����邽�߁A���̎��ɂ́A
�f�B�[�[���g���b�N�E�o�X���C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p���S�ʓI�ɍ̗p�������̂Ɨ\�z��
����B�@
�@���͂Ƃ�����A�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p�����݂̃f�B�[�[���g���b�N�E�o�X�̕����Ă���
�ۑ��w��lj����ł���@�\�E���\��L���Ă��邱�Ƃ́A�ԈႢ�Ȃ��ƍl������B�������A�����_�ł́A��^�g���b�N��
NO���팸�ƔR�����ɗL���ȋC���x�~��َE����w�ҏ����ɏڏq���Ă���悤�ɁA�����̓��{�̊w�ҁE���Ƃ⒆��
���R�c��̎����Ԕr�o�K�X���ψ���́A�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p����Ȃɖ����E
�َE���Ă���悤�ł���B����ɂ��ẮA�M�҂ɂ͑S�������ł��Ȃ����Ƃ��B
�ۑ��w��lj����ł���@�\�E���\��L���Ă��邱�Ƃ́A�ԈႢ�Ȃ��ƍl������B�������A�����_�ł́A��^�g���b�N��
NO���팸�ƔR�����ɗL���ȋC���x�~��َE����w�ҏ����ɏڏq���Ă���悤�ɁA�����̓��{�̊w�ҁE���Ƃ⒆��
���R�c��̎����Ԕr�o�K�X���ψ���́A�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p����Ȃɖ����E
�َE���Ă���悤�ł���B����ɂ��ẮA�M�҂ɂ͑S�������ł��Ȃ����Ƃ��B
�@�Ƃ���ŁA�]�k�ƂȂ邪�A�p��̌��Ɂu�n�𐅕ӂɓ������Ƃ͂ł��邪�A�i�n�ɂ��̋C���Ȃ���j�������܂��邱�Ƃ�
�ł��Ȃ��v�yA man may lead a horse to the water�C but he cannot make him drink�iunless he will�j�z�Ɖ]�����̂�����B
����́A2015�N�x�d�ʎԔR���ɕs�K���̑�^�g���b�N�E�g���N�^�̎Ԏ�𐔑��������Ă����g���b�N���[�J���A�C��
�x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p����ȂɖَE���Ă���l�q�ɓ��ěƂ܂肻�����B
�ł��Ȃ��v�yA man may lead a horse to the water�C but he cannot make him drink�iunless he will�j�z�Ɖ]�����̂�����B
����́A2015�N�x�d�ʎԔR���ɕs�K���̑�^�g���b�N�E�g���N�^�̎Ԏ�𐔑��������Ă����g���b�N���[�J���A�C��
�x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p����ȂɖَE���Ă���l�q�ɓ��ěƂ܂肻�����B
�@�܂��A�u�������ދC�̖����n�ɐ������܂��邽�߂ɂ́A�A�������܂Ŕn�ʂɑ��点��I�i���A�������܂Ŕn�����
�Ēu���I�j�v�Ƃ̗��o�[�W�����̌�������悤���B���̗��o�[�W�����̌��̎�|�ɉ����ăg���b�N���[�J�̍s����\������
�ƁA�e�g���b�N���[�J���]���ʂ���R����P�ɖ����ȋZ�p�̊J�����p������2015�N�x�d�ʎԔR���ɕs�K������^
�g���b�N�E�g���N�^���Ԏ킪��|�ł��Ȃ����Ƃ����A�������J���̌����i���J���̐l�H�A�ݔ��A�����j��Q��Ă��܂���
����A���X�Ȃ�����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p�J���ɒ��肷��ꍇ���l������B���̂悤�ȁA
�g���b�N���[�J�ɂ������R�����̌�����J���s�ׂ̓^���́A���̗��o�[�W�����̌��ɂ��s�b�^���Ɠ��ěƂ܂�̂ł͂�
�����Ǝv���Ă���B
�Ēu���I�j�v�Ƃ̗��o�[�W�����̌�������悤���B���̗��o�[�W�����̌��̎�|�ɉ����ăg���b�N���[�J�̍s����\������
�ƁA�e�g���b�N���[�J���]���ʂ���R����P�ɖ����ȋZ�p�̊J�����p������2015�N�x�d�ʎԔR���ɕs�K������^
�g���b�N�E�g���N�^���Ԏ킪��|�ł��Ȃ����Ƃ����A�������J���̌����i���J���̐l�H�A�ݔ��A�����j��Q��Ă��܂���
����A���X�Ȃ�����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p�J���ɒ��肷��ꍇ���l������B���̂悤�ȁA
�g���b�N���[�J�ɂ������R�����̌�����J���s�ׂ̓^���́A���̗��o�[�W�����̌��ɂ��s�b�^���Ɠ��ěƂ܂�̂ł͂�
�����Ǝv���Ă���B
�@���݂ɁA���݁A�e�g���b�N���[�J���J���𐄐i���Ɖ]���Ă���u�R�������[���ɂ��300MPa���x���̒��������ˁv�A
�u�R�i�ߋ��ior�Q�i�ߋ��j�v�A�u�J�����X�V�X�e����p����HCCI�R�āi��PCI�R�āj�v�̑g�����Z�p�́A���ɂm�d�c�n �v�V�I
���������Q�ԑ����Z�p�J���́u�����x�R�Đ���G���W�V�X�e���̌����J���i�������ԁF2004�N8���`2009�N3���A
�\�Z�F�W���~�ȏ�j�v�̐��ʕ�http://app3.infoc.nedo.go.jp/gyouji/events/FK/rd/2008/nedoevent.2009-02-16.
5786478868/shiryo.pdf�ɖ��L����Ă���悤�ɁA�R��팸�̍���Ȃ��Ƃ����Ɏ�����Ă���̂ł���B���������āA
���݂̂Ƃ���A��^�g���b�N�E�g���N�^�̑S�Ă��Ԏ��2015�N�x�d�ʎԔR���ɓK�����������p���̗e�ՂȋZ�p�́A
�M�҂���Ă��Ă����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̑��ɂ͖����Ǝv���Ă���B
�u�R�i�ߋ��ior�Q�i�ߋ��j�v�A�u�J�����X�V�X�e����p����HCCI�R�āi��PCI�R�āj�v�̑g�����Z�p�́A���ɂm�d�c�n �v�V�I
���������Q�ԑ����Z�p�J���́u�����x�R�Đ���G���W�V�X�e���̌����J���i�������ԁF2004�N8���`2009�N3���A
�\�Z�F�W���~�ȏ�j�v�̐��ʕ�http://app3.infoc.nedo.go.jp/gyouji/events/FK/rd/2008/nedoevent.2009-02-16.
5786478868/shiryo.pdf�ɖ��L����Ă���悤�ɁA�R��팸�̍���Ȃ��Ƃ����Ɏ�����Ă���̂ł���B���������āA
���݂̂Ƃ���A��^�g���b�N�E�g���N�^�̑S�Ă��Ԏ��2015�N�x�d�ʎԔR���ɓK�����������p���̗e�ՂȋZ�p�́A
�M�҂���Ă��Ă����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̑��ɂ͖����Ǝv���Ă���B
�@���łɐ\���グ��ƁA�Q�O�P�U�N�R���R���ɍ��y��ʏȂ́A�N���[���f�B�[�[���G���W�������ڂƐ�`���Ďs�̂����
���錻�s�̃����h�N���[�U�[�E�v���h�i�g���^�j�̃f�B�[�[���Ԃ́A�����ߍx�̓~��̂P�O���ߖT�ȉ��ł̘H�㑖�s�ł�
�ی쐧��\�t�g�ɂ���Ăm�n���팸���u���~�����邽�߂ɂm�n���K���l�̂Q�D�X�{�`�P�Q�D�V�{�̍��Z�x�̂m�n���𐂂ꗬ
�����ׁH�̂��邱�Ƃ\�����B�������A�������ƂɁA���y��ʏȂ́A���̓~��̘H�㑖�s�łm�n���𐂂ꗬ�������h�N��
�[�U�[�E�v���h�i�g���^�j�̃f�B�[�[���Ԃ��G�R�J�[���ł̐��{�̗D������č�����s�̂��邱�Ƃ����F���Ă���悤
�ł���B
���錻�s�̃����h�N���[�U�[�E�v���h�i�g���^�j�̃f�B�[�[���Ԃ́A�����ߍx�̓~��̂P�O���ߖT�ȉ��ł̘H�㑖�s�ł�
�ی쐧��\�t�g�ɂ���Ăm�n���팸���u���~�����邽�߂ɂm�n���K���l�̂Q�D�X�{�`�P�Q�D�V�{�̍��Z�x�̂m�n���𐂂ꗬ
�����ׁH�̂��邱�Ƃ\�����B�������A�������ƂɁA���y��ʏȂ́A���̓~��̘H�㑖�s�łm�n���𐂂ꗬ�������h�N��
�[�U�[�E�v���h�i�g���^�j�̃f�B�[�[���Ԃ��G�R�J�[���ł̐��{�̗D������č�����s�̂��邱�Ƃ����F���Ă���悤
�ł���B
�@���݂ɁA���B�̃f�B�[�[�������Ԃł́A�Q�O�P�V�N�X���ɂ́u�H�㑖�s��NOx�r�o�l����㎎����NOx��l�̂Q�D�P
�{�ȓ��v�̘H�㑖�s��NOx�r�o�l�ɋK������\������ɔ��\���Ă���B�������A�����V���f�W�^���̂Q�O�P�U�N�R���T��
�̕��L���ɂ��ƁA���{�̍��y��ʏȂ́A���ꂩ��T�N��i���Q�O�Q�P�N�Q�����H�j�ɉ��B�Ɠ��l�̃f�B�[�[��������
�ł̘H�㑖�s��NOx�r�o�l�̋K�����{���������n�߂��悤�ł���B���ꂪ�����ł���A�����ߍx�̓~��̂P�O����
�T�ȉ��ł̘H�㑖�s�łm�n���K���l�̂Q�D�X�{�`�P�Q�D�V�{�̍��Z�x�̂m�n���̐��ꗬ���̌��ׂ����P���������h�N���[
�U�[�E�v���h�i�g���^�j�̃f�B�[�[���Ԃ́A�Q�O�Q�P�N�Q�����ɂȂ�܂ŁA���{�ł͎s�̂���Ȃ��\��������ƍl������B
����́A�g���^�����Ԃ������h�N���[�U�[�E�v���h�i�g���^�j�̃f�B�[�[���Ԃ̘H�㑖�s�ł̍��Z�x�̂m�n���̐��ꗬ���̌�
�ׂ����P�ł���Z�p�����J���ƁA���y��ʏȂ��F�����Ă��邽�߂ł��낤���B
�{�ȓ��v�̘H�㑖�s��NOx�r�o�l�ɋK������\������ɔ��\���Ă���B�������A�����V���f�W�^���̂Q�O�P�U�N�R���T��
�̕��L���ɂ��ƁA���{�̍��y��ʏȂ́A���ꂩ��T�N��i���Q�O�Q�P�N�Q�����H�j�ɉ��B�Ɠ��l�̃f�B�[�[��������
�ł̘H�㑖�s��NOx�r�o�l�̋K�����{���������n�߂��悤�ł���B���ꂪ�����ł���A�����ߍx�̓~��̂P�O����
�T�ȉ��ł̘H�㑖�s�łm�n���K���l�̂Q�D�X�{�`�P�Q�D�V�{�̍��Z�x�̂m�n���̐��ꗬ���̌��ׂ����P���������h�N���[
�U�[�E�v���h�i�g���^�j�̃f�B�[�[���Ԃ́A�Q�O�Q�P�N�Q�����ɂȂ�܂ŁA���{�ł͎s�̂���Ȃ��\��������ƍl������B
����́A�g���^�����Ԃ������h�N���[�U�[�E�v���h�i�g���^�j�̃f�B�[�[���Ԃ̘H�㑖�s�ł̍��Z�x�̂m�n���̐��ꗬ���̌�
�ׂ����P�ł���Z�p�����J���ƁA���y��ʏȂ��F�����Ă��邽�߂ł��낤���B
�@�Ƃ��낪�A���̌��s�̃����h�N���[�U�[�E�v���h�i�g���^�j�̃f�B�[�[���Ԃ��C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j��
�����Z�p���̗p�����ꍇ�ɂ́A�~��̘H�㑖�s�ō��Z�x�̂m�n���̐��ꗬ�����ׂ�e�Ղɉ��P���邱�Ƃ��\�ł�
��B�܂�A�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p���̗p���������h�N���[�U�[�E�v���h�i�g���^�j�̃f�B�[
�[���Ԃ́A�~��̘H�㑖�s�ɂ����Ă��A�m�n���K���l�̃N���[���Ȃm�n���r�o��Ԃł̂̉^�q���\�ɂȂ�B����ɂ�
���ẮA�C���x�~�́A�v���h�i����j�ި���َԂ̓~��̂m�n�����ꗬ���̌��ׂ����P�ɏڏq���Ă���̂ŁA�����̂����
�́A�䗗�������������B
�����Z�p���̗p�����ꍇ�ɂ́A�~��̘H�㑖�s�ō��Z�x�̂m�n���̐��ꗬ�����ׂ�e�Ղɉ��P���邱�Ƃ��\�ł�
��B�܂�A�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p���̗p���������h�N���[�U�[�E�v���h�i�g���^�j�̃f�B�[
�[���Ԃ́A�~��̘H�㑖�s�ɂ����Ă��A�m�n���K���l�̃N���[���Ȃm�n���r�o��Ԃł̂̉^�q���\�ɂȂ�B����ɂ�
���ẮA�C���x�~�́A�v���h�i����j�ި���َԂ̓~��̂m�n�����ꗬ���̌��ׂ����P�ɏڏq���Ă���̂ŁA�����̂����
�́A�䗗�������������B
�@�ȏ�̂��Ƃ���A�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j������e�g���b�N���[�J�̌����J���̎p���������
��A���݂̊e�g���b�N���[�J�ɂ������^�g���b�N�́u�R��팸�v��uNO���팸�v�̋Z�p�J���̎��g�݂́A�I�O��ƌ���
�Ă��ߌ��ł͂Ȃ��悤�ȋC�����Ă���B����A�����o�ĂA���̂��Ƃ��ؖ������̂ł͂Ȃ����낤���B�������Ȃ���A
���ɁA�M�҂���Ă��Ă���C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j���^�g���b�N�ɍ̗p�����ꍇ�Ƀg���b�N�̉^�q��
�v���I�ȕs��������Ă��܂��̂ł���A�M�҂͖{�z�[���y�[�W�Ŏ��g���D���D�������̒p�����炵�����Ă��邱
�ƂɂȂ�B
��A���݂̊e�g���b�N���[�J�ɂ������^�g���b�N�́u�R��팸�v��uNO���팸�v�̋Z�p�J���̎��g�݂́A�I�O��ƌ���
�Ă��ߌ��ł͂Ȃ��悤�ȋC�����Ă���B����A�����o�ĂA���̂��Ƃ��ؖ������̂ł͂Ȃ����낤���B�������Ȃ���A
���ɁA�M�҂���Ă��Ă���C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j���^�g���b�N�ɍ̗p�����ꍇ�Ƀg���b�N�̉^�q��
�v���I�ȕs��������Ă��܂��̂ł���A�M�҂͖{�z�[���y�[�W�Ŏ��g���D���D�������̒p�����炵�����Ă��邱
�ƂɂȂ�B
�@���̂��߁A���̃y�[�W�������ɂȂ�ꂽ�������̋C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�ɂ͒v���I�Ȍ�
�ׂ̂��邱�Ƃ��C�t���ꂽ�ꍇ�ɂ́A���̓��e����w�E����������K���ł���B����Ɠ����ɁA�����C���x
�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p�����D�ꂽ�u�R����P�v�Ɓu�m�n���팸�v�̗����������ł���Z
�p���������̏ꍇ�ɂ́A���̓��e��Ƃ��������������������Ǝv���Ă���B���ɁA�C���x�~�G���W���i������
�J2005-54771�j�����D�ꂽ�Z�p�����̒��Ɋ��ɑ��݂��Ă���ꍇ�ɂ́A�M�҂��z�[���y�[�W�Ŏ��g�̖��m���ۏo��
�ɂ��Ȃ���Ƃ�P����̒p���N���Ă��邱�ƂɂȂ邽�B���̏ꍇ�ɂ́A�����A���̃y�[�W������A�Ⴕ���͏�����������
�v������B
�ׂ̂��邱�Ƃ��C�t���ꂽ�ꍇ�ɂ́A���̓��e����w�E����������K���ł���B����Ɠ����ɁA�����C���x
�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p�����D�ꂽ�u�R����P�v�Ɓu�m�n���팸�v�̗����������ł���Z
�p���������̏ꍇ�ɂ́A���̓��e��Ƃ��������������������Ǝv���Ă���B���ɁA�C���x�~�G���W���i������
�J2005-54771�j�����D�ꂽ�Z�p�����̒��Ɋ��ɑ��݂��Ă���ꍇ�ɂ́A�M�҂��z�[���y�[�W�Ŏ��g�̖��m���ۏo��
�ɂ��Ȃ���Ƃ�P����̒p���N���Ă��邱�ƂɂȂ邽�B���̏ꍇ�ɂ́A�����A���̃y�[�W������A�Ⴕ���͏�����������
�v������B
�@�Ō�ɁA��L�{�����Ō�蓙���������܂�����A���[�����ɂĂ��w�E�������܂��B�܂��A�^��_�A������A�䊴�z���A
�ǂ̂悤�Ȏ����ł����\�ł��B�Ջ��l���ĂɃ��[���������肢��������A�o����͈͂őΉ������Ă��������܂��B
�ǂ̂悤�Ȏ����ł����\�ł��B�Ջ��l���ĂɃ��[���������肢��������A�o����͈͂őΉ������Ă��������܂��B

|