�i�^�[�{�R���p�E���h�ɂ���^�f�B�[�[���g���b�N�̏d�ʎԃ��[�h�R��̉��P�́A�P�������ɉ߂��Ȃ��Ɨ\�z�j
�ŏI�X�V���F2011�N9��26��
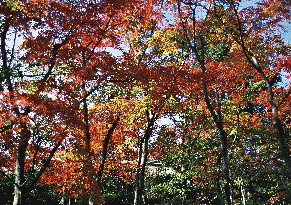 |
�P�@��^�g���b�N�E�g���N�^�̔R�����́A�g���b�N���[�J�̍ł��d�v�ȊJ���ۑ�
�@���݁A���쎩���ԁA�����U�����ԁA�O�H�ӂ����AUD�g���b�N�X����у{���{�̊e���[�J�́A�|�X�g�V�����r�o�K�X�K��
�i2009�N�K���j�ɓK����������^�g���b�N�E�g���N�^��̔����ł���B���̂悤�ɁA��^�g���b�N�E�g���N�^�̑S�Ă̎Ԏ킪
NO����PM�̔r�o�����������������|�X�g�V�����r�o�K�X�K���i2009�N�K���j�ɓK���ł��Ă��邱�Ƃ���A���{�̃g���b�N
���[�J�ł̃f�B�[�[���G���W���̋Z�p�J���̔\�͂ɂ́A������肪�����ƍl���Ă���l�́A���������m��Ȃ��B����
���A�����_�ł́A�e�g���b�N���[�J�́A2015�N�x�d�ʎԔR���ɕs�K���ƂȂ��Ă����^�g���b�N�E�g���N�^�̎Ԏ��
���������Ă���̂����B�����ŁA�e�g���b�N���[�J�ł�2015�N�x�d�ʎԔR���ɕs�K���ȑ�^�g���b�N�E�g���N�^��
�Ԏ�̊����ׂ��݂��Ƃ���A�\�P�Ɏ������ł��邱�Ƃ��������B
�i2009�N�K���j�ɓK����������^�g���b�N�E�g���N�^��̔����ł���B���̂悤�ɁA��^�g���b�N�E�g���N�^�̑S�Ă̎Ԏ킪
NO����PM�̔r�o�����������������|�X�g�V�����r�o�K�X�K���i2009�N�K���j�ɓK���ł��Ă��邱�Ƃ���A���{�̃g���b�N
���[�J�ł̃f�B�[�[���G���W���̋Z�p�J���̔\�͂ɂ́A������肪�����ƍl���Ă���l�́A���������m��Ȃ��B����
���A�����_�ł́A�e�g���b�N���[�J�́A2015�N�x�d�ʎԔR���ɕs�K���ƂȂ��Ă����^�g���b�N�E�g���N�^�̎Ԏ��
���������Ă���̂����B�����ŁA�e�g���b�N���[�J�ł�2015�N�x�d�ʎԔR���ɕs�K���ȑ�^�g���b�N�E�g���N�^��
�Ԏ�̊����ׂ��݂��Ƃ���A�\�P�Ɏ������ł��邱�Ƃ��������B
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
8e0ef07935a1�j |
| |
|
|
| |
|
|
�@���̕\�P������Ɩ��炩�Ȃ悤�ɁA�����U�����Ԃ̑�^�g���b�N�E�g���N�^�̖w�ǂ̎Ԏ킪2015�N�x�d�ʎԔR����
�K�����Ă��邪�A����̓G���W���̏��r�C�ʉ��ɂ��_�E���T�C�W���O�̌��ʂƍl������B��^�g���b�N�E�g���N�^�̃G
���W�����_�E���T�C�W���O�����ꍇ�ɂ́A��^�g���b�N�E�g���N�^�̒�R����\�ɂȂ邪�A�ԗ��̑��s���\������
���ɂȂ邽�߁A�S�Ẵ��[�U�Ɋ��}������^�g���b�N�ł͖����ƍl������B�܂��A���쎩���ԁAUD�g���b�N�X�����
�O�H�ӂ����̑�^�g���b�N�E�g���N�^�ɂ����ẮA�|�X�V�����r�o�K�X�K���i2009�N�K���j�ɓK�����������̎Ԏ�̑�^�g
���b�N�E�g���N�^��2015�N�x�d�ʎԔR���ɕs�K���ƂȂ��Ă���̂�����ł���B
�K�����Ă��邪�A����̓G���W���̏��r�C�ʉ��ɂ��_�E���T�C�W���O�̌��ʂƍl������B��^�g���b�N�E�g���N�^�̃G
���W�����_�E���T�C�W���O�����ꍇ�ɂ́A��^�g���b�N�E�g���N�^�̒�R����\�ɂȂ邪�A�ԗ��̑��s���\������
���ɂȂ邽�߁A�S�Ẵ��[�U�Ɋ��}������^�g���b�N�ł͖����ƍl������B�܂��A���쎩���ԁAUD�g���b�N�X�����
�O�H�ӂ����̑�^�g���b�N�E�g���N�^�ɂ����ẮA�|�X�V�����r�o�K�X�K���i2009�N�K���j�ɓK�����������̎Ԏ�̑�^�g
���b�N�E�g���N�^��2015�N�x�d�ʎԔR���ɕs�K���ƂȂ��Ă���̂�����ł���B
�@���̂��Ƃ���A��^�g���b�N���[�J�ɂ����ẮA��^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W���̏d�ʎԃ��[�h�R��l���T�p�[�Z���g
���x�̉��P���\�ɂ���Z�p�𑁋}�ɊJ�����A�e�Ђ̑�^�g���b�N�E�g���N�^�̑S�Ԏ��2015�N�x�d�ʎԔR����
�K���ł���悤�ɂ��邱�Ƃ��i�ق̉ۑ�ł��邱�Ƃ͖��炩�ł���B�����āA�����U�����Ԃɂ����Ă��A���s���\�̍���
13���b�g�����̃G���W���𓋍ڂ����}�j���A���~�b�V�������ڂ̑�^�g���b�N�E�g���N�^��2015�N�x�d�ʎԔR���ɓK��
�ł���Z�p���J���ł���A�����U�����Ԃ����s���\�̍�����r�C�ʃG���W���𓋍ڂ�����^�g���b�N�E�g���N�^�����i
�ɉ����邱�Ƃ��\�ƂȂ�̂ł���B
���x�̉��P���\�ɂ���Z�p�𑁋}�ɊJ�����A�e�Ђ̑�^�g���b�N�E�g���N�^�̑S�Ԏ��2015�N�x�d�ʎԔR����
�K���ł���悤�ɂ��邱�Ƃ��i�ق̉ۑ�ł��邱�Ƃ͖��炩�ł���B�����āA�����U�����Ԃɂ����Ă��A���s���\�̍���
13���b�g�����̃G���W���𓋍ڂ����}�j���A���~�b�V�������ڂ̑�^�g���b�N�E�g���N�^��2015�N�x�d�ʎԔR���ɓK��
�ł���Z�p���J���ł���A�����U�����Ԃ����s���\�̍�����r�C�ʃG���W���𓋍ڂ�����^�g���b�N�E�g���N�^�����i
�ɉ����邱�Ƃ��\�ƂȂ�̂ł���B
�@���݂̃|�X�g�V�����r�o�K�X�K���i2009�N�K���j�ɓK��������^�g���b�N�E�g���N�^�i��^�_���v���܂ށj�ɂ����āA�P�O
���b�g���G���W���𓋍ڂ��������U�����Ԃ̑�^�g���b�N�E�g���N�^�́A�R��\�ɗD��Ă��邪���i�����̓��͐��\��
��肪����ƍl������B���������āA�����U�����Ԃł��A�P�R���b�g���G���W�����̃G���W���ɂ����Ă��Q�O�P�T�N�x�d��
�ԔR���ɓK���ł���Z�p���J���ł���A���͐��\�̗D�ꂽ��^�g���b�N�E�g���N�^���s�̂ł��A�g���b�N���[�U��
�������Ă��炤�����ł���ł���B�ܘ_�A�P�R���b�g���G���W���𓋍ڂ�������ƎO�H�̑�^�g���b�N�E�g���N�^�́A2015�N
�x�d�ʎԔR���ɑS�Ԏ��K���ł���A�S�Ẵg���b�N���[�U�̗v���������Ƃ��ł���̂��B����A�����U�A
�t�c����юO�H�ӂ����̉���̃g���b�N���[�J�̊J������ɂ����Ă��A�������������B��̕��@�����}�ɑ�^�g���b
�N�E�g���N�^�̏d�ʎԃ��[�h�R��l���T�p�[�Z���g���x�̉��P���\�ɂ���V���ȋZ�p�𑁊��Ɏ��p�����邱�Ƃł��邱
�Ƃ́A�N�����F�߂�Ƃ��낾�낤�B���̂��߂Ɋe�g���b�N���[�J�̃G���W���J������̐l�B�́A�K���ɓw�͂��Ă������
�Ǝv�����A�s�K�Ȃ��ƂɁA�����ɏd�ʎԃ��[�h�R��l���T�p�[�Z���g���x�̉��P�������ł���f�B�[�[���G���W���̔R��
���P�̋Z�p���J���ł��Ă��Ȃ��悤���B
���b�g���G���W���𓋍ڂ��������U�����Ԃ̑�^�g���b�N�E�g���N�^�́A�R��\�ɗD��Ă��邪���i�����̓��͐��\��
��肪����ƍl������B���������āA�����U�����Ԃł��A�P�R���b�g���G���W�����̃G���W���ɂ����Ă��Q�O�P�T�N�x�d��
�ԔR���ɓK���ł���Z�p���J���ł���A���͐��\�̗D�ꂽ��^�g���b�N�E�g���N�^���s�̂ł��A�g���b�N���[�U��
�������Ă��炤�����ł���ł���B�ܘ_�A�P�R���b�g���G���W���𓋍ڂ�������ƎO�H�̑�^�g���b�N�E�g���N�^�́A2015�N
�x�d�ʎԔR���ɑS�Ԏ��K���ł���A�S�Ẵg���b�N���[�U�̗v���������Ƃ��ł���̂��B����A�����U�A
�t�c����юO�H�ӂ����̉���̃g���b�N���[�J�̊J������ɂ����Ă��A�������������B��̕��@�����}�ɑ�^�g���b
�N�E�g���N�^�̏d�ʎԃ��[�h�R��l���T�p�[�Z���g���x�̉��P���\�ɂ���V���ȋZ�p�𑁊��Ɏ��p�����邱�Ƃł��邱
�Ƃ́A�N�����F�߂�Ƃ��낾�낤�B���̂��߂Ɋe�g���b�N���[�J�̃G���W���J������̐l�B�́A�K���ɓw�͂��Ă������
�Ǝv�����A�s�K�Ȃ��ƂɁA�����ɏd�ʎԃ��[�h�R��l���T�p�[�Z���g���x�̉��P�������ł���f�B�[�[���G���W���̔R��
���P�̋Z�p���J���ł��Ă��Ȃ��悤���B
�Q�@NEDO�́u�����x�R�Đ���G���W�V�X�e���̌����J���v�ł́A�R����̑厸�s
�@�f�B�[�[���G���W���̔R����P��NO���팸��}�邽�߁A�]�����瑽���ʂŐ��͓I�Ɍ����J�������{����Ă���B��
�N�A���̒��ł����ɗL���Ȍ����v���W�F�N�g�́A�V�G�l���M�[�E�Y�ƋZ�p�����J���@�\�iNEDO)�̊v�V�I��������
�Q�ԑ����Z�p�J���i�N���[���f�B�[�[���v���W�F�N�g�A2004�`2009�N�j�ł���B���̑�^�g���b�N�̔R����P��NO���팸
�̌����́A8��6��5�S���~�̗\�Z�Ŏ��{���ꂽ�u�����x�R�Đ���G���W�V�X�e���̌����J���v�̑�^�v���W�F�N�g�ł�
��B���̌����v���W�F�N�g�ł́A���̖��̂̒ʂ�A�f�B�[�[���G���W���̔R����P��NO���팸�ɑ傫�Ȍ��ʂ������
�����̊w�ҁE���Ƃ����҂��Ă���V�Z�p���̗p���ꂽ�̂ł���B�����āA���́u�����x�R�Đ���G���W�V�X�e���̌�
���J���v�̌����v���W�F�N�g�ł̖ڕW�́A�\�Q�Ɏ������ʂ�A�uNO�� = 0.2g/kWh�v����сu2015�N�x�d���ҔR������
��10���̔R�����v���ݒ肳�ꂽ�̂ł���B
�N�A���̒��ł����ɗL���Ȍ����v���W�F�N�g�́A�V�G�l���M�[�E�Y�ƋZ�p�����J���@�\�iNEDO)�̊v�V�I��������
�Q�ԑ����Z�p�J���i�N���[���f�B�[�[���v���W�F�N�g�A2004�`2009�N�j�ł���B���̑�^�g���b�N�̔R����P��NO���팸
�̌����́A8��6��5�S���~�̗\�Z�Ŏ��{���ꂽ�u�����x�R�Đ���G���W�V�X�e���̌����J���v�̑�^�v���W�F�N�g�ł�
��B���̌����v���W�F�N�g�ł́A���̖��̂̒ʂ�A�f�B�[�[���G���W���̔R����P��NO���팸�ɑ傫�Ȍ��ʂ������
�����̊w�ҁE���Ƃ����҂��Ă���V�Z�p���̗p���ꂽ�̂ł���B�����āA���́u�����x�R�Đ���G���W�V�X�e���̌�
���J���v�̌����v���W�F�N�g�ł̖ڕW�́A�\�Q�Ɏ������ʂ�A�uNO�� = 0.2g/kWh�v����сu2015�N�x�d���ҔR������
��10���̔R�����v���ݒ肳�ꂽ�̂ł���B
| |
|
�E�R�i�ߋ��V�X�e��
�E300MP���̒������R������
�E�J�����X�V�X�e��
�EPCI�R��
�iPremixed. Compression Ignition combustion�j
�EDPF
�EDeNO���G�}�i�A�fSCR�G�}�j
|
�ENO�� = 0.2g/kWh�̖ڕW�́A�B��
�@(NO�����|�X�g�V������1/3�ɍ팸�j
�E�ڕW��10���̔R����P�ɑ��A���ʂ�2���̔R���
�@�i2015�N�x�d���ҔR������̔R�����̊����j
|
�@�@�܂��A���̌����v���W�F�N�g�ɂ�����G���W���V�X�e���̊T�v�Ƒ_���Ƃ���Z�p�I�ȉ��P�̒���_��}�P�Ɏ������B
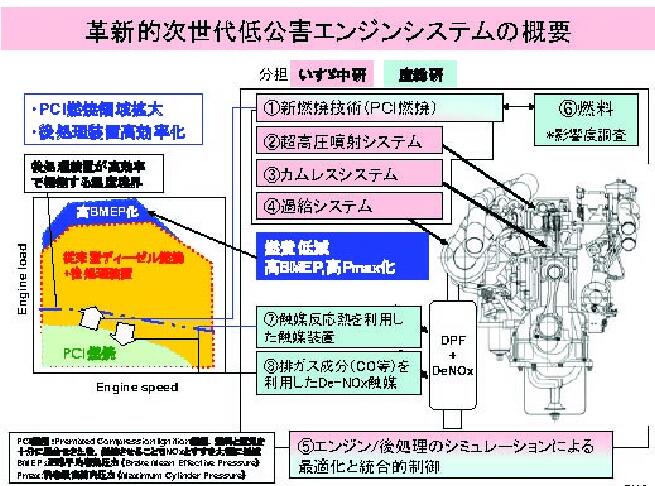
�@���̂悤�ɁA�V�G�l���M�[�E�Y�ƋZ�p�����J���@�\�iNEDO)�̊v�V�I���������Q�ԑ����Z�p�J���́u�����x�R��
����G���W�V�X�e���̌����J���v�̑�^�v���W�F�N�g�́ANO�����|�X�g�V������1/3�ጸ���A�R��������2015�N
�x�d���ҔR������10�����P���鍂���ڕW���������悤�Ƃ�����̂ł������B�ܘ_�A���̂悤�ɒN���������悤�ȍ�
���ڕW���f����ꂽ�̂́A���̌����v���W�F�N�g���G���W���̃R�X�g������d�ʑ�����S���l�����Ȃ��ŏ����̎��p��
��������ł̏����ɋZ�p�̉\����Njy���錤���J���ł��������߂ƍl������B���̌����J�����J�n���ꂽ
2004�N�����A���̌����̊W�����w�ҁE���Ƃ�NO���팸�ƔR�����Ɋ�^����ƍl����ꂽ�S�Ă̋Z�p�i�R�i�ߋ�
�V�X�e���A300MP���̒������R�����ˁA�J�����X�V�X�e���APCI�R�āADPF�ADeNO���G�}�j���̗p���ꂽ���̂ƍl�����
��B
����G���W�V�X�e���̌����J���v�̑�^�v���W�F�N�g�́ANO�����|�X�g�V������1/3�ጸ���A�R��������2015�N
�x�d���ҔR������10�����P���鍂���ڕW���������悤�Ƃ�����̂ł������B�ܘ_�A���̂悤�ɒN���������悤�ȍ�
���ڕW���f����ꂽ�̂́A���̌����v���W�F�N�g���G���W���̃R�X�g������d�ʑ�����S���l�����Ȃ��ŏ����̎��p��
��������ł̏����ɋZ�p�̉\����Njy���錤���J���ł��������߂ƍl������B���̌����J�����J�n���ꂽ
2004�N�����A���̌����̊W�����w�ҁE���Ƃ�NO���팸�ƔR�����Ɋ�^����ƍl����ꂽ�S�Ă̋Z�p�i�R�i�ߋ�
�V�X�e���A300MP���̒������R�����ˁA�J�����X�V�X�e���APCI�R�āADPF�ADeNO���G�}�j���̗p���ꂽ���̂ƍl�����
��B
�@�Ƃ��낪�A�W���~�ȏ�̖c��ȗ\�Z�𒍂�����Ŗ蕨����Ŏ��{���ꂽ�u�����x�R�Đ���G���W�V�X�e���̌����J
���v�̌����J���́A�̐S�̔R�����P�ɂ��Ă͎S�邽�錋�ʂŏI����Ă��܂����悤���B���̏؋��Ƃ��ẮA����܂�
�̑�����NEDO�̌����J���̗�ƈقȂ�A���̌����J���ł͓����̖ڕW�ƍŏI���ʂƂ̔R�����P���]��ɂ���������
���Ă��邩��ł���B�����āA���̃v���W�F�N�g�ł�2015�N�x�d�ʎԔR�������P�O���̑啝�ȔR�����P��ڕW�Ɍf
���Ȃ���A�ŏI���ʂł́A�������Ƃ�2015�N�x�d�ʎԔR���ɑ��ĂQ�����̔R������������Ă��܂��Ă���̂�
��B
���v�̌����J���́A�̐S�̔R�����P�ɂ��Ă͎S�邽�錋�ʂŏI����Ă��܂����悤���B���̏؋��Ƃ��ẮA����܂�
�̑�����NEDO�̌����J���̗�ƈقȂ�A���̌����J���ł͓����̖ڕW�ƍŏI���ʂƂ̔R�����P���]��ɂ���������
���Ă��邩��ł���B�����āA���̃v���W�F�N�g�ł�2015�N�x�d�ʎԔR�������P�O���̑啝�ȔR�����P��ڕW�Ɍf
���Ȃ���A�ŏI���ʂł́A�������Ƃ�2015�N�x�d�ʎԔR���ɑ��ĂQ�����̔R������������Ă��܂��Ă���̂�
��B
�@����NEDO�̌����J���̎��ۂ̍ŏI���ʂł́A�}�Q�Ɏ������悤�ɁANOx�͖ڕW��B���ł������A���݂̏ȃG
�l���M�[�E�Ȏ����E��CO2�̎���ɋ��߂��Ă���̐S�v�̔R�����P�͖ڕW��10���팸�ɂ͑S���y���A�}
�炸��2015�N�x�d�ʎԔR���ɑ��ĂQ���̈����ƂȂ��Ă��܂����̂ł���B���s�̑����̑�^�g���b�N��2015
�N�x�d�ʎԔR���ɓK�����Ă��邱�Ƃ���A�u�����x�R�Đ���G���W�V�X�e���̌����J���v�ɂ�����2015�N�x�d��
�ԔR���ɑ��ĂQ���̔R����́A���̌����J���������Ȃ܂ł̑厸�s�ɏI����Ă��܂����Ɖ]����̂ł͂Ȃ�
���낤���B
�l���M�[�E�Ȏ����E��CO2�̎���ɋ��߂��Ă���̐S�v�̔R�����P�͖ڕW��10���팸�ɂ͑S���y���A�}
�炸��2015�N�x�d�ʎԔR���ɑ��ĂQ���̈����ƂȂ��Ă��܂����̂ł���B���s�̑����̑�^�g���b�N��2015
�N�x�d�ʎԔR���ɓK�����Ă��邱�Ƃ���A�u�����x�R�Đ���G���W�V�X�e���̌����J���v�ɂ�����2015�N�x�d��
�ԔR���ɑ��ĂQ���̔R����́A���̌����J���������Ȃ܂ł̑厸�s�ɏI����Ă��܂����Ɖ]����̂ł͂Ȃ�
���낤���B
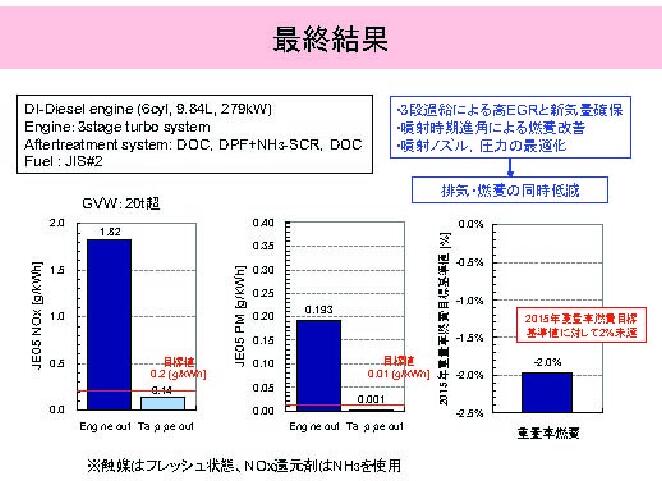
�@���̐}�Q�Ɏ������悤�ɁANEDO�́u�����x�R�Đ���G���W�V�X�e���̌����J���v�ł̖��́ANOx��PM�͍팸�ł���
���A�R���2015�N�x�d�ʎԔR���Q���̈����ƂȂ��Ă��܂����Ƃ̂��Ƃł���B���́u�����x�R�Đ���G���W�V�X�e
���̌����J���v�ɂ�����PCI�R�Ă��܂߂��R�ĉ��P�ł̔R����オ�s�����ɏI������������ʂ��͂�����ƌ�����
������ƁA�f�B�[�[���R�Ẳ��P�ɂ���ĔR�������������邱�Ƃ͋ɂ߂ē�����Ƃ�w�ǂ̃f�B�[�[���W�̊w
�ҁE���Ƃ����������̂ł͂Ȃ����낤���B�����āA����NEDO�̃f�B�[�[���R��̌���Ɋւ��Ă̔ߎS�Ȏ������ʂ�
�����w�ҁE���Ƃ͋����Ռ����A�傢�ɗ��_���ꂽ�l�������������̂Ɛ��@�����B���݂ɁA�����ԋZ�p��s
�́u�����ԋZ�p�v��Vol.64�ANo.�P�A2010�i2010�N1���P�����s�j�̔ѓc�P�� �c���勳���@���R�����́u�f�B�[�[���G���W
�����̂P�O�N�v�ɂ́A�f�B�[�[���G���W����CO�Q�팸�i���R��팸�j���u�傫�Ȓ���ۑ�v�ƒf�肵�A�R�ĉ��P�ɂ��f�B
�[�[���G���W���̔R��팸���u�Z�p�I�ɔ����ǂ���̏v�Ƃ̎�|���L�ڂ���Ă���B����́A����NEDO�́u����
�x�R�Đ���G���W�V�X�e���̌����J���v�i2004�`2009�N�j�ł̔R�����Ɏ��s���������܂��Ă̋L�q�ł͂�
�����Ƃ��l������B
���A�R���2015�N�x�d�ʎԔR���Q���̈����ƂȂ��Ă��܂����Ƃ̂��Ƃł���B���́u�����x�R�Đ���G���W�V�X�e
���̌����J���v�ɂ�����PCI�R�Ă��܂߂��R�ĉ��P�ł̔R����オ�s�����ɏI������������ʂ��͂�����ƌ�����
������ƁA�f�B�[�[���R�Ẳ��P�ɂ���ĔR�������������邱�Ƃ͋ɂ߂ē�����Ƃ�w�ǂ̃f�B�[�[���W�̊w
�ҁE���Ƃ����������̂ł͂Ȃ����낤���B�����āA����NEDO�̃f�B�[�[���R��̌���Ɋւ��Ă̔ߎS�Ȏ������ʂ�
�����w�ҁE���Ƃ͋����Ռ����A�傢�ɗ��_���ꂽ�l�������������̂Ɛ��@�����B���݂ɁA�����ԋZ�p��s
�́u�����ԋZ�p�v��Vol.64�ANo.�P�A2010�i2010�N1���P�����s�j�̔ѓc�P�� �c���勳���@���R�����́u�f�B�[�[���G���W
�����̂P�O�N�v�ɂ́A�f�B�[�[���G���W����CO�Q�팸�i���R��팸�j���u�傫�Ȓ���ۑ�v�ƒf�肵�A�R�ĉ��P�ɂ��f�B
�[�[���G���W���̔R��팸���u�Z�p�I�ɔ����ǂ���̏v�Ƃ̎�|���L�ڂ���Ă���B����́A����NEDO�́u����
�x�R�Đ���G���W�V�X�e���̌����J���v�i2004�`2009�N�j�ł̔R�����Ɏ��s���������܂��Ă̋L�q�ł͂�
�����Ƃ��l������B
�@�Q�@�^�[�{�R���p�E���h�Ɋւ���Z�p�Ɗw�ҁE���Ƃ̃f�B�[�[���R�����̊���
�@�O�q�̂悤�ɁA�A�����̊w�ҁE���Ƃ�NO���팸�ƔR�����Ɋ�^�ł���Ɗ��҂���Ă���S�Ă̋Z�p�i�R�i�ߋ��V�X
�e���A300MP���̒������R�����ˁA�J�����X�V�X�e���APCI�R�āADPF�ADeNO���G�}�j�荞��NEDO�́u�����x�R
�Đ���G���W�V�X�e���̌����J���v�̍ŏI�ł́A2015�N�x�d�ʎԔR������Q�������������R��̌�������
�����\���ꂽ�̂ł���B���̌����́A����܂��킪���̃f�B�[�[���G���W���W�̎w���I����ɂ����w�ҁE���
�Ƃ����M���X�Ɏ咣����Ă����u��^�g���b�N�ɂ����鍡��̔R�����̋Z�p�̒E��āv���w�NJԈႢ�ł�������
�Ƃ��߂ɂ������Ă��܂����̂ł���B
�e���A300MP���̒������R�����ˁA�J�����X�V�X�e���APCI�R�āADPF�ADeNO���G�}�j�荞��NEDO�́u�����x�R
�Đ���G���W�V�X�e���̌����J���v�̍ŏI�ł́A2015�N�x�d�ʎԔR������Q�������������R��̌�������
�����\���ꂽ�̂ł���B���̌����́A����܂��킪���̃f�B�[�[���G���W���W�̎w���I����ɂ����w�ҁE���
�Ƃ����M���X�Ɏ咣����Ă����u��^�g���b�N�ɂ����鍡��̔R�����̋Z�p�̒E��āv���w�NJԈႢ�ł�������
�Ƃ��߂ɂ������Ă��܂����̂ł���B
�@
�@����NEDO�̌����́A�킪�����f�B�[�[���G���W���W�̎w���I����ɂ����w�ҁE���Ƃ̎咣��M���ď���
�̑�^�g���b�N�̔R������M���ċ^��Ȃ����������̃g���b�N���[�U�̐l�B�����]���������Ƃ͖ܘ_�ł���B�����āA
�w�ҁE���Ƃ̎咣�����̂܂��肵�āu���i�ߋ��V�X�e���A�������R�����ˁAPCI�R�āi��HCCI�R�āj�ɂ����
�f�B�[�[���R��̌��オ�\�v�Ƃ̎咣�����ł��������Ƃ���A���̊w�ҁE���Ƃ̐K�n�ɏ���Ă��̎咣���Г���
�������Ă����g���b�N���[�J�̃f�B�[�[���G���W���Z�p�҂������ɒ�q���O���ꂽ�Ɋׂ������ƍl������B�g���b�N
���[�J�̃f�B�[�[���G���W���Z�p�҂ɂƂ��Ă͐V���̂̏Ռ������̂ł͂Ȃ����낤���B�Ƃ��낪�A�킪�����f�B
�[�[���G���W���W�̎w���I����ɂ����w�ҁE���Ƃ��܂ޑ����̃f�B�[�[���G���W���Z�p�҂́A����܂ł̃f�B�[�[
���G���W���̔R����P�̌�����咣�E�����ɂ��Ă̎Ӎ߂┽�Ȃ�����܂ŕ��������Ƃ��Ȃ��B���̂��Ƃ��画�f����
�ƁA�f�B�[�[���G���W���W���w�ҁE���ƁE�Z�p�҂́A�u�ԐM���A�F��Ȃœn��@�|���Ȃ��v�̃u���b�N���[���A����
�H���Ă���l�B�̂悤�Ɍ�����̂ł���B
�̑�^�g���b�N�̔R������M���ċ^��Ȃ����������̃g���b�N���[�U�̐l�B�����]���������Ƃ͖ܘ_�ł���B�����āA
�w�ҁE���Ƃ̎咣�����̂܂��肵�āu���i�ߋ��V�X�e���A�������R�����ˁAPCI�R�āi��HCCI�R�āj�ɂ����
�f�B�[�[���R��̌��オ�\�v�Ƃ̎咣�����ł��������Ƃ���A���̊w�ҁE���Ƃ̐K�n�ɏ���Ă��̎咣���Г���
�������Ă����g���b�N���[�J�̃f�B�[�[���G���W���Z�p�҂������ɒ�q���O���ꂽ�Ɋׂ������ƍl������B�g���b�N
���[�J�̃f�B�[�[���G���W���Z�p�҂ɂƂ��Ă͐V���̂̏Ռ������̂ł͂Ȃ����낤���B�Ƃ��낪�A�킪�����f�B
�[�[���G���W���W�̎w���I����ɂ����w�ҁE���Ƃ��܂ޑ����̃f�B�[�[���G���W���Z�p�҂́A����܂ł̃f�B�[�[
���G���W���̔R����P�̌�����咣�E�����ɂ��Ă̎Ӎ߂┽�Ȃ�����܂ŕ��������Ƃ��Ȃ��B���̂��Ƃ��画�f����
�ƁA�f�B�[�[���G���W���W���w�ҁE���ƁE�Z�p�҂́A�u�ԐM���A�F��Ȃœn��@�|���Ȃ��v�̃u���b�N���[���A����
�H���Ă���l�B�̂悤�Ɍ�����̂ł���B
�@���āA��k�̘b�͂��ꂭ�炢�ɂ��āA����NEDO�́u�����x�R�Đ���G���W�V�X�e���̌����J���v�ł̔R����P�̎��s
�����\���ꂽ2009�N�������̃f�B�[�[���G���W���W�̏����I��NO���팸�ƔR�����̋Z�p�J���̕��j�⌤���v
���W�F�N�g�ɋL�ڂ��ꂽ�Z�p������ƁA����܂ő����̊w�ҁE���Ƃɂ���Đ�������Ă�����^�g���b�N�p�f�B�[�[���G
���W���̔R�����̒�ċZ�p�ł���u���i�ߋ��V�X�e���v�A�u�������R�����ˁv�A�uPCI�R�āi��HCCI�R�āj�v�̋Z�p��
�O�ɁA�}篁A�V���Ƀ^�[�{�R���p�E���h�̋Z�p��lj�����n�߂��悤���B�P���ɍl����^�[�{�R���p�E���h���r�C�K
�X�̃G�l���M�[���G���W���o�͂ɉł���@�\�����邽�߁A���_�I�ɂ͑�^�g���b�N�̔R����P�̋@�\�����邱��
�͊m���ł���B�������A���̃^�[�{�R���p�E���h�̋Z�p�������I�ɑ�^�g���b�N�̏d�ʎԃ��[�h�R���啝�ɉ��P�ł�
��Ƃ͕M�҂ɂ͂ƂĂ��v���Ȃ��̂ł���B���̍����́A�^�[�{�R���p�E���h�ɂ��f�B�[�[���R�����ɂ��Č�����
�����܂Ƃ߂��̌������܂Ƃ߂��O�H�d�H�̘_���̓��e������Ζ��炩�ł͂Ȃ����ƍl���Ă���B
�����\���ꂽ2009�N�������̃f�B�[�[���G���W���W�̏����I��NO���팸�ƔR�����̋Z�p�J���̕��j�⌤���v
���W�F�N�g�ɋL�ڂ��ꂽ�Z�p������ƁA����܂ő����̊w�ҁE���Ƃɂ���Đ�������Ă�����^�g���b�N�p�f�B�[�[���G
���W���̔R�����̒�ċZ�p�ł���u���i�ߋ��V�X�e���v�A�u�������R�����ˁv�A�uPCI�R�āi��HCCI�R�āj�v�̋Z�p��
�O�ɁA�}篁A�V���Ƀ^�[�{�R���p�E���h�̋Z�p��lj�����n�߂��悤���B�P���ɍl����^�[�{�R���p�E���h���r�C�K
�X�̃G�l���M�[���G���W���o�͂ɉł���@�\�����邽�߁A���_�I�ɂ͑�^�g���b�N�̔R����P�̋@�\�����邱��
�͊m���ł���B�������A���̃^�[�{�R���p�E���h�̋Z�p�������I�ɑ�^�g���b�N�̏d�ʎԃ��[�h�R���啝�ɉ��P�ł�
��Ƃ͕M�҂ɂ͂ƂĂ��v���Ȃ��̂ł���B���̍����́A�^�[�{�R���p�E���h�ɂ��f�B�[�[���R�����ɂ��Č�����
�����܂Ƃ߂��̌������܂Ƃ߂��O�H�d�H�̘_���̓��e������Ζ��炩�ł͂Ȃ����ƍl���Ă���B
�R�@�O�H�d�H�̘_��������ƁA��^�g���b�N�ɂ�����^�[�{�R���p�E���h�ɂ��R�����͍���
�R�|�P�@�^�[�{�R���p�E���h�Ɋւ���O�H�d�H�̘_���i���a60�N7���j
�@�O�H�d�H�� �y���z�O�� ���S���́A���{�@��w��_���W�iB�ҁj51��467���i��60-7�j�ɘ_���u�r�C�^�[�{�R���p�E��
�h�G���W���̃G�l���M��������v�\����Ă���B���̘_���̊T�v�́A�ȉ��̕\�R�Ɏ������ʂ�ł���B
�h�G���W���̃G�l���M��������v�\����Ă���B���̘_���̊T�v�́A�ȉ��̕\�R�Ɏ������ʂ�ł���B
| |
|
| |
_no=&ppv_type=0&lang_sw=&no=1316760112&cp=�j |
| |
(1) �^�[�{�R���p�E���h�G���W���̍\���}
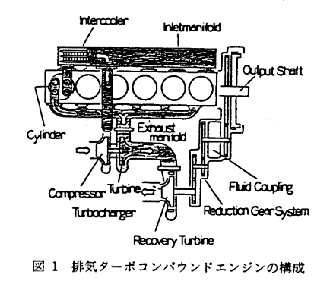 (2) �x�[�X�G���W���ƃ^�[�{�R���p�E���h�G���W���̎�v�����̔�r
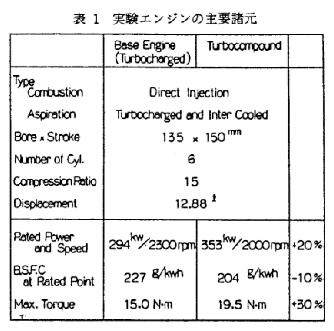 (3) �x�[�X�G���W���ƃ^�[�{�R���p�E���h�G���W���̓��R��Ȑ��̔�r
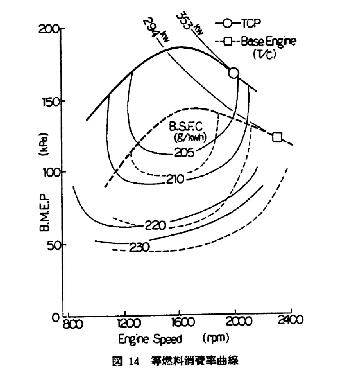 (4) ��L�̐}14�ɂ��Ă̖{�_���̋L�q���e
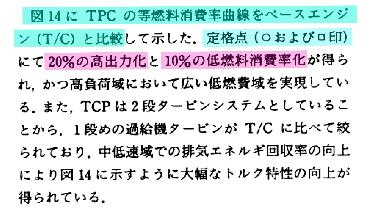 �@�y���ړ_ �y�� �R�����g�z
�@�{�_���̐}�P�S�Ɏ����ꂽ�x�[�X�G���W���ƃ^�[�{�R���p�E���h�G���W���̓��R��Ȑ��̔�r�}�ł́A�x�[
�X�G���W���̒�i�_��2300rpm�ł���̂ɑ��A�^�[�{�R���p�E���h�G���W���̒�i�_��2000rpm�ő傫����
�Ȃ��Ă���d�l��ݒ肵�A2300rpm�̃x�[�X�G���W����i�_�̔R���2000rpm�̃^�[�{�R���p�E���h�G���W��
��i�_���r���āA�u�^�[�{�R���p�E���h�G���W���̔R��x�[�X�G���W������10���̔R����P�v�ł����|
���q�ׂ��Ă���B�g���b�N�p�G���W���Ƃ��̊ϓ_���炷��A��{�d�l�̈قȂ�R���r�̌��ʂ����̂܂�
�g���b�N�p�G���W���̐��\��r�̋Z�p���Ƃ��Ĉ��p���邱�Ƃ͌��ƍl����B
�@���������A��^�g���b�N�ɂ������i�o�͂̃G���W����]���x�́A���̃g���b�N���K�v�Ƃ��Ă���ō����x��
�m�ۂ��邽�߂ɁA���̃g���b�N�ɓ��ڂ��Ă���g�����X�~�b�V�����M�A���f�t�@�����V�����M�A��Ō��܂����
�ł���B���������āA�{���A�g���b�N�p�G���W���Ƃ��ă^�[�{�R���p�E���h�G���W���ƃx�[�X�G���W������
�R��Ȃ�o�͐��\��P���ɔ�r����ꍇ�ɂ́A�x�[�X�G���W���ƃ^�[�{�R���p�E���h�G���W���̒�i
�_�̃G���W����]���x�i���ō��o�͎��̃G���W����]���x�j�͓���Ƃ��ׂ��ł����B
�@���̂��߁A�^�[�{�R���p�E���h���^�g���b�N�p�G���W���ɍ̗p�����ꍇ�̔R����P�̕]�����s���ꍇ�ɂ́A
�^�[�{�R���p�E���h�G���W���ƃx�[�X�G���W������i�_����]���x�i���ō��o�͂̃G���W����]���x�j��
2000rpm�ɑ����A�x�[�X�G���W���̒�i�_�i��294kW/2000rpm�j�ƃ^�[�{�R���p�E���h�G���W���̒�i�_�i��
353kW/2000rpm�j�Ƃ̓���̃G���W����]���x�ł̔R��̔�r�E�]�����s���ׂ��ł���B�Ȃ��Ȃ�A��i
�_�̃G���W����]���x�̃G���W���ł́A�t���N�V���������ƃ|���s�����O�����̑����ɂ��A�R��m���Ɉ�
�����邽�߂��B
�@���������āA�����O�H�d�H���@��w��_���ɋL�ڂ���Ă���悤�ȁA�u�x�[�X�G���W���̒�i�_
�i294kW/2300rpm�j�̔R��ƃ^�[�{�R���p�E���h�G���W���̒�i�_�i353kW/2000rpm�j�̔R��Ƃ�
��r���A�^�[�{�R���p�E���h�G���W���̔R��x�[�X�G���W���̔R�����10���̉��P���\�v�Ƃ�
�_���̋L�q���e���A���̂܂����ԗp�f�B�[�[���G���W���Ƀ^�[�{�R���p�E���h���̗p�����ꍇ�̔R
����P�̗\���Ƃ��Ĉ��p���邱�Ƃ͌���ƍl����B
|
�R�|�Q�@�O�H�d�H�_���̓��R��Ȑ�����\�z�����^�[�{�R���p�E���h�ɂ��R�����̊���
�O�H�d�H�� �y���z�O�� ���S�������������{�@��w��_���W�iB�ҁj51��467���i��60-7�j�Ɍf�ڂ́u�r�C�^�[�{�R���p
�E���h�G���W���̃G�l���M��������v���}�P�S�Ɏ����ꂽ�x�[�X�G���W���ƃ^�[�{�R���p�E���h�G���W���̓��R��Ȑ���
��r�}�ɂ́A�u2300rpm��i��]���x�̃x�[�X�G���W���̒�i�_294kW/2300rpm�v�Ɓu2000rpm��i��]���x�̃^�[�{
�R���p�E���h�G���W���̒�i�_353kW/2000rpm�v���L�ڂ���Ă���B����ɐV���ɒ�i��]���x���^�[�{�R���p�E���h
�G���W���Ɠ���Ƃ����u���d�l��2000rpm�̃x�[�X�G���W���̒�i�_294kW/2000rpm�v��NjL�����x�[�X�G���W���ƃ^�[
�{�R���p�E���h�G���W���̓��R��Ȑ��̔�r�}���A�ȉ��̐}�R�Ɏ������B
�E���h�G���W���̃G�l���M��������v���}�P�S�Ɏ����ꂽ�x�[�X�G���W���ƃ^�[�{�R���p�E���h�G���W���̓��R��Ȑ���
��r�}�ɂ́A�u2300rpm��i��]���x�̃x�[�X�G���W���̒�i�_294kW/2300rpm�v�Ɓu2000rpm��i��]���x�̃^�[�{
�R���p�E���h�G���W���̒�i�_353kW/2000rpm�v���L�ڂ���Ă���B����ɐV���ɒ�i��]���x���^�[�{�R���p�E���h
�G���W���Ɠ���Ƃ����u���d�l��2000rpm�̃x�[�X�G���W���̒�i�_294kW/2000rpm�v��NjL�����x�[�X�G���W���ƃ^�[
�{�R���p�E���h�G���W���̓��R��Ȑ��̔�r�}���A�ȉ��̐}�R�Ɏ������B
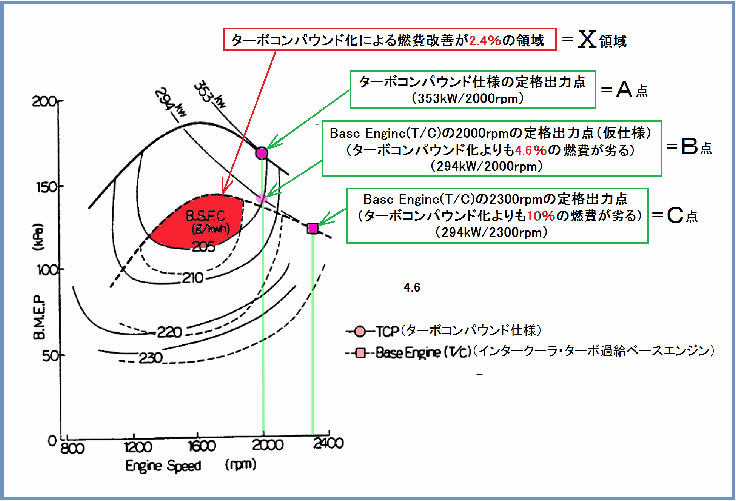
�@��L�̐}�R�Ɏ������`�_�A�a�_����тb�_�́A�O�H�d�H�Ƙ_���̐}�P�S�����R��Ȑ���r�}�̒��Ƀ^�[�{�R���p�E��
�h�G���W������уx�[�X�G���W���̂��ꂼ��̒�i�_�ł���B�ڍׂ͈ȉ��̒ʂ�ł���B
�h�G���W������уx�[�X�G���W���̂��ꂼ��̒�i�_�ł���B�ڍׂ͈ȉ��̒ʂ�ł���B
�`�_�@�F�@2000rpm��i��]���x�̃^�[�{�R���p�E���h�G���W���̒�i�_�i353kW/2000rpm�j
�a�_�@�F�@2000rpm�̃x�[�X�G���W���̒�i�_�i294kW/2000rpm�j�i���d�l�j
�b�_�@�F�@2300rpm��i��]���x�̃x�[�X�G���W���̒�i�_�i294kW/2300rpm�j
�@�O�H�d�H�Ƈ��̃^�[�{�R���p�E���h�_���ł́A�^�[�{�R���p�E���h�̂`�_�i353kW/2000rpm�j�̔R��i204 g/kWh)�ƃx
�[�X�G���W���̂b�_�i294kW/2300rpm�j�̔R���i227 g/kWh)���r���āA�u�^�[�{�R���p�E���h�G���W���̔R��x�[�X�G
���W������10���̔R����P�v�ł����ƋL�ڂ���Ă���B�������A��^�g���b�N�ɂ������i�o�͂̃G���W����]���x
�i����i��]���x�j�́A���̃g���b�N�ŕK�v�Ƃ���Ă���ō����x�����m�ۂ��邽�߂ɁA���̃g���b�N�ɓ��ڂ���Ă���g
�����X�~�b�V�����M�A���f�t�@�����V�����M�A�䌈�肳�����̂ł���A�^�[�{�R���p�E���h���̃G���W���d�l�ɂ����
���܂���̂ł͂Ȃ��B���������āA�g���b�N�p�G���W���̊ϓ_����^�[�{�R���p�E���h�G���W���ƃx�[�X�G���W���̔R���
��r����ꍇ�ɂ́A�^�[�{�R���p�E���h�G���W�����`�_�ƃx�[�X�G���W�����b�_�̔R����r���ĔR��̗D���_���邱
�Ƃ͖��Ӗ��ł���B�g���b�N�p�G���W���̊ϓ_����^�[�{�R���p�E���h�d�l�̔R����P�̌��ʂ𐳊m�ɔ�r���邽�߂�
�́A�^�[�{�R���p�E���h�G���W���ƃx�[�X�G���W���̗��G���W���̒�i��]���x��2000rpm�œ���ł���^�[�{�R���p�E
���h�G���W����A�_�ƃx�[�X�G���W����B�_�̔R����r����ׂ��ł���B���������āA�g���b�N�p�G���W���̊ϓ_����^
�[�{�R���p�E���h�G���W���̒�i�_�̔R��𐳊m�ɕ]�������ꍇ�ɂ́AA�_��B�_�̔R����r���邱�Ƃɂ��\��
�Ȃ�B����A�_��B�_�̔R���r�ɂ��A�u��i�_�ɂ�����^�[�{�R���p�E���h�G���W���̔R��x�[�X�G���W������4.
6���̔R����P�v�ł���Ƃ��邱�Ƃ��g���b�N�p�G���W���̊ϓ_����̃^�[�{�R���p�E���h�ɂ����鐳�����R����P��
�F���ł͂Ȃ����낤���B
�[�X�G���W���̂b�_�i294kW/2300rpm�j�̔R���i227 g/kWh)���r���āA�u�^�[�{�R���p�E���h�G���W���̔R��x�[�X�G
���W������10���̔R����P�v�ł����ƋL�ڂ���Ă���B�������A��^�g���b�N�ɂ������i�o�͂̃G���W����]���x
�i����i��]���x�j�́A���̃g���b�N�ŕK�v�Ƃ���Ă���ō����x�����m�ۂ��邽�߂ɁA���̃g���b�N�ɓ��ڂ���Ă���g
�����X�~�b�V�����M�A���f�t�@�����V�����M�A�䌈�肳�����̂ł���A�^�[�{�R���p�E���h���̃G���W���d�l�ɂ����
���܂���̂ł͂Ȃ��B���������āA�g���b�N�p�G���W���̊ϓ_����^�[�{�R���p�E���h�G���W���ƃx�[�X�G���W���̔R���
��r����ꍇ�ɂ́A�^�[�{�R���p�E���h�G���W�����`�_�ƃx�[�X�G���W�����b�_�̔R����r���ĔR��̗D���_���邱
�Ƃ͖��Ӗ��ł���B�g���b�N�p�G���W���̊ϓ_����^�[�{�R���p�E���h�d�l�̔R����P�̌��ʂ𐳊m�ɔ�r���邽�߂�
�́A�^�[�{�R���p�E���h�G���W���ƃx�[�X�G���W���̗��G���W���̒�i��]���x��2000rpm�œ���ł���^�[�{�R���p�E
���h�G���W����A�_�ƃx�[�X�G���W����B�_�̔R����r����ׂ��ł���B���������āA�g���b�N�p�G���W���̊ϓ_����^
�[�{�R���p�E���h�G���W���̒�i�_�̔R��𐳊m�ɕ]�������ꍇ�ɂ́AA�_��B�_�̔R����r���邱�Ƃɂ��\��
�Ȃ�B����A�_��B�_�̔R���r�ɂ��A�u��i�_�ɂ�����^�[�{�R���p�E���h�G���W���̔R��x�[�X�G���W������4.
6���̔R����P�v�ł���Ƃ��邱�Ƃ��g���b�N�p�G���W���̊ϓ_����̃^�[�{�R���p�E���h�ɂ����鐳�����R����P��
�F���ł͂Ȃ����낤���B
�@�Ƃ���ŁA�}�S�́A�]���̔r�o�K�X�����T�C�N���iJE05 ���[�h�j��WHTC�����@�ɂ�����Q��ނ̃G���W���i12.91���b�g
���A4.01���b�g���j�̉�]���E���וp�x���z�}�Ɏ��������̂ł���B�����r�o�K�X�����T�C�N���iJE05 ���[�h�j��WHTC
�����@�́A�g���b�N�̎����s�ɂ�����G���W���^�]�p�x����쐬���ꂽ���̂ł���A�g���b�N�̎����s�ɂ�����G���W��
�^�]��Ԃ��\���Ă�����̂ƍl������B���̐}�S���Q��ނ̃G���W���i12.91���b�g���A4.01���b�g���j�̉�]���E����
�p�x���z�}������ƁA����̃G���W���ɂ����Ă�100�����ׂ�100���G���W����]���x�ł̃G���W���^�]�i���G���W����
�i�_�j�́A�F���ɋ߂����Ƃ�����B���̂��Ƃ���A�G���W����i�_�ɂ����ă^�[�{�R���p�E���h�G���W���̔R��x�[�X
�G���W������4.2���̔R����P���ꂽ�Ƃ��Ă��A�g���b�N�̑��s�R��ɂ͑S����^���Ȃ����Ƃ����炩���B�����āA��
���}�S���Q��ނ̃G���W���i12.91���b�g���A4.01���b�g���j�̉�]���E���וp�x���z�}������Ɩ��炩�Ȃ悤�ɁA�g
���b�N��JE05 ���[�h���Ōv�������d�ʎԃ��[�h�R�������s�R������P���邽�߂ɂ́A�ő�g���N�̃G���W
����]���x�̈�ł̕��������̔R����P��}�邱�Ƃ��K�v�ł��邱�Ƃ͖��炩���B
���A4.01���b�g���j�̉�]���E���וp�x���z�}�Ɏ��������̂ł���B�����r�o�K�X�����T�C�N���iJE05 ���[�h�j��WHTC
�����@�́A�g���b�N�̎����s�ɂ�����G���W���^�]�p�x����쐬���ꂽ���̂ł���A�g���b�N�̎����s�ɂ�����G���W��
�^�]��Ԃ��\���Ă�����̂ƍl������B���̐}�S���Q��ނ̃G���W���i12.91���b�g���A4.01���b�g���j�̉�]���E����
�p�x���z�}������ƁA����̃G���W���ɂ����Ă�100�����ׂ�100���G���W����]���x�ł̃G���W���^�]�i���G���W����
�i�_�j�́A�F���ɋ߂����Ƃ�����B���̂��Ƃ���A�G���W����i�_�ɂ����ă^�[�{�R���p�E���h�G���W���̔R��x�[�X
�G���W������4.2���̔R����P���ꂽ�Ƃ��Ă��A�g���b�N�̑��s�R��ɂ͑S����^���Ȃ����Ƃ����炩���B�����āA��
���}�S���Q��ނ̃G���W���i12.91���b�g���A4.01���b�g���j�̉�]���E���וp�x���z�}������Ɩ��炩�Ȃ悤�ɁA�g
���b�N��JE05 ���[�h���Ōv�������d�ʎԃ��[�h�R�������s�R������P���邽�߂ɂ́A�ő�g���N�̃G���W
����]���x�̈�ł̕��������̔R����P��}�邱�Ƃ��K�v�ł��邱�Ƃ͖��炩���B
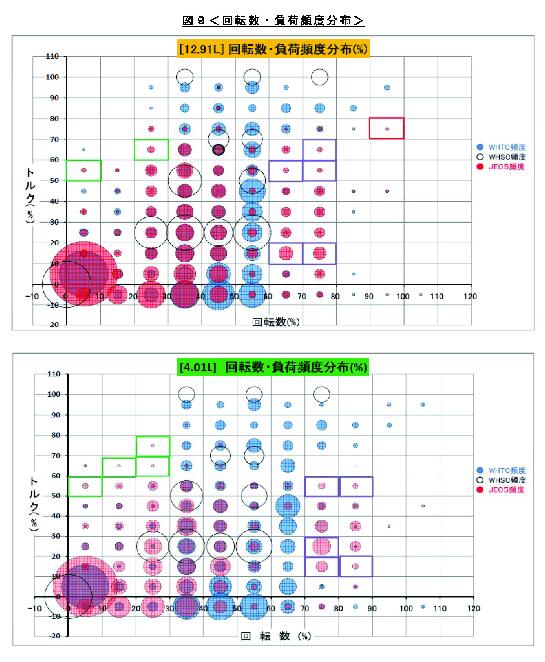
�@�ȏ�̂悤�ɁA�ő�g���N�̃G���W����]���x�̈�ł̔R����P���g���b�N�̏d�ʎԃ��[�h�R�������s�R�����
�P�Ɋ�^���邱�Ƃ���A�^�[�{�R���p�E���h�G���W���ɂ����Ă��ő�g���N�̃G���W����]���x�̈�ł̔R����P�̊�
�����d�v���d�v�ł���B�����ŁA�^�[�{�R���p�E���h�G���W���ɂ�����ő�g���N�̃G���W����]���x�̈�ł́A�}�R��
�}���̐ԓh��Ŏ�����X�̈�ŔR�2.4���̉��P����Ă��邱�Ƃ�����B���̂��Ƃ���A��^�g���b�N���^�[�{�R���p�E
���h�ɂ���ĔR������P���邱�Ƃ��ł���̂́A�ő�̏ꍇ�ł��A�G���W���ő�g���N�̉^�]��Ԃ�2.4���̉��P����
���邾���ł����B�����āA�}�S���疾�炩�Ȃ悤�ɁA���ۂ̑�^�g���b�N�̑��s�ɂ����ẮA�G���W���^�]�̎g�p�p
�x�́A�G���W���̒���]���x�̒��g���N�t�߂̉^�]���������̂��B���̑�^�g���b�N�̑��s�ł̎g�p�p�x�̑����G��
�W���̒���]���x�̒��g���N�t�߂̉^�]�̈�ł́A�}�R���疾�炩�Ȃ悤�ɁA�^�[�{�R���p�E���h�ɂ��R����P�͌�
��Ȃ���p�[�Z���g�ɋ߂��̂ł���B���̂��Ƃ���A���ۂ̃g���b�N���s�ɂ�����^�[�{�R���p�E���h�ɂ��R�����͋�
�߂ď��Ȃ����̂ƂȂ邱�Ƃ͖��炩�ł���B���������āA�^�[�{�R���p�E���h�Z�p�ɂ��d�ʎԃ��[�h�R��̉��P
�́A�P���ɂ������Ȃ��ɂ߂ċ͂��ł���Ɨ\�z�����B
�P�Ɋ�^���邱�Ƃ���A�^�[�{�R���p�E���h�G���W���ɂ����Ă��ő�g���N�̃G���W����]���x�̈�ł̔R����P�̊�
�����d�v���d�v�ł���B�����ŁA�^�[�{�R���p�E���h�G���W���ɂ�����ő�g���N�̃G���W����]���x�̈�ł́A�}�R��
�}���̐ԓh��Ŏ�����X�̈�ŔR�2.4���̉��P����Ă��邱�Ƃ�����B���̂��Ƃ���A��^�g���b�N���^�[�{�R���p�E
���h�ɂ���ĔR������P���邱�Ƃ��ł���̂́A�ő�̏ꍇ�ł��A�G���W���ő�g���N�̉^�]��Ԃ�2.4���̉��P����
���邾���ł����B�����āA�}�S���疾�炩�Ȃ悤�ɁA���ۂ̑�^�g���b�N�̑��s�ɂ����ẮA�G���W���^�]�̎g�p�p
�x�́A�G���W���̒���]���x�̒��g���N�t�߂̉^�]���������̂��B���̑�^�g���b�N�̑��s�ł̎g�p�p�x�̑����G��
�W���̒���]���x�̒��g���N�t�߂̉^�]�̈�ł́A�}�R���疾�炩�Ȃ悤�ɁA�^�[�{�R���p�E���h�ɂ��R����P�͌�
��Ȃ���p�[�Z���g�ɋ߂��̂ł���B���̂��Ƃ���A���ۂ̃g���b�N���s�ɂ�����^�[�{�R���p�E���h�ɂ��R�����͋�
�߂ď��Ȃ����̂ƂȂ邱�Ƃ͖��炩�ł���B���������āA�^�[�{�R���p�E���h�Z�p�ɂ��d�ʎԃ��[�h�R��̉��P
�́A�P���ɂ������Ȃ��ɂ߂ċ͂��ł���Ɨ\�z�����B
�@�ȏ�̂��Ƃ���A���{�@��w��_���W�iB�ҁj51��467���i��60-7�j�́u�r�C�^�[�{�R���p�E���h�G���W���̃G�l���M��
�������v�i���ҁF�O�H�d�H�Ƈ� �y���z�O�� ���S���j�̘_���̓��e��M�҂̏���Ȋϓ_�œZ�߂����Ă��������ƁA�^�[�{
�R���p�E���h�̓����́A�ȉ��̕\�S�Ɏ������悤�ɂȂ�̂ł͂Ȃ����ƍl���Ă���B
�������v�i���ҁF�O�H�d�H�Ƈ� �y���z�O�� ���S���j�̘_���̓��e��M�҂̏���Ȋϓ_�œZ�߂����Ă��������ƁA�^�[�{
�R���p�E���h�̓����́A�ȉ��̕\�S�Ɏ������悤�ɂȂ�̂ł͂Ȃ����ƍl���Ă���B
| |
| �P�D�^�[�{�R���p�E���h�́A�C�����̍ō����͂����߂邱�ƂȂ��A�G���W���̍��o�͉����\
�@�@�E �ő�g���N��30������ �@�@�E �ō��o�͂�20������ �Q�D�^�[�{�R���p�E���h�́A�R�����̋@�\�͏��Ȃ��A���̌��ʂ͋͏� �@ �i�^�[�{�R���p�E���h�́A��^�g���b�N�̔R����\���Ɍ���ł���@�\�͖����j �@�@�E �ő�g���N�t�߁i�}3��X�̈�j��2.4���̔R����P�ł��邪�A���A�ᕉ�ׂł͔R��̉��P���ʂ͊F�� �@�@�E ��i�_�i100����]��100�����ׁj��4.2���̔R����P�ł��邪�A����̓g���b�N�̔R����P�ɂ͖��� �@�@�E ���s���ɂ̓G���W���̒����E�����ׂ����p����邽�߁A�^�[�{�R���p�E���h�̓g���b�N�̔R����P�ɕs���� �@�@�E �^�[�{�R���p�E���h�ɂ��d�ʎԃ��[�h�R��̉��P�́A�P���ȉ��Ɛ��� |
�R�|�R�@�^�[�{�R���p�E���h�Ɋւ���JPEC�̘_���i2001.M4.2.1�j
�@�Ζ��G�l���M�[�Z�p�Z���^�[�^�[�iJPEC)�̔��\�_���u�r�o���ጸ�ɂ����Ή��^�f�B�[�[���G���W���̌����J
���v�i�o�T�Fhttp://www.pecj.or.jp/japanese/report/2001report/2001M4.2.1.pdf�j�ł�
���v�i�o�T�Fhttp://www.pecj.or.jp/japanese/report/2001report/2001M4.2.1.pdf�j�ł�
| |
|
||||||||||||||
| |
|
||||||||||||||
| |
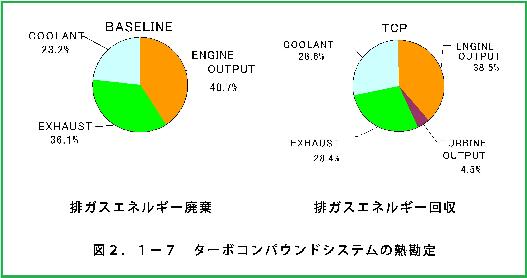 �y���ړ_ �y�� �R�����g�z
�@�{�_���̐}�Q�ɂ́A��i�_�i���G���W���̍ō��o�͓_�j�ɂ������x�[�X�G���W���ƃ^�[�{�R���p�E���h�G���W���̔M
���肪������Ă���B����ɂ��ƃx�[�X�G���W���ƃ^�[�{�R���p�E���h�G���W���̔M����́A�ȉ��̒ʂ�ł���B
�@
�@�^�[�{�R���p�E���h�G���W���̏o�́F38.5 ���́A�x�[�X�G���W���̏o�́F40.7 ����� 2.3�����Ȃ��B����́A�^
�[�r���̃m�Y���i��ɂ���R�̂��߂ɉߋ��@�^�[�r���̓�������́��r�C�}�j�z�[���h���͂̏㏸�ɂ��A�G���W ���{�̂̔M�������ቺ�������ʂł���B���̂��Ƃ́A�^�[�{�R���p�E���h�G���W���ł̔������Ȃ������ł���B���� ���A�^�[�{�R���p�E���h�G���W���ł́A�^�[�r���ɂ���Ĕr�C�K�X����4.5���̏o�͂���������B���̂��߁A�^�[ �{�R���p�E���h�G���W���̎��o�͂́A�i�G���W���o�́F38.5 ���j�{�i�^�[�r��4.5���j��43.0 ���ƂȂ�A�x�[�X�G���W ���̎��o��40.7 �������P�ł��Ă��邱�Ƃ�����B �@���̂悤�ɁA����JPEC�_���ł́A�^�[�{�R���p�E���h�G���W���̎��o�͂���i�_�i���G���W���̍ō��o�͓_�j���M
�����i���M����j��43.0���ɑ������A�x�[�X�G���W���̔M�����i���M����j���2.3���̑����i���R���r�ł�5.6���j �̉��P������邱�Ƃ�������Ă���B���݂ɁA�O�q�̎O�H�d�H�̃^�[�{�R���p�E���h�_���ł̒�i�_�i���d�l���a �_�j�̔R����P�́A4.6���ł������B�����JPEC�_���ƎO�H�d�H�_���̃^�[�{�R���p�E���h�G���W���̎��o�͂���i �_�̔R�����P�́A5���O��łقڈ�v���Ă���悤���B�����̂��Ƃ���A�^�[�{�R���p�E���h�G���W�̒�i�_�i���G�� �W���̍ō��o�͂̉^�]�����j�̔R��́A�x�[�X�G���W���̔R�����5���O��̉��P���\�ƍl���ĊԈႢ�Ȃ��悤 ���B �@���̂悤�ɁA��i�_�i���G���W���̍ō��o�͓_�̉^�]�����j�̌���ꂽ�G���W���^�]�ł̃^�[�{�R���p�E��
�h�G���W���R���́A�x�[�X�G���W���ɔ�ׂ�5���O��̏\���ȔR����P���\�ł���B�������A�ő�g���N �̃G���W���^�]��Ԃł̃^�[�{�R���p�E���h���R�����P�́A�x�[�X�G���W���ɔ�ׂ�2���O��̔R����P ������Ƃ̂��Ƃ��B���̏�A�c�O�Ȃ��ƂɁA�̐S�v�̑�^�g���b�N�̏d�ʎԃ��[�h�R�������s�ł̎g�p�p �x�̍���������]�̕������ׂł̃G���W���^�]��Ԃɂ����ẮA�^�[�{�R���p�E���h�G���W�́A�x�[�X�G�� �W�������P�������̔R����P���������ł��Ȃ��Ɛ��@�����B���̂悤�ɁA�^�[�{�R���p�E���h�̋Z�p�́A�� �^�g���b�N�̏d�ʎԃ��[�h�R����P��������������ł��Ȃ����߁A��^�g���b�N�̔R������P����Z�p�Ƃ��� �͎��i�ƍl����ׂ��ł���B |
�S�@��^�g���b�N�̏d�ʎԃ��[�h�R��̉��P�Z�p�ɂ��Ă̊w�ҁE���Ƃ̍ŋ߂̒��q
�@���݂̓��{�̃g���b�N�ƊE�ɂ����ẮA�O�q�̕\�P�Ɏ������悤�ɁA�e�g���b�N���[�J�́A��^�g���b�N�E�g���N�^�̑�����
�Ԏ킪2015�N�x�d�ʎԔR���ɕs�K���̏ł���B�e�g���b�N���[�J������Ă��̏���E�o�ł���悤�ɂ�
�邽�߂ɂ́A�d�ʎԃ��[�h�R����T�����x�̔R����P�ł���Z�p���J�����A���p������K�v������B�ܘ_�A�����_
�ł͊e�g���b�N���[�J�Ƃ����̂悤���ȔR����P���J���ł��Ă��Ȃ����炱���A��^�g���b�N�̈ꕔ�̎Ԏ��2015�N�x�d
�ʎԔR���ɖ��B���̂܂ܔ̔���������������Ȃ����̂ƍl������B
�Ԏ킪2015�N�x�d�ʎԔR���ɕs�K���̏ł���B�e�g���b�N���[�J������Ă��̏���E�o�ł���悤�ɂ�
�邽�߂ɂ́A�d�ʎԃ��[�h�R����T�����x�̔R����P�ł���Z�p���J�����A���p������K�v������B�ܘ_�A�����_
�ł͊e�g���b�N���[�J�Ƃ����̂悤���ȔR����P���J���ł��Ă��Ȃ����炱���A��^�g���b�N�̈ꕔ�̎Ԏ��2015�N�x�d
�ʎԔR���ɖ��B���̂܂ܔ̔���������������Ȃ����̂ƍl������B
�@���̂悤�ɁA���݂́A��^�g���b�N�̏d�ʎԃ��[�h�R��̉��P���Z�p�I�ɍs���l�܂�̏Ɋׂ��Ă���悤���B����
�ɑ��A��^�g���b�N�̔R����P��}�邽�߂ɁA�킪���̃f�B�[�[���G���W���W�̊w�ҁE���Ƃ́A�@���Ȃ�Z�p��
�L���ł���Ƃ̌����〈�ʂ���������Ă���̂ł��낤���B�����T�邽�߁A��^�g���b�N�̔R����P�ɂ��Ă̊w
�ҁE���Ƃ̍ŋ߂̒��q���ȉ��Ƀs�b�N�A�b�v�����B
�ɑ��A��^�g���b�N�̔R����P��}�邽�߂ɁA�킪���̃f�B�[�[���G���W���W�̊w�ҁE���Ƃ́A�@���Ȃ�Z�p��
�L���ł���Ƃ̌����〈�ʂ���������Ă���̂ł��낤���B�����T�邽�߁A��^�g���b�N�̔R����P�ɂ��Ă̊w
�ҁE���Ƃ̍ŋ߂̒��q���ȉ��Ƀs�b�N�A�b�v�����B
�@
�S�|�P�@�u�����ԋZ�p�v���i2011�N9�����s�j�ɂ�����吹�����i����c��w�j�̎咣
�@2011�N9�����s�́u�����ԋZ�p�v���iVol.65,No.9,2011)�ɂ����āA����c��w�̑吹�����́u�����ԗp�G���W���Z�p
�̌���Ə����v�Ƒ肵���_���\����Ă���B���̒��́u3.2.�@�d�ʎԂ̔R����P�v�̍��ɂ����ă^�[�{�R���p�E���h
�̋Z�p�ɂ��ċL�q����Ă���̂ŁA���̓��e���ȉ��̕\�S�ɏЉ��B
�̌���Ə����v�Ƒ肵���_���\����Ă���B���̒��́u3.2.�@�d�ʎԂ̔R����P�v�̍��ɂ����ă^�[�{�R���p�E���h
�̋Z�p�ɂ��ċL�q����Ă���̂ŁA���̓��e���ȉ��̕\�S�ɏЉ��B
| |
|
| |
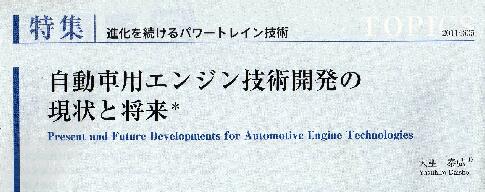 |
| |
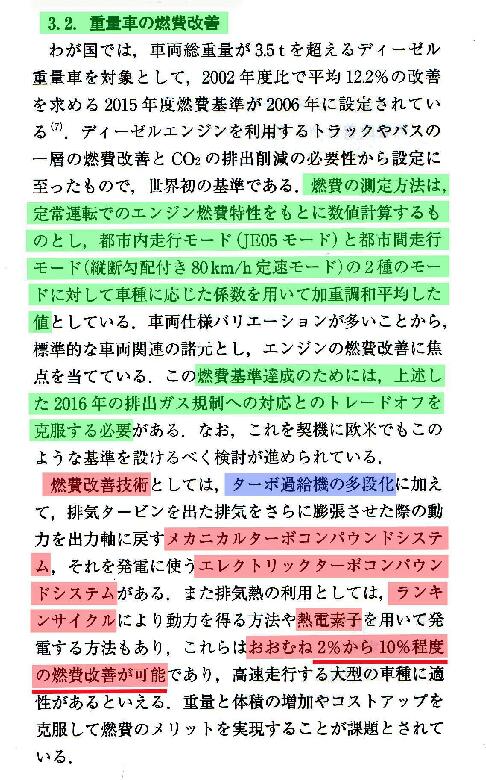 |
�@��L�̕\�S�Ɏ������悤�ɁA�@�����ԋZ�p�v��2011�N9�����́u�����ԗp�G���W���Z�p���͂̌���Ə����v�̘_����
�́A3.2. �̍��ɂ����āu�d�ʎԂ̔R����P�v�ɂ��Ắu����Ə����v�ɂ��ċL�ڂ���Ă���B���̍��ł́A�吹����
�́A�d�ʎԃ��[�h�R��̑�����@���ڂ����������A2015�N�x�d�ʎԔR���̒B����2016�N�̔r�o�K�X�K��������
�̃g���[�h�I�t�̍����̕K�v���ɂ����y����Ă���B����ɑ����āA�d�ʎԁi�g���b�N�E�o�X�j�̔R����P�Z�p�Ƃ��āu�^
�[�{�ߋ��@�̑��i���v�Ɓu�^�[�{�R���p�E���h�v��u�����L���T�C�N���v����сu�M�d�f�q�v�ɂ��u�r�C�K�X�̃G�l���M�[
���o�͎���d�C�G�l���M�[�Ƃ��Ē~�d�r�ɉ������Z�p��������Ă���B�����āA�r�C�K�X�̃G�l���M�[�ɂ��
�ďd�ʎԁi�g���b�N�E�o�X�j�́A�u�����ނ˂Q������P�O���̔R����P���\�v�Ǝ咣����Ă���̂ł���B
�́A3.2. �̍��ɂ����āu�d�ʎԂ̔R����P�v�ɂ��Ắu����Ə����v�ɂ��ċL�ڂ���Ă���B���̍��ł́A�吹����
�́A�d�ʎԃ��[�h�R��̑�����@���ڂ����������A2015�N�x�d�ʎԔR���̒B����2016�N�̔r�o�K�X�K��������
�̃g���[�h�I�t�̍����̕K�v���ɂ����y����Ă���B����ɑ����āA�d�ʎԁi�g���b�N�E�o�X�j�̔R����P�Z�p�Ƃ��āu�^
�[�{�ߋ��@�̑��i���v�Ɓu�^�[�{�R���p�E���h�v��u�����L���T�C�N���v����сu�M�d�f�q�v�ɂ��u�r�C�K�X�̃G�l���M�[
���o�͎���d�C�G�l���M�[�Ƃ��Ē~�d�r�ɉ������Z�p��������Ă���B�����āA�r�C�K�X�̃G�l���M�[�ɂ��
�ďd�ʎԁi�g���b�N�E�o�X�j�́A�u�����ނ˂Q������P�O���̔R����P���\�v�Ǝ咣����Ă���̂ł���B
�@���̘_���ő吹�����́A�d�ʎԁi����^�g���b�N���j�̔R����P�̎�i�Ƃ��āA�u�^�[�{�ߋ��@�̑��i���v�Ɓu�r�C�K�X
�̃G�l���M�[�v�𐄏�����A�u�r�C�K�X�̃G�l���M�[�ɂ���ĂQ������P�O���̉��P���\�v�Ǝ咣����Ă�
��B�������A�O�q�̂Q�@���Ɏ������Ƃ���ANEDO�́u�����x�R�Đ���G���W�V�X�e���̌����J���v�ł́A�u�^�[�{�ߋ��@
�̑��i���v���g�ݍ��܂�Ă���ɂ�������炸�A�R��������Ă��錋�ʂ����\����Ă���̂ł���B���̂��Ƃ���A
�吹�������R����P�̎�i�Ƃ��ċ������Ă���u�^�[�{�ߋ��@�̑��i���v�́A��^�g���b�N�i���d�ʎԁj�̔R����P
������ƍl������B
�̃G�l���M�[�v�𐄏�����A�u�r�C�K�X�̃G�l���M�[�ɂ���ĂQ������P�O���̉��P���\�v�Ǝ咣����Ă�
��B�������A�O�q�̂Q�@���Ɏ������Ƃ���ANEDO�́u�����x�R�Đ���G���W�V�X�e���̌����J���v�ł́A�u�^�[�{�ߋ��@
�̑��i���v���g�ݍ��܂�Ă���ɂ�������炸�A�R��������Ă��錋�ʂ����\����Ă���̂ł���B���̂��Ƃ���A
�吹�������R����P�̎�i�Ƃ��ċ������Ă���u�^�[�{�ߋ��@�̑��i���v�́A��^�g���b�N�i���d�ʎԁj�̔R����P
������ƍl������B
�@�܂��A�吹�����́A�u�r�C�K�X�̃G�l���M�[�ɂ���ĂQ������P�O���̉��P���\�v�Ǝ咣����Ă��邪�A���̔R
����P�̐��l�́A�d�ʎԃ��[�h�R��̔R����P���H�Ⴕ���̓G���W���̓���̃g���N�Ɖ�]���x�̔R����P���H��
���Ă͖��L����Ă��Ȃ��B�����ŁA���̂Q������P�O���̔R����P���A���ɃG���W���̓���̃g���N�Ɖ�]���x�̔R
����P�̐��l�́A�O�q�̐}�R�Ɏ������O�H�d�H�_�������R��Ȑ���r�}�ɂ�����^�[�{�R���p�E���h�ɂ��R���
�P�̊����i���d�l�̒�i�_B�_�F4.2���A��i�_C�_�F10���AX�̈�F2.4���j�Ƌ��R�ɂ��ǂ���v���Ă��悤���B�������A�^�[
�{�R���p�E���h�ɂ��A���d�l�̒�i�_B�_�ŁA4.2���A��i�_C�_��10���AX�̈��2.4���̔R����P�������Ă���
���A�s�K�Ȃ��ƂɁA��^�g���b�N�����d�ʎԁi�g���b�N�E�o�X�j�ɂ������d�ʎԃ��[�h�R���s���̔R����P�͂P������
�̋͂��ł���B���̂��Ƃ���A���̘_���ő吹�������q�ׂ��Ă���r�C�K�X�̃G�l���M�[�̕��@��p���Ď���
�\�ȂQ������P�O���̔R����P�́A�G���W���̍ő�g���N�_��G���W����i�_�̃G���W���^�]��Ԃɂ�����R���
�P�̂��Ƃł���A��^�g���b�N�����d�ʎԁi�g���b�N�E�o�X�j���d�ʎԃ��[�h�R���s���̔R�����ɂ͗]���^�ł���
���R����P�̐��l���L�q����Ă���Ɛ��������B
����P�̐��l�́A�d�ʎԃ��[�h�R��̔R����P���H�Ⴕ���̓G���W���̓���̃g���N�Ɖ�]���x�̔R����P���H��
���Ă͖��L����Ă��Ȃ��B�����ŁA���̂Q������P�O���̔R����P���A���ɃG���W���̓���̃g���N�Ɖ�]���x�̔R
����P�̐��l�́A�O�q�̐}�R�Ɏ������O�H�d�H�_�������R��Ȑ���r�}�ɂ�����^�[�{�R���p�E���h�ɂ��R���
�P�̊����i���d�l�̒�i�_B�_�F4.2���A��i�_C�_�F10���AX�̈�F2.4���j�Ƌ��R�ɂ��ǂ���v���Ă��悤���B�������A�^�[
�{�R���p�E���h�ɂ��A���d�l�̒�i�_B�_�ŁA4.2���A��i�_C�_��10���AX�̈��2.4���̔R����P�������Ă���
���A�s�K�Ȃ��ƂɁA��^�g���b�N�����d�ʎԁi�g���b�N�E�o�X�j�ɂ������d�ʎԃ��[�h�R���s���̔R����P�͂P������
�̋͂��ł���B���̂��Ƃ���A���̘_���ő吹�������q�ׂ��Ă���r�C�K�X�̃G�l���M�[�̕��@��p���Ď���
�\�ȂQ������P�O���̔R����P�́A�G���W���̍ő�g���N�_��G���W����i�_�̃G���W���^�]��Ԃɂ�����R���
�P�̂��Ƃł���A��^�g���b�N�����d�ʎԁi�g���b�N�E�o�X�j���d�ʎԃ��[�h�R���s���̔R�����ɂ͗]���^�ł���
���R����P�̐��l���L�q����Ă���Ɛ��������B
�@�܂��A���ɁA���̎����ԋZ�p�v��2011�N9�����́u�����ԗp�G���W���Z�p���͂̌���Ə����v�̘_���ő吹������
�u�r�C�K�X�̃G�l���M�[�ɂ�����Q������P�O���̏d�ʎԃ��[�h�R��̉��P���\�v�Ǝ咣����Ă���Ƃ�����
���ɂ́A�吹�������@���Ȃ���p�������̃f�[�^�������ɂQ������P�O���̔R����P���咣����Ă��邩�ɂ��Đ�
��Ƃ��������������������Ǝv���Ă���B����ɂ��Ă��A�u�r�C�K�X�̃G�l���M�[�ɂ���ĂQ������P�O���̉��P��
�\�v�Ƃ̑吹�������咣����Ă���R����P�̐��l�́A�u�d�ʎԃ��[�h�R��̔R����P�v���H�A�Ⴕ���́u�G���W����
����̃g���N�Ɖ�]���x�̃|�C���g�ɂ�����R����P�v���H�ɂ��Ă͖��L����Ă��Ȃ��̂��B���̂��߁A�����ԋZ
�p�v��2011�N9�����̑吹�����́u�����ԗp�G���W���Z�p�̌���Ə����v�̘_���ɂ��ẮA�ǎ҂��^�[�{�R���p�E��
�h�ɂ��R����P�̊����𐳊m�ɔc�����邱�Ƃ�����Ȃł���B
�u�r�C�K�X�̃G�l���M�[�ɂ�����Q������P�O���̏d�ʎԃ��[�h�R��̉��P���\�v�Ǝ咣����Ă���Ƃ�����
���ɂ́A�吹�������@���Ȃ���p�������̃f�[�^�������ɂQ������P�O���̔R����P���咣����Ă��邩�ɂ��Đ�
��Ƃ��������������������Ǝv���Ă���B����ɂ��Ă��A�u�r�C�K�X�̃G�l���M�[�ɂ���ĂQ������P�O���̉��P��
�\�v�Ƃ̑吹�������咣����Ă���R����P�̐��l�́A�u�d�ʎԃ��[�h�R��̔R����P�v���H�A�Ⴕ���́u�G���W����
����̃g���N�Ɖ�]���x�̃|�C���g�ɂ�����R����P�v���H�ɂ��Ă͖��L����Ă��Ȃ��̂��B���̂��߁A�����ԋZ
�p�v��2011�N9�����̑吹�����́u�����ԗp�G���W���Z�p�̌���Ə����v�̘_���ɂ��ẮA�ǎ҂��^�[�{�R���p�E��
�h�ɂ��R����P�̊����𐳊m�ɔc�����邱�Ƃ�����Ȃł���B
�@�����͉]���Ă��A�吹�������u�����ԋZ�p�v��2011�N9�����́u�����ԗp�G���W���Z�p���͂̌���Ə����v�̘_����
���ł́A�u3.2. �d�ʎԂ̔R����P�v�̍��̍ŏ��̕����ɂ����āA�\��́u�d�ʎԂ̔R��v�ł���d�ʎԃ��[�h�R��v��
�v���E�v�Z�̏ڍׂȕ��@��吹�����͏ڂ�����������Ă���̂ł���B�����āA���́u�d�ʎԂ̔R��̌v���E�v�Z�̕�
�@�v�����������ɁA�u�r�C�K�X�̃G�l���M�[���������Z�p�v�ɂ���āA�u�����ނ˂Q������P�O���̔R����P���\�v
�ƋL�q����Ă���B���������āA�u3.2. �d�ʎԂ̔R����P�v�̒��ɋL�q����Ă���u�R��v�́A�u�d�ʎԃ��[�h�R��v�Ɠǎ�
����������悤�ɋL�q����Ă���B���Ƃ���A���̍��ʂɓǂ݉����A���́u�Q������P�O���̔R����P�v�̋L�q��
���ẮA���R�A�吹�����̎咣�́A�u�r�C�K�X�̃G�l���M�[�ɂ���ĂQ������P�O���̏d�ʎԃ��[�h�R��
�����P�ł���v�ƁA�w�ǂ̓ǎ҂��������Ă�����̂ƍl������B�ܘ_�A�M�҂������̓ǎ҂Ɠ��l�ɁA�u�吹�������r
�C�K�X�̃G�l���M�[�ɂ���ĂQ������P�O���̏d�ʎԃ��[�h�R��̉��P�v���咣����Ă�����̂Ɨ������ėǂ���
�v�����A�@���Ȃ��̂ł��낤���B���̏ꍇ�A�^�[�{�R���p�E���h�ɂ��d�ʎԃ��[�h�R��P�O�������P���邱�Ƃ��\
�Ƃ́A�M�҂ɂ͂ƂĂ��l�����Ȃ��̂ł���B
���ł́A�u3.2. �d�ʎԂ̔R����P�v�̍��̍ŏ��̕����ɂ����āA�\��́u�d�ʎԂ̔R��v�ł���d�ʎԃ��[�h�R��v��
�v���E�v�Z�̏ڍׂȕ��@��吹�����͏ڂ�����������Ă���̂ł���B�����āA���́u�d�ʎԂ̔R��̌v���E�v�Z�̕�
�@�v�����������ɁA�u�r�C�K�X�̃G�l���M�[���������Z�p�v�ɂ���āA�u�����ނ˂Q������P�O���̔R����P���\�v
�ƋL�q����Ă���B���������āA�u3.2. �d�ʎԂ̔R����P�v�̒��ɋL�q����Ă���u�R��v�́A�u�d�ʎԃ��[�h�R��v�Ɠǎ�
����������悤�ɋL�q����Ă���B���Ƃ���A���̍��ʂɓǂ݉����A���́u�Q������P�O���̔R����P�v�̋L�q��
���ẮA���R�A�吹�����̎咣�́A�u�r�C�K�X�̃G�l���M�[�ɂ���ĂQ������P�O���̏d�ʎԃ��[�h�R��
�����P�ł���v�ƁA�w�ǂ̓ǎ҂��������Ă�����̂ƍl������B�ܘ_�A�M�҂������̓ǎ҂Ɠ��l�ɁA�u�吹�������r
�C�K�X�̃G�l���M�[�ɂ���ĂQ������P�O���̏d�ʎԃ��[�h�R��̉��P�v���咣����Ă�����̂Ɨ������ėǂ���
�v�����A�@���Ȃ��̂ł��낤���B���̏ꍇ�A�^�[�{�R���p�E���h�ɂ��d�ʎԃ��[�h�R��P�O�������P���邱�Ƃ��\
�Ƃ́A�M�҂ɂ͂ƂĂ��l�����Ȃ��̂ł���B
�@�Ƃ���ŁA�}�S��JE�O�T�����WHTC�̎����@�ɂ������]���E���וp�x���z�}������ƁA����JE�O�T�����WHTC��
�������[�h�́A�g���b�N�̎����s�f�[�^����ɍ쐬���ꂽ�G���W���^�]���[�h�ł���B���������āA�}�S��JE�O�T�����
WHTC�̎����@�ɂ������]���E���וp�x���z�}�̉^�]�p�x�̍����̈�ɂ�����G���W���^�]�����i���g���N�Ɖ�]
���x�j�j�Ńf�B�[�[���G���W���̔R��啝�ɉ��P����Ă���A�g���b�N�̎����s��d�ʎԃ��[�h�R��傫�������
����̂ł���B���̌������^�[�{�R���p�E���h�ɂ��R����P�̊������������O�q�̐}�R�ƁA�d�ʎԁi�g���b�N�E�o�X�j��
JE�O�T�����WHTC�̎����@�ɂ������]���E���וp�x���z���������O�q�̐}�S�Ƃ��d�˂Č���ƈ�ڗđR�ł��邪�A
�^�[�{�R���p�E���h�ɂ��ڗ������R����P��������G���W���^�]�i���G���W���̕��ׂƉ�]���x�j�̗̈�́A��^�g
���b�N�̔R�����������s���Ɏg�p�����G���W���^�]�����Ɉ�v����̂��}�R�̃^�[�{�R���p�E���h�G���W����
��X�̈�i���ő�g���N�t�߂̉�]�ԓh��Ŏ����ꂽ2.4���̗̈�j�����ł���B�������A�}�R�̐ԓh��Ŏ����ꂽ�R���
�P��2.4����X�̈�i���G���W���̒�����]�ōő�g���N�ߖT�j�́A�}�S��JE�O�T�����WHTC�̎����@�ɂ������]
���E���וp�x���z�}�ł��G���W���^�]�p�x���ɂ߂ď��Ȃ��G���W���^�]�̈�ł��邱�Ƃɒ��ڂ��ׂ��ł���B
�������[�h�́A�g���b�N�̎����s�f�[�^����ɍ쐬���ꂽ�G���W���^�]���[�h�ł���B���������āA�}�S��JE�O�T�����
WHTC�̎����@�ɂ������]���E���וp�x���z�}�̉^�]�p�x�̍����̈�ɂ�����G���W���^�]�����i���g���N�Ɖ�]
���x�j�j�Ńf�B�[�[���G���W���̔R��啝�ɉ��P����Ă���A�g���b�N�̎����s��d�ʎԃ��[�h�R��傫�������
����̂ł���B���̌������^�[�{�R���p�E���h�ɂ��R����P�̊������������O�q�̐}�R�ƁA�d�ʎԁi�g���b�N�E�o�X�j��
JE�O�T�����WHTC�̎����@�ɂ������]���E���וp�x���z���������O�q�̐}�S�Ƃ��d�˂Č���ƈ�ڗđR�ł��邪�A
�^�[�{�R���p�E���h�ɂ��ڗ������R����P��������G���W���^�]�i���G���W���̕��ׂƉ�]���x�j�̗̈�́A��^�g
���b�N�̔R�����������s���Ɏg�p�����G���W���^�]�����Ɉ�v����̂��}�R�̃^�[�{�R���p�E���h�G���W����
��X�̈�i���ő�g���N�t�߂̉�]�ԓh��Ŏ����ꂽ2.4���̗̈�j�����ł���B�������A�}�R�̐ԓh��Ŏ����ꂽ�R���
�P��2.4����X�̈�i���G���W���̒�����]�ōő�g���N�ߖT�j�́A�}�S��JE�O�T�����WHTC�̎����@�ɂ������]
���E���וp�x���z�}�ł��G���W���^�]�p�x���ɂ߂ď��Ȃ��G���W���^�]�̈�ł��邱�Ƃɒ��ڂ��ׂ��ł���B
�@���̂��Ƃ́A�^�[�{�R���p�E���h��X�̈��2.4���̔R����P�́A��^�g���b�N�̏d�ʎԃ��[�h�R���s���̔R���
�͑傫����^���Ȃ����Ƃ��Ӗ����Ă���B�܂�A���̐}�S��JE�O�T�����WHTC�̎����@�ɂ������]���E���וp�x��
�z�}�ł���^�g���b�N�̏d�ʎԃ��[�h�R���s���̃G���W���^�]�p�x�̑����̈�́A�}�R��X�̈悩����O�ꂽ�^
�[�{�R���p�E���h�ɂ��R����P�̏��Ȃ��^�]�̈�ƂȂ��Ă���̂ł���B���̂��Ƃ���A�^�[�{�R���p�E���h�ł́A��
�^�g���b�N�����d�ʎԁi�g���b�N�E�o�X�j�̏d�ʎԃ��[�h�R��̉��P�����ł��Ȃ����Ƃ������ł���B���������āA�^�[�{�R
���p�E���h�ɂ��d�ʎԃ��[�h�R��̉��P������悭�����ł����ꍇ�ł��A���X�A�P�������ł͂Ȃ����Ɛ�����
���B
�͑傫����^���Ȃ����Ƃ��Ӗ����Ă���B�܂�A���̐}�S��JE�O�T�����WHTC�̎����@�ɂ������]���E���וp�x��
�z�}�ł���^�g���b�N�̏d�ʎԃ��[�h�R���s���̃G���W���^�]�p�x�̑����̈�́A�}�R��X�̈悩����O�ꂽ�^
�[�{�R���p�E���h�ɂ��R����P�̏��Ȃ��^�]�̈�ƂȂ��Ă���̂ł���B���̂��Ƃ���A�^�[�{�R���p�E���h�ł́A��
�^�g���b�N�����d�ʎԁi�g���b�N�E�o�X�j�̏d�ʎԃ��[�h�R��̉��P�����ł��Ȃ����Ƃ������ł���B���������āA�^�[�{�R
���p�E���h�ɂ��d�ʎԃ��[�h�R��̉��P������悭�����ł����ꍇ�ł��A���X�A�P�������ł͂Ȃ����Ɛ�����
���B
�@�ȏ�̂悤�ɁA�����ԋZ�p�v��2011�N9�����́u�����ԗp�G���W���Z�p�̌���Ə����v�̘_���Łu�吹�������r�C�K
�X�̃G�l���M�[�ɂ���ĂQ������P�O���̏d�ʎԃ��[�h�R��̉��P���\�v�Ǝ咣����Ă���Ƃ̗�����O��ɕM
�҂̈ӌ����q�ׂ����Ă��������ƁA�吹�����̃^�[�{�R���p�E���h�ɂ��Ă̌����ɂ��ẮA�����^��Ɏv���Ƃ��낪
����B���̂Ȃ�A�����吹�����́u�^�[�{�R���p�E���h�́A�Q������P�O���̔R����P�ɗL���v�Ƃ���咣�́A�O
�q��3-2���Ɏ������O�H�d�H�̓��{�@��w��_���̎����f�[�^���疾�炩�ƂȂ����u�^�[�{�R���p�E���h���A�C
�����̍ō����͂����߂邱�ƂȂ��G���W���̍��o�͉����\�ł��邪�A�d�ʎԃ��[�h�R��̌���̌��ʂ͂P��
�����ł���v�Ƃ̌��ʂƑ傫���قȂ��Ă������߂ł���B
�X�̃G�l���M�[�ɂ���ĂQ������P�O���̏d�ʎԃ��[�h�R��̉��P���\�v�Ǝ咣����Ă���Ƃ̗�����O��ɕM
�҂̈ӌ����q�ׂ����Ă��������ƁA�吹�����̃^�[�{�R���p�E���h�ɂ��Ă̌����ɂ��ẮA�����^��Ɏv���Ƃ��낪
����B���̂Ȃ�A�����吹�����́u�^�[�{�R���p�E���h�́A�Q������P�O���̔R����P�ɗL���v�Ƃ���咣�́A�O
�q��3-2���Ɏ������O�H�d�H�̓��{�@��w��_���̎����f�[�^���疾�炩�ƂȂ����u�^�[�{�R���p�E���h���A�C
�����̍ō����͂����߂邱�ƂȂ��G���W���̍��o�͉����\�ł��邪�A�d�ʎԃ��[�h�R��̌���̌��ʂ͂P��
�����ł���v�Ƃ̌��ʂƑ傫���قȂ��Ă������߂ł���B
�@�Ƃ���ŁA�吹�����������ꂽ�����ԋZ�p�v��2011�N9�����́u�����ԗp�G���W���Z�p�̌���Ə����v�̘_���ł́A
�u3.2. �d�ʎԂ̔R����P�v�̍��ɂ����ẮA�u�d�ʎԁi�g���b�N�E�o�X�j�̔R����P�ɂ��Ă̌���Ə����v�ɘ_������
���锤�ł���B�����ŁA2015�N�x�d�ʎԔR���ɕs�K���ƂȂ��Ă����^�g���b�N�̎Ԏ�𐔑��������č����Ă���g
���b�N���[�J�̋Z�p�҂́A�R����P�̋Z�p�J���̎Q�l�ɂ��邽�߁A�吹�����̘_�������҂��ēǂ܂ꂽ�l����������
�̂ł͂Ȃ����낤���B�Ƃ��낪�A���̘_���́u3.2. �d�ʎԂ̔R����P�v�̍��ɂ́A��^�g���b�N�̔R����P�̋Z�p�Ƃ���
�́A�O�q�̂m�d�c�n�v�V�I���������Q�ԑ����Z�p�J���i�N���[���f�B�[�[���v���W�F�N�g�A2004�`2009�N�j�ɂ����ĔR
����P�ɖ����ł��邱�Ƃ������ꂽ�u�^�[�{�ߋ��̑��i���v�ƁA�u�r�C�K�X�̃G�l���M�[�v�̋Z�p���L�ڂ���Ă�
�����ƂɊ��҂𗠐��A���_���ꂽ�g���b�N���[�J�̋Z�p�҂����������̂ł͂Ȃ����낤���B
�u3.2. �d�ʎԂ̔R����P�v�̍��ɂ����ẮA�u�d�ʎԁi�g���b�N�E�o�X�j�̔R����P�ɂ��Ă̌���Ə����v�ɘ_������
���锤�ł���B�����ŁA2015�N�x�d�ʎԔR���ɕs�K���ƂȂ��Ă����^�g���b�N�̎Ԏ�𐔑��������č����Ă���g
���b�N���[�J�̋Z�p�҂́A�R����P�̋Z�p�J���̎Q�l�ɂ��邽�߁A�吹�����̘_�������҂��ēǂ܂ꂽ�l����������
�̂ł͂Ȃ����낤���B�Ƃ��낪�A���̘_���́u3.2. �d�ʎԂ̔R����P�v�̍��ɂ́A��^�g���b�N�̔R����P�̋Z�p�Ƃ���
�́A�O�q�̂m�d�c�n�v�V�I���������Q�ԑ����Z�p�J���i�N���[���f�B�[�[���v���W�F�N�g�A2004�`2009�N�j�ɂ����ĔR
����P�ɖ����ł��邱�Ƃ������ꂽ�u�^�[�{�ߋ��̑��i���v�ƁA�u�r�C�K�X�̃G�l���M�[�v�̋Z�p���L�ڂ���Ă�
�����ƂɊ��҂𗠐��A���_���ꂽ�g���b�N���[�J�̋Z�p�҂����������̂ł͂Ȃ����낤���B
�@���͂Ƃ�����A�u3.2. �d�ʎԂ̔R����P�v�̍��ɂ����āA�吹�������u�^�[�{�ߋ��̑��i���v�Ɓu�r�C�K�X�̃G�l���M
�[�v�ȊO�̑�^�g���b�N�̔R����P�Z�p�������L�ڂ���Ă��Ȃ��̂́A�����ł���B����A���̘_���́u2 �K�\����
�G���W���v�́u�i2�j �����\���ƔR����P�Z�p�v�ɍ��ł́A�K�\�����G���W���R����P�Ɋւ��鑽�푽�l�̋Z�p����
��Ă��邪�A�������A�f�B�[�[���G���W������̂́u3.2. �d�ʎԂ̔R����P�v�̍��ɂ����āA�f�B�[�[���G���W�������
�Ƃ���Ă���吹�������u�^�[�{�ߋ��̑��i���v�Ɓu�r�C�K�X�̃G�l���M�[�v�ȊO�̃f�B�[�[���R����P�̋Z�p
�́A�����L�ڂ���Ă��Ȃ��̂ł���B���̂��Ƃ���A�吹�����́A�^�[�{�R���p�E���h���́u�r�C�K�X�̃G�l���M�[��
���v�͏d�ʎԁi�g���b�N�E�o�X�j�̏d�ʎԃ��[�h�R����\���ɉ��P�ł��邱�ƂɊm�M�������̂悤�Ɏv����̂ł���B����
�āA�吹�����́A�^�[�{�R���p�E���h���́u�r�C�K�X�̃G�l���M�[�v�̋Z�p�ɂ���ďd�ʎԁi�g���b�N�E�o�X�j�ł��T��
���x�̏d�ʎԃ��[�h�R������P���A�e�g���b�N���[�J��2015�N�x�d�ʎԔR���ɕs�K���̑�^�g���b�N�̎Ԏ����
�|�ł��邱�Ƃ����M��������Ă���\��������B���̂��߁A�吹�����́A�d�ʎԁi�g���b�N�E�o�X�j�̃f�B�[�[���R��
���P�ɗL���ȋZ�p�Ƃ��āA�d�ʎԁi�g���b�N�E�o�X�j�̏d�ʎԃ��[�h�R��̉��P���^�[�{�R���p�E���h�̂悤���u�r�C�K�X
�̃G�l���M�[�v�̋Z�p�ɂ���ĂQ������P�O���̉��P���\�v�Ƃ������L�q�E����Ă���悤�Ɏv����̂ł�
��B�����Ƃ��A�O�q�̂Q���́uNEDO�́u�����x�R�Đ���G���W�V�X�e���̌����J���v�ł̏d�ʎԃ��[�h�R��̂Q���̈�
�������ʂ�����ƁA�吹�������d�ʎԁi�g���b�N�E�o�X�j�̃f�B�[�[���R����P�ɗL���ȋZ�p�̈�Ƃ��ċ������Ă�
��u�^�[�{�ߋ��̑��i���v�̋Z�p�́A��^�g���b�N�̏d�ʎԃ��[�h�R������P�ł��Ȃ����Ƃ����Ɏ�����Ă���ƍl��
����B
�[�v�ȊO�̑�^�g���b�N�̔R����P�Z�p�������L�ڂ���Ă��Ȃ��̂́A�����ł���B����A���̘_���́u2 �K�\����
�G���W���v�́u�i2�j �����\���ƔR����P�Z�p�v�ɍ��ł́A�K�\�����G���W���R����P�Ɋւ��鑽�푽�l�̋Z�p����
��Ă��邪�A�������A�f�B�[�[���G���W������̂́u3.2. �d�ʎԂ̔R����P�v�̍��ɂ����āA�f�B�[�[���G���W�������
�Ƃ���Ă���吹�������u�^�[�{�ߋ��̑��i���v�Ɓu�r�C�K�X�̃G�l���M�[�v�ȊO�̃f�B�[�[���R����P�̋Z�p
�́A�����L�ڂ���Ă��Ȃ��̂ł���B���̂��Ƃ���A�吹�����́A�^�[�{�R���p�E���h���́u�r�C�K�X�̃G�l���M�[��
���v�͏d�ʎԁi�g���b�N�E�o�X�j�̏d�ʎԃ��[�h�R����\���ɉ��P�ł��邱�ƂɊm�M�������̂悤�Ɏv����̂ł���B����
�āA�吹�����́A�^�[�{�R���p�E���h���́u�r�C�K�X�̃G�l���M�[�v�̋Z�p�ɂ���ďd�ʎԁi�g���b�N�E�o�X�j�ł��T��
���x�̏d�ʎԃ��[�h�R������P���A�e�g���b�N���[�J��2015�N�x�d�ʎԔR���ɕs�K���̑�^�g���b�N�̎Ԏ����
�|�ł��邱�Ƃ����M��������Ă���\��������B���̂��߁A�吹�����́A�d�ʎԁi�g���b�N�E�o�X�j�̃f�B�[�[���R��
���P�ɗL���ȋZ�p�Ƃ��āA�d�ʎԁi�g���b�N�E�o�X�j�̏d�ʎԃ��[�h�R��̉��P���^�[�{�R���p�E���h�̂悤���u�r�C�K�X
�̃G�l���M�[�v�̋Z�p�ɂ���ĂQ������P�O���̉��P���\�v�Ƃ������L�q�E����Ă���悤�Ɏv����̂ł�
��B�����Ƃ��A�O�q�̂Q���́uNEDO�́u�����x�R�Đ���G���W�V�X�e���̌����J���v�ł̏d�ʎԃ��[�h�R��̂Q���̈�
�������ʂ�����ƁA�吹�������d�ʎԁi�g���b�N�E�o�X�j�̃f�B�[�[���R����P�ɗL���ȋZ�p�̈�Ƃ��ċ������Ă�
��u�^�[�{�ߋ��̑��i���v�̋Z�p�́A��^�g���b�N�̏d�ʎԃ��[�h�R������P�ł��Ȃ����Ƃ����Ɏ�����Ă���ƍl��
����B
�@�ȏ�̂悤�ɁA�吹�������^�[�{�R���p�E���h�̂悤���u�r�C�K�X�̃G�l���M�[�v�̋Z�p�ł͏d�ʎԃ��[�h�R���
�Q������P�O���̉��P���\�v�Ƃ̌������������ł���Ƃ̐������A���Ɏ����ł���A���̑吹�����̌����́A�O�q
���O�H�d�H �y�����̋@��w��_���ɂ������^�[�{�R���p�E���h�ɂ��d�ʎԃ��[�h�R��̉��P���P�������̏d�ʎ�
���[�h�R��ł��邱�Ƃ̌��ʂ���傫���������Ă��邱�ƂɂȂ�B���̂��߁A�M�҂́A�吹�����́u�r�C�K�X�̃G�l���M
�[�v�̋Z�p�ł͂Q������P�O�����x�̏d�ʎԃ��[�h�R��̉��P���\�v�Ƃ̌����ɂ́A�S�����ӂł��Ȃ��̂ł�
��B���������āA�����ԋZ�p�v��2011�N9�����́u�����ԗp�G���W���Z�p�̌���Ə����v�̘_���ɂ����āA�����f�[�^��
�����������ꂸ���^�[�{�R���p�E���h�̂悤���u�r�C�K�X�̃G�l���M�[�v�̋Z�p�ɂ���ĂQ������P�O���̔R����P
�i���d�ʎԃ��[�h�R��̉��P�Ɛ����j���\�v�Ƃ̑吹�����̌�ӌ��ɂ́A�M�҂͋^��Ɏv���Ďd���������B
�Q������P�O���̉��P���\�v�Ƃ̌������������ł���Ƃ̐������A���Ɏ����ł���A���̑吹�����̌����́A�O�q
���O�H�d�H �y�����̋@��w��_���ɂ������^�[�{�R���p�E���h�ɂ��d�ʎԃ��[�h�R��̉��P���P�������̏d�ʎ�
���[�h�R��ł��邱�Ƃ̌��ʂ���傫���������Ă��邱�ƂɂȂ�B���̂��߁A�M�҂́A�吹�����́u�r�C�K�X�̃G�l���M
�[�v�̋Z�p�ł͂Q������P�O�����x�̏d�ʎԃ��[�h�R��̉��P���\�v�Ƃ̌����ɂ́A�S�����ӂł��Ȃ��̂ł�
��B���������āA�����ԋZ�p�v��2011�N9�����́u�����ԗp�G���W���Z�p�̌���Ə����v�̘_���ɂ����āA�����f�[�^��
�����������ꂸ���^�[�{�R���p�E���h�̂悤���u�r�C�K�X�̃G�l���M�[�v�̋Z�p�ɂ���ĂQ������P�O���̔R����P
�i���d�ʎԃ��[�h�R��̉��P�Ɛ����j���\�v�Ƃ̑吹�����̌�ӌ��ɂ́A�M�҂͋^��Ɏv���Ďd���������B
�@�܂��A�u�^�[�{�ߋ��̑��i���v�́A�G���W���̒ᑬ�g���N�̌���ƑS���׃g���N�i��4/4���׃g���N�j�t�߂̔R����P��
�͗L���ł��邪�A�������ׂł̏\���ɔR������P�ł���@�\�͖����B���������āA�G���W���������ׂ̉^�]�p�x����
���R����̂i�d05���[�h�ɂ����ẮA�u�^�[�{�ߋ��̑��i���v�ɂ��d�ʎԃ��[�h�R��̏\���ȉ��P�́A����ł��邱
�Ƃ͖��炩���B
�͗L���ł��邪�A�������ׂł̏\���ɔR������P�ł���@�\�͖����B���������āA�G���W���������ׂ̉^�]�p�x����
���R����̂i�d05���[�h�ɂ����ẮA�u�^�[�{�ߋ��̑��i���v�ɂ��d�ʎԃ��[�h�R��̏\���ȉ��P�́A����ł��邱
�Ƃ͖��炩���B
�@���̂悤�ɁA�A�����ԋZ�p�v��2011�N9�����́u�����ԗp�G���W���Z�p�̌���Ə����v�̘_���ł́A�g���b�N���[�J����
�^�g���b�N�̏d�ʎԃ��[�h�R��̉��P���ł��Ȃ����߂�2015�N�x�d�ʎԔR���ɕs�K���̑����̎Ԏ���s�̂���
���Ă��錻��ɂ�������炸�A�吹�����͑�^�g���b�N�i���d�ʎԁj�̏d�ʎԃ��[�h�R�������ł���Z�p�������L��
����Ă��Ȃ��̂ł���B�����āA�h�����ăf�B�[�[���G���W���̑S�����̔R����P���\�ȁu�^�[�{�ߋ��̑��i���v��
�u�r�C�K�X�̃G�l���M�[�v���L����Ă��邾�����B���̂��Ƃ���A�吹�����͑�^�f�B�[�[���g���b�N�̏d�ʎԃ��[
�h�R����\���ɉ��P�ł���Z�p�̒m�����������łȂ��悤�Ȉ�ۂ�M�҂͎�̂ł���B���̂Ȃ�A���ɁA�吹��
�����f�B�[�[���G���W���̏d�ʎԃ��[�h�R����\���ɉ��P�ł������̋Z�p�����������ł���A�u2 �K�\�����G
���W���v�́u�i2�j �����\���ƔR����P�Z�p�v�ɍ��Ɠ��l�ɁA�u3.2. �d�ʎԂ̔R����P�v�̍��ɂ́A����̃f�B�[�[���G
���W���̔R����P�ł���Z�p�����L�q����Ă��锤�ƍl�����邩�炾�B
�^�g���b�N�̏d�ʎԃ��[�h�R��̉��P���ł��Ȃ����߂�2015�N�x�d�ʎԔR���ɕs�K���̑����̎Ԏ���s�̂���
���Ă��錻��ɂ�������炸�A�吹�����͑�^�g���b�N�i���d�ʎԁj�̏d�ʎԃ��[�h�R�������ł���Z�p�������L��
����Ă��Ȃ��̂ł���B�����āA�h�����ăf�B�[�[���G���W���̑S�����̔R����P���\�ȁu�^�[�{�ߋ��̑��i���v��
�u�r�C�K�X�̃G�l���M�[�v���L����Ă��邾�����B���̂��Ƃ���A�吹�����͑�^�f�B�[�[���g���b�N�̏d�ʎԃ��[
�h�R����\���ɉ��P�ł���Z�p�̒m�����������łȂ��悤�Ȉ�ۂ�M�҂͎�̂ł���B���̂Ȃ�A���ɁA�吹��
�����f�B�[�[���G���W���̏d�ʎԃ��[�h�R����\���ɉ��P�ł������̋Z�p�����������ł���A�u2 �K�\�����G
���W���v�́u�i2�j �����\���ƔR����P�Z�p�v�ɍ��Ɠ��l�ɁA�u3.2. �d�ʎԂ̔R����P�v�̍��ɂ́A����̃f�B�[�[���G
���W���̔R����P�ł���Z�p�����L�q����Ă��锤�ƍl�����邩�炾�B
�@���݂ɁA�����ԋZ�p��s�́u�����ԋZ�p�v��Vol.64�ANo�P�A2010�i2010�N1���P�����s�j�̔ѓc�P�� �c���勳���@
���R�����u�f�B�[�[���G���W�����̂P�O�N�v�ɂ̓f�B�[�[���G���W����CO�Q�팸���u�傫�Ȓ���ۑ�v�ƒf�肵�A���́u��
��B���v�ɂ��u�]���̃f�B�[�[���G���W���̗v�f�V�X�e���ɉ����A�R���A�R�āA�G�}�̌����A�V�X�e������̓������Z
�p�����߂��Ă���v�ƋL�ڂ���Ă���A�f�B�[�[���G���W���̐��\�E�r�o�K�X�ɂ������قƂ�ǑS�Ă̗v�f�E���ڂ�
���ǂƂ����̘A�g�����œK���䂪�K�v�Ƃ���|���L�ڂ���Ă���̂��B������t�̌������Œ[�I�ɒ��킷�ƁA����
�_�ł̓f�B�[�[���G���W���̔R��팸�i���b�n�Q�팸�j�́A�u�Z�p�I�ɔ����ǂ���̏v�ɂ���Ƃ̈Ӗ��ɗ����ł���
�̂ł���B���̂悤�ɁA���̔ѓc�����̘_���ł́A�b�n�Q�팸�i���R��팸�j�̕K�v����i�����Ă��邪�A�b�n�Q�팸
�i���R����P�j�̋�̓I�ȋZ�p��������������Ă��Ȃ��̂ł���B
���R�����u�f�B�[�[���G���W�����̂P�O�N�v�ɂ̓f�B�[�[���G���W����CO�Q�팸���u�傫�Ȓ���ۑ�v�ƒf�肵�A���́u��
��B���v�ɂ��u�]���̃f�B�[�[���G���W���̗v�f�V�X�e���ɉ����A�R���A�R�āA�G�}�̌����A�V�X�e������̓������Z
�p�����߂��Ă���v�ƋL�ڂ���Ă���A�f�B�[�[���G���W���̐��\�E�r�o�K�X�ɂ������قƂ�ǑS�Ă̗v�f�E���ڂ�
���ǂƂ����̘A�g�����œK���䂪�K�v�Ƃ���|���L�ڂ���Ă���̂��B������t�̌������Œ[�I�ɒ��킷�ƁA����
�_�ł̓f�B�[�[���G���W���̔R��팸�i���b�n�Q�팸�j�́A�u�Z�p�I�ɔ����ǂ���̏v�ɂ���Ƃ̈Ӗ��ɗ����ł���
�̂ł���B���̂悤�ɁA���̔ѓc�����̘_���ł́A�b�n�Q�팸�i���R��팸�j�̕K�v����i�����Ă��邪�A�b�n�Q�팸
�i���R����P�j�̋�̓I�ȋZ�p��������������Ă��Ȃ��̂ł���B
�S�|�Q�@�u�����ԋZ�p�v���N�Ӂi2011�N8�����s�j�ɂ����邢���U�����Ԃ̊`�����̎咣
�܂��A�����ԋZ�p��2010�N8�����iVol.65�AN0.8�A2011�j�̓��W�F�N�Ӂ@�u�f�B�[�[���G���W���v�i���ҁF�����U�����ԇ��@
�`���q���@���j�́u�S�@�����J���̓����v�ɂ́A�����_�̃f�B�[�[���G���W���̔r�o�K�X�ƔR����팸���邽�߂̍ŋ�
�̋Z�p�������܂Ƃ߂��Ă��锤�ł��邽�߁A���̔N�ӂ́u�S�@�����J���̓����v�����L�̕\�T�Ɏ������B�������A��
���U�����Ԃ̊`���q�����́A�f�B�[�[���G���W���ɂ�����u�r�o�K�X�팸�v�A�u�R����P�v�̉ۑ����������Z�p����
�̓I�ɉ����L�ڂ���Ă��Ȃ����Ƃ���A�g���b�N���[�J�́A�����_�ł̓f�B�[�[���G���W���ɂ�����uNO���팸�v��
�u�R����P�v���Z�p�I�Ɏ�l�܂�̏��ł���ƍl���āA�傫�ȊԈႢ�͖������̂Ɛ��@�����B
�`���q���@���j�́u�S�@�����J���̓����v�ɂ́A�����_�̃f�B�[�[���G���W���̔r�o�K�X�ƔR����팸���邽�߂̍ŋ�
�̋Z�p�������܂Ƃ߂��Ă��锤�ł��邽�߁A���̔N�ӂ́u�S�@�����J���̓����v�����L�̕\�T�Ɏ������B�������A��
���U�����Ԃ̊`���q�����́A�f�B�[�[���G���W���ɂ�����u�r�o�K�X�팸�v�A�u�R����P�v�̉ۑ����������Z�p����
�̓I�ɉ����L�ڂ���Ă��Ȃ����Ƃ���A�g���b�N���[�J�́A�����_�ł̓f�B�[�[���G���W���ɂ�����uNO���팸�v��
�u�R����P�v���Z�p�I�Ɏ�l�܂�̏��ł���ƍl���āA�傫�ȊԈႢ�͖������̂Ɛ��@�����B
| |
|
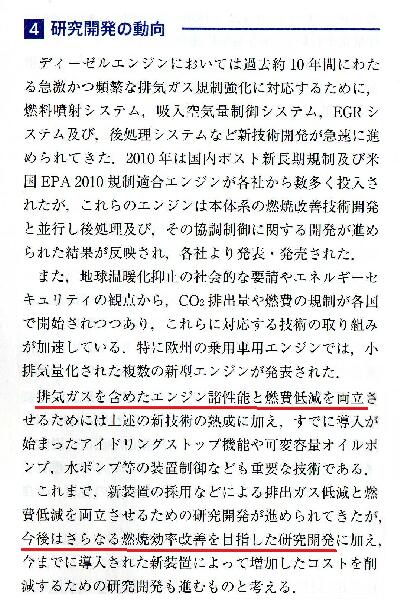 |
�@�����ԋZ�p��201�P�N8�����̓��W�F�N�Ӂ@�u�f�B�[�[���G��
�W���v�́u�S�@�����J���̓����v�ł́A�����U�����Ԃ̊`���q��
���́A����A�u�r�o�K�X���܂߂��G���W�������\�ƔR��ጸ��
�����v��}�邽�߂̗L���ȐV���ȋZ�p�Ƃ��āA�u����Ȃ�R�Č�
�����P��ڎw���������J���v�ƋL�ڂ���Ă��邾���ł���B����
�āA���̔R�Č������P�̊O�̔r�o�K�X�ጸ�ƔR����P�̕��@
�Ƃ��ẮA���Ɏ��p������Ă���A�C�h���X�g�b�v�A�ϗe�ʃI
�C���|���v�A���|���v���̑��u����������A�����āA�s�̎Ԃɓ�
�ڂ̊����Z�p���u�n���v����Əq�ׂ��Ă���B
�@�������A�����Z�p�̉��ǂ́A�G���W���S�̂ŏ�Ɏ��{�����
�ׂ����e�ł���A�r�o�K�X�팸�ƔR����P�Ɋ֘A�����Z�p����
�Ɍ��肳�����̂ł͂Ȃ��B���������āA�����ԋZ�p���̔N��
�́u�S�@�����J���̓����v�ɓ��ɋL�q����K�v�̖������e�ƍl
������B
�@�܂��A���������f�B�[�[���G���W���͓��R�@�ւł��邽�߁A�R
�ĉ��P���K�v�Ȃ��Ƃ́A���̃G���W���̒a���ȗ��̏h���ł�
��A�����ĉۑ�ł�����B���������āA�����ԋZ�p���̓ǎ҂��m
�肽�����Ƃ́A�R�ĉ��P���\�ɂ����̓I�ȐV�����Z�p�ł�
�邪�A�`���q�����́u�S�@�����J���̓����v�ł́A�R�ĉ��P��
��̓I�ȋZ�p�������L�ڂ���Ă��Ȃ��̂��B
�@���������āA�����U�����Ԃ̊`���q�����́A���L���u�S�@����
�J���̓����v�ł́A�f�B�[�[���G���W���ɂ�����u�r�o�K�X��
���v�A�u�R����P�v����сu�R�ĉ��P�̕K�v���v�̉ۑ���q�ׂ�
��Ă��邾���ł���A�����J���̓����ł���ۑ����������Z
�p�̓��e�������L�ڂ���Ă��Ȃ��̂��B���������āA���L�́u�S
�@�����J���̓����v�̍��́A���ʂ̖��ʎg���ƍl������B
�@�ȏ�̂悤�ɁA�g���b�N���[�J�̋Z�p�҂ł���`���q�����́A
�u�S�@�����J���̓����v�ł́A�f�B�[�[���G���W���ɂ�����u�r�o
�K�X�팸�v�A�u�R����P�v�̉ۑ�������ł���V�����Z�p�����
�I�ɉ����L�ڂł��Ȃ������悤���B���̂��Ƃ���A�g���b�N���[�J
�́A�����_�ł̓f�B�[�[���G���W���ɂ�����uNO���팸�v��
�u�R����P�v���Z�p�I�Ɏ�l�܂�̏ł����ƍl���āA��
���ȊԈႢ�͖������̂Ɛ��@�����B
�@���̂悤�ɁA�����U�����Ԃ̊`���q�������A���̔N�ӂł́u�S
�@�����J���̓����v�̍��ɂ����āA�f�B�[�[���G���W���ɂ�����
�u�r�o�K�X�팸�v�A�u�R����P�v�̉ۑ����������Z�p����̓I
�ɉ����ł��Ȃ��������Ƃ���A�g���b�N���[�J�ɂ�����f�B�[
�[���G���W���́uNO���팸�v�Ɓu�R����P�v�̎�i�E�Z�p�����S
�Ɍ͊����Ă���؋��ӎ��ɖ\�I���Ă��Ă���悤�Ɏv����
�̂ł���B����͕M�҂̕��������ł��낤���B
�@�����Ƃ��A�����U�����Ԃ��ŋߗ��s�̃^�[�{�R���p�E���h�̌�
���J�����s���Ă���Ƃ���A�����U�����Ԃ̎Ј��Ƃ��Ă̋@
���ێ��̗��ꂩ��A�`���q�����͂��̔N�ӂ́u�S�@�����J����
�����v�̍��Ƀf�B�[�[���́u�R����P�v�̐V�����Z�p�Ƃ��āA�^
�[�{�R���p�E���h���L�ڂł��Ȃ������\�����ے�ł��Ȃ��B��
�����A���ɁA���̔N�ӂɃ^�[�{�R���p�E���h���L�ڂ��Ă����Ƃ���
���A�^�[�{�R���p�E���h���f�B�[�[���R��̏\���ȔR����P��
�͖����ȋZ�p�̂��߁A�����U�����Ԃ̊`���q�����́A���̔N
�ӂŃf�B�[�[���G���W���ɂ�����u�R����P�v�̉ۑ����������
�Z�p�������I�ɉ����L�ڂ���Ă��Ȃ����Ƃɕς��͖����ƍl
������B
|
�@�ȏ�̂悤�ɁA�����U�����Ԃ̊`���q���́A�����ԋZ�p��2010�N8�����iVol.65�AN0.8�A2011�j�̓��W�F�N�Ӂ@�u�f�B�[
�[���G���W���v�i���ҁF�́u�S�@�����J���̓����v�ɂ́A�f�B�[�[���G���W���ɂ�����u�r�o�K�X�̍팸�v�A�uCO2�팸�v����
�сu�R����P�v�̉ۑ肪������Ă��邪�A�����̉ۑ������������@�Ƃ��Ắu�n���v�Ə̂���u�]���Z�p�̉��ǁv��
���q�ׂ��Ă��Ȃ��B���s�Z�p�̉��ǂ́A�g���b�N���[�J���g���b�N���Y�𑱂��Ă������A���R�A�N�����s���ׂ�����
�Ɩ��ł���B�����āA���̂悤�Ȍ��s�Z�p�̉��ǂ����ł̓f�B�[�[���G���W���̏\���ȔR����P����������Ɖ]���d�v
�ȉۑ���������邱�Ƃ́A����A�s�\�Ȃ��Ƃł��邱�Ƃł���B����ɂ�������炸�A�����N�ӂł́A�����U�����Ԃ�
�`���q�����f�B�[�[���G���W���̉ۑ�����ɍv���ł������ȐV�����Z�p���������Ă��Ȃ��Ƃ��������ƁA��
���_�Ńg���b�N���[�J�́A�uNO���팸�v�Ɓu�R����P�v���Z�p�I�Ɏ�l�܂�̏ɂ�����̂Ɛ��@�����B
�[���G���W���v�i���ҁF�́u�S�@�����J���̓����v�ɂ́A�f�B�[�[���G���W���ɂ�����u�r�o�K�X�̍팸�v�A�uCO2�팸�v����
�сu�R����P�v�̉ۑ肪������Ă��邪�A�����̉ۑ������������@�Ƃ��Ắu�n���v�Ə̂���u�]���Z�p�̉��ǁv��
���q�ׂ��Ă��Ȃ��B���s�Z�p�̉��ǂ́A�g���b�N���[�J���g���b�N���Y�𑱂��Ă������A���R�A�N�����s���ׂ�����
�Ɩ��ł���B�����āA���̂悤�Ȍ��s�Z�p�̉��ǂ����ł̓f�B�[�[���G���W���̏\���ȔR����P����������Ɖ]���d�v
�ȉۑ���������邱�Ƃ́A����A�s�\�Ȃ��Ƃł��邱�Ƃł���B����ɂ�������炸�A�����N�ӂł́A�����U�����Ԃ�
�`���q�����f�B�[�[���G���W���̉ۑ�����ɍv���ł������ȐV�����Z�p���������Ă��Ȃ��Ƃ��������ƁA��
���_�Ńg���b�N���[�J�́A�uNO���팸�v�Ɓu�R����P�v���Z�p�I�Ɏ�l�܂�̏ɂ�����̂Ɛ��@�����B
�@�������A���݁A�����̃g���b�N���[�J�ł́A2015�N�x�d�ʎԔR���ɕs�K���ƂȂ��Ă����^�g���b�N�̎Ԏ�𐔑���
�����Ă���̂��B���̂��߁A�g���b�N���[�J�́A�f�B�[�[���G���W���̏\���ȔR����P�������ł���Z�p�𑁊��Ɏ��p
�����邱�Ƃ��A�҂����Ȃ��̊J���e�[�}�̔��ƍl������B�������A�����_�Ńg���b�N���[�J�ł͏\�����u�R����P�v����
�\�ɂ���V�����Z�p�����������o�����ɋZ�p�I�Ɂu����グ��ԁv�ł���Ƃ���A�g���b�N���[�J�̃G���W���Z�p��
�̃X�g���X�́A�ō����ɒB���Ă�����̂Ɛ��������B
�����Ă���̂��B���̂��߁A�g���b�N���[�J�́A�f�B�[�[���G���W���̏\���ȔR����P�������ł���Z�p�𑁊��Ɏ��p
�����邱�Ƃ��A�҂����Ȃ��̊J���e�[�}�̔��ƍl������B�������A�����_�Ńg���b�N���[�J�ł͏\�����u�R����P�v����
�\�ɂ���V�����Z�p�����������o�����ɋZ�p�I�Ɂu����グ��ԁv�ł���Ƃ���A�g���b�N���[�J�̃G���W���Z�p��
�̃X�g���X�́A�ō����ɒB���Ă�����̂Ɛ��������B
�@�S�|�R�@��ʌ��̃X�[�p�[�N���[���f�B�[�[���G���W�������ɂ�����R�����
���t�H�[�����Q�O�P�O�v�Ə̂���Z�p���\�̍u����J�Â��ꂽ�悤���B���̍u����ɂ́A�䂪�����\���鑽���̌�
�ʊW�̊w�ҁE���Ƃ��o�Ȃ���A����̕��y�����҂���鎟���㎩���Ԃɂ��Ă̋Z�p���\�Ƃ����Ɋւ���c
�_���s��ꂽ�Ƃ̂��Ƃł���B
| |
|
| |
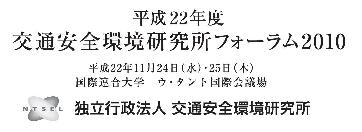 |
�@�����i�Ɓj�ʈ��S���������̍u�����\��ł́A�u�X�[�p�[�N���[���f�B�[�[���iSCD�j�G���W���ɂ�����V�W�J�v�Ƒ�
������^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W���̔R������_���������J���̘_��������Ă���B���̘_����q�ǂ�����
�����������Ƃ���A�L�q�̓��e�ɑ����̋^��_���ڂɕt�����̂ŁA�\�V�ɂ܂Ƃ߂��B
������^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W���̔R������_���������J���̘_��������Ă���B���̘_����q�ǂ�����
�����������Ƃ���A�L�q�̓��e�ɑ����̋^��_���ڂɕt�����̂ŁA�\�V�ɂ܂Ƃ߂��B
| |
|
���
����
�@�@�@�V�G�B�V�[�C�[ �F �� �F�O�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ |
�i�Ɓj�ʈ��S���������ƐV�G�B�V�[�C�[�Ƃ̋��� |
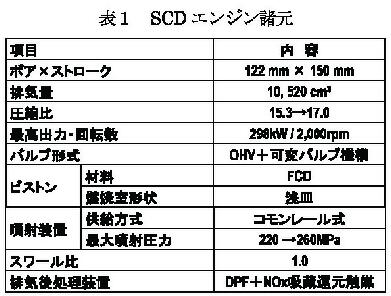 �i�\�P�̃x�[�X�G���W���͓��쎩���Ԃ�PC�P�P�^�Ɛ���j
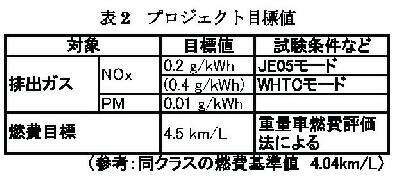 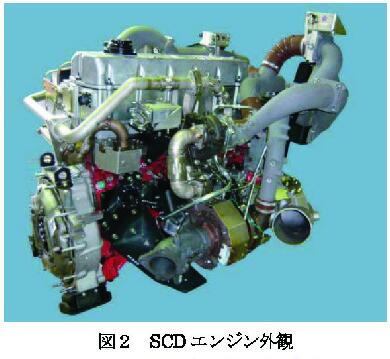 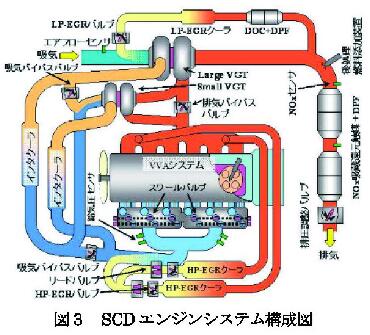 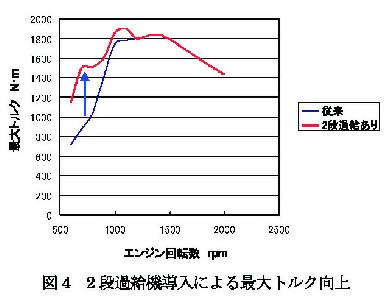 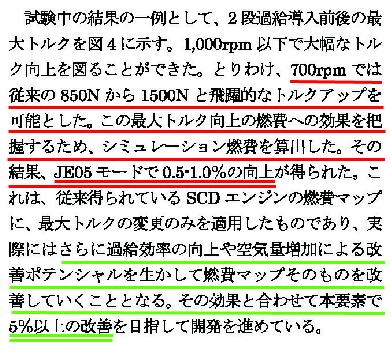 |
�@���L�̌�ʈ��S���������́u�X�[�p�[�N���[���f�B�[�[��
�iSCD�j�G���W���ɂ�����V�W�J�v�̘_���i�Ȍ�A�u��ʈ��S��
��������SCD�G���W���_���v�Ə̂��j�ł́A���L�́u�}�R�@SCD�G
���W���V�X�e���\���}�v�Ɏ�����Ă���悤�ɁA�ȉ��̋Z�p���g
�ݍ��܂�Ă���B
�� �Q�i�V�[�P���V�����ߋ��@
�� �����R�������[���i��260MPa�j
�� LP-EGR�̗̍p�ɂ��EGR����̍��x��
���X
�@�����āA���L�̌�ʈ��S����������SCD�G���W���_���̐}
�R�̃V�X�e���ł́A1000rpm�ȉ��̒ᑬ�ł̃G���W���g���N�A�b
�v�ɂ��AJE�O�T���[�h�R�0.5�`1.0�����x�̉��P�ł�������
�̂��ƁB���̒��x�̔R����P�͔R���̍ۂɐ����鑪��덷
�͈̔͂ɉ߂��Ȃ��B���������āA���̒��x�̔R����P��_����
�ւ炵���ɋL�ڂ��邱�Ƃ́A�@���Ȃ��̂ł��낤���B
�@����A�{�y�[�W�� �y�P�S�|�P�@NEDO�́u�����x�R�Đ���G���W
�V�X�e���̌����J���v�ł́A�R����̑厸�s�z �̍��Ŏ�����
����悤�ɁA8���~�ȏ�̗\�Z�Ŏ��{���ꂽNEDO�Ƃ����U������
�����̊v�V�I���������Q�ԑ����Z�p�J���i�N���[���f�B�[�[
���v���W�F�N�g�A2004�`2009�N�j�́u�����x�R�Đ���G���W�V�X
�e���̌����J���v�̑�^�v���W�F�N�g�ł́A��^�g���b�N�p�f�B�[
�[���G���W���Ɉȉ��̋Z�p��g�ݍ��V�X�e���ɂ��NO����
���ƔR����P�̌����J�������Ɏ��{����Ă���B
�� �R�i�ߋ��V�X�e���i�����ϗL�������j
�� 300MP���̒������R�����ˁi�����ϗL�������j�A�� �J�����X
�V�X�e����g�ݍ��uPCI�R�āv(PCI�R�ā�HCCI�R�āj
����NEDO�̌����J���ł́A�P�S�|�P���̐}�P�U�Ɏ������悤�ɁA
�R��팸�͖ڕW��10���팸�ɂ͑S���y���A2015�N�x�d
�ʎԔR���ɑ��ĂQ���̈������m�F���ꂽ�B���̂悤
�ɁANEDO�̃N���[���f�B�[�[���v���W�F�N�g�́A�f�B�[�[���̔R��
���P�ɂ��Ċ��S�Ɏ��s�ł��������Ƃ�����Ă���̂ł�
��B
�@���āA��ʈ��S����������SCD�G���W���_���ɋL�ڂ����
���鍶�L�́u�}�R�@SCD�G���W���V�X�e���\���}�v�ɐ��荞�܂�
����v�ȋZ�p�́A�O�q�̂W-1���Ŏ������f�B�[�[���̔R����P
�ɂ��Ċ��S�Ɏ��s����NEDO�̊v�V�I���������Q�ԑ����Z
�p�J���i�N���[���f�B�[�[���v���W�F�N�g�A2004�`2009�N�j�́u��
���x�R�Đ���G���W�V�X�e���̌����J���v�Ɨގ��̋Z�p���w��
�ǂł���B���̂��߁A��ʈ��S���������́u�}�R�@SCD�G���W
���V�X�e���\���}�v�ɐ��荞�܂ꂽ�Z�p�ɂ���ăf�B�[�[���G��
�W���̏\���ȔR����P�́A�S�����҂ł��Ȃ����Ƃ͖����łł�
��B�����āA���L�̌�ʈ��S����������SCD�G���W���_����
�́AJE�O�T���[�h�R�0.5�`1.0�����x�̉��P���������Ȃ���
���ƋL�ڂ���Ă��邱�Ƃ́A���R�̌��ʂł͂Ȃ����ƍl�����
��B
�@�Ƃ���ŁA��ʈ��S���������̗�؉��ꎁ�A�Έ�f���A��
���㎁����ѐV�G�B�V�[�C�[�̐� �F�O���́A���L�̌�ʈ�
�S����������SCD�G���W���_���ł́A�u�}�R�@SCD�G���W���V
�X�e���\���}�v�̋Z�p�ɂ���āA����A�u�ߋ��@�����̌�����
�C�ʑ����ŔR��}�b�v�����P���A���L�̐}�R�̃V�X�e���łT����
��iJE�O�T���[�h�j�̔R����P��ڎw���v�ƋL�ڂ���Ă���B����
���A�M�҂ɂ͂��̂悤�Ȃ��Ƃ������ł���Ƃ͂ƂĂ��l�����Ȃ�
�̂��B�Ȃ��Ȃ�A�ߋ��@�̌���������́A�M�c���̖����^�[�r
����u���A�̍ޗ����J���ł����ꍇ�ɏ��߂ċ��C��r�C�K�X��
�R��������ɖh�~�ł���ꍇ��A�^�[�r���H�����ɔ��ł���ޗ�
��������̋Z�p���J���ł����ꍇ�ɂ����āA���߂Ď����ł�
�邱�Ƃł���B�����̉ߋ��@�W�̋Z�p���A����A����I�ɔ�
�W���Ȃ�����A�߂������ɉߋ��@�̌������傫������ł����
�\���͑S�������ƍl����̂��Ó��ł���B�܂��AJE�O�T���[�h��
�̓G���W���������ח̈�ł̉^�]�䗦���������߁AJE�O�T���[
�h�̏\���ȔR�����ɂ́A�������ח̈�ł̔R����P���K�v
�ł���B�����A�f�B�[�[���G���W���͕������ׂł͒�������C��
��̏�Ԃʼn^�]�����̂ł���B����ɂ�������炸�A���L��
��ʈ��S����������SCD�G���W���_���ł́A��C�ʂ̑���
�ŔR��}�b�v�����P�ł���Ǝ咣����Ă��鍪�����M�҂ɂ͗ǂ�
�����ł��Ȃ��Ƃ���ł���B���������āA���L�̘_���ɂ����āA��
�ʈ��S���������̗�A�Έ�A���̏�������ѐV�G�B�V�[
�C�[�̐����́A�u�ߋ��@�����̌�����C�ʑ����ŔR��}�b
�v�����P���A���L�̐}�R�̃V�X�e���łT���ȏ�iJE�O�T���[�h�j��
�R����P��ڎw���v�ƋL�q����Ă��邪�A�����I�ȔR����P��
�Z�p����̓I�ɉ���������Ă��Ȃ��̂ł���B���������āA���L
�̘_���ɂ�����u�T���ȏ�iJE�O�T���[�h�j�̔R����P�v�̏q�́A
���҂̒P�Ȃ��]���q�ׂĂ��邾���ł���A�f�B�[�[���G���W��
�̏\���ȔR����P�����ۂɎ����ł���\���͑S�������Ǝv��
����B
�@�������A�M�҂̗\�z�ɔ����A��ʈ��S���������̗�؉���
���A�Έ�f���A����㎁����ѐV�G�B�V�[�C�[�̐� �F�O��
���A���L�̘_���ɋL�ڂ���Ă���悤�ɁA�u�}�R�@SCD�G���W���V
�X�e���\���}�v�̋Z�p��p���āu�ߋ��@�����̌�����C�ʑ�
���ŔR��}�b�v�����P���A���L�̐}�R�̃V�X�e���łT���ȏ�iJE
�O�T���[�h�j�̔R����P��ڎw���ĊJ����i�߂�v���Ƃɂ���āA��
�^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W���̔R����T���ȏ���̉��P����
�Ɏ����ł����Ƃ���A����͖��@������̈̋Ƃł����
�]����̂ł͂Ȃ����낤���B
�@�ʂ����āA��ʈ��S���������̗�؉��ꎁ�A�Έ�f���A��
���㎁����ѐV�G�B�V�[�C�[�̐� �F�O���́A�{���Ƀf�B�[
�[���R������P���錻�݂̖��p�t�̐l�B�ł���̂��A�����
���A����܂Ō��O��������g���Č����\�Z���l�����Ă����P�Ȃ�
�y�e���t�E���\�t�ɗނ���l�B�ł���̂��́A���̂Ƃ���s����
����B���͂Ƃ�����A��ʈ��S���������̗�؉��ꎁ�A�Έ�
�f���A����㎁����ѐV�G�B�V�[�C�[�̐� �F�O�����R���
�P�̖��p�t���A�Ⴕ���̓y�e���t�E���\�t���̉���ł��邩�́A
�߂������ɂ͖��炩�ɂȂ邱�Ƃł���A�M�҂ɂ͋����[�X�ł�
��B���̌��ʂ��y���݂��B
�Ƃ���ŁA���L�̘_���́A�����̑�^�g���b�N��2015�N�x�d�ʎ�
�R���ɓK�����Ă���2010�N11��24�i���j�E25���i�j�ɊJ��
����Ă���u��ʈ��S���������t�H�[�����Q�O�P�O�v�ł����\��
��Ă���B���̂��Ƃ���A���L�̘_���̓ǎ҂́A���̘_���̃x�[
�X�G���W��(���쎩���Ԃ�PC11�^�Ɛ����j�̏d�ʎԃ��[�h�R��
�l�́A2015�N�x�d�ʎԔR���ɓK�����Ă���R��x���ƍl
���Ă�����̂Ɛ��������B�������A���L�̌�ʈ��S��������
�́u�X�[�p�[�N���[���f�B�[�[���iSCD�j�G���W���ɂ�����V�W�J�v
�̘_���ł́A��^�g���b�N�p�̃x�[�X�G���W��(���쎩���Ԃ�
PC11�^�Ɛ����j�̏d�ʎԃ��[�h�R��l��2015�N�x�d�ʎԔR��
��ɓK�����Ă���|�������L�ڂ���Ă��Ȃ��悤���B���̂���
����A���L�̘_���̃x�[�X�G���W��(���쎩���Ԃ�PC11�^�Ɛ�
���j�̔R��l(�Ⴆ��JE�O�T���[�h�R��j�Ƃ��ė�����l���v����
�ꂽ�ƋL�ڂ��Ă����A���L�́u�}�R�@SCD�G���W���V�X�e���\
���}�v�Ŕ@���Ȃ�R��l���v������悤�Ƃ��A���̍��L�́u�}�R�@
SCD�G���W���V�X�e���\���}�v�̋Z�p��p���āu�ߋ��@������
������C�ʑ����ŔR��}�b�v�����P���A���L�̐}�R�̃V�X�e
���łT���ȏ�iJE�O�T���[�h�j�̔R����P�������ł����v�Ƙ_����
�L�ڂ��Ă����̌��������Ȃ����ƂɂȂ�̂ł���B�v�́A�x�[�X
�G���W��(���쎩���Ԃ�PC11�^�Ɛ����j���P�O�N�ȏ���Â��^��
�G���W���̂��߁A�R��̈����x�[�X�G���W���ł��邱�Ƃ��L�ڂ�
�Ă����A�u�}�R�@SCD�G���W���V�X�e���\���}�v�̋Z�p��p����
���Ƃɂ����JE�O�T���[�h�ł̂T����P�O���̔R����P�̎�����
�ʂ��������Ƃ́A�ɂ߂ĊȒP�Ȃ��Ƃł���B�ܘ_�A���̂悤�Ȏ�@
�ł܂Ƃ߂�ꂽ�_���́A�f�B�[�[���G���W���̔R�����̋Z�p�I
�Ȑi���Ɋ�^���Ȃ����Ƃ͓��R�ł���B�����āA���̂悤�ȕ��@
�́A���\�t��y�e���t�����풃�ю��ɗp�����@���B�������A
���{���\����w�ҁE���Ƃł����ʈ��S���������̗��
���ꎁ�A�Έ�f���A����㎁����ѐV�G�B�V�[�G�[�̐� �F
�O�������\�����_���ɂ����ẮA���̂悤�ȍ��\��y�e���ɗ�
�����@����g���Ę_�����쐬����邱�Ƃ́A�펯�I�ɂ͈��
�����̂ƍl�����邪�E�E�E�E�E�E�B
|
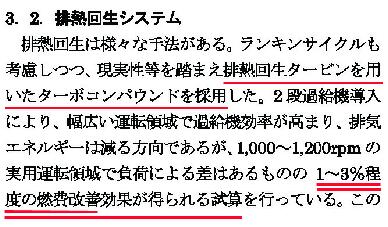 |
�@�O�q�́u�Q�D�f�B�[�[���G���W���ɂ�����r�o�K�X�ጸ�ƔR���
�P�v�ɋL�ڂ��Ă���ʂ�A �^�[�{�R���p�E���h�̔r�M����^�[�r��
�̓����̔r�C�K�X�͒ቷ�E�ሳ�ł��邽�߁A�r�C�K�X�̃G�l��
�M�[�̃|�e���V�������Ⴂ�B���̂��ߔr�C�K�X�̑̐ϗ��ʂ���
���A����^�[�r���͑�^�����K�v�ƂȂ�B���̌��ʃR�X�g�������A
���ԗ����ڂ��e�ՂȂ��Ƃł͂Ȃ��B�܂��A�R����P�́A������
���Ɍ��肳����ɁA���̍����ח̈�ɂ�����R�0�`1.
5�����x�̉��P���邾���ł���B���������āA�^�[�{�R���p
�E���h�ɂ��d�ʎԃ��[�h�R��l�̉��P�́A�����ח̈�ɂ���
��R����P�̔����ȉ��A����0�`0.7���ȉ��ł͂Ȃ����Ɛ���
�����B
�@���������āA���̃^�[�{�R���p�E���h�̋Z�p�́A�R�����ł͖� ���A�����ő刳�͂��㏸�����邱�Ɩ����o�͂������ł����i�� ���邱�Ƃ��ő�̓����ł���B�ȏ�̓��e���^�[�{�R���p�E���h �Z�p�ɂ��Ă̐��E�̑�^�g���b�N�ƊE�ɂ����錻��F���ł� ��B�����Č��݁A�{���{�A�f�g���C�g�f�B�[�[���̑�^�g���b�N�p�G ���W���ɍ̗p����Ă���B �@���āA���L����ʈ��S����������SCD�G���W���_���ɂ��� �āA��ʈ��S���������̗�؉��ꎁ�A�Έ�f���A����� ������ѐV�G�B�V�[�G�[�̐� �F�O�����^�[�{�R���p�E���h�� �̗p�ɂ���ĂP�`�R�����x�̔R����P�i���̌��őS������ �P�O���̔R����P�ƋL�ڂ���Ă��邽�߁A���̂P�`�R�����x�̔R ����P��JE�O�T���[�h�Ɛ����j�ƋL�q����Ă���B���L����ʈ� �S����������SCD�G���W���_���ɂ������P�`�R�����x�̔R�� ���P�̎��Z���ʂ́A���E�̈�ʏ��ɔ�ׂĐ��{�̔R����P �ł���A���̎��Z�ɗp����ꂽ�r�M����^�[�r���̃^�[�r������ �Ƃ��Ĕ��I�ȍ���������p���Čv�Z���ꂽ���̂Ɛ������� ��B���̔��I�ȍ����^�[�r��������p�������\�v�Z�ł́A�R ���Ⴍ�Z�o�ł���̂ł���B���̐́A�^�[�{�G���W���̐��\�V ���~���[�V�����v�Z�����I�ɍs���Ă������Z�p���̕M�҂��猩 ��A���I�ȍ����^�[�r��������p�����G���W���R��̌v �Z�́A�ԈႢ�Ȃ����\�s�ׂł���A�Z�p�҂Ƃ��Ă̗ǐS�̌����� �@���Ɏ����s�ׂƍl���Ă���B �@���������A����̃f�B�[�[���g���b�N�Ƀ^�[�{�R���p�E���h�𓋍� ����ꍇ�́A�ߋ��@�̔r�C�^�[�r������r�o���ꂽ�ቷ�̔r�C �K�X�������^�[�r���ɂ���ăG�l���M�[��������邱�ƂɂȂ�B ���������āA����^�[�r���ł̃G�l���M�[����͒Ⴂ�����ƂȂ� ��������Ȃ��̂ł���B���������āA���̂悤�ȏh�������^�[ �{�R���p�E���h��p���ăf�B�[�[���G���W���̔R������P���悤�� ���邱�Ƃ́A����ł��邱�Ƃ����炩���B���̂��߁A���L����� ���S����������SCD�G���W���_���ɂ����āA��ʈ��S���� �����̗�؉��ꎁ�A�Έ�f���A����㎁����ѐV�G�B�V�[�G �[�̐� �F�O�����^�[�{�R���p�E���h���f�B�[�[���G���W���̔R ����P�̎�i�ƔF������Ă��邱�Ƃ͌��ƍl������B���� �ɁA�C�O�ł̓^�[�{�R���p�E���h�͓����ő刳�͂��㏸�����邱 �Ɩ����o�͂������ł����i�Ɨ�������Ă���A���̕��������� �F���̂悤�ɍl������B �@�Ƃ���ŁA�^�[�{�R���p�E���h��p���ăf�B�[�[���G���W���̔R ��������ł����P������@�́A�M�҂́A�O�q���W�|�R���uAVL�� �u���ł��R����P�̋�̓I�Ȓ�āv�ɂ��L�ڂ��Ă���悤�ɁA�� �^���b�N�̑��s�ő��p�����f�B�[�[���f�B�[�[���G���W���̕� �����^�]���̔r�C�K�X���x�̍�������}�邱�Ƃ��K�v�ł� ��B���̃G���W�����������̔r�C�K�X���x�̍�������}��� �@�Ƃ��āA�M�Ғ�Ă��C���x�~�G���W���i�������J2005- 54771�j�̓����Z�p��p���邱�Ƃ��L���ł���B���������āA��� ���S���������̗�؉��ꎁ�A�Έ�f���A����㎁����� �V�G�B�V�[�G�[�̐� �F�O�����^�[�{�R���p�E���h���R�� �iJE05���[�h�R��܂��͏d�ʎԃ��[�h�R��j�������ł����P���� ���Ƃ̂��l�����������ł���A�S�O�Ȃ����L����ʈ��S�� ��������SCD�G���W���ɕM�Ғ�Ă��C���x�~�G���W���i������ �J2005-54771�j�̋Z�p���̗p���ׂ��ł���B �@ |
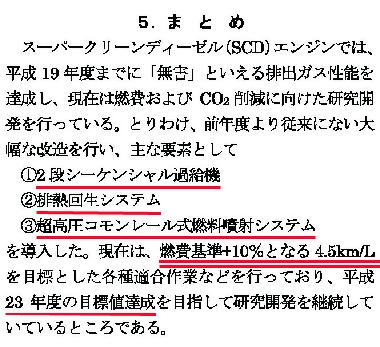 |
�@���L����ʈ��S����������SCD�G���W���_���ɂ����ẮA
SCD�G���W���ɑg�ݍ��܂ꂽ�e��̔R��팸�̋Z�p�ƁA���ꂼ
��̋Z�p�ɂ�����R����P�̖ڕW�����L����Ă���A������
�Z�߂�ƈȉ��̒ʂ�ł���B�i�Ȃ��A�e�Z�p�̂����̔R����P
�̖ڕW�́A�������琄�@����ƁA�����JE�O�T���[�h�̔R��Ɨ\
�������B�j
�� �Q�i�V�[�P���V�����ߋ��@
�R����P���T��
�� �������R�������[���i��260MPa�j
�@�@�R����P���R�`�T��
�� �r�M����V�X�e���i���^�[�{�R���p�E���h�j �@�@�R����P���P�`�R�� �ȏ�̂悤�ɁA���L����ʈ��S����������SCD�G���W���_�� �ł́A�ŋ߁A�b��ƂȂ��Ă���ڐV�����Z�p�́A�啝�ȔR����P ���\�ƍl�����悤�ȋL�q�Ŗ�������Ă���B���������ƁA �u�o�i�i�̂���������v��A�z������悤�ȔR����P�Z�p�́u��� ����v�̗l����悵�Ă���B���̋ɂߕt���́A���L����ʈ��S�� ����������SCD�G���W���_���́u�T�@�� �� �߁v�ł́A�u�Q�i�V�[�P ���V�����ߋ��@�v�{�u�r�M����V�X�e���v�{�u�������R�������[ ���v�ɂ���đ�^�g���b�N�iGVW�Q�T�g���j��2015�N�x�d�ʎԔR�� ����P�O�����R����サ��4.5 �����^���b�g���̏d�ʎԃ��[�h�R ������Q�R�N�x�Ɏ����ł���Ɛ錾����Ă��邱�Ƃł͂Ȃ��� �낤���B���҂̌�ʈ��S���������̗�؉��ꎁ�A�Έ�f���A ����㎁����ѐV�G�B�V�[�G�[�̐� �F�O���̏����́A�� ���Q�R�N�x�����L����ʈ��S����������SCD�G���W���_���� �u�T�@�� �� �߁v�ɋL�ڂ��ꂽ��^�g���b�N�̔R�����̖ڕW�i���d �ʎԗʎԃ��[�h�R��F 4.5 �����^���b�g���j��{���Ɏ����ł���l �����Ă���̂ł��낤���B���݂ɁA�M�҂͂��̖ڕW�B�������� ����\�����ɂ߂č����Ǝv���Ă���B �@�Ȃ��Ȃ�ANEDO�̊v�V�I���������Q�ԑ����Z�p�J���i�N ���[���f�B�[�[���v���W�F�N�g�A2004�`2009�N�j�́u�����x�R�Đ� ��G���W�V�X�e���̌����J���v�ł́A�u���i�ߋ��V�X�e���v�{ �u�������R�������[���v�𓋍ڂ����f�B�[�[���ł͊��ɔR����P �̍���Ȃ��Ƃ��m�F����Ă���̂ł���B�܂��A�u�^�[�{�R���p�E ���h�V�X�e���v�ɂ��ẮA���̃V�X�e���𓋍ڂ�����^�g���b�N ���s�̂��Ă���{���{�A�f�g���C�g�f�B�[�[��������́u�^�[�{�R�� �p�E���h�ł͔R����P������v�Ƃ̏���M����Ă���̂� ����B�����̂��Ƃ���A�u�Q�i�V�[�P���V�����ߋ��@�v���u�r�M�� ���V�X�e���v���u�������R�������[���v�̊e�Z�p�́A����܂ł� �����J���ɂ���ĔR����P���w��NJ��҂ł��Ȃ����Ƃ����ɔ� �����Ă���̂ł���B �@���������āA��ʈ��S���������̗�؉��ꎁ�A�Έ�f���A ����㎁����ѐV�G�B�V�[�G�[�̐� �F�O���̏����́A���� �����ɂ��āu�Q�i�V�[�P���V�����ߋ��@�v�{�u�r�M����V�X�e���v �{�u�������R�������[���v�ɂ���Ă�2015�N�x�d�ʎԔR���� �P�O�����R����サ�� 4.5 �����^���b�g���̏d�ʎԃ��[�h�R��� ��^�g���b�N�iGVW�Q�T�g���j�������Q�R�N�x�Ɏ����ł���Ɛ錾�� ��Ă���̂ł��낤���B�M�҂ɂ͑S�������ł��Ȃ����Ƃł���A �u������������I�v�̐S���ł���B |
�ƂȂ��G���W���̍��o�͉����\�ł��邪�A�R�����̋@�\�͏��Ȃ��A���̌��ʂ͋͏��ł���B�����āA�^�[�{�R���p�E
���h�ɂ��d�ʎԃ��[�h�R��̉��P�́A�P���ȉ��Ɛ��������B���̂��߁A�ȏ���u��ʈ��S���������t�H�[�����Q
�O�P�O�v�Ŕ��\�̘_���u�X�[�p�[�N���[���f�B�[�[���iSCD�j�G���W���ɂ�����V�W�J�v�ł́A�u�Q�i�V�[�P���V�����ߋ��@�v
���u�r�M����V�X�e���i�^�[�{�R���p�E���h�j�v���u�������R�������[���v�̋Z�p��p����2015�N�x�d�ʎԔR�����P
�O�����R����サ�� 4.5 �����^���b�g���̏d�ʎԃ��[�h�R��̑�^�g���b�N�iGVW�Q�T�g���j�������Q�R�N�x����������\
��Ɛ錾����Ă���B�������A�u�Q�i�V�[�P���V�����ߋ��@�v���u�r�M����V�X�e���i�^�[�{�R���p�E���h�j�v���u�������R��
�����[���v�̊e�Z�p�́A������f�B�[�[���̔R����P�̌��ʂ��w��NJ��҂ł��Ȃ��V�X�e���ł���B���������āA����
�Q�R�N�x���d�ʎԃ��[�h�R� 4.5 �����^���b�g���̑�^�g���b�N�iGVW�Q�T�g���j����������ڕW�B���͎��s�ɏI����
�̂Ɨ\�z�����B
�S�|�S�@�^�[�{�R���p�E���h�̂��R����P��AVL�u���i�����ԋZ�p��2010�N�t�G���j
�@�����ԋZ�p��́u�Q�O�P�O�N�l�Ƃ���܂̃e�N�m���W�[�W�v(2010�N5��19�`21�j�Ő��E�I�Ȍ����@�ւł���AVL�i�I�[�X�g
���A�j�̃w�����[�g�E���X�g����u�����A�f�B�[�[���G���W���̔R�����ɂ́A�u�R���s���[�^�v�Z�p�����܂��g���v�Ƃ�
������lj����āu�t���N�V�������X�i���C�����j�̒ጸ�v�Ɓu�V�����_�[���̔R�ĉ��P�v�̃G���W���H�w�̋��ȏ��ɋL�ڂ�
��Ă����̋Z�p���ڂɂ����25���̌������オ�\�Ɣ��\���Ă��邪�A��̓I�ȋZ�p���e�͉��������Ă��Ȃ���
�����B����́A���E�I�Ȍ����@�ւ�AVL����̓I�ȋZ�p���e�������������ɁA�f�B�[�[���G���W���̌�������̒P��
���]���q�ׂĂ���ɉ߂��Ȃ��̂��BAVL�͑S���₵�����e�̍u�����s�������̂��B
���A�j�̃w�����[�g�E���X�g����u�����A�f�B�[�[���G���W���̔R�����ɂ́A�u�R���s���[�^�v�Z�p�����܂��g���v�Ƃ�
������lj����āu�t���N�V�������X�i���C�����j�̒ጸ�v�Ɓu�V�����_�[���̔R�ĉ��P�v�̃G���W���H�w�̋��ȏ��ɋL�ڂ�
��Ă����̋Z�p���ڂɂ����25���̌������オ�\�Ɣ��\���Ă��邪�A��̓I�ȋZ�p���e�͉��������Ă��Ȃ���
�����B����́A���E�I�Ȍ����@�ւ�AVL����̓I�ȋZ�p���e�������������ɁA�f�B�[�[���G���W���̌�������̒P��
���]���q�ׂĂ���ɉ߂��Ȃ��̂��BAVL�͑S���₵�����e�̍u�����s�������̂��B
�@�܂��AAVL�́A��̓I�ȃf�B�[�[���̌�������̕��@�Ƃ��āu�r�C�M��d�C�G�l���M�[�ɕς���R���o�[�^�[��t��
�邱�ƂŁA6 - 7���قnj�������悹�ł���v�Ɣ��\���Ă��邪�A����̓f�B�[�[���G���W���̔r�C�K�X�̔M�G�l���M�[
�������L���T�C�N���A�r�C�K�X�^�[�r���܂��̓X�^�[�����O�G���W�����œ��͂ɕϊ����A���̓��͂Ŕ��d�@���쓮���ēd
�C�G�l���M�[��������鑕�u��t���������̂ƍl������B���́u�r�C�M��d�C�G�l���M�[�ɕς���R���o�[�^�[�v�́A
�Η͔��d�����^�D���ł̓f�B�[�[���G���W������i�o�͂ʼn^�]����邽�߂ɏ�ɍ����̔r�C�K�X��r�o���邽��
�ɍ��������ʼnғ��ł��邽�߁A���ɉΗ͔��d�����^�D���ɂ����čL�����y���Ă��鑕�u�ł���B�������A��^�f�B�[
�[���g���b�N�͏�ɃG���W���o�͂��ϓ������ɕ������ׂ̉^�]�ŒႢ�r�C�K�X���x�ƂȂ邱�Ƃ��������߁A��^�g��
�b�N�Ɂu�r�C�M��d�C�G�l���M�[�ɕς���R���o�[�^�[�v�𓋍ڂ����ꍇ�ɂ͌���������������Ă��܂����ƂɂȂ�B����
���߁A��^�g���b�N�ɂ��̃R���o�[�^�[�𓋍ڂ��Ă��\���ȔR��̌���͓���B���������āAAVL�����̃R���o�[�^�[
�̓��ڂɂ���đ�^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W���̌�����6 - 7���قlj��P�ł���Ƃ̍u���ł̔��\�́A�傫�Ȍ���
�͂Ȃ����낤���B���̗��R�́A�O�q��3-2���Ɏ������O�H�d�H�̓��{�@��w��_���ɂ��ƁA�^�[�{�R���p�E���h���A
�C�����̍ō����͂����߂邱�ƂȂ��G���W���̍��o�͉����\�ł��邪�A�R�����̋@�\�͏��Ȃ��A���̌��ʂ͋͏�
�ł���B�����āA�^�[�{�R���p�E���h�ɂ��d�ʎԃ��[�h�R��̉��P�́A�P���ȉ��Ɛ�������邽�߁AAVL�ɂ��^�[�{
�R���p�E���h���̃R���o�[�^�[�̓��ڂɂ���đ�^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W���̌�����6 - 7���قlj��P�ł���Ƃ�
�u���́A���ƍl������B�@
�邱�ƂŁA6 - 7���قnj�������悹�ł���v�Ɣ��\���Ă��邪�A����̓f�B�[�[���G���W���̔r�C�K�X�̔M�G�l���M�[
�������L���T�C�N���A�r�C�K�X�^�[�r���܂��̓X�^�[�����O�G���W�����œ��͂ɕϊ����A���̓��͂Ŕ��d�@���쓮���ēd
�C�G�l���M�[��������鑕�u��t���������̂ƍl������B���́u�r�C�M��d�C�G�l���M�[�ɕς���R���o�[�^�[�v�́A
�Η͔��d�����^�D���ł̓f�B�[�[���G���W������i�o�͂ʼn^�]����邽�߂ɏ�ɍ����̔r�C�K�X��r�o���邽��
�ɍ��������ʼnғ��ł��邽�߁A���ɉΗ͔��d�����^�D���ɂ����čL�����y���Ă��鑕�u�ł���B�������A��^�f�B�[
�[���g���b�N�͏�ɃG���W���o�͂��ϓ������ɕ������ׂ̉^�]�ŒႢ�r�C�K�X���x�ƂȂ邱�Ƃ��������߁A��^�g��
�b�N�Ɂu�r�C�M��d�C�G�l���M�[�ɕς���R���o�[�^�[�v�𓋍ڂ����ꍇ�ɂ͌���������������Ă��܂����ƂɂȂ�B����
���߁A��^�g���b�N�ɂ��̃R���o�[�^�[�𓋍ڂ��Ă��\���ȔR��̌���͓���B���������āAAVL�����̃R���o�[�^�[
�̓��ڂɂ���đ�^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W���̌�����6 - 7���قlj��P�ł���Ƃ̍u���ł̔��\�́A�傫�Ȍ���
�͂Ȃ����낤���B���̗��R�́A�O�q��3-2���Ɏ������O�H�d�H�̓��{�@��w��_���ɂ��ƁA�^�[�{�R���p�E���h���A
�C�����̍ō����͂����߂邱�ƂȂ��G���W���̍��o�͉����\�ł��邪�A�R�����̋@�\�͏��Ȃ��A���̌��ʂ͋͏�
�ł���B�����āA�^�[�{�R���p�E���h�ɂ��d�ʎԃ��[�h�R��̉��P�́A�P���ȉ��Ɛ�������邽�߁AAVL�ɂ��^�[�{
�R���p�E���h���̃R���o�[�^�[�̓��ڂɂ���đ�^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W���̌�����6 - 7���قlj��P�ł���Ƃ�
�u���́A���ƍl������B�@
�@����AVL����������u�r�C�M��d�C�G�l���M�[�ɕς���R���o�[�^�[�v�́A��^���b�N�̑��s�ő��p�����f�B�[�[��
�f�B�[�[���G���W���̕������^�]���ɂ͔r�C�K�X���x���Ⴍ�A�r�C�K�X�̔M��d�C�G�l���M�[�ɕς���ۂ̌���
����錇�_������B���̌��_�i�����ׁj�����P���邽�߂ɂ́A�f�B�[�[���G���W���̕������^�]���̔r�C�K�X���x
������������V���ȋZ�p��lj����邱�Ƃ��K�v�ł���B���������āAAVL�̒�Ă̂悤�ɁA�u�r�C�M��d�C�G�l���M�[
�ɕς���R���o�[�^�[�v��P�ɑ�^�g���b�N�ɓ��ڂ��������ł́A��^�g���b�N�̏\���ȔR�����͖]�߂Ȃ��̂ł���B
����AVL����^�g���b�N�̔R�����̂��߂Ɂu�r�C�M��d�C�G�l���M�[�ɕς���R���o�[�^�[�v���^�g���b�N�ɓ��ڂ�
�邱�Ƃ��Ă������̂ł���A��^���b�N�̑��s�ő��p�����f�B�[�[���f�B�[�[���G���W���̕������^�]���ɔr
�C�K�X���x������������Z�p���ŏ��ɒ�Ă��ׂ��ł͂Ȃ����ƍl������B�f�B�[�[���G���W���̕������^�]����
�r�C�K�X���x���������ł���Z�p���������Ȃ��Łu�r�C�M��d�C�G�l���M�[�ɕς���R���o�[�^�[�v���^�g���b�N
�ɓ��ڂ���Ƃ�AVL�̍u���ł̒�ẮA�M�҂ɂ͋��̍����Ǝv����̂��BAVL�����̂悤�ȍu�����\�����Ă���Ƃ���
������ƁA�f�B�[�[���G���W���̔R�����ɂ��Ă�AVL���Z�p�A�C�f�A���͊����A�傫�ȕǂɓ˂��������Ă���悤��
�l������B�����āA���̂悤��AVL�ɑ����̃g���b�N���[�J����^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W���̔R�����̃R���T��
�e�B���O��O���������ɎĂ��錻����l����ƁA����̑�^�g���b�N�ɂ͔R�����ɑ傫�Ȋ��҂��ł��Ȃ��ƍl��
��̂��Ó��ł͂Ȃ����낤���B
�f�B�[�[���G���W���̕������^�]���ɂ͔r�C�K�X���x���Ⴍ�A�r�C�K�X�̔M��d�C�G�l���M�[�ɕς���ۂ̌���
����錇�_������B���̌��_�i�����ׁj�����P���邽�߂ɂ́A�f�B�[�[���G���W���̕������^�]���̔r�C�K�X���x
������������V���ȋZ�p��lj����邱�Ƃ��K�v�ł���B���������āAAVL�̒�Ă̂悤�ɁA�u�r�C�M��d�C�G�l���M�[
�ɕς���R���o�[�^�[�v��P�ɑ�^�g���b�N�ɓ��ڂ��������ł́A��^�g���b�N�̏\���ȔR�����͖]�߂Ȃ��̂ł���B
����AVL����^�g���b�N�̔R�����̂��߂Ɂu�r�C�M��d�C�G�l���M�[�ɕς���R���o�[�^�[�v���^�g���b�N�ɓ��ڂ�
�邱�Ƃ��Ă������̂ł���A��^���b�N�̑��s�ő��p�����f�B�[�[���f�B�[�[���G���W���̕������^�]���ɔr
�C�K�X���x������������Z�p���ŏ��ɒ�Ă��ׂ��ł͂Ȃ����ƍl������B�f�B�[�[���G���W���̕������^�]����
�r�C�K�X���x���������ł���Z�p���������Ȃ��Łu�r�C�M��d�C�G�l���M�[�ɕς���R���o�[�^�[�v���^�g���b�N
�ɓ��ڂ���Ƃ�AVL�̍u���ł̒�ẮA�M�҂ɂ͋��̍����Ǝv����̂��BAVL�����̂悤�ȍu�����\�����Ă���Ƃ���
������ƁA�f�B�[�[���G���W���̔R�����ɂ��Ă�AVL���Z�p�A�C�f�A���͊����A�傫�ȕǂɓ˂��������Ă���悤��
�l������B�����āA���̂悤��AVL�ɑ����̃g���b�N���[�J����^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W���̔R�����̃R���T��
�e�B���O��O���������ɎĂ��錻����l����ƁA����̑�^�g���b�N�ɂ͔R�����ɑ傫�Ȋ��҂��ł��Ȃ��ƍl��
��̂��Ó��ł͂Ȃ����낤���B
�@����AVL�����́u�r�C�M��d�C�G�l���M�[�ɕς���R���o�[�^�[�v����^�g���b�N�p�Ƃ��Ď��p�ɑς����鍂��������
�ғ��ł���悤�ɂ��邽�߂ɂ́A��^���b�N�̑��s�ő��p�����f�B�[�[���f�B�[�[���G���W���̕������^�]���ł�
�r�C�K�X���x�̍�������}�邱�Ƃ��K�v�ł���B���̕��@�Ƃ��āA���̃R���o�[�^���̗p����ꍇ�ɂ́A�M�Ғ�Ă��C
���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p��p���邱���K�{�ƍl���Ă���B�t�Ȍ�����������AAVL����
�̔r�C�M��d�C�G�l���M�[�ɕς���R���o�[�^�[�̃V�X�e���ɕM�Ғ�Ă��C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j
�̓����Z�p��p���Ȃ��ꍇ�ɂ́A�����̌��オ�]�߂Ȃ��̂ł���B���̂��߁AAVL����Ă���u�r�C�M��d�C�G�l��
�M�[�ɕς���R���o�[�^�[�v�̃V�X�e���ł́A�d�ʎԃ��[�h�R��̌��オ�\���łȂ��A���p���Ɍ������Z�p�ƍl�����
��B�f�B�[�[���G���W���̔M�����̌����}��Z�p�Ƃ��āAAVL�����́u�R���o�[�^�[�̃V�X�e�����Ă������̂ł���
�A�f�B�[�[���G���W���̕������^�]���̔r�C�K�X���x������������Z�p�ł���M�Ғ�Ă��C���x�~�G���W���i��
�����J2005-54771�j�̓����Z�p�̗̍p�������ɒ�Ă��ׂ��ł���B
�ғ��ł���悤�ɂ��邽�߂ɂ́A��^���b�N�̑��s�ő��p�����f�B�[�[���f�B�[�[���G���W���̕������^�]���ł�
�r�C�K�X���x�̍�������}�邱�Ƃ��K�v�ł���B���̕��@�Ƃ��āA���̃R���o�[�^���̗p����ꍇ�ɂ́A�M�Ғ�Ă��C
���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p��p���邱���K�{�ƍl���Ă���B�t�Ȍ�����������AAVL����
�̔r�C�M��d�C�G�l���M�[�ɕς���R���o�[�^�[�̃V�X�e���ɕM�Ғ�Ă��C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j
�̓����Z�p��p���Ȃ��ꍇ�ɂ́A�����̌��オ�]�߂Ȃ��̂ł���B���̂��߁AAVL����Ă���u�r�C�M��d�C�G�l��
�M�[�ɕς���R���o�[�^�[�v�̃V�X�e���ł́A�d�ʎԃ��[�h�R��̌��オ�\���łȂ��A���p���Ɍ������Z�p�ƍl�����
��B�f�B�[�[���G���W���̔M�����̌����}��Z�p�Ƃ��āAAVL�����́u�R���o�[�^�[�̃V�X�e�����Ă������̂ł���
�A�f�B�[�[���G���W���̕������^�]���̔r�C�K�X���x������������Z�p�ł���M�Ғ�Ă��C���x�~�G���W���i��
�����J2005-54771�j�̓����Z�p�̗̍p�������ɒ�Ă��ׂ��ł���B
�@���݂ɁAAVL�́u�r�C�M��d�C�G�l���M�[�ɕς���R���o�[�^�[�v�ł̓f�B�[�[���G���W���̔r�C�K�X����G�l���M�[
���������6 - 7���i�d�ʎԃ��[�h�R��H�j�̌�������悹����Ƃ̔��\���s���Ă��邪�A����AVL��ẴR���o�[�^�[
���ғ������ۂ̌����͋ɂ߂ĒႢ�Ɨ\�z����邽�߁A���̃R���o�[�^�[���^�g���b�N�ɓ��ڂ����ꍇ�ɂ́A���ۂɑ�
�^�g���b�N�̏d�ʎԃ��[�h�R���6 - 7���قǂ̔R�����悹���邱�Ƃ͋ɂ߂ē�����̂ƍl������B����ɂ���
�́AAVL�͖��ӔC�Ȍ�������̐��l�\�����Ă���̂ł͂Ȃ����Ɗ����Ă���B
���������6 - 7���i�d�ʎԃ��[�h�R��H�j�̌�������悹����Ƃ̔��\���s���Ă��邪�A����AVL��ẴR���o�[�^�[
���ғ������ۂ̌����͋ɂ߂ĒႢ�Ɨ\�z����邽�߁A���̃R���o�[�^�[���^�g���b�N�ɓ��ڂ����ꍇ�ɂ́A���ۂɑ�
�^�g���b�N�̏d�ʎԃ��[�h�R���6 - 7���قǂ̔R�����悹���邱�Ƃ͋ɂ߂ē�����̂ƍl������B����ɂ���
�́AAVL�͖��ӔC�Ȍ�������̐��l�\�����Ă���̂ł͂Ȃ����Ɗ����Ă���B
�@�܂��AAVL�����̍u���Œ�Ă��Ă��������̌�������̋Z�p���G���W���_�E���T�C�W���O�ł���B���̃G���W���_
�E���T�C�W���O�́A�Â�����ǂ��m��ꂽ�R�����̋Z�p�ł���A��^�f�B�[�[���g���b�N�̃��[�J������܂ŋ����ĊJ
�������{���Ă����Z�p�ł��邽�߁A�Z�p�I�ɂ͉��̖ڐV�����������R�����̎�@�ł���B
�E���T�C�W���O�́A�Â�����ǂ��m��ꂽ�R�����̋Z�p�ł���A��^�f�B�[�[���g���b�N�̃��[�J������܂ŋ����ĊJ
�������{���Ă����Z�p�ł��邽�߁A�Z�p�I�ɂ͉��̖ڐV�����������R�����̎�@�ł���B
�@�ȏ�̂悤�ɁA���E�I�Ȍ����@�ւł���AVL��2010�N�T���̍u���ł̒�ẮA�f�B�[�[���G���W���̌�������ɂ�
���Ă͌ÓT�I�Ȋ��m�̋Z�p�Ɍ����Ă���A�Z�p�I�ȖڐV�����͖����B�����āA��^�g���b�N�̔R�����Ɏ��ۂɖ�
�������ȐV�����Z�p�������������Ȃ��̂ł���B����ɂ�������炸�A���݁A���{�̑����̃g���b�N���[�J���L����
AVL����f�B�[�[���G���W�����̋Z�p�R���T���e�B���O���Ă���悤�ł��邪�AAVL�̃R���T���e�B���O�̃R�X�g�p
�[�t�H�[�}���X���Ⴂ���̂ƍl�����邪�A���ۂ̂Ƃ���͂ǂ̂悤�Ȃ��̂ł��낤���B
���Ă͌ÓT�I�Ȋ��m�̋Z�p�Ɍ����Ă���A�Z�p�I�ȖڐV�����͖����B�����āA��^�g���b�N�̔R�����Ɏ��ۂɖ�
�������ȐV�����Z�p�������������Ȃ��̂ł���B����ɂ�������炸�A���݁A���{�̑����̃g���b�N���[�J���L����
AVL����f�B�[�[���G���W�����̋Z�p�R���T���e�B���O���Ă���悤�ł��邪�AAVL�̃R���T���e�B���O�̃R�X�g�p
�[�t�H�[�}���X���Ⴂ���̂ƍl�����邪�A���ۂ̂Ƃ���͂ǂ̂悤�Ȃ��̂ł��낤���B
�S�|�T�@���R�̑�\�����\�ł̃f�B�[�[���R��̌���Z�p�Ƀ^�[�{�R���p�E���h���L��
�@����2010�N�V��28�����\�̒������R�c��E��C������́u����̎����Ԕr�o�K�X�ጸ��̂�����ɂ���
�i��\�����\�j�v�ɂ����āA�������R�c��̎����Ԕr�o�K�X���ψ���̊w�ҁE���Ƃ��쐬���ꂽ�u��\���v
�ł́A�u����A�ȉ��̂悤�ȋZ�p�̐i�W�������ނ��Ƃɂ��A�R��̐L�т�����m�����A�G���W���o���́iNO���́j
�r�o�ʂ�1.5g/kWh���x�܂Œጸ���邱�Ƃ͉\�ł���ƍl������B�v�ƋL�ڂ���Ă���B
�i��\�����\�j�v�ɂ����āA�������R�c��̎����Ԕr�o�K�X���ψ���̊w�ҁE���Ƃ��쐬���ꂽ�u��\���v
�ł́A�u����A�ȉ��̂悤�ȋZ�p�̐i�W�������ނ��Ƃɂ��A�R��̐L�т�����m�����A�G���W���o���́iNO���́j
�r�o�ʂ�1.5g/kWh���x�܂Œጸ���邱�Ƃ͉\�ł���ƍl������B�v�ƋL�ڂ���Ă���B
�@
�@�y��\���ɗ���Ă���Z�p�z
�@�@�E�@2�i�ߋ��A2�i�ߋ������ɂ��G���W���_�E���T�C�W���O
�@�@�E�@EGR���̌���AEGR����̍��x���A�ꕔ�Ԏ�ւ�LP-EGR�̗̍p
�@�@�E�@�R�����ˈ��͂̌���APCI�R�Ăł͈̔͊g�哙�̔R�����ː���̍��x��
�@�@�E�@�ꕔ�Ԏ�ւ��^�[�{�R���p�E���h�V�X�e���̗̍p
�@���̂悤�ɁA�������R�c��̎����Ԕr�o�K�X���ψ���̊w�ҁE���Ƃ́A�u��\���v�ɂ����āA��L�ɗ�
���ꂽ�u�����Z�p�v�ɂ���đ�^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W���́u�R��̐L�т�����m�ہv�Ə̂���R����オ��
�҂ł���Ɛ�������Ă���B�������A���́u�R��̐L�т�����m�ہv�Ə̂���R�����̞B���ȋL�q�����ł́A��^�g���b
�N�p�f�B�[�[���G���W���̏d�ʎԃ��[�h�R������p�[�Z���g�̉��P�����҂ł���̂��A�����͑�^�g���b�N��2015�N�x
�d�ʎԔR���������p�[�Z���g�̔R��̉��P�����҂ł���̂��ɂ��Ă̋�̓I�Ȋ����i�����j�́A�����L�ڂ�
��Ă��Ȃ��̂ł���B�ʂ����āA���́u��\���v�ɗ��ꂽ�Z�p�����p�����邱�Ƃɂ���āA�������R�c���
�����Ԕr�o�K�X���ψ���̊w�ҁE���Ƃ����҂���Ă���d�ʎԃ��[�h�R����p�[�Z���g�̉��P���ł��邩��
���āA�����m�̕���������A����Ƃ����������������������̂ł���B
���ꂽ�u�����Z�p�v�ɂ���đ�^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W���́u�R��̐L�т�����m�ہv�Ə̂���R����オ��
�҂ł���Ɛ�������Ă���B�������A���́u�R��̐L�т�����m�ہv�Ə̂���R�����̞B���ȋL�q�����ł́A��^�g���b
�N�p�f�B�[�[���G���W���̏d�ʎԃ��[�h�R������p�[�Z���g�̉��P�����҂ł���̂��A�����͑�^�g���b�N��2015�N�x
�d�ʎԔR���������p�[�Z���g�̔R��̉��P�����҂ł���̂��ɂ��Ă̋�̓I�Ȋ����i�����j�́A�����L�ڂ�
��Ă��Ȃ��̂ł���B�ʂ����āA���́u��\���v�ɗ��ꂽ�Z�p�����p�����邱�Ƃɂ���āA�������R�c���
�����Ԕr�o�K�X���ψ���̊w�ҁE���Ƃ����҂���Ă���d�ʎԃ��[�h�R����p�[�Z���g�̉��P���ł��邩��
���āA�����m�̕���������A����Ƃ����������������������̂ł���B
�@���̑�\���ɗ���Ă���Z�p�ɂ���đ�^�g���b�N�̏d�ʎԃ��[�h�R������P�ł��銄���́A�����H�����
���T�����x�H�Ⴕ���͂P�O�����x�H�̉���łł��낤���B�����Ƃ��A�u��\���v�ɂ����āA�������R�c��̎�����
�r�o�K�X���ψ���̊w�ҁE���Ƃ��R����P�̊����̐��l����̓I�Ȗ��L���Ȃ��Łu�R��̐L�т�����m�ہv�Ƃ�
�B���ȋL�q�́A��L�ɗ��ꂽ�Z�p�v�ɂ���ĔR�����ł��Ȃ������ꍇ�ɁA�u�ŏ�����\���ȔR����P���\
�Ƃ͉����ɂ��L�ڂ��Ă��Ȃ��v������������Ղ����邽�߂̈Ӑ}���B����Ă���悤�Ɏv����̂ł���B�M�҂̈ӌ���
���킹�Ă���������A�O�q���R�|�Q���Ɏ������悤�ɁA�O�H�d�H�_���̓��R��Ȑ�����\�z�����^�[�{�R���p�E
���h�ɂ��d�ʎԃ��[�h�R��̔R�����̊������P�������ł��邱�Ƃ��l����ƁA��\���ɗ���Ă���Z�p
�ɂ���đ�^�g���b�N�̏d�ʎԃ��[�h�R��̉��P�́A�͂��ȃ��x���ɗ��܂���̂Ɛ��������B
���T�����x�H�Ⴕ���͂P�O�����x�H�̉���łł��낤���B�����Ƃ��A�u��\���v�ɂ����āA�������R�c��̎�����
�r�o�K�X���ψ���̊w�ҁE���Ƃ��R����P�̊����̐��l����̓I�Ȗ��L���Ȃ��Łu�R��̐L�т�����m�ہv�Ƃ�
�B���ȋL�q�́A��L�ɗ��ꂽ�Z�p�v�ɂ���ĔR�����ł��Ȃ������ꍇ�ɁA�u�ŏ�����\���ȔR����P���\
�Ƃ͉����ɂ��L�ڂ��Ă��Ȃ��v������������Ղ����邽�߂̈Ӑ}���B����Ă���悤�Ɏv����̂ł���B�M�҂̈ӌ���
���킹�Ă���������A�O�q���R�|�Q���Ɏ������悤�ɁA�O�H�d�H�_���̓��R��Ȑ�����\�z�����^�[�{�R���p�E
���h�ɂ��d�ʎԃ��[�h�R��̔R�����̊������P�������ł��邱�Ƃ��l����ƁA��\���ɗ���Ă���Z�p
�ɂ���đ�^�g���b�N�̏d�ʎԃ��[�h�R��̉��P�́A�͂��ȃ��x���ɗ��܂���̂Ɛ��������B
�T�@�^�[�{�R���p�E���h�ɂ���^�g���b�N�̔R����P���咣����ŋ߂̕E���q�E������
�@�ȏ�ɂ悤�ɁA�^�[�{�R���p�E���h�́A�C�����̍ō����͂����߂邱�Ɩ����f�B�[�[���G���W���̍��o�͉����\�ł�
�邪�A�G���W���R��̏\���Ȍ���̍���ȋZ�p�ł���B���̂��߁A�^�[�{�R���p�E���h�ɂ��d�ʎԃ��[�h�R��̉��P
�́A�P���ȉ��̒��x�Ɛ��@�����B�������A���̃^�[�{�R���p�E���h���d�ʎԃ��[�h�R����\���Ɍ���ł��Ȃ��Z�p��
���邱�Ƃ�s���m�̂��߂��A����Ƃ��A���̂��Ƃ��Ӑ}�I�ȖَE�������ʂ��ǂ����͔���Ȃ����A�ŋ߁A�^�[�{�R���p�E
���h�͑�^�f�B�[�[���g���b�N�̏d�ʎԃ��[�h�R����\���Ɍ��シ�邱�Ƃ��\�Ǝ咣����_���E�o�ŕ��E�����
�ɂ���@��}�ɑ����ɂȂ����B
�邪�A�G���W���R��̏\���Ȍ���̍���ȋZ�p�ł���B���̂��߁A�^�[�{�R���p�E���h�ɂ��d�ʎԃ��[�h�R��̉��P
�́A�P���ȉ��̒��x�Ɛ��@�����B�������A���̃^�[�{�R���p�E���h���d�ʎԃ��[�h�R����\���Ɍ���ł��Ȃ��Z�p��
���邱�Ƃ�s���m�̂��߂��A����Ƃ��A���̂��Ƃ��Ӑ}�I�ȖَE�������ʂ��ǂ����͔���Ȃ����A�ŋ߁A�^�[�{�R���p�E
���h�͑�^�f�B�[�[���g���b�N�̏d�ʎԃ��[�h�R����\���Ɍ��シ�邱�Ƃ��\�Ǝ咣����_���E�o�ŕ��E�����
�ɂ���@��}�ɑ����ɂȂ����B
�@���̂悤�ɁA�d�ʎԃ��[�h�R������シ��Z�p�Ƃ��āA�����̊w�ҁE���Ƃ��^�[�{�R���p�E���h�𐄏�����悤�ɂȂ�
���w�i�́A�u�R�i�ߋ��V�X�e���p�{�u300MP���̒������R�����ˁv�{�u�J�����X�V�X�e���v�{�uPCI�R�āi��HCCI�R�āj�v�{
�uDPF�v�{�uDeNO���G�}�i���A�fSCR�G�}�j�v�̋Z�p��g�ݍ���NEDO�̊v�V�I���������Q�ԑ����Z�p�J���i�N���[
���f�B�[�[���v���W�F�N�g�A2004�`2009�N�j�ɂ����ẮANOx��PM�͍팸�ł������A�R�2015�N�x�d�ʎԔR����
����Q�����������邱�Ƃ������ꂽ���߂ɑ�^�g���b�N�̔R�����̂��߂ɐ�������Z�p�������Ȃ��Ă��܂������Ƃ�
�����̂悤�ɍl������B�����ʂ����^�g���b�N�����̔R�����̋Z�p�ɂ��Ă̎��������߂���@��̑����w
�ҁE���Ƃ́A�R�����̋Z�p�̒m�����͊����Ă��邱�Ƃ�I�����邱�Ƃ�̍ق悭�B�����߁A�ꂵ����ɔR������
�Z�p�Ƃ��ă^�[�{�R���p�E���h�𐄏����n�߂��̂ł͂Ȃ����Ǝv���Ă���B
���w�i�́A�u�R�i�ߋ��V�X�e���p�{�u300MP���̒������R�����ˁv�{�u�J�����X�V�X�e���v�{�uPCI�R�āi��HCCI�R�āj�v�{
�uDPF�v�{�uDeNO���G�}�i���A�fSCR�G�}�j�v�̋Z�p��g�ݍ���NEDO�̊v�V�I���������Q�ԑ����Z�p�J���i�N���[
���f�B�[�[���v���W�F�N�g�A2004�`2009�N�j�ɂ����ẮANOx��PM�͍팸�ł������A�R�2015�N�x�d�ʎԔR����
����Q�����������邱�Ƃ������ꂽ���߂ɑ�^�g���b�N�̔R�����̂��߂ɐ�������Z�p�������Ȃ��Ă��܂������Ƃ�
�����̂悤�ɍl������B�����ʂ����^�g���b�N�����̔R�����̋Z�p�ɂ��Ă̎��������߂���@��̑����w
�ҁE���Ƃ́A�R�����̋Z�p�̒m�����͊����Ă��邱�Ƃ�I�����邱�Ƃ�̍ق悭�B�����߁A�ꂵ����ɔR������
�Z�p�Ƃ��ă^�[�{�R���p�E���h�𐄏����n�߂��̂ł͂Ȃ����Ǝv���Ă���B
�@������A�O�q�́u�R �O�H�d�H�̘_��������ƁA��^�g���b�N�ɂ�����^�[�{�R���p�E���h�ɂ��R�����͍���v�̍�
�ɏڏq���Ă���悤�ɁA�^�[�{�R���p�E���h�́A�f�B�[�[���G���W���̍��o�͉��ɂ͗L���ł��邪�A�G���W���R��̏\��
�Ȍ���̍���ȋZ�p�ł��邱�Ƃ����ɉ𖾂���Ă���̂ł���B����ɂ�������炸�A���̂悤�ȔR����P�̋@�\��
���^�[�{�R���p�E���h�̋Z�p���^�g���b�N�̔R�����̋Z�p�Ƃ��Đ�������w�ҁE���Ƃ̍l�����́A�M�҂ɂ͑S
�������ł��Ȃ����̂��B�Q�l�Ƃ��āA�ȉ��̕\�W�ɁA�M�҂��ڂɂ�����^�g���b�N�̔R�����̋Z�p�Ƃ��ă^�[�{�R���p
�E���h�𐄏����Ă����_���E�o�ŕ��E�����܂Ƃ߂��B
�ɏڏq���Ă���悤�ɁA�^�[�{�R���p�E���h�́A�f�B�[�[���G���W���̍��o�͉��ɂ͗L���ł��邪�A�G���W���R��̏\��
�Ȍ���̍���ȋZ�p�ł��邱�Ƃ����ɉ𖾂���Ă���̂ł���B����ɂ�������炸�A���̂悤�ȔR����P�̋@�\��
���^�[�{�R���p�E���h�̋Z�p���^�g���b�N�̔R�����̋Z�p�Ƃ��Đ�������w�ҁE���Ƃ̍l�����́A�M�҂ɂ͑S
�������ł��Ȃ����̂��B�Q�l�Ƃ��āA�ȉ��̕\�W�ɁA�M�҂��ڂɂ�����^�g���b�N�̔R�����̋Z�p�Ƃ��ă^�[�{�R���p
�E���h�𐄏����Ă����_���E�o�ŕ��E�����܂Ƃ߂��B
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
�u3.2.�@�d�ʎԂ̔R����P�v
�E�E�E�E�E�E�@�R����P�Z�p�Ƃ��ẮA�^�[�{�ߋ��@�̑��i���ɉ����āA�r�C�^�[�r�����o ���r�C������ɖc���������ۂ̓��͂��o�͎��ɖ߂����J�j�J���^�[�{�R���p�E���h�V�X �e���@�E�E�E�E�E�E�@�����͂����ނ��Q������P�O�����x�̔R����P���\�@�E�E�E�E�E�E�E |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
�y��\���ɗ���Ă���Z�p�z
�@�@�E�@2�i�ߋ��A2�i�ߋ������ɂ��G���W���_�E���T�C�W���O
�@�@�E�@EGR���̌���AEGR����̍��x���A�ꕔ�Ԏ�ւ�LP-EGR�̗̍p
�@�@�E�@�R�����ˈ��͂̌���APCI�R�Ăł͈̔͊g�哙�̔R�����ː���̍��x��
�@�@�E�@�ꕔ�Ԏ�ւ��^�[�{�R���p�E���h�V�X�e���̗̍p
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
��̓I�ȃf�B�[�[���̌�������̕��@�Ƃ��āu�r�C�M��d�C�G�l���M�[�ɕς���R
���o�[�^�[�i���^�[�{�R���p�E���h���̂��Ɓj��t���邱�ƂŁA6 - 7���قnj������� �����ł���v�Ɣ��\ |
�@���������A��^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W���Ɋւ��āu�R����シ��Z�p�v�Ƃ��Đ�������ꍇ�ɂ́A��^�g���b�N��
�u���ۂ̑��s�R��i�������s�R��j�v��u�d�ʎԃ��[�h�R��v������ł���Z�p�𐄋����ׂ��ł��邱�Ƃ́A���R�̂���
�Ȃ�����Ƃł���ΒN�����n�m���Ă��邱�Ƃł����B�����āA��^�g���b�N�́u���ۂ̑��s�i�������s�j�v��u�d�ʎԃ�
�[�h�R��̌v�������v�ɂ�����G���W���^�]�p�x�̋͏��̃G���W���^�]��Ԃł���u�G���W������i�_�i���G���W����
�ō��o�͓_�̉^�]�����j�v��u�G���W���̍ő�g���N�_�v�̃|�C���g�ɂ�������u�G���W���R������シ��Z�p�v�́A��^
�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W���Ɋւ��āu�R����シ��Z�p�v�Ƃ��Ă͎��i�ł��邱�Ƃ��\���ɐS���Ă��锤���B���̂Ȃ�
�A�u�G���W������i�_�i���G���W���̍ō��o�͓_�̉^�]�����j�v��u�G���W���̍ő�g���N�_�v�̃|�C���g�ɂ�������u�G
���W���R������シ��Z�p�v�́A��^�g���b�N�́u���ۂ̑��s�R��i�������s�R��j�v��u�d�ʎԃ��[�h�R��v��w�nj���
�ł��Ȃ����Ƃ����炩�Ȃ��߂��B
�u���ۂ̑��s�R��i�������s�R��j�v��u�d�ʎԃ��[�h�R��v������ł���Z�p�𐄋����ׂ��ł��邱�Ƃ́A���R�̂���
�Ȃ�����Ƃł���ΒN�����n�m���Ă��邱�Ƃł����B�����āA��^�g���b�N�́u���ۂ̑��s�i�������s�j�v��u�d�ʎԃ�
�[�h�R��̌v�������v�ɂ�����G���W���^�]�p�x�̋͏��̃G���W���^�]��Ԃł���u�G���W������i�_�i���G���W����
�ō��o�͓_�̉^�]�����j�v��u�G���W���̍ő�g���N�_�v�̃|�C���g�ɂ�������u�G���W���R������シ��Z�p�v�́A��^
�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W���Ɋւ��āu�R����シ��Z�p�v�Ƃ��Ă͎��i�ł��邱�Ƃ��\���ɐS���Ă��锤���B���̂Ȃ�
�A�u�G���W������i�_�i���G���W���̍ō��o�͓_�̉^�]�����j�v��u�G���W���̍ő�g���N�_�v�̃|�C���g�ɂ�������u�G
���W���R������シ��Z�p�v�́A��^�g���b�N�́u���ۂ̑��s�R��i�������s�R��j�v��u�d�ʎԃ��[�h�R��v��w�nj���
�ł��Ȃ����Ƃ����炩�Ȃ��߂��B
�@����A�^�[�{�R���p�E���h�́A�u�G���W������i�_�i���G���W���̍ō��o�͓_�̉^�]�����j�v�ł̃^�[�{�R���p�E���h�G
���W���R�����P��5���O��ł���A�u�G���W���̍ő�g���N�_�v�ł̃^�[�{�R���p�E���h���R�����P��2���O��ɉ߂���
���Z�p�ł���B�����āA�G���W���̕������ׁi���G���W���̂R�^�S���ȉ��j�ł́A�^�[�{�R���p�E���h�́A�x�[�X�G���W
�������O���`�P�������̔R����P�ɂ����߂��Ȃ��Z�p�ł���B���������āA��^�g���b�N�́u�d�ʎԃ��[�h�R��̃G��
�W���^�]�v��u�����s�̃G���W���^�]�v�ɂ����ăG���W���^�]�p�x�̍����G���W���̒����i���ő�g���N�t�߂̃G���W��
��]���x�j�̒����ׂł́A�^�[�{�R���p�E���h�G���W�́A�x�[�X�G���W�������P�������̔R����P�����ɉ߂��Ȃ��Z�p
�ł���B���������āA��^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W���Ƀ^�[�{�R���p�E���h�����������ł́A�^�[�{�R���p�E���h�G
���W���ɂ����^�g���b�N�́u�d�ʎԃ��[�h�R��v��u�����s�̔R��v�̉��P�́A�P�������Ɏ~�܂���̂Ɛ��@�����B��
�������āA�^�[�{�R���p�E���h�̋Z�p�́A��^�g���b�N���u�d�ʎԃ��[�h�R��v��u�����s�̔R��v���\�������シ
��Z�p�Ƃ��Ă͎��i�ł����ƍl������B
���W���R�����P��5���O��ł���A�u�G���W���̍ő�g���N�_�v�ł̃^�[�{�R���p�E���h���R�����P��2���O��ɉ߂���
���Z�p�ł���B�����āA�G���W���̕������ׁi���G���W���̂R�^�S���ȉ��j�ł́A�^�[�{�R���p�E���h�́A�x�[�X�G���W
�������O���`�P�������̔R����P�ɂ����߂��Ȃ��Z�p�ł���B���������āA��^�g���b�N�́u�d�ʎԃ��[�h�R��̃G��
�W���^�]�v��u�����s�̃G���W���^�]�v�ɂ����ăG���W���^�]�p�x�̍����G���W���̒����i���ő�g���N�t�߂̃G���W��
��]���x�j�̒����ׂł́A�^�[�{�R���p�E���h�G���W�́A�x�[�X�G���W�������P�������̔R����P�����ɉ߂��Ȃ��Z�p
�ł���B���������āA��^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W���Ƀ^�[�{�R���p�E���h�����������ł́A�^�[�{�R���p�E���h�G
���W���ɂ����^�g���b�N�́u�d�ʎԃ��[�h�R��v��u�����s�̔R��v�̉��P�́A�P�������Ɏ~�܂���̂Ɛ��@�����B��
�������āA�^�[�{�R���p�E���h�̋Z�p�́A��^�g���b�N���u�d�ʎԃ��[�h�R��v��u�����s�̔R��v���\�������シ
��Z�p�Ƃ��Ă͎��i�ł����ƍl������B
�@����ɂ�������炸�A�ȏ�̕\�W�Ɏ������悤�ɁA�_���E�o�ŕ��E�����ɂ����āA�����̊w�ҁE���Ƃ��A�u��^�g
���b�N�́u�d�ʎԃ��[�h�R��v��u�����s�̔R��v�̉��P���P���������^�[�{�R���p�E���h�̋Z�p���u��^�g���b�N�̔R��
���P���\�v�ƒp���������������A���X��������咣�\���Ă���̂ł̂ł���B�M�҂ɂ͐M�����Ȃ����Ƃł���B
���̏�A�w�ҁE���Ƃ̒��ɂ́A������NEDO�̊v�V�I���������Q�ԑ����Z�p�J���i�N���[���f�B�[�[���v���W�F�N
�g�A2004�`2009�N�j�ɂ����ďd�ʎԃ��[�h�R�2015�N�x�d�ʎԔR�������Q�����������邱�Ƃ������ꂽ�u�R
�i�ߋ��V�X�e���p�{�u300MP���̒������R�����ˁv�{�u�J�����X�V�X�e���v�{�uPCI�R�āi��HCCI�R�āj�v�{�uDPF�v�{
�uDeNO���G�}�i���A�fSCR�G�}�j�v�̋Z�p���A��^�g���b�N�̔R����P�̋Z�p�Ƃ��Đ������Ă��邱�Ƃ��A�M�҂ɂ́u�{��
�ɁH�v�Ƒ傢�ɋ�������邱�Ƃł���B
���b�N�́u�d�ʎԃ��[�h�R��v��u�����s�̔R��v�̉��P���P���������^�[�{�R���p�E���h�̋Z�p���u��^�g���b�N�̔R��
���P���\�v�ƒp���������������A���X��������咣�\���Ă���̂ł̂ł���B�M�҂ɂ͐M�����Ȃ����Ƃł���B
���̏�A�w�ҁE���Ƃ̒��ɂ́A������NEDO�̊v�V�I���������Q�ԑ����Z�p�J���i�N���[���f�B�[�[���v���W�F�N
�g�A2004�`2009�N�j�ɂ����ďd�ʎԃ��[�h�R�2015�N�x�d�ʎԔR�������Q�����������邱�Ƃ������ꂽ�u�R
�i�ߋ��V�X�e���p�{�u300MP���̒������R�����ˁv�{�u�J�����X�V�X�e���v�{�uPCI�R�āi��HCCI�R�āj�v�{�uDPF�v�{
�uDeNO���G�}�i���A�fSCR�G�}�j�v�̋Z�p���A��^�g���b�N�̔R����P�̋Z�p�Ƃ��Đ������Ă��邱�Ƃ��A�M�҂ɂ́u�{��
�ɁH�v�Ƒ傢�ɋ�������邱�Ƃł���B
�@���āA��ʂ̕����������̂����������ہA�����̎}�슯�[�������u�����Ɍ��N�ɉe���͖����i���^���́A���Ԃ��o
�߂���Ί��ǂ��郊�X�N���B���j�v�ƘA�Ă��Ă������Ƃ�A���q�͊W���w�ҁE���ƂƏ̂���l�B���u���ː���
100�~���V�[�x���g�܂ň��S�i���^���́A3��11���������������̂̈ȑO�ł́A���̕��˔\�픚�̈��S����P�~���V
�[�x���g�ł��������Ƃ��j�v���e���r���A���A������������Ƃ́A�����̐l�ɂƂ��ċL���ɐV�������Ƃł���B��������
�����̎��̔����̒�����w�ҁE���Ƃ���ʐl�ɉR�Ǝv�������\�I�Ȍ����ŋ\���Ă����̂Ɠ����悤�ɁA�ŋ߂̃f�B
�[�[���G���W���W�̊w�ҁE���Ƃ́A��^�g���b�N�̔R����P�̋Z�p�Ƃ��āu�^�[�{�R���p�E���h�v�A�u���i�ߋ��V�X�e
���v�A�u�������R�����ˁv�A�uPCI�R�āi��HCCI�R�āj�v���̋Z�p�ɂ���đ�^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W���̏\���ȔR
����オ�ł���Ƃ̋��U�Ƃ����������Ȕ��\��p�ɂɍs���A�����̃g���b�N���[�U���ʂ̐l�X�ɁA�߂������ɂ͑�^
�g���b�N�̏\���ȔR����オ�����ł���Ƃ̌��z��������Ă���悤�Ɏv����̂ł���B
�߂���Ί��ǂ��郊�X�N���B���j�v�ƘA�Ă��Ă������Ƃ�A���q�͊W���w�ҁE���ƂƏ̂���l�B���u���ː���
100�~���V�[�x���g�܂ň��S�i���^���́A3��11���������������̂̈ȑO�ł́A���̕��˔\�픚�̈��S����P�~���V
�[�x���g�ł��������Ƃ��j�v���e���r���A���A������������Ƃ́A�����̐l�ɂƂ��ċL���ɐV�������Ƃł���B��������
�����̎��̔����̒�����w�ҁE���Ƃ���ʐl�ɉR�Ǝv�������\�I�Ȍ����ŋ\���Ă����̂Ɠ����悤�ɁA�ŋ߂̃f�B
�[�[���G���W���W�̊w�ҁE���Ƃ́A��^�g���b�N�̔R����P�̋Z�p�Ƃ��āu�^�[�{�R���p�E���h�v�A�u���i�ߋ��V�X�e
���v�A�u�������R�����ˁv�A�uPCI�R�āi��HCCI�R�āj�v���̋Z�p�ɂ���đ�^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W���̏\���ȔR
����オ�ł���Ƃ̋��U�Ƃ����������Ȕ��\��p�ɂɍs���A�����̃g���b�N���[�U���ʂ̐l�X�ɁA�߂������ɂ͑�^
�g���b�N�̏\���ȔR����オ�����ł���Ƃ̌��z��������Ă���悤�Ɏv����̂ł���B
�@���̂悤�ȉR�E���\�Ǝv�������C�Ŕ��\�����ŋ߂��w�ҁE���Ƃ̌������݂Ă���ƁA�����Ȋw�ҁE���Ƃ�
�͋��U���M���Ă����������ʂȖƍߕ����^�����Ă���ƔF�����Ă���悤�Ɏv����̂ł���B���̂悤�Ȗ�
�ߕ��́A��́A�N�ɗ^����ꂽ�̂ł��낤���B���Ȃ��Ƃ��A����ł́A�ŋ߂��w�ҁE���Ƃ́A���ɓ��X�Ɖ��H��ʊ��
���U�E���\�Ǝv�����u��^�g���b�N�̒�R��̋Z�p���v��ɔ��\���Ă��邢��悤���B
�͋��U���M���Ă����������ʂȖƍߕ����^�����Ă���ƔF�����Ă���悤�Ɏv����̂ł���B���̂悤�Ȗ�
�ߕ��́A��́A�N�ɗ^����ꂽ�̂ł��낤���B���Ȃ��Ƃ��A����ł́A�ŋ߂��w�ҁE���Ƃ́A���ɓ��X�Ɖ��H��ʊ��
���U�E���\�Ǝv�����u��^�g���b�N�̒�R��̋Z�p���v��ɔ��\���Ă��邢��悤���B
�@���݂ɁA����܂ł̓��{�ł́A���������Ȋw�ҁE���Ƃ��Ⴆ�R�⍼�\�I�ȋZ�p���\�����Ƃ��Ă��A�`���I��
�N�����ʂ�����ɂ��Ĕᔻ���S���s���Ȃ�����ȎЉ�̂悤���B���̌��ʁA�킪���ł́A�����̊w�ҁE����
�́A��������ɓ���ėL���ɂȂ��Ă��܂��ƁA�ȒP�Ɂu���̉��l�v�ɂȂ��Ă��܂��悤�Ɍ�����B���̂悤�ȕM�҂�
����Ȋ��z�͂��Ă����A�����ȃf�B�[�[���G���W���W�̊w�ҁE���Ƃ����R�Ƒ�^�g���b�N�̔R����P�̋Z�p�Ƃ���
�u�^�[�{�R���p�E���h�v�A�u���i�ߋ��V�X�e���v�A�u�������R�����ˁv�A�uPCI�R�āi��HCCI�R�āj�v���̋Z�p�ɂ���đ�^�g
���b�N�p�f�B�[�[���G���W���̏\���ȔR����オ�ł���Ƃ��R�E���\�Ǝv�����Z�p���\���Ă��錻��ɂ���
�́A�V���ڂ�̃|���R�c���Z�p���̕M�҂ɂƂ��ẮA�S�������ł��Ȃ����Ƃ��B����Ƃ��A���̂悤�Ɏv���Ă��܂��̂́A
�M�҂��N�����߂��Đ��m�ȋZ�p�������U�E���\�I�ȋZ�p���ƌ�����Ă��܂��Ă��錋�ʂł���A���Ɂu�����낭�V
�l�v�̒��ԓ�������Ă��鏊�ׂł��낤���B
�N�����ʂ�����ɂ��Ĕᔻ���S���s���Ȃ�����ȎЉ�̂悤���B���̌��ʁA�킪���ł́A�����̊w�ҁE����
�́A��������ɓ���ėL���ɂȂ��Ă��܂��ƁA�ȒP�Ɂu���̉��l�v�ɂȂ��Ă��܂��悤�Ɍ�����B���̂悤�ȕM�҂�
����Ȋ��z�͂��Ă����A�����ȃf�B�[�[���G���W���W�̊w�ҁE���Ƃ����R�Ƒ�^�g���b�N�̔R����P�̋Z�p�Ƃ���
�u�^�[�{�R���p�E���h�v�A�u���i�ߋ��V�X�e���v�A�u�������R�����ˁv�A�uPCI�R�āi��HCCI�R�āj�v���̋Z�p�ɂ���đ�^�g
���b�N�p�f�B�[�[���G���W���̏\���ȔR����オ�ł���Ƃ��R�E���\�Ǝv�����Z�p���\���Ă��錻��ɂ���
�́A�V���ڂ�̃|���R�c���Z�p���̕M�҂ɂƂ��ẮA�S�������ł��Ȃ����Ƃ��B����Ƃ��A���̂悤�Ɏv���Ă��܂��̂́A
�M�҂��N�����߂��Đ��m�ȋZ�p�������U�E���\�I�ȋZ�p���ƌ�����Ă��܂��Ă��錋�ʂł���A���Ɂu�����낭�V
�l�v�̒��ԓ�������Ă��鏊�ׂł��낤���B
�@�Ƃ���ŁA�O�q�̂悤�ɁA�����U�����Ԃ̊`���q�����́A�����ԋZ�p��2010�N8�����̔N���u�f�B�[�[���G���W���v��
�u�S�@�����J���̓����v�������āA�����_�̃f�B�[�[���G���W���̔r�o�K�X�ƔR����팸���邽�߂̍ŋ߂̋Z�p������
�܂Ƃ߂��Ă���B�������A���̔N�ӂł́A�\�X�Ɏ������悤�ɁA�������^�g���b�N�̏d�ʎԃ��[�h�R������P����Z
�p�Ƃ��āA�`���q�����́A��̓I�ȋZ�p���e�̐����������Ɂu�R�Č������P�v�Ƃ̕M�҂ɂ��Ӗ��s���̋Z�p���ڂƁA
�u���s�Z�p�̉��ǁv�����Ă��邾���ł����B���̂悤�ɁA�����U�����Ԃ̊`���q�����́A�u�^�[�{�R���p�E���h�v�A
�u���i�ߋ��V�X�e���v�A�u�������R�����ˁv�A�uPCI�R�āi��HCCI�R�āj�v���̋Z�p�ɂ���đ�^�g���b�N�p�f�B�[�[���G��
�W���̏\���ȔR����オ�ł���Ƃ̐��Ԃɔ×����Ă��������Z�p���������L�q������Ă��Ȃ��Ƃ��������ƁA�M
�҂ɂ͋ɂ߂Đ^�ʖڂŗǐS�I�Ȃȃf�B�[�[���G���W���Z�p�҂̂悤�Ɏv����̂ł���B
�u�S�@�����J���̓����v�������āA�����_�̃f�B�[�[���G���W���̔r�o�K�X�ƔR����팸���邽�߂̍ŋ߂̋Z�p������
�܂Ƃ߂��Ă���B�������A���̔N�ӂł́A�\�X�Ɏ������悤�ɁA�������^�g���b�N�̏d�ʎԃ��[�h�R������P����Z
�p�Ƃ��āA�`���q�����́A��̓I�ȋZ�p���e�̐����������Ɂu�R�Č������P�v�Ƃ̕M�҂ɂ��Ӗ��s���̋Z�p���ڂƁA
�u���s�Z�p�̉��ǁv�����Ă��邾���ł����B���̂悤�ɁA�����U�����Ԃ̊`���q�����́A�u�^�[�{�R���p�E���h�v�A
�u���i�ߋ��V�X�e���v�A�u�������R�����ˁv�A�uPCI�R�āi��HCCI�R�āj�v���̋Z�p�ɂ���đ�^�g���b�N�p�f�B�[�[���G��
�W���̏\���ȔR����オ�ł���Ƃ̐��Ԃɔ×����Ă��������Z�p���������L�q������Ă��Ȃ��Ƃ��������ƁA�M
�҂ɂ͋ɂ߂Đ^�ʖڂŗǐS�I�Ȃȃf�B�[�[���G���W���Z�p�҂̂悤�Ɏv����̂ł���B
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
�u�S�@�����J���̓����v
�E�E�E�E�E�E�@�r�o�K�X���܂߂��G���W�������\�ƔR����P�𗼗������邽�߂ɂ͏�q�� �V�Z�p�i�����s�̎s�̃g���b�N�ɍ̗p�ς݂̋Z�p�j���n���ɉ����E�E�E�E�E�E����͂���� ���R�Č������P��ڎw���������J���E�E�E�E�E�E�E |
�@���̂悤�ɁA�����U�����Ԃ̊`���q�����́A�����ԋZ�p��2011�N8�����̔N���u�f�B�[�[���G���W���v�́u�S�@�����J
���̓����v�������ẮA��^�g���b�N�̏d�ʎԃ��[�h�R��̉��P�̋Z�p�ɂ��ẮA�������Ƃɏ]���Z�p�̉��LjȊO
�ɁA�V�����Z�p�������L�ڂ���Ă��Ȃ����Ƃ��������B�����āA�g���b�N���[�J�̊`���q�������\�z���鍡��̃f�B�[�[
���R����P�̋Z�p�́A�u���݂̎s�̃g���b�N�ɍ̗p����Ă���]���Z�p�̉��ǁv�ƁA�ڍד��e���s���Łu�_���݁v�Ƃ��]
�������Ȑ̂���́u�G���W���J���̏C����v�Ƃ��������u�R�Č������P�v�����ł���B���̓��e������ƁA�g���b�N���[�J��
�Z�p�҂́A��^�g���b�N��5�����x�̏d�ʎԃ��[�h�R������P�ł���V�����Z�p������J���ł��Ă��Ȃ��ɂ���
�Ɛ��������B���̂悤�ȑ�^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W���̋Z�p�J���̌��������ƁA�߂������A���{�̑�^�g��
�b�N�ɂ����āA5�����x�̏d�ʎԃ��[�h�R������P���A2015�N�x�d�ʎԔR���ɖ��B���̎Ԏ����|���A��
���I�ɂT�����x�̔R����シ��Ɖ]���ۑ���g���b�N���[�J���߂������ɉ������邱�Ƃ́A����Ɨ\�z������B
���̓����v�������ẮA��^�g���b�N�̏d�ʎԃ��[�h�R��̉��P�̋Z�p�ɂ��ẮA�������Ƃɏ]���Z�p�̉��LjȊO
�ɁA�V�����Z�p�������L�ڂ���Ă��Ȃ����Ƃ��������B�����āA�g���b�N���[�J�̊`���q�������\�z���鍡��̃f�B�[�[
���R����P�̋Z�p�́A�u���݂̎s�̃g���b�N�ɍ̗p����Ă���]���Z�p�̉��ǁv�ƁA�ڍד��e���s���Łu�_���݁v�Ƃ��]
�������Ȑ̂���́u�G���W���J���̏C����v�Ƃ��������u�R�Č������P�v�����ł���B���̓��e������ƁA�g���b�N���[�J��
�Z�p�҂́A��^�g���b�N��5�����x�̏d�ʎԃ��[�h�R������P�ł���V�����Z�p������J���ł��Ă��Ȃ��ɂ���
�Ɛ��������B���̂悤�ȑ�^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W���̋Z�p�J���̌��������ƁA�߂������A���{�̑�^�g��
�b�N�ɂ����āA5�����x�̏d�ʎԃ��[�h�R������P���A2015�N�x�d�ʎԔR���ɖ��B���̎Ԏ����|���A��
���I�ɂT�����x�̔R����シ��Ɖ]���ۑ���g���b�N���[�J���߂������ɉ������邱�Ƃ́A����Ɨ\�z������B
�U�@���E�ɂ�����^�[�{�R���p�E���h�G���W���̌����J���̗��j�Ǝs�̂̏�
�@�O�q�̂悤�ɁA�^�[�{�R���p�E���h�́A�ߋ��f�B�[�[���G���W���̑S���o�͎��̍����r�C�K�X����G�l���M�[���G
���W���o�͎��ɉ���ł���V�X�e���ł��邱�Ƃɒ��ڂ��A��^�g���b�N�̔R�����Z�p�Ƃ��ČÂ����猤���J�����s��
��Ă����B���̌��ʁA�^�[�{�R���p�E���h�́A�C�����̍ō����͂����߂邱�Ɩ����f�B�[�[���G���W���̍��o�͉�����
�\�ł��邪�A��^�g���b�N���d�ʎԃ��[�h�R��̉��P���P���ȉ��̒��x�ɗ��܂邱�Ƃ����炩�ƂȂ��Ă���B���̂��߁A
���݂ł́A�f�u�v50�g���̂悤�Ȓ��d�ʃg���[���̗p�ɂ��������鍂�o�͂̕K�v�ȑ�^�g���N�^�Ƀ^�[�{�R���p�E���h�G
���W�����̗p����Ă���B�����āA�^�[�{�R���p�E���h�G���W���͏d�ʎԃ��[�h�R��̉��P�ɂ͑傫�Ȍ��ʂ�������
�߁A�ʏ�̑�^�g���b�N�Ƀ^�[�{�R���p�E���h�G���W�����̗p����Ă����͖w�ǂȂ��悤���B���̏𗝉����Ղ���
�邽�߂ɁA�^�[�{�R���p�E���h�̃V�X�e���T�v�A�J���̗��j�����ȉ��̕\�P�O�Ɏ������B
���W���o�͎��ɉ���ł���V�X�e���ł��邱�Ƃɒ��ڂ��A��^�g���b�N�̔R�����Z�p�Ƃ��ČÂ����猤���J�����s��
��Ă����B���̌��ʁA�^�[�{�R���p�E���h�́A�C�����̍ō����͂����߂邱�Ɩ����f�B�[�[���G���W���̍��o�͉�����
�\�ł��邪�A��^�g���b�N���d�ʎԃ��[�h�R��̉��P���P���ȉ��̒��x�ɗ��܂邱�Ƃ����炩�ƂȂ��Ă���B���̂��߁A
���݂ł́A�f�u�v50�g���̂悤�Ȓ��d�ʃg���[���̗p�ɂ��������鍂�o�͂̕K�v�ȑ�^�g���N�^�Ƀ^�[�{�R���p�E���h�G
���W�����̗p����Ă���B�����āA�^�[�{�R���p�E���h�G���W���͏d�ʎԃ��[�h�R��̉��P�ɂ͑傫�Ȍ��ʂ�������
�߁A�ʏ�̑�^�g���b�N�Ƀ^�[�{�R���p�E���h�G���W�����̗p����Ă����͖w�ǂȂ��悤���B���̏𗝉����Ղ���
�邽�߂ɁA�^�[�{�R���p�E���h�̃V�X�e���T�v�A�J���̗��j�����ȉ��̕\�P�O�Ɏ������B
| |
|
| |
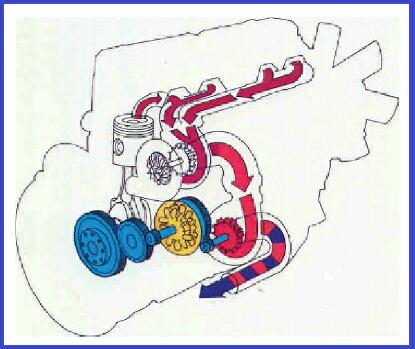 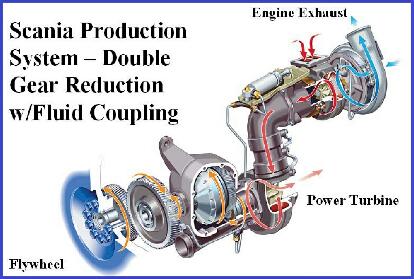 |
| |
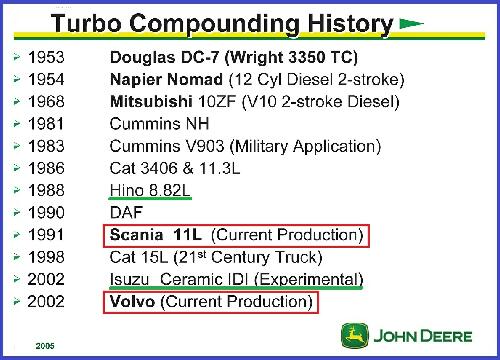 |
�@���̕\�P�O������ƁA���݁A�X�J�j�A�ƃ{���{���^�[�{�R���p�E���h�G���W�����ڂ̑�^�g���N�^���s�̂��Ă���A�X�J�j
�A�̃^�[�{�R���p�E���h���ڂ̑�^�g���N�^�́A���삪���{�Ŕ̔����Ă������Ƃ�����悤���B�����āA�ߋ��ɓ���Ƃ�
���U�̓^�[�{�R���p�E���h�̌��������{���Ă���A�^�[�{�R���p�E���h�́A�C�����̍ō����͂����߂邱�Ɩ����f�B�[�[
���G���W���̍��o�͉����\�ł��邪�A��^�g���b�N���d�ʎԃ��[�h�R��̉��P���P���ȉ��̒��x�ɗ��܂邱�Ƃ��\
���ɗ������Ă�����̂Ɛ��@�����B�R��ɁA�O�q�̕\�T�Ɏ������悤�ɁA���݂ł������̊w�ҁE���Ƃ��^�[�{�R���p
�E���h�ɂ���^�g���b�N�̏d�ʎԃ��[�h�R��̌��オ�\�Ǝ咣����Ă���̂́A����₢���U���^�[�{�R���p�E���h
�̎������ʂ𖢂��Ɍ��\���Ă��Ȃ����Ƃ��A�����̈�Ƃ��l������B
�A�̃^�[�{�R���p�E���h���ڂ̑�^�g���N�^�́A���삪���{�Ŕ̔����Ă������Ƃ�����悤���B�����āA�ߋ��ɓ���Ƃ�
���U�̓^�[�{�R���p�E���h�̌��������{���Ă���A�^�[�{�R���p�E���h�́A�C�����̍ō����͂����߂邱�Ɩ����f�B�[�[
���G���W���̍��o�͉����\�ł��邪�A��^�g���b�N���d�ʎԃ��[�h�R��̉��P���P���ȉ��̒��x�ɗ��܂邱�Ƃ��\
���ɗ������Ă�����̂Ɛ��@�����B�R��ɁA�O�q�̕\�T�Ɏ������悤�ɁA���݂ł������̊w�ҁE���Ƃ��^�[�{�R���p
�E���h�ɂ���^�g���b�N�̏d�ʎԃ��[�h�R��̌��オ�\�Ǝ咣����Ă���̂́A����₢���U���^�[�{�R���p�E���h
�̎������ʂ𖢂��Ɍ��\���Ă��Ȃ����Ƃ��A�����̈�Ƃ��l������B
�V�@�ި���ق̔R�����́A�����߳��ނł͍���ł��邪�A�C���x�~�ł͎������\�I
�@���݂̓��{�̃g���b�N�ƊE�ɂ����ẮA�O�q�̕\�P�Ɏ������悤�ɁA�e�g���b�N���[�J�́A��^�g���b�N�E�g���N�^�̑�����
�Ԏ킪�Q�O�P�T�N�x�d�ʎԔR���ɕs�K���̏ł���B�e�g���b�N���[�J������Ă��̏���E�o���邽�߂�
�́A�T�����x�̏d�ʎԃ��[�h�R������P�ł���Z�p�����p������K�v������B�ܘ_�A�����_�ł͊e�g���b�N���[�J�Ƃ�
�T�����x�̏d�ʎԃ��[�h�R������P�ł���Z�p���J���ł��Ă��Ȃ����炱���A��^�g���b�N�̈ꕔ�̎Ԏ��2015�N�x
�d�ʎԔR���ɖ��B���̂܂ܔ̔�����������Ȃ��Ɋׂ��Ă���̂ł���B
�Ԏ킪�Q�O�P�T�N�x�d�ʎԔR���ɕs�K���̏ł���B�e�g���b�N���[�J������Ă��̏���E�o���邽�߂�
�́A�T�����x�̏d�ʎԃ��[�h�R������P�ł���Z�p�����p������K�v������B�ܘ_�A�����_�ł͊e�g���b�N���[�J�Ƃ�
�T�����x�̏d�ʎԃ��[�h�R������P�ł���Z�p���J���ł��Ă��Ȃ����炱���A��^�g���b�N�̈ꕔ�̎Ԏ��2015�N�x
�d�ʎԔR���ɖ��B���̂܂ܔ̔�����������Ȃ��Ɋׂ��Ă���̂ł���B
�@����܂ő����̊w�ҁE���Ƃ́A�u���i�ߋ��V�X�e���v�A�u�������R�����ˁv�A�uPCI�R�āi��HCCI�R�āj�v�̋Z�p�ɂ��
�đ�^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W���̔R����オ�ł���ƁA�������̘_���Ŏ咣����Ă����B�������A�O�q�̒ʂ�A
2009�N��NEDO�̊v�V�I���������Q�ԑ����Z�p�J���i�N���[���f�B�[�[���v���W�F�N�g�A2004�`2009�N�j�ł́A�u���i
�ߋ��V�X�e���v�A�u�������R�����ˁv�A�uPCI�R�āi��HCCI�R�āj�v��g�ݍ��킹���G���W���̌��������{���ꂽ�B������
���̃v���W�F�N�g�̌������ʂ�2009�N�ɔ��\���ꂽ�B���̃v���W�F�N�g���ŏI�ɂ�����u���i�ߋ��V�X�e���v�A�u��
�����R�����ˁv�A�uPCI�R�āi��HCCI�R�āj�v��g�ݍ��킹�Z�p�́A 0.2 g/kWh�܂ł�NO���팸�̖ڕW�͒B��
�ł��邪�A�d�ʎԃ��[�h�R��� 2015�N�x�d�ʎԔR�����2���������������Ƃ����炩�ƂȂ����B����2009�N
�̕ɂ�����f�B�[�[���G���W����NO���팸�ƔR�����̋Z�p�Ƃ��āu���i�ߋ��V�X�e���v�A�u�������R�����ˁv�A
�uPCI�R�āi��HCCI�R�āj�v�̋Z�p�ɂ���đ�^�g���b�N�̔R����P���s�\�ł��邱�Ƃ�������Ă��܂����̂ł���B
�đ�^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W���̔R����オ�ł���ƁA�������̘_���Ŏ咣����Ă����B�������A�O�q�̒ʂ�A
2009�N��NEDO�̊v�V�I���������Q�ԑ����Z�p�J���i�N���[���f�B�[�[���v���W�F�N�g�A2004�`2009�N�j�ł́A�u���i
�ߋ��V�X�e���v�A�u�������R�����ˁv�A�uPCI�R�āi��HCCI�R�āj�v��g�ݍ��킹���G���W���̌��������{���ꂽ�B������
���̃v���W�F�N�g�̌������ʂ�2009�N�ɔ��\���ꂽ�B���̃v���W�F�N�g���ŏI�ɂ�����u���i�ߋ��V�X�e���v�A�u��
�����R�����ˁv�A�uPCI�R�āi��HCCI�R�āj�v��g�ݍ��킹�Z�p�́A 0.2 g/kWh�܂ł�NO���팸�̖ڕW�͒B��
�ł��邪�A�d�ʎԃ��[�h�R��� 2015�N�x�d�ʎԔR�����2���������������Ƃ����炩�ƂȂ����B����2009�N
�̕ɂ�����f�B�[�[���G���W����NO���팸�ƔR�����̋Z�p�Ƃ��āu���i�ߋ��V�X�e���v�A�u�������R�����ˁv�A
�uPCI�R�āi��HCCI�R�āj�v�̋Z�p�ɂ���đ�^�g���b�N�̔R����P���s�\�ł��邱�Ƃ�������Ă��܂����̂ł���B
�@����܂ł̓����������U��Ԃ��Ă݂�ƁA�����̊w�ҁE���Ƃ́A��^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W����NO���팸�ƔR��
����̋Z�p�Ƃ��āA�u���i�ߋ��V�X�e���v�A�u�������R�����ˁv�A�uPCI�R�āi��HCCI�R�āj�v�̋Z�p�ɂ���ĔR����オ
�ł���Ɛ���ɐ�������Ă����B�Ƃ��낪�A�ˑR�A����NEDO�̃v���W�F�N�g���ŏI��m�炳�ꂽ�̂ł���B����
NEDO�̃v���W�F�N�g���ŏI��ǂ�ŋ����Ռ��ɏP��ꂽ�̂́A�u���i�ߋ��V�X�e���v�A�u�������R�����ˁv�A�uPCI
�R�āi��HCCI�R�āj�v�ɂ���đ�^�g���b�N�̏d�ʎԃ��[�h�R��̏\���ȉ��P���\�Ǝ咣����Ă����f�B�[�[���G���W
���W�̑����̊w�ҁE���Ƃł͂Ȃ����낤���B�Ȃ��Ȃ�ANEDO�̃v���W�F�N�g���ŏI�ɂ���āA�����̊w�ҁE���
�Ƃ��咣����Ă����d�ʎԃ��[�h�R��̉��P�Z�p���u�I�O��v�ł��������Ƃ��ؖ�����Ă��܂����̂ł���B�����ŁA��
���̊w�ҁE���Ƃ́A�̖ʂ����U�����߂ɁA�}篁A��ĂɌ��𑵂��đ�^�g���b�N�̏d�ʎԃ��[�h�R��̉��P�Z�p�Ƃ�
�ĐV���Ƀ^�[�{�R���p�E���h�̋Z�p��lj������悤�ɂȂ����悤���B���̂悤�ɁA�ŋ߂ł́A�f�B�[�[���G���W����NO��
�팸�ƔR�����̋Z�p�Ƃ��ă^�[�{�R���p�E���h�̖��̂́A�����̊w�ҁE���Ƃ̒���ł́u�������肾���v�̂悤�ł�
��B
����̋Z�p�Ƃ��āA�u���i�ߋ��V�X�e���v�A�u�������R�����ˁv�A�uPCI�R�āi��HCCI�R�āj�v�̋Z�p�ɂ���ĔR����オ
�ł���Ɛ���ɐ�������Ă����B�Ƃ��낪�A�ˑR�A����NEDO�̃v���W�F�N�g���ŏI��m�炳�ꂽ�̂ł���B����
NEDO�̃v���W�F�N�g���ŏI��ǂ�ŋ����Ռ��ɏP��ꂽ�̂́A�u���i�ߋ��V�X�e���v�A�u�������R�����ˁv�A�uPCI
�R�āi��HCCI�R�āj�v�ɂ���đ�^�g���b�N�̏d�ʎԃ��[�h�R��̏\���ȉ��P���\�Ǝ咣����Ă����f�B�[�[���G���W
���W�̑����̊w�ҁE���Ƃł͂Ȃ����낤���B�Ȃ��Ȃ�ANEDO�̃v���W�F�N�g���ŏI�ɂ���āA�����̊w�ҁE���
�Ƃ��咣����Ă����d�ʎԃ��[�h�R��̉��P�Z�p���u�I�O��v�ł��������Ƃ��ؖ�����Ă��܂����̂ł���B�����ŁA��
���̊w�ҁE���Ƃ́A�̖ʂ����U�����߂ɁA�}篁A��ĂɌ��𑵂��đ�^�g���b�N�̏d�ʎԃ��[�h�R��̉��P�Z�p�Ƃ�
�ĐV���Ƀ^�[�{�R���p�E���h�̋Z�p��lj������悤�ɂȂ����悤���B���̂悤�ɁA�ŋ߂ł́A�f�B�[�[���G���W����NO��
�팸�ƔR�����̋Z�p�Ƃ��ă^�[�{�R���p�E���h�̖��̂́A�����̊w�ҁE���Ƃ̒���ł́u�������肾���v�̂悤�ł�
��B
�@���̂悤�ɁA�������w�ҁE���Ƃ́ANEDO�̃v���W�F�N�g���ŏI�ɂ���āA�u���i�ߋ��V�X�e���v�A�u�������R����
�ˁv�A�uPCI�R�āi��HCCI�R�āj�v�̋Z�p�ɂ���ďd�ʎԃ��[�h�R����P�ł���Ƃ̂���܂ł̎咣���u�I�O��v�ł���
�����Ƃ̎��Ԃ��B�����߂̋���̍�Ƃ��āA�Z�p���e���\���ɗ������Ă��Ȃ��^�[�{�R���p�E���h���^�g���b�N�̏d
�ʎԃ��[�h�R��̉��P�̋Z�p�Ƃ��Ĉ�������o���ꂽ�悤�ɍl������B�Ƃ��낪�A���̃^�[�{�R���p�E���h�̋Z�p�́A
�O�q�́u�R�|�Q�@�O�H�d�H�_���̓��R��Ȑ�����\�z�����^�[�{�R���p�E���h�ɂ��R�����̊����v�̍���������
�悤���A�u�^�[�{�R���p�E���h�́A�C�����̍ō����͂����߂邱�ƂȂ��A�G���W���̍��o�͉����\�ȋZ�p�ł�
��A�R�����̋@�\�͏��Ȃ��A�d�ʎԃ��[�h�R����P�����������ł��Ȃ��悤�ȔR����P�ɕs�K�ȋZ�p�v�ł���B
���̂��Ƃ́A2005�N���\���O�H�d�H�̋@��w��_���̓��e����e�Ղɗ����ł��邱�Ƃ��B�������A�������w�ҁE����
����^�g���b�N�̏d�ʎԃ��[�h�R��̉��P�̋Z�p�Ƃ��ă^�[�{�R���p�E���h�̋Z�p��M�S�ɐ�������Ă��邱�Ƃɂ�
�Ă̕M�҂̊��z�́A�����̉����ł��Ȃ��Ƃ̌��t�ȊO���v�������Ȃ��B
�ˁv�A�uPCI�R�āi��HCCI�R�āj�v�̋Z�p�ɂ���ďd�ʎԃ��[�h�R����P�ł���Ƃ̂���܂ł̎咣���u�I�O��v�ł���
�����Ƃ̎��Ԃ��B�����߂̋���̍�Ƃ��āA�Z�p���e���\���ɗ������Ă��Ȃ��^�[�{�R���p�E���h���^�g���b�N�̏d
�ʎԃ��[�h�R��̉��P�̋Z�p�Ƃ��Ĉ�������o���ꂽ�悤�ɍl������B�Ƃ��낪�A���̃^�[�{�R���p�E���h�̋Z�p�́A
�O�q�́u�R�|�Q�@�O�H�d�H�_���̓��R��Ȑ�����\�z�����^�[�{�R���p�E���h�ɂ��R�����̊����v�̍���������
�悤���A�u�^�[�{�R���p�E���h�́A�C�����̍ō����͂����߂邱�ƂȂ��A�G���W���̍��o�͉����\�ȋZ�p�ł�
��A�R�����̋@�\�͏��Ȃ��A�d�ʎԃ��[�h�R����P�����������ł��Ȃ��悤�ȔR����P�ɕs�K�ȋZ�p�v�ł���B
���̂��Ƃ́A2005�N���\���O�H�d�H�̋@��w��_���̓��e����e�Ղɗ����ł��邱�Ƃ��B�������A�������w�ҁE����
����^�g���b�N�̏d�ʎԃ��[�h�R��̉��P�̋Z�p�Ƃ��ă^�[�{�R���p�E���h�̋Z�p��M�S�ɐ�������Ă��邱�Ƃɂ�
�Ă̕M�҂̊��z�́A�����̉����ł��Ȃ��Ƃ̌��t�ȊO���v�������Ȃ��B
�@�ȏ�ɗp�ɁA�ŋ߁A�������w�ҁE���Ƃ���^�g���b�N�̏d�ʎԃ��[�h�R������P����Z�p�Ƃ��āA�^�[�{�R���p�E���h
�𐄏�����Ă��邱�Ƃ́A����܂ł��u���i�ߋ��V�X�e���v�A�u�������R�����ˁv�A�uPCI�R�āi��HCCI�R�āj�v�̋Z�p�ɂ�
��d�ʎԃ��[�h�R��̉��P�̎咣�����ł������̂Ɠ��l�ɁA�f�B�[�[���G���W���̏\���ȔR����P�̕��@�Ƃ��ă^�[
�{�R���p�E���h�̗̍p�𐄏��������������E�咣�ӔC�ɌJ��Ԃ���Ă���悤�Ɏv����̂ł���B���̂悤��
�Ȃ��Ă��܂��Ă���傫�Ȍ����̈�Ƃ��āA�w�ҁE���Ƃ��^�[�{�R���p�E���h�̋Z�p�ɂ��Ă̎��g�ł̏\���ȋ�
���E�����E�l�@�������邱�Ɩ����A�����ɓ��������̓��e���\�b�N�����̂܂��肳��Ă���\�����l�����
��B������̌����Ƃ��ẮA��^�g���b�N�̏d�ʎԃ��[�h�R������P����Z�p���s���Ȃ��߁A���炩�̋Z�p�������o
�����܂ł̎��ԉ҂��̂��߂̃_�~�[�̋Z�p�Ƃ��āA�w�ҁE���Ƃ��^�[�{�R���p�E���h�𐄏�����Ă���\������
���ɂ����ƍl������B�������A����̗��R�ɂ��Ă��A�w�ҁE���Ƃ���^�g���b�N�̏d�ʎԃ��[�h�R����\���ɉ�
�P�ł��Ȃ��^�[�{�R���p�E���h�������̑�^�g���b�N�̔R����P�̋Z�p�Ƃ��Đ�������Ă��邽�߁A�w�ҁE���Ƃ�M
������l�B�𗠐�s�ׂł��邱�Ƃɂ́A�ς��͂Ȃ��ƍl������B
�𐄏�����Ă��邱�Ƃ́A����܂ł��u���i�ߋ��V�X�e���v�A�u�������R�����ˁv�A�uPCI�R�āi��HCCI�R�āj�v�̋Z�p�ɂ�
��d�ʎԃ��[�h�R��̉��P�̎咣�����ł������̂Ɠ��l�ɁA�f�B�[�[���G���W���̏\���ȔR����P�̕��@�Ƃ��ă^�[
�{�R���p�E���h�̗̍p�𐄏��������������E�咣�ӔC�ɌJ��Ԃ���Ă���悤�Ɏv����̂ł���B���̂悤��
�Ȃ��Ă��܂��Ă���傫�Ȍ����̈�Ƃ��āA�w�ҁE���Ƃ��^�[�{�R���p�E���h�̋Z�p�ɂ��Ă̎��g�ł̏\���ȋ�
���E�����E�l�@�������邱�Ɩ����A�����ɓ��������̓��e���\�b�N�����̂܂��肳��Ă���\�����l�����
��B������̌����Ƃ��ẮA��^�g���b�N�̏d�ʎԃ��[�h�R������P����Z�p���s���Ȃ��߁A���炩�̋Z�p�������o
�����܂ł̎��ԉ҂��̂��߂̃_�~�[�̋Z�p�Ƃ��āA�w�ҁE���Ƃ��^�[�{�R���p�E���h�𐄏�����Ă���\������
���ɂ����ƍl������B�������A����̗��R�ɂ��Ă��A�w�ҁE���Ƃ���^�g���b�N�̏d�ʎԃ��[�h�R����\���ɉ�
�P�ł��Ȃ��^�[�{�R���p�E���h�������̑�^�g���b�N�̔R����P�̋Z�p�Ƃ��Đ�������Ă��邽�߁A�w�ҁE���Ƃ�M
������l�B�𗠐�s�ׂł��邱�Ƃɂ́A�ς��͂Ȃ��ƍl������B
�@���͂Ƃ�����A���݂̃g���b�N���[�J�ɂ�����؎��Ȗ��E�ۑ�́A�T�����x�̏d�ʎԃ��[�h�R���R����P�ł���
�Z�p�𑁋}�Ɏ��p�����A�e�g���b�N���[�J�ɂ�����2015�N�x�d�ʎԔR���ɕs�K���̑�^�g���b�N�̎Ԏ�𑁋}��
��|���Ă��܂����Ƃ��B�Ƃ��낪�A��w�A�����@�ւ͌����ɋy���A�g���b�N���[�J�ɂ����Ă��A���ނ̋Z�p�ő�^�g���b
�N�ł��T�����x�̏d�ʎԃ��[�h�R������P�ł��錈��I�ȋZ�p�������Ɍ����o���Ă��Ȃ��悤�ł���B���̂��߁A�e
�g���b�N���[�J�ł́A�u�σo���u�^�C�~���O�E���t�g�v�A�uLow-pressure EGR�v�A�u�^�[�{�R���p�E���h�v�A�u2�i��
���v�A�uPCI�R�āi��HCCI�R�āj�v���̔R���̌덷�ɂ��C�G����P�����x�̏d�ʎԃ��[�h�R��̉��P������
�҂ł��Ȃ��R����P�@�\�̗��Z�p���W�߂āA��^�g���b�N�ł̂T�����x�̏d�ʎԃ��[�h�R������P����
���Ɩ�N�ɂȂ��Ă������̂ƍl������B���̂悤�ɁA�����̋Z�p���W�߂��Z�p��p����A��^�g���b�N�ł�
�T�����x�̏d�ʎԃ��[�h�R��̉��P�������ł��邩���m��Ȃ����A�펯�I�ɍl����R�X�g���ŏ��i�͂Ɍ����邱��
�͖����ł���B��^�g���b�N�ł̂T�����x�̏d�ʎԃ��[�h�R��̉��P�̂��߂ɁA�����ꒃ�Ƃ����������ȑ��푽�l�̋Z
�p�J�����s�킴��Ȃ��g���b�N���[�J�̋Z�p�҂̐l�B�ɂ́A�u�ق�܂ɁA����J�Ȃ��Ƃ�Ȃ��`�B�v�ƘJ���̐����|��
�����Ƃ��낾�B��̋Z�p�ő�^�g���b�N�ł̂T�����x�̏d�ʎԃ��[�h�R��̉��P���ł��Ȃ����Ƃɂ��āA�ނ玩�g
�́A�Z�p�J���̔\�͕s���ɉ��������������Ă���̂ł͂Ȃ����낤���B
�Z�p�𑁋}�Ɏ��p�����A�e�g���b�N���[�J�ɂ�����2015�N�x�d�ʎԔR���ɕs�K���̑�^�g���b�N�̎Ԏ�𑁋}��
��|���Ă��܂����Ƃ��B�Ƃ��낪�A��w�A�����@�ւ͌����ɋy���A�g���b�N���[�J�ɂ����Ă��A���ނ̋Z�p�ő�^�g���b
�N�ł��T�����x�̏d�ʎԃ��[�h�R������P�ł��錈��I�ȋZ�p�������Ɍ����o���Ă��Ȃ��悤�ł���B���̂��߁A�e
�g���b�N���[�J�ł́A�u�σo���u�^�C�~���O�E���t�g�v�A�uLow-pressure EGR�v�A�u�^�[�{�R���p�E���h�v�A�u2�i��
���v�A�uPCI�R�āi��HCCI�R�āj�v���̔R���̌덷�ɂ��C�G����P�����x�̏d�ʎԃ��[�h�R��̉��P������
�҂ł��Ȃ��R����P�@�\�̗��Z�p���W�߂āA��^�g���b�N�ł̂T�����x�̏d�ʎԃ��[�h�R������P����
���Ɩ�N�ɂȂ��Ă������̂ƍl������B���̂悤�ɁA�����̋Z�p���W�߂��Z�p��p����A��^�g���b�N�ł�
�T�����x�̏d�ʎԃ��[�h�R��̉��P�������ł��邩���m��Ȃ����A�펯�I�ɍl����R�X�g���ŏ��i�͂Ɍ����邱��
�͖����ł���B��^�g���b�N�ł̂T�����x�̏d�ʎԃ��[�h�R��̉��P�̂��߂ɁA�����ꒃ�Ƃ����������ȑ��푽�l�̋Z
�p�J�����s�킴��Ȃ��g���b�N���[�J�̋Z�p�҂̐l�B�ɂ́A�u�ق�܂ɁA����J�Ȃ��Ƃ�Ȃ��`�B�v�ƘJ���̐����|��
�����Ƃ��낾�B��̋Z�p�ő�^�g���b�N�ł̂T�����x�̏d�ʎԃ��[�h�R��̉��P���ł��Ȃ����Ƃɂ��āA�ނ玩�g
�́A�Z�p�J���̔\�͕s���ɉ��������������Ă���̂ł͂Ȃ����낤���B
�@���āA�ȏ�̂悤�ȃg���b�N���[�J�̗l�q�O�҂ł���M�҂��猩��ƁA�g���b�N���[�J�́A�I�O��Ƃ��]�������ȔR��
���P�̋@�\�̗��Z�p���W�߂āA��^�g���b�N�̔R����P��}�낤�Ƃ��鈣��ȏɊׂ��Ă���悤�Ɏv�����
�ł���B���̂悤�ȃg���b�N���[�J�̏��ӂ݁A�|���R�c���Z�p���̕M�҂���Ă��Ă���Z�p���A��^�g���b�N�ł̂T�`
�P�O�����x�̏d�ʎԃ��[�h�R������P�ł����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�ł���B���̋Z�p�́A2006�N6
���ɊJ�݂����z�[���y�[�W�Ō��J���Ă�����̂ł���B���̋Z�p�̓��e�ɂ��ẮA�C���x�~�G���W���ɂ���^�g��
�b�N�̒�R��A�C���x�~�́A�R��팸�ƔA�fSCR��NO���팸���̌���ɗL�����I������C���x�~��DPF�̎��ȍ�
���𑣐i (�R����̖h�~�ɗL���j�̃y�[�W�ɏڍׂȐ������f�ڂ��Ă���̂ŁA�䗗�������������B�X�ɁA�C���x�~
�́A�f�B�[�[���r�C�K�X�̃G�l���M�[���u�̌����������̃y�[�W�ɏڏq���Ă���悤�ɁA�C���x�~�G���W���i����
���J2005-54771�j�̋Z�p�́A��^�g���b�N�̃^�[�{�R���p�E���h���̗p�����ꍇ�̃^�[�{�R���p�E���h�ɂ������s�R
���d�ʎԃ��[�h�R����\���Ɍ���ł���@�\�������Ă���̂ł���B
���P�̋@�\�̗��Z�p���W�߂āA��^�g���b�N�̔R����P��}�낤�Ƃ��鈣��ȏɊׂ��Ă���悤�Ɏv�����
�ł���B���̂悤�ȃg���b�N���[�J�̏��ӂ݁A�|���R�c���Z�p���̕M�҂���Ă��Ă���Z�p���A��^�g���b�N�ł̂T�`
�P�O�����x�̏d�ʎԃ��[�h�R������P�ł����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�ł���B���̋Z�p�́A2006�N6
���ɊJ�݂����z�[���y�[�W�Ō��J���Ă�����̂ł���B���̋Z�p�̓��e�ɂ��ẮA�C���x�~�G���W���ɂ���^�g��
�b�N�̒�R��A�C���x�~�́A�R��팸�ƔA�fSCR��NO���팸���̌���ɗL�����I������C���x�~��DPF�̎��ȍ�
���𑣐i (�R����̖h�~�ɗL���j�̃y�[�W�ɏڍׂȐ������f�ڂ��Ă���̂ŁA�䗗�������������B�X�ɁA�C���x�~
�́A�f�B�[�[���r�C�K�X�̃G�l���M�[���u�̌����������̃y�[�W�ɏڏq���Ă���悤�ɁA�C���x�~�G���W���i����
���J2005-54771�j�̋Z�p�́A��^�g���b�N�̃^�[�{�R���p�E���h���̗p�����ꍇ�̃^�[�{�R���p�E���h�ɂ������s�R
���d�ʎԃ��[�h�R����\���Ɍ���ł���@�\�������Ă���̂ł���B
�@�������A�f�B�[�[���G���W���W�̊w�ҁE���Ƃ́A�������C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p��S����
���m�Ȃ��̂��A����Ƃ������E�َE���Ă���悤�ł���B���ɁA���̋C���x�~�̋Z�p���E�َE���Ă���Ƃ���A��
���C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p�ɂ͒v���I�Ȍ��ׂ�����Ƃ̕]���������Ă���\�����l�����
��B���̏ꍇ�ɂ́A���̋Z�p������ɂ������Ă��Ȃ��͓̂��R�̂��Ƃ��B���ɂ����ł���A�����C���x�~�G���W��
�i�������J2005-54771�j�̋Z�p�ɂ����錇�ׂɂ��āA����Ƃ����������������������̂ł���B
���m�Ȃ��̂��A����Ƃ������E�َE���Ă���悤�ł���B���ɁA���̋C���x�~�̋Z�p���E�َE���Ă���Ƃ���A��
���C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p�ɂ͒v���I�Ȍ��ׂ�����Ƃ̕]���������Ă���\�����l�����
��B���̏ꍇ�ɂ́A���̋Z�p������ɂ������Ă��Ȃ��͓̂��R�̂��Ƃ��B���ɂ����ł���A�����C���x�~�G���W��
�i�������J2005-54771�j�̋Z�p�ɂ����錇�ׂɂ��āA����Ƃ����������������������̂ł���B
�@�����͉]���Ă��A�K�\���������Ԃł́A�C���x�~�̋Z�p�́A���Ƀz���_�A�N���C�X���[�AGM�����Ɏs�̎Ԃɍ̗p����
����A�܂��A2012�N�ɂ������Z�f�XAMG�ƃt�H���N�X���[�Q�����C���x�~���̗p�����Ԏ������Ƃ̂��Ƃł���B��
�̂悤�ɁA�K�\���������Ԃł́A�C���x�~�ɂ���ăK�\���������Ԃ̔R������}�鎩���ԃ��[�J���A�Q���A��������
���邱�Ƃ��l����ƁA�M�Ғ�Ă��C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p����^�f�B�[�[���g���b�N�̔R���
��̋Z�p�Ƃ��Ēv���I�Ȍ��ׂ�����Ƃ͂ƂĂ��l�����Ȃ��B���̂��߁A�C���x�~�ɂ͑�^�f�B�[�[���g���b�N�ɍ̗p
�ł��Ȃ��v���I�Ȍ��ׂ������ƍl���Ă��܂��̂́A�|���R�c�̌��Z�p���̕M�҂���w��˂ł��邪�̂ɁA�f�B�[�[��
�G���W���̒�R��Z�p�Ɋւ��Ă̒P�Ȃ�u�����Ӂv�Ɋׂ��Ă��܂��Ă��邽�߂ł��낤���B
����A�܂��A2012�N�ɂ������Z�f�XAMG�ƃt�H���N�X���[�Q�����C���x�~���̗p�����Ԏ������Ƃ̂��Ƃł���B��
�̂悤�ɁA�K�\���������Ԃł́A�C���x�~�ɂ���ăK�\���������Ԃ̔R������}�鎩���ԃ��[�J���A�Q���A��������
���邱�Ƃ��l����ƁA�M�Ғ�Ă��C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p����^�f�B�[�[���g���b�N�̔R���
��̋Z�p�Ƃ��Ēv���I�Ȍ��ׂ�����Ƃ͂ƂĂ��l�����Ȃ��B���̂��߁A�C���x�~�ɂ͑�^�f�B�[�[���g���b�N�ɍ̗p
�ł��Ȃ��v���I�Ȍ��ׂ������ƍl���Ă��܂��̂́A�|���R�c�̌��Z�p���̕M�҂���w��˂ł��邪�̂ɁA�f�B�[�[��
�G���W���̒�R��Z�p�Ɋւ��Ă̒P�Ȃ�u�����Ӂv�Ɋׂ��Ă��܂��Ă��邽�߂ł��낤���B
�@ �Ō�ɁA���̃z�[���y�[�W�ł̌���^��ƍl������L�ړ��e�ɂ��C�t���̏ꍇ�ɂ́A�S�O�������w�E��������
����K���ł��B�܂��A�ǂ̂悤�Ȃ��Ƃł��\���܂���̂ŁA���_���܂߂ė����Ȍ�ӌ��E�䊴�z��������肦���
�v���Ă���܂��B
����K���ł��B�܂��A�ǂ̂悤�Ȃ��Ƃł��\���܂���̂ŁA���_���܂߂ė����Ȍ�ӌ��E�䊴�z��������肦���
�v���Ă���܂��B
�Ջ��l���Ă����[��
|
