�Ջ��l�̃A�C�f�A
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�g�b�v�y�[�W�ɖ߂��@�@�@�@�@�T�C�g�}�b�v
�ŏI�X�V���F2012�N6��5��
 |
�P�D�o�C�I�}�X�R���̔R���́A�]������g���b�N����̒�Y�f�E�E�Ζ��̎�i�Ƃ��ĕK���o��
�@���{�̐��{�⌤���@�ւ��甭�\���ꂽ���{�̏����R���Ɋւ��鎑���ɂ́A���{�����ő�^�g���b�N�̔R���Ƃ��Ė{
�i�I�ɋ������邱�Ƃ�����ȃo�C�I�}�X�R����p���đ�^�g���b�N��CO�Q�̍팸��E�Ζ��̎Љ���\�z���Ă����Ƃ�
���͂�p�ɂɖڂɋ@�����B�������Ȃ���A����玑���̍쐬�҂́A�o�C�I�}�X�R�����g�p���đ�^�g���b�N��CO�Q
�̍팸��E�Ζ��̎Љ�{���Ɏ����\�Ƃ͒N���{�C�ōl�����Ȃ����낤�B�킪���̑�^�g���b�N��CO�Q�̍팸��
�E�Ζ����\�ɂ���Z�p�A�C�e���Ƃ��āA�o�C�I�}�X�R���ȊO�ɋL�ڂ��鑼�̋Z�p���v�������Ȃ����߁A��^�g��
�b�N�ɂ�����CO�Q�팸�ƒE�Ζ��̗��z�̔R���Ƃ��Ďd���Ȃ��Ƀo�C�I�}�X�R�����̎^���Ă���悤�Ɏv����̂��B����
�悤�ɁA���{�̐��{�����\���鐭��ɂ́A�����^��̎v�����Ƃ�����B���̐���̈�̔��\�����Ƃ��ĂɁA�\�P
�Ɏ������o�ώY�ƏȂ��u�V�E���ƃG�l���M�[�헪�v�i2006�N5���j�����邪�A�����ɂ��ԈႢ�Ȃ��A�o�C�I�}�X�R���̔R��
���o�ꂵ�Ă���̂ł����B���̂悤���A���{�̊w�ҁE���Ƃ́A�g���b�N�ݕ��A������̒�Y�f�i��CO2�팸�j�E�E�Ζ�
�̎�i�Ƃ��āA�o�C�I�}�X�R���̔R���������Ă����Ηǂ��ƍl���Ă���悤���B
�i�I�ɋ������邱�Ƃ�����ȃo�C�I�}�X�R����p���đ�^�g���b�N��CO�Q�̍팸��E�Ζ��̎Љ���\�z���Ă����Ƃ�
���͂�p�ɂɖڂɋ@�����B�������Ȃ���A����玑���̍쐬�҂́A�o�C�I�}�X�R�����g�p���đ�^�g���b�N��CO�Q
�̍팸��E�Ζ��̎Љ�{���Ɏ����\�Ƃ͒N���{�C�ōl�����Ȃ����낤�B�킪���̑�^�g���b�N��CO�Q�̍팸��
�E�Ζ����\�ɂ���Z�p�A�C�e���Ƃ��āA�o�C�I�}�X�R���ȊO�ɋL�ڂ��鑼�̋Z�p���v�������Ȃ����߁A��^�g��
�b�N�ɂ�����CO�Q�팸�ƒE�Ζ��̗��z�̔R���Ƃ��Ďd���Ȃ��Ƀo�C�I�}�X�R�����̎^���Ă���悤�Ɏv����̂��B����
�悤�ɁA���{�̐��{�����\���鐭��ɂ́A�����^��̎v�����Ƃ�����B���̐���̈�̔��\�����Ƃ��ĂɁA�\�P
�Ɏ������o�ώY�ƏȂ��u�V�E���ƃG�l���M�[�헪�v�i2006�N5���j�����邪�A�����ɂ��ԈႢ�Ȃ��A�o�C�I�}�X�R���̔R��
���o�ꂵ�Ă���̂ł����B���̂悤���A���{�̊w�ҁE���Ƃ́A�g���b�N�ݕ��A������̒�Y�f�i��CO2�팸�j�E�E�Ζ�
�̎�i�Ƃ��āA�o�C�I�}�X�R���̔R���������Ă����Ηǂ��ƍl���Ă���悤���B
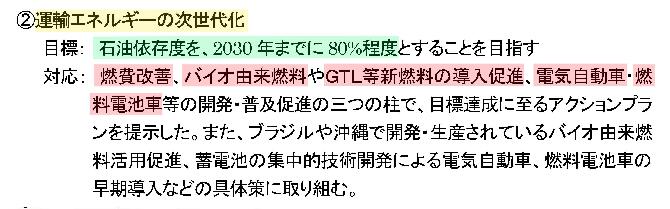 |
�@
�Q�D�o�C�I�}�X�R����DME�R���Ńg���b�N�ݕ��A������̒�Y�f�ƒE�Ζ��̎����͍���
�Q�|�P�D DME�g���b�N�̕��y�ɕK�v�\���ȃo�C�I�}�X�R����DME�R�����m�ۂ��邱�Ƃ́A�������s�\�Ɨ\�z
�@���݁A���E�I�Ɍ���ΐl�������������A���E�e�n�ł̐��s�����[���Ȃ��Ƃ���A�����̐H���s�������O����Ă�
��B���ɁA�ŋ߂ł́A����Ȑl����������������o�ϔ��W�ɂ���Đ������x�������サ�A���E�����ʂ̐H����A��
���鍑�ɂȂ��Ă��܂��Ă��邱�Ƃɂ����ڂ��ׂ��ł��낤�B�����āA���{�̌��������A�H�����������S�O���i�J�����[
�x�[�X�j�ł��邽�߁A���ʂ̃o�C�I�}�X�R����DME�R�������邽�߂ɕK�v�Ȋ����؎��Ȃǂ̃o�C�I�}�X��������
�����邱�Ƃ�A�����邱�Ƃ��s�\�ł��邱�Ƃ́A���炩���B
�@���������āA���Ƀo�C�I�}�X�R����DME��R���Ƃ���g���b�N�y���������Ă��A���{�����ő�����DME�g���b�N���^
�s�����邽�߂ɕK�v�ƂȂ�o�C�I�}�X�R����DME�̗ʂ��m�ۂ��邱�Ƃ͕s�\�Ɨ\�z�����B���̂��߁A�����Ƃ��o�C
�I�}�X�R����DME��R���Ƃ���DME�g���b�N���킪���ŕ��y�����邱�Ƃ́A��]�I�ƍl����ׂ��ł͂Ȃ����낤���B����
���߁A�M�҂̓o�C�I�}�X�R����DME��R���Ƃ���DME�g���b�N�̌����J���́A���S�ɖ��ʂȌ��������ƍl���Ă���B
�Q�|�Q�D �o�C�I�}�X�R����DME�́A�G�l���M�[�����̒Ⴂ�����Q��̌��הR�����I
�@�p�ނȂǂ̖؎��n�o�C�I�}�X���R���K�X�ɕς��A���̃K�X����G�}�����ɂ���ĉt�̒Y�����f����邱�Ƃ��\
�ł���B���̕��@�́A�}�P�Ɏ������悤�ɁA�悸�ŏ��ɖ؎��n�o�C�I�}�X��800�`1000���̍����ɂ������Ă���Ԃ�
�ێ����ăK�X�����A���f�iH2�j�ƈ�_���Y�f�iCO�j�����B�����ăK�X����H2��CO�̔�����A�G�}�̓��������u��
��H2��CO�������E�����Ŕ���������邱�Ƃɂ���ĉt�̒Y�����f������B���̍ہA�G�}�̎�ށA�������́A���x
��ς��邱�ƂŁA�y���iFT�f�B�[�[���j�A�K�\�����A�����A���R�[���A�W���`���G�[�e���ȂǁA���܂��܂ȕ�������邱�Ƃ�
�\�ł���B
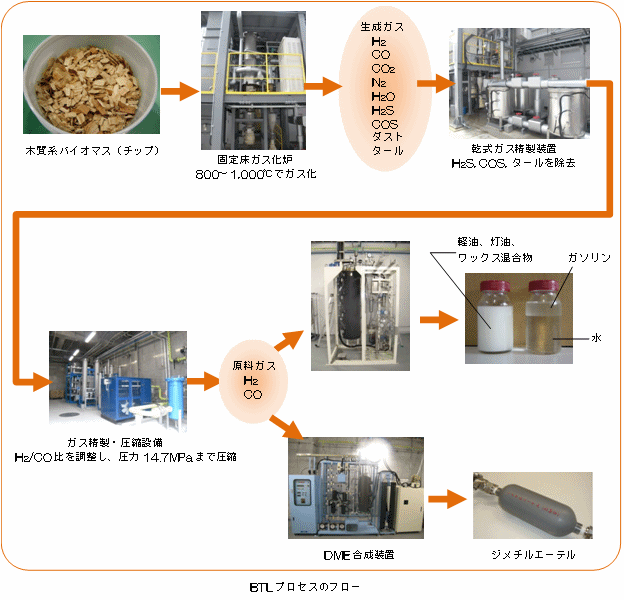
�@�����̃g���b�N�p�̔R���ɖ؎��n�`�b�v�������Ƃ����R���������ł���悤�ɂ��邽�߂ɂ́A���ʂ̖؎��n�`�b�v����
��ʂ̉t�̒Y�����f�i���y���yFT�f�B�[�[���z�ADME���j���H�ƓI�ɐ�������K�v������B�������A������������邽��
�ɁA�}�P�Ɏ������悤�ɁA�؎��n�`�b�v����t�̒Y�����f���Z�p�ł́A�A�������⍂�������ێ�����v���Z�X���K
�{�ł���A���̐����H���ɂ����鍂�����E�������̂��߂ɑ�ʂ̃G�l���M�[�̓������K�v�ł���B���̂��߁A�؎��n
�`�b�v���琻�������t�̒Y�����f�i���y���yFT�f�B�[�[���z�ADME���j�́AWell-to-Tank�̃G�l���M�[�������ɂ߂ĒႢ
�l�ɂȂ��Ă��܂����_������B
�@���̖؎��n�`�b�v���琻������DME�̃G�l���M�[�����̒����f�[�^�́A�u�A���p�R����Well-to-Wheel�]���v�y���{��
������A���p�R�������iWell-to-Wheel�j�𒆐S�Ƃ����������ʃK�X�r�o�ʂɊւ��錤�����z�@����16�N11���@�g��
�^�����ԇ��@�݂��ُ�����ɋL�ڂ���Ă���B����ɂ��ƁA�\�P�Ɏ������悤�ɁA���ᗰ���y���i�����̊ܗL��
��0.0001�������ȉ��j��Well-to-Tank�̃G�l���M�[������ 0.883 �ł���ALNG�i�t���V�R�K�X�j��Well-to-Tank�̃G�l��
�M�[������ 0.858 �@�ł���̂ɑ��A�؎��n�`�b�v���琻������DME��Well-to-Tank�̃G�l���M�[������ 0.536 ��
�Ⴂ�l�i��������̒l�j�������Ă���B���̂��߁A�ȃG�l���M�[���������߂��Ă��錻�݂ɂ����ẮA�V�R�K�X�R��
�ƃo�C�I�}�X�R���̉����DME����^�g���b�N�̔R���Ƃ��ẮA���炩�Ɍ��הR���ƍl������B�i�\�Q�Q�ƕ��j
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
���P�F�o�T�́A�u�A���p�R����Well-to-Wheel�]���v�y���{�ɂ�����A���p�R�������iWell-to-Wheel�j�𒆐S�Ƃ����������ʃK�X�r�o�ʂɊւ���
�������z�@����16�N11���@�g���^�����ԇ��@�݂��ُ����
���Q�F�o�T�́A�V�R�K�X��Ă�CNG��^�g���b�N�́A�d�ʎԔR���ɕs�K���̌��׃g���b�N�̃y�[�W
���R�F�o�T�́A�f�B�[�[���ɔ�ׂP�T���̂b�n�Q�팸���\�Ȃc�c�e�G���W���ADDF�^�]�ƃf�B�[�[���^�]�̑I�����\�Ȃc�c�e��^�g���b�N ����сA
�����ԋZ�p��w�p�u����O���WNo.71-00�i2000�N5���j �u323�@���^�g���b�N�pECOS-DDF�@�V�R�K�X�G���W���̊J���@�v�i20005001�j �i�咘�ҁF
�Γc)
�ȏ�̕\�Q�Ɏ������u�A���p�R����Well-to-Wheel�]���v�y���{�ɂ�����A���p�R�������iWell-to-Wheel�j�𒆐S�Ƃ�
���������ʃK�X�r�o�ʂɊւ��錤�����z�@����16�N11���@�g���^�����ԇ��@�݂��ُ�����̃f�[�^������ƁA
��^�g���b�N�̔R���ɓV�R�K�X�R����DME��p�����ꍇ�́A��^�g���b�N�Ɍy����p����ꍇ�ɔ�ׁA�G�l���M�[��
����3�Q���ȏ���Q��A���l�ɖ؎��n�`�b�v�n�o�C�I�}�X�R����DME��p�����ꍇ�́A��^�g���b�N�Ɍy����p����
�ꍇ�ɔ�ׁA�G�l���M�[�������U�T���ȏ���Q����邱�Ƃ��M���̂���g�D�E�c�̂̕���16�N�i��2003�N�j�̕�
�Ɍ��\����Ă���B���������āA�Ȏ����E�ȃG�l���M�[�����߂��Ă��錻�ݎЉ�ł́A�펯�̂���w�ҁE���Ƃ́A
����16�N�̎��_�ő�^�f�B�[�[���g���b�N�̔R���Ƃ���DME�����i�ł��邱�Ƃ𗝉����Ă��锤�ł���B
�@���̂悤�ɁA��^�g���b�N�̔R���ɓV�R�K�X�R���ƃo�C�I�}�X�R���̉����DME��p�����ꍇ�ł��A��^�g���b�N�Ɍy
����p����ꍇ�ɔ�ׁA�G�l���M�[�����𑽗ʂɘQ��Ă��܂����ׂ�����B����A��L�̕\�Q�Ɏ������悤�ɁA��^
�g���b�N�̃G���W����DDF�G���W���i�y�����Ό^�V�R�K�X�G���W���j���̗p�����ꍇ�ɂ́A�y����R���ɗp�����ꍇ�̑�
�^�g���b�N�Ɠ�����Well-to-Wheel�̃G�l���M�[�����ő�^�g���b�N���^�s�ł���̂ł���B���̂��Ƃ́A�M�҂̘_���y��
���ԋZ�p��w�p�u����O���WNo.71-00�i2000�N5���j �u323�@���^�g���b�N�pECOS-DDF�@�V�R�K�X�G���W���̊J���@�v
�i20005001�j �i�咘�ҁF�Γc�j�z�ɂ����ĕ����P�R�N�i2000�N�j�Ɋ��ɔ��\���Ă��邱�Ƃ��B���̂��߁A���݂ł́A�V�R�K�X
�R���ƃo�C�I�}�X�R���̉����DME����^�g���b�N�̔R���Ƃ��Ă͎��i�ł��邱�Ƃ����ɔ������Ă������ADDF��^
�g���b�N�͏]���̌y���f�B�[�[����^�g���b�N�ɔ�ׂāu�E�Ζ��v�Ɓu��Y�f�i��CO2�̍팸�j�v�������ł��邱�Ƃ����Ɋm
�F�ł��Ă���̂ł���B���̂悤�ɁA�����P�U�N�i��2003�N�j�̎��_�ɂ����āA��^�g���b�N�́u�E�Ζ��v����сu��Y�f
�i��CO2�̍팸�j�v�̎�i�Ƃ��ẮADME�����i�ł���ADDF�G���W���i��DDF�g���b�N�j�̋Z�p�ȊO�ɖ������Ƃ����ɖ���
���ƂȂ��Ă���B����ɂ�������炸�A�����P�U�N�i��2003�N�j�ȍ~���A�g���b�N�̏����R����DME�𐄏�����_���̔�
�\������ɍs���Ă���悤���B���̂��Ƃ́A�M�҂ɂ͕s�v�c�̎v���Ďd���̖������Ƃł���B
�Q�D�ŋ߂̎����ԋZ�p��ɂ�����DME�R����DME�g���b�N�Ɋւ���_�����\�̏�
�@����܂ŁA���N�T���ɊJ�Â���Ă��鎩���ԋZ�p��̏t�G���ł́ADME�����ԁi��DME�g���b�N�j�Ɋւ���ŐV��
������Z�p�����������\����ADME�g���b�N������Q�ƒE�Ζ��̖ʂŗD�ꂽ�����������߂ɏ����I�ɗL�]�Ɛ����
��������Ă����B�Ƃ��낪�ADME�g���b�N��Well-to-Wheel�̃��C�t�T�C�N���A�Z�X�����g�ŕ]�������ꍇ�ɂ́A���̕]��
���ʂ��u�V�R�K�X�R����DME�́A�y���f�B�[�[��������R�O����Well-to-Wheel�̔M���������A�������̖����R���v
�ł��邱�Ƃ������ł���B
������Z�p�����������\����ADME�g���b�N������Q�ƒE�Ζ��̖ʂŗD�ꂽ�����������߂ɏ����I�ɗL�]�Ɛ����
��������Ă����B�Ƃ��낪�ADME�g���b�N��Well-to-Wheel�̃��C�t�T�C�N���A�Z�X�����g�ŕ]�������ꍇ�ɂ́A���̕]��
���ʂ��u�V�R�K�X�R����DME�́A�y���f�B�[�[��������R�O����Well-to-Wheel�̔M���������A�������̖����R���v
�ł��邱�Ƃ������ł���B
�@���̂��߁A�M�҂́A�R��������Q���DME�g���b�N�́A�����I�ɍL�����y����\�����S���������Ƃ��A���Ƃ�
�܂߂������̐l�B�ɒm���ĖႤ���߂ɁA2010�N8��24 ���Ɂu�y�������G�l���M�[������30�������DME�𐄏�����
�@�B�w��̋^��v�Ƒ肷��y�[�W��lj������B���̃z�[���y�[�W�ɂ���āA�R��������Q���DME�g���b�N�������I
�ɕ��y����\�����F���ł��邱�Ƃ�F�m���ꂽ���ۂ��́A���̂Ƃ���s���ł���B�����ŁADME�g���b�N�Ɋւ����
�V�̌����E�J���̏������ł��c�����邽�߂ɁA�ŋ߂̎����ԋZ�p��̏t�G���Ŗ��N�̔��\�����_���̖{��
�ƁADME�g���b�N���R��������Q��錇�ׂ���������{�z�[���y�[�W�̊J�݂ɂ��āA���n��ňȉ��̕\�R�ɐ�����
���B
�܂߂������̐l�B�ɒm���ĖႤ���߂ɁA2010�N8��24 ���Ɂu�y�������G�l���M�[������30�������DME�𐄏�����
�@�B�w��̋^��v�Ƒ肷��y�[�W��lj������B���̃z�[���y�[�W�ɂ���āA�R��������Q���DME�g���b�N�������I
�ɕ��y����\�����F���ł��邱�Ƃ�F�m���ꂽ���ۂ��́A���̂Ƃ���s���ł���B�����ŁADME�g���b�N�Ɋւ����
�V�̌����E�J���̏������ł��c�����邽�߂ɁA�ŋ߂̎����ԋZ�p��̏t�G���Ŗ��N�̔��\�����_���̖{��
�ƁADME�g���b�N���R��������Q��錇�ׂ���������{�z�[���y�[�W�̊J�݂ɂ��āA���n��ňȉ��̕\�R�ɐ�����
���B
| |
|
| 2009��5�� | |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
�@��L�̕\�R������ƁA2010�N8��24 ���ɕM�҂��u�y�������G�l���M�[������30�������DME�𐄏�����@�B�w��
�̋^��v�Ƒ肷��z�[���y�[�W��lj����A�R���G�l���M�[�̎�����Q���DME�g���b�N�������I�ɕ��y����\��
���F���ł��邱�Ɛ��������ȑO�ł́A2009�N�t�G���F�T�{�A2010�N�t�G���F�P�O�{��DME�֘A�̘_�������\�����
����B�������A2010�N8���ɕM�҂��R���G�l���M�[�̎�����Q���DME�g���b�N�������I�ɕ��y����\�����F��
�ł��邱�Ɛ��������z�[���y�[�W���J�݂������2011�N�t�G���ł�DME�֘A�̘_�������\���F���ł������B����
�́A�{�z�[���y�[�W�̕\�P�Ɏ������u�V�R�K�X�R����DME�ł�Well-to-Wheel�̃��C�t�T�C�N���A�Z�X�����g�iLCA�j�ɂ�
�鐳�����]���v�ɒ������ď��������ƁADME�͌y���f�B�[�[��������R�O����Well-to-Wheel�̔M���������A�����I
�ɃG�l���M�[�Q����������הR���v�ł��邱�Ƃ𗝉�����A�f�B�[�[���g���b�N�̔R���ɓV�R�K�X��DME��p���邱�Ƃ�
���_�E���ׂ𗝉����ꂽ�ADME�֘A�̘_�������\����Ȃ��������̂ƁA����܂Ő������Ă����B
�@�������Ȃ���A2012�N5���̏t�G���ł́A�v�X�ɂQ�{��DME�֘A�̘_�������\����Ă��邱�Ƃ����������B�����āA
����2012�N5���̎����ԋZ�p��E�t�G���Ŕ��\���ꂽ�Q�{�̃o�C�I�}�X�R����DME�֘A�_���̒��҂ɂ́A�������U
�����������̓��蒼���������Ă���̂ł���B���̇������U�����������̓��蒼��́A�O�q�̕\�P�Ɏ�����
���{�@�B�w�2010�N5�����̌f�ژ_���uDME�g���b�N�̍ŐV�J���v�̒��ŁA�uWell-to-Wheel�̃��C�t�T�C�N���A
�Z�X�����g�iLCA�j�̕]�����s�Ȃ킸�ATank-to-Wheel�̎����f�[�^�������Ƃ���(�V�R�K�X�R���́jDME���f�B�[�[���G
���W���ɗp����ׂ������̗L�]�ȔR���v�ƁA������咣�X�ƍs���Ă������Ƃł���B
�@�Ƃ��낪�A�ŋ߁A�\�S�Ɏ������悤�ɁA�������U�����������̓��蒼��́A�f�B�[�[���g���b�N�̔R���Ƃ��Ēv���I��
���ׂ�����u�V�R�K�X�R��DME�v����A�u�o�C�I�}�X�R����DME�v�ɖ����ɑ�]�����邱�Ƃ����f�����悤���B���̏؋�
�Ƃ��āA2012�N5���̎����ԋZ�p��E�t�G���Ŕ��\�̇������U���������� ���蒼��̓o�C�I�}�X�R����DME��
�ւ���Q�{�̘_���\�����悤���B���̒��̂P�{�̘_���́A�i�Ɓj��ʈ��S���������̍����R�Y���Ƃ̋����ł�
��B���̂��߁A�������U���������� ���蒼��Ɓi�Ɓj��ʈ��S���������̍����R�Y���́A���Ƀg���b�N�ɂ�����
�����̐Ζ���֔R���Ƃ��āA�o�C�I�}�X�R����DME�R���������̗L�]�ȔR���ł���Ƃ̈ӌ��E�����E�咣�̎������
�悤�ł���B�������A�o�C�I�}�X�R����DME�R�����g���b�N�̔R���ɗp����_���\����Z�b�V�����̑薼���u��Y�f
�Љ��S���V�R���v�Ƃ́A�����ł���B���̂Ȃ�A�o�C�I�}�X�R����DME��Well-to-Tank�̃G�l���M�[�������y����
����啝�ɗ�錇�ׂ����邽�߁A�o�C�I�}�X�R����DME�́A�u��Y�f�v�]�X�̈ȑO�ɁA�g���b�N�̔R���ɗp���邱�Ƃ���
���Ƃ��s�\�ł���B
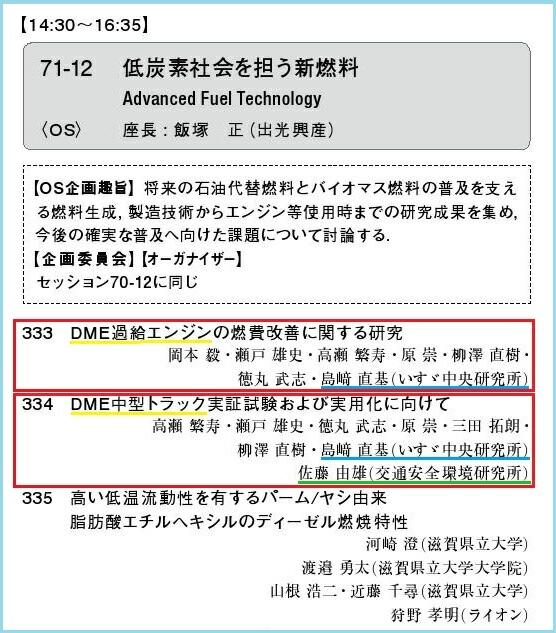
�@����܂ŁA�������U�����������̓��蒼��́A�y�������G�l���M�[�������R�O�������c�l�d�𐄏�����@�B�w
��̋^��ɏڏq���Ă���悤�ɁA���{�@�B�w�2010�N5�����iVol.113�AN0.1098�j�Ɍf�ڂ��ꂽ�uDME�g���b�N�̍ŐV
�J���v�̘_���ɂ����āA�u�V�R�K�X�R����DME�́A�y���f�B�[�[��������R�O����Well-to-Wheel�̔M��������
��A�������̖����R���v�ł��鎖���ɂ͑S���G�ꂸ�A�u�iTank-to-Wheel�̎����f�[�^�������ɂ��Ă��邱�Ƃ��B�����āj
DME���f�B�[�[���G���W���̍������������R���ł���A�����̗L�]�ȔR���v�Ƃ̍��\�I�Ƃ��]�������Ȍ�����咣��
���X�ƍs���Ă����̂ł���B
�@�Ƃ��낪�A�ŋ߂ł́A2012�N5���̎����ԋZ�p��E�t�G���Ŕ��\�̇������U���������� ���蒼��ƓƁj��ʈ�
�S���������̍����R�Y���Ƃ������Ŕ��\����DME�֘A�̘_�����\�̃Z�b�V�����̐���������Ɓu�o�C�I�}�X�R����
���y���x����E�E�E�E�v�ƋL�ڂ���Ă���B���̂��Ƃ���A���ɓ��蒼��́ADME�g���b�N�ɗp����DME�R�����A����܂�
�̓V�R�K�X�R����DME����A�o�C�I�}�X�R����DME�ɑ�]���������Ƃ��m���Ȃ悤�ɍl������B����́A�V�R�K�X�R
����DME�ƃo�C�I�}�X�R����DME�Ƃ́A�������V�R�K�X�ƃo�C�I�}�X�Ƃ��قȂ邾���ł��邽�߁A�V�R�K�X�R����
DME����o�C�I�}�X�R����DME�ɑ�]������u�ς��g�v�E�u��ϐg�v�����̒f���������ɍs�����Ƃ̗��s�s�E�s����
���e�ՂɘI�����Ȃ����_�����������߂ł͂Ȃ����낤���B����́A�V�R�K�X�R����DME�ƃo�C�I�}�X�R����DME�Ƃ́A
DME�Ƃ��Ă͑S������ł��邩��ł��邱�Ƃ���B���̂悤�ȕϐg��N�̖ڂɂ��C�t���ꂸ�ɂł������Ƃ́A�������U��
���������̓��蒼��ɂƂ��ẮA�K�^�Ȃ��Ƃł������Ɛ��������B�������A���Ă܂ł̓��蒼��̓��{�@�B�w��
��2010�N5�����iVol.113�AN0.1098�j�Ɍf�ڂ��ꂽ�uDME�g���b�N�̍ŐV�J���v�̘_�����_����M�S�ɓǂ܂�Ă���
�l�B�́A�ŋ߂̓��蒼��̘_���ł́A�m��ʊԂ�DME�g���b�N�̔R�����V�R�K�X�R����DME����o�C�I�}�X�R����
DME�ɁA�ˑR�A�]�����Ă��邱�Ƃɂ��āA�����͋����ꂽ�l������̂ł͂Ȃ����낤���B
�@���͂Ƃ�����A�������U�����������̓��蒼��́A�f�B�[�[���g���b�N�ɗp���鏫���̔R���Ƃ��āA�]���̘_����
�͌y�������G�l���M�[�������R�O�������c�l�d�𐄏�����@�B�w��̋^��ɏڏq���Ă���悤�ɓV�R�K�X�R����
DME�𐄏����Ă������A�ŋ߂�2012�N5���̎����ԋZ�p��E�t�G���ł�DME�R���W�̔��\�_���ł́A�o�C�I�}�X
�R����DME�𐄑E���Ă���悤�ł���B���̂悤�ɁA�������U�����������̓��蒼��́A�f�B�[�[���g���b�N�ɗp����
�����̔R���Ƃ��āA�V�R�K�X�R����DME����o�C�I�}�X�R����DME�ɕύX�����Ă���悤�ł��邪�ADME�𐄏����Ă�
�邱�Ƃɂ͕ς��͂Ȃ��悤�ł���B�Ƃ��낪�A�O�q�̕\�Q�Ɏ������悤�ɑ�^�g���b�N�̔R���ɖ؎��n�`�b�v�n�o�C�I�}
�X�R����DME��p�����ꍇ�́A��^�g���b�N�Ɍy����p����ꍇ�ɔ�ׁA�G�l���M�[�������U�T���ȏ���Q����邱
�Ƃ��M���̂���g�D�E�c�̂̕���16�N�i��2003�N�j�̕��Ɍ��\����Ă���B���̂悤�ȑ�^�g���b�N�Ƀo�C�I�}�X�R
����DME��p�����ꍇ�̓G�l���M�[������Q��邱�Ƃ����炩�ɂ�������炸�A���蒼��́A���݂ł��u�i�o�C�I
�}�X�R���́jDME���f�B�[�[���G���W���̏����̗L�]�ȔR���v�Ǝ咣���Ă���̂��B����́A���Љ�I�Ƃ������Ă��ߌ�
�ł͂Ȃ����Ǝv�����A�@���Ȃ��̂ł��낤���B
�@���ݎЉ�ł́A���w����ƒ�̎�w�ɂ��Ȏ�����O���ɂ��������������߂��Ă��鎞��ł���B���̂悤�ȏȃG
�l���M�[�E�Ȏ������ŏd�v������錻�݂ɂ����ẮA�G�l���M�[�������������Q���DME���f�B�[�[���g���b�N�̏�
���̔R���ɂ͎��i�ł��邱�Ƃ́A���ƂłȂ��Ă��e�Ղɗ����ł��邱�Ƃ��B���������āA�u�o�C�I�}�X�R���v�Ɓu�V�R�K
�X�R���v�̉����DME�ł����Ă��A�킪���̃g���b�N�ݕ��A������ɂ����āA�����I�ɑ�^�g���b�N�̒�Y�f�A�E�Ζ�
�̎Љ����������R���Ƃ���DME���L����ʂɕ��y���Ă������Ƃ͑S���l�����Ȃ��B���̂悤�Ȃ��Ƃ́A�ސE�����|���R
�c���Z�p���̕M�҂ɂ��e�Ղɔ��邱�Ƃł��邱�Ƃ���A�����̐��Ƃł��释�����U�����������̓��蒼���i�Ɓj
��ʈ��S���������̍����R�Y���́A�O�q�̕\�Q�Ɏ������u�A���p�R����Well-to-Wheel�]���v�y���{�ɂ�����A��
�p�R�������iWell-to-Wheel�j�𒆐S�Ƃ����������ʃK�X�r�o�ʂɊւ��錤�����z�@����16�N11���@�g���^�����ԇ�
�@�݂��ُ�����̃f�[�^����A��^�g���b�N�̔R���ɓV�R�K�X�R����DME��p�����ꍇ�́A��^�g���b�N�Ɍy����
�p����ꍇ�ɔ�ׁA�G�l���M�[������3�Q���ȏ���Q��A���l�ɖ؎��n�`�b�v�n�o�C�I�}�X�R����DME��p������
���́A��^�g���b�N�Ɍy����p����ꍇ�ɔ�ׁA�G�l���M�[�������U�T���ȏ���Q����邽�ߑ�^�f�B�[�[���g���b�N
�̔R���Ƃ���DME�����i�ł��邱�Ƃ�����16�N�i��2003�N�j���_�Ŕ������Ă���̂�������炸�A����24�N�i��2012
�N�j�̎��_�ł����X�ɑ�^�f�B�[�[���g���b�N�̔R���Ƃ���DME�𐄏�����ړI�E���@�͈�́A���Ȃ̂ł��낤���B
�@���̂悤�ɁA�������U�����������̓��蒼��Ɓi�Ɓj��ʈ��S���������̍����R�Y���̗����́A�o�C�I�}�X�R
����DME���ȃG�l���M�[�E�Ȏ����̖ʂ���f�B�[�[���R���Ƃ��Ă͒v���I�Ȍ��ׂ����邱�Ƃ��E�َE���A�o�C�I�}
�X�R����DME�ɂ������Y�f�i��CO2�팸�j�̗D�ʐ����������グ�ăo�C�I�}�X�R����DME���f�B�[�[���G���W��
�̏����̔R���Ƃ��Ĉӌ��E�咣������Ă���悤���B�ʂ����āA�A��Y�f�i��CO2�팸�j�̗D�ʐ������������Ƀo�C�I�}
�X�R����DME���f�B�[�[���G���W���̏����̔R���ł���Ƃ̇������U�����������̓��蒼��Ɓi�Ɓj��ʈ��S��
�������̍����R�Y���̗����̕M�҂ɂ͂ƂĂ������̖{�S�Ƃ͂ƂĂ��v���Ȃ��̂ł���B�����āA�o�C�I�}�X�R����
DME���f�B�[�[���G���W���̏����̔R���ł���Ƃ̓ڒ����Ș_���\���Ă��释�����U�����������̓��蒼���
�i�Ɓj��ʈ��S���������̍����R�Y���̗����̖ړI�́A�P�Ȃ鐭�{�W�\�Z����̎���������̊m�ۂ�������
�I�ł���悤�Ɏv����̂ł���B���ɁA���ꂪ�����ł���A���̂悤�ȍs�ׂ́A2012�N10�����ɐ��Ԃ���킹������
�t���a�@�E���C�������̐X�����j�������{�������P���U�疜�~�̈ꕔ���g���Ďg���Ď��{�����u���o�r�זE�i�l�H���\
�����זE�j����S�؍זE�����A���҂̐S���ɈڐA���鐢�E���̗Տ����p���s�����Ƃ��鋕�U�̌������\�v�Ɨގ���
��������\�ɑ�������悤�Ɏv���邪�A����͕M�҂̒P�Ȃ�v���߂����ł��낤���B�����āA�������U������������
���蒼���i�Ɓj��ʈ��S���������̍����R�Y���̃o�C�I�}�X�R����DME�̌����ɍ��̗\�Z����������Ă���
�̂ł���A��v�����@���ŋ��̖��ʎg�����������`�F�b�N���ׂ��Č��ɑ�������悤�Ɏv�����A�@���Ȃ��̂ł��낤
���B
�@�Ȃ��A�V�k�S�Ȃ��猾�킹�Ă���������A���蒼��ƍ����R�Y���̗����́A���ꂼ��̌䎩�g�̖��_�̂���
�ɂ��A�����̃g���b�N�p�̐V�����R���Ƃ��ăo�C�I�}�X�R����DME��M�S�ɐ������Ă��邱�Ƃ��A�����ɒ��~���������]
�܂����Ǝv�����A�@���Ȃ��̂ł��낤���B�]�v�Ȃ����b�ł��낤���A�f�B�[�[���G���W���̐��ƂƂ��Ẳ��_���c����
�ꂪ�����ɂ���悤�ȋC�����ĂȂ�Ȃ��̂��B����Ƃ��A���蒼��ƍ����R�Y���̗����́A���̃y�[�W��V�R�K�X��
�獇����DME��GTL�́A�g���b�N�p�R���ɕs�K�ɏڏq���Ă���悤�ȁA�u�V�R�K�X�ƃo�C�I�}�X�Ƃ̉��ꂪ�����ł���
�Ă��A��������ޗ��Ƃ��Đ��������DME�́A�����̃f�B�[�[���g���b�N�p�̐V�����R���Ƃ��Ă͕s�K�ł���v��
����M�҂̈ӌ��E�咣�����ł���Ƃ̌����������Ă���̂ł��낤���B�����āA�M�҂���w�ɍ˂̌��Z�p���ł����
�ɁA������ނ��Ē������Ԃ��o�߂��Ă��邽�߂ɍŐV�̋Z�p���ɑa���Ȃ��Ă��邽�߁A�o�C�I�}�X�R����DME��
�y���Ɣ�r�����ꍇ�ɃG�l���M�[�����̘Q��������ƁA�M�҂�����Ɍ�����Ă���Ƃ̌����������Ă���̂ł��낤
���B�����āA��^�g���b�N�̏����R���Ƃ��Ď��i�ł���Ƃ̓I�O��ȃo�C�I�}�X�R����DME�̔ᔻ��n���ȕM�҂�����
�ɍs���Ă���ɉ߂��Ȃ��ƁA���蒼��ƍ����R�Y���̗����͍l���Ă���̂ł��낤���B
���̏ꍇ�ɂ́A�M�҂�DME�Ɋւ���ӌ��E�咣�Ɍ�肪����Ƃ��āA�M�҈��Ƀ��[���������肢�����������Ǝv���Ă�
��B���̃��[������邱�Ƃɂ���āu�����̃f�B�[�[���g���b�N�p�̐V�����R���Ƃ���DME���s�K�v�Ƃ���M�҂̈�
���E�咣�����ł��邱�Ƃ��m�F�ł���A���̃y�[�W�̋L�ړ��e�́A�����ɒ����܂��͍폜�������ƍl���Ă���B
�@���͂Ƃ�����A���̂悤�ȇ������U�����������̓��蒼��ƓƁj��ʈ��S���������̍����R�Y���̎�������
�́A�����̂킪���́u��Y�f�v�A�u�E�Ζ��v�ɑS���v���ł��Ȃ��ŋ��̖��ʎg���ł���Ɛ��@����邽�߁A�����A���~��
�ė~�������̂ł���B�߂������ɍ��ƍ����̔j�]���\�z����邽�߂ɏ���ł̑��ł��c�_����Ă�����{�ɂ����āA
���̂悤�Ȑŋ��̖��ʎg�������X�ƍs���Ă���Ƃ���A�����̍����ɂƂ��Ă͖��f�疜�Ȃ��Ƃł͂Ȃ����낤���B
�����āA�������U�����������̓��蒼��ƓƁj��ʈ��S���������̍����R�Y���̗����̌����ɍ��̗\�Z������
����Ă���̂ł���A��v�����@���ŋ��̖��ʎg�����������`�F�b�N���ׂ��Č��ɑ�������悤�Ɏv�����A�@���Ȃ�
�̂ł��낤���B��v�����@�ɂ��ŋ��ɑ��H���V���A���ގ����]�܂��Ƃ��낾�B
�R�DDDF�g���b�N�̎��p���ɂ���đ�^�g���b�N�̕���ł̒�Y�f�E�E�Ζ����\���I
�@�ȏ�̂悤�ɁA�o�C�I�}�X�R����DME�́A�u�c��ȃo�C�I�}�X�����̎����Q��v��u�����ԗp�R���̗ʓI�m�ۂ���
��v�ƂȂ��肪���邽�߁A�����̃g���b�N�p�̐V�����R���Ƃ��Ă͕s�K�ł���B�܂��A�V�R�K�X���獇����DME��GTL
�́A�g���b�N�p�R���ɕs�K������y�������G�l���M�[�������R�O�������c�l�d�𐄏�����@�B�w��̋^���ɏڏq��
�Ă���悤�ɁA�V�R�K�X�R����DME���u�c��ȃG�l���M�[�����̘Q��v�̌��ׂ����邽�߂ɁA�����̃f�B�[�[���G���W
���̐V�����R���Ƃ��Ă͕s�K�ł���B���̂��߁A�o�C�I�}�X�R���ƓV�R�K�X�R���̉����DME�ł����Ă��ADME���̂�
�̂������̃g���b�N�p�f�B�[�[���G���W���̔R���Ƃ��Ă͎��i�ł��邱�Ƃ͖��炩�ł���B�����ŁA�킪���ɂ�����g���b
�N�ݕ��A������ɂ�����u��Y�f�v�Ɓu�E�Ζ��v��}���i�Ƃ��āA�����̃f�B�[�[���g���b�N�ɐ������ׂ��R���́A�V�R
�K�X�i��CNG or LNG)�ł���ƁA�M�҂��\�z���Ă���B
��v�ƂȂ��肪���邽�߁A�����̃g���b�N�p�̐V�����R���Ƃ��Ă͕s�K�ł���B�܂��A�V�R�K�X���獇����DME��GTL
�́A�g���b�N�p�R���ɕs�K������y�������G�l���M�[�������R�O�������c�l�d�𐄏�����@�B�w��̋^���ɏڏq��
�Ă���悤�ɁA�V�R�K�X�R����DME���u�c��ȃG�l���M�[�����̘Q��v�̌��ׂ����邽�߂ɁA�����̃f�B�[�[���G���W
���̐V�����R���Ƃ��Ă͕s�K�ł���B���̂��߁A�o�C�I�}�X�R���ƓV�R�K�X�R���̉����DME�ł����Ă��ADME���̂�
�̂������̃g���b�N�p�f�B�[�[���G���W���̔R���Ƃ��Ă͎��i�ł��邱�Ƃ͖��炩�ł���B�����ŁA�킪���ɂ�����g���b
�N�ݕ��A������ɂ�����u��Y�f�v�Ɓu�E�Ζ��v��}���i�Ƃ��āA�����̃f�B�[�[���g���b�N�ɐ������ׂ��R���́A�V�R
�K�X�i��CNG or LNG)�ł���ƁA�M�҂��\�z���Ă���B
�@���̓V�R�K�X�̓Z�^�������ɂ߂ĒႢ���Ƃ���A��C�ƓV�R�K�X�̍����C��R�Ă�����ɂ́C�O������̓_���K
�v�ƂȂ�B���̓V�R�K�X��R���Ƃ���G���W���͑傫�������ĂQ��ނ���A���̈�̓X�p�[�N�v���O�̉Ήԕ��d��p��
�ēV�R�K�X�݂̂�R�Ă�����X�p�[�N�v���O�����V�R�K�X��ăG���W��������B�����đ��̓V�R�K�X�G���W���́A�R��
�����Ƀp�C���b�g���˂����y���̎��Ȓ��̉Ή��ɂ��V�R�K�X��R�Ă�����y�����Ό^�̃f�B�[�[���f���A���t��
�G���i�c�c�e�j�G���W���ł���D
�v�ƂȂ�B���̓V�R�K�X��R���Ƃ���G���W���͑傫�������ĂQ��ނ���A���̈�̓X�p�[�N�v���O�̉Ήԕ��d��p��
�ēV�R�K�X�݂̂�R�Ă�����X�p�[�N�v���O�����V�R�K�X��ăG���W��������B�����đ��̓V�R�K�X�G���W���́A�R��
�����Ƀp�C���b�g���˂����y���̎��Ȓ��̉Ή��ɂ��V�R�K�X��R�Ă�����y�����Ό^�̃f�B�[�[���f���A���t��
�G���i�c�c�e�j�G���W���ł���D
�@�悸�A�O�҂̃X�p�[�N�v���O���V�R�K�X�G���W���̑�^CNG�g���b�N�́A�]���̑�^�f�B�[�[���g���b�N�ɔ�r������
���A�f�B�[�[���Ɠ����̂b�n�Q��r�o���A�f�B�[�[�������R���G�l���M�[���R�P���������Q���v���I�Ȍ��ׂ�����B
���̃X�p�[�N�v���O���V�R�K�X�G���W���̑�^CNG�g���b�N�́A�V�R�K�X��đ�^�g���b�N�́A�d�ʎԔR���ɕs�K
���̌��׃g���b�N���I�ɏڏq���Ă���悤�ɁA�]���̑�^�f�B�[�[���g���b�N�ɔ�r�����ꍇ�ɂ̓f�B�[�[�������R��
�G�l���M�[���R�P���������Q���v���I�Ȍ��ׂ�����B
���A�f�B�[�[���Ɠ����̂b�n�Q��r�o���A�f�B�[�[�������R���G�l���M�[���R�P���������Q���v���I�Ȍ��ׂ�����B
���̃X�p�[�N�v���O���V�R�K�X�G���W���̑�^CNG�g���b�N�́A�V�R�K�X��đ�^�g���b�N�́A�d�ʎԔR���ɕs�K
���̌��׃g���b�N���I�ɏڏq���Ă���悤�ɁA�]���̑�^�f�B�[�[���g���b�N�ɔ�r�����ꍇ�ɂ̓f�B�[�[�������R��
�G�l���M�[���R�P���������Q���v���I�Ȍ��ׂ�����B
�@�����āA��҂̓V�R�K�X�G���W���́A�R�Ď����Ƀp�C���b�g���˂����y���̎��Ȓ��̉Ή��ɂ��V�R�K�X��R�Ă�
����y�����Ό^�̂c�c�e�G���W���ł���B���̌y�����Ό^�̂c�c�e�G���W���́A�]���̑�^�f�B�[�[���g���b�N�ɔ�r��
���ꍇ�A�f�B�[�[���Ɠ����̔M�����ł��邱�Ƃɉ����A�f�B�[�[�����b�n�Q��15�����Ȃ��ł��钷��������B�ȏ�̓�
�e�ɂ��ẮA��N�i2008�N�j��11��14���ɇ��G�k�E�e�B�[�E�G�X�ihttp://www.nts-book.co.jp/)�ɔ��s���ꂽ�u�N���[���f
�B�[�[���J���̗v�f�Z�p�����v�Ɖ]����发(http://www.nts-book.co.jp/item/detail/summary/energy/20081114_51.
html)�̑�T�͂̂V���ɁA�u�����ׂ������---�V�R�K�X�p����f�B�[�[���G���W��---�v�̍��ɏڂ����L��
����Ă���̂ŁA�Q�l�ɂ��Ă������������B
����y�����Ό^�̂c�c�e�G���W���ł���B���̌y�����Ό^�̂c�c�e�G���W���́A�]���̑�^�f�B�[�[���g���b�N�ɔ�r��
���ꍇ�A�f�B�[�[���Ɠ����̔M�����ł��邱�Ƃɉ����A�f�B�[�[�����b�n�Q��15�����Ȃ��ł��钷��������B�ȏ�̓�
�e�ɂ��ẮA��N�i2008�N�j��11��14���ɇ��G�k�E�e�B�[�E�G�X�ihttp://www.nts-book.co.jp/)�ɔ��s���ꂽ�u�N���[���f
�B�[�[���J���̗v�f�Z�p�����v�Ɖ]����发(http://www.nts-book.co.jp/item/detail/summary/energy/20081114_51.
html)�̑�T�͂̂V���ɁA�u�����ׂ������---�V�R�K�X�p����f�B�[�[���G���W��---�v�̍��ɏڂ����L��
����Ă���̂ŁA�Q�l�ɂ��Ă������������B
�@���̂悤�ɂc�c�e�G���W���́A�f�B�[�[���Ɠ����̍����M������L���Ă���̂ŁA��^�g���b�N�ɂ����ăf�B�[�[���G��
�W���ɑ�ւ��ėp���邱�Ƃɂ��Ă͔M�����̖ʂ���͉��̖��������B���������āA�V�R�K�X�p����c�c�e�G���W
���́A����̑�^�g���b�N�́u�b�n�Q�팸�v��u�E�Ζ��v�𐄐i���邽�߂̍œK�ȓV�R�K�X�G���W���ł���ƒf�����ėǂ�
�̂ł͂Ȃ����낤���B ���������āA�����A�䂪���ɂ�����DDF��^�g���b�N���J�����Ď��p�����A��ʂɍL�����y������
���ɂ́A��^�g���b�N����ɂ������Y�f�i��CO2�팸�j�E�E�Ζ���}�邱�Ƃ��\�ł���B����DDF�G���W���̏ڍׂ�
���Ă��f�B�[�[���ɔ�ׂP�T���̂b�n�Q�팸���\�Ȃc�c�e�G���W���ADDF��^�g���b�N�ɂ��Ă�DDF�^�]�ƃf�B�[�[
���^�]�̑I�����\�Ȃc�c�e��^�g���b�N �̃y�[�W�ɏڏq���Ă���̂ŁA�����̂�����͌䗗�������������B
�W���ɑ�ւ��ėp���邱�Ƃɂ��Ă͔M�����̖ʂ���͉��̖��������B���������āA�V�R�K�X�p����c�c�e�G���W
���́A����̑�^�g���b�N�́u�b�n�Q�팸�v��u�E�Ζ��v�𐄐i���邽�߂̍œK�ȓV�R�K�X�G���W���ł���ƒf�����ėǂ�
�̂ł͂Ȃ����낤���B ���������āA�����A�䂪���ɂ�����DDF��^�g���b�N���J�����Ď��p�����A��ʂɍL�����y������
���ɂ́A��^�g���b�N����ɂ������Y�f�i��CO2�팸�j�E�E�Ζ���}�邱�Ƃ��\�ł���B����DDF�G���W���̏ڍׂ�
���Ă��f�B�[�[���ɔ�ׂP�T���̂b�n�Q�팸���\�Ȃc�c�e�G���W���ADDF��^�g���b�N�ɂ��Ă�DDF�^�]�ƃf�B�[�[
���^�]�̑I�����\�Ȃc�c�e��^�g���b�N �̃y�[�W�ɏڏq���Ă���̂ŁA�����̂�����͌䗗�������������B
�@�Ƃ���ŁA�X�E�F�[�f���̃{���{�E�g���b�N�X�́A2011�N5��31���ɒ������A�������ɑ�^�c�c�e�g���b�N�i�ʐ^�P�Q�Ɓj��
�����i�o�T�Fhttp://www.volvotrucks.com/trucks/global/en-gb/newsmedia/pressreleases/Pages/pressreleases.aspx?
pubid=10743�j�����B���̔��\�ɂ��ƁA�G���W����13���b�g���A�ō��o�͂�440�g�o�i338���v�j�A�ő�g���N��2300�m����
����B�V�R�K�X�i�k�m�f�j�̗��p����75���ł���A�G���W���̔M�����́A�X�p�[�N�v���O���V�R�K�X�G���W���ɔ�ׂāA30
�`40�������A�b�n�Q�r�o�ʂ̓f�B�[�[���g���b�N�ɔ�ׂ�10���팸���邱�Ƃ��ł���Ƃ̂��ƁB�܂��A�M�҂�����܂Ő���
���Ă����悤�ɁA���s���ɓV�R�K�X�i�k�m�f�j���g���ʂ������ꍇ�ɂ́A�y���݂̂ő��s���邱�Ƃ��\�ł���B2011�N��
��100����x���I�����_�A�C�M���X�A�X�E�F�[�f���Ŕ̔�����\��ŁA�W�����琶�Y���J�n�����Ƃ̂��Ƃ��B����A2�N
���x�ŁA���B�̂U�`�W����ŔN��400����x�̔̔����\�肳��Ă���悤���B
�����i�o�T�Fhttp://www.volvotrucks.com/trucks/global/en-gb/newsmedia/pressreleases/Pages/pressreleases.aspx?
pubid=10743�j�����B���̔��\�ɂ��ƁA�G���W����13���b�g���A�ō��o�͂�440�g�o�i338���v�j�A�ő�g���N��2300�m����
����B�V�R�K�X�i�k�m�f�j�̗��p����75���ł���A�G���W���̔M�����́A�X�p�[�N�v���O���V�R�K�X�G���W���ɔ�ׂāA30
�`40�������A�b�n�Q�r�o�ʂ̓f�B�[�[���g���b�N�ɔ�ׂ�10���팸���邱�Ƃ��ł���Ƃ̂��ƁB�܂��A�M�҂�����܂Ő���
���Ă����悤�ɁA���s���ɓV�R�K�X�i�k�m�f�j���g���ʂ������ꍇ�ɂ́A�y���݂̂ő��s���邱�Ƃ��\�ł���B2011�N��
��100����x���I�����_�A�C�M���X�A�X�E�F�[�f���Ŕ̔�����\��ŁA�W�����琶�Y���J�n�����Ƃ̂��Ƃ��B����A2�N
���x�ŁA���B�̂U�`�W����ŔN��400����x�̔̔����\�肳��Ă���悤���B
 |
|
 |
 |
�@�Ƃ���ŁA�{���{�́A�g���b�N���[�J�Ƃ��Ă͐��E�Ŏn�߂đ�^�c�c�e�g���b�N�̎s�̂��J�n�������A�c�O�Ȃ��ƂɁA����
�{���{�̑�^�c�c�e�g���b�N�E�g���N�^�ɓ��ڂ��ꂽ�G���W���́A�����̋Z�p�Ƃ��]����z�C�Ǔ����ˎ��̂c�c�e�G���W��
�ł���B����A���̋����̋z�C�Ǔ����ˎ��c�c�e�G���W���̐��\���X�Ɍ���ł���V�����Z�p�����ɐ��̒��ɑ��݂�
�Ă���A���ꂪ�V�R�K�X���V�����_���ɒ��ڕ��˂��钼�����c�c�e�G���W���ł���B���̒������c�c�e�G���W���́A�z�C
�Ǔ����ˎ��c�c�e�G���W���ɔ�ׁA�c�c�e�G���W���ɂƂ��ďd�v�ȗv�f�ł���u�r�o�K�X���\�̌���v��u�V�R�K�X�i�k�m
�f�A�b�m�f�j�̎g�p����������v�ł��邱�Ƃ������ł���B
�{���{�̑�^�c�c�e�g���b�N�E�g���N�^�ɓ��ڂ��ꂽ�G���W���́A�����̋Z�p�Ƃ��]����z�C�Ǔ����ˎ��̂c�c�e�G���W��
�ł���B����A���̋����̋z�C�Ǔ����ˎ��c�c�e�G���W���̐��\���X�Ɍ���ł���V�����Z�p�����ɐ��̒��ɑ��݂�
�Ă���A���ꂪ�V�R�K�X���V�����_���ɒ��ڕ��˂��钼�����c�c�e�G���W���ł���B���̒������c�c�e�G���W���́A�z�C
�Ǔ����ˎ��c�c�e�G���W���ɔ�ׁA�c�c�e�G���W���ɂƂ��ďd�v�ȗv�f�ł���u�r�o�K�X���\�̌���v��u�V�R�K�X�i�k�m
�f�A�b�m�f�j�̎g�p����������v�ł��邱�Ƃ������ł���B
�@���������āA���ɁA���{�ő�^�c�c�e�g���b�N���J�������̂ł���A�{���{�̋z�C�Ǔ����ˎ��̂c�c�e�G���W
���𓋍ڂ�����^�c�c�e�g���b�N�����D�ꂽ���\�����������c�c�e�G���W���𓋍ڂ�����^�c�c�e�g���b�N�E�g��
�N�^��Ƃ������Ɏ��p�����ė~�����Ƃ��낾�B�����āA���̑�^�c�c�e�g���b�N�E�g���N�^�ɂ́A�M�҂���Ă�������
��DDF�G���W���i�������J2008-51121�j�̋Z�p���̗p���ė~�������̂��B���̏ꍇ�ɂ́A��^�c�c�e�g���b�N�E�g���N�^�́A
�������c�c�e�G���W���𓋍ڂ��Ă���ɂ�������炸�A�u�f�B�[�[�����s�v�Ɓu�c�c�e���s�v�Ƃ̔C�ӂ̑��s���[�h��I����
�ĉ^�s�ł���悤�ɂȂ�̂ł���B�@
���𓋍ڂ�����^�c�c�e�g���b�N�����D�ꂽ���\�����������c�c�e�G���W���𓋍ڂ�����^�c�c�e�g���b�N�E�g��
�N�^��Ƃ������Ɏ��p�����ė~�����Ƃ��낾�B�����āA���̑�^�c�c�e�g���b�N�E�g���N�^�ɂ́A�M�҂���Ă�������
��DDF�G���W���i�������J2008-51121�j�̋Z�p���̗p���ė~�������̂��B���̏ꍇ�ɂ́A��^�c�c�e�g���b�N�E�g���N�^�́A
�������c�c�e�G���W���𓋍ڂ��Ă���ɂ�������炸�A�u�f�B�[�[�����s�v�Ɓu�c�c�e���s�v�Ƃ̔C�ӂ̑��s���[�h��I����
�ĉ^�s�ł���悤�ɂȂ�̂ł���B�@
�@���͂Ƃ�����A�V�R�K�X�p����c�c�e�G���W���́A�f�B�[�[���Ɠ����̍����M������L���Ă����ɁA��^�g���b�N
�́u�b�n�Q�팸�v��u�E�Ζ��v�𐄐i���邱�Ƃ��\�Ȃ��߁A�䂪���ɂ����đ��}��DDF��^�g���b�N�̎��p�����]�܂�
��B�킪���ɂ����鍡��̃g���b�N�W�̊w�ҁE���Ƃ�g���b�N���[�J�̑傢�Ȃ錒�������҂����Ƃ���ł���B
�́u�b�n�Q�팸�v��u�E�Ζ��v�𐄐i���邱�Ƃ��\�Ȃ��߁A�䂪���ɂ����đ��}��DDF��^�g���b�N�̎��p�����]�܂�
��B�킪���ɂ����鍡��̃g���b�N�W�̊w�ҁE���Ƃ�g���b�N���[�J�̑傢�Ȃ錒�������҂����Ƃ���ł���B
�Ȏ����ł����\�ł��B�Ջ��l���ĂɃ��[���������肢��������A�o����͈͂őΉ������Ă��������܂��B

|
