:
�Ջ��l�̃A�C�f�A
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�g�b�v�y�[�W�ɖ߂� �T�C�g�}�b�v
�iDDF�F�f�B�[�[���f���A���t���G���G���W�����y�����Ό^�V�R�K�X�G���W���j
�ŏI�X�V���F2015�N�V��9��
 |
�P�D�����Ɏ��p�����\�ȑ�^�g���b�N�̒���Q���Z�p�ɂ���
1-1�D���p�����i�ޏ�p�ԁE���^�g���b�N�̒���Q���Z�p
�@��p�ԁE���^�g���b�N�͓s�s���𑖍s����䗦�����|�I�ɑ������߁C�ᑬ���s�p�x�C�����E�����p�x�C���i�E��
�~�p�x�������C����̑��s�����͒Z�����Ƃ��������B���̂悤�ȏ�p�ԁE���^�g���b�N�̑��s�`�Ԃɂ����ẮA���k
�V�R�K�X�i�b�m�f�j�����Ԃƃn�C�u���b�h�����Ԃł́C���ꂼ��̒������������邽�߁C���ɐ������̏�p�ԁE���^�g
���b�N�ɍ̗p����Ă���B�܂��C�A�������G�X�e���������o�C�I�f�B�[�[���R���͓�_���Y�f�i�b�n�Q�j�̍팸���ʂ�
���邽�߁C���^�g���b�N���ł̎������s���s���Ă���B���̑��ɂ��d�C�����Ԃ̏�p�Ԃ�2009�N�ɔ�����\��
���郁�[�J�[������Ă���B���̂悤�ɁC�ߔN�C��p�ԁE���^�g���b�N�̕���ł͒���Q�Ԃ������ɑ������Ă���C�b
�n�Q�̍팸���܂ޒ���Q������ђE�Ζ��̋Z�p�������ɐZ�����Ă���l�q���f����B
�~�p�x�������C����̑��s�����͒Z�����Ƃ��������B���̂悤�ȏ�p�ԁE���^�g���b�N�̑��s�`�Ԃɂ����ẮA���k
�V�R�K�X�i�b�m�f�j�����Ԃƃn�C�u���b�h�����Ԃł́C���ꂼ��̒������������邽�߁C���ɐ������̏�p�ԁE���^�g
���b�N�ɍ̗p����Ă���B�܂��C�A�������G�X�e���������o�C�I�f�B�[�[���R���͓�_���Y�f�i�b�n�Q�j�̍팸���ʂ�
���邽�߁C���^�g���b�N���ł̎������s���s���Ă���B���̑��ɂ��d�C�����Ԃ̏�p�Ԃ�2009�N�ɔ�����\��
���郁�[�J�[������Ă���B���̂悤�ɁC�ߔN�C��p�ԁE���^�g���b�N�̕���ł͒���Q�Ԃ������ɑ������Ă���C�b
�n�Q�̍팸���܂ޒ���Q������ђE�Ζ��̋Z�p�������ɐZ�����Ă���l�q���f����B
1-2�D��^�g���b�N�ɂ͕s�����ȏ�p�ԁE���^�g���b�N�̒���Q�ԋZ�p
�@��^�g���b�N�́A���{�̌o�ϊ����̕����ʂŎ����S���Ă��邱�Ƃ͒N�����F�߂�Ƃ���ł���B���{�̍��y��
��k�ɍג����`������Ă��邽�߁A��^�g���b�N�̏ꍇ�ɂ͈����1000km�ȏ�����s���邱�Ƃ��������͂Ȃ��B
��k�ɍג����`������Ă��邽�߁A��^�g���b�N�̏ꍇ�ɂ͈����1000km�ȏ�����s���邱�Ƃ��������͂Ȃ��B
���̂悤�Ȏg�p���ɂ����ẮA����Q�Ԃ̂b�m�f�����Ԃ͈�[�U���s�������Z���C���{�S���ɏ\���Ȃb�m�f�X�^
���h����������Ă��Ȃ����Ƃ���C�s�s�ԑ��s�̑�^�g���b�N�ɂ͕s�����ł���B�܂��C����������Q�Ԃ̃n�C�u���b
�h�����Ԃ́A�ᑬ���s��A�C�h�����O�̏ꍇ��p�ɂȒ�~���̐����G�l���M�[�̉ɂ���ĔR��R����P��
��C�r�o�K�X�̒ጸ�Ɍ��ʂ������ł��邪�A�������H��A�����s���鎞�ɂ͂����̔R���єr�o�K�X�̒ጸ
���ʂ��S�������Ȃ��B���̂��߁C�s�s�Ԃ̘A���������s��������^�g���b�N�Ƀn�C�u���b�h�Z�p���̗p���Ă��A�{
���̋@�\���S�������ł��Ȃ��㕨�ł���B�܂��A�d�C�����Ԃł͈��̃o�b�e���[�[�d�ł̑��s�������Z�����Ƃ�
�����C�g���b�N�ł̓o�b�e���[�̏d�ʑ��ɂ��ݕ��ύڗʂ̍팸���������߁C����Ƃ��f�B�[�[����^�g���b�N���d�C
�����Ԃɕς��\���͖��Ɉ���L�蓾�Ȃ��B���̂悤�ɁA���݂̏�p�ԁE���^�g���b�N�Ŋ��Ɏ��p������A�Ⴕ
���͎��p������悤�Ƃ��Ă������Q�ԋZ�p�́A�s�s�ԑ��s�̑�^�g���b�N�ɂ͓K���Ă��Ȃ����Ƃ͖������B���̂�
�߁A��^�g���b�N�̓��͌��ɂ͍���Ƃ��f�B�[�[���G���W���ɗ��炴��Ȃ����Ƃ͎��m�̎����Ƃ��ĔF�������
����B
���h����������Ă��Ȃ����Ƃ���C�s�s�ԑ��s�̑�^�g���b�N�ɂ͕s�����ł���B�܂��C����������Q�Ԃ̃n�C�u���b
�h�����Ԃ́A�ᑬ���s��A�C�h�����O�̏ꍇ��p�ɂȒ�~���̐����G�l���M�[�̉ɂ���ĔR��R����P��
��C�r�o�K�X�̒ጸ�Ɍ��ʂ������ł��邪�A�������H��A�����s���鎞�ɂ͂����̔R���єr�o�K�X�̒ጸ
���ʂ��S�������Ȃ��B���̂��߁C�s�s�Ԃ̘A���������s��������^�g���b�N�Ƀn�C�u���b�h�Z�p���̗p���Ă��A�{
���̋@�\���S�������ł��Ȃ��㕨�ł���B�܂��A�d�C�����Ԃł͈��̃o�b�e���[�[�d�ł̑��s�������Z�����Ƃ�
�����C�g���b�N�ł̓o�b�e���[�̏d�ʑ��ɂ��ݕ��ύڗʂ̍팸���������߁C����Ƃ��f�B�[�[����^�g���b�N���d�C
�����Ԃɕς��\���͖��Ɉ���L�蓾�Ȃ��B���̂悤�ɁA���݂̏�p�ԁE���^�g���b�N�Ŋ��Ɏ��p������A�Ⴕ
���͎��p������悤�Ƃ��Ă������Q�ԋZ�p�́A�s�s�ԑ��s�̑�^�g���b�N�ɂ͓K���Ă��Ȃ����Ƃ͖������B���̂�
�߁A��^�g���b�N�̓��͌��ɂ͍���Ƃ��f�B�[�[���G���W���ɗ��炴��Ȃ����Ƃ͎��m�̎����Ƃ��ĔF�������
����B
�@�Ƃ���ŁA�Q�O�O�V�N�Q���̎Y�ƍ\���R�c�������n�������ψ���E�������R�c��n���������P�O��
������@��ʐ����R�c���ʑ̌n���ȉ��P�P�������@������c�̎����Q�@�u�^�A�����CO�Q�팸���
�ۑ�v(http://www.mlit.go.jp/singikai/koutusin/koutu/kankyou/11/02.pdf)�̉^�A����ɂ�����CO�Q�r�o�팸�̂�
�߂́u�V���̓V�X�e���E�V�R���̗��p�v�̍��ɋL�ڂ���Ă���CO2�팸�̋Z�p�́A�n�C�u���b�h�ԁA�d�C�����Ԃ���
�уo�C�I�}�X�R���ł���(���\���Q�ƕ��j�B�O�q�̒ʂ�A�n�C�u���b�h�ԂƓd�C�����Ԃ͓s�s�ԑ��s�̑�^�g���b�N��
�͍̗p�ł��Ȃ��Z�p�ł���A�h�����ăo�C�I�}�X�R���݂̂���^�g���b�N�ɍ̗p���\�ł���B�������A�䂪���ł�
�K�v�ʂ��m�ۂ��邱�Ƃ�����Ȃ��߁A�o�C�I�}�X�R���ɂ���^�g���b�N��CO2�팸���s�\�ł��邱�Ƃ͒N����
�F�߂�Ƃ���ł���B
������@��ʐ����R�c���ʑ̌n���ȉ��P�P�������@������c�̎����Q�@�u�^�A�����CO�Q�팸���
�ۑ�v(http://www.mlit.go.jp/singikai/koutusin/koutu/kankyou/11/02.pdf)�̉^�A����ɂ�����CO�Q�r�o�팸�̂�
�߂́u�V���̓V�X�e���E�V�R���̗��p�v�̍��ɋL�ڂ���Ă���CO2�팸�̋Z�p�́A�n�C�u���b�h�ԁA�d�C�����Ԃ���
�уo�C�I�}�X�R���ł���(���\���Q�ƕ��j�B�O�q�̒ʂ�A�n�C�u���b�h�ԂƓd�C�����Ԃ͓s�s�ԑ��s�̑�^�g���b�N��
�͍̗p�ł��Ȃ��Z�p�ł���A�h�����ăo�C�I�}�X�R���݂̂���^�g���b�N�ɍ̗p���\�ł���B�������A�䂪���ł�
�K�v�ʂ��m�ۂ��邱�Ƃ�����Ȃ��߁A�o�C�I�}�X�R���ɂ���^�g���b�N��CO2�팸���s�\�ł��邱�Ƃ͒N����
�F�߂�Ƃ���ł���B
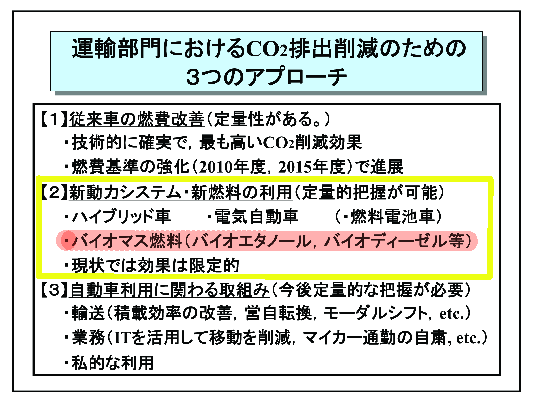
1-3�D��^�f�B�[�[���g���b�N�ɋ��߂��Ă������Q�Z�p
�@�f�B�[�[���G���W�������Q������Z�p�͓��X�i�W���Ă���C���f�_�����i�m�n���j�͔A�f�r�b�q�G�}�ɂ��\����
�팸���\�ł���B�����āC�p�e�B�L�����[�g�i�o�l�j�̓f�B�[�[�������q�������u�i�c�o�e�j�ɂ��K�v�ȃ��x���܂ł�
�팸�ł���Z�p���m������Ă���B���̂��߁A�|�X�g�V�����K���i2009�N���{�j�₻�̌�̔r�o�K�X�K�������ɑ�
���ẮC�����Z�p�̑g�����ɂ��K���ւ̓K�����\�Ɖ]���Ă���B�������Ȃ���A�䂪���ɑ��ċC��ϓ�
�g�g���Ɋ�Â������s�c�菑�ɂ�����2008�N����2012�N�܂ł̊��Ԃ�1990�N���_�̂b�n�Q�r�o�ʂɔ�ׂ�6��
�̍팸�����߂��Ă��邪�A�f�B�[�[���G���W���̂b�n�Q�r�o������ȏ�ɍ팸�ł���Z�p�͖����m������Ă���
���B���s�c�菑��CO2�팸�ڕW�B���ɂ́A�s�s�ԑ��s�̃f�B�[�[����^�g���b�N�̂b�n�Q�r�o�ɂ��Ă��A����
��X�ɍ팸�ł���V���ȋZ�p�̊J�����K�v�ł���B�o�C�I�}�X�R���̔R����p���邱�Ƃɂ���ăf�B�[�[���G���W
���̂b�n�Q�̍팸���\�ł��邪�C���̔R���͂킪���ł͏����Ƃ��K�v�ʂ̊m�ۂ�����Ɨ\�z����邽�߁C���s
�c�菑�̖ڕW��B�������i�ɂ͂Ȃ蓾�Ȃ����Ƃ͑����̐��Ƃ��F�߂Ă��邱�Ƃł���B
�팸���\�ł���B�����āC�p�e�B�L�����[�g�i�o�l�j�̓f�B�[�[�������q�������u�i�c�o�e�j�ɂ��K�v�ȃ��x���܂ł�
�팸�ł���Z�p���m������Ă���B���̂��߁A�|�X�g�V�����K���i2009�N���{�j�₻�̌�̔r�o�K�X�K�������ɑ�
���ẮC�����Z�p�̑g�����ɂ��K���ւ̓K�����\�Ɖ]���Ă���B�������Ȃ���A�䂪���ɑ��ċC��ϓ�
�g�g���Ɋ�Â������s�c�菑�ɂ�����2008�N����2012�N�܂ł̊��Ԃ�1990�N���_�̂b�n�Q�r�o�ʂɔ�ׂ�6��
�̍팸�����߂��Ă��邪�A�f�B�[�[���G���W���̂b�n�Q�r�o������ȏ�ɍ팸�ł���Z�p�͖����m������Ă���
���B���s�c�菑��CO2�팸�ڕW�B���ɂ́A�s�s�ԑ��s�̃f�B�[�[����^�g���b�N�̂b�n�Q�r�o�ɂ��Ă��A����
��X�ɍ팸�ł���V���ȋZ�p�̊J�����K�v�ł���B�o�C�I�}�X�R���̔R����p���邱�Ƃɂ���ăf�B�[�[���G���W
���̂b�n�Q�̍팸���\�ł��邪�C���̔R���͂킪���ł͏����Ƃ��K�v�ʂ̊m�ۂ�����Ɨ\�z����邽�߁C���s
�c�菑�̖ڕW��B�������i�ɂ͂Ȃ蓾�Ȃ����Ƃ͑����̐��Ƃ��F�߂Ă��邱�Ƃł���B
�@
�@�����������s�c�菑���P�X�X�V�N�P�Q���P�P���ɋc�������CO�Q�팸�̕K�v�����L���F������n�߂ĂP�O�N�ȏヌ
�x���̒����N�����o�߂��Ă���ɂ�������炸�A���{�̐��{�E�w��E��Ƃ���̓o�C�I�}�X�R���̔R���ȊO�ɁA��
�s�̑�^�f�B�[�[���g���b�N��CO�Q�r�o�������ł��팸�ł���悤�ȋZ�p�́A�����ɉ������\����Ă��Ȃ��̂��B��
�̂��Ƃ͉䂪���̑�^�f�B�[�[���g���b�N��CO�Q�팸�Ɋւ��A�P�O�N�]��̊Ԃɉ��̌������ʂ������Ă��Ȃ�����
�̏؋��ł���B
�x���̒����N�����o�߂��Ă���ɂ�������炸�A���{�̐��{�E�w��E��Ƃ���̓o�C�I�}�X�R���̔R���ȊO�ɁA��
�s�̑�^�f�B�[�[���g���b�N��CO�Q�r�o�������ł��팸�ł���悤�ȋZ�p�́A�����ɉ������\����Ă��Ȃ��̂��B��
�̂��Ƃ͉䂪���̑�^�f�B�[�[���g���b�N��CO�Q�팸�Ɋւ��A�P�O�N�]��̊Ԃɉ��̌������ʂ������Ă��Ȃ�����
�̏؋��ł���B
�@����A�ߔN�̒�����C���h�Ȃǂ̋}���Ȍo�ϔ��W��Ζ��s�[�N�̎���ɓ˓��������Ƃ���A�߂������A�䂪����
�͐Ζ��R�����s�����鎖�Ԃ��ے�ł��Ȃ��ɂȂ����B���̏ꍇ�̌y���s�����琶����g���b�N�ݕ��A
���̎x��ɂ��o�ϓI�ȍ���������ł���悤�ɂ��邽�߁A�o�ώY�ƏȂ�2006�N5���Ɂu�V�E���ƃG�l���M�[�헪�v
�\�����B���̐헪�ł́u�ق�100����Ζ��n�R���Ɉˑ�����^�A����̓G�l���M�[�����\���̒��ōł��Ǝ�
�����������߂ɐΖ��ˑ�����̒E�p��}��ׂ��v�Ƃ��C�u����A2030�N�܂łɁA�^�A����̐Ζ��ˑ��x��80�����x
�Ƃ��邱�Ƃ�ڎw���v�Ƃ�����j�Ƃ��Ă���B���R�A��^�g���b�N�ɂ��Ă����}�ɒE�Ζ�����}��K�v�����邱�Ƃ�
���R�ł���B���������āA���݂̓s�s�ԑ��s�̑�^�g���b�N�ɋ��߂��Ă���Z�p�I�ɉ��P���ׂ��d�v�ȉۑ�́A
�uCO�Q�팸�v�Ɓu�E�Ζ��v�ł���B���̉ۑ���������邽�߂ɂ́A�����^�̑�^�g���b�N�p�Ƃ��āuCO�Q�팸�v�Ɓu�E��
���v���ɖ����ł���V�����G���W���𑁋}�ɊJ������K�v�����邱�Ƃ͖��炩�ł���B
�͐Ζ��R�����s�����鎖�Ԃ��ے�ł��Ȃ��ɂȂ����B���̏ꍇ�̌y���s�����琶����g���b�N�ݕ��A
���̎x��ɂ��o�ϓI�ȍ���������ł���悤�ɂ��邽�߁A�o�ώY�ƏȂ�2006�N5���Ɂu�V�E���ƃG�l���M�[�헪�v
�\�����B���̐헪�ł́u�ق�100����Ζ��n�R���Ɉˑ�����^�A����̓G�l���M�[�����\���̒��ōł��Ǝ�
�����������߂ɐΖ��ˑ�����̒E�p��}��ׂ��v�Ƃ��C�u����A2030�N�܂łɁA�^�A����̐Ζ��ˑ��x��80�����x
�Ƃ��邱�Ƃ�ڎw���v�Ƃ�����j�Ƃ��Ă���B���R�A��^�g���b�N�ɂ��Ă����}�ɒE�Ζ�����}��K�v�����邱�Ƃ�
���R�ł���B���������āA���݂̓s�s�ԑ��s�̑�^�g���b�N�ɋ��߂��Ă���Z�p�I�ɉ��P���ׂ��d�v�ȉۑ�́A
�uCO�Q�팸�v�Ɓu�E�Ζ��v�ł���B���̉ۑ���������邽�߂ɂ́A�����^�̑�^�g���b�N�p�Ƃ��āuCO�Q�팸�v�Ɓu�E��
���v���ɖ����ł���V�����G���W���𑁋}�ɊJ������K�v�����邱�Ƃ͖��炩�ł���B
�Q�DCO2�̍팸���\�ȔR���ɂ���
�@�ߔN�̒�����C���h�ł́A�������o�ϔ��W�ɔ����ĐΖ�����̑������������B����A���E��̋ٔ�����C���E
�̐Ζ��s��ł̎������N�����C�y���s���ɂ���ĉ䂪���̑�^�g���b�N���~���ɉ^�s�ł��Ȃ��Ȃ鋰����ے肷��
���Ƃ͂ł��Ȃ��B�ň��̎��Ԃɔ�����̂���@�Ǘ��ł���Ƃ���C�g���b�N�A���̊�@�Ǘ��ɖ��S���������߁C
�����ɑ�^�g���b�N�ɂ����ĒE�Ζ��̔R���̑��}�ȓ������]�܂��Ƃ��낾�B
�̐Ζ��s��ł̎������N�����C�y���s���ɂ���ĉ䂪���̑�^�g���b�N���~���ɉ^�s�ł��Ȃ��Ȃ鋰����ے肷��
���Ƃ͂ł��Ȃ��B�ň��̎��Ԃɔ�����̂���@�Ǘ��ł���Ƃ���C�g���b�N�A���̊�@�Ǘ��ɖ��S���������߁C
�����ɑ�^�g���b�N�ɂ����ĒE�Ζ��̔R���̑��}�ȓ������]�܂��Ƃ��낾�B
�@���̂悤�ȏ܂��C�R���̒���Q�������l�����C�E�Ζ��̗L�͂ȔR�����Ƃ��Ă͓V�R�K�X�����獇����
���W���`���G�[�e���i�c�l�d�j�܂��͉t�̔R���i�f�s�k:gas to liquids�j�𐄏�����l�������B�����c�l�d�Ƃf�s�k�̓f�B
�[�[���R�ĂɓK���Ă��邱�Ƃ������āC�f�B�[�[���g���b�N�ɗp���錤��������ɍs���Ă���Ƃ���ł���B
���W���`���G�[�e���i�c�l�d�j�܂��͉t�̔R���i�f�s�k:gas to liquids�j�𐄏�����l�������B�����c�l�d�Ƃf�s�k�̓f�B
�[�[���R�ĂɓK���Ă��邱�Ƃ������āC�f�B�[�[���g���b�N�ɗp���錤��������ɍs���Ă���Ƃ���ł���B
�@���݁A�b�m�f�̌����ł���t���V�R�K�X�i�k�m�f�j��c�l�d����тf�s�k�́C�V�R�K�X�̎Y�o�n�Ő�������Ă���B��
�̍ۂɍ̌@�����V�R�K�X���̂��G�l���M�[���Ƃ��Ďg�p�����ꍇ�̊e�R���̍̌@���琻�i���܂ł̂��ꂼ��̃G
�l���M�[�����́C�k�m�f�ł�0.870�`0.930�i����0.900�j�C�c�l�d�ł�0.680�`0.730�i����0.704�j�C�f�s�k�ł�0.490�`0.680
�i����0.593�j�ł���B����C��������y��������ۂ̃G�l���M�[�����́C0.850�`0.960�i����0.924�j�ł���B�i�o
�T�F�i�g�e�b���������������ʈψ���C����15�N�x�u�i�g�e�b���������������ʁv���ԕ��C���c�@�l�@���{����
�Ԍ������C����16�N3���j�@�}�P�́A�����̃G�l���M�[���������������̂ł���B
�̍ۂɍ̌@�����V�R�K�X���̂��G�l���M�[���Ƃ��Ďg�p�����ꍇ�̊e�R���̍̌@���琻�i���܂ł̂��ꂼ��̃G
�l���M�[�����́C�k�m�f�ł�0.870�`0.930�i����0.900�j�C�c�l�d�ł�0.680�`0.730�i����0.704�j�C�f�s�k�ł�0.490�`0.680
�i����0.593�j�ł���B����C��������y��������ۂ̃G�l���M�[�����́C0.850�`0.960�i����0.924�j�ł���B�i�o
�T�F�i�g�e�b���������������ʈψ���C����15�N�x�u�i�g�e�b���������������ʁv���ԕ��C���c�@�l�@���{����
�Ԍ������C����16�N3���j�@�}�P�́A�����̃G�l���M�[���������������̂ł���B
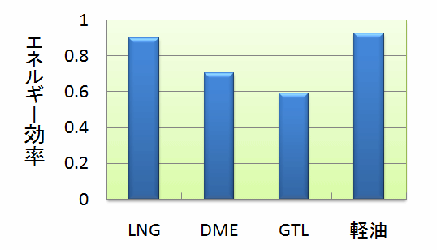
�@�����̃f�[�^���琶�Y���ɓ��������G�l���M�[���܂ނk�m�f�C�c�l�d�C�f�s�k����ьy���̔��M�ʓ�����̂b�n�Q
�r�o�ʂ��v�Z���C�k�m�f����Ƃ�����r��}�Q�Ɏ������B
�r�o�ʂ��v�Z���C�k�m�f����Ƃ�����r��}�Q�Ɏ������B
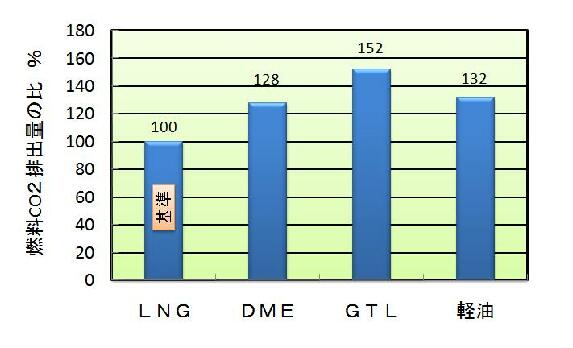
�@���݂̐����Z�p�ł̓V�R�K�X�̍̌@���琻�i���܂ł̊Ԃ̉��M���ɔr�o����b�n�Q���܂߂��ꍇ�̊e�R���̂b
�n�Q�r�o�ʂ��r����ƁA�c�l�d�ƌy���̂b�n�Q�r�o�ʂ͂k�m�f����30�������C�f�s�k�̂b�n�Q�r�o�ʂ͂k�m�f����
50���������B���ɁA�f�s�k�͌y��������15���������̂b�n�Q��r�o���邽�߁C�y��������C��������������R��
�Ɖ]����B�V�R�K�X�������Ƃ���LNG�ADME�����GTL�̎O�҂��r�����ꍇ�ALNG�ADME�����GTL�̂b�n�Q�̔r
�o�ʂ̔�́A���ꂼ�������ݔ����������Ă��R�����i�̔�ɑ�������Ɛ��@����ADME�̉��i��LNG
����1.3�{�AGTL�̉��i��LNG����1.5�{���x�ɂȂ�Ɨ\�z�����B
�n�Q�r�o�ʂ��r����ƁA�c�l�d�ƌy���̂b�n�Q�r�o�ʂ͂k�m�f����30�������C�f�s�k�̂b�n�Q�r�o�ʂ͂k�m�f����
50���������B���ɁA�f�s�k�͌y��������15���������̂b�n�Q��r�o���邽�߁C�y��������C��������������R��
�Ɖ]����B�V�R�K�X�������Ƃ���LNG�ADME�����GTL�̎O�҂��r�����ꍇ�ALNG�ADME�����GTL�̂b�n�Q�̔r
�o�ʂ̔�́A���ꂼ�������ݔ����������Ă��R�����i�̔�ɑ�������Ɛ��@����ADME�̉��i��LNG
����1.3�{�AGTL�̉��i��LNG����1.5�{���x�ɂȂ�Ɨ\�z�����B
�@�Ȃ��ADME�Ɋ֘A����l�B�́A�Ȃ�ӂ�\�킸�A�uDME�̓f�B�[�[���G���W���̍������������R���ł���A����
�̗L�]�ȔR���v�Ƃ̐�`������ɍs�Ȃ��Ă���悤���B�Ⴆ�A�y�������G�l���M�[�������R�O�������c�l�d
�𐄏�����@�B�w��̋^���̃y�[�W�ɏڏq���Ă���悤�ɁA���{�@�B�w�2010�N5�����iVol.113�AN0.1098�j�Ɍf
�ڂ��ꂽ�uDME�g���b�N�̍ŐV�J���v�̘_���ɂ����āA���蒼��Ɛ����P�ꎁ�̗����́ADME���Ƃł���
���Ƃ��l������ƈӐ}���Ă̍s�ׂƌ����邪�ATank-to-Wheel�̎����f�[�^�������Ƃ��Ȃ���A���̎����f�[�^��
Tank-to-Wheel�̎����f�[�^�������ɓ����o���ꂽ���_�ł��鎖����S���L�ڂ��Ȃ��ŁuDME�̓f�B�[�[���G���W��
�̍������������R���ł���A�����̗L�]�ȔR���v�Ǝ咣����Ă���̂ł���B���̓��{�@��w��̘_���ł́A
DME�ƌy���Ƃَ̈�̔R���̗D��̋c�_�ɕK�{��Well-to-Wheel�̃��C�t�T�C�N���A�Z�X�����g�iLCA�j�ł̕]����
�S���s��Ȃ���DME�������̗L�]�ȔR���ƌ��_�Â����Ă��邽�߁A�v���I�Ȍ��ׂ��������_���ł���l���ĊԈ�
���͖������낤�B
�̗L�]�ȔR���v�Ƃ̐�`������ɍs�Ȃ��Ă���悤���B�Ⴆ�A�y�������G�l���M�[�������R�O�������c�l�d
�𐄏�����@�B�w��̋^���̃y�[�W�ɏڏq���Ă���悤�ɁA���{�@�B�w�2010�N5�����iVol.113�AN0.1098�j�Ɍf
�ڂ��ꂽ�uDME�g���b�N�̍ŐV�J���v�̘_���ɂ����āA���蒼��Ɛ����P�ꎁ�̗����́ADME���Ƃł���
���Ƃ��l������ƈӐ}���Ă̍s�ׂƌ����邪�ATank-to-Wheel�̎����f�[�^�������Ƃ��Ȃ���A���̎����f�[�^��
Tank-to-Wheel�̎����f�[�^�������ɓ����o���ꂽ���_�ł��鎖����S���L�ڂ��Ȃ��ŁuDME�̓f�B�[�[���G���W��
�̍������������R���ł���A�����̗L�]�ȔR���v�Ǝ咣����Ă���̂ł���B���̓��{�@��w��̘_���ł́A
DME�ƌy���Ƃَ̈�̔R���̗D��̋c�_�ɕK�{��Well-to-Wheel�̃��C�t�T�C�N���A�Z�X�����g�iLCA�j�ł̕]����
�S���s��Ȃ���DME�������̗L�]�ȔR���ƌ��_�Â����Ă��邽�߁A�v���I�Ȍ��ׂ��������_���ł���l���ĊԈ�
���͖������낤�B
�@���̓��蒼��Ɛ����P�ꎁ�̗�����Tank-to-Wheel�̏������ɂ�����uDME�̓f�B�[�[���G���W���̍�����
�������R���ł���A�����̗L�]�ȔR���v�Ƃ̎咣�́A�R���̗D��̋c�_�ɕK�{��Well-to-Wheel�̃��C�t�T�C�N
���A�Z�X�����g�iLCA�j�ł̐������]���ɏ��������ƁA�uDME�͌y���f�B�[�[��������R�O����Well-to-Wheel�̔M��
�������A�����I�ɂ������ԂɎg�p�ł��Ȃ����הR���v�Ƃ̋L�q�ɖ{�_����������ׂ��ł���B���̂悤�Ȃ��Ƃ́A
�֑��`��ʂ�z���A���U��`�ɋ߂��悤�Ɏv����̂ł���B���̂悤�Ȑ�`�ɓ��{�@�B�w��S�ʓI�ɋ��͂���
����悤�Ɍ�����́A���ɒQ���킵�����ƂƎv���Ă���B���݂ɁA���{�@�B�w��̃z�[���y�[�W�ł��u�c�l�d�i�W
���`���G�[�e���j�R�����y�̂��߂̒v�ihttp://www.jsme.or.jp/teigen/teigb01.htm�j���y�[�W��݂��A�y���f�B�[
�[��������R�O����Well-to-Wheel�̃G�l���M�[���������DME�X�Ɛ������Ă���̂ł���B���{�@�B�w�
�G�l���M�[�����̘Q��𐄏����Ă��邱�Ƃ́A�������B
�������R���ł���A�����̗L�]�ȔR���v�Ƃ̎咣�́A�R���̗D��̋c�_�ɕK�{��Well-to-Wheel�̃��C�t�T�C�N
���A�Z�X�����g�iLCA�j�ł̐������]���ɏ��������ƁA�uDME�͌y���f�B�[�[��������R�O����Well-to-Wheel�̔M��
�������A�����I�ɂ������ԂɎg�p�ł��Ȃ����הR���v�Ƃ̋L�q�ɖ{�_����������ׂ��ł���B���̂悤�Ȃ��Ƃ́A
�֑��`��ʂ�z���A���U��`�ɋ߂��悤�Ɏv����̂ł���B���̂悤�Ȑ�`�ɓ��{�@�B�w��S�ʓI�ɋ��͂���
����悤�Ɍ�����́A���ɒQ���킵�����ƂƎv���Ă���B���݂ɁA���{�@�B�w��̃z�[���y�[�W�ł��u�c�l�d�i�W
���`���G�[�e���j�R�����y�̂��߂̒v�ihttp://www.jsme.or.jp/teigen/teigb01.htm�j���y�[�W��݂��A�y���f�B�[
�[��������R�O����Well-to-Wheel�̃G�l���M�[���������DME�X�Ɛ������Ă���̂ł���B���{�@�B�w�
�G�l���M�[�����̘Q��𐄏����Ă��邱�Ƃ́A�������B
�@�Ƃ���ŁA���ɁA�f�B�[�[���G���W�����y���ɗ��Ȃ��M�����œV�R�K�X��p���ĉ^�]���邱�Ƃ��\�ł���Ȃ�
�A�V�R�K�X�ɑ��ʂ̃G�l���M�[�𓊓����č�������c�l�d��f�s�k���f�B�[�[���̔R���Ɏg�p���邱�Ƃ�CO2��
�傳���邾���łȂ��A�R���̘Q��ƔR���R�X�g�̏㏸���������ƂɂȂ�B���̂悤�ɁAC�n�Q�̔r�o�ƔR�����i�Ƃ̗���
����l�����ꍇ�ADME��GTL�͑�^�g���b�N�p�̒E�Ζ��̔R���ɓK���Ă��Ȃ����Ƃ͗e�Ղɗ����ł��邱�Ƃ��B����
���Ƃ́A�V�R�K�X���獇����DME��GTL�́A�g���b�N�p�R���ɕs�K�ɏڏq���Ă���̂ŁA�Q�Ɗ肢�����B
�A�V�R�K�X�ɑ��ʂ̃G�l���M�[�𓊓����č�������c�l�d��f�s�k���f�B�[�[���̔R���Ɏg�p���邱�Ƃ�CO2��
�傳���邾���łȂ��A�R���̘Q��ƔR���R�X�g�̏㏸���������ƂɂȂ�B���̂悤�ɁAC�n�Q�̔r�o�ƔR�����i�Ƃ̗���
����l�����ꍇ�ADME��GTL�͑�^�g���b�N�p�̒E�Ζ��̔R���ɓK���Ă��Ȃ����Ƃ͗e�Ղɗ����ł��邱�Ƃ��B����
���Ƃ́A�V�R�K�X���獇����DME��GTL�́A�g���b�N�p�R���ɕs�K�ɏڏq���Ă���̂ŁA�Q�Ɗ肢�����B
�@DME��GTL�ɂ��ẮA�����A�̌@���\�ȐΖ��ƓV�R�K�X���͊����A�����̔R���������ԗp�ɏ\���ɋ�����
��Ȃ��Ȃ������_�ŁC�ΒY���K�X�����č�������R���Ƃ��ăf�B�[�[���G���W���Ɏg�p����`�Ԃ��ł��]�܂����ƍl
������B
��Ȃ��Ȃ������_�ŁC�ΒY���K�X�����č�������R���Ƃ��ăf�B�[�[���G���W���Ɏg�p����`�Ԃ��ł��]�܂����ƍl
������B
�R�D�b�m�f��R���Ƃ���G���W���i�V�R�K�X�G���W���j
3-1�D�V�R�K�X�G���W���̎��
�@�V�R�K�X�̓Z�^�������ɂ߂ĒႢ���Ƃ���C��C�ƓV�R�K�X�̍����C��R�Ă�����ɂ́C�O������̓_���K�v
�ƂȂ�D��̓X�p�[�N�v���O�̉Ήԕ��d�ɂ��V�R�K�X�݂̂�R�Ă�����X�p�[�N�v���O�����V�R�K�X��ăG��
�W��������C���͔R�Ď����Ƀp�C���b�g���˂����y���̎��Ȓ��̉Ή��ɂ��V�R�K�X��R�Ă�����y�����Ό^
�̃f�B�[�[���f���A���t���G���i�c�c�e�j�G���W��������D�i�}�R�Q�Ɓj �X�p�[�N�v���O�����V�R�K�X��ăG���W��(�X�p
�[�N�v���O��CNG�G���W���j�́A�s�̂̂b�m�f��p�ԁA���^�b�m�f�g���b�N�A���^�b�m�f�g���b�N����тb�m�f�o�X�̃G��
�W���Ƃ��č̗p����Ă���B
�ƂȂ�D��̓X�p�[�N�v���O�̉Ήԕ��d�ɂ��V�R�K�X�݂̂�R�Ă�����X�p�[�N�v���O�����V�R�K�X��ăG��
�W��������C���͔R�Ď����Ƀp�C���b�g���˂����y���̎��Ȓ��̉Ή��ɂ��V�R�K�X��R�Ă�����y�����Ό^
�̃f�B�[�[���f���A���t���G���i�c�c�e�j�G���W��������D�i�}�R�Q�Ɓj �X�p�[�N�v���O�����V�R�K�X��ăG���W��(�X�p
�[�N�v���O��CNG�G���W���j�́A�s�̂̂b�m�f��p�ԁA���^�b�m�f�g���b�N�A���^�b�m�f�g���b�N����тb�m�f�o�X�̃G��
�W���Ƃ��č̗p����Ă���B
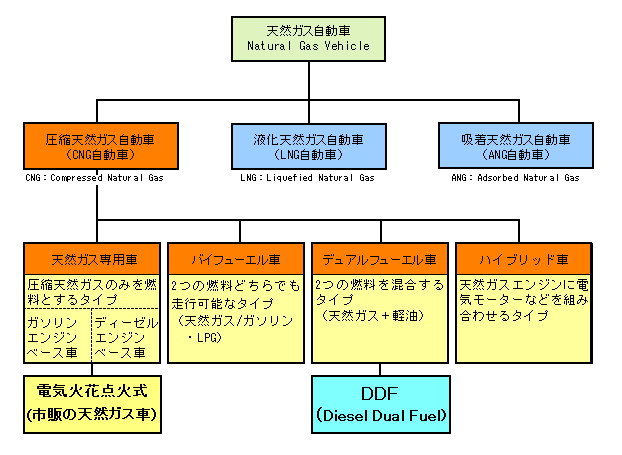
3-2�D�]���̃X�p�[�N�v���O���V�R�K�X�G���W�����̔M������CO2�r�o���\
�@�@�@�@�@�iDDF�G���W���Ƃ̑���_�j
�@���y��ʏȂł͕����P�S�`�P�U�N�x�̂R��N�v��ŎY�w���̘A�g�̂��ƂɁu���������Q��^�����Ԃ̌����J
���v�ihttp://www.ntsel.go.jp/jutaku/15files/06.pdf#search='���������Q'�j�����{���ꂽ�B�����ł͐}�S�Ɏ����v��
�W�F�N�g���{�̐����̂��ƂɁA��^�̓V�R�K�X�g���b�N�ADME�g���b�N�A�n�C�u���b�h�o�X�A�X�[�p�[�N���[���f�B�[�[��
�G���W���A�R���d�r�o�X�̊J���������s��ꂽ�B
���v�ihttp://www.ntsel.go.jp/jutaku/15files/06.pdf#search='���������Q'�j�����{���ꂽ�B�����ł͐}�S�Ɏ����v��
�W�F�N�g���{�̐����̂��ƂɁA��^�̓V�R�K�X�g���b�N�ADME�g���b�N�A�n�C�u���b�h�o�X�A�X�[�p�[�N���[���f�B�[�[��
�G���W���A�R���d�r�o�X�̊J���������s��ꂽ�B
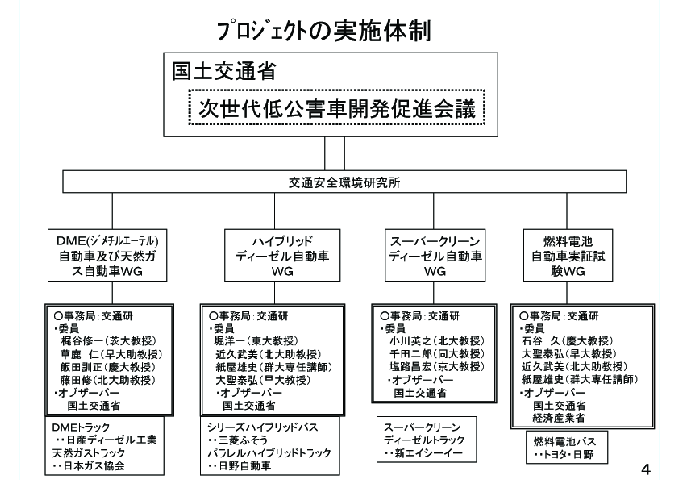
�@���̒��̓V�R�K�X�����Ԃ̃v���W�F�N�g�ł́A�X�p�[�N�v���O���V�R�K�X�G���W���𓋍ڂ���GVW�Q�T�g���N���X��
��^CNG�g���b�N�̊J���������s���A�������ʂ�����Ă���B���ʕ̏ڍׂ�http://www.ntsel.go.jp/
jutaku/15files/06.pdf#search='���������Q'�́u���������Q��^�����Ԃ̌����J���v'���Q�Ɗ肢�����B
��^CNG�g���b�N�̊J���������s���A�������ʂ�����Ă���B���ʕ̏ڍׂ�http://www.ntsel.go.jp/
jutaku/15files/06.pdf#search='���������Q'�́u���������Q��^�����Ԃ̌����J���v'���Q�Ɗ肢�����B
�@���̕��ɂ��ƁA�i�d�O�T���[�h�����ł́AGVW�Q�T�g���N���X��^CNG�g���b�N�p�̃X�p�[�N�v���O���V�R�K�X
�G���W����CO2�r�o�ʂ́A�u����r�C�ʃG���W���Ńf�B�[�[���G���W���̃g�b�v�N���X�ɕ��Ԓ�CO2�r�o�ʂƂ��邱��
���ł����B�v�ƋL�ڂ���Ă���B�@�܂�A�i�d�O�T���[�h�����ł͑�^CNG�g���b�N�p�̃X�p�[�N�v���O���V�R�K�X�G��
�W����CO2�r�o�ʂ́A����r�C�ʂ̃f�B�[�[���G���W����CO2�r�o�ʂƓ����ł���ƕ���Ă���B
�G���W����CO2�r�o�ʂ́A�u����r�C�ʃG���W���Ńf�B�[�[���G���W���̃g�b�v�N���X�ɕ��Ԓ�CO2�r�o�ʂƂ��邱��
���ł����B�v�ƋL�ڂ���Ă���B�@�܂�A�i�d�O�T���[�h�����ł͑�^CNG�g���b�N�p�̃X�p�[�N�v���O���V�R�K�X�G��
�W����CO2�r�o�ʂ́A����r�C�ʂ̃f�B�[�[���G���W����CO2�r�o�ʂƓ����ł���ƕ���Ă���B
�@����A�V�R�K�X�ƌy���̒P�ʔ��M�ʓ������CO2�����ʂ́A�V�R�K�X���T�P��/MJ�A�y�����U�V��/MJ�ł���A�V�R
�K�X��CO2�r�o�ʂ͌y�������啝�ɏ��Ȃ��B����ɂ�������炸�A�i�d�O�T���[�h�����ł͂��̃v���W�F�N�g�ŊJ��
���ꂽGVW�Q�T�g���N���X��^CNG�g���b�N�p�̃X�p�[�N�v���O���V�R�K�X�G���W����CO2�r�o�ʂ́A����r�C�ʂ�
�f�B�[�[���G���W����CO2�r�o�ʂƓ����ł������Ƃ̂��Ƃ��B���̂��Ƃ́A�V�R�K�X�ƌy���̂��ꂼ��̒P�ʔ��M��
�������CO2�����ʂ���ɂ��Čv�Z����ƁA���̃v���W�F�N�g�ŊJ�����ꂽGVW�Q�T�g���N���X��^CNG�g���b�N�p��
�X�p�[�N�v���O���V�R�K�X�G���W���̔M�������A����r�C�ʂ̑�^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W���̔M���������A
�v�Z��A�R�P��������Ă��邱�ƂɂȂ�B�z�C�i��ق�������ሳ�k��̃X�p�[�N�v���O���V�R�K�X�G���W�����z�C
�i��ق̖��������k��̃f�B�[�[���G���W���ɔ�ׂĂi�d�O�T���[�h�����̔M�������啝�ɗ���Ă��邱�Ƃ́A�G��
�W���T�C�N�����_����l���ē��R�̂��Ƃł���B ����ɂ��ẮA�ʂ̃y�[�W�V�R�K�X��đ�^�g���b�N�́A�d�ʎ�
�R���ɕs�K���̌��׃g���b�N���I�ɂ��ڏq���Ă���̂ŁA�䗗�������������B
�K�X��CO2�r�o�ʂ͌y�������啝�ɏ��Ȃ��B����ɂ�������炸�A�i�d�O�T���[�h�����ł͂��̃v���W�F�N�g�ŊJ��
���ꂽGVW�Q�T�g���N���X��^CNG�g���b�N�p�̃X�p�[�N�v���O���V�R�K�X�G���W����CO2�r�o�ʂ́A����r�C�ʂ�
�f�B�[�[���G���W����CO2�r�o�ʂƓ����ł������Ƃ̂��Ƃ��B���̂��Ƃ́A�V�R�K�X�ƌy���̂��ꂼ��̒P�ʔ��M��
�������CO2�����ʂ���ɂ��Čv�Z����ƁA���̃v���W�F�N�g�ŊJ�����ꂽGVW�Q�T�g���N���X��^CNG�g���b�N�p��
�X�p�[�N�v���O���V�R�K�X�G���W���̔M�������A����r�C�ʂ̑�^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W���̔M���������A
�v�Z��A�R�P��������Ă��邱�ƂɂȂ�B�z�C�i��ق�������ሳ�k��̃X�p�[�N�v���O���V�R�K�X�G���W�����z�C
�i��ق̖��������k��̃f�B�[�[���G���W���ɔ�ׂĂi�d�O�T���[�h�����̔M�������啝�ɗ���Ă��邱�Ƃ́A�G��
�W���T�C�N�����_����l���ē��R�̂��Ƃł���B ����ɂ��ẮA�ʂ̃y�[�W�V�R�K�X��đ�^�g���b�N�́A�d�ʎ�
�R���ɕs�K���̌��׃g���b�N���I�ɂ��ڏq���Ă���̂ŁA�䗗�������������B
�@���̕��Ŋm�F���ꂽ�d�v�Ȃ��Ƃ́A�X�p�[�N�v���O���V�R�K�X�G���W���̑�^CNG�g���b�N�͏]���̑�^�f�B
�[�[���g���b�N�����R�P���������̔R���G�l���M�[��Q��邱�Ƃ����m�ɂ��ꂽ���Ƃł���B�M�����̈����X�p�[
�N�v���O���V�R�K�X�G���W���𓋍ڂ�����^CNG�g���b�N�́A��ɉ^�s�R�X�g�̗}���̂��߂ɔR������ʂ̍팸��
���߂��Ă���s�s�ԉݕ��A���ɂ͑S���g�p�ł��Ȃ����Ƃ͖��炩�ł���B���������āA�����A�E�Ζ��̕K�v����
�����Ƃ��Ă��A�X�p�[�N�v���O���V�R�K�X�G���W���̑�^CNG�g���b�N�����p�ɋ������\���͊F���ƍl���ėǂ�
���낤�B����������A�X�p�[�N�v���O���V�R�K�X�G���W���̑�^CNG�g���b�N�́A�ȃG�l���M�[���������߂���
���錻�݂ł́A���݂��鉿�l�̖�����^�g���b�N�ƍl������B���̕����P�S�`�P�U�N�x�Ɏ��{���ꂽ���y��ʏȂ�
��^CNG�g���b�N�J���v���W�F�N�g�ɂ��ẮA�u���r�C�ʂP�R���b�g���N���X�̃X�p�[�N�v���O���V�R�K�G���W����
�ڂ����ԗ����d�ʂQ�T�g�����̑�^CNG�g���b�N�́A�J�����Ă����p�����S���������Ƃ����������Ɓv���ő�̐���
�ƌ����Ă��ߌ��ł͖������낤�B
�[�[���g���b�N�����R�P���������̔R���G�l���M�[��Q��邱�Ƃ����m�ɂ��ꂽ���Ƃł���B�M�����̈����X�p�[
�N�v���O���V�R�K�X�G���W���𓋍ڂ�����^CNG�g���b�N�́A��ɉ^�s�R�X�g�̗}���̂��߂ɔR������ʂ̍팸��
���߂��Ă���s�s�ԉݕ��A���ɂ͑S���g�p�ł��Ȃ����Ƃ͖��炩�ł���B���������āA�����A�E�Ζ��̕K�v����
�����Ƃ��Ă��A�X�p�[�N�v���O���V�R�K�X�G���W���̑�^CNG�g���b�N�����p�ɋ������\���͊F���ƍl���ėǂ�
���낤�B����������A�X�p�[�N�v���O���V�R�K�X�G���W���̑�^CNG�g���b�N�́A�ȃG�l���M�[���������߂���
���錻�݂ł́A���݂��鉿�l�̖�����^�g���b�N�ƍl������B���̕����P�S�`�P�U�N�x�Ɏ��{���ꂽ���y��ʏȂ�
��^CNG�g���b�N�J���v���W�F�N�g�ɂ��ẮA�u���r�C�ʂP�R���b�g���N���X�̃X�p�[�N�v���O���V�R�K�G���W����
�ڂ����ԗ����d�ʂQ�T�g�����̑�^CNG�g���b�N�́A�J�����Ă����p�����S���������Ƃ����������Ɓv���ő�̐���
�ƌ����Ă��ߌ��ł͖������낤�B
3-3�D�y�����Ό^�̓V�R�K�X�G���W���ł���f�B�[�[���f���A���t���G���i�c�c�e�j�G���W��
�@���Ă̓V�R�K�X���e�Ղɓ���ł���n��ł́A�����ȓV�R�K�X�p���Čo�ϓI�Ƀg���b�N���^�s�����邽�߁A
�y�����Ό^�̓V�R�K�X�G���W���ł���c�c�e�G���W���𓋍ڂ����g���b�N����ʂɎg���Ă���Ⴊ���邪�A�䂪��
�ł͂c�c�e�G���W���𓋍ڂ����g���b�N���s�̂��ꂽ��͌�������Ȃ��B�M�҂��ȑO�ɋΖ����Ă������{�G�R�X����
�J�i�_��Alternative Fuel Systems Inc.�Ƌ����ł����U�t�H���[�h�i�ύڗʂS�g���N���X�j�̃f�B�[�[���G���W�����x�[
�X��zu �z�C�|�[�g���ˎ��c�c�e�G���W�����J�����A���̋z�C�|�[�g���ˎ��c�c�e�G���W���𓋍ڂ��������U�t�H���[�h
�̂c�c�e�g���b�N���������s�����{�����Ⴊ����B�z�C�|�[�g���ˎ��c�c�e�G���W���͐}�T�̖͎��}�Ɏ������悤�Ɋe
�V�����_�̋z�C�ق̊J�ْ��ɋz�C�|�[�g����V�����_�Ɍ������ēV�R�K�X�˂�������̃G���W���ł���B
�y�����Ό^�̓V�R�K�X�G���W���ł���c�c�e�G���W���𓋍ڂ����g���b�N����ʂɎg���Ă���Ⴊ���邪�A�䂪��
�ł͂c�c�e�G���W���𓋍ڂ����g���b�N���s�̂��ꂽ��͌�������Ȃ��B�M�҂��ȑO�ɋΖ����Ă������{�G�R�X����
�J�i�_��Alternative Fuel Systems Inc.�Ƌ����ł����U�t�H���[�h�i�ύڗʂS�g���N���X�j�̃f�B�[�[���G���W�����x�[
�X��zu �z�C�|�[�g���ˎ��c�c�e�G���W�����J�����A���̋z�C�|�[�g���ˎ��c�c�e�G���W���𓋍ڂ��������U�t�H���[�h
�̂c�c�e�g���b�N���������s�����{�����Ⴊ����B�z�C�|�[�g���ˎ��c�c�e�G���W���͐}�T�̖͎��}�Ɏ������悤�Ɋe
�V�����_�̋z�C�ق̊J�ْ��ɋz�C�|�[�g����V�����_�Ɍ������ēV�R�K�X�˂�������̃G���W���ł���B
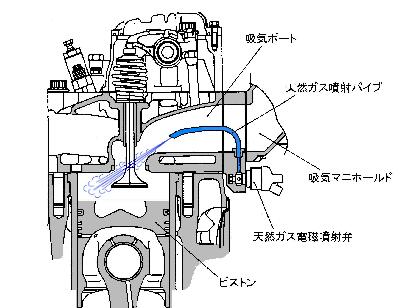
�@���̂����U�t�H���[�h�ɓ��ڂ����z�C�|�[�g���ˎ��c�c�e�G���W���̏ڍׂ́A���i���ҁF�Γc���j�@���C323 ��
�^�g���b�N�pECOS-DDF�V�R�K�X�G���W���̊J���C�w�p�u����O���WNo.71-00�C�Вc�@�l�@���{�����ԋZ�p��)��
�܂Ƃ߂Ă���B
�^�g���b�N�pECOS-DDF�V�R�K�X�G���W���̊J���C�w�p�u����O���WNo.71-00�C�Вc�@�l�@���{�����ԋZ�p��)��
�܂Ƃ߂Ă���B
�@�����ł́A���̕��ɂ��ƂÂ��Ăc�c�e�G���W���̍\����\�̗v�_���܂Ƃ߂��̂ŁA�c�c�e�G���W���̗D�ꂽ��
���𗝉�����ꏕ�ɂ��Ăɂ���������Ǝv���Ă���B
���𗝉�����ꏕ�ɂ��Ăɂ���������Ǝv���Ă���B
3-4�DDDF�G���W���̍쓮�ƔR��
�@DDF�G���W���ł́C�e�V�����_�̋z�C�|�[�g�ɐ݂����K�X�C���W�F�N�^����z�C�ق̊J�ي��Ԓ��Ɏ�R���̓V�R
�K�X���V�����_���Ɍ������ĕ��˂�����@���̗p����Ă���D���̗��R�́C�V�����_���ɓV�R�K�X�̉ߔZ�̈�Ƌ�
�C�̑����̈�ɕ������s�ψ�ȍ����C���`�������C�f�B�[�[���̍������k���ς����ɑS�����ɑ��ʂ̓V�R
�K�X�����������ꍇ�ł��m�b�L���O�������Ȃ��悤�ɂ��邽�߂��BDDF�G���W���ł́C�R�Ď����Ƀp�C���b�g����
�����y���̗\�����C���ŏ��Ɏ��Ȓ����ĉΉ����`������C���̉Ή����V�R�K�X�̊\�����C��R�Ă�����
�v���Z�X�ʼn^�]���s����BDDF�G���W���̔R�ẮC�}�U�̔M�������̖͎��}�Ɏ������悤�ɁC�f�B�[�[���R�Ă�
����y���̊g�U�R�Ă��傫���팸����C����ɓV�R�K�X�̗\�����R�Ă��t�����ꂽ���̂ƍl������B
�K�X���V�����_���Ɍ������ĕ��˂�����@���̗p����Ă���D���̗��R�́C�V�����_���ɓV�R�K�X�̉ߔZ�̈�Ƌ�
�C�̑����̈�ɕ������s�ψ�ȍ����C���`�������C�f�B�[�[���̍������k���ς����ɑS�����ɑ��ʂ̓V�R
�K�X�����������ꍇ�ł��m�b�L���O�������Ȃ��悤�ɂ��邽�߂��BDDF�G���W���ł́C�R�Ď����Ƀp�C���b�g����
�����y���̗\�����C���ŏ��Ɏ��Ȓ����ĉΉ����`������C���̉Ή����V�R�K�X�̊\�����C��R�Ă�����
�v���Z�X�ʼn^�]���s����BDDF�G���W���̔R�ẮC�}�U�̔M�������̖͎��}�Ɏ������悤�ɁC�f�B�[�[���R�Ă�
����y���̊g�U�R�Ă��傫���팸����C����ɓV�R�K�X�̗\�����R�Ă��t�����ꂽ���̂ƍl������B
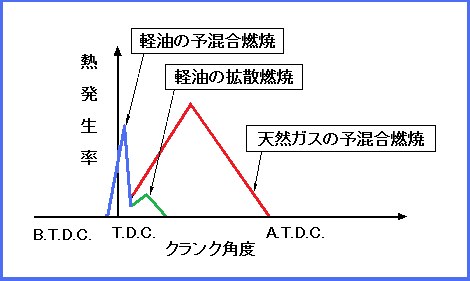
3-5�D���삵��DDF�G���W���̊T�v
�@�����U6�g�g1-�b�f�B�[�[���G���W�����c�c�e�G���W���ɉ����������^�g���b�N�̃G���W���̏�����\�P�A�V�X�e����}
�V�Ɏ������B
�V�Ɏ������B
| |
|
|
�G���W���^��
|
|
|
�G���W���`��
|
|
|
�ߋ��̗L��
|
|
|
�r�C�ʁ@�@(cm3)
|
|
|
�V�����_���\�z��
|
|
|
�{�A�~�X�g���[�N �@ (mm)
|
|
|
���k��
|
|
|
�_����
|
|
|
�R�������V�X�e��
|
|
|
�dGR���u
|
|
|
�R��
|
|
|
�ō��o�́@�@�@(kW/rpm)
|
|
|
�ő�g���N�@�@(Nm/rpm)
|
|
|
�G�}���u
|
|
|
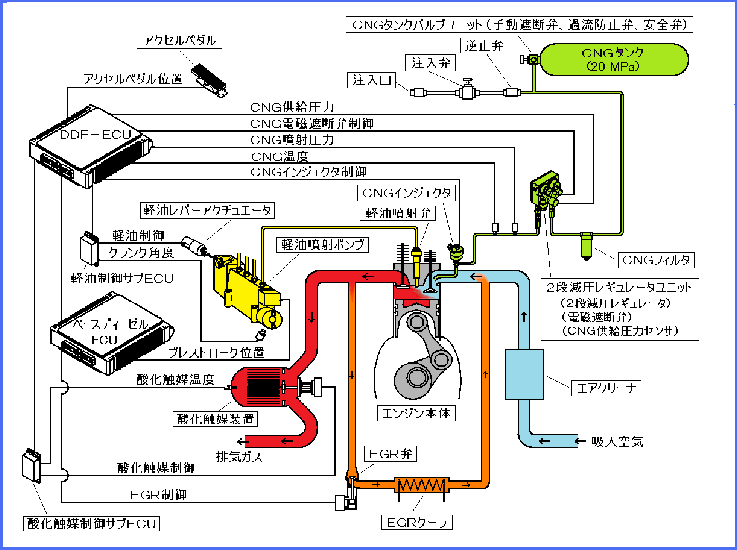
�@�x�[�X��6�g�g1-�b�f�B�[�[���̓d�q���䃆�j�b�g�i�d�b�t�j�ɂc�c�e�G���W���̂d�b�t���V���ɒlj�����C�_���G�}��
�u����тd�f�q�N�[�����lj����ꂽ�D����ɂ��G���W����]���y�уA�N�Z���y�_���ʒu�M���ɂ��������Čy������
�ѓV�R�K�X�̕��˗ʂ����䂳��C�G���W���o�͂���єr�o�K�X�̍œK�����}���Ă���D���̂c�c�e�G���W���́A��
���U�t�H���[�h�i�ύڗʂS�g���N���X�j�ɓ��ڂ���C(��)���{�����Ԍ������Ɉϑ�����C�V���V�[�_�C�i���ݔ��ɂ��G
���W�����\����єr�o�K�X�̎��������{���ꂽ�B
�u����тd�f�q�N�[�����lj����ꂽ�D����ɂ��G���W����]���y�уA�N�Z���y�_���ʒu�M���ɂ��������Čy������
�ѓV�R�K�X�̕��˗ʂ����䂳��C�G���W���o�͂���єr�o�K�X�̍œK�����}���Ă���D���̂c�c�e�G���W���́A��
���U�t�H���[�h�i�ύڗʂS�g���N���X�j�ɓ��ڂ���C(��)���{�����Ԍ������Ɉϑ�����C�V���V�[�_�C�i���ݔ��ɂ��G
���W�����\����єr�o�K�X�̎��������{���ꂽ�B
3-6.�@�c�c�e�G���W���̔r�o�K�X���\
�@�c�c�e�G���W���̔r�o�K�X�������ʂ�}�W����ѐ}�X�Ɏ������B�x�[�X�̕����U�N�K���K���f�B�[�[���ɑ��m�n��
�̖�40���C��_���Y�f�i�b�n�j�̖�90���C�Y�����f�i�s�g�b�j�̖�35���C�o�l�̖�70���̍팸������ꂽ�D����́C�J
�����������̕����V�N�̒���Q�ԓ��r�o�K�X�Z�p�w�j�i�����j�̏d�ʎԒ�r�o�K�X���x�����������̂ł�
��B�c�c�e�G���W���̌y�����ɂ́C�ꕔ�̃V�����_�ɓV�R�K�X�̋����𒆎~����X�L�b�v�t�@�C�A�̐�����s���C
�V�R�K�X�̉ߏ�Ȋ���h�~���Ė��R�V�R�K�X�̔r�o�팸���}���Ă���B
�̖�40���C��_���Y�f�i�b�n�j�̖�90���C�Y�����f�i�s�g�b�j�̖�35���C�o�l�̖�70���̍팸������ꂽ�D����́C�J
�����������̕����V�N�̒���Q�ԓ��r�o�K�X�Z�p�w�j�i�����j�̏d�ʎԒ�r�o�K�X���x�����������̂ł�
��B�c�c�e�G���W���̌y�����ɂ́C�ꕔ�̃V�����_�ɓV�R�K�X�̋����𒆎~����X�L�b�v�t�@�C�A�̐�����s���C
�V�R�K�X�̉ߏ�Ȋ���h�~���Ė��R�V�R�K�X�̔r�o�팸���}���Ă���B
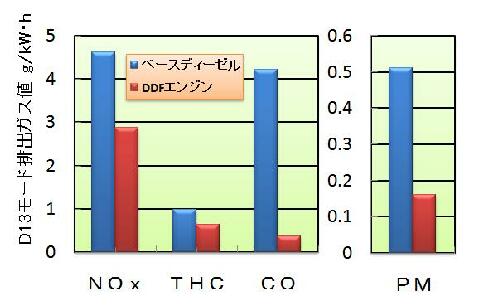
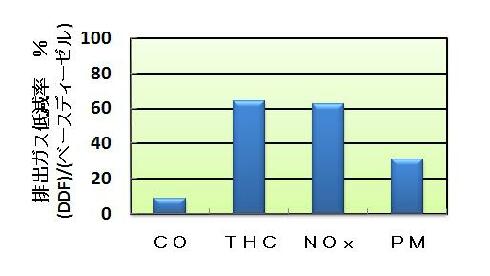
�@�}�P�O�͂c�c�e�G���W���̂c13���[�h�r�o�K�X�������ɏ�����y���ƓV�R�K�X�̕��ϗ��ʂł���D�o�l���r�o��
��Ȃ��V�R�K�X���R���S�̂�60���߂����߂邽�߁C�x�[�X�̃f�B�[�[���ɑ��Ăo�l�̖�70�����팸�ł�������
�ƍl������D
��Ȃ��V�R�K�X���R���S�̂�60���߂����߂邽�߁C�x�[�X�̃f�B�[�[���ɑ��Ăo�l�̖�70�����팸�ł�������
�ƍl������D
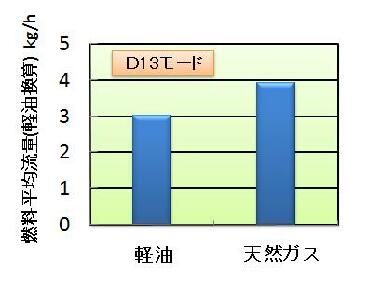
�@�܂��C�c�c�e�G���W���̑S�����̂R���[�h��������і����}���������͉������i�����x���j�ł��邱�Ƃ��m�F
�����D
�����D
3-7.�@�c�c�e�G���W���̏o�͐��\
�@�}�P�P�Ɏ������悤�ɁC�c�c�e�G���W���̑S�����̏o�́C�g���N����єR������̓x�[�X�̃f�B�[�[���Ƃقړ�
���̐��\��������.
���̐��\��������.
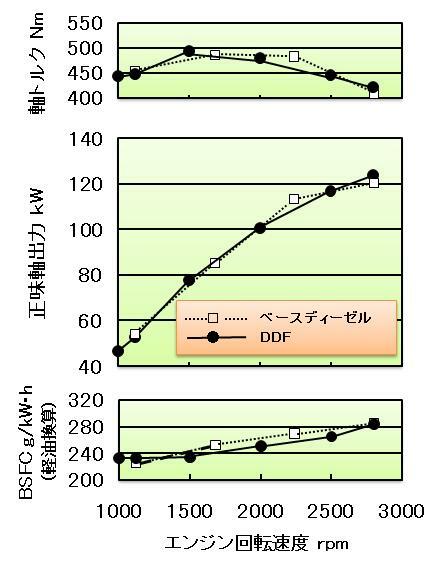
�@�܂��C�c�c�e�G���W���̑S���^�]���̓V�R�K�X�䗦�͐}�P�Q�Ɏ������ʂ�C80���O��ł���D
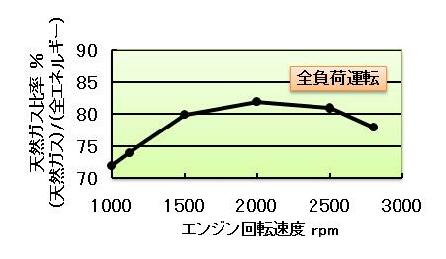
�@�����āA�}�P�R�̓f�B�[�[���G���W������Ƃ����ꍇ��DDF�G���W���iD13���[�h�̔R��j����уX�p�[�N�v���O
���V�R�K�X�G���W���i�����s�̔R��j�̔R��̔�r�������B���̌��ʁA�c�c�e�G���W���̂c13���[�h�R�����
�̓x�[�X�f�B�[�[���ɑ���8���̑����ɉ߂��Ȃ��D���݂ɁC�^�A����Q�ԕ��y�@�\�̎����s�����̒����ł̓X
�p�[�N�v���O�����V�R�K�X��ăG���W���̈�苗�����s���̔R������ʂ̓f�B�[�[���ɑ�35����������������
���i�o�T�F����Q���֔R�������Ԃ̕��y����i�̂��߂̒����������C�i���j�����Z�p�Z���^�[�^�A���
�Q�ԕ��y�@�\�Cp.6-11�@����11�N3���j����Ă���D�܂��A��q�̂S���Ɏ��������ł́A�X�p�[�N�v���O��CNG
�G���W���G���W���̔M�����́A�f�B�[�[���G���W�����R�O����������Ă��邱�Ƃ����炩�ł���B���������āC�f�B�[
�[���Ɓ@�����̍����M������L����c�c�e�G���W���́A��ɔR���������߂��Ă����^�g���b�N�ɍ̗p�\�ȁA
�D�ꂽ�V�R�K�X�G���W���ł���Ƃ��͖��炩�ł���D
���V�R�K�X�G���W���i�����s�̔R��j�̔R��̔�r�������B���̌��ʁA�c�c�e�G���W���̂c13���[�h�R�����
�̓x�[�X�f�B�[�[���ɑ���8���̑����ɉ߂��Ȃ��D���݂ɁC�^�A����Q�ԕ��y�@�\�̎����s�����̒����ł̓X
�p�[�N�v���O�����V�R�K�X��ăG���W���̈�苗�����s���̔R������ʂ̓f�B�[�[���ɑ�35����������������
���i�o�T�F����Q���֔R�������Ԃ̕��y����i�̂��߂̒����������C�i���j�����Z�p�Z���^�[�^�A���
�Q�ԕ��y�@�\�Cp.6-11�@����11�N3���j����Ă���D�܂��A��q�̂S���Ɏ��������ł́A�X�p�[�N�v���O��CNG
�G���W���G���W���̔M�����́A�f�B�[�[���G���W�����R�O����������Ă��邱�Ƃ����炩�ł���B���������āC�f�B�[
�[���Ɓ@�����̍����M������L����c�c�e�G���W���́A��ɔR���������߂��Ă����^�g���b�N�ɍ̗p�\�ȁA
�D�ꂽ�V�R�K�X�G���W���ł���Ƃ��͖��炩�ł���D
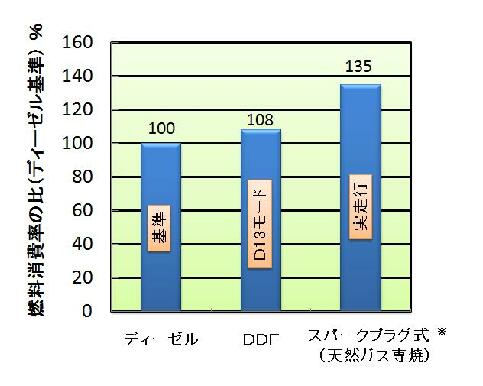
3-8.�@�c�c�e�G���W���̂b�n�Q�r�o���\
�@�}1�S��D13���[�h�����ɂ�����f�B�[�[���G���W����DDF�G���W����CO2�r�o�l�������B
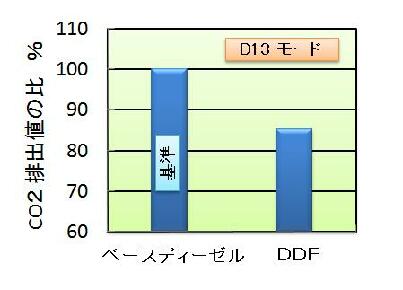
�@�}�P�S�Ɏ������悤�ɂc�c�e�G���W���̂b�n�Q�́C�c13���[�h�Ńf�B�[�[���G���W������15�������Ȃ����Ƃ��m�F��
���D�c13���[�h���̏���R����60���߂����Y�f�����̏��Ȃ��V�R�K�X�ł���C���̔M�������f�B�[�[���G���W����
�قړ����ł��������߂ƍl������B
���D�c13���[�h���̏���R����60���߂����Y�f�����̏��Ȃ��V�R�K�X�ł���C���̔M�������f�B�[�[���G���W����
�قړ����ł��������߂ƍl������B
�Ƃ���ŁA�y���̔R�Ď��ɂ́u���K�����v���^���Ă���i�m���q�i50nm�N���X�̔��ׂȗ��q�j��APM2.5(.5�ʂ�[�~
�N����]�ȉ��̔����q�j����ɔr�o����錇�_������B����ɑ��A�V�R�K�X�̔R�Ăł̓i�m���q��PM2.5���r�o��
��Ȃ����Ƃ��傫�ȓ����ł���B����ADDF�G���W���ɂ����ẮA13���[�h���̏���R����60���߂����V�R�K�X�ł�
��B���̂��Ƃ���A�c�c�e�G���W���̉^�]���ɂ́A�G���W������r�o�����u���K�����v���^���Ă���i�m���q��A
PM2.5���f�B�[�[���G���W���ɔ�ׂĔ������邱�Ƃ��\�ƂȂ�̂ł���B
�N����]�ȉ��̔����q�j����ɔr�o����錇�_������B����ɑ��A�V�R�K�X�̔R�Ăł̓i�m���q��PM2.5���r�o��
��Ȃ����Ƃ��傫�ȓ����ł���B����ADDF�G���W���ɂ����ẮA13���[�h���̏���R����60���߂����V�R�K�X�ł�
��B���̂��Ƃ���A�c�c�e�G���W���̉^�]���ɂ́A�G���W������r�o�����u���K�����v���^���Ă���i�m���q��A
PM2.5���f�B�[�[���G���W���ɔ�ׂĔ������邱�Ƃ��\�ƂȂ�̂ł���B
�@����C�����s�ɋ߂��������[�h�^�]�ɂ����āA�f�B�[�[���G���W���ɔ�r���ĂR�O�������M���������X�p�[�N�v
���O�����V�R�K�X��ăG���W���̂b�n�Q�r�o�ʂ́A�f�B�[�[���G���W���Ƃقړ����ł��邱�Ƃ́A�����P�S�`�P�U�N�x
�ɍ��y��ʏȂ����{�����u���������Q��^�����Ԃ̌����J���v�ihttp://www.ntsel.go.jp/jutaku/15files/06.pdf#
search='���������Q'�j�v���W�F�N�g��A���H���G���̕��u�����ԗp�G���W���̔M��������"�����ԋZ�p�CVol.
53�CNo.9 (1999)�v�Ŗ��炩�ɂ���Ă���B���̂��߁A�f�B�[�[���G���W�����b�n�Q��15�����Ȃ��c�c�e�G���W���́C��
���_�ł͂b�n�Q�̔r�o���ł����Ȃ����R�@�ւł���ƍl������B
���O�����V�R�K�X��ăG���W���̂b�n�Q�r�o�ʂ́A�f�B�[�[���G���W���Ƃقړ����ł��邱�Ƃ́A�����P�S�`�P�U�N�x
�ɍ��y��ʏȂ����{�����u���������Q��^�����Ԃ̌����J���v�ihttp://www.ntsel.go.jp/jutaku/15files/06.pdf#
search='���������Q'�j�v���W�F�N�g��A���H���G���̕��u�����ԗp�G���W���̔M��������"�����ԋZ�p�CVol.
53�CNo.9 (1999)�v�Ŗ��炩�ɂ���Ă���B���̂��߁A�f�B�[�[���G���W�����b�n�Q��15�����Ȃ��c�c�e�G���W���́C��
���_�ł͂b�n�Q�̔r�o���ł����Ȃ����R�@�ւł���ƍl������B
�T�DDDF�G���W���̓���
�@�y�����Ό^�̓V�R�K�X�G���W���ł���c�c�e�G���W���̓������܂Ƃ߂�ƁA�ȉ��̕\�Q�̒ʂ�ł���B
| |
|
| |
�c�c�e�G���W���͉ߋ������\�ł���A�]���̃f�B�[�[���Ɠ����̏o�͂��\�ł�
�� |
| |
�X�p�[�N�v���O��CNG�g�G���W���̔M�����̓f�B�[�[������R�O������邪�ADDF
�G���W���̔M�����́A�f�B�[�[���Ƃقړ����ł���B |
| |
�c�c�e�G���W����PM�̔r�o�́A�f�B�[�[���̖�P�^�R�ł���B�iD13 ���[�h |
| |
�c�c�e�G���W���̓V�R�K�X�̏���ʔ䗦��D13 ���[�h�Ŗ�U�O���ł���B |
| |
�c�c�e�G���W����CO�Q�̔r�o�̓f�B�[�[�����15���iD13 ���[�h�j���Ȃ��A�b�n�Q�̔r
�o���ł����Ȃ����R�@�ւł���B |
| |
DDF�G���W�����ڂ̃g���b�N�́A�c�c�e�^�]�ƃf�B�[�[���^�]�Ƃ��݂��ɐ�ւ���
�\�ȃf���A���^�]���[�h�ő��s���邱�Ƃ��\�ł���B |
| |
��^�g���b�N�ɓV�R�K�X�p����DDF�G���W���𓋍ڂ��邱�Ƃ́A�Z�p�I�ȏ�Q
�����Ȃ��A�E�Ζ��̑����������\�ł���B |
| |
�����R����60�����x���V�R�K�X�ł��邽�߁A�f�B�[�[���G���W���ɔ�ׂĂ�
�i�m���q�i50nm�N���X�̔��ׂȗ��q�j�̔r�o��APM2.5(2.5�ʂ�[�~�N����]�ȉ��̔� ���q�j�̔r�o�����邱�Ƃ��\�ł���B |
�@�X�p�[�N�v���O���V�R�K�X�G���W���̑�^CNG�g���b�N�́A�]���̑�^�f�B�[�[���g���b�N�ɔ�r�����ꍇ�A�f�B�[
�[���Ɠ����̂b�n�Q��r�o���A�f�B�[�[�������R���G�l���M�[���R�P���������Q���v���I�Ȍ��ׂ�����B�����
���A�R�Ď����Ƀp�C���b�g���˂����y���̎��Ȓ��̉Ή��ɂ��V�R�K�X��R�Ă�����y�����Ό^�̂c�c�e�G��
�W���́A�]���̑�^�f�B�[�[���g���b�N�ɔ�r�����ꍇ�A�f�B�[�[���Ɠ����̔M�����ł��邱�Ƃɉ����A�f�B�[�[����
��b�n�Q��15�����Ȃ��ł��钷��������B�ȏ�̓��e�ɂ��ẮA��N�i2008�N�j��11��14���ɇ��G�k�E�e�B�[�E�G�X
�ihttp://www.nts-book.co.jp/)�ɔ��s���ꂽ�u�N���[���f�B�[�[���J���̗v�f�Z�p�����v�Ɖ]����发(http://www.
nts-book.co.jp/item/detail/summary/energy/20081114_51.html)�̑�T�͂̂V���ɁA�u�����ׂ������---
�V�R�K�X�p����f�B�[�[���G���W��---�v�̍��ɏڂ����L�ڂ���Ă���̂ŁA�Q�l�ɂ��Ă������������B
�[���Ɠ����̂b�n�Q��r�o���A�f�B�[�[�������R���G�l���M�[���R�P���������Q���v���I�Ȍ��ׂ�����B�����
���A�R�Ď����Ƀp�C���b�g���˂����y���̎��Ȓ��̉Ή��ɂ��V�R�K�X��R�Ă�����y�����Ό^�̂c�c�e�G��
�W���́A�]���̑�^�f�B�[�[���g���b�N�ɔ�r�����ꍇ�A�f�B�[�[���Ɠ����̔M�����ł��邱�Ƃɉ����A�f�B�[�[����
��b�n�Q��15�����Ȃ��ł��钷��������B�ȏ�̓��e�ɂ��ẮA��N�i2008�N�j��11��14���ɇ��G�k�E�e�B�[�E�G�X
�ihttp://www.nts-book.co.jp/)�ɔ��s���ꂽ�u�N���[���f�B�[�[���J���̗v�f�Z�p�����v�Ɖ]����发(http://www.
nts-book.co.jp/item/detail/summary/energy/20081114_51.html)�̑�T�͂̂V���ɁA�u�����ׂ������---
�V�R�K�X�p����f�B�[�[���G���W��---�v�̍��ɏڂ����L�ڂ���Ă���̂ŁA�Q�l�ɂ��Ă������������B
�@�Ȃ��A�c�c�e�G���W���́A�f�B�[�[���Ɠ����̍����M������L���Ă���̂ŁA��^�g���b�N�ɂ����ăf�B�[�[���G���W
���ɑ�ւ��ėp���邱�Ƃɂ��Ă͔M�����̖ʂ���͉��̖��������B���������āA�V�R�K�X�p����c�c�e�G��
�W���́A����̑�^�g���b�N�́u�b�n�Q�팸�v��u�E�Ζ��v�𐄐i���邽�߂̍œK�ȓV�R�K�X�G���W���ł���ƒf������
�ǂ��̂ł͂Ȃ����낤���B
���ɑ�ւ��ėp���邱�Ƃɂ��Ă͔M�����̖ʂ���͉��̖��������B���������āA�V�R�K�X�p����c�c�e�G��
�W���́A����̑�^�g���b�N�́u�b�n�Q�팸�v��u�E�Ζ��v�𐄐i���邽�߂̍œK�ȓV�R�K�X�G���W���ł���ƒf������
�ǂ��̂ł͂Ȃ����낤���B
�U�DDDF�G���W���ɂ�����X�Ȃ鐫�\����̋Z�p
�@����܂ł̐����ɗp���������U�t�H���[�h�c�c�e�G���W���̃f�[�^�́A�z�C�|�[�g�ɓV�R�K�X�˂���z�C�|�[�g
���ˎ��c�c�e�G���W���̎������ʂł���B���̐}�T�Ɏ������z�C�|�[�g���ˎ��c�c�e�G���W�������ǂ��A�}�P�T�Ɏ�����
�悤�ȃV�����_���ɓV�R�K�X�ڕ��˂���������DDF�G���W���i�������J2008-51121�j�Ƃ��邱�Ƃɂ���āA�V����
�_���ւ̓V�R�K�X���˂̓K������}�邱�Ƃ��ł��邽�߁A�c�c�e�G���W���̐��\���X�Ɍ��コ���邱�Ƃ��\�ł�
��B�܂��C�������^�]���̔R��ጸ�̂��߂��C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�╔�������̂g�b��
���̂��߂ɕ��������Ɏ_���G�}�̉��x�㏸���\�ɂ����㏈������V�X�e���i�������J2005-69238�j���̐V
���ȃA�C�f�A�����邱�Ƃɂ��C�X�Ȃ�����\�̌����}�邱�Ƃ��\���B
���ˎ��c�c�e�G���W���̎������ʂł���B���̐}�T�Ɏ������z�C�|�[�g���ˎ��c�c�e�G���W�������ǂ��A�}�P�T�Ɏ�����
�悤�ȃV�����_���ɓV�R�K�X�ڕ��˂���������DDF�G���W���i�������J2008-51121�j�Ƃ��邱�Ƃɂ���āA�V����
�_���ւ̓V�R�K�X���˂̓K������}�邱�Ƃ��ł��邽�߁A�c�c�e�G���W���̐��\���X�Ɍ��コ���邱�Ƃ��\�ł�
��B�܂��C�������^�]���̔R��ጸ�̂��߂��C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�╔�������̂g�b��
���̂��߂ɕ��������Ɏ_���G�}�̉��x�㏸���\�ɂ����㏈������V�X�e���i�������J2005-69238�j���̐V
���ȃA�C�f�A�����邱�Ƃɂ��C�X�Ȃ�����\�̌����}�邱�Ƃ��\���B
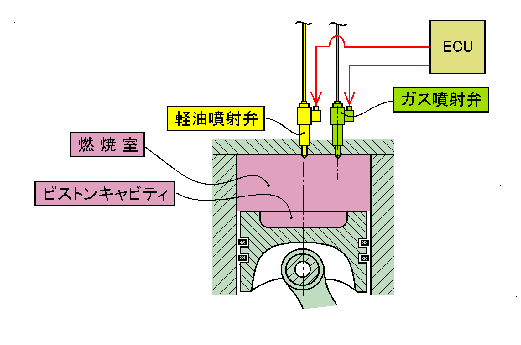
�@�Ƃ���ŁA���̂c�c�e�G���W���𓋍ڂ����g���b�N�ł́A�^�]��̃X�C�b�`������s�����Ƃɂ��A�c�c�e�^�]�ƃf�B�[�[
���^�]�Ƃ�C�ӂɑI�����Đ�ւ��邱�Ƃ��\�ȁu�f���A���^�]���[�h�v�̑��s���\�ł���B�f���A���^�]���[
�h��DDF��^�g���b�N�����p�����ꂽ�ꍇ�̃����b�g�ɂ��ẮADDF�^�]�ƃf�B�[�[���^�]�̑I�����\�Ȃc�c�e��
�^�g���b�N �̃y�[�W�ɏڍׂɋL�ڂ����̂ŁA�����������������B
���^�]�Ƃ�C�ӂɑI�����Đ�ւ��邱�Ƃ��\�ȁu�f���A���^�]���[�h�v�̑��s���\�ł���B�f���A���^�]���[
�h��DDF��^�g���b�N�����p�����ꂽ�ꍇ�̃����b�g�ɂ��ẮADDF�^�]�ƃf�B�[�[���^�]�̑I�����\�Ȃc�c�e��
�^�g���b�N �̃y�[�W�ɏڍׂɋL�ڂ����̂ŁA�����������������B
�V�D�\���Ȓm������������DDF�G���W����ᔻ����f�B�[�[���G���W�����Ƃ̖��f
�@�c�c�e�G���W���͐V�����Z�p�ł��邽�߁A�䂪���ł͂��̃G���W�����\���ɗ������Ă���G���W���Z�p�҂͋ɂ߂�
���Ȃ��B�c�c�e�G���W���̓f�B�[�[���f���A���t���G���G���W���Ɖ]�����̖��̎����Ƃ���A�f�B�[�[���G���W������h
�������y�����k���Ό^�̃G���W���ł���B���̂��߂c�c�e�G���W���ɂ��Ă̏\���ȕ�������W���s���Ă���
���ɂ�������炸�A�f�B�[�[���G���W���Z�p�Ҏ��g����Ղ̘_����ǂ����łc�c�e�G���W���𗝉����Ă���Ǝ�
�g���[�����Ă��܂��Ă���Ƃ��낪�傫�ȊԈႢ�̌����ƂȂ��Ă���悤���B�ŋ߂܂ň�����{���\���錤������
�G���W����������̕�������ꂽ�l����c�c�e�G���W���ɂ��Ď��̂悤�Ȍ��ׂ�����Ǝw�E�̏�ŁA�c�c�e�G���W
���͎��p���������Ƃ̈ӌ���������A����������ꂽ���Ƃ�����B
���Ȃ��B�c�c�e�G���W���̓f�B�[�[���f���A���t���G���G���W���Ɖ]�����̖��̎����Ƃ���A�f�B�[�[���G���W������h
�������y�����k���Ό^�̃G���W���ł���B���̂��߂c�c�e�G���W���ɂ��Ă̏\���ȕ�������W���s���Ă���
���ɂ�������炸�A�f�B�[�[���G���W���Z�p�Ҏ��g����Ղ̘_����ǂ����łc�c�e�G���W���𗝉����Ă���Ǝ�
�g���[�����Ă��܂��Ă���Ƃ��낪�傫�ȊԈႢ�̌����ƂȂ��Ă���悤���B�ŋ߂܂ň�����{���\���錤������
�G���W����������̕�������ꂽ�l����c�c�e�G���W���ɂ��Ď��̂悤�Ȍ��ׂ�����Ǝw�E�̏�ŁA�c�c�e�G���W
���͎��p���������Ƃ̈ӌ���������A����������ꂽ���Ƃ�����B
�@ �u�i���{���\���錤�����̃G���W����������̌������́j�V�R�K�X�̓�R�����˂͎��{���Ă܂��A�Ύ��
�y���Ƃ��āA���^�m�[���̓������˂́A��\���N�O�ɍ��ƃv���W�F�N�g�Ŏ��{���܂����B���̂Ƃ��̌o��������_��
�܂Ƃ߂�ƁA�ᕉ�ׂł̃f�B�[�[���ȉ��̔M�����i���ɁA���^�m�[�����ˎ��j�A�R�X�g�ʁi�ˌn�̓R�X�g��������
���j�A�M�����E�ϋv���i���ɔR�����ˌn�̐M�����E�ϋv�����f�B�[�[������邱�Ɓj���グ���܂��B���������āA�y
���ȊO�̔R���ɂ��ɔR�����˃V�X�e���́A�ᕉ�ׂł̔M�����A�R�X�g�ʁA�ϋv���E�M�����Ńf�B�[�[���𗽉킷
�邱�Ƃ͓���Ǝv���܂��B�v�@
�y���Ƃ��āA���^�m�[���̓������˂́A��\���N�O�ɍ��ƃv���W�F�N�g�Ŏ��{���܂����B���̂Ƃ��̌o��������_��
�܂Ƃ߂�ƁA�ᕉ�ׂł̃f�B�[�[���ȉ��̔M�����i���ɁA���^�m�[�����ˎ��j�A�R�X�g�ʁi�ˌn�̓R�X�g��������
���j�A�M�����E�ϋv���i���ɔR�����ˌn�̐M�����E�ϋv�����f�B�[�[������邱�Ɓj���グ���܂��B���������āA�y
���ȊO�̔R���ɂ��ɔR�����˃V�X�e���́A�ᕉ�ׂł̔M�����A�R�X�g�ʁA�ϋv���E�M�����Ńf�B�[�[���𗽉킷
�邱�Ƃ͓���Ǝv���܂��B�v�@
�@���̌������̂c�c�e�G���W���ɑ��Ă̖��w�E�́A�c�c�e�G���W����S����������Ă��Ȃ����Ƃ�@���Ɏ����Ă���
�؋��ł���B���������c�c�e�G���W���̓A�C�h�����O�^�]�ł͌y���݂̂̃f�B�[�[���^�]�ł���B�����Ăc�c�e�G���W��
�̒ᕉ�ׂɂ�����V�R�K�X�̊R�Ă�����ȉ^�]�̈�ł́A�y���݂̂�R�Ă����ĉ^�]����f�B�[�[�����̂�
�̂ʼn^�]����G���W���ł���B���̌������̃G���W����������̌������́A���̂悤��DDF�G���W���̉^�]�����
�S�����������ɁA�c�c�e�G���W���ł͒ᕉ�ׂɂ����ĉΎ�̃p�C���b�g���˂ɏ��ʂ̓V�R�K�X���������ăG���W���^
�]������̂Ə���Ɏv�����݁A�u�ᕉ�ׂł̔R�Ă̕s�����f�B�[�[���ȉ��̔M�����ƂȂ��Ă��܂����Ƃ����v��
�v������ł���悤���B�c�c�e�G���W���̒ᕉ�ׂɂ����ĉΎ�̃p�C���b�g���˂ɕK�����ʂ̓V�R�K�X���������ăG
���W�����^�]���Ȃ���Ȃ�Ȃ��@����K���͉����ɂ������̂ł���B�c�c�e�G���W���ł̓p�C���b�g���˂̌y����
��R���̓V�R�K�X�̋����́A���R���݂ɐ��䂷��Ηǂ��̂��B�ᕉ�^�]�Ŗ����ɓV�R�K�X���������Ăc�c�e�G
���W�����^�]������悤�ɂ��Ă��c�c�e�G���W���̑��R������ʂɐ�߂�V�R�K�X�̏�����̑����͋͂��ł���A
�c�c�e�G���W���ɂ�����V�R�K�X����ʂ̊����̑����ɑ傫�ȉe���͂Ȃ��̂ł���B
�؋��ł���B���������c�c�e�G���W���̓A�C�h�����O�^�]�ł͌y���݂̂̃f�B�[�[���^�]�ł���B�����Ăc�c�e�G���W��
�̒ᕉ�ׂɂ�����V�R�K�X�̊R�Ă�����ȉ^�]�̈�ł́A�y���݂̂�R�Ă����ĉ^�]����f�B�[�[�����̂�
�̂ʼn^�]����G���W���ł���B���̌������̃G���W����������̌������́A���̂悤��DDF�G���W���̉^�]�����
�S�����������ɁA�c�c�e�G���W���ł͒ᕉ�ׂɂ����ĉΎ�̃p�C���b�g���˂ɏ��ʂ̓V�R�K�X���������ăG���W���^
�]������̂Ə���Ɏv�����݁A�u�ᕉ�ׂł̔R�Ă̕s�����f�B�[�[���ȉ��̔M�����ƂȂ��Ă��܂����Ƃ����v��
�v������ł���悤���B�c�c�e�G���W���̒ᕉ�ׂɂ����ĉΎ�̃p�C���b�g���˂ɕK�����ʂ̓V�R�K�X���������ăG
���W�����^�]���Ȃ���Ȃ�Ȃ��@����K���͉����ɂ������̂ł���B�c�c�e�G���W���ł̓p�C���b�g���˂̌y����
��R���̓V�R�K�X�̋����́A���R���݂ɐ��䂷��Ηǂ��̂��B�ᕉ�^�]�Ŗ����ɓV�R�K�X���������Ăc�c�e�G
���W�����^�]������悤�ɂ��Ă��c�c�e�G���W���̑��R������ʂɐ�߂�V�R�K�X�̏�����̑����͋͂��ł���A
�c�c�e�G���W���ɂ�����V�R�K�X����ʂ̊����̑����ɑ傫�ȉe���͂Ȃ��̂ł���B
�@���̂悤�Ȃc�c�e�G���W����S�����������ɓI�O��Ȃc�c�e�G���W���ᔻ�ł����Ă��A���{���\���錤�����̃G��
�W����������̌������̔����ł���ΐM����l�������A�c�c�e�G���W���̌��ׂƂ��ė��z����Ă���\�����ɂ�
�č����Ǝv����B�c�c�e�G���W���ɂƂ��Ă͖����̍߂𒅂����Ă���悤�Ȃ��̂ł���A���ɒQ���킵�����Ƃ��B
�n�ʂ̂���G���W�����Ƃ������g�̒m����o�����s�\���ȕ���ɂ��Ă̖��ӔC�Ȕ�����咣�������f��
�s�ׂ́A���ɂ͋ނ�ł��������������̂ł���B
�W����������̌������̔����ł���ΐM����l�������A�c�c�e�G���W���̌��ׂƂ��ė��z����Ă���\�����ɂ�
�č����Ǝv����B�c�c�e�G���W���ɂƂ��Ă͖����̍߂𒅂����Ă���悤�Ȃ��̂ł���A���ɒQ���킵�����Ƃ��B
�n�ʂ̂���G���W�����Ƃ������g�̒m����o�����s�\���ȕ���ɂ��Ă̖��ӔC�Ȕ�����咣�������f��
�s�ׂ́A���ɂ͋ނ�ł��������������̂ł���B
�@���āA�䂪���ł͎��ۂɂc�c�e�G���W�����������ꂽ�G���W���W�̊w�ҁE���Ƃ����Ȃ����߁A�c�c�e�G���W����
�ւ�����͏��Ȃ��̂�����ł���B���̂��߁A�O�q�̈��錤�����̃G���W����������̌������́u�c�c�e�G���W
���ᔻ�v�Ɠ������A�c�c�e�G���W�����\���ɗ�������Ă��Ȃ��G���W���W�̊w�ҁE���Ƃ́A����Ƃ��c�c�e�G���W��
�ɑ��ĕ��X�œI�O��̔ᔻ���J��Ԃ������̂Ɛ��@�����B���̂悤�Ȃ��Ƃ͑����Ɏ~�߂ė~�������̂ł����A
���g���I�O��̔ᔻ�ł��邱�Ƃ�F������Ă��Ȃ����߂ɍ�����������������DDF�ᔻ�𑱂����邱�Ƃ��l��
��ƁADDF�G���W�����s���łȂ�Ȃ��B���̂悤�Ȃ��Ƃ��A�����̊w�ҁE���Ƃ���c�c�e�G���W������������Ă��闝
�R�̈�ɂȂ��Ă���̂ł͂Ȃ����낤���B
�ւ�����͏��Ȃ��̂�����ł���B���̂��߁A�O�q�̈��錤�����̃G���W����������̌������́u�c�c�e�G���W
���ᔻ�v�Ɠ������A�c�c�e�G���W�����\���ɗ�������Ă��Ȃ��G���W���W�̊w�ҁE���Ƃ́A����Ƃ��c�c�e�G���W��
�ɑ��ĕ��X�œI�O��̔ᔻ���J��Ԃ������̂Ɛ��@�����B���̂悤�Ȃ��Ƃ͑����Ɏ~�߂ė~�������̂ł����A
���g���I�O��̔ᔻ�ł��邱�Ƃ�F������Ă��Ȃ����߂ɍ�����������������DDF�ᔻ�𑱂����邱�Ƃ��l��
��ƁADDF�G���W�����s���łȂ�Ȃ��B���̂悤�Ȃ��Ƃ��A�����̊w�ҁE���Ƃ���c�c�e�G���W������������Ă��闝
�R�̈�ɂȂ��Ă���̂ł͂Ȃ����낤���B
�W�D��^�g���b�N�́uCO�팸�v�Ɓu�E�Ζ��v�������ł���Z�p�����o���Ă��Ȃ��w�ҁE����
�@�ߔN�̒�����C���h�Ȃǂ̋}���Ȍo�ϔ��W��Ζ��s�[�N�̎���ɓ˓��������Ƃ���A�߂������A�䂪���ł͐Ζ�
�R�����s�����A�y���s�����琶����g���b�N�ݕ��A���̎x�����댯�������Ă����B�����Ōo�ώY�ƏȂ�2006
�N5���Ɂu�V�E���ƃG�l���M�[�헪�v�\���A�^�A����ɂ�����Ζ��ˑ�����̒E�p��}�邽�߂ɁA2030�N�܂�
�ɁA�^�A����̐Ζ��ˑ��x��80�����x�Ƃ�����j�\�����B��^�g���b�N�ɂ��Ă����}�ɒE�Ζ�����}��K�v
�����邱�Ƃ͓��R�ł���B�܂��A�Q�O�O�X�N�P�Q���̍��A�C��ϓ��g�g�ݏ���P�T�����c�i�b�n�o�P�T�j�Ŕ��R
�́u�X�O�N��Q�T����CO�Q�팸�v��錾���A�̖ڕW����{���{�͂Q�O�P�O�N�P���Q�U���ɂQ�T���팸�̖ڕW������
�����ǂɒ�o�����Ƃ̂��Ƃł���B���{�͑�^�g���b�N�ɂ�����CO�Q�팸�ڕW���������A�E�Ζ����������čs������
�̌v��𑁋}�ɍ��肷��K�v������B���̂��߁A���{�̒S�������͊w�҂���Ƃ�CO�Q�팸��E�Ζ��ɕK�v��
�Z�p�헪�̒�Ă����߂Ă������Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��B
�R�����s�����A�y���s�����琶����g���b�N�ݕ��A���̎x�����댯�������Ă����B�����Ōo�ώY�ƏȂ�2006
�N5���Ɂu�V�E���ƃG�l���M�[�헪�v�\���A�^�A����ɂ�����Ζ��ˑ�����̒E�p��}�邽�߂ɁA2030�N�܂�
�ɁA�^�A����̐Ζ��ˑ��x��80�����x�Ƃ�����j�\�����B��^�g���b�N�ɂ��Ă����}�ɒE�Ζ�����}��K�v
�����邱�Ƃ͓��R�ł���B�܂��A�Q�O�O�X�N�P�Q���̍��A�C��ϓ��g�g�ݏ���P�T�����c�i�b�n�o�P�T�j�Ŕ��R
�́u�X�O�N��Q�T����CO�Q�팸�v��錾���A�̖ڕW����{���{�͂Q�O�P�O�N�P���Q�U���ɂQ�T���팸�̖ڕW������
�����ǂɒ�o�����Ƃ̂��Ƃł���B���{�͑�^�g���b�N�ɂ�����CO�Q�팸�ڕW���������A�E�Ζ����������čs������
�̌v��𑁋}�ɍ��肷��K�v������B���̂��߁A���{�̒S�������͊w�҂���Ƃ�CO�Q�팸��E�Ζ��ɕK�v��
�Z�p�헪�̒�Ă����߂Ă������Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��B
�@����A���{��������CO�Q�팸��E�Ζ��ɕK�v�ȋZ�p�헪�̒�Ă����߂��闧��̊w�҂���Ƃ́A�u����
�_�ł͓s�s�ԑ��s�̑�^�f�B�[�[���g���b�N�ɂ�����CO�Q�팸�������ł��錩�ʂ��͑S�������Ă��Ȃ��v���߂ɁA��
�̋Z�p�Ă��������Ƃ��ł��Ȃ��̂�����̂悤���B�s�s�ԑ��s�̑�^�f�B�[�[���g���b�N�̃o�C�I�}�X�R���R����
�O�ł�CO�Q�팸�ɂ��āA�����ԋZ�p�@Vol.64�ANo.�P�A2010�i2010�N1��1�����s�j�́u���W�F�����ԋZ�p�̐i���v��
�����āA�ѓc�P���@���R�����u�f�B�[�[���G���W������10�N�v�̍Ō�́u�T�@�����Ɂv�̍��Ɂu�i�f�B�[�[���G���W��
�́jCO�Q�̂���Ȃ�팸�͍�����傫�Ȓ���ۑ�v�ƋZ�p�J���̕K�v�����L�ڂ���Ă���݂̂ł���B�����āuCO�Q
�팸�̉ۑ�B���v�ɂ́u�]���̃f�B�[�[���G���W���̗v�f�Z�p�J���ɉ����A�R���A�R�āA�G�}�̌����A�V�X�e����
��̓������Z�p�����߂��Ă���v�ƋL�ڂ���Ă���B�ᔻ�����ꂸ�ɕM�҂̌��t�ł��̋L�ړ��e��Ղ�����
����ƁA�u�f�B�[�[���G���W����CO�Q�팸�̉ۑ�B���͋ɂ߂č���ł���A���̂Ƃ���A�f�B�[�[���G���W����CO�Q
��啝�ɍ팸�ł���L���ȋZ�p�͉�����o����Ă��Ȃ��̂�����ł���B�f�B�[�[���G���W����CO�Q�팸����
���ł����i����@���S���s���ł���A�Z�p�I�ɔ����ǂ���̏�悵�Ă���B�f�B�[�[���G���W����CO�Q���
���ɍ팸���邽�߂ɂ́A���̂Ƃ���f�B�[�[���G���W���̗v�f�Z�p�A�R�����ǁA�R�ĉ��P�A�G�}�̌����A�V�X�e��
�Z�p�̉��ǂ̐��i�ȂǁA�����_�ōl������f�B�[�[���G���W���̐��\�E�r�o�K�X�Ɋւ���S�ẴA�C�e���̉���
�������p�����Ă������Ƃ������@�͎c����Ă��Ȃ��B�������Ȃ��炱���̉��nj����𐄐i���Ă��A�f�B�[�[���G���W
����CO�Q�팸���m���Ɏ����ł���ۏ͂Ȃ��v�Ɖ]�����ƂɂȂ�B
�_�ł͓s�s�ԑ��s�̑�^�f�B�[�[���g���b�N�ɂ�����CO�Q�팸�������ł��錩�ʂ��͑S�������Ă��Ȃ��v���߂ɁA��
�̋Z�p�Ă��������Ƃ��ł��Ȃ��̂�����̂悤���B�s�s�ԑ��s�̑�^�f�B�[�[���g���b�N�̃o�C�I�}�X�R���R����
�O�ł�CO�Q�팸�ɂ��āA�����ԋZ�p�@Vol.64�ANo.�P�A2010�i2010�N1��1�����s�j�́u���W�F�����ԋZ�p�̐i���v��
�����āA�ѓc�P���@���R�����u�f�B�[�[���G���W������10�N�v�̍Ō�́u�T�@�����Ɂv�̍��Ɂu�i�f�B�[�[���G���W��
�́jCO�Q�̂���Ȃ�팸�͍�����傫�Ȓ���ۑ�v�ƋZ�p�J���̕K�v�����L�ڂ���Ă���݂̂ł���B�����āuCO�Q
�팸�̉ۑ�B���v�ɂ́u�]���̃f�B�[�[���G���W���̗v�f�Z�p�J���ɉ����A�R���A�R�āA�G�}�̌����A�V�X�e����
��̓������Z�p�����߂��Ă���v�ƋL�ڂ���Ă���B�ᔻ�����ꂸ�ɕM�҂̌��t�ł��̋L�ړ��e��Ղ�����
����ƁA�u�f�B�[�[���G���W����CO�Q�팸�̉ۑ�B���͋ɂ߂č���ł���A���̂Ƃ���A�f�B�[�[���G���W����CO�Q
��啝�ɍ팸�ł���L���ȋZ�p�͉�����o����Ă��Ȃ��̂�����ł���B�f�B�[�[���G���W����CO�Q�팸����
���ł����i����@���S���s���ł���A�Z�p�I�ɔ����ǂ���̏�悵�Ă���B�f�B�[�[���G���W����CO�Q���
���ɍ팸���邽�߂ɂ́A���̂Ƃ���f�B�[�[���G���W���̗v�f�Z�p�A�R�����ǁA�R�ĉ��P�A�G�}�̌����A�V�X�e��
�Z�p�̉��ǂ̐��i�ȂǁA�����_�ōl������f�B�[�[���G���W���̐��\�E�r�o�K�X�Ɋւ���S�ẴA�C�e���̉���
�������p�����Ă������Ƃ������@�͎c����Ă��Ȃ��B�������Ȃ��炱���̉��nj����𐄐i���Ă��A�f�B�[�[���G���W
����CO�Q�팸���m���Ɏ����ł���ۏ͂Ȃ��v�Ɖ]�����ƂɂȂ�B
�@�̂���u���I�R�N�A�`�W�N�v�Ɖ]����悤�ɁA�ʕ��̏ꍇ�ɂ͕c��A���Ă�����̔N�����߂���Ήʕ�����
�n�ł��邱�Ƃ͒N�����m���Ă��邱�Ƃł���B�������A�Z�p�J���ł́A�ʕ��̎��n�Ɠ��l�Ɉ��̔N�����₹��
��������ۏ͉��������̂ł���B��^�g���b�N��CO�Q�팸��E�Ζ��̂悤�ȋZ�p�J���ł́A�����J�������{��
��Z�p�A�C�e���̑I�������s����ꍇ��A�Z�p�A�C�e���̑I�����K�ł������Ƃ��Ă������J�������{����Z�p
��̃A�C�f�A�s���̏ꍇ�ɂ́A���̋Z�p�J�����\��ʂ�ɐ������Ȃ����Ƃ��N���蓾�邱�Ƃł���B�܂��āA�����_
�ŋZ�p�I�Ȍ��ʂ����S�������Ă��Ȃ���^�g���b�N��CO�Q�팸��E�Ζ��ɂ��āA���ꂪ�����ł��鎞����\�z��
���Ȃ����Ƃ͓��R�ł���B�O�q�̒ʂ�A�u�����ԋZ�p�v���i2010�N1���P�����s�j�Ɍf�ڂ̘_���u�f�B�[�[���G��
�W�����̂P�O�N�v�i���ҁF�ѓc�P�� �c���勳���@���R���j�ł́A�f�B�[�[���G���W����CO�Q�팸���u����I��
��v�ƋL�ڂ���A����CO�Q�팸�̂��߂Ɂu�]���̃f�B�[�[���G���W���̗v�f�Z�p�J���ɉ����A�R���A�R�āA
�G�}�̌����A�V�X�e������̓������Z�p�����߂��Ă���v�ƌ��_�t�����Ă���B����͓s�s�ԑ��s��
��^�f�B�[�[���g���b�N�ł́uCO�Q�팸���Z�p�I�ɔ����ǂ���̏v�ł���A�u�f�B�[�[���G���W���̐��\�E
�r�o�K�X�֘A�̎v�����S�ẴA�C�e���ɂ��Ă̌��������{���ׂ��v���Ƃ�U�ȂɋL�ڂ������̂ƍl����
���B���́u�����ԋZ�p�v���������ԋZ�p��̉�ҏW�ψ���ɂ���ĕҏW����Ă��邱�Ƃ���l����ƁA
���̈ӌ��́A���҂̔ѓc�P���@���R���̏��������łȂ��A�����̓��{�̎����ԊW�f�B�[�[���G���W���̊w
�ҁE���ƂɎ^������Ă�����̂ƌ��č����x���Ȃ��ƍl������B
�n�ł��邱�Ƃ͒N�����m���Ă��邱�Ƃł���B�������A�Z�p�J���ł́A�ʕ��̎��n�Ɠ��l�Ɉ��̔N�����₹��
��������ۏ͉��������̂ł���B��^�g���b�N��CO�Q�팸��E�Ζ��̂悤�ȋZ�p�J���ł́A�����J�������{��
��Z�p�A�C�e���̑I�������s����ꍇ��A�Z�p�A�C�e���̑I�����K�ł������Ƃ��Ă������J�������{����Z�p
��̃A�C�f�A�s���̏ꍇ�ɂ́A���̋Z�p�J�����\��ʂ�ɐ������Ȃ����Ƃ��N���蓾�邱�Ƃł���B�܂��āA�����_
�ŋZ�p�I�Ȍ��ʂ����S�������Ă��Ȃ���^�g���b�N��CO�Q�팸��E�Ζ��ɂ��āA���ꂪ�����ł��鎞����\�z��
���Ȃ����Ƃ͓��R�ł���B�O�q�̒ʂ�A�u�����ԋZ�p�v���i2010�N1���P�����s�j�Ɍf�ڂ̘_���u�f�B�[�[���G��
�W�����̂P�O�N�v�i���ҁF�ѓc�P�� �c���勳���@���R���j�ł́A�f�B�[�[���G���W����CO�Q�팸���u����I��
��v�ƋL�ڂ���A����CO�Q�팸�̂��߂Ɂu�]���̃f�B�[�[���G���W���̗v�f�Z�p�J���ɉ����A�R���A�R�āA
�G�}�̌����A�V�X�e������̓������Z�p�����߂��Ă���v�ƌ��_�t�����Ă���B����͓s�s�ԑ��s��
��^�f�B�[�[���g���b�N�ł́uCO�Q�팸���Z�p�I�ɔ����ǂ���̏v�ł���A�u�f�B�[�[���G���W���̐��\�E
�r�o�K�X�֘A�̎v�����S�ẴA�C�e���ɂ��Ă̌��������{���ׂ��v���Ƃ�U�ȂɋL�ڂ������̂ƍl����
���B���́u�����ԋZ�p�v���������ԋZ�p��̉�ҏW�ψ���ɂ���ĕҏW����Ă��邱�Ƃ���l����ƁA
���̈ӌ��́A���҂̔ѓc�P���@���R���̏��������łȂ��A�����̓��{�̎����ԊW�f�B�[�[���G���W���̊w
�ҁE���ƂɎ^������Ă�����̂ƌ��č����x���Ȃ��ƍl������B
�@���́u�����ԋZ�p�v���i2010�N1���P�����s�j�̔ѓc�P�� �c���勳���̘_�����e���������悤�ɁA�����_�ł͑�
�^�g���b�N��CO�Q�팸��E�Ζ����\�ɂ���Z�p�I�Ȍ��ʂ��������Ă��Ȃ��̂ł���B���̂悤�ȏ̒��ŁA�M
�҂�DDF�G���W���𓋍ڂ���DDF��^�g���b�N�̎��p���ɂ���āuCO�Q�팸�v����łȂ��A�u�E�Ζ��v���������ł���
���Ƃ�K���ɑi���Ă��邪�A�����ԋZ�p��̉�ҏW�ψ�����DDF��^�g���b�N�̋Z�p�����S�ɖ�������Ă�
��悤�ł���B�����̕M�҂̎咣�̓͂��͈͂��ɂ߂ă��[�J���Ɍ����Ă��邽�߁A�����ԋZ�p��̉�ҏW��
����̖ڂɐG��Ă��Ȃ��̂��낤���B����Ƃ���ҏW�ψ���̃����o�[���M�҂̎咣��ڂɂ����Ƃ��Ă��A����
�ԋZ�p��̗ϗ��K��ɂ�����u�i���̔��M�j��ɒ����I�A�q�ϓI���ꂩ�琽�ӂ������Č������e��ʂ��Љ�
�ɐ�������������悤�ɓw�߂܂��B�v�Ƃ̋K��̂ɂ��ĕM�҂̂c�c�e��^�g���b�N�Ɋւ���咣���Ӑ}�I�ɖ�����
�Ă���̂��낤���B����ɂ��Ă��A�u�����ԋZ�p�v���ɗႦ�U�Ȃȕ\���ł����Ă��f�B�[�[���G���W���́uCO�Q�팸��
�Z�p�I�ɔ����ǂ���̏v���f�킹��悤�ȋL�q�ɂ��ẮADDF�G���W���ɂ���đ�^�g���b�N��CO�Q�팸��E
�Ζ����Ă��Ă���M�҂ɂƂ��Ắu���������߂��v�̊����@����Ȃ��̂ł���B���̂悤�ȏ�����ƁA����
�ԋZ�p��͗ϗ��K��̒ʂ�ɉ^�c����Ă���̂��낤���ƁA�M�҂ɂ͋^��Ɏv���Ă���̂ł���B
�^�g���b�N��CO�Q�팸��E�Ζ����\�ɂ���Z�p�I�Ȍ��ʂ��������Ă��Ȃ��̂ł���B���̂悤�ȏ̒��ŁA�M
�҂�DDF�G���W���𓋍ڂ���DDF��^�g���b�N�̎��p���ɂ���āuCO�Q�팸�v����łȂ��A�u�E�Ζ��v���������ł���
���Ƃ�K���ɑi���Ă��邪�A�����ԋZ�p��̉�ҏW�ψ�����DDF��^�g���b�N�̋Z�p�����S�ɖ�������Ă�
��悤�ł���B�����̕M�҂̎咣�̓͂��͈͂��ɂ߂ă��[�J���Ɍ����Ă��邽�߁A�����ԋZ�p��̉�ҏW��
����̖ڂɐG��Ă��Ȃ��̂��낤���B����Ƃ���ҏW�ψ���̃����o�[���M�҂̎咣��ڂɂ����Ƃ��Ă��A����
�ԋZ�p��̗ϗ��K��ɂ�����u�i���̔��M�j��ɒ����I�A�q�ϓI���ꂩ�琽�ӂ������Č������e��ʂ��Љ�
�ɐ�������������悤�ɓw�߂܂��B�v�Ƃ̋K��̂ɂ��ĕM�҂̂c�c�e��^�g���b�N�Ɋւ���咣���Ӑ}�I�ɖ�����
�Ă���̂��낤���B����ɂ��Ă��A�u�����ԋZ�p�v���ɗႦ�U�Ȃȕ\���ł����Ă��f�B�[�[���G���W���́uCO�Q�팸��
�Z�p�I�ɔ����ǂ���̏v���f�킹��悤�ȋL�q�ɂ��ẮADDF�G���W���ɂ���đ�^�g���b�N��CO�Q�팸��E
�Ζ����Ă��Ă���M�҂ɂƂ��Ắu���������߂��v�̊����@����Ȃ��̂ł���B���̂悤�ȏ�����ƁA����
�ԋZ�p��͗ϗ��K��̒ʂ�ɉ^�c����Ă���̂��낤���ƁA�M�҂ɂ͋^��Ɏv���Ă���̂ł���B
�X�D�V�R�K�X��ăg���b�N��CO2�r�o�ʂ́A�f�B�[�[���g���b�N��CO2�r�o�ʂƂقړ���
�@�i�Ɓj��ʈ��S����������2010�N11��24�i���j�E25���i�j�̍u����ɂ����āA��ʈ��S���������́A�\�P��
�������_���u��^�V�R�K�X�g���b�N�̎��؉^�s�����̐��ʂƕ��y�ւ̉ۑ�v�i�Q�Ɓj�\�����B���̘_���ł́A��
��21�N�x�ɏI������GVW25�g�����I�b�g�[�T�C�N���̃X�p�[�N�v���O�����V�R�K�X�G���W���𓋍ڂ������k�V�R�K
�X�iCNG)��^�g���b�N�i�Ȍ�A�V�R�K�X��đ�^�g���b�N�Ə̂��j�ɂ��ݕ��A�����Ƃ̌v30��km�ɋy�ԁi�Ɓj���
���S�������������؎����̌���( ��http://www.ntsel.go.jp/forum/forum2010.html�j������Ă���B���̕�
���ł́A�V�R�K�X��ăg���b�N��CO2�r�o�ʂ́A�f�B�[�[���g���b�N��CO2�r�o�ʂƂقړ����ł��邱�Ƃ����L����
����B
�������_���u��^�V�R�K�X�g���b�N�̎��؉^�s�����̐��ʂƕ��y�ւ̉ۑ�v�i�Q�Ɓj�\�����B���̘_���ł́A��
��21�N�x�ɏI������GVW25�g�����I�b�g�[�T�C�N���̃X�p�[�N�v���O�����V�R�K�X�G���W���𓋍ڂ������k�V�R�K
�X�iCNG)��^�g���b�N�i�Ȍ�A�V�R�K�X��đ�^�g���b�N�Ə̂��j�ɂ��ݕ��A�����Ƃ̌v30��km�ɋy�ԁi�Ɓj���
���S�������������؎����̌���( ��http://www.ntsel.go.jp/forum/forum2010.html�j������Ă���B���̕�
���ł́A�V�R�K�X��ăg���b�N��CO2�r�o�ʂ́A�f�B�[�[���g���b�N��CO2�r�o�ʂƂقړ����ł��邱�Ƃ����L����
����B
�܂Ƃ�(��http://www.mlit.go.jp/common/000168127.pdf�j�v�ɂ́A�u�I�b�g�[�T�C�N���̃X�p�[�N�v���O�����V�R�K�X
�G���W���𓋍ڂ����V�R�K�X��đ�^�g���b�N�v�́A�u��^�f�B�[�[���g���b�N�v�ɔ�r���Ď����s�ł̔R��i���M��
���j���Q�T��������Ă��邱�Ƃ��������i�Ɓj��ʈ��S���������̌v���f�[�^����������Ă���B���̂��Ƃ���A��
�y��ʏȂƁi�Ɓj��ʈ��S���������́A���Ȃ�ȑO����A�u��^�f�B�[�[���g���b�N�v�ɔ�r���āu�I�b�g�[�T�C�N��
�̃X�p�[�N�v���O�����V�R�K�X�G���W���𓋍ڂ����V�R�K�X��đ�^�g���b�N�v�̎����s��CO2�r�o�ʂ������ł�
��A�R��i���M�����j���Q�T�����x������Ă��邱�Ƃ��\���ɏ��m���Ă����Ɣ��Ɛ��������B�����̓��e�ɂ���
�́A�V�R�K�X��Ă�CNG��^�g���b�N�́A�d�ʎԔR���ɕs�K���̌��׃g���b�N�ɏڏq���Ă���̂ŁA�����̂�
����͌䗗�������������B
�P�O�DDDF�G���W���̗̍p�ɂ���đ�^�g���b�N�́uCO�팸�v�Ɓu�E�Ζ��v�������\
�@���R�͂Q�O�O�X�N�X���Q�Q���ɍ��A�{���ŊJ���ꂽ���A�C��ϓ���]����łQ�O�Q�O�N�܂łɉ������ʃK�X
���P�X�X�O�N��łQ�T���팸������{�̒����ڕW��\�������B�ȃG�l�̔��B�������{�ł�CO�Q�̂Q�T���팸�̎���
���ɂ߂č���ł��邱�Ƃ͊��ɐ��E�I�ɗǂ��m���Ă��邱�Ƃ������āA���R�̔��I��CO�Q�팸�錾�ɑ�
���A���A�ł͂قƂ�ǒ��ڂ���Ȃ������悤���B�펯�I�ɍl����Δ��R�̘I���Ȕ����s�ׁE���Ȑ�`�ł��邱
�Ƃ��e�Ղɔ��f�ł��邽�߁A�e���̃}�X�R�~�������Ė��������̂ł͂Ȃ����낤���B���ʂ��猾���ACO�Q�팸�ɂ�
���Đ��E�e������O�Ȕ��f�̊�ɍs�����Ă��邱�Ƃ𗝉��ł��Ă��Ȃ����R�́ACO�Q�̂Q�T���팸��\����
�邱�Ƃɂ���Ď��g�����E�̏̎^����̂Ə���Ɏv�����݁ACO�Q�r�o�Ɋւ��ē��{�̎Љ�S�̂ɏd����
������Ƃ߂Ă��܂����̂��B���̂悤�ȓI�O��̔��R�̍s���́A�����ɂƂ��Ă͖��f�Șb�ł���B
���P�X�X�O�N��łQ�T���팸������{�̒����ڕW��\�������B�ȃG�l�̔��B�������{�ł�CO�Q�̂Q�T���팸�̎���
���ɂ߂č���ł��邱�Ƃ͊��ɐ��E�I�ɗǂ��m���Ă��邱�Ƃ������āA���R�̔��I��CO�Q�팸�錾�ɑ�
���A���A�ł͂قƂ�ǒ��ڂ���Ȃ������悤���B�펯�I�ɍl����Δ��R�̘I���Ȕ����s�ׁE���Ȑ�`�ł��邱
�Ƃ��e�Ղɔ��f�ł��邽�߁A�e���̃}�X�R�~�������Ė��������̂ł͂Ȃ����낤���B���ʂ��猾���ACO�Q�팸�ɂ�
���Đ��E�e������O�Ȕ��f�̊�ɍs�����Ă��邱�Ƃ𗝉��ł��Ă��Ȃ����R�́ACO�Q�̂Q�T���팸��\����
�邱�Ƃɂ���Ď��g�����E�̏̎^����̂Ə���Ɏv�����݁ACO�Q�r�o�Ɋւ��ē��{�̎Љ�S�̂ɏd����
������Ƃ߂Ă��܂����̂��B���̂悤�ȓI�O��̔��R�̍s���́A�����ɂƂ��Ă͖��f�Șb�ł���B
�@�����͉]���Ă��A���ɓ��{�͑啝�Ȃb�n�Q�팸�𐢊E�Ɍ������Đ錾�������Ƃ���A��^�g���b�N�ɂ�����b�n�Q��
���̕K�v������������ттĂ����̂ł���B����A�o�ώY�ƏȂ�2006�N5���́u�V�E���ƃG�l���M�[�헪�v�ł́u��
��100����Ζ��n�R���Ɉˑ�����^�A����̓G�l���M�[�����\���̒��ōł��Ǝ㐫���������߂ɐΖ��ˑ�����
�̒E�p��}��ׂ��v�Ƃ��C�u����A2030�N�܂łɁA�^�A����̐Ζ��ˑ��x��80�����x�Ƃ��邱�Ƃ�ڎw���v�Ƃ�����
�\���Ă���̂��B���̂悤�Ɍ��݂̐��{�͑�^�g���b�N�ɂ����Ă͂b�n�Q�팸�ƒE�Ζ��Ɖ]�����h�ȕ��j�E�ڕW��
���X�ƌf���Ă���̂ł���B�������Ȃ��炱�����j�E�ڕW�������E�����ł��錩���݂͏����ł�����̂ł��낤���B
�u��^�g���b�N�́u�b�n2�팸�v�Ɓu�E�Ζ��v�̋Z�p�́A�����ɕs�����H�v�ɏڏq�����悤�ɁA�M�҂͐��{����^�g���b�N
�̂b�n�Q�팸�ƒE�Ζ��̐����ϋɓI�ɐ��i���Ă���Ƃ͂ƂĂ��l�����Ȃ��̂ł���B
���̕K�v������������ттĂ����̂ł���B����A�o�ώY�ƏȂ�2006�N5���́u�V�E���ƃG�l���M�[�헪�v�ł́u��
��100����Ζ��n�R���Ɉˑ�����^�A����̓G�l���M�[�����\���̒��ōł��Ǝ㐫���������߂ɐΖ��ˑ�����
�̒E�p��}��ׂ��v�Ƃ��C�u����A2030�N�܂łɁA�^�A����̐Ζ��ˑ��x��80�����x�Ƃ��邱�Ƃ�ڎw���v�Ƃ�����
�\���Ă���̂��B���̂悤�Ɍ��݂̐��{�͑�^�g���b�N�ɂ����Ă͂b�n�Q�팸�ƒE�Ζ��Ɖ]�����h�ȕ��j�E�ڕW��
���X�ƌf���Ă���̂ł���B�������Ȃ��炱�����j�E�ڕW�������E�����ł��錩���݂͏����ł�����̂ł��낤���B
�u��^�g���b�N�́u�b�n2�팸�v�Ɓu�E�Ζ��v�̋Z�p�́A�����ɕs�����H�v�ɏڏq�����悤�ɁA�M�҂͐��{����^�g���b�N
�̂b�n�Q�팸�ƒE�Ζ��̐����ϋɓI�ɐ��i���Ă���Ƃ͂ƂĂ��l�����Ȃ��̂ł���B
�@�������Ȃ���A���{�̑�^�g���b�N����̊Ǘ���S�����銯���́A��^�g���b�N���b�n�Q�팸�ƒE�Ζ��̎��p�\
�ȋZ�p�Ă��S�����m�ł������Ƃ��Ă��A���ɔ��\����Ă��鐭�{��CO�Q�팸��E�Ζ��̖ڕW�ɉ������悤�ȑ�^�g
���b�N��CO�Q�팸��E�Ζ��̋Z�p�헪�𑁋}�ɍ��肷��K�v������B���̂��߂ɁA�w�ҁE���Ƃɑ��đ�^�g��
�b�N��CO�Q�팸��E�Ζ�����������Z�p���Ă��邱�Ƃ����ɗv�����Ă��邩���m��Ȃ��B���̏ꍇ�A��^�g���b
�N��CO�Q�팸��E�Ζ��̋Z�p�����o���Ȃ��w�ҁE���Ƃ́A�����_�ł͌������ior ������ or �������j�Ɖ�
����Ȃ����낤�B����ł͑�^�g���b�N��CO�Q�팸��E�Ζ��̋Z�p�헪�\�ł��Ȃ��B���̂��߁A���{�Ɗw
�ҁE���Ƃ̊Ԃő�^�g���b�N��CO�Q�팸��E�Ζ��̋Z�p�헪���ł��Ȃ����Ƃ̐ӔC�̉����t���������n�܂��
�ł͂Ȃ����낤���B���̂悤�Ȑ��{�����Ɗw�ҁE���Ƃ̐ӔC����̖��ʂȑ�����h���A�킪���ɂ����Ă����^
�g���b�N��CO�Q�팸��E�Ζ��������ł���悤�ɂ�����@�́A�w�ҁE���Ƃ�DDF�G���W���́uCO�Q�팸�v�Ɓu�E��
���v�̗L�����𗦒��ɔF�߁ADDF�G���W���𓋍ڂ�����^�g���b�N�̊J�����i�𐭕{�ɒ�Ă���ȊO�ɖ����ƍl��
����B
�ȋZ�p�Ă��S�����m�ł������Ƃ��Ă��A���ɔ��\����Ă��鐭�{��CO�Q�팸��E�Ζ��̖ڕW�ɉ������悤�ȑ�^�g
���b�N��CO�Q�팸��E�Ζ��̋Z�p�헪�𑁋}�ɍ��肷��K�v������B���̂��߂ɁA�w�ҁE���Ƃɑ��đ�^�g��
�b�N��CO�Q�팸��E�Ζ�����������Z�p���Ă��邱�Ƃ����ɗv�����Ă��邩���m��Ȃ��B���̏ꍇ�A��^�g���b
�N��CO�Q�팸��E�Ζ��̋Z�p�����o���Ȃ��w�ҁE���Ƃ́A�����_�ł͌������ior ������ or �������j�Ɖ�
����Ȃ����낤�B����ł͑�^�g���b�N��CO�Q�팸��E�Ζ��̋Z�p�헪�\�ł��Ȃ��B���̂��߁A���{�Ɗw
�ҁE���Ƃ̊Ԃő�^�g���b�N��CO�Q�팸��E�Ζ��̋Z�p�헪���ł��Ȃ����Ƃ̐ӔC�̉����t���������n�܂��
�ł͂Ȃ����낤���B���̂悤�Ȑ��{�����Ɗw�ҁE���Ƃ̐ӔC����̖��ʂȑ�����h���A�킪���ɂ����Ă����^
�g���b�N��CO�Q�팸��E�Ζ��������ł���悤�ɂ�����@�́A�w�ҁE���Ƃ�DDF�G���W���́uCO�Q�팸�v�Ɓu�E��
���v�̗L�����𗦒��ɔF�߁ADDF�G���W���𓋍ڂ�����^�g���b�N�̊J�����i�𐭕{�ɒ�Ă���ȊO�ɖ����ƍl��
����B
�@�������Ȃ���A�A�����̊w�ҁE���Ƃ́A��v�c������DDF�G���W���̋Z�p����Ȃɖ������鋦��̂��邪�@���A��
�{������CO�Q�팸��E�Ζ��̗L���Z�p�Ƃ��Ă�DDF�G���W���̕]���E�]�_���Ă��S���s���Ă��Ȃ��悤�Ɏv
����B���̂悤�ɃG���W���w�ҁE���Ƃ�CO�Q�팸��E�Ζ��ɗL����DDF�G���W���̋Z�p��َE���Ȃ���A����
�ł́u�傫�Ȓ���ۑ�v�Ə̂��āuCO�Q�팸�v�Ɓu�E�Ζ��v�̋Z�p�J�����X�I�Ɏ��{���ׂ��K�v���𐺍��ɑi����
����̂ł���B����́A��^�g���b�N��CO�Q�팸��E�Ζ������N�ɂ킽��w�͂ɂ�������炸�����ɒN���J����
�������Ă��Ȃ�����Z�p�Ƃ�������s���Ă���悤�Ɋ�������B��^�g���b�N��CO�Q�팸��E�Ζ�����
��Z�p�Ƃ̔F�����L�߂邱�Ƃɂ���āA����܂ňȏ�̌����\�Z���l�����A�w�ҁE���Ƃ̊e�X���]��������{
���Ă��鎩�猤���e�[�}���p�����Č����ł���悤�ɂ��邱�Ƃ�_������דI�ȍs�ׂɂ�������̂ł���B���ɁuCO
�Q�팸�v�Ɓu�E�Ζ��v�ɗL���ł���DDF�G���W���̋Z�p�����邱�Ƃ𑽂��̐l���m��Ƃ���ɂȂ�A�����̃G���W���w
�ҁE���Ƃ����ݎ��{���̎��Ȃ̌����e�[�}�ւ̒��ړx�̒ቺ��\�Z�팸�̗J���ڂɑ����\�����ے�ł���
���B���̂�Ȏ��ԂɂȂ邱�Ƃ�������邽�߂ɒ��Ԍ��������Ă���悤�Ɏv���邪�A����͕M�҂̕��������ł���
�����B�M�҂��Ⴉ�������A�u�G���W�j�A�͐^����Nj����ׂ��v�Ƒ��h���ׂ���i����Z�p���Ƃ��Ă̗��O����������
�������܂ꂽ�o��������B�������A���݂̓��{�̎w���I����̊w�ҁE���Ƃ́A�^���̒Nj��Ɖ]���G���W�j�A�{��
�̗��O��Y��Ă��܂��Ă���悤�Ŏ₵������ł���B
�{������CO�Q�팸��E�Ζ��̗L���Z�p�Ƃ��Ă�DDF�G���W���̕]���E�]�_���Ă��S���s���Ă��Ȃ��悤�Ɏv
����B���̂悤�ɃG���W���w�ҁE���Ƃ�CO�Q�팸��E�Ζ��ɗL����DDF�G���W���̋Z�p��َE���Ȃ���A����
�ł́u�傫�Ȓ���ۑ�v�Ə̂��āuCO�Q�팸�v�Ɓu�E�Ζ��v�̋Z�p�J�����X�I�Ɏ��{���ׂ��K�v���𐺍��ɑi����
����̂ł���B����́A��^�g���b�N��CO�Q�팸��E�Ζ������N�ɂ킽��w�͂ɂ�������炸�����ɒN���J����
�������Ă��Ȃ�����Z�p�Ƃ�������s���Ă���悤�Ɋ�������B��^�g���b�N��CO�Q�팸��E�Ζ�����
��Z�p�Ƃ̔F�����L�߂邱�Ƃɂ���āA����܂ňȏ�̌����\�Z���l�����A�w�ҁE���Ƃ̊e�X���]��������{
���Ă��鎩�猤���e�[�}���p�����Č����ł���悤�ɂ��邱�Ƃ�_������דI�ȍs�ׂɂ�������̂ł���B���ɁuCO
�Q�팸�v�Ɓu�E�Ζ��v�ɗL���ł���DDF�G���W���̋Z�p�����邱�Ƃ𑽂��̐l���m��Ƃ���ɂȂ�A�����̃G���W���w
�ҁE���Ƃ����ݎ��{���̎��Ȃ̌����e�[�}�ւ̒��ړx�̒ቺ��\�Z�팸�̗J���ڂɑ����\�����ے�ł���
���B���̂�Ȏ��ԂɂȂ邱�Ƃ�������邽�߂ɒ��Ԍ��������Ă���悤�Ɏv���邪�A����͕M�҂̕��������ł���
�����B�M�҂��Ⴉ�������A�u�G���W�j�A�͐^����Nj����ׂ��v�Ƒ��h���ׂ���i����Z�p���Ƃ��Ă̗��O����������
�������܂ꂽ�o��������B�������A���݂̓��{�̎w���I����̊w�ҁE���Ƃ́A�^���̒Nj��Ɖ]���G���W�j�A�{��
�̗��O��Y��Ă��܂��Ă���悤�Ŏ₵������ł���B
�@�킪���̊w�ҁE���Ƃ���v����DDF�G���W���̋Z�p������s�ׂ́ADDF��^�g���b�N�̎��p�����x
��邱�ƂɂȂ�A����̓s�s�ԑ��s�̑�^�g���b�N����ɂ�����CO2�팸�����łȂ��A�E�Ζ��̃G�l���M�[
���p�V�X�e���̍\�z���x�������Ă��܂����Ƃ͖��炩�ł���B���̂悤�ɓ��{�̐��{�E���[�J�E��w�E�����@�ւ�
�w�ҁE���Ƃ�DDF��^�g���b�N�����邱�Ƃɂ���Đ����鑹���́A�}��m��Ȃ����̂�����B���ɂȂ��
DDF��^�g���b�N�̋Z�p���F�m����A���p���ɒ��肳���̂ł��낤���B
��邱�ƂɂȂ�A����̓s�s�ԑ��s�̑�^�g���b�N����ɂ�����CO2�팸�����łȂ��A�E�Ζ��̃G�l���M�[
���p�V�X�e���̍\�z���x�������Ă��܂����Ƃ͖��炩�ł���B���̂悤�ɓ��{�̐��{�E���[�J�E��w�E�����@�ւ�
�w�ҁE���Ƃ�DDF��^�g���b�N�����邱�Ƃɂ���Đ����鑹���́A�}��m��Ȃ����̂�����B���ɂȂ��
DDF��^�g���b�N�̋Z�p���F�m����A���p���ɒ��肳���̂ł��낤���B
�@�Ƃ���ŁA�O�q�̒ʂ茻�݂ł͌����̐��Y�����v�̐L�т����Ȃ��A���ł��ƂȂ�u�Ζ��s�[�N�v�̎���ɓ˓�
���Ă���Ƃ����Ă���B���̂��߁A2010�N2��22�����݁A���E�I�ȕs���̒��ɂ���ɂ�������炸�A�j���[���[�N
���Ǝ�����iNYMEX�j�̌����敨����́A�č��Y�W������WTI�̒��S����3�����́A1�o������80�h���O��ł�
��B����A�C���h�⒆���̔��W�ɂ��Ζ�����̑����␢�E�i�C�������ꍇ�ɂ́A�������Ȃ��������i����
������\���������ƌ��鎯�҂͑����悤���B�e���r������2010�N2��14���́u�����`���̃��V���g���E���|�[�g�v��
�́A�������͌����_��1�o������100�h���ȉ��̌������i�́A����̌i�C���������_�ł�1�o������200�h��
���x�܂ŏ㏸����Ɨ\�z����Ă����B���̂悤�Ȏ���ɂȂ����ꍇ�A�K�v�ʂ̌y���̓��肪����ƂȂ�ɂȂ�
���Ƃ��\���ɍl�����A��^�g���b�N�̉^�s�Ɏx��𗈂����G�l���M�[��@�������鋰����뜜�����B���̂悤��
���Ԃ̔��������O�ɉ������œK�ȕ��@�́A���������ɔR���ɓV�R�K�X�ƌy���p����c�c�e��^�g���b�N�̎�
�p����}��A�L�����y�����Ă������Ƃł���B�����̂ɑސE�������Z�p���̕M�҂́A�����̐Ζ���@�̓����ɂ��
�Đ�����䂪���̃g���b�N�ݕ��A������ł̍����h�~��ACO�Q�팸�ɂ��n�����g���h�~�̖ʂŋ͂��ł��v����
�����Ƃ̎v������A���͂ł͂����Ă�������n���ɑ�^�g���b�N��CO�Q�팸�ƒE�Ζ��ɗL����DDF�G���W���̎��p
�����i���A�s�[���������čs�������Ǝv���Ă���B
���Ă���Ƃ����Ă���B���̂��߁A2010�N2��22�����݁A���E�I�ȕs���̒��ɂ���ɂ�������炸�A�j���[���[�N
���Ǝ�����iNYMEX�j�̌����敨����́A�č��Y�W������WTI�̒��S����3�����́A1�o������80�h���O��ł�
��B����A�C���h�⒆���̔��W�ɂ��Ζ�����̑����␢�E�i�C�������ꍇ�ɂ́A�������Ȃ��������i����
������\���������ƌ��鎯�҂͑����悤���B�e���r������2010�N2��14���́u�����`���̃��V���g���E���|�[�g�v��
�́A�������͌����_��1�o������100�h���ȉ��̌������i�́A����̌i�C���������_�ł�1�o������200�h��
���x�܂ŏ㏸����Ɨ\�z����Ă����B���̂悤�Ȏ���ɂȂ����ꍇ�A�K�v�ʂ̌y���̓��肪����ƂȂ�ɂȂ�
���Ƃ��\���ɍl�����A��^�g���b�N�̉^�s�Ɏx��𗈂����G�l���M�[��@�������鋰����뜜�����B���̂悤��
���Ԃ̔��������O�ɉ������œK�ȕ��@�́A���������ɔR���ɓV�R�K�X�ƌy���p����c�c�e��^�g���b�N�̎�
�p����}��A�L�����y�����Ă������Ƃł���B�����̂ɑސE�������Z�p���̕M�҂́A�����̐Ζ���@�̓����ɂ��
�Đ�����䂪���̃g���b�N�ݕ��A������ł̍����h�~��ACO�Q�팸�ɂ��n�����g���h�~�̖ʂŋ͂��ł��v����
�����Ƃ̎v������A���͂ł͂����Ă�������n���ɑ�^�g���b�N��CO�Q�팸�ƒE�Ζ��ɗL����DDF�G���W���̎��p
�����i���A�s�[���������čs�������Ǝv���Ă���B
�@�Ƃ���ŁA�M�҂̃z�[���y�[�W�ŏڏq���Ă���悤�ɁA�V�R�K�X���獇����DME��GTL�́A�g���b�N�p�R���ɕs�K��
����ɂ�������炸�A�����ɑ��z�̐��{�\�Z���₵�đ�^�g���b�N�̔R���ɂc�l�d��f�s�k�����錤���𐄐i
����Ă���̂ł���B�����āA�y�������G�l���M�[�������R�O�������c�l�d�𐄏�����@�B�w��̋^���ɏڏq��
�Ă���悤�ɁADME�g���b�N�Ɋւ��č��\�I�Ƃ��]��������DME�𐄏�����_�������X�Ɣ��\����Ă��邱�Ƃ́A����
�ł���B���̂悤�Ȋ����ɂ���āA�g���b�N�p�R����DME��GTL���g�p���錤���J���ɑ����̍��Ɨ\�Z�𓊓������
���錻��ɂ��Ă͑��}�ɐ������ׂ��l���Ă��邪�A����͕M�҂̌���������ł��낤���B
����ɂ�������炸�A�����ɑ��z�̐��{�\�Z���₵�đ�^�g���b�N�̔R���ɂc�l�d��f�s�k�����錤���𐄐i
����Ă���̂ł���B�����āA�y�������G�l���M�[�������R�O�������c�l�d�𐄏�����@�B�w��̋^���ɏڏq��
�Ă���悤�ɁADME�g���b�N�Ɋւ��č��\�I�Ƃ��]��������DME�𐄏�����_�������X�Ɣ��\����Ă��邱�Ƃ́A����
�ł���B���̂悤�Ȋ����ɂ���āA�g���b�N�p�R����DME��GTL���g�p���錤���J���ɑ����̍��Ɨ\�Z�𓊓������
���錻��ɂ��Ă͑��}�ɐ������ׂ��l���Ă��邪�A����͕M�҂̌���������ł��낤���B
�P�P�D�ŋ߁A�{���{�͂c�c�e��^�g���b�N��
�@���āA�X�E�F�[�f���̃{���{�E�g���b�N�X�́A2011�N5��31���ɒ������A�������ɑ�^�c�c�e�g���b�N�i�ʐ^�P�Q�Ɓj��
�����i�o�T�Fhttp://www.volvotrucks.com/trucks/global/en-gb/newsmedia/pressreleases/Pages/pressreleases.
aspx?pubid=10743�j�����B���̔��\�ɂ��ƁA�G���W����13���b�g���A�ō��o�͂�440�g�o�i338���v�j�A�ő�g���N��
2300�m���ł���B�V�R�K�X�i�k�m�f�j�̗��p����75���ł���A�G���W���̔M�����́A�X�p�[�N�v���O���V�R�K�X�G���W
���ɔ�ׂāA30�`40�������A�b�n�Q�r�o�ʂ̓f�B�[�[���g���b�N�ɔ�ׂ�10���팸���邱�Ƃ��ł���Ƃ̂��ƁB�܂��A
�M�҂�����܂Ő������Ă����悤�ɁA���s���ɓV�R�K�X�i�k�m�f�j���g���ʂ������ꍇ�ɂ́A�y���݂̂ő��s���邱��
���\�ł���B2011�N�ɂ�100����x���I�����_�A�C�M���X�A�X�E�F�[�f���Ŕ̔�����\��ŁA�W�����琶�Y���J�n��
���Ƃ̂��Ƃ��B����A2�N���x�ŁA���B�̂U�`�W����ŔN��400����x�̔̔����\�肳��Ă���悤���B
�����i�o�T�Fhttp://www.volvotrucks.com/trucks/global/en-gb/newsmedia/pressreleases/Pages/pressreleases.
aspx?pubid=10743�j�����B���̔��\�ɂ��ƁA�G���W����13���b�g���A�ō��o�͂�440�g�o�i338���v�j�A�ő�g���N��
2300�m���ł���B�V�R�K�X�i�k�m�f�j�̗��p����75���ł���A�G���W���̔M�����́A�X�p�[�N�v���O���V�R�K�X�G���W
���ɔ�ׂāA30�`40�������A�b�n�Q�r�o�ʂ̓f�B�[�[���g���b�N�ɔ�ׂ�10���팸���邱�Ƃ��ł���Ƃ̂��ƁB�܂��A
�M�҂�����܂Ő������Ă����悤�ɁA���s���ɓV�R�K�X�i�k�m�f�j���g���ʂ������ꍇ�ɂ́A�y���݂̂ő��s���邱��
���\�ł���B2011�N�ɂ�100����x���I�����_�A�C�M���X�A�X�E�F�[�f���Ŕ̔�����\��ŁA�W�����琶�Y���J�n��
���Ƃ̂��Ƃ��B����A2�N���x�ŁA���B�̂U�`�W����ŔN��400����x�̔̔����\�肳��Ă���悤���B
 |
|
 |
 |
�@���݂ɁA�{���{�E�g���b�N�X���s�̂����^�c�c�e�g���b�N�́A�V�R�K�X�����C�Ǔ��ɕ��˂�������̂c�c�e�G���W��
�ł���B���̃{���{�E�g���b�N�X�̑�^�c�c�e�g���b�N�Ɠ������C�Ǔ����ˎ��̂c�c�e�G���W���𓋍ڂ����g���b�N�̃G��
�W�����\�Ɣr�o�K�X�������ʂɂ��ẮA�M�҂́A2000�N5���̎����ԋZ�p��̍u����Ř_���\�����B����
�_���́A�����ԋZ�p��w�p�u����O���WNo.71-00�i2000�N5���j �u323�@���^�g���b�N�pECOS-DDF�@�V�R
�K�X�G���W���̊J���@�v�i20005001�j �ł���B���̂悤�ɁA�M�҂�10�N�ȏ���O����A�c�c�e�g���b�N�̗L�p����i
���Ă����B�����āA2008�N12��9����DDF�g���b�N�̂��̃y�[�W��lj����A��^�c�c�e�g���b�N�̑������p���̕K�v����
�A�s�[�����Ă������肾�B�������Ȃ���A����܂ŁA���{�̊w�ҁE���Ƃ�g���b�N���[�J����͕M�҂����������
�^�c�c�e�g���b�N��₽����������Ă����̂ł���B
�ł���B���̃{���{�E�g���b�N�X�̑�^�c�c�e�g���b�N�Ɠ������C�Ǔ����ˎ��̂c�c�e�G���W���𓋍ڂ����g���b�N�̃G��
�W�����\�Ɣr�o�K�X�������ʂɂ��ẮA�M�҂́A2000�N5���̎����ԋZ�p��̍u����Ř_���\�����B����
�_���́A�����ԋZ�p��w�p�u����O���WNo.71-00�i2000�N5���j �u323�@���^�g���b�N�pECOS-DDF�@�V�R
�K�X�G���W���̊J���@�v�i20005001�j �ł���B���̂悤�ɁA�M�҂�10�N�ȏ���O����A�c�c�e�g���b�N�̗L�p����i
���Ă����B�����āA2008�N12��9����DDF�g���b�N�̂��̃y�[�W��lj����A��^�c�c�e�g���b�N�̑������p���̕K�v����
�A�s�[�����Ă������肾�B�������Ȃ���A����܂ŁA���{�̊w�ҁE���Ƃ�g���b�N���[�J����͕M�҂����������
�^�c�c�e�g���b�N��₽����������Ă����̂ł���B
�@���̈���ŁA���{�̊w�ҁE���Ƃ́A����܂Ōy���f�B�[�[�������V�R�K�X�G�l���M�[������30���������Q�
��u�X�p�[�N�v���O���V�R�K�X�G���W���𓋍ڂ����g���b�N�v��u�V�R�K�X���獇�������c�l�d��R���Ƃ���c�l�d�g��
�b�N�v��M�S�̐�������Ă����̂ł���B���̂悤�ɁA�u�X�p�[�N�v���O���V�R�K�X�G���W���𓋍ڂ����g���b�N�v��u�V
�R�K�X���獇�������c�l�d��R���Ƃ���c�l�d�g���b�N�v��Well-to-Wheel�̔M�����́A�u�y���f�B�[�[���g���b�N�v��
�uDDF�g���b�N�v����30�����x���M�����̗����������邱�Ƃ͎��m�̎����ł���B�M�҂̃z�[���y�[�W�V�R�K�X
���獇����DME��GTL�́A�g���b�N�p�R���ɕs�K��DDF�^�]�ƃf�B�[�[���^�]�̑I�����\�Ȃc�c�e��^�g���b�N ��
�����̂��Ƃ��ڏq���Ă���B�܂��A�O�q�̃{���{�̃z�[���y�[�W�ɂ����Ă��A�X�p�[�N�v���O���V�R�K�X�G���W����
���ڂ����g���b�N�́A�����V�R�K�X��R���Ƃ��Ă���c�c�e�G���W�����ڂ̃g���b�N����30���ȏ���M��������邱��
���L�ڂ���Ă���B
��u�X�p�[�N�v���O���V�R�K�X�G���W���𓋍ڂ����g���b�N�v��u�V�R�K�X���獇�������c�l�d��R���Ƃ���c�l�d�g��
�b�N�v��M�S�̐�������Ă����̂ł���B���̂悤�ɁA�u�X�p�[�N�v���O���V�R�K�X�G���W���𓋍ڂ����g���b�N�v��u�V
�R�K�X���獇�������c�l�d��R���Ƃ���c�l�d�g���b�N�v��Well-to-Wheel�̔M�����́A�u�y���f�B�[�[���g���b�N�v��
�uDDF�g���b�N�v����30�����x���M�����̗����������邱�Ƃ͎��m�̎����ł���B�M�҂̃z�[���y�[�W�V�R�K�X
���獇����DME��GTL�́A�g���b�N�p�R���ɕs�K��DDF�^�]�ƃf�B�[�[���^�]�̑I�����\�Ȃc�c�e��^�g���b�N ��
�����̂��Ƃ��ڏq���Ă���B�܂��A�O�q�̃{���{�̃z�[���y�[�W�ɂ����Ă��A�X�p�[�N�v���O���V�R�K�X�G���W����
���ڂ����g���b�N�́A�����V�R�K�X��R���Ƃ��Ă���c�c�e�G���W�����ڂ̃g���b�N����30���ȏ���M��������邱��
���L�ڂ���Ă���B
�@���̂悤�ɁA�u�X�p�[�N�v���O���V�R�K�X�G���W���̑�^�g���b�N�v��u�c�l�d�g���b�N�v��Well-to-Wheel�̔M������
�u�y���f�B�[�[���g���b�N�v��uDDF�g���b�N�v����30�����x������Ă���ɂ�������炸�A���{�̈ꕔ�̊w�ҁE���
�Ƃ́A�y�������G�l���M�[�������R�O�������c�l�d�𐄏�����@�B�w��̋^���̃y�[�W�Ő������Ă���悤�ɁA
�u�X�p�[�N�v���O���V�R�K�X�G���W���̑�^�g���b�N�v��u�c�l�d�g���b�N�v�������́u�E�Ζ��v�����������i�I�ȃg��
�b�N�Ƃ��ď^���A����܂Ő���ɐ������Ă����̂ł���B
�u�y���f�B�[�[���g���b�N�v��uDDF�g���b�N�v����30�����x������Ă���ɂ�������炸�A���{�̈ꕔ�̊w�ҁE���
�Ƃ́A�y�������G�l���M�[�������R�O�������c�l�d�𐄏�����@�B�w��̋^���̃y�[�W�Ő������Ă���悤�ɁA
�u�X�p�[�N�v���O���V�R�K�X�G���W���̑�^�g���b�N�v��u�c�l�d�g���b�N�v�������́u�E�Ζ��v�����������i�I�ȃg��
�b�N�Ƃ��ď^���A����܂Ő���ɐ������Ă����̂ł���B
�@�Ƃ��낪�A�{���{�́A2011�N5��31���Ƀg���b�N���[�J�Ƃ��Ă͐��E�Ŏn�߂Ē������A�������̑�^�c�c�e�g���b�N��
�����\���A8�������^�c�c�e�g���b�N�̎s�̂��J�n�����̂��B���̂��Ƃ́ADDF�g���b�N���g�p���ĉݕ��A�����s
�����ꍇ�ɂ́A�u�X�p�[�N�v���O���V�R�K�X�G���W���̑�^�g���b�N�v��u�c�l�d�g���b�N�v���g�p���ĉݕ��A�����s����
�ꍇ�ɔ�r���āA�V�R�K�X�̃G�l���M�[������30�����x���L���ɗ��p�ł��邱�Ƃ��{���{�ɂ���Č��������ꂽ��
�ł���B�����āADDF�g���b�N���Well-to-Wheel�̔M������30�����x�����u�X�p�[�N�v���O���V�R�K�X�G���W����
��^�g���b�N�v��u�c�l�d�g���b�N�v�𐄏����邱�Ƃ́A�u�E�Ζ��v�̊ϓ_��������̍����ł��邱�Ƃ��A�����̐l�ɒm�炵
�߂邱�ƂɂȂ����̂ł���B
�����\���A8�������^�c�c�e�g���b�N�̎s�̂��J�n�����̂��B���̂��Ƃ́ADDF�g���b�N���g�p���ĉݕ��A�����s
�����ꍇ�ɂ́A�u�X�p�[�N�v���O���V�R�K�X�G���W���̑�^�g���b�N�v��u�c�l�d�g���b�N�v���g�p���ĉݕ��A�����s����
�ꍇ�ɔ�r���āA�V�R�K�X�̃G�l���M�[������30�����x���L���ɗ��p�ł��邱�Ƃ��{���{�ɂ���Č��������ꂽ��
�ł���B�����āADDF�g���b�N���Well-to-Wheel�̔M������30�����x�����u�X�p�[�N�v���O���V�R�K�X�G���W����
��^�g���b�N�v��u�c�l�d�g���b�N�v�𐄏����邱�Ƃ́A�u�E�Ζ��v�̊ϓ_��������̍����ł��邱�Ƃ��A�����̐l�ɒm�炵
�߂邱�ƂɂȂ����̂ł���B
�@���̃{���{�̑�^�c�c�e�g���b�N�̔�������m�������{�̃f�B�[�[���W�̊w�ҁE���Ƃ́A���ɂ�����������
�ꂽ�̂ł͂Ȃ����낤���B����ɂ���āA���{�̊w�ҁE���Ƃ́A��^�c�c�e�g���b�N������S�̋���ǂ������
���A�˘f���������Ă���̂ł͂Ȃ����Ɛ��@�����B�u�X�p�[�N�v���O���V�R�K�X�G���W���̑�^�g���b�N�v��u�c�l�d
�g���b�N�v��M�S�ɐ������Ă���w�ҁE���Ƃ́A�{���{���V�R�K�X��R���Ƃ���c�c�e�g���b�N�̎s�̂��J�n��������
�ɂ���āA���N�O�̋��Z��@�̃��[�}���V���b�N�Ȃ�ʁu�{���{ �V���b�N�v�Ƃ��Ăׂ����ȏՌ��������̂Ɛ��@��
���B�ʂ����āA���{�̃f�B�[�[���W�̊w�ҁE���Ƃ�g���b�N���[�J�́A���ꂩ�����Ȃɂc�c�e�g���b�N����
��������j���Ŏ������̂ł��낤���B����Ƃ��A����܂ł̂c�c�e�g���b�N��َE������j���]�����A�ȑO�̂���
�����S�ɖY�ꋎ�������̂悤�ɁA���H��ʊ�ŐϋɓI�ɂc�c�e�g���b�N���^���n�߂�̂ł��낤���B
�ꂽ�̂ł͂Ȃ����낤���B����ɂ���āA���{�̊w�ҁE���Ƃ́A��^�c�c�e�g���b�N������S�̋���ǂ������
���A�˘f���������Ă���̂ł͂Ȃ����Ɛ��@�����B�u�X�p�[�N�v���O���V�R�K�X�G���W���̑�^�g���b�N�v��u�c�l�d
�g���b�N�v��M�S�ɐ������Ă���w�ҁE���Ƃ́A�{���{���V�R�K�X��R���Ƃ���c�c�e�g���b�N�̎s�̂��J�n��������
�ɂ���āA���N�O�̋��Z��@�̃��[�}���V���b�N�Ȃ�ʁu�{���{ �V���b�N�v�Ƃ��Ăׂ����ȏՌ��������̂Ɛ��@��
���B�ʂ����āA���{�̃f�B�[�[���W�̊w�ҁE���Ƃ�g���b�N���[�J�́A���ꂩ�����Ȃɂc�c�e�g���b�N����
��������j���Ŏ������̂ł��낤���B����Ƃ��A����܂ł̂c�c�e�g���b�N��َE������j���]�����A�ȑO�̂���
�����S�ɖY�ꋎ�������̂悤�ɁA���H��ʊ�ŐϋɓI�ɂc�c�e�g���b�N���^���n�߂�̂ł��낤���B
�@�����Ƃ��A����܂œV�R�K�X�G�l���M�[������Q���u�X�p�[�N�v���O���V�R�K�X�G���W���𓋍ڂ����g���b�N�v��
�u�V�R�K�X���獇�������c�l�d��R���Ƃ���c�l�d�g���b�N�v��M�S�̐�������Ă����w�ҁE���ƂƉ]���ǂ��A�펯
�̂���l�B�ł���A�V�R�K�X�G�l���M�[������L���Ɋ��p�ł����^DDF�g���b�N�̎s�̂��J�n���ꂽ���݂�
�́A����܂ł̂悤�Ɂu�X�p�[�N�v���O���V�R�K�X�G���W���̃g���b�N�v��u�c�l�d�g���b�N�v���J�����i��i����w�ҁE
���Ƃ́A���ꂩ��͉������������Ђ�����Ǝp�������čs���̂ł͂Ȃ����ƁA�M�҂ɂ͎v���邪�A�@���Ȃ��̂ł�
�낤���B
�u�V�R�K�X���獇�������c�l�d��R���Ƃ���c�l�d�g���b�N�v��M�S�̐�������Ă����w�ҁE���ƂƉ]���ǂ��A�펯
�̂���l�B�ł���A�V�R�K�X�G�l���M�[������L���Ɋ��p�ł����^DDF�g���b�N�̎s�̂��J�n���ꂽ���݂�
�́A����܂ł̂悤�Ɂu�X�p�[�N�v���O���V�R�K�X�G���W���̃g���b�N�v��u�c�l�d�g���b�N�v���J�����i��i����w�ҁE
���Ƃ́A���ꂩ��͉������������Ђ�����Ǝp�������čs���̂ł͂Ȃ����ƁA�M�҂ɂ͎v���邪�A�@���Ȃ��̂ł�
�낤���B
�@�܂��A�X�E�F�[�f���̃{���{�E�g���b�N�X���������A�������̑�^�c�c�e�g���b�N���������Ƃ���A�̂��牢�ċZ
�p�𐒔q���Ď~�܂Ȃ����{�̊w�ҁE���Ƃ́A�����A��^�c�c�e�g���b�N�̐M��҂ɏ@�|�ւ�����\�����l�����
��B����́A���{�l�ɂ́A�u�o�X�ɏ��x���ȁI�v�ƒ����ɋ����ϔO�ɑ����Ղ��l�������悤�Ɏv���邩��
���B�܂��A�Z�p���e�̗D�������̎v�l�ɂ���č�������Nj����Ĕ��f����̂ł͂Ȃ��A�t�a�������Ĉӌ��̎咣
������悤�Ȋw�ҁE���Ƃ����������݂��邱�Ƃ��A���̌����Ǝv���邽�߂��B
�p�𐒔q���Ď~�܂Ȃ����{�̊w�ҁE���Ƃ́A�����A��^�c�c�e�g���b�N�̐M��҂ɏ@�|�ւ�����\�����l�����
��B����́A���{�l�ɂ́A�u�o�X�ɏ��x���ȁI�v�ƒ����ɋ����ϔO�ɑ����Ղ��l�������悤�Ɏv���邩��
���B�܂��A�Z�p���e�̗D�������̎v�l�ɂ���č�������Nj����Ĕ��f����̂ł͂Ȃ��A�t�a�������Ĉӌ��̎咣
������悤�Ȋw�ҁE���Ƃ����������݂��邱�Ƃ��A���̌����Ǝv���邽�߂��B
�@���̂��߁A�߂������A���{�̃f�B�[�[���W�̊w�ҁE���Ƃ�g���b�N���[�J�́A�u�ϋɓI�ɑ�^�c�c�e�g���b�N����
�^���n�߂�v���ƂɁA�傫���ǂ��\�������肻�����B�����Ƃ��A���̏ꍇ�̌������Ƃ��āA�u�c�c�e�G���W���̗L�p
���͐̂���\���ɏ��m���Ă������A����܂ł͂��̓�������������鎞��ł͂������B�������A�ŋ߂ł͂b�n�Q��
���ƒE�Ζ����d�v�������悤�ɂȂ����̂ŁA�c�c�e��^�g���b�N�̓������\�ɔ����ł��鎞�オ���������v��
���X�����咣���n�߂�悤�Ɏv����̂ł���B������ł��A���ɂ����Ȃ����ꍇ�ɂ́A�킪���̑�^�g���b�N�̕���
�ɂ����āA��^�c�c�e�g���b�N�ɂ��u�b�n�Q�팸�v�Ɓu�E�Ζ��v�����i����邱�ƂɂȂ�A�傢�ɍD�܂������Ƃł͂Ȃ���
�Ǝv���Ă���B
�^���n�߂�v���ƂɁA�傫���ǂ��\�������肻�����B�����Ƃ��A���̏ꍇ�̌������Ƃ��āA�u�c�c�e�G���W���̗L�p
���͐̂���\���ɏ��m���Ă������A����܂ł͂��̓�������������鎞��ł͂������B�������A�ŋ߂ł͂b�n�Q��
���ƒE�Ζ����d�v�������悤�ɂȂ����̂ŁA�c�c�e��^�g���b�N�̓������\�ɔ����ł��鎞�オ���������v��
���X�����咣���n�߂�悤�Ɏv����̂ł���B������ł��A���ɂ����Ȃ����ꍇ�ɂ́A�킪���̑�^�g���b�N�̕���
�ɂ����āA��^�c�c�e�g���b�N�ɂ��u�b�n�Q�팸�v�Ɓu�E�Ζ��v�����i����邱�ƂɂȂ�A�傢�ɍD�܂������Ƃł͂Ȃ���
�Ǝv���Ă���B
�@
�P�Q�D�c�c�e�g���b�N�Z�p�́u�َE������p���v�ɕ��j�ύX���������U�����Ԃ̍ŋ߂̌���
�P�Q�|�P�D2000�N5���ɕM�҂����\�����c�c�e�G���W���𓋍ڂ����c�c�e�g���b�N�Ɋւ���_��
�@�M�҂́A2000�N5���ɊJ�Â̓��{�����ԋZ�p��t�G���ɂ����āA�����U�t�H���[�h�i�ύڗʂS�g���̃g���b�N�j��
���ڂ����z�C�|�[�g���ˎ��c�c�e�G���W���̏o�͐��\�Ɣr�o�K�X�����̌��ʂ��܂Ƃ߂��_���\�����B����
�_���̊T�v���ȉ����\�R�Ɏ����B
���ڂ����z�C�|�[�g���ˎ��c�c�e�G���W���̏o�͐��\�Ɣr�o�K�X�����̌��ʂ��܂Ƃ߂��_���\�����B����
�_���̊T�v���ȉ����\�R�Ɏ����B
| |
|
| ���\���e | �� DDF�g���b�N�i�ύڗʂS�g���j�̊O�ώʐ^
 �� �R������i���M�����j�̔�r�}
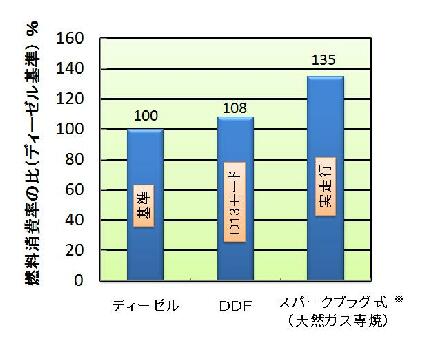 �� �{�_���̌��_ (=�V�R�K�X��ăg���b�N�ɔ�ׁADDF�g���b�N�̗D�ʂȋ@�\�E���\�j
�EDDF���s�ƃf�B�[�[�����s�̐�ւ����\�Ȃ��߁ADDF�g���b�N���f�B�[�[���Ɠ�����
�@�R���[�U��̑��s���������B�i�V�R�K�X�̕⋋������Ȓn��ł́A�y�������̃f�B�[�[
�@�����s���\�j �E�V�R�K�X��ăg���b�N�́A�f�B�[�[���g���b�N����30�����R������������A�������A
�@DDF�g���b�N�̓f�B�[�[���g���b�N����8���̔R����ɗ��܂�B�i��}�Q�Ɓj
�E DDF�g���b�N��CO2�r�o�́A�f�B�[�[���g���b�N����15�����x�̍팸���\
�E DDF�g���b�N��PM�r�o�́A�f�B�[�[���g���b�N��1/3���x�܂ł̍팸���\
�EDDF�g���b�N������R����60���オ�V�R�K�X�i��D13���[�h�������s�H�j
�E DDF�g���b�N�́A��^�g���b�N�̒E�Ζ��ɍœK�ȏ����^�̃g���b�N
|
�@�ȏ�̂悤�ɁA��15�N���̂�2000�N5���ɊJ�Â̓��{�����ԋZ�p��t�G���ɂ����āA�����U�t�H���[�h�ɓ���
�����z�C�|�[�g���ˎ��c�c�e�G���W���𓋍ڂ����̃g���b�N�i�ύڗʂS�g���j�̏o�͐��\�Ɣr�o�K�X�̎������ʂ��܂Ƃ�
���_����M�҂����\�����B����DDF�g���b�N�̘_�����\�̌��ʁA�g���b�N���[�J�̃G���W���W�̐��ƁE�Z�p��
�́A��15�N���x���ȑO����A�y����R�Ď����Ƀp�C���b�g���˂��ēV�R�K�X����R���ɂ��ĉ^�]����c�c�e�G���W��
�𓋍ڂ����c�c�e�g���b�N���ȉ��̇@�`�C�̗D�ꂽ������������E�Ζ��ɍœK�ȏ����^�̃g���b�N�ł���Ƃ̋Z�p��
��Ă���ƍl������B
�����z�C�|�[�g���ˎ��c�c�e�G���W���𓋍ڂ����̃g���b�N�i�ύڗʂS�g���j�̏o�͐��\�Ɣr�o�K�X�̎������ʂ��܂Ƃ�
���_����M�҂����\�����B����DDF�g���b�N�̘_�����\�̌��ʁA�g���b�N���[�J�̃G���W���W�̐��ƁE�Z�p��
�́A��15�N���x���ȑO����A�y����R�Ď����Ƀp�C���b�g���˂��ēV�R�K�X����R���ɂ��ĉ^�]����c�c�e�G���W��
�𓋍ڂ����c�c�e�g���b�N���ȉ��̇@�`�C�̗D�ꂽ������������E�Ζ��ɍœK�ȏ����^�̃g���b�N�ł���Ƃ̋Z�p��
��Ă���ƍl������B
�@ DDF�g���b�N�́A�f�B�[�[���Ɠ����̔R���[�U��̑��s����
�A �V�R�K�X��ăg���b�N�ł̓f�B�[�[���g���b�N����30�����M�����̈������������ADDF�g���b�N�ł̓f�B�[
�[���g���b�N�ɋ߂��M�����ł̉^�s���\
�[���g���b�N�ɋ߂��M�����ł̉^�s���\
�i�V�R�K�X��ăg���b�N�̓f�B�[�[���g���b�N����30�����M��������������؋��ɂ��ẮA�V�R�K�X��Ă�CNG��^�g���b�N�́A
�d�ʎԔR���ɕs�K���̌��׃g���b�N�̃y�[�W�̂P�`�Q���ɏڏq���Ă���B�����̂�����͌䗗�������������B�j
�d�ʎԔR���ɕs�K���̌��׃g���b�N�̃y�[�W�̂P�`�Q���ɏڏq���Ă���B�����̂�����͌䗗�������������B�j
�B DDF�g���b�N��CO2�r�o�́A�f�B�[�[���g���b�N����15�����x�̍팸���\
�C DDF�g���b�N��PM�r�o�́A�f�B�[�[���g���b�N��1/3���x�܂ł̍팸���\
�@�Ƃ���ŁA�ǎ҂̖w�ǂ̐l�B�́A����܂ł��x�X�A�u�G�R�g���b�N�v�Ɖ]�����t�����ɂ��A�܂��A�����E�������Ŗڂɂ�
�����Ƃ����锤���B�����G�R�g���b�N�Ƃ́A�G�R���W�[�ȃg���b�N�Ɖ]���Ӗ��ł���B�����̒n����̊��j���
���Q���������ɗL���ȃg���b�N�ɕt�^����閼�̂ł���B�����A�G�R�g���b�N�Ƃ́A�u�G�R���W�[�ȃg���b�N�v
�̗��̂ł���A�u�R���G�l���M�[�����̗L�����p�i�������M�����ʼn^�s�E���s�\�j�v�Ɓu��C���j��̗}
���i���D�ꂽ�r�o�K�X���\�j�v�̗����A�܂��͕Е����f�B�[�[���g���b�N�����D�ꂽ���\�����������g���b�N
�̂��Ƃł���B�����āA�u�R���G�l���M�[�����̗L�����p�i�������M�����ʼn^�s�E���s�\�j�v�Ɓu��C���j���
�}���i���D�ꂽ�r�o�K�X���\�j�v�̉��ꂩ����̐��\���f�B�[�[���g���b�N�����D�ꂽ���\������g���b�N�ł�
���Ă��A���̕Ј���̐��\���f�B�[�[���g���b�N����������g���b�N�́A�u�G�R���W�[�ȃg���b�N�v�A�����u�G�R�g���b�N�v
�Ƃ͌ĂׂȂ��㕨�ł���B���̏ꍇ�ɂ́A�������́u���׃G�R�g���b�N�v�Ƃ̌ď̂��K�ł͂Ȃ����낤���B
�����Ƃ����锤���B�����G�R�g���b�N�Ƃ́A�G�R���W�[�ȃg���b�N�Ɖ]���Ӗ��ł���B�����̒n����̊��j���
���Q���������ɗL���ȃg���b�N�ɕt�^����閼�̂ł���B�����A�G�R�g���b�N�Ƃ́A�u�G�R���W�[�ȃg���b�N�v
�̗��̂ł���A�u�R���G�l���M�[�����̗L�����p�i�������M�����ʼn^�s�E���s�\�j�v�Ɓu��C���j��̗}
���i���D�ꂽ�r�o�K�X���\�j�v�̗����A�܂��͕Е����f�B�[�[���g���b�N�����D�ꂽ���\�����������g���b�N
�̂��Ƃł���B�����āA�u�R���G�l���M�[�����̗L�����p�i�������M�����ʼn^�s�E���s�\�j�v�Ɓu��C���j���
�}���i���D�ꂽ�r�o�K�X���\�j�v�̉��ꂩ����̐��\���f�B�[�[���g���b�N�����D�ꂽ���\������g���b�N�ł�
���Ă��A���̕Ј���̐��\���f�B�[�[���g���b�N����������g���b�N�́A�u�G�R���W�[�ȃg���b�N�v�A�����u�G�R�g���b�N�v
�Ƃ͌ĂׂȂ��㕨�ł���B���̏ꍇ�ɂ́A�������́u���׃G�R�g���b�N�v�Ƃ̌ď̂��K�ł͂Ȃ����낤���B
�@���Ȃ킿�A�V�R�K�X��ăg���b�N�i���ύڗʂQ�g���ȏ�j�́ANO����PM���f�B�[�[����菭�Ȃ��D�ꂽ�r�o�K
�X���\�������A�f�B�[�[���g���b�N����30���O����M��������邽�߁A�u�G�R�g���b�N�v�Ƃ��Ă͎��i�ł���
���Ƃ��N�̖ڂɂ����炩�Ȃ��Ƃ��B����ɂ�������炸�A�V�R�K�X��ăg���b�N�i���ύڗʂQ�g���ȏ�j�́A1998�N
���ɍ����Ŏs�̂��{�i�I�ɊJ�n���ꂽ1998�N������A�u�G�R�g���b�N�v�ɕ��ނ���A�����^�̃g���b�N�Ƃ��Đ��{�̕�
�����t���Ŕ̔�����Ă������Ƃ��A��R���鎖���ł���B
�X���\�������A�f�B�[�[���g���b�N����30���O����M��������邽�߁A�u�G�R�g���b�N�v�Ƃ��Ă͎��i�ł���
���Ƃ��N�̖ڂɂ����炩�Ȃ��Ƃ��B����ɂ�������炸�A�V�R�K�X��ăg���b�N�i���ύڗʂQ�g���ȏ�j�́A1998�N
���ɍ����Ŏs�̂��{�i�I�ɊJ�n���ꂽ1998�N������A�u�G�R�g���b�N�v�ɕ��ނ���A�����^�̃g���b�N�Ƃ��Đ��{�̕�
�����t���Ŕ̔�����Ă������Ƃ��A��R���鎖���ł���B
�@
�@����A1998�N���ɍ����œV�R�K�X��ăg���b�N�i���ύڗʂQ�g���ȏ�j�̎s�̂��{�i�I�ɊJ�n���ꂽ����
����A�V�R�K�X��ăg���b�N���f�B�[�[���g���b�N����30���O����M�����̗��Ɖ]�������́A�����U����
�ԓ��̃g���b�N���[�J���Г��̑��s�R����œ��R�̂��ƂȂ���m�F�ł����������ł���B�������A�����U��
���ԓ��̃g���b�N���[�J�́A���̎������ЊO��Ƃ��Čł����A�V�R�K�X��ăg���b�N���f�B�[�[���g���b�N��
����m�n���Ƃo�l�i���f�B�[�[�����q���j���Ⴂ���Ƃ𗝗R�ɂ��āu�G�R�g���b�N�v�Ə̂��A�����ɔ̔�������
�Ă����悤���B
����A�V�R�K�X��ăg���b�N���f�B�[�[���g���b�N����30���O����M�����̗��Ɖ]�������́A�����U����
�ԓ��̃g���b�N���[�J���Г��̑��s�R����œ��R�̂��ƂȂ���m�F�ł����������ł���B�������A�����U��
���ԓ��̃g���b�N���[�J�́A���̎������ЊO��Ƃ��Čł����A�V�R�K�X��ăg���b�N���f�B�[�[���g���b�N��
����m�n���Ƃo�l�i���f�B�[�[�����q���j���Ⴂ���Ƃ𗝗R�ɂ��āu�G�R�g���b�N�v�Ə̂��A�����ɔ̔�������
�Ă����悤���B
�@���̂悤�ɁA1998�N���ɍ����œV�R�K�X��ăg���b�N�i���ύڗʂQ�g���ȏ�j�̎s�̂��{�i�I�ɊJ�n���ꂽ������
��A�قƂ�ǂ̓��{�̊w�ҁE���ƁE�Z�p�҂��f�B�[�[���g���b�N����30���O����M�����̗��V�R�K�X��ăg��
�b�N���u�G�R�g���b�N�v�ɕ��ނ��Ă��������́A�ߋ��̕����E�L���E�_��������Έ�ڗđR�ł���B�����āA�قƂ�ǂ�
���{�̊w�ҁE���ƁE�Z�p�҂́A����܂ł̓f�B�[�[���g���b�N����30���O����M�����̗��V�R�K�X��ăg���b
�N������u�G�R�g���b�N�v�Ƃ��������ď̂�^���Ă����̂ł���B�ܘ_�A�w�p�I�ȗ̈�ɂ����Ă��A�V�R�K�X��
�ăg���b�N������u�G�R�g���b�N�v�Ə^���鍼�\�Ƃ�������L���E�_����ϋɓI�ɔ��\���Ă����̂����{�́u�V�R
�K�X����g���b�N�v�̎��Ԃ̂悤�ł���B���̏�����ƁA���{�ɂ��V�R�K�X��ăg���b�N���f�B�[�[���g���b�N
����30���O����M�����̗�鎖���𗝉����Ă��Ȃ��u�n���E�Ԕ����v�Ȋw�ҁE���ƁE�Z�p�҂��A�Ⴕ����
�V�R�K�X��ăg���b�N���u�G�R�g���b�N�v�ł���Ƃ̍��\�I�ȋL���E�_���C�Ŕ��\����u�l�Ƃ��Ă̗ǐS�v��
�����Ȃ��w�ҁE���ƁE�Z�p�҂��啔�����߂Ă���悤�Ɏv����̂ł���B���̏�����ƁA�V�R�K�X��
���Ԃ̕���ł́A���{�ɂ͐^�ʖڂŗL�\���w�ҁE���ƁE�Z�p�҂��F���̂悤�Ɋ����邪�A�@���Ȃ��̂ł��낤
���B
��A�قƂ�ǂ̓��{�̊w�ҁE���ƁE�Z�p�҂��f�B�[�[���g���b�N����30���O����M�����̗��V�R�K�X��ăg��
�b�N���u�G�R�g���b�N�v�ɕ��ނ��Ă��������́A�ߋ��̕����E�L���E�_��������Έ�ڗđR�ł���B�����āA�قƂ�ǂ�
���{�̊w�ҁE���ƁE�Z�p�҂́A����܂ł̓f�B�[�[���g���b�N����30���O����M�����̗��V�R�K�X��ăg���b
�N������u�G�R�g���b�N�v�Ƃ��������ď̂�^���Ă����̂ł���B�ܘ_�A�w�p�I�ȗ̈�ɂ����Ă��A�V�R�K�X��
�ăg���b�N������u�G�R�g���b�N�v�Ə^���鍼�\�Ƃ�������L���E�_����ϋɓI�ɔ��\���Ă����̂����{�́u�V�R
�K�X����g���b�N�v�̎��Ԃ̂悤�ł���B���̏�����ƁA���{�ɂ��V�R�K�X��ăg���b�N���f�B�[�[���g���b�N
����30���O����M�����̗�鎖���𗝉����Ă��Ȃ��u�n���E�Ԕ����v�Ȋw�ҁE���ƁE�Z�p�҂��A�Ⴕ����
�V�R�K�X��ăg���b�N���u�G�R�g���b�N�v�ł���Ƃ̍��\�I�ȋL���E�_���C�Ŕ��\����u�l�Ƃ��Ă̗ǐS�v��
�����Ȃ��w�ҁE���ƁE�Z�p�҂��啔�����߂Ă���悤�Ɏv����̂ł���B���̏�����ƁA�V�R�K�X��
���Ԃ̕���ł́A���{�ɂ͐^�ʖڂŗL�\���w�ҁE���ƁE�Z�p�҂��F���̂悤�Ɋ����邪�A�@���Ȃ��̂ł��낤
���B
�@�@���̂��߁A����܂ł̓V�R�K�X��ăg���b�N�i���ύڗʂQ�g���ȏ�j�Ɋւ�����{�̊w�ҁE���ƁE�Z�p�҂��L
���E�_���E�咣�̔��\�̂قƂ�ǂ��o�L���i���f�^�����j�ȓ��e�ł��������Ƃ́A���R�̌��ʂ̂悤�Ɏv����B���̂�
���ɁA���{�̊w�ҁE���ƁE�Z�p�҂���v�c�����A���N�ɘj���ďo�L�ځi���f�^�����j�A�Ⴕ���͍��\�I�Ɣ��f
������L���E�_���E�咣�\�����������ʁA�f�B�[�[���g���b�N����30���O����M�����̗��V�R�K�X��
�ăg���b�N�i���ύڗʂQ�g���ȏ�j�̔̔��ł̐��{�⏕���̕t�^�ɂ��ŋ��́u���ʌ����v�̐��ꗬ�����Q�O
�N�߂��������Ă��܂������Ƃł���B���̂悤�ȃG�R�g���b�N���i���R�K�X��ăg���b�N�i���ύڗʂQ�g���ȏ�j�ɂQ�O
�N�߂��j���đ��z�̐��{�⏕�����x�������������y��ʏȂ̊����́A�u�I���I�����\�E�U�荞�ߍ��\�v���x���ꂽ
�����V�l�ɕC�G������s�̂悤�Ɏv�����A�@���Ȃ��̂ł��낤���B�����āA���̂悤�Ȑŋ��́u���ʌ����v�́A�[�ł�
�`���킳�ꂽ�����̗��ꂩ�猾�킹�ĖႦ�A�ɂ߂Ďc�O�Ȃ��Ƃł���B
���E�_���E�咣�̔��\�̂قƂ�ǂ��o�L���i���f�^�����j�ȓ��e�ł��������Ƃ́A���R�̌��ʂ̂悤�Ɏv����B���̂�
���ɁA���{�̊w�ҁE���ƁE�Z�p�҂���v�c�����A���N�ɘj���ďo�L�ځi���f�^�����j�A�Ⴕ���͍��\�I�Ɣ��f
������L���E�_���E�咣�\�����������ʁA�f�B�[�[���g���b�N����30���O����M�����̗��V�R�K�X��
�ăg���b�N�i���ύڗʂQ�g���ȏ�j�̔̔��ł̐��{�⏕���̕t�^�ɂ��ŋ��́u���ʌ����v�̐��ꗬ�����Q�O
�N�߂��������Ă��܂������Ƃł���B���̂悤�ȃG�R�g���b�N���i���R�K�X��ăg���b�N�i���ύڗʂQ�g���ȏ�j�ɂQ�O
�N�߂��j���đ��z�̐��{�⏕�����x�������������y��ʏȂ̊����́A�u�I���I�����\�E�U�荞�ߍ��\�v���x���ꂽ
�����V�l�ɕC�G������s�̂悤�Ɏv�����A�@���Ȃ��̂ł��낤���B�����āA���̂悤�Ȑŋ��́u���ʌ����v�́A�[�ł�
�`���킳�ꂽ�����̗��ꂩ�猾�킹�ĖႦ�A�ɂ߂Ďc�O�Ȃ��Ƃł���B
�@���̂悤�ɁA���{�̊w�ҁE���ƁE�Z�p�҂ɂ��V�R�K�X��ăg���b�N�i���ύڗʂQ�g���ȏ�j�Ɋւ����o�L
���i���f�^�����j�ȋL���E�_���E�咣�̔��\�ƁA2000�N5���ɘ_�����\�������M�҂��f�B�[�[���g���b�N�ɋ߂�
�M�����ł̉^�s���\�Ȃc�c�e�g���b�N�̋Z�p�̑��݂��������������E�َE���Ă������ʁA2000�N5�����\
���M�҂̂c�c�e�g���b�N�̘_�����\�̈ȍ~���A�����U�����ԓ��̃g���b�N���[�J�́A���{�̕⏕�����Ă�
�Ă����Ԃ��牽�̔ᔻ���邱�ƂȂ��A�f�B�[�[���g���b�N����30���O����M�����̈����ύڗʂQ�g����
��̓V�R�K�X��ăg���b�N���u�G�R�g���b�N�v�Ƃ���2015�N6�����݂ɓ���܂Œ��X�ƁA�̔��������邱�Ƃ��ł�
�����̂Ɛ���������B
���i���f�^�����j�ȋL���E�_���E�咣�̔��\�ƁA2000�N5���ɘ_�����\�������M�҂��f�B�[�[���g���b�N�ɋ߂�
�M�����ł̉^�s���\�Ȃc�c�e�g���b�N�̋Z�p�̑��݂��������������E�َE���Ă������ʁA2000�N5�����\
���M�҂̂c�c�e�g���b�N�̘_�����\�̈ȍ~���A�����U�����ԓ��̃g���b�N���[�J�́A���{�̕⏕�����Ă�
�Ă����Ԃ��牽�̔ᔻ���邱�ƂȂ��A�f�B�[�[���g���b�N����30���O����M�����̈����ύڗʂQ�g����
��̓V�R�K�X��ăg���b�N���u�G�R�g���b�N�v�Ƃ���2015�N6�����݂ɓ���܂Œ��X�ƁA�̔��������邱�Ƃ��ł�
�����̂Ɛ���������B
�@
�@�Ƃ���ŁAGM��1997�N�ɓd�C�����ԁuEV1�v�Y�������A���́uEV1�v�̌v���2003�N���ɒ��~�����Ⴊ����B��
�̍ۂ́uEV1�v�v�撆�~�̗��R�́A�K�\�����̔��ʂ̌������������Ζ��ƊE�̋��͂Ȉ��͂Ƃ̉\�������Ƃ���
��B���̂悤�Ȃ��Ƃ����Ɏ����ł���A���{�̑�w�E�����@�ւ̊w�ҁE������g���b�N���[�J�����ƁE�Z
�p�҂��f�B�[�[���g���b�N�ɋ߂��M�����ł̉^�s���\�Ȃc�c�e�g���b�N�̋Z�p�̑��݂��������������E�َE
�����̂́A�y���̔��ʂ��������������Ζ��ƊE�i���Ζ��A�����j�����͂��c�c�e�g���b�N�̔r�ˊ����i������
�Ȍ���������^���邱�Ƃɂ�����{�̊w�ҁE���Ƃ��c�c�e�g���b�N�̖����E�َE��O�ꂳ������_�����j
��ϋɓI�ɍs�����\�����l������B�����Ζ��ƊE�i���Ζ��A�����j���c�c�e�g���b�N�̔r�ˊ����ɂ��ẮA
�m����؋��������A�P�Ȃ�M�҂̐����ɉ߂��Ȃ��B
�̍ۂ́uEV1�v�v�撆�~�̗��R�́A�K�\�����̔��ʂ̌������������Ζ��ƊE�̋��͂Ȉ��͂Ƃ̉\�������Ƃ���
��B���̂悤�Ȃ��Ƃ����Ɏ����ł���A���{�̑�w�E�����@�ւ̊w�ҁE������g���b�N���[�J�����ƁE�Z
�p�҂��f�B�[�[���g���b�N�ɋ߂��M�����ł̉^�s���\�Ȃc�c�e�g���b�N�̋Z�p�̑��݂��������������E�َE
�����̂́A�y���̔��ʂ��������������Ζ��ƊE�i���Ζ��A�����j�����͂��c�c�e�g���b�N�̔r�ˊ����i������
�Ȍ���������^���邱�Ƃɂ�����{�̊w�ҁE���Ƃ��c�c�e�g���b�N�̖����E�َE��O�ꂳ������_�����j
��ϋɓI�ɍs�����\�����l������B�����Ζ��ƊE�i���Ζ��A�����j���c�c�e�g���b�N�̔r�ˊ����ɂ��ẮA
�m����؋��������A�P�Ȃ�M�҂̐����ɉ߂��Ȃ��B
�@�����͌����Ă��A���{�̊w�ҁE���ƁE�Z�p�҂́A�f�B�[�[���g���b�N�ɋ߂��M�����ł̉^�s���\�ł���A
���A�E�Ζ��i���E�y���j�ɗL���Ȃc�c�e�g���b�N�i���ύڗʂQ�g���ȏ�j�̐V�Z�p���A�M�҂ɂ��2000�N5��
���c�c�e�g���b�N���_�����\���10�N�ȏ�ɘj��A���S�ɖ����E�َE����������������R�Ƒ��݂Ƃ��Ă���B
�����āA���{�̊w�ҁE���ƁE�Z�p�҂��c�c�e�g���b�N�i���ύڗʂQ�g���ȏ�j�̎��p���̕K�v����F�߂��L
���E�_���E�咣�\���n�߂��̂́A���ŋ��i��2012�`2013�N���j�ɂȂ��Ă���̎��ł���B
���A�E�Ζ��i���E�y���j�ɗL���Ȃc�c�e�g���b�N�i���ύڗʂQ�g���ȏ�j�̐V�Z�p���A�M�҂ɂ��2000�N5��
���c�c�e�g���b�N���_�����\���10�N�ȏ�ɘj��A���S�ɖ����E�َE����������������R�Ƒ��݂Ƃ��Ă���B
�����āA���{�̊w�ҁE���ƁE�Z�p�҂��c�c�e�g���b�N�i���ύڗʂQ�g���ȏ�j�̎��p���̕K�v����F�߂��L
���E�_���E�咣�\���n�߂��̂́A���ŋ��i��2012�`2013�N���j�ɂȂ��Ă���̎��ł���B
�@���݂ɁA�o�ώY�Əȁi�G�l���M�[���j�́A2002�N6���{�s�̃G�l���M�[�����{�@�i�����\�l�N�Z���\�l���@��
�掵�\�ꍆ�j�𐧒肵���B���̑掵���ł́A�u���Ǝ҂́A�G�l���M�[�̌����I�ȗ��p�ɓw�߂�Ӗ���L��
��B�v �Ɩ��L����Ă���B�܂�A�G�l���M�[�����{�@�́A���Ǝ҂ł��邢���U�����ԓ��̃g���b�N���[�J�ɑ��A
�s�̂���g���b�N�ɂ����Ă��G�l���M�[�̌����I�ȗ��p�ɓw�߂�Ӗ��킹�Ă���B�Ƃ��낪�A�����U�����ԓ�
�̃g���b�N���[�J�́A�G�l���M�[�����{�@���{�s���ꂽ2002�N6��14���ȍ~���A���X�ƃf�B�[�[���g���b�N
����30���O����M�����̗��V�R�K�X��ăg���b�N���u�G�R�g���b�N�v�Ə̂��Ďs�̂��������̂ł���B���̂�
�Ƃ́A�����U�����ԓ��̃g���b�N���[�J��2002�N6��14���Ɏ{�s���ꂽ�G�l���M�[�����{�@�Ɉᔽ�������Љ�I
�Ȍo�ϊ����N�ɂ킽���Ď��{���Ă������h�ȏ؋��ƌ��邱�Ƃ��\�ƍl������B
�掵�\�ꍆ�j�𐧒肵���B���̑掵���ł́A�u���Ǝ҂́A�G�l���M�[�̌����I�ȗ��p�ɓw�߂�Ӗ���L��
��B�v �Ɩ��L����Ă���B�܂�A�G�l���M�[�����{�@�́A���Ǝ҂ł��邢���U�����ԓ��̃g���b�N���[�J�ɑ��A
�s�̂���g���b�N�ɂ����Ă��G�l���M�[�̌����I�ȗ��p�ɓw�߂�Ӗ��킹�Ă���B�Ƃ��낪�A�����U�����ԓ�
�̃g���b�N���[�J�́A�G�l���M�[�����{�@���{�s���ꂽ2002�N6��14���ȍ~���A���X�ƃf�B�[�[���g���b�N
����30���O����M�����̗��V�R�K�X��ăg���b�N���u�G�R�g���b�N�v�Ə̂��Ďs�̂��������̂ł���B���̂�
�Ƃ́A�����U�����ԓ��̃g���b�N���[�J��2002�N6��14���Ɏ{�s���ꂽ�G�l���M�[�����{�@�Ɉᔽ�������Љ�I
�Ȍo�ϊ����N�ɂ킽���Ď��{���Ă������h�ȏ؋��ƌ��邱�Ƃ��\�ƍl������B
�@���݂ɁA��L�̕\�S�Ɏ������ʂ�A2000�N5���J�Â̓��{�����ԋZ�p��t�G���Ŕ��\�����M�҂́u�f�B�[�[��
�g���b�N�ɋ߂��M�����ł̉^�s���\�Ȃc�c�e�g���b�N�̋Z�p�v���_���ɂ��A�����U�����ԓ��̃g���b�N���[�J�́A�G
�l���M�[�����{�@�̎{�s���ꂽ2002�N6��14���̎��_�ł́A�V�R�K�X����R���Ƃ���R��i���M�����j�̗ǍD
�Ȃc�c�e�g���b�N�̋Z�p�̑��݂����ɏ��m�E�n�m���Ă������ł���B����ɂ�������炸�A�����U�����ԓ��̃g���b
�N���[�J�́A���̔R��i���M�����j�̗ǍD�ȓV�R�K�X����R���Ƃ���c�c�e�g���b�N�̋Z�p�����ăf�B�[�[
���g���b�N����30���O����M�����̗��V�R�K�X��ăg���b�N�̎s�̂𑱂��Ă������Ƃ́A2002�N6��14��
�ȍ~���p�����ăG�l���M�[�����{�@�̈ᔽ�̊m�M�Ƃƌ��邱�Ƃ��\�ł͂Ȃ����낤���B���͂Ƃ�����A
�����U�����ԓ��̃g���b�N���[�J���\���N�̒����ɂ킽���āA�f�B�[�[���g���b�N�Ɠ����̗D�ꂽ�G�l���M�[������
���s�E�^�s���\�Ȃc�c�e�g���b�N�̋Z�p����Ȃɖ����E�َE���Ă������Ƃ́A�M�҂ɂ͉��Ƃ�����������Ƃł���B
�g���b�N�ɋ߂��M�����ł̉^�s���\�Ȃc�c�e�g���b�N�̋Z�p�v���_���ɂ��A�����U�����ԓ��̃g���b�N���[�J�́A�G
�l���M�[�����{�@�̎{�s���ꂽ2002�N6��14���̎��_�ł́A�V�R�K�X����R���Ƃ���R��i���M�����j�̗ǍD
�Ȃc�c�e�g���b�N�̋Z�p�̑��݂����ɏ��m�E�n�m���Ă������ł���B����ɂ�������炸�A�����U�����ԓ��̃g���b
�N���[�J�́A���̔R��i���M�����j�̗ǍD�ȓV�R�K�X����R���Ƃ���c�c�e�g���b�N�̋Z�p�����ăf�B�[�[
���g���b�N����30���O����M�����̗��V�R�K�X��ăg���b�N�̎s�̂𑱂��Ă������Ƃ́A2002�N6��14��
�ȍ~���p�����ăG�l���M�[�����{�@�̈ᔽ�̊m�M�Ƃƌ��邱�Ƃ��\�ł͂Ȃ����낤���B���͂Ƃ�����A
�����U�����ԓ��̃g���b�N���[�J���\���N�̒����ɂ킽���āA�f�B�[�[���g���b�N�Ɠ����̗D�ꂽ�G�l���M�[������
���s�E�^�s���\�Ȃc�c�e�g���b�N�̋Z�p����Ȃɖ����E�َE���Ă������Ƃ́A�M�҂ɂ͉��Ƃ�����������Ƃł���B
�@�ȏ�̂悤�ɁA�����U�����ԓ��̃g���b�N���[�J�́A�G�l���M�[�����{�@���{�s����āu�G�l���M�[�̌����I��
���p�ɓw�߂�Ӗ��v���ۂ��ꂽ�ł����Ă��A�c�c�e�g���b�N�̋Z�p���E�َE�����i�E��@��p���āA�f�B�[
�[���g���b�N����30���O����M�����̗��i���R���G�l���M�[������Q���j�V�R�K�X��ăg���b�N���g���b�N��
���A������̒E�Ζ��̂��߂̋ɂ߂ėL���Ȏ�i�ł���Ƃ̋��U�̐������J��Ԃ����Ƃɂ��A���N�ɂ킽���Đ�
�{�̕⏕���t���œV�R�K�X��ăg���b�N��̔����邱�Ƃɐ��������̂ł���B���̂��Ƃ́A����܂ł̏�������
�A��R���鎖���ł���B
���p�ɓw�߂�Ӗ��v���ۂ��ꂽ�ł����Ă��A�c�c�e�g���b�N�̋Z�p���E�َE�����i�E��@��p���āA�f�B�[
�[���g���b�N����30���O����M�����̗��i���R���G�l���M�[������Q���j�V�R�K�X��ăg���b�N���g���b�N��
���A������̒E�Ζ��̂��߂̋ɂ߂ėL���Ȏ�i�ł���Ƃ̋��U�̐������J��Ԃ����Ƃɂ��A���N�ɂ킽���Đ�
�{�̕⏕���t���œV�R�K�X��ăg���b�N��̔����邱�Ƃɐ��������̂ł���B���̂��Ƃ́A����܂ł̏�������
�A��R���鎖���ł���B
�@���̂悤�ɁA�G�l���M�[�����{�@�Ɉᔽ�����V�R�K�X��ăg���b�N�̍w���҂ɍ��y��ʏȂ��⏕�������o����
�Ă������Ƃ́A�o�ώY�Əȁi�G�l���M�[���j�ƍ��y��ʏȂ̎{��ɖ���������Ǝv���邪�A���̕M�҂̌����́A���
�Ă���̂ł��낤���B�܂�A�o�ώY�Əȁi�G�l���M�[���j���G�l���M�[�����{�@�i�����\�l�N�Z���\�l��
�@���掵�\�ꍆ�j�ɂ���Ă����U�����ԓ��̃g���b�N���[�J�ɃG�l���M�[�̌����I�ȗ��p�ɓw�߂�Ӗ���
�킹��{������{�����Ă���ɂ����āA���y��ʏȂ��⏕���̌�t�܂ł��ēV�R�K�X��ăg���b�N�̕�
�y�ɂ��R���G�l���M�[������Q���}��{����s���Ă��邱�Ƃ́A�o�ώY�ƏȂƍ��y��ʏȂ��ԋt�̎{
����s���Ă��邱�ƂɂȂ�ƕM�҂ɂ͎v���Ďd�����Ȃ��̂ł���B���̂悤�Ȃ��Ƃ́A���{�̊e�Ȓ��Ԃł͗L��
�Ă͂Ȃ�Ȃ��{��ƍl�����邪�A����͕M�҂����̌���������ł��낤���B
�Ă������Ƃ́A�o�ώY�Əȁi�G�l���M�[���j�ƍ��y��ʏȂ̎{��ɖ���������Ǝv���邪�A���̕M�҂̌����́A���
�Ă���̂ł��낤���B�܂�A�o�ώY�Əȁi�G�l���M�[���j���G�l���M�[�����{�@�i�����\�l�N�Z���\�l��
�@���掵�\�ꍆ�j�ɂ���Ă����U�����ԓ��̃g���b�N���[�J�ɃG�l���M�[�̌����I�ȗ��p�ɓw�߂�Ӗ���
�킹��{������{�����Ă���ɂ����āA���y��ʏȂ��⏕���̌�t�܂ł��ēV�R�K�X��ăg���b�N�̕�
�y�ɂ��R���G�l���M�[������Q���}��{����s���Ă��邱�Ƃ́A�o�ώY�ƏȂƍ��y��ʏȂ��ԋt�̎{
����s���Ă��邱�ƂɂȂ�ƕM�҂ɂ͎v���Ďd�����Ȃ��̂ł���B���̂悤�Ȃ��Ƃ́A���{�̊e�Ȓ��Ԃł͗L��
�Ă͂Ȃ�Ȃ��{��ƍl�����邪�A����͕M�҂����̌���������ł��낤���B
�P�Q�|�Q�D�����ԋZ�p��2015�N5�����Ɂu�����U�����Ԃ̊W�ҁv���c�c�e�g���b�N�𐄏�����L���\
�@���������A�g���b�N�ݕ��A���̕���ɂ����āA�R���G�l���M�[�����̘Q���V�R�K�X��ăg���b�N���u�G�R�g���b
�N�v�ƋU���āH���{�̕⏕�����Ȃ���1998�N�O��ɔ̔����J�n���������U�����Ԃ́A2000�N5���̎��_�ŕM��
�̔��\�����c�c�e�g���b�N�̘_���ɂ�����f�B�[�[���g���b�N�ɋ߂��M�����ł̉^�s���\�Ȃc�c�e�g���b�N�̋Z�p�̑�
�݂��\���ɒm���Ă������ł���B����ɂ�������炷�A����܂ł����U�����Ԃ��f�B�[�[���g���b�N����30���O��
���M�����̈����ύڗ��Q�g���ȏ���V�R�K�X��ăG���W���𓋍ڂ����V�R�K�X�g���b�N�����݁i��2015�N7���̎�
�_�j�܂ʼn��X�Ǝs�̂������Ă������Ƃ́A��R���鎖���ł���B���̂悤�ȏɂ����āA���ʁA�����ԋZ�p��
2015�N5�����iVol.69�AN0.5�A2015�j�Ɍf�ڂ��ꂽ�u�V�R�K�X�����Ԃ̍ŐV�����v�i���ҁF�j�̋L���ł́A��
�R�A�����U�G���W�j�A�����O���@���@�T��@�����uDDF�g���b�N���E�Ζ��ɍœK�ȏ����^�̃g���b�N�v�Ƃ̋���
�̎咣���s�����̂ł���B���̋L���̓��e�ɂ��āA�M�҂̋^��_���ȉ����\�T�ɂ܂Ƃ߂��̂Ō䗗����������
���B
�N�v�ƋU���āH���{�̕⏕�����Ȃ���1998�N�O��ɔ̔����J�n���������U�����Ԃ́A2000�N5���̎��_�ŕM��
�̔��\�����c�c�e�g���b�N�̘_���ɂ�����f�B�[�[���g���b�N�ɋ߂��M�����ł̉^�s���\�Ȃc�c�e�g���b�N�̋Z�p�̑�
�݂��\���ɒm���Ă������ł���B����ɂ�������炷�A����܂ł����U�����Ԃ��f�B�[�[���g���b�N����30���O��
���M�����̈����ύڗ��Q�g���ȏ���V�R�K�X��ăG���W���𓋍ڂ����V�R�K�X�g���b�N�����݁i��2015�N7���̎�
�_�j�܂ʼn��X�Ǝs�̂������Ă������Ƃ́A��R���鎖���ł���B���̂悤�ȏɂ����āA���ʁA�����ԋZ�p��
2015�N5�����iVol.69�AN0.5�A2015�j�Ɍf�ڂ��ꂽ�u�V�R�K�X�����Ԃ̍ŐV�����v�i���ҁF�j�̋L���ł́A��
�R�A�����U�G���W�j�A�����O���@���@�T��@�����uDDF�g���b�N���E�Ζ��ɍœK�ȏ����^�̃g���b�N�v�Ƃ̋���
�̎咣���s�����̂ł���B���̋L���̓��e�ɂ��āA�M�҂̋^��_���ȉ����\�T�ɂ܂Ƃ߂��̂Ō䗗����������
���B
�i���F�����U�G���W�j�A�����O���́A�����U�����ԇ��̓���H����ɂ��邢���U�����Ԃ̐v�E�����F�E�}�ʊǗ�����S��100���q��Ёj
 |
�P�D�_���́u3.2.�@�f���A���t���[�G���G���W���v�̍��ɂ���
�P�|1�D�_���́u3.2�D���v�̃R�s�[�@
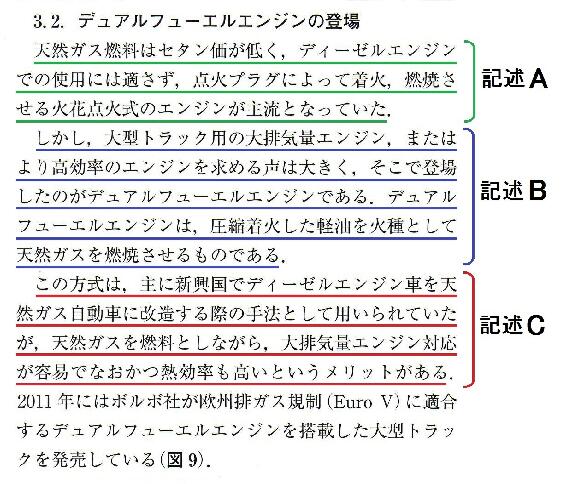 �P�|�Q�|�P�D�_���́u3.2�D���v�́u�L�q�`�v�ɂ��� �E��L�̋L�q�`�ł́A�����U�G���W�j�A�����O���̌� �T�� ���̋L�ړ��e�́A�u�V�R�K�X�R���̓Z�^�������Ⴍ�A�f�B�[�[���G���W���ł̎g �p�ɂ͓K�����A�_�v���O�ɂ���Ē��A�R�Ă�����Ήԓ_�Ύ��̃G���W�����嗬�ƂȂ��Ă����v�Əq�ׂ��Ă���B���̌����́A�f�B�[�[ ���g���b�N����30���O����M�����̗�邱�Ƃ����m�̏�ŁA����܂ʼnΉԓ_�Ύ��̃G���W���𓋍ڂ����V�R�K�X��ăg���b�N�������E �̔����Ă������ʂł���B���̋L�q�`�́u�Ήԓ_�Ύ��G���W���𓋍ڂ����V�R�K�X��ăg���b�N���嗬�v�Ƃ̋L�q�́A�����U�G���W �j�A�����O���̌� �T�� �����f�B�[�[���g���b�N����30���O����M�����̗��G�l���M�[������Q���V�R�K�X��ăg���b�N �g���b�N���u�G�R�g���b�N�I�v�Ƃ̔��펚��ŋU����������܂ł́u���\�I�ȍs�ׁv���B�������������߂̋L�q�Ƃ����邱�Ƃ��\�� �l���������A�@���Ȃ��̂ł��낤���B �E��L�̋L�q�`�̉ӏ��𐳊m�ɋL�ڂ���Ƃ���A���̂悤�ɋL�ڂ���̂��K�ƍl������B�܂�A�u�V�R�K�X�R���̓Z�^�������Ⴍ ���B���̂��߁A�G���W���̔R���ɓV�R�K�X��p����ꍇ�ɂ́A�V�����_���̓V�R�K�X�́A�_�v���O�ɂ��Ήԕ��d��A�V�����_���Ƀp�C ���b�g���˂����y���̎��Ȓ��̉Ή��ɂ��A�V�����_���̓V�R�K�X��R�Ă�����K�v������B����܂œ��{�̓V�R�K�X�G���W���̎� �����Ήԓ_�Ύ��̃G���W���ł��������R�́A�����U�����ԓ��̃g���b�N���[�J���V�����_���Ƀp�C���b�g���˂����y���̎��Ȓ� �̉Ή��ɂ���ēV�R�K�X�̍����C��R�Ă�����c�c�e�G���W���̋Z�p���Ӑ}�I�ɖ����E�َE���Ă������Ƃ������ł���B�v�܂� �́A�u����܂œ��{�̓V�R�K�X�G���W���̎嗬���Ήԓ_�Ύ��̃G���W���ł��������R�́A�����U�����ԓ��̃g���b�N���[�J�� 2000�N5���ɕM�҂̔��\�����c�c�e�g���b�N�̘_���̋L�ړ��e��N��l�Ƃ��ė����ł��Ȃ����������U�����ԓ��̃g���b�N���[�J �́w�G���W���Z�p�҂Ƃ��Ă̔\�͕s���x�������ł���v�ƋL�ڂɂƂ��邱�Ƃ����m�ȋL�q�ƍl���������A�@���Ȃ��̂ł��낤���B �P�|�Q�|�Q�D�_���́u3.2�D���v�́u�L�q�a�v�ɂ��� �E��L�̋L�qB�́u��^�g���b�N�p�̑�r�C�ʃG���W���A�܂��́A����������̃G���W�������߂鐺�͑傫���A�����œo�ꂵ���̂��f���A ���t���[�G���G���W���i���c�c�e�G���W���j�ł���v�Ƃ̂����U�G���W�j�A�����O���̌� �T�� ���̋L�ړ��e�́A�u�R�E���U�v�ɑ���������e�� �M�҂ɂ͎v���Ďd�����Ȃ��B �E���́u��^�g���b�N�p�̑�r�C�ʃG���W���A�܂��́A��荂�����̃G���W�������߂鐺�͑傫���v���u�R�E���U�v�ɑ���������e�Ɛ������闝 �R�́A�ȉ��̓�ł��� ���R �@ �@���������A�V�R�K�X�g���b�N�̂悤�ȐV�^�g���b�N�̊J���ɂ�����g���b�N���[�J�ł̍ŏd�v�̌v�����ڂ̈���A���s�R��̌v���ł���B ���̂��߁A�����U�����ԓ��̃g���b�N���[�J�́A1998�N���ɍ����œV�R�K�X��ăg���b�N�i���ύڗʂQ�g���ȏ�j�̎s�̂��{�i�I�ɊJ�n���� ��������A�V�R�K�X��ăg���b�N���f�B�[�[���g���b�N����30���O����M�����̗�邱�Ƃ��n�m���Ă����ɂ�������炸�A���̔R��s�ǂ� �V�R�K�X��ăg���b�N���u�G�R�g���b�N�v�Ə̂��ĕs���H�Ȕ̔������Ă������Ƃɑ���u�Z�p�҂Ƃ��Ă̗ǐS�̙�Ӂv�������͂������̂ł͂� �����ƍl������B���̏�A�ŋ߂̃C���^�[�l�b�g���̕��y��������ł́A�f�B�[�[���g���b�N����30���O����M�����̗�錇�׃g���b�N �ł��鎖����A�V�R�K�X����R���Ƃ���DDF�g���b�N�ɂ�����D�ꂽ�R��\�i���D�ꂽ�M�����j�̏����A���[�U���m��n�߂����̂Ɛ� �������B���̌��ʁA�����U�����ԓ��̃g���b�N���[�J�́A�~�ޖ����A�V�R�K�X��ăg���b�N�̔R����P�̈ӎv�E���j�Ɍ��y������Ȃ� �ɂȂ��Ă����Ɛ���������B���̂��߁A�����U�����ԓ��̃g���b�N���[�J�́A�ŋ߂ł́A�V�R�K�X��ăg���b�N�̎s�̂𒆎~����K�v ���������Ă����\��������B���̂��߁A�䂪���ł��߂�������DDF�g���b�N�̎��p����}��K�v���̍����Ƃ��āA����܂ł̂����U���� �ԓ��̃g���b�N���[�J����܂ł́u�V�R�K�X��ăg���b�N�ɂ�����R��s�ǂ̏��̉B���v��uDDF�g���b�N�̋Z�p���̉B���v���Ă����� ���U�����ԓ��̃g���b�N���[�J�̍s�ׂ��I���B�����߁A���L�̋L�qB�́u��^�g���b�N�p�̑�r�C�ʃG���W���A�܂��́A��荂�����̃G���W�� �����߂鐺�͑傫���v�Ƃ́u�R�E���U�v�ɑ���������e�ƋL�ڂ���Ă���\�����l������B���̏ꍇ�ɂ��āA���L�̋L�qB�𐳊m�ȓ� �e�ɏ���������Ƃ���ƁA�u�Ήԓ_�Ύ��̓V�R�K�X��ăG���W���𓋍ڂ����V�R�K�X��ăg���b�N���f�B�[�[���g���b�N����30���O����M �����̗�錇�׃g���b�N�ł��邱�Ƃ̉B���v��u�D�ꂽ�R��\�i���D�ꂽ�M�����j��DDF�g���b�N�̋Z�p���̉B���v���Ӎ߂��A����͔M �����̍����V�R�K�X����R���Ƃ���DDF�g���b�N�̑����Ɏ��p�����A������s�̂�����j�ł���v�ƋL�ڂ���̂����m�ł���A�ǐS�I�ł� �Ȃ����ƍl������B ���R �A
�@�o�ώY�Əȁi�G�l���M�[���j��2002�N6���Ɏ{�s�����G�l���M�[�����{�@�i�����\�l�N�Z���\�l���@���掵�\�ꍆ�j�̑掵����
�́A�u���Ǝ҂́A�G�l���M�[�̌����I�ȗ��p�ɓw�߂�Ӗ���L����B�v �Ɩ��L����Ă���B�܂�A�����U�����ԓ��̃g���b�N���[�J�� ���A�s�̂���g���b�N�ɂ����Ă��G�l���M�[�̌����I�ȗ��p�ɓw�߂�Ӗ��킹�Ă���̂ł���B�������A�����U�����ԓ��̃g���b�N�� �[�J�́A�G�l���M�[�����{�@���{�s���ꂽ2002�N6��14���ȍ~���A�f�B�[�[���g���b�N����30���O����M�����̗��V�R�K�X��ăg�� �b�N�C�Ŏs�̂������A����܂Œ��N�ɂ킽��A�G�l���M�[�����{�@�Ɉᔽ�����o�ϊ������s���Ă����ƍl������B�������A�ߔN�A�� �ƃR���v���C�A���X�i��Ƃ̖@�ߏ���j�����������߂��鎞��ɂ������������߁A�u����܂Ńf�B�[�[���g���b�N����30���O����M������ ��錇�׃g���b�N�v�̎s�̂ɂ����Ă͌o�ώY�Əȁi�G�l���M�[���j�������U�����ԓ��̃g���b�N���[�J�ɑ��u�f�B�[�[���g���b�N����30���O ����M�����̗��V�R�K�X��ăg���b�N���s�̂̒��~�v�����߂�v�������X�ɍs��ꂽ�\��������B���̏ꍇ�́A���L�̋L�qB�́u�� �^�g���b�N�p�̑�r�C�ʃG���W���A�܂��́A��荂�����̃G���W�������߂鐺�͑傫���v�Ƃ̋L�ڂ́u���U�v�ł���A������A�u�G�l���M�[���� ��{�@���{�s���ꂽ2002�N6��14���ȍ~���A�f�B�[�[���g���b�N����30���O����M�����̗��V�R�K�X��ăg���b�N���s�̂������A����� �Œ��N�ɂ킽��A�G�l���M�[�����{�@�Ɉᔽ�����o�ϊ������s���Ă������Ƃ��������߂āA����͔M�����̍���DDF�g���b�N��̔����� �\��ł���v�ƋL�ڂ���̂����m�ł͂Ȃ����ƍl������B �E�ȏ�̇@�A�A�̗��R����A��L�̋L�q�a�ɂ��ẮA�u�ߔN�A�V�R�K�X��ăg���b�N�ɂ�����f�B�[�[���g���b�N����30���O����M �����̗��v���I�Ȍ��ׂ����[�U��o�ώY�Əȁi�G�l���M�[���j�ɒm��n�鎞��ɂȂ��Ă��܂������߁A�u���Ǝ҂́A�G�l�� �M�[�̌����I�ȗ��p�ɓw�߂�Ӗ���L����B�v�ƋK�肵���G�l���M�[�����{�@�Ɉᔽ�̊Y�����Ă��鎖�ۂ̘I���E���o�̋� ��������Ď~�ޖ����A�M�����̗D�ꂽ�V�R�K�X����R���Ƃ���f���A���t���[�G���G���W���i���c�c�e�G���W���j�𓋍ڂ����g���b �N�𑁊��Ɏ��p�����A�s�̂���K�v�������Ă����v�Ƃ����|���L�ڂ��邱�Ƃ����m�ł͂Ȃ����ƍl�����邪�A�@���Ȃ��̂ł��낤 ���B����ɂ��āA�o���鎖�Ȃ�A�����U�G���W�j�A�����O���̌� �T�� ���̌�����Ƃ��f���Ă݂������̂ł���B �P�|�Q�|�R�D�_���́u3.2�D���v�́u�L�qC�v�ɂ��� ��L�̋L�qC�́u���̕����i���f���A���t���[�G���G���W�����c�c�e�G���W���j�́A��ɐV�����Ńf�B�[�[���G���W���̎Ԃ�V�R�K�X������ �ɉ�������̎�@�Ƃ��ėp�����Ă����v�̋L�ڂ́A���S�Ɂu�R�E���U�v�Ɛ��������B���̂Ȃ�A�V�R�K�X����R���Ƃ���DDF�G�� �W���̋Z�p�́A�M�҂̒m�����ł͏��Ȃ��Ƃ�30�N�ȏ�̐̂���A�č��A�J�i�_�A���B�̐�i���ɂ����āA�f�B�[�[�������Ԃ� �V�R�K�X�Ԏ����Ԃɉ��������@�Ƃ��Ċ��ɑ��݂��Ă����Z�p�ł���B�������Ȃ���A�����U�G���W�j�A�����O���̌� �T�� �� �́A���L�̋L�qC�ɂ����āA�u�f���A���t���[�G���G���W���i���c�c�e�G���W���j�́A��ɐV�����Ńf�B�[�[���G���W���̎Ԃ�V�R �K�X�����Ԃɉ�������̎�@�Ƃ��ėp�����Ă����v�Ƃ́u�R�E���U�v�̓��e���A�����U�G���W�j�A�����O���̌� �T�� ������ �ʂ������A���X�ƋL�ڂ���Ă���悤�ł���B �E���́u�c�c�e�G���W���́A��ɐV�����Ńf�B�[�[���G���W���̎Ԃ�V�R�K�X�����Ԃɉ�������̎�@�Ƃ��ėp�����Ă����v�Ƃ̋L�q �́A����܂ŕč��A�J�i�_�A���B�̐�i����DDF�G���W���J�����Ă��Ȃ��������߂ɁA�����U�����ԓ��̃g���b�N���[�J�������M������DDF �G���W���̋Z�p���I舂ɂ������Ƃ��Ă����Ƃ̌������ۂ�ǎ҂ɗ^���邽�߂ɁA�����U�G���W�j�A�����O�� �� �T�� �����Ƒ��ɂ��s���� ���L�q�ƍl������B���̂悤�ȝs���L����ǂ܂��ꂽ�����ԋZ�p���4���l�̉���ɂƂ��ẮA�ɂ߂Ė��f�Șb�ł���B�����āA���̝s ���L���������Ƃ������Ƃ́A�����ԋZ�p��2015�N5�����̕ҏW�ψ���̎��ԂƂ��l������B�����̒������ɖ]�܂��Ƃ���ł���B |
�Q�D�_���́u4.2.�@�R�ċZ�p�̉��ǁv�̍��ɂ���
�Q�|1�D�_���́u4.2.�v���̃R�s�[
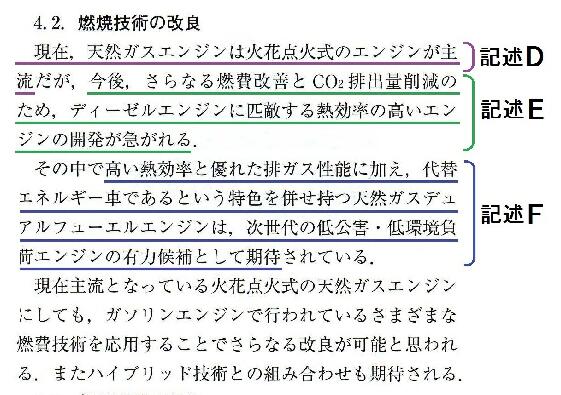 �Q�|�Q�|�P�D�_���̘_���́u4.2.�v�́u�L�qD�v�ɂ��� �E��L�̋L�qD�́u���݁A�V�R�K�X�G���W���͉Ήԓ_�Ύ��̃G���W�����嗬�v�ƂȂ��Ă��܂��Ă��錻�݂̓��{�̏����o���ꂽ����
�́A�����U�����ԓ��̃g���b�N���[�J���A����܂ʼnΉԓ_�Ύ��̓V�R�K�X�G���W���𓋍ڂ����V�R�K�X��ăg���b�N�����������Œ��N�ɂ��
�ċ����Ɏs�̂������Ă������ʂł���B�܂�A�����U�����ԓ��̃g���b�N���[�J�́A����܂łɁu���݂̉䂪���ł́A�f�B�[�[���g���b�N���
��30���O����M�����̗��v���I�Ȍ��ׂ̓V�R�K�X��ăg���b�N���嗬�v�́A�R���G�l���M�[�����i���V�R�K�X�G�l���M�[�j��Q���
�����o�����̂ł���B����́A�f�B�[�[���g���b�N�ɋ߂��M�����ł̉^�s���\�Ȃc�c�e�g���b�N�i���Ⴆ�ΕM�҂�2000�N5���̓��{
�����ԋZ�p��t�G����DDF�g���b�N�̘_�����\�j�̋Z�p�������U�����ԓ��̃g���b�N���[�J�������E�َE���Ă������Ƃ������ł���ƍl��
����B���̂��Ƃ́A�ꗬ��ƂƂ��Ă̎Љ�I�ȐӔC�̕����ł͂Ȃ����ƍl������B
�E���̂悤�ȓV�R�K�X�g���b�N�̕���ɂ�����R���G�l���M�[�����i���V�R�K�X�G�l���M�[�j��Q�������o���������U�����ԓ���
�g���b�N���[�J�ɂƂ��Ă̐ӔC��B���͌ЂƂ���ړI�̂��߁A�����U�G���W�j�A�����O���̌� �T�� ���́A��L�̋L�qD�́u���݁A�V�R�K�X�G
���W���͉Ήԓ_�Ύ��̃G���W�����嗬�v�Ƃ̌���������L�ڂ������̂Ɛ��������B�����āA���̋L�q�̈Ӑ}����Ƃ���́A�����U������
���̃g���b�N���[�J����v�c�����āA����܂Œ��N�ɂ킽���ăf�B�[�[���g���b�N����30���O����M�����̗�邱�Ƃ��B�����A�V�����_����
�p�C���b�g���˂����y���̎��Ȓ��̉Ή��ɂ���ēV�R�K�X�̍����C��R�Ă�����c�c�e�G���W���̋Z�p���Ӑ}�I�ɖ����E�َE���A�M����
�̗��Ήԓ_�Ύ��̃G���W���𓋍ڂ����g���b�N�Ɍ��肵�Ĕ̔����Ă����������B���ʂ����Ƃł͂Ȃ����Ɛ�������邪�A�@���Ȃ��̂ł���
�����B
�Q�|�Q�|�Q�D�_���̘_���́u4.2.�v�́u�L�qE�v�ɂ���
�E�O�q�̕\�S�Ɏ������悤�ɁA2000�N5���J�Â̓��{�����ԋZ�p��t�G���ɂ����āA�M�҂��u�f�B�[�[���g���b�N�ɋ߂��M�����ʼn^�s��
�\�Ȃc�c�e�g���b�N�̋Z�p�v�̘_���\���Ă��邱�Ƃ���A�����U�����ԓ��̃g���b�N���[�J�̐��ƁE�Z�p�҂́A�V�R�K�X����R���Ƃ���
�R��i���M�����j�̗ǍD�Ȃc�c�e�g���b�N�̋Z�p�̑��݂����ɏ��m�E�n�m���Ă��锤�ł���B����ɂ�������炸�A�����U�G���W�j�A�����O��
�� �T�� ���́A��L�̋L�qE�ɂ����āu����A����Ȃ�R����P��CO2�r�o�ʍ팸�̂��߁A�f�B�[�[���G���W���ɕC�G����M�����̍����G
���W���̊J�����}�����B�v�ƋL����Ă���A�f�B�[�[���G���W���ɕC�G����M�����̍����V�R�K�X�G���W���������_�ł͖����Ɂu�s����
�Z�p�v�Ⴕ���́u���J���̋Z�p��ł��邩�̂悤�ɏq�ׂ��Ă���B����́A�����U�G���W�j�A�����O�� �� �T�� �����A���̋L�qE��ڂɂ���
�V�R�K�X�����Ԃ����O�̑啔���̋Z�p�҂ɁA�f�B�[�[���G���W���ɕC�G����M�����̍����V�R�K�X�G���W��������̐V���ɊJ����
�ׂ��u�V�Z�p�v�Ƃ̌�����F����ǎҁi����S���l�̎����ԋZ�p����j�ɗ^���悤�Ƃ����דI�ȋL�ڂ��s���Ă���悤�Ɍ����Ďd����
�Ȃ��B���ɁA���ꂪ�����ł���A�����U�G���W�j�A�����O�� �� �T�� ���́A�u�o�L�ځv�ȋZ�p���������ԋZ�p��2015�N5�����Ɍf�ڂ�
���Ƃ��āA�������ᔻ�����ׂ��Ǝv�����A�@���Ȃ��̂ł��낤���B
�Q�|�Q�|�R�D�_���̘_���́u4.2.�v�́u�L�qF�v�ɂ���
�E��L�̋L�qF�ł́A�u�����M�����ƗD�ꂽ�r�K�X���\�ɉ����A��փG�l���M�[�Ԃł���Ƃ������F�����V�R�K�X�f���A���t���[�G
���G���W���́A������̒���Q�E������׃G���W���̗L�͌��Ƃ��Ċ��ҁv�ƋL�ڂ���Ă���B���̓��e�́A�O�q�̕\�S�Ɏ������悤
�ɁA2000�N5���J�Â̓��{�����ԋZ�p��t�G���ɂ����āA�M�҂��u�f�B�[�[���g���b�N�ɋ߂��M�����ʼn^�s���\�Ȃc�c�e�g���b�N�̋Z
�p�v�̘_���̌��_�v�|���̂��̂ƍl������B���̂悤�ɁA�M�҂���15�N�O�̓��{�����ԋZ�p��2000�N�t�G���Ŕ��\�����uDDF�G���W
���𓋍ڂ���DDF�g���b�N�̘_���v�̌��_���A�����U�G���W�j�A�����O�� �� �T�� ���������ԋZ�p��2015�N5�����ɂ������䎩�g�̈ӌ���
���Ď咣����Ă���悤�ł���B�ʏ�A���̂悤�Ȃ��Ƃ́A���ƁE�Z�p�҂Ƃ��ē��`�E�ϗ��ɔ����邱�ƂƎv�����A�@���Ȃ��̂ł��낤���B��
��ɂ��ẮA���p�����ɁA���{�����ԋZ�p�� �w�p�u����O���WNo.71-00�A�u���^�g���b�N�pECOS-DDF�@�V�R�K�X�G���W���̊J���v
�i20005001�j�A���ҁF�Γc���j�@���@�ƁA���L���ĖႦ�Ȃ��������Ƃ́A�ɂ߂Ďc�O�Ȃ��Ƃł���B
|
�R�D�_���́u4.3.�@�q�������̉��L�v�̍��ɂ���
�R�|1�D�_���́u4.2.�v���̃R�s�[
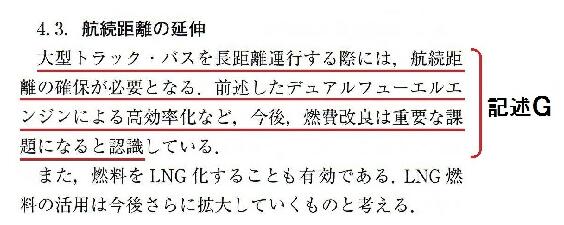 �R�|�Q�|�P�D�_���̘_���́u4.3.�v�́u�L�qG�v�ɂ��� �E�O�q�̕\�S�Ɏ�����2000�N5���ɔ��\�̕M�҂̂c�c�e�g���b�N�̘_���ɖ��L�����悤�ɁA�z�C�|�[�g���ˎ���DDF�G���W���𓋍ڂ���DDF�g
���b�N�́A�uDDF���s�ƃf�B�[�[�����s�̐�ւ����\���f���A���^�]���[�h�̋@�\�v�Ɓu�f�B�[�[���g���b�N�ɋ߂��M�����ʼn^�s���\�v
�Ȃ��Ƃ������ł���B����ɂ��ẮADDF�^�]�ƃf�B�[�[���^�]�̑I�����\�Ȃc�c�e��^�g���b�N �ɂ��ڏq���Ă���B�����̂�����͌�
���������������B�����āA���̂c�c�e�g���b�N�́uDDF���s�ƃf�B�[�[�����s�̐�ւ����\���f���A���^�]���[�h�̋@�\�v�́A���s���ɓV
�R�K�X�^���N�i��CNG�^���N�j����ƂȂ������Ƃ��Z���T�����m�������_�ł́ADDF���s�̓r���ł������I�Ƀf�B�[�[���^�]�ł̑��s�i���f
�B�[�[���g���b�N�Ɠ��l�ɁA�y��������R���Ƃ������s�j�ɐ�ւ����邽�߁A�V�R�K�X�̕⋋������Ȓn��i�V�R�K�X�⋋�X�^���h�̖�
���n��j�ł��ݕ��A�����~���ɍs����B���̂悤�ɁA�M�҂��_�����\�����z�C�|�[�g���ˎ���DDF�g���b�N�́A�f�B�[�[���g���b�N�Ɠ����̔R
���[�U��̑��s�����������Ƃ������̈����B
�E���̂悤�ɁA�z�C�|�[�g���ˎ���DDF�g���b�N�́A�f�B�[�[���g���b�N�Ɠ����̔R���[�U��̑��s�����������Ƃ������ł���ɂ��������
���A�����U�G���W�j�A�����O�� �� �T�� ���́A��L�̋L�qG�ɂ����ẮA�u��^�g���b�N�E�o�X�����^�s����ۂɂ́A�q����
���̊m�ۂ��K�v�ƂȂ�B�O�q�����f���A���t���[�G���G���W���ɂ�鍂�������ȂǁA����A�R����P�͏d�v�ȉۑ�ɂȂ�ƔF
���v�ƈӖ��s���H�ȓ��e���咣���Ă���B���̂��Ƃ���A�����U�G���W�j�A�����O�� �� �T�� ���́A�u�z�C�|�[�g���ˎ���DDF�g���b�N�́A
�f�B�[�[���g���b�N�Ɠ����̔R���[�U��̑��s���������D�ꂽ�����v���E�َE���Ă���悤�Ɍ�����B���̂悤�Ɂu�f�B�[�[���g
���b�N�Ɠ����̍q�������������z�C�|�[�g���ˎ���DDF�g���b�N�D�ꂽ�����v���Ӑ}�I�ɉB�������L���������ԋZ�p��2015�N5�����ɔ��\
���������U�G���W�j�A�����O�� �� �T�� ���́A��S���l�̎����ԋZ�p����Ɂu�o�L�ځv�ȋZ�p�����g�U���Ă��邱�ƂɂȂ�ƍl������B
�E�Ƃ���ŁA���݁A�����U�����Ԃ́A������DDF�G���W���ł���E�F�X�g�|�[�g�Ёi�J�i�_�j�̒������V�R�K�X�G���W���ł���DFCI�����̑�^
DDF�g���b�N���J�����ihttp://blog.livedoor.jp/comoannex/archives/4600007.html�j�̂悤�ł���B�E�F�X�g�|�[�g�Ёi�J�i�_�j��
DFCI�����̑�^DDF�g���b�N�́A�uDDF���s�ƃf�B�[�[�����s�̎����I�Ȑ�ւ��������DDF�g���b�N�v�ł���Ɛ��������B���������āA
�����āA�����U�����Ԃ��uDDF���s�ƃf�B�[�[�����s�̎����I�Ȑ�ւ����s�\�v��DFCI�����̑�^DDF�g���b�N���߂������Ɏs�̂���
�\��Ɛ��������B�B�������A�����U�����Ԃ��J�������E�F�X�g�|�[�g�Ёi�J�i�_�j�̒������V�R�K�X�G���W���ł���DFCI������
DDF�G���W���𓋍ڂ�����^DDF�g���b�N�́ADDF���s�ƃf�B�[�[�����s�̐�ւ����\���f���A���^�]���[�h�̋@�\����
���B���̂��߁ADFCI�����̑�^DDF�g���b�N�́A�ȉ��Ɏ�������̒v���I�Ȍ��ׂ����g���b�N�ł���B
�@ ���s�̑�^�f�B�[�[���g���b�N�ɔ�r���Ē������Z���q������(���V�R�K�X��ăg���b�N�ɋ߂��q�������j
�A �V�R�K�X�����X�^���h�̏��Ȃ��n���̉ݕ��A���ɂ́A�g�p�s�\�ȑ�^�g���b�N
���̂��߁ADFCI������DDF�G���W���𓋍ڂ�����^DDF�g���b�N�́A���݂̑�^�f�B�[�[���g���b�N�Ɠ��l�̓s�s�Ԃ̒������A���ɂ͎g�p
�s�\�ȃg���b�N�ł���Ɛ��������B���������āA�����U�����Ԃ��߂�������DFCI�����̑�^DDF�g���b�N���s�̂���Ӗ��́A�M�҂ɂ͗���
�ł��Ȃ����Ƃł���B
�E�Ȃ��A�����U�����Ԃ�DFCI������DDF�g���b�N��Ƃ��s�̂������̂ł���A���E���^DDF�g���b�N�ɕύX���邱�Ƃ��]�܂����ƍl����
���B���̂Ȃ�A�ʏ�A���E���^�g���b�N�́A�Z���q�������̋@�\�E���\�ł��\���Ɏg�p�\�ȋߋ����̉ݕ��z������̂̂��߂ł���B
���������ADFCI������DDF�G���W���̔R����P�ɂ��͂��ȔR����P�ɂ����DFCI��������^DDF�g���b�N�̍q���������^�f�B�[�[���g
���b�N�Ɠ����ɂ��邱�Ƃ͕s�\�ł���B�������A�Z���q�������̋@�\�E���\�����Ȃ�DFCI�����̑�^DDF�g���b�N�ł́A�V�R�K�X�����X�^
���h�̏��Ȃ��n���ł̉ݕ��A���́A���{�I�ɕs�\�Ȃ��Ƃ����X���X�ł���B���̂����U�����Ԃɂ��߂������ł�DFCI�����̑�^
DDF�g���b�N�̎s�̂�O���ɂ������������ۂ��͕s���ł��邪�A��L�̋L�qG�ɂ�����u��^�g���b�N�E�o�X�����^�s����ۂɂ́A�q��
�����̊m�ۂ��K�v�ƂȂ�B�O�q�����f���A���t���[�G���G���W���ɂ�鍂�������ȂǁA����A�R����P�͏d�v�ȉۑ�ɂȂ�ƔF���v�Ƃ�
�����U�G���W�j�A�����O�� �� �T�� �����L�q�́A�u���̍����v�̂悤�Ɏv�����A�@���Ȃ��̂ł��낤���B
�E���݂ɁADFCI������DDF�G���W���𓋍ڂ�����^DDF�g���b�N�ɂ����Ă��A�M�҂̔�������������DDF�G���W���i�������J2008-51121�j
�̓����Z�p���̗p����A�uDDF���s�ƃf�B�[�[�����s�̐�ւ����\���f���A���^�]���[�h�̋@�\������DDF�g���b�N�v�̎������\
�ƂȂ�A�f�B�[�[���Ɠ����̍q������������������DDF�G���W���𓋍ڂ�����^DDF�g���b�N�������ł��锤�ł���B���������āA�����U��
���Ԃ��f�B�[�[���Ɠ����̍q������������DFCI������DDF�G���W���𓋍ڂ�����^DDF�g���b�N���r���Ďs�̂������̂ł���A��
��������DDF�G���W���i�������J2008-51121�j�̓����Z�p���̗p���ׂ��ƍl���邪�A�@���Ȃ��̂ł��낤���B
�E����Ƃ��A���{���g���b�N���[�J�������ɂ����āA1998�N������20�N�߂��ɘj���āA�f�B�[�[���g���b�N����30���O����M�����̗��V�R
�K�X��ăg���b�N�𐭕{�̕⏕�����Ȃ���u�G�R�g���b�N�v�ƋU�̂��ĕs���H�Ǝv�����̔����s���Ă����^�f�E���^������B���̂悤�ȉߋ�
�̊��܂킵���s�ׂɂ��Ă̏����̔��Ȃ������A�߂������ɂ��܂��A�����U�����Ԃ́ADFCI������DDF�G���W���𓋍ڂ�����^DDF�g���b�N
���A�u��^�f�B�[�[���g���b�N�̒E�Ζ���CO2�팸�ɗL���v�ȏ����^�̓V�R�K�X��^�g���b�N�Ɛ�`���A���{�̕⏕�����ē��{�S����
�S�Ă̓s���{���ɘj��s�s�Ԃ̒������ݕ��A���Ɏg�p�̍����DFCI�����̑�^DDF�g���b�N���s�̂��悤�Ƃ��Ă���̂ł��낤���B����
���A���ꂪ�{���Ɏ��{�����悤�Ȃ��Ƃ�����A�����U�����Ԃ́A���{�⏕���̎|�����Y����Ȃ��u����Ȃ��l�B�̑��A�v�ƌ��邱�Ƃ�
�\�ƍl�����邪�A�@���Ȃ��̂ł��낤���B
|
�P�Q�|�R�D�䂪���ɂ�����V�R�K�X�g���b�N�̌���Ə��������̗\��
�@��w�ɍ˂̃|���R�c���Z�p���̕M�҂��Z�߂��䂪���ɂ�����V�R�K�X�g���b�N�̌���Ə��������̗\�����A��
�����\�U�ɂ܂Ƃ߂��̂ŁA�䗗�������������B
�����\�U�ɂ܂Ƃ߂��̂ŁA�䗗�������������B
�� �V�R�K�X�g���b�N�Ɋւ���ߋ��̌o�܂ƌ���
�E���{�̃g���b�N���[�J�����ƁE�Z�p�҂́A2000�N5�����\���M�҂̃f�B�[�[���g���b�N�ɋ߂��M�����ł̉^�s
���\�Ȃc�c�e�g���b�N�̔��\�_�����E�َE�����B �iDDF�g���b�N�̋Z�p���E�َE�j
�E2000�N5�����\���M�҂̂c�c�e�g���b�N�̘_�����\�̈ȍ~���A�����U�����ԓ��̃g���b�N���[�J�́A�u�G�R�g���b�N�v��
�̂��Đ��{�̕⏕�����Ȃ���A�f�B�[�[���g���b�N����30���O����M�����̈����ύڗʂQ�g���ȏ�̓V�R�K �X��ăg���b�N��2015�N6�����݂ɓ���܂ʼn��X�ƁA�̔��������Ă��� �i�f�B�[�[������30���O����M�����̈����V�R�K�X��ăg���b�N[�ύڗʂQ�g���ȏ�]�̎s�̂��p�����{�j
�E�����U�����ԓ��̃g���b�N���[�J�́A�R��i���M�����j�̗ǍD�Ȃc�c�e�g���b�N�̋Z�p�̑��݂����A�ȍ~���p��
���ăG�l���M�[�����{�@[2002�N6��14���{�s]��10�N�ȏ�̒����ɂ킽���Ĉᔽ���Ȃ���A�f�B�[�[���g���b�N ����30���O����M�����̗��V�R�K�X��ăg���b�N�̎s�̂������Ă����B �i�f�B�[�[�������M�����̗��V�R�K�X��ăg���b�N�̎s�̂ɂ��g���b�N���[�J�̃G�l���M�[�����{�@�ɑ��钷���̈ᔽ�j
�� �V�R�K�X�g���b�N�̏��������̗\��
�E�����ԋZ�p��2015�N5�����iVol.69�AN0.5�A2015�j�́u�V�R�K�X�����Ԃ̍ŐV�����v�i���ҁF�����U�G���W�j�A����
�O���@���@�T��@���j�̋L���ɂ����āA�M�����̗D�ꂽ�V�R�K�X����R���Ƃ���f���A���t���[�G���G���W���i���c �c�e�G���W���j�𓋍ڂ����g���b�N�������Ɏ��p�����A�s�̂���K�v�������Ă����v�Ƃ����|���L�ڂ����B �i�M�����̗D�ꂽ�V�R�K�X����R���Ƃ���c�c�e�G���W���𓋍ڂ���DDF�g���b�N�������Ɏ��p�������Ɨ\���j
|
�@�Ȃ��A�{�z�[���y�[�W�̂P�Q���̑S�̂ɘj��L�ړ��e�ɂ��Ă͑����̐������܂܂�Ă��邽�߁A�ꕔ�ɂ͕M��
�̎�����F�����邩���m��Ȃ��B�����ŁA��w�E�����@�ւ̊w�ҁE���ƁA����сA�����U�����ԓ��̃g���b�N���[�J
�̐��ƁE�Z�p�ҁA�܂��́A�����U�G���W�j�A�����O���@���@�T��@���̏������{�y�[�W���{�����ꂽ�ۂɁA���炩
�Ɍ��ƋC�t���ꂽ�L�q�ɂ��ẮA���̎|���̕M�҂�E���[�����ĂɌ�A�����������������B�������
�����������ʁA������L�q�ł��邱�Ƃ��[���ł����ꍇ�ɂ́A�����ɒ����������ƍl���Ă���B
�̎�����F�����邩���m��Ȃ��B�����ŁA��w�E�����@�ւ̊w�ҁE���ƁA����сA�����U�����ԓ��̃g���b�N���[�J
�̐��ƁE�Z�p�ҁA�܂��́A�����U�G���W�j�A�����O���@���@�T��@���̏������{�y�[�W���{�����ꂽ�ۂɁA���炩
�Ɍ��ƋC�t���ꂽ�L�q�ɂ��ẮA���̎|���̕M�҂�E���[�����ĂɌ�A�����������������B�������
�����������ʁA������L�q�ł��邱�Ƃ��[���ł����ꍇ�ɂ́A�����ɒ����������ƍl���Ă���B
�P�R�D���{�ł����}�Ȏ��p�����]�܂���^�c�c�e�g���b�N
�@
�@�O�q�̂悤�ɁA�{���{�́A�g���b�N���[�J�Ƃ��Ă͐��E�Ŏn�߂đ�^�c�c�e�g���b�N�̎s�̂��J�n�������A�c�O�Ȃ���
�ɁA���̃{���{�̑�^�c�c�e�g���b�N�E�g���N�^�ɓ��ڂ��ꂽ�G���W���́A�����̋Z�p�Ƃ��]����z�C�Ǔ����ˎ��̂c�c
�e�G���W���ł���B����A���̋����̋z�C�Ǔ����ˎ��c�c�e�G���W���̐��\���X�Ɍ���ł���V�����Z�p�����ɐ�
�̒��ɑ��݂��Ă���A���ꂪ�V�R�K�X���V�����_���ɒ��ڕ��˂��钼�����c�c�e�G���W���ł���B���̒������c�c�e�G
���W���́A�z�C�Ǔ����ˎ��c�c�e�G���W���ɔ�ׁA�c�c�e�G���W���ɂƂ��ďd�v�ȗv�f�ł���u�r�o�K�X���\�̌���v
��u�V�R�K�X�i�k�m�f�A�b�m�f�j�̎g�p����������v�ł��邱�Ƃ������ł���B
�ɁA���̃{���{�̑�^�c�c�e�g���b�N�E�g���N�^�ɓ��ڂ��ꂽ�G���W���́A�����̋Z�p�Ƃ��]����z�C�Ǔ����ˎ��̂c�c
�e�G���W���ł���B����A���̋����̋z�C�Ǔ����ˎ��c�c�e�G���W���̐��\���X�Ɍ���ł���V�����Z�p�����ɐ�
�̒��ɑ��݂��Ă���A���ꂪ�V�R�K�X���V�����_���ɒ��ڕ��˂��钼�����c�c�e�G���W���ł���B���̒������c�c�e�G
���W���́A�z�C�Ǔ����ˎ��c�c�e�G���W���ɔ�ׁA�c�c�e�G���W���ɂƂ��ďd�v�ȗv�f�ł���u�r�o�K�X���\�̌���v
��u�V�R�K�X�i�k�m�f�A�b�m�f�j�̎g�p����������v�ł��邱�Ƃ������ł���B
�@���������āA���ɁA���{�ő�^�c�c�e�g���b�N���J�������̂ł���A�{���{�̋z�C�Ǔ����ˎ��̂c�c�e�G
���W���𓋍ڂ�����^�c�c�e�g���b�N�����D�ꂽ���\�����������c�c�e�G���W���𓋍ڂ�����^�c�c�e�g���b
�N�E�g���N�^��Ƃ������Ɏ��p�����ė~�����Ƃ��낾�B�����āA���̑�^�c�c�e�g���b�N�E�g���N�^�ɂ́A�M�҂���
�Ă���������DDF�G���W���i�������J2008-51121�j�̋Z�p���̗p���ė~�������̂��B���̏ꍇ�ɂ́A��^�c�c�e�g���b
�N�E�g���N�^�́A�������c�c�e�G���W���𓋍ڂ��Ă���ɂ�������炸�A�uDDF���s�v�Ɓu�f�B�[�[�����s�v�̐�ւ���
�\���f���A���^�]���[�h�̋@�\�E���ʂɂ��A���{�S���̑S�Ă̓s���{���ɘj��s�s�Ԃ̒������ݕ��A������
�\�ƂȂ�̂ł���B����ɂ���āA�������c�c�e�G���W���𓋍ڂ�����^�c�c�e�g���b�N�E�g���N�^�́A�]���̑�^�f�B�[
�[���g���b�N�Ɠ������������ݕ��A���������ł����悤�ɂȂ�̂ł���B�@���͂Ƃ�����A���p���̂����^�c�c�e�g
���b�N�E�g���N�^�������Ɏ�������邽�߂ɂ́A�킪���̃f�B�[�[���W�̊w�ҁE���Ƃ�g���b�N���[�J�̍���̌�
�������҂����Ƃ���ł���B
���W���𓋍ڂ�����^�c�c�e�g���b�N�����D�ꂽ���\�����������c�c�e�G���W���𓋍ڂ�����^�c�c�e�g���b
�N�E�g���N�^��Ƃ������Ɏ��p�����ė~�����Ƃ��낾�B�����āA���̑�^�c�c�e�g���b�N�E�g���N�^�ɂ́A�M�҂���
�Ă���������DDF�G���W���i�������J2008-51121�j�̋Z�p���̗p���ė~�������̂��B���̏ꍇ�ɂ́A��^�c�c�e�g���b
�N�E�g���N�^�́A�������c�c�e�G���W���𓋍ڂ��Ă���ɂ�������炸�A�uDDF���s�v�Ɓu�f�B�[�[�����s�v�̐�ւ���
�\���f���A���^�]���[�h�̋@�\�E���ʂɂ��A���{�S���̑S�Ă̓s���{���ɘj��s�s�Ԃ̒������ݕ��A������
�\�ƂȂ�̂ł���B����ɂ���āA�������c�c�e�G���W���𓋍ڂ�����^�c�c�e�g���b�N�E�g���N�^�́A�]���̑�^�f�B�[
�[���g���b�N�Ɠ������������ݕ��A���������ł����悤�ɂȂ�̂ł���B�@���͂Ƃ�����A���p���̂����^�c�c�e�g
���b�N�E�g���N�^�������Ɏ�������邽�߂ɂ́A�킪���̃f�B�[�[���W�̊w�ҁE���Ƃ�g���b�N���[�J�̍���̌�
�������҂����Ƃ���ł���B
�@��L�{�����Ō�蓙���������܂�����A���[�����ɂĂ��w�E�������܂��B�܂��A�^��_�A������A�䊴�z���A�ǂ�
�悤�Ȏ����ł����\�ł��B�Ջ��l���ĂɃ��[���������肢��������A�o����͈͂őΉ������Ă��������܂��B
�悤�Ȏ����ł����\�ł��B�Ջ��l���ĂɃ��[���������肢��������A�o����͈͂őΉ������Ă��������܂��B

|

