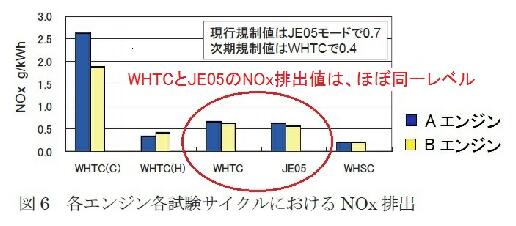�Ջ��l�̃A�C�f�A
�@�@�@�@�@�@�@�g�b�v�y�[�W�ɖ߂��@�@�@�@�T�C�g�}�b�v
�ŏI�X�V���F2015�N4��3��
 |
�P�D����̑�^�g���b�N�̐V���Ȓ�R��̊�ɂ���
�@���݁A�����ԔR��\�]���E���\���x�i�u�����Ԃ̔R��\�̕]���y�ь��\�Ɋւ�����{�v�́v�j�ɂ��A�f�B�[�[
����p�ԓ��̕���17�N�x�R���ƁA�K�\������p�ԓ��̕���22�N�x�R���ɂ́A�e�R���ɑ��ā{�T���A
�{10������с{20����B���������ꂼ��̎Ԏ�ɑ��A���y��ʏȂ͔R�����̌��ʂ�F�肵�Ă���̂ł���B����
�āA���ꂼ��̔R�����̃��x���ɑΉ������R�������D��Ă��邱�Ƃ����y��ʏȂ����ɔF�肵�A���L��4�i
�K�ɋ敪�������\1�̃X�e�b�J�̓\�t��F�߂Ă���B
����p�ԓ��̕���17�N�x�R���ƁA�K�\������p�ԓ��̕���22�N�x�R���ɂ́A�e�R���ɑ��ā{�T���A
�{10������с{20����B���������ꂼ��̎Ԏ�ɑ��A���y��ʏȂ͔R�����̌��ʂ�F�肵�Ă���̂ł���B����
�āA���ꂼ��̔R�����̃��x���ɑΉ������R�������D��Ă��邱�Ƃ����y��ʏȂ����ɔF�肵�A���L��4�i
�K�ɋ敪�������\1�̃X�e�b�J�̓\�t��F�߂Ă���B
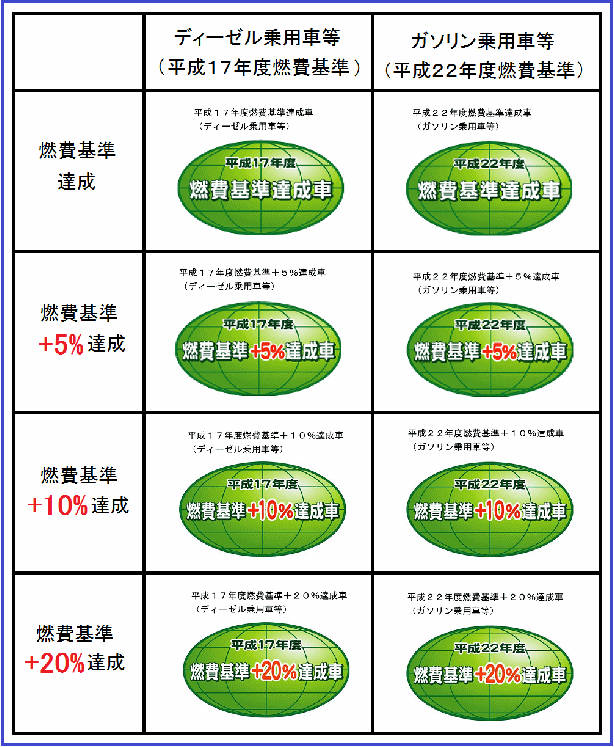
�@�������A��p�Ԃ̔R���Ƃ͈قȂ�A��^�g���b�N�E�g���N�^���̏d�ʎԂɂ��ẮA���y��ʏȂ́A�u2015�N�x�d��
�ԔR���v��B�����Ă��邩�ۂ��̔��f���ł���R�����̃X�e�b�J�̓\�t��F�߂Ă��邾���ł���B�����āA�g���b
�N���[�J���u2015�N�x�d�ʎԔR���v�����{�T�� ��{10���̔R������B��������^�g���b�N�E�g���N�^���s�̂ł�
���Ƃ��Ă��A�����̑�^�g���b�N�E�g���N�^�Ɂ{�T�� ��{10���̔R�����������ł��Ă���|��\���ł���X�e�b�J�́A
�����_�ł͍��y��ʏȂ������ݒ肵�Ă��Ȃ��̂ł���B�܂�A�g���b�N���[�J�́A���Ɂu2015�N�x�d�ʎԔR���v��
����{�T�� ��{10���̔R������B��������^�g���b�N�E�g���N�^���s�̂ł����Ƃ��Ă��A���̃g���b�N��g���N�^�ɂ́A�\
2�Ɏ������u2015�N�x�d�ʎԔR���v�̃X�e�b�J�����\�t�ł��ɂȂ��̂ł���B
�ԔR���v��B�����Ă��邩�ۂ��̔��f���ł���R�����̃X�e�b�J�̓\�t��F�߂Ă��邾���ł���B�����āA�g���b
�N���[�J���u2015�N�x�d�ʎԔR���v�����{�T�� ��{10���̔R������B��������^�g���b�N�E�g���N�^���s�̂ł�
���Ƃ��Ă��A�����̑�^�g���b�N�E�g���N�^�Ɂ{�T�� ��{10���̔R�����������ł��Ă���|��\���ł���X�e�b�J�́A
�����_�ł͍��y��ʏȂ������ݒ肵�Ă��Ȃ��̂ł���B�܂�A�g���b�N���[�J�́A���Ɂu2015�N�x�d�ʎԔR���v��
����{�T�� ��{10���̔R������B��������^�g���b�N�E�g���N�^���s�̂ł����Ƃ��Ă��A���̃g���b�N��g���N�^�ɂ́A�\
2�Ɏ������u2015�N�x�d�ʎԔR���v�̃X�e�b�J�����\�t�ł��ɂȂ��̂ł���B
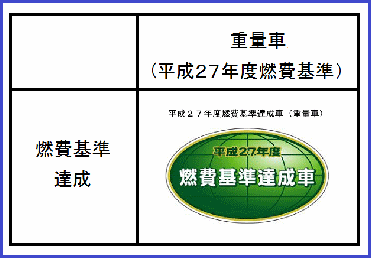
�@���̂悤�ɁA���݂̎��_�ł́A�g���b�N���[�J���Ӑg�̔R����P�̋Z�p�J�����s���A����2015�N�x�i����27�N�x�j�d
�ʎԔR���ɑ��A�{�T�� ��A�X�Ɂ{10����B�������g���b�N�E�g���N�^���s�̂ł��������Ƃ��Ă��A���̃g���b�N�E�g���N
�^�̔R�����𐳂����]���������Ƃ��ؖ�����X�e�b�J��\�t���邱�Ƃ�����ł͂ł��Ȃ��̂��B���̂��߁A���̃g���b
�N�E�g���N�^�́u�R�����v�ƁuCO2�팸�v���g���b�N���[�J�����[�U�ɃA�s�[�����Ă��A�]������̒P�Ȃ��`����̂悤��
���Ȃ���A�g���b�N���[�U�ɂ��̐^�ӂ��`����ƍl������B���̂��߁A�����_�ł́A2015�N�x�d�ʎԔR����
���ā{�T�� or �{10����B�������g���b�N�E�g���N�^���J�����Ă��A�R�X�g�A�b�v�����������ł���B���̂悤�ɁA2015�N�x
�d�ʎԔR��������R��̑�^�g���b�N�E�g���N�^���J���ł����Ƃ��Ă��A���̔̔��ɂ����ẮA2015�N�x�d�ʎ�
�R������̔R�����̊�������ڗđR�Ńg���b�N���[�U�ɗ������ĖႦ���`���ł��Ȃ��̂ł���B�����āA����
2015�N�x�d�ʎԔR������T���̔R����������������^�g���b�N���s�̂ł����Ƃ��Ă��A���̑�^�g���b�N��2015
�N�x�d�ʎԔR���ɓK���̑�^�g���b�N�g���b�N�Ɠ����̐ŋ��̗D��������Ȃ��̂�����ł���B���̂悤�Ȃ�
�Ƃ���A����̕s�\���ȏd�ʎԂ̔R���̐��x�ɂ����ẮA�����̃R�X�g�A�b�v���Ă��Ă��A2015�N�x�d�ʎ�
�R���ɑ��ā{�T�� ��{10����B�������g���b�N�E�g���N�^�J�������͂ɐ��i���悤�Ƃ���g���b�N���[�J�́A�o����
�Ȃ��\�����ɂ߂č����B�Ȃ��Ȃ�A2015�N�x�d�ʎԔR���ɑ��ā{�T�� ��{10���̔R���������������g���b
�N�E�g���N�^�́A�����Ƃ����i�̏㏸�����߁A�擾�œ��̐Ő��̗D���������ꍇ�ɂ̓g���b�N���[�U�����悵�čw
�����Ă����ۏႪ�������߂��B
�ʎԔR���ɑ��A�{�T�� ��A�X�Ɂ{10����B�������g���b�N�E�g���N�^���s�̂ł��������Ƃ��Ă��A���̃g���b�N�E�g���N
�^�̔R�����𐳂����]���������Ƃ��ؖ�����X�e�b�J��\�t���邱�Ƃ�����ł͂ł��Ȃ��̂��B���̂��߁A���̃g���b
�N�E�g���N�^�́u�R�����v�ƁuCO2�팸�v���g���b�N���[�J�����[�U�ɃA�s�[�����Ă��A�]������̒P�Ȃ��`����̂悤��
���Ȃ���A�g���b�N���[�U�ɂ��̐^�ӂ��`����ƍl������B���̂��߁A�����_�ł́A2015�N�x�d�ʎԔR����
���ā{�T�� or �{10����B�������g���b�N�E�g���N�^���J�����Ă��A�R�X�g�A�b�v�����������ł���B���̂悤�ɁA2015�N�x
�d�ʎԔR��������R��̑�^�g���b�N�E�g���N�^���J���ł����Ƃ��Ă��A���̔̔��ɂ����ẮA2015�N�x�d�ʎ�
�R������̔R�����̊�������ڗđR�Ńg���b�N���[�U�ɗ������ĖႦ���`���ł��Ȃ��̂ł���B�����āA����
2015�N�x�d�ʎԔR������T���̔R����������������^�g���b�N���s�̂ł����Ƃ��Ă��A���̑�^�g���b�N��2015
�N�x�d�ʎԔR���ɓK���̑�^�g���b�N�g���b�N�Ɠ����̐ŋ��̗D��������Ȃ��̂�����ł���B���̂悤�Ȃ�
�Ƃ���A����̕s�\���ȏd�ʎԂ̔R���̐��x�ɂ����ẮA�����̃R�X�g�A�b�v���Ă��Ă��A2015�N�x�d�ʎ�
�R���ɑ��ā{�T�� ��{10����B�������g���b�N�E�g���N�^�J�������͂ɐ��i���悤�Ƃ���g���b�N���[�J�́A�o����
�Ȃ��\�����ɂ߂č����B�Ȃ��Ȃ�A2015�N�x�d�ʎԔR���ɑ��ā{�T�� ��{10���̔R���������������g���b
�N�E�g���N�^�́A�����Ƃ����i�̏㏸�����߁A�擾�œ��̐Ő��̗D���������ꍇ�ɂ̓g���b�N���[�U�����悵�čw
�����Ă����ۏႪ�������߂��B
�@���̂悤�ɁA��^�g���b�N�E�g���N�^�ł�2015�N�x�d�ʎԔR��������R��̊�������ɐݒ肳��Ă��Ȃ���
�́A2015�N�x�d�ʎԔR���́{�T����+10���̔R����オ����ł͋Z�p�I�ɍ���ƍl���鍑�y��ʏȂ̌���F
��������\�����l������B�����͌����Ă��A���� 2015�N�x�i����27�N�x�j�d�ʎԔR���́A�{�s��A���ɂT�N��
��̍Ό����o�߂��Ă���̂ł���B���̂��߁A2015�N�x�i����27�N�x�j�d�ʎԔR���ɓK�����������Ԃ��������s
�̂����悤�ɂȂ�A2015�N�x�i����27�N�x�j�d�ʎԔR���������Ԃ̒�R���Ƃ��Ă̖�ڂ������I�ɏI����
���邱�Ƃ͎����ł���A���݂ł͊��ɒ����̗l����悵�Ă��܂��Ă����Ƃ͊ԈႢ�Ȃ����낤�B
�́A2015�N�x�d�ʎԔR���́{�T����+10���̔R����オ����ł͋Z�p�I�ɍ���ƍl���鍑�y��ʏȂ̌���F
��������\�����l������B�����͌����Ă��A���� 2015�N�x�i����27�N�x�j�d�ʎԔR���́A�{�s��A���ɂT�N��
��̍Ό����o�߂��Ă���̂ł���B���̂��߁A2015�N�x�i����27�N�x�j�d�ʎԔR���ɓK�����������Ԃ��������s
�̂����悤�ɂȂ�A2015�N�x�i����27�N�x�j�d�ʎԔR���������Ԃ̒�R���Ƃ��Ă̖�ڂ������I�ɏI����
���邱�Ƃ͎����ł���A���݂ł͊��ɒ����̗l����悵�Ă��܂��Ă����Ƃ͊ԈႢ�Ȃ����낤�B
�@�]���A���y��ʏȂ́A�f�B�[�[����p�ԓ��̕���17�N�x�R���ƁA�K�\������p�ԓ��̕���22�N�x�R����
���ẮA���ꂼ��̊�ɑ��ā{�T���A�{10������с{�Q�O���̔R������F�肵����R����ݒ肵�Ă���
�̂ł���B�������A�d�ʎԁi����^�g���b�N�E�g���N�^���j��2015�N�x�i����27�N�x�j�d�ʎԔR���ɑ��ā{�T���A�{
10������с{20���̔R������B��������^�g���b�N�E�g���N�^���R��g���b�N�E�g���N�^�ƔF�肷���R�����A��
�y��ʏȂ͖����ɐݒ肵�Ă��Ȃ��̂ł���B����̂悤�ɁA���{���d�ʎԂ̒�R��̊�𑁋}�ɐݒ肵�Ȃ���
��������p����������A�u�l�͈Ղ��ɗ����v�Ƃ̌��̒ʂ�A�g���b�N���[�J�͑�^�g���b�N�̔R�����̌����J����
�w�͂�ӂ�\����������̂ƍl������B
���ẮA���ꂼ��̊�ɑ��ā{�T���A�{10������с{�Q�O���̔R������F�肵����R����ݒ肵�Ă���
�̂ł���B�������A�d�ʎԁi����^�g���b�N�E�g���N�^���j��2015�N�x�i����27�N�x�j�d�ʎԔR���ɑ��ā{�T���A�{
10������с{20���̔R������B��������^�g���b�N�E�g���N�^���R��g���b�N�E�g���N�^�ƔF�肷���R�����A��
�y��ʏȂ͖����ɐݒ肵�Ă��Ȃ��̂ł���B����̂悤�ɁA���{���d�ʎԂ̒�R��̊�𑁋}�ɐݒ肵�Ȃ���
��������p����������A�u�l�͈Ղ��ɗ����v�Ƃ̌��̒ʂ�A�g���b�N���[�J�͑�^�g���b�N�̔R�����̌����J����
�w�͂�ӂ�\����������̂ƍl������B
�@���̌����Ŕj���邽�߁A�M�҂��悸��Ă��������Ƃ́A���}�ɑ�^�g���b�N�̒�R����Ԃ̐V���ȔR���Ƃ�
�ẮA�Ⴆ�Έȉ��̕\�R�Ɏ������x�����K�ƍl���Ă���B���̕\�R�̂悤�ȐV���ȔR���̓������A�R����P�̒�
�x�ɉ����Đŋ���D�����鐧�x�����ׂ��ł͂Ȃ����ƍl���Ă���B����ɂ���āA�g���b�N���[�J�����������Ē�R
��̃g���b�N���J�����邱�ƂɂȂ邱�Ƃ͊m���ł���A�킪���̑�^�g���b�N�̒�R������i�������̂ƍl�����
��B
�ẮA�Ⴆ�Έȉ��̕\�R�Ɏ������x�����K�ƍl���Ă���B���̕\�R�̂悤�ȐV���ȔR���̓������A�R����P�̒�
�x�ɉ����Đŋ���D�����鐧�x�����ׂ��ł͂Ȃ����ƍl���Ă���B����ɂ���āA�g���b�N���[�J�����������Ē�R
��̃g���b�N���J�����邱�ƂɂȂ邱�Ƃ͊m���ł���A�킪���̑�^�g���b�N�̒�R������i�������̂ƍl�����
��B
| |
|
| |
|
| |
|
�@�ȏ�A��^�g���b�N�ɂ�����R��K���̗��z�I�ȁu�݂�ׂ��p�v���q�ׂ����A�킪���ɂ������^�g���b�N�̔R��
�̍����́A��p�Ԃɔ�ׂđ啝�ɒx��Ă���̂�����̂悤���B����́A�ȉ��̕\�S�Ɏ������悤�ɁA��p�ԊW��
2015�N�x��p�����ԔR������������2020�N�x��p�����ԔR����2011�N�ɑ��X�ƒ���Ă���
���A��^�g���b�N�W��2015�N�x�d�ʎԔR����2013�N�̎��_�ł������ɒ���Ă��Ȃ����Ƃ́A�����
�����������B���̂悤�ɁA��^�g���b�N��2015�N�x�d�ʎԔR���̋����\�肪�����ɒ���Ă��Ȃ������́A��
�{�̎����ԃ��[�J�i���g���b�N���[�J�j�⌤���@�ւ��A�����_�ő�^�g���b�N�̔R�����̋Z�p���J����l���Ă��Ȃ��Ǝ�
�����Ă��邽�߂Ɛ��������B
�̍����́A��p�Ԃɔ�ׂđ啝�ɒx��Ă���̂�����̂悤���B����́A�ȉ��̕\�S�Ɏ������悤�ɁA��p�ԊW��
2015�N�x��p�����ԔR������������2020�N�x��p�����ԔR����2011�N�ɑ��X�ƒ���Ă���
���A��^�g���b�N�W��2015�N�x�d�ʎԔR����2013�N�̎��_�ł������ɒ���Ă��Ȃ����Ƃ́A�����
�����������B���̂悤�ɁA��^�g���b�N��2015�N�x�d�ʎԔR���̋����\�肪�����ɒ���Ă��Ȃ������́A��
�{�̎����ԃ��[�J�i���g���b�N���[�J�j�⌤���@�ւ��A�����_�ő�^�g���b�N�̔R�����̋Z�p���J����l���Ă��Ȃ��Ǝ�
�����Ă��邽�߂Ɛ��������B
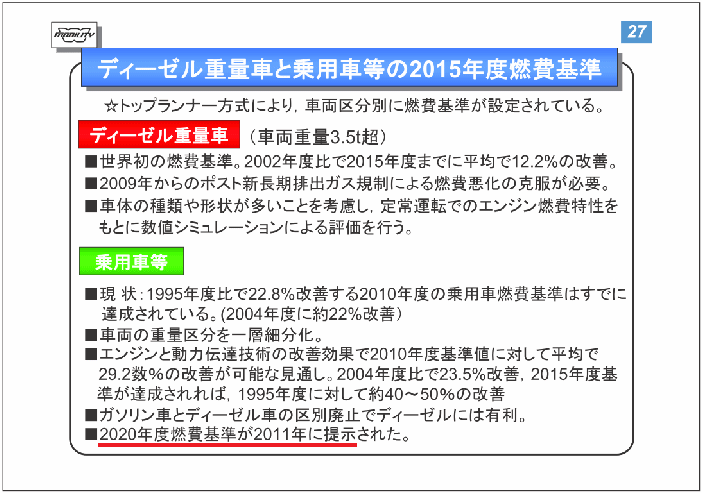
�@�ʂ����āA���{�̎����ԃ��[�J�i���g���b�N���[�J�j�⌤���@�ւ��咣���Ă���悤�ɁA�����_�ő�^�g���b�N�̔R���
��̋Z�p�I�Ȍ��ʂ����{���ɊF���ł���̂��낤���B����ɂ��ẮA�M�҂͑傢�ɋ^��Ɏv���Ă���B�Ȃ��Ȃ�A
�C���x�~�G���W���ɂ���^�g���b�N�̒�R���A�ȉ��̍��ɂɏڏq���Ă���悤�ɁA�C���x�~�G���W���i�������J
2005-54771�j�̋Z�p�����p�����A���̋Z�p���^�g���b�N�ɍ̗p�����ꍇ�ɂ́A��^�g���b�N�̏d�ʎԃ��[�h�R����T�`
�P�O�������シ�邱�Ƃ��\�ƍl�����邽�߂��B
��̋Z�p�I�Ȍ��ʂ����{���ɊF���ł���̂��낤���B����ɂ��ẮA�M�҂͑傢�ɋ^��Ɏv���Ă���B�Ȃ��Ȃ�A
�C���x�~�G���W���ɂ���^�g���b�N�̒�R���A�ȉ��̍��ɂɏڏq���Ă���悤�ɁA�C���x�~�G���W���i�������J
2005-54771�j�̋Z�p�����p�����A���̋Z�p���^�g���b�N�ɍ̗p�����ꍇ�ɂ́A��^�g���b�N�̏d�ʎԃ��[�h�R����T�`
�P�O�������シ�邱�Ƃ��\�ƍl�����邽�߂��B
�Q�D����̑�^�g���b�N�̐V���Ȓ�NO���̊�ɂ���
����̔r�o�K�X�K���̋����ɂ��āA2010�N��7��28���ɒ������R�c�����Ȃɑ�\�����\���s��ꂽ�B��
�̑�\�����\�ɂ��ƁAGVW7.5�g�������̑�^�g���b�N�E�o�X�̂m�n���K���̋����́A�ȉ��̕\�T�Ɏ������ʂ�A������
�m�n���K���l�@���@0.4 g/kWh�@�ł���A2016�N�Ɏ��{���\�肳��Ă���Ƃ̂��Ƃł����B
�̑�\�����\�ɂ��ƁAGVW7.5�g�������̑�^�g���b�N�E�o�X�̂m�n���K���̋����́A�ȉ��̕\�T�Ɏ������ʂ�A������
�m�n���K���l�@���@0.4 g/kWh�@�ł���A2016�N�Ɏ��{���\�肳��Ă���Ƃ̂��Ƃł����B
| |
|
|
| |
|
|
�@���������̂m�n���K���l�i2016�N�̎��{�\��j�̔r�o�K�X�����ł́A�ȉ��Ɏ����������@�̕ύX���s����Ƃ̂���
�ł���B
�ł���B
�@ �Z�p�J���R�X�g�̌y�����Ɏ����邽�߁A���s�̔r�o�K�X�����T�C�N���iJE05 ���[�h�j���A�䂪�����Q��̂��ƍ��A
���B�o�ψψ�����Ԋ���a���E�t�H�[�����i�ȉ��uUN-ECE/WP29�v�Ƃ����B�j�ɂ����č��肳�ꂽ���E���ꎎ��
�T�C�N���ł���WHTC�iWorld Harmonized Transient Cycle�j�ɕύX����B
���B�o�ψψ�����Ԋ���a���E�t�H�[�����i�ȉ��uUN-ECE/WP29�v�Ƃ����B�j�ɂ����č��肳�ꂽ���E���ꎎ��
�T�C�N���ł���WHTC�iWorld Harmonized Transient Cycle�j�ɕύX����B
�A �r�o�K�X�㏈�����u�̏����Ⴂ�G���W����Ԏ��̔r�o�K�X�̒ጸ��}�邽�߁A�]���̃G���W���g�@���i�z�b
�g�X�^�[�g�j�r�o�K�X�����ɉ����A�G���W����Ԏ��i�R�[���h�X�^�[�g�j�r�o�K�X���������A�R�[���h�X�^�[�g�r�o�K�X
�����ɂ�鑪��l��14���̔䗦�ŁA�܂��A�z�b�g�X�^�[�g�r�o�K�X�����ɂ�鑪��l��86���̔䗦�ŁA���ꂼ��d�ݕt
�����č��v�����l��r�o�K�X����l�Ƃ���B
�g�X�^�[�g�j�r�o�K�X�����ɉ����A�G���W����Ԏ��i�R�[���h�X�^�[�g�j�r�o�K�X���������A�R�[���h�X�^�[�g�r�o�K�X
�����ɂ�鑪��l��14���̔䗦�ŁA�܂��A�z�b�g�X�^�[�g�r�o�K�X�����ɂ�鑪��l��86���̔䗦�ŁA���ꂼ��d�ݕt
�����č��v�����l��r�o�K�X����l�Ƃ���B
�@���ɁA�R�[���h�X�^�[�g�r�o�K�X�����ɂ��ẮA����܂ł̔r�o�K�X�K���̋����ɂ��A�z�b�g�X�^�[�g���̔r�o�K
�X�ʂ́A���ɒႢ���x���ƂȂ����A����A�R�[���h�X�^�[�g���̔r�o�K�X�ʂ����ΓI�ɑ傫���Ȃ�ƍl������
�̂��ƁB���������āA�z�b�g�X�^�[�g���̔r�o�K�X����l�݂̂ɂ��K���ł́A�r�o�K�X��L���ɒጸ�ł��Ȃ��ƍl����
��邽�߁A�����r�o�K�X�K���ɂ����ẮA�R�[���h�X�^�[�g���̔r�o�K�X���������邱�Ƃ��K���Ƃ̗��R�ł���B
�X�ʂ́A���ɒႢ���x���ƂȂ����A����A�R�[���h�X�^�[�g���̔r�o�K�X�ʂ����ΓI�ɑ傫���Ȃ�ƍl������
�̂��ƁB���������āA�z�b�g�X�^�[�g���̔r�o�K�X����l�݂̂ɂ��K���ł́A�r�o�K�X��L���ɒጸ�ł��Ȃ��ƍl����
��邽�߁A�����r�o�K�X�K���ɂ����ẮA�R�[���h�X�^�[�g���̔r�o�K�X���������邱�Ƃ��K���Ƃ̗��R�ł���B
�@���āA�\�Q�̎����̂m�n���K���l�́A�Q005�N�̑攪�����\�ɂm�n���̒���ڕW�Ƃ��Ď�����Ă����@0.7 g/kWh�� 1/3
���x�i���@0.23�@g/kWh�j����0.4 g/kWh�܂łɑ啝�Ɋɘa���ꂽ�悤�ł���B���̑啝��NO���K���l�̊ɘa�Ɋւ��āu��
��̎����Ԕr�o�K�X�ጸ��̂�����ɂ��āi��\�����\�j�v�ɓY�t����Ă���i��\���j�́u�Q�D�T�D�Q �攪��
���\�ɂ����钧��ڕW�l�Ƃ̔�r�v�ɂ́A�ȉ��̂悤�ɋL�ڂ���Ă���B
���x�i���@0.23�@g/kWh�j����0.4 g/kWh�܂łɑ啝�Ɋɘa���ꂽ�悤�ł���B���̑啝��NO���K���l�̊ɘa�Ɋւ��āu��
��̎����Ԕr�o�K�X�ጸ��̂�����ɂ��āi��\�����\�j�v�ɓY�t����Ă���i��\���j�́u�Q�D�T�D�Q �攪��
���\�ɂ����钧��ڕW�l�Ƃ̔�r�v�ɂ́A�ȉ��̂悤�ɋL�ڂ���Ă���B
�w�攪�����\�ɂ����ẮA�f�B�[�[���d�ʎԂ�NOx�r�o�ʂ�09�N�K���i0.7g/kWh�j��1/3���x�Ƃ��钧��ڕW�l���
�����B����́AJE05���[�h�Ɋ�Â��z�b�g�X�^�[�g���̔r�o�ʂ�O��Ƃ������l�ł���B�����r�o�K�X�K���ł́A�z�b�g�X
�^�[�g�������r�o�ʂ���������R�[���h�X�^�[�g���̔r�o�K�X���������邱�ƂƂ����B���������āA�攪�����\��
�����钧��ڕW�l�Ǝ����ڕW�l�i0.4g/kWh�j��P���ɔ�r���邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B���̂悤�ȏł͂��邪�A09�N�K��
�����̌����J���p�̃G���W���̃f�[�^�����ƂɁA�����ڕW�l��JE05���[�h�Ɋ�Â��z�b�g�X�^�[�g���̔r�o�ʂɊ��Z��
�Ă݂��Ƃ���A�\���ȃf�[�^���ł͂Ȃ����߁A�����܂Ŗڈ��Ƃ��ĂƂ炦��ׂ����̂ł��邪�A0.26g/kWh�ƂȂ����i����
���A����ł����f�[�^�̓��A09�N�K����NOx�K���l0.7g/kWh�������Ă�����̂͏��O���Ă���B���O���Ȃ������ꍇ
�́A0.31g/kWh�j�B����ɁA�I�t�T�C�N����A���x��OBD�V�X�e���̓����A�攪�����\�����ɂ͍��肳��Ă��Ȃ�����
����27�N�x�d�ʎԔR���ɂ��Ή����邱�Ƃ��l������A������NO���ڕW�l�i�K���l�j�́A�攪�����\�ɂ����钧
��ڕW�l�̃��x���ɒB���Ă���ƍl������B�x
�����B����́AJE05���[�h�Ɋ�Â��z�b�g�X�^�[�g���̔r�o�ʂ�O��Ƃ������l�ł���B�����r�o�K�X�K���ł́A�z�b�g�X
�^�[�g�������r�o�ʂ���������R�[���h�X�^�[�g���̔r�o�K�X���������邱�ƂƂ����B���������āA�攪�����\��
�����钧��ڕW�l�Ǝ����ڕW�l�i0.4g/kWh�j��P���ɔ�r���邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B���̂悤�ȏł͂��邪�A09�N�K��
�����̌����J���p�̃G���W���̃f�[�^�����ƂɁA�����ڕW�l��JE05���[�h�Ɋ�Â��z�b�g�X�^�[�g���̔r�o�ʂɊ��Z��
�Ă݂��Ƃ���A�\���ȃf�[�^���ł͂Ȃ����߁A�����܂Ŗڈ��Ƃ��ĂƂ炦��ׂ����̂ł��邪�A0.26g/kWh�ƂȂ����i����
���A����ł����f�[�^�̓��A09�N�K����NOx�K���l0.7g/kWh�������Ă�����̂͏��O���Ă���B���O���Ȃ������ꍇ
�́A0.31g/kWh�j�B����ɁA�I�t�T�C�N����A���x��OBD�V�X�e���̓����A�攪�����\�����ɂ͍��肳��Ă��Ȃ�����
����27�N�x�d�ʎԔR���ɂ��Ή����邱�Ƃ��l������A������NO���ڕW�l�i�K���l�j�́A�攪�����\�ɂ����钧
��ڕW�l�̃��x���ɒB���Ă���ƍl������B�x
�@���̂悤�ɁA�����Ԕr�o�K�X�ጸ��̂�����ɂ��āi��\���j�ɂ��ƁA�攪�����\�ɂ����Ē���Ă�
���f�B�[�[���d�ʎԂ�JE05���[�h�Ɋ�Â��z�b�g�X�^�[�g����NOx�r�o�ʂ�2009�N�K���i0.7g/kWh�j��1/3���x�Ƃ��钧
��ڕW�l�́AJE05���[�h�Ɋ�Â��z�b�g�X�^�[�g�ƃR�[���h�X�^�[�g��NO���r�o�ʂɊ��Z�����ꍇ�ɂ́A�����̂m�n���ڕW
�l�i�K���l�j�ɋ߂�NO���r�o�l�ɑ�������Ƃ̂��ƁB���������āA�������R�c��́A��\�����\�̎���NO���ڕW�l
�i�K���l�j�́A�����I�ɂ́A�攪�����\��NO������ڕW�l��w�ǂ��̂܂܋���������̂Ƃ������ł���B,�������Ȃ�
��A���́u2009�N�K���i0.7g/kWh�j��1/3���x�Ƃ����������R�c��̑攪�����\��NO������ڕW�l���A2016�N���܂�
�Ɏ��{�\��ł�����\�����\���m�n���ڕW�l�i����NO���K���l�j���@0.4 g/kWh�Ƃقړ����v�Ƃ����\���ɋL�ڂ�
��Ă����������R�c��̌����ɂ��āA�M�҂͑傢�ɋ^�₪����Ǝv���Ă���B
���f�B�[�[���d�ʎԂ�JE05���[�h�Ɋ�Â��z�b�g�X�^�[�g����NOx�r�o�ʂ�2009�N�K���i0.7g/kWh�j��1/3���x�Ƃ��钧
��ڕW�l�́AJE05���[�h�Ɋ�Â��z�b�g�X�^�[�g�ƃR�[���h�X�^�[�g��NO���r�o�ʂɊ��Z�����ꍇ�ɂ́A�����̂m�n���ڕW
�l�i�K���l�j�ɋ߂�NO���r�o�l�ɑ�������Ƃ̂��ƁB���������āA�������R�c��́A��\�����\�̎���NO���ڕW�l
�i�K���l�j�́A�����I�ɂ́A�攪�����\��NO������ڕW�l��w�ǂ��̂܂܋���������̂Ƃ������ł���B,�������Ȃ�
��A���́u2009�N�K���i0.7g/kWh�j��1/3���x�Ƃ����������R�c��̑攪�����\��NO������ڕW�l���A2016�N���܂�
�Ɏ��{�\��ł�����\�����\���m�n���ڕW�l�i����NO���K���l�j���@0.4 g/kWh�Ƃقړ����v�Ƃ����\���ɋL�ڂ�
��Ă����������R�c��̌����ɂ��āA�M�҂͑傢�ɋ^�₪����Ǝv���Ă���B
�@���͂Ƃ�����A�������ł́A2010�N�V���̒������R�c�����\�����\�ɂ����āA��^�g���b�N�ɑ���2016�N��
NO�� �� 0.4 g/kWh�̋K�����������{����邱�Ƃ����\����Ă���B�������A�}�P�Ɏ��������{�A�č��A���B�̏��p��(��
�����d��3.5����)��NO����PM�̋K�������̕ϑJ������Ɩ��炩�Ȃ悤�ɁA�č��ł́A����2010�N��NO�� �� 0.27 g/kWh
�ɋK�����������{����Ă���̂��B�������A���{�ł́A2016�N�ɂ����NO���� 0.4 g/kWh��NO���K�������������ɉ�
���Ȃ����Ƃ��A�������R�c�����\�����\�Ŕ��\���ꂽ�̂ł���B���̂��߁A��^�g���b�N�i���d�ʎԁj�̕���ł́A
���{�ɂ�����2016�N��NO�� �� 0.4 g/kWh�̋K�����������{���ꂽ���_�ł��A���{�ł̂m�n���K���́A2010�N��NO��
�� 0.27 g/kWh���č��m�n���K�����������Ɋɂ�NO���K�������{���邱�ƂɂȂ�B
NO�� �� 0.4 g/kWh�̋K�����������{����邱�Ƃ����\����Ă���B�������A�}�P�Ɏ��������{�A�č��A���B�̏��p��(��
�����d��3.5����)��NO����PM�̋K�������̕ϑJ������Ɩ��炩�Ȃ悤�ɁA�č��ł́A����2010�N��NO�� �� 0.27 g/kWh
�ɋK�����������{����Ă���̂��B�������A���{�ł́A2016�N�ɂ����NO���� 0.4 g/kWh��NO���K�������������ɉ�
���Ȃ����Ƃ��A�������R�c�����\�����\�Ŕ��\���ꂽ�̂ł���B���̂��߁A��^�g���b�N�i���d�ʎԁj�̕���ł́A
���{�ɂ�����2016�N��NO�� �� 0.4 g/kWh�̋K�����������{���ꂽ���_�ł��A���{�ł̂m�n���K���́A2010�N��NO��
�� 0.27 g/kWh���č��m�n���K�����������Ɋɂ�NO���K�������{���邱�ƂɂȂ�B
�@�ȉ��̐}�P������Ɩ��炩�Ȃ悤�ɁA�����ȑO�܂ł́A���{�̂m�n���K���l�́A�č��̂m�n���K���l��菭�����������A
����Ƃ������̃��x���ł������B�������A���̂��ŋ߂ł́A�č��̂m�n���K�������ɂ�NO���K������{�Ŏ��{�����
�j�ɑ傫���ǂ��ꂽ�悤���B���̂悤�ɁA���ȁE���y��ʏȂ����s���̑傫�����j��ύX���A�č��̂m�n���K��
�l�ɔ�r���āA���{�̂m�n���K���l���ɂ����x���ɐݒ肵�����R�́A��́A���Ȃ̂ł��낤���B2016�N�Ɏ��{������
�{��NO���K���l���č��̂m�n���K���l�����傫���ɘa����邱�Ƃɂ���ė��v��̂́A�m�n���ጸ�̌����J���̓�
�����팸�ł���g�b���b�N���[�J�����ƍl������B�����āA�]������̂́A�������C���̒��œ���̐����𑗂�
����Ȃ������̈�ʎs���ł��邱�Ƃ͊m�����B�M�����Ȃ����Ƃł͂��邪�A���ȁE���y��ʏȂ̐l�B�́A�č�
�l�ɔ�ׂē��{�l�̕��������͂�����Ƃ̍l������A���{�̑�C�����č������A�����A����Ă��Ă��ǂ��Ɣ��f
����Ă���̂ł��낤���B�M�����Ȃ����Ƃł��B
����Ƃ������̃��x���ł������B�������A���̂��ŋ߂ł́A�č��̂m�n���K�������ɂ�NO���K������{�Ŏ��{�����
�j�ɑ傫���ǂ��ꂽ�悤���B���̂悤�ɁA���ȁE���y��ʏȂ����s���̑傫�����j��ύX���A�č��̂m�n���K��
�l�ɔ�r���āA���{�̂m�n���K���l���ɂ����x���ɐݒ肵�����R�́A��́A���Ȃ̂ł��낤���B2016�N�Ɏ��{������
�{��NO���K���l���č��̂m�n���K���l�����傫���ɘa����邱�Ƃɂ���ė��v��̂́A�m�n���ጸ�̌����J���̓�
�����팸�ł���g�b���b�N���[�J�����ƍl������B�����āA�]������̂́A�������C���̒��œ���̐����𑗂�
����Ȃ������̈�ʎs���ł��邱�Ƃ͊m�����B�M�����Ȃ����Ƃł͂��邪�A���ȁE���y��ʏȂ̐l�B�́A�č�
�l�ɔ�ׂē��{�l�̕��������͂�����Ƃ̍l������A���{�̑�C�����č������A�����A����Ă��Ă��ǂ��Ɣ��f
����Ă���̂ł��낤���B�M�����Ȃ����Ƃł��B
�@
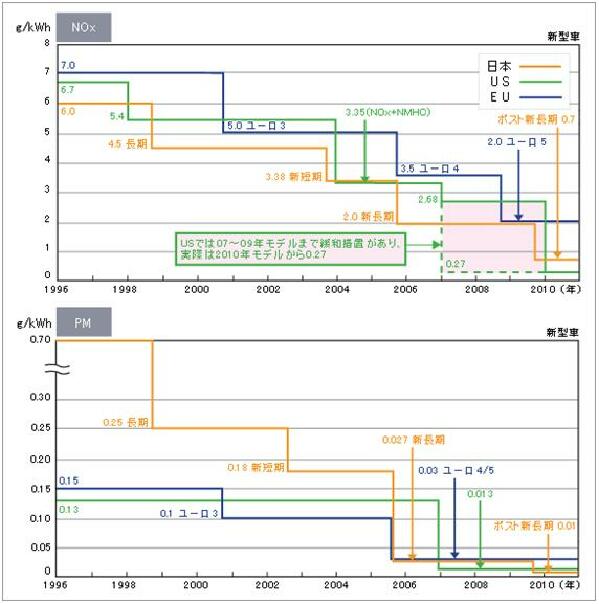
�@���݂ɁA���̒������R�c�2010�N�V������\�����\�����\����2016�N�Ɏ��{�\���NO�� �� 0.4 g/kWh�̋K��
�����́A2005�N�ɔ��\���ꂽ�攪�����\�ɋL�ڂ���Ă��鏫����NO���팸�̖ڈ��Ƃ��Ă�NO���팸������ڕW�ł�
��0.7 g/kWh�� 1/3���x�i���@0.23�@g/kWh���x���j�����S�ɖ������Ă���ł���B�����āA��\�����\�ɂ́A�攪�����\
�ɖ��L���ꂽ������NO���팸�̖ڈ��Ƃ���NO���팸������ڕW�iNO����0.23g/kWh�j�̂ɂ����������Ƃ��v���闝
�R�����X�Ɨ���Ă���̂ł���B���̂悤�ɁA�攪�����\�ɖ��L���ꂽ������NO���팸������ڕW�iNO����0.23g/
kWh�j����啝�Ɋɘa����Ă���̂ł���B���̌��ʁA�}�Q�Ɏ������ʂ�A���{�̎����̂m�n���K���́A2016�N�̎�
�{�\��ł�NO�� �� 0.4 g/kWh�j�ł���A2010�N���č��̂m�n���K���iNO�� �� 0.27 g/kWh�j���������Ɋɂ��m
�n���K�������{���ꑱ������\���ł���B�����āA���̑傫���ɘa���ꂽ���{��2016�N�̎���NO���K����������
���R�c�����\�����\�œ��\���ꂽ�����ɂ��āA�{���̗��R��m�肽���Ƃ���ł���B
�����́A2005�N�ɔ��\���ꂽ�攪�����\�ɋL�ڂ���Ă��鏫����NO���팸�̖ڈ��Ƃ��Ă�NO���팸������ڕW�ł�
��0.7 g/kWh�� 1/3���x�i���@0.23�@g/kWh���x���j�����S�ɖ������Ă���ł���B�����āA��\�����\�ɂ́A�攪�����\
�ɖ��L���ꂽ������NO���팸�̖ڈ��Ƃ���NO���팸������ڕW�iNO����0.23g/kWh�j�̂ɂ����������Ƃ��v���闝
�R�����X�Ɨ���Ă���̂ł���B���̂悤�ɁA�攪�����\�ɖ��L���ꂽ������NO���팸������ڕW�iNO����0.23g/
kWh�j����啝�Ɋɘa����Ă���̂ł���B���̌��ʁA�}�Q�Ɏ������ʂ�A���{�̎����̂m�n���K���́A2016�N�̎�
�{�\��ł�NO�� �� 0.4 g/kWh�j�ł���A2010�N���č��̂m�n���K���iNO�� �� 0.27 g/kWh�j���������Ɋɂ��m
�n���K�������{���ꑱ������\���ł���B�����āA���̑傫���ɘa���ꂽ���{��2016�N�̎���NO���K����������
���R�c�����\�����\�œ��\���ꂽ�����ɂ��āA�{���̗��R��m�肽���Ƃ���ł���B
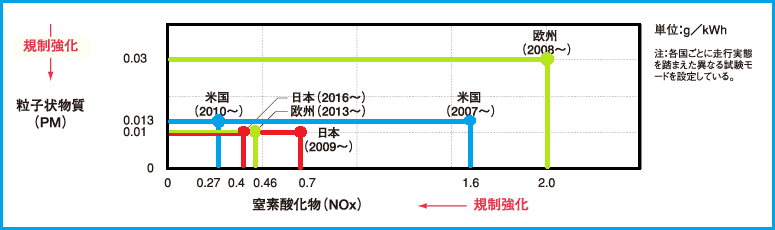
�@�ȏ�̂悤�ɁA���݂̓��{�ł́A�č������ɂ��̑�^�g���b�N��NO���K�����{�s����A�����āA���ꂩ�瓖���̊ԁA
���{�ł��č������ɂ���^�g���b�N��NO���K�����p�������Ɋׂ��Ă���悤���B�������A�M�҂���Ă��Ă����C
���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p���^�g���b�N�ɍ̗p���邱�Ƃɂ�����č��������������{��NO���K
����NO���K���ɋ����iNO�� �� 0.23 g/kWh )�iWHTC�r�o�K�X�����@�j��e�ՂɎ������邱�Ƃ��\�ł���B���̂��Ƃ�
���ẮA�č������ɂ���^�g���b�N��NO���K�����{�s����������{���{�̑Ӗ��̃y�[�W�ɂ��ڏq���Ă���̂ŁA��
���������������B
���{�ł��č������ɂ���^�g���b�N��NO���K�����p�������Ɋׂ��Ă���悤���B�������A�M�҂���Ă��Ă����C
���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p���^�g���b�N�ɍ̗p���邱�Ƃɂ�����č��������������{��NO���K
����NO���K���ɋ����iNO�� �� 0.23 g/kWh )�iWHTC�r�o�K�X�����@�j��e�ՂɎ������邱�Ƃ��\�ł���B���̂��Ƃ�
���ẮA�č������ɂ���^�g���b�N��NO���K�����{�s����������{���{�̑Ӗ��̃y�[�W�ɂ��ڏq���Ă���̂ŁA��
���������������B
�R�D���{�̎����̂m�n���K���i2016�N���{�j�����s�̕č��̂m�n���K�������ɂ����R
�@�ȉ��̕\�U�Ɏ������悤�ɁA2011�N9�����s�́u�����ԋZ�p�v���iVol.65,No.9,2011)�́u�����ԗp�G���W���Z�p�J����
����Ə����v�Ƒ肵���_���́u3.2.�@�d�ʎԂ̔R����P�v�̍��ɂ����āA���҂̑���c��w�̑吹�����́A�d�ʎԁi��
�f�B�[�[���g���b�N�E�o�X�j�ɂ������w2016�N�̔r�o�K�X�K���ւ̓K���x���w2015�N�x�d�ʎԔR���ւ̓K���x��
�g���[�h�I�t�̍������K�v�ł���Əq�ׂ��Ă���B
����Ə����v�Ƒ肵���_���́u3.2.�@�d�ʎԂ̔R����P�v�̍��ɂ����āA���҂̑���c��w�̑吹�����́A�d�ʎԁi��
�f�B�[�[���g���b�N�E�o�X�j�ɂ������w2016�N�̔r�o�K�X�K���ւ̓K���x���w2015�N�x�d�ʎԔR���ւ̓K���x��
�g���[�h�I�t�̍������K�v�ł���Əq�ׂ��Ă���B
| |
|
| �� �� �� �� �� �� �� |
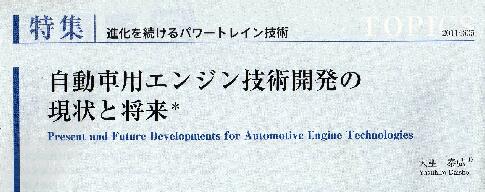 |
| �_ �� �� �� |
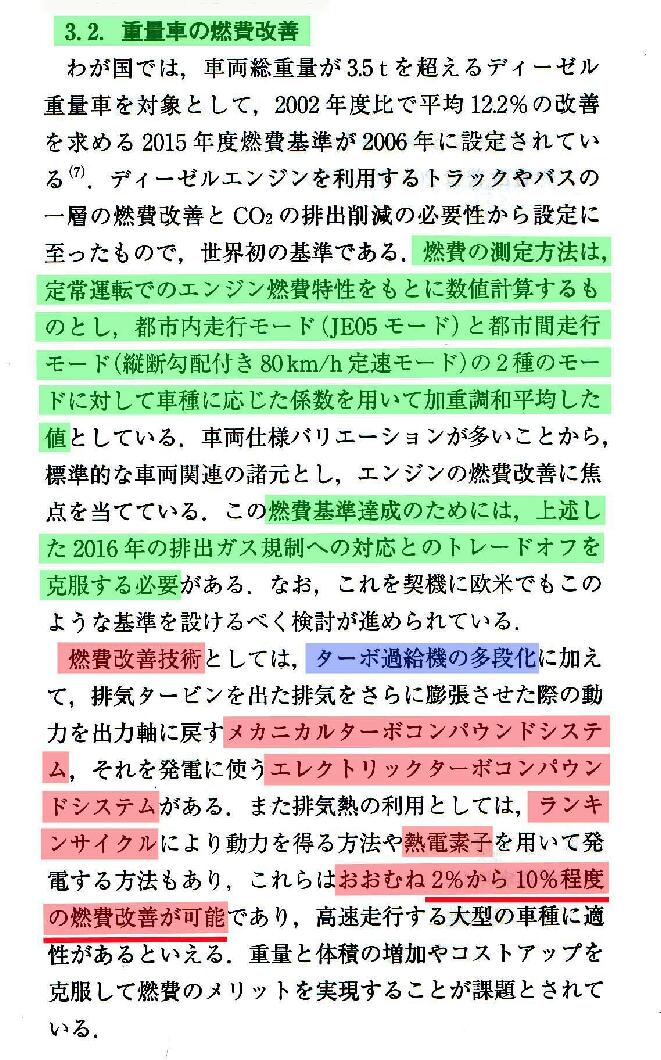 |
�@�@���̕\�T�Ɏ������u�����ԋZ�p�v���̓��e������ƁA ����c��w�̑吹�������A�f�B�[�[����^�g���b�N�ɂ����Ă�
�uNO���̍팸�v�Ɓu�R��̉��P�v�ɂ̓g���[�h�I�t�̊W�����邽�߁A�uNO���̍팸�v�Ɓu�R��̉��P�v���Ɏ�������Z
�p�������_�ł͕s���ƔF������Ă�����̂Ɛ��@�����B���̂��߁A����c��w�̑吹�������A��^�g���b�N�ɂ���
�āA���{�̃g���b�N���[�J�ł́u2015�N�x�d�ʎԔR���̒B���v�ƁA�u2016�N��NO���K���l�� 0.4 g/kWh�iWHTC���[
�h�j�̔r�o�K�X�K���ւ̓K���v�̃g���[�h�I�t�̍������Z�p�I�Ɍ��E�ł���A���{�ł͂���ȏ�̃��x���́uNO���K��
�̋����v�Ɓu�R���̋����v������Ƃ̈ӌ���������Ă���悤�ɐ��������B�t�Ȍ�����������A�������R�c
����吹�������܂������Ԕr�o�K�X���ψ�����w�ҁE���Ƃ́A�u2015�N�x�d�ʎԔR�����\���ɒ�����R��
����v�ƁA�uNO���K���l�� 0.4 g/kWh�iWHTC���[�h�j�ȏ�̃��x���܂ł�NO���팸�v�̗������Ɏ����ł���Z�p��
�m������������ۗL����Ă��Ȃ����̂Ɛ��������B���̂��߁A2010�N7�����������R�c��̑�10�����\�ł́A
2016�N�Ɏ��{������{�̎�����NO���K���l�́A2010�N���č��̂m�n���K���iNO�� �� 0.27 g/kWh�j���������Ɋɂ�����
�uNO���� 0.4 g/kWh�iWHTC���[�h�j�v�\������Ȃ��������̂Ɛ��������B
�uNO���̍팸�v�Ɓu�R��̉��P�v�ɂ̓g���[�h�I�t�̊W�����邽�߁A�uNO���̍팸�v�Ɓu�R��̉��P�v���Ɏ�������Z
�p�������_�ł͕s���ƔF������Ă�����̂Ɛ��@�����B���̂��߁A����c��w�̑吹�������A��^�g���b�N�ɂ���
�āA���{�̃g���b�N���[�J�ł́u2015�N�x�d�ʎԔR���̒B���v�ƁA�u2016�N��NO���K���l�� 0.4 g/kWh�iWHTC���[
�h�j�̔r�o�K�X�K���ւ̓K���v�̃g���[�h�I�t�̍������Z�p�I�Ɍ��E�ł���A���{�ł͂���ȏ�̃��x���́uNO���K��
�̋����v�Ɓu�R���̋����v������Ƃ̈ӌ���������Ă���悤�ɐ��������B�t�Ȍ�����������A�������R�c
����吹�������܂������Ԕr�o�K�X���ψ�����w�ҁE���Ƃ́A�u2015�N�x�d�ʎԔR�����\���ɒ�����R��
����v�ƁA�uNO���K���l�� 0.4 g/kWh�iWHTC���[�h�j�ȏ�̃��x���܂ł�NO���팸�v�̗������Ɏ����ł���Z�p��
�m������������ۗL����Ă��Ȃ����̂Ɛ��������B���̂��߁A2010�N7�����������R�c��̑�10�����\�ł́A
2016�N�Ɏ��{������{�̎�����NO���K���l�́A2010�N���č��̂m�n���K���iNO�� �� 0.27 g/kWh�j���������Ɋɂ�����
�uNO���� 0.4 g/kWh�iWHTC���[�h�j�v�\������Ȃ��������̂Ɛ��������B
�@���ɁA���̘_���ɒ��ł́A�吹�����́A��^�g���b�N�̔R����P�Z�p�Ƃ��āA�u�^�[�{�ߋ��̑��i���v�A�u�^�[�{�R���p
�E���h�v�A�u�����L���T�C�N���v����сu�M�d�f�q�v�̋Z�p���������Ă���B�������A�^�[�{�R���p�E���h�ɂ��f�B�[�[��
�g���b�N�̏\���ȔR����P�͍���I���C���x�~�́A�f�B�[�[���̂m�n���팸�ƔR�����̈ꋓ�����̋Z�p���I�ɏ�
�q�����ʂ�A�u�^�[�{�ߋ��̑��i���v�Ɓu�^�[�{�R���p�E���h�v�̉���̋Z�p���f�B�[�[���G���W���̕������ׂ̔R����\
���ɉ��P���邱�Ƃ�����ł���A�u�^�[�{�ߋ��̑��i���v�Ɓu�^�[�{�R���p�E���h�v�̋Z�p���̗p���Ă���^�g���b�N�̏d
�ʎԃ��[�h�R����\���Ɍ��シ�邱�Ƃ͍���ł���B
�E���h�v�A�u�����L���T�C�N���v����сu�M�d�f�q�v�̋Z�p���������Ă���B�������A�^�[�{�R���p�E���h�ɂ��f�B�[�[��
�g���b�N�̏\���ȔR����P�͍���I���C���x�~�́A�f�B�[�[���̂m�n���팸�ƔR�����̈ꋓ�����̋Z�p���I�ɏ�
�q�����ʂ�A�u�^�[�{�ߋ��̑��i���v�Ɓu�^�[�{�R���p�E���h�v�̉���̋Z�p���f�B�[�[���G���W���̕������ׂ̔R����\
���ɉ��P���邱�Ƃ�����ł���A�u�^�[�{�ߋ��̑��i���v�Ɓu�^�[�{�R���p�E���h�v�̋Z�p���̗p���Ă���^�g���b�N�̏d
�ʎԃ��[�h�R����\���Ɍ��シ�邱�Ƃ͍���ł���B
�@�܂��A�吹��������^�g���b�N�̔R����P�Z�p�Ƃ��Đ�������Ă���u�����L���T�C�N���v����сu�M�d�f�q�v�̋Z�p
�́A�u�^�[�{�R���p�E���h��Ɠ��l�ɃG���W�������^�]�ɂ�����r�C�K�X���x�̍������ɔr�C�K�X�̉��x�G�l���M�[
���G���W���o�͎��ɉ���V�X�e���ł���B���̂��߁A��^�g���b�N�̃G���W���Ɂu�����L���T�C�N���v����сu�M�d�f
�q�v�̋Z�p�𓋍ڂ����ꍇ�ɂ́A�r�C�K�X���x�������ƂȂ�G���W���̑S���o�͉^�]���ɁA������x�̍���������
�r�C�K�X�̉��x�G�l���M�[���G���W���o�͎��ɉ��邱�Ƃ��ł��邽�߁A�G���W���R��̉��P��}�邱�Ƃ��\���B
�������A��^�g���b�N�̎����s�ł́A�r�C�K�X���x�̒Ⴂ�G���W���������^�]����̂ƂȂ邽�߁A��^�g���b�N�̎�
���s�ɂ�����u�����L���T�C�N���v����сu�M�d�f�q�v�ɂ��r�C�K�X�̉��x�G�l���M�[���G���W���o�͎��ɉ��鎞
�̌����́A�啝�ɒቺ���邱�ƂɂȂ�B���̂悤�ɁA��^�g���b�N�̎����s��d�ʎԃ��[�h�R��̌v���i���V���~���[�V
�����v�Z�j�ł́A�C���x�~�G���W���ɂ���^�g���b�N�̒�R����C���x�~�́A�f�B�[�[���̂m�n���팸�ƔR������
�ꋓ�����̋Z�p���I�̃y�[�W�ɏڏq���Ă���悤�ɁA�r�C�K�X���x�̒Ⴂ�G���W���������ׂ̉^�]���啔������
�邽�߁A��^�g���b�N�̃f�B�[�[���G���W���Ɂu�����L���T�C�N���v����сu�M�d�f�q�v�̋Z�p���̗p�����Ƃ��Ă��A��^�g
���b�N�̎����s�R���d�ʎԃ��[�h�R��́A�ɁA�͂��ȉ��P�ɗ��܂���̂ƍl������B
�́A�u�^�[�{�R���p�E���h��Ɠ��l�ɃG���W�������^�]�ɂ�����r�C�K�X���x�̍������ɔr�C�K�X�̉��x�G�l���M�[
���G���W���o�͎��ɉ���V�X�e���ł���B���̂��߁A��^�g���b�N�̃G���W���Ɂu�����L���T�C�N���v����сu�M�d�f
�q�v�̋Z�p�𓋍ڂ����ꍇ�ɂ́A�r�C�K�X���x�������ƂȂ�G���W���̑S���o�͉^�]���ɁA������x�̍���������
�r�C�K�X�̉��x�G�l���M�[���G���W���o�͎��ɉ��邱�Ƃ��ł��邽�߁A�G���W���R��̉��P��}�邱�Ƃ��\���B
�������A��^�g���b�N�̎����s�ł́A�r�C�K�X���x�̒Ⴂ�G���W���������^�]����̂ƂȂ邽�߁A��^�g���b�N�̎�
���s�ɂ�����u�����L���T�C�N���v����сu�M�d�f�q�v�ɂ��r�C�K�X�̉��x�G�l���M�[���G���W���o�͎��ɉ��鎞
�̌����́A�啝�ɒቺ���邱�ƂɂȂ�B���̂悤�ɁA��^�g���b�N�̎����s��d�ʎԃ��[�h�R��̌v���i���V���~���[�V
�����v�Z�j�ł́A�C���x�~�G���W���ɂ���^�g���b�N�̒�R����C���x�~�́A�f�B�[�[���̂m�n���팸�ƔR������
�ꋓ�����̋Z�p���I�̃y�[�W�ɏڏq���Ă���悤�ɁA�r�C�K�X���x�̒Ⴂ�G���W���������ׂ̉^�]���啔������
�邽�߁A��^�g���b�N�̃f�B�[�[���G���W���Ɂu�����L���T�C�N���v����сu�M�d�f�q�v�̋Z�p���̗p�����Ƃ��Ă��A��^�g
���b�N�̎����s�R���d�ʎԃ��[�h�R��́A�ɁA�͂��ȉ��P�ɗ��܂���̂ƍl������B
�@���̂悤�ɁA�u�^�[�{�ߋ��̑��i���v�A�u�^�[�{�R���p�E���h�v�A�u�����L���T�C�N���v����сu�M�d�f�q�v�̋Z�p�́A�G���W
�����������̔R����P�̋@�\�����Z�p�ł���B���̂��߁A�����̋Z�p���^�g���b�N�ɍ̗p�����Ƃ��Ă��A��^
�g���b�N�̎����s�R���d�ʎԃ��[�h�R����\���Ɍ��シ�邱�Ƃ́A����ł���B����ɂ�������炸�A2011�N9����
�s�́u�����ԋZ�p�v���iVol.65,No.9,2011)�́u�����ԗp�G���W���Z�p�J���̌���Ə����v�i�\�T�Q�Ɓj�Ƒ肵���_���́u3.2.
�@�d�ʎԂ̔R����P�v�̍��ɂ����āA���҂̑���c��w�̑吹�����́A��^�g�f�B�[�[���g���b�N�E�o�X�i���d�ʎԁj��
������R�����̎�i�Ƃ��āA��^�g���b�N�̎����s�R���d�ʎԃ��[�h�R����\���ɉ��P�ł���@�\�����u�^�[�{
�ߋ��̑��i���v�A�u�^�[�{�R���p�E���h�v�A�u�����L���T�C�N���v����сu�M�d�f�q�v�̋Z�p�𐄋�����Ă��邱�Ƃɂ��āA
�M�҂ɂ͋^��Ɏv���Ďd�����Ȃ��̂ł���B
�����������̔R����P�̋@�\�����Z�p�ł���B���̂��߁A�����̋Z�p���^�g���b�N�ɍ̗p�����Ƃ��Ă��A��^
�g���b�N�̎����s�R���d�ʎԃ��[�h�R����\���Ɍ��シ�邱�Ƃ́A����ł���B����ɂ�������炸�A2011�N9����
�s�́u�����ԋZ�p�v���iVol.65,No.9,2011)�́u�����ԗp�G���W���Z�p�J���̌���Ə����v�i�\�T�Q�Ɓj�Ƒ肵���_���́u3.2.
�@�d�ʎԂ̔R����P�v�̍��ɂ����āA���҂̑���c��w�̑吹�����́A��^�g�f�B�[�[���g���b�N�E�o�X�i���d�ʎԁj��
������R�����̎�i�Ƃ��āA��^�g���b�N�̎����s�R���d�ʎԃ��[�h�R����\���ɉ��P�ł���@�\�����u�^�[�{
�ߋ��̑��i���v�A�u�^�[�{�R���p�E���h�v�A�u�����L���T�C�N���v����сu�M�d�f�q�v�̋Z�p�𐄋�����Ă��邱�Ƃɂ��āA
�M�҂ɂ͋^��Ɏv���Ďd�����Ȃ��̂ł���B
�@�����āA�u���J�j�J���^�[�{�R���p�E���h�v�A�u�G���N�g���b�N�^�[�{�R���p�E���h�v�A�u�����L���T�C�N���v�A�u�M�d�f�q�v����
�сu�X�^�[�����O�G���W���v�����f�B�[�[���G���W���̔r�C�K�X�̃G�l���M�[�����鑕�u��p������^�g���b�N�̎�
���s�R�������ł���悤�ɂ��邽�߂��́A�C���x�~�́A�f�B�[�[���r�C�K�X�̃G�l���M�[���u�̌�����������
�ڏq���Ă���悤�ɁA��^�g���b�N�̎����s���̔r�C�K�X���x�������ɐ���ł���Z�p�p���邱�Ƃ��K�{�ł���B
�����āA������^�g���b�N�̎����s���̔r�C�K�X���x�������ɐ���ł���Z�p���M�Ґ������C���x�~�G���W���i����
���J2005-54771�j�ł���B���݂̂Ƃ���A�����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p�ȊO�ɁA��^�g���b�N��
�����s���̔r�C�K�X���x�������ɐ���ł���Z�p�́A���̒��Ɍ�������Ȃ��B
�сu�X�^�[�����O�G���W���v�����f�B�[�[���G���W���̔r�C�K�X�̃G�l���M�[�����鑕�u��p������^�g���b�N�̎�
���s�R�������ł���悤�ɂ��邽�߂��́A�C���x�~�́A�f�B�[�[���r�C�K�X�̃G�l���M�[���u�̌�����������
�ڏq���Ă���悤�ɁA��^�g���b�N�̎����s���̔r�C�K�X���x�������ɐ���ł���Z�p�p���邱�Ƃ��K�{�ł���B
�����āA������^�g���b�N�̎����s���̔r�C�K�X���x�������ɐ���ł���Z�p���M�Ґ������C���x�~�G���W���i����
���J2005-54771�j�ł���B���݂̂Ƃ���A�����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p�ȊO�ɁA��^�g���b�N��
�����s���̔r�C�K�X���x�������ɐ���ł���Z�p�́A���̒��Ɍ�������Ȃ��B
�@�Ƃ���ŁA�����U�����Ԃ́A�f�B�[�[���S�g���g���b�N�u�t�H���[�h�v�ɂ����āA�����Q�Q�N�̔r�o�K�X�K���i�|�X�g�V����
�K���j�̓K���Ԃł́A�Q�i�V�[�P���V�����^�[�{�V�X�e�����̗p���Ă���B�������A�C���x�~�G���W���ɂ���^�g���b�N
�̒�R��ɏڏq���Ă���悤�ɁA�����u�t�H���[�h�v�ł͑��s�R��s�ǂȂ��Ƃ������Ɛ�������邪�A�L�낤�����A
�����U�����Ԃ́A�s�̂����u�t�H���[�h�v�̂SHK1-TCS�G���W���Ɉ�@�ȃG���W��������s����NO���𐂂ꗬ���đ��s�R
��̉��P��}�����s���ȃG���W������𓋍ڂ��Ă����̂ł���B�Ƃ��낪�A���̕s���ȍs�ׂ����I�悵�A�����U������
������23�N5���ɓ����s�ɂ���č��y��ʏȂɓ��H�^���ԗ��@�ᔽ��ʕꂽ�̂��B���̂��Ƃ���A�Q�i�V�[�P��
�V�����^�[�{�V�X�e���̃G���W���ᑬ�̃g���N�A�b�v�Ɋ�^���邪�A�R��팸�̃����b�g�͋ɂ߂ď��Ȃ����̂ł��邱��
�������̈�ł͂Ȃ����Ɛ��@�����B
�K���j�̓K���Ԃł́A�Q�i�V�[�P���V�����^�[�{�V�X�e�����̗p���Ă���B�������A�C���x�~�G���W���ɂ���^�g���b�N
�̒�R��ɏڏq���Ă���悤�ɁA�����u�t�H���[�h�v�ł͑��s�R��s�ǂȂ��Ƃ������Ɛ�������邪�A�L�낤�����A
�����U�����Ԃ́A�s�̂����u�t�H���[�h�v�̂SHK1-TCS�G���W���Ɉ�@�ȃG���W��������s����NO���𐂂ꗬ���đ��s�R
��̉��P��}�����s���ȃG���W������𓋍ڂ��Ă����̂ł���B�Ƃ��낪�A���̕s���ȍs�ׂ����I�悵�A�����U������
������23�N5���ɓ����s�ɂ���č��y��ʏȂɓ��H�^���ԗ��@�ᔽ��ʕꂽ�̂��B���̂��Ƃ���A�Q�i�V�[�P��
�V�����^�[�{�V�X�e���̃G���W���ᑬ�̃g���N�A�b�v�Ɋ�^���邪�A�R��팸�̃����b�g�͋ɂ߂ď��Ȃ����̂ł��邱��
�������̈�ł͂Ȃ����Ɛ��@�����B
�@���̂悤�ɁA2011�N9�����s�́u�����ԋZ�p�v���iVol.65,No.9,2011)�́u�����ԗp�G���W���Z�p�J���̌���Ə����v�Ƒ�
�����_���ł́A2.2 (2)�́u�i�K�\�����G���W���́j�����\���ƔR����P�Z�p�v�̍��ł́A�吹�����́A�u�E�E�E�e��ϋ@�\
�̗��p�A���ڕ��˂��܂ޔR�������n����ɐ��k���A�E�E�E�E�E�E�A�ߋ��V�X�e���ɂ��G���W���̃_�E���T�C�W���O�A�e�^
�����̖��C���L�ޑ����̒ጸ�ȂǁE�E�E�E�E�v�ƋL�ڂ���A�K�\�����G���W���̔R����P�Ɋւ��鑽���̋Z�p������
�Ă��邪�A�������A�u3.2.�@�d�ʎԂ̔R����P�v�̍��ł́A�吹�����́A��^�g���b�N�̎����s�R���d�ʎԃ��[�h�R��
���\���ɉ��P�ł���@�\�E���ʂ̊��҂ł��Ȃ��u�^�[�{�ߋ��̑��i���v�A�u�^�[�{�R���p�E���h�v�A�u�����L���T�C�N���v��
��сu�M�d�f�q�v�̂悤�ȋZ�p���҂�����������Ă���̂��B���������āA���̘_����q������ƁA�吹�����́A�����
�X�Ȃ��^�g���b�N�̏d�ʎԃ��[�h�R��̌��オ�ɂ߂Ď����̍���Ȃ��Ƃ�[���F������Ă���̂ł͂Ȃ����Ɛ��@��
���B
�����_���ł́A2.2 (2)�́u�i�K�\�����G���W���́j�����\���ƔR����P�Z�p�v�̍��ł́A�吹�����́A�u�E�E�E�e��ϋ@�\
�̗��p�A���ڕ��˂��܂ޔR�������n����ɐ��k���A�E�E�E�E�E�E�A�ߋ��V�X�e���ɂ��G���W���̃_�E���T�C�W���O�A�e�^
�����̖��C���L�ޑ����̒ጸ�ȂǁE�E�E�E�E�v�ƋL�ڂ���A�K�\�����G���W���̔R����P�Ɋւ��鑽���̋Z�p������
�Ă��邪�A�������A�u3.2.�@�d�ʎԂ̔R����P�v�̍��ł́A�吹�����́A��^�g���b�N�̎����s�R���d�ʎԃ��[�h�R��
���\���ɉ��P�ł���@�\�E���ʂ̊��҂ł��Ȃ��u�^�[�{�ߋ��̑��i���v�A�u�^�[�{�R���p�E���h�v�A�u�����L���T�C�N���v��
��сu�M�d�f�q�v�̂悤�ȋZ�p���҂�����������Ă���̂��B���������āA���̘_����q������ƁA�吹�����́A�����
�X�Ȃ��^�g���b�N�̏d�ʎԃ��[�h�R��̌��オ�ɂ߂Ď����̍���Ȃ��Ƃ�[���F������Ă���̂ł͂Ȃ����Ɛ��@��
���B
�@�܂��A�ѓc�P�� �c�勳���́A�u�����ԋZ�p�v��Vol.64�ANo.�P�A2010�i2010�N1���P�����s�j�Ɍf�ڂ̘_���u�f�B�[�[��
�G���W�����̂P�O�N�v�i���ҁF�Ƒ��R���j�́u�T �����Ɂv�ɂ́A�ȉ��̕\�V�悤�ɋL�q����Ă���B
�G���W�����̂P�O�N�v�i���ҁF�Ƒ��R���j�́u�T �����Ɂv�ɂ́A�ȉ��̕\�V�悤�ɋL�q����Ă���B
�T�@������
�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E �r�o�K�X�̃N���[������B�������f�B�[�[���G���W���ɂƂ��āA�r�oCO�Q�̂����
��팸�͍�����傫�Ȓ���ۑ��ł���A����ۑ�̒B���ɂ́A�]���̃f�B�[�[���G���W���̗v�f�Z�p�J��
�ɉ����A�R���A�R�āA�G�}�̌����A�V�X�e������̓������Z�p�����߂��Ă���B�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E
|
�@���̂悤�ɁA�������R�c��̎����Ԕr�o�K�X���ψ���̃����o�[�ł���ѓc�����́A�f�B�[�[���G���W����CO
�Q�팸�i���R����P�j���u�傫�Ȓ���ۑ�v�ƒf�肳��Ă���A���́u�ۑ�B���v�ɂ́u�]���̃f�B�[�[���G���W���̗v�f
�V�X�e���ɉ����A�R���A�R�āA�G�}�̌����A�V�X�e������̓������Z�p�����߂��Ă���v�ƋL�ڂ���Ă���݂̂ł�
��B�����āA�f�B�[�[���G���W����CO�Q�팸�i���R����P�j�ɗL���ȋZ�p�������̓I�ɋL�q����Ă��Ȃ��̂ł�
��B���̂悤�ɁA�ѓc�����́A��^�f�B�[�[���g���b�N�̔R���2015�N�x�d�ʎԔR���ȏ�ɉ��P�ł����̓I��
�Z�p�A�C�e��������������Ɩ����A�f�B�[�[���G���W����CO�Q�팸�i���R����P�j�́u�傫�Ȓ���ۑ�v�ƁA�u�����ԋZ
�p�v���̓ǎ҂�P�Ɏ��B���コ��Ă��邾�����B���̂��Ƃ���A�ѓc�����́A�吹�����Ɠ��l�ɁA����̍X�Ȃ��^�g
���b�N�̏d�ʎԃ��[�h�R��̌��オ�ɂ߂Ď����̍���Ȃ��Ƃ�[���F������Ă�����̂Ɛ��@�����B�����āA���̂���
�͑����̃f�B�[�[���G���W���W�̊w�ҁE���Ƃł̋��ʂ����F���Ƃ��l������B�����āA���̋��ʔF���̂��ƂɁA��
���������܂��������R�c��������Ԕr�o�K�X���ψ�����w�ҁE���Ƃ́A�g���b�N���[�J����^�g���b�N�ɂ���
��u2015�N�x�d�ʎԔR���ȏ�̔R�����v�ƁA�u2016�N��NO���K���l�� 0.4 g/kWh�iWHTC���[�h�j�̔r�o�K�X�K��
�l�ȏ�̂m�n���팸�v���������邱�Ƃ��߂������Ɏ����\�ȋZ�p�J���̌��E�Ɣ��f���A2010�N7�����������R�c
��̑�10�����\���܂Ƃ߂��̂ł͂Ȃ����ƍl������B
�Q�팸�i���R����P�j���u�傫�Ȓ���ۑ�v�ƒf�肳��Ă���A���́u�ۑ�B���v�ɂ́u�]���̃f�B�[�[���G���W���̗v�f
�V�X�e���ɉ����A�R���A�R�āA�G�}�̌����A�V�X�e������̓������Z�p�����߂��Ă���v�ƋL�ڂ���Ă���݂̂ł�
��B�����āA�f�B�[�[���G���W����CO�Q�팸�i���R����P�j�ɗL���ȋZ�p�������̓I�ɋL�q����Ă��Ȃ��̂ł�
��B���̂悤�ɁA�ѓc�����́A��^�f�B�[�[���g���b�N�̔R���2015�N�x�d�ʎԔR���ȏ�ɉ��P�ł����̓I��
�Z�p�A�C�e��������������Ɩ����A�f�B�[�[���G���W����CO�Q�팸�i���R����P�j�́u�傫�Ȓ���ۑ�v�ƁA�u�����ԋZ
�p�v���̓ǎ҂�P�Ɏ��B���コ��Ă��邾�����B���̂��Ƃ���A�ѓc�����́A�吹�����Ɠ��l�ɁA����̍X�Ȃ��^�g
���b�N�̏d�ʎԃ��[�h�R��̌��オ�ɂ߂Ď����̍���Ȃ��Ƃ�[���F������Ă�����̂Ɛ��@�����B�����āA���̂���
�͑����̃f�B�[�[���G���W���W�̊w�ҁE���Ƃł̋��ʂ����F���Ƃ��l������B�����āA���̋��ʔF���̂��ƂɁA��
���������܂��������R�c��������Ԕr�o�K�X���ψ�����w�ҁE���Ƃ́A�g���b�N���[�J����^�g���b�N�ɂ���
��u2015�N�x�d�ʎԔR���ȏ�̔R�����v�ƁA�u2016�N��NO���K���l�� 0.4 g/kWh�iWHTC���[�h�j�̔r�o�K�X�K��
�l�ȏ�̂m�n���팸�v���������邱�Ƃ��߂������Ɏ����\�ȋZ�p�J���̌��E�Ɣ��f���A2010�N7�����������R�c
��̑�10�����\���܂Ƃ߂��̂ł͂Ȃ����ƍl������B
�@���̂悤�ȑ�^�g���b�N�̊ɂ�����NO���K���Ƃ����������R�c��̑�10�����\�i2010�N7���j�����肳�ꂽ�w�i�E��
���́A��^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W���ɂ������uNO���r�o�ƔR��\�̃g���[�h�I�t�W�������ł���Z�p���s
���v�Ƃ̒������R�c��̎����Ԕr�o�K�X���ψ�����w�ҁE���Ƃ�����F���ɂ����̂Ɛ��@�����B��^�g��
�b�N�p�f�B�[�[���G���W���ɂ����āA�����u2015�N�x�d�ʎԔR���v�Ƃقړ���������2016�N��NO�� �� 0.4 g/kWh�v
��茵�����m�n���K���̋������ۂ����Ȃ�A�������R�c��̎����Ԕr�o�K�X���ψ���̊w�ҁE���Ƃ́A�uNO��
�r�o�ƔR��\�̃g���[�h�I�t�W�������ł���Z�p���s���v�����{���g���b�N���[�J���Z�p�I�ɑΉ��ł��Ȃ����߁A
���{�ł̃f�B�[�[���g���b�N�����Y�E�̔�������ƂȂ�A�傫�ȍ������������Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��Ƃ̌��_�Ɏ��������̂Ɛ�
�������B�����āA�������R�c��̎����Ԕr�o�K�X���ψ���̊w�ҁE���Ƃ́A2016�N��NO�� �� 0.4 g/kWh���
���������m�n���K���̋��������ꍇ�ɂ��A���{�ł̃f�B�[�[���g���b�N�����Y�E�̔��̒��~�ƂȂ�s���̎��Ԃ������Ƃ�
������F���̂��߂ɁA2010�N�V���̒������R�c�����\�����\�ɂ����āA��^�g���b�N�i���d�ʎԁj��2016�N�Ɏ�
�{����鎟���̂m�n���K���l�Ƃ��āA2010�N���č��̂m�n���K���iNO�� �� 0.27 g/kWh�j���������Ɋɂ�NO�� �� 0.4 g/
kWh���K�����Ɍ��肵���\����������̂ƕM�҂ɂ͎v����̂ł���B
���́A��^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W���ɂ������uNO���r�o�ƔR��\�̃g���[�h�I�t�W�������ł���Z�p���s
���v�Ƃ̒������R�c��̎����Ԕr�o�K�X���ψ�����w�ҁE���Ƃ�����F���ɂ����̂Ɛ��@�����B��^�g��
�b�N�p�f�B�[�[���G���W���ɂ����āA�����u2015�N�x�d�ʎԔR���v�Ƃقړ���������2016�N��NO�� �� 0.4 g/kWh�v
��茵�����m�n���K���̋������ۂ����Ȃ�A�������R�c��̎����Ԕr�o�K�X���ψ���̊w�ҁE���Ƃ́A�uNO��
�r�o�ƔR��\�̃g���[�h�I�t�W�������ł���Z�p���s���v�����{���g���b�N���[�J���Z�p�I�ɑΉ��ł��Ȃ����߁A
���{�ł̃f�B�[�[���g���b�N�����Y�E�̔�������ƂȂ�A�傫�ȍ������������Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��Ƃ̌��_�Ɏ��������̂Ɛ�
�������B�����āA�������R�c��̎����Ԕr�o�K�X���ψ���̊w�ҁE���Ƃ́A2016�N��NO�� �� 0.4 g/kWh���
���������m�n���K���̋��������ꍇ�ɂ��A���{�ł̃f�B�[�[���g���b�N�����Y�E�̔��̒��~�ƂȂ�s���̎��Ԃ������Ƃ�
������F���̂��߂ɁA2010�N�V���̒������R�c�����\�����\�ɂ����āA��^�g���b�N�i���d�ʎԁj��2016�N�Ɏ�
�{����鎟���̂m�n���K���l�Ƃ��āA2010�N���č��̂m�n���K���iNO�� �� 0.27 g/kWh�j���������Ɋɂ�NO�� �� 0.4 g/
kWh���K�����Ɍ��肵���\����������̂ƕM�҂ɂ͎v����̂ł���B
�@���̌��ʁA�O�q�̐}�Q�Ɏ��������{�A�č��A���B�̏��p��(�ԗ����d��3.5����)��NO����PM�̋K�������̕ϑJ������
�Ɩ��炩�Ȃ悤�ɁA�č��ł́A����2010�N��NO�� �� 0.27 g/kWh�ɋK�����������{����Ă���̂��B�������A���{�ł́A
2016�N�ɂ����NO���� 0.4 g/kWh��NO���K�������������ɉ߂��Ȃ����Ƃ��A�������R�c�����\�����\�Ŕ��\��
�ꂽ�̂ł���B���̂��߁A��^�g���b�N�i���d�ʎԁj�̕���ł́A�č��̂m�n���K����2010�N��NO�� �� 0.27 g/kWh�ł�
��ɂ�������炸�A���{�ɂ����Ă�2016�N�ɋK�����������{���ꂽ���_�ł�NO�� �� 0.4 g/kWh�̑����Ɋɂ�NO���K
�������{����邱�ƂɂȂ�B
�Ɩ��炩�Ȃ悤�ɁA�č��ł́A����2010�N��NO�� �� 0.27 g/kWh�ɋK�����������{����Ă���̂��B�������A���{�ł́A
2016�N�ɂ����NO���� 0.4 g/kWh��NO���K�������������ɉ߂��Ȃ����Ƃ��A�������R�c�����\�����\�Ŕ��\��
�ꂽ�̂ł���B���̂��߁A��^�g���b�N�i���d�ʎԁj�̕���ł́A�č��̂m�n���K����2010�N��NO�� �� 0.27 g/kWh�ł�
��ɂ�������炸�A���{�ɂ����Ă�2016�N�ɋK�����������{���ꂽ���_�ł�NO�� �� 0.4 g/kWh�̑����Ɋɂ�NO���K
�������{����邱�ƂɂȂ�B
�@�Ƃ���ŁA�����Ԕr�o�K�X���ψ�����w�ҁE���Ƃ́A�������m�n���K���������������ꂽ�ہA2015�N�x�d�ʎԔR
���̎{�s���l�����Ȃ���2016�N���{�Ɏ��{�ł������Ȃm�n���K���l�̋������x�����c�_���ꂽ���̂ƍl������B
���̂悤�ɁA�����̂m�n���K�������{�����2016�N�ɂ́A2015�N�x�d�ʎԔR�����{�s����Ă��邽�߁A�g���b�N���[
�J�́A�������m�n���K�������ɑΉ������^�f�B�[�[���g���b�N�ł́A�m�n���̍팸�ƔR��̌����}�邱�Ƃ��K�v�Ƃ�
��B�������A�f�B�[�[���G���W���ł́A�̂���m�n���팸�ƔR����P���g���[�h�I�t�̊W�ł��邱�Ƃ��ǂ��m���Ă���A
�m�n���팸�ƔR����P���Ɏ������邱�Ƃ́A�Z�p�I�ɍ���ƍl����̂��f�B�[�[���W�҂̂���܂ł̏펯�E�F��
�ł���A���݂������펯�E�F����������Ă���w�ҁE���Ƃ́A�ɂ߂đ����ƍl������B
���̎{�s���l�����Ȃ���2016�N���{�Ɏ��{�ł������Ȃm�n���K���l�̋������x�����c�_���ꂽ���̂ƍl������B
���̂悤�ɁA�����̂m�n���K�������{�����2016�N�ɂ́A2015�N�x�d�ʎԔR�����{�s����Ă��邽�߁A�g���b�N���[
�J�́A�������m�n���K�������ɑΉ������^�f�B�[�[���g���b�N�ł́A�m�n���̍팸�ƔR��̌����}�邱�Ƃ��K�v�Ƃ�
��B�������A�f�B�[�[���G���W���ł́A�̂���m�n���팸�ƔR����P���g���[�h�I�t�̊W�ł��邱�Ƃ��ǂ��m���Ă���A
�m�n���팸�ƔR����P���Ɏ������邱�Ƃ́A�Z�p�I�ɍ���ƍl����̂��f�B�[�[���W�҂̂���܂ł̏펯�E�F��
�ł���A���݂������펯�E�F����������Ă���w�ҁE���Ƃ́A�ɂ߂đ����ƍl������B
�@���ɁA2016�N�Ɏ��{����鎟���̑�^�g���b�N�̂m�n���K���Ƃ��āu2005�N�̑攪�����\��NO������ڕW�� 0.23 g/
kWh�܂ł��m�n���팸�v���K�肵���ꍇ�ɂ́A�����̑�^�g���b�N�́A���R�A2015�N�x�d�ʎԔR����B�����Ă��邱
�Ƃ��K�v�ł���B���̂��߁A�����i��2016�N�j�̂m�n���K���K���̑�^�g���b�N�́A�Z�p�I�ɍ���Ȃm�n���팸�ƔR���
�P�̃g���[�h�I�t���������邱�Ƃ��K�{�ƂȂ�B�������A�O�q�̕\�T�Ɏ������悤�ɁA���݁A�m�n���팸�ƔR����P�̃g���[
�h�I�t�������ł���Z�p�́A�����ɑ��݂��Ȃ��Ƒ����̊w�ҁE���Ƃ��F������Ă��邱�Ƃ������̂悤���B�����āA��
���Ԕr�o�K�X���ψ�����w�ҁE���Ƃ����̑����̊w�ҁE���ƂƓ��l�ɁA�m�n���팸�ƔR����P�̃g���[�h�I�t��
�����ł���Z�p���������m����Ă��Ȃ��Ɖ��肵���ꍇ�ɂ́A2015�N�x�d�ʎԔR�����{�s����Ă�����{�̓�
�ꎖ����l���āA�č���2010�N�̂m�n���K���iNO�� �� 0.27 g/kWh�j�����啝�Ɋɂ����A�����Ԕr�o�K�X���ψ��
NO�� �� 0.4 g/kWh�̂m�n���K���l��2016�N�Ɏ��{���邱�Ƃ���������ꂽ���Ƃ́A�d���������悤�Ɏv����B
kWh�܂ł��m�n���팸�v���K�肵���ꍇ�ɂ́A�����̑�^�g���b�N�́A���R�A2015�N�x�d�ʎԔR����B�����Ă��邱
�Ƃ��K�v�ł���B���̂��߁A�����i��2016�N�j�̂m�n���K���K���̑�^�g���b�N�́A�Z�p�I�ɍ���Ȃm�n���팸�ƔR���
�P�̃g���[�h�I�t���������邱�Ƃ��K�{�ƂȂ�B�������A�O�q�̕\�T�Ɏ������悤�ɁA���݁A�m�n���팸�ƔR����P�̃g���[
�h�I�t�������ł���Z�p�́A�����ɑ��݂��Ȃ��Ƒ����̊w�ҁE���Ƃ��F������Ă��邱�Ƃ������̂悤���B�����āA��
���Ԕr�o�K�X���ψ�����w�ҁE���Ƃ����̑����̊w�ҁE���ƂƓ��l�ɁA�m�n���팸�ƔR����P�̃g���[�h�I�t��
�����ł���Z�p���������m����Ă��Ȃ��Ɖ��肵���ꍇ�ɂ́A2015�N�x�d�ʎԔR�����{�s����Ă�����{�̓�
�ꎖ����l���āA�č���2010�N�̂m�n���K���iNO�� �� 0.27 g/kWh�j�����啝�Ɋɂ����A�����Ԕr�o�K�X���ψ��
NO�� �� 0.4 g/kWh�̂m�n���K���l��2016�N�Ɏ��{���邱�Ƃ���������ꂽ���Ƃ́A�d���������悤�Ɏv����B
�@�������A����͖O���܂ł��A�����Ԕr�o�K�X���ψ�����w�ҁE���Ƃ����̑����̊w�ҁE���ƂƓ��l�ɁA�uNO���r
�o�ƔR��\�̃g���[�h�I�t�W�������ł���Z�p���s���v�Ƃ̌��������F���Ɋ�Â��ē����o�������_�ł���ƕM
�҂͍l���Ă���B�������A���݁A��^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W���̂m�n���팸�ƔR����P�̐V�����Z�p�Ƃ��ẮA�C��
�x�~�́A�f�B�[�[���̂m�n���팸�ƔR�����̈ꋓ�����̋Z�p���I�ɏڏq���Ă���悤�ɁA2006�N4��7���ɊJ�݂���
�M�҂̃z�[���y�[�W�ł́A�uNO���r�o�ƔR��\�̃g���[�h�I�t�W�������ł���Z�p�v�Ƃ��āA�C���x�~�G���W���i��
�����J2005-54771�j�̋Z�p���Ă��Ă���̂ł���B�������A�����Ԕr�o�K�X���ψ�����w�ҁE���Ƃ⑼�̑���
�̊w�ҁE���Ƃ́A��^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W����NO���r�o�ƔR��\�̃g���[�h�I�t�W�������ł���M�Ғ�
�Ă��C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p����Ȃɖ����E�َE���Ă���̂ł���B���̈���ŁA�����Ԕr�o
�K�X���ψ�����w�ҁE���Ƃ��uNO���r�o�ƔR��\�̃g���[�h�I�t�W�������ł���Z�p���s���v�Ƃ̌���F����
��Â����č���2010�N�̂m�n���K���iNO�� �� 0.27 g/kWh�j�����啝�Ɋɂ����A�����Ԕr�o�K�X���ψ��NO�� ��
0.4 g/kWh�̂m�n���K���l��2016�N�Ɏ��{���邱�Ƃ����肵�����Ƃ́A���{�̍����ɑ��Ă̔w�M�s�ׂƂ��l������B
�o�ƔR��\�̃g���[�h�I�t�W�������ł���Z�p���s���v�Ƃ̌��������F���Ɋ�Â��ē����o�������_�ł���ƕM
�҂͍l���Ă���B�������A���݁A��^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W���̂m�n���팸�ƔR����P�̐V�����Z�p�Ƃ��ẮA�C��
�x�~�́A�f�B�[�[���̂m�n���팸�ƔR�����̈ꋓ�����̋Z�p���I�ɏڏq���Ă���悤�ɁA2006�N4��7���ɊJ�݂���
�M�҂̃z�[���y�[�W�ł́A�uNO���r�o�ƔR��\�̃g���[�h�I�t�W�������ł���Z�p�v�Ƃ��āA�C���x�~�G���W���i��
�����J2005-54771�j�̋Z�p���Ă��Ă���̂ł���B�������A�����Ԕr�o�K�X���ψ�����w�ҁE���Ƃ⑼�̑���
�̊w�ҁE���Ƃ́A��^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W����NO���r�o�ƔR��\�̃g���[�h�I�t�W�������ł���M�Ғ�
�Ă��C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p����Ȃɖ����E�َE���Ă���̂ł���B���̈���ŁA�����Ԕr�o
�K�X���ψ�����w�ҁE���Ƃ��uNO���r�o�ƔR��\�̃g���[�h�I�t�W�������ł���Z�p���s���v�Ƃ̌���F����
��Â����č���2010�N�̂m�n���K���iNO�� �� 0.27 g/kWh�j�����啝�Ɋɂ����A�����Ԕr�o�K�X���ψ��NO�� ��
0.4 g/kWh�̂m�n���K���l��2016�N�Ɏ��{���邱�Ƃ����肵�����Ƃ́A���{�̍����ɑ��Ă̔w�M�s�ׂƂ��l������B
�@�Ȃ��Ȃ�A�f�B�[�[���G���W���̐��Ƃł���A���N�ɂ킽���ĒN�����A����肪�o��قNJ��]���Ă����uNO��
�r�o�ƔR��\�̃g���[�h�I�t�W�������ł���Z�p�v���A�u�C���x�~�f�B�[�[���G���W���v�ł���B���̂悤�ȁu�C���x
�~�f�B�[�[���G���W���v�̋Z�p���A�C���^�[�l�b�g�Ɍ��J���ꂳ��Ă���A�N�ł��ȒP�Ɏ�ɓ���̂ł���B���̂��Ƃ��l
����ƁA�����Ԕr�o�K�X���ψ��2016�N�Ɏ��{����鎟���̂m�n���K���l�̋c�_����Ă���ے��ɂ����āA����
�Ԕr�o�K�X���ψ���̏��Ȃ��Ƃ��ꕔ�̐l�B�́A�f�B�[�[���G���W���̕��������̂m�n���팸�ƔR�����ɗL��
���C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p���b��ɂȂ��Ă����\���́A�\���ɍl������B����͖O���܂�
�����̘b�ł��邪�A�����Ԕr�o�K�X���ψ�����w�ҁE���Ƃ��A�f�B�[�[���G���W���́u�d�ʎԃ��[�h�R��̌���v
�Ɓu�m�n���팸�v�̓����팸�ɋɂ߂ėL���ȁu�C���x�~�v�̋Z�p�����m���ꂽ�����ɂ�������炸�A���{�������̂m�n��
�K���Ƃ��āA�č������啝�Ɋɘa���ꂽNO���K���l�� 0.4 g/kWh�iWHTC���[�h�j�̔r�o�K�X�K����2016�N�Ɏ��{����
���Ƃ����肳�ꂽ�����Ƃ���A�傢�ɖ�肪����Ǝv�����A�@���Ȃ��̂ł��낤���B���̏ꍇ�ɂ́A�f�B�[�[���G���W
���̕��������̂m�n���팸�ƔR�����ɗL���ȁu�C���x�~�v�̋Z�p�̗̍p�ɂ��R�X�g�������������g���b�N���[�J��
��������̈ӌ��ɂ���āA�A�����Ԕr�o�K�X���ψ���č������啝�Ɋɘa���ꂽNO���K���l�� 0.4 g/kWh
�iWHTC���[�h�j�̔r�o�K�X�K����2016�N�Ɏ��{���邱�Ƃ����肳�ꂽ���Ƃ����Ɏ����ł���A�傢�ɖ�肪�����
���킴��Ȃ��B
�r�o�ƔR��\�̃g���[�h�I�t�W�������ł���Z�p�v���A�u�C���x�~�f�B�[�[���G���W���v�ł���B���̂悤�ȁu�C���x
�~�f�B�[�[���G���W���v�̋Z�p���A�C���^�[�l�b�g�Ɍ��J���ꂳ��Ă���A�N�ł��ȒP�Ɏ�ɓ���̂ł���B���̂��Ƃ��l
����ƁA�����Ԕr�o�K�X���ψ��2016�N�Ɏ��{����鎟���̂m�n���K���l�̋c�_����Ă���ے��ɂ����āA����
�Ԕr�o�K�X���ψ���̏��Ȃ��Ƃ��ꕔ�̐l�B�́A�f�B�[�[���G���W���̕��������̂m�n���팸�ƔR�����ɗL��
���C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p���b��ɂȂ��Ă����\���́A�\���ɍl������B����͖O���܂�
�����̘b�ł��邪�A�����Ԕr�o�K�X���ψ�����w�ҁE���Ƃ��A�f�B�[�[���G���W���́u�d�ʎԃ��[�h�R��̌���v
�Ɓu�m�n���팸�v�̓����팸�ɋɂ߂ėL���ȁu�C���x�~�v�̋Z�p�����m���ꂽ�����ɂ�������炸�A���{�������̂m�n��
�K���Ƃ��āA�č������啝�Ɋɘa���ꂽNO���K���l�� 0.4 g/kWh�iWHTC���[�h�j�̔r�o�K�X�K����2016�N�Ɏ��{����
���Ƃ����肳�ꂽ�����Ƃ���A�傢�ɖ�肪����Ǝv�����A�@���Ȃ��̂ł��낤���B���̏ꍇ�ɂ́A�f�B�[�[���G���W
���̕��������̂m�n���팸�ƔR�����ɗL���ȁu�C���x�~�v�̋Z�p�̗̍p�ɂ��R�X�g�������������g���b�N���[�J��
��������̈ӌ��ɂ���āA�A�����Ԕr�o�K�X���ψ���č������啝�Ɋɘa���ꂽNO���K���l�� 0.4 g/kWh
�iWHTC���[�h�j�̔r�o�K�X�K����2016�N�Ɏ��{���邱�Ƃ����肳�ꂽ���Ƃ����Ɏ����ł���A�傢�ɖ�肪�����
���킴��Ȃ��B
�@�Ȃ��A���݁A�l�����Ă���f�B�[�[���G���W���ɂ�����u�C���x�~�v�̕��@�Ƃ��ẮA�\�W�́u�e��̋C���x�~�G���W
���̃V�X�e���v�Ɏ������Q��ނ���Ă���Ă���B
���̃V�X�e���v�Ɏ������Q��ނ���Ă���Ă���B
| |
|
|
| |
|
���@�Q��̃^�[�{�ߋ��@�����ɑ�������Q�^�[�{�����̋C���x�~�f�B�[�[��
�G ���W���̋C���x�~�V�X�e���B
���@���̃V�X�e���̏� �ׂ��C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̃y�[�W �������������������B |
| |
���@�C���x�~�̍ő�ړI�ł������������̑啝�ȔR��팸��SCR�G�}
�̊������i�ɂ��\����NO���팸���\
�i�T�`�P�O�����x�̏d�ʎԃ��[�h�R��l�̍팸���\�j ���@�x�~�^�]����C���Q�̋z�C�قƔr�C�ق̗����A���͕Ј���𖧕� ��z�E�r�C�ق̃��t�g���䂪�s�v |
|
| |
���@�^�[�{�ߋ��@�͂Q��i���������e�ʁj �̂��߃R�X�g�������傫������
���@���C�n�Ɣr�C�n�����G |
|
| |
|
���@�]���̃V���O���^�[�{��Q�i�ߋ��̃f�B�[�[���G���W����P���ɋC���x�~��
���ꍇ �̋C���x�~�̃V�X�e���ł���B
���@�{���{�̂b�n�Q�팸�i���R�����j�̋Z�p�������� �@�@�i�z�E�r�C�ق��x�~�����V���O���^�[�{�����̋C���x�~�𐄏�����L���j �i�o�T�Fhttp://www.its.ucdavis.edu/events/outreachevents/asilomar2007/ presentations/Day%202%20Session%201/Anthony%20Greszler.pdf�j 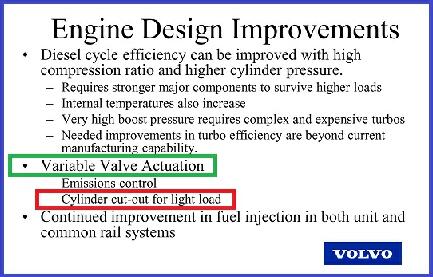 |
| |
���@�V���O���^�[�{�̃f�B�[�[���G���W���ł́A�^�[�{�ߋ��@�͂P��i��������e
�ʁj���߂ɃR�X�g���������Ȃ�����
���@���C�n�Ɣr�C�n���V���v�� |
|
| |
���@�C���x�~�̍ő�ړI�ł������������̔R��팸��SCR�G�}�̊���
���ɂ��NO���팸���啝�ɗ�邱��
���@�C���x�~�^�]���̔M�����̌����}�邽�߂ɂ́A�x�~�^�]����C���Q�� �z�C�قƔr�C�ق̗����A���͕Ј���𖧕���z�E�r�C�ق̃��t�g���䂪 �K�v (���݂ɁA�x�~�^�]����C���Q�̋z�C�قƔr�C�ق̗����A���͕Ј���𖧕� ��z�E�r�C�ق̃��t�g��������{���Ȃ��ꍇ�͔r�C�K�X���x�̒ቺ�ɂ��A�f SCR�G�}�ł�NO���팸�@�\����錇�_������B�j |
|
�Q�^�[�{�����̋C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�ɔ�r���A�u�C���x�~���^�]�ł��镉�ׂ̗̈悪��
�����Ɓv�A�u���������̔R��팸��SCR�G�}�̊������ɂ��NO���팸�̋@�\���啝�ɗ�邱�Ɓv����сu�z�E
�r�C�ق̃��t�g���䂪�K�v�Ȃ��߂ɑ傫�ȃR�X�g���ƂȂ邱�Ɓv���̌��_������B�{���{�Ɠ��l�ɁA�����U������
���A�C���x�~�G���W���ł͋z�E�r�C�ق�ٕ��䂪�K�v�ƍl���Ă���悤���B���̏؋��ɁA�����U�����Ԃ̎q��ЂŋZ
�p�J������v�Ɩ��̊�����Ђ����U�Z���~�b�N�X�����������J�Q�O�O�O�|�P�S�T�S�Q�R�i�C�����䎮�G���W���ً̕x�~�@
�\����ыC�����䎮�G���W���j�̓������o�肵�Ă��邱�Ƃ��疾�炩���B�ǂ����A�g���b�N���[�J�̃f�B�[�[���G���W��
�̐��Ƃ́A�f�B�[�[���G���W���̋C���x�~�ɂ����Ă��A�K�\�����G���W���Ɠ��l�̋z�E�r�C�ق̋x�~�@�\��
�K�v�Ƃ̐���ς������悤�Ɏv����̂ł���B
���������A�K�\�����G���W���ł́A�\�����R�Ă̂��߂ɃV�����_���̂m�n���́A�g�U�R�Ẵf�B�[�[���G���W�������\
�{�ȏ��������������B�������A���̃K�\�����G���W���ł́A�R�ĂŐ��������ʂ̂m�n�����O���G�}�ɂ���ĊҌ����A�m�n��
�̔r�o�ʂ�啝�ɍ팸���������Ă���̂��B���������āA�A�C�h�����O�^�]���܂߂ĎO���G�}�ő啝�ɂm�n���̔r�o��
�팸�ł��Ȃ���A���݂̔r�o�K�X�K���ɂ͓K���ł��Ȃ��̂ł���B���̂��߁A�A�C�h�����O�^�]���܂߂āA���ɋx�~
�C���^�]����ғ��C���i���R�ċC���j�ɐ�ւ�����ꍇ�ɂ͍��Z�x�̂m�n���̔r�C�K�X���O���G�}�ɗ������邱��
�ɂȂ邪�A���̏ꍇ�ɂ��m���ɂm�n�����Ҍ����邽�߂ɁA�G���W���̉^�]���͏�ɎO���G�}�̉��x�������Ɉێ�����
���Ă���K�v������B���̂Ȃ�A�K�\���������Ԃ̑��s���x���ς��ꍇ�A�C���x�~�G���W���̕��וϓ��ɉ�����
�x�~����C������Ⴂ���x�̔r�C�K�X���O���G�}�ɗ��������ꍇ�ɂ́A�G�}���x�̒ቺ�ɂ���ĎO���G�}�ł̂m�n
�����̔r�o�K�X�팸�̋@�\���������ቺ����s��������Ă��܂����߂��B���̋x�~�C������̒ቷ�̔r�C�K�X���O
���G�}�ɗ������邱�Ƃɂ��O���G�}�ł̔r�o�K�X�팸�̋@�\�ቺ��h�~���邽�߁A�C���x�~�K�\�����G���W���ł�
�z�E�r�C�قٓ̕���̋x�~�@�\�i���ٕ@�\�j���K�{�ƂȂ�B
�@�������A�f�B�[�[���G���W���ł́A�O���G�}�ɂ��m�n�����̔r�o�K�X�̍팸�̋Z�p���p�����Ă��Ȃ����߁A�x�~�C
������z����C�����̂܂܉��x�̒Ⴂ�r�C�K�X�Ƃ��ăG���W������r�C�ǂɐڑ������r�o�K�X�㏈�����u�i���A�f�r
�b�q�G�}��c�o�e���u�j�ɗ������Ă��A�傫�Ȗ����邱�Ƃ͂Ȃ��B���̏؋��ɁA���݂̒ʏ�̃f�B�[�[���G���W����
�A�C�h���^�]���ɂ�����r�C�K�X���x�́A100���ȉ��̒ቷ�ƂȂ��Ă���̂�����ł���B���������āA�f�B�[�[���G��
�W���̋C���x�~�ł́A�K�\�����G���W���̋C���x�~�ō̗p����Ă���z�E�r�C�قٓ̕���̋x�~�@�\�i���ٕ@�\�j��
�p���Ȃ��ꍇ�ł��A�f�B�[�[���G���W���̔R�����̋@�\�����h�ɉʂ�����̂ł���B
�@�����Ɣ���Ղ���������A�M�҂���Ă��Ă���Q�^�[�{�����̋C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�́A������
���̔R��팸��SCR�G�}�̊������ɂ��NO���팸���啝�ɗD��Ă����ɁA�z�E�r�C�ق̃��t�g���䂪�s�v�Ȓ�R
�X�g�̋C���x�~�V�X�e���Ɖ]�����Ƃł���B���������āA�����̑�^�g���b�N�̋C���x�~�̋Z�p�Ƃ��ẮA�M�Ғ�Ă̂Q
�^�[�{�����̋C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�������������Ƃ͖��炩���B�����Ƃ��A�M�҂̒�Ă���f�B�[�[
�����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�ɂ����āA�x�~�C���ɍ����ȋz�E�r�C�ق̋x�~�@�\��t�������ꍇ��
�́A�x�~�C���̋z�C�ٕ��Ɣr�C�ٕ��̋C�̗���̒�R�ɂ�鑹���������ł��邱�ƂɂȂ�B���̂��߁A���̋z�E�r�C
�ٕ��̗���̒�R�ɂ���̔R�����h�~�ł��郁���b�g������B�������A�z�r�C�̃|���s���O�������K�\�����G
���W���ɔ�ׂđ啝�ɏ��Ȃ��f�B�[�[���G���W���ɂ����ẮA�f�B�[�[�����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j
�ɋz�E�r�C�ق̋x�~�@�\��t�������ꍇ�̔R�����́A���X������̂Ɛ��@�����B���������āA�C���x�~�G���W��
�i�������J2005-54771�j�ɂ́A�z�E�r�C�ق̋x�~�@�\�́A�R�X�g�����̃f�����b�g���l������ƁA�̗p���Ȃ�����������
�l������B
�����āA�ߋ��U�C���f�B�[�[���̋C���x�~�G���W���ɂ����āA���쎩���Ԃ́u�S�C���A���̉ߋ��@��������z�E�r�C��
��~���̋C���x�~�V�X�e���v�ł́A�R�C�����x�~����G���W���^�]�̗̈�͖w�Ǒ��݂��Ȃ��B�������A�M�Ғ�Ă�2�^
�[�{�����̋C���x�~�V�X�e���i���C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�j�ł́A�G���W����1�^�Q���ȉ��ɂ���
�āA�R�C���̋C���Q�������ғ�����C���x�~�^�]���\�ł���B
��~���̋C���x�~�V�X�e���v�ł́A�R�C�����x�~����G���W���^�]�̗̈�͖w�Ǒ��݂��Ȃ��B�������A�M�Ғ�Ă�2�^
�[�{�����̋C���x�~�V�X�e���i���C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�j�ł́A�G���W����1�^�Q���ȉ��ɂ���
�āA�R�C���̋C���Q�������ғ�����C���x�~�^�]���\�ł���B
�@�����āA��^�g���b�N�̎��ۂ̑��s�ɂ����ẮA�G���W���^�]��1�^�Q���ȉ��̌y���ׂ����p����邽�߁A
�y���ׂɂ����ĂR�C�����x�~����G���W���^�]���\���M�Ғ�Ă�2�^�[�{�����̋C���x�~�V�X�e���i���C��
�x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�j�́A��^�g���b�N�̏\���ȑ��s�R��̌��オ�\�ł���B
�y���ׂɂ����ĂR�C�����x�~����G���W���^�]���\���M�Ғ�Ă�2�^�[�{�����̋C���x�~�V�X�e���i���C��
�x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�j�́A��^�g���b�N�̏\���ȑ��s�R��̌��オ�\�ł���B
�\�X�@�����ĂƕM�Ғ�Ă̋C���x�~�V�X�e�����ߋ��U�C���G���W���ɂ�����ғ��C�����̃}�b�v�ƔR��̔�r
| |
|
�i�P�j �M�Ғ�Ă��C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j
�̋C���x�~����̃}�b�v�@�i�U�C���ߋ��G���W���j
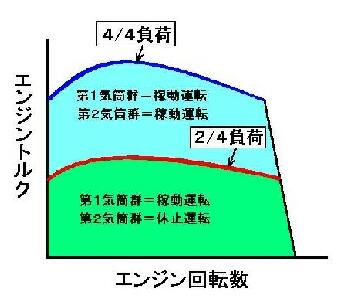 |
�i�P�j ����́u�z�E�r�C�ْ�~���̋C���x�~�V�X�e���v
�ɂ���C���x�~����̃}�b�v�@�i�U�C���ߋ��G���W���j
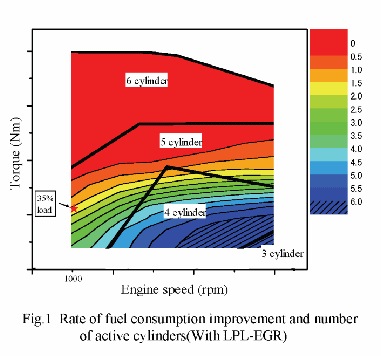 |
�i�Q�j��^�g���b�N�̍��������s���̔R����P
�@�E�������H�̑��s�R��́A�T�`�P�O���̒ጸ
�@�@�i���҂̐���j
|
�i�Q�j��^�g���b�N�̍��������s���̔R����P
�@�E�������H�̑��s�R��́A�S���̉��P
|
�i�Q�j��^�g���b�N��JE0�T���[�h�̔R����P
�@�E�d�ʎԃ��[�h�R��́A�T�`�P�O���̒ጸ
�@�@�i���҂̐���j
|
�i�R�j��^�g���b�N��JE0�T���[�h�̔R����P
�E�d�ʎԃ��[�h�R��́A�Q�`�R���̉��P
�@�i���҂̐���j
|
�@�ȏ�̂��Ƃ���A�����I�ɑ�^�g���b�N�̔R������}��Z�p�Ƃ��ẮA���҂���Ă��Ă����C���x�~�G���W
���i�������J2005-54771�j���䂪���ōL�����p�������\���́A�قڊԈႢ�Ȃ��ƍl�������B�Ȃ��A���쎩
���Ԓ�Ắu�S�C���A���̉ߋ��@��������z�E�r�C�ْ�~���̋C���x�~�V�X�e���v�̋Z�p�ɔ�r�����ꍇ�A�M�Ғ�
�Ă��C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�́A��^�g���b�N�̔R����i�i�ɉ��P�ł���@�\�E���\���������Z�p
�ł���B���̂��Ƃɂ��ẮA���쎩���Ԃ��_�����\�����R����P�@�\�̗��C���x�~�V�X�e���̃y�[�W�ɏڏq����
����̂ŁA�����̂�����͂����������������B
���i�������J2005-54771�j���䂪���ōL�����p�������\���́A�قڊԈႢ�Ȃ��ƍl�������B�Ȃ��A���쎩
���Ԓ�Ắu�S�C���A���̉ߋ��@��������z�E�r�C�ْ�~���̋C���x�~�V�X�e���v�̋Z�p�ɔ�r�����ꍇ�A�M�Ғ�
�Ă��C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�́A��^�g���b�N�̔R����i�i�ɉ��P�ł���@�\�E���\���������Z�p
�ł���B���̂��Ƃɂ��ẮA���쎩���Ԃ��_�����\�����R����P�@�\�̗��C���x�~�V�X�e���̃y�[�W�ɏڏq����
����̂ŁA�����̂�����͂����������������B
�@�Ƃ���ŁA�ŋ߁A�M�҂��^��Ɏv�������Ƃ́A���ȁE�������R�c��̎����Ԕr�o�K�X���ψ�����w�ҁE���
�Ƃ́A�u2015�N�x�d�ʎԔR���v���{�s�������{�ł�NO���̑啝�ȍ팸������ƒf�肵�A���{�������̂m�n���K
���Ƃ��āA�č������啝�Ɋɘa���ꂽNO���K���l�� 0.4 g/kWh�iWHTC���[�h�j�i�}�Q�Q�Ɓj�̔r�o�K�X�K����2016�N��
���{���邱�Ƃ����肵�����Ƃ��B����́A�����Ԕr�o�K�X���ψ�����w�ҁE���Ƃ́A�uNOx�̍팸�v�Ɓu�R��̌�
��v���\�ȃf�B�[�[���G���W���Z�p�������_�ő��݂��Ȃ��Ƃ̔��f����A���{�������̂m�n���K���Ƃ��āA�č�����
�啝�Ɋɘa���ꂽNO���K���l�� 0.4 g/kWh�iWHTC���[�h�j�̔r�o�K�X�K����2016�N�Ɏ��{���邱�Ƃɂ������̂Ɛ�����
���B�Ƃ��낪�A�uNOx�̍팸�v�Ɓu�R��̌���v���\�ȃf�B�[�[���G���W���Z�p�́A���ɐ��̒��ɑ��݂��Ă���̂ł�
��B����́A�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p���B���̂Q�^�[�{�����̋C���x�~�G���W���i�������J
2005-54771�j�̋Z�p�́A�d�ʎԃ��[�h�R��̍팸�ɗL���Ȃ��Ƃɉ����A����������SCR�G�}�̊������ɂ��\��
��NO���팸���\�ł���B���̂悤�ȁA��^�g���b�N�́uNOx�̍팸�v�Ɓu�R��̌���v�ɗL���ȋZ�p�����ȁE������
�R�c��̎����Ԕr�o�K�X���ψ�����w�ҁE���Ƃ��َE���A�����āA�������R�c��č������啝�Ɋɘa��
�ꂽ2016�N�Ɏ��{��NO���K���l�� 0.4 g/kWh�iWHTC���[�h�j�i�}�Q�Q�Ɓj�̔r�o�K�X�K���l�����Ȃɓ��\��������
�́A�S���[���̂ł��Ȃ����Ƃł���B
�Ƃ́A�u2015�N�x�d�ʎԔR���v���{�s�������{�ł�NO���̑啝�ȍ팸������ƒf�肵�A���{�������̂m�n���K
���Ƃ��āA�č������啝�Ɋɘa���ꂽNO���K���l�� 0.4 g/kWh�iWHTC���[�h�j�i�}�Q�Q�Ɓj�̔r�o�K�X�K����2016�N��
���{���邱�Ƃ����肵�����Ƃ��B����́A�����Ԕr�o�K�X���ψ�����w�ҁE���Ƃ́A�uNOx�̍팸�v�Ɓu�R��̌�
��v���\�ȃf�B�[�[���G���W���Z�p�������_�ő��݂��Ȃ��Ƃ̔��f����A���{�������̂m�n���K���Ƃ��āA�č�����
�啝�Ɋɘa���ꂽNO���K���l�� 0.4 g/kWh�iWHTC���[�h�j�̔r�o�K�X�K����2016�N�Ɏ��{���邱�Ƃɂ������̂Ɛ�����
���B�Ƃ��낪�A�uNOx�̍팸�v�Ɓu�R��̌���v���\�ȃf�B�[�[���G���W���Z�p�́A���ɐ��̒��ɑ��݂��Ă���̂ł�
��B����́A�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p���B���̂Q�^�[�{�����̋C���x�~�G���W���i�������J
2005-54771�j�̋Z�p�́A�d�ʎԃ��[�h�R��̍팸�ɗL���Ȃ��Ƃɉ����A����������SCR�G�}�̊������ɂ��\��
��NO���팸���\�ł���B���̂悤�ȁA��^�g���b�N�́uNOx�̍팸�v�Ɓu�R��̌���v�ɗL���ȋZ�p�����ȁE������
�R�c��̎����Ԕr�o�K�X���ψ�����w�ҁE���Ƃ��َE���A�����āA�������R�c��č������啝�Ɋɘa��
�ꂽ2016�N�Ɏ��{��NO���K���l�� 0.4 g/kWh�iWHTC���[�h�j�i�}�Q�Q�Ɓj�̔r�o�K�X�K���l�����Ȃɓ��\��������
�́A�S���[���̂ł��Ȃ����Ƃł���B
�@���̂悤�ɁA�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�Ɖ]����^�g���b�N�́uNOx�̍팸�v�Ɓu�R��̌���v���\�ȋZ
�p�����ɑ��݂��Ă���ɂ�������炸�A���{�̐��{�����⎩���Ԕr�o�K�X���ψ���̐l�B�́A�@���Ȃ闝�R�ɂ�
���āA���́u�C���x�~�v�̋Z�p��َE���Ă���̂ł��낤���B���́u�C���x�~�v�̋Z�p��َE�������ʁA���{�̐��{����
�⎩���Ԕr�o�K�X���ψ���̐l�B�́A���{�������̂m�n���K���Ƃ��āA�č������ɂ����x����NO���K���l�� 0.4 g
/kWh�iWHTC���[�h�j�̔r�o�K�X�K����2016�N�Ɏ��{���邱�Ƃ����肹����Ȃ������̂ł͂Ȃ����Ɛ��@�����B
�ӂƎv�����Ƃ́A�č��l�ɔ�r���A���{�l�̕����Ȃm�n���Z�x�̑�C���̉��ł����N���Q���邱�Ɩ����A痂�����
���ł�����ʂȐ����͂�����Ă���Ƃ̍����ƂȂ�u�Ȃm�n���Z�x�̑�C���ɂ����錒�N��Q�ɂ��Ă̕č��l
�Ɠ��{�l�̉u�w�I�Ȕ�r�����̌��ʁv�̃f�[�^���A���{�̐��{�����⎩���Ԕr�o�K�X���ψ���̐l�B���ۗL����
�Ă���̂ł��낤���B�펯�I�ɍl����A���{�l���ȑ�C���ł��č��l�������N��Q���Ȃ��悤�Ȑ���
�͂�ۗL���Ă���Ƃ͍l����B���̂��߁A�����Ԕr�o�K�X���ψ���uNOx�̍팸�v�Ɓu�R��̌���v���\���C
���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p�����āA�č������啝�Ɋɂ��m�n���̃��x���ɗ}�������{������
�̂m�n���K�������肵�����Ƃɂ��ẮA�M�҂ɂ͗���������Ƃł���B
�p�����ɑ��݂��Ă���ɂ�������炸�A���{�̐��{�����⎩���Ԕr�o�K�X���ψ���̐l�B�́A�@���Ȃ闝�R�ɂ�
���āA���́u�C���x�~�v�̋Z�p��َE���Ă���̂ł��낤���B���́u�C���x�~�v�̋Z�p��َE�������ʁA���{�̐��{����
�⎩���Ԕr�o�K�X���ψ���̐l�B�́A���{�������̂m�n���K���Ƃ��āA�č������ɂ����x����NO���K���l�� 0.4 g
/kWh�iWHTC���[�h�j�̔r�o�K�X�K����2016�N�Ɏ��{���邱�Ƃ����肹����Ȃ������̂ł͂Ȃ����Ɛ��@�����B
�ӂƎv�����Ƃ́A�č��l�ɔ�r���A���{�l�̕����Ȃm�n���Z�x�̑�C���̉��ł����N���Q���邱�Ɩ����A痂�����
���ł�����ʂȐ����͂�����Ă���Ƃ̍����ƂȂ�u�Ȃm�n���Z�x�̑�C���ɂ����錒�N��Q�ɂ��Ă̕č��l
�Ɠ��{�l�̉u�w�I�Ȕ�r�����̌��ʁv�̃f�[�^���A���{�̐��{�����⎩���Ԕr�o�K�X���ψ���̐l�B���ۗL����
�Ă���̂ł��낤���B�펯�I�ɍl����A���{�l���ȑ�C���ł��č��l�������N��Q���Ȃ��悤�Ȑ���
�͂�ۗL���Ă���Ƃ͍l����B���̂��߁A�����Ԕr�o�K�X���ψ���uNOx�̍팸�v�Ɓu�R��̌���v���\���C
���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p�����āA�č������啝�Ɋɂ��m�n���̃��x���ɗ}�������{������
�̂m�n���K�������肵�����Ƃɂ��ẮA�M�҂ɂ͗���������Ƃł���B
�R�D��^�g���b�N�ɂ����鑖�s�R���d�ʎԃ��[�h�R��̉��P�̉ߋ��E���݁E����
�@���������A��^�g���b�N�ɂ����ẮANO���팸�ɔ�r���A���s�R���d�ʎԃ��[�h�R��̉��P�͋ɂ߂č���ł���B��
�����A����ł��g���b�N���[�J�́A1970�N��O������P���I�C���V���b�N�ȗ��A�������R����ɑł������߂Ɍ�����
��^�g���b�N�̑��s�R���d�ʎԃ��[�h�R��̉��P�ɓw�߂Ă����̂ł���B���̕s�f�̓w�͂̌��ʁA���݂̑�^�f�B
�[�[���g���b�N�ł̑��s�R��B������Ă���B�����ŁA�ȉ����\�P�O�ɂ́A��P���I�C���V���b�N���_�@�Ƃ��ĔR�����P
�̎s��j�[�Y�����܂���1970�N���ȍ~�ɂ��āA��^�g���b�N�ɂ�����{�T�� ���x�ȏ�̑��s�R���d�ʎԃ��[�h�R
��̉��P�����ۂɎ�������Ă����Z�p���A�N�㏇�ɐ��������B�܂��A���̕\�P�O�ɂ́A���ɋ߂������ɍ��y��ʏȂ�
2015�N�x�d�ʎԔR������{�P�O�� ���x�̔R���̂����������{���ꂽ�ꍇ�ɂ����āA�e�g���b�N���[�J���s�{
�ӂɂ��̗p������Ȃ���^�g���b�N�̏d�ʎԃ��[�h�R��̉��P�Z�p�ɂ��Ă��t�L�����̂ŁA�����������������B
�����A����ł��g���b�N���[�J�́A1970�N��O������P���I�C���V���b�N�ȗ��A�������R����ɑł������߂Ɍ�����
��^�g���b�N�̑��s�R���d�ʎԃ��[�h�R��̉��P�ɓw�߂Ă����̂ł���B���̕s�f�̓w�͂̌��ʁA���݂̑�^�f�B
�[�[���g���b�N�ł̑��s�R��B������Ă���B�����ŁA�ȉ����\�P�O�ɂ́A��P���I�C���V���b�N���_�@�Ƃ��ĔR�����P
�̎s��j�[�Y�����܂���1970�N���ȍ~�ɂ��āA��^�g���b�N�ɂ�����{�T�� ���x�ȏ�̑��s�R���d�ʎԃ��[�h�R
��̉��P�����ۂɎ�������Ă����Z�p���A�N�㏇�ɐ��������B�܂��A���̕\�P�O�ɂ́A���ɋ߂������ɍ��y��ʏȂ�
2015�N�x�d�ʎԔR������{�P�O�� ���x�̔R���̂����������{���ꂽ�ꍇ�ɂ����āA�e�g���b�N���[�J���s�{
�ӂɂ��̗p������Ȃ���^�g���b�N�̏d�ʎԃ��[�h�R��̉��P�Z�p�ɂ��Ă��t�L�����̂ŁA�����������������B
| |
|
|
| |
�E�u�\�R�Ď��f�B�[�[���v�����u�������f�B�[�[���v�ɕύX | |
| |
�E�u���ߋ��f�B�[�[���v�����u�C���^�[�N���ߋ��f�B�[�[���v�ɕύX | |
| |
�E�g���b�N���u�A�C�h�������O�X�g�b�v�v�̎��p��
�i�����U�����Ԃ��ȃG�l��܂���܂��A���̌�A���̋Z�p���g���b�N�E�o �X�ɍL�����y�j |
|
| |
�E2015�N�x�d�ʎԔR�����{�s
�i���̊�ɓK��������^�g���b�N�ɗD���Ő��̓K�p���J�n�j |
|
| |
�E�u�V�i�}�j���A���g�����X�~�b�V�����v����
�u12�i�@�B�������g�����X�~�b�V�����v�ɕύX �i��^�g���b�N�ɍ����ȁu12�i�@�B�������g�����X�~�b�V�����v�𓋍� ���邱�Ƃɂ��A���{�̃g���b�N���[�J�́A�啔���̑�^�g���b�N�� 2015�N�x�d�ʎԔR���ɐh�����ēK���j |
|
| |
�E�u���َ�̧ݶ����ݸށv�����u�d�q����I�[�g�N�[���t�@���J�b�v
�����O�v�ɕύX �E�u�]���^���������߁v�����u�d�q����ϗ��ʃE�H�[�^�[�|���v�v �ɕύX �i�o�T�Fhttp://www.mitsubishi-fuso.com/jp/news/news_content/ 140529/140529.html�j |
|
| |
�E�u�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�v�̓����Z�p
���̗p�H �i�߂�������2015�N�x�d�ʎԔR����10�����x�̋�����}���� �V���ȔR���̋��������y��ʏȂ����{�����ꍇ�ɂ́A �́A�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p���^ �g���b�N�Ɉ�Ăɍ̗p�������̂Ɨ\�z�����B���̂Ȃ�A�d�ʎ� ���[�h�R��� 5�`10�� ���x���̉��P���\�ɂ���Z�p�́A ���̂Ƃ���A�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̑��ɂ� ��������Ȃ����߂ł���B�j �i���쎩���Ԃ́u�z�E�r�C�ْ�~���̋C���x�~�V�X�e���v�́A ���쎩���Ԃ��_�����\�����R����P�@�\�̗��C���x�~�V�X�e�� �Ɏ������悤�ɁA�G���W�����������ɋx�~�ł���C������ �����Ɏ~�܂�\���I�Ȍ��ׂ̂��߁A�g���b�N�̑��s�R������P ����Z�p�Ƃ��Ă͎��i�ł���B�j |
|
�@�ȏ�̂悤�ɁA1970�N��O������P���I�C���V���b�N�����^�g���b�N�ɂ����āA ���s�R���d�ʎԃ��[�h�R���
�T�� ���x�̉��P���������邽�߂ɍ̗p����Ă����Z�p�́A�ȉ��̂T���ڂł���B
�T�� ���x�̉��P���������邽�߂ɍ̗p����Ă����Z�p�́A�ȉ��̂T���ڂł���B
�@ �u�������f�B�[�[���v
�A �u�C���^�[�N���ߋ��f�B�[�[���v
�B �u�A�C�h�������O�X�g�b�v�v
�C �u12�i�@�B�������g�����X�~�b�V�����v
�D �u�d�q����I�[�g�N�[���t�@���J�b�v�����O�v�Ɓu�d�q����ϗ��ʃE�H�[�^�[�|���v�v�̑g����
�@�ȏ�̏��Z�p�̒����D�� �u�d�q����I�[�g�N�[���t�@���J�b�v�����O�v�Ɓu�d�q����ϗ��ʃE�H�[�^�[�|���v�v�̑g
�����́A�ŋ߁i��2014�N6���j�A�O�H�ӂ����̑�^�g���b�N�ɏ��߂č̗p���ꂽ�Z�p�ł���B�����Ƃ��A�u�d�q����I�[�g
�N�[���t�@���J�b�v�����O�v�͐��\�N���̂��畁�y����FF�쓮��p�ԁi���t�����g�G���W���E�t�����g�h���C�u�̏�p�ԁj��
�̗p����Ă����u�d����p�t�@���v�Ƌ@�\�E���\�������Z�p�ł���A�u�d�q����ϗ��ʃE�H�[�^�[�|���v�v�͍ŋ߂̃n
�C�u���b�h��p�Ԃɍ̗p����Ă���u�d���E�H�[�^�[�|���v�v�Ƌ@�\�E���\�������Z�p�ł���B���������āA �u�d�q����
�I�[�g�N�[���t�@���J�b�v�����O�v�Ɓu�d�q����ϗ��ʃE�H�[�^�[�|���v�v�́A���ɏ�p�Ԃɍ̗p�ς݂̔R���
�P�̋@�\�E���\��L�����ގ��Z�p���^�f�B�[�[���g���b�N�ɗ��p�����ƌ��邱�Ƃ��ł����B
�����́A�ŋ߁i��2014�N6���j�A�O�H�ӂ����̑�^�g���b�N�ɏ��߂č̗p���ꂽ�Z�p�ł���B�����Ƃ��A�u�d�q����I�[�g
�N�[���t�@���J�b�v�����O�v�͐��\�N���̂��畁�y����FF�쓮��p�ԁi���t�����g�G���W���E�t�����g�h���C�u�̏�p�ԁj��
�̗p����Ă����u�d����p�t�@���v�Ƌ@�\�E���\�������Z�p�ł���A�u�d�q����ϗ��ʃE�H�[�^�[�|���v�v�͍ŋ߂̃n
�C�u���b�h��p�Ԃɍ̗p����Ă���u�d���E�H�[�^�[�|���v�v�Ƌ@�\�E���\�������Z�p�ł���B���������āA �u�d�q����
�I�[�g�N�[���t�@���J�b�v�����O�v�Ɓu�d�q����ϗ��ʃE�H�[�^�[�|���v�v�́A���ɏ�p�Ԃɍ̗p�ς݂̔R���
�P�̋@�\�E���\��L�����ގ��Z�p���^�f�B�[�[���g���b�N�ɗ��p�����ƌ��邱�Ƃ��ł����B
�@���̂悤�ɁA �u�d�q����I�[�g�N�[���t�@���J�b�v�����O�v�Ɓu�d�q����ϗ��ʃE�H�[�^�[�|���v�v�́A��p�Ԃł̔R
����P�̋@�\�E���\�����p�����Z�p�ł��邽�߁A��^�g���b�N�̕���ŐV���ɓƎ��ɊJ�����ꂽ�V�K�̔R����P�Z�p
�ƌĂԂ��Ƃɂ͏����S�O�����ƍl������B�������Ȃ���u�d�q����I�[�g�N�[���t�@���J�b�v�����O�v�������ɉ�����
�ϐ��䂵�Č����I�ȃG���W����p���������邽�߂ɕK�v�ɉ�������p�t�@�������Ƃŋ쓮������ጸ���A�u�d�q
����ϗ��ʃE�H�[�^�[�|���v�v�́A�d����p�t�@���Ɠ��l�ɂŕK�v�ɉ����ė�p���ʂ��z�����ăG���W���������I
�ɗ�p���ăE�H�[�^�[�|���v�̗]���ȋ쓮������ጸ���邱�Ƃɂ��A�u��^�g���b�N�ɂ������{�T�� ���x�̏d�ʎ�
���[�h�R��́A���P���\�v�ƂȂ��B����ɂ���āA2014�N�̎��_�ɂ����āA��^�g���b�N�́A2015�N�x�d�ʎԔR���
���́{�T���̒�R��������ł����悤�ł���B
����P�̋@�\�E���\�����p�����Z�p�ł��邽�߁A��^�g���b�N�̕���ŐV���ɓƎ��ɊJ�����ꂽ�V�K�̔R����P�Z�p
�ƌĂԂ��Ƃɂ͏����S�O�����ƍl������B�������Ȃ���u�d�q����I�[�g�N�[���t�@���J�b�v�����O�v�������ɉ�����
�ϐ��䂵�Č����I�ȃG���W����p���������邽�߂ɕK�v�ɉ�������p�t�@�������Ƃŋ쓮������ጸ���A�u�d�q
����ϗ��ʃE�H�[�^�[�|���v�v�́A�d����p�t�@���Ɠ��l�ɂŕK�v�ɉ����ė�p���ʂ��z�����ăG���W���������I
�ɗ�p���ăE�H�[�^�[�|���v�̗]���ȋ쓮������ጸ���邱�Ƃɂ��A�u��^�g���b�N�ɂ������{�T�� ���x�̏d�ʎ�
���[�h�R��́A���P���\�v�ƂȂ��B����ɂ���āA2014�N�̎��_�ɂ����āA��^�g���b�N�́A2015�N�x�d�ʎԔR���
���́{�T���̒�R��������ł����悤�ł���B
�@�ȏ�̂悤�ɁA�����N���ɂ킽��Z�p�ҁE���Ƃ̒n���ȓw�͂ɂ���āA��^�g���b�N�ɂ�����{�T�����x�̑��s�R
��̌�����\�ɂ���Z�p�����p������Ă����̂ł���B���̂悤�ȔR����P�̋Z�p�J���̌o�܁E���т�����ƁA��
�^�g���b�N�̑��s�R���d�ʎԃ��[�h�R��́{�T�� ���x�����P���邱�Ƃ��@���ɓ�����Ƃ����锤�ł���B��������
�āA�߂������ɑ�^�g���b�N�̎����s�R���d�ʎԃ��[�h�R��{�T�����x�ȏ� �̉��P�������ł���V�����R���
��̋Z�p����肷�邱�Ƃ́A�ɂ߂ē�����Ƃł���B����ɂ��āA�M�҂��l����Ƃ���ł́A�����_�ɂ����đ�^�g
���b�N�̎����s�R���d�ʎԃ��[�h�R��{�T�����x�ȏ� �̉��P���\�ɂ���Z�p�́A���̂Ƃ���A�C���x�~�G���W
���i�������J2005-54771�j�̑��ɂ͑��݂��Ȃ��ƍl���Ă���B�܂�A�|�X�g�V�����r�o�K�X�K���i��2009�N�K���j
�K���̎d�l�Ɂu�d�q����I�[�g�N�[���t�@���J�b�v�����O�v�Ɓu�d�q����ϗ��ʃE�H�[�^�[�|���v�v���̗p����
��^�g���b�N�i��2015�N�x�d�ʎԔR���{�T���̒B���̑�^�g���b�N�j�ɁA�V�����C���x�~�G���W���i������
�J2005-54771�j�̓����Z�p��g�����邱�Ƃɂ��A2015�N�x�d�ʎԔR������{�P�O���ȏ�̔R������
�B��������^�g���b�N�������ł����Ɖ]�����Ƃł���B
��̌�����\�ɂ���Z�p�����p������Ă����̂ł���B���̂悤�ȔR����P�̋Z�p�J���̌o�܁E���т�����ƁA��
�^�g���b�N�̑��s�R���d�ʎԃ��[�h�R��́{�T�� ���x�����P���邱�Ƃ��@���ɓ�����Ƃ����锤�ł���B��������
�āA�߂������ɑ�^�g���b�N�̎����s�R���d�ʎԃ��[�h�R��{�T�����x�ȏ� �̉��P�������ł���V�����R���
��̋Z�p����肷�邱�Ƃ́A�ɂ߂ē�����Ƃł���B����ɂ��āA�M�҂��l����Ƃ���ł́A�����_�ɂ����đ�^�g
���b�N�̎����s�R���d�ʎԃ��[�h�R��{�T�����x�ȏ� �̉��P���\�ɂ���Z�p�́A���̂Ƃ���A�C���x�~�G���W
���i�������J2005-54771�j�̑��ɂ͑��݂��Ȃ��ƍl���Ă���B�܂�A�|�X�g�V�����r�o�K�X�K���i��2009�N�K���j
�K���̎d�l�Ɂu�d�q����I�[�g�N�[���t�@���J�b�v�����O�v�Ɓu�d�q����ϗ��ʃE�H�[�^�[�|���v�v���̗p����
��^�g���b�N�i��2015�N�x�d�ʎԔR���{�T���̒B���̑�^�g���b�N�j�ɁA�V�����C���x�~�G���W���i������
�J2005-54771�j�̓����Z�p��g�����邱�Ƃɂ��A2015�N�x�d�ʎԔR������{�P�O���ȏ�̔R������
�B��������^�g���b�N�������ł����Ɖ]�����Ƃł���B
�@�S�D���{�̑�^�g���b�N�ɑ������������̂m�n���K�������̃��x��
�@�s�K�Ȃ��ƂɁA�������R�c��̓��\�Ɋ�Â����]���̂m�n���K���̎菇�ɂ��������Ď����m�n���K���̋��������{
���ꂽ�ꍇ�ɂ��A�����Ƃ��č������啝�Ɋɂ�NO���K�����p�����{����邱�Ƃ����炩���B����ɂ��A���{�̃g���b
�N���[�J�͕č��̃g���b�N���[�J����NO���팸�̋Z�p�J�����ߖ�ł��邱�ƂɂȂ�Ɛ��@�����B����NO���팸�̌�
�������̍팸�ɂ���ĔP�o����鎑���͑S�ė��v�Ƃ��Čv��ł��邽�߁A���{�̃g���b�N���[�J�͕č��̃g���b�N���[�J
�������v����e�ՂɌ��コ���邱�Ƃ��\�Ȍo�c������ɓ��ꂽ���ƂɂȂ�B���̂��߁A2010�N�V���ɒ�����
�R�c�2016�N��NO�� �� 0.4 g/kWh�ɋK������������\�����\�̔��\��m�������{�̃g���b�N���[�J�̌o�c����
�́A���{�⒆�����R�c���NO���팸�̋Z�p�J����̐ߖ�ɂ�闘�v����̑��蕨�������Ƃ��āA���에����
�Ċ�̂ł͂Ȃ����낤���B����ɑ��A��ʍ����́A�����ɂ킽���ĕč�����NO���K�����ɂ����߂�NO���Z�x��
������C���ɔ����ꑱ������f���邱�ƂɂȂ�B���̂悤�ɁA�č������ɂ�������NO���K������{�Ŏ��{����r
�o�K�X�K���́A���{�̃g���b�N���[�J�̌o�c��������͑傢�Ɋ��ӂ���邩������Ȃ��B�������A���̓��{�ɂ�����NO��
�K���̎{��́A�킪���̑�C���̉��P�����N���摗��ɂ���]�������Ƃ͖��炩�ł���B
���ꂽ�ꍇ�ɂ��A�����Ƃ��č������啝�Ɋɂ�NO���K�����p�����{����邱�Ƃ����炩���B����ɂ��A���{�̃g���b
�N���[�J�͕č��̃g���b�N���[�J����NO���팸�̋Z�p�J�����ߖ�ł��邱�ƂɂȂ�Ɛ��@�����B����NO���팸�̌�
�������̍팸�ɂ���ĔP�o����鎑���͑S�ė��v�Ƃ��Čv��ł��邽�߁A���{�̃g���b�N���[�J�͕č��̃g���b�N���[�J
�������v����e�ՂɌ��コ���邱�Ƃ��\�Ȍo�c������ɓ��ꂽ���ƂɂȂ�B���̂��߁A2010�N�V���ɒ�����
�R�c�2016�N��NO�� �� 0.4 g/kWh�ɋK������������\�����\�̔��\��m�������{�̃g���b�N���[�J�̌o�c����
�́A���{�⒆�����R�c���NO���팸�̋Z�p�J����̐ߖ�ɂ�闘�v����̑��蕨�������Ƃ��āA���에����
�Ċ�̂ł͂Ȃ����낤���B����ɑ��A��ʍ����́A�����ɂ킽���ĕč�����NO���K�����ɂ����߂�NO���Z�x��
������C���ɔ����ꑱ������f���邱�ƂɂȂ�B���̂悤�ɁA�č������ɂ�������NO���K������{�Ŏ��{����r
�o�K�X�K���́A���{�̃g���b�N���[�J�̌o�c��������͑傢�Ɋ��ӂ���邩������Ȃ��B�������A���̓��{�ɂ�����NO��
�K���̎{��́A�킪���̑�C���̉��P�����N���摗��ɂ���]�������Ƃ͖��炩�ł���B
�@�Ƃ���ŁA�M�҂́A������k��ƂT�N�ȏ���ȑO�ƂȂ�2006�N4��7���ɁA���߂ăz�[���y�[�W���J�݂����B�����ł��A
NO���팸�Ɠ����ɏd�ʎԃ��[�h�R������オ�\���C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p�����J���Ă�
��B�����āA�����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p����^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W�����̗p�����ꍇ
�ɂ́A�A�N�Z�y�_���̓����ݗ�50���ȉ��̒ᕉ���ɂ������A�fSCR�G�}�̓����̔r�C�K�X���x��2�{�߂��ɍ���
���ł��邽�߁A�u�A�fSCR�G�}�̏����z�b�g�X�^�[�g���A�R�[���h�X�^�[�g���̕��ρi�R�[���h�X�^�[�g�䗦14���j�łW
�T�����x�Ƃ���v���Ƃ��\�ł���Z�p�����\�����B���̋C���x�~�̋Z�p��p����A������NO���ጸ�̖ڕW�l�́A
���́i�Q�j���ŎZ�o�����l�܂Œጸ���邱�Ƃ��\�ƂȂ�B
NO���팸�Ɠ����ɏd�ʎԃ��[�h�R������オ�\���C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p�����J���Ă�
��B�����āA�����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p����^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W�����̗p�����ꍇ
�ɂ́A�A�N�Z�y�_���̓����ݗ�50���ȉ��̒ᕉ���ɂ������A�fSCR�G�}�̓����̔r�C�K�X���x��2�{�߂��ɍ���
���ł��邽�߁A�u�A�fSCR�G�}�̏����z�b�g�X�^�[�g���A�R�[���h�X�^�[�g���̕��ρi�R�[���h�X�^�[�g�䗦14���j�łW
�T�����x�Ƃ���v���Ƃ��\�ł���Z�p�����\�����B���̋C���x�~�̋Z�p��p����A������NO���ጸ�̖ڕW�l�́A
���́i�Q�j���ŎZ�o�����l�܂Œጸ���邱�Ƃ��\�ƂȂ�B
�i�G���W���o���̔r�o�ʂ�1.5g/kWh���x�j�~�i�A�fSCR�G�}����85���̍팸�j��0.225g/kWh�@�E�E�E�E�E�i�Q�j
�@���̂悤�ɁA����A��^�g���b�N�ɋC���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j���̗p�����ꍇ�ɂ́A��L���i�Q�j���ŎZ
�o���ꂽ0.225g/kWh����A�����̑�^�g���b�N��NO���r�o�l�́u0.23g/kWh�v�iWHTC�r�o�K�X�����@�j�܂ŗe�Ղɍ팸
���邱�Ƃ��\�ł���A�d�ʎԃ��[�h�R����T�`�P�O��������ł���̂ł���B���̂悤�ɁA2010�N�V��28�����\�̒�
�����R�c��E��C������́u����̎����Ԕr�o�K�X�ጸ��̂�����ɂ��āi��\�����\�j�v�ɋL�ڂ�
��Ă���e��Z�p�ɁA�V�����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p��lj����邱�Ƃɂ���āA����
�̑�^�g���b�N�ɂ����ẮuNO���r�o�l��0.23g/kWh�܂ł̍팸�v�Ɓu�d�ʎԃ��[�h�R��̂T�`�P�O���̌���v��
�\�ƂȂ�B
�o���ꂽ0.225g/kWh����A�����̑�^�g���b�N��NO���r�o�l�́u0.23g/kWh�v�iWHTC�r�o�K�X�����@�j�܂ŗe�Ղɍ팸
���邱�Ƃ��\�ł���A�d�ʎԃ��[�h�R����T�`�P�O��������ł���̂ł���B���̂悤�ɁA2010�N�V��28�����\�̒�
�����R�c��E��C������́u����̎����Ԕr�o�K�X�ጸ��̂�����ɂ��āi��\�����\�j�v�ɋL�ڂ�
��Ă���e��Z�p�ɁA�V�����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p��lj����邱�Ƃɂ���āA����
�̑�^�g���b�N�ɂ����ẮuNO���r�o�l��0.23g/kWh�܂ł̍팸�v�Ɓu�d�ʎԃ��[�h�R��̂T�`�P�O���̌���v��
�\�ƂȂ�B
�@���������āA�����A�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p�����p���ł���ڏ������������_�ŁA������
�R�c��́A��\�����\�ł�2016�N�̎���NO���K���iNO����0.4g/kWh�j�iWHTC�r�o�K�X�����@�j�ɑ����āA����������
NO���K���̋����iNO�� �� 0.23 g/kWh )�iWHTC�r�o�K�X�����@�j�̓��\���o�����Ƃ��\�ƂȂ�B����ɂ���āA��^�g
���b�N����ɂ�����u��NO���v�Ɓu��R��i����CO2�j�v��i�W�����A�䂪���ɂ������C���̉��P�����I�ɑ��i��
���邱�Ƃ��ł���ƍl������B�������������B��̕��@�́A�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p��
�ڂ�����^�g���b�N���g���b�N���[�J���������Ɏs�̉�����邱�Ƃ��K�v���B���̂��߂ɂ́A���Ȃ⍑�y��ʏȂ���
�̂Ƃ������{�����͂ȃ��[�_�[�V�b�v�������C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̌����J���𑣐i���A����
�Z�p�������Ɏ��p�����邱�Ƃł���B
�R�c��́A��\�����\�ł�2016�N�̎���NO���K���iNO����0.4g/kWh�j�iWHTC�r�o�K�X�����@�j�ɑ����āA����������
NO���K���̋����iNO�� �� 0.23 g/kWh )�iWHTC�r�o�K�X�����@�j�̓��\���o�����Ƃ��\�ƂȂ�B����ɂ���āA��^�g
���b�N����ɂ�����u��NO���v�Ɓu��R��i����CO2�j�v��i�W�����A�䂪���ɂ������C���̉��P�����I�ɑ��i��
���邱�Ƃ��ł���ƍl������B�������������B��̕��@�́A�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p��
�ڂ�����^�g���b�N���g���b�N���[�J���������Ɏs�̉�����邱�Ƃ��K�v���B���̂��߂ɂ́A���Ȃ⍑�y��ʏȂ���
�̂Ƃ������{�����͂ȃ��[�_�[�V�b�v�������C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̌����J���𑣐i���A����
�Z�p�������Ɏ��p�����邱�Ƃł���B
�@�����ŁA�M�҂́A�\�P�P�Ɏ������悤�ɁA2010�N��7��28���ɒ������R�c�����Ȃɑ�\�����\�������̂m�n
���K���l�@���@0.4 g/kWh�@�i2016�N�Ɏ��{�\��j�̑��ɁA�攪�����\��NO������ڕW�l�ł���m�n���K���l�@���@0.23 g
/kWh���r�o�K�X�g���b�N��NO����l�Ƃ��ĐV���ɐ݂��邱�Ƃ��Ă������B����ɂ���āA�攪�����\�ŋ��߂��
�Ă�����NO���̔r�o�K�X�̃g���b�N�����p������A���y���Ă������|���肪�ł���̂ł���B
���K���l�@���@0.4 g/kWh�@�i2016�N�Ɏ��{�\��j�̑��ɁA�攪�����\��NO������ڕW�l�ł���m�n���K���l�@���@0.23 g
/kWh���r�o�K�X�g���b�N��NO����l�Ƃ��ĐV���ɐ݂��邱�Ƃ��Ă������B����ɂ���āA�攪�����\�ŋ��߂��
�Ă�����NO���̔r�o�K�X�̃g���b�N�����p������A���y���Ă������|���肪�ł���̂ł���B
| |
|
|
| |
|
|
�T�@�V���ȑ�^�g���b�N�̒�NO���E��R��g���b�N�E�o�X�̊�i�V���ȃG�R�g���b�N��j�y�āz
�@2010�N�V��28���t�̊��Ȃ̒������R�c��E��C������́u����̎����Ԕr�o�K�X�ጸ��̂�����ɂ�
���i��\�����\�j�v�ɂ����ẮA��^�g���b�N��ΏۂƂ���2016�N�Ɏ��{�����uNO���K���l�� 0.4 g/kWh
�iWHTC���[�h�j��NO���K�������v�����\���ꂽ�B�����āA�����������R�c�����\�����\�̍������ڍׂɐ�
��������\����(http://www.env.go.jp/press/file_view.php?serial=16034&hou_id=12768)�ł́A2016�N��
��^�g���b�N���uNO���K���l�� 0.4 g/kWh�v�iWHTC���[�h�j�ɓK��������Ƌ��Ɂu�R��̐L�т�����m�ہv������
������Z�p�Ƃ��āA�|�X�g�V�����r�o�K�X�K���K���̋Z�p�Ɂu2�i�ߋ��v�A�uEGR���̌���i�ꕔ�ɂ�LP-EGR��
�p�j�v�A�u�R�����ˈ��͂̌����PCI�R�āv�A�u�ꕔ�Ԏ�ɂ̓^�[�{�R���p�E���h�v�̑������Z�p��V���ɒlj�����
���Ƃ��K�v�Ƃ̌������L�ڂ��������B�i�\�P�Q�Q�Ɓj
���i��\�����\�j�v�ɂ����ẮA��^�g���b�N��ΏۂƂ���2016�N�Ɏ��{�����uNO���K���l�� 0.4 g/kWh
�iWHTC���[�h�j��NO���K�������v�����\���ꂽ�B�����āA�����������R�c�����\�����\�̍������ڍׂɐ�
��������\����(http://www.env.go.jp/press/file_view.php?serial=16034&hou_id=12768)�ł́A2016�N��
��^�g���b�N���uNO���K���l�� 0.4 g/kWh�v�iWHTC���[�h�j�ɓK��������Ƌ��Ɂu�R��̐L�т�����m�ہv������
������Z�p�Ƃ��āA�|�X�g�V�����r�o�K�X�K���K���̋Z�p�Ɂu2�i�ߋ��v�A�uEGR���̌���i�ꕔ�ɂ�LP-EGR��
�p�j�v�A�u�R�����ˈ��͂̌����PCI�R�āv�A�u�ꕔ�Ԏ�ɂ̓^�[�{�R���p�E���h�v�̑������Z�p��V���ɒlj�����
���Ƃ��K�v�Ƃ̌������L�ڂ��������B�i�\�P�Q�Q�Ɓj
| |
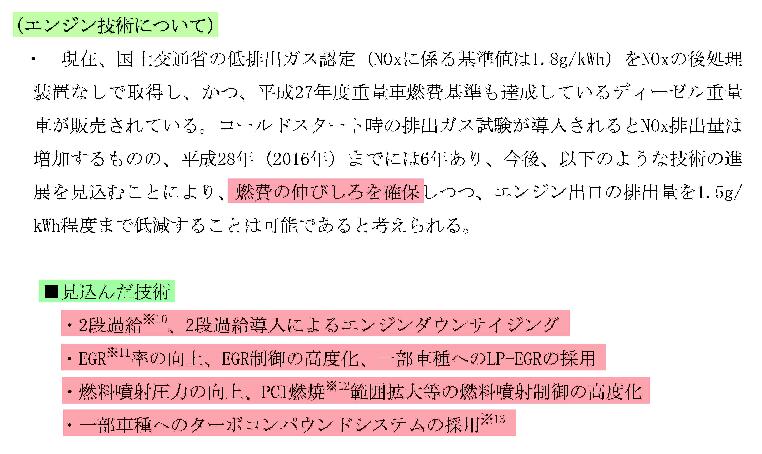 |
�@��L�̕\�V�Ɏ�������\���̋L�q���e������ƁA���̓��\�����ۂɍ쐬���ꂽ�������R�c��E��C����
��̎����Ԕr�o�K�X���ψ���̊w�ҁE���Ƃ́A�|�X�g�V�����r�o�K�X�K���K���̃f�B�[�[���G���W���ɍŋ߂�
�����ԋZ�p�����{�@�B�w��̍u����Ő��������グ���Ă����Z�p��Ђ��ς�����̗p�������͏��Ƃ��]����
�f�B�[�[���G���W�����J�����邱�Ƃɂ��A�u�m�n���r�o�l�� 0.40 g/kWh�iWHTC���[�h�j�v�܂ł�NO���̍팸�ƁA�u�R���
�L�т�����m�ہv���B���ł���Ƃ̌������q�ׂ��Ă���B�������A���́u�R��̐L�т�����m�ہv�̋L�q�́A�e�ǎ҂�
����Ď������قȂ�Ǝv�����A�펯�I�ɔ��f����Ɓu2015�N�x�d�ʎԔR�����琔�p�[�Z���g���x������
�R�����v�̂悤�Ȉ�ۂ���B�������A������\����ǂ��ǎ҂��u���p�[�Z���g���x�̔R�����v�ƍl������
���Ă��A����͓ǎ҂̏���ȑz���ɉ߂��Ȃ��̂ł���B�����āA�m���Ȃ��Ƃ́A���̒������R�c�����\����
�́A�u�R��̐L�т�����m�ہv���L�q����Ă����R����P�Ɋւ��ẮA2015�N�x�d�ʎԔR�����牽�p�[�Z���g���x
�̉��P��ڕW�Ƃ��Ă��邩�ɂ��āA��̓I�Ȑ��l���ɑS���L�ڂ���Ă��Ȃ��̂��B���̂悤�ɁA��\���ł́A�R
�����ɂ��ẮA�ǎ҂�f�킷�s���m�ȓ��e�̋L�q�ɗ��߂��Ă���̂ł���B
��̎����Ԕr�o�K�X���ψ���̊w�ҁE���Ƃ́A�|�X�g�V�����r�o�K�X�K���K���̃f�B�[�[���G���W���ɍŋ߂�
�����ԋZ�p�����{�@�B�w��̍u����Ő��������グ���Ă����Z�p��Ђ��ς�����̗p�������͏��Ƃ��]����
�f�B�[�[���G���W�����J�����邱�Ƃɂ��A�u�m�n���r�o�l�� 0.40 g/kWh�iWHTC���[�h�j�v�܂ł�NO���̍팸�ƁA�u�R���
�L�т�����m�ہv���B���ł���Ƃ̌������q�ׂ��Ă���B�������A���́u�R��̐L�т�����m�ہv�̋L�q�́A�e�ǎ҂�
����Ď������قȂ�Ǝv�����A�펯�I�ɔ��f����Ɓu2015�N�x�d�ʎԔR�����琔�p�[�Z���g���x������
�R�����v�̂悤�Ȉ�ۂ���B�������A������\����ǂ��ǎ҂��u���p�[�Z���g���x�̔R�����v�ƍl������
���Ă��A����͓ǎ҂̏���ȑz���ɉ߂��Ȃ��̂ł���B�����āA�m���Ȃ��Ƃ́A���̒������R�c�����\����
�́A�u�R��̐L�т�����m�ہv���L�q����Ă����R����P�Ɋւ��ẮA2015�N�x�d�ʎԔR�����牽�p�[�Z���g���x
�̉��P��ڕW�Ƃ��Ă��邩�ɂ��āA��̓I�Ȑ��l���ɑS���L�ڂ���Ă��Ȃ��̂��B���̂悤�ɁA��\���ł́A�R
�����ɂ��ẮA�ǎ҂�f�킷�s���m�ȓ��e�̋L�q�ɗ��߂��Ă���̂ł���B
�@
�@���̑�\���ł́A�u2�i�ߋ��v�A�uEGR���̌���i�ꕔ�ɂ�LP-EGR�̗p�j�v�A�u�R�����ˈ��͂̌����PCI�R�āv�A
�u�ꕔ�Ԏ�ɂ̓^�[�{�R���p�E���h�v���Z�p�ɂ��R�����̖ڕW����\���ɋL�ڂ���Ă��Ȃ����Ƃ��画�f����
�ƁA�����Ԕr�o�K�X���ψ���̊w�ҁE���Ƃ́A�����̋Z�p�������Ă��A2015�N�x�d�ʎԔR������̔R
����オ�]����҂ł��Ȃ��Ɣ��f����Ă�����̂ƍl������B���̂��߂ɁA�����Ԕr�o�K�X���ψ���̊w�ҁE��
��Ƃ́A��\�����u�R��̐L�т�����m�ہv�Ƃ̒ʏ�̋Z�p�ł͒ʏ�ł͖w��ǖڂɂ��Ȃ��悤�ȁA�ɂ߂ĞB
���ȕ��w�I�\�����g���Ă���̂ł���B�܂�A����́A�����Ԕr�o�K�X���ψ���̊w�ҁE���Ƃ���\����
��2015�N�x�d�ʎԔR������̔R����オ���Ȃ����Ƃ�̍ق悭�B�����߂ɍl����ꂽ�g��̋L�q�ł͂Ȃ�����
���������B�Ȃ��Ȃ�A�����Ԕr�o�K�X���ψ���̊w�ҁE���Ƃ���\���ɔR�����ɂ��Đ��m�ȏ��
���L�ڂ���ӎv���������Ȃ�A�u2015�N�x�d�ʎԔR������u�����v�́u�R��̐L�т�����m�ہv�ƔR��̐L�т���
�̊����i�����j����̓I�ɋL�ڂ���Ηǂ����ł���B�������A���Ȃɒ�o���ꂽ�����Ԕr�o�K�X���ψ���̊w
�ҁE���Ƃ́A��\���ł́u�����v�̋L�q���Ȃ��A�u�R��̐L�т�����m�ہv�������L�ڂ��Ă���̂��B����́A��
�\��������Ă���W�ߋZ�p�ł͎��ۂɂ͔R��̉��P�����҂ł��Ȃ����ƌ��݉����邱�Ƃ�h�����߁A��
��������背�x���̔R�����������ł��邩�̂悤�Ȉ�ۂ�ǎҁi�������j�ɗ^���悤�Ƃ��邽�߂̒m�b���i��������
�̏��H�ł͂Ȃ����ƕM�҂ɂ͎v����̂ł���B
�u�ꕔ�Ԏ�ɂ̓^�[�{�R���p�E���h�v���Z�p�ɂ��R�����̖ڕW����\���ɋL�ڂ���Ă��Ȃ����Ƃ��画�f����
�ƁA�����Ԕr�o�K�X���ψ���̊w�ҁE���Ƃ́A�����̋Z�p�������Ă��A2015�N�x�d�ʎԔR������̔R
����オ�]����҂ł��Ȃ��Ɣ��f����Ă�����̂ƍl������B���̂��߂ɁA�����Ԕr�o�K�X���ψ���̊w�ҁE��
��Ƃ́A��\�����u�R��̐L�т�����m�ہv�Ƃ̒ʏ�̋Z�p�ł͒ʏ�ł͖w��ǖڂɂ��Ȃ��悤�ȁA�ɂ߂ĞB
���ȕ��w�I�\�����g���Ă���̂ł���B�܂�A����́A�����Ԕr�o�K�X���ψ���̊w�ҁE���Ƃ���\����
��2015�N�x�d�ʎԔR������̔R����オ���Ȃ����Ƃ�̍ق悭�B�����߂ɍl����ꂽ�g��̋L�q�ł͂Ȃ�����
���������B�Ȃ��Ȃ�A�����Ԕr�o�K�X���ψ���̊w�ҁE���Ƃ���\���ɔR�����ɂ��Đ��m�ȏ��
���L�ڂ���ӎv���������Ȃ�A�u2015�N�x�d�ʎԔR������u�����v�́u�R��̐L�т�����m�ہv�ƔR��̐L�т���
�̊����i�����j����̓I�ɋL�ڂ���Ηǂ����ł���B�������A���Ȃɒ�o���ꂽ�����Ԕr�o�K�X���ψ���̊w
�ҁE���Ƃ́A��\���ł́u�����v�̋L�q���Ȃ��A�u�R��̐L�т�����m�ہv�������L�ڂ��Ă���̂��B����́A��
�\��������Ă���W�ߋZ�p�ł͎��ۂɂ͔R��̉��P�����҂ł��Ȃ����ƌ��݉����邱�Ƃ�h�����߁A��
��������背�x���̔R�����������ł��邩�̂悤�Ȉ�ۂ�ǎҁi�������j�ɗ^���悤�Ƃ��邽�߂̒m�b���i��������
�̏��H�ł͂Ȃ����ƕM�҂ɂ͎v����̂ł���B
�@���āA�������R�c����Ȃɑ�\�����o����O�ɁA�����Ԕr�o�K�X���ψ���e�g���b�N���[�J�ɑ�
�^�g���b�N��NOx�팸�̋Z�p�̃q�A�����O��K���s���Ă��锤�ł��邪�A���̍ہA�e�g���b�N���[�J�ɂ�����CO2�팸��
�֘A���ĔR�����̋Z�p�ɂ��Ẵq�A�����O���������{����Ă�����̂Ɛ��������B���̂��Ƃ��画�f����ƁA�e�g
���b�N���[�J����^�g���b�N�ɂ�����2015�N�x�d�ʎԔR������̏\���ɔR�����ɗL���ȋZ�p�������ɊJ���ł�
�Ă��Ȃ����̂Ɛ��肳���B���̂��߂Ɏ~�ނɎ~�܂ꂸ�A�����Ԕr�o�K�X���ψ���̊w�ҁE���Ƃ́A��\����
�ł͔R�����Ɋւ��āu�R��̐L�т�����m�ہv�����̒P�Ȃ郊�b�v�T�[�r�X���L�ڂ��A�Z�p�炵����ʋL�q�ɂ�
����Ȃ������̂ł͂Ȃ����Ɛ��������B
�^�g���b�N��NOx�팸�̋Z�p�̃q�A�����O��K���s���Ă��锤�ł��邪�A���̍ہA�e�g���b�N���[�J�ɂ�����CO2�팸��
�֘A���ĔR�����̋Z�p�ɂ��Ẵq�A�����O���������{����Ă�����̂Ɛ��������B���̂��Ƃ��画�f����ƁA�e�g
���b�N���[�J����^�g���b�N�ɂ�����2015�N�x�d�ʎԔR������̏\���ɔR�����ɗL���ȋZ�p�������ɊJ���ł�
�Ă��Ȃ����̂Ɛ��肳���B���̂��߂Ɏ~�ނɎ~�܂ꂸ�A�����Ԕr�o�K�X���ψ���̊w�ҁE���Ƃ́A��\����
�ł͔R�����Ɋւ��āu�R��̐L�т�����m�ہv�����̒P�Ȃ郊�b�v�T�[�r�X���L�ڂ��A�Z�p�炵����ʋL�q�ɂ�
����Ȃ������̂ł͂Ȃ����Ɛ��������B
�@�ȏ�̌��ʁA�������R�c�����\��������ƁA�����Ԕr�o�K�X���ψ���̊w�ҁE���Ƃ́A�ŋ߂̎���
�ԋZ�p�����{�@�B�w��̍u����Řb����u2�i�ߋ��v�A�uEGR���̌���i�ꕔ�ɂ�LP-EGR�̗p�j�v�A�u�R�����ˈ�
�͂̌����PCI�R�āv�A�u�ꕔ�Ԏ�ɂ̓^�[�{�R���p�E���h�v�̋Z�p��g���������Ƃɂ���āA2016�N���{���m�n���r�o�l
�� 0.40 g/kWh�iWHTC���[�h�j��NO���팸�͒B���\�Ɣ��f����Ă���悤�ł���B�������A�R�����Ɋւ��Ắu�R��
�̐L�т�����m�ہv�ƞB���ȋL�q�ƂȂ��Ă��邱�Ƃ���A�����Ԕr�o�K�X���ψ���̊w�ҁE���Ƃ́A��\����
���ꂽ�Z�p�������Ă��A2015�N�x�d�ʎԔR������̏\���ȔR����P������Ƃ̌�����������Ă����
�̂Ɛ���������B
�ԋZ�p�����{�@�B�w��̍u����Řb����u2�i�ߋ��v�A�uEGR���̌���i�ꕔ�ɂ�LP-EGR�̗p�j�v�A�u�R�����ˈ�
�͂̌����PCI�R�āv�A�u�ꕔ�Ԏ�ɂ̓^�[�{�R���p�E���h�v�̋Z�p��g���������Ƃɂ���āA2016�N���{���m�n���r�o�l
�� 0.40 g/kWh�iWHTC���[�h�j��NO���팸�͒B���\�Ɣ��f����Ă���悤�ł���B�������A�R�����Ɋւ��Ắu�R��
�̐L�т�����m�ہv�ƞB���ȋL�q�ƂȂ��Ă��邱�Ƃ���A�����Ԕr�o�K�X���ψ���̊w�ҁE���Ƃ́A��\����
���ꂽ�Z�p�������Ă��A2015�N�x�d�ʎԔR������̏\���ȔR����P������Ƃ̌�����������Ă����
�̂Ɛ���������B
�@�ȏ�̂悤�ɁA��\�����\�̎�����NO���K�������i2016�N���{�j�ɑ�^�g���b�N��K�������邽�߂ɂ͕K�v���Z�p��
�P�Ƃł��R����P��NO���팸�̗����ɏ\���Ȍ��ʂ��ł���Z�p�ł���ꍇ��A�Ⴕ���͔R����P��NO���팸�̉�
�ꂩ����ɏ\���ɗL���ȋZ�p�ł���ꍇ�ɂ́A�|�X�g�V�����r�o�K�X�K���K���Z�p���P�`�Q��ނ̋Z�p�̒lj��ŗ�
�����ł���B�������A��\���ł̓|�X�g�V�����r�o�K�X�K���K���̋Z�p�ɐV���ɒlj����K�v�ȋZ�p�Ƃ��āA����
���Z�p������Ă������Ƃ��画�f������A��L���\�V�ɋL�ڂ���Ă����lj��Z�p�́A����̋Z�p���P�Ƃ̗̍p��
�͋͂����R����P��NO���팸�̋@�\�����L���Ă��Ȃ��ȋZ�p�ł��邱�Ƃ������Ɛ��肳���B
�P�Ƃł��R����P��NO���팸�̗����ɏ\���Ȍ��ʂ��ł���Z�p�ł���ꍇ��A�Ⴕ���͔R����P��NO���팸�̉�
�ꂩ����ɏ\���ɗL���ȋZ�p�ł���ꍇ�ɂ́A�|�X�g�V�����r�o�K�X�K���K���Z�p���P�`�Q��ނ̋Z�p�̒lj��ŗ�
�����ł���B�������A��\���ł̓|�X�g�V�����r�o�K�X�K���K���̋Z�p�ɐV���ɒlj����K�v�ȋZ�p�Ƃ��āA����
���Z�p������Ă������Ƃ��画�f������A��L���\�V�ɋL�ڂ���Ă����lj��Z�p�́A����̋Z�p���P�Ƃ̗̍p��
�͋͂����R����P��NO���팸�̋@�\�����L���Ă��Ȃ��ȋZ�p�ł��邱�Ƃ������Ɛ��肳���B
�@���̂��Ƃ́A���̑��\���̌��č쐬��S�����Ɛ����������ȁE�������R�c��̎����Ԕr�o�K�X���ψ�
��̊w�ҁE���Ƃ́A��^�g���b�N��NO���팸�ƔR�����ɏ\���Ȍ��ʂ��グ��Z�p�𖢂��Ɍ����o���Ă��Ȃ��؋�
�ƌ��ĊԈႢ�Ȃ��̂ł͂Ȃ����낤���B����ɂ��Ă��A���ɑސE�����|���R�c�̌��Z�p���̕M�҂ł����A�ŏ��ɒ�����
���R�c�����\��q�������ہA�u��^�g���b�N�ɂ����鎟��NO���K���ւ̓K���Z�p�ƔR�����̋Z�p�v�Ƃ��āA��
�ߘb��̐V�����Z�p������������Ă������ƂɁA���R�Ƃ��Ă��܂����̂ł���B���ɁA�����������R�c�����\
�������ꂽ�\�T�̋Z�p��g�������Z�p�����ł́A��^�g���b�N�̏d�ʎԃ��[�h�R����\���Ɍ��コ���邱��
���ɂ߂č���ł��邱�Ƃ́A�����Ԕr�o�K�X���ψ���̊w�ҁE���Ƃ��\���ɏ��m����Ă���̂ł͂Ȃ����낤
���B���������āA�����Ԕr�o�K�X���ψ���̊w�ҁE���Ƃ�������NO���K�������i2016�N���{�j�ɂ����āA��\��
�ɗ����Z�p���̗p���Ă��R����オ�u����グ�v�̏�Ԃł��邱�Ƃ��A��\���̋L�q�̒��������ɓf�I
����Ă���悤�Ɏv����̂ł���B
��̊w�ҁE���Ƃ́A��^�g���b�N��NO���팸�ƔR�����ɏ\���Ȍ��ʂ��グ��Z�p�𖢂��Ɍ����o���Ă��Ȃ��؋�
�ƌ��ĊԈႢ�Ȃ��̂ł͂Ȃ����낤���B����ɂ��Ă��A���ɑސE�����|���R�c�̌��Z�p���̕M�҂ł����A�ŏ��ɒ�����
���R�c�����\��q�������ہA�u��^�g���b�N�ɂ����鎟��NO���K���ւ̓K���Z�p�ƔR�����̋Z�p�v�Ƃ��āA��
�ߘb��̐V�����Z�p������������Ă������ƂɁA���R�Ƃ��Ă��܂����̂ł���B���ɁA�����������R�c�����\
�������ꂽ�\�T�̋Z�p��g�������Z�p�����ł́A��^�g���b�N�̏d�ʎԃ��[�h�R����\���Ɍ��コ���邱��
���ɂ߂č���ł��邱�Ƃ́A�����Ԕr�o�K�X���ψ���̊w�ҁE���Ƃ��\���ɏ��m����Ă���̂ł͂Ȃ����낤
���B���������āA�����Ԕr�o�K�X���ψ���̊w�ҁE���Ƃ�������NO���K�������i2016�N���{�j�ɂ����āA��\��
�ɗ����Z�p���̗p���Ă��R����オ�u����グ�v�̏�Ԃł��邱�Ƃ��A��\���̋L�q�̒��������ɓf�I
����Ă���悤�Ɏv����̂ł���B
�@�Ƃ���ŁA2005�N4��8�������ȁE�������R�c����攪�����\�ł́A�|�X�g�V�����r�o�K�X�K���i2005�N�K���j��
NO���� 0.7 g/kWh�� 1/3���x��NO���� 0.23 g/kWh�̂m�n������ڕW����������Ă����B����2005�N�̑攪�����\�ɂ�
���āA�M�҂��܂߂đ����̍�����g���b�N���[�J�́A�|�X�g�V�����r�o�K�X�K���i2005�N�K���j�ɑ�������NO���K������
�ł́A���R�ANO���K���l�� 0.23 g/kWh�ɂȂ���̂Ɨ\�z����Ă����B�Ƃ��낪�A2010�N�V�������\���ꂽ�������R�c
�����\�����\�ł́A�|�X�g�V�����r�o�K�X�K���i2005�N�K���j�̎���NO���K�������́A2016�N�Ɏ��{�����uNO��
�K���l�� 0.4 g/kWh�iWHTC���[�h�j�v�Ɣ��\����A����܂ŗ\�z����Ă���NO���l�� 0.23 g/kWh����NO���l�� 0.4 g/
kWh�ɑ啝�Ɋɘa���ꂽ�����Ƃ����炩�ƂȂ����B����ɂ��āA�������R�c�����\���ł́A����NO���K��
�l���\���NO���l�� 0.23 g/kWh����NO���l�� 0.4 g/kWh�ɑ啝�ɕύX���ꂽ�̂́A�r�o�K�X�������[�h��JE05
���[�h����WHTC���[�h�ɕύX�������ƂƃR�[���h�X�^�[�g������V���Ȓlj��������߂ł���A�u�攪�����\��NO���l�� 0.
23 g/kWh�iJE05���[�h�j�v�Ɓu��\�����\��NO���l�� 0.4 g/kWh�iWHTC���[�h�j�v�Ƃ̓G���W�������NO���r�o�́A�����
���x���ł���Ƌ����ɐ�������Ă���B������\���������ɂ͑����̖���������A�u�攪�����\��NO���l�� 0.
23 g/kWh�iJE05���[�h�j�v����u��\�����\��NO���l�� 0.4 g/kWh�iWHTC���[�h�j�v�ւ̕ύX�́A�M�҂ɂ͖���
����NO���K���̊ɘa�ƌ�����̂ł����B
NO���� 0.7 g/kWh�� 1/3���x��NO���� 0.23 g/kWh�̂m�n������ڕW����������Ă����B����2005�N�̑攪�����\�ɂ�
���āA�M�҂��܂߂đ����̍�����g���b�N���[�J�́A�|�X�g�V�����r�o�K�X�K���i2005�N�K���j�ɑ�������NO���K������
�ł́A���R�ANO���K���l�� 0.23 g/kWh�ɂȂ���̂Ɨ\�z����Ă����B�Ƃ��낪�A2010�N�V�������\���ꂽ�������R�c
�����\�����\�ł́A�|�X�g�V�����r�o�K�X�K���i2005�N�K���j�̎���NO���K�������́A2016�N�Ɏ��{�����uNO��
�K���l�� 0.4 g/kWh�iWHTC���[�h�j�v�Ɣ��\����A����܂ŗ\�z����Ă���NO���l�� 0.23 g/kWh����NO���l�� 0.4 g/
kWh�ɑ啝�Ɋɘa���ꂽ�����Ƃ����炩�ƂȂ����B����ɂ��āA�������R�c�����\���ł́A����NO���K��
�l���\���NO���l�� 0.23 g/kWh����NO���l�� 0.4 g/kWh�ɑ啝�ɕύX���ꂽ�̂́A�r�o�K�X�������[�h��JE05
���[�h����WHTC���[�h�ɕύX�������ƂƃR�[���h�X�^�[�g������V���Ȓlj��������߂ł���A�u�攪�����\��NO���l�� 0.
23 g/kWh�iJE05���[�h�j�v�Ɓu��\�����\��NO���l�� 0.4 g/kWh�iWHTC���[�h�j�v�Ƃ̓G���W�������NO���r�o�́A�����
���x���ł���Ƌ����ɐ�������Ă���B������\���������ɂ͑����̖���������A�u�攪�����\��NO���l�� 0.
23 g/kWh�iJE05���[�h�j�v����u��\�����\��NO���l�� 0.4 g/kWh�iWHTC���[�h�j�v�ւ̕ύX�́A�M�҂ɂ͖���
����NO���K���̊ɘa�ƌ�����̂ł����B
�@���������A2016�N���{�����NO���K�������ɑ�^�g���b�N��K�������邽�߂̏d�v�ȋZ�p�J���̉ۑ�́A�r�o�K�X
�������[�h�^�]�ɂ�����y���^�]���̔r�C�K�X���x�̒Ⴂ�G���W���^�]�̈�ɂ����āA�A�fSCR�G�}��NO���팸
�������コ����Z�p���J�����邱�Ƃł���A���̂��Ƃ̓f�B�[�[���G���W���W�҂ł���ΒN�����m���Ă��邱�Ƃł�
��B�������Ȃ���A�������R�c�����\���ɂ́A2016�N�̎���NO���K�������ւ̓K���̂��߂ɁA�|�X�g�V����
�r�o�K�X�K���K���̋Z�p�ɐV���ɒlj�����Z�p�Ƃ��āA�\�V�Ɏ������悤�Ɂu2�i�ߋ��v�A�uEGR���̌���i�ꕔ�ɂ�LP-
EGR�̗p�j�v�A�u�R�����ˈ��͂̌����PCI�R�āv�A�u�ꕔ�Ԏ�ɂ̓^�[�{�R���p�E���h�v���Z�p������Ă��邪�A�r
�C�K�X���x�̒Ⴂ�G���W���^�]�̈�ł̔A�fSCR�G�}��NO���팸�������コ����Z�p���������Ă��Ȃ��B
�������[�h�^�]�ɂ�����y���^�]���̔r�C�K�X���x�̒Ⴂ�G���W���^�]�̈�ɂ����āA�A�fSCR�G�}��NO���팸
�������コ����Z�p���J�����邱�Ƃł���A���̂��Ƃ̓f�B�[�[���G���W���W�҂ł���ΒN�����m���Ă��邱�Ƃł�
��B�������Ȃ���A�������R�c�����\���ɂ́A2016�N�̎���NO���K�������ւ̓K���̂��߂ɁA�|�X�g�V����
�r�o�K�X�K���K���̋Z�p�ɐV���ɒlj�����Z�p�Ƃ��āA�\�V�Ɏ������悤�Ɂu2�i�ߋ��v�A�uEGR���̌���i�ꕔ�ɂ�LP-
EGR�̗p�j�v�A�u�R�����ˈ��͂̌����PCI�R�āv�A�u�ꕔ�Ԏ�ɂ̓^�[�{�R���p�E���h�v���Z�p������Ă��邪�A�r
�C�K�X���x�̒Ⴂ�G���W���^�]�̈�ł̔A�fSCR�G�}��NO���팸�������コ����Z�p���������Ă��Ȃ��B
�@
�@���̂��Ƃ���A�����Ԕr�o�K�X���ψ���̊w�ҁE���Ƃ́A�y���^�]���̔r�C�K�X���x�̒Ⴂ�G���W���^�]��
��ł̔A�fSCR�G�}��NO���팸��������ł���Z�p���s���Ȃ��߂ɑ啝��NO���팸������ƔF�����A�ߋ���NO���l
�� 0.23 g/kWh�iJE05���[�h�j�̑攪�����\�̕��j��ύX���A��\�����\�ɂ����āuNO���K���l�� 0.4 g/kWh�iWHTC��
�[�h�j�v�ւ̑啝�Ȋɘa���邱�Ƃ����f���ꂽ�Ɛ��������B�܂�A�A�����Ԕr�o�K�X���ψ���̊w�ҁE���Ƃ́A
����ł͑�^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W���̑啝��NO���팸���u�����ǂ���v�̏�Ԃł���Ƃ̔F���ňӌ�����v��
�Ă���悤�ɍl������B
��ł̔A�fSCR�G�}��NO���팸��������ł���Z�p���s���Ȃ��߂ɑ啝��NO���팸������ƔF�����A�ߋ���NO���l
�� 0.23 g/kWh�iJE05���[�h�j�̑攪�����\�̕��j��ύX���A��\�����\�ɂ����āuNO���K���l�� 0.4 g/kWh�iWHTC��
�[�h�j�v�ւ̑啝�Ȋɘa���邱�Ƃ����f���ꂽ�Ɛ��������B�܂�A�A�����Ԕr�o�K�X���ψ���̊w�ҁE���Ƃ́A
����ł͑�^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W���̑啝��NO���팸���u�����ǂ���v�̏�Ԃł���Ƃ̔F���ňӌ�����v��
�Ă���悤�ɍl������B
�@���̂悤�ɁA�r�C�K�X���x�̒Ⴂ�G���W���^�]�̈�ł̔A�fSCR�G�}��NO���팸�������コ����Z�p�������_�ŕs
���ł���Ƃ͉]���A�����Ԕr�o�K�X���ψ���̊w�ҁE���Ƃ�����NO���K���l�������\���NO���l�� 0.23 g/kWh
����NO���l�� 0.4 g/kWh��NOx�K���l���啝�Ɋɘa���ꂽ���Ƃ́A�g���b�N���[�J��NO���팸�̋Z�p�J���̓����팸��
�\�ƂȂ邽�߁A�g���b�N���[�J�ɂƂ��Ă����v�̌���̋@������ƂɂȂ�A�g���b�N���[�J�Ƃ��Ă͏����~��Ȃ���
�l������B�u�I����ڂ��݁v�Ƃ́A���̂悤�Ȃ��Ƃ��w���̂ł͂Ȃ����낤���B�����āA�����Ԕr�o�K�X���ψ���̊w
�ҁE���Ƃ́A�g���b�N���[�J���犴�ӂ���邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ����낤�B
���ł���Ƃ͉]���A�����Ԕr�o�K�X���ψ���̊w�ҁE���Ƃ�����NO���K���l�������\���NO���l�� 0.23 g/kWh
����NO���l�� 0.4 g/kWh��NOx�K���l���啝�Ɋɘa���ꂽ���Ƃ́A�g���b�N���[�J��NO���팸�̋Z�p�J���̓����팸��
�\�ƂȂ邽�߁A�g���b�N���[�J�ɂƂ��Ă����v�̌���̋@������ƂɂȂ�A�g���b�N���[�J�Ƃ��Ă͏����~��Ȃ���
�l������B�u�I����ڂ��݁v�Ƃ́A���̂悤�Ȃ��Ƃ��w���̂ł͂Ȃ����낤���B�����āA�����Ԕr�o�K�X���ψ���̊w
�ҁE���Ƃ́A�g���b�N���[�J���犴�ӂ���邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ����낤�B
�@�Ƃ���ŁA�������R�c�����\���ɋL�ڂ���Ă���ŋ߂������ԋZ�p��Řb��ƂȂ��Ă���Z�p���W
�߂ė����ƌ������\�T���Z�p�̑g�����ł́A��^�g���b�N�̏\���Ȓ�NO�����ƒ�R����������邱�Ƃ������
���Ƃ͖��炩���B�����āA�攪�����\�i2005�N�j�ɋL�ڂ��ꂽNO���팸�̒���ڕW��NO���l�� 0.23 g/kWh�iJE05���[
�h�j�����A�č���2009�N��NO���K���l�� 0.27 g/kWh�ɔ�ׂĂ��i�i�Ɋɘa�����ɂ���\�����\�i2010�N7���j�uNO
���K���l�� 0.4 g/kWh�iWHTC���[�h�j�v�����\����Ă��邱�Ƃ͎����ł���B����ɂ��āA���݂̂킪���ł́A�Z�p�I
�Ɂu�r�C�K�X���x�̒Ⴂ�G���W���^�]�̈�ł̔A�fSCR�G�}��NO���팸�������コ�����攪�����\�i2005�N�j�ɋL��
���ꂽNO���팸�̒���ڕW��NO���l�� 0.23 g/kWh��B�������Z�p���s���v�ł��邱�Ƃ������ł���A���A�u2015
�N�x�d�ʎԃ��[�h�R������̂T�����x�̔R�����������ł���Z�p���s���v�ł���Ȃ�A�������R�c�
��\�����\�ɂ����āuNO���K���l�� 0.4 g/kWh�iWHTC���[�h�j�v�ւ̑啝�Ɋɘa�������Ƃ́A���R�̂��Ƃƍl������B
�߂ė����ƌ������\�T���Z�p�̑g�����ł́A��^�g���b�N�̏\���Ȓ�NO�����ƒ�R����������邱�Ƃ������
���Ƃ͖��炩���B�����āA�攪�����\�i2005�N�j�ɋL�ڂ��ꂽNO���팸�̒���ڕW��NO���l�� 0.23 g/kWh�iJE05���[
�h�j�����A�č���2009�N��NO���K���l�� 0.27 g/kWh�ɔ�ׂĂ��i�i�Ɋɘa�����ɂ���\�����\�i2010�N7���j�uNO
���K���l�� 0.4 g/kWh�iWHTC���[�h�j�v�����\����Ă��邱�Ƃ͎����ł���B����ɂ��āA���݂̂킪���ł́A�Z�p�I
�Ɂu�r�C�K�X���x�̒Ⴂ�G���W���^�]�̈�ł̔A�fSCR�G�}��NO���팸�������コ�����攪�����\�i2005�N�j�ɋL��
���ꂽNO���팸�̒���ڕW��NO���l�� 0.23 g/kWh��B�������Z�p���s���v�ł��邱�Ƃ������ł���A���A�u2015
�N�x�d�ʎԃ��[�h�R������̂T�����x�̔R�����������ł���Z�p���s���v�ł���Ȃ�A�������R�c�
��\�����\�ɂ����āuNO���K���l�� 0.4 g/kWh�iWHTC���[�h�j�v�ւ̑啝�Ɋɘa�������Ƃ́A���R�̂��Ƃƍl������B
�@�������Ȃ���A�M�҂�2006�N4���Ƀz�[���y�[�W���J�݂��A�u�r�C�K�X���x�̒Ⴂ�G���W���^�]�̈�ł̔A�fSCR�G
�}��NO���팸�������コ�����攪�����\�i2005�N�j�ɋL�ڂ��ꂽNO���팸�̒���ڕW��NO���l�� 0.23 g/kWh�̒B��
���\�v�ł���A���A�u2015�N�x�d�ʎԃ��[�h�R������̂T�����x�̔R�������������\�v���C���x�~�G���W
���i�������J2005-54771�j�̋Z�p�����J���Ă���B�����āA�����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p���
�^�g���b�N�̃G���W���ɍ̗p����A�e�Ղ��u�m�n���r�o�l�� 0.23 g/kWh�iWHTC���[�h)�v�Ɓu2015�N�x�d�ʎԃ��[�h�R��
�����̂T�����x�̔R�����v�̑�^�g���b�N�����p���ł��邱�Ƃ����\���Ă���̂ł���B����ɂ�������炸�A
�������R�c�2010�N7���̑�\�����\�ő�^�g���b�N�̎���NO���K���l�Ƃ����uNO���l�� 0.4 g/kWh�iWHTC��
�[�h�j�v�\���ꂽ���Ƃɂ��ẮA�킪���ɂ����閾�炩��NO���K���̊ɘa�ƕM�҂ɂ͌������̂ł���B
�}��NO���팸�������コ�����攪�����\�i2005�N�j�ɋL�ڂ��ꂽNO���팸�̒���ڕW��NO���l�� 0.23 g/kWh�̒B��
���\�v�ł���A���A�u2015�N�x�d�ʎԃ��[�h�R������̂T�����x�̔R�������������\�v���C���x�~�G���W
���i�������J2005-54771�j�̋Z�p�����J���Ă���B�����āA�����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p���
�^�g���b�N�̃G���W���ɍ̗p����A�e�Ղ��u�m�n���r�o�l�� 0.23 g/kWh�iWHTC���[�h)�v�Ɓu2015�N�x�d�ʎԃ��[�h�R��
�����̂T�����x�̔R�����v�̑�^�g���b�N�����p���ł��邱�Ƃ����\���Ă���̂ł���B����ɂ�������炸�A
�������R�c�2010�N7���̑�\�����\�ő�^�g���b�N�̎���NO���K���l�Ƃ����uNO���l�� 0.4 g/kWh�iWHTC��
�[�h�j�v�\���ꂽ���Ƃɂ��ẮA�킪���ɂ����閾�炩��NO���K���̊ɘa�ƕM�҂ɂ͌������̂ł���B
�@�Ȃ��Ȃ�A�C���x�~�G���W���ɂ���^�g���b�N�̒�R�������C���x�~�́A�f�B�[�[���̂m�n���팸�ƔR�����
�̈ꋓ�����̋Z�p���I�ɏڏq���Ă���悤�ɁA�������R�c��E��C���������\�����\�ɋL�ڂ���Ă���
����̑�^�g���b�N�̒�NO�����ƒ�R����������邽�߂̋Z�p�Ƃ��ẮA�����Ԕr�o�K�X���ψ���̊w
�ҁE���Ƃ���\���̒�������Ă���W�ߋZ�p�i�\�X�Q�Ɓj�����A��̋Z�p�ł���ɂ�����
��炸�\�����R����P�Ƒ啝��NO���팸�̗����������ł����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z
�p�̕����i�i�ɗD��Ă������߂ł���B
�̈ꋓ�����̋Z�p���I�ɏڏq���Ă���悤�ɁA�������R�c��E��C���������\�����\�ɋL�ڂ���Ă���
����̑�^�g���b�N�̒�NO�����ƒ�R����������邽�߂̋Z�p�Ƃ��ẮA�����Ԕr�o�K�X���ψ���̊w
�ҁE���Ƃ���\���̒�������Ă���W�ߋZ�p�i�\�X�Q�Ɓj�����A��̋Z�p�ł���ɂ�����
��炸�\�����R����P�Ƒ啝��NO���팸�̗����������ł����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z
�p�̕����i�i�ɗD��Ă������߂ł���B
���̂��Ƃ́A�O���܂ł��M�҂̒P�Ȃ鐄���ɉ߂����A�������R�c��̑�\���ɂ������C���x�~�G���W���i����
���J2005-54771�j�̋Z�p�����荞�܂�Ă��Ȃ��̂́A�����Ԕr�o�K�X���ψ���̊w�ҁE���Ƃ����̋Z�p���Ӑ}
�I�ɖَE���ꂽ���ʂł���̂��A�͂��܂��A�M�Ғ�Ă̋C���x�~�̋Z�p�̑��݂�S�����m����Ă��Ȃ����Ƃɂ���
�̂ł��邩�́A���̂Ƃ���M�҂ɂ͕s�����B
���J2005-54771�j�̋Z�p�����荞�܂�Ă��Ȃ��̂́A�����Ԕr�o�K�X���ψ���̊w�ҁE���Ƃ����̋Z�p���Ӑ}
�I�ɖَE���ꂽ���ʂł���̂��A�͂��܂��A�M�Ғ�Ă̋C���x�~�̋Z�p�̑��݂�S�����m����Ă��Ȃ����Ƃɂ���
�̂ł��邩�́A���̂Ƃ���M�҂ɂ͕s�����B
�T�|�P�@�����Ԕr�o�K�X���ψ���͋C���x�~�i���J2005-54771�j�̋Z�p��َE���H
�@
�@�Ƃ���ŁA���݂́uCO�Q�팸�v�A�u�ȃG�l���M�[�v�A�u�Ȏ����v�������߂��Ă��鎞��ł��邱�Ƃ́A��ʂ̎�w�⏬
�w���ł��ǂ��������Ă��邱�Ƃł���B����ɂ�������炸�A�����Ԕr�o�K�X���ψ���̊w�ҁE���Ƃ́A�uNO����
���v�Ɓu�R�����v�̗������Ɏ����ł����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p�����钆�����R
�c��̑�\�����쐬����Ă���̂��B���̂悤�ɁA�����Ԕr�o�K�X���ψ���̊w�ҁE���Ƃ̎�ɂȂ��
�ȁE�������R�c�����\���ɂ́A����̑�^�g���b�N�̒�NO�����ƒ�R����������邽�߂̋Z�p�Ƃ��āA�M
�Ғ�Ă��C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j���S���L�ڂ���Ă��Ȃ����Ƃ͎����ł���B���̂��Ƃɂ��āA����
���́A�Z�p�����L�����W���ċq�ϓI�ȕ]���ɂ���ēZ�߂�ꂽ���̂ł͖����A�����Ԕr�o�K�X���ψ���̊w
�ҁE���Ƃ̜��ӓI�Ȉӌ��̏W��̂悤�ɕM�҂ɂ͎v���邪�A�@���Ȃ��̂ł��낤���B
�w���ł��ǂ��������Ă��邱�Ƃł���B����ɂ�������炸�A�����Ԕr�o�K�X���ψ���̊w�ҁE���Ƃ́A�uNO����
���v�Ɓu�R�����v�̗������Ɏ����ł����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p�����钆�����R
�c��̑�\�����쐬����Ă���̂��B���̂悤�ɁA�����Ԕr�o�K�X���ψ���̊w�ҁE���Ƃ̎�ɂȂ��
�ȁE�������R�c�����\���ɂ́A����̑�^�g���b�N�̒�NO�����ƒ�R����������邽�߂̋Z�p�Ƃ��āA�M
�Ғ�Ă��C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j���S���L�ڂ���Ă��Ȃ����Ƃ͎����ł���B���̂��Ƃɂ��āA����
���́A�Z�p�����L�����W���ċq�ϓI�ȕ]���ɂ���ēZ�߂�ꂽ���̂ł͖����A�����Ԕr�o�K�X���ψ���̊w
�ҁE���Ƃ̜��ӓI�Ȉӌ��̏W��̂悤�ɕM�҂ɂ͎v���邪�A�@���Ȃ��̂ł��낤���B
�@���̂悤�ɁA�|�X�g�V�����r�o�K�X�K���K���̑�^�g���b�N�ɐV�����C���x�~�G���W���i�������J2005-
54771�j��lj����邱�Ƃɂ���āA�e�Ղɑ�\�����\�̎�����NO���K�������i2016�N���{�j�ɑ�^�g���b�N��K
��������Ɠ����ɒ�R��������ł���Z�p�����ɑ��݂��Ă���̂ł���B����ɂ�������炸�A�����Ԕr�o
�K�X���ψ���̊w�ҁE���Ƃ����̋Z�p���Ӑ}�I�ɖ����E�َE���Ċ��ȁE�������R�c���2010�N�V��
����\�����܂Ƃ߂Ă����Ƃ�����A�ɂ߂Ďc�O�Ȃ��Ƃ��B
54771�j��lj����邱�Ƃɂ���āA�e�Ղɑ�\�����\�̎�����NO���K�������i2016�N���{�j�ɑ�^�g���b�N��K
��������Ɠ����ɒ�R��������ł���Z�p�����ɑ��݂��Ă���̂ł���B����ɂ�������炸�A�����Ԕr�o
�K�X���ψ���̊w�ҁE���Ƃ����̋Z�p���Ӑ}�I�ɖ����E�َE���Ċ��ȁE�������R�c���2010�N�V��
����\�����܂Ƃ߂Ă����Ƃ�����A�ɂ߂Ďc�O�Ȃ��Ƃ��B
�T�|�Q�@�����Ԕr�o�K�X���ψ���͋C���x�~�i���J2005-54771�j�̋Z�p��s���m���H
�@����͒P�Ȃ鉼��E�����̘b�ƂȂ邪�A�������R�c�����\�����\�ł̎�����NO���K�������i2016�N���{�j�ɑ�
�^�g���b�N��K�������邱�Ƃ��ł�����ҋZ�p�Ƃ��āA��\����NO���팸��R����P�̋@�\����鐔�����̋Z�p��
�W�߂�����Ă��鐄�����R�́A�����Ԕr�o�K�X���ψ���̊w�ҁE���Ƃ���\�����\������b�ɒ�
�o���ꂽ2010�N�V��28�����ȑO�ɁA�M�Ғ�Ă��C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�����m����Ă��Ȃ�����
�ꍇ���l������B���̂悤�ɁA�M�Ғ�Ă��C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�Ɋւ������S������ł���
���ꍇ�Ƃ��ẮA�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p��2006�N4��7���ɊJ�݂����z�[���y�[�W�����Ɍf
�ڂ��Ă���Z�p�ł��邽�߁A�C���^�[�l�b�g�����y���������ł�google��yahoo�̌������g���ăf�B�[�[���G���W���̔r
�o�K�X�팸��R�����̋Z�p���̎��W��S�����ۂ���Ă��������Ԕr�o�K�X���ψ���̊w�ҁE���Ƃ̏ꍇ��
�́A�M�Ғ�Ă��C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p�̑��݂�m�邱�Ƃ��ł��Ȃ������\�����l�����
��B
�^�g���b�N��K�������邱�Ƃ��ł�����ҋZ�p�Ƃ��āA��\����NO���팸��R����P�̋@�\����鐔�����̋Z�p��
�W�߂�����Ă��鐄�����R�́A�����Ԕr�o�K�X���ψ���̊w�ҁE���Ƃ���\�����\������b�ɒ�
�o���ꂽ2010�N�V��28�����ȑO�ɁA�M�Ғ�Ă��C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�����m����Ă��Ȃ�����
�ꍇ���l������B���̂悤�ɁA�M�Ғ�Ă��C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�Ɋւ������S������ł���
���ꍇ�Ƃ��ẮA�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p��2006�N4��7���ɊJ�݂����z�[���y�[�W�����Ɍf
�ڂ��Ă���Z�p�ł��邽�߁A�C���^�[�l�b�g�����y���������ł�google��yahoo�̌������g���ăf�B�[�[���G���W���̔r
�o�K�X�팸��R�����̋Z�p���̎��W��S�����ۂ���Ă��������Ԕr�o�K�X���ψ���̊w�ҁE���Ƃ̏ꍇ��
�́A�M�Ғ�Ă��C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p�̑��݂�m�邱�Ƃ��ł��Ȃ������\�����l�����
��B
�@�������Agoogle��yahoo�̌������g�����Z�p���̎��W��S�����ۂ���Ă��������Ԕr�o�K�X���ψ���̊w�ҁE��
��Ƃ����݂���Ƃ��Ă��A����͋ɂ߂ď����̊w�ҁE���Ƃł͂Ȃ����Ɛ��@�����B���ɁA�C���^�[�l�b�g�̌����G��
�W���ŋZ�p�������W����Ȃ��w�ҁE���Ƃł����Ă��A�����Ԕr�o�K�X���ψ���̉�c���ɑ��̊w�ҁE���Ƃ�
���C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̏����ꂽ���̂ƍl������B���������āA�������R�c�����\
�����\������b�ɒ�o���ꂽ2010�N�V��28�����ȑO�ɁA�����Ԕr�o�K�X���ψ���̊w�ҁE���Ƃ́A�M�Ғ�
�Ă��C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p�����m����Ă����ƍl���邱�Ƃ��Ó��ł͂Ȃ����낤���B
��Ƃ����݂���Ƃ��Ă��A����͋ɂ߂ď����̊w�ҁE���Ƃł͂Ȃ����Ɛ��@�����B���ɁA�C���^�[�l�b�g�̌����G��
�W���ŋZ�p�������W����Ȃ��w�ҁE���Ƃł����Ă��A�����Ԕr�o�K�X���ψ���̉�c���ɑ��̊w�ҁE���Ƃ�
���C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̏����ꂽ���̂ƍl������B���������āA�������R�c�����\
�����\������b�ɒ�o���ꂽ2010�N�V��28�����ȑO�ɁA�����Ԕr�o�K�X���ψ���̊w�ҁE���Ƃ́A�M�Ғ�
�Ă��C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p�����m����Ă����ƍl���邱�Ƃ��Ó��ł͂Ȃ����낤���B
�@���������āA�����Ԕr�o�K�X���ψ���̊w�ҁE���Ƃ���̂ƂȂ��č쐬���ꂽ���ȁE�������R�c�����\
���ɂ́A����̑�^�g���b�N�̒�NO�����ƒ�R����������邽�߂̋Z�p�Ƃ��āA�M�Ғ�Ă��C���x�~�G���W��
�i�������J2005-54771�j���L�ڂ���Ă��Ȃ��̂́A�����Ԕr�o�K�X���ψ���̊w�ҁE���Ƃ́A�M�҂���Ă��Ă�
���^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W�����R����P��NO���팸�ɋɂ߂ėL�����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j
�̋Z�p���Ӑ}�I�ɖَE���ꂽ���ʂƐ��@�����B���̈���ŁA�����Ԕr�o�K�X���ψ���̊w�ҁE���Ƃ́A��\
���̒��ɂ��\�T�Ɏ������悤�ɁA����̑�^�g���b�N�̒�NO���ƒ�R���}��Z�p�Ƃ����R����P��NO���팸�̋@
�\������Z�p���W�߂ē��X�Ɛ������̋Z�p����A����Ă��邱�Ƃł���B����ɂ��āA�u�����������
��I�v�Ƌ��т����Ȃ�̂́A�M�҂����ł��낤���B
���ɂ́A����̑�^�g���b�N�̒�NO�����ƒ�R����������邽�߂̋Z�p�Ƃ��āA�M�Ғ�Ă��C���x�~�G���W��
�i�������J2005-54771�j���L�ڂ���Ă��Ȃ��̂́A�����Ԕr�o�K�X���ψ���̊w�ҁE���Ƃ́A�M�҂���Ă��Ă�
���^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W�����R����P��NO���팸�ɋɂ߂ėL�����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j
�̋Z�p���Ӑ}�I�ɖَE���ꂽ���ʂƐ��@�����B���̈���ŁA�����Ԕr�o�K�X���ψ���̊w�ҁE���Ƃ́A��\
���̒��ɂ��\�T�Ɏ������悤�ɁA����̑�^�g���b�N�̒�NO���ƒ�R���}��Z�p�Ƃ����R����P��NO���팸�̋@
�\������Z�p���W�߂ē��X�Ɛ������̋Z�p����A����Ă��邱�Ƃł���B����ɂ��āA�u�����������
��I�v�Ƌ��т����Ȃ�̂́A�M�҂����ł��낤���B
�T�|�R�@�C���x�~�i���J2005-54771�j�́A��^�g���b�N�̒�NO���ƒ�R��ɍœK�ȋZ�p
�@����̑�^�g���b�N�̒�NO���ƒ�R���}��Z�p�Ƃ��āA�����Ԕr�o�K�X���ψ���̊w�ҁE���Ƃ���\����
�̒��Ɏ������R����P��NO���팸�Ɋւ����W�ߑg�����Z�p�ƁA�M�҂���Ă��Ă����R����P��NO���팸�̋Z�p
�����āA�ȉ��̕\�P�R�Ɏ������B
�̒��Ɏ������R����P��NO���팸�Ɋւ����W�ߑg�����Z�p�ƁA�M�҂���Ă��Ă����R����P��NO���팸�̋Z�p
�����āA�ȉ��̕\�P�R�Ɏ������B
| |
|
|
| |
�E �|�X�g�V�����r�o�K�X�K���̓K���Z�p�i���s�Z�p�j
�E 2�i�ߋ��A2�i�ߋ������ɂ��G���W���_�E���T�C�W���O
�E EGR���̌���AEGR����̍��x��
�@�@�i�ꕔ�Ԏ�ւ�LP-EGR�̗̍p�j
�E �R�����ˈ��͂̌��さPCI�R�Ăł͈̔͊g��
�@�@�i�R�����ː���̍��x���j
�E �ꕔ�Ԏ�ւ̃^�[�{�R���p�E���h�V�X�e���̗̍p
|
�@ NO���K���l�� 0.4 g/kWh�iWHTC���[�h�j
�A �R��̐L�т�����m��
�i��2015�N�x�d�ʎԔR������
���p�[�Z���g���x������R�����Ƃ�
�Ӗ��H�Ɛ����j
�y���F���L�̋Z�p���̗p���Ă��A2015�N�x
�d�ʎԔR�����琔�p�[�Z���g���x��
���x���̔R������シ�邱�Ƃ�����ł�
�Ȃ����ƕM�҂͗\�z���Ă���B�ڍׂ́A
|
| |
�E �|�X�g�V�����r�o�K�X�K���̓K���Z�p�i���s�Z�p�j
�E �u�d����p�t�@���v+�u�d���E�H�[�^�[�|���v�v
|
�@ ��m�n�����0.23g/kWh�iWHTC���[�h�j
�A�@�啝�ȔR�����
�i��2015�N�x�d�ʎԔR������
�{10���`15���̔R�����j
|
��L�̕\10�Ɏ����Ă���悤���A�������R�c�����\���̋L�ړ��e������ƁA�����Ԕr�o�K�X���ψ����
�w�ҁE���Ƃ́A�����Ԕr�o�K�X���ψ���̑�\���ɂ��ƃ|�X�g�V�����K���K���G���W���Ɂu2�i�ߋ��v�A
�uEGR���̌���i�ꕔ�ɂ�LP-EGR�̗p�j�v�A�u�R�����ˈ��͂̌����PCI�R�āv�A�u�ꕔ�Ԏ�ɂ̓^�[�{�R���p�E���h�v��
�W�߂��������̋Z�p��lj����Ă��A2016�N���{�́uNO���K���l�� 0.4 g/kWh�iWHTC���[�h�j�ւ̓K���v��NO���팸
�ƁA�u�R��̐L�т�����m�ہv�Ə̂�����x�̔R����P���x���̑�^�g���b�N���������ł��Ȃ��悤���B������A����
�߳��ނ��ި���ٔR���啝�ɉ��P�ł���Ƃ̎咣�́A��肾�I�ɏڏq���Ă���悤�ɁA�^�[�{�R���p�E���h�̋Z�p��
�̗p�����Ƃ��Ă��A���̋Z�p�͋C�����̍ō����͂����߂邱�ƂȂ��A�G���W���̍��o�͉����\�ȋZ�p�ł���A�R���
��̋@�\�͏��Ȃ��A�d�ʎԃ��[�h�R����P�����������ł��Ȃ��悤�ȔR����P�ɕs�K�ł��邩�炾�B����ɑ��M�҂�
��Ă���Z�p�ł́A�|�X�g�V�����K���K���G���W�����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̈���Z�p�̒lj�
���邱�Ƃɂ���āA�u�m�n���l��0.23g/kWh�iWHTC���[�h�j�̒B���v�ɑ啝��NO���팸�ƁA�u2015�N�x�d�ʎԔR������
10���̔R�����v�̑啝�ȔR����P������^�g���b�N�������ł���̂ł���B
�w�ҁE���Ƃ́A�����Ԕr�o�K�X���ψ���̑�\���ɂ��ƃ|�X�g�V�����K���K���G���W���Ɂu2�i�ߋ��v�A
�uEGR���̌���i�ꕔ�ɂ�LP-EGR�̗p�j�v�A�u�R�����ˈ��͂̌����PCI�R�āv�A�u�ꕔ�Ԏ�ɂ̓^�[�{�R���p�E���h�v��
�W�߂��������̋Z�p��lj����Ă��A2016�N���{�́uNO���K���l�� 0.4 g/kWh�iWHTC���[�h�j�ւ̓K���v��NO���팸
�ƁA�u�R��̐L�т�����m�ہv�Ə̂�����x�̔R����P���x���̑�^�g���b�N���������ł��Ȃ��悤���B������A����
�߳��ނ��ި���ٔR���啝�ɉ��P�ł���Ƃ̎咣�́A��肾�I�ɏڏq���Ă���悤�ɁA�^�[�{�R���p�E���h�̋Z�p��
�̗p�����Ƃ��Ă��A���̋Z�p�͋C�����̍ō����͂����߂邱�ƂȂ��A�G���W���̍��o�͉����\�ȋZ�p�ł���A�R���
��̋@�\�͏��Ȃ��A�d�ʎԃ��[�h�R����P�����������ł��Ȃ��悤�ȔR����P�ɕs�K�ł��邩�炾�B����ɑ��M�҂�
��Ă���Z�p�ł́A�|�X�g�V�����K���K���G���W�����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̈���Z�p�̒lj�
���邱�Ƃɂ���āA�u�m�n���l��0.23g/kWh�iWHTC���[�h�j�̒B���v�ɑ啝��NO���팸�ƁA�u2015�N�x�d�ʎԔR������
10���̔R�����v�̑啝�ȔR����P������^�g���b�N�������ł���̂ł���B
�@���̂悤�ɁA�������R�c�����\���ɋL�ڂ��ꂽ�|�X�g�V�����K���K���Z�p�ɑ����̋Z�p��lj�������i�E
�Z�p�ɂ���^�g���b�N��NO���팸�ƔR����P�̃��x���́A�M�҂���Ă���|�X�g�V�����K���K���Z�p���C���x�~�G
���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p��lj�������i�E�Z�p�ɂ���^�g���b�N��NO���팸�ƔR����P�̃��x�������A
�啝�ɗ���Ă���̂ł���B���������āA��^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W����NO���팸�ƔR����P�̋Z�p�Ƃ��ẮA��
�̕\�W���������R�c�����\���ɋL�ڂ̋Z�p�����A�M�҂���Ă����C���x�~�G���W���i�������J2005-
54771�j���Z�p�̕����i�i�ɗD��Ă��邱�Ƃ́A�N�ł��e�Ղɗ����ł��锤���B
�Z�p�ɂ���^�g���b�N��NO���팸�ƔR����P�̃��x���́A�M�҂���Ă���|�X�g�V�����K���K���Z�p���C���x�~�G
���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p��lj�������i�E�Z�p�ɂ���^�g���b�N��NO���팸�ƔR����P�̃��x�������A
�啝�ɗ���Ă���̂ł���B���������āA��^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W����NO���팸�ƔR����P�̋Z�p�Ƃ��ẮA��
�̕\�W���������R�c�����\���ɋL�ڂ̋Z�p�����A�M�҂���Ă����C���x�~�G���W���i�������J2005-
54771�j���Z�p�̕����i�i�ɗD��Ă��邱�Ƃ́A�N�ł��e�Ղɗ����ł��锤���B
�@���x���J��Ԃ����A�M�҂���Ă��Ă����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p���^�g���b�N�ɍ̗p����
�ꍇ�ɂ́A���̋C���x�~�̋Z�p�����ő�^�g���b�N�ł͗D�ꂽNO���팸�ƔR����オ�����ł���̂��B�������A������
�r�o�K�X���ψ����́A���̑�^�g���b�N���\����NO���팸��R����オ�\�ȕM�Ғ�Ă��C���x�~�G���W���i����
���J2005-54771�j�̋Z�p�ɂ��āA�����E���Ƌ{�́u������v�{�u���킴��v�{�u��������v�̎O���̔@���A����������j
�����肳�ꂽ�悤�Ɏv����̂ł���B���ꂪ�����ł���A�����Ԕr�o�K�X���ψ�����w�ҁE���Ƃ���NO���ƒ�
�R��̗����ɗL���ȋZ�p���Ӑ}�I�ɔr������s�ׂł���A�M�҂ɂ͔[���ł��Ȃ����Ƃ��B
�ꍇ�ɂ́A���̋C���x�~�̋Z�p�����ő�^�g���b�N�ł͗D�ꂽNO���팸�ƔR����オ�����ł���̂��B�������A������
�r�o�K�X���ψ����́A���̑�^�g���b�N���\����NO���팸��R����オ�\�ȕM�Ғ�Ă��C���x�~�G���W���i����
���J2005-54771�j�̋Z�p�ɂ��āA�����E���Ƌ{�́u������v�{�u���킴��v�{�u��������v�̎O���̔@���A����������j
�����肳�ꂽ�悤�Ɏv����̂ł���B���ꂪ�����ł���A�����Ԕr�o�K�X���ψ�����w�ҁE���Ƃ���NO���ƒ�
�R��̗����ɗL���ȋZ�p���Ӑ}�I�ɔr������s�ׂł���A�M�҂ɂ͔[���ł��Ȃ����Ƃ��B
�@�Ƃ���ŁA��^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W���ɂ����ẮA����܂ł̗��j������Ζ��炩�Ȃ悤�ɁA�X�Ȃ��R������
NO���팸�͗e�ՂȂ��Ƃł͂Ȃ��B���̂��߁A�M�Ғ�Ă��C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p�ɕC�G����
�悤�ȁA��^�g���b�N��NO����0.23g/kWh�iWHTC���[�h�j�܂ł�NO���팸�ƁA2015�N�x�d�ʎԔR������10����
�R������Ƃ��Ɏ����ł���Z�p�́A�߂������ɊJ���ł���悤�ɂ͎v���Ȃ��B���̂悤�ȏɂ����āA���ɁA��
�����ɂ������^�g���b�N��NO���K���ƔR��K���̃��[�����[�L���O�ɑ���̉e���͂��s�g����Ă��������Ԕr�o�K
�X���ψ�����w�ҁE�������C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j���Z�p��َE����Ă���Ƃ���A��^�g��
�b�N�ɂ����鍡���NO���팸�ƔR�����ɑ傫�Ȑi�W���S�����҂ł��Ȃ��Ɖ]���Ă��ߌ��ł͂Ȃ����낤�B
NO���팸�͗e�ՂȂ��Ƃł͂Ȃ��B���̂��߁A�M�Ғ�Ă��C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p�ɕC�G����
�悤�ȁA��^�g���b�N��NO����0.23g/kWh�iWHTC���[�h�j�܂ł�NO���팸�ƁA2015�N�x�d�ʎԔR������10����
�R������Ƃ��Ɏ����ł���Z�p�́A�߂������ɊJ���ł���悤�ɂ͎v���Ȃ��B���̂悤�ȏɂ����āA���ɁA��
�����ɂ������^�g���b�N��NO���K���ƔR��K���̃��[�����[�L���O�ɑ���̉e���͂��s�g����Ă��������Ԕr�o�K
�X���ψ�����w�ҁE�������C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j���Z�p��َE����Ă���Ƃ���A��^�g��
�b�N�ɂ����鍡���NO���팸�ƔR�����ɑ傫�Ȑi�W���S�����҂ł��Ȃ��Ɖ]���Ă��ߌ��ł͂Ȃ����낤�B
�@���āA����A�P�O�N�P�ʂ̒����N�����o�߂��Ă��A�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�𗽉킷��V�����Z�p��
�����E�J�������Ɖ]���ۏ͉����ɂ��Ȃ��B���������āA�����Ԕr�o�K�X���ψ�����w�ҁE������������C���x
�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p��َE���ꑱ����ꍇ�ɂ́A�����ɂ������C���x�~�G���W���i�������J
2005-54771�j�𗽉킷���f�B�[�[���G���W���ł̏\���Ȓ�NO�����ƒ�R����\�ɂ���V�����Z�p�������E�J����
���܂ŁA�\�S�Ɏ������悤�ȑ�^�g���b�N�̐V���ȁu��NO���E��R��g���b�N�E�o�X�̊(�āj�v�����X�Ɛݒ肳�ꂸ�A��
NO���E��R��̑�^�g���b�N�����p������Ȃ��������čs���\��������̂��B����ɑ��ẮA�����̔ᔻ����
�܂��Ă�����̂Ɨ\�z�����B�������A����ł������Ԕr�o�K�X���ψ�����w�ҁE���Ƃ́A�C���x�~�G���W���i����
���J2005-54771�j�̋Z�p���������A�M�Ғ�Ă̋C���x�~�ɕC�G����V�����Z�p���o�����鎞����A���̋C���x
�~�̓����������̏I�����鎞���܂ŁA�����̔ᔻ�ɑς��čs������Ȃ̂ł��낤���B�����āA�����Ԕr�o�K�X����
������w�ҁE���Ƃ́A�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�𗽉킷��Z�p���������o�����邱�Ƃ��Ђ�����
�V�ɋF�葱�������ł��낤���B�����āA���̊ԁA��^�g���b�N��NO���팸�ƔR�����ɗL�����C���x�~�G���W���i��
�����J2005-54771�j���B�����Ă��邱�Ƃɂ��āA�w�ҁE���ƂƂ��Ă��ǐS�̙�ӂɔY�܂��ꑱ����o��ł��낤
���B���J�Ȃ��Ƃł���A�M�҂ɂ͂ƂĂ��^���̂ł��Ȃ����Ƃ��B���͂Ƃ�����A���ۂ������Ԕr�o�K�X���ψ����
�w�ҁE���Ƃ����ۂ��C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p��َE����Ă���̂ł���Ȃ�A���َ̖E
�̖{���̗��R�E���v�E�����b�g�ɂ��Đ���Ƃ��m�肽�����̂ł���B
�����E�J�������Ɖ]���ۏ͉����ɂ��Ȃ��B���������āA�����Ԕr�o�K�X���ψ�����w�ҁE������������C���x
�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p��َE���ꑱ����ꍇ�ɂ́A�����ɂ������C���x�~�G���W���i�������J
2005-54771�j�𗽉킷���f�B�[�[���G���W���ł̏\���Ȓ�NO�����ƒ�R����\�ɂ���V�����Z�p�������E�J����
���܂ŁA�\�S�Ɏ������悤�ȑ�^�g���b�N�̐V���ȁu��NO���E��R��g���b�N�E�o�X�̊(�āj�v�����X�Ɛݒ肳�ꂸ�A��
NO���E��R��̑�^�g���b�N�����p������Ȃ��������čs���\��������̂��B����ɑ��ẮA�����̔ᔻ����
�܂��Ă�����̂Ɨ\�z�����B�������A����ł������Ԕr�o�K�X���ψ�����w�ҁE���Ƃ́A�C���x�~�G���W���i����
���J2005-54771�j�̋Z�p���������A�M�Ғ�Ă̋C���x�~�ɕC�G����V�����Z�p���o�����鎞����A���̋C���x
�~�̓����������̏I�����鎞���܂ŁA�����̔ᔻ�ɑς��čs������Ȃ̂ł��낤���B�����āA�����Ԕr�o�K�X����
������w�ҁE���Ƃ́A�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�𗽉킷��Z�p���������o�����邱�Ƃ��Ђ�����
�V�ɋF�葱�������ł��낤���B�����āA���̊ԁA��^�g���b�N��NO���팸�ƔR�����ɗL�����C���x�~�G���W���i��
�����J2005-54771�j���B�����Ă��邱�Ƃɂ��āA�w�ҁE���ƂƂ��Ă��ǐS�̙�ӂɔY�܂��ꑱ����o��ł��낤
���B���J�Ȃ��Ƃł���A�M�҂ɂ͂ƂĂ��^���̂ł��Ȃ����Ƃ��B���͂Ƃ�����A���ۂ������Ԕr�o�K�X���ψ����
�w�ҁE���Ƃ����ۂ��C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p��َE����Ă���̂ł���Ȃ�A���َ̖E
�̖{���̗��R�E���v�E�����b�g�ɂ��Đ���Ƃ��m�肽�����̂ł���B
�@�܂��A��^�g���b�N��NO���팸�ƔR�����ɗL���ȋC���x�~��َE����w�ҏ����ɂ��ڏq���Ă���悤�ɁA�����Ԕr
�o�K�X���ψ�����w�ҁE���Ƃ́A��v�c�������C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p���Ӑ}���ĖَE
���Ă��邱�Ƃ����Ɏ����ł���A�킪���ɂ������^�g���b�N�̒�NO�����ƒ�R���x�点��s�ׂ��s���Ă����
�����Ă��d�����Ȃ��悤�Ɏv����B�����āA���̂悤�Ȃ��Ƃ������ɍs�Ȃ��Ă���Ƃ���A�����Ԕr�o�K�X���
�ψ�����w�ҁE���Ƃ͑�^�g���b�N��NO���K���ƔR��K����x�������邱�Ƃɂ���ăg���b�N���[�J�̌����J���̓�
���팸���\�ɂ�����𐮂��Ă��邱�ƂɂȂ�A�g���b�N���[�J�̗��v�������ł���悤�ɐϋɓI�ɋ��͂��Ă���ƌ�
�邱�Ƃ��\���B�{���A�����Ԕr�o�K�X���ψ���������̗��v���ŗD��Ƃ���Ɩ����i�����߂��Ă��邱�Ƃ���
�l����A��\�����L�q���e�ɂ͏�����肪����悤�Ɏv�����A���̂悤�Ɋ����Ă��܂��͕̂M�҂����ł��낤
���B
�o�K�X���ψ�����w�ҁE���Ƃ́A��v�c�������C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p���Ӑ}���ĖَE
���Ă��邱�Ƃ����Ɏ����ł���A�킪���ɂ������^�g���b�N�̒�NO�����ƒ�R���x�点��s�ׂ��s���Ă����
�����Ă��d�����Ȃ��悤�Ɏv����B�����āA���̂悤�Ȃ��Ƃ������ɍs�Ȃ��Ă���Ƃ���A�����Ԕr�o�K�X���
�ψ�����w�ҁE���Ƃ͑�^�g���b�N��NO���K���ƔR��K����x�������邱�Ƃɂ���ăg���b�N���[�J�̌����J���̓�
���팸���\�ɂ�����𐮂��Ă��邱�ƂɂȂ�A�g���b�N���[�J�̗��v�������ł���悤�ɐϋɓI�ɋ��͂��Ă���ƌ�
�邱�Ƃ��\���B�{���A�����Ԕr�o�K�X���ψ���������̗��v���ŗD��Ƃ���Ɩ����i�����߂��Ă��邱�Ƃ���
�l����A��\�����L�q���e�ɂ͏�����肪����悤�Ɏv�����A���̂悤�Ɋ����Ă��܂��͕̂M�҂����ł��낤
���B
�@�������R�c�����\����ǂތ����A�������R�c��̎����Ԕr�o�K�X���ψ���̊w�ҁE���Ƃ́A�G�z
�Ȃ���A��^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W���ɂ�����\����NO���팸�ƔR����P�������߂�Z�p�E�A�C�f�A�E�����\��
�ɂ������łȂ��悤�ɁA�M�҂ɂ͎v����̂ł���B�����ł����Ă��A�������R�c��̎����Ԕr�o�K�X���ψ����
�w�ҁE���Ƃ́A�s�v�c�Ȃ��Ƃ���^�g���b�N�̒�NO�����ƒ�R����m���Ɏ����ł��C���x�~�G���W���i�������J
2005-54771�j�̋Z�p����ȂɖَE����Ă���̂ł���B���̂��Ƃɂ��āA�������R�c��̎����Ԕr�o�K�X����
����̊w�ҁE���Ƃ́A�w�ҁE�����E���ƂƂ��Ă̗ǐS�̙�ӂɔY�܂���邱�Ƃ��Ȃ��̂ł��낤���B����Ƃ��A�w
�ҁE�����E���ƂƂ��Ă̗ǐS�̂���l�B�́A�ŏ����璆�����R�c��̎����Ԕr�o�K�X���ψ�����������
���Ȃ��̂ł��낤���B�����̂Ƃ���́A�M�҂ɂ͕s���ł���B
�Ȃ���A��^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W���ɂ�����\����NO���팸�ƔR����P�������߂�Z�p�E�A�C�f�A�E�����\��
�ɂ������łȂ��悤�ɁA�M�҂ɂ͎v����̂ł���B�����ł����Ă��A�������R�c��̎����Ԕr�o�K�X���ψ����
�w�ҁE���Ƃ́A�s�v�c�Ȃ��Ƃ���^�g���b�N�̒�NO�����ƒ�R����m���Ɏ����ł��C���x�~�G���W���i�������J
2005-54771�j�̋Z�p����ȂɖَE����Ă���̂ł���B���̂��Ƃɂ��āA�������R�c��̎����Ԕr�o�K�X����
����̊w�ҁE���Ƃ́A�w�ҁE�����E���ƂƂ��Ă̗ǐS�̙�ӂɔY�܂���邱�Ƃ��Ȃ��̂ł��낤���B����Ƃ��A�w
�ҁE�����E���ƂƂ��Ă̗ǐS�̂���l�B�́A�ŏ����璆�����R�c��̎����Ԕr�o�K�X���ψ�����������
���Ȃ��̂ł��낤���B�����̂Ƃ���́A�M�҂ɂ͕s���ł���B
�@�����Ƃ��A�����Ԕr�o�K�X���ψ���̊w�ҁE���Ƃ��w�ҁE�����E���ƂƂ��Ă̗ǐS�𗧔h�ɋ������Ă���l
�B�ł���Ȃ�A���R�̂��ƂȂ���킪���́u�����̌��N��Q�̗}���v�Ɓu��R��E�ȃG�l���M�[�E�b�n�Q�팸�̐��i�v��
��{���̋Ɩ��E�d���E�����������ɉʂ��������Ƃ̈ӎv�������̔��ł���B���̏ꍇ�ɂ́A�����Ԕr�o�K�X���ψ�
��̊w�ҁE�����ҁE���Ƃ́A����܂ł̒������R�c��̑�\���ł̈ӌ��E�咣���L�b�p���ƖY�ꋎ�����傫��
�ύX���A�߂���������^�g���b�N�ɑ��Ắu�Q005�N�̑攪�����\���x������NO�����v�Ɓu2015�N�x�d�ʎԔR����
�������R��v���m���Ɏ����ł����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p�̌����J�������͂ɐ����E��
�i�����̂ł͂����ƍl���Ă���B
�B�ł���Ȃ�A���R�̂��ƂȂ���킪���́u�����̌��N��Q�̗}���v�Ɓu��R��E�ȃG�l���M�[�E�b�n�Q�팸�̐��i�v��
��{���̋Ɩ��E�d���E�����������ɉʂ��������Ƃ̈ӎv�������̔��ł���B���̏ꍇ�ɂ́A�����Ԕr�o�K�X���ψ�
��̊w�ҁE�����ҁE���Ƃ́A����܂ł̒������R�c��̑�\���ł̈ӌ��E�咣���L�b�p���ƖY�ꋎ�����傫��
�ύX���A�߂���������^�g���b�N�ɑ��Ắu�Q005�N�̑攪�����\���x������NO�����v�Ɓu2015�N�x�d�ʎԔR����
�������R��v���m���Ɏ����ł����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p�̌����J�������͂ɐ����E��
�i�����̂ł͂����ƍl���Ă���B
�T�|�S�@�V���ȑ�^�g���b�N�̒�NO���E��R��̊�i�V���ȃG�R�g���b�N��j�̐ݒ�
�@�������R�c��̓��\���ɂ��āA�f�B�[�[���d�ʎԂɂ��Ă�NO���K�������Ɋւ���ŋ߂̓������ȉ��̕\A
�ɂ܂Ƃ߂��B
�ɂ܂Ƃ߂��B
| |
|||
| |
�� �f�B�[�[���d�ʎԁi12�g�������̐V�^�ԁj�ɂ����āA�u�攪�����\�̋��e���x
�ڕW�l�i���ϒl�j�� 0.7 ��/��W���v�i���z�b�g�X�^�[�g��JE05���[�h�����j��
2009�N�Ɏ��{
�i���F�č��̃f�B�[�[���d�ʎԂ́A�u2010�N��NO���K���l��0.27��/kW���i���z�b�g�X�^�[�g�{�R�[���h �X�^�[�g��1199���[�h�j�����{�j �� �u���\�̈Ӌ`�v�Ƃ��āA�u�����2009�N�ڕW��0.7��/kW�������{���邱�Ƃɂ� ��A2009�`2010�N���_�ł͑�^�f�B�[�[���g���b�N�̕���Ő��E�ō����x ���@��NO���K�������{�Ŏ��{�����v�ƋL�ڂ���Ă��邪�A����͌��ł���B �i2009�`2010�N���̃f�B�[�[���d�ʎԂɂ����ẮA���{�͕č��̔�r�����đ啝 �Ɋɂ��K�������{�j �� ���́u�攪�����\�v�ɂ́A�����̃f�B�[�[���d�ʎԂ�NO���K�������Ƃ��āA�� ��ڕW�i��0.7��/kW����1/3 ��0.23��/kW���j��� |
||
| |
�� �f�B�[�[���d�ʎԁi7.5�g�������̐V�^�ԁj���u��\�����\�̋��e���x�ڕW�l
�i���ϒl�j�� 0.4 ��/��W���v�i���z�b�g�X�^�[�g�{�R�[���h�X�^�[��WHTC���[�h
�����j��2016�N�Ɏ��{
�i���F�č��̃f�B�[�[���d�ʎԂ́A�u2010�N��NO���K���l��0.27��/kW���i���z�b�g�X�^�[�g�{�R�[���h �X�^�[�g��1199���[�h�j�����{�j �� �u��\�����\�̋��e���x�ڕW�l�i���ϒl�j�� 0.4 ��/��W���iWHTC���[�h�j�v �́A�攪�����\�̒���ڕW��0.23��/kW���i��0.7��/kW����1/3�FJE05���[�h�j �Ɂu�B���Ă���ƍl������v�ƋL������Ă���B���̂��Ƃ���A�䂪���̏����I �ȃf�B�[�[���d�ʎԂ�NO���K�������́A�攪�����\�̒���ڕW��0.23��/kW�� �iJE05���[�h)�̃��x���ɂ���K�v�̂��邱�Ƃ𒆉����R�c��\���ɏ��m�E�� �����Ă��邱�Ƃ������������̂ƍl������B �����āA�f�B�[�[���d�ʎԂ�NO���K���������m���ɑ攪�����\�̒���ڕW��0. 23��/kW���iJE05���[�h)�̃��x���Ƃ��邽�߁A��\�����\�ɓY�t�̑�\���� �́A�iJE�O�T���[�h��NO���F0.4 ��/��W���j���iWHTC���[�h��NO���F0.26 ��/kW���j������ �āA�u�\���ȃf�[�^���łȂ����߁A�����܂ł��ڈ��Ƃ��ĂƂ炦��ׂ����́v�Ƃ� �������L����Ă���B �܂�A�u��\�����\�̋��e���x�ڕW�l�i���ϒl�j�� 0.4 ��/��W���Ƒ攪�����\�� ����ڕW��0.23��/kW���Ɠ����ł��邱�Ƃ��\���Ȏ����f�[�^�ɂ���Ċm�F����� ���Ȃ����߁A����̎������ʂɂ���Ċm�肷�ׂ����Ǝ�������A���������L�ڂ� ��Ă��邱�ƂɂȂ�B |
||
| �u�����d�ʎԗp�����T�C�N ���̔r�o�K�X���\�]���v 2014�v�Ŕ��\ |
�� JE�O�T���[�h���G���W���́A���E�ᕉ�ׂ̗̈�Ɍ��肵���^�]�i���}�́Z�̗�
��j�ł��邪�A WHTC���[�h���G���W���́A���E�ᕉ�ׁ{�����ׂ̑S�̈�ʼn^�]
�i���}�́Z�{�Z�̗̈�j�ł���B
�� �R��̋����G���W���̒���C�G���W���́A�G���W���̍����ׂ̗̈�i��JE�O�T�A WHTC�A�vHSC�̃G���W���^�]�́Z�̕��ח̈�j�ł́A�A�f���̋������~�܂� �͍팸���A�A�fSCR�G�}��NO���̊Ҍ��ɂ��r�C�K�X�@�\���Ӑ}�I�ɒ��~ �܂��͒ቺ������u�r�o�K�X����̖������v�̐�����̗p���Ă���E�@�E��@�ȃG ���W���Ɛ��������B �� ���}�́A�u�r�o�K�X����̖������v��C�G���W���Ɏ����f�[�^���폜����JE�O�T ���[�h�AWHTC���[�h�AWHSC���[�h��NO���r�o�l�ł���B
�� �d�ʎԗp�����T�C�N����WHTC���[�h�i���R�[���h�X�^�[�g�{�z�b�g�X�^�[�g�j��
JE�O�T���[�h�i���z�b�g�X�^�[�g�j��NO���r�o�l�́A�قړ���ł��邱�Ƃ����炩��
����B���������āA���{�̃f�B�[�[���d�ʎԂ�NO���K���́A�߂������ɂ́A�攪
�����\��NO������ڕW�Ɠ�����NO����0.23 ��/kW���i��WHTC���[�h�j�̃��x����
�������ׂ����Ƃ͖��炩�ł���B
�������R�c��E��\�����\�Ɏ����ꂽ�u�f�B�[�[���d�ʎԂɂ�����NO�����e�� �x�ڕW�l�F0.4 ��/��W���i��WHTC���[�h�j�́A�攪�����\��NO������ڕW�F0.23��/ kW���i��JE�O�T���[�h�j�Ɠ����̃��x���ł���v�Ƃ̓��\�̓��e�́A���S�Ɍ��ł� ��Ɛ��@�����B �� �Ȃ��A�������R�c��E��\�����\�Ɏ����ꂽ�u�f�B�[�[���d�ʎԂɂ����� NO�����e���x�ڕW�l�F0.4 ��/��W���i��WHTC���[�h�j�́A�攪�����\��NO������� �W�F0.23 ��/kW���i��JE�O�T���[�h�j�Ɠ����̃��x���ł���v�Ƃ̓��\�ɂ��āA�u�T�� �Ó��Ȑ����Ƃ�����v�Ƃ���i�Ɓj��ʈ��S���������̗�؉��ꎁ�̎咣�́A �G���W���̍����ׂ̗̈�ł̔A�fSCR�G�}��NO���팸���\���ɋ@�\���Ȃ��悤 �ɐ��䂵���u�r�o�K�X����̖������v���̗p������@�E�E�@�����C�G���W���ɂ� ����WHTC���[�h�ł̍���NO���r�o�l�������̂ƂȂ��Ă���͖̂��炩�ł���B �u�r�o�K�X����̖������v���̗p������@�E�E�@�����C�G���W����NO���r�o�l�� ����NO�����e���x�ڕW�l�F0.4 ��/��W���i��WHTC���[�h�j�́A�攪�����\��NO ������ڕW�F0.23 ��/kW���i��JE�O�T���[�h�j�Ɠ����̃��x���ł���v���Ǝ������Ƃ� �i�Ɓj��ʈ��S���������̗�؉��ꎁ�̘_�����\�́A�f�B�[�[���d�ʎԂ� 2016�NNO����0.4 ��/��W�����s����NO���K���̊ɘa�ł��邱�Ƃ��B�����邽�߂� �Ƒ��ȍs�ׂƍl������B |
�O�q�̒ʂ�A�m�n���K���ɂ��ẮA���Ȃ̒������R�c��́A2005�N4���̑攪�����\�ɂ́A�f�B�[�[���d�ʎ�
�ɂ��āA0.7 g/kWh�� 1/3���x�i���@0.23�@g/kWh�j�̂m�n���̒���ڕW��������Ă���B���������āA�|�X�g�r�o�K�X�K
���ɑ���2009�N�ɂm�n���K�������́A���R�A���̂m�n��������ڕW�ł���@0.23�@g/kWh�ɂȂ�Ƒ����̐l���\�z���Ă�
���B�������A�������R�c��̑�\�����\�i2010�N7��28���Ɋ��Ȃɓ��\�j�ł́A2016�N�Ƀf�B�[�[���d�ʎԁi7.5�g
�������̐V�^�ԁj�́u��\�����\�̋��e���x�ڕW�l�i���ϒl�j�� 0.4 ��/��W���v�i���z�b�g�X�^�[�g�{�R�[���h�X�^�[��
WHTC���[�h�����j�̎��{�����\���ꂽ�B�������Ȃ���A�f�B�[�[���d�ʎ�2016�NNOx�K����0.4g/kWh�́A�s���Ȋɘa
�̌��K���ɏڏq���Ă���悤�ɁA���{�̃f�B�[�[���d�ʎԂ�NO���K���́A�߂������ɂ́A�攪�����\��NO�������
�W�Ɠ�����NO����0.23 ��/kW���i��WHTC���[�h�j�̃��x���ɋ������ׂ����Ƃ͖��炩�ł���B
�ɂ��āA0.7 g/kWh�� 1/3���x�i���@0.23�@g/kWh�j�̂m�n���̒���ڕW��������Ă���B���������āA�|�X�g�r�o�K�X�K
���ɑ���2009�N�ɂm�n���K�������́A���R�A���̂m�n��������ڕW�ł���@0.23�@g/kWh�ɂȂ�Ƒ����̐l���\�z���Ă�
���B�������A�������R�c��̑�\�����\�i2010�N7��28���Ɋ��Ȃɓ��\�j�ł́A2016�N�Ƀf�B�[�[���d�ʎԁi7.5�g
�������̐V�^�ԁj�́u��\�����\�̋��e���x�ڕW�l�i���ϒl�j�� 0.4 ��/��W���v�i���z�b�g�X�^�[�g�{�R�[���h�X�^�[��
WHTC���[�h�����j�̎��{�����\���ꂽ�B�������Ȃ���A�f�B�[�[���d�ʎ�2016�NNOx�K����0.4g/kWh�́A�s���Ȋɘa
�̌��K���ɏڏq���Ă���悤�ɁA���{�̃f�B�[�[���d�ʎԂ�NO���K���́A�߂������ɂ́A�攪�����\��NO�������
�W�Ɠ�����NO����0.23 ��/kW���i��WHTC���[�h�j�̃��x���ɋ������ׂ����Ƃ͖��炩�ł���B
�@����A��^�g���b�N�̂m�n�����팸����Z�p�Ƃ��āA�M�҂̃z�[���y�[�W�ł́A�S�N�O�����C���x�~�G���W���i�������J
2005-54771�j��M�S�ɒ�Ă��Ă����̂ł���B���̋C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p���̗p����A�i
�d�O�T���[�h�r�o�K�X�����ɂ����ăG���W���ł̉^�]�p�x�̍����A�N�Z���y�_�������ݗ�Accel���T�O���ߖT�₻���
���̃G���W���^�]�̈�ł́A�A�f�r�b�q�G�}�̊������ɂ��啝�Ȃm�n���팸���\�ɂ���@�\�����邽�߁A�i�d�O�T��
�[�h�r�o�K�X�����ł� 0.23�@g/kWh�̂m�n�����x���́A�]�T�œK���ł��锤�ł������B�ܘ_�A2016�N�Ɏ��{�\��̎���
�m�n���K���ɍ̗p�����V�������E���ꎎ���T�C�N���ł���WHTC�iWorld Harmonized Transient Cycle�j�ɕύX�����
���A�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p���̗p����A2005�N4���̑攪�����\�� 0.7 g/kWh�� 1/3��
�x�i���@0.23�@g/kWh�j�̂m�n���̍팸�ڕW���B���ł��邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��ƍl���Ă���B
2005-54771�j��M�S�ɒ�Ă��Ă����̂ł���B���̋C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p���̗p����A�i
�d�O�T���[�h�r�o�K�X�����ɂ����ăG���W���ł̉^�]�p�x�̍����A�N�Z���y�_�������ݗ�Accel���T�O���ߖT�₻���
���̃G���W���^�]�̈�ł́A�A�f�r�b�q�G�}�̊������ɂ��啝�Ȃm�n���팸���\�ɂ���@�\�����邽�߁A�i�d�O�T��
�[�h�r�o�K�X�����ł� 0.23�@g/kWh�̂m�n�����x���́A�]�T�œK���ł��锤�ł������B�ܘ_�A2016�N�Ɏ��{�\��̎���
�m�n���K���ɍ̗p�����V�������E���ꎎ���T�C�N���ł���WHTC�iWorld Harmonized Transient Cycle�j�ɕύX�����
���A�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p���̗p����A2005�N4���̑攪�����\�� 0.7 g/kWh�� 1/3��
�x�i���@0.23�@g/kWh�j�̂m�n���̍팸�ڕW���B���ł��邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��ƍl���Ă���B
��B
�@�܂��A��^�g���b�N���C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p���̗p����A�s�s�����s���[�h�i�i�d�O�T���[
�h�j�Ɠs�s�ԑ��s���[�h�i�c�f���z�t�W�O�����^���葬���[�h�j�̗����[�h�̔R��]���̃G���W���ɔ�ׂđ啝�ɉ��P
�ł��邽�߁A�d�ʎԃ��[�h�R��]���̃G���W���̏ꍇ�ɔ�ׂĂT�`�P�O�����팸�ł����@�\������B���������āA��
�^�g���b�N�ɋC���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j���̗p���邱�Ƃɂ���ẮA�d�ʎԃ��[�h�R����T�������P�͂�
��قǂ̒����J�����Ԃ�݂��Ȃ��Ă��e�ՂɎ����ł���̂ł���B
�h�j�Ɠs�s�ԑ��s���[�h�i�c�f���z�t�W�O�����^���葬���[�h�j�̗����[�h�̔R��]���̃G���W���ɔ�ׂđ啝�ɉ��P
�ł��邽�߁A�d�ʎԃ��[�h�R��]���̃G���W���̏ꍇ�ɔ�ׂĂT�`�P�O�����팸�ł����@�\������B���������āA��
�^�g���b�N�ɋC���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j���̗p���邱�Ƃɂ���ẮA�d�ʎԃ��[�h�R����T�������P�͂�
��قǂ̒����J�����Ԃ�݂��Ȃ��Ă��e�ՂɎ����ł���̂ł���B
�@���������āA2016�N�Ɏ��{���\�肳��Ă���uNO���K���l�� 0.4 g/kWh�iWHTC���[�h�j��NO���K�������v�Ƃ͕ʂɁA��
�������ɂ������A������^�g���b�N�Ɂu�m�n��� �� 0.23�@g/kWh�iWHTC���[�h�j�v�Ɓu2015�N�x�d�ʎԔR���́{�P
�O �����x������v�����߂��\�P�O�̐V���ȁu��NO���E��R��g���b�N�E�o�X�̊�i�āj�v�̎{��𐭕{�i���Ȃ����y��
�ʏȁj�����{�����ꍇ�ɂ́A���̒�NO���E��R��̊�ɑ�^�g���b�N��K�������邽�߂ɂ́A�e�g���b�N���[�J����^
�g���b�N�̔R����P��NO���팸�ɗL�����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̌����J�������{���A���̋Z�p����
�p������^�g���b�N�𑁋}�Ɏ��p�����邱�Ƃ��K�v�ł���B����ɂ���āA�킪���̑�^�g���b�N����ɂ�����uNO����
�팸�v�A�uCO�Q�̍팸�v����сu�ȃG�l���M�[���v������I�ɐi�W����ƍl������B���̂��Ƃ́A�ȃG�l���M�[��CO2
�팸�����߂鍑���̊肢���������邱�Ƃ��ł���Ƌ��ɁA�g���b�N���[�U�ɂƂ��ẮA����͔R����P���ꂽ��^�g��
�b�N���w�����邱�Ƃɂ���āA�^�s�R��̉��P�������ł��邱�ƂɂȂ�B���������āA����A���{�i���Ȃ����y���
�ȁj���������\�S�̐V���ȁu��NO���E��R��g���b�N�E�o�X�̊�i�āj�v�𐭕{���{�s�����ꍇ�ɂ́A���{�������̂���
�̎d���𗧔h�ɉʂ����Ă���Ƃ��āA�����S�̂���A�傢�Ɋ��ӂ���A�̎^����邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��B
�������ɂ������A������^�g���b�N�Ɂu�m�n��� �� 0.23�@g/kWh�iWHTC���[�h�j�v�Ɓu2015�N�x�d�ʎԔR���́{�P
�O �����x������v�����߂��\�P�O�̐V���ȁu��NO���E��R��g���b�N�E�o�X�̊�i�āj�v�̎{��𐭕{�i���Ȃ����y��
�ʏȁj�����{�����ꍇ�ɂ́A���̒�NO���E��R��̊�ɑ�^�g���b�N��K�������邽�߂ɂ́A�e�g���b�N���[�J����^
�g���b�N�̔R����P��NO���팸�ɗL�����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̌����J�������{���A���̋Z�p����
�p������^�g���b�N�𑁋}�Ɏ��p�����邱�Ƃ��K�v�ł���B����ɂ���āA�킪���̑�^�g���b�N����ɂ�����uNO����
�팸�v�A�uCO�Q�̍팸�v����сu�ȃG�l���M�[���v������I�ɐi�W����ƍl������B���̂��Ƃ́A�ȃG�l���M�[��CO2
�팸�����߂鍑���̊肢���������邱�Ƃ��ł���Ƌ��ɁA�g���b�N���[�U�ɂƂ��ẮA����͔R����P���ꂽ��^�g��
�b�N���w�����邱�Ƃɂ���āA�^�s�R��̉��P�������ł��邱�ƂɂȂ�B���������āA����A���{�i���Ȃ����y���
�ȁj���������\�S�̐V���ȁu��NO���E��R��g���b�N�E�o�X�̊�i�āj�v�𐭕{���{�s�����ꍇ�ɂ́A���{�������̂���
�̎d���𗧔h�ɉʂ����Ă���Ƃ��āA�����S�̂���A�傢�Ɋ��ӂ���A�̎^����邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��B
�@�Ƃ��낪�A�������R�c��́A�킪���̑�^�g���b�N�̎���NO���K���Ƃ���NO�� �� 0.4 g/kWh�i2016�N���{�j�̃��x
���ɋK��������������10�����\��2010�N7������o���Ă��܂��Ă���̂ł���B�M�����Ȃ����Ƃł͂��邪�A����
2016�N�Ɏ��{����������̓��{��NO���K���́A�č��ɂ�����2010�N��NO�� �� 0.27 g/kWh�̋K�������啝�Ɋɂ�
NO���K���ƂȂ��Ă��܂��Ă���̂��B���̂��߁A���{�����͕č���������C���ɔ����ꑱ���邱�ƂɂȂ�Ɨ\�z��
���B���̂悤�ȏɂ��āA���{�̊��s���ɊW����Ă���ꕔ�̏펯�̂��鐭�{�E�����̐l�B�́A�K����u��
�̏͑��}�ɉ��P���ׂ��v�Ƃ̑z����������Ă�����̂Ɛ��������B���̂悤�Ȑ��{�E�����̐l�B�́A�킪����
�������^�g���b�N�̔R�������NO���팸�������ł���̐��𑁊��ɍ\�z���邽�߁A�ł��邾�������ɔr�o�K
�X�K���ƔR��K���̃I�v�V�����Ƃ��āA���Ȃƍ��y��ʏȂ�NO���팸�ƔR�������K�肵���u��NO���E��R��
�g���b�N�E�o�X�̊�v���V�����ݒ肷���s�����N�����ׂ��ł͂Ȃ����낤���B�����āA�����u��NO���E��R��g���b
�N�E�o�X�̊�v�Ƃ��ẮA�\�P�S�Ɏ������悤�ȁA2005�N�̑攪�����\�ɂm�n���̒���ڕW�Ƃ��Ď�����Ă���
0.7 g/kWh�� 1/3���x�� 0.23 g/kWh�̂m�n�� �K���l�ƁA2015�N�x�d�ʎԔR������{�P�O�� ���x�̔R��
�����サ����l��ݒ肷�邱�Ƃ��K���ł͂Ȃ����ƍl���Ă���B
���ɋK��������������10�����\��2010�N7������o���Ă��܂��Ă���̂ł���B�M�����Ȃ����Ƃł͂��邪�A����
2016�N�Ɏ��{����������̓��{��NO���K���́A�č��ɂ�����2010�N��NO�� �� 0.27 g/kWh�̋K�������啝�Ɋɂ�
NO���K���ƂȂ��Ă��܂��Ă���̂��B���̂��߁A���{�����͕č���������C���ɔ����ꑱ���邱�ƂɂȂ�Ɨ\�z��
���B���̂悤�ȏɂ��āA���{�̊��s���ɊW����Ă���ꕔ�̏펯�̂��鐭�{�E�����̐l�B�́A�K����u��
�̏͑��}�ɉ��P���ׂ��v�Ƃ̑z����������Ă�����̂Ɛ��������B���̂悤�Ȑ��{�E�����̐l�B�́A�킪����
�������^�g���b�N�̔R�������NO���팸�������ł���̐��𑁊��ɍ\�z���邽�߁A�ł��邾�������ɔr�o�K
�X�K���ƔR��K���̃I�v�V�����Ƃ��āA���Ȃƍ��y��ʏȂ�NO���팸�ƔR�������K�肵���u��NO���E��R��
�g���b�N�E�o�X�̊�v���V�����ݒ肷���s�����N�����ׂ��ł͂Ȃ����낤���B�����āA�����u��NO���E��R��g���b
�N�E�o�X�̊�v�Ƃ��ẮA�\�P�S�Ɏ������悤�ȁA2005�N�̑攪�����\�ɂm�n���̒���ڕW�Ƃ��Ď�����Ă���
0.7 g/kWh�� 1/3���x�� 0.23 g/kWh�̂m�n�� �K���l�ƁA2015�N�x�d�ʎԔR������{�P�O�� ���x�̔R��
�����サ����l��ݒ肷�邱�Ƃ��K���ł͂Ȃ����ƍl���Ă���B
�@�����āA�����V���ɐݒ肵���\�P�S�́u��NO���E��R��g���b�N�E�o�X��i�āj�v�ɓK��������^�g���b�N�ɂ́A���݂̃n
�C�u���b�h�Ԃ�d�C�����ԓ��̃G�R�J�[���łƓ��l�̐ŋ��̗D��������D���Ő���K�p���邱�Ƃ��B���ɁA����
�u��NO���E��R��g���b�N�E�o�X�̊�i�āj�v�ɓK��������^�g���b�N�ɑ��Đŋ���D������鐧�x���������ꂽ�Ȃ�
�A��^�g���b�N�̐Ő��D�����������߁A�e�g���b�N���[�J�͐�𑈂��A���̕\�P�S���u��NO���E��R��g���b�N�E�o�X
�̊�i�āj�v�ɓK����������Q�E�ȃG�l�̑�^�g���b�N�̊J����K���ɐ��i���邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ����낤�B
�C�u���b�h�Ԃ�d�C�����ԓ��̃G�R�J�[���łƓ��l�̐ŋ��̗D��������D���Ő���K�p���邱�Ƃ��B���ɁA����
�u��NO���E��R��g���b�N�E�o�X�̊�i�āj�v�ɓK��������^�g���b�N�ɑ��Đŋ���D������鐧�x���������ꂽ�Ȃ�
�A��^�g���b�N�̐Ő��D�����������߁A�e�g���b�N���[�J�͐�𑈂��A���̕\�P�S���u��NO���E��R��g���b�N�E�o�X
�̊�i�āj�v�ɓK����������Q�E�ȃG�l�̑�^�g���b�N�̊J����K���ɐ��i���邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ����낤�B
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
�@�����\�P�S�Ɏ������u��NO���E��R��g���b�N�E�o�X�̊(�āj�v��NO���r�o�l�iJE05���[�h or WHTC���[�h�j�Əd�ʎԃ�
�[�h�R��l�̗����̊�ɑ�^�g���b�N��K�������邱�Ƃ̂ł���Z�p���A�M�҂̒�Ă��Ă����C���x�~�G���W���i��
�����J2005-54771�j�ł���B�����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�́A�f�B�[�[���G���W���̏d�ʎԃ��[�h�R
��l���T�`�P�O���̉��P����Ɠ����ɁAJE05���[�h or WHTC���[�h�ł��A�fSCR�G�}��NO���팸����啝�Ɍ���ł�
��V�����Z�p�ł���B���������āA�����M�Ғ�Ă��C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p���^�g���b
�N�̃f�B�[�[���G���W���ɍ̗p����A�u�m�n���r�o�l�� 0.23 g/kWh�iJE05���[�h or WHTC���[�h)�܂ł̍�
���v�Ɓu2015�N�x�d�ʎԃ��[�h�R�������{�P�O�����x�̔R�����v������������^�g���b�N���e�ՂɎ��p
���ł����̂ł���B
�[�h�R��l�̗����̊�ɑ�^�g���b�N��K�������邱�Ƃ̂ł���Z�p���A�M�҂̒�Ă��Ă����C���x�~�G���W���i��
�����J2005-54771�j�ł���B�����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�́A�f�B�[�[���G���W���̏d�ʎԃ��[�h�R
��l���T�`�P�O���̉��P����Ɠ����ɁAJE05���[�h or WHTC���[�h�ł��A�fSCR�G�}��NO���팸����啝�Ɍ���ł�
��V�����Z�p�ł���B���������āA�����M�Ғ�Ă��C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p���^�g���b
�N�̃f�B�[�[���G���W���ɍ̗p����A�u�m�n���r�o�l�� 0.23 g/kWh�iJE05���[�h or WHTC���[�h)�܂ł̍�
���v�Ɓu2015�N�x�d�ʎԃ��[�h�R�������{�P�O�����x�̔R�����v������������^�g���b�N���e�ՂɎ��p
���ł����̂ł���B
�@���݂ɁA���B��EEV-NO���r�o�K�X��l�i�ߓn���[�h�j�� NO�� �� 0.2 g/kWh�ł���A�č���2010�N�m�n���K
����NO�� �� 0.27 g/kWh�ł���A���{��2016�N�K�����m�n���� 0.4 g/kWh�����啝�Ɍ�����NO���K�����s��
��Ă���B�i�ȉ��̕\�P�T�Q�Ɓj
����NO�� �� 0.27 g/kWh�ł���A���{��2016�N�K�����m�n���� 0.4 g/kWh�����啝�Ɍ�����NO���K�����s��
��Ă���B�i�ȉ��̕\�P�T�Q�Ɓj
���@EEV�FEnhanced Environmentally Friendly Vehicles�̗��BEEV�K���l�́A��C���������ɐi�s���Ă���s�s���̒n��������̂��߁A����
�o�[�e���������I�Ɏg�p���邽�߂̒l�i��F�s�s�ւ̏����ꐧ����݂���ۂ̊�Ƃ��Ďg�p�j�ŁA�b��l�B
�o�[�e���������I�Ɏg�p���邽�߂̒l�i��F�s�s�ւ̏����ꐧ����݂���ۂ̊�Ƃ��Ďg�p�j�ŁA�b��l�B
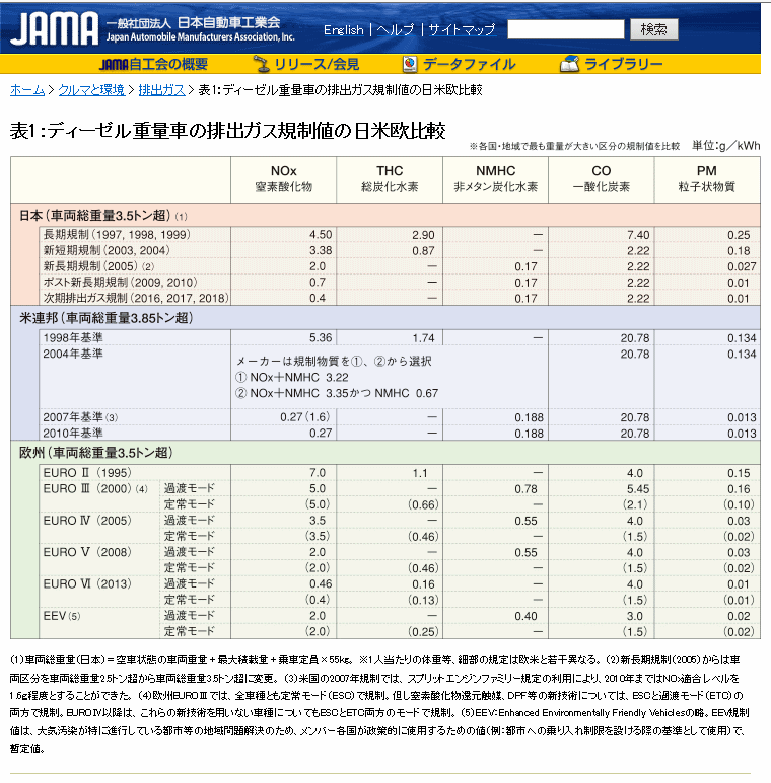 |
�@�Ȃ��A�����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p�ɂ���đ�^�g���b�N�̔R����P��NO���팸���e�ՂɎ�
���ł��闝�R�E�����̐����́A���̃y�[�W�̋L�q�������Ȃ邱�Ƃ�����邽�߁A�����ł͊�������B�������A�C���x�~�G
���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p���̗p���邱�Ƃɂ���đ�^�g���b�N�̔R����P��NO���팸���\�ƂȂ闝�R��
������m�肽���ǎ҂́A�C���x�~�G���W���ɂ���^�g���b�N�̒�R��A�܂����C���x�~�́A�f�B�[�[���̂m�n����
���ƔR�����̈ꋓ�����̋Z�p���I��Ƃ��䗗������������
���ł��闝�R�E�����̐����́A���̃y�[�W�̋L�q�������Ȃ邱�Ƃ�����邽�߁A�����ł͊�������B�������A�C���x�~�G
���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p���̗p���邱�Ƃɂ���đ�^�g���b�N�̔R����P��NO���팸���\�ƂȂ闝�R��
������m�肽���ǎ҂́A�C���x�~�G���W���ɂ���^�g���b�N�̒�R��A�܂����C���x�~�́A�f�B�[�[���̂m�n����
���ƔR�����̈ꋓ�����̋Z�p���I��Ƃ��䗗������������
�@�Ƃ�����A2016�N�Ɏ��{���\�肳��Ă���uNO���K���l�� 0.4 g/kWh�iWHTC���[�h�j��NO���K�������v�Ƃ͕ʂɁA�߂�
�����A���ɍ��y��ʏȂ��u2015�N�x�d�ʎԔR���́{�P�O�����x�̌���v�����߂���^�g���b�N�̔R���̋���
�����f�����ꍇ�A�g���b�N���[�J�́A���́uNO���K���l�� 0.4 g/kWh�iWHTC���[�h�j�v�Ɓu2015�N�x�d�ʎԔR���́{�P
�O�����x�̌���v������u��NO���E��R��g���b�N�E�o�X�v���J��������Ȃ����ƂɂȂ�B���̏ꍇ�A��^�g���b�N
�p�f�B�[�[���G���W�����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p���̗p����A���́u��NO���E��R��g��
�b�N�E�o�X�v�͗e�ՂɎ��p���ł��邱�ƂɂȂ�B���������āA���݂̃g���b�N���[�J�̋Z�p�ҁE���Ƃ́A���̒m�I�J�͂�
���K�v�Ƃ��邱�Ɩ����A�P�Ȃ�r�͂����ł͊e���̊J���Ɩ��̊�����}��邱�ƂɂȂ�B���̂��Ƃ���A�ߋ��́u�m�n���K
���v��u�R��K���v�̓����⋭���̌����J���ɏ]�������Z�p�ҁE���Ƃɔ�ׁA���݂̃g���b�N���[�J�̋Z�p�ҁE���
�Ƃ͋ɂ߂Čb�܂ꂽ���ɒu����Ă�����̂ƍl������B
�����A���ɍ��y��ʏȂ��u2015�N�x�d�ʎԔR���́{�P�O�����x�̌���v�����߂���^�g���b�N�̔R���̋���
�����f�����ꍇ�A�g���b�N���[�J�́A���́uNO���K���l�� 0.4 g/kWh�iWHTC���[�h�j�v�Ɓu2015�N�x�d�ʎԔR���́{�P
�O�����x�̌���v������u��NO���E��R��g���b�N�E�o�X�v���J��������Ȃ����ƂɂȂ�B���̏ꍇ�A��^�g���b�N
�p�f�B�[�[���G���W�����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p���̗p����A���́u��NO���E��R��g��
�b�N�E�o�X�v�͗e�ՂɎ��p���ł��邱�ƂɂȂ�B���������āA���݂̃g���b�N���[�J�̋Z�p�ҁE���Ƃ́A���̒m�I�J�͂�
���K�v�Ƃ��邱�Ɩ����A�P�Ȃ�r�͂����ł͊e���̊J���Ɩ��̊�����}��邱�ƂɂȂ�B���̂��Ƃ���A�ߋ��́u�m�n���K
���v��u�R��K���v�̓����⋭���̌����J���ɏ]�������Z�p�ҁE���Ƃɔ�ׁA���݂̃g���b�N���[�J�̋Z�p�ҁE���
�Ƃ͋ɂ߂Čb�܂ꂽ���ɒu����Ă�����̂ƍl������B
�@���͂Ƃ�����A�߂����������y��ʏȂ��u2015�N�x�d�ʎԔR���́{�P�O�����x�̌���v�����߂���^�g���b�N��
�R���̋��������f�����ꍇ�ɂ́A�����_�Œ�NO���E��R��̗L���ȋZ�p�������o���Ă��Ȃ��g���b�N���[�J�́A��
�̕\�P�S�̂悤�ȑ�^�g���b�N�̐V���Ȓ�NO���E��R��̊���{�s����ďꍇ�ɂ́A���̔R��̐V��Ɏ��Ђ̑�^
�g���b�N��K�������邽�߂ɁA�R����P��NO���팸�ɗL�����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̌����J������
�{���A���̋Z�p���̗p������^�g���b�N�̊J���ɒ��肷����̂ƍl������B����ɂ���āA�C���x�~�G���W���i������
�J2005-54771�j�̋Z�p���̗p������^�g���b�N�������Ɏ��p������A�킪���ɂ������^�g���b�N����́uNO���̍�
���v�A�uCO�Q�̍팸�v����сu�ȃG�l���M�[���v������I�ɐi�W����ƍl������B���̂��Ƃ́A�ȃG�l���M�[��CO2��
�������߂鍑���̊肢�𑁂������Ɏ������邱�Ƃ��ł���Ƌ��ɁA�g���b�N���[�U�ɂƂ��ẮA����͔R����P����
����^�g���b�N���w�����邱�Ƃɂ���āA�^�s�R��̉��P���ł��邱�ƂɂȂ�B���������āA����A���{�i���Ȃ����y��
�ʏȁj�������ɁA�\�P�S�̐V���ȁu��NO���E��R��g���b�N�E�o�X�̊�i�āj�v�𐭕{���{�s�����ꍇ�ɂ́A���{������
�̂��߂̎d���𗧔h�ɉʂ����Ă���Ƃ��āA�����S�̂���A�傢�Ɋ��ӂ���A�̎^����邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��B���̏ꍇ
�ɂ́A���{�i�����Ȃ���э��y��ʏȁj�́A�w�č������i�i�Ɋɂ��d�ʎԁi����^�g���b�N�E�g���N�^�j��NO���K����
����x��Ŕj�ł��邱�ƂɂȂ�A��������̐M������������̂ƍl������B
�R���̋��������f�����ꍇ�ɂ́A�����_�Œ�NO���E��R��̗L���ȋZ�p�������o���Ă��Ȃ��g���b�N���[�J�́A��
�̕\�P�S�̂悤�ȑ�^�g���b�N�̐V���Ȓ�NO���E��R��̊���{�s����ďꍇ�ɂ́A���̔R��̐V��Ɏ��Ђ̑�^
�g���b�N��K�������邽�߂ɁA�R����P��NO���팸�ɗL�����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̌����J������
�{���A���̋Z�p���̗p������^�g���b�N�̊J���ɒ��肷����̂ƍl������B����ɂ���āA�C���x�~�G���W���i������
�J2005-54771�j�̋Z�p���̗p������^�g���b�N�������Ɏ��p������A�킪���ɂ������^�g���b�N����́uNO���̍�
���v�A�uCO�Q�̍팸�v����сu�ȃG�l���M�[���v������I�ɐi�W����ƍl������B���̂��Ƃ́A�ȃG�l���M�[��CO2��
�������߂鍑���̊肢�𑁂������Ɏ������邱�Ƃ��ł���Ƌ��ɁA�g���b�N���[�U�ɂƂ��ẮA����͔R����P����
����^�g���b�N���w�����邱�Ƃɂ���āA�^�s�R��̉��P���ł��邱�ƂɂȂ�B���������āA����A���{�i���Ȃ����y��
�ʏȁj�������ɁA�\�P�S�̐V���ȁu��NO���E��R��g���b�N�E�o�X�̊�i�āj�v�𐭕{���{�s�����ꍇ�ɂ́A���{������
�̂��߂̎d���𗧔h�ɉʂ����Ă���Ƃ��āA�����S�̂���A�傢�Ɋ��ӂ���A�̎^����邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��B���̏ꍇ
�ɂ́A���{�i�����Ȃ���э��y��ʏȁj�́A�w�č������i�i�Ɋɂ��d�ʎԁi����^�g���b�N�E�g���N�^�j��NO���K����
����x��Ŕj�ł��邱�ƂɂȂ�A��������̐M������������̂ƍl������B
�@�������Ȃ���A�����_�i��2014�N10�����݁j�ł́A�č������ɂ���^�g���b�N��NO���K�����{�s����������{���{��
�Ӗ��ɏڏq���Ă���悤�ɁA���{�i���y��ʏȂ���ъ��ȁj�́A��^�g���b�N�ɂ����Ă͌��s�̕č���NO���K���l��
0.27 g/kWh�i��2010�N�K���j�ɔ�ׂđ啝�Ɋɂ��uNO���K���l�� 0.4 g/kWh�iWHTC���[�h�j�v�̋K����2016�N�Ɏ��{��
��\��ł���B����́A��^�g���b�N��NO���팸�ƔR�����̐V�Z�p��َE�E�B������w�ҏ����ɏڏq���Ă���悤
�ɁA���{�̊w�ҁE���Ƃ���v�c�����đ�^�g���b�N��NO���팸�ƔR����P�ɗL�����C���x�~�G���W���i�������J
2005-54771�j�̓����Z�p���E�َE���Ă��錋�ʂƐ��@�����B���̐��ʁE���ʂƂ��āA���{�ł͍�����č��ɔ��
�Ċɂ���^�g���b�N��NO���K���̏��������߁A���{���e�g���b�N���[�J�́A��^�g���b�N�̔R����P��NO���팸�ɗL
�����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p�J���ɋ��z�̊J�������Ƒ����̊J���l�H�𓊓�����K�v����
���A��^�g���b�N�̔R����P�̋Z�p�̋Z�p�J�����S���i�W���Ȃ��Ă����̖��������Ȃ��ɒu����邱�ƂɂȂ�Ɛ�
�@�����B
�Ӗ��ɏڏq���Ă���悤�ɁA���{�i���y��ʏȂ���ъ��ȁj�́A��^�g���b�N�ɂ����Ă͌��s�̕č���NO���K���l��
0.27 g/kWh�i��2010�N�K���j�ɔ�ׂđ啝�Ɋɂ��uNO���K���l�� 0.4 g/kWh�iWHTC���[�h�j�v�̋K����2016�N�Ɏ��{��
��\��ł���B����́A��^�g���b�N��NO���팸�ƔR�����̐V�Z�p��َE�E�B������w�ҏ����ɏڏq���Ă���悤
�ɁA���{�̊w�ҁE���Ƃ���v�c�����đ�^�g���b�N��NO���팸�ƔR����P�ɗL�����C���x�~�G���W���i�������J
2005-54771�j�̓����Z�p���E�َE���Ă��錋�ʂƐ��@�����B���̐��ʁE���ʂƂ��āA���{�ł͍�����č��ɔ��
�Ċɂ���^�g���b�N��NO���K���̏��������߁A���{���e�g���b�N���[�J�́A��^�g���b�N�̔R����P��NO���팸�ɗL
�����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p�J���ɋ��z�̊J�������Ƒ����̊J���l�H�𓊓�����K�v����
���A��^�g���b�N�̔R����P�̋Z�p�̋Z�p�J�����S���i�W���Ȃ��Ă����̖��������Ȃ��ɒu����邱�ƂɂȂ�Ɛ�
�@�����B
�@���̏ꍇ�ɂ́A�g���b�N���[�J�́A�R����P�̌����J���̓������ߖ�ł��邽�߁A���̊�Ɠw�͂������Ƀg���b�N���[
�J���G���Ɉ��̔@�����v��ł��邱�Ƃ��ł��邱�ƂɂȂ�A���������āA���{�i���y��ʏȂ���ъ��ȁj���\�P
�S�Ɏ������V���Ȓ�NO���E��R��̊���{�s�������x����Βx���قǁA�g���b�N���[�J�������̗��v�邱�Ƃ��ł�
�邱�ƂɂȂ�B���̂悤�ɁA���ɁA���݂̐��{�i���y��ʏȂ���ъ��ȁj���\�P�S�Ɏ������V���Ȓ�NO���E��R��̊�
���̎{�s���Ӑ}�I�ɒx�����������Ƃ���A���y��ʏȂ���ъ��Ȃ̓g���b�N���[�J����u�������A�K������v�Ɗ�
�ӂ���邱�Ƃ͖��炩���B�������A���̂悤�Ȃ��Ƃ́A�ȃG�l���M�[�ACO�Q�팸�A�����NO���팸�̕K�v��������Ă�
�錻�݁A���{�i�����y��ʏȂ���ъ��ȁj���������狭���ᔻ�𗁂т邱�Ƃ́A�ԈႢ�Ȃ����낤�B
�J���G���Ɉ��̔@�����v��ł��邱�Ƃ��ł��邱�ƂɂȂ�A���������āA���{�i���y��ʏȂ���ъ��ȁj���\�P
�S�Ɏ������V���Ȓ�NO���E��R��̊���{�s�������x����Βx���قǁA�g���b�N���[�J�������̗��v�邱�Ƃ��ł�
�邱�ƂɂȂ�B���̂悤�ɁA���ɁA���݂̐��{�i���y��ʏȂ���ъ��ȁj���\�P�S�Ɏ������V���Ȓ�NO���E��R��̊�
���̎{�s���Ӑ}�I�ɒx�����������Ƃ���A���y��ʏȂ���ъ��Ȃ̓g���b�N���[�J����u�������A�K������v�Ɗ�
�ӂ���邱�Ƃ͖��炩���B�������A���̂悤�Ȃ��Ƃ́A�ȃG�l���M�[�ACO�Q�팸�A�����NO���팸�̕K�v��������Ă�
�錻�݁A���{�i�����y��ʏȂ���ъ��ȁj���������狭���ᔻ�𗁂т邱�Ƃ́A�ԈႢ�Ȃ����낤�B
�@���̂悤�ɁA�߂������ɁA���ɐ��{�i���y��ʏȂ���ъ��ȁj���\�P�P�Ɏ�������^�g���b�N�̐V���Ȓ�NO���E��R
��̊���{�s���Ȃ��Ȃ�A���{�̐l�B�́u�̂�Y�ꂽ�J�i������v�Ȃ�ʁu��NO���E��R���Y�ꂽ���{�E�����v��
�����Ԃ�Ă��܂��Ă���ƌ����Ă��d�����Ȃ��悤�Ɏv����̂ł���B�����āA���̂悤�ȏꍇ�ɂ́A���{�i���y���
�Ȃ���ъ��ȁj�̊�����{�̊֘A�R�c��̈ψ��́A�����̗��v��D�悷��{���̎d�������ڂ�A�ŋ����Â閳
�דk�H�̔y�Ƒ����̍�������ᔻ���ꂻ�����B���̂悤�ȏɊׂ邱�Ƃ�����邽�߂̗B��̕��@�́A���{�i���y��
�ʏȂ���ъ��ȁj�v�́A�\�P�S�Ɏ������悤���V���ȁu��NO���E��R��g���b�N�E�o�X�̊�i�āj�v���{�s���A�킪���ɂ�
�����^�g���b�N����́u�ȃG�l���M�[�v�A�uCO�Q�팸�v����сuNO���팸�v�̎{��𐄐i�����ׂ��ł���B���̎{��ɂ�
���āA�g���b�N���[�U�́A�߂������ɒ�NO���E��R��̑�^�g���b�N���w�����邱�Ƃɂ���āA�R����̍팸�̉��b�ɗ�
����Ƌ��ɁA��C���̉��P�ɂ���^�ł���̂ł���B
��̊���{�s���Ȃ��Ȃ�A���{�̐l�B�́u�̂�Y�ꂽ�J�i������v�Ȃ�ʁu��NO���E��R���Y�ꂽ���{�E�����v��
�����Ԃ�Ă��܂��Ă���ƌ����Ă��d�����Ȃ��悤�Ɏv����̂ł���B�����āA���̂悤�ȏꍇ�ɂ́A���{�i���y���
�Ȃ���ъ��ȁj�̊�����{�̊֘A�R�c��̈ψ��́A�����̗��v��D�悷��{���̎d�������ڂ�A�ŋ����Â閳
�דk�H�̔y�Ƒ����̍�������ᔻ���ꂻ�����B���̂悤�ȏɊׂ邱�Ƃ�����邽�߂̗B��̕��@�́A���{�i���y��
�ʏȂ���ъ��ȁj�v�́A�\�P�S�Ɏ������悤���V���ȁu��NO���E��R��g���b�N�E�o�X�̊�i�āj�v���{�s���A�킪���ɂ�
�����^�g���b�N����́u�ȃG�l���M�[�v�A�uCO�Q�팸�v����сuNO���팸�v�̎{��𐄐i�����ׂ��ł���B���̎{��ɂ�
���āA�g���b�N���[�U�́A�߂������ɒ�NO���E��R��̑�^�g���b�N���w�����邱�Ƃɂ���āA�R����̍팸�̉��b�ɗ�
����Ƌ��ɁA��C���̉��P�ɂ���^�ł���̂ł���B
�@�ܘ_�A�\�P�S�Ɏ������悤���V���ȁu��NO���E��R��g���b�N�E�o�X�̊�i�āj�v�ɓK��������^�g���b�N�ɑ��ẮA�]
�����G�R�J�[���łƓ��l�ɁA�ŋ���D�����邱�Ƃ��K�v�ł���B���̂悤�Ȏ{��ɂ�����A�߂������ɂ́A�m�n�� ��0.
23 g/kWh�܂ō팸���A2015�N�x�d�ʎԔR������{�P�O�� ���x�̔R������サ���V���Ȓ�NO���E��R���
��^�g���b�N�̔̔��䐔�́A�����̊������߂���̂ƍl������B�����āA�킪���ɂ������^�g���b�N�̕���ɂ���
��uNO���̍팸�v�A�u�ȃG�l���M�[�v����сu��CO2�v������I�ɐ��i����邱�Ƃ͊m���ł��낤�B���������āA���݂���
�{�i���y��ʏȂ���ъ��ȁj�����}�ɍs�Ȃ��ׂ����Ƃ́A��L�̕\�P4�ɗނ����^�g���b�N�ΏۂƂ����u��NO
���E��R��̃g���b�N�E�o�X�̊�v�Ⴕ���́u��R��E��r�o�K�X�����Ԃ̊�v�Ə̂���G�R�J�[���ł̑Ώۂ�
�Ȃ�V���Ȋ�𑁊��ɓ������邱���ł͂Ȃ����낤���B���̂��Ƃ́A�����̍����̋�����]�ł��邱�Ƃ͊ԈႢ��
�����낤�B
�����G�R�J�[���łƓ��l�ɁA�ŋ���D�����邱�Ƃ��K�v�ł���B���̂悤�Ȏ{��ɂ�����A�߂������ɂ́A�m�n�� ��0.
23 g/kWh�܂ō팸���A2015�N�x�d�ʎԔR������{�P�O�� ���x�̔R������サ���V���Ȓ�NO���E��R���
��^�g���b�N�̔̔��䐔�́A�����̊������߂���̂ƍl������B�����āA�킪���ɂ������^�g���b�N�̕���ɂ���
��uNO���̍팸�v�A�u�ȃG�l���M�[�v����сu��CO2�v������I�ɐ��i����邱�Ƃ͊m���ł��낤�B���������āA���݂���
�{�i���y��ʏȂ���ъ��ȁj�����}�ɍs�Ȃ��ׂ����Ƃ́A��L�̕\�P4�ɗނ����^�g���b�N�ΏۂƂ����u��NO
���E��R��̃g���b�N�E�o�X�̊�v�Ⴕ���́u��R��E��r�o�K�X�����Ԃ̊�v�Ə̂���G�R�J�[���ł̑Ώۂ�
�Ȃ�V���Ȋ�𑁊��ɓ������邱���ł͂Ȃ����낤���B���̂��Ƃ́A�����̍����̋�����]�ł��邱�Ƃ͊ԈႢ��
�����낤�B
�@��L�{�����Ō�蓙���������܂�����A���[�����ɂĂ��w�E�������܂��B�܂��A�^��_�A������A�䊴�z���A�ǂ̂悤
�Ȏ����ł����\�ł��B�Ջ��l���ĂɃ��[���������肢��������A�o����͈͂őΉ������Ă��������܂��B
�Ȏ����ł����\�ł��B�Ջ��l���ĂɃ��[���������肢��������A�o����͈͂őΉ������Ă��������܂��B
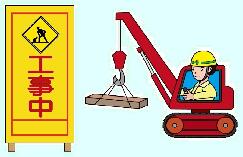
|