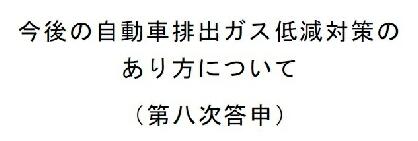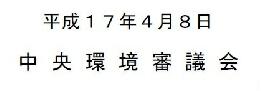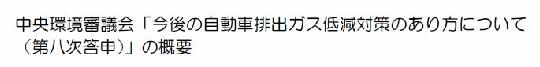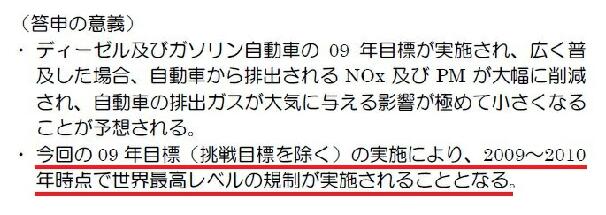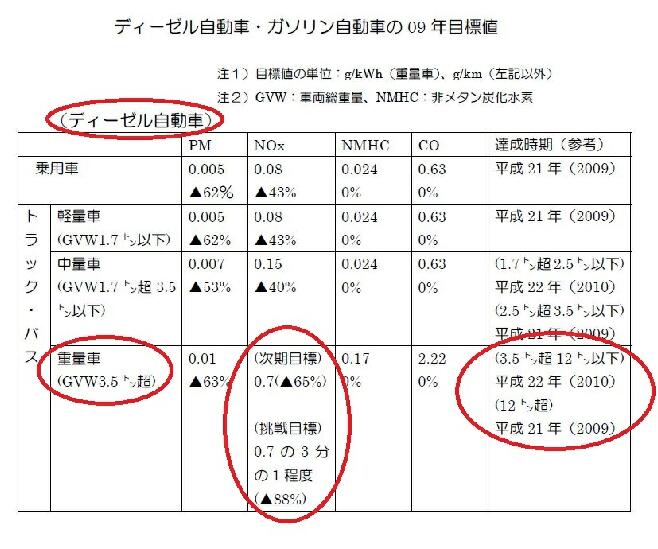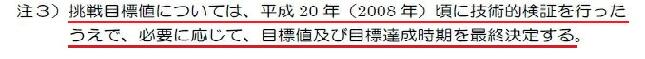�Ջ��l�̃A�C�f�A
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�g�b�v�y�[�W�ɖ߂�
�ŏI�X�V���F2016�N6��25��
 |
�P�D���{�̃f�B�[�[���W�̊w�ҁE���Ƃ��F�������^�g���b�N�̉������ׂ��ۑ�
�@����܂Ŋ������{�͑�^�g���b�N�̐V���Ȓ�R��E��r�o�K�X��𑁊��ɐݒ肹��I�A�C���x�~�G���W���ɂ���
�^�g���b�N�̒�R��A������C���x�~�́A�f�B�[�[���̂m�n���팸�ƔR�����̈ꋓ�����̋Z�p���I�̃y�[�W�ɏ�
�q���Ă���悤�ɁA��^�g���b�N�Ɋւ��鐢�E�̔r�o�K�X��R��K���̐i�W�̏����Ă���ƁA���{�ł͋߂�����
�Ɂu2015�N�x�d�ʎԔR������{10�����x�̔R�����v�Ɓu�m�n����0.23�@g/kWh ��NO���K���v�̋K�����������{��
��K�v������Ƃ́A��i���Ƃ��Ă͓��R�̂��Ƃł͖������ƍl������B���̏����́u�m�n���K���v�Ɓu�R��K���v�̋���
�ɓK�������邽�߂ɋi�قɉ����ׂ���^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W�����ۑ�ɂ��āA����܂œ��{�̃f�B�[�[���G
���W���W�̊w�ҁE���ƁE�Z�p�҂��o�ŕ���C���^�[�l�b�g�z�[���y�[�W���ŒE����Ă������e���A�ȉ���
���������̂ŁA����Ƃ��䗗�������������B
�^�g���b�N�̒�R��A������C���x�~�́A�f�B�[�[���̂m�n���팸�ƔR�����̈ꋓ�����̋Z�p���I�̃y�[�W�ɏ�
�q���Ă���悤�ɁA��^�g���b�N�Ɋւ��鐢�E�̔r�o�K�X��R��K���̐i�W�̏����Ă���ƁA���{�ł͋߂�����
�Ɂu2015�N�x�d�ʎԔR������{10�����x�̔R�����v�Ɓu�m�n����0.23�@g/kWh ��NO���K���v�̋K�����������{��
��K�v������Ƃ́A��i���Ƃ��Ă͓��R�̂��Ƃł͖������ƍl������B���̏����́u�m�n���K���v�Ɓu�R��K���v�̋���
�ɓK�������邽�߂ɋi�قɉ����ׂ���^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W�����ۑ�ɂ��āA����܂œ��{�̃f�B�[�[���G
���W���W�̊w�ҁE���ƁE�Z�p�҂��o�ŕ���C���^�[�l�b�g�z�[���y�[�W���ŒE����Ă������e���A�ȉ���
���������̂ŁA����Ƃ��䗗�������������B
�P�|�P�D�@����c��w�E�����������w�E�����^�g���b�N�ɂ�����i�قɉ������ׂ��ۑ�
�@
�@���{�����ԍH�Ɖ�̃z�[���y�[�W��JAMAGAZINE�@�i2012�N3�����j�Ɍf�ڂ́u�N���[���E�f�B�[�[���G���W���Z�p��
�����v�Ƒ肷��y�[�W�ɂ����āA�ȉ��̕\�P�Ɏ������悤�ɁA����c��w�̑��������́A�u���p�ԃN���[�����Z�p�v�̍�
�Ɂu���p�ԁi����^�g���b�N���j�ɂ������i�قɉ������ׂ��ۑ肪����Ă���B
�����v�Ƒ肷��y�[�W�ɂ����āA�ȉ��̕\�P�Ɏ������悤�ɁA����c��w�̑��������́A�u���p�ԃN���[�����Z�p�v�̍�
�Ɂu���p�ԁi����^�g���b�N���j�ɂ������i�قɉ������ׂ��ۑ肪����Ă���B
�� �o�T�̃z�[���y�[�W �F ���{�����ԍH�Ɖ� JAMAGAZINE�@2012�N3����
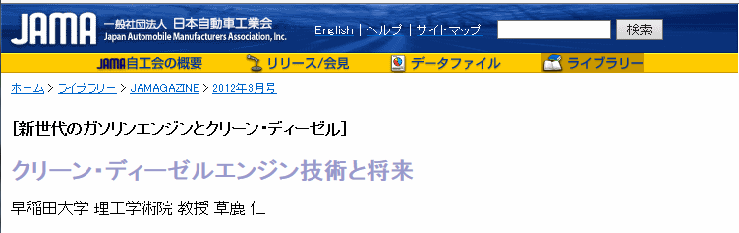 |
�� ���{�����ԍH�Ɖ� JAMAGAZINE�@2012�N3�����ɋL�ڂ���Ă���N���[���E�f�B�[�[���G���W���Z�p
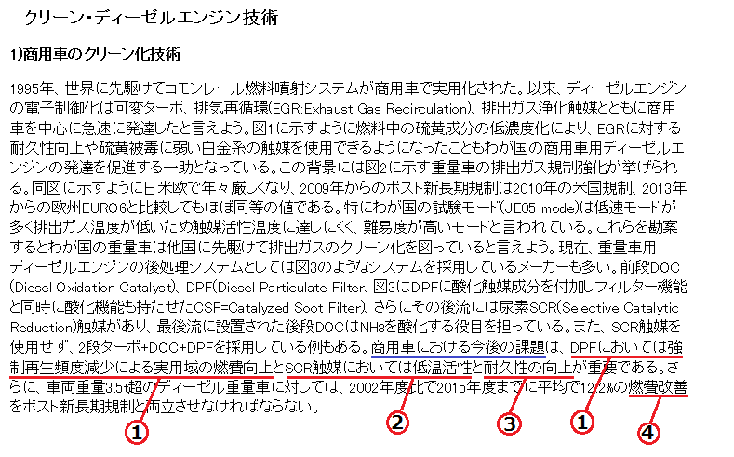 |
�@���̓��{�����ԍH�Ɖ�̃z�[���y�[�W��JAMAGAZINE�@�i2012�N3�����j�Ɍf�ڂ́u�N���[���E�f�B�[�[���G���W���Z
�p�Ə����v�Ƒ肷��_��������ƁA����c��w�̑��������́A2012�N3���̎��_�ł́A��^�g���b�N������i�قɉ��P
���ׂ��d�v�ۑ�Ƃ��āA�ȉ��̂S���ڂł���ƍL�����Ԃɔ��\����Ă���悤���B
�p�Ə����v�Ƒ肷��_��������ƁA����c��w�̑��������́A2012�N3���̎��_�ł́A��^�g���b�N������i�قɉ��P
���ׂ��d�v�ۑ�Ƃ��āA�ȉ��̂S���ڂł���ƍL�����Ԃɔ��\����Ă���悤���B
�@ �|�X�g���ˎ���r�C�Ǔ��R�����ˎ��̃t�B���^�Đ��V�X�e�����̗p����DPF���u�ɂ����鋭���Đ���
�p�x�����ɂ��R����̖h�~
�A SCR�G�}�ɂ�����ቷ�����̌���
�B SCR�G�}�̑ϋv���̌���iSCR�G�}��HC��ł̍Đ����u�H�j
�C �d�ʎԃ��[�h�R��̉��P
�@���̑���c��w�̑���������2012�N3���̎��_�ŋ�����ꂽ�@�`�C�̂S���ڂ̑��}�ɉ������ׂ���^�g���b�N��
�ۑ�́A�|���R�c���Z�p�̕M�҂����S�ɓ��ӂ���Ƃ���ł���B�����āA���̓��{�����ԍH�Ɖ�̃z�[���y�[�W��
JAMAGAZINE�i2012�N3�����j�Ɍf�ڂ́u�N���[���E�f�B�[�[���G���W���Z�p�Ə����v�ɂ����āA������������^�g���b�N
�̋i�قɉ��P���ׂ��S���ڂ̏d�v�ۑ�ƂƂ��ɋ��ɁA�����̉ۑ�̉����Ɏ�����Z�p�I�Ȏ������L�ڂ���Ă���
�A���̃z�[���y�[�W���{�������g���b�N���[�J�̃G���W���Z�p�҂ɂƂ��ẮA�ނ�̓���̌����J���̎菕���ɂȂ�
���ƍl������B�����āA���̏ꍇ�ɂ́A���̃z�[���y�[�W���{�������g���b�N���[�J�̃G���W���Z�p�҂́A�傢�Ɋ���
�������ł���B
�ۑ�́A�|���R�c���Z�p�̕M�҂����S�ɓ��ӂ���Ƃ���ł���B�����āA���̓��{�����ԍH�Ɖ�̃z�[���y�[�W��
JAMAGAZINE�i2012�N3�����j�Ɍf�ڂ́u�N���[���E�f�B�[�[���G���W���Z�p�Ə����v�ɂ����āA������������^�g���b�N
�̋i�قɉ��P���ׂ��S���ڂ̏d�v�ۑ�ƂƂ��ɋ��ɁA�����̉ۑ�̉����Ɏ�����Z�p�I�Ȏ������L�ڂ���Ă���
�A���̃z�[���y�[�W���{�������g���b�N���[�J�̃G���W���Z�p�҂ɂƂ��ẮA�ނ�̓���̌����J���̎菕���ɂȂ�
���ƍl������B�����āA���̏ꍇ�ɂ́A���̃z�[���y�[�W���{�������g���b�N���[�J�̃G���W���Z�p�҂́A�傢�Ɋ���
�������ł���B
�@�������Ȃ���c�O�Ȃ��ƂɁA���̓��{�����ԍH�Ɖ�z�[���y�[�W�́u�N���[���E�f�B�[�[���G���W���Z�p�Ə����v�Ƃ�
���X����薼���f��������c��w�̑��������̘_���ɂ́A�������������{���\����G���W�������ł���ɂ�����
��炸�A��^�g���b�N�̋i�قɉ��P���ׂ��S���ڂ̏d�v�ۑ肪����Ă��邾���ł���B�����āA�����S���ڂ̉�
�����������Z�p�I�Ȏ���������q�ׂ��Ă��Ȃ��̂ł���B���̂��߁A�u�N���[���E�f�B�[�[���G���W���Z�p�Ə�
���v�̘_�����{�������g���b�N���[�J�̑����̃G���W���Z�p�҂́A�K���⎸�]�������̂Ɛ��������B
���X����薼���f��������c��w�̑��������̘_���ɂ́A�������������{���\����G���W�������ł���ɂ�����
��炸�A��^�g���b�N�̋i�قɉ��P���ׂ��S���ڂ̏d�v�ۑ肪����Ă��邾���ł���B�����āA�����S���ڂ̉�
�����������Z�p�I�Ȏ���������q�ׂ��Ă��Ȃ��̂ł���B���̂��߁A�u�N���[���E�f�B�[�[���G���W���Z�p�Ə�
���v�̘_�����{�������g���b�N���[�J�̑����̃G���W���Z�p�҂́A�K���⎸�]�������̂Ɛ��������B
�@���̂悤�ɁA�u�N���[���E�f�B�[�[���G���W���Z�p�Ə����v�Ƃ̗��h�ȑ薼�̘_���ł���ɂ�������炸�A���̘_���ł�
���������͑��}�ɑP���ׂ���^�g���b�N�̂S���ڂ̏d�v�ۑ����������Z�p�Ă��������Ă��Ȃ��悤�ł�
��B���̂��Ƃ��画�f����ƁA���������́A2012�N3���̎��_�ɂ����ẮA��^�g���b�N�̂S���ڂ̏d�v�ۑ����������
�Z�p�I�Ȓ�Ă⌤���J���𐄐i���ׂ��Z�p�̕��j�E�Ă�����������Ă��Ȃ������Ɣ��f���Ă��傫�ȊԈႢ��������
�̂Ɛ��������B
���������͑��}�ɑP���ׂ���^�g���b�N�̂S���ڂ̏d�v�ۑ����������Z�p�Ă��������Ă��Ȃ��悤�ł�
��B���̂��Ƃ��画�f����ƁA���������́A2012�N3���̎��_�ɂ����ẮA��^�g���b�N�̂S���ڂ̏d�v�ۑ����������
�Z�p�I�Ȓ�Ă⌤���J���𐄐i���ׂ��Z�p�̕��j�E�Ă�����������Ă��Ȃ������Ɣ��f���Ă��傫�ȊԈႢ��������
�̂Ɛ��������B
�@���݁i��2016�N5�����_�j�ł́A�������������{�����ԍH�Ɖ�z�[���y�[�W�́u�N���[���E�f�B�[�[���G���W���Z�p��
�����v�Ƒ肷��_���\����Ă���S�N���x���o�߂��Ă��邪�A���������́A��^�g���b�N�̇@�`�C�̂S���ڂ̏d�v
�ۑ����������Z�p����ł������ł���V�Z�p�����o���ꂽ�̂ł��낤���B�|���R�c���Z�p���̕M�҂́A��w�ɍ�
�̏�ɋZ�p���̎��W�\�͂���邱�Ƃ�����A��^�g���b�N�̇@�`�C�̂S���ڂ̏d�v�ۑ������������p�I�ȋZ�p��
�������������ꂽ�Ƃ̏��Ă��Ȃ��B��킭�A�{�z�[���y�[�W���{�����ꂽ���̒��ŁA������������^�g
���b�N�̇@�`�C�̂S���ڂ̏d�v�ۑ����������Z�p���Ă���Ă���Ƃ̏���������Ă���ꍇ�́A���̏���{
�y�[�W�̖����̃��[���A�h���X�ɂ��A������������K���ł���B
�����v�Ƒ肷��_���\����Ă���S�N���x���o�߂��Ă��邪�A���������́A��^�g���b�N�̇@�`�C�̂S���ڂ̏d�v
�ۑ����������Z�p����ł������ł���V�Z�p�����o���ꂽ�̂ł��낤���B�|���R�c���Z�p���̕M�҂́A��w�ɍ�
�̏�ɋZ�p���̎��W�\�͂���邱�Ƃ�����A��^�g���b�N�̇@�`�C�̂S���ڂ̏d�v�ۑ������������p�I�ȋZ�p��
�������������ꂽ�Ƃ̏��Ă��Ȃ��B��킭�A�{�z�[���y�[�W���{�����ꂽ���̒��ŁA������������^�g
���b�N�̇@�`�C�̂S���ڂ̏d�v�ۑ����������Z�p���Ă���Ă���Ƃ̏���������Ă���ꍇ�́A���̏���{
�y�[�W�̖����̃��[���A�h���X�ɂ��A������������K���ł���B
�@���̂悤�ɁA2012�N3���ɔ��s�̓��{�����ԍH�Ɖ�z�[���y�[�W�́u�N���[���E�f�B�[�[���G���W���Z�p�Ə�
���v�̘_���ł́A���{���\����G���W����������Ƃ���鑁��c��w�E���������́u�@ DPF���u�̋�����
���̕p�x�����v�A�u�A SCR�G�}�̒ቷ�����v�A�u�BSCR�G�}��HC��ł̉����v�A�u�C �d�ʎԃ��[�h�R��̉�
�P�v�v�̂S���ڂ̑�^�g���b�N�̌����J�����ׂ��ۑ肾������A�����̉ۑ������������̓I�ȋZ�p�I��
�����E�J������Ă��Ȃ��悤�ł���B���̂悤�ɁA���̑���c��w�E���������̘_���́A��^�g���b�N�́u��
NO�����v����сu��R��v�̎����ɂ́A���ړI�ɖ𗧂Z�p��w�lj������y����Ă��Ȃ����߁A�u�N���[
���E�f�B�[�[���G���W���Z�p�Ə����v�̕\��ƒ��g�̋L�q���e���s��v�̌��ׂ�����_���Ƃ����Ă��ߌ��ł�
�Ȃ��ƍl������B
���v�̘_���ł́A���{���\����G���W����������Ƃ���鑁��c��w�E���������́u�@ DPF���u�̋�����
���̕p�x�����v�A�u�A SCR�G�}�̒ቷ�����v�A�u�BSCR�G�}��HC��ł̉����v�A�u�C �d�ʎԃ��[�h�R��̉�
�P�v�v�̂S���ڂ̑�^�g���b�N�̌����J�����ׂ��ۑ肾������A�����̉ۑ������������̓I�ȋZ�p�I��
�����E�J������Ă��Ȃ��悤�ł���B���̂悤�ɁA���̑���c��w�E���������̘_���́A��^�g���b�N�́u��
NO�����v����сu��R��v�̎����ɂ́A���ړI�ɖ𗧂Z�p��w�lj������y����Ă��Ȃ����߁A�u�N���[
���E�f�B�[�[���G���W���Z�p�Ə����v�̕\��ƒ��g�̋L�q���e���s��v�̌��ׂ�����_���Ƃ����Ă��ߌ��ł�
�Ȃ��ƍl������B
�P�|�Q�DUD�g���b�N�X�� ���ѐM�T �����w�E�����^�g���b�N�ɂ�����i�قɉ������ׂ��ۑ�
�@�@
�@�����ԋZ�p��2010�N8�����iVol.64�AN0.8�A2010�j�̓��W�F�N�Ӂ@�u�f�B�[�[���G���W���v�i���ҁFUD�g���b�N�X���@���ѐM
�T�@���j�́u�S�@�����J���̓����v�ɂ́A�f�B�[�[���G���W���̔r�o�K�X�ƔR����팸���邽�߂̍ŋ߂̋Z�p�������܂�
�߂��Ă���B���́u�S�@�����J���̓����v�ɂ́A�g���b�N���[�J���w�E�����@�ւ̑����̐��Ƃ��f�B�[�[���G���W��
�̔r�o�K�X�ƔR����팸���邽�߂ɗL���ƍl���Ă���Z�p�ɂ��āA�܂Ƃ߂��Ă��锤�ł���B�����N�Ӂ@�u�f�B�[�[
���G���W���v�́u�S�@�����J���̓����v�ɑ��A�M�҂��^��Ɋ�������e�ɂ��āA���L�̕\�Q�ɂ܂Ƃ߂��B
�T�@���j�́u�S�@�����J���̓����v�ɂ́A�f�B�[�[���G���W���̔r�o�K�X�ƔR����팸���邽�߂̍ŋ߂̋Z�p�������܂�
�߂��Ă���B���́u�S�@�����J���̓����v�ɂ́A�g���b�N���[�J���w�E�����@�ւ̑����̐��Ƃ��f�B�[�[���G���W��
�̔r�o�K�X�ƔR����팸���邽�߂ɗL���ƍl���Ă���Z�p�ɂ��āA�܂Ƃ߂��Ă��锤�ł���B�����N�Ӂ@�u�f�B�[�[
���G���W���v�́u�S�@�����J���̓����v�ɑ��A�M�҂��^��Ɋ�������e�ɂ��āA���L�̕\�Q�ɂ܂Ƃ߂��B
| |
|
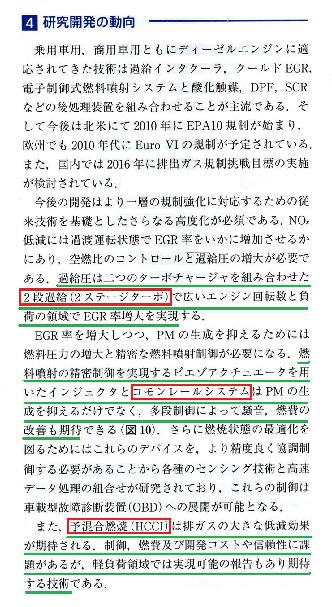 |
�@�����ԋZ�p��2010�N8�����̓��W�F�N�Ӂ@�u�f�B�[�[���G���W���v��
�u�S�@�����J���̓����v�ł́A����A�f�B�[�[���G���W����NO���팸��
�G���W���R��̍팸��}�邽�߂̗L���ȋZ�p�Ƃ��āA�g���b�N���[�J��
��w�E�����@�ւ̑����̐��Ƃ́A�ȉ��̋Z�p�Ɋ��҂���Ă���Ƃ�
���ƁB
���Q�i�ߋ�
���R�������[���i�������˂ƃs�G�]�C���W�F�N�^�ɂ�镬�˂̐�������j
���\�����R�āiHCCI�܂���PCI�j
�������A�O�q�̂W-1���Ŏ������悤�ɁA8���~�ȏ�̗\�Z�Ŏ��{���ꂽ
NEDO�̊v�V�I���������Q�ԑ����Z�p�J���i�N���[���f�B�[�[��
�v���W�F�N�g�A2004�`2009�N�j�́u�����x�R�Đ���G���W�V�X�e����
�����J���v�̑�^�v���W�F�N�g�ł͈ȉ��̋Z�p��g�ݍ��r�o�K�X
�팸�ƔR��팸�̌����J�������{���ꂽ�B
���@�R�i�ߋ��V�X�e���i�����ϗL�������j
���@300MP���̒������R�����ˁi�����ϗL�������j
���@�J�����X�V�X�e����g�ݍ��uPCI�R�āv
�@�@(PCI�R�ā�HCCI�R�āj
�@����NEDO�̑�^�v���W�F�N�g�ł́A�}�P�T�Ɏ������悤�ɁANOx�͖ڕW
��B���������A���݂̏ȃG�l���M�[�E�Ȏ����E��CO2�̎���ɋ��߂��
�Ă���̐S�v���R��팸�͖ڕW��10���팸�ɂ͑S���y���A
2015�N�x�d�ʎԔR���ɑ��ĂQ���̈����ƂȂ��Ă��܂���
�̂ł���B
�@�ȏ��NEDO�̑�^�v���W�F�N�g�̎������ʂ����\����Ă���ɂ�
������炸�A���L�������ԋZ�p��2010�N8�����̓��W�F�N�Ӂ@
�u�f�B�[�[���G���W���v�́u�S�@�����J���̓����v�ł́A���҂�UD
�g���b�N�X�����ѐM�T�����u�Q�i�ߋ��v�A�u�R�������[���ɂ�钴����
�R�����ˁv����сu�\�����R�āiHCCI�j�v�ɂ���ăf�B�[�[��
�G���W���̔R��팸�𖢂��Ɋ��҂���Ă���悤�ɋL�q����Ă���
���ƂɈ�a���������Ă���B
�@���������ԋZ�p��2010�N8�����̓��W�F�N�ӂ����҂ł���UD
�g���b�N�X�����ѐM�T���́ANEDO�̑�^�v���W�F�N�g�̎������ʂ�����
����Ɓu�Q�i�ߋ��v�{�u�R�������[���i�������˂ƃs�G�]�C���W�F�N�^�ɂ��
���˂̐�������j�v�{�u�\�����R�āiHCCI�܂���PCI�j�v�̋Z�p�ł͔R��
�팸������Ȃ��Ƃ͏��m����Ă���̂ł͂Ȃ����낤���B
�������Ȃ���A�����̋Z�p�ȊO�ɑ�^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W����
�R��팸�Z�p���c�_����Ă��Ȃ��̂ł͂Ȃ����낤���B�܂�A�����_
�ŔR��팸�ɗL���ȋZ�p�Ă������o���Ă��Ȃ����̂Ɛ��������B
���������āA���̏𐳒��ɋL�ڂ���A2010�N8�������N�ӂ�
�u�����J���̓����v�ł͑�^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W���̔R�
�팸�ł���Z�p���u���݂̂Ƃ���s���v�ƕs�l�ȓ��e�̋L�ڂƂȂ���
���܂��̂ł���B
�������A��牽�ł��u�f�B�[�[���G���W���̔R��팸�Z�p���s���v�Ƃ�
�L�q�ł��Ȃ����߁A���҂̏��ѐM�T���́A�s�{�ӂȂ����^�g���b�N�p
�f�B�[�[���G���W���̔R��팸�����҂ł���Z�p�Ƃ��Ďd�������u�Q�i
�ߋ��v�{�u�R�������[���i�������˂ƃs�G�]�C���W�F�N�^�ɂ�镬�˂̐���
����j�v�{�u�\�����R�āiHCCI�܂���PCI�j�v���L�ڂ����ꂽ�̂ł͂Ȃ�
���낤���B
�P�O�N�v�i���ҁF�ѓc�P�� �c���勳���@���R���j�ł͑�^�g���b�N�p �f�B�[�[���G���W���ł͔R�ĉ��P�ɂ��R��팸�i���b�n�Q�팸�j�� �u����ۑ�v�L�q����A�w��^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W���ɂ�����R�� �팸�́A�����_�ł͋Z�p�I�ɔ����ǂ���̏x�̎|���f���Ɏ咣 ����Ă���̂ł���B������ѓc�P�� �c���勳������^�g���b�N�p �f�B�[�[���G���W���ɂ�����R��팸���ɂ߂č���ł���Ƃ̌����� �����ɓf�I����Ă���̂ł͂Ȃ����Ǝv���Ă���B �@���݁A�|�X�g�V�����r�o�K�X�K���i2009�N�K���j�ɓK���̑�^�g���b�N�E �g���N�^�ł́A��q�̕\�X�Ɏ����Ă���悤�ɁA�����̎Ԏ킪2015�N�x �d�ʎԔR���ɕs�K���ƂȂ��Ă���̂ł���B���̂��Ƃ��琄�@ ����ƁA�g���b�N���[�J�ł͑�^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W���ɂ����� ���p���̍����R��팸�̋Z�p���J���ł��Ă��Ȃ����̂ƍl������B �@�������Ȃ���A�g���b�N���[�J�̋Z�p�҂ł��钘�҂̏��ѐM�T���́A �ѓc�P�� �c���勳���̂悤�ɋC�y�ɁA�w��^�g���b�N�p�f�B�[�[�� �G���W���ɂ�����R��팸�́A�����_�ł͋Z�p�I�ɔ����ǂ��� �̏��x�̎�|�̔��������邱�Ƃ��ł��Ȃ�����ł��邱�Ƃ͊m���� ���Ƃ��B���̗��R�́A���ɁAUD�g���b�N�X���̏��ѐM�T�����w��^ �g���b�N�p�f�B�[�[���G���W���̔R��팸�̋Z�p���s���x�Ƃ̔����� �s�����Ƃ���AUD�g���b�N�X���́A�g���b�N���[�J�̋Z�p�͂ɑ��� �g���b�N���[�U����M������r�����Ă��܂��ƍl�����邽�߂��B �@���̂悤�ɁA��^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W���̔R��팸�̋Z�p�J�� ����l�܂�̏Ɋׂ��Ă��鎞���ɁA�����ԋZ�p��2010�N8������ ���W�F�N�Ӂ@�u�f�B�[�[���G���W���v�̒��q��S�������ꂽUD�g���b�N�X ���̏��ѐM�T���̕s�K�ɂ́A�����̐l������̔O�������Ă��� �̂ł͂Ȃ����낤���B |
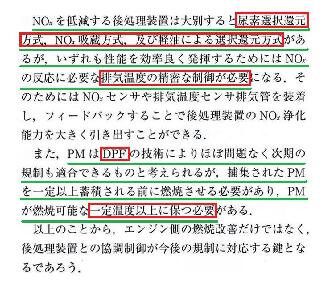 |
�@��ʓI�ɑ�����NOx�ጸ�̌㏈�����u�ɂ����č���NO���팸����
�������邽�߂ɂ́A�r�C�K�X���x����背�x���ȏ�̍����Ɉێ�����
���Ƃł���B���̂��߂ɂ́A�r�C�K�X���x�̒Ⴂ�G���W���ᕉ�ׂ�
�����Ĕr�C���x�����������鑕�u�E��i�i�A�C�f�A�j���K�v������B
�����āA���̔r�C���x�����������鑕�u�E��i���G���W���ɓ��ڂ��A
���̑��u�E��i��r�C�K�X���x�̃t�B�[�h�o�b�N���䂵�A��背�x��
�ȏ�̍����̔r�C�K�X���x�Ɉێ��ł���悤�ɂ���̂ł���B
����ɂ���āA���߂�NOx�ጸ�̌㏈�����u�ł�NO���팸��������
�ł���̂��B�������A���炩�̔r�C���x�����������鑕�u�E��i��p����
���Ɩ����A�u�r�C���x�̐����Ȑ���v�����ł�NOx�ጸ�̌㏈�����u
�ł�NO���팸���̌���͋ɂ߂č���ł���B
�@�Ƃ��낪�A�u�S�@�����J���̓����v�̍��L�̋L�q�ɂł́ANOx�ጸ��
�㏈�����u�ł̍���NO���팸�����������邽�߂ɁA���𐧌䂵��
��背�x���ȏ�̍����r�C���x�ɐ��䂷�邩�ɂ��āA��̓I��
�Z�p���e�������L�ڂ���Ă��Ȃ��̂ł���B����́ANO���팸�̉ۑ�
��������������Ă���̉߂��Ȃ��̂ł���B���̂悤��NO���팸�̉ۑ�
�����̋L�q�ł́A�����J���̓����ƌ����Ȃ����낤�B
��ʓI�ɉ]���āA���L�̂悤�Ɂu�����J���̓����v�̍��Ɂu�r�C�K�X ���x�̍����Ɉێ����邱�Ƃ��K�v�v�Ƃ́u�ۑ��v�������L�ڂ��A���� �u�ۑ�v������������Z�p�������L�ڂ���Ă��Ȃ��ꍇ�́A�u�ۑ�v�� ��������Z�p(�A�C�f�A�j���u�s���v�̂��߂ƍl���ĊԈႢ�Ȃ��� �l������B ���������č��L�̂悤�Ɂu�����J���̓����v�̍��ɂ́u�A�fSCR�G�} ���ɂ��NO���팸�̌����DPF���u�ł̋����Đ��̕p�x�팸 �̂��߂ɕK�v�ȃG���W���ᕉ���ɔr�C�K�X���x������������ �Z�p�́A�����_�ł͕s���ł���v�ƋL�q���ׂ��ł͂Ȃ����낤���B �@���āA�����ԋZ�p���́A���ǐ��x�ɂ���ċL���͐�������Ă���� �����Ă���B���̔N�ӂɂ����āA�u�����J���̓����v�Ƒ肵�����ڂ̒� �ł́A�G���W���ᕉ���ɔr�C�K�X���x�����������邽�߂̋�̓I�� �Z�p�������L�ڂ���Ă��Ȃ��̂��B���̂��Ƃ́A���҂̏��ѐM�T���� �r�C�K�X���x�����������邽�߂̋�̓I�ȋZ�p�ɂ��Ă̌��\�ł��� �m���E�����������łȂ������Ɖ]�����A�g���b�N���[�J���w�E���� �@�ւ̑����̐����������ԋZ�p���̔N�ӂɖ��L�ł���悤�� �u�r�C�K�X���x������������Z�p�̈āi�A�C�f�A�j�������A�Z�p�I�� �����ǂ���̏Ɋׂ��Ă���v�ƍl����̂��Ó��̂悤�Ɏv���� �̂ł���B �@����A�M�҂́A�u�f�B�[�[���G���W���ᕉ���ɔr�C�K�X���x�� ���������邽�߂̋Z�p�v�Ƃ��āA�Q�^�[�{�����̋C���x�~�G���W�� �i�������J2005-54771�j�v�̋Z�p���Ă��Ă���B�����C���x�~ �G���W���i�������J2005-54771�j�́A�A�N�Z���y�_�������ݗ� ��50���ȉ��̃G���W���^�]�̗̈�ɂ����Ĕ����̋C�����x�~ ���A����ɂ���āA�����I�ȃG���W���̃_�E���T�C�W���O�ɂ���� �R��팸�ł���Z�p���B���̔R��팸�Ɠ����ɁA�ғ��C���Q �̔r�C�K�X���x���\���ɍ������ł��邽�߁A�A�fSCR�G�}���� NO���팸�̌㏈�����u�ł�NO���팸��������ł��ADPF���u�� ���R�Đ��̑��i���\�ɂȂ��̂ł���B �@���̋C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p���A2006�N4�� �ɊJ�݂����M�҂̃z�[���y�[�W�ɋL�ڂ��A����4�N�ȏ���ȑO������J ���Ă���B�������A���L�������ԋZ�p���̔N�ӂ̋L�q���������A�M�� �̒�Ă����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�́A���S�ɖ��� ����Ă��邱�Ƃ������B �@�����_�Ŕr�C�K�X���x�������Ɉێ��ł���Z�p�Ă������ۗL ���Ă��Ȃ��g���b�N���[�J���w�E�����@�ւ̑����̐��Ƃ��A�r�C �K�X���x�̍������ɗL�����C���x�~�G���W���i�������J2005- 54771�j����ȂɖَE���A�ь������闝�R�́A��̑S�́A���Ȃ̂� ���낤���B |
�̓����v�ɋL�ڂ���Ă�����e������ƁA���̎��_�ł̎����ԋƊE��f�B�[�[���G���W���w��ł́A�f�B�[�[��
�G���W���̔R��팸�̋Z�p���s���ł���A�܂��A�fSCR�G�}����NO���팸�̌㏈�����u��ADPF���u�ł̋�
���Đ��̕p�x�팸�̂��߂̃G���W���ᕉ���ɔr�C�K�X���x����������R����P����������Z�p���s����
�̂��Ƃł���B
�P�|�R�DUD�g���b�N�X�� �O�G �����w�E�����^�g���b�N�ɂ�����i�قɉ������ׂ��ۑ�
�@�����ԋZ�p��2014�N8�����iVol.68�AN0.8�A2014�j�̓��W�F�N�Ӂ@�u�f�B�[�[���G���W���v�i���ҁF�t�c�g���b�N�X���@�O��@
���G�@���j�́u�S�@�����J���̓����v�ɂ́A�f�B�[�[���G���W���̔r�o�K�X�ƔR����팸���邽�߂̍ŋ߂̋Z�p������
�܂Ƃ߂��Ă���B���́u�S�@�����J���̓����v�ɂ́A�g���b�N���[�J���w�E�����@�ւ̑����̐��Ƃ��f�B�[�[���G��
�W���̔r�o�K�X�ƔR����팸���邽�߂ɗL���ƍl���Ă���Z�p�ɂ��āA�܂Ƃ߂��Ă��锤�ł���B�����N�Ӂ@�u�f�B
�[�[���G���W���v�́u�S�@�����J���̓����v�ɑ��A�M�҂��^��Ɋ�������e�ɂ��āA���L�̕\�R�ɂ܂Ƃ߂��B
���G�@���j�́u�S�@�����J���̓����v�ɂ́A�f�B�[�[���G���W���̔r�o�K�X�ƔR����팸���邽�߂̍ŋ߂̋Z�p������
�܂Ƃ߂��Ă���B���́u�S�@�����J���̓����v�ɂ́A�g���b�N���[�J���w�E�����@�ւ̑����̐��Ƃ��f�B�[�[���G��
�W���̔r�o�K�X�ƔR����팸���邽�߂ɗL���ƍl���Ă���Z�p�ɂ��āA�܂Ƃ߂��Ă��锤�ł���B�����N�Ӂ@�u�f�B
�[�[���G���W���v�́u�S�@�����J���̓����v�ɑ��A�M�҂��^��Ɋ�������e�ɂ��āA���L�̕\�R�ɂ܂Ƃ߂��B
| |
|
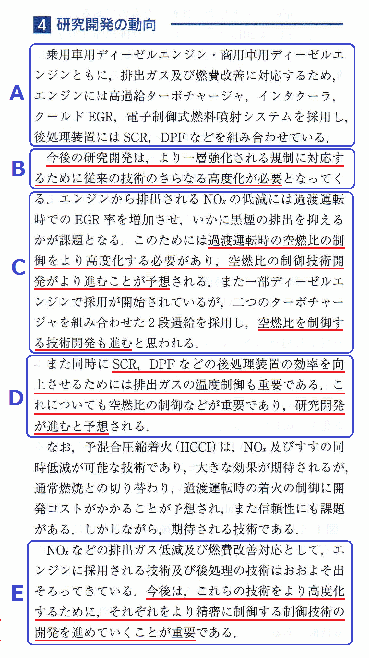 |
�� �f�B�[�[���G���W����NO���팸�ƔR��ጸ�̋Z�p���e
�@���L�̂`�i���ɂ́A���s���f�B�[�[���G���W���ł́A�r�o�K�X
�팸�ƔR����P�̂��߂Ɉȉ��̋Z�p���̗p����Ă���Əq��
������B
�E���ߋ��^�[�{�`���[�W���i���Q�i�ߋ����j
�E�C���^�[�N�[��
�E�N�[���h�d�f�q
�E�d�q���䎮�R�����˃V�X�e��
�E�㏈�����u�i���r�b�q�G�}�A�c�o�e���u�j
�@�����āA���L�̂a�i������тd�i���ɂ́A�ȏ�̌��s�f�B�[
�[���G���W���ɍ̗p�̏��Z�p�̍X�Ȃ�u���x���v�ɂ���āA
����̂m�n���y�єR��̋K�������ɓK���\�Ƃ́u���ʂ��v��
�q�ׂ��Ă���B�����O�G ���̌����ɂ́A�|���R�c
���Z�p���̕M�҂ɂ͋^��Ɏv����Ƃ���ł���B
�@���݂ɁA�߂������̑�^�g���b�N���m�n���K���y�єR��K��
�ȉ��̋K���l�̐����ɂȂ���̂Ɨ\�������B
�E �m�n���K���̋����@���@0.23�@g/kWh
�i 2016�N�̎����m�n���K���l���� 43 �� ���j
�i2005�N�̑攪�����\��NO������ڕW���x���j
�E �R���̋����@
��2015�N�x�d�ʎ�Ӱ�ޔR������{10�����x�̌���
�@���̂悤�ɁA��^�f�B�[�[���g���b�N�ɂ����āA�u�m�n����0.23
(g/kWh)�v�Ɓ@�u2015�N�x�d�ʎ�Ӱ�ޔR������{10��
���x�̔R�����v�����{�����\�����ɂ߂č������A����
�ꍇ�A���L�̂`�i���ɋL�ڂ́u���s�f�B�[�[���G���W���ɍ̗p
�̏��Z�p�̍X�Ȃ鍂�x���v�����ł́A�m�n���ƔR��̋K����
�K���ł��Ȃ��Ɛ��������B
�@���������āA���{�̃g���b�N���[�J�������L�̂`�i�������
�a�i������тd�i���ɏq�ׂ��Ă���悤�ȋZ�p���u����
�J���v�����{���Ă��邾���ł���A�����I���m�n���ƔR���
�K�������ɓK���ł����^�g���b�N�����p�����邱�Ƃ́A
�|���R�c���Z�p���̕M�҂ɂ�����Ǝv���Ďd�����Ȃ��B
�o���邱�ƂȂ�A�O�G ���̖{�S���f���Ă݂������̂�
����B
�� ���L�́u�����J���̓����v�ɋL�ڂ̌����J���̉ۑ�
�@���L�̂a�i���ɂ́A����̍X�Ȃ�r�o�K�X�ƔR��̋K��
�����ɑΉ����邽�߂ɂ́A�]���̋Z�p�̍X�Ȃ鍂�x�����K�v
���q�ׂ��Ă���B���̂��߂ɉ������ׂ��Z�p�I�ȉۑ�
�Ƃ��āA���L�̂b�i������тc�i���ɂ́A�ȉ��̂��Ƃ�����
�������B
�@ �G���W������r�o�����m�n���̍팸�̂��߂ɂ́A
�ߓn�^�]���ł̂d�f�q�����w�����邱�Ɓi=�b�i���j
�E�M�҂̌����F�ߓn�^�]���ɂd�f�q���������ăG���W��
����r�o�����m�n���̍팸��}��Ƃ̋L�q�́A�٘_������
�]�n�̂Ȃ����R�̂��Ƃł���A�M�҂����ӂ���Ƃ���ł���B
�A �ߓn�^�]���̋�R��̐������荂�x�����邱��
�i=�b�i���j
�E�M�҂̌����F�ߓn�^�]���ɋ�R���K�ɐ��䂷�邱�Ƃ́A
�m�n���A�o�l�A�����̑�����h�~���邽�߂ɕK�v�Ȃ��Ƃł���
���߁A���̋L�q�Ɉ٘_�����ޗ]�n�̂Ȃ����R�̂��Ƃł���A
�M�҂����ӂ���Ƃ���ł���B
�B 2�i�^�[�{�ߋ����̗p������R�䐧��̋Z�p�J����
���i���邱�Ɓi=�b�i���j
�E�M�҂������F2�i�^�[�{�ߋ��i���Q�i�V�[�P���V�����^�[�{
�V�X�e���j�́A�C���x�~�G���W���ɂ���^�g���b�N�̒�R� �́u�R�D�J�������܂߂���v�ȃf�B�[�[���G���W���̔R����P �̋Z�p�v�̍��̐}�S�ɏڏq���Ă���悤�ɁA���i�g�����X �~�b�V�����Ƒg�ݍ��킹�đ��s���̃G���W����Ⴂ��]���� �ێ��ł���悤�ɂ��邱�Ƃɂ��A�g���b�N�̑��s�R������P �ł���悤�ɂ���Z�p�ł���B���������āA�u�b�i���v�ɂ����� �u2�i�^�[�{�ߋ��ɂ����R�䐧��v�Əq�ׂ��Ă��邱�Ƃ� ���ẮA�O�G �����u2�i�^�[�{�ߋ��V�X�e���v�̖{�� �̋@�\�E���\�ɂ��āA����ė�������Ă���悤�Ɏv�����A �@���Ȃ��̂ł��낤���B �C SCR�����DPF���̌㏈�����u�̌�������̂���
�̔r�o�K�X�̉��x����i���G���W�����������ɂ�����
�r�C�K�X���x�̍������j�̎����i=�c�i���j
�E�M�҂̌����F�c�i���ɂ����āA�G���W�����������ɂ�����
�r�C�K�X���x�̍���������������SCR�����DPF���̌㏈��
���u�̌��������}��Əq�ׂ��Ă���B�������A�G���W��
���������ɔr�C�K�X���x�����������邽�߂̋Z�p��
���ẮA�t�c�g���b�N�X���̎O�G ��������L�ڂ����
���Ȃ��̂ł���B�܂�A���݂̃f�B�[�[���G���W���ɂ�����
�uSCR�ɂ��m�n���팸�v��uDPF�̎��ȍĐ��̑��i�v�̋@�\
����̉ۑ肪�q�ׂ��Ă��邾���ł���B����́A�O�q��
�\�Q�Ɏ������u�����ԋZ�p��2010�N8�����iVol.64�AN0.8�A
2010�j���W�F�N�Ӂ@�f�B�[�[���G���W���̂S�����J���̓���
�i���ҁFUD�g���b�N�X���@���ѐM�T�@���j�v�Ƃقړ������e
�ł���B
�@���̂��Ƃ́A2010�N8������4�N�o�߂������݁i2014�N
8���j�ł��AUD�g���b�N�X���̃G���W���Z�p�ҁE���Ƃ�
�G���W�����������ɂ�����r�C�K�X���x��������
�ɂ��SCR�����DPF���̌㏈�����u�̌��������
�}��ۑ�̉���������o���Ă��Ȃ��؋��ƍl������B
���̂悤�ɁA�S�N�̍Ό����₵�Ă�SCR�����DPF����
�㏈�����u�̌�������ɗL���ȃG���W������������
������r�C�K�X���x���������̋Z�p���J���ł��Ȃ���
�ł���ɂ�������炸�A�ނ�̓f�B�[�[���G���W���̕���
�����ɂ�����r�C�K�X���x���������ɗL���ȕM�Ғ��
���C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p
�i��2006�N4���ɊJ�݂̃z�[���y�[�W��Ō��J�ς݁j��
��Ȃɖ����E�َE�������Ă���̂ł���B
�@���̂��Ƃ́AUD�g���b�N�X����UD�g���b�N�X���ȊO�̃g���b�N
���[�J�̃G���W���Z�p�ҁE���Ƃ����l�ȏɊׂ��Ă���
���̂Ɛ��������B���̂��Ƃ���A���{�̃g���b�N���[�J��
�G���W���Z�p�ҁE���Ƃ́A�N��l�Ƃ����C���x�~�G���W���i����
���J2005-54771�j�ɂ�����G���W�����������̔r�C�K�X ���x�������̗D�ꂽ�@�\�E���\�𗝉��ł��Ȃ����Ƃ�����
�����m��Ȃ��B���ɁA���ꂪ�����ł���A���Ƃ��Q���킵��
���ł͂Ȃ����낤���B����Ƃ��A�|���R�c���Z�p���̒�Ă���
�����Z�p�k�i���C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�l��
�̗p���邱�ƂɁA���{�̃g���b�N���[�J�̃G���W���Z�p�ҁE
���Ƃ̃v���C�h�E�����S�������Ȃ������ł��낤���B
���ɁA�����ł���A���̑����䖝�͂��܂ő����邱�Ƃ�
�ł���̂ł��낤���B�|���R�c���Z�p���ɂƂ��ẮA�����[�X��
���Ƃł���B
�i�Ȃ��A�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̃G���W��
���������ɂ�����r�C�K�X���x�̍������Ɋւ���@�\�E
���\���ɂ��ẮA�C���x�~�G���W���ɂ���^�g���b�N�̒�R��
���A�C���x�~��DPF�̎��ȍĐ��𑣐i (�����Đ��̍팸�ŔR�� ������h�~�j�A�C���x�~�́A�f�B�[�[���r�C�K�X�̃G�l���M�[�� ���u�̌����������A�f�B�[�[���̋C���x�~�́A�R�[���h�X�^�[�g�� NO���팸�ɂ��L�����I�A���쎩���Ԃ��_�����\�����R����P�@ �\�̗��C���x�~�V�X�e���ɏڏq���Ă���̂ŁA�����̂��� ���͌䗗�������������B�j
|
�@�ȏ�̂̂悤�ɁA�t�c�g���b�N�X�� �O�G ���́ASCR�G�}�����DPF���̌㏈�����u�̌�������̂��߂�
�r�o�K�X�̉��x����i���G���W�����������ɂ�����r�C�K�X���x�̍������j��R����P���K�v�Ɩ��L����
�Ă���B�������A�t�c�g���b�N�X���̎O�G ���́A�O�q�́i�P�j���̏��ѐM�T ���Ɠ��l�ɁA�f�B�[�[���G���W��
�̃G���W�����������ɂ�����r�C�K�X���x�̍�������R����P�����������̓I�ȋZ�p���i�E���@�ɂ�
���ẮA�����q�ׂ��Ă��Ȃ��B
�r�o�K�X�̉��x����i���G���W�����������ɂ�����r�C�K�X���x�̍������j��R����P���K�v�Ɩ��L����
�Ă���B�������A�t�c�g���b�N�X���̎O�G ���́A�O�q�́i�P�j���̏��ѐM�T ���Ɠ��l�ɁA�f�B�[�[���G���W��
�̃G���W�����������ɂ�����r�C�K�X���x�̍�������R����P�����������̓I�ȋZ�p���i�E���@�ɂ�
���ẮA�����q�ׂ��Ă��Ȃ��B
�Q�D��^�g���b�N�́uNO���팸�v�Ɓu�R����P�v�̎����ɕK�v�ȉ������ׂ��ۑ�
�@
�@�����_�i��2015�N7�����݁j�ɂ����āA��^�g���b�N�̍X�Ȃ�uNO���̍팸�v�Ɓu�d�ʎԃ��[�h�R��̉��P�v�𐄐i���邽
�߂ɋi�قɉ������ׂ��ۑ�́A�O�q�̂P���Ɏ���������c��w�E���������̔��\���e�i�����{�����ԍH�Ɖ�̃z�[
���y�[�W��2012�N3����JAMAGAZINE�Ɍf�ځj��AUD�g���b�N�X�� ���ѐM�T ���̎咣�i�������ԋZ�p��2,010�N8��
���f�ځj�Ƃt�c�g���b�N�X���@�O��@���G�@���̎咣�i�������ԋZ�p��2014�N8�����f�ځj���疾�炩�Ȃ悤�ɁA�ȉ��̂S
���ڂɏW���ƍl������B ����ɂ��ẮA���{�̃f�B�[�[���G���W���W�̊w�ҁE���ƁE�Z�p�҂ɂ́A�٘_
��������]�n���������ł���B
�߂ɋi�قɉ������ׂ��ۑ�́A�O�q�̂P���Ɏ���������c��w�E���������̔��\���e�i�����{�����ԍH�Ɖ�̃z�[
���y�[�W��2012�N3����JAMAGAZINE�Ɍf�ځj��AUD�g���b�N�X�� ���ѐM�T ���̎咣�i�������ԋZ�p��2,010�N8��
���f�ځj�Ƃt�c�g���b�N�X���@�O��@���G�@���̎咣�i�������ԋZ�p��2014�N8�����f�ځj���疾�炩�Ȃ悤�ɁA�ȉ��̂S
���ڂɏW���ƍl������B ����ɂ��ẮA���{�̃f�B�[�[���G���W���W�̊w�ҁE���ƁE�Z�p�҂ɂ́A�٘_
��������]�n���������ł���B
�@ �|�X�g���ˎ���r�C�Ǔ��R�����ˎ��̃t�B���^�Đ��V�X�e�����̗p����DPF���u�ɂ����鋭���Đ���
�p�x�����ɂ��R����̖h�~
�A SCR�G�}�ɂ�����ቷ�����̌���
�B SCR�G�}�̑ϋv���̌���iSCR�G�}��HC��ł̍Đ����u�H�j
�C �d�ʎԃ��[�h�R��̉��P
�R�D�i�قɉ������ׂ���^�g���b�N�̉ۑ����������Z�p��E��Ăł��Ȃ��w�ҁE����
�R�|�P�D����c��w�E���������A�����UD�g���b�N�X���̏��ѐM�T ���ƎO��@���G�@���̏ꍇ
�@�ȏ�̂P���Ɏ��������{�����ԍH�Ɖ�̃z�[���y�[�W��2012�N3����JAMAGAZINE�Ɍf�ڂ��ꂽ����c��w�E��
�������̔��\���e��A�Q���Ɏ����������ԋZ�p����2010�N8�����Ɍf�ڂ�UD�g���b�N�X�� ���ѐM�T ������ю�����
�Z�p����2014�N8�����Ɍf�ڂ̎O��@���G�@���̋L�����疾�L����Ă����^�g���b�N�̋i�قɉ������ׂ��ۑ�i��
�@ �|�X�g���ˎ���r�C�Ǔ��R�����ˎ��̃t�B���^�Đ��V�X�e�����̗p����DPF���u�ɂ����鋭���Đ��� �p�x������
���R����̖h�~�A�A SCR�G�}�ɂ�����ቷ�����̌���A�B SCR�G�}�̑ϋv���̌���kSCR�G�}��HC��ł�
�Đ����u�H�l�A�C �d�ʎԃ��[�h�R��̉��P�j�́A�����_�i��2014�N12�����݁j�ł́A������������邽�߂̗L���ȋZ
�p���s���̏̂悤�ł���B
�������̔��\���e��A�Q���Ɏ����������ԋZ�p����2010�N8�����Ɍf�ڂ�UD�g���b�N�X�� ���ѐM�T ������ю�����
�Z�p����2014�N8�����Ɍf�ڂ̎O��@���G�@���̋L�����疾�L����Ă����^�g���b�N�̋i�قɉ������ׂ��ۑ�i��
�@ �|�X�g���ˎ���r�C�Ǔ��R�����ˎ��̃t�B���^�Đ��V�X�e�����̗p����DPF���u�ɂ����鋭���Đ��� �p�x������
���R����̖h�~�A�A SCR�G�}�ɂ�����ቷ�����̌���A�B SCR�G�}�̑ϋv���̌���kSCR�G�}��HC��ł�
�Đ����u�H�l�A�C �d�ʎԃ��[�h�R��̉��P�j�́A�����_�i��2014�N12�����݁j�ł́A������������邽�߂̗L���ȋZ
�p���s���̏̂悤�ł���B
�@���̂Ȃ�A�w�ҁE���Ƃ��������ʏ�̋Z�p�_����Z�p���̋L���ł���A�{���A�u���p�Ԃ̃N���[�����Z�p�v
��u�����J���̓����v�Ƃ̕\����f�����ꍇ�ɂ́A��L�@�`�C�̑�^�g���b�N�̉������ׂ��ۑ�������ŁA����
��@�`�C�̉ۑ�̉����ɗL���ƌ����܂�����̋Z�p����������A���L����锤�ł���B�������Ȃ���A����c��
�w�E���������A�����UD�g���b�N�X���̏��ѐM�T ���ƎO��@���G�@���́A�u���p�Ԃ̃N���[�����Z�p�v��u�����J����
�����v�Ƃ̕\��̍��ɁA��^�g���b�N�̉������ׂ��ۑ肾���������āA��^�g���b�N�̏�L�@�`�C�̉ۑ�������ł���
�Z�p�ɂ��ẮA����E��Ă�������Ă��Ȃ��̂ł���B����́A�Z�p�_����Z�p���Ƃ��Ă͌��ׂ����邱��
���N�̖ڂɂ����炩�Ȃ��Ƃł���B
��u�����J���̓����v�Ƃ̕\����f�����ꍇ�ɂ́A��L�@�`�C�̑�^�g���b�N�̉������ׂ��ۑ�������ŁA����
��@�`�C�̉ۑ�̉����ɗL���ƌ����܂�����̋Z�p����������A���L����锤�ł���B�������Ȃ���A����c��
�w�E���������A�����UD�g���b�N�X���̏��ѐM�T ���ƎO��@���G�@���́A�u���p�Ԃ̃N���[�����Z�p�v��u�����J����
�����v�Ƃ̕\��̍��ɁA��^�g���b�N�̉������ׂ��ۑ肾���������āA��^�g���b�N�̏�L�@�`�C�̉ۑ�������ł���
�Z�p�ɂ��ẮA����E��Ă�������Ă��Ȃ��̂ł���B����́A�Z�p�_����Z�p���Ƃ��Ă͌��ׂ����邱��
���N�̖ڂɂ����炩�Ȃ��Ƃł���B
�@��ʓI�ɉ]���A�Z�p����ΊO�I�ɔ��M�����ꂽ�����Ȋw�҂�g���b�N���[�J�̐��Ƃ�����Ė��ӎ��Ɍ��ט_
���⌇�L���\���邱�Ƃ́A���Ɉ���L�蓾�Ȃ����Ƃł���B���������āA�u���p�Ԃ̃N���[�����Z�p�v��u����
�J���̓����v�Ƃ̕\����f���Ȃ���A���̓��e�Ƃ��ď�L�̇@�`�C�́u�i�قɉ������ׂ���^�g���b�N�̉ۑ�v������
���L���A�{���A�L�ڂ��K�{�̉ۑ����������Z�p��S���L�ڂ��Ă��Ȃ��̂́A�����_�ɂ����āA����c��w�E������
���A�����UD�g���b�N�X���̏��ѐM�T ���ƎO��@���G�@������^�g���b�N�̉ۑ�������ł���Z�p���������ۗL����
���Ȃ����Ƃ������Ɛ��������B
���⌇�L���\���邱�Ƃ́A���Ɉ���L�蓾�Ȃ����Ƃł���B���������āA�u���p�Ԃ̃N���[�����Z�p�v��u����
�J���̓����v�Ƃ̕\����f���Ȃ���A���̓��e�Ƃ��ď�L�̇@�`�C�́u�i�قɉ������ׂ���^�g���b�N�̉ۑ�v������
���L���A�{���A�L�ڂ��K�{�̉ۑ����������Z�p��S���L�ڂ��Ă��Ȃ��̂́A�����_�ɂ����āA����c��w�E������
���A�����UD�g���b�N�X���̏��ѐM�T ���ƎO��@���G�@������^�g���b�N�̉ۑ�������ł���Z�p���������ۗL����
���Ȃ����Ƃ������Ɛ��������B
�@�����Ƃ��A����c��w�E���������A�����UD�g���b�N�X���̏��ѐM�T ���ƎO��@���G�@����2012�N3����
JAMAGAZINE�́u���p�Ԃ̃N���[�����Z�p�v�i���{�����ԍH�Ɖ�̃z�[���y�[�W�j��A�����ԋZ�p����2010�N��2014
�N��8�����̔N�ӂɋZ�p�_����Z�p���̋L�����Ȃ���A�@�`�C�̑�^�g���b�N�̉ۑ�������ł���Z�p��
��������ۗL���Ă��Ȃ����Ƃ��I�����邱�Ƃ����������̂ł���B���̂��Ƃ́A����c��w�E���������A�����UD�g���b
�N�X���̏��ѐM�T ���ƎO��@���G�@�������ʂ̎����JAMAGAZINE�⎩���ԋZ�p���̎��M��S������H�ڂɂȂ�
�Ă��܂������Ƃɂ���Ĉ����N�����ꂽ���ʂƍl������B���ꂪ�����ł���A���Ƃ��A���D���Ȃ��Ƃł���B
JAMAGAZINE�́u���p�Ԃ̃N���[�����Z�p�v�i���{�����ԍH�Ɖ�̃z�[���y�[�W�j��A�����ԋZ�p����2010�N��2014
�N��8�����̔N�ӂɋZ�p�_����Z�p���̋L�����Ȃ���A�@�`�C�̑�^�g���b�N�̉ۑ�������ł���Z�p��
��������ۗL���Ă��Ȃ����Ƃ��I�����邱�Ƃ����������̂ł���B���̂��Ƃ́A����c��w�E���������A�����UD�g���b
�N�X���̏��ѐM�T ���ƎO��@���G�@�������ʂ̎����JAMAGAZINE�⎩���ԋZ�p���̎��M��S������H�ڂɂȂ�
�Ă��܂������Ƃɂ���Ĉ����N�����ꂽ���ʂƍl������B���ꂪ�����ł���A���Ƃ��A���D���Ȃ��Ƃł���B
�R�|�Q�D�������R�c��E��C������E�����Ԕr�o�K�X���ψ��ψ���̊w�ҁE���Ǝ҂̏ꍇ
�@�Ƃ���ŁA�C���x�~�G���W���ɂ���^�g���b�N�̒�R���15���ɏڏq�����Ă���悤�ɁA2010�N�V��28�����\��
�������R�c��E��C������́u����̎����Ԕr�o�K�X�ጸ��̂�����ɂ��āi��\�����\�j�v�ihttp://www.
env.go.jp/press/file_view.php?serial=16034&hou_id=12768�j�ł́A�����_�i��2014�N12���j�̎s�̑�^�g���b�N�ɂ�����
�R��i�����s�R��E�d�ʎԃ��[�h�R��j�̉��P�i���u�R��̐L�т�����m�ہv�Ƃ̕\���j�ɗL���Ɣ��f�����Z�p�Ƃ�
�āA�ȉ���(a)�`(d)�̋Z�p���ڂ�����Ă���B
�������R�c��E��C������́u����̎����Ԕr�o�K�X�ጸ��̂�����ɂ��āi��\�����\�j�v�ihttp://www.
env.go.jp/press/file_view.php?serial=16034&hou_id=12768�j�ł́A�����_�i��2014�N12���j�̎s�̑�^�g���b�N�ɂ�����
�R��i�����s�R��E�d�ʎԃ��[�h�R��j�̉��P�i���u�R��̐L�т�����m�ہv�Ƃ̕\���j�ɗL���Ɣ��f�����Z�p�Ƃ�
�āA�ȉ���(a)�`(d)�̋Z�p���ڂ�����Ă���B
�@�@(��)�@2�i�ߋ��A2�i�ߋ������ɂ��G���W���_�E���T�C�W���O
�@�@(��)�@EGR���̌���AEGR����̍��x���A�ꕔ�Ԏ�ւ�LP-EGR�̗̍p
�@�@(��)�@�R�����ˈ��͂̌���APCI�R�Ăł͈̔͊g�哙�̔R�����ː���̍��x��
�@�@(��)�@�ꕔ�Ԏ�ւ̃^�[�{�R���p�E���h�V�X�e���̗̍p
�Ȃ��A����璆�����R�c��E��C������́u����̎����Ԕr�o�K�X�ጸ��̂�����ɂ��āi��\�����\�j�v��
�L�ڂ�(a)�`(d)�̔R����P�Ɋւ���Z�p���ڂ̋L�ڏ؋��́A�ȉ��̕\�S�Ɏ������ʂ�ł���B
�L�ڂ�(a)�`(d)�̔R����P�Ɋւ���Z�p���ڂ̋L�ڏ؋��́A�ȉ��̕\�S�Ɏ������ʂ�ł���B
| |
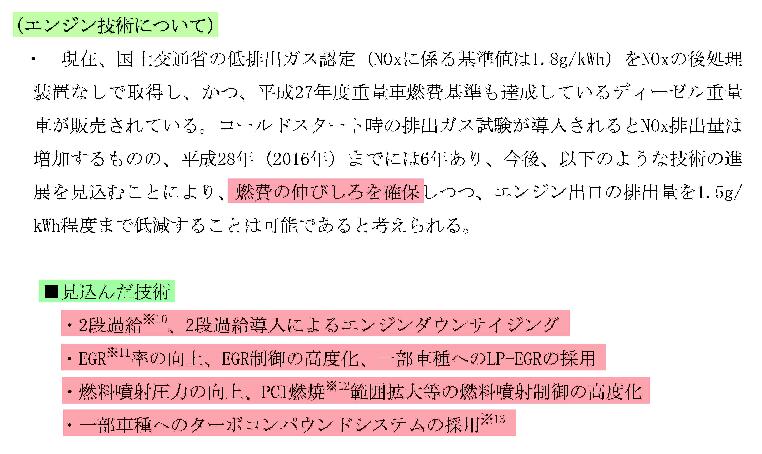 |
�@����2010�N�V��28�����\�̒������R�c��E��C������́u����̎����Ԕr�o�K�X�ጸ��̂�����ɂ���
�i��\�����\�j�v�ɗ��ꂽ�d�ʎԁi����^�g���b�N���j�p�f�B�[�[���G���W���̔R������_����(��)�`(��)�̋Z�p
�́A�ȉ��̕\�T�Ɏ������ʂ�A����̋Z�p�������_�i��2014�N12���j�̎s�̂̑�^�g���b�N�ɂ�����R��i�����s�R��E
�d�ʎԃ��[�h�R��j�̉��P���y���i���O�`�P�����x�j�ȔR����P�̋@�\�E���\�̗��u����Z�p�v�E�u�K���N�^�Z�p�v��
���f�����B���������B
�i��\�����\�j�v�ɗ��ꂽ�d�ʎԁi����^�g���b�N���j�p�f�B�[�[���G���W���̔R������_����(��)�`(��)�̋Z�p
�́A�ȉ��̕\�T�Ɏ������ʂ�A����̋Z�p�������_�i��2014�N12���j�̎s�̂̑�^�g���b�N�ɂ�����R��i�����s�R��E
�d�ʎԃ��[�h�R��j�̉��P���y���i���O�`�P�����x�j�ȔR����P�̋@�\�E���\�̗��u����Z�p�v�E�u�K���N�^�Z�p�v��
���f�����B���������B
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
�@���̂��߁A�����_�i��2014�N12���j�ł́A��L�̇@�`�C�́u�i�قɉ������ׂ���^�g���b�N�̉ۑ�v���������A�C���x
�~�G���W���ɂ���^�g���b�N�̒�R����C���x�~�́A�f�B�[�[���̂m�n���팸�ƔR�����̈ꋓ�����̋Z�p���I
�ɏڏq���Ă���悤����^�g���b�N�ɂ����鍡����u2015�N�x�d�ʎԔR������{10�����x�̔R�����v��
�u�m�n����0.23�@g/kWh ��NO���K���v�̃��x���i���K���l�j�̋K�������ɓK�������^�g���b�N���߂������Ɏ�
�����邽�߂̋Z�p�Ƃ��ẮA2010�N�V��28�����\�̒������R�c��̑�\�����\�ɗ��ꂽ(��)�`(��)�̔R
����P�̋Z�p�́A���炩�Ɏ��i�ł����ƍl������B�܂�A��\�����\�ɗ�(��)�`(��)�̔R����P�̋Z�p�́A
�������^�g���b�N�̏d�ʎԃ��[�h�R��̉��P���P���ȉ��̔����ɗ��܂邽�߁A����̑�^�g���b�N���u2015�N�x�d��
�ԔR������{10�����x�̔R�����v�Ɓu�m�n����0.23�@g/kWh ��NO���K���v�̃��x���i���K���l�j�̋K�������ɑ�^
�g���b�N��K��������@�\�E���\�����������ƍl������B���̂��߁A��\�����\�ɗ�(��)�`(��)�̔R����P�̋Z
�p�́A���炩���u����Z�p�v�E�u�K���N�^�Z�p�v�ƕ��ނ���đR��ׂ��ƍl������B
�~�G���W���ɂ���^�g���b�N�̒�R����C���x�~�́A�f�B�[�[���̂m�n���팸�ƔR�����̈ꋓ�����̋Z�p���I
�ɏڏq���Ă���悤����^�g���b�N�ɂ����鍡����u2015�N�x�d�ʎԔR������{10�����x�̔R�����v��
�u�m�n����0.23�@g/kWh ��NO���K���v�̃��x���i���K���l�j�̋K�������ɓK�������^�g���b�N���߂������Ɏ�
�����邽�߂̋Z�p�Ƃ��ẮA2010�N�V��28�����\�̒������R�c��̑�\�����\�ɗ��ꂽ(��)�`(��)�̔R
����P�̋Z�p�́A���炩�Ɏ��i�ł����ƍl������B�܂�A��\�����\�ɗ�(��)�`(��)�̔R����P�̋Z�p�́A
�������^�g���b�N�̏d�ʎԃ��[�h�R��̉��P���P���ȉ��̔����ɗ��܂邽�߁A����̑�^�g���b�N���u2015�N�x�d��
�ԔR������{10�����x�̔R�����v�Ɓu�m�n����0.23�@g/kWh ��NO���K���v�̃��x���i���K���l�j�̋K�������ɑ�^
�g���b�N��K��������@�\�E���\�����������ƍl������B���̂��߁A��\�����\�ɗ�(��)�`(��)�̔R����P�̋Z
�p�́A���炩���u����Z�p�v�E�u�K���N�^�Z�p�v�ƕ��ނ���đR��ׂ��ƍl������B
�@���̂悤�ɁA2010�N�V�����\�̒������R�c��E��C������̑�\�����\�ɂ́A�d�ʎԃ��[�h�R��̉��P
�i���R��̐L�т�����m�ہj�̂��߂̐V�Z�p�Ƃ��ė��ꂽ�S��ނ̐V�Z�p���d�ʎԃ��[�h�R��̉��P��
�P���ȉ��̌y���Ɏ~�܂�R����P�́u����Z�p�v�E�u�K���N�^�Z�p�v�ł��邱�Ƃ��琄������ƁA���̑�\�����\
���쐬���ꂽ�����̒������R�c��E��C������E�����Ԕr�o�K�X���ψ��ψ���̃G���W���W�̊w
�ҁE���Ƃ́A��^�g���b�N�̔R����P�̉ۑ�������ł���Z�p���������ۗL���Ă��Ȃ��ƌ��ĊԈႢ����
�����̂Ɛ��������B
�i���R��̐L�т�����m�ہj�̂��߂̐V�Z�p�Ƃ��ė��ꂽ�S��ނ̐V�Z�p���d�ʎԃ��[�h�R��̉��P��
�P���ȉ��̌y���Ɏ~�܂�R����P�́u����Z�p�v�E�u�K���N�^�Z�p�v�ł��邱�Ƃ��琄������ƁA���̑�\�����\
���쐬���ꂽ�����̒������R�c��E��C������E�����Ԕr�o�K�X���ψ��ψ���̃G���W���W�̊w
�ҁE���Ƃ́A��^�g���b�N�̔R����P�̉ۑ�������ł���Z�p���������ۗL���Ă��Ȃ��ƌ��ĊԈႢ����
�����̂Ɛ��������B
�@�ȏ�̂��Ƃ���A2010 �N�����̒������R�c��E��C������E�����Ԕr�o�K�X���ψ��ψ���̃G���W���W
�̊w�ҁE���Ɓi���͖쓹�������A���ѓc�P�������A�㓡�V��E�Y�����V�R�������ԋZ�p�����Z���^�[�������H��
�G�����A���R���EJARI�v���W�F�N�g�J������ǁA�吹�G�����j�́A��^�g���b�N�̔R����P�̉ۑ�������ł���Z�p
���������ۗL���Ă��Ȃ������Ɛ��������B���̌�A�S�N�ȏ���o�߂������݁i��2014�N12�����_�j�ł��A�����ԋZ
�p�����{�@�B�w��̍u����ɂ����ẮA�������R�c��̑�\�����\�i��2010�N�V�����\�j�ihttp://www.env.
go.jp/press/file_view.php?serial=16034&hou_id=12768�j�ɗ��ꂽ��^�g���b�N�̔R����P��NO���팸���\�ɂ���
�@�\�E���\�̗��u����Z�p�v�E�u�K���N�^�Z�p�v�i��2�i�ߋ��A�G���W���_�E���T�C�W���O�AEGR����̍��x���ALP-EGR
�̗̍p�A�R�����ˈ��͂̌���APCI�R�āEHCCI�R�āA�^�[�{�R���p�E���h�V�X�e�����j�ɂ��Ă̑����̘_�����A����
�S�O�������A���݂ł���^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W���̏����Z�p�Ƃ֑̌�ȏC�����p���Ȃ���A���{�����ԋZ�p
�����{�@�B�w��̍u����Ő���ɔ��\����Ă���悤�ł���B
�̊w�ҁE���Ɓi���͖쓹�������A���ѓc�P�������A�㓡�V��E�Y�����V�R�������ԋZ�p�����Z���^�[�������H��
�G�����A���R���EJARI�v���W�F�N�g�J������ǁA�吹�G�����j�́A��^�g���b�N�̔R����P�̉ۑ�������ł���Z�p
���������ۗL���Ă��Ȃ������Ɛ��������B���̌�A�S�N�ȏ���o�߂������݁i��2014�N12�����_�j�ł��A�����ԋZ
�p�����{�@�B�w��̍u����ɂ����ẮA�������R�c��̑�\�����\�i��2010�N�V�����\�j�ihttp://www.env.
go.jp/press/file_view.php?serial=16034&hou_id=12768�j�ɗ��ꂽ��^�g���b�N�̔R����P��NO���팸���\�ɂ���
�@�\�E���\�̗��u����Z�p�v�E�u�K���N�^�Z�p�v�i��2�i�ߋ��A�G���W���_�E���T�C�W���O�AEGR����̍��x���ALP-EGR
�̗̍p�A�R�����ˈ��͂̌���APCI�R�āEHCCI�R�āA�^�[�{�R���p�E���h�V�X�e�����j�ɂ��Ă̑����̘_�����A����
�S�O�������A���݂ł���^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W���̏����Z�p�Ƃ֑̌�ȏC�����p���Ȃ���A���{�����ԋZ�p
�����{�@�B�w��̍u����Ő���ɔ��\����Ă���悤�ł���B
�@�ȏ�̏��ӂ݂�ƁA2010 �N�����̒������R�c��E��C������E�����Ԕr�o�K�X���ψ��ψ���̃G���W
���W�̊w�ҁE���Ɓi���͖쓹�������A���ѓc�P�������A�㓡�V��E�Y�����V�R�������ԋZ�p�����Z���^�[����
���H���G�����A���R���EJARI�v���W�F�N�g�J������ǁA�吹�G�����j�́A�N��l�Ƃ��āA��^�g���b�N�̋i�قɉ�����
�ׂ��@�|�X�g���ˎ���r�C�Ǔ��R�����ˎ��̃t�B���^�Đ��V�X�e�����̗p����DPF���u�ɂ����鋭���Đ��� �p�x��
���ɂ��R����̖h�~�A�ASCR�G�}�ɂ�����ቷ�����̌���A�BSCR�G�}�̑ϋv���̌���iSCR�G�}��HC���
�̍Đ����u�H�j�A�C�d�ʎԃ��[�h�R��̉��P���̇@�`�C�̉ۑ����������Z�p������ł��Ȃ��ߎS�Ȍ����J
���̏ɂ������Ɛ��������B
���W�̊w�ҁE���Ɓi���͖쓹�������A���ѓc�P�������A�㓡�V��E�Y�����V�R�������ԋZ�p�����Z���^�[����
���H���G�����A���R���EJARI�v���W�F�N�g�J������ǁA�吹�G�����j�́A�N��l�Ƃ��āA��^�g���b�N�̋i�قɉ�����
�ׂ��@�|�X�g���ˎ���r�C�Ǔ��R�����ˎ��̃t�B���^�Đ��V�X�e�����̗p����DPF���u�ɂ����鋭���Đ��� �p�x��
���ɂ��R����̖h�~�A�ASCR�G�}�ɂ�����ቷ�����̌���A�BSCR�G�}�̑ϋv���̌���iSCR�G�}��HC���
�̍Đ����u�H�j�A�C�d�ʎԃ��[�h�R��̉��P���̇@�`�C�̉ۑ����������Z�p������ł��Ȃ��ߎS�Ȍ����J
���̏ɂ������Ɛ��������B
�R�|�R�D�i�Ɓj�Y�ƋZ�p�����������́u�����㎩���ԃG���W���A�g�����́v�̊w�ҁE���Ǝ҂̏ꍇ
�@�ȉ��̕\�U�Ɏ������悤�ɁA�i�Ɓj�Y�ƋZ�p�����������́u�����㎩���ԃG���W���A�g�����́v�́A�u�����ԃ��[�J��
�e��R����V�K�r�o�K�X�K���A���E���ꎎ���T�C�N���Ή��ɍv�����A�G���W���V�X�e���Ƃ��ĔM����50�����B��
�傫�ȖڕW�Ƃ���v�Ƃ̗��h�ȖڕW���f���Ă���B�����āA���̖ڕW�B���̂��߂ɁA�u�w���Z�@�ɂ��R�������ڍ�
�́v�Ɓu������X�[�p�[�G�}�v�̂Q���ڂ̌������v�悳��Ă��邾���ł���B���̂��Ƃ���A�i�Ɓj�Y�����́u�����㎩��
�ԃG���W���A�g�����́v�̏��F�������A���H�����A���������A�㓡�V�ꎁ���܂ފw�ҁE���Ƃ́A�u�w���Z�@�ɂ��R
�������ڍ�́v�Ɓu������X�[�p�[�G�}�v�̂Q���ڂ̌��������������łɂ́A�G���W���́uNO���팸�v��u�d�ʎԃ��[
�h�R��̉��P�v���\�ƂȂ�A�G���W���V�X�e���Ƃ��ĔM����50���̃G���W������������Ƃ̋ɂ߂čr�����m�Ȏv�l�E
�����̐l�B�̂悤�ł���B
�e��R����V�K�r�o�K�X�K���A���E���ꎎ���T�C�N���Ή��ɍv�����A�G���W���V�X�e���Ƃ��ĔM����50�����B��
�傫�ȖڕW�Ƃ���v�Ƃ̗��h�ȖڕW���f���Ă���B�����āA���̖ڕW�B���̂��߂ɁA�u�w���Z�@�ɂ��R�������ڍ�
�́v�Ɓu������X�[�p�[�G�}�v�̂Q���ڂ̌������v�悳��Ă��邾���ł���B���̂��Ƃ���A�i�Ɓj�Y�����́u�����㎩��
�ԃG���W���A�g�����́v�̏��F�������A���H�����A���������A�㓡�V�ꎁ���܂ފw�ҁE���Ƃ́A�u�w���Z�@�ɂ��R
�������ڍ�́v�Ɓu������X�[�p�[�G�}�v�̂Q���ڂ̌��������������łɂ́A�G���W���́uNO���팸�v��u�d�ʎԃ��[
�h�R��̉��P�v���\�ƂȂ�A�G���W���V�X�e���Ƃ��ĔM����50���̃G���W������������Ƃ̋ɂ߂čr�����m�Ȏv�l�E
�����̐l�B�̂悤�ł���B
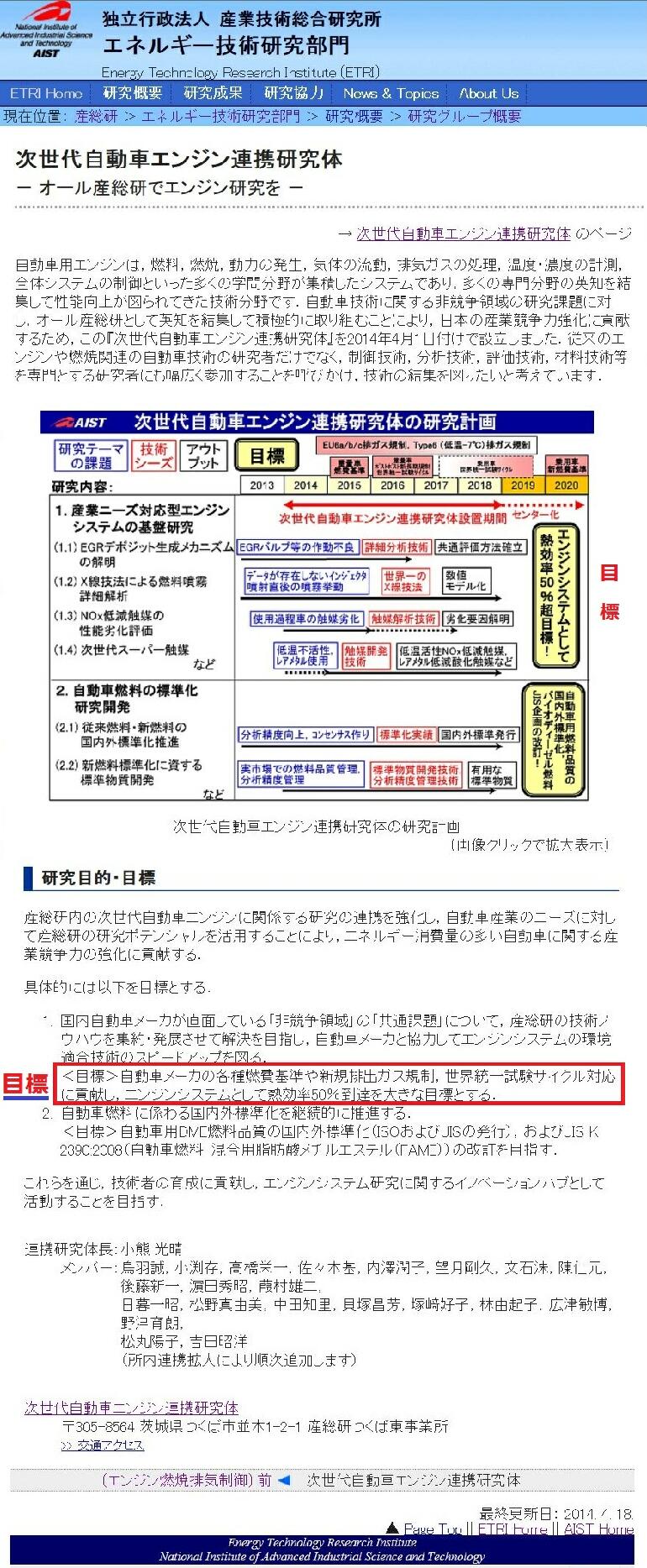 |
�@���̂悤�ɁA�i�Ɓj�Y�����́u�����㎩���ԃG���W���A�g�����́v�̏��F�������A���H�����A���������A�㓡�V�ꎁ
���܂ފw�ҁE���Ƃ́A�u�����ԃ��[�J�̊e��R����V�K�r�o�K�X�K���A���E���ꎎ���T�C�N���Ή��ɍv���v
��A�u�M����50���̃G���W���̎����v�̑s��ȖڕW���f���Ă���悤���B�������A���̌����v��ł́A�u�w���Z�@�ɂ��
�R�������ڍ�́v�Ɓu������X�[�p�[�G�}�v�̂Q��ނ����̒m�b�̖����e���ȋZ�p�̌������i�ɂ���āu�M����
50���̃G���W���̎����v�Ɖ]���f�B�[�[���G���W���ɂƂ��ċɂ߂č����ڕW��B������Ɛ錾���Ă���̂ł���B
���܂ފw�ҁE���Ƃ́A�u�����ԃ��[�J�̊e��R����V�K�r�o�K�X�K���A���E���ꎎ���T�C�N���Ή��ɍv���v
��A�u�M����50���̃G���W���̎����v�̑s��ȖڕW���f���Ă���悤���B�������A���̌����v��ł́A�u�w���Z�@�ɂ��
�R�������ڍ�́v�Ɓu������X�[�p�[�G�}�v�̂Q��ނ����̒m�b�̖����e���ȋZ�p�̌������i�ɂ���āu�M����
50���̃G���W���̎����v�Ɖ]���f�B�[�[���G���W���ɂƂ��ċɂ߂č����ڕW��B������Ɛ錾���Ă���̂ł���B
�@��L�̕\�U�Ɏ����������v�������ƁA�i�Ɓj�Y�����́u�����㎩���ԃG���W���A�g�����́v�̏��F�������A
���H�����A���������A�㓡�V�ꎁ���܂ފw�ҁE���Ƃ́A�O�q�̑�^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W���̇@�`�C
�̉ۑ���������đ�^�g���b�N�́uNO���팸�v��u�R����P�v���߂������Ɏ����ł�����p�I�ȋZ�p�������
���ł��Ȃ��ߎS�ȏɂ��邱�Ƃ�@���Ɏ������؋��ł����Ǝv�����A�@���Ȃ��̂ł��낤���B
���H�����A���������A�㓡�V�ꎁ���܂ފw�ҁE���Ƃ́A�O�q�̑�^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W���̇@�`�C
�̉ۑ���������đ�^�g���b�N�́uNO���팸�v��u�R����P�v���߂������Ɏ����ł�����p�I�ȋZ�p�������
���ł��Ȃ��ߎS�ȏɂ��邱�Ƃ�@���Ɏ������؋��ł����Ǝv�����A�@���Ȃ��̂ł��낤���B
�@���̂Ȃ�A���ɁA�ڕW�Ƃ���u�w���Z�@�ɂ��R�������ڍ�́v�ɐ��������Ƃ��Ă��A���̉�͌��ʂ�L�����p��
���R�ĉ��P�̎v�z�E�헪�E���z��������A�f�B�[�[���G���W���̇@�`�C�̉ۑ���������đ�^�g���b�N�́uNO���팸�v
��u�R����P�v���������邱�Ƃ��ł��Ȃ��̂ł���B�܂��A�u������X�[�p�[�G�}�v�̊J���́A�G���W���W�̊w�ҁE��
��Ƃ̎�̓I�Ȍ����Ɩ��ł͖����A�G�}����Ƃ���w�ҁE���Ƃ̎�v�Ȍ����Ɩ��ł���B���̂��߁A���́u����
��X�[�p�[�G�}�v�̊J���ł́A�G���W���W�̊w�ҁE���Ƃ͒P�Ȃ�⍲���ɉ߂��Ȃ��ƍl������B���������āA�u��
����X�[�p�[�G�}�v�̊J�����u�M����50���̃G���W���̎����v�̑s��ȖڕW�B���̏d�v�����Ƃ̈ʒu�Â��ł���A
�i�Ɓj�Y�����́u�����㎩���ԃG���W���A�g�����́v�w�ҁE���Ƃ́A���͖{��̌����v����쐬���Ă��邱�ƂɂȂ��
�]�������ł���B�܂�A���l�Ɋۓ����ł͂Ȃ����Ɖ]�����Ƃł���B
���R�ĉ��P�̎v�z�E�헪�E���z��������A�f�B�[�[���G���W���̇@�`�C�̉ۑ���������đ�^�g���b�N�́uNO���팸�v
��u�R����P�v���������邱�Ƃ��ł��Ȃ��̂ł���B�܂��A�u������X�[�p�[�G�}�v�̊J���́A�G���W���W�̊w�ҁE��
��Ƃ̎�̓I�Ȍ����Ɩ��ł͖����A�G�}����Ƃ���w�ҁE���Ƃ̎�v�Ȍ����Ɩ��ł���B���̂��߁A���́u����
��X�[�p�[�G�}�v�̊J���ł́A�G���W���W�̊w�ҁE���Ƃ͒P�Ȃ�⍲���ɉ߂��Ȃ��ƍl������B���������āA�u��
����X�[�p�[�G�}�v�̊J�����u�M����50���̃G���W���̎����v�̑s��ȖڕW�B���̏d�v�����Ƃ̈ʒu�Â��ł���A
�i�Ɓj�Y�����́u�����㎩���ԃG���W���A�g�����́v�w�ҁE���Ƃ́A���͖{��̌����v����쐬���Ă��邱�ƂɂȂ��
�]�������ł���B�܂�A���l�Ɋۓ����ł͂Ȃ����Ɖ]�����Ƃł���B
�@�Ƃ���ŁA���́u������X�[�p�[�G�}�v�̊J���𐬌�������ɂ́A�|���R�c���Z�p���̕M�҂ɂ̓m�[�x���܋��̑唭
�����K�v�ƍl�����邽�߁A�߂������Ɏ����ԗp�Ƃ��Ď��p�������\���͊F���Ǝv����̂ł���B�������A�i�Ɓj�Y
�����́u�����㎩���ԃG���W���A�g�����́v�̏��F�������A���H�����A���������A�㓡�V�ꎁ���܂ފw�ҁE����
�́A�u������X�[�p�[�G�}�v��������𓊓�����ΒN�ɂł��e�ՂɊJ������������Ƃ̌��ʂ��̂悤�ł���B���̂Ȃ�
�A�u������X�[�p�[�G�}�v���e�ՂɊJ���ł��Ȃ��Z�p�Ƃ̔��f�E�����ł���A�i�Ɓj�Y�����́u�����㎩���ԃG���W
���A�g�����́v���u�M����50���̃G���W���̎����v�̌����v��Ɂu������X�[�p�[�G�}�v���������ڂɋ����Ă��Ȃ���
�l�����邽�߂ł���B
�����K�v�ƍl�����邽�߁A�߂������Ɏ����ԗp�Ƃ��Ď��p�������\���͊F���Ǝv����̂ł���B�������A�i�Ɓj�Y
�����́u�����㎩���ԃG���W���A�g�����́v�̏��F�������A���H�����A���������A�㓡�V�ꎁ���܂ފw�ҁE����
�́A�u������X�[�p�[�G�}�v��������𓊓�����ΒN�ɂł��e�ՂɊJ������������Ƃ̌��ʂ��̂悤�ł���B���̂Ȃ�
�A�u������X�[�p�[�G�}�v���e�ՂɊJ���ł��Ȃ��Z�p�Ƃ̔��f�E�����ł���A�i�Ɓj�Y�����́u�����㎩���ԃG���W
���A�g�����́v���u�M����50���̃G���W���̎����v�̌����v��Ɂu������X�[�p�[�G�}�v���������ڂɋ����Ă��Ȃ���
�l�����邽�߂ł���B
�@�܂��A���̌����v��ł́A�u�M����50���̃G���W���̎����v�̖ڕW��B�����鎞�������L����Ă��Ȃ��悤���B����
���R�́A���ɁA�����̉��ꂩ�̎����ɁA�M����50���̃G���W���V�X�e���̖ڕW�������ł��Ă��Ȃ��Ƃ̔ᔻ����
�ہA�i�Ɓj�Y��������������ݒ肵�Ă�������J�̖ڕW�B���̎�����100�`200�N��ł������Ƃ̌�����������邽��
�̏��������m��Ȃ��B���̏ꍇ�ɂ́A�i�Ɓj�Y�����́u�����㎩���ԃG���W���A�g�����́v�̏��F�������A���H�����A
���������A�㓡�V�ꎁ���܂ފw�ҁE���Ƃ́A�u�����ԃ��[�J�̊e��R����V�K�r�o�K�X�K���A���E���ꎎ��
�T�C�N���Ή��ɍv���v��A�u�M����50���̃G���W���̎����v�̖ڕW��B�����邱�Ƃɂ��ẮA���̈Ӑ}�E�ӌ����ŏ�
����S�����������ƍl������B���ꂪ�������ۂ��̐^���́A�����҂݂̂��m���Ă��邱�Ƃ��B
���R�́A���ɁA�����̉��ꂩ�̎����ɁA�M����50���̃G���W���V�X�e���̖ڕW�������ł��Ă��Ȃ��Ƃ̔ᔻ����
�ہA�i�Ɓj�Y��������������ݒ肵�Ă�������J�̖ڕW�B���̎�����100�`200�N��ł������Ƃ̌�����������邽��
�̏��������m��Ȃ��B���̏ꍇ�ɂ́A�i�Ɓj�Y�����́u�����㎩���ԃG���W���A�g�����́v�̏��F�������A���H�����A
���������A�㓡�V�ꎁ���܂ފw�ҁE���Ƃ́A�u�����ԃ��[�J�̊e��R����V�K�r�o�K�X�K���A���E���ꎎ��
�T�C�N���Ή��ɍv���v��A�u�M����50���̃G���W���̎����v�̖ڕW��B�����邱�Ƃɂ��ẮA���̈Ӑ}�E�ӌ����ŏ�
����S�����������ƍl������B���ꂪ�������ۂ��̐^���́A�����҂݂̂��m���Ă��邱�Ƃ��B
�@���͂Ƃ�����A��L�̕\�U�Ɏ������i�Ɓj�Y�����́u�����㎩���ԃG���W���A�g�����́v�̔M����50���̃G���W���V�X
�e�����������錤���v��́A������n���ɂ������e�ł��邱�Ƃ����炩�ł���B���̂��߁A���́i�Ɓj�Y�����́u����
�㎩���ԃG���W���A�g�����́v�̌����v��́A�P�ɗ\�Z���l�����邽�߂̍��\�I�Ȍv��̂悤�Ɍ��邱�Ƃ��\�Ȃ�
���Ɏv�����A�@���Ȃ��̂ł��낤���B
�e�����������錤���v��́A������n���ɂ������e�ł��邱�Ƃ����炩�ł���B���̂��߁A���́i�Ɓj�Y�����́u����
�㎩���ԃG���W���A�g�����́v�̌����v��́A�P�ɗ\�Z���l�����邽�߂̍��\�I�Ȍv��̂悤�Ɍ��邱�Ƃ��\�Ȃ�
���Ɏv�����A�@���Ȃ��̂ł��낤���B
�@�܂��A�i�Ɓj�Y�����́u�����㎩���ԃG���W���A�g�����́v�̏��F�������A���H�����A���������A�㓡�V�ꎁ���܂�
�w�ҁE���Ƃ́A�u�����ԗp�c�l�d�R���i���̍����O�W�����v�̋Ɩ��𐄐i����Ƃ̂��Ƃł���B�������A�y�������G
�l���M�[�������R�O�������c�l�d�𐄏�����@�B�w��̋^�����o�C�I�}�X�R����DME�ɂ�鎩���Ԃ̒�Y�f�E�E��
���́A�s�\���I�ɏڏq���Ă���悤�ɁA�c�l�d�͎����ԗp�R���Ƃ��ẮA���הR���ł���B���̂��߂ɁA���{�ł͏�
���ɂ����Ă��A�c�l�d�������ԗp�R���Ƃ��ĕ��y����\�����F���ƍl������B����Ƃ����{�̎����ԗp�R���ɗp
�����Ȃ��c�l�d�ɂ��āA�u�����ԗp�c�l�d�R���i���̍����O�W�����v�́A���{�̍����ɂƂ��đS�����ʂȋƖ��ƍl��
����B�Ȃ��A�ŋ߂̓��{�����ԋZ�p�����{�@�B�w��̍u����ɂ����ẮA���{�l�͂c�l�d�G���W����c�l�d����
�Ԃ̘_���́A�w�ǔ��\����Ă��Ȃ��ł���B���̂��Ƃ́A�ŋ߂̓��{�ł͂c�l�d�����Ԃ͎��p���̖������Ƃ���
������Ă������߂ƍl������B���̂��߂ɁA�c�l�d�G���W����c�l�d�����Ԃ̌����J���̂����~�ƂȂ������̂Ɛ�����
���B���̂悤�ȏɂ���ɂ�������炸�A�i�Ɓj�Y�����́u�����㎩���ԃG���W���A�g�����́v�̏��F�������A��
�H�����A���������A�㓡�V�ꎁ���܂ފw�ҁE���Ƃ��]���̕��j��ς��邱�ƂȂ��A��ȂɁu�����ԗp�c�l�d�R���i��
�̍����O�W�����v�̋Ɩ��𐄐i���邱�Ƃ́A�ꌾ�Ō����A�u���̍����v�Ɖ]�����Ƃł͂Ȃ����낤���B
�w�ҁE���Ƃ́A�u�����ԗp�c�l�d�R���i���̍����O�W�����v�̋Ɩ��𐄐i����Ƃ̂��Ƃł���B�������A�y�������G
�l���M�[�������R�O�������c�l�d�𐄏�����@�B�w��̋^�����o�C�I�}�X�R����DME�ɂ�鎩���Ԃ̒�Y�f�E�E��
���́A�s�\���I�ɏڏq���Ă���悤�ɁA�c�l�d�͎����ԗp�R���Ƃ��ẮA���הR���ł���B���̂��߂ɁA���{�ł͏�
���ɂ����Ă��A�c�l�d�������ԗp�R���Ƃ��ĕ��y����\�����F���ƍl������B����Ƃ����{�̎����ԗp�R���ɗp
�����Ȃ��c�l�d�ɂ��āA�u�����ԗp�c�l�d�R���i���̍����O�W�����v�́A���{�̍����ɂƂ��đS�����ʂȋƖ��ƍl��
����B�Ȃ��A�ŋ߂̓��{�����ԋZ�p�����{�@�B�w��̍u����ɂ����ẮA���{�l�͂c�l�d�G���W����c�l�d����
�Ԃ̘_���́A�w�ǔ��\����Ă��Ȃ��ł���B���̂��Ƃ́A�ŋ߂̓��{�ł͂c�l�d�����Ԃ͎��p���̖������Ƃ���
������Ă������߂ƍl������B���̂��߂ɁA�c�l�d�G���W����c�l�d�����Ԃ̌����J���̂����~�ƂȂ������̂Ɛ�����
���B���̂悤�ȏɂ���ɂ�������炸�A�i�Ɓj�Y�����́u�����㎩���ԃG���W���A�g�����́v�̏��F�������A��
�H�����A���������A�㓡�V�ꎁ���܂ފw�ҁE���Ƃ��]���̕��j��ς��邱�ƂȂ��A��ȂɁu�����ԗp�c�l�d�R���i��
�̍����O�W�����v�̋Ɩ��𐄐i���邱�Ƃ́A�ꌾ�Ō����A�u���̍����v�Ɖ]�����Ƃł͂Ȃ����낤���B
�@�ȏ�̏���A�i�Ɓj�Y�����́u�����㎩���ԃG���W���A�g�����́v�̏��F�������A���H�����A���������A�㓡�V
�ꎁ���܂ފw�ҁE���Ƃ́A���Ɨ\�Z���g���č����̐����ɖ𗧂��Ȃ��Ɩ��𐋍s���邱�Ƃɉ��̍߈����������Ȃ�
�l�B�̂悤�Ɏv����̂́A�M�҂����̕Ό��ł��낤���B����́A�M�҂̌l�I�Ȉӌ��ł��邪�A��v�����@�́A�Ɓj�Y
�����́u�����㎩���ԃG���W���A�g�����́v�ɂ����鐭�{�\�Z�������̂��߂Ɏg���Ă��邩�ۂ��ɂ��āA�\��
�ɐ������ė~�������̂ł���B
�ꎁ���܂ފw�ҁE���Ƃ́A���Ɨ\�Z���g���č����̐����ɖ𗧂��Ȃ��Ɩ��𐋍s���邱�Ƃɉ��̍߈����������Ȃ�
�l�B�̂悤�Ɏv����̂́A�M�҂����̕Ό��ł��낤���B����́A�M�҂̌l�I�Ȉӌ��ł��邪�A��v�����@�́A�Ɓj�Y
�����́u�����㎩���ԃG���W���A�g�����́v�ɂ����鐭�{�\�Z�������̂��߂Ɏg���Ă��邩�ۂ��ɂ��āA�\��
�ɐ������ė~�������̂ł���B
�R�|�S�D��^�g���b�N�̉ۑ����������V�Z�p�������E��Ăł��Ȃ����{�̊w�ҁE���Ƃ̌���
�@�ȏ�̂��Ƃ���A���{�̃G���W���W�̊w�ҁE���Ƃ́A��^�g���b�N�ɂ�����u2015�N�x�d�ʎԔR������{
10�����x�̔R�����v�Ɓu�m�n����0.23�@g/kWh ��NO���K���v�̋K�����������{�\�ɂ��邽�߂ɂ́A�O�q�̑�^�g���b
�N�ɂ�����@�`�C�̉ۑ���i�قɉ����ׂ��ł��邱�Ƃ��A���ɏ\�ɗ����E�F�����Ă���悤�ł���B�������A���{��
�G���W���W�̊w�ҁE���Ƃ��E��Ă���̐S�v�̑�^�g���b�N�ł�NO���팸��R����P�̋K�������ɓK������
�邽�߂̎�i�E���@�́A�C���x�~�G���W���ɂ���^�g���b�N�̒�R����ڏq���Ă���悤�ɁA�������R�c��̑�
�\�����\�i��2010�N�V�����\�j�ihttp://www.env.go.jp/press/file_view.php?serial=16034&hou_id=12768�j�Ɂu�R��̐L��
������m�ہv�ƋL�ڂ���Ă���O�q��(��)�`(��)�́u����Z�p�v�E�u�K���N�^�Z�p�v�����̎�C�̕t�����ÐF���R����Z�p��
����ł���B����璆�R�̑�\�����\��(��)�`(��)�̔R����P�́u����Z�p�v�E�u�K���N�^�Z�p�v�̒��g�́A�Ⴆ�A20
�N���x���ȑO���碗��z�̔R�ċZ�p�v�Ƒ�����ĔL���ێq�������J���Ɏ���o�������A�����Ɏ��p���ł��Ă��Ȃ��o�b�h
�R�āi���g�b�b�h�R��)�̂悤�ȋZ�p��A�u����̍��x���v�̂悤�ȓK���ȏC���ꂾ���̋Z�p���u�V�Z�p�I�v�Ƃ��Ė��L����
�Ă���̂ł���B���̂悤�ȁu����Z�p�v�E�u�K���N�^�Z�p�v�����p���ł����Ƃ��Ă��A�����́u2015�N�x�d�ʎԔR��
����{10�����x�̔R�����v�Ɓu�m�n����0.23�@g/kWh ��NO���K���v�̃��x���i���K���l�j�̋K�������ɑ�^�g���b�N��K
�������邱�Ƃ�����Ȃ��Ƃ́A�f�B�[�[���G���W���W�҂ł���A�N�ł��e�Ղɗ����ł��邱�Ƃł���B
10�����x�̔R�����v�Ɓu�m�n����0.23�@g/kWh ��NO���K���v�̋K�����������{�\�ɂ��邽�߂ɂ́A�O�q�̑�^�g���b
�N�ɂ�����@�`�C�̉ۑ���i�قɉ����ׂ��ł��邱�Ƃ��A���ɏ\�ɗ����E�F�����Ă���悤�ł���B�������A���{��
�G���W���W�̊w�ҁE���Ƃ��E��Ă���̐S�v�̑�^�g���b�N�ł�NO���팸��R����P�̋K�������ɓK������
�邽�߂̎�i�E���@�́A�C���x�~�G���W���ɂ���^�g���b�N�̒�R����ڏq���Ă���悤�ɁA�������R�c��̑�
�\�����\�i��2010�N�V�����\�j�ihttp://www.env.go.jp/press/file_view.php?serial=16034&hou_id=12768�j�Ɂu�R��̐L��
������m�ہv�ƋL�ڂ���Ă���O�q��(��)�`(��)�́u����Z�p�v�E�u�K���N�^�Z�p�v�����̎�C�̕t�����ÐF���R����Z�p��
����ł���B����璆�R�̑�\�����\��(��)�`(��)�̔R����P�́u����Z�p�v�E�u�K���N�^�Z�p�v�̒��g�́A�Ⴆ�A20
�N���x���ȑO���碗��z�̔R�ċZ�p�v�Ƒ�����ĔL���ێq�������J���Ɏ���o�������A�����Ɏ��p���ł��Ă��Ȃ��o�b�h
�R�āi���g�b�b�h�R��)�̂悤�ȋZ�p��A�u����̍��x���v�̂悤�ȓK���ȏC���ꂾ���̋Z�p���u�V�Z�p�I�v�Ƃ��Ė��L����
�Ă���̂ł���B���̂悤�ȁu����Z�p�v�E�u�K���N�^�Z�p�v�����p���ł����Ƃ��Ă��A�����́u2015�N�x�d�ʎԔR��
����{10�����x�̔R�����v�Ɓu�m�n����0.23�@g/kWh ��NO���K���v�̃��x���i���K���l�j�̋K�������ɑ�^�g���b�N��K
�������邱�Ƃ�����Ȃ��Ƃ́A�f�B�[�[���G���W���W�҂ł���A�N�ł��e�Ղɗ����ł��邱�Ƃł���B
�@����ɂ�������炸�A���{�̃f�B�[�[���G���W���W�̊w�ҁE���Ƃ́A���R�̑�\�����\��(��)�`(��)�̔R���
�P�́u����Z�p�v�E�u�K���N�^�Z�p�v�̌����J���𐄐i���邱�Ƃɂ��A�����́u2015�N�x�d�ʎԔR������{10����
�x�̔R�����v�Ɓu�m�n����0.23�@g/kWh ��NO���K���v�̃��x���i���K���l�j�̋K�������ɑ�^�g���b�N��K�������邱��
���\�Ƃ��鋕�U�̋Z�p�\�����A���݂����X�Ɣ��\��������Ă���悤���B����́A���{�̃f�B�[�[���G���W���W��
�w�ҁE���Ƃ��Ӑ}�I���āu�R�v�E�u�U��v�E�u���v�̋Z�p�\���̔��\���s���Ă���ƍl������B
�P�́u����Z�p�v�E�u�K���N�^�Z�p�v�̌����J���𐄐i���邱�Ƃɂ��A�����́u2015�N�x�d�ʎԔR������{10����
�x�̔R�����v�Ɓu�m�n����0.23�@g/kWh ��NO���K���v�̃��x���i���K���l�j�̋K�������ɑ�^�g���b�N��K�������邱��
���\�Ƃ��鋕�U�̋Z�p�\�����A���݂����X�Ɣ��\��������Ă���悤���B����́A���{�̃f�B�[�[���G���W���W��
�w�ҁE���Ƃ��Ӑ}�I���āu�R�v�E�u�U��v�E�u���v�̋Z�p�\���̔��\���s���Ă���ƍl������B
�@�����Ƃ��A���{�̃f�B�[�[���G���W���W�̊w�ҁE���Ƃ��l�I�ɂ́A���̂悤�ȁu�R�v�E�u�U��v�E�u���v�̋Z�p�\��
�̔��\�́A���������ƍl���Ă��锤�ł���B�������A���ꂪ�ł��Ȃ��̂́A���{�̃G���W���W�̊w�ҁE���Ƃ́A��
���_�ł́A��^�g���b�N�̇@�`�C�̉ۑ�����ɗL���ȏ����Z�p�E�V�Z�p��{���ɉ����ۗL���Ă��Ȃ��̂���R���鎖
���ł��邱�Ƃ������Ɛ��������B���������āA���R�̑�\�����\��(��)�`(��)�̔R����P�́u����Z�p�v�E�u�K���N�^
�Z�p�v�̗̍p�ɂ���đ�^�g���b�N�́uNO���팸�v��u�R����P�v���\�Ǝ咣������{�̃G���W���W�̊w�ҁE����
�̏����́A���ꂪ�u�ȍs�ׁv�E�u�Y�I�Ȋ����v�E�u�s�^�ʖڂȐE���s�ׁv�ł��邱�Ƃ��\���Ɏ��o���Ă���ƍl��
����B�������A���̂��Ƃ𐳒��ɓf�I�E�����ł��Ȃ��̂́A���{�̃G���W���W�̊w�ҁE���Ƃ́A�u�����v���C�h�E��
���S�v��������ɁA�u�n�ʁE�g���̑r���v�Ɖ]���d��Ȗ��������N�������˂Ȃ��Ƃ̊뜜���Ă��邽�߂Ɛ��������B
�̔��\�́A���������ƍl���Ă��锤�ł���B�������A���ꂪ�ł��Ȃ��̂́A���{�̃G���W���W�̊w�ҁE���Ƃ́A��
���_�ł́A��^�g���b�N�̇@�`�C�̉ۑ�����ɗL���ȏ����Z�p�E�V�Z�p��{���ɉ����ۗL���Ă��Ȃ��̂���R���鎖
���ł��邱�Ƃ������Ɛ��������B���������āA���R�̑�\�����\��(��)�`(��)�̔R����P�́u����Z�p�v�E�u�K���N�^
�Z�p�v�̗̍p�ɂ���đ�^�g���b�N�́uNO���팸�v��u�R����P�v���\�Ǝ咣������{�̃G���W���W�̊w�ҁE����
�̏����́A���ꂪ�u�ȍs�ׁv�E�u�Y�I�Ȋ����v�E�u�s�^�ʖڂȐE���s�ׁv�ł��邱�Ƃ��\���Ɏ��o���Ă���ƍl��
����B�������A���̂��Ƃ𐳒��ɓf�I�E�����ł��Ȃ��̂́A���{�̃G���W���W�̊w�ҁE���Ƃ́A�u�����v���C�h�E��
���S�v��������ɁA�u�n�ʁE�g���̑r���v�Ɖ]���d��Ȗ��������N�������˂Ȃ��Ƃ̊뜜���Ă��邽�߂Ɛ��������B
�@�����ŁA���{�̃G���W���W�̊w�ҁE���Ƃ̐l�B�́A���]�̍�Ƃ��āA��^�g���b�N�́uNO���팸�v��u�R����P�v��
�L���ȋZ�p�J���Ɏ��s���Ă��錻���I�����Ȃ��悤�ɂ��邽�߂̊������A��v�c�����čs���Ă���ƍl������B��
�̂��߂̗L���Ȏ�i�E���@�́A �O�q�̒��R�̑�\�����\�ɂ�����(��)�`(��)�̔R����P�́u����Z�p�v�E�u�K���N�^�Z
�p�v�̗̍p�ɂ���đ�^�g���b�N�́uNO���팸�v��u�R����P�v���\�Ƃ�����疳�p�ȁu�R�v�E�u���v�̋Z�p�\���X
�Ǝ咣�������A���̎咣�𑼂̊w�ҁE���Ƃ���^����Ɖ]�����Ԍ���ɉ����邱�Ƃł���B
�L���ȋZ�p�J���Ɏ��s���Ă��錻���I�����Ȃ��悤�ɂ��邽�߂̊������A��v�c�����čs���Ă���ƍl������B��
�̂��߂̗L���Ȏ�i�E���@�́A �O�q�̒��R�̑�\�����\�ɂ�����(��)�`(��)�̔R����P�́u����Z�p�v�E�u�K���N�^�Z
�p�v�̗̍p�ɂ���đ�^�g���b�N�́uNO���팸�v��u�R����P�v���\�Ƃ�����疳�p�ȁu�R�v�E�u���v�̋Z�p�\���X
�Ǝ咣�������A���̎咣�𑼂̊w�ҁE���Ƃ���^����Ɖ]�����Ԍ���ɉ����邱�Ƃł���B
�@�����āA���̂悤�Ȓ��Ԍ��i���h�^�o�^�쌀�j�����{�����ԋZ�p�����{�@�B�w��ŔM�S�ɉ�����ꑱ�����Ƃ��Ă��A
�u2015�N�x�d�ʎԔR������{10�����x�̔R�����v�Ɓu�m�n����0.23�@g/kWh ��NO���K���v�̃��x���i���K���l�j��
�K�������ɓK�������^�g���b�N���߂������Ɏ����ł��Ȃ����Ƃ́A���R�̑�\�����\��(��)�`(��)�̔R����P��
�u����Z�p�v�E�u�K���N�^�Z�p�v�̓��e�������ł���������Ζ��炩�Ȃ��Ƃł���B
�u2015�N�x�d�ʎԔR������{10�����x�̔R�����v�Ɓu�m�n����0.23�@g/kWh ��NO���K���v�̃��x���i���K���l�j��
�K�������ɓK�������^�g���b�N���߂������Ɏ����ł��Ȃ����Ƃ́A���R�̑�\�����\��(��)�`(��)�̔R����P��
�u����Z�p�v�E�u�K���N�^�Z�p�v�̓��e�������ł���������Ζ��炩�Ȃ��Ƃł���B
�@���̂܂܂ł́A�O�q�̒��R�̑�\�����\�ɗ��ꂽ(��)�`(��)�̔R����P�́u����Z�p�v�E�u�K���N�^�Z�p�v�₻��
�ɗނ���Z�p�̗̍p�ɂ���đ�^�g���b�N�ł̏\���ȁuNO���팸�v��u�R����P�v���\�Ƃ�����{�̃f�B�[�[���G���W
���W�̊w�ҁE���Ƃ̈Ӑ}�I�ȁu�R�v�E�u�U��v�E�u���v�̋Z�p�\���̃h�^�o�^�쌀�́A���ꂩ������{�̃G���W���W
�̊w�ҁE���Ƃ����X�Ɖ�����������̂Ɛ��@�����B���̏ꍇ�A�M�҂́A���ꂩ��������ɂ킽��A���̏Ύ~�疜��
�h�^�o�^�쌀���ӏ܂����ĖႦ�邱�ƂɂȂ肻�����B����́A�|���R�c���Z�p���̂����₩�ȉɒׂ��̃l�^�ł��邽�߁A��
���Ɋ��ӂ��ׂ����Ƃ��ƌ��������ł���B�Ȃ��A�h�^�o�^�쌀�Ɖ]�����̂́A���҂��^�ʖڂɉ�����قǁA����Ƃ̂���
���B
�ɗނ���Z�p�̗̍p�ɂ���đ�^�g���b�N�ł̏\���ȁuNO���팸�v��u�R����P�v���\�Ƃ�����{�̃f�B�[�[���G���W
���W�̊w�ҁE���Ƃ̈Ӑ}�I�ȁu�R�v�E�u�U��v�E�u���v�̋Z�p�\���̃h�^�o�^�쌀�́A���ꂩ������{�̃G���W���W
�̊w�ҁE���Ƃ����X�Ɖ�����������̂Ɛ��@�����B���̏ꍇ�A�M�҂́A���ꂩ��������ɂ킽��A���̏Ύ~�疜��
�h�^�o�^�쌀���ӏ܂����ĖႦ�邱�ƂɂȂ肻�����B����́A�|���R�c���Z�p���̂����₩�ȉɒׂ��̃l�^�ł��邽�߁A��
���Ɋ��ӂ��ׂ����Ƃ��ƌ��������ł���B�Ȃ��A�h�^�o�^�쌀�Ɖ]�����̂́A���҂��^�ʖڂɉ�����قǁA����Ƃ̂���
���B
�S�D�G���W�����������ɔr�C�K�X���x�̍��������\�ɂ���Q�^�[�{���C���x�~�̋Z�p
�@�ȏ�̂悤�ɁA2010�N�`2014�N�ɂ����āAUD�g���b�N�X�� ���ѐM�T ���� �O�G ���́A��^�g���b�N�ɂ������u�@
DPF���u�̋����Đ��̕p�x�����v�A�u�A SCR�G�}�̒ቷ�����v�A�u�BSCR�G�}��HC��ł̉����v�̉ۑ���������邽
�߂��r�C�K�X���x�̍�������}��Z�p�J���̕K�v���ƁA�X�Ȃ�u�C �d�ʎԃ��[�h�R��̉��P�v�̕K�v�������������
����悤���BUD�g���b�N�X�� ���ѐM�T ���� �O�G ���̗����́A����c��w�E���������Ɠ��l�ɁA�u�@ DPF���u��
�����Đ��̕p�x�����v�A�u�A SCR�G�}�̒ቷ�����v�A�u�BSCR�G�}��HC��ł̉����v�A�u�C �d�ʎԃ��[�h�R��̉�
�P�v�v�̂S���ڂ̑�^�g���b�N�̌����J�����ׂ��ۑ肾������A�����̉ۑ������������̓I�ȋZ�p�I��������
���E�J������Ă��Ȃ��̂ł���B�܂�A�O�G ���̗����́A����c��w�E���������Ɠ��l�ɁA��^�g���b�N�́u��
NO�����v����сu��R��v�̎���������Ƃ̂ɂ́A���ړI�ɖ𗧂Z�p���������E��������Ă��Ȃ��̂ł�
��B���̂悤�ɁA�ŋ߁i��2010�N�`2014�N�j�ɂ����ẮA���{���\����G���W���W�̒����ȑ���c��w�E������
���A����уg���b�N���[�J�ł���UD�g���b�N�X���̏��ѐM�T ���� �O�G ���̐��Ƃ́A���{�����ԍH�Ɖ�̃z�[��
�y�[�W�������ԋZ�p���̔N�ӂł́A��^�g���b�N�́u��NO�����v����сu��R��v���������邽�߂́u�@ DPF���u��
�����Đ��̕p�x�����v�A�u�A SCR�G�}�̒ቷ�����v�A�u�BSCR�G�}��HC��ł̉����v�A����сu�C �d�ʎԃ��[�h�R��
�̉��P�v���ۑ肾����������A�ۑ�������ł����̓I�ȋZ�p�������L�ڂ���Ă��Ȃ��̂ł���B
DPF���u�̋����Đ��̕p�x�����v�A�u�A SCR�G�}�̒ቷ�����v�A�u�BSCR�G�}��HC��ł̉����v�̉ۑ���������邽
�߂��r�C�K�X���x�̍�������}��Z�p�J���̕K�v���ƁA�X�Ȃ�u�C �d�ʎԃ��[�h�R��̉��P�v�̕K�v�������������
����悤���BUD�g���b�N�X�� ���ѐM�T ���� �O�G ���̗����́A����c��w�E���������Ɠ��l�ɁA�u�@ DPF���u��
�����Đ��̕p�x�����v�A�u�A SCR�G�}�̒ቷ�����v�A�u�BSCR�G�}��HC��ł̉����v�A�u�C �d�ʎԃ��[�h�R��̉�
�P�v�v�̂S���ڂ̑�^�g���b�N�̌����J�����ׂ��ۑ肾������A�����̉ۑ������������̓I�ȋZ�p�I��������
���E�J������Ă��Ȃ��̂ł���B�܂�A�O�G ���̗����́A����c��w�E���������Ɠ��l�ɁA��^�g���b�N�́u��
NO�����v����сu��R��v�̎���������Ƃ̂ɂ́A���ړI�ɖ𗧂Z�p���������E��������Ă��Ȃ��̂ł�
��B���̂悤�ɁA�ŋ߁i��2010�N�`2014�N�j�ɂ����ẮA���{���\����G���W���W�̒����ȑ���c��w�E������
���A����уg���b�N���[�J�ł���UD�g���b�N�X���̏��ѐM�T ���� �O�G ���̐��Ƃ́A���{�����ԍH�Ɖ�̃z�[��
�y�[�W�������ԋZ�p���̔N�ӂł́A��^�g���b�N�́u��NO�����v����сu��R��v���������邽�߂́u�@ DPF���u��
�����Đ��̕p�x�����v�A�u�A SCR�G�}�̒ቷ�����v�A�u�BSCR�G�}��HC��ł̉����v�A����сu�C �d�ʎԃ��[�h�R��
�̉��P�v���ۑ肾����������A�ۑ�������ł����̓I�ȋZ�p�������L�ڂ���Ă��Ȃ��̂ł���B
�@����ɑ��A�|���R�c���Z�p���̕M�҂�2004�N5��25���ɏo�肵���C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�i�o�T�F
http://www6.ipdl.inpit.go.jp/Tokujitu/tjsogodbk.ipdl�j�������̖����ɂ́A��^�g���b�N�ɂ����đ��}�ɉ������ׂ���
��Ƃ����u�@ DPF���u�̋����Đ��̕p�x�����v�A�u�A SCR�G�}�̒ቷ�����v�A����сu�C �d�ʎԃ��[�h�R��̉��P�v��
�����A�����̉ۑ���������邽�߂̋Z�p�Ƃ��āu�Q�^�[�{�����̋C���x�~�V�X�e���v�̏ڍׂƁuNO���팸�v�Ɓu�R���
�P�v�̋@�\�E���ʂ��L�ڂ��Ă���̂ł���B�����āA�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p�́A2005�N3
���ɓ������J����Ă����ɁA2006�N4��7�����J�̕M�҂̃C���^�[�l�b�g�̃z�[���y�[�W�ɂ����ċZ�p���e���ڍׂ�
�������Ă�����ł���B���������āA�ŋ߁i��2010�N�`2014�N�j�ɂ����ẮA���{���\����G���W���W�̒����ȑ�
��c��w�E���������A����уg���b�N���[�J�ł���UD�g���b�N�X���̏��ѐM�T ���� �O�G ���̐��Ƃ����{������
�H�Ɖ�̃z�[���y�[�W��AMAGAZINE�i2012�N3�����j�������ԋZ�p���̔N�Ӂi��2010�N�y��2014�N�̂W�����j�̒���
�q�ׂ��Ă�����^�g���b�N�́u��NO�����v����сu��R��v���������邽�߂́u�@ DPF���u�̋����Đ��̕p�x��
���v�A�u�A SCR�G�}�̒ቷ�����v�A�u�BSCR�G�}��HC��ł̉����v�A����сu�C �d�ʎԃ��[�h�R��̉��P�v���ۑ�́A
�|���R�c���Z�p���̕M�҂�2004�N5��25���ɏo�肵���C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p�̖���
���ɏڂ����L�ڂ��Ă���̂ł���B
http://www6.ipdl.inpit.go.jp/Tokujitu/tjsogodbk.ipdl�j�������̖����ɂ́A��^�g���b�N�ɂ����đ��}�ɉ������ׂ���
��Ƃ����u�@ DPF���u�̋����Đ��̕p�x�����v�A�u�A SCR�G�}�̒ቷ�����v�A����сu�C �d�ʎԃ��[�h�R��̉��P�v��
�����A�����̉ۑ���������邽�߂̋Z�p�Ƃ��āu�Q�^�[�{�����̋C���x�~�V�X�e���v�̏ڍׂƁuNO���팸�v�Ɓu�R���
�P�v�̋@�\�E���ʂ��L�ڂ��Ă���̂ł���B�����āA�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p�́A2005�N3
���ɓ������J����Ă����ɁA2006�N4��7�����J�̕M�҂̃C���^�[�l�b�g�̃z�[���y�[�W�ɂ����ċZ�p���e���ڍׂ�
�������Ă�����ł���B���������āA�ŋ߁i��2010�N�`2014�N�j�ɂ����ẮA���{���\����G���W���W�̒����ȑ�
��c��w�E���������A����уg���b�N���[�J�ł���UD�g���b�N�X���̏��ѐM�T ���� �O�G ���̐��Ƃ����{������
�H�Ɖ�̃z�[���y�[�W��AMAGAZINE�i2012�N3�����j�������ԋZ�p���̔N�Ӂi��2010�N�y��2014�N�̂W�����j�̒���
�q�ׂ��Ă�����^�g���b�N�́u��NO�����v����сu��R��v���������邽�߂́u�@ DPF���u�̋����Đ��̕p�x��
���v�A�u�A SCR�G�}�̒ቷ�����v�A�u�BSCR�G�}��HC��ł̉����v�A����сu�C �d�ʎԃ��[�h�R��̉��P�v���ۑ�́A
�|���R�c���Z�p���̕M�҂�2004�N5��25���ɏo�肵���C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p�̖���
���ɏڂ����L�ڂ��Ă���̂ł���B
�@�܂�A���{�����ԍH�Ɖ�̃z�[���y�[�W��AMAGAZINE�i2012�N3�����j�������ԋZ�p���̔N�Ӂi��2010
�N�y��2014�N�̂W�����j�̂悤�Ȑ��Ԃɉe���͂�M�����̍����Ƃ�����M�}�̂ɂ����āA����c��w�E
���������AUD�g���b�N�X���̏��ѐM�T ���� �O�G �����������A���ѐM�T ���A������O�G ���̂R��
����^�g���b�N�J���̍ŐV�̋Z�p���ƋL�ڂ��ꂽ�@�`�C�̉ۑ�́A�|���R�c���Z�p���̕M�҂�10�N���ȑO
��2004�N5��25���ɓ������ɏo�肵���C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����i�o�T�Fhttp://www6.
ipdl.inpit.go.jp/Tokujitu/tjsogodbk.ipdl�j�̖����ɖ��L���Ă����̂ł���B�܂��A���{�����ԍH�Ɖ��
AMAGAZINE�i2012�N3�����j�������ԋZ�p���i��2010�N�y��2014�N�̂W�����j�̔N�ӂɂ����āA���������́A��^�g��
�b�N���@�`�C���Z�p�J���̉ۑ���q�ׂ��Ă��邾���ł���A�����̉ۑ�������ł����̓I�ȋZ�p�ɂ��ẮA
���̏����E�J������Ă��Ȃ��B�������A�|���R�c���Z�p���̕M�҂�10�N�ȏ���̂ɏo�肵���C���x�~�G���W��
�i�������J2005-54771�j�̓����Z�p���^�g���b�N�ɍ̗p�����ꍇ�ɂ́A�@�`�C���Z�p�I�ۑ肪�S�ĉ����ł��邽
�߁A�e�Ղɑ�^�g���b�N�́u��NO�����v����сu��R��v�������ł���̂ł���B���̏ɂ��āA�ȉ��̕\�V�ɔ���
�Ղ��܂Ƃ߂��̂ŁA�䗗�������������B
�N�y��2014�N�̂W�����j�̂悤�Ȑ��Ԃɉe���͂�M�����̍����Ƃ�����M�}�̂ɂ����āA����c��w�E
���������AUD�g���b�N�X���̏��ѐM�T ���� �O�G �����������A���ѐM�T ���A������O�G ���̂R��
����^�g���b�N�J���̍ŐV�̋Z�p���ƋL�ڂ��ꂽ�@�`�C�̉ۑ�́A�|���R�c���Z�p���̕M�҂�10�N���ȑO
��2004�N5��25���ɓ������ɏo�肵���C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����i�o�T�Fhttp://www6.
ipdl.inpit.go.jp/Tokujitu/tjsogodbk.ipdl�j�̖����ɖ��L���Ă����̂ł���B�܂��A���{�����ԍH�Ɖ��
AMAGAZINE�i2012�N3�����j�������ԋZ�p���i��2010�N�y��2014�N�̂W�����j�̔N�ӂɂ����āA���������́A��^�g��
�b�N���@�`�C���Z�p�J���̉ۑ���q�ׂ��Ă��邾���ł���A�����̉ۑ�������ł����̓I�ȋZ�p�ɂ��ẮA
���̏����E�J������Ă��Ȃ��B�������A�|���R�c���Z�p���̕M�҂�10�N�ȏ���̂ɏo�肵���C���x�~�G���W��
�i�������J2005-54771�j�̓����Z�p���^�g���b�N�ɍ̗p�����ꍇ�ɂ́A�@�`�C���Z�p�I�ۑ肪�S�ĉ����ł��邽
�߁A�e�Ղɑ�^�g���b�N�́u��NO�����v����сu��R��v�������ł���̂ł���B���̏ɂ��āA�ȉ��̕\�V�ɔ���
�Ղ��܂Ƃ߂��̂ŁA�䗗�������������B
| ��2010�`2014�N�ɗ��ꂽ |
|
|
|
| �@ | |
��^�g���b�N�̎����s���ɑ��p�����
�G���W�����������ɂ�����
�r�C�K�X���x��������
|
�� �ۑ�����̓����Z�p
�� �W�����i�Q�l�j
�E�{�y�[�W�̑��̍��i�Ⴆ�A4�����Q�Ɓj
|
| �A | |
||
| �B | |
||
| �C | |
��^�g���b�N�̎����s���ɑ��p�����
�G���W�����������ɂ�����
�R��̌���
|
�� �ۑ�����̓����Z�p
�� �W�����i�Q�l�j
|
�@���Ă��āA�A�C���x�~�G���W���ɂ���^�g���b�N�̒�R��A�C���x�~�́A�f�B�[�[���̂m�n���팸�ƔR�����̈�
�������̋Z�p���I�A���{�͑�^�g���b�N�̐V���Ȓ�R��E��r�o�K�X��𑁊��ɐݒ肹��I������č������ɂ�
��^�g���b�N��NO���K�����{�s����������{���{�̑Ӗ��܂����C���x�~�́A�f�B�[�[���̂m�n���팸�ƔR�����̈�
�������̋Z�p���I�ɏڏq���Ă���悤�ɁA����͕M�҂̗\���ɉ߂��Ȃ����Ƃł��邪�A�����̉��ꂩ�̎����ɂ���
�āA�킪���̑�^�g���b�N�́A�u2015�N�x�d�ʎԔR������{10�����x�̔R�����v�Ɓu�m�n����0.23�@g/kWh��NO��
�K���v�̋K�������́A�����I�Ɏ��{������Ȃ��ƍl������B�����āA�|���R�c���Z�p���̕M�҂�10�N�O��2004
�N5��25���ɏo�肵���Q�^�[�{�����̋C���x�~�V�X�e�����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p�́A
���{�����ԍH�Ɖ�̃z�[���y�[�W��JAMAGAZINE�@�i2012�N3�����j�ɂ����đ���c��w�E�����������w�E�́u�@
DPF���u�̋����Đ��̕p�x�����v�A�u�A SCR�G�}�̒ቷ�����v�A�u�BSCR�G�}��HC��ł̉����v�A����сu�C �d�ʎ�
���[�h�R��̉��P�v�̂S���ڂ̋Z�p�I���ۑ�̑S�Ă��������邱�Ƃ��\�ƂȂ�A�u2015�N�x�d�ʎԔR������{
10�����x�̔R�����v�Ɓu�m�n����0.23�@g/kWh��NO���K���v�̋K�������ɓK���\����^�g���b�N���e�ՂɎ����ł���
���ł���B
�������̋Z�p���I�A���{�͑�^�g���b�N�̐V���Ȓ�R��E��r�o�K�X��𑁊��ɐݒ肹��I������č������ɂ�
��^�g���b�N��NO���K�����{�s����������{���{�̑Ӗ��܂����C���x�~�́A�f�B�[�[���̂m�n���팸�ƔR�����̈�
�������̋Z�p���I�ɏڏq���Ă���悤�ɁA����͕M�҂̗\���ɉ߂��Ȃ����Ƃł��邪�A�����̉��ꂩ�̎����ɂ���
�āA�킪���̑�^�g���b�N�́A�u2015�N�x�d�ʎԔR������{10�����x�̔R�����v�Ɓu�m�n����0.23�@g/kWh��NO��
�K���v�̋K�������́A�����I�Ɏ��{������Ȃ��ƍl������B�����āA�|���R�c���Z�p���̕M�҂�10�N�O��2004
�N5��25���ɏo�肵���Q�^�[�{�����̋C���x�~�V�X�e�����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p�́A
���{�����ԍH�Ɖ�̃z�[���y�[�W��JAMAGAZINE�@�i2012�N3�����j�ɂ����đ���c��w�E�����������w�E�́u�@
DPF���u�̋����Đ��̕p�x�����v�A�u�A SCR�G�}�̒ቷ�����v�A�u�BSCR�G�}��HC��ł̉����v�A����сu�C �d�ʎ�
���[�h�R��̉��P�v�̂S���ڂ̋Z�p�I���ۑ�̑S�Ă��������邱�Ƃ��\�ƂȂ�A�u2015�N�x�d�ʎԔR������{
10�����x�̔R�����v�Ɓu�m�n����0.23�@g/kWh��NO���K���v�̋K�������ɓK���\����^�g���b�N���e�ՂɎ����ł���
���ł���B
�T�D�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p���E�َE����w�ҁE����
�@�ߔN�̃f�B�[�[���G���W���Ɋւ���V�Z�p�Ɖ]���A�R�O�N���x���̂ɔ��Ă��ꂽ�u���z�̃f�B�[�[���R�ċZ�p�I�v�A
�u�����̔R�ċZ�p�I�v�Ƃ��đ����ꂽ�f�B�[�[���G���W����HCCI �R�āi��PCI �R�āF�\�������k���ΔR�āj�̋Z�p��
�v���o�����B�������A���̃f�B�[�[���G���W����HCCI �R�āi��PCI �R�āj�́A�G���W���̌y���^�]����NO���팸��
�͗L���ł��邪�A�R�Ă��s����ȏ�ɁA�R����P�̌��ʂ��w�ǖ������Ƃ����炩�ƂȂ������߁A�ŋ߂ł͎��p���̖�
���u�V�Z�p�H�v�ƍl����w�ҁE���ƁE�Z�p�҂������悤���B�����āA�f�B�[�[��HCCI �R�āi��PCI �R�āj�̐V�Z�p�́A
�R�O�N���x�̍Ό��Ƒ����̊w�ҁE���ƁE�Z�p�҂���𑈂��Č����J���ɋ��에�����A�c��ȗʂ̘_�������\���ꂽ
�̂ł���B�������A�ŋ߂ł́A���̃f�B�[�[��HCCI �R�āi��PCI �R�āj�̌����J���́A���ǂ̂Ƃ���A�厸�s�ł�������
������Ă���w�ҁE���ƁE�Z�p�҂������悤�Ɏv����̂ł���B�ܘ_�A���߂̈����w�ҁE���ƁE�Z�p�҂́A������
�������炵�������J���s���Ă���悤�ł��邪�A���s�ׂ̂悤�Ɋ�����̂́A�M�҂����ł��낤���B
�u�����̔R�ċZ�p�I�v�Ƃ��đ����ꂽ�f�B�[�[���G���W����HCCI �R�āi��PCI �R�āF�\�������k���ΔR�āj�̋Z�p��
�v���o�����B�������A���̃f�B�[�[���G���W����HCCI �R�āi��PCI �R�āj�́A�G���W���̌y���^�]����NO���팸��
�͗L���ł��邪�A�R�Ă��s����ȏ�ɁA�R����P�̌��ʂ��w�ǖ������Ƃ����炩�ƂȂ������߁A�ŋ߂ł͎��p���̖�
���u�V�Z�p�H�v�ƍl����w�ҁE���ƁE�Z�p�҂������悤���B�����āA�f�B�[�[��HCCI �R�āi��PCI �R�āj�̐V�Z�p�́A
�R�O�N���x�̍Ό��Ƒ����̊w�ҁE���ƁE�Z�p�҂���𑈂��Č����J���ɋ��에�����A�c��ȗʂ̘_�������\���ꂽ
�̂ł���B�������A�ŋ߂ł́A���̃f�B�[�[��HCCI �R�āi��PCI �R�āj�̌����J���́A���ǂ̂Ƃ���A�厸�s�ł�������
������Ă���w�ҁE���ƁE�Z�p�҂������悤�Ɏv����̂ł���B�ܘ_�A���߂̈����w�ҁE���ƁE�Z�p�҂́A������
�������炵�������J���s���Ă���悤�ł��邪�A���s�ׂ̂悤�Ɋ�����̂́A�M�҂����ł��낤���B
�@���̂悤�ɁA�f�B�[�[���G���W����HCCI �R�āi��PCI �R�āj�̌����J���̎��s������ƁA�@���قǍ��l�ɁA�f�B�[�[
���G���W���́uNO���팸�v�Ɓu�R����P�v���Ɏ����ł���V�Z�p���J�����邱�Ƃ�����ł��邩�������ł��锤�ł�
��B�����āA����HCCI �R�āi��PCI �R�āj�̌����J���̎��s�̂悤�ɁA�f�B�[�[���G���W���́uNO���팸�v�Ɓu�R����P�v
�̓��������́A�Z�p�I�ɋɂ߂ē�����Ƃł���B�������A���̍�������������̂��C���x�~�G���W���i�������J2005
-54771�j�̓����Z�p�ł���A�����āA���̓����Z�p�͑�^�f�B�[�[���g���b�N�́uNO���팸�v�Ɓu�R����P�v�̗�����
�Ɏ����ł������I�ȐV�Z�p�ł���B���̂��߁A���݁i��2014�N9���j�̂Ƃ���A�u2015�N�x�d�ʎԔR������{
10�����x�̔R�����v�Ɓu�m�n����0.23�@g/kWh��NO���K���v�̋K�������ɓK���ł���Z�p�́A�����C���x�~�G���W��
�i�������J2005-54771�j�̓����Z�p�̑��ɂ͑��݂����A���炭�A���ꂩ��P�O�N�`�Q�O�N���x���o�߂��āA�����̓����Z
�p�𗽉킷���^�g���b�N�́uNO���팸�v�Ɓu�d�ʎԃ��[�h�R��̉��P�v�̗������Ɏ����ł���Z�p�͐��܂�Ȃ���
�̂Ɛ��������B�����āA���̕M�Ғ�Ă��C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p�́A�uNO����
���v�Ɓu�R����P�v�̋@�\�E���\��������ɍ\���I�ɊȒP�Ȃ��߂Ɏ��p�����e�Ղł��邱�Ƃ���A���̓����Z�p
���^�g���b�N�ɍ̗p�����ꍇ�A�u2015�N�x�d�ʎԔR������{10�����x�̔R�����v�Ɓu�m�n����0.23�@g/
kWh��NO���K���v�̃��x���̋K���ɓK��������^�g���b�N��2020�N�x���ɂ͎s�̂��\�ɂȂ�ƍl������B
���G���W���́uNO���팸�v�Ɓu�R����P�v���Ɏ����ł���V�Z�p���J�����邱�Ƃ�����ł��邩�������ł��锤�ł�
��B�����āA����HCCI �R�āi��PCI �R�āj�̌����J���̎��s�̂悤�ɁA�f�B�[�[���G���W���́uNO���팸�v�Ɓu�R����P�v
�̓��������́A�Z�p�I�ɋɂ߂ē�����Ƃł���B�������A���̍�������������̂��C���x�~�G���W���i�������J2005
-54771�j�̓����Z�p�ł���A�����āA���̓����Z�p�͑�^�f�B�[�[���g���b�N�́uNO���팸�v�Ɓu�R����P�v�̗�����
�Ɏ����ł������I�ȐV�Z�p�ł���B���̂��߁A���݁i��2014�N9���j�̂Ƃ���A�u2015�N�x�d�ʎԔR������{
10�����x�̔R�����v�Ɓu�m�n����0.23�@g/kWh��NO���K���v�̋K�������ɓK���ł���Z�p�́A�����C���x�~�G���W��
�i�������J2005-54771�j�̓����Z�p�̑��ɂ͑��݂����A���炭�A���ꂩ��P�O�N�`�Q�O�N���x���o�߂��āA�����̓����Z
�p�𗽉킷���^�g���b�N�́uNO���팸�v�Ɓu�d�ʎԃ��[�h�R��̉��P�v�̗������Ɏ����ł���Z�p�͐��܂�Ȃ���
�̂Ɛ��������B�����āA���̕M�Ғ�Ă��C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p�́A�uNO����
���v�Ɓu�R����P�v�̋@�\�E���\��������ɍ\���I�ɊȒP�Ȃ��߂Ɏ��p�����e�Ղł��邱�Ƃ���A���̓����Z�p
���^�g���b�N�ɍ̗p�����ꍇ�A�u2015�N�x�d�ʎԔR������{10�����x�̔R�����v�Ɓu�m�n����0.23�@g/
kWh��NO���K���v�̃��x���̋K���ɓK��������^�g���b�N��2020�N�x���ɂ͎s�̂��\�ɂȂ�ƍl������B
�@�Ƃ��낪�A�������ƂɁA���{���\����G���W���W�̑��l�҂ł��鑁��c��w�E����������A�g���b�N���[�J�ł���
UD�g���b�N�X���̐��ƁE�Z�p�҂̏��ѐM�T ���� �O�G ������^�g���b�N�ɂ������L �@�`�C �̋ɂ߂ĉ�����
����ȉۑ�̑��݂����������_���E�L���������{�����ԍH�Ɖ�̃z�[���y�[�W��AMAGAZINE�i2012�N3�����j����
���ԋZ�p���̔N�Ӂi��2010�N�y��2014�N�̂W�����j�ɔ��\�E���J����Ă���B�܂�A����c��w�E����������UD�g��
�b�N�X���̐��ƁE�Z�p�҂̏��ѐM�T ���̂R���́A2010�N�`2014�N�ɂ����āA��^�g���b�N�́uNO���팸�v�Ɓu�R���
�P�v�ɗL�����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p�̑��݂������S�ɖ����E�َE�����_���E�L������
���\����Ă���̂ł���B�܂�A��^�f�B�[�[���g���b�N�́uNO���팸�v�Ɓu�R����P�v�̎����ɕK�v�ȉۑ肾�����
���āA�ۑ�����������̓I�ȋZ�p�̏��J����E��Ă��s���Ă��炸�A�uNO���팸�v�Ɓu�d�ʎԃ��[�h�R���̉�
�P�v�ɗL�����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p�������E�َE���Ă����̂ł���B
UD�g���b�N�X���̐��ƁE�Z�p�҂̏��ѐM�T ���� �O�G ������^�g���b�N�ɂ������L �@�`�C �̋ɂ߂ĉ�����
����ȉۑ�̑��݂����������_���E�L���������{�����ԍH�Ɖ�̃z�[���y�[�W��AMAGAZINE�i2012�N3�����j����
���ԋZ�p���̔N�Ӂi��2010�N�y��2014�N�̂W�����j�ɔ��\�E���J����Ă���B�܂�A����c��w�E����������UD�g��
�b�N�X���̐��ƁE�Z�p�҂̏��ѐM�T ���̂R���́A2010�N�`2014�N�ɂ����āA��^�g���b�N�́uNO���팸�v�Ɓu�R���
�P�v�ɗL�����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p�̑��݂������S�ɖ����E�َE�����_���E�L������
���\����Ă���̂ł���B�܂�A��^�f�B�[�[���g���b�N�́uNO���팸�v�Ɓu�R����P�v�̎����ɕK�v�ȉۑ肾�����
���āA�ۑ�����������̓I�ȋZ�p�̏��J����E��Ă��s���Ă��炸�A�uNO���팸�v�Ɓu�d�ʎԃ��[�h�R���̉�
�P�v�ɗL�����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p�������E�َE���Ă����̂ł���B
�@�܂��A���쎩���Ԃ́A�����ԋZ�p��2014�N�t�G���i��2014�N5��21���i���j�`23���i���j�J�Áj�ɂ����āA�u�ߋ��f�B
�[�[���G���W���̋C���x�~�ɂ��Ă̈�l�@�v�i�����ԍ�20145364�j�Ƒ肷���^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W���̋C
���x�~�V�X�e���Ɋւ���_���\�����B���쎩���Ԃ��_�����\�����R����P�@�\�̗��C���x�~�V�X�e���̃y�[
�W�ɏڏq���Ă���悤�ɁA���̘_���Ŕ��\���ꂽ���쎩���Ԃ́u�S�C���A���̉ߋ��@��������z�E�r�C�ْ�~��
�̋C���x�~�V�X�e���v�́A��^�g���b�N�̎����s���ɑ��p�����G���W���̂P�^�Q���ߕӂ��ȉ��̒ᕉ��
�ł̓^�[�{�ߋ��@�̃T�[�W���O��肪�������邽�߁A�U�C���G���W���̂R�C�����x�~������^�]���w��Ǖs�\
�ƂȂ錇�ׂ������B���̂悤�Ȍ��Z�p��_���ɓZ�߂Ď����ԋZ�p��2014�N�t�G���Ŕ��\�������쎩���Ԃ̉i
�g �w���A���� �������A�� �K�_���̏����̖ړI�́A�ȉ����iA)�A�iB�j�܂����iC)�̉��ꂩ�Ɛ��������B
�[�[���G���W���̋C���x�~�ɂ��Ă̈�l�@�v�i�����ԍ�20145364�j�Ƒ肷���^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W���̋C
���x�~�V�X�e���Ɋւ���_���\�����B���쎩���Ԃ��_�����\�����R����P�@�\�̗��C���x�~�V�X�e���̃y�[
�W�ɏڏq���Ă���悤�ɁA���̘_���Ŕ��\���ꂽ���쎩���Ԃ́u�S�C���A���̉ߋ��@��������z�E�r�C�ْ�~��
�̋C���x�~�V�X�e���v�́A��^�g���b�N�̎����s���ɑ��p�����G���W���̂P�^�Q���ߕӂ��ȉ��̒ᕉ��
�ł̓^�[�{�ߋ��@�̃T�[�W���O��肪�������邽�߁A�U�C���G���W���̂R�C�����x�~������^�]���w��Ǖs�\
�ƂȂ錇�ׂ������B���̂悤�Ȍ��Z�p��_���ɓZ�߂Ď����ԋZ�p��2014�N�t�G���Ŕ��\�������쎩���Ԃ̉i
�g �w���A���� �������A�� �K�_���̏����̖ړI�́A�ȉ����iA)�A�iB�j�܂����iC)�̉��ꂩ�Ɛ��������B
�iA) ���쎩���Ԓ�Ắu�z�E�r�C�ْ�~���̋C���x�~�V�X�e���v�́A�����I�Ɏ��p��������ȁu���Z�p�v�ł͂���
���A��^�g���b�N�̑��s�R����{�S�����x������ł��邱�Ƃ���A���쎩���Ԃɂ�����f�B�[�[���G���W���Ɋւ��鍂
���Z�p�J���͂̂��邱�Ƃ𐢊ԂɃA�s�[���E�������邱�Ƃ�����ړI�ɁA���̘_���\�����\��������B�v����
�ɁA�����_�Łu2015�N�x�d�ʎԔR������{10�����x�̔R�����v�̋K�������ɓK���\�Ƃ���Z�p�͖��J����
�ł��邪�A���쎩���Ԃ���R��̋Z�p�J���Ɍ����Ɏ��g��ł���p�������\�I�ȍs���̉\��
���l������B
���A��^�g���b�N�̑��s�R����{�S�����x������ł��邱�Ƃ���A���쎩���Ԃɂ�����f�B�[�[���G���W���Ɋւ��鍂
���Z�p�J���͂̂��邱�Ƃ𐢊ԂɃA�s�[���E�������邱�Ƃ�����ړI�ɁA���̘_���\�����\��������B�v����
�ɁA�����_�Łu2015�N�x�d�ʎԔR������{10�����x�̔R�����v�̋K�������ɓK���\�Ƃ���Z�p�͖��J����
�ł��邪�A���쎩���Ԃ���R��̋Z�p�J���Ɍ����Ɏ��g��ł���p�������\�I�ȍs���̉\��
���l������B
�iB�j ���쎩���Ԓ�Ắu�z�E�r�C�ْ�~���̋C���x�~�V�X�e���v�̐V�Z�p�v�́A�v���I�ȍ\����̌��ׂ����Ă�
�邽�߁A�����̎��p��������ł��邱�Ƃ��ڍׂɐ������邱�Ƃ��\�ł���B���̂��߁A���̓���̋C���x�~�V�X�e
���̌��ׂ̗��_�I�ȉ�͂ɂ��A���ԑ�^�g���b�N�ɂ�����u2015�N�x�d�ʎԔR������{10�����x�̔R�����v
�̋K�������̑������{��������Ƃ��Ɍ����E�A�s�[�������i�Ƃ��ẮA�L���ł���B�����ŁA���̓���̋C���x�~
�V�X�e���̒v���I�ȍ\����̌��ׂ̉������Z�p�I�ɍ���ł��邱�Ƃ𗝗R�ɁA��^�g���b�N�ɂ�����u2015�N�x�d
�ʎԔR������{10�����x�̔R�����v�̋K�������̑������{���s�\�ł��邱�Ƃ������A���̋K������
�̐摗����L�����Ԃɑi�������Ƃ�ړI�ɂ��Ă���\�����l������B
�邽�߁A�����̎��p��������ł��邱�Ƃ��ڍׂɐ������邱�Ƃ��\�ł���B���̂��߁A���̓���̋C���x�~�V�X�e
���̌��ׂ̗��_�I�ȉ�͂ɂ��A���ԑ�^�g���b�N�ɂ�����u2015�N�x�d�ʎԔR������{10�����x�̔R�����v
�̋K�������̑������{��������Ƃ��Ɍ����E�A�s�[�������i�Ƃ��ẮA�L���ł���B�����ŁA���̓���̋C���x�~
�V�X�e���̒v���I�ȍ\����̌��ׂ̉������Z�p�I�ɍ���ł��邱�Ƃ𗝗R�ɁA��^�g���b�N�ɂ�����u2015�N�x�d
�ʎԔR������{10�����x�̔R�����v�̋K�������̑������{���s�\�ł��邱�Ƃ������A���̋K������
�̐摗����L�����Ԃɑi�������Ƃ�ړI�ɂ��Ă���\�����l������B
�iC) ���쎩���Ԓ�Ắu�z�E�r�C�ْ�~���̋C���x�~�V�X�e���v�̐V�Z�p�v�́A�v���I�ȍ\����̌��ׂ����u�z�E
�r�C�ْ�~���̋C���x�~�V�X�e���v�̘_���������ԋZ�p��2014�N�H�G�������\�����̂́A��^�g���b�N�p�f�B�[�[
���G���W���́uNO���팸�v�Ɓu�d�ʎԃ��[�h�R��̌���v���Z�p�I�ɍ���ł��邱�Ƃ����y��ʏȂ���ȂɌ��`�E�A�s
�[�����邱�Ƃ��\�ł���B����ɂ���āA�f�B�[�[���G���W�����ڂ̑�^�g���b�N�ɂ��������s�R��i���d�ʎԃ��[�h
�R��j�̉��P�ɗL���ȋZ�p�������_�ŕs���E���J���ł���Ƃ̐S�E����ς����y��ʏȂ���Ȃ̊����ɐA����
���邱�Ƃ��_���̉\�����l������B�����āA���y��ʏȂ���Ȃ̊����ɑ��A�C���x�~�G���W���i�������J
2005-54771�j�̓����Z�p�ɂ���^�g���b�N��NO���팸�Ƒ��s�R����P���\�Ƃ���Z�p���Ɏ����X����
���Ȃ��悤�ɂ��邱����ړI�ɂ��Ă���\�����l������B
�r�C�ْ�~���̋C���x�~�V�X�e���v�̘_���������ԋZ�p��2014�N�H�G�������\�����̂́A��^�g���b�N�p�f�B�[�[
���G���W���́uNO���팸�v�Ɓu�d�ʎԃ��[�h�R��̌���v���Z�p�I�ɍ���ł��邱�Ƃ����y��ʏȂ���ȂɌ��`�E�A�s
�[�����邱�Ƃ��\�ł���B����ɂ���āA�f�B�[�[���G���W�����ڂ̑�^�g���b�N�ɂ��������s�R��i���d�ʎԃ��[�h
�R��j�̉��P�ɗL���ȋZ�p�������_�ŕs���E���J���ł���Ƃ̐S�E����ς����y��ʏȂ���Ȃ̊����ɐA����
���邱�Ƃ��_���̉\�����l������B�����āA���y��ʏȂ���Ȃ̊����ɑ��A�C���x�~�G���W���i�������J
2005-54771�j�̓����Z�p�ɂ���^�g���b�N��NO���팸�Ƒ��s�R����P���\�Ƃ���Z�p���Ɏ����X����
���Ȃ��悤�ɂ��邱����ړI�ɂ��Ă���\�����l������B
�@�ȏ�̂悤�ɁA���쎩���Ԃ́A��^�g���b�N�́u2015�N�x�d�ʎԔR������{10�����x�̔R�����v�̋K������
��摗�肷�鐢�_�E������邽�߁A�^�[�{�ߋ��@�̒m���������ł������Ă���l��������ƁA�ŏ�������p�s�\�ł�
��u�z�E�r�C�ْ�~���̋C���x�~�V�X�e���v�̌��Z�p���A�����̑�^�g���b�N�̔R�����ɗL���ȐV�����Z�p�Ƃ���
���d�ȓ��e�̘_���\�����\�����ɂ߂č����Ɛ��������B���̏ꍇ�ɂ́A���Z�p�ł������̋C���x�~�V
�X�e�������i�g �w���A���� �������A�� �K�_���̏����́A�ŏ�����u�z�E�r�C�ْ�~���̋C���x�~�V�X�e���v��
���Z�p�ł��邱�Ƃ�m��Ȃ���A��i�̖��߂Ő��Ԃ��x�����߂ɁA���̌��Z�p�̘_���\�������ƂɂȂ�ƍl��
����B�܂�A���쎩���Ԃ̌��Z�p�̘_�����\�́A�u2015�N�x�d�ʎԔR������{10�����x�̔R�����v��
���݂̋Z�p���x���ł͍���Ƃ��������Z�p���𐢊ԂɊg�U���鍼�\�I�ȖړI�Ƃ̌������\�ł���B
��摗�肷�鐢�_�E������邽�߁A�^�[�{�ߋ��@�̒m���������ł������Ă���l��������ƁA�ŏ�������p�s�\�ł�
��u�z�E�r�C�ْ�~���̋C���x�~�V�X�e���v�̌��Z�p���A�����̑�^�g���b�N�̔R�����ɗL���ȐV�����Z�p�Ƃ���
���d�ȓ��e�̘_���\�����\�����ɂ߂č����Ɛ��������B���̏ꍇ�ɂ́A���Z�p�ł������̋C���x�~�V
�X�e�������i�g �w���A���� �������A�� �K�_���̏����́A�ŏ�����u�z�E�r�C�ْ�~���̋C���x�~�V�X�e���v��
���Z�p�ł��邱�Ƃ�m��Ȃ���A��i�̖��߂Ő��Ԃ��x�����߂ɁA���̌��Z�p�̘_���\�������ƂɂȂ�ƍl��
����B�܂�A���쎩���Ԃ̌��Z�p�̘_�����\�́A�u2015�N�x�d�ʎԔR������{10�����x�̔R�����v��
���݂̋Z�p���x���ł͍���Ƃ��������Z�p���𐢊ԂɊg�U���鍼�\�I�ȖړI�Ƃ̌������\�ł���B
�@�����āA������̌����́A�u�z�E�r�C�ْ�~���̋C���x�~�V�X�e���v���ŏ�������p�s�\�ł��錇�Z�p�ł����
�̔F�������쎩���Ԃ̉i�g �w���A���� �������A�� �K�_���̏����ɂ͍ŏ�����F���ł������ꍇ���l������B��
�̏ꍇ�ɂ́A�^�[�{�ߋ��@�Ɋւ���m�����R�������߂ɐ������Z�p�҂Ƃ��Ắu���\�v�������Ō��Z�p�̘_����
�\���Ă��܂������ƂɂȂ�B���̏ꍇ�ɂ́A���쎩���Ԃ̖��m�ȎЈ������g�̔n�������������琢�ԂɎN���_�����\
���s�������ƂɂȂ�B�������Ȃ���A���݂̎s�̎ԗ��̑S�ĂɃ^�[�{�ߋ��f�B�[�[���G���W�����̗p���Ă�����쎩��
�Ԃɂ����āA�ʏ�̏ꍇ�A�i�g �w���A���� �������A�� �K�_�����������_������i�����ǁE�`�F�b�N����Ă��邱�Ƃ�
�l������A���쎩���Ԃ̖��m�ȎЈ����ƒf�Łu�z�E�r�C�ْ�~���̋C���x�~�V�X�e���v�̌��Z�p�̘_�����\��
�s���Ă��܂����Ɖ]�����Ƃ́A�L�蓾�Ȃ����Ƃƍl������B
�̔F�������쎩���Ԃ̉i�g �w���A���� �������A�� �K�_���̏����ɂ͍ŏ�����F���ł������ꍇ���l������B��
�̏ꍇ�ɂ́A�^�[�{�ߋ��@�Ɋւ���m�����R�������߂ɐ������Z�p�҂Ƃ��Ắu���\�v�������Ō��Z�p�̘_����
�\���Ă��܂������ƂɂȂ�B���̏ꍇ�ɂ́A���쎩���Ԃ̖��m�ȎЈ������g�̔n�������������琢�ԂɎN���_�����\
���s�������ƂɂȂ�B�������Ȃ���A���݂̎s�̎ԗ��̑S�ĂɃ^�[�{�ߋ��f�B�[�[���G���W�����̗p���Ă�����쎩��
�Ԃɂ����āA�ʏ�̏ꍇ�A�i�g �w���A���� �������A�� �K�_�����������_������i�����ǁE�`�F�b�N����Ă��邱�Ƃ�
�l������A���쎩���Ԃ̖��m�ȎЈ����ƒf�Łu�z�E�r�C�ْ�~���̋C���x�~�V�X�e���v�̌��Z�p�̘_�����\��
�s���Ă��܂����Ɖ]�����Ƃ́A�L�蓾�Ȃ����Ƃƍl������B
�@���̂��߁A���̓���̋C���x�~�V�X�e���̌��Z�p�ɂ��Ă̘_���́A��^�g���b�N�̔R����オ�Z�p�I�ɍ���v
�Ƃ��鋕�U�̋Z�p���̊g�U��_�����u���쎩���v�̂悤�ɁA�M�҂ɂ͎v����̂ł���B���̌��Z�p�̘_�����\�Ɖ]
���u���쎩���v�́A�����I�ɑ�^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W���̔R�����̋Z�p�I�Ȑi�W�E���W��W�Q���锽�Љ�I
�ȍs�ׂƂ̌������\�ł���B�����āA���̓��쎩���Ԓ�Ă̌��Z�p���������u���쎩���v�̘_�����\�̖ړI���A
��^�g���b�N�̇@�`�A�̉ۑ�����������u2015�N�x�d�ʎԔR������{10�����x�̔R�����v�Ɓu�m�n����0.23�@g/
kWh ��NO���K���v�̃��x���i���K���l�j�̋K�������ɂ��K���\�Ƃ����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓�
�����u���Z�p�v�Ƃ̌������ۂ��L�����ԂɊg�U���邱�Ƃł���A������s�ׂ̂悤�Ɏv���邪�A�@���Ȃ��̂ł�
�낤���B
�Ƃ��鋕�U�̋Z�p���̊g�U��_�����u���쎩���v�̂悤�ɁA�M�҂ɂ͎v����̂ł���B���̌��Z�p�̘_�����\�Ɖ]
���u���쎩���v�́A�����I�ɑ�^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W���̔R�����̋Z�p�I�Ȑi�W�E���W��W�Q���锽�Љ�I
�ȍs�ׂƂ̌������\�ł���B�����āA���̓��쎩���Ԓ�Ă̌��Z�p���������u���쎩���v�̘_�����\�̖ړI���A
��^�g���b�N�̇@�`�A�̉ۑ�����������u2015�N�x�d�ʎԔR������{10�����x�̔R�����v�Ɓu�m�n����0.23�@g/
kWh ��NO���K���v�̃��x���i���K���l�j�̋K�������ɂ��K���\�Ƃ����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓�
�����u���Z�p�v�Ƃ̌������ۂ��L�����ԂɊg�U���邱�Ƃł���A������s�ׂ̂悤�Ɏv���邪�A�@���Ȃ��̂ł�
�낤���B
�@�����āA���ɁA���Z�p�ł���u�z�E�r�C�ْ�~���̋C���x�~�V�X�e���v�̓��쎩���Ԃ̘_�����̂悤�ɁA�C���x�~
�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p��s�����Ȃ߂邽�߂ɂ\�����̂������ł���A���쎩���Ԃ��܂�
�����ԃ��[�J���C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p�Ɠ������x���̋Z�p�����݂̎����ԃ��[�J�ł�
���J���̏Ɋׂ��Ă���ƒf�肵�Ă��A�傫�ȊԈႢ�͖����ƍl������B���̂Ȃ�A�����ԃ��[�J�́A�C���x�~
�G���W���i�������J2005-54771�j�𗽉킵���V�Z�p�̊J���ɐ������Ă���̂ł���A���̐V�Z�p�\����ς�
���Ƃł���B���̏ꍇ�ɂ́A�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�́A�ۉ��Ȃ��A��������čs�����߂ł���B
�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p��s�����Ȃ߂邽�߂ɂ\�����̂������ł���A���쎩���Ԃ��܂�
�����ԃ��[�J���C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p�Ɠ������x���̋Z�p�����݂̎����ԃ��[�J�ł�
���J���̏Ɋׂ��Ă���ƒf�肵�Ă��A�傫�ȊԈႢ�͖����ƍl������B���̂Ȃ�A�����ԃ��[�J�́A�C���x�~
�G���W���i�������J2005-54771�j�𗽉킵���V�Z�p�̊J���ɐ������Ă���̂ł���A���̐V�Z�p�\����ς�
���Ƃł���B���̏ꍇ�ɂ́A�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�́A�ۉ��Ȃ��A��������čs�����߂ł���B
�@���������āA�V���ɒ�Ă������Z�p�̌��ד��e�̏ڍׂȐ����ɂ���Ď��p�s�\�Ƃ��錋�_�̋Z�p�_���������ԃ�
�[�J�����\���邱�Ƃ́A���̘_���\�����Ђ̒p�ƂȂ邽�߁A�ʏ�ł͗L�蓾�Ȃ����Ƃł���B�������A���̂悤��
��^�g���b�N�́u��NO�����v�Ɓu��R��v�ɔ�����ُ�Ș_������쎩���Ԃ������Ĕ��\�����̂́A��^�g���b�N�ɂ���
��u2015�N�x�d�ʎԔR������{10�����x�̔R�����v�Ɓu�m�n����0.23�@g/kWh ��NO���K���v�̃��x���i���K���l�j
�̋K�������̐摗����������邽�߂̎����ԃ��[�J�̎��X�Ȋ����̈�̂悤�Ɏv�����A�@���Ȃ��̂ł��낤���B
�[�J�����\���邱�Ƃ́A���̘_���\�����Ђ̒p�ƂȂ邽�߁A�ʏ�ł͗L�蓾�Ȃ����Ƃł���B�������A���̂悤��
��^�g���b�N�́u��NO�����v�Ɓu��R��v�ɔ�����ُ�Ș_������쎩���Ԃ������Ĕ��\�����̂́A��^�g���b�N�ɂ���
��u2015�N�x�d�ʎԔR������{10�����x�̔R�����v�Ɓu�m�n����0.23�@g/kWh ��NO���K���v�̃��x���i���K���l�j
�̋K�������̐摗����������邽�߂̎����ԃ��[�J�̎��X�Ȋ����̈�̂悤�Ɏv�����A�@���Ȃ��̂ł��낤���B
�@�����āA��^�g���b�N�́uNO���팸�v�Ɓu���s�R��̌���v�ɗL�����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓�����
�������x���̋Z�p�����ɑ��݂��Ă��Ȃ����������ƁA���݂̎����ԃ��[�J�ɂ́A�f�B�[�[���G���W���́uNO���팸�v��
��R�����v�̂��߂̐V�K�Ȕ��āE��Ă��ł���Z�p�J���͂̍����Z�p�ҁE���Ƃ���l�����Ȃ��Ɖ]�������ł���B
���̂Ȃ�A�Z�p�I�����āE����́A�l�I�Ȕ��z���琶�܂����̂ł���B���̂��Ƃ��l������ƁA���݂̊e������
���[�J�ɂ͐������̃G���W���W�̋Z�p�ҁE���Ƃ��������Ă�����̂́A���̐l�B�̐V�Z�p�̔��āE���z�̔\�͂�
���ꍇ�ɂ́A����̎����ԃ��[�J�ł��V�Z�p�����܂�Ȃ��̂́A���R�̂��Ƃł���B
�������x���̋Z�p�����ɑ��݂��Ă��Ȃ����������ƁA���݂̎����ԃ��[�J�ɂ́A�f�B�[�[���G���W���́uNO���팸�v��
��R�����v�̂��߂̐V�K�Ȕ��āE��Ă��ł���Z�p�J���͂̍����Z�p�ҁE���Ƃ���l�����Ȃ��Ɖ]�������ł���B
���̂Ȃ�A�Z�p�I�����āE����́A�l�I�Ȕ��z���琶�܂����̂ł���B���̂��Ƃ��l������ƁA���݂̊e������
���[�J�ɂ͐������̃G���W���W�̋Z�p�ҁE���Ƃ��������Ă�����̂́A���̐l�B�̐V�Z�p�̔��āE���z�̔\�͂�
���ꍇ�ɂ́A����̎����ԃ��[�J�ł��V�Z�p�����܂�Ȃ��̂́A���R�̂��Ƃł���B
�U�D�킪���ɂ������^�g���b�N�̔R����NO���K���̋K�������݂̍�ׂ��p
�@���ȁE�������R�c��̑�\�����\�ɓY�t���ꂽ��\���ł́A�u�\���ȃf�[�^���łȂ����߁A�����܂ł��ڈ�
�Ƃ��ĂƂ炦��ׂ����́v�Ƃ̒��ߕt����WHTC���[�h��NO���r�o�l��0.4 ��/��W���́AJE�O�T���[�h��NO���r�o�l��0.26 ��
/��W���ɑ������邱�Ƃ����L����Ă���B����WHTC���[�h��NO���r�o�l��JE�O�T���[�h�����R�T�������Ȃ�NO���r�o�l
�ɂȂ邱�Ƃ������ɂ��āA�u��\�����\�̋��e���x�ڕW�l�i���ϒl�j�� 0.4 ��/��W���iWHTC���[�h�j�v�́A�攪�����\�̃f
�B�[�[���d�ʎԂ̒���ڕW�i��0.7��/kW����1/3��0.23��/kW���iJE05 ���[�h�j�j�Ɓu�������x���v��NO���K���l�ł���ƒf
�肵�Ă���B�����āA�u��\�����\�̋��e���x�ڕW�l�i���ϒl�j�� 0.4 ��/��W���iWHTC���[�h�j�v�́A�A�攪�����\�̃f�B
�[�[���d�ʎԂ̒���ڕW��0.7��/kW����1/3��0.23��/kW���iJE05 ���[�h�j������������̂ł���A�f�B�[�[���d�ʎ�
�̎�����NO���K���l�Ƃ��ēK�ł���ƌ��_�t���Ă���B���̂悤�ɁA���ȁE�������R�c��̑�\�����\��
�u��\�����\�ɂ́ANO�����e���x�ڕW�l�i���ϒl�j�� 0.4 ��/��W���iWHTC���[�h�j�v�́A�u�\���ȃf�[�^���łȂ�
���߁A�����܂ł��ڈ��Ƃ��ĂƂ炦��ׂ����́v�Ɛ�������Ă���悤�ɁA�s�\���ŕs���m�Ȏ����f�[�^����ݒ�
���ꂽ���Ƃ����L����Ă���B
�Ƃ��ĂƂ炦��ׂ����́v�Ƃ̒��ߕt����WHTC���[�h��NO���r�o�l��0.4 ��/��W���́AJE�O�T���[�h��NO���r�o�l��0.26 ��
/��W���ɑ������邱�Ƃ����L����Ă���B����WHTC���[�h��NO���r�o�l��JE�O�T���[�h�����R�T�������Ȃ�NO���r�o�l
�ɂȂ邱�Ƃ������ɂ��āA�u��\�����\�̋��e���x�ڕW�l�i���ϒl�j�� 0.4 ��/��W���iWHTC���[�h�j�v�́A�攪�����\�̃f
�B�[�[���d�ʎԂ̒���ڕW�i��0.7��/kW����1/3��0.23��/kW���iJE05 ���[�h�j�j�Ɓu�������x���v��NO���K���l�ł���ƒf
�肵�Ă���B�����āA�u��\�����\�̋��e���x�ڕW�l�i���ϒl�j�� 0.4 ��/��W���iWHTC���[�h�j�v�́A�A�攪�����\�̃f�B
�[�[���d�ʎԂ̒���ڕW��0.7��/kW����1/3��0.23��/kW���iJE05 ���[�h�j������������̂ł���A�f�B�[�[���d�ʎ�
�̎�����NO���K���l�Ƃ��ēK�ł���ƌ��_�t���Ă���B���̂悤�ɁA���ȁE�������R�c��̑�\�����\��
�u��\�����\�ɂ́ANO�����e���x�ڕW�l�i���ϒl�j�� 0.4 ��/��W���iWHTC���[�h�j�v�́A�u�\���ȃf�[�^���łȂ�
���߁A�����܂ł��ڈ��Ƃ��ĂƂ炦��ׂ����́v�Ɛ�������Ă���悤�ɁA�s�\���ŕs���m�Ȏ����f�[�^����ݒ�
���ꂽ���Ƃ����L����Ă���B
�@���̂��Ƃ���A�������R�c��E��\�����\�ɓY�t���ꂽ��\���ɂ́A�f�B�[�[���d�ʎԂ̏����I��
�uNO�����e���x�ڕW�l�v�́A�攪�����\�̃f�B�[�[���d�ʎԂ̒���ڕW��0.7��/kW����1/3��0.23��/kW��
�iJE05 ���[�h�j��NO�����x����K��������ׂ��Ƃ̎|�����L����Ă���Ɠǂݎ�邱�Ƃ��\�ł���B������
���̒��ŁA�i�Ɓj��ʈ��S����������2014�N11��5�`6���ɊJ���u��ʈ��S���������t�H�[����2014�v�ɂ���
�āA��ʈ��S���������E�������̈�̗�؉��ꎁ�A�R���������A�Έ� �f������ю����Ԋ�F�؍��ے��a�Z
�p�x�����̐��V�a�K���́A�u�����d�ʎԗp�����T�C�N���̊T�v�Ɣr�o�K�X���\�]���@�Ƃ��Ă̓����v(�o�T�Fhttp://
www.ntsel.go.jp/forum/2014files/1105_1130.pdf�Ƒ肷��_�������\���ꂽ�B���̌�ʈ��S���������̗�؉��ꎁ
�����\�����u�����d�ʎԗp�����T�C�N���̔r�o�K�X���\�]���v�̘_���̎��������ł́A�`�A�a�A�b�̂R��̋����G���W
�����g�p����Ă��邪�A���̒���C�G���W���͍����ׂ̗̈�ł̔A�fSCR�G�}��NO���팸���\���ɋ@�\���Ȃ��悤��
���䂵���u�r�o�K�X����̖������v���̗p������@�E�E�@����̃G���W���ł���B����C�G���W���悤�Ȉ�@�E�E�@����
�̃G���W�������������Ɏg�p�����ꍇ�ɂ́A���m�Ȍ������ʂ������Ȃ��͓̂��R�̂��Ƃł���B�����ŁAJE�O�T��
�[�h�r�o�K�X�������̃G���W���^�]�̗̈�O�ɂ����āuNO���팸�@�\�������鐧��v���s�����ƌ�����
��@�E�E�@�����C�G���W����NO���r�o�f�[�^���폜�����̂��A�ȉ��̐}�P�ł���B
�uNO�����e���x�ڕW�l�v�́A�攪�����\�̃f�B�[�[���d�ʎԂ̒���ڕW��0.7��/kW����1/3��0.23��/kW��
�iJE05 ���[�h�j��NO�����x����K��������ׂ��Ƃ̎|�����L����Ă���Ɠǂݎ�邱�Ƃ��\�ł���B������
���̒��ŁA�i�Ɓj��ʈ��S����������2014�N11��5�`6���ɊJ���u��ʈ��S���������t�H�[����2014�v�ɂ���
�āA��ʈ��S���������E�������̈�̗�؉��ꎁ�A�R���������A�Έ� �f������ю����Ԋ�F�؍��ے��a�Z
�p�x�����̐��V�a�K���́A�u�����d�ʎԗp�����T�C�N���̊T�v�Ɣr�o�K�X���\�]���@�Ƃ��Ă̓����v(�o�T�Fhttp://
www.ntsel.go.jp/forum/2014files/1105_1130.pdf�Ƒ肷��_�������\���ꂽ�B���̌�ʈ��S���������̗�؉��ꎁ
�����\�����u�����d�ʎԗp�����T�C�N���̔r�o�K�X���\�]���v�̘_���̎��������ł́A�`�A�a�A�b�̂R��̋����G���W
�����g�p����Ă��邪�A���̒���C�G���W���͍����ׂ̗̈�ł̔A�fSCR�G�}��NO���팸���\���ɋ@�\���Ȃ��悤��
���䂵���u�r�o�K�X����̖������v���̗p������@�E�E�@����̃G���W���ł���B����C�G���W���悤�Ȉ�@�E�E�@����
�̃G���W�������������Ɏg�p�����ꍇ�ɂ́A���m�Ȍ������ʂ������Ȃ��͓̂��R�̂��Ƃł���B�����ŁAJE�O�T��
�[�h�r�o�K�X�������̃G���W���^�]�̗̈�O�ɂ����āuNO���팸�@�\�������鐧��v���s�����ƌ�����
��@�E�E�@�����C�G���W����NO���r�o�f�[�^���폜�����̂��A�ȉ��̐}�P�ł���B
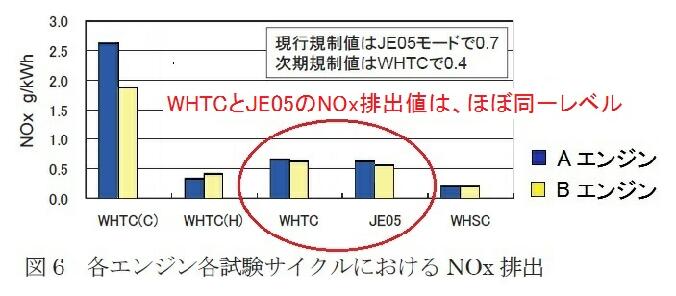 |
�@���̐}�P���画���������Ƃ́A��@�E�E�@������̗p���Ă��Ȃ�A�G���W����B�G���W����WHTC���[�h�i���R�[
���h�X�^�[�g�{�z�b�g�X�^�[�g�j��JE�O�T���[�h�i���z�b�g�X�^�[�g�j��NO���r�o�l���A�قړ���ł��邱�Ƃm��
�������������ʂł����B���̎����f�[�^����A�������R�c��E��\�����\�Ɏ����ꂽ�u�f�B�[�[���d�ʎԂ�
������NO�����e���x�ڕW�l�F0.4 ��/��W���i��WHTC���[�h�j�́A�攪�����\��NO������ڕW�F0.23 ��/kW���i��
JE�O�T���[�h�j�Ɠ����̃��x���ł���v�Ƃ̎�|�̓��\���e�́A���S�Ɍ��ł���ƍl������B���̂��߁A��
��A���Ȃ́A2016�N���{�\��́u�f�B�[�[���d�ʎԂɂ�����NO�����e���x�ڕW�l�F0.4 ��/��W���i��WHTC���[�h�j����
�������u�攪�����\�̃f�B�[�[���d�ʎԂ̒���ڕW��0.7��/kW����1/3��0.23��/kW���v�̃��x����NO���r�o�K��������
���}�Ɏ��{���邱�Ƃ��]�܂����ƍl������B����ɂ��ẮA�f�B�[�[���d�ʎ�2016�NNOx�K����0.4g/kWh�́A�s��
�Ȋɘa�̌��K���̃y�[�W�ɂ����ďڏq���Ă���̂ŁA�����̂�����͌䗗�������������B
���h�X�^�[�g�{�z�b�g�X�^�[�g�j��JE�O�T���[�h�i���z�b�g�X�^�[�g�j��NO���r�o�l���A�قړ���ł��邱�Ƃm��
�������������ʂł����B���̎����f�[�^����A�������R�c��E��\�����\�Ɏ����ꂽ�u�f�B�[�[���d�ʎԂ�
������NO�����e���x�ڕW�l�F0.4 ��/��W���i��WHTC���[�h�j�́A�攪�����\��NO������ڕW�F0.23 ��/kW���i��
JE�O�T���[�h�j�Ɠ����̃��x���ł���v�Ƃ̎�|�̓��\���e�́A���S�Ɍ��ł���ƍl������B���̂��߁A��
��A���Ȃ́A2016�N���{�\��́u�f�B�[�[���d�ʎԂɂ�����NO�����e���x�ڕW�l�F0.4 ��/��W���i��WHTC���[�h�j����
�������u�攪�����\�̃f�B�[�[���d�ʎԂ̒���ڕW��0.7��/kW����1/3��0.23��/kW���v�̃��x����NO���r�o�K��������
���}�Ɏ��{���邱�Ƃ��]�܂����ƍl������B����ɂ��ẮA�f�B�[�[���d�ʎ�2016�NNOx�K����0.4g/kWh�́A�s��
�Ȋɘa�̌��K���̃y�[�W�ɂ����ďڏq���Ă���̂ŁA�����̂�����͌䗗�������������B
�V�D���}�Ȏ��{�����߂��Ă�����{�́uNO���K���v�Ɓu�R���v�̋����ƁA���̃��x��
�@�ȉ��̕\�W�Ɏ������ʂ�A2005�N4��8���Ɋ��Ȃ֒�o���ꂽ���ȁE�������R�c����攪�����\�ł́A�f�B
�[�[���d�ʎԂ�2009�N�r�o�K�X�K���l NO�� �� 0.7��/kW���@�ƁA����ɑ����f�B�[�[���d�ʎԂ�NO���K����
���Ƃ��Ă� NO�� ���@0.23�@g/kW�@������ڕW�Ƃ��Ė��L����Ă���B
�[�[���d�ʎԂ�2009�N�r�o�K�X�K���l NO�� �� 0.7��/kW���@�ƁA����ɑ����f�B�[�[���d�ʎԂ�NO���K����
���Ƃ��Ă� NO�� ���@0.23�@g/kW�@������ڕW�Ƃ��Ė��L����Ă���B
| |
||||
| |
|
|||
| |
|
|||
| |
�@�M�҂̃R�����g
�@�@�������R�c�����Ȃɑ攪�����\����o���ꂽ2005�N4��8�����̓����ɂ����ẮA
�@�����A�č��ł�2010�N�̑�^�g�f�B�[�[���g���b�N��NO���K���Ƃ��āA0.27��/kW���̌�����
�@NO���K������������Ă����̂ł���B���̂悤�ȕč��̏��������Ă����ɂ�������炸�A
�@�������R�c��̑攪�����\�ł́A���{����^�g�f�B�[�[���g���b�N�ɂ����āA�č�����
�@�啝�Ɋɂ�0.7��/kW����NO���K����2009�N�Ɏ��{���邱�Ƃ\�����̂ł���B
�@
�@�@����ɂ�������炸�A�������R�c��̑攪�����\�ł́A�u�����2009�N�ڕW��0.7��/kW��
�@�����{���邱�Ƃɂ��A2009�`2010�N���_�ł͑�^�f�B�[�[���g���b�N�̕���Ő��E�ō����x��
�@��NO���K�������{�Ŏ��{�����v�ƋL�ڂ���Ă���B���̑攪�����\�ł́A�č���2010�N��
�@NO���K���l��0.27��/kW���ƁA���{��2009�N��NO���K���l��0.7��/kW���Ƃ��u�������x����
�@NO���K���v�ƒf�肵���o�L�ڂƂ��v����L�q�ƂȂ��Ă���B
�@�@���̂��Ƃ́A�|���R�c���Z�p���̕M�҂ɂƂ��ẮA���Ƃ����s�s�Ȃ��Ƃ̂悤�Ɏv���Ďd����
�@�Ȃ����Ƃł���B���̂��߁A�攪�����\���쐬���ꂽ�������R�c��E�����Ԕr�o�K�X���
�@�ψ���̊w�ҁE���Ƃ��č���2010�N��NO���K���l��0.27��/kW���ƁA���{��2009�N��
�@NO���K���l��0.7��/kW���Ƃ��u�������x����NO���K���v�ƒf�肳�ꂽ�����E�؋���Ƃ�������
�@���������������̂ł���B���͂Ƃ�����A�|���R�c���Z�p���̕M�҂ɂ́A�s���ȋL�q�Ǝv����
�@�攪�����\��2005�N4��8���ɒ������R�c�����Ȃɒ�o���ꂽ���Ƃ��A���Ƃ��[����
�@�ł��Ȃ����Ƃł���B
|
|||
| |
�@�M�҂̃R�����g
�@�������R�c��̑攪�����\�ł́A���{��2009�N��NO���K����0.7��/kW���̑��ɁA
�@����ڕW�i��0.7��/kW����1/3 ��0.23��/kW���j�Ə̂��鏫����NO���K�������̒l����Ă���B
�@���̗��R�́A�č���2010�N���{�\��Ƃ��ĂɌ�������0.27��/kW���ɔ�r���āA���{��2009�N��
�@��^�g�f�B�[�[���g���b�N��NO���K����0.7��/kW�����啝�Ɋɂ�NO���K���ł���Ƃ̔ᔻ�������
�@���߁A�����̒������R�c��̎����Ԕr�o�K�X���ψ���̊w�ҁE���Ƃɂ��Ƒ���
�@���H�̂悤�ɂ��v���邪�A�@���Ȃ��̂ł��낤���B
|
�@ ���݂ɁA�č������ɂ���^�g���b�N��NO���K�����{�s����������{���{�̑Ӗ��ɂ��ڏq���Ă���悤�ɁA��^�f�B
�[�[���g���b�N�Ɋւ�����{��NO���K���́A�\�X�Ɏ������ʂ�A���A�Ă�NO���K�������ɂ��K���l���{�s����Ă���
�̂�����̂悤�ł���B
�[�[���g���b�N�Ɋւ�����{��NO���K���́A�\�X�Ɏ������ʂ�A���A�Ă�NO���K�������ɂ��K���l���{�s����Ă���
�̂�����̂悤�ł���B
�@�� ���B �F 2013�N��EURO�Y�i�ߓn���[�h�j�́A�m�n�� �� 0.46 g/kWh�A
�@ EEV(5)�i�ߓn���[�h�j�́ANO�� �� 0.2 g/kWh
���@EEV�FEnhanced Environmentally Friendly Vehicles�̗��BEEV�K���l�́A��C���������ɐi�s���Ă���s�s���̒n��������̂��߁A����
�o�[�e���������I�Ɏg�p���邽�߂̒l�i��F�s�s�ւ̏����ꐧ����݂���ۂ̊�Ƃ��Ďg�p�j�ŁA�b��l�B
�o�[�e���������I�Ɏg�p���邽�߂̒l�i��F�s�s�ւ̏����ꐧ����݂���ۂ̊�Ƃ��Ďg�p�j�ŁA�b��l�B
�@�� �č� �F 2010�N�̂m�n���K���́ANO�� �� 0.27 g/kWh
�@�� ���{ �F 2016�N�̂m�n���K���́A�m�n���� 0.4 g/kWh
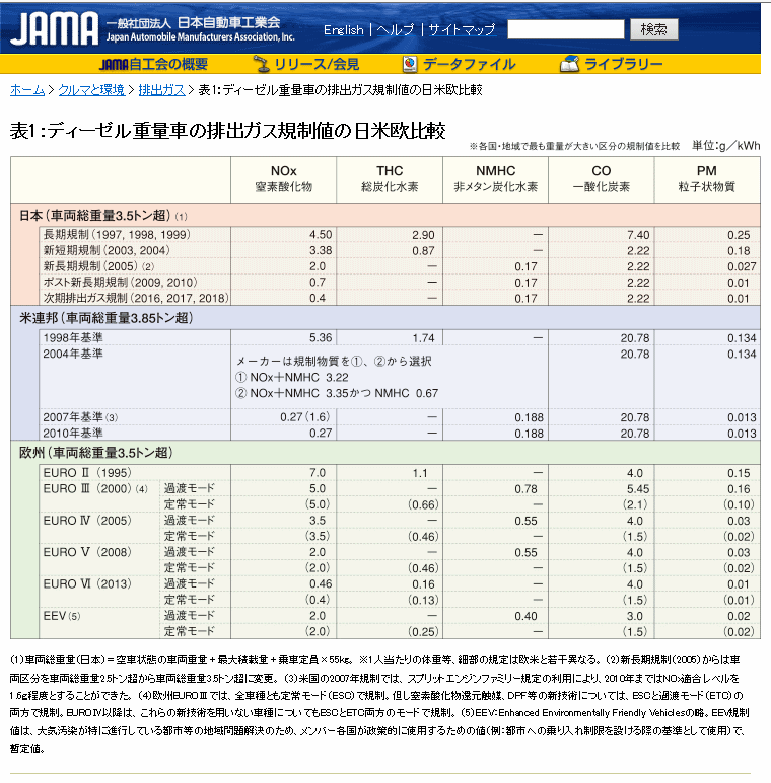 |
�@���̂悤�ɁA���A�Ăɂ������^�f�B�[�[���g���b�N��NO���r�o�K�X�K���́A���{�����������̂�����ł���B����
���߁A���{�ɂ����ẮA2005�N4��8���Ɋ��Ȃ֒�o���ꂽ���ȁE�������R�c����攪�����\�����L���ꂽ
�f�B�[�[���d�ʎԂ� NO�� ���@0.23�@g/kW�@������ڕW��NO���K���������Ɏ��{����K�v�������ƍl�����
��B�܂��A���{�̑�^�g���b�N�̔R��K���ł���2015�N�x�d�ʎԔR���́A2006�N�i����18�N�j4��1������{�s����
�Ċ���10�N�߂����o�߂��A�g���b�N�̔R����P�Z�p�ɑ����̐i���E�i�W�������邱�Ƃ���A���}��2015�N�x�d�ʎ�
�R���̋�����}��K�v������B�ȏ�̂��Ƃ����Ă���ƁA�߂������A���{�̑�^�g���b�N�́uNO���K���v��
�u�R���v�́A�ȉ��̕\10�Ɏ��������x���ɋ�������K�v�������ƍl������B
���߁A���{�ɂ����ẮA2005�N4��8���Ɋ��Ȃ֒�o���ꂽ���ȁE�������R�c����攪�����\�����L���ꂽ
�f�B�[�[���d�ʎԂ� NO�� ���@0.23�@g/kW�@������ڕW��NO���K���������Ɏ��{����K�v�������ƍl�����
��B�܂��A���{�̑�^�g���b�N�̔R��K���ł���2015�N�x�d�ʎԔR���́A2006�N�i����18�N�j4��1������{�s����
�Ċ���10�N�߂����o�߂��A�g���b�N�̔R����P�Z�p�ɑ����̐i���E�i�W�������邱�Ƃ���A���}��2015�N�x�d�ʎ�
�R���̋�����}��K�v������B�ȏ�̂��Ƃ����Ă���ƁA�߂������A���{�̑�^�g���b�N�́uNO���K���v��
�u�R���v�́A�ȉ��̕\10�Ɏ��������x���ɋ�������K�v�������ƍl������B
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
�W�D��^�g���b�N�́u�m�n��=0.23g/kWh�v�Ɓu2015�N�x�R���{10���v�������ł���Z�p
�@�|���R�c���Z�p���̕M�҂�10�N�O��2004�N5��25���ɏo�肵���Q�^�[�{�����̋C���x�~�V�X�e�����C���x�~�G���W
���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p���^�g���b�N�̗̍p�����ꍇ�́A�u�m�n����0.23�@g/kWh�̋K�������v�A�����
�u2015�N�d�ʎԔR�����{10���������v�ɓK��������^�g���b�N��e�ՂɎ������邱�Ƃ��\�ł���B���̍����ɂ�
���Ă̐����́A�����ł͊������邱�Ƃɂ����B���̕M�Ғ�Ă��Q�^�[�{�����̋C���x�~�V�X�e�����C���x�~�G���W��
�i�������J2005-54771�j�̓����Z�p����^�g���b�N�́u�m�n����0.23�@g/kWh�̋K���v�A����сu2015�N�d�ʎԔR����
�{10���v��e�ՂɎ����ł��闝�R�ɂ��ẮA�M�҂̃z�[���y�[�W�@�C���x�~�G���W���ɂ���^�g���b�N�̒�R��
���A������C���x�~�́A�f�B�[�[���̂m�n���팸�ƔR�����̈ꋓ�����̋Z�p���I�ɏڏq���Ă���̂ŁA�����̂���
���͌䗗�������������B
���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p���^�g���b�N�̗̍p�����ꍇ�́A�u�m�n����0.23�@g/kWh�̋K�������v�A�����
�u2015�N�d�ʎԔR�����{10���������v�ɓK��������^�g���b�N��e�ՂɎ������邱�Ƃ��\�ł���B���̍����ɂ�
���Ă̐����́A�����ł͊������邱�Ƃɂ����B���̕M�Ғ�Ă��Q�^�[�{�����̋C���x�~�V�X�e�����C���x�~�G���W��
�i�������J2005-54771�j�̓����Z�p����^�g���b�N�́u�m�n����0.23�@g/kWh�̋K���v�A����сu2015�N�d�ʎԔR����
�{10���v��e�ՂɎ����ł��闝�R�ɂ��ẮA�M�҂̃z�[���y�[�W�@�C���x�~�G���W���ɂ���^�g���b�N�̒�R��
���A������C���x�~�́A�f�B�[�[���̂m�n���팸�ƔR�����̈ꋓ�����̋Z�p���I�ɏڏq���Ă���̂ŁA�����̂���
���͌䗗�������������B
�@�����āA�����Q�^�[�{�����̋C���x�~�V�X�e�����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p�́A2005�N3
���ɓ������J����Ă����ɁA2006�N4��7�����J�̕M�҂̃C���^�[�l�b�g�̃z�[���y�[�W�ɂ����ċZ�p���e���ڍׂ�
�������Ă���B�����āA���̕M�҂̃z�[���y�[�W�́A�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p�Ɋւ���Z
�p���́A�T�`�U�N���̐̂���A�C���^�[�l�b�g������Yahoo�����G���W���ł͏�ʂɌ��o����Ă������т�����B�i��
���̌��o���ʂ��Q�Ɓj�@���̂��߁A���{�̊w�ҁE���ƁE�Z�p�҂̏����́A�M�Ғ�Ă��Q�^�[�{�����̋C���x�~�V�X
�e�����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p�̑��݂����m���Ă�����̂ƍl������B
���ɓ������J����Ă����ɁA2006�N4��7�����J�̕M�҂̃C���^�[�l�b�g�̃z�[���y�[�W�ɂ����ċZ�p���e���ڍׂ�
�������Ă���B�����āA���̕M�҂̃z�[���y�[�W�́A�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p�Ɋւ���Z
�p���́A�T�`�U�N���̐̂���A�C���^�[�l�b�g������Yahoo�����G���W���ł͏�ʂɌ��o����Ă������т�����B�i��
���̌��o���ʂ��Q�Ɓj�@���̂��߁A���{�̊w�ҁE���ƁE�Z�p�҂̏����́A�M�Ғ�Ă��Q�^�[�{�����̋C���x�~�V�X
�e�����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p�̑��݂����m���Ă�����̂ƍl������B
�� 2009�N6��11���@Yahoo�����Łu�|�X�g�V�����v�v�̂P�ꌟ���ɂ����āA6��8�猏���̂Q�ʂƂV�ʁi����P�y�[�W�ځj��
���o���ꂽ���т���B�i��2009�N6��11���ł́u�|�X�g�V�����v�̂P���Yahoo�������� ���Q�ƕ��j
���o���ꂽ���т���B�i��2009�N6��11���ł́u�|�X�g�V�����v�̂P���Yahoo�������� ���Q�ƕ��j
�� 2010�N2��24���@Yahoo�����Łu�g���b�N�v�{�u��R��v�̂Q�ꌟ���ɂ����āA102�������̂P�ʁi����P�y�[�W�ځj��
���o���ꂽ���т���B�i��2010�N2��24���ł́u�g���b�N�v�{�u��R��v�̂Q���Yahoo�������� ���Q�ƕ��j
���o���ꂽ���т���B�i��2010�N2��24���ł́u�g���b�N�v�{�u��R��v�̂Q���Yahoo�������� ���Q�ƕ��j
�@�ߔN�̎����ԋZ�p���̔N�ӂ̎Q�l����������ƁA���̑������C���^�[�l�b�g���ł��邱�Ƃ��������ʂ�A�ŐV��
���ƁE�Z�p�҂͍ŐV�̋Z�p�����C���^�[�l�b�g�̃z�[���y�[�W������W���Ă���l�q���f����B���̂悤�ɁA�ߔN
�ł́A�C���^�[�l�b�g�͎�y�ȏ����W�̎�i�ł���B���̂��߁A�Љ�l�Ɗw���̋�ʖ����A�C���^�[�l�b�g�͑S�Ă̐l
�̏d�v�ȋZ�p���̎��W�̎�i�ɗp�����Ă���B���̂��߁A���{�ɂ�����命���̃G���W���W�̊w�ҁE���ƁE
�Z�p�҂́A��^�g���b�N�́u�m�n����0.23�@g/kWh�̋K���v�A����сu2015�N�d�ʎԔR�����{10���v��e�ՂɎ����ł�
��M�Ғ�Ă��C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p�̑��݂ɂ��ẮA����2009�N�`2010�N�̍���
����ɏ��m�E�F�����Ă������̂Ɛ��������B�ܘ_�A��������A���Ȃ�NO���K�������Ɍg��������Ԕr�o�K�X���
�ψ��ψ���A����э��y��ʏȂ̔R��K�������Ɍg��������ԔR�����ψ���̓��{���\����G���W���W
�������W�����w�ҁE���Ƃ����l�ɁA��^�f�B�[�[���g���b�N�́uNO���팸�v�Ɓu�R����P�v�̗����ɗD�ꂽ�@�\�E���ʂ�
��������M�Ғ�Ă��C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����̋Z�p�����\���ɓ��Ă������̂Ɛ�������
��B
���ƁE�Z�p�҂͍ŐV�̋Z�p�����C���^�[�l�b�g�̃z�[���y�[�W������W���Ă���l�q���f����B���̂悤�ɁA�ߔN
�ł́A�C���^�[�l�b�g�͎�y�ȏ����W�̎�i�ł���B���̂��߁A�Љ�l�Ɗw���̋�ʖ����A�C���^�[�l�b�g�͑S�Ă̐l
�̏d�v�ȋZ�p���̎��W�̎�i�ɗp�����Ă���B���̂��߁A���{�ɂ�����命���̃G���W���W�̊w�ҁE���ƁE
�Z�p�҂́A��^�g���b�N�́u�m�n����0.23�@g/kWh�̋K���v�A����сu2015�N�d�ʎԔR�����{10���v��e�ՂɎ����ł�
��M�Ғ�Ă��C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p�̑��݂ɂ��ẮA����2009�N�`2010�N�̍���
����ɏ��m�E�F�����Ă������̂Ɛ��������B�ܘ_�A��������A���Ȃ�NO���K�������Ɍg��������Ԕr�o�K�X���
�ψ��ψ���A����э��y��ʏȂ̔R��K�������Ɍg��������ԔR�����ψ���̓��{���\����G���W���W
�������W�����w�ҁE���Ƃ����l�ɁA��^�f�B�[�[���g���b�N�́uNO���팸�v�Ɓu�R����P�v�̗����ɗD�ꂽ�@�\�E���ʂ�
��������M�Ғ�Ă��C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����̋Z�p�����\���ɓ��Ă������̂Ɛ�������
��B
�X�D��^�f�B�[�[���g���b�N�́u�R���v�ƁuNO���K���v�̋����̐E�ӂ��w�ҁE����
�@��^�f�B�[�[���g���b�N�Ɋւ��A�\�P�P�Ɏ������ʂ�A�u�d�ʎԃ��[�h�R���v�̋����ɂ��ẮA���y��ʏȂ̔R��
�K�������Ɍg��������ԔR�����ψ����̈ψ��߂�G���W���W�̊w�ҁE���Ƃ��d�v�Ȗ������ʂ�����A
�uNO���K���̋����v�ɂ��Ă͊��Ȃ�NO���K�������Ɍg��钆�����R�c���C�E�����U��������Ԕr�o�K�X
���ψ��ψ���̈ψ��߂�G���W���W�̊w�ҁE���Ƃ����S�ɐݒ�E���肳��Ă�����̂Ɛ��������B
�K�������Ɍg��������ԔR�����ψ����̈ψ��߂�G���W���W�̊w�ҁE���Ƃ��d�v�Ȗ������ʂ�����A
�uNO���K���̋����v�ɂ��Ă͊��Ȃ�NO���K�������Ɍg��钆�����R�c���C�E�����U��������Ԕr�o�K�X
���ψ��ψ���̈ψ��߂�G���W���W�̊w�ҁE���Ƃ����S�ɐݒ�E���肳��Ă�����̂Ɛ��������B
�@�� �����ԔR�����ψ���̈ψ�����A 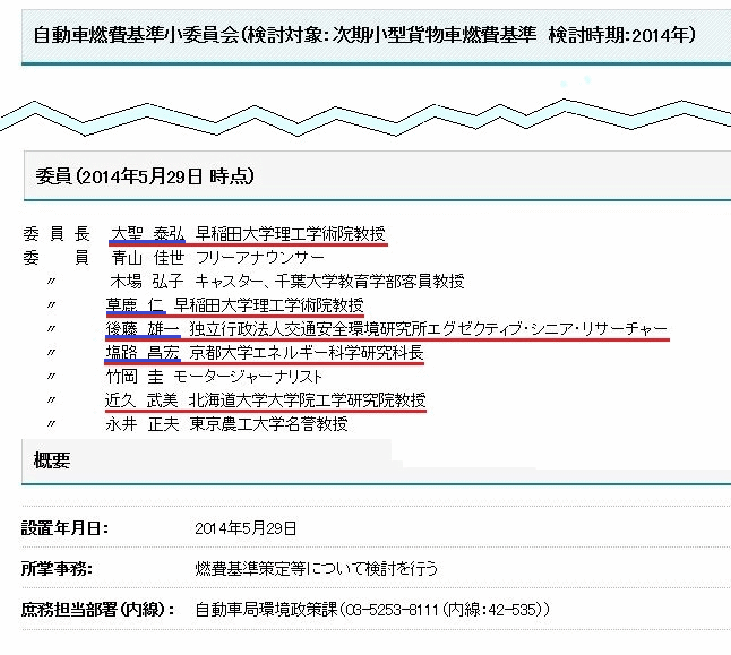 |
�@�� �������R�c���C�E�����U��������Ԕr�o�K�X���ψ����]
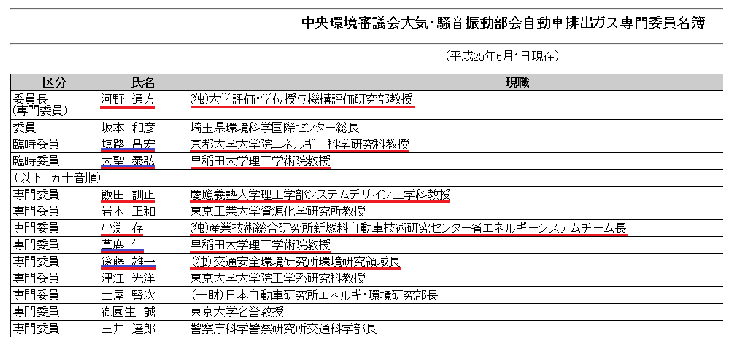 |
�@�@�@�@�@�@�ԐF�ƐF�̉����́A�����Ԕr�o�K�X���ψ��ψ���Ǝ����ԔR�����ψ���Ƃ����C����Ă���ψ�
�@�ȏ�̕\�V�Ɏ������悤�ɁA���Ȃ�NO���K�������Ɍg����������R�c���C�E�����U��������Ԕr�o�K�X
���ψ��ψ���̃G���W���W�̊w�ҁE���Ƃ͈ψ������܂߂ĂV���ł���A���y��ʏȂ̔R��K�������Ɍg���
�����ԔR�����ψ����̃G���W���W�̊w�ҁE���Ƃ͈ψ������܂߂ĂT���ł���B�������A���ψ���ɂ͏d����
�ꂽ�G���W���W�̊w�ҁE���Ƃ͂S���ł���B���̂��ߗ��ψ���̃G���W���W�̊w�ҁE���Ƃ́A�ȉ��Ɏ�����
���� �W ���ł���B
���ψ��ψ���̃G���W���W�̊w�ҁE���Ƃ͈ψ������܂߂ĂV���ł���A���y��ʏȂ̔R��K�������Ɍg���
�����ԔR�����ψ����̃G���W���W�̊w�ҁE���Ƃ͈ψ������܂߂ĂT���ł���B�������A���ψ���ɂ͏d����
�ꂽ�G���W���W�̊w�ҁE���Ƃ͂S���ł���B���̂��ߗ��ψ���̃G���W���W�̊w�ҁE���Ƃ́A�ȉ��Ɏ�����
���� �W ���ł���B
| �吹�@�G | ����c��w���� |
| �����@�m | ����c��w���� |
| �㓡�@�Y�� | �i�Ɓj��ʈ��S���������G�O�[�N�e�B�u�E�V�j�A�E���T�[�`���[ |
| ���H�@���G | ���s��w���� |
| �ߋv�@���� | �k�C����w���� |
| �͖�@���� | �i�Ɓj��w�]���E�w�ʎ��^�@�\�]������������ |
| �ѓc�@�P�� | �c���`�m��w���� |
| �����@�� | �i�Ɓj�Y�����E�G�l���M�[�V�X�e���`�[���� |
�@���݁i��2014�N9���j�̂Ƃ���A���Ȃ�NO���K�������Ɍg��������Ԕr�o�K�X���ψ��ψ���A����э��y���
�Ȃ̔R��K�������Ɍg��������ԔR�����ψ���ɂ́A�����Ⴕ���͕Е��̈ψ���̈ψ��ɔC������Ă���G��
�W���W�̊w�ҁE���Ƃ́A�����W���ł���B�����āA�����i��2014�N9���j�A���̂W���̓��{���\����G���W���W
�̊w�ҁE���Ƃ́A���{�̎����Ԃɂ����鏫���́uNO���̋K���v�Ɓu�R��K���i���R���j�v�̋K�����������鐅��
�i���������郌�x���j�Ƌ��������{���鎞�����������A�����ݒ肷�鋭�����������{�i�����ȁE���y��ʏȁj����
�^�����Ă���̂ł���B
�Ȃ̔R��K�������Ɍg��������ԔR�����ψ���ɂ́A�����Ⴕ���͕Е��̈ψ���̈ψ��ɔC������Ă���G��
�W���W�̊w�ҁE���Ƃ́A�����W���ł���B�����āA�����i��2014�N9���j�A���̂W���̓��{���\����G���W���W
�̊w�ҁE���Ƃ́A���{�̎����Ԃɂ����鏫���́uNO���̋K���v�Ɓu�R��K���i���R���j�v�̋K�����������鐅��
�i���������郌�x���j�Ƌ��������{���鎞�����������A�����ݒ肷�鋭�����������{�i�����ȁE���y��ʏȁj����
�^�����Ă���̂ł���B
�@�����āA���������W���̓��{���\����G���W���W�̊w�ҁE���Ƃ́A���݁i��2014�N9���j�܂ł̂Ƃ���A
��^�g���b�N�ɂ������u�@ DPF���u�̋����Đ��̕p�x�����v�A�u�A SCR�G�}�̒ቷ�����v�A�u�BSCR�G�}��HC
��ł̉����v�A����сu�C �d�ʎԃ��[�h�R��̉��P�v�̂S���ڂ̏d�v�ۑ�̑S�Ă����ނ̋Z�p�ʼn����ł���
�Z�p���A������āE�E���J����Ă��Ȃ��悤�ł���B���̂����A���̑����W���̓��{���\����G���W���W��
�w�ҁE���Ƃ̑S���́A�����_�i��2015�N�V�����݁j�ł́A��^�g���b�N�ɂ����� �@�`�C�̂S���ڂ��ۑ�̑S�Ă�����
�ł���Z�p���s���Ɣ��f����Ă���悤�Ɍ�����̂ł���B
��^�g���b�N�ɂ������u�@ DPF���u�̋����Đ��̕p�x�����v�A�u�A SCR�G�}�̒ቷ�����v�A�u�BSCR�G�}��HC
��ł̉����v�A����сu�C �d�ʎԃ��[�h�R��̉��P�v�̂S���ڂ̏d�v�ۑ�̑S�Ă����ނ̋Z�p�ʼn����ł���
�Z�p���A������āE�E���J����Ă��Ȃ��悤�ł���B���̂����A���̑����W���̓��{���\����G���W���W��
�w�ҁE���Ƃ̑S���́A�����_�i��2015�N�V�����݁j�ł́A��^�g���b�N�ɂ����� �@�`�C�̂S���ڂ��ۑ�̑S�Ă�����
�ł���Z�p���s���Ɣ��f����Ă���悤�Ɍ�����̂ł���B
�P�O�DNO���E�R��̋K��������S���w�҂��C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j��َE
�@�ߔN�̃C���^�[�l�b�g�̕��y�ɂ��A���Ȃ�NO���K�������Ɍg��������Ԕr�o�K�X���ψ��ψ���A����э��y
��ʏȂ̔R��K�������Ɍg��������ԔR�����ψ���̓��{���\����G���W���W�������W�����w�ҁE���
�Ƃ́A��^�g���b�N�́u�m�n����0.23�@g/kWh�̋K���v�A����сu2015�N�d�ʎԔR�����{10���v��e�ՂɎ����ł���M
�Ғ�Ă��C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p�̑��݂��A2009�N�`2010�N�̍��ɂ͊m���ɏ��m�E�F
�����Ă������̂ƍl������B
��ʏȂ̔R��K�������Ɍg��������ԔR�����ψ���̓��{���\����G���W���W�������W�����w�ҁE���
�Ƃ́A��^�g���b�N�́u�m�n����0.23�@g/kWh�̋K���v�A����сu2015�N�d�ʎԔR�����{10���v��e�ՂɎ����ł���M
�Ғ�Ă��C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p�̑��݂��A2009�N�`2010�N�̍��ɂ͊m���ɏ��m�E�F
�����Ă������̂ƍl������B
[�����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p�́A2009�N�`2010�N�̍��ɂ́A�G���W���ɋ����̂���l�B�i���w�ҁE���ƁE�Z�p
�ҁE�w���j�ɃC���^�[�l�b�g�����Œm��n���Ă������Ƃ��O�q�́u�W�D��^�g���b�N�́u�m�n��=0.23g/kWh�v�Ɓu2015�N�x�R���{10���v�������ł�
��Z�p�v�̍��ɋL�ڍς݁B]
�ҁE�w���j�ɃC���^�[�l�b�g�����Œm��n���Ă������Ƃ��O�q�́u�W�D��^�g���b�N�́u�m�n��=0.23g/kWh�v�Ɓu2015�N�x�R���{10���v�������ł�
��Z�p�v�̍��ɋL�ڍς݁B]
�P�O�|�P �C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�ɂ��Ă̊w��������̎��������w�����̑Ή�
�@�O�q�̂W���ɏq�ׂĂ���悤�ɁA�M�҂̃z�[���y�[�W���{�����������̃G���W���ɋ����̂��鑽���̊w���́A���Ȃ���
��2009�N�ȍ~�ɂ����ẮA�����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p�ɂ��Ă̋Z�p���ʂɓ�
�Ă�����̂ƍl������B���̏ꍇ�A�����̊w���́A�ނ炪�ʊw�����w�̃G���W�����̋����ɁA�C���x�~�G���W
���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p�ɂ��āuNO���팸�v�Ɓu�R����P�v�̗L������A���̎��p���E�������ɂ��Ċ�
���Ȏ���𗁂т��Ă�����̂Ɛ��@�����B�����āA���̎���́A���N�A�V�����������ɓ���w������J��Ԃ���Ă���
���̂Ɨ\�z�����B���Ă��āA���Ȃ̂ƍ��y��ʏȂ̈ψ���ɑ�����Ă���G���W�����̂U���̑�w�����i���͖�
���������A�ѓc�P�������A���H���G�����A�吹�G�����A�����m�����A�ߋv���������j�́A�M�҂��C���x�~�G���W
���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p�ɂ��Ă̊w��������̎���ɑ��āA�@���Ȃ��^���Ă����̂ł��낤
���B�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p�N�ɘj���Ė����E�َE����Ă�����猩��ƁA��w
�ɍ˂̃|���R�c���Z�p���̕M�҂̎v�������́A�ȉ��̇@�ƇA����ł���B
��2009�N�ȍ~�ɂ����ẮA�����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p�ɂ��Ă̋Z�p���ʂɓ�
�Ă�����̂ƍl������B���̏ꍇ�A�����̊w���́A�ނ炪�ʊw�����w�̃G���W�����̋����ɁA�C���x�~�G���W
���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p�ɂ��āuNO���팸�v�Ɓu�R����P�v�̗L������A���̎��p���E�������ɂ��Ċ�
���Ȏ���𗁂т��Ă�����̂Ɛ��@�����B�����āA���̎���́A���N�A�V�����������ɓ���w������J��Ԃ���Ă���
���̂Ɨ\�z�����B���Ă��āA���Ȃ̂ƍ��y��ʏȂ̈ψ���ɑ�����Ă���G���W�����̂U���̑�w�����i���͖�
���������A�ѓc�P�������A���H���G�����A�吹�G�����A�����m�����A�ߋv���������j�́A�M�҂��C���x�~�G���W
���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p�ɂ��Ă̊w��������̎���ɑ��āA�@���Ȃ��^���Ă����̂ł��낤
���B�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p�N�ɘj���Ė����E�َE����Ă�����猩��ƁA��w
�ɍ˂̃|���R�c���Z�p���̕M�҂̎v�������́A�ȉ��̇@�ƇA����ł���B
�@ �u�|���R�c���Z�p�������p���̂����^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W����NO���팸�ƔR�����ɗL���ȓ���
�Z�p���ł��锤�������B���Z�Ȏ��ɁA�|���R�c�����̕ςȎ��������ȁI�v�ƈꊅ���A��O�������s���B
�Z�p���ł��锤�������B���Z�Ȏ��ɁA�|���R�c�����̕ςȎ��������ȁI�v�ƈꊅ���A��O�������s���B
�@���ɁA�����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p�ɂ́A��^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W���ɂ�����u�@ DPF���u�̋����Đ���
�p�x�����v�A�u�A SCR�G�}�̒ቷ�����v�A�u�BSCR�G�}��HC��ł̉����v�A����сu�C �d�ʎԃ��[�h�R��̉��P�v�̂S���ڂ̉ۑ�������ł����
�@�\�E���\�������A�|���R�c���Z�p���́u�o�L�ڂȓ����v�Ⴕ���́u�n���ȃ}�j�A�̓ƑP�I�Ȉ�������v�ł���ƂU���̑�w�������w���ɉ���
�ꍇ�ɂ́A���₵���w���̑S�����@�`�C�̉ۑ�����ɗL���ȐV�Z�p�ɂ��āA��w�����Ɋm���ɖ₢�������̂Ɛ��������B���̏ꍇ�A����
�_�i��2015�N7���j�ł͑�^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W���̇@�`�C�̉ۑ�����ɗL���Ȏ��p�ȋZ�p������E��Ăł��Ă��Ȃ���w����
�́A�w���̎���ɓ����邱�Ƃɋ�������̂Ɛ��������B�����ő�w�����́A���̂悤�ȋ��n�Ɋׂ邱�Ƃ����O�ɉ�����邽�߂ɐ������A�C��
�x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p�Ɋւ���w���̎�����O���������邽�߂ɁA�u���Z�Ȏ��ɁA�|���R�c�����̕ςȎ��������
�ȁI�v�ƌ��������t�Ŗ�O���������邱�Ƃł���B�����Ƃ��A���{���\����G���W�����̂U���̑�w�����������q�̊w���ɁA���̂悤�ȌƑ���
�Ή��������Ƃ́A�L�蓾�Ȃ��ƍl����̂��Ó��ł͂Ȃ����낤���B
�p�x�����v�A�u�A SCR�G�}�̒ቷ�����v�A�u�BSCR�G�}��HC��ł̉����v�A����сu�C �d�ʎԃ��[�h�R��̉��P�v�̂S���ڂ̉ۑ�������ł����
�@�\�E���\�������A�|���R�c���Z�p���́u�o�L�ڂȓ����v�Ⴕ���́u�n���ȃ}�j�A�̓ƑP�I�Ȉ�������v�ł���ƂU���̑�w�������w���ɉ���
�ꍇ�ɂ́A���₵���w���̑S�����@�`�C�̉ۑ�����ɗL���ȐV�Z�p�ɂ��āA��w�����Ɋm���ɖ₢�������̂Ɛ��������B���̏ꍇ�A����
�_�i��2015�N7���j�ł͑�^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W���̇@�`�C�̉ۑ�����ɗL���Ȏ��p�ȋZ�p������E��Ăł��Ă��Ȃ���w����
�́A�w���̎���ɓ����邱�Ƃɋ�������̂Ɛ��������B�����ő�w�����́A���̂悤�ȋ��n�Ɋׂ邱�Ƃ����O�ɉ�����邽�߂ɐ������A�C��
�x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p�Ɋւ���w���̎�����O���������邽�߂ɁA�u���Z�Ȏ��ɁA�|���R�c�����̕ςȎ��������
�ȁI�v�ƌ��������t�Ŗ�O���������邱�Ƃł���B�����Ƃ��A���{���\����G���W�����̂U���̑�w�����������q�̊w���ɁA���̂悤�ȌƑ���
�Ή��������Ƃ́A�L�蓾�Ȃ��ƍl����̂��Ó��ł͂Ȃ����낤���B
�A ���쎩���Ԃ��_�����\�����R����P�@�\�̗��C���x�~�V�X�e���ɏڏq�����v���I�ȋZ�p�I���ׂ�����
���쎩���Ԃ��u�z�E�r�C�ْ�~���̋C���x�~�V�X�e���v�i�����ԋZ�p��2014�N�t�G���Ŕ��\�j�̘_���̃R�s
�[���w���Ɏ�n���A�M�Ғ�Ă��C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j���Q�^�[�{�����̋C���x�~�V�X�e��
�����Z�p�Ƃ̉R�̐���������B
���쎩���Ԃ��u�z�E�r�C�ْ�~���̋C���x�~�V�X�e���v�i�����ԋZ�p��2014�N�t�G���Ŕ��\�j�̘_���̃R�s
�[���w���Ɏ�n���A�M�Ғ�Ă��C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j���Q�^�[�{�����̋C���x�~�V�X�e��
�����Z�p�Ƃ̉R�̐���������B
�@�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p�I�ȗL�������������w���ɑ��A��w�����͍ŏ��������ԋZ�p��2014�N�t�G����
���\�����쎩���Ԃ��u�z�E�r�C�ْ�~���̋C���x�~�V�X�e���v�̘_���̎����ꂽ�C���x�~�ɂ͎��p���̖ʂŒv���I�Ȍ��ׂ̂��邱�Ƃ�
�؋��������B�����āA�M�Ғ�Ă��Q�^�[�{�����̋C���x�~�V�X�e�����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p�ɂ����p���
���ׂ����邽�߁A��^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W���̇@�`�C�̂S���ڂ̉ۑ�������ɖ����ł��邱�Ƃ��w���ɐ�������B����ɂ���āA
��w�����́A���N�ɘj���C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̖����E�َE���_���I�ɐ������悤�Ɍ��������邱�Ƃł���B���̏ꍇ�A
��ʓI�Ȍ����ł́A��w�������w���ɋɂ߂Đ����ɉ��Ă���悤�Ɍ����邽�߁A�D�ꂽ�����������q�̊w���ɑf���炵��������s����
���邩�悤�Ȍ��i�Ǝv�������ł���B�Ƃ��낪�A����͑S���t�ł���A��w��������������e�̋�����w���ɍs���Ă��邱�ƂɂȂ�B���̍����́A
�\���I�ɏd��Ȍ��ׂ̂�����쎩���Ԃ��u�z�E�r�C�ْ�~���̋C���x�~�V�X�e���v�����p���A�e�ՂɎ��p���̉\�Ȍ��ׂ̖���
�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p�����p���̍�����u���Z�p�v�Ƃ̌���������E�������A��w�������w���ɍu���Ă���
���ƂɂȂ�ƍl������B����ɂ��āA���̑�w�������C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p���u���Z�p�v�ƒf�肵��
���@�́A(a�j�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p�𗝉�����\�͕s���i�����\�j�̂��߂ɁA���̓����Z�p�����쎩���Ԃ�
�u�z�E�r�C�ْ�~���̋C���x�~�V�X�e���v�Ɨގ��������Z�p�Ƃ̌�������f�E�F�������Ă��܂����ꍇ��A�i���j���ʂ̎����i����q��7-8��
�Ɏ�����������܂ށj�̂��߂��C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p�����Z�p�Ƃ��鋕�U������������Ȃ�����E����
������Ă���ꍇ���l������B���������āA��w���������쎩���Ԃ��u�z�E�r�C�ْ�~���̋C���x�~�V�X�e���v�����p����
�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p���u���Z�p�v�ƒf�肵�Ċw���ɐ��������ꍇ�ɂ́A�u���\�v�A�Ⴕ���́u���\�t�v��
�悤�ȑ�w�����ƌ����Ă��d���̖����ƍl������B�����͌����Ă��A�U���̑�w�����́A���{���\����G���W�����̊w�҂ł��邱��
����A(a�j�̂悤�ɐV�Z�p�𗝉�����\�͕s���i�����\�j�ƍl���邱�Ƃ͖��O�ł���A�i���j�̂悤�ɓ��ʂȎ������������߂ɋ��U����������
�s�ސT�ȑΉ������邱�Ɠ����A�펯�I�ɂ͗L�蓾�Ȃ��ƍl����̂��Ó��ł͂Ȃ����낤���B���݂ɁA�\���I�ɏd��Ȍ��ׂ̂�����쎩����
���u�z�E�r�C�ْ�~���̋C���x�~�V�X�e���v�̘_���́A2014�N5���ɔ��\���ꂽ���̂ł���B���������āA2014�N5���ȑO�ɂ����ẮA�U����
��w�����́A�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p�����p���̍�����u���Z�p�v�ƒf�肷�邽�߂̏؋��Ƃ��ẮA�@��
�Ȃ�_�������w���ɒ����̂ł��낤���B
�@���̂悤�ɁA���y��ʏȂƊ��Ȃ̎���ψ����U���̑�w�������C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓���
�Z�p�̋@�\�E���\����p���ɂ��Ċw�����玿������ꍇ�A��w�ɍ˂̃|���R�c���Z�p���̕M�҂ɂ́A�ȏ��
�@���A�̖R�������e�̗̉\�������v�������Ȃ��B�v����ɁA���Ȃ�NO���K�������Ɍg��������Ԕr�o�K�X
���ψ��ψ���A����э��y��ʏȂ̔R��K�������Ɍg��������ԔR�����ψ���ɑ�����U���̑�w����
�i���͖쓹�������A�ѓc�P�������A���H���G�����A�ߋv�@���������A�吹�G�����A�����@�m�����j���A�C���x�~�G
���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p���E�َE���闝�R�E������M�҂��\���E���@���邱�Ƃ́A����ł��邱��
�����炩�ł���B
�Z�p�̋@�\�E���\����p���ɂ��Ċw�����玿������ꍇ�A��w�ɍ˂̃|���R�c���Z�p���̕M�҂ɂ́A�ȏ��
�@���A�̖R�������e�̗̉\�������v�������Ȃ��B�v����ɁA���Ȃ�NO���K�������Ɍg��������Ԕr�o�K�X
���ψ��ψ���A����э��y��ʏȂ̔R��K�������Ɍg��������ԔR�����ψ���ɑ�����U���̑�w����
�i���͖쓹�������A�ѓc�P�������A���H���G�����A�ߋv�@���������A�吹�G�����A�����@�m�����j���A�C���x�~�G
���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p���E�َE���闝�R�E������M�҂��\���E���@���邱�Ƃ́A����ł��邱��
�����炩�ł���B
�@��킭�A���{���\����G���W�������U���̑�w���������C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�̓����Z�p
���E�َE���鍪���E���R�̐����������́A���̓��e�������x���̂Ȃ��͈͂ŕM�҂ɂ�����������K���ł�
��B�i�M�҂�E���[���̈���́A�{�y�[�W�̖����ɋL�ځj�@�����āA���̐����̒����C���x�~�G���W���i�������J2005-
54771�j�̓����Z�p�̒v���I�Ȍ��ׂ����m�Ɍ�w�E����Ă���̂ł���A�����A���̓����Z�p�ɊW����z�[���y
�[�W����������ƍl���Ă���B���̂Ȃ�A���̓����������I�Ɏ��p��������ȋZ�p�ł���A���{�̑�^�g���b�N
�̏����I�ȁuNO���팸�v�Ɓu�R��̌���v�Ɋ�^���Ȃ��Z�p���̃m�C�Y�E�G���E��Q�ɑ���Ȃ��Ɣ��f�ł��邽�߂ł�
��B
���E�َE���鍪���E���R�̐����������́A���̓��e�������x���̂Ȃ��͈͂ŕM�҂ɂ�����������K���ł�
��B�i�M�҂�E���[���̈���́A�{�y�[�W�̖����ɋL�ځj�@�����āA���̐����̒����C���x�~�G���W���i�������J2005-
54771�j�̓����Z�p�̒v���I�Ȍ��ׂ����m�Ɍ�w�E����Ă���̂ł���A�����A���̓����Z�p�ɊW����z�[���y
�[�W����������ƍl���Ă���B���̂Ȃ�A���̓����������I�Ɏ��p��������ȋZ�p�ł���A���{�̑�^�g���b�N
�̏����I�ȁuNO���팸�v�Ɓu�R��̌���v�Ɋ�^���Ȃ��Z�p���̃m�C�Y�E�G���E��Q�ɑ���Ȃ��Ɣ��f�ł��邽�߂ł�
��B
�P�O�|�Q ���Ȃƍ��y��ʏȂ��ψ����̊w�҂��C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j��َE���闝�R
�@���Ȃ������Ԕr�o�K�X���ψ��ψ���A����э��y��ʏȂ������ԔR�����ψ����̗����Ⴕ���͕Е���
�ψ���ɓo�^����Ă��鑍���W���̃G���W���W�̊w�ҁE���Ɓi���͖쓹�������A�ѓc�P�������A�㓡�V��k�Ɓl�Y
�����E�Z���^�[���A���H���G�����A���R�������劲�A�吹�G�����j�́A�G���W���Ɋւ��锎�w�̒m�������������
�ł��邽�߁A�M�҂̃z�[���y�[�W���C���^�[�l�b�g�ŗe�ՂɌ�������o����2009�N6�����̎��_�ɂ����ẮA��^�g���b
�N�ɂ������u�@ DPF���u�̋����Đ��̕p�x�����v�A�u�A SCR�G�}�̒ቷ�����v�A�u�BSCR�G�}��HC��ł̉����v�A����
�сu�C �d�ʎԃ��[�h�R��̉��P�v�̂S���ڂ̍ŏd�v�ۑ�̑S�Ă��C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z
�p�����������ł��邱�������ɏ��m�E�F������Ă��Ɛ��������B�������Ȃ���A���̑����W���̃G���W���W�̊w�ҁE
���Ƃ̏����́A�����_�i��2015�N7���j�ł��A��^�g���b�N�ɂ�����@�`�C���S���ڂ̍ŏd�v�ۑ�̑S�Ă������ł�
���C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p�����S�ɖ����E�َE����Ă��邱�Ƃ���R���鎖���̂悤�ł�
��B
�ψ���ɓo�^����Ă��鑍���W���̃G���W���W�̊w�ҁE���Ɓi���͖쓹�������A�ѓc�P�������A�㓡�V��k�Ɓl�Y
�����E�Z���^�[���A���H���G�����A���R�������劲�A�吹�G�����j�́A�G���W���Ɋւ��锎�w�̒m�������������
�ł��邽�߁A�M�҂̃z�[���y�[�W���C���^�[�l�b�g�ŗe�ՂɌ�������o����2009�N6�����̎��_�ɂ����ẮA��^�g���b
�N�ɂ������u�@ DPF���u�̋����Đ��̕p�x�����v�A�u�A SCR�G�}�̒ቷ�����v�A�u�BSCR�G�}��HC��ł̉����v�A����
�сu�C �d�ʎԃ��[�h�R��̉��P�v�̂S���ڂ̍ŏd�v�ۑ�̑S�Ă��C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z
�p�����������ł��邱�������ɏ��m�E�F������Ă��Ɛ��������B�������Ȃ���A���̑����W���̃G���W���W�̊w�ҁE
���Ƃ̏����́A�����_�i��2015�N7���j�ł��A��^�g���b�N�ɂ�����@�`�C���S���ڂ̍ŏd�v�ۑ�̑S�Ă������ł�
���C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p�����S�ɖ����E�َE����Ă��邱�Ƃ���R���鎖���̂悤�ł�
��B
�@�R��A���Ȃ������Ԕr�o�K�X���ψ��ψ���A����э��y��ʏȂ̔R�����ԔR�����ψ���������Ⴕ��
�͕Е��̈ψ���̈ψ��̑����W���̃G���W���W�̊w�ҁE���Ƃ́A��^�g���b�N�ɂ�����@�`�C���S���ڂ̍ŏd�v
�ۑ�̑S�Ă������ł����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p��@���Ȃ铮�@�E���R�ɂ���������E��
�E����Ă���̂ł��낤���B�|���R�c���Z�p���̕M�҂��א������C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z
�p�������E�َE�E�B������铮�@�E���R�́A�ȉ��̒ʂ�ł���B
�͕Е��̈ψ���̈ψ��̑����W���̃G���W���W�̊w�ҁE���Ƃ́A��^�g���b�N�ɂ�����@�`�C���S���ڂ̍ŏd�v
�ۑ�̑S�Ă������ł����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p��@���Ȃ铮�@�E���R�ɂ���������E��
�E����Ă���̂ł��낤���B�|���R�c���Z�p���̕M�҂��א������C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z
�p�������E�َE�E�B������铮�@�E���R�́A�ȉ��̒ʂ�ł���B
�� �������R A�F���Ȃ⍑�y��ʏȂ̈ψ��̊w�҂����g�̋Z�p�J���̔\�͕s�����B�����邽�߂̏��u
�@���Ȃ⍑�y��ʏȂ̈ψ���̗����Ⴕ���͕Е��̈ψ��ł��鑍���W���̃G���W���W�̊w�ҁE���Ƃ́A��{
�I�Ƀf�B�[�[���G���W�����uNO���팸�v�Ɓu�R����P�v�̋Z�p�J���i���V�Z�p�̊J���j����E�ӂ�S���Ă����ɁA�����
�ő�^�g���b�N���uNO���팸�v�Ɓu�R����P�v���ɂ߂č���ȋZ�p�J���ł��邱�Ƃ��@��̂��邲�Ƃɑ����ʂŋ�������
�Ă����o�܂�����B����ɂ�������炸�A�����_�i��2015�N7���j�ɂ������C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j
�̓����Z�p����^�g���b�N�łɂ������u�@ DPF���u�̋����Đ��̕p�x�����v�A�u�A SCR�G�}�̒ቷ�����v�A�u�BSCR�G
�}��HC��ł̉����v�A����сu�C �d�ʎԃ��[�h�R��̉��P�v���S���ڂ̍ŏd�v�ۑ�������ł��邱�ƗB��̋Z�p�ł�
�邱�Ƃ𑽂��ɐl���m��Ƃ���ƂȂ�A���Ȃ⍑�y��ʏȂ̈ψ��ł��鑍���W���̃G���W���W�̊w�ҁE����
�́A�u���U�̋Z�p���v�\���Ă������ƂɂȂ�B���̏�A��^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W���ɂ�����@�`�C���S����
�̋Z�p�ۑ���������������J���̔\�͂��|���R�c���Z�p���̕M�҂ɔ�ׂė���Ă������ƂɂȂ�A�������玸��
�邱�ƂɂȂ�Ɛ��������B�����āA���Ȃ������Ԕr�o�K�X���ψ��ψ���⍑�y��ʏȂ������ԔR��
���ψ���ɑ�����������̐M�������Ă��Ă��܂����ꂪ����B
�I�Ƀf�B�[�[���G���W�����uNO���팸�v�Ɓu�R����P�v�̋Z�p�J���i���V�Z�p�̊J���j����E�ӂ�S���Ă����ɁA�����
�ő�^�g���b�N���uNO���팸�v�Ɓu�R����P�v���ɂ߂č���ȋZ�p�J���ł��邱�Ƃ��@��̂��邲�Ƃɑ����ʂŋ�������
�Ă����o�܂�����B����ɂ�������炸�A�����_�i��2015�N7���j�ɂ������C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j
�̓����Z�p����^�g���b�N�łɂ������u�@ DPF���u�̋����Đ��̕p�x�����v�A�u�A SCR�G�}�̒ቷ�����v�A�u�BSCR�G
�}��HC��ł̉����v�A����сu�C �d�ʎԃ��[�h�R��̉��P�v���S���ڂ̍ŏd�v�ۑ�������ł��邱�ƗB��̋Z�p�ł�
�邱�Ƃ𑽂��ɐl���m��Ƃ���ƂȂ�A���Ȃ⍑�y��ʏȂ̈ψ��ł��鑍���W���̃G���W���W�̊w�ҁE����
�́A�u���U�̋Z�p���v�\���Ă������ƂɂȂ�B���̏�A��^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W���ɂ�����@�`�C���S����
�̋Z�p�ۑ���������������J���̔\�͂��|���R�c���Z�p���̕M�҂ɔ�ׂė���Ă������ƂɂȂ�A�������玸��
�邱�ƂɂȂ�Ɛ��������B�����āA���Ȃ������Ԕr�o�K�X���ψ��ψ���⍑�y��ʏȂ������ԔR��
���ψ���ɑ�����������̐M�������Ă��Ă��܂����ꂪ����B
�@���̂悤�ȏɂȂ邱�Ƃ�������邽�߂ɂ́A���Ȃ⍑�y��ʏȂ̈ψ��ł��鑍���W���̃G���W���W�̊w�ҁE
���Ƃ́A�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p����^�g���b�N�ɂ�����@�`�C���S���ڂ̍ŏd�v��
��������ł���B��̋Z�p�ł��邱�Ƃ����Ƃ��Ă��B������K�v������B�܂��A�C���x�~�G���W���i�������J2005-
54771�j�̓����Z�p����^�g���b�N�ɂ�����@�`�C���S���ڂ̍ŏd�v�ۑ�������ł���B��̋Z�p�ł���Ƃ̋Z�p��
��̘I���́A�u�g���b�N���[�J�̐��ƁE�Z�p�ҁv�Ɓu���Ȃ⍑�y��ʏȂ̈ψ��ł��鑍���W���̃G���W���W�̊w
�ҁE���Ɓv�Ƃ̗��҂��Z�p�J���̔\�͕s����I�悷�邱�ƂɂȂ��A���Ԃɒp���N�����ƂɂȂ�B�����������C���x
�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p�̉B���́A�u�g���b�N���[�J�̐��ƁE�Z�p�ҁv�Ɓu���Ȃ⍑�y��ʏ�
�̈ψ��ł��鑍���W���̃G���W���W�̊w�ҁE���Ɓv�Ƃ͋��ʂ̗��v�ƂȂ邽�߁A���҂���v�c�����āA���̓����Z
�p�̉B���E�铽�ɍő���̓w�͂��X�����Ă���\��������B
���Ƃ́A�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p����^�g���b�N�ɂ�����@�`�C���S���ڂ̍ŏd�v��
��������ł���B��̋Z�p�ł��邱�Ƃ����Ƃ��Ă��B������K�v������B�܂��A�C���x�~�G���W���i�������J2005-
54771�j�̓����Z�p����^�g���b�N�ɂ�����@�`�C���S���ڂ̍ŏd�v�ۑ�������ł���B��̋Z�p�ł���Ƃ̋Z�p��
��̘I���́A�u�g���b�N���[�J�̐��ƁE�Z�p�ҁv�Ɓu���Ȃ⍑�y��ʏȂ̈ψ��ł��鑍���W���̃G���W���W�̊w
�ҁE���Ɓv�Ƃ̗��҂��Z�p�J���̔\�͕s����I�悷�邱�ƂɂȂ��A���Ԃɒp���N�����ƂɂȂ�B�����������C���x
�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p�̉B���́A�u�g���b�N���[�J�̐��ƁE�Z�p�ҁv�Ɓu���Ȃ⍑�y��ʏ�
�̈ψ��ł��鑍���W���̃G���W���W�̊w�ҁE���Ɓv�Ƃ͋��ʂ̗��v�ƂȂ邽�߁A���҂���v�c�����āA���̓����Z
�p�̉B���E�铽�ɍő���̓w�͂��X�����Ă���\��������B
�� �������R B�F�g���b�N���[�J�̗v�]��������C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j���E�َE
�@���ɁA��^�g���b�N�ɂ����āA���Ȃ��u�m�n����0.23�@g/kWh�̋K�������v�����{���A���y��ʏȂ��u2015�N�d�ʎԔR
���́{�P�O���x�̌���v�̔R��K�������{�����ꍇ�A��^�g���b�N�ł��u�@ DPF���u�̋����Đ��̕p�x�����v�A
�u�A SCR�G�}�̒ቷ�����v�A�u�BSCR�G�}��HC��ł̉����v�A����сu�C �d�ʎԃ��[�h�R��̉��P�v�̂S���ڂ��ۑ�
�̉�����}��K�v������B�����_�i2015�N7�����݁j�ł́A�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓������A����
��@�`�C�̉ۑ��e�Ղɉ�������B��̋Z�p�ƍl������B���̂��߁A��^�g���b�N�ɂ����āA�C���x�~�G���W���i��
�����J2005-54771�j�̓����Z�p�̓����������ł���2024�N�x�ȑO�Ɂu2015�N�x�d�ʎԔR������{10�����x��
�R�����v�Ɓu�m�n����0.23�@g/kWh��NO���K���v����^�g���b�N���K�����������{���ꂽ�ꍇ�A�����̋K���ɑ�^�g��
�b�N��K�������邽�߂ɂ́A�g���b�N���[�J�́A�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p���̗p�������
�Ȃ��B���̏ꍇ�A���̓����Z�p�ɂ͓����������݂��邽�߁A���̓����Z�p��L���ő�^�g���b�N�ɍ̗p���邱�Ƃɂ�
��B���̍ہA�g���b�N���[�J�́A���Ђ̗D�ꂽ�Z�p�J���͂���g���āu2015�N�x�d�ʎԔR������{10�����x�̔R
�����v�Ɓu�m�n����0.23�@g/kWh��NO���K���ւ̓K���v�����������ƌւ炵����`���邱�Ƃ��s�\�ɂȂ�B���̂悤�ȏ�
���́A�����̃g���b�N���[�J�̐��ƁE�Z�p�҂ɂƂ��ẮA�Z�p�J���̔\�͕s�������ԂɘI�����邱�ƂɂȂ�B���̏�A
�g���b�N���[�J�́A�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����̎��{�����x�����H�ڂɊׂ邱�ƂɂȂ�B���̂悤
�Ȃ��Ƃ́A�g���b�N���[�J�̃G���W���W�̐��ƁE�Z�p�҂ɂƂ��ẮA�p�J�̋ɂ݂ƍl������B
���́{�P�O���x�̌���v�̔R��K�������{�����ꍇ�A��^�g���b�N�ł��u�@ DPF���u�̋����Đ��̕p�x�����v�A
�u�A SCR�G�}�̒ቷ�����v�A�u�BSCR�G�}��HC��ł̉����v�A����сu�C �d�ʎԃ��[�h�R��̉��P�v�̂S���ڂ��ۑ�
�̉�����}��K�v������B�����_�i2015�N7�����݁j�ł́A�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓������A����
��@�`�C�̉ۑ��e�Ղɉ�������B��̋Z�p�ƍl������B���̂��߁A��^�g���b�N�ɂ����āA�C���x�~�G���W���i��
�����J2005-54771�j�̓����Z�p�̓����������ł���2024�N�x�ȑO�Ɂu2015�N�x�d�ʎԔR������{10�����x��
�R�����v�Ɓu�m�n����0.23�@g/kWh��NO���K���v����^�g���b�N���K�����������{���ꂽ�ꍇ�A�����̋K���ɑ�^�g��
�b�N��K�������邽�߂ɂ́A�g���b�N���[�J�́A�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p���̗p�������
�Ȃ��B���̏ꍇ�A���̓����Z�p�ɂ͓����������݂��邽�߁A���̓����Z�p��L���ő�^�g���b�N�ɍ̗p���邱�Ƃɂ�
��B���̍ہA�g���b�N���[�J�́A���Ђ̗D�ꂽ�Z�p�J���͂���g���āu2015�N�x�d�ʎԔR������{10�����x�̔R
�����v�Ɓu�m�n����0.23�@g/kWh��NO���K���ւ̓K���v�����������ƌւ炵����`���邱�Ƃ��s�\�ɂȂ�B���̂悤�ȏ�
���́A�����̃g���b�N���[�J�̐��ƁE�Z�p�҂ɂƂ��ẮA�Z�p�J���̔\�͕s�������ԂɘI�����邱�ƂɂȂ�B���̏�A
�g���b�N���[�J�́A�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����̎��{�����x�����H�ڂɊׂ邱�ƂɂȂ�B���̂悤
�Ȃ��Ƃ́A�g���b�N���[�J�̃G���W���W�̐��ƁE�Z�p�҂ɂƂ��ẮA�p�J�̋ɂ݂ƍl������B
�@���̂悤�ȏɊׂ邱�Ƃ����O�ɉ�����邽�߂̍ŗǂ̎�i�E���@�́A�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j
�̓�������2024�N5�������ł�����̎����ɁA��^�g���b�N�̎g�p�ߒ����ɂ�����u2015�N�d�ʎԔR���́{�P�O
���x�̌���v����сu�m�nX��0.23�@g/kWh�܂ł̍팸�v�̂��ꂼ��̋K���������A���y��ʏȂƊ��ȂɁu2024�N5��
�ȍ~�Ɏ��{�v���ĖႤ���Ƃł���B���̂��߂ɂ́A�f�B�[�[���G���W�����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓�
���Z�p���̗p���邱�Ƃɂ���āu2015�N�x�d�ʎԔR������{10�����x�̔R�����v�Ɓu�m�n����0.23�@g/kWh ��NO��
�K���v�ɑ�^�g���b�N���K���\�Ƃ̋Z�p����2020�N���ɐ��ԂɌ��\���邱�Ƃł���B�����āA�����ɁA�K��������
�T�N�Ԓ��x�̃��[�h�^�C����݂����u2024�N5���ȍ~�v�ɑ�^�g���b�N���u2015�N�x�d�ʎԔR������{10�����x��
�R�����v�Ɓu�m�n����0.23�@g/kWh ��NO���K���v�̋K�����������{���Ă��A�N�����٘_�������邱�Ƃ������Ȃ�̂ł�
��B
�̓�������2024�N5�������ł�����̎����ɁA��^�g���b�N�̎g�p�ߒ����ɂ�����u2015�N�d�ʎԔR���́{�P�O
���x�̌���v����сu�m�nX��0.23�@g/kWh�܂ł̍팸�v�̂��ꂼ��̋K���������A���y��ʏȂƊ��ȂɁu2024�N5��
�ȍ~�Ɏ��{�v���ĖႤ���Ƃł���B���̂��߂ɂ́A�f�B�[�[���G���W�����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓�
���Z�p���̗p���邱�Ƃɂ���āu2015�N�x�d�ʎԔR������{10�����x�̔R�����v�Ɓu�m�n����0.23�@g/kWh ��NO��
�K���v�ɑ�^�g���b�N���K���\�Ƃ̋Z�p����2020�N���ɐ��ԂɌ��\���邱�Ƃł���B�����āA�����ɁA�K��������
�T�N�Ԓ��x�̃��[�h�^�C����݂����u2024�N5���ȍ~�v�ɑ�^�g���b�N���u2015�N�x�d�ʎԔR������{10�����x��
�R�����v�Ɓu�m�n����0.23�@g/kWh ��NO���K���v�̋K�����������{���Ă��A�N�����٘_�������邱�Ƃ������Ȃ�̂ł�
��B
�@������������邽�߂ɂ́A��^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W���ɂ�����@�`�C���S���ڂ��ۑ�����������uNO���팸�v
�Ɓu�R����P�v�̗����̖ʂŗD�ꂽ�@�\�E���\�������Q�^�[�{�����̋C���x�~�V�X�e�����C���x�~�G���W���i����
���J2005-54771�j�̓����Z�p�̑��݂��A���Ȃ������Ԕr�o�K�X���ψ��ψ���A����э��y��ʏȂ̔R������
�R�����ψ���������W���̃G���W���W�̊w�ҁE���Ƃɂ�2020�N���܂Ŋ����ɖ����E�َE���ĖႤ���Ƃł�
��B�܂�A���Ȃƍ��y��ʏȂ̈ψ���̃G���W�����̑����W���̊w�ҁE���Ƃ��A�ނ�̒n�ʂƐ��m������
�g���ėL���ȋZ�p�����B�����邱�Ƃɂ��A�u2015�N�x�d�ʎԔR������{10�����x�̔R�����v�Ɓu�m�n����0.23
�@g/kWh ��NO���K���v��2024�N5��25���ȍ~�Ƃ���Ɖ]���A���Ȃƍ��y��ʏȂ̊��������\�I�ɗU���������ӓI��
��^�g���b�N��NO���ƔR��̋K���̐ݒ肪����������̍l������B
�Ɓu�R����P�v�̗����̖ʂŗD�ꂽ�@�\�E���\�������Q�^�[�{�����̋C���x�~�V�X�e�����C���x�~�G���W���i����
���J2005-54771�j�̓����Z�p�̑��݂��A���Ȃ������Ԕr�o�K�X���ψ��ψ���A����э��y��ʏȂ̔R������
�R�����ψ���������W���̃G���W���W�̊w�ҁE���Ƃɂ�2020�N���܂Ŋ����ɖ����E�َE���ĖႤ���Ƃł�
��B�܂�A���Ȃƍ��y��ʏȂ̈ψ���̃G���W�����̑����W���̊w�ҁE���Ƃ��A�ނ�̒n�ʂƐ��m������
�g���ėL���ȋZ�p�����B�����邱�Ƃɂ��A�u2015�N�x�d�ʎԔR������{10�����x�̔R�����v�Ɓu�m�n����0.23
�@g/kWh ��NO���K���v��2024�N5��25���ȍ~�Ƃ���Ɖ]���A���Ȃƍ��y��ʏȂ̊��������\�I�ɗU���������ӓI��
��^�g���b�N��NO���ƔR��̋K���̐ݒ肪����������̍l������B
�@���̂悤�ɁA���Ȃƍ��y��ʏȂ���^�g���b�N�̌p�����Y�Ԃ́u2015�N�x�d�ʎԔR������{10�����x
�̔R�����v�Ɓu�m�n����0.23�@g/kWh ��NO���K���v�̎��{�������g���b�N���[�J�̗v�]����2024�N5��25���ȍ~
�ɜ��ӓI�ɐݒ肷�邱�Ƃ́A���Ȃ̎����Ԕr�o�K�X���ψ��ψ���ƍ��y��ʏȂ̎����ԔR������
����̃G���W�����̑����W���̒����Ȋw�ҁE���Ƃ��A���{�̑�^�g���b�N�ɂ�����uNO���팸�v�Ɓu�R���
�P�v�̐i�W��傫���j�Q����Ɖ]�����Љ�I�ȍs�ׂ��s���Ă��邱�ƂɂȂ��ƍl������B���̂悤�ɁA���Ȃ̎�
���Ԕr�o�K�X���ψ��ψ���ƍ��y��ʏȂ̎����ԔR�����ψ���̃G���W�����̑����W���̒����Ȋw�ҁE
���Ƃɔ��Љ�I�ȍs�ׂ��m���Ɏ��s�����邽�߂Ɍ�������x�����邱�Ƃ́A�ƍ߃e���r�h���}���D��Ŏ�������|
���R�c���Z�p���̕M�҂̗\���ł́A�u�d�G���^�v�Ⴕ���́u���̉��v�ɗނ���s���ȍs�ׂł͂Ȃ����Ǝv���Ă���B
�̔R�����v�Ɓu�m�n����0.23�@g/kWh ��NO���K���v�̎��{�������g���b�N���[�J�̗v�]����2024�N5��25���ȍ~
�ɜ��ӓI�ɐݒ肷�邱�Ƃ́A���Ȃ̎����Ԕr�o�K�X���ψ��ψ���ƍ��y��ʏȂ̎����ԔR������
����̃G���W�����̑����W���̒����Ȋw�ҁE���Ƃ��A���{�̑�^�g���b�N�ɂ�����uNO���팸�v�Ɓu�R���
�P�v�̐i�W��傫���j�Q����Ɖ]�����Љ�I�ȍs�ׂ��s���Ă��邱�ƂɂȂ��ƍl������B���̂悤�ɁA���Ȃ̎�
���Ԕr�o�K�X���ψ��ψ���ƍ��y��ʏȂ̎����ԔR�����ψ���̃G���W�����̑����W���̒����Ȋw�ҁE
���Ƃɔ��Љ�I�ȍs�ׂ��m���Ɏ��s�����邽�߂Ɍ�������x�����邱�Ƃ́A�ƍ߃e���r�h���}���D��Ŏ�������|
���R�c���Z�p���̕M�҂̗\���ł́A�u�d�G���^�v�Ⴕ���́u���̉��v�ɗނ���s���ȍs�ׂł͂Ȃ����Ǝv���Ă���B
�P�O�|�R ���{�̈ψ���Ŏ�����NO���E�R��K�����E�ӂ��w�ҁE���Ƃɋ��^����鎩���ԃ��[�J�̘d�G
�P�O�|�R�[�iA�j�@�����ԃ��[�J�������Ȃƍ��y��ʏȂ��ψ���̊w�ҁE���Ƃւ̘d�G���^�̓��@�E�K�v��
�@�����_�i2015�N7�����݁j�ɂ����āA��^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W���ɂ�����@�`�C���S���ڂ��ۑ����������
�uNO���팸�v�Ɓu�R����P�v�̗����̖ʂŗD�ꂽ�@�\�E���\������B��̋Z�p�́A�Q�^�[�{�����̋C���x�~�V�X�e
�����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p�ł���B���̓����Z�p���^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W��
�ɍ̗p����A�u2015�N�x�d�ʎԔR������{10�����x�̔R�����v�Ɓu�m�n����0.23�@g/kWh ��NO���K���v�ɓK����
����^�g���b�N���e�ՂɎ��p���ł��邱�ƂɂȂ�B���������āA���Ȃ̎����Ԕr�o�K�X���ψ��ψ���ƍ��y���
�Ȃ̎����ԔR�����ψ���̃G���W�����̑����W���̒����Ȋw�ҁE���Ɓi���͖쓹�������A���H���G�����A
�吹�G�����A�ѓc�P�������A���������ް���ђ��A���������A�㓡�Y�괸è�ށE�Ʊ�Eػ�����A�ߋv����
�����j���C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j���uNO���팸�v�Ɓu�R����P�v�̗����̖ʂŗD�ꂽ�@�\�E���\�̑���
��F�߂����\����A���Ȃƍ��y��ʏȂ́A�����ɑ�^�g���b�N�ɂ�����u2015�N�x�d�ʎԔR������{10����
�x�̔R�����v�Ɓu�m�n����0.23�@g/kWh ��NO���K���v�̋K�������̎��{�������_�i2015�N7�����݁j�ɂ����đ����Ɍ�
�肷��K�v����������̂Ɛ��������B���̂��Ƃɂ��ẮA�č������ɂ���^�g���b�N��NO���K�����{�s���������
�{���{�̑Ӗ��A�C���x�~�G���W���ɂ���^�g���b�N�̒�R�������C���x�~�́A�f�B�[�[���̂m�n���팸�ƔR���
��̈ꋓ�����̋Z�p���I�ɂ��ڏq���Ă���̂ŁA�����̂�����͌䗗�������������B�������č��E���B�ɔ�r���Ċ�
��NO���K���̓��{�̌�������l������ƁA
�uNO���팸�v�Ɓu�R����P�v�̗����̖ʂŗD�ꂽ�@�\�E���\������B��̋Z�p�́A�Q�^�[�{�����̋C���x�~�V�X�e
�����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p�ł���B���̓����Z�p���^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W��
�ɍ̗p����A�u2015�N�x�d�ʎԔR������{10�����x�̔R�����v�Ɓu�m�n����0.23�@g/kWh ��NO���K���v�ɓK����
����^�g���b�N���e�ՂɎ��p���ł��邱�ƂɂȂ�B���������āA���Ȃ̎����Ԕr�o�K�X���ψ��ψ���ƍ��y���
�Ȃ̎����ԔR�����ψ���̃G���W�����̑����W���̒����Ȋw�ҁE���Ɓi���͖쓹�������A���H���G�����A
�吹�G�����A�ѓc�P�������A���������ް���ђ��A���������A�㓡�Y�괸è�ށE�Ʊ�Eػ�����A�ߋv����
�����j���C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j���uNO���팸�v�Ɓu�R����P�v�̗����̖ʂŗD�ꂽ�@�\�E���\�̑���
��F�߂����\����A���Ȃƍ��y��ʏȂ́A�����ɑ�^�g���b�N�ɂ�����u2015�N�x�d�ʎԔR������{10����
�x�̔R�����v�Ɓu�m�n����0.23�@g/kWh ��NO���K���v�̋K�������̎��{�������_�i2015�N7�����݁j�ɂ����đ����Ɍ�
�肷��K�v����������̂Ɛ��������B���̂��Ƃɂ��ẮA�č������ɂ���^�g���b�N��NO���K�����{�s���������
�{���{�̑Ӗ��A�C���x�~�G���W���ɂ���^�g���b�N�̒�R�������C���x�~�́A�f�B�[�[���̂m�n���팸�ƔR���
��̈ꋓ�����̋Z�p���I�ɂ��ڏq���Ă���̂ŁA�����̂�����͌䗗�������������B�������č��E���B�ɔ�r���Ċ�
��NO���K���̓��{�̌�������l������ƁA
�@�܂�A���Ȃ̎����Ԕr�o�K�X���ψ��ψ���ƍ��y��ʏȂ̎����ԔR�����ψ���̃G���W�����̑���
�W���̊w�ҁE���Ƃ��C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j���uNO���팸�v�Ɓu�R����P�v�̗����̖ʂŗD�ꂽ�@
�\�E���\�̑��݂�F�߂����\����A���{�̑�^�f�B�[�[���g���b�N�ɂ�����u2015�N�x�d�ʎԔR������{10��
���x�̔R�����v�Ɓu�m�n����0.23�@g/kWh ��NO���K���v�̋K�������́A�����_�i2015�N7�����݁j����T�N�Ԓ��x�̃��[
�h�^�C����݂���2020�N���̎��{�Ƃ��邱�Ƃɂ��āA���̖��������Ȃ����̂ƍl������B���̂悤�ɁA��^�g���b�N
�̌p�����Y�Ԃɂ�����u2015�N�x�d�ʎԔR������{10�����x�̔R�����v�Ɓu�m�n����0.23�@g/kWh ��NO���K���v
�̋K���������u2020�N���̎��{�v�ƂȂ����ꍇ�A�����̋K�������ɓK�������S�Ă̑�^�f�B�[�[���g���b�N�ɂ��C��
�x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p���̗p����Ă�����̂Ɛ��������B���݂ɁA�����C���x�~�G���W��
�i�������J2005-54771�j�̓����Z�p�́A2020�N���̎��_�ł͓����������݂��邽�߁A�A�g���b�N���[�J�́A���Ђ̗D��
���Z�p�J���͂���g���āu2015�N�x�d�ʎԔR������{10�����x�̔R�����v�Ɓu�m�n����0.23�@g/kWh��NO���K��
�ւ̓K���v�����������ƌւ炵����`���邱�Ƃ��s�\�ɂȂ�A�g���b�N���[�J�̐��ƁE�Z�p�҂̋Z�p�J���̔\�͕s��
�����ԂɘI�����邱�ƂɂȂ�B���̏�A�g���b�N���[�J�́A�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����̎��{����
�x�����H�ڂɊׂ�A�g���b�N���[�J�Ƃ��Ă̖ʖڂ��ےׂ�̏������Ă��܂����ƂɂȂ�B
�W���̊w�ҁE���Ƃ��C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j���uNO���팸�v�Ɓu�R����P�v�̗����̖ʂŗD�ꂽ�@
�\�E���\�̑��݂�F�߂����\����A���{�̑�^�f�B�[�[���g���b�N�ɂ�����u2015�N�x�d�ʎԔR������{10��
���x�̔R�����v�Ɓu�m�n����0.23�@g/kWh ��NO���K���v�̋K�������́A�����_�i2015�N7�����݁j����T�N�Ԓ��x�̃��[
�h�^�C����݂���2020�N���̎��{�Ƃ��邱�Ƃɂ��āA���̖��������Ȃ����̂ƍl������B���̂悤�ɁA��^�g���b�N
�̌p�����Y�Ԃɂ�����u2015�N�x�d�ʎԔR������{10�����x�̔R�����v�Ɓu�m�n����0.23�@g/kWh ��NO���K���v
�̋K���������u2020�N���̎��{�v�ƂȂ����ꍇ�A�����̋K�������ɓK�������S�Ă̑�^�f�B�[�[���g���b�N�ɂ��C��
�x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p���̗p����Ă�����̂Ɛ��������B���݂ɁA�����C���x�~�G���W��
�i�������J2005-54771�j�̓����Z�p�́A2020�N���̎��_�ł͓����������݂��邽�߁A�A�g���b�N���[�J�́A���Ђ̗D��
���Z�p�J���͂���g���āu2015�N�x�d�ʎԔR������{10�����x�̔R�����v�Ɓu�m�n����0.23�@g/kWh��NO���K��
�ւ̓K���v�����������ƌւ炵����`���邱�Ƃ��s�\�ɂȂ�A�g���b�N���[�J�̐��ƁE�Z�p�҂̋Z�p�J���̔\�͕s��
�����ԂɘI�����邱�ƂɂȂ�B���̏�A�g���b�N���[�J�́A�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����̎��{����
�x�����H�ڂɊׂ�A�g���b�N���[�J�Ƃ��Ă̖ʖڂ��ےׂ�̏������Ă��܂����ƂɂȂ�B
�@���̂悤�ȏɊׂ邱�Ƃ́A�g���b�N���[�J�̃G���W���W�̐��ƁE�Z�p�҂ɂƂ��ẮA�p�J�̋ɂ݂Ɗ�����l�Ԃ�
�w�ǂł͂Ȃ����Ɛ��������B�����ŁA���̂悤�ȏ�ԂɂȂ�O�ɁA�g���b�N���[�J�̃G���W���W�̐��ƁE�Z�p�҂́A
��^�g���b�N�̌p�����Y�Ԃ́u2015�N�x�d�ʎԔR������{10�����x�̔R�����v�Ɓu�m�n����0.23�@g/kWh ��NO��
�K���v�̋K���������A�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����������ł���u202�S�N5���ȍ~�v�����{�ƂȂ�
�悤�ɑS�͂������ĉ�邱�Ƃ́A���R�ƍl������B���̂悤�ɁA��^�g���b�N�̌p�����Y�Ԃ́u2015�N�x�d�ʎԔR
������{10�����x�̔R�����v�Ɓu�m�n����0.23�@g/kWh ��NO���K���v�̋K���������u202�S�N5���ȍ~�v�����{�ɒx
��������ł��L���Ȏ�i�E���@�́A���Ȃ������Ԕr�o�K�X���ψ��ψ���A����э��y��ʏȂ̔R�����ԔR���
�����ψ���������W���̃G���W���W�̊w�ҁE���Ƃɂ��C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p��
2020�N���܂Ŋ����ɖ����E�َE���ĖႤ���Ƃł���B
�w�ǂł͂Ȃ����Ɛ��������B�����ŁA���̂悤�ȏ�ԂɂȂ�O�ɁA�g���b�N���[�J�̃G���W���W�̐��ƁE�Z�p�҂́A
��^�g���b�N�̌p�����Y�Ԃ́u2015�N�x�d�ʎԔR������{10�����x�̔R�����v�Ɓu�m�n����0.23�@g/kWh ��NO��
�K���v�̋K���������A�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����������ł���u202�S�N5���ȍ~�v�����{�ƂȂ�
�悤�ɑS�͂������ĉ�邱�Ƃ́A���R�ƍl������B���̂悤�ɁA��^�g���b�N�̌p�����Y�Ԃ́u2015�N�x�d�ʎԔR
������{10�����x�̔R�����v�Ɓu�m�n����0.23�@g/kWh ��NO���K���v�̋K���������u202�S�N5���ȍ~�v�����{�ɒx
��������ł��L���Ȏ�i�E���@�́A���Ȃ������Ԕr�o�K�X���ψ��ψ���A����э��y��ʏȂ̔R�����ԔR���
�����ψ���������W���̃G���W���W�̊w�ҁE���Ƃɂ��C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p��
2020�N���܂Ŋ����ɖ����E�َE���ĖႤ���Ƃł���B
�@�܂�A���Ȃƍ��y��ʏȂ̈ψ���̃G���W�����̑����W���̊w�ҁE���Ƃ��C���x�~�G���W���i�������J
2005-54771�j�̓����Z�p��2020�N���܂Ŋ��S�ɖ����E�َE�����Ƃ���A��^�g���b�N�̌p�����Y�Ԃ́u2015�N�x�d
�ʎԔR������{10�����x�̔R�����v�Ɓu�m�n����0.23�@g/kWh ��NO���K���v�̋K�������́A�]���Ɠ��l�ȂT�N��
���x�̃��[�h�^�C����݂����u2025�N5���ȍ~�̎��{�v���ԈႢ�Ȃ������ł��邱�ƂɂȂ鐄�������B���̂����̍ł�
�m���Ȏ�i�́A���Ȃ������Ԕr�o�K�X���ψ��ψ���A����э��y��ʏȂ̔R�����ԔR�����ψ��������
�W���̃G���W���W�̊w�ҁE���ƂɎ����ԃ��[�J�i���g���b�N���[�J�j���u�d�G�v�Ⴕ���́u���̉��v�ɗނ�����i�E���v
�邱�Ƃł���ƍl������B
2005-54771�j�̓����Z�p��2020�N���܂Ŋ��S�ɖ����E�َE�����Ƃ���A��^�g���b�N�̌p�����Y�Ԃ́u2015�N�x�d
�ʎԔR������{10�����x�̔R�����v�Ɓu�m�n����0.23�@g/kWh ��NO���K���v�̋K�������́A�]���Ɠ��l�ȂT�N��
���x�̃��[�h�^�C����݂����u2025�N5���ȍ~�̎��{�v���ԈႢ�Ȃ������ł��邱�ƂɂȂ鐄�������B���̂����̍ł�
�m���Ȏ�i�́A���Ȃ������Ԕr�o�K�X���ψ��ψ���A����э��y��ʏȂ̔R�����ԔR�����ψ��������
�W���̃G���W���W�̊w�ҁE���ƂɎ����ԃ��[�J�i���g���b�N���[�J�j���u�d�G�v�Ⴕ���́u���̉��v�ɗނ�����i�E���v
�邱�Ƃł���ƍl������B
�@���݂ɁA�u�d�G�v�Ⴕ���́u���̉��v�Ƃ́A�C���^�[�l�b�g�̃E�B�L�y�f�B�A�ɂ��ƁA�u�匠�҂̑㗝�Ƃ��Č����͂����s
����א��҂⊯�����A���͎��s�̍ٗʂɏ���������͂���ł��炤���Ƃ����҂��鑼�҂���A�@�⓹���ɔ�����`��
�����T�[�r�X�Ƃ̂��Ƃł���B�i�o�T�F�E�B�L�y�f�B�Ahttp://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B3%84%E8%B3%82�j���Q�Ɓj
���́u�d�G�v�Ⴕ���́u���̉��v�̒�`���画�f����ƁA��^�f�B�[�[���g���b�N��NO���E�R��̋K�������ɂ����āA�u�d
�G�v�Ⴕ���́u���̉��v�����Ƃ̔���́A�ȉ��̏��m�F���ꂽ�ꍇ�ƍl������B�܂�A���Ȃ������Ԕr�o
�K�X���ψ��ψ���A����э��y��ʏȂ̔R�����ԔR�����ψ���������W���̃G���W���W�̊w�ҁE����
�i���匠�҂̑㗝�Ƃ��Č����͂����s����א��҂⊯���ɊY���j����^�g���b�N�̌p�����Y�Ԃ́u2015�N�x�d�ʎԔR
������{10�����x�̔R�����v�Ɓu�m�n����0.23�@g/kWh ��NO���K���v�̋K�����{�̎����i�����͎��s�̍ٗʁj��
�u2020�N���̎��{�v�����u202�S�N5���ȍ~�v�ɉ����i���ٗʂɏ���������͂���ł��炤���Ɓj�������Ƃ��m�F���ꂽ�ꍇ��
�l������B
����א��҂⊯�����A���͎��s�̍ٗʂɏ���������͂���ł��炤���Ƃ����҂��鑼�҂���A�@�⓹���ɔ�����`��
�����T�[�r�X�Ƃ̂��Ƃł���B�i�o�T�F�E�B�L�y�f�B�Ahttp://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B3%84%E8%B3%82�j���Q�Ɓj
���́u�d�G�v�Ⴕ���́u���̉��v�̒�`���画�f����ƁA��^�f�B�[�[���g���b�N��NO���E�R��̋K�������ɂ����āA�u�d
�G�v�Ⴕ���́u���̉��v�����Ƃ̔���́A�ȉ��̏��m�F���ꂽ�ꍇ�ƍl������B�܂�A���Ȃ������Ԕr�o
�K�X���ψ��ψ���A����э��y��ʏȂ̔R�����ԔR�����ψ���������W���̃G���W���W�̊w�ҁE����
�i���匠�҂̑㗝�Ƃ��Č����͂����s����א��҂⊯���ɊY���j����^�g���b�N�̌p�����Y�Ԃ́u2015�N�x�d�ʎԔR
������{10�����x�̔R�����v�Ɓu�m�n����0.23�@g/kWh ��NO���K���v�̋K�����{�̎����i�����͎��s�̍ٗʁj��
�u2020�N���̎��{�v�����u202�S�N5���ȍ~�v�ɉ����i���ٗʂɏ���������͂���ł��炤���Ɓj�������Ƃ��m�F���ꂽ�ꍇ��
�l������B
�@����A�����ԃ��[�J�i���g���b�N���[�J�j�����Ȃƍ��y��ʏȂ̈ψ���̃G���W�����̑����W���̊w�ҁE���Ƃ�
�u�d�G�v�Ⴕ���́u���̉��v�ɗނ�����i�E���v��A���̌��ʁA���Ȃƍ��y��ʏȂ̈ψ���̑����W���̊w�ҁE��
��Ƃ��C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p��2020�N���܂Ŗ����E�َE���A��^�g���b�N�̌p�����Y
�Ԃ́u2015�N�x�d�ʎԔR������{10�����x�̔R�����v�Ɓu�m�n����0.23�@g/kWh ��NO���K���v�̋K��������
�u2025�N5���ȍ~�̎��{�v�Ƃ��邱�Ƃ����肵���ꍇ�ɂ́A�d�G�v�̒�`�܂���Ɩ��炩�Ɂu�d�G�߁v�������������
�Ɛ��������B�R��A�����_�i2015�N7�����݁j�̓��{�ɂ������^�g���b�N�̌p�����Y�Ԃ́u2015�N�x�d�ʎԔR��
�����{10�����x�̔R�����v�Ɓu�m�n����0.23�@g/kWh ��NO���K���v�̋K�������Ɋ֘A���鎩���ԃ��[�J�i���g���b�N
���[�J�j�̊����ɂ��Đ������Ă݂��̂ŁA�ȉ��Ɏ������Ƃɂ����B
�u�d�G�v�Ⴕ���́u���̉��v�ɗނ�����i�E���v��A���̌��ʁA���Ȃƍ��y��ʏȂ̈ψ���̑����W���̊w�ҁE��
��Ƃ��C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p��2020�N���܂Ŗ����E�َE���A��^�g���b�N�̌p�����Y
�Ԃ́u2015�N�x�d�ʎԔR������{10�����x�̔R�����v�Ɓu�m�n����0.23�@g/kWh ��NO���K���v�̋K��������
�u2025�N5���ȍ~�̎��{�v�Ƃ��邱�Ƃ����肵���ꍇ�ɂ́A�d�G�v�̒�`�܂���Ɩ��炩�Ɂu�d�G�߁v�������������
�Ɛ��������B�R��A�����_�i2015�N7�����݁j�̓��{�ɂ������^�g���b�N�̌p�����Y�Ԃ́u2015�N�x�d�ʎԔR��
�����{10�����x�̔R�����v�Ɓu�m�n����0.23�@g/kWh ��NO���K���v�̋K�������Ɋ֘A���鎩���ԃ��[�J�i���g���b�N
���[�J�j�̊����ɂ��Đ������Ă݂��̂ŁA�ȉ��Ɏ������Ƃɂ����B
�P�O�|�R�[�iB�j�@�����ԃ��[�J�������Ȃƍ��y��ʏȂ��ψ���̊w�ҁE���Ƃɘd�G��g�D�E�c�́H
�i�@�j ���{�̎����ԃ��[�J �X�Ђ������Őݗ����������ԗp���R�@�Z�p�����g���i�`�h�b�d�j�Ƃ́H
�@AICE�i��the Research Association of Automotive Internal CombustionEngines )�Ɨ��̂���������ԗp���R�@�Z
�p�����g���́A�g���^�����ԁA���Y�����ԁA�{�c�Z�p�������A�X�Y�L�A�_�C�n�c�H�ƁA�x�m�d�H�ƁA�}�c�_�A�O�H����
�ԍH�Ƃ̍��������ԃ��[�J�W�Ђ���сA��ʍ��c�@�l���{�����Ԍ��������A�����Ԃ̂���Ȃ�R�����Ɣr�o�K�X
�̒ጸ�Ɍ����āA���R�@�ւ̔R�ċZ�p����єr�o�K�X�Z�p�ɂ����鎩���ԃ��[�J�̉ۑ�ɂ��āA�u�����ԃ��[
�J�e��Ƃ��������Č����j�[�Y�M�v�Ɓu�i����������̋��^���āj�w�̉p�m�ɂ���b�E���p�����������Ŏ��{�v
���A�u���̐��ʂ����p���Ċe��Ƃł̊J������������v�Ƃ̍������O���f���āA2014�N4��1���ɐݗ����ꂽ�����g�D
�ł���B�i�\�P�Q�Q�Ɓj�@�����āA�����ԗp���R�@�Z�p�����g���i���`�h�b�d�j�ɂ́A2014�N12���̎��_�ɂ����āA��^�g
���b�N���[�J�̂����U�����ԂƁi�Ɓj�Y�ƋZ�p�������������V���ɎQ�������悤���B���������āA���݁i��2015�N�P���j��
�́A�����ԗp���R�@�Z�p�����g���i���`�h�b�d�j�́A���������ԃ��[�J�X�Ђ���тQ�c�̂ɂ��^�c����邱�ƂɂȂ���
�悤�ł���B
�p�����g���́A�g���^�����ԁA���Y�����ԁA�{�c�Z�p�������A�X�Y�L�A�_�C�n�c�H�ƁA�x�m�d�H�ƁA�}�c�_�A�O�H����
�ԍH�Ƃ̍��������ԃ��[�J�W�Ђ���сA��ʍ��c�@�l���{�����Ԍ��������A�����Ԃ̂���Ȃ�R�����Ɣr�o�K�X
�̒ጸ�Ɍ����āA���R�@�ւ̔R�ċZ�p����єr�o�K�X�Z�p�ɂ����鎩���ԃ��[�J�̉ۑ�ɂ��āA�u�����ԃ��[
�J�e��Ƃ��������Č����j�[�Y�M�v�Ɓu�i����������̋��^���āj�w�̉p�m�ɂ���b�E���p�����������Ŏ��{�v
���A�u���̐��ʂ����p���Ċe��Ƃł̊J������������v�Ƃ̍������O���f���āA2014�N4��1���ɐݗ����ꂽ�����g�D
�ł���B�i�\�P�Q�Q�Ɓj�@�����āA�����ԗp���R�@�Z�p�����g���i���`�h�b�d�j�ɂ́A2014�N12���̎��_�ɂ����āA��^�g
���b�N���[�J�̂����U�����ԂƁi�Ɓj�Y�ƋZ�p�������������V���ɎQ�������悤���B���������āA���݁i��2015�N�P���j��
�́A�����ԗp���R�@�Z�p�����g���i���`�h�b�d�j�́A���������ԃ��[�J�X�Ђ���тQ�c�̂ɂ��^�c����邱�ƂɂȂ���
�悤�ł���B
�@
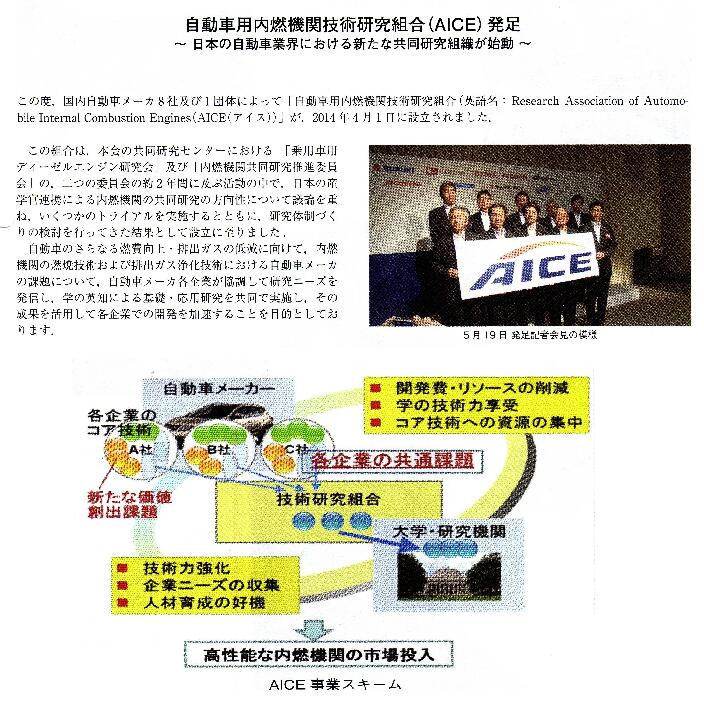 |
�܂��A�o�ώY�ƏȂ́A�ȉ��̕\�P�R�Ɏ������ʂ�A�u�N���[���f�B�[�[���G���W���Z�p�̍��x���Ɋւ��錤���J�����Ɓv
�Ƃ���2014�N�x�\�Z��5���~���v�サ�Ă���B����5���~���܂�܂鎩���ԗp���R�@�Z�p�����g���iAICE�j�ɑ���
�⏕���Ƃ��đS�z�̎x�������肵�Ă���悤���B�܂�AICE�́A���⏕���̎M�Ƃ��Đݗ����ꂽ���ʂ�����ƍl��
����B
�Ƃ���2014�N�x�\�Z��5���~���v�サ�Ă���B����5���~���܂�܂鎩���ԗp���R�@�Z�p�����g���iAICE�j�ɑ���
�⏕���Ƃ��đS�z�̎x�������肵�Ă���悤���B�܂�AICE�́A���⏕���̎M�Ƃ��Đݗ����ꂽ���ʂ�����ƍl��
����B
 |
�@���݂ɁA���̎����ԗp���R�@�Z�p�����g���i���`�h�b�d�j��2014�N�x�̌�����́A�o�ώY�ƏȂ̃N���[���f�B�[�[
�������\�Z�̂T���~�ƍ��������ԃ��[�J�X�Ђ��o�������Q�D�T���~�Ƃ̍��v�z�ł���V�D�T���~�ihttp://www.aice.or.jp/
about/index.html�j�Ƃ̂��Ƃł���B�ʏ�A���̂悤�ȑ����̎����ԃ��[�J���Q�悵�������J���̑g���ɂ����ẮA����
���ʂ��e���[�J�̐��Y�i�ɉ��p�E���f������ꍇ�������悤�ł���B���̂��߁A�e�����ԃ��[�J�̏o�����́A�o����
�Ƃ̔��グ���̃V�F�A�E�䗦�ɑ������銄���ŕ��S���邱�Ƃ������Ɛ��������B���������āA���̎����ԗp���R�@��
�Z�p�����g���i���`�h�b�d�j�ł́A�������グ���z�̃V�F�A��42.6���i����25-26�N�j�̃g���^�����Ԃ́A���̎����ԗp��
�R�@�Z�p�����g���i���`�h�b�d�j�ɑ��鎩���ԃ��[�J����̏o������42�`43���S���Ă�����̂Ɨ\�������B��
�������āA���̎����ԗp���R�@�Z�p�����g���i���`�h�b�d�j�ł́A�����߂��̏o���S����g���^�����Ԃ̈ӌ��E�ӌ�
���ŗD�悳�����̂ƍl������B
�������\�Z�̂T���~�ƍ��������ԃ��[�J�X�Ђ��o�������Q�D�T���~�Ƃ̍��v�z�ł���V�D�T���~�ihttp://www.aice.or.jp/
about/index.html�j�Ƃ̂��Ƃł���B�ʏ�A���̂悤�ȑ����̎����ԃ��[�J���Q�悵�������J���̑g���ɂ����ẮA����
���ʂ��e���[�J�̐��Y�i�ɉ��p�E���f������ꍇ�������悤�ł���B���̂��߁A�e�����ԃ��[�J�̏o�����́A�o����
�Ƃ̔��グ���̃V�F�A�E�䗦�ɑ������銄���ŕ��S���邱�Ƃ������Ɛ��������B���������āA���̎����ԗp���R�@��
�Z�p�����g���i���`�h�b�d�j�ł́A�������グ���z�̃V�F�A��42.6���i����25-26�N�j�̃g���^�����Ԃ́A���̎����ԗp��
�R�@�Z�p�����g���i���`�h�b�d�j�ɑ��鎩���ԃ��[�J����̏o������42�`43���S���Ă�����̂Ɨ\�������B��
�������āA���̎����ԗp���R�@�Z�p�����g���i���`�h�b�d�j�ł́A�����߂��̏o���S����g���^�����Ԃ̈ӌ��E�ӌ�
���ŗD�悳�����̂ƍl������B
�@���̎����ԗp���R�@�Z�p�����g���i���`�h�b�d�j�Ɏ����ԃ��[�J����̏o���̔����߂��S���Ă���g���^������
�́A��^�g���b�N���[�J�̃g�b�v��Ƃł�����쎩���Ԃ̎��{��50.1���ۗ̕L���Ă���B���̂��߁A���쎩���Ԃ́A�g��
�^�����Ԃ̘A���q��Ђł���ƍl������B���̂��Ƃ���A�g���^�����Ԃ́A��p�Ԃ⏬�^�g���b�N�ȊO�ɂ��A��^�g���b
�N���[�J�̗��v��}�邽�߂̍s�ׁE�s�������I�ɍs���Ă���ƍl����̂��Ó��Ǝv����B�����āA���̎����ԗp��
�R�@�Z�p�����g���i���`�h�b�d�j�ɂ́A��^�g���b�N���[�J�̂����U�����Ԃ��Q�悵�Ă���B���̂��Ƃ���A���̎�����
�p���R�@�Z�p�����g���i���`�h�b�d�j�̃f�B�[�[���G���W���W�̌����J���̕��j�ɂ��ẮA��^�g���b�N��
�p�����Y�Ԃ́u2015�N�x�d�ʎԔR������{10�����x�̔R�����v�Ɓu�m�n����0.23�@g/kWh ��NO���K���v
�̃��x���i���K���l�j�̋K�������̎��{�́A�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓������̊�������
���202�S�N5���ȍ~�̎��{�Ƃ����^�g���b�N���[�J�i�������U�����ԁA���쎩���ԓ��j�̋����v�]�����f����
��\�����ɂ߂č������̂Ɛ��������B
�́A��^�g���b�N���[�J�̃g�b�v��Ƃł�����쎩���Ԃ̎��{��50.1���ۗ̕L���Ă���B���̂��߁A���쎩���Ԃ́A�g��
�^�����Ԃ̘A���q��Ђł���ƍl������B���̂��Ƃ���A�g���^�����Ԃ́A��p�Ԃ⏬�^�g���b�N�ȊO�ɂ��A��^�g���b
�N���[�J�̗��v��}�邽�߂̍s�ׁE�s�������I�ɍs���Ă���ƍl����̂��Ó��Ǝv����B�����āA���̎����ԗp��
�R�@�Z�p�����g���i���`�h�b�d�j�ɂ́A��^�g���b�N���[�J�̂����U�����Ԃ��Q�悵�Ă���B���̂��Ƃ���A���̎�����
�p���R�@�Z�p�����g���i���`�h�b�d�j�̃f�B�[�[���G���W���W�̌����J���̕��j�ɂ��ẮA��^�g���b�N��
�p�����Y�Ԃ́u2015�N�x�d�ʎԔR������{10�����x�̔R�����v�Ɓu�m�n����0.23�@g/kWh ��NO���K���v
�̃��x���i���K���l�j�̋K�������̎��{�́A�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓������̊�������
���202�S�N5���ȍ~�̎��{�Ƃ����^�g���b�N���[�J�i�������U�����ԁA���쎩���ԓ��j�̋����v�]�����f����
��\�����ɂ߂č������̂Ɛ��������B
�i�A�j �����ԗp���R�@�Z�p�����g���i��AICE�j�̌������e�ƁA���̌������ϑ������w�i����w�����j
�@�����ԗp���R�@�Z�p�����g���i�`�h�b�d�j���Ȋw�Z�p�U���@�\�i�i�r�s�j�Ɍ������ϑ������헪�I�C�m�x�[�V�����n��
�v���O�����i�r�h�o�j�̓��e�́A�����ԗp���R�@�Z�p�����g���i�`�h�b�d�j���Ȋw�Z�p�U���@�\�i�i�r�s�j�Ɉϑ��̌����i�r�h
�o�j�ɏڏq�����ʂ�A�ȉ��̂P�O���ڂ̌����e�[�}�̂悤�ł���B
�v���O�����i�r�h�o�j�̓��e�́A�����ԗp���R�@�Z�p�����g���i�`�h�b�d�j���Ȋw�Z�p�U���@�\�i�i�r�s�j�Ɉϑ��̌����i�r�h
�o�j�ɏڏq�����ʂ�A�ȉ��̂P�O���ڂ̌����e�[�}�̂悤�ł���B
�i�C�j�������K�\�����G���W���̂��߂̃X�[�p�[���[���o�[�������J��
�i���j��p�ԗp�f�B�[�[���G���W���ɂ����鍂�x�R�Đ���
�i�n�j�v�V�I�R�ċZ�p��������郂�f�����O�Ɛ���
�i�j�j�r�C�G�l���M�[�̗L�����p�Ƌ@�B���C�����̒ጸ�Ɋւ��錤���J��
�i�z�j�U�d�̃o���A���d��p�����\�����C�̔R�đ��i�@�̊J��
�i�w�j�g������ɂ�钴�R�ẲΉ��`�d���艻�Z�p�̊J��
�i�g�j�����M�����T�O�������Ɍ����������R�Ă̌v�Z�Ȋw�I�A�v���[�`
�i�`�j�M�I�E�@�B�I�ɍ��ϋv�Ȏ��p�M�d�r�M���d�V�X�e���J��
�i���j���m���X�\���𗘗p�����i�m�u���V�̊K�w���ɂ��v�V�I���x����
(�k�j�ʎq�_����̐ςݏグ�ɂ����G���W���ǖʂ̔M�����E�����e���]���V�~�����[�^�̊J���Ɗv�V�I�R�ċZ
�p�J���ւ̉��p
�p�J���ւ̉��p
�ȏ��10���ڂ̌����e�[�}�̒��ŁA��^�f�B�[�[���g���b�N�ɂ�����u�@ DPF���u�̋����Đ��̕p�x�����v�A�u�A SCR
�G�}�̒ቷ�����v�A�u�BSCR�G�}��HC��ł̉����v�A����сu�C �d�ʎԃ��[�h�R��̉��P�v�̂S���ڂ��ۑ�ɉ�����
�傫���v�����錤���́A�Ԏ��Ŏ������i�j�j�A�i�`�j�A�i���j�A�i�k�j�̂S���ڂƍl������B�Ȃ��A�����ԗp���R�@�Z�p��
���g���i���`�h�b�d�j���Ȋw�Z�p�U���@�\�i�i�r�s�j�Ɉϑ�����10���ڂ̌����e�[�}���琬��헪�I�C�m�x�[�V�����n���v��
�O�����i�r�h�o�j�́A�ȉ��̕\�P�T�Ɏ������Ȋw�Z�p�U���@�\�i�i�r�s�j�̐���`�[���A�f�B�[�[���R�ă`�[���A�K�\�����R
�ă`�[���A�����ጸ�`�[���̂S�`�[���ɂ���Ď��{�����Ƃ̂��Ƃł���B�i�\�P�S�Q�Ɓj
�G�}�̒ቷ�����v�A�u�BSCR�G�}��HC��ł̉����v�A����сu�C �d�ʎԃ��[�h�R��̉��P�v�̂S���ڂ��ۑ�ɉ�����
�傫���v�����錤���́A�Ԏ��Ŏ������i�j�j�A�i�`�j�A�i���j�A�i�k�j�̂S���ڂƍl������B�Ȃ��A�����ԗp���R�@�Z�p��
���g���i���`�h�b�d�j���Ȋw�Z�p�U���@�\�i�i�r�s�j�Ɉϑ�����10���ڂ̌����e�[�}���琬��헪�I�C�m�x�[�V�����n���v��
�O�����i�r�h�o�j�́A�ȉ��̕\�P�T�Ɏ������Ȋw�Z�p�U���@�\�i�i�r�s�j�̐���`�[���A�f�B�[�[���R�ă`�[���A�K�\�����R
�ă`�[���A�����ጸ�`�[���̂S�`�[���ɂ���Ď��{�����Ƃ̂��Ƃł���B�i�\�P�S�Q�Ɓj
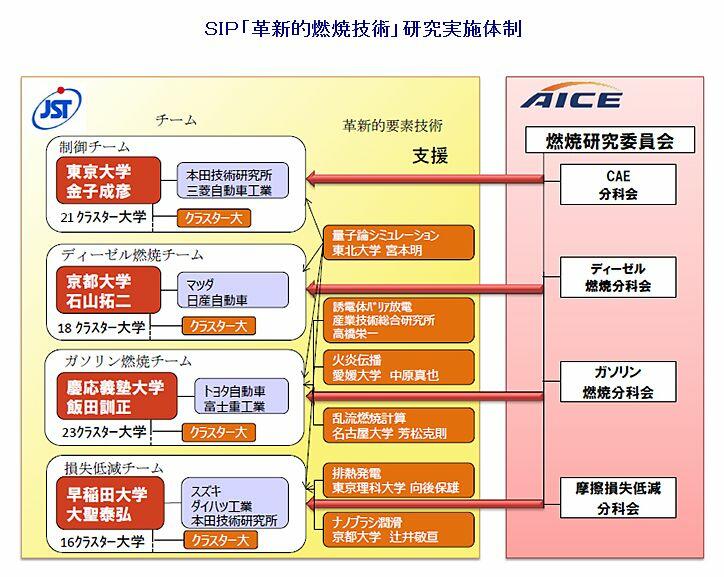 |
�����āA�Ȋw�Z�p�U���@�\�i�i�r�s�j�́iA)�`�iD)�̂S�`�[���̔N�ԗ\�Z�́A�ȉ��̂ɒʂ�Ƃ̂��Ƃł���B�i�\�P�T�Q�Ɓj
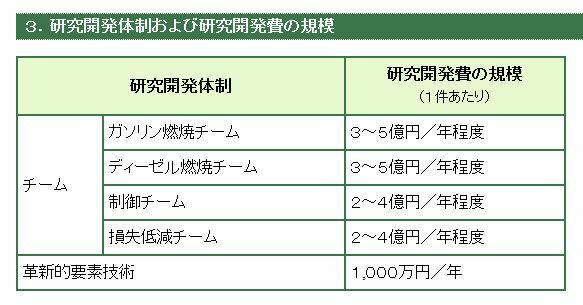 |
�@�ȏ�̂悤�ɁA�����ԗp���R�@�Z�p�����g���i���`�h�b�d�j���Ȋw�Z�p�U���@�\�i�i�r�s�j�Ɉϑ�����10���ڂ̌����e
�[�}���琬��헪�I�C�m�x�[�V�����n���v���O�����i�r�h�o�j�����{�����Ȋw�Z�p�U���@�\�i�i�r�s�j�̃K�\�����R�ă`�[
���̎�S�����c����w�E�ѓc�P�������A�����ጸ�`�[���̎�S��������c��w�E�吹�G�����Ƃ̂��Ƃł���B
�[�}���琬��헪�I�C�m�x�[�V�����n���v���O�����i�r�h�o�j�����{�����Ȋw�Z�p�U���@�\�i�i�r�s�j�̃K�\�����R�ă`�[
���̎�S�����c����w�E�ѓc�P�������A�����ጸ�`�[���̎�S��������c��w�E�吹�G�����Ƃ̂��Ƃł���B
�i�B�j NO���K���ƔR�������肷�������͂�����w�����������ԃ��[�J����������x������o�H
�@���̂����A����2014�N4��1���ɐݗ����ꂽ�����ԗp���R�@�Z�p�����g���i���`�h�b�d�j�́A�����̎����ԃ��[�J�X��
���o�����������ԃ��[�J�̑g���ł���B���̂��߁A���R�̂��ƂȂ���A���̑g���i��AICE�j�́A�����ԃ��[�J�̋��ʂ�
���v��}�銈�����s���ƍl���ĊԈႢ���������ł���B���̎����ԗp���R�@�Z�p�����g���i���`�h�b�d�j���Ȋw�Z�p
�U���@�\�i�i�r�s�j��10���ڂ̌����e�[�}���琬��헪�I�C�m�x�[�V�����n���v���O�����i�r�h�o�j�i2014�N�`2019�N�̂T�N
�ԁj�̌����ϑ������{�����̂ł���B�����āA���̐헪�I�C�m�x�[�V�����n���v���O�����i�r�h�o�j�̈ꕔ�𑁈�c��w�E��
���G�����ƌc����w�E�ѓc�P�������̗������S������Ƃ̂��Ƃł���B�����āA���̐헪�I�C�m�x�[�V�����n���v��
�O�����i�r�h�o�j�́A2014�N�`2019�N�̂T�N�Ԃ̎��{���v�悳��Ă���B���̂��߁A����c��w�E�吹�G�����ƌc����
�w�E�ѓc�P�������̗����́A�����ԃ��[�J�̋��ʂ̗��v��}�邽�߂̊������s�������ԗp���R�@�Z�p�����g��
�i���`�h�b�d�j����2019�N�܂ł̂T�N�Ԃɘj���Č���������\��̂悤�ł���B
���o�����������ԃ��[�J�̑g���ł���B���̂��߁A���R�̂��ƂȂ���A���̑g���i��AICE�j�́A�����ԃ��[�J�̋��ʂ�
���v��}�銈�����s���ƍl���ĊԈႢ���������ł���B���̎����ԗp���R�@�Z�p�����g���i���`�h�b�d�j���Ȋw�Z�p
�U���@�\�i�i�r�s�j��10���ڂ̌����e�[�}���琬��헪�I�C�m�x�[�V�����n���v���O�����i�r�h�o�j�i2014�N�`2019�N�̂T�N
�ԁj�̌����ϑ������{�����̂ł���B�����āA���̐헪�I�C�m�x�[�V�����n���v���O�����i�r�h�o�j�̈ꕔ�𑁈�c��w�E��
���G�����ƌc����w�E�ѓc�P�������̗������S������Ƃ̂��Ƃł���B�����āA���̐헪�I�C�m�x�[�V�����n���v��
�O�����i�r�h�o�j�́A2014�N�`2019�N�̂T�N�Ԃ̎��{���v�悳��Ă���B���̂��߁A����c��w�E�吹�G�����ƌc����
�w�E�ѓc�P�������̗����́A�����ԃ��[�J�̋��ʂ̗��v��}�邽�߂̊������s�������ԗp���R�@�Z�p�����g��
�i���`�h�b�d�j����2019�N�܂ł̂T�N�Ԃɘj���Č���������\��̂悤�ł���B
�@����A�O�q�̂X���u��^�f�B�[�[���g���b�N�́u�R���v�ƁuNO���K���v�̋����̐E�ӂ��w�ҁE���Ɓv�Ɏ�������
���ɁA���{�́u�d�ʎԃ��[�h�R���v�̋����ɂ��Ă͍��y��ʏȂ������ԔR�����ψ���R��K��������
�K���l�Ǝ��{�����������I�ɐݒ肵�A�uNO���K���̋����v�ɂ��Ă͊��Ȃ�NO���K�������Ɍg��钆�����R�c
���C�E�����U��������Ԕr�o�K�X���ψ��ψ��NO���K�������̋K���l�Ǝ��{������{���I�Ɋm�肷�錠
���E���Ђ�t�^����Ă���ƍl������B�܂�A���Ȃ̒������R�c���C�E�����U��������Ԕr�o�K�X���
�ψ��ψ���⍑�y��ʏȂ������ԔR�����ψ���ꂼ��̈ψ���́A�����ԂɊւ���uNO���K���v��u�R���
���v�����������������㗝�Ƃ��Č����͂����s���錠�����^�����Ă���B���̊��Ȃ̎����Ԕr�o�K�X���ψ�
�ψ���̈ψ���������c��w�E�吹�G�����ł���A�ψ��߂�̂��c����w�E�ѓc�P�������ł���B�����āA��
�y��ʏȂ������ԔR�����ψ�����ψ����߂�̂�����c��w�E�吹�G�����ł���B
���ɁA���{�́u�d�ʎԃ��[�h�R���v�̋����ɂ��Ă͍��y��ʏȂ������ԔR�����ψ���R��K��������
�K���l�Ǝ��{�����������I�ɐݒ肵�A�uNO���K���̋����v�ɂ��Ă͊��Ȃ�NO���K�������Ɍg��钆�����R�c
���C�E�����U��������Ԕr�o�K�X���ψ��ψ��NO���K�������̋K���l�Ǝ��{������{���I�Ɋm�肷�錠
���E���Ђ�t�^����Ă���ƍl������B�܂�A���Ȃ̒������R�c���C�E�����U��������Ԕr�o�K�X���
�ψ��ψ���⍑�y��ʏȂ������ԔR�����ψ���ꂼ��̈ψ���́A�����ԂɊւ���uNO���K���v��u�R���
���v�����������������㗝�Ƃ��Č����͂����s���錠�����^�����Ă���B���̊��Ȃ̎����Ԕr�o�K�X���ψ�
�ψ���̈ψ���������c��w�E�吹�G�����ł���A�ψ��߂�̂��c����w�E�ѓc�P�������ł���B�����āA��
�y��ʏȂ������ԔR�����ψ�����ψ����߂�̂�����c��w�E�吹�G�����ł���B
�@���̂悤�ɁA����c��w�E�吹�G�����ƌc����w�E�ѓc�P�������́A���{�̎����Ԃ́uNO���K���ƔR���̋�
���v�ɊW�������I�Ȍ��͂����s���錠����������ł���Ȃ���A�Ȋw�Z�p�U���@�\�i�i�r�s�j��10���ڂ̌����e�[
�}���琬��헪�I�C�m�x�[�V�����n���v���O�����i�r�h�o�j��S�����邱�Ƃɂ��A�����ԗp���R�@�Z�p�����g���i���`�h
�b�d�j���瑽�z�̌������2014�N�����̂��n�߂Ă���悤�ł���B�܂�A���{�̎����ԃ��[�J�ɑ��Ď����Ԃ�
�uNO���K���ƔR���̋����v�ɊW�������I�Ȍ��͂����s���錠���������������c��w�E�吹�G��
���ƌc����w�E�ѓc�P���������A�����ԃ��[�J�̋��ʂ̗��v��}�銈�����s�������ԗp���R�@�Z�p�����g
���i���`�h�b�d�j����A�u�헪�I�C�m�x�[�V�����n���v���O�����i�r�h�o�j�v�Ə̂���ϑ������̖��ڂŁA2014�N�`2019
�N�̂T�N�Ԃɘj���Č���������\��ɂȂ��Ă���悤�ł���B
���v�ɊW�������I�Ȍ��͂����s���錠����������ł���Ȃ���A�Ȋw�Z�p�U���@�\�i�i�r�s�j��10���ڂ̌����e�[
�}���琬��헪�I�C�m�x�[�V�����n���v���O�����i�r�h�o�j��S�����邱�Ƃɂ��A�����ԗp���R�@�Z�p�����g���i���`�h
�b�d�j���瑽�z�̌������2014�N�����̂��n�߂Ă���悤�ł���B�܂�A���{�̎����ԃ��[�J�ɑ��Ď����Ԃ�
�uNO���K���ƔR���̋����v�ɊW�������I�Ȍ��͂����s���錠���������������c��w�E�吹�G��
���ƌc����w�E�ѓc�P���������A�����ԃ��[�J�̋��ʂ̗��v��}�銈�����s�������ԗp���R�@�Z�p�����g
���i���`�h�b�d�j����A�u�헪�I�C�m�x�[�V�����n���v���O�����i�r�h�o�j�v�Ə̂���ϑ������̖��ڂŁA2014�N�`2019
�N�̂T�N�Ԃɘj���Č���������\��ɂȂ��Ă���悤�ł���B
�i�C�j NO���K���E�R���W�������͂�����w���������^����鎩���ԃ��[�J������d�G�ɊY��
�@��^�g���b�N�Ɋւ��A���{��NO���K���l�́A�č��≢�B�ɔ�r���āA�ȉ��̒ʂ�A�啝�Ɋɂ��ł���B
�@�� ���B �F 2013�N��EURO�Y�i�ߓn���[�h�j�́A�m�n�� �� 0.46 g/kWh�A
�@ EEV(5)�i�ߓn���[�h�j�́ANO�� �� 0.2 g/kWh
�w���@EEV�FEnhanced Environmentally Friendly Vehicles�̗��BEEV�K���l�́A��C���������ɐi�s���Ă���s�s���̒n��������̂��߁A����
�o�[�e���������I�Ɏg�p���邽�߂̒l�i��F�s�s�ւ̏����ꐧ����݂���ۂ̊�Ƃ��Ďg�p�j�ŁA�b��l�B�x
�o�[�e���������I�Ɏg�p���邽�߂̒l�i��F�s�s�ւ̏����ꐧ����݂���ۂ̊�Ƃ��Ďg�p�j�ŁA�b��l�B�x
�@�� �č� �F 2010�N�̂m�n���K���́ANO�� �� 0.27 g/kWh
�@�� ���{ �F 2016�N�̂m�n���K���́A�m�n���� 0.4 g/kWh
�@�܂��A���{�ɂ����ẮA2005�N4��8���Ɋ��Ȃ֒�o���ꂽ���ȁE�������R�c����攪�����\�����L���ꂽ
�f�B�[�[���d�ʎԂ� NO�� ���@0.23�@g/kW�@������ڕW��NO���K���������Ɏ��{����K�v�������ƍl�����
��B�܂��A���{�̑�^�g���b�N�̔R��K���ł���2015�N�x�d�ʎԔR���́A2006�N�i����18�N�j4��1������{�s����
�Ċ���10�N�߂����o�߂��A�g���b�N�̔R����P�Z�p�ɑ����̐i���E�i�W�������邱�Ƃ���A���}��2015�N�x�d�ʎ�
�R���̋�����}��K�v������B�ȏ�̂��Ƃ����Ă���ƁA�߂������A���{�̑�^�g���b�N�́uNO���K���v��
�u�R���v�́A�ȉ��̕\1�U�Ɏ��������x���ɋ�������K�v�������ƍl������B
�f�B�[�[���d�ʎԂ� NO�� ���@0.23�@g/kW�@������ڕW��NO���K���������Ɏ��{����K�v�������ƍl�����
��B�܂��A���{�̑�^�g���b�N�̔R��K���ł���2015�N�x�d�ʎԔR���́A2006�N�i����18�N�j4��1������{�s����
�Ċ���10�N�߂����o�߂��A�g���b�N�̔R����P�Z�p�ɑ����̐i���E�i�W�������邱�Ƃ���A���}��2015�N�x�d�ʎ�
�R���̋�����}��K�v������B�ȏ�̂��Ƃ����Ă���ƁA�߂������A���{�̑�^�g���b�N�́uNO���K���v��
�u�R���v�́A�ȉ��̕\1�U�Ɏ��������x���ɋ�������K�v�������ƍl������B
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
�@�������A�����_�i��2015�N7��27�����݁j�ɂ����ẮA���{�̃f�B�[�[���G���W���W�̊w�ҁE���Ƃ̍ŋ߂̒��q
���������A��^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W���ɂ������u�@ DPF���u�̋����Đ��̕p�x�����v�A�u�A SCR�G�}�̒ቷ
�����v�A�u�BSCR�G�}��HC��ł̉����v�A�u�C �d�ʎԃ��[�h�R��̉��P�v�v�̂S���ڂ̉ۑ��������ł���Z�p�������
�\���E�J���ł��Ȃ��̂悤�ł���B���̂悤�ȏɂ����āA�|���R�c���Z�p���̕M�҂�10�N�O��2004�N5��25��
�ɏo�肵���Q�^�[�{�����̋C���x�~�V�X�e�����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p�́A��^�g���b�N
�p�f�B�[�[���G���W���̇@�`�C�̂S���ڂ̉ۑ����������A�u�m�n����0.23�@g/kWh�̋K�������v�A����сu2015�N�d�ʎԔR
�����{10���������v�ɓK��������^�g���b�N��e�ՂɎ������邱�Ƃ��\�ƂȂ�B
���������A��^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W���ɂ������u�@ DPF���u�̋����Đ��̕p�x�����v�A�u�A SCR�G�}�̒ቷ
�����v�A�u�BSCR�G�}��HC��ł̉����v�A�u�C �d�ʎԃ��[�h�R��̉��P�v�v�̂S���ڂ̉ۑ��������ł���Z�p�������
�\���E�J���ł��Ȃ��̂悤�ł���B���̂悤�ȏɂ����āA�|���R�c���Z�p���̕M�҂�10�N�O��2004�N5��25��
�ɏo�肵���Q�^�[�{�����̋C���x�~�V�X�e�����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p�́A��^�g���b�N
�p�f�B�[�[���G���W���̇@�`�C�̂S���ڂ̉ۑ����������A�u�m�n����0.23�@g/kWh�̋K�������v�A����сu2015�N�d�ʎԔR
�����{10���������v�ɓK��������^�g���b�N��e�ՂɎ������邱�Ƃ��\�ƂȂ�B
�@��^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W���́uNO���팸�v�Ɓu�R����P�v�̗����̖ʂŗD�ꂽ�@�\�E���\�������Q�^�[�{��
���̋C���x�~�V�X�e�����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p�̑��݂��A���Ȃ������Ԕr�o�K�X
���ψ��ψ���A����э��y��ʏȂ̔R�����ԔR�����ψ���������W���̃G���W���W�̊w�ҁE���Ƃ��F
�m���A���\�����ꍇ�ɂ́A���Ȃ������Ԕr�o�K�X���ψ��ψ����^�g���b�N���u�m�n����0.23�@g/kWh ��NO���K
���v�̑����̎��{�\���A���y��ʏȂ̔R�����ԔR�����ψ�������^�g���b�N���u2015�N�x�d�ʎԔR��
����{10�����x�̔R�����v�̑����̎��{�����肷��\�����ɂ߂č����ƍl������B���̏ꍇ�A�g���b�N���[�J
�́A�ۉ��Ȃ��ɁA�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓������{������ŁA���̓����Z�p�����Ђ̑�^�g��
�b�N�ɍ̗p������Ȃ����ƂɂȂ�ƍl������B���̂悤�ȏɊׂ邱�Ƃ́A�g���b�N���[�J�̖R�����Z�p�J���͂�
���ԂɎN�����ƂɂȂ邱�Ƃ���A�f�łƂ��ĉ�����������Ƃł���B
���̋C���x�~�V�X�e�����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p�̑��݂��A���Ȃ������Ԕr�o�K�X
���ψ��ψ���A����э��y��ʏȂ̔R�����ԔR�����ψ���������W���̃G���W���W�̊w�ҁE���Ƃ��F
�m���A���\�����ꍇ�ɂ́A���Ȃ������Ԕr�o�K�X���ψ��ψ����^�g���b�N���u�m�n����0.23�@g/kWh ��NO���K
���v�̑����̎��{�\���A���y��ʏȂ̔R�����ԔR�����ψ�������^�g���b�N���u2015�N�x�d�ʎԔR��
����{10�����x�̔R�����v�̑����̎��{�����肷��\�����ɂ߂č����ƍl������B���̏ꍇ�A�g���b�N���[�J
�́A�ۉ��Ȃ��ɁA�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓������{������ŁA���̓����Z�p�����Ђ̑�^�g��
�b�N�ɍ̗p������Ȃ����ƂɂȂ�ƍl������B���̂悤�ȏɊׂ邱�Ƃ́A�g���b�N���[�J�̖R�����Z�p�J���͂�
���ԂɎN�����ƂɂȂ邱�Ƃ���A�f�łƂ��ĉ�����������Ƃł���B
�@�����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p�����Ђ̑�^�g���b�N�ɍ̗p���鎖�Ԃ��m���ɓ�����
�i�́A���Ȃ������Ԕr�o�K�X���ψ��ψ���A����э��y��ʏȂ̔R�����ԔR�����ψ���������W���̃G
���W���W�̊w�ҁE���ƂɁA���̓����Z�p�̑��݂��E�َE���ĖႤ���Ƃł���ƍl������B���̏ꍇ�A����
�⍑�y��ʏȂ��ψ���������W���̊w�ҁE���Ƃ��C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p��
���݂��E�َE������m�������@�́A�ނ�i���ψ���������W���̊w�ҁE���Ɓj�ɘd�G�邱���ł͂Ȃ�
���ƍl������B�����Ƃ��A�|���R�c���Z�p�����M�҂ɂ́A�d�G�ȊO�̕���͎v���t���Ȃ����E�E�E�E�B
�i�́A���Ȃ������Ԕr�o�K�X���ψ��ψ���A����э��y��ʏȂ̔R�����ԔR�����ψ���������W���̃G
���W���W�̊w�ҁE���ƂɁA���̓����Z�p�̑��݂��E�َE���ĖႤ���Ƃł���ƍl������B���̏ꍇ�A����
�⍑�y��ʏȂ��ψ���������W���̊w�ҁE���Ƃ��C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p��
���݂��E�َE������m�������@�́A�ނ�i���ψ���������W���̊w�ҁE���Ɓj�ɘd�G�邱���ł͂Ȃ�
���ƍl������B�����Ƃ��A�|���R�c���Z�p�����M�҂ɂ́A�d�G�ȊO�̕���͎v���t���Ȃ����E�E�E�E�B
�@�����ŐU��Ԃ���2014�N4��1���ɐݗ����ꂽ�����̎����ԃ��[�J�X�Ђ��o�����������ԗp���R�@�Z�p�����g��
�i���`�h�b�d�j�̊������e������ƁA���Ȃ������Ԕr�o�K�X���ψ��ψ���A����э��y��ʏȂ̔R�����ԔR��
���ψ���������W���̃G���W���W�̊w�ҁE���Ƃ̒�������c��w�E�吹�G�����ƌc����w�E�ѓc�P������
�́A�Ȋw�Z�p�U���@�\�i�i�r�s�j��10���ڂ̌����e�[�}���琬��헪�I�C�m�x�[�V�����n���v���O�����i�r�h�o�j��S������
���Ƃɂ��A�����ԗp���R�@�Z�p�����g���i���`�h�b�d�j���瑽�z�̌������2014�N�����̂��n�߂Ă���悤�ł�
��B
�i���`�h�b�d�j�̊������e������ƁA���Ȃ������Ԕr�o�K�X���ψ��ψ���A����э��y��ʏȂ̔R�����ԔR��
���ψ���������W���̃G���W���W�̊w�ҁE���Ƃ̒�������c��w�E�吹�G�����ƌc����w�E�ѓc�P������
�́A�Ȋw�Z�p�U���@�\�i�i�r�s�j��10���ڂ̌����e�[�}���琬��헪�I�C�m�x�[�V�����n���v���O�����i�r�h�o�j��S������
���Ƃɂ��A�����ԗp���R�@�Z�p�����g���i���`�h�b�d�j���瑽�z�̌������2014�N�����̂��n�߂Ă���悤�ł�
��B
�@�܂�A����c��w�E�吹�G�����ƌc����w�E�ѓc�P�������́A���{�̎����Ԃ́uNO���K���ƔR����
�����v�ɊW�������I�Ȍ��͂����s���錠����������ł���Ȃ���A�����ԗp���R�@�Z�p�����g���i���`
�h�b�d�j���Ȋw�Z�p�U���@�\�i�i�r�s�j�Ɉϑ������헪�I�C�m�x�[�V�����n���v���O�����i�r�h�o�j�̌��������̂���
����̂͗�R���鎖���̂悤�ł���B���̏ꍇ�A�����ԗp���R�@�Z�p�����g���i���`�h�b�d�j��Ȋw�Z�p�U��
�@�\�i�i�r�s�j�̑g�D���I�đ���c��w�E�吹�G�����ƌc����w�E�ѓc�P�������ɋ��^���ꂽ������́A
�����ԃ��[�J����x�����ꂽ�u�d�G�v�ƌ��邱�Ƃ��\�ł͂Ȃ����ƍl������B�������A����́A�@���ɕs�ē��ȃ|
���R�c���Z�p���̕M�҂̌�������������m��Ȃ��B�������A�����ԃ��[�J���瑁��c��w�E�吹�G�����ƌc����w�E
�ѓc�P�������ɋ��^���ꂽ������́A�M�҂��猩��A�u�����Ƃ̉I���܂��͕s�������i�����{�⏕���x����
��Ђ���̌����j�v��u��s�̉I��Z���v���̕s���E�s�@�Ȏ����x���̍s�ׂɍ������Ă���悤�Ɏv�����A�@���Ȃ��̂�
���낤���B���ɁA���̂悤�Ȍ�����̋��^�����@�ł���A�����̖͂L�x�Ȗ��ԑg�D�i����ЁE�c�̓��j�́A�R������
����ɔY�ޑ�w�����E���Ɓi�����I�Ȍ��͂����s���錠���������{�̈ψ���̈ψ��j�̈ӌ��E�咣���A���z�̌�
����̋��^�Ɖ]���u���ʁv�E�u�a�v�ɂ���Ď��R�ɑ��邱�Ƃ��\�ƍl������B���̏ꍇ�A���ԑg�D�i����ЁE�c�̓��j��
�ӌ����ŗD�悳�ꂽ�K���l�E�K���E��������{�ł͔×����Ă��܂��Ɨ\�z����邪�A����͕M�҂̕��������ł���
�����B
�����v�ɊW�������I�Ȍ��͂����s���錠����������ł���Ȃ���A�����ԗp���R�@�Z�p�����g���i���`
�h�b�d�j���Ȋw�Z�p�U���@�\�i�i�r�s�j�Ɉϑ������헪�I�C�m�x�[�V�����n���v���O�����i�r�h�o�j�̌��������̂���
����̂͗�R���鎖���̂悤�ł���B���̏ꍇ�A�����ԗp���R�@�Z�p�����g���i���`�h�b�d�j��Ȋw�Z�p�U��
�@�\�i�i�r�s�j�̑g�D���I�đ���c��w�E�吹�G�����ƌc����w�E�ѓc�P�������ɋ��^���ꂽ������́A
�����ԃ��[�J����x�����ꂽ�u�d�G�v�ƌ��邱�Ƃ��\�ł͂Ȃ����ƍl������B�������A����́A�@���ɕs�ē��ȃ|
���R�c���Z�p���̕M�҂̌�������������m��Ȃ��B�������A�����ԃ��[�J���瑁��c��w�E�吹�G�����ƌc����w�E
�ѓc�P�������ɋ��^���ꂽ������́A�M�҂��猩��A�u�����Ƃ̉I���܂��͕s�������i�����{�⏕���x����
��Ђ���̌����j�v��u��s�̉I��Z���v���̕s���E�s�@�Ȏ����x���̍s�ׂɍ������Ă���悤�Ɏv�����A�@���Ȃ��̂�
���낤���B���ɁA���̂悤�Ȍ�����̋��^�����@�ł���A�����̖͂L�x�Ȗ��ԑg�D�i����ЁE�c�̓��j�́A�R������
����ɔY�ޑ�w�����E���Ɓi�����I�Ȍ��͂����s���錠���������{�̈ψ���̈ψ��j�̈ӌ��E�咣���A���z�̌�
����̋��^�Ɖ]���u���ʁv�E�u�a�v�ɂ���Ď��R�ɑ��邱�Ƃ��\�ƍl������B���̏ꍇ�A���ԑg�D�i����ЁE�c�̓��j��
�ӌ����ŗD�悳�ꂽ�K���l�E�K���E��������{�ł͔×����Ă��܂��Ɨ\�z����邪�A����͕M�҂̕��������ł���
�����B
�i�D�j NO���K���ƔR���̌���̐E�ӂ�������w���������^�̘d�G�Ŋl�����鎩���ԃ��[�J�̐���
�@���Ȃ������Ԕr�o�K�X���ψ��ψ���A����э��y��ʏȂ̔R�����ԔR�����ψ���������W���̃G���W
���W�̊w�ҁE���Ƃ��C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p�́uNO���팸�v�Ɓu�R����P�v�̗D�ꂽ
�@�\�E���\��F�m�����ꍇ�ɂ́A���Ȃ������Ԕr�o�K�X���ψ��ψ����^�g���b�N���u�m�n����0.23�@g/kWh ��
NO���K���v�̑����̎��{�\���A���y��ʏȂ̔R�����ԔR�����ψ�������^�g���b�N���u2015�N�x�d�ʎԔR
������{10�����x�̔R�����v�̑����̎��{�����肷��\�����ɂ߂č����ƍl������B���̏ꍇ�A�g���b�N
���[�J�́A�ۉ��Ȃ��ɁA�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓������{������ŁA���̓����Z�p�����Ђ̑�
�^�g���b�N�ɍ̗p������Ȃ����ƂɂȂ�ƍl������B���̂悤�ȏɊׂ邱�Ƃ́A�g���b�N���[�J�̖R�����Z�p�J
���͂𐢊ԂɎN�����ƂɂȂ邽�߁A�f�łƂ��ĉ�����������Ƃł���B
���W�̊w�ҁE���Ƃ��C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p�́uNO���팸�v�Ɓu�R����P�v�̗D�ꂽ
�@�\�E���\��F�m�����ꍇ�ɂ́A���Ȃ������Ԕr�o�K�X���ψ��ψ����^�g���b�N���u�m�n����0.23�@g/kWh ��
NO���K���v�̑����̎��{�\���A���y��ʏȂ̔R�����ԔR�����ψ�������^�g���b�N���u2015�N�x�d�ʎԔR
������{10�����x�̔R�����v�̑����̎��{�����肷��\�����ɂ߂č����ƍl������B���̏ꍇ�A�g���b�N
���[�J�́A�ۉ��Ȃ��ɁA�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓������{������ŁA���̓����Z�p�����Ђ̑�
�^�g���b�N�ɍ̗p������Ȃ����ƂɂȂ�ƍl������B���̂悤�ȏɊׂ邱�Ƃ́A�g���b�N���[�J�̖R�����Z�p�J
���͂𐢊ԂɎN�����ƂɂȂ邽�߁A�f�łƂ��ĉ�����������Ƃł���B
�@�����_�i��2015�N7�����݁j�ɂ����āA�Q�^�[�{�����̋C���x�~�V�X�e���ł����C���x�~�G���W���i�������J2005-
54771�j�̓����Z�p�̑��ɂ́A��^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W�����uNO���팸�v�Ɓu�R����P�v���\�ɂ���Z�p�����J
���̏ł���A�߂������ɁA���̓����Z�p�𗽉킷��V�Z�p���g���b�N���[�J���J���ł���ۏ�͊F���ł���B����
�����āA�����I�ɁA��^�g���b�N�̂̎g�p�ߒ��Ԃ��u�m�n����0.23�@g/kWh ��NO���K���v�Ɓu2015�N�x�d�ʎԔR����
��{10�����x�̔R�����v�̋K�������̎��{�����ꍇ�ɂ́A�����Q�^�[�{�����̋C���x�~�V�X�e���̓����Z�p��
��^�g���b�N�ɍ̗p������Ȃ��Ɨ\�z�����B���̂悤�ȏɂȂ鎞���́A�C���x�~�G���W���i�������J2005-
54771�j�̓����������ł���2024�N5��25���ȍ~�ɐ扄�����邱�Ƃ��A������g���b�N���[�J�ɂƂ��Ă͍őP�̏�
����B
54771�j�̓����Z�p�̑��ɂ́A��^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W�����uNO���팸�v�Ɓu�R����P�v���\�ɂ���Z�p�����J
���̏ł���A�߂������ɁA���̓����Z�p�𗽉킷��V�Z�p���g���b�N���[�J���J���ł���ۏ�͊F���ł���B����
�����āA�����I�ɁA��^�g���b�N�̂̎g�p�ߒ��Ԃ��u�m�n����0.23�@g/kWh ��NO���K���v�Ɓu2015�N�x�d�ʎԔR����
��{10�����x�̔R�����v�̋K�������̎��{�����ꍇ�ɂ́A�����Q�^�[�{�����̋C���x�~�V�X�e���̓����Z�p��
��^�g���b�N�ɍ̗p������Ȃ��Ɨ\�z�����B���̂悤�ȏɂȂ鎞���́A�C���x�~�G���W���i�������J2005-
54771�j�̓����������ł���2024�N5��25���ȍ~�ɐ扄�����邱�Ƃ��A������g���b�N���[�J�ɂƂ��Ă͍őP�̏�
����B
�@���̂悤�ɁA����A��^�g���b�N�̎g�p�ߒ��Ԃ��u�m�n����0.23�@g/kWh ��NO���K���v�Ɓu2015�N�x�d�ʎԔR������
�{10�����x�̔R�����v�̋K�������̎��{�����ꍇ�ɂ́A�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓�������
�x�������Ɩ������R���݂ɁA���̓����Z�p�����Ђ̑�^�g���b�N�ɍ̗p�ł����ɁA���̓����Z�p�ɔ��ׂȕύX������
�āu���Ђ̐V�J���Z�p�I�v�Ƃ��Đ���ɐ�`���邱�Ƃ��\�ɂȂ�B������A���{�̑�^�g���b�N���[�J�ɂƂ��ẮA���l
�̐V�Z�p�𓐂ނ��Ƃɐ����������ƂɂȂ�A���̎~�܂�Ȃ��ƂȂ�̂ł���B����́A�l�ԂƂ��Ẵ������E�ǐS
�̌��������ڂ����s�ׂł��邪�A�V�Z�p���J������\�͂ɗ�鑽���̃g���b�N���[�J�̃T�����[�}���Z�p�҂ɂƂ��ẮA
�o���̂��߂ɂ͔w�ɕ��͕ς����Ȃ����Ƃ������Ȃ̂����m��Ȃ��B
�{10�����x�̔R�����v�̋K�������̎��{�����ꍇ�ɂ́A�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓�������
�x�������Ɩ������R���݂ɁA���̓����Z�p�����Ђ̑�^�g���b�N�ɍ̗p�ł����ɁA���̓����Z�p�ɔ��ׂȕύX������
�āu���Ђ̐V�J���Z�p�I�v�Ƃ��Đ���ɐ�`���邱�Ƃ��\�ɂȂ�B������A���{�̑�^�g���b�N���[�J�ɂƂ��ẮA���l
�̐V�Z�p�𓐂ނ��Ƃɐ����������ƂɂȂ�A���̎~�܂�Ȃ��ƂȂ�̂ł���B����́A�l�ԂƂ��Ẵ������E�ǐS
�̌��������ڂ����s�ׂł��邪�A�V�Z�p���J������\�͂ɗ�鑽���̃g���b�N���[�J�̃T�����[�}���Z�p�҂ɂƂ��ẮA
�o���̂��߂ɂ͔w�ɕ��͕ς����Ȃ����Ƃ������Ȃ̂����m��Ȃ��B
�@���̂悤�ɁA��^�g���b�N�̎g�p�ߒ��Ԃ��u�m�n����0.23�@g/kWh ��NO���K���v�Ɓu2015�N�x�d�ʎԔR������{10��
���x�̔R�����v�̋K���������A�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓������̏��ł���2024�N5��25���ȍ~
�ɐ扄�����邱�Ƃ́A�g���b�N���[�J�ɂƂ��Ă͊i�i�̗��v������ł�������ݏo����邱�ƂɂȂ�B���������āA
���{�i�����y��ʏȁE���ȁj����^�g���b�N�̎g�p�ߒ��Ԃ��u�m�n����0.23�@g/kWh ��NO���K���v�Ɓu2015�N�x�d�ʎԔR
������{10�����x�̔R�����v�̋K��������2024�N5���ȍ~�Ɏ��{����悤�ɍH��E��邱�Ƃ́A�g���b�N��
�[�J�ɂƂ��Ă̍ŗD��̎��ۂƐ��������B
���x�̔R�����v�̋K���������A�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓������̏��ł���2024�N5��25���ȍ~
�ɐ扄�����邱�Ƃ́A�g���b�N���[�J�ɂƂ��Ă͊i�i�̗��v������ł�������ݏo����邱�ƂɂȂ�B���������āA
���{�i�����y��ʏȁE���ȁj����^�g���b�N�̎g�p�ߒ��Ԃ��u�m�n����0.23�@g/kWh ��NO���K���v�Ɓu2015�N�x�d�ʎԔR
������{10�����x�̔R�����v�̋K��������2024�N5���ȍ~�Ɏ��{����悤�ɍH��E��邱�Ƃ́A�g���b�N��
�[�J�ɂƂ��Ă̍ŗD��̎��ۂƐ��������B
�@�����ŁA��^�g���b�N�̎g�p�ߒ��Ԃ��u�m�n����0.23�@g/kWh ��NO���K���v�Ɓu2015�N�x�d�ʎԔR������{10����
�x�̔R�����v�̋K��������2024�N5���ȍ~�̎��{�������ł���m���ȕ��@�́A�O�q�̂悤�ɁA���Ȃ������Ԕr
�o�K�X���ψ��ψ���A����э��y��ʏȂ̔R�����ԔR�����ψ�����G���W���W�̊w�ҁE���Ƃɘd�G��
����A���̗����̈ψ���̊w�ҁE���Ƃɂ͑�^�g���b�N�̎g�p�ߒ��Ԃ��u�m�n����0.23�@g/kWh ��NO���K���v�Ɓu2015
�N�x�d�ʎԔR������{10�����x�̔R�����v�̋K�������ɑ�^�g���b�N��K��������Z�p�ł����C���x�~�G��
�W���i�������J2005-54771�j�̓����̖����E�َE�E�B����2020�N���܂œO�ꂵ�Đ��s���ĖႤ���Ƃ������ԃ��[�J�i���g
���b�N���[�J�j�̗v�]�ƍl������B
�x�̔R�����v�̋K��������2024�N5���ȍ~�̎��{�������ł���m���ȕ��@�́A�O�q�̂悤�ɁA���Ȃ������Ԕr
�o�K�X���ψ��ψ���A����э��y��ʏȂ̔R�����ԔR�����ψ�����G���W���W�̊w�ҁE���Ƃɘd�G��
����A���̗����̈ψ���̊w�ҁE���Ƃɂ͑�^�g���b�N�̎g�p�ߒ��Ԃ��u�m�n����0.23�@g/kWh ��NO���K���v�Ɓu2015
�N�x�d�ʎԔR������{10�����x�̔R�����v�̋K�������ɑ�^�g���b�N��K��������Z�p�ł����C���x�~�G��
�W���i�������J2005-54771�j�̓����̖����E�َE�E�B����2020�N���܂œO�ꂵ�Đ��s���ĖႤ���Ƃ������ԃ��[�J�i���g
���b�N���[�J�j�̗v�]�ƍl������B
�@�����̖��Ƃ��Ď��ۂɂ́A���Ȃ������Ԕr�o�K�X���ψ��ψ���A����э��y��ʏȂ̔R�����ԔR����
�ψ�����G���W���W�̊w�ҁE���ƂɁA2020�N���܂��C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p�̑���
���E�َE�E�B�������s���ĖႤ���Ƃɐ�������A2020�N���ɂ͑�^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W�����uNO���팸�v��
�u�R����P�v�ɗL���ȐV�Z�p�Ƃ����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p�𐢊ԂɍL�����\���Ă��ǂ�
�ƍl������B�����āA2020�N�����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p�̑��݂�F�m�E���\����Ɠ�
���ɁA��^�g���b�N�̎g�p�ߒ��Ԃ��u�m�n����0.23�@g/kWh ��NO���K���v�Ɓu2015�N�x�d�ʎԔR������{10�����x��
�R�����v�̋K�������̕��j�\����̂ł���B���̂Ȃ�A�ʏ�̏ꍇ�A�K�������̔��\������{�܂łɂ�4�`
5�N���x�̃��[�h�^�C����݂���K�v�����邽�߁A2020�N���̎��_�ɂ�������^�g���b�N�̎g�p�ߒ��Ԃ��u�m�n����0.23
�@g/kWh ��NO���K���v�Ɓu2015�N�x�d�ʎԔR������{10�����x�̔R�����v�̋K��������2024�N5���ȍ~�Ɏ��{
����Ƃ̔��\���s���Ă��A��^�g���b�N�̈Ӑ}�I�ɐ摗�肵���K�������Ƃ͍����̒N�ɂ����������Ȃ����̂ƍl�����
��B
�ψ�����G���W���W�̊w�ҁE���ƂɁA2020�N���܂��C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p�̑���
���E�َE�E�B�������s���ĖႤ���Ƃɐ�������A2020�N���ɂ͑�^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W�����uNO���팸�v��
�u�R����P�v�ɗL���ȐV�Z�p�Ƃ����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p�𐢊ԂɍL�����\���Ă��ǂ�
�ƍl������B�����āA2020�N�����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p�̑��݂�F�m�E���\����Ɠ�
���ɁA��^�g���b�N�̎g�p�ߒ��Ԃ��u�m�n����0.23�@g/kWh ��NO���K���v�Ɓu2015�N�x�d�ʎԔR������{10�����x��
�R�����v�̋K�������̕��j�\����̂ł���B���̂Ȃ�A�ʏ�̏ꍇ�A�K�������̔��\������{�܂łɂ�4�`
5�N���x�̃��[�h�^�C����݂���K�v�����邽�߁A2020�N���̎��_�ɂ�������^�g���b�N�̎g�p�ߒ��Ԃ��u�m�n����0.23
�@g/kWh ��NO���K���v�Ɓu2015�N�x�d�ʎԔR������{10�����x�̔R�����v�̋K��������2024�N5���ȍ~�Ɏ��{
����Ƃ̔��\���s���Ă��A��^�g���b�N�̈Ӑ}�I�ɐ摗�肵���K�������Ƃ͍����̒N�ɂ����������Ȃ����̂ƍl�����
��B
�@�܂�A�g���b�N���[�J�́A���Ȃ������Ԕr�o�K�X���ψ��ψ���A����э��y��ʏȂ̔R�����ԔR������
������G���W���W�̊w�ҁE���Ƃɘd�G�邱�Ƃɂ�����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p
��2020�N���܂��������E�َE�E�B����}��A��^�g���b�N�̎g�p�ߒ��Ԃ��u�m�n����0.23�@g/kWh ��NO���K���v�Ɓu2015�N
�x�d�ʎԔR������{10�����x�̔R�����v�̋K��������2024�N5���ȍ~�ɐ扄�����邱�Ƃ��\�ɂȂ�ƍl
������B���ꂪ�A���Ȃ������Ԕr�o�K�X���ψ��ψ���A����э��y��ʏȂ̔R�����ԔR�����ψ�����G
���W���W�̊w�ҁE���ƂɃg���b�N���[�J���d�G�����ꍇ�̍H�슈���̐��ʂł���ƍl������B����́A�P��
��|���R�c���Z�p���̕M�҂��\���������Ȃ������Ԕr�o�K�X���ψ��ψ���A����э��y��ʏȂ̔R�����ԔR
�����ψ�����G���W���W�̊w�ҁE���ƂɃg���b�N���[�J���d�G��ꍇ�̖ړI�Ɗ��҂��鐬�ʂ̗\���ł�
��B
������G���W���W�̊w�ҁE���Ƃɘd�G�邱�Ƃɂ�����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p
��2020�N���܂��������E�َE�E�B����}��A��^�g���b�N�̎g�p�ߒ��Ԃ��u�m�n����0.23�@g/kWh ��NO���K���v�Ɓu2015�N
�x�d�ʎԔR������{10�����x�̔R�����v�̋K��������2024�N5���ȍ~�ɐ扄�����邱�Ƃ��\�ɂȂ�ƍl
������B���ꂪ�A���Ȃ������Ԕr�o�K�X���ψ��ψ���A����э��y��ʏȂ̔R�����ԔR�����ψ�����G
���W���W�̊w�ҁE���ƂɃg���b�N���[�J���d�G�����ꍇ�̍H�슈���̐��ʂł���ƍl������B����́A�P��
��|���R�c���Z�p���̕M�҂��\���������Ȃ������Ԕr�o�K�X���ψ��ψ���A����э��y��ʏȂ̔R�����ԔR
�����ψ�����G���W���W�̊w�ҁE���ƂɃg���b�N���[�J���d�G��ꍇ�̖ړI�Ɗ��҂��鐬�ʂ̗\���ł�
��B
�@�����āA�O�q�̒ʂ�A2014�N�x����A�����ԃ��[�J����̖̂��ԑg�D�̎����ԗp���R�@�Z�p�����g���i���`�h�b
�d�j ���獑�������J���@�l�̉Ȋw�Z�p�U���@�\�i�i�r�s�j�̑g�D���I�āA���Ȃ̎����Ԕr�o�K�X���ψ��ψ�
��A����э��y��ʏȂ̔R�����ԔR�����ψ���̃G���W���W�̊w�ҁE���Ƃł��鑁��c��w�E�吹�G��
���ƌc����w�E�ѓc�P�������Ɍ�����Ə̂���d�G�Ǝv�������������^���Ă���悤�ł���B���̌�����Ə̂���u�d
�G�Ǝv�����������^�v�́A�T�N�Ԃ̗\��̂��߁A2019�N�x�܂Ōp�����Ď��{�����Ƃ̂��Ƃł���B���́u�d�G�Ǝv����
�������^�v�̏́A�|���R�c���Z�p���̕M�҂̗\������g���b�N���[�J�ɂ���C���x�~�G���W���i�������J2005-
54771�j�̓����Z�p�̖����E�َE�E�B���̍H�슈���̖ڕW�ł���2020�N���ɕ�������悤�Ɏv�����A�@���Ȃ��̂ł���
�����B�Ȃ��A�����ԗp���R�@�Z�p�����g���i���`�h�b�d�j���狟�^�����d�G�Ǝv����������̂Q�^�R�́A�o�ώY�Ə�
�̐��{�\�Z�ł��邱�Ƃ��A�����̈�l�Ƃ��āA���Ƃ��[���̂ł��Ȃ����Ƃł���B����ɂ́A��v�����@�̌������č���
�K�v�Ǝv�����A�M�҂̎v���߂����ł��낤���B
�d�j ���獑�������J���@�l�̉Ȋw�Z�p�U���@�\�i�i�r�s�j�̑g�D���I�āA���Ȃ̎����Ԕr�o�K�X���ψ��ψ�
��A����э��y��ʏȂ̔R�����ԔR�����ψ���̃G���W���W�̊w�ҁE���Ƃł��鑁��c��w�E�吹�G��
���ƌc����w�E�ѓc�P�������Ɍ�����Ə̂���d�G�Ǝv�������������^���Ă���悤�ł���B���̌�����Ə̂���u�d
�G�Ǝv�����������^�v�́A�T�N�Ԃ̗\��̂��߁A2019�N�x�܂Ōp�����Ď��{�����Ƃ̂��Ƃł���B���́u�d�G�Ǝv����
�������^�v�̏́A�|���R�c���Z�p���̕M�҂̗\������g���b�N���[�J�ɂ���C���x�~�G���W���i�������J2005-
54771�j�̓����Z�p�̖����E�َE�E�B���̍H�슈���̖ڕW�ł���2020�N���ɕ�������悤�Ɏv�����A�@���Ȃ��̂ł���
�����B�Ȃ��A�����ԗp���R�@�Z�p�����g���i���`�h�b�d�j���狟�^�����d�G�Ǝv����������̂Q�^�R�́A�o�ώY�Ə�
�̐��{�\�Z�ł��邱�Ƃ��A�����̈�l�Ƃ��āA���Ƃ��[���̂ł��Ȃ����Ƃł���B����ɂ́A��v�����@�̌������č���
�K�v�Ǝv�����A�M�҂̎v���߂����ł��낤���B
�@�Ȃ��A�Y���i�ז@��Q�R�X���y�����z�ł́A�K�肳��Ă���B
(1) ���l�ł��A�ƍ߂�����Ǝv������Ƃ��́A���������邱�Ƃ��ł���B
(2) �������͌����́A���̐E�����s�����Ƃɂ��ƍ߂�����Ǝv������Ƃ��́A���������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
���̋K�肩�炷��ƁA���Ȃ̎����Ԕr�o�K�X���ψ��ψ���A����э��y��ʏȂ̔R�����ԔR�����ψ���
�̌��I�ȔC�ɓ�����G���W���W�̊w�ҁE���Ƃł��鑁��c��w�E�吹�G�����ƌc����w�E�ѓc�P����������
����Ə̂���d�G�Ǝv�������������^���Ă��邱�Ƃ́A�d�G�߂̋^��������Ǝv������鎖�ۂƍl������B����
���߁A�o�ώY�ƏȂ��v�����@�́A��������`��������Ǝv�����A�@���Ȃ��̂ł��낤���B
�̌��I�ȔC�ɓ�����G���W���W�̊w�ҁE���Ƃł��鑁��c��w�E�吹�G�����ƌc����w�E�ѓc�P����������
����Ə̂���d�G�Ǝv�������������^���Ă��邱�Ƃ́A�d�G�߂̋^��������Ǝv������鎖�ۂƍl������B����
���߁A�o�ώY�ƏȂ��v�����@�́A��������`��������Ǝv�����A�@���Ȃ��̂ł��낤���B
�@�����Ƃ��A�����ԗp���R�@�Z�p�����g���i���`�h�b�d�j�����{�̑g�D�i�����I�@�ցE�s���{�j�ł���A���{�̌��I��
�C�ɓ�����G���W���W�̊w�ҁE���Ƃł��鑁��c��w�E�吹�G�����ƌc����w�E�ѓc�P�������������ԗp��
�R�@�Z�p�����g���i���`�h�b�d�j���猤��������^����Ă��d�G�ɓ�����Ȃ����Ƃ������ł���B���̂��߂��ǂ�����
�s���ł͂��邪�A����c��w�E�吹�G�����́A�ȉ����\�P�V�Ɏ������悤�ɁA�����ԋZ�p��2015�N9�����iVol.69�A
N0.8�A2015�j�́u�����ԗp�p���[�g���C���̍��������Z�p�Ɋւ��铮���Ə����W�]�v�i���ҁF����c��w�E�吹�G��
��)�ł́A�u�o�ώY�ƏȂɂ�鎩���ԗp���R�@�Z�p�����g���i���`�h�b�d�j�����N�i��2014�N�j�X�^�[�g���Ă���v�ƁA�`�h�b
�d�����{�̑g�D�i�����I�@�ցE�s���{�j�ł��邩�̔@���A�L�ڂ���Ă���B
�C�ɓ�����G���W���W�̊w�ҁE���Ƃł��鑁��c��w�E�吹�G�����ƌc����w�E�ѓc�P�������������ԗp��
�R�@�Z�p�����g���i���`�h�b�d�j���猤��������^����Ă��d�G�ɓ�����Ȃ����Ƃ������ł���B���̂��߂��ǂ�����
�s���ł͂��邪�A����c��w�E�吹�G�����́A�ȉ����\�P�V�Ɏ������悤�ɁA�����ԋZ�p��2015�N9�����iVol.69�A
N0.8�A2015�j�́u�����ԗp�p���[�g���C���̍��������Z�p�Ɋւ��铮���Ə����W�]�v�i���ҁF����c��w�E�吹�G��
��)�ł́A�u�o�ώY�ƏȂɂ�鎩���ԗp���R�@�Z�p�����g���i���`�h�b�d�j�����N�i��2014�N�j�X�^�[�g���Ă���v�ƁA�`�h�b
�d�����{�̑g�D�i�����I�@�ցE�s���{�j�ł��邩�̔@���A�L�ڂ���Ă���B
| �� �����ԗp���R�@�Z�p�����g���i���`�h�b�d�j�Ɋւ���L�ڂ̋Z�p��
�E �����ԋZ�p��2015�N9�����iVol.69�AN0.8�A2015�j �E ��� �F �����ԗp�p���[�g���C���̍��������Z�p�Ɋւ��铮���Ə����W�] �E ���� �F ����c��w�E�吹�G���� �� �����ԗp���R�@�Z�p�����g���i���`�h�b�d�j�Ɋւ���L�ڂ̓��e �E �u�S�D���̈�̌����J���ɂ�����Y�w���̘A�g�v�̍��ɋL�ڂ��ꂽ���e�̈ꕔ 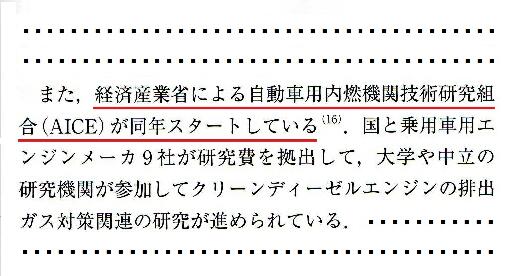 |
| �� �u�o�ώY�ƏȂɂ�鎩���ԗp���R�@�Z�p�����g���i���`�h�b�d�j�����N�X�^�[�g�v�̈Ӗ�
�E ���̐���ς������Ɂu�o�ώY�ƏȂɂ�鎩���ԗp���R�@�Z�p�����g���i���`�h�b�d�j�����N�i��2014�N�j�X�^�[�g���Ă� ��v�Ƃ̋L�ڂ������ǎ҂̑啔���́A�o�ώY�ƏȂ������ԗp���R�@�Z�p�����g���i���`�h�b�d�j��ݗ��������I�@�ցi�� ���{�@�ցj�ł���Ɗm���Ɍ�����Ă��܂����̂Ɛ��������B �E �������A���ۂ̂Ƃ���́A�O�q�̕\�P�R�Ɏ������悤�ɁA���̎����ԗp���R�@�Z�p�����g���i���`�h�b�d�j�ɂ͌o�ώY�Ə� �̕⏕������������Ă͂��邪�A���ۂ̎����ԗp���R�@�Z�p�����g���i���`�h�b�d�j�́A�����ԃ��[�J�X�Ђ���̂ƂȂ� �Đݗ����ꂽ���S�Ȗ��ԑg�D�ƍl������B���̗��R�́A�����ԗp���R�@�Z�p�����g���i���`�h�b�d�j�̗������A�ꖱ�� ���A�����A�����̖����̑S�����A���Ԑl�ł��邽�߂��B �E �����ԗp���R�@�Z�p�����g���i���`�h�b�d�j�����R���閯�ԑg�D�ł���ɂ�������炸�A�u�o�ώY�ƏȂɂ�鎩���ԗp ���R�@�Z�p�����g���i���`�h�b�d�j�����N�X�^�[�g���Ă���v�Ƃ̑���c��w�E�吹�G�����̋L�q�́A�����ԗp���R�@�� �Z�p�����g���i���`�h�b�d�j�����I�@�ւƂ̌�����Ӑ}�I�ɓǎ҂ɗ^���邽�߂̍����ł͂Ȃ����ƍl������B �E ���ɁA�����ԗp���R�@�Z�p�����g���i���`�h�b�d�j�����I�@�ւ̏ꍇ�ɂ́A�Ȋw�Z�p�U���@�\�i�i�r�s�j����Ă`�h�b�d�� �瑁��c��w�E�吹�G���������^����錤����́A�u�d�G�v�̋^�f���F���ƂȂ�B�������A�����ԗp���R�@�Z�p���� �g���i���`�h�b�d�j�����S�Ȗ��ԑg�D�̏ꍇ�ɂ́A�Ȋw�Z�p�U���@�\�i�i�r�s�j����Ă`�h�b�d���瑁��c��w�E�吹�G���� �����^����錤����́A�u�d�G�v�̋^�f���Z���ƂȂ�B �E ���Ȃ̎����Ԕr�o�K�X���ψ��ψ���A����э��y��ʏȂ̔R�����ԔR�����ψ���̌��I�ȔC�ɓ�����G�� �W���W�̊w�ҁE���Ƃł��鑁��c��w�E�吹�G�����́A���S�Ȗ��ԑg�D�̎����ԗp���R�@�Z�p�����g���i���`�h �b�d�j����Ȋw�Z�p�U���@�\�i�i�r�s�j����Ď�̂��錤����u�d�G�v�ɑ�������Ƃ̔F�������������Ă���\�����l�� ����B���̏ꍇ�A���̂��Ƃ����ԂɍL���m��j�����ꍇ�ɂ́A����c��w�E�吹�G�������ᔻ�̓I�ɂȂ��Ă��܂��뜜 ���Ă���\�����l������B�����ŁA���̏�����������Ƃ��āA�����ԗp���R�@�Z�p�����g���i���`�h�b�d�j�����I �@�ւł���Ɛ��Ԃ̐l�B���I����������邱�Ƃ��ł���A�����ԗp���R�@�Z�p�����g���i���`�h�b�d�j����Ȋw�Z�p�U�� �@�\�i�i�r�s�j����đ���c��w�E�吹�G�������������������u�d�G�v�Ƃ̔ᔻ���鋰��������ɖ��������Ƃ� �ł���B���̂��߁A����c��w�E�吹�G�����́A�u�����ԗp���R�@�Z�p�����g���i���`�h�b�d�j�͌o�ώY�ƏȂ���ݗ��� �����I�@�ցi�����{�@�ցj�ł���v�Ƃ̌���ޓ��e�������ԋZ�p��2015�N9�����iVol.69�AN0.8�A2015�j�ɋL�ڂ������� �Ɛ��������B���ɁA���ꂪ�����ł���A���Ƃ��Ƒ��Ȃ��Ƃł͂Ȃ����낤���B |
�i�E�j ���d�ɂ�����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p���B������w�҂̈�@��
�@���݂̓��{�ł́A���Ȃ������Ԕr�o�K�X���ψ��ψ���A����э��y��ʏȂ̔R�����ԔR�����ψ����
���{���\�����G���W���W�̊w�ҁE���Ƃ́A�d�G�Ǝv�������������̂��Ď����ԃ��[�J�̗v�]�ʂ�́uNO���K
���v��u�R���v��ݒ肷��s���������������ϗ��E��������������������������Ȑl���Ő�߂��Ă���Ǝv��
����ł���l���w�ǂ̂悤�ł���B���̂��Ƃ������āA���{�ł��A���E���ōł��������u��C���̉��P�v�Ɓu�g���b�N�A
������̏Ȏ����E�ȃG�l���M�[���v�̎{���{����Ă���Ə���Ɏv������ł���l�������̑命�����߂Ă���
�悤�Ɋ�������B
���{���\�����G���W���W�̊w�ҁE���Ƃ́A�d�G�Ǝv�������������̂��Ď����ԃ��[�J�̗v�]�ʂ�́uNO���K
���v��u�R���v��ݒ肷��s���������������ϗ��E��������������������������Ȑl���Ő�߂��Ă���Ǝv��
����ł���l���w�ǂ̂悤�ł���B���̂��Ƃ������āA���{�ł��A���E���ōł��������u��C���̉��P�v�Ɓu�g���b�N�A
������̏Ȏ����E�ȃG�l���M�[���v�̎{���{����Ă���Ə���Ɏv������ł���l�������̑命�����߂Ă���
�悤�Ɋ�������B
�@���ɁA���ꂪ�����ł���A�����_�i��2015�N7�����݁j�ɂ����āA���Ȃ������Ԕr�o�K�X���ψ��ψ���A����
�э��y��ʏȂ̔R�����ԔR�����ψ�����G���W���W�̊w�ҁE���Ƃ́A��^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W����
�uNO���팸�v�Ɓu�R����P�v�ɗL���ȂQ�^�[�{�����̋C���x�~�V�X�e���ł����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j
�̓����Z�p�̑��݂�F�߁A��^�g���b�N�̎g�p�ߒ��Ԃ��u�m�n����0.23�@g/kWh ��NO���K���v�Ɓu2015�N�x�d�ʎԔR���
������{10�����x�̔R�����v�̋K��������x���Ƃ�2020�N���Ɏ��{�����\��ƂȂ��Ă��锤�ł���B�Ƃ��낪�A��
��́A����Ƃ͑傫���قȂ�A�ȉ��̏ƂȂ��Ă���悤�ł���B
�э��y��ʏȂ̔R�����ԔR�����ψ�����G���W���W�̊w�ҁE���Ƃ́A��^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W����
�uNO���팸�v�Ɓu�R����P�v�ɗL���ȂQ�^�[�{�����̋C���x�~�V�X�e���ł����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j
�̓����Z�p�̑��݂�F�߁A��^�g���b�N�̎g�p�ߒ��Ԃ��u�m�n����0.23�@g/kWh ��NO���K���v�Ɓu2015�N�x�d�ʎԔR���
������{10�����x�̔R�����v�̋K��������x���Ƃ�2020�N���Ɏ��{�����\��ƂȂ��Ă��锤�ł���B�Ƃ��낪�A��
��́A����Ƃ͑傫���قȂ�A�ȉ��̏ƂȂ��Ă���悤�ł���B
| �@���{�̑�^�g���b�N�����鏫���́uNO���K���̋����v�������������Ȃ������Ԕr�o�K�X���ψ��ψ� ����u�R���̋����v�����肷�����y��ʏȂ̔R�����ԔR�����ψ���̕Ј���A�܂��͗����̈� �����܂��͈ψ���C���������I�Ȍ��͂����s���錠������������c��w�E�吹�G��������ьc���� �w�E�ѓc�P�������̗������́A�����ԗp���R�@�Z�p�����g���i���`�h�b�d�j��Ȋw�Z�p�U���@�\�i�i�r�s�j �̑g�D���I�������ԃ��[�J�����������Ə̂���d�G�Ǝv����������2014�N�����̂��J�n���Ă� ��B���������ԃ��[�J������d�G�Ǝv���������i��������j�́A2019�N�x�܂łT�N�Ԃɘj���Čp������\�� �Ƃ̂��Ƃł���B�����āA�吹�����Ɣѓc�����̗������́A�`�h�b�d�i�������ԃ��[�J�̐ݗ������g���j����d�G�Ǝv �������������錩�Ԃ�Ƃ��āA��^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W�����uNO���팸�v�Ɓu�R����P�v�ɗL���ȂQ�^�[ �{�����̋C���x�~�V�X�e���ł����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p��2020�N���܂Ŗ����E�� �E��O�ꂷ�銈�����s�����̂Ɛ��@�����B�����āA�����Ԕr�o�K�X���ψ��ψ�����u�R���̋����v������ �������y��ʏȂ̔R�����ԔR�����ψ���̋c�_�E�����̒��ő吹�����Ɣѓc�������C���x�~�G���W���i�� �����J2005-54771�j�������Z�p��2020�N���܂Ŗ����E�َE����ӌ��E�����������咣�����ꍇ�ɂ́A�uNO���K���� �����v�����肷����^�g���b�N�̎g�p�ߒ��Ԃ��u�m�n����0.23�@g/kWh ��NO���K���v�Ɓu2015�N�x�d�ʎԔR���� ��{10�����x�̔R�����v�̋K��������2024�N�T���ȍ~�̎��{�Ɍ��肳���\�����ɂ߂č������̂Ɨ\�z�� ���B |
�`�h�b�d�i�������ԃ��[�J�̐ݗ������g���j����d�G�Ǝv��������������吹�G�����Ɣѓc�P��������
2020�N���܂��C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̖����E�َE��O�ꂷ�銈���E�s�ׂ����s��
��^�g���b�N�̎g�p�ߒ��Ԃ��u�m�n����0.23�@g/kWh ��NO���K���v�Ɓu2015�N�x�d�ʎԔR������{10�����x
�̔R�����v�̋K�������������ԃ��[�J�̊�]�E�v�]��2024�N�T���ȍ~�ɜ��ӓI�ɏ��������銈���E�s�ׂ�
���ۂɍs���Ă���Ɖ��肵���ꍇ�ɂ��āA�吹�G�����Ɣѓc�P���������s�����s���́u���@�E�����v��
�u���_�v������B
|
| �P�D�吹�����Ɣѓc�������C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j���E�َE���铮�@�E����
�E�u���H�v�E�u���݁i���i�j�v���������C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p�� �i�吹�G�����Ɣѓc�P���������C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j���E�َE����s�ׂ́A �����_�i��2015�N7�����݁j�ɂ��� �āA�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p�𗽉킷����^�g���b�N�́uNO���팸�v�Ɓu�R����P�v�ɗL���ȐV�Z�p���Ă��� ���Ȃ��u���H�v�E�u���݁i���i�j�v�������̉\��������B���ɁA�����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�����Ă̎����ԃ��[�J�� �l�Ă��������Z�p�ł���A�吹�G�����Ɣѓc�P�������́A���g�̐V�Z�p�̗���́E���@�\�͂̍������֎����邽�߂ɁA���̓����Z�p �𗦐悵�ďЉ�Ă����\��������B�j �Q�D�吹�����Ɣѓc�����̍s�ׁE�s���̖��_ �E�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p���̉B���́A�w�҂̗ǐS�����
�i��^�f�B�[�[���g���b�N�́uNO���팸�v�Ɓu�R����P�v�ɗL���ȂQ�^�[�{�����̋C���x�~�V�X�e�����C���x�~�G���W���i�������J2005-
54771�j�̓����Z�p�́A2005�N3�����ɓ������J����Ă����ɁA2006�N4��7�����J�̕M�҂̃C���^�[�l�b�g�̃z�[���y�[�W�ɂ����ċZ�p
���e���ڍׂɐ������Ă���B�����āA���̕M�҂̃z�[���y�[�W�́A�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p�Ɋւ���Z�p���
�́A2009�N�`2010�N�̐̂���A�C���^�[�l�b�g������Yahoo�����G���W���ł͏�ʂɌ��o����Ă�������[22009�N6��11���ł́u�|�X�g�V
�����v�̂P���Yahoo�������� �����2010�N2��24���ł́u�g���b�N�v�{�u��R��v�̂Q���Yahoo�������� ]������B�Ȃ��A�ŋ߂̎����ԋZ
�p���́u�Z�p�����L���v������ƁA���̏�̑啔�����C���^�[�l�b�g���ł��邱�Ƃ���A�����̐��ƁE�Z�p�҂́A�ŐV�̋Z�p�����C
���^�[�l�b�g�̃z�[���y�[�W������W���Ă���̂�����ƍl������B���������āA�吹�����Ɣѓc�������A��^�g���b�N�́u�m�n����0.23�@g/
kWh�̋K���v�A����сu2015�N�d�ʎԔR�����{10���v��e�ՂɎ����ł���M�Ғ�Ă��C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓�
���Z�p�̑��݂ɂ��ẮA����2009�N�`2010�N�̍�������ɏ��m�E�F�����Ă������̂Ɛ��������B�j
�E�d�G�Ǝv�������������̂����u���Ȃ��������v�ɊY�����吹�����Ɣѓc�����́A�d�G�߂ɑ����Ɛ��@
�i���Ȃ̎����Ԕr�o�K�X���ψ��ψ���́uNO���K���̋����v�����肵�A���y��ʏȂ̔R�����ԔR�����ψ���́u�R���̋�
���v�����肷��ψ���ł���B�����āA�吹�����Ɣѓc�����́A���Ȃ̎����Ԕr�o�K�X���ψ��ψ���A����э��y��ʏȂ̔R������
�R�����ψ���̕Ј���A�܂��͗����̈ψ����܂��͈ψ���C�����Ă���B���̂��߁A�吹�����Ɣѓc�����́A�����i���匠�ҁj�̑�
���Ƃ��Č����͂����s����א��҂⊯���ɑ����̌��������u���Ȃ��������v�ɊY������ƍl������B���̂悤�ȑ吹�����Ɣѓc�����́A
�����ԗp���R�@�Z�p�����g���i���`�h�b�d�j��Ȋw�Z�p�U���@�\�i�i�r�s�j�̑g�D���I�������ԃ��[�J����̌�����Ə̂���d�G�Ǝv����
������2014�N�����̂��J�n�����Ƃ̂��Ƃł���B�����āA���ꂪ2019�N�x�܂łT�N�Ԃɘj���Čp�������\��Ƃ̂��ƁB�u���Ȃ��������v��
�Y���Ɛ��@�����吹�����Ɣѓc�������d�G�Ǝv����������̋��^���邱�Ƃ́A�d�G�߂ɑ�������ƍl�����邪�A�@���Ȃ��̂ł��낤
���B�j
�i�吹�����Ɣѓc�����́A�����ԗp���R�@�Z�p�����g���i���`�h�b�d�������ԃ��[�J�̐ݗ������g���j����d�G�Ǝv�������������� ���Ԃ�Ƃ��āA��^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W���́uNO���팸�v�Ɓu�R����P�v�ɗL���ȂQ�^�[�{�����̋C���x�~�V�X�e���ł����C���x�~�G�� �W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p��2020�N���܂œO��I�ɖ����E�َE�����銈���E�s�ׂ�ϋɓI�ɍs�����̂ƍl������B�����āA �uNO���K���̋����v�����肷�鎩���Ԕr�o�K�X���ψ��ψ����u�R���̋����v�����肷�鍑�y��ʏȂ̔R�����ԔR�����ψ��� �̒��̋c�_�E�����ɂ����āA���̓����Z�p�̖����E�َE��吹�����Ɣѓc�����������咣���邱�Ƃɂ��A�����ԃ��[�J�i���g���b�N���[�J�j�� �v�]�ł����^�g���b�N�̎g�p�ߒ��Ԃ́u�m�n����0.23�@g/kWh ��NO���K���v�Ɓu2015�N�x�d�ʎԔR������{10�����x�̔R�����v�̋K ��������2024�N5���ȍ~�ɒx��������H��𐬌��ɓ����\�����ɂ߂č������̂Ɛ��@�����B�j |
�@�����Ƃ��A����c��w�E�吹�G�����ƌc����w�E�ѓc�P�������́A�|���R�c���Z�p���̕M�҂��l�Ă����Q�^�[�{��
���̋C���x�~�V�X�e�����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p�́A��^�f�B�[�[���g���b�N�́uNO����
���v�Ɓu�R����P�v�̋@�\�E���\�̖����u�K���N�^�����v�E�u�n�������v�ł���Ƃ̊m�M��������Ă��邩���m��Ȃ��B����
�ꍇ�́A�吹�����Ɣѓc�������C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p���E�َE���đ�^�g���b�N��
�g�p�ߒ��Ԃ́u�m�n����0.23�@g/kWh ��NO���K���v�Ɓu2015�N�x�d�ʎԔR������{10�����x�̔R�����v�̋K����
����2024�N�T���ȍ~�ɐ扄����}�銈����ϋɓI�ɍs�����Ƃ́A�����ɓK�������Ƃł���ƍl������B���̏ꍇ��
�́A�M�҂̔ᔻ�́A���S�ȁu���v�ł���B
���̋C���x�~�V�X�e�����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p�́A��^�f�B�[�[���g���b�N�́uNO����
���v�Ɓu�R����P�v�̋@�\�E���\�̖����u�K���N�^�����v�E�u�n�������v�ł���Ƃ̊m�M��������Ă��邩���m��Ȃ��B����
�ꍇ�́A�吹�����Ɣѓc�������C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p���E�َE���đ�^�g���b�N��
�g�p�ߒ��Ԃ́u�m�n����0.23�@g/kWh ��NO���K���v�Ɓu2015�N�x�d�ʎԔR������{10�����x�̔R�����v�̋K����
����2024�N�T���ȍ~�ɐ扄����}�銈����ϋɓI�ɍs�����Ƃ́A�����ɓK�������Ƃł���ƍl������B���̏ꍇ��
�́A�M�҂̔ᔻ�́A���S�ȁu���v�ł���B
�@���̂悤�ɁA�吹�����Ɣѓc�������C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j����^�f�B�[�[���g���b�N�́uNO����
���v�Ɓu�R����P�v�ɖ����ȋZ�p�Ƃ̊m�ł���ӌ��E�M�O��������Ă���̂ł���A���̎|���ɋL�ڂ�E���[���A
�h���X�̕M�҂̕��ɁA����Ƃ���A�����������������B�����āA�M�ҍl�Ă��C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j
�̓����Z�p����^�f�B�[�[���g���b�N�́uNO���팸�v�Ɓu�R����P�v�ɖ����ł��闝�R������Ղ��������Ă���������A
�����A�{�z�[���y�[�W���������ƍl���Ă���B�������A�M�ҍl�Ă̓����Z�p����^�f�B�[�[���g���b�N�́uNO����
���v�Ɓu�R����P�v�ɖ����ł���Ƃ̐����𑗕t���������Ȃ��ꍇ�́A�吹�����Ɣѓc�����́A�����ԃ��[�J����d�G
�Ǝv����������������C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p��2020�N���܂Ŗ����E�َE��}���i�E
���@��p���āA��^�g���b�N�̎g�p�ߒ��Ԃ́u�m�n����0.23�@g/kWh ��NO���K���v�Ɓu2015�N�x�d�ʎԔR������{
10�����x�̔R�����v�̋K��������2024�N�T���ȍ~�Ɂu�扄���v�E�u�摗��v�E�u�����v��}��s���ȍH�슈����F�߂�
�ꂽ���̂ƁA�M�҂͗����E���߂����Ē������Ƃɂ���B
���v�Ɓu�R����P�v�ɖ����ȋZ�p�Ƃ̊m�ł���ӌ��E�M�O��������Ă���̂ł���A���̎|���ɋL�ڂ�E���[���A
�h���X�̕M�҂̕��ɁA����Ƃ���A�����������������B�����āA�M�ҍl�Ă��C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j
�̓����Z�p����^�f�B�[�[���g���b�N�́uNO���팸�v�Ɓu�R����P�v�ɖ����ł��闝�R������Ղ��������Ă���������A
�����A�{�z�[���y�[�W���������ƍl���Ă���B�������A�M�ҍl�Ă̓����Z�p����^�f�B�[�[���g���b�N�́uNO����
���v�Ɓu�R����P�v�ɖ����ł���Ƃ̐����𑗕t���������Ȃ��ꍇ�́A�吹�����Ɣѓc�����́A�����ԃ��[�J����d�G
�Ǝv����������������C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p��2020�N���܂Ŗ����E�َE��}���i�E
���@��p���āA��^�g���b�N�̎g�p�ߒ��Ԃ́u�m�n����0.23�@g/kWh ��NO���K���v�Ɓu2015�N�x�d�ʎԔR������{
10�����x�̔R�����v�̋K��������2024�N�T���ȍ~�Ɂu�扄���v�E�u�摗��v�E�u�����v��}��s���ȍH�슈����F�߂�
�ꂽ���̂ƁA�M�҂͗����E���߂����Ē������Ƃɂ���B
�@�Ȃ��A���Ȃ������Ԕr�o�K�X���ψ��ψ���A����э��y��ʏȂ̔R�����ԔR�����ψ���̕Ј���A�܂�
�͗����̈ψ����܂��͈ψ���C�����āuNO���K���ƔR���̋����v�ɊW�������I�Ȍ��͂����s���錠��������
��Ă�������c��w�E�吹�G�����ƌc����w�E�ѓc�P�������������ԃ��[�J���狟�^���ꂽ�d�G�Ǝv�����������
�f�킳��A�g���b�N���[�J�i�������ԃ��[�J�j�̗v�]�ɉ����āA��^�g���b�N���uNO���팸�v�Ɓu�R����P�v�ɗL�����C���x
�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p�����E�َE�E�B�����ē��{�̑�^�g���b�N�̎g�p�ߒ��Ԃ��u�m�n����0.
23�@g/kWh ��NO���K���v�Ɓu2015�N�x�d�ʎԔR������{10�����x�̔R�����v�̋K��������2024�N�T���ȍ~�ɐ�
�����ɂ��銈�����B�����ɍs���Ă��邱�Ƃ������ł���A�����̍����͕s�����ȋ]�����������邱�ƂɂȂ�B��
���āA���{�̐��{�����E���ōł��i�u��C���̉��P�v�Ɓu�g���b�N�A������̏Ȏ����E�ȃG�l���M�[���v�𐄐i��
��{���^�ʖڂɐ��i���Ă���Ƃ̎v�����݂́A���z�ɉ߂��Ȃ����ƂɂȂ�B
�͗����̈ψ����܂��͈ψ���C�����āuNO���K���ƔR���̋����v�ɊW�������I�Ȍ��͂����s���錠��������
��Ă�������c��w�E�吹�G�����ƌc����w�E�ѓc�P�������������ԃ��[�J���狟�^���ꂽ�d�G�Ǝv�����������
�f�킳��A�g���b�N���[�J�i�������ԃ��[�J�j�̗v�]�ɉ����āA��^�g���b�N���uNO���팸�v�Ɓu�R����P�v�ɗL�����C���x
�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p�����E�َE�E�B�����ē��{�̑�^�g���b�N�̎g�p�ߒ��Ԃ��u�m�n����0.
23�@g/kWh ��NO���K���v�Ɓu2015�N�x�d�ʎԔR������{10�����x�̔R�����v�̋K��������2024�N�T���ȍ~�ɐ�
�����ɂ��銈�����B�����ɍs���Ă��邱�Ƃ������ł���A�����̍����͕s�����ȋ]�����������邱�ƂɂȂ�B��
���āA���{�̐��{�����E���ōł��i�u��C���̉��P�v�Ɓu�g���b�N�A������̏Ȏ����E�ȃG�l���M�[���v�𐄐i��
��{���^�ʖڂɐ��i���Ă���Ƃ̎v�����݂́A���z�ɉ߂��Ȃ����ƂɂȂ�B
�@���݂ɁA�����ԃ��[�J �X�Ђőg�D���ꂽ�����ԗp���R�@�Z�p�����g���i���`�h�b�d�j���Ȋw�Z�p�U���@�\�i�i�r�s�j��
�ϑ������헪�I�C�m�x�[�V�����n���v���O�����i�r�h�o�j�̌�����́A�\�P�S�Ɏ������悤�ɁA���{�̐��\�̑�w�ɋ��^��
��Ă���B���̎����ԗp���R�@�Z�p�����g���i���`�h�b�d�j������������^�������{�̐��\�̑�w�̒��ɂ́A����c
��w�E�吹�G�����ƌc����w�E�ѓc�P�������̑��ɂ��A���Ȃ̎����Ԕr�o�K�X���ψ��ψ���ƍ��y��ʏȂ�
�����ԔR�����ψ���̃G���W�����̑����W���̒����Ȋw�ҁE���Ɓi���͖쓹�������A���H���G�����A�吹
�G�����A�ѓc�P�������A���������ް���ђ��A���������A�㓡�Y�괸è�ށE�Ʊ�Eػ�����A�ߋv������
���j�̏��������w���܂܂�Ă��邩���m��Ȃ��B���̏ꍇ�ɂ́A���R�̂��ƂȂ���A�g���b�N���[�J�i�������ԃ��[�J�j
�̗v�]�ɉ����āA��^�g���b�N���uNO���팸�v�Ɓu�R����P�v�ɗL�����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p
�����E�َE�E�B�����ē��{�̑�^�g���b�N�̎g�p�ߒ��Ԃ��u�m�n����0.23�@g/kWh ��NO���K���v�Ɓu2015�N�x�d�ʎ�
�R������{10�����x�̔R�����v�̋K��������2024�N�T���ȍ~�ɐ扄�����銈�����A����c��w�E�吹�G
�����ƌc����w�E�ѓc�P�������Ƌ��͂��čs�����̂Ɛ��������B
�ϑ������헪�I�C�m�x�[�V�����n���v���O�����i�r�h�o�j�̌�����́A�\�P�S�Ɏ������悤�ɁA���{�̐��\�̑�w�ɋ��^��
��Ă���B���̎����ԗp���R�@�Z�p�����g���i���`�h�b�d�j������������^�������{�̐��\�̑�w�̒��ɂ́A����c
��w�E�吹�G�����ƌc����w�E�ѓc�P�������̑��ɂ��A���Ȃ̎����Ԕr�o�K�X���ψ��ψ���ƍ��y��ʏȂ�
�����ԔR�����ψ���̃G���W�����̑����W���̒����Ȋw�ҁE���Ɓi���͖쓹�������A���H���G�����A�吹
�G�����A�ѓc�P�������A���������ް���ђ��A���������A�㓡�Y�괸è�ށE�Ʊ�Eػ�����A�ߋv������
���j�̏��������w���܂܂�Ă��邩���m��Ȃ��B���̏ꍇ�ɂ́A���R�̂��ƂȂ���A�g���b�N���[�J�i�������ԃ��[�J�j
�̗v�]�ɉ����āA��^�g���b�N���uNO���팸�v�Ɓu�R����P�v�ɗL�����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p
�����E�َE�E�B�����ē��{�̑�^�g���b�N�̎g�p�ߒ��Ԃ��u�m�n����0.23�@g/kWh ��NO���K���v�Ɓu2015�N�x�d�ʎ�
�R������{10�����x�̔R�����v�̋K��������2024�N�T���ȍ~�ɐ扄�����銈�����A����c��w�E�吹�G
�����ƌc����w�E�ѓc�P�������Ƌ��͂��čs�����̂Ɛ��������B
�@�ܘ_�A�����ԗp���R�@�Z�p�����g���i���`�h�b�d�j���猤��������^���ꂽ��w�i���\�P�S�Ɏ������Ȋw�Z�p�U���@
�\�i�i�r�s�j�ɂ����闪�I�C�m�x�[�V�����n���v���O�����i�r�h�o�j�ɋL�ڂ̐��\�̑�w���N���X�^�[��w�ƌď́j�̋����́A
��^�g���b�N���uNO���팸�v�Ɓu�R����P�v�ɗL�����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p���̖����E�َE�E
�B���ɋ��͂��A���{�̑�^�g���b�N�̎g�p�ߒ��Ԃ��u�m�n����0.23�@g/kWh ��NO���K���v�Ɓu2015�N�x�d�ʎԔR����
��{10�����x�̔R�����v�̋K��������2024�N�T���i���C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����������ł�
�鎞���j�̈ȍ~�ɐ摗�肷�銈����ϋɓI�ɍs�����̂Ɛ��������B
�\�i�i�r�s�j�ɂ����闪�I�C�m�x�[�V�����n���v���O�����i�r�h�o�j�ɋL�ڂ̐��\�̑�w���N���X�^�[��w�ƌď́j�̋����́A
��^�g���b�N���uNO���팸�v�Ɓu�R����P�v�ɗL�����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p���̖����E�َE�E
�B���ɋ��͂��A���{�̑�^�g���b�N�̎g�p�ߒ��Ԃ��u�m�n����0.23�@g/kWh ��NO���K���v�Ɓu2015�N�x�d�ʎԔR����
��{10�����x�̔R�����v�̋K��������2024�N�T���i���C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����������ł�
�鎞���j�̈ȍ~�ɐ摗�肷�銈����ϋɓI�ɍs�����̂Ɛ��������B
�@���̏�����ƁA2014�N�x�`2019�N�x�̂T�N�Ԃɘj���āA�����ԃ��[�J�������ԗp���R�@�Z�p�����g���i���`�h
�b�d�j����ē��{�̑啔���̎�v��w�ɘd�G�Ǝv��������������^����H�슈���́A��^�g���b�N���uNO���팸�v��
�u�R����P�v�ɗL�����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p�����E�َE�E�B�����ē��{�̑�^�g���b�N
�̎g�p�ߒ��Ԃ��u�m�n����0.23�@g/kWh ��NO���K���v�Ɓu2015�N�x�d�ʎԔR������{10�����x�̔R�����v�̋K��
������2024�N5���i���C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����������ł��鎞���j�̈ȍ~�Ɋm���ɐ扄��
�ɂ��閜�S�ȑ̐����\�z���Ă���悤�Ɍ�����B����́A�|���R�c���Z�p���̕M�҂̖ϑz�ł��낤���B
�b�d�j����ē��{�̑啔���̎�v��w�ɘd�G�Ǝv��������������^����H�슈���́A��^�g���b�N���uNO���팸�v��
�u�R����P�v�ɗL�����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p�����E�َE�E�B�����ē��{�̑�^�g���b�N
�̎g�p�ߒ��Ԃ��u�m�n����0.23�@g/kWh ��NO���K���v�Ɓu2015�N�x�d�ʎԔR������{10�����x�̔R�����v�̋K��
������2024�N5���i���C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����������ł��鎞���j�̈ȍ~�Ɋm���ɐ扄��
�ɂ��閜�S�ȑ̐����\�z���Ă���悤�Ɍ�����B����́A�|���R�c���Z�p���̕M�҂̖ϑz�ł��낤���B
�@����͗]�k�ł��邪�A����c��w�E�吹�G�����́A�|���R�c���Z�p���̕M�҂��l�Ă����C���x�~�G���W���i����
���J2005-54771�j�̓����Z�p���������Ă���悤�ł���B���̏؋��Ƃ��ẮA�ȉ����\�P�W�Ɏ������u�����Q�T�N�x
��ʈ��S���������u����ɂ�����吹�����̍u�������v����������B
���J2005-54771�j�̓����Z�p���������Ă���悤�ł���B���̏؋��Ƃ��ẮA�ȉ����\�P�W�Ɏ������u�����Q�T�N�x
��ʈ��S���������u����ɂ�����吹�����̍u�������v����������B
| |
 |
| |
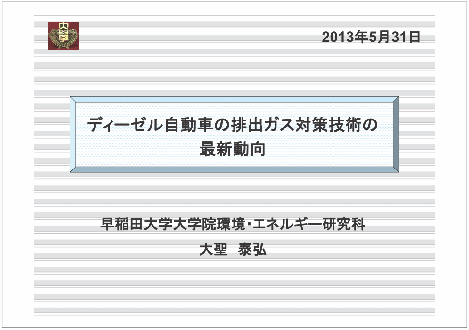 |
| |
�@�@���@����c��w�@�吹�����̍u�������̂Q�X�y�[�W
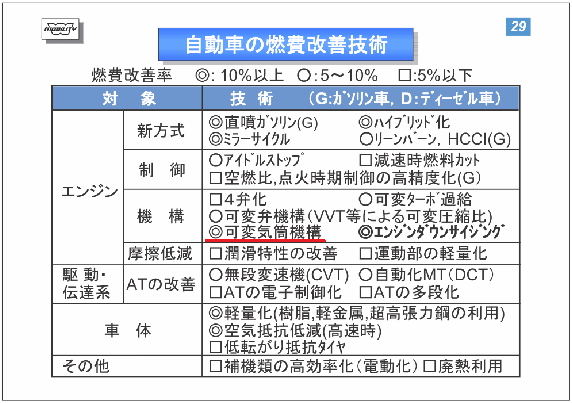 �@�@���@����c��w�@�吹�����̍u�������̂R�O�y�[�W
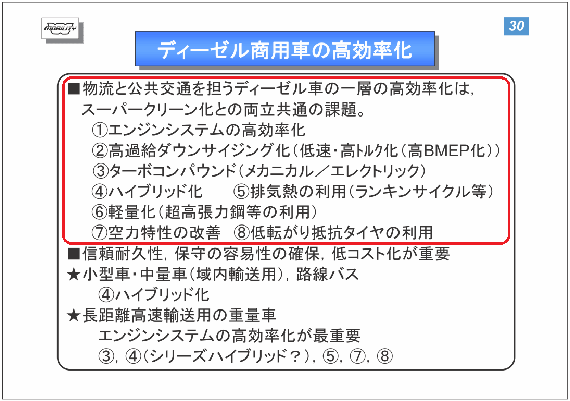 �@�y ���L �z
�@��L�̂R�O�y�[�W�̕\�i�Ԙg���Q�Ɓj�Ɏ����ꂽ�u�������ƌ�����ʂ�S���f�B�[�[���Ԃ̈�w�̍���
�����́A�X�[�p�[�N���[�����Ƃ̗������ʂ̉ۑ�v�̍��Ɏ����ꂽ�@�`�G�̋Z�p�ɂ́A29�y�[�W�ɗ� �����ꂽ�f�B�[�[���G���W���̔R�����̋Z�p�ł���u�ϋC���@�\�v���L�ڂ���Ă��炸�A�����E�r�� ����Ă���B |
�@���̂悤�ɁA����25�N5��31��(��2013�N5��31���j�ɊJ�Â��ꂽ�u�����Q�T�N�x��ʈ��S���������u����v�ɂ���
�āA����c��w�E�吹�����́u�f�B�[�[�������Ԃ̔r�o�K�X��Z�p�̍ŐV�����v�̍u�������̂Q�X�y�[�W�ɂ́u����
�Ԃ̔R����P�Z�p�v���܂Ƃ߂��Ă���B���̒��ł́A�f�B�[�[�������Ԃ���уK�\���������Ԃ̔R����P�����P�O��
�ȏ�̋Z�p�Ƃ��āA�u���ϋC���@�\�i���C���x�~�j�v�����X�Ƌ������Ă���B�Ƃ��낪�A���̎��̂R�O�y�[�W�́u�f�B
�[�[�����p�Ԃ̍��������v�̗Z�p�̒�����́A�R����P�����P�O���ȏ�́u�ϋC���@�\�i���C���x�~�j�v�̋Z
�p�����S�ɔ��������Ă���̂ł���B
�āA����c��w�E�吹�����́u�f�B�[�[�������Ԃ̔r�o�K�X��Z�p�̍ŐV�����v�̍u�������̂Q�X�y�[�W�ɂ́u����
�Ԃ̔R����P�Z�p�v���܂Ƃ߂��Ă���B���̒��ł́A�f�B�[�[�������Ԃ���уK�\���������Ԃ̔R����P�����P�O��
�ȏ�̋Z�p�Ƃ��āA�u���ϋC���@�\�i���C���x�~�j�v�����X�Ƌ������Ă���B�Ƃ��낪�A���̎��̂R�O�y�[�W�́u�f�B
�[�[�����p�Ԃ̍��������v�̗Z�p�̒�����́A�R����P�����P�O���ȏ�́u�ϋC���@�\�i���C���x�~�j�v�̋Z
�p�����S�ɔ��������Ă���̂ł���B
�@�܂�A����25�N5��31���i��2013�N5��31���j�ɊJ�Â��ꂽ�u�����Q�T�N�x��ʈ��S���������u����v�ł́u�f�B�[
�[�������Ԃ̔r�o�K�X��Z�p�̍ŐV�����v�ł́A�吹�����́A�O�i�ł͉ϋC���@�\�i���C���x�~�j���f�B�[�[��
�G���W���̔R����P�̖ʂŊi�i�ɗD�ꂽ�@�\�E���\������Ɛ������Ă���ɂ�������炸�A��i�ł̓f�B�[�[��
���p�Ԃ̍��������̋Z�p����ϋC���@�\�i���C���x�~)���l�̜��ӓI�Ȕ��f�Ŗ�������Ă���悤�ł���B����
�́A�M�҂ɂƂ��Ă͈Ӗ����S�������ł��Ȃ����e���B����c��w�E�吹�����́A���{���\����G���W���̊w�ҁE���
�ƂƉ]���Ă��邪�A���Ȗ����̕s�����Ș_���W�J�̍u�����s���Ă���̂ł��낤���B�ܘ_�A���̍u�������������
��A�u�f�B�[�[�����p�Ԃ̍��������v�̋Z�p�̒�����ϋC���@�\�i���C���x�~�j�̋Z�p�����E����Ă��闝�R�ɂ�
�āA�吹��������͉��̐������s���Ă��Ȃ��悤�Ɍ�����B
�[�������Ԃ̔r�o�K�X��Z�p�̍ŐV�����v�ł́A�吹�����́A�O�i�ł͉ϋC���@�\�i���C���x�~�j���f�B�[�[��
�G���W���̔R����P�̖ʂŊi�i�ɗD�ꂽ�@�\�E���\������Ɛ������Ă���ɂ�������炸�A��i�ł̓f�B�[�[��
���p�Ԃ̍��������̋Z�p����ϋC���@�\�i���C���x�~)���l�̜��ӓI�Ȕ��f�Ŗ�������Ă���悤�ł���B����
�́A�M�҂ɂƂ��Ă͈Ӗ����S�������ł��Ȃ����e���B����c��w�E�吹�����́A���{���\����G���W���̊w�ҁE���
�ƂƉ]���Ă��邪�A���Ȗ����̕s�����Ș_���W�J�̍u�����s���Ă���̂ł��낤���B�ܘ_�A���̍u�������������
��A�u�f�B�[�[�����p�Ԃ̍��������v�̋Z�p�̒�����ϋC���@�\�i���C���x�~�j�̋Z�p�����E����Ă��闝�R�ɂ�
�āA�吹��������͉��̐������s���Ă��Ȃ��悤�Ɍ�����B
�@���������āA���̕\�P�V�Ɏ������u���������画�����邱�Ƃ́A����25�N5���i��2013�N5���j�̎��_�ł͊��ɁA�吹��
���́A�u�f�B�[�[���G���W���̋C���x�~�v�̋Z�p���l�I�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��M���m�邱�Ƃ��ł���B���̂��Ƃ���A
�����ԗp���R�@�Z�p�����g���i���`�h�b�d�j��Ȋw�Z�p�U���@�\�i�i�r�s�j�̑g�D���I�������ԃ��[�J����́u�d
�G�v�Ǝv�����������吹��������̂��J�n����2014�N�x�ȑO��2013�N5���̎��_�ɂ����āA�吹�����́A���ɑ�^
�g���b�N�̔R����P�Z�p�Ƃ��ẲϋC���@�\�i���C���x�~�j�̋Z�p�ӓI�ɖ����E�َE������e�̍u�����s���Ă�
�����Ƃ�����e�Ղɗސ��ł��邱�Ƃł���B���̂��Ƃ���A����c��w�E�吹�����́A���Ȃ��Ƃ�2013�N5���̎��_��
��A�u���Ȃǂ�ʂ��āA�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p���܂߂��C���x�~�i���ϋC��
�@�\�j��p���ăf�B�[�[���G���W���́uNO���팸�v�Ɓu�R����P�v��}��ӌ��E��ĂE���邽�߂̊������A��
�O�E�M�O�������Ď��s����Ă���悤�Ɍ�����B
���́A�u�f�B�[�[���G���W���̋C���x�~�v�̋Z�p���l�I�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��M���m�邱�Ƃ��ł���B���̂��Ƃ���A
�����ԗp���R�@�Z�p�����g���i���`�h�b�d�j��Ȋw�Z�p�U���@�\�i�i�r�s�j�̑g�D���I�������ԃ��[�J����́u�d
�G�v�Ǝv�����������吹��������̂��J�n����2014�N�x�ȑO��2013�N5���̎��_�ɂ����āA�吹�����́A���ɑ�^
�g���b�N�̔R����P�Z�p�Ƃ��ẲϋC���@�\�i���C���x�~�j�̋Z�p�ӓI�ɖ����E�َE������e�̍u�����s���Ă�
�����Ƃ�����e�Ղɗސ��ł��邱�Ƃł���B���̂��Ƃ���A����c��w�E�吹�����́A���Ȃ��Ƃ�2013�N5���̎��_��
��A�u���Ȃǂ�ʂ��āA�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p���܂߂��C���x�~�i���ϋC��
�@�\�j��p���ăf�B�[�[���G���W���́uNO���팸�v�Ɓu�R����P�v��}��ӌ��E��ĂE���邽�߂̊������A��
�O�E�M�O�������Ď��s����Ă���悤�Ɍ�����B
���͂Ƃ�����A�����_�i��2015�N7�����݁j�ł́A�u�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p�́A�m�n����0.
23�@g/kWh ��NO���K���v�Ɓu2015�N�x�d�ʎԔR������{10�����x�̔R�����v�̋K�������ɓK����������^�f�B
�[�[���g���b�N��e�ՂɎ������邱�����\�ł���B�Ƃ��낪�A����c��w�E�吹�����́A���Ȃ��Ƃ�2013�N5���̎��_
����A���̐����������A�����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p�̑��݂�K���ɉB���E�B�����悤�Ƃ�
�Ă���悤�Ɍ�����̂ł���B���̂悤�ɁA�M�҂��l�Ă����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�𑁈�c��w�E��
�������������ɖ����E�َE�E���E���悤�Ƃ��Ă���ő�̓��@�E�����́A���̓����Z�p�𗽉킷��V�Z�p��吹������
�E��Ăł��Ȃ����Ƃ��琶�����u�w�ҁE���ƂƂ��Ă̎S�߂Ȕs�k��p���������v���I���B�����߂ł͂Ȃ����Ɛ��@��
���B�������A����̓|���R�c���Z�p���̕M�҂̋����Ȏא������m��Ȃ��B
23�@g/kWh ��NO���K���v�Ɓu2015�N�x�d�ʎԔR������{10�����x�̔R�����v�̋K�������ɓK����������^�f�B
�[�[���g���b�N��e�ՂɎ������邱�����\�ł���B�Ƃ��낪�A����c��w�E�吹�����́A���Ȃ��Ƃ�2013�N5���̎��_
����A���̐����������A�����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p�̑��݂�K���ɉB���E�B�����悤�Ƃ�
�Ă���悤�Ɍ�����̂ł���B���̂悤�ɁA�M�҂��l�Ă����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�𑁈�c��w�E��
�������������ɖ����E�َE�E���E���悤�Ƃ��Ă���ő�̓��@�E�����́A���̓����Z�p�𗽉킷��V�Z�p��吹������
�E��Ăł��Ȃ����Ƃ��琶�����u�w�ҁE���ƂƂ��Ă̎S�߂Ȕs�k��p���������v���I���B�����߂ł͂Ȃ����Ɛ��@��
���B�������A����̓|���R�c���Z�p���̕M�҂̋����Ȏא������m��Ȃ��B
�@�������A���ɁA����c��w�E�吹�����̜��ӓI���C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p�̖����E�َE
�������ł���A���{�̑�^�f�B�[�[���g���b�N���uNO���팸�v�Ɓu�R����P�v�̐i�W��傫���j�Q���Ă���v���ł����
�l������B���̂��߁A�����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j���܂ދC���x�~�̋Z�p���̖��E��}�낤��
���鑁��c��w�E�吹�����̍s�ׁE�����́A����������������ᔻ����ׂ��Ǝv�����A�@���Ȃ��̂ł��낤���B��
�݂ɁA����c��w�E�吹�����́A�O�q�̂悤�ɁA�uNO���K���̋����v�������������Ȃ̒������R�c��E����
�Ԕr�o�K�X���ψ��ψ���̈ψ��ł���A�u�R���̋����v�����肷�����y��ʏȂ������ԔR������
����̈ψ����ł��邽�߁A�킪���̑�^�f�B�[�[���g���b�N���uNO���팸�v�Ɓu�R����P�v�̋����ɂ��ẮA��
��������^����ꂽ���ʂȗ���̊w�҂ł��邱�Ƃ�Y��Ă͂Ȃ�Ȃ��B���̂��߁A���{���u�m�n����0.23�@g/
kWh ��NO���K���v�Ɓu2015�N�x�d�ʎԔR������{10�����x�̔R�����v�̋K�������ɓK���\����^�g
���b�N��e�ՂɎ����ł����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p��吹���������ӓI�ɖ����E
�َE���s���Ă��邩�ۂ��̐^�U�ɂ��āA�吹�����͍����ɏڂ��������ɂ���Ӗ�������Ǝv�����A�@���Ȃ�
�̂ł��낤���B
�������ł���A���{�̑�^�f�B�[�[���g���b�N���uNO���팸�v�Ɓu�R����P�v�̐i�W��傫���j�Q���Ă���v���ł����
�l������B���̂��߁A�����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j���܂ދC���x�~�̋Z�p���̖��E��}�낤��
���鑁��c��w�E�吹�����̍s�ׁE�����́A����������������ᔻ����ׂ��Ǝv�����A�@���Ȃ��̂ł��낤���B��
�݂ɁA����c��w�E�吹�����́A�O�q�̂悤�ɁA�uNO���K���̋����v�������������Ȃ̒������R�c��E����
�Ԕr�o�K�X���ψ��ψ���̈ψ��ł���A�u�R���̋����v�����肷�����y��ʏȂ������ԔR������
����̈ψ����ł��邽�߁A�킪���̑�^�f�B�[�[���g���b�N���uNO���팸�v�Ɓu�R����P�v�̋����ɂ��ẮA��
��������^����ꂽ���ʂȗ���̊w�҂ł��邱�Ƃ�Y��Ă͂Ȃ�Ȃ��B���̂��߁A���{���u�m�n����0.23�@g/
kWh ��NO���K���v�Ɓu2015�N�x�d�ʎԔR������{10�����x�̔R�����v�̋K�������ɓK���\����^�g
���b�N��e�ՂɎ����ł����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p��吹���������ӓI�ɖ����E
�َE���s���Ă��邩�ۂ��̐^�U�ɂ��āA�吹�����͍����ɏڂ��������ɂ���Ӗ�������Ǝv�����A�@���Ȃ�
�̂ł��낤���B
�i�F�j �헪�I�C�m�x�[�V�����n���v���O�����i�r�h�o�j�̎��{�Ŏ����ԃ��[�J���猤������^�����w�҂̎d��
�@���������ԃ��[�J�X�Ђ��o�����Đݗ����ꂽ�����ԗp���R�@�Z�p�����g���iAICE�j�̃z�[���y�[�W�ɂ́A�Y�w��
���A�g���Ċ�b�E���p���������{���ē��R�@�ւ̊����\�̌������������Ċe��Ƃł̊J���𑣐i�����邱�Ƃ��A��
�̑g���̐ݗ��̖ړI�Əq�ׂ��Ă���B�����āA���̎����ԗp���R�@�Z�p�����g���iAICE�j�́A�����Q�V�N�P���R�O
���ɁA�Ȋw�Z�p�U���@�\�i�i�r�s�j�ƘA�g�����������A�헪�I�C�m�x�[�V�����n���v���O�����i�r�h�o�j�̌������ϑ�����
(�o�T�Fhttp://www.aice.or.jp/docs/news/SIP_AICE-JST_20150130.pdf�j�Ƃ̂��Ƃł���B���̐헪�I�C�m�x�[�V�����n��
�v���O�����i�r�h�o�j�̎��{�ɂ��A�A���������ԃ��[�J�X�Ђ��o�����Đݗ����ꂽ�����ԗp���R�@�Z�p�����g��
�iAICE�j���猤���2014�N�x�`2015�N�x�̂T�N�Ԃɘj���ċ��^�����Ȋw�Z�p�U���@�\�i�i�r�s�j�̌����@�ցi����
�w���j�ƌ����S���ҁi����w�������j�ƃe�[�}�́A�����ԗp���R�@�Z�p�����g���i�`�h�b�d�j���Ȋw�Z�p�U���@�\�i�i�r
�s�j�Ɉϑ��̌����i�r�h�o�j�Ɏ������ʂ�A�W�X�e�[�}�ł���B�����e�e�[�}�̌����S���ҁi����w�������j�́A�ȉ��̂V
�U���̂悤�ł���B
���A�g���Ċ�b�E���p���������{���ē��R�@�ւ̊����\�̌������������Ċe��Ƃł̊J���𑣐i�����邱�Ƃ��A��
�̑g���̐ݗ��̖ړI�Əq�ׂ��Ă���B�����āA���̎����ԗp���R�@�Z�p�����g���iAICE�j�́A�����Q�V�N�P���R�O
���ɁA�Ȋw�Z�p�U���@�\�i�i�r�s�j�ƘA�g�����������A�헪�I�C�m�x�[�V�����n���v���O�����i�r�h�o�j�̌������ϑ�����
(�o�T�Fhttp://www.aice.or.jp/docs/news/SIP_AICE-JST_20150130.pdf�j�Ƃ̂��Ƃł���B���̐헪�I�C�m�x�[�V�����n��
�v���O�����i�r�h�o�j�̎��{�ɂ��A�A���������ԃ��[�J�X�Ђ��o�����Đݗ����ꂽ�����ԗp���R�@�Z�p�����g��
�iAICE�j���猤���2014�N�x�`2015�N�x�̂T�N�Ԃɘj���ċ��^�����Ȋw�Z�p�U���@�\�i�i�r�s�j�̌����@�ցi����
�w���j�ƌ����S���ҁi����w�������j�ƃe�[�}�́A�����ԗp���R�@�Z�p�����g���i�`�h�b�d�j���Ȋw�Z�p�U���@�\�i�i�r
�s�j�Ɉϑ��̌����i�r�h�o�j�Ɏ������ʂ�A�W�X�e�[�}�ł���B�����e�e�[�}�̌����S���ҁi����w�������j�́A�ȉ��̂V
�U���̂悤�ł���B
�� �R�e�[�}��S�����錤���ҁi�h�̗��j�́A�Q���ł���B
�@�@�@�@����c��w�F���� �m�A������w�F���V �N��
�� �Q�e�[�}��S�����錤���ҁi�h�̗��j�́A�X���ł���B
�@�@�@�@���{��w�F�H�_ ��O�A���R��w�F�͌� �L�K�A��t��w�F�X�g �א��A���u�Б�w�F���� �b���q
�@�@�@�@����w�F���� ���A������w�F�O�D ���A���H�Ƒ�w�F�K�� �ꐬ�A����H�Ƒ�w�F���� �D�[
�@�@�@�@����F�w�x �i
�� �P�e�[�}��S�����錤���ҁi�h�̗��j�́A�U�T���ł���B
�@�@�@�@�c��`�m�F��w�ѓc �P���A������w�F�Í] ���m�A�����H�ƁF��w�X�� ��A�R����w�F�O�� �^�l
�@�@�@�@��B��w�F���� �p��A���{����w�F���� �厑�A������w�F���c ���A�����H�Ƒ�w�F���� �p��
�@�@�@�@�����_�H��F�w��{ �O�A�����s�s��w�F�O�� �Y�i�A������w�F��� �Y��A������w�F���ʕ{ �C
�@�@�@�@���{��w�F�c�� �����A���k��w�F�ۓc �O�A��q��F���� �a�v�A������w�F���� �m�j
�@�@�@�@�����w�F���� �N�s�A���s��w�F�ΎR ���A�L����w�F���c �b�ƁA�����w�F�A�� �O�M
�@�@�@�@�����w�F���V ���K�A�Y�ƋZ�p�����������F�� �Ο��A��t��w�F�E�R �B��A������w�F�،ˌ� �P�s
�@�@�@�@���H�Ƒ�w�F���� �i�A��B��w�F�X�� �C�A�R����w�F�O�� �^�l�A�k���C����w�F���� �p�V
�@�@�@�@������w�F���q ���F�A�c��`�m��w�G��X �_�[�A�F�s�{��w�G���c ���j�A�F�{��w�G���{ ��N
�@�@�@�@�F���q���J���@�\�F�a�� ���A�C��Z�p���S�������F���� ���p�A�L����w�F���` �z��
�@�@�@�@������w�F���� �m�j�A���s��w�F��ߕ� �m�A�Y�ƋZ�p�����������F���� �G��A���ꌧ����w�F�͍� ��
�@�@�@�@��q��w�F��� ���v�A���{��w�F�H�_ ��O�A�啪��w�F���{ �~�A�Q�n��w�F�r�� ����
�@�@�@�@����c��w�F�吹 �O�A����c��w�F�{�� �a�F�A����c��w�F�֍� �ׁA������w�F���� �m�j
�@�@�@�@������w�F�O�D ���A�����s�s��w�F�O�� �Y�i�A�����H�Ƒ�w�F�� �ˎq�A�����w�F�F���� ���F
�@�@�@�@���C��w�F���� ���s�A���k��w�F�I�� �a�}�A��B��w�F���� �a�s�A�����w�F�{�c �m��
�@�@�@�@�����w�F��� �����A���É���w�F�F�� �����A���Q��w�F���� �^��A�Y�ƋZ�p�����������F���� �h��
�@�@�@�@���s��w�F�҈� �h�j�A�������ȑ�w�F���� �ۗY�A���k��w�F�{�{ ��
�@���̉Ȋw�Z�p�U���@�\�i�i�r�s�j�̐헪�I�C�m�x�[�V�����n���v���O�����i�r�h�o�j�́A���������ԃ��[�J�X�Ђ����R�@��
�̊����\�̌������������鐒���ȖړI���������邽��搂��A2014�N�x�`2015�N�x�̂T�N�Ԃɘj���āA7.5���~�`10
���~�^�N�̑��z�̗\�Z�����������\��Ƃ̂��Ƃł���B�����āA�Ȋw�Z�p�U���@�\�i�i�r�s�j��ʂ��Ď����ԗp���R
�@�Z�p�����g���iAICE�j����ϑ������헪�I�C�m�x�[�V�����n���v���O�����i�r�h�o�j�̌��������{���錤���e�[�}
�́A�W�X�e�[�}�Ƃ̂��Ƃł���B���̌��ʁA���̃v���O�����i�r�h�o�jP�̌����S���ҁi����w�������j�ɋ��^����錤����
�́A�P�����ςłP�e�[�}������ɔN�ԂłP�疜�~�O��i��843���~�`1224���~�j�̌v�Z�ƂȂ�B
�̊����\�̌������������鐒���ȖړI���������邽��搂��A2014�N�x�`2015�N�x�̂T�N�Ԃɘj���āA7.5���~�`10
���~�^�N�̑��z�̗\�Z�����������\��Ƃ̂��Ƃł���B�����āA�Ȋw�Z�p�U���@�\�i�i�r�s�j��ʂ��Ď����ԗp���R
�@�Z�p�����g���iAICE�j����ϑ������헪�I�C�m�x�[�V�����n���v���O�����i�r�h�o�j�̌��������{���錤���e�[�}
�́A�W�X�e�[�}�Ƃ̂��Ƃł���B���̌��ʁA���̃v���O�����i�r�h�o�jP�̌����S���ҁi����w�������j�ɋ��^����錤����
�́A�P�����ςłP�e�[�}������ɔN�ԂłP�疜�~�O��i��843���~�`1224���~�j�̌v�Z�ƂȂ�B
�@�܂�A�����ԃ��[�J�������ԗp���R�@�Z�p�����g���iAICE�j����ĉȊw�Z�p�U���@�\�i�i�r�s�j�̐헪�I�C�m�x
�[�V�����n���v���O�����i�r�h�o�j�̌��������{����V�U���̌����S���ҁi����w�������j�ɔN�ԂłP�e�[�}������P�疜
�~�O��̌���������^����{���̖ړI�́A�u���R�@�ւ̊����\�̌�������������v���Ƃł͖����A���{�̒��S�I��
�G���W���W�̂V�U���̌����S���ҁi����w�������j�Ɂu�����ԃ��[�J�̗v�]������ĖႤ���߂̍H�쎑���v�ƌ�
�邱�Ƃ��\�ł���B���̌�����̋��^��2014�N�x�`2015�N�x�̂T�N�Ԃł��邱�Ƃ���A���̌��������̂��Ă���V
�U���̌����S���ҁi����w�������j�́A�ʏ�A2014�N�x�`2015�N�x�̂T�N�Ԃɘj���Ď����ԃ��[�J�̗v�]�ɉ������s
���┭���E���\���m���ɗ��z������̂ƍl������B���̂Ȃ�A�H�쎑�������^����Ă����l�̌����S���ҁi��
��w�������j�����Ɏ����ԃ��[�J�̗v�]�ɔ����������E���\���s�����ꍇ�ł��A�����ԃ��[�J���猤�������̂��Ă�
��c��̂V�U���̌����S���ҁi����w�������j����Ăɑ����Ĕے肷�邱�ƂɂȂ锤�Ɨ\�������B���̂悤�ɁA�c���
�V�U���̌����S���ҁi����w�������j�������ɖ����̏������ɍ��o�����Ƃɂ��A�����ԃ��[�J�̗v�]�ɔ�����
�����E���\�́A�����ɔے肳����ԂɂȂ��Ă��܂��ƍl������B
�[�V�����n���v���O�����i�r�h�o�j�̌��������{����V�U���̌����S���ҁi����w�������j�ɔN�ԂłP�e�[�}������P�疜
�~�O��̌���������^����{���̖ړI�́A�u���R�@�ւ̊����\�̌�������������v���Ƃł͖����A���{�̒��S�I��
�G���W���W�̂V�U���̌����S���ҁi����w�������j�Ɂu�����ԃ��[�J�̗v�]������ĖႤ���߂̍H�쎑���v�ƌ�
�邱�Ƃ��\�ł���B���̌�����̋��^��2014�N�x�`2015�N�x�̂T�N�Ԃł��邱�Ƃ���A���̌��������̂��Ă���V
�U���̌����S���ҁi����w�������j�́A�ʏ�A2014�N�x�`2015�N�x�̂T�N�Ԃɘj���Ď����ԃ��[�J�̗v�]�ɉ������s
���┭���E���\���m���ɗ��z������̂ƍl������B���̂Ȃ�A�H�쎑�������^����Ă����l�̌����S���ҁi��
��w�������j�����Ɏ����ԃ��[�J�̗v�]�ɔ����������E���\���s�����ꍇ�ł��A�����ԃ��[�J���猤�������̂��Ă�
��c��̂V�U���̌����S���ҁi����w�������j����Ăɑ����Ĕے肷�邱�ƂɂȂ锤�Ɨ\�������B���̂悤�ɁA�c���
�V�U���̌����S���ҁi����w�������j�������ɖ����̏������ɍ��o�����Ƃɂ��A�����ԃ��[�J�̗v�]�ɔ�����
�����E���\�́A�����ɔے肳����ԂɂȂ��Ă��܂��ƍl������B
�i�G�j �����ԃ��[�J��AICE��n�݂��ĂV�U���̃G���W�������ҁi����w�������j�Ɍ���������^���闝�R�@
�@�����ԗp���R�@�Z�p�����g���iAICE�j�́A2014�N�x�`2018�N�x�̂T�N�ԁA�V�U���̌����҂ɒP�����ςň�l����
��N�ԂłP�疜�~�`�R�疜�~���x�̌���������^����\��Ƃ̂��Ƃł���B�������A�G���W���̔R����P��NO���팸��
�����J���̓�����l������A��l�̌����ҁi����w�����E���Ɠ��j�ɂP�疜�~�`�R�疜�~�^�N�Ԃ̌�������T
�N�̒����ɘj���ċ��^�����Ƃ��Ă��A���̒��x�̗\�Z�̌����ł͑傫�Ȍ������ʂ����҂ł��Ȃ����Ƃ́A�펯�I�ɍl
����Ζ��炩�Ȃ��Ƃł���B
��N�ԂłP�疜�~�`�R�疜�~���x�̌���������^����\��Ƃ̂��Ƃł���B�������A�G���W���̔R����P��NO���팸��
�����J���̓�����l������A��l�̌����ҁi����w�����E���Ɠ��j�ɂP�疜�~�`�R�疜�~�^�N�Ԃ̌�������T
�N�̒����ɘj���ċ��^�����Ƃ��Ă��A���̒��x�̗\�Z�̌����ł͑傫�Ȍ������ʂ����҂ł��Ȃ����Ƃ́A�펯�I�ɍl
����Ζ��炩�Ȃ��Ƃł���B
�@�������A���̐헪�I�C�m�x�[�V�����n���v���O�����i�r�h�o�j�̂P�疜�~�`�R�疜�~�^�N�Ԃ̌�����́A�ʏ�ł͑�����
��w�������̌����҂�����I�ɑ�w����x������Ă��錤����ɕC�G������z�Ɛ��������B���̂悤�ɁA��w����
��x������錤����Ƃ͕ʓr�ɁA��w������x������錤����ɕC�G������z�̌���������ԗp���R�@�Z�p��
���g���iAICE�j�̈ϑ����������V�U���̑�w�������̌����҂ɁA2014�N�x�`2018�N�x�̂T�N�Ԃɘj���Ďx������
��̂ł���B���̂悤�ȏ����Ă���ƁA2014�N�x�`2018�N�x�̂T�N�Ԃɘj���Ďx�������헪�I�C�m�x�[�V�����n
���v���O�����i�r�h�o�j�́i�P�疜�~�`�R�疜�~�j�^�i�N�ԁE��l������j�̌�����́A�����ԗp���R�@�Z�p�����g��
�iAICE�j�̈ϑ����������V�U���̑�w�������̌����҂�傢�ɖ��������郌�x���̋��z�Ɛ��������B���̂悤
�ɁA�����ԃ��[�J���玩���ԗp���R�@�Z�p�����g���iAICE�j����ẲȊw�Z�p�U���@�\�i�i�r�s�j�̐헪�I�C�m�x�[
�V�����n���v���O�����i�r�h�o�j�����{����V�U���̑����̑�w�������̌����҂́A���Ȃ��Ƃ�2014�N�x�`2018�N�x�̂T�N
�Ԃɂ����ẮA�����ԃ��[�J�ɑ��Ċ��ӂ̔O�����܂�邽�߁A������̎x�����ł��鎩���ԃ��[�J�̈ӌ��ɔ�����
�����E���\�E�s�����ӎ��I�ɍT���邱�Ƃ��ԈႢ�Ȃ����̂ƍl������B�����������ԃ��[�J�̖{���̑_���ł͂Ȃ���
�Ɛ��@�����B
��w�������̌����҂�����I�ɑ�w����x������Ă��錤����ɕC�G������z�Ɛ��������B���̂悤�ɁA��w����
��x������錤����Ƃ͕ʓr�ɁA��w������x������錤����ɕC�G������z�̌���������ԗp���R�@�Z�p��
���g���iAICE�j�̈ϑ����������V�U���̑�w�������̌����҂ɁA2014�N�x�`2018�N�x�̂T�N�Ԃɘj���Ďx������
��̂ł���B���̂悤�ȏ����Ă���ƁA2014�N�x�`2018�N�x�̂T�N�Ԃɘj���Ďx�������헪�I�C�m�x�[�V�����n
���v���O�����i�r�h�o�j�́i�P�疜�~�`�R�疜�~�j�^�i�N�ԁE��l������j�̌�����́A�����ԗp���R�@�Z�p�����g��
�iAICE�j�̈ϑ����������V�U���̑�w�������̌����҂�傢�ɖ��������郌�x���̋��z�Ɛ��������B���̂悤
�ɁA�����ԃ��[�J���玩���ԗp���R�@�Z�p�����g���iAICE�j����ẲȊw�Z�p�U���@�\�i�i�r�s�j�̐헪�I�C�m�x�[
�V�����n���v���O�����i�r�h�o�j�����{����V�U���̑����̑�w�������̌����҂́A���Ȃ��Ƃ�2014�N�x�`2018�N�x�̂T�N
�Ԃɂ����ẮA�����ԃ��[�J�ɑ��Ċ��ӂ̔O�����܂�邽�߁A������̎x�����ł��鎩���ԃ��[�J�̈ӌ��ɔ�����
�����E���\�E�s�����ӎ��I�ɍT���邱�Ƃ��ԈႢ�Ȃ����̂ƍl������B�����������ԃ��[�J�̖{���̑_���ł͂Ȃ���
�Ɛ��@�����B
�@�܂�A�G���W���̔R����P��NO���팸�̑傫�Ȍ������ʂ����҂ł��Ȃ������ɑ��āi�疜�~�`�R�疜�~�j�^�i�N
�ԁE��l������j�̌�������V�U���̑����̑�w�������̌����҂�2014�N�x�`2018�N�x�̂T�N�Ԃɘj���Ďx������{
���̖ړI�́A�l�I�ɖ���������x�̌�������V�U�����̑����̑�w�������̌����҂ɋ��^���邱�Ƃɂ���āA����
�ԃ��[�J�i�������ԗp���R�@�Z�p�����g���EAICE�j�̗��v�ɂȂ�uNO���K���v�Ɓu�R���v�̋����Ɋւ�����
�����������邱�Ƃł͂Ȃ����Ǝv���Ă���B�v����ɁA�����ԃ��[�J���猤������x�����ꂽ�V�T���̑�w�������̌�
���҂́A������̎�̂́u���Ԃ�v�E�u���������v�Ƃ��āA�ȉ����\�P�X��(�A�j�`�i�L�j�Ɏ�������^�g���b�N�́uNO���K���v
�Ɓu�R���v�̋����Ɋւ������ɉ������s���E���\�E���������s�E���s���邱�Ƃ��A�����ԃ��[�J�i�������ԗp
���R�@�Z�p�����g���EAICE�j�ɈÖق̗������������Ă���\�����ɂ߂č����Ɛ��������B
�ԁE��l������j�̌�������V�U���̑����̑�w�������̌����҂�2014�N�x�`2018�N�x�̂T�N�Ԃɘj���Ďx������{
���̖ړI�́A�l�I�ɖ���������x�̌�������V�U�����̑����̑�w�������̌����҂ɋ��^���邱�Ƃɂ���āA����
�ԃ��[�J�i�������ԗp���R�@�Z�p�����g���EAICE�j�̗��v�ɂȂ�uNO���K���v�Ɓu�R���v�̋����Ɋւ�����
�����������邱�Ƃł͂Ȃ����Ǝv���Ă���B�v����ɁA�����ԃ��[�J���猤������x�����ꂽ�V�T���̑�w�������̌�
���҂́A������̎�̂́u���Ԃ�v�E�u���������v�Ƃ��āA�ȉ����\�P�X��(�A�j�`�i�L�j�Ɏ�������^�g���b�N�́uNO���K���v
�Ɓu�R���v�̋����Ɋւ������ɉ������s���E���\�E���������s�E���s���邱�Ƃ��A�����ԃ��[�J�i�������ԗp
���R�@�Z�p�����g���EAICE�j�ɈÖق̗������������Ă���\�����ɂ߂č����Ɛ��������B
�@�����Ƃ��A����́A�|���R�c���Z�p���̕M�҂̌l�I�Ȑ����ł���A�m���ȏ؋��������ł͂Ȃ��B�������A���̒���
���Ď��R�Ȕ����͂����V�U�����̑����̑�w�̋�������̂Ƃ������̌����҂Ɂi�疜�~�`�R�疜�~�j�^�i�N�ԁE��
�l������j�̌���������^����O�㖢���̏��画�f����ƁA�ȉ��̕\18�Ɏ����������ԃ��[�J�̉�~�I�ȋZ�p��
��𐢊ԂɍL�����z���邽�߂̎����ԃ��[�J�̐��_�H��i���d�G�Ǝv���������������j�ƌ���̂��A�ɂ߂đÓ��̂悤
�Ɏv����̂ł���B
���Ď��R�Ȕ����͂����V�U�����̑����̑�w�̋�������̂Ƃ������̌����҂Ɂi�疜�~�`�R�疜�~�j�^�i�N�ԁE��
�l������j�̌���������^����O�㖢���̏��画�f����ƁA�ȉ��̕\18�Ɏ����������ԃ��[�J�̉�~�I�ȋZ�p��
��𐢊ԂɍL�����z���邽�߂̎����ԃ��[�J�̐��_�H��i���d�G�Ǝv���������������j�ƌ���̂��A�ɂ߂đÓ��̂悤
�Ɏv����̂ł���B
�����ԃ��[�J���v�]�����^�g���b�N�́uNO���K���v�Ɓu�R���v�̋����Ɋւ������̓��e
|
| (�A�j ��^�g���b�N�ɂ�������{��2016�N�̂m�n���K�� �� 0.4 g/kWh �́A�č���2010�N�̂m�n���K��
�� 0.27 g/kWh �����啝�Ɋɂ��K���ł��錻����A���{�̍��������Ȃ��Ƃ�2020�N���܂� �����E�َE���邱�ƁB(��^�g���b�N�̓��{�̂m�n���K�����č������啝�ɗ��ɂ����Ƃ�َE�j �@�@�@�i�ڍׂ́A�O�q�̂V�����Q�ƕ��j �i�C�j ��^�g���b�N�ɂ����鉢�B��EEV(5)�i�ߓn���[�h�j��NO���K�� �� 0.2 g/kWh�̑��݂ɓ��{�̍�����
�@�@�@���Ȃ��Ƃ�2020�N���܂Œ��ڂ����Ȃ��悤�ɂ��邱�ƁB
�@�@�@�i�ڍׂ́A�O�q�̂V�����Q�ƕ��j
�@�@�@�@�w���@EEV�FEnhanced Environmentally Friendly Vehicles�̗��BEEV�K���l�́A��C���������ɐi�s���Ă���s�s���̒n�����
�@�@�@�@�������邽�߁A�����o�[�e���������I�Ɏg�p����l�i��F�s�s�ւ̏����ꐧ����݂���ۂ̊�Ƃ��Ďg�p�j�ŁA�b��l�B�x
�i�E�j �������R�c��E��\�����\�́u�f�B�[�[���d�ʎԂ�NO�����e���x�ڕW�l�F0.4 ��/��W���i��WHTC
�@�@�@���[�h�j�́A�攪�����\��NO������ڕW�F0.23 ��/kW���i��JE�O�T���[�h�j�Ɠ����̃��x���ł���v�Ƃ�
�@�@�@���\���e�����S�Ɍ��ł��邱�Ƃ��A���Ȃ��Ƃ�2020�N���܂Ő��ԂɉB���ʂ������B
�@�@�@�i�ڍׂ́A�f�B�[�[���d�ʎ�2016�NNOx�K����0.4g/kWh�́A�s���Ȋɘa�̌��K���̂Q�����Q�ƕ��j
�i�G�j ��^�g���b�N�ɂ�����WHTC���[�h�i���R�[���h�X�^�[�g�{�z�b�g�X�^�[�g�j��JE�O�T���[�h�i���z�b�g
�@�@�@�X�^�[�g�j��NO���r�o�l���A�قړ���ł��鎖���̋Z�p�������Ȃ��Ƃ�2020�N���܂ʼnB�����邱�ƁB
�@�@�@�i�ڍׂ́A�O�q�̂U�����Q�ƕ��j�@
�i�I�j ��^�g���b�N�̌p�����Y�Ԃ́u�m�n����0.23�@g/kWh ��NO���K���v�̃��x���i���K���l�j�̋K��������
�@�@�@�����Ă�2025�N5���ȍ~�̎��{�Ƃ��邱��
�@�@�@�i�ڍׂ́A�O�q�̂V�����Q�ƕ��j
�i�J�j ��^�g���b�N�̌p�����Y�Ԃ́u2015�N�x�d�ʎԔR������{10�����x�̔R�����v�𑁂��Ă�
�@�@�@2025�N5���ȍ~�̎��{�Ƃ��邱��
�@�@�@�i�ڍׂ́A�O�q�̂V���������Q�ƕ��j
�i�L�j ��^�g���b�N�̌p�����Y�Ԃ́u2015�N�x�d�ʎԔR������{10�����x�̔R�����v��
�@�@�@�u�m�n����0.23�@g/kWh ��NO���K���v�̋K���������Ɏ����\�ȓ����Z�p
�@�@�@�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�́A���Ȃ��Ƃ�2020�N���܂ʼnB���E�B�����邱�ƁB
�@�@�@�i�ڍׂ́A�O�q�̂V���������Q�ƕ��j
|
�@���̉Ȋw�Z�p�U���@�\�i�i�r�s�j�̐헪�I�C�m�x�[�V�����n���v���O�����i�r�h�o�j�̌������������75���̑�w��������
�����҂́A�����ԗp���R�@�Z�p�����g���iAICE�j���o�R���Ď����ԃ��[�J����2014�N�x�`2018�N�x�̂T�N�Ԃɘj
���āA�P�����ςň�l������ɔN�ԂłP�疜�~�`�R�疜�~���x�̌���������u���Ԃ�v�E�u���������v�Ƃ��āA
2020�N���܂ŏ�L�������ԃ��[�J�̗v�]����(�A�j�`�i�L�j�Ɏ�������^�g���b�N�́uNO���K���v�Ɓu�R���v��
�� ���Ɋւ������ɉ������s���E���\�E���������s�E���s�������̂Ɨ\�������B���ۂɁA�헪�I�C�m�x�[�V
�����n���v���O�����i�r�h�o�j�̌�������������V�U���̑�w�������̌����҂�2020�N���܂ŏ�L��(�A�j�`�i�L�j�Ɏ�����
�s���E���\�E�����𐳒��Ɋ��s�E���s�����ꍇ�A�����ԃ��[�J�̋��郁���b�g�E���v�́A�ȉ����\�Q�O�Ɏ������ʂ��
���������B
�����҂́A�����ԗp���R�@�Z�p�����g���iAICE�j���o�R���Ď����ԃ��[�J����2014�N�x�`2018�N�x�̂T�N�Ԃɘj
���āA�P�����ςň�l������ɔN�ԂłP�疜�~�`�R�疜�~���x�̌���������u���Ԃ�v�E�u���������v�Ƃ��āA
2020�N���܂ŏ�L�������ԃ��[�J�̗v�]����(�A�j�`�i�L�j�Ɏ�������^�g���b�N�́uNO���K���v�Ɓu�R���v��
�� ���Ɋւ������ɉ������s���E���\�E���������s�E���s�������̂Ɨ\�������B���ۂɁA�헪�I�C�m�x�[�V
�����n���v���O�����i�r�h�o�j�̌�������������V�U���̑�w�������̌����҂�2020�N���܂ŏ�L��(�A�j�`�i�L�j�Ɏ�����
�s���E���\�E�����𐳒��Ɋ��s�E���s�����ꍇ�A�����ԃ��[�J�̋��郁���b�g�E���v�́A�ȉ����\�Q�O�Ɏ������ʂ��
���������B
| |
�� �����_�i��2015�N7�����݁j�ɂ����āA�Q�^�[�{�����̋C���x�~�V�X�e���ł���
�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j���J2005-54771�j�̓����Z�p�̑��ɂ́A��^�g���b�N�p
�f�B�[�[���G���W���́uNO���팸�v�Ɓu�R����P�v���\�ɂ���Z�p�����J���̏ł���B
�� �����I�ɁA��^�g���b�N�̂̎g�p�ߒ��Ԃ́u�m�n����0.23�@g/kWh ��NO���K���v�Ɓu2015�N�x
�d�ʎԔR������{10�����x�̔R�����v�̋K�����������{�̏ꍇ�ɂ́A���̂Q�^�[�{������
�C���x�~�X�e���̓����Z�p���^�g���b�N�ɍ̗p������Ȃ��Ɨ\�z�����B
�� �����ԃ��[�J����̂̎����ԗp���R�@�Z�p�����g���iAICE�j����Ȋw�Z�p�U���@�\�i�i�r�s�j
���o�R���Ĉϑ����ꂽ�헪�I�C�m�x�[�V�����n���v���O�����i�r�h�o�j�����{������{�̃G���W���W
�̂V�U�l�̃G���W�������ҁi����w�������j���C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓�����
�����E�َE�E�B����2020�N���܂œO�ꂵ�Đ��s����A��^�g���b�N�̎g�p�ߒ��Ԃ́u�m�n����0.23
g/kWh ��NO���K���v�Ɓu2015�N�x�d�ʎԔR������{10�����x�̔R�����v�̋K�������́A
�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����������ł���
2024�N5��25���ȍ~�ɐ扄�����邱�Ƃ��\�ƂȂ�B
���L �F 2020�N���܂ŋC���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p�̑��݂��E�َE�E�B�������s���ĖႤ���Ƃɐ���
����A 2020�N���ɂ͑�^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W���́uNO���팸�v�Ɓu�R����P�v�ɗL���ȐV�Z�p�Ƃ���
�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p�𐢊ԂɍL�����\���Ă��ǂ��ƍl������B
�����āA2020�N�����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p�̑��݂�F�m�E���\����Ɠ����ɁA��^�g���b�N��
�g�p�ߒ��Ԃ́u�m�n����0.23�@g/kWh ��NO���K���v�Ɓu2015�N�x�d�ʎԔR������{10�����x�̔R�����v�̋K�������̕��j
�\����̂ł���B���̂Ȃ�A�ʏ�̏ꍇ�A�K�������̔��\������{�܂łɂ�4�`5�N���x�̃��[�h�^�C����݂���K�v��
���邽�߁A2020�N���̎��_�ɂ����đ�^�g���b�N�̎g�p�ߒ��Ԃ́u�m�n����0.23�@g/kWh ��NO���K���v�Ɓu2015�N�x�d�ʎԔR��
����{10�����x�̔R�����v�̋K��������2024�N5���ȍ~�Ɏ��{����Ƃ̔��\���s���Ă��A��^�g���b�N�̈Ӑ}�I�ɐ摗�肵��
�K�������Ƃ͍����̒N�ɂ����������Ȃ����̂ƍl������B��^�g���b�N�̎g�p�ߒ��Ԃ́u�m�n����0.23�@g/kWh ��NO���K���v��
�u2015�N�x�d�ʎԔR������{10�����x�̔R�����v�̋K�������̎��{���C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j��
�����������ł���2024�N5��25���ȍ~�ɐ扄���̏ꍇ�A�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓��������x�������Ɩ���
���R���݂ɁA���̓����Z�p�����Ђ̑�^�g���b�N�ɍ̗p�ł����ɁA���̓����Z�p�ɔ��ׂȕύX�������āu���Ђ̐V�J���Z�p�I�v
�Ƃ��Đ���ɐ�`���邱�Ƃ��\�ɂȂ�B����́A���l�̐V�Z�p�𓐂ނ��Ƃɐ��������̂Ɠ����̌��ʂ����邽�߁A���{��
��^�g���b�N���[�J�ɂƂ��ẮA���̎~�܂�Ȃ��������ł���̂ł���B
|
�@���������A�Ȋw�Z�p�U���@�\�i�i�r�s�j�̐헪�I�C�m�x�[�V�����n���v���O�����i�r�h�o�j�́A���������ԃ��[�J�X�Ђ����R
�@�ւ̊����\�̌������������鐒���ȖړI���������邽�߂�搂��A2014�N�x�`2018�N�x�̂T�N�Ԃɘj���āA7.5��
�~�`10���~�^�N�̑��z�̗\�Z�����������傫�ȃv���W�F�N�g�\��Ƃ̂��Ƃł���B�Ƃ��낪�A�Ȋw�Z�p�U���@�\�i�i�r
�s�j��ʂ��Ď����ԗp���R�@�Z�p�����g���iAICE�j����ϑ������헪�I�C�m�x�[�V�����n���v���O�����i�r�h�o�j�̌�
�������{�����w�����ƌ����҂́A���{�ł̃G���W���W�̔����͂̂���w�҂̂قڑS���ƍl������V�U�����̑�
���ł���B���̂��߁A���̃v���O�����i�r�h�o�j�����{���邽�߂ɋ��^����錤����́A�P�����ςň�l������ɔN�ԂłP
�疜�~�`�R�疜�~�̏��z�Ɏ~�܂��Ă���悤�ł���B���̂悤��(�P�疜�~�`�R�疜�~���x)�^(�N�ԁE��l)�̌������
�́A�傫�Ȍ������ʂ͗]����҂ł��Ȃ��ƍl������B���̂��߁A�헪�I�C�m�x�[�V�����n���v���O�����i�r�h�o�j�����R
�@�ւ̊����\�̌������������邱�Ƃ��ŏ�����ڕW�ɂ��Ă��Ȃ��Ƃ���A���_���s�����Ƃł���B
�@�ւ̊����\�̌������������鐒���ȖړI���������邽�߂�搂��A2014�N�x�`2018�N�x�̂T�N�Ԃɘj���āA7.5��
�~�`10���~�^�N�̑��z�̗\�Z�����������傫�ȃv���W�F�N�g�\��Ƃ̂��Ƃł���B�Ƃ��낪�A�Ȋw�Z�p�U���@�\�i�i�r
�s�j��ʂ��Ď����ԗp���R�@�Z�p�����g���iAICE�j����ϑ������헪�I�C�m�x�[�V�����n���v���O�����i�r�h�o�j�̌�
�������{�����w�����ƌ����҂́A���{�ł̃G���W���W�̔����͂̂���w�҂̂قڑS���ƍl������V�U�����̑�
���ł���B���̂��߁A���̃v���O�����i�r�h�o�j�����{���邽�߂ɋ��^����錤����́A�P�����ςň�l������ɔN�ԂłP
�疜�~�`�R�疜�~�̏��z�Ɏ~�܂��Ă���悤�ł���B���̂悤��(�P�疜�~�`�R�疜�~���x)�^(�N�ԁE��l)�̌������
�́A�傫�Ȍ������ʂ͗]����҂ł��Ȃ��ƍl������B���̂��߁A�헪�I�C�m�x�[�V�����n���v���O�����i�r�h�o�j�����R
�@�ւ̊����\�̌������������邱�Ƃ��ŏ�����ڕW�ɂ��Ă��Ȃ��Ƃ���A���_���s�����Ƃł���B
�@���̂悤�ɁA�헪�I�C�m�x�[�V�����n���v���O�����i�r�h�o�j�́A���R�@�ւ̊����\�̌������������邱�Ƃ��ŏ�����
�ڕW�ɂ��Ă��Ȃ��Ƃ���A��^�g���b�N�́uNO���K���v�Ɓu�R���v�̋����Ɋւ��Z�p�����R���g���[�����邽��
�ɁA�����͂̂���G���W����������̊w�҂̗��S���ƌ��������ȂV�U���̑�w�����E�����҂Ɏ����ԃ��[�J���u�d�G��
�v����������v�����^������s�����߂̃v���W�F�N�g�ƌ���̂��ł��Ó��ƍl������B���̗��R�́A�ȉ��̇@�`�B�ł�
��B
�ڕW�ɂ��Ă��Ȃ��Ƃ���A��^�g���b�N�́uNO���K���v�Ɓu�R���v�̋����Ɋւ��Z�p�����R���g���[�����邽��
�ɁA�����͂̂���G���W����������̊w�҂̗��S���ƌ��������ȂV�U���̑�w�����E�����҂Ɏ����ԃ��[�J���u�d�G��
�v����������v�����^������s�����߂̃v���W�F�N�g�ƌ���̂��ł��Ó��ƍl������B���̗��R�́A�ȉ��̇@�`�B�ł�
��B
�@ (�P�疜�~�`�R�疜�~���x)�^(�N�ԁE��l)�̌�����ł́A�傫�Ȍ������ʂ͗]����҂ł��Ȃ����ƁB
�A (�P�疜�~�`�R�疜�~���x)�^(�N�ԁE��l)�̌�����́A��������l�Ԃ�����������z�i���d�G���j�ł��邱
�ƁB
�ƁB
�B (�P�疜�~�`�R�疜�~���x)�^(�N�ԁE��l)�̌�����́A�����͂̂���G���W�������������̂Ƃ����V�U���Ɖ]���c
��Ȑ��̑�w�������̌����҂ɋ��^����Ă��邱�ƁB
��Ȑ��̑�w�������̌����҂ɋ��^����Ă��邱�ƁB
�C (�P�疜�~�`�R�疜�~���x)�^(�N�ԁE��l)�̌�����̋��^�́A2014�N�x�`2018�N�x��5�N�Ԃł��邱��
�@���݂ɁA�����ԃ��[�J����^�g���b�N�́uNO���K���v�Ɓu�R���v�̋����Ɋւ������𐬌��ɓ����錍�́A�o
���邾�������̔����͂̂���G���W����������̑�w�����E�����҂ɁA��������l�Ԃ�����������z�i���d
�G���j�����^�E���^���邱�Ƃ��ƍl������B�����āA�u�헪�I�C�m�x�[�V�����n���v���O�����i�r�h�o�j�v�́A(�P�疜�~�`�R��
���~���x)�^(�N�ԁE��l)�Ɖ]�������ȋ��z�̌�������A�����͂̂���G���W�������������̂Ƃ����V�U���Ɖ]������
�̑�w�����E�����҂ł���B���̂��Ƃ����Ă���ƁA�����ԃ��[�J���Ȋw�Z�p�U���@�\�i�i�r�s�j�Ɉϑ������u�헪�I�C�m
�x�[�V�����n���v���O�����i�r�h�o�j�v�́A�����ԃ��[�J�̗v�]�����^�g���b�N�́uNO���K���v�Ɓu�R���v�̋���������
���邽�߂ɁA2020�N���܂ŏ�L�̑O�q��(�A�j�`�i�L�j�Ɏ������ʂ�ɐ��Ԃ̋Z�p�����R���g���[���E������ړI�Ƃ���
�v���W�F�N�g�ł���Ɛ��@�����B
���邾�������̔����͂̂���G���W����������̑�w�����E�����҂ɁA��������l�Ԃ�����������z�i���d
�G���j�����^�E���^���邱�Ƃ��ƍl������B�����āA�u�헪�I�C�m�x�[�V�����n���v���O�����i�r�h�o�j�v�́A(�P�疜�~�`�R��
���~���x)�^(�N�ԁE��l)�Ɖ]�������ȋ��z�̌�������A�����͂̂���G���W�������������̂Ƃ����V�U���Ɖ]������
�̑�w�����E�����҂ł���B���̂��Ƃ����Ă���ƁA�����ԃ��[�J���Ȋw�Z�p�U���@�\�i�i�r�s�j�Ɉϑ������u�헪�I�C�m
�x�[�V�����n���v���O�����i�r�h�o�j�v�́A�����ԃ��[�J�̗v�]�����^�g���b�N�́uNO���K���v�Ɓu�R���v�̋���������
���邽�߂ɁA2020�N���܂ŏ�L�̑O�q��(�A�j�`�i�L�j�Ɏ������ʂ�ɐ��Ԃ̋Z�p�����R���g���[���E������ړI�Ƃ���
�v���W�F�N�g�ł���Ɛ��@�����B
�@���̂r�h�o�v�V�R�Ă̑̐��́A���t�{�̃v���O�����f�B���N�^�[�Ɂi�Ɓj�Ȋw�Z�p�U���@�\JST���Ǘ��@�l�Ƃ��āASIP
�v�V�R�Ă̑S�̂��������Ă���Ƃ̂��Ƃł���B�����āA���t�{�̃v���O�����f�B���N�^�[�ɂ́A�ȉ��̒ʂ�A�g���^����
�ԁE�G���W���Z�p�̈�@�̈撷�̐��R�둥�����v���O�����f�B���N�^�[��C������Ă��邻�����B
�v�V�R�Ă̑S�̂��������Ă���Ƃ̂��Ƃł���B�����āA���t�{�̃v���O�����f�B���N�^�[�ɂ́A�ȉ��̒ʂ�A�g���^����
�ԁE�G���W���Z�p�̈�@�̈撷�̐��R�둥�����v���O�����f�B���N�^�[��C������Ă��邻�����B
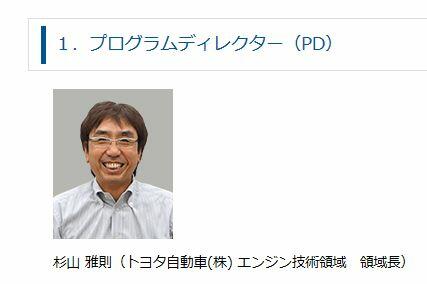 |
�@���̂��Ƃ���A�r�h�o�v�V�R�ăv���W�F�N�g�̗\�Z�z�����܂߂��������i�́A�v���O�����f�B���N�^�[�ł���g���^����
�ԁE�G���W���Z�p�̈�@�̈撷�̐��R�둥���𒆐S�Ɏ��{����Ă���ƍl������B���������āA���̂r�h�o�v�V�R�ăv
���W�F�N�g�́A�M�҂̕Ό���������Ȃ����A�����ԃ��[�J����^�g���b�N�́uNO���K���v�Ɓu�R���v�̋������T�N�ȏ�
���x�点��ړI���܂�ł���ƌ��邱�Ƃ��\�ł���B���̏ꍇ�ɂ́A�u�헪�I�C�m�x�[�V�����n���v���O�����i�r�h�o�j�v
�́A�����ԃ��[�J���ɂ߂čI���Ɂu�Y�E�w�E���A�g�̌����J���v���W�F�N�g�v�����p�H���ăG���W�������������̂Ƃ�
���V�U���̑�w�������̔��\���e�ɂ��Ă̏����s���Ă��邱�Ƃ������ɂ����ƍl������B ���̂Ȃ�A
�r�h�o�v�V�R�ăv���W�F�N�g�́A�����ԃ��[�J�̏o��������������A�������A���̃v���W�F�N�g���g���^�����ԁE�G���W���Z�p
�̈�@�̈撷�̐��R�둥�����v���O�����f�B���N�^�[�Ƃ��đ��w�����s���Ă��邽�߂��B
�ԁE�G���W���Z�p�̈�@�̈撷�̐��R�둥���𒆐S�Ɏ��{����Ă���ƍl������B���������āA���̂r�h�o�v�V�R�ăv
���W�F�N�g�́A�M�҂̕Ό���������Ȃ����A�����ԃ��[�J����^�g���b�N�́uNO���K���v�Ɓu�R���v�̋������T�N�ȏ�
���x�点��ړI���܂�ł���ƌ��邱�Ƃ��\�ł���B���̏ꍇ�ɂ́A�u�헪�I�C�m�x�[�V�����n���v���O�����i�r�h�o�j�v
�́A�����ԃ��[�J���ɂ߂čI���Ɂu�Y�E�w�E���A�g�̌����J���v���W�F�N�g�v�����p�H���ăG���W�������������̂Ƃ�
���V�U���̑�w�������̔��\���e�ɂ��Ă̏����s���Ă��邱�Ƃ������ɂ����ƍl������B ���̂Ȃ�A
�r�h�o�v�V�R�ăv���W�F�N�g�́A�����ԃ��[�J�̏o��������������A�������A���̃v���W�F�N�g���g���^�����ԁE�G���W���Z�p
�̈�@�̈撷�̐��R�둥�����v���O�����f�B���N�^�[�Ƃ��đ��w�����s���Ă��邽�߂��B
�@�����ŁA���ɁA�v���O�����f�B���N�^�[�̐��R�둥���i���g���^�����ԁE�G���W���Z�p�̈�@�̈撷�j���u�@���{�̑�^
�g���b�N��2016�N�m�n���K���FNO�� �� 0.4 g/kWh�����2010�N�m�n���K���FNO�� �� 0.27 g/kWh����������
�ɂ��m�n���K���ł��邱�Ƃɋ^��𓊂��|���锭���E���\���s��Ȃ����Ɓv��A�u�A�攪�����\�ɖ��L���ꂽ��^
�g���b�N��NO���팸�̒���ڕW�FNO����0.23g/kWh��2016�N�m�n���K���FNO�� �� 0.4 g/kWh�Ɠ����ł���Ƃ̉R
�̔����E���\���s�����Ɓv���r�h�o�v�V�R�ăv���W�F�N�g�̌���������^����Ă���V�U���̑�w�������ɋ����v�����Ă�
��Ƃ���A����͑�^�g���b�N��NOx�K���Ɋւ��闧�h�ȋZ�p���̑���ƍl������B
�g���b�N��2016�N�m�n���K���FNO�� �� 0.4 g/kWh�����2010�N�m�n���K���FNO�� �� 0.27 g/kWh����������
�ɂ��m�n���K���ł��邱�Ƃɋ^��𓊂��|���锭���E���\���s��Ȃ����Ɓv��A�u�A�攪�����\�ɖ��L���ꂽ��^
�g���b�N��NO���팸�̒���ڕW�FNO����0.23g/kWh��2016�N�m�n���K���FNO�� �� 0.4 g/kWh�Ɠ����ł���Ƃ̉R
�̔����E���\���s�����Ɓv���r�h�o�v�V�R�ăv���W�F�N�g�̌���������^����Ă���V�U���̑�w�������ɋ����v�����Ă�
��Ƃ���A����͑�^�g���b�N��NOx�K���Ɋւ��闧�h�ȋZ�p���̑���ƍl������B
�@���̂悤�ɁA�����ԃ��[�J����������r�h�o�v�V�R�ăv���W�F�N�g�̌���������^����Ă���V�U���̑�w�����́A
�G���W���W�̊w�ҁE���ƂƂ��Ă̐��̒�����Ă���M���E�h�ӂ��t��Ɏ��A��^�g���b�N��NOx�K���Ɋւ�
�鍼�\�I�ȋZ�p�����u�ϋɓI�ɍm�肷�锭���E���\�v�Ⴕ���́u�Ӑ}�I�ɖٔF�v����s�����s���Ă���ƌ����邱��
�ł���B���̂��Ƃ́A�V�U���̑�w�����̊w�ҁE���Ƃ����U�̋Z�p���̑���ɂ����{�ł̑�^�g���b�N��NOx�K
���̌������������摗��ɏd�v�Ȗ������ʂ����Ă���ƍl�����邱�Ƃł���B�����āA���̋U�̋Z�p���̊g�U����
�̐����ɂ��A�g���b�N���[�J������̗��v�邱�Ƃ��ł���Ɛ��������B
�G���W���W�̊w�ҁE���ƂƂ��Ă̐��̒�����Ă���M���E�h�ӂ��t��Ɏ��A��^�g���b�N��NOx�K���Ɋւ�
�鍼�\�I�ȋZ�p�����u�ϋɓI�ɍm�肷�锭���E���\�v�Ⴕ���́u�Ӑ}�I�ɖٔF�v����s�����s���Ă���ƌ����邱��
�ł���B���̂��Ƃ́A�V�U���̑�w�����̊w�ҁE���Ƃ����U�̋Z�p���̑���ɂ����{�ł̑�^�g���b�N��NOx�K
���̌������������摗��ɏd�v�Ȗ������ʂ����Ă���ƍl�����邱�Ƃł���B�����āA���̋U�̋Z�p���̊g�U����
�̐����ɂ��A�g���b�N���[�J������̗��v�邱�Ƃ��ł���Ɛ��������B
�@�����āA�v���O�����f�B���N�^�[�̐��R�둥���i���g���^�����ԁE�G���W���Z�p�̈�@�̈撷�j���哱���Ď��{����Ă�
��2014�N�x�`2018�N�x��5�N�ԂłV�U���̑�w������(�P�疜�~�`�R�疜�~���x)�^(�N�ԁE��l)�̌�����i�����z38
���~�`50���~�j�����^����r�h�o�v�V�R�ăv���W�F�N�g�ł́A�Œ�ł��u���{�̑�^�g���b�N��2016�N�m�n���K���FNO�� ��
0.4 g/kWh���č���2010�N�m�n���K���FNO�� �� 0.27 g/kWh���������Ɋɂ��m�n���K���ł��邱�Ƃɋ^��𓊂��|���锭
���E���\���s��Ȃ����Ɓv���u�攪�����\�̒���ڕW�FNO����0.23g/kWh��2016�N�m�n���K���FNO�� �� 0.4 g/kWh�Ɠ�����
����Ƃ̋��U�̋Z�p����2020�N�̎��_�ɂȂ�܂ō����ɐM�����܂��邱�Ɓv�̂Q���̋Z�p���̑���́A��������
�I���\�����ɂ߂č����ƍl������B���̗��R�́A�V�U�����̒����ȓ��{�̃G���W���W�̑�w�����́A����A�A
�r�h�o�v�V�R�ăv���W�F�N�g�̏I���Ō�����̋��^����������2020�N���}���鎞�_�܂ł́A���̂Q���̋Z�p���̑���
�ɂ��Ċm���ɋ��͂�����̂Ɨ\������邽�߂ł���B
��2014�N�x�`2018�N�x��5�N�ԂłV�U���̑�w������(�P�疜�~�`�R�疜�~���x)�^(�N�ԁE��l)�̌�����i�����z38
���~�`50���~�j�����^����r�h�o�v�V�R�ăv���W�F�N�g�ł́A�Œ�ł��u���{�̑�^�g���b�N��2016�N�m�n���K���FNO�� ��
0.4 g/kWh���č���2010�N�m�n���K���FNO�� �� 0.27 g/kWh���������Ɋɂ��m�n���K���ł��邱�Ƃɋ^��𓊂��|���锭
���E���\���s��Ȃ����Ɓv���u�攪�����\�̒���ڕW�FNO����0.23g/kWh��2016�N�m�n���K���FNO�� �� 0.4 g/kWh�Ɠ�����
����Ƃ̋��U�̋Z�p����2020�N�̎��_�ɂȂ�܂ō����ɐM�����܂��邱�Ɓv�̂Q���̋Z�p���̑���́A��������
�I���\�����ɂ߂č����ƍl������B���̗��R�́A�V�U�����̒����ȓ��{�̃G���W���W�̑�w�����́A����A�A
�r�h�o�v�V�R�ăv���W�F�N�g�̏I���Ō�����̋��^����������2020�N���}���鎞�_�܂ł́A���̂Q���̋Z�p���̑���
�ɂ��Ċm���ɋ��͂�����̂Ɨ\������邽�߂ł���B
�@�ܘ_�A�����ԃ��[�J����������r�h�o�v�V�R�ăv���W�F�N�g�̌���������^����Ă���V�U�����̒����ȓ��{�̃G
���W���W�̑�w�������������R�c��E��C������E�攪�����\�i2005�N4��8���j�̑�^�g���b�N�i���f�B�[�[��
�d�ʎԁj��NO������ڕW�F0.23 ��/kW����B���ł���Z�p�i���V�Z�p�H�j�������_�i2016�N4�����݁j�܂łɒ��Ă���
�̂ł���A�V�U���̊w�ҏ������C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p���E�َE����s�ׂɂ�
�ĕM�҂��٘_�����ޗ]�n�̑S���������Ƃ͏\���ɗ������Ă���B�Ƃ��낪�A�c�O�Ȃ��ƂɁA�r�h�o�v�V�R�ăv���W�F�N�g��
����������^����Ă���V�U���̑�w�����́A���݂̂Ƃ���ł́A��^�g���b�N�i���f�B�[�[���d�ʎԁj��NO�������
�W�F0.23 ��/kW����B���ł���Z�p�i���V�Z�p�H�j�������Ă��Ă��Ȃ����Ƃ�����I�ȏ؋��̈�ƍl������B
���W���W�̑�w�������������R�c��E��C������E�攪�����\�i2005�N4��8���j�̑�^�g���b�N�i���f�B�[�[��
�d�ʎԁj��NO������ڕW�F0.23 ��/kW����B���ł���Z�p�i���V�Z�p�H�j�������_�i2016�N4�����݁j�܂łɒ��Ă���
�̂ł���A�V�U���̊w�ҏ������C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p���E�َE����s�ׂɂ�
�ĕM�҂��٘_�����ޗ]�n�̑S���������Ƃ͏\���ɗ������Ă���B�Ƃ��낪�A�c�O�Ȃ��ƂɁA�r�h�o�v�V�R�ăv���W�F�N�g��
����������^����Ă���V�U���̑�w�����́A���݂̂Ƃ���ł́A��^�g���b�N�i���f�B�[�[���d�ʎԁj��NO�������
�W�F0.23 ��/kW����B���ł���Z�p�i���V�Z�p�H�j�������Ă��Ă��Ȃ����Ƃ�����I�ȏ؋��̈�ƍl������B
�@���̂悤�ȏł���Ȃ���A�����_�i2016�N4�����݁j�ł́A�r�h�o�v�V�R�ăv���W�F�N�g�̌���������^����Ă���V
�U���̑�w�����́A���R�E��C������E�攪�����\�̑�^�g���b�N�i���f�B�[�[���d�ʎԁj��NO������ڕW�F0.23 ��
/kW����B���ł����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p�����S�ɖ����E�َE���Ă���悤�ł���B����
���Ƃ́A���̂V�U���̑�w�����������ԃ��[�J�̎�������r�h�o�v�V�R�ăv���W�F�N�g�̌����������Ă��邱
�Ƃ������ƍl���邱�Ƃ��\�Ȃ悤�Ɏv���邪�A�@���Ȃ��̂ł��낤���B������X�ɔ���₷�������A�r�h�o�v�V�R�ăv
���W�F�N�g�ŋ��^����錤����̒��ɂ́A�V�U���̑�w�������C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p��
���݂��E�َE���ĖႤ���߂́u���~�ߗ��v��u���~�߂̎ӗ���v�̗v�f���܂܂�Ă���悤�ɂ��v����̂ł���B�@
���������A���{�̈�ʎЉ�ł́A�����ԃ��[�J�̌�������l�������w�҂́A���̑㏞�Ƃ��ĂƂ��Ċw�Ҏ��g�̂�
�ߑ���������邱�Ƃ��Öق̗����ƍl������B���̂��߁A�r�h�o�v�V�R�ăv���W�F�N�g�̌��������̂��Ă���
�V�U���̓��{�l�̑�w�����́A�u�����ԃ��[�J�̏��w�ҁH�E���l�i�����ׁj�w�ҁH�v�Ƃ̔ᔻ�����o��̏�Ɛ���
�����B���̂��Ƃ͒P�Ȃ�M�҂̐����ł���B�����Ƃ��A���̂悤�ɍl���Ă��܂��̂́A�|���R�c���Z�p���̕M�҂��ŋ�
�̋Z�p���̎��W�͂�����Ă��邽�߂̌�������m��Ȃ��B
�U���̑�w�����́A���R�E��C������E�攪�����\�̑�^�g���b�N�i���f�B�[�[���d�ʎԁj��NO������ڕW�F0.23 ��
/kW����B���ł����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p�����S�ɖ����E�َE���Ă���悤�ł���B����
���Ƃ́A���̂V�U���̑�w�����������ԃ��[�J�̎�������r�h�o�v�V�R�ăv���W�F�N�g�̌����������Ă��邱
�Ƃ������ƍl���邱�Ƃ��\�Ȃ悤�Ɏv���邪�A�@���Ȃ��̂ł��낤���B������X�ɔ���₷�������A�r�h�o�v�V�R�ăv
���W�F�N�g�ŋ��^����錤����̒��ɂ́A�V�U���̑�w�������C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p��
���݂��E�َE���ĖႤ���߂́u���~�ߗ��v��u���~�߂̎ӗ���v�̗v�f���܂܂�Ă���悤�ɂ��v����̂ł���B�@
���������A���{�̈�ʎЉ�ł́A�����ԃ��[�J�̌�������l�������w�҂́A���̑㏞�Ƃ��ĂƂ��Ċw�Ҏ��g�̂�
�ߑ���������邱�Ƃ��Öق̗����ƍl������B���̂��߁A�r�h�o�v�V�R�ăv���W�F�N�g�̌��������̂��Ă���
�V�U���̓��{�l�̑�w�����́A�u�����ԃ��[�J�̏��w�ҁH�E���l�i�����ׁj�w�ҁH�v�Ƃ̔ᔻ�����o��̏�Ɛ���
�����B���̂��Ƃ͒P�Ȃ�M�҂̐����ł���B�����Ƃ��A���̂悤�ɍl���Ă��܂��̂́A�|���R�c���Z�p���̕M�҂��ŋ�
�̋Z�p���̎��W�͂�����Ă��邽�߂̌�������m��Ȃ��B
�@�����ŁA�{�z�[���y�[�W�̉{���҂̒��ŁA�r�h�o�v�V�R�ăv���W�F�N�g�̌���������^����Ă���V�U���̑�w
���������R�E��C������E�攪�����\�̑�^�g���b�N�i���f�B�[�[���d�ʎԁj��NO������ڕW�F0.23 ��/kW
����B���ł���Z�p�i���V�Z�p�H�j�����ɒ���Ă��������m����Ă���ꍇ�ɂ́A���̋Z�p�i���V�Z
�p�H�j��{�y�[�W�̖����Ɏ������M�҂̂d���[���A�h���X�Ɍ�A���������������B���ɁA�d���[���Ō䑗�t����
�������Z�p�i���V�Z�p�H�j���{�����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p�𗽉킷����̂ł�
��A�����ɖ{�z�[���y�[�W���폜���鏊���ł���B
���������R�E��C������E�攪�����\�̑�^�g���b�N�i���f�B�[�[���d�ʎԁj��NO������ڕW�F0.23 ��/kW
����B���ł���Z�p�i���V�Z�p�H�j�����ɒ���Ă��������m����Ă���ꍇ�ɂ́A���̋Z�p�i���V�Z
�p�H�j��{�y�[�W�̖����Ɏ������M�҂̂d���[���A�h���X�Ɍ�A���������������B���ɁA�d���[���Ō䑗�t����
�������Z�p�i���V�Z�p�H�j���{�����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p�𗽉킷����̂ł�
��A�����ɖ{�z�[���y�[�W���폜���鏊���ł���B
�@�Ƃ���ŁA�r�h�o�v�V�R�ăv���W�F�N�g�ɎQ�悵�Č���������^����Ă���V�U���̑�w�����́A���ꂼ��̑�w�Ŋw��
�ɑ��A�����_�i��2016�N4�����݁j�ł́u���{�̑�^�g���b�N��2016�N�m�n���K���FNO�� �� 0.4 g/kWh�́A�č���2010
�N�m�n���K���FNO�� �� 0.27 g/kWh�ł���ɂ�������炸�A���{�̑�^�g���b�N�ł͕č��Ɠ����̐��E�ōł�������NOx
�K�������{����Ă���B�v������u���{�̑�^�g���b�N�ɂ��Ă̑攪�����\�̒���ڕW�FNO����0.23g/kWh�́A2016�N
�m�n���K���FNO�� �� 0.4 g/kWh�Ɠ����ł���B(���O�q�̂U�����Q�Ɓj�v�Ƃ̋��U�E�o�L�ڂȋZ�p���e�̍u�`���s���Ă���
�̂ł��낤���B���̂悤�ȑ�w�ł̍u�`�����݂���Ƃ���A���̑�w�����́A����҂Ƃ��Ắu���i�v�����������
��Ă��d���������ƍl�����邪�A�@���Ȃ��̂ł��낤���B����ɂ��Ă̐��m�Ȓm���������Ƃ�����A�r�h�o�v�V�R
�ăv���W�F�N�g�̌��������̂��Ă���V�U���̑�w�����̍u�`����u���Ă���w�����{�z�[���y�[�W���{�������ꍇ
�ɂ́A���̌��Ɋւ��鋳���̍u�`���e��M�҂ɋ����Ă���������K���ł���B
�ɑ��A�����_�i��2016�N4�����݁j�ł́u���{�̑�^�g���b�N��2016�N�m�n���K���FNO�� �� 0.4 g/kWh�́A�č���2010
�N�m�n���K���FNO�� �� 0.27 g/kWh�ł���ɂ�������炸�A���{�̑�^�g���b�N�ł͕č��Ɠ����̐��E�ōł�������NOx
�K�������{����Ă���B�v������u���{�̑�^�g���b�N�ɂ��Ă̑攪�����\�̒���ڕW�FNO����0.23g/kWh�́A2016�N
�m�n���K���FNO�� �� 0.4 g/kWh�Ɠ����ł���B(���O�q�̂U�����Q�Ɓj�v�Ƃ̋��U�E�o�L�ڂȋZ�p���e�̍u�`���s���Ă���
�̂ł��낤���B���̂悤�ȑ�w�ł̍u�`�����݂���Ƃ���A���̑�w�����́A����҂Ƃ��Ắu���i�v�����������
��Ă��d���������ƍl�����邪�A�@���Ȃ��̂ł��낤���B����ɂ��Ă̐��m�Ȓm���������Ƃ�����A�r�h�o�v�V�R
�ăv���W�F�N�g�̌��������̂��Ă���V�U���̑�w�����̍u�`����u���Ă���w�����{�z�[���y�[�W���{�������ꍇ
�ɂ́A���̌��Ɋւ��鋳���̍u�`���e��M�҂ɋ����Ă���������K���ł���B
�@�����Ƃ��A�r�h�o�v�V�R�ăv���W�F�N�g��2018�N�x�ɏI������2020�N���}�������_�ł́A�r�h�o�v�V�R�ăv���W�F�N�g�̌�
��������^�����V�U���̑�w�����́A�w�ҁE���ƂƂ��Ắu�ǐS�v�E�u�����ӎ��v�����������l�Ԃł��邱�Ƃ�I��
���邱�ƂɂȂ�Ǝv�����A����͎��Ǝ����Ɖ]�����̂ł��낤�B�����Ƃ��A���̂悤�Ȃ��Ƃ́A���I�Ȃ��Ƃł���A�M��
�̒P�Ȃ�ϑz�ł��邩���m��Ȃ��B�^�U�̒��́A���̃z�[���y�[�W�̓ǎ҂̔��f�Ɉς˂邱�Ƃɂ���B���̂Ȃ�A
��ʓI�ɂ́A�r�h�o�v�V�R�ăv���W�F�N�g�̌���������^���Ă���V�U���̓��{�̃G���W���W�̒����ȑ�w����
�̏����́A���̒��̏펯�Ƃ��ẮA�����Ȑl�i�̐l�Ԃł���A��簂ȗϗ��ςɕx�ގ����̍����l���Ő�߂��Ă���
�ƍl�����Ă��邽�߂ł���B
��������^�����V�U���̑�w�����́A�w�ҁE���ƂƂ��Ắu�ǐS�v�E�u�����ӎ��v�����������l�Ԃł��邱�Ƃ�I��
���邱�ƂɂȂ�Ǝv�����A����͎��Ǝ����Ɖ]�����̂ł��낤�B�����Ƃ��A���̂悤�Ȃ��Ƃ́A���I�Ȃ��Ƃł���A�M��
�̒P�Ȃ�ϑz�ł��邩���m��Ȃ��B�^�U�̒��́A���̃z�[���y�[�W�̓ǎ҂̔��f�Ɉς˂邱�Ƃɂ���B���̂Ȃ�A
��ʓI�ɂ́A�r�h�o�v�V�R�ăv���W�F�N�g�̌���������^���Ă���V�U���̓��{�̃G���W���W�̒����ȑ�w����
�̏����́A���̒��̏펯�Ƃ��ẮA�����Ȑl�i�̐l�Ԃł���A��簂ȗϗ��ςɕx�ގ����̍����l���Ő�߂��Ă���
�ƍl�����Ă��邽�߂ł���B
�@�������Ȃ���A�č������ɂ���^�g���b�N��NO���K�����{�s����������{���{�̑Ӗ��ɏڏq���Ă���悤�ɁA�����_
�i2016�N4�����݁j�ł́A���{�̑�^�g���b�N��2016�N�m�n���K���FNO�� �� 0.4 g/kWh���č���2010�N�m�n���K���FNO��
�� 0.27 g/kWh���������Ɋɂ��m�n���K���ł��邱�Ƃ��^�⎋���锭���E���\���M�҂̃z�[���y�[�W�ȊO�Ɉ������
���Ƃ�A���ԐR�E�攪�����\�ɖ��L���ꂽ��^�g���b�N��NO���팸�̒���ڕW�FNO����0.23g/kWh��2016�N�m�n���K���F
NO�� �� 0.4 g/kWh�Ƃقړ����ł���Ƃ̔����E���\���p�ɂɌJ��Ԃ���Ă���̂�����̂悤�ł���B���̂悤�Ȃ���
����A���{�ł͑�^�g���b�N��NOx�K���Ɋւ���Z�p���̑��삪���ۂɍs���Ă���悤�Ɋ����邪�A�@���Ȃ��̂�
���낤���B
�i2016�N4�����݁j�ł́A���{�̑�^�g���b�N��2016�N�m�n���K���FNO�� �� 0.4 g/kWh���č���2010�N�m�n���K���FNO��
�� 0.27 g/kWh���������Ɋɂ��m�n���K���ł��邱�Ƃ��^�⎋���锭���E���\���M�҂̃z�[���y�[�W�ȊO�Ɉ������
���Ƃ�A���ԐR�E�攪�����\�ɖ��L���ꂽ��^�g���b�N��NO���팸�̒���ڕW�FNO����0.23g/kWh��2016�N�m�n���K���F
NO�� �� 0.4 g/kWh�Ƃقړ����ł���Ƃ̔����E���\���p�ɂɌJ��Ԃ���Ă���̂�����̂悤�ł���B���̂悤�Ȃ���
����A���{�ł͑�^�g���b�N��NOx�K���Ɋւ���Z�p���̑��삪���ۂɍs���Ă���悤�Ɋ����邪�A�@���Ȃ��̂�
���낤���B
�@�Ȃ��A2014�N�x�`201�W�N�x�̂T�N�Ԃɘj���ē��������헪�I�C�m�x�[�V�����n���v���O�����i�r�h�o�j�� 37.5 ���~�`
50 ���~�Ɖ]�����z�̌�����̂Q�^�R�́A�o�ώY�ƏȂ̗\�Z�̂悤�ł���B���̂悤�ɁA2014�N�x�`2018�N�x�̂T�N��
�ɘj��o�ώY�ƏȂ̑��z�̗\�Z����^�g���b�N�́u�m�n����0.23�@g/kWh ��NO���K���v�Ɓu2015�N�x�d�ʎԔR����
��{10�����x�̔R�����v�̋K��������2025�N5���ȍ~�܂Ő摗�肷�鎩���ԃ��[�J�̗v�]���������邽�߂ɁA��L
�̑O�q��(�A�j�`�i�L�j�Ɏ������ʂ�ɐ��Ԃ̋Z�p�����R���g���[���E��������ړI�̃v���W�F�N�g�ɓ��������Ɛ��@
����邱�Ƃł���B����́A��^�g���b�N�́uNO���K���v�Ɓu�R���v�̋�����扄�����邽�߂ɍ����ɋ]����������
�v���W�F�N�g�ł���Ɛ��@����邽�߁A���̃v���W�F�N�g�Ɍo�ώY�ƏȂ����Ɨ\�Z�𓊓����邱�Ƃ́A���炩�ɐŋ��̖�
�ʌ����ł͂Ȃ����ƍl������B�����āA���ꂪ�����ł���A��v�����@���o�ώY�ƏȂɁA���̃v���W�F�N�g�̒��~
�ْ̍f�������K�v������Ǝv�����A�@���Ȃ��̂ł��낤���B�����Ƃ��A����́A�@���ɕs�ē��ȃ|���R�c���Z�p���̕M
�҂̌���������ł��낤���B
50 ���~�Ɖ]�����z�̌�����̂Q�^�R�́A�o�ώY�ƏȂ̗\�Z�̂悤�ł���B���̂悤�ɁA2014�N�x�`2018�N�x�̂T�N��
�ɘj��o�ώY�ƏȂ̑��z�̗\�Z����^�g���b�N�́u�m�n����0.23�@g/kWh ��NO���K���v�Ɓu2015�N�x�d�ʎԔR����
��{10�����x�̔R�����v�̋K��������2025�N5���ȍ~�܂Ő摗�肷�鎩���ԃ��[�J�̗v�]���������邽�߂ɁA��L
�̑O�q��(�A�j�`�i�L�j�Ɏ������ʂ�ɐ��Ԃ̋Z�p�����R���g���[���E��������ړI�̃v���W�F�N�g�ɓ��������Ɛ��@
����邱�Ƃł���B����́A��^�g���b�N�́uNO���K���v�Ɓu�R���v�̋�����扄�����邽�߂ɍ����ɋ]����������
�v���W�F�N�g�ł���Ɛ��@����邽�߁A���̃v���W�F�N�g�Ɍo�ώY�ƏȂ����Ɨ\�Z�𓊓����邱�Ƃ́A���炩�ɐŋ��̖�
�ʌ����ł͂Ȃ����ƍl������B�����āA���ꂪ�����ł���A��v�����@���o�ώY�ƏȂɁA���̃v���W�F�N�g�̒��~
�ْ̍f�������K�v������Ǝv�����A�@���Ȃ��̂ł��낤���B�����Ƃ��A����́A�@���ɕs�ē��ȃ|���R�c���Z�p���̕M
�҂̌���������ł��낤���B
�@�O�q�̂悤�ɁA���Ȃ̎����Ԕr�o�K�X���ψ��ψ���̈ψ����͑���c��w�E�吹�G�����ł���A�ψ���
�߂Ă���̂��c����w�E�ѓc�P�������Ƒ���c��w�E���� �m�����ł���A���y��ʏȂ̎����ԔR�����ψ����
�ψ����߂Ă���̂�����c��w�E�吹�G�����ł���B���̂��߁A����c��w�E�吹�G�����A�c����w�E�ѓc
�P�������A����c��w�E���� �m�����̂R���́A���{�̎����Ԃ́uNO���K���ƔR���̋����v�ɊW������I�Ȍ�
�͂����s���錠����������̊w�҂ł���B�܂�A�吹�G�����A�ѓc�P�������A���� �m�����́A���ʐE�������E
���������̔C�ɂ���ƍl������B���̂悤�ɁA���I�Ȍ��͂����s���錠�����������吹�G�����A�ѓc�P����
������тƑ��� �m�����̂R���́A�헪�I�C�m�x�[�V�����n���v���O�����i�r�h�o�j�����{����V�U���̑�w�������̌���
�҂̒��Ɋ܂܂�Ă���B
�߂Ă���̂��c����w�E�ѓc�P�������Ƒ���c��w�E���� �m�����ł���A���y��ʏȂ̎����ԔR�����ψ����
�ψ����߂Ă���̂�����c��w�E�吹�G�����ł���B���̂��߁A����c��w�E�吹�G�����A�c����w�E�ѓc
�P�������A����c��w�E���� �m�����̂R���́A���{�̎����Ԃ́uNO���K���ƔR���̋����v�ɊW������I�Ȍ�
�͂����s���錠����������̊w�҂ł���B�܂�A�吹�G�����A�ѓc�P�������A���� �m�����́A���ʐE�������E
���������̔C�ɂ���ƍl������B���̂悤�ɁA���I�Ȍ��͂����s���錠�����������吹�G�����A�ѓc�P����
������тƑ��� �m�����̂R���́A�헪�I�C�m�x�[�V�����n���v���O�����i�r�h�o�j�����{����V�U���̑�w�������̌���
�҂̒��Ɋ܂܂�Ă���B
�@�ȏ�̂悤�ɁA���{�̐R�c��̈ψ����E�ψ��Ƃ��Ď����I�ɔR���NO���̋K���l��ݒ肷�錠�������吹
�G�����A�ѓc�P����������тƑ��� �m�����̂R���́A�R���NO���̋K�����鑤�̎����ԃ��[�J�̏o
���E�ݗ����������ԗp���R�@�Z�p�����g���i���`�h�b�d�j���Ȋw�Z�p�U���@�\�i�i�r�s�j�Ɉϑ������헪�I�C�m�x
�[�V�����n���v���O�����i�r�h�o�j�̌��������̂��Ă���̂ł���B���̂悤�ɁA�����ԃ��[�J�̏o���E�ݗ�����
�����ԗp���R�@�Z�p�����g���i���`�h�b�d�j����Ȋw�Z�p�U���@�\�i�i�r�s�j�̑g�D���I�đ���c��w�E��
���G�����A�c����w�E�ѓc�P�������A����c��w�E���� �m�����ɋ��^����錤����́A�����ԃ��[�J����
�x���́u�d�G�v�ƌ��邱�Ƃ��\�ł͂Ȃ����ƍl������B
�G�����A�ѓc�P����������тƑ��� �m�����̂R���́A�R���NO���̋K�����鑤�̎����ԃ��[�J�̏o
���E�ݗ����������ԗp���R�@�Z�p�����g���i���`�h�b�d�j���Ȋw�Z�p�U���@�\�i�i�r�s�j�Ɉϑ������헪�I�C�m�x
�[�V�����n���v���O�����i�r�h�o�j�̌��������̂��Ă���̂ł���B���̂悤�ɁA�����ԃ��[�J�̏o���E�ݗ�����
�����ԗp���R�@�Z�p�����g���i���`�h�b�d�j����Ȋw�Z�p�U���@�\�i�i�r�s�j�̑g�D���I�đ���c��w�E��
���G�����A�c����w�E�ѓc�P�������A����c��w�E���� �m�����ɋ��^����錤����́A�����ԃ��[�J����
�x���́u�d�G�v�ƌ��邱�Ƃ��\�ł͂Ȃ����ƍl������B
���̂悤�ɁA���{�̎����Ԃ̔r�o�K�X�K���l��R���l�����肷�鐭�{����ψ���̐E����S���吹�G��
���A�ѓc�P�������A���� �m�����ɑ��A�r�h�o(�헪�I�C�m�x�[�V�����n���v���O�����j�̉ۑ�u�v�V�I�R�ċZ�p�v��
�����v���O�����ł��邱�Ƃ𗝗R�ɁA�����ԃ��[�J���o�̑��z�̌�������^����Ă���B�������A���́u�v�V�I
�R�ċZ�p�v�̃v���O���������s�����c�̈ψ����ł�����t�{�����������i�Ȋw�Z�p�E�C�m�x�[�V�����S���j�t
�v���O�����f�B���N�^�[�́A�g���^������(��)�G���W���Z�p�̈�@�̈撷�̐��R �둥���ł���B����́A���̋K����
���Ƃ̐l�������̋K���l�����肷�鋳���Ɏ����ԃ��[�J�̋��o����������������Ƃ��Ďx�����Ă��邱�Ƃ�
�Ȃ�B
�@�E�B�L�y�f�B�A�ɂ��ƁA�u�d�G�i�킢��j�Ƃ́A�匠�҂̑㗝�Ƃ��Č����͂����s����א��҂⊯�����A���͎�
�s�̍ٗʂɏ���������͂���ł��炤���Ƃ����҂��鑼�҂���A�@�⓹���ɔ�����`�Ŏ����T�[�r�X�̂�
�ƁB�v�ƋL�ڂ���Ă���B�헪�I�C�m�x�[�V�����n���v���O�����i�r�h�o�j�̃v���O�����f�B���N�^�[�̐��R �둥���i�g���^
������)����́uSIP�v�V�I�R�ċZ�p�v�̌�����^�̌��Ԃ�Ƃ��đ吹�G�����A�ѓc�P����������тƑ��� �m
�����̂R�������{�̎����Ԃ́uNO���K���ƔR���̋����v�̃��x�����ɂ����邱�Ƃ�K�������̎��{������
�扄�������S�������Ă����Ȃ�A�u�匠�҂̑㗝�Ƃ��Č����͂����s����א��҂⊯�����A���͎��s�̍ٗ�
�ɏ���������͂���ł��炤���Ƃ����҂��鑼�҂���A�@�⓹���ɔ�����`�Ŏ����T�[�r�X�v�̃E�B�L�y�f�B�A
�ʼn������Ă���u�d�G�v�ɊY������ƍl������B�����Ƃ��A�吹�G�����A�ѓc�P����������тƑ��� �m������
�R�������{�̎����Ԃ́uNO���K���ƔR���̋����v�̃��x�����ɂ������S�������Ă���m����؋���M�҂�
�����Ă���킯�ł͖����B
�@�������A���{�̎����Ԃ̔r�o�K�X�K���l��R���l�����肷�鐭�{����ψ���̐E����S���吹�G�����A
�ѓc�P�������A���� �m�����́A�r�h�o(�헪�I�C�m�x�[�V�����n���v���O�����j�̉ۑ�u�v�V�I�R�ċZ�p�v�̌����v��
�O������ʂ��A�����ԃ��[�J�����o�������������̂��Ă��鎖���́A��R�Ƒ��݂��Ă���̂ł���B�����āA����
�ł́A�č������啝�Ɋɂ���^�g���b�N��NO���K�������{������{���{�̑Ӗ��ɏڏq���Ă���悤�ɁA���{��
��^�g���b�N�̂m�n���K���́A2016�N�̎��{�\��ł�NO�� �� 0.4 g/kWh�j�ł���A2010�N�̕č��̂m�n���K��
�iNO�� �� 0.27 g/kWh�j���������Ɋɂ��m�n���K�������{����Ă���̂�����ł��邪�A���̂悤�ȓ��{�̏�
���u���ꑱ���Ă���̂���R���鎖���ł���B
�@����A�������R�c���C�E�����U������E�����Ԕr�o�K�X���ψ��ψ�����吹�G���A�ѓc�P�������A
���� �m�����ɑ��A�r�h�o(�헪�I�C�m�x�[�V�����n���v���O�����j�̉ۑ�u�v�V�I�R�ċZ�p�v�̑��z�̌����
�����ԃ��[�J�����^����Ă���B���̎����ԃ��[�J���玑�����ꂽ�r�h�o�̌�����̋��^�́A�|���R�c���Z�p����
�M�҂ɂ͕č��̂m�n���K�������啝�Ɋɂ����{����^�g���b�N�̂m�n���K����������m���Ɍp�������悤�ɂ���
���߂́u�H�쎑���v�̂悤�Ɏv���Ďd���������B�M�҂ɂ̓E�B�L�y�f�B�A�̉���ɏ]���Ƒ吹�G�����A�ѓc�P��
��������ё��� �m��������̂��Ă���r�h�o�̌�����́A���h�ȁu�d�G�v�Ɣ��f�ł���̂ł͂Ȃ����Ɛ��������B
�@�������A����SIP�́u�v�V�I�R�ċZ�p�v�̌�����̂Q/�R�́A�o�ώY�ƏȂ̕⏕���̂悤�ł���B�i�O�q��
�P�O�|�R�[�iB�j�����Q�ƕ��j�@���̂悤�ɁA�����ԃ��[�J�̎����݂̂Ȃ炸�A�o�ώY�ƏȂ̕⏕�����u�d�G�v�Ƃ���
���^����Ă��邱�Ƃ͗R�X�����s�ׂł���A�ʏ�ł͍l�����Ȃ����Ƃł���B�������A���́u�d�G�v���^�����X�Ǝ��{
����Ă���Ƃ��������ƁA���Ȃ⍑�y��ʏȂ̎����Ԃ̔r�o�K�X�K���Ɋ֘A���鎐��ψ���̍\���ψ���
�����ԃ��[�J���猤���������Ă��u�d�G�v�ɊY�����Ȃ��Ƃ̓����I�ȋK�肪�d�G�߂������܂�@���Ȃɂ�
���݂���̂ł��낤���B�����Ƃ��A���̂悤�Ȃ��Ƃ́A�@�����Ƃ̓��{�ł͗L�蓾�Ȃ��ƍl�����邪�E�E�E�E�E�E�E�B
�@���̂悤�ȓ����K�肪�@���Ȃɖ����ƍl�����邽�߁A���{�̎����Ԃ̔r�o�K�X�K���l��R���l������
���鐭�{����ψ���̐E����S���吹�G�����A�ѓc�P�������A���� �m�����ɑ��Ď����ԃ��[�J�����z��
����������^���Ă���́A��ʐl�ɂ́u�d�G�v�Ǝv���Ďd�����Ȃ��B�Ƃ��낪�A�ȉ��̂悤�ɁA���̏����X��
�}�X�R�~���ɔ��\����Ă���Ƃ��������ƁA�r�h�o�u�v�V�I�R�ċZ�p�v�����v���O�����̃v���O�����f�B���N�^�[
�i�����̃v���O�����̎��������鑍�ӔC�ҁH�j�̐��R �둥���i�g���^�����ԁj�́A�吹�G�����A�ѓc�P�������A
���� �m�����ւ̌�����̋��^�E�z�����u�d�G�v�ɑ������Ȃ��Ɗm�M����Ă���悤�Ɍ����邪�A���̍����́A
��́A���Ȃ̂ł��낤���B����Ƃ������Ă��������������̂ł���B
�@�Ƃ���ŁA�u�r�h�o�v�V�I�R�ċZ�p�v�v���W�F�N�g�̌�����̋��^�����{�̎���@�ւ̈ψ��ɑ��鎩���ԃ��[�J
����̘d�G���^�̉B�ꖪ�Ƃ���Ă���\��������̂ł͂Ȃ����ƕM�҂͍l���Ă���B���̏ꍇ�ɂ́A
�u�r�h�o�v�V�I�R�ċZ�p�v�v���W�F�N�g�̌���������^����v���O�����f�B���N�^�[�̐��R �둥���i�g���^�����ԁj��
�d�G�̑��d�҂ƍl�����A�v���W�F�N�g�̌��������̂���吹�G�����A�ѓc�P�������A���� �m�������d�G��
���d�҂ƍl������B���̂悤�ȋ^�f��ے�ł��Ȃ��ɂ����āA�ȉ��́u�r�h�o�v�V�I�R�ċZ�p�v�v���W�F�N�g��
��v�����o�[�̎ʐ^���C���^�[�l�b�g�Ō��J����Ă���̂�ڂɂ����̂ł���B
�i�o�T�F���o�e�N�m���W�[�@�I�����C���@http://techon.nikkeibp.co.jp/atcl/news/16/060102379/?SS=imgview&FD=-1342295411�j
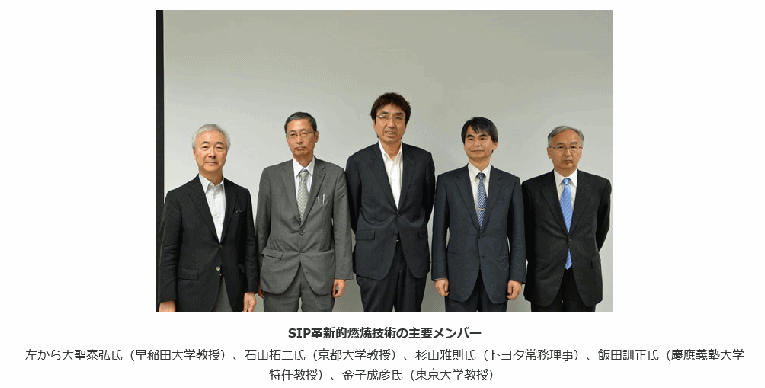 |
�@���̍ہA���̎ʐ^����́A�d�G�̑��d�҂ƍl�����鐙�R �둥���i�g���^�����ԁj�Ƙd�G�̎��d�҂ƍl������
�吹�G��������єѓc�P�������Ƃ͗ǍD�Ȉӎv�̑a�ʂ��}���Ă���悤�Ȉ�ۂ����̂ł���B���̂���
������A�u�r�h�o�v�V�I�R�ċZ�p�v�v���W�F�N�g�̌�����d�G�Ƃ��ċ@�\���Ă���\�����\���ɂ���ƕM�҂͊�����
����B�����Ƃ��A���̂悤�Ȍ��������Ă��܂��̂́A�M�҂��u�r�h�o�v�V�I�R�ċZ�p�v�v���W�F�N�ɂ��āA�ŏ�����Ό�
�������Ă��܂��Ă��邽�߂����m��Ȃ��B
�@�ܘ_�A���R �둥���́A�g���^�����Ԃ̊����ł��邱�Ƃ���A�g���^�����Ԃ̖@���W����ł��吹�G�����A
�ѓc�P�������A���� �m�����ւ̌�����̋��^�E�z�����u�d�G�v�ɑ������Ȃ��Ƃ̌����ł���Ɛ��������B
�����āA���R�̂��ƂȂ���A�g���^�����Ԃ̊����ł��鐙�R �둥���́A�g���^�����Ԃ̖@���W���傩��A
���{�̎����ԊW�̋K�������Ɋ֗^����E����S���Ă���吹�G�����A�ѓc�P�������A���� �m������
�u�r�h�o�v�V�I�R�ċZ�p�v�v���W�F�N�g�̌���������^���邱�Ƃ��u�d�G�v�ɊY�����Ȃ��Ɣ��f�E������������Ă������
�ƍl������B�@
�@�������Ȃ���A��w�ɍ˂̕M�҂ɂ́A�����R�l�̋����ɋ��^����Ă���r�h�o�́u�v�V�I�R�ċZ�p�v�̌����
�u�d�G�v�Ɏv���Ďd���������B�����ŁA�g���^�����ԂƐ��R �둥�����r�h�o�́u�v�V�I�R�ċZ�p�v�̌�����u�d�G�v��
�����Ȃ��Ɣ��f����Ă��鍪���◝�R�ɂ��āA�@���ɕs�ē��̕M�҂ɂ������ł���悤�ɐ������Ă�����������
���̂ł���B�܂��A���̃v���W�F�N�g�ɂ����ăg���^�����Ԃ̊��������S�I�Ȗ������ʂ����Ă��邱�Ƃɂ��ẮA
����������Ƃ̃R���v���C�A���X�i���@�ߏ���j�̓O���搂��g���^�����Ԃ̌������A�����ɊJ�����Ă�����������
�Ƃ���ł���B
�@�Ȃ��A���̎���͕M�Ҍl�̃z�[���y�[�W�ōs���Ă�����̂ł����A���̕M�҂̃z�[���y�[�W�́AGoogle������
�ł͔�r�I��ʂŌ�������Ă���y�[�W�ł���B���̂��߁A�吹�G�����A�ѓc�P�������A���� �m�����ɋ��^
����Ă��鎩���ԃ��[�J���o�̑��z�̌�����u�d�G�v�̋^�`���F���̏ꍇ�ɂ́A�g���^�����ԂƂr�h�o(�헪�I
�C�m�x�[�V�����n���v���O�����j�̉ۑ�u�v�V�I�R�ċZ�p�v�v���O�����f�B���N�^�[�̐��R �둥���́A���̎|��M�҈�
�Ăɂd���[�����ł̐������Ă�����������̂Ɗ��҂��Ă���B�ܘ_�A�R�l�̋����ɋ��^����Ă���r�h�o�́u�v�V�I�R��
�Z�p�v�̌�����u�d�G�v�Ŗ����Ƃ���g���^�����ԎႵ���͐��R �둥������M�҈��Ă̂d���[�����́A���̃z�[��
�y�[�W�ɑS�����f�ڂ���\��ł���B���̂Ȃ�A�r�h�o�́u�v�V�I�R�ċZ�p�v�̌�����ɂ��Ă̕M�҂̘d�G�^�`
�̎w�E�ɂ��Ẵg���^�����ԂƐ��R �둥���̔��_���z�[���y�[�W�̉{���҂ɓ`���邱�Ƃɂ���đ����̓ǎ҂�
���m�Ȕ��f�E����������ĖႤ���߂ł���B
�@�����Ƃ��A���̂r�h�o�́u�v�V�I�R�ċZ�p�v�Ɋւ��錤����̎x���Ɂu�d�G�v�̋^�O���@������Ȃ��ꍇ�ɂ́A�g���^
�����ԂƐ��R �둥���́A99���̊m���ŕM�҂̎����������O�ꂵ�ĖَE������̂Ɛ��������B���̂��Ƃ���A
����A�d���[�����łr�h�o�́u�v�V�I�R�ċZ�p�v�v���O�����f�B���N�^�[�̐��R �둥����g���^�����Ԃ���́u�d�G���v
��ے肷�������M�҂ɍs���鎞�_�܂ł́A�r�h�o(�헪�I�C�m�x�[�V�����n���v���O�����j�̉ۑ�u�v�V�I�R��
�Z�p�v�v���O�����Ɋ֘A����吹�G�����A�ѓc�P�������A���� �m�����ɋ��^����Ă��鎩���ԃ��[�J���o��
���z�̌�����̋��^�́A�g���^�����ԂƐ��R �둥���̗��҂��{�S�ł́u�d�G�v�̑��^�ɗނ��锽�Љ�I�ȍs��
�ł���Ƃ̋^�`��������Ă�����̂Ə���Ȃ��痝�������Ă����������Ƃɂ���B�܂�A�ƍ߂̕���ł͍߂̏d��
�m�M�Ƃɕ��ނ����ƍl������B
�@���̏ꍇ�A�g���^�����ԂƂr�h�o(�헪�I�C�m�x�[�V�����n���v���O�����j�̉ۑ�u�v�V�I�R�ċZ�p�v�v���O����
�f�B���N�^�[�̐��R �둥���́A�d�G���^�̕s�������m�̏�ŁAS�h�o(�헪�I�C�m�x�[�V�����n���v���O�����j�̉ۑ�
�u�v�V�I�R�ċZ�p�v�v���O�����𐄐i���Ă��邱�ƂɂȂ�ƍl������B���ɁA���ꂪ�����ł���AS�h�o(�헪�I
�C�m�x�[�V�����n���v���O�����j�̉ۑ�u�v�V�I�R�ċZ�p�v�v���O�����́A�����ԃ��[�J�ɂ��d�G���^��
�J���t���[�W���i���U���j�Ɏg���Ă��邱�ƂɂȂ�A���t�{�̊����������ԃ��[�J�i���g���^�����ԁj�́u�d�G���^��
�g������v�������Ă��邱�ƂɂȂ�ƍl������B
�@���������A�Y���i�ז@�Q�R�X���Q���́u�������͌����́A���̐E�����s�����Ƃɂ��ƍ߂�����Ǝv������Ƃ��́A
���������Ȃ���Ȃ�Ȃ��v�ƁA�������ɍ����i���i���܂ށj�̋`�����ۂ��Ă���B���̂��߁A���t�{�̊����́A�g���^
�����ԂƂr�h�o(�헪�I�C�m�x�[�V�����n���v���O�����j�̉ۑ�u�v�V�I�R�ċZ�p�v�v���O�����f�B���N�^�[�̐��R
�둥�����d�G���^�̕s�������m�̏�ŁAS�h�o(�헪�I�C�m�x�[�V�����n���v���O�����j�̉ۑ�u�v�V�I�R�ċZ�p�v
�v���O�����𐄐i���Ă��邱�Ƃ���������`�����Ă���ƍl������B���t�{�̊������g���^�����ԂƂr�h�o
(�헪�I�C�m�x�[�V�����n���v���O�����j�̉ۑ�u�v�V�I�R�ċZ�p�v�v���O�����f�B���N�^�[�̐��R �둥����d�G�߂�
��������ėL�߂ƂȂ����ꍇ�ɂ́A�Y�@��197���i���d�A������d�y�ю��O���d�j�ł́A�u��197��1.���������A
���̐E���Ɋւ��A�d�G�����A���͂��̗v���Ⴕ���͖������Ƃ��́A5�N�ȉ��̒����ɏ�����B���̏ꍇ
�ɂ����āA���������Ƃ��́A7�N�ȉ��̒����ɏ�����B�v�Ɩ��L����Ă���B�����Ƃ��A���t�{�̊�����������
���[�J�i���g���^�����ԁj�́u�d�G���^�̎g������v�����Ă���F�����F���ł���A�c�O�Ȃ��犯�����͌����ɂ�鍐
���́A�L�蓾�Ȃ����ƂɂȂ�B
���́A�L�蓾�Ȃ����ƂɂȂ�B
�@���Ă��āA����c��w�E�吹�G�����A�c����w�E�ѓc�P�������A����c��w�E���� �m�����ȊO�̐헪�I�C�m
�x�[�V�����n���v���O�����i�r�h�o�j�̌�������������V�R���̑�w�������̌����҂Ɏx���̌�����́A�����ԃ��[�J
����x���u�d�G�v�ƒf�肷�邱�Ƃ��`���I�ɂ͍���ƌ�����B���̂��߁A����c��w�E�吹�G�����A�c����w�E
�ѓc�P�������A����c��w�E���� �m�����ȊO�̐헪�I�C�m�x�[�V�����n���v���O�����i�r�h�o�j�̌������������
�V�R���̑�w�������̌����҂��O�q�̕\�P�W�́u�����ԃ��[�J���v�]�����^�g���b�N�́uNO���K���v�Ɓu�R���v
�̋����Ɋւ������v�ɐϋɓI�ɋ��͂����Ƃ��Ă��A�@���Ɉᔽ�����s�ׂƂ͂Ȃ�Ȃ��ƍl������B
�@���̂悤�ɁA����c��w�E�吹�G�����A�c����w�E�ѓc�P�������A����c��w�E���� �m�����ȊO�̂V�R����
��w�������̌����҂��O�q�̕\�P�W�́u�����ԃ��[�J���v�]�����^�g���b�N�́uNO���K���v�Ɓu�R���v�̋�����
�x���܂��͐摗�肷�邽�߂̔����E���\��ϋɓI�ɍs�����Ƃ��Ă��A���̂��Ǝ��̂����m�Ȗ@���Ɉᔽ����s�ׂƂ�
�Ȃ�Ȃ��ƍl������B�������A�����͉]���Ă��A�w�҂����g�̐�啪��ɂ����đO�q�́u�\�P�W�@�����ԃ��[�J��
�v�]�����^�g���b�N�̏���̓��e�v�Ɏ������悤�ȁA��^�g���b�N�́uNO���팸�v�Ɓu�R����P�v�ɗL���ȋZ�p��
���ӓI�ɖ����E�َE���邱�Ƃ́A�w�҂̗ǐS�ɔ�����s�ׂƍl������B�܂�A����c��w�E�吹�G�����A�c��
��w�E�ѓc�P�������A����c��w�E���� �m�����ȊO�̂V�R���̑�w�������̊w�҂́A2014�N�x�`2019�N�x��
�T�N�Ԃɘj���āA�O�q�̕\�P�W�́u�����ԃ��[�J���v�]�����^�g���b�N�́uNO���K���v�Ɓu�R���v�̋����Ɋւ���
�Z�p���̓����ɐϋɓI�ɋ��͂����Ƃ��Ă��A �l�ςɔw���s�ׂł͂����Ă����m�ɖ@����Ƃ��Ă���؋��ɂ�
�Ȃ�Ȃ��ƍl������B ���̂��Ƃ������āA�V�R���̑�w�����́A�w�҂Ƃ��č��������E�������̌������s�̐Ӗ������S
�ɖY�ꋎ��AS�h�o�u�v�V�I�R�ċZ�p�v�v���O�����̌�����̎x�����Ă�����̂Ɛ��������B
�ɖY�ꋎ��AS�h�o�u�v�V�I�R�ċZ�p�v�v���O�����̌�����̎x�����Ă�����̂Ɛ��������B
�@
�@�܂�A�헪�I�C�m�x�[�V�����n���v���O�����i�r�h�o�j�̌�������������V�U���̑�w�������̌����҂́A�ȉ��̂悤��
��^�f�B�[�[���g���b�N�ɂ��āA2019�N�x�܂ŁA���̂悤�ȁu�R�v�E�u���U�v�̔����E���\�̌J��Ԃ���A��^�g���b�N��
�uNO���팸�v�Ɓu�R����P�v�ɗL���ȐV�Z�p�i���C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�j�̓����Z�p�j�̖����E�َE��
���s����������̂Ɛ��������
��^�f�B�[�[���g���b�N�ɂ��āA2019�N�x�܂ŁA���̂悤�ȁu�R�v�E�u���U�v�̔����E���\�̌J��Ԃ���A��^�g���b�N��
�uNO���팸�v�Ɓu�R����P�v�ɗL���ȐV�Z�p�i���C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�j�̓����Z�p�j�̖����E�َE��
���s����������̂Ɛ��������
�� ���{�̑�^�g���b�N��2016�N�̂m�n���K����0.4 g/kWh �́A�č���2010�N�̂m�n���K����0.27g/kWh �Ɠ���
�ł���A���E�ōł�������NO���K���ł���Ƃ́u�R�v�E�u���U�v�̋Z�p���̊g�U���s�����ƁB �Ⴕ���́A����
�u�R�v�E�u���U�v�̋Z�p���Ɉًc�������Ȃ����ƁB
�ł���A���E�ōł�������NO���K���ł���Ƃ́u�R�v�E�u���U�v�̋Z�p���̊g�U���s�����ƁB �Ⴕ���́A����
�u�R�v�E�u���U�v�̋Z�p���Ɉًc�������Ȃ����ƁB
�� �������R�c��E��\�����\�́u�f�B�[�[���d�ʎԂ�NO�����e���x�ڕW�l�F0.4 ��/��W���i��WHTC���[�h�j
�́A�攪�����\��NO������ڕW�F0.23 ��/kW���i��JE�O�T���[�h�j�Ɠ����̃��x���ł���Ƃ́u�R�v�E�u���U�v�̋Z
�p���̊g�U���s�����ƁB �Ⴕ���́A���́u�R�v�E�u���U�v�̋Z�p���Ɉًc�������Ȃ����ƁB
�́A�攪�����\��NO������ڕW�F0.23 ��/kW���i��JE�O�T���[�h�j�Ɠ����̃��x���ł���Ƃ́u�R�v�E�u���U�v�̋Z
�p���̊g�U���s�����ƁB �Ⴕ���́A���́u�R�v�E�u���U�v�̋Z�p���Ɉًc�������Ȃ����ƁB
�� ��^�g���b�N�̌p�����Y�Ԃ́u2015�N�x�d�ʎԔR������{10�����x�̔R�����v�Ɓu�m�n����0.23�@g/
kWh ��NO���K���v�̋K���������Ɏ����\�ȓ����Z�p�ł����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j
�́A���Ȃ��Ƃ�2020�N���܂ʼnB���E�B������Z�p���̕s���ȑ�����s�����ƁB�Ⴕ���́A���̉B���E�B������Z
�p���̕s���ȑ���Ɉًc�������Ȃ����ƁB
kWh ��NO���K���v�̋K���������Ɏ����\�ȓ����Z�p�ł����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j
�́A���Ȃ��Ƃ�2020�N���܂ʼnB���E�B������Z�p���̕s���ȑ�����s�����ƁB�Ⴕ���́A���̉B���E�B������Z
�p���̕s���ȑ���Ɉًc�������Ȃ����ƁB
�@�����ŕs�v�c�Ȃ��Ƃ́A�헪�I�C�m�x�[�V�����n���v���O�����i�r�h�o�j�̌�������������V�U���̑�w�������̌�����
�̒N�����u�R�v�E�u���U�v�̔����E���\�̌J��Ԃ���A��^�g���b�N�́uNO���팸�v�Ɓu�R����P�v�ɗL���ȐV�Z�p�i��
�̒N�����u�R�v�E�u���U�v�̔����E���\�̌J��Ԃ���A��^�g���b�N�́uNO���팸�v�Ɓu�R����P�v�ɗL���ȐV�Z�p�i��
�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�j�̓����Z�p�j�̖����E�َE�����s�������邱�Ƃɂ��āA�w�ҁE�����҂Ƃ�
�Ă̗ǐS�̙�ӂ������Ă���悤�ɕ��O�҂̕M�҂ɂ͌����邱�Ƃł���B�܂��A�u���{�̑�^�g���b�N��2016�N�̂m�n��
�K����0.4 g/kWh �́A���E�ōł�������NO���K���v�A�Ⴕ���́u�������R�c��E��\�����\�́u�f�B�[�[���d�ʎԂ�
NO�����e���x�ڕW�l�F0.4 ��/��W���i��WHTC���[�h�j�́A�攪�����\��NO������ڕW�F0.23 ��/kW���i��JE�O�T���[�h�j�Ɠ�
���̃��x���v�Ƃ̌�����Z�p���Ɉًc�������Ȃ����Ƃ́A�V�U���̑�w�������̌����҂̒N�����e�F���Ă���悤��
�����邱�Ƃł���B����́A�u�^���̒Nj����Z�p�J���̍����v�Ɗw�������炷���w�������̐E�ӂ�S�������҂Ƃ���
�́A�^���E�����̉B���Ɖ]���ł��p���ׂ��s�ׂƎv�����A�@���Ȃ��̂ł��낤���B��ʐl�̃|���R�c���Z�p���ɕM�҂�
�Ƃ��ẮA�M�����Ȃ����Ƃł���B���ꂪ�A��w�������̌����҂����Ɍ����u�~�̔炪�˂��������l�ԁv�Ɖ]�����Ƃł�
�낤���B
�Ă̗ǐS�̙�ӂ������Ă���悤�ɕ��O�҂̕M�҂ɂ͌����邱�Ƃł���B�܂��A�u���{�̑�^�g���b�N��2016�N�̂m�n��
�K����0.4 g/kWh �́A���E�ōł�������NO���K���v�A�Ⴕ���́u�������R�c��E��\�����\�́u�f�B�[�[���d�ʎԂ�
NO�����e���x�ڕW�l�F0.4 ��/��W���i��WHTC���[�h�j�́A�攪�����\��NO������ڕW�F0.23 ��/kW���i��JE�O�T���[�h�j�Ɠ�
���̃��x���v�Ƃ̌�����Z�p���Ɉًc�������Ȃ����Ƃ́A�V�U���̑�w�������̌����҂̒N�����e�F���Ă���悤��
�����邱�Ƃł���B����́A�u�^���̒Nj����Z�p�J���̍����v�Ɗw�������炷���w�������̐E�ӂ�S�������҂Ƃ���
�́A�^���E�����̉B���Ɖ]���ł��p���ׂ��s�ׂƎv�����A�@���Ȃ��̂ł��낤���B��ʐl�̃|���R�c���Z�p���ɕM�҂�
�Ƃ��ẮA�M�����Ȃ����Ƃł���B���ꂪ�A��w�������̌����҂����Ɍ����u�~�̔炪�˂��������l�ԁv�Ɖ]�����Ƃł�
�낤���B
�@���ɁA�����ԃ��[�J���瑁��c��w�E�吹�G�����ƌc����w�E�ѓc�P�������ɋ��^���ꂽ�헪�I�C�m�x�[�V�����n
���v���O�����i�r�h�o�j�̌�����́A�M�҂��猩��A�u�����Ƃ̉I���܂��͕s�������i�����{�⏕�����x�����ꂽ
��Ђ���̌����j�v��u��s�̉I��Z���v���̕s���E�s�@�Ȏ������^�̍s�ׂɍ������Ă���悤�Ɏv�����A�@���Ȃ��̂�
���낤���B���ɁA���̂悤�Ȍ�����̋��^�����@�ł���A�����̖͂L�x�Ȗ��ԑg�D�i����ЁE�c�̓��j�́A�R������
����ɔY�ޑ�w�����E���Ɓi�����I�Ȍ��͂����s���錠���������{�̎���ψ���̈ψ��j�̈ӌ��E�咣���A���z
�̌�����̋��^�Ɖ]���u���ʁv�E�u�a�v�ɂ���Ď��R�ɑ��邱�Ƃ��\�ƍl������B���̏ꍇ�A�����̗v�]�����S�ɖ�
�����A�����͂̂��閯�ԑg�D�i����ЁE�c�̓��j�̈ӌ����ŗD��ɂ����K���l�E�K���E��������{�ł͔×����Ă���
���Ɨ\�z����邪�A����͕M�҂̕��������ł��낤���B
���v���O�����i�r�h�o�j�̌�����́A�M�҂��猩��A�u�����Ƃ̉I���܂��͕s�������i�����{�⏕�����x�����ꂽ
��Ђ���̌����j�v��u��s�̉I��Z���v���̕s���E�s�@�Ȏ������^�̍s�ׂɍ������Ă���悤�Ɏv�����A�@���Ȃ��̂�
���낤���B���ɁA���̂悤�Ȍ�����̋��^�����@�ł���A�����̖͂L�x�Ȗ��ԑg�D�i����ЁE�c�̓��j�́A�R������
����ɔY�ޑ�w�����E���Ɓi�����I�Ȍ��͂����s���錠���������{�̎���ψ���̈ψ��j�̈ӌ��E�咣���A���z
�̌�����̋��^�Ɖ]���u���ʁv�E�u�a�v�ɂ���Ď��R�ɑ��邱�Ƃ��\�ƍl������B���̏ꍇ�A�����̗v�]�����S�ɖ�
�����A�����͂̂��閯�ԑg�D�i����ЁE�c�̓��j�̈ӌ����ŗD��ɂ����K���l�E�K���E��������{�ł͔×����Ă���
���Ɨ\�z����邪�A����͕M�҂̕��������ł��낤���B
�@���ɁA�헪�I�C�m�x�[�V�����n���v���O�����i�r�h�o�j�̌�������������V�U���̑�w�������̌����҂�2014�N�x�`
2019�N�x�̂T�N�Ԃɘj���đO�q�̕\�P�W��(�A�j�`�i�L�j�Ɏ�������^�g���b�N�́uNO���K���v�Ɓu�R���v�̋����Ɋւ�
�鋕�U�̋Z�p���𐢊ԂɊg�U�E�Z��������s���E���\�E�����𐽎��Ɋ��s�E���s�����ꍇ�ɂ́A�����ԃ��[�J�́A��
�̐헪�I�C�m�x�[�V�����n���v���O�����i�r�h�o�j�������ԃ��[�J�ɂƂ��Ă̐������ɏI�������ƕ]��������̂Ɛ�������
��B���̏ꍇ�ɂ́A��^�g���b�N�̎g�p�ߒ��Ԃ́u�m�n����0.23�@g/kWh ��NO���K���v�Ɓu2015�N�x�d�ʎԔR������
�{10�����x�̔R�����v�̋K�������̎��{���C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����������ł���2024�N
5��25���ȍ~�ɐ扄���ɂȂ���̂Ɨ\�z�����B
2019�N�x�̂T�N�Ԃɘj���đO�q�̕\�P�W��(�A�j�`�i�L�j�Ɏ�������^�g���b�N�́uNO���K���v�Ɓu�R���v�̋����Ɋւ�
�鋕�U�̋Z�p���𐢊ԂɊg�U�E�Z��������s���E���\�E�����𐽎��Ɋ��s�E���s�����ꍇ�ɂ́A�����ԃ��[�J�́A��
�̐헪�I�C�m�x�[�V�����n���v���O�����i�r�h�o�j�������ԃ��[�J�ɂƂ��Ă̐������ɏI�������ƕ]��������̂Ɛ�������
��B���̏ꍇ�ɂ́A��^�g���b�N�̎g�p�ߒ��Ԃ́u�m�n����0.23�@g/kWh ��NO���K���v�Ɓu2015�N�x�d�ʎԔR������
�{10�����x�̔R�����v�̋K�������̎��{���C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����������ł���2024�N
5��25���ȍ~�ɐ扄���ɂȂ���̂Ɨ\�z�����B
���̌��ʁA2024�N5��25���ȍ~�ł́A��^�g���b�N���[�J�́A�������̏��������C���x�~�G���W���i�������J2005-
54771�j�̓����Z�p���^�g���b�N�̎g�p�ߒ��Ԃɍ̗p���āu�m�n����0.23�@g/kWh ��NO���K���v�Ɓu2015�N�x�d�ʎ�
54771�j�̓����Z�p���^�g���b�N�̎g�p�ߒ��Ԃɍ̗p���āu�m�n����0.23�@g/kWh ��NO���K���v�Ɓu2015�N�x�d�ʎ�
�R������{10�����x�̔R�����v�̋K�������ɓK�������邱�Ƃ��\�ƂȂ�B���̏ꍇ�ɂ́A�C���x�~�G���W��
�i�������J2005-54771�j�̓����Z�p���̗p���Ă���ɂ�������炸�A��^�g���b�N���[�J�́A���������x�������Ɩ���
�i�������J2005-54771�j�̓����Z�p���̗p���Ă���ɂ�������炸�A��^�g���b�N���[�J�́A���������x�������Ɩ���
���R���݂ɁA���̓����Z�p�����Ђ̑�^�g���b�N�ɍ̗p�ł���̂ł���B���̎��ɂ́A�C���x�~�G���W���i�������J
2005-54771�j�̓��������������Ă��邱�Ƃ��L��A���̓����Z�p�ɔ��ׂȕύX�������āu���Ђ̐V�J���Z�p�I�v
2005-54771�j�̓��������������Ă��邱�Ƃ��L��A���̓����Z�p�ɔ��ׂȕύX�������āu���Ђ̐V�J���Z�p�I�v
�Ƃ��Đ���ɐ�`���邱�Ƃ��\�ɂȂ�ƍl������B�����Ƃ��A�ȏ�̂��Ƃɂ��ẮA�|���R�c���Z�p���̕M�҂�
�P�Ȃ鉯���ł���A�m�̂���\���ł͂Ȃ����Ƃ����L���Ă����B�����ĉ��ɁA���̏������I�Ɏ���ǂ������ł�
���Ƃ���A��^�g���b�N���[�J�ɂƂ��ẮA���̎~�܂�Ȃ����Ƃł���A�u������芐������v�̏������ł���
���ƂɂȂ�A����̋ɂ݂̗l�Ԃ����܂����̂ƍl������B
�@������������邽�߂� ���������ԃ��[�J�X�Ђ́A���t�{�̋��͂ĉȊw�Z�p�U���@�\�i�i�r�s�j�̐헪�I
�C�m�x�[�V�����n���v���O�����i�r�h�o�j�Ƃ��āA���{�̎����Ԃ̔r�o�K�X�K���l��R���l�����肷�鐭�{����
�ψ���̐E����S���吹�G�����A�ѓc�P�������A���� �m�����ɑ��A2014�N�x�`2019�N�x�̂T�N�Ԃɘj����
��l������ɔN�ԂłP�疜�~�`�R�疜�~���x�̘d�G�Ǝv��������������^���Ă��錩�邱�Ƃ��Ó��Ȃ悤�Ɏv�����A
�@���Ȃ��̂ł��낤���B�����ŁA�Ȋw�Z�p�U���@�\�i�i�r�s�j�̐헪�I�C�m�x�[�V�����n���v���O�����i�r�h�o�j�ł́A
2014�N�x�`2015�N�x�̂T�N�Ԃɘj���āA76���̑�w��������7.5���~�`10���~�^�N�̑��z�̌�������^�����
���邽�߁A���{�̎����Ԃ̔r�o�K�X�K���l��R���l�����肷�鐭�{����ψ���̐E����S���吹�G
�����A�ѓc�P�������A���� �m�����ւ�SIP�̌�����̋��^���d�G�ł͖����ƌ��Ă��܂������ł���B�������Ȃ���A
���ꂪ���������ԃ��[�J�X�Ђɂ��吹�G�����A�ѓc�P�������A���� �m�����ւ̘d�G�Ƃ��Ă�SIP�������
���^�Ɋւ��I���ȉB���H��ƌ���ƁA�M�҂ɂ͖��ɔ[���̏o���邱�Ƃł���B
�i�H�j ���U�̋Z�p���𐢊ԂɊg�U�E�Z�������邱�Ƃ����ӂȓ��{�̃G���W���W�̊w�ҁE���Ɓ@
�@���{�̃G���W���W�̊w�ҁi����w�������j�̐��E�ł́A��w������̖��߁H������A�Z�p�E�w���̎����ɔ�
�����u���v�̋Z�p���ł����Ă��A���́u�o�L�ځv�ȋZ�p���𑽐��̊w�ҁi����w�������j����v���͂��Ē��˖Ґi
�ɐ��ԂɊg�U���鋰���W�c�ł͂Ȃ����Ɛ��������B���̌����ȗႪ�A�\�Q�P�Ɏ������X�p�[�N�v���O�����̓V�R�K�X
��ăg���b�N���u�G�R�g���b�N�v�Ə̂��ĕ��y���銈���ł���B�@
�����u���v�̋Z�p���ł����Ă��A���́u�o�L�ځv�ȋZ�p���𑽐��̊w�ҁi����w�������j����v���͂��Ē��˖Ґi
�ɐ��ԂɊg�U���鋰���W�c�ł͂Ȃ����Ɛ��������B���̌����ȗႪ�A�\�Q�P�Ɏ������X�p�[�N�v���O�����̓V�R�K�X
��ăg���b�N���u�G�R�g���b�N�v�Ə̂��ĕ��y���銈���ł���B�@
�@�@���V�v���G���W���̔R�Ď����ɂ����ė��_������ߖT�̍����C���X�p�[�N�v���O�̓d�C�Ήԓ_�Œ����ĔR�Ă�����I�b�g�[�T�C�N
�� �̃G���W���i���K�\�����G�� �W�����j�́A�f�B�[�[���G���W���ɔ�r�����ꍇ�A�ሳ�k��̂��߂ɔM�������Ⴍ�A�����ȊO�̃G���W���^
�] �̈�ł͋z�C�i��فi���X�� �b�g���فj�ɂ��ߑ�ȃ|���s���O�s���O�����̂��߂ɔM��������錇�_������B���̂��Ƃ́A���Ƃł���
�� ��ʂ̎����ԍD���̐l�Ԃł���A�N�����n �m���Ă��邱�Ƃ��B���̃I�b�g�[�T�C�N���̃K�\�����G���W���𓋍ڂ��������Ԃ������k���
�z �C�i��فi���X���b�g���فj�̕s�v�ȃf�B�[�[ ���G���W���̎����Ԃ����M�����i���R��j���R�O���O�����邱�Ƃɂ��ẮA��w�̃G��
�W�� �H�w�̍u�`�ŋ������̋������w�� �ɑ��ē���I�ɐ����E�u�`���Ă��邱�Ƃł���B
�@�����Ƃ��A�V�R�K�X�i��CNG�܂���LNG�j��R���Ƃ���I�b�g�[�T�C�N���̃X�p�[�N�v���O�����̓V�R�K�X��ăG���W���𓋍ڂ��������Ԃ́A
�V �R�K�X�̃Z�^�������K�\���������������߂ɍ����k��ɂł��邱�Ƃ���A�K�\�����G���W���𓋍ڂ��������Ԃ������������M�����i���R
��j �����������������B�������A���̍����k��ɂ���ē�����X�p�[�N�v���O�����̓V�R�K�X��ăG���W���̔M�����̑����i��������
�R����P�j�́A�K�\�����G ���W�������͂��ł���B���̂��߁A�X�p�[�N�v���O�����̓V�R�K�X��ăG���W���𓋍ڂ��������Ԃ́A�f�B�[�[��
�G ���W���𓋍ڂ��������Ԃ��������ԑ��s���̔M�����i�������ԑ��s���̔R��j���R�O���߂�����錇�ׂ����邱�Ƃɂ́A�ԈႢ�̖���
�� ���ł���B���̂��Ƃ��A��w�̃G���W���H�w�̍u�` �ł́A�������̋������̂���w���ɍu�`���Ă��邱�Ƃł���B�����āA���̂��Ƃ��G��
�W�� �H�w�ɂ�����X�p�[�N�v���O�̓d�C�Ήԓ_�Œ������ĔR �Ă�����I�b�g�[�T�C�N���̃X�p�[�N�v���O�����̓V�R�K�X��ăG���W��
���W ���𓋍ڂ��������Ԃ����Ă̌Â�����́u����v�ł���B���̂��Ƃɂ��ẮA�ŋ߂̃I�b�g�[�T�C�N���̃X�p�[�N�v���O�����̓V�R�K�X
��� �G���W�����W���𓋍ڂ�����^�g���b�N�ɂ���������s���̔R���f�[�^���܂߁A�V�R�K�X��Ă�CNG��^�g���b�N�́A�d�ʎԔR���
���ɕs�K���̌��׃g���b�N�ɏڏq���Ă���̂ŁA�����̂�����͌䗗�������������B
�@���̂悤�ɁA�X�p�[�N�v���O�����̓V�R�K�X��ăG���W���𓋍ڂ����g���b�N�i�������ԁj�́A�f�B�[�[���G���W���𓋍ڂ����g���b�N�i������
�ԁj�����M�����i���R��j���R�O���߂�����錇�ׂ����邱�Ƃ����m�̎����ł���B����ɂ�������炸�A���\�N���̐̂���A�����̊w�ҁi��
��w�������j�́A�I�b�g�[�T�C�N���̃X�p�[�N�v���O�����V�R�K�X��ăG���W���𓋍ڂ����V�R�K�X��ăg���b�N���u�G�R�g���b�N�v�ł���ƒf
�� ���A�����I�ɓV�R�K�X��ăg���b�N�̕��y��}��ׂ��Ƃ��锭���┭�\�����X�ɌJ��Ԃ��Ă����̂ł���B
�@�Ƃ��낪�A�I�b�g�[�T�C�N���̃X�p�[�N�v���O�����V�R�K�X��ăG���W���𓋍ڂ����V�R�K�X��ăg���b�N���u�G�R�g���b�N�v�ł���Ƃ̏]����
��̑����̊w �ҁi����w�������j�̔����┭�\�́A���炩�Ɍ��ƍl������B���̂Ȃ�A���������A�G�R�g���b�N�A�����u�G�R���W�[�ȃg���b
�N�v�Ƃ́A���� �̒n����̊��j�����Q���������ɗL���ȃG�R���W�[�ȃg���b�N�Ɖ]���Ӗ��ł���B�܂�A�G�R�g���b�N�́A�u�R���G�l��
�M�[�����̗L �����p�i�������M�����ʼn^�s�E���s�\�j�v�Ɓu��C���j��̗}���i���D�ꂽ�r�o�K�X���\�j�v�̗����A�܂��͕Е����f�B
�[ �[���g���b�N��� ���D�ꂽ���\�����������g���b�N�̂��Ƃł���ƒ�`�����B�����ʂ̌������Ő�������A�u�R���G�l���M�[�����̗L
�� ���p�i�������M�����ʼn^�s�E���s�\�j�v�� �u��C���j��̗}���i���D�ꂽ�r�o�K�X���\�j�v�̉��ꂩ����̐��\���f�B�[�[���g���b�N
��� ���D�ꂽ���\������g���b�N�ł����Ă��A ���̕Ј���̐��\���f�B�[�[���g���b�N����������g���b�N�́A�u�G�R���W�[�ȃg���b�N�v�A��
���u�G �R�g���b�N�v�Ƃ͌ĂׂȂ��Ɖ]�����Ƃ� ����B
�@����ɂ�������炸�A�킪���ɂ����Ă͐��\�N���̐̂���A�����̒����ȃG���W�����̊w�ҁi����w�������j�́A�f�B�[�[���G
���W���𓋍ڂ����g ���b�N�i�������ԁj�����M�����i���R��j���R�O���߂�����錇�ׂ����X�p�[�N�v���O�����̓V�R�K�X��ăG
���W���𓋍ڂ����g ���b�N�i�������ԁj���u�G�R�g���b�N�v�ł���ƒf�肵�Ă����̂ł���B�����āA�X�p�[�N�v���O�����̓V�R�K�X��
�ăG���W���𓋍ڂ����g ���b�N�i�������ԁj���u�G�R�g���b�N�v�Ɛ������邽�߂ɁA���{�̃G���W�����̊w�ҁi����w�������j�́A
�V �R�K�X��ăg���b�N�i�������ԁj���f�B�[�[���g���b�N�i�������ԁj�� ����M�����i���R��j���R�O���߂�����錇�ׂN�ɘj����
�� ���E�َE���Ă����悤���B�܂�A���{�̃G���W�����̊w�ҁi����w�������j�́A�V�R�K�X��ăg���b�N���f�B�[�[���g���b�N��
��� �u��NO���v�� �u��PM�v�̗D�ꂽ�r�o�K�X���\�̈�ʂ�����]�����A�f�B�[�[���g���b�N�i�������ԁj�� ����M�����i���R��j���R
�O�� �߂�����錇�ׂ��B�����锽�Љ�I�ȍs�ׂ��s���Ă����ƍl������B
�@���̌����́A���{�̃G���W���W�̊w�ҁi����w�������j�̐��E�ł́A�w�E�̃s���~�b�h�^�̒i�K�I�ȑg�D�\���i���q�G�����L�[�I�ȍ\
���j�� �Öق̂����ɑ��݂��A�w�E�̒��_�Ɉʒu����w�ҁi����w�������j���u�X�p�[�N�v���O�����V�R�K�X��ăg���b�N�i�������ԁj�̓G�R�g
�� �b�N�� ����v�Ƃ̌����\����A���̌����ɏ]��Ȃ��ӌ������\�����w�ҁi����w�������j�͊w�E���瑺�����̐��ق��銵�Ⴊ
�� �邽�߂Ɛ��������B�܂�A���̓��{�̃G���W���W�̊w�E���瑺�����̏��������w�ҁi����w�������j�́A���̌�ɂ͊w�E�̘_
�� �ܓ��̑Ώۂ���O����邽�߂Ɋw�ҁi����w�������j�Ƃ� �Ă̏o�������҂����҂ł����A�ň��̏ꍇ�͐E���������������悤���B����
�悤 �ȑ̐��̂킪���ɂ����āA�ߋ��̈��鎞�_�ɂ����Ĕn���Ȋw�E�̒��_�Ɉʒu���� �w�ҁi����䏊�̑�w�������j���u�X�p�[�N�v���O
���� �V�R�K�X��ăg���b�N�i�������ԁj�̓G�R�g���b�N�ł���v�Ɛ錾���Ă��܂������ʁA�f�B�[�[���g���b�N�i�������ԁj�� ����M�����i���R��j
���R �O���߂�����錇�ׂ����X�p�[�N�v���O�����̓V�R�K�X��ăG���W���𓋍ڂ����g ���b�N�i�������ԁj�́A���{�ł́u�G�R�g���b�N�v�Ɛ���
���� ��Ɋׂ������̂ƍl������B
�@���̌��ʁA�킪���ɂ����ẮA�f�B�[�[���g���b�N�i�������ԁj�����M�����i���R��j���R�O���߂�����錇�ׂ����X�p�[�N�v���O�����V
�R �K�X��ăg���b�N�i�������ԁj���u�G�R�g���b�N�v�ł���Ƃ̑����̊w�ҁi����w�������j�ɂ�鐔�\�N���̐̂���̔����E���\�ɂɂ��Ĉق�
�� ����w�ҁE���Ƃ́A�����_�i��2015�N8�����_�j�܂ŒN��l�Ƃ��Č���Ă��Ȃ����̂ƍl������B���̏����ĕs�v�c�Ȃ��Ƃ́A��
�w�� �G���W���H�w�̍u�`�ł͋������̋������w���ɁA�u�X�p�[�N�v���O�����̓V�R�K�X��ăG���W���̓f�B�[�[���G���W�������M����
�i���R ��j���R�O���߂������M�����i���R��j�̖ʂł̏d��Ȍ��ׂ�����v���Ƃ�������Ă���ɂ�������炸�A���\�N���̐̂��猻���_
�i�� 2015�N8���� �_�j�Ɏ���܂ŁA���{�̑����̊w�ҁi����w�������j�́A�L�����Ԃɑ��A�I�b�g�[�T�C�N���̃X�p�[�N�v���O�����V�R�K�X
��� �G���W���𓋍ڂ��� �V�R�K�X��ăg���b�N���u�G�R�g���b�N�v�ł���Ɣ����E���\���J��Ԃ��Ă��Ă���鎖������R�Ƒ��݂��Ă���̂ł�
��B �� ��́A���Ƃ��s�v�c�Ȃ��Ƃ��B
�@���̏�����ƁA�f�B�[�[���g���b�N�i�������ԁj�����M�����i���R��j���R�O���߂�����錇�׃g���b�N�ł����Ă��A�f�B�[�[���g���b�N����
�u��NO���v�Ɓu��PM�v�̗D�ꂽ�r�o�K�X���\��L���Ă���g���b�N�ł���u�G�R�g���b�N�v�ƌď̂���̂��A���{�̊w�ҁi����w�������j�́u�G
�R �g���b�N�v�̒�`�̂悤�ł���B���̓��{�̊w�ҁi����w�������j�́u�G�R�g���b�N�v�̒�`�́A�|���R�c���Z�p���̕M�҂ɂ͊��S�Ɂu���v��
���� �́u�o�L�ځi�f�^�����j�v�ƍl������B�����āA�I�b�g�[�T�C�N���̃X�p�[�N�v���O�����̓V�R�K�X��ăg���b�N�i�������ԁj���f�B�[�[���g��
�b�N �i�������ԁj�����M�����i���R��j���R�O���߂�����錇�׃g���b�N�ł���A�u�G�R�g���b�N�v�ƌď̂��邱�Ƃ����S�Ɂu���v�Ⴕ���́u�o�L��
�i�f�^ �����j�v���w�E���锭���E���\���s�������{�̊w�ҁi����w�������j�́A���\�N���̐̂���F���ł��������Ƃ������ł���B�m���ɁA���{
�̃G�� �W���W�̑�䏊�Ɖ]���钘���Ȋw�ҁi����w�������j�́u���v�E�u�o�L�ځv�̔����E���\�𐳂��w�ҁi����w�������j�́A����
�]���� �o�傷�邱�Ƃ��K�v�ƍl������B�������A���̋]��������A�d��ȁu���v�E�u�o�L�ځv�̔����E���\�𐳂��E�C�̖������{�̃G���W��
�W�� �́A�w�ҁi����w�������j�Ƃ��Ă̖{���̐E�ӂ���������Z�p�̐i���E���W��j�Q���锽�Љ�I�ȁu���f�Ȑl�B�v�ɉ߂��Ȃ��悤�Ɏv
�����A �@���Ȃ��̂ł��낤���B
�@���͂Ƃ�����A�X�p�[�N�v���O�����̓V�R�K�X��ăG���W���𓋍ڂ��������Ԃ́A�f�B�[�[���G���W���𓋍ڂ��������Ԃ����M
�����i���R��j���R�O���߂�����邱�Ƃ��Ƃ���A�u�G�R���W�[�ȃg���b�N�v�A�����u�G�R�g���b�N�v�ƌď̂��邱�Ǝ��Ԃ����S�Ȍ��ł�
�� ���Ƃ��N�ł������ł��锤�ł���B�܂�A�X�p�[�N�v���O�����̓V�R�K�X��ăG���W���𓋍ڂ����g���b�N�������I�ɕ��y�����ꍇ��
�́A ����Ɠ����̃g���b�N�ݕ��̗A���ʂł����Ă��g���b�N����̃G�l���M�[����ʂ��R�O���߂������傷��s�K�ȎЉ���o����Ă��܂�
���� �ɂȂ�B����́A�N���l���Ă��u���̍����v�ł���B���̂��߁A���\�N���̐̂���A���{�̑����̒����ȃG���W�����̊w�ҁi����w����
���j ���I�b�g�[�T�C�N���̃X�p�[�N�v���O�����V�R�K�X��ăG���W���𓋍ڂ����V�R�K�X��ăg���b�N���u�G�R�g���b�N�v�ƒf�肵�ĕ��y�̑��i��
�� �����Ă������Ƃ́A���炩�Ɍ��ł���B���ɁA�V�R�K�X��ăg���b�N���f�B�[�[���g���b�N�ɂ�����f��M�����i���R��s�ǁj���B�����āu��
NO ���v�Ɓu��PM�v�̗D�ꂽ�r�o�K�X���\�̈�ʂ������Ӑ}���ċ������邱�Ƃ́A���\�t���l���x���퓅�I�Ȏ�@�ł���B����𐔏\�N����
�̂� �牄�X�𑱂��Ă������Ƃ́A���{�̃G���W���W�̊w�ҁi����w�������j���Ӑ}�I�ɍ��\�I�ȍs�ׂ��s���Ă������m�ȏ؋��ƍl�����
��B
�@�����āA���{�̃G���W���W�̊w�ҁE���ƁE�Z�p�҂́A�f�B�[�[���g���b�N�ɔ�ׂĎ����s��d�� �ԃ��[�h�R��R�O���O�����錇��
�̂��߂ɓV�R�K�X�i���G�l���M�[�����j��Q���u�I�b�g�[�T�C�N���̃X�p�[�N�v���O�����V�R �K�X�G���W���𓋍ڂ����V�R�K�X��ăg���b
�N�v���u�G�R�g���b�N�v�Ə̂��āA���{(�����y��ʏȓ��j�́A�P�X�X�O�N��̏����̍����猻�݂܂ł̓�\���N�Ԃɘj���đ��z�̕⏕�������^
�� �āu�V�R�K�X��ăg���b�N�v�̕��y��}���Ă�������������B�i���݂ɁA�I�b�g�[�T�C�N���̃X�p�[�N�v���O�����̓V�R�K�X��ăg���b�N���u�G
�R�g ���b�N�v�ł���ƔF�肵�A���́u�G�R�g���b�N�v�ɐ��{(�����y��ʏȓ��j���x���������z�̐��{�̕⏕���́A���ʓI�ɓ��{�̃G�l���M�[��
��� �Q��g��Ɖ]�����Љ�I�ȍs�ׂɓ������ꂽ���̌��邱�Ƃ��\�ł���B�܂�A�ŋ��̖��ʌ����ƍl������B�j
�@���̌����́A�u�I�b�g�[�T�C�N���̃X�p�[�N�v���O�����V�R �K�X�G���W���𓋍ڂ����V�R�K�X��ăg���b�N�́A�f�B�[�[���g���b�N�ɔ�r����
�R �O���߂����M�����i�������s��d�� �ԃ��[�h�R��j�̗�錇�ׂ���{�̓��{�̃G���W���W�̊w�ҁE���Ƃ��B�����Ă������ʂƍl����
�� ��B���̂悤�ȓ�\���N�Ԃɘj���Ĉꎅ���ꂸ�ɍ��\�I�Ȕ��\�E�����E�s���𐋍s���Ă�����w��������̂Ƃ������{�̃G���W���W��
�w �ҁE���Ƃ́A���\�W�c�Ƃ��Ă͒��ꗬ�̂悤�Ɏv�����A�@���Ȃ��̂ł��낤���B�����Œ��ڂ��ׂ����Ƃ́A���{�̃G���W���W�̑�䏊
�Ɖ] ���钘���Ȋw�ҁi����w�������j�́u���v�E�u�o�L�ځv�̔����E���\���B�����邽�߁A�i���s���~�b�h�^�̒i�K�I�ȑg�D�\���j�̏�w��
�牺 �w�Ɏ��鑽���̊w�ҁi����w�������j�́A�헪�I�C�m�x�[�V�����n���v���O�����i�r�h�o�j�̏ꍇ�̎����ԃ��[�J����̌�����̂悤�ȍH��
���� �Ǝv���������̋��^�������Ă��A�R��s�ǂ̃I�b�g�[�T�C�N���̓V�R�K�X��ăg���b�N���u�G�R�g���b�N�v�Ɠ�\���N�Ԃɘj���ď^������
���� �ł���B���̏�����ƁA���{�̑命���̃G���W���W�̊w�ҁi����w�������j�́A���ʂȍH�쎑���̋��^�������ꍇ�ł��A��w��
���� �̖��߁H������A�Z�p�E�w���́u���v�E�u�o�L�ځv�ȋZ�p���ł����˖Ґi�Ɋg�U����W�c�̂悤�ł���B���̂悤�ɍs��������{
�̃G ���W���W�̊w�ҁi����w�������j�̖{���̐E��������҂ł��邱�Ƃ́A�M�҂ɂ��D�ɗ����Ȃ��Ƃ���ł���B
�@�e�ɂ��p�ɂ��A�����_�i2015�N9���P�����݁j�ɂ����āA�I�b�g�[�T�C�N���̃X�p�[�N�v���O�����V�R �K�X�G���W���𓋍ڂ����V�R �K�X���
�g���b�N���f�B�[�[���g���b�N�ɔ�ׂĎ����s��d�� �ԃ��[�h�R��i�������s�̔M�������j���R�O���O�����錇�ׂ̂� �߂Ɂu�G�R�g���b�N�v��
���Ď��i�ł���ƒf�����Ă���̂́A�|���R�c���Z�p���̕M�҂����̂悤�ł���B(���̗��R�́A2011�N12��13���ɕM�҂��J�݂����V�R�K�X
��Ă�CNG��^�g���b�N�́A�d�ʎԔR���ɕs�K���̌��׃g���b�N�̃z�[���y�[�W�ɏڏq�j�@�����āA��\���N�ȏ� ���̐̂���A�قƂ��
�S�Ă̓��{�̃G���W���W�̊w�ҁi����w�������j�́A�X�p�[�N�v���O�����̓V�R�K�X��ăg���b�N���u�G�R�g ���b�N�v�Ɣ��\�E�������A�^���E
��^�������Ă����̂ł���B���̏؋��͖����ɂ��Ƃ܂��Ȃ��̂ŁA�����ł͏ȗ�����B ����ɂ��ċ^�`�̂�����́A�Ⴆ�AGoogle����
�G���W���ŁA�u�吹�����v�{�u�V�R�K�X�����ԁv�̂Q��̌������s���Ă������������B��������A���{���\����G���W���w�҂̑���c��
�w�E�吹�������X�p�[�N�v���O�����̓V�R�K�X��ăg���b�N���u�G�R�g ���b�N�v�Ə^���A�����^�g���b�N�Ƃ��Đ�������Ă���c��Ȏ�������
������锤�ł���B���̒��ɂ́A�X�p�[�N�v���O�����̓V�R�K�X��ăg���b�N���f�B�[�[���g���b�N�ɔ�ׂĎ����s��d�� �ԃ��[�h�R��i����
���s�̔M�������j�łR�O���O�����錇�׃g���b�N�Ɩ������ꂽ����c��w�E�吹�����̎����́A�F���̔��ł���B�Ȃ��A�ŋ߂ł́A����c
��w�E�吹�O�����́A�X�p�[�N�v���O�����̓V�R�K�X��ăg���b�N���u�G�R�g ���b�N�v�Ə^���锭�\�E�������T�����Ă���悤�Ɍ���
���B
�@���̂悤�ɁA�ŋ߂ɂȂ��đ���c��w�E�吹�O�����́A�X�p�[�N�v���O�����̓V�R�K�X��ăg���b�N���u�G�R�g ���b�N�v�Ə^���锭�\�E����
�𒆎~�����悤�ł���B���̓��@�E���R�́A�M�҂��V�R�K�X��Ă�CNG��^�g���b�N�́A�d�ʎԔR���ɕs�K���̌��׃g���b�N�̃z�[���y
�[�W���J�ɂ��A�I�b�g�[�T�C�N���̃X�p�[�N�v���O�����̓V�R�K�X��ăg���b�N���f�B�[�[���g���b�N�ɔ�ׂĂR�O���O����R���G�l���M�[��
�Q��錇�׃g���b�N�ł��鎖�����I���������Ƃł͂Ȃ����Ɛ��������B���̂Ȃ�A�X�p�[�N�v���O�����̓V�R�K�X��ăg���b�N���R���G
�l���M�[��Q��錇�׃g���b�N�ł��鎖���𑽂��̐l�B���m�邱�ƂɂȂ�A����܂ł̐��\�N�Ԃɘj���āu�X�p�[�N�v���O�����̓V�R�K�X
��ăg���b�N���G�R�g ���b�N�ł���v�Ƃ̔��\�E�������J��Ԃ��Ă�������c��w�E�吹�O���������Ԃ��猵�����w�e����邱�ƂɂȂ�Ɛ��@
�����B���̂悤�Ȏ��ԂɊׂ邱�Ƃ����O�ɉ�����邽�߁A����c��w�E�吹�O�����́A�ŋ߂ł́u�X�p�[�N�v���O�����̓V�R�K�X��ăg��
�b�N���G�R�g ���b�N�v�Ɣ��\�E���������̂Ɛ��������B�{���Ȃ�A�����_�ɂ����āA����c��w�E�吹�O�����́A����܂ł́u�X
�p�[�N�v���O�����̓V�R�K�X��ăg���b�N���G�R�g ���b�N�v�Ƃ̔��\�E�������u���v�E�u���U�v�ł��������Ƃ�F�߁A���ԂɎӍ߂��ׂ��ł���ƍl
������B�Ƃ��낪�A����ł́A����c��w�E�吹�O�����́A����܂ł́u�X�p�[�N�v���O�����̓V�R�K�X��ăg���b�N���G�R�g ���b�N�v�Ƃ�
���U�̔��\�E�������Ӎ߂���f�U��́A�F���̂悤�ł���B����c��w�E�吹�O�����́A���̌��ɂ��Ắu����܂�i���ق�j�E���فv�ɂ�
���ėL�떳��ɏI��点�悤�Ƃ���Ӑ}���L�肻���Ɍ�����B�������Ȃ���A����́A�Ƒ����̂��̂ł͂Ȃ����낤���B
�[�[�[�[
�@����A����c��w�E�吹�O�����ȊO�̓��{�̃G���W���W�̊w�ҁi���� �w�������j���A�f�B�[�[���G���W���ɔ�r�����ꍇ�ɂ͒ሳ�k
��̂��߂ɔM�������Ⴍ�A�����ȊO�̃G���W���^�]�̈�ł͋z�C�i��� �i���X���b�g���فj�ɂ��ߑ�ȃ|���s���O�s���O�����̂��߂�
�M ���������I�b�g�[�T�C�N���̃X�p�[�N�v���O�����V�R�K�X�G���W���𓋍� �����V�R�K�X��ăg���b�N���u�G�R�g���b�N�v�ł���Ƃ́u�R�v�E
�u�o�L �ځi�f�^�����j�v�ȏ]���̎咣�E�����ɂ��Ă̒�����Ӎ߂��s���l�q�́A���̂Ƃ���F���̂悤�ł���B���͂Ƃ�����A����܂ł́u�X
�p�[�N�v ���O�����̓V�R�K�X��ăg���b�N���G�R�g ���b�N�v�Ɛ������Ă������Љ�I�Ȓ��Ԍ������Ă���ƁA����c��w�E�吹�O�������܂�
���{�̃G ���W���W�� �w�ҁi����w�������j�́A�u�ǐS�������Ȃ��V���̍��\�t�v�̐l�B�����̓���ȏW�c�̂悤�Ɏv���Ďd������ ���B
�������A�� ��́A�M�҂̐�w�ɍ˂ł��邪�̂̌���������ł��낤���B
�@���݂ɁA�M�҂̓f�B�[�[���g���b�N�Ɠ����̔R��i���M�����j�̐ύڗʂS�g���̒��^DDF�g���b�N�̎��؎����̌��ʂ��܂Ƃ߂��_���i������
�� �Z�p��w�p�u����O���WNo.71-00�i2000�N5���j �u323�@���^�g���b�N�pECOS-DDF�@�V�R�K�X�G���W���̊J���v20005001�j ���A2000�N
5 �� �̎����ԋZ�p��̏t�G�u����Ŕ��\�����B���������āA2000�N5���̎��_�ɂ����ẮA���̐ύڗʂS�g���̒��^DDF�g���b�N�̘_������
�� �A�f�B �[�[���g���b�N�Ɠ����̔R��i���M�����j�̓V�R�K�X����R���Ƃ���c�c�e�G���W���i���f�B�[�[���f���A���t���G���G���W�����y��
�� �Ό^�V�R�K�X�G���W���j�𓋍ڂ����c�c�e�g���b�N�y�����邱�Ƃɂ��A�킪���̃g���b�N�ݕ��A������� �b�n�Q�팸�ƒE�Ζ��������ł�
�� �����Ă���B���̓��e�ɂ��ẮA�f�B�[�[���ɔ�ׂP�T���̂b�n�Q�팸���\�Ȃc�c�e�G���W����DDF�^�]�ƃf�B�[�[���^�]�̑I������
�\�Ȃc�c�e��^�g���b�N �ɏڏq���Ă���̂ŁA�����̂�����͌䗗�������������B�����āA���̃f�B �[�[���g���b�N�Ɠ����̔R��i���M�����j��
�V �R�K�X����R���Ƃ���c�c�e�g���b�N�̑��݂́A2000�N5�� �̎��_�ł́A���{�̃G���W���W�̊w�ҁE���ƁE�Z�p�҂̒N�����n�m���Ă�
�� ���ł���B�Ƃ��낪�A�s�v�c�Ȃ��ƂɁA���{�̃g�� �b�N���[�J�E��w�E�����@�ւ̊w�ҁE���ƁE�Z�p�҂́A2000�N5���ȍ~���A ����DDF�g��
�b�N �̋Z�p�����S�ɖ����E�َE���������̂ł���B�����āA���̈���ł́A���{�̃G���W���W�̊w�ҁE���Ƃ́A�f�B�[�[���g���b�N�ɔ�r
���� �R�O���O������̔R��s�ǂ̌��ׂ����� �I�b�g�[�T�C�N���̓V�R�K�X��ăg���b�N��������́u�G�R�g���b�N�v�ł���Ƃ́u�R�v�E�u���U�v�E
�u�o �L�ځi�f�^�����j�v�Ȏ咣�E�������J��Ԃ��Ă����̂ł���B���̏�����ƁA����c��w�E�吹�O�������܂ޓ��{�̃G���W���W�̊w
�� �i���� �w�������j�́A�Z�p���e�𐳓��ɕ]������w�҂Ƃ��Ắu�ǐS�v�������Ă��܂����l�B�̏W�c�̂悤�Ɏv���邪�A�@���Ȃ��̂ł���
�� ���B
�����Ƃ��A�ŋ߁i��2013�N�ȍ~�H�j�ł́A�ꕔ�̊w�ҁE���Ƃ́A�f�B�[�[���g���b�N�ɔ�r���ĂR�O���O������̔R��s�ǂ̌��ׂ����I
�b�g�[�T�C�N���̓V�R�K�X��ăg���b�N��������́u�G�R�g���b�N�v�ł���Ƃ̉ߋ��́u�R�v�E�u���U�v�E�u�o�L�ځi�f�^�����j�v�Ȏ咣�E�����𒆎~��
�n �߂Ă���悤�ł���B�����āA���H��ʊ�����ēˑR�ɁA2000�N5���̎��_�ŕM�҂������ԋZ�p��E�t�G�u����Ŕ��\�����_���Ɠ�����
�e �́u�f�B �[�[���g���b�N�Ɠ����̔R��i���M�����j�̓V�R�K�X����R���Ƃ���c�c�e�g���b�N�𐄏����锭����咣�v���n�߂��悤�ł���B����
�� ��������ƁA���{�̃G���W���W�̊w�ҁi���� �w�������j�́A�Ƒ��ȐӔC����̍I�݂Ȑl�ԂŐ�߂��Ă���悤�Ɏv�����A�@���Ȃ���
�� ���낤���B �V�R�K�X���獇����DME��GTL�́A�f�B�[�[���g���b�N�̔R���ɕs�K�A�G�l���M�[�����𑽗ʂɘQ���c�l�d�g���b�N�𐄏���
��ُ�Ȑl�B�A�y�������G�l���M�[�������R�O�������c�l�d�𐄏�����@�B�w��̋^���̃y�[�W�ɏڏq�����悤�ɁA�f�B�[�[���g���b�N ��
��r����Well-to-Wheel�łR�O���O����̑����̃G�l���M�[������Q���c�l�d�g���b�N�̏����I�ȕ��y�𐄏�����u�R�v�E�u���U�v�E�u�o�L ��
�i�f�^�����j�v�Ȏ咣�E�������ߋ��ɂ͐���ɍs���Ă������������邱�Ƃ��A�Y��Ă͂Ȃ�Ȃ����Ƃ��A�����ɕt�L���Ă��������B
�@�ȏ�̂悤�Ȃ��Ƃ���A���{�̃G���W���W�̊w�ҁi����w�������j�́A�c�l�d�g���b�N��I�b�g�[�T�C�N���̓V�R�K�X��ăg���b�N��������
�� �u�G�R�g���b�N�v�Ƃ́u�R�v�E�u���U�v�E�u�o�L�ځi�f�^�����j�v�Ȏ咣�E��������v�c�����Č��`���Č������⏕�����Â邱�Ƃɉ��̍߈�������
�� �Ȃ��l������̂悤�ł���B���ɁA�����ł��ǐS�̙�ӂ�������l�Ԃł���A�̂���c�l�d�g���b�N��I�b�g�[�T�C�N���̓V�R�K�X��ăg
�� �b�N�̌����╁�y�̂��߂ɋM�d�ȍ����̐ŋ��������Ƃ��鐭�{�̌������⏕���̎x���ɔ��̐��������Ă������ł���A���{�ł͂c
�l �d�g���b�N��I�b�g�[�T�C�N���̓V�R�K�X��ăg���b�N�̌����J���╁�y�������s���Ă��Ȃ��������̂Ɛ��������B
�@�����āA�ŋ߂ɂȂ��āA�M�҂̃z�[���y�[�W���̑i���ɂ���Ăc�l�d�g���b�N��I�b�g�[�T�C�N���̓V�R�K�X��ăg���b�N���u�G�R�g���b�N�v�ł�
�邱�Ƃ́u�R�v���I������ƁA���{�̃G���W���W�̊w�ҁi����w�������j�́A�c�l�d�g���b�N��I�b�g�[�T�C�N���̓V�R�K�X��ăg���b�N���u�G�R
�g���b�N�v�Ƃ̋��U�̋Z�p�������`���ĕs���H�ɐ��{�̌������⏕���̎x�����Ă������ƂɎӍ߂������A�P�Ɂu����܂�v��u���فv
�����ߍ���ł�悤�ł���B���̏́A����܂œ��{�̃G���W���W�̊w�ҁi����w�����������m������g���A�u�G�R�g���b�N�v���u���D��
�a�H�v�Ƃ��Č������⏕����s���Ɋl���������Ƃ�L�떳��ɂ��čI�������邽�߂̍s�ׂ̂悤�Ɏv���Ďd���������B����́A���Ƃ���
�ӔC�Ȃ��Ƃł���A�ڗ�Ȃ����Ƃł͂Ȃ����낤���B
�@���ɁA����܂�����c��w�E�吹�O�������܂ޓ��{�̃G���W���W�̊w�ҁi���� �w�������j����v�c�����āu�I�b�g�[�T�C�N
�� �̓V�R�K�X��ăg���b�N�̓G�R�g���b�N�v�Ƃ��鋕�U�̎咣�ɍ��y��ʏȁE���ȓ��̒S�����������S���x���ꂽ���ʁA���{��
�� �{�͒��N�ɘj���ăf�B�[�[���g���b�N�ɔ�r����Well-to-Wheel�łR�O���O����̑����̓V�R�K�X�̃G�l���M�[������Q���
�I �b�g�[�T�C�N���̓V�R�K�X��ăg���b�N�̕��y�̂��߂ɖc��Ȑ��{�̕⏕�����x�����������ƍl������B���̂��Ƃ́A���{�̐�
�{ ���V�R�K�X�̃G�l���M�[�����̘Q��𑣐i���邽�߂ɕ⏕�����x������Ɖ]��������{������{���Ă������ƂɂȂ�B���̂悤�Ȑ��{�\
�Z�� ���ʌ����́A����c��w�E�吹�O�������܂ޓ��{�̃G���W���W�̊w�ҁi���� �w�������j�ɂ��u�R�v�E�u�U��v�̋Z�p���M��
������ �������ƍl������B
�@���̂悤�Ȑ��{�\�Z��Q��鎸�s���J��Ԃ��Ȃ����߂́A���y��ʏȁE���ȓ��̒S�������́A�I�b�g�[�T�C�N���̓V�R�K�X��ăg���b
�N ���u�G�R�g���b�N�v�ɔF�肷��悤�Ɏd�������ƌ�������{�̃G���W���W�̊w�ҁi���� �w�������j�̉ߋ� �̕s���s�ׂ̐ӔC����������
�����邱�Ƃ��K�{�ƍl������B���ɁA�u�I�b�g�[�T�C�N���̓V�R�K�X��ăg���b�N���u�G�R�g���b�N�v�Ƃ���� �����Z�p�������`�E�g�U
�������{�̃G���W���W�̊w�ҁi���� �w�������j�́A���̓V�R�K�X ��ăg���b�N�ւ̕⏕���x���Ɋւ��锽�Љ�I�ȉR�̋Z�p
�����Ӑ}�I�ɗ��z�E���������s�ׂ̐ӔC�̒Njy���s���Ȃ����� �ꍇ�ɂ́A�����I�ɑ�Q�A��R�̋U�́u�G�R�g���b�N�v��V��
�ɝs������\��������ƍl������B���̏ꍇ�ɂ́A���y��ʏȁE�� ���Ȃ́A�ĂуG�l���M�[�����̘Q��𑣐i���邽�߂ɕ�
�������x������Ɖ]���A�ߋ��Ɠ����߂���Ƃ����ꂪ����B���̂Ȃ�A ����A�ĂсA���{�̃G���W���W�̊w�ҁi���� �w�������j��
���Ƃ��L�x�Ȑ��m������g�������U�� �Z�p�������`�E�g�U�����ꍇ�ɂ́A���y��ʏȁE���ȓ��̒S�������́A���̉R����������
�����Ƃ������Ɛ�������邽�߂��B �@
|
�@�ȏ�́A��w��������̂Ƃ������{�̃G���W���W�̊w�҂��A��\���N�Ԃɘj��A�M�����s�ǁi���R��s�ǁj�̃I�b
�g�[�T�C�N���̃X�p�[�N�v���O�����V�R�K�X��ăG���W���𓋍ڂ����V�R�K�X��ăg���b�N���u�G�R�g���b�N�v�Ɏd���ď�
���Ă������\�I�ȍs�ׂ̓^���ł���B�����āA���̃X�p�[�N�v���O�����V�R�K�X��ăg���b�N���u�G�R�g���b�N�v�ł����
�u�R�v�E�u�o�L�ځi�f�^�����j�v�Ȕ����E���\����s�ׂ́A���{�̃G���W���W�̊w�ҁi����w�������j�̑哯�c�������ɂ�
�ē����̎�ꂽ�̐��Ŏ��{����Ă������Ƃ��ǂ����鎖�ۂł���B�A�܂�A���{�̃G���W���W�̊w�ҁi����w����
���j�́A1990�N�̏��������\���N�Ԃɘj��A�M�����s�ǁi���R��s�ǁj�̃I�b�g�[�T�C�N���̃X�p�[�N�v���O�����V
�R�K�X��ăg���b�N���G�R�g���b�N�ɍՂ�グ�鍼�\�I�Ȋ��������{���Ă����悤�ł���B���̂��Ƃ́A���{�̃G���W����
�W�̊w�ҁi����w�������j���P���̊T�O�ɑ�������Ȃ��o���~�̋����l�Ԃ̂����������c��鐢�E�ł��邩�炱��
�����������ۂƂ��l������B�t�Ɍ����A�u�I�b�g�[�T�C�N���̃X�p�[�N�v���O�����V�R�K�X��ăg���b�N���G�R�g���b
�N�v�Ƃ̎����ɔ����������E���\�X�ƕ��C�ōs�����Ƃ̂ł���l�Ԃ������A���{�̃G���W���W�̊w�ҁi����w��
�����j�̗�����l�����邱�Ƃ��ł��鐢�E�ł��邩���m��Ȃ��B �����Ȃ�A���݂̓��{�̃G���W���W�̑�w����
�́A�N�������\�t�̃v���t�F�V���i���ƌĂԂɑ��������l�B�Ő�߂���Ă���ƍl���ĊԈႢ�������ƌ���ׂ���
�̂悤�ɍl������B
�g�[�T�C�N���̃X�p�[�N�v���O�����V�R�K�X��ăG���W���𓋍ڂ����V�R�K�X��ăg���b�N���u�G�R�g���b�N�v�Ɏd���ď�
���Ă������\�I�ȍs�ׂ̓^���ł���B�����āA���̃X�p�[�N�v���O�����V�R�K�X��ăg���b�N���u�G�R�g���b�N�v�ł����
�u�R�v�E�u�o�L�ځi�f�^�����j�v�Ȕ����E���\����s�ׂ́A���{�̃G���W���W�̊w�ҁi����w�������j�̑哯�c�������ɂ�
�ē����̎�ꂽ�̐��Ŏ��{����Ă������Ƃ��ǂ����鎖�ۂł���B�A�܂�A���{�̃G���W���W�̊w�ҁi����w����
���j�́A1990�N�̏��������\���N�Ԃɘj��A�M�����s�ǁi���R��s�ǁj�̃I�b�g�[�T�C�N���̃X�p�[�N�v���O�����V
�R�K�X��ăg���b�N���G�R�g���b�N�ɍՂ�グ�鍼�\�I�Ȋ��������{���Ă����悤�ł���B���̂��Ƃ́A���{�̃G���W����
�W�̊w�ҁi����w�������j���P���̊T�O�ɑ�������Ȃ��o���~�̋����l�Ԃ̂����������c��鐢�E�ł��邩�炱��
�����������ۂƂ��l������B�t�Ɍ����A�u�I�b�g�[�T�C�N���̃X�p�[�N�v���O�����V�R�K�X��ăg���b�N���G�R�g���b
�N�v�Ƃ̎����ɔ����������E���\�X�ƕ��C�ōs�����Ƃ̂ł���l�Ԃ������A���{�̃G���W���W�̊w�ҁi����w��
�����j�̗�����l�����邱�Ƃ��ł��鐢�E�ł��邩���m��Ȃ��B �����Ȃ�A���݂̓��{�̃G���W���W�̑�w����
�́A�N�������\�t�̃v���t�F�V���i���ƌĂԂɑ��������l�B�Ő�߂���Ă���ƍl���ĊԈႢ�������ƌ���ׂ���
�̂悤�ɍl������B
�@���̂悤�ɁA���݂̓��{�̃G���W���W�̊w�ҁi����w�������j�̐��E�́A�킪�g�̏o���������ŗD��ɂ���w��
�i����w�������j�̏W�c�̂悤�Ɏv���邪�A�@���Ȃ��̂ł��낤���B���̂悤�Ȃ��Ƃ���A���݂̓��{�̃G���W���W��
�w�ҁi����w�������j�́A�������B�����č��\�I�Ȕ��\�E�����E�s���̐��s�ɂ����āA�ɂ߂č����\�͂�����l��
����̂̂悤�ł���B���̏�����ƁA�����_�ł́A�w�ǂ̓��{�̃G���W���W�̊w�ҁi����w�������j�́A�u�ǐS
�̙�Ӂv�������Ȃ��l�B�Ő�߂��Ă���悤�ł���B���̂��߁A���{�̃G���W���W�̊w�ҁi����w�������j�́A����
�ԃ��[�J�̌�����^�̌��Ԃ�ɁA�O�q�̎����ԃ��[�J�̗v�]����\�P�W��(�A�j�`�i�L�j�Ɏ�������^�g���b�N�́uNO��
�K���v�Ɓu�R���v�̋����Ɋւ��Ă̎����ԃ��[�J�̖]�ޏ���ɉ��������\�I�ȍs���E���\�E�����𐽎��E�m��
�Ɋ��s�E���s���邱�Ƃ��u���͓̉��v�Ⴕ���́u���ёO�v�̂��ƂƐ��������B
�i����w�������j�̏W�c�̂悤�Ɏv���邪�A�@���Ȃ��̂ł��낤���B���̂悤�Ȃ��Ƃ���A���݂̓��{�̃G���W���W��
�w�ҁi����w�������j�́A�������B�����č��\�I�Ȕ��\�E�����E�s���̐��s�ɂ����āA�ɂ߂č����\�͂�����l��
����̂̂悤�ł���B���̏�����ƁA�����_�ł́A�w�ǂ̓��{�̃G���W���W�̊w�ҁi����w�������j�́A�u�ǐS
�̙�Ӂv�������Ȃ��l�B�Ő�߂��Ă���悤�ł���B���̂��߁A���{�̃G���W���W�̊w�ҁi����w�������j�́A����
�ԃ��[�J�̌�����^�̌��Ԃ�ɁA�O�q�̎����ԃ��[�J�̗v�]����\�P�W��(�A�j�`�i�L�j�Ɏ�������^�g���b�N�́uNO��
�K���v�Ɓu�R���v�̋����Ɋւ��Ă̎����ԃ��[�J�̖]�ޏ���ɉ��������\�I�ȍs���E���\�E�����𐽎��E�m��
�Ɋ��s�E���s���邱�Ƃ��u���͓̉��v�Ⴕ���́u���ёO�v�̂��ƂƐ��������B
�@�܂�A�O�q�̐헪�I�C�m�x�[�V�����n���v���O�����i�r�h�o�j�̌�����������āi�疜�~�`�R�疜�~�j�^�i�N�ԁE��l����
��j�̌���������^���ꂽ����c��w�E�吹�G�����A�c����w�E�ѓc�P�������A����c��w�E���� �m�������܂ނV
�U�����̑����̑�w�̋�������̂Ƃ��������҂́A2014�N�x�`2019�N�x�̂T�N�Ԃɘj���āA�O�q�̕\�P�W��(�A�j�`
�i�L�j�Ɏ�������^�g���b�N�́uNO���K���v�Ɓu�R���v�̋����Ɋւ��鋕�U�̋Z�p���𐢊ԂɊg�U�E�Z�������銈��
��ϋɓI�ɍs�����̂Ɛ��������B�����āA��^�g���b�N�̎g�p�ߒ��Ԃ́u�m�n����0.23�@g/kWh ��NO���K���v�Ɓu2015�N
�x�d�ʎԔR������{10�����x�̔R�����v�̋K�������̎��{���C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓�
�����̏��ł���2024�N5��25���ȍ~�ɐ扄����}��g���H���O�ꂵ�Đ��s�������̂Ɨ\�������B
��j�̌���������^���ꂽ����c��w�E�吹�G�����A�c����w�E�ѓc�P�������A����c��w�E���� �m�������܂ނV
�U�����̑����̑�w�̋�������̂Ƃ��������҂́A2014�N�x�`2019�N�x�̂T�N�Ԃɘj���āA�O�q�̕\�P�W��(�A�j�`
�i�L�j�Ɏ�������^�g���b�N�́uNO���K���v�Ɓu�R���v�̋����Ɋւ��鋕�U�̋Z�p���𐢊ԂɊg�U�E�Z�������銈��
��ϋɓI�ɍs�����̂Ɛ��������B�����āA��^�g���b�N�̎g�p�ߒ��Ԃ́u�m�n����0.23�@g/kWh ��NO���K���v�Ɓu2015�N
�x�d�ʎԔR������{10�����x�̔R�����v�̋K�������̎��{���C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓�
�����̏��ł���2024�N5��25���ȍ~�ɐ扄����}��g���H���O�ꂵ�Đ��s�������̂Ɨ\�������B
�@���̌��ʂƂ��āA���̂V�U�����̑����̑�w�̋�������̂Ƃ��������҂ɂ���^�g���b�N�́u�m�n����0.23�@g/kWh ��
NO���K���v�Ɓu2015�N�x�d�ʎԔR������{10�����x�̔R�����v�̋K��������2024�N5��25���ȍ~�ւ̐摗��
�̊����E�H�삪���������ꍇ�ɂ́A���{�̍����́A��^�g���b�N�̕���ɂ�����ȃG�l���M�[���C�����P�̗�
�v�E�K���𑁊��ɋ���ł��錠����r�����邱�ƂɂȂ�ƍl������B���̂��Ƃ́A�����ԃ��[�J���玩���ԗp���R�@
�Z�p�����g���iAICE�j��Ȋw�Z�p�U���@�\�i�i�r�s�j����Č���������^���ꂽ�V�U�����̑����̒����ȑ�w����
����̂Ƃ��������ҏW�c�̔��Љ�I�ȍs�ׂ�����Ĉ����N������Ă��鎖�ۂ̗l�ɂ��v���邪�A����͕M�҂̕Ό���
���낤���B
NO���K���v�Ɓu2015�N�x�d�ʎԔR������{10�����x�̔R�����v�̋K��������2024�N5��25���ȍ~�ւ̐摗��
�̊����E�H�삪���������ꍇ�ɂ́A���{�̍����́A��^�g���b�N�̕���ɂ�����ȃG�l���M�[���C�����P�̗�
�v�E�K���𑁊��ɋ���ł��錠����r�����邱�ƂɂȂ�ƍl������B���̂��Ƃ́A�����ԃ��[�J���玩���ԗp���R�@
�Z�p�����g���iAICE�j��Ȋw�Z�p�U���@�\�i�i�r�s�j����Č���������^���ꂽ�V�U�����̑����̒����ȑ�w����
����̂Ƃ��������ҏW�c�̔��Љ�I�ȍs�ׂ�����Ĉ����N������Ă��鎖�ۂ̗l�ɂ��v���邪�A����͕M�҂̕Ό���
���낤���B
�@���̂悤�ɁA�����ԃ��[�J��̂Őݗ����ꂽ���ԑg�D�̎����ԗp���R�@�Z�p�����g���iAICE�j���Ȋw�Z�p�U���@
�\�i�i�r�s�j������^����헪�I�C�m�x�[�V�����n���v���O�����i�r�h�o�j�̌�����́A���{�̑�^�g���b�N�ɂ�����uNO��
�K���̋����v��u�R��K���̋����v��2024�N5���ȍ~�ɒx�������锽�Љ�I�ȖړI���m���Ɏ������邽�߂ɁA���{��
�V�U�����̑����̑�w�������̌����҂Ɏx������Ă���\��������ƍl������B���̐헪�I�C�m�x�[�V�����n���v
���O�����i�r�h�o�j�̌�����̂Q�^�R�́A�O�q�̕\�P�R�Ɏ������悤�ɁA�o�ώY�ƏȂ̕⏕���ł���B���������āA���ɁA��
�ꂪ�����ł���A�o�ώY�ƏȂ́A��^�g���b�N�́uNO���K���̋����v��u�R��K���̋����v��2024�N5���ȍ~�ɒx��
�����鍑���̕s���v��]����������{��ɋM�d�Ȑ��{�\�Z�𓊓����Ă��邱�ƂɂȂ�ƍl������B�܂�A���̏ꍇ
�ɂ́A�o�ώY�ƏȂ́A�����ԃ��[�J��̖̂��ԑg�D�̔��Љ�I�Ȋ����̕Ж_��S���ł���ƌ��邱�Ƃ��\�ł���B
�\�i�i�r�s�j������^����헪�I�C�m�x�[�V�����n���v���O�����i�r�h�o�j�̌�����́A���{�̑�^�g���b�N�ɂ�����uNO��
�K���̋����v��u�R��K���̋����v��2024�N5���ȍ~�ɒx�������锽�Љ�I�ȖړI���m���Ɏ������邽�߂ɁA���{��
�V�U�����̑����̑�w�������̌����҂Ɏx������Ă���\��������ƍl������B���̐헪�I�C�m�x�[�V�����n���v
���O�����i�r�h�o�j�̌�����̂Q�^�R�́A�O�q�̕\�P�R�Ɏ������悤�ɁA�o�ώY�ƏȂ̕⏕���ł���B���������āA���ɁA��
�ꂪ�����ł���A�o�ώY�ƏȂ́A��^�g���b�N�́uNO���K���̋����v��u�R��K���̋����v��2024�N5���ȍ~�ɒx��
�����鍑���̕s���v��]����������{��ɋM�d�Ȑ��{�\�Z�𓊓����Ă��邱�ƂɂȂ�ƍl������B�܂�A���̏ꍇ
�ɂ́A�o�ώY�ƏȂ́A�����ԃ��[�J��̖̂��ԑg�D�̔��Љ�I�Ȋ����̕Ж_��S���ł���ƌ��邱�Ƃ��\�ł���B
�@�܂��A����͕M�҂̕Ό������m��Ȃ����A���ԑg�D(�������ԃ��[�J��̂̑g�D�j�̎����ԗp���R�@�Z�p�����g
���iAICE�j�����肵���헪�I�C�m�x�[�V�����n���v���O�����i�r�h�o�j�ɂ��V�U�����̑����̑�w�������̌����҂ւ̌�
����̎x���́A��^�g���b�N�́uNO���K���̋����v��u�R��K���̋����v��2024�N5���ȍ~�ɒx�������邱�Ƃ��^�̖ړI
�ł���悤�Ɏv���Ďd�����Ȃ��̂ł���B���̂��Ƃ́A�f�B�[�[���g���b�N�ɔ�ׂĎ����s��d�� �ԃ��[�h�R��R�O��
�O�����錇�ׂ̂��߂ɓV�R�K�X�i���G�l���M�[�����j��Q���u�I�b�g�[�T�C�N���̃X�p�[�N�v���O�����V�R �K�X
�G���W���𓋍ڂ����V�R�K�X��ăg���b�N�v���u�G�R�g���b�N�v�ł���Ƃ̓��{�̃G���W���W�̊w�ҁE���Ƃ����U�̔�
�\�ӓI�ɍs�������Ă������ʁA�P�X�X�O�N��̏����̍����猻�݂܂ł̓�\���N�Ԃɘj���ĉ��X�ƁA���{(�����y
��ʏȓ��j���V�R�K�X�̃G�l���M�[�����̘Q��𑣐i���邽�߂ɑ��z�̕⏕���i���G�R���W�[�ɔ�����⏕���j���x
�����Ă����u�ŋ��̖��ʌ����v�Ɖ]�����Љ�I�s�ׂ̎��ۂɍ������Ă���悤�Ɏv�����A�@���Ȃ��̂ł��낤���B
���iAICE�j�����肵���헪�I�C�m�x�[�V�����n���v���O�����i�r�h�o�j�ɂ��V�U�����̑����̑�w�������̌����҂ւ̌�
����̎x���́A��^�g���b�N�́uNO���K���̋����v��u�R��K���̋����v��2024�N5���ȍ~�ɒx�������邱�Ƃ��^�̖ړI
�ł���悤�Ɏv���Ďd�����Ȃ��̂ł���B���̂��Ƃ́A�f�B�[�[���g���b�N�ɔ�ׂĎ����s��d�� �ԃ��[�h�R��R�O��
�O�����錇�ׂ̂��߂ɓV�R�K�X�i���G�l���M�[�����j��Q���u�I�b�g�[�T�C�N���̃X�p�[�N�v���O�����V�R �K�X
�G���W���𓋍ڂ����V�R�K�X��ăg���b�N�v���u�G�R�g���b�N�v�ł���Ƃ̓��{�̃G���W���W�̊w�ҁE���Ƃ����U�̔�
�\�ӓI�ɍs�������Ă������ʁA�P�X�X�O�N��̏����̍����猻�݂܂ł̓�\���N�Ԃɘj���ĉ��X�ƁA���{(�����y
��ʏȓ��j���V�R�K�X�̃G�l���M�[�����̘Q��𑣐i���邽�߂ɑ��z�̕⏕���i���G�R���W�[�ɔ�����⏕���j���x
�����Ă����u�ŋ��̖��ʌ����v�Ɖ]�����Љ�I�s�ׂ̎��ۂɍ������Ă���悤�Ɏv�����A�@���Ȃ��̂ł��낤���B
�P�P�D��C�����P�ƏȃG�l�̂��߂̑�^�g���b�N�́uNO���K���v�Ɓu�R���v�̑��}�ȋ���
�@�킪���ɂ������^�g���b�N�̌p�����Y�Ԃ́u2015�N�x�d�ʎԔR������{10�����x�̔R�����v�Ɓu�m�n����0.
23�@g/kWh ��NO���K���v�̃��x���i���K���l�j�̋K��������2020�N���ɗe�ՂɎ����ł����C���x�~�G���W���i������
�J2005-54771�j�̋Z�p�������_�i��2014�N12�����݁j�ŗ�R�Ƒ��݂���ɂ�������炸�A�����̋K��������202�S�N
�T���ȍ~�ɐ摗�肵�Ď��{����邱�ƂɂȂ����ꍇ�ɂ́A�����ԃ��[�J�i���g���b�N���[�J�j�̂ɂ�鎩���ԗp���R�@��
�Z�p�����g���i���`�h�b�d�j�����2014�N�x�`2019�N�x�̂T�N�Ԃɘj��d�G�Ǝv����������̕s���H�ȃo���}�L�H��
�����������ꍇ�̌��ʂ����m��Ȃ��B���̏ꍇ�ɂ́A���Ȃ̎����Ԕr�o�K�X���ψ��ψ���ƍ��y��ʏȂ̎�
���ԔR�����ψ���̃G���W�����̑����W���̊w�ҁE���Ƃ̗���s�ׂɂ���āA�����Ȃƍ��y��ʏȂ�
�����̐l�B�����{�̑�^�g���b�N�ɂ�����uNO���팸�v�Ɓu�R����P�v�̐i�W��傫���j�Q������Ɖ]�����Љ�I�ȍs��
�̕Ж_��S�����ꂽ�ƌ��邱�Ƃ��\�ł���B�����āA���̏ꍇ�ɂ́A���Ȃƍ��y��ʏȂ̊����̐l�B�����ʓI��
������n���ɂ��Ă��邱�ƂɂȂ�A�ŋ���K���Ŕ[�߂Ă��鍑���ɂƂ��Ă͉��Ƃ�����Ȃ����Ƃł���B
23�@g/kWh ��NO���K���v�̃��x���i���K���l�j�̋K��������2020�N���ɗe�ՂɎ����ł����C���x�~�G���W���i������
�J2005-54771�j�̋Z�p�������_�i��2014�N12�����݁j�ŗ�R�Ƒ��݂���ɂ�������炸�A�����̋K��������202�S�N
�T���ȍ~�ɐ摗�肵�Ď��{����邱�ƂɂȂ����ꍇ�ɂ́A�����ԃ��[�J�i���g���b�N���[�J�j�̂ɂ�鎩���ԗp���R�@��
�Z�p�����g���i���`�h�b�d�j�����2014�N�x�`2019�N�x�̂T�N�Ԃɘj��d�G�Ǝv����������̕s���H�ȃo���}�L�H��
�����������ꍇ�̌��ʂ����m��Ȃ��B���̏ꍇ�ɂ́A���Ȃ̎����Ԕr�o�K�X���ψ��ψ���ƍ��y��ʏȂ̎�
���ԔR�����ψ���̃G���W�����̑����W���̊w�ҁE���Ƃ̗���s�ׂɂ���āA�����Ȃƍ��y��ʏȂ�
�����̐l�B�����{�̑�^�g���b�N�ɂ�����uNO���팸�v�Ɓu�R����P�v�̐i�W��傫���j�Q������Ɖ]�����Љ�I�ȍs��
�̕Ж_��S�����ꂽ�ƌ��邱�Ƃ��\�ł���B�����āA���̏ꍇ�ɂ́A���Ȃƍ��y��ʏȂ̊����̐l�B�����ʓI��
������n���ɂ��Ă��邱�ƂɂȂ�A�ŋ���K���Ŕ[�߂Ă��鍑���ɂƂ��Ă͉��Ƃ�����Ȃ����Ƃł���B
�@���̂悤�ȏɊׂ�Ȃ����߂ɂ́A�S�`�T�N���ȑO������Ȃ̎����Ԕr�o�K�X���ψ��ψ���ƍ��y��ʏȂ�
�����ԔR�����ψ���̃G���W�����̑����W���̊w�ҁE���Ƃƃg���b�N���[�J�Ƃ��������Ď��s����Ă���Ɛ�
��������^�g���b�N�́uNO���팸�v�Ɓu�R����P�v�ɗL�����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p��
���E�َE��������B���H����A���l�̐E�ӂ�S������ӗ~�ɖ�����ꂽ�D�G�Ȋ��Ȃƍ��y��ʏȂ̊����̐l�B��
�o���邾�������ɒ��~�E���f�����邱�Ƃ��B�����āA���Ȃƍ��y��ʏȂ́A���{�̍����̗��v�ɑ�������^�g��
�b�N�̌p�����Y�Ԃ��u2015�N�x�d�ʎԔR�������{10�����x�̔R����P�v���u�m�n����0.23�@g/kWh ��NO��
�K���v�̋K��������2020�N���Ɏ��{���邱�Ƃ��ƍl������B
�����ԔR�����ψ���̃G���W�����̑����W���̊w�ҁE���Ƃƃg���b�N���[�J�Ƃ��������Ď��s����Ă���Ɛ�
��������^�g���b�N�́uNO���팸�v�Ɓu�R����P�v�ɗL�����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p��
���E�َE��������B���H����A���l�̐E�ӂ�S������ӗ~�ɖ�����ꂽ�D�G�Ȋ��Ȃƍ��y��ʏȂ̊����̐l�B��
�o���邾�������ɒ��~�E���f�����邱�Ƃ��B�����āA���Ȃƍ��y��ʏȂ́A���{�̍����̗��v�ɑ�������^�g��
�b�N�̌p�����Y�Ԃ��u2015�N�x�d�ʎԔR�������{10�����x�̔R����P�v���u�m�n����0.23�@g/kWh ��NO��
�K���v�̋K��������2020�N���Ɏ��{���邱�Ƃ��ƍl������B
�@���łɐ\���グ��ƁA�Q�O�P�U�N�R���R���ɍ��y��ʏȂ́A�N���[���f�B�[�[���G���W�������ڂƐ�`���Ďs�̂����
���錻�s�̃����h�N���[�U�[�E�v���h�i�g���^�j�̃f�B�[�[���Ԃ́A�����ߍx�̓~��̂P�O���ߖT�ȉ��ł̘H�㑖�s�ł�
�ی쐧��\�t�g�ɂ���Ăm�n���팸���u���~�����邽�߂ɂm�n���K���l�̂Q�D�X�{�`�P�Q�D�V�{�̍��Z�x�̂m�n���𐂂ꗬ
�����ׁH�̂��邱�Ƃ\�����B�������A�������ƂɁA���y��ʏȂ́A���̓~��̘H�㑖�s�łm�n���𐂂ꗬ�������h�N��
�[�U�[�E�v���h�i�g���^�j�̃f�B�[�[���Ԃ��G�R�J�[���ł̐��{�̗D������č�����s�̂��邱�Ƃ����F���Ă���悤
�ł���B
���錻�s�̃����h�N���[�U�[�E�v���h�i�g���^�j�̃f�B�[�[���Ԃ́A�����ߍx�̓~��̂P�O���ߖT�ȉ��ł̘H�㑖�s�ł�
�ی쐧��\�t�g�ɂ���Ăm�n���팸���u���~�����邽�߂ɂm�n���K���l�̂Q�D�X�{�`�P�Q�D�V�{�̍��Z�x�̂m�n���𐂂ꗬ
�����ׁH�̂��邱�Ƃ\�����B�������A�������ƂɁA���y��ʏȂ́A���̓~��̘H�㑖�s�łm�n���𐂂ꗬ�������h�N��
�[�U�[�E�v���h�i�g���^�j�̃f�B�[�[���Ԃ��G�R�J�[���ł̐��{�̗D������č�����s�̂��邱�Ƃ����F���Ă���悤
�ł���B
�@���݂ɁA���B�̃f�B�[�[�������Ԃł́A�Q�O�P�V�N�X���ɂ́u�H�㑖�s��NOx�r�o�l����㎎����NOx��l�̂Q�D�P
�{�ȓ��v�̘H�㑖�s��NOx�r�o�l�ɋK������\������ɔ��\���Ă���B�������A�����V���f�W�^���̂Q�O�P�U�N�R���T��
�̕��L���ɂ��ƁA���{�̍��y��ʏȂ́A���ꂩ��T�N��i���Q�O�Q�P�N�Q�����H�j�ɉ��B�Ɠ��l�̃f�B�[�[��������
�ł̘H�㑖�s��NOx�r�o�l�̋K�����{���������n�߂��悤�ł���B���ꂪ�����ł���A�����ߍx�̓~��̂P�O����
�T�ȉ��ł̘H�㑖�s�łm�n���K���l�̂Q�D�X�{�`�P�Q�D�V�{�̍��Z�x�̂m�n���̐��ꗬ���̌��ׂ����P���������h�N���[
�U�[�E�v���h�i�g���^�j�̃f�B�[�[���Ԃ́A�Q�O�Q�P�N�Q�����ɂȂ�܂ŁA���{�ł͎s�̂���Ȃ��\��������ƍl������B
����́A�g���^�����Ԃ������h�N���[�U�[�E�v���h�i�g���^�j�̃f�B�[�[���Ԃ̘H�㑖�s�ł̍��Z�x�̂m�n���̐��ꗬ���̌�
�ׂ����P�ł���Z�p�����J���ƁA���y��ʏȂ��F�����Ă��邽�߂ł��낤���B
�{�ȓ��v�̘H�㑖�s��NOx�r�o�l�ɋK������\������ɔ��\���Ă���B�������A�����V���f�W�^���̂Q�O�P�U�N�R���T��
�̕��L���ɂ��ƁA���{�̍��y��ʏȂ́A���ꂩ��T�N��i���Q�O�Q�P�N�Q�����H�j�ɉ��B�Ɠ��l�̃f�B�[�[��������
�ł̘H�㑖�s��NOx�r�o�l�̋K�����{���������n�߂��悤�ł���B���ꂪ�����ł���A�����ߍx�̓~��̂P�O����
�T�ȉ��ł̘H�㑖�s�łm�n���K���l�̂Q�D�X�{�`�P�Q�D�V�{�̍��Z�x�̂m�n���̐��ꗬ���̌��ׂ����P���������h�N���[
�U�[�E�v���h�i�g���^�j�̃f�B�[�[���Ԃ́A�Q�O�Q�P�N�Q�����ɂȂ�܂ŁA���{�ł͎s�̂���Ȃ��\��������ƍl������B
����́A�g���^�����Ԃ������h�N���[�U�[�E�v���h�i�g���^�j�̃f�B�[�[���Ԃ̘H�㑖�s�ł̍��Z�x�̂m�n���̐��ꗬ���̌�
�ׂ����P�ł���Z�p�����J���ƁA���y��ʏȂ��F�����Ă��邽�߂ł��낤���B
�@�Ƃ��낪�A���̌��s�̃����h�N���[�U�[�E�v���h�i�g���^�j�̃f�B�[�[���Ԃ��C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j��
�����Z�p���̗p�����ꍇ�ɂ́A�~��̘H�㑖�s�ō��Z�x�̂m�n���̐��ꗬ�����ׂ�e�Ղɉ��P���邱�Ƃ��\�ł�
��B�܂�A�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p���̗p���������h�N���[�U�[�E�v���h�i�g���^�j�̃f�B�[
�[���Ԃ́A�~��̘H�㑖�s�ɂ����Ă��A�m�n���K���l�̃N���[���Ȃm�n���r�o��Ԃł̂̉^�q���\�ɂȂ�B����ɂ�
���ẮA�C���x�~�́A�v���h�i����j�ި���َԂ̓~��̂m�n�����ꗬ���̌��ׂ����P�ɏڏq���Ă���̂ŁA�����̂����
�́A�䗗�������������B
�����Z�p���̗p�����ꍇ�ɂ́A�~��̘H�㑖�s�ō��Z�x�̂m�n���̐��ꗬ�����ׂ�e�Ղɉ��P���邱�Ƃ��\�ł�
��B�܂�A�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p���̗p���������h�N���[�U�[�E�v���h�i�g���^�j�̃f�B�[
�[���Ԃ́A�~��̘H�㑖�s�ɂ����Ă��A�m�n���K���l�̃N���[���Ȃm�n���r�o��Ԃł̂̉^�q���\�ɂȂ�B����ɂ�
���ẮA�C���x�~�́A�v���h�i����j�ި���َԂ̓~��̂m�n�����ꗬ���̌��ׂ����P�ɏڏq���Ă���̂ŁA�����̂����
�́A�䗗�������������B
�@��L�̖{�����Ō�蓙���������܂�����A���[�����ɂĂ��w�E�������܂��B�܂��A�^��_�A������A�䊴�z���A�ǂ̂�
���Ȏ����ł����\�ł��B�Ջ��l�i���M�ҁj���ĂɃ��[���������肢��������A�o����͈͂őΉ������Ă���������
���B
���Ȏ����ł����\�ł��B�Ջ��l�i���M�ҁj���ĂɃ��[���������肢��������A�o����͈͂őΉ������Ă���������
���B

|