�Ջ��l�̃A�C�f�A
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�g�b�v�y�[�W�ɖ߂��@�@�@�@�@�@�T�C�g�}�b�v
�ŏI�X�V���F201�S�N2��2��
 |
�P�@�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̗̍p�ɂ��f�B�[�[���G���W���̎�ȉ��P
�@���݁A�킪���̑�^�g���b�N�ɂ��āA���Ȃ⍑�y��ʏȂ́ANO�� �� 0.�S g/kWh��NO���K�������i��2016�N���{
�\��j��A2015�N�x�d�ʎԔR���̋������������ł���B�܂��A�g���b�N���[�U�̓g���b�N�̉^�s�̒��f���������
��D�o�e�̎蓮�Đ��̔p�~���������߂Ă���A����ɂ��Ă͓��{�g���b�N������y��ʏȂɋ����v�]���Ă���Ƃ���
�ł���B���̂��Ƃ���A�����_�ő��}�ɉ����E�������K�v�ȑ�^�g���b�N�̉ۑ�́A�f�B�[�[���G���W���ɂ�����u�G���W
���̒ᕉ���i���r�C�K�X���x�̒ቷ���j�ɂ�����A�f�r�b�q�G�}��NOx�팸���̌���v�A�u�R����P�v����сu�c�o�e��
�����Đ��p�x�̌����v�ł��邱�Ƃ������ł���B
�\��j��A2015�N�x�d�ʎԔR���̋������������ł���B�܂��A�g���b�N���[�U�̓g���b�N�̉^�s�̒��f���������
��D�o�e�̎蓮�Đ��̔p�~���������߂Ă���A����ɂ��Ă͓��{�g���b�N������y��ʏȂɋ����v�]���Ă���Ƃ���
�ł���B���̂��Ƃ���A�����_�ő��}�ɉ����E�������K�v�ȑ�^�g���b�N�̉ۑ�́A�f�B�[�[���G���W���ɂ�����u�G���W
���̒ᕉ���i���r�C�K�X���x�̒ቷ���j�ɂ�����A�f�r�b�q�G�}��NOx�팸���̌���v�A�u�R����P�v����сu�c�o�e��
�����Đ��p�x�̌����v�ł��邱�Ƃ������ł���B
�@���̂悤�Ȍ��݂̑�^�g���b�N�ɂ�����ۑ�́A��^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W�����C���x�~�G���W���i�������J
2005-54771�j�̓����Z�p���̗p���邱�Ƃɂ��A�����ɉ����E�������邱�Ƃ��e�Ղɉ\�ł���B���̗��R�́A�C���x
�~�G���W���ɂ���^�g���b�N�̒�R��A�C���x�~�́A�f�B�[�[���̂m�n���팸�ƔR�����̈ꋓ�����̋Z�p���I�A
������C���x�~��DPF�̎��ȍĐ��𑣐i (�����Đ��̍팸�ŔR�����h�~�j�̃y�[�W�ɏڏq���Ă���̂ŁA������
�͏ȗ����邱�Ƃɂ���B�����̂�����́A�ȏ�̃y�[�W��Ƃ��������������B
2005-54771�j�̓����Z�p���̗p���邱�Ƃɂ��A�����ɉ����E�������邱�Ƃ��e�Ղɉ\�ł���B���̗��R�́A�C���x
�~�G���W���ɂ���^�g���b�N�̒�R��A�C���x�~�́A�f�B�[�[���̂m�n���팸�ƔR�����̈ꋓ�����̋Z�p���I�A
������C���x�~��DPF�̎��ȍĐ��𑣐i (�����Đ��̍팸�ŔR�����h�~�j�̃y�[�W�ɏڏq���Ă���̂ŁA������
�͏ȗ����邱�Ƃɂ���B�����̂�����́A�ȏ�̃y�[�W��Ƃ��������������B
�Q�@�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�ɂ���ި���ق̺�����Ď���NO���팸
�Q�|�P�@���s�̃f�B�[�[���G���W���̃R�[���h�X�^�[�g�r�o�K�X�����ɂ�����NO�������̌���
�@2012�N11��6���A7���ɊJ�Â��ꂽ�u�i�Ɓj��ʈ��S���������t�H�[����2012�v�ɂ����Ĕ��\���ꂽ�u�A �A�fSCR�V
�X�e�����ډݕ��Ԃ̘H�㑖�s���ɂ�����NO���ANH�R,�����N�QO�̔r�o���� [���ҁF�R�{ �q�N�E�� ��q�i��������
��j�E��c �P�v�E���� ���O�i��c�d�Ɓj ���� �T�i���{MKS�j�Ahttp://www.ntsel.go.jp/forum/2012files/pt_02.pdf]�̘_
���ł́A�ȉ��̐}�P�Ɏ������悤�ɁA���s�̃f�B�[�[���G���W���ɂ�����JE05���[�h���R�[���h�X�^�[�g�r�o�K�X������
�z�b�g�^�[�g�r�o�K�X�����̎������ɂ�����uNO���̔r�o�l�v�Ɓu�r�C�Ǐo���K�X���x�v�̎������ʂ�������Ă���B��
�����̂��A�ł���B
�X�e�����ډݕ��Ԃ̘H�㑖�s���ɂ�����NO���ANH�R,�����N�QO�̔r�o���� [���ҁF�R�{ �q�N�E�� ��q�i��������
��j�E��c �P�v�E���� ���O�i��c�d�Ɓj ���� �T�i���{MKS�j�Ahttp://www.ntsel.go.jp/forum/2012files/pt_02.pdf]�̘_
���ł́A�ȉ��̐}�P�Ɏ������悤�ɁA���s�̃f�B�[�[���G���W���ɂ�����JE05���[�h���R�[���h�X�^�[�g�r�o�K�X������
�z�b�g�^�[�g�r�o�K�X�����̎������ɂ�����uNO���̔r�o�l�v�Ɓu�r�C�Ǐo���K�X���x�v�̎������ʂ�������Ă���B��
�����̂��A�ł���B
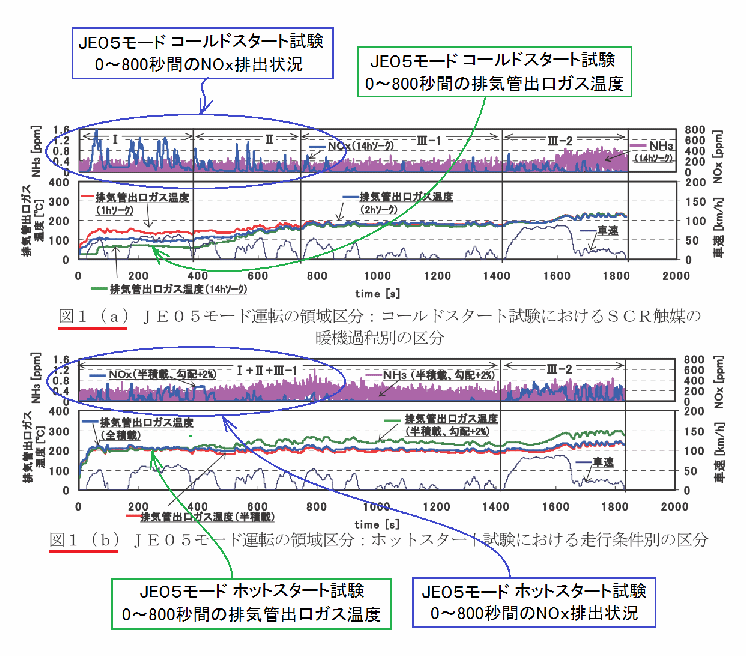 |
�@�����}�P���疾�炩�̂悤�ɁA�f�B�[�[���G���W����JE�O�T���[�h�̃z�b�g�X�^�[�g�����ł́A�����̊J�n��̋͂�30
�`40�b��ɂ͔r�C�Ǐo���K�X���x��200���ɏ㏸���Ă���B�������AJE�O�T���[�h�ł̃R�[���h�X�^�[�g�����̔r�C�Ǐo
���K�X���x���z�b�g�X�^�[�g������200�����x���ɓ��B����̂́A�����̊J�n���800�b��i����13��20�b��j�ł���B
���ɁAJE�O�T���[�h�̃R�[���h�X�^�[�g�����ɂ����ẮA�����̊J�n�ォ��400�b�܂ł̊��Ԃł́A�r�C�Ǐo���K�X��
�x��20�`70���̒ቷ��ԂɊׂ��Ă��܂��Ă���悤���B�����āA�R�[���h�X�^�[�g�����ɂ����ẮA�r�C�Ǐo���K�X���x
���z�b�g�X�^�[�g�����Ɠ������x����200���ɓ��B����܂ł̊��ԁi�������J�n����800�b���o�߂���܂ł̊��ԁj��
�́A�z�b�g�X�^�[�g�����ɔ�r���ċɂ߂č���NOx�r�o�ƂȂ��Ă��邱�Ƃ��ώ@�����B
�`40�b��ɂ͔r�C�Ǐo���K�X���x��200���ɏ㏸���Ă���B�������AJE�O�T���[�h�ł̃R�[���h�X�^�[�g�����̔r�C�Ǐo
���K�X���x���z�b�g�X�^�[�g������200�����x���ɓ��B����̂́A�����̊J�n���800�b��i����13��20�b��j�ł���B
���ɁAJE�O�T���[�h�̃R�[���h�X�^�[�g�����ɂ����ẮA�����̊J�n�ォ��400�b�܂ł̊��Ԃł́A�r�C�Ǐo���K�X��
�x��20�`70���̒ቷ��ԂɊׂ��Ă��܂��Ă���悤���B�����āA�R�[���h�X�^�[�g�����ɂ����ẮA�r�C�Ǐo���K�X���x
���z�b�g�X�^�[�g�����Ɠ������x����200���ɓ��B����܂ł̊��ԁi�������J�n����800�b���o�߂���܂ł̊��ԁj��
�́A�z�b�g�X�^�[�g�����ɔ�r���ċɂ߂č���NOx�r�o�ƂȂ��Ă��邱�Ƃ��ώ@�����B
�@���݂ɁA�A�fSCR�G�}�́A�G�}���x��180�`200���ȉ��ł͐G�}�̊������������ቺ���A�A�f�ɂ��NO���̊Ҍ���
���Ⴂ�l�ƂȂ��Ă��܂�����������B����A�R�[���h�X�^�[�g�����ɂ����ẮA�r�C�Ǐo���K�X���x���z�b�g�X�^�[�g��
���Ɠ������x����200���ɓ��B����܂ł̊��ԁi�������J�n����800�b���o�߂���܂ł̊��ԁj�ł́A�z�b�g�X�^�[�g��
���ɔ�r���ĔA�fSCR�G�}�̐G�}���x���������ቺ���邽�߁A�ɂ߂č���NOx�r�o�ƂȂ��Ă���Ɛ��������B���̂�
���ɁA�R�[���h�X�^�[�g�����ɂ����ẮA�����J�n����800�b���o�߂���܂ł̊��Ԃł́A�r�C�Ǐo���K�X���x�̒ቺ
�ɂ���ĔA�fSCR�G�}�̐G�}���x���ቷ�ƂȂ邽�߂ɁA����NOx�r�o�l���v���������̂ƍl������B���������āA
�R�[���h�X�^�[�g�����̎����J�n����800�b���o�߂���܂ł̊��Ԃɂ����鍂��NOx�r�o�l���팸���邽�߂ɂ́A�R�[
���h�X�^�[�g�����̎����J�n����Z���ԂŔA�fSCR�G�}�̐G�}���x������������Z�p���J�����邱�Ƃ��A�f�B�[�[��
�G���W����JE�O�T���[�h�̃R�[���h�X�^�[�g�����ɂ�����NO���팸�ɂ͕K�{�ƂȂ�B
���Ⴂ�l�ƂȂ��Ă��܂�����������B����A�R�[���h�X�^�[�g�����ɂ����ẮA�r�C�Ǐo���K�X���x���z�b�g�X�^�[�g��
���Ɠ������x����200���ɓ��B����܂ł̊��ԁi�������J�n����800�b���o�߂���܂ł̊��ԁj�ł́A�z�b�g�X�^�[�g��
���ɔ�r���ĔA�fSCR�G�}�̐G�}���x���������ቺ���邽�߁A�ɂ߂č���NOx�r�o�ƂȂ��Ă���Ɛ��������B���̂�
���ɁA�R�[���h�X�^�[�g�����ɂ����ẮA�����J�n����800�b���o�߂���܂ł̊��Ԃł́A�r�C�Ǐo���K�X���x�̒ቺ
�ɂ���ĔA�fSCR�G�}�̐G�}���x���ቷ�ƂȂ邽�߂ɁA����NOx�r�o�l���v���������̂ƍl������B���������āA
�R�[���h�X�^�[�g�����̎����J�n����800�b���o�߂���܂ł̊��Ԃɂ����鍂��NOx�r�o�l���팸���邽�߂ɂ́A�R�[
���h�X�^�[�g�����̎����J�n����Z���ԂŔA�fSCR�G�}�̐G�}���x������������Z�p���J�����邱�Ƃ��A�f�B�[�[��
�G���W����JE�O�T���[�h�̃R�[���h�X�^�[�g�����ɂ�����NO���팸�ɂ͕K�{�ƂȂ�B
�@�����Ƃ��A���s�̔A�fSCR�G�}�ɂ�����180�`200���̐G�}�����̒ቺ���鉷�x���X�ɒቷ�����邱�Ƃ��\�ƂȂ�
�A�f�B�[�[���G���W���̃R�[���h�X�^�[�g�����ɂ�����NO���팸�͉\�ƂȂ邪�A�߂������ɒቷ���ł��G�}������
�啝�ɍ��߂��A�fSCR�G�}��V���ɊJ���ł���ۏ͖w��ǖ����ƍl������B���̂��߁A�펯�̂���w�ҁE���
�ƁE�Z�p�҂́A�f�B�[�[���G���W���̃R�[���h�X�^�[�g�����ɂ�����NO���팸��ړI�Ƃ���ꍇ�ɂ́A�r�C�K�X���x��
���������ɂ��R�[���h�X�^�[�g�����̎����J�n����Z���ԂŔA�fSCR�G�}�̐G�}���x������������Z�p���J����
�邱�Ƃ��ŗD�悷�ׂ��ƍl����B�Ȃ��Ȃ�A���ɔA�fSCR�G�}�̒ቷ�������̋Z�p�J���ɐ��������Ƃ��Ă��A���s��
����[10�`-20�����x�̒ቷ����}�����x�ł���A�R�[���h�X�^�[�g�����ɂ�����NO���팸�͋͂��ɉ߂��Ȃ��Ɛ���
����邽�߂ł���B
�A�f�B�[�[���G���W���̃R�[���h�X�^�[�g�����ɂ�����NO���팸�͉\�ƂȂ邪�A�߂������ɒቷ���ł��G�}������
�啝�ɍ��߂��A�fSCR�G�}��V���ɊJ���ł���ۏ͖w��ǖ����ƍl������B���̂��߁A�펯�̂���w�ҁE���
�ƁE�Z�p�҂́A�f�B�[�[���G���W���̃R�[���h�X�^�[�g�����ɂ�����NO���팸��ړI�Ƃ���ꍇ�ɂ́A�r�C�K�X���x��
���������ɂ��R�[���h�X�^�[�g�����̎����J�n����Z���ԂŔA�fSCR�G�}�̐G�}���x������������Z�p���J����
�邱�Ƃ��ŗD�悷�ׂ��ƍl����B�Ȃ��Ȃ�A���ɔA�fSCR�G�}�̒ቷ�������̋Z�p�J���ɐ��������Ƃ��Ă��A���s��
����[10�`-20�����x�̒ቷ����}�����x�ł���A�R�[���h�X�^�[�g�����ɂ�����NO���팸�͋͂��ɉ߂��Ȃ��Ɛ���
����邽�߂ł���B
�Q�|�Q�@�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�ɂ��R�[���h�X�^�[�g��NO���팸
�@�f�B�[�[���G���W����JE�O�T���[�h�ł̃R�[���h�X�^�[�g�����̔r�C�Ǐo���K�X���x���z�b�g�X�^�[�g������200�����x
���ɓ��B����̂́A�����̊J�n���800�b��i����13��20�b��j�ł���B���̂��߁A�R�[���h�X�^�[�g�����ɂ����ẮA
�����J�n����800�b���o�߂���܂ł̊��Ԃł́A�z�b�g�X�^�[�g�����ɔ�r���ċɂ߂č���NOx�r�o�ƂȂ��Ă��邱�Ƃ�
�ώ@�����B �����ŁA���̃R�[���h�X�^�[�g�����ł�0�`800�b�̊��Ԃɂ����āA�A�fSCR�G�}�̉��x���}���ɍ�����
�ł���A�]���̃R�[���h�X�^�[�g�����ɂ����鍂��NOx�r�o�l���팸���邱�Ƃ��\�ɂȂ�B
���ɓ��B����̂́A�����̊J�n���800�b��i����13��20�b��j�ł���B���̂��߁A�R�[���h�X�^�[�g�����ɂ����ẮA
�����J�n����800�b���o�߂���܂ł̊��Ԃł́A�z�b�g�X�^�[�g�����ɔ�r���ċɂ߂č���NOx�r�o�ƂȂ��Ă��邱�Ƃ�
�ώ@�����B �����ŁA���̃R�[���h�X�^�[�g�����ł�0�`800�b�̊��Ԃɂ����āA�A�fSCR�G�}�̉��x���}���ɍ�����
�ł���A�]���̃R�[���h�X�^�[�g�����ɂ����鍂��NOx�r�o�l���팸���邱�Ƃ��\�ɂȂ�B
�@�Ƃ���ŁA�M�҂�2006�N4���ɊJ�݂����z�[���y�[�W�ɂ����āA�u�G���W���̒ᕉ���i���r�C�K�X���x�̒ቷ���j��
������A�f�r�b�q�G�}��NOx�팸���̌���v�A�u�d�ʎԃ��[�h�R���ю����s�R��̉��P�v����сu�c�o�e�̋����Đ�
�p�x�̌����v����^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W���̉ۑ�����������i�E���@�Ƃ��ĂQ�^�[�{�������C���x�~�G���W��
�i�������J2005-54771�j�̓����Z�p���Ă��Ă���B���̂Q�^�[�{�������C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j��
�����Z�p�́A�u�G���W���̒ᕉ���ɂ�����A�f�r�b�q�G�}��NOx�팸���̌���v�A�u�R����P�v����сu�c�o�e�̋�����
���p�x�̌����v�̑��ɂ��A�K�^�Ȃ��ƂɁA�f�B�[�[���G���W�����R�[���h�X�^�[�g�����ɂ����鍂��NOx�r�o�l���팸��
��@�\�������Ă���̂ł���B
������A�f�r�b�q�G�}��NOx�팸���̌���v�A�u�d�ʎԃ��[�h�R���ю����s�R��̉��P�v����сu�c�o�e�̋����Đ�
�p�x�̌����v����^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W���̉ۑ�����������i�E���@�Ƃ��ĂQ�^�[�{�������C���x�~�G���W��
�i�������J2005-54771�j�̓����Z�p���Ă��Ă���B���̂Q�^�[�{�������C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j��
�����Z�p�́A�u�G���W���̒ᕉ���ɂ�����A�f�r�b�q�G�}��NOx�팸���̌���v�A�u�R����P�v����сu�c�o�e�̋�����
���p�x�̌����v�̑��ɂ��A�K�^�Ȃ��ƂɁA�f�B�[�[���G���W�����R�[���h�X�^�[�g�����ɂ����鍂��NOx�r�o�l���팸��
��@�\�������Ă���̂ł���B
�@�����āA�����Q�^�[�{�������C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p���f�B�[�[���G���W�����R�[���h�X
�^�[�g������NOx�r�o�l�̍팸�ł��闝�R�́A�ȉ��̒ʂ�ł���B
�^�[�g������NOx�r�o�l�̍팸�ł��闝�R�́A�ȉ��̒ʂ�ł���B
�� JE�O�T���[�h�ł̃R�[���h�X�^�[�g�����ɂ����鍂��NOx�r�o�l���팸����0�`800�b�̊��Ԃł́A�ō��ԑ��� 50km
/h ���x�ł��邽�߁A�G���W���^�]�̕��וp�x�� 50 �� �ȉ����啔���ł���Ɛ��������B����A�Q�^�[�{�������C��
�x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�́A�f�B�[�[���G���W���̕��ׂ� 50 �� �ȉ��̉^�]�ł́A�r�C�K�X���x���]��
�̃G���W���̂Q�{���x�ɍ������ł��������Z�p�ł���B���̂悤�ɁA�Q�^�[�{�������C���x�~�G���W���i�������J2005-
54771�j�̓����Z�p���̗p�����f�B�[�[���G���W���ł́A�]���G���W���̂Q�{���x�̍����������r�C�K�X���x��JE�O�T
���[�h�̃R�[���h�X�^�[�g�������s�����Ƃ��ł��邽�߁A�A�fSCR�G�}�̋}���ȍ������ɂ��R�[���h�X�^�[�g������0
�`800�b�̊��Ԃɂ�����NO���̔r�o���팸���邱�Ƃ��\�ł���B
/h ���x�ł��邽�߁A�G���W���^�]�̕��וp�x�� 50 �� �ȉ����啔���ł���Ɛ��������B����A�Q�^�[�{�������C��
�x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�́A�f�B�[�[���G���W���̕��ׂ� 50 �� �ȉ��̉^�]�ł́A�r�C�K�X���x���]��
�̃G���W���̂Q�{���x�ɍ������ł��������Z�p�ł���B���̂悤�ɁA�Q�^�[�{�������C���x�~�G���W���i�������J2005-
54771�j�̓����Z�p���̗p�����f�B�[�[���G���W���ł́A�]���G���W���̂Q�{���x�̍����������r�C�K�X���x��JE�O�T
���[�h�̃R�[���h�X�^�[�g�������s�����Ƃ��ł��邽�߁A�A�fSCR�G�}�̋}���ȍ������ɂ��R�[���h�X�^�[�g������0
�`800�b�̊��Ԃɂ�����NO���̔r�o���팸���邱�Ƃ��\�ł���B
�� �Q�^�[�{�������C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�ł́A�]���G���W���̖��̋@�\�E�\�́E�e�ʂ��ߋ�
�@����єr�o�K�X�㏈�����u�i���_���G�}�A�A�fSCR�G�}�ADPF���u�j�����ɑ�������V�X�e���i���P��̃G���W��
�ɍ��v�A�Q�������V�X�e���j�ł���B����AJE�O�T���[�h�ł̃R�[���h�X�^�[�g�����ɂ����鍂��NOx�r�o�l���팸
����0�`800�b�̊��Ԃł́A�ō��ԑ��� 50km/h ���x�ł��邽�߁A�G���W���^�]�̕��וp�x�� 50 �� �ȉ����啔����
����Ɛ��������B���̂��߁A�R�[���h�X�^�[�g������0�`800�b�̊��Ԃł́A�����̋C���Q���x�~���A�Ε����̎c���
�����̋C���Q�ɂ��f�B�[�[���G���W�����^�]�����B���̂��߁A�Q�^�[�{�������C���x�~�G���W���i�������J2005-
54771�j���̗p�����f�B�[�[���G���W���ł́A�R�[���h�X�^�[�g������0�`800�b�̊��Ԃɂ����ẮA�]���G���W���̂Q�{
�̔r�C�K�X���x�ɂ���ď]���G���W���̖��̋@�\�E�\�́E�e�ʂ��ߋ��@����єr�o�K�X�㏈�����u�i���_���G
�}�A�A�fSCR�G�}�ADPF���u�j��r�C�K�X���x�ʼn��M���邱�ƂɂȂ�B
�@����єr�o�K�X�㏈�����u�i���_���G�}�A�A�fSCR�G�}�ADPF���u�j�����ɑ�������V�X�e���i���P��̃G���W��
�ɍ��v�A�Q�������V�X�e���j�ł���B����AJE�O�T���[�h�ł̃R�[���h�X�^�[�g�����ɂ����鍂��NOx�r�o�l���팸
����0�`800�b�̊��Ԃł́A�ō��ԑ��� 50km/h ���x�ł��邽�߁A�G���W���^�]�̕��וp�x�� 50 �� �ȉ����啔����
����Ɛ��������B���̂��߁A�R�[���h�X�^�[�g������0�`800�b�̊��Ԃł́A�����̋C���Q���x�~���A�Ε����̎c���
�����̋C���Q�ɂ��f�B�[�[���G���W�����^�]�����B���̂��߁A�Q�^�[�{�������C���x�~�G���W���i�������J2005-
54771�j���̗p�����f�B�[�[���G���W���ł́A�R�[���h�X�^�[�g������0�`800�b�̊��Ԃɂ����ẮA�]���G���W���̂Q�{
�̔r�C�K�X���x�ɂ���ď]���G���W���̖��̋@�\�E�\�́E�e�ʂ��ߋ��@����єr�o�K�X�㏈�����u�i���_���G
�}�A�A�fSCR�G�}�ADPF���u�j��r�C�K�X���x�ʼn��M���邱�ƂɂȂ�B
�@�܂�A�f�B�[�[���G���W�����R�[���h�X�^�[�g������0�`800�b�̊����ł́A�ғ��C���Q�̔r�C�K�X���x���]���G��
�W���̂Q�{�ƂȂ�A�r�C�n�i���ߋ��@�A�_���G�}�A�A�fSCR�G�}�ADPF���u�j�̔M�e�ʂ��]���G���W���̂P�^�Q�ɔ�����
���邽�߁A�z�b�g�X�^�[�g�����̔r�C�K�X���x�ɓ��B���鎞�Ԃ́A�]���G���W����800�b����200�b���x�܂ŒZ�k�ł���
���ƂɂȂ�B���̂��߁A�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�������Z�p���̗p�����f�B�[�[���G���W���ɂ�����
JE�O�T�����R�[���h�X�^�[�g�����ł�NO���r�o��啝�ɍ팸���邱�Ƃ��\�ƂȂ�B
�W���̂Q�{�ƂȂ�A�r�C�n�i���ߋ��@�A�_���G�}�A�A�fSCR�G�}�ADPF���u�j�̔M�e�ʂ��]���G���W���̂P�^�Q�ɔ�����
���邽�߁A�z�b�g�X�^�[�g�����̔r�C�K�X���x�ɓ��B���鎞�Ԃ́A�]���G���W����800�b����200�b���x�܂ŒZ�k�ł���
���ƂɂȂ�B���̂��߁A�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�������Z�p���̗p�����f�B�[�[���G���W���ɂ�����
JE�O�T�����R�[���h�X�^�[�g�����ł�NO���r�o��啝�ɍ팸���邱�Ƃ��\�ƂȂ�B
�@�ȏ�̂悤�ɁA�Q�^�[�{�������C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p���̗p�����f�B�[�[���G
���W�����R�[���h�X�^�[�g������0�`800�b�̊����ł́A50���ȉ��̃G���W���^�]��Ԃ��啔�����߂邽�߁A
�����̋C�����x�~������Ԃ̉^�]����̂ƂȂ�B���̋C���x�~�̉^�]��Ԃł́A���̎��̃G���W���̏o��
�́A�����̋C�����ғ������Ԃ̂��߂ɉғ��C���̔r�C�K�X���x���]���G���W���̂Q�{���x�ɍ������ł���
���ƂɂȂ�B���̏�ɁA�]���G���W�ɔ�ׂĔ����̗e�ʂ̔r�C�n�i���ߋ��@�A�_���G�}�A�A�fSCR�G�}�ADPF
���u�j�����ɔz�u�����\���ł��邽�߂ɁA�C���x�~�̉^�]��Ԃł̉ғ��C���̔r�C�n�̔M�e�ʂ��]���G��
�W����������������ԂƂȂ邱�Ƃ���A�ғ��C���Q�̔r�C�n��Z���Ԃɍ��������\�ł���B���̂��߁A�R
�[���h�X�^�[�g�����ł�NO���r�o�l��啝�ɍ팸���邱�Ƃ��\�ƂȂ�B
���W�����R�[���h�X�^�[�g������0�`800�b�̊����ł́A50���ȉ��̃G���W���^�]��Ԃ��啔�����߂邽�߁A
�����̋C�����x�~������Ԃ̉^�]����̂ƂȂ�B���̋C���x�~�̉^�]��Ԃł́A���̎��̃G���W���̏o��
�́A�����̋C�����ғ������Ԃ̂��߂ɉғ��C���̔r�C�K�X���x���]���G���W���̂Q�{���x�ɍ������ł���
���ƂɂȂ�B���̏�ɁA�]���G���W�ɔ�ׂĔ����̗e�ʂ̔r�C�n�i���ߋ��@�A�_���G�}�A�A�fSCR�G�}�ADPF
���u�j�����ɔz�u�����\���ł��邽�߂ɁA�C���x�~�̉^�]��Ԃł̉ғ��C���̔r�C�n�̔M�e�ʂ��]���G��
�W����������������ԂƂȂ邱�Ƃ���A�ғ��C���Q�̔r�C�n��Z���Ԃɍ��������\�ł���B���̂��߁A�R
�[���h�X�^�[�g�����ł�NO���r�o�l��啝�ɍ팸���邱�Ƃ��\�ƂȂ�B
�@���͂Ƃ�����A�����_�ł́AJE�O�T���̃R�[���h�X�^�[�g������NO���r�o��啝�ɍ팸�ł�����p�\�ȋZ�p
�́A�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p�̑��ɂ͑��݂��Ȃ��ƍl����̂��Ó��ł���B���̂�
��A�����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p�ȊO�ɁAJE�O�T���̃R�[���h�X�^�[�g������NO���r�o
��啝�ɍ팸�ł����i�E�Z�p�����\���ꂽ�Ƃ̏��́A���̂Ƃ���A�������������Ƃ���������ł���B���������āA
�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p���E�َE����w�ҁE���Ƃ́A�f�B�[�[���G���W���ɂ�����
��JE�O�T���̃R�[���h�X�^�[�g�����ł�NO���r�o�̑������ۑ肾�����q�ׂ������̍u����_�����\������������邴
��Ȃ����̂Ɛ��������B
�́A�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p�̑��ɂ͑��݂��Ȃ��ƍl����̂��Ó��ł���B���̂�
��A�����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p�ȊO�ɁAJE�O�T���̃R�[���h�X�^�[�g������NO���r�o
��啝�ɍ팸�ł����i�E�Z�p�����\���ꂽ�Ƃ̏��́A���̂Ƃ���A�������������Ƃ���������ł���B���������āA
�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p���E�َE����w�ҁE���Ƃ́A�f�B�[�[���G���W���ɂ�����
��JE�O�T���̃R�[���h�X�^�[�g�����ł�NO���r�o�̑������ۑ肾�����q�ׂ������̍u����_�����\������������邴
��Ȃ����̂Ɛ��������B
�@���̂悤�ɁA�R�[���h�X�^�[�g�����ɂ�����NO���r�o����������ۑ肾�����q�ׁANO���̍팸�Z�p�Ɍ��y���Ȃ��u��
��_�����\�́ANO���팸�̋Z�p�I�Ȏ����悤�Ƃ���Z�p�҂ɂƂ��ẮA���S�Ɍ��ׁE�����̍u���̒��O�┭�\�_
���ł���A���ҊO��̉��҂ł������B���̂悤�ɁA�f�B�[�[���G���W���̉ۑ肾�����q�ׂĉۑ�̉�����ɉ������y��
�Ȃ��u���┭�\�_���́A�u���̒��O�┭�\�_���̓ǎ҂�̎��E�y�����A�R�[���h�X�^�[�g�����ɂ�����NO���팸�̉�
������̕����K���Ŗ͍�����Z�p�҂�n���ɂ����s�ׂł͂Ȃ����낤���B�����āA���̏��ÂɌ���A�C��
�x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p�����E�َE����w�ҁE���Ƃ́A�R�[���h�X�^�[�g�����ɂ�����
�B���NO���팸�̕��������̈ӎv�ŕ��A���ׁE�����̍u����_�����\���s���X�Ԃ������Ă��邱�ƂɂȂ�̂�
����B���Ă��āA����A�f�B�[�[���G���W���W�̊w�ҁE���Ƃ̒N�����ׁE�����H�̍u����_�����\�����ۂɍs�Ȃ�
���ɂ��ẮA�M�҂ɂ͋����ÁX�ł���B�Ȃ��A���̕M�҂̍l���ɂ��āA�٘_�̂�����́A�M�҈��ɂ��̎|��E���[
���������肢��������K���ł���B
��_�����\�́ANO���팸�̋Z�p�I�Ȏ����悤�Ƃ���Z�p�҂ɂƂ��ẮA���S�Ɍ��ׁE�����̍u���̒��O�┭�\�_
���ł���A���ҊO��̉��҂ł������B���̂悤�ɁA�f�B�[�[���G���W���̉ۑ肾�����q�ׂĉۑ�̉�����ɉ������y��
�Ȃ��u���┭�\�_���́A�u���̒��O�┭�\�_���̓ǎ҂�̎��E�y�����A�R�[���h�X�^�[�g�����ɂ�����NO���팸�̉�
������̕����K���Ŗ͍�����Z�p�҂�n���ɂ����s�ׂł͂Ȃ����낤���B�����āA���̏��ÂɌ���A�C��
�x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p�����E�َE����w�ҁE���Ƃ́A�R�[���h�X�^�[�g�����ɂ�����
�B���NO���팸�̕��������̈ӎv�ŕ��A���ׁE�����̍u����_�����\���s���X�Ԃ������Ă��邱�ƂɂȂ�̂�
����B���Ă��āA����A�f�B�[�[���G���W���W�̊w�ҁE���Ƃ̒N�����ׁE�����H�̍u����_�����\�����ۂɍs�Ȃ�
���ɂ��ẮA�M�҂ɂ͋����ÁX�ł���B�Ȃ��A���̕M�҂̍l���ɂ��āA�٘_�̂�����́A�M�҈��ɂ��̎|��E���[
���������肢��������K���ł���B
�Q�|�R�@�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�ɂ��R�[���h�X�^�[�g��NO���팸
�@�M�҂�2006�N4���ɊJ�݂����z�[���y�[�W���C���x�~�G���W���ɂ���^�g���b�N�̒�R��A�C���x�~�́A�f�B�[
�[���̂m�n���팸�ƔR�����̈ꋓ�����̋Z�p���I�A�C���x�~��DPF�̎��ȍĐ��𑣐i (�����Đ��̍팸�ŔR�
����h�~�j���ɂ����āA�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�́A�u�G���W���̒ᕉ���i���r�C�K�X���x�̒ቷ
���j�ɂ�����A�f�r�b�q�G�}��NOx�팸���̌���v�A�u�d�ʎԃ��[�h�R���ю����s�R��̉��P�v����сu�c�o�e�̋���
�Đ��p�x�̌����v������^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W���̉ۑ�������ł�������Z�p�ł��邱�Ƃ��ڏq���Ă���B��
���A���̑��ɂ��A�����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓��������𒍈Ӑ[���ǂ߂A���������Z�p����
�p�������ꍇ�ɂ́A�f�B�[�[���G���W����JE�O�T���[�h�ł̃R�[���h�X�^�[�g�����ɂ�����NOx�r�o�l���팸�ł������
�Z�p�ł��邱�Ƃ��e�Ղ������ł��锤�ł���B�܂�AJE�O�T���[�h���̃R�[���h�X�^�[�g�����ɂ�����NOx�r�o�l����
���\���C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�́A2005�N3��3���ɂ͓������J����A2006�N4���ɂ͕M�҂̃z�[
���y�[�W�ɂČ��\�E���J���Ă���̂ł���B�������Ȃ���A�������R�c��E��C����������\�����\�i��2010�N7
��2���j�ł́A�ȉ��̕\�P�Ɏ������悤�ɁA�g���b�N�E�o�X�i���d�ʎԁj�ɂ�����JE�O�T���[�h���ł̃R�[���h�X�^�[�g������
������NOx�r�o�l�̍팸���ɂ߂č���ȉۑ�ł��邩�̔@���L�ڂ���Ă���B
�[���̂m�n���팸�ƔR�����̈ꋓ�����̋Z�p���I�A�C���x�~��DPF�̎��ȍĐ��𑣐i (�����Đ��̍팸�ŔR�
����h�~�j���ɂ����āA�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�́A�u�G���W���̒ᕉ���i���r�C�K�X���x�̒ቷ
���j�ɂ�����A�f�r�b�q�G�}��NOx�팸���̌���v�A�u�d�ʎԃ��[�h�R���ю����s�R��̉��P�v����сu�c�o�e�̋���
�Đ��p�x�̌����v������^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W���̉ۑ�������ł�������Z�p�ł��邱�Ƃ��ڏq���Ă���B��
���A���̑��ɂ��A�����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓��������𒍈Ӑ[���ǂ߂A���������Z�p����
�p�������ꍇ�ɂ́A�f�B�[�[���G���W����JE�O�T���[�h�ł̃R�[���h�X�^�[�g�����ɂ�����NOx�r�o�l���팸�ł������
�Z�p�ł��邱�Ƃ��e�Ղ������ł��锤�ł���B�܂�AJE�O�T���[�h���̃R�[���h�X�^�[�g�����ɂ�����NOx�r�o�l����
���\���C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�́A2005�N3��3���ɂ͓������J����A2006�N4���ɂ͕M�҂̃z�[
���y�[�W�ɂČ��\�E���J���Ă���̂ł���B�������Ȃ���A�������R�c��E��C����������\�����\�i��2010�N7
��2���j�ł́A�ȉ��̕\�P�Ɏ������悤�ɁA�g���b�N�E�o�X�i���d�ʎԁj�ɂ�����JE�O�T���[�h���ł̃R�[���h�X�^�[�g������
������NOx�r�o�l�̍팸���ɂ߂č���ȉۑ�ł��邩�̔@���L�ڂ���Ă���B
| |
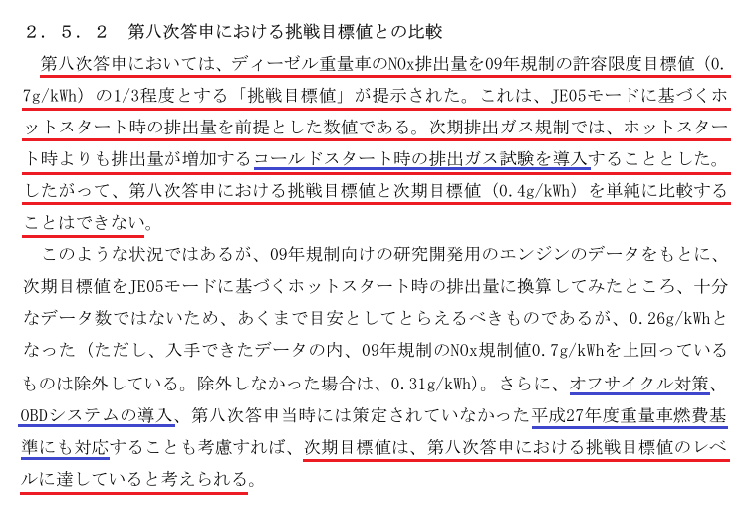 |
�@��L�̕\�P�Ɏ������������R�c��E��C����������\�����\�̋L�ړ��e������ƁA��\�����\�i2010�N���\�j
��NO�� �� 0.4 g/��W���i��2016�N�̎��{�\��j�́A�����Ԕr�o�K�X�̑攪�����\�i2005�N���\�j�ɋL�ڂ́u����ڕW
NO�� �� 0.23 g/��W���v�Ɠ����ƋL�ڂ���Ă���B�����āA�u��\�����\�i2010�N���\�j��NO�� �� 0.4 g/��W���v�Ɓu�攪����
�\�i2005�N���\�j�ɋL�ڂ́u����ڕWNO�� �� 0.23 g/��W���v�������ƌ��Ȃ���闝�R�Ƃ��āA���\�����\�ł́A�u�R�[��
�h�X�^�[�g�����̓����v�A�u�I�t�T�C�N����v�A�uOBD�V�X�e���̓����v�A����сu����27�N�x�d�ʎԔR���v���ɂ��
�uNO�������̗v���v�Ƃ��ė���Ă���̂ł���B
��NO�� �� 0.4 g/��W���i��2016�N�̎��{�\��j�́A�����Ԕr�o�K�X�̑攪�����\�i2005�N���\�j�ɋL�ڂ́u����ڕW
NO�� �� 0.23 g/��W���v�Ɠ����ƋL�ڂ���Ă���B�����āA�u��\�����\�i2010�N���\�j��NO�� �� 0.4 g/��W���v�Ɓu�攪����
�\�i2005�N���\�j�ɋL�ڂ́u����ڕWNO�� �� 0.23 g/��W���v�������ƌ��Ȃ���闝�R�Ƃ��āA���\�����\�ł́A�u�R�[��
�h�X�^�[�g�����̓����v�A�u�I�t�T�C�N����v�A�uOBD�V�X�e���̓����v�A����сu����27�N�x�d�ʎԔR���v���ɂ��
�uNO�������̗v���v�Ƃ��ė���Ă���̂ł���B
�@�������Ȃ���A�g���b�N�E�o�X�i���d�ʎԁj�ɂ�����u�R�[���h�X�^�[�g�����̓����v�A�u�I�t�T�C�N����v�A�uOBD�V�X�e
���̓����v�A����сu����27�N�x�d�ʎԔR���v�́A�u����ڕWNO�� �� 0.23 g/��W���v���L�ڂ��ꂽ�u�攪�����\
�i2005�N���\�j�v������b�ɒ�o����Č��\���ꂽ��ɁA�s�ӂɒlj����ꂽ�V���ȏ����̂悤�ɁA���̑�\�����\
�i2010�N���\�j�ɂ͋L�ڂ���Ă���B�������A���ۂ̂Ƃ���A2010�N�V��29���ɑ�\�����\������b�ɒ�o����Č�
�\�����ȑO����A�g���b�N�E�o�X�i���d�ʎԁj�ɂ�����u�R�[���h�X�^�[�g�����̓����v�A�u�I�t�T�C�N����v�A�uOBD�V�X
�e���̓����v�A����сu����27�N�x�d�ʎԔR���v�́A�c�_����Ă������Ƃł���B���������āA��\�����\�i2010�N
���\�j�̍쐬��S�����������R�c��E��C������̎����Ԕr�o�K�X���ψ���̊w�ҁE���Ƃ��u�R�[���h�X�^
�[�g�����̓����v�A�u�I�t�T�C�N����v�A�uOBD�V�X�e���̓����v�A����сu����27�N�x�d�ʎԔR���v���߂�������
�f�B�[�[���g���b�N�E�o�X�i���d�ʎԁj�ɓ�������邱�Ƃ�S���\�����Ă��Ȃ��������Ƃ������Ƃ���A�����Ԕr�o�K�X
���ψ���̃����o�[�́A�f�B�[�[���G���W������̊w�ҁE���ƂƂ��Ă͎��i�ɒl����̂ł͂Ȃ����낤���B
���̓����v�A����сu����27�N�x�d�ʎԔR���v�́A�u����ڕWNO�� �� 0.23 g/��W���v���L�ڂ��ꂽ�u�攪�����\
�i2005�N���\�j�v������b�ɒ�o����Č��\���ꂽ��ɁA�s�ӂɒlj����ꂽ�V���ȏ����̂悤�ɁA���̑�\�����\
�i2010�N���\�j�ɂ͋L�ڂ���Ă���B�������A���ۂ̂Ƃ���A2010�N�V��29���ɑ�\�����\������b�ɒ�o����Č�
�\�����ȑO����A�g���b�N�E�o�X�i���d�ʎԁj�ɂ�����u�R�[���h�X�^�[�g�����̓����v�A�u�I�t�T�C�N����v�A�uOBD�V�X
�e���̓����v�A����сu����27�N�x�d�ʎԔR���v�́A�c�_����Ă������Ƃł���B���������āA��\�����\�i2010�N
���\�j�̍쐬��S�����������R�c��E��C������̎����Ԕr�o�K�X���ψ���̊w�ҁE���Ƃ��u�R�[���h�X�^
�[�g�����̓����v�A�u�I�t�T�C�N����v�A�uOBD�V�X�e���̓����v�A����сu����27�N�x�d�ʎԔR���v���߂�������
�f�B�[�[���g���b�N�E�o�X�i���d�ʎԁj�ɓ�������邱�Ƃ�S���\�����Ă��Ȃ��������Ƃ������Ƃ���A�����Ԕr�o�K�X
���ψ���̃����o�[�́A�f�B�[�[���G���W������̊w�ҁE���ƂƂ��Ă͎��i�ɒl����̂ł͂Ȃ����낤���B
�@�������A��w�ɍ˂̃|���R�c���Z�p���̕M�҂������ł��Ȃ����Ƃ́A���̑�\�����\�i2010�N���\�j�ł́A��\����
�\�i2010�N���\�j��NO�� �� 0.4 g/��W���i��2016�N�̎��{�\��j���攪�����\�i2005�N���\�j�ɋL�ڂ́u����ڕWNO��
�� 0.23 g/��W���v�Ɠ�������Ɩ��L����Ă���̂ł���B�����āA��\�����\�i2010�N���\�j��NO�� �� 0.4 g/��W���i��
2016�N�̎��{�\��j���攪�����\�i2005�N���\�j�ɋL�ڂ́u����ڕWNO�� �� 0.23 g/��W���v�Ɠ����ł���ƌ��Ȃ�����
�Ƃ��āA��\�����\�i2010�N���\�j�ɂ́u�R�[���h�X�^�[�g�����̓����v�A�u�I�t�T�C�N����v�A�uOBD�V�X�e���̓����v�A
����сu����27�N�x�d�ʎԔR���v���S���ڂ̗v��������Ă���B�������A�����S���ڂ̉���̗v�����A�攪
�����\�́uNO������ڕW�FNO�� �� 0.23 g/��W���v�̂ɂ��鍪���ɂȂ蓾�Ȃ��ƍl�����邽�߁A���̗��R���ȉ���
�܂Ƃ߂��B
�\�i2010�N���\�j��NO�� �� 0.4 g/��W���i��2016�N�̎��{�\��j���攪�����\�i2005�N���\�j�ɋL�ڂ́u����ڕWNO��
�� 0.23 g/��W���v�Ɠ�������Ɩ��L����Ă���̂ł���B�����āA��\�����\�i2010�N���\�j��NO�� �� 0.4 g/��W���i��
2016�N�̎��{�\��j���攪�����\�i2005�N���\�j�ɋL�ڂ́u����ڕWNO�� �� 0.23 g/��W���v�Ɠ����ł���ƌ��Ȃ�����
�Ƃ��āA��\�����\�i2010�N���\�j�ɂ́u�R�[���h�X�^�[�g�����̓����v�A�u�I�t�T�C�N����v�A�uOBD�V�X�e���̓����v�A
����сu����27�N�x�d�ʎԔR���v���S���ڂ̗v��������Ă���B�������A�����S���ڂ̉���̗v�����A�攪
�����\�́uNO������ڕW�FNO�� �� 0.23 g/��W���v�̂ɂ��鍪���ɂȂ蓾�Ȃ��ƍl�����邽�߁A���̗��R���ȉ���
�܂Ƃ߂��B
�� �u�I�t�T�C�N����v
�@���\�N�O�Ɉ���g���b�N���[�J����^�g���b�N�̔R�����˃|���v�ɓd�q�^�C�}�[���̗p�����ہA�����s�̔R������
���߂ɔr�o�K�X�����̉^�]���[�h���O�ꂽ�^�]�̈�ɂ�����NO������������G���W��������s�������Ƃ�����B����
�G���W�����䂪�I�����������A�d�q�^�C�}�[���f�B�t�B�[�g�f�o�C�X�i�o�T�Fhttp://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE
/2011/09/20l9d202.htm�j�ɑ������鑕�u�Ƃ��Ė��ɂȂ�A�u�T�C�N���r�[�e�B���O�v�Ə̂���r�o�K�X�����̉^�]���[
�h���O�ꂽ�^�]�̈�ɂ�����NO������������G���W������͈�@�ł���Ƃ��āA���ȁE���y��ʏȂ��u�T�C�N���r�[
�e�B���O�v�̒��~���g���b�N���[�J�ɋ����w�������o�܂�����B����ȗ��A�g���b�N���[�J�ł́A�V���ȃG���W���J���ɍۂ�
�Ă͔r�o�K�X�����̉^�]���[�h���O�ꂽ�^�]�̈�ɂ�����NO�����}������G���W��������̗p���Ȃ����Ƃ��펯�Ƃ�
���Ă��邱�Ƃł�����B���������āA��\�����\�i2010�N���\�j�ɂ����āA�V���Ɂu�I�t�T�C�N����v�ɂ����NO������
�ʂɑ�������Ƃ������Ԕr�o�K�X���ψ���̊w�ҁE���Ƃ̎咣�́A�M�҂ɂ͗����ł��Ȃ����Ƃł���B
���߂ɔr�o�K�X�����̉^�]���[�h���O�ꂽ�^�]�̈�ɂ�����NO������������G���W��������s�������Ƃ�����B����
�G���W�����䂪�I�����������A�d�q�^�C�}�[���f�B�t�B�[�g�f�o�C�X�i�o�T�Fhttp://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE
/2011/09/20l9d202.htm�j�ɑ������鑕�u�Ƃ��Ė��ɂȂ�A�u�T�C�N���r�[�e�B���O�v�Ə̂���r�o�K�X�����̉^�]���[
�h���O�ꂽ�^�]�̈�ɂ�����NO������������G���W������͈�@�ł���Ƃ��āA���ȁE���y��ʏȂ��u�T�C�N���r�[
�e�B���O�v�̒��~���g���b�N���[�J�ɋ����w�������o�܂�����B����ȗ��A�g���b�N���[�J�ł́A�V���ȃG���W���J���ɍۂ�
�Ă͔r�o�K�X�����̉^�]���[�h���O�ꂽ�^�]�̈�ɂ�����NO�����}������G���W��������̗p���Ȃ����Ƃ��펯�Ƃ�
���Ă��邱�Ƃł�����B���������āA��\�����\�i2010�N���\�j�ɂ����āA�V���Ɂu�I�t�T�C�N����v�ɂ����NO������
�ʂɑ�������Ƃ������Ԕr�o�K�X���ψ���̊w�ҁE���Ƃ̎咣�́A�M�҂ɂ͗����ł��Ȃ����Ƃł���B
�� �uOBD�V�X�e���̓����v
�@�ԍڎ��̏�f�f�V�X�e���i�n�a�c�V�X�e���j�́A�ԗ����g���r�o�K�X�����u�ُ̈�i�˔��I�̏�j�����m�E�Ď����A
�ُ픭�����Ɍx��\�����ĉ^�]�҂ɒm�点��ƂƂ��ɁA���̌̏���e���L���ێ����鑕�u�̂悤�ł���B����OBD�V
�X�e�����g���b�N�E�o�X�ɍ̗p���邱�Ƃɂ��AJE�O�T���[�h���̔r�o�K�X�����ő��肳���NO�������ʂɑ�������v��
�ɂȂ�Ƃ������Ԕr�o�K�X���ψ���̊w�ҁE���Ƃ̎咣�́A�M�҂ɂ͗����ł��Ȃ����Ƃł���B
�ُ픭�����Ɍx��\�����ĉ^�]�҂ɒm�点��ƂƂ��ɁA���̌̏���e���L���ێ����鑕�u�̂悤�ł���B����OBD�V
�X�e�����g���b�N�E�o�X�ɍ̗p���邱�Ƃɂ��AJE�O�T���[�h���̔r�o�K�X�����ő��肳���NO�������ʂɑ�������v��
�ɂȂ�Ƃ������Ԕr�o�K�X���ψ���̊w�ҁE���Ƃ̎咣�́A�M�҂ɂ͗����ł��Ȃ����Ƃł���B
�� �u����27�N�x�d�ʎԔR���v
�@2004�N9���Ɍo�ώY�ƏȂɂ����đ��������G�l���M�[������E�ȃG�l���M�[�����̉����g�D�Ƃ��āu�d�ʎԔ�
�f����ψ���v���ݒu�����ƂƂ��ɁA���y��ʏȂɂ����āA�u�d�ʎԔR��������v���ݒu���ꂽ�悤���B����
�āA���ғ���̍\���ψ����琬�鍇����c�`���ŁA�W�҂���̃q�A�����O�����s���A�������Ǝғ��̔��f��
���ƂȂ�ׂ������i�ΏۂƂȂ鎩���Ԃ͈̔́A�R�����@�A�R��敪�A�R���l�A�ڕW�N�x�j�ɂ��ĐR�c���d
�˂��Ă����o�܁ihttp://www.tossnet.or.jp/staticContents/public_html/mtou_saikin/img/17nendo/050929_nenpi.pdf�j
������B���̂悤�ɁA2004�N9������d�ʎԂ̔R���̌������n�܂��Ă��邱�Ƃ���A�攪�����\�i2005�N���\�j��
��o���ɂ́A�����I�ɏd�ʎԂ̔R���̓����͊��Ɍ������ł������Ɛ��������B���̂悤�ȏɂ����āA����
���������R�c��E��C�������������Ԕr�o�K�X���ψ���̊w�ҁE���Ƃ́A�u����ڕWNO�� �� 0.23 g/��W���v
�ƍ��ӂ��A�攪�����\�i2005�N���\�j�ɋL�ڂ����̂ł���B���������āA���̑攪�����\�i2005�N���\�j�Ɂu����ڕWNO
�� �� 0.23 g/��W���v���d�ʎԂ̔R���̎��{�E�{�s��S�������������̂Ƃ͍l���邱�Ƃ́A�ɂ߂č���ł���B������
���āA�u����27�N�x�d�ʎԔR���v�𗝗R�ɁA�攪�����\�i2005�N���\�j�́u����ڕWNO�� �� 0.23 g/��W���v��
�ɂ��闝�R�ɋ����邱�Ƃɂ́A�M�҂ɂ͗����ł��Ȃ����Ƃł���B
�f����ψ���v���ݒu�����ƂƂ��ɁA���y��ʏȂɂ����āA�u�d�ʎԔR��������v���ݒu���ꂽ�悤���B����
�āA���ғ���̍\���ψ����琬�鍇����c�`���ŁA�W�҂���̃q�A�����O�����s���A�������Ǝғ��̔��f��
���ƂȂ�ׂ������i�ΏۂƂȂ鎩���Ԃ͈̔́A�R�����@�A�R��敪�A�R���l�A�ڕW�N�x�j�ɂ��ĐR�c���d
�˂��Ă����o�܁ihttp://www.tossnet.or.jp/staticContents/public_html/mtou_saikin/img/17nendo/050929_nenpi.pdf�j
������B���̂悤�ɁA2004�N9������d�ʎԂ̔R���̌������n�܂��Ă��邱�Ƃ���A�攪�����\�i2005�N���\�j��
��o���ɂ́A�����I�ɏd�ʎԂ̔R���̓����͊��Ɍ������ł������Ɛ��������B���̂悤�ȏɂ����āA����
���������R�c��E��C�������������Ԕr�o�K�X���ψ���̊w�ҁE���Ƃ́A�u����ڕWNO�� �� 0.23 g/��W���v
�ƍ��ӂ��A�攪�����\�i2005�N���\�j�ɋL�ڂ����̂ł���B���������āA���̑攪�����\�i2005�N���\�j�Ɂu����ڕWNO
�� �� 0.23 g/��W���v���d�ʎԂ̔R���̎��{�E�{�s��S�������������̂Ƃ͍l���邱�Ƃ́A�ɂ߂č���ł���B������
���āA�u����27�N�x�d�ʎԔR���v�𗝗R�ɁA�攪�����\�i2005�N���\�j�́u����ڕWNO�� �� 0.23 g/��W���v��
�ɂ��闝�R�ɋ����邱�Ƃɂ́A�M�҂ɂ͗����ł��Ȃ����Ƃł���B
�� �u�R�[���h�X�^�[�g�����̓����v
�@���������A�]���́u�z�b�g�X�^�[�g�����v�����ɕ������s�̓��{�̏d�ʎԔr�o�K�X�����@�ɂ́A���ۂ̑��s��Ԃ�
��傫�������������ׂ̂��邱�Ƃ́A�̂���L���F������Ă������Ƃł���B���̂Ȃ�A�č��̏d�ʎԂ̔r�o�K�X��
���@�i��FTP Transient Cycle �F �ʏ� 1199�b���[�h�j�ł́A�̂���u�z�b�g�X�^�[�g�����v�Ɓu�R�[���h�X�^�[�g��
���v�̗��������{����Ă���i��http://www.dieselnet.com/standards/cycles/ftp_trans.php���Q�Ɓj���߂�
����B���������āA2016�N�Ɏ��{�̎����̔r�o�K�X�K���ɂ�����r�o�K�X�����@�̕ύX���Ɂu�R�[���h�X�^�[�g�����v
�����邱�Ƃ́A����܂ł̓��{�̔r�o�K�X�����̌��ׂ𐳂����u�ɑ��Ȃ�Ȃ��B���̂��߁A���{�̏d�ʎԂ̔r�o
�K�X�����@�ɂ�����u�R�[���h�X�^�[�g�����v�̐V���Ȓlj��́A���ɁA���R�Ȕr�o�K�X�����@�̐����Ɖ]���邾�낤�B��
�������āA�u�R�[���h�X�^�[�g�����̐V���ȓ����v�ɂ����NO���K���l���ɘa���邱�Ƃ́A�{���]�|���r���������Ƃł�
��B�܂��A�f�B�[�[���G���W���́u�R�[���h�X�^�[�g�����v�ɂ���Đ�����NO������������E�}�����\�ȋZ�p�ł����C��
�x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p�́A2005�N3��3���Ɍ��J����A2006�N4���ɂ͕M�҂��z�[���y�[�W
�Ɍf�ڂ��Ă��邱�Ƃł���B���̂��߁A��\�����\�i2010�N���\�j���쐬���ꂽ���_�ł́A�f�B�[�[���G���W���W��
�����̐��ƁE�Z�p�҂ɂ́A���̋C���x�~�G���W���̓����Z�p�́A���m�ł������Ɛ��������B���������āA������
�R�c��E��C������̎����Ԕr�o�K�X���ψ���̈ꕔ�̊w�ҁE���Ƃ��A�u�R�[���h�X�^�[�g�����v�ɂ���Đ���
��NO������������E�}�����\���C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p�̑��݂�F������Ă����\
��������Ɛ��@�����B
��傫�������������ׂ̂��邱�Ƃ́A�̂���L���F������Ă������Ƃł���B���̂Ȃ�A�č��̏d�ʎԂ̔r�o�K�X��
���@�i��FTP Transient Cycle �F �ʏ� 1199�b���[�h�j�ł́A�̂���u�z�b�g�X�^�[�g�����v�Ɓu�R�[���h�X�^�[�g��
���v�̗��������{����Ă���i��http://www.dieselnet.com/standards/cycles/ftp_trans.php���Q�Ɓj���߂�
����B���������āA2016�N�Ɏ��{�̎����̔r�o�K�X�K���ɂ�����r�o�K�X�����@�̕ύX���Ɂu�R�[���h�X�^�[�g�����v
�����邱�Ƃ́A����܂ł̓��{�̔r�o�K�X�����̌��ׂ𐳂����u�ɑ��Ȃ�Ȃ��B���̂��߁A���{�̏d�ʎԂ̔r�o
�K�X�����@�ɂ�����u�R�[���h�X�^�[�g�����v�̐V���Ȓlj��́A���ɁA���R�Ȕr�o�K�X�����@�̐����Ɖ]���邾�낤�B��
�������āA�u�R�[���h�X�^�[�g�����̐V���ȓ����v�ɂ����NO���K���l���ɘa���邱�Ƃ́A�{���]�|���r���������Ƃł�
��B�܂��A�f�B�[�[���G���W���́u�R�[���h�X�^�[�g�����v�ɂ���Đ�����NO������������E�}�����\�ȋZ�p�ł����C��
�x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p�́A2005�N3��3���Ɍ��J����A2006�N4���ɂ͕M�҂��z�[���y�[�W
�Ɍf�ڂ��Ă��邱�Ƃł���B���̂��߁A��\�����\�i2010�N���\�j���쐬���ꂽ���_�ł́A�f�B�[�[���G���W���W��
�����̐��ƁE�Z�p�҂ɂ́A���̋C���x�~�G���W���̓����Z�p�́A���m�ł������Ɛ��������B���������āA������
�R�c��E��C������̎����Ԕr�o�K�X���ψ���̈ꕔ�̊w�ҁE���Ƃ��A�u�R�[���h�X�^�[�g�����v�ɂ���Đ���
��NO������������E�}�����\���C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p�̑��݂�F������Ă����\
��������Ɛ��@�����B
�@�������A�������R�c��E��C������̎����Ԕr�o�K�X���ψ���̊w�ҁE���ƂɂƂ��ẮA�|���R�c���Z�p
���̕M�҂���Ă����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p��F�߂邱�Ƃ́A�ނ���v���C�h�Ǝ����S��
�[�����t���鎖�ۂƐ��������B�������߁A�����Ԕr�o�K�X���ψ���́A�u�R�[���h�X�^�[�g�����v�ɂ�����NO������
�̉���E�}�����\���C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p���E�َE�������邱�Ƃɍ��ӁH������
�\��������Ɨ\�z�����B���̌��ʁA��\�����\�i2010�N���\�j�ł́A�u�R�[���h�X�^�[�g�����v�ɂ�����NO�������̖�
����w�E���邾���ł���A���̖������������Z�p�������Ꭶ���邱�Ƃ��ł��Ȃ��������̂Ɛ��������B���̂�
�Ƃ́A�����Ԕr�o�K�X���ψ���u�R�[���h�X�^�[�g�����v��NO���팸���\�Ȏ��p���̂���B��̋Z�p�ł����C
���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j���E�َE�������Ƃɂ�铖�R�̋A���Ɖ]����̂ł͂Ȃ����낤���B�����āA
�������R�c��E��C������̎����Ԕr�o�K�X���ψ���́A�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j
�̓����Z�p���������Ȃɖ����E�َE�����������A�u�R�[���h�X�^�[�g�����v��NO���팸���f�B�[�[���G���W��
�̉������ׂ��ۑ�Ə�����������甲���o�����Ƃ�����Ɛ��������B���̂悤�ȏX�ԂƂ��]���鎖�ԂɏI�~
����łB��̕��@�́A�������R�c��E��C������̎����Ԕr�o�K�X���ψ���C���x�~�G���W���i������
�J2005-54771�j�̓����Z�p���E�َE���鍇�ӁH�𑁊��ɓP�邱�Ƃ��Ǝv�����A�@���Ȃ��̂ł��낤���B
���̕M�҂���Ă����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p��F�߂邱�Ƃ́A�ނ���v���C�h�Ǝ����S��
�[�����t���鎖�ۂƐ��������B�������߁A�����Ԕr�o�K�X���ψ���́A�u�R�[���h�X�^�[�g�����v�ɂ�����NO������
�̉���E�}�����\���C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p���E�َE�������邱�Ƃɍ��ӁH������
�\��������Ɨ\�z�����B���̌��ʁA��\�����\�i2010�N���\�j�ł́A�u�R�[���h�X�^�[�g�����v�ɂ�����NO�������̖�
����w�E���邾���ł���A���̖������������Z�p�������Ꭶ���邱�Ƃ��ł��Ȃ��������̂Ɛ��������B���̂�
�Ƃ́A�����Ԕr�o�K�X���ψ���u�R�[���h�X�^�[�g�����v��NO���팸���\�Ȏ��p���̂���B��̋Z�p�ł����C
���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j���E�َE�������Ƃɂ�铖�R�̋A���Ɖ]����̂ł͂Ȃ����낤���B�����āA
�������R�c��E��C������̎����Ԕr�o�K�X���ψ���́A�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j
�̓����Z�p���������Ȃɖ����E�َE�����������A�u�R�[���h�X�^�[�g�����v��NO���팸���f�B�[�[���G���W��
�̉������ׂ��ۑ�Ə�����������甲���o�����Ƃ�����Ɛ��������B���̂悤�ȏX�ԂƂ��]���鎖�ԂɏI�~
����łB��̕��@�́A�������R�c��E��C������̎����Ԕr�o�K�X���ψ���C���x�~�G���W���i������
�J2005-54771�j�̓����Z�p���E�َE���鍇�ӁH�𑁊��ɓP�邱�Ƃ��Ǝv�����A�@���Ȃ��̂ł��낤���B
�@���������A�č��̏d�ʎԂ̔r�o�K�X�����@�i��FTP Transient Cycle �F �ʏ� 1199�b���[�h�j�ł́A���\�N���̐̂���
�u�z�b�g�X�^�[�g�����v�Ɓu�R�[���h�X�^�[�g�����v�̗��������{����Ă��邱�Ƃł���B���̂��߁A�u�R�[���h�X�^�[�g�����v
���s�v�ȁA����܂ł̓��{�̏d�ʎԂ̔r�o�K�X�����́A���̎����@�Ɍ��ׂ������������ł���B�����āA��\�����\
�i2010�N���\�j�ɂ����āA���{�̏d�ʎԂ̎����̔r�o�K�X�����Ɂu�R�[���h�X�^�[�g�����v���lj�����邱�ƂɂȂ�����
�́A����܂ł̓��{�̏d�ʎԂ̔r�o�K�X�����̌��ׂ����������ɉ߂��Ȃ��̂ł���B�����A�]������r�o�K�X��
���Ɂu�R�[���h�X�^�[�g�����v�����{����Ă�������̏d�ʎԂ�2010�N�K���ɂ�����NO���K�����ANO�� �� 0.27 g/kWh
�ł���B����ɂ�������炸�A���{�̏d�ʎԁi���g���b�N�E�o�X�j�ɂ������������R�c��E��C���������\����
�\�i2010�N���\�j�Ɏ����ꂽNO���̎����K���l�Ƃ��ẮA�u�R�[���h�X�^�[�g�����̓����v�A�u�I�t�T�C�N����v�A�uOBD
�V�X�e���̓����v�A����сu����27�N�x�d�ʎԔR���̎{�s�v�̎��ۂɂ��ANO�� �� 0.4 g/��W���̊ɂ�NO���K���l
�����\����Ă���B�������A�u��\�����\�i2010�N���\�j�v�ɂ́A�u�攪�����\�i2005�N���\�j�ɋL�ڂ̒���ڕW��NO��
�� 0.23 g/��W���v���u��\�����\�i2010�N���\�j��NO�� �� 0.4 g/��W���v�Ɠ����ƒf�肷��悤�ȁA�ǎ҂�����������u��
���s���H�v�̓��e�����X�ƋL�ڂ���Ă���̂ł���B�����Ƃ��A���̂悤�ȁu�Ӗ��s���H�v�̂��߂ɋL�ړ��e�𗝉��ł�
�Ȃ������ǎ҂ł����Ă��A���{�ł����Ђ�����ȁE�������R�c��E��C��������u��\�����\�i2010�N���\�j�v
�ɋL�ڂ���Ă���y�u�攪�����\�i2005�N���\�j�ɋL�ڂ̒���ڕW��NO�� �� 0.23 g/��W���v�́A�u��\�����\�i2010�N��
�\�j��NO�� �� 0.4 g/��W���v�Ɠ����z�Ƃ̓��e�́A���m�ȋZ�p���ƕs�{�ӂȂ�����l����l�͑����悤�ł���B���̗�
���ȉ��̐}�P�Ɏ����B���̂悤�Ȍ�����Z�p��L�����z���Ă��܂��Ă��錻��ɂ��āA�������R�c��E��C��
������̎����Ԕr�o�K�X���ψ���̃����o�[�̐l�B�́A�G���W���W�̊w�ҁE���ƂƂ��Ắu���߂����v��u��
�����v�������邱�Ƃ������̂ł��낤���B
�u�z�b�g�X�^�[�g�����v�Ɓu�R�[���h�X�^�[�g�����v�̗��������{����Ă��邱�Ƃł���B���̂��߁A�u�R�[���h�X�^�[�g�����v
���s�v�ȁA����܂ł̓��{�̏d�ʎԂ̔r�o�K�X�����́A���̎����@�Ɍ��ׂ������������ł���B�����āA��\�����\
�i2010�N���\�j�ɂ����āA���{�̏d�ʎԂ̎����̔r�o�K�X�����Ɂu�R�[���h�X�^�[�g�����v���lj�����邱�ƂɂȂ�����
�́A����܂ł̓��{�̏d�ʎԂ̔r�o�K�X�����̌��ׂ����������ɉ߂��Ȃ��̂ł���B�����A�]������r�o�K�X��
���Ɂu�R�[���h�X�^�[�g�����v�����{����Ă�������̏d�ʎԂ�2010�N�K���ɂ�����NO���K�����ANO�� �� 0.27 g/kWh
�ł���B����ɂ�������炸�A���{�̏d�ʎԁi���g���b�N�E�o�X�j�ɂ������������R�c��E��C���������\����
�\�i2010�N���\�j�Ɏ����ꂽNO���̎����K���l�Ƃ��ẮA�u�R�[���h�X�^�[�g�����̓����v�A�u�I�t�T�C�N����v�A�uOBD
�V�X�e���̓����v�A����сu����27�N�x�d�ʎԔR���̎{�s�v�̎��ۂɂ��ANO�� �� 0.4 g/��W���̊ɂ�NO���K���l
�����\����Ă���B�������A�u��\�����\�i2010�N���\�j�v�ɂ́A�u�攪�����\�i2005�N���\�j�ɋL�ڂ̒���ڕW��NO��
�� 0.23 g/��W���v���u��\�����\�i2010�N���\�j��NO�� �� 0.4 g/��W���v�Ɠ����ƒf�肷��悤�ȁA�ǎ҂�����������u��
���s���H�v�̓��e�����X�ƋL�ڂ���Ă���̂ł���B�����Ƃ��A���̂悤�ȁu�Ӗ��s���H�v�̂��߂ɋL�ړ��e�𗝉��ł�
�Ȃ������ǎ҂ł����Ă��A���{�ł����Ђ�����ȁE�������R�c��E��C��������u��\�����\�i2010�N���\�j�v
�ɋL�ڂ���Ă���y�u�攪�����\�i2005�N���\�j�ɋL�ڂ̒���ڕW��NO�� �� 0.23 g/��W���v�́A�u��\�����\�i2010�N��
�\�j��NO�� �� 0.4 g/��W���v�Ɠ����z�Ƃ̓��e�́A���m�ȋZ�p���ƕs�{�ӂȂ�����l����l�͑����悤�ł���B���̗�
���ȉ��̐}�P�Ɏ����B���̂悤�Ȍ�����Z�p��L�����z���Ă��܂��Ă��錻��ɂ��āA�������R�c��E��C��
������̎����Ԕr�o�K�X���ψ���̃����o�[�̐l�B�́A�G���W���W�̊w�ҁE���ƂƂ��Ắu���߂����v��u��
�����v�������邱�Ƃ������̂ł��낤���B
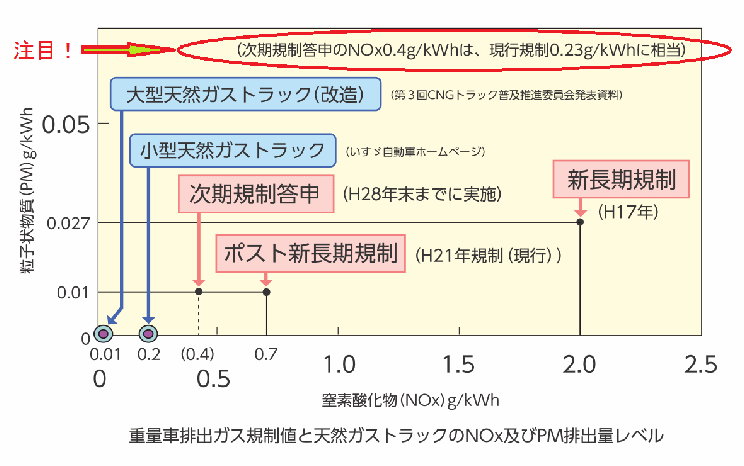 |
�@���̂悤�ɁA�������R�c��E��C������̎����Ԕr�o�K�X���ψ���́A�u�攪�����\�i2005�N���\�j�ɋL��
�̒���ڕW��NO�� �� 0.23 g/��W���v���u��\�����\�i2010�N���\�j��NO�� �� 0.4 g/��W���v�Ɠ����ƒf�肷�闝�s�s�Ȏ�
������\�����\�i2010�N���\�j�ɓ��X�ƋL�ڂ���Ă���̂ł���B�����A���̎咣�ɂ��āA�N�����[���ł���悤�Ș_
���I�E�����I�ȍ������u��\�����\�i2010�N���\�j�v�ɖ��L����Ă��Ȃ��悤���B
�̒���ڕW��NO�� �� 0.23 g/��W���v���u��\�����\�i2010�N���\�j��NO�� �� 0.4 g/��W���v�Ɠ����ƒf�肷�闝�s�s�Ȏ�
������\�����\�i2010�N���\�j�ɓ��X�ƋL�ڂ���Ă���̂ł���B�����A���̎咣�ɂ��āA�N�����[���ł���悤�Ș_
���I�E�����I�ȍ������u��\�����\�i2010�N���\�j�v�ɖ��L����Ă��Ȃ��悤���B
�@����ɂ��āA�M�҂̌l�I�Ȑ��������킹�ĖႦ�A�C���x�~�G���W���ɂ���^�g���b�N�̒�R����C���x
�~�́A�f�B�[�[���̂m�n���팸�ƔR�����̈ꋓ�����̋Z�p���I�ɂ��ڏq���Ă���悤�ɁA�����Ԕr�o�K�X���ψ�
��̊w�ҁE���Ƃ��A�uJE�O�T���[�h���̃z�b�g�X�^�[�g�������R�[���h�X�^�[�g�����ɂ�����NO���팸�v�A�u�d��
�ԃ��[�h�R��̍팸�v�ɋɂ߂ėL�����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p���Ӑ}�I�ɖ����E
�َE�������ʁA�������R�c��E��C��������u��\�����\�i2010�N���\�j��NO�� �� 0.4 g/��W���v�́A�u��
�������\�i2005�N���\�j�ɋL�ڂ́u����ڕWNO�� �� 0.23 g/��W���v�������Ɋɘa������Ȃ������Ƃ��l��
�����B���ɁA���ꂪ�����ł���A�������R�c��E��C������̎����Ԕr�o�K�X���ψ���̊w�ҁE����
�́A���{���d�ʎԁi���g���b�N�E�o�X�j��NO���K�������̃��x���������ł��ɂ����邽�߂̊�����ϋɓI�ɍs���Ă��邱
�ƂɂȂ�B����ɂ��āA��ʍ����̕M�҂ɂ͐^����m��R���������A�����Ԕr�o�K�X���ψ���̊w�ҁE���Ƃ�
��ӌ����f���Č��������̂ł���B
�~�́A�f�B�[�[���̂m�n���팸�ƔR�����̈ꋓ�����̋Z�p���I�ɂ��ڏq���Ă���悤�ɁA�����Ԕr�o�K�X���ψ�
��̊w�ҁE���Ƃ��A�uJE�O�T���[�h���̃z�b�g�X�^�[�g�������R�[���h�X�^�[�g�����ɂ�����NO���팸�v�A�u�d��
�ԃ��[�h�R��̍팸�v�ɋɂ߂ėL�����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p���Ӑ}�I�ɖ����E
�َE�������ʁA�������R�c��E��C��������u��\�����\�i2010�N���\�j��NO�� �� 0.4 g/��W���v�́A�u��
�������\�i2005�N���\�j�ɋL�ڂ́u����ڕWNO�� �� 0.23 g/��W���v�������Ɋɘa������Ȃ������Ƃ��l��
�����B���ɁA���ꂪ�����ł���A�������R�c��E��C������̎����Ԕr�o�K�X���ψ���̊w�ҁE����
�́A���{���d�ʎԁi���g���b�N�E�o�X�j��NO���K�������̃��x���������ł��ɂ����邽�߂̊�����ϋɓI�ɍs���Ă��邱
�ƂɂȂ�B����ɂ��āA��ʍ����̕M�҂ɂ͐^����m��R���������A�����Ԕr�o�K�X���ψ���̊w�ҁE���Ƃ�
��ӌ����f���Č��������̂ł���B
�@�����͌����Ă��A�u��\�����\�i2010�N���\�j�v�ł́A�u��\�����\�i2010�N���\�j��NO�� �� 0.4 g/��W���v���u�攪
�����\�i2005�N���\�j�ɋL�ڂ̒���ڕWNO�� �� 0.23 g/��W���v�Ɠ����ł���q�ׂ��Ă��邱�Ƃ͎����ł�
��B�����āA����́A�N�����Ă��H�w�I�Ɍ��ĈӖ��s���ɂ����v���Ȃ��L�ړ��e�ł����B���̗��R�́A�����u��\
�����\�i2010�N���\�j�v�̋L�ړ��e�����t�ʂ�ɐM����A�d�ʎԂ̎���NO���K���l�i��2016�N���{�\��j�́ANO��
�� 0.23 g/��W���ɑ������邱�ƂɂȂ�A������NO�� �� 0.27 g/kWh�i��2010�N�K���j����������NO���̃��x���ɂȂ��
���_�t�����邱�ƂɂȂ�B�������A�����̐��E�ł́A�u��\�����\�i2010�N���\�j�v�̒ʂ���d�ʎԂ̎���NO���K���l
�i��2016�N���{�\��j�����{���ꂽ�ꍇ�́ANO�� �� 0.4 g/��W���̋K�����s����Ɛ��������B���������āA�u��\��
���\�i2010�N���\�j��NO�� �� 0.4 g/��W���v���u�攪�����\�i2005�N���\�j�ɋL�ڂ̒���ڕWNO�� �� 0.23 g/��W���v�Ɠ�
���ł���ƋL�ڂ���Ă���u��\�����\�i2010�N���\�j�v�̋L�ړ��e�̈Ӗ��́A�M�҂ɂ͑S�������ł��Ȃ����Ƃł���B
�����\�i2005�N���\�j�ɋL�ڂ̒���ڕWNO�� �� 0.23 g/��W���v�Ɠ����ł���q�ׂ��Ă��邱�Ƃ͎����ł�
��B�����āA����́A�N�����Ă��H�w�I�Ɍ��ĈӖ��s���ɂ����v���Ȃ��L�ړ��e�ł����B���̗��R�́A�����u��\
�����\�i2010�N���\�j�v�̋L�ړ��e�����t�ʂ�ɐM����A�d�ʎԂ̎���NO���K���l�i��2016�N���{�\��j�́ANO��
�� 0.23 g/��W���ɑ������邱�ƂɂȂ�A������NO�� �� 0.27 g/kWh�i��2010�N�K���j����������NO���̃��x���ɂȂ��
���_�t�����邱�ƂɂȂ�B�������A�����̐��E�ł́A�u��\�����\�i2010�N���\�j�v�̒ʂ���d�ʎԂ̎���NO���K���l
�i��2016�N���{�\��j�����{���ꂽ�ꍇ�́ANO�� �� 0.4 g/��W���̋K�����s����Ɛ��������B���������āA�u��\��
���\�i2010�N���\�j��NO�� �� 0.4 g/��W���v���u�攪�����\�i2005�N���\�j�ɋL�ڂ̒���ڕWNO�� �� 0.23 g/��W���v�Ɠ�
���ł���ƋL�ڂ���Ă���u��\�����\�i2010�N���\�j�v�̋L�ړ��e�̈Ӗ��́A�M�҂ɂ͑S�������ł��Ȃ����Ƃł���B
�@�܂��A�č������ɂ���^�g���b�N��NO���K�����{�s����������{���{�̑Ӗ��ɏڏq���Ă���悤�ɁA���\�����\
�i��2010�N7���j�ɂ��A�d�ʎԁi���g���b�N�E�o�X�j�Ɋւ��A�č���NO�� �� 0.27 g/kWh�i��2010�N�K���j�����啝��
�ɂ�NO�� �� 0.4 g/kWh��NOx�K����2016�N�Ɏ��{�����ƍl������B���̏ꍇ�A�펯�I�ɂ́A���{�̑����̍���
�́A�u�č������啝�Ɋɂ����{�̏d�ʎԂ�NO���K���v�ɒǂ����܂ꂽ�Ƃ̔F���������̂Ɨ\�z�����B���̂悤��
�F������{�̍����Ɏ������Ȃ��悤�ɂ��邽�߁A�������R�c��E��C������̎����Ԕr�o�K�X���ψ���̊w
�ҁE���Ƃ́A�u��\�����\�i2010�N���\�j�v�ł́A�u��\�����\�i2010�N���\�j��NO�� �� 0.4 g/��W���v���u�攪�����\
�i2005�N���\�j�ɋL�ڂ̒���ڕWNO�� �� 0.23 g/��W���v�Ɠ����ł���Ƌ����ɋL�ڂ��ꂽ�\�����ے�ł��Ȃ��B����
�悤�Ȍ�����������e�́u��\�����\�i2010�N���\�j�v�����\�E���\���邱�Ƃɂ���āA�߂������i��2016�N�j�̓��{���d
�ʎԁi���g���b�N�E�o�X�j��NO�� �� 0.4 g/��W����NO���K���́A�u�z�b�g�X�^�[�g�����v�Ɓu�R�[���h�X�^�[�g�����v�̗�������
������{����Ă����č���NO�� �� 0.27 g/kWh�i��2010�N�K���j�Ɠ����̌������ł���Ƃ̌�����F���������ɐA����
���邽�߂̍��\�s�ׂ̂悤�ɂ��v���邪�A�@���Ȃ��̂ł��낤���B
�i��2010�N7���j�ɂ��A�d�ʎԁi���g���b�N�E�o�X�j�Ɋւ��A�č���NO�� �� 0.27 g/kWh�i��2010�N�K���j�����啝��
�ɂ�NO�� �� 0.4 g/kWh��NOx�K����2016�N�Ɏ��{�����ƍl������B���̏ꍇ�A�펯�I�ɂ́A���{�̑����̍���
�́A�u�č������啝�Ɋɂ����{�̏d�ʎԂ�NO���K���v�ɒǂ����܂ꂽ�Ƃ̔F���������̂Ɨ\�z�����B���̂悤��
�F������{�̍����Ɏ������Ȃ��悤�ɂ��邽�߁A�������R�c��E��C������̎����Ԕr�o�K�X���ψ���̊w
�ҁE���Ƃ́A�u��\�����\�i2010�N���\�j�v�ł́A�u��\�����\�i2010�N���\�j��NO�� �� 0.4 g/��W���v���u�攪�����\
�i2005�N���\�j�ɋL�ڂ̒���ڕWNO�� �� 0.23 g/��W���v�Ɠ����ł���Ƌ����ɋL�ڂ��ꂽ�\�����ے�ł��Ȃ��B����
�悤�Ȍ�����������e�́u��\�����\�i2010�N���\�j�v�����\�E���\���邱�Ƃɂ���āA�߂������i��2016�N�j�̓��{���d
�ʎԁi���g���b�N�E�o�X�j��NO�� �� 0.4 g/��W����NO���K���́A�u�z�b�g�X�^�[�g�����v�Ɓu�R�[���h�X�^�[�g�����v�̗�������
������{����Ă����č���NO�� �� 0.27 g/kWh�i��2010�N�K���j�Ɠ����̌������ł���Ƃ̌�����F���������ɐA����
���邽�߂̍��\�s�ׂ̂悤�ɂ��v���邪�A�@���Ȃ��̂ł��낤���B
�@���͂Ƃ�����A�C���x�~�G���W���ɂ���^�g���b�N�̒�R����C���x�~�́A�f�B�[�[���̂m�n���팸�ƔR�����
�̈ꋓ�����̋Z�p���I�ɏڏq���Ă���悤�ɁA�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p�����p������
�A�R�[���h�X�^�[�g�������������ꂽ�ꍇ�ł��d�ʎԂ̑攪�����\�i��2005�N�j���m�n������ڕW�ł���m�n�� �� 0.
23 g/kWh���B���ł����ɁA2015�N�x�d�ʎԔR������ �T�� ���x�̔R������オ�\�ƂȂ�Ɨ\�z�����B����
���A�������R�c��E��C������̎����Ԕr�o�K�X���ψ���̊w�ҁE���Ƃ́ANO���팸�ƔR����P�ɋɂ߂�
�L�����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p�����������E�َE���A�u��\�����\�i2010�N���\�j�v�̒��Ɂu��
�\�����\�i2010�N���\�j��NO�� �� 0.4 g/��W���v���u�攪�����\�i2005�N���\�j�̒���ڕWNO�� �� 0.23 g/��W���v�Ɠ���
�ł���Ƃ̈Ӗ��s���ȋL�ڂ��s���Ă���̂ł���B
�̈ꋓ�����̋Z�p���I�ɏڏq���Ă���悤�ɁA�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p�����p������
�A�R�[���h�X�^�[�g�������������ꂽ�ꍇ�ł��d�ʎԂ̑攪�����\�i��2005�N�j���m�n������ڕW�ł���m�n�� �� 0.
23 g/kWh���B���ł����ɁA2015�N�x�d�ʎԔR������ �T�� ���x�̔R������オ�\�ƂȂ�Ɨ\�z�����B����
���A�������R�c��E��C������̎����Ԕr�o�K�X���ψ���̊w�ҁE���Ƃ́ANO���팸�ƔR����P�ɋɂ߂�
�L�����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p�����������E�َE���A�u��\�����\�i2010�N���\�j�v�̒��Ɂu��
�\�����\�i2010�N���\�j��NO�� �� 0.4 g/��W���v���u�攪�����\�i2005�N���\�j�̒���ڕWNO�� �� 0.23 g/��W���v�Ɠ���
�ł���Ƃ̈Ӗ��s���ȋL�ڂ��s���Ă���̂ł���B
�@�����āA���{�̏d�ʎԁi���g���b�N�E�o�X�j�Ɋւ��A�č���NO�� �� 0.27 g/kWh�i��2010�N�K���j�����啝�Ɋɂ�NO��
�� 0.4 g/kWh��NOx�K����2016�N�Ɏ��{���ׂ��ł���Ƃ���\�����\�i2010�N���\�j������b�ɒ�o���Ă��Ă���
���߁A�߂������ɂ����Ă̓��{���d�ʎԁi���g���b�N�E�o�X�j��NO���K���́A�č��ɔ�ׂđ啝�Ɋɘa���ꂽ���p
�����邱�ƂɂȂ�B���̍ő�̌����́A2005�N3��3���ɓ������J����A2006�N4���ɂ͕M�҂��z�[���y�[�W�Ɍf�ڂ�
�Ă����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p�������Ԕr�o�K�X���ψ���̊w�ҁE���Ƃ������E��
�E���A�r�����Ă��邱�Ƃ������Ɛ��@�����B�����āA�d�ʎԁi���g���b�N�E�o�X�j�́uNO���팸�v�Ɓu�R����P�v�̗L���ȋZ
�p�����o���Ă��Ȃ������F�����Ă��Ȃ���A�uNO���팸�v�Ɓu�R����P�v�̗����ɗL�����C���x�~�G���W���i�������J
2005-54771�j�̓����Z�p�̖����E�َE����u�₹�䖝�v���A�����Ԕr�o�K�X���ψ���̊w�ҁE���Ƃ́A�����
���X�Ƒ����鏊���ł��낤���B
�� 0.4 g/kWh��NOx�K����2016�N�Ɏ��{���ׂ��ł���Ƃ���\�����\�i2010�N���\�j������b�ɒ�o���Ă��Ă���
���߁A�߂������ɂ����Ă̓��{���d�ʎԁi���g���b�N�E�o�X�j��NO���K���́A�č��ɔ�ׂđ啝�Ɋɘa���ꂽ���p
�����邱�ƂɂȂ�B���̍ő�̌����́A2005�N3��3���ɓ������J����A2006�N4���ɂ͕M�҂��z�[���y�[�W�Ɍf�ڂ�
�Ă����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p�������Ԕr�o�K�X���ψ���̊w�ҁE���Ƃ������E��
�E���A�r�����Ă��邱�Ƃ������Ɛ��@�����B�����āA�d�ʎԁi���g���b�N�E�o�X�j�́uNO���팸�v�Ɓu�R����P�v�̗L���ȋZ
�p�����o���Ă��Ȃ������F�����Ă��Ȃ���A�uNO���팸�v�Ɓu�R����P�v�̗����ɗL�����C���x�~�G���W���i�������J
2005-54771�j�̓����Z�p�̖����E�َE����u�₹�䖝�v���A�����Ԕr�o�K�X���ψ���̊w�ҁE���Ƃ́A�����
���X�Ƒ����鏊���ł��낤���B
�����āA���̈���ŁA�����Ԕr�o�K�X���ψ���̊w�ҁE���Ƃ́A���ꂩ����u�z�b�g�X�^�[�g������NO���팸�v�A�u�R
�[���h�X�^�[�g������NO���팸�v�A�u�d�ʎԃ��[�h�R��̉��P�v�A�uFPF���u�̃t�B���^�[�̋����Đ��p�x�̍팸�v���d��
�ԁi���g���b�N�E�o�X�j�p�f�B�[�[���G���W���̉������ׂ��d�v�ۑ�ł���ƁA���l�ɋ��ё�����̂ł��낤���B�Ȃ��A��
�\�����\�i2010�N���\�j�ɂ́A�C���x�~�G���W���ɂ���^�g���b�N�̒�R��ɂ��ڏq���Ă���悤�ɁA�R����P��
���ẮA�d�ʎԃ��[�h�R������P���ʂ��P���������u2�i�ߋ��v�A�uEGR���̌���i�ꕔ�ɂ�LP-EGR�̗p�j�v�A�u�R��
���ˈ��͂̌����PCI�R�āv�A�u�^�[�{�R���p�E���h�v���́u�K���N�^�v�E�u�|���R�c�v���Z�p�����X�Ɨ���Ă���B����
���A�u�R�[���h�X�^�[�g������NO���팸�v�̋Z�p�ɂ��ẮA�u�K���N�^�v�E�u�|���R�c�v�ɗނ���Z�p�������L�ڂł��Ă���
���̂ł���B���������āA�����Ԕr�o�K�X���ψ���̊w�ҁE���Ƃ́A�d�ʎԗp�f�B�[�[���G���W���́u�R�[���h�X�^
�[�g������NO���팸�v�̋Z�p�I�ۑ����������Z�p���������L���Ă��Ȃ��ƌ���̂��Ó��̂悤�ł���B���̏�
����ƁA�����Ԕr�o�K�X���ψ���̊w�ҁE���Ƃ́A�f�B�[�[���G���W���́u�z�b�g�X�^�[�g������NO���팸�v�A�u�R�[
���h�X�^�[�g������NO���팸�v�A�u�d�ʎԃ��[�h�R��̉��P�v�A�uFPF���u�̃t�B���^�[�̋����Đ��p�x�̍팸�v�̉ۑ��
���ɗL�����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p���E�َE���Ȃ���A���̂��̃f�B�[�[���G���W
���̉ۑ�����̗L���ȕ���������E��Ă��邱�Ƃ��ł��Ȃ��X�Ԃ��N���Ă���悤�Ɏv����A�@���Ȃ��̂ł��낤
���B
�[���h�X�^�[�g������NO���팸�v�A�u�d�ʎԃ��[�h�R��̉��P�v�A�uFPF���u�̃t�B���^�[�̋����Đ��p�x�̍팸�v���d��
�ԁi���g���b�N�E�o�X�j�p�f�B�[�[���G���W���̉������ׂ��d�v�ۑ�ł���ƁA���l�ɋ��ё�����̂ł��낤���B�Ȃ��A��
�\�����\�i2010�N���\�j�ɂ́A�C���x�~�G���W���ɂ���^�g���b�N�̒�R��ɂ��ڏq���Ă���悤�ɁA�R����P��
���ẮA�d�ʎԃ��[�h�R������P���ʂ��P���������u2�i�ߋ��v�A�uEGR���̌���i�ꕔ�ɂ�LP-EGR�̗p�j�v�A�u�R��
���ˈ��͂̌����PCI�R�āv�A�u�^�[�{�R���p�E���h�v���́u�K���N�^�v�E�u�|���R�c�v���Z�p�����X�Ɨ���Ă���B����
���A�u�R�[���h�X�^�[�g������NO���팸�v�̋Z�p�ɂ��ẮA�u�K���N�^�v�E�u�|���R�c�v�ɗނ���Z�p�������L�ڂł��Ă���
���̂ł���B���������āA�����Ԕr�o�K�X���ψ���̊w�ҁE���Ƃ́A�d�ʎԗp�f�B�[�[���G���W���́u�R�[���h�X�^
�[�g������NO���팸�v�̋Z�p�I�ۑ����������Z�p���������L���Ă��Ȃ��ƌ���̂��Ó��̂悤�ł���B���̏�
����ƁA�����Ԕr�o�K�X���ψ���̊w�ҁE���Ƃ́A�f�B�[�[���G���W���́u�z�b�g�X�^�[�g������NO���팸�v�A�u�R�[
���h�X�^�[�g������NO���팸�v�A�u�d�ʎԃ��[�h�R��̉��P�v�A�uFPF���u�̃t�B���^�[�̋����Đ��p�x�̍팸�v�̉ۑ��
���ɗL�����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p���E�َE���Ȃ���A���̂��̃f�B�[�[���G���W
���̉ۑ�����̗L���ȕ���������E��Ă��邱�Ƃ��ł��Ȃ��X�Ԃ��N���Ă���悤�Ɏv����A�@���Ȃ��̂ł��낤
���B
�@�����Ƃ��A����܂��������R�c��E��C������̎����Ԕr�o�K�X���ψ���̊w�ҁE���Ƃ��g���b�N��
�[�J���C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p�����p�����邱�Ƃ�ϋɓI�ɐ������Ă���A��
�݂̃f�B�[�[���G���W���́u�d�ʎԃ��[�h�R��̉��P�v��uFPF���u�̋����Đ��p�x�̍팸�v�̉ۑ��������
����W�]���J�������Ƃ����A2016�N�Ɏ��{�\��ł���d�ʎԁi���g���b�N�E�o�X�j�̓��{�̎���NO���K����2010
�N���č��d�ʎ�Nox�K���i�m�n�� �� 0.27 g/kWh�j�Ɠ����̃��x���ł���攪�����\�i��2005�N�j���m�n�������
�W�̂m�n�� �� 0.23 g/kWh�Ƃ��邱�Ƃ��\�ł������Ɛ��������B���̂悤���C���x�~�G���W���i�������J2005-
54771�j�̓����Z�p�������E�َE���������Ԕr�o�K�X���ψ���̊w�ҁE���Ƃ̕s�������s�ׂ��A���݂̓��{��
�d�ʎԁi���g���b�N�E�o�X�j�ɂ�����NO���K�������̒x���������N�����Ă����ȗv���ƍl������B���̕M�҂̈ӌ���
���āA�����Ԕr�o�K�X���ψ���̊w�ҁE���Ƃ̔��_��Ƃ��������ė~�������̂ł���B�܂��A�ȏ�̂悤��
���Ƃ������ł�����A�������R�c��E��C������̎����Ԕr�o�K�X���ψ���̊w�ҁE���Ƃ́A���{���{��
���l�ɏ�����l�ԂƂ��Ă̖{���̐Ӗ��ł��鍑���ɑ��鐽�ӂ����d�̋`������傫����E���Ă���悤�Ɏv�����A
�@���Ȃ��̂ł��낤���B
�[�J���C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p�����p�����邱�Ƃ�ϋɓI�ɐ������Ă���A��
�݂̃f�B�[�[���G���W���́u�d�ʎԃ��[�h�R��̉��P�v��uFPF���u�̋����Đ��p�x�̍팸�v�̉ۑ��������
����W�]���J�������Ƃ����A2016�N�Ɏ��{�\��ł���d�ʎԁi���g���b�N�E�o�X�j�̓��{�̎���NO���K����2010
�N���č��d�ʎ�Nox�K���i�m�n�� �� 0.27 g/kWh�j�Ɠ����̃��x���ł���攪�����\�i��2005�N�j���m�n�������
�W�̂m�n�� �� 0.23 g/kWh�Ƃ��邱�Ƃ��\�ł������Ɛ��������B���̂悤���C���x�~�G���W���i�������J2005-
54771�j�̓����Z�p�������E�َE���������Ԕr�o�K�X���ψ���̊w�ҁE���Ƃ̕s�������s�ׂ��A���݂̓��{��
�d�ʎԁi���g���b�N�E�o�X�j�ɂ�����NO���K�������̒x���������N�����Ă����ȗv���ƍl������B���̕M�҂̈ӌ���
���āA�����Ԕr�o�K�X���ψ���̊w�ҁE���Ƃ̔��_��Ƃ��������ė~�������̂ł���B�܂��A�ȏ�̂悤��
���Ƃ������ł�����A�������R�c��E��C������̎����Ԕr�o�K�X���ψ���̊w�ҁE���Ƃ́A���{���{��
���l�ɏ�����l�ԂƂ��Ă̖{���̐Ӗ��ł��鍑���ɑ��鐽�ӂ����d�̋`������傫����E���Ă���悤�Ɏv�����A
�@���Ȃ��̂ł��낤���B
�@�������A�f�B�[�[���G���W���́u�z�b�g�X�^�[�g��������уR�[���h�X�^�[�g������NO���팸�v�A�u�d�ʎԃ��[�h�R��̉�
�P�v�A�uFPF���u�̃t�B���^�[�̋����Đ��p�x�̍팸�v�̖ʂ��C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j���D�ꂽ�@�\�E
���ʂ���������Z�p�ł��邱�Ƃ������Ԕr�o�K�X���ψ���̊w�ҁE���Ƃ������ł��Ȃ��ꍇ�ɂ́A������
�r�o�K�X���ψ�����������Z�p���E�َE���邱�Ƃ����ӁE���肵�����Ƃ́A���R�̐���s���ł���B�܂�A��
���Ԕr�o�K�X���ψ���C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p�̋@�\�E���ʂ��[���ł��Ȃ�����
�Ɂu�|���R�c�Z�p�v�E�u�K���N�^�Z�p�v�Ɣ��f���A�r�������\�����ے�ł��Ȃ��B���̏ꍇ�ɂ́A�����Ԕr�o�K�X����
����́A�w�ҁE���ƂƂ��Ă̓��R�̏��u���s�������̂ƍl������B�����āA�����Ԕr�o�K�X���ψ���̊w�ҁE��
��Ƃ́A���{���{�̌��l�Ƃ��Ă̖{���̐Ӗ��ł��鍑���ɑ��鐽�ӂ����d�̋`�����ʂ����Ă��邱�ƂɂȂ�B��
���낪�A���̏ꍇ�ɂ́A�����Ԕr�o�K�X���ψ���́A�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j���D�ꂽ�@�\�E��
�ʂ𗝉�����\�͂Ɍ�����l�B�̏W�c�ł���A���̈ψ���w�ҁE���ƂƂ��Ă̔\�́E�����ɖ�肪����l�B�ō\
������Ă��邱�ƂɂȂ�B�������A�����ψ�����{���\�����w�ҁE���Ƃō\������Ă��邽�߁A�C���x�~�G���W��
�i�������J2005-54771�j���D�ꂽ�@�\�E���ʂ𗝉�����\�͂Ɍ������Ƃ́A�펯�I�ɂ͍l�����Ȃ����Ƃł���B
�P�v�A�uFPF���u�̃t�B���^�[�̋����Đ��p�x�̍팸�v�̖ʂ��C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j���D�ꂽ�@�\�E
���ʂ���������Z�p�ł��邱�Ƃ������Ԕr�o�K�X���ψ���̊w�ҁE���Ƃ������ł��Ȃ��ꍇ�ɂ́A������
�r�o�K�X���ψ�����������Z�p���E�َE���邱�Ƃ����ӁE���肵�����Ƃ́A���R�̐���s���ł���B�܂�A��
���Ԕr�o�K�X���ψ���C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p�̋@�\�E���ʂ��[���ł��Ȃ�����
�Ɂu�|���R�c�Z�p�v�E�u�K���N�^�Z�p�v�Ɣ��f���A�r�������\�����ے�ł��Ȃ��B���̏ꍇ�ɂ́A�����Ԕr�o�K�X����
����́A�w�ҁE���ƂƂ��Ă̓��R�̏��u���s�������̂ƍl������B�����āA�����Ԕr�o�K�X���ψ���̊w�ҁE��
��Ƃ́A���{���{�̌��l�Ƃ��Ă̖{���̐Ӗ��ł��鍑���ɑ��鐽�ӂ����d�̋`�����ʂ����Ă��邱�ƂɂȂ�B��
���낪�A���̏ꍇ�ɂ́A�����Ԕr�o�K�X���ψ���́A�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j���D�ꂽ�@�\�E��
�ʂ𗝉�����\�͂Ɍ�����l�B�̏W�c�ł���A���̈ψ���w�ҁE���ƂƂ��Ă̔\�́E�����ɖ�肪����l�B�ō\
������Ă��邱�ƂɂȂ�B�������A�����ψ�����{���\�����w�ҁE���Ƃō\������Ă��邽�߁A�C���x�~�G���W��
�i�������J2005-54771�j���D�ꂽ�@�\�E���ʂ𗝉�����\�͂Ɍ������Ƃ́A�펯�I�ɂ͍l�����Ȃ����Ƃł���B
�@���������āA�����Ԕr�o�K�X���ψ���̊w�ҁE���Ƃ́A�f�B�[�[���G���W���́u�z�b�g�X�^�[�g��������уR�[���h
�X�^�[�g������NO���팸�v�A�u�d�ʎԃ��[�h�R��̉��P�v�A�uFPF���u�̃t�B���^�[�̋����Đ��p�x�̍팸�v�̋@�\�E����
�������C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p���Ӑ}�I�ɖ����E�َE�E�B����}���Ă���ƍl�����
���Ó��̂悤�Ɏv����B���̂悤�Ȍ����́A�M�҂���w�ɍ˂ȃ|���R�c���Z�p���ł��邪�̂̑傫�ȉ߂��ł���A��
�������A�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j��D�ꂽ�����Z�p�Ƃ̐M�����݂��琶�����Ƃ�P����̉ߌ�E���
���ȕM�҂̖ϑz�ɉ߂��Ȃ��ꍇ���l������B����ɂ��ẮA���̃z�[���y�[�W�����������������ǎҎ��g�Ŕ��f
���������������B
�X�^�[�g������NO���팸�v�A�u�d�ʎԃ��[�h�R��̉��P�v�A�uFPF���u�̃t�B���^�[�̋����Đ��p�x�̍팸�v�̋@�\�E����
�������C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p���Ӑ}�I�ɖ����E�َE�E�B����}���Ă���ƍl�����
���Ó��̂悤�Ɏv����B���̂悤�Ȍ����́A�M�҂���w�ɍ˂ȃ|���R�c���Z�p���ł��邪�̂̑傫�ȉ߂��ł���A��
�������A�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j��D�ꂽ�����Z�p�Ƃ̐M�����݂��琶�����Ƃ�P����̉ߌ�E���
���ȕM�҂̖ϑz�ɉ߂��Ȃ��ꍇ���l������B����ɂ��ẮA���̃z�[���y�[�W�����������������ǎҎ��g�Ŕ��f
���������������B
�@�����͌����Ă��A�������R�c��E��C������̎����Ԕr�o�K�X���ψ���̊w�ҁE���Ƃ́A2005�N3��3����
�������J����A2006�N4���ɂ͕M�҂��z�[���y�[�W�Ɍf�ڂ��Ă����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓���
�Z�p���\�����\�i2010�N���\�j�̒��ɂ͋L�ڂ����A�����E�َE�A�Ⴕ���͔r�����Ă��邱�Ƃ����́A�m���鎖���ł�
��B�����āA��\�����\�i2010�N���\�j�ɂ́A���{�̏d�ʎԁi���g���b�N�E�o�X�j�̉ۑ�����������i�E���@�ɂ��āA
�u�d�ʎԃ��[�h�R��̉��P�v�ɂ��Ă͋@�\�E���\�̗���u�|���R�c�v�E�u�K���N�^�v�̋Z�p����Ă��邪�A�u�z�b�g�X�^
�[�g��������уR�[���h�X�^�[�g������NO���팸�v�ɂ��Ă��Z�p�I�Ȏ������F���ł������Ƃ���R���鎖���ł���B
���ɁA��\�����\�i2010�N���\�j�ł́A�u�攪�����\�i2005�N���\�j�v�̒���ڕW�ł���NO�� �� 0.23 g/��W���̂ɂ�
�����ŁA���{�̎�����NO���K���l�Ƃ���NO���̔r�o���x����č������啝�Ɋɘa����NO�� �� 0.4 g/��W�������\��
��Ă���B���̎�����NO���K���l��NO�� �� 0.4 g/��W���̊ɂ�NO�����x�������肳�ꂽ�����̈�Ƃ��āA�R�[���h�X
�^�[�g�����̐V�K�������������Ă��邱�Ƃ��琄�@����ƁA�����Ԕr�o�K�X���ψ���̊w�ҁE���Ƃ́A��\��
���\�i2010�N���\�j�̍쐬���ɂ́A�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p�ȊO�́u�R�[���h�X�^�[�g��
����NO���팸�v���\�ɂ���m���E���������L���Ă��Ȃ���������̂��Ó��ƍl������B
�������J����A2006�N4���ɂ͕M�҂��z�[���y�[�W�Ɍf�ڂ��Ă����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓���
�Z�p���\�����\�i2010�N���\�j�̒��ɂ͋L�ڂ����A�����E�َE�A�Ⴕ���͔r�����Ă��邱�Ƃ����́A�m���鎖���ł�
��B�����āA��\�����\�i2010�N���\�j�ɂ́A���{�̏d�ʎԁi���g���b�N�E�o�X�j�̉ۑ�����������i�E���@�ɂ��āA
�u�d�ʎԃ��[�h�R��̉��P�v�ɂ��Ă͋@�\�E���\�̗���u�|���R�c�v�E�u�K���N�^�v�̋Z�p����Ă��邪�A�u�z�b�g�X�^
�[�g��������уR�[���h�X�^�[�g������NO���팸�v�ɂ��Ă��Z�p�I�Ȏ������F���ł������Ƃ���R���鎖���ł���B
���ɁA��\�����\�i2010�N���\�j�ł́A�u�攪�����\�i2005�N���\�j�v�̒���ڕW�ł���NO�� �� 0.23 g/��W���̂ɂ�
�����ŁA���{�̎�����NO���K���l�Ƃ���NO���̔r�o���x����č������啝�Ɋɘa����NO�� �� 0.4 g/��W�������\��
��Ă���B���̎�����NO���K���l��NO�� �� 0.4 g/��W���̊ɂ�NO�����x�������肳�ꂽ�����̈�Ƃ��āA�R�[���h�X
�^�[�g�����̐V�K�������������Ă��邱�Ƃ��琄�@����ƁA�����Ԕr�o�K�X���ψ���̊w�ҁE���Ƃ́A��\��
���\�i2010�N���\�j�̍쐬���ɂ́A�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p�ȊO�́u�R�[���h�X�^�[�g��
����NO���팸�v���\�ɂ���m���E���������L���Ă��Ȃ���������̂��Ó��ƍl������B
�@���������āA���{���d�ʎԁi���g���b�N�E�o�X�j�̎���NO���K���ɂ����A�č���NO�� �� 0.27 g/kWh�i��2010
�N�K���j�����啝�Ɋɂ�NO�� �� 0.4 g/kWh��NOx�K����2016�N�Ɏ��{���邱�Ƃ���\�����\�i��2010�N7
���j�ɋL�ڂ�����Ȃ������ő�̌����E���R�́A�������R�c��E��C������̎����Ԕr�o�K�X���
�ψ���̊w�ҁE���Ƃ��C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p�������E�َE�������߂ł͂�
���������������B�܂�A�����Ԕr�o�K�X���ψ���̊w�ҁE���Ƃ́A�C���x�~�G���W���i�������J2005-
54771�j�������Z�p���E�َE�A�Ⴕ���͔r�����Ȃ���A��\�����\�i2010�N���\�j�ɂ́A���{�̏d�ʎԁi���g���b
�N�E�o�X�j�ɂ����鎟����NO���K���l�Ƃ��āA�攪�����\�i2005�N���\�j�̒���ڕW�ł���NO�� �� 0.23 g/��W����NO��
�K����2016�N�Ɏ��{����|�m�ɋL�ڂł������ƍl������B�����āA��\�����\�i2010�N���\�j�ɂ́A�u��\����
�\�i2010�N���\�j��NO�� �� 0.4 g/��W���v���u�攪�����\�i2005�N���\�j�ɋL�ڂ̒���ڕWNO�� �� 0.23 g/��W���v�Ɠ���
�Ƃ̈Ӗ��s���ȓ��e�̖��l�ȋL�q���s�v�ł������Ɛ��������B
�N�K���j�����啝�Ɋɂ�NO�� �� 0.4 g/kWh��NOx�K����2016�N�Ɏ��{���邱�Ƃ���\�����\�i��2010�N7
���j�ɋL�ڂ�����Ȃ������ő�̌����E���R�́A�������R�c��E��C������̎����Ԕr�o�K�X���
�ψ���̊w�ҁE���Ƃ��C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p�������E�َE�������߂ł͂�
���������������B�܂�A�����Ԕr�o�K�X���ψ���̊w�ҁE���Ƃ́A�C���x�~�G���W���i�������J2005-
54771�j�������Z�p���E�َE�A�Ⴕ���͔r�����Ȃ���A��\�����\�i2010�N���\�j�ɂ́A���{�̏d�ʎԁi���g���b
�N�E�o�X�j�ɂ����鎟����NO���K���l�Ƃ��āA�攪�����\�i2005�N���\�j�̒���ڕW�ł���NO�� �� 0.23 g/��W����NO��
�K����2016�N�Ɏ��{����|�m�ɋL�ڂł������ƍl������B�����āA��\�����\�i2010�N���\�j�ɂ́A�u��\����
�\�i2010�N���\�j��NO�� �� 0.4 g/��W���v���u�攪�����\�i2005�N���\�j�ɋL�ڂ̒���ڕWNO�� �� 0.23 g/��W���v�Ɠ���
�Ƃ̈Ӗ��s���ȓ��e�̖��l�ȋL�q���s�v�ł������Ɛ��������B
�@�����āA���ɁA�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p���\�����\�i2010�N���\�j�ɋL�ڂ��邱�Ƃ�
�Ӑ}�I�ɔr������Ă������Ƃ������ł���A���{���\����Ɗw�ҁE���Ƃ̏W�c�Ɖ]���������Ԕr�o�K�X���
�ψ���́A���{���d�ʎԁi���g���b�N�E�o�X�j�ɂ�����NO���̋K�������̐i�W��j�ލs�ׁE������M�S�ɍs���Ă���悤
�Ɏv���邪�A�@���Ȃ��̂ł��낤���B�����āA�����Ԕr�o�K�X���ψ���̊w�ҁE���Ƃ́A�u�z�b�g�X�^�[�g�����ƃR�[
���h�X�^�[�g������NO���팸�v����сu�d�ʎԃ��[�h�R��̉��P�v���D�ꂽ�@�\�E���ʂ������C���x�~�G���W���i��
�����J2005-54771�j�̓����Z�p�������E�َE�E�r����������ȍs�ׂɂ��A�����̓��{�̏d�ʎԁi���g���b�N�E�o�X�jNO
���K���l���u�攪�����\�i2005�N���\�j�v�̒���ڕW�ł���NO�� �� 0.23 g/��W�̃��x���ɋ����ł��Ȃ����ꎩ���̏�
���Ɋׂ��Ă���Ɖ]���������B���Ƃ��A�n���������Ƃł͂Ȃ����낤���B���̌��ʁA�������R�c��E��C�������
�����Ԕr�o�K�X���ψ���̊w�ҁE���Ƃ́A���ꂩ����u2015�N�x�d�ʎԔR���̑��݂Ƃ��̋�����}
�邽�߂�����ڕW��NO�� �� 0.23 g/��W�̒B��������v�Ƃ��A�u���{�ł̔r�o�K�X�����ɂ������R�[���h�X�^�[
�g�����̐V���ȓ����̂��߂�����ڕW��NO�� �� 0.23 g/��W�̒B���������v�Ƃ̖�̕�����Ȃ����Ƃ𗝗R��
�����Ȃ���A�u�攪�����\�i2005�N���\�j�v�ɋL�ڂ��ꂽ�d�ʎԂ̒���ڕW�ł���NO�� �� 0.23 g/��W�̋K��
�����̎��{��摗�肵�悤�Ƃ��Ă���悤�ł���B���̂��Ƃ́A��^�g���b�N��NO���팸�ƔR�����ɗL���ȋC���x�~
��َE����w�ҏ����̃y�[�W�ɂ��G��Ă���̂ŁA�����̂�����͌䗗�������������B
�Ӑ}�I�ɔr������Ă������Ƃ������ł���A���{���\����Ɗw�ҁE���Ƃ̏W�c�Ɖ]���������Ԕr�o�K�X���
�ψ���́A���{���d�ʎԁi���g���b�N�E�o�X�j�ɂ�����NO���̋K�������̐i�W��j�ލs�ׁE������M�S�ɍs���Ă���悤
�Ɏv���邪�A�@���Ȃ��̂ł��낤���B�����āA�����Ԕr�o�K�X���ψ���̊w�ҁE���Ƃ́A�u�z�b�g�X�^�[�g�����ƃR�[
���h�X�^�[�g������NO���팸�v����сu�d�ʎԃ��[�h�R��̉��P�v���D�ꂽ�@�\�E���ʂ������C���x�~�G���W���i��
�����J2005-54771�j�̓����Z�p�������E�َE�E�r����������ȍs�ׂɂ��A�����̓��{�̏d�ʎԁi���g���b�N�E�o�X�jNO
���K���l���u�攪�����\�i2005�N���\�j�v�̒���ڕW�ł���NO�� �� 0.23 g/��W�̃��x���ɋ����ł��Ȃ����ꎩ���̏�
���Ɋׂ��Ă���Ɖ]���������B���Ƃ��A�n���������Ƃł͂Ȃ����낤���B���̌��ʁA�������R�c��E��C�������
�����Ԕr�o�K�X���ψ���̊w�ҁE���Ƃ́A���ꂩ����u2015�N�x�d�ʎԔR���̑��݂Ƃ��̋�����}
�邽�߂�����ڕW��NO�� �� 0.23 g/��W�̒B��������v�Ƃ��A�u���{�ł̔r�o�K�X�����ɂ������R�[���h�X�^�[
�g�����̐V���ȓ����̂��߂�����ڕW��NO�� �� 0.23 g/��W�̒B���������v�Ƃ̖�̕�����Ȃ����Ƃ𗝗R��
�����Ȃ���A�u�攪�����\�i2005�N���\�j�v�ɋL�ڂ��ꂽ�d�ʎԂ̒���ڕW�ł���NO�� �� 0.23 g/��W�̋K��
�����̎��{��摗�肵�悤�Ƃ��Ă���悤�ł���B���̂��Ƃ́A��^�g���b�N��NO���팸�ƔR�����ɗL���ȋC���x�~
��َE����w�ҏ����̃y�[�W�ɂ��G��Ă���̂ŁA�����̂�����͌䗗�������������B
�@
�@����A2024�N5�����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�������������ł��Ă��܂������Z�p�ł���B���̂���
���l�����āA���ɁA�����Ԕr�o�K�X���ψ���̊w�ҁE���Ƃ��d�ʎԂ̌p�����Y�Ԃɂ�����NO�� �� 0.23 g/��W��
NO���K����������10�N���x���摗��ɂ���202�S�N6���ȍ~�Ɏ{�s���鏈�u���s�����ꍇ�A�e�g���b�N���[�J�́A�C���x
�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����������ł��Ă��邽�߂ɁA���̓����Z�p���̗p����NO�� �� 0.23 g/��W�̋K
���ɓK���������g���b�N�E�o�X�i���d�ʎԁj�́A���������x�������Ɩ����s�̂��邱�Ƃ��\�ƂȂ�B�Ȃ��A202�S�N6����
�p�����Y�Ԃ�NO���K���������{�s�����ꍇ�ɂ́A�V�^�Ԃ�NOx�K�������́A2022�N�Ⴕ����2023�N�̎{�s�ƂȂ�
�̂��ʗ�ł���B
���l�����āA���ɁA�����Ԕr�o�K�X���ψ���̊w�ҁE���Ƃ��d�ʎԂ̌p�����Y�Ԃɂ�����NO�� �� 0.23 g/��W��
NO���K����������10�N���x���摗��ɂ���202�S�N6���ȍ~�Ɏ{�s���鏈�u���s�����ꍇ�A�e�g���b�N���[�J�́A�C���x
�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����������ł��Ă��邽�߂ɁA���̓����Z�p���̗p����NO�� �� 0.23 g/��W�̋K
���ɓK���������g���b�N�E�o�X�i���d�ʎԁj�́A���������x�������Ɩ����s�̂��邱�Ƃ��\�ƂȂ�B�Ȃ��A202�S�N6����
�p�����Y�Ԃ�NO���K���������{�s�����ꍇ�ɂ́A�V�^�Ԃ�NOx�K�������́A2022�N�Ⴕ����2023�N�̎{�s�ƂȂ�
�̂��ʗ�ł���B
�@�܂��A�d�ʎԂ̌p�����Y�Ԃɂ�����NO�� �� 0.23 g/��W�̐V����NO���K����202�S�N6���ȍ~�Ɏ{�s���ꂽ�ꍇ��
�́A�p�����Y�Ԃ̃g���b�N�E�o�X�́A�������̏��ł������x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p���̗p����
���邱�ƂɂȂ邽�߁A������s�̂���ۂɂ́A�g���b�N���[�J���u���ЊJ���̐V�Z�p���̗p�I�v�Ƃ̐�`���s���Ă��N��
����ᔻ���邱�Ƃ������Ȃ�̂ł����B����́A�g���b�N���[�J�ɂƂ��ẮA����Ă��Ȃ����Ƃ��B���̂悤���A������
�r�o�K�X���ψ���C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓������̏��ł��鎞����_���ē��{���d�ʎԂ�
NO���K���������Ӑ}�I�ɍ��肵���ꍇ�ɂ́A�Ƒ��Ȏ�i��p�����g���b�N���[�J�ɓ��ʂȕX���^���s�����ƂɂȂ�A
���ꓹ�f�Ǝv�����A�@���Ȃ��̂ł��낤���B�����Ƃ��A���̂悤�ȕM�҂̌����ɂ��āA�������R�c��E��C������
�̎����Ԕr�o�K�X���ψ���̊w�ҁE���Ƃ́A�S���́u�����Ⴂ�v�Ƃ̌����ł���Ȃ�A���{�͑�^�g���b�N�̐V
���Ȓ�R��E��r�o�K�X��𑁊��ɐݒ肹��I�ɏڏq���Ă���悤�ɁA���{���d�ʎԁi���g���b�N�E�o�X�j�ɂ�����
�uNO�� �� 0.23 g/��W�̒�NO����v���u2015�N�x�d�ʎԃ��[�h�R������T�����x�����サ����R���v
�Ƃ𑁋}���ݒ肷�ׂ��ƍl���邪�A�@���Ȃ��̂ł��낤���B
�́A�p�����Y�Ԃ̃g���b�N�E�o�X�́A�������̏��ł������x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p���̗p����
���邱�ƂɂȂ邽�߁A������s�̂���ۂɂ́A�g���b�N���[�J���u���ЊJ���̐V�Z�p���̗p�I�v�Ƃ̐�`���s���Ă��N��
����ᔻ���邱�Ƃ������Ȃ�̂ł����B����́A�g���b�N���[�J�ɂƂ��ẮA����Ă��Ȃ����Ƃ��B���̂悤���A������
�r�o�K�X���ψ���C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓������̏��ł��鎞����_���ē��{���d�ʎԂ�
NO���K���������Ӑ}�I�ɍ��肵���ꍇ�ɂ́A�Ƒ��Ȏ�i��p�����g���b�N���[�J�ɓ��ʂȕX���^���s�����ƂɂȂ�A
���ꓹ�f�Ǝv�����A�@���Ȃ��̂ł��낤���B�����Ƃ��A���̂悤�ȕM�҂̌����ɂ��āA�������R�c��E��C������
�̎����Ԕr�o�K�X���ψ���̊w�ҁE���Ƃ́A�S���́u�����Ⴂ�v�Ƃ̌����ł���Ȃ�A���{�͑�^�g���b�N�̐V
���Ȓ�R��E��r�o�K�X��𑁊��ɐݒ肹��I�ɏڏq���Ă���悤�ɁA���{���d�ʎԁi���g���b�N�E�o�X�j�ɂ�����
�uNO�� �� 0.23 g/��W�̒�NO����v���u2015�N�x�d�ʎԃ��[�h�R������T�����x�����サ����R���v
�Ƃ𑁋}���ݒ肷�ׂ��ƍl���邪�A�@���Ȃ��̂ł��낤���B
�@�Ȃ��A���{�̃g���b�N�E�o�X�i���d�ʎԁj�̎g�p�ߒ��Ԃɂ�����NO�� �� 0.23 g/��W�i���攪�����\�̒���ڕW�j��NO��
�K����������10�N���x���摗��ƂȂ�2024�N6���ȍ~�̎{�s�ƂȂ����ꍇ�ɂ́A�����Ԕr�o�K�X���ψ���̊w
�ҁE���Ƃ́A�g���b�N���[�J����傢�Ɋ��ӂ���邱�Ƃ͊ԈႢ�����ƍl������B�Ƃ��낪�A���̈���ł́A�������
���ɂ킽���ăg���b�N�E�o�X�ɂ�����č��Ɠ������x����NO���K��������10�N�P�ʂ̑啝�Ȑ摗��ƂȂ邽�߁A���{��
�����͑�C�����P�̒�Ɖ]���s�K�Ɍ�����ꑱ���邱�ƂɂȂ�B���̂悤�ɁA���{�̃g���b�N�E�o�X�i���d�ʎԁj��
�p�����Y�Ԃɂ�����NO�� �� 0.23 g/��W�i���攪�����\�̒���ڕW�j��NO���K����������10�N���x���摗��ɂ����
2024�N6���ȍ~�̎{�s�ƂȂ����ꍇ�ɂ́A�������R�c��E��C������̎����Ԕr�o�K�X���ψ���̊w�ҁE��
��Ƃ́A�g���b�N���[�J����́u���̐_�v�Ə^�����ł��낤���A��ʂ̍�������́u�u�a�_�v�ƌ�������A�y�̂����
�̂ł͂Ȃ����낤���B���͂Ƃ�����A���������ƁA�������R�c��E��C������̎����Ԕr�o�K�X���ψ����
�w�ҁE���Ƃ́A�M�Ғ�Ă��C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����������݂�����ԓ��ɂ����ẮA����
�����Z�p���̗p���Ȃ��Ă��K���ł���悤�ɁA��^�g���b�N�E�o�X�i���d�ʎԁj�ɂ��Ă͕č������啝�Ɋɂ�NO���K��
�̏��ێ��������邱�Ƃɖ��䖲���̂悤�Ɏv����̂ł���B�����Ƃ��A���̂悤�Ȍ����́A�M�҂����̕Ό��ƈ�R��
�ꂻ���ł��邪�A�@���Ȃ��̂ł��낤���B
�K����������10�N���x���摗��ƂȂ�2024�N6���ȍ~�̎{�s�ƂȂ����ꍇ�ɂ́A�����Ԕr�o�K�X���ψ���̊w
�ҁE���Ƃ́A�g���b�N���[�J����傢�Ɋ��ӂ���邱�Ƃ͊ԈႢ�����ƍl������B�Ƃ��낪�A���̈���ł́A�������
���ɂ킽���ăg���b�N�E�o�X�ɂ�����č��Ɠ������x����NO���K��������10�N�P�ʂ̑啝�Ȑ摗��ƂȂ邽�߁A���{��
�����͑�C�����P�̒�Ɖ]���s�K�Ɍ�����ꑱ���邱�ƂɂȂ�B���̂悤�ɁA���{�̃g���b�N�E�o�X�i���d�ʎԁj��
�p�����Y�Ԃɂ�����NO�� �� 0.23 g/��W�i���攪�����\�̒���ڕW�j��NO���K����������10�N���x���摗��ɂ����
2024�N6���ȍ~�̎{�s�ƂȂ����ꍇ�ɂ́A�������R�c��E��C������̎����Ԕr�o�K�X���ψ���̊w�ҁE��
��Ƃ́A�g���b�N���[�J����́u���̐_�v�Ə^�����ł��낤���A��ʂ̍�������́u�u�a�_�v�ƌ�������A�y�̂����
�̂ł͂Ȃ����낤���B���͂Ƃ�����A���������ƁA�������R�c��E��C������̎����Ԕr�o�K�X���ψ����
�w�ҁE���Ƃ́A�M�Ғ�Ă��C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����������݂�����ԓ��ɂ����ẮA����
�����Z�p���̗p���Ȃ��Ă��K���ł���悤�ɁA��^�g���b�N�E�o�X�i���d�ʎԁj�ɂ��Ă͕č������啝�Ɋɂ�NO���K��
�̏��ێ��������邱�Ƃɖ��䖲���̂悤�Ɏv����̂ł���B�����Ƃ��A���̂悤�Ȍ����́A�M�҂����̕Ό��ƈ�R��
�ꂻ���ł��邪�A�@���Ȃ��̂ł��낤���B
�@�Ƃ���ŁA�č������ɂ���^�g���b�N��NO���K�����{�s����������{���{�̑Ӗ��ɂ��ڏq���Ă���悤�ɁA��\����
�\�i2010�N���\�j�̒ʂ��NO�� �� 0.4 g/��W�̏d�ʎԂ�NO���K��������2016�N�Ɏ{�s���ꂽ�Ƃ��Ă��A���{���d�ʎ�
�i���g���b�N�E�o�X�j�ł́A���̌���č���NO�� �� 0.27 g/��W�i��2010�N�K���j�����啝�Ɋɂ�NO���K���̏�����
��炸�������ƂɂȂ�B���̂��߁A���{�̍����́A�č��������NOx�̑�C���ɔ����ꂽ������]�V�Ȃ��������
��Ɨ\�z�����B���̈���ł́A�g���b�N���[�J�́A�č������ɂ�NO���K���̂�������NO���팸�̌����J������p��
���č팸�ł���Ɖ]���u������肩�Ȃ�����v�̉��b����������̂Ɛ��@�����B�����̂��Ƃ��l����ƁA��\����
�\�i��2010�N���\�j���A���{�̍����ɂƂ��ẮA���Ƃ��D�܂����Ȃ����e�̂悤�Ɏv���邪�A�@���Ȃ��̂ł��낤���B����
2016�N��NO�� �� 0.4 g/��W�̂悤�ȏd�ʎԂ̊ɂ�NO���K�������{���ׂ��Ƃ����\�����\�i��2010�N���\�j���쐬��
���������R�c��E��C������̎����Ԕr�o�K�X���ψ���̊w�ҁE���Ƃ́A���ӂ�s�����ĐE����S��������
�����Ɍ����ł���̂ł��낤���B
�\�i2010�N���\�j�̒ʂ��NO�� �� 0.4 g/��W�̏d�ʎԂ�NO���K��������2016�N�Ɏ{�s���ꂽ�Ƃ��Ă��A���{���d�ʎ�
�i���g���b�N�E�o�X�j�ł́A���̌���č���NO�� �� 0.27 g/��W�i��2010�N�K���j�����啝�Ɋɂ�NO���K���̏�����
��炸�������ƂɂȂ�B���̂��߁A���{�̍����́A�č��������NOx�̑�C���ɔ����ꂽ������]�V�Ȃ��������
��Ɨ\�z�����B���̈���ł́A�g���b�N���[�J�́A�č������ɂ�NO���K���̂�������NO���팸�̌����J������p��
���č팸�ł���Ɖ]���u������肩�Ȃ�����v�̉��b����������̂Ɛ��@�����B�����̂��Ƃ��l����ƁA��\����
�\�i��2010�N���\�j���A���{�̍����ɂƂ��ẮA���Ƃ��D�܂����Ȃ����e�̂悤�Ɏv���邪�A�@���Ȃ��̂ł��낤���B����
2016�N��NO�� �� 0.4 g/��W�̂悤�ȏd�ʎԂ̊ɂ�NO���K�������{���ׂ��Ƃ����\�����\�i��2010�N���\�j���쐬��
���������R�c��E��C������̎����Ԕr�o�K�X���ψ���̊w�ҁE���Ƃ́A���ӂ�s�����ĐE����S��������
�����Ɍ����ł���̂ł��낤���B
�@�ȏ�̂悤�ɁA�����Ԕr�o�K�X���ψ���̊w�ҁE���Ƃ����s�s�E�s�𗝂Ƃ��v�����C���x�~�G���W���i�������J
2005-54771�j�̓����Z�p�������E�َE�A�Ⴕ���͔r�������s�ׂ��s�����Ƃ��Ă��A�C���^�[�l�b�g�̕��y�������݂ł́A
�߂������A���̓����Z�p���d�ʎԁi���g���b�N�E�o�X�j�́u�z�b�g�X�^�[�g��������уR�[���h�X�^�[�g������NO���팸�v�A
�u�d�ʎԃ��[�h�R��̉��P�v�A�uFPF���u�̃t�B���^�[�̋����Đ��p�x�̍팸�v�ɗL���ȓ����Z�p�ł��邱�Ƃ��A������
�f�B�[�[���G���W���Z�p�҂��F�����鎞���E����́A�����炸����������̂Ɨ\�������B���ɁA���̎��������ۂ�
�́A�����Ԕr�o�K�X���ψ���̊w�ҁE���Ƃ́A����܂łɒ������R�c��E��C���������\�����\�i2010
�N���\�j�̋L�ړ��e�����S�����苎��A����܂ł̈ӌ��E�咣�𖧂��ɓP�A�C���x�~�G���W���i�������J2005-
54771�j�̓����Z�p�̎��p���Ɍ����������J���̐��i�����H��ʊ�Ő�������̂ł��낤���B����Ƃ��A�����Ԕr�o
�K�X���ψ���̊w�ҁE���Ƃ́A����ʕ����ɖڂ����Ȃ���A�u�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�Ɋւ�
��Z�p����@�����܂Ŗ��������v�Ƃٖ̕����s���A�V�����̂ł��낤���B����̏ꍇ���A�����̐l����
��܂����s�ׂƂ��Č��w���w����Ă��d���̖������Ƃ��Ǝv����B�����āA���s�̃f�B�[�[���G���W���̉ۑ������
�����i�Ƃ��āA�߂��������C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p���m���Ɏ��p�������ƐM���Ă���
���A�ʂ����āA�M�҂̗\���ʂ�̓W�J�ɂȂ邩�ۂ��́A�u�_�݂̂��m��v�ł���B
2005-54771�j�̓����Z�p�������E�َE�A�Ⴕ���͔r�������s�ׂ��s�����Ƃ��Ă��A�C���^�[�l�b�g�̕��y�������݂ł́A
�߂������A���̓����Z�p���d�ʎԁi���g���b�N�E�o�X�j�́u�z�b�g�X�^�[�g��������уR�[���h�X�^�[�g������NO���팸�v�A
�u�d�ʎԃ��[�h�R��̉��P�v�A�uFPF���u�̃t�B���^�[�̋����Đ��p�x�̍팸�v�ɗL���ȓ����Z�p�ł��邱�Ƃ��A������
�f�B�[�[���G���W���Z�p�҂��F�����鎞���E����́A�����炸����������̂Ɨ\�������B���ɁA���̎��������ۂ�
�́A�����Ԕr�o�K�X���ψ���̊w�ҁE���Ƃ́A����܂łɒ������R�c��E��C���������\�����\�i2010
�N���\�j�̋L�ړ��e�����S�����苎��A����܂ł̈ӌ��E�咣�𖧂��ɓP�A�C���x�~�G���W���i�������J2005-
54771�j�̓����Z�p�̎��p���Ɍ����������J���̐��i�����H��ʊ�Ő�������̂ł��낤���B����Ƃ��A�����Ԕr�o
�K�X���ψ���̊w�ҁE���Ƃ́A����ʕ����ɖڂ����Ȃ���A�u�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�Ɋւ�
��Z�p����@�����܂Ŗ��������v�Ƃٖ̕����s���A�V�����̂ł��낤���B����̏ꍇ���A�����̐l����
��܂����s�ׂƂ��Č��w���w����Ă��d���̖������Ƃ��Ǝv����B�����āA���s�̃f�B�[�[���G���W���̉ۑ������
�����i�Ƃ��āA�߂��������C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p���m���Ɏ��p�������ƐM���Ă���
���A�ʂ����āA�M�҂̗\���ʂ�̓W�J�ɂȂ邩�ۂ��́A�u�_�݂̂��m��v�ł���B
�R�@�f�B�[�[����NO���ƔR������P�����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j [�܂Ƃ�]�@
�@�C���x�~�́A�f�B�[�[���̂m�n���팸�ƔR�����̈ꋓ�����̋Z�p���I�ɂ��ڏq���Ă���悤�ɁA�M�Ғ�Ắu�f�B�[
�[���G���W���̔R���NO���Ƃ̓����̍팸�������ł���v�V�I�ȋZ�p�v�ł����C���x�~�G���W���i�������J2005-
54771�j�̓����Z�p�����p������A���{�i�����ȁE���y��ʏȁj�́A���{�́uNOx�ƔR��̋K�������v���e�ՂɎ�
���ł���ƕM�҂͌ł��M���Ă���B�܂�A�č������ɂ���^�g���b�N��NO���K�����{�s����������{���{�̑Ӗ��ɂ�
�ڏq���Ă���悤�ɁA��^�g���b�N���C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p���̗p����������A�u���{
�̑�^�g���b�N�ɂ����Ă��č������ɂ�NO���K���v�����{������Ȃ��ߎS�ȏ��A�����_�ł������ɉ����E��
���ł���̂ł���B
�[���G���W���̔R���NO���Ƃ̓����̍팸�������ł���v�V�I�ȋZ�p�v�ł����C���x�~�G���W���i�������J2005-
54771�j�̓����Z�p�����p������A���{�i�����ȁE���y��ʏȁj�́A���{�́uNOx�ƔR��̋K�������v���e�ՂɎ�
���ł���ƕM�҂͌ł��M���Ă���B�܂�A�č������ɂ���^�g���b�N��NO���K�����{�s����������{���{�̑Ӗ��ɂ�
�ڏq���Ă���悤�ɁA��^�g���b�N���C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p���̗p����������A�u���{
�̑�^�g���b�N�ɂ����Ă��č������ɂ�NO���K���v�����{������Ȃ��ߎS�ȏ��A�����_�ł������ɉ����E��
���ł���̂ł���B
�@���̑��ɂ��A�\�Q�Ɏ������悤�ɁA�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p�́A�uDPF���u�ł̎��ȍĐ�
�̉^�]�̈�̊g��ɂ��R�����v�A�u�^�[�{�R���p�E���h���̔r�M�G�l���M�[�̉������������v�A�u�G���W��������
�ׂɂ������A�fSCR�G�}�̐G�}�������ɂ��NO���팸�v�A�u�g�p�ߒ��Ԃɂ�����A�fSCR�G�}��HC��ł̉v�A��
����uJE�O�T���[�h�ł̃R�[���h�X�^�[�g�����ɂ�����NOx�r�o�̍팸�v�̗D�ꂽ�@�\�E���\�������ł��邽���A���݂�
��^�g���b�N�������Ă���ۑ�̖w��ǂ������ł���V�Z�p�ł���B
�̉^�]�̈�̊g��ɂ��R�����v�A�u�^�[�{�R���p�E���h���̔r�M�G�l���M�[�̉������������v�A�u�G���W��������
�ׂɂ������A�fSCR�G�}�̐G�}�������ɂ��NO���팸�v�A�u�g�p�ߒ��Ԃɂ�����A�fSCR�G�}��HC��ł̉v�A��
����uJE�O�T���[�h�ł̃R�[���h�X�^�[�g�����ɂ�����NOx�r�o�̍팸�v�̗D�ꂽ�@�\�E���\�������ł��邽���A���݂�
��^�g���b�N�������Ă���ۑ�̖w��ǂ������ł���V�Z�p�ł���B
| |
|
|
| |
�����������C���x�~�̌��ʂɂ��A�d�ʎԃ��[�h�R��͂T�`�P�O���̌��オ�\
�i���������ɂ�����u�T�C�N�������̌���v����сu��p�����̍팸�v�ɂ��R����P���ʁj �m�Ⴆ�A�C���x�~�́A�f�B�[�[���̂m�n���팸�ƔR�����̈ꋓ�����̋Z�p���I���Q�Ɓn |
|
| |
���������̔r�C�K�X�̍������ɂ��ADPF���u�ł̎��ȍĐ��̉^�]�̈�̊g��ɂ��R�����
�i�㏈������V�X�e���i�������J2005-69238�j���̗p�����ꍇ�ɂ́A�X�Ȃ�R���Q��̖h�~�𑣐i�j �i�|�X�g���˂܂���HC�r�C�Ǖ��˂�DPF�����Đ��̉������A�����Đ��ɂ��R���Q���h�~�j �m�Ⴆ�A�C���x�~��DPF�̎��ȍĐ��𑣐i (�����Đ��̍팸�ŔR�����h�~�j���Q�Ɓn |
|
| |
���������̔r�C�K�X�̍������ɂ��A�^�[�{�R���p�E���h�ł̔r�M�G�l���M�[�̉������������
�m�Ⴆ�A�^�[�{�R���p�E���h�́A��^�g���b�N�̑��s�R��̉��P������ȋZ�p���I���Q�Ɓn �m�Ⴆ�A�C���x�~�́A�f�B�[�[���̂m�n���팸�ƔR�����̈ꋓ�����̋Z�p���I���Q�Ɓn [�Ⴆ�A�C���x�~�́A�f�B�[�[���r�C�K�X�̃G�l���M�[���u�̌������������Q�Ɓn |
|
| |
���������̔r�K�X���x�̍������ɂ��A�A�fSCR�G�}�ł�NO���팸���̌��オ�\
�m�Ⴆ�A�C���x�~�́A�f�B�[�[���̂m�n���팸�ƔR�����̈ꋓ�����̋Z�p���I���Q�Ɓn |
|
| �D | �����s�����r�K�X���x�̍����ێ��@�\�ɂ��A�g�p�ߒ��ɂ�����A�fSCR�G�}��HC��ł̉�
�i�㏈������V�X�e���i�������J2005-69238�j���ꍇ�ɂ́A�X�Ȃ�A�fSCR�G�}��HC��ł̉j
�m�Ⴆ�A�C���x�~��DPF�̎��ȍĐ��𑣐i (�����Đ��̍팸�ŔR�����h�~�j���Q�Ɓn
|
|
| |
JE�O�T���[�h���ɂ�����R�[���h�X�^�[�g������NOx�r�o�̍팸�ɗL��
�iJE�O�T���̃R�[���h�X�^�[�g������NO���r�o��啝�ɍ팸�ł���B��̎��p�I�ȋZ�p�j |
|
�@�ȏ�̂悤�ɁA�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p�����p�����A���̋Z�p���^�g���b�N�ɐV���ɍ̗p
���邱�Ƃɂ���āA���݂̑�^�g���b�N�̉ۑ肪�w��lj����ł���̂ł���B���̂��߁A�䂪���ɂ����鍡��̑�^�g
���b�N�ɂ�����R������NO���팸�̑��i��}�邽�߂ɂ́A�������R�c��̎����Ԕr�o�K�X���ψ�����܂ސ�
�{�E�����i�����ȁE���y��ʏȓ��j�̐l�B�́A�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p�𑁊��Ɏ��p������
���߂̍s�����N�����ׂ��ƍl���邪�A�@���Ȃ��̂ł��낤���B
���邱�Ƃɂ���āA���݂̑�^�g���b�N�̉ۑ肪�w��lj����ł���̂ł���B���̂��߁A�䂪���ɂ����鍡��̑�^�g
���b�N�ɂ�����R������NO���팸�̑��i��}�邽�߂ɂ́A�������R�c��̎����Ԕr�o�K�X���ψ�����܂ސ�
�{�E�����i�����ȁE���y��ʏȓ��j�̐l�B�́A�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p�𑁊��Ɏ��p������
���߂̍s�����N�����ׂ��ƍl���邪�A�@���Ȃ��̂ł��낤���B
�@
�@��L�̖{�����Ō�蓙���������܂�����A���[�����ɂĂ��w�E�������܂��B�܂��A�^��_�A������A�䊴�z���A�ǂ̂�
���Ȏ����ł����\�ł��B�Ջ��l���ĂɃ��[���������肢��������A�o����͈͂őΉ������Ă��������܂��B
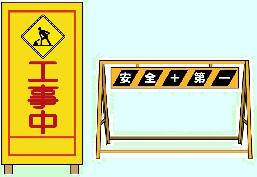
|
